2019年04月の記事
全8件 (8件中 1-8件目)
1
-

桜咲く北陸7名城巡りと、あさひ舟川春の四重奏。
いよいよ今日から平成から令和へと、年号をまたぐ連続10日間のゴールデンウィークだが低気圧が続けてやってくる関係から、芳しくなく、お勧めなのは28日、2日、5&6日であるらしい。娘とのお出かけ予定は雨予報今更、ホテルをキャンセルするのも気の毒なので雨覚悟でドライブ。曇り時々雨レベルだったらいいけど。北海道は雪予報だとか雷とか不安定な天気みたいですよね。今日もすごく冷たい風で、冬物残してて良かったしさてさて、4月5日に娘と出かけた1泊2日の北陸三県のバス旅ですが、最初にバスが向かったのは富山県の一番、東に位置する朝日町で、真っ白な北アルプスを望む海辺の街だ今回の旅行の最初の観光先は「あさひ舟川春の四重奏」といいまして、地元の皆さんの手入れで素晴らしい春の景色が望めるというもので、チューリップと菜の花、桜並木、残雪の朝日・白馬岳による四重奏なのだが寂しい会場にあった看板によればピーク時にはこのような素晴らしい四重奏となるそうですが時期が少し早かったみたいですね今年の場合、あと数日後の10日あたりから見頃だったみたいでチューリップも、いろんなのが植えてあったんですが早咲きなのか、この花だけが綺麗に咲いてました。あと数日もすれば、他の花も咲きだして花の絨毯になるみたいです菜の花は、この一角だけ咲いてましてこの後、畑の一面が菜の花畑になるのだろうか。フェイスブックとか見ると確かに、ピーク時には今年も綺麗だ肝心の主役の桜が、まだ咲きかけなのをアジア系外国人観光客の団体客も、残念そうに写真に撮っていた。私が参加をした1泊2日の北陸三県の桜旅は、旅行日程が4月上旬~中旬にかけての10日間から選択するタイプだったのでうちのように早い時期のお客さんも中旬を選んだ遅めのお客さんも桜が楽しめるように、早咲きのものから北部の遅めのものを、チョイスしていたんじゃないかと思います。桜が全く見れないのはサイアクですからですから後半の日程の皆さんは、きっと看板通りの素晴らしい四重奏を楽しまれたんじゃないかと思いますよ。まぁ雪も降るような4月アタマの寒波到来がなければ、もう少し咲いていたんじゃないかそんな気持ちもあります舟川の桜並木は、松山ケンイチ主演の山岳映画「春を背負って」のタイトルバックにも使われたものです。あれを見て、見に行きたいなぁ~とは思っていたんですが、わずか数日のずれでも桜は見れませんいかに、事前に予約をしている桜の旅が難しいのか。うちからは高山経由で車で4時間程度で行けると思うし、直前までキャンセル料のかからないホテルの予約でもしておいて、咲き具合から個人で行くしかなさそうですねでもね、そこの係の人が言ってましたけど昨日まで雨が降ったりして、空気が綺麗になったから、今日の北アルプスはとっても美しく見えるそうでして。う~む、これで桜が咲いてたらさぞかし素晴らしい風景が行きの高速では、山の反対側に座っていたので見れなかったが、今度は逆向きになり車窓から、散居村の向こうに北アルプスがバッチリ見れて、もう釘付けだ飛騨から砺波に出て、富山県の西から1時間はかかって、東端の朝日町まで桜がまだ咲いてない舟川まで行ったがこのような素晴らしいパノラマを見たのだから文句などない。山を楽しむ為出かけたようなものだ楽天ブログを始めた頃から知っている越中おわら節をされてい富山県の方がよく、北アルプスの写真を載せられていて、いいなぁ~と写真では眺めていて数年前の夏に、家族ドライブで出かけてそれ以来の山の光景。しかも高速道路からなので、街中を走る一般道より高い位置から、ずっと山を眺められていられるし奥の鉄橋は新幹線朝日町から富山市までを、撮った順番に写真を載せてます。どのあたりからとか山の名前はサッパリわかりません。さて今回の旅行は、1月に上海旅行で利用をした、阪急交通社トラピックスのメール広告で知りました本当は春には中国の北京旅行で、娘と万里の長城や紫禁城、パンダを見に行こうと思ってましたが、この桜の旅行を見つけて乗り換えました。それ程、自分の琴線に触れるものがあった訳でして名古屋発1泊2日で、3万円ポッキリで桜咲く7つの北陸の名城と、舟川四重奏ここでも、100名城の話をしたばかりですが北陸地方のお城って、北ノ庄城と金沢城しか行った事が無くって隣県であっても、なかなか行く機会にない北陸三県で、あちこちに点在する城を今後も、全部見る機会はなかなかないだろうし、この機会に一気に見てしまおうと。しかも桜の咲くお城って一年で一番、華やかではなかろうか天空の城で売り出し中の地元の苗木城址のライバルの「越前大野城」とか、準地元的扱いの松本の、松本城の日本最古ライバル現存天守の「丸岡城」は最近もニュースでやってたばかりだし、もうワクワク富山城、高岡城、金沢城、丸岡城、越前大野城、北ノ庄城、福井城との富山、石川、福井三県にまたがった桜咲く北陸の7名城、その中には日本さくら名所100選に選ばれた城もありますといった訳で、富山県の県庁所在地の富山市街に入りました。このあたりは神通川の下流域で、複合扇状地の恩恵を受け、大化の改新よりも前から北陸道における農作地であったそうだ旅情をそそるレトロな路面電車が走っていましたよ。富山地方鉄道が運営をする路面電車(軌道路線)は大正期に始まり地元では「市電」「富山市電」と呼ばれ親しまれているそうだ北陸7城のうちの最初の訪問先の「富山城址公園」に着きました。ウィキペディアによると>富山の地は北陸街道と飛騨街道が交わる>越中中央の要衝であり、富山城は16世紀>中ごろ越中東部への進出を図る神保長職に>より築かれたとされる>神通川(現在の松川)の流れを城の防御に>利用したため、水に浮いたように見え、>「浮城」の異名をとった。当時の神通川は>富山城の辺りで東に大きく蛇行しており、>その南岸に富山城は築かれていた。>室町時代の越中守護は三管領の畠山氏で>あったが越中には来任せず、東部を椎名氏、>西部を神保氏を守護代として治めさせて>いた。富山城は1543年(天文12年)頃に>越中東部の新川郡への進出をもくろむ>神保長職(じんぼう ながもと)が、椎名>氏の支配地であった神通川東岸の安住郷に>家臣の水越勝重(みずこしかつしげ)に>命じて築城したとされる。しかし最近の>発掘調査により室町時代前期の遺構が発見>され、創建時期はさらにさかのぼると>考えられている>長職は1560年(永禄3年)、椎名氏を支援>する上杉謙信の攻撃により富山城を追われ、>神保氏の在城は僅かな間であった。その後、>富山城は上杉氏と一向一揆の争奪の的と>なったが、1578年(天正6年)、長職の子と>される神保長住が織田信長の後ろ盾を得て>富山城に入城した>しかし、1582年(天正10年)3月、長住は>上杉方に内応した家臣に背かれて城内に幽閉>されて失脚し、替わって富山城主となった>のが佐々成政である。富山城に拠点を構えた>成政は富山城の大規模な改修を行った>本能寺の変の後、豊臣秀吉と離れた佐々>成政は1585年(天正13年)8月、秀吉>自ら率いる10万の大軍に城を囲まれ降伏し>(富山の役)、富山城は破却された>越中一国が前田家に与えられると、前田>利長が大改修を行い金沢城から移り住み>隠居城としたが1609年(慶長14年)に>建物の主要部をことごとく焼失したため、>高岡城を築いて移り、富山城には家臣の>津田義忠が城代として入った。1639年>(寛永16年)、加賀藩第三代藩主前田>利常が次男の利次に10万石を与えて分家>させ、富山藩が成立した>1661年(万治4年)、幕府の許しを得て>富山城を本格的に修復し、また城下町を>整え、以後富山前田氏13代の居城として>明治維新を迎えるまでの基礎となった。>1858年4月9日(安政5年2月26日)、飛越>地震が発生した。富山城も被災し、本丸や>二の丸、三の丸が破損したほか石垣が崩れる>など大きな被害を出した>1871年(明治4年)廃藩置県により廃城と>なり、翌年建築物は払い下げられた。>1954年(昭和29年)4月11日より富山城>跡の敷地一帯で富山産業大博覧会が開催>され、鉄筋コンクリート構造による模擬>天守が記念に建てられることとなり、>1953年(昭和28年)7月に着工>翌1954年(昭和29年)4月3日に完成し、>通称「富山城」と呼ばれることになった。>この模擬天守は同年11月17日より富山市>郷土博物館として運営が始まった。2003年>(平成15年)6月より、富山市郷土博物館>(富山城)の耐震補強工事に着手、>2005年(平成17年)11月3日に、展示内容も>見直しリニューアルオープンした。2004年>(平成16年)「地域の景観の核」との評価に>より富山市郷土博物館(富山城)が、国の>登録有形文化財(建造物)に登録されたとの事で富山城址公園には、様々な石碑なども建てられていた。ここではフリーでの見学時間が20分程しかなく速足でぐるっと見て回るだけだったせめて30分はくれないと、門とかも遠目で見ただけだったしこちらは砺波出身の実業家である佐藤家が戦後に建てた佐藤記念美術館で、茶道具類古陶磁、日本画、墨蹟など千点以上に及ぶ収蔵品の殆どが佐藤家から寄贈され、今は富山市が先ほどの富山市郷土博物館と共に運営にあたっているそんな感じで、一番最初の富山城址では桜も良い具合で、市民の方ものんびりとお散歩をされていた。次は令和で盛り上がる万葉集にゆかりの高岡市の高岡城へと。令和に続く~ 平成31年4月5日に富山県で撮影にほんブログ村
2019年04月27日
コメント(77)
-

出発は前日入りした名古屋。渓谷や、雪山。秘境の先には
さてさて4月のあたまに、娘と出かける花見旅で桜の開花具合が心配だと言ってた4月5日&6日の旅日記をスタートさせます。この旅行では名古屋駅に午前7時チョイには集合だというので集合時間までに、名古屋駅に着くには5時台の始発に乗る必要があり、その為には、家を5時出発だなんて辛すぎって事で、娘が仕事が終わった夕刻に名古屋に出て、駅前のビジネスホテルに安く前泊をするという事でホテルにチェックインをしてから、夕食を食べに出かけた先は、ユニモール地下街でビールと餃子とおつまみのセットで千円というのを、私と娘でそれぞれ注文をしたが私のビールは、殆ど娘が飲みましたちょっと足りないなぁ~と、ラーメンを1杯頼んで二人で半分こ。お腹も一杯になったので、そろそろホテルへGO名古屋駅付近にも新しいホテルが出来ていますが、ツイン(二人価格)で9千円以下に設定したので、古めビジネスしか検索で出なかった中で、朝食にはパンと飲み物付きで、二人で8千円程で普通に宿泊できました同じように、初日の仕事に間に合う為には5時台の始発なのはキツイからと、息子が岡崎の出張に前泊をしてるが、出張費とか出ない個人の宿泊になるんで、ポイントも貰えるし私がネットサイトで予約を取っている狭い部屋で素泊まりの4300円と、広くて快適な朝食付き6680円の二つでどちらがいいかと息子に聞くと、6680円と、躊躇なく答える息子だ。私なら安い方だろうなぁ~さてさて自分の旅行の話に戻すと、午前7時チェックアウトをして、無事に集合場所へと向かうと添乗員さんがリストにチェックをしてから「お昼ご飯を買えないので、ここで食べるものを買ってきてください♪」 安い旅行ではお昼頃にフリータイムを作って、各自食事をとる事が多いけど、そうゆう時間もないのか。ホームにはJRのワイドビューしなのと、ひだ今回参加したのは、1泊2日の団体旅行で基本的にはバス旅行なんだけど、途中までJRを利用するタイプで、今回は初めてのワイドビューひだ。車ではよく通る道だが今回は高山線でというのが、物珍しくって電車から見る風景はどんなかな?高山線は、まずは岐阜へ向かいますが岐阜駅でスイッチバックを行って方向転換をするので、座席は後ろを向いてセットされてます。車窓からは金華山にそびえる岐阜城が遠くに見えた反対側に座ったので、写真は撮れなかったけど途中で犬山城も見えました。ちゃんと右側に見えますとか車内アナウンスしていましたよ。そして、いよいよ七宗町に入って飛水峡のゴツゴツした岩場が見えたウィキペディアによれば>飛水峡を含めた飛騨川流域一帯は、飛騨>木曽川国定公園区域の河川公園である。なお、>飛水峡のうち、JR高山本線上麻生駅の東>約600mの飛騨川に架かる「上麻生橋」から>上流約2kmの間の峡谷部分は、甌穴(ポット>ホール)が河床の岩盤の上に数多く見られる>ことから>「飛水峡の甌穴群」(「ロックガーデン」とも>称される)として、国指定の天然記念物となって>いる。初夏に飛水峡の岩肌に花咲く岩躑躅>(イワツツジ)も見所。この付近一帯の地質帯は、>「美濃帯・上麻生ユニット」に属し、採集された>チャートの礫から中生代の三畳紀からジュラ紀の>放散虫化石が発見されている国の天然記念物、日本の地質百選だそうだ。ここも車でよく通っているので、お馴染みの光景だが電車からだと、また違った感じだし偶然、なんかカッコイイ写真が撮れたどちらも窓際に座りたいので、娘とは30分くらいで交互に交代をした。帰りの方はもう暗くなってたので、娘がずっと窓際だ。圧迫感がないので通路際の方が好き同じワイドビューのしなのと、ひだは何が違うのか。しなのは制御付き自然振り子式車両の383系電車が使用されているのだが高山線は電化されてないので、ひだの方はJR東海のキハ85系気動車を使用している1989年の通商産業省グッドデザイン商品(日本産業デザイン振興会グッドデザイン賞)1990年のブルーリボン賞は次点となった通路より20センチ程高い位置に、座席が設置され、窓の縦寸法も95cmに拡大して眺望をよくしているそうだ普通車の座席の前後間隔(シートピッチ)もキハ80系の91cmから100cmに拡大しているので、足元も広々。居心地の良い列車でひだは下呂を抜け、どんどん北へ臥竜桜は、この時点でまだまだつぼみで先週あたりに綺麗に咲いていたようです一度、桜の時期に出かけた事があります名古屋駅で乗車をしてから、2時間以上かかって午前10時頃に終点の高山駅に到着しました。うちから下呂経由で下道を普通に車でくるよりも、時間がかかった。しかも前泊までしてるし富山までそのまま行けたらいいのに、次のひだなら富山まで行く事が出来たけど、それだと遅くなってしまう。それ以前に名古屋から高山までワイドビューを使って、そこから、濃飛バスをチャーターする事が何かしらメリットがあるんだろうさて、ここからは濃飛バスに乗車をしていよいよ本格的に出発だぁ~。なんかもう旅行しちゃった感もあって、何をやっているんだろうね。ホント。ともかく岐阜県(東の端っこ)にとって、愛知県発着での旅行は、それだけでハードルが高い高山から見た乗鞍岳は、北アルプスの南部にあり、北は「安房山」から南の主峰「剣ヶ峰(3026m)」の23峰の総称だ。およそ128万年前程前から活動をしている火山で火山としては富士山、御嶽山に次ぐ日本で3番目の高さがあるバスの方は、高山から反対側の西へと向かい東海北陸道で富山に入るようだ。この道路は前に、家から下呂経由で2時間で車で来てそこから白川郷に足を延ばした時に利用をした事がある富山に出かけた事は1度だけあって、その時はまだ娘が松本にいたので、前日に旦那と娘のアパートに泊まって、松本から白馬、糸魚川に出て、そこからは日本海に沿って魚津に出かけた富山からの帰りは飛騨神岡、奥飛騨温泉の安房トンネルを通り松本に戻ったら、すぐ帰ってこれたので、松本から富山って近いもんだなぁ~と驚いたものだ。今回は高速利用と言う事で、新たな富山ルート開拓だおとなり金沢には、名古屋から高速バスを使った事があり、名神から北陸道を使ったものだった。そんなんでお隣の県でも富山県は山深い飛騨を挟んでいるので地理的にも結構、遠い行く機会も少ない地域である途中で1度だけ、トイレ休憩を行って名古屋駅で昼ごはんを買い損ねた人はそこの併設コンビニで調達をして下さいという話だった。バス2台なのでレジにはツアー客の大行列そして山深い飛騨から抜けて、何やら風光明媚なところにやってきましたよここは砺波平野。昭和46年の歌会始ではてもなき砺波のひろの杉むらに とりかこまるる家々の見ゆとの昭和天皇の御歌が披露された。これは前年度の富山県植樹祭に臨席をされ、砺波平野の散居村において、カイニョ(屋敷林)に囲まれた家々に感動され歌われたそうである散居村は、ウィキペディアによると>広大な耕地の中に民家(孤立荘宅)が散ら>ばって点在する集落形態。一般的には散村>(さんそん)と呼ばれる。集村と対比して>語られることが多く、一般には集村が普遍>的で散村は比較的少ないと考えられているが、>実際には世界的に広く見られる集落形態で>ある。砺波平野の散居村>この景観が成立したのは、16世紀末から17>世紀にかけてであると考えられている。砺波>平野を流れる庄川は江戸時代以前にはしばしば>氾濫したため、この地域に住みついた人々は>平野の中でも若干周囲より高い部分を選んで>家屋を建て、周囲を水田とした随分と北上しました。もう長野県まですぐ近くと言う感じ。もう昼も過ぎてやっと一番最初の観光先に到着しそうです。その様子は次回で・・・さてさて旅行日記の構成上、初日の観光を全部すっとばし、先ずはこの旅行の宿泊先である山中温泉の温泉ホテルについて紹介します。名前の通り、山中温泉は山の中でした(↑次の朝の写真)子供が小さな頃に、うちは泊りで北陸方面に出かけていたので、片山津とか粟津温泉は利用した事があるが、ここ山中温泉はまだなかったので、それも楽しみの一つだったここも、かつては社員旅行の団体さんが沢山やってきてたんだろうなぁ。まるでクラブみたいなシャンデリアは、大浴場のだだっ広い脱衣所にもあった。更にそこに電動の岩盤浴の機械が物珍しくて、利用してみた初期のウォシュレットがあったりと、建てられた頃にはお金をかけ、最新の設備を誇っていたのだろう。泉質はカルシウム・ナトリウム硫酸塩泉(低張性弱アルカリ性低温泉)昼ご飯もないような格安旅行の、団体料理なので、あまり期待はできないが高齢者が多いので、量が少なめなのはかえって良いのかもしれないアワビの踊り焼きは、しっかり踊っていたし。冷たい天ぷらを横に並べて暖かくしてから食べた。まぁ天ぷらが冷たい宿は、個人でもたまに見かけるしかしお肉のたれが、うちで普段から食べているのにそっくりな味だったので完全お残し。娘が私の肉を食べてくれたしかし次の朝食は、海辺の県であるのかひものがよりどりのブッフェで、これはなかなか、面白い新鮮そうなひものを焼いて、自分で選んだとはいえ、やっぱ高齢者向きのヘルシーな朝食だった。なかなか観光豊富、移動時間の多い旅行だったので山中温泉に着いたのは夜7時半になりそれからの夕食あったし、疲れもあって朝は散歩より温泉につかったので、もう行く事はないかもしれないだろう、山中温泉の温泉街は散歩できずに残念2日目はランチがありました。こちらは焼き鯛まぶし丼御膳という事で、越前のお蕎麦がセットされていた。なんと高山7時近くのワイドビューひだ利用で、夜遅くの9時前に、名古屋に到着なのだが夕食は自分で調達をしなければならないしかし格安バス旅行によくある、事前にバスの中で、千円程のお弁当を注文して夕刻に受け取るというので半数近い人がお弁当を注文していたが、私らは高山駅での空き時間にコンビニで調達できたが初日のお昼といい、コンビニおにぎりな旅だった。次回から肝心の観光の紹介を 平成31年4月5日に愛知、岐阜、北陸で撮影にほんブログ村
2019年04月23日
コメント(57)
-

アルプスを望む桜の城ドライブで伊那谷ニュー・スポット巡り
平成最後の桜も当地方に咲きだした、4月も半ば。毎年必ず桜の時期にお花見に出かけるのが、清内路を超えての信州伊那谷。昨年も出かけたが、韓国の旅やお相撲の日記が多くお蔵入りをさせてしまった4月15日月曜日、娘が会社がお休みだったので、どこかに行こうという話となったが名古屋はよく出かけてもいるし、やっぱり今年も伊那谷の桜を見に行こうと。うちのあたりが咲いてるし、あちらもバッチリだまずは、花桃も咲きだした昼神温泉を過ぎて旧杵原学校へ。吉永小百合の映画「母べぇ」でロケに使われた、今はもう廃校となった学校の校庭に咲く枝垂れ桜で樹齢は70年程らしい国の登録有形文化財にも登録された校舎前には若い桜の樹も植えてあり、これは樹齢350年という、飯田の麻積の里の舞台桜のものであるらしくやっぱり花弁がむちゃくちゃ多い。これは「半八重枝垂れ紅彼岸桜」という花ごとに花弁が5~10枚とまちまちで、平成17年に新種と断定された大変に珍しい桜なのだ今回の伊那谷ドライブは、桜が目当てだとは言っても、冬物の見切りなどがないかと飯田市街のイオンモールやアピタなどで買い物をするのも目的で、今回も大収穫防寒機能もありそうな、厚めのパンツ類は4000円近くのものが1000円どころかそこからの半額の「500円ポッキリ」でいやぁ~良い買い物が出来ましたイオンモールの雑誌コーナーで、久々に信州のタウン雑誌などをペラペラしてた娘が、道の駅が出来てる~!というので昼も近いし、そこでランチを食べようと出かけました飯田市街から少し北に行って、天竜川を越えた豊岡村に昨年春に「南信州とよおかマルシェ」が出来たそうで、観光客が目当てというより地元車ばっかだし。それもそのはず、スーパーマーケットがメインだしここにある「kitchen そらら」は広々として大きな窓の向こうには山々が広がって、長居出来そうな感じ。ランチ以外での利用にも良さそうだ。今日も年配のお客さんを中心に大盛況娘は、平日ランチの牛すじ醤油ラーメンとミニカレーとサラダというがっちりなのをカレーと、ラーメンを少し食べてくれといわれて、私もパクリ私の方は南信州牛合挽きハンバーグトマトソースチーズ風味と、パンと、ラーメンのと同じがっつりサラダのセットだ。もちろん娘にハンバーグもおすそ分け。ハンバーグの上にはコロッケも乗っていたスパーマーケットの他に、直売所とかパンや、ジェラードのお店もあるので次はそちらも食べてみたいお腹もいっぱいになったので、天竜川に沿った国道153号線を北上し、目的地である、アルプスの見える桜の城に到着天下に名高い高遠城の桜よりも、風光明媚でもあるので娘が大好きな、中川村にある大草城址だ桜の向こうには中央アルプス(木曽山脈)早かったりしがちな、ここの桜も今年はベストの満開で、むちゃくちゃ綺麗だしここには、定番の染井吉野以外にも様々な桜が咲いているのが良い城址については、↑で南朝ゆかりのお城であるらしい。うちのあたりも南朝の伝承が幾つも残されている特に書くこともないので「宗良親王」について、ウィキペディアによると>歌道の家であった二条家出身の母から>生まれたことにより、幼い頃から和歌に>親しんでいた。妙法院に入り正中2年>(1325年)妙法院門跡を継承。続いて>元徳2年(1330年)には天台座主に任じ>られるも、元弘の変により捕らえられ>讃岐国に流罪となる。>父後醍醐の鎌倉幕府倒幕が成功し、建武の>新政が開始されると再び天台座主となるが、>建武の新政が崩壊し、南北朝の対立が本格化>すると還俗して宗良を名乗り、大和国吉野>(奈良県)の南朝方として活躍をするように>なる。(中略)>暦応3年、興国元年(1340年)に足利方の>高師泰・仁木義長らに攻められて井伊谷城が>落城した後、越後国(新潟県)の寺泊(現・>新潟県長岡市)や、越中国(富山県の放生津>現・富山県射水市)などに滞在した後、興国>5年/康永3年(1344年)に信濃国(長野県)>伊那郡の豪族香坂高宗(滋野氏支流望月氏の>一族)に招かれ、大河原(現・長野県大鹿村)に>入った。>宗良はこの地を文中二年(1373年)までの>約三十年間にわたり拠点とし、「信濃宮」と>呼ばれるようになる。その間に上野国や>武蔵国(武蔵野合戦)にも出陣し、駿河国>(静岡県)や甲斐国(山梨県)にも足を>運んだことが『新葉和歌集』や私家集で>ある『李花集』の内容から判明している。>拠点となった大河原は伊那谷に属し、南に>下れば井伊谷(井伊氏)から東海地方へ、>北上すると長谷(後述する終焉の地の一つ)を>経由して諏訪(諏訪氏)や関東へと通じる>位置にあり、別名「南朝の道」とも呼ば>れる後の秋葉街道の中心に位置していた>そのため、劣勢が続く南朝方にとっては>最重要拠点となり、各地で破れた南朝方の>武士達(新田一門など)が逃げ込む事も>多かった。(中略)応安2年/正平24年>(1369年)には信濃守護を兼ねる関東管領>上杉朝房の攻撃を受け、文中3年/応安7年>(1374年)、ついに頽勢を挽回できぬ>まま36年ぶりに吉野に戻った。>この頃から南朝側歌人の和歌を集めた和歌集の>編集を開始していたが、再び出家している。>宗良の編集していた和歌集は当初は私的な>ものであったが、長慶天皇は勅撰集に准ずる>ように命じた。弘和元年/永徳元年(1381年)に>完成した『新葉和歌集』である。>晩年については、新葉和歌集の選集がほぼ>終わったと思われる天授4年(1378年)に>大河原に一度戻った事が判明しているが、>弘和元年/永徳元年(1381年)に吉野に>戻って新葉和歌集を長慶天皇に奉覧して>以後は、確たる記録が残されていない。>終焉場所については、天文19年(1550年)に>作成された京都醍醐寺所蔵の「大草の宮の>御哥」と題された古文書の記述から、長らく>拠点であった信濃国大河原で薨去したとする>説が有力とされている他にも諸説があり、遠江国井伊城や入野谷郷浪合、河内山田、美濃国坂下、越後や越中などなど。大鹿村大河原や中津川市高山には宗良の墓が、静岡県の井伊谷宮は宗良親王を祀っているそうだ低気圧と東日本上空に強い寒気が流れ込んだ影響で、4月10日はうちも雪が降ってたが伊那谷は積雪に見舞われた為、桜の花にも雪どころか、枝に積もった雪の重みから折れてしまってこんな無残な姿となってしまった。なんとか修復して、これからも美しい桜花を咲かせてくれたらいいのだけど。江戸彼岸桜のようだ平日なので地元の方などが、のんびりとお花見をしていた大草城址。出店などもあって鹿肉とか、やっぱジビエな伊那谷だ中川村には様々な桜の名所があり、西丸尾の枝垂れ桜などは、もう一度見たいとは思うけど、アクセスが一車線山道で行く勇気はないでも、天竜川にかかる坂戸橋付近の桜は道沿いに駐車場も完備してあるので、私でもこんな写真が撮れるのがありがたい駐車場へと向かう階段は、桜の下で坂戸橋は1933年に建設された、鉄筋コンクリート製の単アーチ橋で、橋長77.8m、橋高20m、幅員5.5m、スパン70m、アーチライズ12m。建設当時は国内最大スパンを誇り、1965年(昭和40年)以前に造られた、現存する鉄筋コンクリート製単アーチ橋では日本一の長さを有する。橋の向こうには桜並木前にも紹介をした、国道153号線の伊南バイパスの立派な橋からの、中央アルプスやっぱ、この道はおすすめの絶景ドライブロードだ伊南バイパスの道沿いに、2016年夏にオープンをしたのが、飯島町の「道の駅田切の里」で地域の農産物や特産品などを販売し、地元産食材を使ったレストランもこの道って何度も通っていたのに、私は反対側の中央アルプスばかり見てたので、道の駅の存在は全く気が付かなかった。しかも桜の名所みたいだし道の駅のすぐ近くに、このような桜並木もあったので、しばしのお散歩タイム桜越しの中央アルプスも、雪があって美しいこの後には、駒ケ根の馬見塚公園でお花見をしようかな~なんて、車で向かうが娘が駒ケ根にパンケーキのお店が出来ている!と、ネットで見つけた「ルビーカフェ」の看板が道路にあったので、行先変更~。1年半程前にオープンしたみたいだけど赤そばの花も咲く広い敷地を持つ、ルビーの里にあるカフェからは南アルプスも眺める事が出来る。次は、赤そばの花の咲いている時に出かけたい名古屋で食べるようなこじゃれた、パンケーキが伊那谷でも食べる事ができるなんて。しかもこれ700円(ふわしゅわパンケーキ)なんですよ~更に100円で飲み物をセットできるので、娘はコーヒーを一緒に注文。これはお得だしとりわけ皿も貰って、二人でパンケーキを食べたので、私の方はアイスコーヒーを300円で頼むが、かわいいミニケーキがおまけについていたこのお店はおすすめです。このブログによく登場する養命酒の工場にも近いです。といった感じでいろいろお店もオープンする伊那谷ドライブ最後はやっぱり、信州のスーパーと言えばツルヤ駒ケ根にあるツルヤ赤穂店からも、南アルプスが見えましたうちの方では売っていない、娘の好きなプチトマトも購入し、いろいろと赤札になったものを購入道の駅の直売所や、大草城跡の出店でも果物を購入しました。ジュース用の林檎もおやつにかじりましたが、普通においしかったですよ 平成31年4月15日に信州伊那谷で撮影にほんブログ村
2019年04月17日
コメント(66)
-

我が家の春の訪れは女城主の里から、今年もグルメ旅
中国旅行の日記が続いたので、まだ紹介が出来てなかったのが、一足早く我が家の春を告げる、恒例のあれですよ、あれ節分を過ぎて、恵那市の山間にある霊験あらたかな妙法山満勝寺(飯高観音)に厄除けの参拝です。今年は旦那は後厄で娘は前厄にあたりますある年に厄年にも当たらないし、寒いしめんどくさいから、参拝はいいかぁ~と言ってたら、体調も悪いまま兄に誘われ買ったばかりの株価も落ちるし、散々で慌てて、ここにお参りに行ってから特に災難は起きませんでした以来、毎年出かけてお札を貰ってきています。さて参拝も済んだし、前から来たかった岩村近くにあるパン屋へとうちのあたりのパン屋は、市街地ではなく山間部にあるので行くのも大変だ前に、テレビでも取り上げられていた夫婦で営む小さなパン屋さんは評判も良いのか、店の前に行列も出来ていましたよでかいパンは買ってすぐに、車の中でちぎって食べました。これからランチだし、これで我慢。もっちり、しっとり美味しいですまた行けたらいいけど、恵那市街から車で15分、うちからだと50分位はかかるので、来年の飯高観音に参拝をする時になってしまうかなぁ~ランチもテレビでやっていたとんかつ屋でこんなところがあるのかぁ~と、行きたいと思っていた店で、駐車場には他府県ナンバーも無性にとんかつが食べたくなる時がある値段も手ごろだし、また来たいけどここも遠いし、チャンスでもあればお腹もいっぱいになったので、今春も参戦しますか! 岩村醸造の「蔵開き」500円(ここのおちょこ持参の人は300円)でお酒をガンガン飲めるというもので、300円は商品の割引に使えるのだが以前は500円以上のもので、300円割り引けたのに、今年は1000円以上になっていた。まぁ世の中、値上げの嵐だしアマゾンプライム年会費も予告なく値上げしたくらいだし(3900円→4900円)娘は前から入るかを迷っていたが年明けに年間会員になったばかりなので「良かった~、駆け込みで入っていて」とそれでなくてもBS放送で映画やドラマを録画して見なきゃいけないのに、アマゾンプライムで、少し前の映画やドラマとか見放題なので大忙しだお正月頃に、レンタルDVDで初めの方を借りたスーツのシーズン6もアマゾンプライムにあったのでドラマの続きを見る事も出来た。そんな訳でうちのBS放送のドラマはどんどんたまるばかりで地上波の方は、すぐに見るようにしてるんだけど先週は借りようかなぁ~とか、迷ったままだったサバイバルファミリーを鑑賞。旧作は100円だから月に4本でも見れば、アマゾンプライムの会費の元は取れる。娘はアメリカ系ドラマ、旦那はガンダムシリーズを見てるしさて息子は、出張で岡崎に行っていないので今年も、私がドライバー役を買って出ました試飲会場の様子は、娘に撮って貰いましたよ直ぐに出てくるとか言ってた旦那は、会社の人たちに会って宴会になってしまい、寒い中岩村の中をうろつきましたわアルコールの入っていない「甘酒ソフト」を娘とはんぶんこ今年から1000円以上のお酒でしか、割引券を使えないので、旦那と、娘の300円を使って前より大きな瓶を買ってお土産に。まぁ、あんだけ飲ませて貰ってるし、酒屋さんも慈善事業ではないんだから仕方あるまいでは、旦那と娘が宴会状態になってご機嫌だった頃に、私は岩村の街を毎年のようにうろつきまして、やってきたのは明知線の岩村駅ですわとりあえず来ました。蔵開きなのでJR中央線恵那駅を経由して、ここに降りたつ人たちも沢山いました。私は1回だけ、前に乗った事があります。普通車を使いますが明知線のマスコット「てつじぃ」と、その横には、岩村の悲劇の女城主おつやの方なのでしょうか岩村駅にはグルメショップも併設をしており岩村駅丼は、お城盛りなるものも・・・さてさて商店街の方に戻ります。最近は真田丸の真田昌幸を彷彿するような草刈正雄の朝ドラ「なつぞら」の泰樹おんじ登場して2週間程なのに、もう神回だの名シーンに涙する人もいるそうだがいいキャラクターだなぁ。おじいちゃんだ~い好き!となつが抱きつくシーンとかハイジ思い出しちゃいました。ネットによると今回の朝ドラは子供や、高齢男性の視聴が多いそうだが、泰樹おんじの影響もあるのかもお忘れでしょうか。1年前の朝ドラはここ岩村が、ロケ地となった「半分、青い」のふくろう商店街でした。恋愛ドラマに強いという女流脚本家さんだけに、歴代朝ドラ名シーンのリクエスト番組では律と毛布にくるまるという胸キュンシーンが選ばれてました。私はやっぱり「うんまっ!真実の食べ物だ」と五平餅をほおばる漫画家秋風先生でしょうね。岐阜(&愛知、長野)のローカルフードであった五平餅が、全国に知られフクロウ商店街のロケ地となった山間の城下町岩村も、少しは知名度が上がって良かったように思います。たぶんドラマで使われた商店街のシンボルが、そのまま残されてました町の人たちにも良い思い出になったと思いますし、街の活性にも少しは結び付いたようにも思います。とは言っても岐阜県恵那市自体は、既に来年の大河「麒麟がくる」の主人公、明智光秀にシフトしてますね。これは恵那市街の図書館の入り口にあったノボリですでもでも岩村の女城主は織田信長の叔母武田に攻められて降伏したのを、今度は織田勢に攻められ、逆さ磔にもされたという悲劇は、信長のドラマにも出てくる事もあるし、1年の長い大河だから出てくるかもしれないでも光秀の前半生メインらしいし。どんなもんだろ。信長も染谷将太といった若い俳優を使っているから、本能寺はないのかもしれないし。道三が本木雅弘というのもイメージが違って新鮮。今までとは違った戦国が観れるかも斎藤道三というと、過去には昭和48年の大河「国盗り物語」(原作は司馬遼太郎)で平幹二朗が演じたのを子供ながらに覚えている。信長は高橋英樹、濃姫は武士の娘の松坂慶子だった光秀は近藤正臣、家康は寺尾聡で、秀吉は火野正平と、今でも朝ドラや大河ドラマ、そしてチャリンコで全国でまわる旅などNHKで活躍中の役者さんたちだしそれにしても、時代を飛び越えてしまったような昭和の時代を思い起こさせる町並みだこれは、何に使うもんだろう?山里のひな祭りは、旧暦に近い4月3日で、3月では花がまだないからなんていうのを何かで読んだ昔ながらのお雛様が3月1日からひな祭の4月3日まで飾られて山間の里を華やかにしている岩村駅に近い町並みは、昭和チックだけど、お城に近い上手は江戸時代の建物も幾軒か残されて、公開もされている武家ではなく、商売をしていたお宅などだろう。そうそうお札がかわるそうで、女性は作家の樋口一葉さんから次は教育家の津田梅子なんだとか武士の娘として生まれ、僅か6歳で米国に留学。ウィキペディアによれば>(帰国後)外務卿・井上馨の邸で開かれた>夜会に招待され、伊藤博文と再会し、華族>子女を対象にした教育を行う私塾・桃夭女>塾を開設していた下田歌子を紹介される。>このころ父・仙との確執もあったこと>から、梅子は伊藤への英語指導や通訳の>ため雇われて伊藤家に滞在、歌子からは>日本語を学び、「桃夭女塾」へ英語教師と>して通う。と言ったわけでお札になる津田梅子と同様に女子教育の先駆者であった下田歌子は、ここ岩村藩の出身です。ウィキペディアによれば>岩村藩士の家に生まれる。幕末に勤王派の>藩士だった父は蟄居謹慎を命じられるが、>苦難の中、鉐は祖母から読み書きを習い、>5歳で俳句と漢詩を詠み、和歌を作るなど>神童ぶりを発揮した。書物を読んで善い>事だと思うと、すぐに行動にうつす事も>多かった。(中略)>元号が明治になり祖父と父は新政府の>招聘を受けて東京に出るが、17歳になっ>た鉐もその後を追って上京。そのとき、>故郷の国境、三国山の峠で「綾錦着て>帰らずは三国山 またふたたびは越えじ>とぞ思ふ」という歌を詠んでいる。>明治5年(1872年)、女官に抜擢され>宮中へ出仕する。武家の子として身に>付けた礼儀作法や、儒学者の祖父仕込みの>学識、和歌の才能で皇后・美子から>寵愛され「歌子」の名を賜る。 宮廷で>和歌を教えるようになる。木村家は問屋にして苗字・帯刀が許された士分待遇で、藩の財政困窮のたびに御用金を調達してその危機を救い、藩主より特別な存在として認められ、藩主自身が幾度となく訪れたそうですそんな優遇からか、岩村城で使われた欅も床板にしているとは・・・岩村のご城下は東農地方随一の賑わいであったとか今回も500円で数百円相当のグルメなどが楽しめるおとくーぽんを購入しお土産に活用する事とした女城主の岩村醸造の真ん前で、かすてらの試食も美味しい松浦軒本店で、おとくーぽん3枚(500円)で交換ができるのは470円のかすてらと、半分、青いのフクロウ商店街にちなんだ「ふくろう焼き」150円で、合計620円分とお得にお土産が購入できた更に岩村にやってきたら、必ず購入するのがかんから餅。黒ゴマ味のは息子が好物だしこうして春の兆しは2月の岩村で始まり花粉症の旦那がはっくしょん!と始めてあぁ平成の終わりに・・・固定資産税の納付書が、市会議員の選挙入場券と一緒に届いた。間もなく車4台の10万円越えの税金の納付書も届くし・・・お金がいくらあっても足らない。というかゴールデンウィーク前にガンガン、お金払わさせられたら、行楽も行く気が失せる年に数度のジャンボ宝くじは10枚買っていたが、今年はジャンボとミニと1枚ずつ300円×2でも、宝くじの夢は見れるし 平成31年2月17日に岐阜県恵那市岩村町で撮影にほんブログ村
2019年04月14日
コメント(51)
-

高級料亭で華燭の宴に集いし良き日に。岡崎城の桜
今年70歳となって、あまり遠出もしなくなった姉だが、姪が結婚する事になったと弾んだ声で電話をよこしたのは昨秋だったで、年を越しての1月半ば、良く晴れた日お相手が名古屋の方でもあるので名古屋の老舗の料亭で挙式と、披露宴を行い、旦那と夫婦で参列をさせて貰った千葉の次兄のところの甥も、奥さんの方が四国出身で、私らはみんな岐阜県。で次兄家族は千葉という事で、中間の名古屋で式を行った姉が「夕方からの式だけど、名古屋で泊まるか?」と言うので、「そんなん家に帰れるよ」とそのまま帰るつもりでいたが、千葉の兄夫婦は遠いからと姪が手配した、名古屋駅のホテルの超高層階ホテルに泊まると当日に聞いて旦那が羨ましがってた千葉の兄夫婦は新幹線代とか、お金もかけてきているからまだしも、うちら夫婦で参列、ホテルの宿泊代までをとなったら、どんだけご祝儀が必要となるんだぁ~?と、想像しただけで諭吉がひらひらと頭の中で舞う実家の長兄夫婦と式場から徒歩で、近くの地下鉄駅から名古屋駅に出て、普通電車に揺られて帰宅をした。今回の結婚式場は名古屋の「料亭河文」で、結婚式場とかホテルなどの式と披露宴はあるが、こういったところは初めてだ私の実家は二階にお蚕様も飼育していたので部屋が15位もあって、座敷も表から奥まで4つあるんで、長兄の結婚式は自宅で行った。三々九度を子供が行うというのも私が行った。姉の方は、嫁ぎ先で結婚式を行うというので私は家で見送っただけで、式には父母と長兄だけが参列をしたそんな昔ながらの結婚式などが、現代風に変化したのは、やっぱり大阪万博の頃でテレビがどの家にもやってきて、農業だけでは生活出来ず、田舎でもサラリーマンが増えた時代であるだろう。新婚旅行も宮崎とか、熱海といったところか私の頃はチェーン化した、どこの都市にもあるような結婚式場で、新婚旅行先はグアムだった。偶然、巨人キャンプをしていたので気を利かせて、観光コースにも入っていたので江川や、桑田を目の前にして旦那が大喜び果たして、姪夫婦がどこに出かけたかは判らない。テレビとかである、ライスシャワーってのはやった事はないが、神式、仏式、人前式などなど今回のお式は夕刻スタートで、午後7時前にお開きになったのは、この後に友人や同僚とカジュアルなスタイルの披露宴(二次会)が行われるようで、玄関先にはドレスを着込んだ妙齢の女性らが集まってきていたなるほどね~。お友達もご祝儀に気を使う事もないし、予算的にそうゆうのもいいかもしれない。呼ぶ方も、呼ばれる方もお財布に優しいうちの場合はネットで、一般的な姪に対する叔母夫婦が参列する時のご祝儀を、調べた上で、銀行でピカピカの新札を用意して包みました子供の頃に家で牛や豚、鶏を飼育していた事もあってか、どうもお肉が苦手で次兄の披露宴は京都ホテルで行ったんですが、私がステーキに手を付けず残したので、ホテルの方が「お召し上がりにならないんですか?」と、驚かれたが今思えば、隣席の親族とかに食べて貰えばよかったしかし20歳の頃に、母親と参加した50万円もしたヨーロッパ旅行で、名物料理だという事からスイスのミートフォンデュは、牛肉しか出てこなくって、おなかがすきすぎて仕方なく食べたら意外に旨くて、それから肉は食べれるようになったけど、今でも鶏肉は苦手ださて今回の結婚式場は、老舗の「料亭河文」で名古屋政財界の迎賓館みたいな存在だったようです。 ウィキペディアによれば>清須越えにて移り住み、魚の棚通りに魚屋と>して寛永年間に河内屋文左衛門が創業。 江戸>時代は、尾張徳川家御用達として利用された。>明治時代には、伊藤博文など歴代の総理経験>者も訪れ、博文の書が掛軸として残されている>(中略)2011年にプラン・ドゥ・シー(東京都>千代田区)に経営権を譲渡した。建物の改装を>行い、同年9月30日より再オープンした。2005年に>主屋、表門・塀・脇門、新用亭、渡廊下、用々亭、>厨房が登録有形文化財に登録された。という事で、歴史ある建物と同じ敷地に建てられた近代的な結婚式場の利用となりました料亭河文の伝統を受け継いだ、お出汁の鯛茶漬けは、ここの名物料理だそうだ。あっデザート写真を忘れました今年は名古屋に出かける機会が、毎月のようにあり、この結婚式を始めとして、ここでも紹介した、あれやこれやという感じですがまだ紹介してなかったのが、例のジョイセブンの安く購入していたミッドランドスクエアシネマのチケットを利用しての、娘との映画鑑賞は、それだけの為に名古屋へ出かけましたこれは映画までの時間つぶしで、名古屋駅前をうろついていた時に大名古屋ビルヂングで、お花畑~とはいっても造花でして、冷たい強い風にゆらゆら揺れてました映画の為だけとはいっても、せっかく名古屋まできたのならランチぐらいは楽しみたい。しかもその日は平日なので、お得な「平日ランチ」も食べることが出来るからと、前の日からネットで娘が検索~「名古屋駅前 平日ランチ」で見つかったのは大名古屋ビルヂングのすぐ近くにある「中国料理王宮 OHKYU」で、幾つかある千円程~のメイン料理を選ぶと点心やスープ、お粥、サラダ、デザートなどがブッフェタイプで楽しめるという平日ランチだ杏仁豆腐が好きなので3つも食べてしまった~さてさてお昼も食べたし、腹ごなしでウィンドウショッピングも楽しんだので、そろそろ映画館に行きますか。名古屋駅に着いてすぐに指定席券に交換したので、真ん中あたりでばっちり楽しめたマーベルが大好きな娘が、海外で大ヒットしたという、この映画は家のテレビではなくて映画館のでっかいスクリーンでこそだというので、公開がされると早速、出かけてみたのだ(2月)子供の頃に海のトリトンを見て育ったんで、懐かしくもゴールデンウィークには、アベンジャーズエンドゲームも公開をされるので、5月にはどこかに観に出かけなくっちゃ!!そんな訳でうちのDVDレコーダーはこんなんばっか録画保存されています映画を見ているうちに夕暮れになったので名古屋駅の新幹線口側の地下街にあるお店で好物のとろろ飯を食べて、電車で名古屋に出かける時にはよく利用する瑞浪駅へすると、秀吉様のイラストのある電車がとまっていた。瑞浪ならば中津川までより電車賃もかなり安く済むし、瑞浪止まりの電車もあるので利便性が高いのだ名古屋で紹介をしていなかったと言えば昨年の春に、名古屋市の科学館で開催をしていた「マーベル展」にも、娘と出かけました。その時もジョイセブンのお安いチケットが利用できましたよ入り口には巨大なハルク。息子からレンタルDVDで「ハンコック」を借りてきてと頼まれ間違えて「ハルク」を借りてしまい、思ったのと違う・・・と叱られたのも、つい昨日のようだし。あの当時は、マーベル系ヒーローはかけだしだったそれまでのヒーロー映画と言えば、やっぱバットマンとスーパーマンあたりだったのがアイアンマンはお金持ちとはいえヒゲの中年のおっさんと異色だった。あれからマーベル系のヒーローが続々、増殖中で今年は5作品も公開されるそうでアイアンマン、ハルク、キャプテンアメリカマイティ・ソー、スパイダーマン、アントマンブラックパンサー・・・もう、次から次に出てくるヒーロー軍団。その縦軸にアベンジャーズなんてシリーズもあるしマーベル展では、そんなかっこいいヒーローたちのコミック原画とか、映画の衣装とかいろんなモノがところせましと展示をされており、基本的に撮影禁止だが、SNSなどで拡散もして欲しいので、撮影コーナーも用意されていたこれらはアイアンマンのマークⅠ、マークⅡマークⅢ、マークⅦだそうだ。どんどん進化。それにしてもアベンジャーズエンドゲームの内容が気になる。エンドだなんて・・・米国も日本と同じく4月26日の公開らしい科学館なので、科学的な展示物もいっぱいあり、こちらは写真撮影がOKだったので恐竜なんぞも撮ってみたアンモナイトもついつい撮りたくなる素材です。1個、こうゆうのを家にも欲しいほど、化石とかも好きだ。とお蔵入りだった昨春のマーベル展を紹介が出来た再び今年の3月半ば。今度は舅の弟の娘(旦那の従妹)が名古屋で式をあげるというので、旦那が参列をさせて貰ったのだが、帰りがけに義叔父さんが花嫁さんのブーケをうちの娘に持たせてくれた昔は白砂糖の入ったビニールの大きな魚や赤飯とかだったけど、最近は洋菓子や鰹節調味料やギフトブックなど。姪の事だからとこちらのご祝儀は、舅姑が包んでくれたので助かりましたここからはオマケ。4月7日、息子が出張で出かけていた愛知県岡崎市での休日、花見写真をおくってくれた。楽天ブログのお友達の方も、複数の方が岡崎城の桜の写真を紹介されていたが、私自身は桜の時期には行った事がない写真はスマホで撮ったのをラインで送ってくれたけど、それを自分のスマホにダウンロードが出来るので本当に便利岡崎城について、ウィキペディアによると>岡崎城は、三河国岡崎藩(現・愛知県岡崎市>康生町)にあった日本の城。徳川家康の生地>である。別名、龍城。戦国時代から安土桃山>時代には松平氏の持ち城、江戸時代には岡崎藩の>藩庁であった。>存城当時の東海地方の城では3番目に数えられる>規模であったが、1873年(明治6年)の廃城令に>よって廃城となった。城内の天守以下の建物及び>土地を払い下げ、現在は一切の建物を失い、本丸と>周辺の持仏堂曲輪、隠居曲輪、風呂谷等の曲輪と>石垣、堀などの遺構を残すのみである。>敷地は龍城神社、岡崎公園として整備された。>1959年(昭和34年)3月、天守が復興された「城なのにエアコンの室外機がぁ~笑」と息子。やっぱ、新しい名古屋城はエレベーターは無い方がいいと思うけど(私見ですが)岡崎城は江戸時代に「神君出世の城」とも言われていたそうだ。また城のある岡崎公園は「日本さくら名所100選」に選ばれた桜の名所でもあるそうだそれにしても半端ない寒さだった。4月10日朝起きたら、平成最後のなごり雪。道には雪が積もらなかったから通勤にも支障はなかったが冬ものをしまわなかったのが、功を奏した 平成30年5月 マーベル展(名古屋・科学館) 平成31年1月 姪の結婚式(名古屋・河文) 2月 映画アクアマン(名古屋・駅前) 3月 旦那の従妹の結婚式(名古屋) 4月 岡崎城の桜(息子が岡崎市で) 雪降り(自宅で・10日朝)にほんブログ村
2019年04月11日
コメント(57)
-

金鯱輝く桜花の名古屋城で、信長様とお花見!
令和と新元号が発表された、4月1日ですが赤福の朔日餅目当てで、名古屋へ出かけたついでのお花見ハシゴ。鶴舞公園から山崎川そしてラストにやって来たのが「名古屋城」3年前のお花見は雨だったが今回は絶好の花見日和で、お濠の菜の花も色鮮やかだった。先日も利用したばかりの地下鉄、市役所駅で下車すると、もうそこには名古屋城。満開とまではいかないけど桜の咲き具合もいい感じださて江戸城は別格として、大阪城、熊本城と並び名古屋城が「日本三大名城」と言われており、更に三大天守閣名城(熊本城、姫路城名古屋城)、三大城郭名城(江戸城、大阪城名古屋城)と、正に天下の名城の名古屋城だ慶長17(1612)年に天守が完成後は何度かの震災、大火や明治維新後の廃城も免れた。明治期の推定マグニチュード8の濃尾地震にも耐えながら、第二次世界大戦で昭和20(1945)年5月14日の空襲で大小天守や建物の殆どが焼失してしまった焼失を逃れた建物は、御深井丸戌亥隅櫓、本丸辰巳隅櫓、本丸未申隅櫓、二之丸西鉄門二之門本丸南二之門、旧二之丸東鉄門二之門(現在は本丸東二之門跡に移築)の6棟でいずれも国の重要文化財に指定をされている (昨年7月の撮影)旧二之丸東鉄門二之門は別名を東黒金門といい、もとは二の丸にあったが昭和38年愛知県体育館が建設をされる事になった為解体をされて保管。昭和47年に現在地へ移築されたそうだ二之丸西鉄門二之門は、別名が枡形御門で切妻造り本瓦葺の高麗門の形式のものだ表二之門は門柱、冠木とも鉄板張りで、用材は木割が太く堅固に造られている。この内側には表一之門があったが、空襲で焼失してしまった再建されたものだが、この門はかつて榎多御門と呼ばれる西の丸の門で、明治24(1891)年の濃尾地震で大破した為、江戸城の蓮池御門が移築されたのだが空襲で焼失。天守と共に再建をされた名古屋城の本丸付近が明治期には「離宮」となり準皇居だったので「正門」と名づけられたそうだウィキペディアによると>名古屋城は、織田信長誕生の城とされる今川氏>築城の那古野城の跡周辺に、徳川家康が天下>普請によって築城した。以降は徳川御三家の一つ>でもある。尾張徳川家17代の居城として明治まで>利用された。大阪城、熊本城とともに日本三名城に>数えられ、伊勢音頭は「伊勢は津でもつ、津は>伊勢でもつ、尾張名古屋は城でもつ」と詠っている>大天守は層塔型で5層5階、地下1階、天守台19.5>メートル、建屋36.1メートル、合計55.6メートルで>18階建ての高層建築に相当する。高さは江戸城や徳川>大坂城の天守に及ばないが、江戸城、大阪城天守は>江戸時代前期にいずれも焼失しており、江戸時代>通期で現存した天守で名古屋城天守が最も高かった>延べ床面積は4424.5m2で史上最大の規模である。>体積は姫路城天守の約2.5倍で、柱数・窓数・破風数>最上階規模・総高・防弾壁・防火区画など14項目で>日本一である。>大天守の屋根の上には徳川家の威光を表すものとして>金の板を貼り付けた金鯱が載せられた。>1612年(慶長17年)名古屋城天守が竣工した当時の>金鯱は一対で慶長大判1940枚分、純金にして215.3>キログラムの金が使用されたといわれている。高さは>約2.74メートルあった。しかし、鯱の鱗は藩財政の>悪化により、1730年(享保15年)・1827年(文政>10年)・1846年(弘化3年)の3度にわたって金板の>改鋳を行って金純度を下げ続けた。>そのため、最後には光沢が鈍ってしまい、これを隠す>ため金鯱の周りに金網を張り、カモフラージュした。>徳川の金鯱の中では最も長く現存していたが、1945年>(昭和20年)に名古屋大空襲で焼失した。現在の金鯱は>復元されたもので、(中略)一対に使用された金の重量>は88キログラムである。現在の鯱の大きさは、雄2.62m、>雌2.57m。昨夏の大相撲名古屋場所のついでに、本丸御殿に出かけた時のことはお正月の日記で詳しく紹介をしているので、下記リンクからどうぞ新年を寿ぐ。黄金に輝くピッカピカッの名古屋城本丸御殿さてさて名古屋大空襲から逃れたお宝は他にもあるこの小さな倉庫に、本丸御殿の障壁画などが外されここに保管をされていたので、焼失を逃れたのだ狩野探幽ら狩野派の絵師による旧本丸御殿障壁画331面(附16面)や、旧本丸御殿天井板絵331面(附369面)が難を逃れて、国の重要文化財に指定をされているウィキペディアによると>清須城は長らく尾張の中心であったが、関ヶ原の>戦い以降の政治情勢や、水害に弱い清須の地形の>問題などから、徳川家康は1609年(慶長14年)に>九男義直の尾張藩の居城として、名古屋に城を築く>ことを定めた。1610年(慶長15年)、西国諸大名の>助役による天下普請で築城が開始された>普請奉行は滝川忠征、佐久間政実ら5名、作事奉行に>大久保長安、小堀政一ら9名が任ぜられた。縄張は>普請奉行の一人である牧長勝。石垣は諸大名の分担>によって築かれ、中でも最も高度な技術を要した>天守台石垣は普請助役として加藤清正が築いた。>天守は作事奉行の小堀政一、大工頭は中井正清と伝え>られ、1612年(慶長17年)までに大天守が完成する。>名古屋城築城普請助役としては、加藤清正以外に、>寺沢広高、細川忠興、毛利高政、生駒正俊、黒田長政、>木下延俊、福島正則、池田輝政、鍋島勝茂、毛利秀就、>加藤嘉明、浅野幸長、田中忠政、山内忠義、竹中重利、>稲葉典通、蜂須賀至鎮、金森可重、前田利光の外様大名>が石に刻印を打って石垣工事を負担し、延べ558万人の>工事役夫で4カ月余で石垣を完成した>清須からの移住は、名古屋城下の地割・町割を実施>した1612年(慶長17年)頃から徳川義直が名古屋城に>移った1616年(元和2年)の間に行われたと思われる。>この移住は清須越しと称され、家臣、町人はもとより、>社寺3社110か寺、清須城小天守も移る徹底的なもので>あった。石垣の改修工事が行われおり、石が置かれていたが随分と奥に長細く大きなものを使っているんだなぁウィキペディアによると>現在、名古屋城の全体整備計画があり、整備計画>では史跡としての名古屋城の保存活用と価値を>高めたいとしている>平成30年現在、計画されている整備計画では、本丸>御殿の復元整備、天守閣の木造復元の整備、東北隅櫓の>復元整備、本丸表一之門と本丸東一之門と二之丸門の>復元、馬出の復元、本丸多聞櫓の復元、二之丸庭園の>保存整備と二之丸御殿及び向屋敷の復元整備、大手門>東門と二之丸の櫓の復元整備、展示収蔵施設の整備、>石垣補修などである再び、天下の名城としての往時を取り戻してくれるものだろうか。という訳でさくらまつり絶賛開催中という訳で車いすのお年寄りも、名古屋城のお花見に信長様もにこやかなお顔だ。NHKでやっていたが、物語などで面白おかしく描かれた為今のような信長像が出来上がってしまったが実は、マジメすぎて融通が利かない人だったみたいだ一部の歴女を除いて、多くの老若男女は信長様よりもグルメに夢中。花より団子!さてさて天守は空襲で焼けてしまったがけど、門意外にも焼失を逃れたのが、3棟の「隅櫓」である(残念ながら、東北隅櫓は焼失)隅櫓とは↑、こういったものだそうで本丸の南西隅(未申隅櫓)は、慶長17(1612)年に建てられたもので、外から見ると屋根は二層だが内部は三階の櫓という珍しい形式で、二階西面と南面には敵を攻撃する為の石落しが張り出している (昨年7月の撮影)本丸の東南隅櫓(辰巳隅櫓)は、西南隅櫓と同じ構造で三階東側の屋根の軒には弓なりになった軒唐破風(のきからはふ)という格式の高い装飾が施されているそして西北隅櫓(御深井丸戌亥隅櫓)は、御深井丸の北西隅に位置し、元和5(1619)年に建てられたもので、外観三重、内部も三階の構造。江戸時代から現存する三階櫓の中で、全国で2番目の大きさである江戸時代から「清洲櫓」とも呼ばれ、織田信長の居城だった、清洲城の古材を転用をした可能性があるそうだ↑こんな、感じ普段は、非公開の西北隅櫓だが、名古屋城春まつり(~5月6日)期間中は、内部の特別公開をしていた内部に人が溢れないように、人数制限をしていたので、中もこんな感じでほうほう・・・・なるほどね。この古い木材は↑こうゆうものらしい石落としもあったやっぱお城に使われている木材は、どれもぶっとくて立派なものだなぁ~。などとあっちをきょろきょろ、こっちもきょろきょろ最上階から、外ものぞいてみました。空堀のイメージの名古屋城ですが、反対側には水もはってあります。特に隅櫓も書くこともないので、一般的なお城について紹介したいと思いますかつて日本の城は、2万5000以上もあったそうだが、現在は一般的に見学が出来る城郭は200城ほどで、その中で江戸時代以前からの天守が現存をしているのはわずかに12城のみである。これは江戸幕府が、諸大名に一国に一城しか持たせないようにした為、かなりの城が減ったうえ明治維新で前政権(江戸幕府)の象徴でもあるような諸藩の城を破却させた事、そして戦争や地震、火災などなどといった事情で・・・貴重な現存天守12城のうち、国宝に指定をされているのが、姫路城、松本城、犬山城、彦根城、松江城の五城で、一応は全部出かけている国の重要文化財に指定をされているのは、弘前城丸岡城、備中松山城、丸亀城、松山城、宇和島城高知城で、一つも行ったことはないという有様だ文化財的には、このようなお城が貴重であるけど歴史的だったり、絶景だったりと人気面では色々トリップアドバイザーによる「旅好きが選ぶ!日本の城ランキング(2018)」の1位は3連覇世界遺産の「姫路城」であるが、2位 二条城3位松山城、4位松本城、5位岡城阯、6位中城城跡、7位犬山城、8位備中松山城、9位松江城10位岩村城址って、岩村城址が入ってきてるしまさかの朝ドラ半分、青い効果?昨夜のBS放送「出発!ローカル線聞き込み旅」で再びの「明知鉄道」をしていたけど、前回より今回の方が観光っぽいメジャーな内容で、岩村の町並みやお雛様、かすてら、山岡の寒天、そして終点の明智町は、大河がらみの明智光秀推し最初の東野のお寺は、今は亡き母親の実家のお寺さんですし、「極楽駅なんて何もないのに~」とか、地元民ならではの突っ込みも入れられますそれにしても田舎でした。まっ、山と川しかない岐阜県ですのであしからず脱線しました。いろんなランキングがありますがGPSアプリ「ニッポン城めぐり」の16万人もの利用者データから見た「お城ファンが実際に訪れたお城ランキング」の2018年度の順位の方ではやっぱり姫路城が1位ですが、2位に松山城で3位松本城、4位高知城、5位犬山城、6位松江城7位彦根城などと現存天守が上位陣にずらりと8位会津若松城、9位竹田城、そして10位には名古屋城ランクインですよ。市内の苗木城が24位で、続100名城の中では最上位となりましたよ。岐阜県からは岩村城や苗木城の他に郡上八幡城、美濃金山城も続100名城にも入っていて、城めぐりに力を入れているので明智光秀の来年の大河「麒麟がくる」がらみで歴女や城好きな皆さんを、岐阜県におもてなししようと万端整えているような。大河の主人公明智光秀の他、斎藤道三や、斎藤義龍、濃姫といった父子や、土岐頼芸といった美濃国も前半舞台になるしという割に、2011年4月に光秀に加え細川幽斎忠興、細川ガラシャのゆかりの地として京都府亀岡市や福知山市などの8市町や、兵庫県2市福井県1町で、光秀を主人公にした大河ドラマの誘致推進協議会を設立し、署名活動を行ってきたそうで、岐阜県はゆかりのある岐阜市など8市町でドラマの推進協議会を昨年10月に設立って、遅っ次回からは、先週末に出かけたお花見旅行の日記スタートです。花は咲いていたりまだだったりという感じでしたがお天気に恵まれなによりでした 平成31年4月1日に名古屋で撮影にほんブログ村
2019年04月09日
コメント(51)
-

桜咲く山崎川四季の道で、令和を知るなつぞらな朝
さてさて平成最後の名古屋のお花見。鶴舞から地下鉄で向かったのは、桜通線の瑞穂区役所だちなみに東西に延びる桜通の地下を通っており桜通線だけど、正式名は名古屋市高速度鉄道第6号線だそうだ沿線には桜本町駅や、名古屋市立博物館訪問時によく利用する桜山駅などもあるが、今回は桜山の次にある「瑞穂区役所」駅で下車。お堅い名前の駅だけど、ここの壁画「四季の旅」は近くにある名古屋女子大学から寄贈されたものだとか駅からキャンパスへと向かう道は、汐路桜ロード(桜のトンネル)と呼ばれておりこの時期には、なおさら華やかな雰囲気を携えているとは言っても、春休み中なので女子大生はおらず前を行く女性らは、外国人の観光客のようである何もない魅力のない街と言われていたナゴヤだが最近は、外国人観光客の姿があちこちで見られる栄のオアシスなどは、夜のライトアップがフォトジェニックだと言うので大人気らしい思うに世界遺産の白川郷や熊野古道とか、高山木曽など外国人ウケをする観光地への交通での拠点でもあるのも影響があるのかもしれない今回の名古屋のお花見でも、鶴舞公園以外ではかなりの外国人の方がお花見をされていた日本を代表する桜の花が街や、野に咲く春それを目当てに、来日をされているのかも。日本人でも、桜と紅葉シーズンの京都には激混で近寄れない位だけど、日本全国にはあちこちに桜の名所もあるので、お花見も時期さえ合えば出来るというもの個人で行くならネットなどで花の咲き具合を調べてから現地に行く事も簡単だが、かなり事前の予約が必要なツアーの場合、その年の天候次第で早かったり、遅かったりもあってまさか、冬並みの寒波到来で雪が降るなんて既に咲いている地域では、桜が長く楽しめて良いらしいがまだ桜も咲いてなかったりすると、寒さで開花もどんどん遅れてしまう状況で、明日娘と出かけるお花見旅行も期待が出来ない開花状況を見ては、ため息ばかりでしてそう思うと、赤福の朔日餅目当てで出かけた名古屋のお花見はお天気も良くて、桜の咲き具合もいい感じのお花見日和だ。次にやってきたのは「山崎川四季の道」の桜で、ここもさくら名所100選となっている実はここは初めて来たんですよ。テレビのニュースで山崎川の桜は・・・と知ってはいたんですが、どこにあるのかも知らないままで。何せ忙しい季節だし、飯田とかの桜も見に行きたいしとか言う以前に、肝心の岐阜県でさくら名所100選となっている所もひとつも出かけた事がないし、全国となった場合桜のシーズンに行ったのは14つだけでその多くが東京、奈良、大阪、奈良とか長野くらいなものでだいたい桜の季節が短すぎなのと、年によって花の咲き具合が、前後もするし忙しい時期なのがね・・・。週末のお花見旅行でも100選のうち3つランクインをしているので、ぜめて5分咲き位には山崎川だが、ウィキペディアによると>愛知県名古屋市千種区の平和公園内に>ある猫ヶ洞池などに源を発し、南西方向の>昭和区、瑞穂区、南区へと流れ、港区で>名古屋港へ注ぐ。>約1万年前の縄文時代には現在の瑞穂>陸上競技場付近が河口であったが、海面の>後退や土砂の堆積によって平安時代には>現在の新瑞橋付近が河口になっていたと>推定されている。西暦717年の尾張古図>には、星崎のとなりに山崎の地名があり>川の名の由来にもなったと考えられる。>江戸時代には下流部で新田開発が進んで>次第に流路が延長された。(中略)上流>域では1953年(昭和28年)頃から宅地>開発が進み、道路の冠水や宅地の浸水が>発生。1959年(昭和34年)には伊勢湾>台風によって下流域を中心に破堤が発生した。>1964年(昭和39年)から1974年にかけて>猫ヶ洞池から矢田川への排水設備が整備>されたのに加えて、池の環境保全を目的と>して山崎川への水の流入は1979年(昭和54年)>から2010年(平成22年)2月までは池の>水位を元に制御されており、冬季や夜間には>停止されていた。>2010年2月に山崎川への導水施設の損傷が>発生、施設の修繕・新設を経て2012年(平成>24年)7月以降は通年導水が行われている。>なお、かつては愛知県によって管理されて>いたが、2007年(平成19年)4月に管理>権限が名古屋市に移譲されているさて世間では桜の季節だが、ここ数日の寒波到来でアラレは降るし、みぞれだ雪だと寒い日が続いているが「香炉峰(かうろほう)の雪」というのを覚えておいでだろうか。これは清少納言による「枕草子」にあるもので、雪の降った寒い朝に、中宮定子が「香炉峰の雪いかならむ」とおっしゃったので清少納言が御格子や、御簾を高く上げさせたので、中宮定子が流石だと喜ばれたというものだ。というのも中国旅行の日記で紹介したばかりの白居易(白楽天)が、詠んだ漢詩に「遺愛寺の鐘は枕をそばだてて聴き香炉峰の雪は簾をかかげてこれを看る」とあるからだ 中宮定子は外を見たいと言わずに、白居易の香炉峰の雪で表したというように平安時代の高貴な女性ですら、漢籍に馴染んでいた日本において、シルクロードの終点として栄えた平城京に持ち込まれた海外の文物や、遣唐使が学んできた知識などが最新の流行であった中で平城京の知識人が漢籍を読みこなし、優れた文章を取り入れるというのも、当たり前の事らしいです。中国では梅や桃、牡丹のお花見が昔から盛んで、その席では花見の詩を順番に作るというのが、こっちに伝わっての大宰府で大伴旅人の邸宅での花の宴。だったらなおさらでしょうはい、万葉集からと言われる「令和」ですけども万葉集の注釈から、もとは漢籍を取り入れたものだったようだ。中国の蕭統が編集をした「文選」に載っている張衡(ちょうこう)の「帰田賦」にある「仲春令月、時和気清」からの万葉集の「初春令月、気淑風和」であるらしい昨春の韓国のお花見旅行でも、韓国人ガイドが日本のお花見は桜ですが、こちらでは梅ですと言ってたしなぁ・・・だいたいが太宰府だしね有名な菅原道真といい、都から遠い太宰府って左遷されるイメージもあるし。しかもネットで検索をしたところ ウィキペディアによれば>『歸田賦』は後漢順帝永和三年(紀元138年)に>作られた。張衡は首都洛陽の腐敗した政治から>退き、河北河間の行政官の任を務めた後、138年に>喜んで引退を迎えた。張衡の詩は、彼の儒家教育>よりも道教思想に著しく重きを置きながら、引退>して過ごすことを望んでいた生活を反映しているある意味、大宰府にいた人たちが「歸田賦」を愛読していてもおかしくないような、符号性を感じてもいる。しかも万葉集を編纂をした大伴家持(大伴旅人の子)が左遷された因幡国の庁の新年の宴での「新しき年の始めの初春の今日降る雪のいや重け吉事」が万葉集の最後の歌だしねまっ、この家持のうたは私のお気に入りで年賀状やこのブログでもお正月に何度も使った事もある。上海、蘇州、無錫の旅日記でも書いたように古代中国から様々なことを学び、今の日本が作られてきた事実は変えようもないし、今回の年号だって漢籍からとっていたんだからいいんじゃないかとFUJIは日本一の山だから~(大伴家持と万葉集)だいたい数十年足らずの今の中国の政権とは古代の中国大陸にあった王朝は、関係がないように思えるし。日本のものでと言う心情もわかるけど。他の元号の候補の中には読みが私の甥の名前まであったし、エイコウもなぁそれどころか読めそうにないものもあるし結構、レイワはすっきりしてて読みやすいし家族の名前が1文字あって、本人も喜んでるし年号に限らず良い漢字って限られているのでうちも数人の家族の中で「仁義礼智忠信孝悌」から2人いるし、私の名前も有名な天皇の諱(〇仁の、〇)と同じ漢字を使っているそれもそのはず、八卦見みたいな人に名前を付けて貰ったそうで、もう一つの候補は聖子だとかで、そっちじゃなくて良かった。更に古代史の少女マンガにはまった旦那が、本気で息子の名を不比等(藤原)としたいと言い出し当時はフヒトなんて~と、ごく普通の名前にしかし今となれば、とんでもないキラキラ☆ネームが多いから、逆にかっこ良かったかもこの道を行きかう人が「レイワ」「レイワ」と言ってるのを聞いて、新しい元号を知った。名古屋市瑞穂公園陸上競技場、またの名を「パロマ瑞穂スタジアム」は、Jリーグの名古屋グランパスエイトのホームスタジアム(豊田スタジアムも)。私もここも豊田もどちらも観戦に来た事がある名古屋と言えば、やっぱ・・・・ドラゴンズいえいえ、第91回センバツ高校野球大会でセンバツ史上最多の5度目、30年ぶりでしかも平成最初と、最後に優勝をしたという「東邦高等学校」が話題となって、今も地元のワイドショーに生出演中だ学校法人東邦学園が運営する私立の高校だが東山動物園や高速の名古屋インターのあたりに学校があり、プロ野球選手もたくさん輩出しているけど、天知茂 、奥田瑛二、伊武雅刀などの男優さんも。天知茂の芸名はファンである中日ドラゴンズの天知俊一監督と杉下茂投手が由来だそうですよ~知らなかった最近は山田裕貴で、海賊戦隊ゴーカイジャーでデビューを飾り、今春からの朝ドラ「なつぞら」では、主人公の友達で一緒に上京をするという重要な役どころの小畑雪次郎役で出演の売れっ子イケメン男優さんで、その父親は山田和利といい名古屋市出身で東邦高校から中日ドラゴンズに入団したけどレギュラーに定着できず、広島に交換トレードになり広島で活躍した元プロ野球選手で、引退後は中日や広島のコーチを勤めている方ですって(現広島1軍内野守備走塁コーチ)いやぁ~なんだかすごい。「なつぞら」での草刈正雄。真田丸を彷彿するようなワイルドな爺さんで、ハイジのおんじも思い出すような。今度のは、北海道の酪農農家で育った少女が東京でアニメーターを目指すみたいだ。漫画にラーメンと続いて、アニメとは・・・しかも、朝ドラ100作目の記念作品らしくて歴代のヒロインも登場するそうで、第1作目の「娘と私」のヒロイン、北林早苗の他に小林綾子(おしん)とか、山口智子(純ちゃんの応援歌)松嶋菜々子(ひまわり)、比嘉愛未(どんど晴れ)貫地谷しほり(ちりとてちん)の6人だとか更に、十勝が舞台と言う事で北海道出身者によるTEAMNACSから安田顕、戸次重幸、音尾琢真の3人の出演が決まっており、残りのメンバーである大泉洋や森崎博之の出演の交渉もありうるのかな?今朝の安田顕演じる菓子屋の息子(今は子役)が前述の小畑雪次郎だひよっこの奥茨城の農家の父母が、沢村一樹と木村佳乃というのもどうかと思ったが、今度のなつぞらも十勝の酪農家の養父母が藤木直人と松嶋菜々子で、おんじは草刈正雄とは顔が良すぎるような・・・・いや、そうゆうイケメンに美人の農家さんもいるとは思うけど。まっ、女性のハートを掴む為にはイケメンを揃える必要もあるのだろう山田裕貴君には注目だ。そうそうBS放送ではあの不朽の名作「おしん」の再放送も始まり「なつぞら」と一緒に見始めた戦前と、戦後の時代が違いこそすれ世間の荒波に立ち向かう女の子たちの成長に期待する。街で争奪戦となった号外だが、中日新聞では朝聞におまけとして付いていた 平成31年4月1日に名古屋で撮影にほんブログ村
2019年04月04日
コメント(75)
-

鶴が舞い、桜舞う春の日に。さくら名所百選の鶴舞公園で
昨日は、次の元号が「令和」と決まり列島が沸いたが、私はその報を名古屋で行き交う人たちの会話から知った。と言うのも、楽天ブログをされている方が毎月1日になると伊勢の名物である赤福の「朔日餅」を日記にアップされるので、私も食べたいなぁ~と思ってはいたのだが、ちょうど3月1日に名古屋で用事をがあり、デパ地下に人の行列を発見。これは!?次の月に、赤福の朔日餅を購入する予約が出来るというので、私も並び遂に4月1日に、わざわざ朔日餅を購入をする為に名古屋のデパ地下に行ってきたのだ。4月は桜餅だった伊勢神宮に1日に参拝をする朔日参りにちなんで赤福が、毎月1日に季節に合う違う種類の「朔日餅」を、販売しているのだが、毎月1日になかなか行けないし5月の予約はしなかった。でもお餅だけでは名古屋までの交通費が勿体ない!お餅を買うついでに、今が見頃となった名古屋のお花見の名所にGO!という訳でやってきたのは、構内のタイルでの鶴の壁画も美しい地下鉄「鶴舞駅(つるまいえき)」であるが、実際にはJR東海の中央線の鶴舞駅で下車をした地下鉄鶴舞駅の方は、ここから次の名古屋市内の花見場所に移動をした時に、写真を撮ったものだが、写真の構成上、地下鉄の方の鶴の壁画を紹介をさせて貰った。駅を出ると、駅の目の前にあるのが「鶴舞公園(つるまこうえん)」だお気づきの方いましたか? 駅の方は鶴舞をつるまいと呼ぶが、公園の方はつるま。ちなみに行政区は鶴舞一丁目でつるまいの方だし、鶴舞小学校はつるま二つの読み方が混在をしているウィキペディアによれば>字鶴舞は「ツルマ」とカタカナ表記>だったものが、適当な漢字を宛てた>ものであるという。『名古屋市史』>(1907年)は由来を不明であると>する>また、『金鱗九十九之塵』は、かつて>当地が海辺であり、鶴が多くいたことに>よるという伝承を伝えている。このほか>水流(つる)の間(水がよどむ場所の>意味)が語源とする説もある東京の上野公園での、お花見宴会がテレビニュースで流されるが、ここ名古屋では駅最寄りの「鶴舞公園」がお花見の代表格となっている。無料だし・・・1990年に公益財団法人日本さくらの会の創立25周年記念として、建設省、運輸省環境庁、林野庁、全国知事会、財団法人国際花と緑の博覧会協会の後援によって選定をされた「日本さくら名所100選」に選ばれてもいる各都道府県から最低1か所を選ぶといった9つの選定基準があったそうで、愛知県は4つ。そのうち2つが名古屋市内にあるし今日は、名古屋市内で桜の名所のハシゴだなんだかんだで、この時期に名古屋に出かける事もあるし、この鶴舞公園の桜も初めてでもないが、お天気も良くちょうど満開になった咲き具合かな?寒の戻りで寒い中、午前中からたぶん夕刻からの花見宴会の場所取りの人が暇そうにしていたが、カメラを構えたアマチュアカメラマンの姿もちらほら鶴舞公園であるが、翌年に開催を予定をしていた第10回関西府県連合共進会の主会場に使用する為、明治42(1909)年名古屋最初の公園として開設された共進会の終了後も公園は整備され、動物園(後に東山に移転)、図書館、普選記念壇(普通選挙制度の成立を記念)、名古屋市公会堂などが作られた鶴の噴水~。至る所に鶴のモチーフが明治43年の第10回関西府県連合共進会が鶴舞公園で開かれた際、当地方で活躍をした鈴木禎次の設計で造られた噴水塔は名古屋市の有形文化財に指定されている同じく、鈴木禎次の設計による奏楽堂は1934(昭和9)年の室戸台風で倒壊復旧された二代目の奏楽堂も、老朽化で解体撤去。今のものは平成9(1997)年創設当時の姿に復元されたレプリカである駿河の旧旗本で大蔵官僚の長男である鈴木禎次は帝国大学工科大学で学びフランス留学を経て、名古屋高等工業学校(名古屋工業大学)の教授を退官後に独立彼が設計をした建築物は80棟に及び、その半数が名古屋に集中しており、「名古屋をつくった建築家」とも呼ばれているそうだ半田市の中埜半六邸は、国の重要文化財に岡崎市の岡崎銀行本店や、徳島市にある旧高原商店社屋は、国の登録有形文化財に指定をされているそうだ。松坂屋百貨店はどこの都市のも彼の設計だったようだ昭和天皇の御成婚を記念した事業で、昭和5(1930)年に完成した名古屋市公会堂は第二次世界大戦中は、高射第二師団司令部として、戦後直後はGHQに接収され、連合軍兵士の専用劇場として使用をされていた昭和55(1980)年に市制90周年記念事業として大改修が行われ、 名古屋市都市景観重要建築物に指定され、名古屋市都市景観賞(まちなみ部門)も受賞をしたあちらの近代的なビルは名古屋大学医学部の附属病院で、通称は名大(めいだい)病院。ここの病院のレンガ造りの門と外塀が、国の登録有形文化財にも指定される、戦前のものだとか鶴舞公園は明治38年から始められた精進川(現新堀川)開削工事の土砂で造成をされたもので、それ以前にこの一帯は旧御器所村の水田や大根畑であったそうで、竜ヶ池は元は潅がい用のため池だったものが残されたこんな小さな滝もあったりするその近くにある巨大なソテツ鶴舞公園の奥の方まで、ぐるっと一周するのは初めてで、面白いものも色々あったりもするえ? これは何?と思ったらこうゆう事だったのか・・・・作り直す発想はなかったのかな。お金かかるし第24代内閣総理大臣だった加藤高明は尾張藩の下級藩士の子で、親戚に養子となり、東京大学法学部を首席で卒業して法学士の学位を授与された三菱に入社して頭角を現し、副支配人の地位につき、岩崎弥太郎の長女の春路と結婚。三菱の大番頭とも言われたが政界入りし外相等を歴任。大正13(1924)年明治憲法下における選挙結果で選ばれた唯一の内閣総理大臣となった憲政会総裁となって、第二次護憲運動をおこし、護憲三派(憲政会・革新俱楽部・政友会)内閣の首相となり、日ソ国交回復に努め、治安維持法や普通選挙法を成立させたそうであるこちらは、このような碑でLED照明灯を有する人工芝多目的グラウンド2面、立派なクラブハウスを要する、「テラスポ鶴舞(つるま)」があり、様々なスポーツ活動を中心に交流・憩い・価値創造の場として幅広い活用がされておるこの日も2つのグランドでは、スポーツを楽しむ青少年の姿が・・・・かたや、このような文化的な施設もあった玄関先には陶器の鶴の姿が・・・鶴舞公園を中核に、周囲には様々な施設があるので、いつも沢山の来場者の姿がありそうだ名古屋市の緑化センターは、緑化に関する相談や指導、各種資料の展示、講習会など行っているそうだこちらは名古屋市鶴舞中央図書館で、名古屋市内に21館ある、名古屋市立図書館の中央図書館機能を担っている。大正12(1923)年大正天皇御大典奉祝記念事業として開館した市立名古屋図書館を前身としている一番最後に紹介するのは、こんな感じでして駅前に戻るとジャグリングをやっており沢山の人たちが楽しそうに見物をしていたさっ、地下鉄に乗り次のお花見ポイントへ 平成31年4月1日に名古屋で撮影にほんブログ村
2019年04月02日
コメント(46)
全8件 (8件中 1-8件目)
1
-
-
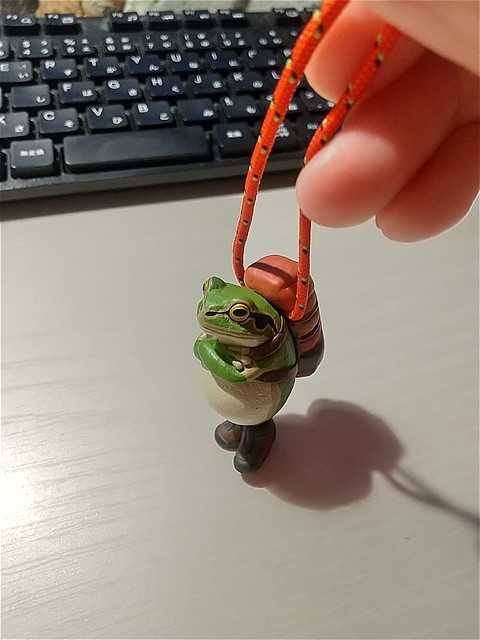
- 山登りは楽しい
- 登山愛好家界隈で静かに話題になって…
- (2025-11-21 22:23:25)
-
-
-

- ★シーバス(スズキ)★
- バチシーズン終了、成績はどうやった…
- (2025-06-11 00:32:53)
-
-
-

- 遊びの基本はアウトドア
- RATEL WORKSのテーブルが優秀すぎた🏕️
- (2025-11-05 23:27:28)
-







