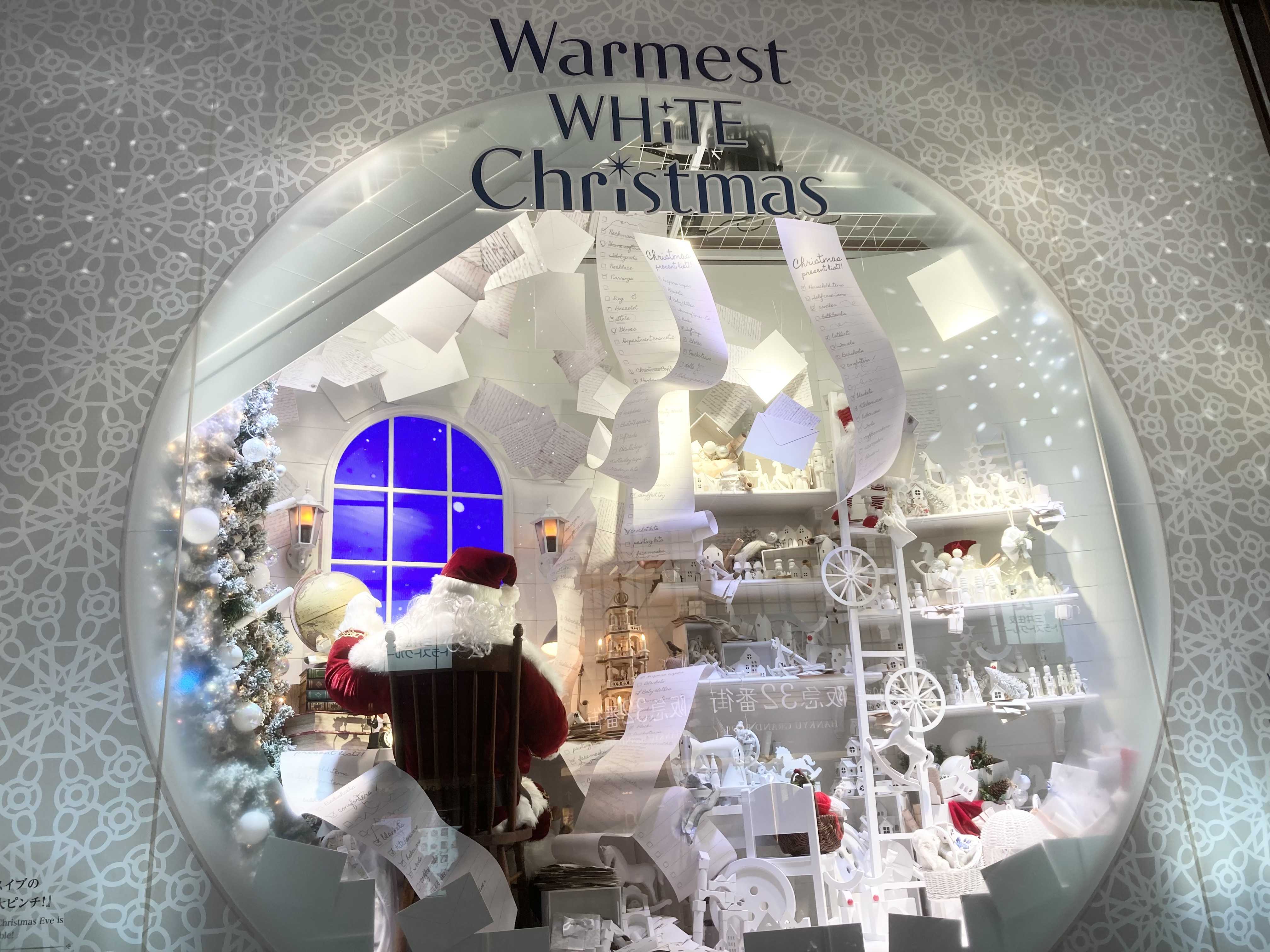2022年10月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
「大人は頭で考え、子どもはからだで考える」
現代人は「考える」というのは「頭で行う活動」だと思い込んでいますが、実際には「からだ」も考えているのです。というか、からだの思考の方が原初的で、根本的なんです。その「からだの思考」の上に「頭の思考」が成り立っているのです。つまり、「頭の思考」は「からだの思考」の一部に過ぎないのです。脳を持っていない粘菌やアメーバなどでも、ちゃんと「生存のための思考」はしているのですから。人間の場合でも、腸は腸だけで思考しているのです。でも現代人はその「からだの思考」を大切にしていません。そして「頭」だけで考え、「頭の思考」で「からだの思考」を無視し、押さえ込んでいます。だからすぐに迷路に入ってしまったり、心やからだを壊してしまったりするのです。環境問題が起きるのもそのためです。「健康にいいから」とやっていることで、逆にからだを壊してしまう人もいっぱいいます。健康にいいはずの食事で、からだを壊す人もいます。健康のためのスポーツでも、やり過ぎると健康を害します。薬なども頭の論理で作られたものですから、短期的には効果があっても、長期的にはからだの調子を崩す原因になりかねません。本来は内部処理で治すべきものを、外部から業者を呼んで治させてばかりいたら、からだが薬に依存するようになってしまい、全体の活動レベルが低下してしまう可能性もあるのです。頭が痛い時には、からだの内部に原因があるのです。頭だけが勝手に痛くなっているわけではないのです。それを無視して、頭痛薬で症状を消してばかりいたら、短期的にはそれで問題は解決しますが、長期的にはからだがドンドンおかしくなっていくのです。薬は症状を消してくれるだけで原因を治してくれるわけではないからです。頭の論理は短期的で直接的な影響しか考慮しません。というか、意識の働きや科学は、短期的で直接的な影響がある範囲でしか、因果関係を確認することが出来ないからです。3.11の事故で放射能が漏れた時にも、国は「ただちには影響はありません」と言いましたが、長期の影響については不明なのに、それは「科学的な検証が不能」と無視するのです。明らかな影響が出ていても、複雑な要因が絡んでいて直接的な因果関係が証明出来なければ無視するのです。ワクチンの後遺症に関しても同じです。そして、大人達もその「頭の論理」で子育てや教育を行っています。「早くから勉強を始めた方がきっと将来も優秀な子に育つに違いない」と、からだを動かしたい盛りの子を椅子に座らせお勉強に追い立てている人もいます。でも、思春期前の子どもたちは「頭の論理」ではなく「からだの論理」で感じ、考え、行動しています。その「からだの論理」は、無数の生き物たちが様々な体験を通して35億年もかけて創り上げ、からだの中に組み込まれてきたものです。幼い子どもの「からだを動かしたい」というのも、その「からだの思考」の結果です。思春期前の子どもたちは、頭も、心も、からだも、からだを動かすことで育つように出来ているので、本能的に子どもはからだを動かそうとするのです。そして、からだを動かしていないと苦しくなるのです。「からだの論理」が、自分の成長にとって必要なことを満たすように子どもの心とからだに働きかけているのです。でも大人は、「なんでジーッとしていられないの!」と、「頭の論理」で、子どもの「からだの論理」を否定します。でも、そのように「からだの論理」が否定され続けていると、子どもの頭と、心と、からだを成長させるために必要な「からだの思考」が止まってしまうのです。すると、依存心が強い状態になります。心もからだも自立できない状態になります。それは、薬ばかり飲んでいると、からだが薬に依存するようになってしまうのと同じです。食事の時に子どもがダラダラ食べるのも。すぐに残すのも。からだの論理がそのように働いているからなんです。「出されたものは制限時間の中でちゃんと全部食べる」というのは、大人が頭の中で創り出した「頭の論理」なんです。そして、子どもが生きている「からだの論理」は世界共通です。世界中、どこに行っても、子どもは同じように感じ、考え、行動しているのです。なぜなら「からだの論理」が共通しているからです。それに対して、「頭の論理」は国や文化や時代が違えば違います。もっといえば、一人一人みんな違います。「頭の論理」に普遍性はないのです。でも大人達はその「普遍性のない論理」で、「普遍的な世界に生きている子どもたち」を管理コントロールしようとしています。
2022.10.31
コメント(0)
-

「子どもを観察してみよう」(子どもは大人が思うほどバカじゃない)
昨日は、筑波山の方まで芋掘りに行くので早起きしなければ行けなかったのに、寝坊してブログをお休みしてしまいましたが、おかげさまで、大豊作でした。20~30kg入れた袋が6袋、計、100kg以上も取れました。その後、笠間の方まで行って陶器を見たり、笠間稲荷に行ったりしました。この芋で焼き芋大会などします。**********************子育てが困難な状態になってしまっている人ほど、子どものことを見ていません。「困ったことをしていないか」などと監視はしているのですが、子どものやることを面白がって観察はしていないのです。そして、多くのお母さんが、子どもが「困ったことをしていないかどうか」、「自分が言った通りに行動しているかどうか」だけを一生懸命に見ています。そして、少しでも「困ったこと」をしていると、それをめざとく見つけ即座に叱ります。その際、子どもがどういう気持ちで、どういう理由でそういうことをしたのかは考えません。というか「事件」が起きるまで何も見ていないのですから、理由が分かるわけがないのです。そして、その行為が子どもにとってどういう意味があろうと、お母さんにとって「やってもらっては困る」と思うことをしていると一方的に叱られます。でも、子どもが、「お母さんが困るようなこと」をしないで、一人で大人しく遊んでいると、お母さんは子どもの側を離れたり、家事やスマホなど自分がやりたいことを始めます。側にいたとしても、心は子どもから離れています。子どもが「困ったこと」をすると、お母さんは子どもの近くに寄ってきて子どもを叱り、子どもが「良い子」にしていると離れて行くのです。そのため、お母さんに側にいて欲しい子は、お母さんの気を引くために色々と困ったことをします。その場合の「困ったこと」は「一人でこそーっとやるようなもの」ではなく、誰かを泣かせたり、ケンカをするような目立った行為です。目立たなければお母さんの気を引けませんからね。兄弟ゲンカもその一つです。全ての兄弟ゲンカがそうであるとは限りませんが、兄弟ゲンカがちょくちょく起きるような場合は、その可能性も考えた方がいいと思います。兄弟ゲンカや困ったことをするとお母さんに叱られはするのですが、それでも子どもは、お母さんに見放されるよりは叱られる方を選ぶのです。とにかく、自分に気持ちを向けてくれるのですから。子どもは「無視される孤独」よりは、「叱られるつながり」の方を選ぶのです。それにいつも叱られている子は叱られ慣れしているので、叱られても悲しくなりません。もちろん反省などしません。それよりも、「お母さんが叱ってくれているうちは大丈夫」という安心感の方を選ぶのです。もちろん、子ども本人はそんなこと意識していませんけどね。そのため、お母さんが自分のことで忙しい時ほど、子どもはお母さんに分かるような形で、お母さんが困るようなことを始めるます。子どもの側にいたとしても、お母さんの心が子どもから離れていると「こっち向いて」と子どもは困ったことを始めます。でも、お母さんが子どもの側にいて、子どもがやっていることを面白がって見ているような時には、子どもはそれほど過激なことはしません。また、ケンカを止めようとすると、子どもはお互いに「僕は悪くないアピール」をし始めます。それは「お母さんの奪い合い」でもあります。そしてそこでまた言い合いが始まります。そんな時は止めるのではなく、ケンカの実況中継なんかやると面白いですよ。○○君が叩きました。△△くんが泣きました。さあ、△△くんはどう反撃するのでしょう。などと実況中継しながらケンカを見ていると、いつもよりも早くケンカは終わると思いますよ。ただし、噛む、ひっかく、もので殴るなどの反則行為をした時には「ブレイク」などといって止めてその点だけを指導して下さい。ケンカ自体を止める必要はありません。反則行為がなければ堂々とケンカしてもOKです。そこまでしなくても、兄弟ゲンカが起きた時に、側に寄ってジーッと観察しているだけで、お母さんが無理に止めようとしなくてもいつもより早くケンカが収まると思いますよ。ただし、ここに書いたようなことは7才前の子どもに関してです。成長と共に、イタズラやケンカの動機も、その仕方も変わってきますから。イジメの場合は見えないように、知られないようにやります。***********************笠間稲荷で「菊祭り」をやっていました。キツネの顔は菊の葉っぱと花で出来ています。
2022.10.30
コメント(0)
-
「今日はお休みします」
今日は筑波山の方で畑をやっている友人の所まで芋掘りに行くの早起きしなければいけなかったのに、寝坊しました。ということで、今日は書いている時間がありません。スミマセン。
2022.10.29
コメント(0)
-
「声なきものの声を聞く」(子どもの心に耳を傾ける)
子どもの不登校、イジメの件数が過去最高になったと今朝見たネットの記事に書いてありました。その背景には、大人達によって「子どもの成長に必要なつながり」が奪われてしまったことがあるとおもいます。教室の子どもたちに「学校、楽しい?」と聞くと、「楽しくない」と答える子が結構います。「楽しい」と答える子もいますが、「どうして?」と聞くと、「友達と会えるから」と答えます。「勉強が楽しいから」と答える子は皆無です。もともと、学校は「学びの場」として存在しているはずなのに、その、本来の目的の部分が完全に失敗してしまっているのです。確かに追い立てれば嫌々でも勉強します。でも、追い立てられて勉強している子は、勉強が嫌いになります。それでは、「成績のための勉強」は出来ても、「自分の成長のための勉強」が出来なくなってしまうのです。学校が「学ぶって楽しい」ということを子どもたちに伝えられていないので、子どもは積極的に勉強しません。また、勉強以外のことで学校にいる時間を楽しもうとします。友達と遊ぶのもその一つですが、中には先生達を困らせるようなことをして楽しもうとする子も多くいます。特に、友達と助け合って遊ぶ能力が育っていない子ほど、授業中でも自分勝手なことを始めます。そのように「楽しい事」を求めるのは子どもたちの本能なので、いくら先生が叱っても子どもは先生の言う通りには行動しません。まだ自我の働きが弱い状態の子どもたちは、本能の働きから生まれてくる衝動を自分の力では抑えることが出来ないからです。先生達はそれを子どものせいにしますが、これは子どものせいではなく、子どもの成長本能を無視したやり方を続けている学校や、先生や、大人の責任なんです。でも、大人達は自分たちの責任を認めずに、罪を子どもたちになすりつけて、さらに厳しく指導しようとします。記事のようにコロナのせいにしようとする人もいます。確かにコロナはその状態を加速させましたが、それは大人達がコロナのことばかり考えて子どもたちのことを考えなかったことの表れでもあります。そういう状態の学校が楽しいわけありません。ストレスも溜まります。心や体に不調が出る子もいます。で、学校に行けなくなる子が増えます。行かないのではなく行けなくなるのです。子どもには「自分の成長に害のあるような場」を避けようとする本能もあるからです。当然、イジメも増えます。心とからだに余裕が無くなった子どもたちは、自分の心とからだを守ることだけを考えて行動するようになるからです。(こういうことは大人でも同じですけどね。)でも、大人の都合と、価値観と、欲求だけで作られた現代社会の中には、学校の外にも、学校の外にも、「子どもが子どもらしく感じ、考え、行動することを許してくれる場」がありません。最近は、コロナのこともあって、子どもたちが公園で群れて遊んでいるだけで文句を言ってくる人もいると聞きます。そんな時は、家庭が「子どもを守る最後の砦」にならなければならないはずなのですが、多くの家庭が、学校や社会の手先機関のようになってしまっています。また学校も、そのような役割を家庭に求めています。そして多くの親たちが、その学校の要求に積極的に協力して、子どもを追い詰めています。本来、「学校の役割」と「家庭の役割」は全く別のものののはずなのに、家庭が自分の役割を放棄して学校に従ってしまっているのです。その結果、子どもたちが「自分らしくいることが出来る場」はゲームの中だけになりました。だから、ゲームは子どもの育ちに悪い影響があるからといって、子どもたちからゲームを奪ってはいけないのです。子どもに「ゲームがなくても自分らしくいることが出来る場」をいっぱい与えてあげれば、子どもは自分の意思でゲームから離れることが出来るようになるのです。不登校やイジメの増加はそんな子どもたちの「心とからだからの叫び」なんです。(ゲーム中毒も・・・)言葉で自分の苦しみを表現出来ない子どもたちは、心とからだの状態や、様々な問題行動を通して、自分の苦しみを表現しようとしているのです。それは「声なき叫び」です。でも、「声なき叫び」は耳を傾け、聞こうとする人にしか聞こえません。子どもたちは不登校やイジメという形で叫び声を上げているのです。どうかその「耳では聞こえない声」に耳を傾けてあげて下さい。
2022.10.28
コメント(0)
-
「つながれない子どもたち」(つながりを支えるものを育てる)
一般的に、物と物をつなげる時には接着剤を使います。接着剤を使わない時には、組み合わせたり、縛ったりして構造的につなげます。いずれにしても、何かと何かを持ってきて、そのままの状態でくっつけようとしてもくっつきません。くっつけるためには「くっつきを支えるための何か」が必要になるからです。それでも、材質的に異なるものはそんな簡単にくっついたりはしません。「固いもの」と「柔らかいもの」を接着剤でくっつけたら、簡単に「柔らかいもの」が壊れてしまいます。また、最初から「くっつくこと」を拒否しているような形状や材質のものもくっつきません。最近は表面に特殊な加工をしてテープや汚れなどがくっつかないような素材のものも多く出回っていますが、そういうものは接着剤を使ってもくっつけることが出来ません。接着剤のような「くっつけるもの」があっても、似たような固さや特性を持ち、かつ、「くっつくことを受け入れるようなもの」同士でないとくっつけることは出来ないのです。そして実は、これは子どもと子ども、人と人がつながる場合も同じなんです。ただ子どもたちを大勢集めただけでは、子どもたちの間につながりは生まれないのです。一緒に遊んだりもしません。子どもと子どもをつなげようとするのなら、まず、接着剤のような「つなげるもの」が必要になります。それは、言葉や、遊びや、それまでの生活体験であったりします。共通の言葉、共通の遊び、共通の生活体験を持っている子同士なら、大人が何かしなくても、簡単につながり、勝手に遊び始めます。自然の中で遊ぶことが好きな子を自然の中で出会わせれば、大人が何もしなくても自然につながり、勝手に遊び始めます。でも、「自然の中で遊ぶのが好きな子」と「部屋の中でゲームで遊ぶのが好きな子」を出会わせてもつながれません。「つながりを支えるもの」を共有していないからです。これはゲームが好きな子同士でも同じです。好きなゲームが異なっていたら、一緒には遊べないのです。でも、みんなで一緒に遊ぶのが好きな子同士なら、一緒に遊び始めます。その際、どのように遊ぶのかは話し合って決めることが出来ます。そのような子は、家族と遊ぶのも好きです。お母さんや、お父さんや、兄弟と遊ぶのも好きです。というか、そういう環境で育ったから友達とも遊ぼうとするのです。子どもと子どもがつながり合うためには、子ども自身がつながりを求めている必要があるのです。「一人で遊んでいる方が好き」という子を何人も集めても、つながりは生まれないし、一緒に遊び始めることもないのです。ただそういう子は、自分のテリトリーや権利だけは守ろうとするので、テリトリーが重なってしまっている場合には争いが起きます。他の子に自分の権利が阻害された場合も争いが起きます。ゲーム好きな子が何人かいるのに、ゲーム機が一つしかなければ必然的にケンカが起きます。「縄跳び」にこだわる子と「鬼ごっこ」にこだわる子も一緒に遊べません。そのような子は自分の欲求を通すことばかりを考え、「一緒に遊ぶ楽しさ」を求めていないからです。そして今、そういう状態の子が多いのです。そのため、ちょっとしたことで簡単にトラブルになってしまいます。でも、話し合う能力も育っていないので、自分たちでは解決することが出来ません。また、「一緒に遊びたい」という目的も共有していないので仲直りも出来ません。子どもたちから、共につながり合うために必要な言葉や、体験や、生活や、環境を取り上げたのは大人達です。家族や兄弟の間で「一緒に遊ぶ楽しさ」を伝えていないのも大人達です。子どもを家の中に閉じ込め、ゲームやスマホを与え、みんなで遊ぶ楽しさを伝えていないのも大人達です。それでも、子どもたちはつながりを求めて他の子と関わろうとします。それが成長本能でもあるからです。でも、関わり方が分かりません。つながり方も分かりません。それがケンカやイジメという形で現れていることも多いです。でも、仲直りの仕方も知らないし、一緒に遊びたくもない子と仲間直りしたいとも思いません。子どもたちがつながり合うためには「一緒に遊べる遊び」や、「共通の体験」や、「喜びの共有」が必要なんです。そういうものを与えることなく、「なんで仲良く遊べないの」などと子どもを叱るのは筋違いなんです。
2022.10.27
コメント(0)
-
「子どものケンカ」(子どもの言葉に耳を傾けて下さい)
昨日は、大事なことは双方の「言いたいこと」を吐き出させてあげることなんです。「言いたいこと」を吐き出せば、それだけで子どもはまた遊び出すのです。またそれが、子どもが自分の感情に気付き、感情表現の方法を学ぶ手助けにもなるのです。というところで終わりましたが、大人がそのような関わり方を大切にしていると、子どもはケンカからも多くを学び成長する事が出来ます。「ケンカしなくても良い方法」に気付くかも知れません。人は他の誰かに真剣に話を聞いてもらうだけで、自分の心の中が整理され、自分が見えてきて、何をしたらいいのかが分かるようになるのです。でも、大人が子どもの言葉に耳を傾けずに、大人の価値観だけでジャッジしたり、問答無用でケンカを止めてしまうと、子どもの心の中に恨みが残ります。すると、子どもの意識や感覚がその恨みに囚われ不自由になります。ちなみに、支配者が誰かを洗脳、支配しようとする場合は、自由な言葉を封じます。自由な会話や自由な発言を禁止します。相手が何を言ってきても耳を傾けません。そのようにして、言葉を不自由にしてしまうと心も不自由になり、自由に考えたり、自由に活動できなくなってしまうのです。もうすでに心が不自由になってしまっている人の話を聞いていると、同じ所をグルグルと回っているだけで一向に新しい展開がありません。こちらが何を言っても受け入れません。当然、成長もありません。何らかの宗教や思想に洗脳されている人と話をしているとこんな感じです。都合が悪くなると「すみません。まだ勉強が足らないので・・・」と逃げようとします。だからいくら説得しても無理なんです。そんな場合は、逆にいっぱい話をさせるといいです。自由に色々な表現活動をさせるのもいいと思います。自由を与えられることで自分の中の不自由に気付くからです。今、日本中の学校で「コロナ対応」ということで、子どもたちの自由な会話や発言や活動を封じています。でもそれは、子どもの成長にとっては非常に危険なことなんですが、でも、大人達はそのことに気付いていません。まあ最も、それ以前から日本の学校では子どもたちに自由に発言させたり行動させたりはしませんけどね。心の自由を失ってしまっている大人には、子どもたちの自由な発言や行動に対応出来ないからなのでしょう。それで、子どもの自由な言葉や活動を封じようとするのではないかと思います。これは、学校の中だけでなく家庭の中でも同じです。「屁理屈を言うんじゃありません」「ワガママを言うんじゃありません」「訳の分かんないことを言うんじゃありません」などと、子どもの言葉を否定することが多い人は、もしかしたら心の自由を失ってしまっているのかも知れません。そのような状態の人が一番恐れるのが「自由」です。「他者から束縛されない自由」ではなく、「表現の自由」です。「自分の言葉で語って下さい」と言っても、誰かの言葉を借りる形でしか話すことが出来ません。あと、子ども同士のケンカは基本的に見守っているだけでいいのですが、でも、止めた方がいい場合もあります。それは、戦う意思がない相手を一方的に攻撃し続けているような場合です。これはケンカではなくイジメです。でも、からだが小さくても、腕力が弱くても、一方的に負けていても、本人が戦う意思を見せているのなら黙って見守っていてあげて下さい。ただし、決着が見えた時点でドクターストップは入れる必要はあります。負ければ悔しいでしょう。泣くでしょう。でも、その「悔しさ」は子どものエネルギーになります。もっと、努力をするようになるかも知れません。でも、本人が戦う意思を見せているのに大人が一方的に止めてしまうと、相手と、止めた大人に対する恨みが残ります。「悔しさ」は成長へのエネルギーになりますが、「恨み」は成長へのブレーキになります。
2022.10.26
コメント(0)
-
「子どものケンカ」(ジャッジしないで下さい)
最近、いくつかの場所で「子どものケンカをどうしたらいいのでしょうか?」と聞かれることが続いたので、今日は「子どものケンカ」について書かせて頂きます。子どものケンカには、多くのお母さんが手を焼いています。放っておいてもそんなに大事にはならないことは分かっているのですが、とにかくうるさいです。ケンカの声を聞いてたり、ケンカをしている所を見ているとイライラしてきます。見えない所で勝手にケンカしていてくれるのなら、そんなに気にもならないのですが、子どもはお母さんが側にいると、お母さんにジャッジを求めてきます。また、わざわざお母さんに見える所でケンカを始めることも多くあります。(お母さんの奪い合いがその背景にあります。)そして、お母さんがジャッジをすると、悪者にされた方が泣き、怒ります。時に、「正しいとされた子」が「悪いとされた子」をバカにします。でも、お母さんの目には明らかに「○○君」の方が悪くても、「あんたの方が悪い」と言われた「○○君」は絶対に納得しません。先日も書いた通り、子どもはやられたことは覚えていても、やったことは覚えていないからです。そして、一緒に遊ぶことを止めてしまいます。お母さんに対する信頼も揺らぐでしょう。また、「お兄ちゃんなんだから」「お姉ちゃんなんだから」などという「本人にはどうしようも出来ない理由」で悪者にされてしまうこともあります。でも、これを繰り返していると兄弟の仲が悪くなります。「ケンカ両成敗」などと、本人達の理解を超えた判断を押しつけることもあります。でも、これをすると双方ともに不満が残ります。「ケンカ両成敗」は「早くケンカを収めたい大人の都合」の押しつけに過ぎないからです。ここで大切なことは「子どもはなぜケンカするのか」と言うことです。まず、子ども同士の距離が近くなければケンカは起きません。子ども達全員にゲーム機を与えておのおの一人で遊ばせれば、当然ケンカは起きません。実際、こういうことをやっている人もいるでしょう。でも、いつも一人だけで遊んでいる子は「人との関わり方」を学べなくなくなります。「コミュニケーション能力」も「自己表現能力」も育ちません。また、自分の感情の抑制の仕方も分からないままになります。そして、このことは子どもが思春期を迎える頃になって問題になります。また子どもには、「見たい」、「やりたい」、「言いたい」欲求があります。これは子どもの成長本能の表れです。子どもが自分の能力を高めるためには、自分が生まれてきた世界と能動的に関わる必要があるからです。だから積極的に色々なものと関わろうとするのです。でも、その成長本能は「自分の成長欲求」だけを満たそうとします。他の子の成長のことなんか考えません。子どもは元々利己的な生き物なんです。だから簡単にぶつかり合うのです。でも、子どもがケンカするのは子どもにとっては自然な状態なんです。それもまた、子どもが人間らしさを身につけるためには必要な成長の一過程だからです。ただ、そのまま大人になってもらっては困ります。(最近は、その利己的な状態のまま大人になってしまう人も増えて来ましたが・・・)あと、「お母さんの奪い合い」や「オモチャの奪い合い」でケンカが起きることも多いです。お母さんが、普段から兄弟同士をつなぐような関わり合いをしていないと、子どもはお母さんを巡ってケンカするようになります。オモチャの奪い合いによるケンカはある程度は諦めるしかないです。上の子が遊んでいると、下の子が興味を持って上の子の遊びに介入して、遊びを台無しにしてしまうこともあります。すると、上の子は怒って、下の子をぶったりします。こんな時、お母さんは「お兄ちゃんなんだから」などと上の子を責めます。でも、それをしていると、上の子は下の子を恨むようになります。かといって、下の子を叱ってもなぜ叱られているのかが分かりません。子どもたちはよくケンカをします。でも、ケンカがしたいわけではないのです。ただ、一緒に遊びたいだけなんです。イジメも同じです。他の子をいじめている子もイジメをしたいわけではないのです。ただ、「みんなと一緒に仲良く遊ぶ遊び」を知らないから「イジメという遊び」を始めるのです。その「遊びたい」というのは子どもの本能です。なぜなら「遊び」に伴う様々な活動には子どもの成長を支える働きがあるからです。でも、ケンカそのもの、イジメそのものには子どもの成長を支える働きはありません。むしろ阻害してしまいます。ケンカやイジメは子どもの成長本能に反する行為なんです。だから、ケンカしてもただ悲しくなるだけで、楽しくならないのです。子ども同士のケンカは、勝っても負けても悲しくなるだけなんです。そもそも、子どもたちが最初から一緒に遊びたくないのならケンカは起きないのです。まただから、大人が大人の力でケンカを収めても、子どもは納得できません。子どもが求めているのは「遊びの再開」であって、善悪のジャッジではないからです。また、大人によって善悪をジャッジされることで、子ども同士の対等な関係が崩れます。ただし、「一人でばかり遊んで育った子」同士のケンカや、「一人でしか遊べないオモチャ」を巡ってケンカをしている時には、子どもが大人に善悪のジャッジを求めることがあります。そのような場合、「一緒に仲良く遊ぶ」という選択肢がないからです。でも、自然の中でみんなと一緒に遊んでいる時に起きるようなケンカの場合は、ただ双方の話をちゃんと聞いてあげるだけでいいのです。それだけで子どもの気持ちは収まるからです。そして、気持ちが収まればまた一緒に遊び出すのです。ついさっきまで、大声で怒鳴りあい、殴り合い、「もう○○君とは遊ばない」と叫んでいた子が、数分後にはまた仲良く遊び出すのです。大人にはこういうことは出来ませんよね。でも、子どもにはこれができるのです。でも、大人がジャッジしてしまうことで、心の中にわだかまりが残り、遊びが再開できなくなってしまうことがあるのです。大事なことは双方の「言いたいこと」を吐き出させてあげることなんです。「言いたいこと」を吐き出せば、それだけで子どもはまた遊び出すのです。またそれが、子どもが自分の感情に気付き、感情表現の方法を学ぶ手助けにもなるのです。
2022.10.25
コメント(0)
-
「子どもは子どもの時だけ天才」
「子どもは天才だ」とはよく聞く言葉ですが、その天才のまま大人になった子は滅多にいません。この「子どもは天才だ」という言葉は、「子どもは大人が思い付かないような発想をする」ということなんでしょう。でも、本当の天才はそれを具体的な形に出来ますが、子どもたちは発想するだけで具体的な形まで創り上げることが出来ません。そのための知識と技術が伴っていないからです。大人はものを感じる時も、考える時も、行動する時も「常識」に縛られています。その「常識」は子どもの頃から繰り返し刷り込まれてきたものです。でも、幼い子どもたちはまだその常識を知りません。だから、自由に感じ、自由に考え、自由に行動します。そして大人たちはその自由な発想や、感性や、行動に驚き「子どもは天才だ」などと驚くのでしょう。でも、その自由な発想や、感性や、行動は芸術的な行為や、創造的な活動の場では長所に働くのですが、常識を求められるような場では否定されてしまうのです。日常生活でも、学校生活でも、公共の場でも否定されます。なぜなら、子どもが常識にとらわれずに行動したら、大人が常識によって創り上げた世界の秩序が崩壊してしまうからです。そのため、大人たちは自分達が創り上げた世界を守るために、子どもの自由な発想や、感性や、行動を否定します。また、自由な発想が長所として働くような芸術的な活動や、創造的な場を日常的に与えられている子は滅多にいません。それに、大人が否定しなければ子どもは大人になっても天才のままなのかというとそれもまた違います。常識にとらわれない自由な発想を具体的な形にまで仕上げるためには常識が必要だからです。非常識なままでは発想を具体的な形にまで作り上げる事が出来ないのです。ここで必要になるのは常識を知っていながら、常識に捉われない自由な心なんです。「非常識」と「常識に捉われない心」は一見似ていますが、本質的には全く別のものです。「かたなし」と「型破り」の違いと同じです。これは踊りでも、武道でも、仕事でも同じです。この場合、「常識」とは基礎のことです。基礎がないまま自由にやってもいいのですが、基礎がなければ自己満足の世界に囚われます。子どもが自由に生きることが出来るようになる為にも、「常識を学ぶこと」と「常識に捉われない自由な心を育てること」の両方が求められるのです。でも、ほとんどの子どもたちは「常識」だけを学ばされ、「常識に捉われない自由な心」を育てる場を与えてもらっていません。その結果、天才のように見えた子どもたちはみんな、成長と共に平々凡々とした普通の大人に育って行きます。大人の皆さん。常識はもういっぱい身に着けているでしょうから、今度は、その常識に囚われない生き方を試してみませんか。きっと新しい世界がひらけますよ。子どもだけでなく大人も天才になれますよ。
2022.10.24
コメント(0)
-
「9才頃に社会というものが理解出来るようになってくるのです」
あと、9才前の子どもは自分中心に世界が回っているので、自分が単なる「一員」になってしまう「社会」というものが理解出来ません。この「自分中心に世界が回っている」ということは、単に「自分勝手だ」という意味ではなく、自分の感覚や、思考や、価値観だけを基準にして自分の周囲の世界を見て、その是非を判断していると言うことです。それは、「他の人の感覚や考え方も考慮して物事を考える」ということが出来ないと言うことでもあります。他の人に気を使うことは出来ても、あくまでも、判断基準は「自分」だということです。それは、ピーマンが好きな人が、「ピーマンは美味しいんだから食べなさい」とピーマンが嫌いな人に押しつけるような状態です。ちなみに大人になってもそのような状態のままの人もいます。そのような人は自分の趣味や興味や価値観を平気で人に押しつけてきます。このような時、「食べなさい」ではなく、「食べてみない」という言葉かけが出来る人は自分中心の世界から抜け出せている人です。それは、最終判断は相手に任せることが出来る状態ということです。大人になってもそういうことが出来ない人もいっぱいいますが、そういう状態から抜け出せるようになるのが9才頃からだということです。本来、「社会」と呼ばれるものは、自分とは異なった考え方や、価値観や、生き方も大切にされることで成り立っています。だからみんなが幸せに生きるためには「みんなが守るべきルール」が必要になるのです。みんなが、自分の好き嫌いだけで生きていたら社会は崩壊してしまうからです。でも、子どもたちは基本的に自分の好き嫌いだけで生きています。気が合う仲間だけでグループを作ったり、遊んだりします。気が合う仲間だけで出来たグループにはルールは必要ありません。「みんなで決めた約束」は守りますが、誰が決めたか分からない規則は無視します。(叱られれば守りますが、自分自身の判断としては守らないと言うことです。)でも大人になると、「誰が決めたか分からない規則」であっても、その大切さが理解出来るようになるし、また自分の意思で守ることも出来るようになります。その境目が9才、10才頃だと言うことです。「社会」には色々な価値観、色々な考え方、色々な感覚の人がいます。ですからそういう人達が一緒に生活し、活動し、仕事をするためにはルールが必要になります。「お金」もそのルールの一つです。ですから「社会」というものがちゃんと理解出来ない状態の子には「お金」というものの意味も価値もよく分かりません。そのため、自由になるお金があればばんばん使ってしまいます。ゲームに課金もしてしまいます。また、「時間」も社会が決めたルールの一つです。ですから「社会」というものがちゃんと理解出来ない状態の子には時間の意味も価値も理解出来ません。そのため、「時間を大切にする」ということが理解出来ません。お母さん達はよく、「早くしなさい」、「ちゃんとしなさい」などと言いますが、これも社会的な価値観や活動とつながっている言葉なので、「社会」というものが理解出来ない状態の子にはお母さんが自分に何を求めているのがよく分かりません。お母さんは子どもに簡単に約束をさせますが、この「約束」の意味も分かりません。「約束よ、分かった?」と言えば、子どもは「分かった」と言います。でも、「分かった」と言ったからといって、分かったわけではありません。「分かる」という言葉の意味自体が分かっていないからです。皆さんは、「分かるってどういうこと?」と聞かれたら答えられますか。こういう諸々のことが分かるようになるのが「9才頃」だということです。9才頃になると部分と全体、自分と社会を分けて考えることが出来るようになるのです。
2022.10.23
コメント(0)
-
「心の成長プロセス」(幼い子どもは写生が出来ません)
幼い子どもは、景色や物を見て絵を描く、いわゆる「写生」ということが出来ません。大人だって写生は難しいです。大人だって、ある程度ちゃんとした写生が出来るようになるためにはある程度の訓練が必要になります。なぜなら、写生が出来るようになるためには、客観的に対象を見る能力と、二次元の世界と三次元の世界の違いを理解し、目で見た三次元の世界を紙の上の二次元の世界に変換する能力が必要になるからです。そして幼い子どもにはその両方の能力がありません。立体的な実物の世界が平面的な紙の上に描けるということ自体が分からないのです。大人はそこで「輪郭線」という現実の世界には存在していないものを使います。立体物のシルエットを輪郭線で描いてから、その中を塗るという方法を取るのです。これは映像をプロジェクターで投影して、映った映像の輪郭線をなぞって描いたり、片目で透明な板を通して物を見て、その輪郭線をなぞるというような方法で簡単に出来ます。立体を平面に投影して、その平面を写すのです。ちなみに素人は輪郭線を使わないと描けませんが、プロは輪郭線を使わなくても絵を描くことが出来ます。なぜなら素人は「物の形」を描こうとするのに対して、プロは「空間」を描くことが出来るからです。だから素人の絵は「平面的」で「存在感」がないのです。(ただし、プロでも表現方法としてあえて輪郭線を使う人はいます。)でも、その「輪郭線」は三次元的な存在を二次元的な世界に変換するための便宜的な道具であり、大人の頭の中にしか存在していない概念的な存在なので、子どもには見えないし、理解をすることも出来ません。立体物から輪郭線を抽出することも出来ません。見えている様々な形の関係性も分かりません。「空間」も見えません。だから写生が出来ないのです。そんな子どもたちでも、5,6才頃になると輪郭線が現れ始めます。それは、「お花はこういう形だ」「チョウチョはこういう形だ」という概念が目覚め始めるからです。そして、その概念をなぞるようにして絵を描くのです。ですから、いつも同じ形の絵になります。実際のお花は一つ一つ形が違うのですが、「概念としてのお花の形」を描くだけなので、実際のお花の形とは無関係にいつも同じ形になるのです。その結果、絵がパターン化してイラスト的になります。女の子はそのパターン化した絵を真似し合ってお絵描き遊びをしたりもします。お母さんは「もっと自分らしい絵を描けばいいのに」と思いますが、そんなこと言っているお母さんだって「自分らしい絵」など描けません。それにそれは意識の成長に伴って自然に現れる現象なので、肯定的に受け入れてあげる必要があるのです。確かに輪郭線が現れるまでの子ども絵は「自分らしい」ものです。なぜなら、輪郭線が生まれる前の子どもは「物の形」ではなく「自分の心の中のイメージ」を描こうとしているだけですから。幼い子どもには「物を見て描く」という行為は出来ませんが、「自分の心の中のイメージを描く」ということは出来るのです。「心の中のイメージ」はスクリーンに映った映像のようなものだからなのでしょう。そんな子どもたちでも、5,6才頃になって形の認識が出来るようになってくると、絵に輪郭線が現れ始めます。その頃になると、先生がお手本を見せてくれれば、そのお手本を写すことも出来るようになります。それに、そのお手本にはもう輪郭線が描かれています。近所の幼稚園の入口に貼ってある「何が描いてあるかちゃんと分かる上手な絵」は多分お手本を見て描いたものだろうと思います。でもそれは単なる「身体的な作業」であって「心の表現として絵を描く」という行為ではありません。また、それをやらせ過ぎると、絵を描くときに「自分の心との対話」が出来なくなります。7才を過ぎる頃から、子どもは「客観的に物事を見る能力」が少しずつ目覚め始めます。すると、「目の前に存在しているものの形や関係性を理解する」ということも理解出来るようになります。そして、その「理解した形」を輪郭線を使って描くことも出来るようになります。その結果、少しずつ写実的な絵も描けるようになります。
2022.10.22
コメント(0)
-
「心の成長プロセス」(やられたことは覚えているがやったことは覚えていない)
大人と子どもとでは記憶の仕方も違います。大人は自分の記憶を、時間列、空間位置に従って整理することが出来ます。記憶に「時間」と「空間」のタグが付いているからです。大人でもそういうことが苦手な人はいっぱいいますが、そういう人でも子どもの時よりは出来るようになっているはずです。性別や気質も関係しています。ですから大人の場合は、ある記憶に対して、「これはいつ、どこで体験したことだ」ということを想い出すことが出来ます。「昨日の夕食はどこで何を食べましたか?」と聞かれた場合でも、自分の記憶を検索して答えることが出来ます。まただから、何かに失敗した時もその原因を探ることも、記憶を論理的につなげ、論理的に考えることも出来るのです。でも、思春期前の子どもたちはそれが苦手なんです。頭の中に記憶自体はあるのですが、それに「時間」と「空間」のタグが付いていないからです。「時間」と「空間」のタグが付いていないので、時間順、空間別に記憶を並び替えることが出来ないのです。そのため、子どもの話に対して「それはいつ、どこで起きたこと?」と聞いてもラチがあきません。旅行で遠くに行った時でも、自分の家の近くと似た風景を見ると「ぼく、ここ知っている」などと言ったりもします。何時間も車で移動したのでそんなことある訳ないのですが、子どもの記憶には「空間タグ」が付いていないので、簡単に「場所の違い」が無視されてしまうのです。ただし、大人でもそういう事は起きます。いわゆるフラッシュバックというものも同じです。私は毎年、夏が終わり空気が乾燥してくるとスペインにいた時のことを想い出してしまいます。道を歩いていてジャスミンの香りがして来たり、クラクション騒がしい音を聞くと、突然インドにいた頃のことを想い出してしまいます。記憶には時間と空間のタグの他に、感覚記憶と感情記憶のタグが付いているので、ある出来事に対して特別な感覚や感情を感じた時に、似たような感覚や感情タグが付いた記憶も同時に引き出されてしまうのです。そして、思春期前の子どもたちの記憶は、時間、空間タグではなく、感覚、感情タグで管理、整理されているのです。記憶自体は残っているのですが、その整理の仕方が大人とは違っているので、大人が「それはいつのこと?」「どこのこと?」と聞いても答えることが出来ないのです。また、子どもがケンカしている時に双方の言い分を聞いていても、子どもは「起きたこと」を時間軸に従って話すことが出来ないので、いくら話を聞いても実際に何が起きたのかを正確に知ることは困難です。実は、子どもは「自分が話したいこと」からしか話せないのです。記憶がそういう順序で整理されてしまっているからです。で、ケンカしている子の話を聞いても、双方とも「やられたこと」ばかりを言い立てます。それが一番言いたいことだからです。でも、「やったこと」は言いたいことではないので、記憶の後方に追いやられています。やったことの記憶がないわけでないのですが、なかなか想い出せないのです。「ばか」と言われた事はすぐ想い出せるのですが、その前に自分が「ばか」と言ったことはなかなか想い出せないのです。これは子どもが嘘を言っているわけではなく、これが子どもの記憶の特性なんです。だからこそ、子どもの頃には「気持ちがいい」、「嬉しい」、「楽しい」、「きれい」、「楽しい」などの肯定的な感覚や感情とつながった体験をいっぱいさせてあげる必要があるのです。子どもの頃のことを想い出した時に、「気持ちがいい」、「嬉しい」、「楽しい」、「きれい」、「楽しい」という肯定的な感覚や感情とつながった記憶がパッと想い出せる人は幸せな人です。ちなみに、傾向としてということですが、男性の記憶は女性の記憶よりも、時間と空間のタグが強いです。女性の記憶は男性の記憶よりも、感覚や感情のタグが強いです。男性と女性が話し合っても話が噛み合わないことが多いのはそのためです。
2022.10.21
コメント(5)
-
「心の成長プロセス」(子どもが大人になれない社会)
子どもは7才頃から幼児期を抜け出します。その頃から外の世界に興味を持ち始めます。そして、お母さんから離れ、家から出て、ドンドンと外の世界に遊びに行くようになります。仲間だけで遊ぶようにもなります。ただし、本来は・・・という事ですけど。幼い頃から室内だけで、一人だけで、オモチャや電子機器に依存した遊びだけで遊んで育った子は、7才頃になっても外に出ていきません。出て行く必要を感じないからです。外に行っても仲間もいない、自由に遊べる空間もない、安全もない、周囲の大人に子どもの遊びを温かく見守る目もありません。さらに、子どもが子どもらしく遊んでいるだけで叱られたり、時には学校に通報されたりします。でも、家の中にいれば安心だし、楽しく遊ぶものもあるし、食べ物もあるし、ゲームがあれば寂しくもありません。だから外に出ていく理由がないのです。最近は、コロナによる自粛やマスクのせいで、子どもたちはさらに外に出ていくことを億劫がるようになっています。(マスクは人の意識を内側に向けさせます。)本来、そういう状態は子どもの成長には好ましいことではないのですが、親の意識も、周囲の大人の意識も、社会全体の意識も、それが当たり前になってきてしまいました。昔は、毎日、学校から帰ったら暗くなるまで友達と遊んでいました。家まで直接行って「○○ちゃん、あーそーぼー」と声をかけていました。でも、今、教室の子に聞いても友達の家の場所を知らないそうです。電話番号も知りません。子どもだけでなく、親も知りません。学校が教えなくなってしまったからです。社会と出会い、自分と社会とのつながりを知り、社会とのつながり方を学ぶべき時期に、子どもを社会から遠ざけてしまっているのです。病気やケガがなく、大人の言うことを良く聞いて、ちゃんとお勉強さえしていれば、最近の大人達は満足なんです。それ以上、何が必要なのかを知らないのです。でも、それだけでは子どもは精神的自立が出来なくなってしまうのです。大人になっても幼児性が抜けなくなってしまうのです。それは依存心の強さとして表れます。9才頃になるとさらに子どもは親から離れ、社会の中に出ていこうとします。7才頃から社会というものに目覚め始めますが、9才頃までは、社会に出て行ったり親の所に戻ってきたりということを繰り返します。でも、9才を過ぎると行ったきりになるのです。子育ての終了です。その後の親の役割は、子どもを信じ、子どもの意思を支えるだけです。それ以上のことは出来ません。それ以上のことをしようとすればするほど、子どもの気持ちは親から遠ざかっていきます。この頃から、子どもは親に隠し事をするようになります。上手に嘘をつくことも出来るようになります。親の権威、大人の権威が通用しなくなります。そして急に「一人ぼっち」になります。この頃から子どもの仲間作りの形も変わってきます。それ以前はただ群れて遊べれば良かったのですが、この頃から「個」と「個」の付き合いを求め始めるのです。でも、それ以前の「群れ」の体験がない子は、「個」と「個」の付き合いも出来ないのです。人間の成長は、ちゃんと段階を踏まないと次のステップに上がれないように出来ているからです。基礎をちゃんと作らないと、ちゃんとした上物は建ちませんよね。それと同じです。だからこそ、子どもが幼い頃に、お母さんが自分と同じような価値観を持った他のお母さん達とつながり、みんなで一緒に遊び、一緒に子育てを楽しむことが出来るような仲間作りをする必要があるのです。私はそのためのお手伝いをしています。
2022.10.20
コメント(2)
-
「心の成長プロセス」(7才前は地図も時計も読めないのです)
知らない町を歩いている時、地図を持っていない人はすぐに迷子になります。なぜなら、地図を持っていない人は自分中心にしか「今、自分がいる所」を認識出来ないからです。「今どこにいるの?」と聞かれても、「私は今ここにいる」としか答えることが出来ないでしょう。その「ここがどこなのかを知るための地図」を持っていないのですから。ただし、地図を持っているだけでは「自分がいる場所」は分かりません。今自分がいる場所をよく観察して、地図の中でそれに合う場所を探さなければならないからです。「自分がいる場所」をよく観察するだけでも、「地図を持っている」だけでも、その両方が揃っていないと「今自分がいる場所」を正確に認識する事はできないのです。7才前の子どもは「今、自分がいる場所」を観察するのは得意です。でも、地図を持っていないので、「今自分がどこにいるのか」を客観的に知ることが出来ません。でもそんなことは気にしません。7才前の子どもにとって大切なのは「今、ここが楽しいか、楽しくないか」だけだからです。そして、日々の生活や遊びを通して、「今、自分がいる場所」をよく観察しています。でも、7才を過ぎて9才頃になると、急に「ここはどこなんだろう」ということが気になり始めるのです。「このままでいいんだろうか」とか「迷子になったらどうしよう」などということが気になり始めるのです。7才頃から少しずつその感覚が目覚め始め、9才頃に大きな変革が起きます。どうしてそういう変革が起きるのかというと、9才頃に時間感覚が変わるからなんです。それまでは「今」にしか関心がありませんでした。というか「今」しか見えなかったのです。そして、「今」が存在するのは「ここ」だけです。でも、9才頃から、時間が、「今」を中心にして過去にも未来にもつながっているということが見えるようになってくるのです。ただし、「9才頃」というのは大体の目安で、それよりも早い子もいれば遅い子もいます。大人になってもそれがよく分からない人もいます。その頃から時計(アナログ式)が読めるようになってきます。地図も読めるようになってきます。時間感覚と空間感覚はつながっているからです。また論理的に考えることも出来るようになってきます。サンタクロースの存在にも疑いを持ち始めます。そして否定する子もいれば、サンタクロースが存在する理由を論理的に考え出す子もいます。いずれにしても何にも疑いを持たずに無邪気に信じる時期は過ぎてしまうのです。7才前の子ども「サンタクロースなんかいない」と言う子はいますが、それはそういう風に周囲の大人や仲間が言っているからであって、自分の頭で論理的に考えた結果ではありません。その頃から「自分」が世界の中心ではなく、「自分と同じような大勢の人の中の一人に過ぎないんだ」という事に気付き始めるのです。今、ここしかかなかった世界が、急に広がり始め、見えなかった過去や未来が見えるようになってくるのです。小さなテントの中だけで生活し、小さなテントの中の世界だけしか知らなかったのに、急にテントが取り払われて、「広大な自然の中にポツンと存在している自分」に気付き始めるのが9才から10才前後なんです。ただし、この時期に、その広い世界に対して「希望を感じる子」と「不安を感じる子」がいます。それまでに「自己肯定感や自信」というものが身についている子は「希望」を感じるでしょう。でも、それが身についていない子は「不安」を感じるでしょう。7才から9才頃までに色々な人と出会い、色々な体験をし、単に知識を覚えるのではなく、自らの感覚や思考や行動を通して、発見し学ぶ楽しさを身につけることが出来た子は、希望を感じるでしょう。今、自分がいる周囲のことをよく知っている子は、地図を与えられればすぐに「自分がいる場所」が分かります。そして、地図上で自分が行きたい場所を見つければそこへの行き方も分かります。でも、「自分がいる場」と関わらず、画面ばかりを見て暮らしてきた子は、地図を与えられても、今自分がどこにいるのか分かりません。その結果、不安ばかりが増え、地図を持っているのに迷子になります。お勉強で、どんなに詳しい地図を学んでも、今自分がどこにいるのか分からなければ、その地図を使う事はできないのです。7才から、9才、10才頃までは、自分の感覚や、思考や、行動を通して、「今」「ここ」のことについていっぱい学ぶ時期なんです。知識を学ぶのはその後にした方がいいのです。そうでないと子どもは迷子になります。いっぱい知識を持っていても、その知識の使い方が分からないからです。身体能力が育っていない子にノコギリを与えても使えません。でも、身体能力が育っている子はその使い方を教えなくても他の人がやっているのを見るだけで使いこなせるようになります。それと同じようなことです。
2022.10.19
コメント(2)
-
「心の成長プロセス」(7才頃に起きること)
あと、幼い子どもの感覚は外側に向かって開いています。ですから、外の世界の事に関してはよく気付くのですが、自分自身のことに関しては気付きません。そして常に自分中心の世界の中にいます。自分自身を見る目がないので、自分の感覚や考えを客観視することが出来ないからです。そのため、客観的に物事を見たり、関係性の中で物事を見るようなことも苦手です。119番通報で「火事です」と消防署に電話してくる人に、「火事はどこですか」と聞き返すと「ここです。ここが燃えているんです。」と答える人がいるそうです。確かに通報した人にとっては、燃えているのは「ここ」なんでしょうが、消防署の人はその「ここ」がどこなのか知りたいのです。そんなこと当たり前のことなんですが、パニックになるとそれが分からなくなってしまうこともあるようです。そして幼い子どもたちは常にそのような状態です。「自分に見える風景」は理解出来ても、「自分以外の人が見ている風景」は理解出来ないのです。そのため、他の人に自分がどう見えているのかも分かりません。だから「はだかん坊」でも恥ずかしくないのです。「かくれんぼ」をしていても、自分から相手が見えなければ、相手からも見えていないと思い込み、「頭隠して尻隠さず」ということを普通にやります。円柱形のものを正面から見ると「○」です。横から見ると「□」です。大人は、その両方からの情報を合わせて「ああ、これは円柱形なんだ」と理解出来するのですが、幼い子どもは自分から「○」に見えたなら、他の人にも「○」に見えているはずだと思い込んでしまうのです。子どもがケンカしている時、両者の言い分を聞くと、必ず両者とも「自分は悪くない」と言います。「自分が言ったこと」、「やったこと」の意味を相手の立場に立って考えることが出来ないのでそれは当然の状態です。だからイジメをしても、「悪いことをしている」という感覚がないのです。「イジメは良くない」といくら言っても、相手の気持ちが分からない状態の子どもたちには「イジメ」の意味さえ分からないでしょう。大人は、子どもがケンカすると、双方の話や目撃した子の話を聞いて「○○君の方が悪い」と勝手に「悪い方」を決めますが、当の本人は「僕は悪くない」と絶対に納得しません。だからそういうときは、子どもの話を聞き、「太郎君はこう言ったんだね」「それに対して、次郎君はこう感じたんだね」と、太郎君には見えない情報を太郎君に教えてあげる必要があるのです。その結果、太郎君は自分がやったことの意味が分かるようになるのです。絵本や物語をいっぱい読んであげているとその辺の感覚が育ちます。ゲームで遊んでいる時には、ゲームをやっている子の視点しかありませんが、物語の中には登場人物の全ての視点が出てきますから。その際、大人が大人の視点だけで善悪のジャッジをしてしまうと、子どもは相手の気持ちを考えることが出来なくなります。罰則を厳しくすることでイジメをなくそうとする人もいますが、そんなことをすると逆にイジメは増えます。目に見えない所で・・・。善悪のジャッジをするのではなく、ただ「相手がどう感じたのか」ということをちゃんと伝えてあげるだけでいいのです。それが分からないからイジメをするのですから。そのためには大人が子ども一人一人の立場に立って、子どもの言葉に耳を傾ける必要があるのです。それでも子どもは7才、9才とそういう状態から抜け出します。そして、「他者から見た自分」を意識することが出来るようになります。その結果、「自分が中心でいることが出来た世界」が崩れて行きます。その時、それまでに他の子や周囲の世界と良好な関係を築けてきた子は、自分以外の世界の中に自分の居場所を見つけることが出来るのですが、幼い時から一人で遊んでばかりいた子は、自分以外の世界の中に自分の居場所を見つけることが出来ません。そのため、「自分」にこだわるようになり、自分中心の世界から抜け出せなくなり、自分勝手に生きるようになります。そのような人は相手の気持ちを考えずに発言したり、行動したりします。それを注意すると「僕は何も悪くないのに」と逆ギレします。また、7才頃から、客観的に物事を見たり、考えたりする能力も目覚め始めるので、学問を勉強することも可能になります。客観的に物事を見る能力が目覚めていない時期の子に勉強を教えても意味がないのです。早くから勉強を教えすぎると「暗記する勉強」は出来ても「理解する勉強」が出来なくなってしまうのです。そういう状態の子は、中学校に入ってから急に勉強が分からなくなります。
2022.10.18
コメント(0)
-
「心の成長プロセス」(自分らしさの目覚め)
幼い子どもたちが自分が生まれた世界を認識するためにまずしているのは、世界をそれぞれの特徴に従ってグループ分けすることです。そのために、「似ている所探し」をします。自分と他の子の間にも「似ている所探し」をします。そのため、「自分と同じような行動をしている子」を仲間として認識します。その際、肌の色の違いや障害の有無は関係がありません。ゲームが好きな男の子は「ゲームをしている子」を仲間として認識します。「毀滅の刃」が好きな子は「毀滅の刃」が好きな子を仲間として認識します。まただから、仲間には同じ行動を求めます。大人は「みんな一人一人違ったっていいんだよ」と言いますが、一人一人違うのは当たり前なので、違いをそのまま肯定していたら、世界を認識出来なくなってしまうのです。「木」という概念を得るためには「木というものに共通する何か」を知る必要があります。色々な木を見て「似ている所探し」をするから「木というもの」が分かるようになり、そして「この木」の特徴(個性)が分かるようになるのです。絵を描く時もパターン化した絵を描きます。家を描く時は「まさにこれが家」というような絵を描きます。イヌやネコを描く時も「イヌと分かる絵」「ネコと分かる絵」を描きます。このようなパターン化が始まるのは、子どもが群れ遊びを始める時期と重なっています。「みんな一緒」が出来るようになる頃です。その頃から、「仲間」と「仲間以外の子」が分かれ始めます。そして、この頃から「仲間ではない子」に対してイジメが始まったりします。絵を描かせてもみんな似たような絵を描き始めます。それまでは自由に描いていたのに、急にパターン化されたつまらない絵を描くようになるのです。「上手に描きたい」という意識も目覚め始めます。この場合の「上手」は「自分らしく」ではなく「みんなと同じように」描きたいということです。それでお母さんは「もっと自由に、もっと自分らしく描いていいんだよ」と言うのですが、でもそれは、「一人ぼっちでいること」を意味してしまいます。幼い子どもは一人ぼっちは嫌なんです。誰かの仲間になりたいのです。だからみんなと同じように描こうとするのです。子育てでも、他の子と関わらせることなく特別な子育てをしてしまうと、子どもは「みんなと一緒」という安心感と喜びを持てなくなり、寂しくなったり不安を感じたりしてしまいます。それがどんなに理想的な教育方法であっても、他の子と切り離されて育てられた子は「自分らしさ」に目覚めるのではなく、「自分」へのこだわりが生まれます。その結果、他者と対立しやすくなります。もし、自分の周囲にいる人と異なった教育をしたいのなら、同じような価値観を持った仲間とつながり、その仲間の中で子育てをするようにした方がいいです。ここに書いたようなことはいい悪いの問題ではありません。「子どもはこういう過程を通って成長していくんだ」というだけのことです。子どもはまず、誰かの仲間になろうとするのです。そして、仲間達と色々な形で関わることで「僕はぼくだ」「私はわたしだ」という意識に目覚め始めるのです。例えば、基地作りをするような時でも、みんなが同じように考え、同じように行動しているだけではいつまで経っても基地は出来ません。「三人寄れば文殊の知恵」という諺がありますが、それぞれが触発し合って色々な意見を発し、色々な事に気付き、さらに、それらを持ち寄って同じ目的のために行動する結果として素敵な基地が出来るのです。まずは「同じ目的を持つこと」、これが始まりです。でもそれが実現するためには考え方の多様性が必要になるのです。「全体」がしっかりとしているから「個」が生きてくるのです。子どもが自分を知り、個に目覚めるためには、自分を映す鏡が必要になるのです。そのためには目的を共有出来るような仲間が必要になるのです。「自分は自分だ。無理してみんなと同じことをやろうとしなくてもいいんだ」という事に気付き始めるのは思春期になってからです。でも、「あなたはあなたのままでいいのよ」と子どもを群れから引き離してしまうと、子どもは自分を映す鏡を失ってしまいます。そのため、「自分は自分」という感覚が目覚めなくなってしまうのです。お母さんが「あなたはあなたらしく生きればいいのよ」と言っても、「自分と他の子の違い」は分かっても「自分らしさ」が分からない子にはそういう生き方は出来ないのです。違いが肯定される仲間の中で「自分らしさ」に気付き、「自分は自分」という感覚が目覚めるのです。そういう体験がないまま思春期を迎えると、違いを肯定出来なくなってしまうのです。そして、「似ている所」ではなく「違っている所」ばかりを探すようになり、「みんなと違う自分」を自己嫌悪したり、恥ずかしがるようになります。例として適当かどうかは分かりませんが、例えば「ポメラニアン」という犬種がありますよね。そのポメラニアンの特徴や、個性や、いい所は「イヌ」という大きなグループの中で意味を持つのですよね。でもそのポメラニアンを、「犬という生き物が存在しない世界」に連れて行ったら、他の生き物との違いは分かっても何がポメラニアンの特徴なのか、個性なのか、いい所なのか分かりませんよね。そのようなことです。
2022.10.17
コメント(4)
-
「心の成長のプロセス(中)」(ファンタジーの世界)
生まれたばかりの赤ちゃんは、音も、色も、光も、触覚も、味も、「物」と一対一対応させて認識する事が出来ません。赤ちゃんに赤いリンゴを見せて、「これが赤という色よ」と教えても、赤ちゃんは「色という概念」そのものが認識出来ません。また、「あか」という音がリンゴを示すものなのか、丸い形を示すものなのか、リンゴを持っている手を指すものなのか、「リンゴを見せる仕草」を指すものかも分かりません。ネコがいた時に「ニャンニャンいるね」と言っても、その「ニャンニャン」が「うごくもの」を指すのか、「毛が生えているもの」を指すのか、「なんとなく丸っこいもの」を指すのか分からないのです。ですから、「ニャンニャン」という言葉を覚えると、イヌも、クマも、カンガルーのぬいぐるみも、トトロもみんな「ニャンニャン」になります。「パパ」という言葉を覚えると、隣のお父さんにも、知らないおじさんにも「パパ」と言います。(パパは焦ります)でも、繰り返し、繰り返し、そういう言葉を実際にそういうものと関わりながら聞くことで、少しずつ「パパ」の対象範囲が狭くなっていき、最後は「たった一人のパパ」にたどり着きます。ですから、図鑑だけで「ニャンニャン」という言葉を覚えた子は「本物のニャンニャン」を認識出来ません。言葉と実物が一対一対応出来ないからです。最初は「動くもの」全てが生き物だと思い込みます。だから、自動車も電車も生き物です。だからアニメの中で自動車や電車が擬人化され話をしていても違和感を感じないのです。幼い子どもは、大人から与えられたヒントを基にまず大きくグループ分けをするのです。その際重要となるのは「違っている所」ではなく「似ている所」です。子どもは「違い」よりも「共通点」を探そうとするのです。だから、肌の色なんか気にしません。障害の有無も、性別も全く気にしません。とにかく一緒に遊べるのならみんな仲間なんです。幼い子どもは「違っている所を探して分ける」のではなく、「似ている所を探してつなげる」のです。そうやって自分が生まれてきた世界を認識しようとしているのです。こういう状態が、大体7才頃まで続きます。(個人差は大きいですけど)「7才までは夢の中」と言いますが、7才前の子どものファンタジーの世界もその「つながり」によって生まれています。おとなでも、「違い探し」ではなく「似ている所探し」をすれば、自他の境が次第に消えて行きますよ。戦争もなくなるでしょう。
2022.10.16
コメント(0)
-
「心の成長のプロセス(前)」
「心の育ち」が遅れると、自分の感覚で感じ、自分の頭で考え、自分の意思と責任で行動することが困難になります。そして自分に自信が持てなくなり、いつも人目を気にしてみんなと同じことをするようになります。その結果、自分らしく生きることが困難になってしまいます。「自分らしい子育て」も、「自分らしい生き方」も困難になります。じゃあ、その「心」はどのように育つのか、ということです。産まれたばかりの赤ちゃんには「自分」と「自分以外の世界」しか存在していません。木も、石も、花も、家も、太陽も、全部一緒くたになってしまっていて個別には存在していません。色も形も一緒くたになっています。そしてその「自分」と「自分以外の世界」をつないでくれているのが「お母さん」という存在です。だから、お母さんが側にいないと不安を感じるのです。そして、色々なものに触れたり、口に入れたりして「自分以外の世界」を感じ取ろうとしています。そのような行為を通して、「自分の以外の世界」を知ることが、そのまま「心の成長」につながるのです。心は他者との出会いによって育つのです。なぜなら、他者と出会うことは自分と出会うことでもあるからです。赤ちゃんは、身近な色々なものを触り、そしてしゃぶりながら心を育てているのです。(そのような行為で、からだの機能も、能動的な意思も、免疫系も育っています)でも、過剰に清潔を気にする現代人は、あまり赤ちゃんが色々なものに触れたり、しゃぶったりすることを肯定しません。すみません。ちょっと色々な事情で今日は時間がないので、この続きは明日書きます。
2022.10.15
コメント(0)
-
「子どもが成長すると言うことは」(肉体の成長と内面の成長)
人間は「肉体」「意識」「心」「感覚」「思考力」などの集合体です。そして、これらの要素は、分離不可能な状態でつながり合い、支え合って働いています。そのつながりを支えているのが「生まれる前の記憶」に支えられた「命の働き」です。お母さんの胎内で命を得た生命体は、その「命の働き」に基づいて、これらの集合体を成長させていきます。私たちに見えるのは「肉体の成長」だけですが、実際には目には見えない部分も一緒に成長しているのです。でも、「命あるもの」が成長するためには、その成長を支えるための「栄養」が必要になります。そして、人間の「人間としての活動」を支えている「肉体」「意識」「心」「感覚」「思考力」などの要素が成長するためにも栄養が必要です。でも、それぞれの成長に必要な栄養素は同じではありません。肉体の成長に必要な栄養と、「意識」「心」「感覚」「思考力」などの成長に必要は異なっているのです。でも現代人は、目で見ることが出来る「肉体の成長」にばかり意識を向けています。そして、肉体の成長に必要な栄養は十分に与えていますが、「意識」「心」「感覚」「思考力」などの成長には無頓着です。それぞれが育つような栄養も与えていません。そのため、「意識」「心」「感覚」「思考力」の成長が遅れてしまっている子がいっぱいいます。でも、簡単で便利な生活をしていると、その遅れが見えないのです。自分の頭で考える必要がない生活をしていたら、「考える力」が育っていなくても分かりません。感じる必要がない生活をしていたら「感じる能力」が育っていなくても分かりません。「人間らしい心」が育っていなくても、自由が与えられていないような場ではそれが見えません。「意識の働き」がちゃんと育っていなくても、みんなと同じようなことだけをして生活しているだけならその遅れは見えません。そしてそれが「今時の子」の普通の生活環境です。だからお母さんや大人達は、子どもの「意識」「心」「感覚」「思考力」などの成長には関心を持たないのでしょう。また必要がない能力だから成長しないのでしょう。子どもの成長に関して、それなりの意識と知識がなければ、子どもの内側で働いている「目には見えない働き」を大切にしようと思わないのは当然の結果です。それが目で見える形で現れてくるのが、9才から10才頃です。9才から10才という年齢は、子どもが親から離れ始める年齢でもあります。自立が始まる年齢なんです。でも、「意識」「心」「感覚」「思考力」の成長が遅れている子は、肉体は普通に育っていても「内面の育ち」がそれに追いついていないため自立が困難になってしまうのです。子どもの自立を支えてくれるのは、「肉体の成長」ではなく、「意識」「心」「感覚」「思考力」などの「内面の成長」なんです。肉体が成長すれば肉体としては一人前の大人になります。でも、「内面の成長」がそれに伴っていなければ、肉体の要求に振り回されることになります。そして、簡単で便利な生活ばかりを求めるようになります。苦しくても頑張ることが出来るようになるためには「内面の成長」が必要になるのです。でも最近の子は、ちょっと苦しいだけで簡単に投げ出します。でも、この年齢を超えてから「子どもの内面」を育てようとしても、かなり難しいのです。この頃から「生命の素直さ」が消えて、疑い深くなるからです。
2022.10.14
コメント(0)
-
「子どもの内面の成長と、成長の節目」
産まれたばかりの赤ちゃんには、大人の感じ方、考え方、価値観は100%理解出来ません。でも、何か特別なことをしなくても、普通に生活して、普通に勉強して、普通に遊んでいれば、知らないうちに、子どもとは全く違う状態の普通の大人になっていきます。でも、本人にその変化の自覚はありません。人は自分と自分を比較することが出来ないからです。その変化には「量の変化」と「質の変化」の2種類があります。量の変化とは、例えば身長や、体重や、知識の量のようなものです。出来ることも増えていきます。この「量の変化」は分かりやすいです。そして、この「量の変化」は自覚することも出来ます。体重の変化は体重計に乗ればすぐ分かります。知識の量の変化はテストをすれば分かります。問題は「質の変化」の方です。「量の変化」は測れますが、「質の変化」は感じるものであって測れないからです。そのため、大人達は「調べることが出来る量の変化」の方に「子育てや教育の目的」を見いだそうとしています。でも、見ることも調べることも出来ない「量の変化」の方は無視しています。それは意識の変化、感覚の変化、考え方の変化などです。それらをまとめて簡単に言うと「内面の変化」と言うことです。その「内面の変化、成長」が、その子どもの「人間性の変化、成長」につながって行くのです。でもこの「内面の変化」を客観的に判断する方法は存在していません。子どもの内面の変化は、大人の内面の働きを通して感じ取るしかないのです。でもそれは、誰にでも出来るものではありません。子どもの内面の変化を感じ取ることが出来るのは、常に、自分自身の内面と向き合っている大人だけです。ちなみに、自己否定している人はいつも自分の心のことばかり考えていますが、それは「向き合っている」と言うことではありませんからね。我が子と他の子を、自分と他の人を比較ばかりしているような人には子どもの内面の変化は見えないのです。成績や人目ばかり気にしている子育てしている人にも見えません。目に見える「からだの成長」と共に、目には見えない「子どもの内面」も成長していくのですが、その内面の成長は連続的に平均して起きているわけではありません。成長の節目があるのです。もうすぐ七五三ですが、その3才、5才、7才という年齢もその節目です。ただし個人差も大きいので大まかにその前後ということですけど。これらの節目を境にして子どもの意識、感覚、思考力の状態(質)が変わります。それは言葉や遊びや行動の変化として表れます。その節目を境にして急にそれまでとは異なった事を言い出したり、やり出したりするのです。(この切り替えの時、高い熱を出す子もいるみたいです。「高い熱を出した後、急に性格が変わった」という話を何人かから聞いたことがありますから。)いわゆる「ヤダヤダ期」とか「反抗期」と呼ばれるものも、この節目の一つです。そしてこの節目の時には、子どもの心やからだが不安定になります。そのため子どもは原因が分からない不安を感じます。そのため、それまで自分でやっていたことなのに急に「お母さんやって」と言い出したり、甘え出したりもします。反抗期や赤ちゃん返りは成長へのサインなんですが、それが分からないお母さんは簡単にそういう状態の子どもを否定してしまいます。でも、叱られても子どもにもどうしようも出来ないのです。それは「子ども自身の意思」ではなく、「成長しようとする生命の意思」の表れだからです。7才を過ぎても、9才(10才)とか14才という節目があります。特に、7才、9才(10才)、14才の節目は大きいです。この節目を境にして子どもは大きく変わります。ちなみに、人間は21才頃まで成長を続ける生き物だそうです。そこから先は老化が始まります。<続きます>
2022.10.13
コメント(0)
-
「子どもの成長と生まれる前の記憶」(子どもらしさを否定する社会)
お腹の中で受精した卵子は、細胞分裂を繰り返しながら、単なる「細胞の固まり」から、一つの「生命体」になります。その「原始生命体」は魚、両生類、爬虫類、哺乳類と生命の歴史をたどりながらやがて「人の形」を得て産まれてきます。でも、この時点で出来上がっているのは「人間としての形」だけです。中味はまだ人間にまで進化していません。実際、神経系の状態も、脳や骨の状態も、大人のそれらとは異なった状態です。7才頃に歯が抜け替わりますが、7才前の子どものからだには大人よりも高い再生能力が備わっています。からだの中の状態が違えば当然、感覚の状態も、思考の状態も異なります。もちろん、無意識の状態も異なります。大人になってからでも、日々の「からだの状態」が、自分の感覚や思考の状態に大きく影響していることは感じることが出来ますよね。それよりももっと大きな違いが子どもと大人の間にはあるのです。でも、大人はそのことに気付きません。自分も昔はそうだったのですが忘れてしまっているのです。よく観察していれば、「子どもは大人とは異なった生態を持った生き物だ」ということが分かるのですが、多くの大人の人がそれをただ「単なる未熟なせいだ」と思い込んでしまっているのです。だから「早く人間らしく、一人前にさせてやろう」と、大人の感覚、大人の考え方を子どもに押しつけています。でもそれは、水の中で暮らしているオタマジャクシを陸にあげ、「さあ、ジャンプしろ」と追い立てるようなことです。その結果は想像できますよね。問題は、オタマジャクシとカエル(成体)の違いは見れば分かりますが、人間の子どもと大人の間の違いは見ても分からないと言うことです。それでも、多くの子どもたちが自由に遊んでいる姿を見れば、「ああ、子どもとはこういう生き物なんだ」ということが分かるのですが、我が子を家の中に囲い込んで子育てをしているような人にはそれが分からないのです。そして、人間らしくない我が子を見て失望し、怒り、追い立てています。私はよく子育てや仕付けの相談を受けるのですが、多くのお母さんが子どもの素直な「子どもらしさ」や「子どもらしい行動」を肯定出来ずに、「発達の問題」や「仕付けの問題」だと思い込んでしまっています。そして「私がちゃんと仕付けないと、私がちゃんと教育しないと困った子になってしまう、困った大人になってしまう」と、嫌がる子どもを追い立てて、一生懸命に仕付けや教育を押しつけています。イモムシに空を飛ぶ練習をさせたり、オタマジャクシにジャンプする練習をさせるような無茶な事をやらせているのです。その結果、「イモムシとして必要な栄養や学び」や、「オタマジャクシとして必要な栄養や学び」を十分に得ることが出来なくなります。それでも、多少でも栄養を得ることが出来ているのなら、やがて成体になります。そのようにプログラムされているからです。(実際にこんなことをしたら成体になる前に死んでしまうでしょうけど)でも、当然のことながら子どもの時に栄養が足らなければ立派なチョウやカエルにはなりません。子どもの思考や行動や感覚は、大人には理解出来ないことが多いですが、でも、子どもの成長には必要なことばかりなんです。だから、それを大人の価値観だけで否定したり、禁止したり、取り上げてしまうと、子どもの成長に必要な栄養が満たされなくなってしまい、一人の人間として、一人前の大人として自立する事が困難になってしまうのです。大人には無駄なこと、意味がないこと、困ることでも、子どもには必要なこと、意味があることなんです。でも今、社会全体でそれをやっています。それどころかさらにそれを進めようとしています。「子どもらしさ」は、大人が目標とする(大人の価値観に基ずく)「便利で、効率的で、安全で、安心で、清潔な社会」のルールを破壊するので、それを肯定出来ないのです。その結果、自己肯定感が低い子ども、自己肯定感が低い大人が、すごい勢いで増えています。<続きます>
2022.10.12
コメント(0)
-
「人は無意識の世界ではみんなつながっているのです」(生まれる前の記憶)
「無意識」の話は今日で終わりにします。私たちが「私はわたし」と感じることが出来るのは意識の働きの結果です。そして、「私とあなたとは別の考え方をして、別の体験をして、別の知識を持っている別の存在だ」と感じるのも意識の働きの結果です。そして、その「私とあなたは別々の存在だ」という感覚の根拠になっているのが「幼い頃からの記憶」です。「私の記憶」は私だけのものです。そして「私」という存在はその「私だけの記憶」の上に成り立っています。逆に言えば本当は「太郎さん」でも、「次郎さん」の記憶を植え付けられれば「自分は次郎だ」と思い込むのです。太郎さんが死んでいく時、太郎さんの記憶を全部AIロボットに記憶させれば、そのロボットは「からだは機械になってしまったけど、私は太郎だ」と言い出すでしょう。この手の話はマンガやSFの世界ではよくあります。(事実確認は困難ですが)前世の記憶が蘇ることで、「私は昔ヨーロッパのどこどこで暮らしていた○○だ」と言い出すこともあります。でも人は、生まれた後の記憶だけに頼って生きている訳ではありません。お腹の中の赤ちゃんでも、自分の産まれ方、産まれた後にすべきことをちゃんと知っています。学びの仕方も、成長の仕方も知っています。また、世界中の言語、文化を学ぶ共通の素地も持っています。人間として生まれれば、人間として共通の感覚や、感情や、からだも持っています。日本人の笑っている顔の写真を、日本人を見たこともないアフリカの人に見せても「笑っている顔だ」と認識出来ます。「笑い声」も同じです。全く同じではありませんが、色に対する感覚や、光に対する感覚もある程度は共通しています。赤い色に暖かさを感じ、青い色に涼しさを感じるのは世界共通だろうと思います。幼い子どもが最初に発する声も、最初に描く絵も、最初に行う行動も共通しています。そういうことは、生まれた後からの記憶ではなく、生まれる前の記憶なんです。「生まれる前の記憶」が共通しているから、そういう感覚や行動も共通しているのです。「生まれる前の記憶」と言うと怪しい感じがしますが、人間を人間たらしめているDNAはそのまま記憶装置ですからね。DNAは生命誕生以来の命の記憶を記録しているのです。人は生まれた後から作られる「脳の記憶」は別々ですが、DNAに書き込まれている「生まれる前からの記憶」は一緒なんです。だから世界中の赤ちゃんが産まれた後すぐにお母さんを求め、お母さんに抱かれると安心するのです。また、物語の構造も共通しているのです。歌や踊りを楽しむ感性も、赤ちゃんを見て和む感性も共通しています。自分とは異なった文化圏の歌や踊りに惹かれることがあるのもそのためです。死を恐れ、死を怖がるのも人類共通です。さらに、遺伝子の中には人間が人間になる前の記憶も書き込まれています。太古の海に漂っていた頃の記憶も書き込まれているのです。無意識の世界ではその生まれる前の記憶も働いています。だから悩んだり、苦しんだり、色々感じたり、発見したり、希望を感じたりすることが出来るのです。自由であることに希望を感じるのもその生まれる前の記憶によるものなのでしょう。一人の個人として産まれた後からの記憶ばかりでなく、そういう「生まれる前の記憶」を想い出してみませんか。世界の見方が変わると思いますよ。全ての命はつながっているということも、理屈ではなく感覚で分かるかも知れません。
2022.10.11
コメント(0)
-
「私たちの命は無意識の働きによって支えられているのです」
人間は「無意識の働き」に支配されています。何を見るか、何を聞くか、何を感じるか、何を考えるか、何をするかということの全てが無意識の働きの結果です。何かを選ぶ時も、人は自分の意思で選んでいるように感じていますが、実際には無意識の働きが選んでいるのです。だからいつも同じような選択結果になるのです。「自分が生きている世界」は、自分の無意識が創り出した世界なんです。ですから、苦しみの中に居る人も、幸せの中に居る人も、それは無意識の働きの結果です。人間以外の生き物たちは100%無意識の世界の中だけで生きています。なぜなら、「無意識の働き」は「命を支える働き」とダイレクトにつながっているものだからです。それはどういうことかというと、生物は何らかの行動によって自分の命をつなぎ、子孫を残していますよね。生きるための行動をする事が出来ない生き物は、命を与えられてもすぐに死ぬしかありません。そして、無意識の働きはその行動を管理しているのです。そしてこれは人間においても同じです。ただ人間は、意識というものを持っています。この場合の意識とは「自分というものを認識出来る働き」のことです。他の動物でも音や動きなどに意識を向けることは出来ますが、自分自身に意識を向けることが出来るのは人間だけなんです。そして、その意識の働きを持っているので、無意識の働きの結果を認識することが出来るのです。「子どもを叱らないようにしようと思っていても、気付いたら叱っていた」などというようなことはよくありますが、「つい叱ってしまう」というのは「無意識の働き」の結果です。それに対して、「ああ、また叱ってしまった、もう叱らないようにしよう」という自覚が生まれるのは「意識の働き結果」です。でも、いくら無意識の働きの結果を意識できても、感情を管理しているのは「意識の働き」ではなく「無意識の働き」なので、またすぐに同じことを繰り返します。人間は「感情の動物」であると言われていますが、その感情が吐き出されることなく過度に溜まってしまうと、生命維持やからだの働きの方に困った影響が出てしまうのです。そのため、命の働きとダイレクトにつながっている無意識の働きが、一時的に意識の働きを遮断して溜まってしまった感情を吐き出させようとするのです。それを吐き出すことが出来ないと、心とからだが病んでしまいます。我慢は命の働きにとって有毒なんです。だから苦しいのです。また、無意識の働きは生命維持機能と直結しているため、生まれてから死ぬまで停止しません。眠っている時も働いています。でもそれを自覚出来ないのは、認知機能を支えている意識の働きもまた無意識の働きの結果だからです。私たちは目で見ているものは自覚出来ますが、その「見る」という機能を支えている目の働きは自覚出来ませんよね。それと同じです。意識の働きで無意識の働きを認識出来ないのですから、意識の働きで無意識の働きを変えることも出来ません。だから、いくら叱らないようにしようとしても無駄なんです。でも、間接的になら変えられます。目の働きが「見る」という働きを支えているのなら、見るものを変えれば目の働きも変わりますよね。自分の意思で瞳孔の大きさは変えられませんが、明るい所に行ったり、暗い所に行ったりすることで間接的になら瞳孔の大きさを変えることは出来ますよね。それと同じようなことが無意識に対しても出来るのです。いくら自分を責めても、悩んでも、苦しんでも、無意識の働きから出る自分の行動を変えることは出来ません。でも、新しい活動に取り組もうとするとそれに対処出来ない無意識の働きは奥に引っ込んでしまうのです。無意識の働きは今までと同じことをするのは得意ですが、新しいことをするのは苦手だからです。新しいことをやるためには意識の働きが必要になるのです。だからこそ、自分を変えたいと思ったら、それまでやったことがないような「新しいこと」に挑戦する必要があるのです。それまでと同じことをやりながら自分を変えるのは無理なんです。まただから、無意識に支配されている人ほど「新しいこと」や「自由」から逃げようとするのです。また「無意識の働き」は「命の働き」と密接につながっています。その「命の働き」は「からだの働き」と直結しています。そして、からだの働きは、「からだにつながる全てのもの」とつながっています。部屋の壁の色が変われば、からだの状態も命の状態も変わります。そしてそれは無意識の状態にも変化を与えます。赤い部屋にいる時の無意識的な行動と、青い部屋にいる時の無意識的な行動は違うのです。食べ物の影響も受けます。月や太陽の動きの影響も受けます。気温や湿気の影響も受けます。それに伴い、考え方も、感じ方も、行動の仕方も変わります。自分を変えたいと思ったら、無意識の状態を変える必要があります。そして無意識の状態を変えるためには、新しいことやものに挑戦してみる必要があります。自分の行動は変えずに、自分の心だけを変えようとしても無理なんです。
2022.10.10
コメント(0)
-
「無意識とは何か」(私たちを支配してる働き)
このブログは、「楽天ブログ」と「アメバブログ」の両方で発表しているのですが、昨日「取り上げてもらいたいテーマありますか」と書いた所、アメバの方に以下のような投稿がありましたので、今日は「無意識」について私の考えを書いています。無意識とは何者なのでしょうか?生まれてから出来上がったものでしょうか?それらは何か大きな力で、宇宙とか時空とか自然とか。私達はその一部であり、自然のバランスゆえに気質があるのでしょうか?気質は優劣も上下もないと思いますが、多血が多い人に丁寧に無意識を感じるのが難しい?それぞれの感じ方でいいのかな...とも思ったり。まず、多血が多い人に丁寧に無意識を感じるのが難しい?この部分から説明しますが、多血質に限らず胆汁質の人も、「外側の世界」には興味があっても、「内側の世界」には興味がない人が多いです。だから自分の内側にある無意識を感じることが難しいのです。ちなみに、「内側の世界」とは、感覚世界、精神世界、心の世界、霊的な世界などです。ただし、「内側の世界」に興味があるからといって無意識の世界を直接「自分の意識」で感じることが出来るわけではありません。なぜなら意識の働きをコントロールしているのも無意識の働きだからです。何を見ているのか、何を考えているのか、何が気になるのかということ全てが「無意識の働き」の結果なんです。だから、自分の目で直接「自分の目」を見ることが出来ないのと同じように、意識の働きで無意識の世界を直接のぞき込むことは出来ないのです。それは、粘液質の人でも憂鬱質の人でも同じです。でも、無意識の働きを直接見ることは出来なくても、自分の内側の世界を丁寧に感じようとするなら、無意識の働きの結果としての感覚の変化、心の変化、意識の変化、からだの変化を感じることは出来るのです。そして、その点に関しては胆汁質や多血質の人よりも、粘液質や憂鬱質の人の方が得意なんです。でもそれ故に、粘液質の人でや憂鬱質の人は内側の変化に引きずられやすいです。例えば、「なんか嫌な感じがするとき」その「嫌な感じ」をもたらしているのは無意識の働きです。でも、胆汁質の人や多血質の人はあまりその感覚に気付きません。「嫌な感じ」が無意識の中やからだの中だけに止まって意識の方にまで流れにくいのです。簡単に言うと「鈍い」のです。(ただし、体の変調として出ることはあります。)でも、粘液質や憂鬱質の人は常に内側からの声に耳を傾けていますから、そういう微かな感じでも意識の働きを通して感じ取りやすいのです。でもそれ故に、その思考や、行動や、からだがその「感じ」に支配されやすくもあります。学校などにその「嫌な感じ」を生み出すものがあった場合、胆汁質の子や多血質の子の場合は、よっぽどのことがないとそれを自覚出来ませんが、粘液質や憂鬱質の子は「そんなことが気になるの」というようなことでも敏感に感じ取ることが出来るのです。そして、お腹が痛くなったり、熱が出たりして学校に行けなくなります。でも、お母さんが「じゃあ、今日はお休みしていいよ」というと急に元気になったりします。だからお母さんは「仮病だ」とか「嘘をついた」などと言うのですが、子ども自身にしてみたら素直に感じたままを言っているだけなんです。病院で血圧を測られる時にも、無愛想で嫌な感じの先生に脈をとられる時と、優しそうな先生に声かけをされながら脈をとられるのとでは血圧に差が出るかも知れません。緊張すれば血圧は上がり、リラックスすれば血圧は下がる傾向があるからです。それもまた無意識の働きです。無意識の働きはからだの状態に直結しているのです。でも、その時のからだの変化を感じることが出来るかどうかは人それぞれです。明日に続きます。
2022.10.09
コメント(0)
-
「科学的方法と人間的方法」
明日からテーマを変えますが、何かご希望のテーマはありますか。****************** 先日、新聞を読んでいましたら「代替医療の嘘を暴く」的な内容の本が紹介されていました。例えば、鍼灸師に本物の針で治療してもらった時と、先が引っ込む偽物の針で治療してもらった時とで、治療効果に差が出るのかというような実験をいっぱい行って、代替医療の効果が実は心理的なものであって、実際の効果はない、ということを証明しようとした本です。この本は読んではいませんが、似たようなテーマの本は結構出ています。この心理的な効果をもたらすものを「プラシーボ」(偽薬)と言って、医学の世界では「偽物」として極力排除しようとしています。心理的な効果は科学的な裏付けがないので、インチキであり、排除すべき事であるということです。ですから、新しい薬などを開発する時にも、患者を2グループに分け、一方には本物の薬を与え、別のグループには全く関係のない「薬のようなもの」を与え、効果に差が出るのかどうかを検証します。一般的には、このように「人間的な要素」を極力排除して物事を考えることを「科学的」といい、「人間的な要素」が大切にされている世界を「非科学的」といって、レベルの低いものとして考える傾向があります。「科学的な方法」と「人間的な方法」の大きな違いは、「普遍性」と「再現性があるかないか」という事だろうと思います。「科学的な方法」には「普遍性」と「再現性」があります。でも、「人間的な方法」にはそれがありません。科学的な方法で確認されたことは、同じ前提条件を与えることが出来るのなら、いつ、どこで、誰がやっても、同じ結果を得ることが出来ます。それが「科学的」ということです。そのことを確認するために科学者達は実験室の中で出来るだけ「人間的な要素」を排除して研究をしています。でも、「人間的な方法」に於いては、そもそも、その「同じ前提条件」というもの自体が存在しません。科学における「同じ」というのはあくまでも「物質的な状況」に於いて「同じ」ということです。だから、同じ状態を再現することが出来るのです。でも、人間的な方法に於いては、人間的な要素が結果に影響するので、それを行う人が違うだけで、「同じ」は再現できないのです。Aさんと、Bさんが、全く同じようにやったとしても、同じ結果になるとは限らないのが「人間的な世界」なのです。また、昨日と今日とでも、朝と夜とでも結果に違いが出てくるでしょう。「人間的な方法」には再現性がないのです。いつでも「一期一会」です。でも、だからといって効果がないわけではありません。それどころか、下手をすると「科学的な方法」よりも効果がある場合もあります。だから、科学者達は神経質になって「プラシーボ的な要素」を排除しようとするのです。そうしないと「科学」が成り立たないからです。ケガをして泣いているわが子に対して、お母さんが「いたいの いたいの 飛んでいけ」と言って泣きやんだからといって、同じことを他の子にやっても泣き止むとは限りません。それは当たり前のことなんですが、科学者はその「当たり前」を「インチキ」(科学的根拠がない)として否定しようとするのです。でも、「科学」というものが、ロケットを飛ばし、コンピュータを開発するためだけのものならそれでいいのですが、もし、人間のために科学を開発しているのだとしたらその方向性は間違っています。科学の正しさは物質世界の中だけでしか再現出来ないからです。それは、人間は「科学的に反応する生き物」ではなく、「人間的に反応する生き物」だからです。人間的に反応する生き物だからこそ「人間的な方法」が効果を発揮するのです。科学的に開発された薬でも、名医からもらう時と、薬局で買ってきた時とでは効果が違うかも知れません。無愛想な男性の医者からもらうのと、優しい女医さんから「大丈夫だよ」という言葉がけと共にもらうのとでは効果が違うかも知れません。研究開発の段階でどんなに心理的な効果を排除しても、実際にそれらが使われている現場では必ず心理的な効果が働いてしまうのです。その効果は決して排除できません。薬局で、笑顔で渡された薬と、嫌な顔をして渡された薬が同じ効果を発揮するかどうかは明確ではないのです。それが人間なのです。でも、いくら科学的ではなくても、こういうことは実際に起きています。それを認めない、受け入れないという態度は科学的ではありません。「科学」は開発する時には「科学的方法」に従い、実際にそれを人間に対して使う時には「人間的な方法」に従うべきなんです。そうすることで、効果が倍増することもあるかも知れません。でもみんな、その「人間的な方法」の大切さも、その方法も忘れてしまいました。だから子育てや教育の現場ではみんな、「正解」を押しつけるようなことばかりやっているのです。それに、科学ですら、実際に人間が使っている場では非科学的に扱われています。例えば、「科学的に証明された」と言うと、みんな信じますよね。その検証が理解出来なくても・・・。科学を信仰している人たちは、非常に矛盾したことをやっているわけです。でも、現代人はその「人間的な方法」の大切さが分からなくなってしまいました。そのため、子育ての場でも科学的に子どもと関わろうとしている人がいっぱいいます。「いたいの いたいの 飛んでいけ」という言葉や、動物達が洋服を着ていたり、話をする昔話などを「ばかげたもの」として、子どもから遠ざけようとしているお母さんは少なくありません。でも、カルト集団はその大切さも、方法もよく知っています。だから、科学的な知識は持っていても、自分の頭で考える能力を持っていない人は簡単に引っかかってしまうのです。人間は、「科学的な方法」よりも、「人間的な方法」の方に強く影響を受けるように出来ているからです。また、子どもの「なぜ?」「どうして?」に科学的に答えようともしている人も多いです。でも、いくら科学的に正しい答えであっても、人間の子どもはそれでは納得することが出来ません。子どもは、もっと「人間らしい答え」が聞きたいのです。でも私たちは、その「人間らしい答え」がどのようなものであるのか、忘れてしまっています。だから、「人間らしい人間」を育てることが困難になってしまっているのです。ちなみに「人間的な方法」が肯定的な効果を発揮するためには、その人の「人間性」と、その相手との「信頼関係」が非常に重要になります。ですから、「人間的な方法」を大切にしようとするなら、自分の人間性を磨き、その相手との間にしっかりとした信頼関係を築くところから始める必要があります。科学的な方法ではそのようなものは必要ありません。「人間」ではなく「方法」によって効果が出ると考えられているからです。だから、自分を磨く必要も、相手との信頼関係も必要ありません。でも、そのような方法では「人間」を育てることは出来ないのです。また、どんなに科学的な子育てを取り入れても、子どもとの間に信頼関係が築けていないのなら、逆効果になってしまう可能性が高いです。ご注意下さい。********夕べは喘息とアレルギー(花粉症)でよく眠れませんでした。それで頭がボーッとしています。文章にもおかしなところがあるかも知れません。お許し下さい。
2022.10.08
コメント(6)
-
「顔はマスクをするためのものではありません」(個性を隠そうとする人達)
人と人のつながりの中で生まれ、人と人とのつながりの中で育ち、人と人のつながりの中で生活している人間という生き物にとって、「顔」は非常に重要な働きをしています。なぜなら、その「人と人のつながり」を支えているつながりの中でも一番根本的な所にあるのが「顔」だからです。子どもはお母さんの顔を見ると安心します。声さえ聞いていれば「何を言っているのか」は分かりますが、「何を言いたいのか」は顔を見ないと分かりません。顔を知らない相手と信頼関係を築くのは難しいです。子どもは自分がやっていることの是非をお母さんの顔色を見て判断しています。言葉を交わさなくても、顔を合わせているだけでそこにつながりが生まれます。毎朝同じ電車に乗っている同じ顔を見るだけで安心したり、親近感を持ったりします。毎日メールでやり取りしていても、顔を知らない相手とはリアルな世界ではつながれません。また、顔を合わせることで一緒に遊ぶことも出来ます。言葉が通じない外国に行っても、お互いの顔が見える状態なら一緒に遊べます。相手が「何を考えているか」、「何を言いたいのか」、「何を感じているのか」、「どういう人なのか」ということが分かるからです。ある意味で「顔」はその人そのものでさえあります。心の状態も、知的な状態も、からだの状態も、個性も、その人の顔に現れます。数日前に「声はそのままで言葉なんです」ということを書きましたが、顔もまた人と人がやり取りするときの大切な「言葉」の一部なんです。文字化できるものだけが言葉ではないのです。「何を言っているのか」ということと、声や、仕草や、表情がセットになって「人間としての言葉」を形成しているのです。でも、現代人は「文字化できる言葉」だけを大切にして、その他の「文字化できない言葉」を切り捨ててしまっています。でもそれは、人間が「人間らしい関わり合いをするための方法」を失うことでもあるのです。その結果、人間がどんどん「リアルが存在している現実の世界」ではなく「リアルが存在していない観念の世界」で生きるようになってしまいました。「何を言ったか」は気にしても、「どういう声や表情で言ったのか」ということには関心を持たなくなりました。その流れの中で、現代人は「からだ」も失いました。健康は大切にしていますが、その健康の土台となる「からだ」には関心を持たなくなりました。ですから、病気になったときも「自分のからだとの対話」を通してからだの状態を整えようとはせずに、すぐに、薬やお医者さんに自分のからだを預けてしまいます。でもそのくせ、「人からどう見えるか」は非常に気にします。ですからスタイルやファッションも気にします。整形もその感覚の中で使われています。子育てでも、「目の前にいるリアルな我が子」のことよりも、「他の人からどう見えるか」とか「成績」のことばかり考えている人がいっぱいいます。「どう育っているか」には関心があるのですが、「どう育てるのか」という所には関心がないのです。ですから「うちの子は優しくない」と言う人に「じゃあ、優しい子に育つためにどのようなことを心がけているのですか」と聞いてもまともな返事が返ってきません。子どもの成績は気にしていますが、だからといって「子どもの学びを支えるためにどのようなことを大切にしていますか」と聞いても答えが返ってきません。せいぜい、「塾に通わせています」程度です。結果は求めるのに、その結果を支えるような努力やサポートはしていないのです。優しさも、知的な状態も「心やからだの状態」の表れなのですが、その心やからだの状態自体に関心がないため、子どもの育ちをサポートすることが出来ないのです。でも、結果だけはちゃんと要求するのです。作り方も教えてくれず、材料も与えてくれないのに、結果としての製品はちゃんと作れと要求してくるのです。これでは子どもはたまったものではありません。これは自分自身に対しても同じです。自分育てはせずに、結果だけを自分に求めている人がいっぱいいます。でも、そんな事できるわけがないので、結果、そのような人は「結果を出せない自分」を自分で否定する事になります。マスクは、そんな「自分に自信がない人」にとっては救世主のような存在です。自分に自信がない人ほど人に自分の顔を見せたくないのですから。人は本能的に「顔には自分の心の状態や本音が表れる」ということを知っているのでしょう。でも、マスクで顔を隠すということは、他者との関わり合いを拒否し、自分の成長を諦めるということでもあるのです。もちろん、マスクが必要な状況でマスクをすることには何の問題もありません。でも、マスクが必要がない状況でもマスクをするのは「顔を隠したい」とか、「他者との関わり合いを拒否したい」という心の表れなんです。「マスクを外す事への不安」は「自分の顔を見せる事への不安」でもあるのです。(冬場は「暖かいから」という理由もあるでしょうけど・・・)また、マスクは自分の顔を他者から見えないようにするだけでなく、自分の意識を自分の内側に閉じ込める働きをするため、外側の世界への興味や関心を低下させます。これは簡単に自分で確認(実験)出来ます。マスクをした状態で見る景色と、マスクを外した状態で見る景色は、心への響き方が全く違いますから。確かに、マスクをした状態でも、他の人と会話することは出来ます。でも、顔が見えなければ話の内容は理解出来ても相手の気持ちが読めません。相手の感情に共感することも出来ません。そして、このようなことは子どもの成長に対して、非常に大きな影響を与えます。幼ければ幼いほどその影響は大きいです。もちろん悪い影響です。まず、言葉の学びが遅れます。「音としての言葉」は覚えることが出来ても、その音の中味が分からなくなってしまうからです。「楽しい」という言葉を覚えても、その「楽しい」が笑顔とつながらなければ、「楽しい」という言葉の意味が分かった事にはならないのです。第二外国語を覚えるときには母国語を基準にします。でも、その母国語を学んでいる時期の子どもは相手の表情を基準にして母国語を学んでいるのです。だから、その表情が見えない状態で育っている子は母国語の習得に遅れが出てしまうのです。
2022.10.07
コメント(0)
-
「呼吸を取り戻そう」(息を止めるとからだが固まります)
緩める系のからだの活動をしている人達は、時々怪しいことを言います。足の裏で呼吸しろとか、頭のテッペンや指先や手のひらから呼吸しろとか・・・。もちろん、現実的にはそんなこと不可能です。不可能なはずなんですけど慣れてくるとそういう感覚のことが出来るようになってくるのです。足の裏や頭のテッペンだけでなく、からだのどこからでも呼吸が可能になります。ストレッチなどで詰まっている所があると、そこに呼吸を送って緩めることもあります。からだが痛いときなどにも、痛い部位に呼吸を送って痛みを緩めることもあります。実際、からだに呼吸を通すようにするとからだが緩むのです。ゆるむだけでなく統合もされます。足の裏で呼吸をするようにするとからだ全体が一つにつながるのです。ここで実際に通っているのは「呼吸」ではなく「意識」なんだろうと思います。「息(いき)」ではなく「意識(いしき)」です。足の裏を見つめながら(感覚的にです、実際に見ているわけではありません)同時に呼吸にも意識を向けていると、足の裏で呼吸をしているような感覚になるのです。これは私の解釈ですが、それは呼吸に伴う肺の動きが、胴体周辺の筋肉や筋膜や皮膚などを通して足の裏だけでなくからだ全体に伝わっているからなのだろうと思います。呼吸に合わせて血圧も変化しているでしょう。それは非常にデリケートな変化なので、普通の人はそんなもの感じませんが、その部位と呼吸に同時に意識を向け続けることで、呼吸の変化をその部位の変化とつなげて感じ取れるようになるのではないかと思います。今この文章を書きながら手のひらで試して居るのですが、息を吸うときには手のひらが緊張して、息を吐くときには緩むような気がします。息を詰めると固くなります。実際に手のひらで呼吸しているわけではないのですが、手のひらで呼吸を感じることは出来るようです。これが「手のひらで呼吸する」ということなのではないかと思います。また、息を吸っているときには感覚や意識がからだの外側を向き、息を吐いているときには内側を向くような気もします。息を吸っているときと吐いているときとではからだの動かしやすさも変わってきます。「からだを開くような動き」(手を広げるような)は、息を吸いながらやるとやりやすいです。息を吸うことで胸が開き、からだが張るからなのでしょう。まただから、それに合わせて感覚や意識も外側に向くのかも知れません。その逆に「からだを閉じるような動き」は息を吐きながらやるとやりやすいです。風船が縮んでゆるむようにからだが緩むからなのでしょう。まただから感覚や意識も内側に向くのかも知れません。人のからだも意識も、呼吸に合わせて膨張(拡散)と収縮(集中)を繰り返しているのです。そしてそれがからだ全体に対してマッサージのような効果を与えているのです。ただ問題は、日常的にからだを動かさなくなってしまった現代人のからだは、この呼吸がスムーズに出来なくなってしまっているということです。本来呼吸はからだ全体で行うものですが、胸だけで呼吸している人がいっぱいいます。怒りや緊張でお腹が固まっているときには、胸だけでしか呼吸が出来ません。そんな時、大きな声を出すとお腹が緩みお腹まで息が入ります。するとからだが楽になります。怒りを溜めているとからだが苦しくなり、怒りを吐き出すとからだが楽になるのです。心では、大きな声を出してしまったことを後悔するのですが、からだは楽になるのです。だから「怒らないように」と我慢しても無駄なんです。いくら我慢していても、からだがいっぱいいっぱいになったら、からだは勝手にそれを吐き出してしまうからです。普段からからだ全体を使うような活動をして、からだ全体で呼吸するようにしていれば怒りは溜まらないのです。からだのどこかが詰まっているから怒りが溜まるのです。疲れやストレスも溜まります。ズーッと椅子に座っていると、腰が固まり腰から下に呼吸が届かなくなります。肩を固めて仕事をしていると、腕の方に呼吸が届かなくなります。そして腰や肩が動かなくなります。それと同時に、怒りや、疲れや、ストレスが溜まりやすくなります。頭を使った活動ばかりしていると呼吸が浅くなります。呼吸が浅くなると胸が固くなります。するとからだ全体も固くなります。感覚の働きも心の働きも固くなります。それでなくても現代人はすぐに呼吸を止めてしまいます。本人は気付いていませんが、ちょっとしたことで呼吸を止めてしまうのです。呼吸を止めるとからだは固まります。その状態で重いものを持とうとするとからだが壊れます。「あーあ」とか「どっこいしょ」と言いながら起き上がったり、重いものを持ったりすると「ああ、私も年だわ」などと言う人がいますが、実は、あれは理にかなっているのです。声を出すことは息を吐くことですから、声に合わせてからだが緩み動くからです。声を出すと動きやすくなるから、からだを守るために無意識的に声が出てしまうのです。一番いけないのは、頑張ろうとして息を詰めてしまうことです。息を詰めた方が頑張れるし、力も出るような気がするのですが、それは錯覚です。単なる自己満足です。実際には息を吐きながらの方が力が出るのです。なぜなら全身がつながるからです。実際、息を詰めた状態で相手を押しても大して動きません。また反発力も大きいです。でも、「あーあ」とか言いながらからだを緩めるような気持ちで相手を押すと、相手は大きく動くのです。
2022.10.06
コメント(0)
-
「深い呼吸がからだを緩めてくれます」(マスクはからだを固くする)
「声」にはその声の持ち主の「からだの状態」を含んでいます。その「からだの状態」は「意識や感情の状態」でもあります。「声」はただの音ではなく、それ自体が大量の情報を含んだ「言葉」なんです。ですから、緊張しているときの声と緩んでいるときの声は違います。緊張しているときはからだが固まりからだの動きがぎこちなくなります。胸の筋肉も固くなっているので呼吸が浅くなります。喉も固くなっているので声も固く、少し高くなります。長く息が吐けなくなるためゆっくりと話せなくなります。そして、呼吸が浅くなると思考も浅くなります。感覚の働きも鈍くなります。ですから物事の表面しか見ることが出来なくなります。また、イライラしてゆったりと待つことも出来なくなります。だから緊張しているときには深呼吸すると落ち着くのです。深呼吸することで胸の筋肉が緩みます。胸の筋肉が緩めばからだ全体の筋肉も緩みます。また、脳やからだに酸素がいっぱい入ります。だから、意識もはっきりしてきます。緊張しているときだけでなくマスクをしている時にも胸が固くなります。マスクをしていると当然、鼻からの息の出入りが困難になるため息がしにくくなります。そのため胸周りの筋肉が固くなり呼吸も浅くなります。そして、胸周りの筋肉が固くなるとからだは自由を失います。それと同時に、感覚の自由、思考の自由も低下します。また空気が十分に供給されないのでからだを動かすのも億劫になります。意識もボーッとしてしまいます。緊張して呼吸が浅くなっているときもこういう状態になりますが、マスクをしているだけでも似たような状態になってしまうのです。実は、「深い呼吸」と、「自由なからだ」と、「自由な感覚や思考」とは密接につながっているのです。なぜなら、もともと脳は「からだの動き」を管理するために生まれたものだからです。人間の大きな脳はお勉強するために生まれたのではなく、人間の多様な動きをコントロールするために生まれたのです。それをお勉強にも使っているだけです。だから、からだを動かすと脳が活性化するのです。そして脳が活性化すると、感覚や思考の働きも活性化するのです。そして、その脳の活動には大量の酸素が必要です。でも、からだを使わない生活をしていたり、日常的にマスクをしている生活をしているとその酸素が足らなくなってしまいます。そのため、勉強や仕事の効率が悪くなります。人は、お勉強するから賢くなるのではなく、幼いときからからだをいっぱい使って遊んでいるから賢くなるのです。ただし、この賢さは直接学校の成績とはつながっていません。(少なくとも小学生のうちは)だからみんな平気で子どもから遊びを取り上げたり、マスクを押しつけたりしているのでしょう。なんか頭がボーッとする、やる気が出ない、からだが動かないというようなときには、マスクを外して深い呼吸を意識しながらゆっくりと、そして丁寧にからだを動かしてみて下さい。いわゆる「有酸素運動」のようなものがいいです。すると、胸が緩みます。胸が緩むと呼吸が深くなります。からだも楽になります。脳にもいっぱい酸素が届くようになるので、頭もはっきりしてきます。でも、幼いときから胸を固めた状態で育ってしまっている子は、これすらも嫌がるでしょう。ちなみにゲームでばかり遊んでいると、胸が固くなってしまいます。ゲームばかりしていたりマスクを外さない生活をしていると、子どもでも老人のような心とからだになってしまうのです。逆に老人でも深い呼吸を心がけていると、心もからだも若くいられます。
2022.10.05
コメント(0)
-
「からだが緩むと声も緩みます、するとその声を聞いた人も緩みます」
人は「声」と「言葉」に反応する生き物です。動物も「声」には反応しますが、「言葉」には反応しません。一見、イヌは「言葉」に反応しているように見えますが、実際には「言葉」ではなく「声の調子」に反応しているのです。だから、言葉を理解しているように見えるイヌでも、言葉を話すことが出来ないのです。でも、言葉は話せなくても声の調子で何かを訴えることは出来ます。お腹がすいている時の声、怒っているときの声、甘えているときの声は違いますよね。イヌ同士はこの声の調子でコミュニケーションを取っているのです。「声」がそのまま言葉なんです。ちなみにこれは人間の赤ちゃんでも同じです。というか、人間も含めた動物たちは、本来、皆「声」でメッセージをやり取りするように出来ているのです。その「声」が複雑化することで「人間としての言葉」が生まれたのです。この原初的な「声という言葉」は、相手の本能や、からだや、生命感覚そのものにダイレクトに働きかけます。赤ちゃんの柔らかい声を聞いているだけで、こちらも柔らかい気持ちになります。子どもの楽しそうな声を聞いているだけでこちらも楽しくなります。悲しい声、泣いている声を聞いていると、それだけでこちらも悲しく苦しくなります。安心に満たされている人の声を聞いていると、こちらも安心してきます。同じ「大丈夫だよ」という言葉でも、自分がちゃんとしている人の「大丈夫」は相手にそのまま伝わりますが、自分自身が大丈夫ではない人の「大丈夫」は相手を余計に不安にさせてしまいます。赤ちゃんや幼い子どもも同じ言葉の世界にいます。ですから、お母さんの怒っている声を聞くだけで子どものからだは固まります。言っている言葉自体は「大丈夫よ」「頑張ったね」などの優しい言葉であっても、声が怒っているのなら、子どもはお母さんが「頭で創り出した言葉」よりも、「からだの本音から出た声」の方に反応してしまうのです。それはまるで嘘発見器のような能力です。だから子どもには「嘘」が通用しないのです。でも、からだの声に耳を傾けることを忘れてしまった現代人は、「からだから出た声」よりも「頭で創り出した言葉」の方を重視してしまいます。だから、「文字言葉(からだとのつながりを持たない記号)」だけで用を足そうとするのです。その「文字言葉」では、楽しくなくても「楽しいです」と書くことが出来ます。でも、「声という言葉」ではそういう事が出来ません。人は自分の声には嘘をつくことが出来ないように出来ているからです。また、「優しくしなさいって言ってるでしょ!!」と怒鳴る人も多いですが、子どもはこの「優しくしなさいって言ってるでしょ!!」という文字化できる言葉ではなく、その時のお母さんの声からお母さんが本当に言いたいことを感じ取ってしまいます。それは、自分に対するお母さんの怒りであったり、「面倒くさいことを起こすなって言ってるでしょ」というような内容です。でも、お母さんの心とからだが落ち着いているのなら、特に優しい言葉かけなどしなくても子どもは落ち着きます。お母さんが緩んでいるのなら、子どもも緩みます。「目の前の子どもの状態」は「お母さんの状態」そのものなんです。
2022.10.04
コメント(0)
-
「幸せな子どものからだは緩んでいる」(緩むためには安心が必要なんです)
幸せな子どものからだは緩んでいます。そして、からだが緩んでいる子は自由に動くことも、自由に感じ、考えることも出来ます。また、発散する活動だけでなく集中する活動も出来ます。そのため学習能力も高いです。(ちなみに「学習能力=成績」ではありませんからね)例えば、泥だらけになって遊ぶことも、静かにお話を聞くことも出来ます。そして、その笑顔は人を幸せにする力を持っています。そういう子が何人か居るとみんなで仲良く遊ぶことが出来ます。でも、心が満たされない状況で生活している子どものからだには緩みがありません。ですから、自由に動くことが苦手です。声にも、表情にも、考え方にも、動きにも柔らかさがありません。そして疲れやすいです。心のトラブルがからだを動かすときのブレーキとして働いてしまうからです。憂鬱質の子の状態も一見これと似ていますが、憂鬱質の子の場合は場所と仲間を選ぶだけなので、安心出来る場と仲間が与えられているのならからだが緩み、自由に動いたり集中することも出来ます。でも、気質に関係なく心が満たされていない子の場合は常にそういうことが苦手です。また、からだが緩んでいない子は人とつながることも苦手で、いつも心にバリヤーを張っています。そして、他者に対して攻撃的であったり、その逆に、自己否定的であったりします。大騒ぎして発散することは出来ても、静かに集中するようなことは苦手な子も多いです。待つことも苦手です。じっくりと観察したり、じっくりと考えることも困難なので学習能力も低いです。そういう子が多い場では、トラブルが起きやすいです。でも、妙な連帯感もあって自由に考え、自由に行動する子がいると、そういう子を排除しようとすることもあります。(これは大人の社会にもありますよね)このようなことは子どもたちと「からだを使ったワーク」のようなことをすると見えてきます。そういう活動に積極的に参加してくれるのはからだが緩んでいる子どもたちです。ちなみにからだが緩んでいない子は「手」を使う活動も苦手なような気がします。単なる不器用と言うことではなく、手を使うのが面倒くさいみたいです。「手」と「からだ」の間にどういう関係があるのかよく知りませんが、実感として「手」の使い方が上手な子は「からだ」の使い方も上手なような気がします。ちなみに幼い子どものからだは、家庭の中や仲間の中で安心に満たされ、自然との触れ合い遊びや、自然を感じるような生活をしていれば自然に緩みます。また、お母さんとよくお話ししている子や、いっぱい絵本を読んでもらっている子のからだも緩んでいるような気がします。でも、いくらお母さんが優しくしていても、色々なことをやってあげていても、人工的な環境の中で、一人で人工的な機器と触れ合う時間が多ければ子どものからだは固まってしまいます。ハードウェアとの触れ合いは、子どもの心とからだをハードにしてしまうのです。小さいときからお勉強に追い立てれば、少なくとも小学生のうちは良い成績を取ることも出来るでしょう。でもその結果、からだから緩みが失われてしまい、自由に感じ、考えることも苦手になってしまうでしょう。そのため、中学生頃から学習が困難になっていきます。
2022.10.03
コメント(0)
-
「緩めることは柔らかくなること」(緩めるとつながれるのです)
3人の初めて会う人と握手するとします。最初の人は、一方的に強く握って来るので手が痛いです。そんな時は思わず強く握り返してしまうか、手を引いてしまいます。二番目の人はヒニャッと力を抜いてやる気がなさそうに手を出してきます。こちらが手を握っても反応がありません。人形の手を握っているようです。三番目の人は力強いですがでも、包み込むように柔らかく、温かく握ってきます。こちらの手の動きにもちゃんと反応してくれます。どうですか、皆さんだったらどの人となら友達になりたいですか。最初の人はただ自己主張を押しつけてくるだけです。だから、こちらも身を固くしてしまいます。コミュニケーションも困難です。そういう人と友達にはなりたいと思いません。その逆に二番目の人は全く受け身で自己主張をしません。こちらの言うことに対しても、何でも「それでいいよ」という反応しかしません。こういう人ともコミュニケーションは困難です。この人とも友達になりたいとは思いません。三番目の人はこちらの意見をしっかりと受け止め、こちらの意図に合わせてちゃんと反応してくれます。自分の意見を押しつけても来ません。でも、ちゃんと自分の考えを持っていて芯がぶれません。こちらが強く出ても温かく受け止めて柔らかく返してくれます。だから良好なコミュニケーションを取ることが出来ます。この人となら友達になれそうです。緩めるということはそういう事なんです。緩めることで相手とのつながりが生まれるのです。力を入れて頑張るだけでは対立しか生まれません。それは自己満足の世界です。逆に、ただ力を抜くだけではつながりが消えてしまいます。つながりが切れてしまうので対立は生まれませんが何も始まりません。それもまた自己満足の世界です。それに、力を抜くだけの人は一番目の人のように力ずくで来る相手に簡単に支配されてしまいます。「緩める」というのは「自分らしさ」をちゃんと持ちながらも相手とつながることが出来る状態になることなんです。それは、支配しようとすることも、支配されることもない状態です。それはまた、「柔らかくなる」ということでもあります。「緩んだ人」は「柔らかい人」でもあるのです。そういう人を攻撃しようとすると、相手に対する攻撃がそのまま自分に返ってきてしまうのです。
2022.10.02
コメント(2)
-
「緩めるということは力を抜くことではありません」(頑張ることをやめる)
「からだを緩める」ということは単に「力を抜く」ということではありません。確かにからだを緩めてもらうときに「もっと力を抜いて下さい」という言い方はします。私もそういう言い方をします。でも、ただ単純に力を抜くだけでは動けなくなってしまいます。立ってもいられません。じゃあどういうことなのかというと、「力を抜いて下さい」という言葉の正確な意味は、「無駄な力を抜いて下さい」ということなんです。「無駄な」という言葉を省略して「力を抜いて下さい」と言っているだけなんです。当然、「必要な力」は抜いてはいけないのです。でも、全部抜いたり、全部入れたりするのは簡単なんですが、「必要な力」は入れて「必要ではない力」は入れないようにすることが出来るようになるためには、自分のからだの状態を感じることが出来るようになる必要があります。自分のからだの状態を感じることが出来ないとこういうことは出来ないのです。だから「緩める」ということが難しいのです。ちなみに全部力が抜けている状態は「弛緩」という状態です。弛緩してしまったら動けなくなります。鬱病の人は全身の筋肉が弛緩してしまいからだに力が入らなくなります。表情筋も弛緩してしまうので無表情になります。ただし、近くに他の人がいる場合は、その状態を人に悟られないために不自然に明るい表情を作ったりすることもあるようです。そのような場合でも、一人になると無表情に戻ります。(町で時々こういう状態の人を見かけます。)でも、こういう状態を「緩んでいる」とは言わないのです。それに対して、子どものからだはエネルギーに満ちています。表情筋も生き生きとしています。からだも自在に動きます。(ちゃだし、ゲームばかりしている子は別です。)そして、これが「緩んでいる」という状態なんです。それはただ単に「力が抜けている」という状態ではなく、力が一カ所に滞らず、つながり合い、循環している状態です。昔、太極拳を習っていたとき、「馬歩」(マーブー)という空気椅子のような中腰で立つ練習をよくさせられました。中腰で立っているわけですから当然足には力が入っていますよね。足の力を抜いたら倒れてしまいますから。それなのに「もっと力を抜け」と言われるのです。中腰で立っていると足がきついですからそれを我慢しようとします。そして我慢しようとすると上半身も固まります。背中も肩も首も固まります。立つのに必要な足以外の部分まで固まってしまうのです。それで「もっと力を抜け」、「頑張るな」、「笑え」と言われました。そこまでは分かります、でも、立っている足の力までも抜けというのです。これが分からなかったです。「頑張るな」と言われたから「止めてもいいのかな」と思って立ち上がって「止めるな」と叱られたこともあります。中腰で立ったままの状態で足の力を抜き、さらに頑張ってもいけないのです。当時の私にとってはこれは意味不明な世界でした。システマの練習でも「重いものを軽く持つ」というものがあります。普通、重いものを持つときには肩に力を入れて肩を固めます。すると肩だけに重さがかかります。さらに、肩が固まれば背中や足腰も固まります。そういう状態で動こうとすると肩や腰に負担がかかりすぎて時には壊れます。それを止めるのです。肩だけに重さを負わせるのではなく、からだ全体で重さを引き受けてあげるのです。すると重さがからだ全体に分散されるため、そのもの自体の重さは変わらなくても軽く持てるようになるのです。肩への負担も減ります。(そのためには骨格を変える必要があります。)実はこれは子育てでも同じなんです。「子育てを頑張らないで」という言葉の意味は、「子育てを止めてもいいですよ」とか「育児放棄していいよ」と言うことではありませんよね。「子育てを頑張らないで」という言葉の意味は、「もっと子育てを楽しんで下さい」とか「もっと子育てを楽しむ工夫をして下さい」ということなんです。重さをからだ全体で味わうようにすれば肩の無駄な力は抜けるのです。それが力を抜くと言うことであり、緩めるということなんです。子育てで言えば「自分一人で頑張らない」ということです。子育てを子どもと一緒に、夫婦で一緒に、仲間と一緒にやるようにすれば無駄な力が抜けて緩むのです。ただ力を入れて頑張るだけでは自他の対立が起きるだけです。するとバトルが起きます。 かといって力を抜くだけでは相手の力に押し流されてしまいます。そうではなく、一度相手を受け入れてしまうのです。ただし、「子どもを受け入れる」と言うことは、子どもの言いなりになることでも、支配されることでもありません。ちゃんとからだ全体で受け止めてあげるということです。それは、お母さんと子どもの関係を変えるということです。またからだの話に戻りますが、自分のからだを緩めるためには、自分のからだを自分の意識でチェックして、固くなっている所があったら呼吸と意識の働きを使って柔らかくしてあげて下さい。その部分を感じ、温かい気持ちを送りながらゆっくりと動かしてあげると柔らかくなります。冷たく感じる所があったら温かい気持ちと呼吸を送って温めてあげて下さい。ただ単純に力を抜くのではなく、力を入れたままの状態で筋肉を柔らかくするのです。筋肉を固めて動くのではなく、筋肉を柔らかくした状態のままで動くのです。すると力が分散するのです。それが「緩める」ということです。今の所の私の理解では、と言うことですけど。
2022.10.01
コメント(0)
全31件 (31件中 1-31件目)
1