2023年01月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-

「子育てを楽に、楽しくする方法」(絵本の力-読む力より聴く力を育てる)
「クシュラの奇跡」という本があります。これは「クシュラ」という、重度の障害を持って生まれてきた女の子が、絵本の力によって、奇跡的な成長を遂げたという実話です。少し長いですが、「BOOKWAVE」というサイトからそんの紹介分を引用させて頂きます。もし、自分の子どもが重度の病気を抱えて生まれてきてしまったら、生まれてすぐに長生きできないと宣告されたら、あなたはどうするだろう。ニュージーランドに住む、クシュラに起きた奇跡をご存知だろうか?重度の病気を抱えて生まれてきた彼女は、1歳を迎えることさえ難しいと医師に診断された。そんな絶望の中にあっても彼女の両親は諦めず、愛情を持って接し、最適な治療法を探し続けた。そして母親が見つけだした方法は、「絵本の読み聞かせ」だった。絵本によって、クシュラの成長に変化が現れたのである。この、ニュージランドで本当に起こったクシュラの奇跡は、読み聞かせの効能といった話に終始せず、親が子どもに接する際に大切なことを教えてくれる。絵本との出会い1971年12月18日、ニュージーランドにてクシュラは生を受けた。他の親と同様、母親であるパトリシアと父親のスティーブンは彼女の生誕を心から喜んだが、生まれた直後から黄疸や痙攣といった様々な病状がクシュラを襲った。また、筋肉麻痺の症状も持っていたため、体を自由に動かすことも困難だった。関節も異常に柔らかく物を握ることもできなかったという。そして、一番の問題はクシュラの視覚と聴覚がほとんど機能していない、ということだった。それはつまり、目や耳からの外的刺激による知能の発達が難しい、ということを意味している。クシュラを苦しませるあらゆる症状の原因を探るため、検査を繰り返し受け続けた。その結果、クシュラは染色体異常を持って生まれたことが明らかになった。的確な治療法が見つからず、絶望的な状況ではあったが、クシュラの両親はそれでも諦めなかった。外的刺激を与えるため、おもちゃをクシュラの口元に触れさせたり、たくさん話しかけたりといったことを実践した。また、クシュラが眠りにつくとき以外はずっと抱きかかえ続けた。そういった努力を続けても、生後6ヶ月の乳幼児並の成長をするまでに、クシュラは17ヶ月をも費やしたそうだ。そんな中で、クシュラが最も反応を示したものが、絵本だった。絵本を顔に近づけて、かすかながらに何かを発見するとクシュラは微笑んだという。クシュラに起きた奇跡生後4ヶ月目にして、クシュラが絵本に反応を示すことを知った両親は毎日絵本を読み聞かせた。長いときには1日10時間も読み聞かせを実践したそうだ。クシュラはこの両親の絶え間ない努力によって、3歳9ヶ月までになんと、140冊もの絵本に出会うこととなる。この膨大な読み聞かせの体験が、クシュラに奇跡を起こした。知能の成長が不可能であると診断されたクシュラは、3歳8ヶ月の検査において標準以上の知能を持っていることがわかったのだ。知能の劇的な発達とともに、根気強い治療によって筋力も強くなり、不安点ながらも以前より体にも自由が効くようになった。絵本の文章を丸暗記したり、絵柄から感情を読み取ったりといった経験がクシュラの脳に外的刺激を与え、奇跡的な成長を促す結果となったのだ。「子どもは体験によって育つ」というのは誰でも知っていることだと思います。どんなに知識を溜め込んでもそれは「成長」とは異なります。コンピューターに百科事典を全部記録しても、そのコンピュータが成長するわけでも、賢くなるわけもはありません。「賢い」というのは、学んだことを自分の思考や感覚や行動とつなげて実際に使いこなせることです。そしてそのためには「体験と共に学ぶ」ことが必要なのです。そうでないと、「知識」と「現実」がつながらないからです。だとすると、クシュラはその「成長に必要なもの」を学ぶことが出来ない状態で生まれてきたことになります。完全に見えない、聞こえないということではないにしろ、聴力も視力も非常に低くさらには筋肉麻痺の状態なので、動くことも出来ないのですから。では、そんなクシュラがどうして普通の子に追いつくことが出来るほどに成長することが出来たのか、ということです。そこに「絵本と声の持つ力」があるのです。このクシュラの奇跡の話を通して「絵本の素晴らしさ」を語る人は多いですが、絵本をDVDで見せてもクシュラには働きかけなかったと思います。絵本がクシュラの心とからだに働きかけるためには、「クシュラに語りかける声」が必要だからです。それは「DVDから勝手に流れてくる声」、ではなく直接クシュラに向けられた声です。絵本には絵が描かれています。ですから、私たちは絵を見れば言葉の意味も理解出来ると思ってしまいます。でもそれは絵本以外の世界で色々な体験をしている人間の発想です。怒っている顔が描いてあって、「○○君は怒りました」と書いてあれば、普通はそのまま分かります。でもそれは、絵本以外の場で「怒った顔」を見て、「怒っている」という言葉を聞いているから分かるのです。クシュラのように生活の場での体験がない場合は、「怒っている顔」の絵を見て、「怒っている」という言葉を聞いても、それが何なのか分からないのです。その時、「声」がその補助をしてくれるのです。人は「気持ちがいいね」という言葉を発する時には「気持ちがいいからだ」になっています。そして、「気持ちがいいからだ」の人から出た「気持ちいいね」という言葉を聞くと、その言葉を聞いた人のからだも緩むのです。「声」には「感覚と感覚」、「感情と感情」、「からだとからだ」を共鳴させる働きがあるからです。逆に、「怒っているからだ」「緊張しているからだ」の人が「気持ちいいね」と言っても、その言葉を聞いた人のからだは緩みません。むしろ、緊張してしまいます。だからこそ、「語りかける声」で「文字」以上のリアルなメッセージが伝わるのです。確かにDVDも声は出ます。でも、その声は「スピーカーから流れるだけの音」であって、「子どもに向けられたもの」ではありません。だから、子どもの感覚にも、感情にも、からだにも届かないのです。子どもは自分に向けて発せられた声だけ「言葉」として聞いて、自分に向けられていない声は単なる「音」として処理してしまうのです。幼い子どもに一日中テレビを見せていれば「音としての言葉」は覚えますが、「自分の思考や、感覚や、心や、からだとつながった自分の言葉」を学ぶことが出来ないのです。これは基本的に大人でも同じです。だから大勢の人が話している人混みの中でも、他の人の声に惑わされずに会話することが出来るのです。ただ、大人は、「聞こう」と意識することでその「音」を「言葉」に変換して聞き取ることが出来るだけです。でも、子どもにはこの能力はありません。「絵本の力」は「子どもに向けて語りかける声」とセットになって表れるのです。DVDで見せてもダメなんです。クシュラは、生まれつきの障害によって障害によって、実際に見たり、体験したり、多くの人と出会うことが出来なかったのですが、このコロナ騒動の中で育っている子どもたちもまた、実際に見たり、体験したり、多くの人と出会う機会を奪われてしまっています。だからこそ、絵本をいっぱい読んであげて欲しいのです。問題は、幼い頃からスマホやゲーム機を与えられている子は、絵本を読んでもらうことを喜ばなくなってしまうことです。小さい時から文字を教えられてきた子は、読んでもらうより自分で読むことを選びます。「文字を読む力」は育っても「聴く力」が育っていないからです。確かに、自分で読んでも意味は分かるかも知れません。でも、「文字では書き表すことが出来ない大切なこと」が伝わらなくなってしまうのです。子どもの心の成長に必要なのは「読む力」よりも「聴く力」なんです。今、それが育っていない子が多いのです。クシュラの奇跡普及版 140冊の絵本との日々 [ ドロシー・バトラー ]
2023.01.31
コメント(3)
-
「子育てを楽に、楽しくする方法」(感覚と感情と体験の共有と言葉の育ち)
子育てが楽になるためには、子どもの心が成長する必要があります。心が成長すれば、子どもは自分で感じ、自分で考え、自分の判断と意思で行動出来るようになるので、成長と共にお母さんから離れて活動することが出来るようになるからです。逆に、心の成長が遅れてしまった子はいつまでもお母さんや、物や、他の人からの評価に依存するようになります。「イイネ」が欲しくて、平気で他の人に迷惑をかけるようなことをやってしまう人は「心の育ち」が遅れてしまった人です。その「心の育ち」に必要になるのは、お勉強でも、仕付けでも、習い事でもなく「言葉の学び」です。なぜなら、人間の「心」は「言葉」で出来ているからです。ですから、その人が使っている言葉を調べれば、その人の心の中が分かります。だからといって、お勉強という形では言葉を育てることが出来ません。言葉は「伝えるもの」であって「教えるもの」ではないからです。じゃあどうしたらいいのかというと、「子どもと一緒の時間」を楽しむようにすればいいのです。感覚や、感情や、考えや、行動を共有するようにすると、必然的に「言葉」が必要になるので、子どもは体験を通して言葉を学ぶことが出来るのです。トランプをして楽しもうとすれば、トランプについてのあれこれを説明する所から始まり、遊んでいる時にも「言葉」が必要になりますよね。折り紙やあやとりで遊ぶ時にも「言葉」は必要ですよね。粘土や水で遊ぶ時にも「言葉」は必要ですよね。でも最近、色々なお母さんの話を聞いていると、「子どもと一緒の時間」を楽しめないお母さんが多いようです。一緒にいても「何を話したらいいのか」、「何をしたらいいのか」が分からないと言うお母さんも多いです。そういうお母さんには「自分が昔やった遊びを想い出して子どもと一緒に楽しめばいいんですよ」と伝えています。問題は、最近「子どもと一緒にいたくない」とか、「子どもと関わるよりも自分の時間が欲しい」と考えるお母さんが増えて来たことです。そういうお母さんに、「自分が昔やった遊びを想い出して」と言っても、「覚えていない」と言う人が多いのです。そういう人は、子どもの頃に「一緒に遊ぶ楽しさ」を体験してこなかったのでしょう。そういうお母さんだけでなく、現代人は、なぜかみんな「自分のこと」で忙しいのです。でも、そういう考えが「子育て」を余計に辛く苦しいものにしてしまっているのです。イライラするから関わりたくない=>子どもは欲求不満になり、余計にお母さんがイライラするような行動を始めるそういう構図になってしまうからです。子どもが幼ければ幼い時ほど、その心の成長にはお母さんとの関わりが絶対的に必要になります。そのため、お母さんが積極的に関わろうとしないと、子どもは心の育ちに遅れが出てしまうのです。その結果、いつまで経っても幼児的な問題行動が消えなくなってしまうのです。「遊び」としてイジメをする。「遊び」として万引きをする。「遊び」として周囲の人が困るようなことをする。そして、それを「遊び」として動画に撮ってSNSにアップして、「イイネ」を貰おうとする子も、そして、大人も増えて来ています。「自分が犯罪を犯しているところを動画で撮って、自分で拡散して楽しんでいる」なんて感覚、私にはとうてい理解出来ません。そういう子に説教しても、そもそも言葉が通じないのでこちらの言っていることが伝わりません。「他の人が困るから」と言っても、「他の人が困る」という言葉の意味が通じないのです。以前、友人の家に出入りしている高校生が勝手に他の子の自転車を乗って行ってしまったそうです。それで、自転車の持ち主が困ってしまって友人に相談しました。で友人が、自転車に乗っていってしまった子に「○○くんが困っていたよ」と伝えたら、「僕だって困っていたんだからしょうがないでしょ」と言い返されたそうです。友人は絶句してしまって、それ以上言えなかったそうです。こういう子は言葉が育っていないのです。言葉が育っていない子は、他の人の気持ちを理解することが困難になってしまうのです。昔のお母さんは子どもに「お手伝い」を求めました。そしてその過程で言葉を伝えました。でも、簡単で便利な機械に恵まれている最近のお母さんは「お手伝い」を必要としていません。それどころか、手伝わせたら余計に手間と時間がかかってしまいます。で結局、家事は自分一人で行い、子どもは子どもだけで遊ばせようとします。その方が効率的だし、ちゃんとお手伝いが出来ない子どもにイライラすることもありません。そして、少しでも手早く家事を終わらせて自分の時間を楽しもうとします。でもその結果、子どもは「言葉」を学べなくなりました。ある小児科の先生の本の中に書いてあったのですが、最近言葉の発達が遅れている子どもが増えて来たそうです。で、「言葉が遅い」ということで相談に来たお母さんに「話しかけはちゃんとやっていますか?」と聞いたところ、「言葉が分からない赤ちゃんに話しかけて、何の意味があるんですか?」という答えが返ってきたので驚いたそうです。色々な所で似たような話を聞きます。最近、子どもとの関わり合い全般に関してそういう自分中心的な感覚のお母さんが増えて来たような気がします。自分中心的だからと言ってワガママなのではありません。イジワルでもありません。ただ単純に「相手の気持ち」が分からないのです。子どもの立場に立って、感じ考えるということが苦手なんです。だから平気で子どもが傷つくようなことを言ったり、やったりしてしまうのです。絵本なども、「まだ意味が理解出来ないから」と読んでいないお母さんも多いですが、でも、意味が理解出来るようになってから読んだのでは遅いのです。言葉を「意味を伝える道具」として使っているのは大人だけです。子どもにとって「言葉」は感覚や感情や体験を共有するためのものなんです。美味しいものを食べている赤ちゃんに、笑顔と共に「美味しいね」と話しかけることで、赤ちゃんとお母さんとの間に感覚と感情の共有が生まれるのです。赤ちゃんは、その「共有されたもの」を表すものとして「美味しい」という言葉を学んでいくのです。「言葉」を育てるためには「感覚と感情と体験の共有」が必要なんです。そしてそれが、「一緒の時間を楽しむ」ということなんです。そういう楽しい事をいっぱい積み上げることで子どもの言葉も心も育っていくのです。その結果、子育てがどんどん楽になっていくのです。
2023.01.30
コメント(0)
-
子育てを楽に、楽しくする方法」(男の子と女の子の違いを理解する)
現代社会では「男性」と「女性」の違いを認めません。少なくとも公的にはそういうことになっています。それは、「男性と女性の間には違いはない、だから扱いも同じにすべきだ」ということなんでしょうが、それは政治や観念の世界の中での話であって、私たちが生きている現実の世界の話ではありません。そこを勘違いしていると、子育てが困難になります。平等にすべきなのは「扱い方」ではなく、一人一人の「らしさへの対応」なんです。それは、からだが大きな子には、「からだに合った大きな服」を与え、小さな子には「からだに合った小さな服」を与えると言うようなことです。また中には、からだは小さくても「ぼくは大きい服が欲しい」と言う子もいるかも知れませんが、それもまた「らしさ」です。それを、「平等にしなければいけないから」と全員に「平均サイズの洋服」を与えたら、平均サイズの子以外の子はみんな困るのです。それは「与える側の平等」であって、「受け取る側の平等」ではないからです。それは「価値観の押しつけ」に過ぎないのです。このことに気付けば、ジェンダーの問題だけでなく、人種や肌の色による差別や、自然保護の問題や、発達障害の子の問題もみんな、一つの基準だけで解決してしまうのです。でも、それが分かっていないから、分野ごとに別々の基準が必要になってしまうのです。問題は、現代社会を維持しているシステム自体が、一人一人の「らしさ」を否定する事で成り立っているということです。一人一人の「らしさ」を否定し、「人間」や「命あるもの」を数字として扱うことで社会の近代化が成功したのですからそれは当然の事です。コロナ対策でも、国が相手にしているのは数字であって、私たち一人一人の命や、心や、からだではありません。皆さんの子どもの成長への影響なんて全く考えていません。でもそれでは不満が出てしまいますから、その問題を解決するために「選択の自由」を与えています。色々なサイズの服を作っておいて、自分の「らしさ」に合わせて自分で選ばせるのです。経済界はその「選択の自由」をうまく使って、一人一人が自分の好みに合ったものを得ることが出来るようになっています。でも、経済界はそういうことが出来ますが政治の世界はそういうことが出来ません。そして、一律に平等を決め、平等を押しつけてきます。でもそれは、「女性も男性と同じように」という「男性を基準とした平等」であって、「男性も女性と同じように」という平等ではありません。私は、女性の多くは「男性と同じようにして欲しい」とは思っていないと思います。実際、「男性にあこがれている女性」には会ったことがありません。中にはそういう人もいるとは思いますが、少数だと思います。これは、私の思い込みかも知れませんが、私には女性の多くが望んでいるのは、「男性化」でも、「男性と同じ扱い」でもなく、ただ「自分らしさ」を肯定してもらうことと「自分らしく生きること」のように思えるのです。そしてこれは子どもも同じです。男性は競争が好きです。そして、競争は数字の戦いです。人間を数字化せず個々の「らしさ」を認めていたら競争は出来ないのです。でもだから、社会の近代化や、文明や、大きな国家を維持するためには男性原理が必要になるのです。実際、一人一人の「らしさ」を肯定していたら、「子どもたち全員を椅子に座らせ、全員に同じことを教える」というやり方が出来なくなってしまいます。でもその男性原理では子育ても、子どもの育ちを支えることも来ないのです。そこが分かっていないから子育てや教育がおかしな事になってしまうのです。発達障害と呼ばれる子や、学校に行かない子が大量に生まれてしまうのです。性別も、「らしさ」も一人一人異なる子どもたちを一律に同じように扱おうとしているから、子どもも、お母さんも、そして先生も苦しくなってしまうのです。そのそも、平等の基準を作り出しているのは観念論が大好きな男性ですからね。だから男女平等が「男性も女性と同じように」ではなく、「女性も男性と同じように」という話になってしまっているのです。最初から、男性は変わる気が無いのです。だから、「女性の社会進出を助けよう」という議論はあっても、「男性を家庭に戻そう」という議論がないのです。だから子育てがおかしくなってしまっているのです。お母さん達が苦しんでいるのです。教育の世界で、子どもに平等を与えようとするならば「自分が受ける教育に対して選択の自由」を与えるべきなんです。一つのやり方しか与えていないのに教育の平等を言うのはおかしいのです。それは子どもに対するイジメと同じです。からだの大きな子にも標準的な大きさの服を与え、「ちゃんと着れない子はダメな子なんだぞ」と脅しているようなものです。そして、お母さん達も我が子に対して同じことをしています。自分の子と他の子を比較しています。兄弟を比較しています。そして、子どもの子どもらしさを否定し、自分の価値観に合わない行動を否定しています。その時問題になるのが、多くの場合、お母さんには男の子の感覚や感情や行動が理解出来ないということです。そのため、男の子の「男の子としては普通の行動」を問題行動、異常な行動として感じてしまい、否定し、叱り、直させようとしているお母さんが非常に多いのです。でも、「女の子の育ちに必要なもの」と「男の子の育ちに必要なもの」は違うのです。実際、「男の子」も「女の子」も両方育てたお母さんは、みんな「男の子と女の子は別の生き物だ」と言います。基本的に男の子はチャレンジャーです。危ないことでもやりたがります。戦いや競争が好きです。(憂鬱質の子は例外です)森や林の中で木の枝を見つければ拾います。男の子は「棒」が大好きなんです。石を見つければ拾います。そして投げます。時にはいっぱい集めます。刃物や電車のような「機械もの」が大好きです。固くて、大きくて、強いものが好きです。高いところも大好きです。ジーッとしているのは苦手です。反抗的です。また、群れたがります。大勢で群れて遊ぶのが好きなんです。(憂鬱質の子は例外です)お母さんには理解出来ないこと、困ったことでも「男の子とはそういう生き物」なんですから、しょうが無いのです。ただし、これらは「一般的な傾向としては」ということであって、実際には一人一人違いますからね。気質の影響も大きいです。女の子でも胆汁質が強い子の行動は男の子に似ています。棒を振り回している女の子もいます。男の子でも憂鬱質が強い子の行動は女の子に似ています。大事なのは「男の子らしく」でも、「女の子らしく」でも、「男の子も女の子も同じ」でもなく、「○○ちゃんらしく感じ、考え、行動すること」を肯定してあげることなんです。だから、子どものことを学んだり観察したりして、我が子の「らしさ」を見極める必要があるのです。
2023.01.29
コメント(0)
-
「子育てを楽に、楽しくする方法」(今を楽しむ)
多くのお母さんが、小学校に入って困らないように、幼稚園の頃から文字を教えたり、色々な勉強を教えたりしています。そんなお母さん達の気持ちに応えるように、文字を教えたり、色々な勉強を教えたりする幼稚園もいっぱいあります。そういう幼稚園では「ちゃんとお椅子に座る」、「ちゃんとみんなと一緒に行動する」「ちゃんと先生の指示に従う」ということも教えています。実際には教えると言うよりも訓練なんですが、アメとムチの原理を使ってペットの調教と同じようなことをやっているわけです。また、最近は「仕付け」も幼稚園に依存しようとするお母さんも多いみたいです。そのため、「自分」を主張しようとする子どもは「療育」を勧められたりします。また、先生に差別的な扱いを受けたりします。お母さんもしょっちゅう先生から指導されます。でも、そのような訓練によって集団生活が出来るようになった子は、「自分の感覚と、思考と、判断で動く能力」が育たなくなってしまうので、いわゆる「指示待ち人間」になってしまうのです。そして今、そういう子がいっぱいいます。そういう子は大人の指示があると動けるのですが、指示が無い自由な状態に置かれると急に烏合の衆になってしまうのです。そして、自分の感情や欲求だけで行動し始めます。どうでもいいようなことでケンカやイジメが始まったりもします。助け合うということも、一緒に遊ぶということも出来ません。説明しても理解出来ません。以前、そのような指導をしている保育園に呼ばれて3年ほど遊びと造形の指導をしたことがあるのですが、なかなかでしたよ。私は子どもを自由にさせます。子どもの成長には自由が絶対的に必要だと思っているからです。指示や命令では動かしません。でもその園の子は、普段先生の指示に従って動いているだけなので、自由にさせるとただ混乱し、大騒ぎを始めるのです。ある時はケンカが始まって、一人の子が他の子上の乗って相手の首を絞めていました。「輪になって」と言っても意味が通じません。意味が通じる子は私の隣争いを始めます。それなりに人気があったので・・・。で、いつまでも輪が作れません。その時、その園の副園長から「先生が甘やかすからいけないんです」と言われました。子どもたちがお散歩から帰ってきた時、付き添っていた先生達が疲れ切って笑顔がありませんでした。ちなみに園長先生はもと中学校の先生で、お父さんの後を継いで保育園の園長になったそうです。そのせいかどうか、その先生は幼児教育の基本も、「子どもとはどういう生き物なのか」ということも分かっていませんでした。そして、「ちゃんと管理すればうまく行く」と思い込んでいるようでした。で、ある時本当にぞっとした出来事がありました。いつものように子どもが大騒ぎしていると、副園長先生がいきなりピアノを弾き始めたのです。それは、子どもたち達が整列して歩く時にいつも演奏する曲のようでした。すると、それまで大騒ぎしていた子どもたちが急に整列してちゃんと歩き出したのです。あまりの変化にビックリ仰天です。副園長先生としては、「ほら、ちゃんとやれば子どもはちゃんと出来るのです」ということを見せたかったのでしょう。結局、何を言っても園長先生と意見が合わなくて止めてしまいましたが、あの子達の将来が心配です。うちの近所の幼稚園でも、色々なことをやらせているようです。あるお母さんからは「秒単位で子どもを管理している」とか、「器楽演奏会の時にはちゃんと吹けない子の笛の穴にセロテープを貼って音が出ないようにしている」とかいう話も聞いたことがあります。先生達は、うまく調教された子どもたちを見て自己満足するのでしょう。また、お母さん達も上手にみんなに合わせることが出来ている我が子を見て安心するのでしょうね。昔、その園に行っている子が一人だけうちの教室に来ていましたが、ストレスでガチガチでした。幼稚園に入って困らないように、小学校に入って困らないように、中学校に入って困らないように、と先回りして色々やってあげる、また、色々と子どもにやらせるお母さんは多いですが、子どもの人生はそこで終わりではありませんからね。「いい成績を取って、いい大学に入ったら人生終わり」ではないですからね。むしろ、子どもの人生はそこから始まるのですからね。その時、自分の感覚で感じ、自分の頭で考え、自分の意思で行動出来ない子は、精神的に自立できなくなってしまい苦しむことになるでしょう。そして子どもの苦しみは様々な問題行動となって、お母さんやお父さんを苦しめることになるでしょう。そして困ったことに、この苦しみは終わりがありません。成長を急がせようとすると、皮肉なことに、逆に成長が遅れてしまうのです。子育てでは、「今子どもの育ちに必要なこと」は後回しにしない方がいいですよ。その時はちょっと大変でも、そういう努力をすることで年齢相応に子どもが育ちます。そして、年齢相応に成長することで、結果として子育てが楽になっていくのです。ただし、「今、我が子に何が必要なのか」は、子どものことをよく学び、子どもをよく観察していないと分かりませんけどね。知らないから、そして、ちゃんと見ていないから不安になるのです。だから色々余計なことを考え、余計なことをやってしまい、却って子どもの成長を阻害してしまうのです。そして、「苦しい子育て」が始まるのです。
2023.01.28
コメント(0)
-

「子育てを楽に、楽しくする方法」(家に子どもの友達を呼ぶ)
あと、子育てを楽に楽しくする方法法として、「子どもの友達を呼んじゃう」というのがあります。子育てをしている子どもにまとわりつかれて、家事や自分のことが出来なくなることが多いですよね。でも、家に子どもの友達を呼んじゃうと、子どもがお母さんにまとわりつかなくなるのです。お母さんは安全を見守り、時々おやつを出しているだけで、子どもは子どもだけで遊びます。そうなればお母さんも楽だし、子どもは楽しいし、また他の子との関わり合いを通して子どもたちも成長します。ちなみに「我が子の成長」を望むなら、「我が子の友達の成長」も手伝けしてあげた方がいいですよ。お母さんがいくら頑張って「我が子」を成長させようとしても、子どもはお母さんよりも友達の影響の方を強く受けるのですから。だから友達もひっくるめて成長出来るような場を作ってあげないと、努力が無駄になってしまうのです。でもそれをしておくと後が楽なんです。子どもが成長するにつれどんどん楽になりますから。ただ、気をつける点もあります。それは、お母さんと価値観が近い家の子ならいいのですが、そうでないと色々なトラブルが起きる可能性があるからです。現代社会では価値観の多様化が起きています。そのため、どういう遊び方をさせたいのか、どういうお菓子ならいいのか、どういうオモチャならいいのか、ケンカが起きた時はどうするか、ケガをした時にはどうするか、などというようなことが共通している家の子でないと子どもを預かってもトラブルに発生する可能性が高いのです。だからこそ、昨日書いたように、お母さんが自分の価値観を大切に生きる必要があるのです。お母さんが自分の価値観を大切にして生きていれば、自然と同じ価値観の仲間が集まります。自然が大好きなら周囲にもそのことを発信し、子どもを出来るだけ自然の中で遊ばせるようにしていると、自然と仲間が集まってくるのです。他の価値観でも同じですが、自分と同じ価値観の仲間を探している人は結構いるのです。でもみんな自分からは動けないだけなんです。だから、自分の意思表示をして動いている人を見つけると集まって来るのです。私は自然の中で子どもを遊ばせることを大切にしていました。だから、子どもの友達もその家族も誘いました。すると、その家族も別の家族を誘いました。そうやって子どもの群れと大人の群れを作ってきました。また、長男の友達はゲームが大好きでした。家にはゲームがなかったので、長男はいつもその子の家に行ってゲームをしていました。でも、うちが家族で自然の中に遊びに行く時はその子も誘いました。その子が一緒だとうちの子も喜びました。その子の家はお母さんがシングルで仕事が忙しかったので、子どもだけ預かって遊びに行きました。それは小学生の頃なんですが、長男はその友達を結婚式にも呼びました。大切な仲間になったのでしょうね。また、長男以外の子どもたちも、よく友達を連れてきていました。最初はテレビを付けようとしたり、「ゲームはないの?」と聞いてきたりもしましたが、「テレビは見ない、ゲームはない、でも、自由に工作していいよ」と工作させたら、「しのんちに行くと工作が出来る」と遊びに来てくれました。このブログを読んで下さっている人の中にも、自宅を子どもの遊び場として開放している人がいます。是非皆さんもどうですか?うちの子と友人の家の子が我が家に集まって、勝手に劇遊びをしていました。生誕劇のようです。そして大人を招待してくれました。このうちの二人はもう結婚しています。
2023.01.27
コメント(2)
-
「子育てを楽に、楽しくする方法」(仲間作りの方法)
最近の子どもたちには「仲間」がいません。それは「仲間作りが出来るような場」がないからです。「ない」というよりも「大人が奪ってしまった」と言う方が正しいのですが、とにかく最近の子には「仲間作り出来る場」がないのです。ちなみに「友達」と「仲間」は違いますからね。「仲間」はいなくても「友達」を持っている子はいっぱいいます。じゃあ、「友達」と「仲間」はどう違うのかというと、「友達」とは、おしゃべりをしたり、遊んだりして「一緒に楽しい時間を過ごすことが出来る相手」のことです。ですから「友達」のような関係の親子もいます。それに対して「仲間」とは「目的を共有している相手」のことです。ですから、「仲間」の間では「支え合い」とか「励まし合い」ということも起きます。また、1回も会ったり話したことがなくても「あいつは仲間だ」と感じることもあります。私にとっては、「子どものために」と活動している人は、会ったことがなくてもみんな仲間です。一緒に活動していなくても目的を共有しているのなら「仲間」なんです。でも、会ったことも、話したこともなければ友達ではありません。実際には、「友達」と「仲間」の境界は曖昧です。でも、ただ単に、おしゃべりをして一緒に楽しい時間を過ごしているだけでは「仲間」とは言わないのです。そして、最近の子には仲間がいません。昔の子どもたちは、目的を共有して自由に遊ぶことで仲間作りをしていたのですが、その「自由な遊びの場」が消えてしまったからです。ただ、みんながゲームをしているので楽しく情報交換をする事はできます。今時の子は、「目的」ではなく「情報」を共有することで友達を作っているのです。そして「情報」を共有していれば「仲間」だと思っています。でも、この関係では支え合いも助け合いも発生しません。ゲームを止めれば簡単に消えてしまう関係です。また、ちょっとこじれればイジメにも発展する可能性もあります。そして、お母さん達にも「仲間」がいません。「ママ友」のような「楽しくおしゃべりをしたり、情報交換をしたりするような友達」はいても、「支え合い、助け合うことが出来るような仲間」がいないのです。そして、ママ友関係でも、ちょっとこじれただけでイジメが始まることがあります。支え合い、助け合う関係が出来ていないからです。だから子育てが苦しくなってしまうのです。じゃあどうしたらいいのかと言うことですが、ここで問われるのが、お母さんの「一人の人間としての生き方」なんです。ただ「みんなに合わせるだけ」、「子どもに合わせるだけ」、「他の人から褒められるような良い子、お母さんの言うことをちゃんと聞いてくれるような良い子を育てること」だけが目的のような子育てをしている限り仲間は出来ないのです。目的の共有が出来ないからです。だから子育てが苦しくなってしまうのです。でも、お母さんが「自分の価値観や、生き方や、大切にしていること」を自覚し、その方向で学んだり活動をするようにすれば、自然と仲間が集まるのです。子どもの要求に合わせて子育てをするのではなく、自分の生き方に合わせて子どもを育てるのです。山登りが好きなら、子どもが公園に行きたいと言っても、ゲームをやりたいと言っても、山に連れ出せばいいのです。お料理が好きなら、一緒にお料理すればいいのです。映画が好きなら、子どもと一緒に映画作りをして遊ぶことも出来ます。映画を作るのに、昔は高価な機材が必要でしたが、今ではスマホで簡単に作れるのですから。旅行が好きなら、子どもと一緒に「ご近所旅行」をして遊ぶことも出来ます。大人の趣味でも、工夫次第で子どもと一緒に遊ぶことは出来るのです。そして、成長と共に子どもは大人と一緒の活動が出来るようになるでしょう。最初は嫌がっていても、その活動を通して仲間が出来れば、子どもは嫌がらなくなるのです。「子どものために犠牲になる」という考え方は止めた方がいいですよ。仲間作りも出来ないし、親子の関係も築けませんから。***************4月から茅ヶ崎で、月一で一年継続する、「気質の講座」(土曜か日曜)と「ゆりかご」(第四金曜)という子育て講座が始まります。「からだの会」(月一、月曜)というのもやっています。いずれも参加費は2000円です。それと、まだ先の話ですが、4月22日(土)に、「気質の一日講座」をします。10:00~16:00です。講義と簡単なワークをします。 こちらの参加費は5000円です。ご興味のある方は「シノ」までお問い合わせ下さい。
2023.01.26
コメント(0)
-
「子育てを楽に、楽しくする方法」(お母さんの仲間作り)
子育ては絶対に一人では出来ません。保育園や幼稚園の先生で子どもの扱いには慣れている人でも、一人では子育て出来ません。どんなに偉い子育ての専門家でも一人では子育てできません。そしてまた、一人でやろうとしてもいけません。なぜならば、人間は社会的な動物だからです。人は社会とつながっていないと人間らしく生きて行くことも、人間らしさを学ぶことも出来ない生き物なんです。「個育て」では、からだは育てることが出来ても、感覚と、意識と、心と、人間らしさを育てることが出来ないのです。具体的に言うと、まず、人とつながっていないと「言葉」を学ぶことが出来ません。お母さんが教えようとしてもお母さんが教えることが出来るのは生活の場で必要になる言葉だけです。「ルールを守る」という時の「ルール」の意味も、「挨拶」という言葉の意味も使い方も教えることが出来ません。いくら丁寧に言葉で説明しても無駄です。子どもはオウムのようにお母さんの言葉を知識として覚えることはしますが、その言葉を使うことは出来ません。自分自身の体験を通して学んだ言葉ではないからです。例えば、ほとんどの子が「イジメは良くない」ということを知識としては知っています。実際に、他の子をいじめている子だってそんなことぐらい知っているのです。でも、知識として知っているだけで感覚的には分かっていないのです。だから、「今、自分がやっていることがイジメなんだ」ということに気付かないのです。学校での道徳教育はそういう状態の子を増やしているだけです。テレビやyoutubeをいっぱい見せれば、「知識としての言葉」を覚えることは出来るでしょうが、でも、自分の意識や、感覚や、心とつながった「自分の言葉」を学ぶことは出来ないのです。また、人と人の距離感、他の人と向き合った時の向き合い方、話し方、関わり方、人間関係を把握する能力も育ちません。家の外の世界では「自分と対等な他者」との関わり合いが求められます。でも、「お母さん」は子どもにとって永遠に「お母さん」です。お母さんは子どもにとって「自分と対等な他者」にはなり得ないのです。そのため、お母さんには家の外で必要になる「自分と対等な他者との関わり方」を教えようがないのです。実際、お母さん自身も、子どもが成長するにつれて自分では教えることが出来ない事の多さを感じるようになります。子どもの行動範囲が広がってお母さんでは教えようのないこととの出会いも増えるからです。それで、子どもが2,3才頃になると子どもの仲間を探そうとしています。仲間になれそうな子が集まっている所に子どもを連れて行こうともします。私の教室にもそういう問い合わせが来ます。そういうお母さんは「どういう子が参加しているか」「うちの子と同じくらいの年齢の子はいるか」「男の子と女の子の割合は」などと色々聞いてきます。でも、そういう意識のお母さんに限って自分には仲間がいません。そして、子どもの仲間を選ぼうとします。困った行動が多い子には近づかないように指示したりもします。そして、自分自身は仲間を作ろうとはしません。情報交換をする程度の知り合いは作りますが、色々なことを相談したり、助け合ったりするような仲間は作ろうとしません。何でもかんでも自分一人でやろうとして頑張っているのです。だからといって自分に自信があるわけではありません。私の印象では、他の人とのつながりを避けようとする人ほど、なぜか自分に自信がない人が多いのです。そのような人でも、「情報を交換し、軽くお付き合いする程度のお友達」は出来るかも知れませんが、「信頼し、支え合い、許し合える仲間」は出来ません。子育てを助け合い、支え合う仲間も出来ません。また、表面的なつながりしかできません。そのため、子どもがケンカしたら慌てて止めます。ケンカしそうな気配を感じただけで子どもを引き離そうとします。そうやって。子ども同士、親同士の「本音のやり取り」が必要になるような状況を避けようとするのです。でもそんなやり方をしていたら、子どもは仲間を作れないのです。表面的な付き合いの「お友達」は出来ても、「一緒に育ち合う仲間」が出来ないのです。だからこそ、「子どもの仲間作り」は「お母さんの仲間作り」とセットにしないとうまく行かないのです。子どもはお母さんがやっていることを模倣しながら育っているため、お母さんがそういう意識では、子どもも他の子と仲良くなれないのです。でも、お母さんが勇気を出して「エイヤー」と仲間作りを始めると、子どもを取り巻く人間関係が変わります。その結果、子どもも自然と仲間作りが出来るようになるのです。すると、子どもはいつの間にか自分の力で育つことが出来るようになります。そして、子育てが楽になります。
2023.01.25
コメント(0)
-
「子育てを楽に、楽しくする方法」(外に出よう、自然の中に行こう)
子育てが辛く、苦しくなる理由の一つに「狭い室内での子育て」「人工的に管理された環境での子育て」が大きく関係しています。本来、人間は自然と共に暮らす動物です。生命誕生以来、命あるものは皆自然の中で生まれ、自然の中で生活し、自然の中で死んで行きました。現代人は産まれてから死ぬまで、人生のほとんどの時間を人工的な環境の中で過ごしていますが、だからといって、何億年とかけて作られてきた人間の本質的な部分での「動物としての心とからだの仕組み」が変わったわけではありません。ただ、その高い適応能力によって一時的に適応しているだけです。それは、動物園の動物が動物園という「人工的に管理された環境」に適応して生きているのと同じです。でも、動物たちは「人工的に管理された環境」に適応することで、生命力や生きる能力が低下し、人間に依存しなければ、出産も、食べ物を得ることも、敵から身を守ることも出来なくなってしまいます。そして同じようなことが人間にも起きています。実際、自然分娩という「命をつなぐために必要な動物としては最も自然な活動」ですら困難な女性が増えて来ています。人間性や文化をつなぐための子育てが困難な女性も増えて来ています。「子どもが嫌い」とはっきりと言うお母さんも増えて来ています。いずれも、人類誕生以来何十万年と受け継がれてきた行為なんですが、それが急激に途絶え始めているのです。これは生き物としては異常事態なんですが、人間は、これも人工的な方法で解決しようとしています。でも、その行き着く先は不明です。いずれにしても「持続可能な方法」ではないことだけは確かです。いつかは破綻します。動物としての人間は、人工的な環境には違和感を感じていながらも、人工的な環境に依存しなければ生きて行くことが出来なくなってしまっているのです。でも、人工的な環境に適応し、人工的な環境に依存しなければ生きて行くことが出来なくなってしまっているのは大人だけです。子どもは何万年も前と同じ遺伝子を持ち、同じ心とからだの感性を持って生まれてきているので、幼いうちは、自然の中にいる時と同じように感じ、考え、行動するのです。だから、人工的な環境、管理された環境に依存し、それなしでは生活出来なくなってしまった大人との間でトラブルが発生するのです。幼い子どもに取っては部屋の中の床も、野原の地面も同じなんです。部屋の壁も、洞窟の中の壁も同じなんです。電車の中も森の中も同じなんです。だから、部屋の中にいても森の中にいる時と同じように行動しようとします。公共の場所にいても野原にいる時のように行動しようとします。何回「早くしなさい」、「片付けなさい」と言っても言うことを聞かないのは、古代人の世界に生きている幼い子どもたちはそういう感性を持っていないからです。でも、子どもに自然の中と同じように行動されたらお母さんが困ります。色々なものが汚れたり、壊れたり、グチャグチャになってしまいます。だから、子どもの感性とお母さんの感性がぶつかり合い、「どちらが生き延びるのか」という戦いになってしまい、子どももお母さんも苦しくなってしまうのです。その無駄で、子どもの育ちには否定的な影響しかもたらさない戦いと苦しみを減らすためには、時々でもいいですから、子どもを連れて外に、出来れば自然の中に行けばいいのです。それだけで、子どもも、お母さんも、ストレスが減るのです。怒鳴る回数も減ります。子どももお母さんにまとわりつきません。そして、子どもは色々な世界に興味を持つようになります。感覚やからだを働かせることで、心やからだのバランスも整います。ストレスを感じない環境で子どもと関わることで、子どもとの信頼関係も築きやすくなります。今日はものすごく寒そうですが、今が寒さの底です。これから少しずつ明るく、暖かく、春めいてきます。今でも、水仙や梅やロウバイも咲いています。(茅ヶ崎近辺ではですが・・・)お子さんと一緒に春を探しに自然の中に出かけてみませんか。それだけで子育てが楽に、楽しくなりますよ。
2023.01.24
コメント(5)
-
「子育てを楽に、楽しくする方法」(子どもは社会のルールが理解出来ない)
子育てが辛く苦しくなる理由の一つに、「何回言っても、何回説明しても、どんなに易しく説明しても、子どもが理解してくれない、行動が変わらない」とか、「何を言ってもすぐに忘れてしまう」ということがあります。で、お母さんはイライラしてきます。そして、「何回言ったら分かるの!!」と怒鳴ります。そして、「うちの子は頑固だ」とか、「ワガママだ」とか、「悪い子だ」とか、「反抗的だ」と言うお母さんもいます。「なんであんたはそんなにバカなの!!」と言う人もいます。でも、私から見たら、何回言っても通じないことを体験的に知っているはずなのに、それでも、「○○の一つ覚え」のように同じことを繰り返し続けるお母さんの方がおかしいのです。これは「子どもの問題」ではなく、「子どもとはどういう生き物だ」という事を知らない「お母さんの問題」なんです。9才前の子どもには社会のルールが理解出来ません。これは知識の問題ではなく、感覚の問題です。だから、どんなに易しい言葉で丁寧に説明しても理解出来ないのです。理解力の問題ではなく生理的に理解出来ないのです。熱帯地方で暮らしている人間には北極圏で暮らしている人の生活が理解出来ないのと同じことです。そして、子どもと大人とでは「暮らしている世界」が違うのです。そもそも、子どもには「社会」というものが理解出来ません。皆さんは子どもに「社会」について説明出来ますか。「社会」というものが理解出来ないのですから、当然「社会のルール」も理解出来ません。「お金」とか「時間」の価値も社会によって決められているので、お金の価値も、時間の価値も分かりません。というか「お金」とか「時間」というもの自体が理解出来ません。「時間」が理解出来ない子に「早くしなさい」と言っても無駄なんです。お金の価値が分からない子にお金を渡して「大切に使いなさい」と言っても無駄なんです。「公共の場所では静かにする」というのも理解出来ません。「公共」という概念が理解出来ないのですから。あと、地図も読むことが出来ません。幼い子どもは常に主観の世界に生きています。それは、世界が自分を中心に動いている世界です。自分という存在を客観的に見る感覚が目覚めていないのです。だから簡単に迷子になってしまうのです。勝手に歩き回って迷子になっても、「ぼくはズーッとここにいるのに、お母さんがどっかに行っちゃった」と感じるのです。動いたのは自分なのに、お母さんの方が動いたと思ってしまうのです。定点カメラで動物を観察すれば動物が動いているところを見ることが出来ます。でも、動物にカメラを取り付けたら、動物の動きは見えません。見えるのは周囲の動きだけです。幼い子どもの意識はそのようなものです。幼い子どもたちは「自分中心の世界」にいるから、時間のことも、空間のことも、社会のことも理解出来ないのです。まただから、どんなに易しい言葉で、何回説明しても子どもには伝わらないのです。私たちは「社会」の中で生活しています。ですから、「社会」は一種の空気のような存在です。目で見ることも手で触れることも出来ません。でも、そこには社会を守るための「暗黙のルール」があります。その暗黙のルールがシステムとしての社会を維持しているのです。でも、これが理解出来るようになるためには、「自分」という存在を「自分中心の視点」ではなく「社会中心の視点」で捉え直す必要があるのです。それは「ちっぽけな自分」への気付きでもあります。それが出来るようになるのが9才前後なんです。(大雑把に言って9才頃ということです。個人差も大きいです。大人になっても「世界は自分を中心に回っている」と思い込んでいる人もいます。)9才頃に子どもは、「鏡を見たことがない子が、初めて鏡を見るような体験」をするのです。そこで「自分が知らなかった自分」と出会うのです。ですから、その時精神の危機が訪れるのです。ここに書いたようなことを理解しているだけで、子どももお母さんも、無駄な心配、無駄な苦しみ、無駄な努力が減るのです。そうは思いませんか。
2023.01.23
コメント(2)
-
「子育てを楽に、楽しくする方法」(子どもの生態と習性を知ろう)
ネコを飼う時にはネコの生態と習性を学ぶ必要があります。そうでないとネコも飼い主もストレスが溜まってしまいます。さらには、お互いの心とからだの健康を害してしまうこともあります。ネコが部屋の中のもので爪研ぎをするのを「仕付けが出来ていないからだ」と考えて、一生懸命に仕付けようとしても無駄です。ネコが飼い主の指示に従わないのを、「仕付けが出来ていないからだ」と考えて、一生懸命に仕付けようとしても無駄です。そんなことをしたらネコはストレスが溜まり、トイレ以外でもオシッコをするようになってしまうかも知れません。そして、飼い主の意図とは逆に状態がさらに悪化して行ってしまうでしょう。でも、ネコの生態と習性を学べば「これがネコなんだ」「これがネコの普通なんだ」「ネコってこういう生き物なんだ」ということが分かるようになります。すると、無駄な努力をする必要がなくなります。また「上手に仕付けが出来ない自分」を責めることもなくなります。ネコの生態を観察する余裕も生まれるかも知れません。「ネコを飼うということはこういうことなんだ」と「ネコのありのまま」を受け入れ、対処することも出来るようになります。すると、ネコは落ち着きます。ストレスも消えます。そして、心とからだの健康を害することもなくなり、問題行動も減ります。色々な所で勝手に爪を研ぐのを防ぎたかったら、仕付けによって爪研ぎを防ごうとするのではなく、自由に爪研ぎが出来るものや場所を与えればいいのです。それでもダメなところは、「ネコを飼うとはこういうことなんだ」と諦めるしかありません。自分の意思で飼い始めたのですから、諦めるのもネコを飼う時の責任の一部です。そしてこれは、ネコだけでなく、どんな生き物を飼う時も同じです。人間の子どもでも同じです。ただ違うのは、ネコは何年飼ってもネコのままですが、「子ども」はやがて「大人」になってしまうということです。子どもの世話をしている親もまた子どもでした。だから大人達は「分かっているつもり」になってしまって、「違っている」ということに気付かないのです。改めて子どもの生態や習性について学ぼうとしないのです。でも実際には、子どもの生態や習性と、大人の生態や習性は大きく異なっているのです。でも多くの子どもが大人になる過程でその子どもの時の感覚を忘れてしまうのです。だから、その「大人と違っているところ」を「無知故の違い」だと思い込み、仕付けや教育で直そうとしてしまうのです。時々、子どもの頃の感覚を覚えている人もいますが、そういう人は子ども時代に「子どもであること」を肯定されて育った人なのではないかと思います。子どもの感じ方、考え方、行動パターンは大人とは大きく違います。見る、聞く、感じる働きも、子どもと大人とでは異なります。同じものを見ても、子どもと大人とでは見方が違うのです。同じ音を聞いても、子どもと大人とでは聴き方が違うのです。そのことに気付かず、子どもに大人と同じように感じ、考え、行動することを求めてしまうと、子どもは強いストレスを感じます。「お母さんに否定されている」と感じ、幼い子どもが誰でも持っている原初的自己肯定感を失って行きます。心とからだの育ちにも歪みが生じ苦しくなります。そしてそれを、心やからだのトラブルや行動で訴えようとします。子どもとしては不自然な問題行動も多くなります。子どもの笑顔も減ります。精神的な自立も困難になります。不安も強くなるためお母さんに守って貰うためにお母さんから離れなくなることもあります。そして子育てがどんどん辛く、苦しくなります。子どもが水溜まりで遊ぶのは子どもにとっては自然な行動です。子どもがキャーキャー言って走り回るのも、忘れ物をするのも、食事の時に動き回ったりするのも、洋服を汚してくるのも、開けた戸を閉めないのも、片付けをしないのも、子どもとしては自然な状態です。でも、放っておいたからといって、その状態のままで成長するわけではないのです。成長するに従って、感覚や、考え方や、意識や、行動が少しずつ大人に近づいていくからです。小さい時はサンタクロースを信じていても、大人が教えなくてもある程度の年齢になったら自分の力で分かるようになるのです。子どもの子どもらしい感覚や、考え方や、行動や、生態は、子どもの時にしか見ることが出来ないものなんです。すぐに消えてしまうのです。だからそれを消そうとするのではなく、よく見て、聞いて、関わって、楽しんで下さい。懐かしい想い出になりますよ。また、生態や習性を理解することで、子どもがストレスを感じないようなやり方で子どもの行動を変えることも出来るようになります。どうしても片付けさせたいのなら、子どもの生態を利用して片付けが楽しくなるような工夫をしてあげることです。そすれば、片付けが遊びになります。すると、自分から片付けるようになるのです。子どもは楽しければ親に言われなくても進んでやるのです。でも、楽しくないことは叱られてもやらないのです。これもまた子どもの生態です。
2023.01.22
コメント(0)
-
「子育てを楽にする方法」(楽しくすると楽になるのです)
昨日は、「子育ては、最初苦しくてもちゃんと向き合った方が、後からどんどん楽になりますよ」ということを書きました。だからといって、ただ苦しいのを我慢するだけの子育てでは子どもも苦しくなるし、また、親子の信頼関係を築くのも難しいでしょう。人は、我慢している時には感覚も、心も、からだも閉じてしまうからです。子どもも、「感覚も、心も、からだも石のように固まってしまっているお母さん」と一緒に居ても楽しいわけがありません。そして子どもは楽しくなければ、ただ欲望に従って行動するようになります。そのため、頑張っても頑張っても泥沼にはまっていきます。子どもがお手伝いをするのは「楽しいから」であって「義務だから」ではないのです。じゃあどうしたらいいのかと言うことですが、子育てを楽にするためには、子育てを楽しむようにすればいいのです。楽しくなるような工夫をすれば、同じこととしていても楽になるのです。我慢しているだけだと、大したことをしていなくてもすぐ疲れてしまうし、また苦しくなるのです。楽になるために子どもを保育園に預けても、楽になるのは一時的です。「苦しみからの逃避」は、長い目で見たら逆に苦しみを増やしてしまうからです。どうしても仕方がない事情があって子どもを保育園に預けるような人は、一緒に居る時間を楽しい時間にする工夫も出来るでしょう。子どもも、その短い時間の中でお母さんとの間の信頼関係を築けるでしょう。でも、楽になるのが目的だったら、子どもを保育園に預けるのは逆効果になってしまうのです。子育てを楽にしたいのなら、子どもとの日々の関わり合いを楽しいものに変えるような工夫をした方が絶対的に効果的なんです。苦しみを先送りすると、苦しみの利子が雪だるま的に膨らんでしまうだけだからです。「楽しくなるような工夫をすると苦しみが和らぎ楽になる」というのは、簡単なからだのワークで確認する事が出来ます。二人で組んで一人が他の人をオンブします。そして、最初は「嫌だな、苦しいな、なんで自分が、早く終わらないかな」などと否定的な事をブツブツ言いながら歩きます。そしてその時の重さを覚えておきます。次に、一旦降ろして、心とからだをリセットして、また同じ人をオンブします。でも、今度は「楽しいな」「嬉しいな」と言いながら歩きます。そして、さっきの重さと今の重さを比較してもらいます。すると不思議なことに、同じ人をオンブしているのにそれだけで重さが軽くなるのです。中にはオンブした途端に「あ、軽い!」と言う人もいます。「苦しいな」と言っている時には重さがずしんと来ます。足も重くなります。でも、「楽しいな」と言っていると、それだけで実際に楽しくなるし、楽しくなると楽になるのです。どうやら、人の心とからだには「楽しい時には苦しい事を忘れるような仕組み」が備わっているようなのです。昔太極拳を習っていた先生は、「戦っている相手を大好きな人だと思え」とか、「楽しいな、楽しいなと思いながら動け」というようなことを言っていました。そうすると、不思議なことに力は抜けるのに技は効くようになるのです。でも、「ただ楽しいな」と言っているだけでは魔法がすぐに解けてしまいます。だから、実際に子育てが楽しくなるような工夫を色々とするのです。すると、本当に子育てが楽になるのです。これは勉強でも、仕事でも、家事でも同じです。楽しくなるような工夫をすれば、楽になるのです。勉強が好きな子は、勉強の中に楽しさを発見出来る子でもあるのです。高い成績は、単なる頑張りと努力の結果ではなく、勉強をどれだけ楽しんでいるのかということの表れなんです。とはいっても、子育てが楽しくない人は、子育てを楽しくするような工夫を考えるのも苦手です。だから、子育てが苦しくなってしまうのですから。でも、子育てを楽しくする工夫や方法は色々とあるのです。私が「気質」や「親子遊び」を指導しているのも、子育てを楽しくするだけでなく楽にするためでもあるのです。呼んで下さればどこへでも行きますよ。<続きます>
2023.01.21
コメント(0)
-
「だんだん楽になる子育てと、だんだん苦しくなる子育て」(安心を育てる子育て)
私はいつもお母さん達に子育てには「だんだん楽になる子育て」と「だんだん苦しくなる子育て」の二種類があるんだよ。と言っています。「だんだん楽になる子育て」の方の「苦しみ」に終わりがあります。また、「喜び」もいっぱいあります。「苦しみ」から逃げずに子どもと向き合い、子どもの気持ちを大切にしながら子どもと関わり合っていると親子の信頼関係が育って行きます。すると、3才頃から少しずつ楽になっていくのです。お手伝いも出来るようになってきます。会話も出来るようになるので、子どもといるのが楽しくなってきます。話し相手にもなってくれます。さらに5才頃になると、お母さんと離れて友達と遊ぶのが楽しくなってくるのでまた楽になります。小学校に入って、自分のことは自分で出来るようになってくると、さらに楽になってきます。そして、そのような子どもの成長を楽しむ事も出来ます。それに対して、子育てに一番手がかかる時期に、お母さんが自分を守るために「楽な方法」を選んだり、「苦しみ」から逃げようとしてしまうと「だんだん苦しくなる子育て」が始まります。そのような人は、最低限の子どもの世話はしますが、必要以上に子どもと関わろうとはしません。そんな時間があったら自分のために使いたいからです。でも、そのような子育てでは親子の信頼関係が築けません。子どものことを理解出来るようにもなりません。子どもの安心も育ちません。その結果、子どもの心が不安定になったりり、無気力にもなったりしてしまいます。成長への意欲も育ちません。当然、積極的にお母さんの手伝いをしようともしません。子どもは「お母さんと一緒」が楽しいからお手伝いをするのであって、義務感でやっているわけではないからです。実は、「一番手がかかる時期」というのは、子どもの成長にとって一番「お母さんとの関わり合い」が必要な時期でもあるのです。その時期に、子どもはお母さんとの関わり合いを通して「親子の信頼関係」を築いたり、言葉を学んだり、自分が生まれてきた世界の事を学んだり、安心を育てたりしているのです。一番、赤ちゃんがお母さんを必要としている時期に親子の信頼関係を築けなかった人は、子どもとの関わり方が分からないので、2才頃になって子どもの自我が目覚め始めるとすぐに困難に突き当たります。それまでは世話をするだけで済んでいた子が、2才頃から急に「一人の人間」としての自己主張を始めるからです。そして子育てがさらに辛く、苦しいものになります。その結果、大きな声で怒鳴ったり、時には叩いたりするようになってしまうこともあります。でも、お母さんの力ずくの脅しが通用するのは9才頃までです。9才を過ぎてしまうと、次第にお母さんの脅しは通用しなくなってしまうのです。そして、それまでお母さんが怖いから言うことを聞いていた子どもが言うことを聞かなくなります。そしてそれまでの「いい子」が消えて行きます。それで、さらに子育てが苦しくなります。それに対して、お母さんを必要とする時期にいっぱいお母さんと関わることが出来た子は、「安心」が育つため、2~3才頃になると少しずつお母さんから離れて、友達と遊ぶことが出来るようになっていきます。そういう子でも、2才頃からヤダヤダ期は始まりますが、それまでに信頼関係が育っていれば、少し距離を置いて見守ることも出来ます。5才になったらもっと離れ、必要がある時にしかお母さんの側に来なくなります。このようにして、子どもが成長するにつれて子育てが段落、楽になっていくのです。それに対して、「親子の信頼関係」や「安心」を育てることが出来なかった子の方は、成長に伴って新しい出会いが増える度に不安と苦しみが強くなります。そして、この不安と苦しみには出口がありません。成長と共に増えることはあっても消えることがないからです。だから、赤ちゃんがお母さんを必要としている2,3才頃までは、お母さんは子どもと一緒に居てあげて欲しいのです。(可能なら3才まで、最低でも2才まで)だからといって、ただ我慢して子どもの側にいるだけでは親子の信頼関係も子どもの安心も育ちませんからね。「我慢する子育て」では、子どももお母さんも苦しくなるばかりです。「だんだん楽になる子育て」をするためには、「子どもとの関わり合いを楽しむ子育て」が必要になるのです。そしてそのためには「子ども」についての学びも必要になります。「子どもとはどういう生き物なのか」ということを理解するだけで子育ては楽になるのです。「育て方」や「仕付け方」を学ぶのではなく、「子ども」について学ぶのです。ただし私は、周囲の手助けもなく、我慢する子育てしか出来ない人が、子どもと自分の命を守るために緊急避難的に保育園に子どもを預けることまでは否定しません。でもそういう人は、積極的に自分の周囲とつながりを作って「支え合う仲間」を増やしていかないと、さらに苦しくなります。保育園はいつまでも子どもを預かってはくれないのですから。
2023.01.20
コメント(0)
-
「本来、人はみんな発達障害なんです」
赤ちゃんは自分勝手です。人の迷惑なんか気にしません。いくら言ってもいうことを聞かないし、汚いものにも触れ(時には自分のうんちでも遊びます)、危ないことも平気でやります。オシッコうんちは垂れ流しで、お腹がすいたら泣き、寂しくても泣き、からだの調子が悪くても泣きます。大人がやらせたいことはやらないのに、自分がやりたいことはいくら禁止してもやってしまいます。でもみんな「赤ちゃんってそういうもんだ」と納得していたり、時々見せてくれる笑顔や、天使のような可愛さがあるから耐えられますが、そのまま大きくなってしまったら間違いなく「障害を持った子」として扱われてしまうでしょう。人は皆、障害を持った子と同じような状態から自分の人生を始めるのです。(死ぬ時もですけど・・・)本来、人はみんな障害児なんです。そしてそれが、動物としては未熟な状態で産まれてくる人類の特徴でもあるのです。そのような時期の子どもたちはみんな「自分だけの世界」に生きています。「他者と共有するもの」も持っていません。言葉も分からなければ、お母さんの気持ちも、やっていいことといけないことの区別も分かりません。そんな赤ちゃんが最初に学ぶのは「笑う」ということです。産まれたばかりの赤ちゃんは、何にも楽しい事がなくてもフッと笑顔を見せますが、これは「新生児微笑」という生理的な「反射」であって、感情表現としての「笑い」ではないそうです。だから、周囲に人がいなくても笑うのです。もしかしたら天使を見て笑っているのかも知れませんが・・・。でもそれを「笑い」と勘違いした大人達が「あー、わらった、わらった!」と喜び、赤ちゃんに「笑い返し」をします。その繰り返しで赤ちゃんは、「笑う」という感情表現を学ぶらしいのです。周囲の人が笑い返しをする事で、赤ちゃんは「笑顔」を他の人と共有出来るようになるのです。そしてこれが、赤ちゃんが社会(自分以外の人)とつながる第一歩です。「じゃあ、大人が笑い返さなかったらどうなるんだろう」ということを、昔、実験した人がいるらしいのです。その人は、赤ちゃんが笑っても笑い返さなかったそうです。すると次第に赤ちゃんは笑わなくなってしまったそうです。もともと、反射としての「新生児微笑」は大体二ヶ月程度で消えてしまうそうです。でも、それまでにお母さんや周囲の大人によって「笑う」ということを共有してもらえた子は、その時期を過ぎても、楽しい時の感情表現として笑うようになるのです。でも、笑い返してもらえない子は、その移行が出来ないようなんです。これは「泣く」ということでも同じだと思います。赤ちゃんは不快なことがあると泣きます。するとお母さんがすぐに対応してくれます。その繰り返しで赤ちゃんは「泣く」ということでお母さんに「自分の心やからだの状態を伝える」という方法を学ぶのです。コミュニケーションの始まりです。でも、赤ちゃんが泣くとすぐに対応しようとするお母さんに対して、「放っておけば泣かなくなると」とアドバイスする人もいます。確かにそうなんだろうと思います。でもそれは「赤ちゃんとお母さんの感覚的、感情的なつながりが切れる」とか、「赤ちゃんがお母さんと感情を共有することを諦めた」ということでもあるのです。そして、「お母さんと共有するもの」を育てることが出来なかった子は、他の子とも共有するものを育てることが難しくなってしまうでしょう。社会性を身につけるのも困難になるでしょう。ちなみに、私が見ている範囲でですが、発達障害と言われている子はあまり笑いません。笑ったとしても周囲の人も楽しくなるような笑い方はしません。痛い時には泣きますが、悲しい時などの感情表現としては泣きません。そしていつも、心もからだも緩むことなく緊張した状態です。周囲には大勢の人がいるのに、周囲の人とつながることが出来ずにたった一人で生きているからなのでしょう。
2023.01.19
コメント(0)
-
「自分の成長を望んでいない子は一人もいないのです」(つながりが子どもの成長を支える)
私は、この世界に「自分の成長を望んでいない子」は一人もいないと思っています。どんな障害を持っている子でも、どんなに困った行為を繰り返す子でも、心の奥底ではみんな「自分の成長」を望んでいるのです。なぜなら、(身も蓋もロマンもない言い方をしてしまうと)成長する事で生存が有利になるからです。だから、成長欲求は食欲と同じ根っこなんです。だからこそ、その成長がちゃんと実現された時には喜びが生まれるのですが、阻害された時には悲しみと苦しみが生まれるのです。子どもたちの様々な問題行動はそのサインです。でもだから、子ども自身が自分の成長を実感できるようにしてあげると問題行動も減っていくのです。子どもが問題行動を起こしている時、大人達はその問題行動を止めさせようとします。でもその問題行動が、自分自身の成長が阻害されている悲しみや苦しみから来ているとしたら、子どもの行為を否定して止めさせるだけでは逆効果になるだけなんです。そんな時、その子が好きな分野で課題を与え、その分野での成長を実感させてあげると悲しみや苦しみが減り、色々な場面での問題行動も減って行くのです。例えばその子が電車が好きなら積極的に電車のことを学ばせたり、電車と関わらせるようにすれば、自分が好きな分野で自分の成長を感じることが出来ます。すると、問題行動も少しずつ減っていくのです。また、「成長する喜び」を知った子は、それを別の分野にも広げて行くことが出来ます。一芸は多芸に通じているからです。入口は一つでも、中ではみんなつながっているのです。一見遠回りのように見えますが、実はこれが一番確かな道でもあるのです。大人が与えた目的に真っ直ぐに向かわせても、子どもが「前に向かう気力」を失ってしまったら、いつまで経っても目的地にはたどり着けないのです。そして、途中で動けなくなってしまうでしょう。でも、日本の教育システムは「子どもの画一化」を目的としているため、子ども一人一人の興味や才能に合わせてその子の成長に必要なものを与えることが出来ません。だから、学校が苦しくなり、学校に行けなくなる子、行きたくない子が増えてしまうのです。子育てが苦しくなるのも「我が子」と「他の子」、「自分」と「他の人」を比較してしまうからです。子どもと自分を画一化しようとするから成長が阻害され、苦しくなってしまうのです。学校という場に適応出来ている子もいっぱいいますが、学校での学びによって自分自身の成長を実感できている子は少ないのではないかと思います。多くの子が、みんなに置いて行かれないように頑張っているだけなのではないかと思います。だからちょっと躓くだけで、学校に行けなくなってしまうのです。また、子どもは「つながり」の中で成長するように出来ています。特に人間の場合は、「つながり」から切り離されたら「人間」として成長することすら出来なくなってしまいます。そのため子どもたちは本能的に「つながり」を求めます。「言葉」を覚えるのもお母さんとつながるためです。「知識」を覚えるのは社会とつながるためです。「遊び」を覚えたり「群れて遊ぶ」のも仲間とつながるためです。ケンカもまた「つながり」の一つの形です。子どもたちがお話しや物語が好きなのは、物語が「見える世界」と「見えない世界」、「人間の世界」と「自然や動物の世界」、「過去」と「未来」をつないでくれるからです。様々な「遊び」や「芸術行為」が問題を抱えている子どもに対して治療的な効果を持つのは、これらの行為が、「子ども」と「子どもが生まれてきた世界」をつなげる働きをしてくれるからです。「つながり」を感じることは、「成長」を感じることとつながっているのです。「成長する」ということは、「つながりを広げる」ということでもあるのです。「学び」はつながりを広げるためにあるのです。テストのためにあるのではありません。
2023.01.18
コメント(0)
-
「療育としての遊びと芸術活動」(社会化されない子どもたち)
私が幼児教室(「ポランの広場」というお母さんも子どもも一緒になって群れて遊ぶ会です)を始めてしばらくした頃、不思議な行動をする不思議な子どもたちや、療育に通っている子どもが多いので、療育では一体どういうことをしているのか」ということを本を何冊か買って読んだことがあります。そうしたら何のことはない、私がポランの広場でやっているようなことばかりだったので、なんとなく問題の根っこが見えたような気がしました。(実際、以前、「療育を勧められて行ったけど、子どもを遊ばせるだけだったので止めてしまった」と言っていたお母さんもいました。そのお母さんは「遊びの力」が分かっていなかったのでしょう。)ちなみに私がやっているのは、みんなで群れて遊んだり、からだを使って遊んだり、歌ったり、音遊びや劇遊びをしたり、作ったり、描いたり、お話を聞いたりするような「何十万年も前から人々が生活の中で普通にやっていたこと」ばかりです。それだけで子どももお母さんも変わって行くのです。でも、そういうことの多くが現代人の生活の場からは消えてしまいました。しかも、たった数十年でです。生活が近代化すると共に、「群れ」も、「群れて遊ぶ遊び」も消えました。それと同時に「仲間」や「自由」も消えました。ゲームの中には「選択する自由」はありますが「想像したり創造する自由」はありません。大人が管理する「ゲームの外の世界」では、その「選択する自由」すらないので、子どもは「ゲームの中での自由」に取り憑かれてしまうのでしょう。遊びも近代化し、仲間がいなくても簡単で楽しく遊ぶことが出来るオモチャがいっぱい発明されました。その結果、「遊び」が「個人化」しました。そして、「遊び」が個人化することで成長も「個人化」し始めました。昔の子どもたちは、年齢も性別も様々な仲間達と群れて遊ぶ過程の中で「社会化」されて来たのですが、最近の子は「社会化」という過程を経ることなく成長するようになったのです。「個人化」された遊びばかりをして「社会化」されることなく育った子は、感じ方、考え方、行動の基準が常に「自分」だけになります。そこに「他者」がいないのです。この状態は、最近の「発達障害」と呼ばれる子の状態に近いです。発達障害と呼ばれるような子でも、みんな自分なりの感覚や考え方は持っています。特別に知的に劣っていると言うこともありません。でも、その感覚や思考や意識や行動の中に「他者」がいないのです。そのため常に自分の論理で考え、自分の論理で判断し、自分の論理で行動します。でも、最近のお母さん達は「群れて遊ぶ」よりも「個人としての能力を育てること」の方に熱心です。群れて遊ぶためには子どもだけで家から外に出なければなりませんが、それも許しません。家の中で一人で遊んでいて欲しいのです。そして、個人の能力を育てるために様々な習い事には通わせます。でも、自由な状況の中での直接的な他者との関わり合いがなければ、子どもは社会化しないのです。また、様々な習いごとをして個人としての能力を高めても、他者との関わり合いの中で社会化されることなく大人になった子はその能力を生かすことが出来ません。それでも、兄弟がいて、お父さんも子育てに参加して、家族がつながり合い、家族がミニ社会として機能しているのなら、子どもは家族との関わりを通してある程度は社会化することが出来ます。でも、兄弟がいてもバラバラに遊び、お父さんも子育てに参加せず、お母さんも自分のことに忙しければ、子どもは社会化されることなく、自分の世界の中で個人化していくだけです。お母さんが一人でいくら頑張っても、子どもの社会性は育たないのです。お母さんが子どもに一生懸命に話しかけ、子どもに共感し、子どもと楽しく遊ぶことで子どもの人間性を育てることが出来ます。でも、お母さん一人では子どもの社会性を育てることは出来ないのです。そして、社会性が育っていない子は集団の中でどうしていいのか分からなくなります。集団にストレスを感じるようにもなります。今、発達障害と呼ばれるような問題行動を起こす子だけでなく、問題行動は起こさないけど、学校に適応できない子どもたちも増えて来ています。「みんなと一緒」を楽しめる子は「みんなと一緒」を楽しもうとしない子に違和感を感じ、「みんなと一緒」が出来ない子は、「みんなと一緒」を強制してくる先生にストレスを感じます。<続きます>
2023.01.17
コメント(0)
-
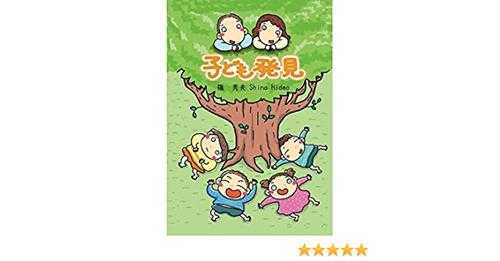
「発達障害に対する私見と仮説」(共感能力の欠如)
最近、発達障害と呼ばれるような症状の子が増えて来ています。「診断が厳しくなったから増えて来ただけだ」と言う人もいますが、実際に、私の子どもの頃にはあまり見かねなかったような不思議な状態の子が増えて来ているのは事実です。教室を始めた30年前頃からも確実に増えて来ています。私の感覚では、その発達障害には二種類あるような気がしています。「先天的なもの」と「後天的なもの」の二種類です。最近急激に増えて来ているのは後天的なものの方です。先天的なものは昔からありました。そして、先天的な発達障害を持っている子は特別な才能も持っているような気がします。私が知っている子の中にも何人かいます。そういう子は幼い時は「ただ困った子」なんですが、10才を過ぎた頃から他の子にはない才能が目覚め始めます。ただ、幼い時にその違いを見分けるのは困難です。今日のブログで扱っているのは後天的な発達障害の子についてです。発達障害の子でも、いつも困ったことをするわけではありません。自由な遊びの場ではその特異性はあまり表れないからです。好きなことをやっている時にも表れません。でも、みんなと一緒を求めるような場、ジーッとしていなければいけないような場、感じたり、考えることを求められるような場、やりたくないことをやらされるような場では、発達障害が疑われるような子は異常な行動を取り始めるのです。森の中や家の中で自由に行動している時には普通に見えるのですが、「みんなと一緒」が求められるような教室の中では異常な行動を取り始めるのです。まただから分かりにくいのです。私が観察した範囲での「発達障害と呼ばれる子の特徴」は、「みんなと一緒が出来ない」、「出来たとしても強い緊張を感じ苦しくなってしまう」ということです。当然、「みんなと一緒」を楽しむことも出来ません。というか、そのような子は「みんなと一緒」という感覚自体がよく分からないのはないかと思います。また、「見て学ぶ」ということも苦手です。「やって学ぶ」事は出来るのですが、「見て学ぶ」のが苦手なんです。だから、「みんなと一緒」が出来ないのです。一般的な子は、他の子がやっていることを見ているだけで真似をする事が出来ます。みんなが椅子に座っていれば、自分も椅子に座るのです。みんなが絵を描いていれば自分も絵を描こうとします。実際には描かなくても、「今は絵を描く時間だ」ぐらいは分かります。なぜなら、それが子どもの成長を支えている基本的な模倣能力だからです。その能力があるから、わざわざ教えなくても子どもは言葉を覚え、生活の様々な事を覚え、大人から考え方や感じ方を学ぶことが出来るのです。でも、発達障害と呼ばれるような子は、年相応の模倣能力が育っていないのです。走り回っている子の真似はすぐするのですが、お椅子に座っている子の真似はしないのです。どうしてそういう状態になってしまっているのかいうことですが、私は「共感能力が育っていないからだ」というように考えています。その共感能力は3才頃までのお母さんとの関わり合いの中で育ちます。赤ちゃんはお母さんを模倣することで言葉を覚えます。笑い方や感情表現もお母さんを模倣することで覚えます。その赤ちゃんの頃の模倣能力は遺伝子の働きの中に組み込まれているものだろうと思います。それは赤ちゃんが持つ様々な原始的な反射能力の一つなのでしょう。ですからこれは世界共通です。でも、その原始的な模倣能力は成長と共に次第に消えて行きます。そして、後天的な学習によって自分が生まれてきた文化に合わせた新しい模倣能力が育ち始めます。その模倣能力の育ちを支えているのがお母さんとの関わりなんです。だから、子どもが何を感じて何を模倣するのかは、お母さんが生活している文化の違いによっても違って来ます。お母さんの気質によっても違って来ます。その時に重要になるのが「共感能力の育ち」なんです。(本来は)お母さんはいつも赤ちゃんの顔を見て、赤ちゃんの側にいて、赤ちゃんからのメッセージを感じ、そのメッセージに応えようとしています。赤ちゃんが笑えばお母さんも笑い、赤ちゃんが泣けばお母さんはその泣き声によって赤ちゃんの要求や状態を感じ取り赤ちゃんの要求に応えようとします。赤ちゃんがムニャムニャ訳の分からないことを言っても、お母さんは「ハイハイ、分かりましたよ」などと応えます。本来、赤ちゃんとお母さんの関係はこのようなものだったのです。何十万年も昔から、お母さんは赤ちゃんに寄り添っていたのです。そして、お母さんが赤ちゃんの気持ちにより添っているうちに、赤ちゃんの方もお母さんの共感能力を模倣するようになるのです。言語能力も、わざわざお母さんが言葉を教えようとしなくても、ただいつも話しかけているだけで育って行きますよね。それと同じように、子どもは他の人から共感される体験を通して、共感する能力を育てているのです。幼い子どもがお母さんのやっていることを見て模倣することが出来るようになる背景には、そのような形での共感能力の育ちがあるのです。「一緒が楽しい、おんなじが楽しい」という感覚を支えているのが共感能力なんです。だから、日本で生まれ育った子は日本人の感性を身につけることが出来るのです。他の子どもたちと一緒に楽しく群れて遊ぶことが出来るようになるのも、その共感能力があるからです。その共感能力が育っていない子は自分だけ楽しもうとするのです。また、他の子から学ぶことも出来ません。勉強も困難になるでしょう。そして今、その共感能力が育っていないと思われる子が多いのです。「お母さんがいつも赤ちゃんの側にいる」という何十万年と続いてきた子育ての根幹的な部分が崩れてきてしまっているからです。共感能力が育っていない子は平気で他の子が嫌がるようなことをします。今どういう状況なのかを感じることも出来ないため、常に自分のやりたいことだけを優先させます。意図的にイジワルをしているのでも悪意があるのでもないのです。ただ分からないのです。だから、叱られてもなんで叱られているのかが分かりません。目を閉じて歩けば色々なものにぶつかりますよね。他の子にケガをさせるかも知れませんが自分自身もケガをするかも知れませんよね。でも、目を閉じているので他の子の泣き声が聞こえても何で泣いているのかが分かりません。自分がケガをしても何でケガをしたのかも分かりません。何でみんながお椅子に座っているのか、なんでみんなが先生の話を聞いているのかも分かりません。というか、自分の周囲のそういう状態にも気付きません。目には見えていても脳や意識には見えていないのです。でも叱られます。そのため、本人も混乱して苦しんでいるのです。周囲も大変ですが、本人も苦しんでいるのです。そのことだけは忘れないで下さい。どうしたらいいのかと言うことですが、発達障害の子は見ても学べません。言葉で教えても理解出来ません。言葉の理解には共感能力が必要だからです。でも、体験を通してなら理解出来るのです。そこが糸口なんだろうと思います。ただそれは学校という場では出来ないと思います。「学校は言葉で教える場」であって「体験する場」ではないからです。まただから発達障害の子の状態が顕著に出てしまうのです。*******************告知です。2022年度もやったのですが、続けて欲しいという声もあるので2023年もZoomでの子育て講座をします。名称は「ゆりかごオンライン」です。内容は子どものこと、子育ての事、子どもとの遊び方や関わり方、気質のことなどをお話しします。皆さんからの質問にもドンドン答えます。毎月第三金曜日の10:00~11:30(実際には12:00頃までになってしまいますけど)参加費 2000円/回録画もするので後から見ることも出来ます。参加申し込みやお問い合わせは「しの」までお願いします。以下は私が出した本です。アマゾンで買えます。
2023.01.16
コメント(3)
-
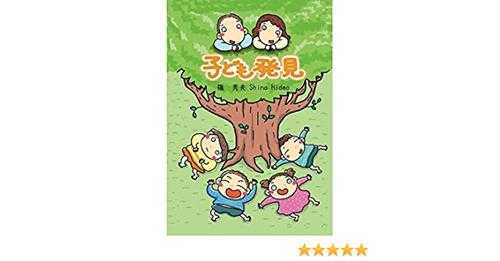
「子育てに簡単便利を望んではいけないのです」(精神的に未熟な子どもと大人達)
先日、森の幼稚園「もりわら」の浅井智子さんと松井和さん(音楽家/ 作家/ 元・埼玉県教育委員長)とのトークライブに行ってきました。そこでは、様々な実例を出しながら「今、保育業界、保育現場、子育ての現場が大変なことになっている」というお話しがありました。私自身も、お母さんや子どもたちとの関わりを通して、「子育ての現場や、保育の現場や、教育の現場が大変なことになっている」ということを少しは知っています。その表れなんでしょうが、私の周囲でも、「学校に行きたくても行けない子」、「自分の意思で学校に行かないという選択をする子」「学校に行かせないという選択をする親」が増えているような気がします。また、普通に学校に行っている子でも、精神的に幼い子がすごく増えて来ています。というか、そういう子の方が今では普通です。私の感覚では精神年齢が実年齢よりも3才以上は低い子が多いような気がします。小学3年生なのに幼稚園児を相手にしているような感覚なんです。そういう子には「人の話を聞くのが困難だ」とか、「自分よりも小さい相手や弱い相手に対しても優しく出来ない」いう特徴があります。実は、「優しさ」は精神的な成長の表れでもあるのです。そのため、イジメを楽しむような子は精神的な育ちが遅れているのです。そして今、その「優しさ」が育たないままの状態の子が非常に多いのです。そして、その遅れが取り戻されることなく、大人になっても精神的に幼い状態のお母さんやお父さんも増えて来ています。今、肉体的には大人になっても、精神的には大人になれない人が増えて来ているのです。そのような精神的に幼いお母さんやお父さんは、「親」になることも困難です。肉体的には親になっても、精神的に親になることが出来ないのです。本来、「親」の役割は「子どもを守り育てること」です。そのためには様々な犠牲も必要になります。でも、自分もまたそうやって育てられて来たのですからそれは理不尽なことではないのです。そしてまた、それが「親としての喜び」にもつながっているのです。でも最近の人達の中には、子どもを守るのではなく、子どもと同じレベルで我が子と利害の奪い合いをしている人が多いのです。昔の人は当たり前にやっていた「子どものために」という行動でも、「子どもの犠牲になるのはイヤダ」と訴え、拒否しようとする人も増えて来ました。そういう人は、「子どものために」=「子どもの犠牲になる」という発想をするのです。世の中が簡単で便利になるにつれて、いつの間にか、簡単便利が通用しない子育てが「喜び」ではなく「苦痛」になってしまったのです。「子どもはやってもらうばっかりでズルイ」というようなことを言う人もいます。でもこれは子どもの感覚であって、親や大人としての感覚じゃないですよね。大分以前ですが、お父さんが子どもとゲームの奪い合いをして、子どもを殺してしまったという事件がありました。もちろん子どもの主体性を肯定した素晴らしい子育てをしている人もいっぱいいます。すばらしい保育や教育をしている保育園や幼稚園や学校もいっぱいあります。でも今、そういう子育てをしている人や、園や学校はどんどん減ってきているような気がします。なぜなら、そういう園や教育をしている所では親にも様々な努力や義務や犠牲を強いて来るからです。保育園や幼稚園がちゃんとした保育や教育をするためには親との連携が絶対的に欠かせません。保育園や幼稚園は、親の代わりに子育てや仕付けや教育をしてくれるところではないので、それは当然のことなんですが、それを、「当然」とか「喜び」と感じる人が減ってきてしまったのです。私が子育ての勉強会をしても、「仕付けの仕方が分からない」「子どもが嫌いだ」「子どもから離れたい」と訴える人がいっぱいいます。どうやら私たちは、簡単便利な生活と引き替えに、人類が何百年、何千年、何万年と受け継いできた「子どもとの関わり方」や「子どもの育て方」を忘れてしまったようです。子育てや教育の現場で今起きていることは、私たちがこれまでやって来たことの結果に過ぎないからです。子育てや教育の世界に簡単便利を望んではいけないのです。子どもを管理したり支配することで、仕付けや教育をしようとしてはいけないのです。そういうことをするから、精神的に未熟な子どもや大人が増えて来てしまっているのです。*********************告知です。2022年度もやったのですが、続けて欲しいという声もあるので2023年もZoomでの子育て講座をします。名称は「ゆりかごオンライン」です。内容は子どものこと、子育ての事、子どもとの遊び方や関わり方、気質のことなどをお話しします。皆さんからの質問にもドンドン答えます。毎月第三金曜日の10:00~11:30(実際には12:00頃までになってしまいますけど)参加費 2000円/回録画もするので後から見ることも出来ます。参加申し込みやお問い合わせは「しの」までお願いします。以下は私が出した本です。アマゾンで買えます。
2023.01.15
コメント(0)
-
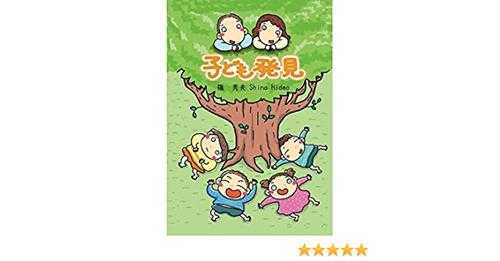
「教えるのではなく導くのです」(大人の都合ではなく子どもの都合に合わせる子育て)
子どもの育ちには、「仲間」と、「自然」と、「導いてくれる大人」が必要です。でも、仲間と自然までは理解している人も多いのですが「導いてくれる大人の存在の重要性」があまり理解されていないように感じています。実際、多くの大人が、導くのではなく教えようとしてしまっていますから。教えるためには、子どもと大人が向き合う(対立する)必要があります。また、言葉での説明が必要になります。それが多くの幼稚園や学校でやっている普通の教育スタイルです。仕付けを教えようとしているお母さんもまた、同じように子どもに教えようとしています。でも、言葉で教えられただけのことは、子どもの頭の中に留まるだけで、心やからだの内側までは入って行かないのです。その結果、知識としては「イジメは良くない」ということを知っていながら、平気で他の子をいじめるようになったりするのです。そういう子に「イジメはダメなんだよ」と言っても、「ぼくだって、それくらい知っているよ。だからぼく、いじめてなんかいないもの」と言い返してくるのです。そういう子は「イジメは良くない」ということを知識としては知っていても、「どういうことがイジメなのか」という〝そもそも〟のところが分かっていないのです。だから他の子をいじめていながら平気で「ぼくはいじめてなんかいないよ」と言い切れるのです。明らかに人を差別するようなことを言っておきながら、それを非難されると「私はそういうつもりで言ったのではありませんが、そう取られたのなら陳謝します」と言い訳する政治家もいっぱいいますが、そのような政治家も「差別するとはどういうことなのか」という、〝そもそも〟のところが分かっていないのです。そういう「知識としての学び」しかしてこなかった子どもや大人達に、「イジメは良くない」とか「差別は良くない」と言っても意味がないのです。そして実は、「教える子育て」や「教える教育」ではそういう頭でっかちの子どもばかりが育ってしまうのです。でも、保育園や幼稚園や学校といった、「一人の先生が大勢の子どもに同時に同じようなこと教えるような場」では、そういう方法でしか子どもと関わることが出来ないのです。一人の先生が大勢の子どもを指導するとなると、「言葉で教える」という方法しかとりようがないからです。また、個々の子どもの興味や成長の状態に合わせることも出来ません。(そういうことを大切にしている、子どもの立場に立った保育園や幼稚園もありますが、数は少ないです。)でも古来から、大人達はただやってみせるだけで一々教えたりはしませんでした。子どもは「大人がやっていること」を見て、自分のタイミングに合わせて勝手に学んでいたのです。学びの基本は模倣だからです。大人は、そんな「学ぼうとする子どもたち」をサポートしていただけです。大人が学ばせようとしたのではなく、子ども自身が学ぼうとしたのです。だからこそ、子ども達は大人と一緒に生活しているだけで、大人の知識や技術や価値観を学ぶことが出来たのです。今でも異年齢の子どもの集団の中では同ようなことが起きています。子どもは他の子に丁寧に教えたりはしません。でも、同じ群れの中で遊んでいるだけで子どもは「遊び」を覚えてしまいます。子どもは、一々教えてもらわなくても、他の子がやっていることを見て自分の興味とタイミングに合わせて勝手に学ぶのです。それが子どもが本能的に持っている学びの能力なんです。そのような群れ遊びの場では「学び」が「教える側の都合」によってではなく、「学ぼうとする子どもの都合」によって成り立っているのです。そしてそれが学びの基本形なんです。そして、子どもの興味とタイミングに合わせて色々なことを伝えていこうとする行為が「導く」ということなんです。だから、「一対多」という状況では、教えることは出来ても導くことが出来ないのです。そもそも、「一人の大人が、いっぺんに大勢の子ども達に同じことを教え、同じ結果を求める」ということ自体が不自然であり、無理があるのです。子どもは一対一で語られる時には相手の言葉に耳を傾けることが出来ます。でも、「皆さん聞いて下さい」という状況で語られた言葉は知識としてしか入ってこないのです。「皆さん」の中に自分も含まれていることが分からない子だっていっぱいいるのです。そういう言葉で教育しても子どもは育たないのです。本来、大人と子どもの関係は「教える人」と「教わる人」ではないのです。同じ道を歩いている「先輩」と「後輩」であり、仲間なんです。先生と生徒は仲間なんです。親と子も仲間なんです。ただ大人の方がちょっと先輩だと言うことに過ぎません。だから「教える」のではなく「伝え、導く」のです。まただから、子どもに対して偉そうな態度を取ってはいけないのです。大人が偉そうな態度を取ると、子どもはそんな大人から学ぶ意欲を失ってしまうのです。そして、今の時代ではそういう導きが出来るのはお母さんやお父さんだけなんです。子どもに寄り添って、子どもの興味とタイミングに合わせて子どもの成長に必要なことを伝えていくことが出来るのは親だけなんです。でも、最近ではその親ですら一方的に子どもに色々なことを教え、覚えさせようとしています。仲間である、先輩であるということを忘れ「自分の方が偉いんだぞ、だから言うことを聞きなさい」という態度で子どもに接しているお母さんもいっぱいいます。保育園や幼稚園や学校に仕付けや教育を依存してしまっているお母さんもいっぱいいます。結果、人間として大切なことを学ぶことが出来ないまま大人になってしまう子が増えて来ました。*********************告知です。2022年度もやったのですが、続けて欲しいという声もあるので2023年もZoomでの子育て講座をします。名称は「ゆりかごオンライン」です。内容は子どものこと、子育ての事、子どもとの遊び方や関わり方、気質のことなどをお話しします。皆さんからの質問にもドンドン答えます。毎月第三金曜日の10:00~11:30(実際には12:00頃までになってしまいますけど)参加費 2000円/回録画もするので後から見ることも出来ます。参加申し込みやお問い合わせは「しの」までお願いします。以下は私が出した本です。アマゾンで買えます。
2023.01.14
コメント(0)
-
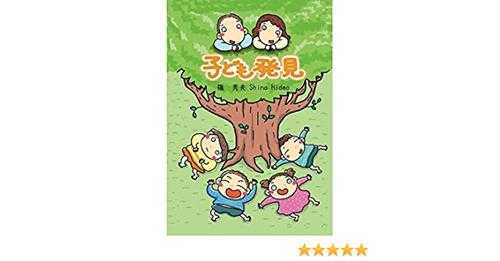
「お散歩を楽しくする遊び方」
私の子育てにおいて、お散歩の時間はゴールデンタイムでした。手をつないで歩くだけで幸せでした。でも、自転車や自動車に乗っていたら、手はつなげません。最近は、歩いていても手をつないで歩いている親子をあまり見かけません。子どもに「イヌに付けるリード」のようなものを付けて歩いている親子は見かけたことがありますが・・・。手をつないで「おててつないで・・」などと一緒に歌を歌いながら歩いたこともあります。でも最近のお母さんは子どもにあまり歌を歌ってあげないようです。おしゃべりはいっぱいしました。影踏みをしながら歩いたこともあります。白と薄茶の四角い石畳が敷き詰められている遊歩道で茶色だけを踏んで歩くとか、そういう遊びをしたこともあります。子どもが学校で「チーちゃんのかげおくり」を勉強してきた時、影送りをしながら歩いたこともあります。グリコ、パイナップル、と遊びながら歩いたことも、落ち葉やドングリを拾いながら歩いたこともあります。道ばたに咲いているタンポポの綿毛を飛ばしたり、花の蜜を吸ったり、桑の実を取ったり、ヤマモモの実を拾って食べたりもしました。以前、子育ての勉強会で子どもの頃の想い出を聞いたら、「お父さんと散歩に出かけて、帰りにオンブされて帰ってきた時のお父さんの背中を覚えている」と言っていた人もいました。子どもが大人になっても懐かしく覚えているのは、そういう日常的なことなんです。山道や野原を歩いたりもしました。食べられる野草を探して歩いたこともあります。シュタイナー教育の嶋村慶子先生とは長い付き合いですが(25年ぐらい前に、からだ関係の勉強会を一緒にやっていたので)、その嶋村先生から「町の中にお母さんとの特別な場所を作っていく」という遊びを教わったことがあります。(嶋村先生からは「シュタイナーの手遊び」も教えてもらいました。)例えば、お散歩の時にちょっと素敵な木、変わった木があったら、立ち止まり、触れてみたり、匂いを嗅いだり、葉っぱや花びらを観察してみたりすると、その木は「お母さんとの想い出の木」になります。お散歩の時にいつも座るベンチを決めておくと、そのベンチは「お母さんとの想い出につながる特別なベンチ」になります。お散歩の途中でちょっと立ち止まって、子どもと一緒に見て、聴いて、感じて、その感覚を共有するだけで、その時間や場所が、子どもに取っては特別な時間や場所になるのです。そして嶋村先生は、「町の中に、そういうお母さんとの思い出につながる特別な場所がいっぱい出来たら素敵ですね」とおっしゃっていました。あと、それと似ていますが「名所作り」という遊びも出来ます。観光地などに行くと、「ライオン岩」とか「○○岩」というようなものがよくありますよね。大体が、「そう言われればそう見えるかも知れない」レベルのものですが、子どもと一緒にそういう名所を発見したり、作ったりして遊ぶことも出来ます。この遊びは、子どもの観察力育てにもつながるでしょう。道ばたで発見した草や、小さな虫の名前を勝手に命名して遊ぶ遊びもあります。あと、お散歩の時に木の実や葉っぱや小石を拾って入れるような小さな袋を持ってくといいですよ。今の時期はお花はあまり咲いていませんが、種がなっていたりします。お花を摘むのは気が引けますが、種だったら取っても大丈夫です。ちなみに子どもは「拾う遊び」が大好きです。種にも色々な形があります。それを観察するのも楽しいです。また、お花の種をいつもの自分の散歩コースの途中に密かに植えて遊ぶことも出来ます。子どもと一緒に、「発見したもの」や「記念場所」を描き込んだ町の地図を描いてみるのも面白いと思います。こういうお母さんやお父さんと一緒に体験したこと、一緒に過ごした時間が、子どもが幸せな人生を送る手助けをしてくれるのです。また、勉強は教えなくても、こういう活動の全てが、後のお勉強の基礎になっていったりもします。*********************告知です。2022年度もやったのですが、続けて欲しいという声もあるので2023年もZoomでの子育て講座をします。名称は「ゆりかごオンライン」です。内容は子どものこと、子育ての事、子どもとの遊び方や関わり方、気質のことなどをお話しします。皆さんからの質問にもドンドン答えます。毎月第三金曜日の10:00~11:30(実際には12:00頃までになってしまいますけど)参加費 2000円/回録画もするので後から見ることも出来ます。参加申し込みやお問い合わせは「しの」までお願いします。以下は私が出した本です。アマゾンで買えます。
2023.01.13
コメント(0)
-

「歩育のススメ」(歩くことは出会う事です)
現代人は歩かなくなりました。歩くことを楽しまなくなりました。歩く時には「健康のため」という理由が必要になりました。一日何千歩と決めて歩いている人もいます。下を向いてひたすら歩いている人もいます。「早歩きの方が健康にいい」と言われているからかどうなのか、正面を向いたまま競歩のようにサッササッサと歩いている人もいます。歩くのでは物足りなくて「走る」人もいます。「トレイルラン」とか「ロングトレイル」というような、自然の中を走ることや、自然の中を長距離歩くことを楽しむようなスポーツをしている人もいますが、それは毎日の生活の一部としての活動ではありません。どうも現代人は「ただ歩く」ということの素晴らしさと楽しさを忘れてしまったようです。歩くためには当然家から出なければなりません。その時、風や光と出会います。家の近所を歩くだけで季節の花々や匂いと出会う事が出来ます。色々な音と出会うことが出来ます。遠くの音、風の音、鳥の声も聞こえてきます。夏には色々な虫とも出会う事が出来ます。歩いている人、買い物している人とも出会う事が出来ます。そういう人間観察も楽しいです。上を見上げれば青い空や、風の流れの中で形を変える雲と出会う事が出来ます。夕方なら夕焼けとも出会えます。空の色の変化とも出会えます。下を見れば、紅葉した落ち葉や、水に濡れた土やアスファルトと出会う事が出来ます。道ばたに咲いている小さな花とも出会う事が出来ます。太陽の光の色も、風の質感も、空の青さも、音の響きも季節によって違います。目的地に行くためだけに歩くのではなく、その過程を楽しみながら自分のリズムと感覚に従って自由に、ノンビリと歩くのです。そうすると本当に素敵なものと出会う事が出来るのです。でも急ぐと見えなくなってしまうのです。聞こえなくなってしまうのです。感じなくなってしまうのです。そのように歩いていると、自然の不思議、命の不思議とも出会う事が出来ます。美しいもの、醜いもの、怖いもの、可愛いものとも出会う事が出来ます。それだけではなく、自分のリズムと感覚に従って自由に歩いていると、呼吸が整います。からだのリズムが整います。すると心が落ち着いて来ます。前や上を見て歩けば胸が開きます。すると、閉ざされていた意識や心が開きます。色々な世界とつながることも出来るようになります。人は青い空を見ているだけで別の世界とつながることが出来るのです。すると、自分の悩みや苦しみに束縛されなくなるのです。そして古来から、日本人はそういうことを楽しむ感性を持っていたのです。そして、ここからが重要なことなんですが、実は、子どもたちを自由に歩かせるとこういう歩き方をするのです。今私が書いたようなことは、子どもが普通にやっていることなんです。子どもはそのような歩き方を通して、色々な世界と出会い、色々なことを感じ、好奇心に目覚めていくのです。同時に、心もからだも整い、安定します。でも忙しい大人達は、そういう子どもたちを「ちゃんと歩きなさ」「速く歩きなさい」と追い立てます。そうやって、子どもから「自分が生まれてきた世界」との出会いを奪っているのです。その結果、「自分が生まれてきた世界」の美しさも、素晴らしさも、不思議さも感じることが出来ないまま大人になっていきます。それが現代人の心の孤独につながっているのです。また、急かされて育った子は色々なことに効率や意味を求めるようになり、「ただ歩く」、「ただ生きる」、「ただ子育てをする」、「ただ学ぶ」、「ただ遊ぶ」ことを楽しめなくなります。ちなみに「忙しい」という文字は「忄(心)」という字と、「亡(うしなう)」という字を組み合わせたものです。心を失うから忙しくなるのです。そして、心を失った人はノンビリと歩くことを楽しめなくなるのです。そういう人は子育ても苦しくなるでしょう。「歩くことを楽しむ」ことと「子育てを楽しむ」ことは似ているからです。でも大丈夫です。子どもと一緒にお散歩して。子どもが見ている世界、子どもが聴いている音、子どもが感じているものを子どもと一緒に見て、聴いて、感じるようにしていると、次第に心が戻ってきますから。子育ての方法は、子どもに教えてもらって下さい。センス・オブ・ワンダー/レイチェル・カーソン/上遠恵子【1000円以上送料無料】【新品】だいじょうぶだいじょうぶ いとうひろし/作・絵
2023.01.12
コメント(0)
-
「老化する子ども、老化する現代人」(老化は脚から)
大分以前から、今時の子どもたちやお母さん達の状態に何らかの違和感を感じていました。何というか、心とからだの中がザワザワしているのです。これは感覚的なものなので分かる人には分かるかも知れませんが、分からない人には説明出来ません。そして、心とからだがザワザワしている人は、他の人の心とからだがザワザワしていてもそれを感じることが出来ません。落ち着きがない人は、落ち着きがない人を見ても「落ち着きがないな」とは感じませんよね。それと同じです。その1つの特徴としては待つことが苦手です。待つことが苦手なので、1つのことに集中するのも苦手です。じっくり考えるのも、工夫したり、イメージしたりするのも苦手です。そして、感覚の状態が不安定なので、小さな刺激にもすぐに振り回されてしまいます。体力も、気力も弱く、ちょっと失敗しただけですぐに投げ出します。そして、努力もしないくせに、うまく行かないとすぐに放り出します。そして、人の言葉に傷つきやすいです。競争相手がいれば少しは頑張るのですが、競争相手が居ない状態では頑張りません。自分の目標を自分で見つけることが出来ないからです。また、競争していても負けそうになるとすぐに放り出します。負けて傷つきたくないからです。自分自身の成長のために頑張るのではなく、勝ち負けを競うゲーム感覚なんです。お母さん達も、子どもがジーッとしていないだけで気になってしまいます。子どもの泣き声に耐えられないので、「どうして泣いているんだろう」と考えることなく、とにかく泣き止ませようとします。子どもの声、動き、行動が気になって仕方がありません。だからスマホに逃避します。また、小さな事ばかりが気になってしまい、子どもの全体の状態には意識を向けません。お母さんの言うことに素直に従っていれば、子どもの笑顔が消えていても気になりません。子どもに合わせることを楽しむことも出来ません。そういう人は「子どもと一緒に居る時間」を拷問のように感じ、「子育て」を「地獄」だと感じてしまうのでしょう。そして、自分を守るために出来るだけ早い時期から子どもを保育園に預けようとするのでしょう。「子どもと一緒に居ると辛いから、出来るだけ早く子どもを預けたい、それが子どもと自分のためだ」と言う人もいます。国もまたそういうお母さん達の声を受けて、保育園を拡充し、子どもを預けやすくしようとしています。この問題はいくら「子育ての正義」を説いても変わりません。「ママがいい」と言われても、そのような子どもの声を「ウザイ」と感じてしまうような人が変わるわけがないのです。言葉が届くためには、相手の中に言葉を受け取るための受け皿が必要になるのです。この場合は、その受け皿を作っているのが「からだの育ち」なんです。このような子どもの成長や子育てを巡る問題の背景には、現代人の「からだの問題」があるのです。だからいくら丁寧に子どもの心や成長のことについて理屈で説明しても解決出来ないのです。上に書いたような状態は一見「心の問題」のように思えますが、実は「からだの問題」なんです。特に、「歩かなくなったことから来る心とからだの萎え」の問題は大きいです。現代人は歩きません。多少は歩きますが、昔の人の歩く量に比べたら微々たるものです。昔の子どもは、平気で野山を何時間も歩いて遊んでいましたから。楽しい事を探して延々と歩いていたのです。歩かなくなることで足腰の筋肉や、「からだのつながりを支える筋肉」や、心肺機能が育たなくなっています。それが姿勢の悪さ、呼吸の浅さにもつながっています。今、風船を膨らませることが出来ない人がいっぱいいます。子どもでも大人でもです。さらには、そのような筋肉や、心肺機能の低下が、意思の力を弱め、思考を浅くし、刺激に対する過敏さと、感覚の不安定化をもたらしています。また家から出るのが億劫になることで、新しいものと出会ったり、自然と触れ合う時間も少なくなります。その結果、意識が閉ざされていきます。昔は、これは老人の問題に過ぎませんでした。子どもや若い大人には無関係な問題だったのです。でも、生活の中から「歩く事を楽しむ」という習慣が失われてしまった現代社会では、子どもたちも同じような状態になってしまっているのです。現代社会では、老人の年齢になる前から老人化が始まってしまうのです。「老化は脚から」という言葉の通りです。多くの子どもたちが、少年、青年、壮年を経過せずに、いきなり老人化し始めているのです。若いお母さんやお父さんの体力や感覚も老人化し始めています。お爺ちゃんやお婆ちゃんは孫が遊びに来ると喜びます。でも、相手が出来るのは短時間です。子どもの体力には限りがありませんが、老人の体力には限りがあるからです。「来て嬉しい、帰って嬉しい」という言葉は、そんな老人の心の状態を表した、なかなかの名言だと思います。でも、お母さんの心やからだも老人と同じような状態になってしまっていたとしたらどうなるでしょうか。孫と違って我が子は帰りません。いつまでもつきまとってきます。一日中、毎日。お母さんの心とからだが老人化してしまっていると、いくら子どもが大好きでも、体力も気力もないのですぐに疲れてしまいます。それでも子どもはまとわりついてきます。すると、イライラが溜まります。何とかして自分を守ろうともするでしょう。大人しく子どもが言うことを聞いてくれたなら・・・とも思うでしょう。その結果、つい、自分を守るために子どもを叱ったり叩いたりしてしまうこともあるでしょう。でも、子どもが嫌いなわけではないので冷静になってから後悔します。自己否定もします。苦しみます。<明日に続きます>
2023.01.11
コメント(3)
-
「子どもに合わせた子育て」(古代人としての子どもに寄り添う)
子どもは何万年も前と変わらない状態で生まれてくる普遍的な存在です。どんなに社会が変化しても、それは変わりません。それはつまり、子どもの心とからだの成長に必要なものも、基本的には何万年前と変わっていないということです。そしてそれはまた、社会が変化したからといって、簡単に子どもに求めるものを変えてはいけないということでもあります。特に、7才前の子どもは「人間社会」に属しているのではなく、人間の命を生み出している「自然」に属しています。そして、自然や神話と共に生きていた古代人と同じような心と、からだと、感覚世界を生きています。だから大人から見たら「訳の分からない存在」なのです。7才前の子どもが見ているものは、大人が見ているものとは異なります。同じリンゴを見ていても、「子どもが見ているもの」と「大人が見ているもの」は同じではないのです。音に対しても同じです。もちろん、言葉に対しても同じです。だから子どもは、大人と同じものを見て同じ音や言葉を聴いても、大人とは異なった反応をするのです。それは子どもを共感的に観察していれば分かることなんですが、現代人は監視は得意でも、共感的に観察することは苦手なようです。 ちなみに、大人でも心やからだは「自然」に属しています。「社会」に属しているのは「意識」や「知識」などの「頭の中味」だけです。その「頭の中味」を支えている「器」の方は「自然」に属しています。だから、いくら考えても悩みを消すことは出来ないのです。いくら考えても病気を治すことも出来ないのです。でも、姿勢や食を変えただけで悩みが消えたり、病気が消えてしまうこともあるのです。そのことを忘れ、「中味」だけを大切にして、「器」をないがしろにすると、「中味」が腐ったり、壊れてしまったりするのです。そしてそれが、現代人が直面している問題です。そんな現代人は、「自然」を「資源」としてしか認識していません。でも、自然の本質的な働きは「生命を育てる」ということなんです。木々も虫たちも動物も人間も自然の働きによって生まれ、自然の働きによって育てられて来ました。それが歴史的な真実です。そのため、人間が自然の働きを否定し破壊してしまったら、その自然によって支えられ、育てられてきた全ての生き物の生命が絶滅の危機にさらされてしまいます。もちろん、その中には「人間」も含まれています。7才までの子どもの成長を支えているのもまたその「自然の働き」です。心の成長も、からだの成長も、感覚の成長も、「人間のからだの中に組み込まれた自然の働き」の結果なのです。そして、その「人間のからだの中に組み込まれた自然の働き」は何万年も前から変わっていません。だからこそ、どんなに社会が効率やスピードを求めても、妊娠期間が短くなったり、3才、5才、7才、9才という成長の節目を早くすることは出来ないのです。また、早くしようとしてもいけないのです。でも、自然から切り離され、自然を感じる力を失ってしまった現代人は、「子どものからだの中で働いている自然の働き」も感じることが出来なくなってしまっています。そして、人工的に管理した状態で、もっと効率的に、もっと早く子どもを育てようとしています。また、現代社会は基本的に大人向けに作られていますから、その社会の中で子ども達が子どもらしく生きることは非常に困難です。家の中でも、家の外でも、子どもが子どもらしく走り回っただけで周囲の大人から苦情が来てしまうことさえあります。その結果、現代の子ども達は「7才まで」という「自然に属する時期」を充実させることが出来ないまま、社会へと押し出されることになってしまっています。昔から伝えられてきた「三つ子の魂百まで」という知恵も「迷信」として扱おうとしています。「子どもの中の自然」を否定しないことには、人工的に大人が創り出した文明社会、経済社会にとって都合が悪いからことが起きてしまうからです。でもそれは、子ども達が充分に人間としての心や、からだや、感覚を育てる事が出来なくなってしまっているということを意味しているのです。心や、からだや、感覚は「自然」に属するものだからです。そして、その上に「人間性」というものが育つのです。 確かに、現代の子ども達は多くの知識や高い能力を持っています。でもその一方で、「自分の生命を支えている心やからだや感覚の働き」は非常に不安定です。そのため、不安が強く、自己肯定感も低くなり、「一人の自立した人間」として生きるのが困難な状態になってしまっています。 子ども達が「自然」に属している時期には、子ども達を無理やり大人の価値観に合わせるように強制してはいけないのです。そうではなく、大人の意識や、社会や、子育ての方を子どもの状態に合わせなければならないのです。そうしないと、「子どもの内側で子どもの成長を支えている自然の働き」が萎えてしまい、子どもは「生きる力」や「成長する意欲」を失ってしまうのです。また、「子どもに合わせる子育て」をしているなら、発達障害の子も自分の能力に合わせて発達することが出来ます。 そんなに慌てなくても、7才を過ぎ、9才を過ぎ、思春期が近くなると子ども達は「社会」というものに興味を持ち始め、自ら大人の価値観を取り入れるようになるのです。それが「子どもの成長を支えている自然の働き」でもあるのです。だから、慌てず、追い立てず、その成長に寄り添って待ってあげることが必要なのです。
2023.01.10
コメント(0)
-

「〝生まれてきて良かった〟を伝える子育て」(7才までの子育て)
私は、3才までの子育てで一番大切なのは「生まれてきて良かった」ということを実感させてあげることだと思っています。3才~7才までの子育てで一番大切なのは、親や家族以外の仲間や大人とつながること、色々なことを体験し色々なことを学ぶこと、自分の考えや感情やイメージを表現することの喜びや楽しさを実感させてあげることだと思っています。前者は「生きていることに喜びを感じる心」を育て、後者は「生きて行くことに希望を感じる心」を育ててくれるでしょう。そして、親が直接子どもに伝えることが出来るのは、3才までの「生まれてきた良かった」ということを実感させてあげることだけです。その後の、3才~7才までの子どもの育ちに必要なことは、親そのものよりも、親がどういうつながりの中で、どういう生き方をしているのかということが大きく影響してきます。子どもは親が生きているつながりの中でしか、自分のつながりを得ることが出来ないからです。親が自然が好きで自然の中で遊ぶことが多ければ、子どもも自然の中で遊ぶことに喜びを感じるようになるでしょう。そして同じような感覚を持った子と仲間になるでしょう。親がゲーム好きなら、子どももゲーム好きになり、ゲームを通して仲間作りをするようになるでしょう。子どもは親の人生の一部として生まれ、思春期が来る頃までは親の人生の一部として生活していくことしか出来ないからです。5才頃から子どもは、幼稚園の先生や祖父母や近所の知り合いなど「親以外の大人」の影響も強く受けるようになりますが、それもまた親がつくったつながりの範囲内です。テレビからも影響を受けますが7才前の子どもが見る番組は親が管理出来ます。でも、7才頃からテレビの中の人物、本の中の人物からも影響を受けるようになります。見せていないテレビからの影響も学校で他の子から伝わってきます。ゲームも同じです。そうやって、子どもは少しずつ親から離れていくのです。でも、3才頃までに身につけた「生まれてきて良かった」という感覚や、7才までに身につけた「つながること、体験すること、学ぶこと、表現すること」を喜び、楽しむ感性は、よっぽど悲劇的なことがない限り、一生子どもの中で子どもの「幸せに生きる力」を支えてくれるでしょう。では、どうやったら幼い子どもは「生まれてきて良かった」と感じるのかというと、愛されていることを実感できる体験を通してです。それは、いつもお母さんが側にいてくれる。笑顔で話しかけてくれる。泣いたら抱き上げてくれる。また、子どもからの声や、表情や、動きに込められたメッセージをちゃんと受け取り、「言葉に依存しない対話」を大切にしてくれている時です。心の中では子どもをどんなに愛していても、実際の子どもとの関わり合いの中でそれが形として実現されていなければ、子どもは「愛されていること」を実感できないのです。子どもには「大人の都合」は理解出来ないのですから。「子どものために」とどんなに頑張っていても、お母さんが側にいなければ子どもは寂しい思いをするのです。また、成長に必要な心のエネルギーを得ることが出来なくなってしまうのです。ただし、3才を過ぎた頃から、少しずつお母さんの状況も理解出来るようになってきます。お母さんがいつも側にいなくても、一緒にいてくれる短い時間の中で愛情を感じることも出来るようになります。でも3才頃までは、お母さんが側にいなければ子どもはお母さんの愛を感じることが出来ないのです。ただし、状況によってはお爺ちゃんやおばあちゃんがその代わりをすることも出来ます。大事なのは、「信頼できる人がいつも側にいてくれる」ということなんです。昨日、「おかあちゃん革命」を出版した岐阜の森の幼稚園「もりわら」の園長である浅井智子さんと、「ママがいい」を書いた松井和さんの対談に行ってきました。そこでは、「大人の都合を優先させることによって生まれる悲劇」についての実例がいっぱい語られていました。ママがいい! 母子分離に拍車をかける保育政策のゆくえ [ 松居 和 ]アマゾンで売ってます。直接「もりわら」でも扱っています。(左が浅井智子さんです)
2023.01.09
コメント(0)
-
「心育ては言葉育てから、言葉育てはからだ育てから」
コミュニケーション力は「身体の感覚」によって決まる可能性が示される!?という記事があります。<こちらです>その記事の最後にはつまり体内の感覚に敏感な人ほど、アイコンタクトにも敏感であり、相手が微笑んだ時に自然と微笑んでしまうのです。アイコンタクトや表情模倣は円滑なコミュニケーション(社会性)と大きく関係しており、この研究結果は「ヒトの社会性が身体に根差す」という仮説を支持するものとなりました。とまとめられています。当たり前のことですが、英語を理解出来ない人は英語で話しかけられても理解出来ません。「英語が出来なければジェスチャーでも通じる」と言う人もいますが、ジェスチャーも世界共通ではありません。「お箸」というものを知らない人に、「お箸を使うジェスチャー」を見せても通じないのです。ジェスチャーもまた、同じ動作文化の人同士でないと通じないのです。日本では「yes」の意味を込めて頭を縦に振ります。でも、インドでは「yes」は頭を横に振ります。そのことを知らないと誤解が生じます。つまり、人と人の間でコミュニケーションが可能になるためには、双方が同じ言葉、同じ感覚、同じ体験を共有している必要があるのです。日本語特有のオノマトペが通じるようになるためには、日本語を通して自然と出会う体験が必要になります。英語でいくら説明しても通じないのです。日本人が感じている「風」は「かぜ」であって「wind」ではないのです。ということは、当然のことながら多様な言葉、多様な感覚、多様な体験をして育った子ほど、多様な人と、多様なコミュニケーションが可能になると言うことでもあります。外国に行っても異文化の人とコミュニケーションを取ることが出来るでしょう。また、そのような体験を通して育った人は、自分自身との対話能力も高いでしょう。(ただし、この場合の「多様な言葉」は、「多様な場面で多様な内容を扱うことが出来る言葉」という意味であって、必ずしも外国語を指すわけではありません。)そして最近の子どもたちは、「ゲーム」や「毀滅の刃」での体験や、その関連の知識を共通言語として使っています。でもそれ故に、「ゲームをやらない子」や「毀滅の刃を知らない子」は仲間に入れなくなります。言葉が通じないのですから。問題は、多くの子がそれ以外の「言葉の体験」、「感覚の体験」、「からだの体験」があまりにも少ないと言うことなんです。ゲーム語や毀滅語しか知らないような状態の子が多いのです。また、最近の子は「大人と共有出来る言葉」もあまり知りません。生活の中で、大人と子どもが対話したり、言葉や感覚や体験を共有するような場面自体が少ないのですからそれは当然の結果です。それでも子ども時代は、自分の周囲にいる子がみんな、自分と同じような状況の中で生活し、自分と同じ言葉を話しているのでコミュニケーションも取れるし、仲間も作れますが、そのままではその枠を超えた広い世界に出ていくことが出来なくなってしまうのです。実際、ゲームや毀滅の刃に夢中になっている子は、ゲームをやらない子や毀滅の刃を知らない子とはコミュニケーションを取ることが出来ません。同時に、ゲームや毀滅の刃を知らない人の中に入っていくことも出来ません。入っていってもコミュニケーションが取れないので楽しくありません。動物を生まれた時から檻の中で育てていると、檻の外で生きていく能力が萎えてしまうのと同じです。「子どもを守ってあげているんだ」と、子どもに「檻の中のような生活」を押しつけている人は多いですが、それは、子どもから「檻の外の世界で生きる能力」を奪っていることと同じなんです。子どもを、「目が届く狭い世界」の中に閉じ込めておくと大人は安心します。そしてそれが「親の義務」であるかのように思い込んでいる人もいっぱいいます。でも本来、親の「親としての役割」は、子どもをただ安全に保護することではなく、多少危険な目に遭っても、ケガをしても、ケンカをしても、子どもが自分の心と、からだと、知性と、意思で、他の人と助け合いながら自分の人生を自分自身のものとして生きる能力を育てることなんです。そしてそのためには、多様な言葉、多様な感覚、多様な体験を子どもに与えてあげる必要があるのです。そういうものが身についた子は自信を持って外の世界に出ていくことが出来るのです。そしてそれらは学校で学ぶような知識では代用できないのです。いくらいっぱい知識を与えても、多様な言葉、多様な感覚、多様な体験を持っていない子にはそれらは「ラベルが貼ってあるだけの空き容器」に過ぎないからです。並べて眺めるだけならそれでもいいのですが、何の実用性もありません。ただ邪魔なだけです。実際の「木」を見たことも、触れたことも、匂いを嗅いだことも、登ったこともない子に、「木」という言葉とその意味を伝えても無意味なんです。でも、親も、教師も、みんなその意味のないことばかりをやっています。そして、子どもに多様な言葉、多様な感覚、多様な体験を伝えるためには、「からだ育て」も同時並行してして行うしかないのです。「からだでの体験」を通してしか、そういうものは心とからだの中に入っていかないからです。雑巾を絞らせることで「絞る」という「感覚体験」と「からだ体験」が出来ます。そしてその「感覚体験」や「からだ体験」と「絞る」という言葉をつなげてあげることで、子どもは「絞る」という言葉を身につけることが出来るのです。その体験抜きに「絞る」という言葉を教えても、言葉が身につかないのです。そして身についていない言葉では、深いコミュニケーションが取れないのです。「心育て」は「言葉育て」から始まります。そして「言葉育て」は「からだ育て」から始まるのです。「賢さ」もその流れの中で育ちます。でも、そんなに難しく考えることはありません。様々な感覚体験や感情体験を子どもと共有するような形で子育てを楽しんでいれば、子どもは自然とお母さんからそういう言葉や感覚を受け取って行くのですから。ご飯を食べる時に「美味しいね」と言って顔を見合わせるだけで、子どもは「美味しい」という言葉と「美味しい」という感覚をつなげることが出来るようになるのです。夕焼けが出ていたら、足を止め「きれいだね」と言って、一緒に見ているだけでいいのです。簡単でしょ。でも、子ども一人だけでご飯を食べさせていたり、買い物の時に自転車や自動車で家とお店を往復するだけではそういう体験は出来ませんけどね。
2023.01.08
コメント(0)
-
「全ての始まり」(頭でも、心でもなく、からだに意識を向けて下さい)
昨日は悲観的なことばかりを書いてしまいましたが、救いがないわけではありません。でもそのためには、人間が「頭」でも、「心」でもなく、「からだ」という視点を取り戻す必要があるのです。人間にとっての全ての原点が「からだ」の中にはあるからです。だから、「からだの中の声」に素直な状態の幼い子どもたちは誰からも教わらないのに「人間として一番大切なこと」をちゃんと知っているのです。また大人でも、病気になったり年を取ったりしてからだが思うように動かなくなると、「からだ」に意識を向けることが多くなり「本当に大切なこと」を想い出すのです。(気付かないままの人も多いですけど・・・)実は、「頭の問題(価値観や思想的な問題)」や「心の問題(感覚、感情の問題)」の背景にも「からだの問題」が隠れているのです。昨日書いたような科学の暴走が起きてしまうのも、人々が「からだの声」に耳を傾けることを忘れてしまったからです。子どものことを理解出来ない大人が増えたのも、人々が、「頭の声」や「心の声」にばかり振り回され、「からだの声」に耳を傾けなくなったからです。でもそのことがなかなか理解されません。人間という存在を「つながり」(システム)として見ようとしていないからです。人は腰が痛いと腰を治療しようとします。すると一時的には良くなります。でも、実際には腰が痛くなる原因が腰ではなく、別の所にあることも多いのです。内臓の状態や、姿勢の状態や、からだの使い方の状態が「腰痛」という形で現れる子ともあるのです。脚の具合が悪くなることで頭痛が起きることもあります。でもみんな、頭が痛い時には頭痛薬を飲み、お腹が痛い時には胃腸薬を飲んで乗り越えようとしています。これは、「からだ」の問題だけではありません。不登校やイジメなどといった「大人にとっては困った問題」を起こすことが多い子が増えて来ましたが、もしかしたら「問題を起こす子の増加」は「問題を起こさない良い子達」の心とからだの歪みが原因かも知れません。「システムとして働いているもの」において何かトラブルが起きるような時には、まず「現象が現れやすい弱いところ」にトラブルが表れるのです。でも人は、本質的な原因を探ることなく、現象が現れたところにしか目を向けません。そして、対症療法だけで何とかしようとします。だから、全体の状態はドンドン悪化していくのです。確かに対症療法でも、一時的には見かけ上の問題は解消されるのですが、しばらくするとまたぶり返します。本質的な問題が解決していないからです。そして、ぶり返す度に悪化していきます。でも多くの人が、さらに薬を飲むことで症状を抑えようとします。問題児であれば、更に強く叱ったりすることで問題を回避しようとします。でも、同じことが何回も繰り返されます。そして、本質的な問題がドンドン悪化していきます。一時的に子どもの問題行動を消すだけなら、強く叱って恐怖心を与えたり、ぶったりして痛みを与えれば可能かも知れません。でも、それを引き替えに子どもから笑顔が消えます。そして、子どもの笑顔が消えるような方法では本質的な問題は解決出来ないため、心の中の歪みはさらに強くなります。そして、抑えきれなくなると破滅的な暴走を始めます。社会全体がこのことに気付くためには、もっと強い痛みが必要なのかも知れません。でも、その過程で悲しいこと、苦しいことも増えていくでしょう。そうなる前に「からだの大切さ」に気付き「からだの声に耳を傾ける」ことに気付いて欲しいと思っています。「幸せ感覚」は「脳」ではなく「からだ」がもたらしてくれるのですから。お酒や麻薬は脳を麻痺させ、一時的にでも悲しみや苦しみを忘れさせてくれます。だから、一時の幸福感を得ることは出来ます。でも、それは本当の幸福ではないのです。
2023.01.07
コメント(0)
-
「不都合な真実に目を向ける」(マスコミに振り回されないでください)
人類が今の知能、精神性を得るまでに10万年以上かかっています。それに対して、「科学」と呼ばれるものが生まれ、今のレベルになるまでに数百年しか掛かっていません。それどころか、ここ数十年の進歩はそれまでの数百年の進歩を簡単に追い越してしまいました。そしても、はや人間には手に負えないレベルにまで進歩してしまいました。今や、自分の望む髪の色、肌の色、背の高さ、顔カタチまで自由にデザインして子どもの遺伝子を設計できるようにまでなりました。将来、自分が怪我をしたり、病気をしたりした時に使える予備臓器として、自分の遺伝子を使って自分のクローンを作ることも出来ます。体力、筋力に優れ、恐怖心を感じない兵士を作り出すことも出来ます。ブタに人間の臓器を生産させたり、人間の赤ちゃんを産ませることも可能になりつつあります。そうなったら、お母さんたちは全く痛みを感じずに自分の子どもを得ることが出来るようになります。今は、「えー」と感じる人も多いでしょうが、普及し始めたら喜ぶ人も多いのではないかと思います。それが今までの科学の流れでもあるからです。テレビが出た時は、子どもの育ちに対する悪い影響を警告した人もいっぱいいました。でも今では、テレビの利点を言う人は多いですが、強く問題点を言う人はあまりいません。言ってももう無駄な状態になってしまっているからです。ゲームも同じです。だから「ブタ母さん」も実用化すればマスコミはその利点ばかりを喧伝し、それに飛びつく人も多いでしょう。何か問題があったとしても、その問題が顕在化する時には、もう取り返しがつかないところまで進んでしまっているでしょう。今までも、同じようなことが繰り返されて来たのですから。自然破壊の問題だって、昔から警告していた人は何人もいたはずです。でも、その時に耳を傾ける人は少数でした。だからこういう結果になってしまっているのです。良心的な科学者たちは、そんな進み過ぎてしまった科学の扱い方に対して慎重になるように求めています。原爆が造られた時も同じです。「こんなもの作っちゃいけない」と反対した科学者たちもいたのです。でも、軍部はそれを受け入れませんでした。現代の日本でも、マスコミはそういう良心的な科学者の言葉はあまり取り上げません。昔も今も、経済の活性化に反するような考え方に対しては、政治家も、経済界も、マスコミも否定的な対応をとるのです。将来的には危険性があっても、目の前に利益があればそれを取るのです。特に権力の座にいる人は、自分の権力を維持するためにそれを利用しようとするのです。本来、民主主義という政治形態にはそういう権力者の暴走を防ぐ機能もあるはずなんですが、今の日本の民主主義は民主主義として機能していません。だからこそ、子どもを育てる立場にいる人たちは、政治家やマスコミの言葉に惑わされずに自分で情報を集め、自分の頭で考え、自分の感覚で感じ、自分の意志で判断し、行動する必要があるのです。子どもの成長に関しては後から後悔しても遅いのです。精神的に未熟な大人が増えれば、ますます、正常な判断が出来る人が減ってしまうからです。現代社会を支えている「不都合な真実」に気づいて下さい。
2023.01.06
コメント(0)
-
「子どもを大切にしない社会は滅びます」
子どもを大切にしない社会は必ず滅びます。これは当然の流れです。確かに、社会を動かしているのは大人です。でも、その大人は子どもが成長した結果です。誰一人として、子どもという過程を通らないで大人になることは出来ないのです。そして、社会を正常に動かし、人々が平和に幸せに生きることが出来るような社会を作り、それを維持するためには当然のことながら、それ相応の能力が必要になります。肉体的には大人であってもその能力を持たないものが社会を支配したら、社会が乱れ、人身も道徳も荒廃し、人間性も精神文化も失われ、社会というシステムを維持出来なくなります。家族というシステムすら維持出来なくなります。だからこそ、子育てや子どもの教育から手を抜いてはいけないのです。でも、現代の大人たちは、子どもたちの「平和で幸せな社会を作り出し、維持する能力」を育てるのではなく、「すでに出来上がっている社会に適合するような能力」ばかり育てようとしています。でも、「すでに出来上がっている社会に適合するような能力」だけでは、社会の流れがおかしな方向に向かい出してもそれを矯正することが出来ません。そのことに気付くことすら出来ません。むしろ、その流れを加速してしまいます。同じようなことが第二次世界大戦の時にも起きていました。国民がみんな軍部が作り出した社会に適合することばかりを目指すようになってしまったため、泥沼に入り込んでも抜け出せなくなってしまったのです。「人間にとって一番大切なものはなんなのか」、私たちはそれを見失ってはいけないのです。子育てや教育の場でもそのことを一番大切にすべきなんです。そのためには、子どもを大人や社会に合せようとするよりも先に、「人間にとって一番大切なことは何なのか」ということを「普遍の世界を生きている子ども」から学ぶ必要があるのです。子どもから笑顔が消えていたら、家庭や学校や社会は間違った方向に進んでいるのです。
2023.01.05
コメント(0)
-
「〝なぜ?〟と問いかけてみませんか」
子どもと大人の違いはいっぱいありますが、「非常に好奇心が強い」ということも、子どもが大人と大きく違うところだと思います。大人でも好奇心の強い人はいますが非常に少数です。でも、幼い子ども達はみんな好奇心の固まりです。多分、人類にもそのような時代があったのだと思います。「子どもの心の発達」は、「人類の心の発達」を繰り返しているように思えるからです。そのような時代に、様々な神話が生まれたのでしょう。「なぜ?」があるから、物語が生まれるのです。それは科学でも同じですよね。そして、幼い子ども達は「なぜ?」の答えを物語の形で求めます。でも知的に目覚め始める思春期が近くなった子どもは「客観的な論理」で求めます。それが「科学的な心」の目覚めです。7才前の子どもなら「どうしてリンゴが落ちてくるの」という問いに、「クマさんがお腹を空かせているからよ」で納得しますが、思春期が近い子どもは「地球には重力というものがあってね」という説明の方で納得します。(実際には、リンゴは「地球の重力」だけによって引っ張られて落ちるのではなく、リンゴもまた地球を引っ張っているのです。リンゴにもその質量に応じた「重力」があるのです。)そして、思春期もまた「なぜ?」がいっぱい生まれる時期です。そして、「生きる意味」のような子どもの頃とは違う物語を求め始めます。でも、なぜだか分かりませんがそれ以降、大人になってしまうとあまり「なぜ?」を感じなくなります。それは「自分の頭で考え、自分の感覚で感じる」ことをしなくなるからなのでしょう。そして、自分の頭で考えるより、本やネットの中に「知識」や「正解」を探すようになります。それに対して、子ども達はいつも自分の頭で考え、自分の感覚で感じています。だからこそ、その答えは常に大人の常識とは無関係に「個性的」なんです。自分の頭で考えなくなった大人達は、子ども達のその「個性的な答え」を馬鹿にして、世間一般の知識や常識を教えます。でも、子どもにはその「世間一般の知識や常識」が理解出来ません。そこで、親と子、大人と子どもの対立が生まれたりします。ただし、大人になってももその「なぜ?」が消えない人もいます。私もその一人です。ですから私はいつも「なぜ?」と考えています。そして「どうしてみんなはなぜ?と考えないのだろう?」と考えています。どうしてマスコミはメリットばかりを言い立てて、デメリットについては言わないのだろうか?というのも、その一つです。ネットで色々な情報を調べていると、今人類も、地球も、自然も大変な状況にあることが分かります。でも、テレビでは単なる娯楽しか流しません。学者達はテレビやゲームや早期教育の害をよく知っていますが、マスコミはその害については知らん顔しています。原発推進派は原発のメリットばかり語り、反原発派は原発を止めるメリットしか語りません。そして、双方共に、デメリットについて語ると「悲観的だ」とか陰謀論者だと言われたり、パッシングを受けたり、仲間から追い出されたりします。戦争中、「兵隊さんがかわいそう」と作文に書いた少女が、「反日的」「赤だ」ということで、厳しく叱られたそうです。今の日本にも同じような状況はあります。そして、「なぜ?」については誰も言及しません。「なぜ?」と言っただけで「反日的」と言われてしまうこともあります。なぜ人は大人になると「なぜ?」と問いかけなくなるのでしょうか。不思議です。自分の身を守るためでしょうか。
2023.01.04
コメント(0)
-
「物語を語ってあげて下さい」(頭育てよりも心育てを先にして下さい)
「物語とは何か?」というと、それは「つながりを言葉で紡ぐこと」です。昔々 あるところに おじいさんと おばあさんがおりましたおじいさんは やまに しばかりにおばあさんは 川に 洗濯に行きましたおばあさんが 川で洗濯をしていると大きなモモが つんぶく かんぶく と流れてきましたここで語られているのは「空間的つながり」と「時間的つながり」です。「おじいさん」と「おばあさん」という「人と人のつながり」も語られています。そこに「桃太郎」が加わり、さらに、人間以外のイヌ、サル、キジが加わります。そして、それぞれが、それぞれの得意技を使って「鬼」と戦うことになります。「桃太郎」だけでなく、日本にも世界にも、太古の昔から「昔話」が存在していて、人々はそれを語り継いできました。その内容の多くは荒唐無稽で、実際にはあり得ないようなものばかりですが、昔の人はそれを大切に受け継いできたのです。神様のことを語った「神話」と呼ばれるものも「昔話」の仲間です。「人と人の物語」「人と自然の物語」「人と動物たちとの物語」「生と死の物語」「善と悪の物語」「見える世界と見えない世界の物語」、そういうものが「昔話」という形で語られ、受け継がれて来ました。人々は「物語」を通して、「自分が生まれてきた世界」の「目では見ることが出来ないつながり」を理解し、「自分もそのつながりの一部であること」を理解して来たのです。人は「科学」を知らなくても生きて行くことが出来ます。実際、人類は何十万年と科学なしで生きてきたのですから。でも、人はなぜか自分のルーツを知りたがります。自然の不思議の意味を知りたがります。なぜ人は生まれ、死んでいくのかということの理由も知りたがります。これは「心」というものに目覚めた人間としての本能なのかも知れません。なぜなら、幼い子どもたちも「心」が目覚める頃になると同じようなことを聞いてくるからです。皆さんも「なんでお月様は私に付いてくるの」と子どもに聞かれたことがあるのではありませんか。子どもから「何で人を殺してはいけないの?」と聞かれて、「今時の子はそんなことも分からないのか」と驚く人もいますが、でも、そのことを子どもにも分かるようにちゃんと説明出来る大人は少ないです。科学でも説明出来ません。皆さんは説明出来ますか。実は、「人が人を殺してはいけない」という理由は物語という形でしか説明出来ないのです。科学が扱っているのは物質世界の事だけです。そして、物質世界だけの話なら、人が人を殺しても「ああ、そうですか」というだけの話です。科学は善悪の判断はしませんから。「心の世界とつながるようなこと」は「科学」という形ではなく、「物語」という形でしか伝えようがないのです。でも現代人は、物質の世界しか扱うことが出来ない科学」のことばかりを大切にして、「心の世界を扱うことが出来る物語」を大切にしません。だから「頭育て」は出来ても「心育て」が出来ないのです。<続きます>
2023.01.03
コメント(0)
-
「人は物語を生きる生き物です」(物語を育てる子育て)
人の心は「物語」で出来ています。人が自分が生まれてきた意味、生きている意味を知りたがるのも、人の心が物語で出来ているからです。人間は「意味」を知りたがる唯一の動物ですが、「意味」というものは「物語の流れ」の中でしか意味を持たないのです。お正月に神社に行って拝むのも、そこの何らかの「意味」を感じるからです。「みんながやっているから」というのも立派な「意味」です。神様を信じる人は「神様が存在する物語」を生きているのです。神様を信じない人は、「神様が存在しない物語を生きているのです。それだけの違いです。科学を信じている人は「科学が創り出した物語」を信じているのです。愛、勇気、希望、不安というような言葉や感情は物語の流れの中で生まれてきます。「人を殺すのは悪いことだ」「牛やブタは人間に食べられるために生きている」というのは社会が創り出した物語です。子育てをする動物はいっぱいいますが、子育てに何らかの意味を見いだそうとするのは人間だけです。人の生き方は、「その人がどういう物語を生きているのか」ということで決まります。そして、子どもはその成長の過程で出会う人の物語の影響も受けます。子どもは「お母さんの物語」と「お父さんの物語」が交差するところで生まれます。そして、「お母さんの物語」と「お父さんの物語」を土台にして、そこに自分固有の要素を加えて「自分の物語」に目覚め始めます。洗脳すると言うことは、その人がそれまで生きてきた物語の筋を強制的に変えてしまうことです。物語の筋が変わると、その人がそれまで持っていた物事の意味も全て書き換わります。また気質の違いも、その物語の形成に大きな影響を与えています。気質の違いがその人の人生を「冒険もの」にしたり、「恋愛もの」にしたり、「ファンタジーもの」にしたりするのです。そして、生きている物語が異なっていると、会話も通じなくなります。「木を大切にしよう」というような簡単な話しですら、会話が通じません。同じように「木は大切だ」と言う人でも、「木は大切だ、だから木を切ったらその分苗木を植えなければいけない」と言う人と、「木は天と地、そして様々な生き物たちのつながりを支えているものだから出来るだけ切らない方がいい」と考える人とでは話が通じないのです。そんな時、幼い時から「他の人との肯定的な出会い」の多かった子は、その人の物語の良いところも取り込もうとします。そうやって、「自分の物語」を豊かにしていくことが出来るのです。また、「自分の物語」の展開にも多様な選択肢を得ることが出来ます。でも、他の人との出会いが少なかったり、否定的な出会いばかりが多いような子は、「否定的で貧弱な物語」しか育てることが出来なくなります。「こんな人生は嫌だな」と思っても、その物語を書き換えることが出来ないのです。そういう人は、誰かに依存し、その人の物語の一部になることで、「違う物語」を得ようとすることもあります。そういう人は、自分の頭で考えようとしません。自分の感覚で感じることも、自分の意思で判断し行動することもありません。
2023.01.02
コメント(0)
-
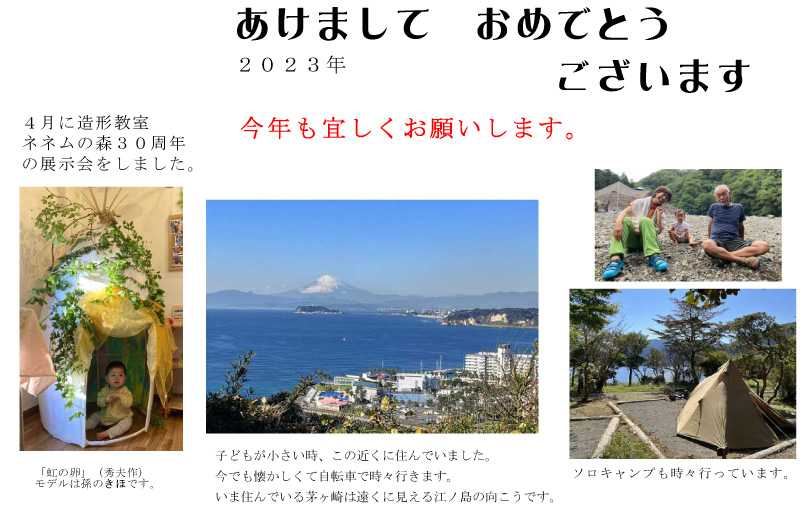
「明けましてお目出度うございます」
色々なことが決着がつかないまま年を越してしまいましたね。こういう時代だからこそ、自分の頭で考え、自分の感覚で感じ、自分の意思で判断し行動することが大切なんですよね。子育てにおいても、子どもたちのそういう能力の育ちを支えることが、未来への希望になって行くのですよね。「良い年」は神様に願うものではなく、自分たちで創り出すものなんですから。
2023.01.01
コメント(0)
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
-

- 子育て奮闘記f(^_^;)
- 子供の水筒を守りたい‼️ついに買いま…
- (2025-11-25 18:00:05)
-
-
-

- 子供服ってキリがない!
- 2026年 春物 アンパンマン スムスパ…
- (2025-11-26 12:10:04)
-
-
-

- 大学生母の日記
- 美濃吉「京の旬彩 丹波若どりの味噌…
- (2025-11-18 10:44:22)
-







