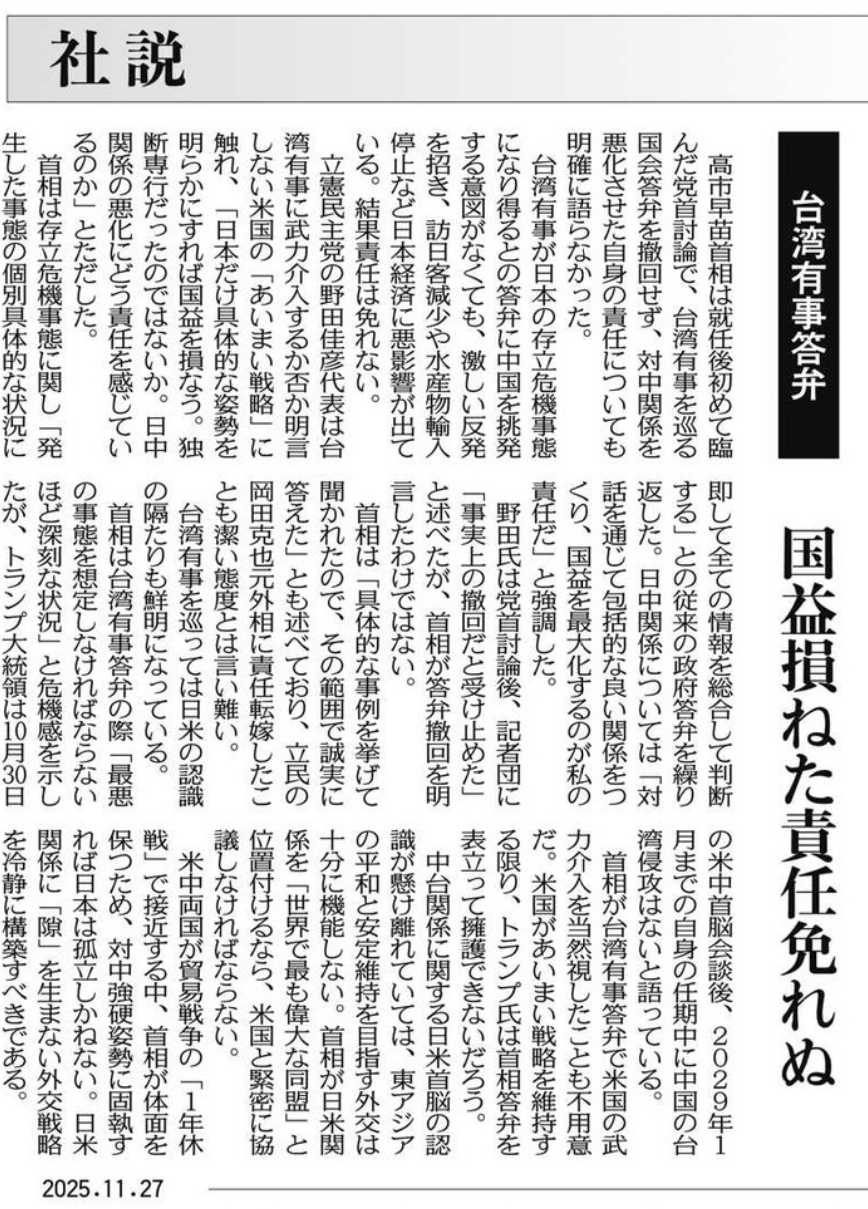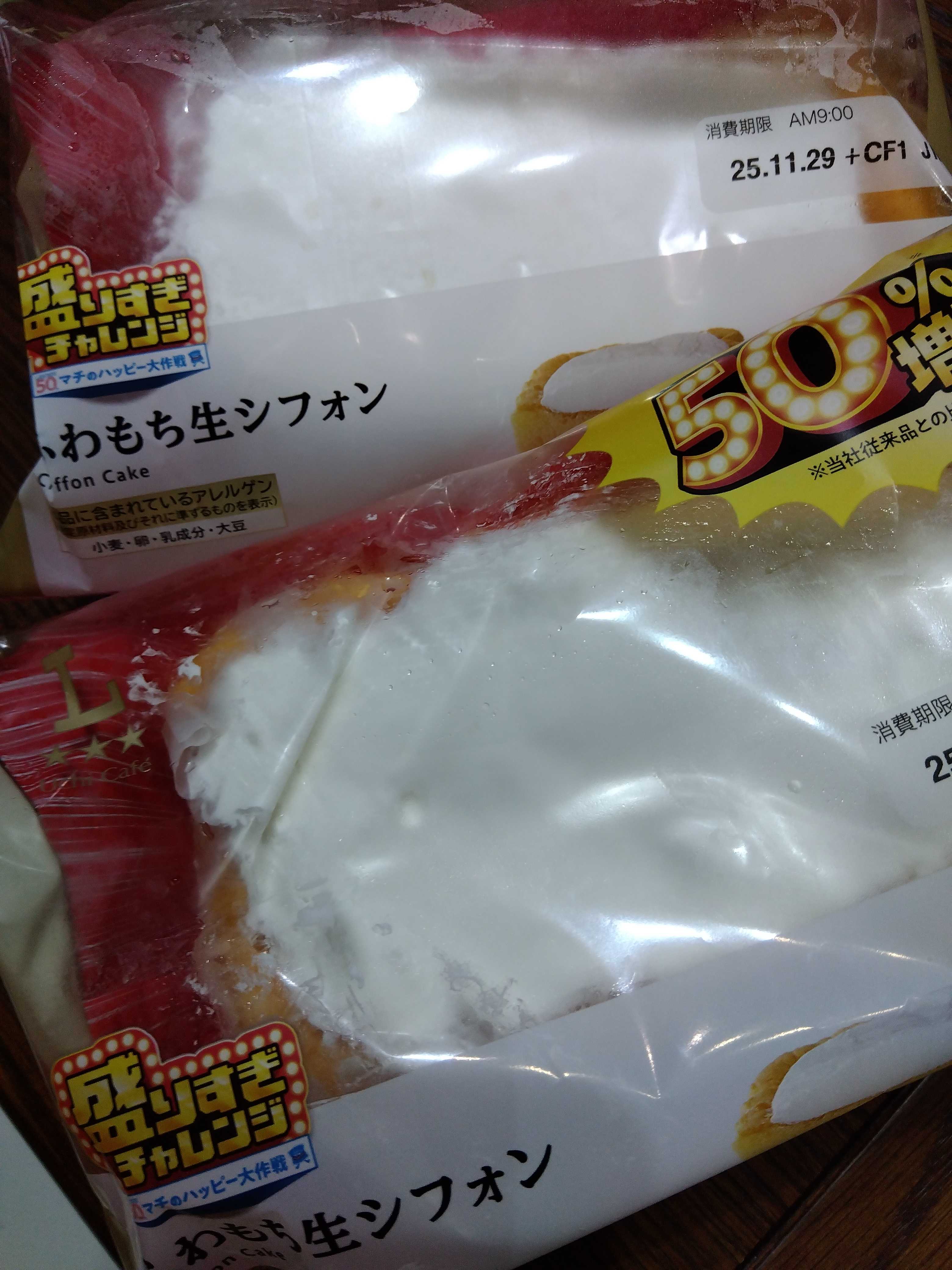2018年07月の記事
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-
段々キツくなってくる
期末試験のシーズンとなり、ようやく夏休み目前となって参りました。 で、今年はどこへ行こうかなと思案したのですが、毎年ロスというのも何とかの一つ覚えかなと、今回はショバを変えることにいたしました。 で、考えた末、今年はポートランドに行くことに決定! カリフォルニア州の北、オレゴン州ですな。 まあ、今全米で一番注目の街。アメリカの都市にしては珍しく、公共交通機関が発達。自転車道の整備もされていて、治安も良いというのですから、今、全米各地から引っ越して来る人が多いのもある意味当然。 しかも、消費税がないという。ここで買い物しないで、どこでするの? もちろん、シアトル同様、サードウェーブ・コーヒーでも有名。街のあちこちからコーヒーのかぐわしい香りが漂ってくる・・・らしいです。 一方、私の研究方面では、街中にポートランド州立大学がドンとある。そして、むしろこちらの方が私の関心を惹くのですけれども、有名な「パウエルズ」という書店の本拠地。新刊本と古本を両方扱う巨大書店で、私はここから随分沢山の本を買いましたが、それはネット上で買うのであって、本店に行くのは初めて。 しかし! 大昔は、名古屋―ポートランドの直行便(デルタ)があったもので、私が最初にロスに行った時は、ポートランド経由で当時の名古屋空港から旅立ったものですが、今はそんな便はなし。下手すると3度乗り換えとか、そんなのばっかりになってしまったのですが、それでもなんとか、往復とも成田乗り換えだけで済む便を探し出して予約したところ。 それにしても、旅慣れない私にとって海外旅行というのは、決して楽しいばかりではありません。飛行機の予約、アパートの予約、そういうのがもう面倒で面倒で。大きいスーツケースを引っぱってえっちらおっちら空港を右往左往するのも相当なストレス。 もう、アメリカ西海岸ですら私には遠い! せいぜい、ハワイがいいところ。 これからはハワイに滞在しなければならない研究課題を探すしかないな・・・。
July 30, 2018
コメント(0)
-
吉岡秀隆版金田一耕助
今日、というより昨夜の話ですが、NHKBSで『悪魔が来たりて笛を吹く』をやっていたので、つい見てしまいました。 今回のシリーズでは、金田一耕助役は吉岡秀隆さん。もちろん、それも見どころであるわけですよね。 で、見た感想ですが・・・ ・・・イマイチかな。 まあ、私も横溝正史ものに詳しいわけではないし、さほど思い入れがあるわけではないのですが、脚本・演出ともにイマイチだったような。 で、吉岡金田一の出来ですが、これまた私のイメージとは少し違いましたかね。 じゃあ、歴代金田一の中でどれを推すかですけれども、私の場合はテレビ版の古谷一行さんなんだよなあ。石坂浩二ではなく。 あの古谷版金田一シリーズは、良かったよね! 雰囲気がすごく良かった。茶木みやこが歌ったテーマソングも凄く良かった。 あのイメージがあるものだから、私としては古谷版を基準に見てしまう。で、その観点からだと吉岡版金田一は、金田一的なバンカラっぽさがモノ足りないわけよ。古谷版が早稲田っぽいとすると、吉岡版は成蹊っぽいというか。言っていることが自分でもよく分かりませんが。 あ、あと、倍賞美津子さんの老けぶりがちょっと心配になるレベルだったのも気になるところ。アントニオ猪木さんは元気なのにね。 しかし、横溝正史ものって・・・結局、貴族とか庄屋とか、とにかく土地のお偉いさんに一人、エロじじいがいて、そいつがエロいことするもんだから後々面倒なことになるっていう筋書きばっかりだね! さてさて、本作の最後で、次は『八つ墓村』みたいなことが予告されていましたが、このままずっとシリーズ化するのでしょうか。でも、ま、次は見ないかな。どうせまた別なエロじじいが悪さするだけだもんね。
July 30, 2018
コメント(0)
-
バーバラ・フレドリクソン著『ポジティブな人だけがうまくいく3:1の法則』を読む
ポジティブ心理学の創始者マーティン・セリグマンの愛弟子、バーバラ・フレドリクソンの書いた『ポジティブな人だけがうまくいく3:1の法則』(原題:Positivity, 2009)を読みましたので、心覚えをつけておきましょう。 「女性向け自己啓発本」の現在地を知るべく、女性著者の手になる自己啓発本を読み漁っているのですけれども、この本もそんな一冊。ポジティブ心理学の本を読むと、大概、バーバラ・フレドリクソンの名前が出てくるので、どんなもんかなと思って読んでみたわけ。 で、その内容ですが、なにせ「ポジティブ心理学」自体が20世紀ももうすぐ終わるという時期に打ち出された概念ですから、2009年に本書が書かれた頃には、まだ出発してから10年程しか経っていないという状況なわけですよ。だから本書でも、「なぜポジティブ心理学なのか」的な前置きから入るんですな。つまり、「ポジティブな感情は何の役に立つのか?」という辺りから話が始まる。 「ネガティブな感情は何の役に立つのか?」という問いには、簡単に答えられます。例えば、原始時代、人間がライオンみたいな野生動物に襲われたとお考えください。もちろん、「やばいっ!」と思うわけですよね。で、とたんに「怖れ」という感情に火がつき、逃走に備える。あるいは「こんなところで死んでたまるか」という感情に火が付き、闘争に備える。あるいはライオンに対する「憎悪」が、そもそもライオンを避ける行動を引き起こす。 かくして「怖れ」「怒り」「憎悪」といったネガティブな感情は、人間が生き延びることを助け、そうやって助かった人間が増え、その感情を次世代につないでいくことで、今日の人間が存在していると。 だから、ネガティブな感情が有意義だ、というのは、すごく分かりやすいわけね。それに、このことは、「感情」というものが自然淘汰によって継承され、感情(精神的なもの)が身体的変化(例えばアドレナリンの分泌など)に影響を及ぼす理由を明らかにしたという点で、価値のあることだった。 で、この調子なら、「ポジティブな感情」のメリットだって簡単に見つかるだろうと思ったのですが・・・案外そうでもなかったんですな。原始人の子供が楽しそうに遊んでいたとして、その楽しい感情が一体彼の何に役立っているのか全然分からないわけ。「怖れ→逃走→生存」といったような直接的な因果関係が思いつかなかったんですな。 で、バーバラさんが色々考えたり、実験したりした揚句、この疑問に対する答えとして打ち出したのが「拡張=形成理論」という奴。 ネガティブな感情が引き起こす行動、例えば危ない状況に陥ったから逃げる、ということを考えてみると良く分かるのだけど、この場合の行動は「逃げる」の一択、あるいは「反撃する」を含めた二択ですよね。つまり、選択肢は極端に狭いわけだ。というか、選択肢を狭めることで、生存の可能性をアップさせているわけね。 だけど、ポジティブな感情は、これとは逆に、選択肢の幅を広げる(拡張する)方向に働くのではないかと、バーバラさんは考えたわけ。 例えば、サルとか地リスの社会を観察すると分かるのですが、それらの動物が子供の時に一緒に遊んだりするわけですな。で、「楽しい」という感情を共有する。すると、大人になって敵に襲われたりしたときに、互いに助け合うらしいんですよ。つまり、DNA的には何のつながりもないのに、相手の危機を救う方向の行動に出たりする。これは「楽しかった子供時代の思い出」が、血縁のない他の個体を救うという、本人にとってはあまりメリットのない行動に駆り立て、そのことによって集団として生存率を高めることに成功していると。 だから、ポジティブな感情の影響の視野は広く、またスパンは長いわけね。そして、本能にはなかった行動様式を形成している。これがバーバラさんの「形成=拡張理論」ね。 で、ポジティブな感情が人の役に立つことは分かったとして、じゃあ、実際にはどういう風に機能しているのか。 ま、人間の生活ですから、日々、いいこともあれば、悪いこともある。ポジティブな感情を抱けるような出来事もあれば、ネガティブな感情を抱かざるを得ないこともある。これはもう、避けられないわけですな。 問題は、むしろ両者の比率なんです。一日のうち、ポジティブな感情を抱いたケースと、ネガティブな感情を抱いたケース、どちらが多かったか、というその比率。 で、もちろん、ネガティブなことが多ければ落ち込み、ポイティブなことが多ければルンルンなわけですけれども、落ち込むかルンルンになるかには、境目(ティッピング・ポイント)があることがバーバラさん(正確には、バーバラさんとマルシャル・ロサダという数学者との共同研究)により明らかになったと。 その比率が、「3対1」だったのね。 つまり、ネガティブなこと1個につき、ポジティブなことが3個もしくはそれ以上あった場合、人間の感情は上昇気流に乗り、どんどん積極的になれる。対して、ネガティブなこと1個につき、ポジティブなことが3個以下、たとえば1個だったりすると、人間は下降気流に巻き込まれ、どんどん落ち込んで行って何をやるにもやる気が出なくなる。それどころか、さらに落ちて鬱になると。 重要なのは、ネガティブな感情は非常に強いので、1個のネガティブに対してポジティブ3個以上じゃないと太刀打ちできないということ。これがいわゆる「ネガティブ・バイアス」という奴。 だけど、毎日毎日、ネガティブなことの3倍のポジティブなことなんて起こる訳ないじゃん! と思ったあなた! あなたは正しいけれども、正しくない。 つまりね、何をネガティブと考え、何をポジティブと考えるかは、あなた次第なの。あなたがポジティブに捉えようと心に決め、それを選択すれば、それはポジティブなものに成り得る。上司に叱られたことは、そのままではネガティブな経験だけど、それを「自分を成長させる機会が来たーーーーっ!」と捉えればポジティブになるわけよ。 あとね、ネガティブな感情をすべてなくせばいいというものでもなくて、例えば不当なことに対する真っ当な怒り、なんてのは、無くしたらいかんものなわけですよ。また、失敗して悔しいと思わなかったら、次は頑張ろうというファイトも出てこない。 だから、ネガティブな感情の中でも悪い性質のもの、例えば「ひがみ」とか「ねたみ」とか「萎縮」とか「嫌悪」とか「侮蔑」とか、そういうのをなるべく減らすよう心掛け、一方、ポジティブに物事を捉えることを心がければ、3対1の比率に近づけることは可能だと。まあ、バーバラさんはそう主張しております。 実際、バーバラさんは、例の「9.11」のテロの時、知人の葬式に出るために家族と離れたところにいたんですな。それで、もちろん飛行機は止まってますから、飛行機で帰るわけにはいかない。そこで、苦労して鉄道を使って、17時間かけて帰路につくのですけれども、その鉄道の中で、見ず知らずの人たちとテロについて語り合い、それぞれの不安を吐露し合い、慰めあったと。その乗客間の一体感というのは、ものすごくポジティブなものだった、というのですな。あの空前の悲しい出来事のさ中ですら、ポジティブな側面はあったと。そしてそのポイティブな感情が、立ち直り(レジリエンス)の原動力になると。 で、そのネガティブな感情の抑え方ですが、本書の中でバーバラさんが提唱しておられる方法が幾つかあって、例えば「ネガティブな感情に反論する」というやり方。これは「認知行動療法」と呼ばれるものだそうですが、例えば「もうダメだ! 身の破滅だ!」というネガティブな感情が起こったら、即、冷静に反論する。「本当に、これができなかったことが、身の破滅を引き起こすのか? そもそも身の破滅って、何?」 すると、確かに身の破滅ほどの大事にはならないだろうな、ということが分かり、必要以上にネガティブに反応していたことが分かると。 あと、「マインドフルネス」も、ネガティブ感情に対処するための有効な方策でありまして。西欧の学者で、最初に仏教的修業の中からマインドフルネスという心理学上の手法を編み出したのは、ジョン・カバット・ジンという人だそうで、1980年代のことだそうですが、とにかく、今自分がやっていることに精神を集中させる(もしくは、良い悪いという価値判断をせず、自分が今何を考え何を感じているかを観察し、それを丸ごと受け容れる)というマインドフルネスのやり方も、相当、いいらしい。例えば、明日の会議でのプレゼンのことを気に病み、失敗したところを想像して苦しむよりも、「今は明日のことを考えず、寝ることに集中しよう」と考えてぐっすり寝ちまった方が、色々上手く行きそうですよね。 その他、自分の一日の行動を記録して、どういう時にネガティブな感情が起ったか、それは繰り返すものかを調べ、例えば通勤時間にしばしばネガティブな思いにとらわれるのであれば、その時間を心地よく過ごす方策を考える、なんてのもいい。 あと、自分の周囲の友人・知人・同僚などに、自分の良い点をアンケートして回って、自分の得意なことは何かを知り、その得意なことを活かすようなことを考えるとか。 あるいは、これはソニア・リュボミスキーの提案していることだそうですが、定期的に「親切デー」を作り、その日には他人に親切にすることを心掛けるとか(他人から親切にされることもポジティブな感情を生み出すが、他人に親切にすることもまた、それ以上にポジティブな感情を生み出す)。 あと、もちろん瞑想ね。瞑想っていうのは、万能ですな。 とまあ、色々手法はあるわけですけれども、そういうノウハウを駆使し、ネガティブな感情をなるべく抑え、ポジティブな感情をなるべく増やし、その比率をティッピング・ポイントである「3:1」以上になるように心がければ、上昇気流に乗れますよと。ま、それが本書の謂わんとしているところでございます。 ま、学者さんの書いたものですから、華やかさはないんですけれども、その分、科学的データに裏付けられた知識が得られますので、悪い本じゃないですよ。特に、「3:1」というリアルな比率を打ち出したところは、評価できるのではないでしょうか。これはすなわち、「悪いことはどうしたって起こるよ」という前提の上で、それでもポジティブの比率を挙げて、幸せになれるという可能性を提示したわけですから、リアリティがあります。 だけど、まあ、ポジティブ心理学ものも大分読んだので、この辺りで打ち止めにしようかな。どれ読んでも、大体同じこと書いてあるしね(爆!)。
July 28, 2018
コメント(0)
-
あの事件についての雑感
例の事件、関係者13人の死刑執行が行われたことで、様々な世論を引き起こしております。 ま、「なぜこの時期なのか」とか、「麻原だけの処刑で良かったのではないか」とか、「まだ事件の真相は解明されていないんじゃないか」とか、色々な観点からの発言があり、さらに死刑制度そのものの是非を問うものまであるので、一筋縄では行かない訳ですけれども、20年もの歳月をかけた我が国の司法制度の結論ではあるわけですし、私としては、まあ、こういう風になったのもやむなしかなと。 ところで、「まだ事件の真相は解明されていない」「連中を全部死刑にしたのでは、今後、テロをどうやって防げばいいかの指針が見つからない」という方向性の世論については、そうかもねと思いつつも、私自身の感じ方とはちょっと違う。 私は、この種のテロっていうのは、この先も起こると思うのね。テロに限らず、人間にとって悪いことは、この先もずーっと起こると思うわけ。有史以後の数千年の人類の歴史を振り返ってみても、世界で犯罪が一件も起らなかった日が一日でもあったかどうか、疑問だもの。数千年そんな状態なら、この先もずーっとそうだと思うわけ。 だから、私も含め、人間誰しも、明日のことは分からないわけよ。明日、また別な誰かがどこかで毒を撒くかもしれない。そして運悪くその現場に居合わせるかも知れない。 そういうもんだと思うんですよ、人間の世界って。悪いことは必ずある。だから、今回の事件をどんなに掘り下げたところで、この先、こういう事件を未然に防げるというものじゃないだろうと思うんだなあ。 だけど。 ここからが重要なんだけど、悪いことは絶対これからも起こるとして、それよりもはるかに多い数、いいことがあるんだろうなと。 例えば、この間の大雨で被害に遭われた地域。あそこに一体何人くらいのボランティアが入って復興のお手伝いをしたか。延べで言ったら既に数万人ですよ。 地下鉄サリン事件やら何やらで処刑されるはめになったのが13人なのに対し、遠くに住む困っている人たちのことを捨て置けないで、自腹切って助けに行った人が数万人。 この比率。これって素晴らしくない? もしこれが逆だったらと考えたら怖ろしいよ。ボランティアに志願した人が13人、それに対して「よーし、今なら略奪しほうだいだ!」とかいって、被害地域に殺到した悪人が数万人だったとしたら、それはもう、地獄ですよ。 だけど実際はそうじゃない。実際には何万人もの人が、このクソ暑い中、人助けに行ったわけだ。それを思えば、この世は既に天国なんじゃね? 心理学で「ネガティブ・バイアス」って言うんだけど、嫌なことのインパクトというのは大きいので、そのことばかりに目が行っちゃうけど、よくよく考えたら、ポジティヴなことの方が多い。それがこの世の素晴らしいところで、そこを考えないといかんと思うわけよ。 だからね、事件を起こした連中のことをもっと深く掘り下げた方が良かったというのであれば、それ以上に、なぜ被害地域にボランティアに行こうとしたのか、その人たちの動機を調べて教えて欲しい。なぜ人は、困っている人を見殺しにできないのか。困っている他人の痛みを、他人事に出来ない人が居るのは何故なのか、そのことも調べて欲しい。 その方が、私は、重要なんじゃないかと思うんだなあ。
July 27, 2018
コメント(0)
-

この夏は山田稔で
毎年、夏の読書にはテーマを決めておりまして。 何年か前の夏に尾崎喜八の『山の絵本』とか串田孫一の『山のパンセ』的なものを集中的に読んで非常に楽しい読書生活をすることができたことがあって、以来、しばらく夏は山の本、と決めていたんですけど、これがね、意外にその後が続かなくて。つまり、あまりにも専門的な本になってしまって、ついていけなくなったのね。 で、その後はテーマをちょこちょこ変えてきたのですけれども、今年はね、山田稔の本をちょっと集中的に読んでみようかなと。 渋いだろぅ? 山田稔。この人こそまさに「知る人ぞ知る」書き手なのではないかと。 もともと京大の先生ですよね? フランス文学の。で、今は定年退官されていて、色々物書きをされている。日本エッセイスト・クラブ賞も獲っておられるはず。 書かれるものも、学問的なところもありーの、エッセイであることもありーの、これは小説か?ってなところもありーの。そういう部分も含め、私の目指す方向に既に進んでおられるっぽい感じじゃないですか。 ということで、夏を前に色々買っちゃった。例えば最新作の『こないだ』とかね。あと、『残光のなかで』とか。『マビヨン通りの店』とか。 で、届いた本をチラチラ開けては見るのですが、確かに面白そうなの。だけど、今はちょっと忙しくて読む時間がない。 まあ、だから、もうちょっとして本格的に夏休みに入ったら、読み始めようかなと。 ということで、今は積み上げられた数冊の山田本を眺めながら、これを読む日の幸せを想像して、楽しんでいるところなのであります。これこれ! ↓こないだ [ 山田稔(仏文学) ]マビヨン通りの店 [ 山田稔(仏文学) ]【中古】 残光のなかで 山田稔作品選 講談社文芸文庫/山田稔(著者) 【中古】afb
July 27, 2018
コメント(0)
-
期末試験が近づくと・・・
小学校ですら既に夏休み入りしたというのに、わが大学ではようやく期末試験の時期に近づいたところ。 で、この毎年この時期になると、色々と下らないことに悩まされることになるのよ・・・。 例えば、「うつ病で家から出られないのですが、期末試験、どうすればいいですか?」という学生からの問い合わせとか。 知らねーよ! あのね、大学ってのはね、すべて学生さんの都合でやっていけばいいの。だから、そちらさんの都合が悪いってのなら、試験を受けなきゃいいだけの話じゃないの。なんでこっちに尋ねるの? 今年がダメなら来年がある。来年がダメならその次の年がある。受けられそうだな、受けたいなって思った時に授業を受けて、試験を受ければいいの。その自由は、すべてあなたの手にある! その自由を謳歌しなされ。 はい、次! お次はね、「私は4年生なのですが」って奴ね。 実は今日も私のところにそういうメールが来たのですけど、散々、授業をさぼっておいて、来週は期末試験だよっていう時になって、「試験範囲はどこですか?」とかいう間抜けな質問をしてくる学生がいるのよ。 で、「試験範囲は授業中に私が話した事柄すべて。それをちゃんと理解できているか、確認するための試験だから。それから、期末試験と同時にレポートも課してあるからね。試験日当日、提出ね」という返事を出して置いたわけ。 すると速攻で返事が返って来て、曰く「私は4年生なのですが」と。「私は4年生なのですが、就職も決まっていて、この授業の単位がないと困るんです。試験の方は準備しますが、レポートを書いている時間がないもので、提出期限を1週間ほど遅らせてもらえますか?」ですと。 これって、「試験準備の方は私がしますから、あなたはレポートの締め切りの方、延ばしておいて下さい」って言っているようなもんじゃん? 私だって頑張るんだから、お前も頑張れよと。苦労は互いに分担しようぜと。 知らねーよ! ま、「ふざけんなボケ!」と返しておきましたけどね・・・。 ただでさえ暑くて鬱陶しいのに、この手の手合いに対処しなければならないのですから、ほんと嫌。
July 25, 2018
コメント(0)
-
スタミナを付けねば・・・
口にしたところでどうなるものでもないとはいえ、この暑さ・・・。異常です。これで一日でもいいから少し涼しい日が挟まってくれれば一息つけるんですけど、全然その気配もなし。 いささかバテてきた私。何でもいいけど、スタミナの付くものでも食べたい・・・。 で、たまたま今日は前期の授業が終ったこともあり、夜、家内を連れて外食することに。 いつもですと、一学期の授業が終った日には、家の近くの焼き鳥屋さんでささやかな「お疲れ会」をするのですけど、いつも同じ焼き鳥屋さんというのもつまらないので、今日は別なお店、米野木駅前にある「大吉」というチェーン店に向いました。 で、血肝だのハツだのも含め、各種焼き鳥を堪能したのですが、ふと、メニューに「馬力」というものがあるのに気が付きまして。 よく見ると、どうやら無臭ニンニクを紫蘇で漬けたものらしい・・・。 ニンニク・・・=スタミナやないですかっ!! ということで、早速これを注文し、馬力を付けたのでございます。 まあ、この馬力がどういう具合に発露するのかは、これからのお楽しみということで・・・。 あ、あと、帰り際にマックスヴァリュに寄って、アーモンドも買っちゃった。噂によると、アーモンドに含まれるビタミンEが、脂肪肝に効くという話でしたので。 それにしても、食べ物に頼ろうとするなんて、私も歳を取ったものですな・・・。
July 24, 2018
コメント(0)
-

ネイティヴの英単語記憶法
前にもこのブログに書いたように、最近、改めてボキャビルを始めてみたのですが、やっぱり寄る年波には勝てず、若い頃のようにホイホイと英単語が覚えられなくなってきたなあと。 高校生くらいの時は、1000語くらいなら丸一日あれば・・・ってな感じだったけどねえ。 ちなみに、日本人にとって、最も効率のいい英単語の覚え方というのは、語呂合わせを利用した覚え方だってご存知? 例えば「穴掘る」とかね。「穴=hole」という意味ですが。 あと「雷さんだー!」とか(「雷=thunder」)。 凝ったところでは、「ラーメン食べる悲しい気持」とか(「lamentable=悲しむべき」)。 たしかにこの方法って、日本人にはうってつけだよね。今でも「語呂合わせ英単語」的な単語集ってあると思うけど。 しかし、そういうのって、大学受験レベルで終っちゃうので、それじゃ私の役には立たないわけよ。 で、なんかもっと難しい英単語の覚え方の本ってないかなと探していたところ、こういうのがありました。題して『Vocabulary Cartoons II』。アメリカで売られているSAT受験レベルの英単語の覚え方集でありまして、売り上げ100万部越えよ。 「Cartoon」とあるのですから、マンガを使うのかな? などと思いながら私もこれを買ってみたのですが・・・ 例えばですね、「Diurnal」という単語がある。意味は「昼行性の」という意味ね。で、この単語のページに「Link(連想語)」として「DAY TURTLE」(=日中のカメ)と書いてあり、その下に南の島で日光浴をしているカメの絵があって、そのキャプションが「A Diurnal Turtle」。 つまり、昼間(DAY)という言葉と「カメ」(TURTLE)という言葉を足した「DAY TURTLE」(デイタートル)という言い方の、その発音に似た「Diurnal」(ダイアーナル)という言葉は、「日中の」とか「日中に活動する」的な意味ですよと。 別なページを見ると、「Onerous」(やっかいな)という英単語の連想語が「Owner」(所有者)で、ペットショップのオーナーが自分の店の様々な動物たちに囲まれて往生している絵があって、キャプション曰く「A pet shop OWNER'S life can become ONEROUS.」(ペットショップのオーナーの人生は厄介なことになり得る)。 微妙! これ相当に微妙じゃね? 逆に覚えにくいわ。 ううむ・・・。ネイティヴの英語話者にとってすら英単語を覚えることはかくも難事業だったとは・・・。まあ、日本人が難しい漢字を覚える時に苦労するようなもんか・・・。 それを考えると、語呂合わせで英単語覚えることの出来る日本人って、実は幸せだったのかもね~! さてさて、「彼氏はお金」(Currency =お金)と。VOCABULARY CARTOONS II,2/E [洋書] VOCABULARY CARTOONS II SAT WOR [ Sam Burchers ]
July 23, 2018
コメント(0)
-
登場人物の名前
たまたまある文献を読んでいて、その昔、文芸評論家の江藤淳が大江健三郎の小説(具体的には『万延元年のフットボール』なんですが)を批判して、登場人物の名前がひどいと。密三郎だの、鷹四だの、およそ日本人の名前にはありそうもないようなのばっかりで、そういうのを読者は「大江健三郎の小説なんだから、きっと何か意味があるんだろう」的に許してしまうのだけど、そういうのが続くと、その手の登場人物の名前に抵抗のない者(=大江健三郎のファン)だけを読者層に取り込むことになり、非常に閉鎖的な世界ができ上がるのではないかと。まあ、そんな趣旨の批判をしたらしいんですな。 ま、同感だね! 古義人だの、ギー兄さんだの、イーヨーだの、とても私には読めない。だから一つも読まないのですけど、少なくとも一人、私と同様な思いを抱いていた人が居たと知ると、ちょっとホッとしますな。 だけど、どうなんだろう。英語に翻訳された大江の小説を読んだ外国人達ってのは、彼の小説の登場人物たちの妙チキリンな名前について、「これは日本人の名前としておかしい」と感じられるものかしら? それとも、そのヘンテコさに気が付かず、そういうもんだと思って読むのでしょうか? 例えば、カポーティの『ティファニーで朝食を』に、日本人の「ユニオシ」というのが出てくる。もちろん、ユニオシなんていう名前の日本人はいないわけで、おそらくは「クニヨシ」(当時アメリカには日本人の有名な画家で「国吉康雄」(英語で訳せば「Y. Kuniyoshi」が居た)という日本人名を誤って使ったのだろうと思いますが、アメリカ人読者は「Yunioshi」という名前に何ら違和感を覚えていなかったわけだ。そこから推測するに、おそらく、英語で大江の小説を読む人達は、彼の登場人物の名前がおかしいとは思わないのでしょう。 だからノーベル賞も獲れたんだろうな。私が審査員だったら、「登場人物の名前に耐えられず、読むに堪えませーん」とかいって、論外で落とすからね。 それにしても、日本人でノーベル文学賞を取ったのが川端と大江か・・・。なんかもっと他に居るような気がするんだけど。 じゃあ誰?って言われると困るけど、少なくとも谷崎とかの方が妥当じゃないかい? まあ、でも、今、若い人で大江を読む人っているのかしら? ・・・愚問か・・・。
July 23, 2018
コメント(0)
-

『なぜ女は男のように自信をもてないのか』を読む
キャティー・ケイ&クレア・シップマンという女性ジャーナリスト・コンビの共著になる『なぜ女は男のように自信をもてないのか』(原題:The Confidence Code: The Science and Art of Self-Assurance -- What Women Should Know, 2014)という本を読了しましたので、心覚えをつけておきましょう。 このところ女性向け自己啓発本を続けざまに読んでいるのですけれども、それらの本が一様に指摘するのは、どうも女性というのは、能力はおそらく男性と同等、あるいはそれ以上にあるのだけれども、自信が持てないらしい、ということ。場合によっては、自分よりよっぽど能力のない男性が自信満々なのに、自分はそこまでの自信が持てない。で、これは一体どういうことなんじゃ? という話になることが多いんですな。 で、この本はまさにそういう「自信が持てない女性」の謎に迫るという意味で、興味津々の本であるわけ。 で、キャティーさんもクレアさんも、ジャーナリストであって、専門家ではないんです。だけど、まさにそこに強みがあって、二人して様々な分野の専門家のところにずけずけと尋ねて行って、この謎の答えを聞き出しに行ける立場にある。というわけで、色々な専門家に「なぜ女性は自信が持てないのか」という問いをぶつけてみたら、こんなことが分かってきました、という体で書かれたのがこの本であります。 だから、尋ねる人によって色々な答えが返って来るわけでありまして、それを一々記していくと大変なので、大ざっぱにまとめますと、確かに女性は自信がない、という事実は現前としてある。それは、スポーツ界であれ、政治の世界であれ、ビジネスの世界であれ、とにかくそれぞれの世界で最も成功していると思しき女性たちに尋ねても、やっぱり「どうも私は自信が持てない」という答えが返ってくると。 ちなみにこれは単に感覚の問題とか個人個人の問題というわけではなく、実験によって確かめられる事実なんですな。例えば一般に男性は自分の実力と見合った自信を持っているどころか、それ以上、つまり3割増しくらいの自信がある(これを「正直な自信過剰(honest over-cinfidence)」という)のですが、女性はその逆、2割も割り引いて自分を評価していると。 だから、会議の場でも、男性はアホな意見であれ、バンバン手を挙げて発言できるのに、女性は、いい意見を持っていても「こんなこと言ったら馬鹿にされるのでは」と怖れて挙手をしない。挙手をしないのだから、発言するチャンスもなく、当然、評価もされない。また昇給の交渉でも、男性は積極的に「こんなに成果出しているんだから、もっと給料くれ」と上司に掛けあえるのに、女性はそういうことはしない。とまあ、そういうことが積み重なって男性と女性では、出世競争に大幅な差が付いてしまうと。 もちろん、出来る女性はこの状況に気が付いているのですが、だからといって、周りの男性と同じようにアホみたいにバンバン発言したり、アホみたいに昇給交渉に行こうという気にならないんですな。つまり、「自信=アホみたいな行動」という意識があって、あそこまで自分を落としたくない、という風に思っちゃうと。 ま、これが現状ですわ。 それでは一体なぜ、こういう状況が起こるのか? キャティーとクレアは、ひょっとして男性と女性では頭の構造が違うのか? と思い、そっち系の科学者のところに行って尋ねるのですが、それによると確かに男性脳と女性脳は、その動き方が異なるというのは確からしい。 だけど、働き方が違うというのは、能力の高低を示すものではないわけね。例えばよく言われる「女性は(先天的に)理数系に弱い」という言い方があって、それを示すようなデータすらあるけれども、実際にはそれは事実ではない。要するに道筋の問題であって、男性脳が通る道筋と女性脳の通る道筋は違うかもしれないけれども、同じところに到達するのだから、結果から言えば両者に差はないわけ。 じゃあ、なぜ「女性は理数系に弱い」というデータが出るかというと、これはもう「自信」のなせるわざなのね。思春期の前期くらいの時にそういう言い方がなされるために、女性たちは「私たちは理数系はダメなんだ」と勝手に思い込み、問題を解く前に努力を放棄してしまうので、悪い結果しか出ないだけで、本気でやれば男性と同じだけの理数系能力を示せると。実際、自信を付けさせるような暗示をかけた後で数学の問題を解かせると、女性も男性も同程度の理数系の能力を示すことが立証されております。 このことが図らずも示しているように、だから自信というのは、能力を発揮した後に出てくるものではなくて、自信そのものがある種の能力なのね。能力があるから自信が生じるのではなく、自信があるから能力が発揮されるわけ。 だから、「自分には自信がない」と思い込んでしまっている女性達というのは、すっごく損をしているわけですよ。そう思っている限り、能力を発揮できず、能力を発揮できないから自信を持てないという悪循環に落ち込んでしまうわけだから。 しかも現代医学の見地からすると、この自信の無さというのは、遺伝すると。だから悪循環も一世代だけじゃなくて、次世代にまで遺伝してしまう。 ではなぜ女性たちは自信がないかというと、環境の影響も大きいらしいんですな。 例えば女性というのは、幼少の頃、男の子よりもませているので、大人たちの思惑に敏感なわけ。で、両親や学校の先生が、自分に何を期待しているのか、いち早く察してしまう。そこで「いい子」であることにメリットがあると学んでしまうわけね。だからどんどんいい子になっていく。勉強も一生懸命やって優等生になる。完璧主義者になる。一方、へまをやることに対しての怖れをどんどん増大させていくと。 一方、同世代の男の子どもは、「いい子」ではないし、そういう風になりたいと思ってすらいないから、悪いことばっかりやって、やたらに叱られて、でも叱られたって平気の平左なわけ。友達同士でも、互いのダメなところを指摘し合い、からかい合い、馬鹿にされることに慣れていく。 子供時代の過ごし方が、男と女でこれだけ違うわけね。 だから実社会が学校の延長だったなら、すべての国の元首は女性になるだろうし、すべての企業の社長は女性がなるはず。だって、学校時代に限って言えば、女性の方が遥かに優等生なんだし、優等生がトップに立つ世界なんだから。 ところが実社会は、残念ながら学校の延長ではないんだなあ・・・。 で、学校から実社会に投げ出された女性達は、学校時代の延長で完璧主義者であり続け、失敗することを怖れ続け、いい子であり続けようとするのですが、その手法は通用しない。逆に、失敗することを怖れず、互いに競争し合うことを怖れない男性たちの方が実社会に適応し易いので、結果として男性天下になってしまうと。 しかし、本書が最も主張したい点というのは、ここから先ね。 つまり、こういう現状を打破する方法はある、といういこと。 本書を通じてキャティーとクレアが到達した一つの見地というのは、結局「自信」とは行動であり、行動によって培われるものである、ということなんですな。 だから、前にこのブログでも取り上げたシェリル・サンドバーグの本のタイトルじゃないけど、とにもかくにも「Lean In(一歩前に踏み出す」)すること。「自信に満ちた人間になろう」という意志を意図的に抱いて、それを行動に移すこと。早いうちに小さな失敗をどんどん犯し、失敗することに慣れること。失敗したって、他人から批判されたって、どうってことない、ということを体験として自分に覚え込ますこと。これは、意志の問題なんですな。意志の問題というか、選択の問題。自分として、それをやろう、勇気を出して一歩踏み出そうという選択をした途端、すべてが変わり始めると。 ま、この本が主張していることは、それに尽きます。やっぱり、「選択」なんですよ。自分次第。そして自分が変わった時、世界が変わる。 だから、この本も自己啓発本なんですな。 というわけで、この本、男の私が読んでも面白かったですけど、女性が読んだら余計に「そう、そう!」ってなるのかも知れません。一読の価値はあるんじゃないかな。なぜ女は男のように自信をもてないのか [ キャティー・ケイ ]
July 21, 2018
コメント(1)
-
ミニストップの新作ハロハロとミスドの新製品を食べて、柔術の稽古へ
今日は色々な初物を食べましたよ。 まずはミニストップがこの夏放った新作ハロハロ、「果実氷いちご」。スライスして凍らせたイチゴにソフトクリームを乗せたものなんですけど、これは旨いよ! 凍らせたイチゴはシャリシャリとした食感で、これだけでも美味しいけど、そこに自慢のソフトクリームが乗るわけだから、その相乗効果たるや。 ただ、一つ注文を付けるとしたら、先ず一番先にソフトクリームを注入し、その上に凍らせたイチゴを乗せ、さらにその上にソフトクリームを乗せるという具合に、イチゴをソフトでサンドイッチしてもらいたい。そうでないと、先にソフトクリームを食べつくしちゃって、後半、イチゴだけを食べるような感じになりがちなもので。でも、まあ、これは合格でございます。 そしてもう一つ、今日食べた初物スイーツは、ミスタードーナツの最新作。チーズタルトで名高い「PABLO」とのコラボでございます。先日、まさにそのパブロのチーズタルトを初めて食べて、旨いなあと思ったもので、今回のミスドとのコラボにも大いに期待したわけですよ。 が! うーん・・・。どうなんだ? 私の個人的な感じから言うと、イマイチだったかも。これだったらむしろパブロのチーズタルトそのものを食べた方がいいかな・・・。しかも、その方が安いというのだから。ま、6種類の新作のうち、まだ2種類しか食べてないので断言はできませんが、ややミスマッチかな・・・。 さてさて、これだけスイーツ三昧した後、今日は柔術の稽古に行って参りました。いつもは木曜日が柔術の日なんですけど、会場の都合で今週だけ金曜日なの。 柔術の稽古に関して言えば、今は停滞期間でありまして、上達した手ごたえが全然感じられない状況が続いております。まあ、長く稽古していると、そういう期間と、上手くなる期間が交互に来るものですから、別に気にしているわけではないのですが、それでもやっぱり「なかなか上手くならないなあ・・・」という期間が続くと若干気落ちするものでありまして。 で、そんな中、師範のA先生に稽古を付けてもらっていたのですが、その際、先生に「なかなか技がかかるようになりません」と愚痴ると、A先生曰く、「誰でもそういう時期がありますよ」と。 で、A先生ご自身もそういう時期があって、先生の先生に愚痴ったことがあったのですと。すると、先生の先生曰く、「技なんて、かからなくていいんですよ」と。 つまり、「技を掛けよう、相手を倒そう」と思って技を掛ける必要などないと。それよりも、自分の姿勢が正しくあることだけに気を付けなさいと。 八光流の場合、「姿勢」というのは常に重要な課題でありまして、自分自身が正しい姿勢を保つことを常に心がけるよう指導されます。逆に、相手に攻撃を仕掛けようとすると、かならず姿勢は崩れる。八光流は護身道ですから、攻撃をしかけて来る人(=姿勢の崩れた人)に対し、その崩れた姿勢をさらに崩すことによって相手を無力化する、というのが原理原則なわけ。 だから、攻撃してきた人を倒すというよりは、そういう人の攻撃にも屈せず、自分の姿勢を正しく守り続けることの方が重要なわけですな。 だから、技なんてかからなくてもいい。そんなことは気に掛けず、自分の姿勢だけ、常に正しくあるようにしなさいと。A先生の先生はそうおっしゃったわけね。 なるほど。 八光流の修業も大分長くなってきましたけれども、それでもまだ私の中に「上手に技をかけて、相手を痛めつけてやろう」という邪心があったわけですな。 護身道の主眼は、「相手を痛めつけてやろう」なんて考えている連中の只中に居て、清く微笑ながらすっくと正しい姿勢で立ち続けることだと、今日は改めて勉強させられましたわ。 来週からの稽古では、そのことを肝に銘じて、己の邪心から身を守ることに専念しましょうかね。
July 21, 2018
コメント(2)
-

『ソイレント・グリーン』の描く今日
先日、NHKの衛星放送でやっていた映画『ソイレント・グリーン』を録画しておいたのを、今日、観ちゃった。ので、心覚えを。以下、ネタバレ注意ということで。 これ、1973年の映画なんですが、設定は2022年。・・・っていうことは、要するに今頃、ということですな。 で、『ソイレント・グリーン』が描く今日は、人口の急増によって地球の資源が枯渇し、一部の特権階級以外は食うや食わずの貧民という状況。食べるものも、ソイレント社という会社が大豆から作るソイレント・イエローだとか、プランクトンから作るソイレント・グリーンという、あまりおいしそうでない人工的な栄養物を食べるようになっていて、それすらも枯渇しがち。なので、人気のソイレント・グリーンの配給がある火曜日には、それを得られなかった民衆による暴動が頻発すると。 そんな中、特権階級の一人、サイモンソンが何者かに殺害される。で、この事件を捜査することになるのが、ソーン刑事(チャールトン・ヘストン)なんですが、彼はこの事件が単なる物取りではなく、暗殺であると直感し、その背後事情を調べ始めるんですな。 で、どうもこの時代、刑事一人一人には文献捜査のための助手みたいなのがつくらしく、ソーンの相棒はソルという年寄りの男なんですな。で、ソーンもソルにサイモンソンがどのような人物だったか、文献を調べてもらうのですが、その結果、サイモンソンはソイレント社の重役であることが判明する。 で、どうもサイモンソンは、ソイレント社の極秘事項を知り、そのあまりの罪の大きさに発狂し、ある意味、暗殺されるのを自ら待っていたような節があると。 で、ソルはこの謎を解明し、それを知ったソルも人類の現状に絶望し、自ら「ホーム」という名の安楽死設備に赴き、かつての美しい地球の映像を見ながら死んでいく。ただ、死ぬ前に、ソーンに自分が知り得たことを教えると。 で、ソーンはソルに教えられた衝撃的な事実を確かめるため、安楽死したソルの遺体がどこへ持っていかれるか、その後を追うのですが・・・ ・・・そこで彼はソイレント社の秘密を知ることになる。 そう、ソイレント社はソイレント・グリーンの原材料をプランクトンだと偽っていましたが、今はもう海も汚れきってプランクトンなんか生息しちゃいない。実は、ソイレント・グリーンの原材料は、死んだ人間だったんですな。ソイレント社は次々と運ばれてくる人間の死体を処理し、それで人工栄養物たるソイレント・グリーンを生産し、人々に喰わせていたと。 そして最後、その事実を知ったソーンが、「ソイレント・グリーンの材料は人間だったんだ~!」と叫ぶシーンで幕。 そんな映画。 まあね、すごく有名な映画であるとはいえ、実際に観てみるとまさに噴飯ものの出来。映画の完成度から言ったら、ほぼ最低です。だけど、1973年時点での暗澹たる未来予想と、人間が人間を食って生きているという状況のショッキングな結末が受けて、いたずらに有名になってしまったんでしょうな。 主演を演じたチャールトン・ヘストンと言えば、1968年の『猿の惑星』の主演でも有名ですが、『猿の惑星』もまた、映画の最後でヘストンが「ひゃー、実はそうだったんだ~!」って絶叫して終わるわけですけれども、1960年代末から1970年代初頭にかけて、未来予想ってのはかくも暗澹としており、その暗澹とした未来の姿をヘストンが絶叫して伝えるというパターンが続いていたわけね。ま、映画の出来としては、『猿の惑星』の方がよっぽど上だけど。 未来がどうなるかを予想する、いわゆる「未来学」ってのは、1960年代のアメリカで盛んになるんですけれども、『ソイレント・グリーン』にしても『猿の惑星』にしても、その辺の影響が大きいのかもね。 ま、『ソイレント・グリーン』が予想した2022年の世界と比べれば、2018年の我々は、まだましな世界を生きている感じはしますけれども、どうだろう、例えば今日のこの殺人的な暑さ。先日の記録的な大雨もそうですけれども、確実に変な方向に行っているような気はしますな・・・。この調子であと4年経ったら・・・。 コワ![100円便OK]【新品】【DVD】ソイレント・グリーン 特別版【DVDスリムトールケース】【RCP】[在庫品]
July 19, 2018
コメント(0)
-
江上茂雄という絵描き
子供の頃の夏も暑かった記憶があるけれども、ここまで暑かったかなあ。昨日も可哀想に、この地方で小学生が熱中症で亡くなったという報道がありましたが、人が死ぬような暑さって、尋常じゃないよね・・・。 さて、こう暑いと勉強なんてしていられないなと、どこかへ逃避したくなるのですけれども、そんな私が狙っているのが「長谷川利行展」。 これ、ちょっと前まで実家の近くの府中市美術館でやっていて、利行ファンの私としては見たかったなあ、残念! と思っていたんですけれども、なんとなんと、向こうから私の家の近くまで来てくれました。そう、今月21日から碧南にある美術館に巡回してくれるんですよね~。ラッキー!これこれ! ↓長谷川利行展@碧南市藤井達吉現代美術館 ちなみに、この「碧南市藤井達吉現代美術館」というところも、割と面白い展覧会を企画してくれるんですけど、キュレーターがいいのかな。 ところで。 長谷川利行は、破滅型の画家で早死にしましたから、一面不幸な画家のようでいて、その画業は後にきちんと評価されるようになったわけだから、ある意味、幸福な画家なわけですよね。 だけど、じゃあ、世間的に超有名になったから幸福な画家で、そこまで名前が知られていない画家が不幸な画家かっていうと、そうでもない気がする。 というのは、最近、私の古本道の師匠、オカタケさんのブログを読んでいて、「江上茂雄」という画家の存在を知ったから。 寡聞にして私はこの画家の名前を初めて聞いたのですけれども、調べてみると、これがまたなかなかいい画家なのよ。少なくとも、私の好きな画風と言いますか。これこれ! ↓江上茂雄って、こんな画家 この人、101歳まで生きたんですな。 その割に、世間的に言って、この人の名前を言っただけで「ああ、その人の絵は知っている」という人がどのくらいいるか。 だけど、そんなこととはまるで無関係に、この人の絵はいい絵だと思うし、この人の画家人生は素晴らしいものだったんじゃないだろうか。 私が知らないだけで、こういう「人知れずいい画家」っていうのが沢山居るんだ、と思うと、楽しくなりますな。そういうの、もっと知りたい。
July 19, 2018
コメント(0)
-
客の目の前で食品廃棄・・・
週末の夜、9時過ぎに長久手にあるイオンに入っている牛タンのお店「利久」で牛タン定食を食べて来ました。 利久って、仙台にある牛タンのお店ですけど、前に仙台で学会が開かれた時に食べて以来、このお店のファンで、実家に戻った時など、渋谷ヒカリエ内にあるお店で食べたりしていたのですが、昨年、長久手イオンが出来た時に利久が入ったと聞き、一度、食べに行こうと思っていたんですよね。 で、やっぱり美味しかった! 私、仙台風の牛タン料理、好きかも。 で、せっかく来たのだからイオンに入っているお店で何かお土産を、と思い、チーズタルトの専門店「PABLO」でチーズタルトをゲット。ここ、いっつも長蛇の列でなかなか買えないのですが、さすがに夜の9時半過ぎだとあっさり買えるのね。 で、最後にデザートも食べようとサーティワンへ。たまたま「ダブルを買うと、自動的にトリプル」になる期間中だったので、得しちゃった! で、買ったアイスクリームを近くにあるベンチに座って家内と食べていたのですが、そこで10時となり、閉店の音楽が。 しかし、そうは言っても、すぐには追い出されないだろうと高をくくってベンチで食べ続けていたのですが、そうしたら、そこでショッキングな光景を目にすることに・・・ 私たちが座っていたベンチの真ん前にドーナツ屋さんがあったのですが、閉店時間となりレジを閉めた途端、バイトの女の子が、店頭にディスプレイしてあった各種ドーナツを大きなポリバケツ2つに捨て始めたんですな。トレーに乗った山積みのドーナツを、どさー、どさー、どさーっと捨てていく。その数たるや、50,60じゃきかないよ。100個以上捨てていたんじゃないかな。 まだ我々が居て、目の前にいるのにだよ! いわゆる「食品廃棄」の現場を目の当たりにすることになったわけ。 もう、「食べ物を粗末にしてはいけない」ときつく教えられて育ってきた昭和のおじさんとしては、目を疑うというか、思わずその女の子に「捨てるなら僕にくれよ!」と言いたくなっちゃった。 いやあ、腐ったわけでもない、食べればおいしい(であろう)食べ物を、目の前でどんどん捨てられるのを見るのって、ショックだねえ・・・。閉店直前になったら、二束三文でもいいから、売り切る努力をした方がいいんじゃないのかねえ・・・。 ・・・と家内に言ったら、「それをしたら、閉店直前まで待って買いにくるお客さんばかりになってしまうし、ブランドにも傷がつくんじゃないの?」と。もっともなご意見でございます。多分、そうなるだろうね。 それにしても、なあ・・・。せめて、目の前のベンチに座っている我々が帰ってから、こっそり捨てるくらいのデリカシーはないのかね。夜10時までバイトして、早く家に帰りたいお嬢ちゃんにそれを要求するのは酷なのかなあ。 食品廃棄の問題は、時折新聞報道などで目にすることはあるけれど、確かに考えなくちゃいかん問題ですな。この世にはまだまだ食べ物がなくて困っている人が沢山いるんだからねえ・・・。
July 17, 2018
コメント(0)
-
文学研究の方法を教える
前にもこのブログに書きましたが、今年、私は初めて「英語科」の学生を教える機会を得まして、アメリカ文学を専門の学生に教えられるのだから、さぞ面白かろうと期待していたのですが、実際には学生さんたちの出来が良くなく、大分、期待外れになってしまったんですな。もう、授業中は怒ってばっかりだよ。「お前ら、この大学で一番、英語が読めると思われている学生じゃないか。それが、この程度なのか?! 恥を知れ、恥を!!」ってな感じで。 でも、やっぱり英語科の学生を教えているのだから、一般教養の英語の授業みたいに、テキストを読むだけでおしまい、というわけにも行かないだろうなと。 ということで、期末考査には、筆記試験に加えてレポートも課すことにし、授業中に読んだヘミングウェイの作品について、論文みたいなものを書いてきやがれと命じたわけ。 しかし、学生の出来からすると、そのように命じただけでは、おそらく、お粗末なものしか書いてこないだろうなと。 そこで、ここ数回、授業の終りの20分位を使って「文学論文の書き方」的なことを講じたわけよ。 で、学生の出来が悪いことはよーく分かっていたので、この出来の悪い学生にも分かる言葉で、文学作品を論じるってことは、具体的には何をすることなのか、説明したと。 で、まず初日は、「文学作品を論じるに当たって必要なもの」を、選択肢つきで説明したんです。 つまり、まず文学作品を論じるとなれば、論じる作品が必要であると。しかもその場合、一つの作品を単体で論じるか、複数の作品を論じるかの選択肢があり、さらに複数の作品を論じるのであれば、同じ作者による作品を複数論じるか、別な作家による複数の作品を論じるかの選択肢がある。だから、これらの選択肢の中から、どれかを選択しろと。 分かり易! 次に必要なものは、「先行研究」。先行研究なしで作品を論じたら、それは感想文である。感想文に意味がないとは言えないが、それを論文にするつもりなら、先行研究への言及が不可欠。そしてその場合の選択肢は二つあって、先行研究を自分の見解をサポートするために「援用」するか、先行研究を「否定」した上で、それより優れた説として自分の見解を披露するか、その二つしかないので、その選択肢のどちらで行くか決めろと。 分かり易! 次に必要なものは、作品の「筋書き説明」。論文の読者は、必ずしも自分が論じようと思っている作品を読んでいるとは限らないので、当該作品がどういう筋書きなのかを説明する必要がある。それなしで論じるのは、独りよがりの論文にしかならないので、これをするかしないかの選択肢はない。しろ。 分かり易! 次に必要なものは、「視点」。文学研究は当該作品が「面白かった」か「面白くなかった」かを判定するものではない。それを決めるのは文学評論。文学研究たるものは、論者がある特定の「視点」を設定し、その視点から当該作品を眺めた時に何が言えるかを考えるもの。「視点」があるかないかの選択肢はないので、決めろ。 分かり易! ここまでが初日ね。で、次の回では、作品の論じ方の選択肢を提示しました。 文学作品を「論じる」というのは、具体的には何をすることかと言えば、簡潔に言えば、当該作品の「下部構造」を明らかにすること。前回に述べたある「視点」から見れば、ある作品について、表面的には見えないけれども、ある構造があることが明らかになる。この構造を掘り起こして提示すること、これが文学作品を「論じる」ことに他ならない。 ただし、その場合、二つの選択肢があって、当該作品をそれ自体、単体として分析すること。これがいわゆる「新批評的アプローチ」。この場合、精読に基づいた「シンボルハンティング」が重要な役割を果す。例えば「自然」という視点を用いてヘミングウェイの作品を分析した場合、作品の登場人物の中で誰が一番自然に近しいか、誰が一番自然と遠いか、といったことを判断し、「自然に最も近しい登場人物が、最も影響力のある登場人物である」というような下部構造を明らかにすることができるかも知れない。そして、例えば「木」を「自然」全体のシンボルと見做した場合、誰が森に居るのか、誰が木に寄りかかっているのか、といったことが、「自然に近しいか、遠いか」を判断する上での判断材料になりえる。 もう一つの選択肢は「新歴史主義批評的アプローチ」。当該作品をそれが書かれた時代に戻した上で考察すると、当時の状況を知らない現代の読者が見落としてしまうような下部構造が見えてくることがある。その下部構造を明らかにするのが、このアプローチの目標。 だから、作品を論じるとなれば、上記2種類のアプローチのどちらを選ぶかという選択肢の中から選ばなければならない。ただし、現代では論文の手法として前者はやや古く、後者の方が歓迎される傾向にあることを承知しておかなければならない。 分かり易! そしてその次の回では、「注」の付け方を伝授。 「先行研究」のない論文がないように、「注」のついてない論文もない。ではどういう時に注を付けるのか。 この場合の選択肢は二つ。先行研究を提示した場合などにつける「出典」の明記と、本文中で十分に論じられなかったことについての「補足説明」。だから、「出典」と「補足説明」を注の中で行え。 分かり易! どう? 気合抜け抜けで説明している割に、超分かりやすくない? 気合抜け抜けで説明したのが逆に良かったのか・・・。相手の出来がよろしくないので、まさに「サルにも分かる論文講座」みたいになったのが奏功したのかもね。 で、次回、最終回では、論文を書くコツとして二つのこと、すなわち「フローチャートを作る」ということと、「自分が論じたいと思っていることを他人に口頭で説明すると、論旨が整う」ということについて説明しようかなと。 結局、いい先生なのよ、私って。
July 16, 2018
コメント(0)
-
パイナップルに根が出た!
昨年、父の葬儀をした時、お供えの果物の中にパイナップルがありまして。 で、それは私がもらったのですが、おいしくいただいた後、切り落とした実の上の方、葉っぱがわしゃわしゃと付いているところを大学のキャンパスのさる場所に秘かに植えたんです。父の記念のパイナップル畑にしてやろうと思って。 しかし、やり方が悪かったのか、その試みは失敗。植えたパイナップルはあえなく枯れてしまったんですな。おやおや、残念。 で、今年の6月に父の一周忌を行なった際、またまたお供え物の中にパイナップルがありまして、またまた我が家で貰って来たわけ。 で、おいしくいただいた後、もう一回、パイナップル再生計画に着手したと。 今回はちゃんとネットで調べて、パイナップルの実からパイナップルを育てる方法を学習したんです。 それによりますと、実の上の方の、葉っぱのところを実から切り離し、下の方の葉っぱをわしゃわしゃと取り除くんですな、1センチ分くらい。 すると、ブロッコリーの芯のような形の芯が剥き出しになる。で、こいつを水耕栽培すると。 で、私もこの方法にならって、その芯の部分を適当な空き瓶みたいなのに水を張ったところに漬けておいたんです。パイナップルの上の方の葉っぱが横に張り出しているので、そこが瓶の口に引っかかって、いい具合になるんだ、これが。 で、そこから3週間ほど経った頃。 なんと! 芯の部分から横に突き出すように、緑色の根が出た。 ひゃー! やった~。 しかし、すごいもんですな、パイナップルの生命力。だってさ、このパイナップル、もらってきてから1週間弱ほども冷蔵庫に入れてあったのよ。それでも、ちゃーんと命を保っていたわけですよ。素晴らしい! で、今はまだ根の長さも3ミリほどなので、もうしばらく水耕栽培を続けて、ある程度長くなってきたら、小さな鉢に植え替えて様子を見、さらに順調に芽が出てきたら、今度こそ大学のキャンパスに植え替えて、パイナップル畑を作ってやろうかなと。父の記念のパイナップルが、我が大学の庭に育つ。わはは。面白い。 ということで、今はその小さな緑色の根っこを事ある毎に眺めては、いつの日かコイツの息子のパイナップルの実がなる日のことを幻視しているワタクシなのであります。今日も、いい日だ!
July 15, 2018
コメント(0)
-

映画『ヘアー』を観た
かの有名なミュージカル『ヘアー』、その映画版を観ましたので、心覚えを付けておきましょう。以下、ネタバレ注意ということで。 『ヘアー』というのは、もともと1967年にオフ・ブロードウェイとして上演され、翌68年に今度はブロードウェイで改変上演されたミュージカル。出演者全員が一瞬全裸になるということが喧伝され過ぎたところもありますが、とにかく、反ベトナム戦争の気運の中で作られた初のロック・オペラですな。特に最初に流れる『アクエリアス』と最後に流れる『レット・ザ・サンシャイン・イン』が素晴らしく、それをカバーしたフィフス・ディメンションのアルバムがバカ売れしたという。実際、今聴いても素晴らしいですけどね。 で、そのミュージカルを『カッコーの巣の上で』や『アマデウス』で名高いミロス・フォアマン監督が1979年に映画化したのがこの映画版『ヘアー』。それを観たというわけ。 で、私はミュージカル版を観ていませんので、映画版とどのくらいの相違があるのか分かりませんが、映画版について言いますと、まずオクラホマの田舎から、素朴な青年クロードがNYにやってくるところから始まります。クロードはベトナム戦争への徴兵を受けていて、間もなく兵隊としての訓練を受けることになっていたのですが、その前にせめてNYというところを見物したいということでこの町にやって来た。 ところが、そんな田舎者のクロードが最初に出くわしたのが、幸か不幸かバーガー率いる同世代のヒッピーの集団だった。彼らもまた徴兵を受けてはいたのですが、真面目なクロードとは異なり、海外まで行って自分たちとは無関係な人々を殺しに行くなんてナンセンスと思っているので、徴兵の赤紙なんか焼き捨てて、自由気ままな生活をしている。 で、そんなバーガーたちと知り合ってしまったクロードは、彼らのいたずらに巻き込まれるような形でNYの上流階級のお嬢さんシーラと出会い、一瞬で恋に落ちることになるんですな。 もちろん、シーラとバーガーたちでは住む世界が違うのですけれども、バーガーはそんなこと気にしたりしない。同じ人間として階級の垣根を飛び越え、ずけずけとシーラに物を言うのですが、シーラの方でもそんな自由なヒッピーの世界への興味があって、少しずつ彼らに心を開いて行くわけ。 しかし、結局、クロードはヒッピーにはなりきれず、新兵としての訓練を受けるべくネバダに飛ばされ、そこで過酷な訓練に明け暮れることになります。 けれど、ベトナムへの出兵も近づいた頃、クロードはシーラにラブレターを出すんですな。で、それを受け取ったシーラは、バーガーらに相談する。と、自由人のバーガーは、それならすぐに皆でネバダに行って、クロードを軍から奪還しようと企む。 で、NYからネバダまで2000マイルのドライブをし、ヒッピー仲間とシーラでクロードに会いに行くのですが、もちろん民間人を軍の施設に入れてくるわけもなし。そこで一計を案じたバーガーは、軍の偉いさんを騙し、その制服を奪って軍に侵入。で、クルマのトランクにクロードを入れて軍から脱出させようとするのですが、クロードは「点呼はしょっちゅうあるし、そんなことできない」とバーガーの好意を断るんですな。 しかし、シーラもすぐ傍まで来ているよ、というバーガーの言葉につい魔が差し、バーガーの着ていた上官の軍服と自分が着ている新兵の軍服を交換し、軍を抜け出してシーラに会うことにします。そしてシーラと愛を交わす。その間、バーガーはクロードのふりをしてカマボコ兵舎で点呼を受けたりするわけ。 が! 急な連絡でクロードの所属していた部隊は、即刻、ベトナムへ向けて出兵が決まるんですな。で、クロードの身代わりになっていたバーガーは、期せずしてそのままベトナムへ発つことになってしまう。クロードがシーラとの逢瀬の後、兵舎に戻った時には、既に飛行機が離陸した後だった。 そして、やがてバーガーの戦死の報が届く。 バーガーの仲間やクロードは、他の無数の若者たちと一緒に反戦デモに参加し、ホワイトハウス前で抗議の声を上げる。そこで『レット・ザ・サンシャイン・イン』が流れ、幕が閉じます。 まあ、何と言っても、最後の最後、あの自由人のバーガーが、クロードの身代わりで出征するシーンが衝撃よ。それで死んじゃうんだもの。 ま、ミロス・フォアマンは『カッコーの巣の上で』(1975)の監督だからね。あれも、自由人のマクマーフィが、自由のない精神病院に潜り込み、その患者たちを解放しようとして失敗し、死んでいく話だから。『ヘアー』もその路線の話ではあるわけですな。 そういう意味では、マクマーフィーやバーガーといった「ヒッピー的精神」の体現者が死ぬことによって、その精神が周囲の人々に受け継がれるという、キリスト教的贖罪羊の物語になっているんでしょうな。もっとも、それはミロス・フォアマンの好むところなのであって、オリジナルのミュージカル版『ヘアー』がそういう物語なのかどうかは分かりませんが。 でも、まあ、アメリカ文化史的にこれだけ有名な作品で、今まで観よう観よう、観なくちゃいかんでしょ、と思っていた作品をようやく観ることが出来て、満足です。オリジナル・ミュージカルが上演された1967・68年という時代、そして挿入歌「アクエリアス」が醸し出すこの時代の雰囲気ってのは、ニューエイジ的な思想史を理解する上で、結構重要なものなのでね。[DVD洋]ヘアー [監督:ミロス・フォアマン/出演:ジョン・サベージ]/中古DVD【中古】【ポイント10倍♪7/13-20時〜7/24-10時迄】
July 14, 2018
コメント(0)
-

アマゾン・プライムになんとなく入会してみる
これだけアマゾンで大量の本を買っている私にして、まだ「アマゾン・プライム」会員でなかったという。ま、入会しなかったのには特段の理由があったわけではなく、なんとなく面倒だから入らなかっただけなのですが。 だけど、先日、道場仲間と雑談をしていて、「いいですよ~」と勧められたこともあり、ようやく重い腰を上げて、今日、入会してしまいました。 といっても、最初は例の「30日無料」という、お試しの奴ですけどね。 そしたら、いきなり映画とか音楽とか、色々見られたり聴けたりするものだから、超ウレシイ! で、とりあえず建さんの『昭和残侠伝 唐獅子仁義』とか観ちゃった! で、まだ使いかたがよく分からないんだけど、これで「アマゾンFire Stick」とかいうのを5000円くらいで買えば、パソコンじゃなくてテレビでも見られるんでしょ? まあ、映画館に1回、2回行くことを考えたら、安いもんですよね? それも買うか・・・。 こうやって、人はアマゾンの奴隷になっていくんだろうな。 まあ、でも、望むところか。奴隷にするなら、して! ということで、まだ何だかよく分からないんですけれども、とにかく、プライムっぽい感じを楽しみ始めた私なのでありました、とさ。【あす楽】Fire TV Stick (New モデル) | amazon amazonビデオ netflix hulu youtube AbemaTV DAZN dTV インターネットtv 映画 海外ドラマ Bluetooth ブルートゥース ムービー シネマ
July 13, 2018
コメント(0)
-

ルイーズ・L・ヘイ著『ライフヒーリング』を読む
ルイーズ・L・ヘイ(Louise L. Hay, 1926-2017)という人の書いた『ライフヒーリング』(You Can Heal Your Life, 1984)という本を読了しましたので、心覚えをつけておきましょう。 この本、1984年に出版されると、アメリカで大ベストセラーになるのですけれども、まあ、久々に読むゴリゴリの「引き寄せ系自己啓発本」でございました。第1章の冒頭からして「人生は、自分について考えていたことが現実になります。私自身を含めて誰もが、良くも悪くも自分の全人生に100%責任を負っています。人生について考えることは、未来を創造することです」、だからね。 つまり、今現在の時点で嫌なこと、思うに任せないことがあるならば、それは自分自身がそういう状況を引き寄せているからだと。 でも心配ご無用、今、この瞬間に自分に対する否定的な考え方をすっぱり捨てて、自分を認め、自分を愛し、これからは自分の思うような人生を生きて行こうとポジティヴに考えれば、その考え通りの人生が展開しますよと。 ま、そういう感じ。 で、本書にはいろいろな自己啓発思想の影響が窺えまして、例えば「ACIM」についての言及もあるし、エメット・フォックスへの言及もある。あと、ニューで、それらの先行する自己啓発思想を、特に優劣をつけることなく、好きなように引用していますから、要するに自分がいいと思ったポジティヴ思想はみんな取り入れちゃおう、という傾向の人なんでしょうな。 だけど・・・。 後半に入ってくると、病気・体の不調についての言及がどっと増えてきて、こういう病気も、心の持ちよう次第で全部治ってしまう、というスタンスを取り始めるんですな。 ちなみにこの人が最初に有名になったのは、『Heal Your Body』という小冊子で、これはそのタイトル通り、精神治療の本だったんですな。で、ここに書かれた内容が、本書『You Can Heal Your Life』にも大幅に採り入れられてると。 で、その結果、たーくさんの病気が並べられ、それぞれについて「(その病気の)考えられる原因・内的要素」と、それを治療するための「新しい思考パターン」を表にしたものがどーんと載っているわけ。 例えば「結膜炎」は、「あなたが目を向けているものに対する怒りや欲求不満」が原因で生じているので、その治療法としては「愛を通して見る。そこには調和があり、私はそれを受け入れる。正しくあらねばならないという気持ちを取り除く」ことをお勧めすると。 なるほどね。 ちなみに「花粉症」はですね、「感情的すぎる」こと、もしくは「被害妄想」が原因らしく、「私はあらゆるものと気持ちが通じている。私はいつでも守られている」と唱えれば快癒するらしいですよ。 あと「ガン」は、「深く傷つけられる。恨みが募る。嫌悪感」などが原因で、対処法としては「心から過去を許して手放」し、「私の人生は喜びに溢れている」ってなことを日々唱えると治るようです。 本書にはノーマン・カズンズが笑いによって難病を治したことへの言及などもありますけど、結局、アレだね。この人の思想の大本は精神治療ですな。ま、タイトルからして「ヒール」なんだから、そりゃそうか。 一つ、ちょっと意外に思ったのは、この人、この種の本の著者にしては性的なことについて割とオープンなところがあって、例えば女性に多い「片頭痛」の対処法として、「そういう時は一人Hしちゃいなさい。片頭痛は、性的抑圧が原因のことがよくあるので」と言っているのにはちょいビックリ。そうなの? とまあ、そんな感じで、ところどころでほんのちょっと驚かされつつも、全体的にはふんふん、そういうことね~と軽い気持ちで読み飛ばしていたんですけれども、最後の最後、ヘイさんが自分の過去を振り返った章を読んで仰天。なんと、語るも涙、聞くも涙ってな感じの悲惨な人生をヘイさんは歩んでいたのでした。 彼女はカリフォルニアで生まれたようですけれども、生後18か月で両親が離婚、その後母親が再婚した相手が最悪の冷血漢で、ヘイさんは幼児期から家庭内暴力に晒され、しかも5歳の時には近所の老人にレイプされるという。で、昔のことですから、周りからは「お前が悪い」的な悪口を言われ、また牢屋に入ることになったその相手の老人がいつまた復讐に来るか、びくびくして暮らしていたそうで。 で、そんなですから、小さい時から自分に自信がなく、自分には価値がないと信じていたので、それゆえに学校でもいじめられたと。 で、その反動からか、興味を持ってくれた男とは誰とでも寝るようになり、16歳の時に出産(生まれた子供は、子供のない夫婦にもらわれていったそうです)。そして、出産後すぐ、継父のあまりの暴力に耐えきれず、妹を残して母と二人でシカゴに逃亡。そこでモデルとして仕事を始めるんですな。で、やがてイギリス人の老紳士と結婚するも、14年後に「他の女と結婚したいから離婚して」と言われ、大ショックのうちに離婚。 で、このショックが一つの契機となり、彼女は精神療法団体の一つであるリリジャス・サイエンスにのめり込むんです。 なるほど、彼女がヒーラーになる素地ってのは、ここにあるわけね。 だけど、いよいよヒーラーとしての活動を始めようという時に、今度は婦人科系のガンが見つかると。彼女曰く、「そりゃ、5歳からレイプされているんだから、そうなりますよね」と。 ですが、ここからがヘイさんの真骨頂で、外科的手術なんかじゃガンは治らんと喝破、精神療法に専念し、自らの力でガンを完治!(マジか!!) レイプされたことへの憎しみや、自分自身を愛せないことからガンになったのだから、その逆を行って、「ルイーズ、あなたが好きよ」ってなことを自分自身に言い聞かせることで、ガンを治してしまったと。 で、その後ヒーラーとしての実績も積み重ね、故郷であるカリフォルニアに凱旋、かつて生き別れとなった妹や、必ずしもいい関係ではなかった母とも再会し、特に目を患っていた母親とは同居もして、少しずつ過去のしがらみを改善していると。それが、この本を書いていた頃のヘイさんの人生だったんです。 まあ、すごいね。いかにもオプラ・ウィンフリーに気に入られそうな経歴ですな。でも、こういう人生があって、それを自己啓発思想で乗り切って有名になったからこそ、自分と同じように人生で苦しんでいる人に福音を届けようと考えたのでしょうな。自分自身という実験材料で既に成功しているから、自分の教えていることに自信があったのでしょう。 でまたこの本がすごく売れちゃったので、その後彼女は「ヘイ・ハウス」という出版社を設立、ディーパック・チョプラを始め、ここから本を出している有名な自己啓発ライターも沢山いるという。ある意味、アメリカン・ドリームを成し遂げております。 ま、そういう人が書いた、こういう本。 で、最後に私としてこの本をどう評価するか、ということなんですけど・・・ うーん。割と好き(爆!)アホみたいな本だとは思うけどね。 っていうかね、私は基本的に、引き寄せ系の本が好きなのよ。自分を肯定し、ポジティヴに願えば、なんでも夢が叶うっていう系の奴が。夢があるじゃん? だから、ヘイさんのおすすめに従って、「限りのない人生/完成され満たされた世界/どの瞬間にも私のうちに流れる力/その力の知恵に身を委ねる/必要なことはすべて啓示され/必要なものはすべて与えられる/私の世界ではすべてがうまくいく」みたいな呪文を密かに唱えちゃったりするの。唱えると、とってもいい気分。ウフ! というわけで、私と同様、そういうのが好きな人にはおすすめ! ということで一つ。ライフヒーリング改訂新訳 [ ルイーズ・L.ヘー ] ところで、ウィキペディアでヘイさんの経歴を見ていて気付いたんですけど、この人、ロスにある「University High School」を中退しているんですよね。 で、その記述を読んでいてふと思ったんですけど・・・ 私、この高校に通ったことがあるかも。 いや、もちろん高校時代に通ったのではないのですが、1998年にUCLAで研究していた時、夜間にこの高校の校舎を使ったロス市のアダルトスクールに通っていたんですよね。うろ覚えだけど、確かそう。 ヘイさんと私は、だから、同窓・・・ってことになるのかな? ・・・そう思ったら、余計、この本が好きになってきたかも!
July 12, 2018
コメント(0)
-
お茶の水女子大のトランジェンダー受け入れに物申す
最近、お茶の水女子大がトランスジェンダーの学生、つまり、戸籍上は男であるが、本人の認識としては女性、という人を今後、入学生として受け入れると発表し、話題になっております。時代に先駆けた先進的な試みとして素晴らしい的な方向で。 が! 私としては「おふざけでないよ」と言いたい。 国立大学でありながら、男性の入学希望者を拒むというあからさまな性差別を行っている大学が、なにを寝ぼけたことを言っているのかと。 まあ、百歩譲って、歴史上、同大が「女子大」として運営することに意味があった時代があったことは認めよう。また津田塾大学や東京女子大、日本女子大などの存在意義も認めよう。それは私立の大学として、創立者の教育理念があってやっていることだからね。 しかし、お茶の水女子大と奈良女子大の二校、すなわち国立大学法人として運営している二校が、21世紀の今日も相変わらず男性差別をし、男性の入学者を認めていないことは、国の機関として法に反しているのではないかと。国立の大学で男性を入学者から排除することが可能だというのなら、その法的根拠をまず示せと言いたい。 逆に、これから国立の男子大学を作る、そこでは女子の入学は認めない(ただし、戸籍上は女性だけど、自分の認識としては男性だ、という者は入学を許可する)ということになったら、世のフェミニストたちはそれを「よろしい」と認めるのか? 国立の女子大は、時代錯誤であり、明白な性差別であると、私は思います。「トランスジェンダー受け入れ」で、あたかも時代に先駆けたようなことを言っているお茶大の姿勢に私は猛省を促したい。お茶大の学長はアホなことを言ってないで、さっさと「トランスジェンダーはもとより、男性の入学希望者も受け入れる」と宣言しなさい。 っていうか、トランスジェンダーを受け入れるのは当たり前のことですよ。一般の大学で、「うちはトランスジェンダーの方は入学できません」とうたっているところなんてある? あるわけないじゃん。だから、そもそも今までトランスジェンダーの入学希望者を拒否していたこと自体、罪深いことであったということに気づいていないお茶の水女子大は、そもそも「性差別」とは何か、まったく認識していないわけですよ。 ほんとに腹立たしいわ~。
July 11, 2018
コメント(0)
-
ケリー・サイモン氏が弾いているこのフラメンコ・ギター曲、なあに?
御多分に漏れず、私も時折、インターネット上の動画にはまるのですけれども、最近、はまっているのがコレ。基本的にはロック系のギタリストであるケリー・サイモン氏が、フラメンコ・ギターを弾いている動画でございます。これこれ! ↓ケリー・サイモン氏の超絶技巧 この動画の最後の数分間、ケリー氏が演奏しているのをお聴きください。素晴らしくない? この人クラスだと、もう弦さえ張ってあれば、なんでも弾けるのね。 ところで、この動画を見てから、フラメンコ・ギターっていいな、と思うようになり、そっち系のCDでも買おうかと考えているのですが、その方面に明るくないので、何を買えばいいか全然わからない。ちょっと検索かけると、すぐに「パコ・デ・ルシア」という人のことが出てきて、確かにそちら方面の代表的な演奏者のようなんですが、ちらっとその演奏を聴いてみても、なんとなくしっくりこない。私にはむしろケリー・サイモン氏のあの演奏の方が好きだったりして。 っていうか、ケリー氏が弾いているあの曲が好きなのか・・・。 と思って、ケリー氏が弾いている曲がなんという曲なのか知りたいと思うのですが、私にはその調べ方が分からないんですな。 一体、この曲は何? 有名な曲なんすか? どなたか、フラメンコ・ギター方面に詳しい方、上の動画でケリー氏が弾いているのが何と言う曲なのか、ご存知でしたらご教示ください。よろしくお願いします。
July 10, 2018
コメント(0)
-

映画『エンドレス・マーダー』を観た
ううむ、歌丸師匠に次いで、今度は加藤剛さんか・・・。昔の俳優は、圧倒的に二枚目だったなあ・・・。 それはともかく、昨夜、録画しておいた『エンドレス・マーダー』(原題は『スーサイド・セオリー』)というオーストラリア映画を観ましたので、ちょっと心覚えをつけておきましょう。以下、ネタバレ注意ということで。 スティーヴンという殺し屋の物語なんですが、ある時彼は、パーシヴァルという若者から自分を殺してほしいという依頼を受けるんですな。パーシヴァルはゲイの画家なんですけど、恋人であったクリスに死なれてから絶望し、何度も自殺を試みるのですが、その都度、なぜか奇跡的に助かってしまう。そこで、どうしても死にたいパーシヴァルは、たまたま出会ってしまったスティーヴンに自分の殺しを依頼したわけ。 で、スティーヴンは、その仕事を引き受け、その場でパーシヴァルに弾丸を3発撃ち込みます。あっさり仕事を片付けたわけ。 ところが、パーシヴァルはまたもや奇跡的に助かってしまう。それどころか、撃たれた弾を摘出する際、腫瘍が見つかり、ついでにこれも摘出したので、むしろ撃たれる前より健康体に。 で、パーシヴァルはもう一度スティーヴンにちゃんと殺してもらいに行くのですが、その後2度、殺害を試みるも、どちらも失敗に終わってしまう。パーシヴァルはどうしても死ねないんですな。 で、どうすればちゃんと殺せるのか、殺し屋のスティーヴンとパーシヴァルは何度も相談を繰り返すんですが、その過程で二人はそれぞれの人生航路を語るようになり、次第に親しくなっていく。 実はパーシヴァルが恋人を失って絶望しているのと同様、スティーヴンの方も愛する妻を自分の目の前でひき逃げされるという最悪の形で失っており、以後、妻のことがどうしても忘れられず、絶望しているんですな。それだけでなく、ひき逃げのトラウマから、道路を自分の足で渡ることができなくなっている(無理に渡ろうとすると気絶してしまう)。殺し屋の方も、そういう悲しい過去を背負っていたわけ。 ところで、パーシヴァルというのは運命論者で、自分がどうしても自殺できないのも、またスティーヴンという殺し屋と出会ったのも一つの運命であり、それは決して偶然ではなく、何か意味があるのだろうと思っているんです。そしてそのことを繰り返しスティーヴンに言うもんですから、スティーヴンも次第に、自分が置かれている状況には何か意味があるのではないかと思い始める。 そんな時、たまたまスティーヴンは、妻子ある警察官を殺そうとしていた暴漢を見かけ、逆にこの暴漢を撃ち殺し、警察官を助けることになってしまう。親の愛も受けずに育ち、殺し屋として生きてきたスティーヴンは、生まれて初めて人のためになることをしたんですな。そして、この経験から彼は、殺し屋稼業から足を洗おうとさえ考え始める。そしてそのことを、今や親友となったパーシヴァルに告げるわけ。自分が今日、警官の命を救うという運命にあったのと同様、君がどうしても自殺できないのにもきっと意味があるに違いないのだから、自殺するのはやめなよと。俺ももう君を殺せないから、お金は返すと。 かくして、スティーヴンもパーシヴァルも、死なずに生きていく道を見い出しかけたかに見えたわけ。 が! パーシヴァルは、3年前にスティーヴンの妻・アニーをひき殺したのが自分であることに気づいてしまったんです。その時、彼は恋人のクリスを失った直後で、自暴自棄になり、浴びるように酒を飲んで車を運転していて、それでハンドル操作を誤ってしまった(あるいは自殺しようとした)と。そして、それに気づいたパーシヴァルは、スティーヴンにそのことを告げ、許しを乞うた上で、改めて殺してほしい旨、伝えるんですな。 しかし、真実を知ったスティーヴンは、どうしてもパーシヴァルを許すことが出来ず、そのまま彼を殺してしまいます。そして、この時、ようやくパーシヴァルは死ぬことになる。 で、パーシヴァルの葬儀に出たスティーヴンは、パーシヴァルの兄から、パーシヴァルの絵の回顧展があるから見に来ないかと誘われ、そこに行くわけ。そしてパーシヴァルが最後に描いていた絵を見る。それは死んだ恋人・クリスの肖像画だったんです。 で、その絵を見た時、スティーヴンは思い出すわけ。3年前、あることがきっかけで彼はある男を殺すのですが、その男がクリスだったことを。 パーシヴァルの言った通り、すべては運命的に定められていたわけ。 絶望したスティーヴンはふらふらと大通りを渡り、車に撥ねられてしまう。そしてブラックアウト。 しかし、その後我々は、病院で治療を受けているスティーヴンの姿を目にすることになる。パーシヴァルがかつてそうだったように、スティーヴンにはもう少し生きながらえる運命があった(らしい)。 そんな映画。 最初、殺したはずの相手が何度でも現れるというストーリーだと聞いていたので、その種の超自然的なスリラーなのかと思っていたら全然違いましたね。 だけど、これがね、不思議な魅力のある映画なのよ。 特に、殺し屋のスティーヴンがいい。あまり近づかない方がいいやばい感じのところもあり、友達甲斐のあるような気のいいところ感じのところもあり、今回のこの役にはこれ以上ないほどの適任ぶり。 で、そこはかとなく可笑しいわけね。だって、殺し屋と殺される側が、「一体どうしたら、ちゃんと殺せるんだろう?」って、一生懸命知恵を出し合ったりするところなんて、普通じゃありえないシチュエーションなんですけど、それが切実な問題としてあるので、なんだか可笑しい。そういう、おふざけでない可笑し味というのが随所にあって、クスッと笑えるわけよ。 しかも、愛する者を共に失うというシリアスなところもあって、そこはそこで哀しい。そういう可笑し味と哀しさがないまぜになったところが、なかなかよろしい。 ま、例によって各種レビューを見ると酷評されていたりしますけれども、私が見るに、佳作ですよ佳作。それなりに評価すべきものだし、実際、賞とかも獲ってます。B級映画の味わいとして、見て損はない映画。教授のさらっとおすすめ! と言っておきましょう。エンドレス・マーダー 【DVD】 ちなみに本作冒頭近く、パーシヴァルが自身の運命論を語るところで、スティーヴンから「それはフロイトの考え方か?」と尋ねられ、それに対してパーシヴァルが「いや、エリザベス・キューブラー・ロスだ」と答えるところがある。 エリザベス・キューブラー・ロスについては、本ブログでも再三取り上げておりますが、こういうB級映画の中でもさらっと触れられるほど、一般的に知られているわけですな。そこは自己啓発思想の研究者として、ちょっと面白いところでした。
July 9, 2018
コメント(0)
-

ロビン・ノーウッド著『愛しすぎる女たち』を読む
ロビン・ノーウッド著、落合恵子訳『愛しすぎる女たち』(原題:Women Who Love Too Much, 1985)を読了しましたので、心覚えを付けておきましょう。 本書は後に「WWL2M」という略称で語り継がれるまでに全米でベストセラーになった自己啓発本でありまして、日本風に言えば「だめんず・うぉ~か~」(@倉田真由美)の病理とその治療法を示した本。男からすると理解しがたい・・・いや、ノーマルな女性にとっても理解しがたいでしょうが・・・「ダメ男」とばっかり常習的に付き合ってしまって、落ちるところまで落ちてしまう女性達が、一体どういう理由でそうなってしまうのかを、ものの見事に分析しております。 で、本書によれば、そういう女性達に共通する状況として、問題アリアリの家族の中で幼少期を過ごす、ということがあると。 例えば、お父さんがアル中だったり、DVを振るう奴だったり、はたまた実の娘に性的いたずらを仕掛ける奴だったり。 で、そもそもそういう奴がいるという時点で大問題なわけですが、この状況をさらに悪化させるのが、母親であったりする。つまり、そういう悪い夫の在り方を見て見ぬふりをしたりするわけですよ。すると、娘としては、助けを求めることができなくなるわけで、逆に、そのことで自分を責めたりするようになってしまう。 あるいは、逆にそういう夫と毎日大喧嘩する妻もいる。来る日も来る日も大喧嘩。その場合、娘としてはそういう日常を受け入れてしまったりする。そして、例えば自分が学校でいい成績を取ったり、家族の中で剽軽者を演じることで、かすがいになろうと必死になったりする。 とまあ、本来、両親に愛されて育つべき時期にそういう経験をしてしまうと、娘ってのは「自分は最低の家庭に育った」という風には考えず、そういう明白な事実は否認してしまって、逆に「自分が頑張ってみんなの面倒を見なくちゃ」という考えかたが身についてしまうんですな。 で、この状況で結婚適齢期になろうものなら、あーた、大変なことになるわけですよ。 つまりね、よりによってダメな男を探し出しては、「この人には私がついていて、面倒を見てやらなきゃダメなんだ」という風に感じ、その使命を愛と勘違いして情熱的に結婚しちゃったりするわけ。 で、ダメ男の方も、そういうタイプの女を本能的に見つけちゃうんですな。で、男の方は面倒見てもらいたいと思っていて、女の方では面倒見たいと思っているわけだから、双方共に「これは運命的な出会いだ」と思っちゃう。 かくして、以後、女の方は男の面倒を見まくる。男が仕事をしないのは、まだ自分の適性を見い出していないから当然であって、それを見つけるために大学に行かせてやろう、とか、そういう風に思っちゃうんですな。それでどんどん甘やかせてしまう。でも、それは単に甘やかせているわけではなくて、むしろ男をがんじがらめに「管理」しようと思っているわけ。で、男を自分の思うように行動させようと必死になる。そういう自分の行動を「愛」だと信じつつ、その愛に邁進してしまう。 ところが、女が管理しようとすればするほど、男はその束縛から逃げようとしますから、彼女をほったらかして、別な女と浮気したりするわけよ。 で、ここがまた幼少期の繰り返しなんですが、明らかに夫が浮気していても、それを認めてしまうと傷つくことを知っているので、女はそれを見て見ぬふりをするわけね。その事実を否認する。ちょうど、自分の母親がそうであったように。そして、さらに自分が頑張れば、夫は自分のもとに帰ってきてくれるんじゃないかと思う。そして更に頑張って夫を管理しようとし、さらに夫に愛想を尽かされ、さらに傷つくことになる。 だけど、傷つくというのは、その女にとって、ある意味、自衛手段でもあるんですな。 つまり、彼女はもともと幼少期の頃からうつ病を発症しそうな環境に育ったわけですよ。だから、通常であればこの時点でうつになってもおかしくない。だけど、逆にそういうダメ夫と結婚して激しく傷ついたりすることによって、痛みによって痛みを制すというのか、そのことでうつになることを辛うじて防いでいたりするわけね。 だから、この状況から逃げるということは考えられないわけ。地獄の中に居ないと、さらなる地獄が待っているんだもん。だから、自ら進んで地獄の中に入って行こうとする。 これが、要するに、「愛しすぎる女たち」の実態であると。まさに地獄絵ね。 で、そんな地獄絵なのに、それを地獄絵と判断できない理由の一端は、世間一般に流通する「愛」についての概念だと、ノーウッドは指摘します。つまり、愛というのは苦しいものだ、苦しければ苦しいほど、その愛は崇高だ、的な概念を、映画やドラマや流行歌なんかが繰り返し提示する。だから、そういう状況にあっても、女たちはそれを異常だとは思わないと。 で、じゃあ、そういう地獄絵の中で苦しむ女性達を救うにはどうすればいいか? まず、本人が自ら助けを求めようと思わないとダメだ、とノーウッドは言います。他人がいくら言ったって本人が「アレ? ちょっと私、おかしくない?」と思っていないんだったら、治療しても効果がない。 だけど、本人が自分の状況はちょっとおかしいんじゃないかと気づきさえすれば、問題解決の方法はあるんですな。 カウンセリングによって、彼女のこれまでの地獄絵のパターンを認識させ、そうなる原因を作った幼少期の家族環境を客観視させ、夫なり彼氏なり、とにかく相手を管理しようとしている癖を把握させる。その上で、そうした管理欲を放棄させ、相手のためにしてきたあらゆる努力をやめて、その分、自分自身の面倒を見ることにその努力分を費やすようにさせる。自分自身を愛せなかったら、対人関係でフェアな関係を築けるはずはないので。 ところが、こういう「愛しすぎる女たち」にとって、相手の面倒を見ない、というのは、とてつもない苦痛なんだそうで。 実際、ダメ男が何かのきっかけで更生し、良い夫になったりすると、「愛しすぎる女たち」としては、その男に興味がもてなくなり、彼と別れて他のダメ男を探してしまったりするというのですから、根は深いんですな。 だから、ダメ男と付き合わない、ダメ男の面倒を見ない、というのは、彼女たちにとってはものすごい努力を要することなんです。相手を管理することでしか、自分の存在意義を感じられないのですからね。 だけど、そういう性癖を克服しない限り、絶対にこの地獄絵からは逃れられない。 そこで、専門家とのカウンセリングで、自分が陥っている地獄のことが分かったら、次のステップとして、同じような状況に苦しんできた同性の仲間と自己啓発のためのグループを作って、定期的に会合に参加し、元の地獄に戻らないよう、助け合わなければならない。この種の助け合いが、地獄からの脱出には必須であるとノーウッドは言います。 ま、とにかく、「愛しすぎる女たち」がノーマルな生活を手に入れるのは、アル中患者がアルコールから手を切るとか、麻薬常習者が麻薬から縁を切るのと同様、ものすごい苦痛と努力を要すると。でも、アル中患者・麻薬常習者と同じく、「愛しすぎる女たち」も、その苦痛を乗り越え、努力を続ければ必ずやノーマルな人間に戻れる。それは確かなんだから、頑張りなさいと。 ま、本書が数多くの例を挙げながら雄弁に語っているのはそういうことでございます。 本書が出版されたのは1985年ですが、その少し前、1981年に出版されてベストセラーになったのがコレット・ダウリングの書いた『シンデレラ・コンプレックス』という本で、これは「他人に面倒を見てもらいたい」という潜在的な願望があるために、本来ある自分の能力を発揮できず、常に他人(=夫)に寄りかかってしまう女性たちの状況を指摘した本。その意味で本書『WWL2M』は、その逆を描いた本と言っていい。 というと、1980年代というのは、管理されたがったり、管理したがったり、女ってのは面倒臭い生き物だ、ということが明らかにされた時代ということになりましょうかね。でも、それは必ずしも女性自身のせいではなくて、社会が、アメリカ文化が、そういう風に女性をしつけたからだと。 その意味で、これら両書は、先行するベティ・フリーダンの『女らしさの神話』の流れを汲む、「社会批判系女性向け自己啓発本」と言うことができる・・・かな。 あ、あとね、この本、「愛しすぎる女たち」の問題をアル中とか薬中の問題に近いモノとして扱っているのですが、この視点は結構重要です。というのは、それまでこういう恋愛問題/結婚問題のゴタゴタというのは、あまりにも個人的な問題過ぎて、恥しくて公けに出来ない、という風潮があったんですな。だけど、それを本書は「アル中・薬中」と同レベルの問題として、つまり一種の病気として扱うことによって、恥しくないもの、そして治療可能なものに変換した。で、本書以後、この種の問題が自己啓発本の中で頻繁に言及されるようになる(例えば Melody Beattie の『Codependent No More』(1986) とか)発端にもなったのですから、本書の存在意義というのは、なかなか大きかったわけ。 ま、でも、そういう系統分類や存在意義の観点は別にしても、この本、なかなか説得力があります。特に、本書が描くような「愛しすぎる女たち」の一人だと自覚があるようなだめんず・うぉ~か~さんたちには、必読の本と言っていいのではないでしょうか。愛しすぎる女たち (中公文庫) [ ロビン・ノーウッド ] しかし、本書には一つ、重大な欠陥があります。 それはロビン・ノーウッドに責任があるのではなく、本書の訳者・落合恵子氏に責任がある。 本書の随所に訳者・落合恵子氏による「訳注」が、本文に直接挿入する形でつけられているのですが、これが実際には「訳注」ではなく、落合氏の意見なんです。 要するにノーウッド氏の本文を翻訳しているうちにエキサイトしてしまったのか、落合恵子さんが勝手に自分の見解を付け加えたり、逆に「こういう書き方は気に入らないと言っておこう」とか言って批判したりするわけ。 そんな、自分の意見だの本書に対する批判を本文に挿入する形で勝手にくっつけるなんて、翻訳者の分を越えた非常識な行為であって、断じて許されるものではございません。また、もし翻訳者がそういう愚行に出たとしたら、編集者は体を張ってでも止めなくてはならない。 あ、あとついでに指摘しておきますが、本書巻末の「あとがき」の中で、本書のペーパーバック版の版元が「Simon & Solueten」社であると記してありますが、こんな名前の出版社は存在しません。それを言うなら「Simon & Schuster」ね。あと、本書のサブタイトルの原語は「When you keep wishing and hoping, he'll change」ではなく、「When You Keep Wishing and Hoping He'll Change」です。カンマなんてついてない。「He'll Change」は「Wishing and Hoping」の目的節だからね。どちらも、ちょっと確認すれば誤りを防げるはずなのに。 色々な意味で、レモンちゃん(昭和生まれなら知っている、落合恵子氏のあだ名)と、この本の編集者には猛省を促しておきましょう。
July 8, 2018
コメント(0)
-

映画『ダンケルク』を観た!
2017年話題の映画、クリストファー・ノーラン監督の『ダンケルク』を観ましたので、心覚えを付けておきましょう。以下、ネタバレ注意ということで。 ダンケルクの戦いというのは、第2次世界大戦初期、イギリス対岸のフランスの町ダンケルクでドイツ軍に包囲されたイギリス・フランスの連合軍の兵士40万人を救うための救出作戦のこと。連合軍の兵士たちは既に砂浜に追いつめられていますから、陸路の脱出は不可能。海から船舶を使って脱出する以外ないのですが、連合軍の船舶が海に近づけばドイツ空軍が狙い定めて爆撃してくる。この窮地のさなか、40万の兵士をどうやって救うのか。 映画は陸・海・空、3つの側面からこの歴史に残る大脱出劇を描いて行きます。しかも陸については1週間、海については1日、空については1時間を描くという具合に、時間のスケールが全部異なる。しかも、それだけ時間軸が異なるのに、3つのフェーズがうまい具合に絡み合うという見事な演出。 陸の部の主役はトミーという若い兵士。彼は敵軍に包囲され、同じ部隊の仲間をすべて失い、一人で命からがら逃げているんですな。彼の願いは、とにかく生きてイギリスに帰ること。そのために頭を絞り、臨機応変に手を尽くして何とか救出船に乗り込もうとするのですが、なかなかうまくいかない。せっかく乗り込んだ船もUボートの魚雷で撃沈したりして、何度も何度も振り出しに戻されてしまう。果して彼のイギリス帰還はなるのか?! 海の部は、ドーソン氏の物語。ドーソン氏はもういい歳のおっさんなのですが、イギリス軍がダンケルクで危機に陥っていると知り、本国海軍に徴収される前に自ら自分の船の舵をとって息子ピーターと共にダンケルクへ兵士救出に向かうんですな。船といっても小さなものですから、救出できる兵士の数はせいぜい20人かその位。それでもとにかく一人でも多くの兵隊を救うべく、同じ志を持った民間人たちと共にイギリス対岸の町ダンケルクに向う。何故、彼は老骨に鞭打ってまで救出に向かうかと言えば、その少し前、彼のもう一人の息子がイギリス空軍の軍人として戦死していたから。ドーソンにとって、ダンケルクで難渋しているイギリスの若い兵隊たちを救うことは、ある意味、死んだ息子の弔いだったんです。さて、民間人救出部隊の一隻としてダンケルクに向うドーソン氏とピーターの運命は?! 空の部は、イギリス空軍で戦闘機スピットファイアを駆るパイロット、ファリアの物語。ダンケルクの救出作戦を阻止するために爆撃を繰り返すドイツ空軍に対抗し、ドイツの戦闘機や爆撃機を撃墜すべく出撃したファリアたち3機は、その任務に死力を尽くすのですが、途中、上司である隊長機は撃墜され、もう一人も海に着水せざるを得ない状況に。ファリアの機体も銃撃を浴び、メーターが壊れてしまったので、自分が操縦する戦闘機にあとどのくらいの燃料があるのか分からない状態。それでも只一機でダンケルクに向うファリアなのですが、ダンケルク上空で敵軍の爆撃機を撃墜したはいいものの、ついにその時点で燃料が空に! 上空でプロペラの止まったスピットファイアとファリアの運命や如何に?! とまあ、そんな感じで3つの物語が同時進行しながら、ダンケルクの救出作戦の顛末が描かれるこの映画、ワタクシの評価点はと言いますと・・・ 「87点」でーす! 高評価! まずね、映像が圧倒的に美しい!! それを批判する映画評(戦争映画なのに、血みどろの映像が一つもないなんて! という評)があるのも重々承知ですけれども、そんなのはどーだっていい。人間どもがアホな戦争を繰り返す、その戦場がかくも美しいということ自体が、強烈な戦争批判になっているんじゃないのかと。 そして圧倒的なリアリティね。本作ではセリフはほとんどないし、敵であるドイツ兵の姿などは一度も描かれない。それを批判する映画評(敵兵が映らない戦争映画なんて! という評)があるのも重々承知ですけれども、そんなのはどーだっていい。よござんすか、よござんすか。実際の近代戦争の戦闘のさ中にある一兵隊が、敵兵の姿を実際に見るなんてこと、あるわけないじゃん。どこからともなく銃撃されたり、空爆されたりする中、右往左往するというのが、むしろリアリティなんじゃないのかと。 そしてこれだけセリフがない中で、しっかりとドラマがあるということ。この点についての否定的な感想(淡々としすぎていて、ドラマがない。この映画の何が面白いの? という感想)があるのも重々承知ですけれども、そんなことを言う人たちのことはどーだっていい。っていうか、この映画、むしろドラマだらけじゃん? 3つのドラマが詰め込まれているんだから。しかも、その3つのドラマのどれもがサスペンスフルで感動的なんだから、もう言うことはない。 で、最後、ほうほうの体で逃げ帰った兵士たちを迎えるイギリスの人々の姿。自分たちは逃げ帰っただけなので、こんな歓迎を受ける資格がないと呟く兵士に、「それで十分じゃないか」と返す一市民。兵器や装備を全部ほったらかして、ただイギリス兵の命だけを救う作戦に出たチャーチルが、「我々は絶対に屈服しない。陸・海・空で戦い、野原でも、丘でも、街中でも闘う」と演説する。 イギリスが戦争に勝つのも当たり前だなと。 というわけで、戦争という状況を用いながら、感動的な人間ドラマとなったこの映画、私はとてもいい映画だなと思いました。まだ観ていない方は、是非!【メール便送料無料】ダンケルク ブルーレイ&DVDセット(ブルーレイ)[2枚組]【B2017/12/20発売】
July 7, 2018
コメント(0)
-
ガンダム実写化と肩車伝統
ガンダムがハリウッドで実写化されるそうで。 まあ、いんだけどさ。ハリウッドはもはや、オリジナル・ストーリーの映画が作れなくなっちゃったんですかねえ・・・。 ところで、今年度、うちのゼミで「アメリカにおけるロボット恐怖」というテーマで卒論書いている奴がおりまして。 まあ、よく言われることなんだけど、日本では、鉄腕アトムだの鉄人28号だのドラえもんだの、人間とロボットの関係が非常に良好で、「ロボットは友だち、コワくないよ!」っていう感じですよね? それはサイボーグも同様で、『サイボーグ009』とか、『キカイダー』とか、サイボーグのいい奴ってのは沢山いる。 一方、アメリカ(もしくは西洋全般)では、ロボットは恐怖の対象となることが多いので、SF映画なんか見ても「人間が、人間の作ったロボットに滅ぼされる(滅ぼされかける)」という話が多い。『ターミネーター』なんてのは典型的なわけでありまして。 ま、これは主としてキリスト教的伝統の影響で、人をつくる(=命あるモノをつくる)のは神の仕事、という明確な意識があるわけですよ。だから「人が人をつくる」というのはタブーなので、『フランケンシュタイン』みたいに、人が人をつくろうとすると、結果として被造物によって人間が酷い目に遭う、ということになりがち。 人(父)がロボット(子)を作ると、その父子関係の優位性はいつの日か覆り、ロボットによる父親殺しが起こるというのが西洋のロボット観なわけですな。だからこそ「ロボット3原則」(アシモフ)なんてのを作ってなんとか「父殺し」を防ごうとするのだけど、3原則自体が持つ自己矛盾によって結局その宿命は防げないというね。だから、仕方ない、ロボットの反乱は人間が実力で鎮めるしかない。『ブレードランナー』っていうのは、そういう映画ですな。 一方日本では、八百万の神とかいって、モノにも命がある、という発想がもともとある。だから、モノ(ロボット)にも命があり、心があってもおかしくない、と思っていると(ホントかよ?!)。 というわけで、西洋ではロボット=コワいモノ、日本ではロボット=友達、っていうのが通念ということになっております。ま、ちょっと画一的過ぎる捉え方のような気もしますが。 だけど、日本におけるロボット受容の寛大さについて、様々な論文・言説を読んでいると、これまた妙チキリンなことが書いてあったりするのよ。 例えばね、ロボットと肩車の関係とか。 それによると日本人は、よく子供を肩車すると。で、肩車された子供は、いつも自分の背丈でしか見ていない世界ががらりと変わり、すごく楽しくなる。何か自分よりよっぽど大きなものの上に乗り、歩き回るのが楽しくて仕方がない。 で、これが「マジンガーZ」のパイルダー・オン状態であると。ま、私はよく知りませんが、『ガンダム』のモビルスーツも、これに近いのかな? だから、日本でマジンガーZとかガンダムのように、「人間とロボットの完全な協働」アニメが受けるのは、視聴者が父親に肩車してもらった幼き日の郷愁を味わっているからだと。 一方、西洋ではあまり父親に肩車されることがなく、子供は普通、母親の胸に抱かれる。だから、西洋人には、本当の意味でのパイルダー・オンの至福を味わうことはできないのであると。 マジかよ! まあ、色々なことを言う人がいるものでありまして。 というわけで、肩車をされないアメリカ人たちが、『ガンダム』の実写版を堪能できるのかどうか、パイルダー・オンして「高みの見物」と行きましょうかね。
July 6, 2018
コメント(0)
-
同僚たちとラーメン屋へ
昨日、雑談の中でおいしいラーメンが食べたいという話になり、今日のお昼は同じ科の同僚4人で、大学の近くに新しく出来たラーメン屋さんに行くことに。 仲いいよね、うちの科。うちの大学でも、同僚がこれだけ仲いいところって、他にないよ。 で、向かった先は「麺屋○○る」というお店。昼時は結構混んでおりますが、お客さんの大半が一人でふらっと来られる感じなので、逆に二つあるテーブル席はがら空き。なので、我々4人はすぐにテーブル席に案内されました。 で、このお店、ラーメンは二郎系なのかな? だけど、まぜソバも各種あるという。それで、我々は2人がラーメン系、二人がまぜソバ系で、全員違うメニューを選択。で、待つことしばし・・・。 ・・・しばし、じゃないな。ラーメンなんか、あっという間に来るかと思いきや、意外に待たされました。 で、4人、意気込んで食べ始めたのですが・・・ うーん・・・ 量は多い。 量は多いのだけど、味は・・・ 結局、4人のうち3人は苦しんで完食しましたけど、私は残しちゃった・・・。 自分で注文したものを残すなんて、昭和の男たる私の最も忌み嫌うところなんですけど、今回はギブ。 ラーメンなんて、基本、何だって旨いだろうというのは単なる思い込みで、あまり美味しくないラーメン屋さんもあるのね。 ま、このお店はこういう感じだということが分かったから、良しとしましょう。今までこの店の前を通る度に「あの店、美味しいのかな? いつか行ってみたいな」と思ってきたんですけど、これからはそういうことを考えなくて済むようになったんだから、勉強代ということで。
July 5, 2018
コメント(0)
-
同窓会報を作る
うちの科では、卒業生に向けてのニューズレターとして、同窓会報を作っているのですが、今年もそれが完成しました。 まあ、私が原稿依頼して、私が編集して、私が印刷して、私が丁合して、私が折りたたんで封筒に詰めて、私が封筒に宛先のシール貼って、私が差出人のシール貼って、私が「料金別納郵便」のシール貼って、私が投函するという、要するに全部私一人でやっているんですけれども・・・。 私が「もうやーめた」って言えば、その瞬間、同窓会報は終刊になるんですけど、卒業生の中で何人かは楽しみにしてくれているんだろうなーという淡い思いもあって、なかなか止めるという決心もつかないという。 まあ、それでも、宛先シールを封筒に貼りながら、昔の卒業生の名前を見ていると、やっぱり懐かしいね。 その一方、OGの中には結婚して姓が変わってしまう人も多いので、「あれ、これ誰だっけ?」という感じになることもある。私の中では、いつまでも旧姓のまま、記憶されているもので。 この会報、今年で26号なんですけど、第1号から関わっている私も、相当のベテランになったということになりますな。 私も定年まであと10年、まあ、私の目の黒い内は、最後まで発行しつづけますか・・・ね。
July 4, 2018
コメント(0)
-
無念! ワールドカップ
昨夜のワールドカップ、キックオフが夜中の3時ということで、さすがの夜型の私も見ずに寝たのですが、気になっていたせいか、何度も試合の夢を見てしまったという。最初の夢では2対1で勝ったことになっていて、次の夢では5対0で大負け。それで自分でも何が何だか分からなくなったところで目が覚め、実際の結果を知りました。 いやあ、惜しかったですな! 一時は2対0で勝っていたというのですから! 素人のタラレバ話になってしまいますが、2対0になった時点で、極端な、反則ギリギリの守備的プレイをしたらどうだったんだろうなどと、ついつい考えてしまいますなあ・・・。やたらにゴールキーパーにボールを戻す的な。自陣でやたらに安全無害なパス回しをする的な。この状況で相手にとって嫌なプレイって何だろう? という観点から、プレイできなかったんだろうか・・・。 まあ、そういうことをしないで正々堂々やるから、日本のサッカーは素晴らしいのでしょうけれどもね。 それにしても、後で結果を聞いた私ですらこれだけ悔しいのだから、実際に戦った選手たちがどれほど悔しい思いをしているか、それを想像するだに、何も言えなくなりますね。 しかも、悔しい負け方をした後の日本代表チームが去った後、ロッカールームが嘘のように整頓されていた、という話を聞くと、日本人として誇らしく、誇らしいがゆえにまた気の毒で、ますます胸がふさがります。 ドイツですら16強に入れなかったことを思えば、またポルトガルやアルゼンチンですら8強に入れなかったことを思えば、圧倒的優勢と思われていたベルギー相手にこれだけ善戦したことはアッパレの一言。サムライ・ブルーの戦士たちには胸を張って日本に帰国してもらいたいと思います。よく頑張りました。お疲れ様!!
July 3, 2018
コメント(0)
-
「眠り」に任せる
自己啓発の世界では、「眠り」の重要性が指摘されることが多くて、何か困ったこと、悩み事を抱えていたりする場合、「眠り」に任せなさい、というようなアドバイスがなされるんですな。寝る前に、「私は今、これこれこういう悩みを抱えていますが、明日の朝までに解決法をお示し下さい」とか呟いて、あとはもう睡眠に任せっきりでグーグー寝てしまう。すると、眠っている間に勝手に脳が働いて、ちゃんと朝までには解決法を探しておいてくれると。 『宝島』の作家、R・L・スティーヴンソンなんてのは、いつもこの手で作品の筋書きを案出していたとか。 で、私も昨夜、この手を試してみたのよ、実は。 このブログにも時々書いていますように、今、私は「女性向け自己啓発本」のことをあれこれ調べておりまして、代表的な作品を読破しているんですけど、今の所、読破しているだけで、論文の構成が全然思いついていなかったんです。 だけど、このままこの調子で読み進んでいったところで、「1960年代にはこういう女性向け自己啓発本が出版されました。1970年代には、こういうのが出ました。1980年代を代表する女性向け自己啓発本はこれこれです。1990年代だと、こんな感じの本がよく読まれました・・・」というのを羅列していくだけで終ってしまう。ま、そういうのを列挙するのだって重要な仕事ではありましょうけれども、それだけではあまり面白い論文とは言えないわけですよ。 つまり、何か一つ「視点」がないとダメなんです。その視点から見れば、すべての女性向け自己啓発本を秩序づけられる、といったような、うまい視点がないと、物語が組み立てられない。いつも言いますが、かっちりとした物語があって初めて、いい論文が書けるんですな。 だけど、昨夜まで、どうもその視点が掴めなかったんです。 そこで。 トライしてみたわけよ、「眠りに任せる」という奴を。 寝る前に、「今、女性向け自己啓発本の全体をうまく位置付けられるような視点が見つからなくて困っています。どうか明日の朝までに、その視点をお示し下さい」と祈って、それで寝ちゃったわけ。あれこれ考えずに。 すると! 今朝の6時30分、その視点がバキっと示されて、ハッと目が覚めた。 もう、完璧。その視点が分かったところで、論文の出だしから最後まで、全部、一瞬で見通せちゃった。事実上、もう論文は完成したようなもんだ。あとは、書くだけ。 じゃあ、どういう視点だったかと言いますと・・・うーん、それは企業秘密だからここでは明かせません。ただね、ヒントを一つだけ言うと、人気のある女性向け自己啓発本には、それを読んだ読者からやたらにファンレターが届くらしい、ということですな。そしてそのファンレターにはこう書いてある:「著者のあなたには、どうして私の気持がこれほどまでに分かるのですか? ひょっとして、私のことをどこかで秘かに見ていたんじゃないですか?」と。 ということは・・・? あー、もう言えね~! まあね、そこから先は、これから私が書く論文を読んでいただくといたしまして、とにかく「眠りに任せる」という自己啓発の方法は、案外、実践的に役立つということが分かりましたね。 もう、アレだ。これからはすべてこの手で行こう。悩まずに、寝よう。下手な考え、休むに似たりってね。
July 2, 2018
コメント(0)
-
ジョン・スタインベック著『知られざる神に』を読む
アメリカのノーベル文学賞受賞作家、ジョン・スタインベックの書いた『知られざる神に』(原題:To A God Unknown, 1933)という小説を読みましたので、心覚えをつけておきましょう。 この小説、書いた順で言うと2番目、出版された順で言うと3番目に当たり、いずれにしてもスタインベックがまだ若い頃に書いた小説ということになりますが、書いた順で言うと3番目、出版された順で言うと2番目の小説『トーティア・フラット』と比べると、小説としての完成度が大分低い気がする。その意味で、『トーティア・フラット』によって自分の声を見い出す前の、助走期の作品と言うことができるのではないでしょうか。 ちなみに、なんでそんな作品を私が読んだかと申しますと、この作品のペーパーバック版(デル社版)の表紙絵が、小説のどの部分を描いたものなのか、知りたかったから。このデル社版の表紙絵って、結構エロいのよ。『To A God Unknown』のデル社版表紙絵 で、この初期の目的は達成いたしました。これは、主人公のジョウゼフ・ウェインが、その妻エリザベスを亡くした日の夜、一人寝ていた時に、兄嫁に当るラーマ(隣の家に住んでいる)がやって来て、いきなり服を脱ぐと「あなたにはこれが必要よ」とか言ってベッドに侵入、夜這いをかけるというすごいシーンを映像化したものだったのでありまーす。この小説の中でエロいシーンってここだけなので、デル社の表紙絵画家は、ここを描くしかない!と思ったのでしょうな。 それはともかくとして、本作全体としてどういう小説かと申しますと、ヴァーモント州で農場を営んでいたウェイン家の三男ジョウゼフは、アメリカ政府のホームステッド法(西部開拓を促進するため、西部の未開拓地を開墾した者に、160エーカー分の土地を無償で与えると定めた法)を利用し、西部に自分自身の土地を持ちたいという熱に取り憑かれるわけ。で、農場をジョウゼフに譲ろうと考えていた老齢の父親が引き止めるのも聞かず、彼は西部に向い、そこに自分の農場を作ると。 で、そこはヴァーモントの農場とは異なって肥沃な土地であり、一見すると農場を作るにはいい土地に見えるわけ。だけど、地元のインディオ達は見向きもしていない様子。というのも、長くこの地に住むインディオは、この土地が時おり激しい干ばつに見舞われるのを知っていたからなんですな。だけど、そんなことを知らない(あるいは、そういう話を聞かされても、耳に入らない)ジョウゼフは、いい土地が手に入ったと大喜び。一本の大きな樫の木の下に家を建て、仲良くなって彼の従者のようになったインディオのファニートの力も借りながら農場経営に精を出す。そして、ヴァーモント州に残った長兄から父の逝去の報を聞くや、彼は長兄・次兄・弟の3人にこっちへ来て一緒にやらないかと話を持ちかけ、結局、160エーカーの4倍、640エーカーの大農場をこの地に築くことになる。 で、この4人兄弟はそれぞれ個性がありまして、長男のトーマスはかなりまともなんですが、次男のバートンはプロテスタントの熱狂的な信者、そして四男のベンジャミンはのんだくれの問題児だけれど、その人格の弱さゆえに兄たちに可愛がられているという感じ。で、この4人の中では最初にこの土地に来たジョウゼフが一番土地への執着が強く、一族のリーダー的存在なんですが、他の連中とは異なり、ちょっと異教的なところがある。例えば、自分の家をその脇に立てたあの大きな樫の木、これを母なる大地に根差す父的存在の象徴として、またより端的に言えば、死んだ父親の魂が宿る場所として、信仰し始めたりする。またその他、農場から少し離れたところにある水の湧き出る場所と、そこに鎮座する岩を一種のサンクチュアリに見立てたりするんですな。 で、そういう異教的な信仰と、それと同根の「豊穣さへの信仰」から、ジョウゼフは嫁を取ることにする。それで、最近、町にやってきた評判の別嬪さんで、学校の先生をしているエリザベスに猛アタックし、彼女を娶るわけ。それで子供も生まれる。だけど、ジョウゼフのエリザベスに対する愛は、個なる人間としての愛というよりは、より大きなもの、すなわち自然の豊穣さへの捧げものとして愛、ってな感じで、そういうこともあり、二人の関係は普通の夫婦の関係ではないようなところもある。 ま、そうこうしている内に、色々な事件が起こります。 まずのんだくれの四男・ベンジャミンがジョウゼフの友人・従者のファニートの家に泥棒に入り、その現場に出くわしたファニートが、それがベンジャミンとも知らずにナイフで刺し殺してしまうという事件が起こる。これはベンジャミンが悪いというのはジョウゼフや他の兄弟たちも分かっているので、ファニートの罪は不問に付されますが、ファニートは責任を感じてしばらくこの土地を離れます。 それから熱狂的なキリスト教信者であるバートンは、家長ジョウゼフの異教的樫の木信仰を快しとせず、この木に斧を打ち込んで枯らしてしまった挙句、この土地から出て行ってしまう。 そしてジョウゼフの妻エリザベスは、ジョウゼフと自分との間にある隔たりを象徴し、自分の存在を脅かしているあの清水の大岩を克服すべく、ジョウゼフと共にそこへ行って、大岩を自らの足で踏みしめ、征服しようとするのですが、その際に足を滑らせて地面に墜ち、頭を強打して死ぬということが起きる。先に述べた「トーマスの妻・ラーマの夜這い」のシーンはこの直後に起こるわけ。 とまあ、ジョウゼフの夢であった、一族の大農場経営の夢は次々に潰えていくのですけれども、トドメを刺すことになったのが、干ばつです。 インディオ達が予知していた通り、やはりこの土地にひどい干ばつが訪れるんです。順調に見えていたジョウゼフたちの農場は、この干ばつによって大打撃を受けることになり、数百頭に増えていた牛もどんどん飢え死にしていく。そこでせめてその一部でも救おうと、まだ草の残っている土地を目指して移動することを計画するのですが、ジョウゼフはまだこの土地を諦めきれず、結局、長兄トーマス一家だけが牛と共に移住することになる。 で、結局、ジョウゼフの夢見た一族の大農場に残ったのは、たった一人、ジョウゼフだけになるわけね。 で、彼は何とかこの土地にまた雨が降り、豊穣さが回復するのを待つのですが、なかなかそう上手くはいかず。それで、カトリックのファニート(彼はジョウゼフが一人で農場を守っているというのを聞きつけ、この地に戻って来ていた)の勧めで、カトリックの司祭にも会うのですが、その司祭が苦しんでいるジョウゼフの魂の救済を申し出たのに対し、ジョウゼフは雨乞いだけを司祭に乞うという具合でコミュニケーションは成立せず。 そして、すべてに絶望したジョウゼフは、あのサンクチュアリの岩の上で、自らの血管を開き、血を大地に注いで自殺する。それは自殺でもあり、雨乞いの儀式でもあったんですな。自分は死ぬけれども、自分が死んだ後に、またこの地が豊穣になればいいと願って。 そして彼の死を待っていたかのように、雨が降り出す、というところでこの小説は幕を閉じます。ちなみに、ジョウゼフの唯一の友であったファニートと妻アリスの間に生まれた男の子は、ジョウゼフと名付けられ、ジョウゼフは死ぬ直前にこの男の子に祝福を与えましたので、おそらく、この土地はまた豊饒さを取り戻し、ファニートの息子のジョウゼフが、ここを継ぐのかも知れません。 つまり、自ら人身御供となったジョウゼフの意志は、一応、引き継がれたわけ。 ま、そんな小説。 私が要約をしたら、すごくいい小説のように見えるでしょ? でも、それは私の要約が上手いからで、実際にはそんなにいい小説じゃありません(爆!)。なんて言うの? こういう精神性のある小説にしたいというスタインベックの意気込みが空回りして、生硬な小説になっちゃっているんですよね。ま、スタインベックって、もともとそういうところがあるけれども、まだ小説家としての腕前が完成する前だから、上手にまとめ切れてないわけよ。 でも、ま、とにかく、なるほどそういう小説なんだ、というのが分かったから、十分収穫あり。これが分からないと書けない原稿を書いているところなのよね~。
July 1, 2018
コメント(0)
全30件 (30件中 1-30件目)
1