2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2009年06月の記事
全37件 (37件中 1-37件目)
1
-
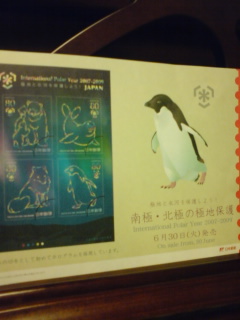
International Polar Year 2007-2009 の切手に感動しました。
450円の定額小為替というものが必要になり、会社の近くの郵便局へ。昨日も郵便局に行ったのですが、30人待ちというあまりの人の多さに、挫折してなにもせずに帰ってきたくらいです。東京のベイエリア、40階建て、50階建てのマンションが急にいくつもできて、おまけに郵便局は駅前のここ1箇所なので、見るからにパンク状態。いつが空いているのかと、局員の人に聴くと、いつ来られても同じ・・・と、投げやりそうな答えが返ってきましたが、無理もないなあと思いました。でも、出直して今日来てよかったと思うことがありました。6月30日発売のすばらしい切手に出会えたからです。27人待ち、待ち時間30分以上でしたが、いろいろ観察もできてよかったです。 http://www.post.japanpost.jp/kitte_hagaki/stamp/tokusyu/2009/h210630_t.html極地と氷河を保護しよう! 南極と北極の極地保護International Polar Year 2007-2009という切手が6月30日発売ということで、ホッキョクグマ、ホッキョクギツネ、ウェッデルアザラシ、アデリーペンギンの4枚1シートのセット。日本の切手として、初めてホログラムを採用しているそうです。衝動買いしました。自分にとってもよく覚えておきたい切手で、デザインのすばらしさに感動しました。(切手デザイナー:星山理佳さん)切手がお好きな方へ。あした郵便局へ行きましょう!!●Polarという文字を見て、ポーラースターというレコードを昔買って、大阪フェスティバルホールへコンサートも行ったなあと、八神純子さんという歌手のことを思い出しました。深夜ラジオ聴きまくりの時代、マイケルジャクソンが有名になりだしたあたりの1980年ごろのこと。ピアノ弾いていませんでしたが、多感な時期がこのころで、よかったかもと思ったりもしています。BGM: ショパン 24の前奏曲 Op.28 ピアノ: ヴラド・ペルルミューテル このあいだヴァンクライバーン国際コンクールで優勝した、 辻井さんの先生の先生の先生が、このピアニストにどうやらなるみたいです。 ショパンでいちばん好きな音を出すピアニストは?といわれたら、 わたしの場合、このピアニストになるように思います。 こういう音が出せるように、1mmでも近づきたいです。 きらきらとお星さまのような音でピアノ弾きたいです。 なかなか店頭にも置いていませんが、このピアニストのCD,お勧めいたします。
June 30, 2009
コメント(1)
-
クールビズと沈没船のはなし。
日経新聞6月29日の朝刊に、クールビズを定着させるのにどうするのかということが書いてあり、沈没しそうな船の船長が、それぞれの人にどういうのかというエピソードをかけて話を展開させていました。朝読んでいて思わず笑ってしまいました。アメリカ人には、「いま飛び込めば、あなたは英雄になれますよ」といい、イギリス人には、「いま飛び込めば、あなたは紳士です」といい、ドイツ人には、「飛び込む規則になっています」といい、イタリア人には、「飛び込めば女性にもてますよ」といい、フランス人には、「飛びこまないでください」といい、日本人には、「皆さん飛び込んでますよ」というのだそうです。国民性を例えるのに本当に面白い例えです。日本人はみんな同じがよく、同質性が高い人が多いと、諸外国の人からも思われているのでしょう。もう少し、ネットで、他の国の人のことを書いているものを探してみました。ロシア人には、「ウォッカの瓶が流されてしまいましたが、今追えば間に合います。」中国人には、「おいしそうな魚が泳いでいます。」北朝鮮の人には、「今が亡命のチャンスです。」韓国人の人には、「日本人が飛び込みました・・・。」大阪の人には、「阪神タイガースが優勝しました・・・・。」とのことです。自分は日本人かもしれませんが、イタリア人に近いような感じがしました。BGM: シューマン アラベスク ハ長調 op.18 ピアノ:マウリツィオ・ポリーニ イタリア人ということで、このピアニストのことを思い出しました。 シューマンのアラベスク、彼が初来日のときにアンコールの最後で弾いた曲だそうです。 それを知って、このピアニストが大好きになりました。センスいいと思います。 6分29秒で、少し早いテンポですが、持っているCDのなかで特に好きなもののひとつ。 ポリーニの演奏はどれもすばらしいですが、 ショパンよりもべートーヴェンよりも、シューマンが私のなかではいちばんしっくりきます。 沈没した船を見たら、何をするのでしょうか。ワールドワイドになりすぎて、 どこの国のひとかもわからなくなってしまっているのかもしれません。
June 30, 2009
コメント(0)
-
グリコのおまけ
大阪ミナミ、戎橋の風景。 ここは、ひっかけ橋という別名もありますが、そういうのにまるで参加できませんでした。 グリコの看板みると、でも元気でますね。 また今週もピアノの練習していないです。 プレリュードは長丁場。がんばります。
June 29, 2009
コメント(0)
-
白糸
和菓子屋さんで葛切りいただきました。 大阪市中央区高麗橋というお店の本店の住所にも惹かれました。 このあたりのビルというビルはみんな上から下まで歩き回ったなあと。 今となっては笑えるような営業活動していたときのおはなし。 甘くない思い出なのだと甘いものをいただきながら感じました。
June 28, 2009
コメント(0)
-

大正浪漫
大正7年にできた大阪中央公会堂。 久しぶりになかに入りました。 ビートルズシネクラブの映画の催し、高校生のころ、よく行きました。 大正浪漫定食、中之島の川沿いで。のどかなランチをいただきました。
June 28, 2009
コメント(2)
-
お好み焼き at 道頓堀
久々になんばから戎橋筋の商店街。 道頓堀へ来てお好み焼き食べています。 道頓堀焼きというメニュー堪能中。 お店のお箸に 「天才と凡人の差はごくわずか、継続の有無。」 とありました。 よく心得ます。
June 27, 2009
コメント(0)
-
のぞみ55号
今日は新幹線空いています。 ゆったり旅しています。 さっき名古屋を出ました。 昼間、みんなでピアノ弾いていました。 ツェルニー30番弾いているときとヘンデルの調子のよい鍛冶屋弾いているときと顔色がぜんぜんちがうと言われました。 音だけでなくさまざまな様子をチェックされているのがよくわかりました。 夕飯は久々に駅弁。 幕の内が多いのですが牛すき重というのにしました。 素朴な絵にも惹かれました。 美味しかったです。
June 27, 2009
コメント(4)
-

数寄屋橋にて
銀座4丁目から、数寄屋橋の方向へ歩いていきました。アルマーニとかグッチとか、そういうテナントのビルがにぎやかだなあとおもっていたら、こういう時計台がありました。太陽の塔のミニ版のようで、仮面ライダーがショッカーのたたかったあとたたかう相手のようで、みていておかしくなりました。数寄屋橋は、昔本当に、数寄屋橋という橋があったことは、ずいぶん後になって知りました。東京オリンピックの手前、首都高速道路を造るために外堀通りの堀を埋め、私が見る景色はもっとあとのこと。昭和56年に日劇がなくなり、その後マリオンになってからが、私の知っている姿。マリオンには阪急百貨店があるので、関西人の私にとっては、文字をみるだけで癒される場所だったりしました。東京で一人暮らしをはじめたころ、ここに時々いってスーツを買ったりもする場所でした。デパートの顧客を集めるための言葉として、シャワー効果と噴水効果というのがあるのですが、見事に生かされているように感じる場所でもありました。シャワー効果とは、階の上のほうに目玉になる催しもの会場を置いて、それが終わった後、お客様が降りて来て買い物をしていただくといった意味。このビルには多数の映画館が上の階にあります。噴水効果とは、デパ地下など食料品売り場を充実させて、そこからお客様が上がってくるという、お客様の導線を考えてのもの。スーツ屋さんの店長さんとあーでもないこーでもないといいながら、2時間くらい遊んでいたこともありました。●阪急という文字をみていると、阪急電車に乗りたくなりました。これは去年の夏休みに実家に帰ったとき、阪急梅田駅での写真。チョコレート色、電車の中は木目調、グリーンのシート。吊革広告は月刊誌のみなので、なんだか落ち着きます。小林一三さんという阪急の創業者、私は尊敬しています。タカラヅカを作ったのも、沿線開発をするために線路をひいたのも、映画を日本で定着させたのも(東宝のこと)、この人がされたこと。カレーライスのとなりに福神漬を置いて、デパートの食堂で大ヒットさせたのもこの方のアイデア。実家に帰る用事があるので、あさってこの電車乗るのが楽しみです。●たそがれ清兵衛の映画、テレビでやっています。真田広之さんが出ていますが、かつて「里見八犬伝」という映画のキャンペーンのアルバイトで朝早く、阪神競馬場へ行ったとき、阪急電車に乗り仁川という駅で降りていきました。「朝早くからわれわれの映画のために来てくださってありがとうございます。」と映画に出る人の馬の世話係で出かけたのですが、真田さんが私に、深く頭を下げられたこと、いまだに覚えています。仕事をする以前にひとりの人間としてすごいと思いました。なんだか、そんなことも思い出してしまいました。
June 26, 2009
コメント(200)
-
花から花へ240000アクセス超えました。
いつもお世話になります。家に帰ってきて240000アクセスを少し超えていたのでうれしかったです。みなさまありがとうございます。さっき、メールの整理をしていて、過去のログをみていたら、今年の初めのスタートが、203555ということでした。一日200前後のアクセスがあるということ自体、はじめたころからみれば奇跡に近いですし、うれしいです。この半年いろんなことがありましたが、いろいろなかたに支えられているというのを特に実感いたしました。1週間があっという間というのも、いいようにとらえよかと思っています。メンデルスゾーンイヤーということで、たくさんメンデルスゾーンの音楽にふれていることもあります。メンデルスゾーン音楽祭2009 も何とかいける見込みがつきましたし、行きたいコンサートのチケットもとれるようで、ほっとしています。4月のおわりに小澤征爾さんと指揮で、メンデルスゾーンの音楽を聴けてよかったです。結婚行進曲とか、身近にオーケストラで聴けるのは今年ならではですし。この曲がもっと身近な音楽だったらいいのになあとおもったりもしています。●それにしても、ブログの文化はおもしろいなあと思います。いろいろため込んできたのもありますが、過去に何をしたのかとか、どこに行ったのかとかメモがわりにしたりすることもありますし、思い出すのにも使ったりもしています。写真も以前よりたくさん撮るようになりましたし、ネットでお話したつづきを、日常会話でしたり、その逆もあったり。まったく不思議です。IT会社にいる手前、使い勝手のいいものは、それなりに自分で評価てきるようになりたいと思うこともあるのですが、いろいろなことに気付かせてもらってよかったと思っています。10年にぶりにお酒を飲んだ人との会話のなかで、娘が私と同じ大学に入ったとか、思わぬ会話になったのもうれしかったです。千本通りとか、平野神社とか、わかるひとにはわかる京都の地名がそのなかでぽんぽんと出てきたのもおもしろかったです。BGM: ブラームス 大学祝典序曲 OP.90 クラウディオ・アバド指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
June 25, 2009
コメント(2)
-

トマトたんめんPART11
すこし夜遅くに、西新宿の白龍館へ。1月にうかがったので5か月ぶり。ヴァイオリンとピアノのライブを聴きながら・・・BGM: フランク ヴァイオリンソナタ、ブラームス ヴァイオリンソナタ2番・・・ (かなり、高いパフォーマンスでした)おしゃべりは、ピアノに戯れるのに得意な方と、たのしく団らん。ひさびさのトマトたんめん、肉団子定食、その他名前がわからないけど、とてもスペシャルなもの。学生時代にお勉強した内容のおはなしをここでするとは思いませんでしたが、楽しかったです。えんぴつを旅先で買ったり、おみやげでいただくのがうれしいので、このキーワードのおはなしは楽しかったです。閉店まぎわ、べーゼンドルファーのピアノでれんしゅうをさせていただきました。いろいろな人のご縁をつなぐ魔法のお店。私にとってはそう思えてなりません。はじめてお世話になった3年4か月前から、この魔法のお店の出会いはいろいろとはじまっています。ひさびさにそのときの日記を見てみました。(2006年2月6日)http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200602060000/ トマトたんめんは、現在PART11くらいだとおもっています。まだまだ続くと思います。
June 24, 2009
コメント(0)
-
ウインブルドンのテニスを観ながら、無言歌を聴く。
最近、少し疲れて家へ帰ってきて、横になることが少しあるのですが、早寝早起きをしすぎる感じになることが時々あります。夜9時にまともに寝てしまうと、5時間後の深夜2時に目覚めてしまいます。ウインブルドンのテニスの試合をちょうどやっていて、クルム伊達公子さんが13年ぶりに試合に出ています。この試合を見なさいという神のお告げだったのだろうと感じています。95年~96年にかけて、テニスで頂点を極めた時期は、よくテレビで見て応援していました。海外に駐在していた自分はワールドワイドに活躍する姿にたいへんあこがれ、一人でテレビを見ていて声を出して応援するような人は、この人くらいだったかもしれません。いろんな意味で、たいへん励まされました。●ぜんぜん話はかわりまして、ピアニストのお話で若くして日本のコンクールに優勝をして海外留学した人の話の回顧録やエッセイを読むことがこれまで、たびたびありました。高校のときにすでに日本音楽コンクールで頂点を極めた中村紘子さんと田部京子さんのこと。そのあと留学してからのことについてです。中村さんはジュリアードに留学するのですが、奏法そのものを否定され、ゼロから弾き方を見直したということを延々と書かれた雑誌の特集号を読んだこともあります。田部さんについては、日本音楽コンクールで優勝したときの演奏を聴いた方の話も聴いたことありますが、当時はノーミスで機械のようにピアノを弾くだったとかうかがったことあります。ベルリンに留学したあと、ゼロベースでピアノを弾くことを余儀なくされ、メンデルスゾーンの無言歌集しか弾かせてもらえなかったというお話を間接的に伺ったこともあります。のちの田部さんのデビューCDとなり、いまでもあたりまえのように、CDショップの店頭に置かれているものだったりします。熱心におしえてくださる日本のピアノの先生は、世界で見れば方向がかみあっているのでしょうか。なんでそういう風になるのでしょうか。いろいろと素朴に感じることは多いです。先人のピアニストのかたがたは、ものすごく遠回りをしているのではなかろうかと。日本のお稽古事市場について、私の子供時代、ピアノ以外であれば、そろばん、お習字、剣道・・・などの教室へ行っている人多かったです。そろばんもお習字も剣道も、3級、2級、1級、初段・・・・と、グレードがあり、それらをモチベーションにして頑張っている人も多くいました。ピアノも、グレードのようなものを音楽教室でつけているものもいますが、楽譜の裏にかいてある体系だてたものにしたがってやっていた風な感じがします。ほかのジャンルと同じように。なにかそうすることによって、見失ってしまったものはないのだろうかと、思ったりもしています。●テニスの試合は、終わってしまい、伊達公子さんは、途中に足の故障もあったのでしょうか、途中まではよかったのですが結局負けてしまいました。選手として、解説者として、どちらもプロフェッショナルな感じがしますが、インタビューを着て、自分自身のテニスの道を進まれていることをますます感じました。BGM: メンデルスゾーン 無言歌集より 五月のそよ風 op.62-1 チェロ:ミッシャ・マイスキー ピアノ:ダニエル・ティエンポ メロディをチェロで、内声部、ベースをピアノで演奏。 この曲、7年前、東京にもどってきたとき、熊谷の太陽のホールというところで聴きました。 この2人の演奏で聴きました。アンコールがこれだったので大変印象に残っています。 なにかのめぐりあわせか、この曲のピアノの練習することになりました。 1台のピアノで表現するのはむずかしいです。 チェロで歌うように弾いているのを聴いていてあこがれます。
June 23, 2009
コメント(0)
-
電車のなかでのひとりごと・・・
ピアノの練習をしていない。練習をしていない。レッスン前なのにほとんど弾いていない・・・とおもいながら、地下鉄に乗っていた時、♪みーどれふぁそどれそふぁどふぁれそどふぁそれ どそれふぁどそふぁどれどふぁそれどそふぁ れそどふぁれそふぁどれそふぁどれどそふぁ ふぁどれそふぁどそれふぁれどそふぁれそど ふぁそどれふぁそれどそどれふぁそどふぁれ それどふぁそれふぁどそふぁどれそふぁれど。 と、かいてみれば、ドラクエのふっかつのじゅもん・・・のようなことを、もごもごといっている自分に気付きました。???な人と思われているだろうなあと。気が先走ってはいけない・・・とおもうものの、指が動く前に口が動いてしまいました。わたしにとってたいせつな練習曲のひとつ。演劇部の人があいうえおを、あえいお・・・といろんないいかたをするのと同じように、こんなことばかりやってきているのですが、いい勉強をさせてもらっている感じです。
June 22, 2009
コメント(0)
-
メンデルスゾーンの生誕200年ガラコンサート BS2で見ています。
http://www.nhk.or.jp/bsclassic/crs/index.htmlライプツィヒのゲバントハウスの前は旅行したときは通っただけ。だから、ホールのなかの風景を見れて、それだけでもうれしいです。ガラ・コンサートの内容、ピアノ協奏曲第1番 ピアノ:ランラン Op.25交響曲第3番「スコットランド」 Op.56 リッカルド・シャイー指揮 ライプツィヒ・ゲバントハウス管弦楽団ヴァイオリン協奏曲でなくピアノ協奏曲、イタリアでなくスコットランド。日本人の一般常識がことごとく覆されること、最近よくあります。交響曲イタリアのほうが有名ですが、メンデルスゾーン自身、正式に作品として認めていないこと、書物で調べていて、わかりました。作品90というものは、没後に後世の人が作品番号をつけたもの。スコットランドは作品の構成をスケッチして、出版にこぎつけるまで、14年かかっているとか。ブラームスと結局はいい勝負のようなほど、練りに練っていること、立教大学の星野洵教授のメンデルスゾーンの論文にもありました。この作曲家は、お金持ちのお坊ちゃまだったことはありますが、それだけが独り歩きし、軽い曲ばかりだとか、速書きだとか、うわべだけでとらえて論評されていることがあまりにも多く、事実をきちんと整理して頭のなかにいれたい、そうおもって作品に取り組んで、趣味でやっていても、ピアノ弾きたい、そうおもうことが多いです。このスコットラド交響曲、2楽章のピクニックにいくような気分の雰囲気のところ、大好きです。シューマンが絶賛していたと、いわれている場所。それから4楽章のおわりのほうのコーダ、これは前にも書きましたが、自分が元気をだしたいときに、いつも聴いています。●ライプツィヒに旅するのは、ちょうど2ヶ月後のあたり。9年前に行ったときより、知識も増えているし、音楽もいっぱい聴いているし、街がどんな風になっているか、見てみたいです。ベルリンの壁がなくなって、ちょうど20年、壁はあたりまえだと、社会科の地理の教科書にもかいてあったことが、全部ひっくりかえってしまったあの時代を振り返ることも旧東ドイツ側にいると感じることができるのでしょうか。これから先、少し楽しみになってきました・・・。
June 21, 2009
コメント(0)
-

くだもの屋さんの上でピアノを弾く。
京王線、下高井戸の駅前。庶民的な商店街がつづきます。この果物屋さんは、駅の改札から素直に歩くとたどり着きます。このビルの3Fにスタインウェイのピアノがある、中華料理屋さんがあります。いつもいただく中国茶も料理もとてもおいしいのですが、たのしくピアノを弾く場所でもあったりします。半年ぶりに伺いました。ひとり30分枠で弾く人もいるので、長丁場になるのですが、料理や飲み物には困らず、それなりに楽しんで聴かせていただきました。今回は弾く順番がいちばん最後になり、少し待ちくたびれましたが、そういう中でも、熱心に聴いてくださる方も多く、貴重な場となりました。聴いた曲:チャイコフスキー 子供のアルバムー24のやさしい商品 朝の祈りop.29-1、、教会でop.29-23/モーツァルト ピアノソナタ第15番 K545/ショパン バラード3番op.47/ラフマニノフ 音の絵Op.39-5/バッハ フランス組曲第6番 アルマンド/アルベニス イベリア第1巻 1.エヴォカシオン、2.港 :スペイン組曲第1集 セビーリャ/レクオーナ スペイン組曲「アンダルシア」より2.コルトバ、6.マラゲーニャ/ショパン 幻想即興曲、英雄ポロネーズ/ヨーゼフ・シュトラウス ワルツ「天体の音楽」/ワルトトイフェル エスパーニャ/ラフマニノフ 練習曲「音の絵」op.33-2、op.39-1/メンデルスゾーン ベニスの舟歌No.1 op.19-6 /シューマン ウィーンの謝肉祭の道化 よりフィナーレOp.26-5/バッハ パルティータ第4番 1.ウーヴェルテュール、2.アルマンド/ベートーヴェン ピアノソナタ第29番ハンマークラヴィーアより第3楽章/グラナドス スペイン舞曲集オリエンタル op.37-2/アルベニス イベリア第3巻 エル・アル・バイシン弾いた曲:ヘンデル 組曲HWV430より「調子のよい鍛冶屋」、メンデルスゾーン無言歌集より 五月のそよ風op.62-1、眠れぬままにop.19-5、瞑想op.30-1はちゃめちゃになった箇所もいくつかありましたが、料理が出たり、気分てきにいい感じだたので、貴重なひとときとなりました。ぜんぜん面識のないかたに、いいように感想いっていただけてよかったです。音色のことでいいようにいっていただいてうれしかったです。出演者の中で、アマチュアピアノコンクール本選出場者がいるので、7月下旬に紀尾井ホールで開かれる予定プログラムをみせていただきました。社会人で仕事をしているなか、ずっとピアノつづけている愛好者のお手本のような演奏される方も多く、見ているだけで励みになりました。長丁場でピアノを聴くにも集中力いりますし、聴き手が楽しめるようなプログラミングもこういう場には必要かと。そういう意味で、ヘンデルの変奏曲はよかったです。この曲、練習曲としても向いているかも、弾いていて楽しいですし。ヘンデル没後250年、メンデルスゾーン生誕200年ですが、アルベニスも没後100年なのだそうです。ほかの出演者に教えていただきました。スペインものの思い入れあふれる演奏、印象に残りました。来週末も似たようなプログラムで演奏することになりますが、途中でどこを弾いているかわからないということにならないよう、充分気をつけたいと思っています。この下高井戸の会は、ビルの建て替えのために8月が最後になるとのこと。とても残念ですが、新天地に向かって、前向きにいろいろ考えておられることを、陰ながら応援させていただきたいです。
June 21, 2009
コメント(3)
-

航空公園のそばでツィメルマンのリサイタル
一昨日は日本の鉄道の発祥の地へ行きましたが、今日は航空公園という日本の航空機の発祥の地へ。1911年、4月1日に日本初の航空機専用飛行場が埼玉県所沢に完成したのがはじまりだとか。たまたま行きたかったコンサートの最寄駅が航空公園だったわけですが、不思議なご縁というものも感じました。●クリスチャン・ツィメルマン ピアノリサイタル 2009 所沢市民文化センター ミューズ アークホールhttp://www.muse-tokorozawa.or.jp/<プログラム>バッハ パルティータ第2番 ハ短調 BMV826ベートーヴェン ピアノ・ソナタ第32番 ハ短調 作品111**ブラームス 4つの小品 作品119シマノフスキー ポーランドの民謡の主題による変奏曲作品 10●人から譲っていただいたコンサートのチケットは、3階の左サイドの席。ピアノを弾いているところを後ろから見下ろす感じ。左手も右手も弾いているところが見え、姿勢のよさと重厚な曲で和音をつかむ大きな手が見えるというB席であっても特等席のような場所でした。どの曲がどうこうというより、どの曲もすばらしく、音楽の響きを堪能した時間となりました。万雷の拍手というものを長く聴いて、そのなかにいて幸せでした。天にまで響いたやわらかいあたたかい音を、たくさん聴けました。当初、プログラムは3大Bとなっていて、曲目未定。でも、じっくり練ってこれしかないという感じでの高い境地でのパフォーマンス、日本での最後となるこの日のリサイタルは、ツィメルマンをいままでいろんなところで聴いたなかでも一番感動したものとなりました。ツィメルマンの日本公演2009は、5月9日の岐阜県サラマンカホールではじまり、岐阜>西宮>浜松>福岡>武蔵野>座間>東京>さいたま>長野>京都>壬生>東京>仙台>盛岡>福島>横浜>所沢と17公演。福島と横浜のあいだが中4日ありおわりの2公演は少しゆったりとしたスケジュール。日本をたくさん、マイピアノとともに、行脚して、たくさん五月雨も梅雨空もそのなかのさわやかな日も過ごしてきたなかでの演奏だったのかもしれません。特に、ベートーヴェン、ブラームスの後期作品、それぞれの作曲家の人生最後に書いたピアノ曲は、旅してきたものもプラスアルファされたのでしょうか。自分自身も土曜日であり休養十分ななか、リラックスして聴けたからでしょうか。このコンサートの場にいれたことに、たいへん幸せなものを感じています。●ブラームスの作品119の4つの小品。間奏曲が3つと最後にラプソディがある曲は4楽章あるソナタのようにも聴こえましたが、ますます興味を持ちました。クララ・シューマンが第1曲目を「灰色の真珠」とたとえ、第2曲は焦燥感のあるなか中間部のワルツでは感動的なやわらかい日差しが差したかのような音楽、第3曲はブラームスにしてはユーモアのあるスケルツォ。第4曲は明るい和音はファンファーレのようですが、途中で込み入った短調になりバラードのようになり劇的におわりますが、こういう風にとらえて弾いてみることがいつかできたら・・・なんてことを考えてしまいました。最近コンサートホールでは、思わぬところで声をかけていただいたりするのですが、そういうこともとてもうれしいできごとのひとつになったりします。いつか4つの小品を弾くことがあったら、この日のことを思い出しながら、真珠が灰色になっているのかどうか教えていただくことにします。●ツィメルマンのリサイタルは4年つづけて聴いております。過去ブログ、アーカイブです。 ご参考まで・・・。http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200807120001/http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200711190000/http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200606100000/
June 20, 2009
コメント(8)
-
♪それどそどしの曲を弾くために
先日、日曜日深夜だったとおもうのですが、小澤征爾さんが子供だったころの特集番組を見ていました。ラグビーをやりながら、ピアノの練習。リヤカーでピアノを自宅に運んでくる風景、小澤さんのお兄さんがピアノを習ったらいいとすすめられたこと、番組の情景が目に浮かびます。そんななかで、ピアノを練習している姿を映しだされたなかでのBGM,ツェルニー30番は3番バッハインベンションは8番、モーツァルトのソナタはK331の1楽章・・・たぶん、そのまんまだったのだろうなあと思いました。代表的な曲なのだろうなあとも思いました。子供のころのレッスンでたいてい通る道というのもありますが。ツェルニー30番の3番は、聴いていてちょっとうれしかったです。●♪それどそどし という曲ではじまるのですが、ツェルニーがそれほど好きでないわたくしですが、この曲は、タイムスリップしそうで、好きだったりします。ハンドルネームのひとつとして、使うこともあるのですが、このあいだ、いまロンドンにいるピアニストのところに書きこみにいったところ、♪それどそどしそれどそどしそれどそどしそれどそしどみーと返して下さいました。カプースチンを弾けば名人で、コンクールでも優勝したことのある方なのですが、ちょっとうれしかったです。あそんでもらえてうれしかったです。●弾こうとおもったのですが、でも、この楽譜、いま家にありません。うるおぼえで、もう30年も弾いていません。楽譜も見てません。実家に電話をしていたら、昭和49年か50年か、そのころに買ってもらった楽譜があるとのことなので、送ってもらうことにしました。あんぷ とか そういう昔習った先生の筆跡をみるのは楽しみ。毎年年賀状おくっているのですが、22年ぶりにピアノ再開しましたとお便りしたとき、かつてどれほど喜んでもらえたか、そのときのことは忘れもしません。最後に出たピアノの発表会は、メンデルスゾーン無言歌集からでした。昭和49年か50年の頃のこと、日本の国の総理大臣は、田中角栄から三木武夫へ、かわったころ。中東戦争のおかげで、石油の価格が4倍になり、日本中パニックになったころ。いまの不況もこの時代と比べられること多いです。トイレットペーパーがない、砂糖がないと、石油はなくなると大騒ぎになったのも覚えています。砂糖は家族総出で並んで買いにいったこともあります。そんな時代にピアノのレッスンはよく通えたものだと、いまさらながらに思います。1週間だけでも、♪それどそどしの曲、れんしゅうします。ほかのひとは、ツェルニー40番とか50番とか、わたしなんかより、はるかにはるかに難しい曲を弾かれるので、たぶんみんなから笑われるかもしれません。でも、この曲しか弾けないのでそれでもいいです。 ツェルニー30番の3番とヘンデルの調子のよい鍛冶屋と、メンデルスゾーンの無言歌2曲弾きます。 ちょっと楽しみになってきました。
June 19, 2009
コメント(2)
-

ここが鉄道の出発点
旧新橋停車場の前です。 http://www.ejrcf.or.jp/shinbashi/shinbashi.html http://blog.adnet.jp/shiseki/index.php?ID=53いまの新橋駅から、歩いて数分、汐留シティセンターのとなりにある、日本鉄道の出発点、0哩標識。明治5年10月14日に開業した鉄道ターミナルの場所。汐留シオサイトは、貨物駅の跡地の再開発の場所でもありますが、歴史的な場所をもとどおりに復元した姿に感動しました。東京という街は関東大震災や空襲で、もとの形になかなかならないものも多いのですが、残そうという意思の強さにも心をうたれました。汐留駅というのが、昭和61年まで貨物の駅として114年間存在していて、その跡地の再開発で、平成8年に旧新橋停車場として史跡として国の指定を受け、平成15年(2003年)駅舎も再現されることになったそうです。東京藝術大学の旧奏楽堂も、たいへんな尽力により、ほぼ元通りに戻されていますが、そういうものがいくつかあって、素直にうれしいと思っています。 いろんな人の出会いの場である駅。旅先で見かけたところも含めて、つい物思いにふけってしまったりします。5月に行った横浜の桜木町の駅と、ここが結ばれたのが出発点なのだと、あらためて思いだしたりもしています。●明治5年12月3日は、明治6年1月1日になったそうです。旧新橋停車場のできた日付も旧暦と新暦とどちらも書かれていて、これもまた勉強になりました。1年365日なかった年もあったのかと、うるう年より激しく動いた年なのだと。明治5年太政官布告第337号という法律制定で太陰暦から太陽暦になったそうです。明治5年=1872年年末が急にお正月になるような年、非常に興味持ちました。BGM: ブラームス 交響曲第1番 ハ短調 Op.68 クラウディオ・アバド指揮 ベルリンフィルハーモニー管弦楽団 ブラ1は、1876年に発表された曲。 まだ明治5年(1872年)には、ベートーヴェンの第9のあとに出す交響曲として、 ブラームスは悩んでいた時期なのでしょうか。 こんな時代背景を知るのもおもしろいです。 日経新聞の夕刊最終面にクラウディオアバドとベルリンフィルのことを批判的な記事がありましたが、私はこの指揮者がいてこそ、いまのベルリンフィルがあると思っています。ブラ1、ベルリンフィル、アバド指揮の演奏は、90年代前半、大阪のザ・シンフォニーホールで確か聴いています。現在、ルツェルンのオーケストラで活躍されている今のクラウディオ・アバドは好きな指揮者のひとりです。時代を行ったり来たり、駅がきっかけで、いろいろ感じたりしています。
June 18, 2009
コメント(0)
-

バラが咲いた
♪バラが咲いたマイク真木のドーナツ盤のレコードがありました。アポロ11号のころ。メキシコオリンピックでサッカーが銅メダルだったころ。記憶に残っている、そのころ家にあったドーナツ盤ブルーライトヨコハマ、小指のおもいで帰ってきたよっぱらい・・・うちの両親はくわしいことは知らないですが音楽好きだったのは、まちがいありません。なぜかクラシックのドーナツ盤もありました。A面 トルコ行進曲 B面 小犬のワルツA面 ドナウ川のさざなみ B面 スケーターズワルツこの2つは、なんだかはっきり覚えています。あきっぽいのに、おもちゃのピアノばかりで、あそんでいて、オルガン教室に通ったのは4歳のころ。NHKのみんなのうた、 よく見ていました。ビートルズの オブラディオブラダ がちょうどはやっていました。平和な時代かと・・・おもっていましたが、あとで知りましたが、学園紛争で、安田講堂がたいへんなことになっていた絵を、何年もたってから知りました。総理大臣は、ずっと佐藤栄作だったので、ずっと変わらないものだと勘違いしていました。阪神電車の沿線にいました。甲子園球場によく連れて行ってもらいました。たまたま行った試合は、高校野球の決勝戦で、東尾というピッチャーが投げていたこと、そうとう後になって知りました。何年前のことかと、あらためて今のカレンダーを見れば、40年も前のことと、下ひとけたの9という文字を見て、気がつきました。電話もありませんでした。家の裏のおばさんが電話がかかってきたら呼びにきてくれました。テレビは白黒でした。 3万円5万円7万円うんめいのわかれみち・・・こんな番組よく見ていました。 タイガーマスク、あしたのジョー、巨人の星、ウルトラセブン、アタックNo.1、ひみつのあっこちゃん、あとで再放送でたくさん見た番組が現役でやっていたころ。お風呂はあったけど狭かったので、お風呂屋さんによく行っていました。おとな36円、こども18円、なぜたか覚えています。お豆腐やさん、魚屋さん、ロバのパン屋さん、かみしばいのおじさん、行商の人がたくさん、そういえばいました。なにかのときに、このあたりを歩いてみたくなりました。いまはどうなっているのだろうかと。肌色とブルーのツートンカラーの阪神電車、大阪に戻ったら、乗ってみたくなりました。
June 17, 2009
コメント(0)
-

雨の日に買ったCD
雨の日、銀座4丁目、紫陽花。強く降ったり、弱く降ったり、ときどき雷がなったり、そんな1日でした。夜に仕事の打ち合わせの合間、ちょっとCDショップにも寄ってみました。オリコン8位と、うわさに聴くCDが店頭にたくさん並んでいました。いま話題の辻井信行さんのCD。ヴァン・クライバーンコンクール優勝といういうことで、1Fのお店の前でも販売されていました。ソロのCDは、2007年録音、岐阜県のサラマンカホールというところでの録音のCD,西岐阜駅からほとんどバスもなく、タクシーで1500円くらいかかって、ものすごい広い駐車場のある国道沿いのところ。東京では考えられないようなところ。ここのホールのとなりに県の庁舎もあり、コンサートホールもあり、仕事をしにいったことも、ピリスとか諏訪内さんの演奏聴きに行ったこともあるところだとおもいながら・・・やっぱり聞いてみたくなって、家に持って帰りました。BGM: ショパン 子守歌、スケルツォ2番、英雄ポロネーズ リスト 愛の夢3番 メフィストワルツ第1番 ハンガリー狂詩曲第2番 ラヴェル 亡き王女のためのパヴァーヌ 水の戯れ ピアノ: 辻井信行 テレビで数分の音しか実は聴いたことありませんでした。 2005年ブレハッチが優勝したときのショパンコンクールのときも、 テレビでしか少し音を聴いただけでした。 このCD,なんて音が明るいのでしょう。きらきらしているのでしょう。 なんて楽しそうに弾いているのでしょう。すべてにおいて輝いていると思いました。 ずっとむかし、ペルルミューテルというピアニストのCD,聴いて、 あっけにとられたことあったのですが、そのときの音になんだか似ているなあと。 と思ったところで、このピアニストの師匠は誰、その師匠はまた誰・・・と たどっていてくことをさっきネットで見ていました。 このあいだから、テレビでもよくでてきている辻井さんの先生は横山幸雄氏、 横山幸雄氏の先生はジャック・ルヴィエ。そこまでは知っていました。 ジャック・ルヴィエの先生は、ぺルル・ミューテル。 ぺルル・ミューテルの先生は、モシュコフスキー、コルトー。 フランス人の弾くショパン弾きにたどりつきました。 王道を行くピアニストになってほしいと、素直に思います。 2枚組のCDなのですが,もうひとつは自作自演。 ロックフェラーの天使の羽、川のささやき、花水木の咲く頃、 セーヌ川のロンド、高尾山の風 という5曲。 セーヌ川はすぐにはいけないけど、高尾山は、中央線に乗ればいけるので、 こんど風の音でも聴きに行こうかと、タイトルを見て、そう思いました。 ピアノコンチェルトは夜も更けてきたので、また明日聴くことにします。
June 17, 2009
コメント(0)
-

カンタービレで弾きたい!
清楚なバラの花を見ながら・・・カンタービレでピアノの曲が弾きたくなりました。雨上がりの6月の夜、そういうときにぴったりな曲を練習しはじめました。楽譜には作曲者が指示したCantabileの文字が。来年の3月末のピアノの発表会、せっかくのショパンイヤー。自分なりに丁寧に練習して、聴いてもらえるようにしようと、心の底からそう思う曲が弾けるとうれしいです。BGM: ショパン プレリュード Op.28-21 B-Dur Cantabile ピアノ: 小菅優このあとの戦いに行くような曲もあるけど、楽しい時間を過ごせるようにしたいものです。半年以上かけるのは、何年か前のシューマンOp.9の後半以来。10年続けたし、すこしは上積みがあると自分でも納得してみたいです。
June 16, 2009
コメント(2)
-
市ヶ谷でのミニコンサート
3日続きで、お誘いを受けたコンサートに行くことになりました。今日は、ルーテル市ヶ谷センターというところで、それぞれのステージのすばらしいコンサートでした。わたしのミニコンサートNO.132 <演奏を聴いたプログラム>ヴィブラフォンでの演奏D.グリードマン ルッキング・バック藤本隆文 まりと殿様メゾソプラノでの歌シューベルト 笑いと涙シューマン 「ミルテの花 Op.25」 より 献呈モーツァルト フィガロの結婚 より 恋とはどんなものかしら コシ・ファン・トゥッテ より 恋はくせものフルートとピアノの演奏ヒンデミット フルートとピアノのためのソナタ フルートとピアノの演奏尾高尚忠 フルート協奏曲 Op.30ソプラノの歌声ロッシーニ 非難 踊りチレア アドリアーナ・ルクヴルールより 私は卑しいしもべフルートの演奏ドビュッシー シリンクスクーラウ 序奏とロンド Op.98ピアノ ソロ演奏ラフマニノフ 楽興の時 Op.16より No.3 ロ短調 No.4 ホ短調ヴィブラフォンは、エレクトーンでボタンを押したらヴィブラフォンになったことはあるけど、生演奏はほとんど聴いた記憶はなく新鮮でした。日本民謡を交えたすばらしい選曲、シューマンの献呈もシューマン=リストのピアノでは何度かありますが、歌声の世界では新鮮でした。ロッシーニもウイリアムテルだけでないということを知りました。すばらしかったです。フルートは、はじめて聴く曲ばかりでしたが、旋律のすばらしい曲が多く、惹きこまれてしまいました。ラフマニノフのピアノ、2か月つづけて、聴かせていただきました。No.3はしっとりと、No.4は今日の雨音のように、激しく切ない音のかずかず、たいへん素敵な演奏を堪能しました。終わった後の外堀通り、市ヶ谷付近を少し歩きました。雨上がりの神田川、市ヶ谷見附があったあたり、新宿区と千代田区の境目。夜の都心は、ラフマニノフの音とともに過ごしました。また「トマトたんめん」もいただきたくなりました。いろんなご縁でいろんな方とお会いできるようになったことにも感謝です!
June 15, 2009
コメント(0)
-

都電荒川線、三ノ輪橋駅の風景と、よその国の路面電車。
http://www.kotsu.metro.tokyo.jp/toden/stations/index.html都電荒川線、早稲田の駅が始発駅。面影橋>学習院下>鬼子母神前と走ります。上記の写真は、この駅で、雑司ヶ谷音楽堂の帰りに乗りました。三ノ輪橋までの乗車している時間は40分ほど、1回160円の電車の旅、たまにはのんびりとよかったです。途中、山手線、地下鉄、舎人ライナー、いろいろな乗換駅もあり、廃れているどころか、満員電車で大盛況であることもわかりました。駅の花壇には紫陽花ほかたくさん見かけました。三ノ輪橋駅の風景 終着駅は、大きなターミナルでもなんでもなく、下町のここまでしか線路はありません・・・といった感じでした。三ノ輪橋は、地下鉄日比谷線の駅も近くにあります。上野から2駅北へいったあたりです。駅には、関東の駅百選というのがあり、それに選ばれているという説明がありました。駅で写真撮ろうと思ったくらいですので、そういうのも分かるような気もします。http://makkou-hyakusen.hp.infoseek.co.jp/ ●この前、40分くらい路面電車に乗ったことはいつかと考えてみたところ・・・ウィーンの路面電車を思い出しました。これも40分くらい乗りました。Dという電車は、国立歌劇場の前から出ていて、ベートーヴェンの散歩道というところが終点。これも、これ以上線路はありません・・というような小さな停留所。ここから田園交響曲に出てくる小川とか小鳥のさえずりとかが聴こえる場所、ハイリゲンシュタットという名所も近く。それにしてもおもしろい1日でした。BGM: 私が子供だったころ・・・小澤征爾 のなかでの音楽 中国の様子がテレビで映っています。昭和10年代。 この番組おもしろそうです。 路面電車に乗っているとき、メンデルスゾーンの「狩の歌」もあたまでなっていました。 ずっと前に弟が弾いていた曲だったので聴けてうれしかったです。
June 15, 2009
コメント(0)
-

雑司ヶ谷ばさーじゅ、待望の都電荒川線の遠足
2日続きで雑司ヶ谷に来ました。 学習院と日本女子大にすぐの界隈ののどかな風景が来るたびに好きになりました。 半分くらいは面識のあるピアノと室内楽の会に堪能しました。 いろんな方の演奏聴いたり、お話したり、こちらの近況をお話したり。楽しい1日になりました。 メンデルスゾーン無言歌集、とても客観的に聴けて勉強になりました。 リズム感があり、前へ前へと推進していけるような曲の作り方は、いつもながらに見習いたいと思いました。 ショスタコもスクリャービンも自分のものにされていて、聴いていて楽しかったです。 それにしてもドビュッシーの子供の領分でリレーができるのですから。ハイレベルなパフォーマンスにも感動しました。 メントリの室内楽で終わったのも渋かったです。 お誘いいただきありがとうございました! ● 帰り道、 雑司ヶ谷の近くを走っている都電荒川線に乗ってみることにしました。 鬼子母神という雑司ヶ谷音楽堂の最寄り駅から、浅草の近くの三ノ輪橋まで。 山手線の少し北をぐるっと回る感じです。 1両編成の電車は満員、下町のなかを大活躍しているようです。 それから坂道がこのあたりはずいぶんあることも感じました。 雑司ヶ谷から東池袋、大塚、庚申塚、王子、町屋と街の風景を見ながら、素敵な演奏を思い出しています。 いまにも雨が降りだしそうな、6月の夕暮れ時。 今日も楽しい1日になりました。 ● おうちに帰ったらピアノの練習します。 来年はショバンイヤーということでop.28のうち少しを今日から練習開始です。
June 14, 2009
コメント(10)
-

Trio di Clarone(トリオ・ディ・クラローネ)/トッパンホール
江戸川橋にあるトッパンホールへ、ちょっと風変わりな経路で行きました。雑司ヶ谷付近にある高田一丁目というバス停から、新宿行きのバスに乗るのですが、ここから、日本女子大学、椿山荘、こういうところを通って江戸川橋に行くことができます。江戸川橋の交差点付近、紫陽花の漢字どおりのようでした。「夕べに」シューマンをまた聴けると、トッパンホールの会場へ向かいました。ここ半年のコンサートで、チケットをとるのに、最もたいへんだったものでもあります。トリオ・ディ・クラローネ リサイタル<プログラム> メンデルスゾーン コンチェルトシュトゥック第2番 ニ長調 Op.114 ザビーネ・マイヤー(Cl)、ライナー・ヴェーレ(Basset horn)シューマン 3つのロマンス Op.94 ライナー・ヴェーレ(Cl) I 速くなく II 素朴に・心より III 速くなく シューマン おとぎ話 Op.132 ザビーネ・マイヤー(Cl)、ヴォルフガング・マイヤー(Basset horn) I いきいきと、しかし速すぎず II いきいきと、しかも際立たせて III 静かなテンポで、繊細な表現をもって IV いきいきと、とても際立つように・・・シューマン(J.ミヒャエルス編)5つのカノン風練習曲 Op.56 (原曲:6つのペダル・ピアノのためのカノン形式の練習曲) ヴォルフガング・マイヤー(Cl) ライナー・ヴェーレ(Basset horn) I. さほど速くなく II.アダージョ III.アンダーティーノ IV.内面的な表現で V. 内面的にシューマン 幻想小曲集 Op.73 ザビーネ・マイヤー(Cl) I. 繊細、かつ表情豊かに II. いきいきと、軽く III.急いで、情熱をもってメンデルスゾーン コンツェルトシュトゥック第1番 ヘ短調 Op.113 ザビーネ・マイヤー(Cl)、ヴォルフガング・マイヤー(Basset horn)全体を通してのピアノ伴奏: コンラート・エルザー(Pf)・・・ザビーネ・マイヤーというクラリネットの女王に、兄のヴォルフガング・マイヤー、夫のライナー・ヴェーレ、トリオ・ディ・クラローネは、ドイツ語であり、クラリネット・トリオの意味であります。世界最強のクラリネット・ファミリーなのでしょうか。圧倒的なオーラのなか、生命感あふれるメンデルスゾーン、シューマンの演奏。響きのいいホールでのクラリネット、最前列でかぶりつきのような席で堪能いたしました。ザビーネ・マイヤーは、1983年ベルリンフィルに女性としてはじめて入団した首席クラリネット奏者、招いた指揮者はカラヤンです。その後、カラヤンとベルリンフィルのごたごたに巻き込まれたのと、ソリストとしての適性の高さから退団、現在は、クラウディオ・アバドが指揮するルツェルン祝祭管弦楽団で演奏しているのと、リューベック音楽大学教授をしているそうです。颯爽と歩く姿から、演奏まで、何から何まで目に焼き付いています。幻想小曲集Op.73は、ずっと頭に鳴り響いているというのが今の状況です。バセット・ホルンという楽器、クラリネットアンサンブルというので、私ははじめて見ました。ホルンとクラリネットの子供のような感じ、クラリネットをふたまわり大きくした感じで、椅子に座って演奏していました。低音の響きがとても渋い音になり、Op.56のカノンでは、2つのクラリネットの響きが見事でした。ピアニストは、アンサンブルとしてのピアノ演奏。ぼんやりとしたうす曇りのようなピアノの音色の中に透き通ったクリアなクラリネットの音色、これは絶妙でした。60-70%くらい、ウナコルダ踏んでいた感じで、ソロとは異なる境地もあるのかもしれません。あたたかく柔らかな音色、忘れることはありません。アルゲリッチ、ニキタ・マガロフに師事、1982年ジュネーブ国際コンクール3位、1989年シューベルト国際コンクール入賞という経歴で、現在リューベック音楽大学教授、いくつかの国際コンクール審査員もされているそうです。凄すぎます・・・、トリオ・ディ・クラローネのお三方にサインいただきました!!!ザビーネ・マイヤーのサインは家宝になります。おかげさまで、すてきな1日になりました。http://www.sabine-meyer.com/BGM: まだシューマンのOp.73が鳴っています。 ザビーネ・マイヤーさんのクラリネット、聴けてよかったです。http://www.youtube.com/watch?v=-R2GQJgig8s&feature=channel_page(これは モーツァルト クラリネット協奏曲K622 の一部。)
June 13, 2009
コメント(0)
-

雑司ヶ谷でのういんどみる
雑司ヶ谷界隈はコートを着ていた冬の季節から、今年は何度か来ています。 初夏の梅雨の合間のこういう日はとても好きです。 閑静なところにある音楽堂で午後は楽しく過ごしました。 ここでは演奏を聴きに行くときもあれば、自分がピアノ弾くときもあります。 思わぬ人にもあったりします。楽器がピアノだけでなく弦楽器だったり木管楽器だったりします。 今日はフルート・アンサンブルの演奏楽しみました。アマチュアオーケストラのフルートパートの人の集まりにピアノが加わった感じです。 フルートは単旋律の楽器だからこそというのもあって歌わせるということが上手だなあと思いました。 フォスターの夢見る人 久石譲の君をのせて 二曲並ぶとなかなかセンスがいいなあと感じました。 ドビュッシーの小舟にてはフルートとピアノ。ピアノ連弾とはまたちがった趣があり、やったことのあるセカンドパートを気にして聴きました。 シューマンのトロイメライはフルート四本。やはり四声の曲なんだと感じ、音の響きを楽しみました。 グリーグのホルベルグ組曲のプレリュード。ピアノでも弦楽合奏でもありますがフルート四本の明るい響きも爽やかなものでした。 ステージにたったみなさまに感謝。 これからバスに乗って4つ目の江戸川橋に向かいます。 ういんどみる。 木管ざんまいの1日になりそうです!
June 13, 2009
コメント(0)
-
バウムクーヘンが食べたい。
食いしん坊な週末です。週末から週明けにかけて、めんどうな仕事を依頼されそうで、食いしん坊になりそうです。「疲れたときに甘いもの」・・・これにうなづいて、特大のプリンアラモードを堪能することもよくあります。今回は、バームクーヘンが食べたい!です。日頃からたいへんお世話になっている、あるところのブログの書き込みで、ショパンがシュークリームで、シューマンがバウムクーヘンというイメージのお話をうかがって、3日ほど経つのですが、夢にまで出てきそうになりました。たとえに感動したことと、やっぱりそういうことを想っていただきたいのと両方です。3時のおやつ時に、気がつけば、Googleの検索画面で、バームクーヘンと、手が勝手に動いてしまい、おいしいお店を探さずにはいられなくなりました。日本経済新聞の週末の特集記事に、ランキング記事があり、そういえば、バウムクーヘンのランキングはあったはず・・・と、探してみることにしました。http://manyblog2.blog118.fc2.com/blog-entry-43.html2009年2月21日号、おすすめのバウムクーヘン・ランキング1位:クラブ・ハリエhttp://clubharie.jp/日本橋三越・銀座三越・池袋西武・新宿小田急・東急本店・・・その気になれば、行けるところばかりだし、散策してみたいです。2位:カール・ユーハイムhttp://www.juchheim.co.jp/karl/index.htmlユーハイムのバームクーヘン専門店。こちらは高島屋東京店、高島屋新宿店、東武百貨店池袋店。3位:ヴィヨン バウムクーヘンhttp://www.villon.co.jp/baum.htm世田谷、桜新町の駅前の洋菓子屋さん。この界隈のオフィスに2年ほど通っていて、ここでケーキは買って、近くの馬事公苑にいる後輩に持っていたことがありますが、バウムクーヘンは知らなかったです。10年前、シューマンのアラベスクちょうど弾いていたころ、毎日ここ通っていたのに・・・・ と、思ってしまいました。このおはなしを見て、わかってくださる方に、お話したいです。シューマンはしゅうまいではなく、バウムクーヘンなのかは、弾いてみて感じて、食べてまた感じてみたいものです。BGM: シューマン 3つのロマンス Op.94 オーボエ: ダグラス・ボイド ピアノ: マリア・ジョアン・ピリス 2曲目を一晩中聴いていたい気分です。
June 12, 2009
コメント(10)
-
渋谷センター街のCDショップにて
ヴァン・クライバーン国際コンクール優勝の辻井伸行さんのCDは軒並み完売。在庫切れ。 サンプルCDがかろうじてあり、ラフマニノフのピアノ協奏曲の頭五分だけを繰り返し聴いています。 ふつうクラシック音楽の話題にならない会社のランチでも、持ちきりでした。 去年の大晦日、オペラシティでのベートーベンコンサート、昨日のブログのビアニストのあとが辻井さんでした。 私は完全にニアミスでオペラシティをあとにして新幹線で実家に帰ってしまいました。 ちょっともったいなかったかも。 またゆっくり演奏聴いてみます。
June 11, 2009
コメント(0)
-
早寝早起きをしすぎると・・・。
最近、1日が飛ぶように過ぎていきます。もう水曜日なのかと思いつつ、あれやこれやとやっていると、会社でも夕方になってしまい、早い目に帰りました。久々に銀座4丁目の楽器店に行きましたが、どうしても・・・というほどのものがなく、見るだけの日となりました。CDもそうですが、楽譜も。このあいだ言っていたショパンとシューマンは、たいていの楽譜は家にあるので、別の出版社での指使いがみたくなったり、微妙なフレージングが違っているとき、またそういうことをしに来るのだろうかと思ってしまいました。今年はすでにある楽譜でありますが、メンデルスゾーンの無言歌集、原典版であるヘンレ版と、解釈版であるペーターズ版と、音のとりかた、フレーズ感、ペダリングとかちがいがあり、比べてみるのは、たいへん勉強になりました。ここ半年、ひと前で何回か弾かせていただいたりしたこともあり、深くかかわれて、これはよかったです。夏休みの予定表なるものを記載するものが会社のメールでまわってきて、メンデルスゾーンハウスに行くのだと宣言するかのように部署でいちばんに書いてしまいました。チケットがとれればのはなしですが、8月下旬のメンデルスゾーン生誕200年の音楽祭にあわせて、ライプツィヒに旅をしに行きます。聴ければ日本にほとんど来なくなってしまったラベック姉妹の2台ピアノ(メンデルスゾーンの2台ピアノの協奏曲)、ゲヴァントハウス管弦楽団のスコットランド交響曲、フィンガルの洞窟、室内楽ではこのコンサートで引退するというボザールトリオのメントリ。いつも楽しみが毎年みつかってうれしいです。このあいだよくお世話になっているピアニストにこの旅行企画をお話すると、異様なまでに話が盛り上がりました。ボザールトリオの譜めくりをウィーンのムジークフェラインでしたことがあるとか、ぼんやりとしたタッチのなかに室内楽の響きのピアノのあることを間近で感じたとか、はっきり音と出し過ぎる日本人的な弾き方が必ずしも曲にマッチするとは限らないことをボザールトリオのピアニストの演奏を通じて感じたとか。去年、ウィーンとザルツブルクから帰ってきてシューベルトの即興曲をまだそれほどひけていないときに聴いてもらったら、音がドイツ語になっているといわれてうれしかったので、自分自身の変化がなにかあるか、これも楽しみにしようと思うことにしています。・・・と、10分くらい、作文してみたところで、午前2時半あたり。ちょっといろいろほっとしたこともあって、よいこのように、夜9時に就寝したのはいいのですが、5時間少し寝れば、確実に目覚めてしまいます。夜中だとピアノも弾けないし、二度寝するにも早すぎるし。まあ、こういう日もたまにはあってもいいかと、思っています。こういうときに、ぽーんと1通のメールが来たら、気分よくなりすぎて、とても長文のメールを返してしまうかもしれません。●ご案内も含めて、もう少しだけ書かせていただきます。8月初旬に、ホールでピアノを15分くらい弾く予定。このなかで、モーツァルトのきらきら★変奏曲のリレーをすることになっているらしく、自分が好きな第2変奏をエントリーしました。ヘンデル 調子のよい鍛冶屋ハイドン ピアノソナタ37番第1楽章メンデルスゾーン 五月のそよかぜとアニバーサリーなものを3つ並べてみようかなあと。じゃがいもコロッケのハイドンは、準備が整うかどうか疑問ですが、気分が乗ってきたら、ちょっと楽しみです。ヘンデルのバリエーションはとても練習しがいのある曲で、これもホールで弾くとどうなるのかは楽しみ。メンデルスゾーンの無言歌は、5月にどうしても弾きたいと、集中的に練習した曲。気が抜けてしまわないように、1回はホールで弾いてみたいです。左手と右手の内声の使い分け、これはけっこうやっかいでした。右手になったとき、気をつけないと少し大きくなるので、微妙な気配りが必要。この曲もメンデルスゾーンのすなおな歌心があって、曲そのものに惚れこんでしまいました。BGM: モーツァルト セレナーデ 「ポストホルン」 K.320 ネヴィル・マリナー指揮 アカデミー室内管弦楽団
June 10, 2009
コメント(0)
-
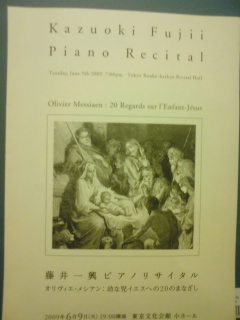
久々の東京文化会館小ホール
夕方の会社の会議、17:30に終わるはずが、18:20手前で終了。でも上野だし、東京文化会館だしと、最寄り駅までタクシーに乗り、地下鉄&JRでホールまで。 開演3分前にホールへ。でもなんだか淡々とした感じでした。あわてふためなくなった分、場数を踏んだのかもしれません。藤井一興ピアノリサイタルオリヴィエ・メシアン 幼な児イエスへの20のまなざし1.父のまなざし/2.星のまなざし3.交換/4.聖母のまなざし5.子を見つめる子のまなざし/6.それにすべてはなされたり7.十字架のまなざし/8.高きみ空のまなざし9.時のまなざし/10.喜びの聖霊のまなざし・・・11.聖母の初聖体/12.全能のことば13.降誕祭/14.天使たちのまなざし/15.幼児イエスの接吻16.預言者たち、羊飼いたちと博士たちのまなざし17.沈黙のまなざし/18.怖るべき感動のまなざし19.わたしは眠っているが、わたしの魂はめざめている20.愛の教会のまなざしパリ国立音楽院で作曲科、ピアノ科を卒業されていますが、メシアンに師事されています。そんなピアニストの演奏というのも、そうそうあるものではありません。玄人はだの聴き手もそれなりにいたようにも思います。文化会館小ホールは、ピアノを聴くのに好きなところのひとつ、ぴんとはりつめた空気のなか、暖かい音を激しい音、多彩な音色をもつ、藤井先生のピアノをひたすら聴きました。メシアンはそれほど聴くことありませんので、細かいことはわかりませんが、楽譜を立てながら、真剣なプログラムでの演奏とあって、たいへん感動しました。●休憩時間中、誰を探すわけではなく、ぼんやりしていたのですが、どこかで見たことある人もやっぱりいるなあと思いながら、はっとさせられました。目の前に会社の先輩にばったりとお会いしました。辞められているので7年ぶりということになりました。 以前、深夜残業していて夜中1時過ぎに、突然ピアノのはなし、クラシック音楽のはなしになり、気がついたら夜が明けていて、土曜の朝に家に帰ったこともありました。北京へトゥーランドットへ聴きに行ったり、シューマンのアラベスクを聴いてもらったり、10年前のことをいろいろ思いだしました。ぴんぽんぱんの原点のころのひとつのできごとかもしれません。「ご飯をつくって待ってくださる人はいらっしゃらないのか・・・」と聴かれましたが、「そのうちに・・・」としか答えようがありませんでしたが、笑ってしまいました。おかげさまで楽しい1日になりました。
June 9, 2009
コメント(0)
-
きょうはシューマンの誕生日。
ロベルト・シューマンの誕生日だということを、シューマンがお気に入りの音楽仲間に教えていただきました。生誕199年、でも同い年のショパンのようにそれほど騒がれません。没後150年だった2006年だった年は、生誕250年のモーツァルトイヤーだと世間ではいわれ、いつもいつも影の人になっているようでもあります。ショパンやモーツァルトと比べてどうかというのは、桜並木とバラ園とラベンダー畑を比べてどれがいいですかと言われるのと同じように聞こえてしまい、私にとっては大切な作曲家であることはいうまでもありません。●書いていておもしろくなってきましたので、ちょっと振り返ってみたくなりました。シューマンは、バイエルのおわりのほうにある、「楽しき農夫」 という曲があり、それを弾いたのが最初だったと思います。高校のころ、家にあるレコードを聴いて、ピアノ習っていなかったのですが、なんとなく「トロイメライ」のピースを買って弾いたのがその次だったと思います。ピアノは弾いていない時期は、ウォークマンでよく聴いたりもしていました。大阪から和歌山まで2時間以上かけて仕事先に通っていたことありました。ホロヴィッツのシューマンのCDでして、おわりから2番目の「アラベスク」、おわりの曲の「花の曲」は、とても印象に残っています。行きも帰りもひとりのときは、シューマンのピアノ曲がお友達でした。南海なんばの駅前にはまだ大阪球場があり、和歌山の手前の関西新空港は建設中でした。そんな平成のはじめごろの出来事です。ピアノは22年のあいだ、習っていない時期がありました。東京で一人暮らしを始めて、最初に練習したいとおもったのが、op.18のアラベスクでした。ピアノを買ってすぐに、なぜか直感でひらめいたように、ピアノピース買いました。この曲から、再スタートとなりました。この年はザルツブルクにも行ったので、帰りにミュンヘンに立ち寄り、ヘンレ版の楽譜を買いなおしました。ラトハウスの裏にあるそこのお店は、自分のなかでは「ヘンレ屋さん」のように思っています。ドイツへ行くたびに立ち寄るようになりました。いつ弾くかどうかわからない、op.9の「謝肉祭」の楽譜もアラベスクと一緒に日本へ持って帰りました。99年から長く習っている今のピアノの先生にお世話になっていますが、2曲目が、op.12の「幻想小曲集」から飛翔を練習しました。その後、ベートーヴェンとシューベルトがなんとなく多かったようにも思いますが、2006年にピアノの発表会で、10分ほどの枠をいただいて、op.9の謝肉祭を弾きました。「ショパン」という曲以降を練習していたのですが、「パンタロンとコロンビーヌ」というスタートしにくい曲から始めました。ドイツ風ワルツのなかの間奏曲「パガニーニ」は本当にたいへんな曲でした。それらしく弾けるまでにたった2ページの楽譜ですが半年かかりました。ちょうどブログをはじめたころで、海外留学している方も謝肉祭やられていたので、刺激を受けて、話相手になってもらえました。「告白」という曲と「ブロムナード」という曲は、この作品でほっとするところ、この2曲だけでPTNAステップにでて、3人からブラボーをもらったのはうれしかったです。「ペリシテ人と戦うダヴィッド同盟の行進」、こんなに弾いていて楽しい曲はあるのかと、心から思いました。その前の「休憩」という曲は、「休憩」どころではなく、なかなか華やかになれませんでした。その後、op.15「子供の情景」からNo.7/8/9という感じで練習したり、op.26「ウィーンの謝肉祭と道化」から間奏曲を練習したりしました。●2010年のショパンイヤーには、op.28の前奏曲からおしまいの4曲ということを決めてかかって弾こうとおもっていますが、シューマンについてはまだ考え中です。やっていない曲は書き出したらきりがありませんし、ゆっくり考えてみます。オーボエの伴奏するop.94「3つのロマンス」とか、op.48「詩人の恋」のピアノ伴奏で、5月に妙になってみるのもいいし、op.29-3「流浪の民」とか合唱団の伴奏できたらうれしいし、考えてみるだけで楽しくなりました。BGM: シューマン 交響曲第2番 ハ長調 op.61 レナード・バーンスタイン指揮 ウィーンフィルハーモニー管弦楽団 すきな交響曲5つ・・・といわれたときに、4番目か5番目にいつも書いています。 最後の楽章はベートーヴェン5番の4楽章、ブラームス1番の4楽章に 似たようなところありますが、辛かった時期に聴いて何度も励まされました。 曲の作られた背景を読むと、シューマン自身とても苦しんでこの曲を書いたことを 知ることとなり、最後の4楽章は、本当に感動的です。 バーンスタインが札幌でPMFを立ち上げた時、テレビでゲネプロみて、 深くしることになったきっかけでもあります。 そのときのことを時々振り返ってみたいとおもうことがよくあります。
June 8, 2009
コメント(200)
-
紫陽花・にほんばし
日本橋三越、地下鉄からの入口。 夏用の、暖簾もありましたが、この紫陽花はお見事。 用事もあり買い物も致しました。 一生お付き合いするところへの贈り物であれば一升瓶がいいです。と、老舗の女将のようなかたに教わりました。力強いお言葉、素直になろうと思いました。 ● 春夏冬 二升五合 あきない ますます はんじょう こんなことばを思い出しました。 本当にいいお天気です。何もいうことありません。
June 7, 2009
コメント(2)
-

桜坂・高輪・あじさい。
ずっと昔ですが、♪歩きたいのよ高輪・・・ という歌があって、ザ・ベストテンという番組やっていたころ、よく見ていました。その高輪を今日は朝がた歩いていました。桂坂という静かな坂があったり、第一京浜沿いに山手線が走っていたり、動も静もあり、なかなかのところでした。 泉岳寺から、しばらくのところには寺院も多く点在します。今日は、友人の7回忌の法要があり、そのあと、偲ぶ会がありましたが、これだけ時間がたっても100人近い人が集まることにも驚きました。人徳ということばを改めて思い起こしました。道半ばで遠くへ行ってしまった分、しっかりしなければとも思いました。6月の高輪界隈の紫陽花、とてもきれいでした。それは忘れることないでしょう。BGM: モーツァルト ヴァイオリン協奏曲 第5番「トルコ風」 K.219 アンネ・ゾフィ=ムター(ヴァイオリン) カラヤン指揮、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団 会場のなかで始まる前に流れていた音楽、モーツァルトは自然な感じがします。 故人とも私とも同世代のヴァイオリニスト、そういうこともあって聞いてみたくなりました。 かつてサントリーホールで聴いた、ベートーヴェンやブラームスのヴァイオリンソナタ、 また聴いてみたくなりました。
June 6, 2009
コメント(0)
-
じゃがいもコロッケ
急にコロッケが食べたくなりました。じゃがいもコロッケのピアノの曲が弾きたくなりました。 ♪じゃがいもコロッケコロッケ、じゃがいもコロッケコロッケ、たたいて、つぶして、カラリと揚げましょう旅行三昧で、新しいピアノの曲はまだまだこれからなのですが、こういう感じの曲を練習することにしました。ハイドンのソナタ ホーボーケン番号でいえば、37番。二長調。雨降りのなか、雨降りでも楽しくなることまちがいないこの曲は、大好きな曲のひとつです。ちょっと前、好きなピアニストのひとりであるファジルサイのCDで刺激を受け、先月はピアノの会で弾いてくださるかたがいて、ますます刺激を受け、ようやく週末になったので、少しはピアノが弾けそうですし、楽しみが増えました。ハイドンのピアノ曲、ちょっと気になりだしたのはブレンデルのCDから、その後、インターネットで知り合いになったピアニストの師事していた先生がハイドンをよく弾かれるブッフビンダーだといわれて全集を買ったり、そんなあたりから徐々にという感じです。こどものときのソナチネは弾くには弾きましたがという感じです。ちょっと練習すればそこそこは弾けるようにはなるでしょうが、そこそこから先、その先へ行くのは、いろいろ勉強してみないとという感じがします。ツェルニー40番や50番やらが弾かれる方のような高度なテクニックがいるのかどうかはわかりませんが、ハイドンはハイドンからしか学べないだろうなあと感じました。時間がないなか、エチュードをやったり遠回りするくらいだったら、一つのソナタを深く弾けるようになりたいものです。ハイドンのソナタは、構成を考えたり、形式を考えたり、楽譜を見るかぎりとても楽しいです。ハイドンのソナタを弾いて感じるないことは、モーツァルトとはちがって、弦楽合奏やオーケストラの観点で曲を書いているようなところもあり、そういう意味ではブラームスとかと似ているのかなあと思うことも。独立した作曲家でフリーターのようなモーツァルトと、おかかえ作曲家で安定した生活のなかのハイドンと、そういう生活背景も曲のつくりに影響したかもと、いろいろ考えさせられたりします。おかかえ作曲家である故、決められた形式による納品するかのような曲づくりのなかで、その範囲で遊びがあったりコミカルであったり、なんだか、弾いていてそれはそれで愛着がわいてきました。なにもかも自由であったモーツァルトは食べていくために曲を書いているのであれば、聴いてもらうためならではのメロディアスな要素もきっと必要でしたでしょうし。この二人、おたがいが仲良かったと言われるのも、音楽家として、生活の立ち位置の違いがあったなかでの才能を認め合ってのことだったのかもしれないと、ちょっと考えたりもしました。BGM: ハイドン ピアノソナタ D-Dur Hob.XVI-37 ピアノ: ファジル・サイ ルドルフ・ブッフビンダー 二人のピアニストのCDを聴いて、楽しく週末を過ごします。
June 5, 2009
コメント(200)
-
JAL オーディオクラシック おぼえがき
http://www.jal.co.jp/inflight/dom/05/audio.html#classic 機内のBGMがあまりにもすばらしかった5月。どなたが構成されているのかも含めて、いろいろメモできるものを探していました。プレゼンターの檀ふみさんは、もとN響アワーでの司会を。構成の林田直樹さんは、もと音楽の友とかレコード芸術とかの担当を経て独立。はまり役というのは、こういうものだろうと、感動しきっています。機内BGMのなかで、ムターがヴァイオリンを弾き、リン・ハレルがチェロを弾く、メントリのCDはぜったいに手に入れようと思いました。この曲ますます好きになりました。ブレンデルが弾く、厳バリは、私にとっても大事なCDの一つですが、改めて聞き返そうと思いました。 飛行機に乗っているときは、行きも帰りも、機長からのアナウンスでというので曲が遮られましたので、消化不良になり、また家で聴こうと思うようになりました。シューマンの詩人の恋の選曲もすばらしかったです。「うるわしき、妙なる5月に・・・」 まさにそんな気分でしたから。なんとか、構成担当のかたにお礼のメールでも送りたいと思っています。
June 4, 2009
コメント(0)
-

Notturno ~やさしい夢、やさしい夜~
夜に、東京オペラシティ・リサイタルホールにいました。日野妙果 メゾ・ソプラノ・リサイタルNotturno ~やさしい夢、やさしい夜~プログラム:シューベルト 夜と夢 D827 夜曲 D672 夜鷲に寄す D497 若者と死 D545b 死と乙女 D531 糸を紡ぐグレートヒェン D118 ズライカ I D720 美も愛もここにいたことを D775 別れ D475 小人 D771ベルリオーズ 「夏の夜」 作品7 (テオフィル・ゴーティエ詩) ヴィラネル ばらの精 入り江のほとり 君なくて 墓地にて 未知の島日野妙果(Mez) 三輪郁(Pf)ウィーン国立音大卒どおしのおふたりのドイツリートの会は、今回で6回目とプログラムにありました。ご自身のことばでのあいさつ文、曲紹介は、思い入れの強さを感じ、たいへん惹きこまれました。欧州には、夜を讃えた歌、夜に恋人を想う詩、夜からのインスピレーションを受けて詠まれたすばらしい詩が数えきれないほどあり、そこからできた歌曲の紹介でありました。ドイツ・リートを芸術の高みに引き上げたシューベルト、詩と音楽の相互作用による芸術歌曲として、フランスでいう「メロディ」という名称をはじめて用いたのがベルリオーズ。独仏歌曲事始め・・・のようなプログラムという、紹介がありました。ドイツリート、ここ半年でそれなりにリサイタルにもいっているつもりですが、奥深いです。夜をテーマに、すてきな世界を堪能しました。すてきなメゾソプラノはもちろんですが、ピアノの指と音に夢中になり、表情・表現・音色・歌とのバランス・・・釘付け状態でした。「夜と夢」 D827詩:コリン 聖なる夜が地上に降りてくると、月の光のように夢が人々の心に静かに満ちていく。 人は夢に喜び戯れ、夜明けには呼びかける。 「やさしい夜よ、やさしい夢よ、また戻ってきておくれ!」と。オペラシティをでたあたりに巨人がたっていましたが、夜に、地上に降りてきたのでしょうか。そんな感じに見えました。
June 3, 2009
コメント(0)
-
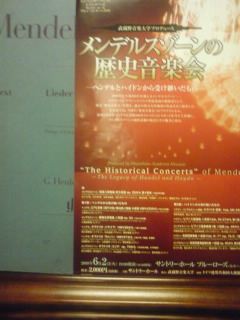
メンデルスゾーンの歴史音楽会 /サントリーH(小)
レインボウ21 サントリーホールデビューコンサート2009武蔵野音楽大学プロデュース「メンデルスゾーンの歴史音楽会-ヘンデルとハイドンから受け継いだものー」<プログラム>メンデルスゾーン 弦楽八重奏曲 変ホ長調 op.20から第1楽章☆第1部 ヘンデルから受け継いだものヘンデル 鍵盤組曲第1巻第5曲 ホ長調 H430から第4楽章 エアと変奏「調子の良い鍛冶屋」メンデルスゾーン 厳格な変奏曲 二短調 op.54 ヘンデル オラトリオ 「メサイア」HMV56から 第1部第17曲 二重唱「主は羊飼いのようにその群れを養い」ヘンデル オラトリオ 「サムソン」HMV57から 第2幕第4場 レチタティーヴォ 「わざわざそんなことを言いに来たのか」 二重奏 「腰抜けめ、失せろ」メンデルスゾーン オラトリオ 「エリア」 op.70から第2部 第26曲 アリア 「主よ、事たれり」 第28曲 天使の三重唱「山に向かい、目を上げよ、かしこから救い来たれり」☆第2部 ハイドンかr受け継いだものハイドン/メンデルスゾーン編曲 オラトリオ「四季」 Hob.XXI-3 から序曲(日本初演)ハイドン ピアノ三重奏曲 ハ長調 Hob.XV-27 から第1楽章メンデルスゾーン ピアノ三重奏曲第1番 二短調 op.49 から第1楽章ハイドン 弦楽四重奏曲 Hob.III-77 op.76-3 「皇帝」から第2楽章メンデルスゾーン 弦楽四重奏曲第6番 ヘ短調 op.80から 第2・第4楽章とてもよく練られた企画、すばらしいコンサートでした。メンデルスゾーンは、1829年にバッハのマタイ受難曲を100年ぶりに蘇生させたことで、よく知られていますが、これ以外の作曲家のコンサートもいろいろ取り上げたそうです。1838年、1841年、1847年と3シリーズにわたり、12の「歴史音楽会」というのを催し、上記の演目は、そのときのプログラムに入っていたもの。2-3日前に聴いた、飛行機内でのメンデルスゾーンのBGM同様、愛着のこもった演目であり、演奏でした。いろんな切り口で、メンデルスゾーンのコンサートがあり、今年は楽しいです。ピアノだけでなく、歌あり、室内楽あり、アニバーサリーの作曲家と聴き比べをし、斬新なところにいれて、うれしかったです。BGM:メンデルスゾーン ピアノ三重奏曲 op.49 第1楽章http://www.youtube.com/watch?v=vp1TRzMeIOUメントリ ということばをピアノの専門のひとに聴いたことありますが、ここ10日でずいぶん聴く機会を得て、ますます好きになりました。
June 2, 2009
コメント(26)
-

雨の中島公園
Kitaraホール(札幌コンサートホール)の前の新緑がきれいでした。前に来た時は雪だるまがあったなあと、2年半前のことも思い出しました。モニュメントもたくさん。小鳥もいました。 Kitaraホールの裏側。小川があります。このそばが渡辺淳一文学館。1時間ほど、のんびりお散歩できてよかったです。昨日のことですが、くつろいだ日曜日の午後でした。
June 1, 2009
コメント(0)
全37件 (37件中 1-37件目)
1
-
-
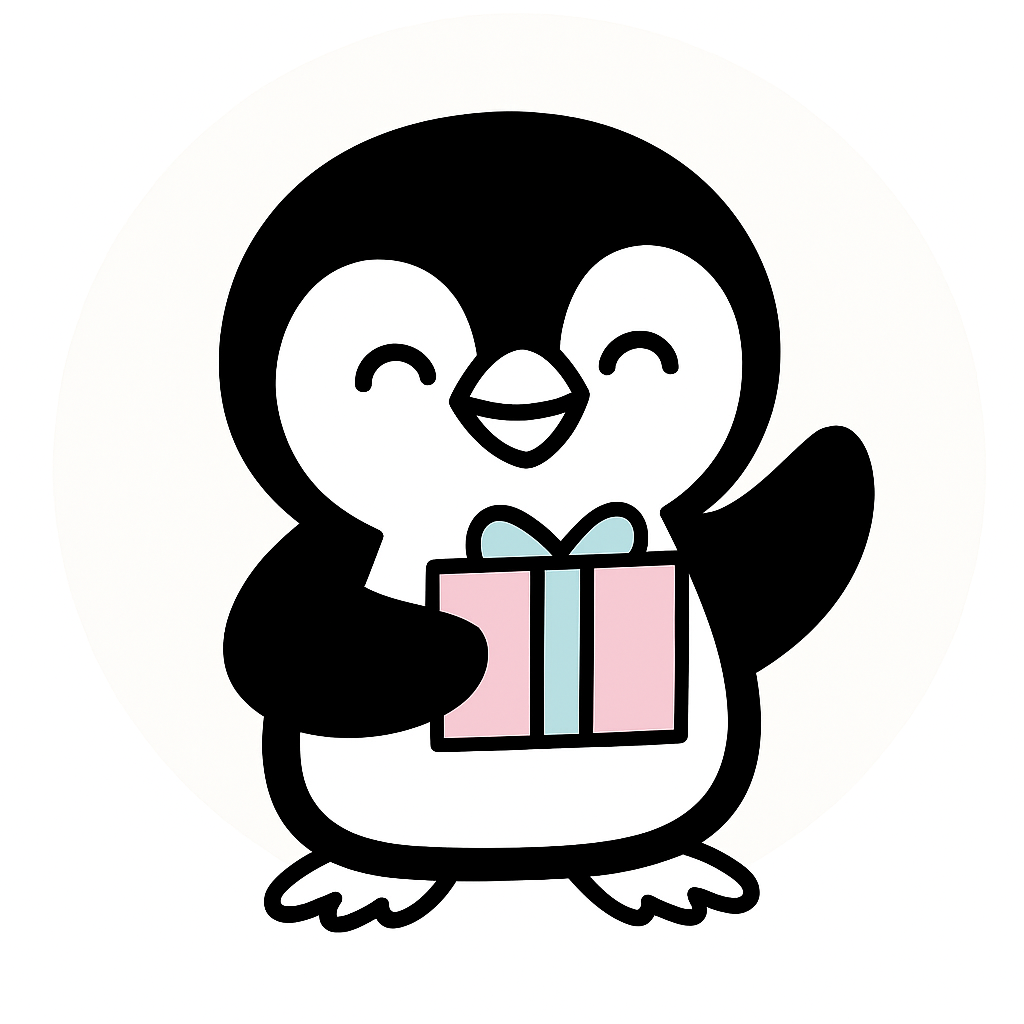
- やっぱりジャニーズ
- 楽天予約 SixTONES Best Album「MILE…
- (2025-11-20 16:44:46)
-
-
-

- 吹奏楽
- 演奏会に行ってきた。
- (2025-11-19 16:33:12)
-
-
-

- Jazz
- Jan Grabarek, Live in Stockholm, D…
- (2025-11-02 07:32:37)
-







