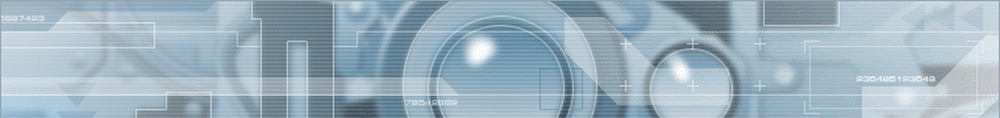2008年06月の記事
全28件 (28件中 1-28件目)
1
-

2008年6月 自宅ワイン会 甘口編
白編、赤編に続いて、最後の甘口編。1995 Macon Clesse Cuvee Botrytis du 14 Octobre(Domaine de la Bongran - Jean Thevenet)マコン・クレッセ キュヴェ・ボトリティス・デュ・14オクトーブレ(ドメーヌ・ド・ラ・ボングラン)Bourgogne, France - 白極甘口\14,500くらい, KAJIWARA, 2002年12月購入ブルゴーニュでは珍しい貴腐ワイン。たしか94と95は、ワイナートで好評価を得ていたはず。名前の"14 Octobre"は、10月14日に収穫したという意味で、ビンテージごとに異なっている。色調は、わずかに赤みも入った濃いゴールド。貴腐、貴腐、貴腐しっかりした甘みと、苦みを伴った強力な酸が印象的で、口に含んだ瞬間、のどの奥がキュンとなる。かなり甘く、ボディもしっかり。ソーテルヌタイプか、ドイツタイプかと聞かれれば、ドイツのほうが近い。酸はドイツほど鋭くないけれど、マコンでここまで酸のレベルが高いのは驚き。高いだけあってさすがの味わい。ボングランのキュヴェ・ド・ボトリティスを探す>01のハーフが\9,000くらいで、95のフルボトルだと\25,095。203 Thungersheimer Scharlachberg Riesling Eiswein 250ml(Weingut Schwab)Franken, German - 白極甘口\3,360, 池袋東武, 2006年10月購入フランケンでは珍しいアイスワイン。それも250mlというプチボトル。ボングランと比べると甘みは弱め。とは言ってもボングランが強力に甘いだけで、こちらも単独で飲めば相当甘い。ブドウを感じる風味。アイスワインらしい透明感。すごくはないけれどおいしい。まとめ:人気が高かったのは、アントのムルソー、ラヴノーのヴァルミュール、パカレのジュヴレ、ルソーのシャンベルタン。一番人気も分かれた。個人的に、今飲んだ点で一番好きだったのはラヴノーのヴァルミュール。熟成の良さを感じさせる素晴らしいもの。次にパカレとアント。ルソーは、飲み頃じゃなかったということで3番手グループの評価。Part1に戻る。気が向いたら投票お願いします→
2008.06.30
コメント(0)
-

2008年6月 自宅ワイン会 赤編
白編に続き赤編。2002 Gevrey-Chambertin 1er Cru La Perriere(Philippe Pacalet)ジュヴレ・シャンベルタン プルミエ・クリュ ラ・ペリエ―ル(フィリップ・パカレ)Bourgogne, France - 赤辛口\13,000くらい, リカーMORISAWA, 2004年6月購入賛否両論の激しいパカレ。個人的には嫌いではありません。比較的若いビンテージでも終わっていると聞くこともあるけれど、そのようなボトルに当たったことはありません。水のような薄っぺらいボトルに当たったことはありますが(笑)。賛否両論の激しい原因は、個人の嗜好差以外にも、コンディション差(ボトル差)が大きいと思う。また個人的にはよいと思っていない「村名ジュヴレ・シャンベルタン」を購入している人が多いことも一因だと思う。村名の赤なら「ポマール」のほうがお勧め。で、このワイン。終わっているどころか若い。リリース直後は、果実味爆弾というかブドウジュース的だったけれど、それも落ち着いて、若い自然派ワインらしい。一級の風格を感じる構造を持っていながらも、ふわりと軽やかな、すがすがしいノートが印象的で、素直においしいと思える味わい。アフターには少しタンニンも残る。分析的に飲んでみると、アフターは長くないという欠点はあるものの、独特の個性は印象的で人気の高かった一本。また暑い季節というのも、このワインに味方したのかもしれない。5年後くらいに、また飲んでみたい。パカレのジュヴレ・シャンベルタン ペリエ―ルを探す>調べてみると2005年ビンテージも01、02と変わらない値段。今までが高すぎたのか。1982 Latricieres-Chambertin(Mommessin)ラトリシエール・シャンベルタン(モメサン)Bourgogne, France - 赤辛口\5,500くらい, 竹澤, 2004年10月購入クロ・ド・タールを持っていることで有名なモメサンのネゴシアンもの。ものすごく安かったので期待していなかったけれど、弱いところやへたったところが無くて一安心。82年から想像するよりは若々しい。とはいえ、それぞれ個性を持った素晴らしいワインが揃った今回では力不足。普通で驚くこともない古酒。1996 Gevrey-Chambertin 1er Cru Les Cazetiers(Philippe Leclerc)ジュヴレ・シャンベルタン プルミエ・クリュ レ・カズティエ(フィリップ・ルクレール)Bourgogne, France - 赤辛口\6,000くらい, よしや, 2000年4月購入濃いー。黒ワイン。おそらく多くの人が想像する、濃いフィリップ・ルクレール節。長年の熟成で酒質に丸みはあるものの、ブルゴーニュだと思って飲むと「違うだろう」と思えてしまう。アペラシオンを気にせず、ワインとして飲めばマズイわけじゃないのだけど、今のような暑い季節に飲むワインではないと思う。残りのワインは長期熟成決定。80年代中盤は樽の印象や濃厚さは感じ取れないので造りが違うのか。恥ずかしながら、10年くらい前に若いビンテージを飲んだときには、若いピチピチ感と相まって、そのインパクトは嫌いじゃありませんでした。自分自身が若かったこともあるけれど。フィリップ・ルクレールのワインを探す>2001 Chambertin(Armand Rousseau)シャンベルタン(アルマン・ルソー)Bourgogne, France - 赤辛口\16,000くらい, はせがわ酒店, 2004年6月購入できかけの球体。誰もが考える正統的なブルゴーニュ。口に入れたときの広がりやアフターの長さ、舌触りのなめらかさは、これまでとは一線を画す。現在は熟成途上でポテンシャルだけで飲んでいる印象。分析的に飲めば偉大なワインなのだけれど、熟成途上&直球すぎる味わいは、直感的に飲んでしまうと今日のなかでは面白みに欠けた。もちろん将来は期待大だけど。あと2本あるので「しまった感」は無いけれど、残りは10年以上熟成させたい。[2001] Chambertin シャンベルタン 【アルマン・ルソー】 750mlヴィンテージにこだわらず探してみると\52,500が最安値(?)。正規インポーター経由のものをリリース直後に買わない限り、もう手の出ない領域。1997 Sito moresco(Gaja)シト・モレスコ(ガイヤ)Langhe, Piemonte, Italia - 赤辛口\3,000くらい, カーヴ・ド・リラックス, 2001年9月購入赤はルソーでおしまいのハズが、もっと飲みたいとのリクエストで登場。ガイヤのシト・モレスコ。品種構成はビンテージによって違うみたいだけれど、ネッビオーロ、カベルネ・ソーヴィニョン、メルローのブレンド。パワー全開。強いー!97というグレートビンテージの恩恵なのか、あまりの強さにヘキヘキしてしまう。現時点では評価不能。10年後に飲み頃になっている自信も無し。ガイヤのシト・モレスコを探す>赤のなかではパカレとルソーの人気が高かった。長くなったので甘口編は次回に繰り越し。気が向いたら投票お願いします→
2008.06.29
コメント(4)
-

2008年6月 自宅ワイン会 泡・白編
今回のメンバーとは約半年ぶりの自宅ワイン会。ジュヴレ・シャンベルタンを中心に、それ以外は気になるワインをピックアップしてみました。料理の写真はないけれど、ガスパチョ、完熟トマトのヨーグルトソース、ラタトゥイユ、牛のたたき、パスタ2種、etc。野菜中心の料理にしてみました。しっかり冷やしたガスパチョが意外に人気。暑い季節のスターターには冷たい料理がいいですね。NV Guy Charlemagne Brut Roseギィ・シャルルマーニュ ブリュット・ロゼLe Mesnil-Sur-Oger, Champagne, France - ロゼ泡辛口\2,980, ひしゃく屋, 2008年3月購入ロゼは初めてだけれど、よく飲んでいるギィ・シャルルマーニュ。キリリと引き締まったスタイルが好み。ロゼっぽさも少しあって誰でもおいしいと思える味わい。これはセールで購入した特売品だけれど、安すぎです。ギィ・シャルルマーニュのロゼを探す>1998 Henri Giraud Fut de Chene Ay Grand Cruアンリ・ジロー・フュ・ド・シェーヌ アイ・グラン・クリュChampagne, France - 白泡辛口\19,800, やまや, 2007年5月購入最近、幻のワインとして注目されたアンリ・ジローのフュ・ド・シェーヌ。アンリ・ジローのなかでは、これだけが飛び抜けて高い。がっちりしたスタイルかと思ったら意外にエレガント。凝縮感はあるのだけれど、それほど濃いわけではなく、ある種、香水のような独特の香味が印象的。ボトル差もあるとは思うし、もっと熟成した姿を見たい気もするけれど、現在3万円前後で売られていることを思うと微妙な心境。アンリ・ジローのフュ・ド・シェーヌを探す>2000 Meursault(Arnaud Ente)ムルソー(アルノー・アント)Bourgogne, France - 白辛口\8,000くらい, 酒のやまいち, 2003年2月購入ジョージアン・クラブの閉店直前に飲んで印象のよかったアルノー・アント。ストックを持っていたことを思い出し、飲んでみました。強靱な酸が印象的。最初ボディの厚みには気がつかなかったのだけれど、温度が上がってくるとムルソーらしいふくよかさも少しは出てくる。再確認のために少しだけ残しておいたものを翌日チェックすると、落ちるどころか向上している。飲みごろは先だけれど、じっくり飲めば今でもポテンシャルをひしひしと感じるはず。一流の生産者だけが持ち得る、凄みのある酸。ピュアでくもりのないボディ。コシュ・デュリ、ラフォンなど、ムルソーのトップクラスと比較しても見劣りしないのではないのだろうか。ラフォンとはスタイルが違うけどね。それにしても村名で、この出来。恐るべし。アントのムルソーを探す>ムルソー[2004] アルノー・アント\8,000から\10,000くらいと村名としては安くないけれど、素晴らしいワイン。でも大人数で飲んでしまうと、わかりづらいかも。1997 Chablis Grand Cru Valmur(Francois Raveneau)シャブリ・グラン・クリュ ヴァルミュール(フランソワ・ラヴノー)Bourgogne, France - 白辛口\5,000くらい, eX-WINE, 2001年12月購入現在とんでもない値段になっているラヴノーさん。このヴァルミュールは、2年くらい前にラ・ロマネさんやhidepxさんと飲んだものと同じ。そのときは若干よれているような印象を受けて、内心「微妙にコンディションが悪い」と思ったので、残りのワインが気になっていた。こちらは完璧なコンディション。ミネラル爆弾。ラヴノーとしては、大きなスケールではないけれど、少し熟成が入り、独特の熟成香が心を魅了する。長大な余韻。ふところの深い淑女。今回は、かなりよい赤も出したのだけれど「今飲んだ点」で今日のNo1候補。ただし今回は意見が分かれました。ラヴノーのヴァルミュールを探す>赤編に続く。気が向いたら投票お願いします→
2008.06.28
コメント(8)
-

意外にうまいサントリー「富士見園ピノ・ノワール」
昨日のマウントアダムに続いて、驚きシリーズ第2弾。2001 特別醸造 富士見園ピノ・ノワール(サントリー登美の丘ワイナリー)山梨, 日本 - 赤辛口\2,643, サントリー登美の丘ワイナリー, 2007年9月購入Profile: 昨年(2007年)の秋に行った、サントリー登美の丘ワイナリー「技師長が語る特別ワイナリーツアー」でお土産として買ったワイン(昨年訪問時のブログ)。何か面白いワインはないかと売店を探して、2本買ったうちの1本。あと1本は樽甲州。今までサントリー登美の丘ワイナリーのワインをたくさん飲んだけれど、酸っぱいワイン好きのわたしとしては、ゆるく感じてしまうものが多い。わたしの好みと、ハウススタイルが違うみたい。そして日本ではマイナーなピノ・ノワールということで期待していなかったので、今まで1年弱放置状態になっていた。 Impression: 意外といっては失礼だけれど、おいしい!透明感のある色調。茎っぽい青い要素が印象的ながらも、けっしてイヤではなくポジティブに評価できるもの。また軽く熟成もあって少し柔らか。またピノ・ノワールという品種のせいか、登美の丘ワイナリーにしては酸もあるほう。今が少し熟成の入った飲み頃。将来的なポテンシャルではなく「今飲んだ点」では、今まで飲んだ登美の丘ワイナリーのワインではNo.1かもしれない。やっぱり熟成は大事。このワインのように特別醸造と書いてあるのは、原則ワイナリーだけで販売。またE-liquorで購入できる銘柄もあります。気が向いたら投票お願いします→
2008.06.27
コメント(2)
-

忘れていた2005プリムールが来てビックリ
最近驚いたことがある。それは2005年のボルドー・プリムールが入荷したので受け取り方法を指定してくれ、というメールが来たこと。2005年のプリムールはスキップしたつもりだったので「はてな?」と思ってしまった。プリムールを含め購入したワインはすべて表計算ソフトで管理しているのだけれども、どこにも記入がない。とはいえメールには、名前と注文番号が記載されているので、送り間違いではないはず。過去のメールを検索してみると注文履歴を発見!レフォール・ド・ラトゥールを6本注文しているではないか!完全に忘れていたのだ。そして4月にも入荷のメールが来ていた。今回は催促メールだったのだ。最近は記憶力が本当にやばい。記憶力がやばいのは心配だけれど、もうかったようでうれしいのも事実。購入価格は6本セットで\73,080。1本あたり\12,180。楽天で在庫のある最安値は\18,144で、最高値は\23,100。現在の価格はセカンドとは思えませぬ。\18,144 - \12,180 = \5,9641本あたりのもうけ\5,964 * 6 = \35,784トータルのもうけ\35,784 / \73,080 = 48.9 %利率投機目的で買ったわけじゃないので、具体的にもうかっていないけれど、たった2年で50%近い値上がりは異常。すぐに飲む予定はないので、そのままセラーに送っちゃいました。レ・フォール・ドゥ・ラトゥール[2005]年・メドック・グラン・クリュ・クラッセ・公式格付第1級...驚きつながりで紹介するのはマウントアダムのシャルドネ。これが予想外にうまかった。1988 Mountadam Chardonnayマウントアダム・シャルドネAustralia - 白辛口\4,000くらい, 松坂屋, 2000年2月購入Profile: 松坂屋のワインラックにこっそり隠れていたのを1本だけ発見。購入した2000年当時でさえ、88年のオーストラリアは珍しかった。当時は購買力max時期で、少しでも気になっていたのは買っていたし、ニューワールドにも手を出していた。当時も、怖いもの見たさで買った部分もあるのだけれど、長い間ストックするうちに、本当に怖くなってしまい、あけるタイミングを失っていた。外で飲んで帰ったとき、飲み足りなくて、ダメもとであけることにした。今は輸入されていないようだけれど、マウントアダムはたぶん中堅ワイナリー。 Impression: うーん、これがうまい。20年近く前のビンテージながら、酸化やへたる兆候は一切なく、きれいに熟成している。トロトロ。樽々ということもないし、酸が弱すぎることもない。ピュリニーと比べればおおらかではあるけれど、このくらいの酸度はブルゴーニュでもあり得る。偉大なワインではないのだけれど、熟成した柔らかいシャルドネ。そういえば2000年くらいに1979 Ch.Montelena Chardonnayを飲んだことがある。これもまったく期待していなかったのだけれども、おいしくいただきました。一般に短命と思われているニューワールドなんだけど、ある意味ブルゴーニュより平気じゃないかという部分もあって怖い。気が向いたら投票お願いします→
2008.06.26
コメント(6)
-

高幡不動で雨のあじさい
前回からの続き。昭和記念公園のついでに高幡不動の金剛寺へ。立川から多摩モノレールに乗って10分弱で到着。雨&夕方で、鎌倉とは違った雰囲気にはなったけれど、あじさいはやっぱり鎌倉だよね。気が向いたら投票お願いします→
2008.06.25
コメント(2)
-

昭和記念公園のあじさい&菖蒲
あじさいと菖蒲を見るために、立川の昭和記念公園へ行ってきた。この日は途中から雨が降ってきた。トカゲだ!ところどころであじさいが咲いているけれど、鎌倉と比べると見劣りがする。木に対して花の数が少なく、去年の花の残骸が残ってるところもあった。鎌倉は、選定など手入れをしているのか?菖蒲の湿地帯は2カ所ある。西立川口から近い、こちらのほうはピークを越えているし花が少ない。池にはオタマジャクシが大量にいた。道路の真ん中で寝るネコハーブ園ここから日本庭園日本庭園の菖蒲は見頃だし、花の数が多いそれにしても昭和記念公園は広い。L字型の変形とはいえ縦横それぞれ約2キロメートル。1周歩くだけでもいい散歩。この季節もいいけれど、昭和記念公園の真骨頂は秋だと思う。黄色に色づいたイチョウや紅葉したモミジは、目の覚めるような鮮やかさ。気が向いたら投票お願いします→
2008.06.24
コメント(2)
-

洗練されたフレンチ「オーボナクイユ」
駒沢にあるフレンチ「オーボナクイユ(Au Bon Accueil)」へ行ってきた。2007年11月にオープンした店で、以前から気になっていたところだ。駒沢は、自宅から近いわりには行かないのだけれど、フレンチの激戦区。老舗のラ・ターブル・ド・コンマなど、駅周辺だけでも5∼6店ひしめいている。三宿まで範囲を広げると、何倍にもなりそう。駒沢大学駅からは近いけれど、表通りの246から少し奥に入った、駒沢病院の裏にある。看板の手前の半地下。店内は、白を基調とした内装で、かなりおしゃれな雰囲気。雰囲気はビストロというよりはレストラン。テーブルには白いクロスがかかっている。席は18席だけれど、シェフ1人、アシスタント1人、サービス1人という体制なので、いっぱいまでは入れないようだ。予約の際、同じ時間帯にほかに2組いるので、料理が出るのが遅くなるかもしれないけれど大丈夫か、という旨をたずねられた。結局待たなかったのだけれどね。シェフは、フランスでの修行後、表参道のフレンチ「ブノワ」のオープンからかかわっていた方。ディナーはコースのみ。プリフィクス形式で、それぞれ2、3品のなかから選べるようになっている。一部追加料金のあるメニューもある。初めての訪問ということもあり、いろいろ試したいので\5,800のコースを注文。・\4,300(アミューズブーシュ・オードブル・メイン(魚or肉)・デザート、コーヒー)・\5,800(アミューズブーシュ・オードブル・魚料理・肉料理・デザート、コーヒー)ガスパチョ。横に添えてあるのがパテ・ド・カンパーニュアミューズの段階で、高級感を感じるよい店の予感。活きホタテのポワレ、そのジュ、ブールノワゼット(豚足、豚耳、レンズ豆の煮込み添え) 下には、豚足やいろいろなものが細かく切ってある。アイナメのポワレと焼き葱、レモン風味の焼き魚ソース松坂豚のロースト、そのジュ、新ジャガと新キャベツのソテー、マスタードの香り豚としてはギリギリ赤みが残ったちょうどいい火加減。クレームブリュレリーズナブルなお店ではよくあるデセールだけれど、少し高級感のある味。ハーブティーとシャンパントリュフ写真は撮らなかったけれどパンもおいしかった。自家製?ワイン編:ワインは赤と白で計40種類くらい。グラスは赤白泡1種類ずつ。フランス産が中心でニューワールドも少々。地域的な偏りはない。3千円台から1万2千円くらいまでが主要価格帯。赤はラトゥールの5万円弱まで。値付けは標準的もしくは安め。(低価格帯は)小売りプラス2千円くらい?2006 Cotes-de-Provence Rose(Chateau Farambert)コート・ド・プロヴァンス ロゼ(シャトー・ファランベール)最近は蒸し暑いってことでプロヴァンスのロゼを注文。抜栓当初は、少しアルコールの浮きが気になったけれど、時間がたつと一体感が出てきた。暑い時期、プロヴァンスのロゼは、広範囲な食事に合わせやすい。今回のメニューなら、これ1本でも問題なさそう。(シャトー・ファランベール)コート・ド・プロヴァンス ロゼ2006 Crozes-Hermitage Les Meysonniers(M.Chapoutier)クローズ・エルミタージュ・レ・メゾニエール(シャプティエ)さすがシャプティエさん、期待通りにおいしいです。若いかなと思って心配したけれど、なめらかでとがるところもなく、凝縮度もちょうどいい。今回のメインならば(豚、鴨、羊があった)、羊がよさそう。シャプティエCrozes-Hermitage Les Meysonniersクローズ・エルミタージュ・レ・メゾニエール2006まとめ:ひとことで表すと、5千円前後のフレンチとしてはとても洗練された店。おそらく、誰が食べても不満を持たないのではないだろうか。上品でそこそこ手の込んだプレゼンテーション、日本人には受け入れられやすい塩加減、女性でも食べきれる量、おいしいパン、シンプルながらも少し高級感のある食器。最近よく通っているオゥレギュームより高く評価する人は多いと思う。少し気になる点をいくつか挙げると、まずは料理のポーション。\4,300と\5,800のコースが、皿数の違いだけでポーションが違わないとしたら、\4,300のコースは小食の人向き。ワインを飲みながら楽しもうと思うと、オードブルとメインの\4,300のコースでは少ない。メニューはどのくらいで変わるのかわからないけれど、オードブルとメイン、それぞれ2、3種類しかないので選択肢は少ない。まあ、選択肢を増やしすぎて、クオリティやサービスを落としてもいけないので、このあたりは店のポリシーなのだけどね。また今回は待たなかったけれど、料理人が少ないので、込んでいる時間帯だと料理を待たされるかもしれない。とくに欠点らしい欠点が見あたらないだけに気になるのが「個性」。2皿構成ならばサリュー(恵比寿)のようにしっかりボリュームがあるとか、得意食材があってそれを売りにするとか、もっと値段が安いとか、もっとマニアックなワインの品揃えをしているとか、「この店に行きたい、この店でなきゃ」と思わせる特徴ができたら、さらによい店になると思う。クリーンヒット!総合評価:★★★+∼★★★★(メニューが変わったら訪問したい)味 :洗練されたおいしさサービス:ちゃんとしている雰囲気 :駒沢という立地を考えると、上品で高級感があるコストパフォーマンス:立地を考えると妥当か。都心と比べると安い。価格帯 :昼コース\1,900から、夜コース\4,300から。サービス料10%。---オーボナクイユ(Au Bon Accueil)東京都世田谷区駒沢 2-5-14 Kハウス駒沢B1TEL: 03-6661-3220http://aubonaccueil.jp/休: 水曜日、第3火曜日11:30-14:00 L.O, 18:00-21:30 L.O気が向いたら投票お願いします→
2008.06.23
コメント(8)
-

いつものカーヴ・デ・ヴィーニュ
ちょっと期間が空いたので、数ヶ月ぶりにカーヴ・デ・ヴィーニュに行ってきた。2006 Sancerre Les Charmes(Andre Vatan)サンセール・レ・シャルム(アンドレ・ヴァタン)ザ・サンセールとも言うべき、誰もがサンセールと考える味わい。すがすがしくて鮮烈。もう少し個性があってもいいように思うけれど、安定したおいしさ。2006 Alsace Pinot Noir(Gerard Schueller)アルザス・ピノ・ノワール(ジェラール・シュレール)\7,000以下のおすすめと聞いて出てきたのがこれ。06のシュレールが、もう出回っているとは。ポジティブな意味でのかすかな自然派香。細身のスタイルながらも、若いピノ・ノワールのおいしさを感じるワイン。キュヴェ・パティキュリエールやシャン・デ・ゾワゾーのような上のキュヴェとは差があるけれど、高くなってしまったブルゴーニュ・ルージュを飲むならこちらを選びたい。とはいっても、年々入手困難&高価になっているのが気がかりだけど。シュレールのピノ・ノワールを探す>2003 Cotes du Roussillon Villages Sarrat del Mas(Domaine des Soulanes)コート・デュ・ルーション・ヴィラージュ サラ・デル・マス(ドメーヌ・デ・スーラーヌ)しっかり&緻密な力強さ。アメリカンオークのような甘いニュアンス。このお店では最低価格帯ながらもしっかりとした作り。好みの分かれるワインだと思うけれど、低価格のワインでも、ちゃんとしているのはさすがのセレクション。料理編:料理はおまかせで頼むことが多いのだけれど、今回はアラカルトでチョイス。ブーダンノワール枝豆のムースとオマール海老のジュレ寄せ 値段のわりにポーションが小さい。また塩も強めか。牛肉のタルタル、アボカド、馬のたてがみ こちらは定番なだけにおいしい。また1枚だけ入っていた馬のたてがみも味わい深い。ナポリタン 邪道と思われるかもしれないけれどワインバーなので許して。ケチャップじゃなくてトマトソースのナポリタン。おいしいし、ボリュームもあるので、リーズナブルな会計にするには力強い味方。豚バラの重ね焼き 今回のようなしっかりしたワインと合わせるには都合がよい。ここに来て思うのはワインのセレクションの良さとコンディションの良さ。そして銀座のワインバーとしてはリーズナブルな値付けのワイン。料理にムラが無いわけじゃないけれど、長年食べていれば高いレベルで安定している。そういえば本店のマノワール・ダスティンは銀座6丁目に移転。また地下にあったアドリブは閉店し、評判の高かったシェフはビストロ・マリージェンヌへ移籍したとのこと。マリージェンヌは新しいシェフになってから、料理の評判がとても良いので行ってみたい。---カーヴ・デ・ヴィーニュ(Cave des Vignes)東京都中央区銀座4-13-15 セイワ銀座 B1F03-3549-6181休:日曜日気が向いたら投票お願いします→
2008.06.22
コメント(2)
-

初体験、コメダ珈琲店
名古屋発祥のコメダ珈琲店が東京にも進出したということで行ってきました。コメダ珈琲店は、ヴィニョーブル・ピータンさんのブログにもびたび登場するお店。関東のコメダ珈琲 一覧マップ今回行ったのは大田区にある下丸子FC店。下丸子駅のすぐ近くにあり、23区内の喫茶店としては珍しく、ファミレス並みの駐車場も完備している。アイスコーヒーミニ・シロノワール名物のシロノワール。入り口に置いてあった見本の大きさに躊躇し、ミニを注文。これでも十分大きい。ハンバーガースクランブルエッグトーストを注文したかったけれど、その大きさに断念。ハンバーガーもバンズは大きい。こちらにメニューの一部が載っている。食事メニューがけっこう充実しているのが東京の珈琲屋と違うところ。今回行ったお店はフライ系が充実していた。こんど行くときは、ほかのメニューもチャレンジしたい。気が向いたら投票お願いします→
2008.06.21
コメント(12)
-

ワイン会の番外編:生物学の話
先日のワイン会の終盤は、薬学関係者が多かったこともあって、薬やサプリの話になってしまった。薬学→生物学から思い出したのは、福岡伸一氏の「生物と無生物のあいだ」。この分野では異例の40万部の大ベストセラー。生物と無生物の違いは何かという切り口から、DNAの発見に関する生物学の歴史、最先端の分子生物学まで、難解な内容でありながら著者の卓越した文章力で読みやすく仕上がっている。生物と無生物のあいだこの本を読むきっかけは、NHKで放映されている「爆笑問題のニッポンの教養」で福岡氏の話に衝撃を受けたこと。とくにシェーンハイマーが解き明かした動的平衡という仕組みには驚いた。簡単に説明すると、識別可能な分子(重窒素)を含むエサを大人のネズミに与えて、これがどのように移動するかを調べてみた。シェーンハイマー自身、エサの多くはエネルギーとして燃やされるだろうと考えていた。ところが調べてみると、識別可能な分子はネズミの体中に広がっていて、頭のてっぺんからしっぽの先までまんべんなく行き渡っていた。実験を数日間続けても、体重は1グラムも増えていない。食べたものが全身に広がっているにもかかわらずである。つまり、もともとあった分子は分解されて、新しい分子につねに置き換わっているということが、この実験によってわかったのだ。人は生きていると排泄物や垢が出るように、細胞単位での生死はつねに起きていると理解していた。ところが生きた細胞のままでも、分子レベルでの入れ替わりが絶えず起きているのは驚きだった。福岡氏は番組のなかで、動的平衡について次のように言っていた。「去年の私と今年の私は、同じ私のように見えても、分子のレベルではすっかりおかわりありまくりなわけですよね」うーむ。深い。それと並んで驚いたのはコラーゲンのうそ。コラーゲンを含むものを食べると肌がきれいになると思われているけれど、科学的に証明されているとは言い難いらしい。なぜならばタンパク質の一種であるコラーゲンは、アミノ酸レベルまで分解されて吸収されるので、それが人のなかでコラーゲンになる保証もないし、全身に行き渡るので、目的の部位に届く保証もない。コラーゲンを含む化粧品もあるけれど、多くは保湿剤としての目的で利用している。結局、タンパク質を含む食品をバランスよく取ればいいらしい。ひー!美容・健康に関しては、エセ科学もしくはエセ科学扱いされているものが少なくない。興味のある方は検索してみてね。マイナスイオン、デトックス、ゲルマニウムの効用、セルライト、etcマイナスイオンは認知度の高い言葉であるけれども、現在の景品表示法では商品の効能の説明に使うことは禁止されている。以前、大手電機メーカーでマイナスイオンを名乗る製品がいくつかあったけれど、現在は完全に廃止されている。弱小メーカーでは現在でもたびたび使っているけれど、ときおり公正取引委員会に摘発されている。NHK「爆笑問題のニッポンの教養」はおすすめ。「ハゲタカ」などの土曜ドラマ、NHKスペシャルなど、NHKには大人の鑑賞に堪えうる良質な番組が多い。こちらも福岡伸一氏の本。「生物と無生物のあいだ」を読んだ勢いで、こちらも読んでしまいました。BSE騒ぎは一段落したけれど、なかなか興味深い本でした「もやしもん」を読んだときも思ったけれど、化学的素養の決定的な欠如を感じるなあ。高校生の化学を、もう一度勉強したい。このあたりの本に興味あり。高校で教わりたかった化学気が向いたら投票お願いします→
2008.06.20
コメント(9)
-

青山某所でワイン会
今回はいつものメンバーに加えて、シャムーさんやshinakunさん、JIL@谷口さんなど初対面の方々などなど。飲んだワインは以下のとおり。NV Jerome Prevost La Closerieジェローム・プレヴォー ラ・クロズリー少し熟成香があってドライな仕上がり。今までけっこう飲んでいるのだけれど、世間の評判ほど好きなタイプではない。でも時間がたつと甘いよい香りがして終盤はよかった。2006 キャネー甲州 万力山(金井醸造)2007 キャネー甲州 万力山(金井醸造)シャムーさんらしい「やさしい味わい」なセレクション。一部では熱狂的なファンがいる金井醸造。ショップで見ないので直販主体なのだろうか。抜栓してすぐは冷たかったこともあり香りが立たなかったけれど、時間がたつと独特の香りがしてきた。一般的に想像する甲州とは違って、誰かが言っていたけれど「ロワールの自然派」っぽいスタイル。きんきんに冷やさず、ゆっくり温度を上げながら、ゆっくり楽しむのがよいのかもしれない。1997 Puligny-Montrachet 1er Cru Les Demoiselles(Guy Amiot)ピュリニー・モンラッシェ プルミエ・クリュ レ・ドモワゼル(ギィ・アミオ)レ・ドモワゼルは、ギィ・アミオのなかでは看板畑の一つ。おいしくはあったのだけれど、あまり印象に残らず。2005 Gevrey-Chambertin(Armand Rousseau)ジュヴレ・シャンベルタン(アルマン・ルソー)ガチガチというわけじゃないけれど、若いなー。2002 Echezeaux(Christian Clerget)エシェゾー(クリスチャン・クレルジェ)2002 Echezeaux(Domaine des Perdrix)エシェゾー(ドメーヌ・デ・ペルドリ)hidepxさんと02エシェゾー対決。hidepxさんがクレルジェで、わたしがペルドリ。ペルドリは96から毎年飲んでいる銘柄。クレルジェは美しいスタイル。なめらかで今飲んでも十分おいしい。ペルドリは抜栓してすぐは微妙な香り。スワリングすると飛んで一安心。でも味わいはタニックで粗さが目立つ。いま開けるべきじゃなかったし、クレルジェに完敗。久しく続いた連勝街道もいったん停止。2000 Chambolle-Musigny 1er Cru Les Aoureuses(J.F.Mugnier)シャンボール・ミュジニ― プルミエ・クリュ レザムルーズ(ジャック・フレデリック・ミュニエ)2004 Morey-St-Denis 1er Cru Clos Sorbes(Jacky Truchot)モレ・サン・ドニ プルミエ・クリュ クロ・ソルベ(ジャッキー・トルショー)ミュニエもトルショーも、それぞれのドメーヌスタイルらしく、やさしく美しい味わい。ミュニエのアムルーズには、もっと期待する部分もあったけれど爆発するまでにはいたらず。でも、いいワインですよ。当たり前か。まとめ今回、驚くようなワインには出会えなかったけれど、クレルジェ、ミュニエ、トルショーが、わたしのトップグループ。飲み頃の問題もあるけれど、ほかのワインとは差があるように感じた。席が離れていて、ほとんど話すことができなかったかたもいて残念だけれど、みなさんありがとうございました。気が向いたら投票お願いします→
2008.06.19
コメント(10)
-

ブログワイン会 赤編
昨日の白編に続いて赤編。1969 Fleurie(???)フルーリー撮った写真がピンぼけで造り手を判読できず。タスト・ヴィナージュのワイン。抜栓当初は、そのヒネた香りに「うーん」と思ったのだけれど、時間がたつほどにその嫌な香りは飛んだ。褐色がかっていながらもしっかりした色調で、40年前のボージョレとしてはしっかりしている。酸の弱さにガメイの片鱗を感じるけれど、このようなオールドビンテージにあれこれ言うのも野暮というもの。これだけ生きながらえたことに感謝したい。写真は白編で掲載1986 Volnay 1er Cru Mitans(Hubert de Montille)ヴォルネイ・プルミエ・クリュ・ミタン(ユベール・ド・モンティーユ)数年前にわたしも飲んでいるワイン。中庸なスケールの中庸な古酒。個人的にはなかなか好み。コンディションも上々。ほかのワインと比べて個性に乏しかったため、ガツンとした印象はないのだけれど、赤がこれ1本だけだったら、もっと違う評価になったと思う。前回飲んだボトルはもっと熟成感があったような気がする。モンティーユのミタンを探す>1995 Gevrey-Chabertin 1er Cru Clos St Jacques(Fourrier)ジュヴレ・シャンベルタン プルミエ・クリュ クロ・サン・ジャック(フーリエ)うーん、若い。白のクロ・デ・ムーシュほどでないにしても、またタンニンもあって熟成途上の雰囲気。数年後に飲んでみたい。それにしてもフーリエの95を持ってるなんてhirozeauxさんすごい。フーリエのクロ・サン・ジャックを探す>1997 Clos de la Roche(Hubert Lignier)クロ・ド・ラ・ロッシュ(ユベール・リニエ)抜栓当初は、かすかに微発泡が気になったけれど、時間がたってからはよかった。透明感のある色調で、なめらかで、香り高く、余韻も長い。グレートビンテージのようなスケールはないけれど、今飲んでおいしいし、ピークの一つだと思う。もう少し艶っぽさがあれば完璧。いちおう今日のベスト。ユベール・リニエのクロ・ド・ラ・ロッシュを探す>楽天だと04で3万円超。この97は1万円以下で買えたのに。1988 Chateauneuf-du-Pape Reserve(Chateau Rayas)シャトーヌフ・デュ・パプ・リザーブ(シャトー・ラヤス)erobertparker.com調べで$500-$600の高額ワインだけに期待は高まる。飲んでみると、まだ熟成途上。若々しいとは言わないまでも、熟成した古酒という領域ではない。ローヌは好きなのだけれど、個人的に苦手な香りがあったため微妙な評価。すみません。ラヤスのシャトーヌフ・デュ・パプを探す>まとめ最近のワイン会―――コシュ・デュリの04ムルソーやルロワの04ACブル―――のように、圧倒的な差はなかったけれど、ベストを選ぶとすれば、リニエのクロ・ド・ラ・ロッシュ。自画自賛のようですみません。続いてラモネのビアンヴィニュ。残りは混戦。料理はたくさん出たなかから1品だけ紹介。このお店は3度目の訪問で、この鴨は2度目。この鴨は都内でトップクラスの素晴らしさ。また料理全体も、3回目の訪問で最高の満足度。コースが1万円前後の店としては都内屈指の素晴らしい店だと思う。鴨のローストいつもみなさんありがとうございました。気が向いたら投票お願いします→
2008.06.18
コメント(6)
-

ブログワイン会 白編
今回は楽天ブログの方々と都内某フレンチでワイン会。飲んだ順番は写真とちょっと違うけど白編から。一番右のヴォルネイは次回紹介予定。今回はシンプルコメントで。NV Gosset-Brabant Grand Cru Brutゴセ・ブラバン グラン・クリュ ブリュットまずはお店の泡でスタート。アイらしい適度な力強さでバランスが良い。1986 Puligny-Montrachet Truffieres(Louis Latour)ピュリニー・モンラッシェ トリュフィエール(ルイ・ラトゥール)hidepxさんのワイン。大丈夫なかたもいたようだけれど、個人的にはイケてない。ピークアウト。1996 Beaune Clos des Mouches Blanc(Joseph Drouhin)ボーヌ・クロ・デ・ムーシュ・ブラン(ジョセフ・ドルーアン)ドルーアンの看板畑の一つ。96とは思えないほど若々しい。きりっとしたシャープなスタイル。ボーヌ・ブランを飲む機会は少ないけれど、コルシャルやペルナンなどの北っぽい味わい。ドルーアンのクロ・デ・ムーシュを探す>2004 Bienvenue Batard-Montrachet(Ramonet)ビアンヴィニュ・バタール・モンラッシェ(ラモネ)さすがの貫禄。心地よいオークの香り。シュヴァリエやバタールとくらべるとボディに差を感じるけれど、この魅惑的な香りは好印象。真の飲み頃はまだ先だけれど、今飲んでもおいしい。正直なところヴィアンヴィニュのような低地のグランクリュは、何か邪道なような気がして自分では手を出さないのだけれど(koichiさん、すみません)、ラモネだけにしっかり作ってます。ラモネのビアンヴィニュを探す>赤編に続く。気が向いたら投票お願いします→
2008.06.17
コメント(6)
-

「もやしもん」知ってますか?
「もやしもん」は、「イブニング」で連載中の石川雅之の漫画。菌やウィルスがみえる主人公の農業大学生活を描いている。もちろんフィクション。タイトルの「もやし」とは、酒造りなどに使う種麹のこと。先日、手塚治虫文化賞大賞を受賞したのを新聞で見て気になっていた。またワイン友達から「ワインのことも書いてあっても面白い」と聞いていた。ワインのことは、5巻と6巻にけっこう出てくる。全巻読んだ感想は「面白い」。醸造の話もけっこう出てくるので、日本酒やワイン好きにはとくにおすすめ。農大に通いたくなってしまった。かもすぞー!気が向いたら投票お願いします→
2008.06.16
コメント(2)
-

2008年 鎌倉あじさい紀行 Part2
前回からの続きで、今回は後編。長谷寺、光則寺、御霊神社の三カ所を見たところでおなかがすいてきた。ランチのために鎌倉駅へ移動しようと思ったのだけど、地図を見ると成就院が近いので行ってみることにした。成就院は、長谷近辺では長谷寺と並ぶあじさいの名所。ここが大ヒット。今回はあきらめていたのに、まさにピーク。また長谷寺ほどの急斜面ではないため、花に元気がある。鎌倉駅に戻って、若宮大路や小町通りを歩きながらランチのお店を探索。若宮大路には、ものすごく古いたたずまいの酒屋があった11時過ぎに着いたときには、それほど込んでいなかったのだけれど、時間が経つほどに込んでいく。いつまでも迷っていると、さらに込んでしまうということで、小町通りの「和彩 八倉」へ。しらす丼 \1,380たっぷりのしらす\1,380という値段には評価が分かれると思うけれど、観光地であることを考えると、まあまあかな。ビールを飲んでおなかいっぱいになると、これ以上観光するのが面倒になってしまった。それでもレンタル自転車を借りようと元気を振り絞ったら、どこもすべて貸し出していて在庫無し。ドテッ!さらには小町通りの劇込み具合を見ているうちにすっかり戦意喪失。夜は飲み会もあるってことで、早々に退散。成就院が印象に残る旅だった。おわり。Part1へ戻る。気が向いたら投票お願いします→
2008.06.15
コメント(4)
-

2008年 鎌倉あじさい紀行 Part1
あじさいを見るために今年も鎌倉に行ってきた(昨年訪問時のブログ)。この季節はとても込んでいるので、朝8時には着きたいと思っていたのだけれど、思いっきり寝坊。現地に着いたのは9時だった。まずは長谷寺へ。鎌倉では明月院と並ぶあじさいで知られたお寺。遅い時間になると、何十分待ち、何時間待ちになることも珍しくない。ここは早い時間に行くに限る。あじさいは山道沿いの斜面に植えられている。日当たりがいいため、鎌倉のなかでは比較的早め。写真だとわかりづらいけれど、最近の天気続きで花に元気がない。日当たりがいいのと、斜面で水はけがいいためだろうか。和み地蔵こちらは入り口付近にあった鉢植えのもの 見ごろはこれからだけど、鉢植えのほうがしっかり水をあげているためか元気が良い。続いて、おとなりの光則寺へ。こちらは花の寺として知られている。境内にはさまざまな花や草木が植えられている。奥に続く道を進んでいくと、そこにはかつて僧侶を幽閉していた土牢があった。うさぎ草 小指の爪の半分くらいのとても小さな花。次も、また近くの御霊神社へ。長谷寺のとなりにある隠れた名所。境内の横を江ノ電が通るので有名。線路沿いには、あじさいとのショットを狙うカメラマンがたくさんいる。まだ早い長谷寺のとなりにあるにもかかわらず、日当たりが悪いため、こちらはまだ咲いていないものも多い。昨年(6/24)来たときは、子供の頭の大きさくらいの見事なあじさいがあったのに残念。今回のハイライトは次回で紹介する成就院。Part2へ続く。気が向いたら投票お願いします→
2008.06.14
コメント(4)
-

久しぶりの焼き肉屋「ら、ぼぅふ」
地元の用賀近辺では評判の高い焼き肉屋「ら、ぼぅふ」に行ってきた。駅から徒歩15分くらいと、アクセスが悪いにもかかわらず、遠方からも来る人が多い有名店。食肉卸問屋直営のお店で、上質の和牛をリーズナブルに楽しめるという評判。用賀に8年住んでいるのに今回が初訪問。ここは予約ができず、店内にあるノートに名前を書いて順番待ちをする。ものすごく待つといううわさも聞いていたけれど、2組待ちだったため並ぶことにした。今回は30分弱で入店。梅パッチョ 見た目がいいので注文したけど、締まりのない味。らぼうふサラダほかにもたくさん食べたけれど特選ものだけを紹介。普通のグレードの肉も、だいたい一皿4,5枚。特選牛冊焼特選ロースさすがに特選は素晴らしい。しっかり厚みがあるのも好印象。とはいえ、普通のグレードとは3倍近く値段が違うので悩ましい。普通のグレードや上などをメインにして、特選を少々というのが賢い注文方法なのかもしれない。結局1人ビール2,3杯と、そこそこいっぱい食べて1人約7千円。焼き肉屋にはめったに行かないので相場観がわからないけれど、思っていたより使ってしまった。でも叙々苑などの有名店で特選は5千円以上するので(今回は2千円くらい)、そういう意味ではリーズナブル。ここは絶対額としてリーズナブルな店ではなく、良質な肉が、その品質と比べてリーズナブルに食べられる店なのだと思う。でも、フレンチなどの手間のかかった料理をよく食べていると、ホールスタッフはほとんどバイト、料理は切って出すだけのものがほとんど、という店にはあまり魅力を感じないんだよね。たまには来てもいいけど。完全な主観でごめんなさい。---La Bouef(ら、ぼぅふ)http://www.la-bouef.com/東京都世田谷区中町5-21-8TEL 03-5707-0291気が向いたら投票お願いします→
2008.06.13
コメント(0)
-

ヴァンピックル丸の内、ふたたび
先日ランチ飲み会で訪問して印象のよかったヴァンピックル丸の内(そのときのブログ)。こんどはディナーで訪問してきた。今回はおまかせコース(\4,200)を注文。電殺名人“岸氏”の豚ハツ?尾長鯛のグリルフォアグラ地鶏 表面はパリパリで絶妙の火入れ〆の焼きおにぎり ハート型プリン飲んだワインは以下のとおり。2006 Beaujolais Blanc(Maison Bonnay)ボージョレ・ブラン(メゾン・ボネイ)遅れて行ったためブラインドで提供。ロワールほどの酸はなく、ミネラル豊か。ボーヌの白のような魅惑的なふくよかさはない。岩のような、人にこびない雰囲気はローヌっぽさもあるけれど、ローヌにしてはボディが細い。暑い年のシャブリっぽい雰囲気もある。結局ボージョレの白。こんなの当たるわけない。いぢわる!ミネラル豊かでなかなかおいしいワイン。ボージョレの白は経験が少なすぎて比較できないけれど、あとで思い出したのは、サヴィニーの白。もう少し軽やかだけど雰囲気は似ている。2006 Macon Rouge Les Vignes de Dom Samoel(Combier)マコン・ルージュ レ・ヴィーニュ・ド・ドン・サモエル(コンビエ)こんどはマコンの赤。ボージョレに続き、ちょうど似たような生産地域で、マイナーな方を選択してしまった。こちらは果実味豊かでチャーミング。ガメイが入っているような気もするけど、典型的なガメイっぽさはない。フレッシュなうちに飲みたいピチピチしたワイン。2002 Bourgogne Hautes Cotes de Nuits(Glantenet)ブルゴーニュ・オート・コート・ド・ニュイ(グラントネ)これはなかなかおいしい掘り出し物。軽く熟成が入って透明感も味わいもあるピノ。調べてみるとドミニク・ローランにブドウを提供しているヴォルネイのドメーヌらしい。楽天で調べるとヴォルネイが5千円くらいで、ACブルが3千円。それだったらヴォルネイかな。グラントネのワインを探す>今回のワインは3本ともおいしかった。3人で3本飲んで1人約1万円。ワインは十分おいしいし、料理の味も量も満足。塩が強いと思う人もいるかもしれないけれど、グリル系は塩をきかせた方がおいしいと思うので、これでよし。繁盛店なので、事前予約は必須。気が向いたら投票お願いします→
2008.06.12
コメント(12)
-

歌舞伎町の立ち飲みフレンチ「プロヴァンサル」
新宿歌舞伎町の立ち飲みフレンチ「プロヴァンサル」に行ってきた。ここは前々から行きたいと思っていたお店。歌舞伎町といっても広いけれど、ちょうど西武新宿駅の前で、新大久保と新宿の中間地点。この写真以外はすべて携帯画像店内には、テーブル代わりの酒樽とカウンターがある。料理は黒板に書いてあり、\300∼\1,500くらい。一番多いのは\800前後。牛すじと牛胃袋の煮込み(左手前) この煮込みは量もそこそこあり、おいしい。グリーンアスパラ地鶏の白レバーとキンカン 柔らかい白レバーと、半生のキンカン。お店のスペシャリテ立ち飲みとしては十分おいしい。写真に撮ったもの以外もいろいろ食べたけれど、肉系のほうがおいしいものが多いと感じた。みんな小皿でポーションは大きくない。ワインは3千円から5千円くらい。ニューワールドやヴァン・ド・ペイなどが主体で、知っている造り手のものがほとんど無い。相当なワイン通でも、飲んだことのあるワインは少ないのではないだろうか。ワインの金額は安いけれど、値付け自体は「立ち飲み」から想像するよりも高い。小売りの3倍以上か? 地域で選ぼうとも思ったけれど、わからないワインが多いので、ソムリエに「軽めのボディでいいので、香りの良いもの」とリクエストして出てきたのがこれ。ロワールのフランは好きなものが多いので、そのまま注文。2001 Saint Nicolas de Bourgueil Les Perruches(Domaine de la Cotelleraie)サン・ニコラ・ド・ブルグイユ レ・ペルーシェ(コテルレ)Loire, France - 赤辛口やや高めの温度だったけれど、軽やかで果実味があって、まあまあおいしい。とりあえず安心。まとめ:ワインの値付けが意外に高かったのは、ワイン好きとして残念だけれど、グラスワインも赤白泡、数種類ずつあり、仕事帰りや映画の帰りなどに軽く引っかけるには都合がよい。根強い固定ファンがいる店だけれど、個人的には、ガッツリ食べるのではなく軽く飲んでつまみたいときに。---プロヴァンサル(Provencale)東京都新宿区歌舞伎町2-45-7 大喜ビル1Fhttp://www.provencale.co.jp/気が向いたら投票お願いします→
2008.06.11
コメント(4)
-

ユベール・リニエで予習のハズが...
家でも順調にワインを飲んでいるのだけれど、ほかのことばかり書いていて紹介していないものが多い。まあ、どうしても紹介したいというほど、すごいのに出会ってないってのも理由なんだけどね。でもブログに書かないと、味の記憶がすぐに薄れてしまうような気がする。備忘録としてでも書くべきか?週末にリニエのクロ・ド・ラ・ロッシュを飲むので、予習にと取り出したのがこれ。1999 Bourgogne Rouge(Hubert Lignier)ブルゴーニュ・ルージュ(ユベール・リニエ)Bourgogne, France - 赤辛口\2,500くらい, ワインセラーウメムラ, 2002年3月購入Impression: うーん、ふつう。凝縮感があるわけでもなく、熟成感があるわけでもない。かといって、若いときのフレッシュさもない。ACブルに大きな期待をかけちゃいけないけど、「99のリニエ」から想像すると、小ぶりなワイン。若いうちに飲んでしまえばよかった。99とはいえ、ACブルで予習なんて考えが甘かった。モレのプルミエを開ければよかったか。気が向いたら投票お願いします→
2008.06.10
コメント(4)
-

平成の名水百選:落合川&南沢湧水群
先日、環境省から発表された「平成の名水百選」に、唯一都内から選ばれた東久留米市の落合川と南沢湧水群というニュースを見て、さっそく行ってきた。・落合川と南沢湧水群 平成の名水百選に(読売オンライン)・「平成の名水百選」プレスリリース(環境省)昭和60年の「名水百選」に加えての選定らしい。環境省の水環境サイトを見ると「名水百選」には、昨年訪れた国分寺のお鷹の道が選ばれている。たしかにお鷹の道もきれいだしね(07年訪問時のブログ)。落合川に行こうとして最初に思ったのは、「東久留米ってどこ?」東京育ちなので、なんとなくはわかっているものの、実際にはどこかわからなかった。調べてみると練馬区の西側で、三鷹から北に7キロくらい。自転車で行くには最適だと思い、ひとっ走りしてきた。Webで調べてもあまり情報がないので、とりあえずは東久留米の駅前へ行くことにした。駅前には周辺の観光案内パネルがあった。どうやら黒目川と落合川の両方がきれいで、今回選定された落合川には、湧水群があるらしいことがわかった。それが今回の選定対象にもなった南沢湧水群。こちらは黒目川 目黒川じゃなくて黒目川。落合川より立派で、川の両側には遊歩道が整備されている。続いて駅前のパネルで知った竹林公園へ。こちらは落合川の近くにある。公園の奥には小川が流れている。ホタルが住んでいそうなきれいさ。ここが源流部分あからさまにわき出しているような雰囲気はないけれど、ここが小川の始まり。このような湧水がたくさんあり、落合川に流れ込んでいる。公園の違う出口にはコース案内があった。今回はこのルートを採用。こちらが落合川 水がきれいなためか、川に入って遊んでいる姿が目につく。鴨もけっこういて、一生懸命水草や底の石をつついていた。氷川神社南沢緑地こちらは雑木林こちらも小川奥に行くと湿地帯があり「東京の名湧水57選」の看板があった。「東京の名湧水57選」のページにはガイドブック(PDF)も載っているので興味のある方はどうぞ。あじさいは、もう少しい色づけば完璧さっきの看板に載っていたコースはまだ残っているのだけれど、主要なところはまわったということで切り上げ。本日の走行距離は約50キロ。最近はどこに行っても50キロくらいの時が多い。これといったハイライトはなく、また個人的な趣味は秋川渓谷や奥多摩なのだけれど、都心からも近く、駅からも近い場所なのに、これだけきれいな川があるのはすごい。それにしても東京は奥が深い。気が向いたら投票お願いします→
2008.06.09
コメント(4)
-

2008年初夏 サントリー登美の丘ワイナリーに行ってきた Part2
前回からの続き。ランチのあとは展示ホールでワイナリーの説明。ここにはワイナリーの歴史が書かれたボードやジオラマなどが展示されている。超高価な白と赤(カベルネ・フラン)の貴腐ステンレスタンク。またの名をイノックス 室内はホワイトバランスが合いづらい。いっそのことRAWで撮ろうとも考えたけれど、面倒になって断念。今の時期は醸造施設を使っていないので軽やかに見学してセラーへ。昨年訪問したときは収穫期だったので、除梗・破砕、ステンレスタンク、瓶詰めなども説明してます(1, 2)。セラーには空調が入っていてすごく寒いこちらはカベルネ・ソーヴィニョンのセニエ樽から抜き出したものなので飲み頃とは言えないけれど、セニエというイメージよりも力強く、また想像していたよりおいしい。87年のオリを見るためにライトでかざしてくれたセラー内のテイスティングルームで、テイスティング開始。1. 樽醗酵 甲州 2005 / \3,1572. 登美の丘(白)2005 / \3,1673. 登美(白)2005 / \10,5004. 登美の丘(赤)2005 / \3,1675. 登美(赤)2004 / \12,6006. 特別瓶熟品 カベルネ・ソーヴィニョン 1987 / 非売品1と3は樽醗酵・樽熟成。2はステンレスタンク醗酵・樽熟成。樽醗酵させると、その発酵過程で樽の内面に膜ができるので、ステンレスタンク醗酵・樽熟成のものとは違う香りになる。たしかに1と3には共通の香りがある。簡単にコメント。テイスティングでも飲む派なので自信なし!1. 柔らかい樽香。熟した柑橘類。トロピカルフルーツ。千円台の典型的な甲州と比べると、その樽香に違和感を持つけれど、そう思わなければいいワイン。個人的な好みとは少しずれるのだけれど、売店で買った人が多いのも納得できる味わい。2. 去年まったく同じワインを飲んでいるのに印象が違う。1,3が柔らかい樽香なのに対し、こちらは焦げっぽい。1,3のほうが好きだったこともあり印象が薄い。3. グラスに注いだ当初はクローズしていたけれど、温度が上がるとともに厚みが増してくる。柔らかな樽香が印象的で、模範的中庸さ。Bar10さんのお気に入り。4. ピーマンの青さ。スパイシー。それほど高く無いボルドースタイルの典型的なワイン。若いけれど、それなりにバランスはよい。5. 今日の主役04の登美。04はグレートビンテージらしい。エレガンスで、すくっと立つ品の良さ。しいて例えれば、昔のやさしいころのラフィット。ボルドーの上級シャトーが持つ凄みはないのだけれど、このワイナリーのスタイルを知ると、これでもいいのかなと思えてくる。6. こちらは非売品の87カベルネ。わずかに酸化したニュアンスがあるけれど、まだタンニンも残っていて寿命はある。栽培・醸造技術の進歩のせいか、新しいもののほうが良くできているように感じた。---ヨーロッパのワインと比べると「酸はおとなしくて凝縮感は中程度」というのは前回と変わらない共通した印象。昨年来たときは、サントリーのワインをこれだけ同時に飲むのは初めてだったので、フランスワインと比較してしまい、少しがっかりした部分もあった。今回はスタイルを知ったうえで飲んでいるためか、昨年よりもおいしく感じた。世界を基準としてワインを評価してしまうと、CPも含めて発展途上の部分はあるけれど、「目指しているのは日本の食卓に合うワイン」というワイナリーの方針を聞いてしまうと、一概にどうこう言うのは難しい。個人的な好みを言えば、白については樽を使わない種類をもっと増やしてほしい。04の登美は熟成させたものを飲んでみたい。とはいえ、1万円以上する国産ワインには手を出しづらいのだけど...。登美・赤[2004]年・特別醸造限定品・サントリー登美の丘ワイナリー・限定品・ワイナリー元詰・...セラーの出口付近にあったワインボトルのシャンデリア続いて、レストランのある頂上に戻り懇親会。ここでは新たなアイテムと、先ほどのテイスティングで出てきた残りのワインが登場。テイスティングで、まったく吐かずなかったため、すでにほろ酔い加減。7. 萌黄台園 2002 / \5,2678. 眺富台園 2004 / \5,2679. 塩尻ワイナリー 信州メルロ 2004 / \3,1577は小樽熟成のソーヴィニョン・ブラン。今回の白は樽がきいているのが多い。このくらいのボディならば、小樽を使わないスタイルのほうが好み。8はカベルネ・フラン。フランにしては青さが少なくグレートビンテージらしい仕上がり。値段の良しあしは別として、なかなかおいしいワイン。カツのせいで、この時点でおなかいっぱいなのだけれど、もうちょっと料理らしいものもつまみたかったかな。欲張り過ぎか(笑)?ほかの人とあまり話すことができずに、あっという間に懇親会は終了。スケジュールがぎっしりだと、あっという間に終わってしまう。途中抜け出して、Bar10さんと貴腐ワインを飲んできました。行きと違って、帰りは順調で19時30分には到着。夜の新宿バスで充電したこともあり、このあと飲みに行くのであった(笑)。ワイナリーの方々、スタッフの方々、今回はこのような機会をありがとうございました。とても楽しく過ごせました。前回同様スケジュールがタイトで忙しかったので、あれほど渋滞するなら8時出発でもいいですね。(おわり)サントリーの公式ブログから、ほかの参加者のブログをたどれます。ワイナリーでしか売っていないような限定ワインはE-liquorで購入できます。気が向いたら投票お願いします→
2008.06.08
コメント(4)
-

2008年初夏 サントリー登美の丘ワイナリーに行ってきた Part1
先日のブログで紹介した「技師長が語る特別ワイナリーツアー 08夏篇」のブロガー限定イベントに当選し、この週末に行ってきた。昨年の秋に続き2回目の参加。最近天気がよくないけれど、この日はくもり。雨じゃなくて一安心。集合場所の新宿に行ってみるとshuz1127さんとBar10さんがいた! shuz1127さんとは初対面。このイベントは、この夏の6月と7月に開催される「技師長が語る特別ワイナリーツアー 08夏篇」の、プレビューイベントとして企画されたもの。今回紹介する内容と通常開催では、以下の違いがあるのでご了承を。・新宿から送迎バス付き・所長の大川氏による説明(通常は必ずしも大川氏とは限らない)・ランチと懇親会付き・非公開エリアへの入場・ツアー代金\2,000は無料昨年と重複している内容もあるので、違う部分を中心に書こうと思う。興味のある方は、昨年秋に訪問したときの様子も見てね。昨年同様、今年もまた渋滞。11時30分に到着予定が12時30分に到着。昨年はワイン造りの古いVTRが流れていたけれど、今回は無し。あの内容ならば、たしかに不要かも。「登美の丘ワイナリー」というように、ワイナリーは丘というか小山の上にある。標高は800m。ブルゴーニュと比べてもだいぶ高い。ワイナリーのゲートを超え、頂上に行くまではけっこうな急坂。昔は蒸気バス(機関車?)を使っていたので登坂力が弱く、その名残としてスイッチバックが残っている。スイッチバック地点 バスのなかから撮影したのでガラスが反射してる。頂上の展望台から畑を眺める大川所長昨年、大川所長の熱さに触れていたので、前回ほどの驚きは感じないけれど、しゃべり出すと話が止まらない。手にしているのは、咲いている花をみせるために持ってきたシャルドネ(?)の枝。カベルネ・ソーヴィニョンメルロー 樹齢5年ということで、カベルネと比べるとずいぶん細い。苗を植えてブドウを収穫できるのは3年目から。そしてワインに使える品質になるのは5年目から。一般に樹齢が高いほど良いと思われているけれど、必ずしもよい面だけではない。第一には、樹齢が高くなりすぎると収穫量が減るので経済合理性が低くなる(つまり高価になってしまう)。またブドウの栄養は根から取るだけでなく、葉っぱの光合成によるものもあるので、葉と実のバランスも重要とのこと。「高樹齢=高品質」とは限らないことについては、堀賢一氏がどこかで書いているのを見たことがある。出典を見つけることができなかったけれど、76年のパリ対決で一位になったスタッグスリープの樹齢は若かったとか。また土壌とブドウの味わいの関係については、これも勘違いの多い分野。たとえばカルシウムの多い土壌はカルシウムの味がするというのは間違い。ブドウにとってカルシウムは栄養取得を阻害する物質なので、カルシウムが多い土壌ではブドウの木ががんばり、よいブドウになるらしい。堀賢一氏も「ワインの個性」などで、土壌の科学的組成とワインの味わいに明確な相関関係は見つかっていないと書いていたっけ。もちろん、水はけのよい土壌のほうがよいブドウができるという相関関係はあるのだけれど、土の成分とブドウの成分の相関関係は解明されていないという話。カベルネ・ソーヴィニョン 実がなっていないときは房が上向きメルローの花 黄色くて小さいのが花1つの房でも同時に咲くことは少なくて、部分ごとに徐々に咲くらしい。花が咲いている期間は3日から1週間くらい。当然、畑や品種によって咲く時期も違う。畑をあとにしてレストランへ。レストラン前のテラスからの眺望「登美の丘」は、ワイナリー設立前からの地名で、登ると美しい眺めであることからついたとのこと。こちらのレストランでランチ。ウッディーな雰囲気で天井が高いランチで出たワイン千円台なかばの、ノンビンテージのデイリークラスのワイン。とくにどうこう言うワインではないけれど、上のクラスのように樽をきかせているわけではないので、ニュートラルで食事とは合わせやすい。登美の詩を探す>今回のランチはチョイス式でパスタかカツ。前回は両方出たうえに、さらに懇親会でも大量に出てきたので全然食べきれなかった。1皿の量が多いことを考えれば、今回は正しい選択。ワイン豚のカツレツ ほかにスープ、サラダ、トースト相変わらずビッグサイズ。やや強めの味ながらも、ここの料理はおいしい。でも、昨年食べた豚のグリルのほうが好み。このあとはテイスティングとセラー見学。Part2へ続く。サントリーの公式ブログから、ほかの参加者のブログをたどれます。気が向いたら投票お願いします→
2008.06.07
コメント(10)
-

ワインスクール考3
「わたしのワイン人生」のようになってしまった今回のテーマもいよいよ最後。アカデミー・デュ・ヴァンのStep-II(中級コース)に通ったあとは、その流れで研究科という上級クラスを受講。今でも尊敬している講師にこのとき出会い、1∼2年通った。このときのモチベーションは、授業の面白さもあるけれど、二次会が面白かったことが大きい。アカデミー・デュ・ヴァンでは講師を含めた二次会があるクラスが多く、持ち込みでやる場合もある。そういうクラスでは、バラエティに富んだワインが飲めるのでとても楽しかった。その後はしばらく間があって、自由が丘ワインスクールの上級クラスを何度か受講(情野ソムリエと石田ソムリエのクラス)。受験で有名な自由が丘だけれど、わたしが通ったのは中上級者向けのふつうのクラス。通った理由は一流ソムリエの話を聞きたかったのと、カリキュラムが面白そうだったから。これらはけっこうよかった。またしばらく間があって、その後は名前を出すのも嫌な神田の某ワインスクール。そして現在は地元の酒屋がやっているワイン教室に通っている。そろそろまとめに入りたい。ワインスクールに通って一番よかったことは、ワイン好きの友達ができたこと。これに尽きる。アカデミー・デュ・ヴァンで出会った友人とは今年で10年目になる。今でもつきあいがあり、昨年は一緒にイタリアに行った。長く継続するためには、みんなの性格や幹事役のたゆまぬ努力、その他諸事情が必要だけれど、これは一生の宝だと思う。だからワインスクールに入って2次会に行かないのは重大な損失だと思う。とはいえ友達を作りやすいのは初級と中級クラス。上級クラスは、下からのステップアップですでに人間関係が出来上がっているので、途中から入り込むのはけっこう難しい。そして2番目によかったことは、ワインの幅が広がったこと。現在は資格も持ち、十分に飲み込んでいる。それにもかかわらずワインスクールに通う理由を聞かれればワインの幅を広げるためだ。ワインを1人もしくは似たような嗜好の友達と飲んでいると、どうしても選択の幅が限られてしまう。受講するクラスを選ぶ必要はあるけれど、自分の知らない素晴らしいワインに出会えるのはいいところ。99/2000年当時、自然派ワインはマイナーだったけれど、そのころロワールやアルザス、ラングドックの自然派(だけに限らないけど)に出会い、マイナー産地に開眼してしまった。そして最後に人の好みは千差万別だと知ったこと。それも想像を超えるほどに。ほとんどのスクールではブラインドでワインを飲む。以前通ったクラスでは、銘柄をオープンにする前に一番好きなワインや嫌いなワインを投票していた。すると「これはないだろう」というものを一番好きという人や、わたしが一番気に入っていたものを(癖のないワインだと思ったのに)「一番苦手」という人もいて、本当に人の嗜好はさまざまだと感じた。もちろん一番安いものを好きだという人もいた。経験の少ない人向けのクラスではなく、上級者向けクラスでの出来事である。友人同士のワイン会だと、ここまでの差は出ないことが多い。これまでにたどってきたキャリアの違いや(短い長いではなく飲んできたワインの違い)、本質的な嗜好(しこう)の違い、ブラインドによる先入観の排除は、いかに大きいかを思い知った。これほどまでに人の好みは千差万別なのだから、他人の目など気にせず、ワインに対して幅広い視野をもちながら、マスコミなどに惑わされない、自分なりのワイン観を確立することが重要なのではないだろうか。今回はワインスクール考というタイトルだったので、ワインスクール中心に話を進めたけれど、ブログの諸氏がそうであるように、ワインスクールに通わない学び方もあるだろう。ワインは自由なものだし、基本的には個人的なものだからだ。でも、ソムリエ試験の学科の勉強は、短期間に要点を覚えるということでは有用だったと思う。アペラシオンを覚えることは、フランスワインを勉強するうえで重要なことだ。ソムリエ試験の勉強をして一番よかったことは、アペラシオンを含む世界地図が頭の中に入ったことかな。またテイスティング能力向上に一番役立ったのは、友人同士のブラインドワイン会。単に答えを当てるのではなく、それぞれの人が、根拠を述べながら意見を言い合う形式。それぞれの人が考えるワインの特徴を知ることができてよかった。また全員で大外ししてしまい、ワインの奥深さや意外性を知ることも多い。ワインスクールについて:ワインスクールにはそれぞれキャラクターがある。また大手の場合、複数講師がいるので講師によって雰囲気は全然違う。また春には受験コースがあるけれど、それも全然違う。ネットや友人の評判もあるけれど、実際のところ通ってみなければ自分に合うかどうかわからないと思う。・内容・評判・場所(通いやすさ)・値段(専業のスクールの場合「安い=よい」とは限らない。安い=安いワインがほとんど)・振り替えシステム・料金の支払い方法や返金などのルールなどを比較して気合いで選ぶしかないと思う。またスクールによっては1∼4回の短期コースや見学などがある場合もあるので、それを利用してもよいだろう。知っているところを短評する。・アカデミー・デュ・ヴァン初級者から上級者まで、老舗らしくカリキュラムが充実しているのが魅力的。また夜のクラスの多くでは2次会をやっている。最近は久しく通っていないけれど、以前とは経営が変わったためビジネスライクといううわさもある。・自由が丘ワインスクール講師は一流ソムリエのみ。秋の上級クラスは面白い。ただしオフィシャルな(?)2次会は無いので、友達は作りづらい。初級・中級クラスなら大丈夫かも。それ以外だと、田崎さんのところはコメントをバンバン指されて厳しいらしい。受験を考えている人にはいいかも。現在興味のあるところは、アカデミー・デュ・ヴァンの上級クラスの一部。堀賢一氏の講座に行きたかったのだけれど満席で断念。あとは自由が丘ワインスクールの、秋にある石田ソムリエや情野ソムリエのクラスかな。あと尊敬する斉藤研一氏のサロン・ド・ヴィノフル。時間が取れるときには、また行ってみたいと思う。・ワインスクール一覧http://www.wine21.ne.jp/link/suku-ru/現在通っているところ:現在通っているのは、隣町の桜新町にある酒屋「エスポア・ナカモト」で開催しているワイン教室。近所だし、安いし(5回で\19,000)、知らないワインに出会えるので通っている。普通のワインスクールでは、授業料に占めるワインの原価率は高くても20%。それに対してここは赤字ではないかと思えるようなワインのクオリティ。それに授業料も大手と比べれば格安。なかには遠くから来ている人もいるみたいだけど、となり駅だしね。おつまみも出てプチワイン会のようで気楽という理由もある。ただし「ワインを勉強しよう」というよりは「ワインを楽しもう」という方向性なので、きっちり勉強したい人よりは楽しみたい人向け。あと、ほとんどが自然派ワインなので、自然派がどうしても嫌いな人も向かないかな。興味のある方はどうぞ。わたしが現在通っているのはCコース。途中からの参加でも、料金も含めて相談に乗ってくれると思いますよ。カリキュラム&スケジュールPart2に戻る。Part1に戻る。気が向いたら投票お願いします→
2008.06.04
コメント(16)
-
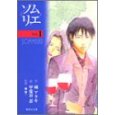
ワインスクール考2
イベントが続いて飛んでしまったけれど前回からの続き。前回は、ワインに興味を持つきっかけから、ワインスクールに申し込むまで。---前回書き終わってから思い出したのだけれど、本格的にワインスクールに通う前、次のワインスクールのミニコース(全1∼4回くらい)に通ったことがあった。・雪印チーズ&ワインアカデミー・サントリーのワインスクールいずれも現在は閉校してしまったスクール。サントリーは職場から徒歩で行けるということで友人と通った。ちょうどドラマソムリエの開始前で、そのときの講師が主演の稲垣吾郎に演技指導したって言ってたっけ。雪印は、ワインは1回コースにしか参加していないけれど、チーズコースにはまじめに通った。とくに中級コース以上は小淵沢工場での実習があって、ここで作ってその場で食べたモッツァレラは、今まで食べたチーズのなかでもっとも印象深い。内容・価格とも、チーズスクールのなかでは一番よかったと思うのだけれど、雪印問題と絡んで数年前に閉校。残念。---脱線したので話を元に戻そう。最初に迎えたのはワインエキスパート試験。まったくの独学だし、受験時点ではボルドーのグランクリュはおろか、ブルゴーニュ赤のプルミエクリュも飲んだことがなかった。白のプルミエクリュはかろうじてシャブリのみ。試験日に合わせて、直前の5日間に夏休みを取得。その間、朝から夜まで図書館に通って勉強。脳みそを揺らさないように、そっと受験会場に向かう。するとラッキーにも一次試験に合格。勢いで二次試験まで合格してワインエキスパート資格を取得してしまった。受験のためにスクールに申し込んだのに、授業開始前に目的を達成してしまった。目的を失ってしまったけれど、当時は払い込んだ授業料が戻ってこないこともあり、いちおう通うことにした(現在は1回目の授業開始前なら返金される)。このあたりからワイン人生がヒートアップ。当時通ったクラス(Step-II)は毎週あったので、授業&二次会で飲みまくり。ワインは今より安かったこともあり、授業でも結構いいワインが出てきた。たしか初回の授業ではクリュッグとムートン93だったような気がする。当然それだけでは「飲んでみたい欲」を満たすことができない。そのため2ヶ月に1回くらいのペースで自宅ワイン会を開催。さらに会社ではワイン愛好会を立ち上げて毎月ワイン会を開催。記念すべき第一回の自宅ワイン会のリストはたぶんこれ。後ろに安いワインが2本入っているのは、飲み足りずに開けたもの。NV Gosset Grande Reserve Brut1995 Sancerre(Pascal Jolivet)1969 Ch.Beychevelle1994 Ch.Trotanoy1995 Opus One1992 Ch.Haut-Brion1996 Kiedricher Grafenberg Riesling Spatlese(Robert Weil)1990 Domaine Boyer Royal Reserve(Bulgaria)1995 Ch.Cap de Faugeres(Saint-Emilion)こちらは会社のワイン愛好会のリスト。すべて2本用意して参加者は20名くらい。会費はたしか\2,500。1996 Sancerre Les Carroy-Marechaux(Gitton Pere et Fils)1995 Chablis 1er Cru Monmains(Louis Jadot)1993 Puligny-Montrachet 1er Cru Les Pucelles(Leflaive)1997 Beaujolais-Villages(Georges Duoebuf)1995 Beaune Cuvee Cyrot-Chaudron(Hospices de Beaune)1992 Clos de la Roche(Armand Rousseau)1994 Hermitage(E.Guigal)1996 Gewurztraminer(Hugel et Fils)どんな味だったか覚えていないものが多いけれど懐かしい。このころよく読んでいたのが漫画「ソムリエ」。その後「瞬のワイン」「ソムリエール」と続くけど、ソムリエが一番好きかな。ソムリエはドラマ化もされた。後半は漫画とは全然別物だけれど、全体で見れば嫌いではない。DVD-BOXも購入済み。ソムリエ DVD-BOX (中古DVD-BOX) 3,549 円定価は2万近くするので、この中古はすごく安い。↑のように書いたら売り切れてしまった。4日夜の時点では中古で1万円くらいが最安値。ソムリエDVD-BOXを探す>あとよく読んでいたのは葉山光太郎氏の「ワイン道」と堀賢一氏の「ワインの自由」。堀賢一氏の本はとくにお薦め。今回で終わらせるつもりが、また燃料切れしてしまった。「ワインスクール考」というよりも「わたしのワイン人生」という内容になってしまったけれど、次回はちゃんとワインスクールの話をする予定。次回が最終回。Part3へ続く。気が向いたら投票お願いします→
2008.06.03
コメント(10)
-

パシフィコ横浜でアフリカンフェア
この日(6/1)は、久しぶりの快晴。パシフィコ横浜で開催されているアフリカンフェア20082008.5.28-6.1に近所の自転車仲間と行ってきた。当初は横浜で中華料理のハズが、なぜかアフリカンフェアでアフリカ料理になってしまった。パシフィコからランドマークタワーを眺めるわたしの自転車 最近カーボンフレームの高額自転車に興味ありアフリカ料理はカレーに似た(違うけど)、スパイシーな料理が多い自転車なのでノンアルコールビール。甘くて変な味。ホップの苦みはなく麦だけ?チュニジアだったかな? 南アフリカのワインは有名だけどフランス統治の影響で北アフリカでも造っています。対人地雷除去機なぜバラ? と思ったら、日本のバラ輸入先の2位がケニアで4位がエチオピア。ドバイ経由で収穫の翌日には到着するらしい。走行距離は50キロちょい。ずっと平坦だし、けっこう楽だった。と思ったけれど、翌日にはちょっと背筋痛。トホホ。やせなきゃ。気が向いたら投票お願いします→
2008.06.02
コメント(0)
-

武蔵工大キャンパスイルミネーション2008
武蔵工業大学で開催されているキャンパスイルミネーション20082008/5/31-6/3 19:00-21:00 入場料無料に行ってきた。このキャンパスイルミネーションは、工学部建築学科の学生が中心となって世田谷キャンパス全体を光で装飾するイベント。今回初めて知ったのだけれど今年で5回目らしい。武蔵工大のある尾山台までは4キロ弱と遠くないこともあり行ってきた。ビデオカメラで撮った映像をプロジェクターで映し、さらにその映像を撮って映し出す。合わせ鏡と同じ原理で不思議な感じ。レーザー&影絵の様子は、昨年秋に訪問した京都高台寺のライトアップを彷彿させる。1時間近く楽しめて入場料無料は太っ腹すぎ。イギリスの美術館方式で寄付を募ってもよいのではないだろうか。きっといろいろな問題があって、やっていないと思うのだけれど。それにしても学生の方々&関係者の方々。こんなに楽しいイベントありがとうございます。来年は学校名が変わってしまうけれど、変わらず続けてくださいね。あした6月3日(火)が最終日。雨で中止の可能性もあるけれど、興味のある方はどうぞ。気が向いたら投票お願いします→
2008.06.01
コメント(8)
全28件 (28件中 1-28件目)
1