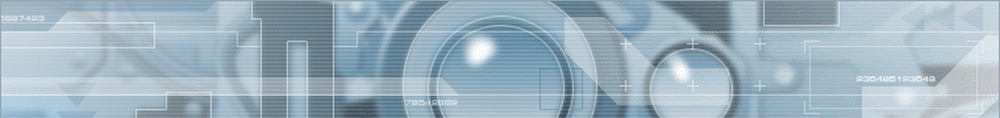2008年10月の記事
全14件 (14件中 1-14件目)
1
-

明治神宮のライトアップイベント「アカリウム」に行ってきた
明治神宮の御社殿復興50周年記念として開催された「アカリウム」に行ってきた。・御社殿復興50周年記念「アカリウム」 2008年10月31日(金)、11月1日(土)原宿駅を出て橋を渡ると、突然まばゆいほどの光が目に入る。今回のイベントを知らなかった人も、みんな写真を撮っていた。これはちょっと写真マジック。実際にはもっと暗く見える。ブルゴーニュのワイン樽 DRCの樽もあった。中身は何だったけ?かがり火全国から奉納された食べ物やお酒が県ごとに並べられられていた。生け花もいろいろ展示されていた。もっと派手なライトアップだと思っていたのだけれど、表参道の入り口が派手なだけで、あとは比較的落ち着いた演出。神社ということを考えれば妥当なところか。あと2ヶ月で来年ですね。気が向いたら投票お願いします→
2008.10.31
コメント(5)
-

長州・大江戸スタンプラリー2008
山口県が主催する長州・大江戸スタンプラリーに参加してきた。このイベントは、山口県にゆかりのある場所をスタンプラリー形式で巡るもの。初参加だけれど、松陰神社のお祭りにあわせて毎年開催されているようだ。スタートは、日本橋高島屋の裏にあるおいでませ山口館。1500名募集していたので朝の受付はけっこうな行列。そして、またもや雨。自転車で参加しているわたしには少々つらい。今年は次の5カ所のうち3カ所以上をまわり、3時までにゴールの松陰神社(吉田松陰墓所:世田谷区若林)に行くこと。・椿山荘庭園(旧山県有朋邸:目白)・南砂緑道公園(長州藩砂村抱屋敷跡:南砂町)・日比谷公園(長州藩上屋敷跡)・檜町公園(長州藩下屋敷跡:六本木ミッドタウン裏)・毛利庭園(長府藩邸跡:六本木ヒルズ)最初の目的地は南砂町の南砂緑道公園。一時はけっこう降っていた雨も公園に着くころにはやんでいた。L字型をした全長約1kmの細長い公園。大砲のレプリカ次は東京駅方面に戻ることにする。永代通りを走っていると富岡八幡宮を発見。このあたりはめったに来ないのだけれど、門前仲町の近辺はとてもにぎやか。それと東京駅から意外に近い(約2.5キロ)ことに驚く。門前仲町の富岡八幡宮今回のコースではないのだけれど「近代日本の巨匠たち」が最終日だったので立ち寄ることにした。出光美術館絵が多いのかなと思ったら、焼き物と半々。焼き物はよくわからないのだけれど、板谷波山のつや消し仕上げのようなうわぐすりは見事。また平櫛田中の超絶技巧彫刻もすごい。そして出光美術館が大量に所有する仙がいの名作がたくさん展示されていた。もっと絵が見たかったという気もするけれど、仙がいがたくさん見れたのでまあまあかな。出光美術館からの皇居の眺め出光美術館の近くではハロウィーンのデコレーション。続いて日比谷公園へ。何回も来ているのに、じっくり見てみるとまた違う印象。続いて早稲田にほど近い椿山荘へ。日曜の都心部は車が少なくて走りやすい。椿山荘椿山荘では、メインダイニングのイタリアンに行こうという野望もあったのだけれど、計画時に断念。自転車なので、あまりきれいな格好じゃないし、5カ所まわって規定時間内にゴールするのは無理だったから。いつか出直したい。ランチは椿山荘の近くの徳島ラーメンで。こってり系。続いて六本木ミッドタウンの檜町公園へ向かう。市ヶ谷の防衛省赤坂見附の豊川稲荷檜町公園に到着。六本木ミッドタウンには何回か来たことがあるけれど、こんなに広くてきれいな公園があるなんて知らなかった。続いて六本木ヒルズ裏の毛利庭園へ。こちらはニュースステーションなどでたびたび登場しているので知っていたけれど、行ったのは初めて。これで5カ所全部制覇。あとはゴールの松陰神社へ。ここだけ都心からちょっと離れるけれど、わたしの家から一番近い。世田谷線松陰神社に近づくと、お祭りで、すごい人込み。大回りして松陰神社に到着。松陰神社の場所はなんとなく知っていたけれど、入ったことはなかったし、吉田松陰を祭っている神社だとは知らなかった。会津の売店も少しだけ出ていた。長州と会津は、幕末の前後で壮絶な殺し合いをしているので、最近まで遺恨が残っていたという話だったけれど、仲直り活動の一環だったのか(ただしこれには諸説あり)。興味のあるかたは「会津 長州」で検索してみて。山口のいろいろな物産展が出ていた全部まわって締め切り1時間前にゴール。これだったら、それぞれの公園をもっと散策すればよかった。とはいえ、今回は天気が悪く余裕がなかったので仕方ない。完走者にはスポンサーからいろいろなプレゼントがもらえます。初参加だったけれど、いろいろな発見があってとてもよいスタンプラリーだった。またそれぞれの場所について歴史的経緯などを解説したPDF冊子を事前に配布するなど開催者側も手慣れている。スタンプラリーのポイントを変えながら毎年開催しているようなので、来年もできたら参加したい。気が向いたら投票お願いします→
2008.10.26
コメント(2)
-

ブルゴーニュ・グラン・クリュがそろったワイン会
代官山のフレンチにて持ち寄りワイン会。今回は、赤も白も全部グランクリュ。コンディションも上々のものが集まりました。NV Jacques Selosse Brut Initialeジャック・セロス ブリュット イニシャルお店の泡。すばらしいとは思うのだけれど、ハズレもつかんでいるセロス。でも支配人が、このボトルはすばらしいというので注文。うーん、すばらしい。きっちりとしたストラクチャを持ちながらも、細かい泡と長い余韻。最近飲んだ泡では一番おいしいかも。ジャック・セロス ブリュット・イニシャルを探す>ジャック セロス ブリュット イニシャル ブラン ド ブラン NV2000 Corton-Charlemagne(Verget)コルトン・シャルルマーニュ(ヴェルジェ)わたしの持参品。最近ブログでヴェルジェを取り上げているので、その流れで決定。軽い熟成が入っていて、少し艶っぽい雰囲気。一般的に考えるコルシャルよりもなじみやすく、中程度の濃縮度ながら密度がありエレガンスを感じる。バタールのようなインパクトはないのだけれど、こなれた艶やかさが魅力的。1万円台前半ならば十分満足いく内容。【11月7日より出荷】ヴェルジェ コルトン・シャルルマーニュ VV 20041996 Batard-Montrachet(Joseph Drouhin)バタール・モンラッシェ(ジョセフ・ドルーアン)カッツーンとインパクトのある香り。さすがバタールと思うものの、ルフレーヴと比べるとボディの密度は薄い。ルフレーヴがなければ、もっと印象はよかったはず。1996 Batard-Montrachet(Leflaive)バタール・モンラッシェ(ルフレーヴ)さすがにルフレーヴ。まだ若々しさがあり、抜栓当初は少しクローズ気味だったけれど、時間がたってからはボディの厚み、インパクトともにさすがと思うもの。1996 Chevalier-Montrachet(Domaine d'Auvenay)シュヴァリエ・モンラッシェ(ドーヴネ)Char@diaryさんの持参品。ものすごい茶色。やばいなと思って飲んでみるとやっぱりシェリー化してた。とはいえ嫌なものではなく、本来の姿ではないものの、おいしいと思えるレベルだったのが救い。Char@diaryさんはまだ何本か持っているようなので、残りはあたりだといいですね。ルフレーヴのバタール・モンラッシェ次に赤編。コメントを各地からが尽きてショートコメントになっているのでご容赦を。1996 Echezeaux(Rene Engel)エシェゾー(ルネ・アンジェル)もう少し熟成していると思ったけれど、まだ熟成途上。中程度のボディで可も不可もなく、やや中途半端な印象。96はリリース直後にも飲んだことがあるけれど、そちらのほうが印象はよかった。1994 Clos de la Roche(Armand Rousseau)クロ・ド・ラ・ロッシュ(アルマン・ルソー)ルソーのロッシュはそれほど評価していないのだけれどthe_eaterさんの持ってきたものはいずれも好印象。こちらは、まだボディもしっかりしており、少し熟成も入って、なかなかおいしい。1978 Clos-Saint Denis(???)クロ・サン・ドニ(生産者不明)krivouさんの生産者不明のワイン。さすが78。もっと若いビンテージと言ってしまいそうな強さがあり、ちゃんと熟成している。偉大ではないけれど、力強さと熟成によるなめらかさの同居。茨城産仔鳩のロティとそのもも肉のフリット料理はメインの一品だけ紹介。相変わらずの完成度。今回は1本だけコンディションの残念なワインがあったけれど、どのワインもレベルは高かった。一番印象に残ったのは、セロスとルフレ―ヴ。2番手グループはヴェルジェとルソーと、クロ・サン・ドニかな。いちおう順番を付けたけれど、好みの差で変わる程度のものもあり、なかなか粒がそろっていたと思う。みなさんいつもごちそうさまでした。気が向いたら投票お願いします→
2008.10.25
コメント(9)
-

ギガル・コート・ロティ単一畑飲み比べ
Char@diaryさんがすでにUPしているので、鮮度がよくないけれど、とりあえず更新。都内某所のフレンチにて、持ち寄りでギガルのコート・ロティ単一畑の飲み比べ。今回は3つ全部揃って、ビンテージもそれぞれ違う。2000 Pierre Peters Les Chetillons Cuvee Speciale Brut Blanc de Blancs Grand CruLe Mesnil-sur-Oger, Champagne, France - 白泡行きつけのワインバーのソムリエがおいしいですよと言っていたのが、このシェティヨン。先日ノーマルキュヴェを飲んだばかりで気になっていた(そのときのブログ)。the_eaterさんが持っているというのでリクエストして持ってきてもらった。ノーマルキュヴェと比べると、あきらかにボディの厚みが増す。まだ若さたっぷりで、切れ味鋭く光る。さすがソムリエがオススメしていただけの銘柄。もうちょっと寝かしたら、さらにおいしくなりそう。ピエール・ペテルのワインを探す>シェティヨンは全部売り切れ。それほど有名じゃない造り手なのに、こんなに売れているとは。ノーマル・キュヴェもおいしいよ。いよいよ本題のコート・ロティ。一般的なビンテージ評価だと、95, 96, 93の順。1993 Cote-Rotie La Moulineグラスに注いだ瞬間から開いている。以前93のラ・トゥルクを飲んだときは、期待とは裏腹に平凡だったので(ラ・トゥルクとしてですよ)、93はまったく評価していなかった。ところがビックリ。少しねっとりしたなめらかなテクスチャを持ち、一部の熟成したボルドーにも通じる香り。ほどよい厚みのボディがありエレガント。ミッドからアフターにかけてスパイシーなところがローヌの証し。すごいときのギガル三兄弟(姉妹)ほど圧倒感はないのだけれど、単独で飲んだらとてもすばらしいワイン。1996 Cote-Rotie La Turque続いてラ・トゥルク。恐るべきシルキーさは共通項として持っていながら、こちらはミルキーで官能的(そこまでは熟成してないけど)。ビンテージ評価通り、こちらのほうが厚みがある。香りの開き具合は93で、ストラクチャのたしかさで96。時間がたつほど96のほうが良くなってきた。1995 Cote-Rotie La Landonneマイ持参品。ここまでは全部当たり。セラーの最下段に入れていたのと、リリース当初は固かった印象があるので、少々不安になりながら飲んでみる。抜栓当初は少し閉じ気味。ほかのワインとは異なりシラー100%のためか、乾いた土っぽいニュアンスがある。時間がたつとともに開いてきた。まだタンニンが残り固い部分があるものの、マイナスファクターではなく、いいビンテージならではの見事なストラクチャ。うーん、すばらしい。共通点は、うねりを伴った酒質のなめらかさ。そして続けて飲んでみると、だんだん直径の大きい打ち上げ花火を鑑賞しているよう。はじめは1本目がいいかなと思ったけれど、2本目が開いてくるとそちらに興味が引かれる。2本目がいいなと思ったら、最後には3本目といった様子。若いながらも95はビッグビンテージらしいポテンシャルを見せてくれた。とはいえ、どれが好きかは何を重視するかによると思う。終了間近の95ランドンヌはすばらしいと思いつつも、93ムーリンヌの芳香豊かな香りにも引かれてしまう。こういうワインを飲んでしまうと「濃い」とか「薄い」なんていうチープな論争がバカバカしくなってくる。飲みごろのギガル・コート・ロティ三兄弟(姉妹)はあまりないけれど、一度は経験してみるべきワイン。ギガルのコート・ロティ ラ・ムーリンヌを探す>ギガルのコート・ロティ ラ・トゥルクを探す>ギガルのコート・ロティ ラ・ランドンヌを探す>今回はいずれも高価で手を出しづらいけれど、買いやすいのは93のムーリンヌ。楽天の最安値は\31,500。もし同じコンディションならば十分満足できるはず。[1993] コート・ロティ ラ・ムーリンヌ ギガルCote Rotie la Mouline Guigal気が向いたら投票お願いします→
2008.10.21
コメント(2)
-

足尾銅山・渡良瀬川ツーリング Part2
Part1からの続き。足尾銅山観光を出発して、さらに山を下る。このあたりは下りといっても、それほど急ではないので、上りでも大丈夫そう。でもダムの下はけっこうな急坂もあるので、いまの脚力&体重だと上りはやっとこかな。草木湖渡良瀬渓谷の中腹にあるのが、ダムによって作られた草木湖。なかなか広大な湖。そろそろいい時間になったので草木湖のほとりにあるソバ屋で昼食。このあたりは手打ちそばが名物のようだ。今回、2つめの観光スポット富弘美術館へ。事故で手足が不自由になり、口にくわえた筆で描いている星野富弘の美術館。温かみのある絵と、味わいのある文字が印象的。口で描いているのに、けっこう緻密な描写だし、字もうまい。優しい気持ちになれる美術館。オススメ。美術館のまわりの木々は一部紅葉していた。駐車場の一角には、地元の特産品を売っている道の駅のようなものがあった。でも時間がおしていたので見ないでスルーしてしまった。いま思うと少しくらいのぞけばよかったかな。これも何かの廃虚走っている途中に見つけた花濃いピンク色の花が一面咲いている。よく見るとハチやチョウなどがたくさん集まっている。今回はカキが見事になっている木が多かった魚道付きのせきうっすらと紅葉がはじまっている続いて貴船神社へ。名前からもわかるように京都の貴船神社の分社。国道と反対側の山の上にあり、本殿のとなりからは渡良瀬川を一望できる。周囲はさびれたところで駐車場もガラガラだったのに、境内には意外に人がいてビックリ。さらに山を下り、新桐生駅の近くにある渡良瀬サイクリングロードのスタート地点へ向かう。この時点で3時30分。暗くなる前にどこまで行けるか。ファーストプランは南栗橋駅(約60キロ)だけれど無理そう。セカンドプランの館林駅(約35キロ)までが目標。最近は5時を過ぎると暗くなるだけに何とも微妙。人口密度が少なく幅も広いので、いつも走っている多摩川サイクリングロードよりも格段に走りやすい。足利工大の風力発電機森高千里の歌で有名な「渡良瀬橋」も途中にあったのだけど、気づかずに通り過ぎてしまった。観光名所になっていて石碑もあるらしい。しまった。5時を過ぎると急に暗くなってきた。街灯もない真っ暗な道を走るのは心もとない。館林駅にほどちかい渡良瀬川大橋でサイクリングロードをリタイアすることにした。大通りは車通りが多くて怖いので、うす暗い農道を走る。ところが予定の距離を走っても全然駅に着かない。ついには真っ暗に。現在位置を確認するために大通りの交差点に行ってみると、予想とまったく違うところにいた。実際に渡った橋と、自分が渡ったと思った橋が違ったのだ。館林までのルートをちゃんとGPSに入れておけばよかった。真っ暗になりすぎて、これ以上自転車で走るのは怖い。そこで一番近いと思われる県(あがた)駅まで走って終了。本日の走行距離は85キロ。今回は下り&平地だけだというのに翌日は昼過ぎまでダウン。輪行が疲れるのか、それとも前日少ししか寝ていないことが悪かったのか。奥多摩に行ったときよりも、翌日に疲労が残った。おまけいつもはドイターのバックパック(Race X)を使っているのだけれど、ロングツーリングは背負わないほうが疲れないということで、最近買ったばかりのトピーク ダイナパックDXを持っていった(シートポストへ装着)。topeak(トピーク) ダイナパック DX ブラック1014PUP2たしかに背負わないと体へ負担は少ない。ただし荷物が重い場合、重心バランスが狂うので、下りコーナーでは少し違和感があった(今回は一眼レフを入れていた)。サイズの小さいタイプもあるけれど、こちらのDXのほうがお勧め。大は小を兼ねる。それとは別に最近活躍しているのが同じトピークのトライバッグ。トップチューブに装着する小物入れ。カメラや携帯を入れるにはちょうどいい。【オススメ品】topeak(トピーク) トライバッグ/オールウェザー1014PUP2気が向いたら投票お願いします→
2008.10.19
コメント(4)
-

足尾銅山・渡良瀬川ツーリング Part1
zzz.santaさんに「足尾銅山」を勧められてから、気になって仕方がない。まだ紅葉には早いと思いつつも、天気がよかったので行ってしまった。足尾銅山は鉱毒事件で知っているだけで、正直なところよく知らなかった。あらためて調べてみると日光中禅寺湖の南10キロに位置し、駅周辺の標高は約630メートル。渡良瀬渓谷沿いにある。中禅寺湖が標高1200メートルなので、近いわりにはだいぶ低い。今回は自転車をかついで輪行(自転車をバックに入れて公共交通機関で運ぶこと)することにした。また当初は自転車でふもとから登ろうとも考えたけれど、結局はわたらせ渓谷鉄道で目的地まで行き、帰りは自転車で山を下ってくることにした。それにしても足尾銅山は遠い。自宅から乗り換え3回で「約4時間半」。今回は奇跡的にスムーズな乗り継ぎだったので、この時間で行けたけれど、5時間以上かかることもあるようだ。東武線で相老(あいおい)まで行って、そこからはわたらせ渓谷鐵道で最終目的地へ。わたらせ渓谷鐵道では1日1往復トロッコ列車も運行されている。 トロッコ列車が運行されることもある渓谷ということで、京都の嵐山や東京の秋川渓谷などを想像すると、意外に人家が多いし、風景も渓谷っぽくないことに気づく。渓谷っぽくなるのは相当上流のほうだけ。それでも人家は多い。神戸(ごうど)駅わたらせ渓谷鐵道に自転車を乗せると\270とられた。電車運賃は\1020。電車運賃とリンクしているのか固定かは不明。1両編成で荷物スペースも少ないので、込んでいるときだと乗せづらいかも。今回のスタート地点の足尾駅自転車を組み立ててさあ出発。足尾駅や通洞駅あたりは、わたらせ渓谷鐵道の終点近くで山の上だというのに、昔の名残なのか意外ににぎやか。足尾銅山観光これに乗って見学場所に向かう。とはいっても、ちょっとしか乗らないけど(200メートルくらい?)。また紅葉には早かったようで、紅葉していたのは、ここと富弘美術館のまわりだけ。トロッコを降りたあとは、徒歩で坑道を見学。壁からは、ものすごく水がわいている。こんなにわいていたら掘削作業は大変だったろうな。江戸時代の掘削風景足尾銅山は400年の歴史を持つ銅山。こちらの観光施設では江戸時代から現代にかけて、時代ごとの掘削風景が解説されている。江戸時代はすべて手作業。こんなところで働いていたら長生きしないだろうな。明治・大正だったかな?昭和に入ると健康対策なども進み、防じんマスクなどをしている。また掘削もダイナマイトを使用したものに変わっている。結局1973年に閉山。この施設は7、8年前にリニューアルしたようで、内部の展示室はきれい。映像や音声の解説もあり、一部ではCGが使われていた。世界遺産登録を目指しているようだけれど厳しそう。足尾銅山自体はとても巨大なのだけれど、この観光施設は1時間もかからずに全部見終わってしまう。それにまわりの風景も特筆するユニークさは感じない。足尾銅山観光を出発し、山を下る。何かの跡地昔、銅山があったおかげで、いろいろな廃虚がある。事前に調べたときには、足尾製錬所の廃虚が見事だと思っていたのだけれど(こちらのブログを参照)、今回は見過ごしてしまった。帰宅後に調べると終点の間藤駅からさらに上流に行ったところらしい。・日光市観光 足尾ほかにも掛水倶楽部や古河橋などいくつか観光スポットがあったようだ。自転車で走っていれば気づくと思っていたのだけれど、上流にあったとは...むむ。せっかく行ったのにもったいない。Part2へ続く。気が向いたら投票お願いします→
2008.10.18
コメント(4)
-

ヴェルジェは、やっぱりわたしの好み
最近「ワインを飲んでない疑惑」があるので(笑)、久しぶりにワインだけの紹介。家では、昔ほど高額なワインは飲んでいないけれど、量的にはそこそこ飲んでます。たぶん...。外食のときは、ひとりで一本飲むし。とはいえ、ピーク時に比べれば半分以下かも。それでも一時期よりだいぶ涼しくなってきたので、おいしいワインが飲みたくなってきた。でも、昔と比べるとテンションは低い。興味の主体は自転車や旅行、レストランだしね。飲みたいのは、いろいろな意味で「ハッ」とするワイン。中くらいにおいしいワインにはあまり興味がない。TPOにもよるけれど、五千円や一万円で価格通りのおいしいワインよりは、千五百円でふつうのワインがいい。とはいえ千五百円は微妙なラインなのだけれど。最近飲んだ中で、よいと思ったものから一本を紹介。2002 Chables 1er Cru "Montee de Tonnerre"(VERGET)シャブリ・プルミエ・クリュ モンテ・ド・トネール(ヴェルジェ)Bourgogne, France - 白辛口\5,000くらい, 松坂屋, 2004年10月購入Impression: 最近ビックリすることが多いヴェルジェ。品質のわりにはリーズナブルだと思うのだけれど、ドメーヌ人気一辺倒のためかイマイチ人気がない。しっかりボディがあり魅惑的な香りのギュファン・エナンも好きだけれど、シャープでかちっとしたヴェルジェも個人的にはストライクゾーン。こちらは初期の熟成が入った飲みごろ。いいビンテージらしい凝縮感がありつつも、シャブリらしさもたっぷり。シャブリは、アペラシオン的にヴェルジェのスタイルに合っているのかもしれない。十分価格を超える味わい。楽天を調べてみると04で5千円以下。マニア受けはしないけれど、味わいだけで評価すれば、いいワインだと思うのだけどね。【10月24日より出荷】ヴェルジェ シャブリ モンテ・ド・トネール 1級 2004気が向いたら投票お願いします→
2008.10.15
コメント(10)
-

すばらしき東京都庭園美術館 Part2
前回からの続き。右側の大きな窓からは正面の庭がよく見える。アーチ状の天井にも細かな装飾が施されている。お気に入りの一枚これもシャンデリア喫茶ルームにて新館にある喫茶ルーム(有名料亭の金田中が運営を担当)であんみつを。ボリュームは少なめだけれど、おいしい。金田中だったら仕方ないか。邸宅の素晴らしさと比較すると、庭は狭い気もするけれど、日本庭園と芝生のエリアがあって気持ちいい――新宿御苑などの広大なところとの比較するとってことで、個人邸宅としては広いですよ――。庭だけの入場もできる(有料)。今回もピクニックしている人や寝転がっている人がたくさんいた。奥に見えるのが茶室ヨーロッパの王侯貴族が主役だった時代の華やかな建築とは違うのだけれど、現代の大量生産的建築が薄っぺらく見えてしまう、たいへん力のこもったもの。施主と職人たちが情熱を注ぎ、コストも惜しみなくつぎ込んだ昭和初期の結晶。気が向いたら投票お願いします→
2008.10.13
コメント(4)
-

すばらしき東京都庭園美術館「アールデコの館」 Part1
目黒の東京都庭園美術館で開催されている開館25周年記念 アールデコの館2008年10月1日-13日に行ってきた。東京都庭園美術館は旧皇族の朝香宮邸を利用した美術館だ。ここの建物は素晴らしいと聞いていたけれど、今回が初訪問なのだ。いつもは写真撮影禁止だけれど、今回のイベントでは特別にフラッシュを使わなければ撮影できるようになっていた。積極的にアナウンスしていたわけではないので、それほど込んでいないだろうと思っていたところ、チケット売り場に短い列ができるくらい込んでいた。初訪問ということもあるけれど、最近訪問した美術展の中ではとても印象に残るものだった。エントランスにあったラリックのレリーフこのイベントを知っている写真好きが多かったようで、男女問わず一眼レフの所有率が高かった。シャンデリアの多くはラリックが担当。部屋ごとに違うのもすばらしい。扉の装飾ラジエーターカバー暖房器具にはすべてラジエーターカバーが掛けられている。これも部屋ごとにデザインが違う。天井シリーズ2点食堂これもシャンデリア 食堂なので野菜や果物などがデザインされている。写真を絞りきれなかったので、2回に分けて掲載します。次回へ続く。気が向いたら投票お願いします→
2008.10.12
コメント(6)
-

神代植物公園の「秋のバラフェスタ」
神代植物公園で開催されている「秋のバラフェスタ」平成20年10月7日(火曜)~平成20年10月31日(金曜)へ行ってきた。現在は秋のバラの季節。旧古河庭園でもバラのライトアップをやっている。どちらに行くか迷ったすえ、出遅れたこともあり、少しだけ近い神代植物公園へ行くことにした。スタートが遅かったので着いたのが5時半過ぎ。ちょうどさっきまでコンサートをやっていたようで、みんなぞくぞく帰っているときだった。しまったー!売店が出ていて、ワインやビールを飲みながらくつろいでいる人がたくさんいた。撮影は手持ちでほとんどISO3200。ピントが甘い写真が多くてごめんなさい。ライトアップのバラの撮影は難しい。この日は原則三脚禁止だし、風で花が揺れる。またいくつかの光源があるためホワイトバランスの選択も悩ましかった。すごくバラが好きというわけでもなく、超写真マニアというわけでもないわたしにとって、音楽などほかのイベントがなく(終わってしまった)、バラ園しか入れないというライトアップだけの参加は、少し後悔の残るものだった。もっと早い時間から行って、ちゃんと園内を一周するべきだったし、音楽イベントに間に合うようにするべきだった。今月末まで開催されているので、興味のあるかたはイベントスケジュールを確認してから行くことをオススメします。気が向いたら投票お願いします→
2008.10.11
コメント(2)
-

初秋の奥日光を楽しむ Part4
Part3からの続き。戦場ヶ原を歩き終えて、ちょうど昼過ぎ。どこで昼ご飯を食べるか迷ったけれど、どうせなら日光駅近くまで行ってしまおうとバスで移動することにした。東照宮から日光駅までのあいだにはいろいろお店がある。天然の湧き水東照宮と日光駅の中間地点で見つけた湧き水。何かの名水にも選ばれていて、生水のまま飲んでも問題ないらしい。ということで一口飲んで、あとは水筒で持ち帰ることにした。お酒で割ると、よりお酒の味わいが生きるような気がした。昼ご飯はどこで食べるか迷ったすえ、地元の人に聞いてみることにした。すると「このあたりでは与多呂が有名だよ」とのこと。おいしいかどうかについても聞いてみたけど、それについては明確な答えが得られず「とりあえず有名だよ」とのこと。多くのお店が通り沿いにあるなか、このお店は一本入った裏通りにある。割烹 与多呂栃木県日光市下鉢石町9650288-54-0198一番のメインは6,006円の本格懐石湯波料理らしいのだけれど、事前調査していなかったのでとりあえず2,993円の湯波ランチを注文。湯波滝川豆腐薄いだしが張ってあってスプーンで押すと麺状にほぐれるようになっている。すごくおいしいというわけじゃないけれど、1皿目としては上々。一皿ずつ出て来るのかと思ったらあとは弁当形式で出てきた。胡麻豆腐引揚湯波たぐり湯波・銀あん・青味うーん、どれもそこそこおいしくはあるのだけれど、ボリュームが少なくて、コストパフォーマンスが悪すぎる。1品目が出てきてから20分ちょいで食べ終わってしまった。東京や京都で3千円出したらもっとおいしいものを食べられると思うのだが...。帰宅後ネットで評判を確かめると、ものすごく評判がいい。ただし、みんな6,006円の本格懐石湯波料理を食べているようだ。とはいえ内容を比較しても、本質的にすごく違いがあるわけではない。仮に本格懐石湯波料理のコースを注文してもネットの評判通りの満足度を得られるかは微妙だと感じた。室内が豪華というわけでもないしね。日光を愛する人には失礼だが、日光通の友人の言葉「日光にうまいものナシ」というのを聞いていたけれど、今回もその言葉を破るものには出会えなかった。残念。まとめ日光までは遠くなくても奥日光は遠い。今回は快速を使っていることもあって、自宅からは片道5時間近い。とはいえ、それを苦痛と感じさせない自然が日光にはある。おそらくこれから月末までは、さらなる活況でいろは坂も込み合うだろう。今回は人込みを避けて一足早く行ったわけだが、人込みにぐったりすることを考えれば悪くない選択だったと思う。次は雪のある季節か、春の花咲く季節に来てみたい。それと日光金谷ホテルに泊まってみたい。とはいえ日光金谷ホテルのまわりに興味のあるものが少ないのは難点だのだけど。気が向いたら投票お願いします→
2008.10.07
コメント(4)
-

初秋の奥日光を楽しむ Part3
Part2からの続き。翌朝は6時前に起きて湯ノ湖のまわりを散歩。このあたりは標高1500mくらいあるだけに、朝は寒い。吐息が白く見える。ホテル前の木朝食を終えてチェックアウトすると、朝とは違いくもり。今日の予定は、湯ノ湖の東岸を歩いて湯滝まで行き、そこから戦場ヶ原に入り、戦場ヶ原の中央あたり――昨日歩いた部分――まで行ったら終了。この写真だけではわかりづらいけれど、湯ノ湖の北東部はとても汚い。生活排水のせいかと思ったら、そういうわけではないらしい。このあたりで温泉がわいていることが原因のようだ。温泉がわいている部分はブクブク泡立っている。湯滝の上部龍頭ノ滝よりも湯滝のほうがスケールが大きい。湯ノ湖にはあまり人がいなかったけれど、こちらは戦場ヶ原ハイキングコースの始まりということで、だいぶにぎわっている。先端だけ色づいている昨年の冬に来たときには透明だった湯川も、今回は水源の湯ノ湖が濁っているせいで少し濁っている。今年も悪いわけじゃないのだけれど、昨年の強烈な印象と比べると見劣りがする。昨年は一部に雪があり草木は枯れて一面灰色。都会とは違う強烈な寒さ。ほとんど人とすれ違わない人口密度。どこの場所とも違う圧倒的な個性に感動したのだけれど、今年は感動するほどではなかった。とはいえ今回は、たまに団体がいるだけで、すれ違うのも大変なほどの大渋滞では無かった。となると風景の違いが大きいのか?昨日歩いたところまで来たので光徳方面に抜けることにする。こちらはメイン通りではないため人が全然いない。こんどは、冬の雪のあるときか、春の花が咲いているときに来たい。Part4へ続く。気が向いたら投票お願いします→
2008.10.06
コメント(4)
-

初秋の奥日光を楽しむ Part2
Part1からの続き。小田代ヶ原から戦場ヶ原へ。戦場ヶ原の周囲にはシカ進入防止のためのゲートが設置されている。小さい草花や木々が荒らされてしまうらしい。ツタウルシ奥日光一帯でツタウルシが一番紅葉していた。ウルシの仲間なので、きれいだからと触るとかぶれてしまうらしい。林の中を歩いていると、ぽとりぽとりと落下物の音がする。その正体はドングリ。緑色のものも多かった。りんどうこのあたりになるとだいぶ疲れた。あともう少しで今日の目的地「龍頭ノ滝」。前回はスニーカーで滑りまくったので、今回はワークブーツを履いてきた。滑ることはなかったけれど、ゆるめのサイズだったこともあり足にまめができた。トレッキングシューズを新調するべきか。龍頭ノ滝のはじまり部分このあとは国道を越えて階段を下れば龍頭ノ滝だ。龍頭之茶屋滝の正面にある龍頭之茶屋で団子を食べながら滝を眺める。けっこうきれいなWebサイトを持っている。お団子が名物。茶屋の横にある「ほこら」に近寄ると円空のような仏像を発見。やっぱり円空。今日の行程はココでおしまい。バスに乗って宿泊地の湯元温泉へ。今回の宿は湯元温泉 奥日光小西ホテル。料理の評判がよかったのと、源泉掛け流しということで選んでみました。食前酒:柚子ワイン先付:胡麻豆腐、天山葵旨汁造り:八汐鱒と寄せ湯波惣譽 生 氷温貯蔵酒 吟醸仕込2006 足利呱呱和飲 白(ココ・ファーム・ワイナリー)ワインも日本酒も栃木産のものをセレクト。足利呱呱和飲(ここわいん)は定価\1,500くらいなのに、\2,310でリストされていて立派。金谷ホテルが、外国産ブドウも使った国産ハウスワインを使っていたのと大違い。すごいワインではないけれど、不自然なところもなく和食と合わせやすい。【ココファームワイナリー】足利呱呱和飲750ml舞茸、里芋、アスパラ鴨鍋よもぎそば まずっ! のびてる?虹鱒の炭火焼き 食堂の中央に炭火のいろりがあってプレゼンテーション的には合格なのだけれど、ずいぶん前に焼いたものようで少し干からび気味。ビーフシチュー インスタントを併用している?ご飯、吸い物、香の物杏仁豆腐料理を期待していたのだけれど平凡。高いコースだと栃木牛のステーキがついているようなのだけれど、少なくとも今回の料理に限っていえばうまいとは言えない。まずくはないけれど、うまくもない。昨年の中禅寺金谷ホテルで経験した、驚愕のまずさから比べればましだけどね。ただし飲み物の値付けが安いのは好印象。2千円台前半で、まっとうなワインがあるのはうれしい。また日本酒も定価\1,000くらいのものが\1,300だった。もう一つよかったのは温泉。大浴場は露天と屋内があり、源泉掛け流し。泉質は、硫黄泉で乳白色の濁り湯。においはきついけれど、最近入った温泉とは違い効能ありそう。建物は新しいとは言えず料理もイマイチだったけれど、部屋は結構広くて清潔、温泉も悪くなく、値段もそこそこなので「ギリ合格」といったところか。それにしても檜原村数馬の山城は最高の宿だった。Part3へ続く。気が向いたら投票お願いします→
2008.10.05
コメント(2)
-

初秋の奥日光を楽しむ Part1
初秋の奥日光へ行ってきた。昨年11月末以来の訪問だ(昨年訪問時のブログ、戦場ヶ原編)。実のところ昨年は、小説「ハゲタカ」に触発され、どうしても「金谷ホテル」に泊まりたくなって訪問した。でも、中禅寺金谷ホテルには感銘しなかったし、東照宮も期待したほどではなかった(とはいえ、いつかは日光金谷ホテルに行きたい)。また紅葉も末期だったので特筆するほどではなかった。しかしながら、湯滝から龍頭の滝までの戦場ヶ原一帯には圧倒的な衝撃を受けた。最近2、3年に行った国内観光では印象度No1なのだ。ということで、今回は東照宮や中禅寺湖はスキップして、1泊で奥日光に行くことにした。東武フリーパスはお得日光で中禅寺湖より向こうに行くなら「まるごと日光 東武フリーパス」 4,400円がオススメ。浅草から東武日光までの電車運賃と、東武日光から湯元温泉までのバス乗り放題が含まれて、この値段は安い。今回乗った区間の運賃を計算したら約30% OFFになっていた。特急が乗れるフリーパスは別に設定されている。日光の場合、特急と快速の時間差が少ない。快速は早朝しかないけれど、特急との差は最大でも40分程度。中禅寺湖までバスで1時間かかり、バスや電車の待ち時間が長いことを考えると、それほど気になる差ではない。 特急スペーシア 約1:50 快速 約2:05 区間快速 約2:30東武日光駅に着いたあとは、戦場ヶ原の中間地点にある赤沼までバスで移動。赤沼からは戦場ヶ原南部を西へ向かう低公害バスに乗り換え。低公害バス乗り場バスから撮影以前は一般車両が通行できたのだけれど、現在は低公害バスだけが通行できるようになっている。終点の千手ヶ浜へ。こちらの水はきれい中禅寺湖西岸の千手ヶ浜この日は風が強く波立っている。青っぽい色調と相まって海のように見える。中禅寺湖をあとにして、低公害バスで来た道を戻る。周囲には樹齢200年を超える木々が生いしげっている。低公害バスは、バス停の場所とは関係なくどこでも乗り降りできる。戦場ヶ原の西側に位置する小田代ヶ原へ。こちらの紅葉は美しい。Part2へ続く。気が向いたら投票お願いします→
2008.10.04
コメント(6)
全14件 (14件中 1-14件目)
1
-
-

- 日本酒の良さを広めよう!
- 光武(佐賀県)手造り純米酒
- (2025-11-25 21:13:17)
-
-
-

- ☆ワインに合うおつまみレシピ大公開☆
- 簡単おつまみレシピ いろいろ🍷 箸…
- (2025-07-15 05:52:26)
-
-
-

- やっぱりブルゴーニュ&シャンパーニ…
- ジャッキー・トルショー・マルタン /…
- (2025-11-16 15:33:26)
-