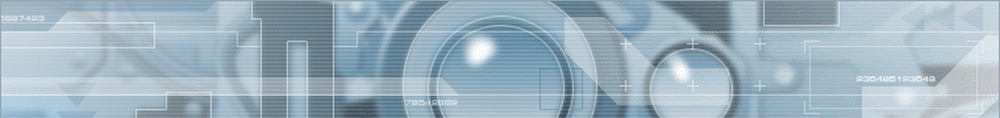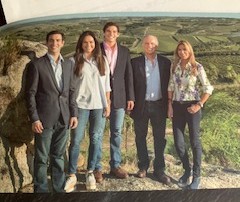2008年03月の記事
全28件 (28件中 1-28件目)
1
-

すばらしい! メゾン・デュ・シャテーニュ
また一つ素晴らしいレストランに出会ってしまった。ロティスリー・メゾン・デュ・シャテーニュ知人のブログで知り、シェフがアピシウスで長く働いていた方だということで気になっていたお店だ。場所は、地下鉄千代田線の根津駅のすぐ近く。ビルの地下1階にある。店内は15から20席程度。テーブルには白いクロスがかかり、店内は白を基調に少々茶色で統一。このあたりのレストランとしてはとても上品な雰囲気。夜の料理は、次の3つの選択肢がある。・\5,000のコース・\7,500以上で応相談のシェフおすすめコース・アラカルト\5,000のコースは、選択肢から選ぶ選ぶプリフィックスに近いが、選択できるものは多くない。バラエティーに富んでいるのはアラカルト。シェフのスペシャリテが食べたいと言ったら、シェフおすすめコースを勧められたのだけれど、今回は初めてなので\5,000のコースにした。アミューズ:キノコのテリーヌ アミューズからして、ただならぬ雰囲気。素晴らしい料理の予感。おつまみサラダ:生ハム、キッシュ、パテ・ド・カンパーニュ、etc鴨マグレのロースト アルマニャック風味 すばらしい! クラスを超えた味わいで、ボリュームも十分。タルトタタンワイン編ワインはすべてフランス産。ハウスワインは赤白ともに\2,800。銘柄はラングドックの雄「ドゥマ・ガサック」が造るテーブルワイン。それ以外のワインは、3千円後半から3万円くらいまで。このクラスのお店としては高額なワインも充実している。だいたい小売りの2倍程度の値付け。グラスワインは、ハウスワインの赤白1種類ずつ。安い店でもコースメニュー価格以上のワインしか用意していない店もあるなかで、まっとうな味わいのワインが\2,800で提供されているのは好印象。2006 Vin de Pays de L'Herault Terrasses de Guilhem(Moulin de Gassac)こちらはハウスワイン。ソーヴィニョン・ブラン系のすっきりとしたワイン。実売価格は1千円強のリーズナブルなワインだけれども、ドゥマ・ガサックだけに手抜きのないちゃんとした味わい。安いワインだとSO2が強すぎたり、樽が強すぎたり、不自然なワインが多いなか、こういうまっとうなセレクトはうれしい。ガサックのワインを探す>2004 Vin de Pays des Collines Rhodaniennes Syrah(Andre Perret)サン・ジョセフで有名なアンドレ・ペレが造るヴァン・ド・ペイ。透明感のある色調で、北の雰囲気の上品な仕上がり。ピュアな透明感の奥底にシラーのノート。サン・ジョセフのような強さはないけれど、おいしいワイン。アンドレ・ペレのワインを探す>ただし、気になったのはグラスの小ささ。ハウスワインはボトルで頼んだのに、ウォーターグラスよりも小さい。安いワインは仕方ないのかなと思って赤ワインに期待すると、先ほどよりは大きいけれど、こちらも小さい。いつも使っているリーデルのオーヴァーチュアレッドワインよりも一回り小さい。さすがに1万円を超える高額ワインは違うと思うけれど、グラスは一度投資したら長く使えるものなので、ある程度の大きさのものを使って欲しい。3千円以下のビストロではないのだから。ショット・ツヴィーゼルのような、リーズナブルで壊れにくいグラスもあるので、改善して欲しいところ。まとめ:最近は、もっと高額でも不満の残るお店が少なくなかっただけに、ひさびさに会心のヒット的な爽快感。最近半年間に新規訪問した、料理が1万円以下のお店では、間違いなくトップクラス。再訪問決定。次はシェフのおすすめコースを食べてみたい。ただしサービスは向上の余地あり。専任のサービスはいなくて、シェフ以外の若い男性がキッチン兼サービスをしている。だから、あまりサービスは期待しないでね。失礼なふるまいはないけれど、ちゃんとした店と比べると落ちます。でも不愉快じゃないし、値段も安いので、個人的には気にならない。All Aboutの嶋啓祐氏の次のコメントが、この店を端的に表現しているように感じる。フランス料理の真髄はソースに醍醐味があるということをよくわからせてくれる匠の技。そこにはコンテンポラリーな新しさや驚きはないかも知れない。しかし安心と和みの日常的フレンチの楽しみがあることをさりげなくメゾン・デュ・シャテーニュは教えてくれたのである。根津というと、東京の西側に住んでいる人にとっては遠いと思うかもしれない。根津駅以外にも、JR鶯谷駅や南北線東大前駅からも、いちおう歩いて行ける。また、上野の美術館の帰りに、散歩がてらに歩いて行くというのはどうだろう。遠くても後悔させない素晴らしい店だと思う。---メゾン・デュ・シャテーニュ東京都文京区根津2-14-10日興パレス文京プラザB1TEL&FAX:03-3827-2503
2008.03.31
コメント(12)
-

桜・桜・桜 Part2 東京国立国立博物館ライトアップ
前回からの続き。東京国立博物館ではこの季節、通常は入場できない裏庭が解放され、また夜はライトアップされている。その前に特別展平城遷都1300年記念「国宝 薬師寺展」を鑑賞。いつもとは違う、大胆で朱色が印象的な展示レイアウト。作品数の少なさをカバーしている。絶対的な作品数があるため物足りなさもあるけれど、斬新な展示方法は一見の価値あり。こちらは裏庭。花大根特別展、本館、東洋館を見て、ついに夜モード。本館の正面入り口階段のライト本館の裏で桜のライトアップ夜は寒かったこともあり、ホットドリンクの売店は盛況気が向いたら投票お願いします→
2008.03.30
コメント(4)
-

桜・桜・桜 Part1 砧公園、上野公園
この日は桜を見に、都内のいろいろな場所に行ってきた。まずは近所の砧公園。まさに満開。砧公園は広々として気持ちがいい。また敷地が十分に広いので、ひとつひとつの木が大きい。木の下にいる人と比べると、桜の大きさがわかるはず。ロゼワインで軽いランチ2000 Cabernet d'Anjou(Chateau Pierre-Bize)カベルネ・ダンジュ(シャトー・ピエール・ビーズ)Loire, France - ロゼやや甘口\1,800くらい, ESPOAナカモト, 2008年3月購入あまり好みではないロゼ・ダンジュやカベルネ・ダンジュ。中途半端な、だれた甘さが苦手なのだ。でも、信頼できる店主から、「ピエール・ビーズのカベルネ・ダンジュいいよ。これからの季節、アウトドアでも使えるし」と勧められ、それほど高くなかったこともあり買ってみた。期待と不安が入り交じりながら開けてみる。日本酒や梅酒にも通じる、品のあるほのかな甘さ。ピュアでクリーンな仕上がり。直接的な甘さはそれほど感じず、ギリギリ辛口にも分類できる程度。アウトドアで良いのはもちろんのこと、自宅でもサラダや軽い味付けの料理にはよさそう。なかなかおいしいワインでした。ピエール・ビーズのワインを探す>魚眼レンズ砧公園をあとにして上野へ。こちらも満開。天気の良さもあってすごい人込み。砧公園がファミリー色豊かだったのに対し、こちらは宴会モードまっしぐら。黒服の出店があると思ったら(社)日本バーテンダー協会のチャリティーも兼ねたもの。\400と安かったこともあり注文。桜ジントニックおそろしいほどのボート密度の不忍池Part2に続く。気が向いたら投票お願いします→
2008.03.29
コメント(10)
-

初台のイタリアンでワイン会
初台の某イタリアンで食事&ワイン会。料理の写真は撮ったけれど、ワインの写真は撮り忘れ。NV Henriot Souverain Brutアンリオ・スーヴェラン・ブリュットChampagne, France - 白辛口しっかりしたストラクチャーで、やっぱりシャンパーニュはおいしいと思わせてくれる。アンリオを探す>2000 Puligny-Montrachet(Jean Boillot)ピュリニー・モンラッシェ(ジャン・ボワイヨ)Bourgogne, France - 白辛口2000年のピュセルは今年の初めに飲んだばかり(そのときのブログ)。うなってしまうような抜群の飲みごろ感。香り高く、骨格があり、なめらか。ちゃんとエチケットを見なかったのだけれど、本当に村名だったのだろうか。年初に飲んだピュセルより印象がいい。次のバルベーラと、本日の双へき。楽天を探すと村名のピュリニーは無くてプルミエクリュばかり。ジャン・ボワイヨのピュリニー・モンラッシェを探す>2000 Barbera d'Alba Marun(Matteo Correggia)バルベーラ・ダルバ マルン(マッテオ・コレッジャ)Piemonte, Italia - 赤辛口今は亡きコレッジャ氏のラストビンテージ。リアルワインガイドの表紙にもなったワイン。久しぶりに飲んでみると、少し熟成したときの満開さ。酸を基調としながらも、しっかり凝縮感があり、華やかな香りがあたりに立ちこめる。素晴らしいバルベーラ。今日のNo1。バルベーラで素晴らしいものといえばラ・スピネッタ。ラ・スピネッタが剛だとすれば、こちらは華。どこか売っているところがあったら買いたい。マッテオ・コレッジャのワインを探す>1999 Pecchia(Gagliole)ペッキア(ガッリオーレ)Toscana, Italia - 赤辛口ワイナート12号で取り上げられて、少しブレイクしたガッリオーレ。著名なエノロゴのルカ・ダットーマ氏を起用。この作り手のスタンダードな赤は、ガッリオーレ・ロッソだけれど、その畑のなかからベストと思うブドウだけを選抜し、年間4000~5000本造ったのが、このペッキア。今までに何本か飲んでいるのだけれど、毎度閉じているワイン。今回は久しぶりに開けてみた。うーん。今まで飲んだなかでは開いている方だけれど、前のバルベーラが全開だったため、閉じていることが目立つ。サンジョベーゼらしい酸に、がっちりとしたグリップ。まだタンニンもたっぷり。次に飲むのは5年、10年後にしたい。ガッリオーレのワインを探す>1998 Lupicaia Rosso(Castello del Terriccio)ルピカイア・ロッソ(カステッロ・デル・テリッチオ)Toscana, Italia - 赤辛口購入直後に飲んだ98年は、背筋がゾッとするくらいすごいポテンシャルで驚いたことを覚えている。久しぶりに飲んでみると、これまた閉じている。あのときの感動はどこへやら。ペッキアよりは、わかりやすいけれど、今飲んでおいしいとは言いがたい。自宅のストックは長期熟成決定。ルピカイアを探す>料理編:料理名は、毎度のこといい加減。シェフはトスカーナで修行したとのことだけれど、フレンチ経験もあるだけに、イタリアっぽくない料理もある。本マグロのあぶりとカニとホワイトアスパラのサラダ カニとアスパラがおいしいタケノコのグリル これからの季節タケノコが楽しいホタテのペペロンチーノ とっても大きなホタテシーフードのリゾット蝦夷鹿とキノコのタリオリーニ 野性味あふれる味わいはGoodオマールエビのなんとか 画像では伝わりづらいのだけれど、大ぶりなオマールエビを1人で半身。爪だけでも相当大きい。bigなボリューム。和牛のパプリカソース 思ったより質の高い肉はおいしいドルチェ今日は期待していたワインが不発で、意外なワインやお店のワインがおいしかった。ともかく、幹事としてはおいしいワインがあって良かった。気が向いたら投票お願いします→
2008.03.27
コメント(2)
-
ひどすぎるぞEVIワインスクール
ブログに、単なる不満や文句を書くのは好きではないけれど、あまりにもひどく、ショッキングな出来事だったので書きたい。主題はEVIワインスクールである。このスクールには、以前わたしも少し通っていたことがあるのだけれど、校長である斉藤信次氏のあまりの幼稚さにあきれて途中から通わなくった過去がある。で、今回である。友人の友人に起きた出来事だ。友人の友人とは言っても、わたしも面識はある人物だ。その人をAさんとする。Aさんは、当時入門コースに通っていて、来期は違うコースに通う予定だった。そのことを口頭では斉藤信次氏に伝えていた。それで2/28までに入金するように言われていた。ところが家庭の事情で来期通うことができなくなり、ちょうど授業のあった2/28に来期通えない旨を伝えた―――あとで判明するのだけれど夫の転勤―――。すると斉藤信次氏は烈火のごとく怒った。当初はバックヤードで話そうと持ちかけられた。でも、このままでは丸め込まれてしまうと思い、Aさんは「みんなの前で」と提案した。これから書くのは、生徒数名がいる授業開始前の教室で起きた出来事である。よっぽど、この出来事が気にくわなかったらしく、ひどい言葉をAさんに浴びせかけた。・(口頭で)申し込んでおきながらお金を払わないのはおかしい。・Aさんが受講することを予定に入れてワインを仕入れたので授業料を払え。・お金を払えないのは、あなたの生活レベルが低いからか?etc,...文言は多少違うかもしれないが、内容はおおむね合っているはずだ。斉藤信次氏の言動があまりにもひどいため、当時教室にいた生徒もフォローした。それでも収まりがつかず、最終的にAさんは5千円払って場を収めた。このあまりにも理不尽な行動に、Aさんは泣きながら友人に電話をかけたのだった。当然、あと一回残っていた授業にも出席しなかった。念のために確認するけど、・申し込もうと思っていた講座は2008年4月スタート・その講座への参加の意志を口頭では伝えていた・2/28までに入金するように言われて、2/28に申し込まない旨を伝えた・指定期日までに申し込まなかった場合の、支払い義務規定はないつまりAさんに、一切瑕疵はないのだ。このような人物が、ワインスクールという人を教える立場の教育者であって良いはずがないし、市場から早々に退場させなければならない。はっきり言って、一連の行為は悪徳商法と一緒ではないか。そもそも仕入れなどは経営の仕事で、そのリスクを生徒に押しつけるのは筋違いだし、生活レベル云々のような個人を明確に傷つけるような発言が許されて良いわけがない。参考までに大手ワインスクール「アカデミー・デュ・ヴァン」のキャンセル規定を確認してみた。昔は、払い込んだら返金されなかったように記憶しているが、現在の規定はおおむね理解(許容)できる内容だ。受講契約成立後(入金確認後)にキャンセルを希望される場合は、所定のキャンセル料や事務手続料が発生します。1.申込講座の開講日(単発講座の場合は受講日)の一週間(7日)前までに、キャンセルの意思を示した書面(電子メール含む)が当方に到着した場合は、無料でキャンセルを承ります(ただし、以下4.に述べる銀行振込手数料、クレジットカードご利用の際の事務手数料については、返金額から差し引かせていただきます)。2.申込講座の開講日(単発講座の場合は受講日)の6日前から前日までに、キャンセルの意思を示した書面(電子メール含む)が当方に到着した場合は、キャンセル料として登録料および登録更新料の全額、受講料の半額をキャンセル料としてお支払いいただきます(以下4.に述べる銀行振込手数料、クレジットカードご利用の際の事務手数料については、別途キャンセル料に加算させていただきます)。3.申込講座の受講開始日(単発講座の場合は受講日)以降に、キャンセルの意思を示した書面(電子メール含む)が当方に到着した場合は、キャンセル料として登録料および登録更新料の全額、受講料の全額をキャンセル料としてお支払いいただきます(返金は一切いたしません)。4.キャンセルにともなう返金処理を銀行振り込みにて実施させていただく場合、振込手数料は受講生ご負担となります(返金額から差し引かせていただきます)。また、クレジットカードにてお支払いの場合は、お支払い額の5%前後の事務手数料を別途、返金額から差し引かせていただきます(手数料はカード会社により異なりますので、キャンセルの意思表示をされる際にお問い合わせください)。5.受講開始後、ご本人様の都合によって通学が困難になり、中途退学をされる場合でも、受講料の返金はいたしません(提携ローンによる分割払いの場合も、残金の清算をしていただきます)。またアカデミー・デュ・ヴァン出身の斉藤研一氏が主催する、もっとも新しいと思われるワインスクール「サロン・ド・ヴィノフィル」では、途中退会時の分割返却や月謝制など、業界としては先端の制度を採用している。斉藤信次氏を知る人たちによる人物評を集約すると次のようになる。自慢が多く、自分の意見に反するものには明確に嫌な態度をとる感情丸出しの人物例をいくつか挙げる。・授業開始前に斉藤信次氏が話すのは自慢話であることが多い。・授業に出すワインについて、洋酒辞典調べとして値段を発表するが、市場価格の2倍程度でいい加減。ふっかけすぎ。・斉藤信次氏が好きなワインを授業で出したとき、そのワインを好きではないと言うと怒気を含んだ対応をされる。また受験クラスに通っていた生徒の実話。アルザスのエーデルツヴィッカーは、シャスラ以外の混醸とAOCに規定されているので、その理由を聞くと受験クラスの生徒は、そんなことを知る必要はありません!と激高して返答された。その激高ぶりに生徒は動揺し、それ以降は質問ができなくなってしまった。ワインについての質問は―――お金を払ってスクールに通っているにもかかわらず―――面識のあるソムリエに聞くようになったそうである。シャスラを混ぜてはいけない理由を知らないことは恥ではないだろう。わたしが講師だったら、正確な理由は知らないと前置きしたうえで、自分なりの推論を説明すると思う。何よりの問題は、質問されたことに対し、一方的に激高し叱り飛ばしたことだ。はっきり言って、子供同然の行動である。わたしには、尊敬するワインスクールの講師がたくさんいる。このような理不尽な行為は、まじめに教えている人たちに対して大変失礼だし冒涜(ぼうとく)だ。このような不適格人物がいること自体、ワイン業界にためにならない。その昔「買ってはいけない」という本があったけれど、EVIワインスクールのような学校に行ってはいけない。Aさんの心の傷はまだ癒えていないので、無理には勧められないけれど、何とかこのような学校の所行を懲らしめる良い方法はないのだろうか。
2008.03.26
コメント(31)
-

ワインの熟成の大切さ
1998 Givry 1er Cru Petit Marole(Francois Lumpp)ジヴリー・プルミエ・クリュ プティ・マロール(フランソワ・ランプ)Bourgogne, France - 赤辛口\3,000くらい, すむら, 2001年11月購入Profile: だぼはぜのように何でもワインを購入していた時代。当時、よく知らない生産者だったのだけれど、メルマガであおられていたので、ものは試しにと購入。3本以上買うことはめったにないのに、6本だと送料サービスという言葉に誘惑されて6本購入してしまった。今だったら、絶対こんなことしないのになあ。 Impression: 購入直後に何本か飲んだけれど、その当時の印象は「煽るほどすごいワインじゃないし、そもそもあまり好みでない」。そんなこともあり、これまた塩漬けになっていたのを発掘し、久しぶりに飲んでみることにした。久しぶりに飲んでみると予想とは裏腹に好印象。すごいワインではないけれど、ほどよい熟成があり、キュートでチャーミング、梅酢。主張しすぎないあたりは食事と楽しむには楽しいワイン。このようなことは何度か経験しているけれど、ワインの熟成マジックはおそろしい。ワインの熟成が、いかに大切かを感じる出来事だった。気が向いたら投票お願いします→
2008.03.25
コメント(4)
-

最近飲んだワインをいくつか
最近は、ワイン会とレストラン、美術館、観光に軸足があるため、家で飲んだワインがなかなか紹介できない。すごーくおいしいとかであれば力も入るのだけれど、想像の範囲内だと力が入らないんだよね。その中からいくつかを簡単に紹介。1983 Kiedricher Sandgrub Riesling Spatlese(Robert Weil)キードリッヒャー・スタンドグラブ・リースリング・シュペトレーゼRheingau, German - 白中甘口\3,500くらい, 小田急ハルク, 2000年8月購入購入時に飲んだときにはヨレヨレだと感じ、すっかり塩漬けになっていたワイン。久しぶりに飲んでみると、柔らかくて熟成したリースリングの良さを感じる。8年間ぶりなのに、今回のほうがしっかりしている。以前の記憶はなんだったのか? ボトル差、熟成による復調、自分の体調、味覚の変化、よくわからないけれど、十分おいしいワイン。ヴァイルはとても好きな造り手。畑名付きのシュペトレーゼは高いのであまり買わないけれど、地域名のシュペトレーゼは良く買っています。予約販売・キートリッヒャー・グレーフェンベルク・R・S [2005] ロバート・ヴァイル1999 Gevrey-Chambertin V.V(Bernard Dugat-Py)ジュヴレ・シャンベルタン(ベルナール・デュガ・ピィ)Bourgogne, France - 赤辛口\8,500くらい, やまや, 2002年1月購入インクやタールのようにクローズしている。そもそもクローズしているのか、それとも違うのか、この1本だけでは判断できず。デュガは、リリース直後に飲むか、それともうんと熟成させた方がよいのかな。2003 Beaujolais Nouveau(Dominique Laurent)ボージョレ・ヌーボー(ドミニク・ローラン)Bourgogne, France - 赤辛口\3,000くらい, ヴァン・ドゥ・ラ・コリーヌ, 2003年11月購入実はボージョレファンです。そんなこともあり、ヌーボーも98年からストックしています。最近はやめちゃったけどね。購入から4年半経って、けっこう熟成しているのかなと思ったら、まだ若くて果実味豊か。リリース直後のような、はじけるような果実味はないけれど、ボージョレのグレートビンテージ03らしい果実の集中があり、ふつうにおいしく飲めます。もうちょっとピノっぽくなっていると思ったんだけどなあ。ヌーボーを探したら、まだ売っているんですね。リリースの半額近い2千円。輸入から半年経って、いまが飲み頃だと思うのだけれど。◎ボジョレー・ヌーボー・ヴィラージュ ドミニク・ローラン [2007] (ワイン/ブルゴーニュ)気が向いたら投票お願いします→
2008.03.24
コメント(2)
-

吉野梅郷・御岳渓谷・青梅めぐり
前回からの続き。梅の公園をあとにして、周囲の梅園などを散策することにした。梅の公園の周囲には、個人梅園があり、自由に見学できるようになっている。大きなところでは売店などが設置されていて、梅の公園よりもゆったり見学できる。宴会をするなら市営梅園の「中道梅園」がよさそう。梅の公園は山なので、ずっこけると場所によっては下まで転げ落ちちゃうし、トイレも山の麓にあるだけでとても込んでいる。酒飲み中年には危険な場所なのだ(笑)。宴会時は「梅の公園見学→中道梅園で宴会」が理想的か。こちらは個人梅園昼食は、梅の里 九兵衛というお店で取ることにした。ほとんどすべての料理に異なる梅が使われている。さすがに梅はおいしい。お土産で買おうと思ったけれど、この日はまだまだ歩かなければいけないので、重くなるものは断念。いま思うと買っておけば良かった。小説「三国志」「宮本武蔵」などで有名な吉川英治の記念館がある。吉川英治は大好きなのだけれど、時間の都合もあり通過。Webで紹介されていた観梅モデルコースでは、ここまでなのだけれど、今回は御岳渓谷ハイキングコースにも行くことにした。軍畑大橋。もう少し上流に登ると川沿いの遊歩道に降りられる。遊歩道をひたすら歩く。沢井駅近辺に澤ノ井の小澤酒造がある。こちらは売店&休憩所。みんな日本酒を飲んでいたけれど、まだ歩かなければならないのでビールを飲んで休憩。また同じ敷地にままごとやという直営の料亭がある。こんどはこちらに来たい。JR御嶽(みたけ)駅近辺まで歩いて、いったん終了。駅へ向かう。電車で青梅へ。青梅駅青梅駅近辺は「昭和の町」という町おこしをしている。有名なのは手書きの映画看板。赤塚不二夫会館と昭和レトロ商品博物館昭和レトロ商品博物館は、駄菓子屋風の内装で、お菓子や薬などの商品パッケージを中心に昭和のものを展示している。懐かしい人も多いのでは。幻のsasukeに維力(ウイリー)。タブクリアとIMOクリアはよく知らず。時代のあだ花的名機と書いてあったけれど、昔のカメラのことはまったく知らないので詳細は不明。きっと変わった機種なのでしょう。看板以外は意外と地味だった青梅。スイカも使える新しい自販機なのに「なぜぼろぼろ」と思いよく見ると、汚し塗装されていた。天候にも恵まれ充実した一日でした。こんどは御岳山のハイキングコースにも行ってみたい。気が向いたら投票お願いします→
2008.03.23
コメント(2)
-

吉野梅郷はすごかった
青梅の吉野梅郷へ梅を見に行ってきた。吉野梅郷とは...JR青梅線日向和田(ひなたわだ)駅から二俣尾(ふたまたお)駅までの多摩川南側に東西4キロにわたって広がる「吉野梅郷」。青梅市の梅の公園や地元農家の各梅園や、吉川英治記念館などが点在し、老木・若木合わせて2万5千本の梅が紅白の花をつける関東有数の梅の里である。(タチカワオンラインより)・吉野梅郷公式Webサイト 開花情報やルートマップなど、とても充実しているので訪問予定のかたは必見。青梅線の日向和田(ひなたわだ)駅を降りると、すぐに多摩川がみえる。自転車では、この10キロ手前くらいまで来たことがあるのだけれど、まったく川の様子が違う。中心となる梅の公園までは1キロ強。道端には、露店がたくさん並ぶ。沿道にもたくさんの梅が植えてあり、ちょうど満開。梅の公園に到着サンシュユ山頂付近は人でいっぱい。とはいえ、全体としては花見のような混雑感はない。東京生まれで東京育ちなのに、今年初めて存在を知った吉野梅郷。この日は好天にも恵まれて最高! 関東有数と言うだけのことはある。来年は花見のプレイベントとして、ワイン仲間と梅見もいいなと思った次第。このあとは梅の公園をあとにして、Webで紹介されていた「観梅モデルコース」を参考に周囲を散策することにした。つづく。気が向いたら投票お願いします→
2008.03.22
コメント(12)
-

もう少し奮起を期待したいマノアール・ダスティン
昨年秋に続き、マノアール・ダスティンに行ってきた(前回訪問時のブログ)。マノアール・ダスティンは、行きつけのワインバー「カーヴ・デ・ヴィーニュ」の本店で、シェフの五十嵐さんの元からは、多数の有名シェフを輩出している。前回は7,875円のコースだったので、今回はアラカルト。定番のものを中心に注文した。アミューズ:ブーダンノワール、トマトのブランマンジェ トマトのジュレは、なかなか面白い人参のムース、ウニとコンソメジュレ添えスペシャリテ。しっかり味のするコンソメと、甘いニンジンのムースの融合。甘い&しょっぱいのコントラストは面白い。でもコンソメはもっと薄味で良いかも。鰻のミルフィーユ(?)鰻はキャラメリゼしてあり、あいだに鰻のキモとケッパーがサンドイッチされている。キモの食感は面白いけれど、鰻は蒲焼きのほうがおいしい。日本人は蒲焼きと比較してしまうので、蒲焼きと同系統の味付けにしないほうがよいかも。子鴨とホタテのロースト、フォアグラ、ソース・ペリグ―ソースは文句なく素晴らしい。フォアグラもおいしい。鴨もおいしいけれど、ホタテをはさんでいる理由がわからない。ソースが素晴らしいだけに、もっとシンプルな料理が良かった。デセールはワゴンもあるけれど単品を注文。コースだと、2段構成で出てくる。トマトのグラタン(?)斬新だし、素直においしい! トマトのジュレの上に、クレームブリュレのようなものが乗っている。ワイン編:今回は注文しなかったけれど、ちょっとしたグランメゾン並みにフロマージュは充実している。訪問の際にはぜひ頼みたい。2005 Alsace Riesling(Trimbach) 375mlアルザス・リースリング(トリンバック)Alsace, France - 白辛口辛口ですっきりしたものが飲みたかったので、こちらをセレクト。アルザスの場合、人気生産者のものは甘いものや主張が強いものが多く、マリアージュを考えると難しいものが多い。それを考えると、トリンバックは食事と合わせやすい。久しぶりに飲んだトリンバック。さわやかな飲み口ではあるものの、単にシンプルではないエレガンスがあり、予想以上においしい。また05のアルザスがいい年なのか、そこそこ凝縮感もある。楽天で価格を調べると750mlで2千円から2千5百円くらい。十分コストパフォーマンスが高い。トリンバックのリースリングを探す>1999 Vin de pays L'Herault(Domaine de la Grange des Peres)ヴァン・ド・ペイ・レロー(ドメーヌ・ド・ラ・グランジュ・デ・ペール)Languedoc, France - 赤辛口リストには載っていないけれど、お勧めといわれた何本かにグランジュ・デ・ペールがあった。先日飲んだ98が素晴らしく(前回のブログ)、またそれほど高く無かったので注文。98同様、99も素晴らしい。99のほうが少し熟成感があって艶っぽい。ポテンシャルで98、飲みごろ感で、やや99といったところか。とはいえ98のポテンシャルには、若いながらも代えがたい魅力があり、個人的にはやや98。グランジュ・デ・ペールを探す>まとめ:アラカルトのほうがよいと聞いていたので、とても期待していたのだけれど、期待ほどではなかった。少なくとも今回頼んだメニューに限っては「アラカルト>コース」ではなかった。料理の好み次第といったころか。今思い返すと前回のコースは悪くなかった、とさえ思えてきた。過去の2回で印象に残ったのはアミューズとデセールという、レストランとしては寂しい状況。ネットを検索してみると、時期によってはもっとシンプルな料理もあるようだ。そちらを食べたかった。今回気になったのはサービス。今回3名のサービススタッフがいたが、一番ベテランと思われる女性と、それ以外の男性スタッフのレベルが違いすぎる。女性のソムリエールが、料理とワインの相談をすべてこなし、ほかの男性スタッフは皿だしなどの補助業務。女性ソムリエールが、ほかのお客との世間話に捕まっている間は、こちらから声をかけても「少々お待ちください」の一点張り。注文を取っている最中ならば仕方ないとしても、お客との世間話であればソムリエールに声をかけるくらいの配慮は必要だと思う。おかげで注文に時間がかかり、入店からアミューズが出てくるまで1時間近くかかった。とても混んでいる店やサービススタッフが少ない店であれば、遅さは仕方ないと思うけれど、十分にサービススタッフのいる店でこれは厳しい。料理とワインで1人2万円近くかかる店だけに、もうひとがんばりして欲しい。五十嵐シェフの実力はこんなものではないと思うのだが...。総合評価:★★★味 :★★★+~★★★★(もっとシンプルで力のあるメニューが食べたい)サービス:★★★(特定の人に負荷がかかりすぎている)雰囲気 :★★★(田舎のレストラン的な雰囲気。近々移転の予定)コストパフォーマンス:★★★価格帯:★★★∼★★★★(\7,000から\15,000)---評価の見方:各項目の星は、3つが普通で、5つで満点。点数のつけ方には問題点があると思うので今後も改良予定。気が向いたら投票お願いします→
2008.03.21
コメント(2)
-

風のなかの浜離宮はさんざんだった
フォトイメージングエキスポでお台場まで行ったので、帰りに浜離宮恩賜庭園のライトアップを見てきた。浜離宮恩賜庭園「菜の花まつり」 平成20年3月8日(土)~3月23日(日)ライトアップは、3月20日(木・祝)~23(日) 日没~21時この日は、けっこうひどい雨と暴風。本当に夜間開園するのかと思ったけれど、電話で確認すると、やるようだったので行ってみることにした。雨だけでなく、本当に風が強い。歩いていて何度も傘が飛ばされそうになった。また地面はけっこうぬかるんでいる。おかげで撮影には、まったく気合いが入らず。なお、すべて手持ちで撮影。今は菜の花がメインのようなのだけれど、風でなぎ倒され花は散り散り。元々はずれ年だったのか、それともピークをすぎていたのか、それとも今回の暴風が原因なのか。よくわからないけれど、けっこう寂しい状況。ひととおり見て回って、あまりの寒さに退散。一時間くらいいたけれど、ほかに出会った入場者は4、5人くらい。客に出会うより、警備員&係員に良く出会った(笑)。今回の夜間開園に合わせて、特別に売店も開いていたのだけれど、たぶん客数はゼロ。かわいそう。天候の悪さもあって、苦痛ばかりの浜離宮でした。気が向いたら投票お願いします→
2008.03.20
コメント(6)
-

フォトイメージングエキスポ2008に行ってきた
東京ビックサイトで行われているフォトイメージングエキスポ20083/19(水)∼3/22(土)に行ってきた。このイベントは、昨年に続き2回目の参加(そのときのブログ)。昨年は、自分自身、カメラ熱が盛り上がっていたこともあって、朝から参加してセミナーを聞きまくっていた。けれども現在はD300を買ったばかりだし、欲しいレンズもそれほど無い。そんなこともあって、好きな写真家「田中希美男」のセミナーを聴くのと、イベントの雰囲気を感じるために、ちょろっと行ってきた。この日(3/20)は雨と風がひどいにもかかわらず、なかなか盛況。今回はスタートが遅かったため、駆け足での見学となった。K20Dを大々的にフィーチャー。 セミナーを聴いてみたかったけれど時間不足でパス。EIZOのモニターいいなあ。現在サムソンのカラーマネージメントモニター(XL20)を持っているのだけれど、購入直後に各メーカーから低価格のカラーマネージメントモニターのリリースラッシュ。正直なところ、サムソンのカラーマネージメントソフトはショボイし、説明書がないのでわかりづらい。それにサムソンは日本の個人向けマーケットから撤退しちゃうし。あせって飛びつかずに、じっくり考えて買えば良かった。ソニーはがんばっている。Panasonicも、マクロや夜景モードを自動的に判別してくれる機能を持っているけれど、ソニーも搭載。シーンの自動識別は、コンパクトには便利な機能。わたしも、マクロモードにし忘れて「ピント合わねー」なんてことを良くやってます。一眼のほうは、他者にはない機能があってソニーらしい。モデルさんは同じ日本人とは思えないくらい細いニコンのブースでは、田中希美男氏のセミナーを聴講。いつもの毒舌暴走ぶりが面白い。サンディスクのブースに置いてあったDucati今回はじっくり見る時間がなかったけれど、できれば朝から行って、もっとしっかり見たい。気が向いたら投票お願いします→
2008.03.19
コメント(0)
-

モンラッシェにラターシュ、豪華ゴチワイン会
今回はChar@diaryさんのWebサイト"Char's Wine Bar"の9周年を記念して、恵比寿の某レストランでワイン会。ワインは、ほとんどChar@diaryさん提供によるもの(ほかにBAR10さんとお店のも少々あり)。お店以外のワインはすべてゴチです。事前にリストを聞いてびっくり。LLのモンラッシェに96のラターシュ、etc。太っ腹過ぎにもほどがあります(笑)。うれしいけど...。それと検索してみると@niftyのココログにChar@diaryさんのものを発見。更新は止まっているようだけど、こちらもやっていたんですね。http://char.cocolog-nifty.com/ムルソーとボーヌは、Charさんのネーム入り1995 Pommery Cuvee Louiseポメリー キュヴェ・ルイーズお店で注文したルイーズ。泡が細かくて上品。しっかり凝縮感があり、フレッシュな果実も感じる。最近だとzzz.santaさんにも飲ませていただいたけれど、ルイーズは安定してますね。2005 Meursault Cuvee Goureau(Hospices de Beaune)ムルソー・キュヴェ・グーロー(オスピス・ド・ボーヌ)エルバージュ:Philippe Bouchard(フィリップ・ブシャール)軽いオークの香り。果実味が豊かなためアタックは、若干ゆるめに感じるけれど、奥底にはきっちり酸がある。プルミエ・クリュと言っても見劣りのない出来で、今飲んでおいしい。オスピスのムルソーを探す>1970 Meursault Cuvee Humblot(Hospices de Beaune)ムルソー・アンブロ(オスピス・ド・ボーヌ)エルバージュ:Raoul Clerget(ラウル・クレルジェ)少し濁った茶色。危険な色だと思ったけれど、やはりお亡くなりになっていました。シェリー&麦芽?(穀物系の発酵物)の香り。飲めなくはないけれど、わたしはダメでした。2002 Chablis Grand Cru Les Clos(Vincent Dauvissat)シャブリ・グラン・クリュ レ・クロ(ヴァンサン・ドーヴィサ)フリンティーでミネラル豊か。レ・クロならではの圧倒的な存在感。とても長いアフター。若いなりのおいしさがあり、現在選択しうるドーヴィサの中ではトップクラスの出来(飲み頃)ではないだろうか。BAR10さん、ありがとう。ドーヴィサのレ・クロを探す>1998 Montrachet(Louis Latour)モンラッシェ(ルイ・ラトゥール)コンディションがよく若々しいものの、少々クローズ気味。がっちり酸も強く硬派なワイン。いま飲んでおいしい2本に挟まれてしまったため、すこし印象が薄い。モンラッシェを飲んで気になるのは、モンラッシェの風格があるかなのだけれど、若すぎてわたしには判断できず。最低でも5年、できれば10年寝かせたい。2004 Beaune 1er Cru Cuvee Nicolas Rolin(Hospices de Beaune)ボーヌ・プルミエ・クリュ キュヴェ・ニコラ・ロラン(オスピス・ド・ボーヌ)エルバージュ:Philippe Bouchard(フィリップ・ブシャール)04にしては凝縮感があり、少し青っぽい雰囲気も。香りも豊かで、独特のつやっぽさがあり前出のムルソーよりも、さらに好み。オスピスというと「安定はしているけれど驚くようなものが少ない」ということで、最近はまったく手を出していないのだけれど、このような良いボトルに当たると十分にCPがよいワインだと感じる。正直なことを話すと、グラスに注いだ当初のラ・ターシュより、こちらのほうが好みでした。05が6千円アンダーなら、十分良いのではないでしょうか。オスピス・ド・ボーヌ プルミエ・クリュキュヴェ・ニコラ・ロラン [2005] 【750ML】1996 La Tache(DRC)ラ・ターシュ(DRC)こんなワインを飲めるとは。電車の中で「3本あるなら1本くらい」と冗談交じりに話したら、本当に出していただけました。抜栓当初は閉じこもっていて少々不安定な感じもあったけれど、時間が経ってからは、むくむくとパワーを発揮。熟成したときのような煌(きら)びやかさはないけれど、複雑で密度感のある酒質はさすがの存在感。とはいえ、まだ相当幼児虐待。真の飲み頃はいつだろう。最低でも10年、できれば20年以上だろうか。飲み頃になるのが待ち遠しい。Char@diaryさん、本当にごちそうさまでした。在庫ありの楽天最安値は30万!1997 Bonnezeaux Cuvee Zenith 500ml(Rene Renou)ボンヌゾー キュヴェ・ゼニス(ルネ・ルヌー)Loire, France - 白極甘口こちらもお店。ボンヌゾーではトップクラスに評判の高いルネ・ルヌー。今年の初めに97を飲んでいる。それと比べるとだいぶフレッシュ。しっかり甘みがありながらも、ロワールならではの酸があり、ソーテルヌのように重くない軽快なデザートワイン。何でも熟成させがちなのだけれど、ボンヌゾーは若いうちのほうがおいしいのかも。岩牡蠣など、牡蠣3種。岩牡蠣は大きい 青く光っているのは、氷の下にライトが入っているから。サーモンとホタテのカルパッチョ温かい牡蠣3種ロブスターのリゾット(?)最高級和牛とフォアグラのミルフィーユ グレービーソースデザートうたげのあとChar@diaryさん、ワインだけでなくお店まで手配していただきありがとうございました。感謝のあまり言葉もありません。気が向いたら投票お願いします→
2008.03.18
コメント(6)
-

驚きのグランジュ・デ・ペール
昨日からの続き。ラピエールもよかったけれど、絶対的にすごかったのはこっち。1999 Vin de pays L'Herault(Domaine de la Grange des Peres)ヴァン・ド・ペイ・レロー(ドメーヌ・ド・ラ・グランジュ・デ・ペール)Languedoc, France - 赤辛口\6,000くらい, KAJIWARA, 2002年8月購入Profile: 南仏でトップクラスの生産者グランジュ・デ・ペール。高品質&高級、南仏ワインの先駆けが、ガサックやトレヴァロンだとすれば、グランジュ・デ・ペールは、そのセカンドグループ。当主は、ガサックやトレヴァロン、シャーヴなどで修行し、ガサックのとなりにドメーヌを設立。1992年がファーストビンテージ。シラー、カベルネ・ソーヴィニヨン、ムールヴェードルのブレンド。 Impression: このワインを知人から教えてもらったときは、「ラングドックのロマネコンティ」と、いかにもなキャッチフレーズだったため、その知人がわたしの師匠格に当たる人物だったにもかかわらず、「それは思い入れ強すぎだろう」と思っていた。実際に飲んでみても、荒々しく、とうていロマネコンティに及ぶものではないと考えていた。とはいえ、ちょっぴりポテンシャルも感じたので、その後に購入したのがこのワイン。#今になって考えてみると、希少性、20hl/haという低収量、高品質ということでロマネコンティと言ったのか?今回久しぶりに開けてみると、開けた瞬間から満開。しっかり凝縮感がありながらも、濃すぎず、ワイルドでスパイシーで、うまみ成分たっぷり。ガリーグ。とくに口に含んだときのうまみのつまり方は半端ではない。上質なシャトーヌフ・デュ・パプに勝るとも劣らない素晴らしさ。人物に例えれば「30代の藤竜也」。ワイルドなのだけれど、洗練されたかっこよさがあり、ダンディ。いま飲んでも素晴らしいけれど、まだ将来も楽しみ。今年のビックリランキング(驚きの度合いと、ワインの味わいの総合評価)では、プロヴィダンスに続き2番手候補。良いビンテージのグランジュ・デ・ペールとガサックが欲しい。でも、ネットで探してみても、あまりないんだよね。このワインを飲むときは、ある程度熟成させるのがお勧め。若いビンテージでは、強すぎて良さがわからないかも。それにしても、この幸運続きは怖い。確率は、いずれ平均値に収束されるものなのだ。グランジュ・デ・ペールを探す>[2004] ラ・グランジュ・デ・ペール 750ml 赤【コク辛口】気が向いたら投票お願いします→
2008.03.15
コメント(6)
-

今年は個人的にワインの当たり年か?
今年は、当たりのワインに出会うことが多い。それも自分で所有しているもの。ある程度自信があるものでも、予想より素晴らしいことが多いし、これは微妙と思うものさえ、予想以上のおいしさをみせてくれる。それが「ちょっとおいしい」という程度ではなく、「すげー、うまい」と驚くくらいのおいしさなのだ。はずれたのはシャトー・ド・フューザル白94とシャトー・セント・ジーンのサンク・セパージュ96くらい。今年の驚きヒストリーで気になったものを挙げると、筆頭はプロヴィダンスのプライベート・リザーヴ97。高価なワインではあるものの、エイジングポテンシャルには疑問を持っていたのでまったく期待していなかった。それが尋常じゃない完成度。唯一無二の個性。あまりの素晴らしさに、楽天を検索しまくってしまった。■プロヴィダンス・プライヴェート・リザーヴ [2000]750ml続いて、無名生産者のコルトン・シャルルマーニュ75。バッドビンテージだし、80年以前のブル白でほとんど良い経験をしたことがない。ところが、貧弱なビンテージを感じさせないおいしさ。よい白をバンバン開けているワラビワイン会の歴史でもトップクラス。偉大ではないけれど絶妙飲みごろ感には感服。あとは最近飲んだばかりのボーカステルのシャトーヌフ・デュ・パプ・ブラン96。ちょうどよい熟成で、ローヌ白嫌いのわたしにとっては驚き。また↓のワインは、ある程度大丈夫だろうとは思いつつも、予想以上に素晴らしく、そのワイン会ではトップクラスのパフォーマンスをみせてくれた。ドーヴネのレ・ナルヴォーシュレールのシャン・デ・ゾワゾーダル・フォルノ・ロマーノのヴァルポリチェッラヴァンサン・パリのコルナス・グラニ 60 V.Vそして今回。とある自然派ワイン好きの会に、↓のワインを寄付として持っていったところ、これも当たり。ブルーイィは、完全にやばいと思っていただけに驚いたし、グランジュ・デ・ペールの素晴らしさには同席したみんなが感心する次第。・1998 Brouilly(Marcel Lapierre) ブルーイィ(マルセル・ラピエール)・1999 Vin de pays L'Herault(Domaine de la Grange des Peres) ヴァン・ド・ペイ・レロー(ドメーヌ・ド・ラ・グランジュ・デ・ペール)とりあえずはラピエールから紹介。携帯画像で汚くてすみません。1998 Brouilly(Marcel Lapierre)ブルーイィ(マルセル・ラピエール)Beaujolais, Bourgogne, France - 赤辛口\2,500くらい, よしや, 1999年8月購入自宅で9年熟成のクリュ・ボージョレ。裏ラベルには「14度以下で保存すること」とフランス語で書いてあるのに、セラーに入れていない期間もあった。蝋封は割れてなく、液漏れもないけれど、ものすごいオリ。エチケットを見ると、domaine par Les MarcellinsChateau du Prieureという生産者の表記。このころはわからないけれど、現在マルセル・ラピエール氏がちゃんと関わっているのは、モルゴンやキュヴェ・マルセル・ラピエールなど一部のワインだけ。それらはMarcel Lapierreという表記されている。それら以外はMarcel Lapierre et Christophe PacaletChateau Cambonのどちらかで、ラピエール氏はほとんど関与せずに、クリストフ・パカレが仕切っている。けっきょっくこのワインはどちらでもないので不明。で、本題はこちらの味。グラスに注ぐとロゼ並みの薄い色合い。少し茶色が入っているので、かろうじて熟成した赤だとわかる。味わいは、多少のシンプルさは否めないが、とろりと柔らかく、奥底には果実味も残っている。熟成香も少々。これだけ楽しませてくれたら十分。これがモルゴンやキュヴェ・マルセル・ラピエールだったら、どうだったのだろうと楽しみが広がる。セラーで寝かせているキュヴェ・マルセル・ラピエールのNV(2000)は、将来が楽しみ。どこかのブラインドワイン会で使おう。マルセル・ラピエール モルゴン [2006] 750mlキュヴェ・マルセル・ラピエール[2003]気が向いたら投票お願いします→
2008.03.14
コメント(6)
-

ムートン・ロスシルド ワインラベル原画展&青山ユニマット美術館
六本木ヒルズの森アーツセンターギャラリーで開催されているムートン・ロスシルド ワインラベル原画展と青山ユニマット美術館に行ってきた。青山ユニマット美術館で開催されているのはシャガール展―――だと思っていたのだけれど、ブログを書くためにWebを確認すると違うみたい。シャガールは常設展示で、特別展示はモネ、ドガ、ルノワールなどの印象派のようだ。4階、3階、2階が展示室の、こぢんまりとした美術館。1階で受付を済ませて4階から見るようになっている。4階には20点近いシャガール作品が展示されている。質的には中くらい。シャガールらしいものもあれば、後期印象派をほうふつさせる、見ただけでは判別不能なものもある。個人的に、国内の美術館が所有するシャガールで印象的なのは川村記念美術館のもの。大型作品でシャガールらしさがあふれている。この春に、リニューアルを経て久しぶりに開館するので行く予定。下のフロアには、素朴派展―――ルソーの小作が1点あり―――と、印象派展と題しモネやドガなどが展示されていた。モネのルーアン大聖堂は、なかなかの作品。ドガもよかった。こぢんまりとした美術館だけに、作品数も少なく、大美術館のような満足感は得られないけれど、ゆっくり見られるのが良いところ。シャガール好きならば行って損はないと思う。次は森アーツセンターギャラリーのある六本木ヒルズへ。青山墓地の道こちらではムートン・ロスシルド ワインラベル原画展2008年3月1日(土)~3月30日(日)が開催されている。この展覧会は、世界各国を巡回しているようだ。ユニークなのは展示方法。50センチ四方くらいの小さなケースに、原画および関連資料、ムートンのエチケット、画家の写真などがまとめて収納されている。この箱が、アートラベルのスタート年の45年から順に展示されている。今まで漠然としかエチケットを見ていなかったけれど、あらためて原画を見ると、「このような絵だったんだ」と思うことが多い。また今ではカラフルな印象のあるムートンのエチケットだけれど、60年代くらいまでは地味な色遣いのものが多いのも意外だった。あと93年のエチケットが2種類あるのは有名な話。しかし、それ以外のビンテージでも、複数バージョン存在するビンテージがいくつかあるのは知らなかった。図録が売っていたので買おうと思ったら、なんと\8,400! ものすごい豪華でもなく、どちらかといえば軽めの図録なのに、である。いくら何でも高すぎます。ということで、今回は買わずに退散。純粋にアートという視点で見ると退屈な部分もあるかもしれないけれど、ワイン好きなら、見ても損をしたとは思わないはず。会期末まであと少し。ムートンファンでなくても、ワイン好きの一般教養として面白い。ムートン・ラベル・コレクションなるWebサイトを発見。ムートンの全ラベルを見れます。気が向いたら投票お願いします→
2008.03.13
コメント(4)
-

評判の高い北島亭でランチ
突然、zzz.santaさんたちと北島亭でランチ。超有名店でありながら初訪問。友人の間でも評判の良い店だけに期待が高まる。場所は四谷と四谷三丁目の中間地点。靖国通りより奥まった、普通の商店街っぽい通りのビルの1階にある。席数は20席程度。フレンチとしては普通の内装。テーブルには白いクロスがかかり、カトラリーはしっかりした日本製。メインの肉のときにはラギオールが出てきた。プレゼンテーション・プレートが置いてあるところに、高級感を感じる程度。ただしプレゼンテーション・プレート以外のお皿は、白地で普通のものが多い。春らしいピンクのプレゼンテーション・プレートサービスは、厨房を兼ねた若い男性スタッフが2名。厨房を兼ねているせいもあって、エプロン姿。1人は元気があって良いけれど、もう1人はもっと修行する必要あり。ランチメニューは大きく分けて三種類。一つめは5千円から数千円刻みの料理固定メニュー。料理は決まっていて、金額によって皿数が変わる。二つめは\10,500のプリフィクスコース。こちらは冷たい前菜、温かい前菜、魚、メインと、それぞれのジャンルから好きなものを計4種類チョイスできる。ただし冷たい前菜以外は、グループで同じものにする必要あり。三つめはアラカルト。ギャルソンが、黒板に書かれたメニューをフレンドリーかつ熱心に説明してくれる。今回は、スペシャリテを食べたかったのと、夜の1万5千円のコースとほとんど変わらないと言うことだったので、\10,500のコースをチョイス。量が多いことで有名な北島亭だけれど、食べる量に合わせて変更してくれる。赤座エビのビスク(スープのようなもの) エビのエキスたっぷり。後味はスパイシー。フランス料理にしては熱々で出てくる生ウニとコンソメゼリー カリフラワークリームソース ものすごく評判が良いので期待していたけれど普通。涙は出ない。白子のソテー これも熱々。表面はカリッと。なかはトロトロ。金目鯛 火入れはまあまあだけど、無造作ビストロ的なつけ合わせには少々ビックリ。赤ワインのソースがおいしい。牛のイチボ肉 そこそこ肉は良いし火入れも良いけれど、かなりしょっぱい。今まで塩分に対しては許容範囲が広いと思っていたけれど、白子のソテー以降は塩が強い。アスパラはおいしい。ブランマンジェアイベリーかと思うくらい、ものすごく大きなイチゴ料理全体の印象は、期待が大きかっただけに失望感がぬぐえない。実際のところ、そこそこのレベルではあるものの、塩が強すぎるし、ここまでビストロチックな料理だとは思わなかった。ビストロ料理が嫌いなわけじゃないのだけれど、このクラスの値段なら目を楽しませる要素も必要なところ。味わいだけを評価しても驚くようなお皿に出会えなかった。前提知識が無ければ、もう少し高い評価になったと思うけど...。ワイン編ワインの品揃えは、シャンパーニュ、ブルゴーニュ、ボルドーがほとんど。それほど品揃えは多くない。またブルゴーニュの場合、とくにこれといった生産者のものが無いので、ワイン好きには少々不満足。価格は、ショップの2倍程度。NVのテタンジェは\8,500。ハウスワイン赤白は\5,250。1万円以上が主体。今回は以下の2本を注文。NV Taittinger Brut Reserveテタンジェ・ブリュット・レゼルヴ最初冷えていないときはイマイチと思ったけれど、冷えてからはまとまりが出てきた。エレガントなシャンパーニュ。2002 Volnay 1er Cru Les Fremiets(Jean Boillot)ヴォルネイ プルミエ・クリュ レ・フルミエ(ジャン・ボワイヨ)ヴォルネイらしい透明感。奥に固さは残っているものの、なめらかで張りのある味わいは好印象。ジャン・ボワイヨのヴォルネイを探す>まとめランチとディナーの評価は一致しないと思っているので、星をつけるのははばかれるけれど、それでも味に星をつけるならば、★★★+価格を考えれば、もう少しがんばって欲しいところ。この日、はたして北島シェフはいたのだろうか。信頼できる友人の評判&みんなの評判と、今回の味わいはどうしても一致しない。夜のアラカルトで、もう一度評価したいけれど、けっして安くはないだけに悩ましい。行きたい店がいっぱいあるんだよね。それと、もう少しワインリストを充実して欲しい。できれば1万円前後。※★3つが普通で、★5つで満点。総合評価:保留。ディナーでアラカルトを食べて評価したい。味 :★★★+サービス:★★★(若くて元気な熱心さに免じて★★★。料理の価格を考えれば要努力)雰囲気 :★★★コストパフォーマンス:★★★価格帯:ランチ:\5,250から気が向いたら投票お願いします→
2008.03.12
コメント(4)
-

ワラビでブル白そろい踏み&アンヌ・グロのリシュはやっぱりよかった
定例のワラビワイン会。本数が多いのと、遅刻&一気飲みでヘロヘロになることが多いのだけど、今回は選択と集中(?)のかいあって、最後まで全然平気でした。NV Duval-Charpentier Brut Traditionデュヴァル・シャルパンティエ ブリュット・トラディションVerzenay, Champagne, France - 泡白辛口泡は弱めで柔らかい。\3,000アンダーと考えると十分納得のいくシャンパーニュ。1998 Meursault Les Narvaux(Domaine d'Auvenay)ムルソー・レ・ナルヴォー(ドメーヌ・ドーヴネ)Bourgogne, France - 白辛口わたしの持参品。抜栓直後からドーヴネ節満開。輝くゴールドイエロー。ゴマ、揮発香。オイリーで、しっかりしたストラクチャーと凝縮感。ムルソーとは思えない引き締まりぐあい。アペラシオンの個性うんぬんと言うより、ドーヴネ味。これだけ凝縮感があっても下品でないのは、さすがマダム。余韻も極めて長い。先日飲んだ99と比べると、こちらのほうが飲み頃。今日の白No1。一昨年くらいまでは、ドーヴネ&ルロワと相性がよくなかったのだけれど、最近はよいものに出会うことが多い。ドーヴネのレ・ナルヴォーを探す>1995 Corton-Charlemagne(Louis Latour)コルトン・シャルルマーニュ(ルイ・ラトゥール)Bourgogne, France - 白辛口しょっぱいコルシャル。ボディは頼りなく少々よれ気味。ドーヴネのあとに出たのと、弱めの酒質もあって、このルイ・ラトゥールとフルーロ・ラローズは印象が薄い。hidepxさんによると、以前飲んだボトルはもっとよかったとのこと。1986 Chassagne-Montrachet 1er Cru La Rocquemaure(Domaine Fleurot-Larose、Rene Fleurot & Fils)シャサーニュ・モンラッシェ プルミエ・クリュ ラ・ロックモール?(フルーロ・ラローズ)Bourgogne, France - 白辛口蔵出しということもあり、86とは思えない若さ。くせのないニュートラルさ。きれいではあるのだけれど、この順番では分が悪い。1986 Montrachet(Paul Reitz)モンラッシェ(ポール・レイツ)Bourgogne, France - 白辛口酸化気味でシェリー風味も少々。とはいえ86年であれば、このくらいは許容範囲だと思う。マロンやべっこう飴のような香り。たっぷりとしたフルボディでトロトロ。ではあるけれど、モンラッシェの風格があるかと聞かれれば、否。良くも悪くもポール・レイツ。個人的には評価していないポール・レイツだけに、もっと悪い状況も考えていたけれど、それほどはひどくなくてよかった。BAR10さんはよくないかもしれないけど(笑)。2001 Richebourg(Anne Gros)リシュブール(アンヌ・グロ)Bourgogne, France - 赤辛口zzz.santaさん。こんなワインを提供いただけるなんて偉大すぎです。感謝。固すぎるのではと心配していたのだけれど、なかなかどうして。けっして全開ではないけれど、その香りをかげば、深遠なる偉大さをひしひしと感じる凄み。奥に隠れてはいるけれど、うねるような胎動感。あきらかに偉大なワインの片鱗。何もわからないくらいクローズしていなくてよかった。ああ、欲しいなあ。アンヌ・グロのリシュブールを探す>NV Chambers Grand Muscat Rosewood Vineyards(375ml)チェンバーズ グランド・マスカット ローズウッド・ヴィンヤーズRutherglen, Victoria Australia - 甘口パーカーさん高評価の酒精強化。このGrand Muscatは、過去には99点を取ったこともあり、最新の評価では96点。そういえば7,8年前に一度飲んだことがある。そのときの印象は「なぜそんなに評価されるのかわからない」(笑)。わたしの好みは別として、値段のわりには高評価なワインだと思っていたのだけれど、公式サイトで調べると、エントリーのMuscatが$16なのに対し、Grand Muscatは$100。こんな高いとは驚きだし、zzz.santaさん太っ腹すぎです。この価格差は何?と思って調べてみると、こちらは第一次世界大戦からストックしている原酒をブレンドしているようだ。で、グラスに注いでみると、マスカットは白ブドウだけど、熟成もあって琥珀色。しっかり甘みは乗っているけれど、酸はそれほど強くない。味わいの表現が難しいのだけれど、どちらかと言えばバニュルス系。そっくりというわけでなく、大きな方向性としてはそっちのイメージ。ソーテルヌでもなく、アイスワインでもなく、トカイでもないという意味で。みなさんはどう感じたかはわからないけれど、酸の弱い甘口は得意ではないので、どうしてもすごいワインだとは思えなかった。N/Vチェンバース ラザグレン・グランド・マスカット(375ml)とりあえず試したいという方は、↓のスタンダードから。パーカーポイント95 チェンバーズ・ラザグレン・マスカット NV 375ml(白)今回は5名で6.5本。1人当たりの分量も十分多いし、ゆっくり飲めたのはよかった。いつもみなさんありがとうございました。気が向いたら投票お願いします→
2008.03.11
コメント(10)
-

ルーションの自然派マジエール
NV V.d.T Maziere(J.M.Labouygues)Roussillon, France -赤辛口\4,000くらい, エスポア・ナカモト, 2007年12月購入Profile: Jean Michel Labouyguesは、自然派の生産者。無名生産者のV.d.Tでありながら、4千円近くする高級品。いくら品質がよいとはいえ、無名生産者の高価なV.d.Tを仕入れるのは、インポーターや酒屋にとって、すごい度胸。わたしは店主と面識があったので買ったけれど、ふつうは売りづらいし、買いづらいよね。セパージュは、カリニャン 100%。 Impression: 抜栓直後は、松の樹液や揮発性オイルなど、独特の雰囲気。それでもウルトラシルキーな口当たりは印象的。このワインが真骨頂を発揮するのは、抜栓して十分に時間がたってから。抜栓直後にあったツンとした香りは飛び、ワインの本質が見えてくる。基本的には自然派スタイルではあるものの、ツルンとした柔らかい口当たりに、何とも言えない複雑なボディ。凝縮感はあるのだけれど重くない。似ているワインがないので、他ワインとの相対評価はできないけれど、抜栓後に十分時間をおけば4千円近い値段を十分納得できる品質。このワインを飲むときには、数時間前にデカンタージュするのがお勧め。少人数ならば大ぶりのグラスでゆっくり飲んでもよい。抜栓当初の香りの好悪や、飲み方を選ぶので、個人によって評価が違うワインだと思うけれど、好きな人にとっては良いワイン。気が向いたら投票お願いします→
2008.03.10
コメント(2)
-

ローヌ品種の白連投 ターリー白
前回ボーカステルの白を飲んだので、ローヌ系品種の白ということで選んだのがこれ。エチケットが破れてます。そして飲んだあとなのでビンは透明だけど、ワインが入っているときは黄金色。2001 Turley The White Coat San Luis Obispo County(Turley Wine Cellars)ターリー・ザ・ホワイト・コート サン・ルイ・オビスポ・カウンティNapa, USA - 白辛口\7,000くらい, 2004年1月購入Profile: ジンファンデルで有名なターリーの白。赤で有名な造り手だけに、白はけっこうレア。いまでは楽天でも買えるけれど、当時は買えずに、どうしても飲みたくて海外輸入したもの。ルーサンヌ主体で、他にはヴィオニエ、マルサンヌなどのブレンド。 Impression: ボーカステルの白と同じくルーサンヌ主体だけに、雰囲気は似ている。トリュフ香。こちらのほうが若く、アルコール度も高いため(14.6度)、ボーカステルよりも元気な印象。けれどもアルコールの高さほど、悪い圧迫感はない。このあたりのうまさは、さすがターリーといったところ。最近ターリーから興味が離れてしまったため、期待していなかったのだけれど、これもそこそこおいしいワインでした。ターリーの白を探す>ターリー ザ・ホワイト・コート [2002]Turley The White Coat気が向いたら投票お願いします→
2008.03.09
コメント(2)
-

トリュフに合わせたいボーカステルのシャトーヌフ・デュ・パプ・ブラン
1996 Chateauneuf-du-Pape Blanc(Chateau de Beaucastel)シャトーヌフ・デュ・パプ・ブラン(シャトー・ド・ボーカステル)Cotes-du-Rhone, France\7,000くらい, 玉喜, 1999年8月購入Profile: 帝国ホテルで気になったことが一つ。となりのテーブルが注文したワインは1本だけなのに、それがボーカステルの白だったこと。たぶんVVじゃなくて、こちら。視界の関係でどのような人が座っていたのかわからないけれど、1本しか注文していないのに―――グラスワインは注文してたかもしれないけど―――、それがボーカステルの白とは渋すぎる。ただ者ではないと思った。それで気になって開けたのが、塩漬け状態だったこれ。ローヌの白は苦手という意識があるので(コンドリューは除く)、すっかり忘れ去られていた。エチケット。ノーマルキュヴェは白赤エチケットが同じでキャップシールの色が違う Impression: ルーサンヌ80%、ブールブラン20%。グラスに注いでみると、ソーテルヌもビックリの黄金色。ピークアウトしているかと思って飲んでみると、とても健全。若いときの角が落ちて、なめらかで一体化。そして紛れもなく黒トリュフ香。表現力が乏しくて申し訳ないけれど、ポムロールから想像する土っぽいのではなく、もっとハイトーンで、帝国ホテルで食べたフレッシュの黒トリュフ(嫌みのようですみません)。この何とも表現しづらい独特の香りと、しっかりとしたボディが織りなす熟成マジック。予想を裏切るおいしさ。ストックしてあるVVも飲んでみたくなりました。これを飲んで思ったのは、ソムリエのお薦めだったかもしれないということ。黒トリュフとは同系統の香りがあるので、それとマリアージュさせたのかもしれない。もし自分の意志で選択したとしたら、すごい人。ボーカステルのシャトーヌフ・デュ・パプ・ブランを探す>楽天を探してみると意外にもほとんどない。VVのほうがあるくらい。価格差が少ないならVVを選びたい。シャトー・ド・ボーカステル シャトーヌフ・デュ・パプ 白 2002 750ml (ワイン)【超得03...気が向いたら投票お願いします→
2008.03.08
コメント(15)
-

帝国ホテルのレ セゾンでトリュフづくし
おいしい物好きの知人から帝国ホテルのメインダイニング「レ セゾン」が素晴らしいという話を聞き、さっそく行ってきた。当初は、最近の豪遊続きもあって躊躇したのだけれど、フランス人シェフがいつまで日本にいるかわからないし、シェフのスペシャリテ“ジェラール・ボワイエ”直伝のトリュフのパイ包み焼きは、シーズンの最後。これを逃したら一生食べられないかもしれないと思い、がんばって行くことにした。シェフは、シャンパーニュ地方の名門レストラン「レ・クレイエール」出身のティエリー・ヴォワザン氏。レ・クレイエールが三ツ星時代のシェフ「ボワイエ氏」のもとで16年間働いていたらしい。レ・クエイエールは、シェフが替わって二ツ星に降格後の2004年に訪問したことがある(そのときのブログ)。ものすごく立派な庭と建物が印象的だった。同席した友人曰く、ボワイエさん時代のほうがおいしかったとのこと。場所は、帝国ホテル本館の中二階。入り口には美食家として有名なブリア・サヴァランの言葉が掲げられている。Webには席数94席と書いてあったけれど、個室も数個あるせいか、広すぎずにちょうどよい感じ。室内はライトブラウンの色調で統一され落ち着いた雰囲気。テーブルは、十分な広さがある円テーブル。席間もグランメゾンらしく十分なスペースを取っている。カトラリーはクリストフル。食器のメーカーは不明だけれど高級感のあるものを、2枚重ね、3枚重ねで使っている。下の写真では、寄りすぎているせいもあって真っ白に見えるけれど、実際には彩り豊かな縁取りがついているものが多い。コースメニューは、16,800円と22,000円。それと黒トリュフづくしの44,000円。スペシャリテの「“ジェラール・ボワイエ”直伝のトリュフのパイ包み焼き」はアラカルトで19,950円もするので、高いと思いつつも44,000円のコースを選択。アラカルトで頼む度胸がなかった。料理は以下のとおり。途中まで写真は撮らないつもりだったけれど、料理とお皿の美しさに負けて撮りたくなってしまった。また撮っても雰囲気を壊さない様子だったので、ギャルソンに許可をもらってから撮影。最初に出てきたのは、フォアグラとナッツを丸めて、キャンディのように包んだもの。驚いたのは、その器。厚さ7、8センチくらいはありそうな透明な氷でできている。アミューズ:コンソメ?のジュレと、クロケットこれにもトリュフが少し乗っている。・黒トリュフのスクランブルエッグてっぺんをカットした卵の殻に、とろとろの卵とトリュフのみじん切りが入っている。・クリーミーなアーティチョークのスープ カプチーノ仕立て 黒トリュフをあしらって次の料理から撮影。インカの目覚めと48ヶ月熟成コンテのニョッキ トリュフを散らしてカボチャのピュレとアーモンドのクーリこの前のスープのトリュフも厚かったけれど、こちらはさらに厚く3、4ミリはありそう。この写真だと伝わらないけど、つや消しで真っ黒のお皿と料理の盛りつけが美しい。セロリのポワレ トリュフのジュと独特な味のソースが絶品。季節の野菜のポトフ仕立て トリュフと花塩を散りばめてスープなしのポトフ。スープは別のカップでサーブ。野菜がおいしい。“ジェラール・ボワイエ”氏 直伝の黒トリュフのパイ包み焼き一緒に入っているフォアグラが絶品。ここで一番感動するはずだけど、このあたりになるとトリュフに飽きてきて感動は薄れる。でも、たっぷりかかったソース・ペリグー(マディラとトリュフのソース)はおいしい。フロマージュ・ブランのソルベ トリュフ風味ヨーグルトのようにフレッシュな風味。これにも、これでもかと言うほど、たっぷりトリュフが乗っている。小さなお菓子滑らかなクーランショコラトリュフの入ったクレームブリュレと赤ポルト酒のクーリフォンダンショコラのようでトロトロ。グランメゾンはデセールとプティフールが素晴らしい。カフェと自家製ショコラ一番右のショコラには、これまたトリュフが練り込んである。これほど黒トリュフを食べたのは初めてだし、今後もないだろう。通常はスライサーでカットしたものや、みじん切りになっているものに出会う程度だったけれど、このコースではおそろしくふんだんに使われている。おかげでトリュフの食感や香りを完全にマスターした。まあ、そりゃそうだ。昨年はフィレンツェで白トリュフをたくさん食べたので、とりあえず白黒マスターつもり。ただし、惜しむらくは、トリュフの香りは素晴らしいものの、味わい自体は(肉や魚と比べると)それほどおいしいものではないということ。メニュー内容を知っていたので事前にわかっていたことだけど、料理の中盤あたりで、「肉か魚を食わせろー」という気分になってしまった。今回はレ・セゾンの実力を計る目的もあったのだけど、特殊なメニューだけに他店との比較が難しい。とはいえ、ソースはグランメゾンらしい素晴らしいできばえ。またサービス陣は、他グランメゾンと比べると年齢は高めで、重厚感と気配りを兼ね備えた素晴らしいもの。ロオジエも昔はよかったけれど、昨年訪問したときはだいぶ若返って、よかったときと比べると低下を感じた。そんなこともあって、レ・セゾンのサービスは日本最高レベルではないだろうか。シェフのティエリー・ヴォワザン氏も、食事のはじめと終わりにあいさつに来てくれた。いちおう日本語もしゃべれるようだ。特殊メニューだけに味の評価はひかえたいけれど、サービスと雰囲気には最高評価をあたえたい。通常メニューでぜひ再訪したい。とはいえ高額だけに秋までは無理かも。サービス:★★★★★雰囲気 :★★★★★ワイン編ワインはフランスだけでなく、イタリア、ドイツ、アメリカ、日本、オーストラリア、ニュージーランド、チリなど、世界中のワインが網羅されている。フランスではボルドーが一番の充実で次にブルゴーニュ。ブルゴーニュ好きにはもう少し充実して欲しいところ。値付けは店頭価格の2、3倍。一部高騰が激しいものについては、それほど高くないものもある。NVのシャンパーニュはテタンジェやゴッセが9千円台後半。注文したのは以下の2本。1998 Pol Roger Brut Chardonnayポール・ロジェ ブリュット・シャルドネChampagne, France - 泡白辛口トリュフにはブラン・ド・ブランがお勧めということで、最近相性のよいポール・ロジェを選択。ブラン・ド・ブランらしい繊細さと98年らしいしっかりとしたボディ。時間がたつと良い香りも出てきてなかなか。1995 Ch.Larmandeシャトー・ラルマンドSaint-Emillion Grand Cru, Bordeaux, France - 赤辛口トリュフに合わせるということで勧められたのがポムロールとサンテミリオン。それほど高額ではなく、ある程度熟成感もあるものを、ということで勧められたのが、このラルマンドとボールガール。迷ったすえ、こちらを選択。たぶん初めて飲むシャトーだけれど、これは当たり。タンニンは8、9割溶け込みなめらかで、まだ果実味も残っている。比較的に軽やかなボディながらも、出始めの熟成香は心地よく、トリュフと合わせるには良い雰囲気。すごいワインではないけれど、おいしいワイン。家でも試したいシャトー。Adrien CamutのカルヴァドスPrivilege 18年あまりハードリカーは飲まないけれど、レストランで勧められるとなぜか飲みたくなってしまう。帰宅後に、もらって帰ったエチケットを見ると、それぞれワインの説明が印刷されていた。さすが帝国ホテル。食後は、レストランで予約してもらったオールド・インペリアル・バーへ。このバーは、フランク・ロイド・ライト設計の旧帝国ホテルの面影を残している唯一の場所。↓の写真は公式Webから拝借。ホテルのバーというと落ち着いて静かというイメージだけれど、とてもにぎわって活気がありビックリ。ロンドンパブのような雰囲気も。フランク・ロイド・ライトを思いながら1杯飲んで終了。トムコリンズとても満足の一夜でした。とりあえず、これでしばらくグランメゾンともおさらば。こんど訪問できるときが待ち遠しい。春は京都の和食巡りかな。気が向いたら投票お願いします→
2008.03.07
コメント(4)
-

ジョージアン・クラブへ最後の訪問(料理編)
ワイン編に続き料理編。料理は、みんなアラカルトで注文。わたしが頼んだのは次の料理。・カナダ セントローレンス湾産 オマール海老のサラダ, 冬の野菜(根セロリ, フェンネル, フルーツトマト, 蕪, 林檎, ・・・), ヨーグルトにエシャロットと胡桃を加えたソース, プーリア州の若いオリーブの実のオイル・シャラン鴨のローストほかにもアミューズ、フロマージュ、デセール、カフェ、プティフール。そういえば口直しはなかった。アラカルトで2皿だと口直しはないのかな。で、料理の印象は、過去の訪問のなかでは一番よいけれど、グランメゾンならばもう一押し欲しいところ。前菜は、盛りつけは美しいけれど、グランメゾンの料理と考えると力がない。たくさんの食材を使っているのに、どれも印象に残らない。ガツンとオマールを食べたい。メインは、鴨グループと子羊グループに分かれて、わたしはシャラン鴨を選択。しっかりソースを使った伝統的なスタイル。火の通し加減もよく深い味わい。付け合わせにはいろいろな野菜が添えられていて、これもなかなかよい。鴨といえば、先日訪問したル・ジュー・ドゥ・ラシエットが印象的。スタイルが違うので、どちらがよいかは好み次第だと思うけれど、いずれも素材の良さを感じる素晴らしいものだと感じた。でも、個人的にはラシエットのほうが好きかな。全体的にいえるのは、アラカルトならば、もう少しポーションを大きくして欲しいこと。皿によってはハーフポーションが設定されていたけれど、それでは2、3口サイズになってしまうのではないだろうか。鴨もオマールも、もう少し食べたかった。ワインが大量に残っているのに料理が無くなってしまった。でも女性陣は、お腹いっぱいと言ってました。本当かなあ。疑惑あり(笑)。もちろんデセールまで食べれば、お腹いっぱいなのだけれどね。モンブラン 友人が写真を撮りたいというので、ほかのお客さんがほとんど帰ってしまったこともありパチリ。夜遅くなり、みんな帰ったあとのダイニング最近の特別ワインセールは例外的なので考慮しないとしても、わかりやすいゴージャスな雰囲気と広々とした空間、比較的リーズナブルで充実したワインリスト、賛否両論のあったお店ではあるけれど、ユニークなお店を失ったのは惜しい。柴田ソムリエ時代のほうがサービス全体は洗練されていたと思うけれどね。とりあえず、閉店間際に2回も訪問できたことは幸運だと思うし、またそれにつきあってくれた友人たちにも感謝したい。もちろん、それを演出してもらった、シェフやソムリエ、スタッフにも感謝。グランメゾン巡りは、まだ続くのであった。気が向いたら投票お願いします→
2008.03.06
コメント(2)
-

ジョージアン・クラブへ最後の訪問(ワイン編)
最近は豪華飲食ざんまいで、罰が当たるんじゃないかと思っている今日このごろ。などと言いながら、また豪遊してしまいました。だって、この機会を逃したら「閉店しちゃうんだもん!」ッてことで許してください。3月7日に閉店を迎えるジョージアン・クラブ。2月に訪問したとき(そのときのブログ)「閉店まで、あと一回くらい行ってしまいそうである」とブログに書いたけれど、予想通りというか、確信的というか、もう一回行ってしまいました。今回はワインをたくさん飲むのだ!という意気込みのもと、5人での訪問となりました。らせん階段でダイニングに下りると、今回は8人掛けのセンターテーブル。テーブルにはヴェネツィアングラスのオブジェが飾られている。またシルバーの立派な燭台も豪華な内装にふさわしい。予約が取れないと聞いていたけれど、2テーブル空いていた(われわれは5人だったこともあり、予約を取るのは苦労した)。一番の目的は、豪華なワインをたくさん飲むこと、それと最後の見納めをすること。着席後、さっそくワインリストとの格闘になった。当初は5人で5本の予定だったけれど、魅力的なワインがありすぎて絞りきれず。結局6本になってしまった。今回は席に余裕があったことを思うと、あと1人くらい誘ってもよかったかも。まだ飲みたいワインがたくさんあったのだ。それにしてもワインの選択には悩む。1ヶ月前とは予想以上にリストが変わっていた。無くなっているのも結構あるし、逆に新たに登場しているのも相当あった。以下のことを総合的に考えながらセレクトしてみた。・いま飲んでおいしそうなもの・マーケットプライスと比較したときのお得感&入手困難度・ワインの予算総額・ソムリエのお薦め信頼関係が築けていないソムリエの場合、ソムリエのお薦めを無視してしまうこともあるのだけれど、島本ソムリエのお薦めはかなり的確。今回も助かりました。1996 Bollinger R.D.ボランジェ・エール・デーChampagne, France - 白辛口昨年zzz.santaさんに飲ませていただき、とても印象的なシャンパーニュ。あのボトルを基準とすると、より熟成感があり、少しよれているような感じもあるけれど、あのすばらしい記憶がなければフルボディのおいしいシャンパーニュ。NV Krugがリストから無くなっていたのは残念だけど、スターターとしては存在感十分。1993 Meursault 1er Cru Goutte d'Or(Arnaud Ente)ムルソー・プルミエ・クリュ グット・ドール(アルノー・アント)Bourgogne, France - 白辛口アントのファーストビンテージ。ほかのビンテージにしようと思っていたのだけれど、このビンテージをソムリエが強力に勧めるので選択。どうなんだろうと思いつつ飲んでみると、思っていた以上に若々しく、かっちりとしたミネラルと酸があり、それでいて熟成から来る香り高さもあって、かなり素晴らしい。ストラクチャの見事さはルロワをほうふつさせる。ルロワほどの凝縮感はないけれど、食事と合わせるのにはちょうど良い。恵まれないビンテージなのに、ファーストビンテージからこんなにレベルの高いワインを仕上げてくるとは驚き。今まで飲んだアントのなかではNo.1。アルノー・アントのグット・ドールを探す>1997 Vosne-Romanee Clos Goillotte(Prieure Roch)ヴォーヌ・ロマネ クロ・ゴワイヨット(プリューレ・ロック)Bourgogne, France - 赤辛口NSGクロ・デ・コルヴェ99と迷ったすえ、こちらもソムリエのお薦めにしたがってこちらに変更。うっとりしてしまう香り。恐ろしく香り高くて、透明感もあり、美しく熟成している。個人的には、隠し味的にぬか漬けが10%くらい入ってそうな香りだと思ったけれど、ほかのメンバーからは疑問の声。げっ。96の球体のような完璧さはないけれど、いま飲んで、ものすごく香りがよくて楽しめるワイン。最近熟成したロックを飲む機会が数回あったけれど、いずれも素晴らしい。96をもっと買っておけばよかった。 プリューレ ロック ニュイ サン ジョルジュ クロ デ コルヴェ [1997] 750mlちょっと高いけれど、このあたりに興味あり。1998 Ch.Lafleurシャトー・ラフルールPomerol, Bordeaux, France - 赤辛口若いことはわかっていたけれど、恐ろしくリーズナブルな価格だったため注文してしまいました。いい意味での軽いインキーさ。顔を埋めたくなるような、上質でふかふかのタオル。均等が取れ、上質のワインだけが持つ、密度はあるけれど重くない仕上がり。グレートビンテージの若いペトリュスを飲んだときのような「しまった感」は無いけれど、やはり若い。あと10年から20年後に飲んでみたい。[1998] シャトー・ラフルール 750ml[1998] Chateau Lafleur 750ml最安値でも8万円台。うーむ。1983 Ch.Lafite-Rothschildシャトー・ラフィット・ロートシルトPauillac, Bordeaux, France - 赤辛口1級シャトーも1本くらい注文したいと思いセレクト。ノーブル。1級筆頭の高貴さ。ラフルールと比べると、高いレベルの酸があり、熟成香も少々。まだしっかりとした酒質で、古酒の雰囲気はないのだけれど、もちろんおいしい。10年後に飲んでみたい。[1983] シャトー・ラフィット・ロートシルト 750ml[1983] Chateau Lafit...最安値でも10万円オーバー。ここまでだとは...1995 Chateauneuf-du-Pape Cuvee Marie Beurrie(Henri Bonneau)シャトーヌフ・デュ・パプ キュヴェ・マリー・ブーリエ(アンリ・ボノー)Cotes-du-Rhone, France - 赤辛口92のセレスタンにしようと思ったら、ソムリエがこちらの方が良いというので変更。一口飲んだときには「強すぎる」と思ったけれど、抜栓して時間がたつと本領発揮。グルナッシュとは思えない洗練。いいビンテージならではのパワー。暴力的ではないのに、目の詰まった恐るべき密度感。東洋系スパイスの香り。量が減っても落ちない香りのボリューム。恐るべき持続力は、年初に飲んだシュヴァル・ブラン53を思わせる。選んだことに後悔はしていないけれど、久しぶりにセレスタンの92も飲んでみたかった。アンリ・ボノー シャトー・ヌフ・デュ・パプ・マリー・ブーリエ[1995]750mlいま飲むなら、デカンタージュして、時間をかけてじっくり飲んでみて。熟成させたら、もっとすごくなりますぜ。でも、いま飲むなら個人的には97キュヴェ・マリー・ブリエかな。まとめどれが好きかは、人によって分かれた。その中でもボノーとロックは、かなりの支持を集めていたと思う。個人的には、それぞれ異なるキャラクターと熟成具合で甲乙つけがたい。それでも強いて選べば、アント、ロック、ボノーか。料理編に続く。気が向いたら投票お願いします→
2008.03.05
コメント(16)
-

銀座で天ぷら&ワイン
この日は、銀座の某天ぷら屋で、天ぷらとワインを楽しむ会。天ぷら専門店に行くのは久しぶりだけど、たまにはこういうところもいいですなあ。飲んだワインは以下のとおり。1982 d'Ambroise Grande Reserve Blanc de Blancsダンブロワーズ グランド・レゼルヴ ブラン・ド・ブラン泡が細かく、濃密でむっちりとしたボディ。しっかり熟成感があり、マロングラッセのよう。おいしいです。1995 Taittinger Comtes de Champagne Roseテタンジェ コント・ド・シャンパーニュ・ロゼ4,5年前に飲んだときは、目が覚めるくらいおいしいと思ったのだけれど、今回は普通。もちろんプレステージレベルでの話ですよ。当時と比べると、酸は穏やかになって均等的なバランス。前回のインパクトを期待していたので少し残念だけど、考えようによっては、食事と合わせるなら主張しすぎないこちらのほうがよいのかも。2005 Corton-Charlemagne(Patrick Javillier)コルトン・シャルルマーニュ(パトリック・ジャヴィリエ)口に含んだ瞬間おいしいと思う味わい。一口飲んでムルソーかなと思ったら、コルトン・シャルルマーニュでした。うげっ! パトリック・ジャヴィリエはムルソーの造り手ということで許してください。分析的に飲むと、コルトン・シャルルマーニュにしては厳しさがないような気もするけど、いま飲んでおいしい。05以外も飲んでみたい。1993 Chapelle-Chambertin(Drouhin-Laroze)シャペル・シャンベルタン(ドルーアン・ラローズ)まだ古酒の雰囲気はなく、中くらいの熟成。(よい意味で)それほど主張はなく、まだ果実味も残っている柔らかなブルゴーニュ。昔は安かったこともあり、ボンヌ・マールをよく飲んでいました。それにしても、幹事のかた、いつもありがとうございます。おいしかったです。気が向いたら投票お願いします→
2008.03.04
コメント(6)
-

梅見に羽根木公園&深大寺植物公園 Part2
前回からの続き。羽根木公園があまりにも不調だったため深大寺植物公園へ。事前にGPSにインプットしていたので、それを使って梅ヶ丘からひたすら西へ向かう。仙川のあたりはバスが通るのに、道が異常に狭いと思いつつも30分くらいで到着。今回は自転車なのでD80+Nikkor 18-200 VR。温室の中で一部Tamrom 90mm Macroを使用。温室に入ると、パリの植物園を愛したアンリ・ルソーが思い浮かぶ↑の写真を撮ったときはジョージア・オキーフっぽいと思ったけれど、比べてみると全然違う。似ているのは全体の色合いだけか(笑)。ジョージア・オキーフ「ピンクの地の上の2本のカラ・リリー」温室を見たあとは、目的の梅エリアへ。写真ではわかりづらいかもしれないけれど、こちらは満開。帰宅後に写真をチェックすると、全然写真を撮っていないことが判明。レンズも交換しなかったしね。ブログに載せることを考えれば、もっと撮れば良かった。いま見るなら深大寺植物公園がお勧め。今後もう一つ狙っているのは青梅の吉野梅郷。関東一の梅の名所のようなので期待してます。それにホームページも、えらく充実している。気が向いたら投票お願いします→
2008.03.03
コメント(4)
-

梅見に羽根木公園&深大寺植物公園 Part1
梅の花を見るために、羽根木公園と深大寺植物公園に行ってきた。写真スポット&散歩場所探しによく使うのが、以下のWebサイト。今回もこちらのサイトを参考に梅スポットを探索。・公園へ行こう!・Let's Enjoy TOKYOまずは自宅から自転車だと近い梅ヶ丘の羽根木公園へ。同じ世田谷区でありながら羽根木公園の存在はまったく知らなかった。ちなみに梅ヶ丘といえば「美登利寿司」。相変わらず、ものすごい行列でした。公園へは、自転車で20分ほどで到着。小山のように盛り上がっていて、梅が約700本も植えられている。今年は寒いためか開花が遅れているようだ。梅まつりの期間は、2008年2月2日(土)∼2008年2月24日(日)なのに、この時点(3/2)でも5分咲き程度。とはいえ、すでに散り始めているものや、つぼみなども混在していて、発育不全というかハズレ年の様相。散りかけのもある咲いている木だけを撮ると、そこそこ咲いているように見えるけど...人出はあるものの、花の少なさにピクニックをしている人はわずか。個人的にも、この花のボリュームではシートを広げて楽しもうという気分にならない。昼食は食べログの評価がよかったピッツェリア「il Mostro(イル・モストロ)」へ。マルゲリータ薪釜がある、真のナポリピッツァ協会の認定のお店。広さのわりに店員が少ないので、店がまわっていない。スタッフが少ないなら、少ないなりのまわし方があると思うのだが...。今回だけ特別なのかと思ったら、食べログでも似たような書き込みがあった。人不足は常態化しているのかもしれない。ピザは、薪釜のなかではまあまあ。おいしくはあるけれど、とくに傑出したものは感じない。パスタは、ブッタネスカを頼んだところ、あれっと思うくらい上品サイズ。オリーブしか具が載っていない比較的シンプルなトマトソースパスタが、上品サイズで\1,400は高い。平日のランチメニューは違うので別評価しなければならないけれど、近所にあるなら、たまにピザだけを食べに来てもいいかなという程度。味やコストパフォーマンス以前にまず人不足を解決するべき。羽根木公園があまりにも不調だったため深大寺植物公園へ向かうことにした。つづく気が向いたら投票お願いします→
2008.03.02
コメント(4)
-

料理もワインも秀逸なワインバー「カーヴ・デ・ヴィーニュ」
先日は満席で入れなかったので、リベンジマッチとばかり、行きつけのワインバー「カーヴ・デ・ヴィーニュ(Cave des Vignes)」(東銀座)を訪問した。ワインは「安い系でおいしい系」と、なんだかわからないようなリクエストでセレクトしてもらった。2005 Montlouis Sur Loire Clos du Breuil(Francois Chidaine)モンルイ・シュール・ロワール クロ・デュ・ブレイユ(フランソワ・シデーヌ)Loire, France - 白辛口2年くらい前にLes Tuffeauxを飲んで、中途半端な甘さにイマイチと思っていたワイン。でも、ソムリエが「今日のグラスワインにも出しているし、おいしいですよ」と言うので注文。シデーヌは、モンルイの中では注目されている自然派の造り手。シュナン・ブラン100%。以前飲んだLes Tuffeauxもそうだけれど重量級のボトル。複雑で少し甘めの香り。飲んでみると、そこそこふくよかなボディできれいな造り。アフターは、少しだけ甘めに仕上がる。中途半端な甘さは得意じゃないのだけれど、これはストライクゾーン。あとで調べてみるとLes Tuffeauxはドゥミ・セックらしい。フランソワ・シデーヌのワインを探す>2005 Arbois Pupillin Trousseau le Garde Corps (Philippe Bornard)アルボワ・ピュピヤン トゥルソー”ル・ガルド・コー”(フィリップ・ボールナール)Jura, France - 赤辛口次に登場したのが蝋封の自然派っぽいボトル。ボールナールについては、MORISAWAのあおりっぽいページが詳しい。簡単に説明するとアルボワでトップクラスの生産者オーヴェルノワで修行していた、自然派の生産者。ちなみにオーヴェルノワのワインは、とっても薄くて不安になるけれど、しっかりうまみが乗って不思議なおいしさのあるワイン。その中でもプールサールはピノ・ノワールのようでお勧め。アルボワ・ピュピヤン プルサール[2002] ドメーヌ・ピエール・オ...で、こちらのボールナール。名前しか知らないようなブドウ品種トゥルソー100%。ピノ・ノワールほどの鋭さはないのだけれど透明感があり、リーズナブルなコート・デュ・ローヌのような雰囲気もある。きれいでゆるさもなく、料理と合わせて飲むにはおいしいワイン。オーヴェルノワは熟成させると面白いので、こちらも、もう少し熟成させたものを飲んでみたい。牛のタルタル? しっかり肉の味がしておいしいタルタル牡蠣のキッシュ これを食べるのは2度目だけれど相変わらず絶品。茶碗蒸しのようなプルルンとした食感と、しっかり味のついた牡蠣のコントラスト。すっぽんのリゾット顔なじみなので星はつけないけれど、ワインバーの最高峰の一軒だと勝手に思ってます。それに、ここよりおいしいフレンチも、あんまり無いと思う。もちろん高額店は別ね。気が向いたら投票お願いします→
2008.03.01
コメント(2)
全28件 (28件中 1-28件目)
1