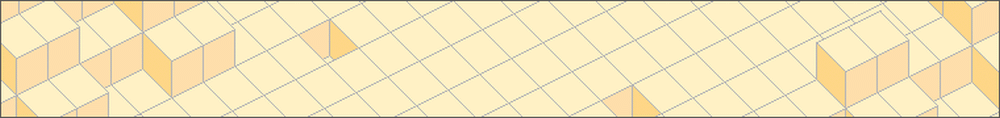2009年11月の記事
全19件 (19件中 1-19件目)
1
-

澤村拓一、プロで最も活躍しそうな投手だ
2009年11月22日に行われた「セ、パ両リーグ誕生60周年記念試合・プロ選抜vs大学日本代表」のこと。■3回表、3番手の投手として登板した中央大・澤村拓一(3年、佐野日大高)のピッチングは、とっても素晴らしかった。特にこの回先頭の1番・坂本勇人(読売、光星学院高)を見逃し三振に仕留めたウイニングショットが好い。149kmの速球が外角ぎりぎりにビシッと決まった。「どうだ!」とばかりに、マウンド上の澤村は誇らしげに胸を張った。■以下、日刊スポーツ(11月23日付)より。「大学最速の中大・沢村拓一投手が片鱗を披露した。3番手で登板、いきなり巨人坂本勇人を149キロで三振。ベンチに引き揚げる坂本が『速い』と漏らすシーンもあり、沢村は『自信になります』。初球はソフトバンクのスピードガンが152キロを記録していた」 (以上、日刊スポーツ)ちなみに初球の球場表示は149km。投球フォームは決してきれいなものではない。法政大の速球派投手・武内久士(4年、徳島城東高)ほどではないものの、変則的なぎこちないフォームに見える。ただひとたび彼の手からボールが離れると、それは豪速球となって捕手のミットを大きく震わせる。神宮最速記録の156kmは、この澤村が今年(2009年)秋に記録した。■ボクは東都リーグを見る機会が少ないため、澤村を見る機会も極端に少ない。唯一見たのは今年7月14日、日米大学野球の第3戦だった(Kスタ宮城)。1勝1敗のタイで迎えたこの試合、どうしても勝ちたい日本代表チームは澤村を先発に起用した(第1戦の先発は法政大・二神一人、第2戦は早稲田大の斎藤佑樹)。ところが澤村、なぜだか大荒れに荒れた。たった1回2/3だけで、被安打6、与四死球1、自責点2。早々に降板してしまった。肩を大きく上下に揺らして息をする姿だけが印象に残った。■澤村拓一。佐野日大高時代に甲子園出場の経験はない。脚光を浴びるようになったのは、中央大入学後のこと(らしい)。元・読売の高橋善正監督の指導の賜物なんだろうか? 対プロ選抜戦の様子を見て、スターターとして最もプロで活躍する投手はこの澤村だろうと、ボクには思えた。※ちなみに佐野日大高は、澤村が卒業直後の07年センバツで甲子園に出場している。1回戦で大牟田高に7-0で完封勝ちしたものの、2回戦で大阪桐蔭高に8-11で敗退した。この試合、大阪桐蔭の長打力がモノをいった。中でも現・日本ハムの中田翔が放った2本の本塁打が勝負を決めた。対プロ選抜戦で中田と勝負し、後輩たちのリベンジを果たすのも格好よかったかもしれない(実際の対戦はなかった)。今日も1クリックお願いします
2009.11.30
コメント(0)
-

セパ誕生の裏事情と近鉄
11月22日に行われた「セ、パ両リーグ誕生60周年記念試合・プロ選抜vs大学日本代表」。ただ今日はこれまでと違い、その「歴史」のこと。■セ・パ両リーグが誕生したのは、1949年(昭和24年)のこと。同年11月26日、日本野球連盟顧問各代表者会議が開かれ、翌50年からセ・リーグとパ・リーグの2リーグ制で行うことが決定された。同じ日、パ・リーグ(太平洋野球連盟)は、阪急・南海・東急・大映の4球団に加え、毎日・西鉄・そして近鉄が新規参入し7球団編成で発足した。一方セ・リーグは少し遅れて同年12月15日、巨人・阪神・中日・松竹・大洋・広島・西日本・国鉄の8球団で結成された。■セ・パあわせて15球団、特にパ・リーグは7球団といういびつな編成だった。そもそも2リーグ誕生を最初に唱えたのは「大正力」こと正力松太郎。新聞界で競合する毎日新聞にプロ野球参入を誘いかけ、読売を中心とするリーグと毎日を中心とするリーグの2リーグ制にして、プロ野球の一層の繁栄を期した壮大なプランだった。ところが、読売新聞社社長だった正力は戦争責任を問われ、当時は公職追放の身。読売社内での影響力が弱まっていた。そのため「なぜ競合する毎日新聞に手を差し伸べるのか?」といった自社の既得利益を守りたい新首脳と正力の間に論争が繰り広げられた。これは読売社内だけに留まらなかった。2リーグ誕生を巡って、既得利益を守りたい既存球団と、プロ野球に参入することで新たな自社利益を得たい新規球団の綱引きが盛んに行われ、悲しいかな2リーグ誕生には大きな混乱を伴った。「2リーグ誕生」という耳に優しい言葉とは裏腹に、実態はさまざまな企業や経営者たちの思惑が絡んだ利権争いだった。計15球団といういびつな編成は、そういった経緯があった末に結着したひとまずの着地点に過ぎなかった。■この混乱の中、ボクが大好きだった近鉄バファローズ(当時、パールス)が生まれた。この近鉄誕生の際、興味深いエピソードがある。それは2リーグ誕生に際し、正力の構想では関西の球団がすべて鉄道会社であることから、「セに阪神、近鉄、パに南海、阪急と4球団を振り分ける」(『近鉄球団、かく戦えり』(浜田昭八著、日経ビジネス人文庫)はずだった。ところが前述の混乱が影響し、どうしたわけか近鉄は一転してパ・リーグに収まった。もしこのとき、近鉄がセ・リーグだったら、後に球団消滅なんて事態にはならなかったかもしれない。ま、セだったら、ボクは近鉄ファンになっていなかったかも知れないけど・・・? 今日も1クリックお願いします
2009.11.28
コメント(0)
-

「木田、ハム入り」?
今日の日刊スポーツより。■ 「木田ハム入り」木田優夫(日大明誠高)が日本ハムと1年契約を結んだ。木田にとってこれが8球団目となる。41歳。ボクは見出しを見た瞬間、木田勇(横浜第一商高-日本鋼管-日本ハム)を連想してしまった。日本ハムの木田といえば、「木田勇」だろうと。ただ現在、その木田の年齢は55歳。現役復帰などするわけないか!■「審判のセパ担当制廃止」NPBは2011年をメドに審判部と記録部のセ・パ担当制をなくす方針。審判員の帽子とロゴを統一、さらに待遇面を統一する。このことによりリーグの垣根を越えて審判を勤めることが可能になる。毎年3億円の赤字が見込まれるNPBとしては、経費の大幅削減が可能になる。いまひとつピンと来ない。削減されるのは審判員の旅費(遠征費)や多少の人件費ぐらいじゃなかろうか?■「大石ヘッドを”無視”」オリックス・岡田監督がソフトバンクのヘッドコーチ就任が決まった大石前監督に無視を決め込んだ。「関係ないで。それより何でや、ということ。スタッフ発表してのあれやからなぁ」と森脇前ヘッドの退団経緯が気になるようだった。ボクも気になる! 大石大二郎(静岡商高-亜細亜大-近鉄)もそうだけど、なぜ王貞治さんの「右腕」と呼ばれた森脇浩司(社高-近鉄)が急に退団することになったのか? 球団幹部との確執が理由という報道もあったが・・・。 今日も1クリックお願いします
2009.11.27
コメント(2)
-

快投演じた菅野智之!
2009年11月22日に行われた「セ、パ両リーグ誕生60周年記念試合・プロ選抜vs大学日本代表」のこと。 ■菅野智之(東海大2年、東海大相模高)がマウンドに上がったのは8回裏だった。この回から登板した明治大の左腕エース・西嶋一記(3年、横浜高)が作った無死一・二塁のピンチの場面に「火消し」役としての登板した。プロ選抜の4番(途中出場)小窪哲也(広島、PL学園高-青山学院大)をセンターフライに打ち取ると、続く5番・亀井義行(読売、上宮太子高-中央大)をサードへのファールフライ、6番・代打の根元俊一(ロッテ、花咲徳栄高-東北福祉大)を95kmの変化球で空振り三振に仕留めた。菅野、続く9回も絶好調。代打の嶋基宏(楽天、中京大中京高-國学院大)にライト前ヒットを許したものの、後続の3人の打者を完璧に抑えた。特に圧巻だったのは、中田翔(日本ハム、大阪桐蔭高)との対戦。投げた5球の球速はすべて140km台。2球目の速球が147km、3球目のカットボールが143km。そしてウイニングショットは141kmのカットボールで空振り三振を奪った。■以前、スポーツニッポンは、菅野を次のように紹介していた。「最速153キロの直球に、140キロを超える高速スライダーが武器。大学では1年秋からエース格に台頭。小1で野球を始めたときから投手一筋。新町中3年時に県大会で優勝し関東大会ベスト8。巨人・原監督のおい」(スポニチ)菅野智之投手の高校時代を調べてみた。高校時代、甲子園の出場経験はない。3年時(2007年)、夏の神奈川県大会は決勝まで勝ち進んだが、決勝で桐光学園高に8-10で敗退(菅野は完投)、惜しくも甲子園行きの切符を逃した。その一年前(06年)、2年時の夏も県大会決勝に駒を進めたが、横浜高にスコア7-15で大敗した(この試合、菅野は3番手で救援)。※ちなみに06年の決勝、横浜高の先発は川角謙(現・青山学院大3年)。救援で登板したのは、先ほど紹介した西嶋一記。■ボクがこの日の試合(対プロ選抜戦)を見るまで、菅野の名前を聞いて思い出すのは、日米大学野球第5戦(神宮球場)のこと。残念ながら、この時の菅野の印象は決して芳しいものではなかった。(第5戦、7月16日)米 002 200 003 00 =7日 200 020 003 01X=8斉藤佑樹(早稲田大3年、早稲田実)、大石達也(早稲田大3年)に次いで3番手の投手として登板した菅野。やはり躍動感溢れる投球で7回・8回を完璧に抑えたものの、3イニング目の9回に大崩れをした。4本のヒットを浴び、自身の暴投も加わって3点を奪われてしまったのだ。(菅野の表情が、ボクにはやや青ざめて見えたっけ)■ま、そんな印象も対プロ選抜戦での投球を見て一気に吹っ飛んだ。はたして3イニングを投げていたらどうだったんだろう? なんて、つまらないことは考えないことにしよう。 今日も1クリックお願いします
2009.11.26
コメント(0)
-

唐川侑己と野村祐輔の対決
2009年11月22日に行われた「セ、パ両リーグ誕生60周年記念試合・プロ選抜vs大学日本代表」のこと。■ボクはテレビ「J-SPORTS」でこの試合を観戦した。番組ではプロ・大学生選手の高校時代の対戦について触れていて、プロ・唐川侑己(成田高)と明治大2年・野村祐輔(広陵高)の甲子園での対決を紹介していた。2人が対決したのは、2007年のセンバツ1回戦(3月26日)。(1回戦)延長12回広陵 010 000 000 001 =2成田 010 000 000 000 =1(広)野村、(成)唐川この試合、ロ-スコアであるものの、野村、唐川ともに大荒れの試合だった。広陵高が13安打、成田高は12安打の「打撃戦」。それでいて残塁がそれぞれ13と10。二人の絶不調ぶりが印象的だった。試合を決めたのは、延長12回に上本健太(現・天理大2年)が放った適時打。この得点が決勝点になり、広陵高が勝利を決めた。※ちなみにこの適時打で三塁から生還したのは土生翔平(現・早稲田大2年)。この土生も60周年記念試合では、大学日本代表の3番打者としてスタメンに名を連ねた。■さて、「セ、パ両リーグ誕生60周年記念試合・プロ選抜vs大学日本代表」の試合に話を戻す。野村は大学日本代表の7番手投手として、7回に登板した。この日の成績は1イニング、打者5人、18球、被安打1、奪三振2、与四死球1。リーグ戦同様に安定感を見せた。8番・中田翔(大阪桐蔭高)への四球は残念だったが、大崎雄太朗(現・西武、常総学院高-青山学院大)と銀仁朗(現・西武、平安高)はビシッと三振に仕留めた。一方、唐川もプロ選抜の7番手投手として登板した。この日の成績は1イニング、打者3人、8球、被安打1、奪三振1、与四死球0と、こちらもプロの貫禄を十分に見せつけた。約2年半ぶりに実現した二人の勝負。(大荒れだった)高校時代とは違い、今回はその安定ぶりで、またしても「互角」だった。今日も1クリックお願いします
2009.11.25
コメント(2)
-

今日は「東西対抗戦」から64周年
今日は11月23日。奇しくも昨日は「セ・パ両リーグ誕生60周年記念試合・プロ選抜vs大学日本代表」が開かれたけれど、いまからちょうど64年前の1945年11月23日にも記念すべき試合が行われた。■それは職業野球復活の狼煙(のろし)となる「東西対抗戦」(神宮球場)のこと。戦前に始まった職業野球。ベーブ・ルースらメジャー選手が大挙来日して大いに盛り上がったものだった。しかしそれも束の間、日々激化する太平洋戦争の影響を受け、1944年(昭和19年)9月17日から3日間開催された「総進軍優勝大会」(後楽園球場)をもって終了を余儀なくされた。そして終戦からわずか3ヶ月あまり。1945年(昭和20年)11月23日、職業野球は奇跡的に復活を遂げた、その記念すべき日が今日なのだ。「セ・パ両リーグ誕生60周年」もいいけど、歴史的には「東西対抗戦」のほうが重いとボクは思うのだ。■この時の様子は『真説・日本野球史』(大和球士著、ベースボール・マガジン社刊)に詳しい。「この試合、終戦直後の大混乱期に開催されたにもかかわらず、4万5千人の大観衆が詰め掛けた。神宮球場で行われるのは1942年(昭和17年)以来5年ぶりではあったが、内野席を超満員にし、外野席も7割がたが埋まったという」「一体どこから4万5千人もが集まってきたのであろうか。(中略)単純な野球愛というよりは、敗戦から立ち上がろうとする日本人の活力の発露と見る。野球人に強靭な精神力があったことは頼母しく、日本人に祖国再建の活力がみなぎっていたことはいよいよ頼母しい限りである。野球人、野球ファンが『ニ位一体』となって野球復活は快速調に進むことになる」■1945年11月23日、観客たちは物資が乏しく、明日の自分たちの生活さえわからない最中、着の身着のままの姿で神宮に駆けつけ、寒風の中、職業野球の再開を祝福したのだった。来年は「東西対抗戦」からちょうど65周年にあたる。また記念行事として「プロ選抜vs大学日本代表」を開催してはいかが?今日も1クリックお願いします
2009.11.23
コメント(0)
-

大会趣旨に反する中田翔の怠慢プレー
2009年11月22日行われた「セ、パ両リーグ誕生60周年記念試合・プロ選抜vs大学日本代表」。■大学選手側はプロの選手と対戦することで一定のモチベーションをもって試合に臨むことは予想できた。ただ開催前、ボクがいまひとつこの大会に興味を持てなかったのは、プロの選手側が真摯な対応で野球をできるのか? という疑問があったから。高田繁監督(明治大)ほか原辰徳(東海大)、岡田彰布(早稲田大)、野村謙二郎(駒澤大)らの各コーチは大学野球に思い入れがあるのはわかるけど、肝心の選手たちがどういった気持ちで試合に臨むのか。「どうせ余興のひとつぐらいといった気持ちなら、つまらない試合になるだろうな」と。結論から言うと、ボクの心配はまったくの杞憂に終わった。時間を忘れるほど、ボクはこの試合を熱心に見てしまった。プロ側の選手たちは、大学生相手であっても真摯な態度で戦ってくれた。趣旨をまるで理解していなかった、ある一人の選手を除いては(※このことは最後に) ■大会のホームページには、趣旨をこう記している。「本大会はプロ野球セ・パ誕生60周年を記念して開催する、26歳以下のプロ選抜チームと大学日本代表による交流戦です。プロ野球界とアマチュア野球界交流の新時代を切り開く、記念碑となる試合です」そのとおり、この大会は「プロとアマの新たな交流が始まる『記念碑』となるべき試合」なのだ。1961年(昭和36年)の「柳川事件」に端を発したプロ・アマの冷戦にピリオドを打ち、新たな交流を図るためにはプロも真摯に対応する必要があった。そうでなければ、この大会の趣旨はすべて台無しだったから。プロの選手たちは、総じて趣旨を理解し対戦していたように見えた。大学野球を経験している選手はもちろん、高校野球しか経験していない選手たちも「プロ・アマ新交流」を理解して、(オフシーズンではあるものの)精一杯のプレーを見せてくれた。■なのに、ただひとつ残念だったのは中田翔(大阪桐蔭高)の怠慢な走塁。本来二塁打コースなのに、一塁で止まってしまったプレー。一塁を守っていたのが高校の後輩・萩原圭悟(関西学院大1年、大阪桐蔭高)だったからか?(まさか、それはないだろうけど!)産経新聞は「ミスをしても(中田の)存在感は絶大だった」と書いていたけど、そういったレベルの話ではない。中田がどんなに二軍で本塁打を打っても、一軍で使わない梨田昌孝監督の気持ちがよ~くわかる気がした。今日も1クリックお願いします
2009.11.23
コメント(2)
-

小石博孝、東都を4連覇に導く
今日(11月20日)、明治神宮大会<大学の部>決勝が行われた。立正大vs上武大の初出場校どうしの対戦となったが、立正大がスコア2-0で勝利。同時に東都大学リーグ代表校の4連覇を果たした。 ■以下、サンケイスポーツより。明治神宮大会第5日(20日、神宮)大学の部・決勝戦は、立正大(東都)が荒木の本塁打などで上武大(関東第1)を2-0で下し、初の決勝進出で初優勝を飾った。東都秋季リーグに続く2冠。1994年の東亜大以来の初出場優勝で3度宙に舞った立正大の伊藤監督は「2度も胴上げされて感無量です」とほおを紅潮させた。序盤に2点を奪って優位に立ち、4年生の小石と菅井が三塁を踏ませず無失点リレー。今大会3試合で1失点と好調だった投手陣を代表して小石は「人生で最高の日」と会心の笑みを浮かべた。春のリーグ戦で入れ替え戦を経験したことで、選手たちに「フォア・ザ・チーム」の意識が芽生えたことが勝利の原動力。神宮大会は東都の代表が3連覇していた中で、指揮官は「プレッシャーがあり、正直ほっとした」と本音を漏らした。(以上、サンケイスポーツより)(決勝、11月20日)上 000 000 000 =0立 101 000 00X =2(上)●松永-斎藤-赤羽、(立)○小石-菅井■この試合、録画で途中から見た。とても際立って見えたのは立正大の投手・小石博孝(4年、鶴崎工高)。テイクバックの小さい、そして球の出所をグラブで隠しながら、腕が遅れて出てくる独特のフォームで、上武大打線を7回までほぼ完璧に抑えた。7回、被安打2、奪三振8、与四死球3、自責点0。100kmのカーブと130km前後のストレートが主体。緩いカーブが効いて、決して速くないストレートがとても速く見えた。卒業後はNTT東日本に進む予定らしい。■立正大、今年(2009年)春のシーズンは1・2部の入替戦を経験したチーム。なのに秋は1部リーグで優勝し、さらに全国(神宮大会)まで制覇するのだからスゴイ。地獄から這い上がった「力強さ」というか「たくましさ」を感じるし、それと同時に、東都リーグのレベルの高さをあらためて思う。そもそも東都・春季の順位(1部)はこうだった。1位 東洋大2位 青山学院大3位 亜細亜大4位 中央大5位 國學院大6位 立正大このため、最下位だった立正大は、入替戦出場を余儀なくされた。入替戦の成績は、次の通り。第1戦 立正大 1-0 専修大第2戦 立正大 4-2 専修大※いずれも先発は小石だった。そして秋季の順位は、春季のAクラスとBクラスがほぼ入れ替わった。1位 立正大 2位 亜細亜大 3位 國學院大4位 中央大5位 東洋大6位 青山学院大ついでに言うと、秋季2部リーグで優勝し、1・2部入替戦で青山学院大に勝利して1部昇格を決めた国士舘大、春季成績は2部の最下位で2・3部入替戦を経験している。◇2009東都・入替戦の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「入替戦。青学大、国士大に敗退」 (2009.11.7) → こちらへ。■大雑把な言い方ではあるけど、東都リーグは1部・2部の12チームの実力はほぼ似通っており、どこが出ても全国制覇できる可能性があると・・・、ま、そんなことが言えるかもしれないのだ。今日も1クリックお願いします
2009.11.20
コメント(0)
-

戦い方間違えた?善波達也監督
巨人ドラ1長野1発!/神宮大会 [19日08:53]この見出しを見て、最初はなんのことかわからなかった。後になって誤植であることに気づいた。見出しの主は日刊スポーツ・ドット・コム。「神宮大会」ではなく、「日本選手権」が正しいんだろうな、きっと。----------------------------------------------------------------------■さて、昨日(11月18日)の明治神宮大会のこと。第3試合(大学の部・準決勝)は上武大と明治大が戦い、上武大がスコア8-5で明治大に逆転勝利した。その結果、決勝戦は立正大との戦いとなり、神宮大会初出場どうしの対戦となった。明 001 000 040 =5上 003 000 05X =8(明)西嶋-難波-●森田-野村、(上)松永-○小向-斎藤以下、サンスポより。「優勝した1996年以来の決勝進出を逃した明大の善波監督は「六大学の代表として勝ちたかったが...。他大学に申し訳ない」と肩を落とした。(以上、サンスポ)■いつもいつも「流れ」で試合を語るのもどうかと思うけど、この試合も「流れ」が明治大の敗戦を決めたようにボクは思う。8回表、小道順平(4年、二松学舎大附高)や安田亮太(4年、PL学園高)らの適時打で逆転(2点差)した明治大。この時、「流れ」は間違いなく明治大にあった。だがその裏、あっという間に「流れ」が上武大のものになる。一死一塁で次打者の打球は平凡な二塁ゴロ。4-6-3のダブルプレーでチェンジになったはずだったが、セカンド・山口将司(3年、春日部共栄高)がショートに悪送球した。さらにこの回から登板した森田貴之(2年、大垣日大高)がボーク、そして悪送球でピンチが広がると、その後は連続適時打を浴びた。明治大、気がついたら上武大に逆転を許していた。■明治大の敗戦理由を考えると、エラーをした山口やミスをした森田の技量に原因を求めることは難しい。そもそも逆転に成功した直後は「流れ」を変えないために、万全を期してエース・野村祐輔(2年、広陵高)をマウンドに送るべきではなかったか?あくまで結果論でしかないけれど、ボクにはそう思えてしまうのだ。 (テレビ解説をしていた元・立教大監督の斎藤章児さんも同様のことを言っていたけど、別に受け売りではないです)■「今の試合より、翌日の決勝戦を睨んで」野村を温存したかった明治大ベンチ。でも、いつものリーグ戦ではその戦い方が通用しても、トーナメントではそれが通用しない。高校野球の歴史には、それを示す例が腐るほどある。トーナメントの戦い方を間違えたことが、善波達也監督にとって最も無念ではなかろうか。結局、雨天のため決勝戦は明日(20日)に順延された。もし事前に中1日空くことがわかっていたら、善波さんは迷わず8回に野村を登板させていたのかもしれない。皮肉と言えばなんとも皮肉な雨ではある。 今日も1クリックお願いします
2009.11.19
コメント(0)
-

高橋尚成の高校・大学時代
今日(11月17日)、FA権を行使してメジャー挑戦を表明した読売・高橋尚成のアマチュア時代のこと。高校時代、大学時代ともに野球の「王道」を歩んできた。■高校は東京・修徳高。1993年夏、高橋は修徳のエースとして甲子園に出場した。初戦、岡山南高を2-0で完封した後は、2回戦も甲府工高に2-0とこれもシャットアウト。3回戦は東海大四高に3点を失ったものの4-3で辛勝し、チームのベスト8入りに大いに貢献した。だが準決勝では育英高に被安打9、与死四球7で9点を失い、スコア1-8で大敗した。ちなみに、2回戦で対戦した甲府工高の投手は現・楽天の山村宏樹(元・近鉄)だったし、準決勝で戦った育英高の3番打者は現・オリックスの大村直之(元・近鉄)だった。※また高橋が修徳高に在籍していた当時、同じ東・東京地区の高校球児には、堀越高の井端弘和(現・中日)、関東一高の武田勝(現・日本ハム)、帝京高の三沢興一(元・近鉄)らがいた。■大学は駒澤大。4年間の通算成績は17勝11敗、防御率2.58。当時の東都大学リーグにいた主な選手は、青山学院大の高須洋介(現・楽天、元・近鉄)。また同時期、他リーグには慶応義塾大の高橋由伸(現・読売)、大阪体育大の上原浩治、明治大の川上憲伸、近畿大の藤井彰人(現・楽天、元・近鉄)らがいた。高橋にとって恩師である太田誠・前駒澤大監督は、著書にこう書いている。「大学時代、私に怒られ続けたピッチャーがいる。高橋尚成である。高橋は、大学時代から、小技に走った時には必ず打たれるピッチャーだった。言い換えれば、投球に『邪心』が入った時にやられるタイプである」「あと少しで勝てる。あと一人でなんとかなる。この球で抑えられたら・・・。そういう思いが入った時に、必ずと言っていいほど痛打を浴びたり、フォアボールを出したりするのである。(中略)高橋を飛躍させるためには、心の問題が最も大きいと、私は思っている」 (『球心、いまだ掴めず』太田誠著、日刊スポーツ出版社刊より)今日も1クリックお願いします
2009.11.17
コメント(0)
-

平野和樹の本塁打空し、立正大に惜敗
■スコア1-1の同点で迎えた9回裏、立正大は1番・黒葛原祥(4年、横浜高)の打席から始まった。対する東北福祉大の投手は、8回から登板した柳沢一樹(3年、上田千曲高)。だが柳沢、コントロールがどうにも定まらない。ストレートの四球を黒葛原に与えると、続く2番・中井雄太(4年、千葉敬愛高)にもまったくストライクが入らず、またもストレートの四球を与えて無死一・二塁のピンチに。顔が青褪めて見える柳沢。迎える打者は小技の得意な3番・中嶋辰也(2年、銚子商高)。100%バントの場面とあって、一塁手・三塁手は猛烈な勢いでダッシュ。簡単に送りバントをさせまいと中嶋にプレッシャーをかけた。このプレッシャーが効いたのか、中嶋はスリーバントも失敗し三振に倒れる。このバント失敗が柳沢に再び元気をもたらす。続く代打・大井裕喜(3年、新居浜東高)に真っ向勝負を挑んで空振り三振に打ち取り、続く5番・越前一樹(3年、横浜高)もカウント1-1からスライダーを引っかけさせて三塁ゴロに打ち取った。さぁ、延長だ! そう思った瞬間に妙なことが起きた。打球が微妙にイレギュラーしたのか、三塁手・舟田博紀(4年、聖光学院高)のグラブの動きがまるで打球に反応せず、舟田の身体に当たってそのままファールグラウンドに弾んでいったのだ。その間に二塁走者の黒葛原が生還し、あっけないサヨナラ劇となった。■今日(11月16日)行われた明治神宮大会3日目。第4試合の立正大vs東北福祉大戦。東 000 000 001 =1立 000 100 001X=2(東)中根-●柳沢、(立)小石-○南■この試合で印象的だったのは、9回表に飛び出した東北福祉大の4番・平野和樹(3年、平安高)が放った、豪快なライトスタンドへの本塁打。立正大のエース・南昌輝(3年、県和歌山商高)が低めに投げ込んだ145kmの速球を上手くすくい上げ、打球はライナーのままライトスタンドの中段に飛び込んだ。打った瞬間に本塁打とわかるそのパワーと打撃術は圧巻だった。平野和樹。平安高時代は捕手(現在は一塁手)、甲子園の出場経験はない。高校時代のチームメイトには、現・法政大3年の大八木誠也らがいた。今日も1クリックお願いします
2009.11.16
コメント(0)
-

大塚豊、学生最後の12球
先ほどの続き。■今日(11月15日)行われた明治神宮大会1回戦の創価大vs九州産業大。創価大のエース・大塚豊(4年、創価高)が3番手として登板したのは、ほぼ敗戦が確定した9回表のことだった。投球練習を心配そうに見つめる岸雅司監督。「心配ないですヨ!」と笑顔で応える大塚。この時点でスコアは0-7。ヒジを痛め登板を控えていたものの、学生最後の登板を志願して実現したマウンドだった。ただやはり故障が影響しているのか、大塚の調子はまるで良くなかった。無失点で切り抜けたものの、速球はなく変化球もすっぽ抜けることがあり、いつもの「爽快感」溢れる投球には程遠いものだった。■「大塚豊の12球」。1番・今泉達也(4年、沖学園高)1球目 フォーク 92km ボール2球目 フォーク 117km ストライク3球目 フォーク 120km 空振り4球目 フォーク 120km ボール5球目 フォーク 120km レフト前安打2番・岡部直樹(1年、沖学園高)6球目 送りバント、成功3番・秋山謙太(2年、沖学園高)7球目 フォーク 92km 大きく外れてボール8球目 スライダー 113km 甘く入ったがレフトフライで難を逃れる4番・百崎一兵(2年、福岡大大濠高)9球目 フォーク 119km 高めに外れたが(手を出してくれて)ファール 10球目フォーク 95km ボール11球目フォーク 94km 空振り12球目フォーク 125km 空振り三振 ■「3種類のフォークを操る」と言われ、今秋のドラフトで日本ハムから2位指名を受けた大塚豊。この12球で学生生活を終えた。故障を早く治して、大学の先輩・八木智哉(現・日本ハム)を超える投手を目指してほしいものだ。◇大塚豊の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「大塚豊は八木以上だ!」 (2009.6.21) → こちらへ。今日も1クリックお願いします
2009.11.15
コメント(0)
-

榎下陽大、創価大に完封勝利
■今日(11月15日)行われた明治神宮大会2日目。第4試合は創価大vs九州産業大の好カードだった。(1回戦)九 011 001 020 =5創 000 000 000 =0(九)榎下、(創)小川-天野-大塚■ボクが注目していたのは創価大の2番打者、そしてショートを守る脇山渉(2年、愛工大名電高)。昨年、東京新大学リーグを観戦していた際、小柄(170cm、67kg)ながら巧みなバットスイングで安打を量産し、強烈な野球センスする感じさせる彼の姿にボクは大いに魅せられたものだった。昨年(2008年)秋には1年生ながら「新人賞」と「ベストナイン(指名打者)」を獲得。今秋はベストナイン(ショート)に選出された。そして今日、脇山の1打席目を見た。でもバットがボールの下をくぐって、まるで当たらない。彼本来のミートの上手さがまったく見られなかった。 「いったい、どうしたことか?」ボクは心配になったが、その答えは後になってわかった。原因は脇山ではなく、相手投手の投球術にあったのだ。◇脇山渉の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「再来年のドラフト注目!脇山渉」 (2009.1.19) → こちらへ。■その相手投手とは、九州産業大・榎下陽大(3年、鹿児島工高)のこと。178cm、70kgの細身な身体が投げおろす速球のスピードは最速148km。スライダー、フォークに100km前後のカーブも操り、緩急をつけた投球術は見事、創価大打線を翻弄した。疲労から制球が乱れた7回、二死満塁のピンチもあったが、打者を見逃し三振に仕留め勝利を決めた。(榎下の今日の成績)9回、被安打1、奪三振11、与死四球6、自責点0。榎下陽大。2006年夏、捕手・鮫島哲新(現・中央大)とともに甲子園に出場した。初戦(2回戦)は高知商高に3-2で勝利。3回戦は香川西高に9-3、準々決勝ではエース・駒谷謙(現・京都産業大)を擁する福知山成美高に3-2で勝利し、チームをベスト4に導くけん引役となった。だが準決勝は、後にこの大会で優勝する早稲田実に、スコア0-5で完封負けを喫した。この時、早実の投手は斎藤佑樹(現・早稲田大)。早実の決勝の相手は言うまでもなく、田中将大(現・楽天)のいた駒大苫小牧高だった。◇2006年夏、甲子園決勝の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「早実vs駒大苫小牧(2)」 (2006.12.26) → こちらへ。スター揃いだったこの大会、榎下のいた鹿児島工高にもスターがいた。「代打の切り札」今吉晃一がその人。ツルツル頭で、打席に立つと「シャー!」と雄たけびを上げる姿が人気を呼び、大いに話題になったものだった。 今日も1クリックお願いします
2009.11.15
コメント(0)
-
「流れ」つかめず青学大が連敗
最後の打者になった青学大の長島は、三振に倒れた直後、打席で膝をつき泣き崩れた。実は入れ替え戦が始まる前から、結果がこうなることは決まっていたのでは? そう思えるほど、青学大の選手たちに元気がなく、そして試合の流れは昨日の1回戦から一貫して国士大にあった。勝敗が決した瞬間、長島に限らず、青学大の多くの選手たちがベンチ前で泣きじゃくった。一方の国士大選手たちはマウンド付近で抱き合い、1部復帰を喜ぶ。あまりに対照的なシーン。これは他に例えようがない。決勝で優勝と準優勝を分けたのとはまるで比較にならない。破れて2部に転落するチームにとっては、二度と陽の目を見ることのない地獄に突き落とされるような衝撃を伴う。誰がこんなルールを考えたのかボクは知らない。ただ今回の入れ替え戦は、青学大にとってあまりに残酷に見えた。
2009.11.08
コメント(0)
-
あぁ、青山学院大2部転落!
東都1・2部入れ替え戦はスコア1-0で国士舘大が青山学院大を破り、14年ぶりの1部復帰を決めた。一方、青山学院大の2部転落は25年ぶりのこと。金縛り状態の青学大にとって、実に残酷な入れ替えとなった。
2009.11.08
コメント(2)
-

入替戦。青学大、国士大に敗退
太田誠・前駒澤大監督の著書によれば、東都大学リーグの1・2部入替戦は、特に1部(6位)チームの監督や選手にとって、相当な緊張感を伴うものらしい。著書には、こう記してある。「入れ替え戦には、いつの時代にも独特の雰囲気がある。ピーンと張りつめた緊張感と切羽詰まった重苦しい空気である」「二部に落としたら、OBにすまないし学校にすまない。そして何より神宮球場で試合できなくなる選手たちに済まない。そんな思いが募ってきて、緊張感で足がガクガクになる」 (『球心、いまだ掴めず』(日刊スポーツ出版社刊)-----------------------------------------------------------■その1・2部入替戦1回戦が今日(11月7日)、神宮球場で行われた。「足をガクガクさせる」ほどの緊張感で臨んだのは強豪・青山学院大。今季、なぜか1部リーグの最下位に転落。この試合の出場を余儀なくされた。応援席の学生たちの数もまばら。相対するのは古豪・国士舘大。久々の1部復帰を狙い、まさに意気軒昂。応援席も試合開始前から大いに盛り上がる。席の両脇には「国士舘大学」と描かれた49本のノボリが立ち、まさに「出陣」の様相。最初に試合結果を言ってしまうと、応援席の雰囲気をそのままグラウンドに持ち込んだ国士舘大がスコア5-4で逆転勝ち。1部復帰に向けて大きな1勝を挙げた。■(1回戦、11月7日)青 200 200 000 =4国 120 000 02X =5(青)垣ヶ原-●石井-川角、(国)○岩澤国士舘大、勝利を決めたのは8回裏、二死走者なしから始まった3連打だった。この試合途中出場の大城亮(2年、中部商高)がセンター前ヒットで出塁すると続く6番・青山直樹(3年、市立船橋高)がライト前にヒットを放ちチャンスを広げる。ここで国士舘ベンチは勝負をかける。代打に花島弘樹(4年、成田高)が登場する。そして初球だった。花島がフルスイングした打球は、快音を残してライト線へ転々。2人の走者が生還する三塁打となって逆転に成功した。国士舘ベンチからは選手たちが総出、生還した走者たちを迎え入れる。スタンドの応援席の盛り上がりも最高潮、勝利を確信したようなお祭り騒ぎだった。 打のヒーローが花島なら、投のヒーローは先発完投した岩澤正登(4年、立命館高)。100~120km台の変化球を繰り出し、青学打線を翻弄した。187cmの長身ゆえ本格派右腕の印象をもったが、さにあらず。直球も130km未満の投球でタイミングを外し凡打の山を築いた。■8回裏に逆転された直後、青学大の河原井正雄監督は投手交代を告げ、ベンチに戻りかけた。と、その時、「河原井さん、まだ負けが決まったわけじゃないよ。頑張れよー!」と、年輩のOBから激励の大きな声が飛んだ。至近距離だったため、たぶんその声は河原井さんの耳にも届いたはずだった。でも河原井さん、俯いたまま帽子を深くかぶり直して、そのままベンチに消えた・・・。結果こそ接戦だったものの、試合の「流れ」は終始、国士舘大にあった。ただ守備の乱れがあって国士館が失点を重ねたに過ぎない。だから、青学大がリードした中盤以降でも青学大にはまるで余裕が見えず、遅かれ早かれ国士舘が逆転する雰囲気が常にグラウンドを包んでいた。太田氏がいう「緊張感」で、青学大の監督や選手が金縛りの状態に見える。お隣りの神宮第二球場が、青学大のナインに向けて「いらっしゃい!」と手招きを始めたか・・・?今日も1クリックお願いします
2009.11.07
コメント(2)
-

明大、優勝決定づけた試合
(前回の続き)あくまで結果論だけど、明治大が優勝を決定づけた試合は対法政大3回戦(10月27日)だった。試合開始前の時点は、明治・法政ともに優勝の可能性が残っていた。だがこの試合で負けたチームは可能性が完全に消滅。勝ったチームでさえ次週の早慶戦の結果を待たなければならない状況。それは慶応の連勝を期待するしかない、極めて可能性の低いものに過ぎなかった。(結局、慶応が早稲田に連勝したが、27日の時点でそう予想するのは難しかった)。■明治大-法政大3回戦を振り返りたい。(11月1日)明 120 000 000 =3法 100 010 000 =2(明)野村-西嶋-森田貴、(法)二神-三上-藤田卓-武内■1回表、明治大の攻撃。1番・荒木郁也(3年、日大三高)、3番・小道順平(4年、二松学舎大附高)がいずれも四球で出塁。そして5番・謝敷正吾(3年、大阪桐蔭高)の打球は、大きく弾んで二遊間のちょうど真ん中へ。このゴロを追ったセカンドとショートが交錯してボールを落球している間に二塁走者の荒木が生還。難なく明治が先制した。(記録は安打)制球力に優れる二神一人(4年、高知高)だから、四球を出すこと自体が珍しい。さすがに2日前(対明治大2回戦)、115球を投げて完投した疲労が見える。二神の調子は最悪のようだった。■1回裏、法政大の攻撃。すぐさま法政は反撃する。このところ1番に定着した和泉将太(4年、横浜高)が右前安打で出塁すると、送りバントで二進後に3番・多木裕史(1年、坂出高)の適時打で生還。あっという間に同点に追いついた。■2回表、明治大の攻撃。この回先頭の6番・多田隼仁(4年、日大三高)が内野安打で出塁。続く7番・上本崇司(1年、広陵高)が左中間に適時二塁打を放ち1点を追加。その後二神の暴投もあって3点目を挙げた。■5回裏、法政大の攻撃。簡単に二死を取られた後、1番・和泉がファースト強襲の安打で出塁すると、続く2番・喜多薫(4年、伝習館高)が三塁線に二塁打を放ち、和泉が生還。法政は1点を返した。■9回表、明治大の攻撃。この回先頭の代打・矢島賢人(3年、桐生一高)が中前打で出塁。ここで法政ベンチは2番手の左腕・藤田卓(4年、丸亀城西高)に代え、武内久士(4年、徳島城東高)をマウンドに送る。だが直後、武内は7番・上本に死球を与えて無死一・二塁のピンチに。ここで8番・安田亮太(4年、PL学園高)が送りバントを試みたが、武内が捕球後すかさず三塁に送球、フォースアウトに仕留めた。そして、後続の打者を三振と一塁ゴロに打ち取ってピンチを脱した。(武内、ナイスフィールディングだった)■9回裏、法政大の攻撃。マウンドには、8回途中から3番手として登板した森田貴之(2年、大垣日大高)。打席には代打・難波真史(2年、中京大中京高)が入った。初球はファール。だがその後ボール球を4つ続けてあっさり四球。続く8番・中尾孝(2年、報徳学園高)はサードへの内野安打で続く。ボール先行でなかなかストライクが入らない森田。スタンドは歓声と悲鳴が交錯し異様な空気に包まれたことが、森田をひどく動揺させたようだ。サードを守る千田隆之(4年、日大三高)が身振りを交えて森田に「落ち着け!」と懸命に声をかける。それが奏功したか2つのアウトを内野ゴロで奪い、二死まではこぎ着けた。だが、その後もストライクは続かず2番・喜多には四球。二死満塁、絶好のチャンスに3番・多木が打席に入った。対する森田は、開き直ったかのように速球一本でグイグイと立ち向かう。1球目 144km。 多木もフルスイングで応じ、空振り。2球目 144km。 多木、またもフルスイングしたが空振り。3球目 144km。 ボール。4球目 146km。 ボール。スタンドの盛り上がりは最高潮に達した。そしてカウント2-2から森田が投げた5球目も速球、146km。これを多木はまたもフルスイングしたが空振り三振に終わり、試合が終了した。勝敗が決した瞬間、顔を覆い隠すようにヘルメットのつばを思いきり下げて、左打席に立ちすくむ多木の姿があった。1日1クリックお願いします
2009.11.02
コメント(11)
-

早大自滅、明大たなぼたV
昨日(11月1日)行われた早稲田大-慶応義塾大の2回戦は、スコア4-7で早稲田が敗退した。1回戦に続く連敗で、早慶戦前は優勝に一番近かったはずの早稲田が、最終結果は(なんと)4位に転落した。これは應武篤良監督が2005年に就任して以来、最悪の順位となった。■日刊スポーツによると、もっとも責任を感じているのは斎藤佑樹(3年、早稲田実)。10月11日の対立教大1回戦で今季3勝目(通算25勝目)を挙げて以来、4試合に先発するものの勝ち星から見放された。(斎藤は)「原因はまったくわからない。神様が与えた試練だと思う」と首をひねった。 (日刊スポーツ)斎藤佑樹、この日は4番手で最終回に登板したが、出来はよくなかった。1回、被安打1、奪三振0、与四死球1、自責点1。また今季の成績は、8試合、3勝2敗、防御率3.08(※8位)となり、初めて防御率が3点を上回った。(参考:これまでの成績)※印は投手十傑。1年春:6試合、4勝0敗、防御率1.65(3位)1年秋:8試合、4勝2敗、防御率0.78(1位)2年春:9試合、3勝2敗、防御率1.75(6位)2年秋:9試合、7勝1敗、防御率0.83(2位)3年春:8試合、4勝2敗、防御率2.25(3位)3年秋までの通算成績は、次のとおり。48試合、25勝9敗、防御率1.60。↑ ま、なんだかんだ言ってもすばらしい成績ではある。ボクとしては原寛信(3年、桐蔭学園高)にもっと活躍してほしかったが・・・■「たなぼた」的に優勝が転がり込んだのは明治大。以下、善波達也監督のコメント。日刊スポーツより。「2勝1敗のカードが3カードもある。粘ったら最後にうちに優勝が転がり 込んできたんです。投手が大崩れしなかったので粘れたかな」(日刊スポーツ)勝率は慶応大が1位(勝率.667、勝ち点3)だったものの、勝ち点で上回る明治大(勝率.615、勝ち点4)に優勝が決まった。こうしてみると、明治大-法政大3回戦(10月27日)の勝敗が明治大優勝の決め手になったともいえる。この試合も記憶に残る接戦だった。次回、その試合の詳細を書きます。1日1クリックお願いします
2009.11.02
コメント(2)
-

山川陽祐、藤原誠人、大前佑輔・・・
今日(11月1日)行われた早稲田大-慶応義塾大の2回戦は、慶応大がスコア7-4で早稲田を破り連勝、3つ目の勝ち点を挙げた。また早稲田が勝ち点を失ったことで、明治大の3季ぶり33回目の優勝が決まった。(2回戦、11月1日)慶 040 200 001 =7早 000 000 013 =4(慶)小室-松尾拓、(早)大石-福井-松下-斎藤佑■まさか奇策はないだろうと思っていたが、早稲田の先発は大石達也(3年、福岡大大濠高)。まさに奇策!(ホントかよ?)ただ、この奇策は見事に外れた。大石という投手は先発に向かないようだ。2回、慶応は無死一・三塁のチャンスを作ると、山本良祐(4年、岡崎高)、漆畑哲也(4年、慶応高)、山口尚記(3年、慶応高)の適時打で一気に4点を挙げ、序盤で勝負を決めた。■慶応のワンサイドゲームに見えたこの試合。だが終盤に早稲田が粘りを見せる。まず8回、代打で登場した藤原誠人(4年、観音寺一高)がライトフェンス直撃の3塁打を放つ。三塁ベース上で雄叫びを上げる藤原、出場機会に恵まれなかった鬱憤を晴らす一打となり、他の4年生たちの心に火を点けた。9回は一死一塁で、4年の大前佑輔(社高)が代打で登場。迷うことなく初球を叩いて、右前に安打を放ちチャンスを広げる。塁上の大前も目から大粒の涙がこぼれていた。そして一人置いて次の代打は、主将の山川陽祐(中京高)。カウント2-3と追い込まれたものの、その後にファールで4球粘り10球目を左前に運んだ。山川も塁上ではベンチに向かって左手を突き上げていた。いつも冷静そうな山川の表情が、少しだけ紅潮して見えた。この試合が最後になった4年生。特に藤原、大前、山川らは下級生にポジションを奪われ、出場機会に恵まれない選手たちだった。なのに、この試合で与えられたわずかなチャンスに自身の最高のパフォーマンスを示して見せた。数えてみると、早稲田の4年生部員の内、背番号さえつけていない部員が24名いる。藤原たちの安打は、スタンドにいた同級生たちの悔しさや期待を背負った一打でもあった。■4年生の気持ちは慶応も同じ。特に、相場勤監督は今シーズンを最後に引退が決まっている。勝利インタビューでは「最後の早慶戦でしたが・・・」と聞かれ、言葉を詰まらせた相場さんの姿が印象的だった 1日1クリックお願いします
2009.11.01
コメント(4)
全19件 (19件中 1-19件目)
1