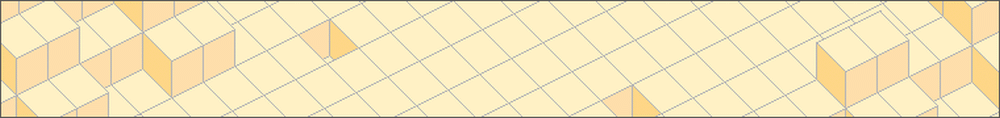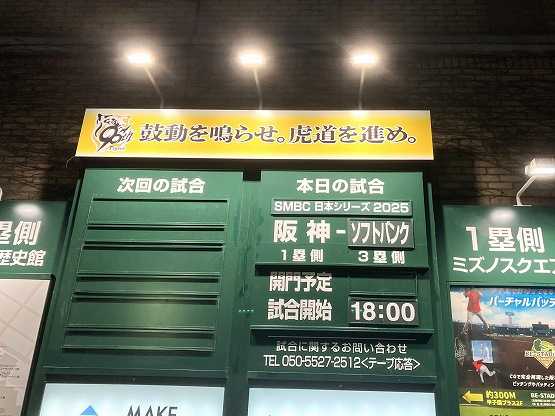2009年09月の記事
全35件 (35件中 1-35件目)
1
-

プロ野球、去る人・来る?人
最近の記事から。 ■今月25日、膵臓(すいぞう)がんのため死去した土井正三氏のこと。葬儀・告別式が29日、東京都大田区の池上本門寺で営まれた。弔辞を読んだのは、V9時代に監督だった川上哲治氏。「守備や走塁がどれほど大事か。ファンの野球を見る目を変えた君は、日本一のチームプレーヤーになった。王、長嶋が気の抜けたプレーをすれば、真顔でかみついた。君なくしてV9はなし得なかった。V9は遠い伝説となったが、心は1つだ。土井よ、ありがとう。さようなら」と別れを告げた。 (参考:日刊スポーツ)そして毎日新聞は、川上さんの弔辞の内容を次のように伝えていた。オリックス監督としてイチローの才能を見出せなかったと批判されたことに関して、「君はイチローの才能をはじめから見抜いていた。『いい新人が入ったからキャンプに来てください』と、オーナーを誘ったという話がある。それが何より証拠」と述べた。(以上、毎日新聞)テレビには川上哲治さん、黒江透修さんらの姿が映っていた。川上さんは脇を他人に支えてもらってやっと立てる状態だったし、黒江さんの風貌もかなり老いたようにボクには見えた。V9時代は遠い過去になったものだ。しみじみとそう思う。◇土井正三の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「土井正三さん、最期の思いは?」 (2009.9.25) → こちらへ。◇川上哲治の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「川上哲治のファンサービス」 (2009.7.22) → こちらへ。◇黒江透修の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「V9の正遊撃手・黒江透修」 (2007.6.10) → こちらへ。■そして、花巻東高・菊池雄星のこと。これも毎日新聞から。花巻東の菊池は(国体)準決勝の都城商戦で、2-3で1点リードされた9回二死二塁の場面で代打出場。菊池は初球をたたいたが、鋭いライナーは遊撃手の正面を突いて試合終了となった。「自分が最後の打者でいいのかなという思いもあったが、幸せです」と話した。卒業後の進路については「向こう(岩手)に帰って、親や先生と相談します」として明言を避けた。(以上、毎日新聞)◇菊池雄星の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「泣くな菊池、甲子園の花!」 (2009.8.24) → こちらへ。 今日も1クリックお願いします
2009.09.30
コメント(0)
-

東都は下剋上。まさに戦国時代
2009年秋、東都大学リーグ(1部)はまさに「下剋上」の様相だ。■ちなみに、春季の最終順位は次のとおりだった。※( )は勝ち点。 1位 東洋大 (4) 2位 青学大 (4)3位 亜細亜大 (3)4位 中央大 (3)5位 國學院大 (1)6位 立正大 (0)■ところが今季、まだ中盤ではあるけれど、AクラスのチームとBクラスがまったく入れ替わる格好になっている。※( )は勝ち点。第4週1日目(9月29日)終了時点。1位 立正大 (2)2位 國學院大 (2)3位 中央大 (1)4位 東洋大 (1)5位 青学大 (1) 6位 亜細亜大 (0)■この「下剋上」はいったいどうしたものか!? とりわけ東洋大と亜細亜大から勝ち点を挙げた立正大の躍進は特筆もの。特に左腕・小石博孝(4年、鶴崎工業)や、右の菅井聡(4年、中央学院高)、南昌輝(3年、県和歌山商高)ら投手陣の踏ん張りがチームを牽引している模様。一方、史上2度目の6連覇を狙う東洋大は大凋落。エース・乾真大(3年、東洋大姫路高)の不振が影響している。また亜細亜大もエース・東浜巨(1年、沖縄尚学高)もこれまで1勝2敗と冴えない状態。■まさに「戦国東都」。だけどボクにとっての心配事は日米大学野球に出場した選手たちが総じて不調であるように見えること(中央大の澤村拓一は除く)。WBCに出場したプロ選手たちがそうであったように、何だか因縁めいて思えるのだ。今日も1クリックお願いします
2009.09.29
コメント(2)
-

最近の記事より、ちょいと不満なこと!
■第64回国体「トキめき新潟国体」、昨日(9月28日)行われた高校野球硬式の2回戦。プロ注目の菊池雄星投手を擁する花巻東が、今夏の甲子園を制中京大中京高をスコア6-4で破った。花巻東は同大会準決勝で中京大中京に敗れており、夏の雪辱を果たした。花巻東は同点の八回、猿川の2ランで勝ち越し。菊池雄は九回からマウンドに上がり、最速153キロの直球を主体に三者三振に抑え、「何とか勝ちたかった。中京にリベンジできた」と話した。「花巻旋風」はまだ終わらない!? いや、そんなことより、菊池雄星は夏から背中の痛みを訴えているのに、報道はいつも「病院に行って検査するとかしない」とか。なんでさっさと検査をしないのか?ボクはそれが不思議で仕方がない。■「創価大・大塚投手が通算最多勝利の連盟記録更新」 (東京新大学リーグH・P)創価大のエース・大塚豊(4年、創価高)が9月26日、対東京学芸大1回戦で完封勝利。39勝目を挙げて通算最多勝利の連盟記録を更新した。注目すべきは勝利数だけではない。勝率が半端じゃない。通算成績が39勝1敗、たったの1敗なのだ。<歴代の勝利数記録> ※( )内は当時。2位 38勝19敗 小倉丞太郎(東京学芸大)3位 35勝 3敗 八木智哉(創価大)4位 25勝 8敗 栗山英樹(東京学芸大)◇栗山英樹の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「栗山英樹氏の学生時代 」 (2007.12.3) → こちらへ。「三種類のフォークを操る投手」と言われる大塚、もっと注目されていい投手だ。今年6月に行われた全日本選手権。閉会式で大塚が表彰選手としてわざわざ呼ばれ出席したのに、連盟会長のスピーチでは大塚のことにあまり触れることがなかったので、ボクはちょいと可愛そうに思えた。■「原が決勝打!早大が開幕4連勝」(サンケイスポーツ)東京六大学野球第3週第2日(27日、神宮)2回戦2試合を行い、早大が8-2で明大を下して開幕4連勝を決め勝ち点を2に伸ばした。六回に勝ち越し、九回に5点を挙げて大勢を決めた。 3年生スラッガー原が2-2の六回二死二塁で左越えに勝ち越しの適時二塁打。「内角の直球をうまくさばけました」。春のリーグ戦では4番を務めていたが、今季は6番に。「春はチーム打撃に徹するあまり当てにいっていた。昨夜、バットを長く持って思い切り振る自分のスタイルでいこうと思った。吹っ切れました」と笑顔を見せた。早稲田大の主砲・原寛信(3年、桐蔭学園高)が今年春以降は下位打線に甘んじている。本来4番打者であり、存在感というか打席で「雰囲気をもつ」打者なのだ。なのにいまの境遇は、あまりに寂しい。勝ち越し二塁打となったあの当たりをキッカケに、早く4番に復活してほしい。 今日も1クリックお願いします
2009.09.28
コメント(0)
-
星野仙一さんが大学野球の解説を
今夜は名古屋のホテルにて。星野仙一さんがスカイAが放送した早稲田--明治戦の解説をしていた。プロ野球に属する人がなぜ大学野球の解説を?と思ったけれど「特別ゲスト」ということで出演が実現したらしい。これもプロアマ雪解けの象徴かもしれない。ボクにとっては明治大時代の島岡御大にまつわる昔話が面白かった。
2009.09.28
コメント(0)
-

法政・大八木誠也、バスターせず
昨日(9月26日)行われた法政大-慶應義塾大1回戦。ボクはこの試合を観ていて、今年6月に行われた全日本大学選手権の決勝戦(対富士大戦)を思い出すシーンがあった。<試合経過>(法政大-慶應義塾大 1回戦)法 000 000 110 =2慶 010 300 000 =4 (法)●加賀美-西-藤田卓-上野悠-武内、(慶)○中林-福谷-小室 ■それは、2点差を追う法政大が9回表に見せた選手起用。無死一・二塁の場面で(途中出場で9番に入っていた)佐々木陽(3年、作新学院高)に代えて大八木誠也(3年、平安高)を打席に送った。このシーンは、全日本大学選手権の決勝(2009年6月14日)とまったく同じだった。スコア1-1の同点で迎えた9回表、法政大攻撃の時のこと。無死一・二塁のチャンスに、(初球、送りバントを失敗した)佐々木に代えて大八木が(カウント1-0から)代打で出場した。シーズン中、こういった場面ではバントするのが大八木の役割。多くの人が大八木のバントを想像したし、事実、バントの構えを見せていた。ところが、大八木が試みたのは意表を突くバスター。これが見事にハマって追加点を挙げることに成功したのだ。◇大八木誠也の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「ドラマを秘めた大八木誠也のバスター」 (2009.6.16) → こちらへ。■ボクはその場面を鮮明に記憶していたから、昨日の9回表に大八木が代打で登場した時は「大八木、またバスターか!?」と勝手に想像していた。たぶん守っている慶應ナインもそのことが脳裏をよぎったかもしれない。ところが、この試合は確実に送りバントを決めて、走者の進塁を好アシスト。全日本で裏をかいた作戦が、今度はその裏の裏をかいた作戦でチャンスを広げたのだった。--------------------------------------------------------------■大八木が送りバントした直後に起きた「珍プレー」のこと。一死二・三塁にチャンスを広げた法政。この試合途中出場の1番・加治屋祐大(4年、育英高)が打席に入った。初球、相手投手が投げた球を捕手が一塁側に大きく弾く。三塁走者だった中尾孝(2年、報徳学園高)はそれを見て、本塁に向かってスタートを切るが、捕手がボールを拾って三塁に送球するや慌てて三塁に戻った。ところが捕手の三塁への送球は大暴投。それを見て、中尾は再び本塁へ突入。だが捕手への返球は悠々と間に合って、中尾はホーム手前でタッチアウトになり、法政は同点のチャンスを失ったのだった。東京六大学野球というよりは、だれもが小さい頃に経験した草野球並みのプレーだった。守備も走塁も・・・。 今日も1クリックお願いします
2009.09.27
コメント(2)
-

富士大敗退、花巻旋風未完のまま
昨日(9月26日)、北東北大学リーグのプレーオフを戦った富士大(岩手・花巻市)は八戸大にスコア6-7でサヨナラ負けを喫し、11月に行われる明治神宮大会への出場権を失った。■以下、読売新聞より。北東北大学野球秋季リーグ戦(北東北大学野球連盟主催、読売新聞東京本社共催)は26日、野田村のライジングサンスタジアムで優勝決定戦が行われ、春の全日本選手権で準優勝した富士大は八戸大(青森県)に6-7でサヨナラ負けし、全国大会の出場権を懸けた東北代表決定戦に進むことはできなかった。 富士大は1点を先制された直後の四回、屋宮や佐藤弘の適時打などで3点を奪い逆転したが、七回に失策などが絡み再逆転された。1点を追う九回、二死から柴田、ジエゴの連打で一、二塁の好機を作ると、続く夏井健が右前適時打を放ち、土壇場で試合を振り出しに戻す粘りを見せた。しかしその裏、二死走者なしから、八戸大の岩佐が右越えの三塁打を放ち、さらに、三塁への送球がそれる間に、そのまま本塁へ駆け込み、劇的な幕切れとなった。主戦守安は「走者がいても踏ん張れるという自分の持ち味が今日は出せなかった」と悔しさをにじませた。夏井大吉主将は「6月の全日本選手権で準優勝して、もう一度日本一を目指そうとみんなで頑張ってきたが...。後輩には絶対に日本一になってほしい」と語った。 (以上、読売新聞)■今年、岩手・花巻勢が巻き起こした「花巻旋風」。ついに全国制覇を果たすことなく、2009年が終わることになった。4月 花巻東高、センバツ高校野球で準優勝6月 富士大、全日本大学選手権で準優勝8月 花巻東高 夏の甲子園でベスト4そして秋、富士大は明治神宮大会に出場ならず・・・。残念だあっ、そういえば、花巻東が出場する国体に可能性がまだ残っていた。今日も1クリックお願いします
2009.09.27
コメント(0)
-

斎藤佑樹、再び野村祐輔に勝つ
今日(9月26日)行われた早稲田大-明治大の1回戦。早稲田・斎藤佑樹(3年、早稲田実)と明治大・野村祐輔(2年、広陵高)の直接対決が注目されたが、前(春)季と同様、斎藤がバランスを活かした投球で勝ち星をゲット、通算24勝目を挙げた。◇斎藤佑樹・野村祐輔の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「斎藤佑樹に軍配、野村祐輔との対決」 (2009.5.16) → こちらへ。■今季開幕の直後、斎藤は「直球で三振を多く取りたい」と目標を掲げていた。その言葉どおり、初戦の東大戦では直球をビシバシ投げ込み、6回までに8個の三振を奪った。ただこの時、「変化球に課題が残った」と反省し、今日は直球の比重を抑え、変化球を主体に明治大打線を翻弄し続けた。(斎藤の今日の成績)7回、被安打5、奪三振7、与四死球2、自責点1。<試合経過>(早稲田大-明治大 1回戦)明 000 000 110 =2早 010 020 100 =4 (明)●野村-大越-隈部、(早)○斎藤佑-大石■明治は1回表、荒木郁也(3年、日大三高)と謝敷正吾(3年、大阪桐蔭高)の連打などで二死満塁のチャンスをつかむ。だが6番・千田隆之(4年、日大三高)が見逃し三振でチャンスが潰えた。■早稲田は2回裏、山田敏貴(3年、早稲田実)の安打をキッカケにして一死満塁のチャンス。ここで8番・宇高幸治(3年、今治西高)がレフト前に先制打を放つ。そして5回裏、9番・斎藤佑が二塁打で出塁後、3番・土生翔平(2年、広陵高)、4番・山田、5番・杉山翔大(1年、東総工高)の3連打で2点を加え、それが決勝点になった。----------------------------------------------------------■ボクにとって気がかりなことがひとつある。それは5回表、無死二塁のチャンスに送りバントを命じられ、それを失敗してしまった早稲田・小島宏輝(4年、愛工大名電高)のこと。失敗したのは初球だったが、應武篤良監督は怒り心頭。まだカウント1-0なのにすぐさま代打を送られてしまったのだ。この小島、実は1年前も送りバントを失敗して應武監督の逆鱗に触れたことがある。その時は、罰として神宮球場から合宿所まで(約20km)走って帰ることを命じられた。「送りバント失敗」も「應武監督の逆鱗」も昨年とまるで一緒。ということは、今日もたぶん合宿所まで走らされているに違いない。ひょっとしたら、今も街のどこかを走っているのだろうか?◇小島宏輝の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「小島宏輝の意地・・・」 (2008.9.28) → こちらへ。 今日も1クリックお願いします
2009.09.26
コメント(0)
-
日本一の法政、慶應にまさかの敗戦
法政が2-4で慶應に敗れた。敗戦投手は加賀美。2本の本塁打を浴びて早々にノックアウト。亀谷のいない打線もつながりに欠けた。
2009.09.26
コメント(2)
-

土井正三さん、最期の思いは?
イチローの活躍を見聞するたび、ボクは土井正三さんのことを思い出すことがたびたびあった。そんな習慣(?)が身についたのは2年前、東京ドームでの土井さんの姿を見てからのこと。■それは2007年6月8日のことだった。東京ドームで行われた巨人軍通算5000勝記念イベントに出席した土井さん。痩せこけた表情で車イスに座る姿を見て、ボクは本当に驚いてしまった。それまで、しばらくは土井さんの近況に関する情報がまるでなく、ボクの記憶が薄れていた時、突然メディアを通して現れた土井さんの姿がそれだった。■土井さんの現役時代に関する「明」の部分は数多くある。やれ「V9戦士」だとか、1969年の日本シリーズで見せた「走塁技術の高さ」だとか。でもそんな「明」にも勝る「暗」が土井さんの人生後半にはあった。オリックス監督時代、イチロー独特の「振り子」打法を認めず、後々強烈なバッシングを浴びるハメになった。もちろん土井さんを擁護する声もあったが、そんな声はすぐにかき消されてしまった。■ボクは野球の「技術論」など持ち合わせていないから、土井さんの判断の真偽はわからない。ただ、いかにバッシングを受けようと、土井さんはそれに対して愚痴を言ったり、不平不満を言うことは一切なかった(ボクの知る限りは)。その姿勢がボクは偉いと思う。並みの人間なら土井さんのマネは絶対にできない。そして、往年の名選手たちは高年齢になり病に伏せると、人前に出ることを避けることが多い。「いまの姿」を見られたくないというプライドがそうさせるのだ。なのに2年前、土井さんは車イスに乗って堂々と東京ドームに現れ、テレビカメラの前に自らの姿をさらけ出したのだ。あの時、土井さんの心に秘めていたのは何だったのだろうか? いまになって、ボクはとても気にかかる。少なくとも悔しさいっぱいの「最期」でなかったと信じたい。ご冥福をお祈りいたします。◇土井正三さんの関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「V9~土井正三さんにまつわる思い出」 (2007.6.9) → こちらへ。 「江藤省三氏が慶大監督に就任」 (2009.9.11) → こちらへ。今日も1クリックお願いします
2009.09.25
コメント(0)
-

亀井義行、子供のため頑張るゾっと!
■昨日(9月23日)、読売巨人軍が早くもセ・リーグの優勝を果たした。詳しいことは知らないけれど、これが3連覇になるらしい。しかもセ・リーグの3連覇は1965年から73年に巨人が9連覇して以来、実に36年ぶり。巨人の強さは群を抜いていた。■今日の朝日新聞、「ひと」欄(2面)には殊勲のひとり、亀井義行が紹介されていた。「プロ5年目の今季、走攻守そろった5番打者として、リーグ3連覇に貢献した。飛躍の始まりは春だった。日本代表に選ばれた3月のWBCには、同じライトの守備位置にはイチローがいた。『あこがれだった。練習での動きひとつから、姿を見ているだけで勉強になった』--------------------------------------------------------------------■WBCの選手に選ばれた頃、「なぜ亀井が?」と言われ、「原監督の縁故採用」とか「原監督の職権濫用」などと陰で囁かれたものだった。でもWBCでチャンスをつかみ、ペナントレースで自身の活躍に活かしたのだから、まわりが何を言おうと「亀井の勝ち」であることは間違いない。実は今から2年半前、女性誌のインタビューで、亀井はそれまでの弱気な気持ちを吐露していたことがあった。「打席に立っても打てる気がしない」と。これは、一軍と二軍を行き来して、自分を見失っている頃を回想して話したコメントだった。ただインタビューの後半では、息子を授かったことでモチベーションが格段に上がったと、亀井本人が語っていた。「子供が大きくなって、父親が現役でプレーする姿を見て、感想を話してくれる日まで頑張らなければならないぞ!」と。■今季の活躍の陰には、原辰徳監督だけでなく息子さん(たぶん今、2~3歳か?)の存在があったのかもしれない。そして、感想を話してくれるまでは、まだだいぶ時間がかかりそうだから、亀井の活躍がまだまだ続くってことになりそうだ。◇亀井義行の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「亀井義行、子供に現役の姿見せるまで」 (2007.5.16) → こちらへ。 今日も1クリックお願いします
2009.09.24
コメント(0)
-

最近の記事から・・・+α
■「花巻東は選抜絶望」(朝日新聞) 昨日(9月21日)の秋季岩手県大会準々決勝で専大北上高に2-4で敗退した。センバツ出場の参考に重要な資料となる東北大会(10月)に出場できないため。今年「花巻旋風」を巻き起こした花巻東高、来春の甲子園で見ることはできない。ただもうひとつの「花巻の雄」富士大は、今秋の神宮大会出場への可能性を残している。■「守安30勝、富士大逆王手」(日刊スポーツ)今年6月に行われた全日本大学選手権で準優勝だった富士大が、北東北リーグの優勝に王手をかけていた八戸大に10-2で大勝。8勝2敗で首位に並び、優勝争いをプレーオフに持ち込んだ。神宮大会にまた一歩近づいた。■「創価大・大塚投手が通算最多勝利の連盟タイ記録」(東京新大学リーグH・P)チームを全日本大学選手権ベスト4に導いた今秋ドラフト候補・大塚豊(4年、創価高)が東京国際大戦に勝利し、通算38勝目を挙げた。同記録は元・東京学芸大の小倉丞太郎氏がもっていたもの。■「立正大・南、完投で通算10勝目」(サンケイスポーツ) 今季、亜細亜大を破り勢いに乗る立正大。今度は東洋大初戦にも勝利した。相次ぐ強豪の撃破。今季、ひょっとしたらひょっとするかもしれない・・・!?■「その時、県営大宮球場のセンターまでの距離は105mだった」(『長嶋はバカじゃない』小林信也著、草思社刊)長嶋茂雄氏が一躍全国に名を馳せたのは、佐倉一高3年の時。南関東大会が行われた県営大宮球場で、バックスクリーンに特大本塁打を打ち込んだことがキッカケだった。翌日の朝日新聞は「佐倉一高・長島、超高校級のホームラン」「長島、攻守に光る」と書き立てた。この「本塁打」と「ハデな記事」がその後に続く「長島伝説」の端緒となったが、実はこの本塁打が飛び出した1953年(昭和28年)8月頃、「県営大宮球場のセンターまでの距離は105mしかなかった」と、同書に書かれていた。普通120m前後(現在の県営大宮球場は120m)と思ってしまうが、当時は意外と狭い球場だった。 今日も1クリックお願いします
2009.09.22
コメント(0)
-

野村祐輔、戸村健次に投げ勝つ
昨日(9月21日)行われた明治大-立教大3回戦。明治大が3-0で立教大を降し2勝目、開幕カードで勝ち点を挙げた。(明治大-立教大 3回戦)明 000 002 010 =3立 000 000 000 =0 (明)○野村-西嶋-川辺、(立)●戸村-仁平■以下、日刊スポーツより。まず明治大のこと。明大は、2勝1敗で勝ち点1を挙げた。先発の野村祐輔投手(2年=広陵)が7回6安打4奪三振無失点で、節目のリーグ通算10勝目を飾った。「負けられないので、向かっていく気持ちだった」と喜んだ。8回以降は2番手の西嶋一記投手(3年=横浜)が無失点に抑え、完封リレーを達成した。そして立教大。立大はドラフト候補右腕、戸村健次投手(4年=立教新座)が8回114球を投げ、3失点と粘ったが、勝ち点を落とした。5回まで無失点だったが、6回に先制を許した。「中盤までは良かったけど、守り切れなかったのが悔しい」と悔やんでいた。(以上、日刊スポーツ)------------------------------------------------------------■明治大・野村祐輔(2年、広陵高)が2年秋の2試合目で通算10勝目を挙げた。神宮デビューから負けなしで9勝したものの、春季途中(対早稲田大1回戦、2009年5月16日)から3連敗しただけに、久しぶりの勝利となった。通算勝利数で現役のトップを走るのは斎藤佑樹(3年、早稲田実)で23勝(9月21日現在)。また斎藤が通算10勝目を挙げたのは2年春だったから斎藤のペースには若干遅れをとった。(野村、今季これまでの成績)2試合、1勝1敗、15回、被安打12、奪三振15、与四死球2、自責点2。そして、防御率1.20、奪三振率9.00、与四死球率1.20。 (ちなみに昨(春)季の成績)8試合、4勝2敗、39回1/3、被安打34、奪三振50、与四死球12、自責点11。そして、防御率2.52、奪三振率11.45、与四死球率2.75。 ■一方、立教大・戸村健次(4年、立教新座高)は苦手としていた3回戦目を8回、被安打10、奪三振1、与四死球2、自責点3と、敗戦投手になったものの、内容は「大崩れ」せずに乗り切ることができた。これまでも素材はプロのスカウト陣から高評価を得ていた。ただ「安定感」がイマイチ。それが戸村のウイークポイントだったが、今季は克服されたように見えなくもない(まわりくどい言い方だが)。今秋のドラフトで上位指名はあるか?(戸村、今季これまでの成績)4試合、2勝2敗、31回、被安打27、奪三振16、与四死球13、自責点11。そして、防御率3.19、奪三振率4.65、与四死球率3.77。(ちなみに昨(春)季の成績)9試合、3勝2敗、45回1/3、被安打45、奪三振28、与四死球29、自責点15。そして、防御率2.98、奪三振率5.56、与四死球率5.76。■戸村、明治大1回戦(9月19日)の8回に見せたピッチングは圧巻だった。直球で真っ向勝負できる投球が、戸村の真骨頂だ。◇「戸村健次の快投で立教先勝」 → こちらへ。 今日も1クリックお願いします
2009.09.21
コメント(2)
-

明立3回戦は投手力がカギ握る
昨日(9月20日)行われた明治大-立教大2回戦は明治大が3-2で勝利。対戦成績を1勝1敗のタイとし、今日の3回戦に勝負が持ち越された。今日行われる一戦、特に明治大にとって大きな意味をもつ。開幕カードとはいえ立教大に敗れると、それは即ち、今季優勝戦線からの脱落を意味する(に等しい)。一方、創部100周年を迎える立教大は先週、慶應義塾大戦で勝ち点を奪い波に乗る。エース・戸村健次(4年、立教新座高)を立てて是が非でも勝ち点を「2」としたい。(明治大-立教大 2回戦)立 002 000 000 =2明 020 001 00X =3 (立)丸山-●斎藤隼、(明)○難波-西嶋■スコアを見ると好ゲームのよう。でも2時間40分という試合時間が、ボクにはとても長く感じられた。理由は両チームとも打撃が振るわない点にある。しかも6回裏の決勝打が犠飛だから、地味な試合には象徴的でさえあった。昨(春)季も両チームの打率は不振を極めた。立教が.227に対し、明治が.228(ちなみに優勝した法政は.300)。そんな数字ゆえ、どちらも「投手任せ」の試合運びにならざるを得ず、まるで満足できないままシーズンを終えた。その傾向は、どうやら今季も変わらない模様。明治の1番打者が主砲であるはずの小道順平(4年、二松学舎大付高)というのも、万策尽きた「窮余の策」と見えなくもない。■さて今日行われる3回戦。先発は戸村健次(4年、立教新座高)と野村祐輔(2年、広陵高)で間違いない。双方の打撃不振を考えれば、9回を最少失点で投げ切るしか勝利は得られない。■昨(春)季、スタミナ不足を指摘された戸村健次。1回戦は好投しても、3回戦では大崩れするパターンが目立った。今季の慶應義塾大戦は3回戦に勝利したけれど、そんな声を跳ね返すには今日の試合が絶好のチャンスなのだ。 (戸村、2009年春の成績 - 1回戦登板時と3回戦登板時の比較)1回戦 3勝1敗 防御率1.59 奪三振率 6.35 与四死球率 5.033回戦 0勝1敗 防御率7.84 奪三振率 3.48 与四死球率 7.84※以上、「あま野球日記」調べ。 今日も1クリックお願いします
2009.09.21
コメント(0)
-

東大、敗戦決めた緩慢プレー
昨日(9月20日)行われた早稲田大-東京大2回戦は、早稲田が12-2で東大に大勝した。早 030 000 504 =12東 020 000 000 = 2(早)○福井-松下、(東)●平泉-西村-和田-揚場-吉松-前田スコアだけを見ると「とんでもないワンサイドゲーム」。ただ7回表、東大守備陣に「緩慢なプレー」が飛び出すまではスコア3-2の好ゲーム。東大にも十分に勝機のある試合だった。■7回表に起きた東大の「緩慢なプレー」とは---、この場面を振り返りたい。追加点の欲しい早稲田は、安打と2個の四球で一死満塁のチャンスを掴む。ここで早稲田ベンチは9番・先発の福井優也(3年、済美高)に代え、藤原誠人(4年、観音寺一高)を代打に送る。東大のマウンドもまだ代わったばかりの和田響(2年、旭丘高)。初球だった。藤原のバットから快音が響いたもののセカンド正面へ飛んだ平凡なゴロ。ゲッツー狙いだった東大内野陣は4-6-3ときれいなボール回しで、見事にピンチを乗り切った・・・ように見えた。ところがショートから転送されたボールを一塁手がポロリ。ボールが地面を転がる間に三塁走者はもちろん、二塁からも走者が生還。この瞬間、早稲田はスコアを5-2として事実上の勝利を決めた。■ショートから転送されたボールは、決して捕球が難しいものには見えなかった。東大の一塁手は小島大信(4年、浅野高)。球から目を切るのが早過ぎたのか?原因がまるでわからないが。たまたま昨日、ボクは小島のことを書いていた。「173cm、88kg。小柄ではあるけれど「ここ一発!」パンチ力をもった打者に見える。今日の対早稲田大2回戦、接戦で後半に勝負がもつれた時、チャンスで小島に打順がまわれば試合が面白くなる」ところが実際はまるで違った。「接戦で後半に勝負がもつれた時、ピンチで小島に送球がまわれば試合がつまらなくなる」が正解。予想は大外れ。次回、得意のバッティングで汚名返上の活躍を期待したい。 今日も1クリックお願いします
2009.09.20
コメント(2)
-

東京大、早稲田大に惜敗
東京大は先週の法政大1回戦に続き、またも勝てる試合を落とした。■今や東大のエースとなった先発・前田善博(3年、栄光学園高)は立ち上がり こそ(前回の法政戦のように)不安定な状態だったが尻あがりに回復。 緩い変化球を主体に早稲田大打線を翻弄し続けた。■今季、東京大の5番に名前を連ねている小島大信(4年、浅野高)にボクは 興味をもった。先週もそうだったけど、この小島、試合の前半は三振が常。 タイミングがまったく合っていないし、さらにバットと球の乖離幅が相当にある。 ところが「なぜこの打者が5番なんだ?」とこちらが思い始めると、それを見透 かしたように打席を重ねるたび次第にタイミングが合っていく。そして4打席目 あたりにはバットの芯で捕らえ、快打を飛ばし始めるのだ(結果はアウトでも)。 173cm、88kg。小柄ではあるけれど「ここ一発!」パンチ力をもった打者に 見える。今日の対早稲田大2回戦、接戦で後半に勝負がもつれた時、チャンス で小島に打順がまわれば試合が面白くなる。(東京大-早稲田大 1回戦)東 000 010 000 =1 早 200 000 01X =3(東)●前田、(早)○斎藤佑-大石<試合の経過>■早稲田は初回、立ち上がりが不安定な前田を攻め立て、4番・山田敏貴(3年、 早稲田実)の適時打などで2点を先制した。■東大は3回、無死一・二塁のチャンスをつかんだが、4番・堀口泰幹(3年、高崎高) が送りバントを失敗。結局この回、絶好の得点機を逃す。そして5回、さきほどの 汚名返上とばかり、走者を三塁において堀口がレフトに犠飛を打ち挙げて1点を 返した。■早稲田は8回、二死二塁のチャンスに7番・後藤貴司(3年、早稲田実)がセンター 前に適時打を放ち、これが決勝点となった。 今日も1クリックお願いします
2009.09.20
コメント(0)
-

戸村健次の快投で立教先勝
立教大・戸村健次(4年、立教新座高)が先週の慶應義塾大3回戦(9月14日)に続き好投。明治大打線を1点に抑え、早々と今季2勝目を挙げた。明 000 100 000 =1立 010 000 01X =2(明)●野村、(立)○戸村圧巻は、8回表に見せた戸村の強気のピッチングだった。一死二・三塁のピンチに、戸村は明治の各打者に真っ向勝負を挑んだ。代打・小町典史(4年、明大中野八王子高)には142km、144kmの直球を続けてカウントを追い込み、3球目は141kmの直球で空振りの(三球)三振を奪った。そして、この試合で3打数3安打と当たりを見せている6番・多田隼仁(4年、日大三高)は手堅く敬遠し、一塁を埋めた後は7番・小林卓麿(4年、豊田西高)と再び真っ向勝負。初球は145kmの直球(ファール)、2球目は130kmの変化球で空振りをとり、フィニッシュは150kmの直球。見逃しの三球三振に仕留めた。このピンチを見事に乗り切ったことが、次の回(8回裏)立教の追加点を呼び込んだ。もし1点でも失っていたら、試合の結果はまるで逆のものになっていた。 (戸村の今日の成績) 9回、148球、被安打6、奪三振7、与四死球6、自責点1。 ◇戸村健次の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「創部100周年なのに・・・」 (2009.5.9) → こちらへ。<試合の経過>■試合が動いたのは2回裏、立教の攻撃。 2本の安打で一死二・三塁のチャンス に7番・浅田麗太(3年、星稜高)がボテボテの投ゴロ。だが当たりが悪かったこと が逆に幸いし、三塁走者が悠々生還し先制。■4回表、明治の攻撃。二死三塁から6番・多田隼仁がライト前に適時打を放ち 同点に追いつく。■8回裏、立教の攻撃。内野ゴロ2つで簡単に二死になったものの、1番・ 田中宗一郎(3年、佐賀西高)が捕手の捕手の送球エラーで二塁に出塁。 続く途中出場の伊藤公俊(3年、清水東高)がライトオーバーの三塁打を を放ち田中が生還、この一打が決勝打となった。今日も1クリックお願いします
2009.09.19
コメント(0)
-

1901年、早大野球部の黎明期
1901年(明治34年)に創部された早稲田野球部。当時一高(現・東京大)と覇権を争っていた学習院に対戦を申込み、そして(だれもが予想しない)勝利を挙げたのはいつだったか。<A>1901年(明治34年)? それとも<B>1904年(明治37年)? ◇早大野球部の黎明期の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「早稲田が学習院に勝つ」 (2009.8.29) → こちらへ。 どちらなのか調べてみたら、早大元監督の飛田穂洲氏が著した『野球人・漫筆』(人文書房、昭和6年刊)の『學習院に善戦す』の章に、答えは<A>1901年だったと書かれていた。「三十四年の夏休暇も過ぎた。秋季に入りては新選手も見付かり、多少勢力も増したので、適當の相手を物色した。(中略)一つ手近な學習院というところから、天下を二分して其の一を納めていた學習院に向かって挑戦状を発した。今迄東京専門学校に野球部があらうなど夢にも思っていなかった學習院では、申し込んできたからどんなものか應諾してやらう位の輕い調子で、應戦の返事を与えた」 ※下線は「あま野球日記」が記した。また、東京専門学校とは早稲田のこと。試合の結果はスコア7-6、大かたの予想裏切って早稲田が逆転勝ちした。早稲田野球部として、これが旧制中等学校以外から挙げた初勝利。世間に早稲田の名を知らしめる第一歩となった。勝利後の歓喜ぶりが同著に記されている。「早稲田方の歓喜は實に非常なもので思はぬ勝利に有頂天であった。翌日の掲示場には、 我が選手は、學習院と戦ひ、一蹴これを粉砕したり。というやうな文字を冒頭に、二畳大の掲示紙にスコアを冩して貼出した。(中略)戦捷晩餐會を寺町の西洋料理明進軒に開催した」という。 ◇ 「ボクにとっての日本野球史」 (2009.7.1)、 INDEXはこちらへ。今日も1クリックお願いします
2009.09.19
コメント(0)
-

1903年、早慶戦の端緒
初めて早慶戦が行われたのは、1903年(明治36年)11月21日、土曜日。場所は慶應綱町球場と言われている。このことは、どの書籍を見ても同じことが書かれている。ただ、なぜ早慶戦が始まったのか、そのキッカケには2つの説がある。(1)『日本野球史』(国民新聞運動部編)より。慶應のグラウンドが稲荷山から綱町に移転した当時のこと。「その頃、早大の橋戸は始終慶應のグラウンドに遊びに行っていた。そして時とするとノックを打ったり選手のコーチまでしたりしていた。その中に『どうだ、早稲田と慶應と試合をしないか』ということになった。慶應の主将・宮原も至極軽い意味で『戦ってみようか』と内輪同志が練習試合でもするように承諾した。」(2)『早慶戦百年 激闘と熱闘の記憶』(富永俊治著、講談社刊)より。1903年(明治36年)10月下旬頃、慶應綱町球場の左翼ファウルグラウンドにある木立の陰で、身を潜めるようにして慶應の練習を凝視する2人の男がいた。11月5日、早稲田野球委員を差出人とする一通の手紙が慶應野球部に舞い込んだ。そのことで2人が早稲田の橋戸信と押川清であり、練習を凝視していた彼らの意図が判明した。「これは、早稲田からの挑戦状にほかならなかった。(中略)2人組は、紛れもなく敵情を探る偵察隊。その結果、早稲田側は『慶應、恐るるに足らず』の結論に達し、挑戦状送付という強気の行動に結びついたのだった」◇橋戸信の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「野球術を普及した安部磯雄と橋戸信」 (2009.6.24) → こちらへ。 さて、どちらが正しいのか? ◇ 「ボクにとっての日本野球史」 (2009.7.1)、 INDEXはこちらへ。今日も1クリックお願いします
2009.09.17
コメント(0)
-

工藤公康46歳も現役続行!
横浜に在籍する工藤公康(愛工大名電高)が球団から戦力外通告を受けた。だが現役続行を諦めない工藤は、次の移籍先を懸命に模索している。当年とって46歳。「日本プロ野球史上最年長勝利」の記録更新を目指し(?)、新たな挑戦はまだまだ続く---。-----------------------------------------------------------------現在、「最年長勝利」の記録保持者は浜崎真二氏(広島商中退-神戸商-慶應義塾大)。その記録は48歳4か月27日。浜崎真二氏。wikipedeiaには、こう記されている。1948年(昭和23年)に阪急の監督に就任した浜崎。2年後の1950年、「若い投手には任せてられない」とばかりに5月7日に自らが登板し勝利したことが、現在にいたるまでの最年長勝利記録になっている。(以上、wikipedia)■慶應義塾大時代はエース。そして「天国と地獄」を大いに経験した投手だった。「地獄」。1925年(大正14年)、19年間にわたり中止になっていた早慶戦が復活した第1戦(10月19日)、慶應先発はこの浜崎だった。とても名誉な役回りだったが、試合はスコア0-11の大敗。浜崎は敗戦責任を一身に背負う屈辱を味わった。※当時人気絶頂だったと早慶戦ゆえ、現在とは比較しようがない。その「屈辱感」の大きさはまるでわからない。現在に例えるなら、何らかの事情で巨人・阪神戦が19年間も中止し、やっと復活した19年後の復活第1戦でメチャメチャに打ち込まれた先発投手といえば、まだわかりやすいかもしれない。そして「天国」。「地獄」から2年後の1927年(大正2年)秋、汚名返上とばかりに早慶戦に先発。被安打3、奪三振10の快投で早稲田を降し、大いに留飲を下げたものだった。■大学を卒業してからの浜崎、毒舌家としても名を馳せた。こんなエピソードがある。以下、『早慶戦百年 激闘と熱狂の記憶』(富永俊治著、講談社刊)より。戦後すぐ、浜崎は社会人野球の新興・熊谷組監督に誘われ、一度は就任を承諾する。だが、浜崎監督とは別に、(早慶戦復活第1戦で早稲田の先発だった)竹内愛一を総監督に招く構想がチームにあると知るや、熊谷組に断りを入れ、プロ野球の世界に進路を変える。その理由がふるっていた。「竹内といえば、生家である京都の仏具屋を呑みつぶしたことで知られる大酒呑み。それに対してオレは一滴も呑めん。そんな男と一緒に野球をやれと言われても、できっこないわ」 ◇ 「ボクにとっての日本野球史」 (2009.7.1)、 INDEXはこちらへ。今日も1クリックお願いします
2009.09.16
コメント(0)
-

イチロー、9年連続200安打達成
9月13日、イチロー(愛工大名電高)が9年連続200本安打を達成した。「日本でいえば、明治時代に活躍したウィリー・キーラーの記録を108年ぶりに更新」した記録らしい。朝日新聞にウィリー・キーラーのことが紹介されていた。曰く、「1872年生まれ。左投げ左打ちの外野手。身長165cm前後と小柄ながら1894年から8年連続で200安打。1902年に現在の「3バント失敗は三振」のルールができたのは、バントを多用する彼の打撃スタイルが問題視されたからだと言われている」--------------------------------------------------------------ウィリー・キーラーが8年連続200安打を達成した1901年(明治34)、その当時の「日本野球事情」について調べてみた。1)ホーレス・ウイルソンが日本に最初に野球が伝えたのが1872年(明治5年)。◇ホーレス・ウィルソンの関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「1872年、野球が日本に上陸した時代」 (2009.6.30) → こちらへ。 2)以降、一高(現・東京大)の全盛時代が続いた。米国人たちからなる横浜アマ チュア倶楽部に初勝利したのは1896年(明治29年)のこと。ちょうどこの頃、 キーラーの200安打記録は「3年連続更新中」だった。◇日米野球対決の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「日米野球初戦、一高が横浜アマチュア倶楽部に圧勝す」 (2009.6.29) → こちらへ。 3)そしてキーラーが8年連続200安打の記録を作った1901年(明治34年)は、 早稲田大(当時、東京専門学校)に野球部が創部した年と同じ。日本国内に おいて、「野球」というスポーツが大きく進歩を始めた記念すべき年でもある。 (ただ当時、早稲田野球部の知名度は極めて低かったが・・・)4)ついでに。初めて早慶戦が行われたのは、その2年後の1903年(明治36年) のことだった。※ボクは今年8月29日のブログに、「早稲田が学習院に試合を申込み勝利を 挙げたのは1904年(明治37年)」と書いた。ただ別の資料を見ると、それは 1901年(明治34年)と記載されていて、3年もの誤差がある。どちらが本当か、 いまのところボクに正解はわからない。◇早稲田野球部の黎明期の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「早稲田が学習院に勝つ」 (2009.8.29) → こちらへ。 ◇ 「ボクにとっての日本野球史」 (2009.7.1)、 INDEXはこちらへ。今日も1クリックお願いします
2009.09.16
コメント(0)
-
戸村、苦手の3回戦で勝つ
今日行われた立教対慶應3回戦は、延長10回の接戦の末、3-2で立教がサヨナラ勝ちした。勝ち投手はスタミナに難があると、(このブログだけでなく)あちこちの新聞に書かれた戸村。苦手の中1日にもかかわらず、延長10回を一人で投げきり見事に勝利した。投手陣の台所事情が苦しい立教、昨日初先発で完投勝利した丸山とといい、今季一筋の光が見えてきた。
2009.09.14
コメント(2)
-
今日の東京六大学
今夜は北海道にいるので、携帯から。今日は2回戦2試合が行われ、立教と法政が勝利した。その結果、立教は1勝1敗のタイとした。1回戦で不本意な投球に終わった戸村、課題の3回戦での雪辱を期待したい。法政は連勝で勝ち点を挙げた。東大は敗戦したが、堀口が適時打を打ったことがボクは嬉しい。
2009.09.13
コメント(0)
-

今季「東大旋風」に期待
先ほどの続き。■以下、日刊スポーツより。 秋季リーグ戦が開幕し、2季連続優勝を狙う法大は延長10回4-2で東大に先勝した。左脇腹痛の影響で、今春のリーグ戦は途中離脱した加賀美希昇投手(3年=桐蔭学園)が9回2失点(自責1)で勝利を挙げた。9回裏に2点を追い付かれる展開に、金光興二監督(53)は「集中力がない。負けて再スタートを切った方がいいのではという思いが、試合中に脳裏をよぎった」と、厳しい言葉で振り返った。 (以上、日刊スポーツ)この試合を観戦しながら、ベンチの金光興二監督の怒りようはわかるような気がした。期待する「切り込み隊長」亀谷信吾(4年、中京大中京高)の骨折による戦線離脱など、金光さんの不安は尽きない様子だ。--------------------------------------------------------------ボクは法政大のいわば「失態」よりも、東京大の健闘ぶりに注目したい。昨(春)季の開幕前、 「エース・鈴木優一が活躍するなら東京大が優勝する」と書いたことがあるけれど、鈴木優一(4年、西尾高)がいなくても、「勝ち点1」なら十分に狙える戦力になったと思う。試合には負けたが、金光さんの指摘した「集中力」なら決して負けていなかった。レフト・古垣弘人(4年、開成高)が9回に見せたファインプレー。左中間に飛んだ低いライナーを倒れながら見事に好捕した。たしか古垣、春もまったく同じプレーがあった・・・。そしてセカンド・高橋雄康(4年、米沢興譲館高)の一・二塁間に飛んだゴロの捌きも巧かった。打撃では岩崎脩平(2年、海城高)が2安打を放ち、相変わらず安定感を見せた。春季、明治大の野村祐輔(2年、広陵高)から本塁打を放ち、ますます自信を深めたようだ。また、この試合で4番に入った堀口泰幹(3年、高崎高)は打席で気合が十分だった。チャンスで三振を喫すると大いに悔しがり、相手投手の落ちる変化球を見極めるとガッツポーズ。9回のチャンスには犠飛を打ち、打点を挙げた。技術では劣っていても「気合い」で相手に立ち向かう東京大。そもそも野球というスポーツが日本に輸入された明治時代、「武士道」として日本に広めたのは、東京大の前身・旧制一高だった。今季、「東大旋風」が吹き荒れるかもしれない!? 今日も1クリックお願いします
2009.09.13
コメント(0)
-

法政-東大1回戦、詳報
全日本大学選手権(今年6月)で「日本一」に輝いた法政大が、東京大を相手によもやの「大接戦」を演じてしまった。その原因は打線の不振。(※不振を極めた昨年までの打線に戻ったよう・・・)序盤は完全に法政のペース。ワンサイドゲームの可能性も十分にあったが、肝心のチャンスに適時打が出ない。中盤からは東京大・前田善博(3年、栄光学園高)の緩い変化球攻めにあって、まるで「金縛り状態」。なかなか追加点を奪えず、結局試合がもつれる結果となった。ただ法政に光明もあった。全日本で日本一になったものの「蚊帳の外」だった加賀美希昇(3年、桐蔭学園高)が先発し、見事に復活を果たしたこと。お得意の緩急自在な投球術で東京大打線を封じ、7回途中までは無安打ピッチングを続けた。だがスタミナ切れか9回に連打を浴び、守備の乱れもあって同点に追いつかれたことが残念。延長10回は三上朋也(2年、県岐阜商高)が登板。危ういシーンもあったが昨季同様の好投を見せ、東大の反撃を断った。法政、加賀美の復活もあり投手陣は優勝した昨季以上に安定していると見た。(今日の加賀美の成績)9回、被安打4、奪三振8、与四死球1、自責点1。-------------------------------------------------------------------(開幕試合 1回戦)法 100 010 000 2 =4東 000 000 002 0 =2(法)○加賀美-三上、(東)前田-●揚場-西村<試合の経過(詳報)>■法政は初回、この試合で1番に入った石川修平(4年、小山西高)の三塁打が飛び出し、2番・和泉将太(4年、横浜高)のセンターへの犠飛であっという間に先制した。続く2回表、2連続ストレートの四球と野選で一死満塁のチャンスを迎えた法政だったが、1番・石川の打球は投手ライナー。一塁走者が飛び出し1-3のダブルプレーでチャンスが潰えた。そして法政は5回表、石川の死球と和泉の二塁打で一死二・三塁のチャンスをつかむと、3番・多木裕史(1年、坂出高)がライト前に安打を放ち1点を追加した。■9回裏、東大が反撃を見せる。この回先頭の1番・古垣弘人(4年、開成高)と2番・岩崎脩平(2年、海城高)の連続安打で無死一・二塁のチャンス。送りバントで二・三塁に走者を進めると、4番・堀口泰幹(3年、高崎高)がレフトに犠飛を打つ。三塁走者が生還し1点、レフトから本塁に返球される間に二塁走者の岩崎は三塁を狙う。それを見た石川捕手は三塁へ送球したものの、和泉三塁手がベースに入るのが遅れて、球はレフトへ転々・・・。岩崎は悠々生還し、土壇場で東大が同点に追いついた。■同点で迎えた延長10回表、東大の2番手・揚場皓(3年、開成高)の調子が良くない。4つの連続四球(※)を与えて降板し、3番手の西村育人(4年、相模原高)から法政の4番・松本雅俊(4年、関西高)がライトへの犠飛で1点。続く5番、途中出場の喜多薫(4年、伝習館高)が三遊間に内野安打を放ち、2点目を追加。東大を突き放した。※「4つの連続四球」があったものの、その途中に盗塁失敗があり、法政はこの時点で1点も奪えていない。揚場投手の制球が乱れている中、なぜ強引に盗塁を狙ったのか疑問が残った。■延長10回裏、東大はまだ諦めない。この回から登板した三上から2連続三振を喫したものの、8番・田中淳(2年、武生高)が浅めに守っていたライトの頭上を超える二塁打で出塁(定位置にいたら平凡なライトフライ?)。続く9番、代打の秋末康佑(4年、浅野高)がセンター前に安打を放ち、二死二・三塁。続く1番・古垣はフルカウントから四球を選び満塁に。一打同点の場面だったが2番・岩崎が三振に倒れてゲームセット。粘る東大だったが、最後に力尽きた。 今日も1クリックお願いします
2009.09.12
コメント(0)
-

元・早大監督、森茂雄氏
昨日、慶應義塾大の次期監督に元プロ野球選手で慶應大OBの江藤省三氏が就任すると書いた。朝日新聞(9月11日付)の記事はこう書いていた。「正式に決まればプロ経験者の監督就任は、東京六大学では大阪タイガース(現・阪神)の初代監督だった故・森茂雄氏が1947年に早大監督になった例などがある・・・」森氏がプロ経験者で六大学の監督になった、唯一の前例らしい。森茂雄氏(松山商高-早稲田大)のこと。調べてみると、森氏が早大監督に就任したのは1947年(昭和22年)秋。以来、57年までの任期21季中に優勝を9回記録するなど、早大の黄金時代を築いた立役者的な存在だったことがわかった。また森氏、早大監督就任前の46年(昭和21年)春、東京帝国大学野球部に請われてコーチをしており、東京帝大さえも2位に躍進させる手腕も発揮した。※六大学では他大学出身者が指導者として要請されること自体が珍しいし、また帝大にとって「2位」は過去最高の記録でもある。■当時のことを『東京六大学野球80年史』(ベースボール・マガジン社刊)が少しだけ触れていた。(以下に引用)「東大が、このシーズン(昭和21年春)の主役だったかもしれない。シーズンに備えて初めて他校OBの森茂雄(後の早大監督)が猛ノックで鍛えた。お蔭で、守備率は早大に次ぐ2位と向上した」「このバックに守られて山崎諭(旧制山形高)が力投に次ぐ力投。東大は6月13日の慶大戦(後楽園)を前に明早立を撃破。慶大を破れば悲願の初優勝というところまで来た。慶大戦は6回まで両チーム無得点。7回に慶大がようやく1点先取。東大は9回に二死三塁まで迫ったが及ばなかった。東大の2位は史上初の快挙だった」(以上、『東京六大学野球80年史』)※後楽園・・・神宮球場は米軍に接収され、後楽園や上井草球場でリーグ戦が行われていた(神宮が返還されるのは1952年3月31日)。また当時は現在と違い、総当たり1回戦制だった。◇戦後、野球の復活の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「東京六大学、復活のノロシはオール早慶戦(1945年10月28日)」 (2009.8.3) → こちらへ。◇ 「ボクにとっての日本野球史」 (2009.7.1)、 INDEXはこちらへ。今日も1クリックお願いします
2009.09.12
コメント(0)
-

江藤省三氏が慶大監督に就任
慶應義塾大野球部の次期監督に、元プロ野球選手で慶應大OBの江藤省三氏が就任する。67歳。実兄の江藤愼一氏とともに、兄弟そろってプロ野球選手だった。省三氏は1965年(昭和40年)に巨人に入団。その後69年に中日に移籍、76年に引退している。兄・慎一氏も69年まで(59年~)中日に在籍し、2人とも中日で活躍した選手だった。※ただ、ボクの記憶では「中日の江藤」といえば兄・愼一氏のほうを思い出す。省三氏のことはあまり憶えていないのが残念。---------------------------------------------------------江藤氏の就任で、またひとりプロ出身の大学野球監督が増えたことになる。「プロ・アマの雪解け」といわれる昨今、伝統では大学野球界の最高峰といえる慶應大の人事だから、これは象徴的な出来事ともいえる。これでプロ出身の監督は何人目だろうか。ボクはもう数え切れなくなった。即座に思いつくだけでも、東京国際大・古葉竹識氏、中央大・高橋善正氏、山梨学院大・高橋一三氏などなど。 江藤省三氏(中京商高-慶應義塾大-読売-中日)。プロ在籍(現役)は通算11年間。464試合に出場し、通算打率は.267。慶應大時代は二塁手として活躍、64年(春秋)・65年(春秋)の4季連続でベストナインに選出された。当時の他の選手も調べてみたが、懐かしい名前が並んでいた。立教大・土井正三、法政大・長池徳二、明治大・高田繁、早稲田大・八木沢荘六・・・。今日も1クリックお願いします
2009.09.11
コメント(0)
-

長野久義、3度目の正直?
今年のドラフトは10月29日に行われるらしい。ホンダ・長野久義(筑陽学園-日本大)。相変わらず「読売入り」を熱望している様子。読売も長野の「1位指名」を約束している。さらに読売以外の球団は、長野を指名する可能性がまるでなさそうだという。「事実上の『逆指名』ではないか!」と日刊ゲンダイは怒っていた。ボクもそのとおりだと思う。過去に2回(日本ハムとロッテ)、ドラフトで受けた指名を蹴っている長野。さすがに今回は「蹴られる」ことを承知で指名する球団などあるわけがない。『逆指名制度(もしくは希望入団枠制度)』は、裏金問題など不正の温床になることから、すでに2007年度のドラフト以来廃止されたルール。だが、ゴネ続ければ他球団はいい加減に嫌気がさし、いずれ意中球団に入団できるといった悪しき前例になりはしないか!!! だとしたら制度の上っ面ばかりを変更しても、根底にある「不正の温床」は絶滅しない。それどころか今後「アングラ」でぬくぬく増殖を続ける輩に免罪符を与えたことになる。(別に読売や長野が該当すると言っているわけではありません。念のため)◇長野久義の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「長野久義、今回はどうする?」 (2008.11.21) → こちらへ。◇プロ野球・不正の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「西鉄ライオンズ「黒い霧」事件」 (2009.7.10) → こちらへ 今日も1クリックお願いします
2009.09.09
コメント(0)
-

早大・相田暢一、吉江一行
先日、『大学野球復活を一番願った人』(2009.8.4)という記事の中で、「早稲田大野球部は戦時中もバットなどの道具をキッチリ守り、戦後の野球復活に備えていた」と書いた。その当時のことを詳しく記された書籍が見つかったので、追記したい。 ■『1943年晩秋 最後の早慶戦』(教育評論社刊)より。当時、早稲田大野球部のマネージャーだった相田暢一もついに1943年12月10日、横須賀第二海兵団に入団した。「その直前、相田はすでに入手困難になっていたボール300ダース、バット300本、ノックバット10数本を準備した。これらの用具は東京大学野球連盟(現・東京六大学野球連盟)の残務整理に伴い、各大学への配分金で購入されたもので、たとえ部員が一人になっても練習を続けるという、飛田穂洲の意を受けた相田の機転によるものだった。その後、新たに主将になった吉江一行にバットやボールの管理を託された。吉江は福島県立磐城中学の出身で、「最後の早慶戦」には5番ライトで出場した。飛田穂洲は吉江の人となりを、心から愛した」■『球道半世紀』(飛田穂洲著)より。「(吉江)一行は五尺八寸五分といふ巨漢であった。ベーブ田中を思わせるやうな好中堅手であり、強打者でもあったが、それよりもなほ忘れかねるのは、彼の人物であった。堂々たるその偉容とはまるで正反対の温厚寡黙、篤実一途の性格、何ともいへぬ床しさだった」◇ 「ボクにとっての日本野球史」 (2009.7.1)、 INDEXはこちらへ。今日も1クリックお願いします
2009.09.08
コメント(0)
-

亜細亜大連敗、中田亮二は?
東都大学リーグ、唯一3回戦にもつれた立正大-亜細亜大戦。優勝候補の一角を占める亜細亜大は、立正大にスコア2-6でまさかの敗退。開幕カードで勝ち点を落とす「最悪のスタート」となった。亜 001 100 000 =2 立 000 103 20X =6(亜)東浜-倉又-中村駿、(立)小石-菅井-大村亜細亜大にとって、エース格の東浜巨(1年、沖縄尚学高)を先発に立てての敗戦だけに、余計に手痛い敗戦となった。■以下、日刊スポーツより。亜大は東浜巨(なお)投手(1年=沖縄尚学)が、5回1/3を4失点でKOされ、今季初黒星を喫した。4回までに2点をリードしたが逆転され、1勝2敗で勝ち点を落とした。東浜は「春より振れているし、真っすぐもしっかりとらえられた。投げ込んで、体力を付けたい」と課題に挙げた。 立正大は同点に追い付いた直後の6回1死一、二塁、越前一樹外野手(3年=横浜)が左翼線に決勝の2点適時三塁打を放った。伊藤由紀夫監督(58)は「(東浜は)春の切れがなかった。本来のスピードと切れではない」と攻略した。 (以上、日刊スポーツより)---------------------------------------------------------------新聞は東浜のことを心配しているようだ。でもボクが案じるのは同じ亜細亜大の中田亮二(4年、明徳義塾高)のほう。今日まで3試合の打撃成績を見ると、9打数2安打、打率.222。ちょいと寂しいスタートのように思える。春季は打率.357で打撃十傑5位にランクイン。さらに先ごろ行われた日米大学野球では、日本代表チームの4番を打つほどの素質溢れるアベレージ・ヒッターでもある。ただ中田、残念ながらその日米大学野球では不振を極めた。まるで球をバットの芯で捕らえることなく凡退を繰り返した。打席に立つ表情もどこか自信なさげで、まるで「ボクは打つ自信がありません」と相手投手に訴えかけているようにも見えた。挙げ句には、投手の投げた内角球に自ら足を出して当たろう(死球)としたこともあった。日本代表の4番を張ること自体、相当なプレッシャーがあったろうし、それは仕方のないことだったと考えよう。もしその時の呪縛が(少しでも)あるのなら、早くをそれを解いて立ち直ってほしい。ボクの希望は、ただそれだけだ。◇中田亮二の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「09ドラフト候補・中田亮二」 (2009.1.13) → こちらへ今日も1クリックお願いします
2009.09.07
コメント(0)
-

立正、中嶋辰也の適時打でダメ押し
今日(9月6日)行われた東都大学リーグ、立正大-亜細亜大2回戦。立正大がスコア3-1で亜細亜大に勝利し、1勝1敗のタイにした。立 200 000 010 =3亜 000 010 000 =1(立)中川祐-木田-○菅井-大村-南、(亜)●中村駿-松田-倉又<試合経過>立正大は初回に2点を先制。8回には代打・高橋翔也(1年、日大三高)が四球で出塁し、1番・黒葛原祥(4年、横浜高)の犠打で進塁後、2番・中嶋辰也(2年、銚子商高)の適時打で追加点を挙げ勝利を決めた 。 ---------------------------------------------------------------8回に適時打を打った「銚子商高出身の中嶋」。ひょっとしたら!と思い、昔のスコアブックを調べたら、たしかにこの中嶋という選手名が見つかった。ボクは2年前、この中嶋選手を見たことがある。中嶋辰也。2007年5月20日、場所は神奈川・保土ヶ谷球場。春季関東大会2回戦(対埼玉・富士見高戦)で銚子商高の4番を打っていた選手が彼だ。試合はスコア0-7で敗退(7回コールド)したけれど、中嶋は3打数2安打(内、二塁打1本)で孤軍奮闘。2番手投手としてマウンドにも上がっていた。銚子商 000 000 0 =0富士見 220 002 1X=7(銚)加藤-中嶋、(富)太田◇「5月20日、富士見-銚子商戦詳報」 (2007.5.22) → こちらへ。ボクは古豪・銚子商高のユニフォームをナマで見るのはこの時が初めて。1974年夏に全国制覇した時の土屋正勝や篠塚利夫の活躍を思い出し、ひとり興奮して観戦していた。◇銚子商高の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「原辰徳、高校時代のライバルたち」 (2009.2.1) → こちらへ一方、勝利した富士見高のエースは太田弾。現在は東洋大の投手(2年)。高校時代の太田は、浦和学院高など強豪に対して敢然とひとり立ち向かう投手だった。同じ埼玉高校球児だった増渕竜義(現・ヤクルト、鷲宮高)がダブって見えたものだった。◇太田弾の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「太田弾の富士見高時代」 (2008.4.9) → こちらへ。今日も1クリックお願いします
2009.09.06
コメント(0)
-

東京六大学リーグ、来週開幕
東都大学リーグが昨日(9月5日)開幕したのに続き、来週(12日)からは東京六大学リーグが始まる。東都と同様、熱戦を期待したい。興味のポイントは法政大連覇の可能性、そして早稲田大・明治大の巻き返しはあるか等々。この点は、後日書きます。----------------------------------------------------------さて、話題を変えて。そもそも東京六大学は、早・慶・明・法・立・東の6大学なのか、ボクはよく知らないことも多いので、その設立の経緯を簡単に調べてみた。まだまだ時間を要する作業だけど、今後は今回の記事を基にそれぞれ出来事の詳細を記していきたいと思っている。※ただ、内容によっては諸説あるらしく、ここで書くことが(参考資料によっては、結果として)偏った見方になってしまう可能性もありそうなので、あらかじめご了承いただきたい。<設立の経緯>・1903年(明治36年)11月21日、早稲田大が慶應義塾大に挑戦状を出し、 初めて早慶戦が実施される。・1906年(明治39年)11月10日、両校の応援が過熱化。早慶戦は開始 からわずか3年で中止になる。・1914年(大正3年)10月29日、明治大が早慶両校の間を取り持つ格好で 三大学リーグを結成した。・1917年(大正6年)春、明治大と友好関係にあった法政大が加盟し、四大学 リーグになる。・1921年(大正10年)秋、 立教大が加盟し五大学リーグになる。・1925年(大正14年)秋、東京帝国大が加盟し東京六大学リーグが成立した。 と同時に1906年以来対戦のなかった早慶戦が復活する。<この六つの大学から構成された理由>・4番目に法政大が加盟した理由自由民権運動の余韻が強く残る当時の時代背景にあって、同じ仏法の流れを汲む法政大は明治大と友好関係にあり、明治大が加盟したことで法政大が4番目に加盟することは明白だった。・5番目に立教大が加盟した理由これは様々な説がある。早稲田大・飛田穂洲氏が六大学構成の実権を握っていたため、氏の指導を受けていた立教が加盟したという説がある。ただそれならば、中央大が立教より早く氏の指導を受けていたので、5番目は中央大でもよかった。なのに立教になった理由は、自由民権運動に関する大学の立ち位置の違いにより、明治や法政と反目していた中央(そして専修大)ではなく、立教が消去法で残ったのが実情のようだ。・6番目に東京帝国大が加盟した理由ここでも諸説がある。野球における早-慶、明-法の対抗関係があるならば、立教の好敵手は東京大でなく青山学院大や明治学院大でもよかった。というより、この2校の野球部は実力的にも高く、この2校の方がよかったともいえる。ただ青山学院は早稲田と親密な関係にあり、明治学院は慶應と交流があったため、早・慶の感情を配慮し、結局は早慶明法と学問的な交流のあった東京帝大が加盟したようだ。※参考:Wikipedia 、『六大学野球』(現代書館刊)ほか◇ 「ボクにとっての日本野球史」 (2009.7.1)、INDEXはこちらへ。今日も1クリックお願いします
2009.09.06
コメント(0)
-

國學院・高木京介好投も惜敗
今日(9月5日)開幕した東都大学リーグ1部。開幕戦の第1試合は、6連覇を狙う東洋大と、昨シーズン5位とまったく振るわなかった國學院大が対戦した。東洋大の先発・乾真大(3年、東洋大姫路高)に対し、國學院大は高木京介(2年、星稜高)が先発。高木という投手をボクはまるで知らなかったが、緩急をつけた見事な投球術で延長11回まで東洋大打線を翻弄し続けたのだから立派、立派・・・。だが継投した2番手・村松伸哉(3年・光星学院高)がまだ復調していないため、東洋大から白星を奪えなかったのが残念だった。◇村松伸哉の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「村松伸哉、復活を祈る!」 (2009.1.11) → こちらへ。(今日の高木の成績)11回、被安打9、与四死球1、奪三振11、自責点1。-------------------------------------------------------------(1回戦)延長12回東洋 010 000 000 002 =3國學 000 000 010 000 =1(東)乾-鹿沼、(國)高木-村松-埜口<試合経過>東洋大は2回、二死ながら走者を3塁に置き7番・鈴木大地(2年、桐蔭学園高)一塁線を破る適時打を放ち先制した。その後も5回の無死一・三塁などチャンスがあったものの、國學院・高木の140km前半の速球とカーブ・スライダーを駆使した投球術の前に沈黙を続けた。一方の國學院大。調子の上がらない乾を攻め立てるが「あと1本」が出ない。 やっと適時打が出たのは8回。エラーで出塁した走者を二塁に置き、6番・渡辺貴美男(3年、文星芸大付高)がレフト線に二塁打を放ち同点に追いついた。(ちょこんと球にバットを当てて、打球を左に流す打撃がとても巧かった・・・)同点で迎えた延長12回、この回からマウンドに上がった村松がパッとしない。力のある球を放っていたものの制球が定まらない。2つの四球を与えて(ル-ル上の※)降板。そして、3番手で登板した埜口卓哉(3年、つくば秀英高)が3番・坂井貴文(3年、春日部共栄高)を一ゴロに打ち取ったはずが、一塁手がカバーに入った埜口に対して暴投し2点を献上、敗戦が確定した。※(ルール状の)降板。延長12回、竹田利秋監督は村松を代えるつもりはなく、マウンドの村松の話をするためマウンドに向かった。だが、その数分前(同じイニング)にも捕手をベンチ前に呼んでおり、東洋大側のアピールにより「タイム2回目」とカウントされ、投手変更を余儀なくされた。 ---------------------------------------------------------------高木京介。星稜高3年の夏(2007年)、エースで4番打者として甲子園に出場した。初戦は長崎日大高と対戦。高木は4打数4安打とひとり奮起したがスコア1-3で敗退した。そして大学入学後、竹田監督の勧めもあり投手専念を決心した。現在の背番号は「11」。当時の長崎日大、エースで4番は浦口侑希だった。現在は日本大に進学して背番号「18」をつけている。今日も1クリックお願いします
2009.09.05
コメント(0)
-

昭和36年、柳川事件
前回の続き。8月31日発表された「日本学生野球憲章」の第1次改正案。主要ポイントの一つには「プロとアマとの練習や試合を、一定の条件のもとで容認されるようになった」こと。■では具体的にどう変わるのか、そしてその問題点は何か。9月1日付の日刊ゲンダイが以下のとおり、解説している。これまで禁止されていた現役のプロ選手による高校・大学生への直接指導や、「巨人対早大」「楽天対東北福祉大」などの練習試合も可能になる。ある現役の大学監督はこう言う。「むしろこれまでが異常でした。OBのプロ野球選手が母校に自主トレに来ても、学生と接触を避けるように隅っこでコッソリやる。2005年まではキャッチボールはもちろん、話すことすら許されなかったのですから。堂々と指導できるようになるのは、現役にとってもプラスです」ただ、大学関係者からは不安視する声も聞かれる。「プロの関係者は大学の野球部員に堂々と接触できる。その気になれば『ウチの球団はいいよ』と歓誘や交渉することができる。特定選手の囲い込みの手段に使われないか心配です」 (以上、日刊ゲンダイ)----------------------------------------------------------------まだ懸念を残すものの、プロとアマの関係は「雪解け」に向かっているようだ。そもそも両者が冷戦関係になったキッカケは、1961年(昭和36年)に起きたこの事件にあった。柳川事件。以下、そのあらまし。発端は、シーズン途中に社会人選手の引き抜きを禁じる協定があったにも関わらず、同年シーズン開幕直後の4月、中日が日本生命の柳川福三選手を入団させたことにある。怒った社会人協会は協定違反として態度を硬化。5月13日、これまでプロ野球退団者を受け入れてきたが、「今後は一切受け入れない」と声明を出し、プロ野球との絶縁を宣言した。これに対し鈴木竜二セ・リーグ会長(当時)は、「職業選択の自由を奪う社会人野球協会の決定はおかしい」と言い放ち、プロ・アマの確執が始まった。以来、さまざまな紆余曲折はあるものの、いまだ奇妙な関係が続いている。◇鈴木竜二の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「戦後・職業野球の復活、東西対抗戦の背景」 (2009.8.1) → こちらへ。さて、大きな事件に発展した「柳川事件」。だが当の柳川、成績は芳しくなかった。通算成績は実働5年、144試合、2本塁打、11打点、打率.202の成績。入団時に事件に巻き込まれると、その選手は大成できないといったジンクスが球界にはあるのかもしれない。荒川 尭とか・・・。 ◇ 「ボクにとっての日本野球史」 (2009.7.1)、INDEXはこちらへ。今日も1クリックお願いします
2009.09.04
コメント(0)
-

学生野球憲章と野球統制令
8月31日、「日本学生野球憲章」の第1次改正案が発表された。■改正案の主なポイントは次のとおり。(参考:朝日新聞9月1日付)(1)前文で「教育の一環」「アマチュアリズム」→ 現憲章を貫いている『精神』は堅持された。学生野球は「学生たることの自覚を 基礎とし」とうたわれているが、改正案では「学生野球は、学校教育の一環であり、 アマチュアリズムをその基底的要素とする」と言い換えた。また行き過ぎた勝利 至上主義や商業主義に歯止めをかけた。(2)加盟校の「学校長」の責任を明確化→ 現憲章では、高校野球は高野連が(中略)これを監督する」とされているが、改正 案では「監督」ではなく、「指導・助言を行う」という表現になった。 戦前の野球統制令から続く上意下達の姿勢を改める狙いがある。(3)プロアマは「交流できる」と肯定的な表現に→ 現憲章の「できない」という否定的な文言から、「協会の承認を受けて(中略)できる」 と前向きな表現に変わった。 (以上、朝日新聞)--------------------------------------------------------「野球統制令」という言葉を見つけた。これは、学生野球の統制と健全化を目的として1932年(昭和7年)に文部省から発令された訓令のこと。当時、野球人気が盛り上がる中、学生野球の商業化や興行化がはびこり、その問題を抑制するために発令された。ま、こう書くと立派な法令に聞こえなくもないが、これは実質的に学生野球の「生殺与奪」の権限(wikipedia)を文部省が握るキッカケとなった。そして1943年(昭和18年)の「戦時下学徒体育訓練実施要綱」制定、学生野球(小学・旧制中学・大学)の禁止につながった「悪法」とも言える。上記の朝日新聞記事にある「改めるべき上意下達」とは、この過去にあった一連の流れを指すものだと思う。ただ当時、「野球統制令」の片棒を担ぎ「学生野球のネガティブキャンぺーン」を執拗に行ったのも、この朝日新聞だったことを付け加えておく必要がある。一方、この統制令の効用もあった。それは1934年(昭和9年)のベーブ・ルースらが来日する米国メジャーの選抜チームとの対戦にあたり、当時人気を誇った大学野球の選手たちが参加できなくなり、職業野球(大日本東京野球クラブ)の創設が加速されたこと。ま、これはあくまで結果論だけど。 ◇ 「ボクにとっての日本野球史」 (2009.7.1)、 INDEXはこちらへ。今日も1クリックお願いします
2009.09.02
コメント(0)
-

橋戸賞は筑川利希也が受賞!
第80回都市対抗野球大会・決勝が今日(9月1日)、東京ドームで行われた。ホンダと、準決勝で日産を降したトヨタの対決。いわば「自動車(メーカー)対決」だったが、結果はホンダがスコア4-2で勝利し13年ぶり2度目の優勝を決めた。(決勝)ホンダ 003 000 001 =4トヨタ 000 020 000 =2(ホ)筑川-坂本-須田、(ト)大谷-中根-佐伯-佐竹ホンダは3回表、2番・川戸洋平(日大藤沢高-日本大)の適時打で1点を先制した。そして読売がドラフトの1位指名を確約している3番・長野久義(筑陽学園高-日本大)が2点適時打をセンター前に放ち、日大OBコンビで一挙3点を奪い勝利を決めた。※この時、トヨタの投手は先発した大谷智久(報徳学園高-早稲田大)。長野、長髪に口ひげの姿で応援席に向かって両手を挙げ、ハデにガッツポーズをしていた。◇長野久義の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「長野久義、今回(2度目のドラフト指名)はどうする?」 (2008.11.21) → こちらへ。投げてはエース・筑川利希也(東海大相模高-東海大)が、トヨタ打線を6回2安打に抑えて勝利投手に。また試合後の表彰式では「橋戸賞」を獲得した。◇橋戸賞の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「橋戸賞の由来」 (2009.6.24) → こちらへ。■筑川のコメント。以下、毎日新聞より。「初戦からさえない投球だったが、安藤監督を日本一の男にしたかった。自分の投球すべてを出し切ろうと思った」筑川利希也。東海大相模高時代はセンバツ優勝投手でもある(2000年)。決勝では智弁和歌山高と対戦し、スコア4-2で勝利し優勝した。この試合、東海大相模高のメンバーを確認できなかったが、相手の智弁和歌山高には現・新日本石油ENEOSの池辺啓二(慶應義塾大)や現・ヤクルトの武内晋一(早稲田大)らがいた。また東海大時代のチームメイトには、現・ロッテの大松尚逸(大府高)がいた。 今日も1クリックお願いします
2009.09.01
コメント(2)
全35件 (35件中 1-35件目)
1