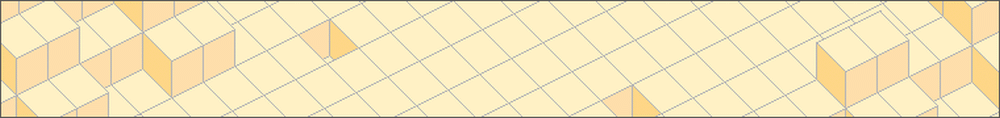2009年12月の記事
全24件 (24件中 1-24件目)
1
-

中田翔にアウトを宣告した林清一審判
2009年11月22日に行われた「セ、パ両リーグ誕生60周年記念試合・プロ選抜vs大学日本代表」のこと。■5回裏、二塁打コースの打球を左中間に放ちながら一塁にストップしていた中田翔(日本ハム、大阪桐蔭高)。次打者・銀仁朗(西武、平安高)の右前安打で二塁をまわり、(なぜか)一旦ストップした後に三塁へ走ったものの、ベース直前でタッチアウト・・・。ライトを守る越前一樹(立正大3年、横浜高)の好返球は見事だったが、中田の走塁はあまりに恥ずかしいプレーだった。というか、哀れでさえあった。この中田にアウトを宣告したのは、東京六大学リーグ所属の審判員・林清一さん(早稲田実-早稲田大)。この試合では4人の審判員が出場した。NPBが2名、アマが2名。林さんはアマ選出の審判員として三塁塁審を務めていた。■神宮でよく聞く審判名なので、ボクも名前だけは知っていたが、林さんの肩書は東京六大学リーグ審判員だけにとどまらない。他にも建設会社社長、日本野球連盟国際審判員、日本高校野球連盟審判員、全日本リトル野球協会・リトルシニア委員会関東連盟理事などの肩書がズラッと並ぶ。そしてアテネオリンピックの際には、日本からただ一人派遣された野球競技審判員でもある。アマチュア野球界の「大御所」的な存在と呼べば当たっているだろうか?甲子園(高校野球)でも審判を務めているから、林さんは今日の試合に出場した多くの選手たちの高校時代のプレーをジャッジしてきた。成長したプロ選手のプレーを直接見ることも楽しみだったに違いないが、中田のプレーには愕然としたのではないか。「アウト!」を宣告した直後、林さんの表情は怒りに満ちたものにボクには見えた。■林さんの甲子園での過去のジャッジには、審判員としての厳格さを示すエピソードがある。それは1988年8月16日に行われた2回戦・豊田大谷高vs宇部商高戦。この試合で「甲子園史上初のサヨナラボーク」といわれる高校野球史にページを刻む事件が起きた。(延長15回)宇部 000 011 000 000 000 =2豊田 000 001 001 000 001X=3その内容は---。以下、wikipediaから一部を引用。 スコア2-2で迎えた延長15回裏、豊田大谷高は左中間安打とセカンドエラー、そして敬遠もあって、無死満塁のサヨナラ勝利のチャンスを作った。そして次打者は7番・持田泰樹。カウント2-1から宇部商高の先発・藤田修平が211球目を投げようとセットポジションに入って腕を少し前に出した時、捕手・上本達之が示した2度目のサインに驚き、投手・藤田は無意識に投球動作を中断し腕を後ろに戻してしまった。この行為を見逃さなかった林清一球審が、宇部商にとっては無情の「ボーク」を宣告した。 (以上、wikipedia)◇このシーンはニコニコ動画で見ることができます → こちらへ。■以上が「甲子園史上初のサヨナラボーク」のあらまし。以前、「KY」という言葉が流行したことがある。もしこの時、林さんが観客やテレビで観戦するファンの空気を読んでいたら、ボークを見逃して藤田投手に打者と勝負をさせる方法もあった。だが林さんはルールに厳格に従ってボークを宣告した。後日、この試合を振り返って林さんは「忘れることのできない試合です」(※1)と話していた。そして藤田修平投手も後にこんなコメントを残している。「あの炎天下の中で、ボークを宣告した林さんはすごいと思う。あの状況で冷静な判断が出来ることがどれだけ難しいか。いろいろ言って下さる方もいましたが、結果的にミスをしてしまったのは自分ですから。出来れば林さんとお話してみたい」 (※2)そして、「あの場面で判定を下す審判の方も勇気がいったでしょう、それが分かった時からいい思い出になりました」 (※3)(※1)と(※3)はブログ『行くぞ メディック 離れるな!』より引用。(※2)はwikipediaより。■林さんの毅然としたジャッジをたまたまテレビで見て、それがきっかけになって審判の道に進んだ人がいる。それは記念試合で林さんと一緒に二塁塁審を務めた秋村謙宏さん。今日も1クリックお願いします
2009.12.31
コメント(7)
-

杉山翔大vs唐川侑己
2009年11月22日に行われた「セ、パ両リーグ誕生60周年記念試合・プロ選抜vs大学日本代表」のこと。■7回表、二死走者なしの場面で杉山翔大(早稲田大1年、東総工高)が右打席に入った。172cmと小柄ながら入学早々に早大の正捕手のポジションをつかんだ強肩・巧打の選手。相対するのは、ロッテの唐川侑己(成田高)。2年前(2007年)のドラフトでは仙台育英高の佐藤由規(現・ヤクルト)や大阪桐蔭高の中田翔とともに大いに注目された投手。プロ入り後はこの唐川がもっとも活躍していて、他の2人より一歩リードの感がある。1球目 104kmのカーブ。2球目 140kmの直球。そして3球目。137kmの直球を杉山のバットが捕えたものの、打球は伸びず、平凡なセンターフライに終わった。笑顔でマウンドを降りる唐川、一塁を駆け二塁に向かう杉山をチラ見して、緩んだ口元をそっとグラブで隠した。■杉山と唐川は同じ千葉県の高校を卒業している。杉山は一学年下だけど、高校時代に2人の対決はなかったろうか? それを知りたくなって、さっそく調べてみた。すると『矢島彩のアマ~い野球ノート』の記事中に答えが見つかった。高校3年に進級するに当たり、杉山にこれまで最も印象に残った試合はどれか? そのことを聞いた際、こんな返答があったという。「印象に残っている試合は『勝ちに行く気だったのにコールド負けに終わったから』という理由で唐川侑己のいた成田との一戦でした」(以上、『アマ~い野球ノート』)■なるほど! たしかに杉山と唐川は高校時代にも対戦経験があることはわかった。だがそこまでわかってくると、「いつ」「どの大会」で対戦したのかを知りたくなった。そこでさらに調べると、それは2006年9月、千葉県秋季大会・地区予選の初戦だったことがわかった。そのことが書かれていたのは、ブログ『ベースボールフリークの部屋』。試合内容まで詳しく書かれていたので、以下に引用します。「結果は9-0で7回コールド。成田の圧勝であった。途中まで好ゲームであったが、守備の乱れによりずるずると成田ペースになってしまった。唐川の投球は鬼気迫るものがあった。常時135キロ~140キロ(マックス144キロ)のストレートは手元で「ぐーん」と伸びていき、東総工業打線は手も足もでなかった。杉山は打ったか覚えていない」(以上、『ベースボールフリークの部屋』より) 今日も1クリックお願いします
2009.12.30
コメント(0)
-

乾真大の長所と短所?
2009年11月22日に行われた「セ、パ両リーグ誕生60周年記念試合・プロ選抜vs大学日本代表」のこと。■2回裏、大学日本代表の2番手として登板したのは東洋大・乾真大(3年、東洋大姫路高)。先発した斎藤佑樹(早稲田大3年、早稲田実)と同様、二死三塁のピンチを作ったが、プロ選抜の9番・銀仁朗(西武、平安高)を得意のスライダーで空振り三振に仕留めスリーアウト。乾は満足げな表情でマウンドを降りた。乾がウイニングショットに使ったスライダーは、打者の手前で大きく落ちるボール球。いかに相手がプロの打者であっても、思わず手が出てしまったに違いない。それほどに見事な球だった。ただ良いことだけではない。この回、先頭の6番・田中浩康(ヤクルト、尽誠学園高-早稲田大)を四球で歩かせたのはいただけない。まるで制球が定まらなかった。特にカウント1-3から投げた球は高めに大きく外れ、「時として制球を乱す」乾の弱点を露呈してしまった。いや、この弱点というのは当たっていないかもしれない。正直なところボクは乾を見る機会が多くないから、ひょっとしたら違うかも? ただそう思ってしまったのには理由がある。それは以前、こんな試合を見たことが影響している。■今年(2009年)6月12日に行われた全日本大学野球選手権の準々決勝(対創価大戦)のこと。大方の予想では「東洋有利」と言われていたこの試合、チームの期待を背負って先発のマウンドに立ったのが、この乾だった。だが初回からまるで冴えなかった。ヒットと四球などで一死満塁のピンチを作ると、創価大の5番・高橋秀信(4年、花崎徳栄高)に対して制球が定まらない。カウント1-2から投げた内角への直球をフルスイングされ2点適時打を浴びた。続く2回も制球が乱れたまま。一死一塁で1番・田上健一(4年、創価高。09年ドラフトでは阪神が育成枠で指名)には大きくストライクのコースを外れるボール球を連発。結局ストレートの四球を与え、堪らず東洋大・高橋昭雄監督はベンチを飛び出し投手交代を告げた。この試合の乾の成績は1回1/3、打者10人、被安打4、奪三振0、与四死球2と散々な出来だった。そしてチームもスコア5-6で創価大に敗退してしまった。■「制球がよく、打者を見ながら投げ分けることができる投手」。以前聞いた乾の評判はこうだった。世界大会や日米大学野球への出場経験も豊富。実力は申し分ないはずなんだけど、残念ながらまだボクは乾の真価を見たことがない。※乾真大のタイプは、左右の違いがあっても斎藤佑樹に似ているのかも?そういえば、斎藤も今秋のリーグ戦は制球が少しおかしかったように思う。いい投手とは、一時的にそういったスランプに陥るものかもしれない・・・。 今日も1クリックお願いします
2009.12.29
コメント(0)
-

斎藤佑樹を凌ぐ!大石達也
今日も11月22日に行われた「セ、パ両リーグ誕生60周年記念試合・プロ選抜vs大学日本代表」のこと。■大石達也(早稲田大3年、福岡大大濠高)が登板したのは6回裏だった。プロ選抜、この回先頭の2番・松本哲也(読売、山梨学院大付高-専修大)をセンターフライ、3番・天谷宗一郎(広島、福井商高)を空振り三振に仕留めた。そして、途中出場の4番・小窪哲也(広島、PL学園高-青山学院大)には127kmの変化球を右中間にヒットを打たれたものの、5番・亀井義行(読売、上宮太子高-中央大)を3球三振に斬って取った。カウント2-0から亀井に投げた3球目。実は捕手・小林誠司(同志社大3年、広陵高)は高めに外す球を要求をした。ところが球はストライクゾーン低めに決まり、亀井のバットは空を切った。ラッキーと言えばラッキーだったが・・・。ちなみにウイニングショットの球速は141kmだった。試合後、大石のコメント。「ある程度真っすぐで空振りが取れた。自信になります」(日刊スポーツ)■この回が始まる時、実況アナの島村俊治さんは、大石をこう紹介した。「早稲田は斎藤、斎藤と騒がれますが、この大石もいいですからねぇ。バッティングもいいです」大石は斎藤佑樹(早稲田大3年。早稲田実)よりもっともっと注目されていい投手だとボクは思っている。またピッチングだけでなく、バッティングも評価が高いのも大石の特徴。なにせ早大野球部に入部当初は、ショートストップで登録していた選手だった。ピッチングとバッティング、両方を少し見てみたい。(1)まずピッチング。大石の特徴は140km台後半の速球と「奪三振率」の高さ にある。・今年(2009年)春季リーグ戦の成績は投球回数20、奪三振数22、防御率 2.70。そして奪三振率は9.9。・秋季リーグ戦は投球回数28回1/3、奪三振数35、防御率2.22、奪三振率 11.1。クローザー役が大石の本業。チーム事情で先発することもあるが、だいたいうまく行った試しがない。例えば早慶戦2回戦(11月1日)で先発した時の結果は、4回を投げ、被安打9、与四死球4、自責点6(嗚呼・・・)散々な出来だったほかにもこんな例がある → こちらへ。(2)そしてバッティングのこと。・今年春季リーグ戦の成績は8打数3安打、打率.375。5月31日の早慶戦 2回戦では、なんと! 7番・ショートでスタメン出場をした。・秋季リーグ戦は12打数6安打、打率.500。代打で出場したことも数回ある。 10月11日の対立教大2回戦では、本来4番打者の原寛信(3年、桐蔭学園高) の代打として出場したこともあった。※原寛信・・・昨年までは4番に固定されていたが、今年は極度のスランプで下位 の打順に下げられていた。■大石、本業のクローザー以外に先発や野手・代打をさせられることが少なくない。これは野球センスの高さによるものだろうが、「投手」「クローザー」に固定したほうが本人にはいいと思う。大石のもつ器用さが「器用貧乏」になっちゃ、もったいない。 今日も1クリックお願いします
2009.12.26
コメント(0)
-

斎藤佑樹、スピードと「間」と
2009年11月22日に行われた「セ、パ両リーグ誕生60周年記念試合・プロ選抜vs大学日本代表」のこと。■1回裏、大学日本代表の先発・斎藤佑樹(早稲田大3年、早稲田実)は二死ながら三塁に走者を背負っていた。そして捕手・小池翔大(青山学院大3年、常総学院高)のサインに2度首を振った直後、カウント2-2からプロ選抜の4番打者・新井貴浩(阪神、広島工高-駒澤大)に投げた5球目は146kmの直球だった。ただその直球は、捕手・小池が構えた外角ではなく、なぜか真ん中に入ってしまう。「あっ!」そう叫ぶ間もなく、新井が叩いた打球はライト前への適時打になり、この一打がプロ選抜唯一の得点になった。思わず天を仰ぐ斎藤・・・。以下、斎藤の試合終了後のコメント。「まっすぐで勝負したかった。球界を代表する長距離打者。見事に打ち返されましたけど、それはそれでよかったと思う」そして「もう一度、真っすぐを磨きたい」と締め括った。(斎藤のコメントは日刊スポーツより)■「もう一度、真っすぐを磨きたい」というコメントは、だいぶ以前も聞いことがある言葉。もっと速い球を投げることができれば『鬼に金棒』に違いない。ただ、なかなかそれが実現できないのが焦れったい。重心を軸足に残したままの投球フォーム(いわゆる「立ち投げ」)に問題あり!と指摘する記事を見かけたことがあるが、はたして真相はいかに?斎藤の強みについて、書籍『甲子園 歴史を変えた9試合』(企画・矢崎良一、小学館、2007年4月刊)に面白いことが書かれていた。それは「間(ま)の取り方」だということ。以下、一部を抜粋して引用。(書き手:中村計)斎藤はちょっと誇らしげに解説する。「間合いの取り方って、自分の中では3つあるんです。プレートにつくまでと、セットに入るまでと、投球フォームの中と。その投球フォームの中の間合いでわかるんです。それで打ってきそうだったらスライダーをワンバウンドさせたり、その逆に、打ってきそうもなかったら簡単にストライクを取りにいく」(何やら「江夏の21球」で広島の守護神だった江夏豊が、投球フォームの中で近鉄・石渡茂のスクイズを察知。急きょカーブの握りのままウエストさせたという逸話を思い出させるが)■斎藤、どうやら間合いがわかる特殊なセンサーを持っているらしい。ただその感度は右打者より左打者を相手にする時、若干反応が鈍る傾向にある。本人が認めるとおり、それを証明する出来事が2006年夏の甲子園、駒大苫小牧高との決勝再試合にあった。(以下も同書より)9回表、無死一塁で左打者の3番・中沢を迎えた場面でのこと。初球、真ん中に入ったスライダーをバックスクリーンに運ばれてしまう。この本塁打により土壇場で4-3と1点差に追い上げられてしまった。「打ってこないと思って簡単に取りにいってしまった。やっぱり左打者は難しいです。自分が右打者だということもあって、右の心理のほうがわかりやすいというか、感じやすいんです」速球のスピードを上げることも大事だけど、斎藤固有の「間合い」にも磨きをかけることも今後の役に立ちそうだ。ちなみに駒大苫小牧高の中沢とは中澤竜也のこと。高校卒業後は國學院大に進学している。 今日も1クリックお願いします
2009.12.24
コメント(0)
-

情熱の記録人、千葉功さん
■朝日新聞(12月21日付)の2面にあった『ひと』欄より。タイトルは「野球週刊誌の連載『記録の手帳』が2500回を超えた」。登場した人は、元・パリーグ記録員だった千葉功さん、74歳。山の標高や川の長さなどの数字を覚えることが大好きだった少年時代。千葉さんはある日、当時読売新聞の記者だった三原脩さんの一文「野球は数字のゲーム」を目にしたことをきっかけに、野球の記録にのめり込んだ。1954年にパ・リーグに就職し、その傍らで「週刊ベースボール」誌上にコラム『記録の手帳』を書き始めた。テーマに合わせ、記録を集計・分析した表に記事を添えるのが千葉さんの手法。たとえば「サヨナラ試合数とチーム成績の関係」や「イチローと過去の打者の比較」など。97年にパ・リーグを退職した後も毎朝、新聞をスクラップ、ノートに記録を整理する。8畳の仕事部屋は紙の資料でギッシリ。「手で記録をつけないとアイデアが浮かばないんだよ」。ペンとそろばん、電卓から記事が生まれる。■ボクは「週刊ベースボール」本誌を読んだことがない。だから、その千葉さんのコラムがどんなものなのかまったくわからないけれど、「ペンとそろばん、電卓を使って整理する」という箇所にとても驚いた。きっと、毎日コツコツやるしかない地味な作業なはず。編集部に頼めば、加工データぐらい用意してもらえるだろうに。あえてそれを断って、自宅の部屋で電卓をたたきながら、原稿を書く様(さま)は感動的ですらある。■話はそれるけれど・・・。ふだん、ボクはスコアブックをつけながら野球を観戦することが多い。数年前はラグビーのスコアをつけようと思い立ち、録画ビデオを見ながら試みたことがあった。「前半24分、Aチームが相手陣ゴール手前、22mライン付近でのモールを起点に、9→10→12と右にボールが転送されたが、12がノッコン。ただ事前にAチームにアドバンテージがあったため、同地点からAチームのマイボール・スクラム~」たとえば、たったこれだけの記録をつけるために何度、画面を「一時停止」にしたことか。とてつもなく時間がかかる作業だった。あっという間に挫折したのは言うまでもない。新聞などの記事にはそういった一連のプレーが正確に記されているのだけど、ラグビーにもスコアブックってあるのかしらん? 今日も1クリックお願いします
2009.12.23
コメント(0)
-

絶対の信頼感、伊志嶺翔大
2009年11月22日に行われた「セ、パ両リーグ誕生60周年記念試合・プロ選抜vs大学日本代表」のこと。■J-SPORTSの事前の取材では「初球から打っていきたい」と抱負を話していた大学日本代表のトップバッター・伊志嶺翔大(東海大3年、沖縄尚学高)。プロ選抜の先発・前田健太(広島、PL学園高)と相対し、言葉どおりに初球を狙ってフルスイングを試みた。結果は一塁ファールフライに倒れてしまったが、ここでヒット一本でも打っていればカッコよかった。■大学日本代表のスタメンについて、榎本保監督(近畿大監督)は、「1番・伊志嶺は決まっているけれど、その他は未定です」と、試合前に話していた。きっとそれは、榎本監督にとって伊志嶺が「絶対の信頼を置ける存在」という証に違いない。伊志嶺は、今年(2009年)7月に行われた日米大学野球で下級生ながら2番打者として打順を固定された。そしてその期待に応えたことが榎本監督の信頼を生んだようだ。この大会、伊志嶺のほかに下級生(3年)ながら第1戦にスタメン出場したのは、青山学院大の小池翔大(3年、常総学院高)と東洋大の林崎遼(3年、東洋大姫路高)だけ。この3人以外はすべて4年生だったから、伊志嶺らへの期待が大きいことがわかる。■伊志嶺の沖縄尚学高時代、2005年のセンバツと同年夏の2回、甲子園に出場している。センバツは準々決勝で敗れ、夏は2回戦で敗退した。特にセンバツに出場した時、1回戦で柳田将利(元・ロッテ)や加守田隆介(現・青山学院大4年)がいた青森山田高と戦い、スコア16-3で圧勝した。なぜか、この試合をボクはよく憶えている。ちなみに当時、沖縄尚学時代のチームメイトだった赤嶺慎は現在、日本大の外野手(4年)。エースだった前嵩雄基は、社会人野球の東芝に投手として在籍している。その東芝の投手陣には元・明治大の江柄子裕樹(つくば秀英高)や、東洋大姫路高時代に「アン投手」と呼ばれ人気者になったグエン・トラン・フォク・アンらがいる。※沖縄県勢で初めて沖縄尚学高を甲子園優勝に導いた比嘉寿光(早稲田大-広島-来年から広島フロント入り予定)がいたのは1999年。また、東浜巨(現・亜細亜大)が沖縄尚学を2度目の全国優勝に導いたのは2008年のこと。※尚、アン投手は2010年1月に東芝野球部を退部した。今日も1クリックお願いします
2009.12.22
コメント(0)
-

大学選手権と平林泰三さん
■ラグビー大学選手権が今日(12月20日)から始まった。関東大学リーグ戦で優勝した東海大が、筑波大(対抗戦3位)を相手に"まさか"の大苦戦。22-22の同点で迎えた後半45分にトライを決め、やっとこさ勝利を決めた。リーグ戦3位まで(1位・東海大、2位・関東学院大、3位・法政大)と、対抗戦4位(1位・早稲田大、2位・慶応義塾大、3位・筑波大、4位・帝京大)までの7チームは実力伯仲。早稲田大が以前のような圧倒的強さがない今季、優勝の行方は全く分からない。■1回戦の注目カード・関東学院大vs帝京大は、最後の最後まで勝敗のわからない接戦になった。後半41分、5点差を追っていた帝京大がゴール右隅にトライを決めて同点に。スコアは引き分けながら、トライ数の差(3-2)で帝京大が勝利を決めた。------------------------------------------------------最後の最後、同点に追いついた帝京大のトライはとても微妙だった。ボールが地面に着くのが先か、相手(関東学院大)ディフェンスに押されて足がラインを切ったのが先か? その判定が難しかった。レフリーの平林泰三さんがアシスタントレフリーに丹念に確認した後、トライを宣言し、その瞬間、帝京大の勝利が決まった。■平林泰三さん。アジア初のフルタイム・ラグビーレフリー。渡豪してラグビー修行した経験をもつ。今年(2009年)12月11日および12日に開催された「IRBセブンズ」南アフリカラウンドのプレート決勝(南アフリカ vs イングランド)をもって、「IRBセブンズ」におけるレフリー担当試合数が通算100試合を達成した。今日も1クリックお願いします
2009.12.20
コメント(1)
-

ちょいと不運だった西嶋一記
2009年11月22日に行われた「セ、パ両リーグ誕生60周年記念試合・プロ選抜vs大学日本代表」のこと。■この試合で、もっとも不運な投手は明治大・西嶋一記(3年、横浜高)だったと思う。両チームから計18人の投手が登板したけれど、西嶋だけが1回を投げ切ることができず、イニングの途中で降板する憂き目にあった。西嶋が登板したのは、スコア1-1の同点で迎えた8回裏のこと。プロ選抜のこの回先頭の松本哲也(読売、山梨学院大付高-専修大)に対し、一球もストライクが入らずストレートの四球を献上。続く3番・天谷宗一郎(広島、福井商高)にはゴロでセンター前に弾き返された。突然訪れた無死一・二塁のピンチに、榎本保監督は慌ててベンチを飛び出す。そして東海大・菅野智之への交代を主審に告げ、西嶋の仕事はたった6球であっけなく終わってしまった。■西嶋一記。同じ明治大・野村祐輔(2年、広陵高)の陰に隠れがちだったけど、今年秋になって頭角を現した。春季の登板数は1試合(対東京大2回戦)のみで勝敗はなかったが、秋は10試合に登板し3勝1敗、防御率は1.13の好成績。野村祐輔や斎藤佑樹(早稲田大3年、早稲田実)らを差し置いて、西嶋は堂々の防御率1位に輝いた。対プロ選抜の試合ではいいところがなかったけど、東京六大学リーグではすごい成績を残した素晴らしい投手だったのだ。■横浜高時代は、2006年センバツで甲子園に出場し、川角謙(現・青山学院大3年)の控え投手として全国優勝を経験した。その頃の恩師・渡辺元智監督の西嶋評は、「素質はナンバーワン。だがハートが弱い」(朝日新聞2006年7月30日付)だったらしい。ちょいと厳しいコメントだけど、そのメンタル面がこの試合で不運を招いたか?今日も1クリックお願いします
2009.12.19
コメント(0)
-

小林誠司が涙のんだ甲子園
2009年11月22日に行われた「セ、パ両リーグ誕生60周年記念試合・プロ選抜vs大学日本代表」のこと。■同志社大の捕手・小林誠司(2年、広陵高)は4回裏の守備から出場、昨年(2008年)センバツV投手の東浜巨(亜細亜大1年、沖縄尚学高)とバッテリーを組んだ。そして、すぐさまその回に持ち味の「強肩」を披露した。それは、代走で一塁にいた小窪哲也(広島、PL学園高-青山学院大)が狙った二盗を刺殺したプレー。素早く、しかも送球が安定していて、二塁ベースで待ち構える多木裕史(法政大1年、坂出高)のグラブにピタリと収まる見事なものだった。さらに打撃でも活躍。6回裏に大隣憲司(ホークス、京都学園高-近畿大)の変化球をセンター前に弾き返すチーム2本目の安打を放ち、得点のきっかけをつくった。■広陵高時代は、野村祐輔(現・明治大2年)や土生翔平(現・早稲田大2年)らとチームメイト。小林を含め3人の名前を見て思い出すのは今から2年前、2007年夏の決勝戦(対佐賀北高戦)のこと。広陵高がスコア4-0でリードし、優勝を目前にして迎えた8回裏。一死満塁のピンチに、野村が佐賀北の井手和馬(現・亜細亜大2年)に、カウント1-3から投げた5球目にドラマが起きた。ボクは明らかにストライクに見えたが、主審の判定はボール。押し出しで1点を献上、続く副島浩史(現・福岡大2年)に逆転満塁本塁打を浴びて、結局広陵高は優勝を逃してしまったのだ。勝敗を分けたのは、間違いなく野村が井手に投げた5球目の微妙な判定。この判定が違っていたら、広陵高がそのまま優勝していたかもしれない・・・。また、この判定をめぐっては様々な波紋もあった。捕手の小林がミットを3度地面に叩きつけて、判定に抗議したとか(しないとか)が話題になった。さらに試合終了後は、判定をめぐって広陵高・中井哲之監督が審判を批判する発言をしたことで物議を醸したものだった。■副島が大逆転の本塁打を放った直後、超満員で埋まったスタンドは最高に盛り上がり、異常な興奮状態の様子に見えた。その時、マウンド上には白い歯を見せて苦笑いする野村と、野村に寄り添うようにして立つ小林の姿があった。無言のまま野村の背中をポンポンと叩く小林。きっとこういう場面では、かける言葉が見つからなかったんだろうなぁ・・・。今日も1クリックお願いします
2009.12.19
コメント(2)
-

中後悠平の千手観音投法
2009年11月22日に行われた「セ、パ両リーグ誕生60周年記念試合・プロ選抜vs大学日本代表」のこと。■5回裏、大学日本代表の5番手としてマウンドに上がったのは近畿大・中後悠平(2年、近畿大新宮高)。実況の島村俊治さんは、いつもの名調子で中後を紹介した。「上・横・下から投げ分ける変則投法は『千手観音投法』と呼ばれています」プロ選抜の8番・中田翔(日本ハム、大阪桐蔭高)との対決がボクは面白かった。中後、変則投法ながらスピードは速い。5球すべて140km台半ばの速球を投げ込み、中田に真っ向勝負を挑んでいた。残念ながら、結果は左中間を破るヒットを打たれたものの、「やんちゃ」そうな風貌同様に、勝ち気な投球に好感がもてた。■ボクが初めて中後悠平という投手を知ったのは、今年(2009年)6月に行われた全日本大学野球選手権。準々決勝の近畿大対富士大戦(6月12日)だった。この試合で8回から登板した中後は、スコア4-4の同点で迎えた9回、満塁のピンチに、サヨナラとなる押し出しの死球を与えてしまったのだ。打者の目時大(4年、福岡高)は死球の痛みを我慢して、尻もちをつきながらガッツポーズをしていたシーンをボクはよく憶えている。サヨナラ勝ちで大喜びの富士大。一方の中後は帽子をはぎとり、ヒザに両手を当て唇を噛んでいた。※ちなみに、この試合を中継したJ-SPORTSの実況アナも島村俊治さんだった。今日も1クリックお願いします
2009.12.17
コメント(0)
-

榎本保監督と学生野球憲章改正
2009年11月22日に行われた「セ、パ両リーグ誕生60周年記念試合・プロ選抜vs大学日本代表」のこと。■試合終了後、大学日本代表の榎本保監督(近畿大監督)がお立ち台に上がり、緊張した面持ちでインタビューに応えた。「プロに一泡吹かせてやりたかったのですが・・・。投手陣はよく頑張りました。攻撃陣がちょっと鈍かったけれど、よく頑張ってくれたと思います。大学生側からすれば、勝ちに等しいゲームでした」(超満員のスタンドから大きな拍手!)続けて、「来年の世界大学野球では、この大会の経験を活かしたいと思います。これだけギョーサン入っている観客の前で野球をやるのは初めて。来年は一番いい色のメダルを取って、大学野球を盛り上げたいです。応援をよろしくお願いします」(再び、スタンドから大きな拍手!!)あまりインタビュー慣れしていない様子の榎本監督。大学日本代表監督の任期は、たしか来年(2010年)まで。日米大学野球の時(今年7月)より、もっともっと大きな感動をファンに提供してほしいものだ。■この日、東京ドームを埋めた観客の数は4万1025人。前売り券はすべて売り切れていた。プロ・アマ「雪解け」の象徴的なこの試合に多くの観客が集まった。以下、日刊スポーツ(11月23日付)より。今年(2009年)8月に公開された日本学生野球憲章改正案では、日本学生野球協会の承認を得れば、高校や大学がプロと試合をすることが可能になった。全日本大学野球連盟・内藤雅之事務局長は「今後は新しい憲章の下でプロ側との交流はますます盛んになるでしょう」と見通しを示した。NPBの加藤良三コミッショナーは「象徴的な意味のある試合だった」とうなずいていた。(以上、日刊スポーツ)■なぜこんなに多くの観客が入ったのか? 正直言って、ボクは今もわからない。「斎藤佑樹vs坂本勇人」を前面に打ち出すPRが奏功したのだろうか???ま、いずれにせよ、プロ・アマの冷戦に雪解けを告げる素晴らしい記念試合だったことは間違いない今日も1クリックお願いします
2009.12.16
コメント(0)
-

林崎遼が魅せた送りバント
2009年11月22日に行われた「セ、パ両リーグ誕生60周年記念試合・プロ選抜vs大学日本代表」のこと。■大学日本代表の9番打者は、東洋大の林崎遼(3年、東洋大姫路高)だった。ポジションはセカンド。たしか今年(2009年)7月に行われた日米大学野球でも同じ打順、そして同じポジションだった。■その林崎、ボクが注目したのは6回表に見せた見事な送りバント。プロ選抜の大隣憲司(ホークス、京都学園高-近畿大)から上手に三塁前にバントを決めた。一塁走者の小池翔大(青山学院大3年、常総学院高)を二塁に進めることに成功し、直後に多木裕史(法政大1年、坂出高)の同点適時打を呼び込んだ。 たかが「送りバント」ではある。成功しても特別なことではないともいえる。ただ林崎には、日米大学野球の肝心な場面で送りバントを失敗した苦い経験がある。ボクはそのシーンをなぜかよく憶えている。以前そのことをブログに書いたところ、「そもそも東洋大の野球は送りバントをしません。だから林崎もバントが下手なのです」とコメントをいただいたことがあった。だから今回はきっちりバントを決めた林崎に、ボクは思わず感動してしまったのだ。ひょっとして、こっそり練習していたのかな?※余談だけど、東京六大学リーグでバントが下手だとボクが思うのは、明治大の野村祐輔(2年、広陵高)。シーズン中、チームのチャンスに何度も送りバントを試みたものの、ほとんどすべて失敗していたのは記憶に新しい。■さて、林崎の東洋大姫路高時代のこと。2006年夏の甲子園に出場した経験がある。この時は、初戦で甲府工高を相手に4-2で勝利した。勝ち投手は現在も東洋大でチームメイトの乾真大(3年)。3回戦は桐生一高に5-2で勝利。桐生一高の3番手で登板した投手は、こちらも現在、東洋大でチームメイトの鹿沼圭佑(3年)だった。そして準々決勝で対戦したのは、3連覇を狙っていた駒大苫小牧高。林崎のいた東洋大姫路は善戦したものの、結局スコア4-5で逆転負けを喫した。ただ林崎、この試合で田中将大(現・楽天)から本塁打をかっ飛ばしている。今日も1クリックお願いします
2009.12.15
コメント(2)
-

大学代表4番・若松政宏
2009年11月22日に行われた「セ、パ両リーグ誕生60周年記念試合・プロ選抜vs大学日本代表」のこと。■大学日本代表の4番は、近畿大の若松政宏(3年、大阪桐蔭高)だった。この試合前、大学代表の榎本保監督(近畿大監督)は、スタメンを聞かれてこう答えていたという。「1番・伊志嶺翔大(東海大3年、沖縄尚学高)は決まっているけれど、その他は未定です」。実況の島村俊治さんはそう話していた。また別の報道では、「今年の日米大学野球(2009年7月)で4番を打った中原恵司(亜細亜大4年、武蔵工大二高)のような選手が、今回はいない」と榎本監督がこぼしていたという話があった。ふつう打順を考える際、1番と4番は最初に決めるはずと思うが、榎本監督の最初のプランに「4番=若松」はなかったようだ。長距離砲が見当たらない大学代表において180cm、87kgの巨漢・若松は、どこから見ても4番にふさわしい打者に、ボクには思えたが・・・。■しかし結論を先に言うと、若松の結果は4打数ヒットなし(2三振)。まるでいい所がなく、まったくの期待外れに終わった。とりわけ残念だったのは6回表の攻撃のこと。2番・多木裕史(法政大1年、坂出高)の適時打でスコア1-1の同点に追いつき、なおも満塁のチャンスに補邪飛を打ち上げてしまったこと。これは近畿大の先輩・大隣憲司(京都学園高)との新旧近畿大対決でもあったが、大隣が苦し紛れに内角へ投げ込んだ球を、何の策もなく簡単に打ち上げてしまったのだから、本人にとってもさぞ後悔の残る打席だったろう。■若松政宏。大阪桐蔭高時代は2度甲子園に出場した(2005年夏と06年夏)。同学年に謝敷正吾(現・明治大3年)が、そして若松の一学年下には現・日本ハムの中田翔がいた。06年夏の甲子園では、初戦の横浜高を11-6で破り2回戦にコマを進めた。この時、相手の横浜高には西嶋一記(現・明治大3年)や、この試合で本塁打を放った越前一樹(現・立正大3年)など、60周年記念試合に一緒に出場している選手たちがいた。そして2回戦は、エース・斎藤佑樹(現・早稲田大3年)を擁する早稲田実に2-11で大敗。この試合の若松は、斎藤に無安打(3三振)に抑え込まれていた。 今日も1クリックお願いします
2009.12.12
コメント(0)
-

岡崎啓介と銀仁朗、前田健太
2009年11月22日に行われた「セ、パ両リーグ誕生60周年記念試合・プロ選抜vs大学日本代表」のこと。■1-1の同点で迎えた9回裏、大学日本代表の選手の中で、ただひとり打席に立つ機会のなかった立教大・岡崎啓介(2年、PL学園高)が三塁の守備についた。「代わったばかりの野手に打球が行く」というジンクスどおり、岡崎には2度も打球が飛んだ。2度目の打球はプロ選抜の1番・坂本勇人(光星学院高)が放った平凡なゴロ。岡崎は打球を正面で待って捕球したたため、捕球から送球までのリズムがまるでない。そのため一塁への送球が低くなったことがボクは気になった。J-SPORTSの報道によると、試合開始前、岡崎はプロ選抜で出場している西武の銀仁朗(平安高)にすぐさま挨拶に行ったそうだ。岡崎のお兄さんが銀仁朗と平安高時代にチームメイトだったため、お互いに顔見知りであることが理由らしい。■岡崎啓介を見て、ボクが思い出すのは今秋のリーグ戦、10月3日に行われた対法政大1回戦で決勝の本塁打を放ったシーン。スコア1-1の同点で迎えた9回表、4番の岡崎は打った瞬間、本塁打とわかる豪快な2点本塁打をレフトスタンドに放ち、これが決勝打になった。このシーズン、通算打率は.235と決して高い数字ではなかった。ただ「ここ!」という場面では何かをやってくれるのが岡崎の持ち味でもあった。■高校は名門のPL学園高。2006年のセンバツに、2年生ながら3番・ショートとして甲子園に出場。真岡工高、愛知啓成高、秋田商高を破って準決勝に進出したが、エース・有迫亮(現・三菱重工長崎)を擁する清峰高にスコア0-6で完敗した。 この大会の時、岡崎のチームメイトにはエースの前田健太(現・広島)や主将を務めた奥平聡一郎(現・青山学院大)、そして木野学(現・青山学院大)らがいた。前田は11月22日の記念試合ではプロ選抜の先発投手として登板、プロの投手として「相手の大学生を見下すような」風格を漂わせていた。また奥平や木野は現在青山学院大に在学中。11月8日に行われた東都大学リーグ1・2部入替戦(対国士舘大戦)にスタメンで出場していた。※だが、青山学院大は2部転落が確定してしまった・・・。今日も1クリックお願いします
2009.12.11
コメント(0)
-

萩原圭悟と中田翔
2009年11月22日に行われた「セ、パ両リーグ誕生60周年記念試合・プロ選抜vs大学日本代表」のこと。■3回表、大学日本代表の攻撃は7番・関西学院大の萩原圭悟(1年、大阪桐蔭高)から始まった。相対するプロ選抜の投手は、この回から3番手として登板した西武・平野将光(浦和実業高-平成国際大-JR東日本東北)。萩原は、昨年(2008年)夏の甲子園では3試合連続本塁打を放ち、大会タイ記録を持つ。カウント1-1から平野が投げた(タイミングを狂わせる)132kmの変化球に、うまくタメを作って、センター前にライナーで打球を弾き返した。これが大学代表にとって初安打となり、スタンドからひときわ大きな拍手が起きた。また5回裏、左中間に二塁打コースの打球を放ちながら一塁に止まるボーンヘッドを見せた中田翔に、「エェ~??」とスタンドから非難の声が上がる中、一塁を守っていた萩原が丁寧に会釈するシーンがあった。萩原と中田、大阪桐蔭高時代は先輩・後輩の間柄のため、ボクには印象的な出来事だった(ちなみに、中田が萩原の1年先輩にあたる)。■萩原圭吾。3試合連続本塁打を放った昨夏の甲子園では、中田が卒業後に大阪桐蔭高の4番に座っていた。また本塁打だけでなく、打率は5割超、さらに1大会個人最多となる15打点(6試合)も記録するなど、萩原は大阪桐蔭が優勝する牽引役となった。この時の大阪桐蔭高は、並いる好投手を次々に打ち砕いた。準々決勝は報徳学園高と対戦し7-4で勝利。この時、報徳の投手は近田怜王(現・ホークス)。準決勝はエース・土屋健二(現・日本ハム)を擁する横浜高と対戦し9-4で圧勝。決勝は常葉菊川高に17-0で大勝した。常葉菊川の先発は、現在社会人野球・ヤマハに所属する戸狩聡希。■また同じ時、萩原と大阪桐蔭高時代のチームメイトであり、大阪桐蔭高のエースだった福島由登はその後、青山学院大(1年)に進学した。現在は小池翔太(3年、常総学院高)とバッテリーを組んでいる。今年11月8日に行われた東都大学リーグ1・2部入替戦(対国士舘大2回戦)は、この福島が必勝を期して先発した。7回を投げ自責点1と好投したものの、前日に続き連敗。2部転落を防ぐことは叶わなかった。ただ試合後、「試合は負けたけど、福島が好投したのは収穫だった。福島に期待しようよ」と話す青山学院大OBたちの声が聞こえた。今日も1クリックお願いします
2009.12.11
コメント(0)
-

最多勝、山中正竹vs江川卓
2009年11月22日に行われた「セ、パ両リーグ誕生60周年記念試合・プロ選抜vs大学日本代表」のこと。J-SPORTSで中継したこの試合。昨日書いたとおり実況アナは島村俊治さん、そして解説は山中正竹さんと秦真司さんだった(どちらも法政大OB)。今日の記事は山中正竹さん(佐伯鶴城高-法政大-住友金属)。■スコア1-1で引き分けたこの試合の終了後、山中さんはこんな感想を話した。「まずこの試合が行われたことがよかった。試合内容もよかった。そしてプロの選手たちが手を抜かずプレーしてくれたこともよかったと思います。プロ野球の底辺を支えているのはアマチュア野球です。今後において両者の健全な発展のために、今日の試合は意義あるものでしたし、将来この大会が意義あるものだったと評価できるようになってほしいものです」「まずこの試合が行われたことがよかった」という言葉は、アマ(監督)・プロ(横浜フロント)の両方を経験した山中さんの言葉だけに重い。少なくともボクにはそう思える。 ■法政大時代は田淵幸一、山本浩二、富田勝ら「法大三羽ガラス」とともに法政大の黄金時代を支えたエース。4年間の通算成績は48勝13敗、東京六大学リーグの最多勝記録保持者である(2位は法政大の江川卓で47勝12敗)。卒業後に入社した住友金属でも活躍、その後に住友金属の監督に就任し1982年の都市対抗野球では優勝監督も経験。92年のバルセロナ五輪では日本代表の監督を務め、チームを銅メダルに牽引した。94年からは母校の法政大監督に。2002年までの間にリーグ優勝が7回、全日本大学選手権でも優勝を経験した。92年五輪の時の主な選手は伊藤智仁(元・ヤクルト)、大島公一(元・近鉄)、小久保裕紀(現・ホークス)らがいた。また法政大監督時代には矢野英司、土居龍太郎ら元・横浜選手や現・西武の後藤武敏などを育てた。※横浜フロント時代(2004年~09年)のことは、あえて省略する。■話題は変わるけど、「怪物」と呼ばれた江川がなぜ、山中さんのもつ最多勝記録を抜くことができなかったか? ボクには不思議だった。その謎を解くエピソードを『東京六大学野球80年史』(ベースボールマガジン社刊)に見つけた。1977年秋の江川にとって最後のシーズン。明大1回戦に勝った法大はV4へ王手をかけた。江川は通算勝利を47勝とし、先輩の山中正竹の持つ48勝に王手。だが江川は「これですべてが終わりました。ほかの投手がたくさんいます。僕の勝ち星はもうこれで結構です」とあっさりこの日で”サヨナラ公演”を決め込んだのだ。48勝の通算記録も先輩を追い越す可能性は十分にあったし、周囲も協力を惜しまなかったはずだ。それを自分から記録への道を閉ざしてしまったのだ。「僕だけが野球をやっているわけじゃない。チームワークの勝利ですよ」と淡々と話しながら静かに神宮を去ったなるほど、そういうことだったか。江川らしいと言えば、江川らしいが・・・。今日も1クリックお願いします
2009.12.10
コメント(0)
-

名アナ・島村俊治さん
今日も飽きずに、11月22日に行われた「セ、パ両リーグ誕生60周年記念試合・プロ選抜vs大学日本代表」のこと。■ボクはJ-SPORTSでテレビ観戦をした。実況は元NHKアナの島村俊治さん(2000年に定年退職後はフリー)だった。とてもソフトで品のある語り口、それでいてテレビを通じて「凛(りん)」とした空気を漂わせる、ボクが最も好きなアナウンサーなのだ。この人が野球を実況すると試合内容がどうであれ、そのゲームは「澄んだ」「潔い」「真剣勝負」に見える。島村さんのNHK時代、高校野球の中継でボクは島村さんの語り口をよく聞いた記憶がある。また、ここ数年間はJ-SPORTSなどのプロ野球・アマチュア野球の中継で、島村さんの声を聞くことが度々ある。そのたびボクは妙な安心感を覚えるのだ。■wikipediaで島村さんのことを調べたら、ボクが好印象を持ったもう一つの理由を初めて知ることができた。(以下、wikipediaより)「プロ野球中継では、1975年のパシフィック・リーグ後期優勝決定試合(阪急西宮球場での近鉄vs阪急戦)や1979年の日本シリーズ最終戦(大阪球場での近鉄vs広島戦)。「江夏の21球」で有名)など、近鉄バファローズの重要な試合に関わることが多かった」(以上、wikipedia)なるほど! ボクはこの2試合ともテレビ観戦をしていたはずだけど、実況が島村さんだったことは記憶にない。ただこれらの試合を通じて、島村さんの声がボクの脳へさらに「好印象」を擦り込んでいたのかもしれない。今日も1クリックお願いします
2009.12.09
コメント(0)
-

東浜巨を見て思い出す2人の投手のこと
2009年11月22日に行われた「セ、パ両リーグ誕生60周年記念試合・プロ選抜vs大学日本代表」のこと。■4回裏、プロ選抜の打者に立ち向かう亜細亜大の投手、東浜巨(1年、沖縄尚学高)を見て、テレビ解説をしていた山中正竹氏さんは、「せっかくプロの打者と対戦するのだから、思い切って内角を攻めればいいのに」と残念がっていた。ボクが好きな実況アナの島村俊治さんは、東浜が打たせて取るタイプの投手のため、「東浜の前(3回裏)に登板した澤村拓一を『剛』と例えるなら、東浜は『柔』」と評していた。■東浜が大学日本代表の4番手投手として登板したのは4回裏だった。対戦した打者は3人。4番・新井貴浩(阪神、広島工高-駒澤大)に四球を与えたものの(その後、盗塁死)、5番・亀井義行(読売、上宮太子高-中央大)をレフトフライ、6番・田中浩康(ヤクルト、尽誠学園高)を空振り三振に仕留めた。田中へのウインニングショットは143kmの速球。外角ぎりぎりのコースにビシッと決まった瞬間、東浜はホッとしたような表情を浮かべ、小さなガッツポーズをしていた。(残念ながら内角を攻めたわけではなかったけれど・・・)試合後、東浜のコメント。「大学生ならボール球を振ってくれるが、プロは手を出さない。レベルは高いです。でも3人で抑えられたんで自信になります」 (日刊スポーツ)■東浜を見ていて、ボクが思い出したのは2人の好投手のこと。それは現・新日本石油ENEOSの大塚椋司(聖望学園高)と、現・法政大1年の三嶋一輝(福岡工高)。→ 詳しくはこちらをどうぞ。今日も1クリックお願いします
2009.12.08
コメント(2)
-

元・近鉄の高木康成が読売へ
オリックスから交換トレードで巨人に移籍した高木康成投手(27)が7日、入団会見を行った。高木の背番号は「13」で、年俸は2400万円。会見で高木は「巨人は伝統あるチーム。気持ちが高ぶっている」と話した上で「自分の特徴は先発も中継ぎもできるという点。キャンプからアピールしていきたい」と決意を示した。 (産経ニュース)■高木康成(静岡高)のこと。昨年の成績は1勝2敗、防御率は4.95。また過去9年間の通算成績は13勝21敗、通算の防御率は4.26。もともとは近鉄バファローズに所属した選手だった(2000年ドラフト2位)。静岡高時代は1999年のセンバツと夏の2回、甲子園に出場した。夏は3回戦まで勝ち進み、エース・正田樹(現・台湾興農ブルズ)を擁する桐生一高と対戦した(結果はスコア3-4でサヨナラ負け)。桐生一高の控え投手には、背番号「11」をつけた一場靖弘(当時2年、現・ヤクルト、明治大)もいた。■また、高木と同じ2000年ドラフトで近鉄に入団した選手に岩隈久志(堀越高)もいた。その時の主な選手は次のとおり。1位 宮本大輔 (延岡学園高、今年10月オリックスから戦力外通告)3位 前田忠節 (PL学園高-東洋大、今年10月阪神から戦力外通告)5位 岩隈久志 (現・楽天)だいぶ以前の報道で知ったが、高木は近鉄の同僚・岩隈への対抗心が相当に強かったらしい。その気持ちは今も維持しているのだろうか。残念ながら現在、高木と岩隈の「差」は大きく開いているけれど、ぜひ岩隈をキャッチアップしてほしいものだ。 今日も1クリックお願いします
2009.12.08
コメント(0)
-

別所引抜き事件、企てた人と理由
前回の続き。■南海・鶴岡一人監督は、「別所引き抜き事件」は読売新聞・武藤三徳常務が謀ったものではなく、巨人・三原脩監督の知恵で行われたものだったと断言している。 「(南海の)別所と木塚を引き抜けば、巨人は強くなる一方、当面のライバルであり、手のつけられないほど整備されていた南海は弱くなるのだから引き抜きは一石二鳥の効果をもっていたわけだ。俊敏な三原さんらしい狙いであった」(『御堂筋の凱歌』鶴岡一人著)■鶴岡さんの予想を後押しする、三原脩の愛弟子でもあった青田昇の証言もある。別所が2ヶ月間の出場停止処分を受けたが、そのことを指して三原監督が青田に語りかけた言葉を青田は憶えている。「べつに別所が出場できなくても、それはそれでいいんだ。たとえ、別所が今シーズン、巨人で1勝もできなかったとしても、彼の(昨年の勝ち星の)26勝が南海から消えるだけで、ウチが優勝できるのだから・・・」 (1)■この考えかた(下線部)は、読売巨人軍に最近まで脈々と受け継がれる編成術でもある。「自軍の日本一を阻む相手チームの選手を招き入れ二軍に干しておく」ことは代表例でもある。そしてその伝統を作ったのは、1978年に起きた「江川事件」で読売と江川陣営に対し「NO!」と反対の声を上げた三原さんだったことが意外ではある。正義感の強い三原さんがなぜ?ただ三原さんの次の言葉に、善悪で判断できない巨人軍監督が背負うものの大きさを感じることもできる。義務づけられた常勝と、巨人ファンの異常な心理と。「一般ファンの職業野球に対する考え方は、いいプレーを見たいという事と面白い勝敗を見たいということにある。(中略)しかし巨人に対する一般ファンの考え方に関する限りはそうではないと思う。つまり巨人ならばどれ程勝ち越して一方的な試合になろうとも、ファンはそれで充分満足してくれるのである」 (2)(三原脩著『私の新しい野球管理術』より。※上記(1)(2)は『三原脩と西鉄ライオンズ 魔術師』(立石泰則著、小学館刊)194~197頁より引用した。 ※文中、敬称略。 今日も1クリックお願いします
2009.12.06
コメント(0)
-

別所引き抜き事件
11月28日に書いた「セ・パ誕生の裏事情と近鉄」の続き。■セ・パ両リーグが誕生したのは、1949年(昭和24年)11月26日。この日、日本野球連盟顧問各代表者会議が開かれ、翌50年からセ・リーグとパ・リーグの2リーグ制で行うことが決定された。■49年という年は、春に正力松太郎が「2リーグ制移行構想」をぶち上げて以降、既存球団や新規参入を希望する球団がそれぞれ「利権」を求めて抗争に明け暮れた1年でもあった(前述)。また、読売と南海が遺恨を残し、その後のプロ野球の勢力図を大きく変える原点となった年でもある。■その顕著な事例は、一年前(1948年)に起きた「別所引き抜き事件」。1946年(昭和21年)に19勝、翌47年(昭和22年)に30勝を挙げて南海のエースに成長していた別所毅彦(当時、昭。のちに改名)だったが、南海の待遇には不満を持っていた。そのことを聞きつけた読売は48年のシーズン中にもかかわらず、第三者を通じて別所に10万円を貸与。さらに契約金50万円と東京都内の住宅(50万円相当)の条件を提示した。日本野球連盟はこの事件が発覚後、シーズン中に行われた引き抜きであることを重視。読売に対し10万円の制裁金の支払いを命じ、さらに別所本人には翌シーズンの2ヶ月間出場停止処分を命じた。だが、結果として別所の読売移籍を認める裁定であり、その裁定内容に多くの疑問の声が上がった。■当時南海の監督だった鶴岡一人は著書で次のように述懐している。「別所の引き抜きは(昭和)24年度の勢力分野をいっきょに逆転した。26年以降の、いわゆる巨人の黄金時代は、これによって達せられたものであるといっても、いいすぎではないだろう。別所引き抜きに対して、南海が釈然たりえなかったのは当然であった」 (『御堂筋の凱歌』)。※『三原脩と西鉄ライオンズ 魔術師』195頁(立石泰則著、小学館刊)そして、別所引き抜き事件の仕掛け人は、読売新聞社常務取締役だった武藤三徳と言われていたが、鶴岡は当時読売の監督だった三原脩が首謀者だと読んでいたし、たぶんその読みに間違いはなかった。このことは次回に。※文中、敬称略。今日も1クリックお願いします
2009.12.05
コメント(0)
-

まずは1部復帰を!小池翔大
2009年11月22日に行われた「セ、パ両リーグ誕生60周年記念試合・プロ選抜vs大学日本代表」。■青山学院大の小池翔大(3年、常総学院高)は、大学日本代表の8番・捕手でスタメン入り、3回までマスクを被った。バッテリーを組んだ投手は早稲田大の斎藤佑樹(3年、早稲田実)、同じ東都大学リーグの東洋大・乾真大(3年、東洋大姫路高)と中央大・澤村拓一(3年、佐野日大高)の3人。大学代表チームの唯一の失点は、この小池がマスクを被っている初回に許した。ただ小池はカウント2-2から外に構えたものの、斎藤の投球が真ん中に入ったたため生まれた適時打(打者・新井貴浩)。小池に責任はない。また3回には、天谷宗一郎(広島、福井商高)が狙った二盗を見事に刺した。■ボクは小池を見ていて2つのことを思い出した。 それは「歓喜」と「悔し涙」のまるで正反対の姿だった。(1)「歓喜」・・・今年(2009年)7月に行われた日米大学野球でのこと。東洋大の佐藤貴穂(4年、春日部共栄高)と捕手2人体制で臨んだ大会だったが、第5戦(7月15日、神宮球場)の延長11回裏、小池は気迫ある粘りの打撃を見せた。この回先頭で打席に入った9番・小池はファールで粘り続け、相手投手に15球も投げさせ、その末に四球を勝ち取った。「何が何でも出塁するんだ!」という強烈な意志が日本代表のチャンスを作り、その後に3番・加藤政義(4年、九州国際大)のサヨナラ適時打を呼び込んだ。小池がサヨナラのホームを踏み、この大会の優勝を決めた。そしてチームメイトたちの歓喜の輪の中に小池の姿があった。(2)「悔し涙」・・・今年11月に行われた東都大学リーグの1・2部入替戦でのこと。秋季リーグ戦で6位に終わった青山学院大は、この入替戦への出場を強いられた。初戦に敗れ断崖絶壁に立たされた2回戦(11月8日、神宮球場)、結局この試合も青山学院は国士舘大(2部・1位)に負け、52季ぶりの2部転落が決定した。初めから青山学院大が敗れるシナリオが用意されていたかのように、2戦ともナインを重苦しい空気が包んでいた。2試合とも青山学院は投打ともに精彩を欠いていた。小池自身も例外ではない。凡打を繰り返し、終始うつむいているように見えた。2部転落が決まった瞬間、ナインはその場に倒れ、また座り込んで悔し涙を流していた。小池をはじめあまりに残酷なシーンに見えた。■小池、今年味わった正反対の体験を生かして、来春は早々の1部復帰を目指してほしいものだ。ただ2部ではあっても日本大、駒澤大、専修大などの古豪がひしめく。復帰は並大抵のことではないが・・・。今日も1クリックお願いします
2009.12.02
コメント(0)
-

打で失策を帳消し多木裕史
2009年11月22日に行われた「セ、パ両リーグ誕生60周年記念試合・プロ選抜vs大学日本代表」。■結局、スコア1対1の引き分けで終わったこの試合。大学代表にあって唯一の打点を挙げたのは、法政大の多木裕史(1年、坂出高)だった。6回表、走者を一・三塁に置いて、多木が放った打球はフライとなってふらふらっと三塁手の後ろに飛んだ。これをショートの坂本勇人(光星学院高)が落球(記録は安打)し、同点に追いつく貴重な1打になった。苦手の守備も3度の守備機会を無難にこなし、チームに迷惑をかけずに済んだ。(ホッ!)多木、打撃はめっぽう評価が高い。今年(2009年)春季リーグ戦では打撃十傑の堂々6位。1年生ながらベストナイン(ショート)に選出された。ただ守備(特に送球)には難がある。春季の失策数は5。先輩投手たちからは「エラー3つまでなら許す」といわれていたほど。■ボクは多木の失策で思い出すシーンがある。それは今年(2009年)6月13日に行われた全日本大学選手権・準決勝の対関西国際大戦のこと。平凡な遊ゴロを捕球後、多木は(ゲッツーを狙って)二塁に送球する際、あまりに慎重になりすぎて暴投をしてしまった。慎重を期したあまり身体から捕球→送球のリズムを完全に奪ってしまったように見えた。その時点で、この大会3試合で4つ目の失策を記録した多木。顔は青ざめ、大きく肩で深呼吸を繰り返していた。この多木の送球を見て、テレビ解説をしていた早稲田大・應武篤良監督は「完全に送球病、イップスですね」と断言していた。■多木、今秋のリーグ戦の失策数はたったの「2」。イップスもどうやら杞憂に終わったよう。ま、失策のことをいつまでも言っていても仕方がない。守備よりも打撃重視。それが多木の真骨頂なのだから。今日も1クリックお願いします
2009.12.01
コメント(2)
全24件 (24件中 1-24件目)
1