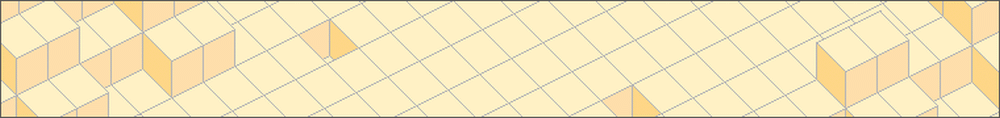2009年08月の記事
全36件 (36件中 1-36件目)
1
-

最後の都市対抗、日産敗退
今年限りで休部が決まっている日産は、都市対抗・準決勝でトヨタと対戦し、スコア0-1の僅差で惜敗した。この試合をもって日産、「最後の都市対抗」となった。創部は1959年(昭和34年)、都市対抗の出場回数29回、優勝は2回。そして日本選手権へは出場15回、優勝1回を誇る名門チームだったが、あとは秋の日本選手権を残すのみとなった。■wikipediaによると、日産野球部にはこんなエピソードがあったという。1999年(平成11年)、本社の社長に「コストカッター」ことカルロス・ゴーン氏が就任し、硬式野球部の存続が不安視されたが、氏は都市対抗野球での社員の応援に感銘を受け、硬式野球部を存続させることを決心したとされる。後にゴーン氏は「都市対抗野球こそが日本の企業文化の象徴だ」とも断言した。それなのに休部となったのは、昨今の経済情勢が影響した。--------------------------------------------------------(準決勝 第1試合)ト 000 000 100 =1日 000 000 000 =0(ト)中澤-佐竹、(日)石田-秋葉勝負を決めたのは7回表、9番・二葉祐貴(PL学園高)の一振りだった。この回先頭打者だった二葉、日産・石田祐介投手(淑徳高-東京国際大)の135kmの速球を叩き、レフトフェンスぎりぎりに本塁打を放ち、結果的にこの一打が決勝打となった。日産、安打「1」では勝ち目がなかった。その1安打が出た6回裏、二死三塁のチャンスを活かせなかったことが、最後まで悔やまれる。今日も1クリックお願いします
2009.08.31
コメント(0)
-

あぁ、佐々木大輔がブレーキに?
第80回都市対抗野球大会・準々決勝4試合が今日(8月30日)、東京ドームで行われている。第1試合はトヨタ自動車と東京ガスが対戦。トヨタが4-1で東京ガスを破り、準決勝進出を決めた。東京ガ 000 000 100 =1トヨタ自 020 200 00X =4(東)安達-坂上-鎌田-徳村、(ト)佐伯-大谷ボクが注目していたのは東京ガスの4番・佐々木大輔(日大三高-明治大)。だが、今日の試合は4打数無安打、しかも3三振と散々な出来。特に6回表、二死一・二塁のチャンスに見逃三振を喫したのは痛かった。(「流れ」を手繰り寄せる絶好機だったのに)8回はトヨタの2番手として登板した大谷智久(報徳学園高-早稲田大)と対戦。東京六大学リーグ時代もよく対戦した間柄だったが、まるで大谷の球にタイミングが合わず、佐々木はここでも三振に終わった。--------------------------------------------------------<試合の経過>トヨタは2回、走者を二・三塁に置き、野選とスクイズで2点を先制した。そして4回、この回先頭の田中幸長(宇和島東高-早稲田大)が左中間フェンス直撃の二塁打で出塁。そして三進後、7番・佐野比呂人(三重高-法政大)のライト線への二塁打を放ち3点目。二死後、9番・二葉祐貴(PL学園高)がレフトオーバーの二塁打で4点目を挙げ、勝利を決めた。-------------------------------------------------------◇佐々木大輔の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「東京六大学のスラッガー 」 (2008.2.14) → こちらへ。◇大谷智久の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「このチームは宮本のチームだから、最後は宮本に」 (2008.11.22) → こちらへ。◇田中幸長の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「社会人選手権、トヨタ優勝」 (2008.11.24) → こちらへ。今日も1クリックお願いします
2009.08.30
コメント(0)
-

リトルリーグ、日本準決勝で敗退
米国ペンシルベニア州ウイリアムスポートで開催されているリトルリーグ「2009年世界選手権」の情報を。(ESPNの録画中継を見た)8月26日(現地時間)、「国際の部」のセミファイナルが行われ、日本代表の千葉市リーグはメキシコと対戦。残念ながらスコア0-6で敗退した。日 000 000 =0メ 510 00X =6----------------------------------------------------7月、江戸川球場で行われた全国大会の準決勝・決勝をボクは見ていた。パワー溢れるバッティングで相手チームを圧倒し続けた千葉市リーグ。「こりゃ、かんたんに世界だって制覇できる!」そう思っていたものだった。だが、メキシコの先発投手(168cm、85kgの巨漢)が外角低めに丁寧に投げ分ける速球とスライダーになかなか手が出ない打線。外角を意識すると、今度は内角にズバッと速球を決められる。そんな「変幻自在」の投球では、いかに千葉市リーグのパワーを持ってしても、バットに当てることさえ容易でなかった。 千葉市リーグ・織田洋文監督のコメント。「相手投手は、緩急を使った素晴らしい投球をしていて、打者がタイミングを掴む前に終わってしまった。(米国に来てからは)打線に元気がなく、最後まで調子を取り戻せなかったことが辛い」 (リトルリーグ公式HPより引用)写真に写った織田監督は、その言葉どおり苦渋に満ちた表情を浮かべていた。だが、なにが「辛い」ものか。日本にリトルのチームはあまたあれど、憧れの聖地に今年行けたのは千葉市リーグただひとつ。選手たちは最高の夏休みになったろうし、家族にとっても素晴らしい記念になったと思う。それで十分じゃなかろうか。千葉市リーグの選手・父母のみなさん、お疲れ様でした。次はシニア(ボーイズ?、軟式?)に進むのでしょうか。いや、すでに入っているかな? ま、いずれにせよ、これからも頑張ってください! 今日も1クリックお願いします
2009.08.30
コメント(0)
-

都市対抗、新日石は3回戦で敗退
都市対抗野球の3回戦、今日(8月29日)の第1試合では昨年(2008年)都市対抗の覇者・新日本石油ENEOSがNTT東日本と戦った。N東日本 000 001 001 =2新日石E 000 000 000 =0(N)大竹-成田-黒田-片山、(新)沼尾-大塚-廣瀬この試合、ボクのお目当てだった新日石・大塚椋司(聖望学園高)は2番手の投手として、7回頭から登板した。150km超の速球をビシバシ投げ込む大塚の姿を期待したかった。でも、この回先頭のNTT・向後光洋(市立銚子高-駒澤大)が初球いきなりセーフティバントを成功させたことが、大塚の調子を微妙に狂わせた。別に失点したわけではないし、敗戦の責任を背負うハメになったわけでもない。ただ内容が「三振」と「四球」のオンパレードでは、ちょいと寂しい。向後の突然のバントが、大塚の気合いを空回りさせるキッカケを作ったようにボクは感じた。今春見た大塚があまりに素晴らしかったので、その残像がたんに期待レベルを押し上げているのかもしれないけど・・・。(今日の大塚の成績)2回、打者9人、被安打2、奪三振4、与四死球2、失点0。--------------------------------------------------------<試合の経過>NTTは6回、ダブルプレー崩れの間に先制した。そして9回、この回先頭の向後光洋がセンターオーバーの3塁打を放ち、追加点のチャンスを作る。二死後、途中出場の3番・岩本康平(上宮太子高-八戸大)がレフトフェンス直撃の適時二塁打を打って、新日石を突き放した。投げては先発の大竹飛鳥(愛知高-関東学院大)が7回2/3を完璧に抑え、新日石打線に得点チャンスさえ与えなかった。--------------------------------------------------------ボクのもう一人の注目選手、新日石の泉尚徳(国士舘高-早稲田大)は9回裏、二死一塁の場面に代打で登場した。だが四球、残念ながら快音を聞くことはできなかった。 また、プロ注目の清田育宏(市立柏高-東洋大)はNTTの4番としてスタメン出場した。結果は、5打席3打数0安打で2四球。8回、二塁走者だった時は、捕手からのけん制で刺されるボーンヘッドもあり、パッとしない一日だった(に違いない)。◇大塚椋司の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「大塚椋司の抑え、完璧!」 (2009.3.15) → こちらへ。◇泉尚徳の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「早稲田大・泉尚徳の決勝打!」 (2008.10.18) → こちらへ。◇清田育弘の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「清田育宏の高校・大学時代 」 (2009.1.21) → こちらへ。今日も1クリックお願いします
2009.08.29
コメント(0)
-

学習院大が日本大に勝つ!
8月26日に行われた東都リーグ交流戦で、学習院大(3部)が日本大(2部)にスコア3-1で勝利したらしい。学習院には悪いが、日大を相手に勝利したのは、それなりに大ニュースじゃなかろうか。例えそれが、公式戦ではない交流戦(いわばオープン戦)に過ぎないものだったとしても・・・。-------------------------------------------------------------ただ、学習院大野球部の歴史を紐解くと、そこには「輝かしい野球部史」が垣間見える。まず伝統がある。創部が1889年(明治22年4月6日)と他の大学野球部と比較すると群を抜いて古い。そして、この(明治)時代においては、一高(現・東京大)ほどではないものの、学習院は強豪の一つに数えられる存在だった。1904年(明治37年)10月の早稲田との一戦、当時は学習院が「格上」であり、それを示すエピソードが面白い。※1904年と書きましたが、1901年の誤りです。こちらを参照ください。中学校(当時の学制)ですでに腕に覚えのある猛者たち(郁文館、青山学院、麻布、水戸中などの出身者)たちが集い創部された早稲田野球部。「天下の覇権我にあり」と威張ってみたものの、だれも早稲田に野球部があることさえ知らない始末。そのため「我が部の存在を知らせねばならぬ」と探しあてた相手が、当時の強豪・学習院だった。学習院からすれば、「早稲田野球部???、どうせ取るに足らぬ敵」と見て、気軽に応じたに過ぎなかったが。試合は意外や意外、たいへんなシーソーゲームになり、ついにはスコア7-6でついに早稲田が学習院を破ってしまった。■以下、『日本野球史』(国民新聞運動部編、昭和4年刊)より。「学習院選手が皆ボンヤリした以上に早稲田のものも茫然とした。「勝った」「勝ったのだ」。早稲田では、学校の掲示場に戦勝の報告をデカデカと張り出した。更に祝勝の晩餐会を開くやら記念撮影をやるやら大騒ぎ」「勝てば官軍となって、更に一高横浜への挑戦(※)を考え、一方部員を集めて雄飛すべく計ったのである」※「一高」は、もちろん現・東京大のこと。 ※「横浜」は、横浜在住のアメリカ人から組織されたアマチュアチーム「横浜倶楽部」 のこと。当時、国内で最も強いと評されていた。◇日米大学野球対決の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「日米野球初戦、一高が圧勝す」 (2009.6.29) → こちらへ。 今日も1クリックお願いします
2009.08.29
コメント(0)
-

泣くな別所、センバツの花
この名文句が生まれたのは1941年(昭和16年)のこと。「別所」とは言うまでもなく別所毅彦さんのことで、同年3月27日のセンバツ2回戦で起きたアクシデントに由来する。滝川中のエースとして春の甲子園に出場した別所さんは、岐阜商戦の9回、本塁にスライディングした際に左腕を骨折。利き腕は右だったため、左腕を肩から三角巾で吊り下げた状態のまま延長戦を投げ続けた。左腕は全く使えないため、キャッチャーから返ってくる球はすべてゴロにしてもらったという話もある。だが、10回、11回と無失点で切り抜けたものの12回途中には体力が限界となって交代を余儀なくされた。結局、延長14回の激戦の末、滝川中はスコア1-2で惜敗した。この時、別所を讃えた言葉が「泣くな別所、センバツの花」。その言葉とともに伝説となった。--------------------------------------------------------------------「本塁に突入する際に捕手と激突、そして負傷」といった降りは今大会(2009年夏の甲子園)の花巻東高・菊池雄星と酷似している。ちなみに、滝川中の4番を打っていたのは青田昇さん。本来は投手だったが、別所さんがエースに君臨していたため控え投手に甘んじ、外野手に転向させられていた。別所さん、青田さんの滝川中時代の先輩・後輩は、プロ入りしてからも何かと縁があった。三原脩さんを軸とした「別所引き抜き事件」 (1948年)もそのひとつ。ま、この事件のことは後日に。◇菊池雄星の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「泣くな菊池、甲子園の花!」 (2009.8.24) → こちらへ◇別所毅彦の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「大下弘の少年・学生時代のこと」 (2009.8.2) → こちらへ。◇青田昇の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「東西対抗戦が実現した背景」 (2009.8.1) → こちらへ。◇「ボクにとっての日本野球史」、 INDEXはこちらへ。 今日も1クリックお願いします
2009.08.27
コメント(0)
-

今夏の甲子園を勝手に総括!
中京大中京高が史上最多7度目の優勝を飾り、今夏の甲子園が幕を閉じた。昨年に続き、「勝手に総括」を。(その1)過密スケジュールの見直しを!やはり準決勝・決勝は大味な試合になった。準決勝・決勝の3試合で2ケタ得点試合が2試合もあった。準決勝 / 日本文理高 2-1 県岐阜商高、中京大中京高 11-1 花巻東高決勝 / 中京大中京高 10-9 日本文理高ちなみに昨夏は、準決勝 / 大阪桐蔭高 9-4 横浜高、常葉菊川高 9-4 浦添商高決勝 / 大阪桐蔭高 17-0 常葉菊川高 こういった大味な試合が多くなる原因は、過密スケジュールによる投手たちの疲労(消耗)が影響していると思う。投手の保護を重要視して、スケジュールの見直しが必要と思う。最近とみに投手どうしの「我慢比べ」になっているように思う。誰もが松坂大輔のようなスーパースターではないのだから。(その2)投手の全力疾走、その是非?花巻東高の菊池雄星投手は、甲子園最後の試合となった準決勝(対中京大中京高戦)では、たった11球しか投げることができず涙を飲んだ。理由は背筋痛。その原因は1回戦(対長崎日大高戦)で本塁突入時に捕手と接触したこと。そして準々決勝(対明豊高戦)での、一塁カバーに入った二塁手との激突も影響していると思う。一塁を駆け抜けても全力疾走する花巻東ゆえ、激突し負傷することは必然でもある。でも投手までが常に全力疾走・相手野手への激突もやむなしでは、(菊池のように)あとになって後悔する事態も起きかねない。ボクは高校野球らしくて、投手も全力疾走のほうが好きなのだけど。(その3)花巻東高・佐藤涼平を見て「高校野球の面白さ」を再認識した このブログでも何度も書いたけど、花巻東高の佐藤涼平の打席を見ていて飽きることがなかった。彼の打席は、そのまま個人的な「パフォーマンスの場」だった。プロとかドラフトとかいった視点では語れない。彼の素晴らしさは「野球をよく知っている野球頭の良さ」にあった。次の一球、次のプレーのイメージが次から次へと彼の頭の中に溢れ出て、また、そのイメージを忠実に具現化できる技術も持っている選手だったように見えた。テレビで解説をしていた山下智茂さん(元・星稜高監督)は佐藤を見て仰っていた。「いま野球をやっている小学生・中学生たちも佐藤君のプレーを見てほしい。そしてたとえ身体が小さくても、佐藤君のような野球選手になることができると希望をもってほしいです」。まさにそう思わずにはいられない、(小柄なのに)圧倒的なパワーをもつ選手だった。今日も1クリックお願いします
2009.08.26
コメント(0)
-

文理、9回二死から怒涛の反撃
夏の甲子園、昨日(8月24日)の決勝戦、日本文理高の最後の粘りは凄まじかった。中京大中京高(愛知)vs日本文理高戦(新潟)。日本 011 000 115 = 9中京 200 006 20X =10(日)伊藤、(中)堂林-森本-堂林-森本優勝が決まった瞬間、中京大中京高のエース・堂林翔太(3年)は悔し涙を流した。「最後は苦しくて・・・、エースとしての責任を果たせず情けない。すいませんでした」。優勝したお立ち台で、堂林の口から最初に出てきた言葉は謝罪だった。■試合の内容は、サンケイスポーツより。華々しく締めるはずだった。6点リードの9回。先発して5回0/3を2失点で、一度は右翼に回った右腕は、大藤敏行監督(47)に再登板を直訴。ところが、2死一塁から連続長打を浴び、さらに死球を与え、一、三塁としたところで右翼に戻った。後は5点を猛追される展開をただ見守るだけだった。 (以上、サンケイスポーツ)「野球は9回二死から」。日本文理は、この言葉を地で行く「怒涛」の攻撃だった。------------------------------------------------------------9回表、日本文理高の攻撃を振り返ってみた。この回から再登板した中京大中京・堂林翔太(3年)は、三振と遊ゴロで簡単に二死を奪った。スコアは10-4、どっからどう見たって中京の優勝が決まっているようだった。優勝投手は堂林になるものと、おそらく誰もがそう思っていた。そして「最後の打者」になるはずだった(失礼!)1番・切手孝太(3年)が打席に。カウント2-2と追い込まれたものの、微妙なコースの球を見極めて、四球を選び出塁。(ただこの時点では、最後の打者が次打者に繰越しただけに見えた)この試合で本塁打を放っている2番・高橋隼之介(2年)が打席へ。堂林、捕手とのサイン交換が合わず何度も首を横に振る。パスボールの後に、高橋は高めに浮いた変化球を叩き、左中間にをライナーで破る二塁打を放つ。スコア5-10。3番・武石光司(3年)。この武石も際どい球は必ず見極める。(この期に及んで、日本文理の打者たちの落ち着きぶりは素晴らしい!)そして中に入ってくる変化球を引っ張ってライト右へライナーで抜けるへ三塁打を放ち、走者がまた1人生還。スコア6-10。4番・吉田雅俊(3年)。三塁へ平凡なファールフライを打ち上げる。日本文理、万事休す。だが、目測を誤った三塁手は捕球できず。(堂林、このプレーでいささか動揺したか)結果は死球。中京大中京高ベンチ、再び森本隼平(2年)をマウンドに上げる(堂林はライトへ)。5番・高橋義人(3年)も四球を選んで出塁、満塁に。このチャンスに6番・エースの伊藤直輝(3年)は三遊間をゴロで抜けるレフトへの適時打を放つ。打った瞬間、両手を叩き喜びを表しながら一塁に駆ける。スコア8-10.判官びいきなのか、大半の観客は日本文理を応援するかのように大歓声。そして代打、背番号「12」をつけた石塚雅俊(3年)が打席に。石塚も初球を叩き、レフト前に適時打を放つ。スコア9-10.(代打がこの場面で、初球からバットを振ること自体がスゴイ!)尚も二死一三塁のチャンス。三塁走者の伊藤が生還すれば同点!8番・若林尚希(3年)がバットを振り切った打球は三塁への強烈なライナー。だが、三塁手が好捕。日本文理の凄まじいまでの反撃はここで終了した。-----------------------------------------------------------------試合終了後、冒頭に記したとおり、堂林は優勝したのに悔し涙を流していた。一方の日本文理ナインは一様にすがすがしい表情をしていた。「精一杯やったんだ」という満足感の現われだったろうか。彼らの爽やかな笑顔が印象的だった。 今日も1クリックお願いします
2009.08.25
コメント(2)
-

泣くな菊池、甲子園の花!
夏の甲子園、決勝・中京大中京高(愛知)vs日本文理高(新潟)戦は、いま録画を見始めたところなので明日書きます。------------------------------------------------------------8月14日のこのブログで、ボクはこんなことを書いた。背筋を痛めた菊池雄星(長崎日大高戦、8月12日)に対して、「もう甲子園で投げられなくなったなら、「『泣くな菊池、甲子園の花』という言葉を贈ろうと思った」と。(もう負けてしまったので、今回はそのままタイトルを使いました)こんな安直なパロディが、その後現実のものになってしまい、ボクはバカなことを書いてしまったと、いまになって後悔している。準決勝(23日、対中京大中京高戦)で見せた彼の姿は、それほどに痛々しかった。ブルペンで投球練習をしている時もほんのキャッチボール程度。思い切り腕を振ることさえできない状態だったが、試合展開は菊池に休養を与えるほど生温くはなかった。準決勝で突然マウンドに上がらざる得なかった場面と、彼が投げた11球をもう一度振り返ってみた。----------------------------------------------------------------(2009年8月23日、準決勝第2試合)花巻 000 000 100 = 1中京 100 512 11X =11(花)吉田-猿川-菊池雄-猿川、(中)堂林-伊藤花巻東の先発は2年生の吉田陵。序盤こそ緊張のせいか制球が定まらない投球だったが、次第に落ち着きを取り戻す。3回裏はカーブやスライダーがキレて1イニングに3三振を奪うなど、当面吉田ひとりで試合を作ることも大丈夫だ!そう思った矢先の4回表、中京高の5番・磯村嘉孝(2年)に本塁打を浴びて吉田の調子が狂ってしまった。後続の打者にも3本の安打と1つの死球を与え、スコア1-3に差が開き、なおも二死満塁のピンチを迎える。ブルペンで投球練習をしていた菊池は盛んにベンチに「投げさせてください」と言うように、盛んにベンチを見つめる。ベンチも腹を決めたように菊池をマウンドに送り出した。「菊池雄星の11球」。■打者は3番・河合完治(3年)。1球目 ボール2球目 外角の球を巧くおっつけて、レフト左をライナーで抜ける適時三塁打 (走者が一掃し、スコアは1-6に) ■4番・堂林翔太(3年)。3球目 一塁ゴロでチェンジ。■(5回裏)5番・磯村嘉孝(2年)4球目 ボール5球目 ストライク6球目 ファール7球目 ファール8球目 ファール9球目 空振りで三振■6番・伊藤隆比古(3年)10球目 ボール11球目 左中間へのソロ本塁打(スコアは1-7に)※「菊池雄星の11球」については、後日もう少し詳しく書きます。------------------------------------------------------------- この11球で、菊池雄星の最後の甲子園は終わった。大会期間中、チームメイトたちは口々(くちぐち)に、皆こう言った。「雄星だけのチームではない!」 センバツ、そして今大会を見ていて、ボクもそう思った。「雄星だけのチームではない」でも、「雄星もいるから、機動力溢れる素晴らしいチームが完成したのだ・・・」今更ながら、そう感じている。 ◇花巻東高の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「花巻東、敵愾心が引寄せた決勝進出」 (2009.4.1) → こちらへ「感動運んだ花巻東・佐藤涼平」 (2009.8.21) → こちらへ今日も1クリックお願いします
2009.08.24
コメント(0)
-

準決勝、日本文理-岐阜商
今日行われた準決勝、第1試合。日本文理高vs県岐阜商高戦。県岐阜商 000 000 001 =1日本文理 000 011 00X =2(県)山田、(日)伊藤 両投手、見事な投球だった。そしてほんのわずかな差で日本文理高が勝利を勝ち取り、新潟勢としては初の決勝進出となった。印象的だったのは9回表、二死一塁の場面に代打で登場した県岐阜商・古川隼也(3年)のこと。 彼の気持ちを込めた一打はレフトオーバーの二塁打に。チームにとって貴重な1点を奪うことができた。二塁ベースに立った古川、目から涙が溢れるシーンをテレビカメラがアップで捕らえていた。ヒットを打てた嬉しさはもちろん、それ以外にも、これまでの悔しいことやら苦労したことなど、様々な思いが脳裏に甦ったんだろうな、とボクにはそう思えた。--------------------------------------------------------------- さて、話は変わる。途中から見たこの試合だったけど、ボクは二塁塁審の顔を見て、「あれは、堅田さんじゃなかろうか」と思った。それは堅田外司昭さんのこと。先日見たNHKテレビ『にんげんドキュメント』~球児たちの延長戦25年目の星稜対箕島~』に出ていたので、よくその顔は憶えている。昨日(8月22日)のブログで書いた1979年夏の甲子園、星稜高のエースはこの堅田さんだった。延長18回、208球をひとりで投げ抜いたが、結局敗戦投手となった。そして今、パナソニックに勤務する傍ら、高校野球の審判も務めている。1979年、夏の甲子園3回戦。(延長18回)星稜 000 100 000 001 000 100 =3箕島 000 100 000 001 000 101X=4そしてその後、この試合で主審を務めた永野元玄さんと堅田の間にドラマがあった。試合終了後、永野さんは選手が退出する出口で堅田を待った。そして、堅田を見つけると、この試合で使っていたボールを一個手渡したのだ。主審が投手に記念ボールを渡すことなど滅多にない。でも、延長18回を投げ抜き、そして敗れた堅田に主審自身が感情移入したのには理由がある。それは(疲労で)堅田の球威が落ちてくるのを間近かで見ていた目撃者だったから。■『スローカーブを、もう一度』(山際淳司氏、角川文庫)に、永野さんのコメントがある。「私のベルトのところには、、ボールを入れる袋が下がっていまして、そこにはいつも4個のボールを入れているんです。ニューボールもあれば、一度使ったボールもある。ここぞという局面で、ボールを交換するときは、私は使い古したボールを渡すようにしている。新しいボールは滑るからです」「そして18回の表に星稜は得点機を逃して、その裏、つまり、18回の裏の堅田君の一球目を見て、私は点が入るかもしれないと思いました。予感がするんですね。私は投げやすいボールを渡したはずです。でも、球が死んでいた。17回までの堅田君の投球とは明らかに違うんですね。疲労がたまっていたのかもしれません。すべての球が死んでいました」 結局、箕島は延長18回に適時打が飛び出して勝利を決めた。甲子園、審判と選手にもいろいろなドラマがあるものだ。--------------------------------------------------------------◇ 「ボクにとっての日本野球史」 (2009.7.1)、 INDEXはこちらへ。今日も1クリックお願いします
2009.08.23
コメント(4)
-

花巻東、お疲れ様でした!
夏の甲子園、準決勝 第2試合、花巻東高vs中京大中京高戦。花巻 000 000 100 = 1中京 100 512 11X =11(花)吉田-猿川-菊池雄-猿川、(中)堂林-伊藤この大会で、常に全力疾走のプレーや執念の逆転劇など、多くの話題を提供してきた花巻東高。だがエース・菊池雄星は背筋痛で先発を回避、残念ながら打撃陣も元気がなく、大差のスコアで敗れ去った。今日の花巻東高、あまりいいところはなかった。というより、中京大中京高とは実力差が大きかったというべきだろうか。花巻東は小技を絡めた攻めが得意と言われるが、相手が横綱(=中京大中京高)では、がっぷり四つに組まれたら、まるで身動きがとれなかったということかもしれない。ただ惜しまれるのは、4回表の攻撃。一死一・三塁の同点のチャンスで試みた7番・佐々木大樹(2年)のスクイズ。打球はホームベースのほぼ手前に止まり2-2-3のダブルプレーとなってしまった。スクイズが決まっていれば、4回裏の5点はなかったかもしれない。それが残念だ最後に、『あま野球日記』の花巻・通信員からの報告を。「今日は花巻東高をはじめ花巻文化会館などに多くの市民が集まり、大スクリーンを見ながら応援してました。文化会館は1500席が埋まっていました。試合中は盛り上がる場面が少なかったのですが、終了後、多くの市民たちが『ありがとう!』「ご苦労さんでした」と、スクリーンに向かってそれぞれの思いを伝えていました」今日も1クリックお願いします
2009.08.23
コメント(4)
-

佐藤翔、熊代聖人を憶えてますか?
甲子園だけではない。都市対抗野球も開幕し、いまアマチュア野球「まっ盛り」なのだ。今日(8月21日)、都市対抗2日目が東京ドームで行われた。第2試合には、ボクの注目する佐藤翔(秋田高-慶應義塾大)がいるJR東日本東北(仙台市)が出場した。対戦相手は今季限りで休部する日産自動車(横須賀市)だったから、正直、どちらにも勝ってほしい組み合わせではあったが。JR 001 000 000 =1日産 100 010 00X =2(J)猪原-森内、(日)石田およそ2年ぶりに見た佐藤翔。今日は久々に定位置である「4番の座」にどっかりと腰を下していて、ボクは嬉しく思った。それは2年前の東京六大学秋季リーグ戦、彼は絶不調(スランプ?)に陥り、定番だった4番どころか、スタメンさえ外れる憂き目にあったまま卒業した姿をボクは見ていたから。佐藤、大学生活ではまさに「天国と地獄」を味わった。2006年に「東京六大学選抜チーム」が編成されたとき、佐藤は3年生ながら4番を務めるほどのスラッガーだった。190cm、98kg(だったかな?)の恵まれた身体を活かして、打球をピンポン玉のようにスタンドに弾き返す「天国」の時代があった。ただ卒業間際の07年秋季リーグ戦は、まるで逆。試合前のフリーバッティングでさえバットの芯で捕らえることもままならず、ゲージに出たり入ったりを繰り返して常に首をかしげる姿が目についた。まさにこの時、佐藤にとっては「地獄」だったと思う。大きな身体がとても小さく見えたものだった。久々に佐藤を見た今日の試合。学生時代に例えると「天国」の時に近い状態に、ボクには見えた。4打数1安打、その1安打も相手守備のミスと思えるもので、手放しで喜べる成績ではなかったけど、常に堂々とフルスイングする姿にボクはホッと胸を撫でおろすことができた(相手投手の低めを丁寧に突く投球術が素晴らしかった)。一部の報道によると、佐藤は今秋のドラフト候補選手だという。大学時代にも当然、そういった話題があったけど、自ら社会人入りを決断した経緯がある。今度こそはプロ入りを果たしてほしいものだ。◇佐藤翔の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「佐藤翔、都市対抗出場決定」 (2009.7.7) → こちらへ。「佐藤翔、最終打席よかったよぉ~」 (2007.10.30) → こちらへ。--------------------------------------------------------------今日の試合の内容は、こちら(毎日新聞のサイト)をご覧ください。あ、そうそう、日産自動車の3番打者は熊代聖人(2年目、今治西高)でした。2007年夏の甲子園、エース・4番としてチームをベスト8に導いた好選手。社会人入りしてからは打者に専念しています。今日の試合では、外角低めに落ちる変化球を巧く捕らえ、ライト前にライナーの安打を放っていました。言うまでもなく、熊代にも注目です。※熊代のいる今治西高、2007年夏のベスト8入りを果たしましたが、準々決勝で広陵高にスコア1-7で敗退しました。その時の広陵の投手は野村祐輔(現・明治大2年)でした。 今日も1クリックお願いします
2009.08.22
コメント(0)
-

投手を酷使する甲子園の日程
夏の甲子園、ベスト4が出揃った。明日の準決勝の組み合わせは次のとおり。(1)日本文理高(新潟) - 県岐阜商高(岐阜)(2)花巻東高(岩手) - 中京大中京高(愛知)いよいよ佳境だ。昨年の甲子園もそうだったけど、心配なのは投手の体力の消耗。過密スケジュールを原因とした炎天下の甲子園での連投では、どうしても大量失点の試合が多くなってしまう。したがって、大会が進むにつれて得(失)点が上昇するのではないか? と考え、実際に計算してみたのが次の数値だ。(『あま野球日記』調べ)昨年の例を見ると、1試合あたり1チームの得(失)点数は、たしかに決勝が近づくにつれて次第に上昇していく傾向にあった。<昨年(2008年)の実績>1回戦 (24試合)1試合・1チームの平均得(失)点 4.7点2回戦 (16試合)同 4.2点 3回戦 (8試合) 同 4.9点準々決勝 (4試合) 同 7.1点準決勝 (2試合) 同 6.5点決勝 (1試合) 同 8.5点そして今年。準々決勝を終わった現時点での経過は次のとおり。昨年と傾向が似ていて、やはり大会が進みに連れて得失点が上昇している。<今年の途中経過> ※( )内+、- は昨年比。1回戦 (17試合)1試合・1チームの平均得(失)点 4.3点(-0.4点)2回戦 (16試合)同 4.1点(-0.1点)3回戦 (8試合) 同 5.2点(+0.3点)準々決勝 (4試合) 同 5.5点(-1.6点)明日の準決勝、明後日の決勝。その勝敗を決めるスコアは6~7点前後と、投手戦は期待できず、「ノーガードの派手な撃ち合い」が演じられるかもしれない。--------------------------------------------------------------昨年8月17日、このブログに「勝手に甲子園を総括する!」を書きました。その中では、ワンサイドゲームが生まれる原因は投手の酷使せざるを得ないスケジュールにあるのでは? という仮説をもとに、勝手に投手の保護を目的とした大会スケジュール変更案を書いたのですが、それに対し多くの人から賛否両論の意見をいただきました。こちらに詳しくそのことが書いてありますので、よろしければどうぞ。。また、その際皆さんからいただいたコメントをまとめた「異論反論」集もあります。こちら(2008.8.21)へどうぞ。今日も1クリックお願いします
2009.08.22
コメント(2)
-

1979年、星稜vs箕島
前回(花巻東高-明豊高戦)の続き。4回、守備についていた花巻東高・柏葉康貴(3年)がファースト後方にふらふらと上ったファールフライを好捕したシーンがあった。それを見た実況アナ氏(BS朝日)は、隣りにいる解説者に問いかけた。「30年前、フライが上がった同じ場所で、歴史に残る試合で、忘れられないプレーがありましたね」。解説をしていたのはその30年前(1979年)、箕島高との名勝負の末に敗れた星稜高監督の山下智茂(当時)さん。そして、忘れられないプレーは延長16回に起きた。一塁後方にふらふらと上がった飛球を追いかけた星稜高・加藤直樹さんが人工芝に足をとられて落球してしまったこと。この飛球を捕球していれば星陵の勝利が確定していた。でも落球したことで息を吹き返した箕島の打者は直後に本塁打を放ち、結局試合は延長18回まで続き、箕島が勝利した。星稜にとっては忘れたくても忘れられない悔しさの残る試合だった。実況アナ氏から30年前のことを問われた山下さん、感慨深げに当時のことを語っていた。山下さんの話を聞きながら、ボクもその試合のことを思い出していた。-----------------------------------------------------------------1979年、夏の甲子園3回戦。(延長18回)星稜 000 100 000 001 000 100 =3箕島 000 100 000 001 000 101X=4このスコアを見ただけでも、ゲームの凄まじさを知ることができる。「高校野球史上、最高の試合」と賞讃するファンも多い名勝負だった。その名勝負の象徴として、「落球」のシーンが取り上げられることが多い。書籍では山際淳司さんが著した『スローカーブをもう一球』(角川文庫)。テレビでは、NHK『にんげんドキュメント』~球児たちの延長戦25年目の星稜対箕島~』など。■『スローカーブ・・・』には、加藤さんの当時を振り返った言葉が収められている。「あの落球のことで、しこりが残っているわけじゃないです。その後、いろいろといわれましたよ。ぼく自身、星稜の野球部出身だということを初対面の人にいうとき、自分の方から先に言うんです。『甲子園の16回にカクテル光線の中で落球した、あの加藤です、あの一塁手がぼくです』と」「だから、しこりはないんです、ホントに。でもね、やはりスッキリできない部分があって、それはおそらくぼくの一生、ついてまわるんじゃないかと思うんです」「あの一球をぼくが捕っていれば・・・」ボクのような平々凡々な人間からすると、甲子園に出場して名勝負を演じただけで素晴らしいことと思う。だけどたった一球のミスが、その後、選手の心に暗い陰を落とすものかもしれない。NHK『にんげんドキュメント』(2004年制作)で見た加藤さん、やっとあのワンプレーの呪縛から(少しだけ)解かれたように見えた。今日も1クリックお願いします
2009.08.22
コメント(2)
-

感動運んだ花巻東・佐藤涼平
夏の甲子園12日目、準々決勝・花巻東高(岩手)-明豊高(大分)戦。(延長10回)花巻 010 300 002 1 =7明豊 000 012 030 0 =6(花)菊池-猿川、(明)今宮-野口-山野-今宮毎度毎度で申し訳ないけれど、今日も花巻東高・佐藤涼平(3年)のこと。ボクは今日の彼のプレーを見ていて、2度、涙がこぼれそうになった。(1度目)送りバントした佐藤涼平が一塁へ駆け込む時、ベースカバーに入った明豊高の二塁手と接触し、脳しんとう(たぶん)を起こしたシーン。佐藤への心配でボクは涙がこぼれそうになったそして、なぜ二塁手は内側に避けずにベースの上に突っ立っているのだろう? とボクは不思議に思った。それは同点で迎えた延長10回表、花巻東高の攻撃中に起きた。一死一塁で2番・佐藤涼平に打順がまわった。器用な佐藤なら何でもできる場面だったが、ここは手堅く送りバント。いつものように一塁に全力疾走で駆け込んだ佐藤と、ベースカバーに入った明豊高の二塁手が交錯。佐藤は相手選手の身体に頭を激突させ脳しんとうを起こしてしまう。倒れたまま、立ち上がることも身動きもできない佐藤。ついには担架でグラウンドの外へ。「佐藤は大丈夫なのか?」 心配げなどんよりした空気が漂う甲子園。だが、そんな空気を振り払ったのは次打者・3番の河村悠真(3年)。初球を思い切り叩いた打球は、センター前に飛ぶ決勝打に。試合中盤から「流れ」が相手に傾きかけていたが、勝利を呼び込む一打となった。(2度目)その裏、少し間を置いてグラウンドに現れた佐藤涼平が笑顔でセンターのポジションンに駆けて行った時。スタンドからは佐藤に向けて大きな拍手が起こり、身長155cmの佐藤がとても「大きく大きく」見えたから。--------------------------------------------------------■佐藤のコメント、スポーツニッポンより。「頭がぼーっとしてたけど、温かい歓声がすごくうれしかった。この場所で野球ができることの幸せを感じた」同点の10回。無死一塁から送りバントを決めた佐藤涼はベースカバーの明豊・砂川と激突し、吹っ飛ばされた衝撃で地面に頭を打ちつけた。担架に運ばれての退場。医務室で手当中に歓声が聞こえた。自分が決死の思いで二塁へ送った柏葉が川村主将の中前打で生還したのだ。頭部打撲との診断を下した医師に「出たい」と直訴。医務室を飛び出すと、10回裏をしっかりと守り抜いた。■菊池がいなくても勝った。岩手県勢90年ぶりの4強。花巻東の夏はまだ終わらない。(以上、スポーツニッポン)今日も1クリックお願いします
2009.08.21
コメント(17)
-

NHK、近鉄バファローズ消滅
昨日NHKで放送されたドキュメンタリー『球団が消える? プロ野球選手会103日の闘い』の録画をいま、見終えた。ボクはとても重苦しい気分になった・・・理由1.番組名は『球団が消える?---』だったのに、タイトルは『たった一人の反乱』だった。「たった一人」とはいうまでもなく古田敦也会長(当時)のことなんだろう。でも番組の中では、他の選手会メンバーもそれなりに頑張っている様子だったし、何よりもファンの応援があって、ファンと一体になったから12球団存続を守れたと番組中では繰り返し言っていたのに、なぜタイトルだけ「たった一人」なのか?理由2.古田氏はインタビューでこう応えていた。「ストライキに一定の成果はあった。ただ、まだまだ課題はある。将来、もっともっと多くの球場で多くの観客が野球を観ることができるよう、プロ野球は発展してほしい」これ、もっともな話ではある。ならば選手会に提案がある。・・・・・(いや、やめておこう。書くことが長くなり過ぎる)ただ、結果として当時の選手会長が「たった一人の反乱」といった冠を戴く嘆かわしい事態にならないために、あの時、近鉄ファンが自ら動くしかなかったんだ。と、番組を見ながら、ボクは思うしかなかった。でも何ができたろうか?「江夏の21球」で敗れた側なのにこの勝負を称え、「10・19」も勝たなかったのにそれを伝説化してしまった「負け癖の体質」(少なくてもボクは)が、何も行動を起こせなかった最も大きな原因だったのかもしれない。巨人ファンなら、いざ球団がなくなるといった事態が起きたら、新聞の不買運動ぐらい平気でやるだろう。(ま、近鉄ファンが「近鉄電車・乗車拒否運動」なんてやっても限界があるけど・・・)あの時、いったい何ができたのか。ボクにはまだよく分からないけれど、何も行動を起こせなかった(近鉄ファンだった)自分にも責任があったんだと思うことにしようと思う。◇近鉄バファローズの関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「球界再編問題NHKで放送 」 (2009.8.15) → こちらへ。「江夏の21球と10・19」 (2009.3.11) → こちらへ。※風はばさん番組の感想を書きましたが、情報を教えていただいたことには感謝しております。ご気分を害されることのなきよう・・・。盛田の番組を録画しておきました。 今日も1クリックお願いします
2009.08.19
コメント(2)
-

花巻東「佐藤涼平劇場!」
昨日(8月17日)行われた2回戦、花巻東高-横浜隼人高戦でのこと。ボクはBS朝日の中継を録画予約していた。その録画映像を見ていたら、7回裏花巻東高の攻撃中、2番・佐藤涼平(3年)が打席にいる時、実況アナ氏はこう言った。「佐藤涼平劇場!」この言葉、見ていたボクにも共感できるとても素晴らしいネーミングだと思った。なぜなら佐藤涼平、身長155cmと小柄な選手ながら、いったん打席に立つと何を仕掛けるかまるでわからない「とてもとてもイヤらしい選手」だからなのだ。象徴的だったのは、アナ氏が叫んでいたその7回裏だった。この試合、佐藤にとって4度打席目。横浜 000 100 000 =1花巻 100 000 21X =4(横)飯田-今岡、(花)菊池------------------------------------------------------------------この時の佐藤の打席の様子を振り返ってみる。 1番・柏葉康貴(3年)が同点の均衡を破る2点本塁打を放った直後、佐藤が左打席に立った。相手投手は代わったばかりのエース・今岡一平(2年)。1球目 バントの構え。 見送って外角にボール。2球目 またもバントの構え。ストライク。 ※この2球だけでもイヤらしさ全開だ。3球目 内角高めへボール。4球目 ど真ん中へストライク。5球目 カットしてファール。6球目 またもカットしてファール。7球目 低めにボール。 ※捕手が捕球できずに落した球を佐藤がわざわざ拾い上げ、さらに自分の ユニフォームで土を落としてから捕手に渡した。(心憎いまでのイヤらしさ!) 8球目 カットしてまたもファール。打球はライナーで自軍ベンチへ飛んだ。9球目 カットしてファール。またも打球は自軍ベンチへ。 ※盛り上がるベンチ。ベンチの仲間にペコリと頭を下げて謝る素振りの佐藤。10球目 またもまたもカットしてファール。11球目 またもまたもまたもカットしてファール。打球は自軍ベンチへ。 ※笑顔でベンチに謝る。打席がまるで自身のパフォーマンスの場のよう。12球目 内角低めに落ちる変化球を空振りして三振。 ※笑顔でベンチに引き揚げる。------------------------------------------------------------------ この打席の佐藤、直前に2点本塁打が飛び出し、相手投手が交代した。交代したばかりの投手はいったいどんな球を投げるのか、どんな球種をもっているのか、それをチームメイトに知らせるため佐藤はカットを繰り返し12球を投げさせたのだ(たぶん)。そして佐藤のもっとすごいのは、それをちゃんと甲子園の大舞台で実践できること。そんな流れを読んだ上での心憎いイヤらしさの実践は、高校野球では稀な「最高の技」に思えた。 ◇佐藤涼平の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「花巻東・佐藤涼平に好感!」 (2009.8.12) → こちらへ。「白河越えは花巻東が果たす?」 (2009.3.29) → こちらへ。今日も1クリックお願いします
2009.08.18
コメント(2)
-

花巻東「最後まで全力を尽くす」
昨日(16日)まで、ボクは実家のある岩手・花巻に帰省していた。花巻の玄関口になっている新花巻駅をはじめ、商店街(といってもシャッターが閉まったままの店が多いが)のあちこちに、花巻東高の「甲子園出場」を讃えるビラ(多くは地元の岩手日報をはじめ新聞各社のもの)が貼られていた。たまに帰省すると、まるで「時間が止まってしまった」かのように思うことがある町だけど、花巻東高のおかげで、今夏ばかりは少しだけ活気を取り戻しているように見えた。※この6月には富士大が全日本大学野球選手権で準優勝したけど、その時も今回のように大いに盛り上がってくれただろうか? もしそうだったら嬉しいけど。 ◇富士大の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「富士大も巻き起こした『花巻旋風』、こちらも準Vで終焉」 (2009.6.14) → こちらへ。「最後まで全力を尽くす」ボクは3泊4日の帰省中、朝の散歩は必ず花巻東高のグランドへ行っていた。早朝だったため人気がまったくないグラウンドの、外野にあるスコアボードにはそう書かれていた。※昨年(2008年)の今頃、花巻東高は甲子園行きを逃したものだから、同じスコアボードに書かれていた文字は「神宮へ行こう」だった。ただ、残念ながら秋季東北大会で敗れたため、神宮行きはならなかったが。----------------------------------------------------------------今日の2回戦(花巻東高vs横浜隼人高)、録画をとったけれど、ボクはまだそれを見ていない(遅い時間なので、今日見るのはたぶんムリ)。ただ「熱闘、甲子園」(テレビ朝日系列)を帰宅後、どうにか見ることができた。その番組の中に印象的なシーンがあった。たしか7回だったか、花巻東の菊池雄星が長打を放ち強引に三塁に駆け込んだシーン。わずかな差でタッチアウトになったのだけど、そのプレーを見守っていた花巻東ベンチの選手たちは、決して強引な走塁を攻め立てるわけでなく、菊池を拍手喝采でベンチに迎えていた。それは「よくやった!」と菊池を讃えていたように見えた。「最後まで全力を尽くす」という彼らの決意。それは、「失敗したっていいじゃないか」「(最悪)負けたっていいじゃないか」。そんな結果なんかを気にすることなく、「常に前を向いて全力でプレーしようよ!」という意味だったんじゃなかろうか。菊池の走塁とベンチの笑顔を見ていて、ボクにはそう思えた。 ※今日はたくさんのコメント、ありがとうございました。 夜も遅いので、明日返事を書かせていただきます。なんだか今日は疲れてしまった・・・ 今日も1クリックお願いします
2009.08.17
コメント(2)
-

ネット裏のラガーシャツのオジサン
たしか今春のセンバツでも見かけたし、ひょっとしたら昨夏の甲子園でもテレビを通じて、「この人」を見かけていた気がする。「この人」とは、甲子園のネット裏中央から少し右側、その最前列に毎日座っているオジサンのこと。毎日、テレビ画面に映っていて、ボクはオジサンが気になって、時々、試合そっちのけで、そのオジサンを凝視する回数が増えている。年齢は50歳代(?)、まっ黄色な野球帽と横縞のラガーシャツがいつものスタイル。ただラガーシャツには相当なこだわりがあると見え、その色は「黄色と青色」「赤色と青色」「橙色と青色」「白色と青色」「黄色と黒色」等々バラエティに富んでいる。そして今日。さすがに暑かったのか、一日に三度も着替えをした模様。朝テレビを見た時は(たしか)シャツの色が「黄色と黒色」だったけれど、昼には「白色と青色」。そして夕方には「橙色と青色」に変わっていた。「甲子園に通い、ネット裏最前列に座って朝から晩まで高校野球を見ながら過ごす毎日」。とても勇気が必要だろうし、ボクにはとてもマネができない。だけど野球好きにとっては、羨ましいライフスタイルとも思えるのだ。 でもいったい、あの人は誰なんだろう?今日も1クリックお願いします
2009.08.16
コメント(4)
-

球界再編問題NHKで放送
先日、このブログに何度かコメントをいただいている風はばさんから、8月18日(火)にNHKで放送されることを教えていただいた。番組の内容を、今日(8月15日)付けのスポーツニッポンが次のように伝えている。04年の球界再編問題にスポットを当てたドキュメンタリー『球団が消える?プロ野球選手会103日の闘い』が18日午後10時からNHK総合で放送される。当時の記録映像や選手会長を務めていた古田敦也氏、松原徹事務局長らのインタビューのほか、映像に残っていない部分についてはドラマ構成。古田氏役は実力派俳優の二階堂智が演じた。突如起こった球団合併騒動から労使交渉、史上初のストライキなど激動の103日間を振り返る内容。 (以上、スポーツニッポン) ----------------------------------------------------------どうやら番組は「選手会礼賛!」の内容になっているようだ。ボクはこれまで数十回書いたとおり、30数年にわたる近鉄バファローズのファンだった。2004年球団消滅の際は、他の近鉄ファンがそうであったようにボクも人並みに衝撃を受け、そして落ち込んだものだった。ただ、 ストライキに「挑んだ」選手会を、ボクはなぜか英雄視することはできなかった。なぜなんだろう? 正直、その理由は今も整理がつかないでいるのだけど。近鉄という球団(フロント)がどうしようもないものだったことは、あの事件でよくわかった。ナベツネさんの「たかが選手が!」発言も常軌を逸したものであったこともよく理解できた。なのに、ライブドア社長の堀江某が救世主のごとく登場した際には、拍手で迎える気はさらさらなかったし、ついで選手会がストライキを起こした時は、正直言って古田某の「個人的なパフォーマンス」にも見えた。選手会という「労働組合」が選手の利権(あの事件の場合、近鉄の選手たちを救うこと)を守ることは必然だった。それは当然のこと。そして結果として2リーグ制が維持されたことも、両リーグの交流戦が始まったことも一定の成果と見ることができる。でも労働組合と消費者(この場合はファン)の関係は利益相反の関係にあるのが常。あの事件でファンと選手会が一致団結したように見えたのが、ボクにはとても嘘っぽく、そして作為的に見えて仕方がなかった。これまで百数十年間に及ぶ野球界の歴史は、資本家(オーナーやフロント)、労働者(選手)、そして消費者(ファン)の絶妙なバランスをもって成長を続けてきた。生き抜いてきた。その時代時代の社会状況(野球を取り巻く環境)に合わせて。 ------------------------------------------------------------- 04年の近鉄球団消滅に際しては、たとえば、・一部の資本家たちが「1リーグにしよう」と言ったのは、今後の長期的視野に 立った時、それは本当に間違いだったと言えるのか?・多くのファンは2リーグ制の堅持を望んでいたが、どうしても1リーグ制になって はいけなかったのか?・そして選手会は・・・?今も一部選手の年俸高騰が続いている。また、西武の裏金問題が発覚したときには(ファンにとって)その全容解明に最も動いてほしい選手会は何もしなかったと記憶している。裏金の実情を最も知っているのは選手たち本人であるはずなのに。選手の利権を守るためだけの団体なら当然ではあるけど、「ファンと一緒になって」ストライキまでしたのに、その時々で自分らにとって都合のいい動きしかしていないようにも見えるのだ。ま、続きは番組を見てから。 今日も1クリックお願いします
2009.08.15
コメント(8)
-

聖望学園、予想外の大敗!
花巻東高の菊池雄星、どうやら一昨日(8月12日)本盗の際に痛めた左脇腹は心配がいらないようだ。まずは一安心。もし、もう甲子園で投げられない状態になったら、「泣くな菊池、甲子園の花」という言葉を贈ろうと思っていたが、いらぬ心配だったようだ。↑ これ、「泣くな別所、選抜の花」という名コピーのパロディ。わかる人はわかるだろうけど、知らない人には全くわからないだろうなぁ。興味のある方は、外部サイトですがこちらをどうぞ。-----------------------------------------------------さて昨日(13日)行われた夏の甲子園4日目。わが埼玉代表の聖望学園高は、第3試合で宮崎・都城商高と対戦。スコア1-5と予想外の大敗を喫した。■以下、日刊スポーツより。第91回全国高校野球選手権大会第4日(都城商5-1聖望学園、13日、甲子園)小島が一直に倒れ敗戦が決まると、聖望のエース佐藤勇吾はあふれる涙をこらえることができなかった。「気持ちが焦っていつも通りの投球ができませんでした。チームに迷惑をかけてしまいました」一回、先頭打者にいきなり死球を与え、内角を突けなくなった。直球が高めに浮いて、二死までこぎ着けてから四球と三連打で4点を失った。準優勝した昨春のセンバツは背番号11でベンチ入り。決勝の沖縄尚学(沖縄)戦で投げた経験もあったが、スタンドを埋め尽くした4万人の大観衆に飲み込まれた。「負けたら(その年のチームは)終わりの夏は、雰囲気が違いました」。岡本監督は「佐藤が頑張って勝ってきたチーム。(負けは)仕方がない」とエースを責めなかった。2勝を挙げた03年以来6年ぶりの夏の勝利に届かず、聖望学園の夏が終わった。(以上、日刊スポーツ)埼玉は(神奈川ほどではないにしても)大激戦の地区。なのに、夏の甲子園ではなぜか勝てない。それがボクにはとても残念だ。■再び日刊スポーツより。埼玉大会決勝には、(昨年センバツの)準優勝エースだった大塚椋司(現・新日本石油ENEOS)が応援に駆けつけてくれた。「大塚さんのように、笑顔を忘れずに投げたい」。試合前、そう話した佐藤が、涙の顔で甲子園を去った。◇聖望学園高の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「聖望が本庄一を破り準決勝へ」 (2009.7.25) → こちらへ。「よくやった、聖望がセンバツ準優勝」 (2008.4.4) → こちらへ。◇大塚椋司の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「新日本石油ENEOS・大塚椋司がまたまた好投だ」 (2009.4.7) → こちらへ。今日も1クリックお願いします
2009.08.14
コメント(0)
-

花巻東・佐々木大樹を見て畠山和洋がダブって見えた
前回の続き。菊池雄星という投手は、つくづく不思議な投手だと思う。センバツと同様にアウトを取るたび派手なガッツポーズを繰り返し、感情を顕(あら)わにする。でも、それでいて彼の投球術は極めて冷静でもある。このアンバランスさがとても不思議であり、魅力的でもある。速球や変化球のキレだけでなく、菊池は大投手に成長する条件をすべて兼ね備えた選手と言えるかもしれない。■花巻東高 8-5 長崎日大高長崎 010 002 110 =5花巻 000 002 24X =8(長)大瀬良-寺尾-大瀬良、(花)菊池ただ勝利した花巻東高、その勝因は「菊池雄星だけのチームじゃないぞ!」と選手個々が意地を見せる全員野球にあったと思う。特徴的だったのは、どの選手もやった一塁への全力疾走。しかも一塁を駆け抜けてからさらに加速して走っていた。これも気合いの現われかも?この試合、特にボクが注目したのは花巻東高の7番を打っていた佐々木大樹(2年)。放った安打は3安打と暴れまくり、8回の無死満塁のチャンスには走者一掃の二塁打を右中間に放ち、それが逆転決勝打となった。佐々木の魅力は打球の速さ。今秋からの新チームでは4番を打つだろうけれど、今後の大活躍が期待できる大物の打者だった。ボクは佐々木の打撃を見ていて、同じ岩手出身の畠山和洋(現・ヤクルト、専大北上高)の高校時代の姿がダブって見えた。畠山を初めて見たのは1998年夏と2000年夏の甲子園だった。いつもフルスイング、ずば抜けて速く強い打球をかっ飛ばす姿に、ボクは大いに感動したものだった。 ◇畠山和洋の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「【イースタンリーグ】ヤクルト・畠山、ロッテ・平下(元近鉄)」 (2006.7.8) → こちらへ。「神戸拓光を見に行き由規と対面、そして畠山を見た」 (2008.4.6) → こちらへ。今日も1クリックお願いします
2009.08.12
コメント(0)
-

花巻東・佐藤涼平に好感!
夏の甲子園大会3日目(8月12日)、第4試合の花巻東高-長崎日大高の一戦(録画)を、いま見始めたところ(もちろん結果は知っているが)。録画は、まだ初回が終わったばかり。いまの段階で言えるのは菊池雄星がどうこうよりも、球をじっくり見極める落ち着き加減、そして狙っていない球を巧くカットする打者の技術が素晴らしいということ。特に身長155cmの2番打者・佐藤涼平(3年)には好感が持てる。センバツの時もそうだったけど、みなぎる野球センスに一段と技術の巧さが加わったように見えた(見てくれは『ナイナイ』の岡村に似ているが)。続きは、録画を見終わった後に。◇花巻東高の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「花巻東、敵愾心が引寄せた決勝進出」 (2009.4.1) → こちらへ。「富士大も巻き起こした『花巻旋風』、こちらも準Vで終焉」 (2009.6.14) → こちらへ。 今日も1クリックお願いします
2009.08.12
コメント(6)
-

迫田穆成監督の江川攻略作戦
大会史上初の2日連続降雨ノーゲームを経て、ついに決着がついた。◇「史上初、2日連続ノーゲーム」 (2009.8.10) → こちらへ。 今日(8月11日)行われた第4試合、高知高-如水館高戦。高知 120 000 501 =9如水 010 001 010 =3(高)公文、(如)幸野■試合の模様。以下、毎日新聞より。先発投手の制球が明暗を分けた。高知の公文は厳しいコースを突いて14奪三振。如水館の幸野は立ち上がりに球が浮いた。高知は一回2死二塁から木下が先制適時打。二回にスクイズなどで2点を奪って流れを作り、七回に打者9人で5点を加えて試合を決定づけた。 (両監督のコメント)如水館高・迫田穆成監督 「敗因は私にある。3点目を取られてしまったのが本当に痛かった。雨は理由にならないし、気持ちを緩めたつもりもない」 高知高・島田達二監督 「公文は3連投になったが、気持ちが切れなかったのが勝因。思い切って打線を組み替え、選手が期待に応えてくれた」※記事、コメントともに毎日新聞より引用。---------------------------------------------------------------迫田 穆成(さこた よしあき)監督の名前を聞いて、ボクは遠い昔のことを思い出してしまった。それは1973年のセンバツのこと。センバツ・準決勝(1973年4月5日)作新 000 010 000 =1広商 000 010 01X =2(作)江川、(広)佃当時、広島商高を率いていた迫田さんは、怪物・江川卓を擁する作新学院高を倒すことに執念を燃やした人だった。 「江川が打てなくても作新を倒す」とばかりに、この大会の準決勝で相対した時、ちょいと変った戦法を選手たちに強いていた。それは、こんな戦法だった。(以下、wikipediaより引用)「江川との対戦では5回までに100球を投じさせることを考え、試合の前半は特に江川のウィニングショットである、高めのボールになるストレート、吊り球に手を出さないように全選手が外角低目だけを狙って打席に入るよう指示した。打者はみな死球覚悟でホームベースギリギリに覆いかぶった。このため二回まで6者連続でフルカウントまで粘り11三振を奪われたものの8四死球を選んだ」その作戦は奏功し、スコア2-1で見事に勝利を収めた。ただ、監督の采配だけで勝利したわけではない。江川に負けず劣らず、広島商高の選手たちもツワモノぞろいだった。現・法政大監督の金光興ニ、元・広島カープ監督だった達川光男、そしていまは故人となったエースの佃正樹らがいた。金光や佃はその後、法政大に進学。江川と同級生となり、「花の昭和49年組」と呼ばれ、法政大の黄金時代を築いた。 今日も1クリックお願いします
2009.08.11
コメント(4)
-

史上初、2日連続ノーゲーム
こんなおかしなことがあるんだなぁ。今日(8月10日)行われる予定だった夏の甲子園のこと。雨天のため昨日に続き2日連続の中止。しかも第1試合の高知高(高知)-如水館高(広島)は試合が開始されたにもかかわらず、2日間ともに雨天ノーゲームとなった。■以下、毎日新聞より。阪神甲子園球場で行われている第91回全国高校野球選手権大会は10日、前日ノーゲームとなった第1試合、如水館(広島)-高知(高知)戦が2試合連続でノーゲームとなった。五回表の高知の攻撃途中、如水館が6-5とリードしていた段階で雨が強くなり、中断。30分後にノーゲームが宣告された。2試合連続ノーゲームは大会史上初。11日はこの試合が第4試合となり、10日の第2試合以降が1試合ずつ繰り上がる。 試合は高知が二回に3点を先取したが、三回に2点を返した如水館が四回に4点を挙げて逆転。高知が五回、西岡の左越え2ランで1点差とし、さらに1死一塁とした場面で雨のため中断された。前日は如水館が2-0とリードした三回裏終了時点で中断し、ノーゲームとなっていた。(以上、毎日新聞)■ちなみに昨日今日の2試合のスコアは次のとおり。(8月9日)如水館 110高知高 000(3回裏終了降雨ノーゲーム)(両監督のコメント)如水館高・迫田穆成監督 「悲しい顔をするようなことじゃない。甲子園で3イニングの練習ができて喜んでいる。選手たちも伸び伸びとやっていた」 高知高・島田達二監督 「まだ三回だったので、これから立て直していこうと選手に話していた。ノーゲームになってラッキーとは思っていない」 (8月10日)高知高 03002如水館 0024(5回表1死降雨ノーゲーム)(両監督のコメント)高知高・島田達二監督 「攻撃はある程度の対応ができたが、守りは完全に受け身だった。3試合できると思って、切り替えていきたい」如水館高・迫田穆成監督 「先制されて嫌な展開だった。よく逆転してくれたと思う。(翌日の)夕方に試合ができるのは、よく眠れるのでうれしい」※両監督のコメントはすべて毎日新聞より。今日も1クリックお願いします
2009.08.10
コメント(0)
-

沢村栄治にアイスをおごる贅沢
さきほどの続き、沢村栄治のこと。といってもあまりに有名な投手だから、ここでは戦績とか「どんな投手だったか」なんてマジメなことは省略。今日の記事に書くのは、『伝説のプロ野球選手に会いに行く』(高橋安幸著、白夜書房刊)中にある往年の名二塁手・苅田久徳さんへのインタビュー記事にあった、沢村にまつわるエピソードのこと。苅田さん、1935年(昭和10年)2月、職業野球チームが初めて米国に遠征したオールジャパンの一員として渡米した。その遠征、実はあまり予算のないもので、しかも3月2日から始まり、7月まで約100試合をこなす強行軍でもあった。チームの総監督は市岡忠男、監督は三宅大輔、そしてマネジャーとして後にベーブ・ルース招聘と日米野球開催に尽力した鈴木惣太郎(当時、読売新聞社嘱託)が帯同。選手は苅田さんのほか、沢村栄治、ビクトル・スタルヒン、水原茂、二出川延明、山本栄一郎らが参加した。「もう大変だよ。金がなくて。ホテルでも、私らは大先輩だからベッドに寝て、補欠の後輩は床に寝かせた時もあった。ユニフォームバッグを枕にしてね。アラメダで泊まったホテルでは、朝飯代としてたったの25セントしかくれなかった。25セントでどういうものが食えると思う? ハムエッグとパンだけ。コーヒーはタダだったけど。昼間は90セント、夜が1ドル20セント。これを持って日本人の店に行くわけ。そこで天丼が1ドル20セント、親子丼が1ドルですよ」「体が資本」の野球選手にとって、朝がパンとハムエッグ。そして夕食が天丼一杯ではとても体が持たなかったであろうことは容易に察しがつく。「そんな生活をしながら4ヶ月か。旅立つ前はいいこと言いやがってね。『月に一人10ドルは出しますから、小遣いはそれほど持っていかなくて大丈夫』だって。で、行ったらね、くれないの。5セントのアイスクリームも買えない」「もうどうにも我慢できなくなって、わたしが代表で抗議に行った。総監督の市岡のところに。するとその場でとりあえず、10ドルくれたよ。その金で、沢村とスタルヒンにアイスクリームを買ってやったんだよ。(中略)まったく、何度ダマされたかわかんない。とにかく、その頃は悪いヤツがたくさんいたんだよ」(以上、『伝説のプロ野球選手に会いに行く』より)その遠征の貧乏さは、このブログの『米国遠征の夢と財布の中身』(2009.7.9)に書いた。「1935年(昭和10年)、大日本東京野球倶楽部(現・読売の前身)というチームが、職業野球として初めて米国に遠征した時のこと。4ヶ月間にわたり約110試合を行った結果、その収支は次のとおり赤字だった。赤字は絶対許されぬ条件のもとでの遠征だったが、観客数が思ったほど伸びず収入は期待を下回った。そのため選手たちは常に食うや食わずの日々を強いられ、空腹と疲労と過密日程でギリギリの状態だった」苅田さんが言う「悪いヤツ」は誰を指すのかわからないけど、ま、そんな状態だったから、もし市岡さん「悪いヤツ」のひとりに数えるなら、それはちょいと違うかもしれないが。ボクが苅田さんの発言で面白かったのは、「沢村とスタルヒンにアイスクリームを買ってやったんだよ」という言葉。歴史上にその名を刻む名投手2人にアイスクリームを買ってやる! なんてことはとっても羨ましいことで、現代においては最高の贅沢、名誉、そしておしゃれなことだとボクは思った。 --------------------------------------------------------------この記事は『ボクにとっての日本野球史』の中で、次の期に属します。→ (第4期)「1925年(大正14年)、東京六大学リーグ成立、早慶戦復活時以降」◇ 「ボクにとっての日本野球史」 (2009.7.1)、 INDEXはこちらへ。今日も1クリックお願いします
2009.08.09
コメント(0)
-

職業野球、戦前最後の東西対抗
先日、1945年(昭和20年)11月23日に復活した職業野球「東西対抗戦」のスタメンを書いた。今日は、「日本野球連盟勤労報国隊」が主催し1943年(昭和18年)11月に後楽園球場や甲子園球場で行われた東西対抗戦(全6戦)のメンバーを。◇職業野球の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「戦後、職業野球の復活(2)」 (2009.8.1) → こちらへ。※一番左の数字は「背番号」、一番右( )内の数字は当時の年齢。【東軍】(監督)30 中島治康 巨人、早稲田大、(35)(投手)35 藤本英雄 巨人、明治大、(26)18 野口二郎 西鉄、中京商、(24)26 石丸進一 名古屋、佐賀商、(22)17 片山栄次 大和、全静岡、(22)(捕手)22 藤原鉄之助 名古屋、帝京商、(25)25 中村民雄 西鉄、熊本工、(27)(内野手)8 野口 明 西鉄、明治大、(27)12 石丸藤吉 名古屋、佐賀商、(30)2 中村信一 西鉄、法政大、(31)8 白石敏男 巨人、広陵中、(26)32 小鶴 誠 名古屋、飯塚商、(22)8 木村孝平 大和、浪速商(23)(外野手)23 呉 昌征 巨人、嘉義農林、(28)5 加藤正二 名古屋、中央大、(29)15 吉田猪佐喜 名古屋、熊本工、(29)24 古川清蔵 名古屋、鹿児島商、(22)17 西沢道夫 名古屋、養成、(21)【西軍】(監督)30 若林忠志 阪神、法政大、(36)(投手)18 真田重蔵 朝日、海草中、(21)19 内藤幸三 朝日、東京市立商、(28)38 三輪八郎 阪神、高崎中、(23) 17 笠松 実 阪急、横浜専門、(28)(捕手)17 門前真佐人 阪神、広陵中、(27)15 小林章良 朝日、滝川中、(21)(内野手)6 景浦 将 阪神、松山商、(29) 10 藤村富美男 阪神、呉港中、(28)23 中谷準次 朝日、和歌山商、(26)6 酒沢政夫 朝日、育英商、(20)5 上田藤夫 阪急、マウイ高、(31)12 大友一朗 朝日、島田商、(28)(外野手)8 坪内道則 朝日、立教大、(30)22 塚本博○ 阪神、呉港中、(26) 2 下社邦男 阪急、享栄商、(21)15 御園生崇男 阪神、関西大、(33)11 山田 伝 阪急、エリグローブ高、(30)■このメンバー表は『鈴木竜二回顧録』(ベースボール・マガジン社刊)から引用した。同書には次のようなことも記されていた。「この大会で第3戦と第6戦に登板した名古屋の石丸進一、第5戦によく投げた阪神の三輪八郎、同じ阪神の景浦将などはこの試合が最後でついに還らなかった。(中略)この東西対抗戦を最後に多くの選手が軍隊に入り、戦火に散った」また、当時のスター選手たちの多くはすでに戦場に行っており、この「東西対抗戦」には出場していない。大スターだった沢村栄治も残念ながら出場していない。--------------------------------------------------------------この記事は「ボクにとっての日本野球史」の中で、次の期に属します。→ (第4期) 1925年(大正14年)、東京六大学リーグが成立し、早慶戦が復活した時以降 ◇ 「ボクにとっての日本野球史」 (2009.7.1)、 INDEXはこちらへ。今日も1クリックお願いします
2009.08.09
コメント(0)
-

高校野球、監督の引き際
夏の高校野球、第1日目(1回戦)。■九州国際大付高(福岡) 8-4 常総学院高(茨城)常総 211 000 000 =4九州 002 500 100 =8(常)小熊-飯野、(九)納富 この試合、開幕戦ということだけでなく、若生正広(九州国際大付高)と木内幸男(常総学院高)の「監督どうしの再戦」という意味でも注目を集めた。再戦の「再」とは、(言うまでもなく)2003年夏の甲子園決勝戦以来ということ。この時の結果は、若生さんが率いた東北高が木内さんの常総学院高にスコア2-4で敗戦。東北人念願の「白河越え」の夢は、ダルビッシュ有(現・日本ハム)を擁してさえも叶わない、ボクにとってもとても残念な試合だった。■まず、若生さんのこと。今日の試合後のコメント。「めちゃくちゃうれしいね。(序盤は)この調子だと何点取られるのかと思ったが、納富がよく立ち直った。今日は納富に尽きるね」以前、明治神宮大会(だったかな?)の観客席で若生さんを見かけたことがある。あちこちから「若生さん、若生さん」と声をかけられ、気さくに応じる人懐こそうな表情は、テレビで見る笑顔そのまんまだった。若生さん、常総学院高に敗戦後、2005年に九州国際大付高の監督に就任し、今回の甲子園大会に見事に出場を果たした。埼玉栄高、東北高の監督を歴任し次々に強豪校を作り上げた実績もある。チームが関東だろうと東北だろうと九州だろうと、高校野球への情熱はまるで衰えないように見える。と、ここまで書いて別のことを思い出した。それは、先日行われた日米大学野球で活躍した九州国際大の加藤政義(4年)のこと。加藤は東北高の出身なのに、なぜはるか遠方の九州国際大に進学したのか、ボクには不思議でならなかった。だが、その裏には若生さんの存在があったからだろうか。ボクはひとり勝手に想像して、そう納得してしまった。■そして木内さんのこと。今日の試合後のコメント。「力の差が大き過ぎた。小熊は勝ちたくなったんでしょうね。四球を出して、リズムを崩してしまった。経験不足だった」序盤に4点を先制しながら逆転されたのだから、先発投手・小熊への怒りもあるのかもしれない。でも「勝ちたくなかった」という発言は、それを聞く小熊にとっては結構キツイはず。木内さん、若生さんと決勝を戦い甲子園優勝を機に勇退(2003年)した。ボクは木内さんのことをほとんど知らないけれど、仮に「木内語録」なるものを集めたら、前出のような発言は事欠かない人のように思える。真っ先にボクが思い出すのは、2007年夏の甲子園大会で初戦敗退した常総学院高の持丸修一監督(当時)に対し、すでに監督を勇退していた木内さん(当時、総監督)が言い放った言葉。「(いまの常総学院は)甲子園に出ることが精一杯のチーム、甲子園で勝てるチームになっていない。エース・清原大貴投手を最後まで引っ張る監督の采配はおかしい、優しすぎる。甲子園で勝ち続けるためには、非常な采配も必要」その言葉の直後、勇退したはずの木内さんは、持丸さんを追い出す格好で再び監督に復帰した。だがその後の戦績も芳しくない。翌08年夏、甲子園に出場したものの初戦敗退(関東一高にスコア5-13で大敗)。そして、残念ながら今年も初戦敗退である。ボクはつい余計なことを心配してしまう。それは、「名将・木内監督の花道」のこと。前監督に対して上記のように痛烈な批判を浴びせた以上、甲子園での初戦敗退が続けば、周囲が花道を用意できない状態に陥ってしまう。たしか今年78歳の高齢でもあり、冷静に考えれば監督業を今後長く続けることは不可能だ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。もちろん「花道」がなければいけないものではない。本人も望んでいないのかもしれない。ただ「あの時、復帰していなければ」という話が後々出るようだと、寂しいように思う。◇木内幸男の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「甲子園、初戦敗退で監督交代劇」 (2007.8.15) → こちらへ。「常総学院高・木内幸男監督、意気軒昂」 (2007.9.16) → こちらへ。「常総学院高、甲子園で初戦敗退」 (2008.8.5) → こちらへ。今日も1クリックお願いします
2009.08.08
コメント(2)
-

戦後、高校野球の復活
今日(8月8日)、夏の甲子園大会(第91回全国高等学校野球選手権大会)が開幕した。ここ数日間、職業(プロ)野球や東京六大学野球の「終戦後の復活」について記してきたので、今日は「高校野球」のことをメモしておきます。◇戦後、大学野球の復活の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「大学野球復活を一番願った人」 (2009.8.4) → こちらへ。◇戦後、職業野球の復活の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「東西対抗戦の背景」 (2009.8.1) → こちらへ。------------------------------------------------------------高校野球(当時は旧制中学)が甲子園で復活したのは1947年(昭和22年)の春(センバツ大会)、3月30日のこと。正式名称は『選抜中等学校野球大会第19回大会』。4月7日までの9日間、26校が出場して開催された。■当時の様子は『真説・日本野球史 昭和篇その五』(大和球士著、ベースボール・マガジン社刊)に詳しい。「開会式には、占領軍大阪軍政部長、民間情報教育部長メリット少佐の祝辞あり、大会を祝福して上空に舞ったのが、米25師団所属軽翼L5機、機上から始球のボールが落とされた・・・眼を水平に向けても、空を仰いでも、敗戦の爪跡は余りにもナマナマしい。それを忘れようとして、超満員6万の大観衆は、第1試合の開始を告げる主審森田のプレーボールの声に万雷の拍手」※「戦争の爪跡」とは、甲子園名物の銀傘が戦時中に撤去されてなくなってしまった風景のこと。また占領軍が依然として内・外野のスタンド下に宿泊していて、「進駐軍専用席」が設けられ多くの米軍兵士が観戦していたなど、それまで日本人の観客らが経験したことのないスタンドの異様な風景などを指している。この当時までの甲子園は米軍に接収されていて、日本人の意のままに使える状況ではなかった。このセンバツ大会の開催前に接収が一部解除になり、初めて挙行されたもの。米軍兵士たちが多く観戦し「専用席」があったのはそういった事情が反映している。■戦時中の甲子園の様子について、『球団消滅 幻の優勝チーム・ロビンス』中野晴行著、筑摩書房刊)が少しだけ触れていた。(当時のいわゆるオープン戦である)「試合は阪神・産業合同の猛虎軍と阪急・朝日の隼軍の間で、昭和20年(1945年)1月1日から5日まで、甲子園球場と西宮球場を舞台にして行われている。真冬で、交通事情も悪く、いつ空襲が来るかもわからない状況であったにもかかわらず、観客はちゃんとやってきた」「金属供出のために名物の銀傘をはぎとられてむき出しの姿になった甲子園球場のスタンドで、国民服や防空頭巾姿で寒そうに観戦する観客たち・・・」「アメリカ軍の艦戴機が、阪神間の飛行場や港、民家などを爆撃したのは、それからほぼ3カ月後、3月19日のことである。爆弾は甲子園球場にも落とされた」--------------------------------------------------------------この記事は「ボクにとっての日本野球史」の中で、次の期に属します。→ (第5期) 1946年(昭和21年)、終戦後、東京六大学リーグ・職業野球が復活した時以降 ◇ 「ボクにとっての日本野球史」 (2009.7.1)、 INDEXはこちらへ。今日も1クリックお願いします
2009.08.08
コメント(0)
-

大学野球復活を一番願った人
昨日の続き。前回、戦後間もない1945年(昭和20年)10月28日、「オール早慶戦」が開幕したのを皮切りに大学野球が復活を遂げた、と書いた。そこで一番の疑問は、用具はどうしたのだろう? ということ。なにせ、「職業野球(東西対抗戦)が復活した時は肝心の用具がなく、鈴木竜二日本野球連盟会長(当時は専務理事)が西宮にあった4ダースのボールをリュックに詰め、死に物狂いで東京に運んできた」のである。大学野球だって事情は似たり寄ったりだったろう。そうボクは思っていた。◇鈴木竜二の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「鈴木竜二が必死になって運んだ4ダースのボール」 (2009.8.1) → こちらへ。ところが、大学野球はちょいと事情が違っていた。早稲田大野球部が戦中もきっちりと道具を守っていたのだ。書籍『早慶戦100年 激闘と熱狂の記憶』(富永俊治著、講談社刊)にそのへんのことが詳しく書かれている。きっかけを作ったのは飛田穂洲のひとこと。「今は戦争で野球がやりにくい時代だけど、戦争が終わりさえすれば、すぐに野球の時代がやってくる。その時に肝心の用具がなかったら、野球そのものがやれないよなぁ」飛田の命を受けたのは当時マネージャーだった相田暢一。慌てて用具を買い集めた。そして相田が出征後は、昭和19年度の主将・吉江一行が管理を引き継ぎ、まさに用具を「死守」した。「空襲警報発令のサイレンが鳴るや、まだ合宿所に残る数人の部員たちと手分けをしてバットやボールを敷地内の防空壕に運び込み、警報解除とともに、今度は部員たちの手渡しで用具を倉庫に戻す重労働を繰り返した。晴れた日には湿気を取るための虫干しも」行っていた。そんな吉江らの労苦があったから、戦後すぐに大学野球が復活したとも言える。吉江主将には悲しい後日談がある。終戦直前、とうとう吉江は戦場に送り込まれることになる。そして戦場で病を患い、その病気がもとで戦後間もなく故郷の福島県で亡くなってしまった。先に「死守」と書いたのはそういった事情があったから(多少の語弊はあるが)。大学野球を復活させるため命を捧げたような人だった。残念ながら「大学野球が復活した試合」を目にすることはなかったんだろうなぁ。--------------------------------------------------------------この記事は「ボクにとっての日本野球史」の中で、次の期に属します。→ (第5期) 1946年(昭和21年)、終戦後、東京六大学リーグ・職業野球が復活した時以降 ◇ 「ボクにとっての日本野球史」 (2009.7.1)、 INDEXはこちらへ。今日も1クリックお願いします
2009.08.04
コメント(0)
-

オール早慶戦が11月開幕
東京六大学野球の早大と慶大の現役、OB混成チームによるオール早慶戦(両大学野球部主催、毎日新聞社など後援)が11月23日、兵庫県西宮市の阪神甲子園球場で行われる。オール早慶戦は不定期に行われているが、甲子園での開催は53年ぶりとなる。 早大3年の斎藤佑樹投手も出場予定。引き分け再試合となった決勝で駒大苫小牧・田中将大(楽天)との投げ合いを制し、早稲田実を初優勝に導いた06年夏以来、3年3カ月ぶりに甲子園のマウンドに立つ。斎藤は「甲子園優勝は今の自分の原点。一つの試合の大切さとチームメートの素晴らしさを教えてくれた甲子園に戻るということで今から楽しみ」とコメントした。(毎日新聞)-----------------------------------------------------------戦後のことでいえば、職業野球が復活したのは1945年(昭和20年)11月23日、神宮球場で開催された東西対抗戦だった。一方、戦後において東京六大学野球の復活のノロシとなったのは、同年10月28日に開かれた「オール早慶戦」だった。(リーグ戦が開始したのは翌1946年5月19日)場所は同じ神宮球場(但し、当時の神宮は進駐軍に接収されていて「ステート・サイド・パーク」と呼ばれていたが)。 この試合、終戦直後の大混乱期に開催されたにもかかわらず、4万5千人の大観衆が詰め掛けた。神宮球場で行われるのは1942年(昭和17年)以来5年ぶりではあったが、内野席を超満員にし、外野席も7割がたが埋まったという。『真説・日本野球史』(大和球士著、ベースボール・マガジン社刊) には、こう記してある。「一体どこから4万5千人もが集まってきたのであろうか。(中略)単純な野球愛というよりは、敗戦から立ち上がろうとする日本人の活力の発露と見る。野球人に強靭な精神力があったことは頼母しく、日本人に祖国再建の活力がみなぎっていたことはいよいよ頼母しい限りである。野球人、野球ファンが『ニ位一体』となって野球復活は快速調に進むことになる」--------------------------------------------------------------この記事は「ボクにとっての日本野球史」の中で、次の期に属します。→ (第5期) 1946年(昭和21年)、終戦後、東京六大学リーグ・職業野球が復活した時以降 ◇ 「ボクにとっての日本野球史」 (2009.7.1)、 INDEXはこちらへ。今日も1クリックお願いします
2009.08.03
コメント(0)
-

大下弘の少年・学生時代のこと
前回の記事の続き。 大下弘。西鉄ライオンズの黄金時代(1950年代後半)には「不動の4番打者」。『打撃の神様』と呼ばれた川上哲治氏が『赤バット』、その好敵手として大下は『青バットの大下』と尊敬の念をもって呼ばれていた。豪放な性格の持ち主で「二日酔いながら7打席連続安打の記録を作った」という逸話もある。小学生時代は神戸小学校に所属し、同じ神戸にあった楠小学校の別所明(のち毅彦)と対戦したことがある。そして中学生時代(1936年)、母親の仕事の関係で生まれ育った神戸を離れ台湾に渡る。入学した学校はこの年に新設されたばかりの高雄商高。当時台湾の野球の名門は嘉義農林(かぎのうりん)であり、甲子園のファンを沸かせていたから、大下の存在は誰にも知られていない地味な存在だった。※嘉義農林のOBには、後の東西対抗戦(1945年11月23日)で西軍の1番を打った呉昌征(1942年までの名前は呉 波)がいる。但し、呉は大下の6歳上であり、直接対戦したことはない。そんな無名の大下を明治大に誘ったのは、明治大OBであり当時の都市対抗チーム「オール台北」の監督だった渡辺大陸。それは大下の「剛球」に目を奪われたことがキッカケだった。ただ1941年、わざわざ台湾から明治大にやってきても、大下のやることは球拾いばかり。リーグ戦に一度も出場することもなく、航空隊に志願して戦場に向かった。※この頃、神宮にはお互いの小学生時代を知る別所(当時・日本大)がいた。甲子園で活躍してすでに名を馳せていた別所。その頃、2人の置かれた立場には大きな開きがあった。大下は別所にこんな言葉をかけている。「別にオレは大選手じゃないし、飛行機乗りが一番てっとり早く死ねるから、飛行機乗りになるよ」(『昭和20年11月23日のプレイボール』鈴木明著、光人社刊より)■大下、公式戦に出場したことはないが、一度だけ立教大との対抗戦(非公式戦)に出場したことがある。それは1943年4月7日に文部省から「六大学リーグ戦」解散命令が出た後、各校が細々と続けていた(公式戦ではない)いわば練習試合のような試合での出場だった。その試合は1943年(昭和18年)5月23日に行われた。8回表、代打で登場した大下は右越えの二塁打を放ち、走者2人が生還。同点に追いつく貴重な殊勲打となった。だがその後、立教大が1点を挙げて勝利。そしてこの試合を最後に明治大野球部は解散、明大にとって戦前最後の試合となった。※『真説・日本野球史』(大和球士著、ベースボールマガジン社刊)を見たら、その試合のメンバー表が記載されていた。そして立教大の5番打者には、主将で一塁を守る西本幸雄の名前があった。西本さんはその後繰り上げで卒業し、中国の戦場に向かったはずだから、西本さんにとっても学生最後の試合になったのかもしれない。◇西本幸雄の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「西本幸雄の立教大時代」 (2009.3.22) → こちらへ。--------------------------------------------------------------この記事は「ボクにとっての日本野球史」の中で、次の期に属します。→ (第4期) 1925年(大正14年)、東京六大学リーグが成立し、早慶戦が復活した時以降 ◇ 「ボクにとっての日本野球史」 (2009.7.1)、 INDEXはこちらへ。今日も1クリックお願いします
2009.08.02
コメント(0)
-

東西対抗は大下弘がMVPに
前回の記事の続き。 東西対抗戦の戦績を、少しだけ触れておきます。(第1戦)1945年11月23日、神宮球場■東軍 13-9 西軍戦中、明治大の学生だった大下弘がいきなり東軍のスタメンに名を連ねた。しかも5番打者として。そしてこの大下が左中間フェンスに直接打球を当てる三塁打を放ち、観客の度肝をぬいた。この試合のオーダー表 → こちらへ。「度肝を抜いた」とは、決してオーバーな表現ではない。当時の神宮球場、現在より4~5mほど大きく、特に左中間や右左間が深く作られていた。そのため戦前の東京六大学野球でも、滅多に本塁打が出ることはなかった。後のスーパースター・長嶋茂雄さんでさえも、立教大時代にこの神宮で打った本塁打数は4年間で8本に過ぎなかった(ただ、しばらくはこの8本がリーグの最多本塁打記録だったが)。(第2戦)同年11月24日、新川球場(群馬県桐生市)■西軍 14-9 東軍(第3戦)同年12月1日、西宮球場■西軍 9-6 東軍(第4戦)同年12月2日、西宮球場■東軍 4-0 西軍戦後初めて行われた職業野球(東西対抗戦)は、両軍とも2勝2敗の成績で幕を閉じた。そして最高殊勲選手賞と首位打者賞は、15打数9安打と打ちまくった大下弘が受賞、賞金(合計200円也)を受け取った。(参考:『昭和20年11月23日のプレイボール』鈴木明著、光人社刊)大下弘。明治大野球部の出身と先に書いたが、下級生だったため球拾いばかりで、東京六大学の公式戦に出場経験はない。戦後に復学した際、明大グラウンドで大飛球をポンポン打ち上げる大下に横沢三郎さん(戦前のセネターズで活躍した明治大の先輩)が目をつけ、大下を職業野球の世界に導いた。 契約したのは45年(昭和20年)10月だったというから、東西対抗戦が開催されるわずか1ヶ月前のこと。観客も選手たちも、だれも大下の名前を知らないまったく無名の選手だった。後にこの大下が日本の野球ファンに「ホームラン」の素晴らしさを伝える「伝道師」になることなど、この時点では誰も気づいていなかった。 (参考:『ジャジャ馬一代 遺稿・青田昇自伝』青田昇著、ザ・マサダ刊)--------------------------------------------------------------この記事は「ボクにとっての日本野球史」の中で、次の期に属します。→ (第5期) 1946年(昭和21年)、戦後、東京六大学リーグ・職業野球が復活した時以降 ◇ 「ボクにとっての日本野球史」 (2009.7.1)、 INDEXはこちらへ。今日も1クリックお願いします
2009.08.02
コメント(0)
-

東西対抗戦の背景
前回の記事の続き。戦後復活した職業野球は、1945年(昭和20年)11月22日、神宮球場を皮切りに、桐生、西宮(2試合)を転戦し、つごう4試合が行われた。■その当時のことを青田昇氏が『ジャジャ馬一代 遺稿 青田昇自伝』(青田昇著、ザ・マサダ刊)で次のように記している。「それにしても、この東西対抗戦、あの戦後の混乱期の中で、よくぞ挙行し得たものだと思う。東京も大阪も満目荒涼(まんもくこうりょう)たる焼け野原。巷には浮浪児とパンパン(街娼)と復員兵があふれ、闇市に人々が列をなして、一杯の汁を争って得ていた時代だ。『なんとしても野球を復活させたい』という熱病のような思いがなければ、実現できるものではない。」「野球の試合をやろうにも、東京にはボールもなければバットもない。そこで当時、一番戦前のボールを保有していたわが阪急が、ボール4ダースを提供することになった。しかしこのボールを東京まで運ぶのが容易ではない。今日のように宅急便で送れば、明日には届いているといった時代ではない。列車という列車は足の踏み場もない超満員。タラップに4、5人がぶら下がっている、といった現代では想像もつかぬ風景である」「このボール運びの役を買って出たのが鈴木竜二日本野球連盟会長(当時は専務理事)だった。会長は4ダースのボールをリュックに詰め、死に物狂いで東京に運んできた」 ※「なんとしても野球を復活させたいといった熱病のような思い」。その思いをもった中心人物は、小西得郎であり、鈴木竜二だった。ボクのこれまでの認識では、小西得郎さんといえば江戸弁で名調子の解説をする面白いおじいさんだった。そして鈴木竜二さんといえばセ・リーグの会長として読売グループの番頭役をそつなく務めた人(多少の皮肉を込めて)としか思っていなかった。だけど、この人たちが職業野球の復活に大きな貢献をしたことをボクは初めて知った。 ※ 「わが阪急」。え、わが阪急? 「青田さんは巨人の選手だった」。これがボクのこれまでの認識だった。ところが、上記のとおり「わが阪急」という表記があって、ボクは初めてこの書籍を読んだ時には驚いたものだった。調べてみると、青田さんは滝川中を中退し、すぐさま1942年(昭和17年)に東京巨人軍に入団している。そして44年(昭和19年)、陸軍航空隊に志願して巨人軍を退団。その際、時のオーナーだった「大正力」こと正力松太郎から、「戦争が終わったらまた巨人に戻ってこい」と言われ、青田さんもそのつもりで退団した。ところが終戦後、巨人は球団の体制復帰が遅れ、逆に早期に復帰のメドが立った阪急に声をかけられ、一時的に在籍(46年~47年)した経緯があった。そして48年、三原脩監督に呼び戻され、青田さんは巨人に復帰した。青田さん、この一時的な阪急への移籍があったため、 「戦後、チームを代わった者は、出場資格なし」というルールに抵触。出場が叶わなかった青田さんは寂しくスタンドから試合を観戦していた。◇三原脩の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「三原脩、職業野球選手になった頃」 (2009.7.14) → こちらへ。--------------------------------------------------------------この記事は『ボクにとっての日本野球史』の中で、次の期に属します。→ (第5期) 1946年(昭和21年)、戦後、東京六大学リーグ・職業野球が復活した時以降 (第5期)に属する他の記事は以下のとおり。◇ 「ボクの日本野球史」 (2009.7.1) → こちらへ。「西本幸雄、職業野球選手になった頃」 (2009.7.18) → こちらへ。「関根潤三、職業野球選手になった頃」 (2009.7.18) → こちらへ。「豊田泰光、職業野球選手になった頃」 (2009.7.19) → こちらへ。「戦後、職業野球の復活」 (2009.7.24) → こちらへ。「戦後、職業野球の復活(2)」 (2009.8.1) → こちらへ。今日も1クリックお願いします
2009.08.01
コメント(0)
-

戦後、職業野球の復活(2)
1945年(昭和20年)11月23日、「職業野球」が再開した。その試合のことを。■その試合のオーダーを7月24日のブログに記しましたが、選手たちの当時の所属球団名がわかったので(『ジャジャ馬一代 遺稿・青田昇自伝』(青田昇著、ザ・マサダ刊)、それを引用・追加しあらめて次に記します。【東軍】監督 横沢三郎1番(8)古川清蔵(名古屋)2番(6)金山次郎(名古屋)3番(4)千葉 茂 (巨人)4番(7)加藤正二(名古屋)5番(9)大下 弘(セネターズ)6番(2)楠 安夫(巨人)7番(3)飯島滋弥(セネターズ)8番(5)三好 圭(巨人)9番(1)藤本英雄(巨人)、白木儀一郎(セネターズ)※大下のことは後日、詳しく書きます。【西軍】監督 藤本定義1番(8)呉 昌征(阪神) 2番(6)上田藤夫(阪急)3番(4)藤村富美男(阪神)4番(5)鶴岡一人(近畿)5番(3)野口 明(阪急)6番(2)土井垣 武(阪神)7番(9)岡村俊昭(近畿)8番(7)下社邦夫(阪急)、本堂保弥(阪神)9番(1)笠松 実(阪急)、別所明(近畿)、丸尾千年次(阪急)※別所明・・・のち毅彦。戦前の「職業野球」での活躍度からすると、青田昇氏が参加していないのは不思議ではある。ただ戦前に「巨人」に在籍し、戦後すぐに「阪急」に所属したため、「戦後、チームを代わった者は、出場資格なし」というルールに抵触し、青田さんは寂しく球場から試合を観戦していた。◇青田昇の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「青田昇さん、遅すぎた殿堂入り」 (2009.1.15) → こちらへ。--------------------------------------------------------------この記事は『ボクにとっての日本野球史』の中で、次の期に属します。→ (第5期) 1946年(昭和21年)、戦後、東京六大学リーグ・職業野球が復活した時以降 (第5期)に属する他の記事は以下のとおり。◇ 「ボクの日本野球史」 (2009.7.1) → こちらへ。「西本幸雄、職業野球選手になった頃」 (2009.7.18) → こちらへ。「関根潤三、職業野球選手になった頃」 (2009.7.18) → こちらへ。「豊田泰光、職業野球選手になった頃」 (2009.7.19) → こちらへ。「戦後、職業野球の復活」 (2009.7.24) → こちらへ。今日も1クリックお願いします
2009.08.01
コメント(0)
-

沖縄を訪ね、思い出したこと
先週日曜日(7月26日)から約1週間、沖縄へ。首里に行く途中、モノレールから(この夏甲子園に出場する)興南高校野球部のグラウンドが見えた時には、ただそれだけなのに不思議と興奮した。なぜかボクは、強豪高のグラウンドとかユニフォームとか、そういったものをナマで見ると嬉しくなる習性があるらしい。数年前、関東大会で初めて東海大相模高のユニフォームを見た時も同じように興奮したし、埼玉・浦和学院高のグラウンドを初めて見た時もひどく感動したっけ。----------------------------------------------------------------以前、NHKが現ロッテ・大嶺祐太の高校時代を特集していたことがあった。興南高のグラウンドを見、これまでの記憶をたどっている内、ボクはその番組のことを思い出していた。それは沖縄・八重山商工高に埼玉・浦和学院高から「野球の厳しさ」を教えられた逸話だった。大嶺のいた八重山商工高、それなりに全国的な注目を集めるチームではあったけど、離島育ちの高校生といった特性のせいか、朝寝坊や練習をさぼる選手たちが当たり前のように存在する、「生ぬるい空気」をもったチームでもあった。業を煮やした伊志嶺吉盛監督は、「野球の厳しさを教えないことには全国で勝ち進むことはできない」と考え、全国レベルにある学校の練習風景を選手たちに直(じか)に見せることを決断した。見学に選んだ先は、沖縄から遥か約1600kmも離れた埼玉の浦和学院高。遠征費用をどうにか工面して訪れた浦和学院のグラウンド。八重山商工高のナインは、浦学選手たちの練習風景や姿勢を見て目を丸くした。全国的に強豪と呼ばれる高校は、いつもこんなに厳しい練習をやっているものなのか!?と。沖縄に戻った後は、これまでの自分たちの練習態度を素直に反省し、新たな気持ちで練習に取り組んだ。その結果、八重山商工は2006年春夏の甲子園に連続出場(2006年)を果たしたのだった。◇沖縄の高校野球部の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「1958年、捨てられた甲子園の土」 (2007.5.8) → こちらへ。「首里高・仲宗根弘さん(68歳)」 (2008.8.1) → こちらへ。◇高校野球、沖縄vs埼玉の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「沖縄水産高・新垣渚vs埼玉栄高・大島裕行」 (2007.4.14) → こちらへ。今日も1クリックお願いします
2009.08.01
コメント(0)
全36件 (36件中 1-36件目)
1