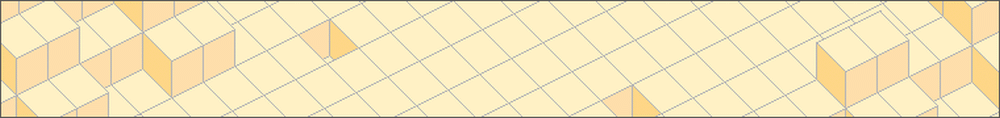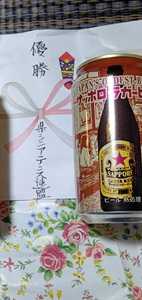2009年07月の記事
全36件 (36件中 1-36件目)
1
-

二松学舎、明日帝京と再戦
7月25日、高校野球・東東京大会の準々決勝が行われた。注目の帝京高は駒場学園高に6-1で勝利、また二松学舎大付高は都総合工科高にスコア4-3でサヨナラ勝ちした。その結果、準決勝は帝京高と二松学舎大付高が対戦することになった。(この試合が事実上の決勝戦でなかろうか? そうボクは思っている)実は今年(2009年)の春季大会・準々決勝でも、この両高の対戦(4月18日、神宮第2球場)があり、たまたまボクはこの試合を観戦していたことを思い出した。(7回コールド)帝京 006 000 1 =7二松 000 000 0 =0(帝)武内、(二)小野田、鈴木大この試合、二松学舎にとってはあまりに悲惨な負け方だった。帝京の3番・平原庸多に2本塁打を浴び、打撃では、背番号「13」をつけた武内就生に(7回ながら)ノーヒットノーランに抑えられた。平原の打球は速く、その点において他の選手を圧倒していたのが印象的だった。この時は三塁を守っていたが、この夏の大会では新エースでもあるらしい。どうやら平原、「投打」にずば抜けたセンスをもつ選手のようだ。ただ「投打」にずば抜けた選手なら二松学舎にもいる。それは京屋陽(きょうや・あたる)。少年時代から常に4番でチームのエースだった。もちろん長打力は抜群。また今春からショートを守っているが、本職は投手。最速は145kmとか。明後日(7月27日)の準決勝、京屋陽と平原庸多の「投打の対決」にぜひ注目したい。そして京屋の勝利をボクは期待する!今日も1クリックお願いします
2009.07.25
コメント(0)
-

聖望が本庄一を破り準決勝へ
埼玉高校野球・準々決勝。聖望学園高vs本庄一高戦を観戦した。聖望学園高は昨年(2008年)のセンバツで好投手・大塚椋司(現・新日本石油ENEOS)を擁して準Vの実績をもつ。一方の本庄一高もブラジル人留学生の奥田ペドロや伊藤ディエゴらの活躍で昨夏の北埼玉大会(記念大会)に優勝、甲子園に出場した実績がある。「全国区」の注目を集めるチームどうしの対決となった。◇大塚椋司の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「新日本石油・大塚椋司が絶好調だ」 (2009.4.7) → こちらへ。◇奥田ペドロの関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「本庄一・奥田のサヨナラ打」 (2008.8.5) → こちらへ。本庄一 003 000 000 =3聖望学 002 110 00X =4(本)萩原-伊藤、(聖)佐藤スコア0-0のまま迎えた3回表、守備の乱れが引き金となって試合が動いた。無死満塁のチャンスに、本庄一の3番・田村和麻は平凡な三塁ゴロ。だが聖望の三塁手・小島尚幸が打球を右手の指に当ててボールを前にこぼした。それでも本塁は十分に走者をフォースアウトできるタイミングだったが、小島の送球は待ち構える河合賢人捕手のはるか頭上を通過・・・。これでニ塁走者までも生還し、本庄一が2点を先制した(その後も捕手の野選があり、3点目を追加)。3点差を追う聖望は、その裏、すぐさま反撃に出る。二死一・三塁のチャンスをつかむと、4番・城戸愉快と5番・西村凌が連続適時打を放ち2点を挙げた。なおも続く4回裏、一死一・三塁のチャンスで1番・佐々木健介の一塁ゴロの間に1点を追加し、聖望が同点に追いついた。勝敗が決したのは5回裏、聖望の攻撃だった。安打と四球で作った無死一・二塁のチャンスに送りバントで確実に走者を進める(一死二・三塁)。そして先ほど悪送球をして先制点を献上するきっかけを作った小島が打席に入る。本庄一はエースの伊藤ディエゴをマウンドに送る。聖望・小島と本庄一・伊藤の対決。初球ストライクの後、小島は2球目を叩いて左中間に大きな犠飛を打ち上げ、貴重な1点を挙げ、これが準決勝進出を決める決勝打となった。小島尚幸、3回の守備ではグラブの前に右手が出て、打球をまともに指に当てたように見えた。それ以降は「つき指」の痛みに耐えながらのプレーだったと思う。それでも、自分のミスをちゃんと自分でリカバーしたのだから立派だった。さて、プロ注目の本庄一・奥田ペドロ。この選手を見たのは何度目だかボクは憶えていないけれど、打撃・守備ともにセンスを感じるプレーヤーだ。今日で高校野球は終わったけれど、次は今秋のドラフト指名を待つことになるのだろうか。今日も1クリックお願いします
2009.07.25
コメント(0)
-

戦後、職業野球の復活
先ほどの続き。そして「職業野球」が再開されたのは、1945年(昭和20年)11月23日。日本という国がこれからどうなるのかわからない、そして食料も物資も不足し、人々はただ生きていくこと自体が大変だった頃、職業野球は奇跡的に早々の復活を果たした。※東京六大学リーグの戦後の復活は、1946年(昭和21年)5月19日。但し、OB戦等は除く。ただ多くの選手たちは戦場にかりだされ、記念すべき復活試合に出場できる選手の数は少ない。苦肉の策として、2チーム分の選手がいれば試合ができる「東西対抗」という方法で開催された。細かなことはさておき、その試合のオーダーは次のとおり。以下、『昭和20年11月23日のプレイボール』(鈴木明著、光人社刊)より。【東軍】監督 横沢三郎1番(8)古川清蔵2番(6)金山次郎3番(4)千葉 茂 4番(7)加藤正二5番(9)大下 弘6番(2)楠 安夫7番(3)飯島滋弥8番(5)三好 圭9番(1)藤本英雄、白木儀一郎【西軍】監督 藤本定義1番(8)呉 昌征 2番(6)上田藤夫3番(4)藤村富美男4番(5)鶴岡一人5番(3)野口 明6番(2)土井垣 武7番(9)岡村俊昭8番(7)下社邦夫、本堂保弥9番(1)笠松 実、別所明、丸尾千年次 ※当時の所属球団も含めたオーダー表は、こちらにあります。---------------------------------------------------------この記事は『ボクにとっての日本野球史』の中で、次の期に属します。→ (第5期) 1946年(昭和21年)、戦後、東京六大学リーグ・職業野球が復活した時以降(第5期)に属する他の記事は以下のとおり。◇ 「ボクの日本野球史」 (2009.7.1) → こちらへ。「西本幸雄、職業野球選手になった頃」 (2009.7.18) → こちらへ。「関根潤三、職業野球選手になった頃」 (2009.7.18) → こちらへ。「豊田泰光、職業野球選手になった頃」 (2009.7.19) → こちらへ。「三原脩、職業野球選手になった頃」 (2009.7.19) → こちらへ。「西鉄、稲尾和久vs和田博実」 (2009.7.7) → こちらへ。「西鉄ライオンズ「黒い霧」事件」 (2009.7.10) → こちらへ。 今日も1クリックお願いします
2009.07.24
コメント(0)
-

戦前、「最後の職業野球」
『最後の早慶戦』が戸塚球場で行われたのは1943年(昭和18年)10月16日のこと。当時は東京六大学野球こそが野球の「花形」であり、常に注目の的だった。一方の職業野球といえば、あくまでマイナーなスポーツであって、そのファンの数は、ほんの微々たるものだった。でも職業野球は、その『最後の早慶戦』が行われた後も1944年(昭和19年)9月まで続いていた。野球連盟の名称を「日本野球連盟」から「日本野球報国会」に変え、最後の試合の大会名を「総進軍優勝大会」(同年9月17日から3日間、於・後楽園球場)と世情に迎合したふりをしながら、細々と生き永らえていたのだ。「総進軍」という名前こそ勇ましいものの、実情は寂しいものだった。なにせ選手たちの多くは戦場にかりだされ、残っている選手は少なかった。当時残っていたチームは巨人、阪神、阪急、産業、朝日、近畿日本の6チーム。ところが、(阪神を除き)どのチームも9人のメンバーすら揃っていなかった。やむなく、「阪神・産業」「阪急・近畿日本」「巨人・朝日」と2つのチームが合体して3チームを作り2回戦総当たり12ゲームを行った。この年の6月15日には米軍がサイパン島へ攻撃を開始。3週間後には3万1629名の日本軍が、嵐のような米軍の攻撃の前に死んでいった。(『昭和20年11月23日のプレイボール』鈴木明著、光人社刊より引用)そんな大混乱を極めた時代だった。なのに東京のど真ん中(後楽園)で職業野球は行われていた。いつ爆撃されるかわからない、そんな状況下での強硬開催だった。なぜ強硬開催されたのか。それは何人かの男たちの「職業野球を続けたい、いや、続けなければならない」といった意地が支えたものだということを前出の『プレイボール』でボクは知った。市岡忠男、小西得郎、鈴木竜ニ・・・。※ただ、なぜ『職業野球』に彼らがそれほどまでにこだわったのか。前出の書籍を読んでも、その理由をボクは知ることができなかった。少なくても金儲け目当てではないだろうし、有り体の『男のロマン』などと呼んでも、ちょっと違う気がするし。いずれ、その点についてはもっと調べてみたいと思う。 ----------------------------------------------------------------- この記事は『ボクにとっての日本野球史』の中で、次の期に属します。→ (第4期)1925年(大正14年)、東京六大学リーグが成立し、早慶戦が復活した時以降◇ 「ボクの日本野球史」 (2009.7.1) → こちらへ。「プロ野球、創設プラン」 (2009.7.5) → こちらへ。「職業野球選手の社会的地位」 (2009.7.8) → こちらへ。「米国遠征の夢と財布の中身」 (2009.7.9) → こちらへ。「三原脩、職業野球選手になった頃」 (2009.7.19) → こちらへ。 今日も1クリックお願いします
2009.07.24
コメント(0)
-

川上哲治のファンサービス
読売巨人軍をV9に導いた川上哲治監督のこと。「打撃の神様」「ボールが止まって見える」「哲(鉄)のカーテン」「石橋を叩いても渡らない」などなど、川上さんを表す言葉は様々ある。ただボクが今まで知らなかったエピソードが『伝説のプロ野球選手に会いに行く』(高橋安幸著、白夜書房刊)に書いてあって、それがとても面白かった。「野球」に対しての洞察が面白く、またミュージシャンでもある大瀧詠一さんが川上さんに関する逸話をいくつか紹介していた。例えば、こんなこと。「川上さんの野球はつまらない」と当時はよく言われていた。その代表的な例に「初回から送りバントをする」戦法がある。でも実はこれ、川上さんなりの究極のファンサービスだったと大瀧さんは指摘している。「面白くない野球でも、堅い野球でもないのよ。ドジャース戦法を取り入れたというのが通説になっていたけど、実はファンサービスだったんじゃないかと。つまり1番の柴田が塁に出て、2番がバントなら、『あ、4番の長嶋まで廻る』ってファンは思うんだよ」「初回の送りバント」の本質は、「長嶋に廻すための、いわばお膳立てだった」。「みんな、その、川上さんの深い考えを知らないから、、堅いとか石橋とかっていうようなことで、形式だけをのちのフォロワーは真似したんじゃないの?それで犠打の数がクローズアップされたり、おかしなことになっちゃった」大瀧さんのコメントの真偽は、ボクにはわからない。ただ、もしそれが本当なら川上さんの采配は「究極のエンターテイメント」だったと言える。ま、ボクは長島茂雄さんよりも、黒江透修さんのほうが好きだったけれど。◇黒江透修の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「V9の正遊撃手・黒江透修」 (2007.6.10) → こちらへ。今日も1クリックお願いします
2009.07.22
コメント(0)
-

小池翔大が粘って決めたV
第37回日米大学野球選手権大会、7月15日に行われた第5戦のこと。(テレビ「J-スポーツ」の録画中継をやっとDVDで見ることができた)米国 002 200 003 00 =7日本 200 020 003 01X=8(米)コール-ペピトーン-ベティス-グレイ(日)斎藤佑-大石-菅野-乾-野村9回に3点を失った日本は、その裏の攻撃で3点差を追いかけるものの、すでに二死一塁の絶体絶命のピンチ。米国ベンチは「あと一人!あと一人!」コールが起きてもおかしくない場面。だが直後、とんでもない物語が幕を開けた。その「最後の一人」になりそうだった2番・伊志嶺翔大(東海大3年、沖縄尚学高)が四球を選んで出塁すると、3番・加藤政義(九州国際大4年、東北高)が左中間を破る三塁打で2点。続く4番・中原恵司(亜細亜大4年、武蔵工大ニ高)が初球を叩いて右中間に適時二塁打を放ち、「あっ!」という間の同点に。中原が打った瞬間、解説していた佐々木正雄氏(横浜商科大監督)は「行ったぁ~、◆÷×◎○◇・・・。よく打ちましたね。一球目から。ナイスバッティング~◎◇&+#・・・」(感極まったのはわかったが、途中何を言っているのかわからなかった)そして勝負を決めた11回裏。 「流れ」を呼び込んだのは、間違いなくこの回先頭の9番・小池翔大(青山学院大3年、常総学院高)だった。ファールで粘り続けて、なんと計15球を相手投手に投げさせ四球を奪い獲る。「何が何でも出塁するんだ!」という意地がチャンスの芽を作った。後続打者の2人がとも三振に倒れたものの、その間に相手投手のけん制悪送球で小池は三塁へ。一打サヨナラの場面で、先ほどの打席で三塁打を放った3番・加藤政義。カウント2-3から打った打球は平凡なショートゴロだったが、これをコロンがお手玉。小池が生還して日本がサヨナラ勝ちと今大会の優勝を決めた。(幕切れは、あまりにあっけなかった)◇加藤政義の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「斎藤佑樹と東京ドーム 」 (2009.7.18) → こちらへ。今日も1クリックお願いします
2009.07.21
コメント(2)
-

理由あって川口青陵を応援してます
夏の甲子園、埼玉県予選の3回戦・川口青陵高vs武南高戦が昨日(7月19日)行われた。武南 000 000 000 =0川口 001 000 00X =1(武)白井、(川)野川-布施川口青陵高の貴重な1点は、意外なシーンで転がり込んできた。それは3回裏、二死二塁のチャンスで5番・野川がレフト前に安打。走者はいったん三塁にストップしたが、武南のレフトの内野への送球が逸れる間に生還。結局このプレーが決勝点になった。守っては注目の左腕エース・野川拓斗がスリークォーターから速球、カーブ、スライダーを自在に操り、武南打線を抑えた。初回から3回にかけては5者連続三振を奪うなど、5回2/3を投げて奪三振8、被安打4(内、投手への内野安打2本)、与四死球3。---------------------------------------------------------ボクは今春のある出来事がきっかけとなって、川口青陵高を応援しながらこの試合を見ていた。それは、センバツの代表校が発表になった時、その選考方法に多少の疑問を感じたから。通常の場合、東京地区から1校、関東地区(埼玉・神奈川・千葉・栃木・群馬・山梨)から5校が選出されるが、昨秋の明治神宮大会で慶應高(関東地区代表)が優勝したことにより、東京・関東地区からもう1校が選出されることになった。最後の一枠を争ったのが、早稲田実(東京・2位評価)と川口青陵(関東・6位評価)の2校。そして結果は「関東は慶応を除けば例年より打力が弱い。早実は安定した力がある」(高野連)との評価があって早稲田実に軍配が上がり、川口青陵は「甲子園行き」の切符を惜しくも逃してしまった。ボクが疑問に感じたのは、神宮大会で優勝したのは関東代表の慶應高であるなら、神宮枠は関東(=川口青陵高)に与えられるべきだろうということ。例年、秋季大会は東京と関東がまったく別に行われているのに、センバツの選考時だけは一緒にするというのが不可解だった。センバツの選考時は同じ土俵で検討するなら、秋季大会も東京と関東を一緒にしたほうが、選手にとってもファンにとっても公平感があると思うのだ。とまれ、そんな事情があって、この夏は川口青陵に雪辱を果たしてほしい。 今日も1クリックお願いします
2009.07.20
コメント(0)
-

大宮東、平尾効果で?5回戦へ
夏の甲子園、埼玉県予選の4回戦・大宮東高vs三郷北高戦を観戦した。大宮東 000 000 000 02 =2三郷北 000 000 000 00 =0(大)竹澤、(三)平井古豪ながら、ここのところ真価を発揮しきれない大宮東高。だがこの大会では、初戦で強豪の武蔵越生高を4-0で破ったことで勢いに乗った。続く3回戦は深谷商高に4-1で勝利して、今日の試合に臨んだ。その大宮東、スコア0-0で迎えた延長11回表にバントヒットと四球などで一死二・三塁チャンスをつかむ。そこで3番・竹澤弘通がレフト左に適時二塁打を放ち、2得点を挙げて勝利を決めた。敗れた三郷北だが、素晴らしいプレーがあった。それは9回表の守備だった。一死一・三塁のピンチに大宮東の5番・野口修二がセンターへフライを打ち上げると、センター・濱野翔大が捕球後すぐさま本塁へ送球。これが絶好の返球となって、タッチアップを狙った三塁走者を刺し得点を許さなかったのだ 濱野、身体は小柄ながら、肩は抜群に強かった。 こういったプレーが飛び出すと、ふつうは「流れ」が三郷北に行くもの。でも大宮東は「流れ」を放すことなく、最終的に勝利を呼び込んだ。今大会の大宮東、「台風の目」的な存在になるかもしれない。次回(5回戦)は市立川越高との対戦が組まれている。昨年、西武ライオンズがパ・リーグ優勝を決めた時、その祝勝会では平尾博嗣が「大宮東高! 大宮東高、バンザイ!」と何度も何度もカメラの前で叫んでいた。もちろん平尾は大宮東のOB。たぶん母校に対し精一杯の声援を送っていたのだろう。その偉大な先輩のエールに見事に応え、後輩たちは着実に勝ち星を重ねている。◇平尾博嗣の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「平尾博嗣の大宮東高時代」 (2008.11.9) → こちらへ。今日も1クリックお願いします
2009.07.20
コメント(0)
-

三原脩、職業野球選手になった頃
その昔、野球を職業とする選手(プロ野球選手)は、現在のように子供たちの「憧れの職業」ではなかった。いやそれどころか、野球が職業になることさえ懐疑的に見ている人も多く、世間からは卑下して見られることも多かった。今回、特集「職業野球選手になった頃」(第4回)で紹介する三原脩氏は、創設当時の「職業野球」を懐疑的に見る急先鋒的な存在だった。※三原脩氏。巨人・西鉄・大洋・近鉄などの監督を歴任。高松中・丸亀中-早稲田大中退。だが懐疑的だったにもかかわらず、プロ野球契約選手第一号になったのは、なぜか三原だった。理由は早稲田大の選手時代に監督であった市岡忠男(当時、読売新聞社運動部部長)からの頼みだったから。市岡は全米軍が来日するプランの仕掛け人の一人だった。「今秋(1934年、昭和9年)、ベーブ・ルースなどのスター選手たちが全米軍として来日するため、対戦する全日本軍を急きょ作らなければならない。(なぜ、私を勧誘するのですか? という三原の問いに)君の判は、社会に対する信用状だ。その契約書が他の選手を勧誘する際の決め手となるからだ」その言葉を聞き、職業野球の将来には疑問を残しつつも、三原はいわば『名義貸し』のつもりで判を押し、契約選手第一号となった。その効果はテキメン。当時、慶應義塾大が執拗にアプローチしていた京都商高の沢村栄治は「あの三原さんも契約したのなら」と、進路を変更してプロ入りを決めたという。ただ、これはそのずっと後になるのだけど、三原は球団のありかたについて現代でも教訓となる根本的な疑問を呈している(1947年、昭和22年頃)。※要約すると、以下のとおり(と言っても、少し長くなるが)。戦前・戦後を通じて独立会社の形態をとっていた巨人軍だったが、1947年頃に資本的にも組織的にも読売新聞社の傘下に入ることとなった。その途端、東京の一地方紙に過ぎなかった読売新聞を朝日新聞や毎日新聞に並ぶ全国紙にするため、巨人軍を拡販の宣伝道具として便利使いするようになった。例えば、全国各地でオープン戦を開催し、その入場券を拡販の材料に使ったりしていた。 「自由と自立」を失った会社(球団)ほど、失速するのははやいもの。巨人軍に限らず、そのような球団経営が続けば、日本のプロ野球に未来はないと、三原は危機感を募らせた。 ※当時、野球解説者だった小西得郎は専門紙『スポーツ・ジャーナル』でこう書き、側面から三原を支援した。 「現在の8球団中その6球団は新聞社と電車会社がこれを経営している。そしてそれ等の会社が、その宣伝広告の一端として球団を手先に使い、利用せんとするならば野球界の将来の大発展は到底望めるものではない」(以上、『魔術師 三原脩と西鉄ライオンズ』立石泰則著、小学館刊より一部を引用)------------------------------------------------------------ この記事は『ボクにとっての日本野球史』の中で、次の期に属します。→ (第4期)1925年(大正14年)、東京六大学リーグが成立し、早慶戦が復活した時以降→ (第5期) 1946年(昭和21年)、戦後、東京六大学リーグ・職業野球が復活した時以降(第4期)に属する他の記事は以下のとおり。◇ 「ボクの日本野球史」 (2009.7.1) → こちらへ。「プロ野球、創設プラン」 (2009.7.5) → こちらへ。「職業野球選手の社会的地位」 (2009.7.8) → こちらへ。「米国遠征の夢と財布の中身」 (2009.7.9) → こちらへ。(第5期)に属する他の記事は以下のとおり。◇ 「ボクの日本野球史」 (2009.7.1) → こちらへ。「西本幸雄、職業野球選手になった頃」 (2009.7.18) → こちらへ。「関根潤三、職業野球選手になった頃」 (2009.7.18) → こちらへ。「豊田泰光、職業野球選手になった頃」 (2009.7.19) → こちらへ。今日も1クリックお願いします
2009.07.19
コメント(0)
-

豊田泰光、職業野球選手になった頃
昭和20年代当時、野球を職業とする選手(プロ野球選手)は、現在のような「憧れの職業」ではなかった。いや逆に、世間からは卑下して見られることが多かったし、その職業を得た選手たち本人からして、あまり気の進まない「就職」のようだった。いくつかの文献で、往年の名選手たちが、自身の職業野球への「就職」当時について心情を語っていた。それらを特集「職業野球選手になった頃」と題して紹介します。■特集「職業野球選手になった頃」の第3回は、豊田泰光氏。(元・西鉄ライオンズ、水戸商高-西鉄ライオンズほか)1950年代初め、関東地方の野球少年、とくに茨城の少年には独特な野球に対する考え方があった。それは「まず、六大学野球ありき」。理由は簡単で、早稲田野球の大功労者・飛田穂洲が地元・茨城の出身だったから。「六大学が一番エライ存在だった。次いでプロ野球の巨人、あとはパ・リーグの選手。神宮での早慶戦や早明戦の切符が手に入ったらウキウキ、ワクワクで東京に行ったものですが、パ・リーグの試合の切符なら『そんなのいらねぇ』で終わり」後に入団することになる「西鉄ライオンズ」のことは、三原脩監督の名前以外は何も知らなかった。1952年(昭和27年)夏、豊田さんは甲子園に出場し、選手宣誓もやった。関東地方では『水戸商に豊田あり』といわれる存在だった。立教大への進学も99%決まっていたが、父親が体を壊して進学を断念。声をかけてきた西鉄ライオンズに入団が決まった(1953年)。「初めて西鉄本社の建物に入ってみると、オンボロのボロ。廊下は歩くたびにうるさいほどギイギイと音を立てる。球団事務所の中も、なんか陰気くさくてねぇ」「入団が決定後、東京にある西鉄の宿舎を訪ねたことがあるのですが、 大広間ではマージャンの真っ最中でした。ガラガラゴロゴロ。大きな体のオッサンたちが、四人一組でワケのわからんものに熱中している。当然、お金が行ったり来たりするわけですから、これは人間関係がギスギスしてきます。当時の西鉄ではイカサマトバクまでが横行していたのです」(以上、『プロ野球を殺すのはだれだ』豊田泰光著、ベースボールマガジン新書より一部を引用)◇職業野球選手の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「職業野球選手の社会的地位」 (2009.7.8) → こちらへ「西本幸雄、職業野球選手になった頃」 (2009.7.18) → こちらへ。「関根潤三、職業野球選手になった頃」 (2009.7.18) → こちらへ。◇豊田泰光の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「元西鉄・和田博実氏、死去」 (2009.6.30) → こちらへ。 ◇三原脩と飛田穂洲の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「早慶戦のホームスチール」 (2009.5.4) → こちらへ。◇西鉄ライオンズの関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「西鉄ライオンズ「黒い霧」事件」 (2009.7.10) → こちらへ。------------------------------------------------------------ この記事は『ボクにとっての日本野球史』の中で、次の期に属します。→ (第5期) 1946年(昭和21年)、戦後、東京六大学リーグ・職業野球が復活した時以降(第5期)に属する他の記事は以下のとおり。◇ 「ボクの日本野球史」 (2009.7.1) → こちらへ。「西本幸雄、職業野球選手になった頃」 (2009.7.18) → こちらへ。「関根潤三、職業野球選手になった頃」 (2009.7.18) → こちらへ。今日も1クリックお願いします
2009.07.19
コメント(0)
-

関根潤三、職業野球選手になった頃
昭和20年代当時、野球を職業とする選手(プロ野球選手)は、現在のような「憧れの職業」ではなかった。いや逆に、世間からは卑下して見られることが多かったし、その職業を得た選手たち本人からして、あまり気の進まない「就職」のようだった。いくつかの文献で、往年の名選手たちが、自身の職業野球への「就職」当時について心情を語っていた。それらを特集「職業野球選手になった頃」と題して紹介します。■特集「職業野球選手になった頃」の第2回は、関根潤三氏。(元・ヤクルト監督、日大三中-法政大-近鉄バファローズほか)東京六大学リーグでは、法政大のエースとして活躍した関根潤三氏。通算成績は41勝30敗、通算最多勝利数は現在でも歴代4位を誇る。関根さんは大学卒業を控え、すでに社会人の八幡製鉄所に就職が決まっていた。ところが、あることが関根さんの運命を大きく変えてしまう。中学・大学時代の恩師にして野球部の監督だった藤田省三さんが近鉄の初代監督に就任したのだ。それは1950年(昭和25年)のこと。「当時、新しく近鉄ができて、藤田さんが『来い』というわけです。その時分は、大学の監督に呼ばれたら『ハイ、ハイ』ですから。お金も条件も何も聞いていないの。命令だったからね。仕方なしに行って・・・。親は反対しましたけどね」「一流企業に入った方が将来的に安定しています。3年ぐらい野球やって、あとは普通の業務に就けばいいんだから。プロ野球は安定するわけないってね」「プロに入っても喜びはなかったねぇ。プロ入りに当たっての覚悟も何もないですよ。だって藤田監督の命令に従いながらね、心ん中じゃ、『プロ? あぁ、行ってやるよ』って感じ。(以上、『伝説のプロ野球選手に会いに行く』高橋安幸著、白夜書房刊より一部を引用)◇職業野球選手の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「職業野球選手の社会的地位」 (2009.7.8) → こちらへ「西本幸雄、職業野球選手になった頃」 (2009.7.18) → こちらへ。------------------------------------------------------------この記事は『ボクにとっての日本野球史』の中で、次の期に属します。→ (第5期) 1946年(昭和21年)、戦後、東京六大学リーグ・職業野球が復活した時以降(第5期)に属する他の記事は以下のとおり。◇ 「ボクの日本野球史」 (2009.7.1) → こちらへ。「西本幸雄、職業野球選手になった頃」 (2009.7.18) → こちらへ。今日も1クリックお願いします
2009.07.18
コメント(0)
-

西本幸雄、職業野球選手になった頃
終戦直後の1945年(昭和20年)11月23日、早くも職業(プロ)野球が「東西対抗戦」といった形で再開した(於、後楽園球場)。ただ昭和20年代当時、野球を職業とする選手(プロ野球選手)は、現在のような「憧れの職業」ではなかった。いや逆に、世間からは卑下して見られることが多かったし、その職業を得た選手たち本人からして、あまり気の進まない「就職」のようだった。いくつかの文献で、往年の名選手たちが、自身の職業野球への「就職」当時について心情を語っていた。■「職業野球選手になった頃」第1回は、西本幸雄氏。(元・近鉄監督、和歌山中-立教大-別府星野組ほか-大毎オリオンズほか)「当時、六大学からプロの道に進んだ者は、卒業生の名前を掲げられるところから名札を外されていた。野球で金を稼ぐとはもってのほかだ。そんな時代だったな。プロ野球の世界に入ることなんかは想像できなかったね」ところが1949年(昭和24年)頃、都市対抗(主催=毎日新聞)の強豪・別府星野組に就職し、監督兼任の選手として活躍していたが、会社の経営状態が悪化。給料もろくにもらえない状態に陥った。ちょうどその頃、毎日新聞がプロ野球に参加を表明、全国のめぼしい選手たちの勧誘を始めていた。ただ一人ひとり選手を集めるのが面倒だった毎日は、別府星野組のめぼしい複数人の選手たちを中心に、まるごと選手を集めようとした。西本さん、監督という立場もあって、好むと好まざるとにかかわらず、その交渉役をやるハメになる。「俺は(指名されなかった他の選手も抱えておくことができんから)全部の選手を引き取ってくれるか?と言った。みんながそれほど安定した生活はしていないわけや。野球を頼りにして就職しているような選手ばかり。そしたら、毎日が了承してくれた。みんながみんな、プロに入れるような選手ばかりじゃなかったけどな」「当時俺はもう29歳やったから、『いつまでも野球してられへんから毎日新聞で雇ってくれるか?』と言って、そういう約束ができた。選手を10人ほど連れて、毎日に入ることになったんや」(以上、『悲運の闘将 西本幸雄』(ぴあ刊)より一部を引用)◇西本幸雄の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「2人の正捕手、梨田昌孝と有田修三」 (2009.4.18) → こちらへ。「西本幸雄の監督信任投票!」 (2007.1.23) → こちらへ。「ボクの選んだ歴代近鉄ベストナイン」 (2008.10.19) → こちらへ。「西本幸雄の立教大時代」 (2009.3.22) → こちらへ。◇職業野球選手の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「職業野球選手の社会的地位」 (2009.7.8) → こちらへ------------------------------------------------------------この記事は『ボクにとっての日本野球史』の中で、次の期に属します。→ (第5期) 1946年(昭和21年)、戦後、東京六大学リーグ・職業野球が復活した時以降(第5期)に属する他の記事は以下のとおり。◇ 「ボクの日本野球史」 (2009.7.1) → こちらへ。今日も1クリックお願いします
2009.07.18
コメント(0)
-

岩井美樹監督、子規を叱る?
先ほどの続き。テレビ「J-スポーツ」の録画中継で解説していたのは国際武道大の岩井美樹監督。岩井さんの解説の中で「そもそも明治時代、米国で言う『ファストボール』を日本で『直球』と訳したのはおかしい」というコメントがあって、ボクは興味をもった。岩井さん曰く、「これまで日本では、米国で言う『ファストボール』を『直球』という言葉に訳して使っていた。『直球』はただ真っ直ぐなだけで、打者からすれば打ちやすい(素直な)球である。『ファストボール』の米国で意味するところは『速球』であり、日本の投手は『速球』を覚えなければいけなかったし、今後世界に通用しない」「米国では『ストレート』は『棒球(ぼうだま)』という意味がある。それに対し、『ファストボール』は”ムーブメント”(揺れ動く)といった特徴があり、直球より有効な球である」「明治時代、『ファストボール』という言葉を輸入したとき、『ストレート』と同じ意味で『直球』と訳したのは間違いだった。『直球』と『速球』の違いを区分して訳すべきだった」(※多少、ボクの解釈を含め岩井さんのコメントを補足して記載しました)-------------------------------------------------------------- そうか、そうだったのか。では、明治時代に『ファストボール』を『直球』と訳した、いわば「犯人」は誰だったのか? ボクはさっそく調べてみた。すると、日本で「直球」という言葉を訳した人はすぐにわかった。その人は、かの俳人・正岡子規。wikipediaによると、正岡子規は「直球」だけでなく他にも「打者」「走者」「飛球」などの野球用語を訳していた。ただ、よ~く読んでみると、子規は「ストレート」を「直球」と訳したと書かれており、「ファストボール」を「直球」と訳した犯人とは断定できなかった・・・。とすると、真犯人は???※ちなみに「ベースボール」を「野球」と訳したのは子規ではないらしい。中馬庚(ちゅうまん・かなえ)が正解。子規は中馬より先に「野球」という言葉を使ったのは事実のようだが、本名「のぼる」を「の(野)」「ぼーる(球)」(つまり「野球」)とペンネームにして使っただけ。「ベースボール」を訳したわけではない。---------------------------------------------------------------この記事は『ボクにとっての日本野球史』の中で、次の期に属します。→ (第1期)「1872年、野球が日本に上陸した時代」に属します。(第1期)に属する他の記事は以下のとおり。◇「ボクにとっての日本野球史」 (2009.7.1) → こちらへ。「1872年、野球が日本に上陸した時代 」 (2009.6.30) → こちらへ。「ホーレス・ウィルソンと数々の偶然と」 (2009.7.2) → こちらへ。 「「野球」と訳した中馬 庚」 (2009.7.4) → こちらへ。今日も1クリックお願いします
2009.07.18
コメント(0)
-

斎藤佑樹と東京ドーム
第37回日米大学野球選手権大会、7月12日行われた第2戦のこと。(テレビ「J-スポーツ」の録画中継をやっとDVDで見ることができた)日本 006 001 000 =7米国 200 000 300 =5(日)斎藤佑-大石-乾-菅野、(米)ポメランツ-ウォルツ-ペピトーン日本の先発は、エース的な存在の斎藤佑樹(早稲田大3年、早稲田実)。序盤は球が高めに浮くことが多く、立ち上がりに苦しみ初回に2点を献上した(過去、このような状態の斎藤を見ることはあまりない。ボクがすぐに思い出すことができるゲームは2つ。いずれも法政大戦、下記参照)。◇斎藤佑樹の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「斎藤佑樹が通算6敗目で、早大連覇が遠のく? 」 (2009.4.28) → こちらへ。 「絶不調・斎藤佑樹vs絶好調・小松剛」 (2008.10.11) → こちらへ。だが斎藤、回を追うごとに次第に調子を上げ、変化球を中心に投球を組み立てて5回を投げ切った。5回、被安打4、奪三振5、与四死球3、自責点2。2番手として6回から登板したのは、同じ早稲田大の大石達也(3年、福岡大大濠高)。初球、いきなり150kmの速球を放って東京ドームに詰めかけたファンをどっと沸かせた。米国打線の「力」に対して、大石の真っ向勝負を挑む姿は、見ていてとても清々しく感じた。斎藤のいつもながらの「クレバー」な投球、大石の「パワー」の投球。いずれも東京六大学のリーグ戦そのままの活躍だった。------------------------------------------------------斎藤佑樹、東京ドームの登板は2年ぶりだと思う。前回登板したのは2007年6月14日、全日本大学野球選手権大会の2回戦、相手は九州国際大だった。ボクはこの試合の最終回に起きたドラマをよく憶えている。敗戦が決まった瞬間、九州国際大の松山竜平(当時4年、現・広島カープ)がヘルメットを思い切り投げつけ、号泣していた姿を。それは、早稲田大が2点リードで迎えた最終回、二死一・三塁のピンチに急きょ斎藤(当時1年)が登板した直後のこと。打者・松山竜平が左中間のフェンス直撃の大飛球を放ち、あわや同点の適時打になりそうな当たりだった。だが内外野の絶好の中継プレーにより本塁で間一髪のアウト。早稲田大が勝利を決めた。松山は号泣のあまり、自分ひとりでは歩けずチームメイトに両脇から抱えてもらい、やっとベンチに戻ることができたほどだった。たぶんこの時の試合に、いま日本代表の選手として活躍している加藤政義(九州国際大4年、東北高)も出場していたと思い調べてみたが、結局わからなかった・・・。◇松山竜平の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「松山竜平、斎藤佑樹を打つ!」 (2007.6.14) → こちらへ今日も1クリックお願いします
2009.07.18
コメント(2)
-

打席に入る前、一礼の理由
先ほどの記事の続き。 今日(15日)の日米大学野球選手権大会・第4戦で2点本塁打を放ち、ヒーローになった亀谷信吾(法政大4年、中京大中京高)。この亀谷、ほかの選手と違う大きな特徴がある。それは打席に入る前、必ずヘルメットを完全に脱いで深々と頭を下げること。ヘルメットのツバに軽く手を当てる仕草はよく見かけるけれど、亀谷ほどキッチリとお辞儀する選手は、高校野球の世界でもあまり見ることがない。それほどに稀有な選手なのだ。■書籍『伝説のプロ野球選手に会いに行く』(高橋安幸著、白夜書房刊)の中で、ミュージシャンであり「大」の野球ファンとしても知られる大瀧詠一さんが「打席に入る前の一礼」について面白いことを仰っていた。要約すると次のようになる。「昔の選手は川上哲治さんにしろ誰にしろ、打席に入る時は必ず打席に対して一礼をしていた。決して審判に対してではない。これは神道なのか何なのか分からないけれど、たぶんアニミズム的(※)な『場に神がいるんだ』という考え方」「今でもグラウンドに入る時は帽子をとって一礼するのが普通に行われている。それはグラウンドという『場に神がいるんだ』という考え方の反映であり、昔は打席もそれと同じと考えられていた。審判にお辞儀するのであれば、それは『対人』といえる。試合開始前に挨拶をして対人は済ませているわけだから、試合中にあらためて対人の挨拶をする必要はない」「さらに昔の選手たちには、打席に入った以上、結果が出るまでの間はそこを出てはいけないという教えもあった。だから、投球の間に滅多なことで打席から出ることを良しとしなかった。それは上記と同様、打席という『場には神がいるんだ』という意識が根底にあったからこそ」 (※)「アニミズム」とは、自然崇拝・精霊信仰という意味。◇亀谷信吾の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「東京六大学のベストナイン」 (2009.6.1) → こちらへ今日も1クリックお願いします
2009.07.15
コメント(0)
-

日本、五分にして逆王手!
第37回日米大学野球選手権大会、今日(7月15日)行われた第4戦の速報。日本 210 210 110 =8米国 001 001 001 =3(日)二神-乾-野村-中後-東浜-澤村-菅野、(米)バウアー-ズイック-ウジュシー-チョウスキーボクは残念ながらこの試合を見ていない。だから、ネットでその模様を知るより他に方法がない。下記のとおり主な記事をまとめたので、もしよろしければご一緒にどうぞ。 ■以下、日刊スポーツより。日本が米国を破って対戦成績を2勝2敗に戻した。日本は2連覇と国内開催13連覇を懸け、16日の最終第5戦(神宮)に臨む。日本は3-1で迎えた4回に亀谷(法大)が2ランを放つなど、今大会初の2けた安打となる11安打を記録。投げては2回を無安打無得点に抑えた東浜(亜大)ら7投手の継投で米国打線を抑えた。 (以上、日刊スポーツ)■以下、サンケイスポーツより。日本の1番・亀谷が四回2死二塁から左翼ポール際にアーチをかけた。2点差に詰め寄られた直後に再び突き放す価値ある一発。「まさか入るとは。二塁ベース付近で米国選手にユー、ゴーと言われ、初めて(本塁打と)知りました」と笑みが浮かんだ。4試合で計5安打だが、本塁打以外はすべてバント安打。「1番打者は塁に出て得点することが大事。現在の自分の状態を考え、足を武器にするのが一番だと思って」と語った。 (以上、サンケイスポーツ)■以下、読売新聞より。日本は一回、荒木(近大)の適時打で2点先制すると、二回にも伊志嶺(東海大)の適時打で1点追加。四回には亀谷(かめがい)(法大)の2ランで突き放し、7投手の継投で逃げ切った。七回から救援した東浜が2回無失点の好投で、前回大会の斎藤に続いて日本の1年生では史上2人目の勝利投手となった。 第5戦(16日・神宮)の日本は斎藤(早大)が先発する。◇2ランの法大・亀谷2「みんなの思いが後押し」◇試合開始前から、球場には右から左に強い風。榎本監督は、選手にこう伝えた。「レフトのポール際、あそこに打ち込めば飛ぶぞ」それが現実となる。四回二死二塁、打席には東京六大学が誇る俊足好打の外野手、亀谷。「自分は左打者なので、風のことはあまり意識しなかった」と長打狙いではなかったことを明かしたが、外角高めの直球を必死に打ち返した打球はぐんぐん伸び、ポール際の左翼席最前列に飛び込んだ。貴重な中押し2ランの次の打席は、本領を発揮。初球を三塁手の前に転がし、今大会通算4本目のバント安打を決めた。不動のリードオフマンに引っ張られるように、日本打線はこの後、エンドラン、スクイズと多彩な攻撃で米国を圧倒し、対戦成績を五分に戻した。鶴岡で追い風を受け上昇気流に乗った日本チーム。連覇をかけ、決戦の地・神宮に乗り込む。 (以上、読売新聞) 明日の第5戦は、斎藤佑樹(早稲田大3年、早稲田実)が先発するそうだ。◇亀谷信吾の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「法政大の中京大中京トリオ」 (2007.5.27) → こちらへ。 今日も1クリックお願いします
2009.07.15
コメント(0)
-

第2戦、大石達也が痛打浴びる
先ほど書いた記事「日本、第3戦敗退で米V王手!」の続き。(ちょいと時間軸が前後してしまったけど・・・)第37回日米大学野球選手権大会、昨日(7月12日)行われた第2戦のこと。日本 006 001 000 =7米国 200 000 300 =5(日)斎藤佑-大石-乾-菅野、(米)ポメランツ-ウォルツ-ペピトーン■以下、日刊スポーツより。佑ちゃんスマイルには充足感が漂っていた。試合後の会見で、斎藤が胸を張って答えた。「立ち上がりは思うように投げられなくて、どうなるかと思いました。100%満足いかない内容だったけど、チームが勝ててうれしい」 この日のMAXは142キロ。直球のキレは納得できなかった。「今の真っすぐでは通用しない」。冷静に自分を判断できるクレーバーさが白星につながった。前日12日の開幕戦。直球を軸に組み立て米国打線に捕まった日の丸投手陣をベンチから見つめた。「変化球が通じると思った。たまに真っすぐを見せたことでスライダーが生きた。次は直球で勝負したい。変化球投手と思われたはずですから」と笑った。 (以上、日刊スポーツ)◇斎藤佑樹の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「斎藤佑樹なるほど?の評価」 (2007.7.7) → こちらへ。 心配なのは2番手で登板した大石達也(早稲田大3年、福岡大大濠高)のこと。1回1/3を投げて、31球、打者8、被安打2、奪三振3、与四死球2、自責点3。まだ詳しい内容はわからないが、なぜ?と思ってしまう。近々テレビ「J-スポーツ」で放送される録画中継を見てみたい。◇大石達也の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「大石達也、益々の飛躍を!」 (2009.1.11) → こちらへ。 今日も1クリックお願いします
2009.07.14
コメント(2)
-

日本、第3戦敗れ米V王手
第37回日米大学野球選手権大会、今日(7月14日)行われた第3戦の速報。米国 040 300 100 =8日本 300 100 000 =4(米)ウィーラー-グレイ、(日)澤村-野村-中後-大石対戦成績は日本の1勝2敗となった。試合の詳細はわからないけど、先発した澤村拓一(中央大3年、佐野日大高)がたった1回2/3だけでKOされたようだ。被安打6、与四死球1、自責点2では早々の降板も仕方ない。2番手として登板した野村祐輔(明治大2年、広陵高)もパッとしなかった。4回1/3を投げ被安打4、自責点3。また昨日の第2戦で登板し自責点3だった大石達也(早稲田大3年、福岡大大濠高)が今日は復調。米国打線を1イニング無安打に抑えた。◇野村祐輔の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「斎藤佑樹に軍配、野村祐輔との対決」 (2009.5.16) → こちらへ。◇大石達也の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「雨中の早慶戦、大石達也が投打で活躍」 (2009.5.31) → こちらへ。打撃陣では、加藤政義(九州国際大4年、東北高)と中原恵司(亜細亜大4年、武蔵工大二高)の2人が絶好調。どちらも3試合連続で安打を放った。一方心配なのは4番の中田亮二(亜細亜大4年、明徳義塾高)のこと。今日も無安打で、今大会の通算成績は12打数1安打3三振、打率.083はあまりに物足りない。◇中田亮二の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「ドラフト上位候補、中田亮二」 (2009.1.13) → こちらへ。 ※今日の試合、そして昨日の試合(第2戦)もテレビ中継がなかった。近々放送されるテレビ「J-スポーツ」の録画中継を見たい。今日も1クリックお願いします
2009.07.14
コメント(0)
-

米国遠征で知った近代野球術
昨日書いた「日本のバント事始め」の続き。1905年(明治38年)に早稲田大が初めて米国に遠征した際に学んできたこと。早大野球部の安部磯雄部長は惜しげもなく日本国内に公開し、その普及に努めた。これらの渡米土産が後に、日本野球を飛躍的に進歩させるキッカケとなった。■以下、『ニッポン野球の青春』(菅野真二著、大修館書店刊)より引用。<練習法の改善>・従来キャッチボールを行う際、最初から力いっぱい投げていたが、少しずつ肩を温めていく(ウォーミングアップ)方法になった。<バントの有効性を認識>・「卑怯な手段」ではなく「有効な手段」であると認識されるようになった。そして用途に応じて使い分けるようになった。セーフティバント、送りバント、スクイズ。<二塁手と遊撃手の連携>・けん制や盗塁の際、二塁手だけが送球を受け取っていたが、遊撃手と連携して行うようになった。また従来、走者が二塁にいる時は二塁手が二塁ベースについたままだったが、走者のリードが大きくないときは定位置に戻るようになった。<コーチャーの設置>・攻撃側のチームは、走者の有無にかかわらず一塁・三塁にコーチャーをひとりずつ置くようになった。<グラブとスパイクの採用>・従来投手と遊撃手以外は内外野ともにミットを用いていたが、捕手、一塁手以外はグラブを用いるようになった。(※)・「裸足か足袋はだし」からスパイク靴を使用するようになった。<その他>・ヒットエンドランの活用・バットを大きく振りまわさず、確実にプッシュして打つ短打法・ダブルスチールやけん制球などの諸種のトリック・手から滑り込むスライディング・シングルハンドキャッチ・先攻選択の有利視・先に2勝した方を勝利者とする三回戦制・動作のある審判術と複数審判制 ほか(※)ちなみに1896年(明治29年)5月23日、一高(現・東京大)が米国人からなる横浜アマチュア倶楽部(以下、横浜)に初勝利を挙げた時、横浜の選手は全員ベース大のミットを使用していたが、一高の選手は捕手以外全員が素手で守っていたという。(痛そぉ~)---------------------------------------------------------------この記事は『ボクにとっての日本野球史』の中で、次の期に属します。→ (第3期)「1905年(明治38年)早稲田大がアメリカに遠征した時」に属します。(第3期)に属する他の記事は以下のとおり。◇ 「ボクにとっての日本野球史」 (2009.7.1) → こちらへ。「日米大学対決は104年前に始まった」 (2009.6.23) → こちらへ。 「野球術を普及した安部磯雄と橋戸信」 (2009.6.24) → こちらへ。 「米国遠征の夢と財布の中身」 (2009.7.9) → こちらへ。「日本のバント事始め」 (2009.7.12) → こちらへ。「野球を通じて「日本」を応援した人々」 (2009.7.12) → こちらへ。今日も1クリックお願いします
2009.07.13
コメント(0)
-

野球を通じて「日本」を応援した人々
先ほど書いた「日本のバント事始め」の続き。早稲田大野球部が日本で初めて米国遠征したのは1905年(明治38年)4月だった。選手たちは米国人に大いに歓迎で現地に迎えられた。いや、歓迎したのは米国人だけではない。「いったい野球とは何か」まるで知らない在留日本人たちの多くも全米各地から球場に集まった。第1戦のスタンフォード戦が行われたのは4月29日。その前日には東郷司令長官率いる日本艦隊がロシアの東洋艦隊を全滅させ、日露戦争で大勝利を得た時。集まった日本人たちにとっては、少なからず気持ちが高揚した瞬間だったろう。■『日本野球史』(国民新聞運動部編、昭和4年刊)には、こう記している。「故国を離れてから全くその面影を偲ぶよすがもない時に、しかも戦勝のそれを示すがごとく現れた早稲田チームを見て、いくらかの慰めにしようとしたのだろう。(中略)球場の処々で『日本、日本』と云う声が聞こえる」先日書いたとおり、早大野球部部長だった安部磯雄の計算した利益は得られず収支の面では散々(大赤字)だったものの、「最新野球技術」の輸入という点や在留日本人たちへの慰問という効果は十分にあったようだ。◇安部磯雄の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「米国遠征の夢と財布の中身」 (2009.7.9) → こちらへ。 そしてもうひとつ。 ここまで書いて思い出したのは、この時から遡ること9年前のこと。1896年(明治29年)5月23日、一高(現・東京大)が米国人からなる横浜アマチュア倶楽部に記念すべき初勝利(スコア29-4)。そして続く2回戦(同年6月5日)もスコア32-9で大勝したのだ。2回戦終了後、試合のあった横浜市内は一高の勝利に大いに盛り上がった。■『にっぽん野球の系譜学』(坂上康博著、青弓社刊)に、その時の様子が記されている。「横浜駅に向かう彼ら(一高の選手たち)に、勝利を祝し、ていねいに礼を告げていく横浜市民の姿を見て、一高の学生たちは『異人サンの金力』に抑圧を受けながらも『治外法権』ゆえに憤慨を骨に刻むよりほかない市民たちの『敵愾心』をひしひしと感じた」◇日米野球の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「日米野球初戦、一高が圧勝す」 (2009.6.29) → こちらへ。---------------------------------------------------------------この記事は『ボクにとっての日本野球史』の中で、次の期に属します。→ (第2期)1896年(明治29年)、一高が横浜アマチュア倶楽部に勝利した時および(第3期)「1905年(明治38年)早稲田大がアメリカに遠征した時」に属します。(第2期)に属する他の記事は以下のとおり。◇ 「ボクにとっての日本野球史」 (2009.7.1) → こちらへ。 「日米野球初戦、一高が圧勝す」 (2009.6.29) → こちらへ。(第3期)に属する他の記事は以下のとおり。◇ 「ボクにとっての日本野球史」 (2009.7.1) → こちらへ。「日米大学対決は104年前に始まった」 (2009.6.23) → こちらへ。 「野球術を普及した安部磯雄と橋戸信」 (2009.6.24) → こちらへ。 「米国遠征の夢と財布の中身」 (2009.7.9) → こちらへ。「日本のバント事始め」 (2009.7.12) → こちらへ。今日も1クリックお願いします
2009.07.12
コメント(0)
-

日本の「バント事始め」
先ほどの続き。いまや日本のお家芸となっている「バント」。ただ、この戦法も元はといえば米国にあったもの。そもそもは1905年(明治38年)に早稲田大が初めて米国に遠征した際に学んできたに過ぎない。それまで、「武士道」の一環として野球というスポーツを考えていた日本にとって、「バント」とは正々堂々としない卑怯な戦法としてとらえられていた。例えば、安部磯雄(当時、早稲田大野球部部長)の「バント」に関する発言にこういったものがある。※以下は早稲田大入学前、神戸中在学時に外人のアマチュア選手たち(主に神戸に寄港する米艦の船員)がバントを多用するのを見て、それを真似してバントを試みた泉谷祐勝に対してのもの。「泉谷君、そんな卑怯な真似(バントを指す)をしちゃいかん。打つなら打つ。避けるなら避けるでどっちかはっきりし給え。打つのか打たないのか分からない。まるでいやいやバットを振っているようだ。そんなことをしてはいかん」(『日本野球史』国民新聞運動部編、昭和4年発行)ところが---。米国遠征の第1戦(1905年4月29日)、相手のスタンフォード大はランナーが出るごとに(送り)バントをした。また三塁にいる時も同様、打者と走者が息を合わせたようにバント(スクイズ)を繰り返した。卑怯な戦法と考えていたためか、「バント」の際の守り方がまるでわからない早大の内野陣。なす術なく茫然と立ち尽くすしかなかった。結局スコア1-9で敗退してしまった。帰国後、安部はバントについての考え方をあらためた。そして最新の野球術を様々な方法で日本国内に広めることに努めた。もちろん、その中に「バント」に関することもあった。「バントを練習し、それによってバントエンドランとかスクイズプレーを行って、野球の玄妙に触れねばならぬ」(同上)「玄妙」とは、道理や技芸などが、奥深く微妙なこと。趣が深くすぐれているという意味(大辞泉)。米国遠征を通じ、初めてバントは「趣が深くすぐれている」戦法として認められたのだった。(※本文中、すべて敬称略) ◇安部磯雄の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「野球術を普及した安部磯雄と橋戸信」 (2009.6.24) → こちらへ。「米国遠征の夢と財布の中身」 (2009.7.9) → こちらへ。------------------------------------------------------------ この記事は『ボクにとっての日本野球史』の中で、次の期に属します。→ (第3期)「1905年(明治38年)早稲田大がアメリカに遠征した時」に属します。(第3期)に属する他の記事は以下のとおり。◇ 「ボクにとっての日本野球史」 (2009.7.1) → こちらへ。「日米大学対決は104年前に始まった」 (2009.6.23) → こちらへ。 「野球術を普及した安部磯雄と橋戸信」 (2009.6.24) → こちらへ。 「米国遠征の夢と財布の中身」 (2009.7.9) → こちらへ。今日も1クリックお願いします
2009.07.12
コメント(2)
-

日本、バントミスが響き敗退
第36回日米大学野球選手権大会・第1回戦が愛媛・坊ちゃんスタジアムで行われた。米国 000 200 001 =3日本 000 000 000 =0(米)コール-グレイ-ベティス、(日)二神-野村-東浜-中後1回表、先頭打者を出しながらも、送りバントを失敗しチャンスを潰した米国。4回表も1回と同様、先頭の1番・フォルトがライト前で出塁、チャンスを作る。ところが先ほど失敗した2番・ウォングがまたも送りバントを失敗。またもチャンスが潰えたように見えたが、3番・コロンが右中間に適時三塁打を放ち先制。続く4番・ニューマンもレフト前に適時打を放ち、米国が2点をリードした。先発した二神一人(法政大4年、高知高)は3回まで安定した投球を見せていたが、4回は球が真ん中高めに集まってしまい痛打を浴びた。地元での「晴れ舞台」とあって、両親が応援に来ていたが結果が残せず残念。日本にもチャンスはあった。例えば8回裏。この回先頭の8番・小池翔大(青山学院大3年、常総学院高)が粘った末にレフト前安打で出塁した。大事に走者を二塁に送りたい場面だったが9番・林崎遼(東洋大3年、東洋大姫路高)は送りバントを失敗。カウントを追い込まれて仕方なくヒッティングしたものの、三塁ゴロ併殺に終わり反撃の糸口を自ら断ってしまった。日本のお家芸である「バント」をきっちり決めてほしかった 米国先発のゲリット・コールは156kmの直球とキレのある変化球で、日本打線をまるで寄せつけなかった。昨年、高校卒業時にはヤンキースに指名されたが、それを蹴ってUCLA(カリフォルニア州立大ロサンゼルス校)に入学した経歴の持ち主。まだ1年生ながら大いに活躍を期待できる投手だ。◇日米大学野球史の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「日米野球初戦、一高が圧勝す」 (2209.6.29) → こちらへ。「日米大学対決は104年前に始まった 」 (2009.6.23) → こちらへ。「日本のバント事始め」 (2009.7.12) → こちらへ。「日米大学野球と東門明氏のこと」 (2009.6.22) → こちらへ。 「原辰徳、WBC日米戦前夜に」 (2009.3.22) → こちらへ。「日本代表エースへ、村松伸哉」 (2007.6.25) → こちらへ。「MVP獲ったぞ、村松伸哉」 (2007.7.10) → こちらへ。今日も1クリックお願いします
2009.07.12
コメント(2)
-

千葉市リーグ優勝、世界大会へ
今日(7月11日)、リトルリーグのザバス杯第43回全日本選手権大会の準決勝・決勝が江戸川球場で開催された。決勝戦は、午前中の準決勝を勝ちぬいた千葉市リーグ(東関東)と泉佐野リーグ(関西1位)が対戦。結果はスコア17-4で千葉市リーグが泉佐野リーグを圧倒、米国ペンシルベニア州ウイリアムスポートで行われる第63回世界選手権出場を決めた。----------------------------------------------------------とにかく、強い!投手陣の安定感はもとより、打撃の「破壊力」は他のチームを圧倒していた。1番から9番までどこからでも得点できるし、特にクリーンアップはバットにかすっただけで本塁打を打てるパワーを持っている。準決勝の大宮リーグ戦ではたしか本塁打数が6本。決勝では4本目あたりから数えるのを止めたが、大宮戦と同程度の本塁打が飛び出していた。いったいどんな練習をすれば、あんなに打てるようになるのか? と思うほど。千葉市リーグのOBには現・読売の小笠原道大がいるけど、小笠原同様に全ての打者がフルスイング。それだけで、たとえ空振りでも相手の投手たちを震え上がらせるのに十分だった。スゴイのは、打つことだけではない。内野の守備、二遊間の連携プレーもスピード感が溢れる。ゲッツーこそとれなかったものの、惜しいプレーが何度かあった(リトルリーグでゲッツーをとるのは、ソフトボールのように塁間が短いため、「高度な技術」と「運」が必要)。特に遊撃手の動きは機敏で、彼のプレーを見せるだけでお金(入場料)が取れそうに思えた。投・攻・守、これだけ完璧に揃った千葉市リーグ。世界制覇はまず間違いないだろう。 今日も1クリックお願いします
2009.07.11
コメント(9)
-
リトルリーグ準決勝2
第2試合、泉佐野対瀬谷。泉佐野が序盤のリードを守り5-2で瀬谷を破った。
2009.07.11
コメント(0)
-
リトルリーグ準決勝1
第1試合、千葉市対大宮は千葉の打線が大爆発。3回に満塁本塁打などで大量6点を奪うと、4回に2点、5回に4点、6回に5点を加え、17-3で大宮を降した。
2009.07.11
コメント(0)
-

西鉄ライオンズ「黒い霧」事件
西鉄ライオンズのこと、ボクはほとんど憶えていない。黄金時代のことだってだいぶ後になって知ったことが多い。ただ「黒い霧事件」だけは、おぼろげながらリアルタイムで見聞していた。黒い霧事件。それは西武ライオンズが西鉄ライオンズだった1969年(昭和44年)のシーズンオフに起きた。野球賭博に絡んで、プロ野球投手の「八百長事件」が発覚し、「黒い霧事件」と呼ばれた。翌年、西鉄のエース・池永正明投手をはじめとする主力6選手にも八百長の疑惑が及び、当時の西鉄球団オーナーや球団社長の退任に発展、池永投手らはこの事件で球界を永久追放されたプロ野球界最大の事件のこと。当時のボクはまだ小さかったが野球が大好きだった。でも残念なことに憧れのプロ野球選手たちが八百長をやって、ヤクザからお金をもらうような悪いことをしたという認識でこの事件を見ていた。「黒い霧」というネーミングはまさに的を射ていて、当時のプロ野球界には重苦しい空気が漂っていた。田舎でテレビ観戦していただけのボクにも、そのことはよくわかった。結局この事件、「永久追放処分」という前代未聞の厳しい処分が下り終息した。処分を受けたのは、当時西鉄ライオンズに在籍していた永易将之、与田順欣、益田昭雄、池永正明(※池永は2005年に復帰を認められた)の4選手。ただ、ほかにも疑惑をもたれた選手も少なからずいたが、そこにはメスを入れられることはなく、軽い処分を数名に行ったのみ。これでは全面解決とはいえず、「うやむや」のうちに事件は終結したような印象を残した。疑惑があったものの、軽い処分に逃れた西鉄選手の一人、田中勉はおよそ事件の10年後にこんな述懐をしている。以下、『魔術師 三原脩と西鉄ライオンズ 決定版』(立石泰則著、小学館刊)より。 「実は、ボクに対して、ある球界筋から、永久追放処分などの厳しい処分をしないかわりに、八百長問題についてしゃべってくれるなという交換条件が出されたんです」「あの当時、西鉄以外の選手で、実際に八百長をやった選手は、今すぐにでも70人の名前を出せますよ。これをしゃべったら、球界は分解していたでしょうね」「だから、僕は、球界全体を救うために犠牲になったと思っとります」(以上、『魔術師---』 )いったい何が「犠牲」なのか、そのことがよくわからない。全てを明らかにすることがこの時、田中に必要だったのではなかろうか。これでは単に「臭いものにフタ」に手を貸しただけに思える。 ※いま調べてみると、永久追放などの厳罰を下したのはコミッショナー委員会と呼ばれる3名の委員からなる組織。その内の1人は、後に「江川の空白の1日」で有名になった金子鋭(後にコミッショナー)だった。しかもこの金子が厳罰を主張する急先鋒だったというから、別な意味で不思議なことではある。というか笑ってしまうが。※本文中、人名はすべて敬称略。 ----------------------------------------------------------------この記事は『ボクにとっての日本野球史』の中で、次の期に属します。→ (第6期)「1958年(昭和33年)、立教大の長嶋茂雄氏が巨人に入団した時以降」(第6期)に属する他の記事は以下のとおり。◇「ボクにとっての日本野球史」 (2009.7.1) → こちらへ。◇ボクにとっての日本野球史の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「西鉄、稲尾和久vs和田博実」 (2009.7.7) → こちらへ。今日も1クリックお願いします
2009.07.10
コメント(7)
-

米国遠征の夢と財布の中身
先ほどの続き。1935年(昭和10年)、「大日本東京野球倶楽部」(現・読売の前身)というチームが、職業野球として初めて米国に遠征した時のこと。4ヶ月間にわたり約110試合を行った結果、その収支は次のとおり赤字だった。赤字は絶対許されぬ条件のもとでの遠征だったが、観客数が思ったほど伸びず収入は期待を下回った。そのため選手たちは常に食うや食わずの日々を強いられ、空腹と疲労と過密日程でギリギリの状態だった。<収支>収入:7万7214円44銭、支出:8万5483円64銭、差引:▲8269円20銭。この話を知り、ボクは早稲田大初めての米国遠征(1905年、明治38年)にまつわるエピソードを思い出した。それは安部磯雄(当時、早稲田大野球部部長)が、米国遠征に向けて大隈候に資金提供を仰ぐため、直談判を試みた時のこと。安部は大隈候に言った。「(早大)野球部は米国の各大学や職業野球団か数十回の試合を行う。米国では見物人から入場料1円を取る。そのうち、実費分を差し引いた入場料の3分の2を早大がもらうことにすれば、1試合で6000円程度の収入になる。そうすれば約3ヶ月の試合で10万円の余剰金をもって日本に帰ることができる」安部はさらに続ける。「その利益で山形有朋の椿山荘から大隈邸に続く、いわゆる早稲田田圃を買い取って堤防を築く。さらに面影橋付近にも堤防を設け、ここに江戸川の清流を呼びいれれば、理想的な湖ができる。これは早稲田の学園に景色を添えるし、あわせて大運動場を作る。そうすれば、早稲田大学は全スポーツの一大殿堂となる」(『ニッポン野球の青春』より)大風呂敷を広げ大隈候から承諾を得た安部だったが、見込んだ入場者を一度も集めることはなく、収支は散々だった。 当てにしていた余剰金は、10万円にはるかに届かない約1000円に過ぎなかった。これでは大学から資金援助を受けた5500円すら返還することができず、逆に4500円の借金を抱えてしまうことになった。堤防、湖、大運動場の夢ははかなく消えた。原因は米国の情報が圧倒的に少なく、大きな期待のみが込められたシミュレーションだったこと。ただ米国から持ち帰った「野球の技術」等の土産は日本の野球界に大きく貢献したことは事実。またその後、少しずつではあるが時間をかけて、安部は大学に借金を返済したという。※本文中、人名はすべて敬称略。 ◇安部磯雄の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「野球術を普及した安部磯雄と橋戸信」 (2009.6.24) → こちらへ。◇日米対決の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「日米大学対決は104年前に始まった」 (2009.6.23) → こちらへ。「75年前の日米野球のこと」 (2009.3.23) → こちらへ。(参考)『ニッポン野球の青春』(菅野真二著、大修館書店刊)『日米野球史』(波多野勝著、PHP刊) ----------------------------------------------------------------この記事は『ボクにとっての日本野球史』の中で、次の期に属します。→ (第4期)「1925年(大正14年)、東京六大学リーグ成立、早慶戦復活時以降」(第4期)に属する他の記事は以下のとおり。◇「ボクにとっての日本野球史」 (2009.7.1) → こちらへ。◇ボクにとっての日本野球史の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「プロ野球、創設プラン」 (2009.7.5) → こちらへ。「職業野球選手の社会的地位」 (2009.7.8) → こちらへ。今日も1クリックお願いします
2009.07.09
コメント(0)
-

職業野球選手の社会的地位
1935年(昭和10年)、「大日本東京野球倶楽部」(現・読売の前身)というチームが、職業野球として初めて米国に遠征した。三原脩(高松中・丸亀中-早稲田大)や水原茂(高松商-慶應義塾大)ら19人の選手が参加し、沢村栄治(京都商高)がブレイクするキッカケとなった遠征として知られている。米国遠征は4ヶ月の間に各地を転戦し、約110試合をこなす相当な強行軍だったらしいが、その時の記録を記した書籍の一節にボクは興味をもった。それは、今でこそ「花形」と言われるプロ野球選手だが、当時の選手(「職業野球」と呼ばれた)に対しての社会的な評価は、とんでもなく低かったこと。外国の地でしかも強行日程。心身がボロボロになりながら、それでも19人の選手たちが懸命に野球をやり続けた理由。それは「職業野球の明日を担う」という各選手たちのプライドが支えたのだという。後日、水原がその時の振り返って、このように語った。「周囲の事情としては、プロ野球に入るようなやつは就職もできない、どこの会社も雇ってくれない、いわばやくざの道に入ったかのように軽蔑した目で見られていた。そういうことがあったために、われわれとしてもよけいに男の意地というか、よしっ、今に見てろ、この道でおれたちは成功してみせるという真剣さがあった」。(『華麗なる反乱』、『日米野球史』波多野勝著・PHP研究所刊より引用) 球団創設75周年記念として、いま(7月7日~)読売巨人軍の選手が着用しているユニフォームは、ちょうどその当時(約1年間の違いはあるが)のものが復刻されたものらしい。◇三原脩の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「岸孝之、川崎徳次、そして三原脩 」 (2009.5.13) → こちらへ。※本文中、選手名すべて敬称略。----------------------------------------------------------------この記事は『ボクにとっての日本野球史』の中で、次の期に属します。→ (第4期)「1925年(大正14年)、東京六大学リーグ成立、早慶戦復活時以降」(第4期)に属する他の記事は以下のとおり。◇「ボクにとっての日本野球史」 (2009.7.1) → こちらへ。◇ボクにとっての日本野球史の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「プロ野球、創設プラン」 (2009.7.5) → こちらへ。今日も1クリックお願いします
2009.07.08
コメント(0)
-

佐藤翔、都市対抗出場決定
まったくもって恥ずかしいことに、ボクはこのニュースにまるで気づいていなかった。それは都市対抗東北2次予選のこと。7月2日、JR東日本東北が決勝で七十七銀行を破り、3年ぶり22度目の本戦出場を決めたそうだ。■以下、日刊スポーツより。4番DHの佐藤翔内野手(23=慶大)が3安打3打点と活躍。190センチの巨体を揺らし、故郷で大暴れだ。初回1死一、二塁で左中間を破る二塁打で先制点を挙げる。2回に中前適時打を放つと、6回には右中間へ適時二塁打。広角打法で本戦出場に貢献し、大会MVPも獲得した。「自分の活躍よりチームが勝てたことがうれしいです」。両チーム合計26本のヒットが飛び交う乱打戦で、佐藤が体でもバットでも目立った。 高校まで秋田市で過ごした。こまちスタジアムは、秋田高3年夏の県決勝で湯沢を11-1で下し、甲子園出場を決めた思い出の球場だ。佐藤はその試合でも4番で3安打2打点を挙げており「慣れ親しんだところなので、力が入りました」と振り返った。チームは昨季までのエース摂津(ソフトバンク)が抜け、打力強化が課題だった。月に1度は摂津から連絡を受ける阿部圭二監督(53)も「頼もしいです」と佐藤の活躍に目を細めた。監督就任3年目で、初の都市対抗出場。座禅やミーティングでメンタル強化をはかってきた指揮官は「ようやく結果が出ましたね」と胸をなで下ろした。 (以上、日刊スポーツ) 佐藤翔(秋田高-慶應義塾大)。久しぶりに聞くことのできた名前だ。ボクが佐藤の姿を最後に見たのは、2007年10月30日の早慶戦・3回戦のこと。佐藤にとって大学生活最後の試合だった。その1年前には3年生ながら東京六大学選抜チームの4番打者として、プロ球団・ヤクルトと戦った実績があったにもかかわらず、最後のシーズンは不振を極めた。そのシーズン、試合の出場機会自体が大幅に減らされていた佐藤。ベンチに控える悲しそうな姿や、試合前のフリーバッティングでは戸惑いながら、そして遠慮勝ちにバットを振る姿は、190cmの彼の巨体がとても小さく見えたものだった。当時、佐藤自身が書いていたブログからも「弱気」な心理が読み取れ、メンタル面が原因だと感じたボクは、何とか応援したい気持でいっぱいになったものだった。あれから約2年弱。都市対抗出場と聞き、ボクはぜひ久々に佐藤の雄姿を見たくなった。 ◇佐藤翔の関連記事「あま野球日記」バックナンバーより。「佐藤翔を応援するぞ!」 (2008.11.22) → こちらへ。「佐藤翔、最終打席よかったよぉ~ 」 (2007.10.30) → こちらへ。 「【大胆予想】早慶戦3回戦」 (2007.10.29) → こちらへ。「慶應・佐藤翔に期待したい!」 (2007.10.28) → こちらへ。「慶大・佐藤が追う石井浩郎の背中」 (2007.2.4) → こちらへ。今日も1クリックお願いします
2009.07.07
コメント(0)
-

西鉄、稲尾和久vs和田博実
■6月22日亡くなった元・西鉄ライオンズの名捕手、和田博実さんのこと。元来、稲尾和久氏と和田氏は西鉄の黄金時代を支えたバッテリーであり、「vs」の関係ではない。ただ今日のブログのタイトルにあえて「vs」としたのは、2人には高校時代に対戦した経験があることを知ったから。それは1954年(昭和29年)、大分県下で行われた夏の甲子園予選大会のこと。2年生エースで4番の稲尾がいた緑ヶ岡高と、和田の臼杵高が対戦した。この一戦、結果は稲尾が臼杵高打線を完璧に抑えて完封勝利を飾る一方、打撃でもバックスクリーンに本塁打を打つなどの大活躍を見せた。■後日談。後に稲尾を西鉄に入団させることに成功したスカウトマン・竹井清の話。竹井はもちろんこの試合を見ていた。ただお目当ては稲尾ではない。当時「九州高校球界No.1捕手」と評判が高かった和田のほうだった。稲尾はその試合でたまたま見かけただけだった。稲尾の凄さを見せつけられても、竹井はすぐには獲得のための行動を起こさなかった。それは自分の「選手への選択眼」にまだ自信がなかったから。ところが、当時の南海・鶴岡一人監督が以前から稲尾に目をつけていると噂を聞くに及び、すぐさま稲尾獲得に向けて猛然とアタックを開始、見事に稲尾のハートを射止めることに成功した。■当時、竹井のいた西鉄のスカウト陣は素人が大半だった。だからその事情ゆえの特別なスカウト方針があった。それは、「南海・鶴岡監督が目をつけた選手を横取りせよ!」。「親分」と呼ばれた鶴岡が目をつけた選手なら、その実力はお墨付きと言って間違いない。何とか条件闘争に持ち込んで横取りしてしまおう!という、なんとも小賢しい?というかお手軽?な作戦だった。(参考)『魔術師 三原脩と西鉄ライオンズ 決定版』(立石泰則著、小学館刊) 今日も1クリックお願いします
2009.07.07
コメント(0)
-

1934年頃、プロ野球創設プラン
■日米親善試合の名目で、ルー・ゲーリックなどメジャー選手らで構成された全米選抜チームが来日したのは1931年(昭和6年)11月だった。それを迎え撃つ全日本チームは、当時人気絶頂だった東京六大学リーグのOBや現役選手たちで占められていた。約1か月間にわたり全17戦が行われ、結果は全日本の全敗。まだ日本にプロ野球がなく、「プロ」と「アマチュア」の違いをはっきり見せつけられた大会となった。そこで持ち上がったのが、日本でもプロ野球を作ろうという創設プラン。時代もちょうど追い風だった。この「追い風」の理由を『日米野球史』(波多野勝著、PHP研究所刊)は、3点挙げている。(1)東京六大学は「実力伯仲の時代」であり、野球人気が盛り上がっていた(2)全米選抜チームのプレーはファンの目を肥えさせ、選手の向上心に火をつけた(3)学生チームが全米選抜と戦うことを禁止する「野球統制令」が結果として、 プロ創設を後押しした。■プロ野球チームの創設に向けて議論を重ねていたのは、市岡忠男、浅沼誉夫、三宅大輔、鈴木惣太郎ら。そして出た結論は、おおよそ次のようなものだった。・最強チームをまず国内にひとつ作る・毎年アメリカの西海岸(パシフィック・コースト・リーグ)に行って50試合を行う・夏には帰国し、秋は逆にアメリカチームを来日させて試合する・・一方で、日本の各都市にチームを結成し、数年後に日本選手権を行う ・200万円の株式会社を作り、水道橋の近くにホームグラウンドを作る などプランだけでは仕方がない。当然、相応の資金が必要だった。これは資本家に委ねるより他に方法はない。昭和9年の夏、4人は日米親善試合を主催してきた読売新聞社・正力松太郎社長にそれを仰いだ。「よろしい、引き受けた!」正力は力強くそう話し、創設プランは急速に現実味を帯び始めた。■ただ読売新聞社に資本を仰ぐことに反対した人もいた。浅沼誉夫もその一人。理由は職業野球が新聞社に利用されることを危惧したからだが、リーダーの市岡忠夫はそれを押し切って、読売に打診することを決定した。鈴木惣太郎も、(残念ながら)読売がこれを興行的に使うことは予想がついていた。だから少なからず不安をもって、この時のことを鈴木はこう記している。「これが、果たしてよかったか、悪かったかは、もう少し後になってからの判断を待つべきものであろう。・・・ひとりプロ野球ばかりではない。日本における野球の発達は、おおむね新聞社の報道関係以外の事業関係と、密接な連絡を持つ宿命に置かれている。 (以上、参考:『日米野球史』)今日も1クリックお願いします
2009.07.05
コメント(0)
-

全国リトル、ベスト4決定
昨日に続き、7月4日行われたリトルリーグの「甲子園」ともいえるザバス杯第43回全日本選手権大会の結果を。1回戦の結果はこちらへ。2回戦の結果は以下のとおり。(美濃谷事務所ホームページより引用)■千葉市 11-7 佐世保中央■大宮 9-2 名古屋北■泉佐野 8-2 笠岡■瀬谷 10-2 松阪この結果により、勝者のベスト4入りが決定した。11日に行われる準決勝に進出する。組み合わせは、次のとおり。■千葉市(東関東) - 大宮(北関東)■泉佐野(関西1位) -瀬谷(神奈川) 昨日始まった大会、ボクも数試合を観戦した。以前もその傾向はあったけれど、選手たちの身体の大きさにはただただ驚くばかり。最近はルールが変わり、ほとんどの選手が中学1年生。なのに身長が170cm超えの選手が多い。その身体の全体重を使って投手が投げ込むものだから、とにかく球が速い。エース級の投手が投げる直球なら、普通に球速120kmくらいは出ているだろう。直球だけではない。さらにスライダーなどの変化球を織り交ぜるものだから、対応する打者も大変だ。プレートからホームベースの距離が14.02m、高校野球やプロ野球のそれと比べると4m以上も短いため、打者にとっての直球の体感速度は140km程度に及ぶかもしれない。※2回戦はスコアから見ると大味な結果になっているけれど、投手の投球数に関するルール制限が厳しくなったためと思われる。1回戦にエース級の投手を出すと、2回戦はどうしても2番手以下の投手が登板せざるを得ない。だから2番手以下の投手の力量の差が、2回戦ではハッキリ結果に出ることが多い。-----------------------------------------------------------≪2回戦に進出したチームの主なOBたち(現役のプロ野球選手)≫【千葉市リトル】・小笠原 道大 (現・読売、暁星国際高)・横川 史学 (現・楽天、常総学院高-青山学院大)【大宮リトル】・松本 啓二朗 (現・横浜、千葉経大付高-早稲田大)・大島 裕行 (現・西武、埼玉栄高)・吉野 誠 (現・オリックス、大宮東高-日本大)【名古屋北リトル】・堂上 剛裕 (現・中日、愛工大名電高)・堂上 直倫 (現・中日、愛工大名電高)【松阪リトル】・清水 昭信 (現・中日、三重高-名城大)・西川 明 (現・中日、三重高-法政大)・古木 克明 (現・オリックス、豊田大谷高)今日も1クリックお願いします
2009.07.05
コメント(2)
-

リトルリーグの「甲子園」開幕
リトルリーグの「甲子園」ともいえるザバス杯第43回全日本選手権大会が7月4日、江戸川球場ほかで開幕した。<1回戦の結果>■千葉市 6-2 武蔵府中■佐世保中央 2-1 松前■大宮 6-4 大和高田 (延長8回)■名古屋北 4-0 いわき平■松阪 4-1 調布■瀬谷 9-0 新潟中央■泉佐野 13-1 旭川大雪■笠岡 2x-1 仙台東 (延長8回)<2回戦> ※すでに終了しているが公式ホームページにはまだアップされていないため不明。組み合わせは下記のとおり。■佐世保中央 - 千葉市■名古屋北 - 大宮■松阪 - 瀬谷■笠原 - 泉佐野大会の優勝チームは日本代表として、「リトルリーガーたちの聖地」米国・ウイリアムスポートで行われるワールドシリーズ(8月21日~)への出場権を獲得する。 -------------------------------------------------------------リトルリーグと言えば思い出すのは仙台東リトル時代の佐藤由規(仙台育英高-現・ヤクルト)のこと。2002年に行われた全日本選手権大会。決して下馬評は高くなかった仙台東リトルだったが、「あれよ、あれよ」という間に勝ち進み、決勝では宝塚リトルを破り全国優勝をした。その勢いでワールドシリーズに出場し、こちらも決勝戦に進出。見事に準優勝を果たした。その時の仙台東、主力選手だったのが佐藤由規。ただ当時の佐藤を見た人に彼のことを聞いたことがある。「あまり大柄な選手でもなくて、球も速いわけじゃなかった。そんなに目立つ選手じゃなかったけどなぁ・・・」という声もあったが。仙台東リトル、佐藤由規のチームメイトには現・東北福祉大の中根佑二(仙台育英高)もいた。 今日も1クリックお願いします
2009.07.04
コメント(0)
-

「野球」と訳した中馬 庚
■米国から伝えられてた「ベースボール」という言葉を「野球」に訳したのは、東京帝国大学の学生だった中馬 庚(ちゅうまん かのえ)だと言われている。一高の野球部史(『一高ベースボール倶楽部史』)を編纂するにあたり、「ball in field」というイメージから「野球」と訳したことが、「野球」と呼ばれるようになった始まり。1895年(明治28年)2月、『一高野球部史』と改題して発行され、その後日本国内に定着したと言われている。※「野球」という呼称が定着するまでは、「ベースボール」以外に様々な訳語があった。書籍『明治維新と日米野球史』(島田明著、文芸社刊)はその例を紹介している。曰く、「ボール」「玉あそび」「打球鬼ごっこ」「塁球」「底球」などなど。中馬庚のこと。以下、wikipediaより引用。1970年には野球殿堂入り(表彰区分:特別表彰)を果たす。彼のレリーフには。以下の顕彰文が刻まれている。「明治27年ベースボールを「野球」と最初に訳した人で、また同30年には野球研究書「野球」を著作。これは単行本で刊行された本邦最初の専門書で、日本野球界の歴史的文献と言われている。また一高時代は名二塁手。大学に進むやコーチ・監督として後輩を指導。明治草創時代の学生野球の育ての親といわれた。」今日も1クリックお願いします
2009.07.04
コメント(0)
-

野球普及=都会+エリート+ファッション
■最初に日本に野球を伝えた米国人のホーレス・ウィルソン。彼は1871年(明治4年)に来日し、現在の東京大の前身、第一大学区第一番中学で英語と数学を担当し、その翌年に学生たちに野球を伝えたと言われている。そしてその後、野球というスポーツは急速に日本国内に普及した。勢いをもって野球の認知が拡大した理由は、ウイルソンによって最初に伝えられたのが偶然にも(現在の)東京大だったからという説がある。以下、書籍『明治5年のプレーボール』(佐山和夫著、日本放送出版協会刊)を参考に記した。■当時の学生たちは総じて大人しく、屋外で活発に行動するいわば「行動派」ではなかった。だから学生たちを屋外に連れ出すための道具として、野球は格好の遊びになった。したがって、ウィルソンは単に野球を学生に教えたというより、学生と一緒に野球という遊びを楽しんだというのが実情だったようだ。そして野球という遊びを日本の片田舎ではなく、東京のど真ん中、さらに東京大の前身となるエリート学校で行われたことが、後に野球人気が全国に拡大する重要なカギになった。なぜなら、「エリート校の学生たちが東京のど真ん中で始めたこと」は即ち、当時の最新ファッションとしてのメッセージ性を強烈に発していたからに他ならない。今日も1クリックお願いします
2009.07.02
コメント(0)
-

ボクにとっての日本野球史
(第1期)1872年(明治5年)、野球が日本に上陸した時以降「1872年、野球が日本に上陸した時代」 (2009.6.30) → こちらへ。 「ホーレス・ウィルソンと数々の偶然と」 (2009.7.2) → こちらへ。「「野球」と訳した中馬 庚」 (2009.7.4) → こちらへ。(第2期)1896年(明治29年)、一高が横浜アマチュア倶楽部に勝利した時以降「日米野球初戦、一高が圧勝す」 (2009.6.29) → こちらへ。 「野球を通じて「日本」を応援した人々」 (2009.7.12) → こちらへ。「1904年、『覇権我にあり』早稲田vs学習院」 (2009.8.29) → こちらへ。「1901年、早大野球部の黎明期」 (2009.9.19) → こちらへ。「1903年、早慶戦の端緒」 (2009.9.17) → こちらへ。(第3期)1905年(明治38年)、早稲田大がアメリカに遠征した時以降「75年前の日米野球のこと」 (2009.3.25) → こちらへ。 「日米大学対決は104年前に始まった」 (2009.6.23) → こちらへ。 「野球術を普及した安部磯雄と橋戸信」 (2009.6.24) → こちらへ。 「米国遠征の夢と財布の中身」 (2009.7.9) → こちらへ。「日本のバント事始め」 (2009.7.12) → こちらへ。「野球を通じて「日本」を応援した人々」 (2009.7.12) → こちらへ。「米国遠征で知った近代野球術」 (2009.7.13) → こちらへ。(第4期)1925年(大正14年)、東京六大学リーグが成立し、早慶戦が復活した時以降「プロ野球、創設プラン」 (2009.7.5) → こちらへ。「職業野球選手の社会的地位」 (2009.7.8) → こちらへ。「米国遠征の夢と財布の中身」 (2009.7.9) → こちらへ。「1935年、初米国遠征選手・苅田久徳の不満」 (2009.8.9) → こちらへ。「三原脩、職業野球選手になった頃」 (2009.7.19) → こちらへ。「戦前、「最後の職業野球」」 (2009.7.24) → こちらへ。「大下弘の少年・学生時代のこと」 (2009.8.2) → こちらへ。 「職業野球、戦前最後の東西対抗戦」 (2009.8.9) → こちらへ。「1941年、泣くな別所、センバツの花」 (2009.8.27) → こちらへ。「1932年、野球統制令」 (2009.9.2) → こちらへ。「1941年、泣くな別所、センバツの花」 (2009.8.27) → こちらへ。(第5期)1946年(昭和21年)、終戦後、東京六大学リーグ・職業野球が復活した時以降「西本幸雄、職業野球選手になった頃」 (2009.7.18) → こちらへ。「関根潤三、職業野球選手になった頃」 (2009.7.18) → こちらへ。「豊田泰光、職業野球選手になった頃」 (2009.7.19) → こちらへ。「三原脩、職業野球選手になった頃」 (2009.7.19) → こちらへ。「戦後、職業野球の復活」 (2009.7.24) → こちらへ。「戦後、職業野球の復活(2)」 (2009.8.1) → こちらへ。「1945.11.23、今日は東西対抗戦から64年」(2009.11.23)→ こちらへ。「東西対抗戦の背景」 (2009.8.1) → こちらへ。「東西対抗は大下弘がMVPに」 (2009.8.2) → こちらへ。「戦後すぐに復活したオール早慶戦」 (2009.8.3) → こちらへ。「大学野球復活を一番願った人」 (2009.8.4) → こちらへ。「戦後、高校野球の復活」 (2009.8.8) → こちらへ。「別所引き抜き事件(1948年)」 (2009.12.5) → こちらへ。「別所引抜き事件を企てた人と理由」 (2009.12.6) → こちらへ。「セ・パ誕生(1949年)の裏事情と近鉄」 (2009.11.28) → こちらへ。 (第6期)1958年(昭和33年)、立教大の長嶋茂雄氏が巨人に入団した時以降「西鉄、稲尾和久vs和田博実」 (2009.7.7) → こちらへ。「西鉄ライオンズ「黒い霧」事件」 (2009.7.10) → こちらへ。「1961年、柳川事件」 (2009.9.4) → こちらへ。(第7期)1973年(昭和48年)、巨人の連覇がV9で途絶えた時以降(第8期)1988年(昭和63年)、阪急球団がオリックスに身売りした時以降(第9期)2004年(平成16年)、近鉄球団の合併に端を発し選手会がストライキを決行した時以降「2004年選手会スト、なぜ選手会長を英雄視?」 (2009.8.15) → こちらへ。「2009年11月22日 セ、パ両リーグ誕生60周年記念試合・プロ選抜vs大学日本代表」の記録 (2010.3.7) → こちらへ。今日も1クリックお願いします
2009.07.01
コメント(0)
全36件 (36件中 1-36件目)
1