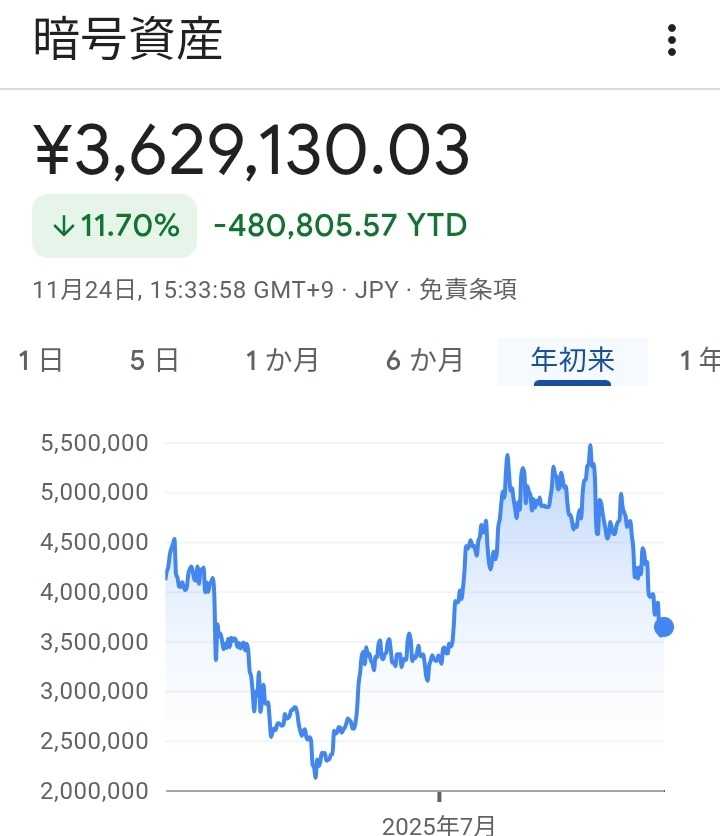2017年09月の記事
全29件 (29件中 1-29件目)
1
-
「山の神」諸説♪
〇興津要さんの「おもしろ雑学日本語」(三笠書房)の中に面白いものを見つけました。それは「山の神」。 「山の神」の語源 山の神通う神をばこなみじん 捨6 ”通う神”と言うのは、遊女が客に出す手紙の封じ目に書く文字だが、怒った女房が引き裂いた光景。 このように結婚後数年を経て、うるさ型になった女房を”山の神”と呼んだ。ほかに、 語源その1 いろは説 それは妻を奥と言うが、<憂いのおくやま・・・>と、”山”の上に”おく”があるから”山の神”と称したとする説。 語源その2 「俚言集覧」説 この書では、上の説を否定し、”とり乱したる姿を喩えて言うなるべし”との見解。 語源その3 柳田国男説 山の神は多くが女性であり、山姥の子育て伝説など、山との関係が深いと説く。 語源その4 暉峻康隆説 農村で、山の神を祀るのは女性が司っていたからという説。 語源その5 杉本つとむ説 山の神というのは、農民の間での女神で、十二の子を産むと言われ、 神への供物であるオコゼ魚を女が食べると、生まれる子が荒っぽくなるとの伝えがあり、 この妙に元気の良すぎる女房を、下々で山の神様になぞらえて、山の神と呼んだのでは?とする説。> 奥さんをして、山の神という表現を耳にするとき、私には恐妻、嬶殿下といういうイメージを持ってしまいます。
2017.09.30
コメント(0)
-
辰巳芳子さんのスープ♪
〇高齢ながらスープの第一人者:辰巳芳子さんのスープ。自然界の恵みから”命を育む”料理者のお心構え。”料理は愛”というのが従来のわが信念でしたが、辰巳さんの”料理は祈り”という言葉に、料理に携わる人々への基本姿勢を学びました。某テレビ番組から、真摯に生きて来られた”摂理めいた言霊”を感じとりました。わたし達は”人から学ぼう”とし勝ちですが、そうではなくて、”自然の現象から学ぶ”とおっしゃいました。スープを作る時、輪切り4分の1の厚みは5mm、ジャガイモは1cm、セロリーや玉葱も薄めに切る。何故?・・・出来上がった時、どの食材も同じ柔らかさを持たせる為。 炒め蒸しの段階では鍋の蓋に集まった滴を大切に。これは人参などの甘さと香りの大切な要素だから。そして料理が良くなるように、良くなるように祈りながら工夫して行く。 ”幸せがやってくる”のを待つのが美味しい料理の極意と言われていました。高知の某病院で600人の患者さんに試まれたスープの種類は、「人参ポタージュ」「なすと大麦のスープ」、食の細い患者さんへの「しいたけスープ」「玄米スープ」でした。料理長初め、病院のスタッフ一同の皆さんの真剣な取り組みも感動ものでした。
2017.09.29
コメント(0)
-
拙作「助言」♪
*** 助 言 *** 1)子供たちよ 俺の言うこと かすかに 憶えておくれ どんなことにも 関心を持て 自然と友達に なることだ 子供の頃に 覚えたことは 一生 忘れはしない だから 遊びなさい 2)子供たちよ 俺の言うこと 何処かに 残しておいて どんなことにも 逃げたりせずに 勇気とファイトを 呼び起こせ 子供の頃に 覚えたことは 一生 身につくものさ だから 遊びなさい 現代の子供は可哀相ですね。道端で遊んだり、原っぱで時間を忘れて遊ぶことなどできないから。人間がパソコンと言う不思議な箱に埋め込んだゲームに躍起になって闘う、ただ、それだけのワンパターン。 私達の時代は自分たちで遊び道具を作ったり、ルールを決めて遊びをアレンジし直したものでしたが。遊び相手の顔も見えないほど、とっぷり暮れた外で時間を惜しむように遊んだものでしたが。 大将になる兄さんが居て、年下の子はその家来になるけれど、やがて自分にもお鉢がまわってくる日を夢見ていたのでしたが。風のそよぎ、空の青さ、広さを肌と目で覚えていました。 遊びの中からいろんな工夫も出来たし、新しい発見もありましたが・・・。
2017.09.28
コメント(0)
-
多くを語らぬ昭和の歌♪
〇いつぞや吉田拓郎とかぐや姫のメンバーが数十年ぶりにライブを行ったところ、三万以上もの聴衆が集まったようでした。合唱曲もポップスも演歌も行き当たりになったのか、随分前からテンポの忙しい難曲ばかりになっていました。 小室哲也氏がテンポのある曲を作ったり、それに同調して、やたら長い歌詞が流行り、アクセントやイントネーションを無視した曲が横行しました。NHK「あなたのメロディ」の審査委員長だった高木東六氏がかんかんになって怒りそうな曲が時流になっていました。 果たしてそれが正しいのでしょうか?合唱曲においてもリズムや音程の不自然さ、不協和の連続した曲が主流になっていますが、それで良いのでしょうか。 演歌なら四小節が既存の曲と一致する場合、新曲として認められないし、ポップスは同様に八小節かぶった(重なった)ら盗作容疑で新曲として受け入れられないから、それらを回避するため矢鱈に装飾部分が増えたので、テンポも速くなったのではないでしょうか? 吉田拓郎氏やかぐや姫バンドに多くの人々が集まって、四半世紀前の良き時代を懐かしんで居られたのは、曲がゆったりと進み、聴衆一人一人の心に染み透る”優しさ”があったからではないでしょうか?
2017.09.27
コメント(0)
-
比叡山、ロテルド比叡にて1泊♪
〇京都駅から送迎バスに乗り、昨日午後3時頃チェックイン。フランス料理、幾種類もの茶を味わいました。翌朝6時から根本中堂に向かい、朝の読経と法話を聞きました。何よりも道中の雲海の見事なこと。ガーデンミュージアム、横川、西塔など巡り、ホテルに戻り、再び送迎バスにて京都駅まで送って貰いました。
2017.09.26
コメント(0)
-
輪違屋と角屋♪
〇京都島原大門の近くには太祇が棲んだと記されています。歌人:吉井勇氏の「不夜庵物語」には、流れるような名調子で、この島原界隈のこと、当時の俳句熱の様が活き活きと書かれています。 大門を潜って間もなく右手に折れると、有名な輪違屋という「置屋」が京都市の文化財にしていされています。元禄時代に建てられ、安政4年に再築、明治4年に改築されていますが、黒光りする廊下や、道中傘の紙を貼り込んだ傘の間や、紅葉の葉をあしらった紅葉の間、太夫さんの書いた恋文の下書きや、近藤勇(又の名を藤原昌宣)筆の屏風が見所です。 一方、揚屋で置屋の「角屋」は料理屋を兼ねていますので、土間が50畳、準備の台所も50畳もあり、43畳の松の間や28畳の網代の間や二階の部屋の窓格子の模様などが逐一異なっていて、且つ美的感覚の斬新な柄を持っています。
2017.09.25
コメント(0)
-
薄(芒)に寄せて♪
〇某年9月23日の朝、ゴミ出しの時間が迫る中、庭木や草の整備を心がけて呉れている家内の出した除草の大半がススキだったので、もう全部刈ってしまったのかと危惧しましたが、 この文を認め乍ら出窓をみると秋の陽を受けて、時には金色に、また銀色に輝く芒がさようならの手を振るかに揺れています。 金田一春彦さんの「ことばの歳時記」から拾いますと、<ススキは昔から日本では屋根を葺く材料として重用され、また炭俵などの材料としても使われた。 日本人にもっとも親しまれる草の一つで、「芒」という正しい字では足りず、 「薄」という中国では全く別の意味に使われる文字まで、いつの間にか当てて使っている。>とあります。また<ススキというのは元来雅語で、口頭語はカヤである。>つまり茅葺の茅、萱のことです。 大阪は住吉・帝塚山の社宅は20坪ほどの狭い住まいでしたが、 黒塀の隅っこにススキが群れ生い、梅雨には俄かに延び始め、秋の穂が済むと、丈夫な茎をチャンバラごっこの刀として隣の子供たちと遊んでいました。また茎を使って、庭の片隅に秘密基地の小屋を作ったりなどしていました。私にとってススキは少年期を想い起こすものでもあります。
2017.09.24
コメント(0)
-
露草や露をこぼして青残る すばる ♪
〇父すばるが亡くなって、十七年半。すばるから直接の指導は受けていませんが、遺してくれた次なる二つの作品は、写生俳句の素晴らしさを教えてくれているように思います。 露草や露をこぼして青残る すばる<露草の咲く墓なれば死んで良い 星子>という位に私も露草が大好きなのですが、何と言っても、あの清楚な青い色に心洗われる清涼感が堪りません。 掲句は、露草の花に大粒の露が溜まり、ほろりと落ちた。露の玉がレンズとなって、その青い色まで落としたかに見えたけれど、すぐさま、無色透明の水滴となって地面に吸い取られ、露草には元通りの青色が残っている。露玉がレンズの役割をして、花の青い色を拡大した刹那の妙が詠われています。 如露の水金登りくる金盞花 すばる 人は総じて花が好き。喩え猫の額ほどの庭であっても、花の種を蒔いて小花を咲かせます。金盞花という花は、太目の茎の先端に濃い橙色の花を着けます。水遣りの如露の先から数条の水糸が流れ落ちる時、細い糸を逆さまに花の金色が登って来ます。濃い金盞花の金色が伝い登って来るのです。単なる水撒きの中にも鋭い観察力以って臨むのが句詠みの宿命なのでしょう。
2017.09.23
コメント(0)
-
火事こばなし三題♪
〇「火事」に関するユーモアを秋田実さんのものから三題拾いました。 540話 釘を刺す 電話のベルが鳴った。消防署員が急いで受話器を取り上げると、 受話器の向うから物静かな婦人の落ち着いた声が聞えて来た。 「もしもし、私共では先だって庭に花壇を作ったのです」 「こちらは、消防署ですよ」 「わかっています」 と老婦人は静かな声で続けた。 「この花壇には薔薇やダリアやチューリップや、その他いろんな高価な球根を植えたばかりの処なんです」 「それが一体どうしたというんです??」 消防員がイライラして怒鳴るように言うと、 「ですから、お宅の署員の方がお出でになった時に私共の花壇を荒らさないように、よく気をつけて欲しいのです。 今、お隣りの家が火事です!」 541話 ちゃっかり ボーイが、ドアを激しく叩いた。 「お客さん、起きて下さい。ホテルが火事です」 すると部屋の中から、泊っていたスコットランド人が答えた。 「よオし、分った。その代り、ホテル代は払わないぞ!」 543話 名答 映画館の経営者が自分の劇場に火災保険をかけることになった。 そして契約書にサインをして加入手続きを終えてすぐ、 保険会社員の方に向き直ると、たずねた。 「もし私の劇場が、今夜焼けたとしたら、どういうことになりますかな?」 「そうですな、今までの私の経験では、まず10年の刑というところですな」 と、冷たく答えた。
2017.09.22
コメント(0)
-
九九の暗唱法♪
〇わが国の九九算の歴史は驚くほど古く、平安時代の九七〇年、源為憲の『口遊kutizusami』に書かれたのが最初だとか。当時の貴族の子弟教育の教科書として使われたもので、九九八十一、八九七十二、七九六十三といった具合に今とは逆順、だから九九と称したのかも知れません。 和算という算術が庶民に広がったのは、江戸時代まで下り、その功労者は京都の人。大堰川や高瀬川の開削で知られる角倉了以の叔父のひ孫にあたる吉田光由がその人で、著書は『塵劫記』。角倉というのは屋号であって、角倉一族の姓は吉田で、了以の子・素庵は土木建築事業に数学は欠かせないと思い、従兄弟の光由の研究をフォローし、共に研究した結果、一六二七年(寛永四)、実用的な『塵劫記』が誕生したと伝えられています。そろばんの使い方、九九の暗唱法、ねずみ算の例題なども鼠の絵入りで書かれているようです。右京区梅ケ畑の菖蒲谷池と、岩をくりぬいた凡そ二百メートルの水道は、光由と兄・光長の尽力によります。傾斜を数学的に考慮しているので、池の最期の一滴まで使えるとか。
2017.09.21
コメント(0)
-
向田邦子さんに学ぶ♪
〇随分前のNHKのテレビ番組で、向田邦子さんは若い女性からの「理想と憧れる女性像」として憧れの対象になっている方だと報じていました。 その中で実の妹さんが言われた言葉に囚われたのは、 {お姉さまは服装のセンスが良くって、気に入った服は色違いでお揃えになっていたようですね?}というアナウンサーの問いに、<「ええ、洋服などのスタイル・柄を選ぶのは殆ど直感だったと思います。随分昔から、そのような直感を蓄える努力をして居たようです。」私はいつも思うことですが、<謙虚な気持ちに立った受動であって、且つ、それは将来、能動の為の受動であるべき>と。 わたし達は生きている限り常に新しい空気を吸い、吐き出し、また新鮮な空気を取り入れる作業を繰り返していますが、 精神面においても、この「仕入れ」を意識した生活を続けたいと思うのです。
2017.09.20
コメント(0)
-
萩まつり♪
〇昨日は御所に隣接する梨木神社にて京都府市民俳句大会(萩まつり)がありました。参加人数は217名。応募作品は434句。12名の審査員が各自佳作7句準特選2、特選1句を選んでおられる同タイム、会場の我々も互選しました。知事賞に輝いたのは句友の 参道は萩の枝垂れの遠近法 峰 月俳句作家賞は ほほゑみはひとつの言葉萩日和 紀代子京都新聞賞は 萩叢に隠しカメラのやうな猫 栄 子毎日新聞賞は 白萩や影のさゆらぎ日のゆらぎ 千津子読売新聞賞は 一指hitosasiに萩の風立つ能舞台 せい子といた秀句でした。運営・進行は京鹿子のメンバーによります。小生も句友と共に、互選句の披講を務めさせていただきました。多田宮司のご挨拶のなか、今年は白萩が随分増えました。手を加えるのではなく、ごく自然に、紅萩が白萩に変化しているとの談に驚きを隠せませんでした。
2017.09.19
コメント(0)
-
三橋節子さんの表札♪
〇もう十数年も前のことですが、銀閣寺の近く、山際の閑静な住宅街にある画廊に入りました。手前は洋館で、特殊な技法で描かれた画の色を見て、何処かで見た色合いだなと思いました。更に奥の和室の画廊を見せて貰いました。緑茶まで振舞っていただきました。 土佐水木や花水木の樹木に金箔を施した葉のオブジェが数珠繋ぎに垂れ下がって居たり、石畳には鉄製の大きな三日月のようなオブジェも据えてありました。亡父の椿の話など、ご夫人と話しながら、ちょっと気になる質問をしてみました。 「お庭へと通じる木戸口に<三橋>という陶器製の表札がありますが、大津の三橋節子画伯と何かご縁でも?」 「ええ? あの表札は三橋節子が作ったものです。主人は節子の弟です。」 という偶然、そして直感的な因縁に驚きました。先方さんも驚いていらっしゃいました。丁重にその邸宅を辞し、平日でシーズンオフゆえ人通りの少ない「哲学の道」沿いの、タイの調度品がユニークな喫茶店で休憩。 道から少し逸れたところにある工房「おくきた」さんは、染物、陶器、ワイヤー加工が個性的で、試験管の一輪挿しを購入、店主のご婦人も素敵な方でしたので、「大山崎ふるさとガイド」の名刺と交換しました。 哲学の道沿いの川には大きな緋鯉や鯉がのんびり泳いでいました。バス停にはノートルダムの生徒たちが一杯。亡父が20年近く教鞭をとった学校の生徒たちです。時の流れを感じながら、ゆったりとした一日を過しました。
2017.09.18
コメント(0)
-
『源氏物語』美女の競演♪
〇平安王朝の衣装を知る上で欠かせないのが、紫式部の『源氏物語』。その「若菜」の下から拾ってみます。六条院の「女楽」は、女性ばかりの弦楽四重奏と言えば解り易いでしょう。とき 旧暦正月二十日ごろ場所 六条院人物 光源氏 四十七歳 紫の上 三十九歳 明石の上 三十八歳 女三の宮 二十一歳 明石女御 十九歳庭の梅の盛りのころ、女三の宮の御殿にて、音楽のわかる厳選した女房などが参集。 表 着 汗ころも 襦 袢紫の上 赤 さくら 薄紫の織物明石女御 青色 蘇芳 山吹の唐のあやぎぬ明石の上 紅梅 桜 青磁 濃紫 薄紫女三の宮 青丹 柳 葡萄染 着衣の順序から言えば、表着の上に細長を着るので、紫の上は赤紫、明石女御は紅梅、女三の宮はさくら色(裏が赤、表は白)、明石の上は柳(裏緑、表白)という出立・女三の宮はあえかに美しく、明石女御は藤の花、紫の上は、桜の匂い充ちた華やかな姿に気おされず、明石の上は「柳の、織物の細長、萌黄にやあらむ、小打掛、うすものの裳のはかなげなるひきかけて、ことさら卑下したれど、へはひ、思ひなしも、心にくく、あなづらはしからず」と。(参考図書・近藤富枝著『服装から見た源氏物語』)
2017.09.17
コメント(0)
-
大奥豆事典♪
〇江戸城本丸の広さは四万七千三百坪(堀井戸十七個)、二の丸一万一千百坪、三の丸六千四百八十坪、西の丸は二万五千坪(堀井戸十一個)、紅葉山二万坪という壮大なスケールだったようです。 表御殿に中奥を加えた将軍の公務や居住区域は四割、一方大奥は六割の建坪を占めていたとか。 その大奥は、御殿向きと御広敷向きと長局(女中たちの居住区)向きの三つの部分から構成されていました。 御台所や側室の多くは、大奥の庭を散歩するのが関の山、運動不足に白米摂取が祟り、脚気を患いがちでした。 将軍と同衾する側室の定年は三十歳で、超えればお褥下がり。子供を設けた場合は、お腹様と称して大奥で子供と一緒に暮らせましたが、 子供のない側室は大奥という牢屋に飼い殺し状態となっていたようです。一方、将軍が亡くなると、 御台所や側室は尼同然の生活を強いられましたので、決して幸福な人生とは言えませんね。 日本の王は天皇ですから、将軍と言えど、非王非侯(公家)だから、通常は公方様と呼ばれていました。将軍と言う呼び名は随分と後のことでした。(参考図書:邦光史郎「大奥の謎」)
2017.09.16
コメント(0)
-
がんこ寿司にて九曲ハモった??
○某年某月の或る日、グリー時代の友人H君から緊急電話が入り、同期のN君が漸く大阪に顔を出すと言うから、身体の空いたメンバーだけでも梅田で逢おうということになり、梅田まで出掛けました。学生時代より馴染みのあるミュンヘンでも良いのですが、九人の声が聞え易いのは和風の小部屋が良かろうということで、がんこ寿司で乾杯することにしました。学生時代の練習や合宿の思い出、沖縄演奏旅行の思い出や逸話など、話題は転々と変りながらも尽きることがありません。生ビールのジョッキーに始まって、焼酎を何本空けたのでしょう。でも、隣りの席の四人組さんからのリクエストもあって、数曲、即興でハモラせました。ふと時計を見ると十時半。わたし達九名は四時間余り飲み続けていた勘定になりますが、再会を誓い合って散会しました。
2017.09.15
コメント(0)
-
「信長公記」から♪
〇わが国の偉大な戦国大名・織田信長公の最期をつづった部分。<六月朔日、夜に入り、老の坂へ上り、・・・(略)。信長も、御小姓衆も、当座の喧嘩を下々の者ども仕出し候と・・・(略)、明智が者と見え申し候と、言上候へば、是非に及ばずと、上意候。(略)信長、初めには、御弓を取り合ひ、二、三つ遊ばし候へば、何れも時刻到来候て、 御弓の絃切れ、其の後、御鎗にて御戦ひなされ、御肘に鎗疵を被り、引き退き、是まで御そばに女どもつきそひて居り申し候を、女はくるしからず、急ぎ罷り出でよと、仰せられ、追ひ出させられ、既に御殿に火を懸け、焼け来り候。・・・(略)> 歴史書として著名な「信長公記」(人物往来社)桑田忠親<校注>から一部抜き出しました。原本を解読するとなると大変ですが、後世の学者の注釈のお陰で、楽に読むことができます。
2017.09.14
コメント(0)
-
拙句記録ちやう♪
○歳は取りたくないもの、何故かと言えば、ここ数か月の自作を抜粋した句を翌月初にまとめることを失念していたことに、今頃気づいたのだから。29年6月分 敵将の裏読む謀将木下闇 蜘蛛の子や伝達母衣衆四散せり◎黒南風kurohaeや村上水軍砦跡○紫陽花やこの身を預く万華鏡○其のかみの寺は城郭山法師○祇園社は断層の上梅雨しとど29年7月分 登り来て山気ひとしほ甘酒屋◎神木に隣る綿菓子夏まつり 禅寺やあれに見ゆるは夏椿 梅雨昏kuraし撚糸工場の老主 甘酒や苔むす屋根も味のうち 下賀茂や蝉極楽の杜の風29年8月分○朝顔や濡れ飛石を利休下駄○海洋図沖の永良部の星流る やすらぎのふうせんかづらそんな彼○新涼や一本挽きの蕎麦どころ○街灯の届かぬ闇や虫の秋◎騒立ちの瀬々や美山の鮎どころ 朝霧やひと目で判る愛宕山○秋声や書院の棚の翁面まぁ、こんなところでしょうか。○祇園社は断層の上梅雨しとど
2017.09.13
コメント(0)
-
女の気持ち♪
○毎日新聞社生活家庭部が編纂した「女の気持ち」(求龍社)という本を繰っていたら、「夢の一人旅」という題で51歳の主婦が書いていらっしゃるものが見つかりました。 旦那様が結婚前には世界一周旅行に連れていくと約束して置きながら、子供のことで手がいっぱい。せめて日本一周ぐらいさせて貰わないと割が合わない。しかしこの歳になると、旦那連れよりも一人旅に憧れると。 <青春の苦い思い出をかみしめながら、若い頃訪れた九州や子育てに専念した北海道へ旅したい。「一人で旅行ですか?」と声をかけられたらどうしよう。 「はい、主人に先立たれまして」と言おうか、それとも「はい、独身を通しまして」と言おうか、想像しただけで胸がワクワクする。だけど、私のことだから毎日家に電話を入れて 「ご飯はたべたの?」「ネコにえさはやった?」「洗濯・掃除は?」と騒ぐんだろうなあ。つくづく損な役回りと、思う。・・・でも、私は夢を見る。心ときめく一人旅。いまにきっと 一人旅にでるぞォ。> 本文そのままの部分と要約した部分がありますが、日本の主婦の心理が浮き彫りにされていますね。
2017.09.12
コメント(0)
-
乙訓の語り部♪
〇父が遺した新聞記事の昭和53年度分の中心は「おとくに語部」という今から40年ほど前、当時70~85歳ぐらいの古老たちの昔話が載せられています。 向日町楓畑の紅葉屋さんの裏辺りに芝居小屋ができ、芝居や漫才、浪曲などが演じられていたそうな、鼓をポンでお馴染みの”砂川捨丸”が若い時代だったそうな。 今のような事前の天気予報の無い時代だったから通常通り授業が行われていた時、風速60メートルの室戸台風が襲ったので、先生や児童が多く犠牲になったそうな。 長岡町の旧役場前の通りには電線が架けられていなかったので、日活がロケ地として頻繁に撮影していたそうな。八条ケ池に面している錦水亭の座敷から侍が飛び込むシーンも何度か撮影されていたそうな。 昭和12年頃、その長岡町に映画館を作ろうという話が持ち上がって神足校の南、墓近くに土地の手配も済んでいたのに許可が下りないまま戦争に突入していったそうな。 小倉神社の春祭りは乙訓(オトクニ)一番の豪華さで、右座・左座の2基の神輿のうち、左座のものは稲荷神社の5基に負けないほど立派で、行列は440メートルほどの長さだったそうな。 石清水八幡さんへのお参りには”山崎の渡し”やそれより上の”狐渡し”を利用して中州で降り、また別の渡しで橋本へと渡ったそうな。狐渡しの方が若干船賃が安かったそうで、昭和11年5月に廃止、山崎渡しも昭和37年4月に廃止されたそうな。 大山崎の現役場前の西べりには5本、東べりには3本の松の大樹が並んでいたそうで、松原の地名の名残のようです。昭和10年新小学校建設当初には西に2本、東に1本残っていたのに、造成で伐採されたそうな。 それを懐かしんで加賀正太郎は中ノ島(背割)に松並木を植えたそうな。巨椋池とこの松並木を天の橋立に模したとも。その松も枯れ、京都府が桜の並木に変えたそうな・・・。
2017.09.11
コメント(0)
-
舞妓から芸妓に♪
〇随分むかしの話ですが、句友O氏のお誘いで、舞妓から芸妓になられた小愛さんのお酌を頂きました。舞妓時代は地毛、芸妓になれば鬘になるのですが、濡れ烏色の髪の艶、程良い化粧のお顔には、どんぐり瞳が愛らしい。小愛さんは勝気な上に頭の回転も素晴らしく、現代っ子の健康な色香の中に、将来の白馬の王子を夢見る乙女。 私たちが俳句を嗜むと聞いて大喜び。実は彼女も数人で句を楽しむ文学芸妓なのでした。毎月、彼女が季題を決め、寸暇を割いて今日的な句を見せ合っているそうな。小愛ちゃんへのわが献句は 来ぬ人に朝の座敷のいとど哉 いとどはコオロギのこと。来ぬのコ、朝のア、いとどのイ、つまり小愛さんの名を織り込んで詠みました。小愛さんはふところに挿していた女物の扇子を取り出し、此処に書いておくれやすとのたまいました。さて彼女も一句ひねり出し、 弾む下駄君の姿に良夜かな かわゆい娘心を詠いこまれました。 愉しい宴が終わる前に、おりくは歌舞伎の声色を遣いました。 <ご新造さんへ、おかみさんへ、お富さんへ、いやさお富、久ぶりだなぁ~>昔春日八郎が歌った流行歌でお馴染みの源氏店・きられ輿三の「輿話情浮名横櫛」の一節です。 小愛姐さんのアンコールに応えて、「三人吉三廓初買」の<月も朧に白魚の、かがりも霞む春の空、・・・も小愛さんと一緒に披露しました。お座敷遊びは、周りの同胞を持ち上げる気配りと、<好かれるお客像>を胸に、座を盛り上げることが大切なのかも知れませんね。
2017.09.10
コメント(0)
-
リフォームの頃の思い出♪
〇この拙文は凡そ11年前、今の住まいのリフォーム時の一コマです。<今月末引渡しとなる生家のリフォームもいよいよ最終段階に入りました。西向日のわが家から大山崎歴史資料館での当番に行く道がてら、午前中に建築中の現場に寄りました。リフォーム前より勾配が緩やかになった表の石段。その両側の自転車昇降坂の工事中でした。 玄関の靴箱にも戸が入り、和室には、押入れの襖、玄関口への両襖、増築した寝室への仕切りも和風の襖(中央部分は障子)で、そのいずれもが明るい薄緑色。かなり上品な和室になりました。 寝室の東側は深い焦げ茶色のウッドデッキで幅を150cm取りましたので、小さなテーブルも置けそう、また蛸足の物干しも中で吊れそうと家内が嬉しそうにしていました。このデッキは洋間からも出入りできるようにしましたので便利だし、蒲団干しも2枚出来ます。 洋間の白壁の塗装も済み、随分明るいままダイニング・キッチンに続いています。仕切りの戸3枚の中央にはガラスをはめ込んでいますので、洋間の戸を閉めても台所はそれほど暗くならない見込みです。 照明に関しては従来から馴染みの電気屋さんに正式に依頼しましたので、来月は、先ず生家の家具等を配置し、中旬頃、向日町のタンスなどの家具を運び入れる段取りです。 そうそう修理依頼していた仏壇具屋さんからお仏壇も運んで貰い、カーテン屋さんにカーテンなどを装って貰った時、リフォームの完成になります。お坊さんに仏壇の魂入れをお願いした日から、亡父・亡母やご先祖さまとの同居が始まります。> 数年前、各部屋の窓やガラス戸は遮光性のものに変え、二重構造に再度工事して現在に至っています。
2017.09.08
コメント(0)
-
作詞「京暦」♪
〇拙作「京暦」 恋という字に 心を染めて 焦がれる女と 知りながら 哀れ散る散る 櫻花 京は円山 花かがり いつも泣き言 言っては拗ねる それでも貴方を 許してる 哀れ降る降る 五月雨に 京は賀茂川 杜若 どうせこの世で 添えないのなら 死んでも貴方の 影法師 哀れ鳴る鳴る 鐘の音に 京は嵐山 紅葉山 夢か現か 幻なのか 貴方に抱かれた あの宿の 哀れはらはら 舞い落ちる 京は鞍馬の 雪景色 大好きな京都の四季を歌詞に折込みました。この歌詞は平成8年ころの作品で、曲の仕上がりは先ず先ずの出来栄え。バックのリズムの附け方に難点があります。
2017.09.07
コメント(0)
-
『明月記』より♪
〇堀田善衛著「定家明月記私抄」続編(新潮社)の頁を繰っていると、現代にも通じる様々な出来事が網羅されていて、興味が尽きません。以前には歯の治療の件りを述べたのですが、続いてこんな奇妙な記述がありました。建暦2(1212)年、<吉富広宿傀儡ノ輩ト、忠弘ノ下人等闘諍ノ由、夜前、使ノ者来タリテ告グト云々。 (略)・・・今日、吉富広宿ノ傀儡等来タリテ訴訟ヲ成ス。(10月5日)・・・子細ヲ含メ、下向セシム。・・・ 明らかに身分が上である定家が、彼らの訴訟に下手から対応しお引取り願ったという。しかも、筋の通らぬ話であるけれど、一歩譲って張り合わなかったようです。 その背景には、後白河院の時代から天皇家が白拍子や傀儡師の芸に惚れ込まれ、こういう下層の芸人たちに身分保証を与えたり、全国出入り自由の証を与えて居られたことや、 公卿たちの中にも遊女・舞女・白拍子を母にしている人が多くなり、これらの女性を母とする皇子もあったようなのです。天皇の権威が落ちてゆくに従い、これらの遊芸集団が賎民視されて来たようです。そして定家を可愛がって下さった後鳥羽院も、白拍子や猿楽の人々を優待していて仮設の舞台などを設営させていました。この贅沢さには定家は上皇との根本的な価値観の違いを感じていたようです。
2017.09.06
コメント(0)
-
大山崎・離宮八幡創建千百五十周年祭♪
○7年程前の9月、大山崎町大山崎の離宮八幡宮で15日、「創建1150周年祭」が営まれました。 製油業界の関係者や地元住民ら約120人が参列し、中世に油座の拠点として栄えた歴史を振り返るとともに、今後の発展を祈願しました。 同八幡宮は859年、僧行教によって豊前国宇佐(大分県)の八幡神が勧請され創建されたとされます。 嵯峨天皇の河陽(カヤ)離宮があったことから「離宮八幡宮」と呼ばれるようになりました。 「創建1150年」に先駆け、昨年は本殿の屋根の葺き替えや拝殿の増床工事が行われました。供え物の油缶がずらりと並んだ本殿で、雅楽が奏でられる中、記念祭が始まりました。 出席者は油を入れて火がともされた小皿を受け取り、正面に据えられた八足台に置き、厳かに献灯。 無病息災を願い、巫女が釜で沸かした湯に笹の葉を浸して振り撒く湯立神楽の神事も行われました。 津田定明宮司は工事に対する企業や個人の協賛に謝意を示され、 「油商人発祥の地として、今後も国家の安康や国民の平穏を目指して務めを果たしたい」と挨拶された。(参考出版物・当時の京都新聞記事)
2017.09.05
コメント(0)
-
女性の髪エトセトラ♪
○古来から髪は女性にとって、それは命に等しいほど大切なもので、吉田兼好も 「女の髪のめでたからんこそ、人のめだつべかんめれ」 と徒然草に書き残しています。 その頃の美容法では、黒胡麻を9度蒸し9度水にさらし、粉にしてなつめのにくとまぜて丸め、日に20粒ずつ朝夕飲めば黒髪になれるという記録もあるようです。 短い髪の女性を助ける法として”おちやない”という商売つまり落ち髪はないか?と言って買い歩き、それをかもじ(加文字)つまり鬘にして売り歩く商売があったようです。 源氏物語や枕草子、栄華物語にも表記されていて、髪の短い女性に鬘が利用され、 表着(ウワギ)の裾から1尺2寸(呉服屋の物差し)ほど出るのが良いとされていた由。 鬘の種類、舞妓、芸妓、花魁などの髪の種類や装飾品については「日本髪の世界」を検索願います。 参考図書・奈良本辰也編「京都故事物語」(河出書房新社)
2017.09.04
コメント(0)
-
童謡「月の砂漠」♪
〇或る夜のこと、月の砂漠のテントから乙女が出てきました。童謡の「月の砂漠」そっくりの、音のしない月夜を二人してラクダに乗って、何処へともなく揺られていました。そんな夢・・・・。 1.月の砂漠を はるばると 旅の駱駝が ゆきました 金と銀との 鞍置いて 二つならんで ゆきました 2.金の鞍には 金の甕 銀の鞍には 銀の甕 二つの甕は それぞれに 紐で結んで ありました 4.曠い砂漠を ひとすじに 二人はどこへ ゆくのでしょう 朧にけぶる 月の夜を 対の駱駝は とぼとぼと 沙丘を越えて 行きました 黙って越えて 行きました 3番の歌詞は誰でも知っていて、前が王子で、後ろがお姫様 、そしてお揃いの白い上着を着ていましたね。 2番の歌詞はうろ覚え、4番は殆ど知りませんね。作詞者:加藤まさを、作曲者:佐々木すぐるです。実にロマンティックな歌詞で、メロディと歌詞が見事に融合しています。広島県三次市の元音楽教師、河本正治さん(平成2年当時70歳)が同好の仲間15人と結成した「赤とんぼの会」が発行した全8集。594曲も掲載された、絵本のような童謡集を8冊とも父が遺していました。 カットの絵が明治・大正・昭和への郷愁を呼び起こさせる図柄で、この歌集は非売品(個別頒布なら1冊1200円)ですが、直接河本さんから取り寄せたものと思われます。今年の中秋の名月は10月4日、9月の15日まであと10日あまり。平和な月に心を寄せて、久しぶりに童心に戻りましょう。
2017.09.03
コメント(0)
-
皇家の末裔から武家誕生♪
〇平安時代の地方行政は、中・下級貴族が任じられて国司(=受領)となり、任務地からの徴税を政府に納めていました。任期が切れてもその地に残り、新しく赴任して来た受領に対し、これまで通りの徴税を代行する代わりに支配力を認めさせるように変遷。 平将門の父は桓武平氏の祖、高望王の次男・良持で、下総国に土着し力を蓄えたのち、陸奥国胆沢城に赴任。その兄の国香は常陸国に土着しつつ勢力を有していましたが、平将門の代になって滅ぼされました。この内乱以降の将門勢力の増大を恐れ、国香の子、常陸掾・平貞盛、貞盛の叔父下野掾・藤原秀郷らが押領使となって将門を征伐。源氏と言い、平氏と言い、皇族の一部が臣籍降下したもので、二度と皇家に戻れない立場から、次第に力をつけ武家として権力を持つようになりました。
2017.09.02
コメント(0)
-
おわら八尾・「風の盆」♪
〇いつか果たしてみようと思いながら何らかの事情で未遂のまま繰越していることが多々ありますね。今なお果たせそうで果たせていないのが、富山県八尾の「風の盆」の見物です。高橋治氏の小説と亡父すばるの俳句によって、伝統的な田舎の盆行事、影絵のような男舞い・女舞い、空の暗さと奔流する水音などが既に脳裏にインプットされているのですが・・・。 風誘ふ手振りとも見ゆ風の盆 風の盆権現立ちの男振り 風の盆反り身で決まる女振り 暮れんとす空濃く濃く濃く風の盆 天界に風の盆あり戻りバス 平成5年にすばるが詠んだ「風の盆」30数句の一部です。 ところで、エッセイは俳句から音楽へ。石川さゆりさんの「風の盆」はカラオケでは十八番(おはこ)の一つ。少しキーを落とせば、女性の声でも歌います。最近は、島津亜矢さんの「八尾恋歌」も歌詞に風情があって好きな曲。セリフ付きの「おつう」は説得力があるのかも?美空ひばる程の歌唱力と評される亜矢さんの歌に嵌りつつあります。異色なところでは、ブラザーズフォーのGreen Fieldなど、グリーの先輩が歌ってらしたもにもtチャレンジして参ります。
2017.09.01
コメント(0)
全29件 (29件中 1-29件目)
1