2017年02月の記事
全2件 (2件中 1-2件目)
1
-
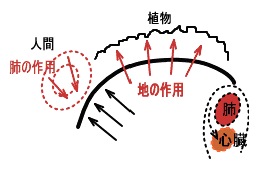
ネット情報の活用法 その1338
またまた久しぶりに書きたい。 巷は某ならず者国家の暗殺事件で大騒ぎだが、暗殺というと戦国時代を彷彿とさせるものがあり、戦国絵巻といえば、信長公記が有名だが、私はこの戦国モノは眉唾モノだと踏んでいる。現代でもワンピースが人気で面白いが、やはりそのストーリーの源流を辿ると、三国志に行きつくように思われる。 三国志の劉備が、信長になったのが大体の信長公記の流れだろう。最近みた「信長協奏曲」がなかなか面白かったのは、個人的に史実だと思い込んでいる八切史観の信長像によく似ていたからである。八切史観での信長像は、英雄というよりも、嫉妬深い普通の人物のように捉えている。 嫁の奇蝶に頭があがらないが、策略家で、どこかお人好しの面もある、信長協奏曲でいうところの、主人公の未来からきた高校生とその高校生に影武者をやらせ、出奔し、明智光秀を名乗って帰ってきた本物の信長の二人の人物を合わせたような信長像だからである。 さて、八切史観についてはこれまで何度も紹介してきたので、改めて紹介するのもなんだが、最近、桶狭間の戦いについて、TVでやっていたのをみて、八切史観にはとても及ばない稚拙さを感じたので、桶狭間の戦いについて、八切史観から紐解いて改めて紹介する。 八切史観では、桶狭間の戦いは、騙し討ちで結果的に奇襲となった見解をとる。今川義元は将軍義輝を軍事で補佐するために、大軍(2万から4万の兵)を率いて京に上洛する際に、信長を臣下に加われと誘って同盟を結ぶ寸前に、大雨が降り、信長は、義元軍の最新兵器の鉄砲隊が使えないとわかると、寝返って義元の首を討ちとった、というのが、それである。 つまり奇襲というのは後付けで、寝返りである。信長も本能寺で寝返りにあって死ぬのをみれば、自業自得というべきだろう。信長は義元の首をとった後、大雨で使えなくなった鉄砲隊を襲って、鉄砲を大量略奪すると、修理して使い、大量の火薬を海外から輸入するために、南蛮貿易を推奨し、切支丹宣教師を、仏教弾圧に利用する。 当時の商売の権益全ては朝廷と仏教徒が占有していたので、神道を信仰してきた被差別原住民は、仏教徒を目の敵としてきたので、神主の末裔であるハ田の末裔の小田の信長が、近江に神道の国をつくろうとしたのが、天下統一である。 戦国時代は、仏教徒と神道徒の身分争いともいえる。信長は身分の低い被差別民を臣下にして、仏教勢力から解放してきたので、いわば奴隷解放運動なので、いまだに人気が高い。だから、秀吉も、家康も卑賎民の出である。何度も改名しているのがその証拠で、お互いを官式名で名乗ったのも卑賎民の身分を隠すためだろう。 詳しくは八切史観に譲るとして、歴史を調べると、裏切れば、裏切られるし、自業自得というカルマが働いていることがわかる。人生の前半で自分が行ったツケが後半に返ってくる。そういう視点で歴史を捉えると不思議と真相がみえてくる。 というわけで、文脈が大きく変わるが、前回に引き続いて、シュタイナーの人智学的医術を紹介する。 ★ ★ ★ 自然科学-医学研究において、病理学的な現象の根源への帰還とでも名づけたい、真実への探求法が、やはり必要不可欠に思える。近代において、病気の根源である精神=霊性から目を逸らし、物質上の表面で生じている事柄に目を向ける傾向が益々盛んになってきた。 そして、この事、つまり表面に拘泥し続ける風潮に関連して、今日(1920年)、一般に通用している医学や、病理学の大部分において、疾患型(病気の種類)に関して、調査し始めると、どんな種類の細菌(ウイルス)が、この病気を引き起こすのか、このとき、人体に、何が感染しているのか、ということが教えられる。 (この教育法は、今日では遺伝子型にそのまま継続されている)。 さて、この「下等生物に感染する」という命題については、至極単純な論理に基づくので、論破するのは唯物論では容易ではない。つまり、疾患を引き起こす病原菌として、細菌(ウイルス)が発見されるので、この下等生物が、なぜ感染したかの理由を、特に明示する必要がなくなるからである。 これらの下等生物が様々な疾病に対して特殊な形態をとって出現することも事実なので、この特殊な形態が指摘されて、ある病気と、この特殊な細菌(ウイルス)の形態との関係が示せれば、論理的に矛盾なく、説明できるのは至極もっともにみえる。 さて、実は以上のように、表面的に全体像を見渡すだけでも、病気の本質、つまり一次的病因から、全く逸れている、という誤謬が露呈してくる。 というのも、何らかの病気の経過のなかで、肉体の何処かの部位に、多数の細菌(ウイルス)が現われたら、たとえ細菌でなくても、どんな異物でも、病状を引き起こし、炎症を生じさせるのは至極当然だからである。 さて、病状全てを、この細菌の働きに帰するなら、本質的に、この細菌が行なうことにしか注意を向けないことになる。つまり、本当の病因から、注意が逸れている。 というのも、下等生物が、その発達に適した土壌を、人体のなかに発見したときは常に、他ならぬ、この適した土壌というものが、本質的な一次的病因として既に作り出されているからである。この一次的病因のある領域に、一度注意を向けてみる必要がある。 その為には、もう一度、霊的な観察法を取り入れる必要があり、注意を向ける必要がある。 地球を覆っている植物界、すなわち地球の植生全体を観察すれば、地面から宇宙空間に向かって生長するだけでなく、ある力により引っ張られ、つまり、既に述べたことだが、この植生の至る処で、地球から植物内に働いている力と全く同様に、植物の生長の一部となる力が、宇宙空間から働いている事実について、はっきりと理解しなくてはならない。 地球から植物のなかに働く力と、地球外の宇宙から植物に働く力との間に、絶え間のない相互作用が成立している。 さて、このような宇宙からの力が、外界の周囲に常在しているわけで、 では一体、この力とは何なのか? 宇宙からの力が、地上に100%現われたなら、つまり、宇宙の力が植物を完全に捉えたなら、或はまた、地球の周囲の惑星が、この宇宙の力を妨害することなく、植物を完全に包み込むように配慮したなら、植物は、茎から花や種子へと生長していく際に、動物となる傾向を持つようになるだろう。 宇宙の力には、このような動物化の傾向が存在する。だから、植物は、このような宇宙の力に対抗して、植物のままでいるように、宇宙の力を抑え、植物内で、鉱物化の傾向をもつようにする、地球からの力がある。 つまり、注意すべきことは、植物には本質的に、塩(鉱物)化の傾向、つまり植物に相応しい物質を沈殿させ、鉱物化する傾向と、その逆の、物質を溶かし、炎症を生じさせる傾向、つまり動物化する傾向があり、その間で、中庸を保っている、という事実である。この事実は、外界の自然のなかの至る処に常在している。 また、今述べた事実は、人体にもコンパクト化されて常在している。人体は、肺を持つことで、小さな地球をもち、そして植物の、地球からの力と同じように、人体の上部にある肺から、下部に向かって、塩(鉱物)化の傾向を呈する力をもつ。 この地球の塩(鉱物)化の力、つまり人体では、肺の呼吸と、心臓の働きを通じての新陳代謝全般に対抗(相対)する力は、外の宇宙の力のように、人体では上方に向かって働く(図参照)。 さて、人体には不可欠の事実がある。心臓の働きのなかに最終的に集約される人体下部の働き全般と、肺の働きのなかに最終的に集約される人体下部の働き全般とが、分離され、隔てられていなければならない、という事実である。 心臓と肺の二つの活動は、両者の間に、いわばエーテルとアストラルの横隔膜がなければ、互いに作用してはならない。つまり、この二つの活動は互いに隔てられていなければならない。すると、次のような疑問が浮かぶ。 「このような非物質性の、人体上部と、人体下部の間を介する横隔膜とは一体何なのか?」 このような横隔膜は実在し、そして、この横隔膜の実体は、外的には、実は呼吸のリズムとして現れる。この横隔膜は、人体上部と人体下部を相互に調律することで実存している。 人間の律動(リズム)活動とも呼べる、この横隔膜は、外的には呼吸のリズムとして出現する。 この呼吸の規則的な振動が、エーテルやアストラルの活動にまで継続され、人体上部の肺に集約されている地の力と、宇宙から地球の中心へと作用し、人体では下から上へと作用し、心臓のなかに集約されている天の力とを、仲介し、互いにわけ隔てている。 いま考察している規則的なリズムが、適切に働かない場合を想定すると、上下のリズムの衝突が起こり、いま比喩的に用いた、物質でない、いわゆるエーテル、アストラルの横隔膜も乱れる。すると、植物での地(鉱物化)の力に類似した力が促進されて、人体に出現する可能性がある。 この塩(鉱物)化の地の力が強くなりすぎると、植物は物質に恵まれ、植物のままで居られ硬くなって生長する。すると、植物が地から生長するように、人体内では、エーテルの植物とでも呼べる力が促進され、肺の硬化の誘因となる。つまり、植物での鉱物化の傾向が、人体でも強くなり過ぎ、肺の硬化を誘発することが想定できる。 塩化(植物)の傾向→肺の硬化(肺の植物化) また逆に動物化の傾向が強くなりすぎる場合もある。動物化の傾向が強くなりすぎると、人体上部に、本来あるべきでない下部の活動領域が作り出される。 動物化の傾向→植物性動物(動物化した植物)の感染 この領域に相応しくないエーテルの器官ができてしまい、人体にとっては促進されてはならない、つまり小さな細菌(動物化した植物)の生息に好都合になる。人体上部に、小さな植物性動物の生育にとって好都合な領域が作り出される。だから、これらの植物性動物がどこから来るのかの、興味を持つ必要は全くない。 興味を持つべきことは、植物性動物に好都合な領域がどのようにして作り出されるのか、という事実である。このような領域が人体にあってはならない。このような領域は、人体では、万遍なく、全体に拡がるように調整しなければならない。特別な領域として生じてはならない。 この領域が全体に拡がれば、全体の生命を維持するが、特定の小さな領域として機能すれば、人体を病気にし、少なくとも後から、その多くが検出される、小さな植物性動物を生育させる環境となる。 以上のように、リズム活動と、その障害に遡ることによって、人体全体に拡がらずに、異質の小さな領域を発生させる一次的病因を追求し、細菌が蔓延る謎を解いていく必要がある。しかし、霊的な病因に遡らないと、この謎は解けない。 地上の植物と同じように、動物や人間にも、地の力と天の力の均衡が生じている。人間や動物にも、植物と同じように、地球外の宇宙からやってきて、体内に影響を与えている地の力に対抗する力が影響を及ぼしている(上図参照、黒色)。 地球の内部から来る力(地の力)の影響が、人体では上部の器官に制限されているのに対し、宇宙から流れ込んでくる力の影響は、人体では主に下腹部に属する器官に制限されている。更に、上述のように考察した上下2つの活動の間に、隔壁が作り出されねばならない。この正常な分離の制御は脾臓の働きによってなされる。 (脾臓は人体全体のリズムを司り、霊と物質の割合を調節しているという。) 以上のように、人体では正しい均衡を基にしたリズムが機能しているのがわかる。ただし、このリズムは、呼吸のリズムとは狭義の意味でまた別のもので、呼吸のリズムは小さく細やかに振動しながら、全生涯を通じて継続していき、人体上部に病気が発生しないように、規則正しく行われなければならない(短波長高振幅)。 というのも、下部の消化活動は、上にも下にも拡がっていくので、下部に起因する病気が上部にも起こりうるからである。だから、上下は別のリズムにより区分けされなければならない。 しかし、人体を、上下に分割された図のように考えてはいけない。上下の器官は、互いに浸透し合い、分割できないからである。とはいえ、地球から来る力のような、人体の上から下への作用と、宇宙から来る力のように、下から上への作用との間には、隔壁が必要である。 実際、人体上部からくる力を高めることで、下部の力に対抗して均衡を図り、両者の間を調整するリズムが必要となる。だから、覚醒(目覚め)と睡眠(眠り)との間に均等な関係が現れるように、リズムを調整する必要がある。目覚める度毎に、このリズムは、一方に揺れ、眠る度毎に、また、このリズムは他方に揺れる。 覚醒(目覚め)-睡眠(眠り)のリズムのなかに、もっと小さな別のリズムが生じている。例えば、覚醒時では、人体上部は覚醒しているが、人体下部は眠っているので、別の小さなリズムが生じるが、そのような別のリズムが組み込まれている。 以上のように、人体の上下の間には、絶え間のない、リズムが見られるが、これらの小さなリズム活動は、目覚め(覚醒)と眠り(睡眠)の交替による、より大きなリズムに捉えられている。 さて、このようなリズムのなかで上部と下部との間にある障壁が破られる場合を考えてみる。 そのとき、何が起こるか? 大抵は、人体上部から下腹部に向かって、上部の活動が侵入するようになる。 すると、エーテルの突破が起こる。人体上部でのみ活動すべきエーテルが、下腹部に侵入し、突破が起こる。そして、この突破が下腹部に起こることで、下腹部にはあってはならない上部の活動領域ができてしまう。 このような突破の帰結として、下腹部に中毒、重い下痢の症状が出る。人体上部の活動が、下部に出現すると、下腹部の活動は不規則になる。更に、下腹部に新たな領域として作り出された、本来上部にあるべき活動領域は、多くの場合、動物性植物(植物化した動物)のような下等生物の生息に好都合の環境となる。 だから、次のような結論に至る。 「上から下へのエーテルの突破を通じて、腸チフスとなる病因が引き起こされる。」 その付随現象として、下腹部に特異な領域ができ、チフス菌などに適した生息環境が作り出される。 以上のように、一次的病因(下部に特異な上部領域ができる)と、その二次的病因(細菌の感染)とを明確に区別でき、次のような結論に至る。 「疾病の一次的病因(根源的病因)と、多数の動物性植物、もしくは腸内細菌の感染による、特に小腸での炎症(二次的=副次的病因)とを区別すべきである。」 細菌を含め、物質として小腸などの器官に出現する二次的病因、つまり、動物性-植物が出現する要因は、人体上部の活動が、横隔膜(障壁)を突破し、下部にまで侵入した一次的病因の結果に付随した反応なのである。 これら二次的(副次的)病因は、一次的病因の結果として生じる現象である。従って、二次的(副次的)病因に向かうのではなく、一次的病因に向かうことにより、治療法を探すのが重要となる。治療法については、後ほど、もう少し述べていきたい。 というのも、治療法を語るには、エーテルの横隔膜にまで、病因を追跡できなくてはいけないからである。今日(1920年)一般に通用する医学では、ほとんど不可能で、というのも、このような医学では、物質から霊に移り変わる過程についての観察を排除しているからである。 しかし、あらゆる物質の根底には霊が存在する。上述の議論に注目すれば、腸チフスの病因も容易に理解できる。ただ考慮に入れるべきことは、この病気は、肺のカタル性の症状、更には意識障害とも結びつくことが非常に多い、ということである。 肺のカタル性の症状とは、上部の働きが、下部にまで侵出し、下部で、上部の働きが生じてしまい、上部から、その働きが奪われるのに起因する。上から下へのエーテルの突破が起こると、下部で生じる働きが、もはや上部で行われなくなる。 同様に、上部での意識伝達も、下部への突破が起こり、下部で意識伝達が生じてしまうと、その活動を、もはや上部で正常に行えなくなる。だから、一次的病因に注目すれば、腸チフスの全体像が理解できる。 通常、外見からは補完関係にみえない特徴が、一次的病因の関係から、結びつく過程が描き出せるようになる。勿論、場合によっては、その結びつきが、意識下(潜在意識上)で強力に働き、肉体に現れる前に、いわばその予兆や警告として表出したい、という意欲が現れる場合もある。 すると、上部で行われなくなった働きを、補完しようとして、壁に青い斑点で何かを描こう、という意欲が現れることがある。例えば、芸術家になる使命が自分にあると感じてはいるが、絵画の技術を、あまり学んでいない人物の体内を、次のように霊的に理解できる。 このような人物が、下腹部に絶えず現れようとする病状を抑えられるほど十分に(エーテル体が)強靭で頑健であるなら、下腹部に病気を発症する代わりに、壁に斑点で絵画を描こうとするだろう。このような人物が描く表現主義の絵画のなかに、一次的病因の産物を見つけることができる。 このような事実から、多くの赤や黄の色彩で表現する、表現主義の絵画を描く人の下腹部に病因を探したり、また青紫色の色彩で表現する人の人体上部や肺に病因を探したり、もしくは詩句を頻繁につくる人の肺から頭に至る器官などに病因を探したりできる。 上述のような霊的な洞察力(神通力)を獲得していくと、外への行為全般と、体内の活動全般との間に、不思議な一致を発見できるようになるだろう。絵画の描き方から、体内の機能不全などを霊的に洞察できるようになるだろう。 (体内に上下を仕切る壁=横隔膜が欲しい代わりに、外の壁に向かって絵画を描く) というのも、外界での人間の活動全てが、実際、神経だけで成立している、と信じるのは全くの間違いだからである。 人間の行為全般は人体全般に関わっている。絵画は、人体そのままの投影像なのである。 だから、子供のときに描いた絵画から、この知性の持ち主が、元々どういう性質なのか(どういうエーテル体をもつのか)、どのように後の年齢に向かって成長していくのか(どのようにエーテル体を完成させていくのか)、というような人物像=人体構造を、霊的に直観視できる。 (例えば、男の子が、乗り物やロボットなど機械の絵を立体的に描く傾向にあるのは、地の力の鉱物化の傾向で、肉体を完成させたい、という意欲の表れといえる。対照的に、女の子が、人間や動物や花など生物の絵を平面的に描く傾向にあるのは、天の力の動物化の傾向で、精神を完成させたいという意欲の表れといえる。だから、同じ年齢なら、女の子の方がマセている。) 例えば、前世でのあらゆる障害を、来世での発育不良として引き継ぐ運命を選んだ人は、エーテル体の作用がなかなか人体上部にまで届きにくい為に、ぎごちなく、重々しく歩く、という動作が、幼年期に示されることがあるが、このような例を霊視すれば直観できる。 子供が比較的軽やかに歩くのか、それとも重々しく歩くのか、という歩き方から、子供の成長についてのイメージが思い浮かべられる。同様の数多くの現象から、歩き方や仕草全般は、その人の体内の活動がそのまま外への運動として現われたものに他ならない、という事実が探究できる。 医学研究のなかに、以上のような事実が受け容れられるのが望まれる。というのも、このような事実を受け入れるのにそれだけの能力が必要だからである。 二十代はじめの若者なら、能力開発の余地があり、大きな機会が与えられれば能力を獲得できる。三十代に達すると、開発の余地を失ってしまう。一度失うと、もはや、この能力を開発するのは容易ではない。 このような霊的洞察力(神通力)を獲得するには、究めて強力に自己教育、自己修練しなければならない。また、現代の中等教育、とりわけ高等教育の破壊的な調教(強制)にも関わらず、子供のときから、天性の素質により、維持されてきたイメージ力のなかへと回帰することで、霊的な直観力へと、自らを修練していくこともできる。 医学研究において、物質よりも微細な、つまり霊的な解剖学及び生理学に正しい価値が置かれるようになれば、人類全体の治療の、非常に大きな助けとなるだろう。 以上に述べたような一次的病因が存在するので、流行性の疾病でも、一次的病因に従って観察しなければならない。というのも、例えば、呼吸が粗く、不規則なリズムをもつ人は、頭部-胸部のリズムに支障をきたしやすい傾向を持ち、気象などの影響を非常に受けやすい、という素質が見られるからである。 呼吸が健全に調整されている人は、気象などの影響に対して抵抗がなされる。例えば、いま冬の天体配置、つまり太陽の影響が、火星、木星、土星という外惑星を通じて強い場合を考えてみる。 このような冬の星位は、太陽から火星、木星、土星が遠く離れていることで、太陽の直接の影響が特に強いのとは逆の働きをする。このような冬の星位では、呼吸のリズムが粗い人の場合、気象や天体の影響を受け易く、粗い呼吸に対して強い影響が及ぼされる。 体内のリズム調節が行き届き、健全な横隔膜をもち、呼吸のリズムが規則正しい人は、このような星位によって、逆に、リズムの規則正しさが強められる。呼吸のリズムに揺らぎがなく、頑強な人は、外見的には細身の可能性がある。このような人は、呼吸のリズムが常に規則正しく、更にそれに応じて頭部-胸部の人体上部のリズム全般が規則正しく調整される。 このような規則正しい呼吸のリズムにより精神が安定した人は、外力によって、容易に妨害されることはない。このリズムを妨害するには、非常に強力な攻撃が必要とされる。 しかし、呼吸のリズムが不規則な人には、いま説明したような影響が究めて強力(相乗的)に影響する。 不規則なリズムは、その不規則さが強調され、更に不規則になる傾向を持つので、呼吸が不規則な人が、上述した星位が特に影響する場所に住むと、例えばインフルエンザなどの流感に罹る候補者となる。インフルエンザなどの流感の第一病因を探求するなら、このような事実を是非考慮に入れるべきである。 このような事実とは別に更に複雑な事実がある。人体のリズム(律動的)活動は、大凡、次のような状態にある。 「体内の個々のリズムいずれもが自立してつくられ、その振動を持続(継続)している。呼吸活動から、外来の粗い物質性のリズムを獲得するのもあり、更に睡眠(眠り)と覚醒(目覚め)のリズムに影響されるのもあり、これら様々なリズム全てが互いに影響しあって一体となり、全体として統一されている。」 そして、人体上部のリズム、つまり頭部-胸部のリズムが弱くなることで、下部のリズムが相対的に強く働く、という場合も生じ得る。上部のリズムが弱くなりすぎる場合、つまり規則正しい状態から逸脱する場合、この上部のリズムは下部のリズムにより、更に不規則にさせられる傾向を持つようになる。 そして、その場合、脾臓などの活動から発する下部のリズムが上へと強力に作用するようになっていき、様々な併発(合併)症状を伴うような、上部にあってはならない消化活動の肥大が引き起こされる。 そしてまた、ある下等生物の生息条件に適した環境が作り出される。このような生物が出現する背景には、人体上部に、炎症や麻痺を誘発させる下部の働きの侵入がある。しかも、上部のなかに器官の奇形化や腫瘍形成の発端すら示される場合もある(ジフテリアの病像)。 これは、上から下へと起こるチフス症の突破とは逆に、下から上への突破とでも呼べる病像で、本質的には、上述したような不規則なリズムによって引き起こされる。 勿論、以上全てに、年齢を考慮に入れなければならない。幼年期の人体は、(エーテル体もアストラル体も未完成なので)人体上部と下部の完全な共同作業でつくられるが、つまり、上下を媒介するリズム(律動)活動が、後の年齢とは全く異なるのを考慮すべきである。 例えば、幼年期には、人体下部に対して、上部の影響が強く及ぼされる必要がある。 実際、子供は大人よりも、「思考する」。奇妙に聞こえるが、これは事実である。ただ、子供の思考は意識されず、人体のなかに入り込み、その発達や形状のなかに現われる。特に幼少期には、思考力が肉体をつくるのに用いられる割合が非常に高い。肉体がほぼ完成に達し、思考力をそれほど用いる必要がなくなると、肉体づくりの代わりに、記憶力の基礎となる。 従って、記憶力は、肉体づくりがほぼ完成してから、はじめて現われてくる。というのも、記憶力の基礎は、肉体づくりの器官形成力から作り替えられたもので、幼少期では、器官などの肉体づくりに特に多く用いられるからである。 根本的に、全ては霊による変容の原理(メタモルファーゼ)に基づいている。霊が眼の前に現れるには、物質性をまとい、物質として作用しなければならず、その物質性を放出すれば、また元のように霊になるだけなのである。だから、子供では、下腹部などで生じるリズムに対して、上部の強い抵抗力が必要なのが納得できるだろう。 下腹部には特に、天の力、つまり地球外の力が現われるので、次のようなことを考慮に入れる必要がある。 「惑星と太陽の配置による特殊な星位があり、地球外(天)の力として、下腹部に特に強く影響する。」 その結果どうなるか? 人体上部と下部との間のリズム(律動的)活動が安定している大人には、この星位はほとんど影響しないが、子供の場合、宇宙(天)の力が、下腹部に強く影響するので、上部に強い抵抗力が生じなければならない。 つまり、この特殊な星位によって、子供の下腹部が非常に強く刺激されると、上部は究めて強く抵抗せざるを得なくなる。だから、その特殊な星位により、本来は強く抵抗すべきでない上部の力が、不自然に強く抵抗することで、流行性の脳脊髄膜炎を引き起こす。 従って、以上のことから、外にある自然から、どのような力が、人体に作用しているのか、がわかる。直観力の背後にある霊眼も獲得できれば、頚筋の強張りに至るまでの髄膜炎の全体像を描ける。というのも、子供では、人体上部に、極度の緊張が起こることで、上部の器官、つまり脊髄膜や脳に炎症が生じ、更に、他の症状も引き起こすようになるからである。 以上の事実から、人体内での一次的な相互作用について、更に、人体内と、地球外も含めて外にある自然との相互作用について、これまでのように人間を総合的に見ることが必要不可欠であることがわかる。 以上のように明らかになった多くの事実関係から、非常に馬鹿げた星占いなどが増加してほしいなどとは勿論、全く望んではいないが、星占いなどの由来がわかるのには十分だろう。そして、また治療法を探すのに、以上のような事実関係が、どれほど必要不可欠か、がわかるだろう。 というのも、矩象(九十度座相)の星位が、人間にどのような影響を与えるか、といったような星占いは、治療にはほとんど役に立たないからである。このような占術の類は、場合によっては、宇宙からの力を診断するのには役に立つかもしれないが、重要なのは診断ではなく、人体の治療である。 それで、今回行なった観察から、次回は外の自然のなかにある物質、つまり、上述のような人体に影響する力に対して、抵抗する人体内の作用や物質となる力の観察に進んでいきたい。 ともかく、この点に関して、医学のなかに、上述したような人体上部と下部という認識が、もっと広まるのが是非とも必要である。というのも、健康への関心について、医師たちの共同作業が生まれるのは、このような認識にはじまると思うからである。医師が臓器別などに専門化すると、人体全体への関心を失う。 医師は専門化すべきではないなどと言いたいのでは毛頭なく、時代と共に様々な技術が出現し、専門化するのは仕方がないことである。けれども、専門化していく医師たちの相互の共同作業や共同社会もまた、更に一層活発になる必要がある、と述べたい。 上述の認識は、聴講者の質問にもあった、歯槽膿漏、つまり歯茎の化膿を考察するときにも明らかになってくる。歯槽膿漏が起こるのは、一般の人が信じているような歯周辺のみの局部を扱うだけでなく、少なくとも人体全体、つまり全体のバランスの悪さが、歯の周辺に局所的に出現しているわけで、そういった全体像を把握できなくてはならない。 例えば、この病気に早く気づいた歯科医が、別の医師に、例えば、次のように配慮し、慣例になればよいだろう。 「歯の化膿が起こっているので、糖尿病に注意してほしい。」 というのも、以前、大まかに特徴を述べた糖尿病というのは、その病因が人体上部にとどまっている限りは治療し易く、つまり歯槽膿漏の段階では治療し易いからである。 人体下部の働きが上部にまで波及し、肥大か、不都合な貧弱化か、が上部か、下部に起こる、というような、下部と上部の相互作用が考慮されることは滅多にない。炎症が、人体上部に現われるか、下部に現れるかで、全く正反対の病気の兆候が現われるので、上下間の相互作用は究めて重要である。 従って、次の事実にも、納得がいくだろう、 「人体の成長力を司っているエーテル体は、幼年期と、老年期とでは全く正反対に働く。」 幼年期には、エーテル体は、物質(肉)体のなかに入り込まなくてはならない。エーテル体は、いわば働きの足場となる器官(臓器)を持たなくてはならない。エーテル体が物質体に作用する足場を持つのは、特に胎児には必要不可欠である。 このような事実から、幼少期に、足場となる器官がつくられるだけでなく同時に、物質体に見合った形を与える彫塑力を育てなくてはならず、この彫塑力の土台となる器官が幼少期に必要不可欠となる。 従って、例えば胸腺のような、また、ある年齢までは甲状腺もだが、このような器官が幼少期の人体には必要不可欠なのである。これらの器官は幼児期に、その最大の課題(エーテル体を物質体に注ぐ)を果たし、その後、物質力にあまりに強く捉えられるようになると、退化しながら変成していく。 幼年期の人体、つまり物質体には化学力(エネルギー)が必要不可欠だが、その後、この化学力は、熱力に交替していく。 人間は、生涯を通じて、光のスペクトルに象徴化されるような七色の力、つまり、紫と青に象徴される化学力と、緑と黄に象徴される光力と、赤に象徴される熱力とからなる力を、色彩は単なる象徴でしかないが、獲得していかなければならない。 人間は、本質的に、上述のような七色の力を獲得し、展開していく(上図参照)。幼年期には化学力を基にした活動に頼ることが多く、その後、光力の活動へ、更に熱力の活動へと移行していく。エーテル体が、物質(肉)体で、その化学力の展開を可能にする器官は、甲状腺、胸腺、副腎のような腺なのである。 これらの(腺)器官は、各々の目的をもって、化学力と結びつくので、物質体の肉色(肉のような紅色)は、これらの器官の背後にあるエーテルの活動との密接な関係を暗示している。副腎には、例えば人体を青白くしたり、血色を良くしたりなどといった働きがある。副腎が退化すると、そのことが皮膚の色合いに現われてくる。 副腎の退化による、いわゆるアジソン病(1)に罹ると褐色になるが、この事実を思い出せば、上述のような関係の根底まで見通せる。これらの器官は、人体内の化学現象を示唆している。 化学力は特に胎児にとって重要だが、また光力は、大体14歳以上の若者にとって重要な課題となってくる。更に、年齢が進むにつれて、熱力が重要な課題となる活動が盛んに現れるようになる。 (1)アジソン病: 1855年、イギリスの病理学者トーマス・アジソン発見の、副腎機能減退による内分泌疾患。心身の甚だしい倦怠感、血圧下降などを伴い、皮膚や粘膜が黒褐色となる。 以上のような事実には、人生についての極めて重要なヒントがある。つまり、次のような結論に至る。 「人生のはじめの幼年期には、特に胎児は、過剰な塩プロセスを示し、中年期には、水銀プロセスを示し、年齢が進んだ高齢期には、硫黄、もしくは燐プロセスを示すので、それぞれ、そのプロセスに注意を払い、適切に調整しなくてはならない。」 人体も、このような三重性のバランス、つまり化学、光、熱と、そして、塩プロセス、水銀プロセス、硫黄プロセスから成ることに注目すれば、これらの三重性が共鳴しながら、バランスをとって、いかに生命体をつくり、人体を成り立たせているかを、はっきりとイメージできるようになる。 栄養摂取だけでなく、人間の行為全般に対して、子供のときには化学力が、物質体の隅々にまで介入し、若者のときには、光力が介入し、あまりにも強いと、魂による人体の障害を後に引き起こす可能性も生じる。 また青少年期には、外界の印象に最も敏感になる。この年代に、無秩序な世界に向き合うか、秩序だった世界に向き合うか、ということが、魂にとって、後の人生に大きな意味を持つ。これらや、特に今回述べた病理学上の事実については、次回にもう一度述べる、それから更に治療上の事実に移る。 1-18 シリカが地上に現れる(地殻の)活動から、人体の(エーテルの)活動が連想できる。人体下部の活動が上部にまで達すると、体内をごちゃ混ぜにし、混沌とさせ、逆に人体上部の活動が下部にまで達すると、体内を区分けし、秩序づけ、器官全般を強く統制し、雁字搦めにする。 だから、人体内には、下から上への混沌、つまり自由な流れがある一方で、上から下への秩序づけ、つまり様々な器官への区分けや分化の流れが他方にあり、個人の人体が、この2つの大きな流れから、どうやって不規則になりえるのか、というような霊的な直観を身につければ、何らかの異常があるとき、この直観に従って、治療する術を学んでいける。 このような事は、次回以降も述べていくが、ただし、この直観に従った診察は究めて慎重でなければならない。というのも、外(唯物)的な科学が、人体を調べるときにすることは、例えば、次のようなことだからである。 「人体の中にはシリカがある。人体の中にはフッ素がある。人体の中にはマグネシウムがある。人体の中にはカルシウムがある。」 つまり、外(唯物)的な科学は、シリカについて、シリカは毛髪の中にある。シリカは血液と尿の中にある、などと言う。なので、この2つのシリカ、つまり毛髪中のものと、尿中のもの、との違いを次回に取り上げてみる。
2017年02月26日
コメント(0)
-
ネット情報の活用法 その1337
久しぶりの書き込みになります。今年は世代交代の年ということを前回紹介しましたが、いよいよ物質文明崩壊の年を迎えるように思います。いよいよ旧約聖書の最後の審判の日が近いと思います。 こういうことを書くと、最近巷を賑わせているインチキ宗教の幸福の科学とかを連想させるでしょうが、こういうものは偽ユダヤの世界統一政府の宣伝工作の一環で、こういうものに関わる人たちは全て人さらいのように地獄に突き落とされるでしょう。 というのも、宗教というのは、あの世の話なんで、この世の話ではなく、あの世に従って、この世で戒律をつくるのは全く滑稽で無意味なことだからです。あの世の話なのに、この世で出世とか金銭とか俗世間の人間関係のたわいもないことを言っても、結局地獄に堕ちるだけなのです。あの世を認識できない限りは何を語ろうが虚言なのです。 だから宗教ではなく、宗教をこの世の話に置き換えた哲学こそが人類の教科書となるべきなのです。 哲学とは一言でいうならば、自分を発見する、ということです。自分発見の旅にでた有名サッカー選手がいましたが、わざわざ世界旅行しなくても、人生そのものが自分発見の旅なんです。お互いに皆自分発見の旅をするために、自分を写す鏡として他者が必要なわけです。 御釈迦さんが、わざわざ修行しなくても、人生そのものが修行なんだよといったのと同じです。つまり、現世を生き抜くことこそが、自分発見の旅であり、哲学なんです。 結局のところ、何かに頼り、依存するのではなく、自分に頼り、自分で行い、自分で責任をもつことで、自分を発見できるというわけなのです。それこそが本物の自由なのです。 要するに、自分の宗教、自分の哲学をもちましょうということなんですね。 さて、話は変わって、最近、ある閃きがきました。その閃きとは、人体の方程式みたいなものです。 ちょっと下火感ありのPPAP風にいうならば、 アイハヴアー量子力学、アイハヴアー一般相対論、ウァーン、超弦理論 アイハヴアー量子力学、アイハヴアー免疫論、ウァーン、免疫弦理論 超弦理論、免疫弦理論、ウァーン、人体弦理論 という感じです。簡単にいえば、人智学をパクって超弦理論に置き換えたものです。超弦理論の11次元のうち、4次元が外界(物質体)、コンパクト化した6次元が人体(アストラル体)、そして超弦膜が、エーテル体という感じですね。 さぁ、この人体弦理論を理解するために、シュタイナーの人智学的医術を以下に紹介します。 ★ ★ ★ これから出来るだけ沢山の事を片づけようと思う。最初の問題提起において重要なのは、主に、人智学が提供する霊的な洞察法から、外界の物質が人体内に及ぼす働きを、より詳細に学び、そして、その物質に対する反作用を学ぶことである。 つまり、物質に対する人体の反作用を詳細に知りえれば、病気を診断でき、その物質を薬とする為の指針が得られる。そして、このような知見のほうが、ある薬はこの病気に効き、別の薬はあの病気に効く、といった経験的な対処療法よりも遥かに良い。 さて、今回もこのような知見を獲得する為に、一見かけ離れた関心事から出発する。提出された質問のなかで、ここにいるほとんど全員が関心を持つと思われる質問、つまり遺伝についての質問が思い浮かぶ。 遺伝は、健康、もしくは病気の診断において極めて大きな役割を果たしている。 しかし、遺伝は、実に現代の唯物論的な自然科学においては、非常に抽象的にしか研究されずに、実際の生活に役立つ形ではほとんど研究されていない(1920年代の時点で)。 一見すると究めて特異にみえるが、遺伝を霊的に研究すれば(秘教に通じないと特異にみえるが、秘教に通じれば一目瞭然の法則性がみえる)、人間が知るべき、宇宙の重要な関係全てが、遺伝(カルマ)という形で、外界のどこかに目に見えるように現れている、ということがわかる。 外界に遺伝として現れることで、ある霊的な特性(カルマ)が隠されるが、遺伝は人間に有効な霊力が、自然の中に存在する、のを示している。遺伝を研究するには、特に、この霊力を知らなければならない。 というのも、遺伝として封じ込められた、霊力には、本質が絶えず損なわれ、幻影を纏わせられている為に、正しい診断ができない、からである。遺伝は特異的で、ある現象には判断が下せても、また別の現象にはあてはまらない。 この特異性は、遺伝が究めて甚だしい幻影に覆われていることに由来するが、遺伝には規則的だが、調整しにくい形で、男性(陽)の力と女性(陰)の力が参画している。参画は規則的だが、その調整は必ずしも可能というわけではない。つまり、遺伝は規則に則ったものだが、調整は困難なのである。 例えば、天秤の棹を水平に保つのは規則性(バランス)に基づくが、左右に錘(おもり)を乗せていくと、微妙な差で、どちらか一方に傾く為に、厳密な調整が困難なのと同じである。この例えは、遺伝にも概ねあてはまる。 遺伝には、水平を保つ天秤の棹のような法則がある。しかし、この法則は動的に可変性(動的平衡)をもって現われ、そして、遺伝には常に男性(陽)の力と女性(陰)の力が参画し、しかも、男性の力は、地上の力により強く依存するようにし、一方女性の力は、地球外の宇宙からやってくる(天の)力により強く依存するように方向づける。 つまり、地球は絶えず男性を要求し、地上の力を通じて男性化する。 地球は実際、男性発生の源流でもある。女性を要求するのは、地とは反対の天である。天は絶えず女性化を引き起こしている。天の力は、人体全体に対して圧倒的な影響を及ぼしている。 この事実はまた既に述べた事実を遡って指し示す。受胎を通じて、地上に女性が発生すると、この本性は、次第に天の力を、自らに組み込んでいく傾向に向かう。 この女性の本性から、益々、人体は天に受け容れられる傾向になっていく。男性の本性が発生すると、それは益々地球に同化する傾向になっていく。すなわち、人体には天と地が共に作用している。 といっても、例えば、女性には天だけが作用し、男性には地だけが作用する、というわけではない。天と地の両方が男女の両方に作用し、女性では、天秤の棹が、天に多少傾き、男性の場合は多少地上に傾く、のである。 だから、この事実は平衡を保つ意味で厳密ではあるが、動的には多少揺らぎ、変動している。この事から、ある結論が導かれる。女性が持つ天の力によって、地上の力は動的に絶えず抑制されている。 しかし、奇妙にも、地の力が抑制されるのは、女性固有の(丸みを帯びる)肉体だけで、男性由来の(角張った)精子や胎児では抑制されない。つまり、この天と地との均衡を巡っての闘いは、精子と卵子による生殖(妊娠)活動は除外される為に、女性は地の力の浸入から免れている。 生殖活動の周囲で、地の力が天の力に抑制されることで、女性は地の力に由来する(物質=肉体性の)遺伝を免れ続ける。従って、次のような結論に達する。 「生殖での遺伝(物質性)は、男性を通じて伝わる。」 女性は、地(破壊)の力に由来する遺伝を免れる傾向にある。しかし、その代わり、女性は卵子のなかに、女性特有(精神性)の遺伝を与える。 従って、次のような疑問が思い浮かぶ。 「破壊力の遺伝に対して、人間社会はどのように対抗できるか?」 遺伝は、精神もしくは物質にも躊躇なく伝わる。この事実は精神病と呼ばれる病気がみられる家系には、糖尿病が出現しやすく、つまり精神から肉体へと遺伝が移る、というような現象に示されている。 だから、このような破壊力の遺伝から、どのように免れるか、というのは途方もなく重要な問いである。この破壊力の遺伝に対しては、とりあえず女性の健康をできるだけ維持するように配慮するしか社会的な方策はないように思われる。 というのも、女性を通じて、天の力が、地上の力を抑制し、その影響から、胎児などに有害な破壊力をもたらす遺伝を、女性の肉体から制圧することも可能となってくるからである。 つまり、女性の健康によく注意が払われている社会では、遺伝に伴う、地の力に発する破壊的な影響に対し、闘いが行なわれる。というのも、天の調停(均衡)力を増幅させる蓄電池が、女性にしかないからで、そのような力の効果に訴えかけられるからである。 以上は、地上の力と天の力の均衡によるもので、普遍的な事実である。このような事実は、血友病(1)を調べれば明らかになる。遺伝については、一般論を様々に述べるのではなく、具体的な事実が手にとれるように、わかりやすい形で示せるように研究すべきに思われるだろう。 血友病患者での遺伝現象を研究すれば、究めて奇妙な現象が見つかるが、今説明した事実がそのまま現れる。 つまり、このような事実から、家系のなかで、血友病の遺伝(継承)が現れるのは、男性だけだが、表に出ない血友病の因子を遺伝するのは女性であることがわかる。例えば、血友病患者の娘が血友病でなくても、彼女の息子に血友病を遺伝させることがあるので、血友病の家系の一人に女性がいれば、その女性が男性を産むと血友病を遺伝させる恐れがある。 血友病の遺伝については、男性は血友病になりやすいが、血友病の家系でない女性と結婚すれば、血友病は遺伝されない。 以上の事実を分析すれば明白な遺伝現象が得られるはずである。この血友病に関する遺伝現象は、少し前にヴァイスマン(2)が行った研究よりも遥かに明確で、遺伝の本質が水面下でどのように進行するのかを示している。 この天の力と地の力の均衡という事実は、人体にはかなり重要なもので、この事実に従って、診断する必要がある。 (2)アウグスト・ヴァイスマン[August Weismann]、1834ー1914 最初は医師、1866年から1912年までブライスガウのフライブルク大学で動物学教授、獲得形質の非遺伝性を仮定した。「遺伝理論の基礎としての生殖質の連続」(イェナ、1885)、「生殖質」(イェナ、1892)、及びその後の論文参照。 では、一体、血友病は何に起因するのか? 何に起因するのかは、物質的に観察しても示せる。血液の凝固力が無い為に、人体に小さな傷などの開口部が生じても、出血多量で死ぬことがあり、鼻血、もしくは簡単な歯などの手術でも、通常なら、血液の凝固で傷が塞がるのに、血友病の場合は塞がらない。 この病気は血液の凝固力不足に因る。血液自身が、凝固力に対抗する力を持ち、この抗凝固力が強すぎると、凝固を促す外力がかかっても抗凝固力を止められなくなる。血液の凝固には外力が関わる。この外力を抑制してしまう力が血液にあると、過度の液体化の傾向が現われてくる。 このような強力な液体化への傾向は、自我による全体制御に関係することがわかるが、この液体化の傾向は、物質を介しての、自我の外への働きと関わるのではなく、自我の内への働きの意志と関わり、表象(イメージ)を介した外への働きではない。 つまり、人間の意志の強弱と、血液の液体化の強弱とが関係する。 以上のような正しい解釈から、歴史上の事件のある秘密へと辿り着く。それは、あの有名なエンガーディン(スイスの一地方)の事件(3)で、つまり有名なエンガーディンの乙女たちの秘密である。 このエンガーディンの乙女二人は、医学が必要とする霊的な認識を、徹底して学ぶことで獲得できた。この乙女たちは、血友病の家系の出で、結婚しないと固く決意していた為、血友病の遺伝を個人的に撲滅した人たちとして歴史に登場している。 (3)エンガーディンの乙女たちの事件:エンガーディンに、これに当たる事件は見当たらない。逆にテナ、ザフィエンタールでは、おそらくここで示唆されているようなケースが起こった。またエルンスト・ツァーンの長編小説「タノの女たち」(1911 タノはテナという地名の詩的な変形)も参照のこと。 さて、このような場合、上述の事実に目を向けなくてはならない。この乙女たちのように結婚を諦めるのは、血友病の家系特有の意志の薄弱さからくるものではなく、強い主観的な意志が自我のなかで働き、アストラル体まで達するように養成されたことにある。 つまり、彼女たちの自我のなかの、この強い意志を成立させている精神は、血友病患者に必要な凝固力と関係している。 この(凝固)力を意識的に強めれば、血友病でない人よりも、容易に強化し得る。この(凝固)力を、霊(精神)的な形で認識できれば、血液のなかの力の本質がわかり、外にある物質と、どのような相互作用が生じるのか、を認識できるようになる。 このように意志と関係する血液の凝固力に注目することで、人間の意志と外にある力との関係が、総じて、どのようなものか、を洞察できるようになる。そして、次のような結論に至る。 「外界のある力は、人間の意志と親和性を持っている。人間の外と内との、この親和性は、宇宙の進化が進むにつれ、人間の意志が、月紀の終わりに自然界のなかに分離された事実に基づいている。」 月紀の終わりに、人間の意志は、自然界のなかに力として分離された。 重要なのは、人間の進化過程のなかで、外の自然のなかに分離された力が、その特性を通して、人間との関係を、どれ程、持ち得るのか、ということを研究することである。 このような力は長い間、古くから、自然のなかに研究されてきたが、それがどの様な研究なのか、を思い知るのは極めて困難である。というのは、十七、十八世紀までの先祖伝来の医学が猶も保持していた霊力を、主知主義的な現代人のなかに再起させるのは困難だからである。 このような研究とは、アンチモンに関するものである。 アンチモンは全く奇妙な物質である。伝説的な、バシリウス・ヴァレンティヌス(4)のような人たちが、熱心にアンチモンを研究したのも、上述した遺伝や意志と、自然との関係を知る為である。アンチモンのある特性に注目するだけで、アンチモンが独特の形で自然全体に分布しているのが認識できる。 (4)バシリウス・ヴァレンティヌス Basilius Valentinus 14世紀と15世紀の変わり目頃生きた。著作:「アンチモンの凱旋車」「太古の賢者の偉大な石」「化学の黙示」 アンチモンは独特の形で、自然全体に分布している。アンチモンは第一に(この性質はまだアンチモンの取るに足らぬ特性だが)、他の金属や物質と究めて高い親和性をもつので、他の物質と共に、とりわけ硫黄を介して現われることが多いが、自然全体に分布している。 アンチモンの名は、ギリシャ語のアンチ(反)-モノス(単独)という「孤独嫌い」の意味からきている。 硫黄は自然のなかでは、このような特殊な働きを持つのを、前に少し述べた。他の物質と硫黄を介して結合する傾向は、アンチモンが自然全体のなかに分布している様を示している。 しかしまた、アンチモンの別の特性は、アンチモンが自然全体のなかに分布しているのを更によく示している。つまり、アンチモンは、できるだけ束(房)状の結晶のなかに現われるが、それはすなわち、地を離れて、線状の形で天を目指し進んでいく、という特性をよく現わしている。 アンチモンが線状に、上へと伸びながら堆積していくような性質のなかに、天から地上へとやってくる結晶力を、外(物質)的に視覚で捉えることができる。というのも、通常は、もっと大きな形で現れる天の力が、アンチモンでは小さな束(房)状の結晶で現れるからである。 上記の特性は、アンチモンが自然全体に分布している様子を露呈する。同様に、地球の溶解過程が、アンチモンの結晶力を露見させる。溶解を通じて、アンチモンは細かい繊維状の形で得られるからである。 アンチモンのまた別の特性は、熱せられると、酸化、燃焼する、というものである。そのとき、放出される白い煙は、冷たい物質との、ある親和性をもつ、という独自性を示すが、この煙が付着して名高いアンチモン華を産出する(1)。 (1)アンチモンの結晶:アンチモンの主要鉱石は輝安鉱。アンチモンは硫黄と結合して現われることが多いと述べられているように、輝安鉱の成分はアンチモン(Sb)71.4%と硫黄(S)28.6%から成る。輝安鉱の結晶は長柱状、針状をなし、繊維状、毛状になることもある。 輝安鉱を木炭上で熱すると、容易に溶融して液状になり、そのまわりに三酸化アンチモンの白色の蒸皮を生ずる。また開管中で熱すると、管の底部に不輝発性の白色昇華物を残し、上部には白色輝発性の昇華物が輪状につく。原鉱石の溶融によって得られる硫化アンチモニーはそのままでもマッチ、花火などに用いられる。 アンチモンのもっとも奇妙な性質は、これまで述べてきた地の力に含まれる電磁気力に対して独特の防御力をもつことにある。アンチモンを電気分解し、陰極に沈殿物を運び、金属の先端で触れると、小さな爆発を引き起こす。 この電気に対するアンチモンの抵抗は、この抵抗を支援するもの(触媒)が得られれば、極めて特徴的な性質となる。アンチモンのこの特性を調べることで、自然全体のなかに、1つの物質が置かれている様子を実際に観察できる。アンチモン以外の他の物質は、アンチモンほどに全体に万遍なく分布しているわけでもなく、アンチモンのような性質を示すことさえない。 さて、アンチモンのように、自然において、明白な形で、自らの存在を示し、認識できるのは、自然のなかにある様々な力が万遍なく作用し、共に打ち消しあって、均衡状態になっているのを前提とする場合である。物質が特別な力を示すとき、そのような力が、物質のなかに集中しているのがわかる。 アンチモンに集中している力は、元々は地球の様々な場所に拡がって存在している。だから、アンチモンの力は普遍的に作用している。アンチモンの力は、人体内でも、均衡(調停)的に作用するが、人間は、このアンチモンの力を、健康時には天の力から取り出す。人間は、天の力から、アンチモンに集中している力を取り出すのである。 健康時には、人間は、地上でアンチモンとなっている力、つまりアンチモンに集中されている力に頼ることはないが、地の力に依存しすぎて、病気になると、アンチモンとなっている天の力に頼らずを得なくなる。だから、次のような疑問をもつのは当然だろう。 「一体、このアンチモンとなっている天の力とは何なのか?」 この天の力とは、占星術風に惑星(天体)の名を用いるなら、水星、金星、月の共同作用のことである。これらの惑星(天体)が、それぞれ別々に作用せず、一緒に作用するのを、錬金術風に言うなら、水銀、銀、銅が各々単独で作用せず、それらの金属をあわせて、地球においてはアンチモンのように作用する、となる。 アンチモンの作用;水星、金星、月の共同作用 この3つの天体の合同力は、月、水星、金星の三つの力が、衝や矩といった適切な座相(2)によって中和されるような配置で、地上の人間に与える作用を探究すれば判明するだろう。 (2)衝、矩:「衝」は惑星どうしが180度の角度で向き合う位置関係、「矩」は互いに90度(四分円)の角度になる位置関係。 これら3つの天体が、中和し合うように作用するとき、地上のアンチモンと同じ作用が起こる。地上で、アンチモンとなる、これら三つの天体の、天から地球に作用するのと同じ力が、今度は均衡をとるために、地上から、反作用として生じる。 さて、やっと重要な事実に辿り着いた。地球の構造を考える上で、アンチモンを、1つ、2つの塊で(量的に)考えるのは正しくない。地球の銀も、金も、構造の上では(質的には)1つであるように、アンチモンも1つとして、考えないといけない。量は、それほど問題ではない。 一塊のアンチモンを、地球から取っても、構造(エーテル)の上では、地球から、全アンチモンを取り出していることになる。つまり、その一塊のアンチモンは、アンチモン全体の活動の1つなのである。以上のことは、アンチモンの地上での働きを通じて明らかになる事実である。 さて、自然においては全ての作用に反作用が相対している。物質は常に(天と地の)作用と反作用の往復運動によって生じる。 さて、今度は、アンチモンの反作用を探す必要がある。この反作用を探すには、人体内で抑制され、制御されている何らかの力が、人体外に出る瞬間に、アンチモンは人体に作用する、という特性を洞察できなければならない。 この外から人体に作用する力とは、血液の凝固力なのである。つまり血液の凝固にはアンチモンが働いている。血液が凝固の傾向を示すところでは、必ずアンチモンが存在する。そして、血液が凝固力から逃れようとするところでは、アンチモンに対する反作用が存在する。 従って、血友病を調べると、奇妙にも、アンチモンに対する反作用をみつける。この反-アンチモンの力は、(一種の造語だが、)アルブミン、蛋白質形成力とでも名づけたいもので、このアルブミンは蛋白質の形成を促進するように作用する。というのも、血液の凝固を妨げる力は、蛋白質をつくる力だからである。 アンチモン=凝固力⇔アルブミン=蛋白質形成力 上述の事実から、人体でのアンチモンとアルブミンとの関係を認識できるようになる。アンチモンとアルブミンの相対関係を研究すれば、罹病と治癒についての根本的な認識が得られる。 では一体、アルブミンとは何なのか? アルブミンを通じて、自然の、あらゆる可塑性の蛋白質形成が、人間や動物の肉体の一部として組み入れられる。逆にアンチモンは、外から人体に作用する、いわば造形芸術家で、人体の器官などに形(フォルム)を与える。このように、アンチモンは、アルブミンの人体内での蛋白質形成力に対して、対極的な関係をもつ。 だから、人体内の器官などについて、この両方を区別して欲しい。例えば食道では、アンチモンとアルブミンのどちらが優勢か、を判別することで、粥状になった食物が食道に沿って通過していく様子などを調べなくても、食道の形状を追求できる。 アンチモンが与える、食道の形状に沿って、摂取した食物から、アルブミンの蛋白質形成力により食道がつくられる。つまり、アンチモンと、外からもたらされた食物を基に、アルブミンが、器官などで共に働くのを洞察することで、診断できる。 器官形成に関わるアンチモンと、外から摂取した食物からの蛋白質形成に関わるアルブミンは、二つの対立し、異なった生命活動(プロセス)である。 器官に形を与えるのはアンチモンである。外から摂取される食物を度外視して考えれば、人間は本質的にアンチモンといえる。だから人間はアンチモンなのである。 重要なことは、健常な器官などに、アンチモンの負荷をかけすぎてはいけない、ということである。健常では、アンチモンを供給してはいけない、さもないと人体を毒し、過度に器官を刺激してしまう。 とはいえ、器官形成を強く刺激する必要があるときは、アンチモンを与える必要がある。上述したアンチモンの独特な作用を加味して、内外から供給しないといけない。 例えば、アンチモンを内から用いるときは、アンチモンの力が人体上部にまで到達できるように、人体内でよく消化できるように希釈して用いないといけない。アンチモンの力が人体上部にまで達すると、アンチモンは、不活発な器官形成力を刺激する。従って、チフスにおいても、アンチモンを人体内で非常に希釈することで、大きな役割を演ずることができる。 また外から用いるときは、アンチモンをあまり希釈せずに、軟膏などで皮膚表面から用いれば、アンチモンの作用は、内服とは異なって達成される。また、この場合も、状況によっては外用だけでなく、内服が必要なのが判明することもある。とはいえ本質的には、外用は、あまり希釈しないで用いる。 究めて有用なアンチモンの内外の使用から、人体が規則的に、しかも同時に物質を絶え間なく希釈する生命活動のなかでつくられている事実がわかるだろう。従って、次のような結論に至る。 「意志の強い人には希釈して内服で、意志の弱い人にはあまり希釈せずに外用がよい。」 以上のように内外の用い方によって、アンチモンの特性を活用すべきである。以上の事実から、鉱物界のなかのアンチモンが、人間の意志と親和性をもち、意志が強いほど一層、自我の感受性にもよるが、アンチモンに対する反作用を引き起こす。 人間の意志は、アンチモンの作用を抑制しようとするが、一方で、肉体の形成などの組織化は、思考力、特に無(潜在)意識の思考力(エーテル;例えば、子供にみられる無意識の思考力)などの影響下に、アンチモンに基本的に支えられ、共同で働く。 従って、もし、人体に恣意的にアンチモンを与え、それが強力に作用したなら、ファントム(幽体;物質となる前のエネルギー分布状態)を形成する。 器官形成力が即座に刺激され、アンチモンと共同して働く為に、食物摂取物を使い果たし、不足してしまう。つまり嘔吐や下痢は、器官形成力が、器官の周辺にまで広がらずに、器官自身へと後退(縮退)してしまうことで生じる。この現象もまた反作用と共に現われてくる。 アンチモン→嘔吐や下痢 このようなアンチモンの人体への有害な作用は、意志の強い人なら、日常のある行為と同様に自我の強化により抑えられる。この、ある行為とは、あるものを通じて、人体のリズムを整え、維持する嗜好のことである。 この、あるものとは、コーヒーである。以下はただ事実を述べるだけで、コーヒーの嗜好を推奨するのではない。というのも、コーヒーに依存して、自我のなかの意志の強化を怠ると、また別の意味で、有害となるからである。 人体のリズムを自らの意志で調整できるほど、充分でない場合、コーヒーを飲むことは、代わりに調整へと導く。従って、アンチモンによる中毒には、コーヒーは特効薬の一つとなる。というのも、コーヒーは、外界と、器官形成との間に、リズムを復元させるからである。 (眠気覚ましにコーヒーを飲むのは、眠らない、という意志を強化するためと考えられる。) アンチモン⇔コーヒー 器官形成力は、外界と、ある一定のリズムによって維持されている。コーヒーを飲むと、器官形成力と、外界から摂取した食物による蛋白質形成力との間にリズムをもたらす。 以上のアンチモンに関わる器官形成力は、アルブミンに注目するように導く。アンチモンと相対するアルブミンに関わる蛋白質形成力は、内向きの器官形成力に乏しく、外向きの、器官を機械的に動かす、運動などによって消化に導くような働きに関わる。 つまり、腸の運動などの機械的作業や、通常の消化に関わる働きは、アルブミンと親密に関係し、同時に蛋白質形成へと向かわせる。 さて、以前に話したが、再度述べる。牡蠣の殻は、非常に興味深い教唆に富む生命活動の教材となるもので、また同時に教師ともいえる。小規模だが、玉子の殻、つまり石灰の分泌にも同じ活動が見られる。 では一体、この殻の根底には何があるのか? 牡蠣や卵の殻とは一体、何なのか。殻は、玉子や牡蠣という生命が自分のなかから放出すべきもので、外に送り出さなければならないものである。しかも、その理由は、もし玉子や牡蠣が、殻を自らのなかに保持していたら、死んでしまうことによる。だから、殻は、生命活動を維持するために、外に出される。 だから、牡蠣を食べると、牡蠣と一緒に、殻として、外界に出現する生命活動を食べることになる。牡蠣と共にその生命活動を一緒に食べることになる。 つまり、牡蠣を食べると、アンチモンと対置されるアルブミンも一緒に食べることになる。牡蠣を食べることで、チフス様の症状に通じる活動を促進する。牡蠣を食べることは究めて興味深い経過である。 牡蠣を食べることは、下腹部での、アルブミンの蛋白質形成力を促進するので、同時に、人体上部の頭から、この蛋白質形成力を解放し、頭の負担を軽くする。すると、主観的に軽くなったように感じるので、牡蠣を食べる度に、頭が空っぽになる。 人間は、このアルブミンの蛋白質形成力を、自らの霊力で発達させなければならない。ところが、蛋白質形成力を頭が担うのを妨げる。牡蠣を食べると、頭の負担が軽くなるので、頭が空っぽになるのを求めるようになる。 従って、牡蠣を食べすぎると、前に特徴を述べた、人体上部の頭から、下部の下腹部へと、蛋白質形成力を移行させる可能性を大きくし、つまり、チフスになりやすくなる。だから、このチフスの傾向があるなら、このアルブミンの作用を同定することで、アンチモンを用いて、どのような方法で、抑制し得るか、考察すべきである。 例えば、体外からは、アンチモンの軟膏を擦り込む、と同時に、体内で、非常に希釈されるように、アンチモンを投与することで、チフスへの傾向を抑制できる。また、このアンチモンの内服と外用を同時に行うことで、相反する反対側の作用を段階的に中和できる。というのも、チフスの傾向以外は、相互に調整し合い均衡をとるからである。 以上のことから、人間を、全宇宙の環境のなかに継続的に据える、という試みが、どのようになされているかが、わかるだろう。この意味を知るには、自然のなかの、地の力に対して、ある形をとって直接的に抵抗することで成立している生命体と、人間との関係を調べてみる必要がある。 植物は、地の力(重力)に対して、直接抵抗し、天に向け生長している。植物は、十分生長した後で、花や種子をつくる為に、生長力をとっておく。人間に、通常は鑑賞され、時には食される植物の基礎をなすのは、地の力のうちの特定量が植物の生長力に転じる、という事実に基づいている。 植物は、地の力に抵抗し、天に向かって生長した後、次いで天の力に曝されることで、花を咲かせ、種子を結実させると、今度は、進化の道筋において、植物の上方にいる動物たちのように、この世界を見渡すように、見渡したい、と思うようになる。 そこで、植物は、知覚への欲求を示すようになる。ただし、植物は知覚器官を持たないので、植物のままにとどまり、人間の眼のような感覚器官を発達させようとする。しかし、植物は、植物の体しかもたず、人間、もしくは動物の体ではないので、眼をもてない。 だから、動物になりたい植物は、アトロパ・ベラドンナになる。ベラドンナになっていく生命活動を、以前なるべくわかりやすく描写した。ベラドンナになることで、その根のなかに、最終的に、黒い液果(果実)を実らせることで、この植物は、次のような人体の活動と親和性をもつようになる、 「肉体形成のエーテル体から感覚形成のアストラル体への活動、つまり、人体の生命活動を、再生=エーテルの領域から、感覚=アストラルの領域へと上昇させる活動」である。 人体上部に達するまで希釈された、微量のベラドンナを服用した場合に生じる作用は、究めて興味深い。それは、夢見の状態からの覚醒(目覚め)に、よく類似しているからである。夢からの目覚めは、ベラドンナの作用が適度に抑制されて起こる。 覚醒(目覚め)の際、感覚がまだあまり不十分で、夢見の意識状態にあるとき、その根底には、上述のようなベラドンナの作用がある。 ベラドンナによる中毒は、夢見の意識状態を引き起こし、しかも、それが継続して行なわれ、意識に目覚めることなく、夢うつつの過渡的状態が、ずっと持続していく。 この中毒を通じて引き起こされる夢見の意識状態が、正しい経過で起こるなら、寝起きの覚醒状態になるのは興味深い。 前に特徴を述べたように、植物がベラドンナになるのは、植物の人間になりたい、という気違い染みた努力なのである。だから、次のような結論に至る。 「人間が、眠りから覚めるのは、ベラドンナの作用をもっているからである。ただし、人間では、その作用は中毒にならず、中和されたベラドンナ、節度あるベラドンナであり、目覚めの瞬間だけに限定されている。」 従って、牡蠣を食べて、アルブミンの重荷を頭から解放したなら、アルブミンの重荷を、再び、魂(アストラル)へと導くために、ベラドンナを人体上部に達するまで、希釈されるように、与えればよい。 ベラドンナは、アルブミンの負荷を除こうとする働きを、再び、魂のなかに引き戻す。ベラドンナ自体は、確かに人間に混乱や幻影に満ちた夢見の状態を与えるが、ベラドンナの作用を中和して正しい経過で進行させたなら、通常の目覚め、肉眼による視覚の世界が眼の前に現われてくる。 夢見の人間を、外から揺り起こしてみた結果、夢見の状態から覚醒状態に移らず、そのまま寝ていたら、死んでしまうだろう。このように、人間は目覚めるとき、常に生命の危険に曝されている。ただ、この生命の危険を回避できるように、ベラドンナの作用を中和し、すばやく目覚める(覚醒意識になる)のである。 上述の事実は、ベラドンナの作用に対して均衡がとられ、正しい経過で進むために、睡眠から瞬時に覚醒意識へと引き戻されているが、均衡が破れ、正しい経過を越えて導かれる瞬間、忽ち異常な状態へと陥る、興味深い関係を示している。 上述の均衡と、正しい経過の関係は、古代の医師たちが繰り返し追求し、試みていた生命活動の扉を開く鍵となるものである。だから古代の医師たちが、ホムンクルス(ホメオスタシス)の製造(5)に言及するとき、まだ残っていた彼らの霊視力で、アンチモンによるファントムを見ていた、のである。 (5)ホムンクルスの製造:たとえばパラケルスス「デ・ゲネラツィオーネ・レールム」(バーゼル1574、第1巻7頁以下)参照。 彼らが実験室で探究していた生命活動とは、人体に投与したアンチモンの力が展開される間に、自我の意志により、アルブミンの力を強めることで、このアンチモンの力を抑制し、均衡を図る方法だった。このアンチモンの力が、自我からのアルブミンの力と均衡をとり、合わさり、まさに1つの力として現われた。 人体内に残っているアルブミンの蛋白質形成力を、アンチモンの器官形成力と均衡させ、そのとき、アンチモンが様々な形(フォルム)をとっていき、出現したホムンクルス(均衡状態=恒常性)を見ていたのである。 アンチモンの凝固力と、アルブミンの蛋白質形成力の中和が起こる均衡状態で、出現する生命活動(動的平衡)を、彼らはホムンクルス(ホメオスタシス)と名付けたのである。 1-19 唯物論的な科学では、例えば、毛髪を調べると毛髪中にシリカ(ケイ素)が見つかり、尿を調べると尿中にもシリカが見つかる、ということ以外に何も発見できない。しかし、何らかの物質が、人体の何処かに見つかる、というのは、生命活動の本質ではない。というのは、毛髪中のシリカは、なんらかの活動の結果、毛髪中にあるからである。 つまり、何の根拠もなく人間は毛髪をもっているわけではなく、毛髪からもまた人体へと究めて精妙な霊力が伝わっている。究めて精妙な霊力が、毛髪から体内に入っていく。尿中に、シリカがあるのは、シリカが、体内に過剰にあるからで、使用されないシリカが、尿中に排出される。 だから、シリカが尿中にある、ということは、さほど重要ではない。尿中にシリカを出した、人体のある部位では、シリカが過剰で、不活発なので、活動に寄与しないシリカが追い出された、のである。だから、尿中にあるシリカは、必要のない、無意味なシリカなのである。 また他の物質、マグネシウムを例にとっても同じである。歯のなかにマグネシウムがないと、歯は成り立たない。というのも、マグネシウムのなかに、究めて重要な意味で、歯の構築に関与する力が生きているからである。 この事実は、レーマー教授の講演で聞ける。さて、唯物論的科学は、「マグネシウムは乳汁のなかにもある。」と言うが、乳汁の中での、マグネシウムはさほど重要ではない。乳汁はマグネシウムを排出するほど、自身で強い形成力をもち、乳汁の中にマグネシウムをみつけるのは容易ではない。 唯物論でも、この事実は分析できるが、乳汁は次のようにつくられる。 「乳汁は、マグネシウムの(形成)力を引き離す(捨てる)ことでつくられる。」 歯の形成過程と、乳汁の形成過程の、この独特の対立については、歯の形成の本質であるマグネシウムが、歯の形成の一部として、ダイナミックに入り込んでいく過程をみていけば少しは実感できる。 乳汁がつくられる過程では、マグネシウムは、5番目の活動の後に排出される。そして、例えば、フッ素についても同様で、これは歯の琺瑯質(エナメル質)の本質で、フッ素無しには歯の発達を理解できない。 フッ素は尿中にもあるが、単なる排泄物であり、尿中でなんらかの機能を担うわけではない。尿中のフッ素は、使用できない、排泄された物で、フッ素を排泄するほど、人体の器官形成が十分であることを現す。
2017年02月15日
コメント(0)
全2件 (2件中 1-2件目)
1










