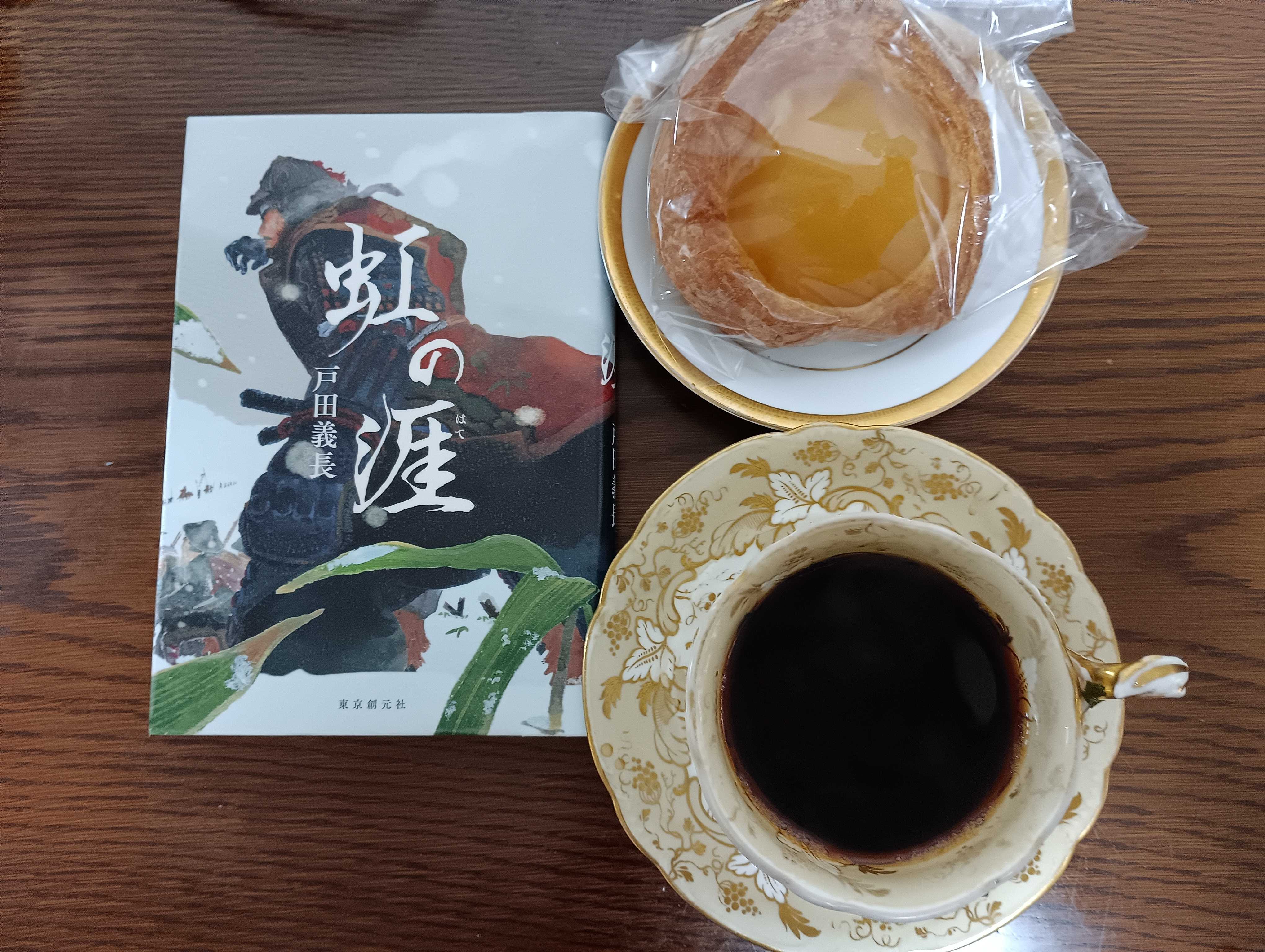2005年07月の記事
全10件 (10件中 1-10件目)
1
-

森博嗣『森博嗣の浮遊研究室5望郷編』
久々に本の感想(紹介)です。森博嗣さんの『浮遊研究室5』を読了しました。このシリーズは、この第5巻が最終巻となります。WEBで連載されていたものが単行本化されたものです。全部で170回、原稿が遅れることなく連載が続いたとか。森さんも含めた四人の会話(フィクションということが強調されています)です。実際、森さんと、あと三人の方がメールで話題のやりとりをしたものを、森さんが編集したものだそうです。最初の頃は、「ご案内」のところには、「ご案内」が書かれていたように記憶されていたのですが、途中からもう「ご案内」ではなくなってきて…でもここが、森さんの価値観によくふれることができて、興味深いところです。本書でいえば、特にvol.149の世界一足の速い男の話など、vol.154の職人さんの話、vol.159の水道管の話にはいろいろ考えさせられました。職人さんのところでは(いつものことながら)涙ぐんでしまいました。その後の、今週の一言、今週の諺、今週の新商品。後者二つには、たいてい笑えることがかいています。本書の最初の方はトンカツを新商品にするのですが、けっこう笑ってしまいました。一つの回の中で、涙ぐみ、笑い、深く考え…と、自分の感情の起伏の大きさを痛感する機会にもなりました。いまさら痛感しなくても、重々承知していることではありますが…。それから、各回ごとに、四人のメンバーの一言があるのですが、車道先生の言葉にはいろいろ笑ってしまいました。vol.147の一文字増やして強調する表現集、vol.151の平らげる話、vol.154のポップコーンの話など、大笑いでした。バイト場所でお昼休みに読んでいたので、笑いをこらえるのにせいいっぱいでした。やっぱり本は家で一人で読むのがよいですね。専門書は、研究室で読むことで、めりはりをつけるのですけれど。
2005.07.31
コメント(0)
-
本購入~鳥山石燕『画図百鬼夜行』
研究室の同期の方が、自分のと一緒に買ってきてくださったので、思いの外はやく入手できました。ありがとうございます(もちろん直接伝えてますが…)。で、前も書きましたが、帯。あれさえ違えば…。「火車、姑獲鳥、狂骨もいるぞ。」京極さんは本書から妖怪をとってきているのだから、いるの当たり前です。
2005.07.28
コメント(1)
-

秋月りす『かしましハウス(1)』
秋月りすさんの『かしましハウス』(竹書房文庫、2005年)第1巻を読了しました。厳密には、読了したのは昨日ですが…。今日、続きを読もうと思ったらしおりがなくて、ぱらぱら読んでいたら昨日読んでいたことに気づいたのです。しおりは最初の人物紹介のページのところにはさんでありました。さて、本書の主人公は野田家の四姉妹。お母さんはもう亡くなっていらして、お父さんが一家で唯一の男性。ちょっと肩身が狭いようです。長女のひとみさんは少女小説家。メルヘン大好きなのに、ときどき凶暴(?)化。次女のふたばさんは力持ちのOL。でも、意外と小心者のところがあります。三女のみづえさんは、大学生。睡眠が大好きで、ほとんど寝ているかぼーっとしているか。でも、要領がよく、鋭い指摘をしたりもします。四女のよもぎさんは小学生。現実的な考え方で、いかに小学生が抑圧されているかと痛感する毎日を送っています。だれってかれってみづえさん大好きです。本書にはった付箋は、一枚以外は全てみづえさんネタで笑ったところ。寒かったら自主休講だし、朝にバイトはいれないし、楽で給料のよいバイトをどこからか探してくるし…。私はこういうタイプの人と実際に友達づきあいするのは苦手だと思うのですが、漫画で、フィクションとして読む分には最高です。顔のつくり(というか目)は、『OL進化論』の課長さん系です。ところで、みづえさんネタ以外に付箋を貼ったところ…。そこには、ひとみさんが、家に遊びにきたよもぎさんの友達に、いまのはやりを聞くシーンがあるのですが、懐かしい言葉があったので。Jリーグとファイナルファンタジーです。私はスポーツには一切興味がないので、Jリーグは見ませんし(というか、テレビでしっかりやっていたのははじまってしばらくくらいで、数年であまり中継されなくなった気がするのですが…)、RPGもドラクエ派なのでファイナルファンタジーはしたことがないのですが、小学生の頃にとても流行ったのを覚えています。後者は学部生の頃も、ネットでできるとかで、話題になっていたようですが。サッカーについてはいまは全く興味がないのでどういう動向なのか把握していません。本書の初出は、1993-1995年の連載だそうなので、まさに私が小学生高学年の頃と重なるのです。懐かしいですね。先日、だいたひかるさんが、忘れてはいけないこと、のネタで、「ミサンガ」と呟いていらっしゃいましたが、流行ってましたね。小学生というと、流行にのっていない子は異端視されますから(断定的に一般化するのは問題かもしれませんが)、大変でしたね。森博嗣さんもおっしゃっていますが、長じるにつれて、良いことが増えていく気がします。よもぎさんも、お姉さんたち(特にみづえさん)を見ながらそう感じているようですし…。本の紹介なのかなんなのかよく分からない雑文になってしまいました。
2005.07.25
コメント(4)
-
のぽ悩む
「のぽ歩く」も、日記タイトルとして使ってみたかったのですが、「のぽ悩む」にしてみました。久々の雑談(?)です。私は、ありがとうのクラクションを鳴らすことについて悩んでいました。そもそもクラクションを鳴らしたことが数えるほどしかありません(キャリアもあると思いますが、数えきれないほどクラクションを鳴らすようなことにはあまりなりたくないものです)。しかも一度は、「警笛(?)鳴らせ」の標識があって、しかも友人が同席していたからで…。覚えている限り、これと別に一度。明るいうちは、道を譲ってくれた方(対向車のドライバーさん)に手を挙げればちゃんと伝わるのですが、夜は…。今までは、夜でも、軽く会釈をして手を挙げていたのですが、ライトのせいで、私から対向車のドライバーさんは見えないわけで…それは、向こうも一緒でしょうから、私が手を挙げたことは相手に伝わっていないかもしれません。そうすると、なんだか不愉快な感じを抱かれてしまったら悪いな、と思っていたのです。そういう、どちらかといえばネガティブな方向の理由とは別に、ポジティブな方向の理由もあります。純粋に、私が道を譲ったときに、手を挙げてもらったり、ありがとうのクラクションを鳴らしてもらったら嬉しいからです。あ、なんだか小学生の日記みたいになってきましたね…。ところがクラクションは、私が遭遇するのがたまたまそういう機会が多いのか、マスコミによるすり込みのせいか、警告というより、「ふざけんなこら!」という意味で鳴らされることが多い気がして、使うのにためらいを感じてしまい…。今日は早く帰宅できるので、上述のようなことを記事に書いてみよう、と思っていた矢先、ありがとうのクラクションを鳴らされる機会がありました。その後、私が道を譲ってもらうという機会もあり…。私は思いきって、お礼のクラクションを鳴らしましたとさ。クラクションも、ありがとうの音と警告の音、二種類あればよいのに、と、変な(?)ことを思う私でした。なお、冒頭に書いた「のぽ歩く」というのは、あるいは先日書いたかも知れませんが、大学からバイト先まで歩いて通っていて、往復80分、岡山の炎天下の下、日に日に肌が焼けていく、というだけのことでした…。こちらのタイトルを採用していたら、記事作成欄三行で終わる記事になっていましたね。
2005.07.22
コメント(2)
-
田中峰雄『知の運動』
田中峰雄『知の運動-十二世紀ルネサンスから大学へ-』~ミネルヴァ書房、1995年~卒業論文執筆の際、一部は読んでいたこの本。一部流し読みもありますが、一通り読みました。まず、江川温先生の「まえがき」で、ショックを受けました。田中峰雄氏は、1993年、自宅の火事により、亡くなられたというのです。ですから、この本は、田中氏が自ら整理したものではなく、生前に発表された論文を網羅的に整理したものです。内容自体とは関係ないのですが、「このような問題点については、いずれ稿を改めて考えてみたいと思う」という記述で、泣きそうになりました。いま引用した部分は、附論一「中世都市の貧民観」にあるのですが、この論文が非常に興味深かったため、田中氏によるさらなる研究はもう読めないという点と、田中氏は今後も研究を続けるつもりだったのに、不運な事故によりそれがかなわなくなったという点。とりわけ後者のことを考えて、です。世の中、本当に何があるか分かりません。さて、本書には、十三章と、附論が二つ収められています。全てに言及するのは困難ですから、簡単に。第一部「十二世紀ルネサンスとソールズベリのヨハンネス」には、二つの論文が収められています。ヨハンネスは、1115年頃-1180年を生きた、当時の代表的な知識人です。彼の学芸観、教育観について述べられています。第二部「十三世紀のパリ大学と対托鉢修道者闘争」、ここも二つの論文からなります。第三章「形成期のパリ大学と托鉢修道会」は、卒業論文で参考にしました。大学の教師は在俗聖職者がメインでしたが、そこに托鉢修道会士が入ってきて、講座を占めるようになります。そうすると、在俗聖職者にとっては、威厳と収入に関する問題が生じますから、両者の間に対立が起こったのです。パリ大学で講座を占めるようになった托鉢修道会はドミニコ会とフランシスコ会です。第四章では、両修道会を一緒に考えるのではなく、区別して検討する必要があるとして、フランシスコ会に関する議論を展開しています。第三部、第四部は、中世末期のパリ大学について。合わせて9章からなり、本書の中でのメインともいえるのですが、中世末期は私の専門とは異なるため、軽く目を通した程度です。ですが、学生の出身地分布について検討している第六章や、学位取得の年齢について論じている第十二章は、興味深く読みました。後者は、三つある学位のうち、一つ目をとる年齢が「14歳」とする規定が残っているのですが、これは二つ目の学位をとる年齢を考えるとおかしいと考えざるをえず、当時(14世紀)には、4と9はよく似た表記がなされたため、19の誤写なのではないか、と論じているものです。先述した附論一は、私が最も興味深く読んだ章です。中世の「貧民」という概念は、現代の概念とは異なることが指摘されています。貧者への施しが、聖職者、都市社会が形成されてからはブルジョワジーを中心とする俗人にとっても重要視されたのですが、これは貧者のことを思ってではなく、自らの職務であり、自らが救済される手段として考えられていた、ということが述べられています(この私の記述は正確ではないかもしれません)。こうした、宗教的な問題だったものが、やがて社会的な問題に変わっていくということが、多くの史料の検討から指摘されています。最後に、托鉢修道会と貧者との問題について、いくつかの問題提起がなされています。私が専門に勉強している説教の中でも、貧者に向けた説教があり、その分析も、田中氏の問題提起に、なんらかの形で一つの見解を与えられるかもしれません。ただ、目下のところ私の関心はそこではないので(興味深い問題とは感じていますが)、修士論文で中心的に扱うことにはならないかと思います。とはいえ、今後の視座が広がったという意味でも、本書は有意義でした。大学の制度についても勉強になりましたし。久々にずいぶん長い記事になってしまいました…。明日からの朝の読書は、本書と並行して既に読み進めているノルベルト・オーラー『中世の死』と、国府田武『ベギン運動とブラバントの霊性』です。(追記)本書の構成は以下のとおりです。ーーーまえがき収録論文初出一覧序説 知の運動―学位と教育の変革第一部 十二世紀ルネサンスとソールズベリのヨハンネス 第一章 ヨアンネス・サレスベリエンシスの学芸観 第二章 ソールズベリのヨハンネスの教育思想第二部 十三世紀のパリ大学と対修道者闘争 第三章 形成期のパリ大学と托鉢修道会 第四章 対修道者闘争とフランチェスコ会第三部 中世末期のパリ大学(一) 大学と社会 第五章 中世後期のパリ左岸地区 第六章 学生の出身地分布―イギリス人・ドイツ人ナシオを中心として 第七章 シスマとパリ大学―シスマ初期における聖職禄の誓願とウルバニスト派教師第四部 中世末期のパリ大学(二) 制度とその運用 第八章 学位制度における<subdeterminatio> 第九章 学位取得状況 第十章 学位取得の変則形態 第十一章 ブルサ考―学位取得料の問題 第十二章 一四歳か一九歳か―学位取得の年齢をめぐって 第十三章 規約と慣行―制度運用をめぐって附論一 中世都市の貧民観附論二 史料の数字の信憑性解題ーーー
2005.07.19
コメント(6)
-

浦賀和宏『火事と密室と、雨男のものがたり』
浦賀和宏『火事と密室と、雨男のものがたり』~講談社ノベルス~ 八木剛士が通う川崎市立商業高校の敷地内で、その学校の生徒が首を吊って死んでいた。雨でぬかるんだ地面には、一人分の足跡しか残っていなかった。自殺の可能性が濃厚だと見られていたが…。二ヶ月前にも、生徒が殺されたばかりである。小田渚は、不安に襲われていた。 同じ頃-。町で、火事が多発していた。めったに雨がふらないこの町で、火事が起こったときには、雨が降る…。 八木と松浦純菜も、火事に遭遇した。火事の家の中に取り残された少年。八木は、火の中へ入っていき、彼を助ける。このときも、その後に、雨が降った。 火事。その現場でしばしば見られるという男。松浦は彼に興味を持ち、八木とともに彼に接近していく。 松浦純菜さんと八木剛士さんのシリーズ二作目です。八木さんはいじめられっこで、いじめの描写が生々しくて、前作でも重たかったのですが、やはり本作も重たかったです。別の人物もいじめにあっていて、その描写が生々しくて…。正直、しんどかったです。他者のせいにして、いじめられている人のせいにして、自分のいじめの行為を正当化する。本作の中で八木さんたちが言っているように、彼ら・彼女らはどうしようもない馬鹿だと思います。ただし、いじめに限らなくても、松浦さんが指摘しているように、人は自分の至らなさを他人や社会のせいにしたがる傾向があります。責任を追及していくと、堂々巡りでどこまでもさかのぼっていって、そして後世にもひきづっていくでしょう。主治医に何度も指摘されたことです。Aが、親の敵、と言って、Bを殺す。Bの子供Cは、親の敵と言ってAを殺す。 Aの子供は、親の敵と言ってCを殺す。Cの親族は、恋人は、親友は…。堂々巡りです。実際には、世の中こうはなっていません。この循環は、たたれています。けれども被害者、あるいはその周辺の人物の受けた苦しみが完全に癒えてしまうということはきっとなくて、意識には登らないとしてもきっと残っていて。不条理ですね。 また話が飛んでしまいました。ミステリとして読めば、足跡のない密室の謎の解明、ということになるんでしょう。他にもいろんなミステリとしての要素はあるのでしょうが。けれども、やはり本作も、ミステリとして読んだ、という感じではありません。少なくとも私は本作を読んで、いろいろと考えさせられました。面白かったです。前作とつながりが深いので、『松浦純菜の静かな世界』を読んでから、この本を読む方がよいでしょう。はてなダイアリーのブログにトラバするためのリンクです。でこぽんさんの記事はこちらです。
2005.07.10
コメント(2)
-
本購入~浦賀和宏『火事と密室と、雨男のものがたり』
大学の帰りに、本屋に寄って買ってきました。浦賀和宏さんの『火事と密室と、雨男のものがたり』(講談社ノベルス)です。前作『松浦純菜の静かな世界』のシリーズ二作目です。松浦純菜シリーズといえばよいのか、八木剛士シリーズといえばよいのか、松浦&八木シリーズといえばよいのか、私には分かりませんが、前作がとても面白かったので、本作も楽しみです。次の日曜日の午前中に読む予定です。ところで、カバー裏の著作リストが、「主要著作リスト」となっていて、デビュー作『記憶の果て』など数冊がのっていません。『記憶の果て』で、私は浦賀さんの大ファンになったのですが…それだけ好きな作品なのに!なんだか残念です。絶版というわけでもないのでしょうが…。
2005.07.07
コメント(2)
-

キアーラ・フルゴーニ『アッシジのフランチェスコ』
キアーラ・フルゴーニ『アッシジのフランチェスコ ひとりの人間の生涯』~白水社、2004年~ フランシスコ会創立者、アッシジのフランシスコ(本書ではフランチェスコと表記されていますが、私はフランシスコという表記になれていますので…やはりフランチェスコとした方がよいのかもしれませんが)に関する伝記です。 一般読者向けの著書なので、注がついていません。そこが多少残念ではありますが、分かりやすくて、興味深い本でした。 序文は、ジャック・ル・ゴフが書いています。彼自身もフランシスコに関する伝記を書いており、私はその英訳を持っているので、いつかは読みたいものですが、それはさておき。 いま読んだばかりの、訳者三森のぞみさんのよるあとがきの影響もありますが、著者フルゴーニは、文字史料と視覚的史料(絵画)を、バランスよく使っています。とりわけ、聖痕(キリストの受難のように、両手両足、脇腹に釘が刺されたような痕ができるのです)に関する箇所は、絵画を使った説明が分かりやすかったです。 フランシスコと天使が向かい合わせにいて、両者の両手、両足、脇腹の間に、うっすら線が描かれています。最初は、鏡のように線が結ばれている(例えば、フランシスコの右手と天使の左手)のですが、後に変わっていく、という指摘がありました(という理解でよいと思うのですが…)。 フランシスコ会は、13世紀に生まれた托鉢修道会の、重要なものの一つです。これと並んで有名なのが、ドミニコ会でしょう。ドミニコ会の創立者聖ドミニコについては、いつか記事として書きました。ドミニコはもともと在俗聖職者で、異端カタリ派などへの説教活動を、教皇から命じられました。こういう意味では、もともと教会の一部として動いていた人物といえるのではないかと思います。 一方、フランシスコは、富裕な商人の家に生まれました。若い頃には、後に聖人となるとは思えないような、贅沢で放蕩な生活をしていました。ところが、幻視などにより、清貧を理想とする生活を送るようになります。 先に托鉢修道会、と書きましたが、彼らは説教活動を行い、民衆からの施しで生計をたてていました。フランシスコは、みすぼらしい服を着て、説教活動を行ったのです。彼はもともとは聖職者でも修道士でもありませんから、異端的ともとれる活動だといえます。 ところで、当時の説教活動は、主に司教によるものでした。司教の下の司祭でもないフランシスコには、公に説教をする権利はなかった、というのです。人間の聴衆を前にした説教のシーンを描いた図像は全くない、とフルゴーニは指摘しています(131頁)。ところが、151頁[図3]は、フランシスコがスルタン(イスラーム教徒)に向けた説教のシーンを描いた図像です。これは明らかな矛盾だと思うのですが…。私の理解不足でしょうか。なお、他の文字史料では、フランシスコの説教に多くの聴衆が集まった、というのもあり、実際には、フランシスコは説教活動をしていたでしょう。司教や司祭の許可をとったのでしたか。 本来ならこの記事も、しっかり本書と照らし合わせながら書いた方がよいのでしょうが…。すみません、ということで。 それから、ジャック・ド・ヴィトリについての言及も何カ所かでなされており、その点でも、本書は私にとって有益な著書です。(追記) 本書の構成は以下のとおりです。ーーー序文―ジャック・ル・ゴフ第一章 幼年期と青年期第二章 決別第三章 これこそ私の望みだ! これこそ私の求めていることだ!第四章 仲間、会則、キアーラ第五章 ダミエッタとグレッチョ第六章 聖痕 それは真の発見か、聖なる物語か、それとも大胆な発明なのか第七章 別れアッシジのフランチェスコ年譜参考文献フランチェスコ史料について訳者あとがきーーー
2005.07.05
コメント(2)
-

森博嗣『ダウン・ツ・ヘヴン』
森博嗣『ダウン・ツ・ヘヴン』~中央公論新社~ 『スカイ・クロラ』『ナ・バ・テア』に続く、シリーズ三作目。 内容紹介も感想も書きづらい。 ま、書こう。 僕-草薙水素は、パイロット。その腕は認められ、様々な任務を負うことになる。 草薙は、空で、戦う者。地上の傍観者たちとは違う。パイロットには、敵も味方もない。みなが、命をかけて戦っている。相手を尊敬しあっている。 -地上は…どうだろう。 * 読書(感想)は、そのときのコンディションによってずいぶん変わると思う。私は、本書を三日に分けて読んだから、まず、まとまった把握ができているとはいえない。シリーズ物なので、前二作もふまえておく方が理解もしやすかったろう。いずれにせよ、戦闘機や、その操縦に関する用語はほとんど分からないままなのだが。 今日は第三章の後半から読んだので、どうしてもその印象が大きい。けれど、そこは紹介に書くわけにもいかないだろうし(アスタリスクの前のところで、若干言及したかな)。 先に挙げた二作、さらにいえば森さんの作品に共通するものとして、詩的な性格の箇所があることだろう。そして、いろいろと考えさせられる。 森さんの作品を読んでいて好きなときは、なにかの定義がされているところ。本書にもあって嬉しかった。ーーーアフィリエイトのリンクを使ってみました。画像があったので。
2005.07.04
コメント(1)
-

神奈川のりこ『白鳥課長の素敵な生活(1)』
神奈川のりこ『白鳥課長の素敵な生活(1)』~竹書房~4コマ漫画です。小学生の頃から女社長になるのが夢のスーパーキャリアウーマン・白鳥小夜子さんは、現在29歳。一度誕生日のお祝いのシーンがあるけれど、あれは29歳になるときのお祝いだったのかな…。無駄な動きがなく、仕事はばりばり速く、ねこ大好き。ねこ好きの私には、ねこがいっぱいでてきて嬉しかったです。白鳥さんにライバル意識をもつ二人が登場しますが、白鳥さんは彼らにまったくライバル意識を持っておらず、そのすれ違いがほのぼの面白いです。やっぱりほのぼの4コマ漫画はよいですね。ーーー今日中に森博嗣さんの『ダウン・ツ・ヘヴン』を読了する予定でしたが、久々に朝ゆっくりしていたので、無理かもしれません。午後から用事で出かけるので。昨日から岡山も激しい雨が降っています。いまも大雨洪水警報が出ていて、雷もどきどき鳴ってますね。一昨日までは、35度を超えるような日もあったのですが、7月に入ってやっと梅雨、という感じです。なんだか、毎年のように「今年は異常気象だ」と聞いている気がします。あ、なんだか久々に日記っぽいことを書いてますね。
2005.07.02
コメント(1)
全10件 (10件中 1-10件目)
1
-
-

- イラスト付で日記を書こう!
- 一日一枚絵(11月1日分)
- (2025-11-15 00:14:23)
-
-
-

- ★ おすすめのビジネス書は何ですか!…
- 働かないおじさんは資本主義を生き延…
- (2025-11-15 17:38:19)
-