2005年09月の記事
全22件 (22件中 1-22件目)
1
-
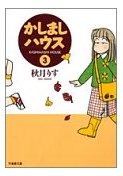
秋月りす『かしましハウス(3)』
秋月りす『かしましハウス(3)』~竹書房文庫、2005年~なんだかんだで、九月中に読了しました。4コマ漫画ですが…。さて、文庫版で全4冊で発売されている『かしましハウス』、その第3巻。来月で第4巻買って、『かしましハウス』も終わっちゃうのか、と思うと少し残念ですが、疲れたときに読み返すのに、こういったほのぼの4コマ漫画を読むと心が和むのです。ネコの絵は、『OL進化論』の絵の方が好きです。『OL進化論』6巻のネコのかわいさといったら!私の中でかなり好きなキャラとなっているみづえさんが大活躍(?)です。4姉妹みなさん活躍していると思うのですが、みづえさんのネタに一番笑っているのです。ひとみさんが、みづえさんに悪夢を見させようとする作品があるのですが、電車の中で読んでいたので、笑いをこらえるのに必死でした。恥ずかしいったらないです…。雪を使ったリアリズム志向のイタズラもそうとう笑えました。みづえさんネタを離れますと、ひとみさんとふたばさんがフランス料理を食べに行き、会話に困る、というのがあるのですが、これも良かったです。共感できる、というか。来月はそれほど買いたい小説が出ないようですし、節約できたらよいな、と思います。でも、古本屋に走るかも知れませんね…。とまれ、来月『かしましハウス』第4巻は買うつもりです。
2005.09.29
コメント(0)
-
映画「薔薇の名前」
映画「薔薇の名前」をビデオで観ました。ウンベルト・エーコの同名の小説が原作です。原作もとても読みたいのですが、私の知る限りハードカバーでしか出ておらず、しかも厚いので、なかなか手が出せないでいます。映画も数年間観たいと思いつづけながら、結局観てこなかったのですが、観る機会ができたので。原作を読んでいないのと、今日はじめて観たために、背景やらなんやらわかっていない部分があるのですが、簡単なあらすじを。14世紀初頭。北イタリアのとあるベネディクト会修道院(6世紀初頭に成立した修道会則に従う修道会で、祈り、瞑想を主な職務とする伝統的な修道会です)に、フランシスコ会士(こちらは、清貧を重視し、托鉢して説教することを主な職務とする、いわゆる托鉢修道会の一派です)であるバルカヴィルのウィリアムとその弟子アドソが訪れます。二人が訪れる直前、その修道院で、一人の修道士が塔から落ちて死んでいました。男が飛び降りたはずの場所の窓は閉じられており、単なる事故とは思えない状況で、修道院に住む人々はおそれを感じていました。また、その修道院には悪魔が住んでいるという者たちもいて…。ある修道士が、ウィリアムに、事件の捜査を依頼します。第一の死の謎を追っているとき、第二の死が起こります。こちらは、明らかに殺人でした。さらに、殺人が続きます。ウィリアムはアドソとともに事件の解明につとめるのですが、捜査も妨害されるようになります。真犯人は、また殺人の動機は?…と、本作は中世修道院を舞台にしたミステリです。謎解きも鮮やかでとても興味深かったのですが、私の中で、登場人物の顔と名前と役職がなかなか一致しなかったので、よくわからない部分もありました。やっぱり原作読みたいです。私は中世ヨーロッパ(特に専門としているのは、12世紀末から13世紀半ばまでのフランスです)の、キリスト教関係のことを勉強しているのですが、この映画は中世修道院の雰囲気をつかむのに良いのでぜひ観なさい、と少なくとも5年前には紹介されていたのです。なるほど、あんな感じだったのか、とまた一つ勉強になりました。なにしろヨーロッパに行ったことがないし、映画もほとんど観ないしで、視覚的なイメージがあんまりないのです…。ベネディクト会修道士は、また黒衣修道士と言われていました。同じくベネディクト会則を守る修道会のシトー会は、白衣修道士と呼ばれますが、とまれ、この映画の修道士たちは黒い服を着ています。また、フランシスコ会士は灰色修道士(訳語は不適切かも知れません)と呼ばれているのですが、映画の中でもちゃんと(?)灰色の服を着ていました。「笑い」に関する議論は非常に興味深かったです。すらすらと聖書など、過去の「権威」を引用して議論をする二人(ウィリアムの方が優勢ですが)。ウィリアムかっこいいです!中世ヨーロッパにはまだ姓が確立していませんから、どこそこのだれそれと呼ぶのが一般的でした。ウィリアムは、バスカヴィルのウィリアムですね。バスカヴィルといえば、コナン・ドイルの作品に『バスカヴィル家の犬』というのがあります。…未読ですが。脱線しました。ともあれ、「権威」を使った議論を映像で見ることができて、なんだか感動しました。感動したといえば、アドソがある罪を犯したあと、ウィリアムに懺悔するシーンもよかったです。終盤にさしかかると、異端審問官が登場します。その名前がベルナール・ギーと聞いて、びっくりしました。かなり有名な人です。現在自宅なので、手元に資料がないため、コメントは控えますが…。とにもかくにも、面白かったです。でもよく分からなかった部分もあり…。本なら、自分が理解できるまでゆっくり読むことができますが、映画は待ってくれないので、やっぱり原作が読みたいです。でもあの厚さ…。難しいらしいですし。大丈夫かな…。とまれ。映画「薔薇の名前」も観る機会があったのですから、小説を読む機会も、いつかくるでしょう。それまで、手持ちで未読の小説も読んでいかなきゃ…。
2005.09.28
コメント(2)
-
本購入~武田泰淳『わが子キリスト』秋月りす『かしましハウス(3)』
宮脇書店の卸センターに行ってきました。さすが、ものすごい本の量です。専門書コーナーでは幾冊もの本に魅了されましたが、断腸の思いで今回は購入を我慢。ネットで注文できることを祈ります。なかなか手に入らないだろうと思っていた本があったのですよ!本当にすごかったです。テンションは上がりっぱなしでしたが、歩き回って少し疲れてしまいました…(今日の記事は、テンションという言葉を多用しちゃってますね)。今日は、片道50分ほど電車での移動時間があったので、ある方から借りていた漫画(『耳をすませば』とその続編)を持っていったのですが、行きの間に両方とも読了してしまったので、卸センターでは漫画を買うつもりでした。さらに、先日torezuさんから紹介していただいていた本も気になっていたので、そちらもあったので購入しました。この記事のタイトルにも書いた、武田泰淳『わが子キリスト』秋月りす『かしましハウス(3)』です。帰りの電車では『かしましハウス(3)』を読み進めました。笑いをこらえるのに一苦労…。みづえさん、面白すぎです。卸センターが、我が家の近所になくてよかったと思います。もしあったら、通いつめてしまいそうですから…。『わが子キリスト』は、来週の土曜日に読みたいと思っています。
2005.09.25
コメント(2)
-
映画「ルパン」
映画「ルパン」を観ました。私はモーリス・ルブランの作品は一冊も読んだことがない(はず)なので、背景など、まったく知らないままに観ました。この映画に関する情報も全くもたないままにみましたので、ここではあらすじも書こうと思います。アルセーヌ・ルパンは、ボクシングを教えている父親に、幼い頃からボクシング(むしろ格闘技?)を習っていました。ところが、父親には殺人などの容疑がかけられており、警察に追われる身でした。ある日、ボクシングの練習中、警察がやってきて、父親はうまく逃げます。…ところが、数日後、ルパンが母親とともにそれまで住んでいた家を去ることになったとき、顔面をひどくつぶされた死体が発見されました。発見現場に偶然居合わせた母子。死体は、アルセーヌの父親がしていた指輪をつけていました。15年後(でしたか)。アルセーヌは、決して殺人をおかさない泥棒として、動き始めていました。いとこクラリスとの恋、殺人を平気でおかす泥棒ジョゼフィーヌとの協力、恋愛(と呼べるのでしょうか)…。有名な修道院にある三つの十字架をそろえたとき、財宝のありかが明らかになる。というので、物語は、三つの十字架の争奪戦、財宝探し、という方向に展開していきます。それでも、アルセーヌ・ルパンの周囲を取り巻く人間模様、環境といったところの描写が丁寧で(といいつつ、人間関係が理解できない部分がありましたが…)、心打たれる部分は多々ありました。フランス映画(しかも字幕!)を観るのは初めてかと思います。テンション上がりました。同時に、もっとフランス語聞き取れるようになりたいな、とあらためて思いました。話もできませんが。辞書をひきひきなんとか読める程度。まだまだ誤読も多いし、訓練していかなきゃいけないですね。ラストがいまいちうまく分からなかったのですが(他にもいろいろ分からない部分はありましたが)、結局何度かうるんで、感動もあったので、良かったです。それにしても、なにより原作を「読みたい」と思いました。「読む」場合、自分のコンディションや理解度によって読むペースが自由にできますが、映画やドラマはこちらの理解を待ってくれません。ルブランの作品がそのまま原作なら読んでみたいですし(というか、ルブランを読みたいと思ったということは、そのまま私のこの映画に対する評価が高かったということかと思います)、それと別になにかもとになる作品があるなら、読んでみたいです。先月も映画館に観にいきましたが、他の映画のCMが案外面白いですね。「リンダ・リンダ・リンダ」なんて、たぶん今日はじめてそういう映画があることを知り、ブルー・ハーツにさして興味もない私は、「へぇ~、こんな映画があるんだ」と思った程度なのですが、CMをみると、面白そう、と思いましたし、「恋する神父」は観たいとさえ思いました。でも韓国映画なのですね。韓国映画だからといって嫌がる理由はないですし、いやでもないですが、巷は韓国ブームのようですし、流行に踊らされるみたいなのにちょっと抵抗が…。それに機会がないと映画を観にいきませんし、レンタル・ビデオも借りに行きませんから、たぶん観ないような気がしています。観るかな…。でもお金…。
2005.09.25
コメント(4)
-

末永照和監修『カラー版 20世紀の美術』
末永照和監修『カラー版 20世紀の美術』~美術出版社、2000年~美術史については、同じくカラー版シリーズの、『西洋絵画史入門』を過去に読んでいる程度で、中世ヨーロッパの芸術に関しては、別の文献で読んでいますが、20世紀の美術となると、もうほとんど知らない分野です。ダリなど、シュールレアリスムの絵画は好きなので、図書館などで画集を眺めたこともあるのですが。画集といえば、ピカソのも割とよく眺めたものです。とまれ、本書の簡単な目次は以下の通りです。01.さまざまな表現主義02.空間と時間の分析=総合03.抽象と構成04.ダダ的反抗と夢の開拓05.両大戦間の国際的動向06.20世紀前半の彫刻07.抽象表現主義からミニマル・アートへ08.20世紀後半の具象絵画09.ポップ・アートの誕生10.視覚と認識の変革11.20世紀後半の彫刻12.モダニズムを超えて01では、強烈な色彩表現が特徴である「フォーヴィズム」などの表現主義絵画が扱われています。02では、キュビスムが主に紹介されます。後半で扱われている「未来派」の絵画は、「運動するものを環境との相互浸透として捉える」動きらしいのですが、きれいな色使いだな、と感じました。割と好きな画風です。03は、章題にある通り抽象絵画を扱っていて、私にはどうもよくわからない絵です。後半で扱われている「デ・ステイル」というのは、四角形など、カラフルな直線で描く様式で、これも意味はわからないですが、なんとなく好きな画風です。04では、大好きなシュールレアリスムが紹介されます。シュールレアリスムと同時期(というより、少し前?)の運動である「ダダ」という言葉もよく知っていたのですが、その絵画がいろいろと紹介されていて、勉強になりました。ダダの運動は、合理性、秩序、芸術そのものを根底から覆そうとする動きで、その名称はフランス語の幼児語である「木馬」、あるいはルーマニア語で「そうだそうだ」の意味なのだそうです。ニューヨーク・ダダの例として、椅子の上に自転車の車輪をつけた作品が紹介されています(他にもありますが…)。同じくよく分からないとはいえ、シュールレアリスムの絵はやっぱり好きです。マグリット、ダリ、エルンスト、ミロなどなど。ミロの絵は、倉敷の大原美術館にあるはずです。なんだかかわいくて好きなのですが、先日某番組でミロの絵が紹介されていましたが、彼はその幻想的な絵画を描くために、絶食したりしていたそうですね。あのかわいい絵は絶食の産物なのですね。少し飛ばして、07で紹介されているミニマル・アートについて。たとえば、ブライス・マーデンのある作品は、画面を直線で縦に三分割し、それぞれを赤、青、黄で塗り分けています。それだけです。ミニマル・アートは、明快で単一な色面による構成、色彩の純粋性を求める様式だそうです。08では、具象絵画が紹介されているわけですが、最後の方で紹介されている「スーパーリアリズム」は、写真のようにリアルです。すごい。08の2番目の図版、アンリ・マティスの[ヴァンスの礼拝堂]という絵が、素敵だと思いました。うん、いろいろ好きになりそうな画家も増えていきます。09で紹介されているポップ・アートは、中学生の頃に習ったときにインパクトが強かったので、ここで例示されている絵のいくつかには見覚えがありました。ウォーホルの[マリリン]など。10では、観客に自由な遊びの場を紹介する傾向をもつアーティストたちの運動が紹介されています。廃物の寄せ集めである「ジャンク・アート」、自然に手を加える「アースワーク」などなど、他にも興味深い絵画が紹介されています。11、12も省略させてください。別の作業しなきゃですし。本書は概説なので、個々の作家や作品、またその時代背景に関する踏み込んだ記述はあまりありませんが、流れをつかむには有用な一冊でした。
2005.09.23
コメント(0)
-
ドラマ「凶笑面」
ある方に借りて、ビデオで観ました。北森鴻さん原作「凶笑面」のドラマ版です。貸してくれた方も言っていたのですが、たしかに、ドラマにしたらあんな感じになるかな、という感想です。当然、設定もいろいろ変わっていて、人間のどろどろした面を一層描いているかな、と思いました。原作は短編ですから、それを二時間ドラマにしているので、ずいぶんいろんな要素が加わっていたかな、と。原作を読んでいる作品を映像で観ることは滅多にないのですが、最近ですと『姑獲鳥の夏』がそうですね。姑獲鳥の方は、映像化(というか、配役)にいろいろ違和感を感じたのですが(特に榎木津さん!いえ、阿部さん自身は好きですけれど)、「凶笑面」の方はそれほど違和感を感じませんでした。原作自体を一度しか読んでいないので、自分の中での十分なイメージができていないことも要因かと思いますが…。***昨日、また別のある方から、ミステリみたいなクイズを出してもらったのですが、その答えを知るために解くべき問題を自分で考えていって、最終的な答えにつなげる、というかたちだったのです。全部頭の中で問題提起し、合理的な解決を見出せればよいのですが、私はイエス・ノーで答えられる問題提起をして、出題者の方に答えてもらっていきました。正解にたどりつくのに必要な情報は大体もらったところで、その方は帰ってしまったので、一人で考えたのですが、正解にたどりついたわけです。問題が問題だったので、正解が分かっても、テンションがあがるというよりは、なんだかむなしくなっちゃいました。相当ミステリを読んできているので、どこかでは間違いなく読んだことがあることなのですが、探偵役ってむなしいものですね(私は探偵役といえるほどすんなり答えにたどりついたわけではないですが…)。とまれ、そのむなしさのようなものを、蓮丈さんの表情から感じたのでした。ーーー今日は高校の頃からの友人と遊びに行くことになったので、研究室に行くのはお休みします。ほぼ毎日研究室に行っているわけですが、こういう時、学生の夏休みなんだなぁ、というのを実感します。
2005.09.21
コメント(1)
-

アラン・ブーロー『鷲の紋章学』
アラン・ブーロー(松村剛訳)『鷲の紋章学―カール大帝からヒトラーまで―』~平凡社、1994年~ 著者のアラン・ブーローはアナール学派第4世代に属する歴史家です。 本書は、紋章や絵画など、図像に現れる鷲を検討することで、それを用いた権力者たちが、鷲をどのように認識していたか、また、権力者たちがそれを利用した意味などを明らかにしています。 目次を簡単に紹介すると、以下の通りです。序第一章 不在の空―カロリング期の権力第二章 崇高なる鳥―八世紀における鷲の潜在的な意味第三章 妥協の産物としての図像―オットーの鷲(十世紀)第四章 象徴と記章―中世の鷲(十一―十五世紀)第五章 逃げ去る鳥―寓意画と銘における鷲(十六―十八世紀)第六章 集結のしるし―アメリカ合衆国とフランス帝政の国家的な鷲(1776-1804年)第七章 視覚の罠―ナチスの鷲結び 原著のタイトルを直訳すれば、『鷲―ある記章=象徴の政治的年代記』(195頁の松村氏による訳)となります。邦訳の副題にあるカール大帝の時期は、<皇帝の鷲>という観念は希薄だったと指摘されています。神聖ローマ帝国以降、そうした観念で鷲が用いられるようになります。 原著のタイトルにあるように、政治的に用いられた鷲の図像について論じている書物なので、逆にいえば、図像(それも鷲という一つの動物)の分析から、政治的編年記を描くことが可能なわけですね。著者自身、結びにおいて、本書の限界を指摘していますが…。 キリスト教動物学の伝統や、使徒と動物の対応関係など、第二章、第三章が、私の関心のあるところで、興味深かったです。 第六章では、アメリカ合衆国と共和制下・ナポレオン下のフランスが、その印璽を決定する過程が詳しく紹介されており、興味深いです。 なにかと作業をしなくちゃなので、適当な紹介になってしまいましたが、このくらいで…。
2005.09.20
コメント(0)
-

舞城王太郎『阿修羅ガール』
舞城王太郎『阿修羅ガール』~新潮文庫~「阿修羅ガール」 アイコが佐野とSEXして、腹をたてて彼をホテルに放って帰宅した翌日、彼女は友達からトイレに呼び出された。そこで、佐野が行方不明になったことを聞いた。女子トイレのさわぎが大きくなってきたとき、好意を寄せていた金田がその場をおさめてくれた。金田によれば、佐野の足の指が、佐野の家に届けられたという。その少し前、グルグル魔人と名乗る何者かが、三つ子を殺してバラバラにしていた。その事件の影響を受け、<天の声>という掲示板が中高生を扇動し、そして「アルマゲドン」が起きる。無差別に中学生を殴る集団、その集団に反対する集団…。騒ぎの中、アイコも被害にあう。そして生死の間をさまよい、自分なりの答えを見つけ、生きていく。「川を泳いで渡る蛇」 作家である直樹が栄美子を待っていると兄から電話があった。母とけんかしたため、母が直樹のもとへ向かっているかもしれないという。一方、栄美子は電車を乗り過ごしたと、直樹に連絡をよこす。いままでも、よくあったことだった。川を泳いで渡る蛇。僕はその光景を思い出し、神について考え…いつもと変わった行動を試す。 表題作は、文庫版で再読。後者の短編は、文庫版に初収録。だから、文庫版も買ったのですが…。 まずは、「阿修羅ガール」から。 アグレッシヴでたたみかけるような文体で、アイコさんの考えがどんどんこちらに訴えてくるのですが、第一部と第三部では、一気に性格が変わっています。汚い言葉も連発されますし、事件も痛いのですが、そのぐちゃぐちゃで醜悪な世界が、ふっ、と―許される、というか、受け入れられるのです。私にはグルグル魔人の思考は理解できないですし、アイコさんの思考にも共感しかねる部分はあるのですが… たぶん前者も理解したくないというのが正直なところですし、後者も、共感する部分はあるけれど、そこまでは私は考えられない、ということです。 我思う、ゆえに我あり。このことについてのアイコさんの考えにはとても共感できました。考えすぎると壊れてしまいそうなので、どこかストッパーがはたらいていますが。 第二部はずいぶんぐちゃぐちゃで、それは比喩に満ちているせいもあるのですが、比喩の意味についても、アイコさん自身が考え、読んでいて、ずいぶん分かりやすくなります。似たようなことは私も考えていましたし、考えていることなのですが、このように物語にして伝えてもらえると、自分の考え方をあらためて見つめなおす機会になります。 <天の声>は、やはり怖いです。インターネットが普及しすぎた現在、たしかにその弊害はあるのでしょう。ブログを通じて、いろんな方と交流がとれていろんな方の価値観にふれることができ、勉強になりますし、また本の注文など、実生活にとってもネットは便利なのですが…。 「川を泳いで渡る蛇」。「阿修羅ガール」よりは、雰囲気がとっつきやすかったです非現実的な事件が起こるわけでもなく、ぐちゃぐちゃの世界も描かれません。それこそ日常の一コマですが、直樹さんが蛇からふくらませていく考えは、読んでいて興味深かったです。
2005.09.17
コメント(0)
-

京極夏彦『百器徒然袋―雨』
京極夏彦『百器徒然袋―雨』(『文庫版 百器徒然袋―雨』)~講談社ノベルス、講談社文庫~「鳴釜 薔薇十字探偵の憂鬱」「僕」の姪が、奉公先の御曹司とその悪友どもによって輪姦された。半年後、姪は自殺をはかるが一命をとりとめ、出産した。「僕」が、その憤りを、婦人運動にも関心をもっている友人の大河内に相談すると、推理も捜査もしない探偵―榎木津を紹介された。探偵助手の益田による調査で容疑者が特定されると、探偵と古本屋の京極堂は、一計を案じて悪者たちをやっつける。 コメント。後半がなんとも間抜けな内容紹介になってしまいましたが(「やっつける」ですね)、それ以外の形容はちょっと浮かびません…。事件自体はシリアスで、私がもっとも憎く思うタイプの犯罪の一つで、榎木津さんのはちゃめちゃな言葉に笑いながらも例によって泣いたりしてしまったのですが、悪者たちがやっつけられていく様子は心地よいです。 いやはや、体調も少し回復して、榎木津さんの活躍を読んでテンション上げようと思っていたのですが、やはりしんみりしてしまいました。「瓶長 薔薇十字探偵の鬱憤」榎木津の父親から、彼に依頼があった。瓶を探して欲しい。そして後日、迷子になった亀も探してほしいという。榎木津はしぶしぶ、下僕どもを動かし、それらを探させる。一方、その場に居合わせた「僕」は勝手に深入りしてしまい、瓶探しをしていた今川のもとを訪れたり、事情をのみこむために京極道のもとを訪れたりと、奔走する。 コメント。くだらない出だしから、壺の呪いなどなど、裏には大掛かりな主題やら団体やらがひそんでいて(そもそも、くだらないながらも「国際問題」だし)、そしてそれらをこてんぱんに粉砕する榎木津さん、きれいに形を整え憑き物落としをしてくれる京極堂さん。実に痛快です。大笑いしながら読むのですが、やはりどこかしんみりしちゃうのは、単なる私の感受性のせいでしょう。なお、瓶長は、表紙を飾っています。私は鳴釜の方がかわいくて好きなのですけれど、表紙にはむかないかな(笑)。「山颪 薔薇十字探偵の憤慨」常信と再会した京極堂は、彼から依頼を受ける。 18年間連絡をとっていなかった僧のいるだろう寺に連絡をとると、どうも不審な様子である。電話では、その僧は死んだと聞かされたが、その僧が生きているという話も聞いていた。いったい、その男は生きているのか死んでいるのか―。その頃、榎木津はヤマアラシを探していた。 コメント。内容紹介を書くとなんだかマヌケになってしまいます…。実際問題マヌケな話なのですが、やっぱり裏に悪者たちがいて、彼らを榎木津さんと京極堂さんがやっつけるのです。なお、本編で「僕」と関口さんが顔合わせします。伊佐間さんも登場。飄々としたところがよいですね。 全体を通じて。 今回、文庫版で再読なのですが、ノベルス版も二回くらいは読んでいるはずなので、読むのは三度目くらいでしょうか。 悪者が分かっていて、主人公(?)たちが仕掛けをつくり、悪者をやっつける―。こういう点では、『巷説百物語』シリーズと共通するものを感じます。ただ、『巷説百物語』では、百介さんが又市さんに大切にされているのに対して、『百器徒然袋』シリーズでは、「僕」がぞんざいに扱われていますが…。それでも榎木津さんはがんばって最中を食べますし、比較的大事にされている…のかな。 榎木津さんのファンにはたまらない中編集です(中編といっても、平均的な長編くらいの長さですが…)。とにかく笑えました。物語も軽快でさくさく読めますし。 なお、文庫版のしおりの絵は、『文庫版 百鬼夜行―陰』のしおりの絵の続きです。 画像は、文庫版の方がまだ出ていなかったので、ノベルス版をあげています。(2005.10.15、文庫版の画像もアップしました)
2005.09.17
コメント(2)
-
オスカー・ワイルド『サロメ』
オスカー・ワイルド(福田恆在訳)『サロメ』Oscar Wilde, Salome~岩波文庫~ ユダヤの王、エロドのもとに捕らえられている預言者、ヨカナーン。エロドの后、エロディアスとエロドの結婚を非難したことで、彼は捕らえられていた。エロディアスは、エロドの兄との間に子供をもうけていた。その子供が、サロメ。 宴の夜。エロドは、サロメに、踊りを見せるように頼む。サロメが望むものならなんでもあげるからと誓って。 サロメはその前に、ヨカナーンと会っていた。彼女は、ヨカナーンの口に口づけしたいと思っていた。そこで彼女は、踊り終わったあと、ヨカナーンの首が欲しいという。エロドは何度も拒むが、誓ったこともあり、結局はヨカナーンの斬首を命じ、サロメに彼の首を与える。 先日、所有作品一覧と感想のリンクを整理しなおしていたのですが、意外なことに『サロメ』の内容紹介と感想は書いていないことに気づいたので、再読しました。旧仮名遣いには次第になれていきましたが、字の密度がそれほどでもないので…。もっとページあたりの文字数が多かったらきつかったでしょうね。 本書は、「マタイによる福音書」14章1-12節(洗礼者、ヨハネ殺される)、「マルコによる福音書」6章14-29節(洗礼者ヨハネ、殺される)が題材となっています。「エロド」と表記されていますが、ヘロデですね。占星術者たちから、ベツヘレムで「指導者」(イエス)が生まれると聞いていたヘロデ。ところが占星術者たちは、ヘロデよりも先に、生まれたイエスに会って、夢で「ヘロデのところへ帰るな」というお告げを聞くのです。また、イエスの父ヨセフにも主の天使が現れ、エジプトに逃げるように告げます。結局ヘロデはイエスに会うことができず、ベツヘレムの二歳以下の子供たちを皆殺しにしたのです(ヨハネによる福音書2章を整理してみました)。 さて、本書に描かれている会話などは、「マルコによる福音書」の方によっているようですね。ただ、聖書では「ヘロディアの娘」(該当個所に、サロメという名前は出てきません)は、母であるヘロディアの願いを聞いてヨハネ(ヨカナーン)の首が欲しいと言ったとありますが、本書では、サロメが自分の意志でヨカナーンの首を欲し、そのことをエロディアスが喜ぶ、という風に描かれています。 こういう作品は、物語として楽しむというよりは、教養のために読む、という姿勢になってしまうので(例によって、聖書の背景があまり分からないのが悔しかったり)、十分に楽しめたとはいいがたいのですが…。 ビアズレー(1872-1898)による挿絵が、強烈です。
2005.09.13
コメント(4)
-

野村順一『色の秘密 最新色彩学入門』
野村順一『色の秘密 最新色彩学入門』~文春文庫PLUS~ いわゆる雑学本・ハウツー本ということになるでしょうか。西洋史関連の新書はよく読みますが、この手のは私がめったに読まないジャンルですね。色彩の歴史という分野に関心をもっているため、簡単な色彩関係の本を読みたいと思っていたので、買っていたのでした。 冒頭に、カラーチャートがあります。「好きな色で分かる人柄と適職」「男性が自分の好む色で分かる理想の女性像」「女性が自分の好む色で分かる理想の男性像」「カラー・コミュニケーション」などなど、ほんまかいな、と思う反面、興味深くもあります。 本書が強調しているのは、日光の重要性です。白は放射エネルギーを肌まで透過させ、自律神経を活性化するそうです。一方黒は体に有効な太陽光線を吸収してしまう。体まで太陽光線が届かない。緑のトマトを使った実験が紹介されています。白い布地、赤い布地、黒い布地をかぶせて、日光があたるところに置いておいた。すると、黒い布地をかぶせた緑のトマトは、熟さず、緑のまましぼんでいたそうです。同じように、黒い服ばかり着ていると、「冗談ぬきで(中略)しわが増えてしまう」んだそうです。若干焦りました、気をつけなきゃ…。 また、夜は当然あかりとして日光を利用することはできませんが、このとき、蛍光灯よりも白熱電球が良い、ということが強調されています。 人間の五感の中で、圧倒的に大きな比率を占めているのは視覚で、87%。一方、味覚は1%だそうです。なので、食事の際も、色が大事であるということが力説されています。 具体的な実験の例を挙げて、青や赤など、色が実際に人体に影響を及ぼすことが紹介されます。身近な話としては、こうした色の効果を利用して、素敵な住まいにするため、おいしく食事をとるための色の使い方などが紹介されます。またお店や企業の戦略としての色の利用法なども紹介されています。 ほんまかいな、と思えてしまう記述、図式の中に見られる意図的な強調など、ツッコミどころもありますが、とにかくいろんな話題があり、興味深かったです。ーーー本書に関して追記。著者の野村さんは、昨年亡くなられているようです。多くの著書を出している方のようですね。なお、私の所有文献一覧では、本書は専門書(歴史関連)のリストに挙げてあります(こちらは、いまのところ、リストからリンクをはるつもりはありません)。上にも書きましたが、色の歴史という分野への関心から本書を買ったため、歴史関連のリストにいれています。本書では、ヨーロッパにおける色彩の歴史が特に扱われているということはないので、注記しておくべきかと思いました。 さらに追記。一部訂正しました。不適切だと思ったので。ーーー昨日も今日も、記事をアップするために管理画面にはいると、トラバ新着で変なサイトからアラシのようにトラバがはられているのがわかりました。即刻削除しましたが、不愉快ですね。
2005.09.11
コメント(0)
-

西尾維新『ニンギョウがニンギョウ』
西尾維新『ニンギョウがニンギョウ』~講談社ノベルス~ 普段書くかたちでのあらすじは自分用にメモをとりましたが、ブログには感想のみ(多少は筋にもふれますが)アップすることにします。 正直、よく分からない話でした。 「ニンギョウのタマシイ」「タマシイの住むコドモ」「コドモは悪くないククロサ」「ククロサに足りないニンギョウ」。以上四つの短編集ですが、連作短編集の性格があります。 昨日、本書を買ったことを書いた記事でもふれましたが、本書は定価1500円ですが、非常に薄いのです。箱入りだし、装丁も凝っていますが、もう少し安くならなかったのでしょうか…。 とまれ。薄い本書の目次には、「ククロサに足りないニンギョウ」……234、とあります。まず、疑問に思い、第四話の扉を確認すると、109ページです。同じく、他の話のはじまるページも、目次と実際との間にズレがありました(第一話は、扉が7ページ目、はじまりが8ページ目で、目次には8とあります。短編の扉(タイトルだけが書いてあるページを、このようにいうかと思うのですが…)がある場合、その扉のページを目次に記すのが一般的だと思っていますので、やはりこのズレも、ズレと考えてよいのでしょうか。なにしろ、本書の奥付に、143pとあるのですから、234なんて数字はありえないのです。これは誤植ではなく、意図的に付された数字なのだと考えるしかないと思うのですが、まったく意図がわかりません。いくらか考えてみたのですが…。 さて、物語の方に話を移しましょう。 一話目は、17番目の妹が死んだため、23人の妹をもつ長男である私が映画を観にいく、という話です。まず、設定されている世界が分からないと厳しいな、と感じたのですが、結局その世界がわかりませんでした。あえていえば、ぐっちゃぐちゃの世界です。私は、靴を三足はいて出かけ、映画館は、銀行の中でキャッシュディスペンサーの場所を尋ねたときに教えてもらった方向の延長だろうと「私」が勝手に認識して行ったところにありました。そこでは映画をさかさまに映すため、客も天井からぶらさがってみる…。こんな世界です。「そういう」世界なんだと割り切り、この世界を理解しようという気持ちをなくして読みました。 第二話は、「私」の右足が腐りかけているので、なおしに行く、という話です。 それぞれの話で、23人の妹のうち一人あるいは二人がクローズアップされています。そして一貫して登場する「熊の少女」。 結局、話が理解できたとはいえません。左手で拳銃を扱ったために起こったこととか、右足の腐敗そして○○とか(珍しく伏せ字)、空がないとか、兎の運転手とか、それぞれに象徴があるのかもしれないし、ないのかもしれません。わからなかったですが、「あ、いいな」と思える言葉には出会えて、付箋を貼って…。私はそれで満足でした。
2005.09.10
コメント(2)
-

霧舎巧『九月は謎×謎修学旅行で暗号解読』
霧舎巧『九月は謎×謎修学旅行で暗号解読』~講談社ノベルス~ 修学旅行で京都へ行っていた小日向棚彦と羽月琴葉。修学旅行中のある朝、二人は脇野に呼び出され、倉崎家に案内された。「探偵ごっこ」をさせてやる、と脇野は言った。 途中、倉崎家の執事と出会い、二人は彼について倉崎家へ向かう(脇野はそこで帰った)。 六角形の形をした家には、中庭があり、11個のオブジェがあった。そして、「アステカの秘宝」のありかを示すという暗号文。その暗号を解いてほしい、とのことだったのだが…。 倉崎家の主人の三人の孫娘のうち、一人が失踪。主人も、既に亡くなっている、という説もあった。 * 一方、霧舎学園。三年生の頭木保も、暗号をみつけ、その解読に追われていた。 霧舎学園では頭木さんが、六角屋敷では小日向さんが、京都の街では羽月さんが暗号解読にいどむという、三重構造。特に、頭木さんと羽月さんが挑む暗号は連鎖していて、面白かったです。 地図が六枚出てきたところ、正直、これを参照しながら読むのは面倒だなぁ、と思っていたのですが、なんとも魅力的なキーワードにチェックがつけられていて、テンションが上がってしまいました。で、この地図を作ったのは「彼」なわけですね、納得です。 京都めぐりで、旅情ミステリ風でもあり、表紙見返しにあるように、サービス盛りだくさんですね。 いやはや、一日ごろごろ横になって読書していると、一年生の頃、同じような生活をしていた頃に、「腐るんじゃないの?」って言われたことを思い出します。読み続けるのは目も疲れるのでしょう、昼寝もしながらの読書でした。 それにしても…。本書でも泣いてしまうなんて…。ラスト3ページがツボでした。
2005.09.10
コメント(0)
-

森博嗣『τになるまで待って』
森博嗣『τになるまで待って』~講談社ノベルス~ 探偵・赤柳からバイトをもちかけられ、彼とともに、山吹、海月、加部谷は「伽羅離館」を訪れた。館の書庫にある文献の調査という仕事だった。 館には、超能力者・神居と、彼の二人の信者が住んでいた。神居の取材のため、新聞記者とカメラマンも同じ日に訪れていた。 加部谷は、神居の「超能力」の被験者となり、海月以外の人々は、不思議な体験をすることになる。 その夜―。館の玄関と、裏口のドアが開かなくなっていた。一階の窓枠には、全て鉄格子がはめられている。外に出られない状況で、神居の部屋からうめき声が聞こえた。その部屋は、内側から鍵がかかっていた。。ドアを無理やり開けると、神居は死んでいた。 少し、「ネタバレ」気味の感想になってしまうかもしれません。 『θは遊んでくれたよ』あたりから感じ始めていましたが(さらにいえば、『四季』とか、 Vシリーズ期に出された短編集でも)、いままでのシリーズの主要な人物の流れを把握していないと、読むのがしんどくなってきました。もちろん、いわゆる「不可能犯罪」と、その謎が解き明かされるミステリとしての醍醐味は十分に楽しめると思うのですが、このシリーズになると、もっとその背景の部分を理解してこそ、楽しめるように思うのです。 いままでのシリーズの簡単な年表(具体的な年月が明記されていたかは定かではありませんが)、人物関係表をつくり、整理したほうがよいかもしれません。その時間をとるかどうかが悩ましいところですが。どこで読んだか忘れましたが、森さんは自分の個々の作品を、大きな作品の一部という風にとらえていらっしゃるようです。飛行機の模型の羽の部分、胴体の部分、といった例があげられていたかと思います。とりわけ講談社ノベルスのシリーズは、全体が関連してきていて、そういう性格を強く感じます。
2005.09.10
コメント(4)
-
アンリ・ピレンヌ『ヨーロッパ世界の誕生』
アンリ・ピレンヌ(増田四郎監修/中村宏・佐々木克巳訳)『ヨーロッパ世界の誕生―マホメットとシャルルマーニュ―』~創文社、1960年~ 本書は、自主ゼミのテキストにしていました。邦語文献を読む自主ゼミのテーマは、有名だけどなかなか読まない(読んだことのない)文献を読もう、ということで、第一回が本書です。 中世ヨーロッパの勉強をしていて、ピレンヌの名前は何度も聞いていました。「ピレンヌ・テーゼ」という言葉も何度となく聞いているのですが、それが批判されていることはわかっていても、はてどんなものか今まで私はよく分かっていなかったのです。今回、本書を読めて、とても勉強になりました。 本書の簡単な目次は以下の通りです。第一部 イスラム侵入以前の西ヨーロッパ 第一章 ゲルマン民族侵入後の西方世界における地中海文明の存続 第二章 ゲルマン民族侵入後の経済的社会的状況と地中海交通 第三章 ゲルマン民族侵入後の精神生活 結論第二部 イスラムとカロリング王朝 第一章 地中海におけるイスラムの伸展 第二章 カロリング家のクーデターとローマ教皇の同家への接近 第三章 中世の開幕 結論 ピレンヌは、ローマ世界の特徴を「地中海的性格」と述べています。 中世は、従来西ローマ帝国滅亡を目安にはじまる、とされてきました。しかしピレンヌは、西ローマ帝国滅亡後(これには、ゲルマン民族の侵入が大きな役割を果たしています)も地中海的性格は存続している、と指摘します。 フランク人による二つの王朝、メロヴィング朝とカロリング朝があるわけですが、彼は、前者にはまだローマ的性格が残っていたとしています。ゲルマン民族の「ローマ化」、商業の性格などの分析から以上のことを言った上で、彼のひとつの結論は、ゲルマン民族の侵入は古代世界にピリオドをうったのではない、ということです。 第二部で、イスラムの侵入を論じ、それが東方世界と西方世界の分離をもたらした、と指摘します。第二部第一章第三節「ヴェネツィアとビザンツ」の終わりで、それまでの整理がなされるのですが、ここはテンション上がりました。かつてのキリスト教的地中海は東方と西方に分離され、キリスト教の海運が活況を維持したのは東方である。西方世界は、海賊の跳梁する舞台となり、海への出口をふさがれた。こうして、西方は純然たる内陸国家となり、西欧文明の枢軸は北方へ移動した、というのです。「古代の伝統は砕け散った。それは、イスラムが、古代の地中海的統一を破壊し去ったためである」(261頁) ですから、結論のもう一つは、イスラムの急激な進出により古代の伝統が断絶され、地中海的統一にピリオドがうたれた。歴史生活の枢軸が、地中海から北方へ移された、ということです。 こうしてピレンヌは、中世への転換期は650-750年にあるとし、それが完成したのは800年(シャルルマーニュ戴冠の年)だと述べています。 ピレンヌ・テーゼの批判も含んだ論文集を紹介されているので、ぜひ読みたいと思います。 次回からのテキストはホイジンガの『中世の秋』。3,4年前に買ったのですが、やっと読む機会が訪れました…。
2005.09.08
コメント(2)
-

鷺沢萠『大統領のクリスマス・ツリー』
鷺沢萠『大統領のクリスマス・ツリー』~講談社文庫~ 19歳のとき、ワシントンDCで、香子は治貴に出会った。治貴は、一歳しか違わなかったが、とても大人びていた。二人は、アメリカに留学していた。 二人が一緒に暮らすようになるのに、それほど時間はかからなかった。しかし、香子は卒業後に日本に帰ることにしていたし、治貴はロー・スクールへの進学を希望していた。その矢先、治貴へ仕送りをしていた人物が亡くなったという知らせが届く。香子は、いったん帰国したものの、両親の反対を押し切りすぐにアメリカに戻ってきて、彼を支える。睡眠時間をひたすらに削り、働きつづける。治貴は、勉強を続ける。 悲しい事故もあったけれど、二人は着実に「夢」をかなえていき、幸せに暮らしていた。 苦学生の二人が支えあい、そして香子さんが卒業してからは、彼女が生計をになう。やがて治貴もロー・スクールを卒業し、就職。さらに二人は結婚もし、本当に幸せな生活をしています。だから…どんどん切なくなっていくのです。 今回、再読なのですが、どうなるか、という部分は覚えていました。幸せすぎるのです。ものすごく努力してつかんだ幸せなのです。なのに…。 大人びた治貴さん、ささいなケンカ、仲直り、気遣い、強い(こわい)心と強い(つよい)心の違い。ドラマティックな事件の描写ももちろんなのですが、日常の中のなにげない気遣い、やりとりや心理の描写、そうした部分に心打たれました。 今まで読んできた鷺沢さんの作品の中で、とても印象に残っている作品です。ーーー午前中に三冊読めました。岡山はまだ風がありますが、晴れたので、大学に行くことにします。
2005.09.07
コメント(0)
-

江國香織『すいかの匂い』
江國香織『すいかの匂い』~新潮文庫~ この本には、11編の短編が収められています。やはり、一話ごとに紹介するのではなく、まとめて、印象深かったところを書いておきます。 表題策「すいかの匂い」。叔母の家に預けられていた、夏の思い出。「私」はお金を持って叔母の家を抜け出し、ある家にやってきました。そこには、母親と、上半身を共有した双子がいました。 …そのときのすいかの光景が、怖くて仕方ありませんでした。 同じく、怖かったのは、「水の輪」です。シネシネシネ…くまぜみの鳴き声。蝸牛を踏み潰す「私」。そんな「私」をずっと見ていた「やまだたろう」。「すいかの匂い」と同じく、虫が、ものすごく怖さをあおる効果を出しています。もちろん、「やまだたろう」が私にかけた言葉も、怖かったです。中途半端なスプラッタより、こういう心理的なところに訴えかけてくる作品の方が、こわいですね。 「蕗子さん」は、「私」の家に下宿していた大学生、蕗子さんのことの回想です。この他、「薔薇のアーチ」「影」などは、いじめをテーマにしています。 本作も再読なのですが、『つめたいよるに』に、心温まる物語が多いのに対して、『すいかの匂い』は怖いし、重い感じのする短編が多いです。 先日、ある方と話していたのですが、本当になんでもない言葉が、文脈の中でうまく使われれば、とても印象的になります。この短編集のラストを飾る「影」の中でMさんが言う「会わなきゃ」で、それを感じました。もちろん、他のところでも感じていますが、それが特に印象に残っています。
2005.09.07
コメント(3)
-

江國香織『つめたいよるに』
江國香織『つめたいよるに』~新潮文庫~ 江國さんの短編が21編収められた短編集です。21編それぞれに紹介・感想を書くのは大変なので、まとめて。 本作は、私がはじめて読んだ江國さんの本です。全体を通しても、二回は読んでいるはずです。 最初の短編が、「デューク」。大好きだった犬、デュークが死んだ。翌日も、「私」はバイトに行かなければならない。けれども家を出たとたんに涙があふれ、泣きながら歩き、泣きながら電車に乗り…。そこで「私」は、ある少年に出会います。この作品は5,6回は読んでいるはずですが、やっぱり泣きました。初めて読んだときから、読むたびに泣ける作品です。 「桃子」という作品は、江國さんのデビュー作だそうです。お寺に、一人の女の子が預けられます。ある僧が女の子と仲良くなり、その僧は日々邪念が増していき…。不思議な結末でした。恋愛の怖さ(?)が、寓意的に描かれているように思います。 「草之丞の話」。これもなんだか不思議な話でした。 不思議な話といえば、「いつか、ずっと昔」もどこか不思議な話です。一人の女性が、ふっと時間をさかのぼっていく。ずっと、ずっと昔まで。そのときどきの恋人たちと、お話をして。 「スイート・ラバーズ」も、「いつか、ずっと昔」のような雰囲気の話でした。 『つめたいよるに』は、前半が「つめたいよるに」、後半が「温かなお皿」というまとまりになっています。「スイート・ラバーズ」までが前半です。後半は、料理(食べ物)がモチーフになっています。 「冬の日、防衛庁にて」。不倫相手の妻に会う「私」。妹のアドバイスを受けながら、身構えていく「私」ですが…。相手の妻である女性は、すごいなぁ、と思います。 「とくべつな早朝」。この短編集のラストを飾る作品です。ある方から、とてもよかった、という話を聞いていて、その方からあらすじを聞いただけで、それは私が泣きそうな話だ、と思っていたのですが、しっかり泣けました。クリスマスイヴ、コンビニでバイトする大学生。好きな女性がいるのに、彼がちょっと休み時間をつくって電話をした相手は、その女性とは別の、女友達。心温まる話でした。
2005.09.07
コメント(2)
-

生垣真太郎『フレームアウト』
生垣真太郎『フレームアウト』~講談社ノベルス~ CMやPR映画の編集を仕事にしているわたしの仕事場に、こころあたりのないフィルムがあった。一人の女性が映っていた。女性は、手にしたナイフで、自分の腹部を刺し…。 わたしは、女性にこころあたりがあった。ともにフィルムを見た男に、わたしは、彼女は一部の映画ファンの間では有名な女優、アンジェリカ・チェンバースだと言った。 フィルムにとてつもない「邪悪さ」を感じたわたしは、そのフィルムの謎をおいはじめる。はたしてこれは、殺人の現場を撮った「スナッフ」なのか?現在消息不明のアンジェリカ、友人で編集者のケリーの姪(彼女の名もアンジェリカで、行方不明である)の行方調査もケリーやダイスの協力をうけながら、探っていく。 冒頭になかなかはいりこめず、買ってからずっと読んでいなかったのですが、途中から(フィルムをみるあたりから)どんどん引き込まれていきました。 フィルムを直視できないほどに強烈な印象を受けたわたし、デイヴィッド。そのフィルムの謎、そして女優たちを探っていく中で、彼は自分自身の過去もかえりみることになります。 女優アンジェリカ、同名の友人の姪、さらには謎の失踪を遂げたかつての恋人。「わたし」をめぐる女性たちにまつわる謎。「スナッフ」のようにも見える、とにかくなんらかのいわくありげなフィルムの謎。どの謎も、主人公の強い感情移入のため、より興味深いものとなっています。 インサート・シーンで、少しずつ恐怖心があおられます。そして、「謎」の解明(あるひとつの世界の解体ともいえるでしょう)にはいると、物語に入り込んでいたせいもありますが、ゾクゾクしてしまいました。 物語の大筋とは離れるのですが、私は映画はほとんど観ませんし、詳しくありません。なので、本作で語られる映画の話にはほとんどついていけなかったのですが(特に監督名や作品名)、一般的な話については、「映画」を「小説」に置き換えながら読みました。ある登場人物が、映画批評家に対する批判として、「誰が言ったわけでもないのに、勝手に<メッセージ>を読み取って、それを批判する(中略)結局自分の感受性の話しかしていないんだから(中略) 感想を書きたいならせめて面白おかしく楽しめるような文章を書いてくれりゃあいいのに…」と述べています。私は批評でごはんを食べているわけではありませんが、本の紹介と感想をホームページに挙げている身として、手厳しい批判だなぁ、と思いました。しかし、何度も他の作品の感想の際に言ってきたことですが、物語を読む(映画を観る)ことで、自分の世界観、社会のありかたなどについて考えることは、大切なことだと思っています。後半については…。う~、耳が痛いです。 また、スナッフ映画の話から発展した都市伝説についての話は、興味深く読みました。 全体を読んで、数作品ほどミステリを連想しましたが、これだけミステリを読んでいれば、そこは仕方ないでしょう。それでも、やはり本作は面白かったです。ーーー追記。明日朝に岡山に台風が直撃するらしいので、明日も家にこもって読書をしようと思います。今晩はもうなにかを読了することはないかもしれませんが、もし読了したら、一日に記事は三つまでしかアップできないので、昨日の記事としてアップするかと思います。なにか読む前に、フリーページの整理をしたいと思います。
2005.09.06
コメント(0)
-
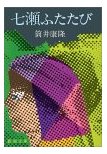
筒井康隆『七瀬ふたたび』
筒井康隆『七瀬ふたたび』~新潮文庫~ 家政婦をやめた七瀬。母親の家へ帰る電車の中、強烈な夢を見る。がけ崩れ、電車の脱線、多くの死傷者…。同じ電車の中で、彼女はテレパス(精神感応能力者)の存在に気づく。ノリオと、恒夫の二人だった。 七瀬は、ノリオと暮らすようになる。そして、さらなるテレパスとの出会い。やがて彼女は、彼女たちを殺そうとする集団の存在に気づき、彼らから逃れるべく動き始める。 目次に5つの章題がありました。短編(中編)として読むこともできたでしょうが、あえて長編として、通して読みました(一編ごとに感想つけると、時間かかるので…)。 テレパスを、もう少し身近な存在として読めば、考えさせられる部分も大きいのでしょう。私は、「鬼」を連想することしかできませんでした(高田崇史さんの作品が念頭にあります)。もちろん、そこから考えを発展させることもできるのですが…。『家族八景』では、テレパスの効果も十分にあるとはいえ、そこに描かれているのは多様な家族のどろどろとした関係、感情、要は人間模様でした。本作、『七瀬ふたたび』は、背表紙の紹介を読んだ時点で予想はしていたのですが、どちらかといえばエンターテイメントとして読みました。 さまざまな能力をもつテレパスたち。自分たちだけの間に暗黙のうちにあるルール。「普通の人」との相違。テレパスとしてのアイデンティティへの疑問…。 あまり勉強もしていないのに言うのはおこがましいのですが、民俗学などの「異人」の問題と関連しても考えられるかな、と思いました(先に書いた、「鬼」と同じようなことですが)。 とまれ、くりかえしになりますが、エンターテイメントとして楽しめる作品でした。面白かったです。 * 追記。一応、『家族八景』『七瀬ふたたび』『エディプスの恋人』は、独立した作品としても楽しめますが、次作につながってくる部分もあるので、順番に読むほうが良いのかもしれません。けれども、それぞれ作品の性格は違っているように感じました。 周囲を見る。自身を見る。人知を超えた存在を見る。…思い切って一言でいえば、このようにいえるかと思います。
2005.09.06
コメント(0)
-

筒井康隆『家族八景』
筒井康隆『家族八景』~新潮文庫~「無風地帯」読心能力をもつ七瀬は、お手伝いとして尾形家にやってきた。主婦の咲子の心の中には、些細な日常のことの「がらくた」があるに過ぎなかった。夫婦に、二人の子供。咲子の心から、家族への反感はうかがえなかったが、他の三人は表面上明るくふるまいながら、心の中では悪意を抱きあっていた。 コメント。読心能力が、あたりまえのように描写され、それからあらためて説明がなされる。悪意を剥き出しにし、露骨に対立しあう家族と、尾形家のように、表面上平穏無事をたもつ家族。私には、どちらも恐ろしいと思う。「澱の呪縛」次に七瀬がお手伝いとして住むことになったのは、13人家族の神波家だった。楽をしたいと考えている主婦の兼子の性格もあってか、家はずいぶんと汚れていた。そのせいか、一種独特の臭気があった。それをなんとかしようとした七瀬だったが…。 コメント。家のにおい、というのは、あると思う。仙台でアパート暮らしをしていたとき、やはりその部屋独特のにおいがあったし、実家には実家のにおいがある。そのにおいで、実家なんだな、と実感したり安心したりしたものだけれど。こういう一家もありえるのだな、と本作を読んで感じた。「青春讃歌」七瀬がつとめることになった河原家は、夫婦二人だけだった。陽子は、若さを求め、理論的な思考をし、七瀬の興味をひいていた。寿郎は、若さを求める妻に反感を抱いていた。そして、事故をきっかけに、二人はささいないさかいを起こす。 コメント。中年と、若さ。人は、赤ちゃん、幼児、子供、少年、青年、中年…と、人生の諸段階を歩むわけだけれど、すでに経験してきた世代の気持ちがなかなか分からなくなるものだ、と思う。自分が経験した頃の「若者」と、現在の「若者」の間に相当のズレがあるとはいえ…。「水蜜桃」桐生家の主人、勝美は、定年が早くなったため、現在無職だった。遊びを嫌い、仕事だけに熱中していた彼は、空虚だった。家族も、ぶらぶらしている彼を疎んじている。勝美の思考に、七瀬は関心を寄せ始める。 コメント。仕事。定年。「うち・そと」。代償。読んでいて、いろんな言葉が浮かんできた。とりあえず、自分には読書という趣味があってよかった、と思った。以前は、読書しか趣味がないため、読書すらできない精神状態にあるとき、どうしていいかわからず焦り、心配されたこともあるけれど…。「紅蓮菩薩」根岸家の主人、新三は、若くして助教授となった心理学者だった。妻の菊子は、巧みな演技で、上品でおとなしい妻、という印象を周囲に与えていた。新三は、「火田」という苗字に心当たりがあった。そのため七瀬は、二人の間に心のすれ違いがあるのを知りつつ、「掛け金」をおろすことができなかった。 コメント。いろんな家族のあり方を、読心能力のある七瀬の視点から描いてきているわけだけれど、七瀬自身の生活、生き方の問題も、「水蜜桃」あたりから、大きな主題になってきている。「芝生は緑」医師、高木輝夫の妻直子は、同じマンションの設計家、市川に好意を寄せていた。七瀬は、一週間、市川家の手伝いをすることになる。そこで、市川の妻が高木輝夫に好意を寄せていることに気づき、彼女は一つの計画を実行にうつす。 コメント。七瀬さんが、なんだか怖くなってきた。家族の中にあるどろどろとした感情に恐れや嫌悪感を抱いていた彼女は、次第に自分がお手伝いにいっている家族の人間関係を変えていこうとする。本作は、それほど重たい結末ではなくて安心したけれど。「日曜画家」竹村家にお手伝いにきた七瀬。日曜画家、竹村天州の妻、登志は、高慢で、七瀬を「女中」として扱った。登志も息子も天州を馬鹿にしていた。売り物にならない抽象画ばかり描いていたからである。二人に対して完全に心を閉ざしていた天州のありかたに、七瀬は好感を抱くのだが…。 コメント。ある個所から、激しい不快感に襲われた。物語に入り込んでしまっているからなのだけれど…。この短編集はどろどろした心情をずいぶん描いているが、本作は、私にとってインパクトが大きかった。「亡母渇仰」清水信太郎は、27歳で、妻がいるにもかかわらず、母離れができなかった。母が死ぬと、彼はひたすらに泣きつづけた。告別式でも、葬儀でも、取り乱して泣きつづけた。わがままで、あらゆる人間を見下していた彼の母。彼も、同じように、他人を見下し、気に食わないことがあればヒステリックになった。彼の妻である幸江は、清水家に嫁ぎ、つらい目にあってきていた。 コメント。この作品も、痛い。母親への極度の依存。母親の、息子への極度の甘やかし。幸江さんや、信太郎さんの会社の方々のことを考えると、気の毒になったが、もっとも気の毒なのは、信太郎さんなのかもしれない。親は、子供がそれなりの年齢になれば、精神的にはそれなりの親離れをさせる必要があるだろうし、自身も子離れをする必要があるだろう。極度の親子のつながりが、こういう事態を生むのだな、と感じた。 全体を通じて。 先日、七瀬さんが登場する『エディプスの恋人』を読んでいたのですが、本作は七瀬さん初登場の短編集です。タイトルの通り、八つの家族が描かれています。たしかに、こちらを先に読んでいた方が良かったのかも、と思う反面、『エディプスの恋人』を先に読んでいたからこそ、注意して読むことのできる部分もあって、これはこれでよかったと思いました。「日曜画家」が、ずいぶん印象に残っています。他人を、抽象画のように認識する男。その思考回路(様式)が描かれていくにつれて、本当に忌まわしいような気分になりました。 もちろん、誰もが口に出さない、どろどろした感情を多少は抱いていることでしょう。七瀬さんは、自分の読心能力に苦しみも感じていますが、自分にそんな能力があれば、私は壊れてしまうと思います。あるいは、その能力をうまく活かすか、悪用するか。七瀬さんは、基本的には、この3パターンの中で揺れ動いている…というか、彼女の中にはこの3パターンが混在しているように感じました。もちろん、実際はもっと複雑な感情でしょうけれど。 どの家族にも、多少のどろどろはあるでしょう。恋愛結婚とはいえ、相手の全てを盲目的に受け入れることは難しいでしょう。他者にいささかの非難も感じないことが、はたしてできるでしょうか。もちろん、その感情を抱いたとき、どうふるまっていくか、ということが大切なのだと思いますが。*注記。リンク(画像)は、改版のものですが、私が読んだのは旧版です。
2005.09.06
コメント(0)
-
高木彬光『刺青殺人事件』
高木彬光『刺青殺人事件』~角川文庫~ 有名刺青師、彫安には、三人の子があった。長男、双子の姉妹。三人には、刺青がなされていたという。タブーとされている、蛙、蛇、蛞蝓の…。 双子の姉、絹枝が、刺青競艶会に出場した。彼女の恋人は、彼女の刺青が他の人々に見られるのをいやがっていたが、彼女は出場、そして当然のように優勝した。彼女には立派な、大蛇丸の刺青があったのである。 競艶会で絹枝と知り合った松下研三のもとへ、彼女から連絡があった。命が狙われている、きてほしい、というのだった。 指定された時間に彼女の家に行くと、部屋に血痕があった。同じ時間、刺青研究家の早川先生も絹枝の家にきていた。二人は、水の音に気づき、浴室へ向かう。扉は、内側から鍵がかかっていた。扉の隙間からのぞくと、そこには胴体のない女性の死体があった。浴室の窓にも鍵がかかっており、そこは密室であった。 久々に昭和の古典的ミステリというべき作品を読みました。私は横溝正史さんが大好きなのですが、やはり時代のせいか、雰囲気が似ていますね。なんだか懐かしいような気分で読みました。 さて、本作は高木さんのデビュー作だそうです。密室、死体切断のトリック、理由のレベルが高い、ということは色々とミステリを読んできた中で知っていたのですが、いやはや、大したものでした。最近は、少々のトリックでは、「へぇ~」と思いながら読むのですが、トリックで「すごい!」と思えたのは久々な気がします。密室トリックは、そうとうミステリを読んできたので、目新しい感じはしませんでしたが、他の部分が良かったです。ただ、最後の方、(実は…、という感じの)付けたしのような部分は、よく分かりませんでしたが…。それまでの事件の解説ですごいなぁと思っていたので、ちょっといいかげんな読み方をしてしまったのは確かですが…。 さて、例によって適当に思ったことをつらつら。 私は蛞蝓が大嫌いです。見ただけで、激しい後悔に襲われます。何を悔いるのか謎ですが…。とにかくひたすらにいやな気分になるのです。脱線しますが、高校のとき、生物の授業で本物のプラナリアを見させてもらったことがあります。図説に載っているプラナリアはずいぶんかわいいのに、本物は蛞蝓小さくしたようなやつじゃないですか!その夜私は、巨大なプラナリアに襲われる夢を見ました…。悪夢です。文字だから読めましたけれど、本作が映像化されたら見たくないです…。 さて、神津恭介さんは、高木さんのシリーズ・キャラクターのようですが、なんともすごい人物です。19歳で、英語、ドイツ語、フランス語、ラテン語、ギリシア語を話し分けてたんですって。うらやましいことこの上ないです。ラテン語なんてめったに話すことないでしょうから、使い分ける、という表現の方が適切なのでは、と少し思いましたけれど。 推理小説としてはすごく面白かったです。ただ、最近は好みが変わってきているので…。もうちょっと社会や自分の日常生活、価値観を見つめなおす機会を与えてくれるような物語が好きになってきているので。中学、高校の頃に読んでいたら、もっとテンション上がっただろうと思います。
2005.09.03
コメント(4)
全22件 (22件中 1-22件目)
1
-
-

- ボーイズラブって好きですか?
- ヒロアカのBL同人誌!緑谷出久と爆豪…
- (2025-07-10 07:00:04)
-
-
-

- 読書備忘録
- 羅生門 芥川 龍之介
- (2025-11-10 13:54:06)
-
-
-

- 最近買った 本・雑誌
- 今年も神田古本まつりに行きました。
- (2025-11-10 15:52:16)
-







