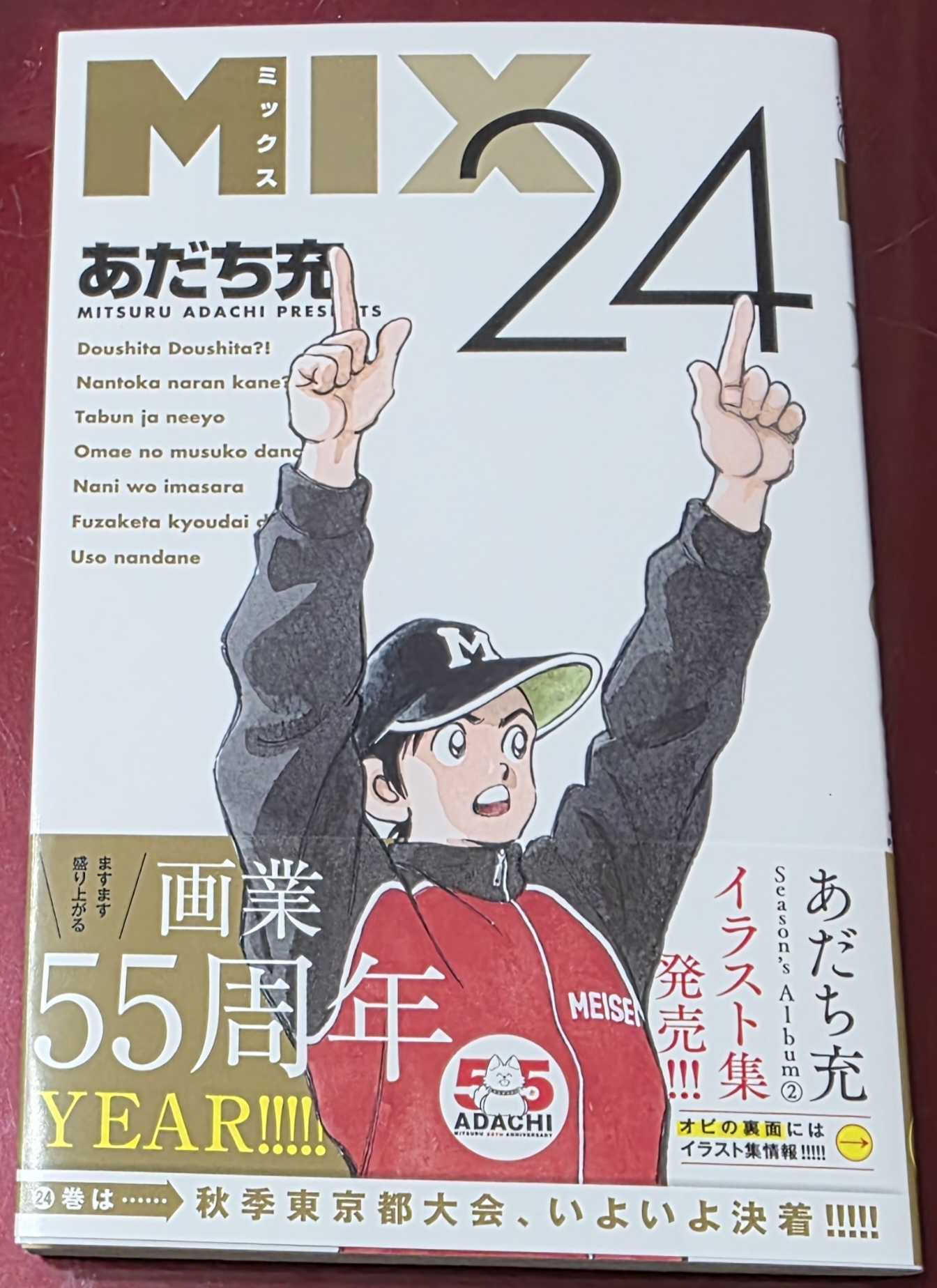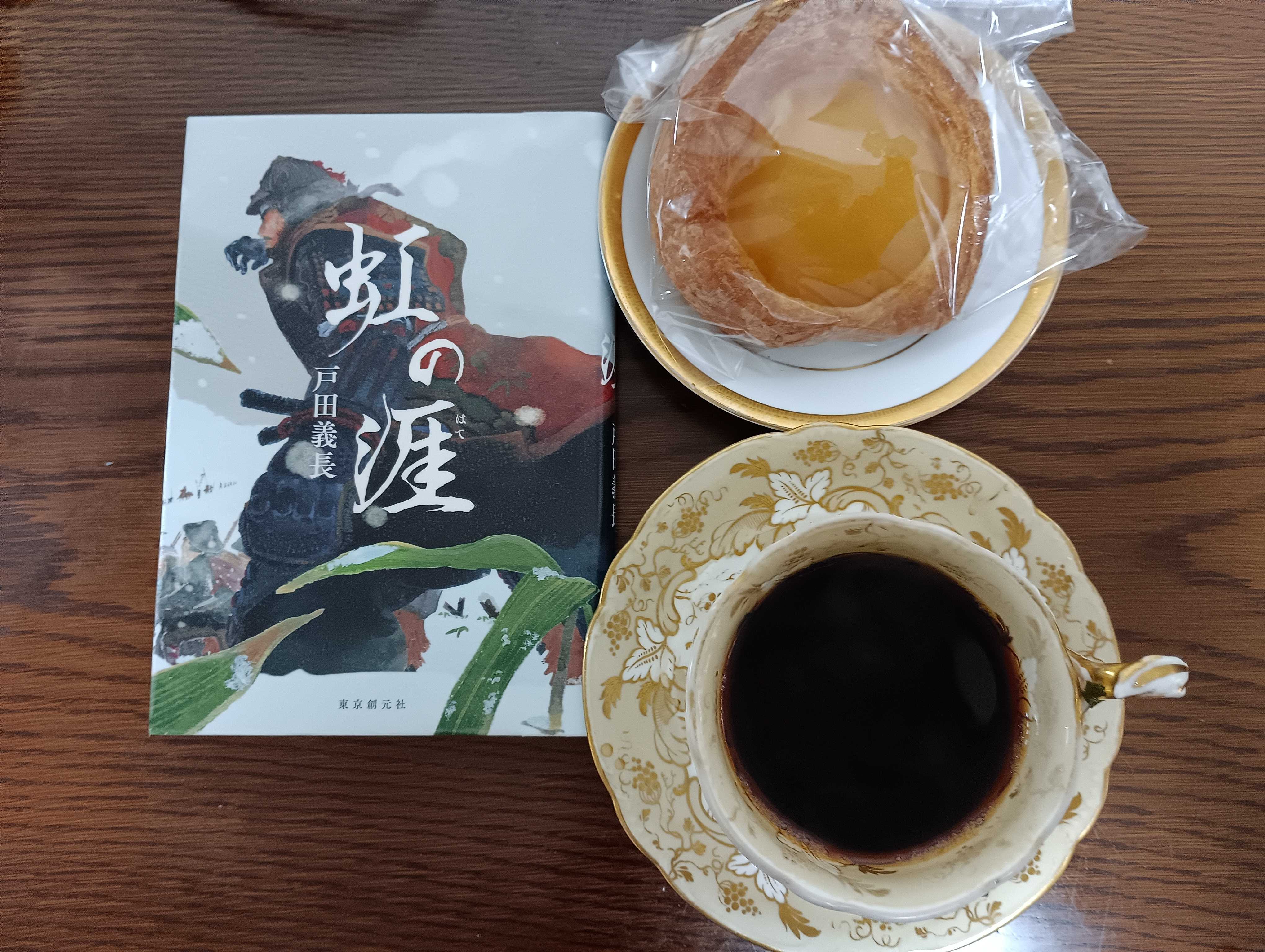2005年12月の記事
全15件 (15件中 1-15件目)
1
-
今年読んだおすすめの10冊
さて、例によって特に順位づけることなく、この一年で読んだ作品の中から10冊選んで紹介しようと思います。作品の順番は、読んだ順番です。また、あくまで今年読んだ作品(再読含む)ですので、ここで紹介している作品が新しい作品とは限りません。…というか、新しい作品は少ないですね。(なお今年、小説・エッセイは106冊読んでいます)・吉本ばなな『哀しい予感』 吉本さんの作品の中で、最も印象に残っている作品の中の一つです。一月下旬頃から、集中的に吉本さんの作品を読んでいた時期がありますし、ここに挙げました。『キッチン』とも悩んだのですが。・島田荘司『改訂完全版 異邦の騎士』 島田さんの作品の中で最も好きな作品です。いろんなエピソードを思い出すだけで泣けてしまいます。運転中は思い出さないようにしないと…。あわせて、『御手洗潔のメロディ』に収録されている「さらば遠い輝き」もおすすめなのですが、いずれも御手洗さんシリーズを順番に読んでこそ、より感動の大きい作品だと思います。・はやみねかおる『僕と先輩のマジカルライフ』 f丸さんから紹介していただいた作品です。安心して楽しめる作品集でした。ミスコン反対運動が描かれた話があったと思いますが、私の出身大学で、今年、似たようなことが起こって、ヤフーの記事にも出たそうですね。別段感慨はありませんでしたが。・佐藤友哉『子供たち怒る怒る怒る』 講談社ノベルス以外から出た佐藤さんの初作品にして、従来の作風とはずいぶん違った方向性をもつ作品です。「りかちゃん人間」「死体と、」がかなり印象に残っています。鏡家サーガも好きでしたが、こういう作風もとても楽しめました。・筒井康隆『エディプスの恋人』 今年新しく読んだ作家の中で、最もインパクトがあったのが、筒井さんです。その中で最初に読んだ本書を挙げることにしましたが、七瀬さんシリーズ『家族八景』『七瀬ふたたび』そして本書の三部作を全ておすすめしたいです。面白かったです。筒井さんに関しては、いろいろおすすめを紹介していただいているので、また機会を見てぜひ読みたいと思っています。・小路幸也『ホームタウン』 私情をはさんで恐縮なのですが、本書について私が書いた記事に、小路さんご自身からコメントをいただきまして、そういう意味でも特別な作品です。・舞城王太郎『阿修羅ガール』 文庫版で再読したわけですが、印象に残りました。森の中の一連の出来事。ぐるぐる魔人の歪みっぷり。強烈な印象、ですね。・武田泰淳『わが子キリスト』 torezuさんに紹介していただいた作品。表題作以外は、中国が舞台で、多少とっつきにくい部分もあったのですが、表題作がとにかく面白かったのです。イエスの奇跡の偽造、「おれ」のイエスへの不信、それがいつのまにか、意外な方向に動いていく…。史的イエスの問題も興味深いのですし、それなりに「キリスト教史」を勉強している者としてはもう少し勉強した方が良い領域だと思うのですが、泥沼にはまりそうで、正直深くつっこんで勉強するにはためらいが大きいです。それでも、本書は面白かったです。あわせて、太宰治の「駆け込み訴え」も、イエスの奇跡についての一つの説明と、裏切り者ユダの再検討をせまってくるようなモチーフで、印象に残っています。・ベン・ライス『ポビーとディンガン』 映画化もされました。ちょうど本書についての感想を書いた後に映画化情報を知ったので、こちらも若干私情をはさむわけですが、大切な作品です。学生時代に一度読んでいたのを、再読した矢先のことですから。年明けに、映画を観にいく予定です。楽しみ。・島田荘司『ハリウッド・サーティフィケイト』 今日読んだばかりというのもあるのですが、メッセージ性の大きさ、物語の大きさに、圧倒されました。『摩天楼の怪人』などは新刊ですし、こちらを挙げるかどうか考えたのですが、やはり私にとってのインパクトなどを考えると、『ハリウッド・サーティフィケイト』の方をおすすめの作品として挙げることが妥当だと考えました。『異邦の騎士』もおすすめの10冊に挙げましたが、やはり、島田荘司さんのすごさを痛感しました。面白いです。 *せっかく読書記録をつけたので、月毎の読了冊数(専門書は除く)をかいておきましょう。1月:17冊2月:13冊3月:9冊4月:2冊5月:7冊6月:6冊7月:3冊8月:16冊9月:12冊10月:7冊11月:4冊12月:9冊やはり、休み期間は読書に割いた時間が長いなぁ、というのが一目瞭然ですね。もうちょっと勉強もしていたつもりなのですが…。*ともあれ、もうすぐ2005年も終わりです。少し前まで、私は年の変わりなんて、あくまで便宜的なもので、いちいち盛り上がる必要があるの、なんて思っていました。明けましておめでとう。たしかに、基本的には365日の一年がなにはともあれ終わり、新しい年を迎えることはめでたいことですが、そんなことを言っていれば、日々、新しい一日を迎えることがかけがえのなくめでたいことではないでしょうか。若いだの青いだのと思わなくもない、そんな考え方が私の主流でしたが、最近、どうも考え方がまるくなってきたようです。「良いお年を」この一言が、すごく素敵な言葉と感じられるようになりました。もちろん、新年を区別してめりはりをつけることの大切さも分かっているつもりです。先にいらないことを言いましたが、この一年も、私は多くの方々にお世話になりました。近くにいる方々には、伝えてるつもりですが、ブログの方でも、いろんな方々にコメントをいただき、元気付けられることしばしばでした。この場を借りて、このブログにいらしてくださる方々、みなさまにお礼申し上げます(このブログを見てくださっているかどうかはともかく、もちろん、身近な方々、さらには物理的には離れてしまっていますが、私に叱咤激励くださった方々にも)。この一年間、ありがとうございました。数時間後にひかえていますが、来年もよろしくお願いします。
2005.12.31
コメント(2)
-

島田荘司『ハリウッド・サーティフィケイト』
島田荘司『ハリウッド・サーティフィケイト』~角川書店~ ハリウッド女優レオナ・マツザキの親友で、同じく女優であるパトリシア・クローガーが殺された。 あるヴィデオが、LAPD(重要犯罪課)に届けられた。パトリシア殺害の犯人が自ら、その殺害の過程を写したスナッフ(殺人を写したヴィデオ)だった。犯人はパトリシアの両手を手錠をかけ、彼女が成功する過程で関係した男たちのことを白状させる。そして、銃殺。その後のことはヴィデオに写されていなかったが、犯人はパトリシアの腹部をのこぎりで切り、子宮などを奪っていた。 この事件に対して、レオナは怒りを表明した。犯人を決して許せない、と。そして彼女は、事件の捜査に深く関わることになる。 同じ頃、レオナの知人が、彼女にジョアンと名乗る女優志願者を紹介する。ジョアンは、記憶を失い、しばらくホームレス生活をしていたという。また、腹部に手術の跡があり、腎臓と子宮がとられている、と言う。ジョアンはイギリスで一緒だったというイアンのおかげで、ケルトの神話に詳しく、いろんな話をレオナにしてくれた。 パトリシア事件からしばらくして、再びLAPDにヴィデオが送られてくる。次のヴィデオの被害者はしかし、殺されず、世間の注目を浴びることになる。 レオナはLAPDのエドの強力をえながら、事件の解決に乗り出していく。 すごいです。やっぱり島田荘司さんはすごい。2005年最後に読む小説となるでしょうが(今日はもう寝るまで小説は読まないことにしようと思うので)、本当に良い読書体験でした。本書を買ったのは、たぶん4年前。ハードカバーで760ページ、最初に読んだとき、第一章あたりであまり楽しめず挫折、そのまま眠らせてしまっていました。その間に文庫版も出てしまったわけですが…。で、私は横になって読書をしているので、途中、本を支える腕がしびれたりしてびっくりする、なんて体験もしながら読み進めたのですが、しつこいですが面白かったです。 第二章。ケルトの神話がいろいろと紹介されます。パトリシアから子宮が奪われたことと、ケルトの神話で重要な役割を果たす子宮。こちらはこちらで興味深いのですが、神話自体が面白いのです。ローマ帝国のブリテン侵入、アングロ・サクソンの侵入。このあたりの史実もふまえた話はとても興味深く、私はいうほど神話関係の本も読んでいませんので、ある神話が「異教」からキリスト教への改宗を示すものだ、という話もとても興味深かったです。 ケルト民族のリーダー的女性が、ローマの兵士にとらえられます。彼女はケルトの伝説を語り、ケルトの民を元気付けていたのでした。ローマ人は彼女に、物語をさせます。そして、それを称えます。やがて、彼女に台本が渡されます。いつも通りの彼女のように、ケルトの伝説を語ることが中心。しかし最後は、その劇の中で、彼女自身が処刑されるという話です。殺される前に、牛に犯されて。 以下、いささかネタバレも含むので、文字色を変えることにします。 こういった話が、ただ物語の紹介に終わらないわけです。全体の中で、重要な役割を果たすことになります。 ハリウッドの女優たちがもつ、名誉への執着、傲慢さ、裏の姿、友人が同時に恨めしい人間でもありえるという世界。本書の中で、こうしたハリウッド女優たちの裏にある暗い部分が果たしている役割ももちろん大きいのですが、国家規模の裏組織の存在、臓器移植にまつわる問題、クローン問題、こういった先端医学の問題が大きくとりあげられており、考えさせられました。クローンは、倫理的に許されがたいものである。一方、クローン技術によって、免疫の問題も克服し、自分が望む臓器移植がうけられるかもしれないという、理想がある。もちろん、私は医学に詳しくないので、クローンの話については、本書で得た知識くらいしかなく、その知識をもとにこれを書いているわけですが、倫理的な規範を犯してまで、人は生きていいのか、人を生かしていいのか、ということを考えました。もちろん、私もそういう状況におちいったら、こんなところでのんきに思索している以上に、もっと深刻に、全力で、その問題について考えることになるのでしょう。所詮、いまの自分はのんきに生きているという現実。けれど、そういうことも含めて、問題を知り、問題意識を抱き、考えさせてもらえた、ということで、この読書体験は貴重だったと思うのです。これさえも奇麗事でしかありませんが…。 作品の性格上、『アトポス』を思い出さずにいられませんでした。あの作品も細かいところまでは覚えていないのですが、レオナさんが中心ですしね。(反転ここまで) さて、本書の主人公はレオナさんです。最後の方は、どうしようもない気分になる事態になってしまいますが…。私は正直、あまりレオナさんに好感を持っていないのですが(そのあたりも、本書を長いこと未読の状態にしておいた原因かもしれません)、それでもかっこいい、と思いました。いたたまれない気持ちにもなりましたが…。御手洗さんも、少しですが(そして電話ですが)、登場します。やっぱりかっこいいですね、御手洗さん。警察のエドさんも活躍します。本書の中で、一番まともな人間というか、「一般」の人に近い人で、彼のおかげでなにかしら安心して読める部分もありました。レオナさんも、彼のおかげでずいぶん安心していますし。(追記)読書中に腕がしびれた、と書きましたが、考えてみれば読了に8時間くらいかかっているわけでして…。その後も、多少ひじが痛いです…。
2005.12.31
コメント(4)
-

西尾維新『ネコソギラジカル(下)青色サヴァンと戯言遣い』
西尾維新『ネコソギラジカル(下)青色サヴァンと戯言遣い』~講談社ノベルス~ 戯言シリーズ最終作です。 友との「別れ」、狐面の男の賭け、橙色と赤色の対決。「ぼく」のまわりでいろんなことがあったわけですし、これからもずっと続いていくようですが、うん、「ぼく」はずいぶんかっこいいと思いました。本名を名乗るときも伏せ字で、結局「ぼく」の名前はわかりませんでしたが。 中巻に伏線(?)がでてきて、本書のカバーイラストからもうかがえるのですが、そのあたりの事情がふれられないままの描写というのは、素敵でした。 このようにシリーズが終わってしまうと、なんともいえぬ感慨にとらわれます。 2002年、発売から数ヶ月遅れで『クビキリサイクル』を購入、読了してから、3年強。『ネコソギラジカル』までは、なんとかミステリと呼べる要素もありましたが、本作はそういう枠を超えた物語になっています。 良い読書体験でした。
2005.12.31
コメント(0)
-
2005年総括
昨年も12月30日に一年を総括する、なんてことをしていますので、今年もしてみようと思います。…一年経つのが早すぎます。4月に入学して新生活が始まり、充実した日々を送っています。仙台にいた頃はアパートで主に勉強していたのですが、いまは研究室を使わせていただけるので、勉強は学校で、と完全にめりはりをつけた生活を送っています。まったく想像もしていなかった生活ですが、楽しんでいます。…今日は、こちらにはこのくらいで。明日も、昨年にならい、今年読んだおすすめの10冊ということで記事を書こうと思います。二日。のんびり過ごそうと思います。
2005.12.30
コメント(3)
-

西尾維新『ネコソギラジカル(中)赤き制裁vs.橙なる種』
西尾維新『ネコソギラジカル(中)赤き制裁vs.橙なる種』~講談社ノベルス~ 自分のパソコンの方にはメモをとりましたが、今回はあらすじは省略します。(多分下巻もそうするでしょう。記事が、ほとんど読んだというメモになってしまうのが恐縮ですが) シリーズ最終作、『ネコソギラジカル』の中巻です。これでもかってくらい話が二転三転します。最初の方はしんどかったですね、情が移ってきた登場人物の数名が、殺されてしまいますから。まぁ好きでこういう小説を読んでいるわけですが…。 で、やっぱり、みいこさんはいいこと言うなぁ、と思いました。『ヒトクイマジカル』でしたか、うじうじ言うぼくにきつく言い聞かせ、そして救ってくれたみいこさん。救いが、あるのです。 真心さんの言葉もよかったですね。 今回も、思わせぶりなところで終わっています。 …本来31日に読む予定だったのですが、今日も風邪が治らず、あんまり無理して作業して悪化しても悪いと思い、早めに帰宅したのでした。このくらいのペースで小説を読めるのは久々です。
2005.12.29
コメント(1)
-
林健太郎『史学概論』
林健太郎『史学概論』~有斐閣、1953年~E.H.カー『歴史とはなにか』に続いて、歴史学の理論に関して、勉強会で読んだ本書。日本で、いまだこれを超える歴史学の概論はない、と評されていたのですが、記述が非常に親切です。先人の言葉を引用したあと、それをうまく要約しています。部分的とはいえ原典を読むことができ(しかも、その原典の本質的な部分が引用されていると思います。このあたりの事情は後述しましょう)、しかもそれがかいつまんで説明されているのですから、とても分かりやすく、勉強になるのです。 なお、著者の林健太郎さんは、最近改訂されるまでの山川出版社から出ている世界史Bの教科書(私はこれを使っていた世代です)の執筆者の一人です。なんだか感慨深いものがありました。 目次は以下のとおりです。第一章 歴史及び歴史学の語義第二章 歴史学の対象とその範囲第三章 歴史学における批判的方法第四章 歴史の研究と歴史の叙述第五章 歴史事実と歴史の理論第六章 歴史理論としての地理的環境論第七章 歴史理論としての発展段階説第八章 唯物史観の諸問題第九章 歴史法則に関する一般的法則第十章 歴史法則に関する結論的考察第十一章 歴史における個別性の問題第十二章 歴史における人間性の理解第十三章 歴史における個別性と一般性第十四章 歴史認識の主観性と客観性むすび第一章では、歴史の語源であるヒストリア(ギリシア語:研究によって得られた知識)とゲシヒテ(ドイツ語:起こった事柄)が紹介され、語源からして歴史が二面性をもつことが示されます。歴史には、人間の主観により形成される歴史像と、客観的所与としての歴史(むすびでの言葉を借りれば、人間の主観とは関わりなく存在する、過去において人間が行った一切の事柄)の二つがあるというのです。第二章では、歴史学の対象はあくまで人間の歴史だとされます。ここで科学の区別がなされるのですが、興味深いので紹介しましょう。まず、A自然科学と、B歴史的諸科学に分類されます。Bには、人文科学、社会科学、精神科学が含まれます。歴史学の趣旨は、人間に関する事柄をその歴史性において追求することです。ところで、政治学などは歴史的なものを対象としていますが、それを歴史性において扱っているわけではありません。また、文学や美学などは、抽象化された人間一般について扱います。ですから、これらは「非歴史的歴史科学」と呼ばれています。Bに共通する共通基盤は、「歴史的歴史学」としての歴史学だとされます。それは、「実証的」といわれる方法と、「叙述」が重要な位置を示すことです。第三章では、歴史学の研究の基盤として、A史料学、B史料批判について論じられます。歴史学研究法について、西洋の研究者はベルンハイム、ラングロワ、セニョボスが紹介されます。Aの中心は、史料の分類。(1)史料自体が実質的に歴史的対象を表現しているもの(例:遺跡、発掘物)、(2)史料が歴史的対象を直接に発言しているもの(例:年代記、伝記)という分類が、批判される点はあっても有効だといいます。Bは、(1)外的批判-a.真純性の批判、b.来歴批判、c.本源性の批判、(2)内的批判に大別されます。(1)は、史料の性質や価値(たとえばc.はオリジナルかどうかということ)を、(2)は内容の信憑性を決定する作業です。第四章では、ベルンハイムによる歴史叙述の三段階区分に沿いながら歴史(叙述・研究)作品を通史的にみています。ここでの結論は、歴史学には(1)史料に基づき事実を決定する、あるいはそれに解釈をほどこし意義を論じる面(研究)と、(2)(1)の作業を総合して、なんらかの歴史叙述を行う面(叙述)の、二つの側面があるということです。第五章では、まず、個々の事実をつなぐ、その裏にある真の事実を見る作業の必要性が説かれ(これは史料批判とは異なる次元の作業だといいます)、歴史の理論の重要性が指摘されます。ここでは、カントの認識論が強調されています。第六章では、歴史理論の中心に地理的環境をおく説が紹介されます。ヘルダー、ヘッケル、バックル、ラッツェルらの説を紹介し、それらの意義を認めつつ、林さんは歴史理論には適用できない、といいます。第七章は、発展段階説ということですが、経済的要因を重視する諸説が紹介されます。ランプレヒトが強調されていますが、第六章と同じく、経済的要因も歴史理論には適用できない、といいます。第八章は、本書の中で第一の山だと思います。林さんは、唯物史観の意義を高く評価しているからです。唯物史観の特徴は、(1)生産を経済行為の基礎とし、生産様式に基づく段階論であること(社会構成の理論であること)、(2)段階の変化を必然的な発展ととらえる動的な史観であること、(3)行動の理論となることなどです。これには、多くの問題点があります。まず、歴史的事実にそぐわない説があること。なにより、学問が政治に従属してしまうという危険性です。(ずいぶん長くなりましたので、以下はさくさくと)第九章では、第六章から第八章を整理し、全ての歴史事実をただ一つの法則で説明するのは不可能だ、と結論します。そして第十章ではこれをさらに展開し、歴史における単一の法則を否定し、主要な法則と副次的な法則の重要性を認めることの重要性が、林さんの結論だとしています。なお、歴史の必然性には、自然の必然性よりもはるかに蓋然性の性質をもつ、と指摘されています。まったくそのとおりでしょう。第十一章では、ヴィンデルバント、リッケルトの、個別性を強調する説が紹介されます。第十二章では、「精神的諸科学」という枠組みを唱えたディルタイが中心に紹介されます。第十三章では、マックス・ウェーバーの歴史理論が主に紹介されます。彼の「理念型」というのが、あくまで思想像であり、それに完全に合致する事実はないこと、これと(歴史的)現実を比較することで、その一般性と特殊性が明らかになる、といった説明は、実に分かりやすかったです。第十四章では、歴史認識の主観性を考察する理論として、(1)クローチェ、トレルチの歴史哲学、(2)唯物史観、(3)プラグマティズムが紹介されます。ここでは、主観性というのは個人の主観ではなく、社会性をもつという指摘と、現代とは特定の意味をもつ「歴史的現代」だという指摘が重要でしょう。長くなってしまいました。ノートのノートということで。(追記)すみません、冒頭のあたりで、「このあたりの事情は後述」などと書いたのですが、記事が長くなってきて慌ててしまったので、結局後述できませんでした。また後日(早ければ明日にでも)あらためて追記します。(追記)たとえば、第十一章では、リッケルトが個別性を追求したことで、「価値」を重視したことが論じられます。8行ほどリッケルトの言葉を引用した後、”いうところはなお曖昧であるが、要するに価値とは「事実上一般に承認されているあるいは『文化人』にとって要請されている規範」ということになるであろう”と、うまく要約されているのです。また、第八章では、マルクスやエンゲルスが公式的に経済的要因によってのみ歴史を説明しているわけではないことが明らかだとし、それを示すためにエンゲルス自身の言葉が紹介されています。もっとも、これについては林さんによる批判が続くわけですが、冒頭でも書いたように、著名な人々の言葉を部分的でも、重要なところをかいつまんで読むことができて、本書は非常に有益な著作だと思います。このあたりで。
2005.12.29
コメント(5)
-
乾くるみ『林真紅郎と五つの謎』
乾くるみ『林真紅郎と五つの謎』~カッパ・ノベルス~「いちばん奥の個室」一部で有名なバンドのライブに、姪の保護者として連れ添った真紅郎。ライブの最後の曲の前に、ちょっとしたマジックが披露された。箱の中に入った女性。箱は鎖で空中に持ち上げられ、そして次に開いたときには、そこから女性がいなくなっていた。…ところが、その女性がライブの終了後、トイレの個室で、頭から血を流しているのが発見される。「ひいらぎ駅の怪」大雨の夜、友人とともにひいらぎ駅にいた真紅郎。そこで、女性が階段から転げ落ちるという事故が起こった。さらに、現場に居合わせた別の女性のカメラも紛失していた。小規模な駅で、そこにいる限られた人々以外に、外部からきた人がいないことが分かっているが、誰もカメラを持っていなかった。「陽炎のように」友人の妻が亡くなった。告別式に友人とその妻とともに参列した真紅郎。その帰り道から、周囲の人々が彼のあたりを怪訝に見ることが重なる。じーっと見つめてくる女性。窓際に座った真紅郎のあたりを見ながら、なにかの理由でお盆を落としてしまったレストランの店員。また、亡くなった女性とその夫をめぐり、真紅郎たちは、最近のテキリマ事件とからめながら、議論を進めていく。「過去から来た暗号」小学校時代の友人でばったり再会した真紅郎。友人は、真紅郎が暗号遊びをしていたことを懐かしげに語った。しかも、その解読表はなくしてしまったようだが、暗号文の一つは、まだ残っているという。届けてもらったその年賀状を見ながら、真紅郎は解読作業を進めていく。「雪とボウガンのパズル」大学で教えていた頃に知っていた学生と、初雪の早朝、ばったり出会った真紅郎。犬の散歩をしていたのだが、犬がその学生を気に入ったようで、二人は結局学生の下宿先まで歩く。ところがそこでは、変死事件が起こっていた。建物と塀に挟まれた狭い裏庭で、学生が死んでいた。ボウガンの矢が突き刺さっていた。怪しい足跡もなく、二階の被害者の部屋の玄関は、内側から施錠されていた。 法医学教室に勤務していた林真紅郎さん。彼は、最愛の妻を亡くしてから、職につかず、ぶらぶら生活しています。林家が裕福なために、そんな生活もできるのだとか。 どれも、謎解きの話として面白いと思います。一話目で、結局謎なんていうものは、ある観察者がそれを謎と認識しているだけで、他の人にとっては実は謎ではない、という実は当たり前のことを、ストレートに訴えてくるようなものを感じました。 二話目は、モラルの話がうまくからんできていて、面白かったです。 三話目は、かなり怖かったです。私が幽霊関係の話が苦手なのもあるのですが、テキリマをめぐる話は、小説という虚構の中でも、さらに想像の話なのに、どこかリアルで。しかもお食事中に、手を切ってどうこう、という話をするわけですよ。 …私も、一般的には食事中はふさわしくないんじゃないかな、という話でもって、食事中に盛り上がることはあるわけですが…。カニバリズムとか。 第四話。本書の中で一番面白かったような。たしかに、暗号解読自体は読んでいて退屈かもしれません。そうとう伏線、というか、真紅郎さんが暗号を解読する思考が忠実にトレースされているので、くどいとさえいえると思います。でも私はそこが楽しめましたし、そうした単調な作業の中に起こるある「ドラマ」がうまく生きているのに感動しました。 第五話は、やるせない結末です。それこそ今日西尾さんの作品の感想のところでずいぶん紹介したジョジョを例にとれば、第6部のマックイイーンの過去みたいな。 全体を通して、素直に楽しめる作品でした。
2005.12.28
コメント(0)
-

西尾維新『ネコソギラジカル(上)十三階段』
西尾維新『ネコソギラジカル(上)十三階段』~講談社ノベルス~ シリーズ最終作、三巻本の第一巻です。 これまでのシリーズの登場人物が(名前だけの人もいますが)これでもかと出てくるので、これまでの作品をおさえておかないと、なかなかしんどいかな、と感じました。なにしろ登場人物表に60人以上の名前があるのですから…。でも全部再読していたら大変ですので、読み進めることにします。 いつもの程度の内容メモは、以下のとおり。 『ヒトクイマジカル』の事件の後、入院している「僕」のもとへ、みいこさんたちがお見舞いにきてくれた。みいこさんと話しているところへ、突如として現れた男、奇野頼知。彼は、「十三階段」の一人だと名乗る。狐面の男のもとにいる人物であり、狐面の男からの使者だった。彼が、みいこさんを「いーちゃん」と勘違いしたため、みいこさんも事件に巻き込まれることになる。 ところで。「僕」は、入院中、狐面の男のことを調べていた。それがあまりに大変な方向に行きそうだったため、「僕」は『クビキリサイクル』の事件で知り合った「メイド」と再会を果たすことになる。彼女はそのまま、「僕」のそばにいるという。 同じ頃、しばらく続いていた玖渚一家の内紛も終わり、「僕」は久々に友のもとへ訪れる。そこには、『クビキリサイクル』の事件で関わった意外な人物がいた。 友と別れたところで、「僕」を待ち受けていた狐面の男。「十三階段」がそろったという。「僕」のことを「俺の敵」と呼ぶ男は、ハンデといって、福岡に行くことを僕にすすめた。 出不精の「僕」だが、福岡へ向かう。そこで、「僕」はある人物と出会う。さらに、自分の身辺の意外な事実が分かり、また狐面の男がしかけた罠もあり、「僕」は男の挑戦に乗っていくことになる。少しずつ、味方を増やしながら。 ジョジョネタがところどころにちりばめられていて、こういう時にジョジョを読んでおいて良かった、と思います(あるいは、他の漫画などのネタもちりばめられているのかもしれませんね)。一週間ほど前くらいから、ジョジョ第5部を再読しているのですが、まさに本書で「たとえ」として出ているスタンドは第5部のスタンドですから、ちょっとテンション上がりました。52頁の奇野さんのセリフなど、第3部のアレッシー(セト神)かスティーリー・ダン(恋人)あたりのセリフを意識していると思うのですが、第3部が手元になく、確認できなかったのが悔やまれます。やはりジョジョは全てそろえておきたいですね…。 最近、読書しながら付箋を貼る機会がずいぶん少なくなっていたのですが、本書にはけっこう貼りました。たとえば、86頁の、新しく知った言葉を、それからやたら目にするように感じるけれど、その言葉とはその言葉を知る前から出会っていた、というような話。これなども常々感じる現象なのですが、このように他の方の言葉にふれられると安心します。それから、他人が傷つくのは、その痛みが分からないから辛い。それよりは、自分が傷つく方がよい、という思考。興味深く読みました。こちらも、なにかしら考えていることですので。 上巻を読了したわけですが、終わらせ方が絶妙です。盛り上がったきたところでCMに入るテレビ番組のように。なにはともあれ、上中下三巻ともそろえてから読み始めたのは、私には正解だったかな、と。発売された都度読んでいたら、どんどん内容を忘れてしまっていたでしょうから。 中巻、下巻は31日に読む予定です。楽しみ。
2005.12.28
コメント(0)
-

鷺沢萠『夢を見ずにおやすみ』
鷺沢萠『夢を見ずにおやすみ』~講談社文庫~「今日も未明に電話は鳴った」父親のガールフレンド、ハマジュンから、未明に何度も電話がくる。父親と喧嘩して。会いたい、話したい。うっとうしく感じている和広だが、本当にハマジュンと父親の関係がやばくなってきたと思われた頃、職場であるデパートの靴コーナーにハナジュンが来たときは慌てて、彼女の話を聞くことにする。バカで、でもカワイソーなところもある。そう彼女のことをとらえていた和広だが、考え方をあらためていくことになる。「あなたが一番好きなもの」かつて、自分に夫と別れるように迫ってきた女-当時、夫の浮気相手だった女、真梨子から電話がかかってきた。結婚することになった。結婚相手に会ってもらえないだろうか。真梨子の言葉は、信代には意味が分からなかった。そうする義理もない。しかし同じ頃、夫と息子との関係の中でいらいらもたまっていたことも重なり、信代は、「面倒くさい」という気持ちにも関わらず、真梨子に会いに行くことになる。「夢を見ずにおやすみ」高橋淳子は、結婚式会場でエレクトーンを演奏する仕事をしていた。そんな彼女の姿は雑誌でも紹介されたのだが、それを見たという、今は亡き父が生前関わっていた女からとつぜん電話がかかってきた。こちらも疲れているのに、ゆっくり休ませてくれない夫。仕事の方でも嫌なことが重なった。淳子は、自分でもそうする理由がわからないまま、彼女に会いに行く。 数年ぶりの再読です。独立した短編集と思い込んでいたのですが、登場人物は重複しています。上の内容紹介でも多少意識しましたが、「できればあまり接したくない人物からの電話」「自分でもうまく理由付けできないままその相手と会う」という点で共通しています。 なんというか、周りの人間をバカだと思い、不満を感じ、自分もがんばっているのにどうしてこんな思いをしなくては、という不条理(でもないか)な思いにとらわれている人々が主人公で、でも自分がバカだと思ったり不満を抱いている相手も、実はがんばっているし、(それがバカげたことかもしれないにしても)夢中になって取り組んでいることがある、ということかな、と。 最初の話は和広さんが主人公ですが、後の二編は夫をもつ女性が主人公で、より類似性を感じました。洗い物などの家事、夫への不満、というところにそれを感じました。 …短いし、さーっと読めると思って読んだのですが、どうもモヤモヤした感覚が残ります。それぞれの終わり方は、決して暗いものではないのですが、物語の中での「暗さ」にいちいち反応してしまうので(それは物語を読む中で自分の中に見つける「暗さ」でもあります)、どうも…。
2005.12.25
コメント(0)
-
ホイジンガ『中世の秋』(上)
ヨハン・ホイジンガ(堀越孝一訳)『中世の秋』(上)~中公文庫、1976年~背表紙に「たぐいまれな想像力の所産であるこの史書」とあるように、根拠がなんなのかわからない、つっこみどころ満載の描写が多いですが、その分中世末期の雰囲気はよく伝わってくるように思います。緒言に、本書は14,15世紀をルネサンスの告知ではなく、中世の終末としてみようとする試みだ、とありますが、文体はそうとうテンション高いです。目次は以下のとおり。1.はげしい生活の基調2.美しい生活を求める願い3.身分社会という考えかた4.騎士の理念5.恋する英雄の夢6.騎士団と騎士誓約7.戦争と政治における騎士道理想の意義8.愛の様式化9.愛の作法10.牧歌ふうの生のイメージ11.死のイメージ12.すべて聖なるものをイメージにあらわすこと本書については、面白かったところ、テンション上がったところをメモしておきます。先に、想像力の所産と紹介されていることにふれましたが、雰囲気で書いているところをいくつか。「誇張のうちにこそ、真実の背景がうかがえる。つまりは、18世紀の感傷人が流す涙と同断であろう。落涙は、ひとの心を高める。涙は美しい」(22頁)…後半、ホイジンガの主観ですよね。「女性のみまもる前で、勇気を示し、あえて危険に身をさらし、強くありたい、苦しみをしのび、血を流したいと願う気持ち、16歳の少年ならば誰でも知っているあの熱望の直接のあらわれである」(145頁)。16歳の少年、と決められているのがたまりませんでした。「愛ゆえに苦しむ男というのは、男自身がそうみられたいと望んだ姿なのか、それとも、女が男にそうふるまえと望むのか。おそらくは前者であろう」(146頁)。このあたりは「恋する英雄の夢」の章ですが、教会がトーナメントに向けた非難などにもふれられていて、興味深かったです。面白かった事項を二つほど。ひとつは、ミニョンです。貴族のうちでも重んじられていた血盟の間柄、戦場での友情とならんで、15世紀にはあるセンティメンタルな友情のかたちが知られるようになったそうです。その関係がミニョンと呼ばれます。こちらは男性同士の関係でして、女性同士ですと、ミニョンヌと呼ばれます。ミニョンヌはおそろいの衣装をつけていたのだそうです。もうひとつは、フィリッピーヌ遊びです。すももを食べていて双生の核がみつかったなら、その場にいる異性の人に、核の一つを渡します。その後、はじめてであったときに、「こんにちは、フィリッピーヌ」と呼びかけた方が、相手から贈り物をもらう権利をもったとか。訳も、私が良い訳ができるわけでは決してありませんが、気になるところが多々ありました。同時に、これは名訳だ!と思えるところもあったので、それぞれいくつか。「生の不安、それは、美と幸福とを否定しようとする気持である、美や幸福には悲惨と悲嘆とがつきものだから、というので」。~である、のところは、句点の方が読みやすいかと…。「それに、なにかたいへんな、おどろくべき啓示でもあったかのように、この会のことを売りこむなんて、と、反対するものたちは非難の声を結ぶ、夢想か幻想、年寄りのたわごともいいところだ、と」。この前のところまで非常に興味深く読んでいたので、この訳で逆にテンション下がってしまいました。「~、と…が言っている」、とか、「…が言っている。~と。」とすればまだ読みやすいと思うのですが…。原文の構造に忠実なのだとは思いますが。続いて、これはすごい、と思った訳もいくつか。「人びとは、いきのいい呪詛の言葉をひねりだそうと競争する。いちばんすごい呪いを発したものが、師匠として尊敬される」。これは内容自体も気になりますね、どんな呪いなんでしょうか…。次は面白かった訳。「口にも鼻にも、なめらかなのと鬚もじゃらなのと」。鬚もじゃら、って…。そして、「日の光のさんさんとふりそそぐドリームランド」訳というか、ホイジンガの文章のすごさですよね…。同時代人がジャンヌ・ダルクについてあまり語っていないこと、「死のイメージ」のところで紹介される、死をめぐる図像の解釈。「牧歌ふうの生のイメージ」では、詩などに描かれたのどかな生活が紹介されます。などなど、他にも内容自体興味深い部分もあるのですが、ずいぶん時間がたってしまったのでこのあたりで。追記。本書はハードカバー版を上下巻に分けて文庫化したものですが、ハードカバーに載っている図版がありません。手にとりやすいのはたしかなのですが、図版がないのが残念です。
2005.12.23
コメント(0)
-

恩田陸『図書室の海』
恩田陸『図書室の海』~新潮文庫~ 10編の短編が収録された短編集です。一編ずつ、簡単な紹介とコメントを。「春よ、来い」入学式、卒業式。桜の季節、二人の少女。デジャヴュの物語。キーワードを列挙すると、こんな感じでしょうか。正直、うまく説明することはできません。不思議な物語でした。「茶色の小瓶」総務部に所属する「私」が新入社員歓迎会の会場へと向かう途中、事故が起こった。野次馬たちの中から、一人の女性が出てきて、怪我した男性を応急処置をした。「私」は、彼女が総務部に新しく入ってきた人だと知った。看護学校を出て、看護師を目指していたという彼女が一般企業に勤めているのはなぜなのか。「私」は彼女に興味を持つ。 ホラーだと感じました。「茶色の小瓶」の中身よりも、「私」(?)にかけられる社員たちの疑いの目、それを生んだきっかけの部分が怖かったです。「イサオ・オサリヴァンを捜して」東南アジアの戦場で、際立った存在だったというイサオ。「私」は、彼を知る人々を訪ね、彼のことを調べていく。 すみません、よく分かりませんでした。最近、私の理解力が低下してきている気がします…。「睡蓮」睡蓮の下には、綺麗な女の子が埋まっている-。二人の兄のどちらからか、「私」は聞いていた。「私」が「汚い女の子」かどうか品定めするように見る長男。「私」と楽しく遊んでくれる次男。「普通」の家庭と自分の家庭が違っていることを自覚していた「私」だったが、ある日から次第に恐怖に襲われるようになる。 …などと紹介してみたものの、あの感情を「恐怖」ととるかどうかは、読者それぞれでしょう。素直に面白いと感じました。源氏物語も読んでみたいものです。「ある映画の記憶」波に囲まれる岩。取り残された女。映画と、実体験で、似たような情景を見ていた「私」。実体験では、叔母が死んだ。奇妙な点が残されたままだった。 海からつきでた岩の上。着物が乾いていたのに、叔母の死因は溺死だった。ミステリ・タッチの短編です。考えてみればミステリとしては分かりやすいと思うのですが、過去に見た映画との絡め方がよかったです。サークルの影響でしょうか、最近読み方が変わってきた気がします…。「ピクニックの準備」こちらは、あらすじは省略します。ピクニック、夜に歩く…。どうも聞いたことがあるなと思ったら、案の定、『夜のピクニック』という恩田さんの別の作品の前日譚だそうです。これは背表紙に書いていたことです。最近私は、背表紙の紹介すらもよく読まずに本編を読んでますので、小さなことから楽しめます(自分の言葉が意味不明です)。えっと、気になります、続き。『夜のピクニック』も、文庫が出たら買うことになりそうです。「国境の南」むかしよく通っていた喫茶店。ある事件が起こってから、その喫茶店は営業を終えたが、あらためてそこにくると、また喫茶店になっていた。その喫茶店で働いていた女性、加代子のことが思い出される。 ちょっと読み返したのですが、人称代名詞を使わないタイプの一人称スタイルですね。「自分が…だと思う」というかたちはありますが、「私」などの一人称がありませんでした。加代子さんの行動を、いかに理解するか。他人の心をそもそも理解できるのか、という疑問は当然あるわけですが(どんなに「君の気持ちがわかる」と言ったところで、本人の気持ちをあますことなくそのまま感じることは他人にはまず不可能でしょう)、一見奇異と思える彼女の行動を、語り手は考えていきます。怖い、とも思います。不思議、よく分からない、とも思います。でもどこか、加代子さんの行動も、私は決してできないと思いますが、十分にありえることだろう、と感じました。「オデュッセイア」あらすじは省略します。ココロコという、都市(?)は、いつの日からか、歩けるようになっていました。多くの住民とともに移動するココロコ。旅の途中には様々な出来事があります。そしてラストは…。なんとも余韻を残す感じです。こういうの、SFですよね。私は観ていないのですが、「ハウルの動く城」を連想しました。「図書室の海」私は主人公になれない-そう自分に言い聞かせて生活する、高校三年生の関根夏。彼女と親しい後輩の克也が、高校の伝説となっているサヨコをこっくりさんのように呼び出す企画がある、と教えてくれた。夏は、なんとかそれをとめようとする。 …というんで、『六番目の小夜子』の後日譚です。『六番目の小夜子』の内容を覚えていないので(いま自分のメモを読み返してみましたが、ほとんど思い出せません)、なんともいえないです。本好きな先輩が借りた本を、探して自分も借りていく-。『耳をすませば』を連想してしまいました。少女漫画かなにかみたいに、という記述もありましたし、恩田さんも意識されているのかと思いました。「ノスタルジア」あらすじは省略します。数人の男たちが、懐かしい話を、順順に語っていきます。ふいに一人称の文章に変わり、さらに暗転。ふしぎな物語でした。最後から二番目の段落が印象的でした。ーーー全体を通して、やはり私はミステリが好きなのでしょう、「ある映画の記憶」が印象に残っています。
2005.12.21
コメント(4)
-
近況報告/もしもスタンドが使えたら
一週間更新しなかったのは、ブログをつくってからはじめてのような気がします。ばたばたしておりました。昨日ようやく(今度こそ)きりがついて、2005年の授業での発表は全て終わりました。もっとも、1月からの授業、それからもちろん修士論文の準備をしなきゃなので、年末年始もほぼ従来どおりの生活リズムでいこうと思っています。西尾さんの『ネコソギラジカル』全三巻は今年のうちに読了したいのですが、はてさて。ーーーー先日、ある方から、ジョジョの名場面集を紹介してくれているサイトを教えてもらいました。泣けるシーンが多々あります。ジョジョもしっかり読み直しておさえておきたいのですが(5部以降はまだよく覚えていませんし、6部にいたっては最後まで読んでないです。読みたい!)で、ジョジョといえば、話題になるのは、スタンドが使えるならなにがいいか、というネタですね(一般論にしてしまいました)。第4部、しげちーのハーヴェストは人気が高いそうです。実用的ですものね。私もハーヴェストがいいなぁ、と思っていたのですが、もっと実用的なスタンドに気づきました。もちろん他にもいろいろあるでしょうが、エニグマです。なんでも紙に保存できる能力。これさえあれば、多くの本をいちいち運ばなくても、全部紙の形にして、必要なときに開けばいいだけです。などともしもの話をしても仕方ないという説もありますが、しばらく続いていた緊張もとけたので、ちょっとのんびりしたいかと思いまして。それにエニグマは、ホットコーヒーをホットのまま保存できたはずですし(コーヒーをいれても、作業している間にどんどん冷めるのが残念だと感じる今日この頃です)、車だって紙にできます。これで駐車場問題は解決です。ーーー次はまたなにか、本の感想を書きたいと思っています。
2005.12.20
コメント(3)
-
歴史バトン
日記カテゴリの「西洋史関連」を使うのは何ヶ月ぶりでしょうか…。ある方から、歴史バトンなるものを頂戴したので、お答えしていきたいと思います。1. Number of your about history(歴史に関係する本の所持数)約230冊ですね(フリーページ歴史関連の目録をざーっと見る限り)。懐かしい書名やら、読んでいない本やらが目について、どこか胸が痛みます…。2. People who patronizes it now(今イチオシの人物)ジャック・ド・ヴィトリ(1160/70-1240)です。最近、教皇選出がありましたね。その権利をもつ高位聖職者を枢機卿というのですが、ジャックも枢機卿をつとめていた人物です。1240年になくなりました。生前親密に交流していたワニーのマリア(こちらは聖人になっています)が埋葬されていた場所に、死後運ばれています。ワニーは現在のベルギーにあります。3. The battle I remained(印象に残っている戦い)なんでしょう…。ポエニ戦争でしょうか。象のアルプス越え!4. Five person favorite of me、or that mean a lot to me (好きな、若しくは特別な思い入れのある人物5人) ネタでいきましょう。一人目:若王フィリップ(ルイ6世の長子) この方は、どんなに強調してもしすぎることはありません。といいながら、名前も覚えてなかったのですが。 3歳で王国の統治に名目上協力、12歳のときに王として聖別されました(当時の慣習として、父王の存命中に長子を王座に関与させていたのだそうです)。そんな彼が、2年後、激しく落馬して亡くなります。落馬の理由は、豚が馬の脚に飛び込んできて、馬を転ばせたからです。気の毒に、彼は何世紀ものあいだ、「豚に殺された国王フィリップ」と歴史書に書かれつづけたのだそうです。 高校生の頃、この話を聞いた私がどれだけテンション上がったことでしょう!中世ヨーロッパに関心を抱いた理由は、こんなところにありました(これだけじゃないですが) ミシェル・パストゥロー『王を殺した豚 王が愛した象』を参考に書きました。二人目:教皇ヨハネス12世 こちらは、適当な文献が手元にないので、そのエピソードの典拠を紹介できなくて残念なのですが、書きます。 神聖ローマ帝国。ナポレオンが名実ともに滅ぼしたこの帝国(ハプスブルク家なんてのもキーワードですね)の第一代皇帝、オットー1世を神聖ローマ皇帝と認め、戴冠したのがヨハネス12世です。教皇です。不倫相手のだんなさんに殴られて亡くなったのだそうです。こちらも、高校世界史で聞いたエピソードです。史実かどうかは調べがついていませんが、興味深かったです。教皇ですよ!? 若王フィリップ、ヨハネス12世。二人が、私を中世ヨーロッパの勉強へといざなってくれたのですね。現在、私が研究を進める上で読んでいる文献に、二人の名を目にすることはないのですが…。三人目:メアリ1世(英王1553-1558)ブラッディ・メアリ!あのカクテルをはじめて飲んだときの衝撃といったらないです。たまらず他の方に差し上げました。メアリ1世の二代前、ヘンリ8世が、離婚したかったのですが、カトリックでは離婚は認められず、教皇と対立しました。そこでヘンリ8世は、教皇庁と縁を断ち、イギリス国教会を創建します。カトリック的な要素とカルヴァン主義の要素をもつ国教会が、文字通りの国教とされるわけですが(このあたり文献あたりながら書いていないので間違いがあったらすみません)、メアリ1世はカトリックを復活させます。ばりばりカトリックの国スペインの王フェリペ2世と結婚するという事情もあったのでしょう。とまれ、カトリックを復活させたメアリは、異端を虐殺、こうしてブラッディ・メアリと呼ばれるようになったのだそうです。四人目:李斯秦の始皇帝が重用した学者さんです。春秋戦国時代、いろんな思想の流れが形成されますが(孔子や老子、孟子、孫子などなど)、その中でも法家に属する彼。高校の頃、李斯の字を、何度も間違えたのです。印象に残っています。いままで挙げてきた三人のようなニュアンスも含めて紹介すると、儒家を弾圧するということで、「焚書坑儒」という政策を行った(考えた?)方です。儒家の書物は焼き、儒家は埋めてしまおう、というのですね。五人目:コシューシコポーランド分割(1772-1795)という事件がありました。ロシア、プロイセン、オーストリアが、こぞってポーランドの領域を自分の領域に併合していったのです。第三回まであるのですが、第二回で名前が出てくるのがこちら。愛国者、として紹介されます。結局敗れるのですが。ちなみに彼はアメリカ独立戦争の際、義勇軍に参加しています。1848年、フランス二月革命を受け、各地に革命が波及します。ハンガリーも、当時ハンガリーを支配していたオーストリアに対して民族蜂起を起こすのですが、そのときの指導者として活躍したのがコッシュート。この二人は、高校生を混乱させるために教科書や参考書に出てくるにちがいない、と研究室の方と話しているのですが、当事国の歴史にとって重要な人物であるには違いありません。三人目から、高校世界史ノートをぱらぱら見ながら書いてました。ちょっと気休めのつもりが、疲れました…。若王フィリップについて書いているときが一番テンション高かったですね。ほとんどネタを提供するつもりで書きました。なにか(番組で紹介されもしないトリビアでしょうか)のお役に立てば幸いです。
2005.12.05
コメント(2)
-

島田荘司『摩天楼の怪人』
島田荘司『摩天楼の怪人』~東京創元社~ 1969年。コロンビア大学助教授、ミタライ・キヨシは、大女優ジュディ・サリナスの肝臓の病をみてほしいと以来を受け、マンハッタン島の摩天楼の一つ、セントラルパーク・タワーの 34階の部屋に呼ばれた。ジュディは、死が近いことを覚悟していたのだが、ミタライが多くの殺人事件を解決してきたことを聞き、いままで家族にも秘密にしていたということを、告げる。 48年前、自分は人を殺した。ひどい嵐の夜、停電のよってエレベーターがとまっていた時間帯。 34階にいた、というアリバイのない時間はわずか15分。その中で、一階にいた男を射殺したという。 自分自身でも、どうやって殺せたのかわからない。彼女はそう言っていた。 セントラルパーク・タワーには、他にも多くの事件が起こり、謎が残っていた。あいつぐ不審死。時計塔の時計の長針で首を切られた男。ときどきジュディのまわりの人々が見かけた、「亡霊」。 劇作家のジェイミー・デントンの協力を得ながら、、ミタライは事件の解明に乗り出す。 やっぱり島田荘司さんの作品は面白い。そう感じながら読み進める、良い読書体験でした。 現代(1969年)については、基本的にジェイミー・デントンの一人称で進みます。ただし、事件が48-53年前のものですので、その大筋は当時事件の捜査にあたっていた警察官サミュエル・ミューラーの一人称で進みます。ミューラーさん、かっこよかったです。 さて、上のあらすじでも簡単にふれましたが、本書は本当に大掛かりな謎を提示してくれます。セントラルパーク・タワーの、ほぼ全室の窓が割れるという事件もあり、こちらもわくわくしました(ただ、こちらについては知っていたことを連想してしまい、解決では、やっぱりあのことか、となってしまいましたが、それと作品の面白さは別ですから)。密室の中、5年の間を隔てて、ほぼ同様の状況で死んでいた二人の女優。作中でもふれられているとおり、まさに「デジャ・ヴュ」を思わせる状況で、誤解を招くかもしれませんが、魅力的な謎でした。 御手洗さんとデントンさんも良いコンビで、試行錯誤していく様子をわくわくしながら読み進めました。 そして、やはり、ある種の人に対する御手洗さんの優しさ・思いやりに胸をうたれます。犯人はどう考えてもとんでもないことをしているわけですが、どこか犯人に対する思いやりも見せる御手洗さん。素敵です。胸がうたれたといえば、先にも少しふれましたが、ミューラーさんの言葉、その生涯も印象に残ります。スープ。陰惨な事件、不可解な事件、深まる謎…その渦の中ででてくる、かつての敏腕刑事の日常には、少し緊張がほどかれ、そして感動した次第です。 * さて、本作の舞台は1969年のニューヨークです。『占星術殺人事件』の解決が1979年ですから、本作は石岡さんと御手洗さんが出会う前の事件ですね。いつか御手洗さんの年譜も整理しておきたいなぁ、と思います。 * 最後に、よく分からなかったところを。文字は白にしておきます。 第四章は、結局どういう位置付けなのでしょうか。とても面白く読んだのですが、真相との関連がよくわかりませんでした。***トラックバック用リンクです。でこぽんさんの記事はこちらです。
2005.12.04
コメント(4)
-

真梨幸子『えんじ色心中』
真梨幸子『えんじ色心中』~講談社~ フリーライターの僕に、マニュアル作成の仕事が入った。相手先はかなりの無理を言ってきているが、なんとか応えなければ、と僕はがんばる。しかし、フリーの仕事だけでは生活もままならない僕は、派遣の仕事もしていた。新しく紹介された職場の環境自体があまり好ましくなく、そして拘束時間も長かったため、マニュアル作成との兼ね合いとあわせて負担になっていき、僕はしだいに睡眠時間が削られていく。 その頃、十六年前に起こった事件が、見直されていた。 有名市立中学を目指す小学生。彼は有名進学塾に入った。彼はテレビのドキュメンタリーで取材されることになり、低落気味だった成績もどんどん上がり、彼は無事合格を果たした。しかし、進学後、彼は家庭内暴力をふるうようになり、やがて、殺された。事件直後、父親は自分が殺したと自供していたが、一審後、無罪を主張、マスコミにしきりに取り上げられるようになる。 * 有名進学塾に通っている僕だが、成績は悪くなるばかり。そんなとき、一人の女の子と出会う。彼女は、週末は塾のためにおばの家にとまっているという。いつしか、僕も、土曜日にはひんぱんにそこで過ごすようになっていく。 真梨幸子さんの第二作です。デビュー作『孤虫症』の感想はこちらです。 本書は、プロローグ、1章、2章からなります。 1章では、社会人の「僕」と、小学生の「僕」の一人称の視点で、交互に物語が進みます。 仕事におわれ、人間関係にも耐え、睡眠時間もけずり…。手料理をし、きちんとゴミ捨てもしていた彼の生活は、いつしかコンビニの惣菜での食生活・ゴミ捨てもままならない生活へと変わってしまいます。さらに、なんとも救われない方向に話が進んでいきます。そのあたり、少ししんどかったです。 奇数の節が、社会人の「僕」の一人称で進むのですが、こちらには、十六年前の事件(西池袋事件)に関する記事が挿入されています。事件から半年後の、被害者となった少年たちの会話が印象に残っています。すごく冷めた目で社会や友人関係を見ていて。 この第一章が、作品の大半で、ここでもやもや感がつのっていきます。ここが伏線になってるんだろうな、などと漠然と見当はつくのですが、どうにももやもやが拭えませんでした。ラストの2章(エピローグという章題にしてもかまわないと思ったのですが)はとても短く、こんな短さで1章でうえつけられたもやもや感が去るのか、とどきどきしながら(少し不安に)読みました。一応の説明はつけられるのですが、分かったような、分からなかったような、というのが正直なところです。 時間的には、だいたい予想していたくらいの時間で読むことができたのですが、どうも読みが浅かったようで、もやもやが晴れてすっきりした、という感覚にはなりませんでした。 本書の大きなテーマになっている受験戦争。身近に受験戦争(しかも、私立の中学受験です!)がなかったので、あんまりぴんときませんでした。塾が忙しい、という人もまわりにはそんなにいなかった覚えがありますし。だから私がむしろ興味深く読んだのは、本作で描かれた子どもたちの、親・あるいは大人たちへの視線です。これは、年齢的な意味の子どもももちろんですが、親子の関係の意味での子どもでもあります。 考えすぎると長くなりそうなので、このあたりで。トラックバック用リンクです。でこぽんさんの記事はこちらです。
2005.12.03
コメント(0)
全15件 (15件中 1-15件目)
1