2005年02月の記事
全19件 (19件中 1-19件目)
1
-

宮城音弥『性格』/桜野みねね『まもって守護月天!』
宮城音弥『性格』(岩波新書)読了。性格の類型として、気質の分類(クレッチマーの分類を例に挙げると、分裂質、躁鬱質、テンカン質)、狭義の性格の分類(ヒステリー、神経質、偏執質、内向性と外向性など)、人格(異常人格、理想の人格)について述べた後、類型学として、それぞれを三つの三角形で表し、人の性質はそれぞれの三角形の一点に位置するという。性格の類別として、性格特性(親切、がんこなど)、態度、役割(父親としての役割、上司としての役割など…会社では偉そうにしているけれど、家では奥さんの尻に敷かれている、なんてね)などについて言及される。興味深かったのは、性格の形成の章。性格は遺伝によるのか、環境によるのか、というやつですね。もちろん、双方の条件がからんでくるわけだけど。双子に関する調査、狼に育てられた姉妹-アマラとカマラの例。これらは学生の頃に授業でも学んだ。人間の性格を形成する社会的条件のうち、もっとも重要な場所としての家の役割について、学校の役割について、などにも言及。文化と性格の章は、社会学的、人類学的な知見にもふれている。あとは、性と性格、性格の診断、筆相・手相・人相についての章が続く。性格の診断について付記。病院で、二種類の心理テストをしてもらった。エゴグラム(これはインターネットでも無料でできる)とロールシャッハテスト。エゴグラムは、「性格特性質問法」に分類されるのだと思う。「自分は~だと思う」という質問について、はい、いいえ、どちらでもない、の三択で答えるもの。この本の中では、性格特性質問法の問題点として、被験者がウソをつくことがある、自分で自分の特性が十分に分かっているわけではない、などを挙げている(価値判断に支配されやすい質問-社交的である、とか、執着質である、とか。前者はその方が良い、後者は悪い、などという風に価値判断がされうる-があるというのも挙げられているが、これは被験者がウソをつく、に含めても良いのではないか)。私は、例えば、ウソをつくとか、そういう可能性まで見越してテストが作られていて、また診断するのだと思っていたのだけれど、そうではないのだろうか。またカウンセラーに尋ねてみよう。ロールシャッハテストもくわしく紹介されている。左右対称の抽象的な絵を見せて、それが何に見えるか尋ねるもの。一つの絵に対して、何通りの答えを出してもよい。全体として見るとこうだけど、この部分はこう見える、というのもありうる。たとえば、この部分が**に見えるから、だから全体は☆☆です、という答え。あんな抽象的な絵を(十枚)見て、何に見えるか答えるだけなのに、いろんな性格が分かる。すごいなぁって思う。ーーーーーーーーー久々に学術書の紹介ができた。最近漫画でごまかしていたから…。それでも、勉強は順調に進んでいて、今日も英語論文一本読了。今日は三時間半くらいかかったかな。なかなか疲れた。図書館に『メリュジーヌ物語』が置いてあった。ジャック・ル・ゴフの論文も収録されている本。こんなのがあるなんて…。フランス文学のコーナーに置いてあったから、今まで気づかなかったのだろう。ーーーーーーーーー『ストーンオーシャン』12巻を読み返して、こないだ買った13巻を読了。スタンド能力、ほんと複雑、難しい。話の流れもあまり覚えていないし、また時間があるときに読み返そう。『まもって守護月天!』は、泣けます。私が涙もろいだけという説もありますが、泣けます。一つの巻に六話しか載ってないから、一気に二巻まで読んでしまうと三巻以降を買いたくなると思うので、どうしようか考え中。読んでしまっても、入学までは買わないように。誓いを守ろう。ーーーーーーーーー桜野みねね『まもって守護月天!』~ガンガンコミックス~七梨太助は14歳。父親は世界への旅に出ており、姉は姉で旅に出ていて、一人で家に住んでいる。彼のもとに、父親から小包が届いた。手紙とともに入っていたのは、「支天輪」という中国で見つけたという輪っか。この輪の中に光を見いだせる者には天の守りが授かる、と父は書いていた。太助は輪をのぞきこんでみた。輪っかのはずなのに、真っ暗で、そこから-女性が現れた。彼女は、守護月天シャオリン(漢字変換できなかった)。敵国の襲撃や刺客から太助を守るというが、太助には敵国もいないし向かってくる刺客もいるはずもなく。シャオリンは太助が住む世界のことをまったく知らないし、太助に迷惑をかけるので、支天輪の中に帰ろうとする。が-寂しそうな太助を見て、シャオリンは声をかける。「もし迷惑でなければ-あなたの中にある『孤独』や『寂しさ』から、あなたを守ってさしあげたいのですが-それでは、いけませんか?」ここです。立ち読みしていてここを読んで、「あ、これは私のツボだ」と思ったのでした。泣けます。山野辺さんは、第一印象は最悪なのだけれど、悪い人ではないようで、主要な登場人物となる。出雲さんは私嫌いです。初対面の女性と一つ屋根の下-って、手持ちでいうと、『ラブひな』もそうだなぁ、なんてちょっと思った。『ラブひな』の場合は女性いっぱいだけど。しかし、さらりと流していたから、二巻の登場人物紹介で再認識したんだけれど、太助くんって14歳なんだ…。お母さんについては一度も言及がないけれど、たぶんいらっしゃらないんだろうし、お父さんは息子をほったらかして旅に行っているしで、そりゃ寂しいよね。ーーーーーーーーー笑点がはじまる前の、「このあと笑点」というCMを、たぶん初めて見たのだけれど、びっくり。会場で、円楽さんの隣に座っている人が、「この後は笑点」と言っていたのだ。いいなぁ。一回は見に行ってもいいかなぁとは思う。吉本新喜劇は生で見たことが一度だけあるけど。テレビ関連で。JACCSカードのCM。あれに憧れる私はマイノリティでしょうか…。漫画も含めてですが、今日は二冊紹介しました。
2005.02.27
コメント(0)
-

銀色夏生『ミタカくんと私』
銀色夏生『ミタカくんと私』~新潮文庫~ 小説の紹介は、あらすじを書いて、気になった描写や全体についての感想などを書く、というかたちできているけれど、本書は本当にふつうの日常生活で、あらすじを紹介しづらいので、感想のみで。 私-岡田並子と、友達のミタカくん、弟のミサオ、母、バイト先で知り合った瞳ちゃん、その妹のハナちゃん。ミタカくんはしょっちゅう私の家にやってきてごろごろしている。並子の家族とご飯を一緒に食べることもしばしば。 私はといえば、学校には最低限行くけれど、家での生活が中心。ボタニカルアートを描いたり。いろんなことを考えたり。悲しみの果てには何があるのだろう。人が人を好きになるって、どうしてなんだろう。 悪い噂も多いジンタと付き合うことになったり。と、いろいろ出来事は起こるけれど、のんびりとしたお話。そういえば、パパは離婚して家を出ていっちゃってる。並子たちはしばらくそのことを知らなかった。ママ、爆弾発言。でも、その事実がすんなりとみんなに受け入れられ、ミサオたちは出ていったパパのものをさっそく自分のものにしてしまったり。 このシリーズで誰が好き、って、お母さん。お母さんの発言はほとんど笑えてしまう。お母さんがこの本の中で取り組むのは、まつたけ振興会の企画で新しいまつたけ料理の開発。まつたけカレー、まつたけつるつる(案のみ)、まつたけプリン。これらに対するミタカくんのリアクションも笑える。そして次は、もずく振興会。…笑。最後の方では、手記を書く。 はじめて読んだとき大笑いしたのは、「ケツで物はさんだことありますよね」というミタカくんの問いに対する答え。お母さんスゴイって思った。 銀色さんによるイラストつき。これがかわいくてほのぼの。 シリーズ二作目『ひょうたんから空』は、文庫の方にはリンクをはっていないので、近いうちに再読しよう。
2005.02.24
コメント(1)
-

ジェームズ・ヒルトン『チップス先生さようなら』
ジェームズ・ヒルトン『チップス先生さようなら』James Hilton, Good-bye, Mr.Chips(菊池重三郎訳)~新潮文庫~ 1870年、22歳のとき、チップス先生はブルックフィールドに赴任した。生徒にいたずらされないように、最初の授業では緊張しながらも、うまくやることができた。 65歳まで、彼はブルックフィールドで教鞭をとった。古典や歴史を教えていた。やめてからも、学校のそばのウィケット夫人のもとに住み、しばしば学校を訪れたり、また生徒や教師らもチップス先生のもとを訪れた。チップス先生はブルックフィールドを誇りに思っていた。 ブルックフィールドでの生活、それが彼の生涯であった。 これはオススメです。 とにかく泣きました。教師ものって弱いのです。やっぱりあこがれの職業だから。まぁ教師ものじゃなくても涙もろい私は泣くけど。 独身と思われているチップス先生だが、結婚していた時期もあった。相手の名前は、キャサリン・ブリッジズ。チップス先生自身はとても保守的な考え方をしているのに対して、キャサリンはとても急進的な考えの持ち主だった。にも関わらず、二人はひかれあい、結婚した。 この二人の出会いが、なんだかステキなのです。きっかけは、ちょっとマヌケかもしれないけれど、二人がひかれあっていくところがいい!こういうのいいなぁ。 学校での出来事にチップス先生が対処するとき、キャサリンは助言をしていた。彼女のアドバイスを、彼も参考にする。本当にいい夫婦。憧れるなぁ。 東部貧民区域の慈善学校とブルックフィールドの試合の件は、印象に残っている。 私自身は、どちらかといえば保守的な人間だと思う。一方で、急進的な考えをする人に(その程度にもよるが)憧れもする。キャサリンの考えには、だから憧れる。もちろん、保守的な考えが悪いとか、急進的な考えが良いとか言っているわけではない。ついさっき述べたように、私自身はどちらかといえば保守的である。保守的な考えの人間も急進的な考えの人間もいて当たり前なのであって、大事なのはお互いがお互いの良さを認めあい、良いところは取り入れていく姿勢を示すことである。当たり前のことのようで、なかなか実現はしていないようだし、自分自身できていない部分もある。すぎな関係者も数人はこの日記を読んでくれていると思うので書くけれど、私はなんだかすぎなの定例会議を思い出した。基本的に多数決によらず、じっくり話して、いろんな意見の善し悪しを検討し、活動を決めていく。あれって、良いスタイルなのだと思う。 さて小説の話にもどって。チップス先生は洒落が上手で、みんなの笑いをとる。生徒たちは、チップス先生の新しい洒落を聞きたいがためにいろんな質問をし、良い洒落が聞けたら、それを友達に自慢するのだ。 爆弾が落ちまくっている中での授業。最初に受け持った生徒の子供、孫も受け持ち、その親の話を冗談交じりに話す。彼自身は、子供をもつことができなかったけれど、でも彼には、何千人もの子供がいる…。 素敵な物語でした。Thank you, Mr.Chips!(and, of course, Mr.Hilton)ーーーーーーーーー久々に本棚紹介。ヒルトンの作品に感動したので、今日は海外作家の作品の棚をば。左側の上三段は、CDです。右側の三段目、赤い背表紙の並びは、大好きな「赤毛のアン」シリーズ。読み返したいけれど、未読の本がまだまだあるから、なかなかできなさそう。
2005.02.23
コメント(0)
-
『神と女の民俗学』
牧田茂『神と女の民俗学』(講談社現代新書)読了。卑弥呼は、祭司的性格をもっていた。浅はかな知識で書くのもためらわれるが、巫女も文字通り女性であり、手持ちの国語辞典によれば、「神に仕えて、神楽・祈祷を行ったり神託をうかがったりする未婚の女性」ということである。この通り、女性は神とのパイプ役を果たす、ということが言える。一方で、お産の際には、女性は産屋にこもった(という風習があった。現在については知識がないのでコメントできない)。月経の際にも、家とは別の小屋をつくり、そこにこもったという。これらは、出産や月経に伴う血を「穢れ」とみなしたことによる、という解釈がある。しかし、女性は神に仕える、いわば神聖な存在でもあるのではないか。沖縄のある地方で行われている「イザイホー」という儀式では、これは女性による儀式なのであるが、生理中だとなお良い、とすらされているという。この事実と、血を「穢れ」として女性を隔離・あるいは蔑視するのは矛盾しているのではないか。こういった議論がなされる。折口信夫氏の名前は聞いたことがあるが、その著作は読んだことがない。もっとも、柳田国男氏の著作も未読であるが。ともあれ、折口氏の説は難解で、あるいは奇異なものとして捉えられる傾向があったのだという(本書の出版年が1981年、私が生まれるよりも前なのだから、現在の民俗学の研究動向がどうなっているのか、もちろん本書からはうかがえない)。ちくま新書から出ている民俗学の冒険、というシリーズを大学一年生の頃に読んだものだが、研究動向について言及があったか覚えていない。妖怪の話や、変身の話など、興味深い話題が多くあり、とても楽しみながら読んだのを覚えている。本の紹介をする際に、どこまで紹介していいのか、いつも悩む。牧田氏は、女性が家の外の小屋などに「こもる」行為が、血の穢れという理由になったのは、本来の行為の意味が見失われ、後付されたためであるという。このあたりのことは、興味がある方は本書を読んでいただければよいだろう。大学一年生では、一般教養の授業がある。高校を卒業したばかりの初々しい私は、わくわくしながら(それでも、場合によっては眠気に襲われ、講義がいつの間にか進んでいたということもあったが)聴講したものだ。社会学の講義で、先生がおっしゃっていた言葉は忘れられない。「事実認識と価値判断は違う」。女性蔑視の傾向があった、というのは事実認識であり、その善悪を問うのは価値判断である。これらは別次元の問題なのだ。例えば私は中世西洋史を勉強しているが、当時の風習なり信仰などが現代的価値観から良いものだった、悪いものだった、という議論をするのはナンセンスだと思う。史料に基づき事実認識を持ち、現代ではどうだろうか、という問題提起に用い、現代の状況は好ましい、あるいは危機的であるといった価値判断に用いるのは、まだ建設的であろう。これは少なくとも今この瞬間の私の見解であり、明日になったら別の見解を述べる、ということはまずあり得ないにしても、勉強を重ねることで、あるいは意見は変わるかもしれない。ーーーーーーーーー今日は病院にデイケアでいった。斬るビルに夢中。先日、私が斬るビル第一幕をクリアし、ゲーム開始の時点で第二幕から始められるようになったのだけれど、しばらくぶりに病院にいってみると、スタッフの方が第二幕で新記録を更新していた。私も挑戦。とんでもないものを斬り、第一幕みたいにもっとおおきな同じものが落ちてくるのかと思っていたら、別のものが落ちてきた。それを斬り終えたら、いくらなんでも斬れないだろう、というものを斬ることになり、さらにあるものを斬ると、彼がビルを斬る理由が明かされる。そして、ものすごいものを斬ることになる。というか、いくら斬っても斬れる気配がない。すさまじいゲームである。第二幕からはじめて、3000万点いった。ジョイパッド使用。自宅のパソコンでは、キーボード操作で700万点いった。キーボードではなかなか第二幕までいけない。ところで、このサイトはヤフーではヒットしないと思っていた。他のサイトの書き込みの、「のぽねこ」がヒットするくらいで、直接本サイトがヒットすることはなかった。著者名と著書名で検索した限りでは。ところが、「斬るビル 第二幕」で検索すると、ヤフーでもこの「のぽねこミステリ館」がヒットした。ヤフーでヒットしたのは嬉しい反面、一応このサイトは本の紹介がメインなんだけど、と、ちょっと悲しくもなった。ーーーーーーーーーデイケアに行くといつも、親しい患者さんと遊ぶのだけれど、勉強も進めている。今日は先日読んだ英語論文のレジュメを完成させた。斬るビルで新記録を出せたこともあり、なかなか充実した一日だった。
2005.02.21
コメント(0)
-
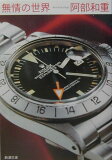
阿部和重『無情の世界』
阿部和重『無情の世界』~新潮文庫~「トライアングルズ」小学六年生の私に家庭教師がついた。彼は私の父の不倫相手に一目惚れし、彼女をストーキングし、二人の仲を裂くために私に接近しようと考え、私の家庭教師になったのだった。しかし、彼の思惑は別の方向に向かった。「無情の世界」不愉快な経験をした夜、インターネットで露出趣味の女性の告白ページを見ていた僕は、実際に露出している女性を見て自慰をしようと、外に出る。その結果、大変な事態に陥ってしまう。「鏖(みなごろし)」夫のいる女性と付き合っているオオタは、バイト先の商品を盗んだり、金を取ったりしていた。店主の弱みを握っていたため、調子にのっていたのだが、ついに窮地に立たされることになった。逃げ回っていたある日、不幸がいくつも重なる。「鏖」について。「不幸がいくつも重なる」と書いたけれど、それは結局オオタがまいた種であり、タケダらはタケダらできわめて醜く感じたけれど、自業自得の面もあるのではないかと感じた。つまり、「不幸」というより、身から出た錆、というか。 聖月さんの日記を読んで、読もうと思ったのが本書、『無情の世界』。私にとって阿部さん初作品。 なんというか、悲惨な話だなぁと思う。不倫にストーカーに妄想に暴力。私には重たい話だった。 好きな話は「トライアングルズ」。登場人物のどの人物にもなりたくないと思うけれど、家庭教師の演説はとても楽しめた。就職試験の面接の話など。 いつものようにのぽねこ回想シーン。最初の本格的な面接は、高校入試のときだった。中学校でも面接練習があり、五人の生徒に何人かの生徒という形で行われた。いわゆる集団面接のスタイル。その中で、「好きな食べ物」は何ですか、という質問が出た。私は一番最後だったと思う。クラスメートたちが答えていき、最後の私が「餃子です」と答えると、ちょっと笑いが起こった。少なくともクラスメートの一人は、再面接になったはず。私の発言のせいだとすると、悲劇的である。 今のは完全に脱線。私立高校の面接、大学は私立の面接あったっけなぁ。ちょっと思い出せないが、その次が教員採用試験、そして岡山大学大学院入試である。 教員採用試験は、一次の自由討論(受験者六人?が一つのテーマについて討論する。試験監督は時間がくるまで一切口をはさまない)はとても面白くて、試験されているというより討論自体を楽しんだ。しかし、二次試験の面接は悲劇的であった。もちろん不合格。 でも、そのおかげで、大学院で研究を続けるという新しい道が開けたのだ、という無理矢理ポジティヴシンキングをしてみている。実際問題、少なくとも今の私は、教員になるより大学院で研究する方が向いている。大学の同期もそう言っていたし。 ともあれ、あの面接ってのはやっぱりどうもねぇ。数分間で人を判断するんだからねぇ。日常生活ではまず使わない言葉遣いと態度でもって受験者はのぞむわけだけれど、試験官はその裏にある本性を見いだしていくのだろうか。実際はうまく見いだせていないからいろいろと起こるんだろうけれど、とも思ったり。 面接の話からここまでひっぱってみた。「無情の世界」。本当に無情だ。 前二作が一人称スタイルであるのに対して、「鏖」は三人称スタイル。オオタが中心人物なのだけれど、ところどころで不意に視点が変わる。視点が一定のスタイルに慣れているので、おっ、と反応してしまう。これはこれで良い手法だと思うけれど。視点が一定だと、一つの事柄に対する一つの見方しか示せないが、ある場面でふっと視点を変えることにより、基本的な視点からはうかがえない別の見方が示される。同じ出来事を複数の視点で書いている場面もあったし、こういうのもありか、と勉強になった。 関連して。ある一つの作品は、視点を変えることで、無限の物語に広がると思う。この世界もそう。客観的現実は一つだけれど、主観的現実は無限にある。
2005.02.20
コメント(0)
-

米澤穂信『春期限定いちごタルト事件』
米澤穂信『春期限定いちごタルト事件』~創元推理文庫~「プロローグ」「羊の着ぐるみ」船戸高校に無事入学した僕、小鳩と小佐内さん。小市民を目指す二人だったが-。ぼくは、友人の堂島くんから呼び出される。堂島くんの友人、吉口さんのポシェットがなくなった。それを探してほしいという。「For your eyes only」堂島くんから、僕にお願い。美術部OBが部室に置いていった二枚の絵。それらはそっくりに、独特の手法で描かれていた。見た目には「下手」と思われるのだが。その絵の謎を解いてほしいという。「おいしいココアの作り方」日曜日、僕はたまたま小佐内さんに会った。そして、堂島くんからメールがきて、二人は彼の家に訪れる。堂島くんがココアを作ってくれたのだが、彼のお姉さん、知里さんと小佐内さん、僕の三人になったとき、知里さんがシンクが乾いていることを指摘し、どうやって堂島くんがココアを作ったかが問題となる。「はらふくるるわざ」中間考査最終日。試験を終えて帰宅した僕に、小佐内さんから電話。二人はケーキ屋で会った。小佐内さんは、試験の際、空のビンがロッカーから落ちて割れたという事件を話した。「孤狼の心」先日、小佐内さんの自転車が盗まれていた。その自転車が、見つかった。車にひかれて、タイヤなどが損傷していた。そこで小佐内さんは、行動を起こす。「エピローグ」後日譚。 本書1ページ目には、簡単な内容紹介がある。そこに、「コメディタッチ」と書かれているが、そうは思わなかった。 第二話のラストシーンで、なんだか悲しくなった。 第三話のラストシーンで、なんだかもどかしくなった。 第四話のラストシーンは、なんだか痛ましく感じた。 第五話。ショッキングだった。 いやはや語彙のなさを痛感。 ともあれ、本書を通じて感じたのは、「もどかしさ」「痛ましさ」である。だから「コメディタッチ」とは思えなかったのだ。ライトではあるけれど…。 小市民を目指す二人。小市民を目指しているのだから、こんなことをしていてはいけない、これではだめだ、そんなんじゃだめだ…。制約だらけじゃない。結局、流れで捨てたかった「以前の」自分を演じたり、そのような行動をしたりしてしまうわけだけれど。 昔を思い出した。変わろうとしていた自分。とにかく今の自分じゃだめだ、強くなろう、変わろう、って。そのころ壊れましたよ。さすがにこの一年の比じゃないけど。 小鳩くんと小佐内さんのように、なんだかんだ言いながら捨てたい自分も持ちつつ、徐々に理想の姿に向かっていくのが負担も少なくて良いのだろうな。そもそも人間なんて、自発的に変わろうと思わずにいても変わっていくものだし。 ああ、今ぱらぱらと解説を読んでいてそういえば、と思ったこと。 本書は(米澤さんの作品には共通しているみたいだけど)、いわゆる「日常の謎」ミステリ。殺人事件は起こりません。今書いていて、ここでいう「日常」とはどこまで「日常」なのか、という疑問がわいたが、考えないことにしよう。ーーーーーーーーーバイト初日でした。11:00から15:00まで、日曜日もできたし大丈夫、と思っていたのに、なのに!あと一時間というところで、精神的不調に陥りました。仕事どころじゃなくなって休ませてもらい、家族に頓服を持ってきてもらい、そして病院へ。バイト四日間の予定でしたが、無理っぽいです。先生には、今は日常生活に慣れていっている時期で、バイトというのは負荷がかかった状態だから、失敗というか、不調になることもあるよ、と言っていただいた。あれこれ入院の原因をうだうだ考えることなく、それなりに楽しい日常生活(もっぱら読書中心の生活で人間関係はきわめて希薄だと言わざるをえないが)も送れるようになってきたけれど、負担がかかるのはまだしんどいところ。せっかく、バイトして**円になって(二桁という意味ではない)あれこれ買えるなぁ、と思っていたところだからきわめて残念な結果となってしまった。気が向いたらバイトに行ってもいいのでは、と先生に言われたけれど、やっぱり不安なのです。途中で今日みたいに調子悪くしたら逆に迷惑かけるし。社会復帰へのリハビリ第一歩、チャレンジはしたけどちょっと失敗、といったところか。
2005.02.19
コメント(0)
-
アンドレ・モラリ=ダニノス『性関係の歴史』
アンドレ・モラリ=ダニノス『性関係の歴史』(白水社文庫クセジュ)読了。日記のカテゴリは西洋史関連にしたけれど、文庫クセジュの分類では同著者による『性関係の社会学』とともに社会科学に分類されている。三部構成からなるが、全ての部のタイトルに「性欲」という言葉がある。「歴史における性欲」「神話と宗教における性欲」「文化及び象徴における性欲」である。第一部では、先史時代から19世紀までが扱われている。旧石器時代から扱われている旧石器時代には、人々は寒さのため服を着込んでいた。したがって、裸体は求められているまれな見物としての価値があった、という。著者は、当時から女性崇拝が形成されていたが、それは宗教的というよりはエロチックな崇拝であったという。農耕・牧畜が開始される時期には、女性の地位は男性の地位よりも重要になったと思われる。やがて、男性が女性を低く評価する時代になり、それが現在でも尾を引いているのは、メディアなどの情報による限り、否定できないだろう。一方で、母権制的社会もあるだろうけれど。キリスト教が広まっていく中での、あるいは広まってからの性に関する問題。初期の福音伝道の「発展の結果は、家族の結びつきと女性の社会的地位との強化であり、それ故、女性は熱心な布教者となる」(34-35頁)。にも関わらず、本書ではあまりふれられていないが、女性は悪魔の手先のようなものとしてみなされたりもする。聖職者たちが激しい女性非難をしていたのは歴史的事実。一方で、聖職者たちの「内縁関係は公然化」していた。無妻帯の聖職者は、税の支払いにより、内妻をもつ権利を持っていたという(40頁)。ああ、このへん掘り下げてみたいテーマだな(手持ちの文献を読み返せば、同様の記述にあたるかもしれない)。第二部の話に移ろう。第一章では神話に見られる性欲の表現を扱われている。第二章の4「母性礼拝」の節で、あらためて先史時代から中世までが概観される。第三部では、人類学的・心理学的な研究がなされている。太平洋上の民俗、アフリカ(特に南アフリカのケープタウン)の事例が述べられる。自分たちの「あたりまえ」がいかにあてはまる範囲が狭いものか、あらためて思い知らされる。第三章「性的象徴作用」では、人体自体のもつ性的象徴性が語られているが、136頁「機能的及び性的象徴作用がすべての器官とその機能に及びうることは明らかである」とあるが、これは言い過ぎじゃないだろうか…。本書で例示されているのは口と歯である。全体に関して説明されていたらもうちょっと納得するのだろうけれど。歯が「男根同等物」であり、「抜歯または歯の脱落は、去勢の観念に照応する」とあるが、うーん、そうなのですか?ちょっと本書の内容からは離れるけれど、夢などで棒状のものを見ればそれは男性器の象徴であり、例えば靴は女性器の象徴である、といわれていることは知っているけれど、上述の内容は、これらと同様に懐疑的なものだと思わざるをえない。もっとも、もっと象徴について勉強すれば、はっきりと肯定あるいは否定できるくらいに理解できるようになるのだろうけれど。まだまだ勉強不足なので印象論ですね。ーーーーーーーーー今日のバニラ・ムードの演奏は、「君の瞳に恋してる」。この曲大好きなのです。なのに、ああ、なのに…。今週は、バニラ・ムードの演奏がラストで行われる、という形をとっているのはここ二日で了承しています。でも、今日はまだ途中で、しかもサビの演奏中に番組終わっちゃったんですよ!ショック(>_
2005.02.16
コメント(2)
-
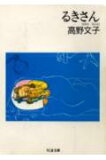
高野文子『るきさん』
高野文子『るきさん』~ちくま文庫~ るきさんは加算機が上手だ。お仕事は、お家でするお医者の保険の請求。お仕事を手早くすませ、あとはのんびり図書館に行っては本を借りたりする生活。 電車のドアにたっぷり体をはさまれたり、運動神経がないからかよわく思われたりするのだけれど、どこかワイルドなところもあるるきさん。 お友達のえっちゃんとよく交流をとっている。 そんなるきさんの日常。 私はほのぼのした漫画が大好きなのです。先日紹介した『有閑みわさん』も好きだし、本書『るきさん』、同じくちくま文庫から出ている『ハナコ月記』なども好き。 さて、本書の紹介。見開き2ページでお話一回分、という形。マガジンハウス刊『Hanako』に連載されていた漫画。 主な登場人物は、るきさん、えっちゃん、小川くん、自転車屋の男、かな。 好きな話は、電車のドアにはさまれる話、寒いのに薄着して外出したときの話、スキップの話、などなど。どの話もほのぼのしていて良い。ーーーーーーーーーー今日は午前中ごろごろしてしまい、読書ができなかったので、今までに何度も読み返している『るきさん』の紹介でごまかすことにした。明日は『性関係の歴史』について書く予定。今日読み終えて感想書いてもよいのだけれど、今日は早く寝たいので。明日からはまた図書館通いをして勉強を進めたいし。今日本が読めなかったもう一つの理由が、テレビ番組「お笑い向上委員会」を見たこと。この日記を読んでくださっている方はお気づきだと思うけれど、私は割とお笑い好きです。昨年の六月、バイトから帰宅してなんとなく「エンタの神様」を見てから好きになったのです。アンガールズ好きなのです。今日の番組にアンガールズが出演していたから観ました。彼らが出ていなかったら観なかったかも。先日「エンタの神様」でも観たと思うのだけど、ペナルティが「ヒゲグリア」のネタやっていた。耳に残ってしかたない!耳に残るといえば、レギュラーのネタもそう。あんな短いフレーズで笑いをとるのはなかなかのものだと思う。でも、「笑い」に関する本なども(学術的な研究)あるかとは思うのだけれど、長井さんにしてもレギュラーにしてもハローケイスケさんにしてもいつもここからにしても、日常生活で、「あ、それよくある!」とか「そうそう、そうよね」ということしか言ってないと思うのです。で、それが面白い。たしかに日常の会話の中でも、ありがちなことを話すと笑いが起こる。これってなぜなのだろう。手元にある文献では、『キリスト教と笑い』の中で、笑いのメカニズムについても言及があったから、またぱらぱら読んでみようかな。ああ、寝ようと思っていたのに、また長々と書いてしまった…。今日はこのあたりで。
2005.02.15
コメント(0)
-

島田荘司『ロシア幽霊軍艦事件』
なんだかんだいって、二月は一日一冊本紹介を目指しているので、今晩にはまた一冊感想を書くつもりです。今日のバニラ・ムードの演奏は、「ラブストーリーは突然に」。ステキでした。でも、番組のエンディングとしての演奏だったから、いつもみたいにバニラ・ムードのみなさんがカメラに向かってバイバイするのは見えませんでした。演奏中に、明日の予定言ったり、出演者のみなさんがカメラにバイバイしたり。そこが残念でした。やっぱり、バニラ・ムードの演奏は番組の途中にしてほしい!でも、企画は面白かった。七か国の方々が、自分の国では赤ちゃんの泣き声やくしゃみをどう表現するか、というのを披露。興味深かった。ハンバーガーから見る各国の物価であるとか。28分くらいまで、祖父が時代劇を見ているので、番組を最初から見られないのが残念。以前は自分の部屋にもテレビがあったけれど、本棚を置くためにテレビはのけたのでした。何かを得るためには何かを犠牲にしなければならないのですね。日記のタイトルを「とりあえず」にしていますが、本を読了したらその本のタイトルにあらためます。文字通り、とりあえずのタイトルということで。島田荘司『ロシア幽霊軍艦事件』~講談社ノベルス~ 石岡、御手洗のもとに届いたレオナからの手紙。そこには、倉持ゆりというファンからレオナへの手紙も同封されていた。手紙の中で、ゆりは、祖父から遺言されたと、次のことを伝える。アメリカに住むアナ・アンダーソン・マナハンに謝罪の言葉を伝えて欲しい。箱根にある富士屋ホテルにある写真を見て欲しい。レオナは、なぜ自分にこのようなことが伝えられたのか分からず、御手洗たちの意見を求めたのだった。 御手洗たちは、富士屋ホテルへ赴く。そこで見せられた、衝撃の写真。激しい雷雨の夜。山の中の湖、芦ノ湖に浮かぶ、「軍艦」の写真だった。 そして、レオナがアナ・アンダーソン・マナハンについて調べると、以下のことが分かった。アナは、自らをロシア最後の皇帝ニコライ2世の娘、アナスタシアと自称していたのだった。 歴史ミステリ、ということになろうか。どこまでが現実でどこまでが島田さんの虚構か、もちろん**とか**とかなどは虚構にしても、分からないところがある。そのあたりはきちんとあとがきで説明してくれている。あとがきは、本編を読んでから読むようにしてください。 さて、感想を一言で言うなら、これは悲劇的である。酷すぎる。具体的なことについては、ふれずにおこう。 手元にある、ロマノフ朝最後の皇帝ニコライ2世や、アナスタシアに関する文献を紹介しよう。・植田樹『最後のロシア皇帝』ちくま新書、1998年。ラスプーチンについてはもちろん、アナスタシア伝説についても言及されている。・桐生操『きれいなお城の怖い話』角川ホラー文庫、1998年。ここでは、ラスプーチンが紹介されている。・桐生操『びっくり!世界史 無用の雑学知識』ワニ文庫、1989年。アナスタシア伝説の紹介あり。・桐生操『世界史迷宮のミステリー』ワニ文庫、1991年。ここでもアナスタシア伝説の紹介がある。 これらの文献は、島田さんの本書の理解を助けるのではないだろうか。もちろん、島田さん自身が紹介している参考文献もよいのだろうけれど、手元にないので紹介は省く。
2005.02.14
コメント(0)
-

北山猛邦『「ギロチン城」殺人事件』
北山猛邦『「ギロチン城」殺人事件』~講談社ノベルス~ 高貴な名探偵の血筋を引くという、幕辺ナコ。彼は、頼科(よりしな)家の経営するホテルに居候の身だった。ナコが、人形を拾ってきた。人々がいらなくなった人形を捨てる、人形塚から。頼科有生-ライカ-は、ここから事件に巻き込まれることになる-。 人形塚の近くにある、『ギロチン城』。そこでは一年前、密室状況の中、城主が首を切断されて死んでいた。未解決の事件である。ナコが拾ってきた人形は、『ギロチン城』から捨てられたものだという。その人形は書記人形であり、紙にメッセージを書いた。「Help」。そして人形につめられていた、一枚の写真。それには、女性が写っていた。二人は、女性を救い出すため、そして昨年の事件を解決するため、『ギロチン城』に赴く。しかしそこで、連続殺人事件が起こる-。 北山さんの世界って、やっぱり不思議な雰囲気。どこかで、佐藤友哉さんと西尾維新さんは同系統、秋月涼介さんと北山猛邦さんは同系統、って感じていたのだけれど、秋月さんとは方向が違うなって思った(あ、佐藤さんたちについては蛇足なのに前に書いちゃった)。登場人物の名前が独特なのが、なんとなく似てるな、って。 昨年死んだ城主は、多くの子供たちをつくったようだけれど、ネーミングがすごい。数字なのだ。一、二、三、四、五。他にもいるけど。名前もつけられていない人もいるし。 新本格の方々が出たころ、さんざん「人間が描けていない」って批判された、ということは知識として知っている。私は別に批判しようとは思っていないけれど、それにしても本書は、人間を描こうとしていない、と感じてしまった。繰り返す、批判するつもりはない。これは、そういう世界なのだ、と思った。 『ギロチン城』の中では生体認証システムが使われており、それぞれの人にはコードネームがつけられている。「王」「執事」「死」など。登場人物が、まるで記号のようなのだ。 『ギロチン城』には、斬首刑につかわれる道具がコレクションされている。日本刀、西洋の剣、ギロチン…。そして物語で重要な役割を果たす、「首狩り人形」。本書の冒頭では、首狩り人形の伝説が語られる。 * 内側にあるものだけが、本来的にこの世の全てではないか-。このあたりで語られることは、昔考えたことがある。たとえば私は今、自分の部屋でパソコンに向かっている。窓の外は見えないし、ドアも閉じている。一つの部屋の中に、私だけ。さて、この部屋の外に世界は果たしてあるのだろうか?私がドアを開けた瞬間に、そこには廊下(階段)が現れるのではないか。外に出た瞬間に、外の世界が構築されるのではないか。なーんてことを考えたことがあったから、懐かしいような気分になった。誰でもこういうことを考えるんだな、とも思い。ーーーー私はテレビは殆ど見ないのだけれど、「エンタの神様」は見ている。今日はアンガールズが出ていて嬉しかった。あと、インパルス好き。板倉さんいい☆
2005.02.12
コメント(0)
-

浦賀和宏『松浦純菜の静かな世界』
浦賀和宏『松浦純菜の静かな世界』~講談社ノベルス~ 松浦純菜は、中学生の頃、何者かに襲われ、ひどい怪我を負った。療養のため、その町を離れた。 数年後、彼女はその町に戻ってきた。旧友たちを集めてパーティーを開いた。しかし、親友だった貴子は来なかった。 貴子は、パーティーの日にはもう、失踪していたという。その頃、体の一部が欠如した女子高生の死体が見つかった。貴子も、同じ犯人に殺されたようだった。 同じ頃。八木剛士と彼の妹の美穂は、銃で撃たれた。しかし、奇跡的に剛士は無傷で助かった。 純菜は、剛士の級友である友人、渚に頼み、彼に接近する。 彼女は、貴子たちを殺した犯人を、自分たちで探そうというのだ。 内容紹介は、純菜の視点で書いてみた。けれど、八木剛士の視点から見ても書けたのだけれど、松浦純菜はタイトルにも出ているので、彼女の視点で書いた。 八木は、不細工で、スポーツもできなくて、多くの同級生、さらには後輩にまでも馬鹿にされ、からかわれていた。彼らをみんな殺してしまいたいと思っていた。「そんな些細なことで?」渚は言う。「私には分かるよ。(中略)殺したい奴って、確かにいるもの」と、純菜(この言葉は帯にも引用されている)。そして今の私は、純菜の言葉に賛同している。憎い相手を殺そうと思うことと、殺すことを実行にうつすことは、まったく異なる。そして、人間なら誰でも、一度は、憎い相手を殺したいと思ったことがあるのではないか。他人から見れば「些細なこと」と思われることで、殺意を抱いたことがあるのではないか。私は、ある。だから入院したんだし。 なんで人を殺してはいけないの?殺そうと思ってもいけないの?これらに対する、一つの考え方も提示される。でも、正直今の私には、その考え方は受け入れられない。自分が、自分の大切な人が、傷つけられ、あるいは殺され、そんな経験をしても、「殺したい」とさえ思わないなんて、絶対無理だと思う。繰り返すけれど、殺人を実行に移すことと「殺したい」と思うことは別次元だ。「殺したい」と思っても、なんらかの形でそれを消化していくから(それは、たとえば、どんな理由があっても殺人はいけないと思うことでもある)、社会は成り立っているのだと思う。 さて、本書の内容に戻ろう。ミステリとして扱われるのは、女子高生連続殺人事件。なぜ、犯人は死体の一部を持ち去ったのか?が、大きな謎かな。 でも、この内容紹介をお読みいただいて分かるように、私は本書で扱われている他のテーマについて考えた。 * 被害者が悪い、という理屈。いじめられっこが悪い。いじめられる原因があるからだ、という理屈。本当に嫌になる。剛士は眼鏡をかけていただけじゃない。階段を、廊下を、道を、歩いていただけじゃない。それなのに馬鹿にされ、暴力を加えられる。彼が悪いの?どうしてそういう理屈になるの? * 追記。「復讐は復讐を呼ぶ」。主治医にも言われた。でも、明らかに悪いことをしているのに、罰せられず、なんの責任も負わず、のうのうと生きていく人たちはいるのだ。許さないといけないの?実際には、許せないけれど、どこかで消化して生きていくのだろうな。やっと、今の私は、そういう状態に、なんとかなれたところなんだと思う。 そして私は、弱い方へ、楽な方へ逃げてしまい、あるいは悪気はないのに人を傷つけてしまうこともあるだろうけれど、「人を傷つけないようにしよう」という気持ちだけは失わずに生きていきたいと、思う。そういう気持ちがあるのとないのとでは、ずいぶんと違うと思うから。さて、ご好評につき、私の本棚紹介第二弾(プロフィールに文庫の棚を紹介しているから、第三弾かな?)。今日は、ハードカバーの棚を紹介します。この本棚は祖父に作ってもらったもので、7段です(プロフィールに載せた文庫の棚も同じです)。上に、別の棚をくっつけて、そこに論文などのコピーをいれているファイルを置いています。この棚の下二段は、西洋史関連の専門書が並んでいます。今日はまた、過去の自分にふんぎりをつける出来事があった。もっと悲しみを感じるかと思っていたけれど、思いの外精神的に揺さぶられることもなかった。ちゃんと浦賀さんの著書も読めたし。明日は図書館が休館なので、『世界の歴史』のレジュメと洋書読みはお休みにしよう。調子が悪いからではなくて、自発的に、ちょっとゆっくりしたい、と思う。ゆっくりしよう。
2005.02.10
コメント(2)
-

佐藤友哉『鏡姉妹の飛ぶ教室』
佐藤友哉『鏡姉妹の飛ぶ教室』~講談社ノベルス~ 2005年6月6日。いつものように蒼葉中学校2年5組で、友達とお話をしていた鏡佐奈。しかし、とつぜん大きな地震が起こり、校舎は地中に沈んでしまう。激しい衝撃。教室中のものが、人も含めて宙に浮いた。天井に激突。机や椅子などにぶつかって。多くの死者。教室の中で生きているのは、佐奈だけだった。 廊下に出る。土砂が襲ってくる。そのとき、兵藤に声をかけられた。 * 祁答院浩之は、「闘牛」を狩るために、双子の姉、唯香とともに、蒼葉中学校に潜入していた。しかし、大きな地震に襲われる…。 * 江崎彰一は、痛みを感じない男だった。痛みというのがどんなものか、「実験」もしていた。 そんな彼のもとに現れた、地震で命を失わなかった女性、鏡那緒美。饒舌をふるう彼女は、江崎に「憑く」と言う。 * 自称「弱者」。優柔不断で弱い男。努力は全てを可能にすると信じる女。「闘牛士」の女。 地震で滅茶苦茶になった「馬鹿げた世界」で彼らは出会う。 キーワードは、「本気」。 やる前から自分にはできっこないと言い聞かせて何もしない人間。努力など無駄で、人間は生まれた瞬間から優れた人間と駄目な人間の二者にはっきり分けられるのだと考える人間。努力は全てを可能にすると信じる人間。彼らの論争。 私は、宇沙里さんの思想に惹かれるものを感じた。 妙子さんの発言は、真実を射抜いているところもある。どんなに頑張っていても報われない(ように見える)人もたしかにいる(と思う)。かっこ書きにしたのは、やっぱり頑張ったら、結果は出なくても、その人の生き方の中ではたしかに何か得られるものがあって、報われないなんてことはない、とも思う(信じたい)から。 唯香さんの発言(180頁)は、だから胸にとどめておきたい。いつからか、私はそういう考え方をしながら生きてきているけれど。 さて、本書は、まず佐奈さんの一人称からはじまる。浩之さんたちの視点で語られていく節もある。それらが混在していて、三つか四つほどの視点からなっている。 スプラッタ色が強い。江崎さんの「実験」は、最初の一例を見ただけで、「ああもうこれは読めない」と、数行だけと読み飛ばした。そこも強烈だったけれど、自然災害や人為的なもので、大量に人が死に、しかも内蔵えぐりだされたり脳が飛び出したりと、惨憺たる描写。 なのに、なのに、11章は、「良い」方向に話が向かっていくのだもの!なんだかじーんとした。 * なにってかにって佐藤友哉さんの新作です。とても楽しみにしていた。とても楽しめた。唯香さんの授業、そしてその後の「夏休み」、それに疑問を抱き始める村木くんといったあたりは、いろいろと考えさせられた。私は決して自分が強い人間だとは思っていない。むしろ、弱いと思っている。「強い」人間、「弱い」人間、それってなに?という議論が展開される。最終的な結論はともかくとして、やっぱり唯香さんの言葉には頷いた。 ところで、オチ(というか、12章)。このオチを理解するには『フリッカー式』を読み返した方がよいだろうな。 * 追記。66頁の、「もーしもーし、ベンチで囁くお二人さん」の元ネタが分からない。分かる方、教えてください。ここ最近、吉本ばななさんの文庫や、200頁程度の新書を読みあさっていたので、二段組332頁の『鏡姉妹の飛ぶ教室』を読むのには思いの外時間がかかった。1頁1分弱、といったところか。まあ、いつもの読書スピードだけれど、一気に読むのが久しぶりだから、余計にそう感じたのだろう。昨日書いた『色彩』について、指摘をいただきました。オングストロームというのは長さの単位で、100億分の1mだそう。なぜ波長が長さの単位で表されるの?と思ったのだけれど、そのあたりも説明してもらった。光というのは、波で、振動している。で、光が一回振動するときにどれだけ進むかが光の波長、だと。(一時ここに思ったことを書いたのですが、誤解を招くおそれがあるとの指摘を受けたので消しました)というので、また一つ賢くなりました。久しく理系の知識にふれていないので、『色彩』を読んだのはなかなかよい経験だったととらえることにします。
2005.02.09
コメント(0)
-

新刊購入/モーリス・デリベレ『色彩』
浦賀和宏『松浦純菜の静かな世界』北山猛邦『「ギロチン城」殺人事件』佐藤友哉『鏡姉妹の飛ぶ教室』島田荘司『ロシア幽霊軍艦事件』西尾維新『ネコソギラジカル(上) 十三階段』氷川透『各務原氏の逆説 見えない人影』(前五冊講談社ノベルス、後一冊トクマノベルス)の六冊購入。浦賀さんの新作、英語のサブタイトルがついているのかと思ったら、タイトルをそのままローマ字表記しているだけで、ちょっと笑ってしまった。さて、佐藤友哉さんです。今日、『色彩』を読み終えたらさっそく読み始めようと思っている。楽しみ。で、佐藤さんの作品は全て持っているのだけれど、デビュー作『フリッカー式』と二作目の『エナメルを塗った魂の比重』は、最近(?)表紙の装丁が変わったのです。さて、ファンとしては、この装丁の違う版も買うべきかどうか、というところで若干悩み中。ちなみに、以下は私の部屋のノベルスの棚。ご覧のようにうまっているので、余りは別の棚においています。今日六冊も増えたからなぁ…。場所の整理を工夫しよう(買う本を減らそう、という発想にはならないので)。今日はデイケアで病院に行っていた。斬るビル(ネットでダウンロードできるゲーム。空から降ってくるビルを斬りまくる)に挑戦。百万のケタまでしか得点メーター(言葉変かな)がないのですが、ついに、999万9999点いきました。すると、とつぜん止まって、「第二幕へ続く」という表示が。第二幕では、とんでもないものが空から降ってくる(ビルが降ってくるのもとんでもないけど)。しかも斬っていいのか、という罰当たりなシロモノ。制作者の方に悪いので、第二幕で降ってくるものの正体は日記には書かないことにします。病院のパソコンにはジョイパッドがついているので、ゲームがしやすいのです。キーボード操作では、とても満点は出ないだろうな。ちなみに、1006万点でゲームオーバーになりました。とんでもないものがとんでもないスピードで落ちてくるから、なかなか防御できずにつぶされてしまうのです。でも、第二幕から始められるようになったので、ラッキー。講談社ノベルスの新刊も買えて、今日はとても嬉しい一日だった。金曜日は久々に調子悪くなって頓服飲んだりして、土日も少し不調だったから、回復してきた感じ。病院で、スタッフの方と、暴走族の漢字使い(夜露死苦など)についての話題になり、ネットで、「暴走族 言語」で検索すると、「族言葉変換スクリプト」というサイトを発見。これも面白い発見だった。興味がある方はいって遊んでみてください。よろしくは、ちゃんと(?)夜露死苦と変換されました。病院のレクで、思春期グループというのに参加しているのだけれど、今日はドーナッツ作り。楽しかった。ドーナッツはあまり好きではないので、小さいのを食べただけだけど。モーリス・デリベレ『色彩』(白水社文庫クセジュ)読了。所有作品一覧でも日記のカテゴリも西洋史関連にしているけれど、本書は、文庫クセジュのカテゴリでは自然科学に分類されている。「各時代における色の認識」「色の象徴化とことば」など、歴史などいわゆる文系の領域に関わる章もあること、パストゥローの研究で色彩学にも興味をもったこと(これに関連して、色彩学に関する本を読んでパストゥローの研究をより理解できるかと思ったこと)から、西洋史関連、に分類したのだけれど。まずは、もうどうにも分からなかったところから。化学式が出てくる。フタリミドとイサチン(そもそもこれらがなんなのかさっぱり分からない)。色は、三つの要素で決まるという。「色相」と「純度」と「明度」。これらがなんなのか、ここで記すのは私の力量を超えているので控えたいけれど、簡単にいうと、色は光の波長に対応していて、たとえば(ああ、簡単にはいえなさそうだ…)紫外線、赤外線という言葉がある。これは、人間に知覚できる波長の一方の端が紫(4000オングストローム。オングストロームがどういうものかは今の私には分かりません。いや、光の波長の単位なんだろうけど)で、もう一方の端が赤(7000オングストローム)。で、それぞれの外側(つまり、4000未満と7000より上の波長)が紫外線、赤外線と呼ばれる。で、色がこの波長のある範囲に独占的に割り当てられるところの波長を、「色相」という。「純度」は、薄い色か純粋な色か(白との比)、「明度」は放射される光の量(明るい色か黒っぽい色か)。で、これら三つで色が決定されるようなのだが、計算式がある。これにもうついていけない。インテグラルまで用いられる計算式もある。インテグラル、忘れているよ…。というんで、このあたりを読むのは正直苦痛だった。理解も殆どできていない。「各時代における色の認識」の章も、中世に関する記述はほとんど無いといってよい。古代についてはアリストテレスやプラトンの紹介がなされているが、中世は「先の考えをうけつぐことで満足する」(24頁)とあるくらいで、記述はいっきに17世紀にとぶ。これは寂しかった。12世紀は、青色が台頭する時代だというのに。なお、ゲーテは色彩の研究に熱心だったという。このあたりのことはパストゥローのBlue-The history of a colorでふれられていたと思う。84-86頁の色の効果、第六章「色の象徴化とことば」(87-94頁)は興味深かった。本書でも、フランス人(ヨーロッパ人)の一番のお気に入りの色は青色とある。ついで、赤だそうだ。緑が、賭博などに使われるということに関する記述もあった。これは、パストゥローの『ヨーロッパの色彩』でも読んでいた記述。知識の補強ができた。でも、その知識をうまく活かせないのが、まだまだ自分の未熟さだと思う。勉強しよう。でも、今日からはノベルスに力を入れて読んでいこう。「のぽねこミステリ館」というブログ名なのに、最近ミステリに関する話題が少ないので。
2005.02.08
コメント(3)
-
吉本ばなな『日々のこと』/古本購入
吉本ばなな『日々のこと』~幻冬舎文庫~ エッセイ集。食べたり温泉いったり、の話など(この二つが印象に残った)。 付箋を貼ったところ。吉本さんの友人の方が、結婚はいい、こんな楽しい生活はしたことない、とおっしゃっている。いいな、そんな結婚したいな。悲惨な結婚の例も知っているから、余計に。 1989年のヒット商品、第三位はフラワーロックだったそうな。ああ、懐かしい。サングラスかけたひまわりみたいなやつよね。買ったことはないと思うけれど、憶えている。うーん、ちょっと欲しいかも。 あとがきでびっくり。吉本さん、「出来心で入れ墨を」入れたそうな。ちょっとショック。まあ、入れ墨いれていようがどうしようが、素敵な作品を読ませてくれるからいいのだけれど。といって、最近の吉本さんの作品はチェックしてないな…。古本屋で本購入。増田四郎『ヨーロッパとは何か』宮城音弥『性格』宮城音弥『愛と憎しみ-その心理と病理-』ギー・テスタス/ジャン・テスタス『異端審問』モーリス・デリベレ『色彩』アンドレ・モラリーダニノス『性関係の歴史』アンドレ・モラリーダニノス『性関係の社会学』(前三冊:岩波新書、後四冊:白水社文庫クセジュ)の七冊。クリストファー・ドウソンの著作を見つけたのだが、これは後日買うことにしよう。今月はなにってかにって講談社ノベルスの新刊が熱い。六冊出るみたいだけど、うち四冊欲しいのです。浦賀和宏さん、北山猛邦さん、佐藤友哉さん、西尾維新さんの新刊は買う。氷川透さんの各務原氏シリーズも出ているみたいだから、これも買う。五冊。お金が、なくなる。ちょっとバイトする予定があるのが救い。買った日にまた書くかもしれないけれど、佐藤友哉さんの新作が出るのが嬉しい。年も近いし、世界観がとても好きだったのです。『クリスマス・テロル』以降は新作出ないと思っていたから、とても嬉しい。講談社ノベルス以外からも新作が出る予定みたいだし。本当に嬉しい。楽しみ。
2005.02.06
コメント(0)
-
『精神分析入門』
宮城音弥『精神分析入門』(岩波新書)読了。宮城さんは先日(2004.12.2)紹介したラッシェル・ベイカーの『フロイト』の訳者。本書の前書きにおいて、著者は「精神分析の分析」を行ったと書いている。本書は、特にフロイトの精神分析を中心に、いろんな学者の見解などを整理している。フロイトといえば、「性」をとかく強調した人物だと認識している。こうした、性の概念を拡大した理論は、「汎性説」と呼ばれる(9頁)。性の心理については、第四章で詳しく論じられている。本書では、精神分析家たちが扱ったケースがいくつも例示されていて、興味深い。水を飲めなくなった女性の例は、たしか高校生の頃英語のテキストで読んだはず。「われわれは、ふつう他人を傷つけるのを恐れる。憎い人間だと思っても殺せない。法にふれるからというのではなく、本心から他人を殺傷するのは恐い。これは一般の人々では、心の内部にコドモ時代から道徳のブレーキがつくられているからであって、無意識的だからである」(164頁)。なるほど、そういうことか、と思った。でも、他人を傷つける人はいる。ここで、弁明をさせていただきたい。私の日記は、善悪二元論的であるという指摘があった。自分ではそういうつもりはなかったのだけれど、『哀しい予感』の感想などを読んでいると、自分でも、そう思われても仕方ないな、と感じた。しかし、私は純然たる善人や純然たる悪人の存在を信じているわけではない。他人に対して一度も不快な思いを抱かせたり、傷つけたりしたことのない人はまずいないだろうし、どんな犯罪を犯して捕まった人だって、一生の間に少なくとも一度は誰かに感謝されることをしているはずだ。その上で、「人を傷つける人はいる」と言いたい。実際いるのだから。私が感情的になっているのは、まだ入院するほどに傷ついた気持ちの整理がいまだについていないからということは認識している。でも世の中、やっぱりいやな気持ちにさせられる出来事に満ちていると思う。もちろん、とても素敵な出来事もある。ああ、なにを言いたいのだろう…。二元論的な思考は危険だとは認識しています。それでも、人を傷つける人(この言葉をどう捉えられるか、が問題なのかもしれませんね)はいて、それが自分には辛い、ということ、です。もちろん自分自身が、知らないうちに他人を傷つけてしまうこともありえるわけで、人間って難しいと思う。攻撃性や犯罪については、158-159頁(フロイトの理論)、193-196頁(アードラーの理論)などが参考になる。アードラー心理学の中心的な考えは、「劣等感」であるとのこと(186頁)。ユングについては177-184頁。彼の「集団的無意識」という概念は知っていたが(異なる国の神話に同様のモチーフが現れる、など)、彼の性格学のことは知らなかった(たとえ何かで読んだことがあっても忘れていた)。たくさん(でもないかな)付箋を貼った。勉強になった。心理学は面白い。
2005.02.05
コメント(2)
-
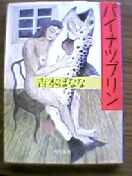
吉本ばなな『パイナップリン』
吉本ばなな『パイナップリン』~角川文庫~ 初のエッセイ集。 笑えるもの、ショッキングなもの(「春の死」)など、様々。基本的には明るい文体だな、と思う。「じゃあ私も入るよ、やっぱり」には相当笑ってしまった。 内田春菊さんを読んでみようかな、と思った。いつになるか分からないけれど。
2005.02.04
コメント(2)
-
木間瀬精三『死の舞踏』
木間瀬精三『死の舞踏-西欧における死の表現』~中公新書~、1974年~目次は以下の通り。ーーー1章 生の無情2章 死の教え3章 死を憶えよ!4章 ダンス・マカブル5章 バロックと死6章 騎士道の死7章 自然美の死ーーー1347年、西欧をペスト(黒死病)が襲った(1348年にいっきに広まるため、こちらの年代が有名)。これには、ノミとネズミを媒介にしてリンパ腺の大きく腫れあがる腺ペストと、空気伝染で肺が侵される肺ペストの二種がある(池上俊一『歴史としての身体』128頁)。死亡率は、三分の一が妥当とされている(『西洋史辞典』)。ペストの広まる様子、人々の苦しみを、ボッカチオは『デカメロン』の中で描いている。中世後期、「死を憶えよ!」(Memento Mori!)というモットーほど、当時の人々の心を表現しているものはないであろう(10頁)。ホルバインが描き、1538年に出版された『死の舞踏』には、様々な身分の人を死に導く「死」(骸骨で表される)が描かれている。死は、農夫にはその仕事を助けるなど、弱者には「よき人生の伴侶」であるが、身分の高い者たちは無情に死に導いていく。死は、あらゆる身分に平等に訪れるのだ。第二章では、叙事詩『ベーベンのアッカーマン』が取り上げられる。アッカーマンは、最愛の妻を失い、「死」を非難するが、「死」は、「善人も悪人も等しく自分のものになる」と言い放ち、また、その役目は神から任されたものだ、と言う。こうして、アッカーマンと「死」が議論をかわす。「死」の言葉の中に、印象的なものがあったので、紹介しておこう。「愛が大きければ大きいほど、苦しみ悩みも大きいということである。おまえが愛を慎んでいたなら、苦しみも避けられたろうに」(24頁)。15世紀の作品であるが、考えさせられる言葉だと思う。第二章ではまた、『往生術』(Ars Moriendi)も紹介される。臨終の床に悪魔と天使が現れる。悪魔はなんとか死にいく人を誘惑しようとする。『往生術』は、そうした誘惑と苦悩について前もって心得ておくべきことを教えるものである(31頁)。悪魔の誘惑に負けそうになる人を、天使が正しい道に導く。このあたりの描写はとても面白い。第三章では、「三人の死者と三人の生者」という主題が扱われる。詩と絵に関わる主題。この形式は、仏教説話にその起源が求められるという(46頁)。ちなみに、仏陀はローマ教会の聖人の一人として定着しているという(47頁)。これにはびっくりした。第四章では、「ダンス・マカブル」(死の踊り)が扱われる。あらゆる身分の人が、死後の自分の姿にそわれている。16世紀にはしかし、その屍は普遍的な「死」であると認識されるにいたる。第五章「バロックと死」は省略(日記が長くなりそうなのと、理解が浅いため)。第六章は「騎士道の死」という題だが、死については殆ど扱われない。ギョーム・ド・ロリスと、彼の作品に手を加えたジャン・ド・マンによる『ばら物語』について論じられている。『ばら物語』には女性蔑視の態度が明示されていた。これに対して、クリスティーヌ・ド・ピザンが非難する。彼女は、「イタリアの人文主義をフランスに普及せしめた功労者の一人」(146頁)であり、また、多くの文学書により傷つけられた女性の名誉を弁護し、婦人の権利を主張することに激しい情熱を注いだ(138頁)。彼女の『ばら物語』への非難は、彼女への反論者と支持者をうみ、ばら物語論争が起こった。…ということで、死というよりは女性問題を扱った章。しかし、とても興味深かった。第七章、自然美の死、も、あまり死に関しては論じていない。マニリズム(ルネッサンスとゴシックの中間の文化史的時代概念)の絵画作品について論じられている。バスティアン・ブラントの『阿呆船』と、これに影響されたとされるヒエロニムス・ボスが論じられるあたりは興味深く読んだ。ヒエロニムス・ボスの絵は好きなので。
2005.02.03
コメント(0)
-

吉本ばなな『TUGUMI つぐみ』
吉本ばなな『TUGUMI つぐみ』~中公文庫~ 私、まりあは母親とともに、母の妹の一家が経営している旅館、山本屋に住んでいた。陽子とつぐみはまりあのいとこ。 つぐみはとても体が弱くて、今までに何度も入院したことがある。しかし、その気質はとても強く、憎まれ口をたたく。しかし、そこに悪意はない。なにか、大きなものと通じているような存在。 その姉、陽子は涙もろい、優しい女性。 まりあの母は、父の愛人だった。父はもとの妻と正式に離婚し、まりあたちは山本屋を離れて東京に行き、父と三人で暮らすようになった。 山本屋が、店じまいをし、ペンションの経営にうつるという。 山本屋最後の夏、まりあはそこを訪れ、つぐみたちと過ごす。 久々に再読。タイトルの『つぐみ』は、この物語の主人公の名前。とても、澄んだ人だな、と感じた。 つぐみが、恋をする。同じような過去を経験している、どこかつぐみと通じる性質をもつ男性に。「告白」の章は、素敵だった。 「怒り」の章では(他の章にもいえるけど)かなり泣いてしまった。なんで悪意は存在するのだろう? とてもつらくなる。 考え事をすると脱線してしまいそうなので、本書の感想はこのくらいで。うまくまとまっていなくて、ときどきこの書評をやめてしまおうかと思うこともある。でも、当初の目的は、あまりにも多くの小説を読むので、その内容と感じたことをメモしようとすること。じゃないと忘れてしまうから。自分の書評を読み返しても(ミステリでいえばトリックとか)内容を忘れてしまっていることもしばしばだけれど。 ともあれ、当初の目的を果たすべく、この書評(もどき)は続けていこう。 追記。文庫の表紙が素敵。今日は岡大へ行ってきた。欲しい論文が収録されている雑誌が、ないことが判明。まだ正式に岡大の学生ではないので、他大学から取り寄せることもできない。入学まで我慢しよう。
2005.02.02
コメント(1)
-
大塚滋『食の文化史』
大塚滋『食の文化史』(中公新書)読了。一応この日記のカテゴリは西洋史関連にしたので西洋史関連のネタを書くことにするが、この本では世界的なレベルで食について考察されている。新書だから読みやすいし。さて、私の小説以外の本の紹介は、学問的な考察ではなくてちょっとしたネタをひっぱってきて、コメントできたらするというお粗末なものになっているけれど、学問的な考察は勉強しているときにしている、ということで、勘弁していただきたい。私はトリビア見ないけれど、このページを見てくださってる方がへぇーって思ってくださったら幸い、といった気持ちで日記をつけている次第です。ああ、最近無駄に文章が長いゾ。本書の紹介にうつろう。魚についての章。魚は、従来「酒菜」と書いた。これは、酒とともに食べるおかずという意味で、野菜も鶏肉も酒菜だった。ところが、魚を尊ぶ気持ちが高まり、魚だけ特別に「真菜」と呼ぶようになった。ここでクエスチョンです。これは、現在使われているあるものの名前の中に今でも残っているのですが、さて、そのあるものとは、一体なんでしょうか? 正解は、「まな板」。魚を切るための板、という意味だったそう(39頁)。あ、次は西洋史関連。lady(レディ)という言葉があるが、この言葉は「粉をこねる人」という意味のチュートン語(チュートンとは、ゲルマン民族の一派で、ドイツの語源だそう)からきているという。パン作りが女性の役だったからだ(88頁)。アンパンも、日本人の発明のようだ。キムラヤの祖、木村安兵衛が明治3年(1870年)に日本最初のパン店を開き、明治7年に銀座に進出、そこでパンの中にアンをいれることを思いついたのだという(89頁)。江戸時代の『倭漢三才図会』には、「(パンとは)蒸餅すなわちマンジュウのアンなきものなり」とある(88頁)。アンが入っているマンジュウの方がいい、というニュアンスみたい。だから、アンが入ったパンは、喜ばれているのだろう。そういえば、大和和紀さんの『はいからさんが通る』の中に、キムラヤのアンパンへの言及があったなぁ。チーズについて。私はチーズに詳しくないけれど、カマンベールチーズの名前は聞いたことがある。食べたことがあるのかないのかも分からない。興味ないことはどうでもいい主義のしわ寄せがここにも…。ともあれ、カマンベールの名付け親はナポレオンだそうな(153頁)。次の枕元の読書は、吉本ばななさんの『つぐみ』と、木間瀬精三さんの『死の舞踏』でいこう。
2005.02.01
コメント(0)
全19件 (19件中 1-19件目)
1
-
-

- マンガ・イラストかきさん
- やっと入れた楽天ブログ!これからの…
- (2025-11-09 16:30:43)
-
-
-

- 読書日記
- 書評【ホットクックお助けレシピ】橋…
- (2025-11-15 00:00:14)
-
-
-

- 本日の1冊
- 読んだ本(青木祐子)・・その百五十…
- (2025-11-13 20:57:17)
-







