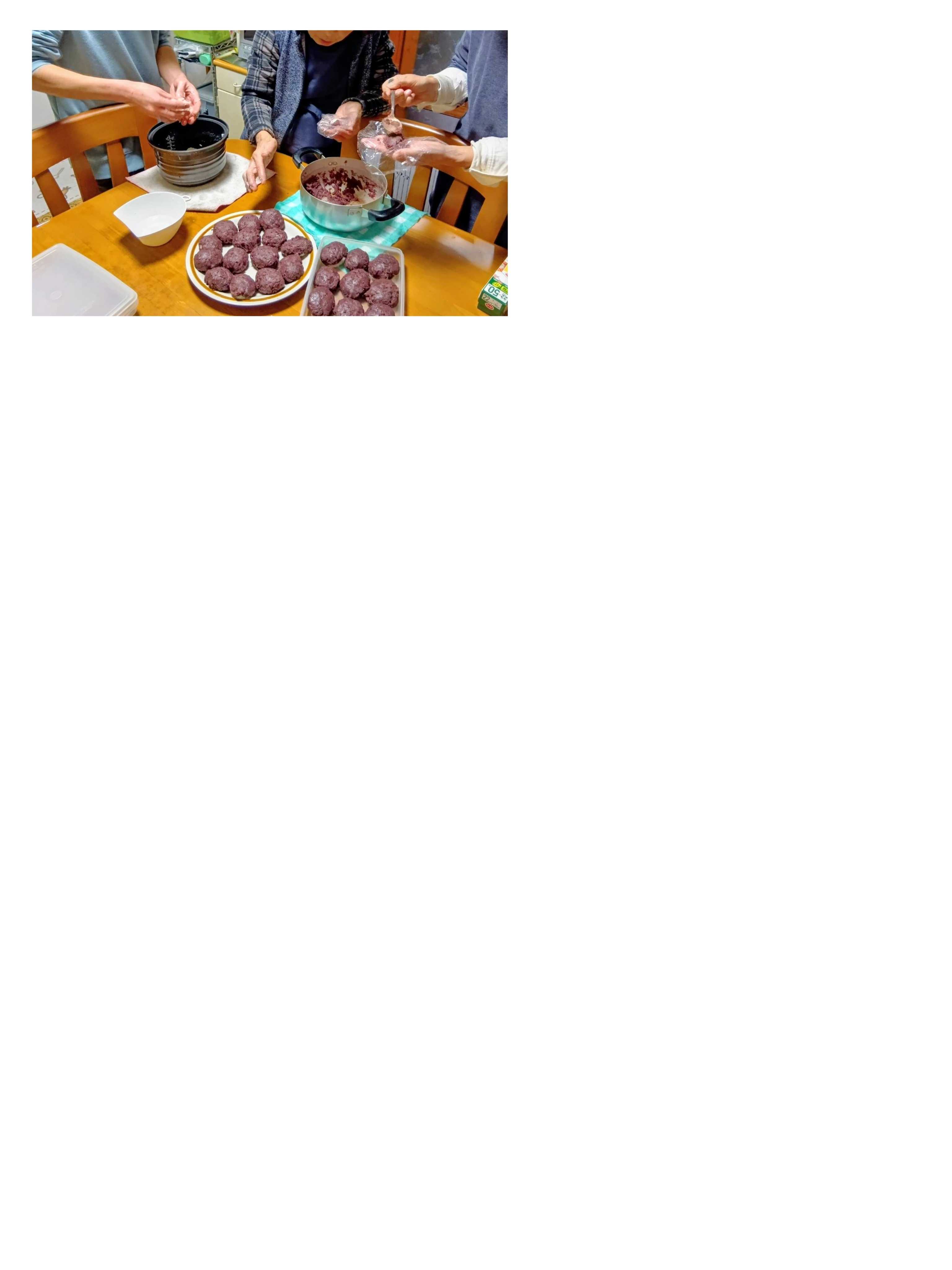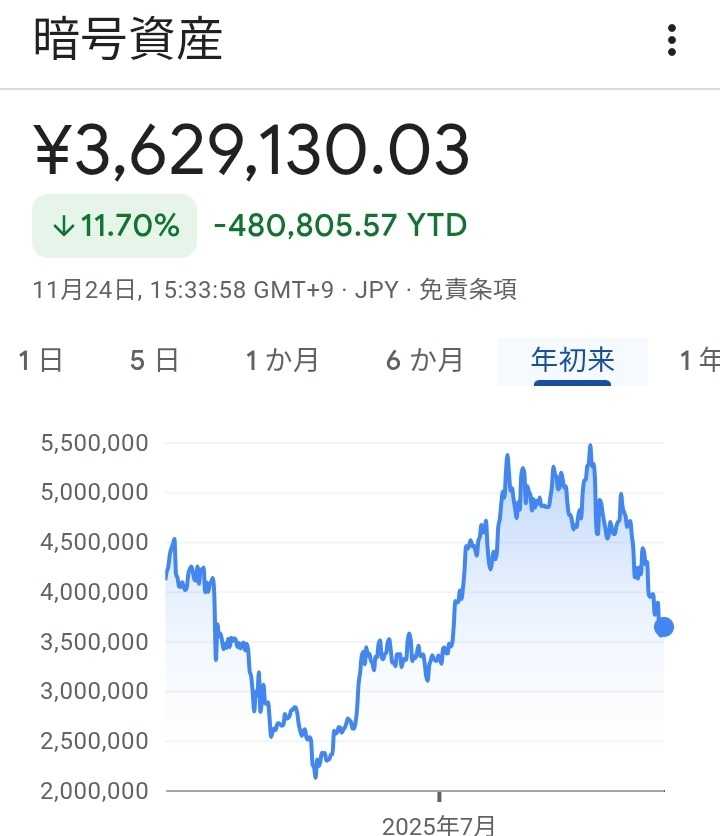2015年11月の記事
全25件 (25件中 1-25件目)
1
-
イスラム国を利したのは誰か
報道ステーション」の偏りぶりに『新潮』が噛みついて 「イスラム国を利するもの」…パリのテロ事件とISに関してテレビ朝日系「報道ステーション」の報道ぶりは目に余る。『週刊新潮』(12月3日号)が早速、噛みついて、「『イスラム国と話し合え』という綺麗事文化人」。読んで胸のつかえが降りた。朝日新聞の投書欄「声」、TBS系「サンデーモーニング」のコメンテーター田中優子法大総長などの意見を批判した後、〈真打ち〉として取り上げたのが「報ステ」の古舘伊知郎キャスター。16日の放送ではこう言い放ったという。〈この残忍なテロはとんでもないことは当然ですけども、一方でですね、有志連合の、アメリカの誤爆によって無辜の民が殺される(中略)ドローンによって無人機から爆弾が投下されて、皆殺しの目に遭う。これも反対側から見るとテロですよね〉~要するに「報ステ」、古舘キャスターは「空爆もテロ」「ISには軍事力より対話を」と言いたいらしい。が、〈論外の主張〉と中西輝政京大名誉教授が一刀両断。〈「テロとは一般の庶民の生命と財産を意図的に奪い、人々に恐怖を与え、自らの主張を通そうというもの(中略)誤爆は決して故意ではない(中略)人道的な意味でのモラルのレベルがテロとはまったく違うのです」〉〈「テロと同一視する議論は、テロの悪質さを覆い隠してしまうという意味で、結果的にイスラム国を利するもの(中略)そのレベルでの発言しかできないのは、国際社会における日本への信頼を傷つけることに繋がります」〉~---テロと誤爆は違うというのは、もちろん理論上はそのとおりです。だけど、現実にはどうか。誤爆の被害を受けた人たちに「これはテロリストに対する正義のための戦いのやむを得ぬミスだから、あきらめてください」と言えば、彼らが納得するのか?納得しないからこそ、反欧米のイスラム過激派が勢力を伸ばしているのでしょう。その現実の前で、こんな理屈が何の説得力を持っていないことは、明らかなのです。「空想的平和主義」を非現実的だと批判したり嘲笑する自称「現実主義者」は数多くいます。しかし、そういう「自称」現実主義者が本当に現実主義なのかは、大いに疑問の余地があります。イスラム国をめぐる問題などは、まさしくその典型だと思われます。いうまでもなく、イスラム国がやっていることは、凶悪なテロであり、また「内政」(イスラム国を国家として承認している国はないけれど)も大変な抑圧による恐怖の支配であるようです。そのような組織を擁護したり賞賛する気は、私にはまったくありません。しかし、です。ここまでの経緯を見る限り、イスラム国の勢力拡大を助長したのは、間違いなく欧米諸国です。シリアにおいては、もともと「アラブの春」を契機として、アサド政権と反政府派の激しい内戦が始まりました。アサド政権は親ロシア派の独裁政権である、というので、欧米諸国はこぞって反政府勢力を支援していました。しかし、反政府勢力の実態は、主張も思惑もまったく違う様々な勢力の呉越同舟に過ぎなかったのです。その中には、現在のイスラム国の母体となった武装組織もありました。そのことは、当時の時点でも盛んに報じられていたように記憶していますが、欧米諸国は、それにもかかわらず、シリア反政府勢力の支援を行っていました。アサド政権のほうがイスラム過激派組織より憎かったのでしょう。彼らは、凶悪ではあったけれど結束が強く、戦意が高かった。それに、資金力もあったのでしょう。それに対して、他の反政府勢力はそうではなかったため、欧米諸国からの軍事援助をイスラム国へ横流し、などという例もあったようです。つまり、イスラム国を、少なくとも途中まで支援してきたのは他ならぬ欧米諸国に他なりません。そして、イスラム国は確かに非人道的ではあるけれど、では他の反政府勢力やアサド政権はどうなのか。結局、いずれも似たり寄ったりで、大した差がないのが現実でしょう。そして、その構図は以前、他の地域で起こったことと瓜二つのように思えます。それは、アフガニスタンです。1980年代のアフガニスタンは、旧ソ連が支援する親ソ派のカルマル政権と、反ソ派のムジャヒディンとの泥沼の内戦でした。旧ソ連は軍事介入したものの、西側諸国が支援するムジャヒディン(イスラム戦士)のゲリラ戦に屈して撤退に追い込まれました。が、西側諸国の支援を受けて勢力を拡大し、ソ連に勝ったムジャヒディンの中に、後のタリバンがいたことはよく知られています。9.11のあと、米国の支援を受けた北部同盟がタリバンを首都から追い払いましたが、米国の支援と軍事介入にもかかわらず、できたのはそこまでです。タリバンは首都を追い払われて山岳地帯に追い詰められますが、壊滅はせず、近年は勢力の復調も著しいと言われます。シリアの例と同様で、タリバンは、もちろん非人道的な勢力ですが、現実問題として、アフガニスタンに、非人道的でない政治勢力など存在しないのです。イラクにおいては多少経緯は異なりますが、結局イラク戦争でフセイン政権を倒したところ、なおいっそう状況がひどくなってしまった、という点では似たようなものです。イラクにおいてイスラム国の主力になっているのは、新政権で冷遇されたフセイン時代の政権・軍関係者で、能力的には新政権より高いといわれます。一方の新政権は腐敗がひどくて、統治能力が低い。政府軍の兵士に給料が行き渡らない(途中で中抜きされてしまう)ので、政府軍の戦意は低く、武器も横流しして金に替えてしまうので、イスラム国との戦闘でも圧倒されてしまっている、と報じられています。そもそも、シーア派主体の政権なので、スンニ派に対しては互いに敵対的な関係で人心を掌握できていません。さらに古い話を持つ出せば、かつてイランでイスラム革命が起こったとき、欧米諸国(旧ソ連も)はこれを敵視して、イランに攻め込んだフセイン政権のイラクを支援していた、という事実もあります。そのイラン・イラク戦争が終わったとたんに、フセインはクウェートに攻め込んで欧米の敵になった。それから更に紆余曲折を経て、今ではスンニ派のイスラム国という共同の敵を前にして、米国はイランとの和解を進めようとしている。結局のところ、欧米諸国が短期的な視野で、「独裁政権」や「非人道的なイスラム過激組織」を武力を以って倒したら(シリアでは、完全には倒れていませんが)、もっとひどい連中が勢力を伸ばしてしまった、という事態を何度も何度も繰り返して現在に至っているわけです。もはや、誰が敵で誰が味方か、さっぱり分からない状態です。イスラム国と話し合うのは、なかなか難しいでしょう。が、間違いなく言えることは、イスラム国を倒したとしても、それに変わる別の過激組織が勢力を拡大するだけだ、ということです。世の自称現実主義者どもは、いったいどういう出口戦略をもってイスラム国に当たれというのか。空爆で戦果を誇って、その実、大した打撃を与えることもできず、彼らの怒りと復讐心だけを掻き立てて、外見上の「成功」を誇れば良しとするのか(当然、その後には激しい報復テロが繰り返される)、あるいは、イスラム国を完全に覆滅させればよいのか(そのあと、イスラム国よりひどい過激組織が勢力拡大しても、それは見て見ぬふりをする)、イスラム過激派敵勢力をこの世から完全に消滅させるまで戦うのか(当然、地上戦ということになり、何十万か何百万の兵力と、果てしない時間が必要、戦費は、想像もつかないし、そもそも成功の保証もない)。私の見るところ、上記に挙げたようなどのようなやり方よりも、軍事的には何もせずに成り行きに任せる(もちろん、人道的支援は行うにしても)ほうが、多少なりともマシな結果になりそうだと思えるのですが、自称現実主義者たちの目算は違うのでしょうか。
2015.11.29
コメント(4)
-
蛍光灯実質製造禁止?
蛍光灯製造、実質不可能に=省エネへLED化促進―政府政府は26日、蛍光灯の省エネルギー性能に関する基準について、厳格化することを決めた。蛍光灯や白熱灯の製造・輸入は、実質的に不可能になる。消費電力が小さい発光ダイオード(LED)照明への切り替えを促進し、二酸化炭素排出量の削減につなげる。2016年度中に経済産業省の有識者会議で詳細を決める予定だ。政府は、自動車や家電などの品目ごとに、最もエネルギー消費効率が高い製品を基準に省エネ性能の目標を定める「トップランナー制度」を導入している。従来は蛍光灯とLEDを区別して企業側に達成を求めていたが、今後は白熱灯も含めて「照明」に一本化する。これにより、最も高性能なLED以外の製造・輸入はできなくなる。経産省によると、LED照明の普及率は12年度時点で9%にとどまる。同省は、30年度にLEDなど高性能照明の普及率をほぼ100%にする計画で、基準厳格化で達成を後押しする。家電量販店の販売価格は60ワット相当の電球型蛍光灯が700円前後に対し、LEDは2000円程度。また蛍光灯をLEDにするには、電球型以外では器具を交換しなければならず、オフィスや商業施設などでは工事が必要だ。ただ、LEDは耐用年数が長く、消費電力も白熱灯の8分の1程度と少ない。政府は26日の「官民対話」で示した省エネ対策に、LED化の促進を盛り込んだ。太陽光発電などで消費電力が実質ゼロの住宅を、20年までに新築の半分以上にする目標も掲げるなど、今後は省エネ投資を経済活性化の呼び水にすることを目指す。---また、政府がすごいことを考え付いたようです。白熱灯はすでに日本国内では製造されていませんが、蛍光灯も実質的に製造できなくするようにすることで、LEDへの置き換えを促進しよう、ということです。省エネはよいことです。少しでも消費電力を減らすことも必要です。が、しかし蛍光灯を実質的に禁止して、すべての電球を半ば強制的にLEDに置き換える、となると、問題が大きそうです。我が家は震災以来、節電に努めています。残念ながら、あれから4年以上たって、少々節電の程度も甘くなってきて、2013年頃に比べるとちょっと電気の使用量も増えてきていますが、それでも震災前に比べればかなり少ない状態を維持しています。で、夏冬は別にして、春と秋も、消費電力はかなり減っているのです。震災前の3/4から2/3程度に収まっています。冷暖房を使わない時期ですから、電灯と冷蔵庫、テレビ・パソコンの電力消費が減っただけでも、それだけ減っているのです。しかし、我が家はLEDはまったく導入していません。冷蔵庫は2012年夏に買い換えましたが、それによる節電効果は月に10~20KWh程度です。テレビ・パソコンの消費電力も大差がない(使用時間は変わっていないので)から、節電の大部分は「電気(蛍光灯)をこまめに消す」ことで実現しています。別に、蛍光灯をLEDに換えなくたって、「人のいない部屋の電気はこまめに消す」というそれだけのことで、我が家で言えば月に70KWhから100KWh程度の節電が実現しているのです。我が家はLEDをまったく導入していないと書きましたが、実は風呂の電気を一時LEDにしたことがありました。元々60Wの白熱球を使っていて、さすがにこれは電機を食うだろうと考えて、震災後電球型のLEDに交換したのです。ところが、使ってみると、暗くて話になりません。どうしようもないので、白熱球よりはマシな電球型蛍光灯に交換しました。実は電球型蛍光灯でも白熱球よりは若干暗いのですが、脱衣所の電気もつけているので、この程度なら問題ありません。この一件で、私はLED電灯に対しては、どうも実用性に疑問符を抱くようになっています。今、この記事を書いているパソコンのディスプレイは、LED液晶を使っていて、これはなかなかよいと思うのですけど。で、家の中は別にして、住宅の共同部分(階段)の照明は去年だったか一昨年だったか、LEDに変わったのです。これは、確かに明るい。蛍光灯と変わらない、ひょっとしたらやや明るいくらいです。ほんの2~3年でLEDもだいぶ進歩したのかな、と一瞬思いました。しかし、管理者が教えてくれたのです。蛍光灯からLEDに変えるとき、施行業者に勧められて、消費電力が蛍光灯に近い強力なLEDにしたのだと。確か、元は20Wくらいの蛍光管だったはずですが、それを公称20W相当のLEDに変えても絶対暗くなるから、と言われたそうです。当然、ソケットごと交換です。つまり、ほとんど節電にはなっていないわけです。(多少は減ったようですが、たいした差ではないらしい)。しかも、10年持つという言葉と裏腹に、わずか数ヶ月でLEDが切れてしまった。これは、さすがに施行業者が無償で交換してくれたようですが。今後の可能性として、LEDはまだまだ発展の余地が多いにあり、やがて蛍光灯(白熱灯は言うまでもなく)を駆逐していくであろうことは確かです。だけど、今の時点ではまだ、LEDには蛍光灯を完全に代替できるだけの性能はありません。価格差も大きい。あと5年という期限を切って、蛍光灯を追放するのは、いろいろな意味で無理があるように私は思います。結局のところ、蛍光灯より単価の高いLED電灯の販売で業界の利益につながるだけではないのか、と思わざるを得ません。
2015.11.27
コメント(6)
-
的外れなのは果たして・・・・・・
朝日新聞の夫婦別姓賛成論は的外れな論旨が多い しわ寄せは子や孫に… 秦郁彦(現代史家)11月4日、最高裁大法廷は「夫婦は同じ姓を名乗る」「女性は離婚後6カ月間は再婚できない」とする民法の規定が憲法違反かどうかを争っている2件の訴訟で、原告と国から意見を聞く弁論を開いた。判決は12月16日に予定され、新聞は大きな話題として取り上げた。ここでは論点を前者、すなわち夫婦別姓問題に限定したい。どんな制度も長所と短所が絡み合っているので、新聞は賛否両論を公平に紹介し読者の判断に委ねるべきだと思うが、そうなっていない。各紙が概して別姓制の導入に好意的ななかで、特に朝日新聞はかなり露骨な賛成論を展開している。たとえば11月7日の社説は「家族の一体感が損なわれるなどを理由とした」反対論は、「今の時代にそぐわないのは明らかだ」とあっさり切って捨てる。そして推進派に立つ理由を次々に列挙するが、的外れの論旨が多い。好例は「海外でも夫婦に同姓を義務づける国はほとんどなく」のくだりだ。わが国の世論は「先進諸国の大勢」とか「グローバルな基準」のような「神託」に弱く簡単に説得されてしまう傾向がある。これもその一例だが、そもそも全国一律の戸籍制度を完備してきた国は日本以外はほとんどないから、次元の違う制度比較は空論になってしまう。~差別といえば現行民法では、夫婦は「夫又は妻の氏を称する」と規定しているが、実際には96・1%が夫の姓を選んでいるのを、朝日社説は「実質的に女性が姓の変更を強いられており、正当化できない」ときめつけているが、果たしてそうか。~ところで別姓反対者の論拠は「家族の一体感を損なう」としか報じられないが、問題の核心は夫婦別姓が親子別姓を意味する点にあると筆者は考える。ここで、結婚の態様を整理してみると、(1)同姓婚(通称併用は可)(2)別姓婚(3)事実婚(4)新姓創造(結合姓を含む)(5)通称拡大(戸籍法の裏付け)-となる。現状は(1)だが、(5)の方向へ進みつつある。~(2)を採用した際の難点は、子の姓を決めるすっきりした名案が見つからぬことだろう。2001年の森山真弓法相時代に別姓実現の一歩前で、(5)を推す高市早苗議員の奔走により流れたことがある。このとき法案の作成を命じられた法務省官僚は、子の姓について、あちらを立てればこちら立たずで、条文化に苦慮した。~最終案は、別姓での結婚時にカップルが協議して子たちの統一姓を決め、登録しないと結婚届を受理しないという「荒業」に落ち着いた。双方の親も加わる協議がまとまらないと事実婚(内縁)状態が続き子は自動的に母親の姓になる~。最近の世論調査では別姓容認と反対は35%前後で拮抗しているが、容認しても実行する人は「百人に一人」(野田聖子議員)という見方もある一方、同姓から別姓に切り替える夫婦が多いと経費増が心配だという声もある。いずれにせよ、しわ寄せが子(や孫)に集まる事情に変わりはない。最高裁は予見される実務上の波及効果も念頭に置いて、理念倒れにならぬ判断を下してほしい。---どうも、長い割には(引用はだいぶ省略しましたが)何が言いたいのかいまひとつよく分からない文章です。ただ、要するに選択的夫婦別姓制には反対、ということでしょう。しかし、「朝日の主張は的外れ」と叫ぶ秦郁彦の主張のほうが、的外れのように思えます。「新聞は賛否両論を公平に紹介し読者の判断に委ねるべき」だそうですが、その種の公平性からはもっとも縁遠い新聞である産経にそんなことを書いてもねえ、と思います。「わが国の世論は『先進諸国の大勢』とか『グローバルな基準』のような『神託』に弱く」とのことですが、それは、「日本以外のすべての国が集団的自衛権を認めている(だから日本も集団的自衛権を認めるべきだ)」などという「神託」を叫ぶ産経新聞(を初めとする右派勢力)にこそ当てはまるんじゃないでしょうか。現状は同姓婚だが通称拡大の方向へ進みつつある、ということですけれど、どうも私には、「通称拡大」が現実に前に進んでするようには、まったく見えないのです。この案が出てきたのは、引用記事にあるように2001年のことで、それから14年も経つのに、何一つ実現していないじゃないですか。要するに、選択的夫婦別姓制の導入を妨げる目くらましのために持ち出しただけで、本当はそれも実現するつもりはないんじゃないの?ということです。別姓での結婚時にカップルが協議して子たちの統一姓を決め、登録しないと結婚届を受理しないという「荒業」に落ち着いた。というのですが、私は、それが「荒業」とは思えません。だいたいにおいて合理的な制度を考えた、と私は思います。あえて言えば、子どもの姓は父母の好きなほうを(出生時に親が)選択する、という制度もありかな、と思います。子どもの姓をどちらにするかでもめるような夫婦なら、夫婦同姓の場合は結婚時にどちらが改姓するかで揉めるに決まっています。同姓ならもめないで済む、というものではありません。今の制度だって離婚と再婚を繰り返せば、あるいは養子縁組によって、親子あるいは兄弟間で苗字が違う、ということは起こります。母子家庭を中心に、そういう例は少なくありません。選択的夫婦別姓制が導入されたとき、実際にそれを実行する夫婦はどの程度いるでしょうか。私は、周囲に別姓実現を心待ちにしている夫婦が何組かいるので、100人に1人よりは多いだろうと思います。とはいえ、1割には届かないだろうとは私も思います。我が家も、別姓にする予定はありません。いずれにしても、そのために戸籍を書き換えるのに、いくらかかるというのでしょうか。心配するような経費増があるとは思えません。世は少子高齢化です。少しでも結婚を増やし、子どもを増やそうと思うなら、少しでも結婚や子育ての敷居を低くしたほうがよいと私は思うのです。夫婦同姓の強制、なんてことをやめれば、効果は微々たるものではあるでしょうが、多少は少子化解消の役には立つでしょう。
2015.11.25
コメント(5)
-
テロとクーデター教唆、殺人未遂
【三島由紀夫没後45年(上)】日本を代表する作家、三島由紀夫=当時(45)=が、自ら結成した民間防衛組織「楯の会」の会員4人と陸上自衛隊市ケ谷駐屯地に乗り込み、会員1人と自決した事件から、25日で45年になる。何が三島らを暴挙とも思える行為に駆り立てたのか。憲法改正問題などが注目されるようになった今、三島と寝食を共にした楯の会の元会員の証言などから、改めて事件の背景と現代日本へのメッセージを考える。(以下略)---【三島由紀夫没後45年(中)】【三島由紀夫没後45年(下)】~高校時代に三島の文章と行動力に魅せられたという女性会社員(32)は「今、楯の会があればぜひ入りたい。先生は日本の真の姿の実現を目指していた。自決は自衛隊の決起を喚起しただけではない。もちろん、あきらめの境地でもない。メッセージだ。自分たちが口火を切ることに意味があった。それだけの影響力があると分かっていた」と話した。少しずつではあるが、三島や森田の思いが広がりつつある。---長い文章だし、中身を紹介したいとも思わないので、最初と最後の引用に留めます。三島事件の詳細については、ご存知の方も多いでしょうが、一応簡単に解説しておきます。三島焼き尾は、小説家として著名であり(真偽のほどは知りませんが、ノーベル文学賞候補になったことがあると言われる)、かつ、盾の会という右翼団体を作った活動家でもありました。元々、自衛隊に体験入隊した経験もあり、市ヶ谷駐屯地には頻繁に出入りしていた三島は、1970年11月25日、4人の「盾の会」会員とともに東部方面総監益田兼利陸将と面会すると、日本刀を振りかざして総監を監禁、自衛隊の「決起」を要求、人質を救出しようとする幕僚らに日本刀で切りかかって傷を負わせ、更に総監室のバルコニーから、自衛官らに決起を呼びかける演説を行うものの、聞き入れる者もなかったため、割腹自殺を遂げた、という結末です。同行した4人の盾の会会員のうちからも、1人森田必勝が三島の介錯を行った後にやはり割腹自殺しています。自衛隊側には、重傷者は出たものの、奇跡的に死者は出ませんでした。政治的要求を掲げて暴力(殺人未遂)に及んでいるのだから、テロ行為そのものであり、また、自衛隊に決起を呼びかけている、つまりクーデターの教唆を行っています。単に口先でクーデターを叫んだのではなく、東部方面総監を監禁し、日本刀という武器で威嚇してクーデターの実行を迫ったのですから、場合によっては内乱罪もあり得るところでしょう。計画としては粗雑の一言に尽き、成功の可能性など皆無ではあったけれど、歴然たる犯罪行為であることは明白です。三島は著名人だった上に、死んでしまったからあまり糾弾もされなかったけれど、凶悪犯罪者であったことは確かです。で、問題は、テロとクーデターの意思を持った三島が、いともあっさりと東部方面総監という陸上自衛隊の要人に面会して監禁できてしまったことです。三島は、以前より市ヶ谷の陸上自衛隊には頻繁に出入りしており、著名人ということで総監とも何回も会っていたようです。いわば自衛隊にとっての友好人物と見られていたわけです。逆に言えば、テロとクーデターを起こそうという意図を持っている人間を、それと見抜けず、友好的人物と考えて自衛隊の最高幹部が付き合っていた、ということです。これが、もしイスラム過激派や新左翼過激派だったら、産経新聞などは狂ったように危機管理はどうなっていると書き立てるでしょうが、相手がお仲間の国粋主義者だから何も言わない。それどころか、「三島や森田の思いが広がりつつある」だと。曲がりなりにも報道機関が、テロとクーデター未遂犯を賛美しているに等しいのだから恐れ入ります。しかし、この一件から明らかなのは、テロはともかく、クーデターの企てというのは、軍隊(自衛隊)の内部、または親しい周辺から起こる、ということです。この時代、新左翼過激派も様々な暴力行為を行っていました。自衛隊にも、反戦自衛官と呼ばれる人たちが、少数ではあったけどいた。しかし、彼らが東部方面総監に面会することなど、できたわけがありません。三島由紀夫だったからできたのです。自衛隊という武力組織が、敵(反戦運動や左派)と味方(右派、保守派)のどちらの影響を受けやすいか、という問題です。実際、この件に限らず、戦前戦後のクーデター計画は、すべて旧軍、あるいは自衛隊の内側か、近い立ち位置の人たちから出ています。2・26事件、三無事件、そしてこの三島事件。敗戦時の宮城事件もそうです。諸外国の例でも同様です。三島事件の時は、さすがにこれは何の成算もない無謀な暴走で、自衛隊に賛同者はいませんでした。しかし、それまで三島に対して総監をはじめとする市ヶ谷駐屯地の幹部たちが、親しい関係を続けてきたことは歴然としています。また、後になって、三島の主張はもっともだと思うとか、恨みはないとか、シンパシーを表明する自衛隊関係者はいます。もし、あのような直情径行で短絡的なやりかたではなく、もっと策を凝らしてのクーデター計画だったら、果たして賛同者が皆無で済んだのかどうかは、断定できないだろうなと私は思います。
2015.11.24
コメント(4)
-

寝台特急カシオペア
来年3月、北海道新幹線の函館まで営業開始と同時に、青函トンネルを通過する2本の夜行列車が廃止となります。1本は青森と札幌を結ぶ急行「はまなす」そして、もう1本は上野と札幌を結ぶ寝台特急カシオペアです。「はまなす」はJRグループ最後の急行列車、そして実質的には最後のブルートレイン(狭義のブルートレインは、「北斗星」の廃止をもってすでに全廃されていますが、「はまなす」も実質ブルートレインのようなもの)なのですが、これを撮影しに青森や札幌まで行くのは無理なので、寝台特急カシオペアを上野駅まで撮影しに行ってみました。上野駅に先立って、田端の機関区を歩いてみました。新幹線がずらっと並んでいるのですが、金網が邪魔ですね。EF81型電気機関車とDE10型ディーゼル機関車。EF81は、先代の「北斗星」牽引機だったものです。現在も、稀に代走で「カシオペア」を牽引することはあるようです。DE10は入れ替えようです。これも、金網が邪魔です。現在の「カシオペア」牽引機(廃止された「北斗星」の牽引機でもあった)EF510です。踏切から撮ったので、ここは金網に邪魔されませんでした。カシオペア塗装機と北斗星塗装機。2009年の新製されたばかりの電気機関車で、そのときは「まだ当分北海道行きの夜行列車は運行を続けるつもりなんだな」と思ったのですが、まさかそれからたった6年で廃止になるとは思いませんでした。元々、これらの電気機関車の目的の半分は、JR貨物からの委託を受けて貨物列車を牽引することにあったようです。その委託契約も中止になったので、これらの機関車は次々とJR貨物に売り払われています。上野駅に行ったら、もう「カシオペア」が入線していました。ブルートレイン型の寝台車(24系25型と14系)は、2回ほど乗ったことがあるのですが(特急「はやぶさ」と急行「銀河」)、カシオペアは乗ったこともないし、本物をじかに見るのも初めてかもしれません。あるいは、車窓からすれ違うところを見たことはあるかもしれませんが、記憶にはありません。昨日撮影しに行ったのは、どうせ廃止直前になると観客が多くて、撮影しにくいだろうから今のうちに、という考えだったのですが、すでに観客は充分多かった。みんな、最後尾車両の前で記念撮影しているものだから、この写真を撮るのもだいぶ待ちました。食堂車です。「北斗星」「トワイライトエクスプレス」廃止後の今、JRグループに残った最後の食堂車です。(いや、「ななつ星」とかにも食堂車はあったかな?でも、あれは例外)ステンレス製のためか、どうも私にとっては米国の大陸横断鉄道のような印象を受ける車両です。1999年に新造されているので、まだ16年しか経っていませんが、カシオペア廃止後はどうするのでしょうか。他に転用するのかな。電源車ですが、ラウンジも併設しているという車両です。牽引機はEF510-515。この日はカシオペア塗装機ではなく北斗星塗装機でした。このあたりはものすごい人だかりで、写真を撮るのも一苦労でしたよ。そのため、残念ながらピンボケ写真しか撮れませんでした。人影の写らない写真はあきらめました。定刻16時20分、カシオペア号は札幌に向けて出発していきました。列車が去ったあと、ぞろぞろと帰っていく人波。カシオペアの乗車定員は178名だそうです。ひょっとすると、見物客のほうが多いんじゃないかという感じ。廃止4ヶ月前の今からこれでは、廃止直前はとても写真なんか撮れないでしょうね。でも、真冬の、雪を載せて到着する写真も機会があれば撮ってみたいところですけどね。列車に乗るのは、仕事やら家庭やらいろいろな条件から考えて、絶対に無理。あきらめてます。
2015.11.23
コメント(2)
-

奥多摩・三頭山
三連休の初日であった昨日、奥多摩の三頭山に登ってきました。檜原村の都民の森から、とてもライトな山登りです。武蔵五日市駅に着いたら、バス停がものすごい混雑で、都民の森に行く人がこんなに多いのかとぎょっとしたら、ほとんどの人が別のバスに乗り、都民の森行きは10人前後だけでした。諸事情により、9時発のバスを逃してしまい、11時35分発というかなり遅いバスだったのですが、都民の森から山頂までの標高差は500mしかないので、まあ大丈夫だろうと。ザックから突き出す、怪しい竹筒(笑)もちろん、常連の皆様にとっては怪しくもなんともないと思います。今回は、ケーナ2本、ケナーチョ1本、サンポーニャ2組(マルタとサンカ)を持っていきました。完全に笛練習前提の山登りです。檜原村、東京都内で、伊豆七島を除く唯一の村。東京都といっても、こんな場所もある、ということで。考えてみると、東京都には最高峰雲取山(2017m)を筆頭に、1700m峰は目白押しです(七ツ石山・鷹ノ巣山・酉谷山・天目山など)。実は意外に山の多い場所です。ただし、行政区分上は東京都ですが、都心方面から行くと、神奈川県にある丹沢のほうが近い上に交通費も安いときています。都民の森に着いたのは、何と12時50分頃になってしまいました。普通なら登山の出発には遅すぎる時間ですが、ここなら大丈夫だろうと歩き始めます。ところが、実は9月に西穂高岳に登って以来、山に登っていなかったばかりでなく、ランニングも怠っていたのです。左足の足首の筋をずっと痛めていて、それがなかなか完治しないからです。まだ治っていません。が、この程度の山なら問題なさそうと考え、実際問題ありませんでした。が、問題なのは脚力です。2ヶ月体力づくりを怠っていたツケは如実でした。ゼーゼーとすごく息が切れるし途中で足が止まるのはなぜ?(笑)こんなキツイ山登りになるなんて、想定もしていませんでした。が、スピードは案外そんなに遅くもなく、2時ちょうどに山頂に到着。登りに要した時間は1時間をわずかに超える程度でした。で、登りの途中はまったく写真を撮らず、山頂で初めてシャッターを切りました。眼前に富士山です。今年はここまで暖冬で、日本アルプスも含めてほとんどの山にまだ根雪が着いていない(日本一の積雪量の立山ですら、うっすらとした雪しかない)のですが、富士山は雪が付いていました。富士山のアップです。朝方は快晴でしたが、この時間にはちょっと雲が出てきました。雲取山、前述のとおり東京都の最高峰です。3回か4回登ったことがあります。以前は、この三頭山からもっときれいな写真が撮れたのですが、潅木が育ってきて視界を遮り気味で、石尾根の山々はちょっと見えにくくなっています。山頂付近は紅葉も完全に終わっています。山頂の表示。山頂は東西に分かれていて、こちらは西峰。実は東峰の方が数メートル高いのですが、山頂に視界がないので、そちらは今回パスしました。過去何回も登っているし。下山は登りとは別コースを取りました。標高が下がると、まだ紅葉が残っているところがあります。この日は晴れでしたが、前日まで天気がよくなかったため、登りのコースも下りのコースも、登山道はだいぶぬかるんで、やや滑りやすくなっていました。三頭大滝。大滝と言ってもたいしたものではありませんが。都民の森入口の駐車場に戻ってきました。途中2箇所で笛の練習をしたので、下ってきた時間は4時20分頃。登りよりはるかに時間がかかった。最終バスに乗ったときには、もう日も暮れてしまいました。で、一夜明けた今日は筋肉痛。なぜ、標高差たった500m(高尾山口から高尾山頂までが標高差400mちょっとなので、それより100m高いだけ)なのに筋肉痛?(笑)やっぱり体力作りしなくちゃ。とはいえ、この間まったく運動していなかったわけでもなく、毎週末に2kmくらいは歩いているし、毎日7階相当くらい(あるいは、もっと)階段を登っているのですが、それじゃ全然足りないってことですね。
2015.11.22
コメント(5)
-
売店でもヤフオクでも売っている軍事機密って
陸自元幹部、ロシアへ資料漏洩容疑 書類送検へ陸上自衛隊の元東部方面総監が2013年、在日ロシア大使館の軍人外交官に防衛省の内部資料を渡したとして、警視庁公安部は来月上旬にも、この2人を含む6人を自衛隊法(守秘義務)違反の疑いで書類送検する方針を固めた。捜査関係者への取材でわかった。~捜査関係者によると、元東部方面総監は退官後の13年5月ごろ、自衛隊の軍事訓練や戦術などをまとめた「教範」と呼ばれる資料をロシア人元武官に渡し、情報を漏洩した疑いがある。部下だった自衛官ら男女4人に頼んで入手したといい、警視庁はこの4人も書類送検する。この教範は、各部隊の行動基準が掲載され、自衛官の教育や訓練に使われる。訓練の計画から実行までの流れや、部隊の運用がまとめてあるという。重要な機密事項は含んでいないが、警視庁は、外部に漏れれば陸自の業務に支障が出るおそれがある内容で、隊員が職務上知り得た秘密にあたると判断した。警視庁や防衛省の関係者によると、ロシア人元武官は2012年2月、ロシア大使館で開かれたレセプションで元東部方面総監と再会した。かつて日本で勤務したときから顔見知りで「もう退官されたんですね」と話しかけ、自衛隊の展開について質問しながら「ロシアの部隊も勉強したい。教科書はありませんか」と持ちかけたという。教範の授受は、東京都千代田区内の高級ホテルで行われたとされる。緑色の表紙で2センチほどの厚さだった。一般には入手できないが陸自では売店で販売されている。公安部幹部は「秘密性の低い資料を頼んだのは、相手に罪の意識を感じさせないためだろう。スパイ活動の入り口で、協力者にする初期段階だったのではないか」と話す。~---スパイ活動と言えばスパイ活動なのでしょうが、罪に問うような内容かというと、大いに疑問の余地はあります。「外部に漏れれば陸自の業務に支障が出るおそれがある内容」というけれど、「陸自では売店で販売されている」というようなものが、「内部資料」と言われても、いささか無理があるように思えます。それなら、そもそも売店で販売などすべきではありますまい。というか、ちょっと検索したところ、同じ教本と思われるもの(普通科運用)が、2015年11月21日午前8時現在、ヤフオクで出品されていますけど。14日から出品されているようで、現在入札価格が10700円になっています。で、以前にももっと古い版が出品されていたことがあるようです。つまり、この程度の「機密」文書ということです。「協力者にする初期段階」と言いますが、いくら元将官級といえども、すでに退官している人が、最新の重要機密情報に触れられるわけもないでしょう。だから、さすがに逮捕というわけにはいかず、書類送検ということになったのでしょうが、結局のところ、ある種の見せしめ、「スパイは危険だぞ」と世論を煽るための材料として立件した、ということに過ぎないように思えます。ちなみに、米陸軍に至っては、この種の野戦教範はネット上に公開されています。Doctrine and Training Publicationsこのことから考えても、世界的に見てこんな情報が「軍事機密」だと思っている国はない、ということでしょう。それにしても、自衛隊というところは、この種の教範まで自費で買わせるんですね。軍服、いや戦闘服すら、以前は自費で購入していたそうです。現在は私物の戦闘服は禁止されているとのことですが、官給品は非常に破れやすいというので、実情は果たしてどうなのでしょうかね。
2015.11.21
コメント(8)
-
それでも、戦前・戦中よりはマシだった、ということだ
知られざる「GHQの洗脳」歴史学ぶ自民の新組織に期待「オウム真理教の信者のマインドコントロールはよく知られていますが、6年8カ月にわたる占領期間中の日本人に対するマインドコントロールについてはあまり知られていません」この言葉は、自民党の稲田朋美政調会長が弁護士当時の平成8年8月、産経新聞の連載企画「教科書が教えない歴史」に執筆した記事の書きだしである。稲田氏はGHQによる言論統制や、日本人に罪悪感を植え付けた宣伝計画の弊害を指摘し、記事をこう締めくくっている。「いまだに日本が占領下の厳しい検閲によるマインドコントロールから抜けきれないでいることは悲しむべきことです」稲田氏は、自民党結党60年記念式典に合わせて設ける日清戦争以降の歴史や極東国際軍事裁判、GHQによる占領政策などを学ぶ安倍首相直属の新組織づくりを主導してきた。組織トップには谷垣禎一幹事長が就くが、今後の活動に期待したい。戦争に負け、占領国民が施される「洗脳」とはどんなものか。われわれの父祖が直接体験した出来事とその影響は、学校教育ではほとんど触れられず、実態はあまり知られていない。その意味で、自民党の新組織がGHQの占領政策について議論し、そこから日本の現状について考えることには大きな意義がある。また、メディアのあり方、報道姿勢にも少なからず関わってくる問題でもある。例えばGHQは稲田氏が指摘した検閲を実施する一方で、真珠湾攻撃4周年の昭和20年12月8日から、10回にわたって全国の新聞に、日本の侵略と悪行を強調する連載記事「太平洋戦争史」を掲載させた。翌9日からは、「太平洋戦争史」をドラマ仕立てにした「真相はかうだ」をNHKラジオで放送させた。(中略)「老いも若きも幅広く、虚心に学ぶということだ」谷垣氏は新組織について周囲にこう語り、特に提言などをまとめることはしない考えだ。確かに70年近く前のことを、今さら恨みがましく言い募るのはみっともない。ただ、何があったか、それが現在にどうつながっているかはきちんと押さえておいた方がいい。---要するに、与党が自分の思い通りの歴史に書き換えたい、その準備作業としての「新組織」ということです。日本は戦争に負け、米軍(連合軍)に占領されて独立を失ったのです。GHQは日本を(親米的な)民主国家にするために、様々な強制力を働かせた。軍国主義排撃ということもあるけれど、共産主義排撃ということもあって、たとえば2.1ゼネストの禁止やレッドパージもまたマッカーサーの指令によるものです。公務員のスト権を否定する現行の国家公務員法、地方公務員法は、まさしく占領軍の2.1スト禁止命令から始まっているものですが、占領政策を見直すということは、GHQの命じた公務員スト権否認も見直しますか?そういうことはしないだろうことは容易に想像がつきます。自分たちに都合のよいところだけのつまみ食いの歴史観を披露するのでしょう。結局、トータルで見て、どちらの時代のほうがよりマシか、ということに尽きると私は思うのです。GHQは正義の集団ではもちろんなかった。そんなことは言うまでもないけれど、戦争に反対する声、反政府的な声はすべて圧殺され、310万人が命を落とし、日本中の主要都市が焦土と化した太平洋戦争と、戦後のGHQの統治と。どちらにも問題はあったにしても、比べるまでもなく、戦後のGHQ統治のほうがはるかにマシです。何といっても、戦争で命を落とす恐怖がないのだから。大方の日本人にとってもそうだったからこそ、戦後GHQによる統治はほとんど抵抗なく受け入れられたのです。みんな、戦争はコリゴリだったのです。しかし、そうではない、という人たちも一部にいるわけです。戦争はコリゴリじゃない、戦後より戦前のほうがよかった、という人たち、その例の一つが稲田朋美であるわけですが、こういう人たちが、一生懸命歴史を書き換えようとしている。その歴史書き換えの先に待っているものは、戦前の繰り返しとしか思えません。
2015.11.19
コメント(4)
-
ハクビシン
イチからオシえて:都会に進出、ハクビシン 空き家にすみ着き抜群の適応力で急増タヌキやアライグマとよく似たジャコウネコ科の動物・ハクビシンが、都会で勢力を急拡大している。生ごみを荒らされたり、天井裏にすみ着かれて悪臭やフン害に苦しめられたりと、被害も多発。だが、都市環境に抜群の適応力を持った彼らを追い出すのは簡単ではなさそうだ。2年前の秋。記者が深夜、東京都新宿区近くの住宅街を歩いていると「キューン、キューン」と声を上げながら電線の上を行き来する小動物に出くわした。暗くて姿はよく見えない。子猫が下りられなくなったのかと思い、近くの交番に助けを求めたら、警察官は一目で「ハクビシンですね」。2人でしばらく眺めていると、電柱から民家の屋根に飛び降り、どこかへ去って行った。数十年前まで、ハクビシンは里山でもめったに見かけない動物で、天然記念物に指定していた自治体もあった。しかしここ10年ほどで急増し、農作物の被害額は「特定外来生物」として駆除が認められているアライグマを上回る。特に都市部への進出は、アライグマより目立っている。害虫・害獣対策の業界団体「日本ペストコントロール協会」によると、2014年の都内のハクビシンに関する相談件数は444件で、シロアリやカラスなどの鳥類より多い。生態に詳しい埼玉県農業技術研究センターの古谷益朗さんは「アライグマは人家近くに高い木が残る丘陵地を好むが、ハクビシンは都会の方が快適らしい」と話す。ハクビシンが都会で暮らせるのは、雑食性であるのに加え、高い運動能力により、地面に下りる危険を冒さず屋根や電線を伝って移動できるからだ。さらに、格好のすみかになる住宅の天井裏も多い。同協会の谷川力・技術委員長は「空き家や物音に気付きにくい1人暮らしの高齢者宅が増えていることも、ハクビシンの進出に関係しているのでは」と指摘する。(以下略)---私も、夜間ジョギング中にハクビシンに遭遇したことが2回あります。いつだったか、時期は忘れましたが、一度目は猫がいるなと思いつつ、その脇を走り抜けたのです。でも、何かが引っかかる、何かが猫と違う、どこが違うのか・・・・尻尾の付け根が猫とは違うのだと気がついた瞬間にひらめきました。あれはハクビシンではないか、と。しかし、残念ながらこのときは顔面を確認することができなかったので、九分九厘間違いないとは思いつつ、確認はできませんでした。それから何年かして、再びジョギング中にハクビシンに遭遇したのです。前回のことが記憶にあったので、このときは前面に回りこんで顔面を確認しました。はっきりと、顔に白い縦筋が入っていたので、ハクビシンであると完全に断定できました。ただし、引用記事の例とは違い、私が見たのは2度とも地面を歩いていましたけど。そのときにちょっと調べたので、東京でハクビシンが増えていることは知っていました。里山よりも都会を好む、これは「都市鳥」と呼ばれる鳥たち(スズメ、ハシブトガラス、ヒヨドリなどなど)によく見られる生態ですが、ハクビシンも同じであるようです。空き家が増えたことが分布拡大の原因の一つ、というのは意外な話です。ただ、引用からは省略しましたが、レプトスピラ症の病原菌とE型肝炎ウィルスのキャリアである例が多いということなので、あまり触ったりはしないほうがよいようです。もっとも、それを言えばドブネズミはどうなんだ、ハエやカだって、という話になってしまうのですが。そういえば、ドブネズミも東京には少なくないですね。2~3ヶ月前、某地下鉄駅の構内で、地下道にドブネズミが姿を現したことがありましたし、現在の勤務先、および昔の勤務先でドブネズミが姿を現したことはあります。(ただし、現在の勤務先に姿を現したのは、ドブではなくクマネズミかもしれません)まあしかし、ドブネズミを見て「自然」という印象はなかなか持たないものですけど。考えてみると、山登りなどで鳥を見かけることは多い(かつて、日本野鳥の会に入っていたこともあり、鳥の種類はある程度は覚えています)のですが、それに比べると山で野生の哺乳類を目撃する機会は多くありません。ニホンザル(北アルプスなど各所)、ニホンカモシカ(八ヶ岳と南アルプス)、ニホンジカ(雲取山と北海道)、イノシシ(雲取山)、キタキツネ(北海道)、エゾヒグマ(知床の登山道で1対1で鉢合わせ)、エゾシマリス、くらいだと思います。鳥に比べて哺乳類との遭遇頻度が低いのは、おそらく生息密度自体が鳥より低い(だいたいは鳥より大型ですから)ことと、夜行性のものが多いので、昼間は出会いにくいからなのだと思います。そういえば、冒頭紹介したハクビシンとの遭遇も、2回とも夜でした。そのため、鳥の写真は時々撮影しますけど、前述のハクビシンも含めて、哺乳類の野生動物の撮影に成功したことは、数えるほどしかありません。ニホンザルとカモシカが1回ずつ、くらいでしょうか。それも、ニホンカモシカは露出を間違えて、ちゃんと写らなかったのですが。
2015.11.18
コメント(2)
-
共謀罪?
テロ対策に「共謀罪」創設検討 自民幹事長が言及自民党の谷垣禎一幹事長は17日、パリの同時多発テロ事件を受けて、テロ撲滅のための資金源遮断などの対策として組織的犯罪処罰法の改正を検討する必要があるとの認識を示した。改正案には、重大な犯罪の謀議に加わっただけで処罰対象となる「共謀罪」の創設を含める見通しだ。この日の党役員連絡会で、高村正彦副総裁が「資金源対策を含む国際条約ができているのに、日本は国内法が整備されていないために批准できていない。しっかりやっていかなければいけない」と指摘。谷垣氏も会議後の記者会見で「来年の伊勢志摩サミットでテロ対策に向けて、いろいろ考えなければならない」と述べた。2000年に国連で国際組織犯罪防止条約が採択された。日本政府は03年から共謀罪を創設するため、組織的犯罪処罰法の改正など関連法案を国会に出してきたが、世論や野党の反発で計3回廃案になっている。---テロ対策という錦の御旗を掲げれば、どんな法律も許される、というものでもないと私は思います。共謀罪というのは、実際に犯罪が行われていなくても、その謀議に加われば罪に問う、という性質の法律です。犯罪が行われなくても、というところがポイントで、つまり犯罪行為を行わなくても、それについて複数の人間が話し合って合意したら、それ自体が犯罪だ、ということです。非常にあいまいで、拡大解釈の余地が大きいのです。確かにテロ対策に有用ではあるのでしょうが、乱用される危険もまた大きい。薬として強力かもしれないけれど、毒としても強力すぎる。薬を誓わなくては命を落とす危険が高いのであれば、強力な薬を使うのもやむをえないとしても、病気のないところに抗がん剤を投与するようなことになったら目も当てられません。以前に、沖縄県知事選に「沖縄独立論」叫ぶ立候補予定者(結局は立候補しなかった模様)が現れた際、作家の竹田恒泰が、「内乱罪か内乱陰謀罪だ」と主張する出来事がありました。政府転覆の恐ろしい陰謀(笑)その際にも指摘しましたが、都知事選では、外山恒一候補が政見放送で「政府転覆の恐ろしい陰謀」を呼びかけたことがあります。もちろん、武力による政府転覆の具体的な準備が存在したわけではありませんから、竹田主張にもかかわらず、彼らはいかなる罪に問われることもありませんでした。公安が非公然の監視対象としたかどうかは知りませんけど。で、共謀罪が成立した場合、沖縄独立を主張しただけで共謀罪、ということは、いくら何でも不可能(武装蜂起というのでない限りは)ですが、政府転覆の恐ろしい陰謀の方は、犯罪に問われる余地はありえるでしょう。何しろ、具体的な行動を行わなくても、謀議しただけで犯罪だ、というのだから。実際にはこの程度のことで逮捕まではしないでしょうが、警察当局の胸先三寸次第ということになる。基本的人権に大幅な制限を、警察の裁量で大幅に認めることになりかねないような法案を、安易に認めることはとてもできません。
2015.11.17
コメント(7)
-
日本が標的になるべき、ということか?
サンデーモーニングに見る相も変わらぬ一国平和主義 11月16日テロを未然に防ぐのは、難しい。とはいえ、成功例はある。その一つが、2006年8月に、英国で発覚した航空機爆破テロ未遂事件だった。米国各地に向かう複数の旅客機を空中爆破する。この計画を事前につかんだロンドン警視庁は、イスラム過激派につながる犯人グループの逮捕にこぎつけた。警察や情報機関にとっては、威信のかかった捜査だった。その1年前、ロンドン中心部で起きた同時爆破テロで、52人が死亡している。国内のイスラム社会を厳しい監視下に置き、電話やメールの傍受まで行った成果だった。13日、パリで起きた戦後最悪の同時多発テロは、中東の過激組織「イスラム国」の犯行とみられている。パリといえば今年1月、風刺週刊紙が、襲撃を受けて記者ら12人が死亡する事件が起きたばかりだ。その教訓を生かせず、テロ計画を察知できなかったのは、治安当局の大失態ではないか。来年にサミット、5年後に五輪を控える日本にとっても、もちろん人ごとではない。昨日の朝、久しぶりにTBSの情報番組「サンデーモーニング」を見た。さすがに、テロ対策について、識者が意見を交わすものと期待していたら、当てが外れた。対策より、テロ組織との政治的な対話が大事だという。そもそも過激組織が勢力を伸ばすきっかけになったのは、米国のイラク攻撃、それを支持した日本にも責任の一端があるそうだ。果ては安保法制がやり玉に挙がった。フランスは米国とともに、イスラム国への空爆を続けている。日本が後方支援に踏み切れば、標的になってしまう。つまり、「テロとの戦い」から、脱落せよというのだ。相変わらずの「一国平和論」、フランス国民が知ったら、何を思うだろう。---例によってネトウヨ機関紙産経新聞の記事です。先日の投稿でも書いたように、日本はこれまで、イスラム過激派のテロの標的にはほとんどなってきませんでした。もちろん、ただ単に幸運な偶然という要素はありますが、イスラム圏と対立するような歴史的経緯がなかった、という要素もまた、決して無視できないでしょう。テロ対策というのは、2つのアプローチがあるように、私は思います。警戒を厳重にして、テロを起こさせないというのが1つ、もう1つはテロ集団との対立点をなくし、標的にならないようにすることです。警戒を厳重にしてと言っても、それですべてのテロを封じ込めることなどできるわけはありません。現に、フランスは1月のシャルリ・エブド襲撃事件以降、相当に警戒していたはずですが、今回のテロを防ぐことはできませんでした。要するに、警戒対象が多すぎて、そのすべてに対処することは物理的に不可能ということでしょう。サミットとかオリンピックのように、期間と場所がある程度特定されていれば対策も取れるでしょうが、いつ、どこが攻撃されるのか見当がつかない中で完璧な対策など、不可能です。産経が槍玉にあげるサンデーモーニングを私は見ていませんが、引用されている文面を見る限りは、全くそのとおりだと思います。もちろん日本がテロの標的となった場合の対策が必要なのは当然として、わざわざテロの標的にしてくださいと、名乗りをあげる必要がどこにあるのか。テロとの戦いから脱落もなにも、そもそもまだ参加もしていないものから脱落も何もないのです。イスラム国の台頭を許した背景には、欧米諸国の失策がいくつもあったことは歴然としています。単一ではなくいくつもの失策の積み重ねの結果ではありますが、中でも一番大きいのがイラク戦争だったことは明らかです。フセインは確かに凶悪な独裁者ではあったけれど、そのフセインが捕まって処刑されてイラクは安定したどころか、まったくその反対です。シリアでも事情は同じで、アサド政権がひどい独裁政権だというので(それ自体は事実でしょうが)米欧が反政府勢力に武器を供与してアサド政権を打倒しようとしたら、その武器を受け取って力をつけたのがイスラム国だった、というのがこれまでの流れです。で、そのイスラム国に対して、ヨルダンやトルコ、サウジアラビアなど周辺諸国、米国、フランス、ロシアまで一緒になって空爆を行っていますが、ここまでの経過を見る限り、軍事作戦によってこの地域からテロや紛争が消滅することは思えません。浜の真砂は尽きるとも、世に盗人の種は尽きまじ、は石川五右衛門の辞世と言われますが、テロリストも同じでしょう。イスラム国に対する空爆がどれだけ効果があるのか?仮に効果があるとしても、結局はイスラム国の力が衰えれば、それに代わって別の過激組織が台頭するだけです。軍事作戦は、確実に一般市民を巻き添えにし、それが軍事介入を行う諸外国に対する憎悪の拡大に結びつき、新たなテロを生み出し続けている。その方向性の「テロとの戦い」に未来も展望もありはしませんし、そんなものに日本が参加して、買わなくてよい憎悪を買う必要はないのです。
2015.11.16
コメント(4)
-

今日も演奏してきました
「エストレージャ・アンディーナ」にて、大和市渋谷学習センターで演奏してきました。何故かオカリナの発表会のゲストでした。この場所では2月・5月に続いて今年3回目の演奏です。こんなに同じ場所で演奏したのは、遠い昔、今は閉店した新宿のあるライブハウスに毎月出演していた頃以来(15年ぶり)です。いつもは5人編成なのですが、今日はメンバーの都合がつかず一人欠け、4人での演奏でした。そのため、普段あまり演奏しない曲が中心になりました。1曲目はチリのキラパジュンというグループの曲で「ククリの歌」Canto del cuculi、2曲目は「コーヒールンバ」です。Cuculiというのは、鳥の名なのですが、私のスペイン語辞書には載っていないので、どんな鳥か分かりません。が、グーグルで検索すると、日本のシラコバトあるいはキジバトによく似たハトの写真が大量に検索されます。↓Cuculi Chileで検索して出てきた画像です。ここからたどっていったところ、学名Zenaida melodaというハトであることが判明しました。写真から見て、キジバトかシラコバトとそっくりと思ったのですが、意外にもこれらとは別属でした。チリのキラパジュンの曲と書きましたが、アルゼンチンのカルチャキスというグループのアレンジを元にして演奏しています。(なおかつ、ギターのリズムはボリビアっぽくなっています)私はギターを弾いています。ものすごく簡単なコードなので、ギターを弾き始めたいちばん最初の頃からこの曲は弾いていました。もっとも、人前でこの曲を演奏したのは数えるほどの回数に過ぎませんが。2曲目のコーヒールンバは、日本でも西田佐知子やザ・ピーナッツ、荻野目洋子などがカバーしているので、ご存知の方も多いと思います。もちろん、本来はいわゆるアンデスのフォルクローレではなく、ベネズエラの、アルパ(ハープ)のための曲です。昔アラブの偉い お坊さんが~で始まる日本語の歌詞が付いていますが、ラテンの曲なのに、何故にアラブのお坊さん??コーヒールンバというのも日本でタイトルで、原題のMoliendo cafeは、「コーヒーを挽きながら」という意味です。そして、実はこのリズムはルンバではない、というおまけ付です。(そういえば、かのマツケンサンバも、実はまったくサンバではない)もともとはフォルクローレではないとはいえ、ケーナで吹かれることが多い曲ではあります。コーヒールンバのいちばんオリジナルの演奏は、おそらくこれだと思われます。ベネズエラのアルパ奏者、ウーゴ・ブランコの演奏です。アルパとベース、それにクアトロを使って演奏しているようです。意外にも、ギターは入っていないように聞こえます。それが、日本に入ってきたら、こうなった。もちろん、これ以外にもラテンアメリカでも様々なアレンジがあるし、オリジナルは器楽曲ですが、スペイン語でも歌詞が付けられています。元は同じ曲でも、ずいぶん変わるものです。
2015.11.15
コメント(5)
-
フランスで大規模テロ
仏パリで連続襲撃事件、少なくとも120人死亡フランス・パリで13日起きた連続銃撃爆発事件は、捜査当局によると少なくとも120人が死亡した。銃撃犯らが人質をとって立てこもっていた市内のコンサートホールには警察が突入し、容疑者3人を殺害したが、死者は約100人に上っているという。パリではこの日、市内3か所で相次いで襲撃が発生した。人質事件が起きたのは市東部にあるコンサートホール「バタクラン」で、午後11時35分ごろ、何者かが人々に向けて発砲した後、人質をとって立てこもった。目撃者の証言によると、発砲した銃撃犯の1人は、「アラーアクバル(神は偉大なり)」と叫んでいたという。同ホールは、1月に襲撃があったシャルリー・エブド本社から200メートルほどの距離にある。一方、サッカーのフランス対ドイツの試合が行われていた市北部にあるスタジアム「スタッド・ド・フランス」近くでも爆発があり、少なくとも3人が死亡した。当時スタジアムにはオランド大統領が試合を観戦していた。スタジアムにいたAFPの記者によれば、爆発音は2回聞こえたという。また、爆発の1つは自爆だったとの複数の情報がある。さらに、バタクラン・コンサートホールからほど近い場所にあるカンボジア料理店でも襲撃事件があったことが伝えられている。オランド大統領は、「かつてない規模のテロ攻撃がパリ周辺で起きている」と述べ、フランス全土に非常事態を宣言した。テロ対策専門チームが予備捜査を開始しており、イダルゴ・パリ市長は、市民らに外出を控えるよう呼び掛けている。---実に痛ましい事件が起こってしまいました。各マスコミ一斉に報道していますが、やはりフランスの通信社であるAFPがいちばん詳しいようです。コンサートホール、サッカー場、カンボジア料理店、3箇所で同時多発テロ、ということになります。犯人が何物であるかは不明ですが、記事中に「アラー・アクバル」と叫んでいたとの証言や、現在の国際情勢から考えれば、犯人がイスラム過激派である可能性はきわめて濃厚と思われます。イスラム過激派を装う偽装工作の可能性も皆無ではありません(イスラム過激派が何故カンボジア料理店を?というのも気にならないことはない)。とはいえ、3箇所同時にこれほどの規模のテロを行う動機、能力を持った集団が他にいるかというと、なかなか考え難いのも事実です。サッカー場にはオランド大統領がいた、とのことで、大統領を狙ったテロだったのかも知れません。コンサートポールで、どのようなライブが行われていたのかも気になるところです。それも、犯行の背景を知る手がかりの一つにはなるかもしれません。別報道によれば、オランド大統領は国境を封鎖したとのことですが、flightradar24によると、少なくともシャルル・ドゴール空港からは国際線が通常通り発着しているようです。(今、現地時間は深夜2時過ぎなので、便数は少ないけれど)ということは、陸路の国境だけ封鎖した、ということでしょうか。何はともあれ、犯人が何者でどのような背景によるのか、真相の究明が待たれます。もちろん、どんな背景があっても、許されるものではありませんが。それはともかく、もし犯人が予想どおりイスラム過激派だったとすると、日本にとっても、今後他人事ではなくなります。これまでのところ、イスラム過激派による日本を標的とした大規模なテロは起こっていません。日本人が巻き込まれたテロ(アルジェリア人質事件とか、ISによる後藤さん殺害事件とか)はあったけれど。日本は、中国韓国との間には、侵略によって被害を与えた歴史が歴然として存在するけれど、イスラム諸国との間には、そのような歴史がありません。だから、イスラム世界から日本が恨みを買うことはなく、従ってテロの標的になることもありませんでした。しかし、今後は分かりません。安保法案が成立してしまった今、米軍が抱える紛争に自衛隊の参戦を求められる可能性は非常に高くなりました。現在の世界の情勢から考えれば、派遣先は真っ先に中東である可能性が一番高い。イラクへの派遣のときは、自衛隊は「後方支援」ということで、戦闘に参加することはなく、1人も殺しも殺されもせずに任務を終了しました(かなり危うい場面はあったことが後に判明していますが)。しかし、次はそうはいかない。今度は後方支援ではなく、戦闘任務で派遣される可能性があり、そうなれば自衛隊が中東で戦闘に参加することになります。そのとき、イスラム過激派は確実に、日本もテロの標的に加えるでしょう。今はともかく、このまま行けば、10年後には我々日本国内に住む人間も、こういったテロに脅えながら生きていくことになりかねません。
2015.11.14
コメント(4)
-
看板を変えればよいというものではなかろう
「民主解党」岡田氏に要請へ=前原、細野、江田氏が一致民主党の前原誠司元外相と細野豪志政調会長、維新の党の江田憲司前代表が11日夜、東京都内のホテルで会談し、野党再編に向けて民主党が「解党」を決断すべきだとの認識で一致した。自民党に対抗し得る野党勢力の結集を一気に進めるのが狙い。前原氏らは近く民主党の岡田克也代表に申し入れる見通しだ。民主、維新両党は合流を視野に政策協議を進めているが、維新分裂の影響もあって停滞気味だ。維新の松野頼久代表は、民主、維新の双方が解党した上で合流すべきだと主張。これに対し、岡田氏ら民主党主流派は党の再建を優先し、解党に慎重な立場を崩していない。民主党内でも若手を中心に解党論が出ているが、前原氏ら保守派が表立って解党を求めれば、党内の路線対立が深刻化し、岡田氏の求心力低下につながる可能性もある。---自民党に対抗しうる野党勢力の結集、十数年前には、そういう掛け声で民主党ができたんじゃなかったでしょうか。政権とったけれど上手くいかずに崩壊して、賞味期限切れになったので新しい党を作ろうと、そういうことでしょうか。だけど、そうやって安易に政党の看板を架け替えても、どうせ中身は似たようなものです。遠からず賞味期限切れになって、また新しい党、ということになるのではないでしょうか。生きた実例があるではないですか。みんなの党→結いの党→維新の党→維新の党大阪組と泥沼の分裂劇の途中、という人たちが。それが正しいと信じるなら、解党論などといわずに自分たちが離党して、維新の党と合流すればいいのです。ところが、自分たちだけで行動する勇気はない(支持を得る自信がないのでしょう)から、他の人も巻き込もうと、解党なんて言っているのでしょう。私は、民主党にいろいろ批判がありつつも、衆院の小選挙区だけは、消去法的にやむを得ず民主党に票を投じたことが何回かあります。前回衆院選もそうでした。民主党政権時代、鳩山政権には、「自民党とは違う政策を目指す」という意思が感じられました。結果的に、何一つ成し遂げられませんでしたが。しかし、菅政権になると、自民党と違う方向性が極めて不鮮明になり(それでも、3.11以降の脱原発姿勢という明白な実績はありますが)、野田政権に至っては、自民党(安倍政権以外の、ですが)との差は何もない、看板だけが「民主党」という、何一つ期待できない政権になってしまいました。ところが、民主党への絶望の果てに生まれた安倍政権は、野田政権よりはるかにヤバかった。もはや民主党が自民党とは違う何かを行うだろう、なんて希望はかけらほどもありませんが、安倍政権よりはマシだろう、とは思います。しかし、前原や長島昭久、笠浩史といった連中が主導する新党が安倍政権よりマシかどうかは、非常に怪しい。彼らはいずれも集団的自衛権にも憲法改正にも賛成なので、安倍政権の安保政策との差などほとんどありません。民主党という、左派も含む雑多な集団の中では彼らの主張がすんなりとは通らないだけで、それを解党して、彼らが主導権を握って「新党」を作ったら、その党は安倍政権と何も変わらない右翼政党となるでしょう。今の民主党には、私は、消去法的にやむを得ずではあっても票を入れることはあります。しかし、そのような新党に票を入れることは、何があってもしないでしょう。
2015.11.13
コメント(2)
-

MRJ
国産旅客機・MRJが初飛行に成功 名古屋空港に着陸国産初のジェット旅客機MRJが11日午前、初飛行した。開発を担う三菱航空機が、愛知県営名古屋空港で最初の飛行試験に成功した。国産旅客機の開発は、プロペラ機YS11以来、半世紀ぶり。欧米の下請けに専念してきた日本の航空産業にとって節目となる。飛行試験は、自衛隊機など3機を伴って1時間半。名古屋空港と遠州灘上の自衛隊の訓練空域を往復し、上昇や下降、左右への旋回など基本的な性能を確認した。三菱航空機の親会社、三菱重工業の大宮会長は「初日としては大成功」と話した。2008年の開発本格化から7年半でたどり着いた初飛行は、設計変更や部品調達の遅れなどで当初予定から4年以上遅れた。今後の飛行試験は主に米国で重ね、課題の洗い出しと改善を進める。航空会社への納入は17年春に始める計画だ。燃費のよさと客室の快適さが特徴で、現時点の受注は6社から合計約400機。その6倍の2500機をめざす。この日飛んだMRJは約90席の機種で、別に約70席のタイプもつくる計画だ。リージョナルジェット(小型ジェット旅客機)の需要は、今後20年間に世界で約5千機と見込み、その半分を占める目標だ。MRJの開発には、日本の航空産業を自動車産業などと並ぶものづくりの柱の一つにしたい、という官民の狙いがある。現在、3千億円近い開発費用は、一部政府が負担。開発主体の三菱航空機には、三菱重工業だけでなく、トヨタ自動車や政府系の日本政策投資銀行も出資している。国産旅客機の開発はプロペラ機のYS11以来。政府が旗を振り、三菱重工などが関わったYS11は売れ行きが悪く、初飛行から11年後の1973年に生産終了に追い込まれた。日本の航空産業は、米ボーイングへの部品供給や自衛隊機の生産に特化してきた。この日飛んだ約90席のタイプは、カタログ価格が4730万ドル、巡航速度マッハ0・78、航続距離は最長タイプで3770キロ。全長は35・8メートルでジャンボの約半分だ。「リージョナルジェット」は地方空港と拠点空港などを結ぶことを想定した座席数100席以下の小型ジェット旅客機だ。この分野では、カナダのボンバルディアとブラジルのエンブラエルが世界2強。---飛行機大好き人間の私としては、大いに興味があるところですが、平日日中では見に行くわけにも行かず(というか、そもそも場所が名古屋だし)、帰宅後にYouTubeで初飛行の動画を見ました。なかなか美しい飛行機ですが、機種の形状が私の好みとはちょっと違うかな。そして、地上では前脚が低めで、ちょっと前かがみ気味のシルエットです。いずれにせよ、なかなか美しい飛行機ですね。ただ、初飛行は当初予定より4年遅れているのに、航空会社への納入は予定どおりに(それ自体、当初予定からはすでに遅れてはいますが)いくのでしょうか。これから様々な試験を行う中で、それがすべて順調にクリアできるのかどうか、何よりもFAAとEASAの形式証明が順調に取れるのかどうか、次第です。遅れる可能性も高いのではないでしょうか。そして、受注2500機が目標というのも、実現性はどうなのでしょう。先行するボンバルディアとエンブラエルを追い抜いて、世界の需要の半分のシェアを確保というのは、ほぼ夢物語と思います。ただし、それよりは少ない生産数でも採算は取れるでしょう。調べたところ、この種の旅客機の採算ラインは400~500機程度のようですから、現在の発注数400機でも、かなり採算ラインに近づいているようです。ただし、発注数約400機の内訳は、Wikipediaによると、確定223機、オプション164機、購入権20機とのことで、確定発注だけではまだ採算ラインには遠く及ばないようです。世界最大の巨人機エアバスA380では、生産の遅延から採算ラインが逃げていく(納入の遅れから、延滞料支払い義務が生じるため)現象が起きてたいます。MRJでも、納入が遅れると同じく採算ラインが上がっていくし、オプション発注が取り消される可能性も増すでしょう。ともかく、売れば売るほど赤字がかさんで、早々に生産中止となったYS11の轍は踏まないでほしいところです。それにしても、国産機とは言え、飛行機の心臓であるエンジンはプラット&ホイットニーなんですね。YS11もエンジンはロールスロイスでしたが。日本では、完全国産の旅客機用エンジンはまだ開発されていないのですが、日本も参加する合弁ならV2500があります。もっとも、V2500はMRJにはちょっと強力すぎるエンジンのようですが。ところで、初飛行の動画を見ると、平行して状況確認の飛行機が飛んでいるのですが、それが自衛隊のT4練習機というのはなぜなのでしょう。民間旅客機の開発という営業行為に自衛隊機を動員するのは、若干違和感を感じます。もっとも、公的資金を開発に投入しているのだから、まったくの民間事業ではない、とも言えますけど。
2015.11.12
コメント(2)
-
あの判決が見直されるようだ
<認知症男性事故>家族の監督責任巡り最高裁が弁論開催へ愛知県大府市で認知症の男性が徘徊中に列車にはねられて死亡し、JR東海が男性の遺族に振り替え輸送代など約720万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷は、遺族側、JR側双方の意見を聞く弁論を来年2月2日に開くことを決めた。認知症を巡る家族の監督責任の有無について年度内にも判断を示すとみられる。民法は、子供や知的障害者ら責任能力のない人の賠償責任について、親などの監督義務者が負うと定めている。2審・名古高裁判決は、遺族となった妻と長男のうち、妻の監督責任を認めた。これに双方が上告した。争われているのは07年12月に起きた事故。要介護度4の認定を受けていた認知症の男性がJRの駅構内で列車にはねられ、死亡した。JR側が「事故で列車が遅れ、損害が出た」として遺族を相手取って訴訟を起こした。1審・名古屋地裁判決は、同居して男性の介護に当たっていた妻が「まどろんで目を離した。徘徊を許した過失がある」と認定。別居中の長男も「介護方針や体制を決めていて、事実上の監督者だった」として2人に約720万円の支払いを命じた。2審は、長男について「監護すべき法的義務を負っていたとは認められない」と判断。妻については「夫婦のいずれかが徘徊の恐れを来すようになった場合には、(相手の夫や妻は)見守りの義務を負う」と指摘し、「監督義務者として対応が十分ではなかった」としつつも「介護体制の構築に努めていた」などと賠償額を約360万円に減額した。---この件については、以前に記事を書いたことがあります。この判決は暴挙である各方面から批判が多かった判決ですが、最高裁はこの判決を見直すようです。ちょっと前にも書きましたが、最高裁が弁論を開くということは、原判決を見直すということです。もちろん、どう見直すのかは分かりませn。しかし、一審判決の方向、つまり賠償額を増額する方向への判決見直しは、まさかしないだろうと思います。被告側の責任を軽減する、あるいは責任を否定する方向への見直しでしょう。であれば、望ましい方向への変化と見ることができます。下級審で先進的な判決が出ても、最高裁ではそれが覆される、というのが、これまで散々繰り返されてきた裁判の歴史ですが、先日の選択的夫婦別姓制と女性の離婚後再婚禁止期間をめぐる裁判と今回の裁判は、例外的に下級審現状追認的判決を最高裁が見直す、ということになりそうです。これは、稀有の例かもしれません。もちろん、何度も書くように、どの程度見直すのかは定かではありませんが。以前の記事にも書きましたが、当時80代の妻がまどろんで一瞬夫から目を離したのが過失だと言われても、人間の能力を超えた要求としか思えません。また、この手の、徘徊癖のある認知症は、介護施設でも敬遠しがちなので、施設にも簡単には入れない場合が多いものです。それにしても、この裁判のことは別にして考えても、高齢者の介護というのはなかなかに難しい問題です。この被告の家族の場合、結果としてみれば、徘徊壁のある夫をベットに縛り付けでもしておけば、こんなことは起こらなかったわけです。が、それは結果論であって、実際にそうしていたら、高齢者虐待と指弾されることだってありえるわけです。施設でも同様です。身体拘束はしばしば批判の的となる。確かに、常軌を逸した身体拘束や、まして虐待は論外としても、多くの介護施設は、出入り口の閉鎖くらいは少なくともやっています。それを悪いと言えるのかというと、やはりそれは難しいです。そういう意味では、本当に、この問題は解決策がない。被告の家族にしても、最高裁では逆転勝訴になったとしても、これまでに費やしたであろう労力と時間、心理的負担には、何の見返りがあるわけでもありません。なかなか救いの見出しにくい話です。
2015.11.11
コメント(2)
-
こだわるべきは、そこではないだろう
「13%援助交際」に抗議=国連報告者の発言―外務省外務省は9日、日本の児童ポルノなどの状況を視察するため来日した国連特別報告者が東京都内で開いた記者会見で、「(日本の)女子学生の13%が援助交際している」と発言したことに対し、抗議し撤回を求めたと発表した。発言したのは児童売買や児童ポルノなどに関する国連特別報告者で、オランダ出身のマオド・ド・ブーア・ブキッキオ氏。10月26日に日本記者クラブで会見した。発言を受け、外務省は今月2日に国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)に「数値の根拠を開示すべきだ」と抗議。これに対し、OHCHRは「数値は公開情報から見つけた概算」であり、緊急に対応すべき事象だという点を強調するために言及したと釈明する声明を出した。しかし、外務省は数値の根拠が明らかになっていないことから7日に、「国連の肩書を持つ者が発言することで事実かのような誤解を生む」として発言撤回を求めた。---なんだか、最初は「30%」という数字が報じられていたような気がするのですが、どうもそれは通訳の間違いらしく、実際は13%と発言しています。更に、13%が「援助交際」(売春行為)を行っているといっているのではなく、表面的には無実に見えるが、より深刻な事態に至るリスクのある行動(JKお散歩など)が13%と言っているようです。このあたり、私の英語力は全然ダメなので、こちらのサイトを参考にしました。13%がウソだというなら、では何パーセントなら事実なのですか?実際のところは、はっきりした数字は誰も知らないのでしょう。様々な推計はありますけど、別のソースによれば「13%」は実態に即しているのかどうか。複数の女子高生支援団体に取材したが、「もっと多い」「ずっと少ない」と意見が割れた。のだそうです。意見が割れたということは、関係者の中でも定説はない、13%は確実に過大な数字だとは断定できない、ということです。もちろん、地域差、学校ごとの差もあるだろうし、世帯の年収にも左右されるでしょう。だから、全国平均の数字を出すことは難しいだろうと思います。いずれにしても、問題の本質はそこですか?13%が、実際にはその半分だったとしたら、何も問題はないのでしょうか。マオド・ド・ブーア・ブキッキオ氏が提起した、未成年女性に対する性的搾取の問題は、数字がもし間違っていたら全部事実無根なのでしょうか?問題視すべきは、13%という数字が正しいか否かではなく、「JKビジネス」なんてものが存在して、未成年者の性的搾取が少なからず存在する、というそのこと自体でしょう。そこを何もいわず、13%という数字だけを問題視するのが日本政府だとしたら、要するに日本政府はこの問題にまじめに取り組む気などない、13%という無根拠(?)な数字という「国家の体面」だけにしか興味がない、そういう政府だ、ということなのでしょうか。
2015.11.10
コメント(4)
-
主張の変遷はお互い様というもの
公明VS共産、「平和の党」めぐりバトル再燃 志位氏のツイッター攻撃に山口氏が応戦 「9条反対したのはどの政党だ?公明党と共産党が対決姿勢を鮮明にしている。支持層が重なり合う両党は古くから党員獲得などで激しく争ってきただけに、怨恨は根が深い。そうした中で、共産党が提唱する野党政権「国民連合政府」構想に公明党の石田祝稔政調会長がかみつき、バトルが再燃した。「平和」を看板に掲げる両党だが、こと互いの関係にいたっては党是を推進するわけにはいかないようだ。10月25日のNHK討論番組が終盤にさしかかり、共産党が呼びかけた野党連携に関する議論の途中、石田氏が「ちょっと一言」と手を挙げた。「50年も60年も自衛隊は違憲とか、日米安保廃棄と言っていたのを脇に置いて選挙で一緒にやりましょうというのはおかしい」共産党の小池晃政策委員長に対する突然の“宣戦布告”だった。~小池氏は「今は意見の違いは脇に置いて安倍晋三政権を倒すために野党は力を合わせるときだ」と述べ、同席した民主党の細野豪志政調会長らに向けて選挙協力を呼びかけた。これに対し、石田氏は「脇に置いて、というものじゃないでしょ」と食ってかかり、小池氏が「憲法を守らない政権を倒すためには緊急課題で団結するのが政党の責任だ」と反論している間も「おかしい、おかしい」とまくしたてた。~安保関連法が国会で審議されるようになり、共産党は選挙の主要争点に据え、与党を攻撃。今年8月の仙台市議選では、山下氏が「公明党支持者の中に戦争法案に強い危機感を感じる方が多いことも明らかになっており、その気持ちをくんだ運動を発展させたい」と仕掛けると、公明党の山口那津男代表は「各政党の支持団体などについて、他の政党がとやかく運動に取り込む姿勢はいかがなものか」と不快感をあらわにし、そして、こうやり返した。「共産党は今の平和憲法の制定時、肯定される戦争があるということで憲法9条に唯一反対した政党だ。自らの主張をよく顧みていただきたい」ただ、共産党は仙台市議選で3選挙区トップ当選を果たした上、10月の宮城県議選でも議席を8に倍増させて県議会第2党に躍り出るなど支持を広げている。石田氏の共産党批判は、公明党内で強まる警戒感の裏返しともいえる。~「共産党の目的は体制の転覆だ。かつて民主党に政権を委ねたときのような気持ちで、共産党に期待をかけてはいけない」---現状、共産党の攻撃対象はもっぱら安倍政権そのものであり、公明党は自民党の補完物でしかないから、今は主な標的とはしていないように見えます。今回の件は、明らかに公明党の側から共産党に攻撃を仕掛けています。しかし、歴史的経緯から考えれば、産経新聞の指摘するように、共産党と公明党は激しく対立してきたことは歴然たる事実です。攻撃されれば、共産党も黙ってはいない、猛反撃に出るのは、当然の成り行きでしょう。私は、どちらの党の地方議員とも付き合いがありまして、主義主張は一切度外視して、人柄や「街中の困った出来事」への対応という点では、公明党の議員はいい人たちばかりです。もちろん、共産党もそうですが、共産党には、若干癖のある人もいるなと、票の半分は共産党に投じているにもかかわらず、そんなことを思ったりもします。でも、だからと言って公明党の主義主張を是とすることは、私にはできませんけど。共産党が、かつて日本国憲法の制定時に憲法第9条に反対していたことは歴然たる事実です。9条の政府解釈の変遷について、私が中学生の頃、憲法制定時点での吉田茂の国会答弁が社会科の教科書に載っていました。「コノ憲法草案ニ戦争一般放棄ト云フ形デナシニ、我々ハ之ヲ侵略戦争ノ放棄、斯ウスルノガモツト的確デハナイカ」(共産党野坂参三議員質問)「近年ノ戦争ハ多ク国家防衛権ノ名ニ於テ行ハレタルコトハ顕著ナル事実デアリマス、故ニ正当防衛権ヲ認ムルコトガ偶々戦争ヲ誘発スル所以デアルト思フノデアリマス」(吉田茂首相答弁)つまり、当時は共産党が「侵略戦争は放棄すべきだが防衛戦争は放棄すべきではない」と主張し、それに対して吉田茂は、「戦争はみんな『防衛』という名目で始まるんだから、防衛戦争だって禁じなければダメだ」と答えていたわけです。その時代と現在で、共産党の主張が180度変わっているのは事実ではあります。が、それを言うなら吉田茂の主張も180度変わっている。だって、1950年警察予備隊、1954年自衛隊を創設したのは、同じ吉田内閣なんだから。日本国憲法制定時点では、共産党以外のすべての議員が、これに賛成票を投じたのです。当時の保守政党である日本自由党、日本進歩党も含めてです。それが、1955年にこれらの保守政党が統一して自民党になったときには「自主憲法の制定」が党是になる。主張を変えたわけです。それでも、所属する議員はともかく、政党としての自民党は、結党のときから一貫して憲法改正を主張していますが、公明党はどうなのか。「50年も60年も自衛隊は違憲とか、日米安保廃棄と言っていたのを脇に置いて選挙で一緒にやりましょうというのはおかしい」だそうですけど、公明党自身、かつては自衛隊は違憲の疑いが強いと言い、日米安保も破棄と言っていました。それが1981年に、日米安保も自衛隊も原発も全部認める政策変更を行った。50年も60年も自衛隊は違憲とか、日米安保廃棄と言っていたのを脇に置くのはいけないけど、10年20年ならいいのか?そういうものでもないでしょう。その公明党は、憲法に関して「加憲」という考え方を取っているそうです。「加憲」の具体的内容は知りませんが、自民党の、あの凄まじい憲法改正草案と同じなのでしょうか?そう聞けば、公明党の「加憲」は、あのような内容ではない、という返事が返ってくるはずです。だとすると、国家のあり方を規定するもっとも根源的な規定である憲法に対する考え方が全然違っても、その違いを「脇に置いて」自民党と公明党は連立政権を組み、選挙も共闘しているわけです。それがよくて、共産党と民主党(あるいは社民党や生活の党)の共闘がいけない、という理屈は成り立たないでしょう。「共産党の目的は体制の転覆だ。」とは、まるで産経新聞みたいな言い草です。私は確信を持って言いますが、山村工作隊の時代じゃあるまいし、いまの共産党が体制の転覆なんて考えているわけなかろう。浮いたり沈んだりしつつも、まあまあ維持されてきた党勢を、そんな危険かつ成功の確率の低い(というか、ほぼゼロの)バクチで一挙に失うようなリスクを、秀才ぞろいの党官僚たちが冒すわけがない。憎さのあまり、目が眩んでいるとしか思えません。まあ、本音でそう思っているというより、プロパガンダの一種でしょうけど。
2015.11.09
コメント(4)
-
歴史的会談
初の中台首脳会談 関係の平和的発展を確認中国の習近平国家主席と台湾の馬英九総統が、1949年の中台分断後初めてとなる首脳会談を、シンガポールでおよそ1時間にわたって行い、「中国大陸と台湾はともに1つの中国に属する」という考え方とともに、中台関係の平和的な発展が重要だと確認しました。~会談の冒頭、習主席は馬総統を総統の肩書きではなく「さん」付けで呼び、歴史的な会談だとしたうえで、「平和の道を歩み、正しい発展の方向性を確保し、交流を深めて、中華民族の復興を図ることを願っている」と述べました。馬総統も「習さん」と呼びかけ、中台の間では経済や人的交流が進んでいるとしたうえで、「両岸の関係は過去66年間で最も平和的な状態にある。双方は敵対関係を弱め、平和的な方法で争いを解決していくべきだ」と応じました。また、両首脳はそれぞれ、「中国大陸と台湾はともに1つの中国に属する」という考え方とともに、中台関係の平和的な発展が重要だと確認しました。会談後、記者会見した馬総統は、「いい雰囲気で、平和的な発展について意見交換ができた」と述べたほか、習主席について、「習さんは実務的で率直な人だということが分かった」と話していました。一方、中国政府の高官も会談後の記者会見で、「率直で突っ込んだ意見交換を行った」と述べ、双方とも、歴史的だとした会談の成果を強調していました。習主席「最大の脅威は台湾独立訴える勢力」~この発言は、来年1月に行われる台湾総統選挙で優勢が伝えられる最大野党・民進党の候補が「中国大陸と台湾はともに1つの中国に属する」という考え方に反対していることなどを念頭に、けん制したものとみられます。一方で、張主任は「国務院台湾事務弁公室は、台湾の選挙には介入しない」と述べました。台湾の台北では、7日午後、首脳会談の中止を求める抗議活動が行われました。抗議活動には、馬英九政権が進めてきた中国との結びつきを強める政策に反対する人権活動家や環境保護活動家などおよそ500人が参加し、「ひとつの台湾、ひとつの中国」と書かれたプラカードや「台湾独立」を目指す横断幕を掲げるなどして、首脳会談の中止を求めていました。~---昨日の友は今日の敵、昨日の敵は今日の友。中国の国民党と共産党は共闘したり対立したりを繰り返してきました。もともとは、1920年代の国民党蒋介石総統は、軍閥との戦いのためにソ連の援助を求め、誕生したばかりの共産党との共闘を進めましたが(第1次国共合作)、1925年、北伐によって軍閥に大きな打撃を与えると、1927年には一転して共産党を弾圧(4.12事件)、しかしその後日本軍の中国侵略が激しくなると、西安事件を契機に、再び共産党と共闘(第二次国共合作)したものの、日本軍の降伏後に再び国共合作は破れて、国共内戦となり、共産党が勝利して中華人民共和国成立、国民党は台湾に逃れて中華民国を名乗り続ける、という経過をたどったことは、よく知られているとおりです。それ以来、国民党と共産党(中国と台湾)は、長らく対立を続けてきましたが、国際的には、当初は旧東側は中国支持、西側は台湾支持だったものの、中ソ対立によって中国は東側の中で孤立する一方、1972年のニクソン訪中以来、西側との関係を劇的に改善、台湾はほとんどの国から外交関係を切られ、国際的孤立を深めて行ったのがこれまでの状況です。※引用記事には「1949年の中台分断後初めて」とありますけれど、実際には、更に遡って1945年の重慶会談で蒋介石と毛沢東が会談して以来。ということになるのではないかと思われます。(当初、「1936年の西安事件の際、張学良に捕らわれた蒋介石が共産党の周恩来と会談して以来」と書きましたが、コメント欄でBill McCrearyさんにご指摘いただきました)。政治的には対立しつつも、経済的には中国の経済発展に伴って、関係は深まる一方であり、もはやお互いに切っても切れない関係になってしまっているのが現実でしょう。私のパソコンは自作機なんですけど、マザーボードはASUS製です。ASUSは台湾の企業ですが、工場は、おそらく中国にある。そんな例は、掃いて捨てるほどあるでしょう。中台間の直行便は2008年は初めて解禁されたけれど、今では1日に何十便飛んでいるのか、台湾を訪れる中国人の数も、凄まじい数に登っているようです。(日本を訪れる中国人だってこれだけ多いのだから、もっと近くて言語が同じ台湾を多くの中国人が訪れるのも道理でしょう)そういった中で、遅ればせながら政治もまた経済の後を追って、両国間のトップ会談がなったのは、喜ばしいことです。もちろん、だからと言って台湾が中国の一部になることを、台湾は認めないだろうし、中国もそれを求めはしないでしょう。実質的には台湾は独立国のようなものであり、その状況は今後も続くのだと思います。次の総統選挙では民進党が勝つかもしれませんが、民進党の前回政権時のことを考えても、独立をにおわす政策くらいが限度で、それ以上のことはしないでしょう。昨日の友は今日の敵、と言えば国民党と日本の右派の関係も同じで、第二次大戦中はもちろん敵、しかし戦後は一転して、中国(共産党)という「共通の敵」の存在から日本の右翼は国民党と深いつながりを維持し続けてきました。日中国交回復後も、自民党内のは、親台派というものが隠然として存在した。その時代の「親台」とは、いうまでもなく国民党の台湾です。だって、当時の台湾はまだ国民党一党独裁の時代ですから。しかし、時代が更に変わって現在のなると、ネトウヨのみなさんは国民党は中国の手先、みたいな見方で凝り固まっているわけです。時代が変わると、敵と味方も変わる、ということなんでしょうね。では、日本のネトウヨは民進党の味方か、というと、まあ今はそうかもしれませんが、多分体質的にはまったく違うのだろうと思います。おそらく、これまた、「大陸がにくい」という点以外に一致点がありそうにない。日本のネトウヨがいちばん喜ぶのは、金美齢とか、李登輝なのでしょうが、彼らは台湾国内で支持があるわけではありませんからね。
2015.11.08
コメント(4)
-
大日本と小日本は表裏一体
特集ワイド:続報真相 いびつな「大日本病」(要旨)人はホメられて成長する−−というが、国家の場合はどうなのだろう。テレビは外国人に日本をホメさせて「日本は世界から尊敬されている!」と自賛する番組だらけ、書店には日本礼賛本と中国・韓国をけなす本が並ぶ。一定の需要があるのは「日本は他国よりすごい」という大国意識、優越感に浸りたい願望なのか。最近の社会・政治状況を「大日本病」と名付けて憂えているのは戦史研究家山崎雅弘さん。新刊「戦前回帰『大日本病』の再発」が波紋を広げている。「教育勅語と我等の行道」(1935年)・「国体の本義」(37年)・「万邦に冠絶せる我が国体」(38年)・「臣民の道」(41年)。「自国を賛美する現在の社会状況や政治状況は、これらの本が出版された時代の風潮と似ています」と山崎さんはいう。これらは総じて「天皇を頂点とする日本の国家体制は『世界に類を見ない神聖で崇高な国のあり方』(万邦無比)とし、体制存続のみに価値を置き、献身と犠牲をいとわないのが国民の務めで、人権や個人主義の考えは欧米的だ」という考えである。国家神道は教育勅語の「危急のことがあれば、国民は公に奉仕し、永遠に続く皇室を助け支えよ」という教えも取り込み、国民や兵士の命を軽視した戦争を続ける原因になった。自国を独善的・排外的に偉大な国として存在価値を膨らませ、他国・他者に不寛容で、個人主義や人権を軽視する状況が、山崎さんのいう「大日本病」である。過去の話に見えるが、今も同じではないか。「一連の動きから見えてくるのは、国家神道的な価値観をよしとする体制への回帰です。安倍首相は戦後レジームは否定しますが『戦前・戦中レジーム』には特に否定的な言及はしません。歴史上、この国を唯一、滅亡の寸前まで追いやったのが、その戦前・戦中レジームなのですが」ヘイトスピーチ団体の取材を続けた安田浩一さんは「戦前回帰」とは少し違う見方。「『日本が大好き!』と声高に叫ぶ人が増えていますが、彼らは中国・韓国など他国、他民族をけなし、排他的な言説をセットにしているんです。他者をおとしめることでしか自国への愛を確認できない。」日本が他国に優越するという考えは、国益のために他国に政治・軍事的影響力を行使してよい、という大国主義の下地。「その意味では、彼らの優越感は大国主義に近いのですが、一方では内向き。まだ受け入れてもいないシリア難民を敵視・蔑視する言説が広がっているし」標的は外国人だけでなく、最近は仮設住宅の被災者に、国に依存するなと罵声を浴びせたり、水俣病患者団体関係者に『いつまで国に甘えているんだ』と電話を掛けたりしている。共通するのは「奪われている」という感覚。領土が他国に奪われている、社会保障が奪われている……。山崎さんは「日本ブランド」をまとって自分の存在価値を高めたい人が、日本が批判されたり、国のお金が他者に使われると「自分が批判され、損をした気になるのでは」と。安田さんは「『領土が奪われている』と言いながら、現に米軍基地として土地を奪われている沖縄県民が基地反対運動をすれば『売国奴』という言葉を投げつける。彼らにすれば、沖縄すら排他の対象。自分だけが正しい、美しい、尊敬されたい、という感情しかない。」という。山崎さんは「キーワードは不安」と言う。国家神道が強調されたのは、満州事変後(33年)頃からで、国際的孤立で国民の不安が高まった時。人口減や景気停滞、原発事故や中国や韓国の経済成長、不安が高まる今と重なる。国と自分を重ね、「万邦無比」といった「大きな物語」に自分が連なるという幻想を抱けば、自分の価値を再確認でき、不安も軽くなるわけだ。山崎さんが言う。「自分の価値観を内面に持ち、一人一人が独立した思考を持つ『個人』でいられるかどうかが、いびつな『愛国』や『大日本病』を克服できるかどうかのカギです」耳に心地よい礼賛や、繰り返される「愛」に気をつけたい。---大日本主義のキーワードは不安、というのは、おそらくそのとおりなのだろうと思います。言い換えれば、「大日本」願望とは、日本が小日本になりつつある現実の裏返し、ということではないでしょうか。かつて、日本が上り調子で経済成長を遂げていた時期、「日本はよい国、世界一の国」なんて言説は、(皆無ではありませんが)さほど影響力はありませんでした。むしろ、日本は欧米諸国よりこんなに遅れている、こんなにダメな国だ、という言説のほうが一般的でした。国士様連中にとっては、そういうのは「日本を貶める言説」ということになるのでしょう。しかし、「遅れている」というのは進めなければならない、ということでもありますから、欧米に追いつき、追い越せ、という向上心の現れ、ともいえます。一方、「日本はすごい、世界一」というのは、一見すると耳に心地よいものの、「もうこれ以上向上の余地はない」ということでもあります。人は、上り調子のときには、「俺はこんなにすごい人間だ」なんてことは、あまり言わないものです。むしろ、下り坂になってきたときに、過去への郷愁、虚勢、そういったものから、自分を大きく見せようとしたがるのです。それが、人間というものの持つ性というものでしょう。つまり、「日本はこんなにすごい国」という言説は、日本が下り坂になっている、という現実の証明である、ということです。あえて言えば、過去の遺産を誇っているだけです。遺産は立派だが、それを築いたのは、誇っている本人ではありません。もちろん、私は生まれてこの方、ずっと日本に暮らしてきて、この国をおおむね気に入っています。日本が、「ある側面において」(それも、結構多くの側面において)世界有数のよい国であることを否定しようとは思いません。けれども、物事には様々な側面があります。何の欠陥もない理想郷などというものは、この世に存在するはずもなく、もちろん日本だって同様です。逆に、どんな国でも、よい側面の一つや二つはあるものですよ。いずれにしても、にほんのすばらしい側面は、別に私が造ったものではありませんから、私の誇り、ではありません。「日本ブランドをまとって自分の存在価値を高めたい人」というのは、実に言い得て妙と思うのですが、要するに自分自身に誇るものがないから、自分の属する属性(日本という国)を誇るのでしょう。自分自身であれ、自分の属する国であれ、自分自身のもつ思想であれ、ある程度の客観性を持ってそれを見る視点がなければ、人間は正常を保てるものではないと私は思います。客観性を失い、自分がすべて正しい、他者がすべて間違っている、となったとき、人は暴走を止められなくなる。これは、もちろん日本国内のネトウヨだけに限った話ではありませんけれど。
2015.11.07
コメント(4)
-
廃炉にすべし
「もんじゅ」巡り異例の勧告 “改善見られず決断”福井県にある高速増殖炉「もんじゅ」を巡り原子力規制委員会は、今の日本原子力研究開発機構に運転を任せるのは不適当だとして、原子力機構に代わる運営主体を明示するよう文部科学大臣に異例の勧告をすることを決めました。原子力規制委員会の田中俊一委員長は会見で「納得できるような改善が見られないということがいちばん大きかった。勧告をせずに進めるのが望ましいと思っていたが、理事長の話などを聞き、安心して任せるわけにいかないと判断し、勧告を出すことを決めた」と述べました。今回異例の勧告に踏み切ることになった理由については、4日の原子力規制委員会で田中俊一委員長は「日本原子力研究開発機構はもんじゅを運転していない状態での保安措置が適切にできておらず、運転するための基本的な能力を持っているとは認めがたい。これは、これまでの長期的な経緯を踏まえた判断だ」としています。そのうえで、もんじゅの特殊性にも触れ、「もんじゅは日本では経験のない新しいタイプの原子炉であり、原子力機構には研究開発の能力などの長所があるという主張もあったが、それをもって運転を任せるわけにはいかない。ナトリウム漏れ事故から20年間、ほとんど施設が動いていないなか、文部科学省が相当の取り組みをしてきたにもかかわらず、問題は解決しておらず、こういった状態をいつまでも放置しておくべきではない」と述べました。(以下略)---高速増殖炉「もんじゅ」の危険性については、だいぶ以前に何回か記事を書いたことがあります。ここにも危険きわまりない原発が運転開始から4ヵ月後にナトリウム漏れによる火災事故を起こし、それによる長期間の運転停止期間を経て、運転再開後今度は3ヶ月で、燃料交換時に原子炉内で燃料を仮置きする装置(炉内中継装置)の落下事故を起こしてしまった。つまり、ほとんどまともに稼動したことがありません。「今の日本原子力研究開発機構に運転を任せるのは不適当」という判断は、まったくそのとおりだと思いますが、ではどの組織に運転を任せるのが適当か、ということになります。もともと「もんじゅ」は動燃(動力炉・核燃料開発事業団)が運営主体でした。しかし、ナトリウム漏れ事故とその後の対応によってその組織体質が問題となり、動燃は解体されて、新たに設立された原子力研究開発機構が運営主体となりました。つまり、動燃がダメだからと設立された原子力研究開発機構も、やっぱりダメだった、ということなのです。なぜそうなのか?おそらく、一つには、動燃とか原子力研究開発機構といった個別の組織ではなく、日本の原子力業界全体に欠陥が存在するということ、もう一つには、高速増殖炉が、技術的にとてもまともに使いこなせるような代物ではない、ということなのでしょう。原子力業界がいかに腐り果てていても、原子力の素人が原発を動かせるわけがありません。従って、もしも原子力研究開発機構を取り潰して、新しい運営主体を設立したとしても、問題は解決せず、結局は同じことの繰り返しにならざるを得ないのです。二度あることは三度あるものです。技術的に見ても、そもそもナトリウムは水や酸素に触れるだけで発火する、という危険極まりない性質を持っています。その時点で、高速増殖炉の危険性は、通常の原子炉と比べても比較にならないくらい高いものです。1995年のナトリウム漏れによる発火事故は、平時における単純なナトリウム漏れだったから対処できたものの、あれが地震や津波など自然災害に起因するナトリウム漏れだったらどうか。当然、計器類の破損や電路、配管の寸断などを伴うことになり、手の施しようもない状況に至ったであろうことは疑いありません。何しろ、福島でやったように、水をかけて冷却ということができないんだから。この二つの側面から考えて、原子力機構に代わる運営主体を作ったところで、それで「もんじゅ」が使いこなせるとは思えません。我々人類の現在の技術水準では、とても使いこなせないようなものを作ってしまった、ということに尽きるのです。だから、こんなものは廃炉にする以外の選択肢はありません。多分、原子力規制委員会も分かっているのではないかと思うのですがね。
2015.11.05
コメント(5)
-
夫婦別姓と再婚禁止規定
夫婦別姓と再婚巡る規定 最高裁きょう弁論夫婦別姓を認めない民法の規定と、女性のみに離婚後6か月間再婚を禁止する別の規定が憲法に違反するかどうかが争われている2つの裁判で、最高裁判所は4日に弁論を開きます。判決は早ければ年内の見通しで、明治時代から続く規定の見直しの議論につながるかどうか注目が集まっています。民法には、夫婦別姓を認めず同じ姓にするという規定と、子どもの父親が誰なのか争いになるのを防ぐため女性のみに離婚後6か月間再婚を禁止する規定があります。これらの規定の見直しを求める人たちがそれぞれ起こした2つの裁判で、最高裁判所は4日、15人の裁判官全員による大法廷で弁論を開きます。2つの裁判では、原告側が男女平等などを保障した憲法に違反するなどと主張しているのに対して、国側は規定には合理性があり憲法に違反しないなどと反論しています。2つの規定は明治時代に定められ、平成8年に国の法制審議会は、夫婦別姓を選べるようにすることや再婚禁止の期間を100日に短縮することを盛り込んだ民法の改正案を答申しましたが、与党内で反対する意見があったことなどから改正は行われていません。最高裁は早ければ年内にも判決を言い渡す見通しで、明治時代から続く規定の見直しの議論につながるかどうか注目が集まっています。 ---最高裁は、原判決(高裁の判決)をそのまま維持する場合は法廷を開きません。「上告理由にあたらない」という理由で上告棄却で終わりです。それも、民事裁判では公判すら開かれず、判決文が出されておしまいです。最高裁が弁論を開くということは、つまり原判決を見直す、ということです。この裁判の場合、高裁の判決(地裁の判決も)は夫婦別姓を認めない規定も女性のみに離婚後6ヶ月の再婚禁止期間を設けることも、憲法違反ではないという判決でした。この判決を最高裁が見直す??それはよい意味で驚きです。大法廷で開くということは、何らかの憲法判断を行う、ということでしょうから。もちろん、この判決のすべてを見直し、原告の言い分をすべて認める-というところまで大幅な変更をするとはとても期待できません。どこの部分をどの程度変更するつもりなのか、大いに興味あるところです。私自身は、相棒が姓を変えて私の姓を名乗っているし、そのことに特に不満を抱いているわけではないのですが、知り合いを見回すと、本当は別姓にしたいけれど、夫婦別姓が認められていないため、やむを得ず妻が姓を変えている(夫が姓を変えた例もありますが、少ない)という夫婦が何組もいます。選択的夫婦別姓を認めない理由はないと私は思います。離婚後6ヶ月の再婚禁止規定も同様です。「子どもの父親が誰なのか争いになるのを防ぐため」というのですが、現実問題として、離婚届を出すその日まで、夫婦としての実質的な生活が維持されている、なんて例はかなりまれであり、たいていの場合は、実質的な夫婦生活が破綻した、その後で離婚届は出されるものです。つまり、離婚届を出した直後に女性が妊娠したとして、その父親が前夫である可能性より、そうではない可能性のほうがはるかに高いことは確実です。今は、そのことをDNA鑑定によって調べることも可能であり、女性のみに課す再婚禁止期間規定などというものは、DNA鑑定のなかった時代の遺物の規定に過ぎないと私は思います。このような時代遅れの規定によって、生まれてくる子どもの(戸籍上の)父親を、本当の父親ではない前夫にしてしまうことは、誰の利益にもなりません。生まれてくる子どもにとっても、生んだ母親にとっても、そしてもちろん「父親」にとっても。だから、女性のみの再婚禁止規定など、完全撤廃すべきなのですが、果たして最高裁がそこまで踏み込めるかどうかは、あまり期待しないほうがよいかもしれません。
2015.11.04
コメント(4)
-
「寿司職人が何年も修行するのはバカ」か?
ホリエモン「寿司職人が何年も修行するのはバカ」発言 数か月で独り立ちの寿司はうまいか?寿司職人として一人前になるためには「飯炊き3年、握り8年」の修行が必要、などという話があるが、堀江貴文さんがツイッターで、問題なのは職人としてのセンスであり「何年も修行するのはバカだ」と切り捨てた。寿司職人になるためには修行をするのはナンセンスで、料理学校に数か月間通えばなれるものだし、自己流でやっている人もいる、というのだが本当だろうか。ホリエモンは2015年10月29日にツイッターで、寿司職人に関してバカなことを書いているブログがあると指摘し、「今時、イケてる寿司屋はそんな悠長な修行しねーよ。センスの方が大事」とつぶやいた。フォロアーからご飯を炊く時の水分調節やシャリを握るのはそう簡単に会得できるものではない、と意見されると、「そんな事覚えんのに何年もかかる奴が馬鹿って事だよボケ」と返した。長い期間の修行や苦労によって手に入れたものは価値がある、というのは偏見であり、寿司職人の修行というのは若手を安月給でこき使うための戯言に過ぎないというのだ。ホリエモンは2014年12月26 日にYouTubeで、コロンビアに寿司店を出したいという男性からの相談に答え、その中で寿司職人になるには10年くらいかかると言われてきたけれど、半年くらいでプロを育成する専門学校も出来ている。長い期間修業が必要なのは「1年間ずっと皿洗いしていろ」などと寿司作りを教えないから。今は独学で寿司を出したり、短期養成の専門学校に行って寿司職人になる人が増えている、問題は寿司を作る人のセンスだ、などと語った。~大阪が本社の「3ヶ月で江戸前寿司の職人になる」と看板を掲げた専門学校に話を聞くと、「授業は厳しいですが、3か月で海外に店舗を出した生徒さんもいるなど、短期間で寿司作りから経営まで学ぶことはできます」と説明した。~ダシの取り方、魚のおろし方、魚の目利きの仕方などのコツを集中して抑えて行くのだそうだ。とはいっても受講した全員が3か月で一人前の寿司職人になれるかというと、そうではないらしい。「和食を長くやっている職人でも寿司は苦手だという人もいます。問題となるのはセンスがあるかどうかで、センスがあれば一気に高みに登って行きます」---この人は、どうしてこう攻撃的な物言いしかしないのかなと思いますけどね。(攻撃的な物言いを受けている、という現実もあるにはあるんだろうけど)基本的に、私はホリエモンは嫌いです。ただ、この件は、一概にどちらが正しい、という言い方は難しい話のように思えます。そもそもの発端は、コロンビアに寿司店を出したいという人からの相談だったそうです。海外の日本料理店で日本人から見ると「これが日本料理?」「これが寿司?」と思えるような料理が出てくるというのは、よく聞く話です。米国のカリフォルニアロールなんて、典型例でしょう(もっとも、今ではカリフォルニアロールも日本に逆輸入され、珍しくなくなったけど)。そういう中で、日本人相手、日本の気候風土での料理の修業を長年積んでも、海外では通用しない例が多々あることは、容易に想像がつきます。最初から「海外で店を出す」という明確な予定があるなら、日本国内で長期間修行するの無駄かもしれない。その限りにおいて、ホリエモンの言い分は正しそうです。では、日本での一般論としてはどうなんだろうか。これは、なかなかに微妙かなと思います。実は、父が寿司が好きで、それが昂じて、年に数回寿司を握っていました。客としてすし屋に行くうちに、寿司職人の手つきを観察して(まさしく、「腕を盗んで」ですね)、自分でやってみたら、結構それなりに握れるようになったようです。もっとも、握るのは父でも、酢飯を炊くのは母でしたが。母は、寿司を握ることはできないので、父の死とともに、実家での握り寿司パーティーはできなくなりましたが、今は手巻き寿司パーティーになりました(笑)多分、父が趣味で握る寿司と、本物の寿司職人が握る寿司の違いは、味よりも、複数の注文に短時間で応じる速度の差とか、ちゃんと利益を出す在庫管理とか、そういった方面のほうが大きかったのではないかと思います。私自身は、父が握った寿司以外は、ほとんど回転寿司か、昼定食1人前1500円みたいなものしか食べたことがないので、高級寿司の味とか職人の腕を語る資格はないですけど、少なくとも回転寿司の職人が「飯炊き3年、握り8年」なんて修行を経てはいるとは思えません。では、回転寿司は不味いのか?そうでもないと私は思うのです。回転寿司といっても、お店によって結構差は大きいですけど。プロとして何かをやるには、多かれ少なかれ技術の習得期間がいります。いきなり一人前なんて人が、いるわけがない。が、「飯炊き3年、握り8年」は、ちょっと極端に過ぎるんじゃね?とは私も思います。1食何万円も取るような高級すし店はともかく、一般庶民が年に何回かは行けるくらいの「ちょっとした贅沢」の寿司屋に、そこまでの修行を、客も求めないでしょう。ただ、数ヶ月で一人前になれるかっていうと、それもまたちょっとね。ま、私はあんまり美食家のクチではないので、料理の味についてあまりえらそうなことは書けないですけど、音楽だったらどうでしょうね。楽器を一から初めて、数ヶ月で人に感動を与えるような演奏ができるかというと、なかなか難しいだろうなと思います。私は、ケーナを吹き始めて数ヶ月後には、3オクターブを出すことはまだできませんでした。当時持っていた教則本には、3オクターブのことは書いていなかったから、3オクターブが出せることすら知らなかったのです。ケーナ教室にでも行っていれば習っていたかもしれませんが、独学だったので、ずいぶん寄り道しました。独学の場合、上手い人と一緒に演奏するのが上達の近道で、私のケーナが目に見えて上手くなったのは、グループを組んで以降だったと思います。今から20年以上前から10年近い期間にわたって、現在プロとして活躍しているSaigenjiさんと一緒に10年近く演奏させてもらって、ずいぶん勉強になった一方、センスの差がどれほど巨大かも痛感しました。一緒に演奏を始めた当初(当時、彼はまだ高校生)、私は独学自己流ながら、ギターを3~4年は弾いていたけれど、Saigenjiさんは、そのときはまだギターを弾いていなかったのです。しかし、それから数ヶ月後、「この間、ギターを手に入れたんですよ」と言うのです。聞くと、1ヶ月くらい前に始めたばかりなのですが、その時点ですでに私よりよほど上手かったのです。やっぱり、プロになる人は違う(当たり前か)。天才っているんだなと、そのとき思いました。ただし、その彼にしても、初めて手にした楽器がギターだったら、さすがに1ヶ月でそこまで上達はできなかったはずです。そのとき、Saigenjiさんは、すでにケーナの天才少年だったし、チャランゴも上手かった。特にチャランゴの経験があったからこそ、ギターがごく短期間で上達したのです。私だって、ケーナは音が出るまで何時間もかかり、3オクターブを吹けるようになるまで4年もかかったけど、フルートは初めて手にした瞬間に音が出て、3オクターブを出せるようになるまでの所要時間は1時間あまりでした。料理でも音楽でも、違うジャンルの音楽(料理)の経験があるか、まったく初めてかで、相当大きな差があることは間違いないでしょう。で、楽器経験がないところから、観客に感動を与えるレベルで演奏できるようになるまでの所要時間って、どのくらいでしょうか。私のように週に2~3日、1回1時間程度の練習か、毎日何時間も練習できるかで、当然大差がありますし、楽器ごとの難易度の差もありますけど、どう頑張っても、数ヶ月では無理だろうと、私の経験では思います。少なくとも年単位の時間は必要です。
2015.11.03
コメント(10)
-

ばれなきゃいい、ってことか
本題の前に、10月3日に川崎で演奏した動画が、主催者によってYouTubeにアップされております。私もアップしましたが、それより音質は若干劣る(音が割れている)ものの、撮影場所がよくて、映像は非常に迫力があります。自分でこんなことを言うのもなんですが、「我々のグループって、こんなに格好よかったっけ?」と思ってしまいました。16分20秒ころからが我々の演奏です。司会者が日系ブラジル人なので、Estrella Andinaを「エストレラ・アンジーナ」とブラジル・ポルトガル語読み(本国のポルトガル語ではかAndinaはアンディーナと発音するはず)されちゃいましたが。---データ偽装、旭化成建材は氷山の一角 専門家「同じようなこと全国的に行われている」と断言旭化成建材が手がけた住宅や公共施設で、杭打ち工事のデータ偽装が次々明らかになった。騒動の発端となった傾いた横浜市のマンションと担当者は異なり、少なくとも3人の担当者がデータ偽装にかかわったことになる。相次ぐデータ偽装は旭化成建材だけの問題なのか。専門家は「業界全体の問題で、全国的にありえる話だ」と言い切る。横浜市は10月29日、旭化成建材が杭打ち工事をした公共施設1件でデータ偽装を確認したと発表。杭の先端部分を地盤に固定するためのセメント量のデータに偽装があったという。北海道では釧路市の2棟の道営住宅で施工データの流用が発覚した。道が独自に行っていた調査で杭打ち工事の電流計の記録に不審な点が見つかった。2棟の工事責任者は同じ社員だった。騒動の発端となった横浜市の傾いたマンションの現場責任者を含め、少なくとも3人の現場責任者が杭打ち工事のデータ偽装にかかわったことになる。また、発表されていないものでも、データの不正はさらに数十件に上ると新聞各紙が報じている。日本各地の現場で次々明るみになったことから、データ偽装は旭化成建材で常態化していたとみられる。しかし、同様の偽装は同社だけの問題なのだろうか。これまで2万件以上の工事に携わってきたという、建築構造調査機構の代表理事で構造設計1級建築士の仲盛昭二さんは、J-CASTニュースに対して「同じようなことは全国的に行われているでしょう」と断言。旭化成建材だけの問題ではないという。杭打ち工事の現場では、作業員のカンや感覚に頼って進められることが多い。そのためデータの管理はおざなりにされてしまうことがあるようだ。データ偽装が行われてしまう背景については、工期のプレッシャーが影響している。横浜市のマンションのケースでは、支持層に打ち込まれた杭の長さが2メートル足りなかった。しかし、より長い杭をあらためて発注するとなると、新しい杭が届くまで1~2週間は工事が遅れてしまう。「気づいても面倒なことを言ってくれるな、という現場の雰囲気もありえる」と仲盛さんは言う。「欠陥住宅関東ネット」事務局次長の谷合弁護士も同様に指摘する。偽装は業界全体の問題だとして、「マンションなどの販売時期や工事の費用は決まってしまっている。納期に間に合わせるため、多少のミスや不具合があってもやり過ごすことはありえる。偽装は末端の施工担当者がやったことだとしても、発注者の黙認があったと考えられます」とJ-CASTニュースの取材に述べた。---本題ですが、横浜でマンションが傾いたことから表沙汰になった、杭工事のデータ偽装問題です。当初は、旭化成建材の特定の現場責任者が関わった物件で偽装があったとされていましたが、その後、この現場責任者とは接点のない物件でも偽装が発覚し、各地に飛び火しつつあります。しかも、旭化成建材だけの問題ですらなくなりつつあるようです。同社に限らず、そのような不正は全国的に行われている、という証言が各所から出ているようです。「縁の下の力持ち」なんて言葉がありますが、実は縁の下で手抜きが行われていたって話です。それも、この広がり方は、特定の個人の資質の問題に帰する問題ではなく、業界全体の体質に関わる問題である疑いが濃厚です。何しろ、杭は打ち込んでしまえば、他人からは見えないですから、データを偽装しても、それが露見することはまずないと思われます。それが、何と建物そのものが傾いたことで悪事が発覚してしまったわけです。ひとたび不正が露見すると、他人に見えない場所ということが逆に「どこに不正があってどこには不正がないか」の判別が困難であり、すべての物件に疑いの目を向けざるを得なくなることになります。思えば、昔から建築と手抜き工事は切っても切れない縁があります。残念ながら、ごく稀な話ではなく、かなりあちこちに見られることです。今回の件でも、公共工事や学校ですら偽装が行われていたと報じられていますから、裾野は広そうです。それにしても、日本の大都市というのは、いかに軟弱な地盤の上に立っているのか、ということを改めて痛感せずにはいられない話です。問題のマンションは横浜市都筑区にあるそうですが、この記事によると、地下に約2万年前の氷河期に100mほど低下した海水面に向かって流れる川が深い谷を刻んでいます。その上に縄文時代の温暖な時期に海が侵入し、プリンのように軟らかい粘土が海の底にたまっている場所。国土地理院のホームページで見ることができます。昭和21年ごろの航空写真を見ると、マンション付近は暗い色で写っています。鶴見川の『後背湿地』で、低湿で軟弱な湿田です。とのこと。つまり、沖積層の上に建っている建物、というわけです。こういう場所でも大型マンションを建てられる、その前提はしっかりした基礎工事のはずなのに、その命綱で手抜きをしているのでは、どうにもなりません。ここだけではなく、沖積平野は日本中の大都市に広がっています。そこで、こういった杭の手抜き工事がまかり通っているとすると・・・・・・これでは、中国の手抜き工事のことを笑えません。
2015.11.02
コメント(2)
-
妄想もここに極まる
サヨクは働いていないのか、デモや集会を「職業」とする人々安全保障法案の時、一部ニュース番組は、こぞって国会前の若者や主婦などを取り上げ、「普通の人たちが声を上げ始めた」とうれしそうに報じました。~○○労組、○○教組、○○連、さらには過激派団体まで、のぼりや旗を見れば、これらがフツーの人だとはだれも思わないはずです。~結局いつもの沖縄基地問題、反原発などのデモと変わらず、彼らの動員がうまくいっただけというのが真相のようです。以前ある保守系の識者の方が、左翼団体の動員力、組織力についてうらやましがっていました。その大きな理由は、「専従者」の数だといいます。専従者は「専従労働組合員」だけではありません。「党職員」とか、「市民団体役員」などよくわからない肩書きの人たちが報酬をもらった上で「職業活動家」として組織の中枢に専従しているのです。何しろデモや集会を「職業」とする人たちですから~組織の力を誇示しなくてはなりません。そのための活動として、末端の組織員までオルグする必要がありますし、ノルマを設けて人を集めなければならないのです。今回のデモのようなハレの大舞台になればなるほど「主催者発表」が膨れ上がるのも当然というわけです。保守系の運動では、こうはいきません。~とはいえ、先の保守系の方も本当に動員で人を集めたいと思っているわけではありません。普通に働き、普通に家族との時間を大切にしている多くの日本人は、そのような政治的イベントに参加する時間などないことを知っているからです。そして、そういう日本人の考え方こそがサイレントマジョリティーであることをよくわかっているからこそ、「保守」なのです。左翼はよく、市民の権利だとか自由だとか「個」を大切にするようなことを言いますが、「彼らほど組織の構成員を自分たちの手足だと思っている連中はいない」とこの方は言います。もちろん、自らの思想信条に従い、手弁当で左翼活動をしている人も多いと思います。ただ、そういう方々の多くは、失礼ながらあまり余裕のある暮らしをしているようにはみえません。そろそろ気付いてほしいのですが、あなた方に動員をかけている団体の上層部の方やテレビで立派なスーツを着て弱者の味方を装っているコメンテーターの方々は、きっと驚くような裕福な暮らしをしていると思いますよ。その頂点に君臨しているのが朝日新聞のような気がします。---いかにも産経らしい、論理も思考力もない、ただ左翼憎しの妄想を文字にしただけの愚劣な記事の典型です。過激派はともかく、労組や教組(それも労働組合ですが)、~連(これだけではどんな団体か分かりませんが)の旗を見ると、それが「フツーの人だとは誰も思わない」というのは、果たしてどういう神経なのか。憲法には、「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」と書いてあります。その規定に基づいて組織されている労働組合の組合員が「フツーじゃない」というのは、その言葉を吐いている人間の価値観の方が「フツーじゃない」ことを示しているようにしか、私には思えません。だいたい、当のフジサンケイグループにすら、労働組合という名称の組織は(まったくの御用組合のようですが)存在するようですけどね。結局いつもの沖縄基地問題、反原発などのデモと変わらず、彼らの動員がうまくいっただけというのが真相のようです。一部の特殊な人たちが動員されているだけなら、沖縄で辺野古移転反対派が知事選に勝てるわけがありません。原発問題も同様です。様々な世論調査において、原発の再稼動に反対、という意見はおおむね過半数に達しています。一部の特殊な人たちの動員だけで、世論調査でそんな結果が出るわけがない。確かに、動員はあるでしょうが、固い組織の動員だけで何万もの参加者を集められるものなら、そんな集会を毎月、いや毎週だってやっているに決まっているじゃないですか。安保法制に関しては、夏場以降は毎日に近いくらいの頻度で国会前で集会が行われていましたが、いつも何万人も集まっていたわけじゃありません。圧倒的に参加者が多かったのは8月30日、そして法案成立直前の1週間に限られます。それ以外の日は、せいぜい数千人程度でしょう。つまり、強い意思を持った「活動家」の動員だけで集められる上限はその程度、ということです。10万人以上集まったというそのことが、集まった人たちの幅の広さを証明するものです。左翼団体の組織力、動員力を専従者に求めるのも、まったくの妄想です。残念ながら、日本で労働組合の組織率は年々下がっています。ということは、組合員の払う組合費も減少しており、組合の専従職員に払える人件費の総額も減少していることは、算術的に自明のことです。「党職員」だって同じこと。共産党は2013年以降党勢が拡大中ですが、それまではずっと党勢低迷していたし、民主党と社民党は現在まで低迷中です。そのため、社民党は専従職員を大幅に解雇せざるを得ず、解雇不当と提訴されたことがありました。労働者の党がリストラで労働争議とは、みっともない話ですが。民主党も、多くの専従職員を抱える余裕などない点は大同小異でしょう。そもそも、「党職員」なんてのは、自民党にだって、他のどの党にだっているものです。ちょっと検索したら、自民党には専従職員が180名もいるそうですよ。あるいは、かの日本会議だって、Wikipediaによれば「組織は都道府県を9区域にまとめ、県毎に県本部を置き、さらにその下に支部が置かれている。各都道府県本部には、専従で勤務する活動家が配置されている。」とのことです。別に、不思議な話じゃない。ある程度以上の規模の組織を運営するのに、専従職員が必要なのは当然のことです。そして、自民党とか日本会議の専従職員はどうか知りませんけど※、産経のいう「左翼団体」の専従職員なんて、給料は安い。他に職を持って手弁当で活動に参加する人より、専従職員のほうが収入が多い、ということは、私の知る限りでは滅多にありません。もちろん、別に職といっても人それぞれなので、国民年金だけの年金生活者よりは専従職員のほうが収入は上、ということはあるでしょう。※検索したところ、自民党の嘱託職員の給与月額は238,300円(2015年度実績・他に賞与あり)とのことです。正職員になれば、もっと上がる、ということのようです。「左翼団体」の専従で、この額の給料がもらえる人が、果たしてどれだけいるんでしょうか。先の保守系の方も本当に動員で人を集めたいと思っているわけではありません。普通に働き、普通に家族との時間を大切にしている多くの日本人は、そのような政治的イベントに参加する時間などないことを知っているからです。そして、そういう日本人の考え方こそがサイレントマジョリティーであることをよくわかっているからこそ、「保守」なのです。これは、何重もの欺瞞に満ちた文章です。「保守系は動員で人を集めたいとは思っていない」というのが本音とは思えません。たとえば、総選挙の際、安部首相が応援演説となれば(もちろん、安倍や自民党政権に限った話ではないけれど)どこに行っても聴衆が人だかりです。あれが動員でないわけがないし、自然発生であれだけ集まるとすれば「普通に働き、普通に家族との時間を大切にしている多くの日本人は、そのような政治的イベントに参加する時間などない」という言葉は、ウソということです。実際のところ、演説に多くの聴衆が集まる候補が落選、演説に聴衆がいない側が当選、なんて例もあるので(たとえば先の都知事選)、聴衆の数=票ではないことは明らかなのですが、それでも、首相が応援演説をするとなると多くの聴衆を集めようとするのは、「首相が演説するのだから多くの聴衆を」という意識が保守系にもあるからに他ならないでしょう。そもそも、です。「普通に働き、普通に家族との時間を大切にしている多くの日本人は、そのような政治的イベントに参加する時間などない」というのは、言い方を変えれば、「普通の日本人は政治的な主義主張など公にせず、文句も言わずにただ黙って働いておれ」と言っているのに等しいのです。要するに、お上にただ従順な政治的奴隷であれ、それが日本人のマジョリティーなのだと、そういうことです。まあ、それが産経新聞、あるいは、「ある保守系の識者」氏の望む、あるべき日本人観なのでしょう。
2015.11.01
コメント(4)
全25件 (25件中 1-25件目)
1