2015年07月の記事
全26件 (26件中 1-26件目)
1
-
あらゆる事態に備えるが、原発が攻撃される事態は考えない
山本太郎「原発がミサイル攻撃されたら?」 「国会質問」機にネットで大反響「原発が弾道ミサイルの攻撃を受けたら、どのぐらい放射性物質が出るのか」。山本太郎参院議員が国会でこんな単刀直入の質問を繰り出して、ネット上で反響を呼んでいる。山本氏はまず、明らかに憲法違反であり、「戦争参加法制だ」と批判して、法案に反対する立場を表明した。続いて、国際紛争については軍事力でなく外交力で対処すべきだなどと自党の対案を述べた後、政府が差し迫った脅威とする中国、北朝鮮、ロシアが弾道ミサイルなどで攻撃してきたケースについての質問を始めた。山本氏は、日本がミサイル攻撃を受けたときのシミュレーションや訓練を政府が行っていることを確認したうえで、鹿児島県の川内原発について、最大でどのぐらいの放射性物質放出を想定しているかをただした。これに対し、原子力規制委員会の田中俊一委員長が、原発へのミサイル攻撃の事態は想定しておらず、事故が起きたときに福島第一原発の事故の1000分の1以下の放射性セシウムが放出される想定だと答弁すると、山本氏は、怒りを露わにした。「要はシミュレーションしていないんだ」「あまりにも酷くないですか、これ」今度は、安倍晋三首相がその理由を述べ、攻撃の手段や規模、パターンが事態によって異なるとして、「実際に発生する被害も様々であり、一概にお答えすることは難しい」とした。すると、山本氏は、待っていましたとばかりに激しく反論した。「でも、考えてみて下さい。今回の法案、中身、仮定や想定を元にされてないですか?」「都合のいいときだけ想定や仮定を連発しておいて、国防上ターゲットになりうる核施設に関しての想定、仮定できかねますって、これどんだけご都合主義ですか」さらに、山本太郎氏は、原発が弾道ミサイル攻撃を受けたとき、何キロ圏までの避難・防災計画を作るべきなのかとただした。政府側は、定量的な被害想定をしておらず、事態の推移を見て避難などの範囲を決めると説明したが、山本氏は、また怒りを爆発させた。(中略)最後に、山本氏は、川内原発から最大でどのぐらいの放射性物質放出があるのかを重ねて聞いた。田中俊一委員長が放射性物質は燃焼度や冷却期間などで変わるため全部が放出されることは想定していないと答えると、山本氏は、「これね、再稼働なんてできるはずないんですよ、川内原発」と強く非難した。安倍首相が原子力規制委で安全基準を満たしたものは再稼働する方針だと述べると、山本氏は、「規制委員会への責任転嫁」だと断じて質問を締めくくった。---まったく山本太郎の言うとおりだと思います。まず、原発にミサイルが命中して(もちろん、ミサイルの破壊力と、原発のどこに命中するかにもよるとは言え)「福島第一原発の事故の1000分の1以下の放射性セシウムが放出される想定」って、ほとんど非現実的とも言える超大甘の被害想定でしょう。この時点で、「何も考えていない」ということは明らかです。原発は、その多くが日本海側の海岸沿いに立地しています。政府が仮想敵と考えている(であろう)国々に対して、むき出しと言ってよい状況です。攻撃を受けたら、とても防ぎきれるものではありません。で、原発に対する攻撃を防ぐことに安保法制は不要でありません。日本が米国の戦争に協力することと、原発に対する攻撃への防御力が、ほとんど何の関係もないことは明らかです。日本国内の原発に対する攻撃は、個別的自衛権で対処する範疇の問題ですから、集団的自衛権は関係ない。ただし、個別的自衛権だろうが集団的自衛権だろうが、弾道ミサイルを迎撃する手段はほとんどありません。一応、自衛隊の持つPAC3ミサイルは、弾道ミサイルの迎撃が可能、ということになっていますが、長射程(つまり高速)の弾道弾相手の迎撃精度自体もかなり未知数です(実験には成功しているけれど、あらかじめ時刻も飛来コースも分かっている1発の標的への迎撃実験と実戦では、勝手が違うのは明らか)そもそも、PAC3は射程の関係で重要地域(たとえば大都市圏、自衛隊と米軍の基地、原発、石油備蓄基地、化学コンビナートなどなど)だけのカバーすらできないのですから、PAC3の射程の及ばないところに弾道弾を打ち込まれたらお手上げです。じゃあ、ミサイルを発射される前に先制攻撃をすればいいのか。それは無理です。ミサイルは移動可能であり、発射台ごと秘匿されるに決まっています。その発射台をすべて発見して、同時に破壊するのは不可能です。先制攻撃をかけたところで、生き残ったミサイルが日本に向けて発射されることになる。つまり、相手側が本気で日本の原発を標的にしたら、軍事的に防御することはほとんど不可能ということです。しかも、戦争になればそういう事態は充分起こりえます。少なくとも、政府が言う、「日本の避難民を乗せた米艦艇が外国軍に攻撃されている場合」などというファンタジーな想定より、原発がミサイル攻撃を受けるほうが、はるかに可能性が高いでしょう。そういう事態の可能性に目を閉ざしておいて、「あらゆる事態に備える」とか、よく言えるなあと思います。結局のところ、解決策は、標的をなくす、つまり原発をなくすか、または標的にされるような事態が起こらなくする、つまり友好関係を構築するか、そのいずれか(あるいは両方)しかないだろうと私は思います。
2015.07.30
コメント(2)
-
ホリエモンのあたまにはウジが湧いているらしい
ホリエモン氏が『安保関連法案に反対するママの会』を非難「頭にウジが湧いてるんだね」子育て中の母親たちでつくるグループ「安保関連法案に反対するママの会」が東京・渋谷駅前で、「戦争立法反対!ママの渋谷ジャック!」と題したデモを開催したそれに対して堀江貴文が頭にウジが湧いてるんだねRT @randa6010: @takapon_jp @katsuyatakasu ベビーカーに乗せられいる子供がぐったりしている、子供の命を危険に晒しているのはどっちだ! pic.twitter.com/dMEB4QAv4R2015年7月26日 18:57などとツィートした、とか。こういう、子どもを極端に腫れ物扱いする意見って、時々見かけるんですけど、何なんだろうなと思います。少し前にも、ある女性タレントが生後2ヶ月のわが子を居酒屋に連れて行った、というだけでバッシングをするばかばかしい報道を批判したことがあります。たいした問題とは思えません(生後2ヶ月の子を居酒屋に?)私自身は、いろいろなデモ、集会に今まで数十回参加していますが、屋外の集会に子どもを連れて行ったことはありません。(子どもが小さいときに、相棒にも用事があったりして屋内の集会や会議に連れて行ったことはある)でも、真夏の炎天下に子どもを連れて屋外に遊びに行ったことなら、ずいぶんありますよ。だいたい、夏休みは家族旅行に行くし、行けば屋内で引きこもっているわけないし。真夏の動物園とか博物館とか、ずいぶん行きました。それで子どもが体調を崩したことなど、一度もありませんね。もちろん、飲み物は充分に持っていきますけど。子どもはそんなにヤワなものじゃない。同じく堀江の戦争になるくらいなら死んだ方がマシ的な笑RT @ChikaYukichi: @takapon_jp @randa6010 @katsuyatakasu はぁ…お子様達が熱中症や汗疹になっても気にしないのかなぁ⁉2015年7月26日 19:24 という発言もあったようです。はっきりいってしまえば、熱中症は気にします。それは当たり前。しかし、あせもは気にしません。なったら、お風呂でよく体を洗って、場合によっては塗り薬で治せばいい(軽ければ、よく洗ってほっとけば治る)。あせもにならないように真夏はエアコンの聞いた室内に閉じ込めておけって?過保護にもほどがあるってものです。もっとも、今回の件は、多分、本心では子どもを腫れ物扱いと言うより、そういうタテマエで安保法制反対派を揶揄したいだけなんだろうけど。
2015.07.29
コメント(0)
-
対案などいらない
安保法案:首相「野党は対案を」 参院実質審議始まる安全保障関連法案を審議する参院平和安全法制特別委員会は28日午前、安倍晋三首相らが出席する総括的質疑を行い、実質審議入りした。首相は「衆院では維新の党に対案を提出してもらい、議論がかみあったところもあった」とし、「野党にも対案、独自案を出してもらい、できる限り一致点を見いだす努力を重ねていくことが与野党を問わず政治家の責務だ」と述べた。首相は「わが国を取り巻く安全保障環境はますます厳しさを増している。政府、政治家は国民を守るための『必要な自衛の措置』は何かを考えなければいけない」と関連法案の必要性を強調。自衛隊が訓練を行うには法律の整備が必要だとし、「日米間でも十分な連携は一朝一夕ではできない。あらゆる事態に対処できるよう、一日も早い法整備が不可欠だ」と主張した。首相はまた、中国が南シナ海で行っている大規模な埋め立てや東シナ海でのガス田開発などに触れ、「状況は大きく変化しており、わが国のみで(主権を)守り切ることはできない」と指摘。(以下略)---もっともらしいことを言っているけれど、「わが国を取り巻く安全保障環境はますます厳しさを増している。」からといって、日本が直接攻撃されているわけでもないのに、他国(米国)の軍事作戦に参加する必然性というのは、まったく理解しがたいものがあります。わが国のみで主権を守り抜くことができない、というのがもし事実だとしても、そのことと集団的自衛権はどう考えても結びつかないのです。わが国だけでは守れないからよその国の戦争に加担する、というのは、理屈として成り立っていません。いずれにしても、「野党にも対案、独自案を出してもらい、できる限り一致点を見いだす努力を重ねていくことが与野党を問わず政治家の責務だ」だそうです。冗談じゃない、対案は今のまま、に決まっているのです。民主党政権時代に、たとえば子ども手当が成立したとき、自民党は対案を出したのですか?「変えるか変えないか」が対立点となっているときに、「変えるな」と主張している側に向かって「別の変え方を示せ」というのは、論理として破綻しています。そんなものは必要ないから反対しているわけで。
2015.07.28
コメント(2)
-
口先だけの「最小限」
憲法解釈変更「法的安定性は無関係」 礒崎首相補佐官礒崎陽輔・首相補佐官憲法9条全体の解釈から、我が国の自衛権は必要最小限度でなければならない。必要最小限度という憲法解釈は変えていない。政府はずっと、必要最小限度という基準で自衛権を見てきた。時代が変わったから、集団的自衛権でも我が国を守るためのものだったら良いんじゃないかと(政府は)提案している。考えないといけないのは、我が国を守るために必要な措置かどうかで、法的安定性は関係ない。我が国を守るために必要なことを、日本国憲法がダメだと言うことはありえない。本当にいま我々が議論しなければならないのは、我々が提案した限定容認論のもとの集団的自衛権は我が国の存立を全うするために必要な措置であるかどうかだ。「憲法解釈を変えるのはおかしい」と言われるが、政府の解釈だから、時代が変わったら必要に応じて変わる。その必要があるかどうかという議論はあってもいい。来年の参院選は、憲法改正が絡む話でしっかりと勝たなければならない。参院もできれば、自民党で単独過半数を取りたい。その中で憲法改正を有利に進めたい。(大分市での国政報告会で)---「必要最小限度」という憲法解釈は変えないのだそうですが、何が「最小限度」かという基準は、客観的指標ではなく、政府が恣意的に決めているといわざるを得ません。日本に外国軍が攻め込んでくるのを撃退するため、というなら「最小限度」というのも分かります。でも、「存立危機事態」という錦の御旗を掲げれば、世界のどこにでも自衛隊を送って戦争に参加できる、というのでは、それのどこが「必要最小限度」なのか、と思わざるを得ません。東京新聞の報道によれば、安倍首相は国会の答弁にて、「存立危機事態」について「日本の存立が脅かされ、国民の生命や権利が根底から覆される明白な危険」が「ない」と判断できない場合に、行使に踏み切る可能性に言及した。とのことです。「あることの証明」と違って、「ないことの証明」は困難です。しかも、それを証明する者自身(政府)が集団的自衛権の発動を決めるのですから、事実上まったくフリーハンドで発動できるのに等しいのです。それのどこが必要最小限度ですか。拡大解釈にもほどがある。で、その後に続く「法的安定性は関係ない。我が国を守るために必要なことを、日本国憲法がダメだと言うことはありえない。」という言葉が批判を呼んでいます。「お国のため」と掲げれば何やってもいい、法的安定性など関係ないというのでは、法治国家という体面を投げ捨てるようなものです。礒崎陽輔は、ツィッターで10代の女性にからまれて、暴言の応酬の挙句に、ロクに反論もできずに相手をブロックして逃亡してしまった人物です。東大卒とのことなので、頭はよいのでしょうが、政治家としての資質は果たしてどうなのか、大いに疑問を感じます。いや、礒崎に限った話ではなく、例の百田を呼んだ連中をはじめとする、安倍応援団はみんなそうです。
2015.07.27
コメント(6)
-

ケーナとサンポーニャ
私のやっているフォルクローレという音楽※には、ケーナとサンポーニャという2種類の笛が使われています。ケーナは日本の尺八とまったく同じ構造の縦笛(吹き口の切込みが尺八より深いので、音はずっと出しやすい)で、縦横の違いはあるけれどフルートや篠笛とも音を出す原理は同じです。一方、サンポーニャは、パンパイプと呼ばれる笛の一種で、底の塞がった長さの異なる管を並べたものです。ビール瓶で音を出すのと同じ理屈です。・・・・・・という話は、おそらく当ブログを以前から見ていただいている読者の皆さんはご存知のことと思います。※フォルクローレの中でも、ボリビアの、ネオ・フォルクローレと呼ばれる、現代的なスタイルの音楽に限った話ですこれがケーナこれがサンポーニャもともと、ケーナもサンポーニャも、先住民が古い時代から受け継いできた楽器が元になっています。ただし、現在使われているケーナやサンポーニャは、音程も奏法も、そもそも音楽そのものも、先住民の伝統的な楽器とは相当に変わっています。現在のスタイルのケーナやサンポーニャが完成したのは、せいぜい1960年代頃の話で、実はそれほど古いものでもありません。ところで、ケーナとサンポーニャ、日本では知名度があるのはどちらでしょうか。多分、圧倒的にケーナのほうが知名度があると思います。なんてったって、かの「コンドルは飛んでいく」はケーナの曲であってサンポーニャの曲ではありません。サンポーニャで吹く人がいないわけではないけれど。近年は、ある著名な俳優さんが吹いているということでも知られていますね。では、ボリビアではどうなんでしょうか。実は、現代的なスタイルのフォルクローレが世に出た当初(前述のとおり1960年代のこと)は、ケーナのほうがずっと演奏に使われる機会が多かったようです。ボリビアの現代的フォルクローレの始祖とも言える「ロス・ハイラス」というグループがあります。1960年代後半から70年代にかけて活躍したグループで、ケーナ奏者はスイス人のヒルベルト・ファブレという人です(おそらく、フランス語のジルベルト・ファーブルをスペイン語読みにしたものだと思いますが)。使われる笛は2/3はケーナであり、サンポーニャは1/3くらいしか使われません。また、その後1980年代初頭に活躍したホセ・ホセロ・マルセロというグループがあります。(先日紹介しました)このグループは、徹頭徹尾、笛はケーナしか使いません。サンポーニャは、まったく使わない。だから、この時代、つまり1980年代初期までは、ボリビアにおいてもサンポーニャよりケーナのほうがポピュラーだったものと思われます。しかし、それ以降、時代が新しくなるにしたがってケーナよりサンポーニャのほうがポピュラーになっていきます。理由はいろいろあるのでしょうが、ひとつには、1980年代から現在まで、ボリビアのフォルクローレ界のスーパースターであるロス・カルカスというグループが、明らかにケーナよりサンポーニャを好んでいる、ということがあげられます。その影響を受けた、後に続くグループがみんなサンポーニャを中心に据えるようになった、ということはありそうです。では、何で彼らはケーナよりサンポーニャを好んだのでしょうか。そこははっきりとは分かりません。ただ、元々器楽曲の要素が強かったフォルクローレの世界で、歌が中心の「ボリビア的歌謡曲」を定着させたのが彼らです。それにしたがって、笛はフォルクローレの旋律楽器ではなく、伴奏楽器になりました。より正しく言えば、歌の前奏と間奏のための旋律楽器です。その役割には、ケーナよりサンポーニャのほうが合うと彼らは考えたのでしょう。話は変わりますが、ケーナは前述のとおり、フルートと音を出す原理が同じであり、音色や吹き方も非常に近い笛です。そのフルートは、人の声に最も近い楽器だ、とも言われます。バイオリンもそうだといわれることがありますが・・・・・・。最も近いか比較的近いかはともかく、フルートが人の声に近い楽器であることは確かでしょう。ということは、同じ原理で音色の近いケーナもまた、人の声に近い楽器と言えそうです。一方、サンポーニャのほうは、こりゃどう考えても人の声に近い、とはいえません。つまり、歌の前奏間奏にケーナを使うと、歌との差が小さく、メリハリがつきにくい、サンポーニャなら歌とは音質が違うので、メリハリが付きやすい、ということなのではないか、と想像するのですが、果たしてどうでしょうか。ちなみに、ボリビアにおいて(多分、ペルーでもチリでも同じ)管楽器奏者は通常、ケーナとサンポーニャを兼ねて演奏するものです。ケーナしか演奏しません、サンポーニャしか演奏しません、という人は、プロの奏者でも皆無ではないけれど、非常に少ない。
2015.07.26
コメント(4)
-

南アルプス北岳
日本で2番目に高い山、南アルプス(赤石山脈)の北岳に登って来ました。実は、北岳に登るのはもう6回目なのですが、前回登ったのは2004年なので、11年ぶりでした。事前の天気予報は、金曜日はあまりよくない予報でしたが、ふたを開けたら、まずまずの天気でした。例によって、後日フィルム一眼レフの写真をアップしますが、とりあえずiPad miniの写真を。コースは、前夜最終の特急「かいじ」で甲府に深夜到着、始発のバスで広河原着が6時半過ぎ。広河原からは大樺沢→八本歯のコル→北岳山荘(テント設営)→間ノ岳まで往復(ここで宿泊)→北岳山頂→肩の小屋→草すべり→白根御池小屋→広河原テントだったので、荷物は登りはじめの時点で16kgくらいありました。(下山した時点では水と食料が減っているので、2kgくらいは軽くなっていたはず)大樺沢です。大樺沢を上から見下ろしました。朝は晴れていたけど、この時間は少しガスが出て、日はかげっていました。昔の記憶では、大樺沢はすごい大雪渓のように思っていたのですが、こうやって見ると、それほどでもなかった。北アルプスに比べれば、南アルプスの積雪量は格段に少ないですからね。大樺沢から八本歯のコルまで、ひたすら階段です。何箇所だったか、数えていないけど、数十回出てきました。この場所を登ったのは、おそらく2001年以来なので14年ぶり。階段はあったけど、こんなに多かったかなあ。記憶違いか、近年整備されたのかは分かりませんけど。北岳山頂直下の巻道。高山植物のお花畑が丁度満開。写真はシナノキンバイの群落です。ただ、花の写真ばかりはiPad miniではマトモに写らないのです。花の写真はフィルム写真をお待ちください。北岳山荘には2時頃到着、テントを設営して、しばし休憩の後、3時頃間ノ岳に向かいました。写真は北岳山荘から北岳を撮影したものです。間ノ岳は標高3189m、北岳より4m低い、日本で4番目に高い山です。山頂には4時10分少し前に着きました。山頂には誰もおらず、独り占め状態です(ただし、帰りに3人ほどとすれ違いました)。写真は農鳥岳方面を撮影したもの。同じく間ノ岳から北岳方面を撮影しました。で、翌朝です。天気は良かったのですが、風が非常に強く、テントの撤収時に風にあおられて、ポールを曲げてしまいました(涙)。まだ3回しか使っていないのに。もっとも、使用には問題ないレベルです。富士山の夜明け。稜線上は激しい風が続く中、テントの重い荷物を背負って、北岳山頂に向かいます。山頂に着いた。6時何分だったか忘れましたが、北岳山荘から1時間ちょっとでした。仙丈岳。その右手奥に、この写真では分かりにくいですが北アルプスの槍穂高連峰が見えます。眼下に、今朝の出発点北岳山荘が見えます。そして先には昨日行った中白峰と間ノ岳。その左奥には農鳥岳、右奥には塩見岳。山頂を越えて北岳肩の小屋まで下ってきました。ここで標高がちょうど3000m。前回2004年に登ったときは、ここにテントを張ったのでした。肩の小屋から中央アルプスを望む、その手前に伊那谷の町並みがちょっと見えます。肩の小屋から更に下っていったあたりで、小太郎尾根の続く稜線の向こうに甲斐駒ヶ岳が見えます。甲斐駒の右奥は八ヶ岳。北岳山頂を振り返り。肩の小屋も小さく見えます。(稜線がえぐれている底の付近)鳳凰三山(地蔵岳・観音岳・薬師岳)草すべりの一番上部。シナノキンバイとハクサンンイチゲの大群落が広がっていました。写真にはハクサンイチゲは写っていません。左奥にナナカマドが花を咲かせているのが少し写っています。ここから先、白根御池までは急降下につぐ急降下。すごい斜度です。テント装備が重い。スリップして尻餅をついてしまいました、白根御池小屋に着きました。ソフトクリームがおいしい。で、ここから広河原への下りが、またまたものすごい急降下の連続。草すべりの急登は記憶にあったけど、白根御池より下も、こんなにきつかったっけ??よれよれになりつつ、やっと広河原に到着したのが12時20分頃。白根御池を出たのが10時20分頃だったので、ちょうど2時間。広河原山荘で昼食。昼間から生ビールを飲んでしまいました。おいしかった!!ちなみに、北岳山荘は稜線上で携帯電波がつながりました。北岳山頂でも同様。しかし、白根御池ではかすかにしかつながらず(メールは受信できたが写真のアップロードはできず)、広河原でもつながりませんでした。
2015.07.25
コメント(3)
-
想像力の欠如はどっちか?
「憲法に守られた平和」という幻想 葛城奈海『自衛隊・防衛問題に関する世論調査』(今年1月内閣府)をめくっていて、「もし日本が外国から侵略された場合は?」というページではたと手が止まった。「一切抵抗しない(侵略した外国の指示に服従し、協力する)」が、5.1%もいるではないか!想像力の欠如もここまで来ると恐ろしい。奴隷でもいいというなら、その尊厳のなさにがくぜんとするが、おそらくは意識下に無抵抗なら命は保証されるという子供じみた甘えがあるのではないか。しかし、強制収容、拷問、虐殺…そうした戦慄すべき事実は、今この瞬間も世界各地で繰り返されている。「一切抵抗しない」方には、自分や自分の大切な存在ののど元に刃が迫る場面を真摯に想像していただきたいと切に思う。回答を男女別で見ると、女性は6.6%と男性3.3%の倍であった。これで思い出したのが、自衛官募集担当者の「安保法制論議の影響で、志願者が激減している」という言葉だ。母親たちが「危ないから」と止めるらしい。国会での自衛官の危険が増す云々の議論も、むなしさを禁じ得ない。そもそも事に臨んでは危険を顧みず国民を守ると宣誓しているのが自衛官だ。だからこそ尊いのだ。より重く論じられるべきはむしろ国民の安全であるはずだ。多くの国民が長く「憲法に守られた平和」という幻想に陥ってきた中、その欺瞞を骨身にしみて感じてきたのが拉致被害者のご家族であろう。(以下略)ーーー葛城奈海というのは、典型的なネトウヨ系女子ライターのようです。侵略を受けたら一切抵抗しない、という回答が5.1%ということは、かなりの少数派というのが現実ですが、そのたった5%の存在が許せないと吹き上がっています。じゃあ何%なら満足なんでしょうかね。もし、日本が外国の侵略を受けたらどうする、というのは、実はかなり奥の深い問題提起です。それに対する回答は、一様ではないのも当然です。例えば、「大東亜戦争は正義の戦争だった」と思っている人たちの視点で見れば、敗戦とは鬼畜米英に膝を屈した時であり、進駐軍(占領軍)に従った日本人は、みんな侵略者への協力者、ということになるかもしれません。その伝で言えば、戦後の日本人はみんな売国奴、ということになるかもしれません。実際のところ、日本国内ではともかく、南方戦線やでは、先に捕虜となった将兵や民間人の中から、米軍に協力する者もいて、まだ降伏しない日本兵との間で殺し合いにまで発展した例もあったように聞きます。ブラジルの勝ち組、負け組なども同様でしょう。では、日本が敗戦を拒否してあくまでも戦い続けていたら、どうなっていたでしょうか。史実以上の焦土と化して、まさに破滅的結末となったでしょう。あるいは敗戦後に日本国内では抗戦を継続するゲリラ部隊が一定規模で存在し続けたら、戦後日本の史実のような復興があり得たか、というのはいささか疑問です。強制収容、拷問、虐殺、それらはなぜ起こるのか。紛争があるから起こるのです。侵略軍に対して武力で抵抗すれば、それに対する反作用として生じるのです。ただただ這いつくばって屈服すれば、命まではとられません。もちろん、国家としては、外国の侵略を受けたら実力でそれを排除する、という選択しかないでしょう。戦わずに屈服する、という選択肢はない。しかし、国家が敗れ去ったり、自分の住む土地が占領されたりした場合に、一人ひとりの市民がどういう選択肢を取るのか、取るべきかは、一概には言えません。侵略に対して一人ひとりが武力で立ち向かう、というのは、とるべき選択肢の一つではあると私も思います。が、同様に、立ち向かわない、協力はしないが、柳に風と受け流して嵐が過ぎ去るのを待つ、というのもまた、選択肢の一つではあるのです。実際のところ、歴史的に見ても、戦場となった土地の住民の多くは、そうやって戦争をやり過ごしています。ナチス占領下のフランスやソ連だって、みんながみんな侵略軍に対するレジスタンスに身を投じたわけでもありません。割合からいえばむしろ、這いつくばって嵐が過ぎるのを待った住民のほうが圧倒的に多かったはずです。それこそ、生き残るための生活の知恵というものです。武力で立ち向かえば、強制収容とか虐殺などの強力な反作用を招く、それでもなお、武力抵抗を行う、という選択肢を、私は否定はしません。トータルで考えて、そうすべきときもあるかもしれない。でも、戦う本人だけではなく、その周辺にもリスクが生じるのだということを理解し、熟考の上でそういう選択をすべきです。「外国が侵略したら服従する、という人が5%もいる、怪しからん、想像力が足りない、キーッ」と吹きあがっているこの執筆者自身のほうが、よほど想像力が足りていないのです。抵抗するのと無抵抗を貫くのと(あるいはその中間を選ぶのと)、長い目で見てどちらが有利なのかは、神ならぬ人間には判断のつかないことです。それぞれが、正しいと信じた手段を選ぶしかありませんし、自分と異なる手段を選んだ人を非難したって始まらないのです。もっとも、現実には、日本が外国から侵略を受ける可能性は極めて低いし、尖閣諸島などの無人島を除けば「起こり得ない」と言っても過言ではないと思いますが。ついでに、「そもそも事に臨んでは危険を顧みず国民を守ると宣誓しているのが自衛官だ。だからこそ尊いのだ。」だそうですが、宣誓することと実際に行動することでは、相当の落差があります。就職のためにとりあえず宣誓した人もいれば、自衛隊に入って勤続何十年で昔の気持ちなんて忘れちゃった、という人もいるはずです。宣誓だけを金科玉条のように考えていると、現実を見誤るでしょう。確実に言えることは、「宣誓をしているから危険に晒してよい」というものではない、ということです。「多くの国民が長く『憲法に守られた平和』という幻想に陥ってきた中、その欺瞞を骨身にしみて感じてきたのが拉致被害者のご家族であろう。」との言い分ですが、憲法9条がなかったとしても、拉致被害は起こったでしょう。なぜなら、憲法第9条のない多くの国々でも、北朝鮮による拉致の被害は発生しているからです。そして、日本が憲法第9条を捨てたら、拉致被害者どころではない、もっと多くの犠牲者が戦争によって生じていたことは間違いありません。
2015.07.23
コメント(6)
-
数字は残酷だ
安倍首相のフジ生出演、平均視聴率は5.3%~6.7%安倍晋三首相が20日夕に生出演したフジテレビの報道番組「みんなのニュース」の平均視聴率(関東地区)は午後4時50分~5時54分で5・3%、5時54分~7時で6・7%だった。関西地区は午後5時~54分で4・5%、5時54分~7時で5・7%、名古屋地区は午後4時49分~5時54分で4・5%、5時54分~7時で6・4%、北部九州地区は4時50分~5時54分で4・4%、5時54分~7時で6・1%。安倍首相は午後4時50分~6時23分に出演し、安全保障関連法案などについて説明。全国のフジテレビ系列局が中継した。「みんなのニュース」の平均視聴率(関東地区)は午後4時50分~5時54分で3・4%、5時54分~7時で5・0%で、20日はどちらも平均を上回った。他のテレビ局が20日夕に放送した番組の平均視聴率(関東地区)は、NHK総合の大相撲(午後5時~6時)で15・5%、テレビ朝日の「スーパーJチャンネル」(4時50分~7時)で7・4%などだった。(ビデオリサーチ調べ)---いくら首相とはいえ、就任・辞任時や選挙の際は別にして、一党の党首だけをゲストに1時間半も出演させるテレビって、過去に例があるのでしょうか。私は記憶がないです。あるいは私に記憶がないだけかもしれませんけど。何というか、政権与党に対する大変な優遇措置だなあという印象を抱いてしまうのです。もっとも、いくら優遇措置を講じたところで、視聴者をテレビの前に縛り付けておくことはできません。視聴率が5~6%、大相撲の半分以下の視聴率というのは、ある意味国民の安倍政権に対する現在の感覚を代弁しているのでしょう。で、私自身もほとんど見ていません。一番最後の5分か10分くらいだけ見ましたけど。だから、一部で話題になっている「生肉」騒ぎというのもよく分からなかったのです。安倍が持ち込んだジオラマを後でネット上で拝見しましたが、確かにあの炎と煙の表現は生肉にしか見えません。私が見た範囲内でいうと、安倍に質問するコメンテーター陣の質問が、何か奥歯に物が挟まったような、非常にぬるい質問の仕方だなあと感じました。津田大介氏、決して右寄りではない、というより、むしろどちらかといえば左寄りのジャーナリストだと私は思っていたのですが、ものすごく遠慮したような質問だったのは、質問内容や質問の仕方について、フジテレビからよほど強いお達しでもあったのかな、と勘ぐりたくなってしまいます。その中で、やくみつるが、安倍が集団的自衛権を火事に対する消火活動に例えていることに対して、「アメリカだって人の家に火を放つようなことをしてきたではないか、火を放った側に与するような危険もあるんじゃないか」という、鋭い(当然の疑問ではあるが)質問をしていました。しかし、それに対しては納得できるような回答がないまま、安部の出演時間は終わってしまいました。この問いに対する、マトモな答えは、おそらく用意できないのでしょう。だいたい、戦争を火事に例えることが不適切であることはすでに多くの方が指摘していることです。火事は反撃したりしないですからね。
2015.07.22
コメント(5)
-
54年ぶりの国交回復
米とキューバ、54年ぶり国交回復…大使館再開米国とキューバは20日、1961年に断絶した国交を54年ぶりに回復し、相互の首都で大使館を再開した。オバマ米大統領とキューバのラウル・カストロ国家評議会議長が昨年12月、国交正常化方針で合意して以来最大の成果で、両国関係は東西冷戦を背景にした対立の解消に向け、歴史的転換点を迎えた。相互の首都に設置されていた利益代表部は20日、国交回復に伴い、それぞれ大使館に格上げされた。ワシントンのキューバ大使館では同日、記念式典が開催され、キューバ国旗の掲揚が行われた。キューバのロドリゲス外相は式典後の20日午後、ケリー米国務長官と国務省で会談し、共同記者会見を行う。キューバ外相が国務省を訪問するのは断交後、初めて。米国務省の玄関ロビーでは20日未明、米国と国交がある国々の国旗が並ぶ中に、キューバ国旗も加えられた。ケリー国務長官は8月中・下旬ごろにハバナを訪問し、米大使館での記念式典に出席する。米CNNは米政府高官などの話として、ケリー氏の訪問は8月14日と報じた。同氏の訪問に合わせ、米国旗掲揚などの行事が行われる。オバマ大統領は大使指名をまだ行っておらず、利益代表部トップがそのまま臨時代理大使を務める。---ついに、歴史的瞬間が訪れました。と言っても、引用記事にあるとおり、実は米国もキューバも「利益代表部」という名の大使館(のようなもの)を互いの首都に設置しており、その看板を「大使館」に架け替えるだけの話ではありますけど。ともかく、米国とキューバの激しい対立の歴史が、とりあえずは終わりを告げた、ということになります。米国は、ずっとキューバを「テロ支援国」に指定して、経済制裁で締め上げ続けてきました。現実には、キューバがテロを支援したと考えられる証拠は何もありません。各国の左翼ゲリラ組織に対する支援は行っていたので、軍事援助は行っていたとは言えますが、それを言うなら米国は世界中に軍事援助を行いまくっています。要するに、キューバは米国に対して敵対的な姿勢であったため、「テロ支援国家」というレッテルを貼った、というだけのことです。ヒロン海岸上陸作戦(いわゆるビッグス湾事件)とか、反カストロ主義者によるキューバ航空爆破事件の犯人をかくまうなど、むしろ米国のほうがキューバに対して侵略とテロ行為を繰り返してきたのが現実です。結局、キューバはフィデル・カストロの巧みな舵取りによって、ヒロン海岸事件以降二度と米国の直接侵略を許さず、経済制裁にも耐え切って生き残ってきました。旧ソ連が崩壊して援助が途絶えると、勢いに乗った米国は経済制裁を強化し、キューバは石油輸入が半減するなど経済的な危機に直面しました。しかし、石油に依存する化学肥料や農薬を多用する農業から、有機農法に切り替えて食料自給率を上げ、さらに観光産業を拡大することで(経済制裁のため米国からの観光客は望めなかったが、カナダ、ヨーロッパ諸国、メキシコなどからの観光客はものすごく増えた)外貨を稼いで、かろうじて危機を回避することができた。さらに、2000年代半ば以降は、原油価格の高騰を背景にチャベス政権のベネズエラから経済援助が始まったことで、危機は遠のいたようです。が、原油価格の低迷によって、そのベネズエラからの支援の今後が不透明になったことが、米国と関係改善を目指すキューバ側の事情となったのでしょう。それにしても、カストロ政権が舵取りを一歩間違えていれば、とうの昔に米国の軍事介入を招いて政権は消滅していたに違いありません。そういう実例は多々あります。1989年パナマ侵攻、1983年グレナダ侵攻、1980年代を通じてのニカラグアのサンディニスタ政権への圧迫、1973年、チリのアジェンデ政権に対するクーデター支援、等々。米国のあからさまな侵略であっても、米国の国際宣伝の下では、「邪悪な共産主義者のテロに対抗する自由のための戦い」とか何とか、そういうレッテル貼りが行われて、「米国を守る戦い」に化けてしまうわけです。そんな自体に至らず、旧ソ連崩壊後もどうにか生き延びて、米国との関係改善に至った、フィデルとラウル・カストロ兄弟の手腕には、ただただ敬服するばかりです。話は変わりますが・・・・・・集団的自衛権に反対しイジメに憤慨する矛盾ケンカを奨励はせぬ。むしろケンカを回避する手段として、同級生の結束が不可欠。いじめは度々国会で問題になるが、現実から目をそらす観念論が先行する点で、進行中の集団的自衛権に関する審議にそっくりだ。国連の無力や民主国家の限界を熟知し、自らの暴力に自信を深める無法国家は軍事侵攻を辞さない。かかる危機に直面する被侵略国の対抗力が万全でない場合、同盟・友好国と協力し合う-これが集団的自衛権の行使である。集団的自衛権と生徒が団結していじめに立ち向かう姿には、共通の合理性が認められる。~残念だが、子供社会は時に国際社会同様、残酷な顔をのぞかせる。侵略国は決死の覚悟で抵抗しそうな国には躊躇するが、イラク戦争時のクウェートの如く国防を怠ると、容赦なく乗っ取る。国連は大国の利害が交差し無力、主要民主主義国家も民主主義故に軍事行使をためらい、話し合い解決を目指す-と見切ると、侵略に着手する。当初こそ、国際の反応を見極めるべく侵略には自制を利かせるが、実力行使に打って出られぬ情勢を再確認するや、侵略をエスカレートさせる。(以下略)---例によってネトウヨ機関紙が集団的自衛権の擁護論を叫んでいます。でも、ここまで見れば分かるように、米国は国際社会の中では明らかにいじめっ子なのです。もちろん、米国だけがそうだとはいいませんけれど。集団的自衛権とは、米国といういじめっ子がほかの子をいじめているとき、そのいじめに協力せよ、という脅しを正当化する側面もあるのです。というより、むしろ現実に「集団的自衛権の行使」が叫ばれた実例の多くは、そういったものであったのが現実です。かつて、ベトナム戦争の際には、米国以外にも多くの国がベトナムに兵を送っています。中でも最大規模は韓国軍ですが、それ以外にも何カ国も出兵しています。それは、ベトナムへのいじめに加担することに他ならなかったわけです。もし日本がベトナム戦争当時集団的自衛権を認めていたら、日本もまたベトナムへの「いじめ」に加担していたかもしれません。そうならないで済んだのは、実に幸運なことだったと思います。残念ながら、今後は日本もいじめに加担することになりかねませんけど。
2015.07.21
コメント(6)
-

キラ・ウィルカ ライブ演奏のご案内→満員のようです
私が参加しているフォルクローレ・グループの「キラ・ウィルカ」がライブ演奏を行います。すでに予約でほぼ満員とのことです日時 9月5日(土)午後6時より(2部)場所 ペルー料理店「ティアスサナ」 総武線信濃町駅より徒歩5分料金 ライブチャージ無料(料理等を注文してください)出演 キラ・ウィルカ以前から何回か演奏させていただいている「ティアスサナ」で、2012年以来3年半ぶりの演奏です。そもそも、人前での演奏自体がほぼ2年ぶりです。↓前回、2012年4月のティアスサナでの演奏です。このグループに私が参加したのは2000年のことで(グループそのものは1997年結成)、それ以来15年間、途中に休止期間を何回もはさみながら15年間、細々と途切れ途切れに、ずっと続いています。今まで私が参加してきたいくつかのグループの中でも、もっとも長期間続いています。参加した当時はメンバー全員30代、私などは30代前半だったのですが、今ではメンバー最年長は50代に突入しています。時の流れの、何と早いことか。ちなみに、今回は、私は笛(ケーナとサンポーニャ)を中心に、何曲かギターを弾く予定です。グループに参加した当初は、私は何とボンボ(太鼓)で参加して、それから笛、続いてギター→再び笛→ギター→笛と、担当楽器がめまぐるしく変化しています。要するに、ギタリストがいなくなると私がギター担当になるわけです。フォルクローレ界は、慢性的にギター奏者が不足しているので。ティアスサナでは、過去3回演奏していますが、初めて演奏したときは、確か2ステージ16曲、すべてギターを弾いたと記憶しています。おかげ様で、このグループでは私の担当楽器は何なのか、自分でもよく分からなくなっています。↓2009年、杉並公会堂「真夏のフォルクローレ・フェスタ」での演奏
2015.07.20
コメント(2)
-

10万人は怪しいが6~7千人もウソだ
礒崎陽輔ツィート国会前に6万人、10万人、11万人の市民が押し寄せたという報道がありましたが、警察発表では5千人未満ということだそうです。道路にあふれない限り、そんなに多くの人がいる場はありません。---安倍政権としては、国会前の抗議行動を少しでも過小評価してごまかしたいところなのでしょう。なお、近年この種の集会の参加者数に関して「警察発表」はありません。ただ、警察関係者かに非公式に数字がマスコミにリークされるようです。そして、主催者発表と警察の非公式リークで、参加者数が大きく違うのはあらゆる集会、デモでほぼ常態となっています。私自身の判断では、主催者発表はその時々で違いますが、確かに時々「水増しされているな」と思う場合があります。一方で、私の体感と大きくは異ならない数字であることも少なくない。一方警察の非公式発表はというと、だいたいいつも、私の体感より少ない。たとえば、今回の国会前抗議行動もそうです。あえて言えば、確かに6万人というのは、ちょっとどうかな、そんなにいたかな、というのは私も疑問に思います。一方で警察の非公式発表※は6~7千人だそうですが、これもまた、きわめて怪しい数字といわざるを得ません。磯崎は5千人未満と書いていますが、様々なソースを総合すると、実際には警察は6~7千人と言っているようです。それこそ、磯崎は警察発表の捏造すら行っているこの日、つまり15日、私は国会前に7時過ぎに行きました。最初は官邸前、ここは人があまりいませんでした。おそらく200人か300人かくらい。そのあと、規制線だらけで移動に時間を要しましたが、国会の正面に着いたら、ここはものすごく人が多かった。ただし、私が到着したのは8時を過ぎた頃で、たまたま知人に遭遇したのですが、その前の時間はもっと多かった、ということです。この地図の、国会正面からの道路の右側、歩道から一つ目の分離帯までが人でいっぱいでした。この幅は、ヤフー地図で大雑把に計ったところ、12~13m程度のようです。私が到着した時点では、その途中からでしたが、その前の時間帯はこの道路の端まで人でいっぱいだった、とのことです。距離は170~180mありますから、面積は2000平米以上となります。私の体感で言うと、ここの混雑率は、朝の通勤電車よりはマシ(その中を、かろうじてではあるが、移動できた)、しかし帰宅時の通勤電車とは大同小異、くらいの感じでした。乗車率100%以上150%以下程度です。山手線の車両は、長さ20m、幅2.95mで、乗車率100%で定員162人(中間車)です。つまり面積59平米に162人、1平米あたり2.7人となります。1平米あたり3人とすると、この場所だけで6000人です。もちろん、道の反対側の歩道にも大勢の人がいました(ただし、反対側では車道まではみ出してはいなかった)。歩道は幅5~6mですから、2000人くらいでしょうか。そして、国会に面した歩道(地図で?と書いてある面)。ここには近付けなかったので、どのくらいの人がいたのかは分かりません。ただ、警察が「こちらはもう人がいっぱいで入れません」と言って阻止線を引いており、進もうとする人たちと押し問答になっていました。夜でしたから遠方まで見通せたわけではありませんが、実際阻止線の先にも多くの抗議者がいることは視認で来ましたから、おそらくは警察の言うとおり、満員だったのでしょう。ここは、距離が300mくらい、歩道の幅が5mくらいですから、先の乗車率の計算からは4000~5000人と推測できます。その他、地図で赤線を引いたあたり、そして赤線は引き忘れましたが財務省上にも、ある程度の人がいました。行っていませんが、おそらく自民党本部前にも、相当数の抗議者がいたのではないでしょうか。これらを合計すると、1万数千人というところでしょうか。ただし、これは同時的に国会周辺の抗議行動に参加していた人の数です。何度も書いているように、私が現地に到着したとき、どんどん帰る人がいた一方、新たに参加する人もどんどん来ていました。抗議行動の開始時間は一応あったようですが、終了時間は明確ではなく、タイムスケジュールがあるわけじゃないので、みんな好きなときに来て好きなときに帰るわけです。したがって、延べ人数は同時的な参加者数よりはるかに多かったはずです。どの程度なのかは、まったく分かりません。主催者にも分からないでしょうし、警察にも分からないでしょう。間違いないのは、いくらなんでも5回転も6回転もはしていないだろう、つまり10万人は水増しに過ぎるだろう、ということはいえます。しかし、警察の言う6~7千人もまた、明らかに過少な数字です。おそらく、その実態は、入れ替わりも含めて3万人前後というところではなかったかと思います。追記 私は、自分が土日休みのサラリーマンだから夜の抗議行動のことしか頭になかったけど、考えてみればこの日は朝から抗議行動をやっていたのです。朝から夜まで通しで参加した、という人は主催者関係者以外はかなり稀でしょう。だから、朝から通しで考えれば、5回転も6回転もは、ありえない話でもありません。ただ、おそらく日中の参加者は夜ほどには多くなかっただろうとも思いますけど。
2015.07.19
コメント(2)
-
投票とは、白紙委任ではない
デモ「だけ」では変わらない。社会を変えたいなら、政治家になりませんか?政治家がデモを恐れない、一過性のものだと考えることは、必ずしも国民の声を軽視しているわけではありません。しかし、民意として最も大事なものは言わずもがな「選挙」です。選挙で最大の信託を受けた政治家・政党の意思決定が、一時的なデモで覆るようなことがあれば、それこそ民主主義国家と言えるのでしょうか?もちろん、今の選挙制度は完璧なものではありません。一票の格差などの問題もあるし、重要政策ごとに国民投票を行い、4年間の空白を埋める仕組みも必要だと思います。それでも現行、客観的に民意を図れる唯一の方法は選挙であり、少なくとも日本はそれが制度上(不正などなく)健全に機能しています。だからこそ、民意を代表できる唯一の手段は、選挙で当選して政治家になることです。デモも憲法で認められた権利ですし、表現の自由もありますから、当然そのすべてを否定するものではありません。一定の効果はあるでしょう。しかしながら、選挙>>>デモの優先順位が政治家たちの頭の中にあるのは当然であり、むしろそうじゃなければけっこうヤバイだろうという話です。デモなどの市民運動に熱心に取り組む人たちに、「選挙に出て、政治家になった方がいいのではないか?」と直接聞いたこともあります。返ってくる答えは様々ですが、「政界の外から、意見を言う存在も必要」「もう少し力をつけてから挑戦したい」「政治家になるのは、60歳くらいになってから」というものが多かったように思います。そうした考え方を否定するものではありませんが、正直なんだか、政治(政治家)の優先順位って低いんだなあ…と感じたりします。一方でそんな彼らが意見をぶつけようとしているのは、政治家の二世三世や、強固な業界団体の支持に支えられた、政界のスーパーサラブレットたち。あるいは、地盤・看板・鞄のないところから、文字通り地べたを這いつくばって「民意」という名の票を集め、自力で議員バッヂを勝ち取った叩き上げの猛者たちです。タイプは違いますが、政治を一生の生業にしようと考えている彼らに対し、「デモ」という一瞬の風が影響を及ぼすことは、極めて難しいのではないでしょうか。(以下略)---「日本を元気にする会」という、みんなの党の流れを組む党派の音喜多駿という都議会議員のブログです。デモを全否定というわけではないものの、あまり肯定的には捕らえていないようです。しかし、「デモ『だけ』では変わらない」というのですが、そもそも「デモだけで政治は変わる」なんて言っている人がいるんでしょうか。社民党共産党も含めて、政治家でそんなことを言っている人も考えている人も、どう考えたっていないと思いますけど。選挙がとても大事だ、というのはいうまでもない話で、そのこととデモとは相互に矛盾するものではありません。たとえば、選挙運動では、政治家の演説に大勢の聴衆が集まったりします。最近の自民党は秋葉原で演説を開いて多くの聴衆を動員したりするわけですが、選挙に勝つためには、投票所で多くの人に票を投じてもらえばよいわけで、演説会に大勢の人を集める必要は必ずしもありません。演説会に多くの人が集まった候補より、全然人が集まらなかった候補のほうが勝った例だってあります(2014年都知事選)。それでも、選挙のときに少しでも多くの徴収を集めようとするのは、自民党から共産党まで同じです。それに加えてもう一つ、民意の発露の場として選挙がもっとも大事なものであることは事実ですが、選挙が民意のすべてではありません。選挙は何年かに一度しかありませんが、民意は移ろいやすいものです。2年前の選挙で得た圧倒的な議席数を背に、完全に民意から孤立して進退窮まった政権、それは、第一次安倍政権の姿であり、また民主党政権の姿でもあったわけです。もともと、現在の選挙制度は小選挙区制を貴重としており、第1党が得票数よりずっと多くの議席数を独占できる、民意を正確に反映しない制度です。自民党政権も民主党政権も、選挙では圧倒的多数の議席数を占めましたが、得票率は議席数ほど圧倒的多数だったわけではありません。そういう選挙制度の中で、選挙に勝った=政策について白紙委任された、というわけではないことは言うまでもありません。そういった、選挙結果と民意の不整合は多々あることであり、その補正の手段の一つとして、デモや集会というものもあるわけです。で、安倍首相の取り巻きから、「支持率も下がるだろうが、国民は時間がたてば忘れるだろう」という発言が出たと報じられています。ふーーん、そう思っているんだ、なるほどね。しかし、今回の安保法案は、自衛隊の海外派兵に道を開く法案です。過去の自衛隊の海外派遣では、奇跡的にも任務中の死者は一人も出ていませんが、今後はそうは行きません。死者が出る可能性はPKOとは桁がいくつも違うくらいに高い。現在想定されている海外派兵は、だいたい海上自衛隊が多いようですが、敵の爆撃でも食らって命中弾でも受けたら、一度に何十人も戦死するかもしれない。そのとき、国民の多くは、安倍が安保法案をごり押ししたことを、そう簡単に忘れるでしょうかね。
2015.07.17
コメント(8)
-

昨日も今日も国会前へ
実は、昨日も今日も国会前に行ってきました。今日は、仕事がちょっと遅かったので、国会前に行ってすぐ帰ってきましたが。昨日は、国会前でケーナの練習をしてきましたよ。今日は写真は撮ったのですが、照明のないところで真っ暗な写真しか撮れなかったので、写真は昨日のものだけです。首相官邸前。このあたりは数百人程度しか人がおらず、今日は少ないのかな、と思ったのですが・・・・・これも首相官邸前奴はここにいる・・・・・・わけではないようですね。首相官邸ですが、実際には安倍はここに住んでいるわけではないようです。規制線だらけで、思うように動けないのですが、だいぶ大回りして国会正面に出たら、そこには大勢の人がいました。通せ、通さないで警官と押し問答になっていました。私としては、抗議行動は抗議行動として、まあ警官隊も大変だなあと思います。国会正面。ここには大勢いました。安保法制断固反対!!警察の指揮車は、デモ隊に取り囲まれています。こんな人も多いところでケーナを吹く肝っ玉はないですが、その手前、人がほとんどいないところで4曲ほど練習してしまいました。ところで、こんな報道もあります。「来年夏までには国民も忘れる」 参院選、米との公約優先した強行可決首相は4月末の米議会演説で、安保法案を「この夏までに必ず成就させる」と宣言しており、今国会成立を断念すれば日米同盟が揺らぐ。反対論が強い安保法案を来年に先送りすれば、夏の参院選を直撃する懸念もある。~ただ、採決強行が支持率にどの程度影響するかは読み切れない。官邸内では「たとえ10ポイント程度下げても、(参院選がある)来年夏までには国民も忘れる。経済が良ければ回復する」(高官)と強気の声が支配的だが、一部世論調査では支持率と不支持率が逆転しており、弱含みだ。---国民の賛同も得ないのに米国で「夏までに成立させる」などと大見得を切って、それを実現しようと暴走し続ける、つまり安倍にとっては民意より米国の意向が大事、ということです。国民の命を守るためではなく、米国の忠実な下僕となるための集団的自衛権です。加えて、「たとえ10ポイント程度下げても、来年夏までには国民も忘れる。」ですか。国民は健忘症だとなめられたものです。
2015.07.16
コメント(2)
-

本日採決?
<安保法案>「戦争させない」2万人超が反対集会15日の安全保障関連法案の衆院特別委員会採決を前に、法案に反対する市民らが14日、東京・日比谷野外音楽堂で集会を開き、「戦争法案の廃案を」「強行採決は絶対反対」などと訴え、国会周辺をデモ行進した。集会は「戦争させない・9条壊すな!総がかり行動実行委員会」が主催。日比谷の会場には2万人以上(主催者発表)が詰めかけた。野党国会議員や作家が登壇して「安倍政権の暴挙と闘う」などと気勢を上げ、プラカードやのぼりを手にした市民の熱気に包まれた。福岡県八女市から夫婦で参加した無職(62)は「3歳の孫が大きくなったときに戦争に行くことがないようにしたい」と力を込めた---私も、参加しました。遅れて行ったので、野外音楽堂は満員でぜんぜんは入れませんでしたが、デモ行進には参加しました。本日衆議院で採決だといいます。参議院は、60日ルールで採決できなくてもやり過ごす算段のようです。議論を尽くすのではなく、国会の数の力で押し通そうということです。断固として反対です。
2015.07.15
コメント(3)
-
民主主義とは何か
多数決って本当に民主的? 問い直す漫画や評論相次ぐ「多数決」は民主的な決め方とされてきたが、その問題点をとらえ直そうとする漫画や評論の刊行が相次いでいる。折しも、安全保障関連法案は週内にも衆議院で採決される公算大だ。異なる意見を取り入れながら物事を決めるにはどうしたらいいのか。「主人公」は人間そっくりの女性アンドロイド。体にはカメラが埋め込まれ、オンライン中継されている。彼女の行動は、ネット上に集まった人たちの「多数決」が決めていく。雑誌「ビッグコミックスピリッツ」の漫画「デモクラティア」の設定だ。彼女を製作した技術者は言う。「動かしているのは、ネットを介して集められた“人類の英知”そのもの…だとすると…それは人間よりも人間的に正しい」作品が生まれたきっかけは、ネット世論が旧体制の崩壊につながった「アラブの春」だった。~多数決こそ民主的な仕組みと考える人は多い。「選ばれた私の言うことが民意」と言う橋下徹・大阪市長はその典型例だろう。慶応大学の坂井豊貴教授(社会的選択論)は、多数決の結果ばかりが重視される状況に危機感を募らせ、『多数決を疑う』(岩波新書)を4月に刊行した。「無邪気に多数決をありがたがるのは、ただの多数決主義。『私たち』をどうにか尊重しようとする民主主義とは違う」そもそも「民意」は選び方次第で変わる。例えば有権者21人がA、B、Cの政策のどれかに投票するとする。結果はA8票、B7票、C6票。多数決ならAが集団を代表する意見になる。だが、Aに投票しなかった全員が「Aだけは嫌だ」と考えていたとする。Aの否定派が13人と過半数なのに、採用されるのはAだ。全員から2番目に支持されても、1票にもならない。「だから多数決で勝つためには、万人に配慮してはいけない。誰かをたたいて対立構図を作った方がいい」---なかなか難しい問題ですが、私の理解では、民主主義とは、構成員が話し合って決める制度です。話し合ってどうしても決着が付かなければ多数決で決着をつける。しかし、その前提は議論を尽くすことであって、議論も尽くさずに多数決ありき、ではない、ということです。当然のことながら、多数決で勝てば、勝った側は何をやってもよいわけではないし、まけた側を無視してよいわけでもありません。さらにいえば、多数決とは善悪とか正誤を決める手段ではない、ということです。多数決の結果が間違えることもありえます。民主主義は、一歩間違えると愚衆主義、ポピュリズムに陥ると批判する人もいます。そういう傾向がないとはいいませんが、民主主義国家が決定的な破綻に至った例は、そう多くはないようにも思います。それに対して独裁国家、あるいは少なくとも民主的な制度が根付いていない国のほうが、はるかに致命的な破綻に至りやすい傾向があるのではないでしょうか。そういう意味では、民主主義はベストの政治制度とは言えないものの、少なくとも非民主的な政治体制に比べれば「よりマシ」である、ということはいえるでしょう。さて、政治における多数派と少数派、ということを考えるとき、ふとあるテレビアニメのことを思い出してしまいました。私が中学生の頃に放送されたロボットアニメで、高橋良輔監督の「太陽の牙ダクラム」です。地球から何百光年かはなれた殖民惑星デロイア星が地球から独立を計る、話で、主人公は、地球連邦政府の「連邦評議会議長」を父に持つものクリン・カシムという青年。いろいろな変転を経て、デロイア独立派のゲリラに身を投じ、父と対決する、という内容です。SFアニメなのですが、宇宙戦闘などは一切出てこず、ひたすら「デロイア星」での地上のゲリラ戦の話なのですが、この中で、主人公クリンが独立ゲリラの指導者サマリン博士と出会って話をする場面があります。父親から「地球人もデロイア人も同じ人類、なぜ二つに分かれる必要がある」と言われた、という話をした際の台詞です。「わしがきみの親父なら、やはり同じことを言っただろうなあ。…元来、政治とはそういうものだ。つまり、誰がたらふく食べられるかということに尽きている。フォン・シュタインややつらのやり口と、デロイア独立を目指す我々のやり方では、どちらがデロイア人に多くの利益をもたらすかと言うことだ。」「でも、デロイア人も地球人も、同じ仲間では」「それは詭弁だ。同じぶどうから作っても、ワインの味が違うようにな。われわれは地球にサービスしすぎた。だが、デロイアが独立して、デロイアの政府ができたとして、すべてのデロイア人が幸せになれるかというと、これまた違う。そこにはまた、必ず反対意見が出る。人間は、悲しいものだ。安住の地を求めながら、永遠にそれを手にすることができずにいる。ま、だからこそ人類は進歩するといえるか。わしが目指しているのは、そういうとき、少数の意見であっても多数の中に充分反映できる社会を作るということだ。このコーヒーと砂糖のようにな。大いなる試練だが、そうなってはじめて人類は政治を持ったといえるだろう。100人のために2人を切り捨てずに済むということだ」https://www.facebook.com/Dougram/videos/388791914522539/※以前YouTubeに動画が上がっていたのですが、削除されたらしく、今はFacebook内でしか見られないようです。たかがロボットアニメというなかれ、政治のあるべき姿、理想とすべき姿について、これほど分かりやすく簡潔にまとめは言葉はない、と私は思います。今の時代だったら、ネトウヨが「サヨクアニメだ」とか騒ぎ出して、とても放送できなかったでしょうね。当時も視聴率は高くはなかったようですが、ロボットアニメは視聴率そのものより、スポンサーの販売する玩具の売り上げに左右され、この作品は売り上げが好調だったのか、75話という長さが打ち切りになることもなく最後まで放送されています。(余談ながら、この台詞はこの作品全体として、最後の展開の重要な伏線にもなっています)まあ、言うは易く行うは難いことではあります。少数の意見であっても多数の中に充分反映できる社会は、そうそう簡単には実現できるものでもありません。が、それでも目指すべき方向として、1票でも多数を制して勝った、だから、敗者は全排除だという方向性であるべきではない、ということはいえると私は思います。それは、時には優柔不断に見えたり、「決められない政治」に見えたりするかもしれない、でも、少数意見を切り捨てて、国会の議席数だけをたよりに、ろくに議論も尽くさずに多数決を振りかざす「決められる政治」より、間違えたときの傷ははるかに浅く済むのではないかと思います。
2015.07.14
コメント(2)
-
集団的自衛権についての根本的勘違い
百田尚樹氏:「偏向メディアが支配」 沖縄2紙にまた持論 /沖縄~琉球新報と沖縄タイムスの2紙について、「極めて偏向した『アジビラ』のような記事ばかり掲載し、両論併記の原則をあまりにないがしろにしている」と主張。「反米感情をあおることが目的」「中国に対しては『素晴らしい』と礼賛するばかり」「2紙は自らの政治的メッセージばかりを沖縄の人たちに押し付けてきた、中国べったりの左翼機関紙」などと批判した。---なるほどね、しかし、残念ながら、「琉球新報と沖縄タイムスの2紙」を「産経新聞」に変えて、「中国」と「米国」をひっくり返すと、そのまま、産経新聞についての解説になってしまうんですね。産経はどう考えたって右翼のアジビラ、それ以外の何者でもない。かつては反ソ感情、今は反中感情をあおることが目的でしょ。最近は、反韓感情も、かな。米国のすべてを礼賛はしていないけど、日米安保体制は無批判に礼賛してます。両論併記なんて、産経はもちろん、その他の新聞もあんまりやらないですね。その産経新聞は、一連の百田をめぐる騒動について、当初は批判的な姿勢を見せていたものの、今では完全に本性をあらわにしています。安保関連法成立は、中国の尖閣占領によるオメザの後?国会審議中の安全保障関連法案に、左翼は《戦争法案》のレッテルを貼り「いつか来た道」だと叫ぶ。小欄は《戦争抑止法案》と思うが「いつか来た道」をたどる懸念は否定しない。もっとも、戦前ではなく戦後の「いつか来た道」。自民党の勉強会で講師に立った作家・百田尚樹氏の勉強会では、安倍晋三政権が成立を目指す安保関連法案に異常に厳しい沖縄県紙への批判が噴出した。百田氏は「沖縄県人がどう目を覚ますか」と同調した上で続けた。戦後の安全保障関係法は「あったらいけないこと」が起きる度、それが起点となり整備されてきた。海外の危機が日本に波及しそうな気配に仰天し、ひねり出した《後追い法》だった。左翼の扇動を真に受け、凶暴な中国や北朝鮮より、安倍氏主唱の《積極的平和主義》のような国際スタンダードを疑い恐れる宿痾が国民に取り憑き離れぬせいでもある。ただ結局、実効性逓減と引き換えに成立。反対した国民の多くも、頭が冷えると自衛隊の新任務に対する抵抗感がフェードアウトしていく。ところが憲法を人質に取られ骨抜きにされた法律は、国際情勢変化にも兵器の進化にも耐えられぬ。欠陥法の穴を埋めるべく新たな欠陥法を創る負の連鎖は続く。現行憲法が在る限り今次安保関連法案も抑制的で欠陥を有す。~今次安保関連法案はやや様子を異にする。中朝の脅威に突き動かされた力学は働いたものの、力に陰りが観える米国の動きを先取り、同盟・友好国との連携を自発的に決心した。内容も、国際常識の背中すら見えない立ち位置を、視認可能な場所まで進め、集団的自衛権のほんの一部を憲法の範囲内で行使する《集団的自衛権モドキ法案》に仕上がった。~好機にもかかわらず、国民の今次安保関連法案に抱く警戒感は強く、世論調査では「説明が不十分」との声が多い。同種の法案に浴びせられる「いつもの声」。確かに法案は難解だが、国民の側も年金問題同様内容を吟味し、雑音を遮断し、政府の説明を聴いているのか。《戦争を起こす法律》は断じて許されない。しかし《戦争ができる法律》が不備では、抑止力が機能せず戦争を未然に防げない。感情やムードに流されていると、この理屈が分からない。---長いので要約しましたが、長ったらしいばかりで中身の乏しい主張です。要するに、中国が尖閣諸島を占領すれば日本人の目も覚めて、みんな安保法案に賛成するだろう、ということです。でも、何度も書いたことですが、集団的自衛権とは、自国が直接攻撃されていなくても、友好国が攻撃されたらそれを自国への攻撃とみなして、共同で反撃する権利のことです。日本の領土を他国が攻撃する事態への対応は、明らかに個別的自衛権に属する問題です。そして、従来の政府の見解でも、個別的自衛権は否定されていません。当然、万が一そのような事態が発生した場合は、政府は自衛隊を出動させるでしょう。そのことと集団的自衛権は、全然関係のない話なのです。それとも、安保法案が成立するまでは、自衛隊は動けませんとサボタージュさせておいて、安保法案成立を誘導しようという作戦でしょうか。もっとも、人の住む島ならともかく、無人島を巡って戦争をやって死者を出すなんて、バカバカしいことではあります。そんな事態を招かないようにすることこそが政府の重要な役割であるはずです。そして従来の日本政府は、無人島の取り合いで武力衝突などという事態に至ることがないよう、しかし尖閣諸島を実効支配しているのが日本であることをさりげなく世界に示す、実に巧妙な立ち回りを見せてきました。最近はそのあたりが危うくなってきていますけど。本題に戻りますが、いくら産経新聞だって、日本の領土に中国軍が攻め込んできたら、それに対応するのは集団的自衛権の範疇ではなく、個別的自衛権で対応できることだ、というくらいのことは、分かっているはずです。それらも関わらず、平然と、こうやって中国が尖閣を占領したら、などとデマを書く。まさしくアジビラそのものと言うしかありません。
2015.07.13
コメント(2)
-
無責任体質
新国立競技場 コスト確認せず決定か改築費が2520億円に膨らんだ国立競技場について、デザインを決める最初の審査の過程で、技術的に建設が可能かどうかチェックされたものの、設定したコストに収まるのかどうかの確認は、事実上行われずに決まった可能性が高いことが関係者への取材で分かりました。新国立競技場のデザインは2020年東京オリンピック・パラリンピックの招致活動が行われていた3年前の7月、競技場を運営するJSC=日本スポーツ振興センターが、「総工事費は1300億円程度を見込む」と設定して募集し、応募した人たちもこの金額に収まることを示していたということです。このあと、建築家の安藤忠雄さんを委員長とする審査委員会が3回開かれ、46の応募作品からイラク人女性建築家のデザインに決まりました。この過程では、1回目の審査委員会のあとに委員会のメンバーとは別の専門家たちによる「技術調査」が行われました。この際に、それぞれのデザインで技術的に建設が可能かどうかのチェックはされましたが、設定したコストに収まるかどうか確認していなかったことが、関係者への取材や当時の資料から新たに分かりました。さらに、委員会の議事録や当時の審査委員への取材によりますと、その後の審査では一部の委員からコストを懸念する声があったものの、複数の審査委員が「技術調査」でコストの確認も同時に行われていたと思ったということで、最後は、オリンピック招致のためのインパクトを優先して今回のデザインが選ばれたと見られています。1300億円と設定されたコストの確認が事実上されないまま、デザインが決まった可能性が高く、その後金額が二転三転した要因になったとみられます。 ---なるほど、そもそも総工費が基準内に納まるかどうかをチェックせずにスタジアム案を決めてしまった、というわけです。そんなところだろうなと想像していましたが、やっぱりです。これについて、もうちょっと掘り下げた記事もありました。「新国立競技場は建てちゃダメです」この問題について、建設計画のずさんさを批判し、「建てちゃダメです」とブログで訴え続けているのが、一級建築士で『マンガ建築考 -もしマンガ・アニメの建物を本当に建てたら―』などの著作もある、森山高至さんだ。なぜ、ハディド氏の原案、JSC案にも反対しているのか。新国立競技場をめぐる今の混乱は、なぜ起こったのか。話を聞いた。(中略)――まず、問題になったきっかけは予算でした。当初、1500億で作ろうとしていたものが、実際に見積もったら倍近くかかることがわかった。この見当違いというのは、どうして起きたんでしょうか。デザインしたハディド氏が間違えていたのか、それともJSCが提出作品をきちんと評価できなかったのか。ザハが間違ったと思います。おそらく、彼女は予算を考えず、「私だったらこうするよ」という案を出した可能性が高い。コンペでは、ルールを破る案を出す人もいるんです。理由はいろいろあって、選ばれることを度外視で目立とう、という人もいるし、コンペそのものの要項や仕組みに異議を申し立てるためにあえて違反した案を出すっていうケースもある。たとえば、新宿都庁のコンペの時に磯崎新さんがあえてコンペの要項を無視した案を出したのは、抗議の意味を込めていたからです。今回のザハの場合は前者で、「どうせ自分は選ばれないから自由にやろう」という気持ちはあったと思います。自分の作家性をアピールする場として応募した。予算の妥当性は二の次だ、という考え方ですね。――たしかに、ザハ案以外でも、屋根全体が森になっていて木が埋えられているものとか、素人目で見ても予算、維持を考えたら難しそうだな、というものも最終選考に残っていましたね。そう。僕がずっと問題にしてるのは、審査する側が実現性をまったく考慮しないで選んでいることなんです。審査員の方も実績のある先生方だから、ちゃんとしてるんだろうってみんな思いますけど、どんな有名な方でも得意分野は違いますから。たとえ話ですけど、立派なお医者さんでも脳外科の人に歯を診せたら、絶対失敗しますよね(笑)――ある分野では立派でも……そうです。今回は(審査委員長の)安藤忠雄さんが、本来ああいう施設に精通されてない、そのことが大きな要因だと思います。著名人で、気さくな人で、政財界とのパイプもあるから、ふさわしいだろうっていう判断で審査委員長に推されたのではないかと。一方で、建築の技術的な問題や実現性には疎く、本来、それを補うために意見を求められた他の先生方も、自分の意見を言えずに流されたということだと思います。このことは、東大名誉教授の内藤廣さんがはっきりそう仰られてます。「決め方が拙速だった」と。(以下略)---私は、建築関係に疎いので、安藤忠雄が「ああいう施設」つまり巨大スタジアムを専門分野にはしていない、ということははじめて知ったのですが、おそらく建築業界では周知のことだったのでしょう。しかし、私でも名前は知っているくらいで、建築家としての知名度は抜群であることは間違いない。実より名を優先して審査委員長に据えたということでしょうか。そして、それを補うはずの、巨大スタジアムを専門分野とする審査委員も、場の雰囲気に流されて意見を言えなかった、と。別の報道によれば、最終選考では委員の間で4対4で意見が割れてしまい、最終的には安藤の「ツルの一声」でザハ案に決まったとのことです。その最終決断に当たって、予算というもっとも重要な要素がないがしろにされていたというのですから、専門家がそろいもそろって何をやっていたんだと言うしかありません。しかも、この新競技場は、実は陸上競技の国際大会の基準を満たさない代物なのだそうです。為末大オフィシャルサイト新しい国立競技場はサブトラック(ウォーミングアップのためのグランド)がありません。五輪本番は仮設のもので行うようですが、その後は撤去される予定で、そうなると陸上競技の世界大会をルール上(サブトラックが必要)ひらくことができません。陸上選手としては国立競技場は陸上競技場でもあってほしいので、サブトラックがない案に反対です。---つまり、オリンピック終了後仮設サブトラックを撤去した後は、陸上競技の国際大会にはつかえない、それを国立「競技場」と呼ぶのは、名前に偽りあり、とさえ言えるのではないでしょうか。実質はラグビー場でありイベントホールであると。誰も責任を負わない、どこに責任の所在があるかあいまいなままで、2520億円が使われようとしているわけです。しかも、2520億で済むかどうかも定かではないようです。今から別の案に変えるのは時間的に間に合わない、といわれるのですが、実際のところ、この案で2019年までに完成できるかどうかも定かではないと言われています。私の推測では、そこは日本ですから、何としても期限内に完成はさせると思います。が、それによる費用の増大は避けられないでしょうから。で、安倍首相はこの問題について、民主党政権時代に決まったことと言っているそうです。確かに、民主党政権に何の責任もなかった、とは言いませんが、その言い分はどうなの、と思わざるを得ません。民主党政権時代決まったとはいえ、予算超過はその時点では顕在化していませんでした。それが露わになったには安倍政権になっったあとの2013年のことで、それ以降の予算圧縮については、現政権の責任に属することでしょう。3000億円から1600億円に減らすと言っておきながら実際には2500億もかかるというのは、自民党政権になってからの話ではないですか。それに、新国立競技場の建設に関しては、自民党の森元首相の暗躍を指摘する声も多いようです。
2015.07.12
コメント(7)
-
唯我独尊
学者と政治家の責任違う…ネット番組で野党批判安倍首相は10日、自民党のインターネット番組で、安全保障関連法案を憲法学者や一部野党が「憲法違反」としていることについて、「憲法学者と政治家の責任は違う。『憲法学者が反対だから私も反対だ』と言う政治家は、自分の責任を憲法学者に丸投げしている」と述べ、野党の対応を批判した。民主、維新両党が国会に共同提出した領域警備法案には「もう少し早く出してほしかった」と述べた。---「憲法学者が反対だから私も反対だ」と言っている政治家がいるのでしょうか。自民党の推薦した憲法学者でさえ、安保法制は憲法違反だと憲法審査会で明言した、という事実に、野党は大いに勢い付いたことは事実としても、憲法学者の主張だけを理由、契機として反対しているわけではないこともまた、自明のことだと思いますけど。それに、法律に関しては法律の専門家の言い分というのは重いものです。責任が違うからと、じゃあ政治家は国会で過半数の賛成さえ得れば、どんな好き勝手な法律でも作れるんですか?作っていいんですか?憲法と法律の整合性というのは、やはり専門家の意見は重い。どうしても集団的自衛権が必要だというなら、(私は大反対ですが)憲法を改正するしかないでしょう。反対しているのは憲法学者だけではありません。世論調査では国民の大多数も反対している。その中で野党の政治家も反対している、と言うのは「自分の責任を憲法学者に丸投げしている」などというものではありません。安倍政権こそ、所属議員に対して、テレビの討論番組には出るな、とか、アンケートには答えるなとか、議論の場、意見表明の場を自ら放棄して、ただ数の力で押し通そうとしている態度がミエミエです。自民党のインターネット番組って、要するに自分の息がかかっている身内の宣伝媒体でしか説明しようとしないという時点で、多くの国民の不安、疑問に答えようという態度を自ら放棄しているとしか言いようがありません。何度も書いていることですが、日本国憲法は、個別的自衛権は否定していないというのは、従来の日本政府の一貫した憲法解釈です。「敵が攻めてきたらどうする」というのは、個別的自衛権に関する話ですから、集団的自衛権とは関係がない。集団的自衛権(今回の安保法制)は、日本が直接攻撃されたわけでもないのに、日本の友好国(つまり米国)が攻撃されたら、それが日本の領土領海以外の場所であっても、日本が攻撃されたものとみなして、共同で反撃する権利のことを指しています。事実上は、米国が世界でおこなう戦争に参加するための集団的自衛権、と言ってもいいでしょう。日本が攻撃されていないのに攻撃されたものとみなす時点で、「自衛のための最低限の行為」ではないことは歴然としており、従来の日本政府の憲法解釈においても、一貫してそれは憲法上許されないとされてきました。それを、昨年安倍政権は、憲法改正の手続きを経ずに、政府の憲法解釈変更だけで「合憲」と言い換えてしまった。それに伴う立法措置が今回の安保法制というわけです。憲法改正に必要な手続き(国民投票も含む)を経ずに、国民大多数の反対も無視して、国会の議席数だけを頼りにこの法制を、あくまでも押し通すのだというわけです。これを唯我独尊と言わずして、何と言うのでしょうか。
2015.07.11
コメント(2)
-
生活保護以下、ではない
新幹線焼身自殺テロ 年金を35年間払っても生活保護以下〈週刊朝日〉6月30日午前11時半頃、男は神奈川県小田原市付近を走行中の東海道新幹線「のぞみ225号」の先頭車両でガソリンをかぶり、焼身自殺を遂げた。一種の“自殺テロ”といえる行為で、炎は天井が焼け落ちるほどだった。逃げ遅れた女性1人が死亡、28人が重軽傷を負う大惨事となった。「今年の春ごろに空き缶回収の仕事を辞めて、6月から年金だけの生活になると話していました。『年金が少ない』とよく言っていて、滞納があったのか、国民健康保険や住民税で6万円も払わないといけないと怒っていました」杉並区の生活保護基準は14万4430円だ。しかも、生活保護の場合は国民健康保険や住民税などの負担が減免される。つまり、容疑者は35年間も真面目に年金を納めたにもかかわらず、生活保護水準以下の12万円の支給しか受けられない「下流老人」だった。アパートの大家によると、1年ほど前に「生活が苦しいから家賃を下げてほしい」と言われ、千円下げたという。ただ、支払いは2カ月分のまとめ払いだったが、「遅れたことはなかった」と話す。(以下略)---生活保護制度に詳しい知人に聞いてみたところ、もちろん正確なところは分かりませんけれど、この人の年金収入は保護基準をわずかに超えるのではないか、ということです。引用記事には、杉並区の保護基準は14万4430円とありますが、これは70代の単身者が住宅扶助(家賃)の特別基準を認められた場合の上限額なのだそうです。問題の犯人のアパートは、家賃4万円と報じられています。生活保護の住宅扶助は、実費額が基準となるそうです。(実費額が基準の上限を超える場合は基準の上限額)4万円の家賃のアパートに住んでいれば、住宅扶助は4万円。それより高い額になることはありえないとのことです。生活扶助基準は70代以上で東京23区では74630円。住宅扶助とあわせると11万5千円くらいが保護基準とのことです。年金は月額で12万と報じられています。12万何千円か、介護保険料はいくらで、年金から天引きされていたかどうか、国民健康保険料はいくらか、などにもよるようですが、一般的には年金が12万円もあれば介護保険料は年金から天引きされている(介護保険料特別徴収)はずで、もし年金の手取額が12万円台で、医療費がかかっていなかったとすると、かなりギリギリだけど保護基準より若干収入は上だったのではないか、ということです。ただ、医療費がかかっている場合、保護基準より収入が多くても、生活保護の対象になる場合はあるそうです。医療費自己負担と言って、たとえば、保護基準が10万円で収入が11万円だと、健康で医者にかかっていない人は生活保護の対象にならないけれど、医者にかかっている人の場合、保護基準と収入の差額分(この例では1万円)だけ医療費を自己負担すれば、それを越える部分は生活保護で医療費を出す「医療費自己負担」という生活保護のかたちがあるのだそうで、その対象にはなりえたかもしれない、との話でした。もっとも、その場合も生活保護による現金の支給はまったくないし、だいたい、医療費がかかっていない人なら、対象にならないですけど。この容疑者がいわゆる下流老人だったことは疑いないものの、その年金が生活保護基準以下、というのは違うのではないか、というのが知人の見解でした。ちなみに、生活保護の基準額は一部自治体のホームページに掲載されています。たとえば、東京23区(1級地の1)の保護基準はこれです。
2015.07.09
コメント(4)
-
2500億の新国立競技場
新国立競技場:突出した総工費 有識者会議「縮小」に反発総工費2520億円に上る新国立競技場の計画が7日、事業主体の日本スポーツ振興センター(JSC)の将来構想有識者会議で了承された。昨春の計画を900億円近く上回る大幅なコスト増に会議では異論がほとんど出ず、むしろ新たな出費につながる意見が相次いだ。「価格についてはここまで圧縮され、私は妥当だと思う」。大会組織委員会会長の森喜朗元首相は評価した。総工費は13年9月の五輪招致段階で1300億円と見込まれたが、建設資材高騰などを背景に同10月、3000億円の見通しが表面化した。見直しが進められ14年5月に1625億円に下げられたが、先月公表された計画で再び2520億円に膨らんだ。2520億円を導くためJSCと文部科学省は、開閉式屋根(遮音装置)設置を大会後に先送りし、常設8万席のうち1万5000席を仮設に変更してコストダウンを図ったが、委員は「計画縮小」に反発した。JASRACの都倉俊一会長は、五輪後にコンサート会場として活用する構想を踏まえ、遮音装置先送りに不満をあらわにして早期設置を訴えた。日本サッカー協会の小倉純二名誉会長は、W杯招致を見据えすべての座席を常設とすることを要望した。過去の五輪主会場の総工費は08年北京大会が540億円、12年ロンドン大会も837億円で、新国立競技場は突出している。16年大会招致に携わった鈴木知幸・順天堂大客員教授は委員の発言に「自分たちの思い入れで言っているだけで、経費や将来構想の視点がない。先々のことまで憂慮して話しているのか」と疑問を呈した。一方、文科省を批判していた東京都の舛添要一知事は「技術的な点を判断するのは私にとって不可能に近い。文科省、JSCの責任で間に合うよう、しかるべきものを完成させていただくことをお願いする」と述べるにとどめた。建築家の安藤忠雄氏は会議を欠席した。遠藤五輪担当相は8日、東京都庁で舛添要一知事と会談し、新国立競技場の建設費の一部負担を要請する。舛添知事は7日夜、記者団に「協力要請を受けて、どうするか考えたい」と語った。---この問題は、3000億の見積もりが出た当時、批判する記事を書いたことがあります。常軌を逸した金額3000億が2500億に圧縮されたのでめでたしめでたし、というわけにはいきません。そもそも、最初は1300億、それが3000億に拡大、批判されて1600億に縮小したけど、結局やっぱり2500億円と、どうしてこう見積もりが二転三転するのか。要するにその場しのぎのデタラメな見積もりとしか言いようがありません。しかも、引用記事にはありませんが、別報道によれば、維持費が50年間で1000億円以上、つまり年間で20億円もかかるそうです。サッカーのワールドカップを今後何回やるつもりなのか、8万人を集める音楽コンサートが、いったいどれほどの頻度で開かれるのか、ということを考えると、JASRAC会長やサッカー協会名誉会長の言い分は、費用対効果という視点をまったく欠いているとしか言いようがありません。「価格についてはここまで圧縮され、私は妥当だと思う」と言い放った森元首相に至っては、あきれてものも言えません。2500億円という巨額、過去のオリンピック会場と比べても異常に高価な建設費を「妥当」と言う感覚はいったい何なのか。要するに、今のアベノミクスもそうですが、公共事業にどんどんお金を注ぎ込もう、それによって利益誘導を計ろう、ということとしか思えません。民主党政権時代の子ども手当てや高校無償化がばら撒きだと散々批判されました。私自身も、子ども手当ては賛成ではありませんでした(高校無償化は賛成ですが)。でも、2500億円のオリンピック会場だって、バラマキだよねえ。その負担は、結局国民にのしかかってくる。しかも、東京都にも建設費の一部負担を求める、ともあります。私は東京都民なので、冗談じゃないよ、と思うんですけどねえ。
2015.07.08
コメント(2)
-
世界遺産のインフレ
明治の産業遺産の登録決定 「徴用工」表現、日韓が合意ドイツ・ボンで開かれているユネスコの世界遺産委員会は5日、「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」を全会一致で世界文化遺産に登録することを決めた。一部の炭鉱などで植民地時代に朝鮮半島出身者が動員された「徴用工」の説明をめぐって日韓が対立していたが、合意にこぎつけた。審議では、日韓それぞれが英語で発言。日本側は徴用工について、1940年代に「その意思に反して(against their will)」一部資産に連れて来られ、「厳しい環境で働かされた(forced to work under harsh conditions)」と言及。「犠牲者を記憶にとどめるために適切な措置を説明戦略に盛り込む」と表明した。---政府声明「強制労働の存在認めていない」…外相岸田外相は7日の記者会見で、世界文化遺産に登録される「明治日本の産業革命遺産」に関する政府声明について、「強制労働があったと認めるものではない」と述べた。声明には、一部施設で戦時中、朝鮮半島出身者らについて「forced to work(働かされた)」と盛り込まれ、韓国内で「日本が譲歩した」との見方が出ている。岸田氏は「当時、国民徴用令に基づく徴用が行われたことを記述したもので、何ら新しい内容を含んでいない」とも語った。---どうも、私には、岸田外相の言い分(というより、従来の日本政府の公式見解)は、ごまかしがあるように思うのです。「国民徴用令に基づく徴用」を英語で表記したら「forced to work against their will」となったわけです。ところが、その英語訳を日本語に戻せば「意思に反して労働を強いられる」つまり「強制労働」になるのです。ということは、「国民徴用令に基づく徴用」の実態は強制労働そのものだった、ということでしょう。実際問題として、「徴用」の実態がほぼ強制労働であったことは歴然としています。というと、ネトウヨ系連中は、「宿舎があった」とか「給料を支払った」とか、「日本人も徴用の対象だった」とか叫ぶのですが、世界史的に見れば、給料をもらう奴隷などいくらでも例がありますし、もちろん宿舎だってありました。給料をもらえば強制労働ではない、などという理屈は成り立ちません。日本人も徴用の対象だったといいますが、本質的にいえば、もちろん日本人の徴用だって強制連行のようなものでしょう。勤労動員で軍需工場などに駆り出された中学生などの、過酷な経験はよく聞きます。私の父も、敗戦時小学校4年生でしたが、学童疎開先で勤労奉仕はやらされていたようです。ただ、日本人にとっては、太平洋戦争は「自分たちの戦争」だったから、徴用でひどい目にあった人でも、それを「強制連行」とまでは表現しないだけです。独立を奪われて日本の戦争に参加させられた朝鮮人にとって、太平洋戦争は「自分たちの戦争」であるはずがなく、徴用を「強制連行」と表現することに遠慮があるはずがない。また、日本本土で、基本的には自宅または疎開先の近辺での動員された日本人と、海を越えて日本まで連れてこられた朝鮮人(もちろん、全員が日本に連れてこられたわけではないが)では、過酷さにおいて同等とはいえないでしょう。もっとも、従軍慰安婦問題もそうなのですが、被害を受けたのは最終的には個人です。それが、何故か国家間の挑発合戦の材料のように扱われているのは、これは韓国側の行動に関しても、どうも違和感を感じざるを得ません。それはそれとして、私は軍艦島の世界遺産登録には、どうも「いくらなんでも世界遺産のインフレが過ぎないか?」という印象を抱いてしまうのです。たとえば、知床、白神山地、京都、奈良、法隆寺、屋久島などは、実に世界遺産の名にふさわしい場所だと思います。厳島神社、平泉、日光の社寺なども、まあまあ良いでしょう。方向性はまったく逆ですが、原爆ドームも世界遺産にふさわしい(負の世界遺産かもしれないけど)。しかし、あえて名を出すと、富士山はやや疑問符が付きます。それでも、日本で一番有名な山だし、霊山であることも事実だから、ギリギリ許容範囲ですが、石見銀山、富岡製糸場、そして今回の軍艦島は、どうも私としては疑問符がいくつも付きます。それを世界遺産と言われても、という感じです。何というか、観光地の新規開発事業のようで、どうも「世界遺産」の重みが感じられないのです。ところで、世界遺産の一覧表を見ながら、私自身が行ったことがあるのはどことどこかなと数えてみました。日本国内知床・平泉・日光・富士山・京都・奈良・法隆寺、それに、今回指定された一連の遺産の中で萩城下町は行ったことがあるメキシコメキシコ市歴史地区・ティオティワカン・オアハカ・プエブラ・グァナファト・モレーリア・グァダラハラのカバーニャス孤児院・UNAM大学年中央キャンパスチリ バルパライソペルー クスコ・マチュピチュ・リマ歴史地区ボリビア ポトシ・ティワナクうーーん、実は結構行っていることに気が付きました。
2015.07.07
コメント(2)
-
ギリシャ国民投票
ギリシャ:国民投票「ノー」疲弊国民が選んだ「尊厳」ギリシャ国民は5日の国民投票で、EUなど債権者側が金融支援の条件として提示した財政緊縮策に「ノー」を突き付けた。背景には、5年に及ぶ緊縮策で経済の疲弊が長引く中、若者を中心に高まる「反緊縮」の機運がありそうだ。未来に希望を見いだせない国民の多くは、欧州他国からの「ユーロ圏離脱につながる」との警告に屈するよりも、チプラス首相の掲げる「ギリシャの尊厳」を選んだ形だ。政府統計によると、ギリシャのGDPは、債務危機を受けて緊縮策が導入された2010年から14年までに25%も縮小した。景気の冷え込みで企業が新規採用を控えているため、25歳未満の若者の失業率は国民平均(25.6%)の倍にあたる49.7%に上る。国民投票前の世論調査によると、若者の8割は反対派だったとされる。また、緊縮策によって拡大した貧富の格差も投票行動に影響を及ぼしたとみられる。首都アテネの中心部ではEU案への賛否が拮抗したが、労働者や低所得層の多い地区では反対が多く、地方の大半で反対が賛成を大幅に上回った。---ギリシャでおこなわれた緊縮財政への賛否を問う国民投票は、事前予測では賛否が拮抗と言われていましたが、ふたを開けたらダブルスコアに近い大佐で反対多数となりました。少し前にギリシャをめぐる問題について記事を書きました。ギリシャ破綻かその中で、「IMFのやっていることは間違ってばかりです。が、しかし放漫財政でよい、というわけでもありません。」と私は書きました。大筋では現在もそう思っていますが、ただ、その後いろいろと調べた中で、ことはそう単純でもないことに気が付きました。まず、ギリシャが放漫財政で財政危機を招いたことは事実ですが、危機が表面化した2010年以降は、厳しい緊縮財政を4年間に渡って続けてきています。年金の大盤振る舞いとか、公務員が全労働人口の1/4を占めるとかが非難の対象となっていますが、それらはいずれも2010年以前の話となっているようです。年金は、こちらの記事によると、ギリシャの平均年金受給額は月額833ユーロ。2009年時点の同1350ユーロからは減少している。政府はまた、年金受給者の45%は貧困ラインの665ユーロを下回る額しか受け取っていないとしている。~過去の政権も年金問題に取り組んできた。2010─14年に年金受給額は平均で27%、最大で50%カットされた。2013年には定年退職年齢が平均で2年引き上げられた。ギリシャは年金前倒し受給をさらに制限する意向を示している。ということです。また、緊縮財政の結果、公務員はかなり削減されており、かつ早期退職を選択した人も相当多い(緊縮財政の始まった当初、2日間で1万人が辞表という報道もありました)。つまり、すでにギリシャは以前の放漫財政のギリシャではなくなってきつつあるわけです。加えて、ギリシャの経常収支は2013年には黒字化し、財政赤字も急激に減少しています。つまり、今のギリシャは、すでに2010年以前の放漫財政の国ではなくなりつつあるわけです。ところが、この間ギリシャのGDPは引用記事にもあるように25%も縮小しています。緊縮財政の結果、経済が疲弊して激しいマイナス成長に陥っているわけです。単年度で財政赤字を減らしても、それ以上にGDPが減少すれば、累積赤字(国債発行残高)のGDP比は全然下がりません。借金を減らしても減らしても、それ以上に経済のパイが小さくなっていくのでは、いくらやっても借金は減らない。つまり解決はできないわけです。それなのに、もっと緊縮しろとEUはいう。それは、結果としてもっとGDPを減らせというのとおなじことであり、その方向性でいくら頑張っても、問題は解決しないと多くのギリシャ人が判断した、ということでしょう。それにしても、日本では高齢者は守旧派だ、既得権者だ、高齢者から選挙権を取り上げろみたいな暴論がまかり通っていますが、ギリシャにおいては若者ほど緊縮財政案に強く反対しているということです。とはいえ、金がない、「ない袖は振りようがない」という現実は動かしがたいこともまた事実です。もはや融資を受けられる望みはなく、独自通貨ではないので、通過切り下げでインフレを起こして切り抜ける手も使えない。脱緊縮財政といっても、それをどう実現するか、という点はなかなか見通しが立たないことは、否定しがたいのが現状です。
2015.07.06
コメント(6)
-
クジラがよくて、犬がいけないという法はない
中国で「犬肉祭」…「何が悪い」と1万匹、盛大に食べ尽くす 世界から約400万人が抗議「犬食いねぇ!」とばかり、中国南部の町で6月下旬、「犬肉祭」が繰り広げられた。2日間で胃袋に収まったされる犬は約1万匹。世界の動物愛護団体などの猛抗議を受けながらも、住民らは「伝統の食文化。どこが悪い」とどこ吹く風で、盛大に食べ尽くしたという。犬肉祭が開かれたのは、ベトナム国境に近い広西チワン族自治区玉林市。夏至に合わせた恒例行事だ。米紙ニューヨーク・タイムズは現地ルポを掲載している。通りにはたくさんの食卓が並べられ、皿には犬料理がてんこ盛り。その裏で、狭い檻に詰め込まれた犬たちが次々に撲殺され、大鍋で調理されて行く。その過程を黙々と撮影する反対派の活動家と、活動家たちの動きを監視し続ける怪しげな男たち…。異様な敵意と緊張感が漂う犬肉祭の様子を伝えている。「あまりに残酷だ」と、開催反対を訴えるサイトへの署名は世界的に約400万人に達したという。しかし、住民らは「アメリカ人は七面鳥を食べる。許されるのか」と反論。インターネット上では、牛や豚は良くて、なぜ犬はいけないのか-などと、西洋的価値観の押しつけ、偽善だと反発する声も少なくない。実は別の問題もある。年間1千万匹とされる中国の犬肉需要。「養犬場」だけでは足りず、犬肉業者がペットの犬を盗んだり、不衛生な野犬を集めたりしているという。金儲けのための犯罪行為であり、犬泥棒に批判は強まる。そもそも養犬場の存在自体も驚きだ。同紙では「日本人はカエルの刺身を食べている」なんて頓珍漢な現地の反論も紹介しているが、それはさておき、韓国や東南アジアでも滋養強壮に効くとして、犬肉食は残っている。食文化をめぐる論争は、“犬も食わない話”で終わるわけにはいかないようだ。---例によって産経新聞の記事ですけど、世界の動物愛護団体が「日本の捕鯨はけしからん」と言うと顔を真っ赤にして怒ってみせる産経新聞も、世界の動物愛護団体が中国の犬食を批判すると、そうだそうだとばかりに、尻馬に乗って見せるわけです。まったく馬鹿馬鹿しいまでのダブルスタンダードです。私の相棒は、犬大好き人間なので、犬を食べるなんて聞くと目を三角にしてしまいそうですが、私自身は、自分が食べたいとは思わないけど、目くじらを立てるべきものとは思いません。まさしく、牛や豚(七面鳥でも)を食べてよいのに犬を食べてはいけない、なんて理屈はとおらないよなと思います。その理屈をとおすなら、まさしく、鯨やイルカを食べることも許されないということになる。いや、牛も豚も七面鳥も犬も、家畜(家禽)ですから、乱獲で生態系を破壊するという危険はないのに対して、クジラやイルカは野生生物ですから、乱獲は生態系を破壊しかねないという危険もあります。(ただし、現在では一部の種を除いて、クジラやイルカは絶滅の危機にあるわけではない)その裏で、狭い檻に詰め込まれた犬たちが次々に撲殺され、大鍋で調理されて行く。とありますが、動物の肉を食べる、というのはそういうことでしょう。われわれが日常生活で食べている牛豚鶏肉は、どこかの工場で肉の形で自動的に生まれてくるとでも思っているのでしょうか。単に屠殺されるところを一般の消費者は見ていない、というだけの話です。そういえば、ラテンアメリカでも、先住民色の強い地域では、市場で生きたまま鶏が縛り上げられて転がされて売られているのを見かけることがあります。買ったその場で絞めてしまうのか、家に持ち帰ってから絞めるのかは知りませんけど、動物の肉を食べるとは、そういうことです。ただ、ペットの犬を盗んでくるという、それだけは確かに問題ですね。それは、どこの国でも(中国でも当然)犯罪行為でしょう。一方で、野犬を集めるのが不衛生だというのであれば、野生動物を食べること一般に不衛生ということになってしまいます。生で食べるならともかく、加熱して食べるのだから、問題ないでしょう。そもそも養犬場の存在自体も驚きだ。とありますが、食肉としての需要があれば養殖施設があるのも当たり前の話で、何を驚く必要があるのでしょうか。だいたい、日本だって犬を食べこそしないけど、捨て犬、野犬が相当の数、殺処分されているわけで、それは残酷じゃないんでしょうか。食べるために殺すのは悪くて、殺しても食べない殺処分は悪くないのでしょうか。「日本人はカエルの刺身を食べている」というのは確かに頓珍漢な言い分です。しかし、クジラの刺身は食べています。(私は、父の存命中にクジラの刺身は食べたことがあります。たぶん7~8年前だったと思います)「世界の動物愛護団体」から見れば、カエルの刺身など問題にもならない(絶滅危惧種でない限り)一方、犬食もクジラ食も、似たようなものとしか見えないでしょう。
2015.07.05
コメント(4)
-

投票年齢は下げるが、政治に興味を持つな
安保関連法案:山口の高校授業で模擬投票…県教委は問題視山口県柳井市の県立柳井高で先月、安全保障関連法案について2年生の生徒が自分たちの考えを発表し、どの意見が説得力があるかを問う模擬投票をする授業があった。これについて、県教育長は県議会で「法案への賛否を問う形になり、配慮が不足していた」と授業を問題視、県教委として「指導が不十分だった」と監督責任にも言及した。来年の参院選から18歳の高校生が投票権を行使する公算も大きい中、専門家から「現場を萎縮させ、教育の自由を奪う発言だ」と批判が起きている。県議会の一般質問で、笠本俊也県議(自民)が「政治的中立性が問われる現場にふさわしいものか、疑問を感じる。県教委としてどういう認識なのか」と尋ねた。教育長は投票を実施した点を問題視したうえで「(県教委として)主権者教育の進め方について学校への指導が不十分だった」とし、今後、政治的中立性の確保や授業の進め方、資料の取り扱いなどを盛り込んだ新たな指針を学校に示すと述べた。模擬投票は先月24日に2年生の「現代社会」の授業であった。生徒は22日の授業で、日経と朝日新聞の記事を参考に政府与党の見解、野党の主張、憲法学者の意見などを学習、集団的自衛権について「どんな時に行使するのか」「他国の領域で行使する可能性は」「違憲か合憲か」などの論点を資料にまとめて授業に臨んだ。生徒は8グループに分かれて議論し、それぞれ法案への賛否を明らかにした。2グループは賛成、6グループは反対と主張。法案の賛否ではなく、どのグループの意見が最も説得力があったかを問う模擬投票を実施した。結果、「他国を守るのであれば、非戦闘地域での食料供給や治療(医療)でも貢献できる。自衛隊が戦争に巻き込まれてからでは遅い」と反対を訴えたグループが最多票を獲得した。高校によると、この授業の前にも安全保障関連の授業をした。授業を担当した教諭は同24日、毎日新聞の取材に「一番の狙いは政治への関心を高めること」と説明。翌日の新聞で毎日、朝日、読売、中国の各新聞などが好意的に取り上げた。教育長は取材に対し「配布した資料が新聞2紙では少ない。全体像が完全でない資料を使い、かつ時間も十分でない形で投票させた。高校生に賛否を問うこと自体、私自身は微妙だ」と答えた。(要旨)---良い授業ではないですか。要するに、今もっとも注目されている政治的テーマを題材にディベートをおこなったわけです。1対1の対決ではないので、狭義のディベートからは若干外れるでしょうが。まさしく、選挙権が18歳以上に引き上げられた今、もっとも注目されている政治的課題を授業で取り上げるのは、高校生が政治に興味・関心を持つための、格好の手段だと私は思うんですけどね。それがけしからんというのです。言い出したのは、やっぱり自民党の議員なんですね。要するに、集団的自衛権に反対の意見が多数を占めたことが気に入らなかった、ということでしょう。集団的自衛権賛成、という意見が最多得票を占めていたら、この議員は何も言わなかったんじゃないでしょうか。私は、選挙権の18歳への引き下げには、もろ出を挙げて大賛成でした。が、年齢を引き下げればそれでよし、というわけではありません。現状、若い世代の投票率は低い。公益財団法人 明るい選挙推進協会のサイトからの引用です。1969年以降、ずっと20代の投票率が最も低くなっています。70代以上を別にすると、20代から60代まで、年代が上がるほど投票率が高い傾向が明確です。前回総選挙は、全体の投票率自体が52.7%と、戦後最悪の投票率でしたが、その中でも20代の投票率は32.6%です。3人に1人も投票に行っていない。1969年の総選挙では、20代の投票率が66.7%ですから、半減以下です。普通に考えれば、このままただ単に選挙権を引き下げたところで、18歳19歳の投票率は目も当てられないことになることは明らかです。選挙のたびに、選挙管理委員会は投票率を上げるための啓発活動を行ってはいますけど、具体性のない標語で関心を集めるのは無理でしょう。安保法案という格好の生きた教材があって、これを政治に関心を持つために使わない手はないでしょう。ところが、それをやると政治的中立がどうのという話になる。教員が「集団的自衛権反対」の方向に議論を誘導したというならともかく、そうでなければ生徒が自分たちで考えて判断した結果、集団的自衛権反対を訴えたグループが最多投票を得た(必ずしも、集団的自衛権そのものに反対多数ということではなく、そのグループの発表がもっとも説得力があった、ということ)というなら、まさしく中立的な投票の結果でしょう。つまり、結局のところは高校生は政治に興味など持たないように仕向けろと、自民党の県議も教育長も、そう公言しているわけではないけれど、結果としてそういっているのと同じです。こんな風に槍玉に挙げられてしまっては、もう後に続いてホットな政治的テーマを高校の授業で取り上げる勇気のある教員など、出てこなくなるでしょう。無味乾燥な制度の説明だけで、政治に興味を持てといったって、無理に決まっています。シルバーデモクラシーだ何だと馬鹿げたことを叫んだいる連中もいるけれど、こんなことをやっている限り若者の投票率が上がるわけもない。そして、18歳19歳の投票率は、20代をも下回る、地を這うような数字となる。きっとそういう結果を望んでいるのでしょう、この自民党の県会議員と教育長は。
2015.07.04
コメント(2)
-
箱根・大涌谷噴火
箱根町 大涌谷周辺に避難指示神奈川県の箱根山の噴火警戒レベルが入山規制を呼びかけるレベル3に引き上げられたことを受けて、地元の箱根町は大涌谷周辺の半径およそ1キロメートルの範囲に避難指示を出しました。気象庁によりますと、30日午前、神奈川県の箱根山の大涌谷で29日確認された新たな噴気孔の周辺に火山灰が積もり、噴出物で周辺が盛り上がっていることが、気象庁などの現地調査で確認されました。このため、気象庁は「箱根山でごく小規模な噴火が発生したとみられる」と発表しました。気象庁は、箱根山では今後、大涌谷周辺の居住地のすぐ近くまで影響を及ぼす噴火が発生する可能性があるとして、改めて火口周辺警報を発表し、噴火警戒レベルをレベル2からレベル3に引き上げました。これを受けて、地元の箱根町は午後0時半、大涌谷周辺の半径およそ1kmの範囲に避難指示を出しました。町はこれまで大涌谷周辺の半径およそ300mの範囲の立ち入りを規制していましたが、噴石などに警戒が必要だとして、この範囲を大きく拡大した措置を取りました。(以下略)---箱根山の火山活動活発化が報じられ始めてから2ヶ月間、噴火してしまうのか、無事収まるのか、と思っていたら、とうとう噴火してしまいました。さらに、噴火が起きた噴気孔から100mほど離れた場所に、新たに3つの噴気孔が生じているとのこと。噴火の規模は、今のところごく小規模だそうです。ただ、映像で見る限り、大涌谷は複数の激しい噴気がもくもくと立ち上っており、とても人が近寄れるような状況ではないことは一見して明らかです。北アルプスの焼岳など、噴気の中を人が歩く場所はありますけど、噴気の勢いのレベルが違う。あの激しい噴気自体を「噴火」と呼んでも間違いではないのでは、と思えてしまいます。警戒レベルは3に引き上げられ、半径1kmが避難指示となった結果、箱根ロープウェイに続いて、強羅と早雲山を結ぶケーブルカーも、一時運航を休止したようです。その後運行は再開したようですが。また、大涌谷周辺では、昨年10月からこの6月までに、最大で30cmも隆起しているとのことです。隆起している範囲は狭い範囲でとどまるものの、噴火が今回の規模だけで収まるのかどうかは、何ともいえません。それにしても、箱根町にとっては観光上大打撃であるようです。自然現象は人間の都合など無関係に生じるので、こればっかりはどうしようもありません。人的被害が生じないために最大限の注意を払っていくしかないでしょう。今のところ、箱根湯本や芦ノ湖まで危険な状態というわけではありません。ただ、以前にも書いたことがありますが、箱根山は、有史以降は噴火の記録が残っていません※が、有史以前は非常に大規模な噴火を何度も起こしたことがあります。今回の噴火がそんなとんでもない規模に拡大する可能性は非常に低いとは思いますが、気になるところではあります。※平安時代末期から鎌倉時代にかけての時期に、今回程度のごく小規模な噴火があったことが、大涌谷周辺の地質調査で判明しているものの、文献記録にはその噴火は残されておらず、したがって噴火が何年に起きたかも正確には分かっていません。今後、この噴火がこのまま終息していくのか、さらに拡大してしまうのか、注視していく必要がありそうです。終息するにしても、大涌谷に以前のように立ち入りができるまでには、下手をすると年単位の時間がかかるんじゃないかと思います。
2015.07.02
コメント(0)
-
新幹線放火
今更の話ですが新幹線放火事件 生活苦が動機の疑いも30日、東海道新幹線のぞみの走行中の車内で乗客の男が油のような液体をかぶって火をつけた事件で、男は周囲に対して年金の受給額が少ないことなどについて不満を漏らしていたことが分かり、警察は生活の苦しさが動機につながった疑いもあるとみて、さらに詳しく調べています。30日昼前、東海道新幹線のぞみの車内で、男が油のような液体をかぶって火をつけ、この男と乗客の女性の2人が死亡し、警察は1日、死亡した容疑者(71)の東京・杉並区の自宅を捜索して、金融機関のキャッシュカードなどを押収しました。容疑者の知人などによりますと、容疑者は、周囲に対して、年金の受給額が少ないことや、家賃の支払いに困っていることなどを漏らしていたということです。新幹線の車内では、火をつける前に、女性の乗客に千円札数枚を渡そうとしていましたが、現場に残されていた財布に現金は入っていなかったということです。~容疑者は、知人男性によりますと、岩手県出身で、去年まで清掃会社で空き缶を回収する仕事をしたあと、その後は、年金暮らしを続けていたということです。林崎容疑者は岩手県にいる親戚にも仕送りをしていたということで、「年金が少なくて税金を支払うと手元には僅かしか残らず、生活が苦しい」などと、周囲に漏らしていたということです。(以下略)---新幹線は、飛行機と違って、乗る際にX線検査があるわけではないし、また簡便に利用できること自体がメリット(自由席であればドアが閉まる5秒前だって乗れる)なので、飛行機のようなチェックは難しいのが現実です。また、その飛行機だって、米国の空港で覆面調査をおこなったら、禁制品の95%は見逃されていて、保安検査はザルだ、という話があります。私の経験でも、ザルのような気がする私の感覚では、米国より日本の空港のほうが保安検査の実効性は高そうな気がするのですが、それだって限界はある。それに、新幹線でX線検査だとしたら、在来線特急は?通勤電車は?地下鉄は?バスは?きりがないことです。バスは35年前に新宿でガソリンによる放火事件がありました。新宿西口バス放火事件この場合は、乗客ではなく、外部からガソリン入りバケツを投げ込んだようですが。地下鉄への放火は、日本ではありませんが、韓国で発生しています。大邱地下鉄放火事件この前例からいえば、どんな交通機関だって、同様の犯罪行為の舞台になりえます。今回、ガソリンを撒いての放火だったにも関わらず、新幹線N700A系の車両は炎上せず、新幹線車両の難燃性はたいしたものだと証明されましたが、でも犯人以外にも一人、死者は出てしまいました。満員の地下鉄や山手線でガソリン撒いて焼身自殺を図る輩が出てきたら・・・・・・、仮に車両自体が難燃性で炎上しなかったとしても、とてつもない大惨事になったであろうことは、想像に難くありません。また、現在の最新鉄道車両といえども、たとえば数年前のJR北海道ではディーゼル特急があっさり全焼してしまった事故がありました。トンネル内火災事故この例から見ると、すべての鉄道車両の難燃性が高いとはいい難い(電車や客車と、床下に燃料を搭載するディーゼル車の違いはありますけど)のも現実です。かといって、地下鉄や山手線までXせん検査なんて、新幹線以上に不可能です。報道によれば、国交省はJR各社に対して、新幹線への一定量以内の可燃物の持ち込みを認めている現行ルールの見直しなどを検討するよう指示したそうです。新幹線への可燃物持ち込み見直し、検討を指示だけど、今回の事例は、報じられているところでは、10リットル以上のポリタンクにガソリンを入れて持ち込んだようですから、現行ルール(3リットルまでは可)のもとでも違反なのです。犯罪を犯そうとするものが規則を守るわけもないので、規則だけ厳しくしても、実効性がなければ意味がありません。むやみに規則が厳しくなると、山登りのときのガス缶なんかも、持ち込みできなくなると、個人的には困るなあ。(すでに、飛行機には持ち込めないので、大雪山に登ったときは、ガス缶は札幌で購入して、使い残しは空港で放棄した)なんにしても、自殺はよくない。けど、どうしても自殺するというなら、せめて、他人を巻き込まないでくれ。
2015.07.01
コメント(2)
全26件 (26件中 1-26件目)
1
-
-
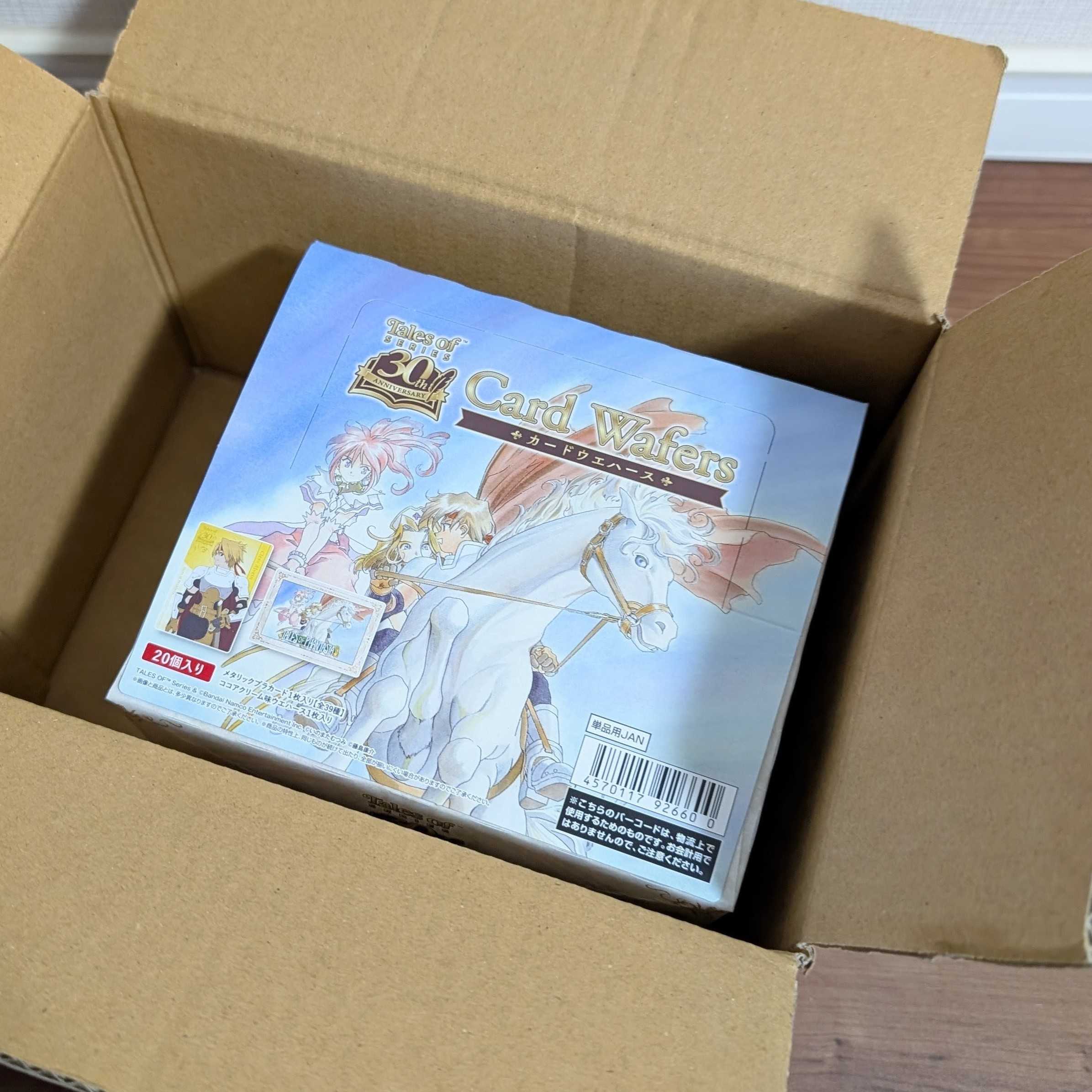
- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…
- 【楽天】人生初!胸アツ買いのテイル…
- (2025-11-25 21:50:38)
-
-
-

- ★つ・ぶ・や・き★
- 日経平均株価、先物下落、日本版DOGE…
- (2025-11-26 00:00:01)
-
-
-
- ひとり言・・?
- 楽天ポイントアップ等で2~3割安く購…
- (2025-11-22 22:12:52)
-







