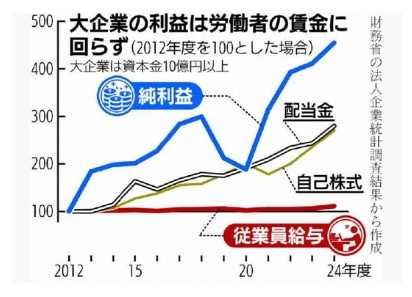2015年08月の記事
全29件 (29件中 1-29件目)
1
-

8.30国会前集会の参加者数(追記あり)
昨日の記事の続きになりますが、参加者数は主催者発表では12万人とのことです。一方、警察発表というものはありません。ありませんが、警察が非公式に示唆した数字として、国会周辺で3万3千人、と言っているようです。で、例によって両者の数字が食い違うと、無条件に警察の発表(それも公式発表ではないのですが)を信じたがる人が少なくないようです。警察の発表がいつも正しいなら、冤罪事件など起こらないんですけどね。私自身の見積もりだと、国会正面の道路(前側2/3は人で埋め尽くされ、後ろ側1/3はややガラガラだった)は、長さ180m、幅45mくらいで、総面積は8100平米(実際は交差点に広がりがあるのでもうちょっと広いけど)、そのうち前方2/3は1平米当たり3人(電車で言えば満員電車並みでしたから)、後方1/3は隙間がかなりあって、1平米あたり1人くらい、合計だいたい2万人くらい。※後述のとおり、この推計は過小評価だったようで、産経新聞が、この一角に3万人以上いたと明らかにしてくれました。国会前庭公園の北側南側とも、数千人はいました。各5000人ずつとして、合計1万人。(もっといたかも知れませんが)国会を囲む道路も、国会の裏側とか国会図書館前までは行っていませんが、歩道はだいたいいっぱいだったらしい。道路の総延長は1.2km以上、幅4mくらいなので5000平米くらいに、1平米当たり2人程度+国会前で車道に人が溢れているので、1万5千人前後。(これについても、後述のとおり上方修正しました)国交省前にも相当の人がいました。そして、航空写真を見ると、財務省と外務省の間の道路(これは、国会図書館と参議院第二会館の間の道路の間違いでした)も、歩道が参加者で埋まっています。これらの合計でおそらく4000人から5000人。自民党本部前、東電前、日比谷公園にも、それぞれかなりの人がいたようです。かなり大雑把な推計ですが、全部あわせると、5万人±1万人くらいかな、というところです(後述のとおり、上方修正しました)。警察の非公式発表3万3千人も、絶対ありえないほどの過小評価ではないかもしれません。が、しかし、それは「一度にいた最大人数」の話です。私は、風邪で体調が悪かったせいもあって、国会前を3時過ぎに後にして、日比谷公園を見て、3時半には帰途につきました。私が国会前を離れるときには、同様に帰る人がぞろぞろと大勢いた一方、来る人もまた大勢いました。何時から何時までいなければならない、という決まりがあるわけではないので、みんな好きな時間に来て、好きな時間に帰るわけです。だから、延べ参加者数は「一度にいた最大人数」の6割増から2倍程度だったと思われます。そうすると、だいたい、7万人から10万人くらい。主催者発表の12万人は、やや多いけれど、ありえない数字ではまったくありません。ただ、正直言って2012年7月に行われた反原発集会の方が、参加者は多かった気がします。あの時は、確か主催者発表15万人、警察発表7万5千人じゃなかったかな。でも、まあ安倍政権を筆頭に、この集会を何とか過小評価したがる人が大勢いるということは、それだけ影響力があった、ということなんでしょう。何の影響力もなければ、わざわざ過小評価などせず、無視すれば済むことですから。人数を過小評価しようとする人たちは、だいたい国会正面の道路しか眼が行かず(それ以外の航空写真はないし、国会前庭公園は樹木があるので航空写真では人数は分からないので、仕方のない面はありますが)他の場所にも大勢の人がいたことを見落としているんですね。昨日アップした写真を、何枚か再掲します。上2枚は国会前庭公園内からの撮影です。こうしてみると、上記の前庭公園南北各5千人という推計は、ひょっとしたら過小評価かもしれない・・・・・・。追記産経新聞が、集会参加者数を一生懸命過小評価しようと記事をかいています。安保法案反対デモ、本当の参加者数を本社が試算それによれば、国会正面の道路上だけで3万2400人だそうです。おや、私はこの一角の参加者を2万人とはじいたので、私の推計より産経新聞の推計の方が多いじゃないですか。でも、これはダメですね。だって、正門前の道路しか計算していない。実際には、前述のとおり、前庭公園内も、国会を取り囲む道路にも、さらに国交省、財務省前にも大勢の参加者がいたのですから。で、この産経新聞の計算に基づいて、ちょっと修正しました。国会正面の道路に3万人(産経は32400人とはじいていますが、計算の根拠となるマス目が一部前庭公園に食い込んでいることからマイナス補正)前庭公園に南北それぞれ5000人ずつで1万人。国会を囲む道路に1万5000人から2万(先に、1万5千としましたが、国会図書館側の道路は、ヘリ空撮動画を見ると人の列が私の計算より広いこと、国会正面左側で車道まで人で埋まっていることし、同じくその一角で国会側の歩道も人で埋まっていることから、もっと多い可能性が高い)国交省前と、国会図書館・参議院第二別館間の道路(当初外務省・財務省間の道路と誤認していました)に、あわせて5000人くらい。合計6万から6万5千くらい。延べ参加者数がその6割増から2倍程度とすると、10万から13万人くらい、というところでしょう。
2015.08.31
コメント(12)
-

8・30国会10万人・全国100万人大行動
行ってきました。午前中は某グループの練習、その後、午後は国会議事堂前へというスケジュール。あいにくの雨模様の空、気温は低いけどやたらと湿度が高くて、風邪は治りきっておらず、それなのに午前中の練習で体力消耗した状態、という、ちょっと厳しいコンディションでした。本日の武器はこちら。練習だったので管楽器ケースをそのまま持ってきました。桜田門駅に着いたのは2時少し前でしたが、すでに国会方面はすごい人波でした。というか、駅の出入り口がすでにすごかった。国会前に人が溢れてます。何回もここに来たけど、車道が上下とも完全解放になったのは初めてじゃなかろうか。国交省前付近から撮影しました。道路を渡ったけど、身動きできません。琉球独立という旗を掲げている人がいました。上空には少なくとも2機のヘリが飛び交っていました。そのうちの1機。毎日新聞ですね。国交省方面。向こう側の歩道もから、どんどん人が渡って来ます。国会正面の大通りに何とか入り込みました。すごい人波。国会前庭(北側)に入りました。ここにも参加者は大勢いましたが、動けないほどじゃないので、国会正面まで出られました。ただし、そこから歩道には出られません。出ても、身動き取れそうにありませんが。このあたりから、雨が降り出してしまいました。国会前庭内も、大勢の参加者でごった返していました。雨さえ降っていなければ、この公園内で笛の練習第二部を開催したかったのですが、さすがに雨と風邪のため、断念しました。創価学会の安保法制反対派が盛んに訴えていました。創価学会内で安保法制に反対を公言する信者が現れていることは、最近時々報じられています。公明党は安倍に唯々諾々と付き従っていますけど、そんな状況を是としない支持者が増えてきたようですね。大通り上をこれより先に進むことは断念しました。東映動画労働組合!!かの高畑勲、宮崎駿が委員長、書記長をやっていた労働組合ですね。今もあったとはしりませんでした。というか、社名は東映アニメーションに変わっていますが・・・・・・。若者を戦場に送るな!!そのとおり!この団体、「若者を戦場に送るな」「安倍を戦場に送る」「安倍独裁を拒否する」という3種類のスローガンを交互に構えていました。財務省上の交差点も人が大勢いました。この先は国会正面なので、おそらく人が溢れていてとてもいけないだろうと、進むことは断念。首相官邸へ続く道も、ずいぶん人がいるようでした。国会前に何回も来たので、さすがにこのあたりの位置関係は頭に入るようになって来ました。日比谷公園でも、リンクして集会が行われていました。この一画でも数百人以上いたようです。相棒は、国会前には行かず、こちらの集会に参加していました。なので、やっと合流。でも、私はもう体力的に限界で、結局相棒とは再び別行動で、先に帰宅してしまいました。参加者数は、12万人(主催者発表)とのことです。この動きが、安保法制を止める力になるように祈っております。
2015.08.30
コメント(2)
-
出来レースにもほどがある
戦争法案廃案!安倍政権退陣!8・30国会10万人・全国100万人大行動明日です。私も参加する予定ですが、風邪がなかなか治らなくて(もう1週間)、天気もあまりよくない予報で、雨の場合は長居出来ないかもしれません。が、今日はその話ではありません。五輪エンブレム 組織委員会が原案公開し盗作否定2020年東京五輪の公式エンブレムが盗作疑惑問題で揺れる中、佐野研二郎氏のデザインを選考した大会組織委員会が28日、都内で会見を行い、あらためて盗作を否定した。佐野氏がコンペに提出した原案などを示し、ベルギーのリエージュ劇場ロゴとの違いを主張。原案は決定版よりも「T」が強調されていた。しかし、原案は似ているデザインが見つかったため、修正を依頼した。修正案が示され「円」の要素が出てきた。しかしこれも、左端にも角がデザインされ「躍動感がなくなった」という理由から、再修正を依頼したという。そして完成したのが現在公表されている五輪エンブレムとなった。72年札幌冬季五輪のエンブレム制作者で審査委員の永井一正氏は「審査では誰がどの作品を出したのは全く分からなかった。後で名簿をもらったら、日本のこれというグラフィックデザイナーはほとんど参加してくれた。それだけ2020年の東京五輪・パラリンピックに参加したいという意欲があったんだと思った。今回のような質の高いコンペティションはなかったと思う」と、選考過程に不備はなかったと強調した。---この盗作騒動、何故か私自身にまで若干の飛び火がありまして、コメント欄を追っている方はすでにご存知と思いますが、佐野研二郎氏を必死で擁護している森本千絵氏というデザイナーの作品にも、盗作があったということで、その一つが、私が撮影してWikipediaにアップしたチャランゴの写真が使われているんですね。(こちらのコメント欄を参照)ま、佐野氏本人の話ではないので、たいしたニュース価値があるわけではありませんし、Wikipediaにアップした時点で私は著作権を放棄したようなものだし、そもそも作品性を主張するような写真ではないので、それ以上そのことを記事にはしませんでしたけど。それにしても、オリンピック組織委員会は佐野を必死で擁護しようとこんな会見を開いたわけですが、その内容を見ると、「語るに落ちた」と言わざるを得ません。要約すれば佐野氏の作品原案は別のロゴに似ていたので急遽修正して、いろいろ変更したら今の形になったと。だからリエージュ劇場ロゴを盗作する意図はなかったと、そういうことです。だけど、この説明だけでは、原案を作ったときはともかくとして、再修正の時点でリエージュ劇場ロゴを真似る意図がなかったかどうかは、まったく保証の限りではありません。でも、霊前の問題として、そもそも原案は別のデザインに似ていたと言っているのです。つまり最初から既存の作品(リエージュ劇場ではないようですが)のパクリだった、選考委員もそれを認識していたと認めているに等しいのです。最初からオリジナリティーに問題があるような作品が、なぜ選ばれたんでしょうか。他の応募作品がゴミみたいなものばかりで、選びようがなかったのでしょうか?そうではありませんね。だって、審査委員自身が「日本のこれというグラフィックデザイナーはほとんど参加してくれた。」と言っているのですから、他にも優れた作品は数多くあったはずです。普通なら、問題が分かった時点で、その作品は候補から外して別の作品を選ぶものなのではないでしょうか。そうでない理由は、一つしか思い浮かびません。それは、佐野氏の作品を(その出来がどんなものであれ)選ぶということがあらかじめ決まっていて、コンペはただのカモフラージュに過ぎなかった、ということです。要するに出来レースということでしょう。
2015.08.29
コメント(3)
-
ウランが「自給」という不可解
【川内再稼働に見る“反原発”新聞の偏向(上)】「見出し」ににじむ「悔しさ」と「歪み」複数の意見が対立する中で、自己に不利な事実をわざと報じないか、あるいは有利な事実を殊更大きく報じることを偏向報道という。九州電力川内原発1号機が再稼働を果たした際の朝日、毎日、東京の各新聞を見るとまさにこの定義が当てはまった。新聞は同じではないのだから、それぞれの主張があってよい。しかし複数の新聞を購読する読者が少ない中、何が偏向報道かを見極めるのは極めて困難だろう。取材班は、再稼働当日の8月11日付と翌日付の記事を洗いざらい分析し、浮き彫りにしてみた。(原子力取材班)一面の見出しにも「主張」入れ込む「リスク抱え原発回帰」(朝日)「再稼働見切り発車」(毎日)「『反対多数』世論の中」(東京)川内原発の再稼働から翌日付の朝刊1面トップの大見出しには、“反原発”新聞の悔しさがあふれていた。解説や論説は別にせよ、事実を素直に伝えるべき記事の見出しに自社の主張を入れ込むのは、あまり好ましいとはいえない。一方で、産経は「川内原発 再稼働」、読売は「川内原発 14日発電」とオーソドックスな1面見出しで、事実の伝達と主張は別という基本を守っている。~“反原発”の記事を読むと、目につくのは「電気は足りている」という主張だ。朝日は1面で「事故で日本のすべての原発が止まり、私たちが『原発なし』の暮らしを始めて約2年。猛暑の夏でさえ電気は足りている」と主張した。同じく東京新聞は「原発に依存しなくても、電力をまかなっていけると、日本が自ら証明した。猛暑の今年も、全国的に安定供給が実現されている」と指摘した。電力がいまも安定供給されている中にどういう欠落が潜んでいるのか。記者は知っているにもかかわらず、なぜ触れないのか。まず東京電力福島第1原発事故前に、全電力の3割をまかなっていた原発の停止により、現在は、ほぼ9割を火力発電に依存しているという異常な実態を見ていない。日本のエネルギー自給率は事故前に2割近かったが、現在は6%しかない。政情不安な中東のエネルギーに依存するのは、国そのものを危うくしかねない。資源の輸入依存度は下げていくのが望ましい。~リスクが存在するのは原発だけではない。リスクに言及するなら、原発や自然災害、あるいは交通事故や殺人事件などを含めた総合的なリスクをどう比較し、どう捉えたらよいかという観点が必要なのではないか。日航ジャンボ機墜落事故や、兵庫県尼崎市のJR福知山線脱線事故を挙げるまでもなく、科学技術の恩恵による便利さの裏側には、人が死亡するという重大なリスクが潜んでいる。飛行機や車が良くて、原発はダメという「明快な根拠」が見当たらない。(以下略)---連日ネトウヨ機関紙の産経に対する論評になってしまいますが・・・・・・「複数の意見が対立する中で、自己に不利な事実をわざと報じないか、あるいは有利な事実を殊更大きく報じることを偏向報道という。」だって!!一瞬、産経がこれまでの自らの報道姿勢を恥じて自己批判する文章かと思ってしまいましたよ。ところが、そうじゃなくて他紙の報道態度への批判なんだから、笑うしかありません。あの産経新聞が、どの口でそういうことを書くんだか。昨日も指摘したとおり、内閣支持率が前回調査より1ポイント上がっただけで(依然として指示より不支持のほうが多いにも関わらず)「朝日は、民意にはしごを外された」なんて口走る新聞が、「有利な事実を殊更大きく報じることを偏向報道という。」って、それは産経新聞自身のことでしょうよ。「事実を素直に伝えるべき記事の見出しに自社の主張を入れ込むのは、あまり好ましいとはいえない。」ともありますが、およそ産経新聞が、自社の政治的主張に絡むことについて、見出しも本文も、自社の主張を入れ込んでいない記事など見たことはありません。で、それはそれとして、引用記事の中でも特に気になったのが「日本のエネルギー自給率は事故前に2割近かったが、現在は6%しかない。政情不安な中東のエネルギーに依存するのは、国そのものを危うくしかねない。資源の輸入依存度は下げていくのが望ましい。」という記述です。日本のエネルギー自給率は事故前に2割もあって、それが6%に「落ちた」という言い分の正当性がまず問題です。マトモに考えれば、水力発電と新エネルギー、わずかな天然ガスを除けば、日本国内で自給できるエネルギーはなく、自給率が2割もあるはずがないのです。それが2割などという数字になっているのは、核燃料を自給エネルギーに含めるという不可解な計算の仕方故です。現在、日本ではウランの採掘はまったく行われておらず。核燃料はすべて輸入に頼っています。それを「自給」とみなすのは、ある種の言葉遊びでしかありません。したがって、実際の日本のエネルギー自給率は、事故前も事故後もほとんど変わっていません。そしてもう一つ。「政情不安な中東のエネルギーに依存」という言い分もおかしいのです。確かに、日本の石油の輸入元は、8割以上が中東です。が、天然ガスでは3割程度であり、石炭は中東からの輸入はほとんどありません。そして、2014年の日本の総発電量に占める石油の割合は、わずか10.6%に過ぎません。確かに、事故の後一時的に石油による発電の割合が18%まで増大(2012年)しましたが、その後2年で急減しています。天然ガスの割合が46%、石炭が31%ですから、総発電量に占める中東への依存度は、せいぜい2割程度ということになります。引用記事では触れられていませんが、「原発が動かないから化石燃料の輸入が増えて、燃料代がかさんでいる」という主張をよく見かけます。以前に検証したことがあるのですが、輸入「量」についていえば、石油と石炭は、事故前に比べて特に増えてはいません。天然ガスだけは、事故前に比べて輸入量が2割程度増えていますが、化石燃料トータルで見れば、4~5%程度の増加に過ぎません。それにもかかわらず燃料費が大幅に増えたのは、原油価格(天然ガス価格も)が大幅に上がったからです。原発が稼動していたとしても、電気の6割近くは化石燃料から発電されるのですから、燃料費の増大はどう転んでも避け得ないのです。そして、このところ原油の天然ガスの価格も急落していますから、燃料費の問題もかなりの程度解決しつつある、ということろでしょう。「リスクが存在するのは原発だけではない」とありますが、原発以外で、あれほど広範囲にわたって、しかも何十年にわたって人の居住が制約されるようなリスクがありえるのか、ということを考えるべきでしょう。飛行機や自動車は、利用者にとってそれを完全に代替しうるものが存在しないのに対して、電気は、切れ目なく供給され続ければよいのであって、発電手段が原発でなければならない必然性など、何もありません。原発が止まっていたこの数年の間、電気が足りなくて社会が困り果てたことなどないんだから。結局のところ、「自己に不利な事実をわざと報じないか、あるいは有利な事実を殊更大きく報じることを偏向報道」と叫ぶその記事自体が、もっとも顕著な「偏向報道」だった、という実に馬鹿馬鹿しい話です。
2015.08.28
コメント(4)
-
それは産経新聞の民主党政権批判のことでしょう
もはや健全な批判というより憎悪や悪意に…「安倍嫌い」の感情論と焦燥郵便ポストが赤いのも、電信柱が高いのも、みんな安倍晋三首相が悪いのよ~とばかりに、一部のメディアや学者、文化人、野党議員らの安倍首相たたきが過熱している。もはや健全な批判というより、憎悪や悪意をぶつけているとしか思えないほどである。この現象について、雑誌『新潮45』9月号の特集「『安倍嫌い』を考える」が興味深い視点を提供していた。例えば、著述家の古谷経衡氏は、5月の憲法記念日のトークイベントで繰り返された「呪詛の言葉」を紹介する。「安倍以外なら誰でも良い」「安倍は史上最悪の独裁者である」「安倍のせいで日本は破滅する」…。◆批判の裏に嫉妬古谷氏は、「安倍総理をヒトラーになぞらえ、それを支持する人々を右翼、社会を右傾化していると批判的に捉える人々は、『極右内閣にもかかわらず、国民的支持を受けている』という事実に狼狽」し、嫉妬していると説く。それは「戦後左派勢力は、もはや自分たちが大衆から離反しているのではないかという事実を薄々感じているから」だという。うなずける指摘だ。~確かに今国会の安全保障関連法案の審議を見ても、国際情勢や安全保障環境にかかわる冷静な議論とはほど遠い。むしろ、憲法という「聖典」の解釈をめぐり自らを一方的に「正」「善」と位置づけた野党が、政府・与党に「邪」「悪」とのレッテルを貼って責め立てる場と化している。特集でも、著述家の神山仁吾氏は安倍首相に対し、感情的に「あの面の皮がいかにも厚そうなブヨブヨの顔にも虫唾が走る」と記し、「暗愚総理」と嫌悪感を隠さない。だが、普通は首相の容姿をここまでけなすことはしない。◆大衆は同調せずともあれ、安倍首相ほど好き嫌い、評価するしないがはっきり二分している首相は珍しい。左派勢力は、自分たちが寄りかかってきた戦後の価値観と既得権益が壊されることに焦燥感にかられ、批判のボルテージを上げるが、大衆はなかなかついてこない。そこで、さらに焦りを募らせ、いよいよ感情的になっていく。戦後70年の安倍首相談話が発表された翌15日の朝日新聞社説は、談話を「極めて不十分な内容」と書き、こう決め付けた。「この談話は出す必要がなかった。いや、出すべきではなかった」逆上したかのような論説だったが、やはり大衆はついてこなかったことが数字に表れている。朝日が22、23両日に実施した世論調査では、安倍談話を「評価する」が40%で「評価しない」の31%を上回り、内閣支持率も1ポイント上がっていた。朝日は、民意にはしごを外されたのである。---例によって、記者もどきの政治運動屋が面白いことを書いています。私のアイドル、安倍首相をいじめる奴は許さないぞー、ってか?(笑)郵便ポストが赤いのも、電信柱が高いのも、みんな安倍晋三首相が悪いのよ~とばかりに、一部のメディアや学者、文化人、野党議員らの安倍首相たたきが過熱している。のだそうですが、私の見るところ、民主党政権時代の産経新聞の民主党叩きの説明としか思えません。それこそ、ありとあらゆる罵倒暴言が産経新聞の紙上に躍ったし、民主党が下野した後も、それはそれはしつこくしつこく民主党への非難攻撃を続けています。産経の言う「一部のメディアや学者、文化人、野党議員」は、自民党が下野していた時代にまで、産経の民主党攻撃ほどの執拗さで自民党や安倍への非難攻撃を行っていたわけではありません。自らを一方的に「正」「善」と位置づけた野党が、政府・与党に「邪」「悪」とのレッテルを貼って責め立てる場とありますが、そもそも与党であれ野党であれ、政治家とは自らの立場を「正」「善」と主張しなければ成り立たないものです。安倍首相なら自らを一方的に「正」「善」とは位置づけないのか?そんなわけがない。むしろ、「マスコミを懲らしめろ」「極端に利己的」発言に代表されるように、安倍の取り巻きこそが、自分たちだけが「正」「善」であり、反対者は「邪」「悪」だという意識を持っているようにしか、私には思えません。普通は首相の容姿をここまでけなすことはしない。なんて大見得を切っているけれど、阿比留瑠比自身、鳩山由紀夫を「不出世の愚か者」「クルクルパー」、菅直人を「ネムリユスリカの幼虫、クマムシ、プラナリア…。そんな驚異の生き物たちと比べても、生命力で負けてはいない。」などと、それはそれはすげーけなし方をしているわけですが、要旨をけなすのがダメで、クルクルパーや愚か者はいいの?まったく理解不能です。(いずれの文章も、民主党下野後のものです)挙句の果てに、内閣支持率が1ポイント上がっただけで「朝日は、民意にはしごを外された」なんて吹き上がっているけど、1ポイント上がっても不支持のほうが多数であることに変わりはないのです。むしろ、こういう言い方をするなら産経と阿比留瑠比が狂ったように安倍擁護をしても、内閣支持率より不支持率のほうが高いのだから、「産経は、民意にはしごを外された」という言い方も充分可能でしょう。要するに、ダブルスタンダードということです。まあネトウヨ機関紙である産経新聞の平常運転であって、いつものこと、ではありますけど。
2015.08.27
コメント(6)
-
飲酒年齢引き下げねえ・・・・・・
飲酒年齢引き下げで賛否=高校生らから意見聴取―自民自民党の成年年齢に関する特命委員会は26日、高校生や大学生ら約20人を党本部に招き、飲酒や喫煙が可能となる年齢の引き下げについて意見を聴取した。出席者からは、「大学の新歓コンパで事実上、未成年による飲酒が行われている」として、18歳への引き下げを求める声が上がった一方、「医学的見地から良くない」といった慎重な対応を求める意見も出た。若者側からは、少年法の適用年齢引き下げについても発言が相次いだ。「社会に守られるのではなく、責任を持って行動することが必要だ」などと引き下げを容認する声が複数上がったが、「少年保護の観点から引き下げる必要はない」との意見もあった。---自民党に成年年齢に関する特命委員会なんてものがあるとは知りませんでしたが、投票年齢を18歳に引き下げたことから、成人年齢(公選法の規定とは別に、民法で成人年齢は20歳と決まっている)もそれとの整合性を考えなければならない、ということでしょう。正直なところ、法律がどうあれ、現実的に18歳の3月31日以降の飲酒は、実質的に社会的認知を受けてしまっている、と思います。私は大学生になって以降、とくに気兼ねすることなくお酒を飲んでいました。というか、小声で言えば、高校生の時だって、飲んだことがないわけではありません。そういえば、高校のとき、同学年だったか一つ下の学年だったか失念しましたが、文化祭の打ち上げと称してコンパを開いて、多分羽目を外したのでしょう、居酒屋の従業員に「お前ら高校生だろ」と叱られて通報されて、1クラス丸ごと停学をくらった、という事件がありました。(私自身ではないですので念のため)まあ、若き日のちょっとした過ち、程度の話ではあります。いずれにしても、高校生までの飲酒を社会的に容認することは難しいでしょう。この種の年齢基準は、「18歳に達した最初の4月1日以降」というような線引きの仕方はしないようなので(児童手当とか児童扶養手当の線引きはそのような形ですが)、高校生の飲酒を容認しかねない18歳への引き下げは無理でしょう。19歳なら、そういう危惧も避けられますが・・・・・・、どうでしょうか。私は、社会全体が飲酒喫煙を推奨するようなこと自体、どうかと思うのです。自分が飲んでおいてこんなことを言うのもなんですが、まあ「酒は万病の元」と痛感する今日この頃ですし。禁止したり過度に制限する必要はないけれど、やや抑制的、くらいが丁度いいのではないかと思います。酒はそれでも適量なら健康に好影響もありますが、タバコはまったく百害あって一利もないですから。※※ただし、タバコは害はあっても、最後肺がんで早死にするだけで、人格が破壊されたり他人に迷惑をかけることは(副流煙による健康被害以外は)ないけれど、酒の害は、命を落とす前に人格がおかしくなって他人に迷惑をかけまくるので、害悪の深さは酒のほうが深刻です。というわけで、私としては、飲酒・喫煙年齢を引き下げることは、どう転んでも青少年に対して「どんどん酒を飲んでタバコを吸うべきだ」という誤ったメッセージとなりかねないので、積極的に賛成はできないな、と思います。実質的には、18歳の4月以降の飲酒喫煙は社会的に容認、だが公認ではない、という現状のままでよいのではないかと思います。自分自身がよい見本ではなかったので、あまり格好良く断言は出来ませんけど。ただ、改めて調べてみると、米国でこそ飲酒年齢は21歳以上ですが、それ以外の国では、18歳以上というところもかなり多いですね。中には16歳という国もありますが、そすがにそれはちょっとどうかと思います。
2015.08.26
コメント(4)
-
右翼的思考の象徴と思わざるを得ない
靖国参拝する日本人は「右翼」なのか日本人にとって靖国神社とはどんな存在なのか。昨年暮れ、しんぶん赤旗に掲載された記事の中に気になる一文があった。「靖国神社は、過去の日本軍国主義による侵略戦争を『自存自衛の正義のたたかい』『アジア解放の戦争』などと美化・宣伝することを存在意義とする特殊な施設です」この記事によれば、靖国神社は「侵略戦争を美化する象徴」であり、ここを訪れるのは、あたかも過去の軍国主義を礼賛するのが目的であるかのような書きぶりである。本当にそうなのか。もしそうだとしたら、靖国を参拝する日本人は、彼らがレッテルを貼りたがる「右翼」そのものではないか。言うまでもなく、参拝者の多くは、侵略戦争を美化したり、軍国主義の復権なんか望んではいない。戦没者の英霊が祀られたこの場所を訪れた人は、国のために戦った人へ哀悼の意を示し、ただただ恒久平和を望んでいる。一昨年暮れに参拝した安倍晋三首相も「靖国には戦争のヒーローがいるのではない。ただ、国のために戦った人々に感謝したい思いがあるだけ。国のために戦った方々に祈りを捧げるのは、世界のリーダーに共通する姿勢である」と後に語っている。首相の靖国参拝は、国益と個人の信条を天秤にかけた難しい決断である。日本の国際的孤立を狙う中国と韓国が、外交カードの切り札として、揺さぶりをかけ続けてきた過去を顧みれば、首相という立場上、簡単に参拝できないのは理解できる。にもかかわらず、安倍首相の靖国参拝を日本の「右傾化」の象徴と煽る中韓と同じように、わが国の一部メディアが声をそろえて騒ぎ立てるのは理解に苦しむ。靖国神社には幕末以降、国に殉じた246万余柱の英霊が祀られている。そして、その多くは先の大戦で亡くなった方々である。戦後70年の歴史は、言うなれば彼らの労苦と尊い命によって築かれたものでもある。先人を敬い、純粋な気持ちで靖国を参拝する人々の思いを踏みにじってはならない。---靖国神社を参拝する人がみんな右翼、などということはないでしょう。靖国神社のことをすべて知った上で参拝している人ばかりではないし、知っていて、その主張に同意はしないけど、自分の親族や知人が祀られているから参拝する人だっているでしょう。私のように、ある意味興味本位で参拝する人(私の場合は境内に入っただけで参拝はしていませんが)もいる。そりゃ、共産党に投票する人がみんな左翼とは限らないのとおなじことです。ただし、少なくとも8月15日に私が見た限りで言うと、絶対的な割合は知りませんけど、参拝者のうちの声の大きい人たちはかなり右翼的、ということはいえます。私は遅い時間だったので遭遇しませんでしたが、8月15日の靖国神社には、旧陸軍の軍服を着た集団(年齢から見て、戦後生まれが大多数)が大挙して押し寄せたりしています。巨大な日の丸を林立される集団、ありとあらゆる右翼的な主張を繰り広げる集団などは、私も目撃しました。言うまでもなく、参拝者の多くは、侵略戦争を美化したり、軍国主義の復権なんか望んではいない。とありますが、そもそも産経新聞自身も含めて、こういった人たちは、太平洋戦争を侵略戦争とは思っていないし、あの時代を軍国主義だとも思っていないのだから、「侵略戦争」の「美化」も「軍国主義の復権」を「望んで」もいないでしょう、彼らの主観的には。ただし、客観的に見れば、靖国神社が太平洋戦争(という単語を靖国神社自身は使わず、大東亜戦争と称しているけれど)とあの時代の日本の姿を美化していることは歴然としています。先人を敬い、純粋な気持ちで靖国を参拝する人々の思いを踏みにじってはならない。などと書いていますが、「国に殉じた」とか「英霊」とか、「純粋な気持ち」とかという枕詞を錦の御旗に掲げて、「思いを踏みにじってはならない」と称して批判を許さない態度は、ほとんど思考停止です。かつて太平洋戦争に突入する直前「ここで引いたら10万の英霊に申し訳が立たない」(日中戦争の、太平洋戦争開戦までの日本側の戦死者が、だいたい10万人前後だった)という理屈で対米開戦を叫んだ陸軍強硬派の主張を彷彿とさせます。その結果、太平洋戦争に突入して、更に300万の英霊を生む結果になったわけです。そういう歴史観の尻尾が靖国神社であり産経新聞であり、また安倍首相やその支持グループであるとしか思えないのです。彼らの好きなように国を動かしたら、70年前と同じことを再び繰り返さないとも限りません。ただし、同じような危惧は左側陣営にも感じないわけではありません。正義は我にあり、と考えるのは当然です。自分が正しいと思わなければ、政治家などできるものではないでしょう。ただ、正義は我「だけ」にあり、となってしまうと、これは偏狭と独善につながりかねません。実際、そうやって、分裂と衰退を繰り返してきた過去もあります。現状、安保法案反対運動に関しては、そういった過去の轍を踏まないように、かなり考えていることが伺えます。非武装中立派(自衛隊違憲・解散論)でも専守防衛派(自衛隊合憲論)でも、この安保法制に反対という一点で一致できれば共闘の輪を広げ、たとえば元々改憲論者の小林節をも味方に引き入れる姿勢は、世論の支持を広げるために大きな力となります。ここで、「非武装中立こそが正義、自衛隊合憲論なんてニセモノの反対派だ」みたいな態度を取ってしまったら、世論の支持も離れていくでしょう。そんな事態は起こらないようにしたいものです。
2015.08.25
コメント(2)
-

内向きの言葉と外向きの言葉
首相に「バカか、お前は」 連合主催集会でシールズメンバー 安保法案反対の具体論語らず 「首相はクーデター」「病院に行って辞めた方がいい」安全保障関連法案反対のデモ活動を行う学生団体「SEALDs」の中核メンバーである奥田愛基氏が23日、連合が主催した国会前の反安保関連法案集会に参加し、安倍晋三首相について「バカか、お前は」などと訴え、退陣を迫った。奥田氏は安保関連法案のどの部分が反対かは一切語らなかった一方、週刊誌や民主党議員らの発言を元にしたとみられる情報で「首相は早く病院に行って辞めた方がいい」「どうでもいいなら総理をやめろ」などと批判した。~約6分間のあいさつで、奥田氏から安保関連法案そのものに触れた発言はなかった。~だが、安保関連法案のどの部分が憲法違反なのかについては最後まで一切語らなかった。さらに奥田氏は「一言でいうと、バカなんじゃないかなと思いながら見ている」と首相を批判。「国会の傍聴には行かない。首相が『どうでもいい』なんてやじを飛ばしたが、ああいうことを見ると、靴でも投げそうになるのでインターネットを通して見るようにする」と述べた。---またも相変わらず産経新聞が約6分の発言のうちの都合のよい部分だけをつないで適当な記事を作っています。問題の発言は、こちらに動画がアップされています。これを見れば、「バカか、お前は」「病院に行って辞めた方がいい」という部分は、「バカか、お前は、思うんですけど、あまりバカかとかですね、そんなひどい言葉を言ってもあまり伝わらないわけでして、もう少し優しく言えば、僕は総理の体調が非常に心配なので、早く病院に行かれて、お辞めになられたほうがよいのではないかと、そういうことを思うわけです」と言っていることが分かります。全体として正論だと私は思いますけどね。「だが、安保関連法案のどの部分が憲法違反なのかについては最後まで一切語らなかった。」というのも、発言時間が6分しかない中で(途中で時計を気にしているところから、あらかじめ時間の指定があったのでしょう)、あれもこれも無制限に話すわけには行かない。「集団的自衛権は銃声の政府見解で憲法違反とされてきた」という話は、ほかの登壇者が行っていたとすれば(憲法学者の小林節も参加していたようですし)、限られた時間の中でその話を盛り込むことを避けたのも当然のことでしょう。どうせ、産経のことだから、どこが憲法違反かに触れたとしても、別の部分で一生懸命あら探しをするだけでしょうから。ただ、そうは言っても、こうやって片言節句を切り取って大々的に報じて、印象操作を図るような質の悪い御用マスコミは存在するのだという前提で、そういう連中に足元をすくわれないように注意をしたほうがいいんじゃないか、ということは思います。私だって、安倍首相など「バカか、お前は」って思いますけど、1日1000アクセスの小さなブログと全国的に(敵からも味方からも)注目されているシールズの中心メンバーでは、揚げ足取りの激しさもまた違いますから。仲間内で話す内向きの言葉と、出来るだけ多くの人に訴えるための外向きの言葉は、ちゃんと使い分けたほうがよいのではないか、と、私は安保法案の廃案を心から願う立場から、そう思います。
2015.08.24
コメント(6)
-
外国人旅行者の増加は、確かに体感します
訪日外国人旅行者 最速で1000万人超ことし1月から先月までの7か月間に日本を訪れた外国人旅行者は、円安が続いていることなどから1100万人余りとなり、これまでで最も早く1000万人を超えました。日本政府観光局によりますと、ことし1月から先月までに日本を訪れた外国人旅行者は推計で1105万人余りと、前の年の同じ時期に比べて46.9%増えました。外国人旅行者の1000万人超えは、去年の10月よりも3か月早く、統計を取り始めた昭和39年以降で最も早くなりました。国や地域別では、中国からの旅行者が最も多く前の年の同じ時期より2倍以上増えて275万人余り、次いで、韓国からが41.7%増えて216万人余り、台湾からが29%増えて215万人余りとなっています。これは、円安が続いているほか、中国人向けビザの発給要件が緩和されたこと、それにクルーズ船の寄港が増えていることなどが主な理由です。また、同時に発表された先月に日本を訪れた外国人旅行者は、推計で前の年の同じ月より51%増えて191万人余りと、1か月間の旅行者としては最も多くなりました。年間1800万人超える見込み観光庁の久保成人長官は記者会見で、中国経済の減速の影響について、「旅行者に与える影響は現時点ではないと聞いているが、今後の動向を注視したい」としたうえで、「今後、特段の悪条件がなければ年間の外国人旅行者は過去最多となる1800万人を超える見込みだ」と述べました。---なるほどね。訪日する外国人が激増している、というのは、私自身も体感しています。まず、山です。2月に北アルプスの唐松岳に登ったときに、麓の白馬スキー場に外国人がものすごく多いな、と気が付きました。感覚的には3~4割が外国人と感じました。さすがに、多いのはスキー場までで、その上の登山道(もちろん、完全冬山)には、外国人は少なかったのですが、それでも皆無ではなかった。続いて、5月のゴールデンウィークに上高地から岳沢まで登ったときも、外国人は多かった。このときは、上高地も多かったけれど、岳沢への登山道にも外国人は点々といました。ゴールデンウィークの岳沢も残雪期雪山の領分ではありますが、このときは天気も安定していたし、滑落して命の危険があるようなところもないので、ほぼハイキングの延長で登れる場所ではありました。7月に登った北岳も、外国人はチラホラと見かけました。そして何より、都心の大きな公園(代々木公園とか日比谷公園など)を通ると、やたらと外国人が多い。特に日比谷公園です。日本の政治の中心のごく近くで、皇居も近いから、元々外国人が多い場所ではありますけど、先日通りかかったときなど、日本人より外国人のほうが多いんじゃない、という感じでした。引用記事では中国韓国台湾からの観光客が激増しているようです。ただ、私の体感では欧米人の観光客も激増しています。都心の公園は欧米人も中国人もどちらも増えたな、と思いますけど、スキー場とか山で見かける外国人は欧米系が大半です。(ただし、中国人や韓国人は、しゃべっている言葉を聞かないと外国人とは気がつかない場合もあります)個人的なことで言えば、Youtibe経由で知り合った、日本のアニメが大好きなチリ人の知り合い(大学生)が、2月に来日したのです。二回会って、超久しぶりに酒を飲みながらスペイン語で話をしました。チリは、南米の中では比較的中流層の厚い国ではあるけれど、ちょっと前までは観光目的でチリから日本に旅行、なんてまずなかっただろうと思います。それもこれも、円安のおかげと、原油価格が下がって飛行機の燃油代追加料金が減ったせいでしょうね。訪日外国人は、一昨年1000万人の大台を突破し、去年は1300万人。それでも、日本人の海外渡航者のほうが多かったのです。しかし、21世紀に入って以降、日本人の海外渡航者は1700万人前後で安定しているので、もし今年訪日外国人が1800万人に達すると、1969年以来46年ぶりに、日本人海外渡航者より来日外国人のほうが多い、ということになるかもしれません。が、それはそれとして、私も南米行きたいよー、メキシコ行きたいよー、スペインだって行きたいよー!!しかし、当面のところ、家庭の事情仕事の事情の両面から、まったく実現の可能性が見えません。ああ、人生とは不如意なもの。でも、いつかまた、必ず!!
2015.08.23
コメント(5)
-
日本の一番長い日
先日、半藤一利原作の映画「日本のいちばん長い日」を見てきました。なかなか興味深い内容でしたが、正直なところ、私は一連の歴史的経緯をある程度知っているので映画についていけましたが、それでも、一瞬「あれっこの人は??」と迷うところがありました。予備知識がない人がこの映画を見たら、付いていくのはかなり厳しいのではないか、という気がしました。敗戦に際して、降伏を主導した鈴木貫太郎首相に対して、阿南陸相は表向きは陸軍強硬派の主張を代弁して「戦争継続」を叫びつつ、裏では鈴木首相に協力して戦争終結に動いていた、という説があり、映画の中の阿南陸相はその説に従って描かれています。いや、そうではなくて阿南は言葉どおりの強硬派で、戦争継続を望んでいたのだ、という説もあります。実際のところ、腹の中で何を考えているかは本人にしか分からないので、何ともいえないところです。ただ、阿南は鈴木貫太郎の人柄に対して、尊敬の念を抱いていて、陸軍からの倒閣の動きを抑えていたことは事実のようです。それにしても、戦争末期の時期、日本中の主要都市は空襲で焼け野原となり、多くの日本兵は飢餓線上をさまよっていた状況です。それでも「戦争継続」と叫んでいた、血の気の多すぎる軍人たちはどこで何をしていたのか。みんな東京の陸軍省や近衛第一師団の参謀とてして権勢を振るっていたのです。映画の中では、空襲のシーン、原爆の爆発するシーンは多少ありますが、話のほとんどは東京の陸海軍省、皇居、首相と陸軍大臣の官邸が舞台です。これらの場所は、海軍省が燃えた以外は空襲では被災していません。当時の日本の中ではもっとも安全な場所で、餓死の危険も比較的少ない立場にいた人たちが、勇ましいことを言って戦死者(半分以上は餓死者)をどんどん増やそうとしていた、といわざるを得ません。映画の中で「2千万人が特攻すれば戦局は打開できる」と叫ぶ軍人が出てきました。後で誰だろうかと調べたら、海軍の大西滝次郎中将、特攻作戦の生みの親であった人物が、そのように発言した記録があるようです。2千万人特攻、想像を絶する話であり、狂気の沙汰としか思えませんし、そんなことをやっても戦局が打開できるはずがないことは明らかでした。それにしても、人の命を何だと思っているのか・・・・、何とも思っていないから、特攻などという作戦を始めたのでしょう。それでも、彼は敗戦直後に一人で自決することで、最低限の責任は取っていますけど。ポツダム宣言が発せられたのは7月26日、その日から8月15日までの20日間、たったそれだけ日本の降伏が早ければ、広島長崎の原爆はなく、ソ連の参戦もなかった。それだけでも、史実より50万人程度は犠牲者が少なく済んだと思われます。そして、結局彼らは降伏を阻止しようと、8月15日の未明にクーデターを図りました。近衛師団の森師団長を殺害して、師団長命令を偽造し、部隊を展開したのですが、最終的には史実の示すとおり、クーデターは失敗に終わり、戦争は何とかおわりました。 遅きに失したとは言え、あそこで戦争が終わっていなかったら日本はどういうことになっていたのか、想像するだに恐ろしいですが、陸軍強硬派のクーデターが成功していたら、そうなっていた可能性は充分にあります。映画を見て、いろいろと思うところはありますが、ともかくいちばんに思うのは、彼ら狂信的な戦争継続派の企みが失敗してよかった、ということに尽きます。とはいえ、クーデターの首謀者の何人かは自決しましたが、生き残った人物も少なくないのです。当時も今もクーデター(現在の刑法では内乱罪)は重大な犯罪行為だし、彼らは近衛師団長(陸軍中将)を射殺するという明白な犯罪行為を犯したにもかかわらず、敗戦のドサクサで一切罪に問われることはなかったのです。
2015.08.22
コメント(9)
-
桜島噴火?
桜島の火口の底に「ふた」 爆発力増すおそれ15日に噴火警戒レベルが3から4に引き上げられた鹿児島市の桜島では、昭和火口の底に噴出物がたまり、「ふた」のように火口をふさいでいることが確認されている。朝日新聞が15日午後に上空から撮影したところ、ふたの周囲から白いガスが噴き出していた。専門家は、ふたによって内部の圧力が高まり、より爆発的な噴火につながる可能性があると指摘している。19日午後に気象庁の調査に同行した京都大火山活動研究センターの井口正人センター長は、こうした状況が続いているのを上空から確認した。昭和火口では同日未明、警戒レベル引き上げ後初めてごく小規模な噴火が起きたものの、「火口はほぼ閉塞状態で、内部の圧力が高まって爆発力が増している」と指摘する。桜島では今年1~6月に672回の爆発的噴火が起きたが、7月は14回と激減した。ふたは噴火活動が激しかった5~6月ごろの噴出物とみられるという。一方、国土地理院は、桜島の南岳山頂火口の東側で、おもに8月10日以降、地盤が東西方向に最大約16センチ広がる変動を観測した。地球観測衛星「だいち2号」によるデータを解析した。昭和火口下でマグマが上昇した動きとみられるという。---終戦の日に突如として桜島の火山活動が激化、周辺住民に避難が呼びかけられているのは、すでに報じられているとおりです。桜島は、日本国内ではおそらくもっとも活発に活動している火山で、引用記事にあるように1日平均2回以上という頻度で噴火を続けています。だから、噴火自体は平常のできごとであり、問題は普段より大きな規模の噴火が起こりそうだ、ということです。ただし、どの程度の大きな規模なのかは皆目見当がつきません。今年5月21日には、桜島は噴煙が4300mに達する噴火(観測史上6番目とのこと)を起こしています。2013年8月18日には噴煙5000mに達する観測史上最高記録の噴火も記録しています。しかし、そのどちらでも住民の避難は行われていません。ということは、少なくとも観測史上最大の噴火よりも規模が大きいと想定されている、ということでしょう。おそらく、ですが、大正噴火と同程度の噴火が懸念されている、ということなのではないかと思います。桜島の大正噴火は1914年1月12日に発生、流れ出した溶岩の総量は2立方km程度、犠牲者58名と記録されています。そりまで文字どおりの「島」だった桜島は、この噴火の溶岩で九州と陸続きになりました。このとき桜島で降り積もった灰は、深さ1mにも達したそうです。もしこの大正噴火と同規模の噴火が今発生したら、どういうことが起こるのか。NHKの報道によれば、気象庁気象研究所のシュミレーションで、東風の想定だと鹿児島市内の降灰量は70~80cmにも達するそうです。都市機能は完全に麻痺することになるでしょう。そして、もう一つ、桜島から見て鹿児島の市街地の向こう側には、再稼動してしまったばかりの川内原発があります。想定が大正噴火程度なら、川内原発まで火砕流や火山弾が押し寄せる、ということは多分ありません。しかし、火山灰は降ります。さきの引用先のシュミレーションでは、川内原発には10cm前後の降灰がありそうです。風向き次第ではもっと多い可能性もありますし、逆に少ない可能性もあります。10cmの火山灰が降ったらどういうことになるのでしょうか。火山灰はかなり重いものです。しかも、濡れた状態では通電します。だから、電線などに付着しやすいし、付着すれば、重さで断線する可能性が高いのです。また、通電しやすいということは、火山灰が付着した電線や電気機器は絶縁不良を起こしやすく、壊れる可能性が高い、ということになります。つまり、火山灰が降り積もると、電気機器が壊れたり停電が起こる可能性が高いのです。70cm積もるという鹿児島市内はもちろんですが、10cm前後の火山灰が積もる川内原発付近も、おそらく停電が発生します。福島第一原発は、送電線の鉄塔倒壊によって外部電源が絶たれたことから大事故が発生したことは記憶に新しいところです。川内原発でも、鉄塔は倒壊しないでしょうが、停電によって外部電源が経たれる可能性は高いと思われます。で、その場合は非常用のディーゼル発電機が電気を供給するわけですが、福島の事故では、この発電機が津波で冠水して壊れてしまい、燃料棒が冷却できなくなりました。川内原発はどうでしょうか。多分津波は来ないのでディーゼル発電機は冠水しないものの、火山灰のすさまじい洗礼を受けます。ディーゼルエンジンが稼動するには当然のことながら酸素(空気)を必要とします。その空気と一緒に火山灰を大量に吸い込めば、エンジンは壊れます。そうならないように、エンジンの吸気口にはフィルターがついているのですが、こんな規模の火山灰が降り注いだら、あっという間に目詰まりします。結局、川内原発でも非常用発電機が故障する可能性は高いと思われます。また、それ以外にも原発の操作機器も電子機器ですから、火山灰が入り込めば故障する可能性が高い。それによって原発の操作自体が出来なくなる可能性もあります。そして、降灰量が10cmにも達したら、おそらく道路と自動車はまったく身動きが取れなくなります。まして鉄道や飛行機はいうまでもありません。つまり、原発が危険な状態になっても、外部から救援に駆け付けることは難しいだろうと思われるのです。そうなると、3.11の際の福島第一原発と同じことが起こるのではないかと思います。もっとも、有史以前には、大正噴火など問題にならないようなとてつもない規模の超巨大噴火が何回か起こっています。そもそも、桜島はそれ自体が単独の火山ではなく、姶良カルデラという、巨大噴火の陥没跡に残った外輪山に過ぎないわけで。2万8000年前の巨大噴火は、噴出物総量が400立方キキロメートルだそうです。多分、南九州一帯が火砕流で何百万人かの死者が出るレベルです。東京でも火山灰が何十センチか積もるでしょうね。この規模の噴火が起きたら、川内原発は当然に火砕流に襲われます。もっとも、それ以前に鹿児島市内も火砕流に襲われることにはなりますが。今回の桜島は、さすがにその規模の噴火ではない・・・・・と、思います。多分。噴出物の総量が100立方キロ(大正噴火の50倍)にも達する超巨大噴火なら、その直前の山体膨張は、山の形が変わるくらいすさまじいものであると思われますが、現実に観測されている山体膨張は、それほどではないからです。もっとも、この規模の超巨大噴火は、日本では約7000年前(そのとき起こったのは、奇しくも桜島に近い南九州沖合いの鬼界カルデラ)、世界的には1815年のインドネシアのタンボラ山で起こったのが最後で、噴火の前兆を科学的に記録した調査はなく、どんな前兆があるのかはよく分からないのですが。ともかく、桜島で大規模の噴火が迫っていると思われる今、川内原発を平然と動かしている場合ではないと、私は思います。
2015.08.21
コメント(4)
-
イラクでも危機一髪だった
銃声、群衆が陸自包囲 撃てば戦闘…サマワ駐留隊員恐怖自衛隊初の「戦地派遣」となったイラクで、隊員たちは危険と隣り合わせの活動を強いられた。政府は当時、「一人の犠牲者も出さなかった」と安全性を強調したが、実際は隊員が銃を撃つ判断を迫られるなどの事態が起きていた。陸上自衛隊の内部文書「イラク復興支援活動行動史」や関係者の証言で明らかになった。新たな安全保障関連法案では活動範囲がより拡大し、危険はさらに高まる。突然、銃撃音と怒声が響いた。サマワから約30キロ離れた街ルメイサ。2005年12月4日、幹部たちはムサンナ県知事らと、修復した養護施設の祝賀式典に参列していた。発端は、会場のそばで起きた反米指導者サドル師派と、自衛隊を警護していた豪州軍の銃撃戦だった。サドル師派は頻繁に多国籍軍を襲撃し、自衛隊も「占領軍」と敵視した。会場内の陸自幹部たちは「ただ事ではすまない」と青ざめた。銃撃戦に続き「ノー・ジャパン」などと抗議しながら押し寄せた群衆の渦は、あっという間に100人前後に膨らんだ。幹部らは建物に閉じ込められ、外で警備にあたっていた十数人の隊員は群衆に包囲された。車両に石を投げつける男、ボンネットに飛び乗って騒ぐ男、銃床で車の窓をたたき割ろうとする男までいた。「どうすべきかわからず、みんな右往左往していた」と当時の隊員は話す。群衆の中には銃器をもつ男たちもいた。もし銃口が自分たちに向けられたら――。政府が認めた武器使用基準では、まず警告し、従わなければ射撃も可能だ。「ここで1発撃てば自衛隊は全滅する」。どの隊員も、1発の警告が全面的な銃撃戦につながる恐怖を覚えた。「撃つより撃たれよう」と覚悟した隊員もいた。結局、地元のイラク人に逃げ道を作ってもらい窮地を脱することができた。---イラクに派遣された自衛隊の宿営地に、迫撃砲が撃ちこまれたことは当時報道されていたように記憶していますが、この出来事は当時はまったく報道されていませんでした。自衛隊は、結果としては一人の戦死者も出さず、一人のイラク人も殺すことなく終わったものの、それはかなり幸運な偶然であって、かなり危機一髪の状況があった、ということです。問題の「イラク復興支援活動行動史」は、この7月に防衛省がやっと全面公開したもので、民主党の辻元議員のホームページに全部公開されています。その中で、イラク復興支援活動行動史完全版2の118ページに、数行この事件が記載されています。撃ったら、自衛隊が全滅する、それが現場の隊員の偽らざる肌感覚だったのだと思います。熱した油に火のついたマッチを投げ込むようなものですから。本当に、撃たないで済んで良かった。撃っていたら、現場の自衛隊員自身の生命も、平和国家としての日本の立場も、全てがそこで終わっていたでしょう。上記の報告書では弾薬装填は実施せず、と書いてあります。自衛隊は実弾の使用に極めて厳しいので、本当に引き金を引くときしか装填はしないようです。実包の入った弾倉はすでに身に帯びており、それを銃に挿し、安全装置を外して引き金を引くのにかかる時間は、ものの2~3秒でしょう。このこともまた、安易な発砲を防ぐ意味があったのではないかと思います。装填した銃を持っていたら、恐怖心から引き金を引かないとも限りません。イラク国内ではもっとも安定して安全とされたサマワで、戦闘任務ではない派遣でもこうだったのです。今後は犠牲者が出ない、あるいは相手側に犠牲者を出さないことは、まったく不可能というしかありません。ここ最近の動きを見ている限り、自衛隊の内部にも安保法制に内心反対の考えは相当にあるのだろうと思われます。共産党の小池議員に統合幕僚監部の内部文書が情報提供されましたが、つまり統幕に勤務する幹部自衛官に、安保法制を快く思っていない人がいる、ということです。引用記事のできごとだって、記者の取材に答えて、そのときの危機的な状況を語ったサマワ派遣経験者が何人かいたわけです。そりゃ、安保法制がとおって自衛隊が海外に派「兵」されて、真っ先に命の危険に晒されるのは自衛隊員自身なんだから、当たり前でしょう。
2015.08.20
コメント(2)
-
極端に利己的な考え
武藤衆院議員:出資金返さず 「未公開株」で4000万円集める 文春報道滋賀4区選出の自民党衆院議員、武藤貴也氏が、未公開株購入を名目に知人から出資を募り、株を購入せず出資金を返さないとして金銭トラブルになっていると、19日発売された週刊文春が報じた。武藤氏は同日、「ご迷惑をおかけした皆さまには心よりおわびを申し上げます。今後関係者らと相談し、きちんと対応してまいりたいと思います」とのコメントを出した。週刊文春によると武藤氏は昨年「国会議員枠で買える」とソフトウエア会社の未公開株購入を知人らに勧め、23人が計約4000万円を武藤氏の政策秘書の口座に振り込んだ。だが、株は実際には購入されず、出資金の一部は戻っていないという。武藤氏は、安全保障関連法案に反対するデモを呼び掛ける学生らのグループを「『戦争に行きたくない』という極端な利己的考え」などとツイッターで批判していた。---「戦争に行きたくない」は極端に利己的で、怪しい儲け話で4000万円を集めて着服するのは利己的ではないらしい。すごい言語感覚です。自称愛国者の真の姿がよくわかりました。愛国商売ということでしょう。それにしても、「国会議員枠」とか、いかにも詐欺話っぽくて、「騙されるほうも」と思わないこともないけど、本物の国会議員本人がそれを言っているんだから、救いがない。要するに、国会議員が詐欺師だった(あるいは詐欺師が国会議員のなったのか)という話。本人は自民党を離党しましたが、離党だけで済むはなしか、と思います。どう考えたって、議員辞職ものでしょう。もっとも、本人がお金を弁済せず、被害者から刑事告訴されれば、遠からず警察の手が入るでしょう。逮捕されるかもしれません。まあ、武藤貴也こそが、極端に利己的な考えの人物だ、ということはとてもよく分かったお話でした。
2015.08.19
コメント(6)
-
雇用保険
<雇用保険料>引き下げに向け議論 厚労省、年内にも結論厚生労働省は、2016年度の雇用保険料引き下げに向けた議論を始めた。雇用情勢の改善で失業給付が減り、積立金は6兆円を超えて過去最高となっており、引き下げ幅のほか、給付拡充に踏み込めるかどうかが焦点となる。同省は年内にも結論を出し、必要な法改正をする。~積立金は、年間失業率が過去最悪の5.4%となった02年度には4064億円に落ち込み、収入確保のため保険料率を一時1.6%にまで引き上げた。その後、08年のリーマン・ショックの影響はあったものの、失業給付を受ける人はピークの01年度の約111万人から14年度には約46万人に減り、積立金は13年度ですでに過去最高の6兆621億円に上っている。雇用保険の積立金は失業者の増加に備えたものだが、過剰な積み立ては必要ない。保険料引き下げは、これまでも積立金残高の「調整弁」として使われてきた。労使双方が要望しており、4年ぶりの引き下げとなる公算が大きく、焦点は下げ幅だ。現在、失業給付に充てる保険料率は1%で、労使0.5%ずつ負担している。厚労省は、過去最低だった0.8%を視野に0.1~0.2ポイント程度の引き下げを検討している。一方、4日の部会では労働側から給付の拡充を求める意見も出た。給付日数は1990年代までは最長300日間だったが、失業率が上昇基調にあった00年の法改正で倒産やリストラによる失業者は330日間に拡大する一方、転職など自己都合退職者は180日間へ短縮、現在は150日間だ。この時に給付率も60~80%から50~80%に下がっている。ただ、失業手当の拡充だけでは職探しの意欲をそぐとの指摘もあり、慎重に判断する。また、65歳以上の高齢者への雇用保険適用や、就職促進給付の拡充なども検討する。積立金は過去最高とはいえ、6月の完全失業率は3.4%と前月より0.1ポイント悪化するなど今後も雇用情勢が安定するかどうかは見通せない。また、給付率を67%に上げた育児休業給付など14年度からの制度拡充が雇用保険財政にどう影響しているのかも踏まえ、判断する。---保険料引き下げも、給付の拡充もよいのですが、一つ大事な視点が抜け落ちているように思います。失業保険は、会社都合退職と自己都合退職で給付期間に差がつけられていることは引用記事にあるとおりですが、もう一つ、自己都合退職の場合は受給できるまでに3ヶ月待たなければなりません。これが非常に曲者です。と言うのは、リストラなどで実質的には会社都合でやめさせられているのに、自己都合退職扱いにされる例がよくあるのです。自己都合退職では3ヶ月待たないと失業保険が出ない、という事実すら、退職して離職票をもらってハローワークに行って、初めて知るような人も少なくないので、そのようなやり方がまかり通ってしまうのでしょう。この3ヶ月待ちの期間があるために、失業手当が受けられない人は、かなり多いんじゃないかと思います。だって、無収入になって、その状態を3ヶ月続けることは(手持ち金が充分あれば別ですが)相当不安でしょう。だから、「失業保険がほしいから、3ヶ月間は仕事に就かずに待っていよう」なんて思う人はそうそういません。そうすると、結局は保険料だけとって、肝心なときに役に立たない失業保険になってしまうのです。「自己都合」というのも、ある意味であいまいな言葉です。長時間残業で病気になって退職に追い込まれれば会社都合ですが、「こんな長時間残業では遠からず病気になる」と病気になる前に自ら退職してしまえば自己都合です。リストラで有形無形の圧力を受けて、自分から「辞めます」と言いだすように仕向けられても自己都合退職です。そういう意味では、自己都合退職と会社都合退職で条件を変えること自体が不合理と思わざるを得ません。完全に差をなくすことが困難なら、せめて受給までの3ヶ月待ちだけはやめる(百歩譲っても、待ち期間を短縮する)べきと私は思うんですけどね。そのことと同時に、現状の制度の下では、会社を辞める(辞めさせられる)ときには、「自己都合退職だと失業保険が出るまで3ヶ月待ちだ」ということをよく認識しておくべきです。何も知らずに唯々諾々と自己都合退職にされて、離職票を持ってハローワークにいって慌てふためくような事態は、できれば避けたいですから。
2015.08.18
コメント(2)
-

西岳・編笠山 リバーサルフイルムの写真
先週登った八ヶ岳の西岳・編笠山のリバーサルフィルムの写真がとりあえず出来ました。登る前日(家族旅行の初日)の午後に登山口近くで撮影しました。このときは、味馬手相棒と子どもを登山口まで連れて行きました。宿から標高差120mほどでしたが、疲れた疲れたといっておりました。私一人だと、宿から登山口まで15分かそこらなのですが、40分もかかった。同じ場所から南アルプスを撮影。甲斐駒ヶ岳が見えます。翌日、西岳の樹林帯はほとんど写真を撮らず、ひたすら登り。山頂直下の開けた場所で初めてカメラを取り出しました。イブキジャコウソウです。晴天時の風景写真だと、iPad miniでもそれなりの写真が取れるのですが、花の写真は一眼レフとは大きく差が出ます。iPadのレンズでは花の写真はまともには撮れません。ウスユキソウ(左上の白い花)とヤマハハコ(中央下の白い花2つ)、ホタルブクロ(その右の紫の花)に加えて、オンタデ(中央やや右の、葉の大きな白い花)もありますね。西岳山頂から、ガスの切れ目に権現岳が見えました。西岳から編笠山への途中、ガスが完全に切れて、樹間に権現岳が完全に姿を現しました。同じ場所で編笠山を撮影。こちらは、ちょっとガスがかかっていますが、おおむね晴。遠い飲み屋、もとい青年小屋の到着(山小屋の玄関に「遠い飲み屋」という赤提灯がかかっていることで有名です)。編笠山を見上げます。青年小屋から編笠への登り。ガレ場の急登。途中で青年小屋を見下ろしました。向こう側は権現岳。青年小屋から編笠山頂までは、標高差150m程度。ガレ場続きだけど危険というわけでもなく、斜度が急な分あっというまに山頂に到着です。眼下に富士見高原、南アルプス。でも、だいぶもやっていて、視界はいまひとつです。真夏ですからねえ。先ほど通過した西岳。地図上のコースタイムで、西岳から編笠山までは1時間20分です。そして、権現岳。青年小屋からコースタイム1時間半。八ヶ岳で唯一残っている未踏峰です。いつ登れるかな。下山にかかります。編笠山は、青年小屋からも富士見高原からもガレ場です。そんなに危険ではないし、歩きにくいわけでもありませんが、転倒したらちょっとまずいかな。樹林帯に入ってから見かけました。マルハダケブキだと思います。南アルプスに結構多い花です。鹿が食べない花なのです。南アルプスでは鹿の食害がひどいため、この花ばかりが残っているところもあるようです。そういう意味では、あまりイメージのよい花ではないのですが、大きくて目立つ花ではあります。ところで、写真がとりあえず出来た、とあいまいな書き方をしましたが、実は現像は出来たのですが、まだいろいろあってプリントに出せていないのです。スライドになっていれば、スキャナに取り込んでパソコンでは見られますけど、やっぱりプリントしてこそだよな、と。
2015.08.17
コメント(2)
-

8月15日の靖国神社は異常な場所であった
昨日8月15日は、午後から日比谷公園まで笛の練習をしに出かけておりました。4時頃まで練習して、その後、ちょっと思うところあって千鳥ヶ淵戦没者墓苑へ向かいました。皇居の周りをぐるっと回って、歩いていきました。ランナーが結構多かった。私も走っているけど(実は、今朝も8kmほど走った)、ただ晴天の真夏の日中に走る気は、さすがにしません。千鳥ヶ淵公園。桜の名所です。ただ、見たところ桜の木はみんな満身創痍の老巨木ばかりでした。あと100年後も桜の名所でいられるかなあ・・・・・・。千鳥ヶ淵戦没者墓苑は、正確には覚えていませんが、10年以上前に一度行ったことがあります。そのときも8月15日でしたが、人がほとんどいなかったような記憶があります。しかし今日は、そこそこに参拝者がいました。日の丸が掲げられていますが、半旗になっています。菊の花を配っておりましたので、わたしも寄付をして参拝することにしました。正直、安倍晋三の札の前で献花するのは、心理的抵抗がないわけではありませんでしたが、社民党党首の献花もあったし、まあいいか、と。祭壇から少し離れて、何故か尺八を吹いている男性がいました。私も、前述のとおり練習の後立ち寄ったので、管楽器ケースにケーナとサンポーニャ、背中のリュックにフルートが入っていましたが、さすがにここで吹く勇気はありません。ケーナは尺八より音が鋭いし。ところで、戦没者墓苑の表示には、戦没者総数240万人とありました。現在、太平洋戦争の日本の犠牲者総数は310万人とされています。どこからその差が出てくるのだろうかと思ったのですが「海外で亡くなられた戦没者(軍人軍属だけでなく、海外で亡くなった一般邦人も含むとのこと)」というところですね。つまり日本国内で亡くなった方を除いた人数、ということなのでしょう。ただ、若干疑問を感じるのは、ここどいう「海外の戦没者」には沖縄と硫黄島を含んでいるようなのです。沖縄も硫黄島も日本です。それなのに、千鳥ヶ淵戦没者墓苑の基準では、海外扱いになっているんですね。その後、靖国神社に向かいました。途中、九段坂病院の前を通りました。実は、父がここに入院していたことがあって、その後もいろいろあって、ここには何回か通ったなあ、と苦い思い出。別に、その病院が何かあったわけじゃないのですが、基本的に病院というのは良い思いでの生まれる場所でもないので。靖国神社の前を通ったことは、もちろん何回もありますが、実は敷地内に足を踏み入れたことはありません。もちろん、ここに参拝などする気は絶対ありません。ただ、一度は見ておくべきだろうと思ったもので。大村益次郎の銅像の脇から入りました。ここはあまり人の出入りがありませんでした。参拝する気はないので、大村益次郎の銅像から社殿には近寄らず、そのまま正門に向かいました。日の丸を林立させた集団が堂々と示威行動をやっていました。ただ、丁度解散するときだったらしく、私が社殿のほうにカメラを向ける前に、林立する日の丸を片付け始めていました。敷地内で示威行動などは禁止します、というような看板がありましたが、きっと、靖国神社のお眼鏡にかなう示威行動なら、敷地内でやってよいのでしょう。何の集会だったか(おおむね想像は付きますが)、よく分かりません。というのは、丁度集会が終わったところらしく、日の丸を片付けているところだったからです。そういえば、「8月14日から17日までの期間中街宣車の境内乗り入れを禁止します」という建て看板があったのですが、それって、逆に言うとその期間以外は街宣車が境内に乗り入れてよい、ということでしょうか?そうは言っても、まさか靖国反対派の街宣車が乗り入れるわけもないので、結局は右翼団体の街宣車は(期間中以外)乗り入れ自由、ということでしょうか。早稲田通り沿いの正門は、大村益次郎の銅像脇入口とは大違いで、大混雑でした。「靖国の英霊に感謝と崇敬の念を捧げます」だそうです。その後、人波に押されるまま、九段下駅方面に歩いていったら、右翼団体の街宣が山のようでした。不敬言動徹底粉砕だそうです。お前らに粉砕なんかさせるか!!とは思うものの、その場は黙って通り過ぎました。しかし、この程度の街宣は、まだまだ序の口なのでした。櫻井よしこの写真を掲げて、みにくい日本、じゃなくて美しい日本がどうのこうの、という団体。書名をやっていて、そこに通行人が行列しているのです。完全に狂信右翼勢力の人波の中に入り込んでしまったようです。日韓断交だそうで。絵に描いたように典型的なネトウヨ言説。しかし、これって靖国通沿いの工事中のビルの仮囲いなんですけど、ビルの所有者の許可を取ったんでしょうか。お盆休みをいいことに、勝手に張ったとしか思えませんけど。「上下朝鮮土人」って、そういうことを書いて、恥ずかしいと思わないのかな。思わないからネトウヨなんだろうけど。誰も「これはやりすぎ」と思わないんだろうか。思わないんでしょうね。ここも署名集め。台湾を守れ、という団体。中国のことを口汚くののしっていました。新宿線九段下の駅に向かっていたところ、丁度駅の上の交差点に大きな人だかりができていました。なんだろうかと思ったら、どうやら靖国反対のデモ隊に向かって、日の丸を掲げた連中が激しいののしり声を浴びせているようでした。何を叫んでいるかはよく分かりませんでしたが。できれば、あの隊列に私も参加したいところでしたが、人垣が厚すぎて、さらに警官隊がガードを固めてしまい、とても近寄れる状況ではありませんでした。交差点を通過できないので、駅の構内を通って反対側に出てみましたが、状況は同じでした。心の中で「デモ隊、応援してるぞ、頑張れ!!」と叫びつつ、この場所を後にしました。それにしても、ああやって「反日勢力」に対するののしりの言葉を叫び、中国や韓国に対する憎悪を掻き立てることが、戦没者に対する慰霊なのでしょうか。戦没者の慰霊を体よく利用しているだけじゃないのか、と思えてなりません。日本を、彼らの望むような姿の国にしてはならない、改めてそう思いました。正直言って、千鳥ヶ淵と靖国の行く順番を逆にすべきでした。後味が悪すぎる。ただ、日比谷公園から歩いていったので、道順がどうしても千鳥ヶ淵が先になってしまうのてだすけどね。靖国神社には、8月15日は一度行けばもう充分。二度とこの日にいくことはないでしょう。
2015.08.16
コメント(9)
-
戦後70年
戦争が終わって、今日で70年目となりました。昨日、どこかの首相が何か発表したらしいですが、それについての論評は明日以降にしたいと思います。太平洋戦争と、その前から続いていた日中戦争、その全期間を通じて、戦争の犠牲者は膨大な数に及びます。日本 310万人朝鮮 20万人台湾 3万人中国 1000~2000万人ベトナム 200万人インドネシア400万人フィリピン 100万人インド 150万人ミャンマー 5-15万人シンガポール・マレーシア10万人など、すべて合計すると、少なくとも2000万人以上になります(餓死者等を含んだ数です)。更に、ヨーロッパ戦線(旧ソ連だけで2000万人以上)もあわせた第二次大戦全体では、5000万人以上、ひょっとしたら6000万人近い犠牲者を出しています。第二次大戦が終わった後も、残念ながら世界の戦火は絶えることなく現在まで続いています。ただ、さすがにこれほどの犠牲者を出した戦争は、第二次大戦以降、これまでのところは起きていません。そして、何よりわが国自身は、戦後70年間、一度も戦争を起こすことも起こされることもなく、戦死者を出すことも、敵を殺すこともほとんどありませんでした。(厳密に言えば朝鮮戦争時に海上保安庁の掃海部隊が派遣され、触雷によって掃海艇1隻が沈没、死者1名を出していますが、これが唯一の例)日本が戦後70年間、いろいろな問題はあったにしても、ともかく一貫して戦争に参加せず、被害者にも加害者にもならずに来たことは、誇るべき歴史である、と私は思います。少なくとも、第二次大戦に至る時代と戦後と、生きる時代を自由に選べるものならどちらを選ぶかといえば、一瞬の猶予もなく戦後を選びます。日本が戦後70年間平和を維持し続けられた理由は様々であり、単一的な理由ではないでしょうが、戦争放棄を謳った憲法第9条の存在は、その大きな部分を占めると私は思います。自衛隊と憲法第9条の関係については、常に議論に対象となっています(私自身は、自衛隊は日本にとって必要と考えています)、しかし、そのことはともかくとして、憲法第9条の存在、そして平和を志向する政治勢力の存在が、戦争に向かう政策への大きな抑止力となりました。また歴代の政権も、積極的に戦争に加担するような政策はとってこなかったことも事実です。我々は、70年間続いてきた平和を、これからの時代にも受け継いでいくべきである、と思います。そのためには、「日本は二度と戦争をしない」という方針、それを体現する憲法第9条の精神を、今後とも守っていくべきです。よく、中国の脅威なるものを強調したがる人がいます。でも、現状の自衛隊の存在でも守りきれないほどの脅威ではありませんし、もちろん中国側もその程度のことは認識しているでしょう。いずれにしても、周辺国との関係を悪化させて「いつ攻めてくるか」と鎧をまとって待ち構えているのと、関係を改善し、そんなに分厚い鎧を着て待ち構える必要性を除去すること、どちらのほうがより安心できるのか。私は後者であると信じます。もう一つ重要なことは、戦争を知らなければ平和のよさは分からない、ということです。日本はなぜ太平洋戦争という大失敗への道に踏み込んだのか、そして、戦争とはどのようなものであり、そこに巻き込まれた人々はどのようなことになるのか、そういったことをきちんと検証しなければ、再び同じ過ちを繰り返してしまうかもしれません。戦争体験の継承と検証は、戦争を避けるうえでも大切なことです。二度と再び日本が戦争の惨禍に巻き込まれたり巻き込んだりすることがないことを、心より願っております。
2015.08.15
コメント(2)
-
ならば談話は不要
自民・稲田氏、「おわび」に否定的 戦後70年談話自民党の稲田朋美政調会長は11日、BSフジの番組で、14日に安倍晋三首相が閣議決定する戦後70年の「安倍談話」について「未来永劫、謝罪を続けるというのは違うと思う」と述べ、「おわび」の文言を盛り込むべきではないとの考えを示した「おわび」は村山談話や小泉談話に盛り込まれているが、稲田氏は「戦争の終結は講和条約がすべて。世界にあった日本の財産はすべて没収され、過酷とも言うべき賠償も払い、日本は国際社会に復帰した」と指摘。「首相は今までの(村山、小泉)談話を引き継ぐとも明言している」と強調した。一方で、「(おわびという)キーワードを入れるべきであるかどうかは、首相の判断に任せるべきだ」とも語った。---極右の稲田なら、いかにも言いそうな内容ではあります。報じられているところでは、「安倍談話」には侵略という言葉とおわびが入ることになったそうです。ただ、原稿に入っていても安倍が読まない、ということもありえます。広島の原爆の日の式典で安倍は非核三原則に言及しませんでしたが、原稿には入っていたものを安倍の判断で読まなかったようです。つまり、戦後70周年談話も、本当に侵略とおわびが入るかどうかは、そのときにならないと分からない、ということです。それにしても、戦争を起こした国のトップとして太平洋戦争というものにあえて言及するのであれば、謝罪に触れるのは当たり前のことだと私は思います。だって、全世界で数千万人の犠牲者を出した戦争ですよ、まだ直接の経験者が生き残っている時点で「未来永劫」とか言っても、そんなの当たり前じゃない、と言うしかありません。そんなことをいうなら、そもそも戦後70周年の談話など必要がありません。もともと、戦後50年の村山談話は、村山首相の強い意思に基づく、大きな意味を持つ談話だったと思いますけれど、それ以降10年ごとに首相が談話を出さなければならない決まりなんかないんですから。安倍が侵略とお詫びに言及したところで、誰もそれが本心からの言葉だなんて思いもしないし、感銘も受けない。こんなろくでもない首相の戦後70年談話なんて、聞きたくもありません。今からでも戦後70周年談話なんて、やめてしまえばいいのに。
2015.08.13
コメント(3)
-
安保法制反対運動のおかげ
カジノ法案、今国会断念=自民、安保成立に全力自民党はカジノ解禁を柱とする「特定複合観光施設区域整備推進法案」について、今国会での成立を断念、先送りする方針を固めた。党幹部が11日、明らかにした。公明党が依然、解禁に慎重なことに加え、安倍政権の最重要課題である安全保障関連法案の成立が見通せないことから、同法案の処理を優先せざるを得ないと判断した。(以下略)---「残業代ゼロ」法案 今国会での成立を断念政府・与党は29日、働く時間ではなく成果に賃金を払う「残業代ゼロ」制度の創設や裁量労働制の対象拡大などを盛り込んだ労働基準法改正案の今国会での成立を断念した。過重労働を助長させ過労死を増やすとの強い反発が出ている上、安全保障関連法案の参院審議や年金の情報流出問題などで改正案の審議入りの見通しが立たず、成立は困難と判断した。秋の臨時国会での成立を目指す。労基法改正案は、4月3日に国会に提出された。衆院厚生労働委員会では「生涯派遣」と批判のある労働者派遣法改正案の審議や、年金情報流出問題に関する審議が続いた。安保法案の衆院強行採決による国会審議の中断も重なり、労基法改正案は審議入りしていない。国会会期は9月27日まで延長されたが、参院では与野党が対立する派遣法改正案の本格審議がこれから始まる。野党は年金情報流出問題も追及する構えで、労基法改正案の今国会での成立は厳しい情勢になっていた。政府・与党は、今国会で審議入りするものの継続審議として臨時国会で成立させる構えだ。(以下略)---安保法案の陰に隠れていますが、ほかにも問題のある法案があります。それが、このカジノ法案と残業代ゼロ法案です。残業代ゼロ法案のほうは、第一次安倍政権のときに持ち出されたホワイトカラーエグゼンプションを少し変えただけのものです。当時、反対が非常に多く、安倍政権が倒れる一因ともなった法案ですが、懲りもせずにまた出してきたわけです。しかし、安保法制が大きく揺れ動いているために、残業代ゼロ法案(労基法改正案)のほうは、7月中に今国会での成立を断念、カジノ法案も断念に追い込まれたようです。安保法制がどうなるかはまだ分かりませんが、反対運動が大きく盛り上がったおかげで、この二つの法案は断念に追い込まれた。まずは喜ぶべきことです。反対運動の盛り上がりは無駄なことではなく、ある程度の効力を発揮した、ということです。もちろん、本丸である安保法制がどうなるかはこれからですけど。ただし、労基法改正案のほうは、継続審議で、秋の臨時国会で成立を目指すそうです。(まだ、実質審議は行われていないので、継続審議も何もゼロからのスタートであることは変わらないですが)安保法制と同様、政府は何が何でもやる、という構えです。それにしても、カジノ法案にしても残業代ゼロ法案にしても、安倍政権というのは、企業の側の利益を追求することしか考えない政権です。そこで働く労働者はどうでもよい、とはもちろん公言はしないでしょうが、「企業が儲かれば労働者(一本国民)にもその利益が回ってくる」という論理しかない。アベノミクスも、基本的にはそういう理屈でしょう。企業というフィルターによる中抜や副作用は考えないんですね。いや、もちろん企業が利益を上げなければ働く人の給料は出ないのですから、企業の利益を守ることは悪ではありません、必要なことです。一般論として、企業が利益を上げることに反対する労働者はいませんから。しかし、問題は、残業代ゼロ法案のように、企業と、そこで働く人の利害が相反する場合です。「企業が儲かれば労働者にもその利益が回ってくる」という論理しかないから、両者の利益が相反する場合、企業の利益を優先することしか考えられないのでしょう。
2015.08.12
コメント(3)
-
ああ、川内原発
川内1号機が再稼働=新規制基準で初―「原発ゼロ」終わる・九電九州電力は11日午前、川内原発1号機の原子炉を起動し、再稼働させた。2011年3月の東京電力福島第1原発事故を受け、原子力規制委員会が策定した新規制基準に基づく原発の稼働は初めて。14日にタービンと接続して発電・送電を始め、徐々に出力を上げて問題がなければ9月上旬にも営業運転に移る。国内で原発が運転されるのは、13年9月に関西電力大飯原発が停止して以来で、「原発ゼロ」は1年11カ月で終わった。1号機の運転は11年5月に定期検査で停止して以来、4年3カ月ぶり。~九電は13年7月の新基準施行と同時に川内1、2号機の審査を申請した。規制委は想定する地震の揺れ(基準地震動)を不十分と指摘。九電は申請時の540ガルから620ガルに引き上げたほか、想定する津波の高さも約1メートル引き上げた。一方、原発に影響を及ぼす恐れのある巨大噴火に関しては「運転期間中に起きる可能性は低い」と判断し、継続的な監視で足りるとした。事故に備え住民の避難を準備する半径30キロ圏には9市町の約21万人が住み、各自治体は避難計画を策定した。バスの手配など避難の具体的手順が整備されつつあるが、住民からは実効性を疑問視する意見が出ている。九電は川内2号機についても、10月中旬の再稼働を目標に準備を進めている。---震災の年の夏は、電力不足の可能性が取り沙汰され、節電の取り組みが大々的に行われました。私は地下鉄で通勤しているので気が付かなかったのですが、地上を走る列車は、日中車内の蛍光灯を全部消灯することまでやっていました。もっとも、車内や駅構内の蛍光灯の間引きは現在に至るまで続いていますけど。節電の掛け声は年々小さくなっていき、最近は震災前と同程度の掛け声しか耳にしなくなっていますが、それにもかかわらず、電力消費は震災前の水準に戻ってはいません。2012年5月にすべての原発が止まって以降、12年7月から13年9月まで大飯原発の2基が稼動していただけですから、この3年3ヶ月はずっと原発はほとんど動いていなかったのですが、この間電力が足りなくなることはありませんでした。よく知られているように、電力消費が最大を記録するのは、決まって夏場、お盆以外の平日の日中です。東京電力管内ですが、各年の最大電力とその日の気温(東京・大手町)は、以下のとおりとなっています。2015年 4957万kw (8/7 ・最高気温37.7度 猛暑? ※8/11までの記録)2014年 4980万kw (8/5 ・最高気温36.1度 8月初めまで猛暑、以降冷夏)2013年 5093万kw (8/9 ・最高気温34.5度 猛暑)2012年 5078万kw (8/30・最高気温35.6度 猛暑)2011年 4922万kw (8/18・最高気温36.1度 普通)2010年 5999万kw (7/23・最高気温35.7度 猛暑)2009年 5450万kw (7/30・最高気温33.2度 やや冷夏)2008年 6089万kw (8/8 ・最高気温35.3度 8月半ばまで猛暑、以降冷夏)震災以前と比べて、ピーク時の最大電力が大幅に落ちていることが分かります。この期間内でもっとも涼しい夏だったのは2009年で、最大電力は前年に比べて600万kw以上も減っていますが、震災以降に比べれば、それでもはるかに多い数値です。今年も、記録的猛暑ですが、これまでのところ東京電力管内の最大電力は5000万kwの大台を超えてはいません。震災の記憶が遠のけば、電力消費も元の木阿弥になってしまうかと思いきや、日本人は案外賢く行動しているようです。震災から4年経った現在も、かつてのような電気の使い方には戻っていないようです。上記は東京電力管内の、その年の最大電力の記録の移り変わりですが、別の資料で日本全国の年間トータルの電力量の推移を見ることもできます。電源別発電電力量構成比 2015年5月22日電気事業連合会作成資料これを見ると、2007年をピークとし、それ以降はずっと発電電力量は減り続けている(記録的猛暑の2010年は唯一の例外)ことが分かります。つまり、もはや原発を動かさないと電気が足りない、などということはまったくないのです。このところ原油も天然ガスも価格がかなり下がっているので、ひところ言われた燃料費の負担もかなり軽減されているはずです。それにも関わらず、原発を今動かすというのです。もちろん、この1基だけではなく、これからどんどん原発を再稼動させていくつもりのようです。そこには、事故があろうが何があろうが、とにかく原発は推進するんだという政府・自民党の執念だけしか見えません。高レベル廃棄物の問題、事故が起きた場合の対策など、様々な課題は置き去りのまま、目先の都合だけしか見えていない、としか思えません。こうやって、福島第一原発の事故の反省も何も、元の木阿弥になっていくのでしょうか。こんなことでは、いつか再び同じような事故が起こらないとも限りません。
2015.08.11
コメント(2)
-

西岳~編笠山(八ヶ岳)
昨日、八ヶ岳の西岳と編笠山に行ってきました。2012年と2013年に登った山で、編笠山は3回目、西岳は2回目なのですが、家族旅行とからめた山登りで、相棒と子どもが、宿をとても気に入っていて「今年も泊まりたい」と言うので、また登ることになってしまいました。良い山なので、何度登っても飽きはしません。それに、最近は八ヶ岳は家族旅行のとき以外は冬しか登っていないのです。左の山が西岳(2398m)、右の山が編笠山(2523m)です。先に西岳に登り、編笠山へと縦走(というほどのものでもないですが)しました。宿を出たのは朝8時半過ぎ、そこから車道を歩いて、登山口に到着したのは8時50分過ぎでした。途中に湧き水があって、そこまでは20分ちょっと、更に視界のない樹林帯の中をひたすら登り。途中、林道を4回か5回横切ります。はじめて視界が開けた場所がここです。まだ山頂ではないのですが、山頂の本の少し手前です。ただ、このときはガスに覆われていて司会がありませんでした。紫色の花が群生しているのが分かるでしょうか。この花です。この辺りと山頂付近にたくさん咲いていました。2年前のブログ記事には、「ベニバナミネズオウじゃないかと思う」と書いたのですが(ミネズオウはツツジ科で、葉の形状もツツジの仲間に似ている)、今回改めて検索したとこ、どうもそうではなくてイブキジャコウソウという花らしいことが分かりました。シソ科ですが、写真で見る限り、葉の形状はやはりツツジに似ている。山頂に到着。11時17分でした。登山口から2時間半かからなかった計算です。雲は多いながらも、日は差していました。編笠山は雲に閉ざされていましたが、権現岳が雲の間から一瞬姿を現しました。写真上のほうのしろっぽい花はウスユキソウ、その下の2輪の白い花はヤマハハコ、紫色の花はホタルブクロ。この後通った編笠山のほうが標高は高く、視界も広いのですが、花は西岳のほうがはるかに多いです。まだ昼食には早いので、西岳山頂を早々に後にして編笠山に向かいます。編笠山と権現岳の鞍部に建つ、青年小屋に到着しました。ここから権現岳までは、登山地図のコースタイムで登り1時間半、下り1時間。往復2時間半。私の足なら、2時間で何とかなりそうです。体力的にも、まだ余裕がある。実は、八ヶ岳の主要なピークの中で、まだ未踏なのは権現岳だけなのです。(八ヶ岳の北端にある蓼科山も未踏ですが、これを八ヶ岳の一部と見るか独立峰と見るかは微妙)できれば権現岳まで・・・・・・と、思ったのですが、このとき12時過ぎ、権現岳まで往復すると戻ってくるのは2時過ぎ(いや、途中で昼食を食べれば、もう少し遅い)、それから編笠を超えて宿に戻ると、宿に着くのはいったい何時?それに、関東甲信の広い範囲で、大気の状態が不安定なため、午後には雷雨がありえると前日の天気予報は伝えていました。(結果的に雨は降らなかったのですが)隠れるところのない森林限界上のガレ場で雷に襲われたらたまったものではないので、権現岳は断念して、編笠山への登りにかかります。青年小屋から編笠山への登りは、前半はガレ場、上のほうは樹林帯です。もっとも、樹林帯の中もかなりガレ場続きですが。眼下に青年小屋、向こうには権現岳が見えます。地図上のコースタイムは青年小屋から山頂まで30分となっていますが、標高差は150mくらいしかないので、実際にはそんなにかかりません。20分くらいだったかな。(このあたり、時間の記録をとっていなかったので、いささか曖昧)編笠山山頂に到着。天気は晴、ただ雲は多くて、目の前の権現岳はよく見えますが、その奥の八ヶ岳の山々は、阿弥陀岳がちょっと見えた以外はほとんど見えませんでした。眼前には、富士見平高原とその先に中央線、そらに先には南アルプスが、見えるのですが、くもが多いので、そんなにはっきりとは見えません。ここで昼食。と言っても、カップラーメンとおせんべい数枚。アルファ米の五目御飯ももって行ったのですが、もっていったポットのお湯が足りなそうだったので、食べるのはやめました。足りない分はチョコレートで補う。1時過ぎに下山にかかりました。富士見高原への下山路も、やっぱりガレ場です。岩の上を伝って歩くのは、登りは、体力さえあれば問題ないですが、下りはバランス感覚を問われます。転んだら、死にはしないでしょうが大怪我は必至です。斜度も結構急です。下りの途中で西岳を撮影。眼下に森林限界が見えてきました。この写真を撮ったところから少し下った付近で、一休みしてケーナを吹きまくってしまいました。ただ、風が少しあったので、そんなに音は響き渡らなかったですが。ガレ場が終わって森林限界に入るところで、わずかな岩場がありますが、そこを超えれば、あとは樹林帯のなだらかな下りです。私は全般的に、登りはコースタイムよりかなり早く登れる反面、下りはコースタイムとほぼ同じ程度でしか歩けないのですが、足場がしっかりしていて緩やかな下り(つまり、このあたり)なら、かなり飛ばして歩くことができます。ここは、標高100mごとに標識があるという、とても親切な登山道なのですが、100mを7分で下りました。我ながら猛烈なスピードで下りましたが、途中登山道が林道を横切るところで大休止。再びケーナとサンポーニャを吹きまくってしまいました。30分近く吹いていたでしょうか。結局、登山口に戻ってきたのは、午後3時50分頃。登りはじめから丁度7時間でした。宿から山頂までの標高差は約1300m(登り返しの含めた累積標高差は1350mくらいか)なので、結構厳しい山登りだし、宿に戻ったらヘトヘトではあったのですが、先月の北岳(標高差1600m、累積では1900mくらい?)に比べると、筋肉痛は明らかにかなり軽いです。テントを担ぐか日帰りの荷物かの差が大きいのでしょう。今回の荷物は、重さを計っていませんが、水が2Lと熱湯500mlで2.5kg、食料、雨具、ケーナ(木製で結構重い)、一眼レフカメラ(500g以上あり)、食料、ポット(保温性が高い分、結構重い)、全部あわせると7~8kgというところでしょうか。水は、熱湯を若干使い残しましたが、それ以外は完全に飲み干し、かつ途中の水場でも飲んだので、3L近く飲んだんじゃないでしょうか。次に行くときは、今度こそ権現岳、と言いたいところですが、この宿は朝食が8時からなので、日帰りで権現岳は、やっぱりちょっと厳しい。あと1時間早く出発できて、かつ途中でケーナ吹きに時間を費やさなければ、行けそうですが。
2015.08.10
コメント(2)
-
今は「非現実的」だとしても
「核運搬可能な法案」と非現実論かざす民主 首相も「机上の空論」とお手上げ 衆院予算委民主党は7日の衆院予算委員会で、安倍首相が6日の広島市の平和記念式典で非核三原則に触れなかったことと安全保障関連法案を関連づけ、政府批判を展開した。「安倍政権は従来の核政策を転換させようとしている」と印象づけたかったようだが、非現実的な追及が目立ち、責任政党とはほど遠い野党第一党の本質が浮き彫りになった。「国是ではないか。被爆者の方々が失望している」民主党の山井氏は予算委で、非核三原則の堅持に言及しなかった首相をこう強く批判した。首相は「国是だから政府として不動の考えだ。(非核三原則を)前提として核兵器のない世界を作るために何をするか述べている」と答え、他意はなかったと説明。その上で9日に長崎市で行われる式典のあいさつでは言及する考えを示した。すると山井氏は、中谷防衛相が、米軍の核弾頭付きミサイルを自衛隊が運ぶ事態は政策的に「あり得ない」としつつも、「法文上は可能だ」と答弁したことも問題視。首相は「政策的にあり得ないから机上の空論だ。あり得るかのごとく印象を与えようとするのは真摯な議論とはいえない」と反論した。そもそも核兵器の運搬を他国に委ねる事態は、およそ考えにくい。首相は「米国が日本に『核弾頭を運んでくれ』ということは120%あり得ない。運ぶ能力も持っていない」と重ねて否定したが、山井氏は聞く耳を持たなかった。民主党は山井氏含め、この日質問に立った4人全員が「核」に言及。岡田克也代表も記者会見で「核弾頭の自衛隊輸送は論理的にはあり得る。机上の空論と片付けるのは間違いだ」と首相を批判した。広島と長崎の悲劇がクローズアップされる時期に党を挙げて安倍政権の危うさを印象づける思惑があったとみられる。ただ、現行の周辺事態法なども法文上は核運搬を禁じていない。岡田氏らの理屈に従えば、民主党政権下でも核運搬は可能だったことになるが、それを禁止する措置をとらなかった。---現実問題としては、米軍が核兵器を同盟国といえども外国の軍に輸送させることはありえません。その限りでは、安倍の言っていることは事実でしょう。ただし、安倍が本音の部分で非核三原則を遵守しようと考えているとは、私にはまったく思えません。核を保有するどこの国も、少なくともタテマエ上は「戦争をやるため核兵器を持つ」などとは言いません。「平和のため」とか何とかと、口ではたいそうなことを言うわけです。安倍も、口では「積極的平和主義」なる言葉を吐いている。おそらく、本音の部分では「平和のためには核兵器を持ちたい」と思っているのだろうと思います。そして、それは安倍の取り巻き連中や、御用メディアである産経も、おそらく同じです。というか、現に自民党内からは度々核武装論を口にする政治家が現れています。現在閣内にいる人物の中では、麻生財務相が2006年に「隣の国が持つとなった時に、一つの考え方としていろいろな議論をしておくことは大事だ」「非核三原則を政府として堅持する立場に変わりはないが、日本は言論統制された国ではない。言論の自由を封殺するということに与しないという以上に明確な答えはない。」と発言しています。核武装に関する議論(を自民党の政治家が行うこと)は自由だというわけです。昨日の記事で紹介したように、同じ麻生自身が、今では自民党議員に対して、安保法制が通るまでは余計なことを口にするな、などと言っている。実際、自民党議員に対しては、安保法制について、マスコミに余計なことを喋るなと、厳しい箝口令が引かれています。ということは、自民党内で、安保法制を通すことの妨げになる言論は統制し封殺するけれど、核武装に関する議論は統制しない、封殺しないという、実に分かりやすい二重基準なのです。そういう背景のある中で、わざわざ「法文上は核の輸送は可能」などと言ったり、広島の平和記念式典で挨拶からあえて非核三原則を省いたりという行動は、後になっていくら口先だけ弁明してごまかしてみても、核についての安倍政権の本音がどこにあるかを、明確に物語っている、と私には思えます。何しろ、法律は変えるのには国会の審議と議決が必要ですが、政策を変えるのは内閣の胸先三寸でできますから、敷居は大幅に低い。非核三原則も、国会の議決ではありますが、法律ではない。歴代の自民党政権は、非核三原則を法制化することにはひたすら消極的でした。安倍も同様でしょう。「今は」核の輸送など120%ありえない、それは事実でしょう。今は、ね。でも、将来は分かりません。「そのとき」がきたらできるだけ簡単に核兵器が保有できるように、できるだけ地ならしをしておきたい、ということとしか、私には思えません。※ところで、この議論では、核兵器までしか俎上に上がらなかったようですが、大量破壊兵器と呼ばれるものは核兵器だけではありません。生物化学兵器もまた、大量破壊兵器です。その輸送の可否も、聞いてみりゃよかったのに。核保有国が自国の核兵器の輸送を、たとえ同盟国でも他国に委ねることはあり得ませんが、化学兵器は必ずしもそうとは限らないと思われるのでね。
2015.08.08
コメント(2)
-
暴言をたしなめるフリをした暴言
麻生氏「発言は法案通ってから」 武藤氏問題念頭にクギ麻生太郎財務相は6日、自民党麻生派の会合で、同派所属の武藤貴也衆院議員がツイッターで安全保障関連法案の反対デモをする学生団体を「利己的」などと批判した問題を念頭に「政府与党の議員の立場を踏まえて発言してもらわないと。自分の気持ちは法案が通ってから言ってくれ。それで十分間に合う」と語った。武藤氏は党本部から報道対応を控えるよう指示されており、この日の会合は欠席した。麻生氏は法案に批判が高まっていることに関し「とにかくここが正念場。聞く耳を持たない人に嫌でも聞いてもらわなければ仕方がない。きちんとやらねばならん」と述べた。---暴言をたしなめているようなフリをしつつ、もっと酷いことを言っているようにしか見えません。要するに、うわべだけ取り繕って、本音は隠して法案を通して、「『戦争に行きたくない』という自己中心、極端な利己的考え」などという発言は、法案がとおった後にしろ、というわけです。要するに、法案が通るまでは甘いえさをばら撒いて、とおった後は、「釣った魚にえさはやらない」というわけです。その発言のほうが、あるいみよほど暴言でしょう。というか、麻生が人のことをとやかく言えるほど行儀のよい発言をしてきたのか、と思いますけどね。それにしても、武藤議員の主張は、おそらく安倍のおともだち連中が多かれ少なかれ腹の中で考えていることなのでしょう。こんな考えの持ち主ばかりが集まって、好きなように国政を動かせば、日本は本当に戦前のような国になりかねません。
2015.08.07
コメント(2)
-

杞憂とは思えない
「原発にミサイルを撃ち込まれたら? 」山本太郎議員の質問は杞憂「原発に弾道ミサイルが撃ち込まれたらどう対処するのか?」この疑問を山本太郎議員が国会で質問し、原子力規制委員会の田中俊一委員長は「そのような事態は原発の設置者に対策を求めていない」と答弁しました。これはミサイル攻撃が一体どういったものかを理解していれば、山本太郎議員の質問は杞憂であると直ぐ分かると思います。そもそも弾道ミサイルには原発施設に命中を期待できるようなピンポイント攻撃能力はありません。~原発に弾道ミサイルが撃ち込まれた場合の想定がなくても妥当な判断だと言えます。巡航ミサイルならばピンポイント攻撃能力がありますが、北朝鮮は保有していません。核弾頭を保有しているなら原発を狙う必要がない(略)ジュネーブ条約第1追加議定書は、危険な力を内蔵する工作物等(ダム、堤防、原発)に対する攻撃を重大な違反行為としています。このジュネーブ条約第1追加議定書は日本の仮想敵国であるロシア、中国、北朝鮮も締約しています。これらの国が戦時国際法を遵守するという保証はありませんが、重大な違反行為と規定されていることを破るとなると、大きなリスクを背負うことになるでしょう。また仮にアメリカが、同盟国の稼働中の原発へ攻撃が行われた場合は大量破壊兵器の使用と同等と見做し核報復を行うと宣言した場合、強力な核抑止力が発生します。これまで原発へのミサイル攻撃の可能性が低いことを説明してきましたが、テロ攻撃ならば可能性が出てきます。だからこそ既に原発へのテロ攻撃対策と訓練は行われています。原発施設の主要部コンクリート壁は航空機が突入してきた程度なら耐えられる強度を持っていて、アメリカではF-4ファントム戦闘機を実際に衝突させる試験を行っています。地上からテロリストが侵入してきた場合は、警察が警備を行って対応することになります。もしも「可能性が低くても原発への弾道ミサイル攻撃の対処が必要だ」とした場合は、自衛隊がミサイル防衛システムを用いて迎撃する、あるいは地下原発・海底原発といった防御力が強固な施設への転換を図るという選択が考えられますが、反原発の立場である山本太郎議員はそういった方向での議論を欲しているようには見えません。弾道ミサイルの命中精度や弾道ミサイルを迎撃する能力を既に日本は保有している事実がすっぽり抜け落ちていたために、あのような質問を国会で行ってしまったのでしょう。---残念ながら、この文章を読んで「ああ、原発に対する攻撃の恐れは杞憂なんだな」とは思えないのです。確かに、弾道ミサイルの命中精度で原発の建屋への直撃の可能性が低いのは事実です。ただし、だから問題ない、とは言えません。第一に北朝鮮の持つノドンミサイルは1発や2発ではありません。200~300発は持っているとされています。発射台が50基程度しかないので、すべてを同時発射はできないものの、逆に言えば50発程度は同時発射ができるということです。そのすべてを原発に撃ちこむという想定は非現実的だとしても、10発くらいは可能性があるでしょう。その全弾がすべて外れる、という想定はいささか甘いのではないかと思われます。第二に、弾頭の種類によっては、必ずしも直撃を要しません。北朝鮮はノドンの弾頭に搭載できるほど核兵器の小型化には成功していないと思われるので、核ミサイルが飛来するという想定は確かに杞憂でしょうが、「大量破壊兵器」とは必ずしも核のみを指すわけではない。弾頭に化学兵器を搭載することは、おそらく可能です。その場合は、原発の風上側にさえ着弾すれば、直撃でなくても、原発で働く人を殺傷することができます。直接的に原子炉が破壊されなくても、コントロールする要員がいなくなれば、結局は原発は暴走します。地下鉄サリン事件で使われたサリンの量は、1リットル入りのビニール袋が11個、合計11リットルに過ぎません。それも低純度で、散布方法も、かさで穴を開けるだけという粗雑な方法です(穴を開け損なった袋もあっただろうし、内容物が全部漏れ出したわけでもないようです)。それでもあれほどの被害が出た。ノドンの登載能力は1.2トンと推定されているようです。1発で地下鉄サリンの100倍搭載できる。10発なら1000倍です。そして、弾道ミサイルの迎撃は、実質的には不可能です。一応、PAC3は弾道ミサイルの迎撃が可能ということになっていますが、その信頼性はきわめて怪しい。しかも、以前の投稿でも指摘したように、PAC3の射程はそれほど長くないので、カバーできる範囲は限られます。弾道ミサイルを発射する側は自由に標的を選べるのに対して、防御する側は事前に迎撃ミサイルの配置場所を決めておかなければなりません。だから、実戦で弾道ミサイルの迎撃はほとんど不可能と踏んでおいたほうがいいです。引用記事は、北朝鮮は巡航ミサイルを持っていないと書いています。それ自体は事実ですが、巡航ミサイルに準ずるものは持っています。つまり、戦闘機や攻撃機です。北朝鮮のもつ軍用機は、ミグ29などごく一握りの新鋭機を除くと、どうしようもない旧式機ばかりで、航続力も足りません。ただ、日本までの片道攻撃なら可能です。もちろん、弾道ミサイルと違って迎撃は可能ですが、旧式機でもいっせいに飛来したら、そのすべてを撃墜することは困難です。引用記事に原発施設の主要部コンクリート壁は航空機が突入してきた程度なら耐えられる強度を持っていて、アメリカではF-4ファントム戦闘機を実際に衝突させる試験を行っています。とありますが、その試験は本物の原発の建屋ではなく、それを模した縦横数メートルのコンクリートの壁にぶつけたというだけの実験です。映像を見る限り、飛行機は補助ロケットを搭載しているものの、爆弾は搭載していないようです。どういう想定での実験か知りませんけど、戦闘爆撃機であるF4ファントムが原発に体当たりするとしたら、爆弾を搭載していると考えるべきでしょう。更にいうと、原発建屋のコンクリートがこんなに分厚いのは、下のほうだけです。壁の上のほうと天井は、そんなに厚くない。どころか、天井はそもそも鉄筋コンクリートですらなく鉄骨作りです。だから、福島第一原発は水素爆発で建屋が吹っ飛びました。つまり、この実験を根拠に、戦闘機・攻撃機が原発の上空から爆撃、あるいは爆弾を抱えたままの体当たり攻撃を行っても原発は大丈夫、などと考えるのは、想定がまるっきり甘すぎてお話にならないのです。更にいえば、航空攻撃にしてもテロにしても、原発を破壊するためには必ずしも原発本体を攻撃しなくてもいいのです。福島第一原発は、原発本体は地震と津波そのものでは壊れなかった(実際のところは、まったく壊れなかったかどうかはかなり怪しいですが)ものの、外部電源が経たれることであのような事故に至りました。現役の経産省官僚が書いたという小説「原発ホワイトアウト」でも、大雪のある日、北朝鮮の特殊部隊が高圧送電線を破壊することで事故を誘発させるという描写があります。他にも、冷却水を供給する水道管などもウィークポイントになりえます。これらも含めた原発システムを、弾道ミサイル、航空攻撃、特殊部隊の襲撃、手段はなんでも良いのですが、それらの攻撃から守り切ることは、どう考えても不可能です。自衛隊がミサイル防衛システムを用いて迎撃する、あるいは地下原発・海底原発といった防御力が強固な施設への転換を図るという選択が考えられますこの記事の一番バカっぽいところはここです。PAC3というミサイル防衛システムはすでに存在するわけですが、その能力はすでに指摘したとおりです。そして、地下原発とか海底原発とか、そんなものは技術的コスト的安全対策的に、実現の見通しはまったくない。実現の見通しもないものに転換を図る、って、そんなものは選択肢となりえません。軍事ブロガーとか名乗っていますけど、マニア的な知識はともかく、総合的な判断力がてんでない、と言うしかないようです。
2015.08.06
コメント(2)
-
唯我独尊のきわみ
社民系組織メンバーの「拉致より憲法」発言に家族会反発 秋田街頭で隣で活動中、「被害者家族の思い踏みにじる」秋田市で4日に行われた北朝鮮による拉致被害者家族会の街頭活動中、隣で活動していた安全保障関連法案に反対する社民党系組織のメンバーが「拉致より憲法だ」と発言し、家族会が反発する一幕があった。家族会元事務局長の照明さんは「拉致被害者や家族の実情を考えてほしい」と話している。家族会の街頭活動は、秋田竿燈まつりに訪れた観光客らに被害者救出を訴えるため~JR秋田駅前で行われた。すぐ隣で、社民党支持者が中心の「秋田・戦争をさせない1000人委員会」が街頭活動を始めたため、救う会秋田メンバーの男性が1000人委員会メンバーの男性に署名を求めたところ、「拉致より憲法だ」と拒否されたという。話を聞いた照明さんは「旧社会党、社民党は拉致問題解決の障害になり、被害者家族の思いを踏みにじってきた」と演説。1000人委員会側に抗議する救う会秋田幹部もいた。照明さんはその後の県庁での記者会見で「被害者家族の多くは安保法案の議論に違和感を覚えている。約40年前に日本人が北朝鮮に拉致された時点で戦争が始まっている。戦っている被害者を放置している状況が平和なのか」と訴えた。飯塚さんは「国民にとって重要な問題なのに、署名活動をしても、横目でちらっと見て通り過ぎる人がいるのが気になる。だが、政府と北朝鮮に対するメッセージとして活動を続けていきたい」と述べた。家族会の反発について、1000人委員会の山縣代表は「拉致問題について、会としての見解はない。それぞれのメンバーの考えで対応している」と話している。---拉致被害の問題に関して、旧社会党の対応が適切さを欠いていたことは事実だと思います。が、それはそれとして、署名に応じないのは許せない、とか、ひとことで言って、「バカじゃねーの」ということに尽きます。署名とは自由意志で行うものです。「拉致より憲法だ」だろうが、「横目でちらっと見て通り過ぎる」だろうが、理由は何だって構わない。したくない署名をする必要も義理もありはしません。また、他人に署名を強要できる権利など、誰も持っていません。だいたい、明らかに主張が対立することが明白な団体のメンバーに対して署名を求める行為自体が、喧嘩を売っているようなものです。その署名簿に住所を書く欄があれば、住所と氏名という個人情報がそのまま相手側に渡るんですよ、そんなの署名できるわけないじゃないですか。逆にその「1000人委員会」の側が「家族会」に署名を求めたら、それに応じるんですか?というわけで、もし私がその場にいて「家族会」に署名を要求されたとしたら、逆に「憲法を守り、安保法案の廃案を求める署名」か何かを出して、署名を求めるでしょうね。相手がそれに署名するなら、相手の署名にも、住所空欄で氏名だけなら応じてもいいかな。相手が拒否すれば、もちろん署名する必要はない。多分、相手は署名を拒否するでしょう。署名を拒否したという男性も、ただ拒否するよりは、そのくらいの機転を利かせればよかったのに、と思わないではありません。「国民にとって重要な問題なのに、署名活動をしても、横目でちらっと見て通り過ぎる人がいるのが気になる。」のだそうですが、世の中には「国民にとって重要な問題」が満ち溢れているのです。何が一番重要かは、それぞれの人が決めることです。家族会の面々にとって拉致問題が重要だというのはそうなのでしょうが、ほかの人にはまた別の判断基準がある。当たり前のことです。それにしても、こんな馬鹿馬鹿しい出来事を大真面目に報じる産経新聞というのも、これまたどうしようもない新聞だなと、改めて思いますね。
2015.08.05
コメント(2)
-
盗聴
※追記:記事の総数が丁度2000件になっていることに、投稿後に気が付きました。2000件か、よく書き続けたなあ。米、仁義なき情報戦 NSA日本盗聴疑惑内部告発サイト・ウィキリークスが7月31日に公表した米政府の機密文書は、米国家安全保障局(NSA)が日本の経済産業相や日銀総裁、大手商社などの電話を盗聴していたことを明かしており、「安全保障」を盾になりふり構わぬ産業スパイ活動をしていた米国の実態があらためて露呈した。一部の盗聴内容は「ファイブ・アイズ」と呼ばれる米英豪など英語圏5カ国で共有された可能性も指摘され、米国の同盟国の間でも情報をめぐる関係の緊密さの違いが大きいようだ。ウィキリークスが公表した米機密文書の内容が事実とすれば、国益追求のために同盟国政府も容赦なく盗聴の対象とする冷徹ぶりを示す一方で、米企業へのサイバー攻撃をめぐり対中非難を強める米国の二重基準が浮き彫りになる。日本を標的にした米国の盗聴疑惑は過去にも指摘されてきた。米国、カナダ、英国、オーストラリア、ニュージーランドの英語圏5カ国による通信傍受網「エシュロン」による産業スパイ疑惑が2000年前後に浮上し、被害を受けたという欧州諸国が問題視。この傍受網は、1995年の日米自動車協議でも暗躍したと批判された。ウィキリークスの一連の暴露をきっかけに、NSAはフランスやドイツでも盗聴をしていたことが明らかになっている。メルケル独首相は自分の携帯電話の盗聴疑惑に激怒し、オバマ米大統領に直接抗議。オバマ氏は「通信を監視していないし、今後もしない」と釈明したが、過去について否定したわけではない。ところが最近、当のドイツがNSAの欧州諸国などに対する監視活動に協力していた疑いが発覚した。今回、ウィキリークスが「ルールなど存在しない」と日本に警告した通り、国益をかけた熾烈な情報戦が無秩序に展開されている。ただ、米国はサイバー攻撃で企業秘密を盗んでいると中国を非難しており、自国の活動との整合性について説明責任が生じるが、7月31日の記者会見でトナー国務省副報道官は「公表された文書に信ぴょう性を与えたくないので(事実関係は)確認しない」と繰り返すだけだった。(以下略)---準技術的な話ですが、米国が日本で、どうやって盗聴をするのでしょうか。携帯に関しては、一説には大使館内に電波の傍受設備がある、とも言われます。以前有名になったエシュロンも、そのための施設でしょう。でも、固定電話はどうやって盗聴するのでしょう。メールなどの電子データに関しては、PRISMという監視プログラムによって盗み見をしているといわれます。米国系のウェブサービスの提供企業がひそかにこれに協力しているといいます。FacebookもyouTubeも対象のようです。Gmailもグーグルが運営しているのですからね同様なのでしょう。これらについては、日本国内では何もしなくても、日本国外のサーバーに接続して情報をとることができるのでしょう。しかし、音声通話はそうは行かないはずです。IP電話もありますが、NTTの加入電話は、なんらかの形で物理的に電話回線に接続しなければ、盗聴はできないでしょうから。どこで、どうやってやるのでしょうね。NTTの交換機に侵入、というのも、そう簡単な話ではないでしょう。官邸の交換機に侵入、もっと大変そうです。しかし、それをやっていたとすると、やっぱり恐ろしい。いずれにしても、米国政府が日本に対して盗聴というのはあからさまな主権侵害であるわけですが、それに対して被害者のはずの日本政府は、最初はまったく無反応。だいぶ時間が経って、世論の批判が高まってから、やっと、思い出したように菅官房長官が不快感を表明しているものの、その一方で自民党の谷垣幹事長はこんなことを言っています。谷垣氏「盗聴想定して発言工夫するのが世界政治の現状」米国の国家安全保障局が日本政府や日銀、日本企業の電話を盗聴していたと、内部告発サイト「ウィキリークス」が公表した問題で、自民党の谷垣禎一幹事長は3日の記者会見で「責任ある政治家は盗聴されていることを想定して、発言の仕方を工夫しなければならないのが世界政治の現状だ」と語った。谷垣氏は「(盗聴が)よいと言っているわけではないが、(盗聴を)きちっと頭のなかに置いて対応しないと、盗聴するほうが悪いとうそぶいていれば済むものではない」とも述べた。ーーー盗聴される方が悪いと言っているようなものです。確かに政治の世界の裏面では、そうなのだろうと思います。しかし、少なくとも表向き、被害者の側がこんな言い方で盗聴を免罪するのは、主権国家の政府としての体面上、どうなのでしょうか。それに、被害者は政治家や官公庁だけでなく、民間企業も含まれるようです。民間企業に対しても、盗聴される方が悪いと言うのでしょうか。結局、こういった反応からは、二つの可能性が推測されます。第一の可能性は、日本政府は米国のあまりに忠実な下僕なので、盗聴されても文句も言えない第二の可能性は、日本政府自身も似たような盗聴をやっているので、他国のことを悪し様には言えないさて、どっちでしょうね。あるいは両方当てはまるという可能性だってありますが。
2015.08.04
コメント(4)
-
要するに、本音では戦争に駆り出したい
自民党:武藤貴也議員、安保反対学生をツイッターで非難自民党の武藤貴也衆院議員がツイッターで、安全保障関連法案の反対運動をする学生団体「自由と民主主義のための学生緊急行動(SEALDs」について「自分中心、極端な利己的な考え」と非難していることがわかった。武藤氏は衆院平和安全法制特別委員会のメンバーで、報道機関への圧力発言や沖縄への侮辱的発言が問題になった自民党若手の勉強会「文化芸術懇話会」にも出席していた。SEALDsは国会前で毎週、デモをしている。武藤氏は「彼ら彼女らの主張は『戦争に行きたくない』という自己中心、極端な利己的考えに基づく。利己的個人主義がここまでまん延したのは戦後教育のせいだろうが、非常に残念だ」と書き込んだ。(以下略)---戦争に行けば死の危険が生じます。当たり前のことです。死にたくない、というのは人間のもっとも根源的な本能です。それを「自分中心、極端な利己的な考え」だというなら、まずは自分自身が戦争になったら真っ先にさっさと死んでくれ。要するに、「国を守るためには人の命を危険に晒したって仕方がない」「国を守るために命を危険に晒すことに文句など言うな」と思っているわけです。その本音がついつい表に出た、というわけです。安倍の取り巻きにはこういう手合いの極右政治家ばかりがそろっている。それで、安倍政権は口先では「徴兵制はやらない、できない」と言っていますが、全然信用できません。徴兵制が違憲とされる根拠は、憲法第18条の奴隷的拘束の禁止ですが、そもそも安倍政権は今の憲法を変えたくて変えたくてしょうがないのです。自民党の憲法改正案で、この条文は「社会的又は経済的関係において身体を拘束されない」という、よく分からない文面に変わっています。徴兵制は、経済的関係の身体拘束ではないし、多分社会的関係の身体拘束でもないでしょう。つまり、徴兵制が憲法違反にならないようにしたわけです。確かに、今すぐ徴兵制、ということは安倍政権は考えていないのでしょう。けれども、憲法を変えて、いざとなれば徴兵制を導入できる布石は打っておきたい、と考えているのでしょう。少なくとも、いざとなれば「お国のために喜んで死にます」という若者を量産したいと考えていることは間違いありません。
2015.08.03
コメント(4)
-

北岳 リバーサルフィルムの写真2
昨日の続きです。風が強い中、夜が明けました。張り綱を岩に縛り付けてでテントをしっかり固定している間は問題なかったのですが、撤収のために張り綱を解いた途端に、すごいことに。あやうくテントを風に飛ばされそうになり、なんとかそれは免れたのですが、風に煽られたためにポールが曲がってしまいました。もっとも、実用上は多少ポールが曲がったからといって、特に問題はないのですが。初日の最後の写真も富士山、2日目の最初の写真も富士山です。前日はどうしても雲に隠れていた仙丈岳が姿を現しています。テントを撤収したら、早々に歩き始めました。今日は北岳山頂を越えて、草すべりコースを広河原に下山です。八本歯のコルへの巻道から、北岳山荘、さらに間ノ岳を望みます。昨日書いたように、巻道は高山植物が豊富です。これはヨツバシオガマ。しかし、巻道経由だと北岳山頂にはかなり大回りになるので、高山植物の豊富なおいしいところだけをとおって、途中から尾根道に合流。さすがにテントの荷物が重くて、あまりスピードは上がりません。北岳山荘から1時間ほどかけて、やっと山頂にたどり着きました。眼下に今朝出発した北岳山荘、その先に中白峰、更に間ノ岳。その左奥に農鳥岳、右遠方には塩見岳。また、富士山を撮ってしまいました。仙丈岳と、その右奥には北アルプスの槍穂高連峰が見えます。伊那谷の向こうに中央アルプスが連なっています。中央アルプスはまだ登ったことがないので、いつか登りたい。八ヶ岳です。この位置からだと、普段見慣れている八ヶ岳とだいぶ形が違いますけど。山頂を後にして、海抜3000mの肩の小屋まで下ってきました。前回2004年に登った際は、ここにテントを張りました。北岳山荘のテント場のほうが広いのと、水をポンプアップしているので、比較的水事情がよい。肩の小屋は雨水をためているのかな、水事情はあまりよくありません。朝、テント撤収時は強風のためロールパン1個しか食べていなかったので、肩の小屋の前で朝食にしました。インスタントラーメンです。風が強くて燃焼効率が悪く、だいぶガスを無駄にしたように思います。肩の小屋から更に下ったところ。小太郎尾根の先に甲斐駒ヶ岳が見えます。北岳山頂、そして肩の小屋を振り返ります。稜線がへこんでいる、底の部分に肩の小屋が見えます。このあたりは、まだまだ体力にも余裕があって、快調に下っていました。草すべりの急登に到着しました。その最上部はシナノキンバイとハクサンイチゲの見事なお花畑になっています。この花は、昨日も紹介しましたがシナノキンバイです。シナノキンバイの群落。黄色いお花畑です。シナノキンバイに囲まれて、ナナカマドも白い花を咲かせています。ハクサンイチゲの白い花。これも、昨日紹介しました。今度は、ハクサンイチゲの白いお花畑です。シナノキンバイの黄色とハクサンイチゲの白が入り混じったお花畑。夏の高山の最大の楽しみが、これです。しかし、ここから先は急降下に次ぐ急降下。テントの荷物が重い。で、やっとの思いで白根御池山荘に到着して、ほっと一息ついて、あとは広河原まで余裕だなと思いきや、しばらく行くと再び大変な勾配の急降下。草すべりが急坂であることは覚えていたけれど、白根御池と広河原の間も、こんな急坂だったっけ。まったく記憶がありませんでした。これだったら、大樺沢を下山するわうが良かったか。まあ、でもこのコースを通ったから高山植物がたくさん見られたわけだし、のぼりと下りで同じコースというのも芸がない。と、思ってあきらめました。さすがに疲労でよれよれ。荷物が重い、膝ガクガクで、やっとのことで広河原にたどり着きました。白根御池小屋を出たのが午前10時、広河原着は12時過ぎでした。もう、これ以上は歩けない、という感じでした。
2015.08.02
コメント(0)
-

北岳 リバーサルフィルムの写真1
1週間前の北岳の写真が、やっとできましたので、紹介します。実際にはプリントは火曜にはできていたのですが、取り込む時間がありませんでした。フィルムから取り込んであります。今日は初日の分の写真を。新宿発最終の特急「かいじ」で甲府についたのは12時半過ぎ、広河原行きのバスが出るのは朝4時半なので、そのまま駅前のバスターミナルで仮眠をとりました。テント用のマットがあるので、アスファルトの上で寝ても快適です。平日金曜の朝でしたが、広河原行きバスは、2台が出て、1台目は満員、2台目は甲府駅ではガラガラでしたが、途中芦安で満員になったようです。25人乗りの中型バスでしたが。広河原に着いたのは朝6時半頃。この日、天気予報はあまり良い天気ではなかったのですが、ふたを開けたらこのとおり、快晴とは言いませんが、まずまずの晴天です。大樺沢の雪渓が目の前に見えます。大樺沢の雪渓の目の前まで来ました。以前来たときは、雪渓はもっと長かったような気がします。(11年ぶりなので記憶はあいまいですが)今年は雪が少ないのかもしれません。北アルプスでは、ゴールデンウィークの時点で例年よりかなり雪が少なかったので、南アルプスも事情は同じかもしれません。この写真は八本歯のコルへのルートと右俣コース(肩の小屋方面に向かう)の分岐付近で撮影したのですが、この後、この場所にカメラを置き忘れるという失態を演じてしまい、10分か15分登ったところで「カメラがない」と気付いて引き返す羽目に陥ってしまいました。雪渓の上端に到着。全般的に、南アルプスは太平洋側に位置するため、北アルプスに比べると降雪量は少なく、夏山の残雪もまた、北アルプスよりは少なめです。大樺沢の雪渓は、そんな南アルプスの中では例外的な存在かもしれません。朝は晴天でしたが、この時間にはだいぶ雲が出てきて、一時は雨がぱらついたりもしたのですが、幸いそれ以上天気が崩れることはなく、その後はおおむね晴れたり曇ったりと言う天気が続きました。オンタデ。大樺沢の雪渓上端付近で撮影しました。高山植物がほとんどない富士山に、唯一やたらと生えている高山植物です。北岳にもありますが、そんなに多くはありません。あまり派手さはありません。最初は御嶽山で発見されたのでこの名がついたそうです。階段階段、また階段、階段の連続を登って、八本歯のコルにたどり着きました。北岳山頂方面とは反対側、池山吊尾根方面を撮影。冬季は大樺沢を登ることはできず(当然、雪崩の巣ですから)、この池山吊尾根を登ります。もちろん、私は冬の北岳に登ったことはありません。ウスユキソウの仲間。ミネウスユキソウでしょうか。八本歯のコルから北岳への登りの途中で撮影しました。各所にずいぶんたくさん生えています。イワオウギです。確か、北岳山荘へのトラバース道の途中だったと思います。シナノキンバイ。黄色く目立つ花で、大群落を作ることが多く、高山植物のお花畑の主役の一つです。やはり北岳山荘へのトラバース道の途中で撮影しました。シナノキンバイの群落です。明日紹介しますが、この翌日北岳山頂をはさんで反対側の草すべり上部にも、シナノキンバイの大群落がありました。ウスユキソウとイワベンケイです。南アルプスは鹿が高山帯まで侵入したため、高山植物に深刻な影響が出てしますが、このあたりまではさすがにシカも来ないのか、花はたくさんありました。この日幕営予定の北岳山荘が見えます。その先には間ノ岳が。この時点では、まだ間ノ岳まで足を伸ばすかどうかは決めていませんでした。午後2時前に北岳山荘に到着しました。広河原からの所要時間7時間以上。我ながら遅い。コースタイムよりかなり時間がかかりました。もっとも、テント装備だから、それは仕方がありません。荷物は、登り始めの時点では16-17kgありました。(水と食料を消費するので、北だけ山荘に付いた時点で1kg以上軽くなっていたはずですが)テント場はまだガラガラでした。設営して、テントの中にひっくり返ってしばし睡眠。しかし、3時頃起きだして、ふと考えました。まだ3時、一時悪化しそうだった天気も回復してきたし、このまま夕飯時までテント内で寝ていても仕方ないなあ、と。というわけで、間ノ岳まで足を伸ばすことにしました。持っている荷物は、カメラ、iPad mini一式、地図と水筒、おやつ、ゴアテックの雨具、万が一の備えてヘッドランプ、そしてケーナ(笑)。テント場を出てすぐのところから、北岳を撮影しました。荷物が超軽量なので、かなりハイスピードで飛ばしました。念のためヘッドランプを持ったとはいえ、日没までには帰ってこなければなりませんから。中白峰に到着、目的地の間ノ岳を撮影しました。北岳山荘から30分で登りました。同じく中白峰から、北岳を振り返って撮影。ここには登山者が3人くらいいて、いずれも間ノ岳に向かうようでした。私も間ノ岳に向かいます。間ノ岳山頂には4時7分前後に到着しました。中白峰からは40分もかかっていません。北岳山荘からで1時間10分。荷物が軽いし、それほど標高差もなくて急勾配でもないので、目いっぱい飛ばしました。正直なところ、翌朝ならもっと速かったと思いますが、さすがに北岳山荘までの疲労があるので、この日はこのくらいのスピードが限界。北岳の標高は3193m、間ノ岳はそれより4mだけ低い3189mです。北岳は日本第2位の標高ですが、間ノ岳は第4位。3位は北アルプスの奥穂高岳3190mです。更に、その間ノ岳と9mの差で5位に3180mの槍ヶ岳が続きます。たった4m差の間に3つの山、13mの差で4つの山ががひしめいています。一説によれば、最終氷期には間ノ岳が日本最高峰だったのではないか、とも言われます。間ノ岳山頂には、大規模な崩壊の跡があるそうで(どれがそうなのか、私にはよく分かりませんでしたが)、それ以前は今より数十メートル高かったと推定されています。そうすると、北岳より高かった可能性が高く、しかも富士山が現在の高度に達したのは1万年前頃で、それ以前は標高3000mに達するかどうか、程度だったためです。まあ、推定ですけどね。写真は西農鳥岳と農鳥岳方面です。北岳に登ったのは2004年以来ですが、間ノ岳まで来たのは1999年以来実に16年ぶりです。そのときは、農鳥岳まで行って、奈良田に下りました。自炊で小屋泊まりで荷物がそれほど重くなかったので、北岳山荘から奈良田まで1日で下った。同じく、間ノ岳山頂から北岳を撮影しました。このとき、山頂には私以外誰もおらず、山頂独り占め状態でした。3人の登山者のうち、1人は途中で引き返したようで、あとの2人は私が山頂から引き返すときにすれ違いました。で、ケーナを持ってはきたのですが、風が強くて、まともに吹ける状態ではなく、断念。ハクサンイチゲ。間ノ岳から北岳山荘に引き返す途中で撮影しました。間ノ岳周辺は、北岳周辺に比べると高山植物が少ないようです。これ以外には、それほど花を見かけませんでした。ハクサンイチゲは、シナノキンバイと並んで日本アルプスの高山植物の代表格と言っていいでしょう。やはり、大規模な群落を作ることがあります。北岳山荘のテント場に戻ってきたのは、5時半。下りの所要時間は1時間5分でした。下りは中白峰の山頂を通らず、巻き道を通ってきました。こんなことを書くのも何ですが、下りの途中からトイレに行きたくなって、登りより切実な事情(笑)で道を急いだのですが、登りより若干早い程度の所要時間でした。いや、そんな事情が生じなければ、中白峰でケーナを吹きまくろうと思っていたんですがねえ。テントに戻ると、まず夕飯(アルファ米とレトルトカレー、それにインスタント味噌汁、そして山荘でビールを買ってきた)。それから、やっとケーナを吹きました。が、案の定風が強くて、息が流されてしまい、残念ながらあまり音が出ませんでした。日没後の残照に中、富士山を撮影しました。続きはまた明日。
2015.08.01
コメント(2)
全29件 (29件中 1-29件目)
1