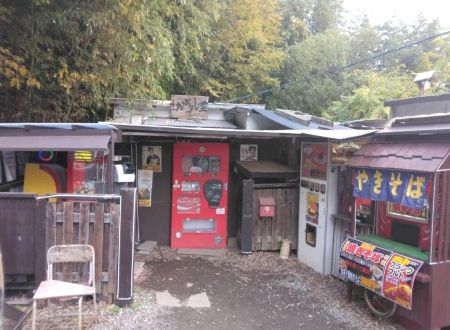2006年09月の記事
全24件 (24件中 1-24件目)
1
-

西国巡礼ー十番 三室戸寺
いきなりおわびです。昨日の日記で法相宗を「三蔵法師(玄奘)の開いた宗」と書きましたが、申し訳ありません。「三蔵法師(玄奘)教えをもとに、門下の慈恩大師の開いた宗」でした。昨日の日記の続きです。奈良を後にして京都へ向かいます。十番 三室戸寺へ山寺と聞いていましたが、駐車場はこのような住宅街に囲まれています。お寺はいずこに?細い参道を進んで山門をくぐるとこんな庭に出ます。萩は咲いていますが・・・庭の見ごろは過ぎています(汗)こんな庭やこんな庭を進むと森の中から、蓮に囲まれた本堂が出現します!後に当院の参拝団を襲う悲劇を考えると、極楽のようなお寺でした!ところで、奈良といえば「歓喜団」!歓喜天さんにお供えするお菓子ですが、吉野蔵王堂にお供えしてあるのが絶品です。京都で歓喜団を見つけて食べましたが、形はそっくりですが味が違います!尋ねてみると奈良から取り寄せているそうです。ご存知の方は情報を! コウユウブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ
2006年09月30日
コメント(36)
-

西国巡礼ー九番南円堂
昨日は西国巡拝に行ってきました。朝6時半徳島発淡路経由で奈良へ向かいます。まず興福寺、南円堂。興福寺の五重の塔です。興福寺は藤原氏の氏寺でかつては強大な勢力を誇っていました。法相宗という一般にはなじみの薄い宗派の本山です。唯識という仏教哲学を研究する宗派で、かの有名な三蔵法師(玄奘)の門下の慈恩大師によって立てられた宗です。桃栗三年柿八年にかけて「唯識三年倶舎八年」といわれるように大変難しいといわれています。鹿がお迎えです。これが平成22年完成といわれる中金堂の礎石です。これが南円堂です。本尊は不空羂索観音!どう見ても密教系の本尊です。誰が持ち込んだのだろうと説明を見ると「な・な・なんと 弘法大師!(汗)」バスの中の解説で一言も触れていません(汗)そういえば以前に勉強したような(汗)ところで、護摩祈祷札が置いてあります?学問宗である法相宗で誰が護摩を焚くんでしょう?当院参拝団の一部の人が護摩祈願しようとしていたので、「ここは専門ではないのでやめたほうがいいですよ」と止めてしまいました!猿沢の池です。周りはお土産物屋さんなど一杯です。風流ではありません。明日へ続きます。 コウユウブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ
2006年09月29日
コメント(32)
-

彼岸のとらねこ四態
お彼岸にはとらねこもいろいろな表情を見せます。仏教の四諦のつもりでしょうか? ゆうきブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ
2006年09月27日
コメント(34)
-
お彼岸ー明日のためにその六 智慧(プランジュニャー)
今日でお彼岸も終わりです。彼岸とは春分、秋分の日の前後一週間です。お彼岸については、とりあえずこちらをご覧ください。「お彼岸とは先祖供養の日ではない!」「お彼岸の法要でー自分に欠けるもの」ということで、彼岸には六波羅密を実践しなければなりません。「明日のためにその一 布施(ダーナ)」「明日のためにその二 持戒(シーラ)」「明日のためにその三 忍辱(クシャーンティ)」「明日のためにその四 精進(ビーリヤ)」「明日のためにその五 禅定(ディヤーナ)」今日は「明日のためにその六 智慧(プランジュニャー)」です。今日で六波羅密も終わりです。五波羅密を完成に導くのが智慧でもあります。また、悟りにいたる為の智慧は他の五波羅密を実践することにより、生まれてきます。弘法大師はその著「般若心経秘鍵」の冒頭で「文殊の利剣は諸戯を絶つ」と書いています。すなわち(文殊の)智慧(利剣)はさまざまな煩悩を絶って、悟りにいたるための障害を取り除くのです。智慧については、これ以上書くことがありません。これを読まれた方が、きっかけとして六波羅密を実践され、悟りにいたることを心よりお祈りいたします。 コウユウブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ
2006年09月26日
コメント(26)
-
お彼岸ー明日のためにその五 禅定(ディヤーナ)
明日でお彼岸も終わりです。彼岸とは春分、秋分の日の前後一週間です。お彼岸については、とりあえずこちらをご覧ください。「お彼岸とは先祖供養の日ではない!」「お彼岸の法要でー自分に欠けるもの」ということで、彼岸には六波羅密を実践しなければなりません。「明日のためにその一 布施(ダーナ)」「明日のためにその二 持戒(シーラ)」「明日のためにその三 忍辱(クシャーンティ)」「明日のためにその四 精進(ビーリヤ)」今日は明日のためにその五 禅定(ディヤーナ)です。禅定というのは一般の方には禅=禅宗としてしか馴染みがないようですが、禅に限らず自分の心の中を見つめる内観・瞑想が禅定です。禅宗のお坊さんのページ真言宗にもさまざまな禅定の方法があるのですが、人に話すと「え、真言宗にも禅があるんですか?」と驚かれてしまいます。一般には知られていないようですが、真言宗の行というのはほとんど禅定といっても過言ではありません。布施・持戒・忍辱・精進を行いながら、禅定によって自分の心の中を探っていきます。慳貪(物惜しみ)瞋恚(いかり)邪見(過った見方)にとらわれた時も不思議と禅定を行うと消えていきます。禅定はなかなか行う機会がありませんが、真言宗寺院では阿字観という禅定を指導してくれるところがあります。機会があったらどうぞ! コウユウブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ
2006年09月25日
コメント(28)
-
明日のためにその四 精進(ビーリヤ)
今日はお彼岸の中日(秋分の日)でした。彼岸とは春分、秋分の日の前後一週間です。お彼岸については、とりあえずこちらをご覧ください。「お彼岸とは先祖供養の日ではない!」「お彼岸の法要でー自分に欠けるもの」ということで、彼岸には六波羅密を実践しなければなりません。「明日のためにその一 布施(ダーナ)」「明日のためにその二 持戒(シーラ)」「明日のためにその三 忍辱(クシャーンティ)」そして今日は「明日のためにその四 精進(ビーリヤ)」です。精進とは不断に努力することで、一心に仏道を励み行うことです。今日はお彼岸の中日でした。朝から何軒かのお宅へ赴き読経致しました。戻って来て2時から本堂で恒例の地蔵講です。ところで、すぐ近くに徳島ではカステラで有名なKというお菓子やさんがあります。そこへ読経にいきましたところ、ショーケースの中に座布団ほどもある切り分けていないカステラが4枚置いてありました。普段はせいぜい一枚しか見たことありません。思わず「たくさんありますね!」と言ってしまいました。帰りに「一本どうぞ!」とカステラをいただきました。催促したようです。精進が足りません(汗) コウユウブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ
2006年09月23日
コメント(31)
-
お彼岸ー明日のためにその三 忍辱(クシャーンティ)
明日はいよいよお彼岸の中日(秋分の日)です。彼岸とは春分、秋分の日の前後一週間です。お彼岸については、とりあえずこちらをご覧ください。「お彼岸とは先祖供養の日ではない!」「お彼岸の法要でー自分に欠けるもの」ということで、彼岸には六波羅密を実践しなければなりません。一昨日は「明日のためにその一 布施(ダーナ)」昨日は「明日のためにその二 持戒(シーラ)」今日は「明日のためにその三 忍辱(クシャーンティ)」忍辱(にんにく)というのは私に最も欠けていると思われるものです(汗)瞬間湯沸かし器とも言われておりますので心して書きます。中村 元 監修の仏教語大辞典には「侮辱や迫害に対して、しのび耐えて心を安らかに落ち着け瞋恚(いかり)の心を持たないこと。」とあります。世の中の物事は自分の思う通りに進みません。何故でしょうか?自分という「我」があって世の中と自分を分けてしまうからです。「無我」になって世の中のすべてを受け入れましょう。自分と他との垣根を取りましょう!そうすれば、怒ることなどありません。と自らに言い聞かせたいと思います(汗) コウユウブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ
2006年09月22日
コメント(18)
-
お彼岸ー明日のためにその二 持戒(シーラ)
昨日から彼岸に入りました。彼岸とは春分、秋分の日の前後一週間です。お彼岸については、とりあえずこちらをご覧ください。「お彼岸とは先祖供養の日ではない!」「お彼岸の法要でー自分に欠けるもの」ということで、彼岸には六波羅密を実践しなければなりません。昨日は「明日のためにその一 布施(ダーナ)」でした。今日は「明日のためにその二 持戒(シーラ)」です。持戒とは戒を保つ(守る)事です。仏教で戒を授かると「よく保や否や」と聞かれ、「よく保つ」と答えます。ところで何故仏教には「戒」があるんでしょう?本来人間は正しい見方が出来るはずです。ところが、欲望(煩悩)があると、よこしまな見方・考え方になりかねません。欲に目がくらんで人の道を外すのは、よく見聞きするところです。したがって欲望を制限することにより、正しい見方・考え方を取り戻す。言い換えれば、(煩悩にとらわれない)自由な見方・考え方を出来るようにする。それが戒の目的です。戒についてはこちらをご覧ください。よく戒律などと言いますが、仏教では戒と律は厳密には違います。戒は(シーラ)は規律を守ろうとする自発的な働き、律は(ビナヤ)は教団の規律です。戒はいわば努力目標です。気軽に挑戦してみてください。特に最近問題になっているお酒(酒気帯び運転ですが)でもとりあえずやってみましょう。 コウユウブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ
2006年09月21日
コメント(18)
-
お彼岸ー明日のためにその一 布施(ダーナ)
今日から彼岸に入りました。彼岸とは春分、秋分の日の前後一週間です。お彼岸については、とりあえずこちらをご覧ください。「お彼岸とは先祖供養の日ではない!」「お彼岸の法要でー自分に欠けるもの」ということで、彼岸には六波羅密を実践しなければなりません。まず、明日のためにその一 布施(ダーナ)布施といいますと法事・葬式などでお寺さんに渡す「お布施」を思い浮かべます。しかし、布施というのは本来、相互供養です。(お互いに渡す)お寺さんから何か貰わなければなりません。さて、なんでしょう?それはさておき、布施の原語は「ダーナ」といいます。この「ダーナ」は与えることという意味です。それが中国・日本では「与える人」=「施主」すなわち仏教の後援者を指すようになりました。それが転じて仏教に限らず与える人を「旦那」と呼ぶようになりました。一般的に夫のことを旦那とも言いますが、ここからきています。「旦那元気で留守がいい」などとお金だけ持ってきてくれれば良いと思っていませんか?(笑)本来の意味は相互供養です。それなりにお返ししなければなりません。せめて、お彼岸の一週間ぐらいはお返ししましょう!(笑) コウユウブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ
2006年09月20日
コメント(21)
-
オウム真理教(アーレフ)よどこへ行く!-2
前回はたくさんのコメントありがとうございました。さまざまな意見が聞けてよかったです。本題に入ります。オウム真理教に入っている信者の救済という問題もあります。「オウム真理教から変わったアーレフを解散せよ。」という意見もありますが、解散しても根本的な解決になりません。そこに集う信者たちは救済を必要としており、別のカルト教団あるいはミニオウム真理教に移動してオウム真理教と同じ間違いを起こさないとも限りません。これをどうするか?さらに宗教の側から見逃せない問題に事件を起こした当事者たちをどう救うか?という問題があります。収監されて公判を行っているうちに憑き物が落ちたようになった人もいますが、現在においても麻原の教えを頑なに奉じている人もいます。それに忘れてはならないのが、麻原彰晃本人をどう救うかです。浄土真宗では悪人こそ救われるという悪人正機説があります。麻原彰晃こそ悪人では無いでしょうか?しかし、私を含めて宗教者の側から麻原本人の救済について語られていないのは残念です。現在に至っても未だ反省の念すら起こさない彼を救うことは宗教が人間にとってどのような働きを持つか?という答えでもあるような気がします。 素光ブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ
2006年09月19日
コメント(33)
-
オウム真理教(アーレフ)よどこへ行く!-1
オウム真理教の麻原彰晃の死刑が確定したようです。逮捕された時からほとんど死刑が確定していたような状況で、それ以外の判決が出るとは誰も考えていないでしょう。遅すぎる判決というようなコメントもいくつかありました。しかし、死刑判決が確定しても、宗教的な問題に関しては全く解決しておりません。何故オウム真理教のような団体が生まれたのか?裁判で麻原個人が黙秘したためにその謎については明らかになりませんでした。それを残念がる声もありますが、本質はそこにはありません。オウム真理教はチベット密教の技法を取り入れていたといわれます。チベット密教に限らず、真言宗を初めとする密教という教えはタントラと呼ばれる経典をもとにしています。これは経典に書いてある内容よりも修行方法を重視する傾向があります。すなわち、自分が得た悟りは真理であるという結論を導き出すのです。これは大変恐ろしいことで、その真理が反社会的であっても正しいと思い込む可能性があります。ちなみに真言宗やチベット密教ではそうならないための柵が設けられており、普通はそれを超えることはありません。麻原個人の資質もさることながら、当時のオウム真理教にはそのような要素があったともいえます。問題は現在のアーレフにそのような傾向があるかどうか?というところです。同じような問題を抱えたままでは同じような事件を引き起こす可能性があります。(続く) 素光ブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ
2006年09月17日
コメント(47)
-
とらねこの憂うつ!
台風が近づくととらねこも憂うつです。雨漏りが・・・・ ゆうきブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ
2006年09月15日
コメント(37)
-
四国遍路の雑記帳54ー三坂峠での一夜
少し間が空いてしまいましたが、久しぶりの雑記帳です。三坂峠から山下りです。ここは車道ではない山道がありました。あるとき夕方に三坂峠を下ったことがあります。予想より早くあたりは暗くなり、途中のアズマヤで一夜を明かすことに決めました。テントはなく寝袋しかありません。懐中電灯は何かの時に使用しなければなりませんので使えません。すなわち真っ暗な闇の中で過ごさざるを得なくなりました。普段文明の利器の中で生活している身であるがゆえ大自然の中に放り出されるとこんなに無力なのでしょうか?多分最寄の民家まで2キロぐらいです。しかし、何かあっても逃げられる距離ではありません。藪が動くたび、あるいは風で木々が揺れるたびに、また動物の鳴き声が聞こえるたびに怖い思いをしました。泊まるところがあり、お風呂に入れ、食事があったらどんなに幸福でしょうか?昔の人はそのような自然を恐れ、ある時は神と崇め仏にすがり、あるいは信仰によって克服し、または戦ってきたのでしょう。その結果が今の時代だとしたら、複雑な気がします。眠れない一夜といいたいところですが、しっかり寝て翌朝46番札所浄瑠璃寺へ向かいました。 素光ブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ
2006年09月14日
コメント(20)
-

がんばれ徳島!
先日の四国アイランドリーグの観戦記を書きます。まだ、日が高い蔵本スタジアム。私のところから唯一歩いていける球場です。(徒歩10分)今シーズン徳島市内での最終戦とあって多くの観客が詰めかけ・・・といいたいところですが午後五時開始とあってまだガラガラです。対戦相手は先日19ー3で敗れた高知、なんとしても雪辱を!初回に一点を失ったものの、それ以降立ち直り4回終了時は1-1の同点。おお~期待できそうだ!ライト後方で火の手が!野焼きでしょうか?球場のすぐ横には徳島西消防署が、なんという大胆な行動でしょうか?なんとなく不吉な予感が・・・やはり?火の手に呼応するかのごとく徳島のピッチャーも炎上!5安打を浴びて4失点!最終的には5-2。返り討ちにあってしまいました。残念です!また来年に期待します!ブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ
2006年09月13日
コメント(34)
-
高野山紀行5-奥の院
一の橋から奥は石畳の道を歩いていきます。両側には墓地が並び、杉の巨木に囲まれています。有名な大名墓も所々点在しています。巨大な五輪塔が苔むして、お参りする人もなくあたかも時が永遠に止まったかのようにひっそりとただずんでいます。一キロほど歩くと道は二股に分かれ、右を選ぶと御供所に着きます。この二股は御廟橋の手前で一つになりますが、往きと帰りは別のルートを選ぶのが決まりです。御供所では奥の院の納経などが出来ます。御供所を過ぎて御廟橋を渡ると、いよいよ御廟です。この中は聖域とされ、物を食べたり、飲んだり、あるいは撮影も禁止されています。橋を渡ってすぐ左に「みろく石」というおもかる石があります。願いごとがあってそれがかなうなら、持ち上がるといわれています。ちなみに私は一度も持ち上げたことがありません(汗)階段を上がると灯籠堂といわれる拝殿があり、その奥が弘法大師が眠っているとも言われる廟があります。絶えず読経が聞こえますが心が洗われるかのような静かな場所です。 一度高野山へどうぞ! コウユウブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ
2006年09月12日
コメント(38)
-
高野山紀行4-壇上伽藍(続き)と金剛峰寺
壇上伽藍には昨日説明した以外の建物もあります。あと重要なのは西塔と四社明神社、不動堂です。西塔は根本大塔と対をなす建物です。根本大塔が金剛界、西塔が胎蔵界の仏を祀っています。それだけなら普通ですが、なんと中心佛が入れ替わっています。すなわち、根本大塔が胎蔵界、西塔が金剛界の大日如来を祀っています。西塔は金堂から御影堂のさらに左奥にひっそりと、お参りする人もなく木々に囲まれて立っています。その西塔の正面の方向に高野山を守護している四社明神社があります。この正面の拝殿である山王院では毎月法要が行われています。一方、根本大塔から右へ下るとすぐの建物が、高野山最古の建築物といわれる国宝の不動堂です。他の建物も興味がおありでしたらお参りください。根本大塔の右側をさらに下って行くと、金剛峰寺前に出ます。金剛峰寺は大高野山の中心の建物と期待するとがっかりします。拝観できる一つのお寺ぐらいに考えましょう。中でお茶のお接待もいただけますし、法話も聞けます。意外にリーズナブルでは?金剛峰寺前から奥の院に向けてメインストリートが伸びています。お寺と土産物店が並んでいます。たくさんありますから、一通り見てから決めましょう。(時間があったらの話ですが)ちなみに私がいきつけの店は、数珠屋四郎兵衛、中本名玉堂、高野山大師堂です。途中に観光案内所もあります。宿を決めていない時はここで尋ねましょう。少しずつ道は下っていきます。一キロぐらい先で二股に分かれた道を左へ取ると、奥の院の入り口である一の橋です。 コウユウブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ
2006年09月11日
コメント(20)
-

お知らせ
とらねこからのお知らせ「楽天フォトコンテスト」が開催されます。~~~~~~~~以下引用~~~~~~~~~~楽天広場にプログを開設している方との交流を目的とし、フォトコンテストを実施します。多数の応募をお待ちしています。1.テーマ:夏の思い出2.応募要領(1)写真のサイズ:六切りでカラー(2)応募点数:一人2点(3)応募資格:楽天広場にプログを開設している方(4)応募方法:様式は問いませんが、画題、住所、氏名(ハンドル名)を記入した応募票を入れて下さい。展示時に原則実名表示と考えていますが、ハンドル名希望の場合はその旨記入して下さい。(5)応募方法:メールまたは郵送○メール oubo@kamadanet.jp のアドレスへ送付して下さい。○郵送の場合 送り先 〒770-0942 徳島市昭和町1-74 西ビル1F ドクターエンドー徳島(6)応募〆切:2006年9月15日(7)その他:応募作品は、展示後返却を予定していますが、返却先が不明の場合は破棄処分といたします。3.審査(1)審査日:9月下旬(2)審査員:幸田青滋 先生(3)賞○最優秀賞:1名 ○優秀賞:2名 ○その他特別賞:若干名(4)発表ならびに展示○発表展示 2006年10月1日~10月15日○展示場所 鳴門ドクターエンドー鳴門市撫養町立岩字七枚 近藤ショッピングセンター 電話088-686-7858~~~~~~~以上引用~~~~~~~詳しくはPAPAさんまたはなみがしらMさんまで特別賞提供予定です。高野菩提樹の腕輪をペアで!菩提樹(天竺、星月、鳳眼、金剛など)の中でも特に珍しい一品です。菩提樹系の数珠は使っているうちに色が変わってきます。ブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ
2006年09月10日
コメント(33)
-
高野山紀行3-壇上伽藍
「お知らせ」この5日間のタイトル変更しました。~~~~~以下本文~~~~~~~高野山の大門横の道を真っ直ぐ下って行くと左側に壇上伽藍が現われます。高野山というと奥の院・そして金剛峰寺をお参りする人が多いですが、高野山の中心は実はこの壇上伽藍です。すぐに見えるのが金堂で、高野山の行事がよく行われています。おすすめは春・秋の結縁灌頂です。その手前の石段を上がると中門の礎石があります。何度も復興しようとしていますが予算の関係で出来ません。取次ぎいたしますので、どなたか30億ぐらい寄付していただけませんか?金堂の右奥に巨大にそびえ立つ朱色の塔が根本大塔で高野山の中心的建物です。内部は密教が大日如来から伝えられたという南天竺の鉄塔を模しているといわれています。一度でも内部に入ったならば極楽往生間違いなし?とも言います。一方金堂の後ろの平たい屋根の建物が御影堂といい、弘法大師を真如親王が描いたお姿が納められています。この御影堂と根本大塔と金堂との間に空地がありますが、この空地はお大師様が亡くなられたところといわれていますので入ってはいけません。 コウユウブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ
2006年09月08日
コメント(26)
-
高野山紀行2ー金剛三昧院
昨日の日記では車での話でしたが、公共交通機関を使っても行けます。南海電鉄の「なんば駅」(大坂)から南海高野線で終点の極楽橋まで行きそこからケーブルカーで高野山駅へ。特急を使うと2時間ぐらいです。高野山駅に着いたらこれも驚きです。土産物屋さんがあるだけで、何もありません。ここから町までバスを使います。歩いてもいけなくはありませんが遠いです!高野山の泊まりはほとんど宿坊です。宿坊というと、ちょっと敬遠しがちです。普通の旅館もありますが、せっかくですから宿坊を選びましょう。ただ、お寺によって泊まりの金額など条件が違いますので、あらかじめ調べたほうがいいでしょう。私はかつて3年間ほど居候させてもらった金剛三昧院に泊めていただきました。金剛三昧院は北条政子が源頼朝の菩提のために建てた寺院で、当時は禅宗(臨済宗)でしたが、後に真言宗に変わったといわれ、10代ぐらいまでは天台宗などからも住職を招聘してます。開山法要は栄西禅師が勤め、初代住職は高弟の行勇禅師です。当時の禅宗(臨済宗)は現在のものと異なり、禅・密・戒の三宗兼学です。現在の禅宗よりは真言宗に近いといえるでしょう。室町時代になっても足利家の信仰を受けて発展。かつては10万石の所領があったとも伝えられる巨大寺院で高野山の中心から離れていることもあり度重なる大火から逃れました。それ故、高野山の宝物の約半分がこの寺に伝えられているともいわれています。高野山においでの際はぜひお立ち寄りください。 コウユウ ブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ
2006年09月07日
コメント(29)
-
高野山紀行1ー高野山へ
今日から本当の紀行です(汗)16時過ぎに和歌山港到着。少し寝ているうちに空は晴れ、波はおさまっていました。和歌山城を横目で見ながら、和歌山市内を横断するように抜けて、国道24号を東へ向かいます。かつらぎ町からいざ山登り!かつらぎ町からは梨の木峠という対向がしづらい細い道を通りますので、初めての方は九度山まで進んでから上るほうがおすすめです。延々とこれでもかというぐらいにくねくねの山道が続きます。途中花坂というところで売店などがあります。ちょうど上までの半分くらいなので、初めての方はここで休憩です。少し暗くなってから高野山の大門到着!いきなり空が開けて町が現われるのではじめての方は驚くでしょう。こんな山奥に都市が存在するとは!比叡山のように山の中に建物がポツポツあるのではありません。高野山平原とでも言う長さ4キロ幅1キロぐらいの盆地が標高1000メートルぐらいの山上に広がっています。弘法大師はその実力もさることながら運にも恵まれていました。このように下界と隔離された平地を見つけることは、先を見る眼だけでは不可能です。この大門から一の橋(奥の院の入り口)にかけて53の塔頭寺院が存在して奥の院を含めて金剛峰寺というお寺を形成しています。いうなれば広大な境内地の中に町があると考えていただいたらいいでしょう。現在では高野町という町になっており、人口は4000ぐらいでしょうか?日用品を売る店はもちろんコンビニもあります。 コウユウブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ
2006年09月06日
コメント(34)
-
高野山受験記2
「紀行」と書きながら昨日の記事は旅の話がありません(汗)もう少しお付き合いお願いします。願書を取り寄せたところで別の方から朗報が!「きちんと書いてあれば資格審査論文では落ちませんよ」本当ならうれしいが・・・本当でしょうか?よく考えてみると願書はタダで大学から送ってもらいました。入学検定料は資格審査のときでなく、一次試験の時に払います。すなわち資格審査で落として一次試験を受けてもらわないと大学は赤字!ということは落ちない!(笑)安心して資格審査論文を送りました(笑)問題は倍率2倍といわれる一次試験の論文です。それに合格すると二次面接試験です。本人が書いたかどうか調べるのでしょうか?二次面接試験を受けることを前提として9月2日に命日が当たりの方の法事を断ってしまいました。かくなる上はなんとしても一次試験合格を!締め切り期日ギリギリに論文を書き上げ提出!祈りが通じたのか、一次試験合格通知が届きました。9月1日午前中は雨 波高し14時5分発のフェリーで徳島港を出て二次面接試験を受けるためいざ高野山へ! 本来ならばここで写真が入るところですが、バタバタして徳島港へ着いたのは出港わずか2分前!デジカメを忘れてしまいました。 コウユウブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ
2006年09月05日
コメント(38)
-
高野山受験記1
9月の1日から2日にかけて高野山に行ってきました。高野山大学の大学院に通信教育課程がありますが、その受験に行ったのです。発端は5月に遡ります。ネットで知り合ったK和尚さんから「高野山大学の大学院に通信教育課程があります。来ませんか」と誘われたのがはじまりです。しかし、受験資格に大学卒業がある!(当たり前ですが)「私は大学を卒業していませんので」と断ると「(本大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達した者)は受験資格があります。」とのお話です。なんかその個別の入学審査に通るのは、大変そうな気が・・・資格審査のための論文を提出しなければなりません。K和尚さんは親切にも論文の書き方を指導してくれました。しかし、私は論文など書いたことがない(汗)とりあえず願書を取り寄せました。 コウユウブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ
2006年09月04日
コメント(43)
-
喪と忌の話3
一昨日の続きです。ごく最近では「結婚式があるので四十九日を35日で切り上げて欲しい」という例もあるようです。本当は世間に出ること事態を控えるのが普通で、結婚式などは辞退するのが普通です。また、仕事があるので四十九日を日曜日に変えて欲しいという話もありますが、これなどは四十九日に出席するのも供養と考えていただきたいものです。一方喪は儒教から来たもので、社会に対して「私は身内が亡くなって悲しんでいる」ということをアピールする狙いがありました。特に親が死んだら悲しみでしばらくは、仕事など手に付かないのが普通で、平気で仕事をするような人間は人非人と思われました。現代は人非人だらけですね。(笑)ところで、よく喪中ですといわれますが、よくよく話を聞いてみると親戚といっても遠いので、喪に当たらない場合が結構あります。「喪中なんですが結婚式に招かれています。どうしましょう」というのもよく聞く質問です。当事者の場合(喪家の場合など)は取りやめにすることも多いので、問題ありませんが、そうでない場合はほとんど問題が無い場合が多いようです。ちなみに服忌令についてはこちらむやみに喪中にならないようにしましょう(笑) コウユウブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ
2006年09月03日
コメント(22)
-
喪と忌の話2
昨日の続きです。その穢れを恐れて昔の人はいろいろと考えました。よく亡くなった人が三角の白い帽子をつけています。これはもともと、棺桶などを担ぐ人がつけていたもので、陰陽師のシルシともいわれています。陰陽師の格好をすることによってその法力を持って穢れに対抗したのでしょう。すなわち穢れは恐ろしいものでした。迷信ではありません。伝染病などで次々に死者に接する人が倒れて行く様は、まだ科学の光が当たっていなかった時代には、まさに真実でした。ちなみに忌中は四十九日までです。ですからその昔は四十九日までの間、精進のものを食べて、人に合わずに穢れが広がらないように過ごさねばなりませんでした。時代が下るにつれてそれが長すぎるという風潮が出てきたのでしょう。三カ月にまたがると、身に付くというゴロ合わせで、四十九日が三カ月にまたがる場合には35日で忌中を切り上げるようになりました。すなわち、ただの語呂合わせで迷信です。さらに続きます。 コウユウブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ
2006年09月01日
コメント(24)
全24件 (24件中 1-24件目)
1