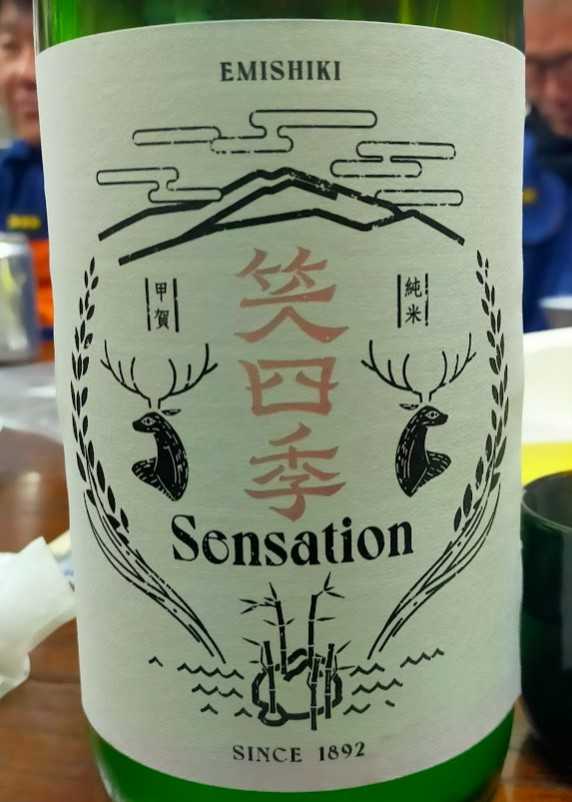2018年09月の記事
全7件 (7件中 1-7件目)
1
-
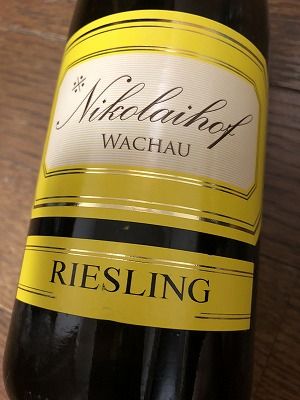
ニコライホフ
リースリング[2011]/ニコライホフオーストリア。ちょっと前?にガイヤーホフが小さなブーム?になったことがありましたが、ニコライホフは静かに、安定的に人気がある感じがします。ベーッシクなリースリングですが、瓶熟の恩恵で綺麗なぺトロール香が心地よく、折しも季節とも7マッチングした感じがします。堅めのアンズを連想させる果実味、糖を喰いきった辛口。余韻、ミネラルとも上々で、たまたまもさんまの塩焼きの腹ワタと抜群の相性でした。オーストリアのリースリング、グリュナフェトリナーと比べるとやや地味な感じもしますが、料理を選ばない万能感がある気がします。
2018年09月26日
コメント(0)
-
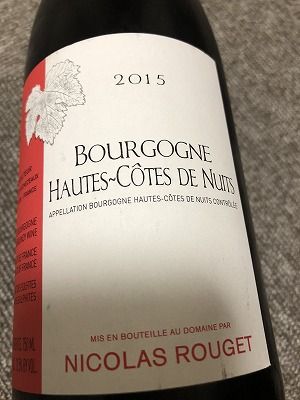
ニコラ・ルジェ
オート・コート・ド・ニュイ・ルージュ[2015]/ニコラ・ルジェ閉店間際の近所のワインショップの隅の、「あと1本だけ」というワイン木箱の中に紛れて入っていました。すでにネット上でも、飲んだ方の感想が複数アップされているのですが、なるほど高評価もうなずける味わい。父上のレジョナルなどにも通じる、独特のブランデー香と酒質の目の詰まり。これはいい意味ですが、アペラシオンよりぶどうの質が上回っていて、さらにぶどうの質より、醸造技術が上回っている。そんな味わいに思えました。この先が楽しみですが、きっと値段も上がっていくのでしょうね^^
2018年09月25日
コメント(0)
-

サンカントネール
ボーヌ 1er Cru サンカントネール[2014]/ドメーヌ・ド・ベレーヌニコラ・ポテルが、父ジェラールが最初にワインを造った年から数えてちょうど50年目の記念に造ったという触れ込みの、太めのボトルの特別?キュヴェ。ボーヌ1級、複数畑のアッサンブラージュ、古木限定とのことで、裏エチケットに使った畑の詳細が書いてありました。ジェラール時代のプスドールには、リーズナブルにいい思いを何度もさせていただいたので入手した次第ですが、2014に続き、2015もリリースされたました。ひょっとして定番化するのでしょうか? 2015のほうが美味しいですよね、きっと。2014ならもう飲めるだろう、ということで。初め、「もしやブ?」といった香りがよぎりましたが、蝋キャップもあってか、還元香だったようで、ほどなく消えました。ボーヌらしい柔らかい果実味は、確かにもう飲んでもOK。紅茶やリコリス、赤すぐり……。スパイス感は控えめで、ややおとなしい赤系果実。複数畑のいいとこ取りの長所も短所もあるような味わいで、優等生的なバランスがあるのが美点、ただそれぞれの畑の持つ特徴はマスキングされている印象があります。ちょい華やかさには欠けますが、滋味のある味わい。でも数年ではなく、古酒になるまで置くと、化けそうな気もしました。
2018年09月21日
コメント(0)
-
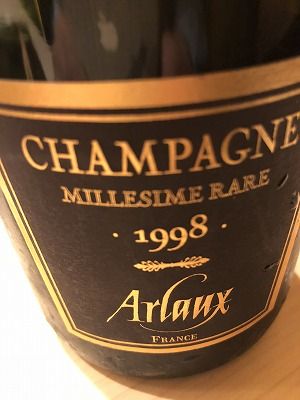
鮨とノンアルコール、懐石、天ぷらとワイン
NYにいるSさんが一時帰国。一年ぶりに定例で会っている4人で。まず昼に鮨。初めて、太一さん。おつまみ~握りのお任せでしたが、私はそのあと仕事があったので、ノンアルコールビール。他のみなさんは日本酒あれこれ。高騰する東京の鮨店の中では、極めてリーズナブルでした。もちろんネタは、最上質ではないにしろ、仕事が的確で、赤シャリに好みが分かれるかもですが、とても好感度が高いお店でした。夜は小室。リピーターなのですが、移転後は初。日本酒も飲みたい&二次会が予定されているので、私は次回でいいよ、とワイン持参ナシで。泡は、NYからハンドキャリーでアルロー98。ムニエ多めで、いい感じの熟成。白は、ラモネのバタール13。もう飲めました。樹脂っぽさが素晴らしい。赤は、ルジェのエシェゾー04。陰性のヴィンテージ。除梗なのに、ルロワ的な美味しさ。二次会は、2人加入で6人で。泡は、エリック・ロデス。赤は、ジャイエ・ジルのHCN12。私の場合、当然ZZZなのですが、赤はきちんと樽が効いていたので、味が記憶に残りました。翌日夜は別メンバーで、これまた初訪問のてんぷら店、ワインリストも定評のある清壽さん。5人で泡、白、赤。アンリオのブラン・ド・ブラン、メゾン・ルロワのオーセイ09、ルーミエのクロ・ド・ラ・ブシエール99。確かに、充実のワインリストでした。天ぷらも今はなき楽亭出身ということで、端正な味わいでした。楽亭に最後に行ったのは、もう30年近く前なのですが、味わいを思い出すことができました。ルロワは、およそオーセイとは思えない味わい。ルーミエは、99のモレだけあって、濃くて堅め。先週のシャンボール06のほうが、はるかに熟成が進んでいました。二次会で泡&赤。85のタイユ・ピエは、かなり優しい味わいでした。私は翌日からまたまた外房だったので、ここで離脱。他のメンバーは、三次会で先代モルテを飲んだ模様。外房では、いつもの和食屋でオスコ・ビアンコを飲みましたが、あれだけの美味しいワインたちの後でも、別物として美味しく飲めました^^外房から帰ってきて、家でフルニエのロンジュロワ14。安定のデイリーブル。14は、ややおとなしくなった模様ですが、ジュヴレの下位互換しては、充分過ぎる味わいでした。よく飲みました^^
2018年09月18日
コメント(0)
-

バンジャマンのブラン
ブルゴーニュ・ブラン[2012」/バンジャマン・ルルーこのボトルはBBR扱いではなく、コルク栓でした。小気味よい3ピースバンドのように、果実味、酸、ミネラルがきちんと揃っていて、飲んでいてとても快適です。要素が多くなくても、きちんとツボを押さえてある感じがします。一世代?前のマイクロ・ネゴスであり、最近の上位畑に特化した後続が出てきたからか、一時期ほどの人気はなくなっていますが、安定した造りに思えます。赤は、ルロワ系の下位互換で、時にバランスのよくないものもある気がしますが、白は安定しているように思えますし、個人的にもかなり好みです。ただバンジャマン、冷涼な年のほうが好きなのか、この銘柄に関しては2011年のほうがより美味しかった気もします。
2018年09月13日
コメント(0)
-

外房ワイン会2018
今年は、人数が増えて7人で。Iさん、Yさんは3年目になります。いつもの送迎してくれるイタリアンに、泡3、白2、赤2を持ち込み。お店に行く前に部屋で、Yさんが2年前に持ってきたまま塩漬けになっていた、テタンジェのマルケットリー(画像ナシ)を食前酒にしてから。1本目は、私が持参したコントの06。外房のセラーは、ほぼデイリーワインなのですが、テタンジェ繋がりでコレがあったので。まだ若く、やや還元的。2本目はユリス・コラン。デコルジュからしばらく経っていて、こなれた美味しさ。ノワールらしさが出ていました。白は、ハイツ・ロシャルデとルフレーヴ。造りと村の違いが面白かったです。マルトロワは2015年、ルフレーヴは2013年(確か)。ロシャルデは、還元と酸化の中間を狙っているとあって、グラスの中でどんどん変化していきました。シャサーニュらしい柔らかさもきちんと表現されています。追記:ルフレーヴは、2011年でした。ルフレーヴのピュセルは、最初はクラヴァイヨン的なぽってりさがあったのですが、だんだんとミネラルが顔を出し、ルフ香も全開に。王道感が感じられ、ロシャルデの今どき感と好対照でした。赤は、ルーミエとデュガ・ピィ。ルーミエの村名06は、ザ・ルーミエという味わい。ルーミエ香で、ほぼほぼ全員がルーミエと気が付いたようです。きれいな熟成がしっかり進んでいて、私は99あたりかと思いました。まあ村名のレベルではないですね。一方のデュガ・ピィのシャルム99は、黒々とした若過ぎる酒質でしたが、含み香と味のレイヤー、要素の複雑さはしっかり感じられ、この目の詰まった味わいはGCの貫録でした。締めシャンは、グラン・ダム。それも90のマグナムでした。実に若く、堂々とした味わい。肯定的な太さと重さ。旨い!部屋に戻って、セラーから赤と白を1本ずつ。個人的定番のデイリー、バイエのオート・コートとバローのラ・ロッシュ。どちらも2014年。みなさんのワインと伍するレベルではなかったのですが、幸い美味しく飲めました。バイエのやや抽出から来る苦み、バローのマコネらしい軽いトロピカルな要素はありましたが、まずまず。夜中の2時くらいまで飲んで、最後は起きていた人々は、ユーチューブ80,90年代歌謡曲を見ながら合唱していましたが、1人を除いてまったく記憶に残っていなかったそうです。幸い私は間にチョイ寝をしたので、一部始終覚えていました^^その週の平日は、外食が多く、しかもいわゆるビオ系ど真ん中ワインばかり飲んでいたので、正統ブルシャンの美味しさを改めて感じることができました。ありがとうございました!
2018年09月10日
コメント(0)
-

ラフォン・ロシェ
シャトー・ラフォン・ロシェ[2014]先日の昼間、バックヴィンテージを含めて、ボルドーをまとめて試飲できる機会があり……。07のパルメやポンテ・カネ、01&04のローザン・ガシ、14のプチ・シュヴァルやパゴ・デ・コス、03&96のクロワゼ・バージュなどなど。やはりパルメやポンテ・カネがよかったです。07もこなれ始めていました。私が手持ちのボルドーも、高騰する一歩手前だったので、07が何本かあるので、少しずつ開けていこうかと思いました。クリュ・ブルジョワクラスの何本か飲みましたが、ローザン・ガシといえども、ちゃんと格付けのレベルの酒質があって、過去の悪評のシャトーたちも2000年代以降は向上していることが確認できました。その日の夜、家で比較の意味をあって開けたのが、ラフォン・ロシェ。過去の無骨な味も意外に好きだったのですが、ビオになって、さらに大量の資本投下をした近年は同じシャトーとは思えない味と聞いていたので。確かに、一変していました! サン・テステフらしいある種の重さを維持したまま、シームレスなテクスチュアを感じる酒質、ブル好きでも美味しいと感じるであろう綺麗な酸、ジャミーさを排した集中力のある果実味と、同じ方向性で評価を上げているポンテ・カネと近しく、たとえば同じ村、同じヴィンテージだったコスのセカンドと比べると、2、3ランクは上の味に思えました。値段は、あちらのほうが高いのですが。おそらく現在の価格の倍くらいまでは、すぐに行くように思えます。セカンドも早く飲む分にはすごく美味しいらしいので、14年以降が特にいいらしいので、探してみようと思います。
2018年09月05日
コメント(0)
全7件 (7件中 1-7件目)
1