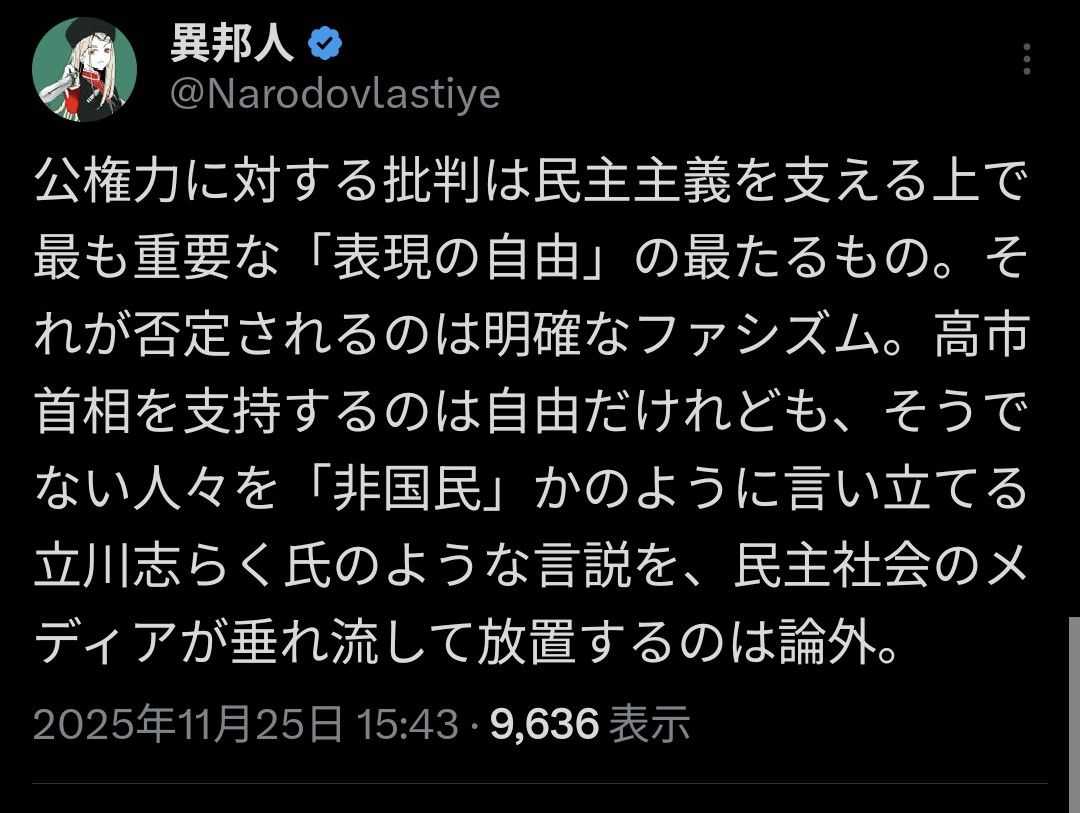2015年02月の記事
全28件 (28件中 1-28件目)
1
-
陸オカ蒸気機関車と京都駅♪
〇18世紀末イギリスのワットが発明した蒸気機関車が島国日本に敷設されるには200猶余年の月日を要しました。日本人で最初に蒸気機関車に乗った人物は土佐の中浜万次郎、次いで新見豊前守ら咸臨丸の人々。鉄道敷設には陸軍を含む反対論者が多く、紆余曲折を経たのち、明治5年、新橋~横浜間で開通しました。当時の天皇は直衣に冠、供の者も直垂に烏帽子姿だったのですが、5年後、京都~神戸間の開業式に臨まれた御姿は大礼服になっていました。で、初代の京都駅は旧七条郵便局、現在のタワー・ビルの場所に、左右対称の切妻屋根、赤煉瓦造り、瀟洒な洋風2階建。明治10年の京都駅附近の地図には大阪へ向かう線路の表示や御土居が点線で描かれています。千年の昔から牛の引っ張る御所車しか見たことのない京都の民は、東寺の塔を覆い隠すほどの陸蒸気の煙や地響き、威圧感に驚きながら、「1時間40分で大阪に着くんやて」と囁きあっていたことでしょう。(参考図書「京都駅物語」荒川清彦)
2015.02.28
コメント(0)
-
をんなのお洒落♪
〇最近は男性用の化粧品や頭髪リキッド、スプレー所か肌に良いとされる化粧品がコーナーの一角を占めていますが、文明国にあっては、何と言っても美への執着心は女性に軍配が挙がりますね。亡父すばるは”美”への探究心が強く、簪や櫛なども集めていました。そして「櫛玉手箱」と言う文化出版局の豪華本がありました。父はこの本を購入しただけで、その欲求・夢が充たされたのでしょうか、手垢のつかない儘古びています。さてページに満載された櫛は、金箔を施したもの、蒔絵のもの、象牙のもの、繊細なもの、重量感のあるもの等、京・江戸の匠の息吹が伝わって来そうなものばかり。黄楊、柞、鼈甲、象牙、擬甲(水牛の角、馬爪、牛爪、卵甲)、金属(真鍮、アルミニウム、銀)、ガラス、水晶、セルロイドなどが材料になっています。さてユニークな櫛と言えば、源内櫛(田沼意次家で愛用された平賀源内発案のもの)、相撲櫛(鬼勝象之助は顔に白粉を塗り二枚櫛を挿したとか)、光輪櫛(尾形光琳の作風を真似たもの)、政子形櫛(頼朝の内室:政子所蔵を模写)、お園櫛、お六櫛などなど。本書の最後を見て驚きました。写真家:清岡純子さんの手に依っているのですが、今は懐かしき安達瞳子さんの所有なさっているものが全体の25%ほど占めていました。そう言えば、安達さんは一見、もの静かで漆黒の長い髪をして居られましたね。
2015.02.27
コメント(0)
-
大文豪・谷崎潤一郎の女友だち♪
〇潤一郎の「京の夢大坂の夢」に”関西の女を語 る”という件りがあって、関西には男の作家が少 なかった関係上、男性との交友が稀で、その分阪 神間に住んでいる夫人令嬢達、次は専門学校程度 の女学生達、それからダンスガール、芸妓といった 面々だった由。 和装は東京の比ではないほど華やかなもので決め ているのに、心斎橋辺りに屯ろする女達の洋装とな ると洗練されていないと評しています。 東京は早くからモダンガールなど短髪にする女性 が多かったのですが、関西ではダンスガールか女 給に限っていたので、間違われてはという危惧の 風潮が。 従って流行の先端を行く派手な柄や色合いの洋服 を着こなせずにいたようで、和装の趣味が洋装にも 影響していると推察していました。 <洋装はいくらか野蛮で無造作なところがあった方 がいいのだが、帽子の好みから靴の爪先まで、あ まりに千代紙式、長襦袢式に綺麗すぎる。それが 欠点といえば欠点だ。> と評する一方、東京者の「そうざんす」や「遊ばせ言 葉(ご免遊ばせ等)」という不愉快な言葉は関西 では聞かないと援護しています。
2015.02.26
コメント(0)
-
二條河原落書♪
〇<此頃都ニハヤル物、夜討強盗謀綸旨、召人早馬虚騒動、生頸還俗自由出家、俄大名迷者、安堵恩賞虚軍、本領ハナルゝ訴訟人、文書入リタル細葛・・・>二条河原の落書は落書の傑作といわれ、1334年建武元年8月、つまり後醍醐天皇が京都へ戻り、凄まじい勢いで大改革政治を始めて1年数ヶ月、新政の綻びが出てきた頃のものです。命令書はよく吟味もなしに発布され、裁判の誤りや賄賂の横行など社会不安は高まるばかり。こうして中興の新政は失敗に終り、南北朝の対立という動乱期に入ってしまったようです。 政治のことは難しくてよく解りませんが温故知新を基礎としながら、底溜りになっている古い慣習を一旦打破して、180度ほど角度を変えた物差しで新しい政治を再度興して欲しいものですね。絶対的な支持を得て政権を取った民主党の殆どが未熟なレベルで国民の期待を裏切った、あの時代が、酷似していたような・・・。
2015.02.25
コメント(0)
-
短編小説「五百羅漢」♪
〇稲荷山の中腹に石峰寺という古刹がある。此処には五百もの羅漢が仏道の悟りを求め、今日も空を睨んで居られる。しかし、これは表向きの話でいわゆる丑三つの頃になると、ぼそぼそ、そこいらで談話が始まる。中には、向うの草むらから歩いて来られ、その座に加わる羅漢も居られる。折から山颪が来て、一斉に乾いた草木が泣き出す。俳句では虎落笛モガリブエと言う季語がこれに相当する。寒さが厳しいから、星がよく光る。すばる星など鮮明に見える位である。 「ほほう、御坊が仏門に入られたのは、十九で御座ったか。」 「はい、忘れることができませぬ。」先に相槌を打ったのは、福禄寿のように頭の長い羅漢であった。垂れんばかりの鷲鼻である。これから正に告白しようとするのは、凡人っぽい、それでいて若さの匂う羅漢であった。羅漢は総じて眼玉が大きいが、この方のは、眼に顔があるといった見事な眼玉であった。 「すると、女人から逃れて参られたかの?」鷲鼻の羅漢が覗くようにして尋ねられた。額の皺は六十の齢を見せつけるようであった。 「はい、高貴な御方に恋慕した訳で・・・・・」恋慕と言う言葉が耳に入ったのか、八方の草陰から、ぞろぞろと来られるわ来られるわ。仏話を拝聴する信心者のように、忽ち円座が出来てしまった。さすがに冷やかすような野暮なことはなさりはしない。只、にやけそうになる顔に神経を通わせ、静聴して居られる。若い羅漢は苦行を乗り越えただけあって、此処に至ってぐっと落ち着かれ、舌もよく回転し始めた。 「いかに高貴な御方とは言え、女人は女人と高を括って居った其の上、己を褒めるのもおこがましいが、容姿にも自信が御座りました。・・・若かったのですな。平井保昌宜しく、紅梅一枝を肩に挿して、寝所に忍んだので御座ります。」 「ふむ。」鷲鼻の羅漢は味わうように、頭を上下させて聴き入ってられる。山颪も止んだらしい。 「偉い御方で御座りました。愚僧の参るのを知っておいでで、諭すように、こう申されたので御座ります。」夥しい視線が若い羅漢の口許に凝集して、辺りの空気が、一瞬、止まった。 「あなた様のお志、有り難う御座りまするが、物盗りになるような子供は、産みとうは御座りませぬ。」 「それだけじゃったか?」 「はい、たったこの一言で御座りました。そのお方からこれ以上の言葉の出る隙の無いことは、血気盛んな愚僧にも感じ得たほど。・・・・考えあぐんだ末、仏門に入った訳で御座ります。」福禄寿の羅漢が、静かに問われた。 「それで、答は出たかのう?」 「はい、今なおこうして考えて居りまする。」 円座の羅漢はそれぞれ尤もだと頷いて、それから首を傾げながら、八方草蕪に戻られた。鷲鼻の羅漢も腕組みして考え込まれた。當の羅漢は、また、きいっと星を睨み返して居られる。 辺りはやはり凍てるような寒さが根を下ろし、草木はますます干乾びて泣き止まない。 この短編は私が社会人2年目、24歳の折に書いたそれはそれは古い作品です。
2015.02.24
コメント(0)
-
嵯峨帝と光源氏♪
〇昨日はおとなしい春雨の中、嵯峨散策の吟行句会 でした。嵯峨山地区を愛されたのが桓武帝の第2皇 子嵯峨天皇。 異母兄に平城天皇、異母弟に淳和天皇。 嵯峨天皇の12番目の皇子が源氏物語のモデルとさ れた源融。私事ながらわが家の菩提寺も融屋敷の一 部とか。 さて嵯峨天皇は薬子の乱を参考に死刑制度を廃止 された方で後、338年間生かされました。また三 筆の一人で達筆だったとか。 現世からあの世へ送り出す釈迦如来と西方浄土へ迎 え入れる阿弥陀如来とを奉る二尊院を建立させた天 皇としても著名。 嵯峨院の跡で皇子源融の別荘でもったのが釈迦堂 で、結社では先師野風呂以来一昨年まで8月の早朝 句会の場でもありました。昨日の拙句 見返れば釈迦堂の門もう朧 星子 侘び棲みの土蔵崩るる沈丁花 など5句。 大山崎ふるさとガイドの会のメンバーとして嵯峨 天皇のもう1つの別荘・離宮八幡(河陽カヤ離宮)や 橘嘉智子皇后の実家筋の守神を祀ったとされる天王 山中腹の酒解神社にも関わって来られるから、歴史 探訪やガイドは辞められません。
2015.02.23
コメント(0)
-
キスの話♪
〇わが国に残っているキスの文献中、最も微笑ましいのは秀吉が愛妾淀君へ送った手紙かも知れません。<20日ごろには必ず参り候て、若君(秀頼)を抱き申すべく候。その夜さ、そもじをそばへ寝させ申すべく候。せっかく御待ち候べく候。返す返すも御ゆかしく候まま、やがて参り候て、口を吸い申すべく候。>いかにも太閤秀吉らしい率直にして大らかな愛情表現ですね。時は巡って江戸時代には好色文学や遊女などが流行り、庶民の間にもキスが行き渡ったようで、”おさしみ””口吸い””くちくち”と呼ばれ、国貞や歌麿など浮世絵師の材料になりました。有名な「春色梅ごよみ」にも、キスを求められた女性が、男を待たせ庭の白梅を口に含んでから応じたというシーンが描かれているそうな。中国ではキスを「呂」という字で表わします。な~るほど♪
2015.02.22
コメント(0)
-
京の味ごちそう展♪
〇急に思い立って家内と高島屋の「京の味ごちそう展」に。(本来は俗字の高)丁度12時過ぎでしたので、先ずはチケットを買うのに、急拵えの囲い壁にそってに列が直角に曲ること、凡そ50人分。日本人はじっと我慢できる民族で、ちびりちびりと前進する中、1時前に漸く席に着けました。これまで運悪く営業時間に寄れなかった西陣「魚新」を味わいました。別コーナーでは和洋食、鮨、蕎麦など多くの御膳が展示されていました。その後、名品販売コーナーを尻目に、手に提げて来た「こけし」関係の冊子60冊を三条の古書店に譲り、針と言えば「みすや針」さん(現17代目)に寄り、また後鳥羽院御製の国宝「菊一文字」に因む屋号の包丁屋さんで、プレバトルで使っておられた蕎麦専用の包丁(3~6万円)を確認したり、麩屋町錦上るの「omo cafe」さんの立派な京町屋でぜんざいや蜜豆にて休息。東京にあった蔵元の京都特約店だった大橋庄三郎の旧宅をリフォームした立派な町屋。蔵を生かした個室や奥の部屋、二つの中庭などを拝見させていただきました。こういう町屋づくりは大いに進めて戴きたいと思いました。
2015.02.21
コメント(0)
-
「京都スーベニイル手帖」♪
〇観光地・京都の土産には何が良いのか、ちょっと入ってみたい喫茶店は何処?とか京都に不慣れな人だけでなく、京都や大阪に何年も住んでいる関西人でも良くは知らない伝統的な店や小粋な土産品を紹介する豪華な案内書。著者沼田元気(白夜書房出版)本体価格2500円。モデル(冬)徳田妃美(春)舞妓・梅わか(上七軒)先日の各句座で、女性たちに配ったのが、舞・芸妓さんが御座敷で名刺代わりに差し出す千社札。この本にある花名刺の作者・松村幸子さんのコーナーでは工房の案内や実際の作品がカラフルに掲載されていて、60個のデザインが剝れるように作ってあって、カラーコピーさえすれば、例えば私の雅号・星子やブログ名の「しぐれ茶屋於りく」などと筆で書けば、実に艶な名刺が・・・。
2015.02.20
コメント(0)
-
”仁丹”おかえり♪
〇昨年9月22日の日記の内容は、「京の町看板 六十七種類」と題して、明治43年に郵便配達員が困らないように設置された歴史に触れながら紹介した”仁丹”の看板が、新たなニュースとして同じ京都新聞の昨日2月17日の朝刊に掲載されました。 盗まれたのは「上京區大宮通寺之内上ル西入二丁目西千本町」と書かれた”軍服姿の仁丹”提供の琺瑯製の看板。1月27日に無くなっていることに住民が気付かれ、交番に届け出。その後、ネットオークションで8万円で売りに出されていたのを、町名表示板の愛好家たちでつくる「京都仁丹楽會」の会員が発見、通報したもの。販売目的で盗んだのに、犯人の「実家のリフォーム時に外し、物置で保管していた」とは、実に白々しいと思いませんか?
2015.02.19
コメント(0)
-
てのひらサイズの俳句読本♪
〇テレビの某番組のお蔭で芸能人はもとより、若年層や主婦に至るまで俳句に興味を持っていただいているこんにちです。江國滋さんの「俳句とあそぶ法」という朝日文庫の掌サイズは何処を読んでも直ぐ溶け込んでしまう小憎い名著。井上ひさしさんとの対談を持ち出して、「みんな年をとったりすると俳句を詠んだりしたくなる。どうも日本人は不思議です」に対して江國氏は「政治業者なんぞが結構うまい句を詠んでいるののをみると、好きな俳句を止めちゃおうかなとも思う」と返し、風邪ひいて母の匂ひの実母散 大野伴睦知れる妓の二度の勤めや秋袷 林 譲治 原爆忌での元総理閼伽ささぐまた熱き日のめぐり来て 中曽根著名な政治家の句を例に挙げておられます。 定型はいのち 切れ字は宝 つかずはなれず 字づらの研究など、20章にわけて俳句的な視点を述べておられます。いろんな入門書がありますが、小説を読むような気楽さの中で、是非とも本書にも目を通していただきたいと思っています。
2015.02.18
コメント(0)
-
才女・岡部伊都子さんの鋭い視点♪
〇本来なら亡父の蔵書をもっともっと処分すべきなのですが、そうした方が物置も有効に利用できるのですが、父の魂が我が身に埋め込まれいるのか、思い切って処分できぬまま、更に地元の古書店で「こころをば なににたとえん」という岡部伊都子さんの本を100円で手に入れました。何と申しましょうか、宗教観、哲学観、人生観などが混然一体となった名文のかずかず。創元社を初め、新潮社、講談社、淡交社、保育社などから刊行された著書は120冊に及ぶとか。特に彼女が掘り起こすのが、京都や大和に残された日本の自然と暮らしの世界、四季の行事や古典、和歌、衣、道具にも注がれています。沖縄への想いも深く、大阪生まれの彼女が沖縄の人だと思い込んでいる人も多数だとか。新潮社の「観光バスの行かない・・・埋もれた古寺」この書名だけでも彼女の世界が推測できそうです。有名な観光地、社寺をオートメーション工場の製品のようにさっさと見物・移動して、京が好き、奈良が好きと思っておられる方々に、日本古来の美、継がれてきたこころの美というものを心底から味わって戴きたいと思わないでもありません。
2015.02.17
コメント(0)
-
再期のことば♪
〇昨日は25日に満100歳になる叔母への誕生カードを求め、家内と四条の東急ハンズに行きました。その後高島屋へ寄ったところ、新書の古書扱い販売コーナーがあって、税込500円の本が230円で買い求めることが出来ました。新書ですから手垢の殆ど無いものですが、半値以下だから、結構主婦層の人だかりが出来ていました。購入した「最期の言葉」は歴史上の有名人124名が最期に遺した言葉を解説しています。参考資料として「臨終の言葉」(主婦の友社)、「知識人99人の死に方」(角川)、「辞世のことば」(中央公論)、「心にしみる臨終さまざま」(日本文芸社)、「作家の臨終・墓碑事典」(東京堂)、「往生際の達人」(新潮社)、「生き方の鑑 辞世のことば」(講談社)など15冊の書などが挙げられています。中流家庭育ちの樋口一葉は17歳のとき、父の借財のため、貧困の裡に亡くなったようです。歌熟の先輩が執筆によって高額な原稿料を得たことを知って、明治の清少納言と称される程の作品を残しました。肺結核に臥す彼女に見舞客が「また今度」と言うと「そのとき、わたしは石にでもなっていましょうか」と漏らした由。その友人が次に対面するのは墓石の下の自分だと婉曲的に告げたものと思われます。
2015.02.16
コメント(0)
-
バーナード・リーチ♪
〇バーナード・リーチに関する特集(1980年4月5日、池田弘編集委員)を参考に一部書いてみます。 自らを”東洋と西洋の間の使者”と称して十三回も来日し、東洋と西洋文化の相互作用の中に人間の在り方を模索、機械文明の果てしなき発展の落胤として枯渇してゆく人間の精神の潤いへの果敢な闘いを陶芸から伝えた人でした。香港で生まれ京都や彦根で幼年期を過した彼は、小泉八雲の著作に感化され再び来日し、英国で学んだエッチング(銅版画)の技術を教えている時、志賀直哉・武者小路実篤・柳宗悦・岸田劉生などの白樺派とねんごろになりました。そんな或る日、招かれた茶会で楽焼の絵付けを経験したことからやきものへの興味が湧き、日本人に溶け込んで日本人が本来欲している素朴な民芸の良さを彼の作品を通して伝えました。11年間日本に在住したリーチは大正9年、浜田庄司を伴って英国へ帰り、漁村セント・アイブスにヨーロッパ初めての”登り窯”を築きました。「人間の魂の宿るやきもの」を鼓舞した彼の著書は世界中で愛読され、欧米随一の陶芸作家として敬愛されるに至りました。英国王室はサーの称号に類するC・Hを彼に贈り、またエリザベス女王は訪日に際して彼のエッチング「手賀沼」を皇后への土産ものに携えられたようです。92歳の生涯を民芸的立場で東西文化の融合に寄与した彼の功績を称え、死後の翌年に日本で大々的な展示会が催されました。
2015.02.15
コメント(0)
-
奥村富久女(富久子)さんのこと♪
〇歌人吉井勇の かにかくに祇園は恋し寝るときも 枕の下を水の流るゝの元の詠みは如何だったかな?と谷崎潤一郎の「京乃夢大阪の夢」(昭和25年日本交通公社出版450円)を手元で繰りました。 最初の詠みは かにかくに祇園は嬉し酔ひざめの 枕の下を水の流るヽ「磯田多佳女のこと」という項は46頁も割いて居り、漱石との心の食い違いや当時の作家との交流も詳しく書かれています。大山崎山荘を設えた加賀正太郎と没1年前の漱石との仲介人として多佳女は知られています。多佳女に続く最終項は昭和22年度の潤一郎の日記が掲載されています。その4月27日の辺りから再々登場されるのが奥村富久子さん。 奥村富久子さんは知る人ぞ知る観世音流能の一人者ですが、わが両親の新婚時代からの知人で、その繋がりで私も年賀状のやりとりをさせて戴いていた間柄でしたが、昨年亡くなりました。7年前から法然院での能・地唄の発表会にはお招き戴ていましたが、ほかの用事と競合する為一度切り。爾来、お会いしないままでした。2008年頂戴した年賀状にはハガキを横向きに、左にご子息南條長柾作の小面(花)の写真、右から左へと迎春の筆致も若々しく、「大福やえにし嬉しき歌の友」(富久女)の句が墨痕瑞々しく書かれていました。南條秀雄氏との共著「花乃むかし」(中央公論社)も戴いているし、某新聞社に投函された一文に見る、若き日のラブロマンスにある情熱の迸りを思うにつけても、青春を忘れない限り、年齢を超えた万年青のままで居られるものなンだと学ばせて戴きました。
2015.02.14
コメント(0)
-
二・二六事件と父の日記♪
〇先日NHKの特別番組で大正から東京オリンピックの開催時を中心にモノクロの映画に彩色したものを流していましたが、昭和十年十二月中旬から丁度一年間の日々を綴った父の日記も、当時の日本の知る手がかりにもなりそうです。二月二十六日の日記では、帝大での期末試験について触れた後、帝都での軍人暗殺事件、いわゆる二・二六事件を帰宅した時に知ったことや、午後九時四十分のラジオニュースで確報を知ったと記し、感慨無量であると述べています。隣家の上棟の騒音などもストレスになっていた模様。この日の来報は友人二人と中央公論社の麻田駒之助。翌日に高橋是清蔵相が亡くなった由。翌日は野風呂先師の便りを受け、返信しています。蛇足ながら、この年は閏年で二十九日まであったようで、三月に入るのに雪降り。
2015.02.13
コメント(0)
-
拙作「Some Dreamy Hours」♪
〇女性が心底好きになった相手への想いを綴ってみました。曲名を日本語にすれば、「或る夢のような時間(ヒトトキ)」とでも。 「Some Dreamy Hours」 貴男は世界で 一番素敵な 優しい心を 持っている人 貴男の瞳は 夜空に輝く 幾多の星より 美しいのね 貴男のベースが 一言ささやく 夢見る乙女を 誘っている 現実 時越え バラ色のように めくるめくよな 渦の中 貴男が両手で 包んでくれたら 素直な気持ちに なれるのです 貴男と居る時 時計は止まるの 不思議の国の アリスのように 貴男がソフトに この髪解いたら 茨の日々も 癒されるの 現実 時越え 真珠みたいな 涙ほろほろ 零れそう
2015.02.12
コメント(0)
-
「くだらない」の語源♪
〇日本で造り酒屋が爆発的に増えたのは室町時代で、何と洛中だけでも三百数十軒と言われています。足利義政や義満ら将軍が所望したのは”柳の酒”という銘酒で、将軍家御用達ともなれば、公家や武士も之に習いました。陶器の壺から樽を使って醸造されたのもこの酒で柳樽は適度な湿り気が木にぬめりをもたせ隙間を無くし絶好の酒樽になったのが名の由縁。 ところで「また、くだらんこと言うて・・・」の下らんの由来はと言えば、上る・下るの下るの否定形、もともとの起点は京の都にありました。京の都の産物は、全国各地にしてみれば京の下りものと呼ばれ賞賛されたのですが、有難くないものは、都から下って行かない「くだらん」ものだた訳です。(参考図書・黒田正子「京都の不思議」)
2015.02.11
コメント(0)
-
京の風物詩を摂取する?
〇大山崎のボランティアガイドを始めて10余年。観光客の皆さんの表情から憶測して、ああ、この話は受けているなとか、皆さんのお顔が今一つ輝いていないなとか、喩えれば”山と谺を分かち合っているような瞬時の判断が必要になって来るのだと思っています。 そこでいろんなジャンルの書物を読書することによって、将来役に立ちそうだと思われる事柄を逐一ノートに記録(それがこの日記)して、私なりの辞書、手控え、ネタ帳を作って参りました。 ちょうど10年前の日記には、長岡の図書館で見つけた岡本佐代子著「京の夢物語」を紹介していました。彼女は京生まれの京育ちですから、彼女自身が京の匂い、京の風を持って居られます。この本は、”京のお寺めぐり”、”京の遊び心”、”京のおいしい話”、”京の夢暮らし”などに分けて書いて居られます。単なる観光案内所ではなく、彼女の気持ち、その日の風の匂い、光の濃淡など・・・・文章に触れていると、小夜子さんと肩を並べて歩いているような。知識そのものを流すのでなく、歴史に刻まれた風土を紹介しているような。こうした蓄積が、不意の質問にも遠からぬ観点からお答えできたり、通常の語り口に加味できたりしているのかも知れません。
2015.02.10
コメント(0)
-
睦月の拙作記録帖♪
〇俳句と言うものは、互選が乏しいと哀しく思わないでもないですが、採って貰おうと無理に受けを狙うのは避け、真実を詠みたいと願っています。◎登り来て旗立て松の初日の出 天王山には光秀公との戦の折、秀吉公が幟を 立てさせたといわれる松が5代目?〇どか雪やお色直しの初景色〇歌かるた尼僧臆せず恋の札◎屠蘇酌むや戸主に劣らぬ下戸ばかり〇南無八幡太郎の凧は八角形◎ものの芽や介護疲れの身に届く 色んな草木の新芽の膨らむ音が聞こえるかに〇初鴉諸方くまなく物見中 寒東風やぎをん置屋の火迺要慎〇日脚伸ぶ住吉さんの招き猫 初辰の時だけ売られる招き猫、沢山集めて ランクアップした招き猫を地元の信者は集 めておられます。
2015.02.09
コメント(0)
-
福引の歴史♪
〇日置昌一著「ものしり事典」には今で言う福引、宝引の始まりに頁を割いておられます。 17世紀前半、宝永年間の書物には<姫子は羽根つき宝引などして>と記され、井原西鶴の「織留」にも<さる大名が御吉例とて正月三日の夜大書院にて家久しき者ばかり召寄せられ、宝引をおほせ付けられる、ふすま障子の内より五色の長緒を数百筋投げ出して、手毎に一筋づつ引取り、この緒の末につけ置かれる物をくだされけるに、小姓ひき出す縄に桑の木の撞木杖をかし、家老職の人引出す縄に銀銭一貫文あるひは唐織の巻物を引出すものあり、・・・(中略)提重箱、なぎなた、印籠、きんちやく、日傘、緞子の夜着ふとんより、しやくしを取るものあり・・・>と正月を愉しんだ一コマなど。
2015.02.08
コメント(2)
-
明治の破天荒なタバコ王♪
〇京都の円山公園に「長楽館」という瀟洒なホテルがありますが、元はと言えば「東洋のタバコ王」と称された村井吉兵衛の別荘兼迎賓館の名残です。歌舞伎などで観るように昔はきざみ煙草でしたが、国の専売となる前に両切り紙巻きタバコ”サンライス”を日本初に製造し、東京の「天狗」タバコとのデッドヒートを繰り広げた男でした。晩夏の風物詩・大文字、如意ケ嶽の大文字山に一字が二メートル四方の文字看板「ヒーロー」「サンライス」を中腹に並べ、市内のどこからでも眺められたとか。後年、明治天皇が京都にお越しになった折、畏れ多いということで撤去したという逸話も残っています。広告の天才・吉兵衛は、タバコにグリコならぬオマケをつけて販売したり、懸賞付きのものもあったそうな。(参考図書・黒田正子著「京都の不思議」)
2015.02.07
コメント(0)
-
木の葉髪(冬の季語)♪
〇サントリーウイスキーが昔発刊していた「洋酒天国(Vol41)」をめくっていると「禿頭席への勧誘」と題して著名人にアンケートをとっています。昭和34年11月の発刊分です。質問は1)あなたの頭髪が薄くなったのは何歳ごろで すか?2)そのときのご感想。3)ご自分の頭髪に対する現在のご心境といった具合で、将棋名人:大山康晴氏→ 1)30歳頃。2)湯川博士に似ていると人から言われ、頭の中もそのようだとよいナと思った。3)これ以上薄くならない法はないかと思うが、不精だから成り行きにまかそうと思っている。作家:北原武夫氏→1)何と26歳頃でした。しかし不思議なことに、それからの方が女に好かれたのですから、女の気持というのはよく分りません。2)バカなことを訊くものだーー勿論、天を仰いでガッカリしましたよ。3)こんなことが楽々と書けるほど、達人の心境に達しました。野球解説者:小西得郎氏→1)第二次世界大戦の頃、むやみにオツムの毛が抜けます。栄養失調のせいだろうとタカをくくっていたら、それが本物のハゲだったのです。2)やんぬるかなと思いました。3)まわりだけにあって天辺は堂々とハゲている私への心境など・・・ナイものネダリはしないで下さい。俳優:十朱久雄氏→1)何時頃かはっきりしませんナ。突如として光り輝いたのではないので。3)急にふさふさとなると営業方針を変えねばならず、やっぱりこのまんまがよい。版画家:棟方志功氏→1)この10年前頃でしょうか?あまり気にしていない時に、こうなりつつあったようです。2)全然手入れをしていないのだから、自業自得とサトッています。3)ナシ。 小冊子にはあと11名のアンケートが載せてありますが、それぞれの想いが綴ってあって親近感が湧きますね。
2015.02.06
コメント(0)
-
憚ハバカることば♪
〇光文社文庫、清水義範著「日本語がもっと面白くなるパズルの本」を参考に隠語について書いてみました。「閑所」「装物所」「高野山」「渡辺綱」これらは、或る場所の別のですが、何処か解りますか?正解はもう少し後にお知らせすることにして、正解の場所を余所の国では、何と表現するのかな?英米=ぶらぶらする社交場、詩人の座仏国=穴あき椅子、エスカルゴ独国=0号室伊国=身だしなみの部屋 そう、そろそろお解りいただけたでしょう。トイレ・便所のことです。閑所=文字通り、其処が淋しい場所だから。装物所=更衣室のことで、いにしえの貴族はトイ レにゆくたび、着替えをしていたようで す。高野山=これが洒落ています。山に行って髪 (=紙)を落とすに由来しています。渡辺綱=トイレには鬼が居るという伝えがあっ て、私も父から脅かされた記憶があり ます。 羅生門の鬼退治をしたのが渡辺綱だか ら、略してこう表現したのでしょうね。トイレの呼び名は古い順に、厠(カワヤ)、雪隠(セッチン)、手水(チョウズ)、御不浄などとなりますが、折角の隠語が一般的になり、浸透し尽くすと、別の隠語が考え出されたものと思われます。わたし達の日常生活と切っても切れないトイレだけでも、話は広がるものですね。
2015.02.05
コメント(0)
-
物真似上手だった寅さん♪
〇昨夜の某局では過去40年間の物真似秘蔵シーンの特集を組んでいて、懐かしくもあり、見応えもありました。 さて、堀切直人さんがまとめた渥美清さんの逸話は数えきれないほどですが、浅草フランス時代の彼の逸話として、アドリブに長けた人物で、例えば相手役が「命は貰った」と凄むと、「命っていうのは、落としたら絶対に拾えないという、あれのことですか」と聞き返したり、「昨日ウエスタン映画をみたよ」と相手が言えば「ウエスタ映画っていうのは、もしコロンブスが太平洋から上陸していたらイーストンと呼ばれたに違いない、アメリカ映画の一種のことですね」と糾してみたり、「おのれの妹は美少女ですね」と言われれば、「美の少ない女だから余ほどブスなんですね」と返したり、「おれはヤクザよ」と睨まられれば、「ああ、身体に日本画を描いていらっしゃるアーチストでおいでですか」と尊敬の表情で見返し、「顔を貸してもらおうか、顔を」と胸倉掴まられれば、「顔って、洗い忘れることはあっても置き忘れる心配は決してない、これのことでございますか」と頬に手を当てて見せたそうな。また自分に与えられたセリフが余り面白くない場合には、人気俳優の口調の物真似で喋り通すという離れ技も。榎本健一、徳川無声、片岡千恵蔵、阪東妻三郎や森繁久弥、そして大河内伝次郎までも。
2015.02.04
コメント(0)
-
黄金の茶室♪
〇大山崎には重要文化財が沢山ありますが、千利休が作ったとされる「待庵」は国宝に指定されています。往復ハガキで事前に予約が必要とされています。利休について書物を繰っている中で、秀吉公の黄金の茶室の件があったので、少し引用します。1586年9月、秀吉は宮中の小御所に黄金の茶室を持ち込み、天皇や親王方に手づから茶をたてました。吉田兼見は日記に前代見聞の見事さと記しています。それから4年後の九州名護屋城の茶会でこの茶室で雑煮を食べ、茶を飲んだ宗湛は、茶室から道具類までが黄金づくしだったと書き残しています。<金の御座敷のこと、平3畳なり。柱は金を延べて包み、敷居も鴨居も同前なり。壁は金を長さ7尺ほど、広さ5寸ほどずつに延べて雁木にしとみ候。縁の口に4枚の腰障子にして、骨と腰の板は金にして、赤き紋紗にてはりて、畳表は猩々緋、へりには金襴ー萌黄小紋・・・(宗湛日記)> 何かの催し物で一度、この黄金の茶室を見たことがありますが、明るい場所で見れば、なるほどけばけばしいものですが、”待庵”の内部を黄金づくしにしても、採光が充分では無いので、それほど派手ではないのかも知れません。(参考図書「京のかくれ話」児島孝一著)
2015.02.03
コメント(2)
-
芸談拾い読み♪
〇和田誠編の「芸談」から一つ二つ拾ってみます。文章は原型を留めないほど変えています。若山富三郎・・・長谷川一夫先生が侍姿の折、正座の右手がやや前に置かれている。いざと言う時に刀の柄に早く手が届くからと教わった。江利チエミ・・・乙女時代に進駐軍で歌い終わると7、8時だから、11時過ぎに終わるバンドの人に送って貰う都合で傍で聞いていたの。それがテネシーワルツ。哀れな時に憶えたのよ。勝新太郎・・・台本を貰ってから役づくりしていては遅い。日頃から自分の幅を広げておく、幾つかの抽斗から繋ぎあわせるようにする。小沢昭一・・・一人芝居の或る日、舞台の真ん前に盲導犬が居て、驚かしていけないなどと考えながら芝居していると妙に上って、失敗をしたけれど、その動転をよそに、大声を出す最後のシーンでは開き直って絶叫したところ、舞台監督から一番良い出来だったと褒められた。犬の御蔭で芸が進化した。勝新太郎氏の説は私も日頃念頭に置き、情報収集に貪欲でありたいと思っています。
2015.02.02
コメント(2)
-
のこちゃん体重日記♪
〇幼年時代を除いて青春期から高齢期に至るまで、人々は美容上、健康の上からも体重や体型に意識を捉われがちです。終戦から十年を経た時代の食べ物に、牛乳や肉を増やした献立の儘暮らして居れば、太り過ぎや血流等の病への心配も回避できたでしょうに・・・。 以前に一度この日記にも書いた記憶がありますが私の住んでいる市では、メタボリックシンドロームへの対策として掲題の「のこちゃん体重日記」という測定表を毎月更新しています。もうかれこれ5年ほど続けています。朝夕の体重を折れ線グラフ化、備考欄には歩数記録や各数値、食品などを付記しています。始めた当初は激減しましたが、現在は増加傾向になるのを必死に防ぐよう、常にエネルギーの消耗を考慮しながら生活しています。本実は月初から本部での例会俳句に参加。
2015.02.01
コメント(0)
全28件 (28件中 1-28件目)
1