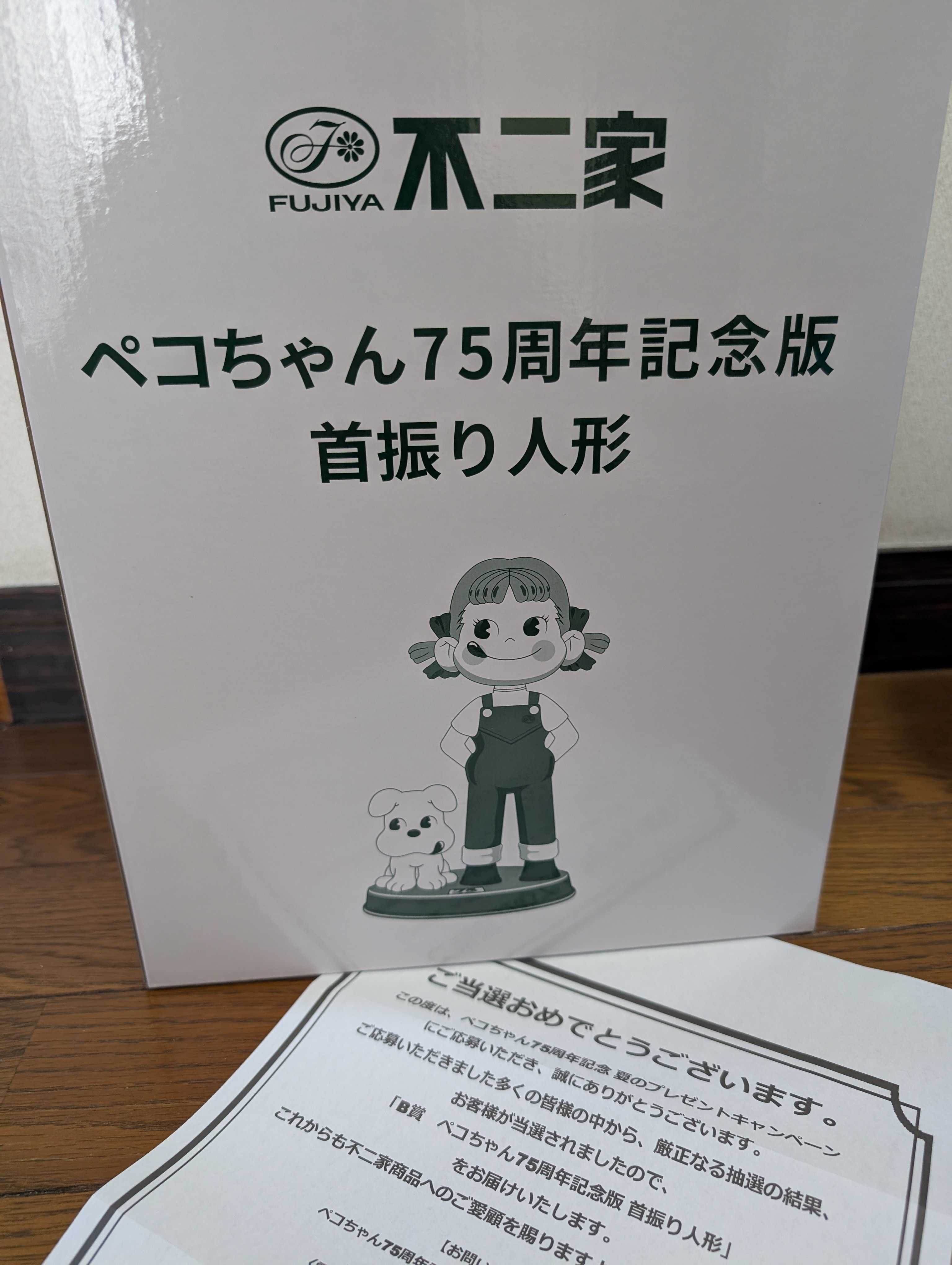2013年01月の記事
全33件 (33件中 1-33件目)
1
-
安倍総理のいう四つの危機
安倍総理は施政方針演説の中で四つの危機なるものをいっている。経済の危機、復興の危機、外交安全保障の危機、教育の危機である。経済の危機とおそらくそれと同様の復興の危機というのはわかる。しかしあとの二つはよくわからない。外交安全保障というのは為政者はいつの時代にも外敵の脅威をいいたてて国内をかためようとするが、それと似たようなものなのだろうか。教育の危機にいたってはいじめなどを例示しているが、こんなものは今に始まったことではない。あえて国家社会の危機というほどのものでもないだろう。学校を舞台にした暴行恐喝などは単に犯罪として処断すればよいだけの話で、そもそも教育問題として扱うことからして間違いではないのか。少年法改正だって検討すればよい。あの女子高生コンクリート殺人事件からだってすでに20年もたっているのに、なぜいつまでも終戦直後の浮浪児が跋扈していたような特殊な時代の特殊な法律が温存されているのか…その方が不思議である。*安倍総理のいう危機の中には貧困格差の是正というものは入っていない。外交安全保障や教育は危機として数えているのに貧困は危機に入れていない。小説「ロスノフスキ家の娘」というのにこんな場面がある。主人公の女性政治家が公園を歩いていると、退役軍人が乞食をやっているのをみかける。貧困層は外敵がくると拍手喝さいして迎えるに違いない…そう直感した彼女はさっそく困窮した退役軍人支援のための政策をまとめる。多くの貧困層をかかえる国というのは外敵の脅威に対しても非常に脆弱である。そしてまた教育の危機の中でとなえる学力低下。この背景にも親世代の貧困が影をおとしている。*貧困格差の問題を問題と認識できない総理はやはり問題である。ただそれとこの間の選挙結果、そして現政権の高支持率がどうもよくわからない。
2013年01月31日
コメント(4)
-
資産家夫婦殺人事件
資産家夫婦殺人事件が世をにぎわしている。資産家というけど、どんな経歴の方なのだろうかと思っていたが、やはりというか、思ったとおりというか、一代で資産を築いた方のようである。大学は親戚の家に寄留しながらアルバイトで学費をねん出したというので、バックもなにもかも無関係であろう。今の社会では能力や才能こそが最大の資産である。そしてこうしたものの多寡こそが神(自然とよび変えてもよい)の定めた身分制度であるのかもしれない。*能力や才能それに運や努力による格差を多くの人は当然と思っている。機会の平等は保障するが結果の平等は保障しないのが民主主義などという言説もマスコミにはあふれている。でも、そうした能力や才能によって途方もない格差ができてくるのをほっておいてよいのだろうか。アダムスミスのいった「神のみえざる手」などは働かない。能力のある者、小才のきく者、機敏な者は際限なく富を集積させ、社会は少数の冨者と多数の貧困層に分解していく。少し前までの身分による差、ちょっと前までにあった生まれた家の資産による差も合理的で仕方ないと思っていた人が沢山いた。しかしそれでも、格差が極限まで広がり、不満が鬱積すればいつかは爆発する。能力や才能による格差だって同様であろう。*あえて言ってしまえば、ワイドショーでこの事件の報道を見ている大衆心理も、18世紀フランスでギロチン処刑を見物していた大衆心理も似たようなものではないのだろうか。
2013年01月30日
コメント(18)
-
下見て暮せ、敵見て暮せ…
格差や貧困が広がり、困難な生活をしている人が増えれば増えるほど、新自由主義的な政党が力を増していくのは奇現象としか思えない。失業や就職難の問題は、深刻で高学歴ワーキングプアにみられるように学歴や偏差値だって生活の安定を保障しやしない。そうなれば誰にとっても貧困は他人事ではないはずなのだから、反貧困、反格差を標榜する政党が力を持ちそうなものだが、そうはならない。むしろ生活保護バッシングの方がますます勢いをまし、そうしたものが支持にむすびつく。明日のわが身という切迫感よりも、自分はまだそれよりもましという感覚の方が受け入れられやすいということなのだろう。上見て暮らすな下見て暮せ…江戸時代からすりこまれたこの庶民感覚は平成の今の世になってもまだ健在である。生活保護受給者を叩き、公務員を叩き、駆け込み退職をする先生を叩く。そして自分たちの生活をよくする政治家ではなく、「誰か」を叩き、「奴らの生活」を破壊する政治家を熱烈に支持する。人気を得る政治家の要件は理想を語ることでも、あるべき社会の姿を提示することでもない。攻撃しやすい目標をみつけ、それを不満のうっぷん晴らしの標的にし、思いっきりメディアに露出してかっこよく演説している姿をみせることである。
2013年01月29日
コメント(12)
-
源氏物語の女君
本の整理をした結果、最後まで捨てずにのこったものの一つは「源氏物語」だ。さらにこれに付随して漫画「あさきゆめみし」も源氏の世界を視覚化した大変な名作であると思うので、これもとっておいてある。*今日は読書家の永遠の話題、これをもちだせばもりあがること必至のテーマ、源氏物語の中で好きな女君について書いてみる。初めて源氏物語を読んだ頃には葵上が一番気に入っていた。恋愛心理はわからないことも多かったのだが、葵上のプライドの高さ故の不器用さは高校生にも十分に理解できた。意識すればするほど打ち解けるきっかけを失ってしまう。そうした人間関係の機微はどんなものにもある。でもさいきん読み返してみたら、葵上もよいのだが、花散里の君もよい。光源氏が須磨に落ちゆく前に最後にあった女人で、いわば逆境にあるときに一番会いたくなる女性である。雨の日の友は真の友なんていう言葉があるが、彼女こそ最も近いところにいた女性だったのかもしれない。それに見栄えもよくなく、ひかえ目で、人に際立った点があるという描写はないのだが、教養や知性はあり、実子夕霧の養育をまかされている。夕霧の母親格として六条院の一角に住み、40の賀でも正妻格の扱いをうけているので、器量のわりにはたいへんな厚遇である。*源氏物語はよく誤解されているのだが決して美女だけの物語ではない。物語の役割に比べ登場場面の多い空蝉は「わろきによれるかたち」とどっちかといえばブスだと書いてあるし、実質的なヒロインではないかとも思う明石上も「この娘よきかたちならねど」と際立った美人というほどでもないとある。花散里は見栄えのしない容貌だと何度も書かれているし、末摘花にいたっては醜い容貌が詳細に描写されている。そういう女性達を光源氏は最後まで後ろ見をし、幸福にした。源氏物語というのは女性が書いた女性の願望の物語であるともいえる。*それでは源氏物語でなりたいヒロインといえば誰であろうか。実は源氏物語には脇役ながら大変に幸い者の女性がいる。五節君である。源氏の腹心の部下唯光の自慢の娘であり、際立った美貌と才気で女房として宮中で働く。そしてまた、実生活では位人臣を極めた夕霧の側女として多くの子供を生む。その子供たちについては、わざわざ正妻雲居雁の子供たちよりも容貌才気ともに勝っているとまである。彼女の娘の六君は匂宮の正妻として迎えられるので将来は中宮となる可能性が高い。源氏物語は中流貴族の娘明石上のサクセスストーリーという読み方もできるのであるが、そうした中流貴族の娘のサクセスはまだまだ続きそうな余韻をもって物語は終わる。自分がもしなるとしたら…迷うことなく五節君だろう。
2013年01月28日
コメント(0)
-
安倍政権の高支持率
麻生政権末期のときは生活保護の母子加算の廃止がごうごうたる非難をよんだ。それにひきかえ母子加算どころか生活保護費そのものを削減した現政権がそれほど批判されないのはどういうわけなのだろうか。わずか数年で社会の雰囲気はこれだけ変わるものなのか。それとも素人同然の民主党クズ政権に嫌気のさした後では自民党政権だというだけで期待が高まるのか。第二期安倍政権は高支持率を保ったまま、マスコミとの友好関係も維持している。*正直いって最近政治ネタを書く気がおきない。既定路線となった消費税増税だけでなく、規制緩和による成長政策。こうした格差や貧困を拡大する施策を多くの人が支持する不思議。そしてその一方で反格差、反貧困の声はどんどんとすみにおいやられていくようだ。蟹工船と小林多喜二ブーム、そして官邸をつつんだ「あじさい革命」。あれはいったい何だったのだろうか。*右とか左とかいう区分はあまり意味がないと思うし、ネトウヨとかブサヨとかといったレッテル貼りも嫌いだ。ただ、最近、一部のサイトで他国人を非難する論調がめだつように思う。中には、週刊新潮の最後に掲載されているコラムを思わせる内容で、よく書けているものもあるのだが、こうした論調がでてくるほど今の日本人は自信にあふれているのだろうか。http://nezu621.blog7.fc2.com/むしろ逆のように思う。国際政治の舞台での発言力は中国に遠く及ばないし、GNPでもすでに抜かれている。そして経済競争や文化による競争では韓国に逆転されつつある。そうした自信のなさが対外的な強硬姿勢を示しているようにみえる安倍政権の支持へとつながっているのなら危険な兆候ではないのだろうか。
2013年01月28日
コメント(10)
-
断捨離について
最近片づけというか断捨離とががブームのようである。いろいろと物をためこんだが、不要なものばかりで片付かないと感じている人がおおいからだろう。人はなぜ収集をしたがるのかについてはいろいろと説があるのだが、人はなぜ捨てたがるのかについてはあまり言っているひとがいないように思う。ことは単なる片づけとかときめきだけではない。たぶん捨てるという行為はリセットと同義の面があるのではないか。今までの衣服、本を一度にどっと捨てることによって過去に決別し、新しい自分に生まれ変わる。断捨離の背景にはそんな願望がきっとある。*最近本の整理を始めた。つくづく思うのは手元にある本というものはよまないものだということだ。書き捨て読み捨ての著名人の人生論(テープ起こしの雑談?)をまとめた新書だけではなく、名作とか古典というものも同様である。思い切ってこうしたものを捨てよう。新しい蔵書はこれから作ればよい。その蔵書は別に部屋を占拠する紙の塊である必要はない。図書館で借りて、表題と感想をネットに書いておいてもよい。そうした形の蔵書だってあってもよい。
2013年01月27日
コメント(11)
-
教師のかけこみ退職に思う
やはりというか思ったとおりというか消費税8%増税時には軽減税率は導入されないという。かわりに低所得者には現金給付を行なうというが、なんかこれって石原知事が派遣村を作った時に入所者に小金を渡したのを連想させる。どうせその後で週刊誌がパチンコ特需とかさんざん書きそうである。一時的な小金のバラマキが生活支援になるとも思えず、むしろこうした前例ができると、選挙前の小金バラマキなどが行なわれるようになるだけではないか。それよりも政府が物価上昇を目標とし、消費税増税もほぼ既定路線となっているのに、生活保護費が1割も削減されることの方が怖ろしい…。それも軽減税率なしで。*( お富さんの節があうのでは) 飢死か牢屋かそれとも過労死 それがいやならフクイチか~♪ いったはずだよあの選挙 肉屋に包丁わたしたからには、これでしまいだおだぶつだ~ や~れそれ 国防軍 上がる物価に下がるは給料 おいうちかけるは消費税~♪ いったはずだよあの選挙 肉屋に包丁わたしたからには、飢えも凍えも身からさび や~れそれ 雇い止め*教師のかけこみ退職を批判する声は多いようだが、それをいうなら2月からの退職金減額なんていう制度自体がおかしい。2月余計に働くと退職金が100万単位で減るのであれば、かけこみ退職はむしろ想定内ではないか。先頭にたって批判している政治家に問いたい…貴方はそんな批判をするほど無私の人間なのかと。我欲と権力欲にまみれて、弱い立場の者をふみつけているような人がここぞとばかりに教師聖職論をもちだすのは笑止千万。駆け込み退職などは1月から退職金が減額された公務員だってやっているのではないか。教師は公務員と違って天下り先などはない。**教師は聖職だと言われだしたのは明治時代からだったと思う。明治維新は武士という階層の大量失業で幕をあけた。勝ち組の武士は官途についた。文官そして武官である軍人である。そこからこぼれた元武士は教師や巡査になった。さらにそこからもこぼれれば没落士族に…。だからある意味、教師や巡査は官吏からみれば武士の負け組だったといえるのかもしれない。負け組が不満をつのらすと大変。そこでなだめる必要があるが、財政難の明治政府では金を出すことはできない。巡査の給料はたった9円でこれでは食えんといわれたが、教師だって薄給では似たようなものだったろう。そこで考え出されたのは上手に元武士というプライドを生かしながら精神的になだめるやり方である。昔の警察手帳には巡査は無知な人民を教え導く家長のようなものという記述があったらしいが、教師聖職論だって似たようなものだろう。聖職という語は主に小学校教師についていわれ、大学教師は聖職なんて誰も言わない。聖職なんて言葉がでてくるときはろくなときではない。たっぷりと給料をもらっている政治家やマスコミ人士が教師のかけこみ退職を許せないなんていうのも然りである。
2013年01月26日
コメント(16)
-
貧困国に転落する日本
政府は国家公務員の給料だけではなく、地方公務員の退職金まで下げようと必死になっている。公務員と言ったってそのかなりの部分は現業職で民間よりも給与は低い人だって大勢いる。公務員の給与が下がれば民間で追随して下げるところもでてくることだろう。そして生活保護の引き下げ…これはある意味、貧困の底が抜けるような政策で、最低賃金もこれで上昇する可能性はなくなる。一方で政府は物価値上げを目標にし、軽減税率なしの消費税増税も規定路線になっている。物価上昇や消費税増税は実質的には所得減と同じなので、これで貧困層はますます首がしめられることになる。民主党の素人政治以下の酷政が進行中である。*言葉には要注意。問題は被害者の実名報道の是非ではない。被害者あるいは遺族の意に反する実名報道の是非というべきであろう。
2013年01月25日
コメント(12)
-
被害者名の非公表と腹話術文化人
アルジェリアの人質事件で被害者の氏名非公表をめぐって各新聞には「専門家」の懸念や批判が掲載されている。こういうコメントをみると腹話術の人形を連想する。マスコミにのっかって日銭をかせいでいる人々が、こうしたときにはここぞとばかりにマスコミよりのコメントを垂れ流す「腹話術文化人」…。また、マスコミによっては批判されにくい人々の困惑を前面にだしているところもある。どっかの新聞では被害者が所属していた会社に友人がいるという人々の声を集め、安否がわからず不安だという記事を掲載した。被害者の遺族や家族からしかるべき人には連絡がいくはずなので、こうした友人たちの困惑や不安というのもあまり説得力がない。未解決の殺人事件で情報提供のために被害者の氏名を公表する必要がある場合はあっても、こうした事件で被害者の氏名を公表する理由などはない。帰国した被害者や亡くなった被害者遺族をマスコミが追い回し「風呂に入りたい」だの「味噌汁がのみたい」だのといったコメントをつかんで記事を書き、涙にくれる遺族に「今のお気持ちは」とか「お父さんの想い出は」とかききながらマイクを向ける。そして、しばらくはワイドショーのネタにもしたうえで、忘れていく。こんなことにどんな社会的意義があるというのだろうか。*しょもない住所や氏名の流出には個人情報流出だといって騒ぐ人々が。犯罪被害者のプライバシーに鈍感なのは理解に苦しむ。過去の報道などを思い起こしてみても、マスコミの報道というのは一種の言論テロとでもいうべきものではないかと思う。記憶しているものをざっと書いてみる。あの殺人事件の被害者となった東電OLについての集中豪雨のような私生活報道。長期監禁事件の被害者となった女性についての自宅上空にヘリコプターをとばしてまでの取材合戦。沖縄の暴行被害者の職場に押し掛け写真まで撮ろうとした写真週刊誌の報道。(これについては「報道加害の現場を歩く」という本にも記載されている。http://www.shahyo.com/mokuroku/gendai_shahyo/media/ISBN978-4-7845-1434-2.php)同じく沖縄で女子小学生が被害に遭った事件で女児の通っていた小学校の校門の前で子供たちに取材をした報道。イタリアで女子大生6人が犯罪被害にあった事件で被害者のバッシングをした上に学校名を公表した週刊誌報道。特に被害者が未成年の女性であるような事件では、ただでさえ立ち直るのが本当に大変だと思うのだが、そうした被害者に対し、まるで倒れている人の背中に鞭をうつような下司な報道をした上に、「これからの厳しい人生」だの「人生を破壊された」だのというコメントを何度も垂れ流す。事故などで重篤な後遺症を負った人に対して、「もうあなたの人生はおしまいですね」なんていうコメントは決して言わないのに、なぜ犯罪被害者に対しては平気で人生終了宣言をするのだろうか。不思議である。こういうのをテロとよばないのなら、何と言えばよいのだろう。*これからはマスコミはテロ被害者の実名が報じられている外国の例などをひきあいに、日本政府や会社の秘密主義を批判するかもしれない。しかしながら、日本と外国とでは社会の雰囲気も、そしてマスコミの在り方もまるで違うだろう。参考にはならない。
2013年01月24日
コメント(22)
-
遺族の意思に反する実名報道
アルジェリアの人質事件で被害にあわれた方の氏名は家族の強い意志等で公表されてこなかった。それにもかかわらずマスコミ各社は被害者の氏名をつきとめ、遺族に取材を試み、報道もしているという。これに対するマスコミの自己弁護が酷い。なにしろ、報道しなければ犠牲者の生きた証が残せないとか、氏名を公表することで「弔いになる」なんて言っているらしい。http://www.enpitu.ne.jp/usr4/45126/diary.html*いうまでもないことだが、人間には善い面もあれば悪い面もある。不幸な人がいれば同情するのも人間の性だが、他人の不幸は蜜の味というのもまた人間の一面である。そうでなくとも、その不幸が犯罪被害など希有なものであれば好奇の目でみる人がいるのも事実だ。営利企業であるマスコミは、こうした人間性の負の側面にのっかって金儲けをしている面があるということをもっと自覚した方がよい。生きた証だの弔いだのと心にもないことをいうのをやめて…。このあたりは「知る権利に応えるばかりでなく、読者の知りたい興味に応えるのも週刊誌の役割」といっていたある出版社の幹部の言葉の方がはるかに正直である。*アルジェリアの人質事件に限らず、犯罪報道では被害者の氏名公表にはもっと慎重であるべきだろう。犯罪を起こした側が報道されるのは自業自得の面もあるが、被害者は意図して被害者になったわけではない。今回の報道でも被害者の実名を報じたマスコミはもっと批判されてもよい。**実名…といえばもう一つ、実名の絶対に報道されない人びとがいる。フクシマ50とよばれる事故当時に原発に残った作業員やその後の事故収束にあたっている原発作業員の方々である。そこで疑問がわく。原発作業員であるということは、それほど社会に知られたくないことなのだろうか。そしてまたこの実名がでないということは本当に作業員自身の意思なのだろうか。実名が報道されないということは社会から見えないということでもある。社会から見えないということは、その中で病気になった人がいても、社会は知りようがないということである。福島原発の事故当時の所長は病気で療養中だというが、原発事故作業員の方の中で病気になった人はいないのだろうか。高濃度の被曝や、線量計に鉛のカバーをつけていたなどの事実が報道されたが、その後の健康被害の有無をフォローした報道はない。本人の意図に反する実名報道は控えるべきであるにしても、こうしたことこそマスコミは追及すべきではないのだろうか。
2013年01月23日
コメント(6)
-
アベノミクスという災厄
アベノミクスなる経済政策が話題となっているが、これは市場にじゃぶじゃぶ金を流して円安物価高を誘導する政策で、これをやればたしかに株は上がり、名目上の企業の業績はよくなるだろう。ただそれはあくまでも名目上で実態経済がよくなるわけではない。そしてさらに問題なのは、こうした物価高と名目上の利益高が給与に反映されるわけではないということだ。正社員が当然で企業一家ともいわれた時代と非正規雇用が一般的となった今日とでは状況が違う。多くの人、特に貧困層や貯金の取り崩しや年金で暮らしている層はインフレによって大きな打撃を受けるのは必至である。ましてや生活保護も切り下げられるので最低賃金の上昇も期待できないとなればなおさらだ。そしてこれに名目上の好景気を理由にして消費税が追い打ちをかける。物価ではなく景気を導入の指標にしたのはこうしたことも念頭においていたのだろうか。かくしてこの政権の下でますます貧困格差の酷い社会となっていく。*非常にファジーな言葉でリベラルという言葉がある。社会主義に対比する意味で自由主義という言葉が使われたことがあり、そうしてみるとこのリベラルはそういう意味のようにもみえるが、実際には再分配重視、経済的弱者重視の立場をリベラルというらしい。今の日本でこうした経済的弱者重視といえるような政治勢力はあるのだろうか。公務員を叩いてうっぷんばらしをするような政策をだしているところは、たとえ経済的弱者の支持を得ていたとしても、リベラルとはいえない。また、いかに主張する政策の中に経済的弱者のためのものがあったとしても、そういう人々に訴える力のない政治勢力もリベラルとはいえないだろう。寒くて腹のへっている人に訴えるのであれば温かい具だくさんスープを前面にだして提示しなければならず、きれいなアイスケーキばかりを前面にだしても訴えるわけもない。「反原発」も直接自分の懐にひびくわけでもなく、しょせんはアイスケーキだったのだろう。案外、今の状況をみているとこういう役割を果たしているのは公明党なのではないか。もちろんこの政党には宗教団体が関係しているが、宗教とは関係なしに、経済的弱者であるという理由でこの政党を支持している人も増えているように思う。現実の経済的困窮者の声に耳を傾け、そうした人々に訴える主張をし、それを与党の懐に入って実現していく。それも実際の金銭給付や検診のクーポンであるだけに非常にわかりやすい。経済的弱者にとっては、せいぜいこの程度のものしかないというのは不幸といえば不幸なことなのだが。
2013年01月22日
コメント(6)
-
大学不認可で真紀子バッシング、入試中止の橋下にはダンマリ~マスコミのダブスタ
橋本市長は体罰が問題となった高校の入試中止という方針をいまだに崩していない。問題となった市立高校はスポーツの名門校だという。ことのよしあしは別にしてスポーツを武器に有利な進学や就職をしようと考えている子にとっては、この高校の入試の有無は死活問題ではないのだろうか。それに今は1月。私立スポーツ高に進学するだけの財力のない家庭では、途方にくれているケースもあるだろう。田中元文部大臣の不認可騒動のときには、「あの新設大学をめざす受験生」の存在を前面におしたてて、若者の夢をつぶすだの、受験生を混乱させるだのと、全マスコミこぞって、ピーピーキーキー真紀子バッシングの大合唱であった。それなのに今回は橋下批判のマスコミ合唱が聞こえてこないのはどういうわけなのだろう。Fランク大学の新設よりも受験生に与える影響ははるかに深刻なのに…。おそらく最後の最後で橋下は入試中止をひっこめる。そしてマスコミはその「英断」をもてはやす。あのコスプレ不倫騒動で、橋下の危機管理をほめたようにマスコミと橋下の蜜月はまだまだ続く。首長と中央政界の政治家との二足のわらじも、落ち目の滋賀県知事についてはぶったたいても、橋下市長には何もいわない。はっきりいって維新の風も橋下人気も半ばはマスコミが煽っているようなものだろう。後の半分は公務員バッシングに対する快感で、それはみんなの党と変わらない。
2013年01月21日
コメント(12)
-
続・教育再生会議に思うこと
財政や経済論議に比べると教育論議は閾が低い。誰しも受験や成績が切実な問題だった時期を経てきており、それだけに教育については多くの人が一家言をもっている。それは政治家だって同様だろう。だからいっちゃあなんだが財政や経済など理解できそうもないような政治家ほど教育論議をしたがる。それだけが理由ではないのだろうが、過去にも多くの教育改革のための有識者会議や諮問機関がたちあげられてきた。*ただこうした政治家主導の教育改革についてはいつも思うことがある。そもそもこうした教育改革論議でいう教育とは何のためにあるのだろう。どうもみていると国家のための教育、産業のための教育ということがあまりにも前面にですぎて個々の子供の幸福のための教育という視点がないがしろにされているように思う。いわば上から目線の教育論議ばかりで下から目線の教育論議がない。下から目線でいえば、いかにしてより多くの子供たちに生きていくために必要な学力を身に着けさせることができるか、そしてまたその必要な学力にはどのようなものが含まれるかということにつきる。それなのに現実の論議をみると、国家や伝統、そして家族といった個人の価値観にわたる分野を、教育の問題としてとりあげている。こうしたことは、今のような情報化時代に学校教育の場だけで、子供たちに一律に植え付けることなどはとうてい不可能である。それともそれを可能にする方法があるとでも思っているのだろうか。子供たちを「余計な情報」から遮断するために、ネット情報を規制したり、子供、特に大衆予備軍の子供には「余計な知識」を得させないために英語教育を手抜きするとか。そして学校ではひたすら日本の伝統は素晴らしいとか日本の貧困はアフリカに比べればマシとか、困窮者がいれば家族親族で助け合えと教える。まさかとは思うけど…。*教育再生会議については、さらに疑問がある。現在の政策課題には様々なものがあり、「教育」はそれほど喫緊の課題なのだろうか。コメントをくださる自律神経失調症さんのいうように「生活保護受給者の増加、低賃金の過酷労働、まともに就職もできない新卒者、仕事もパートかアルバイト、こずかい稼ぎにしかならない」ことが最大の問題であるように思う。そしてまたこうした問題は国民、あるいは民族の質にも関連する。人の成長は学校だけで終わるものではない。職場で時間を守ることや嫌な奴にも挨拶することを学び、人との信頼の大切さを学び、職業的知識を身につけることで成長していく。就職という社会へのとば口で面接不採用が続き自己への否定的評価に悩む人、過酷労働で自己研さんの時間もない人、40を超えても親のスネをかじっている人…今増えているのはこうした人々である。結果として待つものは民族の劣化であり、ひいては社会の劣化や国力の低下ではないのだろうか。
2013年01月20日
コメント(11)
-
教育再生会議のことなど
中国の兵法書『六韜(りくとう』にこんな言葉があるという。「隣国の無能を歓待し褒めたたえ、有能な人間は批判せよ。そうすれば無能が持て囃されて、有能なものは滅ぶ」ルーピーが歓待されているのも納得…。*安倍総理は教育なんたら会議を立ち上げたようだが、今の教育の何が問題だというのだろう。学校を舞台にした恐喝、暴行、強要といった生徒間の犯罪は犯罪行為として処断すればよいだけの話で、これを「教育の問題」として、学校内で教師が解決しようとしているところにそもそもの問題があるのではないか。不可能なことを期待すれば期待された方はひたすら隠ぺいにはしるしかない。あたりまえのことである。また、最近急に問題視されるようになった体罰だって犯罪として扱えばよいだけのことだろう。それにガキ集団による犯罪と異なり、教師の体罰なるものは普通の教室ではすっかり影をひそめている。今回問題になった件は運動部という特殊な空間で悪しき習慣が生き残っていたものにすぎないのではないか。旧軍ではビンタなどの暴力が横行していたことは有名であるし、警察寮でリンチがあったなんていう報道も記憶に新しい。こういうのは元プロレスラーのビンタを喜んで受ける人がいるように、被害者側からも容認されている部分があって、根強く残ってきたのだろうが、一般社会では暴力は犯罪である。*そのほかの教育の問題としては学力低下などもあるのだろうが、その背景には親世代の生活苦や高偏差値ですら就職を保障しない雇用環境の厳しさがある。どうみても問題の本丸は教育ではなく、雇用や就労の問題だと思うのだが、新総理はこちらの方には熱心にとりくむようにはみえない。韓国でも若者の就職難は深刻であるという。ただ、韓国のパックネ次期大統領は、その対策として青年の海外での就労支援を打ち出している。民主党政権時代の介護や林業による雇用創出、そして現政権の無策よりも、目のつけどころは百倍、千倍もよい。**厚労省の推計によると生来的には「一人暮らし」が主流となり「夫婦と子世帯」はますます少なくなるという。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130118-00000139-jij-soci&pos=4今だって「夫婦と子世帯」といったって、「くれよんしんちゃん」や「ひなちゃん」のような家は少数派で、でかくなった独身の娘息子との同居がほとんでないか。そしてときには、その独身娘や息子は、ワーキングプアやニートだったりする。しんちゃんやひなちゃんのほのぼのとは異なり、中年になろうとする娘息子と親との間には諍いが絶えない。そんな諍いが発展したような事件が最近ますます目につく。**選挙以来政治ネタは書く気が起きない。肉屋がいかに豚をきりきざんでいくかのような憂鬱な話しかでてきそうにないから。新政権はじゃぶじゃぶ国債を発行して金を市場にまいているようだが、これは札を刷って市場にまいているのと同じなので、いずれは物価が上がっていくことだろう。これに消費税が追い打ちをかけ、もちろん軽減税率などは無視される。一方で公務員の給与が下がれば追随して給与を下げる民間企業がでる。生活保護支給基準は最低賃金に連動するのでますます最低賃金も下がる。結果的に貧困層はますます追い詰められていくというだけのことだ。そしてそんな貧困は誰にとっても他人事なんかではない。ホームレスでさえ、そのかなりの部分は正社員として勤務した経歴のある人だそうである。
2013年01月19日
コメント(10)
-
体罰についての報道に思うこと
大阪市の某高校の体罰が連日の大ニュースになっている。そしてこれに関連して橋下市長が当該高校に入試中止を要請しているという。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130117-00000039-asahi-sociおかしいのはマスコミの報道ぶりだ。かつて田中大臣が大学を不認可にしたときには、「あの大学を目指していた若者の夢を奪う」といった調子での非難々々の大合唱だった。時期的には普通の受験生は志望校も決まっていないような頃であったにもかかわらず…。それにひきかえ今回はどうだろうか。それこそスポーツでは有名なあの高校を目指して必死に勉強をしている若者もいるだろうが、そうした「若者の夢」はどうなるのだろう。秋に新設大学の不認可をした田中文部大臣は「若者の夢」を奪うけしからんオバサンなのだが、今回の橋下市長はよいのだろうか。マスコミの報道はかくも恣意的だ。今のところ風にのっかっている橋下は叩かず、バッシングがトレンドになっていた田中元大臣なら叩く。*体罰が大問題のように連日報道されているが、素人目にみれば、そんな部活はやめればよいだけどのことであるし、それでも問題だと思えば警察に被害届を行なうこともできたのではないか。少なくとも、逃げ場のない状況で執拗に暴力をうけるような、生徒間の校内犯罪(マスコミでの呼び名は「いじめ」)事案とは性格が異なる。あくまでも特殊な体育系部活の閉じた空間の中で起こった特殊な事案のようにもみえる。**だいたい昔から思っていることなのだが、世の中ではスポーツを美化しすぎる。勉強に打ち込むのはガリ勉で性格が歪んでいるかのように言い、スポーツに打ち込むのはひたむきで純粋な青春だともてはやす。学力での序列化やクラス分けは批判するのに、スポーツでの序列は当然視する。裏口入学には眼の色をかえて批判するのに、学力の怪しいスポーツ推薦は当然のようにまかりとおる。本当はそうしたことも問題なのではないのだろうか。
2013年01月18日
コメント(14)
-
空襲被害国家賠償訴訟
空襲被害に対して国家賠償を求めていた裁判で原告側が敗訴したという。国のために軍人となって戦場に行ったことにより被った被害には酬いるけど、敵国による被害は補償しない…国家とはそうしたものなのだろう。空襲による被害を被った人の中には戦場行きをまぬがれ、本土にとどまっていた者もいた。たとえ被害をうけたとしても、軍人など国家のために何かをやってきた人の補償の方が優先される。http://osakanet.web.fc2.com/osaka-kusyu/*戦争による被害は大きい。実際に戦場にいった軍人(兵)だけではなく、空襲による被害もある。ソ連侵攻後の大陸や日本領土だった樺太での被害も大きい。それに核爆弾による被害や戦後の進駐軍による犯罪被害もある。戦争未亡人はもちろん結婚の機会を逸した女性だって戦争による被害者だろう。そうしたものも含めて、もう戦争はいやだと思ったのが昭和20年代の頃の人々の素直な気持ちだったはずである。現憲法が制定されたとき人々は熱烈に歓迎した。中味も知らずに提灯行列をやった明治憲法のときとは大きな違いである。草の根の国民レベルでみたとき、いったいどっちが「押しつけ憲法」だったのだろうか。*民主党政権のときには財政危機があれほどに叫ばれ、マスコミもなにかあるとすぐに「日本もギリシャのようになっちゃうぞ」と警鐘をならしていた。それなのに現政権が兆単位の金をじゃぶじゃぶ注ぎ込んで「経済対策」をやることについては好意的に報道する。兆単位の公金をつぎこんでいるということは金を市場にまくのと同じなので、株価だけではなく、物価もそのうちに上がっていくことだろう。そしてその一方で生活保護は削減するという。ただでさえぎりぎりの生活をしている人に対し、金額を削減し、そのうえ、物価があがるとなれば、ダブルパンチである。それだけではなく、水際作戦なるものも強化されていることだろう。今までは貧者の暴動などは無縁であったが、今後はそうしたものも頻発するようになるのかもしれない。生活保護を断られた人が暴れたという想定の訓練をどっかの役所がやったといって話題になったが、実際にそうしたこともありうるであろう。
2013年01月17日
コメント(6)
-
厄年を迎えるロスジェネ世代
世に言い伝えや迷信は様々であるがいまなお根強く残っているものに厄年というものがある。男性は数え25歳・42歳・61歳、女性は数え19歳・33歳・37歳・61歳が「本厄」とされ、特に男性の42歳、女性の33歳は「大厄」とされている。世にこれほど喧伝されているからには、やはりそこにはなにかしらの根拠があるのだろう。女性の19歳、33歳、37歳は異性関係のトラブルや出産による障害や婦人科系の病気の起こりやすい時期でなんとなくわかる。男性についても25歳というのは集団の中での責任ある地位に就き始める時期でいわば人生の大きな関門を迎えるときなのであり、それにともなう問題も多い時期だろう。それでは42歳というのは何なのだろうか。これもいってみれば人生の先が見え始める時期で、この時期に焦ったりして身を誤るという例が古来多かったのではないのだろうか。気のせいかもしれないが、新聞などをみていると犯罪を起こす年齢には、わりあいこの近辺が多いようにも見える。*ロスジェネともいわれる就職氷河期世代の先頭がそろそろこの厄年を迎える。非正規雇用やワーキングプアや無業者の多い年齢層であり、そうした人々の先頭世代が後戻りのきかない年代にさしかかってくるわけである。今までは若者の就職支援という枠でこうした世代を支援していればよかった。苦しくても将来の希望はまだある。そうしたことで本人も周囲も納得していた部分はあったのではないか。ところが次第にそうもいっていられなくなる。オレの人生このままかよ…こんなあせりがうねりのようにわきおこってくるのはこれからである。さらにいえば彼らの親世代が本格的に高齢化し、彼らを支え切れなくなる事例も増えてくる。犯罪の頻発、生活保護の激増、年金詐取事件の日常化。このほかにも様々な予期せぬ事態が起きるのかもしれない。*また、この世代に限ったことではないが、低収入や無業者にとって親の相続財産は唯一の命綱ということもある。都会の一戸建てであれば数千万くらいになるところはざらだが、そうした財産も倹約して使えば十年以上の生活費になる。相続課税強化の話もあるが、これもこうした財産に頼らざるをえない人々にとっては脅威ではないか。莫大な相続財産を有する人は社会的強者であるが、そこそこの相続財産を命綱にしなければならない人は必ずしも社会的強者とはいえない。
2013年01月16日
コメント(2)
-
予科練平和記念館
予科練平和記念館に行ってきた。特攻関係の展示は正直涙なくしてはみられない。崇高な英雄か戦争の犠牲者か…特攻戦没者についてはいろいろな見方があるだろう。ただ、国民を愛している国家であれば決してあのような戦法はとらなかったはずだ。散発的な特攻戦術は日本以外にもあるが、国家をあげて組織的に特攻を行なったのは日本だけである。ナチドイツもやらなかった。*戦前の日本は国民を愛した国家だったのだろうか。明治憲法は国民に知られないように極秘裏に制定された。伊藤博文はじめとする当代の秀才4人が夏島の別荘にこもり、草案を練った。4人に接触したのは女中だけであったが、むろん女中は漏れ聞こえる法学論争を聴いてもなにもわからない。憲法発布の際には民衆は絹布の法被が支給されると勘違いして大いに喜んだそうである。それに比べると、今の日本国憲法の制定に関与したゴードン女史は日本女性の窮状をみて日本にも女性の権利を根付かせたいという情熱をもっていたという。少なくともその方にかぎっていえば明治憲法を制定した4人の誰よりも日本人(日本の庶民、大衆)を愛していたのではないか。*今また憲法改正の議論を行なう政治家が増えてきている。彼らをみていて思う。あの方達は日本国民を愛しているのだろうか。
2013年01月15日
コメント(12)
-
テレビの想い出
漫画について書いたので今日はテレビ番組についてなど…。はじめてテレビが家にやってきた日のことを覚えている。テレビは三つあった部屋のうち一番いい部屋の一番いい場所に置かれた。テレビを見るときには必ず部屋の電気を消して家族皆で見た。今のようになんとなくつけているというものではなく、家庭映画館という趣だったのだ。テレビを消した後は画面にカバーをつけておき、今度テレビを見られるのはいつかな~と思ったものだ。テレビはいつでもみられるものではなく、チャンネル権は父がもっていた。最初の頃は隣の子がよくテレビを身に家にやってきた。まもなく隣の家もテレビを買ったのでテレビを見るためだけに家にくることはなくなった。*最初に見たテレビ番組で覚えているのは「チロりん村と胡桃の木」。むかしながらのやさい村の生活とモダンなくだもの町の生活が対比されていた面白い人形劇だったが、その頃は実際にも、農村には伝統的な生活様式が残り、都市では別の生活文化が起こってきたような時代だったように思う。都市では普通にクリスマスを祝っていたが、田舎の祖母はクリスマスを知らなかった。小学校に行く頃にはテレビのない家はほとんどなかった。昨日のプロレスやプロ野球がクラスの話題になり、空手チョップのまねをしてみせる子もけっこういた。あの頃は、夕食時には毎日テレビをみていたように思う。うろ覚えだが、月曜日は「不思議なパック」、火曜日は「はてな劇場」、土曜日は「物知り博士」だったか…。「不思議なパック」はテレビをみながらパックがなにものか本当に不思議だった。当時人気だった外国ドラマはあまり見なかったので、後は印象に残っているのは「忍者舞台月光」と「鉄腕アトム」くらいか。「忍者舞台月光」では仲間が銃を使おうとすると必ず隊長が「拳銃は最後の武器だ」と言って止めていた。飛び道具は卑怯だというのが日本の伝統のようである。拳銃を使えばすぐに方がつくのに…ばかばかしい。「鉄腕アトム」は毎週夢中になって見ていたが、異次元、ロボット、時間旅行、宇宙など様々なSF的アイディアがとっかえひっかえでてきて飽きなかった。その後、テレビが原作に追いつき、オリジナルの話をやるようになってからは次第につまらなくなり、テレビからも離れていった。そういえばテレビ史上の最高視聴率は東京オリンピックの女子バレーの決勝だったというが、あのときは授業時間中にもかかわらず、教室のテレビで先生ともども皆で見ていた。バレーのルールもなんかよくわからなかったし、つまらなかった。あの決勝戦の時間はネットで調べてもよくわからない。映画「三丁目の夕日」では夜になっていたが、どうも家で見ていた記憶はなく、学校でみた記憶だけが残っている。
2013年01月14日
コメント(8)
-
漫画の想い出~手塚治虫の漫画
昨日に続いて漫画の想い出などを書いてみる。子供の頃読んだ漫画を想い出してみると、やはり手塚治虫のものが別格であったように思う。手塚漫画の最初の記憶は床屋や歯医者の待合室で読んだゼロマンであったが、人間と人間によく似た高等生物0マン族(リスから進化した地球に住む生物という設定)との争いというスケールの大きな話は圧巻であり、寒冷都市と化した世界で主人公に次々と襲いかかる危機には目が離せなかった。その後の「ワンダースリー」などの連載も楽しみであったし、とにかく手塚漫画をリアルタイムで読むことができたというのは大変な幸福であったと思う。*手塚治虫の漫画というと、平和主義といったイメージが強いし、たしかにそういう面もあるのだが、その平和主義をさらにつきつめていくと、国家や民族といったものに対する虚無的な見方があるように思う。漫画についての感想や思うところは人によって違うのだろうが、人と人が国家や民族というものをせおって差別したり反目したりするのはばかばかしく愚かなことだというメッセージがかなり多くの手塚治虫の作品にはあるように思う。手塚作品にでてくる人間に似ているけど人間ではないもの、場合によってロボットであり、宇宙人であり、妖精であり、異次元人であったりするのだが、こうしたものは、外国人や異人種の暗喩のようでもある。人が国家や民族にとらわれているかぎり、争いや反目はなくならない。特に、差別され虐げられたものが最後は差別し虐殺する側にまわる「アドルフに告ぐ」や天皇を神格化して統一国家を形成していく古代と宗教神政国家となった未来を対比し、その中での戦乱を描いた「火の鳥~太陽編」などはそうした視点でも読むことができる。手塚治虫は当然国民栄誉賞に値すると思っていたのだが、賞が与えられなかったのは、国家主義や民族主義と相反するメッセージが為政者に嫌われたとしか思えない。*世の中が不況になり、生活苦に苦しむ人が増えると人種至上主義や民族主義が力を得るという説がある。ワイマール体制下のドイツがそうであったし、米国などでは白人貧困層のよりどころは人種的優越感だという話もある。ただ日本では、貧困層が増えても、そうした傾向はそれほどでてこないかもしれない。多くの人が手塚治虫の漫画をよみ、そして多かれ少なかれそのメッセージを受け取っているはずだから。
2013年01月13日
コメント(6)
-
漫画の想い出
子供の頃漫画雑誌を読むのが大好きだった。当時は今と違い雑誌は高価であり、友人と交換して読んだり、床屋(漫画でけっこう子供客を集めていた)などで読んだり…といった具合だったが。そんな漫画の中で印象的だったものをいくつか。*少年漫画を思い出すと、当時は今と違って戦争ものというジャンルが確立していた。たいていは戦闘機のパイロットを主人公にしたもので、数的には最も多かったはずの陸軍歩兵が主役というのは皆無だったように思う。加藤隼戦闘隊を扱った「大空のちかい」やゼロ戦ものの「ゼロ戦はやと」なんかは人気があり、後者はテレビアニメにもなった。あの当時は戦場にいった世代がちょうど働き盛り世代でもあり、戦争の記憶は今よりもずっとなまなましかったように思う。そのほかではスポーツものも人気だったが、ほとんどが野球や柔道もので、野球の場合、主人公は魔球を投げる投手というものが多かった。また、SF冒険ものもあったが、こちらは「鉄腕アトム」に代表されるようなスーパーマンの主人公が活躍するというパターンがほとんどで、スーパーマンである理由は様々であった。アトムはロボットという設定であったが、サイボーグでもよいし、未来人や宇宙人でもよいし、要は主人公がスーパーマンであるという説明になればよいのだろう。今なお古びていない鬼太郎もこの系譜の漫画につらなっているのかもしれない。総じて少年漫画の主人公達は魔球投手やスーパーマンなどのヒーローであり、高度成長の時代を反映させていたように思う。だめな主人公は「丸出ダメ夫」のようなギャグ漫画にしか登場せず、後の時代に流行った内向的な少年や等身大の主人公はあまりいない。*一方、少女漫画についてみると、バレーものと継母ものという大きな系譜があった。バレー(スポーツのバレー漫画がでてくるのは東京五輪後でこちらは踊りのバレー)は当時はほとんどの子供に縁がないものだったが、なぜかバレーを学ぶ少女を主人公にしたものが多く、美しい衣装で踊っている絵が人気を集めていた。継母ものは、たぶん戦前の少女小説の流れをついでいるのだろうが、継母や金持ちの娘にいじめられる主人公が本当の母親を探すのだが、その過程で次々に悲しいことが起こり…というパターンが主だったように思う。話がそれるが、この少女漫画の敵役のお嬢様にはたいてい共通点があって、それは勝気でわがままで自己主張が強く、そこそこ美人で成績優秀なのだが、真に美しく頭のよい主人公の少女にひそかな劣等感と敵意をいだいているということである。このあたりは某女性政治家のキャラとかぶっているので、彼女がよくも悪くも世間の注目を受けるのは、このあたりに理由があるのかもしれない。少女漫画にはもう一つ、思春期前の少女の日常を描いたものがあった。生活漫画とか家庭漫画とかいったものである。「チャコちゃんの日記」は小学生の少女の家族や友人との日常を描いたもので独特の絵のタッチとともに印象に残っている。また、学校を主な舞台にして、様々な子供のでてくる「五年ひばり組」も楽しい漫画であった。主人公の少女のあだ名が新幹線というのも、当時、新幹線が話題であり、憧れでもあったことの反映であろう。そのほかそろばんにうちこむ少女を描いた「そろばん少女」も、バレーよりも習い事としてはずっと現実的なそろばんを扱っており、けっこう人気があったように思う。
2013年01月12日
コメント(9)
-
平成格差小唄♪
しょうこりもなくまた作ってみた。お富さんの節があうように思う。飢死か牢屋かそれとも過労死それがいやならフクイチか~♪いったはずだよあの選挙肉屋に包丁わたしたからには、これでしまいだおだぶつだ~や~れそれ 国防軍上がる物価に下がるは給料おいうちかけるは消費税~♪いったはずだよあの選挙肉屋に包丁わたしたからには、飢えも凍えも身からさびや~れそれ 雇い止め
2013年01月11日
コメント(4)
-
愛は苦手( 山本 幸久)
テレビで紹介されていた本らしい。その番組を見て買ったという人からさらに借りて読んだ本である。内容もタイトルも地味すぎてたぶん本屋でみたら買う気も起きなかっただろう。舞台は今の日本。アラフォーの8人の女性を主人公にした8つの短編で相互の関連はない。専業主婦、パート主婦、元ライター、漫画家、政治家の愛人などの主人公達が、それぞれの日常生活の中でぶつかる大小様々の波紋を描いている。まるで他人の人生を覗き込むような感覚…小説にはこういう楽しみ方もあったのかとあらためて思う。それにしても読みやすい文章に小説としての物語性。知らない作家だったけどこういう人もいたのかとちょっと驚く。ただ何をいえば主人公達の性格描写がもうちょっとはっきりしていた方がよいように思うのだが。
2013年01月10日
コメント(0)
-
緊急経済対策会議など
緊急経済対策会議が三年半ぶりに再開される。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130109-00000035-asahi-pol税金をじゃぶじゃぶそそぎこんで規制緩和で経済再生。そしてその会議に招集された有識者をみるとあの懐かしい竹中氏を中心にして創業セレブ達がめだつ。まるであの格差と貧困を拡大させたコイズミ政権の再来をみているみたい…。*福島では手抜き除染が問題になっているという。あたりまえだろう。だいたい除染といったって放射能が消えてなくなるわけではない。単にこっちからあっちに移すだけだ。そして移した後の放射性物質は置き場所がなくなる。それを「除染」といえば、あたかも「除菌」のように放射能が消えるような印象を与える。*女性の社会進出をめぐる目標をめぐって高市氏と野田氏が論争を行なっているという。そもそもの疑問であるが例えばある分野に女性が何%進出したからって、それが他の女性全体の地位向上に役立つのだろうか。早い話、国会議員の8割を75歳以上にすれば日本の後期高齢者の地位向上に役立つか…そんなことはないだろう。女性議員や女性審議会委員だってそれと同じではないか。さらにつきつめれば、女性の地位は低いのだろうか、そして低いとしたらどんなところが問題なのだろうか。女性の地位向上のイメージにしてもある人は妻の相続分増大や専業主婦の年金確保をイメージするし、ある人は女権と(妻の)座権は違うという。だから女性の国会議員、閣僚、高級官僚、財界人がでれば、素直に女性の地位向上と思う人がいても不思議ではないけど、普通の人はそういうものは女性の地位一般とはあまり関係ないと思っている。それよりも看護師に女性がいくら増えても女性の地位とは無関係だが、医師に女性の比率が増えれば女性の地位が向上したと考えるような職業差別(区別?)的発想がなんともいやらしい。女性か男性かは性差よりもむしろ個人差ではないか。女性だからだめということもないし、女性だからよいということもない。男性にしてもしかりである。数値目標などよりも、これこそ機会を平等にしておけばよいだけのことだろう。
2013年01月10日
コメント(8)
-
年賀状あれこれ
年賀状が年々減っている。かつては職場やちょっとした集まりでも、よく名簿を配っており、けっこうその間での年賀状のやり取りがあったが、そうした名簿の配布がなくなったのも一因だろう。それに交際範囲が減っていることもある…悲しむべきことなのだが、今となっては遠い学生時代の友人よりも、周囲にいる人々とのつながりの方が大切だ。おそらくたいていのひとにとってそうだろう。そしてそうした人々とはしょっちゅう顔をあわせているので、年賀状の交換も特に必要ない。*年賀状で最も付き合いの長い人は小学校時代の友人である。今年の年賀状には「空き地で遊んだことなどを懐かしく想い出します」とあった。あの人の子供時代の追憶の中に自分がいると思うとなぜかうれしい。故郷は遠きにありて想うものと歌った詩人がいたが、昔の友達ともこうした年賀状のやりとりだけでよいのかもしれない。実際にあってみると、かえってつながりが壊れそうでちょっと怖い気もする。そのほかにも、高校や大学、職場で知り合った方など様々である。自分など望むべくもない活躍をしている人もいる。まさに諺にあるように、這う虫の上を飛んでいく鳥がいる…といったところだが、人の能力境遇は差異があるので仕方がない。また、難病や大病での手術など大きな困難を迎えた人もいる。そうした方の年賀状の文面には、生きている有難味等につづられており、それも考えさせられる。でも一番うれしいのは、ちょっと疎遠になりかけていた人からの「近いうちにお会いできれば」という年賀状。松も開けたし、こちらから葉書を出してみようと思う。*あと、年賀状と言えば毎年元日に必ず届くのだが、どうしてもどこであったか想い出せない人もいる。就職してすぐに来るようになったので、学生時代のつながりなのであろうが、思い出せない。
2013年01月09日
コメント(0)
-
安倍総理の歴史認識
安倍総理は憲法改正だけではなく教育問題や歴史認識の問題にも熱心である。失業や貧困が広がるこの社会でそうしたものが喫緊の課題であるとも思えないし、生活保護を削減しながら尖閣防衛に5000億円の国費をかけるのもよくわからない。*それはともかくとして歴史認識の問題の中でかなり大きな比重を占めるのは従軍慰安婦の問題であろう。今日の社会では情報は世界中をかけめぐる。世間の見方を変えないで、身内の中だけで子供は親をこう思え、先祖をこう思えといったところで無理な話で、それはちょうど実像を変えずに鏡に映る映像だけを変えようとするようなものである。本当に従軍慰安婦や南京虐殺などについての認識を変えたいと思うのであれば、真相を発掘して、それを国際社会にアピールをしていけばよい。それをしないで日本国内で日本の子供に教える教科書だけを問題にするのは本末転倒であろう子供たちのうちの何パーセントかは海外で暮らすこともあるだろう。そうした場合、自分の知っていることと、海外では常識となっていることとのギャップに苦労するのは当の本人である。従軍慰安婦については韓半島出身者ばかりがいわれるが、日本人の慰安婦も相当いた。さらに慰安婦といえば、日本のマスコミにはあまりとりあげられないが、オランダ人慰安婦もおり、これは強制性が明白になっている。この事件は本にもなっているし、おそらく欧州では日本よりも広く知られている話であろう。http://blogs.yahoo.co.jp/lamerfontene/48340539.html安倍総理が従軍慰安婦の問題を言えば言うほど、こうした出来ごとについてもまたむしかえされる。国益という目でみたとき、それが本当に得策がどうかよく検討してみるべきである。*安倍総理をみていると、経済とか財政とかはよくわからないから、歴史認識とか教育とかそうしたものをいじくりまわしているとしか思えない。
2013年01月08日
コメント(18)
-
伊豆旅行
お正月は伊豆に行ってきた。堂が島から石廊崎へとまわったのだが、海岸などのすばらしい眺望だけでなく、あちこちに廃墟となったホテル、スナック、レジャー施設が目を引く。いささか口が悪いと思うのだが、伊豆には廃墟半島という呼び名もあるという。また、廃墟ではないが、近いうちに廃墟になりそうなところも多い。日帰り入浴に入ったホテルでは、灯りのついている部屋がほとんどなく、かつては売り物だったであろう展望浴場にも客はいない。そして出入口近くには、カバーの破れたソファと塗料のはげた卓球台があるばかり…。その下の階には閉鎖されて久しいドリンクバーの脇に古いゲーム機の台がいくつも積み重ねてあった。かつては温泉卓球の歓声、カラオケ客の歌声やゲームに興じる子供の声が響いていたであろうに。*観光衰退の原因は社内旅行の減少ばかりではないだろう。世の中全体にお金が回らなくなっているのだ。大河ドラマやアニメ聖地も一過性の客寄せにはなっても、継続した観光振興にはならない。全体に所得が減っていけば、娯楽教養などの不要不急の出費からまず削られる。国内が豊かになるのが待てない、あるいは期待できないというのであれば、海外からの観光客誘致しかないのではないか。箱根など外国人客の多いところはそれなりににぎわっている。ただ、以前、箱根に行ったとき、日本蕎麦屋の店員が外国人ばかりなのには少し驚いた。外国人観光客の増加が日本人の雇用の増加に結び付けばもっとよい。**年金や生活保護などの固定収入を減らすのは抵抗が大きい。しかしそうした抵抗なしに、収入を減らす、支給する側からすれば支出を減らす方法がある。それはインフレ政策である。インフレは表面的には企業収入が増え好景気のように見えるのだから、消費税の増税すれば支出する側では一石二鳥であろう。
2013年01月07日
コメント(10)
-
興味深い統計
ちょっと興味深い統計がある。http://www.pewglobal.org/files/2007/10/258-topline.pdf 秋原葉月さんのブログで紹介されていたもので、原資料は鳩ポッポさんの紹介である。この95頁では、「極貧状態にあり自分自身の能力で生活し生計を立てる能力のない人々を助けることは国や政府の責任である」という設定に対して、Mostly disagreeとCompletely disagreeの合計が日本は38でありトップとなっている。つまり極貧状態で実際に餓死凍死の危険のある人に対してそんなのほっとけと考える人の割合が非常に大きいのである。この結果については驚くというよりもやはりそうなのだろうな…と思う。*だいたい政治家からして生活保護は恥だの公的扶助に頼らないのが日本の美風だのいうくらいであり、それがまた「問題発言」ともみなされない。でもそうした政治家にかぎって愛国心だのなんのというのも不思議である。飢えている自国民を冷酷につきはなすのであれば、愛国というのは何なのか…たしかに愛国と愛国民は違うといえば違うのだが。そしてまたこうした極貧状態の者に対して非常に冷淡な日本人の感覚の背景には何があるのだろうか。だいぶ前の日記にも書いたのだが、どうも背景には日本独特のケガレ意識があるように思う。たしかに日本の社会や精神風土にはよい点が沢山ある。互いに思いやり、助け合い、卑怯な行為を憎み、残虐な行為を不自然なものとして忌み嫌うなど…。恨みを残さないことを美徳とする(恨五百年という国もあるし、他国ではそうでもない。)のも日本人としては良い点だと思う。しかし、こうした美風とはうらはらに不幸なもの、不運なものには限りなく冷酷な風土もこの日本にはあるのではないか。*共同体の成員は、その成員である限り、和を尊んで暮らすのだが、ひとたびケガレた成員は共同体から排除し、その不幸には皆がみてみぬふりをして、触れないようにする。そんな感覚である。ケガレの中には罪のケガレ、恨みのケガレもあるが、同時に病、不幸、そしておそらく極貧もケガレとされる。前科者に対する差別偏見もあるが、それと同時に犯罪被害者に対する冷淡さも際立っている。なぜ日本でだけハンセン病の元患者に対する監禁が公然と長期間行なわれたのか、なぜ日本では拉致被害者が帰国したときこれは一時帰国で北朝鮮に帰るのが当然だということを政府関係者やマスコミが言っていたのか…。これと極貧者が飢えようが凍えようが冷淡でいるという感覚と通じているように思えてならない。不幸、不運にケガレた者は共同体から排除し、あとは遠ざけ、ひたすら見て見ぬふりをする。
2013年01月06日
コメント(2)
-
肉屋を応援する豚の気持ちを考える…
あの選挙以来政治ネタを書く気がうせている。表現はなんだが豚が肉屋に包丁を渡したような選挙結果だとしか思えない。円安誘導による物価上昇に消費税。無為無策の雇用政策に野放しのブラック企業。これに最後のセーフティネットの生活保護まで削られるのだからふんだりけったりとしか思えない。貧困や格差をどんどん拡大させてきた連中が、愛国心だの伝統だのというのはブラックジョークだとしか思えないのだが、それでも、そういうところに票が入っていく不思議。*人の気持ちは本当に複雑で図りがたい。貧困層や過酷な労働、失業に苦しむ人々が再分配強化や雇用法制の改善を唱える政党を必ずしも支持するというわけではない。安倍か橋本かと煽るマスゴミも酷いものだが、必ずしもマスゴミだけのせいでもないだろう。人質が誘拐犯に好意をもつというストックホルムシンドローム。過酷な扱いをすればするほど洗脳の効果があがるという洗脳の実態。それと似たようなことが国家と国民にもあるのではないか。競争社会の中で苦しめば苦しむほど最後の自尊心の根拠を自分の所属する民族や国家に求める。貧困で辛い思いをすればするほど、より貧困なものをたたくことでひとときの優越感にひたる。たぶん江戸時代にもっとも酷い差別をやってきたのは極貧の百姓だったに違いない。あの戦時下で非国民やアカを口角泡をとばして罵倒したのは自分の子供が戦場で殺された親達だろう。*不幸な者がより不幸な者をみつけて叩く。不幸な者が自分と同じような者が不幸を免れるのを許さないとして叩く。念のため言っておくが、不妊だの障害児をもつだのが一般に不幸だなんていう気はない。でも、子供をもたずに高齢になった女性が新しい不妊治療を批判したり、障害児の親が「命の選別を許すな」といって出生前診断に反対したりするのも似たような心理があるように思えるときもある。貧困や格差社会の中で苦しむ人々が許せないのは雲の上でセレブ生活をしている人々なんかではない。それよりも生活保護受給者がパチンコやビールを楽しんでいることが我慢ならないのだろう。同様に国費で留学した後に大学教授や評論家になっている元官僚はあがめたてまつっても、自分とさして学校の成績の変わらなかったような下級公務員がリストラの不安もなくのんびりそうに暮らしているのは憎くてたまらない。こうした中では、富裕層課税の話も労働規制強化の話もでてこないし、そんな主張をしても票は集まらない。生活保護者や公務員をぶったたいておく方がずっと票になる。だから図書館費をけずり、ささやかな娯楽施設を閉鎖するなど住民のために何ひとつよいことをやらなかったような政治家でも、職員や教員をこっぴどく叩き、その生活を破壊したというだけで人気があつまるのだろう。
2013年01月05日
コメント(6)
-
ネットの怪しい情報
被曝が原因であるとすると医師会から除名されるという話があるという。http://ameblo.jp/64152966/entry-11441368843.html出所はネットでしかも伝聞なので真偽のほどはわからない。ただ本当に被曝が原因の健康被害が次々とでてくれば政府だって隠しきれるものではない。*さらにもっとすごい話でこの間の選挙に疑問があるという話もある。票の最終公表が延期されているのにも関連しているというのだが、これも真偽のわからない話だ。たしかにこの間の選挙では、長い列ができ、投票までにかなり時間がかかった。これと低投票率の発表とはどうも結びつきにくい。ただこんなものはそういえばといった類のことで、やはりマスコミの発達した国でそんな不正選挙ができるとも考えにくい。http://ameblo.jp/ghostripon/entry-11440360899.html*ネットでは様々な情報が流布している。マスコミよりもずっと刺激的で出所不明で膨大な情報である。マスコミにも振り回されては困るのだが、ネットにも注意が必要だろう。それでも、マスコミがあえて報道しない事項、海外のマスコミでは報道されていても国内のマスコミが無視する事項を知るという意味ではネットは強力なツールである。http://blog.goo.ne.jp/syokunin-2008/e/ba7ab8df53a0f6dc1b7fabaa50503097#comment-listhttp://news.infoseek.co.jp/article/20130104jcast20132160262**箱根駅伝がお正月テレビの定番になったのは、いつの頃からだろう。昔はなんかお正月と言えばスター隠し芸大会とかいったくだらないのをやっていたように思う。俳優の寸劇がなんで「隠し芸」なのかさっぱりわからない。あれも他にみるものもなかったし、大勢でこたつをかこんでいるときに、テレビがついていた方がにぎやかなので、なんとなくつけていただけだったように思う。箱根駅伝もたぶん他に見るものがないから皆つけているだけではないのだろうか。Uターンラッシュもそろそろはじまろうという時期に学業とは無縁そうな学生のかけっこなんて交通妨害だとしか思えないのだが、あれも伝統ある学生競技ということでそれなりの地歩を得ている。それでもうるさいだけのバラエティなどよりかはずっとよい。
2013年01月05日
コメント(4)
-
新自由主義の行方
私たちは金もうけのためでしたら何でもやりますよ…伝聞で聞いたある人材派遣業経営者の言葉である。発言の真偽はともかくとして、企業経営者の本音というものは概ねこんなところである。こうした金もうけのためなら何でもやる自由を極限にまで広げたものが新自由主義である。儲けのためならお正月だろうがクリスマスだろうが昼だろうが夜だろうが、店を開けておけば金が入る。かくして年中無休、24時間営業を売り物にするところはどんどん増え、元日でもかなりの店や施設が今日では普段とかわりなく営業するようになった。年中無休、24時間営業ということは土日も祝日も昼夜も関係なく働く人が増えたわけだが、過酷労働のまん延のわりには末端の従業員の給与はさして上がっていないことだろう。某新聞の一面トップに有力スポンサーである某大企業のリストラの実態を掲載したのにはちょっと驚いたが、あれも、リストラが問題というよりも、正社員の身分保障が強すぎるのが問題であるという方向に議論が誘導されるのも目にみえている。かつての自民党政権のときにでてきた解雇規制を緩和する労働法改正案がまたでてくるのではないか。残業代を支払わなくともよいというホワイトカラーエグゼンプションも同様である。新自由主義の下では、低収入、失業、過酷労働に苦しむ者の方が、利益を受ける者よりも多い。かくして社会は少数の冨者と多数の貧困層に分断されていく。2012年の選挙というものはそうした方向を大きくすすめた年として記憶されるのだろう。*この冨者か貧困層かというのは、別に親が生産手段を有しているかどうか、つまり親が地主か小作か、資本家か労働者かで決まるというよりも、本人の能力、運、努力によって決まる。特に能力や運によるところが大きい。能力や運なんてものは子供に受け継がせるわけにはいかないものなので、御自身が冨者であったとしても、あまり子供を持ちたいなんて思わないだろう。もちろん貧困層の多くが子供を持てないのは言うまでもない。こうした社会では未婚率が高まり、家族が社会の最小単位ではなくなっていくのも理の当然である。これが社会全般の風潮の与える影響はどんなものなのだろう。全部が全部とは言わないが、家族や子供がいない場合、国家社会に対する関心、次の世代に対する関心はどうしても低下していく。外敵の脅威などいわなくとも、国家社会は内部から変質していく。いくら上から愛国心だの伝統だのを強調しようが、これは止めようがない。
2013年01月03日
コメント(33)
-
紅白に知っている歌がほとんどないなんて…
いつの頃からだろうか。今年流行った歌といってもすぐに思い浮かばなくなったのは…。昔は紅白歌合戦をみながら、そういえば春にはこれが流行っていた、夏ごろにはこれもよく聞いたなあ…なんて思いながら一年を回顧したものだった。もっと長い時間スパンでみても、この歌が何年の大ヒット曲というようにたいていその年を代表する流行歌というものがあった。今年の紅白を聴いたが、知っている歌がさっぱりでてこない。そしてどの歌も全然耳につかないし、印象に残らない。印象に残った歌はいずれも今年新しくでた歌ではなく、以前から知られていた歌ばかりだったように思う。*歌は世につれ世は歌につれ…というが、商店街などにいくと流行歌がじゃんじゃん流れていた時代はとうにすぎ、歌がCDの10万、100万単位の売り上げではなく、ライブの熱狂で消費されるようになってから変わっていったのだろう。世の中に流行っているから聴くのではなく、自分がおしているアイドルの歌だから聴くというように。だから流行歌から世相などは推し量るべくもない。「上海帰りのリル」が流行っていた頃には引揚げ者がまだまだ社会問題になっていてラジオでは「尋ね人」の時間なんてのがあった。「高校三年生」が流行ったころは高校進学率が急上昇していった時代だ。「こんにちわ赤ちゃん」が流行った少し後には第二次ベビーブームが始まる。*テレビで歌をみるよりも、ネットで好きな歌を探す方が楽しい。当時、レコードは高価でなかなか買えなかったが、ネットでは気になっていた歌を探して聴くことができる。演歌っぽいものやご当地ソングのようなものが多いのだが、そういえば、ご当地ソングというのも最近は少なくなった類型だろう。歌謡曲なんて言葉自体もかなりすたれてきたように思う。
2013年01月02日
コメント(8)
-
愛国心と伝統について思うこと
謹賀新年。本年もよろしくお願いいたします。元日は五節句の中には入っていないのであるが、それと同格以上の祝日で古来から人々はこの日は仕事を休み、こうした特別な日の存在が生活のアクセントにもなってきた。昨今では愛国心や伝統の尊重を声高にいう人が多い。しかしそうした人々の主張を聴くと共感するよりも疑問を感じることの方が多い。なぜなら愛国心を叫ぶ人に限って、同国人を愛しているようには見えず、異民族に対する蔑視や敵意を煽ったり、愛国心に欠ける同国人を指弾する傾向ばかりが目につくから。貧困に苦しむ同国人を自己責任だのなんのと切り捨てながら、国に対する「愛」を説くというのは大いなる矛盾ではないか。伝統の尊重も同様である。古くから伝わるもので守るべき価値あるものを伝統とよび、唾棄すべきものを因習とよぶ。元日や節句などの日々の節目もまた尊重すべき伝統なのではないか。近年ではスーパーなど元日から営業している商業施設が多いが某デパートも今年から元日の営業を始めたという。追随するところも増えていくであろうから元日ですら休めない人は増えていく。ああいった店舗や商業施設ではフロアマネージャーや店長は管理職とされ、低賃金長時間労働がまん延していることは誰もが知っている。時給で見るとバイトよりも店長の方が低いという話もある。ところが伝統論者はこうした労働の実態については何もいわない。愛国心や伝統を声高に主張する人が総理になったが、愛国はあっても愛国民はない、そして日本の伝統を無視した弱肉強食型の勝者総取りの資本主義の色彩はますます強くなっていきそうないやな感じである。愛国心と愛国民は違う。そして伝統と因習も違う。
2013年01月01日
コメント(8)
全33件 (33件中 1-33件目)
1