PR
X
カレンダー
カテゴリ
カテゴリ未分類
(1)読書案内「日本語・教育」
(21)週刊マンガ便「コミック」
(88)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝
(33)徘徊日記「日帰りでお出かけ」
(58)演劇「劇場」でお昼寝
(2)映画「元町映画館」でお昼寝
(98)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝
(14)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝
(109)読書案内「映画館で出会った本」
(16)読書案内「翻訳小説・詩・他」
(49)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」
(19)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり
(51)読書案内 「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」
(25)読書案内「現代の作家」
(106)徘徊日記「お泊りでお出かけ」
(63)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり
(84)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ
(46)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」
(67)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」
(31)読書案内「近・現代詩歌」
(51)徘徊「港めぐり」
(4)バカ猫 百態
(21)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」
(17)読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」
(20)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」
(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝
(3)映画「こたつシネマ」でお昼寝
(14)映画「パルシネマ」でお昼寝
(41)読書案内「昭和の文学」
(23)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05
(16)読書案内「くいしんぼう」
(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝
(6)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」
(8)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」
(33)週刊マンガ便「原泰久・鈴ノ木ユウ・野田サトル」
(32)ベランダだより
(133)徘徊日記 団地界隈
(109)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり
(24)徘徊日記 須磨区あたり
(26)徘徊日記 西区・北区あたり
(8)徘徊日記 灘区・東灘区あたり
(37)徘徊日記 美術館・博物館・Etc
(4)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」
(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり
(7)読書案内「大江健三郎・井上ひさし・開高健 他」
(12)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」
(3)読書案内「谷川俊太郎・茨木のり子・大岡信 あたり」
(19)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」
(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」
(9)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」
(13)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」
(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて
(5)読書案内「村上春樹・川上未映子」
(13)映画 パレスチナ・中東の監督
(6)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」
(7)映画 韓国の監督
(22)映画 香港・中国・台湾の監督
(35)映画 アニメーション
(13)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢
(48)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭
(25)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行
(14)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督
(36)映画 イタリアの監督
(18)映画 ドイツ・ポーランド他の監督
(14)映画 ソビエト・ロシアの監督
(6)映画 アメリカの監督
(79)震災をめぐって 東北・神戸・原発
(5)読書案内「旅行・冒険」
(3)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」
(13)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督
(4)映画 フランスの監督
(42)映画 スペイン・ポルトガルの監督
(10)映画 カナダの監督
(3)映画 グルジア(ジョージア)の監督
(9)映画 ウクライナ・リトアニアの監督
(6)映画 イスラエルの監督
(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督
(3)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督
(7)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督
(5)映画 トルコ・イランの映画監督
(8)映画 ギリシアの監督
(2)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルーの監督
(2)映画 ハンガリーの監督
(4)映画 セネガルの監督
(1)映画 スイス・オーストリアの監督
(3)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家
(1)読書案内 ジブリの本とマンガ
(5) ベランダだより 2024年6月14日(金)「メタモルフォーゼ! アゲハが巣立っています!」 ベランダあたり
週刊 読書案内 穂村弘×東直子「回転ドアは、順番に」(ちくま文庫)
週刊 読書案内 池内紀「101冊の図書館」(丸善ライブラリー101)
イーサン・コーエン「ドライブアウェイ・ドールズ」シネリーブル神戸no249
ベランダだより 2024年6月9日(日)「今年も咲いてくれました!」ベランダあたり
週刊 読書案内 立花隆「思索紀行 上」(ちくま文庫)
ラジ・リ「バティモン5」シネリーブル神戸no248
ジョージ・ミラー「マッドマックス フュリオサ」109ハットno44
ベランダだより 2024年6月5日(水) 「( ̄∇ ̄;)ハッハッハ、古稀だそうです!」
徘徊日記 2024年6月6日(木)「団地はアジサイ!」団地あたり
週刊 読書案内 穂村弘×東直子「回転ドアは、順番に」(ちくま文庫)
週刊 読書案内 池内紀「101冊の図書館」(丸善ライブラリー101)
イーサン・コーエン「ドライブアウェイ・ドールズ」シネリーブル神戸no249
ベランダだより 2024年6月9日(日)「今年も咲いてくれました!」ベランダあたり
週刊 読書案内 立花隆「思索紀行 上」(ちくま文庫)
ラジ・リ「バティモン5」シネリーブル神戸no248
ジョージ・ミラー「マッドマックス フュリオサ」109ハットno44
ベランダだより 2024年6月5日(水) 「( ̄∇ ̄;)ハッハッハ、古稀だそうです!」
徘徊日記 2024年6月6日(木)「団地はアジサイ!」団地あたり
コメント新着
キーワードサーチ
▼キーワード検索
カテゴリ: 読書案内「現代の作家」
高村薫「作家的覚書」(岩波新書)
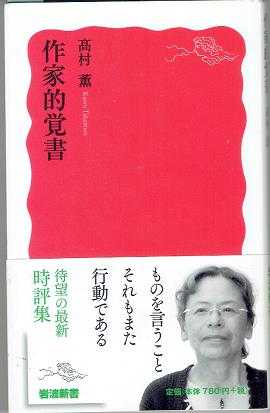 高村薫
の
岩波新書「作家的覚書」
が目に入って、棚からとり出してみると
200円
だったので買いました。
2017年の新刊
ですが、
2014年
ころ、
岩波書店
の
「図書」
とか、新聞とかに書いていた時評を集めた本です。
ほぼ、10年前の、それも時評ですから、書かれている内容や、中には講演の記録もあるわけで、その発言が古びているに違いないとは思ったのですが、まあ、 200円
なので買いました(笑)。
高村薫
の
岩波新書「作家的覚書」
が目に入って、棚からとり出してみると
200円
だったので買いました。
2017年の新刊
ですが、
2014年
ころ、
岩波書店
の
「図書」
とか、新聞とかに書いていた時評を集めた本です。
ほぼ、10年前の、それも時評ですから、書かれている内容や、中には講演の記録もあるわけで、その発言が古びているに違いないとは思ったのですが、まあ、 200円
なので買いました(笑)。
読み始めてみると、過去10年の、そして、今、現在、たとえば、仕事からほぼ引退した 徘徊老人 を困惑させる社会事象の、「はじまの出来事」の指摘でした。
例えば、こんな文章があります。
しかし、今、こうして読んでいると、 10年前 にはじまっていた出来事の、 10年後の未来の帰結 にすぎないことを、 彼女 はすでに 予言 していたといっていいでしょう。ぼくたちは、彼女の予言していた10年後の 「明るくない未来」 を、今、生きていることに気づかされるわけです。
案内はこれくらいでいいのですが、つい先だって 「国葬」 とかで祭り上げられ、世間を騒がせている、当時、宰相の地位にいたAについてもこんな発言があります。
「晴子情歌」三部作 をすでに書いている 高村 ほどの作家であれば、昭和の妖怪Kにはじまり 「虚言」の宰相A にいたる一族の、権力に対するなりふり構わない欲望の実相を見破ることは、さほど難しいことではなかったと思いますが、 高村 がその演説を 「虚言」 であると喝破した10年後の未来にさらけ出された実相は、 高村 をしても、まさかこれほどまでにという醜態ではなかったでしょうか。
まあ、古い時評を読むという、ズレたことをしながら、この作家の次作に、ちょっと期待してしまいますが、まあ、お書きになることはないのでしょうね。それにしても、200円はお安い1冊でした(笑)。







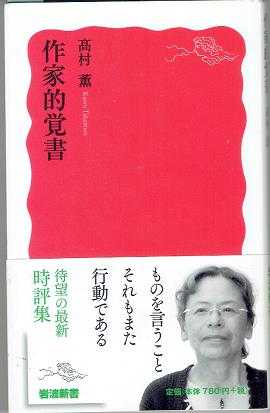 高村薫
の
岩波新書「作家的覚書」
が目に入って、棚からとり出してみると
200円
だったので買いました。
2017年の新刊
ですが、
2014年
ころ、
岩波書店
の
「図書」
とか、新聞とかに書いていた時評を集めた本です。
高村薫
の
岩波新書「作家的覚書」
が目に入って、棚からとり出してみると
200円
だったので買いました。
2017年の新刊
ですが、
2014年
ころ、
岩波書店
の
「図書」
とか、新聞とかに書いていた時評を集めた本です。
読み始めてみると、過去10年の、そして、今、現在、たとえば、仕事からほぼ引退した 徘徊老人 を困惑させる社会事象の、「はじまの出来事」の指摘でした。
例えば、こんな文章があります。
「想像もしていなかったこと」 「図書」2014年6月号P26 あれこれ、言葉はいりませんね、 2022年 、今年の冬、 ロシア の プーチン が、 高村薫 の言う 帝国主義の論理 を、夜郎自大に振り回し、隣国 ウクライナ に対して武力による侵略を始めたときに、実は何が起こっているのか徘徊老人には理解できませんでした。
あるとき市井の想像を超えてゆくのは、時代の状況も同じである。たとえばこの二十一世紀に、ロシアがウクライナを併合するようなことが現実になろうとは―。国連安保理やEUの外相会合で欧米各国の代表が右往左往している状況を眺めながら、二十世紀の二つの大戦や太平洋戦争の前夜はこんなふうだったのだろう、などと想像したりするのは、二十世紀半ばに生まれて多少なりとも戦争の時代の残り香ぐらいは嗅いでいる世代の杞憂だろうか。
それにしても、自国民の保護を名目に軍事力で他国の領土を併合するという帝国主義の論理が今どき現実にまかり通りことを、欧米各国も日本も想像だにしていなかったように見える。想像ができなかったのは、国境を越えて経済的に依存しあう今日のグローバル世界を、旧来の帝国主義が易々と踏みにじってゆくこと、そのことである。あるいは、そんなことはたぶんおこらないという根拠のない希望的観測をもって地政学的なリスクに眼を瞑らない限り、グローバル世界など、標榜できないということなのだろうか。
かつて、未来に行けば行くほど人類は賢くなって所問題は解決に向かい、世界は平和になってゆくだろうと信じていた私はかの9・11とともにいなくなったけれども、未来を悲観しながらも、原発の重大事故や、軍事力を誇示する帝国主義の台頭など想像できなかったこの頭は、まだどこかで明るい未来の幻想を捨てられないでいるのかもしれない。(P27)
しかし、今、こうして読んでいると、 10年前 にはじまっていた出来事の、 10年後の未来の帰結 にすぎないことを、 彼女 はすでに 予言 していたといっていいでしょう。ぼくたちは、彼女の予言していた10年後の 「明るくない未来」 を、今、生きていることに気づかされるわけです。
案内はこれくらいでいいのですが、つい先だって 「国葬」 とかで祭り上げられ、世間を騒がせている、当時、宰相の地位にいたAについてもこんな発言があります。
「いつもの夏ではない」 ここで話題にされているのは A という人物の 「虚言」 についてですが、彼の虚言を支えていたのが、おそらく、虚言を弄して巨大化したインチキ宗教団体であったことが、その、一見すれば、悲劇的だった最期のおかげで、今、明らかになっているのですが、さすがの 高村薫 も、インチキ教団については、この時評のどこでも触れていません。
沖縄戦終結の日から、広島・長崎の原爆投下を経て終戦の日にいたる日本人の毎夏の厳粛な気分が、今年は安倍首相の歪な歴史観や個人的な思い入れによって、たびたびかき回され、混ぜ返された。広島の原爆記念日の挨拶ではあろうことか非核三原則の文言を削って国民の顰蹙を買い、終戦の日に合わせて発表された戦後70年の首相談話では、事前の有識者懇談会の提言で示された侵略や植民地支配の事実から主語を抜いてしまい、長すぎる戦後になんとか一つの区切りをつけたいと願う一国民の切実な思いを、今さらのように愚弄してくれた。60年以上生きてきて、これほど不快な思いが募る八月十五日はほかに知らない。
謝罪や反省とは本来シンプルなものであり、その論理も文言も当然シンプルになる。微妙な言い回しや複雑な文言は無用であり、微妙な言い回しが使われる限り、それは謝罪にも反省にもならない。否、より正確にいえば、戦後七十年談話で語られた「反省」は「我が国は(中略)繰り返し、痛切な反省と心からのお詫びの気持ちを表明してきました」という過去形であり、談話を出した首相本人はけっして反省も謝罪も表明していない。このことを言い換えれば、「アジアの人びとの歩んできた苦難の歴史を胸に刻み」「歴史の教訓を深く胸に刻み」と神妙に繰り返される文言はみな虚言だということである。(P108)
「晴子情歌」三部作 をすでに書いている 高村 ほどの作家であれば、昭和の妖怪Kにはじまり 「虚言」の宰相A にいたる一族の、権力に対するなりふり構わない欲望の実相を見破ることは、さほど難しいことではなかったと思いますが、 高村 がその演説を 「虚言」 であると喝破した10年後の未来にさらけ出された実相は、 高村 をしても、まさかこれほどまでにという醜態ではなかったでしょうか。
まあ、古い時評を読むという、ズレたことをしながら、この作家の次作に、ちょっと期待してしまいますが、まあ、お書きになることはないのでしょうね。それにしても、200円はお安い1冊でした(笑)。



お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[読書案内「現代の作家」] カテゴリの最新記事
-
週刊 読書案内 滝口悠生「水平線」(新… 2024.05.11
-
週刊 読書案内 乗代雄介「掠れうる星た… 2024.05.09
-
週刊 読書案内 井戸川射子「この世の喜… 2024.04.15
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.










