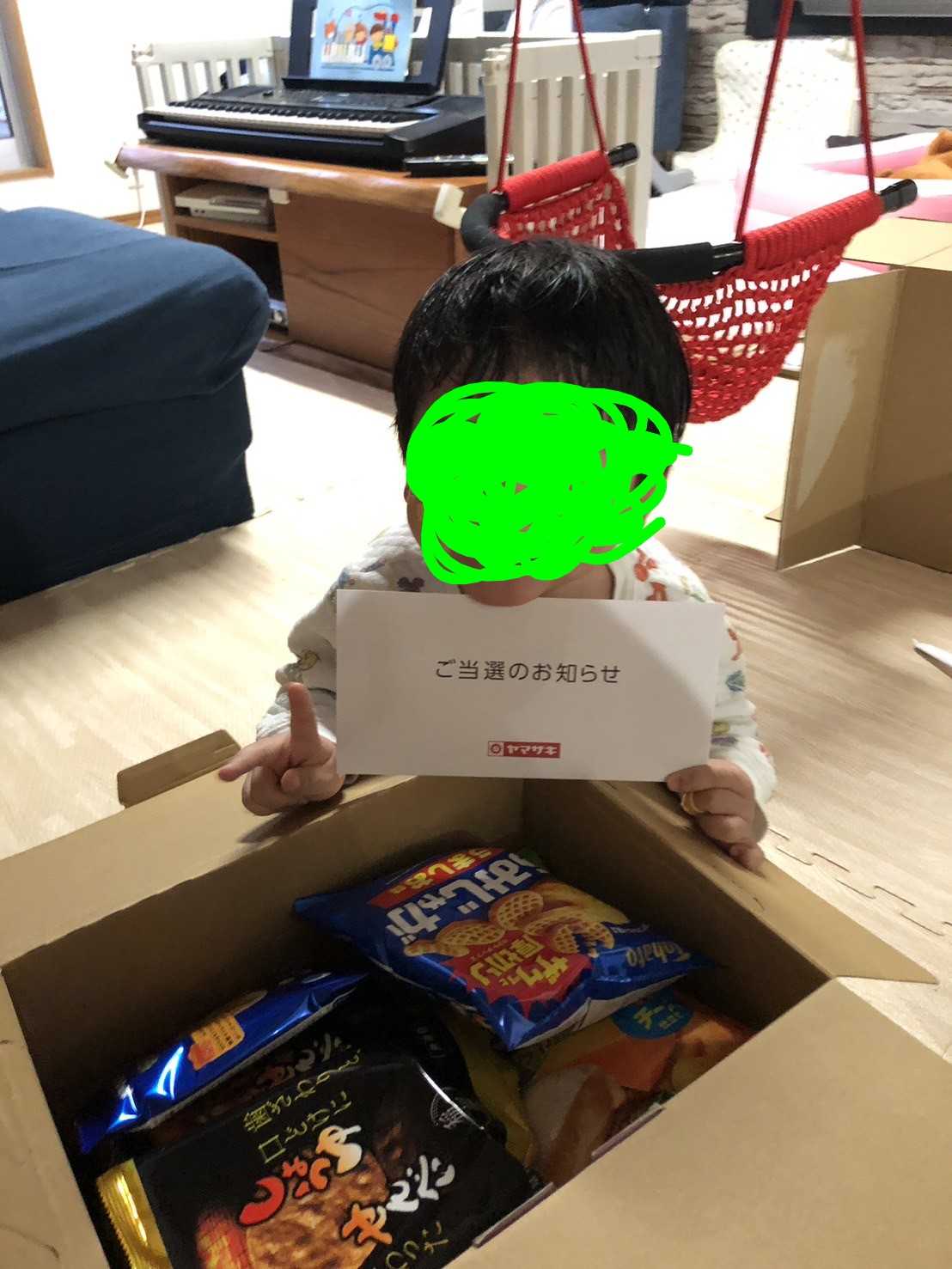2011年03月の記事
全27件 (27件中 1-27件目)
1
-
どちらの言い分が正しいのでしょうか
避難基準超す放射性物質=飯舘村で検出―IAEA国際原子力機関(IAEA)は30日、東日本大震災で事故を起こした福島第1原発から約40キロ北西の福島県飯舘村で、IAEAの避難基準を超す高いレベルの放射性物質が検出されたとして、日本政府に避難地域の見直しを暗に促した。日本側は避難の必要はないとの立場だが、IAEAの指摘は議論を招きそうだ。 IAEAによると、3月18日から26日にかけ、第1原発から25~58キロの9自治体で採取した土壌サンプルに含まれるヨウ素131とセシウム137 の量を測定した結果、飯舘村で1平方メートル当たり200万ベクレルを検出した。これはIAEAが定める避難指示基準の2倍に相当するという。 IAEAは「あくまで初期の評価」と強調しつつも、日本政府に対して慎重に状況を評価するよう伝えた。日本政府は同原発の20キロ圏内を避難地域に、また20~30キロ圏を屋内退避地域に指定しているが、IAEAは事実上、範囲の拡大を迫ったと言える。--------<福島第1原発>飯舘村「避難不要」 保安院が被ばく量試算東京電力福島第1原発から約40キロ離れた福島県飯舘村で、国際原子力機関(IAEA)が測定した放射線レベルが同機関の避難基準を上回った問題で、経済産業省原子力安全・保安院は31日、独自に放射線による被ばく量を試算した結果、内閣府原子力安全委員会の避難基準の約半分にとどまったことを明らかにした。「直ちに避難する必要はない」としている。文部科学省の簡易型線量計のデータを基に、震災以降の累積線量を試算した。その結果、同村周辺で最も線量が高い地点の累積線量は50ミリシーベルトだった。これは一日中屋外にいた場合の線量で、日常生活での累積被ばく量はこの半分程度と見ていいという。原子力安全委の指標では、避難基準は実質的な累積線量が50ミリシーベルト以上。保安院は「一日中屋外で過ごすことは現実的には考えづらく、(水素爆発などが起きた3月中旬に比べて)時間当たりの放射線量も減少傾向にある」と強調した。原子力安全委は31日の会見で「日本の避難の基準は、大気や空中の浮遊物、飲食物の放射線量など、人体への直接的な影響を判断できる数値で決めている。IAEAは、草の表面のちりの放射能を測定しており、日本の基準の方がより正確な評価ができると考えている」と話した。--------相反する2つの意見ですが、果たしてどちらの言い分が正しいのでしょうか。判断は人それぞれですが、私は少なくとも、原子力安全・保安院の言い分を無条件に信じる気にはなりません。彼らの言い分が正しいなら、今回の事故は起こらなかったはずなのですから。でも、仮に原子力安全・保安院の言い分を信じたとしても、累積放射線量50ミリシーベルトというのは、ものすごい量です。日本人が1年間に浴びる放射線量は、確か1.5シーベルトくらいでしたから、その30年分以上をほんの2~3週間で浴びるというのです。で、結局は、例の「直ちに避難する必要はない」というのが結論。直ちに必要はない、というのは分かりました。じゃあこれからずっとその町に住み続けても問題ないのか、という疑問には、この回答はまったく答えていません。いずれにしても、原発から40kmも離れたところで50ミリシーベルト(保安院の主張でも)なら、20km圏内はもっと遙かに高濃度であることは想像に難くありません。
2011.03.31
コメント(0)
-
もはや、脱原発しかない
新エネルギー活用強調=菅首相菅直人首相は29日午前の参院予算委員会で、福島原発事故を受けたエネルギー政策の見直しについて、「今回のことを教訓に、太陽、バイオなどクリーンエネルギーを世界の先頭に立って開発し、新たな日本の大きな柱にしていく」と述べ、再生可能な新エネルギーの活用を積極的に進める考えを強調した。片山虎之助氏(たちあがれ日本)への答弁。 --------「責任は免れない」 原発と共栄の福島・双葉町議ら苦悩「さいたまスーパーアリーナ」(さいたま市中央区)に町機能ごと移転している福島県双葉町。地元に雇用を生み出し、多額の金を落とす福島第一原子力発電所に、町も議会もすがってきた。その選択は正しかったのか。28日の臨時議会に出席した町議は、苦渋の表情を浮かべた。(中略)顔をそろえた全11人の町議の中に、福島市の避難所から高速バスで5時間半かけて駆けつけた岩本久人議員(53)=1期目=もいた。腎不全の父親(83)は1日おきに透析を受ける必要があり、避難所を長期には離れられない。震災2日目。避難先の南相馬市で「ドン」という破裂音を聞いた。十数キロ離れた福島第一原発で爆発があったと聞かされた。第一原発が稼働したのは、ちょうど40年前の1971年。岩本議員が中学生のころだった。これという産業がなく「出稼ぎの町」だった双葉町にとって、原発は金の卵を産むニワトリだった。町は原発との共存共栄を掲げ、議会も7、8号機の増設を求める決議をした。2002年の東京電力による原発トラブル隠し発覚後、決議を凍結したが、07年に凍結を解除。再び増設受け入れに動きはじめたところだった。「町と歩調を合わせてきた議会の責任は免れない。残念でならない」と岩本議員は言う。ふるさとに戻るまで短くても1年以上はかかると思っている。「埼玉で避難生活を送る町民のそばにいられず、申し訳ない気持ちでいっぱいです。何ができるのか、ずっと考えています」。涙をにじませた。凍結解除を発議したひとりの伊沢史朗議員(53)=2期目=は、アリーナで避難生活を送っている。「町の財政破綻(はたん)をなんとか食い止めたかった」と当時を振り返った。町は、原発立地自治体に払われる交付金などを見込んで90年代にハコモノを乱発。借金返済に追われ、早期健全化団体に転落するほど、一時は切迫していた。7、8号機の誘致凍結を解除すると、その見返りに毎年9億8千万円の初期対策交付金が町に入った。だが、町に住民をとどめるために誘致した原発のせいで、いまは町に住民が近づくこともできない。「安全を担保されるのが条件だった。しかし、これだけの事故が起きると、あれで良かったのだろうかとも思う。厳しいのは、いつ戻れるか先が見えないことです」(以下略)--------三陸沖の、津波被災地も深刻な被害を受け、多くの犠牲者が出ましたが、水が引けば、行方不明者を捜し、死者を弔い、がれきを片付け、やがては復興に向けた取り組みが始まるでしょう。死者は還ってこないけれど、町並みや人々のにぎわいは、いつか必ず復興するでしょう。しかし、原発の被災地は違います。彼らの避難生活がいつまで続くかは、まったく分かりません。チェルノブイリの前例から考えると、残念ながら避難期間が半永久的になる地域が現れるでしょう。避難対象地域では、津波による犠牲者は放置され、行方不明者の捜索も、まったく行われていません。つまり、犠牲者の全貌すらつかめないままに放置されているのです。がれきの片付けも出来なければ、復興どころの騒ぎではない。原発によってどれほどお金が落ちようとも、故郷が放射能まみれになり、生活の基盤をすべて失って難民となる(この状況は、「難民」としか言いようがないと思います)リスクに見合うものではないのです。今後、福島第一原発の廃炉は確定的ですし、福島第二原発もまた、再稼働は難しいだろうと私は思います。「太陽、バイオなどクリーンエネルギーを世界の先頭に立って開発し、新たな日本の大きな柱にしていく」というのは当たり前の結論で、好むと好まざるとに関わらず、今後新たな原発建設を受け入れる自治体など、あるはずがないのです。既存の原発は、稼働を続けるでしょうが、それが寿命を迎えるところで、原発は消えていくでしょう。
2011.03.30
コメント(4)
-

キラ・ウィルカ フォルクローレ・ライブのお知らせ
地震で延期になっていたライブを、4月に開催することになりました。4月16日(土)午後6時より(2部構成予定)場所 ペルー料理店・スポーツカフェ「ティア・スサーナ」総武線・信濃町駅より徒歩約5分料金 チャージなし(レストランですから、食事はしてください)演奏 キラ・ウィルカ曲目 コンドルは飛んでいく、トリニダーより、蜃気楼の歌、出会い、など(16曲くらい演奏します)今度は、直前に事件が起こったり電車が止まったりしないことを祈っています。計画停電は、この時期の土日なら、多分大丈夫でしょう。いろいろ不確定要素は多いですが、こんな時だからこそ、楽しく演奏したいです。お店にはPA機器はないので、完全生音ライブです。(つまり、余計な電気は使わないって寸法です)キラ・ウィルカ↓(この曲はライブで演奏する予定)会場地図↓
2011.03.28
コメント(3)
-

福島県伊達郡川俣町
川俣町は、米どころであり、かつては絹織物でも栄えた町ですが、これといった観光資源があるわけではありません。しかし、フォルクローレを演奏している人で、この街の名、あるいは「コスキン・エン・ハポン」というイベントの名を知らない人は、おそらくほとんどいないでしょう。1975年以来36年間にわたって、この街で毎年10月に開催されている、日本最大のフォルクローレ音楽祭です。私も、1992年から2000年まで9年間、毎年参加しました。コスキンというのは、アルゼンチンの町の名前です。アルゼンチン最大の(世界最大でもある)フォルクローレ音楽祭が行われます。その模様は、アルゼンチンの全国テレビ放送で、1週間、毎日ゴールデンタイムに中継されるというものすごいものです。それに対して日本版のコスキン音楽祭は、アマチュア音楽家の祭典です。最初の頃は、初日(土曜)だけ演奏して、2日目は近くの河原で芋煮会をやっていたそうですが、次第に参加グループが増えたため、私が参加し始めた頃には、2日間日程になっていました。参加グループは、90年代初めは100グループ前後。それでも、初日の終演は深夜の1時2時頃でしたが、その後参加グループがどんどん増えて、初日の終演が朝7時、2日目の開演が朝9時というすごいこともありました。その後、10月第2週の3連休が固定化されたため、3日間の日程になったと聞いています。(3日間日程になって以降は参加していません)福島までは新幹線を使えばあっという間なのですが、いつも行きは在来線の快速ラビット号で宇都宮まで行き、黒磯・郡山と各駅停車を乗り継いで松川駅からJRバスで川俣に行ったものです。松川から川俣までは、かつて国鉄川俣線という路線があり(1972年に廃線)その廃線後は国鉄バス→JRバスが運行していたのです。朝9時頃上野を出て、川俣に着くのが午後2時過ぎでしたでしょうか、何とも気の長い話でしたが。(土曜日が仕事だったため、新幹線で行ったことも1回か2回ありましたが)2日間(当時の日程)骨の髄までフォルクローレ漬けという、とにかくすごいイベントです。演奏もしたけれど、よく飲んだなあ。一度、初日のトリを任されたことがあったのですが、メンバー全員、本番の演奏までにベロンベロンになってしまった。でも、我ながらたいしたもので、ベロンベロンになりながら、本番はまあなんとかちゃんと演奏したのです。全国からフォルクローレのファンが集まるばかりではなく、地元にもフォルクローレのグループがたくさんあります。日本中探しても、公立の小学校の課外活動でフォルクローレを演奏するところはここだけでしょう。↓2009年、35周年でした。(一番手前で太鼓を叩いている彼は、現在「キラ・ウィルカ」のメンバーでもあります)↓1989年、私か初めて参加する3年前の演奏です。わたし自身がこのイベントで演奏した映像は、残念ながらありません。写真だけ紹介します。1993年。ダンサ・エレンシア(踊り)の伴奏でギターを弾いています地元の小学生の演奏。1993年1996年。当時参加していた「ダンサ・エレンシア」と「グルポ・インカコーラ」一緒に記念撮影をしたみたいですさて、その福島県川俣町の名が、今回の地震以降(より正確に言うと原発の事故以降)、連日のようにマスコミに出てきます。言うまでもなく、放射能の影響を受けた町として、です。川俣は原発から半径30km以遠なので、避難地域から多くの人が避難してきていますが、同時に川俣町自体にも少なからず放射性物質が降りそそいでいます。東日本大震災:土壌の放射性物質、福島・川俣で最高値 南相馬のセシウムも福島・川俣町でも水道にヨウ素 国発表に遅れもう10年、このイベントから遠ざかっていますけれど、でも、この町のことをほんの少しだけ知っている人間の一人として、とても胸が痛い。頑張れ、川俣町!!と、東京から応援しています。-------(以下転載)国内最大のフォルクローレのイベント「コスキン・エン・ハポン」の開催地である川俣町がかつて経験したことのない地震災害に見舞われております。川俣町内はもとより、津波や放射能の汚染から逃れてきた浪江町・双葉町の住民約5000名が川俣のすべての学校や体育館に避難しております。住民は着の身着のままで避難しており大変つらい生活をしております。つきましては、全国からコスキンに来ていただいた方や、フォルクローレの愛する皆さんにお願いがございます。どうか、川俣で被災している人や川俣に避難している人に、100円でも200円でも義援金をお願いしたいと思います。口座は、コスキンの申込口座と同じです。郵便口座口座記号02240-1 口座番号41534名義 コスキンエンハポン実行委員会通信欄にメッセージを書いていただければ被災者の励みになります。このメッセージに賛同いただける方は、一人でも多くの方に呼びかけていただきたいと思います。この義援金は町役場を通してすべて被災者に渡します。どうかよろしくお願いします。コスキン・エン・ハポン事務局齋藤寛幸
2011.03.27
コメント(0)
-
チェルノブイリの2~6%の規模
福島第一原発事故、スリーマイル超えレベル6相当に東京電力福島第一原発の事故は、放出された放射能の推定量からみて、国際評価尺度で大事故にあたる「レベル6」に相当することがわかった。すでに米スリーマイル島原発事故(レベル5)を上回る規模になった。局地的には、旧ソ連のチェルノブイリ原発事故に匹敵する土壌汚染も見つかっている。放出は今も続き、周辺の土地が長期間使えなくなる恐れがある。原子力安全委員会は、SPEEDI(スピーディ)(緊急時迅速放射能影響予測)システムで放射能の広がりを計算するため、各地での放射線測定値をもとに、同原発からの1時間あたりの放射性ヨウ素の放出率を推定した。事故発生直後の12日午前6時から24日午前0時までの放出量を単純計算すると、3万~11万テラベクレル(テラは1兆倍)になる。国際原子力事象評価尺度(INES)は、1986年のチェルノブイリ原発事故のような最悪の「レベル7=深刻な事故」を数万テラベクレル以上の放出と定義する。実際の放出量は約180万テラベクレルだったとされる。今回は少なくともそれに次ぐ「レベル6」(数千~数万テラベクレル)に相当する。経済産業省原子力安全・保安院は18日、福島第一原発の1~3号機の暫定評価を「レベル5」と発表したが、今後放出量の見積もりが進めば、再検討される可能性が高い。土壌の汚染は、局地的には、チェルノブイリ事故と同レベルの場所がある。原発から北西に約40キロ離れた福島県飯舘村では20日、土壌1キログラムあたり16万3千ベクレルのセシウム137が出た。県内で最も高いレベルだ。京都大原子炉実験所の今中哲二助教(原子力工学)によると、1平方メートルあたりに換算して326万ベクレルになるという。チェルノブイリ事故では、1平方メートルあたり55万ベクレル以上のセシウムが検出された地域は強制移住の対象となった。チェルノブイリで強制移住の対象となった地域の約6倍の汚染度になる計算だ。今中さんは「飯舘村は避難が必要な汚染レベル。チェルノブイリの放射能放出は事故から10日ほどでおさまったが、福島第一原発では放射能が出続けており、汚染度の高い地域はチェルノブイリ級と言っていいだろう」と指摘した。金沢大の山本政儀教授(環境放射能学)によると、1メートル四方深さ5センチで、土壌の密度を1.5程度と仮定すると、飯舘村の1平方メートルあたりのセシウム濃度は約1200万ベクレルに上る。チェルノブイリの約20倍。「直ちに避難するレベルではないが、セシウムは半減期が30年と長い。その場に長年住み続けることを考えると、土壌の入れ替えも必要ではないか」と話した。健康への影響はどうか。チェルノブイリ原発事故では、強制移住の地域では平均50ミリシーベルト程度の放射線を浴びたとされる。しかし汚染地での長期の住民健康調査では、成人では白血病などの発症率は増えていない。甲状腺がんは増えたが、事故当時小児だった住民が放射性ヨウ素で汚染された牛乳などを飲んで内部被曝(ひばく)したためとみられている。飯舘村の24日午後までの放射線の総量は、3.7ミリシーベルトだ。長瀧重信・長崎大名誉教授(被曝医療)は「チェルノブイリ原発事故後でも小児甲状腺がん以外の健康障害は認められず、すぐに健康を害するとは考えにくい。高い汚染が見つかった地域では、データをもとに住民と十分に話し合って対応を考えてほしい」と話している。 ----------国際原子力事象評価尺度によればレベル5 放射性物質の外部流出が数百~数千テラベクレルレベル6 〃 数千~数万テラベクレルレベル7 〃 数万テラベクレル以上となっています。今回の事故の放射性物質放出量が、現段階までで3万~11万テラベクレルということは、「少なくともレベル6、おそらくレベル7」という方が、より正しいでしょう。しかも、これはあくまでも「現段階(24日午前0時)で」の話です。原発からの放射能の流出は、止まったわけではないので、この数字が今後更に大きくなる可能性も充分ある。ちなみに、京都大学原子炉実験所の原子力安全研究グループによると、チェルノブイリで放出されたセシウム137の総量は、広島原爆の800倍とのことです。一方、ウィキペディアの記述によると、チェルノブイリで外部に放出された放射性物質の総量は広島原爆の400倍だそうです。これらの数字から換算すると、今回の原発事故によって、広島原爆のおよそ8~50倍の放射性物質が放出された、ということになります。放射性物質の半減期は長いものも短いもの様々です。半減期の短いものの中には、1秒以下というものもあるので、原爆が爆発した瞬間には大量の放射能が放出されるものの、時間ごとに加速度的に放射能の量は減少していきます。それに対して、原発は、半減期が極端に短い放射性物質は、炉の外に放出された時点ですでに減衰しています。つまり半減期が比較的長い放射性物質だけが大気中に放出されるわけで、時間が経ってもなかなか放射能が減衰しない傾向があります。その意味では、原爆による放射能汚染より原発による放射能汚染の方が、より長期にわたる被害をもたらすと言えます。それでも、「現段階では」今回の事故はチェルノブイリより遙かに小さな規模の事故(20分の1から50分の1)とは言えます。ただし、チェルノブイリ事故のあった旧ソ連より、日本の方が遙かに国土が小さく、人口密度が高い、という事実にも留意すべきでしょう。チェルノブイリ事故の後強制移住の対象となったのは事故当初は約11万人、その3年後に新たな汚染がわかり、更に27万人、合計40万人とされているそうです。避難対象地域は、何と1万平方キロ。後に縮小されたけれど、現在でも3700平方キロが立ち入り禁止になっているとのことです。残念ながら、福島第一原発の事故においても、同様に広大な面積が長期間の立ち入り禁止になることは避けられないでしょう。仮にチェルノブイリの2~6%という放射性物質の量が立ち入り禁止区域の面積に比例すると仮定すると、70~200平方キロが数十年にわたる立ち入り禁止地区ということになります。永久的移住を要する人数は、果たしてどのくらいでしょうか。チェルノブイリの2~6%という人数では済まないに違いありません。朝日の記事には、「直ちに避難するレベルではないが」「すぐに健康を害するとは考えにくい。」などという文字が躍っていますが、「直ちに」「すぐに」ではなくとも、長期的な影響はどうなのか、という疑問には何も答えていません。1平方メートルあたり4万ベクレル以上の放射性物質がある場合、放射線管理区域に指定されます。飯舘村の数値はそれを遙かに上回る。そりゃ、レントゲン室に毎日寝泊まりしたからといって、「すぐに健康を害するとは考えにくい」でしょうが、かといって、長期的に影響がまったくない、ともとても思えません。「汚染地での長期の住民健康調査では、成人では白血病などの発症率は増えていない。」ともありますが、これについては、以下のような反論があります。チェルノブイリ原発事故の「死者の数」と想像力昨年9 月、IAEAやWHO など国連関係8団体とウクライナ、ベラルーシ、ロシア政府の専門家で構成される「チェルノブイリ・フォーラム」がウィーンのIAEA本部で国際会議を開き、「チェルノブイリ事故による放射線被曝にともなう死者の数は、今後発生するであろうガン死も含めて全部で4000人」という報告を行った(1)。これを受けて日本の新聞は、「数万~数10 万人と言われていた従来の死者の数に比べ大幅に減った」と報道した。(中略)総死者4000 人というフォーラム報告の結論は、「放射線被曝にともなう死者の数」について評価したものである。その内訳は、これまでに確認された死者が56 件(急性放射線障害28 人、急性患者のその後の死者19 人、子ども甲状腺ガン死9人)、また被災者60 万人に予測されるガン死3940 件、両方を合わせて総死者4000件ということになっている。揚げ足取りに近いが、「これまでに確認された死者」には、「これまでに確認されていない死者」は含まれていない。子ども甲状腺ガン死9人の内訳は、ベラルーシ8人、ロシア1人となっていて、不思議なことにウクライナがなかった。私は、昨年10月にウクライナ・キエフの内分泌研究所を訪問する機会があった。その病院の話では、子どもの甲状腺ガンはこれまでに約400例で、そのうち約15例が死亡した、とのことだった。つまり、ウクライナで子どもの甲状腺ガン死がなかったのではなく、フォーラムが「確認していなかった」だけであった。チェルノブイリの事故処理作業者のうちには、大変な放射線量のなかで、原子炉建屋のまわりに散乱したガレキを片づけ、破壊された原子炉をコンクリートで囲む「石棺」の建設作業に従事し、かなりの被曝を受けた人々がいた。夫や息子が早死した原因は事故処理作業だった、と多くの妻や母親が訴えている。事実を確認するすべは私にはないが、そうした死者は「確認されていない」としてすべて無視したのがフォーラム報告の数字である。56 人という数は、「これ以下ではない」というミニマムの死者数と考えている。
2011.03.26
コメント(0)
-
実は、昔原発の見学に行ったことがあります
1999年のことです。その頃付き合っていた人が、原発の見学ツアーに申し込んだら当たった、というので、一緒に行ったことがあります。自分で申し込んだのではないので、主催者ははっきり覚えていないのですが、多分東京電力ではなかったかと思います。しかし、行ったのは、日本原子力発電(原電)の東海第二原発でした。もう12年前のことなので、細かいことは正確な記憶がありません。そのとき、定期検査の準備中とかで、実際には原発は稼働していませんでした。そうでなかったら、一般人が原発の中には入れないでしょう。ま、素人がちょこっと中をのぞかせてもらっただけのことだし、記憶もかなり曖昧なので、そのとき見たあそこがどう、ここがどうという具体的な話はできません。ただ、そのとき一つだけよく覚えていることがあるのです。アンケートがあったので、私はかなり正直に、原子力は危険があるのではないかという趣旨のことを書きました。無料招待のバスツアーに参加しておいて、批判的なことを書くのも大人げなかったかも知れませんが。そうしたら、後で、彼女をつうじて「危惧には及びません」的な文章を送ってきたんですよ。これには驚きました。何故って、そのアンケートには記名をしなかったからです。もちろん、そのツアーの客層(平日だったので、ほとんどは主婦層で、若い参加者は私と彼女くらいだった)から考えて、無記名でも誰が書いたかは容易に推測できるだろうとは思いましたけれど、それにしても無記名アンケートの主を特定して文章を送ってくるというのは、どういう神経だ?と思いましたね。ま、しかしそのときの彼女には、その1年後くらいにフラれてしまったのですが。(この記事、相棒には見せられん^^)ところで、この記事を書くために東海第二原発をウィキペディアで調べ、更に原電という会社を調べたら、その社員だったことのある人物として、与謝野馨の名が掲載されていました。昨日の記事で紹介した、地震があっても原発を続けるべき、という発言の主です。なるほど、原子力発電擁護の発言のうらには、そういう経歴があったのか。
2011.03.24
コメント(2)
-
頭上のシャンデリア
原発は重要エネルギー源=地震多いのは運命―与謝野経財相与謝野馨経済財政担当相は22日の閣議後会見で、福島第1原発事故に関連し、「日本中どこの地域を探しても環太平洋火山帯の上に乗っている国だから(地震が多いという)その運命は避けようがない」と述べた。これは原発推進の立場から地震が多いことは原発を止める理由にならないとの考えを強調した発言。同相は「将来とも原子力は日本の社会や経済を支える重要なエネルギー源であることは間違いない」と語り、あくまでも原発を続けるべきだとの考えを示した。-------------我々のいる部屋には、明るくてきらびやかなシャンデリアがあるのです。とても重いのですが、絶対安全なように頑丈に作ってあるし、しっかり固定されているから大丈夫、とこれまで説明されてきました。だけど、なんだか急に梁がメキメキと言って、シャンデリアが傾いて、一部が頭上に降ってきてちょっと怪我をした。さあ大変だ、どうしようか、あんなものが頭上に落ちてきたら、大けが、いや死ぬかも知れないぞ。シャンデリアは取り外して小さな電球にしよう。しかし、待て、小さな電球は暗くて不便だぞ。シャンデリアは重くて、落ちてきたら大変だけど、でも明るくて便利だぞ。というのが、原発を巡る今の状況でしょう。与謝野の言っていることは、落ちてきたらそのときはそのときだ、でも明るいシャンデリアの方がよい、ということ。落ちてきた場合のリスクをきちんと認めた上でそのように主張するなら、それはそれで一つの見識ではあります。確かに電気は便利です。便利を取るか危険性を取るか、さあ、どうしたらいいのでしょうね。
2011.03.23
コメント(2)
-
フルート関係の知人が亡くなりました
知人といっても、ネット上で知り合った方で、直接お会いしたことはないのですが、今は閉鎖されたマイ・サウンドという音楽SNSで自分の演奏を公開していた頃、よくコメントをいただいた方です。メールのやり取りもありました。フルートの上手い方でした。今回の震災で大きな犠牲の出た、ある町(しかも、海の目の前)に住んでいらっしゃったそうです。実は、地震の後、mixiでログインの形跡がないことに気がついて、密やかに不安を感じていたのですが、避難所にいたらネットに接続できるような環境じゃないだろうし・・・・と思っていました。が、意を決して、昨日おそるおそる知人に問い合わせたら、遺体が発見された、とのことでした。非常に残念です。
2011.03.22
コメント(0)
-
想定が甘すぎたのでは (一部訂正)
福島第1原発 周辺の津波 14メートル以上の可能性東京電力福島第1原発周辺で、14メートル以上の津波が押し寄せた可能性があることを21日、経済産業省原子力安全・保安院が明らかにした。設計時に想定した津波の高さの3倍近い。東電と保安院は、津波が原発の安全の根幹にかかわる原子炉の冷却機能を喪失させ、今回の事故につながったとみており、他の原発でも再検証が求められるのは必至だ。保安院は同日午後の会見で、「津波の高さは一番高い所で(水が)触れたものを見れば分かる。未確認だが、14メートルの高さの駐車場を超えていると聞いた」と説明した。東電が同原発で設計時に想定した津波の高さは約5メートル。津波は浅い海岸付近に来ると波の高さが急激に高くなる特徴があるほか、連続して押し寄せるため、沿岸に到達した津波の高さ以上まで駆け上がる。今回、同原発では、3号機を襲った東西方向の揺れの強さが507ガル(ガルは加速度の単位)と、保安院が耐震安全の基準値として認めた数値の1・15倍だったのを除き、揺れはおおむね基準値を下回った。しかし、敷地内にある原発に送電するための鉄塔が倒壊。さらに津波の影響で、原子炉を冷やすための緊急炉心冷却装置(ECCS)を駆動する非常用電源が6号機を除いて使えなくなり、外部からの受電設備も水没して事態を悪化させたとみられる。東電は今回の事故を、設計時の想定を超えて炉心の損傷につながるような「過酷事故(シビアアクシデント)」と認めている。保安院によると、東電は複数の対策シナリオを国の指示で02年に作成したが、津波による被害は考慮されていなかった。国の「原子力白書」でもシビアアクシデント発生の可能性について「工学的には考えられないほど低い」などとしていた。---------------実際の津波の高さが14mというのはともかく、設計時に想定した津波の高さが5mというのは、過去に東北地方を何度も襲ってきた津波被害の実績から見て、あまりに甘い見積もりだったと言うしかないでしょう。今回の地震について、1000年に一度の地震という防災関係者がいるそうですが、それは果たしてどうかと私は思います。1896年明治三陸沖地震 死者行方不明者約22,000人・最大波高38m1933年昭和三陸沖地震 死者行方不明者約3,000人・最大波高28mこの2つの津波も、相当にでかかった。それと比べて、今回の津波が圧倒的にでかかったと言えるのかどうかは、今の時点では定かではありません。仮に今回の地震が本当に1000年に一度だったとしても、想定波高が5mというのでは、明治三陸沖地震にも昭和三陸沖地震にも歯が立たないのは明白です※。はっきり言ってしまえば、福島第一原発が1896年や1933年に存在したら、今回と同じような事態になった可能性が高い。※2つの三陸沖地震の最大波高は、いずれもリアス式海岸の奥で記録されたものです。湾口が広くて奥が先細りのリアス式海岸では、津波の波高は高くなりやすいので、福島第一原発があるような直線の海岸では、波高はもっと低いと思われます。しかし、それでも5mということはないでしょう。さて、一部には、福島第一原発が老朽化しているところに問題があった、という主張があります。福島第一原発の老朽化が問題視されていたことは事実ですけれど、新しい原発だったらこんな事故にはならなかったというのは、正しい見方とは思えません。福島第一原発の事故は、地震や津波で直接的に建屋や原子炉が破壊されたわけではありません。それらの構造物は、確かに地震にも津波にも耐えた。だから、老朽化が原因で起きた事故ではないことははっきりしています。問題は、外部からの受電施設、送電線の鉄塔、非常用の発電機の大部分、発電機の燃料タンクなどが、津波によって破壊されたり浸水で動かなくなったことです。このブログで何度か書きましたが、建屋と原子炉がどんなに強固でも、原発に付随するシステムや、無数のパイプ、保安システムなどのすべてをそれと同様に強固にすることはできません。今回の事故では、非常用発電機がウィークポイントになりました。この事故についてウォールストリート・ジャーナルに、非常に興味深い記事が掲載されています。それによると「福島第1原発の非常用ディーゼル発電機~は地下にあり、安全な部屋に隔離されていた。」「原子力安全・保安院のスポークスマンによれば、福島第1原発の非常用発電機の設計は、日本の他の原発に『かなり普遍的』だという。同スポークスマンは、ディーゼル発電機の設置場所、とりわけエレベーションが問題との議論に反論し、原発は一定の規模の津波に耐えられると結論していたと述べた。同スポークスマンは『11日の大地震に続く津波がわれわれの想定を上回っていたのは疑いない。それが問題だ』と述べた。 」とのことです。つまり、他の原発でも非常用発電機の配置は福島第一原発とほぼ同様で、しかも今回の津波は想定を上回っていたから事故は不可抗力だというのですから、この場所にあったのがどんなに最新の原発だったとしても、同じ津波が来れば同じ事態になったということになります。しかも、すでに見たように、実際には津波の想定が、過去115年間に2度来た津波を防げない程度の甘いものでした。ということは、つまり日本の原発は数十年ごとに来襲する津波災害に対してまったく無力であるということになるわけです。とりあえず、起きてしまった事故は仕方がない。いや、仕方がないでは済まないのですが、とにかく今は何とか事故が収まることを祈るしかありません。しかし、問題は日本の原発は福島第一以外もすべて海岸沿いにあるという事実です。ひょっとすると、福島第二原発と女川原発が福島第一原発と同じ事態にならなかったのは、単なる幸運に過ぎなかったのかも知れません。特に、以前より問題視されているのは、東海/東南海/南海地震の危険域にある浜岡原発です。私は、先日起こった富士山付近を震源とする地震(富士宮で震度6強を記録した)以来、どうも嫌な予感がして仕方がないのです。ま、嫌な予感というのは、何ら科学的根拠に基づかない憶測に過ぎませんが、東海/東南海/南海地震は、近い将来起こ危険が高いというのは、科学的・歴史的な根拠に基づく危惧です。30年以内に巨大地震が発生する確率は、東海地震87%、東南海地震60%、南海地震50%とされています。そして、歴史的に見ると、この3つの地震は連動して短期間に連続して(ときには同時に)起こることが多い。とりあえず、浜岡原発だけでも、何とかしないとまずいんじゃないでしょうか。※訂正です。改めてウィキペディアで「明治三陸沖地震」を調べたところ、「波高は、北海道の襟裳岬では4m、青森県三戸郡八戸町近辺(現・八戸市)で3m、宮城県牡鹿郡女川村(現・女川町)で3.1m」となっていました。福島における波高は記載がありませんが、これらの地域との対比で考えると、5m以下である可能性は充分あると思われますので、該当部分は取り消します。ただし、明治三陸沖地震という個別の例はともかく、日本国内の他の場所では、リアス式海岸ではない地形でも5mを超える津波が押し寄せた例はあります。具体的には、北海道南西沖地震(1993年)における奥尻島や日本海中部地震(1983年)における秋田・青森の両県では、リアス式海岸ではないところで10mを超える津波の波高が記録されています。従って、5mという想定波高は、やはり甘かったと言わざるを得ないでしょう。
2011.03.22
コメント(0)
-
災害に弱い社会 そして計画停電追記
地震があった日のことです。私はあるところにでかけたのですが、そこで灯油ストーブを見かけました。灯油ストーブなのですが、しかしコントロールは電気なのです。たまたま、近くにいた人がうっかりコンセントに足を引っかけて、抜けてしまったら、たちどころに火が消えた。保安機能としては万全ですが、「ああ、これって停電したら使えない灯油ストーブなのね」と気がつきました。現代文明は電気と一心同体ということを痛感します。電気が動かないと、ガス器具や灯油のストーブですら、動かないものが多いのですから。我が家の場合、ガス暖房と風呂釜は電気がないと動きません。ただ、水道と台所のガスレンジは電気なしでも動くのが救いですが。オール電化住宅などというのは、こういうとき最悪なことになります。オール動かない住宅ですからね。でも、ガス器具なども、可能であるなら電気なしでも動くものを購入した方が、停電対策としては有効ですね。ただし、地震に対しては総じて電気よりガスの方が弱い傾向があるし、灯油のストーブも、今回の被災地のように燃料が入手困難になると、使えなくなってしまいますが。※そう考えてみると、やっぱり太陽光発電は災害時にはいいかも。日中なら、停電しても最小限の電源を確保できますからね。それにしても、東京自体が被災地になったわけではないのに、あっという間に店頭から商品が消え、ガソリンほか燃料が消え、電車の運行も不定期。我が家の近所のスーパーは、今日現在は特定のいくつかの商品(カップラーメンなど)を除いて商品は豊富にありましたが、ガソリンスタンドは長蛇の列でした。私はずっと前に、あるスーパーマーケットに4年ほど勤めていたのですが、当時のスーパーはバックヤードにある程度の商品在庫を持っていました(お店によって、バックヤードが広いところと狭いところ、まちまちでしたが)。しかし、私がこの業界を離れて17年、今は、商品在庫をできるだけ持たずに、こまめに配送を受けるスタイルが主流になったと聞きます。スーパーの店頭からあっという間に商品が消えた要因の一つには、そのこともあったようです。社会全体が、「備蓄」というものを無駄なものと捉えて、備蓄を持たないようにしてきた傾向は否めません。平時はその方が確かに効率が良いのでしょうが、「万が一」のときにはたちどころに破綻をきたす。そのような災害に弱い社会の弱点が、今回露呈したように思います。そして、昨日書いた計画停電に関して続報です東電の発電能力、震災前7割に回復へ 2火力再開で 東京電力の藤本孝副社長は19日、東日本大震災で停止した東扇島火力発電所(川崎市)を3月中、鹿島火力発電所(茨城県神栖市)を4月中に全面的に運転再開する見通しを明らかにした。他の火力発電所の稼働率も引き上げる。4月末までに発電能力を現状より2割高い約4200万キロワットに増やし、震災前の約7割に回復させる。ただ需要が拡大する夏場の水準にはまだ届かない。地震で停止した東電の発電所は福島第1、第2原子力発電所(計900万キロワット強)と、東扇島、鹿島、広野(福島県広野町)、常陸那珂(茨城県東海村)の4カ所の火力発電所など。このうち、東扇島の発電能力は全体で約200万キロワット、鹿島全体で約400万キロワット。2つの火力発電所が全面的に再稼働すれば、合計で約600万キロワットの発電能力を上積みできる。東電は稼働中の火力発電所設備でも定期点検の期間短縮などで設備稼働率を引き上げる考え。ガスタービン発電設備の調達も進めており、電力不足解消のため、火力の発電能力を積み増す。東電の被災後の電力供給能力は他社からの受電分も含めて約3400万キロワット。火力発電所の再立ち上げなどが進めば、供給能力は大幅に増える。しかし広野と常陸那珂は需要期の夏までに「復旧できるか今のところ分からない」(藤本副社長)という。東電は通常、冬場で5000万キロワット、夏場で5500万~6000万キロワットの電力供給力が必要。電力不足を完全に解消するには時間がかかる見通しで、東電は「夏には東京都の千代田、中央、港の3区を除く20区でも本格的に計画停電を実施せざるを得なくなるだろう」としている。----------というわけで、暖かくなるとともに計画停電はいったん終了となりますが、夏場には今より大規模で再開ということになりそうです。ないものはないんだから、それは仕方がありません。我々の頭上に大量の放射能がまき散らされる事態さえ回避できれば、計画停電は仕方がない。
2011.03.21
コメント(2)
-
計画停電の今後
自衛隊と東京消防庁の放水に、ある程度効果があったようです。とりあえずは最悪の事態の一歩手前で踏みとどまっている、というところでしょうか。ただし、これはあくまでも応急処置です。継続的な冷却水の循環がなければ、また同じことが起こります。これから先、まさか何ヶ月も現場に消防車を貼り付けて放水し続けるわけにもいかないでしょうから、とにかく原発自体の冷却システムが再稼働し、自力で冷却できるまではまだまだ予断を許さない、というところでしょう。それに、核燃料貯蔵プールと原子炉が外気に対してむき出しのままでいつまでも放置しておくわけにはいきませんから、外壁を補修しなければならないでしょうが、いったい誰がその作業をやるのか、非常に難しい問題です。---ところで、数日前の記事に電力供給の予測について書きましたが、どうやら訂正が必要なようです。「鹿島火力発電所の復旧急ぐ」東電副社長 東京電力の藤本孝副社長は17日夜の会見後、記者団に対し、「鹿島火力発電所の復旧が最優先」と述べた。同発電所は440万キロワットの発電能力がある。ただ、復旧時期の見通しについては明言を避けた。一方、夏場の需要期に向けて発電能力が30万キロワット規模のガスタービン発電設備を既存の発電所などに複数台増設していく考えも示した。ただ「通信会社の非常用発電機を一回り大きくしたようなもの」(藤本副社長)であることから、限界がある。停止中の原子炉が残る柏崎刈羽原発の全面再稼働については、「国民感情からいって相当難しい」と現時点で否定的な見方を示した。----------休眠火力発電所の立ち上げに2~3カ月 老朽化、原油調達など課題も東日本大震災で原子力発電所や主要な火力発電所が停止に追い込まれ、計画停電の実施を余儀なくされている東京電力などは、被害が軽微な火力発電の早期復旧を急ぐとともに、休眠している火力発電所を総動員し、中長期的な供給力の回復を急ぐ。東京電力管内では現在、事故の起きた福島第1原発と、停止中の第2原発の約910万キロワットに加え、火力発電所も、広野(福島県広野町)、大井(東京都品川区)など5発電所の9基、約715万キロワット分が、停止に追い込まれている。東電はこのうち、大井の2号機や東扇島1号機(川崎市川崎区)など、被害が軽微なものを再起動させ、早期復旧を目指す。一方で、地震や津波被害による破損が激しい広野や、常陸那珂火力発電所(茨城県東海村)の復旧には相当時間がかかるとみられ、休眠中の火力発電の再開を検討している。資源エネルギー庁は、休眠火力発電所の立ち上げには最低でも2~3カ月かかるとしているが、比較的早い再開が期待できるのは、横須賀火力発電所(神奈川県横須賀市)の7、8号機だ。同発電所は、平成19年7月の新潟県中越沖地震による東電柏崎刈羽原発の停止に伴って再開させた。同原発の主力の6、7号機の再開後、22年4月に長期停止を視野に入れて停止したばかりで、比較的早期の立ち上げが可能とみられる。東電は、3発電所、10基で約280万キロワット分の休眠火力発電所を持つ。(以下略)----------つまり、現在停止中の柏崎原発2~4号機の再稼働は当分できない広野火力発電所2・4号機・常陸那珂火力発電所1号機の修理もかなり長期ということです。現在の東京電力の電力供給は、約3400万キロワットと報道されています。一方、停止している発電所は、東京電力のプレスリリース(3/19現在)によると、以下のとおりです。福島第一原発(約470万KW)福島第二原発(約440万KW)柏崎原発2~4号機(約330万KW)広野火力発電所2・4号機(160万KW)常陸那珂火力発電所1号機(100万KW)鹿島火力発電所2・3・5・6号機(320万KW)東扇島火力発電所1号機(100万KW)※前の記事では大井火力発電所2・3号機(70万KW)も停止と書きましたが、その後復旧したようで、名前が消えています。全部合計すると1900万KWあまりになります。このうち、鹿島火力発電所と東扇島火力発電所(計420万KW)については復旧が近いようですが、それ以外(計1500万KW)の復旧は当分ない(というか、福島第一原発の復旧は永久にないでしょう)。その代わり休眠発電所(計280万KW)が少なくとも夏場前には間に合いそうだ、ということです。そうすると、差引すると、現状の発電力3400万KW+近いうち復旧予定420万KW+休眠発電所の再開280万KW=合計4100万KWが、近い将来復旧するであろう電力供給量ということになります。これでは、現在はともかく夏場の電力消費にはまったく足りません。2010夏の東電管内の最大電力は、手元の資料では不明ですが、7月21日に5918万KWを記録したという報道があるようです。(その後も猛暑が続いたので、更新されたかも)2009年は7月31日の5450万KWが最大です。(東電のでんき予報より)2008年は何度か6000万KWを超えています。(こちらのブログより)2007年は8月22日6147万KW(同じブログより)というわけで、上記の供給力は、夏場の電力消費に対して1300万KWから2000万KWほど足りないという計算になります。他の電力会社やJR(自前の発電所を持つ)などからの融通は、現状以上には難しいでしょう。最大の融通元である東北電力は地震の影響で、自身が計画停電をしている状況ですし、中部電力以西は周波数が違い、周波数変換施設の能力は100万KWしかなく、すでに能力いっぱい融通されているからです。ということは、夏場には今より更に電力不足が著しい、つまりより大規模な計画停電が必要になる、ということになりそうです。ただし、どうも計算が合わない部分があります。上記の停止している発電所を合計すると1920万KWの発電能力となり、現在の発電能力3400万KW(他社からの融通含む)と合算すると、東電全体の発電能力が約5300万キロワット(他社からの融通を除くと5100~5200万KWくらい?)になります。しかしウィキペディアの「東京電力」の項目にある発電所の供給能力を合算すると6265万KWになる。1000万KWくらい計算が合いません。休眠している火力発電所が280万KW分あるそうですが、それを引いても700~800万KWほど合わない。どうなっているんでしょう。停止しているのに公表されていない発電所が、他にもあるんでしょうか。もっとも、発電能力を6265万KWとして計算しても、そこから停止している発電所の供給力(約1400万KW)を引いて、他社からの融通(100~200万KW)を加えても・・・・・・最大5000万KW以下です。前述の毎年夏の最大電力と比べて大幅に足りない状況に変わりはないようです。
2011.03.20
コメント(0)
-
やはり、そういうことか・・・・・(原発事故)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110318-00000015-mai-soci<福島原発>東電全面退去打診 首相が拒否…水素爆発2日後東京電力福島第1原発の高濃度放射能漏れ・爆発事故で、東電側が14日夜、同原発の職員全員を退去させる方針を政府に打診していたことが分かった。現地での作業継続は困難と判断したとみられ、自衛隊と米軍にその後の対応を委ねる構えだったという。菅直人首相は打診を拒否し、東電側も一部職員を残すことになったが、東電はその時点で高濃度の放射線被ばくが避けられない原子力災害に発展する可能性を認識していたことになる。複数の政府関係者によると、東電側が14日夜、「全員退去したい」との意向を枝野幸男官房長官と海江田万里経済産業相にそれぞれ電話で申し入れた。両氏は認めず、首相に報告した。首相は15日午前4時過ぎ、清水正孝・東電社長を官邸に呼び、「撤退はあり得ない。合同で対策本部をつくる」と通告。その後、東京・内幸町の東電本店を訪れ、「東電がつぶれるということではなく、日本がどうなるかという問題だ」と迫ったという。政府当局者は14日夜の東電側の打診について「全員を撤退させたいということだった」と明言した。一方、東電側も首相への不満がくすぶる。東電によると、同原発では協力会社と合わせ計4000~5000人が働いているが、現在、現地に残っているのは約300人。発電所の制御や復旧などの作業にあたっている。東電関係者によると、15日早朝に首相が東電本店を訪れた際、事故対応に追われる社員が会議室に集まったが、首相は「こんなに大勢が同じ場所にいて危機管理ができるのか」と非難した。東電関係者は「『撤退は許さない』というのは『被ばくして死ぬまでやれ』と言っているようなもの」と漏らした。東電幹部の話 (必要最低限の作業員を残し、あとは退去する)部分的な撤退を検討したのは事実だが、全員撤退を検討した事実は絶対にない。------------先日の記事へのコメント欄で、Bill McCrearyさんが指摘されているとおり、菅首相が東京電力本社に乗り込み、「撤退などあり得ない。覚悟を決めてください。」と怒声を発したと言われる事件の伏線には、このことがあったようです。東電関係者は、「『撤退は許さない』というのは『被ばくして死ぬまでやれ』と言っているようなもの」と言っているそうですが、では自衛隊・警察・消防関係者なら被爆して死んでも良いわけですか?より重要な問題は、自衛隊や警察・消防は原子炉を運転できない、という事実です。報道によると、電源の一部が復旧して、冷却システムが稼働できるかもしれない、とのことです。(実際に稼働できたかどうかの報道はまだありませんが)それも、現場で踏みとどまっている従業員がいるからです。彼ら以外に冷却システムの動かしかたを知っている人間はいないでしょう。その原発従業員が現場からいなくなってしまったら、もはや誰にも原発のコントロールはできません。まさしく、東京電力には「覚悟を決め」てもらう必要がある。その意味で、菅が東電に対して言ったとされる言葉は、まったくそのとおりだと私は思います。もうひとつhttp://mainichi.jp/select/weathernews/news/20110319ddm001040039000c.html東日本大震災:福島第1原発事故 国内最悪レベル5 未明の放水東日本大震災で被災した東京電力福島第1原発の事故で、経済産業省原子力安全・保安院は18日、原子力施設事故の国際評価尺度(INES)で1~3号機について、国内では最悪の5とする暫定評価の結果を発表した。5は79年の米スリーマイル島原発事故と同じレベル。INESは、国際原子力機関(IAEA)が定めた世界共通の尺度で、0~7までの8段階で評価する。第1原発4号機と第2原発1、2、4号機はレベル3とした。これまで史上最悪の原発事故と言われるチェルノブイリ事故(旧ソ連)はレベル7。国内では99年のJCOウラン燃料加工施設臨界事故がレベル4で最悪だったほか、福島第1原発1号機の事故について今月12日、保安院がレベル4と暫定評価していた。(以下略)--------------納得しがたい判定です。4号機は、確かに原子炉本体は点検中で燃料もありませんでしたが、使用済み核燃料保管プールが沸騰して火災が発生、建屋が吹っ飛んだという状況です。15日に、3号機付近で毎時400ミリシーベルトという強い放射線が検出されていますが、この主な発生源は3号機ではなく4号機であると報道されています。その4号機の事故評価が、どうして1~3号機より軽いのか。スリーマイル島の事故も重大ではありましたが、周辺地域での放射線量は最大でも1ミリシーベルト程度だったと報じられています。一方、今回の事故では、福島第一原発正門付近(つまり敷地の境界)で毎時10ミリシーベルトが観測されています。更に一時中性子線も計測されている。中性子線は核分裂の際に放出されますから、それが検出されたということは、遮蔽されていない場所で臨界(核反応)が起こってしまった可能性があります。これらの状況を総合して考えると、今回の事故がスリーマイル島と同程度の規模とは、とても思えません。幸い、チェルノブイリと同程度にまでは、まだ至っていません。(このまま、何と終息して欲しいと願うばかりです)そう考えると、レベル5ではなく、6ではないのかと私は思います。海外の専門家も、そのように判定しているようです。福島原発事故、スリーマイル以上=深刻さは「レベル6」か-仏核安全局第一原発事故はレベル6または7…米機関が見解原子力保安院は、この期に及んでもまだ、事故をできるだけ過小評価したいのかなと疑ってしまいます。
2011.03.19
コメント(0)
-
本気でやるつもりかね
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110317-00000130-jij-spoセ、予定通り25日=パは4月12日に延期―プロ野球開幕プロ野球のセ、パ両リーグは17日、東日本大震災に伴って再検討していた公式戦開幕日を、セは予定通り25日とし、パは4月12日に延期すると発表した。記者会見した加藤良三コミッショナーは「セとパでは事情が違う。タイミングがずれるのはやむを得ない。夢と希望を与えるのがプロ野球の使命」と語った。12球団は開幕日などの見直しを15日に協議。セは予定通りで、楽天の本拠地・仙台市が被災したパは延期する方針をまとめた。同日の実行委員会では結論が出ず継続協議としたが、両リーグの方針は変わらず、17日の持ち回り実行委で承認した。パは4月12日以降のカードを変えず、それまで予定されていた44試合も新たに日程を組む。例年通り1球団144試合を実施し、クライマックスシリーズも行う。また両リーグは今季の全試合を復興支援試合とし、義援活動に取り組む。セの開幕には選手の反発が残っており、労組日本プロ野球選手会の新井貴浩会長(阪神)は「選手会の要望が受け入れられず悔しい。被災者、原発の問題、避難所の方々を思うと、本当に今開幕していいのか」と語った。-----------確かに巨大災害の時こそ「夢と希望」が必要だというのは分かります。「非常時」だから「不要不急」なものや娯楽はすべて排除というのでは、経済はますます萎縮するばかりです。それは分かるのですが、かといって、程度というものがあります。電力が足りるか足りないかというギリギリの状況にある今、それでも3月25日に予定通りプロ野球を開幕するというのは、どうなのでしょう。何ヶ月も待てというならともかく、2週か遅らせるというだけの話なのに。よりによって、開幕戦のセリーグのカードはすべて6時開始のナイター(いかにも照明に電気を食いそう)で、2試合は東京地区(東京ドームと神宮)なのです。数万人の観客が帰宅する際の交通機関が正常に運行される保証もありません。報道によると、セリーグの3月25日開幕は、読売のナベツネの意向で決まったようです。誰も、「それはいけません」と言える人がいないのか、選手会がストをやらなければ止まらないのか・・・・・・・・。ところで、原発ですが、かろうじて自体のさらなる悪化を食い止めている状況のようです。いや、もうすでに充分すぎるくらい事態は悪化しているのですが、これ以上の事態の悪化はチェルノブイリ級の悪夢です(もう、すでにスリーマイル島事故のレベルは遙かに超越してしまっていると思います)。明日になれば電源が復活するとか、それで何とかこれ以上の放射能放出が食い止められればいいのですが、果たして・・・・・・。今日3月17日は、電力供給がギリギリだったようですね。本当は、勤務終了後に職場で人事異動に伴う配置換えの引っ越しをする予定だったのですが、電車が動かなくなる危険があるというので、急遽延期して、あわてて帰宅しました。その時点では、地下鉄はまだ平常とあまり変わらない混みかたでしたが。明日以降も綱渡りの電力供給が続くようです。予報によると、東京の明日朝の最低気温は0度!3月も後半だというのに、ずいぶんな寒さです。目下のところ、東京23区のうち19区は計画停電を実施していないようです。都内も計画停電を実施するしかないんじゃないかなあ。たとえば、3月25日あたりは文京区を午後6時から計画停電区域に入れるといいかも。(東京ドームの開幕戦の時間)
2011.03.17
コメント(8)
-
三重苦
地震、原発事故、物不足という三重苦が続いています。昨日夜の地震、東京は震度3でしたけれど、明らかに「遠方のでかい地震」の揺れ方でした。そうしたら、案の定静岡県で震度6強。そして、震源地が富士山のすぐ南。何となく気になるところですよね。今のところ、地震学者は「東海地震と直接の関係はなし」と言っています。それが事実なら(事実であってほしい)、富士山の噴火はありません。なぜなら、以前の記事にも書きましたが、少なくとも有史以降過去1000年以上の間、富士山の噴火は東海/東南海/南海地震に伴って起こってきたからです。だから、逆に言えばもし富士山が噴火することがあるとすれば、それは東海地震・東南海地震・南海地震・富士山噴火という巨大災害ドミノ倒しの最終シーンとなる可能性が高いわけです。そんな悪夢は見たくありませんし、今のところは高い可能性があるとは言えないと思うのですが、今晩も大きめの地震が2つあったし、どうなのでしょう。ところで、計画停電はいつまで続くのでしょう。私の個人的な状況を言うと、昨日の帰宅時から急激に鉄道の運行状況(混雑状況も)が改善してきたようです。ただし、路線によっては、まだまだのところもあるようです。東京電力の発表によると、計画停電は4月末までということになっているようです。4月にはいると、暖房の需要がなくなるり、電力消費も減るからです。でも、それで解決するわけではありません。夏になると冷房によって電力需要が飛躍的に増大するからです。昨日3月15日現在の電力の需給関係は、需要が4100万KWに対して、供給が3200万KWだそうです。(共同通信の記事より)現在停止中の各発電所の中で、福島第一原発は言うまでもなく今後二度と運転再開などできない(許されない)でしょうし、今のところは重大事態に至っていない福島第二原発も、運転再開はかなり困難でしょう。柏崎原発は、現在2~4号機が点検中だそうですが、これが運転再開しても330万キロワットです。更に、火力発電所で運転を停止しているのは広野火力発電所2・4号機(160万KW)津波による損傷常陸那珂火力発電所1号機(100万KW)津波による損傷鹿島火力発電所2・3・5・6号機(320万KW)大井火力発電所2・3号機(70万KW)東扇島火力発電所1号機(100万KW)の5カ所。どうやら上の2カ所は津波による損傷激しく、運転再開にはかなり時間がかかるようです。残りの3カ所は、おそらくそれほどの被害ではないと思われるので、これが遠からず復旧するとして490万KW。柏崎原発の点検中の原子炉と合わせて合計820万KW。昨日の段階で900万KWの電力不足なんだから、820万KW増えてもまだ足りません。広野と常陸那珂が復旧すれば、合計1080万KW。これなら現在の電力不足は回避できそうです。ただし、広野火力発電所は福島第一原発の南20kmほどのところ、つまり避難指示の出ている範囲内にあります。ということは、今後の動向次第では、復旧どころか稼働中の発電機も停止して、従業員が避難を余儀なくされる事態もあり得るでしょう。いずれにしても、夏場の電力消費には、全然足りない。夏場の電力消費はどのくらいかというと、2009年の夏は「でんき予報」のサイトによると、最大電力は7月31日の5450万KW。火力発電所がすべて復旧しても、まだ1000万KW以上足りないのです。ということは、夏場に再び計画停電が実施されるのは、ほぼ確実でしょう。そして、発電所なんてものは、そうそうすぐに作れるものではありませんから、そのような状況は今後何年か続くかもしれません。だけど、ある意味では今までが便利すぎた、とも言えるのかも知れません。どこぞの暴言知事がまたぞろ「地震は天罰」などとふざけた発言をやらかしたそうですが、そのような発言は論外としても、今回の地震(と原発事故)が、いつでも好きなだけ電気が使える便利生活を見直す契機になるかも知れません。もっとも、見直したときには東京上空に死の灰が降っている、という最悪な事態が起こらないとも言えないのですが・・・・・・。
2011.03.16
コメント(0)
-
今ここにある危機
福島第一原発が、いよいよ危機的な状況です。1号機 建屋が爆発2号機 圧力抑制室が破壊、格納容器が破れた?3号機 建屋が爆発そして、地震時には稼働していなかった4号機で火災が発生、使用済み核燃料の冷却が出来なくなり、大量の放射性物質が漏洩。その結果、主に4号機の事故が原因で、毎時400ミリシーベルトという莫大な量の放射線が検出されています。400ミリシーベルトというのは、自然状態で人が1年間で浴びる放射線(2.4シーベルト)の166倍、浴びた人の半数が死ぬ放射線量(3000~5000シーベルト)の10分の1という数字です。当時、現場は北東の風で、放射性物質は南西つまり東京方面に拡散したようです。茨城や東京、神奈川など関東全域で、通常の10倍から100倍の放射線が検出されています。チェルノブイリの事故は、操作ミスから、ほんの数十秒の間に、何の対策を取るまもなく、あっという間に炉心が吹っ飛ぶ事態に至っていますが、今回の件は、震災の発生から4日間、現場では必死の対策が取られているはずです。にも関わらず、事態の悪化をまったく食い止められないでいます。ということは、これから先も、更に事態の悪化を食い止められない可能性が高い、と思わざるを得ません。なぜそうなったのか。電力会社は、原発の耐震性は万全だと言っていました。結果的にそれは全くのウソとなってしまったわけです。先日の記事のコメント欄に書いたのですが、確かに原子炉そのものは、今回の地震で直接には壊れなかった。だけど、原子力発電所は原子炉だけで出来ているわけではありません。原子炉そのものがいかに強固でも、それに付随するシステム全体をすべて強固にすることは、おそらくできないのです。原発という「複雑系」のシステムの中で、原子炉本体がどれほど強固でも、システムのどこか弱い部分が損壊すれば、結局はシステム全体が危機に陥ることになります。今回の件では、それが冷却システムの動力源、というところにあったのでしょう。(報道されている経過が事実なら)結局、人間のつくるものに「絶対壊れないもの」はないということです。従って、絶対壊れない原発もない。しかし、飛行機や自動車が壊れるのとは違って、原子炉が壊れると、その影響は広範囲におよび(チェルノブイリの放射能は日本まで飛来しています)、期間も非常に長い。つまり、壊れた場合のリスクが、桁外れに大きいのです。そのようなリスクの高いものに、人類はやはり手を出してはいけなかったのではないかと私は思います。
2011.03.15
コメント(4)
-
計画停電・・・・・・・・
計画停電が今日から始まりました。これ自体は仕方がないことです。電気が足りない上に、福島第一原発が今瀬戸際の状態にある。ただ、はっきり言ってしまえば、計画停電ではなく無計画停電になってしまっているように思います。まあ、史上初めての出来事ですから、それも仕方がないのかも知れませんが。今日は、そういうわけで、朝はいつもより20分ほど早く家を出て、職場には5分ほど早く到着しました。つまり、いつもより15分ほど余計に時間がかかった、ということですね。自宅の駅では、たまたま運良く駅に着いたら電車が来たのです。(ムチャ混みだったけど乗れた)しかし、乗換駅では電車を待ちました。朝はよかったのですが、帰りは大変でした。帰りは逆に、職場駅から乗換駅までは、電車を少し待ったものの、来た電車はガラガラでした(反対側はとんでもない混み方でしたが)。乗換駅に近付くに従って混んできましたが、いつもの帰宅時と同じ程度でした。ただし、反対側のホームの混み方は、どんどん凄いことになっていましたが。乗換駅に着いたときには、反対のホームは人であふれかえっていて、改札で入場制限をしていました。そこまではラッシュの方向と逆でラッキーだったのですが、乗り換えた電車は・・・・・・いや、乗り換えられませんでした。乗換駅から自宅駅までの路線は、超混雑で、「電車が来ても満員で乗れない状態です」と場内アナウンスをしている。諦めて、次の駅まで歩きました。しかし次の駅でもやはり似た状況。(3本くらい見送れば乗れたかも知れませんが)結局、家まで歩きました。内心、明日は自転車で通勤しようかなとも思います。多分、電車利用の5割増くらいの時間では着けると思うんですよね、どうしようかな。ところで、その福島第一原発のことですが3号機爆発、作業中の11人けが 福島第一原発東京電力は14日、福島第一原子力発電所の3号機で水素によるとみられる爆発が起き、原発の構内で作業をしていた11人が負傷したと発表した。所属会社の内訳は不明。爆発は午前11時1分ごろ、3号機の原子炉建屋で大きな音とともに白煙が発生したという。爆発の前には原子炉内に海水を入れるため、海から水をくみ上げて貯水槽にためる作業をしていた。けがをした11人がこの作業にあたっていたかどうかは分かっていないという。-------2号機、燃料棒全体が一時露出 海水注入で水位上がる 原子炉内の水位が下げ止まらずに燃料棒全体が露出した福島第一原発2号機で、海水注入作業を続けた結果、14日午後8時すぎに水位がマイナス370センチにまで回復し、燃料棒の一部は水につかったとみられる。東京電力は、炉心溶融の可能性を否定できない、としている。原子炉格納容器内の圧力が設計圧力と同程度まで上昇しており、14日午後8時37分、格納容器内の蒸気を抜くための弁を開ける操作を始めた。-------1号機に続き3号機も爆発、そして2号機は燃料棒が完全に露出しています。その後燃料棒の一部は水につかったと記事にありますが、燃料棒の長さは約4mですから、マイナス370センチということは、わずか30cmほど冷却水に浸かっただけ?もちろん、爆発した3号機の燃料棒も一部が露出しています。メルトダウンの危険が、というか、もうメルトダウンしているかも知れません。それにしても、海水を注入しても注入しても水位が下がるとはどういうこと?その海水はどこに消えているの?ポンプの燃料が切れていたと言うけれど、こんな国家的危機の状況にあって、しかも、2日前から原子炉の危機が続いているというのに、ポンプが動かなくなってから初めて燃料切れが分かるなんて、それまで燃料の補給をしていなかったなんて、そんなバカげたことが、本当にあり得るの?何か隠しているんじゃない?という疑いを抱いてしまいます。もし原子炉本体が吹っ飛ぶようなことがあれば、まさしくチェルノブイリです。チェルノブイリ事故のあったウクライナは、それでもまだ広くて人口密度も少ない。この狭い日本でチェルノブイリが起こったら・・・・・・・・、いや、考えないことにしよう。
2011.03.14
コメント(0)
-
震災についていろいろと思うところ
消えたインスタントラーメン地震の後、とりあえず職場待機をしている間に夕飯の調達に出かけたのですが(午後7時頃)、その時点で、もう職場近くのコンビニには、弁当とかサンドイッチの類は何一つ、残っていませんでした。実は、普段私は食事に「愛妻弁当」ってやつを持っていくのですが、金曜日はそれがなくて、コンビニでカップヌードルを買ったのです。お昼にカップヌードルで、夜もまたカップラーメンか、と一瞬思ったのですが、そんなことを言っている場合でもないので、カップラーメンと、あとお菓子類は残っていたので、それも買いました。そのあと、泊まり込みでどたばたして、翌日朝5時過ぎ頃、最寄り駅に電車の運行状況を聞きに行って、ついでに別のコンビニに寄ったら、今度はサンドイッチ類や弁当類は在庫があって、逆にインスタントラーメン系の在庫がほとんどなかった。で、更に1日経った今日、自宅近くのスーパーに行ったら、インスタントラーメンの売り場が空っぽ。ものの見事に、まったく商品がない。いや、唯一「中華三昧」が数袋残っていたのと、硬焼きそばがあったけど。いや、びっくりしました。それ以外の商品はだいたいあったのですが。皆さんの周囲のスーパーはどうでしたか。---防災対策は必要だが、絶対確実な防災の手段はないところで、岩手県に田老町というところがあります。合併で、現在は宮古市の一部になっていますけれど。ここには、過去何度も津波で大きな被害を受けた教訓から、高さ10mにも及ぶ巨大な防潮堤があります。おそらく、日本で、というより世界でももっとも強大な防潮堤だったはずで、1960年のチリ地震津波では、日本全国で142人の死者を出したものの、田老町では一人の犠牲者も出ませんでした。が、今回の地震では、津波は10mの防潮堤を乗り越えて、市街地が壊滅したと報じられています。つまり、大自然の猛威の前では、人間がどれだけ対策を講じても限界がある、ということです。自然災害に対して絶対安全な対策はないのです。問題となっている福島第一原発もそうです。東京電力(政府も)の説明によれば、原発は地震が来ても大丈夫なように設計されているはずでした。しかし、実際にはそうでないことが今回露呈してしまったわけです。東京電力が想定していた地震(津波)の規模より、実際に来た地震の規模の方が大きかったことが原因でしょう。どんな地震でも壊れない建築物はないし、絶対に被害を出さない方法もない。ただし、家やビルが潰れても、その中に住んでいる人間が死ぬだけですが、原発が潰れると、中に住んでいる人間だけでなく、周囲の非常に広い範囲に致命的な被害を与える可能性がある、そこが原発というものの特殊性でしょう。そういう前提で考えると、地震か来そうな場所、しかも津波に対して無防備な海岸沿いに原発を建設するというのは、非常に問題があるように思います。---戦闘機は「脅威」に対して無力でした今回の地震で、航空自衛隊松島基地が津波によって水没し、F2戦闘機18機が水没したと報じられています。自衛隊松島基地 F2全18機水没 200人連絡とれず津波被害を受けた航空自衛隊松島基地(宮城県東松島市)のF2戦闘機18機が水没し、再起不能の見通しであることが12日、分かった。塩水や泥水が機体に入り込み、修理をしても飛行するのは困難とみられる。松島基地所属の空自隊員約200人の連絡もとれなくなっており、人員・装備面で自衛隊史上最悪の事態となる可能性も出てきた。松島基地には第4航空団と松島救難隊が所属。同基地には2メートル以上の津波が襲い、基地にある隊舎の2階床下まで浸水した。水没したのはF2の全18機のほか、T4練習機4機、UH60ヘリ4機など。津波が押し寄せるのが早く、F2などを避難させる余裕はなかったという。曲技飛行チームであるブルーインパルスの6機のT4はほかの基地に移動しており無事だった。4空団のF2の18機すべてが再起不能となれば、空自の防空任務にも大きな支障が出る。-----------「空自の防空任務にも大きな支障が出る」というのは、産経お得意の煽りというもので、そもそもF2は対地・対艦攻撃を主任務とする戦闘攻撃機だし、松島基地のF2は航空教育集団所属、つまり飛行訓練のための部隊だから、どちらにしても「防空」とはあまり関係がない。しかし、そのことは別にして、1機120億円もする高価な戦闘機が、「脅威」に対して何ら役に立たずに、あっという間にスクラップ。(機体そのものはともかく、エンジンと電子機器は、泥と塩水に浸かってしまったらもう修理不能でしょう)日本の長い歴史の中で、外国が日本に攻めてきた、なんてことは元寇くらいしかありません。しかし、地震や津波が日本を攻めてきたことは、おそらく無数にある。その他の自然災害も同様です。それに対して、高価なF15やF2戦闘機などは、何の役にも立たない、ということです。計画停電東京電力の管内で、明日から始まるようですね。まあ仕方がない。おそらく、電気需要が増大する平日日中に停電を実施することになるのでしょう。夜の停電は困りますが、日中の停電は(晴れていれば)家庭生活の上ではそれほど困らない。電気需要は平日日中が多く、夜間や土日は少ないので計画停電が家庭生活に及ぼす影響は、それほど深刻ではないと思います。仕事(産業)に及ぼす影響は・・・・・・・・、深刻かも知れません。まあ仕方がない。通勤の足は大丈夫だろうか。JRは自前の発電所を持っているけれど、私鉄や地下鉄は東京電力からの電気供給で運行しています。前日までに翌日の停電計画を公表してもらえると、対策が講じられるのですが、無理ですかねえ。・・・・・・と思って検索したところ、計画停電の予定表を発見しました。http://mainichi.jp/select/weathernews/20110311/news/20110313mog00m040012000c.htmlうーーーん、東京23区は荒川区以外は停電しないの??ところが、別のソースで見るとhttp://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20110313-748049.html荒川区以外の23区も停電する。どちらが本物??肝心の、発信源である東京電力のホームページはアクセス不能だし。とりあえず、範囲が広い方を本物と思っておくことにします。
2011.03.13
コメント(2)
-
チェルノブイリ
・・・・・・・・というわけで、皆様昨日の地震はいかがでしたでしょうか。私の相棒は、大阪(天王寺)に住んでいたので、阪神淡路大震災の揺れを、しかもマンションの10階を超えるフロアで体験しているのですが、そのときより今回(我が家は3階)の方が怖かったと言っています。私も、正直言って、震度5強という報道を見て、「こんなに揺れても5強なの???」と思いました。一応、机に手をつきながらですが立っていられたので、震度7とは思わなかったけど、6弱くらいだと思ったのですが。揺れた時間も長かったですね。2度目に来た地震(茨城沖の余震)も、ほぼ同じくらい揺れたけど、ただ揺れた時間は最初より短かった。ま、何のかんの言って、私の職場はビルの2階なので、室内は何もありませんでした。いや、内壁に亀裂が入ったり外壁に亀裂が入ったりはありましたが、内壁は多分石膏ボードだろうし、外壁も構造までひびが入っているわけじゃないだろうから、たいしたことはない。でも、同じビルの8階9階は、すべての備品(ロッカーや本棚)がひっくり返ったそうです。うーーーーん。で、その後の職務上のことは、公開ブログ上ではちょっと省略。(昨晩は1時間くらいしか仮眠していません)帰宅するとき、勤務先周辺も我が家周辺も、とりあえず町並みは普段とほとんど変わっていなかったので、そのときになって初めて、「ああ、確かに震度5強程度だったんだなあ」と納得したような感じでした。震度6や7だったら、あんなに何事もないような町並みで済むはずがない。東京も大変ではありましたけれど、まさしく壊滅的と言える東北地方の惨状に比べれば、まだまだたいしたことはないのかも知れません。現段階で、死者行方不明者1600人を超えた、と報じられていますが、絶対そんな数字で済むはずがない。行方不明になった事実すら分かっていない人がまだ大勢いるはずです。陸前高田市はじめ、市全体、あるいは集落全体が消滅してしまったところが、いくつもあるようですから。残念ながら、犠牲者が1万人超えていたとしても、まったく不思議がない。結果論になりますが、9日に三陸沖で起きたマグニチュード7クラスの地震は、この地震の前震だったんですね。昨日の地震の後すぐに、気象庁のサイトで確認したら、その前数日間に起こっている地震の大半が三陸沖なのです。後から考えれば大地震の予兆はたくさんあったと思うのですが、それでも地震予知って、出来ないんですねえ。地震だけでも大変なのに、福島第一原発が大変なことになっています。地震で冷却水の水位が下がり、炉心が水面上に出て、メルトダウン、そして爆発したと報じられているようです。とりあえず、爆発はしたけれど、原子炉が吹っ飛んで炉心が暴露されたわけでは、まだないようです。だけど、チェルノブイリ一歩手前。いや、半歩手前かも知れない。それにしても、福島第一原発の危機が報じられてからどのくらい経ちました?少なくとも今日の未明から報じられていますよね。私が知らなかっただけで、もっと早くから報じられていたのかも知れない。チェルノブイリとかスリーマイルの事故とは違って、原発の危機が表面化してからある程度の猶予時間は稼げているし、その間、いわば国家の総力を挙げて事故を防ぐべく対策を講じているようですが、まったく防げていない。これまでのところ、想定の最悪コースをたどっているように見えます。「原発は安全」とか「日本の原発は安全」という神話は、神話でしかなかったということというしかないでしょう。やはり、原発は非常に危険なものです。地球の大気の流れは、基本的には西から東に向かうので、太平洋岸の福島第一原発の放射能は、基本的には太平洋上にながされると思うけど、今日明日の風向きはどうなのかな。北東の風、ということになったら非常にヤバイ。
2011.03.12
コメント(4)
-
キラ・ウィルカ ライブ延期のお知らせ
さきほど、やっと帰宅しました。こういうことが起こると動員がかかる性質の職場に勤務しているもので。とりあえず、私も相棒も子どもも無事です。というわけで、こういう状況ですので本日のライブは延期します。大変申し訳ありません。新しい日程は、後日アップします。我が家はとりあえず無事です。本棚の本とCDラックのCDが床じゅうにぶちまけられていますが、片付けは後にします。だって、昨日の晩は1時間くらいしか寝ていないので。
2011.03.12
コメント(4)
-
本物の「在日特権」はこれだ
先に紹介した米国国務省のメア日本部長の過去の暴言に、沖縄国際大ヘリ墜落事故に対し県警が行った捜査について「米側が調査し原因は分かっているのに、整備員の名前を聞いて(県警が)何を調査したいのか疑問だ」と述べた。というものがあります。2004年に米海兵隊普天間基地所属のヘリが沖縄国際大に墜落した事件の際の発言です。言うまでもなく、墜落した場所は沖縄国際大学の構内ですから、米軍基地内ではなく、純然たる日本の領土です。ところが、この墜落事故の時、米軍は墜落現場を封鎖して、墜落機の残骸を搬出するまで、日本側の警察や行政関係者、墜落した沖縄国際大の関係者も閉め出しているのです。これはどういうことか。日米地位協定は、在日米軍が公務中に起こした事件・事故(公務執行中の作為又は不作為から生ずる罪)の一次裁判権が米国にあると規定しています。(地位協定第17条3)それが、米軍機の墜落現場を米軍が封鎖して、日本側を閉め出す根拠になっているわけです。しかし、よく考えてみると、日米地位協定第17条には、裁判権を行使する第一次の権利が米国にある、とは書いてありますが、捜査を行う権利については何も書かれていません。(日米地位協定の全文はこちら)捜査権まで、米国が独占する根拠など、どこにも書かれてはいないのです。にもかかわらず、事故が起こると、それが基地の外の日本領土であっても、米軍が当然のごとく現場を封鎖して、日本側の警察や行政すら閉め出す。沖縄国際大学の墜落事故ばかりではなく、同様の事件は過去に何回か起こっています。更に言えば、本当は公務外であっても、米軍が「公務だ」と言い張れば、一次裁判権は米国側に奪われます。実際に、当初は米国側が「公務外」と認めながら、後から「公務だ」と強弁して「公務証明書」を発行して、日本側の一次裁判権を奪った事例が存在します。1974年、沖縄・伊江島で草刈り中の住民を米兵がトラックで追い回して、信号弾で怪我を負わせた事件がそれです。※この事件の詳細は琉球新報のサイトに詳しく出ています。当時現場には他の日本人もいたそうですが、犯人の米兵は「同じ場にいたほかの村民を追いかけなかった理由を「走らないから面白くない」と答えた」と報じられています。こんなひどい犯罪行為ですら、米軍が「公務だ」と言いさえすれば、公務になってしまうのです。犯人の米兵が、その後米軍内の軍法会議でどんな処罰を受けたのか、そもそも言法会議で裁かれたのかどうかすら、定かではありません。まさしく治外法権であり、在日米軍特権に他ならないわけです。そして、日米地位協定の制約の中で、何とか捜査を行おうとした日本の警察を、冒頭のような言葉で批判したのがメアという人物です。「在特会」などというバカげた団体が、ありもしない「在日特権」なるものを非難しています。在日米軍以外のいかなる外国人もこんな特権など持ってはいないし、そもそも日本人を超えるような権利は持っていません。それにもかかわらず、彼らが、本物の「在日特権」である在日米軍の特権を非難したという話を聞いたためしはありません。
2011.03.10
コメント(1)
-
ネットウヨクという名の「反日分子」
昨日の記事で米国国務省日本部長の暴言について書きました。ところが、この暴言を持ち上げている人たちが、日本の中にいるのです。それは誰かというと、ネットウヨクども。たとえば、今や2ちゃんねるを凌いでネットウヨクの総本山となりつつあるヤフーニュースのコメント欄http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110308-00000086-jij-int>沖縄の政治家は日本政府との交渉で合意しても、地元に戻れば合意していないと言う」と発言事実なので反論できない---言い方は悪いが言ってる内容は間違っちゃいない米軍基地周りで金儲けしようと後から集まってきたくせに被害者ヅラしちゃってるもんね---沖縄県のゆすり体質は事実だが、名人というのは事実に反するな。---(以下延々と続くけれど省略)2ちゃんねるも同様です。(引用しませんが)「民族の独立」だとか「誇り」がどうとか言っている人間が、米国人メアの差別発言の尻馬に乗って、同じ日本人である沖縄の人々を罵倒しているという、実に醜悪な光景です。強いものにはへつらい、弱いものには敵意をむき出しにする。中国や韓国に対しては、「民族の独立」とかを強調するが、宗主国たる米国に対しては、喜々としてその靴をなめる。それがネットウヨクというものの本質だということを、改めて思い知らせてくれました。
2011.03.08
コメント(0)
-
国務省日本部長の暴言
http://www.mainichi.jp/select/world/america/news/20110307k0000m030091000c.html米国務省:和の文化「ゆすりの手段」 メア日本部長が発言米国務省のメア日本部長(前駐沖縄総領事)が昨年末、米大学生らに国務省内で行った講義で、日本人は合意重視の和の文化を「ゆすりの手段に使う」「沖縄はごまかしの名人で怠惰」などと発言していたことが6日までに分かった。メア氏は米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の移設問題など日米交渉に実務者として深く関与、移設先を同県名護市の辺野古崎地区とした現行案決着を米側で強く主張してきた人物の一人。発言は差別的で、日本と沖縄への基本認識が問われる内容だ。講義を聞いた複数の学生がメモを基に作成した「発言録」(A4判3ページ)によると、メア氏は「日本の和の文化とは常に合意を追い求める」と説明したうえで「日本人は合意文化をゆすりの手段に使う。合意を追い求めるふりをしながら、できるだけ多くの金を得ようとする」と述べた。沖縄については、日本政府に対する「ごまかしとゆすりの名人」「怠惰でゴーヤーも栽培できない」などと発言。普天間飛行場は「(住宅地に近い)福岡空港や伊丹空港と同じ」で特別に危険でないとし、日本政府は仲井真弘多・沖縄県知事に「お金が欲しいならサインしろ」と言うべきだと述べている。メア氏は共同通信の取材に、講義は「オフレコ(公開しないこと)で行った」とし、発言録は「正確でも完全でもない」としている。講義は米首都ワシントンのアメリカン大の学生ら14人に対し、彼らが東京と沖縄へ約2週間の研修旅行に出発する直前の昨年12月3日、大学側の要請で行われた。発言録を作成した学生たちは「メア氏は間違いなくこのように言った」と証言。「米政府の地位ある人物の偏見に満ちた言葉にとても驚いた」「人種差別的発言と感じた」などと話している。----------------なかなかキョーレツな発言ですが、そもそも米軍は基地の土地使用料を一文も払わずに、どころか、米軍の駐留経費まで日本側の負担で日本に居座っているのに、その米国の国務省から「ゆすりの名人」と言われるとはね。普天間飛行場は「(住宅地に近い)福岡空港や伊丹空港と同じ」で特別に危険でないというのは、すごい発言です。ウィキペディアの普天間飛行場の項目に、普天間基地に関わる墜落事故についての記載があります。それによると、沖縄復帰以降2002年までの32年間で、普天間基地関係の事故は、固定翼機8件、ヘリ69件の計77件となっています。年平均2件ずつの事故ということになります。墜落だけに限っても、上記記事には復帰以降15件が記録されています。民間航空ではあり得ない事故発生率です。この間、福岡空港関係の墜落事故は、1996年ガルーダインドネシア航空の離陸失敗事故1件のみ、伊丹空港関係の墜落事故も御巣鷹山の日航ジャンボ墜落事故1件だけ(あれは伊丹空港行の便だった)です。騒音一つとっても、軍用機の騒音は、民間航空機とは比較になりません。特に戦闘機は、騒音の大きい低バイパス比のジェットエンジンに加え、離陸時はアフターバーナーを使うから、強烈に騒音がでかい。その、うるさいジェット戦闘機の中でも、普天間に頻繁に飛来するFA18の最新型FA18E/Fは、特に騒音がでかいと言われます。(現在開発中のF35戦闘機は、更に騒音がでかいらしいですが)もっとも、このメア部長の差別的暴言は、今に始まった話ではなく、在沖縄米総領事を勤めていた時代からのものだったようです。毎日新聞の報道によると就任翌月の06年8月、米軍普天間飛行場周辺の住宅が密集した現状に「普天間は特別ではない。飛行場として特に危ないとは思わない」との認識を示した。07年6月、米海軍掃海艦の与那国島寄港計画について「日本の安全保障に貢献している米海軍の入港になぜ反対するのか理解しにくい」と疑問を呈した。08年2月、米兵女子中学生暴行事件を受けた平和団体の抗議行動に対応せず、飲食店に出掛けたため団体側が反発。メア氏が入った飲食店前で抗議行動を展開した。同年4月には日米地位協定改定の動きについて「ある政治家と団体が政治的に利用し、政争の具にしようとしていることは非常に残念だ」と批判した。同年7月、普天間飛行場は米軍内部の安全基準に違反しているとする伊波洋一宜野湾市長の指摘に「なぜ滑走路の近くの基地外に、宜野湾市が建設を許しているのか疑問」と反論。同年8月には、沖縄国際大ヘリ墜落事故に対し県警が行った捜査について「米側が調査し原因は分かっているのに、整備員の名前を聞いて(県警が)何を調査したいのか疑問だ」と述べた。09年4月、米海軍掃海艦の石垣港寄港に反対する市民らが港の金網に掲示した横断幕がなくなったことに「置いていた物が取られても捨てられたごみを片付けただけではないか」と発言。同月、米総領事館に隣接する浦添市当山のコーヒー店で客の男性にホットコーヒーを掛けられた上、胸を両手で押された。----------------暴言のオンパレードです。このような人物が、国務省の日本部長になる、というのはどういう意味でしょうか。反対の立場で、米国に対してこのような問題発言を繰り返す人物が、外務省の中米領事であったり、北米局の局長であったりすることがあり得るでしょうか。日本が米国の属国である、ということを何よりも雄弁に証明しているのではないでしょうか。更に悲しいのは、この発言に対する日本政府の対応琉球新報の報道によるとメア氏発言で枝野氏、米側に照会せず枝野幸男官房長官は7日午前の記者会見で、米国務省のメア日本部長が沖縄県民をゆすりの名人だなどと発言したことについて「実際にどう発言したか承知していないのでコメントは控えたい。日米間ではさまざまな問題で日ごろから不断の協議、連携を図っていて相互理解を深めている。報道のみをもって一つ一つの発言を確認する必要はない」と述べ、米側との信頼関係から発言内容を米側に照会しない考えを表した。----------------やっぱり、自民党の対米服属路線を忠実に継承しているだけの民主党政権は、終わっている。
2011.03.07
コメント(4)
-
外国人からの政治献金は禁止されているわけですが
http://www.asahi.com/politics/update/0304/TKY201103040482.html前原外相に進退論 外国人から献金受領 4年で20万円前原誠司外相は4日の参院予算委員会で、京都市内の在日韓国人の女性から政治献金を受け取っていたことを明らかにした。政治資金規正法は外国人からの寄付を禁じており、献金を受けた経緯や前原氏側の認識次第では同法違反の罰則にも問われかねない。自民、公明両党は外相辞任を要求し、民主党内からも辞任論が出はじめた。進退問題に発展する可能性もある。前原氏は党内で自らのグループを率いながら民主党政権の要職を務めてきた。「ポスト菅」候補の一人でもある。外相辞任の事態となれば、菅直人首相の政権運営がさらに追い込まれることは必至だ。4日の参院予算委で、自民党の西田昌司氏が献金の事実関係を質問したのに対し、前原氏は「中学2年生の時に(京都市の)山科に引っ越した。(献金者は)近くで焼き肉屋の経営をする在日(韓国人)の方だ。返金し、(政治資金)収支報告書を訂正したい」と認めた。予算委終了後、前原氏は首相官邸で首相と会談し、献金の経緯を説明。その後、外務省で記者会見を開き、「大変申し訳なく思っている。全体をしっかり調べた上で、どのように判断するか決めたい」と語った。京都市内にある前原氏の政治団体の報告書には、2005年以降、この女性から4年間で毎年5万円ずつ計20万円の献金を受けたことが記載されている。前原氏は会見で「献金をいただいているという認識はなかった」とした。この女性は朝日新聞の取材に「前原さんの家庭は貧しく、苦労して議員になったので応援したかった。在日の献金がダメだとは知らず迷惑をかけた。私が日本国籍を得ていると思ったのではないか」と話した。 --------私は前原という政治家が嫌いです。競争原理主義、市場原理主義指向の強い政治家であること、尖閣諸島を巡る騒動、北方領土問題を巡る対立が拡大した原因の一つが、前原の硬直的な強硬論にあったと思われることなどが原因です。が、大嫌いな前原ではありますが、今回のこの騒動については「何だかなあ」と思わざるを得ません。もちろん、外国人からの政治献金は法によって禁止されています。それは歴然たる事実ですから、前原はその点について謝罪し、献金を返還する必要がある。しかし、それまでのことだと私は思うのです。明らかに「うっかりミス」の類であり、意図的な不正献金とはとても思えないからです。献金額は、4年間で20万円、つまり年間5万円に過ぎません。歳費だけで数千万円もらっている国会議員が、意図的に法を破る危険を冒すに見合うような莫大な金額とは言えません。記事を読む限り、前原本人は問題の献金者が在日と知っていたように思われますが、前原の事務所関係者はおそらく知らなかったのでしょう。そして、前原がどの程度の政治献金を得ているかは知りませんが、おそらく相当数にのぼるであろう献金者の名前を全部本人がチェックはしていないというのは、不自然なことではありません。もちろん、うっかりだから許されるわけではないけれど、知っていて大量の献金をもらっていた、というのとは「悪質度」がかなり違う。今回の一件は、排外主義を煽るツールとしていいように利用されているような感じがして、私は(大嫌いな前原のことではあるけれど)どうも嫌な気分なのです。それなのに、結局前原が辞意を固めた報道されています。前原外相が首相に辞意 政治資金問題で引責の意向前原なんか外務大臣辞めろ、と常々思ってきたのは事実なのですが、「この問題で」辞任というのは非常に釈然としないものがあります。
2011.03.06
コメント(2)
-

西穂高岳独標 写真2
昨日の続きで、先週登った西穂高岳独標の写真です。が、その前に少々宣伝など---キラ・ウィルカ フォルクローレ・ライブのお知らせ3月12日(土)午後6時より(2部構成予定)場所 ペルー料理店・スポーツカフェ「ティア・スサーナ」総武線・信濃町駅より徒歩約5分料金 チャージなし(レストランですから、食事はしてください)演奏 キラ・ウィルカ(↓せっかくなので、山の写真付きの音源など)---さて、本題に戻りまして、山の写真です。いよいよ、西穂高岳独標の「山頂」が目前に迫ってきました。更に進みます。写真の中央屋や左下寄りの岩場のトラバースを超えます。この写真は、岩場のトラバースを超える少し手前で撮ったのですが、結局、この写真から20mくらい進んで、最後の斜面の真下に出たところで引き返しました。もう少し時間があれば、登れないはずがないのですが・・・・・。引き返した時間は午後1時15分くらいだったでしょうか。登ってきたのは、こんなところです。写真左下に、西穂山荘の屋根が半分頭を出しています。ロープウェーの終点は写真には写っていませんが、右手の黒い森の先にあります。上高地。正確に言うと、河童橋などのある上高地よりすこし下流です。左下に建物が写っているのが分かるでしょうか(川筋の湾曲部の少し右上)。上高地帝国ホテルだと思います。赤い屋根で有名ですが、今は雪で屋根が白くなっています。右奥の池が大正池です。今の時期は道路が閉鎖されているので、中ノ湯から鎌トンネルを歩いて行きます。もちろん、宿は一軒も営業していません。しかし、この日あたりはかなりの登山者が上高地に入ったのではないでしょうか。前夜平湯温泉で同じ宿に宿泊した夫婦も、「上高地に行く」と言っていました。左が霞沢岳、右奥が乗鞍岳。霞沢岳の手前が先ほどの写真の上高地です。霞沢岳です。西穂山荘まで戻ってきました。西穂山荘は海抜2450mほど。ちょうどこの辺りが森林限界で、ここより下は亜高山帯針葉樹林が広がっています。遮るもののない山の写真も好きですが、樹林の間に見える山の写真も、私は好きです。同じく西穂山荘から焼岳(右手前)と乗鞍岳(左奥)を撮影しました。焼岳の噴煙が、この写真でははっきり分かります。ところで、撮影機材ですが、カメラはキヤノンのEOS7を使っています。同じカメラが2台あって、1台はポジフィルム(ISO100)用、もう1台はネガフィルム(ISO400)用にしています。山に持っていくのは、もちろんいつもポジだけです。2台とも中古品です。その前にEOS Kissも使っていましたが、2台目のEOS7を買うときに売り払いました。レンズは、山で使うのは、EF24-85mm F3.5-4.5 USM(標準系のズームレンズ)もう一つEF80-200mm F4.5-5.6 USM(望遠系のズームレンズ)も持っていきましたが、結局使いませんでした。あとひとつ、EF50mm F1.4 USM(標準単焦点レンズ)も持っているのですが、もっぱら室内撮影用で、山に持っていったことはありません。このレンズは非常に明るい。だから室内では役に立ちますが、日中の屋外ではそんなに明るいレンズでなくても用は足りるのです。このレンズだけ、中古で購入したものです。他に、EOS Kissにセットで付いていたズームレンズがありましたが、EOS Kissとともに売り払いました。(28-80mmでしたが、手元に現物がないので、検索したらどれが該当するレンズかよく分かりません。これかこれかこれ)フィルムは、ポジはフジのプロビア100Fを(一時期ベルビア50というポジも使ったことがあります)、ネガはその時々で適当なフジのISO400フィルムを使っています。今は、スーパープレミアム400というもの。ネガでの撮影はデジタル一眼レフに移行しても良いと思うのですが、多分デジタル一眼レフを買ったが最後、ポジでの撮影だって止めてしまうに違いないので、まだデジタル一眼レフには手を出していないわけです。"
2011.03.05
コメント(2)
-

西穂高岳独標 写真1
先週登った、西穂高岳独標の写真をアップしました。やはり、携帯の写真よりずっといいですね。(当たり前ですけれど)2回に分けて公開します。西穂高岳(2908m)の全景です。この位置からは、どこが本当の山頂かよく分かりませんが、多分左奥のはずです。私が目指した独標(2701m)は、右から2番目の茶色いピークです。左が笠ヶ岳(2897m)。真ん中から右にかけてが抜戸岳(2812m)と双六岳(2860m)、その奥に三俣蓮華岳があるはずですが、笠ヶ岳以外は、正確にどの山がどれか、よく分かりません。通称「海老の尻尾」樹氷の一種と思えばいいでしょう。風の強い稜線上で、木や岩の風上側に伸びていきます。この日このときはほとんど無風でしたが、冬場の日本の高山は、常に烈風が吹き荒れているものです。西穂高岳。先ほどの写真よりだいぶ登りましたが、さらに先を目指します。結構ばててきました。風もなく晴天で、まったく寒くありませんでした。左遠方が乗鞍岳、右手前の山が焼岳です。焼岳は噴煙が上がっていました。霞沢岳。上高地の目の前にそびえている山です。独標手前まで来ると、前穂高岳も見えてきました。前穂高の手前が岳沢。向こう側が涸沢です。涸沢は、ゴールデンウィークには雪山登山のメッカになりますが、今の時期は、危なくてとても近づけません。(雪崩の巣なので)目指す西穂高独標まで、だいぶ近付きました。こうやって写真に撮ってしまうと、斜度があまりよく分かりませんね。実際はかなり急斜面です。もっとも、5年ほど前に10月(無雪期)に登ったときは、「急斜面だ」とは思わなかったんですけれどね。雪があるかないかで、難易度が全然変わりますが、「体感斜度」まで変わるんでしょうか。更に先に進みます。ということで、続きはまた明日。
2011.03.04
コメント(2)
-
国旗損壊罪だって・・・・・・
http://www.asahi.com/politics/update/0302/TKY201103020333.html自民党は2日、国旗損壊罪を新設する刑法改正案を今国会に提出する方針を決めた。日本を侮辱する目的で日章旗を焼いたり破いたりしたら2年以下の懲役か20万円以下の罰金を科す内容。民主党や公明党など他党にも協力を呼びかけて成立をめざす。尖閣諸島沖の中国漁船衝突事件などをきっかけに自民党は保守色を強めており、「君が代」の替え歌など国歌への侮辱に刑事罰を科す改正案も検討する。--------------いやあ、最近民主党が本当にどうしようもなくて、まったく愛想が尽きているのですが、それでもこんな記事を見てしまうと、「自民党政権には戻って欲しくない」と思ってしまいます。私個人の好みとしては、日の丸は嫌いじゃありません、というか好きです。(君が代は大嫌いです)だけど、だけど、日の丸を破ったり燃やしたり侮辱する自由というのは、当然にある、これもまた当たり前のことです。(言うまでもなく、損壊する国旗が他者の所有物である場合は、国旗がどうこう以前に器物損壊ですから、話は違います)だいたい、「日本を侮辱する目的で」って、いったい誰がどうやって判定するんですか。非常に曖昧であり、恣意的にどうとでもなる。恣意的にどうとでもなるということは、拡大解釈して悪用しやすいと言うことです。国家を侮辱することを刑罰の対象にしようということ自体が、「お上に逆らうことは許さない」的な、あるいは不敬罪的な、言論の自由と相容れない考え方です。「自由」「民主」党の名が泣くというもの。更に、「『君が代』の替え歌など国歌への侮辱に刑事罰を科す改正案も検討」なのだそうです。正気の沙汰とは思えません。幸いなことに、現在の議席数では、この法案が成立する可能性はまずないものの、自民党が政権に復帰した後は、果たして・・・・・・。本当に怖い。
2011.03.02
コメント(2)
-

恐るべきフルート奏者
先日、このブログの常連であるたかさんに、「マグナムトリオ」というフルートのアンサンブルがあることを教えていただきました。その演奏が素晴らしくて、他の演奏もYouTubeでいろいろと検索してみたら、かなりのけぞってしまいました。まともにフルートを吹いている動画よりも、まともでない吹き方をしている動画の方が、たくさんアップされているかも知れません。特殊奏法もさることながら、管体だけ、頭部管だけで演奏しています。頭部管でメロディーが出せることは想像していましたが、頭部管のない管体だけでも音が出せるとは、想像したことがありませんでした。勉強になりました。私も、頭部管で曲を吹くことは多分出来るんじゃないかと思うので、練習してみようかな。そういえば、ケーナでも逆さに持って管尻から吹いて音を出せる人がいます(私はできない)ので、フルートの管体だけで音を出すのは、それと同じ吹き方なのかも知れません。特殊な頭部管を使って音色を変えて、アラブ風の曲を吹いています。曲の中程あたりで、やはり頭部管なしのアルトフルートを吹いていますが、先ほどとは違ってこの吹き方はディジリドゥ(オーストラリアの笛、音を出す理屈は金管楽器と同じ)の吹き方です。私はディジリドゥーは吹けるので(ただし、循環呼吸は出来ません)、このやり方なら頭部管のないフルートが吹けそうです。小指しか動かさないで演奏する曲「小指エクササイズ」この楽器は、以前に紹介したことがある(このブログではなく、前身の掲示板だったと思います)のですが、尺八+フルートの「尺ルート」。頭部管がリコーダーで、管体がフルートという楽器。上記の尺ルートの延長線上で言えば、リコルートでしょうか。クラシック畑出身のフルート奏者でも、こういうことをやる人がいるんだなあと思いました。実に面白い。とにかく、笛という楽器(フルートに限らず)は、実は表現方法に非常に幅のある楽器だなと、改めて驚きました。
2011.03.01
コメント(4)
全27件 (27件中 1-27件目)
1