2011年09月の記事
全23件 (23件中 1-23件目)
1
-
F2戦闘機が生産終了だそうです
F2戦闘機の生産終了 三菱重工の小牧南工場三菱重工業は27日、2000年から続けてきた航空自衛隊向けF2戦闘機の生産を終了した。次期主力戦闘機(FX)の機種選定が遅れているため、F86戦闘機以来続いてきた、日本国内の戦闘機生産は当面の間、途絶える。愛知県豊山町にある三菱重工小牧南工場で同日、最終号機を防衛省に納入する「完納式」が開かれ、防衛省や部品メーカーなどから約200人が参加した。同工場ではこれまでF2戦闘機94機を量産。今も年間12機を生産できる設備があるが、生産終了でラインは停止。今後は自衛隊機の定期修理が中心となる。F2戦闘機は日米の共同開発で、三菱重工など日本側が約6割を担当してきた。1機120億円で、青森県の三沢基地や福岡県の築城基地の実戦部隊に配備されている。宮城県の松島基地にパイロットの教育訓練用で配備されていた18機は、東日本大震災の津波で水没する被害を受けた。----航空自衛隊の次期主力戦闘機問題については、以前にも何度か記事を書いたことがあります。そんなにF22が欲しいのか立ち往生しているのは誰か高価なオモチャなんかやめてしまえ今もこれらの記事を書いたときと考えは変っていません。いや、この記事を書いた当時以上に、今の日本には戦闘機にお金をつぎ込んでいる余裕はないだろうと思います。現在主力のF15が耐用年数に達するときには、さすがに後継機を考える必要はあると思うけど、たかが50機程度のF4戦闘機は、退役したらそのままでいい。ま、私自身の主張は措くとしても、現実問題として、おそらくF4が退役するまでに次期主力戦闘機を航空自衛隊が決めることはできないだろうと思います。もともと、次期主力戦闘機の選定問題は、自民党政権時代からずっと先延ばしされ続けてきました。最初、航空自衛隊がほしがっていたのは米国のステルス戦闘機F22でしたが、これは米国自身が輸出禁止としたため導入できなかった。(できなくてよかったと、私は思いますが)それで、最終的に現在の候補機は米国製のF35とFA18、ヨーロッパ共同のユーロファイター・タイフーンの3機種です。この中で、航空自衛隊自身の本音として欲しいのは、F35です。しかし、F35は開発が難航しており、いつになったら実用化するのか見当がつきません。F4の退役までに購入できる可能性がないことだけは間違いない。しかも、開発費が高騰中で、もともとは「高価なF22と安価なF35」という組み合わせのはずが、F22と変らないくらいの価格になりそうな状況です。かといって、日本政府は米国様に逆らう気はないので、ヨーロッパ製のユーロファイターを採用する勇気は、航空自衛隊にはおそらくない。そうすると、消去法的に残るのは米国製FA18戦闘攻撃機ですが、いくら再設計した最新鋭機といっても、原型は1970年代に作られた飛行機ですから、自衛隊の本音としてはおそらく、「今更こんな旧式機は」と思っているはずです。加えて、軍需産業界の意向というものがある。F35は、共同開発といいながら、実際の製造は米国のみが行っており、共同開発国はお金は出しているけど実際の製造は行っていません。当然、日本にライセンス生産が認められる可能性もない。だから、三菱重工をはじめとする軍需産業は、F35は採用して欲しくない。自衛隊と軍需産業は半ば一心同体、持ちつ持たれつの関係ですが、こと次期主力戦闘機に関しては、F35が欲しい自衛隊とF35は嫌な軍需産業の利害は対立している。結局のところ、あちら立てればこちらが立たず、どうにも決められないわけです。ええ、このままずっと決められないでいた方が良いんじゃないでしょうか。仮に決めたとしても、財務省だって、さすがにすんなりとはそんな予算を通さないだろうと思うんですけどね。ところで、ここまで次期主力戦闘機がもめていても、「じゃあF2戦闘機をもう少し増産しよう」という話が結局一切出てこないまま、F2は生産終了となりました。F2については、一部に「欠陥戦闘機だ」という説があります。その真偽のほどは私には分かりませんけど、当初予定では140機くらい製造するはずが、100機未満に減らされて、この状況でも生産再開という話がまったく出てこないということは、「欠陥機」という説もあながち事実無根でもないのかな、という気がしてきました。
2011.09.29
コメント(2)
-
冷温停止?
福島第一、1~3号機原子炉100度以下に東京電力は28日、福島第一原子力発電所2号機の原子炉底部の温度が、同日午後5時時点で99・4度と、3月11日の事故後、初めて100度を下回ったと発表した。これで1~3号機すべてで、原子炉を安定して冷却する「冷温停止状態」の2条件の一つである「100度以下」を達成した。1、3号機に比べ原子炉の冷却が遅れていた2号機では、今月14日から毎時3~4トンだった注水量を徐々に増やし、冷却を進めてきた。原子炉上部からシャワーのように水を入れる手法も新たに導入し、26日までに注水量を毎時10トンに増加させた。冷温停止状態の実現は、政府が年内をめどに進める事故収束に向けた工程表の「ステップ2」の大きな柱で、避難住民の帰宅に向けた検討を本格化させる目安となる。実現には「100度以下」の冷却の継続のほか、放射性物質の放出の大幅な抑制が条件となる。東電は、9月上旬の原子炉からの放出量を毎時約2億ベクレルと見積もり、追加放出による敷地境界の線量は目標(年1ミリ・シーベルト)を下回る年0・4ミリ・シーベルトと推定する。しかし、推定精度は低く、東電は放出量を確定させる詰めの作業を進めている。------地震が起きたのは3月11日です。ただちに炉心に制御棒が挿入されて、核分裂反応は停止したはずです。それから原子炉がぶっ壊れて放射能が大量に漏れだして・・・・・・、まあ色々なことがありましたが、それから半年以上、ずっと冷却水を注入し続けてきたはずです。記事によると、二週間前までは毎時3~4トン、現在は毎時10トンとか。昼も夜も休むことなくそれだけの量の注水を続けて、半年以上経ってやっと炉心の温度が100度をわずかに下回ったというのです。ということは、注水が止まってしまえば、たちどころに元の木阿弥ということでしょう。どうも素人目には、100度をわずかに下回っただけの状態を「冷温」と呼ぶことにも、これだけの量の注水を続けて、やっと温度の上昇を防いでいる状態を「停止」と呼ぶことにも、大いに違和感があります。これからさき、どれだけの時間をかければ、それ以上注水を続けなくても一定の温度を維持できるようになるんでしょうか。それまでに、いったいどれほどの量の注水を続けなければならないんでしょうか。しかも、当然のことながら、原子炉はぶっ壊れています。炉心の温度が100度を下回ったといっても、実はその炉心に核燃料がどれだけ残っているかは定かではありません。それに、炉心がぶっ壊れているということは、毎時10トンを注水すれば、そのかなりの部分が炉外に流出しているということです。放射能に汚染された水です。それが地下に染みこみ、あるいは海に流れ込んでいる。だからといって、注水を止めることはできません。本当に、見た目の便利さと引き替えに、なんとやっかいで危険なものに人類は手を付けてしまったんだろうなと思います。そして、もう一つ。福島の医師、12%が自主退職…原発から避難?">福島の医師、12%が自主退職…原発から避難?東京電力福島第一原発事故後、福島県内の24病院で常勤医師の12%に当たる125人が自主退職していたことが、県病院協会の調べでわかった。原発事故からの避難などのためとみられ、看護師の退職者も5%に当たる407人(42病院)に上った。県内の病院では一部の診療科や夜間救急の休止などの影響が出ている。調査は7月下旬、県内の医師らの勤務状況を調べるため、全139病院のうち、同協会に加盟する127病院を対象に実施。54病院から回答を得た。主な市町村で、原発事故前の医師数に占める退職者の割合が高いのは、南相馬市の4病院で46%(13人、警戒区域の1病院1人を含む)、いわき市の5病院で23%(31人)、福島市の6病院で9%(41人)、郡山市の4病院で8%(25人)。看護師では、南相馬市の4病院で16%(44人、警戒区域の1病院2人を含む)、いわき市の7病院で8%(113人)、福島市の9病院と郡山市の6病院は4%でそれぞれ68人、54人減少した。-----以前に何回か記事を書いたことがありますが、100ミリシーベルト以下の被曝による健康被害はよく分からない、ということになっています。よく分からないというのは、あるかないか分からないということであって、決して「ない」ことが証明されているわけではありません。それにもかかわらず、原発推進派は平然と「よく分からない」を「ない」と読み替えて、低線量被曝は安全だとがなり立てている。でも、ふたを開けてみれば、医療に携わる人々(科によっても違いますが、一般人よりは放射線の健康への影響について知識を持っているはずです)が、率先して福島から逃げ出しているのが現実です。南相馬では、退職者の割合が実に46%。それだけの医師が「ここは危ない」と思っているということでしょう。この状態で、「低線量被曝は安全だ」などと言われても、まったく説得力を感じません。
2011.09.28
コメント(0)
-
節電の結末
節電効果 大口29%、家庭は6%減 東電が発表東京電力は26日、今夏の節電効果の分析を発表した。今夏と昨夏の需要ピークを比べたところ、大工場やオフィスビルなど大口利用者の電力需要は29%、小口は19%それぞれ減ったが、家庭は6%減にとどまったという。今夏の需要ピークは8月18日の4922万キロワットで、昨夏7月23日の5999万キロワットより18%低かった。最高気温は今年の方が0.4度高かった。8月に使われた電気の量全体を表す電力販売量でみると、家庭も前年同月より17%も減っており、節電した人は多かったとみられる。ただ、需要がピークとなる午後2~3時は、もともと家にいる人が少ないため、電力需要の減少幅が工場などよりも小さくなった。-----この夏、あれこれ言われたけれど、結局のところ最大電力時でも東京電力管内の消費電力は5000万キロワットにも達しませんでした。今年もかなりの猛暑だったと思うのですが、去年の最大電力より1000万キロワット以上低い。最大電力を記録した8月18日の東京の最高気温は36.1度でした。家庭の電力消費は昨年8月より17%減だそうです。我が家の場合は、去年359KWh→今年261KWhなので、28%減です。ただ、去年最大電力を記録しているのが、実は9月なのです(425KWh)。今年は、9月の検針がまだなので、どうなるか分かりませんが、おそらく8月の使用量を大きく超えることはないと思います。※追記 9月の電気使用量の通知が来ました。去年が425kwhに対して、今年は223kwh。47%の減少です。過去最大の節電幅でした。去年は8月の後半から9月第1周までが酷暑のピークで、毎晩夜通しエアコンをつけていましたが、今年は暑いとはいえ、8月20日以降はそこまでの酷暑ではなかったですからね。6~8月の3ヶ月合計で見ると、やはり昨年比28%減です。少なくとも、原発の占める発電割合分くらいは節電したという自負があります。しいて言うと、節電のために新しい家電製品を買うところまではやりませんでした。冷蔵庫もエアコンも9年前の製品ですから、これを最新のものに変えれば、あともう少し節電はできたと思います。しかし、まだ使える家電を捨てるのはもったいなくて、そこまでは踏み切れませんでした。ただ、9年も使っていますから、あとそんなに長くは使えないだろうと思いますけど。以前の記事にも書いたことがありますが、我が家の節電の基本は、「無理しないこと」です。注意したのは、蛍光灯はこまめに消すことと、エアコンを2台同時に稼働しないことです。特に、日中は2台のエアコンを同時に稼働したことは、一度もないはずです。あとは、極力エアコンは使わないように、できるだけ扇風機を使うようにとは努力しました。ただ、室内温度が32~3度までなると、やっぱりエアコンなしというわけにもいきません。それ以外は、テレビの輝度とか冷蔵庫の節電設定とか、不要と思われる電球を抜いてしまうとか、最初に設定さえしてしまえば、それ以降は何もやらない、やる必要がない。それでも3割近い電力削減は可能でした。もっとも、記事にあるように、平日日中のピーク時間帯に限れば節電量はもっと少ないかも知れませんけど。夏は終わりましたけど、我が家の節電は終わりにするつもりはありません。地下鉄の駅構内の蛍光灯の間引きなどは、現在でも続いていますね。ああいうのは、誰が不便になるわけでもないので、今後もずっと続けてほしいものだと思います。
2011.09.26
コメント(0)
-
上関原発
原発推進派の柏原氏3選確実 山口・上関町長選中国電力が上関(かみのせき)原発建設を計画している山口県上関町の町長選は25日、投開票され、原発を推進してきた現職の柏原重海氏(62)が、反原発団体代表の新顔、山戸貞夫氏(61)を破って3選を果たした。東日本大震災後、原発新規予定地で初めての首長選。東京電力の福島第一原発の事故を受けて上関原発の工事が中断される中、「原発の是非は国に判断を委ね、まちづくりを進める」と訴えた柏原氏への支持が、「原発反対」を掲げた山戸氏を上回った。1982年に原発計画が浮上して以来、町長選は9度目。推進派と反対派の一騎打ちは、これで推進派の9連勝となった。------以前にも「原発は麻薬か」という記事を書いたことがありますが、残念ながら、あれほど大きな事故がありながら、福島以外の原発の地元では、反原発という流れにはなっていません。日本全体で見れば、即時停止はともかく、段階的な原発廃止というのがおおむね世論の多数派になってきていますが、原発の設置されている、あるいは設置されようとしている該当自治体については、そうなっていない。原発を設置する市町村には多くの金が落ちるのだから、ある意味では当然の話でしょう。もちろん、福島のような事故が起これば地域社会が壊滅するというリスクはあります。ただし、被害は原発のある自治体だけでとどまるものではないので、そういう意味では、原発を設置している市町村だけが被らなければならないリスクというのはないのかも知れません。どうせ狭い日本、ひとたび原発事故が起こればどこにいたって放射能が降ってくるのは同じだ、とも言えますから。そういう意味では、原発を設置する市町村には、事故の危険性というデメリットとお金が落ちるというメリットの両方がある。そのメリットとデメリットに釣り合いが取れているのかは、私には分かりませんけれど。一方、それ以外の市町村では、原発によるメリットは特になく、事故の危険というデメリットだけがある。だから、上関原発の場合で言うと、上関町では未だに原発推進だけど、周辺の市町村、更に山口県議会や山口県知事は、軒並み原発建設計画に懐疑的になっています。原発新設、高いハードル=推進派当選でも-山口・上関町長選中国電力が上関原発の新設を計画している山口県上関町の町長選で、推進派で現職の柏原重海氏が25日、3選を果たした。しかし、東京電力福島第1原発事故を受け、上関を含め全国に14基ある原発の新増設計画はいずれも宙に浮いたまま。政府の対応方針が定まらない中、世論の風当たりは強まる一方で、新設に対するハードルは一層高まっているのが実情だ。(中略)しかし、地元住民らの反対が高まる中、山口県の二井関成知事は6月、「計画自体が不透明な状況にある」として、建設予定地の埋め立て免許延長を認めない方針を表明した。県議会や周辺自治体の議会も、中止や凍結を求める意見書を相次いで採択している。(以下略)知事が建設予定地の埋め立て免許延長を認めないと言っている以上、たとえ町長に原発推進派が当選しても原発は建設できないわけですが、今後どうなっていくのでしょう。もし上関原発が予定どおり建設される事態になってしまったら、今まで原発のなかった場所に新たな原発ができる、ということですから、脱原発はおろか、長期的な原発縮小でもない、現状維持ですらなく、原発のさらなる拡大ということになってしまいます。あれほどの事故が起こったにもかかわらず、そんなことが国策になってしまうとしたら、狂気の沙汰としか私には思えません。
2011.09.25
コメント(2)
-

風の谷のナウシカより「ナウシカ・レクイエム~風の伝説」
また多重録音でYouTubeに演奏をアップしました。スタジオジブリの代表作中の代表作(厳密に言うと、この作品の公開時にはスタジオ・ジブリという名はまだなく、その前身のトップクラフトという会社の製作です)風の谷のナウシカより「ナウシカ・レクイエム」と「風の伝説」のメドレーです。なんてったって、ジブリの各作品の中で、一番好きなものを一つだけあげろと言われれば、迷うことなく「ナウシカ」を選びますから。(ジブリではなく、宮崎アニメでということになったら、ナウシカか未来少年コナンか迷うところですが)使っている楽器はギター・ケーナ・ケナーチョ・フルートです。フルートはたった1つの音しか使っていません。ケナーチョでは低音の音程が足りなかったので、その部分だけ後からフルートで吹いた音を足り付けました。多重録音だとこんな芸当も出来てしまうのです。だったら最初からフルートで吹けば良いのでしょうが、この曲に関しては私はフルートよりケーナ(とケナーチョ)で吹きたかったのです。「風の伝説」の原曲はキーがCm/E♭なのですが、そのままだと♭が3つも出てくる・・・・(ケーナにとって見れば、実質的には♭が4つあるのと同じ)とても無理なのでEm/Gに移調しました。映像は、9月19日の「さようなら原発」集会の写真です。だいたいの写真は自分で撮影したものですが、原発の写真、空中からの撮影などは報道写真から転載しました。
2011.09.24
コメント(0)
-

在特会が反原発デモへの攻撃に励んでいるらしい
在特会(在日特権を許さない市民の会)と称する極右差別主義者集団については、過去にこのブログでも取り上げたことがあります。その差別主義者たちが、最近は新たな攻撃目標を反原発派に定めたようです。反原発のデモがある度に、そこに乗り込んでいって聞くに堪えない罵倒暴言を繰り広げています。私は反原発デモに参加したのは9月19日のさようなら原発集会が初めてだし、そのときには在特会の連中はいなかった(少なくとも私の見聞した範囲内では)のですが。改めてYouTubeを検索してみると、彼等が得意がってアップしている、見るに堪えない聞くに堪えない動画が山ほど出てきます。何しろ恥も外聞もなく、「日本のため」という目的さえ正しければどんな罵倒暴言も許されると思っている連中だから、どんなみっともない動画でも平気でアップしてしまうんですね。さすがに、このブログに埋め込みをするのは嫌なのでリンクを貼るだけにしますが【在特会】反原発デモカウンターの裏側 これ、「演説」の内容もすさまじいものがありますが、加えて撮影しながら運転していますね。そればかりか、ハンドルを握る手にマイクも持っている。どうも演説も運転者がやっているみたいです。ということは、「演説」しながら撮影しながら車を運転しているわけで、こんな危険運転が許されていいの???この演説している奴は西村斉という、あちらの世界では有名人らしいです。もう一つは、私が参加した集会の1週間前のデモでのこと。在特会の連中の聞くに堪えない罵倒の中で、警察がデモ参加者を不当逮捕です。少なくともこの動画で見る限り、この人物が何か暴力行為を働いたようにはまったく見えません。実際、このデモでは12人が逮捕されましたが、そのうち7人は2日後には釈放されている。この動画で逮捕された人物(防護服を着ているので分かりませんが、フランス人とのこと)も釈放されている。犯罪の事実があったら、とても2日で釈放はされないでしょう。聞くに堪えない罵倒暴言を繰り広げている側は放任で、それに抗議の意志を示した側は、暴力をふるったわけでもないのに逮捕。公安警察がどっちを向いているのか、何ともわかりやすい話です。で、この動画でも、在特会の連中は「犯罪者は日本から出て行け」「射殺しろ」「生きたまま原子炉にたたき込め」などと、低劣なことを言っていますが、これぞ「天に唾する行為」というやつです。何しろ在特会自身も過去に逮捕者を出しているんですからね、まず自分自身が率先してそれを実行したらどうですかね。まあ、いろいろひどい連中ですが、その一方で今回の原発事故を契機にして、反原発派=左翼という図式ではなくなっていることも事実です。左翼(あるいは元左翼)でありながら公然と原発を擁護している人もいるし、逆に右派保守派にも反原発を公言する人が増えてきています。実際、右翼団体による反原発デモも行われています。ところが、です。6月11日の反原発集会において、そういった反原発派の右翼が参加しようとしたところ、デモの主催者はそれを歓迎していたにもかかわらず、彼等の参加をあくまでも妨害した連中がいるというのです。(このとしきの集会に参加したわけではないので、話に聞いているだけですが)狭い、あまりに狭すぎる。反原発というのは(他のどんな政治的課題でも同じですが)、他の政治的主張は様々に違っても、反原発という共通項で一致できる人たちが集まる場だと私は思うのです。そして、そのくらい賛同者の幅を広げていかなければ、脱原発なんて、遠い遠い夢でしかない。自分たちだけの活動自分たちだけの脱原発だったら、主張は決して広がりません。それでも、どうしても右翼と一緒に反原発をいうのが嫌だというなら、別個に反原発集会を開けばいいのに。日の丸を掲げた人物が発言するのはけしからんとか、そんなことを言っていたら、広がるものも広がりません。日の丸反対でもじゃなくて原発反対デモなんだから、日の丸がどうこうは関係ない。デモに日の丸がないからけしからんとか言っている在特会系のネットウヨクとレベルが全然変わらない。私は、もちろん自分自身が日の丸を掲げてデモ行進をする気はさらさらないですが、日の丸を掲げている人と一緒にでも行進することには何の抵抗もありません(※)。私は君が代は嫌いですが、日の丸は嫌いじゃないですし。※日の丸を掲げてデモ行進はする気もないですが、音楽関係では、日の丸に先導されて行進しながら演奏したり、日の丸を背にして演奏したことはあります。日の丸とペルー国旗とウィパラ旗の3つに先導されています。某所での演奏。去年4月の演奏です。今年4月にも同じ場所で演奏したけど、そのときはこの日の丸はありませんでした。(サッカー日本代表の寄せ書き入りの日の丸です)
2011.09.22
コメント(4)
-
台風直撃
台風で首都圏の交通機関が大混乱です。私も巻き込まれました。職場から乗換駅までの電車は動いていたのですが、その先が止まっていた。振り替え輸送ったって、山手線他使えそうな路線はみんな止まっていて、どうしようもありません。運転再開を待っているうちに雨が止んだので、歩いて帰りました。1時間ほどの行程。雨は止んだけど、風はけっこう強かった。高いビルの近くは特にそうです。もっとも、ものに掴まらないと歩けないとか、這わないと歩けないなんてことはなかったので、山で出会う一番ひどい烈風よりはマシだったかな。冬の八ヶ岳の稜線上なんか、常時このくらいの風が吹いていますからね。家に着いた時点では、その路線はまだ運転再開していなかったので、さっさと見切りを付けて歩いて正解でした。ただ、傘はぶっ壊れました。職場から最寄り駅までのほんの5分の距離を歩いただけで、傘はグチャグチャ。私は長い傘と折りたたみ傘を各1本ずつしか持っていないので、長い傘がなくなっちゃった。新しい傘を買わなくては。それにしても、この台風、沖縄近辺を迷走していたときは中心気圧980ヘクトパスカルくらいのあまり強くない台風だったので、さほど気にしていませんでした。それが本州に接近してきたときには、いきなり940ヘクトパスカルですからね。普通本州付近まで接近してくる頃には、台風の勢力は弱まってくるものですが、今回の台風は本土に近付いてからどんどん勢力が強まってしまった。調べたら、奄美大島と種子島の間あたりで急に勢力が強くなっているんですね。そのあたりの水温がまだ高い、ということなのでしょう。しかし、今年は本当に自然災害が多いですね。ついこの間台風12号で大きな被害が出たばかりなのに。これ以上はもう勘弁して・・・・・・。しかも、この台風、そのまま被災地の方向に向かっているようですが、福島第一原発とか、津波で地盤沈下してしまった地域とか、大丈夫なのだろうか。(いや、大丈夫のはずがないけど、せめてこれ以上大きな被害が出ないことを祈ります。)
2011.09.21
コメント(0)
-

さようなら原発集会に参加してきました
タイトルのとおりです。実は、昨日まで「さよなら原発」集会だと思っていて、このブログでもそう書いてきたのですが、実は間違いで「さようなら原発」が正しい名前でした。が、まあそれはそれとして、集会に一応参加し、デモ行進してきました。何故「一応」参加などと書いたかというと、会場は超満員で、集会の中身はほとんど見ることが出来なかったからです。そもそも、会場は総武線千駄ヶ谷駅下車の明治公園だったのですが、一駅手前で「反原発集会に参加の皆様、ただいま千駄ヶ谷駅は大変混雑しております。当駅から歩いても会場に行けますので」と放送しているような状況です。仕方がないので一駅手前から歩きました。たいした距離じゃなかったですが。これは、明治公園よりはだいぶ手前の国立競技場前の緑地(遊歩道)。この地点で既にかなりの人数が。明治公園、いやその前の道路は超満員。何とか明治公園の入り口まで来ましたが、すし詰め。すごい人数で、とても中には入れません。ステージは遙か彼方でした。ステージを望遠で撮影してみました。先ほどの入り口からは中に入れなかったので、坂を登って日本青年館前の高台にいってみました。ここからは公園内が見渡せました。上から見ても、やっぱり公園内が満杯です。ちょうど、この写真を撮っている頃に山本太郎がステージで演説していました。あと、制服向上委員会の歌もあったらしいです、私は見逃しましたけど。日本青年館前の高台。ここも明治公園の敷地なのかな。この場所だけはぎゅうぎゅう詰めではなく、場所に少しは余裕がありました。公園の反対側の入り口に回ってみました。ステージの脇付近です。駅から一番遠い入り口のせいでしょうか、入り口付近に人のいない空間が少しあって、なんとか公園内に入れました。それも5メートルくらい。その先は人の壁でした。反対側入り口の前の道路もこのとおりです。明治公園の広さは、だいたい100m四方くらい、日本青年館前の高台は100m×50mくらいのようです。つまり、1万平米と5000平米。そこから計算すると、多分会場内だけで3万人近くいたんじゃないでしょうか。会場に入り切らなかった人は、正確には分かりませんが、会場内の人数より多かったかも知れません。大通りの反対側にまで人が溢れていましたから。発表によると、集会参加者数は6万人とのこと。私の体感では、もっと多そうな気もしましたが、まあだいたいそんなものなのでしょう。毎日新聞のサイトに、ヘリコプターから会場を撮影した写真がありました。http://mainichi.jp/select/wadai/graph/20110919/1.htmlで、集会の後デモ行進に移ったわけですが、そんなわけで、集会参加者が多いものだから、隊列の長いこと長いこと。2時間は待ちました。しかも、デモは1コースではなく3コースに分かれていましたからね。実は、ケーナを持っていって、吹きながら歩きました。ただ、風が強くて、息が飛ばされがちでちょっと音が出しにくかったですけど。野外でケーナを吹くときは、風下を向いて吹くようにしているのですが、さすがに歩きながらの場合は、前を向くしかないですからね。諸事情により、デモ行進の写真は撮りませんでした。なので、デモの写真は新聞サイトより。↓読売新聞
2011.09.19
コメント(2)
-
「テロとの戦い」のたどり着いた先は
同時テロ10年一貫して「産・読」VS「朝・毎」 産経は安保環境悪化に言及世界を震撼(しんかん)させた米中枢同時テロ事件から10年。この間、アフガニスタン攻撃やイラク戦争、自衛隊のイラク派遣…とさまざまに展開した「対テロ戦争」だったが、各紙はその意味を社説であらためて問うた。米国に対して厳しい目を向けたのは朝日、毎日、東京の3紙である。朝日は「米国が力を過信し、その価値観を世界に押しつけようとした10年は失敗」と総括し、当時の小泉純一郎首相がイラク戦争を支持したことについても「『米国追随』という反発を日本国内に呼んだ」と批判的に評した。毎日も「『大量破壊兵器の脅威』を大義名分としてイラク戦争に突入したのは、返す返すも短慮だった」とし、東京も「宗教国家とも見紛(みまご)う単独主義的行動」だったと断じた。逆に、対テロ戦争に理解を示したのが産経と読売だ。両紙は多大の犠牲が払われた点にも言及したうえで、武力行使は必要であるとの論陣を張る。(中略)「(日本には)対テロ戦を主導する米国の負担を軽減する役割がある」とした産経は、日本周辺の安全保障環境の悪化を挙げ「アジアで米軍が存在感を維持することは、日本の国益そのものである」と同盟強化の重要性を強調する。同時テロの犠牲者約3千人の中に日本人24人が含まれていたことに触れたのは産経だけだった。「9・11」直後の9月20日付で産経が「主張」に書いたように、わが国は紛れもなく「24人の生命が失われたテロの直接当事国」なのである。この基本認識さえあれば、米とともに戦う日本を「米国追随」と批判するなど、全くの見当外れであることが分かるはずだが。--------途中までは、産経には珍しく「客観的比較」に徹しているなと思いきや、やっぱり最後はやっぱり産経。お決まりの結論という奴です。犠牲者に日本人が含まれていたから、テロの直接当事国である、と。そこまではまあいいでしょう。しかし、だから日本は米国とともに戦え、「米国追随」などと批判するな、というのは、それこそ「全くの見当外れ」の結論としか思えません。同時多発テロの犠牲者の国籍は多岐にわたっています。うろ覚えですが、確かイスラエルに支配される東エルサレム出身のパレスチナ人の犠牲者もいた、と当時報道されていた記憶があります。イスラム圏に属するパキスタンやレバノン、エジプトといった国々の出身者もいました。これらの国々に対しても、「テロの直接当事国だから米国とともに戦え」と言うのでしょうか。産経なら大まじめにそう主張しそうですが、鼻で笑われるだけのことでしょう。「対テロ戦」と称する戦争を仕掛けることがテロを根絶するための有効な手段ではないことは、同時多発テロ以降の10年間を見れば明らかでしょう。2001年アフガニスタン、2003年イラクと、米国(の主導する多国籍軍)は立て続けに戦争を仕掛けたけれど、それによってテロはなくなりましたか?明らかになくなっていません。それどころか、むしろ以前より状況は悪くなっている。そもそも、アフガニスタン(タリバン政権)はともかく、イラクは同時多発テロとは関係なく、米軍の侵攻は根拠のない言いがかりに基づくものでしかありませんでした。もちろん、サダム・フセインは恐怖政治を行う独裁者ではあったけれど、同時にイラクという国を統一して、近代国家としての体裁を整えた立役者でもあります。イスラム原理主義はフセインにとっても敵でした。だからこそ、隣国イランでイスラム原理主義のホメイニ政権が出来たとき、フセインはそのイランに戦争を仕掛けたのです。当時は欧米諸国も、フセインが残酷な独裁者であることを知りながら、イラクを公然と援助していました。フセイン政権は凶悪でも、いや凶悪だからこそ、もっと凶悪(欧米諸国から見て、です)なイランやイスラム原理主義勢力を押さえ込む役に立つと、欧米諸国は考えたのでしょう。いわば毒を以て毒を制そうとしたわけです。そのイラクに攻め込んで、フセイン政権を打倒した。その結果「めでたしめでたし」とはならなかったことは、結果が明白に証明しています。フセインという重しのなくなったイラクは、どう見てもフセイン政権時代より遙かに激しい血で血を洗う暴利よくの応酬で、より悲惨な状況になりました。米国にとっての敵であるはずのイスラム原理主義勢力も、フセイン時代より勢力を伸ばしている。現在、イラクは数年前の最悪の状態は脱していると言われますが、テロの横行が止まったわけではありません。当の米国民自身が、このようなイラク戦争は失敗だったと痛感したからこそ、イラク戦争開戦当時、この戦争に反対したバラク・オバマを大統領に選んだわけです。(大統領になって以降のオバマの政策には疑問が多いですが)アフガニスタンも状況は同じです。米軍侵攻によってイスラム原理主義勢力タリバンは政権を追われたけれど、それに代わって米軍の後押しで政権に就いたカルザイ大統領が実効支配しているのは首都カブールだけ。戦国時代の足利幕府のようなものです。オバマ政権は米軍はイラクからは撤退を進めており、そのおかげでイラクでの米軍の戦死者はどんどん減っていますが、そのかわりアフガニスタンでは戦死者がどんどん増えている。いつまで続くぬかるみぞ、です。10年戦争を続けて、フセインを殺した、ザルカウィも殺した、ビン・ラディンも殺した、でも戦争は終わらない。いつ終わるんですか?50年後ですか100年後ですか、それとも世界中から500万人くらいの部隊を送り込めば戦争が終わるんですか?どれだけの犠牲者を出せば済むんですか?現段階でも戦費は天文学的な額ですが、更にどれだけの金額を注ぎ込むつもりですか?そのときには別の国に「テロの温床」が生まれているんじゃないかと思うのですが、そのときはどうするんですか?また戦争するんですか?前述のとおり、かつて30年前の欧米諸国(旧ソ連も含む)は、フセインという残酷な独裁者を利用し、その武力でイスラム原理主義という敵を打倒しようとしました。しかしイラン・イラク戦争は、長い戦いの後引き分けに終わり、イスラム原理主義を打倒することは出来ませんでした。次は、欧米諸国自らの武力で、かつて利用したフセインもろともイスラム原理主義勢力を打倒しようとした。しかし、それもやっぱり成功していない。つまり、武力によってテロを撲滅することはできないということです。起こってしまった戦争は、元に戻すことは出来ません。しかし、今後二度と同じ失敗を繰り返さないことはできる。しかし、産経新聞は(読売新聞も?)同じ失敗を今後も続けろと、その失敗に日本も協力し続けろと言っているわけです。産経は、やたらと「反日」という言葉を投げつけることを好む新聞ですが、産経新聞の言っていることの方が、どう考えてもよほど「反日」です。
2011.09.19
コメント(2)
-
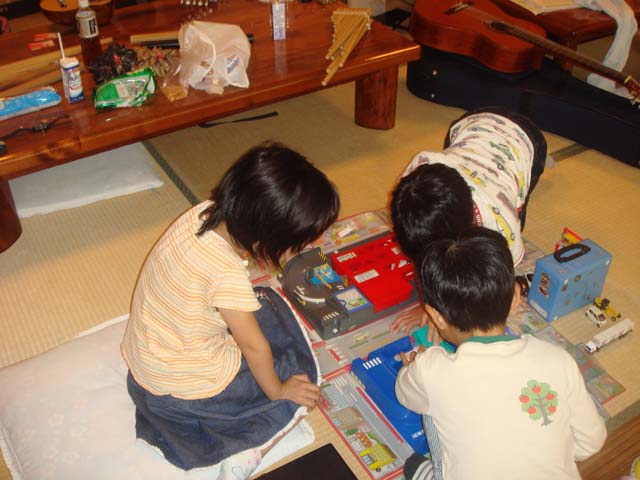
2日続けて子どもを連れて練習に
昨日は、先週に引き続いて、子どもと2人で代々木公園へ。私は笛の練習。子どもはもちろん私の練習になど付き合うはずもなく、池で魚を捕まえて遊んでいました。今、沖縄付近と八丈島付近に、台風が2つあるんですね。そのせいでしょうか、昨日は風が強かった。笛というのは、風が吹くと息が流されるので、強風時には音が出しにくくなります。昨日は、だから風が吹く度に体を風下に向けて、風を避けるようにして吹いていました。時々真っ黒な雲が湧いてきて、途中で雨が降るかと思ったのですが、幸い降られることはありませんでした。が、雨は全然降らなかったのに、我が子はズボンから下がびしょ濡れに。魚を追いかけているうちに、池に落ちちゃったんです。(私は反対を向いて笛を吹いていたので、落ちた瞬間は見ていないのですが)あーあ、やっちゃった。公園の池ですから、もちろんおぼれたりするような深さではありませんけど。まあ、この暑さですから、返るまでには服は乾きましたけど。公園に着いたのは多分2時半頃で、さて、そろそろ帰ろうかと思ったときは、すでに5時少し前。2時間以上ぶっ続けで練習していたんですねえ。それにしても、代々木公園はずいぶんいろんな人がいろんな楽器の練習をしていますね。そのおかげで、私が笛を練習しても、あまり目立たなくて済みます。今日は、キラ・ウィルカの練習でした。メンバーは5人でしたが、残念ながら1人は急遽仕事で欠席。残り4人で練習しました。今日もまた子どもを連れて行きました。もちろん、練習などそっちのけで、子どもたちだけで遊んでいるのですが。↑今日の練習の写真ではないですけどね。今日はいつも使っている施設の和室が取れなくて、別の施設の洋室で練習しました。いつもは、笛の音に負けないくらいの大声でギヤーギャー騒ぎながら遊んでいる豆ギャング団の3人組ですが、今日はかくれんぼをやっていたので、静かでしたよ。ええ、そりゃ、部屋を出たり入ったり、施設中を駆け回ったり倉庫に隠れたりしていたので、そういう意味では騒々しかったのですが、少なくとも大声は出さなかったですからねえ。野外練習では、どうしても音の響きは乏しいし、前述のように風の影響で音が出しにくいこともあります。それに比べると、室内はやっぱり音が響く。昨日屋外で練習したせいでしょうか、今日の室内での練習は、自分の笛の音がやけに響く気がしました。音量も大きくなったかな・・・・、もちろん、そんなわけはありません。そのように感じる、というだけのことです。もっとも、野外でPAなしの演奏でも、条件によっては案外いい音が出る場合もあります。3年前の演奏です(キラ・ウィルカとは別のグループ)。このグループの練習にいつも使っていた施設のお祭りでの演奏です。屋外での演奏で、完全生音、何のPA機材も使っていないのですが、その割には音が響きました。実は建物の壁を背にして演奏しているので、音が跳ね返ったのです。これも、同じ時の演奏です。ところで、明日は「さよなら原発」集会。これには、さすがに子どもを連れて行くのは無理そうです。何か子どもの遊び場でもあればいいのですが、デモ行進じゃ子どもには面白くないでしょうからね・・・・・・。
2011.09.18
コメント(0)
-
「内部被曝の真実」を読んだ
東大アイソトープ総合センター長の児玉龍彦が、国会の参考人としての発言がYouTubeで話題になっています。私自身もそれを見たのですが、その内容がさっそく書籍になりました。「内部被曝の真実」児玉龍彦著 幻冬舎新書非常に参考になり、また感銘を受ける内容でした。以前に、直線閾値なし仮説を巡る論争についての記事を書いたことがあります。直線閾値なし仮説の是非 その1直線閾値なし仮説の是非 その2100ミリシーベルト以上の被曝による発癌率の増加は統計的に認められているのですが、それ以下の被曝の場合は発癌率の増加が統計的には「分からない」とされています。あくまでも「分からない」のであって、「ない」と証明されているわけではありません。だから100ミリシーベルト以下の被曝でも、被曝量に応じた発癌率の増加があるだろう、というのがICRPの見解であり、世界的に見ても放射線防護や公衆衛生の基本原則となっています。しかし、100ミリシーベルト以下の被曝には健康被害はないのだと主張する研究者も存在します。児玉龍彦は、そのような主張(閾値あり説)を「おかしい」と明言しています。彼が例にひくのは、チェルノブイリ事故における小児の甲状腺癌増加についてです。今日では、チェルノブイリの事故によって子どもの甲状腺癌が激増したというのは周知の事実となっています。実際、事故の4年後くらいから周辺地域で甲状腺癌は増加しはじめており、そのことは調査によってすぐ明らかになっていたにもかかわらず、「チェルノブイリの事故によって小児甲状腺癌が増加した」という因果関係がIAEA(国際原子力機関)によって公式に認められたのは、何と事故の20年後だというのです。何故か。そもそもロシアは、チェルノブイリと甲状腺癌の因果関係を認めると補償問題が生じるので認めたくない、という事情がありました。しかし、ロシアの委員だけでなく米国の委員も、因果関係を認めることに反対してそうです。チェルノブイリ以前の甲状腺癌の発生率が分からないから、増えたかどうか分からない、というのです。甲状腺癌の発生率のデータはありますが、比較的良性の甲状腺癌は原発事故以前は見逃されてきたかも知れない、だから、事故以前の「本当の」発癌率は分からないから、発癌率が増えたかどうかは分からない、ということにされてしまったのです。その間に、笹川財団の支援で5万人を対象にした調査が行われましたが、甲状腺癌の増加はその時点では「証明」できなかったそうです。が、20年経ってみるたら、事故によって甲状腺癌が増加した因果関係は明白になりました。甲状腺癌の発生率は、1990年から上がり始めましたが、小児(14歳以下)では95年をピークに下がり始め、2002年には完全に事故以前の水準に戻りました。一方、15~18歳では2001年にピークを迎え、2002年から下がりはじめています。19歳以上の年代では、2002年までずっと発生率は上がり続けています。このことは何を意味するかというと、事故以降に生まれた子どもには、甲状腺癌の増加はない、ということです。これほど明白な因果関係はないでしょう。でも、20年経ってやっとチェルノブイリ事故による甲状腺癌増加の因果関係が立証されても、そのときにはもうみんな甲状腺癌を発症してしまった。増加が「証明」されたときには、すべてが手遅れなのです。チェルノブイリの事故で発癌率が増加したと「証明」されたのは小児甲状腺癌だけです。それ以外の癌や白血病の増加は、統計的には証明されていません。しかし、児玉龍彦は、増えたのが本当に甲状腺癌だけなのか、という点はかなり懐疑的に見ているようです。私もそう思います。被曝から癌の発生に至るまでには、何年もの時間を要します。発癌以前に別の理由で死んでしまう人もいるでしょう。また、被曝以外にも癌を誘発する要因はいろいろあります。そういう中で、被曝者集団とそうでない者の集団を何年、いや何十年も追跡調査して、他の発癌誘因要因を切り離して被曝の影響を統計的に比較する、それがどれほど困難な作業かは、容易に想像がつきます。1950年代から60年代にかけて米ソ両国が繰り広げた大気圏内核実験では、公式には直接の死者はほとんど出ていません。第五福竜丸の久保山さん以外には聞いたことがありません。でも、一説にはこれらの核実験による死者(癌や白血病の増加による)は、50万人とも100万人とも言われます。もちろん、統計的に証明はされていませんが。証明なんか出来るわけがないのです。核実験の放射能は世界中にまき散らされているんだから、被曝した集団と被曝していない集団の比較をしようにも、「被曝をしていない集団」がどこにいるのかという話になる。被曝による健康被害に「閾値がある」と主張する人はいます。そういう本も書店で売られています。たまたま手に取った本がこれでした。「放射能は怖い」のウソ 親子で考える放射能Q&A 服部禎男著 ランダムハウスジャパン一読して、ひっくり返ってしまいました。無茶苦茶な内容。たとえば、福島第一原発の事故で放出された放射能はチェルノブイリ事故の50分の1以下、という趣旨の記述がありました。明らかにウソなのです。原子力安全・保安院が発表している公式数値で、今回の事故の放射能量はチェルノブイリの1/7くらいだったはずです。一つだけ確実に言えることは、「放射能は安全だ」と叫ぶ輩の言い分を真に受けて、20年後30年後に健康被害の状況が明らかになったとき、この連中が責任を取ってくれるわけではない、ということです。いや、仮に責任を取らせることができたとしても、失われた命、失われた健康が返ってくるわけではありません。以前にも書いたように、「安全か危険か分からないもの」はとりあえず危険だと見なしておくのが公衆衛生や医療という考え方の基本原則です。危険だと思っていたものが安全だったと後で証明されても取り返しがつきますが、安全だと思っていたものが後で危険と分かった場合、取り返しのつかない事態が生じてしまいますからね。
2011.09.17
コメント(0)
-
今更福島第二原発が動かせるはずがない
さようなら原発 5万人集会9月19日(祝)午後1時~ パレード午後2時15分~会場 明治公園(東京・新宿区)JR中央線千駄ヶ谷駅下車5分、都営大江戸線国立競技場前下車2分http://d.hatena.ne.jp/byebyegenpatsukyoto/20110831/1314774609----<枝野経産相>福島第2原発 廃炉は不可避の認識示す枝野幸男経済産業相は15日、毎日新聞などとのインタビューで、東京電力福島第1原発事故に関連し、福島第2原発についても「(再稼働に)地元の理解が得られる状況とは誰も思わない」と述べ、廃炉は不可避との認識を明らかにした。福島第1原発については深刻な事故を起こした1~4号機に加え、5、6号機も廃炉にせざるを得ないとの考えを示した。東電はこれまでに福島第1原発1~4号機を廃炉にすると表明しているが、5、6号機と第2原発の1~4号機については言及していない。また、枝野経産相は立地自治体から安全性への不安が出ている老朽化した原発への対応については「原子力政策の見直しのプロセスの中で、なんらかの基準を考えていく必要がある」と指摘。専門的な見地や国民の受け止めを踏まえ、建設から一定期間がたった原発については安全性の観点から廃炉にする基準作りに乗り出す考えを示した。また、福島原発事故を受けて出ている原発の国有化論に対しては「エネルギー政策の抜本的見直しの中で、議論の俎上(そじょう)に載るテーマなのは間違いないが、軽々に結論を出せる話ではない」と述べるにとどめた。-----福島第二原発の再起動なんて、地元が了承するはずなど絶対になく、廃炉が不可避というのは当たり前の話です。まして第一原発の5・6号機なんか、まだ廃炉が決まっていないという事実自体がびっくりです。政治的な面、住民感情を別にしても、技術的に考えて再稼働は容易ではないと私は思います。津波被害の戦闘機12機処分 残り6機は修理800億円防衛省は東日本大震災の津波で被災した航空自衛隊松島基地(宮城県)のF2戦闘機18機のうち12機について、修理は困難と判断し、処分する方針を決めた。残り6機は購入費よりも高い計約800億円をかけて修理して使う。防衛省によると、松島基地には約2メートルの津波が押し寄せ、18機のF2すべてが海水につかった。防衛省は修理できるかどうか見極めるため、136億円の予算を投じて分解調査を進めていた。この結果、12機は被害が大きく、使用を断念。使える部品などは取り出して、別の装備で再利用する。残る6機は修理可能だが、1機につき約130億円の修理費がかかるという。 -----津波で水没した航空自衛隊のF2戦闘機は、2/3は修理不能、残りの1/3も修理代は新造するより高価だそうです。水没したと言えば、福島第1原発・第2原発も同じです。事故に至ったのは第1原発の1~4号機だけですが、そのほかもすべて原発の建屋内に海水がなだれ込んでいます。それらの海水は、その後も原発にたまったままで、まだ排水は終わっていないようです。当然、海水に浸かった電気系統、電子機器はすべて使い物にならないでしょう。それ以外の鋼鉄製の部品なども、腐食したものが相当あるはずです。水没した戦闘機が修理不能なのに、水没した原発が修理可能なのか、というのは大いに疑問です。仮に修理が可能としても、その所要時間は相当の期間に及ぶでしょう。新潟の柏崎刈羽原発は、2007年7月の中越沖地震で全機停止し、最初の1基が運転再開にこぎ着けたのは2年後、地震から3年8ヶ月経った今回の地震の時点でも、まだ3基は点検が終了していませんでした。言うまでもなく、柏崎刈羽原発は地震の揺れによる被害はあっても、津波で海水漬になったわけではありません。それでもこんなに時間がかかるのですから、仮に福島第二原発が運転再開が可能だとしても、その時期は相当先(おそらく5年以上かかる)になるし、修理費も下手をすると新造と変らないくらいの金額ななるかも知れません。いずれにせよ、福島第二原発の再稼働など(第1原発の5・6号機は言うまでもなく)ありえないし、あってはならないことだと私は思います。
2011.09.16
コメント(2)
-

何年吹いても、ケーナはままならぬ
フルート界の巨匠マルセル・モイーズは、1981年92歳の時に、愛用のフルート(ケノンというメーカーの総洋銀製)のコピーの製作を、日本のムラマツフルートに依頼したことがあるそうです。その理由は、思うように音が出ないフルートに癇癪を起こして、投げつけて壊してしまったためだそうです。なるほど、モイーズほどの超一流の演奏家でも、思うように音が出なくていらいらすることがあったんですねえ。(ま、92歳では高齢のため腕が衰えたからという面が強いのでしょうが)私はケーナを25年ほど吹いています。最初の6年はアルゼンチンのアルノルド・ピントス製。それから16年間はボリビアのアハユ製、3年前からはボリビアの作者不詳のケーナを吹いています。他に、アハユ製をコピーした自作ケーナも多少使いましたが。アハユのケーナは、25年も使って、最後は吹き口の近くに亀裂が入って釣り糸で修理、表面は汚れ放題、内側は長年吸った湿気でグズグズと満身創痍の状態だったのですが、とても吹きやすくて、なかなかこれに代わるケーナが見つからず、新しいケーナを買ってはダメ、買ってはダメで、最後にたどり着いたのが、今使っているケーナです。白っぽい方が今使っているケーナ、茶色い方が一代前のケーナです。吹き口部分を拡大すると、↓のような感じです。アップにすると、前のケーナがどれだけ汚れているか分かりますね。吹き口の脇に亀裂があるところは、セロテープを貼って、その上から釣り糸で固定したのですが、この補修をしてから更に4~5年使ったので、セロテープもボロボロらなっています。後で、セロテープなんか貼らずに直接釣り糸を張ればよかったと思いました。↓は上から見下ろしたところ吹き口の構造が少し違うのが分かるでしょうか。古いケーナは吹き口のエッジが肉厚の一番外側に来るようになっていて、外側にはほとんど削り込みがなく、内側に深く削り込まれています。一方、新しいケーナは肉厚の真ん中付近にエッジがあり、内側と外側に同じくらいの削り込みです。世の一般的なケーナは、後者、つまり肉厚の真ん中付近にエッジがあるのが普通です。エッジが外側に来ているのはアハユのケーナ独特の形状で、他のメーカーではあまり見たことがありません。私の自作のケーナは、アハユのコピーなので同じ形状にしていますが。そのアハユも、最近は吹き口の形状が一変して、エッジが肉厚の真ん中付近にくる、「普通のケーナの吹き口」になってしまいました。実は、アハユ製のケーナは他に2本持っているのですが、いずれもこのケーナほどには思うような音が出ないのです。で、今のケーナ。写真ではちょっと分かりにくいですが、先代のケーナに比べて、一回り太いです。ただし、肉厚はそれほど厚くありません。太いだけに、音量はかなり大きいです。音色も悪くないと思います。ただし、太いだけに大きな息が必要です。ロングトーンを計ってみたところ、先代のアハユ製ケーナは1オクターブのドで12~3秒息が続きますが、今使っているケーナは10秒続くかどうかです。そして、なにより厳しいのは、ちょっとでも調子が悪いと悲惨な音になってしまうということです。息の風速がちょっとでも落ちると、唇の形がちょっとでも甘くなると、唇の位置がちょっとでもずれると、途端に音がかすれたりひっくり返ったりします。音の鳴るポイントが狭いのだと思います。3年も使って、そろそろ慣れてきたかと思いきや、3年経ってもまだまだなのです。暴れ馬です、このケーナは。アハユ製のケーナはもう少し安定的に音が出ます。今もケナーチョ(低音用のケーナ)はアハユ製を使っていますが、そんなに吹きにくいことはありません。もっとも、ケナーチョではあまり高音を使わないからそのように感じるだけかも知れませんが。特に夏場は暑さと湿気のために調子が悪いことが多いのです。思うように音が出ないときは、だんだんイライラしてきます。ま、さすがにケーナを投げつけたりはしませんけど、癇癪を起こしてフルートを投げつけてしまったというモイーズの心理が、ちょっとだけ理解できる気がします。もっとも、モイーズが投げつけて壊してしまったというフルートはいったいいくらしたんでしょうか。比較的安価な洋銀が材料に使われていたとは言え、特注品だから相当高価な物だったはずです。
2011.09.15
コメント(2)
-
今どき不敬罪ですか?
民主党会派の平山参院議員、陛下に携帯カメラ向ける無所属で民主党会派に所属する平山誠参院議員が、13日の開会式に臨席される天皇陛下を衆参両院議員が整列して迎えた際、陛下を携帯電話のカメラで撮影していたことが同日、分かった。自民党参院議員ら複数の議員が目撃した。平山氏は産経新聞などの取材に対し、今回に限らず毎回撮影していることを認めたが、「撮影時には陛下は(国会の階段を)上がられていて今回は(お姿を)撮れていない」と釈明。「参列を撮ったり、礼をしているときに撮ったら失礼だが、それはしておらず陛下に礼を欠く態度では撮っていない」と述べた。これに対し、自民党からは「陛下に対して畏敬の念がない。緊張感が足りない」(小坂憲次参院幹事長)などと批判が噴出。同じ会派の民主党の羽田雄一郎国対委員長らからも問題視する声が上がっている。----何が問題なのか、まったく理解できません。式典の最中とか、議場内で国会開会中ならともかく、この「事件」は、読売新聞の報道によると「陛下が(国会中央玄関の)車寄せに到着した段階で、携帯電話で写真を撮っている議員が現認された」とのことです。どこかの中小企業のワンマン社長じゃあるまいし、お車が到着したら直立不動でお出迎えとか、馬鹿馬鹿しすぎます。「陛下に対して畏敬の念がない。緊張感が足りない」というのも、全然理解できません。天皇という一個人に、「畏敬の念」を持つか否かなんて、本人の自由でしょう。ちなみに、私自身は、現在の天皇に対しては悪意も敵意も全くない(実際の人柄は知りませんが、見た印象では人の良さそうな感じで、好感を持てます)けれど、しかし畏敬の念なんてものは持ち合わせていません。まあ、私は国会議員じゃないけどね。自民党の一部議員は(民主党の一部議員も)、未だに戦前の不敬罪のあった時代の価値観で生きているみたいですね。それを報じる産経新聞なども同様です。そのうちに、「陛下にカメラを向けるなんて、目が潰れる」とか言い出すんじゃなかろうか。
2011.09.13
コメント(4)
-
10年目の9.11、そして野外練習を
今日9月11日は、2001年の9.11から10周年、1973年の9.11(チリの軍事クーデター)から38年、そして3.11(震災)から半年という節目の時です。ただ、3.11の節目というには、まだあまりに早すぎるかな。何も解決していないし。1973年のチリクーデターのことは、リアルタイムでは私は知りません。当時私は5歳。さすがに地球の反対側で起こった政変に興味を持つ年齢ではありませんでした。しかし、2001年の9.11の方は、よく覚えています。日本時間では翌12日だったのでしょうか。多分平日だったはずですが、何かの都合で午後から休みを取って、何かの買い物で秋葉原かどこかの電気屋に行ったと記憶しています。店頭でに陳列してあるテレビに、旅客機がWTCビルに突っ込む衝撃のシーンが放送されていたことをよく覚えています。でも、現実のこととはとても思えませんでした。不謹慎ですが、パニック映画の一シーン・・・・・・じゃないんだよね、これ、えーーー、ウソでしょ、何これ??というのが最初の印象でした。もっとも、今となっては今回の震災の映像の方が遙かに衝撃的と思います。※訂正です。調べたところ、9.11の発生時間は、日本時間では同日の夜10時過ぎでした。私が翌12日に電気店の店頭のテレビで見た映像は、おそらく翌日の報道だったのでしょう。ということは、翌日くらいまでは飛行機がWTCに突っ込む映像は放送されていた、ということなのだろうと思います。あの同時多発テロからもう10年も経ってしまったんですね。ついこの間のような気がするのですが。当時、私はまだ独身でしたし(我が相棒とは、まだ付き合ってさえいませんでした)、当然子どももいませんでした。たった10年で、私自身の身の回りもずいぶん変わりました。事件当日(日本時間では翌日)はWTCビルに旅客機が突入するシーンが繰り返し放送されていました。前述のとおり、私もそれを見たのですが、翌日からは、「その瞬間」の映像はまったく放送されなくなりました。犠牲者に遠慮したのでしょう。もっとも、今ではYouTubeでいくらでもその瞬間の映像を見ることが出来ますけど。ただ、驚くのは、日本語でYouTubeにアップロードされているこの事件関係の動画の多くは、陰謀論に染まっていることです。「飛行機は突っ込んでいない」とか、「CGだ」とか、そんなタイトルが目に付きます。(英語でアップロードされているものについては確認していませんが)そんなわけないだろ、と思います。少なくとも2機目に関しては、生中継のただ中に突っ込んでいます。それ以外にも、アマチュアカメラマンも含めて多くのカメラが激突の瞬間を撮影しているのに、捏造もないもんだ。確かに、911の動機や全貌、米国政府がテロの前兆の気がついていながら、どこまで真剣に対応しようとしていたのか未解明の部分は多々あります。また、テロの後の米国の行動(アフガニスタンへ、続いてイラクへの侵略)には非常に大きな問題があります。だけど、それはそれとして、「飛行機は突っ込んでいない」とか、事件全体が米国の仕組んだ陰謀だというような主張というのは、「南京虐殺なんてなかった」というのと同種の歴史修正主義でしかないように、私には思えます。911陰謀論といえば、きくちゆみの専売特許と思っていましたが、支持する人が増えているのでしょうか。(私は、きくちゆみの主張のすべてが間違っているとは思いませんが、少なくとも911に関する彼女の主張には、まったく同意できません)---話はまったく変わりますが、今日は代々木公園に行ってきました。ちょうどスリランカフェスティバルというのが行われていて、屋台でスリランカカレーを食べて(結構おいしかった)、その後相棒と子どもと別行動で、代々木公園内で練習してきました。前々から、私はグループの練習を代々木公園でやりたいなと思っているのですが、どうも他のメンバーの賛同が得られず、実現に至っていません。それなら自分1人ででも練習してしまえと思い立ったわけです。持ち込んだのはケーナ・サンポーニャ各種とフルート。本当はギターも持っていきたかったけれど、さすがにかさばるので、ギターはやめました。(グループの練習の時は持っていくけど)今日は日中の最高気温は30度を超えて、かなり暑かったですけど、やっぱり秋ですね、木陰では風が涼しくて、あまり暑いという気はしませんでした。屋外での練習経験は何度かありますが、代々木公園では初めてです。音が木々に吸われてしまって響かないだろうと予想していたのですが、案外そうでもなくて、ある程度響きました。ただ、ちょっと疲れてくると音が出なくなってしまうのです。ケーナとサンポーニャもその傾向がありますが、特にフルートがひどい。「アルルの女」のメヌエットを吹き始めたら、途中から音がグチャグチャ。最低音のドもやけに出しにくいし、あまり間違えたことのない3オクターブの運指も間違える。やっぱり室内での練習とはちょっと違う力が働いてしまうのでしょう。それに、ケーナ→サンポーニャ→フルートと順番に吹いたので(家で練習するときも同じ順番)、フルートを吹くときにはかなりへたばっていたのかも知れません。もともと、朝8km以上ランニングしたので、体力の余力が乏しかった。それにしても、私はできるだけ目立たないように木陰に身を隠すようにして練習していたのですが、それでも何人かの方が聞き入っていらっしゃいました。お一人、ご自身もケーナを吹いている、という方もいらっしゃいました。自作のケーナを吹かせていただいたのですが、音の出るポイントが私のとは若干違い、3オクターブが私には音がほとんど出ませんでした。その方の話によると、代々木公園では他に2人くらいケーナの練習をしている方がいらっしゃるとか。どのくらいの時間練習したのか、正確には分からないのですが(練習を終えた時間は4時半頃ですが、始めた時間が分からない)、多分2時間くらいじゃないかと思います。さすがに疲れました。屋外での練習にはいろいろ欠点もあるけれど、ひれを差し引いても楽しいです。また練習しに行こう。それに、グループの練習も屋外でやりたいな。実は、キラ・ウィルカは一度だけ野外で練習したことがあるのです。(代々木公園ではないですが)3年くらい前、「南京への道・史実を守る会」の集会で演奏したときのことです。会場内で練習場所を確保できず、やむを得ず近くの公園で練習しました。しかし、真夏の午後だったので、猛烈な暑さでした。それでもがんばって練習していたら、そのうち、向こうの方から急に空が暗くなってきて、黒い雲がどんどん近づいてくる。大慌てで練習を打ち切って会場に逃げ込んだら、直後には滝のような雨。このあたりは、野外練習の難しさですね。やっぱり、野外で練習するなら春か秋。真夏と真冬は厳しいですね。
2011.09.11
コメント(5)
-
菅前首相は、ひょっとしたら救国の英雄だったのかも知れない
「命懸けて。逃げても逃げ切れぬ」 前首相の東電訓示東京電力福島第一原発事故で、本紙は、菅直人前首相が三月十五日未明に東電本店に乗り込んだ際の訓示の記録全文を入手した。現場からの撤退を打診した東電側に「放棄したら、すべての原発、核廃棄物が崩壊する」と警告し、「命を懸けてください」と迫っていた。菅氏は本紙のインタビューで「東京に人がいなくなる」ほどの強い危機感があったと明かしていたが、訓示の内容からもあらためて裏付けられた。第一原発では当時、1、3号機が水素爆発を起こし、2号機も空だき状態の危機が続いていた。政府関係者の記録によると、菅氏は「(撤退すれば)チェルノブイリ(原発の事故)の二~三倍のもの(放射性物質の放出)が十基、二十基と合わさる。日本の国が成立しなくなる」と危機感をあらわにした。その上で、「命を懸けてください。逃げても逃げ切れない」と、勝俣恒久会長や清水正孝社長(当時)ら東電側に覚悟を要求。「六十歳以上が現地に行けばいい。自分はその覚悟でやる。撤退はあり得ない」と訴えた。菅氏は海江田万里経済産業相(当時)から「東電が撤退意向を示している」と報告を受け激怒。清水社長を官邸に呼び政府と東電の統合本部設置を通告し直後に東電を訪れた。東電の松本純一原子力・立地本部長代理は今月六日の記者会見では「撤退を申し上げた事実はない。七十人程度が事故対応のために残り、それ以外は(対応拠点の)『Jヴィレッジ』や福島第二原発に退避することを考えていた」と説明した。----以前から度々書いているように、私は菅前首相をトータルでは支持していなかったけれど、脱原発の方向性だけは全面的に支持するし、震災対応はベストとはとても言えないけれど、誰が首相だってそんなに変わらなかっただろうと思っています。でも、一連の経緯を検討してみると、原発事故対応に限定すれば、ひょっとしたら歴代首相の中でもベストの対応だったかもしれない、と思います。もしこれが電力会社の利権にどっぷり浸かった政治家だったら、東電から「撤退したい」と要求されたとき、果たして何と答えたでしょうか。唯々諾々と要求に従ってしまった可能性が高いのではないでしょうか。東京電力側は、全面撤退の申し入れをしたことはないと主張しています。しかし、枝野前官房長官も、東電は全面撤退の申し入れをしてきたと証言しています。前首相の東電乗り込み、危急存亡の理由が枝野幸男前官房長官は7日、読売新聞のインタビューで、東京電力福島第一原子力発電所事故後の3月15日未明、東電の清水正孝社長(当時)と電話で話した際、作業員を同原発から全面撤退させたい、との意向を伝えられたと語った。東電関係者は、これまで全面撤退の申し出を否定している。菅前首相や海江田万里前経済産業相は「東電が作業員の撤退を申し出てきた」と説明してきたが、枝野氏は今回、撤退問題に関する具体的な経過を初めて公にした。枝野氏は、清水氏の発言について「全面撤退のことだと(政府側の)全員が共有している。そういう言い方だった」と指摘した。枝野氏によると、清水氏はまず、海江田氏に撤退を申し出たが拒否され、枝野氏に電話したという。枝野氏らが同原発の吉田昌郎所長や経済産業省原子力安全・保安院など関係機関に見解を求めたところ、吉田氏は「まだ頑張れる」と述べるなど、いずれも撤退は不要との見方を示した。菅氏はこの後、清水氏を首相官邸に呼んで問いただしたが、清水氏は今後の対応について明言しなかったという。このため、菅氏は直後に東電本店に乗り込み「撤退などあり得ない」と幹部らに迫った。枝野氏は菅氏の対応について「菅内閣への評価はいろいろあり得るが、あの瞬間はあの人が首相で良かった」と評価した。----更に、毎日新聞の報道によると検証・大震災:菅前首相の証言 国難、手探りの日々 「日本がつぶれるかも」海江田経産相が「ちょっと相談があります」と連絡してきたのは、15日午前3時ごろだった、と菅氏は記憶している。電源車の手配、ベント実施、半径20キロ圏内の避難指示、計画停電……に続く新たな難題だった。「海江田さんが『東電が第1原発から撤退したいという意向を持っている』というから、『えっ、本当なの?』と。撤退ってどうするんだ。第1原発だけで六つの原子炉があって、放っておいたら全部がメルトダウン起こして世界中に放射能が放出される。命に懸けても止めるしかないのに、放棄して逃げるなんて。一時的に線量が高いから退避するのは別だが、撤退するなんて考えられん。それで清水社長を呼んだ」午前4時17分、清水社長が官邸を訪れた。「『撤退したい意向があると聞いたけど、どうなんですか』と言ったら、はっきり言わない。撤退したいとも、まったく考えていないとも言わない。一時的に退避するようなしないような」東電は「全面撤退」を否定する。だが、菅氏は「あとになってそういう話ではなかったと東電から聞こえてくるが、経産相を通じたのだから、本格的な提案だと当然思う」と反論する。という経過だったようです。このように問いつめられて、返事をしない時点で、図星(撤退の意志を持っている)だと見なすしかないでしょう。そりゃ、ふざけるなと言うしかありません。自衛隊も消防も、原発を運転することは出来ません。内部構造だってよく知らないでしょう。東電が現場から撤退してしまったら、事故を収拾することはまったく出来なくなってしまうところでした。もう一つ忘れてはならないことは、住民に対してはかなり早期に思い切った避難指示を出したという点です。地震当日の3月11日深夜には半径3km以内の避難指示、翌12日未明には避難指示の範囲を10kmまで拡大。ここまでの指示は最初の爆発の前に行われています。1号機の爆発が午後3時半頃で、午後6時過ぎには避難範囲が20kmに拡大しています。誰が首相でも、爆発以降はこの程度の範囲に避難指示を出したでしょう。でも、爆発が起こる前に避難指示を出せたでしょうか。「原発は危険」という印象を国民に与えたくないという動機から、避難指示が後手後手に回っていた可能性が高いように、私は思います。そうなっていれば、住民の被曝は実際よりもっともっと酷いことになっていたはずです。
2011.09.10
コメント(2)
-
タバコ700円
小宮山厚労相「将来はたばこ700円台」 増税求める小宮山洋子厚生労働相は5日の記者会見で、来年度の税制改正で、たばこ税の増税を求める考えを明らかにした。それ以降も段階的に増税したい考えで、将来の姿として「(1箱の価格が)700円台ぐらいまでは(値上がりしても)税収も減らない。そこまでは少なくともたどり着きたい」と強調した。たばこ税は昨年10月に、1本当たり3.5円引き上げられたばかり。主要な銘柄で1箱(20本)の価格が400円余りする。小宮山氏は、たばこ離れによる税収減を心配する財務省から「1年様子を見させて欲しい」と言われているとしたうえで、「(増税は)税収を上げるためでなく、健康を守るため。たばこ事業法で財源として財務省が持っているのが本当はおかしい。厚労省が持てるようになればいい」と持論を述べた。また、会社員の夫に扶養されている専業主婦らが国民年金の保険料を納めなくても年金をもらえる「第3号被保険者」制度について、報道各社のインタビューで「生き方に公平な制度になるよう努めたい」と強調。将来は廃止が望ましいとの考えを示した。 ------自慢ではありませんが、私は生まれてこの方、ただの1本たりともタバコを吸ったことがありません。管楽器を演奏し続ける限りは、今後も決して吸わないでしょう。ただし、ある時期までは他人のタバコの煙はずいぶん吸って(吸わされて)きました。12~3年前でしょうか、職場で指定の喫煙場所以外での喫煙が全面禁止になったので、それ以降は不快な思いをすることはまれになりました。今は飲み会の席でタバコを吸う人と相席になったときくらいでしょうか。どういうわけか、お酒を飲んでいる間はタバコの臭いはあまり気にならないんです。ただ、翌日服に染み付いたタバコの臭いは非常に嫌ですが。JRには、以前は禁煙車と喫煙車がありました。喫煙車が廃止され、車内が全面禁煙化されたのは、5年くらい前でしょうか。しかし、当時は「元喫煙車」だった車両は、車内にタバコの臭いが染みついていて、「これのどこが『全面禁煙』だよ!!」と思った記憶があります。これだったら、喫煙車を存続させておいて、こういうヤニ漬け車両は喫煙車専用にしておいてもらった方が、まだマシだと、当時は思いました。ただ、おそらくその後、元喫煙車は徹底的な洗浄が行われたのだと思います。近年はタバコの臭いで不快な思いをする車両に出会うことはなくなりました。そんなわけで、社会的に分煙が徹底されるようになったので、タバコで不快な思いをする機会は、最近ではほぼなくなりました。だから、喫煙者が他人に迷惑をかけない範囲で喫煙することについてまで目くじらを立てようとは思いません。ただ、タバコに健康面の問題があることは明らかで、それによって医療費をはじめとする社会的コストが増大していることも、おそらく事実だと思います。だから、タバコ700円という提案は、少なくとも反対ではありません。私は、お酒に関してはそこそこに飲む人間ですが(自宅で日常的に飲むことはありませんが、飲み会などではごく普通に飲みます)、酒税についても、値上げがあっても仕方がないと思っています。酒はタバコとは違い、適量までなら体によいとされますが、適量を超えれば健康に悪影響があることは明らかです。ところで、当ブログで過去散々批判してきた武田邦彦が、タバコを巡る問題でまた何か言っているようです。「タバコと肺がんはほぼ無関係」 武田邦彦教授発言は暴論なのか武田教授は、自らのブログで2011年9月6日、これまでの「先入観」を否定し、「タバコと肺がんはほぼ無関係」とまで言い切ったのだ。ブログでは、国の統計データから、この40年間で、男性の喫煙が8割から4割へと半減し、女性は2割弱で変化がないことを指摘。それにもかかわらず、男性は7倍に、女性は数倍に肺がんが増え、男女合わせれば5倍以上に増えていることから、タバコが肺がんの主要な原因とは言えないとした。これに対し、統計から、年齢が上がるほど発がん率が高くなることが分かっているとして、肺がんの増加は、高齢化が主な原因との見方を示した。武田教授は、100年前に比べ、平均寿命が40歳ぐらいから80歳前後にまで伸びていることが大きいとしている。そのうえで、武田教授は、タバコには、楽しみや精神的安定などのメリットもあると指摘。酒なども健康に害があるのに、タバコだけ社会的に制限して、値段を上げたり、喫煙者を追放したりするのは誤りだと断じている。(以下略)------武田邦彦は、放射能の問題に関しては案外まともなことも言っていますが、それ以外のことについては相変わらずのトンデモぶりです。念のため、原文はこちらにあります。実は、個々のデータ、個々の分析では間違ったことを言っているわけではありません。しかし、そこから導き出された最終結論が頓珍漢なのです。原文には、まずタバコが健康に悪いということは臨床的には明らかで、肺がん、気管支障害、血液障害などを誘発することがよく知られています。とあります。よく分かっているじゃないですか、まったくそのとおりなのです。そこからどうして、「タバコと肺がんはほぼ無関係」などという無茶苦茶な結論が導き出されるのか。武田の言い分を要約すると、こうです。喫煙率は下がっているのに肺ガンは増えている。日本人の平均寿命は伸びている。だから肺ガンの増加は高齢化が主因であるこれも事実です。ただし、人間が年を取ることは絶対に避けようがないことも事実です。年を取るとガンになりやすいから、年を取るのをやめようと言ったって、どうにもなりません。だから、少なくとも「健康への悪影響を減らすにはどうしたらいいか」という文脈で考えるとき、年を取るとガンになりやすいなどという話は持ち出すべきではないのです。一方、喫煙するしないというのは人間の意志と決定の問題です。確かに、肺ガン発生率への影響度は、喫煙より高齢化の方が大きいのかもしれません。けれども、高齢化という変数は人間の力でどうにも動かしようがありません。そうである以上、喫煙という変数を動かすしかないのです。だから、癌の死亡率を云々する場合は、単純な死亡率を比較するのではなく、年齢調整をした上で比較しなければ、意味ある結論は出てこないのです。ところが、武田邦彦は、年齢調整をしない単純な死亡率の比較だけで「肺ガンが増えている」と言ってしまっているのです。年齢調整後の癌死亡率の推移は、がん研究振興財団が公表しています。主要死因別年齢調整死亡率年次推移年齢調整をすれば、肺ガンは1995年をピークにして、以降減少していることが分かります。喫煙率の減少と肺ガンの死亡率(年齢調整後)の減少にはタイムラグがありますが、喫煙を止めればただちに健康リスクが消滅するわけではないので、タイムラグがあるのは当たり前です。統計的に見て、喫煙者の発ガンリスクは、タバコを吸わない人の5倍ですから、タバコと肺ガンに因果関係があるのは間違いありません。
2011.09.08
コメント(2)
-
目的外使用をするからこういうことになる
名古屋市議会リコール署名簿流出:署名簿、ネットに 氏名や住所閲覧可能名古屋市の河村たかし市長が主導した市議会解散請求(リコール)の署名簿が外部に流出した問題で、大量の署名簿がインターネットのファイル転送サイトで公開されていた。署名者の氏名や住所、生年月日を不特定多数の第三者が見られる状態になっており、河村市長や署名集めをした団体が責任を問われるのは必至。一方で、市長を批判するために個人情報を公開したとみられ、その手法も議論を呼びそうだ。ファイル転送サイトは大容量のファイルを一時的に保管し、アドレスを知っていれば誰でも自由にダウンロードできる。毎日新聞が問題のサイトからファイルをダウンロードしたところ、署名用紙1枚ごとにファイル化されたデータが確認された。名古屋市北区で集めた署名とみられ、署名日▽住所▽氏名▽生年月日が記されており、押印もあった。本物の署名簿のコピーである可能性が高い。この問題では、署名簿をスキャナーで取り込んで電子データ化したとみられるものが、3月の出直し市議選候補者の間に出回ったことが分かっている。ファイル転送サイトのアドレスは6日夜、匿名で毎日新聞社に送られてきたファクスに書かれていた。五つのアドレスとともに河村市長を批判する記述があり「署名簿の流出の事実を立証するために、およそ4万人分の名簿を公表する」「該当する市民にはご迷惑な事であろうがご容赦願いたい」と記されていた。リコール署名簿流出問題を巡って河村市長は発覚当初、毎日新聞の取材に経緯などを調べる考えを示した。6月市議会本会議では「流出の事実は確認していない」としたうえで、引き続き調査すると明言した。だが今月5日の定例記者会見で河村市長は「よく分からなかった」と調査結果を説明。調査対象者などの詳細は明らかにせず、結果の公表については「(リコールの)請求代表者に聞いてもらうべきだ」などと述べ、追加調査にも消極的な姿勢を示した。--------河村市長の主張や手法には大いに問題があるにしても、それを批判するために、リコール署名に応じた人の個人情報を流出させるというやり方は卑劣です。しかし、この種の卑劣な人間はどこにでもいるものです。そのような卑劣な人間につけ込まれる原因を作ったのは、そもそも市議会リコール投票のための署名簿をぬけぬけと選挙運動に流用してしまった河村陣営にあります。毎日新聞の別記事によると今年4月、電子データ化された署名簿の一部コピーが、リコール成立に伴う3月の出直し名古屋市議選の候補者らに出回っていたことが発覚。コピーを受け取った落選候補は、河村市長が率いる政党・減税日本の当選候補から入手したと証言していた。のだそうです。こんなのは、個人情報の目的外使用もいいところで、それを問いつめられると「よく分からなかった」「請求代表者に聞いてもらうべきだ」などと開き直った挙げ句、こんな事態を招いているようでは話になりません。しかも、この経緯から考えるに、流出源はリーコル運動に携わった誰か、あるいはそこからデータを受け取った市議選立候補者(もちろん河村支持派にしかそのデータは渡らなかったはず)かその関係者の誰か、ということになります。つまり「卑劣な奴」は河村陣営内のどこかにいる、というわけです。もちろん、今の時点では河村に対して悪感情を持っているから、このような挙に出たのでしょうが。それにしても、バカを見るのは署名に応じた一般市民だけというのが、何とも・・・・。
2011.09.07
コメント(2)
-
尖閣諸島漁船衝突事件から1年
尖閣諸島での漁船衝突事件からちょうど1周年だそうです。この事件については、当時いろいろと書いたし、その見解を特に変える必要もないと思っています。尖閣諸島問題尖閣諸島問題 続報尖閣諸島問題 さらに続報硬直的強硬主義固有の領土なんてものはないごく簡単にまとめると尖閣諸島は疑いなく日本の領土である。(この点に関する限りは、ネット右翼連中とも完全に見解は一致します)しかしバカみたいに、ただ硬直的な強硬主義を振りかざすだけでは、何の解決にもならない民主党政権(当時の前原国交相のち外相)が「軟弱だ」などというのは正反対で、場当たり的で硬直的な強硬論を振りかざして事態を紛糾させてしまっただけ。というのがわたしの考えです。当時、一番正しいことを主張したのは自民党の谷垣総裁だったと私は思っています。すぐに強制送還退去させるべきだったと谷垣は言ったのです。実際、小泉政権の時代に魚釣島に上陸した中国人の活動家は、すぐに強制退去処分となりました。ところが、谷垣はその正しい主張をすぐ撤回してしまった。さらに、1年経ったらすっかりネット右翼脳になってしまったようで、こんなことを言い出しています。自民谷垣氏「政治空白突かれた」 中国の尖閣沖での領海侵犯に自民党の谷垣禎一総裁は25日の記者会見で、沖縄・尖閣諸島沖の領海内に中国の漁業監視船が侵入したことに対し「わが国の領域を犯す許し難い行為で遺憾だ」と述べた。そのうえで「日本の政治空白、民主党政権で脆(ぜい)弱(じゃく)化した外交力の隙を突かれた。政府は外交の再建、強化に全力で取り組む必要がある」と指摘した。----なんというか、漁業監視船を撃沈しろなどと吹き上がっている国士様連中と同じです。国連海洋法条約は、領海における無害通行権というものを認めています。従って、艦船がただ単に領海に侵入したというだけでは「領海侵犯」にはなりません。言うまでもなく、漁船が漁をしたり、軍艦が武力で威嚇したり、潜水艦の場合は潜水したままの状態での航行は「無害通航」とは認められません。あくまでも無害「通行」なので、領海内で停船させる行為はそもそも無害航行ではない。けれども、今回「領海侵犯した」とされる漁業監視船は、領海内で停船したという話は聞いていませんし、武力で威嚇したわけでもない、という以前にそもそも武装はしていなかったようですが。そのような船が単に領海を通過したことを、「わが国の領域を犯す許し難い行為」ということはできません。だいたい、冷戦時代には米ソとも互いの原潜が頻繁に相手国の領海に侵入していたと言われます。前述のとおり、潜水艦が潜水したままの状態は無害通航とは認められません。もちろん相手国に気づかれなかったこともあるでしょうが、ばれちゃったことだって何度もあったはずで、その場合は哨戒機や駆逐艦、潜水艦に追い回され、アクティブソナーでガンガン探信されて、多分百回くらい「演習・撃沈」状態にされて追い払われるわけですが、それでも本当に撃沈しちゃったことなど一度もないし、また公式に相手国に対して領海侵犯を公式に抗議したこともないはずです。抗議なんかしたら「おまえの国も」と言われるのが関の山だし、撃沈なんかしたら撃沈し返される、そんなことをすれば戦争になってしまう、という程度の自制は、当時の米ソにもあったわけです。日本のネット右翼や産経新聞には(多分中国の噴青にも)、そのような自制はないようですが。前述のとおり、私も尖閣諸島は日本の領土だと思っているわけですが、かといってこの無人島のために戦争をすべきだとも思わないし、ただ強硬論を振りかざせばよいとも思いません。
2011.09.06
コメント(7)
-
記録的豪雨
台風12号は、当初の見込みでは静岡付近に上陸するのではないかと見られていたので、かなり警戒していたのですが、結果的に進路が西にずれたために、関東では特に被害はありませんでした。しかし、紀伊半島ではすさまじい被害になってしまいました。台風被害、死者37人不明55人…9千人孤立紀伊半島を中心に大きな被害をもたらした台風12号は5日午後3時頃、日本海上で温帯低気圧に変わった。北海道と青森、岩手付近では、温帯低気圧と太平洋上の台風13号の影響を受け、6日夕にかけて記録的な大雨になる恐れがあり、気象庁では土砂災害や河川の氾濫などへの厳重な警戒を呼び掛けている。同庁によると、6日午後6時までの24時間に予想される雨量は、多い所で北海道400ミリ、青森県150ミリ、岩手県120ミリ。和歌山、奈良、三重などの被災地では5日午後も、取り残された人の救助や行方不明者の捜索が進められた。読売新聞の午後8時現在のまとめでは、新たに9人の死亡が確認され、死者37人、行方不明55人となった。県別では、和歌山で死者25人、行方不明32人、奈良で死者4人、行方不明20人など。奈良、和歌山などでは依然として9000人以上が孤立している。----東日本大震災の被害があまりに巨大すぎるので、感覚がマヒしてしまいそうになりますが、死者行方不明者90人以上というのは、大変な数字です。それにしても、どうしてこう自然災害が集中して起きるんでしょうね。今回の台風で驚くべきは、降水量です。紀伊半島では降り始めからの降水量が軒並み1000mm以上、奈良県上北山村では1800mmにも達しています。ちなみに、東京の年平均降水量は1528mmですから、東京の1年分の降水量を超える雨が、ほんの数日で降ったわけです。※※ただし、紀伊半島の降水量は東京よりずっと多く、上北山村の場合は年平均2713mmなので、その1年分は超えません。1時間あたりの降水量も、新宮市で132mmを記録しています。ほとんどシャワー並の降り方です。1時間降水量と降り方の目安アメダスや降雨レーダーなどで1時間あたりの雨量が表示されることがありますが、あれは「1時間降り続けたとすればこの雨量になる」という意味です。1時間で100mmと表示されても、降雨時間が6分間だったら、実際の雨量は10mmというわけです。しかし、上記の132mmというのは、1時間の連続雨量としての記録ですから、実際に1時間それだけの降り方が続いたわけです。7月下旬にも新潟と福島で集中豪雨で大きな被害が出ているし、これから先もあと1ヶ月くらいは台風シーズンが続くので、いったいどうなることやら。せめて今年くらい、これ以上の自然災害は起こらないで欲しいと願うばかりですが、こればかりは人間の力ではどうこうできないことですからね。
2011.09.05
コメント(0)
-
さようなら原発 5万人集会
9月19日(祝)午後1時~ パレード午後2時15分~会場 明治公園(東京・新宿区)JR中央線千駄ヶ谷駅下車5分、都営大江戸線国立競技場前下車2分http://d.hatena.ne.jp/byebyegenpatsukyoto/20110831/1314774609このブログでは原発についていろいろ書いてはいますけど、私はこれまでこの種の集会に参加したことはありませんでした。今回は、参加しようと思っています。---中間貯蔵、福島第一原発を候補に 細野原発相が示唆細野豪志原発相兼環境相は4日、報道各社のインタビューで、放射能に汚染されたがれきの中間貯蔵施設について「原発内に高い放射線量のがれきが相当あり、簡単に持ち出せない。中での処理をある程度考えなければならない」と述べ、東京電力福島第一原発の敷地内を候補地として検討する考えを示した。ただ「すべてを福島第一原発内で、というのも現実的ではない」とも語った。政権幹部が中間貯蔵施設の候補地に公式に言及したのは初めて。菅前政権は最終処分地を福島県外にする方針を打ち出す一方、菅直人前首相が県内に中間貯蔵施設を造らざるをえないとの見通しを示していた。細野氏はインタビューで「福島を最終処分場にしない」と明言。中間貯蔵施設を福島第一原発内に造ることを検討する考えを示した一方、除染などによって県内で発生した放射性廃棄物を原発内だけで受け入れることは難しいとの認識を示した。「当面は各市町村の仮置き場に置かざるを得ない」と説明し、地元自治体と協議して慎重に場所を検討する考えを示した。 現実問題として、福島の原発事故で発生した放射性物質を他の場所で保管するというのは不可能です。「受け入れてもよい」という自治体があるはずもないし、よしとする住民がいるはずもないですから。福島第一原発から漏れ出した放射性物質は福島第一原発(の位置)に戻すという以外に解決方法があるわけがない。「最終処分地にしない」とも明言したそうですが、それが事実としても、使用済み核燃料の最終処分地だって決まっていないのですから、汚染がれきの最終処分地だって、受け入れる自治体があるとは思えません。結局半永久的に中間貯蔵施設に保管し続けることになるでしょう。私は、除染による放射性物質も、最終的には原発周辺で保管するしかないだろうと思うんですけどね。少なくとも、現在立入り禁止となっている20km圏内の除染による放射性物質は、他のところに持って行くことは不可能でしょう。どんな発電所だって事故が起こることはありますが、これほど広大な面積が深刻な汚染に見舞われたり、これほど広大な面積が数十年にわたって人の住めない土地になるというリスクは、原発にしかありません。
2011.09.04
コメント(0)
-

「さよならの夏」を録音してみました
ギターとフルートで、「さよならの夏」を録音してみました。ギターもフルートも、間違えまくって、何度も録音し直しました。フルートは二重奏にしようと思ったのですが、副旋律がなかなか決まらないうちに時間がなくなってしまったので、フルート1本だけの録音になってしまいました。ギターは何回か練習してみたのですが、フルートはほとんど練習なしでいきなり録音してみたら、指が全然回らずに難渋しました。窓を閉め切って録音したにもかかわらず、蝉の鳴き声が入っていますねえ。もっとも、ずいぶん騒々しく鳴いていたのに、録音してみるとずいぶん小さな音になる、とも言えますが。そういえば、この曲の作曲者は坂田晃一、あの「母を訪ねて三千里」の作曲者ですね。「さよならの夏」も「母を訪ねて三千里」も、どちらも1976年の作品です。しかし、聞いていて思うのですが、この「さよならの夏」、その後の宮崎アニメの音楽によく似た雰囲気があるように感じるのです。ルパン三世カリオストロの城の「炎のたからもの」、天空の城ラピュタの「君をのせて」、魔女の宅急便の「海の見える街(風の丘)」とメロディーラインに相通じるものがあるように思えるのですが、どうでしょう。草原のマルコ(母を訪ねて三千里)炎のたからもの(ルパン三世カリオストロの城)海の見える街~めぐる季節~風の丘(魔女の宅急便)
2011.09.03
コメント(2)
-
右利き、左利き、両手利き
職場のパソコンのマウスが壊れていまいました。新しいマウスを支給してもらえばいいのですが、職場の支給品は、いまどきまだボールマウスなので、自分で買うことにしました。レーザーマウスの方が使いやすいですから。(ボールマウスは時々掃除しないと動きが悪くなるのが面倒)実は、マウスに求める条件がもう一つありまして、それは「左右対称の形であること」なのです。必然的に選ぶのは安物のマウスということになります。(職場で支給されるマウスは、こっちの条件は満たしているんですけどね)何で左右対称が良いかというと、私はマウスを左手に持つ人間だからです。右利き用に左右非対称になっているマウスは、左手では使いにくくて仕方がない。ちなみに、日常生活では私は右利きです。ただ、初めてパソコンを手にしたとき、たまたま左手でマウスを持ってしまったのです。もともと私は、電卓を左手で叩く人間です。右手に鉛筆を持って数字をチェックしながら計算するには、左手で電卓を叩く方がずっと速いからです。だから、もし最初に手にしたパソコンがノートパソコンだったらテンキーを左に置いてマウスを右手に持っただろうと思います。しかし、自宅のパソコンはデスクトップなので、テンキーはキーボードの右側に固定されています。テンキーを左手で打つことは物理的に出来ません。テンキーが右ならマウスは左手に持った方が合理的だな、と思ったのです。ちなみに、マウスは左手で持ちますが、クリックは左右反転させているわけではありません。つまり、普通の人は右手の人差し指でクリック、中指で右クリックしますが、私は左手の中指でクリック、人差し指で右クリックしているわけです。クリックの設定を左右反転させることもできますが、パソコンを持った当初はそんなことは知りませんでしたし、左右反転させてしまうとパソコンを他人と共用しにくくなってしまいます。パソコンを使うようになる前は、左手で字はまったく書けなかった(無理に書こうとすると鏡文字になってしまう)のですが、ずっと左手でマウスを持って線を引いたりしていたら、あら不思議、いつの間にか左手に鉛筆をもっても、鏡文字ではない字が書けるようになっていました。ま、ひどく汚い字ではありますけど。私の子どもは左利きです。箸を持つのも左手、はさみを持つのも左手です。鉛筆も、幼稚園の頃は左手で持っていました。一度だけ、字だけは右で書かせようと練習させたことがあります。だって、文字って右手で書くのに都合がよいように出来ていますからね。しかし、「左手の方が書きやすい」と言うので、すぐに諦めました。ところが、小学校に上がってしばらく経ったら、いつの間にか鉛筆を右手に持つようになっているのです。一時期はどちらの手でも書いていたようですが、今は「右手の方が書きやすい」と言って右手のみになっています。学校の先生に「右手で書きなさい」と指導されたわけでもないようです。何がどうなってそうなったのかはさっぱり分かりません。それにもう一つ、マウスも右手に持っています。私のパソコンは左側にマウスが置いてありますが、相棒のパソコンは普通に右側にマウスが置いてあるので、それを使ううちにマウスは右手になったようです。というわけで、右利きの私は左手にマウスを持ち、左利きの我が子は右手にマウスを持っているのです。何だかとっても変な家族ですね。実際のところ、私は表面的には右利きだけど、潜在的には左利きの要素があるのだろうと思います。うちの子も、左利きだけど両手利き的な要素もあるので、鉛筆を持つ手はころっと変わってしまったのでしょう。ところで、前述のとおり、職場のパソコン用に、一番安いレーザーマウスを買ってきたんですけど、パッケージの上から見たときは左右対称に見えたのに、開けてみたら微妙に左右非対称だったんですよ。ひえええええ、買い間違えた!でも、パッと見て見間違えるくらいの、わずかな左右非対称なので、そのまま左手で使っています。
2011.09.02
コメント(2)
全23件 (23件中 1-23件目)
1
-
-

- 今日のこと★☆
- 今日は、バイラルの日ですよ!(^O^)v
- (2025-11-25 06:30:04)
-
-
-

- 楽天市場
- ♥️ スーパーDEAL 10%ポイントバック …
- (2025-11-25 06:00:06)
-
-
-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…
- 今日11月25日(火)の天気予報 三連休…
- (2025-11-25 06:00:04)
-







