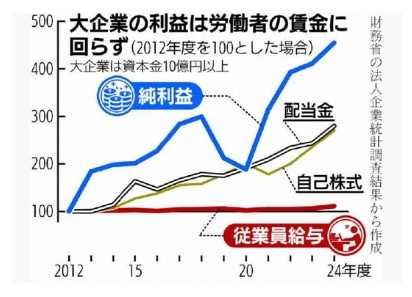2011年04月の記事
全26件 (26件中 1-26件目)
1
-

割り切れないリズム
先日、フォルクローレのギターの弾き方についての話を書きました。このとき、例に挙げたのは、たまたま6/8拍子のリズムばかりでした。フォルクローレは、スペインから来たヨーロッパ系の音楽と、アンデスに元々あった先住民系の音楽が融合して完成された音楽です。リズム的に見ると、6/8拍子というのはスペイン起源のリズムです。一方、先住民系のリズムは、2拍子・4拍子系です。(ただし、スペイン起源の音楽にも2拍子系のリズムが皆無、というわけではありません)どういうわけか、平均的日本人にとっては、3拍子系(6/8拍子・3/4拍子)のリズムは、あまり得意ではないようです。童謡(学校唱歌)には、多少あります。たとえば「ふるさと」「おぼろ月夜」「赤とんぼ」「浜辺の歌」など。しかし、いわゆる民謡の類の中で、3拍子系の曲はおそらく皆無に近いですし、歌謡曲(J-POP)や演歌、ロックなどでも、非常に少ない。昔聞いた説によると、3拍子系(特に6/8拍子)は、馬の走るひずめの音から誕生したリズムなので、農耕民族の日本人にはなじみが薄いのだそうです。なるほど、それが事実だとすれば、南北アメリカ大陸には、スペイン人が持ち込むまで馬がいませんでしたから※、先住民系のリズムに6/8拍子がないことも説明が付きます。※かつてアメリカ大陸にも馬はいましたが、1万年前頃に絶滅しました。ただ、私はいわゆる洋楽についての知識はあまりありませんけれど、スペイン語圏を除く欧米の流行歌は、やはり3拍子系よりも2拍子系の方が遙かに多いように思います。個人的には、ギターを弾く立場なら、6/8拍子の曲の方が格好いい(笑)ま、どちらのリズムの曲も好きですけれどね。地域的に見ると、アルゼンチンは白人国なので、アルゼンチンのフォルクローレは9割方6/8拍子ばかりです。でも、よく考えてみると、タンゴは6/8拍子ではないんですね。だけど何故かフォルクローレは必ず6/8拍子。チリのフォルクローレもやはり6/8拍子が中心です。一方、先住民色の強いボリビアとペルーのフォルクローレは、2拍子系が中心です。ただ、ボリビアの最近の曲は、6/8拍子がかなり多くなっています。さて、単純に2拍子系と書きましたけれど、これが実はなかなか奥が深い。↓これは何拍子の曲でしょうか。一応のお約束ごとで、この手のリズムは、フォルクローレの世界では「2拍子系」ということになっています。フォルクローレで譜面はあまり使いませんが、譜面に起こす場合はたぶん2/4で譜面にする。でも、実際のところは全然2拍子ではありません。むしろ3拍子に近い。これを単純な2拍子にして演奏してしまったら、雰囲気ぶちこわしです。けれど、じゃあ3拍子で演奏すればいいかというと、それともちょっと違う。「2.5拍子」とでも言うのがもっとも正しいかも知れません。フォルクローレの世界で「2拍子系」と言われる曲には、かなりの部分、この手の2.5拍子が多いのです。「カポラル」と呼ばれるリズムですが、これも同様で、「2.5拍子」です。ただ、こういう「譜面どおりではないリズム」というのは、他のジャンルの音楽にもある話かも知れません。ウィンナーワルツは譜面は3拍子だけど、実際は譜面どおりの3拍子ではない、という話を聞いたことがあります。(「譜面どおり」も何も、フォルクローレに譜面はない、という話は措いといて・・・・・・)もう一つ、フォルクローレの2拍子系の特徴は、「字余り」でしょうか。↓これが典型的です。2拍子と思って聞いていくと・・・・・・1970年代にフォルクローレファンの間で人気のあった曲です。この曲は4拍子で取っても2拍子で取ってもいいと思うのですが、どちらで取っても、途中でリズムが1拍余り、そこだけ3拍子になってしまうのです。こういう曲もよくあります。これもそうです。20年以上前に一瞬ヒットして、あっという間に消滅した「ランバダ」(覚えている人、いますか?)の原曲です。この曲は、2/4で取れば字余りになりませんが、メロディーや太鼓のリズムから考えて、4/4で取る方が自然。そうすると字余りになります。同じメロディーを2回繰り返すので、字余りが2回で元に戻るという寸法です。フォルクローレに限った話ではありませんが、リズムというのも突き詰めるとなかなか奥が深いものです。
2011.04.30
コメント(0)
-
1000日目
どうでも良い話で恐縮ですが、2008年8月2日にこのブログを開設して、今日でちょうど1000日になるようです。よく続いたなあ。そして、今この瞬間のアクセス数が182959となっています。つまり、1日平均で183アクセスほど、という計算になります。ま、びっくりするほど多いアクセス数というわけにはいきませんけれど、最近は毎日平均して300アクセスくらいあります。このブログより5ヶ月後の2009年1月に開始したYouTubeの動画は、これまでに累計33万回再生されている(1日平均に割り返すと390回くらい)ので、このブログよりアクセス数は多いです。しかし、不思議なもので、このブログは曜日によってそれほど大きなアクセス数の違いはないのですが、YouTubeは、土日の再生数は平日よりはっきりと多い。最近の傾向だと、だいたい土日は1日800回前後、平日は5~600回というところです。だから、再生数のグラフを見ると、土日ごとに規則正しく再生数が跳ね上がっています。ただし、休日でもその法則が当てはまらない時期が2つあります。一つは年末年始。さすがに、皆さん年末年始は休みでもそんなにYouTubeにかじりつかないのでしょう。そして、もう一つは3月12日と13日の土日。この理由は明白ですね。今後とも、よろしくお付き合いください。
2011.04.29
コメント(3)
-
浜岡原発・・・・・・
中部電が12年3月期業績予想発表、浜岡原発3号機の運転再開織り込み中部電力は28日、2012年3月期の業績予想を発表した。定期検査中の浜岡原子力発電所3号機が7月から稼働することを織り込んでおり、原子力発電所の稼働率を示す原子力利用率は前年の49.7%から84%程度に高まる。同社は「仮に6月末までの停止との前提で、業績予想をした」としている。ただ、東京電力の福島第1原子力発電所の事故を受け、原子力発電に対する国民の不安感が高まっており、浜岡3号機の運転再開には地元住民の反発など曲折があるとみられる。中部電力は、運転再開のスケジュールありきではなく、国や地域の理解を得て立ち上げる段取りだと説明している。原発の安全対策費は300億円以上を予定し、防潮堤などの整備を進める方針だが、完成までには2─3年かかるという。浜岡3号機が運転再開できなかった場合には、原子力利用率は62%程度に低下するという。この場合の代替電源は、液化天然ガス(LNG)による火力発電が有力だとしたが、古い火力発電所の立ち上げなどの準備に3カ月程度かかる。このため、夏の需要ピークに間に合わせるには、遅くとも5月中には代替電源を用いるかどうかを判断するとみられる。 -------福島第一原発の事故はきわめて重大なのものですが、一つだけ幸運な点がありました。それは、原発の東側はすぐに太平洋だということです。放出された放射能は風に乗ります。偏西風があるので、日本上空の大気の流れは西から東に向かっています。つまり、放出された放射能のかなりの部分は無人の太平洋上にばらまかれたわけです。ごく一部がアメリカ大陸まで到達していますけれど。もしも原発より東側にも陸地があったら、被害はとてもこんなものでは済まなかったことは明らかです。さて、原発を巡る問題について、私は脱原発を目指すべきであると思っています。とは言え、今年来年に日本の原発を全部廃止、というわけにいかないこともまた事実です。とりあえずは、危険性の高い原発をまず停止して、それ以外の原発については、段階的に代替発電所(当面はLNG火力、将来的には風力・太陽光など再生可能エネルギー)に置き換えていくべき、というのが私の考えです。「危険性の高い原発をまず廃止」というのは、具体的に言えば、浜岡原発です。日本中に地震の危険のない地域なんてないかも知れませんが、中でも近い将来確実に発生すると見込まれる東海・東南海・南海地震の震源域に近いところにあるのが浜岡原発です。残念ながら、今回の地震の影響で、東海・東南海・南海地震の発生確率はかなり上がっているようです。もしも浜岡原発で事故が発生すると、その東側(東北東)には陸地が続いています。静岡、横浜、そして東京といった巨大都市に放射性物質が大量に降り注ぐことになります。そのような危険地帯に原発が存在すること自体が、そもそも間違いなのです。現在稼働している原発をできるだけ早く停止してほしいくらいなのに、中部電力は何と、停止中の原発を再稼働させるというのです。地震対策を進めるそうですが、完成は3年後。それまでに地震が来たらそれまでです。それに、自然の猛威の前で、事前の「想定」が役に立たなくなる可能性があることは、今回の津波の例からも明らかです。頼むから浜岡原発の運転再開だけは止めてくれ、とそう思っています。
2011.04.28
コメント(4)
-
省エネはそれなりに進んでいる
09年度の国内温室ガス排出、削減目標達成環境省は26日、2009年度の国内の温室効果ガス排出量が12億900万トン(確定値)だったと発表した。1990年度比で4・1%減で、ガスの排出枠を海外から購入した分なども含めると9・5%減となる。日本は、京都議定書で08~12年度の平均排出量を90年度比で6%削減する義務を負っているが、単年度では目標を達成した。今後、東日本大震災の影響による電力不足を、ガス排出量の多い火力発電で補うことが考えられることから、同省では「目標が達成できるかどうか、予断を許さない状況だ」としている。--------2009年度に目標を達成した最大の要因は、おそらく不況で経済活動そのものが不活発になったことではないかと思います。CO2の削減は喜ばしいことですが、不況をよかったとは言えないところがなかなか微妙です。ただ、1990年といえばバブル景気のまっただ中でしたが、その年のGDPは、このサイトによると442兆円(名目)または447兆円(実質)。それに対して、不況のまっただ中の2009年のGDPは470兆円(名目)または519兆円(実質)。つまり、この間に多少は経済成長をしているわけです。GDPは伸びているけれど、CO2の排出は減っている、それはつまり多少は省エネルギーが進んできたということでしょう。このところ、電力不足の問題を度々記事に書いていますけれど、東京電力管内の電力が最大値を記録したのがいつのことか、ご存じでしょうか。去年の酷暑の時、ではないのです。過去最大値は2001年7月24日の6430万Kwという数字です。第2位が2002年8月1日の6320万Kwです。あれだけの猛暑でも、去年夏の最大電力は5999万キロワットでした。つまり、電力消費も、この数年は減少傾向にあるわけです。電化製品だって、20年前のものより現在の方がずっと消費電力は少ないはずですからね。記事によると、「東日本大震災の影響による電力不足を、ガス排出量の多い火力発電で補う」から、今年度の目標達成は苦しそうだ、ということです。これが事実なら、これは仕方がありません。ただ、以前の記事にも書いたように、火力発電でも燃料の種類によってCO2の排出量は異なり、天然ガス(メタンガス)はCO2の排出量はかなり少ない。一方、原発は決してCO2を出さないわけではありません。確かに核反応そのものではCO2を排出しませんが、原発の建設・解体・ウランの採掘・精錬・濃縮・輸送・放射性廃棄物の処理など様々なところでCO2を排出しています。特に、廃炉、更に数千年を要すると言われる高レベル廃棄物の貯蔵に要するコストやCO2排出を先送りしているから、CO2の排出が少ないかのように見えているだけ、とも言えます。私は、火力発電が増えることによるCO2の増加より、全体としての電力消費が減ることによるCO2減少の方が大きいのではないかと予想しています。数値的な明確な根拠があるわけではないですけれど。実際に結果が分かるのはだいぶ先の話になりますけどね。
2011.04.26
コメント(0)
-
節電の道は厳しいのだ・・・・・・・
統一地方選、世田谷区長に保坂展人が当選しましたね。私は、この人を結構応援していて、前回参院選では比例票を投じたのですが、そのときは落選してしまいました。今回は、応援はしていたけれど、まさか当選できるとは思っていなかったので(だって、出馬表明が今月に入ってからだったし)びっくり仰天です。---4月分の電気の検針がありました。今月の使用量は170kwh台(32日間)昨年4月の使用量は270kwh台(30日間)日数の違いを補正すると、去年より39%ほど電気使用量が減った計算になります。徹底的に節電したおかげで、結構減りました。と、思ったのですが、どういうわけか引き出しの奥から去年の検針通知が出てきてしまったんですね。そこには一昨年4月の電気使用量が載っていました。一昨年4月の使用量は、220kwh台(30日間)去年は一昨年より大幅に電気使用量が増えていたんですね。今年の数字は、一昨年と比べると25%しか減っていませんでした(日数補正して)。うーーーん、意外と減っていないなあ。我が家の節電対策1エアコンはコンセントを引き抜いた。(地震以来、暖房はガスしか使っていません)2蛍光灯を全部で3本引っこ抜いた。更に常に半分しか点灯しないようにしている。余計な電気は点灯しない。居間は複数の蛍光灯があるけれど、1つしか点灯しない。3冷蔵庫は節電モードに4たまたま炊飯器が壊れたので、数日土鍋でご飯を炊いて、そのあと一番消費電力の少ない(と、ビックカメラで言われた)炊飯器に買い換えた5使わない電気機器はコンセントを引っこ抜くかタップの電源スイッチを切るしかし、子どもがやりすぎて、ハードディスクレコーダーの電源を切らないままタップのスイッチを切ってしまった。それをやると、ハードディスクレコーダーが壊れるから、やめろ~~~~6パソコンディスプレーの輝度を下げた。相棒のパソコンも同様。(ただし、パソコンやテレビの視聴時間は全然減っていません)と、こう書くといかにも面倒なようですが、実際には、一度設定を変えてしまえば、その後はそれほど面倒でもありません。こまめな消灯だけが、面倒といえば面倒ですが。いずれにしても、生活に影響を及ぼさない範囲ではギリギリまで節電していると思うのですが、それでも一昨年と比べて25%減にしかならないのです。なかなか節電の道は険しいものがあります。特に夏場はね。寒いときにはエアコンの代わりにガス暖房という選択肢がありますが、暑いときにはエアコンの代わりにガス冷房・・・・・・というわけにはいきませんからねえ。(業務用にはガス冷房ってありますけど、一般家庭用はおそらくない)ま、我が家は元々クーラーは極力使わない主義なので、使わない年は一夏に数日(1日に2~3時間)しか運転しません。ただ、去年はさすがに連日稼働しました。設定温度は29度ですけどね。今年は猛暑でないことを祈ります。なお、4月分ガスの使用量(実際はほとんど3月分)は80立米台で、去年と今年でまったく差がありませんでした。ガスで代替できるものは全部ガスにしたので、ガス使用量は増えると思ったのですが、そうはならなかった。(ガスの一昨年の数字は分かりません)で、ふと思ったのは、我が家の消費電力(ガス消費量も)は、3人家族として世の平均的家庭と比べてどうなんでしょう。多いのか少ないのか平均的なのか、よく分かりません。多分、多い方ではないと思うのですが。何にせよ、「節電すればこんなに使用量が減る」と見るか「節電してもこれしか減らない」と見るか、微妙なところではありますが、政府が一般家庭に求めるという15%減という数字をクリアするのは、今の時期はそんなに難しいことではないなと思いました。問題は夏場ですね。
2011.04.25
コメント(4)
-

フォルクローレの要はギターにあり
フォルクローレと一口に言っても、実は様々な音楽があるので、一口にはくくれないのですが、世界的に見て(日本でも)もっとも知名度の高いボリビア系のアンデス・フォルクローレの場合、使われる楽器は管楽器のケーナ・サンポーニャ、弦楽器のギター(クラシックギター)・チャランゴ、打楽器のボンボ(太鼓)、だいたいこの5種類が中心です。その中でどの楽器が一番人気かというと、まず間違いなくケーナなのです。やはり、「コンドルは飛んでいく」で知名度がありますから。それに次いでサンポーニャとチャランゴでしょうか。もっとも、ケーナとサンポーニャは1人の奏者が掛け持ちで演奏するのが一般的ですが。で、最後に残るのはボンボとギターということになるわけです。特にギターは、なかなか人がいません。何故って、「ケーナの音色が好きだからフォルクローレを始めました」という人はいても、「ギターがかっこいいからフォルクローレを始めました」という人はあまりいないじゃないですか。正直言って、私もそうなのです。ところが、では実際にフォルクローレの演奏で何が一番重要かというと、実はボンボ(太鼓)とギターなのです。どちらもリズムの要だからです。特に重要なのはギターです。他の楽器がなくてもギターさえあればフォルクローレは成り立ちますが、ギターがなかったら音楽として成り立ちません。※※あくまでも、現代的なスタイルのフォルクローレの場合です。古いスタイルでは、ギターのない音楽も存在します。というわけで、日本のアマチュア・フォルクローレ界では恒常的にギターの人材が足りない。私がキラ・ウィルカというグループに参加した一番最初の担当はボンボと笛だったのですが、途中からギターのおおさかさんが休業→復帰→休業→復帰→休業と繰り返したため、私の担当楽器も笛→ギター→笛→ギター→笛→ギターと、行ったり来たりしています。この間、他にギター奏者はいないかと思ったのですが、前述のような事情で、なかなか見つからないのです。上手いギター奏者は、すでにグループをいくつも掛け持ちしていたり、仕事が忙しかったり。一時期、関西在住の助っ人(ギターも弾ける)に参加してもらったことがあるのですが、長続きはしませんでした。関西からずっと東京に通い続けてもらうわけにはいきませんからねえ。もっとも、そのおかげで私も随分ギターの練習をしたから、腕前が多少回復しましたが。(ギターをまったく弾かない時期が数年続いたので、一時はかなり下手になっていました)まあ、「腕前が回復した」と言っても、ストロークとアルペジオ、簡単なベースラインしか弾けない「なんちゃってギタリスト」なんですけれどね。ただし、フォルクローレの伴奏ギターにとって、絶対必要なのはストローク。それさえできれば、最低限伴奏者としての役割は果たせます。難しいフレーズはチャランゴに弾いてもらえば何とかなる。(いしのさんのチャランゴはメチャクチャ上手いし)ちょうど1年ほど前に、やっと新しいギター奏者を発掘して、1年練習に参加してもらって、先日のライブでデビューしていただきました。おかげで、私も半分だけ笛担当に戻ったわけです。彼女のギターの腕前は、明らかに私より上手い。私には弾けない難しいフレーズがちゃんと弾ける。ただ、練習に参加した当初は、音量が圧倒的に少なかった。私は、ギターの腕前はないけれど、音量だけは自信ありなのです。フォルクローレの楽器の中で、ギターはもっとも音量の小さい楽器です。ケーナの3オクターブの爆音に負けないためには、とにかく強く弾くしかない。私は、長年フォルクローレの伴奏ばかりやってきたおかげで、音だけはでかい。おかげで左手人差し指は時々爪が剥がれるんですけどね。実は、私のギターそのものも、彼女のギターと比べると弦長が長くて音量が出ます。しかし、1年一緒に練習したら、彼女のギターも見違えるほど音量を増しました。先日のライブの時は、充分な音量が出ていたと思います。---ところで、フォルクローレのギター・ストロークというのはギターの弾き方としてかなり特殊な部類に入るかもしれません。何が特殊かというと、カッティングを多用するところです。カッティングができないとフォルクローレのギターは弾けません。具体的にどういう音かというと、ま、まずは実例から。手前みそで恐縮ですが、私が弾いているギターの例から。ギターは冒頭部分と間奏から後半途中までにしか映っていませんが、ギターの音はずっと入っているので、どんな音かは分かると思います。このリズム(クエッカといいます)を譜面にすると↓のようになります。下段のチャランゴのリズムはとりあえず無視して、上段のギターのリズムの×のついている部分に使われている音、カットコトンカットントンという「カッ」の部分の音がそれです。私は、ギターを弾き始めた頃(20台前半)、周囲にフォルクローレを演奏する知り合いが1人もいなかったので、カッティングの音が、どうやって出しているのか、どうしても分からなかったのです。ああでもない、こうでもないと試行錯誤したのですが、さっぱり分からない。それがカッティングという奏法であること自体に気がついていませんでした。というのは、一般的なギターの教則本には、カッティングとは弦の振動をとめて音を消すことだと書いてあるのですが(当時私が持っていた教則本にもそう書いてあった)、フォルクローレのカッティングはそれとはかなり違うのです。実際のところ「カッティング」という言葉であの奏法を表現するのが正しいのかどうかは私には分かりません。ただ、より正しい他の表現も存在しないと思うので。だから、私がフォルクローレの仲間と知り合ったとき、真っ先に聞いたのは、「ギターのあの音はどうやって出しているんでしょうか」ということでした。知ってみれば、ある意味簡単なことだったのですが。教則本に載っているカッティングは「音を消す(止める)」ことですが、フォルクローレのカッティングは「音を止めながら弾く」ものです。難しい言葉で言えば、ハーモニクス音を出すということです。具体的には、親指の付け根付近を弦に軽く当てる(ほんの瞬間的です)、それと同時に人差し指以下では弦をはじいている。弦に親指の付け根を当てている時間が長ければ、教則本どおりの「音の消えるカッティング」に近くなりますが、そのあたりは微妙なタイミングです。私の演奏は真正面から撮影しているので、指の動きが分かりにくいので、他の動画で指の動きが分かりやすいものを探してみました。カッティングが分かりやすいのは、前奏と間奏の、それぞれ最後の方だけですけれど。このリズムはアルゼンチンサンバといって、リズムを譜面にすると下記のようになります。やはり、×のところにカッティングが入っています。1小節に1回だけです。次はもっと分かりやすい映像。アルゼンチンのチャカレーラというリズムですが、教則用ビデオとして撮影したもののようです。このリズムは、私は全部の音をダウンストロークで弾くのですが、この人はダウン→アップ→ダウン→ダウンと弾いていますね。指の動きに決まりがあるわけではないので、どちらでも間違いではないと思います。このリズムを譜面にすると、以下のようになります。(先と同様、×のところがカッティング)(弾き方のバリエーションが幅広いので、これは一例です)このカッティングができれば、フォルクローレのギターは弾けたも同然(えっっっっ)さあ、あなたも是非フォルクローレのギターを弾いてみませんか・・・・・・参考までに、フォルクローレで使われギターはクラシックギターです。「フォルクローレ」という名前から、まれにフォークギターを使うと思う人もいるようですので念のため。クラシックギターは、更にフラメンコ用と(狭義の)クラシック用に分かれますが、一般的にフラメンコギターはフォルクローレには合いません。フラメンコギターは高音が重視されますが、フォルクローレのギターは低音の響きが求められるからです。
2011.04.24
コメント(4)
-
10年前の演奏
先日、ライブを行った「キラ・ウィルカ」の、昔の映像が出てきましたので、ニコニコ動画にアップしました。ユリ先日のライブでも演奏した曲です。(ただし、先日のライブではこの曲より手前で録画が止まってしまい、録音しかありません)マイクを使っているのに反響板の中で演奏しているのは何故かというと、合唱の発表会のゲストとして演奏したからです。私がキラ・ウィルカに参加したばかりのときの演奏です。確か、このときが2度目のステージだったと思います。10年前なので、みんなそれなりに若い。このころは、既婚者はケーナのいとうさんだけで、子どもはまだいなかった頃でした。練習よりその後の飲み会の方が長い、という時代。いまは、いとうさんは子ども2人、私は1人、ギターのおおさかさん(演奏は長期休業中)は3人子どもがいる。10年一昔といいますが・・・・・・。そしてもう1曲ハチャ・マリュク(偉大なるコンドル)これは、2004年、兵庫県三木市の「三木山フォルクローレフェスティバル」での演奏です。キラ・ウィルカがこのイベントに参加したのは、このときの1回だけ(何しろ東京から遠いですから)です。私といとうさんの2人は、別のグループで何回かこのイベントに行っているんですけどね。ところで、1曲目に紹介した「ユリ」という曲ですが、JASRACのサイトで検索したところ、この曲に日本語の歌詞を付けて歌っている人がいることに気がつきました。「雨霽る」というタイトルで、万里知子さんという方が歌ってらっしゃるようですが、聞いたことのない名前です。検索したところ、ホームページに行き当たりました。演歌歌手のようですね。確かに、この曲は日本人好みのメロディーとは思います。でも、聞いてみたいような、聞かない方がいいような・・・・・・・・。
2011.04.23
コメント(0)
-
風力発電
風力発電で原発40基分の発電可能 環境省試算環境省は21日、国内で自然エネルギーを導入した場合にどの程度の発電量が見込めるか、試算した結果を発表した。風力発電を普及できる余地が最も大きく、低い稼働率を考慮しても、最大で原発40基分の発電量が見込める結果となった。風の強い東北地方では、原発3~11基分が風力でまかなえる計算だ。同省は震災復興にあたり、風力発電を含めた自然エネルギーの導入を提案していく方針だ。今回の試算は、理論上可能な最大導入量から、土地利用や技術上の制約を差し引き、さらに事業として採算性を確保できることを条件に加えた。試算によると、固定価格買い取り制度など震災前に政府が決めていた普及策だけでも、風力なら日本全体で約2400万~1億4千万キロワット分を導入できる。風が吹いているときだけ発電するため、稼働率を24%と仮定。それでも出力100万キロワットで稼働率85%と仮定した場合の原発約7~40基分に相当する。ただし東北など電力需要を上回る発電量が期待できる地域がある一方で、電力会社間の送電能力には現状では限界がある。試算どおりに導入するのは短期的には難しいとみられている。家庭以外の公共施設や耕作放棄地などを利用する太陽光発電や、用水路などを活用する小規模の水力発電についても検討したが、多くの導入量は見込めなかった。これらを普及させるには、さらに技術開発を促すなど追加的な政策が必要だという。----------是非導入して欲しいと思います。約2400万~1億4千万キロワット分を稼働率24%で計算すると、年間発電量は約500億~3000億になります。全国の総発電量はざっと1兆キロワットに少し欠ける程度ですから、風力発電のシェアは5~30%まで伸ばせる、ということです。記事では原発の稼働率を85%と仮定していますが、現実にはそんなに高くありませんので、近年の原発による年間総発電量は2500~3000億キロワット程度、つまりこの試算値によれば、風力発電の発電量は原発と肩を並べる可能性がある、ということです。このほか、水力発電も、現状の稼働率は45%程度と低いので、これを70%程度まで上げるだけでも、発電所を新設しなくても発電量を5割増にすることができます。それがもし可能になれば、再生可能エネルギーによる発電シェアを45%くらいにまで引き上げることが可能です。完全に原発を代替できます。もちろん、そのためには莫大な投資が必要でしょう。しかし、ひとたび原発事故が起こった場合の補償金(10兆円と言われている)ほどの値段ではないでしょう。次の原発事故が起こる前に、是非進めていって欲しいと思います。太陽光発電は、現状では変換効率が低いので、大幅な拡大はちょっと厳しいようですね。ただし、家庭用の場合、発電単独ではなく、給湯も組み込むことでガスの大幅節約も可能になるようです。ただし、費用もかなり高価ですが。
2011.04.22
コメント(0)
-
こんなときにこんなことをやっていて・・・・・・・・
「小沢系」議員、衆院委辞任へ ガソリン減税停止に反対民主党で小沢一郎元代表を支持する複数の衆院議員が21日、税制改正法案に反対する意向を固め、衆院総務委員会の委員を辞任する考えを党に伝えた。内閣不信任案への賛成も視野に対決姿勢を強める狙いがある。法案は、ガソリン価格が一定価格を超えた場合、ガソリン税率を引き下げて価格を安定させる措置を停止するための特例法案。22日の衆院総務委、衆院本会議で可決の見通しだ。民主党内では「ガソリンの値上がりで東日本大震災の被災者の負担が増す」として小沢氏系議員から不満が噴出したが、菅内閣は法案提出に踏み切った。総務委に約10人いる小沢氏系議員のうち皆吉稲生氏は委員辞任を党国会対策委員会に申し出た。大谷啓氏も「賛成できない」と伝え、辞任の方向だ。野党も賛成の法案だけに、委員を辞めて採決に加わらない道を選んだ模様だ。小沢氏系議員は「法案は通過するが政局の火種は残る。いい落としどころだ」と話す。 --------色々なことが震災の前とはまったく変わってしまったのが現状です。とにかく大きな被害であり、復興のためには莫大なお金がかかる。そのお金をどこからか捻出しなければならないわけです。それを考えれば、ガソリン減税の停止はやむを得ないと私は思います。ところが、それはまかり成らぬと小沢支持派は主張しているようです。うーーーん、じゃあ、復興費用はどこから捻出するんでしょうか。赤字国債でしょうか。でも、それって原発の高レベル廃棄物と同じで、負担を後の世代に押しつけているだけなのではないかと思います。それにしても、「法案は通過するが政局の火種は残る。いい落としどころだ」というのは、すごい発言だなあと思います。よりによって、未曾有の大災害というときに、権力闘争の方が大事なんでしょうか。それも、野党の自民党からそういう声が上がるならともかく、与党内でそんな声が出ている、つまり与党内がまったく一致団結していないわけです。与党でありながら、「政権を守る」ということに一致できないなら、「民主党」という一つの党にとどまっている意味があるのかなと思います。菅直人は散々叩かれていますし、私も大いに不満があります。ただし、じゃあ小沢が首相になれば問題が起こらなかったのか、自民党政権だったらよかったのか、というと、私には全然そうは思えないのです。誰が首相だろうと、ほとんど変わらない結果だったはずです。福島第一原発の存在、津波に対する無策、東京電力の体質や原発のトラブルに対する無策は、今現在の首相が誰であるかとは無関係だからです。首相のクビを今すげ替えて何かが変わるとは、まったく思えません。・・・・・・しかし、またでかい地震ですね。携帯をマナーモードにしていたから、緊急地震速報に気がつきませんでした。あー、もうやだやだ。
2011.04.21
コメント(4)
-
再生可能エネルギーを考える
15日の記事で書いたように、東京電力は、火力発電所の復旧と自家発電などの買電によって電力供給力の復旧を進めており、夏場の計画停電も回避されそうな様子であることを書きました。その時点での報道では、7月までに東京電力の電力供給力は5200万キロワットと見込まれていたようですが、その後は5500万キロワットまで回復を目指していると報じられています。このときの記事でも指摘しましたが、2003年には、夏場に東電の原発すべてが停止したことがありますが、それでも電力不足にはなりませんでした。もちろん、火力発電所でも損傷により稼働できないところがあるし、東北電力や東海第二原発(日本原子力発電)から融電を受けられないので、2003年当時と条件が違います。だから、今すぐ原発を全廃する、というのは無理なのですが、しかし原発への依存度を下げる程度のことであれば、電力供給はどうとでもなるわけです。とはいえ、目下のところ、原発の代替は火力発電で、ということになります。当ブログでは、地球温暖化問題について過去に繰り返し記事を書いてきましたけれど、100万KWの火力発電所1基がはき出すCO2と、100万KWの原発1基がレベル7規模の事故ではき出す放射能と、どちらの方が地球環境にとって危険かといったら、それは放射能の方がより危険と言わざるを得ません。だから、当面のところは原発を火力発電で置き換えるのは仕方がない。しかし、長期的に考えると、いくらでも火力発電に代替させておけばよい、とも言えません。火力発電のCO2発生量は燃料の種類によって違います。化石燃料はいずれも、単純化して言えば成分は炭化水素です。炭化水素のうち、炭素の成分が高いものは燃焼時にCO2の発生が多く、水素の多いものはCO2の発生が少ない。石炭は炭素が主成分なので、CO2の発生は非常に多い。石油はそれより少なく(ただし、重油はCO2の発生が多く、軽質油になるほど少なくなる)、天然ガス(特にメタンガス)はCO2の発生がかなり少ない。つまり、CO2の発生を考えると、同じ火力でも、石炭や石油(重油)は減らし、天然ガスを増やす方がCO2は少なくなるわけです。ちなみに、以前の記事で書いたことがありますが、原発はCO2を出さない、というのはウソです。それに、ウランだって限りある資源であることは化石燃料と変わりません。今の勢いで原子力発電を続けていけば、実は埋蔵量は石油とあまり変わりません。とはいえ、天然ガスだって資源には限りがあるわけで、長期的に持続可能な社会ということを考えると、再生可能エネルギーによる発電に移行して行かざるを得ないでしょう。一口に再生可能エネルギーと言っても色々なものがあります。まず、もっとも大規模に行われいて、歴史も古いのは水力発電です。日本の発電量のうち、約10%は水力発電によって賄われています。ただし、これから新たに水力発電所(必然的にダム建設を要する)を大量に建設する余地は、もう日本にはほとんどないでしょう。自然保護上も問題がある。ただし、設備は今のままでも、稼働率を上げることによって水力発電による発電量を増やすことは可能だと思われます。その他の再生可能エネルギーには地熱発電・風力発電・太陽光発電などがあります。地熱発電は、日本ではすでに全国で50万KW以上の発電量があるそうです。これは福島第一原発の1号機より大きな発電量です。ただし、これも地熱発電が可能なところ=火山地帯=国立公園・国定公園または温泉地や風光明媚な場所であり、自然破壊の問題を伴うため、新たな発電所を大量に設置することは難しいと思われます。風力発電は、現在日本での発電容量が200万キロワット以上、つまり100万キロワット原発2基分もあります。コストもかなり安い。ただし、文字どおり風まかせなので、稼働率は低く、実際の発電量はそれよりずっと少ないようですが。また、風力発電には低周波騒音の問題、バードストライクの問題があります。これらについては、技術開発によってある程度解決が可能だと思われます。そしてもう一つは太陽光発電です。太陽光発電は一般家屋でも設置可能なので、現在かなり注目されています。ただ、日中しか発電できないこと、コストがまだ高いこと、発電効率が低い(20%程度)ことが欠点です。つまり、再生可能エネルギーは現在いずれも欠点があって、ただちに原子力や火力をすべて置き換えられるだけの力がありません。ただし、これはあくまでも「現在は」ということです。風力発電の低周波騒音、太陽光発電の効率やコストは、今後の技術開発や量産効果によって解決可能であろうと思われます。これまで原子力に投入されていた公費を、再生可能エネルギーの技術発展に注ぎ込んで欲しいと思います。それによって、近い将来、原発すべてと火力発電所の何割かを再生可能エネルギーによる発電に置き換えることはできないだろうかと思うのですが、どうでしょうか。
2011.04.20
コメント(2)
-
やはり、被害者は高齢者が中心
東日本大震災:死者9割超が水死 60歳以上6割警察庁は19日、東日本大震災で被災した岩手、宮城、福島県の死亡者の死因と年代別の状況をまとめた。死因別では水死が約9割を占め、年齢が判明している死亡者では60歳以上が6割を超えた。警察庁によると、地震が起きた3月11日から4月11日までに収容した遺体は1万3154人で、このうち1万1026人の身元が確認されている。検視が終わった1万3135人について分析したところ、死因別では水死が1万2143人(92.5%)で大半を占めた。岩手県は87.3%、宮城県は95.7%、福島県は87.0%で、なかでも宮城県の津波による被害の甚大さを示している。その他は、焼死148人(1.1%)▽圧死・損傷死・その他578人(4.4%)。不詳は266体(2.0%)だった。焼死は岩手県(1.6%)、圧死・損傷死・その他は福島県(12.6%)の割合が高かった。年齢や性別が判明した遺体は1万1108人で、最も多い年代は70~79歳の2663人(24.0%)。80歳以上が2454人(22.1%)、60~69歳が2124人(19.1%)で、60歳以上は計7241人で65.2%に達した。身元の確認ができないなどの理由で年齢や性別が判明しない遺体は2027人(15.4%)だった。--------検視が終わった1万3135人のうち水死が1万2143人ということは、それ以外の死因は1000人ほど、ということです。つまり、今回の地震で、もしも津波がなかったとすると、おそらく1000人単位の犠牲者で済んだであろう、ということになります(※)。それだって大災害ですが、規模がまるで違う。津波の恐ろしさが改めて実感されます。※行方不明者がまだ多数いますが、今の時点で行方不明の人は、ほとんど津波にさらわれた人でしょうから、ほとんどが水死でしょう。ところで、警察庁が公表している、身元が確認された死亡者のリストを見たときから、「ああ、やっぱり高齢者が多いな」と感じていましたが、やはり60歳以上が6割ですか。寸刻を争うときは、どうしても高齢者は動きが遅くなるので逃げ遅れる可能性が高くなってしまうのでしょう。残念なことです。ただ、若い人、子どもが亡くなる方が、もっともっと残念なことと感じてしまう自分もいるのです。たとえば、80歳の老人が亡くなったという記事と、10歳の子どもが亡くなったという記事を読んだとき、自分が感じる悲しみは、どうしても同等にはならないのです。そういう感じ方は、「人の命は平等である」という理念には反するのかも知れないけれど。私も、子どもの親だから、子どもに死なれてしまった親の気持ちというのは、察するに余りあると思います。自分がその立場だったらと思うと、心底ぞっとする。
2011.04.19
コメント(0)
-

昨日の演奏
昨日のライブ、無事終了しました。事前予想では、お客さんは10人くらいかなと思っていたのですが、ふたを開けたら約30人。店内はぎゅうぎゅう詰めになってしまいました。早速、YouTubeに昨日の演奏をアップしました。画像は、安物のデジカメで録画したものなので、画質は悪いです。ただし、音はレコーダーで別録りしたものなので、音は悪くなありません。(もっとも、YouTubeにアップロードすると音質も落ちますけど)カメラの設置場所の関係で、ディスプレイをはっきり確認できないまま、およその見当で撮影したら、メインの管楽器奏者(いとうさん)が右端にいたため、ほとんど画面からはみ出してしまいました。それに、録画モードにすると、デジカメのバッテリーが70分程度しか保たないのです。そのため、2部の4曲目の冒頭で録画は止まってしまいました。別録りの音源は、最後までちゃんと録音されていますけれど。Desde Trinidad(トリニダーより)Cancion de espejismo 蜃気楼の歌Pollerita ポジェリータ---ところで、3曲目のポジェリータは、前にも別の2つのグループで演奏したことがあります。せっかくなので、比較してみることにします。ポジェリータ(ティエラ・クリオージャ版)ポジェリータ(グルーポ・インカコーラ版)ティエラ・クリオージャ版は、屋外での生音演奏なのですが、ビルの壁を背にして演奏しているで、案外音はよく響いています。昨日演奏したキラ・ウィルカ版はキーがF/Dmですが、こちらは1音高いG/Emで演奏しています。サンポーニャにとっては、こちらの調の方が標準的です。ただ、男声には声が高すぎるので、キラ・ウイルカでは、いとうさん特製のF/Dm調サンポーニャを使って1音下げています。それでもちょっと苦しいけど。しかし、「ティエラ・クリオージャ」は女性2人がメインボーカルだったので(女声には、G/Emの調は苦しくない)、標準サンポーニャの本来の調で演奏しているわけです。一方、グルーポ・インカコーラ版(YouTubeではなく私のホームページのMP3音源)は屋内PA付の演奏です。調は、「ティエラ・クリオージャ」と同じG/Emです。聞き比べれば分かると思いますが、リードボーカルは「ティエラ・クリオージャ」のリードボーカルと同一人物です。ただ、「ティエラ・クリオージャ」は3年前の演奏、「グルーポ・インカコーラ」は11年前の演奏ですが。サンポーニャは、上2つの音源では二人一組の奏法で吹いていますが、この演奏では私が一人で吹いています。この曲は、一人で吹くのはかなりキツイです。
2011.04.17
コメント(6)
-
本日はキラウィルカ・ライブ
予定どおり演奏します。午前中に地震があったときは、ヒヤッとしましたが、鉄道もすべて動いているようです。気がつけば、私の携帯電話の受信メール履歴が緊急地震速報のエリアメールで埋め尽くされています。普段いかに携帯のメールを使っていないかってことですね。キラ・ウイルカ フォルクローレ・ライブ本日 4月16日(土)午後6時より(2部構成予定)場所 ペルー料理店・スポーツカフェ「ティア・スサーナ」総武線・信濃町駅より徒歩約5分料金 チャージなし(レストランですから、食事はしてください)曲目 コンドルは飛んでいく、トリニダーより、蜃気楼の歌、出会い、など(16曲くらい演奏します)
2011.04.16
コメント(2)
-
原発推進は決して間違いではない、のだそうです
「原発推進は決して間違いではない」 与謝野経財相与謝野馨経済財政相は15日の閣議後の記者会見で、「今後も日本経済にとって、電力供給にとって、原子力発電は大事だ。(原発を)推進してきたことは、決して間違いではない」と述べ、東京電力福島第一原発事故を受けても「原子力は必要なエネルギー源」との認識を示した。与謝野氏は日本原子力発電出身で、通産相などとして原発を推進してきた。原発の安全性について「言い訳がましいことは言いたくないが、最良の知見、最善の知識、最良の技術でベストなものをその当時は作ったと確信をしていた」と説明。「原発を推進してきた立場として今回の事故に謝罪をするつもりはないか」という記者の質問に対し、「ないです」と述べた。--------「最良の知見、最善の知識、最良の技術でベストなものをその当時は作ったと確信をしていた」という言葉にウソはないとは思いますが、しょせん人間の知見、知識、技術は限られたものであり、大自然の猛威に対抗できるようなものではありません。何度も書いていますが、人間のつくるものに「絶対壊れないもの」なんてありません。そうである以上、「絶対に壊れてはならないもの」など作ってはいけないと私は思うのです。こう書くと、必ずこのような反論をする者がいます。「飛行機だって墜落すれば死ぬ、車だって事故で死ぬ、では飛行機や車は追放すべきなのか」と。このような主張は、いくつかの意味で詭弁があります。一番大きな違いは、事故が起きた場合の被害規模が桁違いである、という点です。昨日の記事に書いたように、今回の事故による東電の賠償額は、10兆円とも言われています。これまで最悪の飛行機事故(テネリフェ空港ジャンボ衝突事故、単機では日航機御巣鷹山墜落事故)でも、賠償額がそんなその1/100の規模にすらなったことはないでしょう。また、事故によって原発周辺の地域が数十年にわたり人の住めない地域になる、そまり故郷を追われる人が相当数出てくるという点も飛行機や車の事故とは違います。一つの地域の人間の営みが、丸ごと消去されてしまうというのは、ある意味では死ぬこと以上の恐怖かも知れません。更に言えば、飛行機や自動車は、それらとまったく同じ利便性の別の手段が存在しないのに対して、原発は、代替策がいくらでもある。少なくとも電力の消費者から見れば、原発だろうが火力だろうが水力だろうが、電気が供給されてさえいれば、利便性は変わりません。「日本経済にとって、電力供給にとって、原子力発電は大事だ」なのだそうですが、折も折、今日は以下のような記事も出ています。東電、7月までに5200万kw確保へ 節電目標縮小も東京電力は15日、東日本大震災で落ち込んだ電力供給力を7月末までに最大5200万キロワットまで増やせるとの見通しを発表した。これで東電が見込む夏場の電力不足は、従来の850万キロワットから300万キロワットに減り、海江田万里経済産業相は同日、今夏に企業や家庭に求める節電目標幅の縮小を検討することを明らかにした。(中略)これを受け、海江田氏は「来週末に東電が供給力のさらなる積み増しの精査をする。出てきた数字を見て、抑制幅の見直しを考えたい」と表明。政府は最大消費電力の削減目標を大口需要家は前年比25%減、小口需要家が20%減などとする方針を示してきたが、4月末にまとめる総合的な電力需給策では、より少ない削減目標を盛り込む可能性を示したものだ。--------今の段階で節電目標幅を縮小するのはどうかと思います。計画停電は不便です。停電回避のために最大限の努力をするのは当然のことですが、節電はそれほど不便とは思いません。地下鉄駅の構内が暗かったりスーパーの店内や陳列ケースが暗いと、具体的に実害が何かあるかというと、特にないですから。我が家も相当に節電しています。今後の供給力がどうあれ、この節電は続けていこうと思っています。(電気代が安くなるという恩恵もありますからね)それはともかく、地震で、あるいはそれ以前から停止している原発で、震災後に運転を再開したものは一つもありません。しかし東電の電気の供給力はどんどん回復しており、必至と見られていた夏場の計画停電も、原則的に実施しないことを目指すという方針が東電から発表されています。つまり、現在稼働中の柏崎原発の4基を除き、原発なしでも何とか電力供給が出来そうだ、ということです。実のところ、東京電力の管内で夏場にすべての原発が止まったことだってあったのです。2003年のことです。そのときは、計画停電は行われていません。もちろん、その当時は地震の被害があったわけではないので、火力発電所はすべて動いていた点が現在とは違いますけれど、逆に言えば火力発電所を復旧させれば、電気の供給は何とかなるということです。
2011.04.15
コメント(2)
-
もう、やめてくれ・・・・・・
津波伴うM8級、1か月内にも再来…専門家東日本大震災の震源域の東側で、マグニチュード(M)8級の巨大地震が発生する可能性が高いとして、複数の研究機関が分析を進めている。日本海溝の東側で海のプレート(岩板)が引っ張られる力が強くなっているためで、早ければ1か月以内に津波を伴う地震が再来する危険がある。M9・0の東日本大震災は、押し合っていた海のプレートと陸のプレートの境界面が破壊されて起きた。そのため周辺の地殻にかかる力が変化し、東日本全体で地震が誘発されている。京都大防災研究所の遠田晋次准教授(地震地質学)は全地球測位システム(GPS)の測定データから、海のプレート内部で引っ張られる力が強くなっていることを突き止めた。明治三陸地震(1896年)の37年後、昭和三陸地震を起こしたメカニズムと共通しているという。「今、昭和三陸規模の地震が起きると、仙台市で10メートルの津波が押し寄せる計算になる」と言う。--------確かに、マグニチュード8クラスの余震(連動して起こる別の地震と言った方が正確かも)が起こる可能性はあるでしょうが、「1ヶ月以内に」なんて書いてしまって大丈夫なのでしょうか。現状で、そこまで正確な予測が可能とは思えないのですが。とりあえず他の新聞テレビは同じ情報は報道していないようです。もう地震は勘弁してくれと思う反面、ある程度復興が進んでからまたやられるくらいなら、今なら地震が来てもみんな身構えている状態だから、被害も少なくて済むかもしれないな、とも思います。また、好むと好まざるとに関わらず、巨大地震が起こるとそれに連動して大きな地震が頻発する傾向があります。今回の地震でも、すでにその傾向は顕著になっています。だから、1ヶ月以内にM8級という断定はともかく、再び大きな地震が来る可能性はある、ということは覚悟しておいた方がよいのだと思います。ただ、そうではあるのですが、気分的にはさすがにめげますよ。こんなに読後感が陰鬱になる記事もない。もう地震は勘弁してよ、と本当に思います。被災地ではない私だってそう思うくらいだから、まして被災地の人はねえ。それにしても、今この状態で仙台に10メートルの津波とか、ということは、福島第一原発にもまた津波???今の原発の状況で、それが来たら、いったいどういうことになるんだろうか。想像も付きません。
2011.04.14
コメント(0)
-
「原発のコストは安い」神話も崩壊した
福島原発事故、最悪の「レベル7」に引き上げ経済産業省原子力安全・保安院は12日、東京電力福島第一原子力発電所の事故について、原発事故の深刻度を示す「国際原子力事象評価尺度(INES)」の暫定評価を、「レベル5」から最悪の「7」に引き上げると発表した。これまでに放出された放射性物質の量を、推定される原子炉の状態から計算した結果、「7」の基準である「数万テラ・ベクレル以上(テラは1兆倍)」に達した。「7」は0~7の8段階で上限の「深刻な事故」で、過去では1986年に旧ソ連で起きたチェルノブイリ原発事故が唯一の例だ。保安院の発表によると、3月11日から4月12日午前11時までに大気中に放出された放射性のヨウ素131とセシウム137の総量を、原子炉の状態から推計したところ、ヨウ素の量に換算して37万テラ・ベクレルに達した。内閣府原子力安全委員会も12日、周辺で測定された放射線量をもとに推計したヨウ素とセシウムの大気への放出総量は、3月11日から4月5日までで63万テラ・ベクレル(ヨウ素換算)になると発表した。保安院の西山英彦審議官は「現時点までの放射性物質の放出量は、チェルノブイリ事故に比べて1割前後で、被曝(ひばく)量も少ない」と違いを強調した。安全委員会によると、現在の放出量は、ピーク時の約1万分の1に落ちている。--------何を今更というか、福島第一原発からの放射性物質放出量が数万テラベクレル以上になることは3月26日の段階で報道されており、国際原子力事象評価尺度が最低でもレベル6、おそらくはレベル7になることは、尺度の定義を読めば一目瞭然なのです。このブログでも、先月19日に、保安院の主張する「レベル5」という評価に疑問を呈する記事を書き、26日の時点で、「少なくともレベル6、おそらくレベル7」という記事を書いています。それにもう一つ、気になる記事。原発周辺「20年住めない」=菅首相が発言、その後否定菅直人首相は13日、松本健一内閣官房参与と首相官邸で会い、福島第1原発から半径30キロ圏内などの地域について「そこには当面住めないだろう。10年住めないのか、20年住めないのか、ということになってくる」との認識を示した。松本氏が会談後に明らかにしたものだが、首相は同日夜、「私が言ったわけではない」と記者団に語った。(以下略)-----この発言、後で否定したそうですが、「言った言わない」はともかく、実際に原発周辺が数十年単位で人が住めなくなる可能性は高いと思われます。これについても、先ほど引用した3月26日の記事で指摘しました。さすがに、チェルノブイリほど広大な面積ではないと思いますが(これ以上汚染が拡大しなければ、ですが)、そういう地域が出てしまうことは避けられないでしょう。---話は変わりますが、原発のメリットとして、「発電コストが安い」という主張があります。経産省が公表している試算によると、1kWhあたりの発電コストは、水力 8.2~13.3円 設備利用率45%石油 10.0~17.3円 設備利用率30~80%LNG 5.8~7.1円 設備利用率60~80%石炭 5.0~6.5円 設備利用率70~80%原子力 4.8~6.2円 設備利用率70~85%太陽光 46円 設備利用率12%風力 10~14円 設備利用率20%ということになっています。実はこの数字には非常にウソが多いのですが、そのことについては後述します。ところで、今回の事故で東京電力が負う損害賠償額は、10兆円とも言われています。すごい金額です。日本で商業原子炉による発電が始まったのは1970年のことですが、それから2009年度末までの40年間の原発による総発電量は、7兆1195億kWhです。2010年の発電量は2700億kWh前後と思われるので、日本で原子力発電が始まって以来の累計発電量は、だいたい7兆5千億kWhくらいになるわけです。さて、そこに10兆円の損害賠償額が乗っかると、どうなるでしょうか。日本に原子力発電が導入されて以来の全発電量の発電コストが、これによって1.3円ほど上昇する、ということになるわけです。LNGや石炭とのコストの差はもともと小さいので、原子力に1.3円の補償費用が上乗せされれば、コストは当然逆転します。さて、経産省の発表している原発の「発電コスト」にはウソが多いと書きました。具体的にどういうことかというと、基本的に、税金で賄われている費用、先送りされている費用は、このコスト計算には入っていないのです。具体的に言うと、原発設置のために国が地元自治体に出す補助金はコスト計算に入っていません。そして、使用済みの核燃料(高レベル廃棄物)の処理・保管費用も計算に入っていません。日本で原発が動き始めてから40年も経つのに、使用済みの核燃料の最終処分をどうするか、まだ決まっていないのです。決まっていないのをいいことにして、原発の発電コストにその費用を見込んでいません。寿命が尽きた廃炉の処分費用も同様です。では、具体的に、高レベル廃棄物の処理にはどのくらいの費用がかかるのか。具体的な処理方法が決まっていないので、費用も決まっていませんが、電気事業連合会は、2003年に、再処理工場の稼働開始(当時は2006年を予定)から72年間で18兆9100億円という試算を発表しています。今回の事故の補償金10兆円がかすむほどの高額です。この種の数字というのは、おおむね試算より実際の方が金額が膨らむものです。それに、試算は72年間ですが、高レベル廃棄物は半減期の非常の長い放射性物質が多いので、危険性がなくなるまで、数千年間管理し続ける必要があります。数千年・・・・・・そのとき「日本国」が存在するかどうかすらも定かではありません(確実に言えるのは、今から数千年前には「日本」という名称の国家はまだ存在しなかった、ということ)。まして、そんな長期間の保管にどれほどの費用がかかるのか、見当も付きません。要するに、負の遺産を我々の子孫に押しつけることによって、今現在の発電コストが安いかのように装っているのが原子力発電の発電コストなるものの正体なのです。他に原発の発電コストから除外されているのは、揚水発電所の費用です。原発と揚水発電所の関係については、以前の記事で説明したことがあります。原発は、出力を落としての運転が出来ないため、揚水発電所が必須なのですが、その揚水発電所の発電コストは、1kWhあたり30円以上と非常に高い。これを原発のコストから除いているのです。さらに、設備利用率70~85%という計算の全体も、現在の原発の稼働率の実態から乖離しています。原発は、燃料(ウラン)の値段より発電所のうつわの値段の方が遙かに高価です。うつわの値段は固定費なので、稼働率が高ければ高いほどコストは下がる計算です。しかし、現実には現在の原発の稼働率はそんなに高くありません。つまり、このように原発のコストが安く見えるように操作したコスト計算でもなお、石炭やLNGによる火力発電とのコストの差は、ごくわずかしかないのです。実際のところは、石炭やLNGより原発の方が遙かに高コストと思われます。そこに損害賠償が加われば、尚更です。もっとも、損害賠償を国に立替させて、相変わらず「原発は低コスト」と言い続けるつもりでしょうか。もっとも、そんなことを言っても、もはや信じる人は少ないでしょうが。
2011.04.13
コメント(3)
-
とうとう川俣も避難対象
20キロ圏外に「計画的避難区域」 葛尾や浪江・飯舘枝野幸男官房長官は11日午後の記者会見で、福島第一原発から20キロ圏外の一部地域を新たに「計画的避難区域」に指定し、1カ月程度かけて住民を域外に避難させると発表した。原発事故の影響で住民が受け続ける、累積の放射線量が高くなるのを避けるためだ。枝野氏は、福島第一原発北部にある福島県葛尾村、浪江町、飯舘村と、南相馬市の一部と川俣町の一部が対象になると表明した。南相馬市と川俣町については、今後、政権が対象市町村や県と調整したうえで具体的な地域を確定し、原子力災害対策特別措置法に基づいて菅直人首相が避難を指示する。枝野氏は会見で「すぐに避難行動をお願いするものではない」と述べ、落ち着いて準備をするよう呼びかけた。国際放射線防護委員会(ICRP)は、緊急時は一般の人も年間20~100ミリシーベルトの放射線を浴びる場合は対策が必要と勧告。菅政権は原子力安全委員会の助言を踏まえ、事故発生から1年間の放射線積算量が20ミリシーベルトに達すると予想される地域についても、避難対象に加える必要があると判断した。(以下略)-----------川俣で毎年10月に行われる「コスキン・エン・ハポン」のことは、少し前の記事で紹介しましたが、その川俣町の一部も、ついに避難対象地域に入るようです。コスキンの会場となる中央公民館が避難対象地域に入るのどうかは分かりませんけれど、避難地域でないとしても、今年のコスキンは、どう考えても開催不能でしょうね。いや、今年だけで済めばまだいいのですが・・・・・・。2000年を最後に、久しくコスキンに行っていなかったですが、もし再開されたら、行ってみようかな。でも、それは下手をすると5年後10年後の話になってしまうかも知れません。ところで、一昨日の記事で「要は、いずれの原発も、非常用発電機が震災によって多かれ少なかれ損傷している。」と書きました。ところが、このうち、少なくとも東通原発の非常用発電機は、震災によって壊れたのではなく、人為ミスで故障したことが明らかになりました。東通原発の発電機故障、人為ミスか…東北電力東日本大震災の余震による停電に伴って稼働した東北電力東通原子力発電所1号機(青森県東通村)の非常用ディーゼル発電機から燃料が漏れた故障について、東北電力は9日、部品の欠損が原因だったと発表した。定期点検のときに組み立て方法を間違い、それがもとで欠損した人為ミスと東北電力はみている。燃料循環ポンプ付近にあるゴム製の部品が欠損し、そこから燃料の軽油が漏れた。1号機は今年2月、定期点検に入り、発電機は協力会社が分解、組み立て直した。-----------原発の「安全神話」なるものが、いかに幻想に過ぎなかったか、よく分かる事件です。定期点検をやったら、そのあと起動チェックをするはずで、そのときに油漏れに気づいているのが普通だと思うのですが、おそらく点検の後起動しての動作確認を怠ったのでしょうね。おそらく、外部電源が途絶する事態を、真剣に受け止めていなかったのでしょう。非常用発電機なんて、法令の定めで設置しているだけで、実際に使うはずなんかないんだから、適当に点検しておけ、程度の意識だったのかも知れません。しかも、福島第一原発があのような事態になってしまった後でさえ、「うちの原発の非常用発電機は大丈夫か?」というチェックを行っていなかった、ということです。東京電力には大いに問題がありますが、東北電力も似たようなもの、ということです。実は、我々は今まで無免許運転のバスに乗っていたのではないでしょうか。今まで事故に遭わなかったのは、たまたま偶然そうだっただけ。それにもかかわらず、それを「安全だから」と思っていたのは、大いなる勘違いだった、ということなのだと思います。
2011.04.11
コメント(0)
-
来週のライブに向けて、「公開練習」
今日はキラ・ウィルカの練習でした。練習場所は、いつもは区民会館のようなところが多いのですが、今日は、本番の演奏をするのと同じ場所、「ティア・スサナ」で練習してきました。思い返すと、1年余り前に、やはりティア・スサナで練習したのが、ちょうどチリ地震の起きた翌日で、日本全土に津波警報が出ていたのです。練習をしながら店内のテレビを見ていたら、「あ、津波が来た!」と。そのときは最大波高が1メートルあまりだったので、日本では大きな災害にはならなかったのですが。奇しくもその1年後、同じティア・スサナでのライブ(当初の予定ではは3月12日)の前日に、再び津波が起こるとは(あのときとは比較にならない規模ですが)、何という恐るべき偶然でしょうか。さて、今日の練習は、ティア・スサナのホームページに「公開練習」なんて案内が出てしまったのですが、幸か不幸か、我々の演奏を目当てにいらっしゃったお客さんはいませんでした。でも、お昼時にはお客さんが何組かいました。我々が練習を始めた時間(2時頃)までには帰られてしまいましたが。我々の練習は、本番の演奏曲を全曲とおして練習、更に、不安な曲をもう一度練習(結局、全曲の半分くらい)。そのあたりで、体力と時間が限界に到達してしまい、本日の練習はおしまい。課題は、たくさんありますが・・・・・・。疲れましたが、楽しかったです。とりあえず、計画停電はいったんは終了したようですが、夏場にどうなるかが問題です。計画停電によって工場が操業できなくなったり、サーバが動かなくなったりするので、各メンバーの休日も大変動に見舞われています。このまま行くと、計画停電が再開する夏場は、グループの練習や演奏活動が困難になるかもしれません。とりあえず6月中くらいまでと9月中旬以降は、何とかなりそうですが。それにしても、今度こそ本番の演奏まで、いやそれ以降もずっと、大きな災害など起こりませんように、パチャママ(大地の母)よ、パチャママよ、我らを守り給え。---キラ・ウイルカ フォルクローレ・ライブ4月16日(土)午後6時より(2部構成予定)場所 ペルー料理店・スポーツカフェ「ティア・スサーナ」総武線・信濃町駅より徒歩約5分料金 チャージなし(レストランですから、食事はしてください)曲目 コンドルは飛んでいく、トリニダーより、蜃気楼の歌、出会い、など(16曲くらい演奏します)
2011.04.10
コメント(0)
-

か細い一本の糸で支えられた「安全性」
東通原発、非常用発電機全て使えず 女川も1台故障7日深夜に起きた余震では、東北地方の複数の原子力施設で外部電源からの電力供給が途絶した。このうち東北電力東通原発や女川原発では、バックアップ用の非常用ディーゼル発電機が使えないなど、危うい状態が続いたままだ。今回は辛うじて難を免れたが、今後も予想される大規模な余震の揺れと津波に、原発は耐えられるのか。東北電力によると、東通原発(青森県東通村)1号機は、余震で外部からの電力供給が2系統とも遮断されたため、非常用ディーゼル発電機による冷却に切り替えた。8日午前3時半、外部電源が復旧。外部電源とともに非常用発電機による電力供給も続けたところ、午後2時10分ごろ、発電機の燃料循環ポンプ付近で燃料の軽油がもれているのを作業員が見つけ、運転を止めた。燃料漏れの理由は調査中。同原発は3月11日の東日本大震災時には定期検査中で、原子炉に燃料棒はなく、現在、外部電源で使用済み核燃料貯蔵プールの冷却を続けている。非常用ディーゼル発電機は3台あるが、もう2台も、点検中のためすぐには起動できないという。女川原発(宮城県石巻市、女川町)1号機でも、非常用ディーゼル発電機2台のうち1台が壊れたまま、1週間にわたって必要な機能を果たせない状態にあることがわかった。経済産業省原子力安全・保安院が8日、明らかにした。保安院によると、同電力が今月1日、1号機の発電機の定期点検をしたところ、2台のうち1台が発電所内の電源にうまく接続できないことが分かった。東北電力は接続不良の原因をつきとめて8日、原子炉等規制法に基づいて保安院に報告したが、この間、新たな発電機の配備はないという。女川原発はこの状態のまま7日の余震にあい、外部電源3系統のうち2系統が途絶。1系統は生き残ったが、一時は綱渡りの運転を余儀なくされた。東通、女川の両原発で、この状態が続いたまま再び外部電源が失われた場合、どう対処するのか。東北電力は保安院などに対し、福島第一原発の事故を受けて配備した電源車で最低限の冷却はできる、などと説明しているという。女川原発ではまた、地震の揺れの影響で、各号機の使用済み核燃料貯蔵プールの冷却装置が自動停止した。容器の振動で水が波打つように大きく揺れる「スロッシング」という現象が起き、ポンプに負荷がかかってモーターが停止したという。約1時間後に再起動したが、放射性物質を微量に含むプールの水が約3.8リットルあふれ、専用のナプキンで拭いた。周囲の放射線の値に変化はないという。日本原燃の使用済み核燃料再処理工場(青森県六ケ所村)でも、外部電源が途絶え、非常用ディーゼル発電機で使用済み燃料貯蔵プールの冷却を続けたが、8日午後3時ごろ外部電源が復旧した。--------------震災で大事故に至ったのは福島第一原発だけですが、それ以外の被災地内の原発も、実は紙一重の状態であることが分かります。要は、いずれの原発も、非常用発電機が震災によって多かれ少なかれ損傷している。その状態で大きな余震が来て外部電源が断たれると、あっという間に危機的な状況に陥るということです。東通原発は、記事によれば定期点検中で炉内には燃料棒はないそうですが、燃料棒が炉内ではなく燃料プールにあるとしても、冷却水の循環が停止すれば致命的な事態が起こることは、福島第一原発4号基の例を見れば明らかです。外部電源の途絶が長期間に及べば、福島第一原発と同じ事態に至る危険はあったと思われます。記事によると、「東北電力は保安院などに対し、福島第一原発の事故を受けて配備した電源車で最低限の冷却はできる、などと説明しているという。 」とのことですが、果たしてどうでしょうか。福島第一原発でも、地震の直後に電源車が次々と送り込まれましたが、爆発を阻止することはできませんでした。あの電源車がどうなったのか、続報がまったく報じられていないので何がどうなったのかは定かではありませんが、週刊誌情報によると、ケーブルの長さが足りなくて電気を供給できなかったようです。もともと、電源車は原発の非常用として用意されているものではないので、原発への電力供給のための準備はなかったのです。そのことを考えると、電源車があるから冷却ができる、とは思えないのです。しかも、大きな余震がもう来ない、とは断言できない状況です。2004年に巨大津波を引き起こしたスマトラ島沖地震の場合、周辺地域ではそれ以降マグニチュード8クラスの巨大地震(もはや余震というより連動して起きた別の地震という方がおそらく正しい)が3年後の2007年までに2回起こっており、更にマグニチュード7クラスの地震は昨年まで数回起こっています。このことから考えると、余震、あるいは今回の地震に連動する別の巨大地震が、今後数年に渡って頻発する可能性が大いにあります。その度に、保安設備の機能が低下した原発(次第に修理はされていくでしょうが)に肝を冷やし続けなければならないのです。ところで、シンガーソングライター斉藤和義の反原発ソングが話題になっているようです。「ずっとウソだった」自作曲「ずっと好きだった」の替え歌です。痛烈な歌詞ですね、なかなか良い。本人自身が歌って、おそらく本人自身が(少なくとも本人自身の意向に従って)アップしたと思われるにも関わらず、何故かアップロードされては削除(おそらくはレコード会社の意向により)を繰り返したようです。現在では、転載された動画が拡散しているので、もう削除しきれない状況でしょうが。かつて、忌野清志郎が反原発ソングを東芝EMIによって発禁にされた事件がありました。彼も、ひょっとするとこの件が原因で干されるかもしれない、そのリスクを覚悟の上であえて公表したのでしょう。なかなかの覚悟です。それにしても、この件に関するmixi日記などを見ると、斉藤和義に対する批判が多いのにびっくり。その批判を要約すると「原発反対というなら代替案を考えろ」「自分は音楽配信で電気を使っているくせに」という趣旨です。どちらの主張も的はずれです。何度も指摘しているように、現在東京電力で稼働している原発は、柏崎原発の7基のうちの4基だけ、東北電力は全機停止しています。日本原子力発電の東海第二原発(茨城県)も停止。これら停止中の原発は、いずれも何らかの故障・損傷が発生しており、すぐに再稼働できるような状況にはありません。つまり、現状東京電力と東北電力の原発依存度は限りなく低下しており、近いうちにそれが復旧する見込みはありません。それとも、安全設備が損傷している各原発を、いつ余震があるか分からない状況で無理矢理稼働させますか?地元の反対も無視して?出来るわけがない。じゃあ新しい原発を作りますか?今から作って、完成するのは何年後ですか?それ以前に、原発を新設するといって、それを受け入れる自治体がありますか?あるはずがないですよね。つまり、今の時点で「原発推進」などと言っている連中の方が、実はよっぽど非現実的なのです。できもしないことを言っているだけ。「原発推進というなら具体案を考えろ」という話。「自分は音楽配信で電気を使っているくせに」というのはね、これを言い出すと、電気を使わない人間はいないので、日本中の誰一人、電力行政、電力会社に対して批判的なことは口にしてはいけないになります。子ども手当を受給したら、子ども手当という制度を批判してはいけないのか、というのと同じことです。日本において、社会生活を送っていくのに電気の仕様は不可欠です。そのことと、批判することの可否は別の問題です。
2011.04.09
コメント(6)
-
オール停電化住宅
先週のことですが、東京電力はオール電化住宅の販売を休止したと報道されています。そんな折も折、先日ある地下鉄で、「オール電化住宅」という広告があるのを発見しました。もちろん、地震の前に出された広告でしょう。かわいそうに、今「オール電化住宅」なんて触れ込みのマンションを買う人なんか、いませんよね。何しろ今となってはオール停電化住宅ですから。もっとも、灯油やガスでも、今は電気でコントロールされる機器が多いので、電気が止まるとこれらの機器も止まってしまう可能性は高いのですが。ただ、我が家の例で言うと、ガスコンロは電気が止まっても動きます。それに水道も大丈夫なので、炊事は問題ありません。それに、やかんで湯を沸かせば、暖房の代わりにもなるでしょう。ガス暖房と風呂釜は、電気が止まると動きませんけれど、熱源が確保できると言うだけでもオール電化住宅とは大変な違いです。あの大地震以降、これまでの「世の常識」の一部が、ガラガラと音を立てて崩れてしまったように思います。オール電化もそうです。これまで、日本は世界でも有数の電気の品質の高い国でした。電気の品質とは、停電が少ないこと、電圧と周波数が一定であることです。日本は、これまで停電が非常に少ない国でした。年間事故停電時間数が、一顧客あたり日本は年間9分(2003年)、イギリス73分(2001年)、米国69分(2002年)、フランス45分(2001年)という数字があります。発展途上国では、この数値はイギリスより更に大きいはずです。南米など、停電は日常茶飯事ですから。しかし、今となっては、日本は停電発生率の非常に高い国とならざるを得ないでしょう。今年の年間事故停電時間数は一顧客あたりどのくらいでしょうか。3月11日の地震と昨日の余震による停電、計画停電(特に夏に再開された際の規模は今までよりもっと大きくなると予想されます)、停電と縁のない関西以西を含めて考えても、今までより激増することは間違いありません。でも、それも我々の頭上から放射能の雨が降るよりはマシというものです。もっとも、その事実に気がついたのは、放射能の雨が降ってしまった後であるところが悲劇ですけれど。それにしても、改めて思うのは、こういう事態になると、太陽光発電というのはいいかもしれませんね。夜は使えない欠点はあるけれど、日中なら停電でも電気が使えるメリットは大きいです。
2011.04.08
コメント(0)
-
柏崎刈羽原発再起動??
桜井同友会代表幹事、柏崎刈羽の再稼働を提言経済同友会の桜井正光代表幹事は6日の記者会見で、夏場の電力不足を回避するため、新潟県の柏崎刈羽原子力発電所の休止炉を早急に再稼働するべきだと指摘した。桜井氏は、「柏崎刈羽原発の(7基のうち)止まっている3基を早期に復活させるべきだ」と述べた。防災対策を前提に、1基あたりの発電能力が100万キロ・ワットを超える3基が稼働すれば、電力不足は解消に向かうとの認識だ。(以下略)-------柏崎原発は、中越沖地震で緊急停止して、その後7基のうち4基(1・5・6・7号基)は再稼働していますが、3基(2~4号基)はまだ動いていません。何故動いていないかと言えば、点検・復旧・耐震強化作業がまだ終了していないからです。それを端折って再稼働なんてことが許されるはずもありません。それに、地元(新潟県)の同意が得られるはずもない。それに、3基330万KWが加わったとしても、それだけで夏場の電気が足りるわけではありません。柏崎刈羽原発以外に、地震の影響で現在停止中の原発は、福島第一・第二・女川・東海第二の各原発があります。このうち、福島第一の再稼働は絶対にありません。それ以外の原発はどうでしょう。いずれも程度の差はあっても津波によって被害を被っていますから、その修理と点検が完了するまでは再稼働なんてあり得ません。特に、福島第二原発は、立地そのものが福島第一原発の避難指示範囲内にありますから、再稼働はできない(許されない)と思います。仮に再稼働ができるとしても、福島第一原発の状況が解決して以降、早くても数年以上先のことになるでしょう。それ以外の各原発にしても、修理完了まで1年くらいはかかるでしょう。結局のところ、今年の夏までに再稼働できる原発はないということです。つまり、未だに原発の再稼働に望みを託している方がよほど非現実的である、ということです。ないものはないんだから、諦めるしかない。いずれにしても、現在の計画停電は、ほぼ終了しましたが、この夏の電力不足は確実です。・・・・・・・・ここまで入力したら、また緊急地震速報、そして地震が来た。結構でかいぞと思ったらマグニチュード7.4(でも、東京は震度3と出ています、もっと大きい気がしたけど)。津波警報も。うーーーん、気分的に、今日の記事はここまでにします。
2011.04.07
コメント(2)
-
さくらがやっと満開に
我が家近辺では、まだ七分咲きくらいの感じですが、ともかく「さくらが満開」と言えるくらいの咲き方になってきました。今年のさくらは例年より遅い気がします。このところ、3月中に満開を迎えて、4月第1週の週末は散り際くらいのことが多かったですから。どうも、社会情勢が「花見を楽しむ」という雰囲気じゃなくなっていますけれど、人生には楽しみは必要です。それにあれもこれも自粛していたら、経済がどうかなってしまいますから。というわけで、以前にも紹介しましたが、さくらの季節にふさわしい曲をさくら フルート4重奏+ギター---ところで、私のフルートは銀座の山野楽器で購入したものなので、ヤマノフルートフェスティバルのダイレクトメールが送られてきました。毎年、春と秋の2回フルートフェスティバルが行われ、その度に無料調整会があるので、そこでフルートの調整をお願いしています。それにしても、もともと不況の上にこの地震と原発事故、それによる計画停電。芸術関係への影響もまた大きいでしょうね。数え切れないくらいのコンサートやライブが中止になっているはずですし、楽器だって売れてないだろうなと思います。フルートメーカーも経営の苦しいところが多いでしょう。そういうときだからと、ポンと総銀製フルートでも買えたらいいのですが、今使っているムラマツEXを気に入っているので、まだまだ買い換える予定はありません(まだ3年しか使っていないし)。
2011.04.06
コメント(4)
-
ザよこはまパレード中止に・・・・・・・
この数年、「アンデス村まつり隊」の一員として5月3日に「ザよこはまパレード」に参加してきたのですが、残念ながら今年は地震の影響によって中止となってしまいました。http://mainichi.jp/area/kanagawa/news/20110405ddlk14040274000c.html東日本大震災:ザよこはまパレード中止に /神奈川5月3日に予定されている第59回ザよこはまパレード(国際仮装行列)の実行委員会は4日、開催を中止すると発表した。東日本大震災の被災地に配慮するとともに、計画停電の影響なども踏まえて判断した。パレードは横浜経済の復興と観光振興を目的に1953年に始まり、横浜開港記念みなと祭の一環として行われてきたイベントで中止は初めて。---------計画停電といっても、日中屋外で行うイベントなので、それほど電気を消費するとは思えないし、こういうときこそ元気が出るイベントをやってほしいとは思うのですが、実際のところは、被災地に相当数の警官と救急隊が派遣されており、当日の交通規制や沿道の警備に警官を配置できないとのことで、警察から中止要請があったようです。全長3キロ以上、所要時間1時間半という長丁場の演奏で、体力の限界までサンポーニャを吹き続ける、過酷だけど最高に楽しいイベントでした。非常に残念ですが、仕方ありません。でも、キラ・ウィルカのライブは予定どおりやりますよ!4月16日(土)午後6時より(2部構成予定)場所 ペルー料理店・スポーツカフェ「ティア・スサーナ」総武線・信濃町駅より徒歩約5分料金 チャージなし(レストランですから、食事はしてください)曲目 コンドルは飛んでいく、トリニダーより、蜃気楼の歌、出会い、など(16曲くらい演奏します)
2011.04.05
コメント(0)
-
やはり情報操作
昨日の記事で、日本気象学会が会員の研究者らに、大気中に拡散する放射性物質の影響を予測した研究成果の公表を自粛するよう求める通知を出していた件を取り上げました。そして、その記事の中で触れたように、日本気象学会の事務局は気象庁内に置かれています。その気象庁は、放射性物質拡散予測を行いながら、その結果を公表していません。日本で公表されない気象庁の放射性物質拡散予測東京電力福島第一原子力発電所の事故で、気象庁が同原発から出た放射性物質の拡散予測を連日行っているにもかかわらず、政府が公開していないことが4日、明らかになった。ドイツやノルウェーなど欧州の一部の国の気象機関は日本の気象庁などの観測データに基づいて独自に予測し、放射性物質が拡散する様子を連日、天気予報サイトで公開している。日本政府が公開しないことについて内外の専門家からは批判が上がっており、政府の原発事故に関する情報開示の在り方が改めて問われている。気象庁の予測は、国際原子力機関(IAEA)の要請に基づくもの。国境を越える放射性物質汚染が心配されるときに、各国の気象機関が協力して拡散予測を行う。同庁では、東日本大震災当日の3月11日から毎日1~2回、拡散予測を計算している。具体的には、IAEAから送られてきた放射性物質の放出開始時間や継続期間、どれくらいの高さまで上ったかを、風向きや天候など同庁の観測データを加えた上で、スーパーコンピューターに入力し、放射性物質の飛ぶ方向や広がりを予測している。--------昨日の記事で、私はお前ら、悪いデータを隠蔽するために、一般研究者の口を封じようとしているんだな!と、言われても、仕方がないんじゃないでしょうか?実際には、私はそこまで疑っているわけではないのですがと書いたのですが、どうもこの言い方はまだまだ甘かったかも知れません。気象庁自身は放射能拡散予測を行いながら、その結果を隠蔽し、一般研究者の予測公表は制限しようとする。「悪いデータを隠蔽するために、一般研究者の口を封じようとしている」というのは、実際にそうなのだろう、という強い疑いを抱かざるを得ません。知らしむべからず、よらしむべし、ということでしょうか。---とろこで、読売新聞の世論調査によると、原子力発電の今後については「増やすべきだ」10%、「現状を維持すべきだ」46%、減らすべきだ29%、すべてなくすべきだ12%という結果になっているそうです。これほどまでにすさまじい事故の後でも、増やすべき+現状維持すべきで5割を超えているとは、正直言って驚きです。もっとも、「現状維持」には2種類の立場があると思われます。一つは、「今稼働中の原発は現状維持」という場合、もう一つは、「今と同程度の原発依存度を維持」という場合です。前者の場合は、当面は現状維持ですが、やがて寿命で廃炉になるにつれて、原発は減っていき、数十年後には原発がなくなる。しかし、後者の場合は、廃炉になればその分新しい原発をつくる、ということになるわけです。もちろん、「増やすべきだ」という10%も、新しい原発を増設ということになります。で、この人たちは、今から日本のどこが新しい原発の増設を受け入れると思っているのでしょうか。そのあたりが非常に疑問です。以前にも書いたように、もはや新しい原発を受け入れる地域があるはずがない、という現実を踏まえた上での回答とは思えません。
2011.04.04
コメント(4)
-
気象学会が情報操作を始めた、と解釈せざるを得ない
放射性物質予測、公表自粛を 気象学会要請に戸惑う会員福島第一原発の事故を受け、日本気象学会が会員の研究者らに、大気中に拡散する放射性物質の影響を予測した研究成果の公表を自粛するよう求める通知を出していたことが分かった。自由な研究活動や、重要な防災情報の発信を妨げる恐れがあり、波紋が広がっている。文書は3月18日付で、学会ホームページに掲載した。新野宏理事長(東京大教授)名で「学会の関係者が不確実性を伴う情報を提供することは、徒(いたずら)に国の防災対策に関する情報を混乱させる」「防災対策の基本は、信頼できる単一の情報に基づいて行動すること」などと書かれている。新野さんによると、事故発生後、大気中の放射性物質の広がりをコンピューターで解析して予測しようとする動きが会員の間で広まったことを危惧し、文書を出した。情報公開を抑える文書には不満も広まり、ネット上では「学者の言葉ではない」「時代錯誤」などとする批判が相次いだ。「研究をやめないといけないのか」など、会員からの問い合わせを受けた新野さんは「研究は大切だが、放射性物質の拡散に特化して作った予測方法ではない。社会的影響もあるので、政府が出すべきだと思う」と話す。だが、今回の原発事故では、原子力安全委員会によるSPEEDI(緊急時迅速放射能影響予測)の試算の発表は遅すぎた。震災発生から10日以上たった23日に発表したときには、国民に不安が広まっていた。気象学会員でもある山形俊男東京大理学部長は「学問は自由なもの。文書を見たときは、少し怖い感じがした」と話す。「ただ、国民の不安をあおるのもよくない。英知を集めて研究し、政府に対しても適切に助言をするべきだ」火山防災に携わってきた小山真人静岡大教授は、かつて雲仙岳の噴火で火砕流の危険を伝えることに失敗した経験をふまえ、「通知は『パニック神話』に侵されている。住民は複数の情報を得て、初めて安心したり、避難行動をしたりする。トップが情報統制を命じるのは、学会の自殺宣言に等しい」と話している。-------------問題の通達は、こちらにあります。ごく単純化して言えば、放射能の拡散予測は国がやるから、お前ら一般研究者は手を出すな、ということです。「学会の関係者が不確実性を伴う情報を提供することは、徒に国の防災対策に関する情報を混乱させる」まるで国家は無謬であり、学会関係者はデマの発信源であるかのような書き方です。しかし実際には、国の防災対策自体が機能不全であり、国の発信する情報も不確実性だらけの上に混乱している。記事にあるように、12日には原発の水素爆発が起こっているのに、政府機関(原子力安全委員会)が放射性物質の拡散予測を発表したのは10日以上経ってからという状況です。あまりに遅すぎて、「予測」ではなく「事後の推測」にしかなっていません。(海外においては、とっくに拡散予測が公表されています)SPEEDIの予測がどの程度正しいのかも、検証のしようがありません。日本気象学会の事務局は気象庁内に置かれており、気象庁は国土交通省の外局です。そのような学会がこのような通達を出すということは、政府の意向で(あるいは政府の顔色をうかがって)情報を統制しているのだと、そう思いたくなります。お前ら、悪いデータを隠蔽するために、一般研究者の口を封じようとしているんだな!と、言われても、仕方がないんじゃないでしょうか?実際には、私はそこまで疑っているわけではないのですが、こんな通知は、そのような疑いを抱く者の前で「李下に冠を正す」行為を行っているとしか思えません。そうではないというなら、このような馬鹿馬鹿しい通知などただちに撤回することです。
2011.04.03
コメント(0)
-
震災絡みの悪質デマ
震災絡みの悪質デマを公表…警察庁、立件も視野震災絡みの悪質デマを公表…警察庁、立件も視野東日本大震災に絡むデマや根拠の不確かな情報が広まっているとして、警察庁は1日、インターネットや口コミで出回っている流言飛語の一部を公表した。ネット掲示板などに掲載された悪質なデマ28件については、3月31日までに警察からサイト管理者に削除要請を行った。「仙台市郊外で商品の略奪が横行」。宮城県内の避難所などで同様の風評が広がりネット掲示板でも書き込みが相次いだが、実際には名指しされたショッピングモールに窃盗などの被害はなかった。こうしたデマは口コミやチェーンメールのほか、存在しない新聞社名でネットに書き込まれたりして広がる。具体的な地名や店名を交えているために信用されやすく、警察や県庁に事実確認の問い合わせも複数寄せられている。被災地の県警ではデマで名指しされた地域を重点的にパトロールし、被災者の安心感の確保に努めている。また、故意に誤情報を流した人物を特定すれば名誉毀損(きそん)や業務妨害容疑での立件も視野に捜査するという。--------------実は、私の相棒の携帯にも地震の後、デマのチェーンメールが送られてきたのです。その内容は、市原の液化石油ガスタンク炎上で、東京に有毒ガスを含んだ雨が降る、というものでした。実際には、液化石油ガスが炎上したからと言って有毒ガスが出ることは考えにくいし、実際に有毒ガスは放出されていませんでした。更に、これが略奪だ強盗だ誘拐だ、ということになると、話が違ってきます。デマが原因で犯人捜しとか、名指しされた「危険地帯」に人が寄りつかなくなるとか、大きな弊害が生じます。安定ヨウ素剤の変わりにうがい薬を飲め、みたいな話になると、信じてしまった本人の健康を害することになってしまいます(ただし、うがい薬は通常の使用でも誤飲の可能性が多大にありますから、わずかな飲用でも健康を害するほどの成分は入っていないのではないか、という気はします)。関東大震災の際の朝鮮人虐殺事件の頃から、大規模災害とデマは密接に結びついています。人々が不安なときには、デマを信じやすい。阪神淡路大震災のときも、被災地で犯罪が多発している、みたいなデマがあったようですが、実際には犯罪件数は増えていませんでした。※デイリースポーツの記事より阪神・淡路大震災では「性犯罪が増加した」などのデマが流れたが、兵庫県内の強 姦事件数は前年と変わらず、逆に強制わいせつ事件は減少。窃盗や強盗も減っていたという。関東大震災では、大手マスコミすら「朝鮮人が放火した」などとデマの片棒を担ぐ報道を行い、虐殺の拡大に手を貸しています。しかしさすがに現在では、そこまで酷いマスコミは存在しない・・・・・・・・わけでもないですが、少なくともこの震災時にその種の悪質デマに荷担するマスコミは、さすがにないと思います(いくら産○新聞といえども、ね)。相棒の携帯に送られてきたチェーンメールは、「何とか大学の誰それ教授によると」という、いかにも権威を装って(メールはとっくに削除しているので、具体的な氏名は覚えていません)危険性を訴えようとしていました。こうなってくると、チェーンメールの最初の発信元には、悪意すら感じます。もっとも、チェーンメールの内容が最初から不変だったかどうかは、定かではありません。実際には困難でしょうが、誰が最初にチェーンメールを発信して、それがどんな内容だったのか、それが途中でどう内容が変わっていったのかを調べることができたら、かなり有益でしょう。かつて、豊川信金事件の際には、警察はデマの発生経過を捜査して、それを公表しています。
2011.04.02
コメント(6)
全26件 (26件中 1-26件目)
1