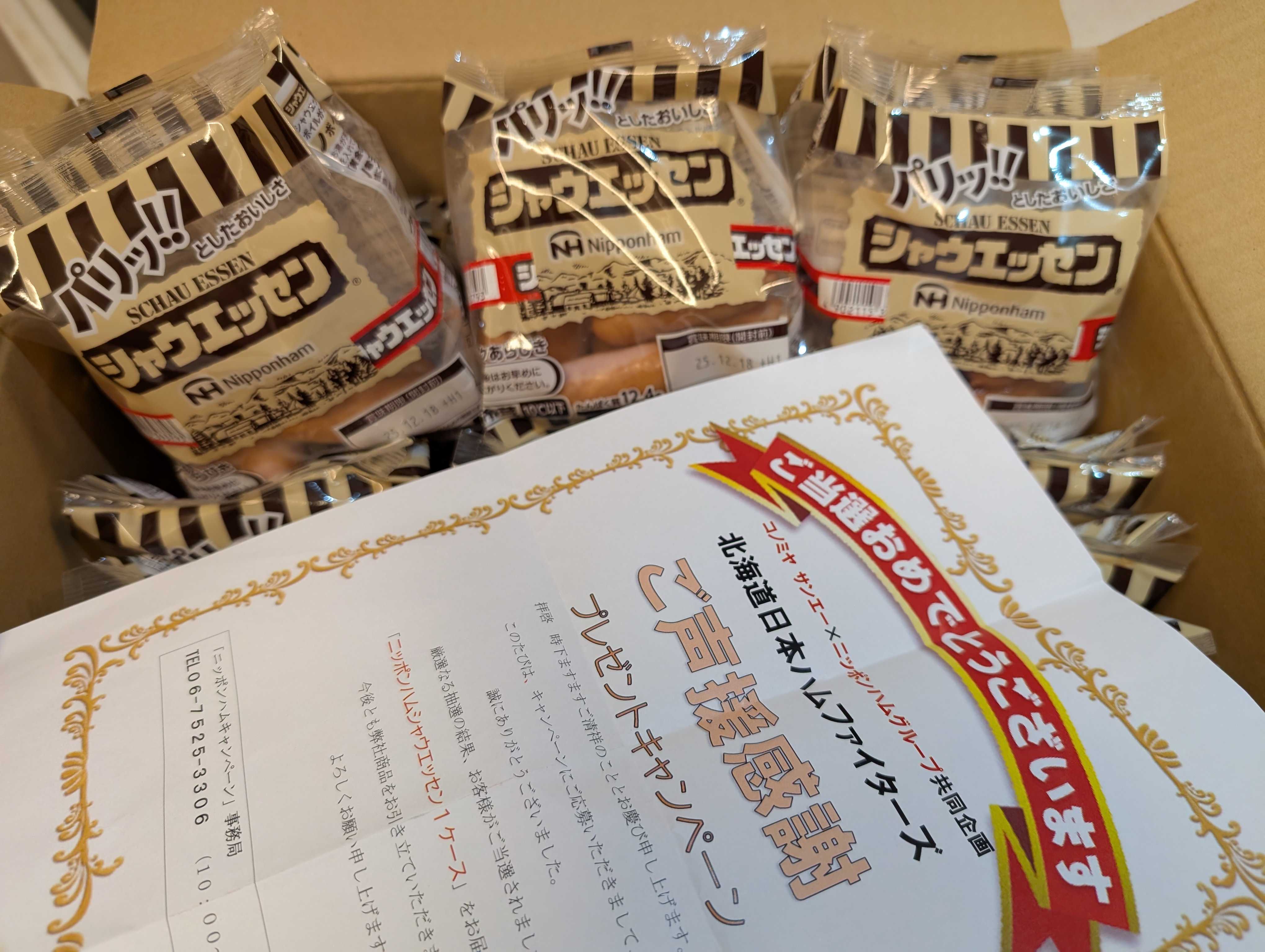2006年08月の記事
全33件 (33件中 1-33件目)
1
-

チェット・ベイカーで Let's get lost!
先日、チェット・ベイカーの『チェット・ベイカー・シングス・アンド・プレイズ』というジャズ・アルバムを買ったんですけど、なかなかいいんだ、これが。 チェット・ベイカーってのは、1950年代から活躍したジャズ・トランペッターで、50年代にはかのマイルス・デイヴィスよりも人気があったというほどの人。ま、ルックスも良いので、そのせいかも知れませんが。その風貌は、ジャズ界のジェームズ・ディーンって感じですからね。 ところでチェット・ベイカーという人の特徴の一つは、彼が歌う、ということなんです。彼はトランペットを吹くだけでなく、ヴォーカルもやるんです。 で、それが人気のもとでもあり、また不人気の理由でもあるんですな。事実、ジャズ関連の本の中で、チェット・ベイカーについて触れている部分を読むと、たいてい彼のヴォーカルのことが批判的に書かれています。たとえば『ジャズCDの名盤』(文春新書)で悠雅彦氏は「打ち明ければ昔から熱心なファンではない。ことに彼の歌は苦手だった」(189頁)と書いているし、『新ジャズの名演・名盤』(講談社現代新書)の著者・後藤雅洋氏は「彼の異様とも思える中性的ヴォーカルが・・・うまいんだかへたなんだかよくわからないが、とにかく個性的であることはまちがいない」(121頁)と述べています。他にも色々ありますが、とにかくジャズ通の間ではチェット・ベイカーのヴォーカルはあまり高く評価されていないんです。 しかし、「異様とも思える中性的ヴォーカル」だなんて言われると、私のような素人は逆に興味が出てくるわけですよ。ヴォーカルが「異様」ってどういうこと!? で、買ってみたわけですよ。で、聴いてみた、と。 ・・・いいじゃん、結構。ワタクシ、好きかも・・・。 ま、確かに「中性的」と言えば、そうかも知れません。こういう感じのくぐもった、アンニュイな感じの歌い方をする女性ヴォーカルって、結構いますからね。でまた、上手いか下手かと言われたら、答えに窮するところがある。しかし、そんなこと言ったら、松任谷(荒井)由美の歌は上手いか下手か、小野リサのボサノバは上手いか下手かを問うのと同じで、あんまり意味がないような気がするんですよねー。 要するに、雰囲気が出てるかどうか、その雰囲気が好きか嫌いかってことですよ。で、それを言ったら、私はかなり好きな部類ですね。特に8曲目の「You Don't Know What Love Is」なんて、歌詞・曲調とも泣かせてくれます。トランペットの方は、洗練されたウェスト・コースト系のクールな音色。 ちなみに50年代に絶大な人気を誇ったチェット・ベイカーは、その後は麻薬に溺れる転落人生で、60年代は地獄を彷徨っていたらしく、73年に復帰した時は、ほとんど同人物とは思えないほど面変わりをしていたそうです。そして80年代にかけて、(麻薬を買うための小遣い稼ぎなのかどうか)、ヨーロッパで盛んなレコーディング活動をしていたようですが、88年5月13日の金曜日、アムステルダムのホテルの2階からホントに転落して、58年の生涯を閉じることになったとのこと。まさに正統ジャズマンらしい一生だったようです。 ま、そういう彼のめちゃくちゃな人生のストーリーのことも含め、気に入っちゃったなあ、チェット・ベイカー。こうなった以上は、続けて彼の代表作である『チェット・ベイカー・シングス』も買っちゃうか。後期の作品、たとえば『ダイアン』なんてのもいいらしいし。あと、『シングス・アンド・プレイズ』の冒頭の曲と同名の『レッツ・ゲット・ロスト』というドキュメンタリー映画もあるらしく、こいつはチェット・ベイカーの破天荒な転落人生をそのまま映像化して一幅の絵になっているようですから、こちらの方も気になります。 ということで、このところチェットのクールなトランペットと、甘く物憂いヴォーカルに酔いしれているワタクシなのでした。チェット・ベイカー、教授のおすすめ!です。これこれ! ↓チェット・ベイカー・シングス・アンド・プレイズチェット・ベイカー・シングス
August 31, 2006
コメント(4)
-
Hallo2 で気晴らしショッピング!
やれやれ、ようやく終わりましたよ、期末試験の採点。 採点している時、あんまり退屈なんで、学生たちの誤字・誤記を全部書き留めちゃいました。以下、ジャンル分けしながらご紹介してみましょう。(1)音は合っているけど編「精心」・・・「精神」だろ?「牧士」・・・「牧師」って書いてくれないと、感じが出ないなあ!「圧到的」・・ 惜しい!「圧倒的」でしょ。「深重」・・・「慎重」のつもりなんだろうけど、自重し過ぎ!「犠性者」・・ レイプの被害者? 「犠牲者」でしょ?「倒着」・・・ マラソン・ランナーのゴール直後か? 「到着」でしょ?「登着」・・・ 登山かよ!(2)そりゃ無理だろう編「私々」・・・ これで「我々」と読ませるのは、ちょっと・・・。「主強」・・・「主張」だろうなあ・・・。「努る」・・・「怒る」でしょ。「幸い」・・・「辛い」と書いてくれないと、意味が逆だって!(3)なるほど一理ある編「噴怒」・・・「憤怒」よりもっと怒髪天を突く感じ。「混惑」・・・「困惑」よりごちゃごちゃになってます。「衝激」・・・ よほど激しい「衝撃」だったのでしょう。「体欲」・・・ それを言うなら「肉欲」と書いてほしかった・・・。「正常心」・・「平常心」のことか?「豪欲」・・・「強欲」より、もっとゴージャスな感じ? そして、今回私を一番納得させてくれた誤記はと言いますと・・・「自記筆」でーす! これ見た時、ワタクシ、思わず唸りました。たしかに「直筆」以上に、その言わんとするところを漢字に直しているでしょ? 閑話休題。 さてさて、つまらない仕事に数日を捧げた見返りに、今日は午後から「フレイバー」というカフェまで季節限定の「ネクタリン・パイ」を食べに行き、その帰りに「Hallo 2 International」(ハロー・ドゥー・インターナショナル)というところで買い物をしてしまいました。 名古屋にお住まいの方にはお馴染みかも知れませんが、このハロー・ドゥーというのはカフェとブティックとワインショップと雑貨屋とスーパーマーケットの複合体でございます。で、そのスーパーマーケットがちょっと変わっていて、海外から輸入したような食材やら食品が色々と取り揃えてある。東京で言えばちょっと紀伊国屋に似ていますが、それよりも2ランクくらい庶民的かなあ。必ずしも値段の高い高級舶来品ばかりではなく、得体の知れない国産品も沢山置いてあるんですが、高いものであれ、安いものであれ、とにかく他のマーケットではあまり見かけないものばかり。ですから、変わったモノに興味がある人にとっては、ワンダーランド的なお店なんです。 たとえば、精肉コーナーでは、ごく普通の肉の他に「牛タン丸ごと」がでーんとあったり、ラム肉の大きな固まりがあったり、フランス産の鶉だとか、アメリカ産の「ゲーム・ヘン」(多分、野生のキジみたいなものでしょう)まで置いてある。それどころか、中国産の「雀」まで置いてありますからね。「あー、今日は何だか雀が食べたいな」と思ったら、ハロー・ドゥーに来るしかないわけですよ。 で、家内と私も「雀」をしこたま買い込んで・・・というのはウソで、買ったのはお菓子ばっかり。オーストラリアのチョコレートだとか、イタリア産のチョコクッキー、ベルギー産のワッフルなんかを買いまくりました。あとアメリカで人気の粒ミント「アイロニー」とかね。それからキャンベルスープの缶詰があったので、「アスパラガスのクリームスープ」の缶詰も買っちゃった。なんかおいしそうでしょ? あ、それから、ワインショップでマンゴーの果汁を発酵させて作ったスパークリングワインというのも買ってしまいました。デザートワイン的にね。 というわけで、採点作業の終了を舶来菓子の乱れ買いで祝った今日のワタクシだったのでした。名古屋にお住まいの方で、ハロー・ドゥーに行ったことがない方がいらっしゃいましたら、一度お試しになることをおすすめします。ここの駐車場にはジャガーとかベンツとかBMWとかレクサスなんかがよく止まってますけど、気後れしちゃあいけません。かく言う私も、可愛いスバルの紅いR2で粋に乗り付けましたから!
August 30, 2006
コメント(4)
-
アジの受難、そしてその叡知!
昨夜遅く、NHKテレビでものすごい映像を見てしまいました。途中から見たので番組名は分かりませんが、多分「世界遺産」系の番組なんだと思います。 たしか「ココ島」とか言っていたと思いますが、世界のどこかにそういう島があるらしいんですよ。そこは栄養豊富な海水が島にぶつかるところらしく、プランクトンが大量に発生し、それを狙う魚も豊富なんだそうで。でまたここは、それらの豊富な魚を狙う大型の肉食魚、特に鮫の棲息地であって、そりゃもうものすごい数の鮫がうじゃうじゃいるわけ。 で、私が目を見張ったのは、その鮫がアジの群れを食べるシーン。何十匹という鮫がチームワークでアジの大群を一箇所に追い込み、そうやって追い詰めたアジを食べていくんです。イルカやシャチがそれをやるというのなら分かりますが、鮫がそんな賢い芸当を見せるとは・・・。アイツら、案外頭いいのかなあ。見かけ、あんまり頭良さそうには見えないけど・・・。 しかし、鮫だけならまだいいんです。そこへキハダマグロの群れがやってきて、こいつらが鮫の群れをも追い払ってアジに総攻撃をかけるわけ。すごいですよ、キハダマグロの大群がアジの大群に突っ込んで行ってこれをむさぼり食っちゃうんです。すると、おお! あんなに巨大だったアジの大群が、見ている間にどんどん小さくなっていくじゃありませんか! しかも海の上からは海鳥が急降下してきて、水面に逃れたアジをこれまたむさぼるという・・・。このままでは全滅だ! ・・・と思った瞬間、アジの群れが予想外のすごい行動をとるんです。 アジが何をしたと思います? 残りわずかになってしまったアジの一群が、思い切って一匹の鮫にまとわりつき始めたんです。そう、鮫の身体に一群のアジがぴったりと寄り添って泳ぎ始めたわけ。アジにびっしりまわりを囲まれ、鮫は頭しか見えません。 つまり、キハダマグロは鮫が怖いので、鮫の身体にまとわりついているアジの群れには手を出せないんですよ。でまた、鮫の身体にぴったりついて泳いでいるので、鮫にも食われなくて済む。鮫は、身体にまとわりつくアジの群れを嫌がって何度も身をくねらせるのですが、その身体の動きにぴったりとシンクロして泳いでいるアジたちを、どうしても振りほどくことができない・・・。そうやって、アジは鮫とキハダマグロと海鳥の総攻撃から身を守り、全滅することを防いだんです・・・。 素晴らしい・・・。何たる叡知・・・。アジだけに、味なことをやるもんだ・・・。 命を失うか生き延びるかの瀬戸際に、とっさに攻撃者の懐に飛び込んだ、こういうアジの大胆な行動を、何と言えばいいんでしょう。 「虎穴に入らずんば、虎児を得ず」。・・・違うな・・・。 「昨日の敵は、今日の友」。・・・趣旨が違うか・・・。 「飛んで火に入る夏の虫」。・・・逆だ・・・。 「肉を切らせて、骨を断つ」。・・・もう一歩! 「身を捨ててこそ、浮かぶ瀬もあり」。・・・ちょっと近くなってきたか・・・? とっさに思いつきませんが、そんな諺がありませんでしたっけ? とにかくそういう叡知に基づく行動を、アジがとったということにワタクシは非常に感心してしまったのでした。 しかし、そうやって逃げ延びたアジたちを、人間が一網打尽! 干物にして食っちゃうんだろうな・・・。身体を開いて、内臓取り出して、太陽に晒した挙げ句、焼いて食うんですよ。自分の子供がそんな仕打ちをされているのを、もし仮にアジの親が見たとしたら、ショックのあまり卒倒するんじゃないでしょうか。思えば人間も、随分と因果なことをするものでございます。 深夜の、ほんの5分ばかりの映像でしたけど、色々考えさせられたワタクシだったのでした。それにしても大自然っちゅーのは、奥が深い!
August 29, 2006
コメント(0)
-

豆腐屋ジョニー
なんかこのところ、毎日非生産的な仕事(=期末試験の採点)をしているので、楽しみといえば三度の食事、ということになっちゃうんですけど、今日、すごいの食べました。冷や奴なんですけど。 冷や奴といって馬鹿にしちゃあいけやせん。今日食べたのは、「風に吹かれて豆腐屋ジョニー」の豆腐なんすから。 「豆腐屋ジョニー」って、このところすごい人気なんでしょ? 某有名モデルさんが毎日食べているとか、雑誌なんかでも話題になっているようで。となると、豆腐好きの私としては、放ってはおけないじゃないですか。 で、たまたま先日、この「豆腐屋ジョニー」が売っていたので、お、これこれ、ってな感じで買っておいたんです。で、それを食べてみた、と・・・。 モグモグ・・・な、なんじゃ、こりゃ~! こ、これが豆腐か・・・。豆腐って、こういうのだったっけ・・・? とにかく、ものすごくまったりしていてクリーミー。やや胡麻豆腐的な食感といいましょうか。豆乳というより、牛乳か生クリームで作ってあるんじゃないの? と思えるほどのもんです。ひゃー、目からウロコ! これ、冷や奴として食べるより、むしろ杏仁豆腐的に甘くして食べたり、黒蜜なんかをかけてデザートにしてもいいんじゃないんですかね。 ま、オーソドックスな「豆腐」の概念とはちょっと違っているような気もするので、カツブシかけて、あるいは生姜でも乗せて、醤油でつるりと、なんてのが「冷や奴」だと思っている方にはおすすめできませんが、ねっちょり・まったりした食感のものがお好きな方だったら、話のタネに、一度、「豆腐屋ジョニー」を試してみても損はないですよ~。私は、うーん、ま、たまにこういうのがあってもいいかな、という感じです。一度食べたら、少なくとももう一回は食べたくなりますよ。 ということで、「風に吹かれて豆腐屋ジョニー」、教授のおすすめ!です。「風に吹かれて豆腐屋ジョニー」が完成するまでを綴った、お豆腐屋さんの一代記もありますぞ! ↓風に吹かれて豆腐屋ジョニー
August 28, 2006
コメント(8)
-
スーパーにて小さな秋を見つける
昨日の夕方、散歩ついでに家の近くのスーパーまで、家内と買い物に行って来ました。 すると、おお! そこには秋の気配が! まず入り口で目を引くのは、果物の山。もうすでに巨峰やら小粒の葡萄やらが、芳醇な黒紫の山をなしているじゃあーりませんか。その他には桃も大分安くなってきたし、大きなハニーデューメロンが丸ごと1個680円ですって。もちろん梨も山積みですし、お、あそこには早摘みのミカンが、まだ青くて酸っぱそうな堅い実を申し訳なさそうに晒しています。 実りの秋ですなあ・・・。 そして魚売り場では、ついに北海道直送の秋刀魚が出たじゃないですか。冷凍ものじゃありませんよ。いよいよ、私の大好きな秋刀魚の塩焼きが食べられる季節になりました。 しかし、そこのところはぐっと我慢。というのは、当日のメニューはもう既に決まっていたのでね。でも、翌日以降の夕飯用として「豚汁」の材料は買い込みました。ゴボウ、大根、人参、それに蒟蒻と油揚、各種キノコ、それらを豚肉と共に味噌で煮込んだ豚汁は、私の大好物なんですが、真夏に食べるにはちょっと暑苦しい。でも、何だかそれが食べたくなってきたということは、身体が秋を感じてきたということなんでしょう。それに、今我が家には、郡上八幡在住の卒業生から送ってもらった当地の知られざる名品「清水みそ」というのがあるんですが、このコクのある最高の味噌で豚汁なんて作ったら、もう食が進むこと請け合い。ひゃー、楽しみ!! ってな具合で、ちょっとした夕飯の買い物をしただけなんですが、何だか妙に秋の到来を感じてしまったワタクシなのでした。そういえば、もう叢では虫が鳴き始めましたよね。 さて、今日、日曜日の私は、採点作業に追われています。前期期末試験の成績提出が8月末日なんです。試験自体は7月末にやったんですから、もっと早く手を着けろって話ですよね・・・。でもワタクシ、自慢じゃないですけど、試験の採点ほど嫌いなものはないっ! で、延ばし延ばしにしているうちに限界が来たというわけ。もう、5分採点しては台所で麦茶を一口、また5分採点してはネットサーフ、ってな具合で、捗らないこと捗らないこと。こんなのがあと数日続くかと思うと、もう目の前真っ暗。宿題に追われる小学生の気分。 ま、これで給料もらってんだと思って、せいぜい頑張ることにします。・・・が、その前にちょっとテレビを・・・。(「こら~! 仕事しなさい!」← by家内)
August 27, 2006
コメント(6)
-

ウズベキスタンに桜咲く
訳あって『ウズベキスタンの桜』(中山恭子著・KTC中央出版・1800円)という本を読みました。 著者の中山さんというのは元ウズベキスタン大使です。つまりこの本は、中山さんが大使として赴任したウズベキスタンの思い出を語ったものなんですな。 ところで、この中山さんという方ですが、大使を勤めてしまうくらいなんですから、能力の点でも人格の点でも優秀な方なんでしょう。が、文才の点から言いますと、ま、ほとんど素人のレベルと言っていい。この本にしても、見聞きしたことをそのまま素直に書きました、みたいな感じです。ま、申し訳ないですけど、その点から言えば私の鑑賞に耐えるものではありません。別に理由がなければ、私が手にとる本とは思えない・・・。 しかし、実際に読んでみてどうかと言いますと、これが結構面白い。というのは、中山大使がウズベキスタンに赴任した直後、大変な事件が起き、この本はその事件の顛末を語っているからです。運の悪いことに、中山さんが1999年8月にこの国に赴任したそのすぐ後に、JICAの職員として隣国キルギスに赴任していた日本人技師4人が当地の反政府ゲリラに拉致されるという事件が起きるんですね。で、赴任早々、中山さんはじめ、ウズベキスタン大使館のスタッフが大騒動に巻き込まれてしまうわけ。 でも、キルギスで起きた事件なんだから、何もウズベキスタン大使(タジキスタン大使を兼任)である中山さんがどうこうするものではないような気がしますが、そうじゃないんです。というのも、日本人を拉致した犯行グループは、もとウズベキスタンから出て、タジキスタンで活動していたイスラム原理主義者たちだったからで、こういう連中は反政府活動グループですから、国境近くの砂漠の山岳地帯を常時移動しているので、たまたま拉致したのがキルギス領内だったからといって、キルギスとは何のつながりもないんです。ですから、犯行グループと接触したり、交渉するには、どうしてもウズベキスタンとタジキスタンの協力が必要だった。 ところがですね。ここで日本の外務省の馬鹿さ加減が露呈するわけですが、我が国のアホな外務省は、この事件の解決をキルギス政府に丸投げするんです。で、中山大使らがいくら本省に掛け合って、「キルギス政府に任せたって解決しません」と進言しても聞く耳もたず、「お前らは近くにいるんだから、せいぜい情報収集でもやっとけ」と言うばかり。 というわけで、中山大使をはじめ、ウズベキスタン大使館のスタッフは、外務省の命令に背いて日本人拉致被害者の救出にあたるしかなかった。昼間は通常の大使館業務をこなし、その後で寝る間を削って犯人グループとの折衝をしたわけです。そして、その救出活動にはウズベキスタン大統領、タジキスタン大統領も非常に大きな貢献をしてくれた。 しかし、犯行グループも疑心暗鬼になっていますから、そう簡単には交渉のテーブルについてくれないわけですよ。もちろんお金で動く連中ではないですし。ですから、そこは「や○ざ」の親分同士の話し合いみたいな感じで、義理と人情で必死の説得を連日連夜にわたって行うわけ。 それで、事件発生から2ヶ月にわたる奮闘の末、ようやく被害者の解放がなされたんです。その影に、中山大使たちのそんなご苦労があったなんて、我々日本にいる日本人は、知る由もないわけですが。 でまた、ここでさらに頭に来るのは、事件解決後の日本の外務省の対応です。日本人拉致被害者はタジキスタンの山中で行われたんですけど、事件の解決をキルギス政府に委任した手前、タジキスタンで解放されました、じゃカッコがつかないってんで、なんとわざわざ解放された被害者たちを徒歩とヘリでキルギスまで移動させ、そこで正式に解放されたことにしたんですって。体面、体面。 で、もちろん拉致被害者を救出するために死ぬような思いで働いたウズベキスタン大使館のスタッフには、なーんの報償もなしですわ。もちろん、誉められようとして一生懸命やったわけではないでしょうけど、それにしても酷い話です。 すごいでしょ、日本の外務省の馬鹿さ加減。現地で一番事情が分かっている人たちの話を絶対に聞かないってんだから、もう常識を超えた馬鹿じゃないですか・・・。ま、本省がそんなでありながら、現地のスタッフは正義感と使命感に燃えて、たとえ自分たちが罰せられようと、被害者救出のために骨身を削って努力した、というところが、せめてもの救いですが。 ってな感じで、この本の前半は日本人拉致の顛末について語っており、「はぁ~、そんなことがあったんですか~」の連続で、それはそれで面白いのですが、後半はまたガラっと趣が変わって、日本人にはあまり馴染みのないウズベキスタンという国のお国柄について、楽しい話を読むことができます。正直な話、私なんぞウズベキスタンがどの辺にある国かすら、明確には知りませんでしたからね。 ただ、ウズベキスタンについて知らないのは日本人の側の話であって、ウズベキスタンの人は日本のことをよく知っています。というのは、第2次大戦後、ロシアに抑留された日本人が遠く中央アジアのウズベキスタンまで運ばれ、そこで強制労働させられたからです。ですから今でもウズベキスタンの各地に日本人が作った橋、日本人が作った道路、日本人が作った建物が残っているんですな。そしてそれが数十年経った今でも立派に使われている。当時を知るウズベキスタンの人々は、日本人労働者がいかに勤勉で、いかに有能で、いかに清潔で、いかに礼儀正しかったかをよく覚えていて、今でも彼らの墓を大事に守っていてくれるのだそうです。 で、そんな日本人とウズベキスタンの人々の交流の証として、中山さんはウズベキスタンに桜を植えようと思いつくんですな。死ぬ前にもう一度日本の桜が見たいといって、彼の地で死んでいった日本人たちの鎮魂の意味を込めて。本書が『ウズベキスタンの桜』となっているのは、そういう意味です。 最初に「著者に文才がない」なんていいましたけど、実際にこの本を読んでみて、色々と勉強になりました。それに中山さんの話を読むと、ウズベキスタンをはじめとする中央アジア諸国って、いいところだなと思います。日本も草の根レベルではこういう国々と交際を続けているようですけど、もっと大規模に国同士の交流を図ればいいのに。なんで日本は、日本のことに文句ばかりつける近隣の国のことばかり気にしているのか、私にはさっぱり分かりません。世界は広い。親日の国なんて、世界中にいくらでもあります。そういう親日の国々と、気持ちのいい交際をしたらいいじゃないですか。 というわけで、そんな親日の国・ウズベキスタンにもっと興味を持ったらいいなとの希望を込め、この本、教授のおすすめ!です。これこれ! ↓ウズベキスタンの桜
August 26, 2006
コメント(6)
-
『サマラで会おう』を読む
「アメリカ大衆小説を読む」キャンペーンを自分勝手に継続中ですが、昨夜、ジョン・オハラ(John O'Hara)の『サマラで会おう』(Appointment in Samarra)を読了しましたー。 これ、アメリカ東部の田舎町Gibbsville というところに住む住民たちの物語なんです。時代設定は1930年のクリスマス。書かれたのが1934年ですから、ほぼ同時代の話。 で、最初のうちはこの町の住人がわらわらと登場し、それぞれ勝手なことをやったり言ったりしているので、ははーん、と思うわけ。アメリカにはこんな感じの「町小説」が多いんです。町の住民のそれぞれの生活を描き、またそういう住民同士の関わり合いを描くことで、その時代の一つの町の生活とその因習を描いていく、みたいな小説が、ね。前に読んだ『ペイトン・プレイス』もそんな感じでしたし。『サマラで会おう』も、そういう小説なんだろうなと。 でも、そのうちに一人の男に焦点が当たってくるんです。ジュリアン・イングリッシュという30歳くらいの男。彼の親父さんは医者で、そのためにジュリアンもこの町のハイソな人々の仲間ではあるんですが、彼自身は家業を継がず、キャデラックのディーラーを経営している。結婚して4年になる妻キャロラインがいますが、子供はなし。 で、物語が動くのは、クリスマス前夜、ジュリアンが町の上流階級の連中で開いているクラブで過ごしていた時に起こるある事件がきっかけとなります。やや深酒をする質のジュリアンが、羽振りのいいビジネスマンであるアイルランド系の男、ハリー・ライリーのおしゃべりにたまりかね、彼にコップに入った酒をいきなりぶっかけてしまうんです。でまたコップに入っていた氷の固まりがハリーの目に当たって、ハリーは目のあたりを黒く腫らしてしまうことに。 ジュリアンがハリーに酒をぶっかけたのは、酔った上での突発的な狼藉ではあるんですが、しかし小説が進むに連れ、それだけではない、ということも分かってくるんですね。というのも、ジュリアンとハリーは、かつてキャロラインをめぐってライバル関係にあったことがあり、結局ジュリアンが彼女を娶ったものの、ジュリアンの心中のどこかに、ハリーとキャロラインの関係を疑うような妄想があるんですな。それが一つ。また前の夏、ディーラーの経営が苦しかったことから、ジュリアンはハリーから相当な額の金を借りているんですが、そういうことも内心面白くなく思っているところがある。ですから、ジュリアンの突発的に見える狼藉も、決して理由がないわけではないんです。 しかし、この「酒ぶっかけ事件」は高いものにつくんですな。何せ小さな町ですから、ジュリアンとハリーの喧嘩はあっという間に町中に知れ渡ってしまいますし、クラブの人たちの中には、酒をぶっかけられたハリーの肩をもって、ジュリアン苛めを始める連中も出てきます。クラブは、もはやジュリアンにとって居心地のいい場所ではなくなってしまうんですね。 また相手も悪かった。ハリーは、一度怒り出したら、そう簡単に人を許す質の人間ではないし、彼が復讐をしようと思えば、いくらでも手段はある。しかもハリーがアイルランド人でカトリックの信仰を持っていることが、事情をより複雑なものにしてしまったんですな。ギブズビルでは、プロテスタントとカトリックの勢力が拮抗しているのですが、カトリックの団結というのは強く、ジュリアンのハリーに対する狼藉を、カトリック世界への挑戦と受け取る人々も多いんです。で、その影響からか、たとえばジュリアンのところからキャデラックを買う予定になっていたとあるカトリック教徒の人が、急にその約束を反故にして、他のディーラーからフォードを買ってしまう、なんてことも起きてくる。 それだけじゃありません。この事件がきっかけで、ジュリアンとキャロラインの夫婦の間にも亀裂が生じてきます。ま、夫が町の住民から「村八分」みたいな状態に置かれるわけですから、キャロラインとしてもつらい立場なわけですよ。 と言って、じゃあこの夫婦の愛が冷めているのか、というと、そういうわけじゃないんです。もちろんジュリアンはキャロラインを、キャロラインはジュリアンを、十分に愛している。しかし、こういう事件が起こって、不愉快な状況が続く中で、そういう互いの愛情が行き違いになるんです。そりゃ、どんなに仲の良い夫婦だって、4年も夫婦をやっていれば不満なところも出てくるわけで、そういう積もり積もったものが、この事件をきっかけに噴出してしまうんですな。 で、そういう不安定な状況の中で、ジュリアンはまた別なパーティーに出席し、そこでも粗相をしてしまうわけ。ヘベレケに酔ったジュリアンは、キャロラインや友人たちの制止も無視し、別なテーブルにいた場末の歌姫に声をかけ、彼女と踊ったり、連れ立って外へ出たりしてしまうんです。ところがこの歌姫というのが、実はギブズビルのギャングの親玉で、この町で酒類の闇販売を一手に引き受けているエド・チャーニーの情婦だったというんですから、事態は非常にまずいことに。自分の女に手を出したということで、エドが激怒しているという噂も伝わってきます。 しかし、そんなことよりももっと悪いのは、妻の目の前で玄人の女といちゃいちゃしたことでしょう。この一事で、彼は妻の友人たちからも総スカンを喰うことになるばかりでなく、キャロラインは実家に戻ってしまいます。 ま、ジュリアンというのは、結局、どこか本質的に自虐的なところがあるのでしょうな。自分が愛しやまない妻や、自分が好きだった友人たちから背を向けられるようなことを、やらずにはいられないようなところがある。そういう自暴自棄なところがあるんですね。事実、その八方塞がりの状況の中で、まだ見知らぬ若い女性をかどわかそうとしてみたりするんです。しかし、そういう状況にも限度があるわけで、酒の力で憂いを晴らそうとしたジュリアンは、泥酔した状態でガレージの車を動かそうとし、一酸化炭素中毒で悲惨な最後を遂げてしまう。 小説の主なストーリーを話せば、以上のようなことになるわけですが、もちろんこの小説には脇筋というのが沢山あって、それもまた面白い。たとえばどんどん悲惨な状況に陥っていくジュリアンを語りながら、彼の子供時代の話とか、キャロラインとの馴れ初めなんかも描かれていますし、またキャロラインの過去というのも描かれます。またジュリアンの親父さん話というのも面白くて、彼は親父さんが銀行の金を横領して自殺してしまうというつらい過去を持っているんです。で、そういう親をもった子供として、後ろ指さされながら苦学して医学の道を修め、奮闘努力して再び町の住民たちの尊敬を勝ち得ることができたんですな。しかし、彼の息子のジュリアンは自分の跡を継ぐこともなく、しかも下らないことで頓死(町ではジュリアンの死を自殺扱いする)してしまうわけで、一体自分の苦労は何だったのか、という思いに耐えなくてはならない。そういうドラマもあるわけですよ。 またこの小説の中で、ジュリアンとキャロライン夫妻の他にもう一組、ルーサーとイルマという夫婦が描かれるんですが、これもなかなか面白い。こちらの夫婦はジュリアンたちとは違って、決して豊かな一家ではないんです。ルーサーに至っては、年齢はジュリアンより10歳も年上なのに、仕事上ではジュリアンの下で、キャデラックのセールスマンをやっている。しかし、彼らはとても堅実で、自分たちの分を弁えながら、波風立てずに暮らしている。で、この夫婦が、いわばジュリアン&キャロライン夫妻と対照をなしているわけ。心の持ちようではこういう生き方だってできたのに、ということなんでしょうな。そして、最後の最後では、なんとなくこのルーサーが出世するような書き方がなされていて、ちょうどシェイクスピアの『ハムレット』みたいに、腐敗したものが去り、健康的なものがあとを継ぐ、という形になっています。典型的な悲劇の終わり方と言いましょうか。 ま、『サマラで会おう』というのは、ざっとこんな感じの小説です。英語ですが、使われている単語は易しいのですが、文体上の特徴というのか、時々構文が取りにくい部分があり、決して読み易いものではありません。ざっと読もうとすると、時々、意味がとれなかったりする。ですが、アレ?と思って2度読みすると、今度は非常によく分かる。不思議な文章ですね。 でも、面白いことは面白いです。さすが、先頃ランダム・ハウスが選んだ「英語で書かれた小説ベスト100」の中で、22位になっただけのことはあります。直前に読んだ『ダヴィンチ・コード』みたいな小説は、一度読んだらもうおしまいですが、『サマラで会おう』は、再読に十分耐えると思います。 残念ながら、ジョン・オハラの作品というのは、現在、ほとんど邦訳がありません。ちょっと前に講談社文庫で、『親友ジョーイ』という作品が「ジョン・オハ」の作品として出ていたようですが、これも既に絶版。もっとも、アメリカにおいてすら、50年、60年前のベストセラーなんて、絶版になっているものが多いですから、仕方がないとは思いますが、これだけの作家の作品が手軽に読めないというのは、残念なことではありますね。ということで、英語に自信のある方が対象になってしまいますが、ジョン・オハラの『サマラで会おう』、教授のおすすめ!です。 あ、一つ言い忘れましたが、この小説のタイトルである『サマラで会おう』というのが何を意味するのか、私には分かりませんでした。サマラなんて地名は出て来ないし、ましてやサマラで会う約束なんて、ぜーんぜん出てきません。これ、何か別に意味があるのでしょうか。ご存じの方、いらっしゃいましたら、ご教示下さい。
August 25, 2006
コメント(4)
-
タワーレコードの危機
海の向こうではタワーレコードが倒産っちゅー話じゃありませんか。日本のタワーレコードは、どうやらまだ大丈夫らしいですが・・・。 ふーむ。レコード屋さん(「CDショップ」という名称がとっさに出て来ない世代なもので・・・)も、経営が厳しいんですかねぇ。私にとっては、本屋さんと同様、入り浸っていたい場所の一つなんですが。 しかし、もはやCDを買って音楽を聴く、という時代じゃないんでしょうな。新聞にも、アップル社の iPod が普及したことが、タワーレコードをはじめとするCDショップに大きな打撃を与えている、というようなことが書いてありましたっけ。今は好きな曲、聴きたい曲をネットでダウンロードするのが主流なのかな。 だけど、私なんぞはやっぱり、音楽は物理的な媒体を通じて聴きたい方だなあ。第一、ジャケットの善し悪しというのだって、重要なファクターじゃないですか。LPからCDになった時に、ジャケットの価値は大幅に下落したとはいえ、やはりジャケットはそのアルバムの顔ですからね。 それに、これは前にも言いましたけど、曲ってーのは、他の曲とのコンテクストの中で味わうべきもんじゃないの? そんな「つまみ食い」するみたいに、このアーティストのこの曲、あのアーティストのあの曲、なんて具合にバラバラに聴いていたら、自分が何を聴いているのか、分からなくならないのかな? ま、ぐたぐた言ったところで、こういうのは老いの繰り言なのかも知れませんが、アーティストとリスナーをつなぐ昔からの媒体であったレコード屋さんが無くなっていくというのは、寂しいものでございます。 でもね、レコード屋さんも生き残りのためには、いろいろ工夫がいると思うんですよね。たとえば出店の場所。人がどういう場合にレコード屋に入りたくなるかをもっと研究して、どういう場所に出店すればいいか、もっと考えなくちゃ。私思うに、レコード屋さんって人と待ち合わせしたりする時に便利じゃないですか。もしレコード屋さんで待ち合わせをするのであれば、相手が多少遅くなっても、むしろ嬉しいくらいでしょ? だから、そういう待ち合わせ場所になるようなところに出店すればいいと思うんですよね。 たとえば、ここ中部地方でもあちこちに郊外型アウトレットが作られていますが、その種のアウトレット・ショッピングモールに、何故かレコードショップがないんですよね。そういうところに出店しておけば、奥さんや子供が買い物をしている間、お父さんは暇が潰せるじゃないですか。 それから、品揃えも重要です。たとえばその地方に一店でもいいから、ものすごくマニアックなジャズ専門のCDショップがあれば、たとえそんなに大きな店でなくても、相当な集客力があると思うんです。どのジャンルも皆カバーするつもりで、結局欲しいCDが置いてない、なんて店ばかりだし。個性化を図らなくっちゃ。 でも一番改善して欲しいのは、「試聴システム」の早期導入です。アメリカの進んだCDショップでは、店においてあるすべてのCDが試聴できます。試聴機の前に持って行って、バーコードをかざせばそれでOK。そのCDに入っている全曲を聴くことができるんです。このシステム、いいですよ~。これさえあれば、買ってみてがっかり、ということがなくなりますからね。日本のCDショップみたいに、店おすすめの2、3枚のCDだけが試聴できる、なんてケチ臭いことやっていると、ネットに負けるのは目に見えていますゾ。 ま、時代の流れで、ビジネスにも流行り廃りはあるでしょうが、私のようなオールドタイマーのためにも、レコード屋さんには健闘してもらいたいです。あ、そういえば、プリンスの新譜がたしか昨日発売じゃなかったかしら。おーし、食後にでも夜のドライブでもして、近所のレコード屋さんにでも、行ってみましょうかね。
August 24, 2006
コメント(4)
-
『ノーラ・ロバーツ 愛の世界』を読む
今朝の新聞を読んでいたら、名古屋市が行っている「名古屋城本丸御殿再建」の話題が出ていました。それによると、この前の戦争で焼けた名古屋城本丸御殿を15年計画で再建することになっていて、2010年に一部完成を目指しているのだとか。 しかし、名古屋市もお馬鹿ですなぁ・・・。いくら名古屋は景気がいいって言ったって、そんなもの再建してどうするんでしょうか。ちなみに、総工費150億円のうち、50億円は市民からの寄付で賄う予定らしいですけど、まだ10分の1程度しか集まっていないらしい。そりゃ、そうでしょ。 あちこちの地方自治体で大層な音楽堂やら観光施設作っちゃって、後で経営が破綻し、そのツケが市民の肩に税金という形でのしかかっているというのに、そういう報道を見ながら、「さてと。じゃ、うちは本丸御殿で行こう!」と決定できる名古屋市のお偉いさんたちの頭の中身が見てみたい。 でも、分かるなあ。うちの大学のお偉いさんたち見てても、まあよくこれだけ愚かなことを思いつくな、ということをやりますもんね。結局、お金の使い方を知っている人と、それを使う権限のある人がいつも違う、ということなんでしょうな。もちろん、お金を出す人と使う人が違う、という側面もあるし。そういや、むかし全国の市町村に「ふるさと創生基金」が配られた時、その1億円で純金のマグロかなんか作っちゃった町だか村だかがありましたっけ。名古屋市の本丸御殿だって、その純金のマグロと本質的には大差ないんじゃないか知らん。 さて、話題は変わりますが。昨日、市の図書館で借りてきた『ノーラ・ロバーツ 愛の世界』(扶桑社)という本を読了しましたー。 「ノーラ・ロバーツ? 誰、それ?」なーんておっしゃる御仁は、愛の世界を、いや、ロマンスの世界を知らない人ですゾ。このジャンルでは知らない人のない人気作家さんで、彼女が四半世紀にわたるロマンス作家としてのキャリアの中で書いたロマンスは百数十冊。それらは世界25ヶ国で翻訳され、そのトータルの売り上げは1億5千万部! 1億5千万部ですよ。百万部のベストセラーを150冊出した、っていうことですから、もの凄いと言わざるを得ません。もちろん、日本でももの凄い人気で、その作品のほとんどが翻訳されています。 ま、それだけ売れていながら、たとえばスティーヴン・キングといった作家より知名度が低いのは、彼女が基本的にロマンス作家だからです。ロマンスというのは、ほとんど女性の間でしか読まれていませんからね。それだけ特殊なジャンルなんですな。ま、かくいう私だって、縁あってこのジャンルの研究をしていなければ、ノーラ・ロバーツの何たるかなんて、一生知らないで終わったことでしょうけどね。 で、そのロマンス界の大御所、ノーラ・ロバーツの公式なガイド本がこの『ノーラ・ロバーツ 愛の世界』なんですけど、この本を読んだら、ノーラ・ロバーツがいかに典型的なロマンス作家であるかってことがよく分かりました。 要するに、はじめは彼女も単なる一ロマンスファンだったんですね。特に文学的な素養があったわけでもない。普通に結婚して、主婦になって、子供が二人生まれて・・・。 でも、そんな彼女に運命的な日がやってくるんです。1979年のある冬の日。その日は雪が降っていて、外で遊ぶことのできない二人の小さな息子たちと家の中で嫌になるほどゲームをしていた彼女は、このままじゃ頭がおかしくなる! という思いと共に、リング式のノートを取り出すや、ロマンスを書き始めたんですな。書き上げた作品は、最低の出来だったそうです。でも、彼女は書くのを止めず、続けざまに6作品を書いてみた。 そして7作目の『アデリアは今』というのを、当時出来たばかりのロマンス叢書である「シルエット・ロマンス」に送って見たんですな。そしたら、それが編集者の目に止まり、本になってしまった。 それから後は書いて書いて書きまくったんです。それはもう、編集者の方が音を上げるくらい書く。もちろん、ノーラ・ロバーツといえども「果たして次の作品は書けるだろうか」という不安に駆られることもあるようですが、書けるか書けないかは実際に書いてみるしか分からないわけで、それで実際に書いてみると、これが書けてしまう。で、その時点でまた「次回作は書けるのかしら」という不安に駆られ、実際に書いてみるとやっぱり書けてしまう。 でまた、書くことについて言えば彼女は完全なワーカホリックで、一日7時間とか8時間とか平気でぶっ続けで書いてしまうらしい。「なぜそんなに書くのか」と言えば、「それが私の仕事だから」。「壁にぶちあたることはないんですか」と問われると、「配管工が仕事の壁にぶちあたることなんかあるかしら?」と答えています。書くのも配管工事をするのも、仕事であることには変わらないのであって、配管工が依頼された配管工事を黙々とこなすのと同じように、彼女も黙々と白い紙を文字で埋めていく。ノーラ・ロバーツにとって、ロマンスを書くということは、もはやそういう世界らしい。 でもってじゃんじゃん書くロマンスが世界中でじゃんじゃん売れるわけですから、彼女は相当なお金持ちであるわけで、事実、彼女は相当なショッピング魔なんだそうです。家の地下にはもちろんプールがあり、庭にはBMWのクーペとレンジローバーが止まっている。でも、常人離れした購買力を持ちながら、彼女はいつも謙虚。ファンが彼女の姿を認めれば、ニッコリ笑ってサインに応じ、しばしおしゃべりを楽しむほどファンを大切にすることでも知られています。作家仲間からの評判も上々ですし、出版各社の担当編集者はこぞって彼女の人柄を絶賛している。 ま、彼女の成功自体が、夢のようなシンデレラ物語ですよね。プライベートな方面に関しても、一度離婚を経験している彼女は、たまたま彼女の家の書棚を作りつけにきた大工さんと恋に落ち、再婚して幸福な結婚生活を送っているようですし。 とまあ、今日はそんなノーラ・ロバーツのサクセス・ストーリーを読んで、私の次の本のためのネタをしこたま仕入れることが出来たのでした。やっぱ、昨日図書館デビューしておいて良かった!
August 23, 2006
コメント(4)
-
図書館デビュー!
我が家の愛車No.2、「紅子」ことスバルのR2のエンジンの掛かりが悪くなってしまいました。多分、バッテリーが弱っているのでしょう。ま、このところの暑さで、エアコン・フル稼働だったもんな・・・。 ということで、早速ディーラーに修理に出すことにしたのですが、その前に立ち寄るところが。最近、私が気になっていたところなんですけど、それはどこかと言いますと・・・、 市立図書館でーす! 市立図書館と言っても、まだ我が街が「○○市」ではなく「○○郡××町」だった頃からのものですから、あまり大きくはないんです。でも、先日家内がここで貸し出しカードを発行してもらい、京極ものをはじめ、あれこれ借り出しては楽しんでいるのを見て、こいつは私も利用しなくちゃそんだなと思ったわけ。 ま、私は職業柄、本を読むのが仕事みたいなものですが、逆にそのプロ意識が邪魔して、地元の小さな図書館のことなんぞ、今まで気にしてなかったんです。でも、よく考えてみれば、そんなヘンテコなプライドなんて愚の骨頂ですよね。利用できるものは何でも利用した方がいいに決まってます。しかも、市民である限りタダで利用できるんですから。 というわけで、今日は家内に手を引かれてこの図書館に足を踏み入れたのですが、夏休みであるせいか、小さな図書館の割に大盛況です。見ていると、多くの人が貸し出し限度の10冊を借りる気らしく、沢山の本を小脇に抱えています。うーん、読書人口が減っていると言われながら、やっぱり本好きの人というのはどこにもいるんだなあ。 でもって本の並びを見てみると、これがまた馬鹿にしたもんじゃないんですわ。案外専門的な本が並んでいたりしますしね。アレ? 私が共著で書いたアメリカ文学の作品ガイドも置いてあるじゃないの。感心、感心。こっそりサインしちゃおうかな・・・(ウソ)。 で、今日のところは一冊だけ、仕事がらみで参考になりそうな本を家内の貸し出しカードで借りてもらうことにし、その間、私も自分用の貸し出しカードを発行してもらうことにしました。免許証のような身分証明があれば、ものの5分で発行してもらえます。わーい、これで私もここで本を借り出すことができるゾ。ちなみに家内は、ウィリキー・コリンズ全集の第1巻『バジル』を借りていました。『月長石』や『白衣の女』で名高いウィルキー・コリンズは、私の大のお気に入りでもあるので、家内が読み終わったら私も読ませてもらおうかな。おお、何だか楽しくなってきた! さて、かくして無事図書館デビューを果たした私は、次にスバル系のディーラーに向かいました。紅子の故郷でございます。 で、メカニックの方に見てもらうと、やはりバッテリーがほとんど死にかけているとのこと。バッテリーばかりは修理してどうなるもんでもないので、もちろん交換です。やれやれ、またお金がかかるなあ。 と思ったら、料金はたったの4200円でした。保証期間に間に合ったので、工賃がタダというのも効いていますが、それにしても軽自動車のバッテリーってそんなに安いの? 当然1万円とか2万円とかするものと思っていましたが・・・。で、聞いてみたら、やっぱり軽自動車のバッテリーは容量もサイズも小さいので、そんなもんなのだそうです。ただ、普通車のバッテリーに比べれば寿命もやや短く、2年目くらいから怪しくなるのがあるのだとか。ま、それは仕方がないですね。 で、そんなこんなで新しいバッテリーに替えたところ、セルモーター始動一発、元気よくエンジンが掛かるようになりました。うーむ、やっぱりこうでなくちゃ。 てなわけで、今日は図書館デビュー&紅子のバッテリー交換で、なんとなく私の気分もリフレッシュしてしまったのでした。今日も、いい日だ!
August 22, 2006
コメント(8)
-

京極夏彦『魍魎の匣』を読む
家内が市の図書館から借りて読んでいた京極夏彦の『魍魎の匣』ですが、面白そうだったのでつい私も読んでしまいました。 たいていの人は、私を見るとマニアックな推理小説ファンだろうと思うらしいのですが、これがさにあらず。シャーロック・ホームズ以外の推理小説というのは受け付けない体質で、アガサ・クリスティーやエラリー・クイーンといったあたりでもまるで読めないし、読んだこともない、という男なんです。ましてや日本の推理小説だとかミステリーなんかになると、まるで知識がない。辛うじて読んだことがあるのは、江戸川乱歩の『孤島の鬼』と、「屋根裏の散歩者」「人間椅子」くらいなもんですかね・・・。 ですから京極夏彦の何たるかなんて、知る由もないわけ。 でも、読んでみたら、案外読まされましたね・・・。『魍魎の匣』ってのは650ページほどもある大作なんですけど、ペロッと読み切っちゃった。 ま、題材もね、人間の手足を切って、首と胴体だけ箱に詰めちゃう、っていうような猟奇殺人事件から話がスタートしますから、そのおどろおどろしさに対する怖いもの見たさもあるんです。で、その後は遺産相続をめぐるごたごたあり、思春期の少女たちの心の綾あり、似非宗教詐欺あり、近親相姦あり、狂気の作家あり、マッドドクターあり、と、まあ何でもありなんですな。 で、これだけ盛り沢山な内容を、「箱」、あるいは「箱につまった魍魎」というテーマに、見事に収斂させているというところがすごい。 しかも、事件に係わる登場人物それぞれのキャラクターが面白いんだなー。純情一途な熱血刑事・木場、膨大な知識と論理で事件の背後を読む陰陽師にして古本屋の主人でもある京極堂、人の過去が見えてしまうという特殊能力を持った妙な探偵・榎木津、カストリ雑誌の編集者にして軽薄な切れ者・鳥口、そして全体の語り手でありながら、いつも事件と友人たちに振り回されてばかりの売れない作家・関口。こういう連中が、それぞれの能力とキャラクターを発揮しつつ、互いに協力して事件の真相に迫っていくというところがいい。特に、何を言い出すか分からない不思議なキャラクターの榎木津探偵、好きだなあ! あと、これはマイナーな登場人物ですが、人体にメスを入れるのが何より好きな里村という医者なんかも、いい味出してます。 私が読んだ講談社ノベルズ版の出版年を見ると、1995年となっていますが、ということは、これを書いた時、京極夏彦は30歳そこそこだったわけですよね。で、この「京極堂シリーズ」には前作があるので、それを書いた時には彼は20代だったのかも知れない。そう考えると、大した構想力と言わざるを得ませんなあ。『魍魎の匣』にしても、これを書くには、小説の構想力の他に、扱うテーマに係わる膨大な知識が必要だったはずで、そういう点から考えてもこれを30歳そこそこで書き上げた京極夏彦って、すごいもんだなあと思います。 とにかく、この『魍魎の匣』という作品、そのおどろおどろしさから言っても、夏の読書にはぴったりじゃないでしょうか。教授のおすすめ! ということにしておきましょう。これこれ! ↓魍魎の匣 さて、話は変わりますが、今日は10年ほど前に卒業した卒業生のMさんとFさんが、それぞれお子さんを連れて大学に遊びに来てくれました。うちの科の5期生ですから、先日結婚したM君たちの二つ上の世代ですな。二人とも、英語の先生なんですが、今は産休をとって休んでいる最中なのだとか。 しかし、卒業して何年経っても、時々大学に顔を出してくれる卒業生ってのは、可愛いもんですなー。ましてや、子連れで戻ってきてくれる卒業生なんて最高ですわ。 で、二人から色々な話を聞きましたけれど、子育て真っ最中の二人ですから、話題の中心は子育てのことになります。でも、大変は大変そうですが、それでも話を聞いたり、話をしながら子供をあやしたりしているのを見ると、おお、なかなか上手にお母さん業をこなしているではないの! という感じがして微笑ましい。大体、「苦労」と言っても「子育ての苦労」というのは、笑顔で話せるところがいいですよね。 しかも、そういう子育ての大変な時期でありながら、そこはそれ二人とも英語の教師ですから、職場を離れていても英語力が落ちないよう、ちゃんと外国人について英語を習っていたりして、感心させられます。 で、MさんFさんのお子さんたちがまた可愛いんだ。Mさんのところは2歳の坊やと5ヶ月の坊や、Fさんのところは2歳のお嬢ちゃんですけど、大人たちが話している間、静かに遊んでいていい子でしたよ。5ヶ月の坊やは、ぐんぐんミルクを飲んでましたけど、私のことをじーーーーっと見て時々笑うんです。それからFさんのお嬢ちゃんですが、車輪つきの椅子に座った私が彼女を膝に抱いてトコトコ部屋を動き回ってやると楽しそうにしていました。 ぐにゃっとして暖かい子供の身体を膝に乗っけていると、甥や姪が小さかった頃、よく遊んでやったことが思い出されて、懐かしかったなあ。 前にも書きましたが、私が本気で子供をあやすとなると、それこそ神がかり的に上手にやるので、すっかり私に魅了された子供は「親をとるか、釈迦楽先生をとるか」で本気で悩むほどになります。今日は、まだ本腰を入れてあやしていないので、すんなり帰りましたが・・・。MさんFさんには、また子供を連れて遊びに来てもらいたいですね。 ということで、今日は巣立った卒業生たちがお子さんを連れて大学に戻ってきてくれて、とても幸福な一日だったのでありました。今日も、いい日だ!
August 21, 2006
コメント(10)
-
結婚式、出席してきました!
今日のこと、というより昨日のことなんですが、ブログにも書き込んだように、行って来ましたよ教え子の結婚式&披露宴。 披露宴が行われたのは、名古屋駅前の結婚式場「クレール」、式の方は道路を隔てたところにある教会(多分、結婚式用(?)の教会だと思いますが・・・)で行われました。 さて、昨日紹介した私の教え子M君は中学校の英語の先生をしています。ということで、自由参加の結婚式の方ではM君が教えている中学生が30人ほども押しかけてきて、えらく賑やかなものになりました。私が中学生の頃は、先生が結婚するからといって式に押しかけるなんてことはなかったですけど、今は随分違いますね。善きにつけ悪しきにつけ、教師と生徒の関係が友達のようになってしまっているんでしょう。 で、その式の方は「キリスト教式」ってんですか? 賛美歌斉唱の後聖書からの朗読があり、牧師の説教があり、結婚の意志の確認があり、指輪の交換やら誓いのキスやらがあり、「主の祈り」の朗読があり、牧師の祝福があり、最後に賛美歌斉唱がもう一度あって新郎新婦退場、みたいな感じ。 ちなみに私、子供の頃はキリスト教系の学校に育った上、聖歌隊にも所属していたので、賛美歌はお手のもの。キリスト教徒にとって一番重要な祈りである「主の祈り」もそらで言えるという似非クリスチャンぶりでございます。 さて、式が滞りなく済むと、今度はお隣の式場で披露宴。昨日のはいきなり口取りの八寸が出て、白身魚のソテーが出て、蟹真薯が出て、フィレステーキが出て、稲庭うどんが出る、といった和洋折衷のご馳走でした。でも、どれもおいしかったですー。 ところでその披露宴ですが、主賓の挨拶があり、乾杯があり、さあご馳走を楽しもうというところで面白い趣向がありました。司会のお姉さんが「さあ! 皆様ご歓談の上、お食事をお楽しみ下さい! それから今日はフリードリンク制ですので、皆さんお好きな飲み物を係のものにどんどん注文なさって下さい」などとアナウンスした時のこと。いきなり新郎のM君がマイクをとると、「すみません、フリードリンクの中に生ビールは含まれますか?」と言い出したんです。アレ? 変なこと言い出したぞ? で、お姉さんも困ってしまって、「あ、あのー、申し訳ございません、ビールは既にテーブルに配りました瓶ビールしかないんですが・・・」などとオロオロして答えるばかり。すると新郎はさらに追い打ちをかけるように、「生ビールのないフリードリンクなんて、フリードリンクじゃないですよねえ・・・」などと難癖をつけ始めたんです。おいおい、お前、何言ってるんだよ。そういうことは事前に打ち合わせとけよ・・・。 しかし、このヘンテコなやりとりは、余興のうちだったのでした。オロオロしていた司会のお姉さんがにわかに元気づいたかと思うと、「ハーイ、皆様、ということで新郎のMさんが、これから急遽ビールマンに変身です!!」と言い出し、M君もタキシードをずばっと脱ぎ捨てると専用のビールタンクをヨイコラショと背負い、新婦と共にテーブルを回って生ビールを注いで回るというパフォーマンス! 学生時代から水泳と水球で鍛え上げたマッチョなM君が、巨大なビールタンクを背負っているという状況があまりにもキャラクターにピッタリしていたので、これには大いに笑わせてもらいました。実際、生ビール、うまかったです。泡の滑らかさが違いますね。 その後、友人たちによって編集されたDVDにより、新郎新婦の生い立ちを記した写真が紹介されたりしましたが、総じてスピーチや余興は少なく、穏やかな宴となりました。私の好みから言うと、その方が好ましいですな。新婦のお色直しも、純白のウェディング・ドレスからペパーミントグリーンのカクテル・ドレスへのチェンジが一回あっただけでした。 そう、それからお色直しの時でしたか、例のキャンドルサービスというのがあったんですけど、今回のはロウソクに火を灯すというのではなく、テーブルセンターに置かれた水盤に水を注ぐ、という方式でした。で、水を注がれると、そこにあった特殊な電気仕掛けの装置が青く発光するという仕組みです。こういうウェディング産業も日進月歩というのか、流行り廃りがあるようで、今はこれが主流なのかも知れません。 そして披露宴も終盤に差し掛かって、これまたお決まりの「花嫁の手紙」朗読があり、ひと泣かせしたあとは親族代表として新郎のお父さんの挨拶、締めの新郎の挨拶とあって、披露宴はお開きに。その後、披露宴会場のすぐお隣の飲み屋さんで2次会があるというので、そちらにも参加し、結局10時過ぎまで新郎新婦を囲んでおしゃべりを楽しんできました。何せ周りにいるのはすべて私の教え子たちですから、久し振りにそいつらの顔を見ることができて楽しかったです。彼らもちょうど30歳を過ぎたあたりで、職場でも部下を従える地位につきはじめており、中間管理職の激務に耐えているとのことで、仕事の話なども色々聞きましたけど、なかなか大変な中、社会人としてみんな頑張っているんだなあと、巣立った子供たちの成長ぶりに感心するやら、同情するやら、といった感じでした。 というわけで、昨日はほとんど朝から晩まで付き合っていたのですが、この種の行事がある度に、いつも私は帰宅してから気がふさぎます。結婚式だの披露宴だの、すべてめでたいことであって、もちろんそこに参加している時はとても楽しいのですが、帰宅するとどうも心が重く沈むんです。 それはもちろん、楽しいことが終わってしまった、ということもあるでしょう。でも、どうもそれだけではないんですな。 結婚式と披露宴というのは、それ自体大ごとですから、そのために費やされるエネルギーは膨大なものになります。式場だってビジネスとして一生懸命仕事をするわけですし、そこに集まってくる人々だって遠方から来るとなると相当なエネルギーが必要となる。そしてそれらはすべて、二人の新たな門出というもののために蕩尽されるわけです。 しかし、それによって何がなされたのか。 何もなされないですよ。だって二人はスタート地点に立っただけですもん。二人がこの先、よい夫婦になるかどうかなんて、全然何の保証もないです。昨日、非日常的なイベントの中であれだけ幸せに結婚した二人が、現実に立ち戻った今日、ささいなことで口喧嘩しているかもしれない。 いや、もちろんM君たちがそうだ、というのではないんですよ。うまく表現できないんですけど、私はそういう一般論としての「非日常から現実への移り変わり」というのがどうももの淋しく思えてしまって、苦手なんですな。私だったら、非日常の中、架空の幸せ劇を演出するために一度に膨大なエネルギーを使った挙げ句、「あーあ、楽しい時間が一瞬のうちに終わっちゃった・・・」となるのではなく、現実の中で平均的にエネルギーを使って、常に幸せでいたいんです。幸福の不言実行、みたいな感じと言えばいいかしら? ま、実際、私と家内はいわゆる「結婚式」というのをやっていませんしね。レストランを借り切って披露宴的なことはちょっとだけやりましたけれど・・・。その代わり、結婚以来9年というもの、ほとんど夫婦喧嘩らしいことをしたこともないし、ささいな喧嘩すらほとんどしたことがないです。1年365日、常に仲良し。 だから、むしろ新婚を祝う行事よりも、銀婚式だ、金婚式だ、といった行事、つまり結婚してずっと幸せで良かった、ということを祝う方がいいんじゃないかと思っているんです。こういう行事は、「今までずっと幸せであった」という歴史を祝うわけですから、祝うことに内容がある。逆に言えば、祝うことに不安がないですからね。もう起こっちゃったことなんですから、覆しようがない。 なんだか、何言っているのか自分でもよく分からなくなってきましたが、理由はともあれ、私は人の結婚式やら披露宴やらに出ると、なんだか気がふさぐってことなんですよ。 というわけで、今日の日曜日はその心の振幅を抑え、もとの平常心に戻すべく、家内と連れ立って昼食を外に食べに行きました。何もご馳走を食べようってのじゃないので、家の近くにあるサンドイッチの名店、「カフェ・ダウニー」というところで、サンドイッチとコーヒーのお昼を食べてきたんですけどね。そして帰りには古本屋に立ち寄って2、3本を買い、買い物も済ませて帰宅した次第。これで、すべて気持ちが御破産になりましたから、今日はこれから少し勉強をしましょう。 それでは、また明日。皆さんもよい週末をお過ごし下さい。
August 20, 2006
コメント(2)
-
教え子の結婚式
今日はこれから教え子の結婚式+披露宴に出席してきます。 今日結婚する二人は、二人とも私の教え子です。ということは、つまり・・・、そう、同級生同士の結婚なんです。ひゅー、ひゅー! 彼らが付き合い出したのは、たしか4年生の冬じゃなかったですかね。英米学科の旅行で教官と学生たちで京都に旅行した時のこと。旅館で夕食を食べ、宴会もたけなわを過ぎ、昼間の疲れも出て三々五々ぐったりしていた時ですわ。数名の男子学生たちが我々教官たちとぐだぐだしゃべっていると、学生の一人、M君がおもむろに「実は最近付き合い出した子がいまして・・・」てなことを言い出したわけ。おお! そういうネタ大好き! 誰なんだよ、相手は?! で、探り出したのがM君と同級、まさに今回の旅行にも参加しているSさんだったのでした。 さて、その後M君は中学校の英語の先生となり、Sさんは一般企業に就職したのですが、案外これがいつまで経っても結婚しないんです。じゃ、別れたのかというと、そういうわけでもなく、時折様子を探ってみると、やっぱり依然として付き合っているという・・・。どうなってるんじゃ? と、我々教官一同の間でも話題にはなっていたわけですが、それがとうとうここへ来てめでたくゴールイン、ということに相成った次第。苦節10年のお付き合いですね。良かった、良かった! ま、そんなわけですから、今日、結婚式&披露宴に出席するのは、その大半が知った顔なんです。教官もほとんど全員参加ですし。そういう結婚式&披露宴って珍しいですからね。同じ教え子の結婚式でも、卒論指導教官だった私一人だけが呼ばれる、なんてことも多く、披露宴のテーブルに誰も知り合いがおらず、手持ち無沙汰で死にかける、ということもしばしばありますから・・・。そういうのと比べると、今日はほとんどお祭り騒ぎですな。 さて、挙式は3時から、名古屋駅前の式場でございます。そろそろ出発の用意をしなくちゃ。それでは、文字通り「今日も、いい日だ!」ということで。行って来まぁす!
August 19, 2006
コメント(4)
-
濁流の中、お魚は?
台風10号の被害が九州地方を中心に広がっているようで、そちらの方面にお住まいの方々にお見舞いを申し上げます。 ところでワタクシ、この大雨で逆巻く濁流となった河川の映像などをテレビで見る度に思うことがありまして。 いや、下らないことなんですが・・・。つまり、こういう川に住んでいるお魚は、この濁流の中、どうしているのかなと。 映像で見る限り、とても小魚の力では流れに逆らって泳ぐことは出来ないだろうと思うんですよね。それに濁流は何十時間も続くんでしょうから、魚だってご飯を食べてる暇もない。いずれは力尽きるでしょう。 その場合、彼らは「アレ~!」ってな感じで海まで運ばれちゃうんでしょうか? しかし愚考するに、その場合、淡水魚としては海水の中では暮らしていけないんじゃないかと。鮎なんか岩についた苔を食べるわけですが、そんなもん海にはないでしょうし。 じゃ、全滅? そんなわけないですよね。台風が過ぎれば、ちゃんと川で魚は釣れるんですから。 じゃ、どうなってるんですか? やっぱり、あの濁流の中、必死で流れに逆らって泳いでいるんですか? ワタクシ、時々こういう下らない問いが浮かんじゃうんですよね・・・。ま、どうでもいいことですけど、どなたか、ご存じの方いらっしゃいましたら、ご教示下さいねー。 さて、先日『ダヴィンチ・コード』を読み終えたばかりの私ですが、同じ頃家内が京極夏彦の『魍魎の匣』という作品を読んでいて、結構面白がっていたんです。で、そんなに面白いかしらんと思って私もつい読み始めてしまったんですが。 それがねー、結構面白いんですわ、これが。まだ途中までなので先行きのことはよく分からんのですが、どうも「隙間恐怖」にとり憑かれ、箱の中に何かをみっしり詰め込まないと気が済まなくなってしまった男が、箱の中に手足を切り落とした少女の死体を詰め込んじゃう、っていうような猟奇殺人を扱った推理小説なんですな。で、ポイントは「箱」でして、「箱」のコンセプトが、物理的なものとして、あるいは象徴的なものとして、輻輳的に小説の中に散りばめられているわけ。 また「箱」の比喩で言えば、小説内小説も効果的に散りばめられいるし、語り手も複数いたりして、それらのストーリーと語り手が「入れ子構造」になっているわけですよ。ですから、一応は「聖杯探し」のストーリーで一貫している『ダヴィンチ・コード』以上に話は複雑で、一体、どの事件とどの事件がどうつながるの! というじれったい思いから、一度読み出すともう最後まで読み切りたいという思いに駆られるんです。 でまた、事件の舞台となるのが東京西部から神奈川にかけてですから、まさに私の土地鑑のある場所ばかり。小説内に地名が出れば、ああ、あの辺ね、と見当がつくわけ。そういうところもまた、面白いんだなあ。 ということで、ホントはこんなもん読んでいる暇ないんですけど、食後の食休みだとか、寝る前のちょっとした時間に、京極夏彦ミステリーをむさぼり読んでいるんです。ちなみに、私、この種の小説って食わず嫌いでほとんど読んだことがないんですけど、なかなかどうして、面白いものだったんですね。ちょっと見直しちゃいました。 さ、そんなこと言ってると仕事が遅れてしまう! それでは、皆さん、また!
August 18, 2006
コメント(5)
-
『The Da Vinci Code』を読了!
アメリカ大衆文学を読む試みの第○弾として選んだ『ダヴィンチ・コード』、あと残り10ページというところまで来ていたんですけど、今朝読了しました! 映画版は先に見ていたのですが、原作を読んでみたらやはり微妙に異なるところがありますね。もちろん原作の方が詳しいし、謎解きの部分がより明確になっているので、原作の方がよほど面白いです。実際、映画版だけではよく分からない事情が、原作を読むとよく分かりますからね。たとえばアリンガローザ司教がなぜ聖杯の入手を目指すのかとか、ソニエール館長と孫娘ソフィーの仲違いの事情、あるいは銀行の貸し金庫に隠されていた「キー・ストーン」をラングドン教授とソフィーが取りに行った時、なぜ銀行の支店長がそれを阻止しようとするのか、など映画版ではよく分からないことが多いですから。 また警察に追われたラングドン教授とソフィーが、もともと聖杯を狙っていたサー・ティービングの家に匿ってもらうというのは、あまりにも都合が良過ぎるように思っていましたが、原作を読むと、二人が彼の家を訪れたことは、むしろティービングにとっては不都合だったんだ、ということも分かります。それを言えば、サー・ティービングがなぜ聖杯の秘密の公表にこだわるのか、ということも原作を読んでようやく分かりました。 さらに映画版では、確かソフィーは血縁の身寄りをすべて失っていたと思いますが、原作ではそうではないんだなー。なーんて、あまり詳しく言うと、これから読もうという人に悪いですね。 とにかく『ダヴィンチ・コード』、なかなかよく書けたサスペンスものだと思います。英語も易しいので、ちょっと心得のある人ならあっさり読めるのではないでしょうか。映画版と同じく、原作も短い章ごとにどんどん場面展開がなされるので、飽きることなくどんどん読み進めることが出来ます。 ただ・・・。ま、こういう短い章建てでどんどん場面展開していく書き方自体は、この種のベストセラー・サスペンスの常套手段ですから、ああ、またね、という感じは否めません。またこの種の大衆小説の常で、読んでいる時は面白くて止められないんですけど、読み終わった後、なーんも残らないんだよなー。その辺が、ねー。しばしの読書のスリルに7ドル99セントを支払って、ああ面白かった、で、あとはポイッ、ということにならざるを得ないというか。何度も何度も読み返して、その都度新しい発見をし、自らの心の糧になるっていうようなもんじゃないんですよね・・・。 うーん、やっぱり大衆小説って、限界があるのかな・・・。それとも、大衆小説の中にも松・竹・梅があるってことか・・・。 ま、そうは言っても、まだまだ読みますよ、大衆小説。ちなみに次に狙いを定めたのはジョン・オハラ(John O'Hara)の『サマラで会おう(Appointment In Samarra)』です。ジョン・オハラは、アメリカ文学史に残る作家ではありますが、大衆性が強いためか、研究対象になるようなタイプの作家ではなく、多分、専門に研究している人なんて、今、いないんじゃないかと思います。『ダヴィンチ・コード』がちょっと娯楽的過ぎたので、方向性を若干修正してみたわけなんですが、さて、この作品、面白いんでしょうか。また読み終わったら報告しますね。 さて、今日の私ですが、野暮用で外へ出たついでにCDショップに寄り、アメリカのバンド、「シカゴ」のベスト盤を買ってしまいました。ちなみに私、ベスト盤というのが嫌いで、個々の曲はアルバムというコンテキストの中で聴くべきだという主義なんですけど、シカゴみたいにキャリアの長いバンドになると、すべてのアルバムを買うのも剣呑なので、ね。 で、さっきからこのベストアルバムを聴きながら仕事をしているんですけど、もう70年代~80年代のサウンドの炸裂で、アメリカのポップス界もこの頃が一番良かったなあ、と涙しているところでございます。ブラス・セクションが懐かしいし、ボーカルのピーター・セテラの声も若々しくて・・・。 こういう音楽を同時代のものとして知っているだけ、年寄りであることが嬉しく、また誇らしくなりますな。今どきの、音楽だかなんだか分からんもの聞いて悦に入っている若者どもが馬鹿に見えてくるこの優越感。あっはっは! ということで、しばらくは70年代、80年代サウンドに酔うつもりです。一応、イメージ的には長髪・髭もじゃ・ラブ&ピースって感じなので、ひとつよろしく!
August 17, 2006
コメント(6)
-
民族の大移動
ほぼ1週間にわたる実家での滞在を終え、名古屋に戻って参りました。 しかし、今日はお盆休み明けの家族連れで高速道路上のどのサービスエリアも夜遅くまで大混雑でしたなあ・・・。下りだから帰省ラッシュとは無縁かと思いきや、どこも一族郎党を乗せたワンボックス・カーで一杯。 駐車場でもどこでも四方八方をワンボックスに囲まれてしまうので、別に覗こうとしたわけではないですけど、否応なく車中の様子が見えてしまうんですが、もう、すごいですよ。どの車も大概、2列目シートと3列目シートがフルフラットにされ、そこに子供用の布団だのタオルケットだのが敷かれていて、玩具だのお菓子だのが散乱している・・・。最早、完全に「動く4畳半」状態。そこへガキンチョたちやら、おじいちゃん、おばあちゃんやらがうじゃうじゃと靴を脱いで上がっていくわけ。オー、ノー! 一度、足柄サービスエリアでガソリン入れようと思ったら、高速道路上の安いガソリン目当ての車が長蛇の列で、それが私のプジョーを除いて全部がワンボックスだったのには笑いました。もう、ほんとに民族の大移動って感じです。 これが今の日本のモータリゼーションの形なんですなあ・・・。幸せっぽいような、貧乏くさいような・・・。 さて、名古屋に戻った私と家内は、荷物を解く間もなく、いきなり鞄からそれぞれ本を取り出し、黙々と読書に専念。なんだか怪しい二人連れですが、二人とも今読んでいる本がちょうどあと数十ページで読み終わるというところだったんです。私は『ダヴィンチ・コード』、家内は京極夏彦の『魍魎の匣』ですが。 で、残念ながら私の方が競争に負け、家内の方が先に読み終わったので、これを汐に風呂に入って寝ることになりました。私だってあとほんの10ページで読み終わるんですけど、ま、それは明日のお楽しみということにいたしましょう。 それでは、明日からまた名古屋からのおしゃべりでございます。『ダヴィンチ・コード』の感想なども書きますので、どうぞお楽しみに! それでは、お休みなさい!
August 16, 2006
コメント(2)
-
「コールドストーン・クリーマリー」でアイスクリームを食す!
今日は南町田にある「グランベリーモール・アウトレット」というところに、家内や姉や甥や姪と共に買い物に出かけて来ました。といっても買い物の方は二の次で、主たる目的はここにある「コールドストーン・クリーマリー」でアイスクリームを食べることでございます。 ところで、コールドストーン・クリーマリーって、ご存じですか? もともとはアメリカのアイスクリーム屋さんで、冷たく冷やした石の台の上で、店員さんが客の注文に合わせて好みのアイスクリームを練り上げてくれるというシステムなんです。アイスクリームの種類も色々ですし、トッピングも色々あるので、たとえば、フレンチバニラ・アイスにストロベリーとオレオクッキーとホワイトチョコを混ぜて、と注文すれば、その通りに作ってくれるわけ。 で、客が自由に好みのアイスクリームを作れる、というところもそうですが、もう一つ、コールドストーンの「売り」は、店員がアイスクリームを捏ねながら歌い踊る、というところなんですね。ニューヨークの街角で、陽気な黒人の兄ちゃんが歌いかつステップを踏みながらアイスクリームを捏ねてくれたら、そりゃ人気も出るでしょう。というわけで、このアイスクリーム・チェーン、あっと言う間にアメリカ中に広まり、そしてその勢いに乗って、ついに日本にも上陸してきたという次第。今はまださほど店舗数はないと思いますが、きっとそのうち日本でもあちこちに支店ができるのではないでしょうか。 で、私もようやくそのコールドストーン・クリーマリーを体験したわけですよ。 ところが店に着いてみると、これがすごい人だかり。長蛇の列がトグロを巻いています。さすがにその列を見て少々たじろぎましたが、これを食べるために来たようなもんだと思い直し、列に並びましたよ。でも、私たちが並んだ後も列は長くなる一方で、大した人気です。 かくして30分程も待たされた挙げ句、ようやく私たちの番になり、私は「チーズケーキ・ファンタジー」というのを注文することに。これはチーズケーキ味のアイスクリームに苺とブルーベリー、それにグラハムクラッカーを混ぜて捏ねる、という奴ですが、目の前で店員のお姉さんがそれを作ってくれるわけですから、なかなか面白いものです。 で、そんなふうに数名の店員さんがそれぞれ客の注文に応じてアイスクリームを捏ねながら、誰かが合図を出すと、彼ら・彼女らが一斉に歌い出すわけ。ま、日本人の同胞に間近で歌い出されると、「楽しい」というよりは、むしろ「こっ恥ずかしい」という感じがして、直視できないところがありますが、ま、ディズニーランド的な雰囲気は出ていましたね。周りを見ると、小さい子供なんかはとても喜んでいました。 で、お味はと言いますと、はっきり言って、かなりうまい。「この次は、あれを食べよう」という気になるくらいのおいしさでした。 ちなみにお値段ですが、一番小さい奴をカップに入れてもらうと450円也。焼きたてのワッフルみたいなのに乗せてもらうと50円アップ。その他、大きさによって、あるいはトッピングの数によって値段は上昇していきます。割高って言えば、割高かなあ・・・。でも、おいしいことはおいしいので、損した気分にはなりません。話のたねにもなりますしね。 しかし、コールドストーン・クリーマリーのアイスクリームを賞味しつつ、つくづく思うのですが、商売っていうのは面白いもんですね。ま、先程も言いましたように、確かにここのアイスクリームはうまい。だけど、じゃあたとえば「31アイスクリームより遥かにうまいか?」と問われれば、「31アイスクリームも、あれはあれでうまい」と言わざるを得ません。結局アイスクリームなんてものは、あるレベルを越してさえいれば、どれもこれもうまいんですよ。 となると、あとは話題性ですよね。ただアイスクリームを客に差し出すのではなく、まずそこに「客の要望によって如何様なものでも作る」というオーダーメイド・システムを導入し、「目の前で捏ねる」という視覚的要素を採り入れ、しかも「店員が歌う」という劇場感覚も採用する、という手法で、従来からあるアイスクリーム屋さんを圧倒する集客力を得ているわけですよ。要するに、ちょっとした付加価値があるかないかで、商品力は全然違ってきてしまうんですな。事実、「31アイスクリーム」よりよほど高い値段設定なのに、あれだけの人が「並んででも食べたい」と思うのですから・・・。 ま、そのことは、多分、今あるどんな商売にも当てはまるんでしょう。激しい同業者同士の競争の中で、できることはすべてやり尽くしたと誰もが思っているかも知れないけれど、まだまだどこかに付加価値をつける余地があるのであって、それに気づくかどうかが突出した成功を収めるかどうかの別れ道なんでしょう。 私は勝手に想像するんですが、コールドストーン・クリーマリーにしても、ひょっとすると最初は一人の陽気な店員が、ふざけて歌いながら客の注文に応じていたんじゃないですかね。で、それが評判になって、アレ? この付加価値はイケルかな? じゃあ、店員全員が歌うことにしようか、ということになり、それが受けて2号店、3号店・・・と増えていって、ついにはそれがチェーン店のシステムとなった、と。真偽のほどは分かりませんけれど、そんなふうに想像すると、いかにもアメリカだなあ!という気がしてきます。「楽しさを売る商売」ということになると、アメリカ人っていうのは天才的なところがありますからね。 ま、他人事ではなく、私自身の研究にしたって、そういう「大きな差を生む、小さな付加価値」というのはあると思うので、その意味でも、こういう新興のビジネスというのは見ているだけでも勉強になります。 さてさて、今日は「終戦記念日」ですから、本当はアイスクリームのことなんか考察している場合じゃないのかも知れませんね。本当は、小泉首相の靖国参拝問題の是非でも考察した方が良かったのかも知れない。それは私もそう思うんです。しかし、今日が何の日かなんて気にしたこともなさそうな人々の群れが、コールドストーン・クリーマリーの前に長蛇の列をなしているのを見ると、善きにつけ悪しきにつけ、60年間の平和ってのは、つまりはこういうことなんだよなと、思わざるを得ないところもある。 今日はしかつめらしく大上段に構えたことは言わずにおいて、多くの善男善女と共に、珍しいアイスクリームを賞味した一日ということにしておきましょうか。
August 15, 2006
コメント(2)
-
バーベQパーティー!
今日は夏休み恒例、「家族でバーベQパーティー」をやりました! ま、毎年のことなので、手慣れたもんです。まずは炭火の着火から。前回、気張って「備長炭」なんてのを買ってしまったら、これがなかなか火がつかなくて往生したので、今回はごく安い普通のバーベQ用木炭をゲット。着火剤を使って火をおこすこと20分、いい感じで火力が安定してきました。よく若い人で、初めてバーベQをやる人の中には、マッチの火で木炭に火がつくと思っている人がいますが、とんでもない。木炭に火をつけるのは、着火剤を使うにしても、ちょっとしたコツが要ります。ま、その辺、私はこう見えて百戦錬磨なもんで。 で、まず最初は「焼き鳥」から。モモ肉を適当な大きさに切ったものに塩・胡椒をし、網焼きしていきます。肉ってのは、炭火の風味がつくとなんでこううまいんでしょうね。あっと言う間に売れてしまいました。そして次はステーキ肉とカルビ、それからソーセージも網焼きし、同時に茄子やタマネギ、そして忘れちゃいけない、トウモロコシを焼いていきます。トウモロコシには醤油をたらして、焦げた醤油の風味をつけるのが基本。 で、この後は網焼きから鉄板焼きに切り換えますが、ここでアルミホイルにくるんで炭火の中に放り込んでおいたジャガイモを取り出し、「ジャガバター」にして食べました。これもホックホクで、うまかったですよ! さて、次は鉄板を使った焼き肉です。最初はタレに漬け込んだ薄切り肉を強い火力で一気に焼き上げ、あらかじめ用意していたオムスビと一緒に食べました。うまーい! しかし、その後、ごく普通の牛の薄切りを、シンプルに塩と胡椒だけで鉄板で焼いて食べてみたら、むしろこっちの方がおいしかった! 焼き肉ってのは、シンプルなのが一番ですな。 そして最後、締めはやっぱり焼きそばでしょう! ということでキャベツやタマネギ、茄子などの野菜を炒め、ソバを投入し、飲み残しのビールを注いで蒸し焼きにした後、最後に残っていた焼き肉とモヤシを入れて、粉末ソースで味付けしたら完成です。これもおいしかった! もう食べられない、というところまで食べて満足、満足。 それからしばし食休みした後、これも恒例となったお楽しみの花火をして、夏の風情を楽しみました。もちろん、最後の最後は、線香花火で締めくくります。線香花火の火薬の匂いってのは、日本の夏、という感じがしますからね。 今回は炭火の火力もうまく維持できましたし、買ってきた食材も全部無駄なく消費したので、その点でもよかった。途中、焼き担当の私がちょっと目を離して食べていた隙に、鉄板に残っていた食用油に火がついてあわや自宅をバーベQにするところでしたが、それもご愛敬ということで・・・。ちなみに、今回の食材の中で特に評判が良かったのは、焼き鳥と焼きトウモロコシ、そして塩・胡椒だけで焼いた牛薄切り肉でした。こういうのは覚えておくと、次の年の食材選びに活かせますのでね。 ところで、夏の一日、家族でバーベQをやる、という習慣が出来てからもう十数年が経つでしょうか。確か、私が友人たちとどこかでバーベQをやって、それがとてもおいしく、また楽しかったので、これはぜひ自宅でもやろうと思い立ち、コールマンのバーベQコンロを買ってきたのが最初でした。それ以来、毎年必ず夏にはバーベQを楽しんでいますので、もうこのコンロも完全にもとを取りましたね。アンチ・アウトドア派揃いの我が一族の中で、多少ともこういうことに興味があるのは私だけなので、この夏の楽しみができるかどうかはすべて私の双肩にかかって来るんですけど、もちろん実際にやってみれば家族全員が楽しんでくれるので、私としても張り合いがあります。釈迦楽家の夏のイベントとして、来年以降もずっと続けて行きたいですね。 ちなみに、まだバーベQというものをやったことがないというご家庭もあると思いますが、これほど安上がりなレジャーもないんですよ。下手なファミレスなんか行くより、よほどおいしくて楽しいですし、炭火に着火するという難事業を鼻唄まじりにこなせば、家族から尊敬されること必定。バーベQ用のコンロだって、ホームセンターみたいなところへ行けば3000円くらいで売ってます。一度買えばほとんど半永久的に使えるんですから。 ということで、夏に家族でバーベQ、これ、教授のおすすめ! です。ぜひ、お試し下さい。
August 14, 2006
コメント(0)
-
誕生日会
今日は私の家内の誕生日、そして父の誕生日もつい3日前だったので、その合同誕生会を兼ねた昼食会をすることになりました。会場は新百合ケ丘にあるホテル・モリノが経営するフランス料理の店、「シェ・ユリノ」です。 総勢7名の大所帯でしたが、早めに行けば予約をとらなくても席がとれるだろうとの思惑で12時少し前にレストランに到着すると、案の定ガラガラで、隅ッコの方の落ち着いた一角にテーブルをとることができました。注文したのはランチのコースです。 で、期待を胸に食べ始めたんですが、うーん、どうなんでしょう。最初の冷製スープ(ビシソワーズ)はまあまあだったものの、メインの魚料理(カジキの夏野菜&チーズ乗せグリル)と肉料理(ビーフの甘酢ソース)は、ちょっと誉められたものではなかったですねぇ・・・。魚料理の方は今一つ塩味が効いてなくて、味がピンぼけていましたし、肉料理の方は肉が堅いし、甘酢ソースもよくなかった。だいたいこの夏のクソ暑い時に、甘味の強いソースなんて食欲を失わせますよ。 また洋食系レストランの善し悪しを見きわめるポイントの一つである「パン」の味も、それほど特筆すべきものではありませんでした。デザートの「カモミールゼリー」とやらも、感激するような味ではなかったし、どうもいけません。「シェ・ユリノ」の店の雰囲気自体は決して悪くないですし、サービスが悪いというわけでもないのですが、肝心の料理のレベルがちょいと低かったかな~・・・。 やっぱり、新百合ケ丘で洋食を食べるなら、イタリアンの「ラ・カンパァーナ」ですね。ま、今日は誕生会ですから、少しリッチな雰囲気を味わいたかったので、ホテルのレストランを選んでしまいましたけど、「高級=味が良い」とは限らないところが難しいところです。 で、口直しとばかりに、帰りがけに「FLO」というタルトの店で「キャラメルプリン・タルト」をホール買いし、3時のおやつに家族皆でこれを食べました。FLO という店は全国展開している店だと思いますが、ここの「キャラメルプリン・タルト」、めちゃくちゃうまいですよ。ちょっと冷蔵庫で冷やして食べるのがコツ。ホールで買っても1260円ですから、お近くにお店があるなら、教授のおすすめ!です。 てなわけで、今日は家族揃ってよく食べて、よくしゃべった一日でした。ま、あんまり勉強はできなかったので、その点では「ダメな一日」なんですが、こうしていられるのも私の父と母がいまだに元気でいてくれるからであって、これがもし、どちらかが病気で寝込むなんてことになったらと思うと、今、家族皆で楽しく食事をし、屈託なくおしゃべりができるということが、これ以上ないほどの幸福に思えてきます。そう考えて、不勉強な一日の正当化をしましょうかね。 ・・・と言いながら、実は明日も「自己正当化」の必要がありそうだったりして・・・。と言うのも、明日は恒例、自宅の庭でのバーベQパーティーなんです~! これは私の姉や、今年高1になった私の甥ッコも楽しみにしているイベントなので、ぜひやらねばなりますまい。 で、私は一体いつになったら、勉強を始めるのでしょうか。その答えは、風の中に・・・。(ボブ・ディランかよ!)
August 13, 2006
コメント(2)
-
『曼陀羅コード』 by 釈迦楽
先日来読んでいる『ダヴィンチ・コード』の原作ですが、かれこれ3分の2ほど読み進みました。よく人が「原作と映画は全然違う!」というのを聞いていた割に、原作の前半部分はほとんど映画版そのものだったので、「どこが違うの?」と不思議に思っていましたが、このあたりに来てようやく、若干ですが映画版とちょっと違う部分が出てきました。この先、どういうふうになるのか楽しみです。 しかし、やっぱり映画版を見てから原作を読むというのは、あんまりよくないですね。先に原作を読むのであれば、当然、個々の読者の頭の中に登場人物の風貌なり、場面ごとの景色なりというものが勝手に想像されるわけで、その自由な想像力の飛翔こそが楽しいわけですし、またそうであるからこそ、後からその小説の映画版を見たときに「イメージと違う!」というような感想も出てくるわけですが、映画版の方を先に見てしまうと、後から原作を読んでも、頭に浮かんでくるのは映画版の映像なんですよね。だから私も、今、原作を読みながら、頭の中に浮かんでいるラングドン教授は、やっぱり変な髪形のトム・ハンクスですーーー。 ところで、私の勤務先の大学は、今、「リベラルアーツ(総合的教養)重視型」の大学への転身を図っており、そのモデルの一つがアメリカにある「アマースト大学」なんです。この大学、ま、日本での知名度から言えばそんなに有名な大学ではないですが、歴史もあり、人材も色々輩出していて、「小粒でぴりりと辛い」的な大学なんですね。で、『ダヴィンチ・コード』の作者であるダン・ブラウンという人も、実はこのアマースト大学の出身なんですって。先日、うちの大学で「大学見学説明会」ってのをやったんですが、その際、見学に来た高校生たちに向かって、私の同僚の先生が「君たちも、うちの大学に入学して、次世代のダン・ブラウンになれ!」と獅子吼していたので、「あら、そうだったの?」と思った次第。ま、果たして受験生たちに通じたかどうかは不明ですが・・・。 しかし、『ダヴィンチ・コード』って、4000万部以上が売れたんですよね・・・。あー、うらやましい! できるものなら私がダン・ブラウンになりたいようなもんですわ。彼と私はほとんど同い年と言っていいようなもんで、彼も英語の一教師から、いきなり『ダヴィンチ・コード』で流行作家の仲間入りをしたそうですから。 そうだ! 私も「空海が残した史上最大の秘密!」などと銘打って、『曼陀羅コード』なんて小説でも書こうかな・・・。「お釈迦様にも子孫がいた! 」とか言っちゃって! 作者名が「釈迦楽」なんだから、その時点で信憑性もあるし・・・。 パクリかよ・・・。 さて、話は変わりますが、今日は仙台に嫁いだ姉が甥や姪を連れて里帰りしてきたので、久し振りに姉に会うことができました。普段は仙台と名古屋に離れて暮らしているので、なかなか顔を見られませんのでね。ということで、これからまた「深夜の茶会」と称して、家族揃っての茶話会をやって来ます。え? もう勉強はしないのかって? ・・・まあまあ、そうお固いこと言いなさんなって!!
August 12, 2006
コメント(2)
-
東急東横店の古本市
今日は午後から渋谷・東急東横店、西館8階催事場で行われている古本市に行って来ました! ってことはつまり、「今日も遊んでしまった」ってことですけど・・・。 ま、私、最近では、神保町などの古書店街を歩くより、デパートなんかで開催されるイベントとしての古本市がお気に入りなんですよねー。古本市の魅力ってのは、結局、探していた本や未知の本に偶然出くわす楽しみであるわけですから、その点から言うと、勝手知ったる店に行くより、未知の書店がずらりと出店しているこの種の古本市の方が楽しいところがあるんです。で、たまたま今日から東急東横店で古本市が開催されることを知ったので、ま、行ってみようかなと思い、父と連れ立って渋谷まで足を運んだという次第。 で、会場に到着してみると、まあ凄いもんです。広い会場に様々な古書店のブースが軒を連ね、そこに黒山の人だかり。今日は初日ですからね。 でまた、いつも言うようですが、古本市に目の色変えてやってくる人々って、客観的に見るとどうも「変な人たち」が多いんですよね・・・。上半身裸にオーバーオールのジーンズを履いたチョンマゲのオジサンとか、どう見ても女の子にもてそうもないな~と思えるゴルフスラックス履いたオタクっぽいお兄さんとか、あるいは髪振り乱して何かに憑かれたようなオバサンとか、そんな皆様ばっか。しかし、そんなことに構ってはいられません。この異様な風采の人々の中では、どう見てもどこかの国の皇太子か何かにしか見えないワタクシも、武者震いをしながら突撃でございます。 で、いつものように片端から見ていくわけですが・・・アレ? なんかどうも今一つ調子が上がらないゾ。こういう大きな古本市になりますと、どこかに自分の趣味とぴったり合うようなブースに出会うものなんですが、今日はそれがないですなあ。何物も見逃さない眼力で書棚を舐めるように見ていくのですが、その目がピタっと吸い寄せられるようになる瞬間がなかなかやって来ない・・・。 それでも根気よく探して行って、角川源義さんの遺稿集『幻の赦免船』という本を見かけ、冒頭に折口信夫についての文章があったり、石田波郷や石川桂郎などにも触れた部分があると知り、とりあえず確保。私は折口信夫の短歌が好きだし、角川さんが折口信夫に親炙していたことも知っていたので、何か新しく得るものがあるかな、と思いまして。 それから植草甚一氏の『いつも夢中になったり飽きてしまったり』(番町書房)が、イカした函入りで売っているのを発見して、これもゲット。この函は、傑作です。 また私が毎年夏になると「山のエッセイ」を読むことにしているので、どなたかお薦めの本はありませんかと、つい先日、このブログで呼びかけたところ、「くまぜみ」さんから田部重治という人のエッセイがいいですよと教えられていたのですが、その田部さんがお書きになった岩波文庫版の『山と渓谷』の美本が300円で売っているのを見つけ、これも喜び勇んで買い求めました。これ、既に絶版になっていたので、ね。 とまあ、そんな感じで買い進んで行きましたが、そこまででした。いや、もちろん他にも何点かいい本がありましたが、既に入手済みのものばかりだったのでね。やはり最初の数分で、「アレ? 今日はちょっと収穫が少なそうだゾ」と思った直感は正しかったですなあ。ま、こういう直感は、たいてい当たるものなんですが。 しかし、こういう大きな古本市に来る度に思いますが、これだけ膨大な数の本があるのに、自分が買いたくなる本の数なんて、ほんの少ししかないということに驚かされます。個々の人間の興味は限られているけれど、総体としての人類の興味は無限大、ということなんでしょうけどね。ま、そうだからこそ、本のコレクションという趣味が成立するわけですが。私にしたって「1950年代に出版されたアメリカのペーパーバック本」とか「出版物のデザインに関する本」、あるいは「ヘンリー・ミラーの絵についてのエッセイ」とか「池田満寿夫のエッセイ」というふうに、非常に限定されたジャンルの本を集めているからこそ、「このジャンルについてはどんなものでも全部集めたい」という目標が定まるのであって、そうでなければ果てしがないですもんね。いくらお金があったって、とても買い切れるものじゃない。 ただ今日の古本市でちょっと残念だったのは、洋書を商う店がなかったこと。それから「蔵書票」を扱う店がなかったこと、かな。そういうことや、収穫がやや少なかったことを含め、今日の古本市はぎりぎり及第点というところでしょうか。しかし、先程も言いました通り、私以外の人にとってはこれも宝の山かも知れませんので、16日まで開催しているこの古本市、教授のおすすめ! と言っておきましょう。夏の半日、本の山と格闘して、自分の好みの絶版本を掘り出すなんてのも、なかなかいい時間の潰し方ですよ。本好きの方は、是非!
August 11, 2006
コメント(4)
-
東京に移動
今日、10日に東京の実家に戻ってきましたー。とりあえず1週間ほどこちらで過ごす予定です。 今日の東名は結構混んでいましたね。それでも、一度横浜・町田インターあたりで事故渋滞に巻き込まれた以外、混雑による渋滞はなく、4時間ちょいで走りきったかな? いつも名古屋・東京間を走る時、ステキな車に出会うと、私の独断で「本日の一等賞」というのに(勝手に)指定するのですが、今回の一等賞は「ワインレッドのマセラティ・クーペ」でした! でも、それ以外にはあまりパッとした車に出会わなかったなあ。トラックとミニヴァンばっかりで、一台のフェラーリ、一台のポルシェ、一台のアストンマーティンにも出会わなかった・・・。せめて可愛いフィアット・パンダでも走っていたら、「本日の2等賞」をあげたのに。 さてさて、毎年夏に実家に戻る時は、気合を入れてやたらに勉強道具を車のトランクに積み込み、あれもやろう、これもやろうとやる気満々なんですけど、実際には準備したものの3分の1も使わないんですよね・・・。が、それでも懲りず、やっぱり今年も山のように勉強道具を持って帰省してしまったワタクシ。果たして今年はしっかり勉強できるのか、はたまた例年の通り遊び呆けるのか。多分、このブログをお読みの方には、たいがい予想はついていると思いますが、その予想を覆すべく、明日から頑張ります。 それでは、明日からは(というか、もう「今日から」ですが・・・)我が故郷、東京からのブログの発信です。どうぞお楽しみに!
August 10, 2006
コメント(2)
-
屋台ラーメン初デビュー!
昨夜、屋台にラーメンを食べに行くという話をしましたが、考えてみれば、私、屋台なぞというところでモノを食したことが今までなかったので、これが「屋台初体験」ということになります。キャー! 「サンキューらーめん」という名のその屋台のラーメンは、鶏と魚でとったと思しき透明・白色のスープに細目のストレート麺、それにトロトロに煮込んだチャーシューにシナチクが乗り、あとは刻んだネギに海苔が一枚というシンプルなもの。味はさっぱり系で、なかなかおいしかったですよ。15席ほどの屋台ですが、お客さんが途絶えないのも頷けます。基本となるラーメンがおいしかったので、次は上級者編で「台湾ラーメン」をいただいて見ようかな。 ただ本当のことを言いますと、私としてはもっとシンプルな「醤油ラーメン」を期待していたので、その点では期待外れではありました。しかし、今日、シンプルな醤油ラーメンほど得難いものはなく、近所に新しいラーメン店が出来たとしても、たいていは「豚骨系」白濁ラーメンの店なんですよね。子供の頃、町の小さな中華料理店で出していたような、ごく普通の醤油ラーメンが食べたいという私の願いは、なかなか叶う日が来ません。 ちなみに名古屋の北西、一宮にある「一喜」という小さな中華料理店では、私が恋い焦がれる類の、昔ながらの醤油ラーメンを食わせてくれるのですが、そこまで行くのが大変なので、もう10年くらい行ってない・・・。かつてその店に家内と共に訪れ、醤油ラーメンに味噌チャーハン、焼き餃子に瓶入りのコカコーラを注文して、それら全部合わせて1000円でお釣りがきたのに驚いたことを覚えていますが、出てきた料理のどれもがまた絶品でね。まさしく、こういう店こそ理想の中華料理屋なんですけどねぇ・・・。 さて、帰宅してから食休みに本を読み、読みかけだった島崎藤村の『千曲川のスケッチ』を読み切ってしまいました。高校生の課題図書じゃあるまいし、なんでそんなものを読んでいるのかと言いますと、私としてはこれ、「山のエッセイ」を読んでいるつもりだったんです。数年前から私は、夏休み中に少なくとも一冊、山や登山にまつわるエッセイを読むことにしているのですが、今年は何を読もうかと思い惑い、たまたま目についたこの本をパラパラとめくって、藤村が小諸に籠もっていた時期のエッセイなんだから、山のエッセイに違いはあるまい、と思ってしまったんですな。それでこの歳になって未読だったこの藤村の本を読む気になったわけ。 ま、有名な本ですから既に読まれている方も多いと思いますが、『若菜集』を皮切りに次々と優れた詩集を出し、新進の詩人として売り出し中だった藤村が、一旦詩を諦め、そこから散文小説に手を染めようとしていた、その移行期に書いた散文エッセイです。ま、今読むとまったく何のこともない散文ですが、まだ言文一致の大革命の途上にあった当時の日本の言語状況の中で、ここまで完成された口語による散文作品というのはこれが初めてであるとも言われ、その意味で時代を画する散文文学の傑作、ということができるのだとか。 エッセイとしては、要するに信州・小諸というところにある学校(小諸義塾)に国語の教師として赴任した島崎藤村が、同僚やら地元の人との付き合いの中で次第に北信州の土地柄・風俗に親しんでいく様子を描いたもので、梅と桜と桃が一斉に咲き出す信州の遅い春のことから書き始め、季節の進行に従って夏・秋・冬のことに話がおよび、最後に次の春が来たところで締めくくられます。「小諸の四季」ってところですね。 で、読んでいて感銘を受けるのは、やはり小諸やその周辺の人々の厳しい暮らしぶりと、素朴な人柄です。このエッセイが書かれたのは1899年と言いますから、今からわずか100年程しか違わないわけですけど、100年前の日本ってのは、今とはまったく別世界ですな。 まず100年前の日本っちゅーのは、基本的に地方と地方の間に流動性がない。人がもし北信州に生まれたのだとしたら、その人はそこで生き、そこで死ぬしかないわけですよ。ですから、いかにその土地が痩せていて、また寒さの厳しい土地であったとしても、そこに齧りついて暮らしていかなければならない。事実、藤村が描く小諸の人々の激しい労働のさまは、すごいもんです。上州なんかと比べると格段に地味の薄い北信州では、それだけ必死に家族総出で田畑を耕さないと、とても食べていけないんですな。大人も子供も必死で働いている。 それでいて、やはりそこは人間ですから、楽しみもなくては生きていけないのであって、それゆえ、こんな片田舎にも季節ごとの祭りがあったり、伊勢神宮への巡礼があったりといった、小さいながらも楽しい風俗というものがある。その一方、もちろん時には集落ごとの争いも起こったりもし、また田舎の持つ狭量さも、時には顔を出すこともあります。 で、そんなものの集合体として、その土地固有の風俗が生まれ、またそこに生きる人々特有の人柄が生まれていくんですな。だからこそ、他所から来た藤村のような観察者からすれば、小諸の風俗やそこに住む人々の人柄が新奇なものとして目に映り、面白くて仕方がないし、また逆に小諸の素朴な人々も、他所から来た珍しい客人として藤村を厚くもてなしてくれる。そういう地元の人と他所者との間の「つかず離れず」といった付き合いの中から、この名エッセイが生まれたということなんですな。 それにしても、私にとって特に印象深かったのは、小諸の人々の言葉遣いですね。朴訥ではあるんですが、穏やかで、丁寧で、礼にかなっている。そしてそれはもちろん、彼らの人との接し方にも当てはまることなんですな。それは読んでいて、非常に気持ちがいい。 はあ~。昔の日本人は、こういう言葉で話し、こういうふうに人に対していたんですなあ。小林秀雄じゃないけれど、本当に昔の日本人は、「人間の形」をしていましたよ。今の日本人は、本当に人間なのか、疑わしいのが多いですからね。親は子を殺すは、子は親を殺すは・・・。 ま、それはともかく、藤村の、というか、日本人の口語散文に対する初挑戦、私はそれなりに楽しんで読みましたけれど、私の望んでいた「山のエッセイ」としてどうかと言うと、ちょっと物足りないところがありましたかね。これはあくまで「人についてのエッセイ」でしたな。 でもねー。山や登山についてのエッセイって、あることは沢山あるんですが、私の心にぴったり来るようなものとなると、案外少ないんですよね。たとえば深田久彌のエッセイなんて、有名だしいいのかと思ったら、そうでもなかった。串田孫一、尾崎喜八クラスのエッセイが書ける人って、そうはいないんですよね。 ということで、もしどなたか、「この人の山のエッセイはいいよ!」っていうのをご存じでしたら、ご教示下さーい。
August 10, 2006
コメント(4)
-
オシムの指導法
今朝新聞を読んでいたら、サッカー日本代表監督となったオシム氏の指導法のことが話題として取り上げられていました。 その中でちょっと私の興味を惹いたのは、その独自の「紅白戦」のこと。 ま、サッカーの指導者なんですから、実戦形式の練習をするのは当然で、オシム・ジャパンでも練習中に「紅白戦」をするらしいんですけど、彼の場合、紅白に分けられたチームの中に、一人だけ「フリーマン」というのを入れるんですって。 で、このフリーマンは、紅組・白組のどちらかに所属するわけではなく、ケース・バイ・ケースでどちらかのチームに加担するんだそうです。 つまり、ある時は紅組側に加担し、白組に攻め込むのですが、時として紅組を裏切り、白組の反撃に加担したりするわけです。ですから、フリーマンが加わっているために、どちらかのチームが優勢を確信した次の瞬間、思わぬ劣勢に陥っていることに気づいたりするわけ。フリーマンの存在によって、ゲームの行方は常に油断がならなくなるんです。それだけに、紅組・白組ともメンバーは常に瞬時に変わる状況に的確に対応するため、ピリピリしていなければならない。 ひゃー、すごい指導法ですね。賢い! その他、彼は練習方法を説明する時も、通訳の人の説明が終わるかどうかという瞬間に、もうパッとボールを選手に蹴り出し、それに選手が対応することを求めるんですって。ですから、いつオシムがプレーをスタートさせるか分からないので、選手たちは常に緊張しており、ぼんやり突っ立って説明を聞いていることなんか出来ないのだそうです。 いやー。やっぱりオシムって、指導者として有能ですなあ。指導の方法論がしっかりしているし、まだ就任して間もないのに、もうその方法論を選手に叩き込んでいるじゃないですか。決定力がないと批判されると、泥縄式に誰もいないゴールに向かってひたすらシュート練習させるジー○さんとは大違いだ。早くも、次のワールドカップが楽しみになってきます。 それにしても、オシムさんの指導者としての確固たるスタンスには感銘を受けますなあ。私も一応教職に就いていて、学生を「指導」する立場にあるんですが、オシムさんが経験の中から培ってきた効果的な指導法に相当するようなものを、編み出してないということを痛感します。考えてみれば、私こそジー○式の泥縄指導だよなあ。少しはオシムさんを見倣わなければなりますまい。反省! 閑話休題。 さて、このところの私ですが、毎日本ばかり読んでいます。先日読み始めた『ダ・ヴィンチ・コード』も面白いですし、寺山修司の一種の伝記である杉山正樹著『寺山修司・遊戯の人』も面白い。また思うところあって島崎藤村の『千曲川のスケッチ』も読み始めており、開高健の『ピカソはほんまに天才か』も読みかけです。この他にも大竹伸朗の『既にそこにあるもの』、タキの『ハイ・ライフ』などなど、読みかけの本が数冊ある状態ですから、もう大変。今日も、研究用に買った洋書が2冊届いてしまったし。 ま、本を沢山読むのは私の商売ですから、それはそれでいいのですが、それにしても読むばっかりでアウトプットが少ないよなあ・・・。一度この「読書ブーム」に入り込んでしまうと、どこかでケリをつけて、生産的活動に入るのが難しくなるんですよね。そりゃ、読む方が書くより遥かに楽ですから。でも、それもいかんなあと思っているんです。そろそろ何とかしないとね。 今日は夕食食べたら、なんか少しでも書こうっと。 ちなみに今日の夕食は、外食の予定。実は家の近くに気になるラーメン屋さんの屋台があって、夜だけ営業しているんですが、夜遅くその前を通っても結構繁盛しているんです。ということで、今日はひとつ、その屋台のラーメンを試してみようかな、と思っておりまして。 ということで、そこのラーメンを食べてから、今日は少しは「書く」方の作業もするつもりでございます。ラーメンの味の方は、また明日にでも報告しましょう。それでは、また!
August 9, 2006
コメント(2)
-
仮面の忍者 赤影参上!
朝、目が覚める時に、なんか自分が歌を歌っているのに気づく時ってありません? 今朝、私はいにしえのテレビ番組、『仮面の忍者 赤影』のテーマソング、「忍者のマーチ」を歌いながら目が覚めたのでした。 いい歌なんだよねー、あれ。メロディーも良くって、歌ってると涙が出そう。 「赤い仮面は 謎の人 どんな顔だか 知らないが きらりと光る 涼しい目 仮面の忍者だ 赤影だ 手裏剣しゅっしゅっしゅっしゅしゅっ! 赤影がゆく」 「どんな顔だか 知らないが」ってところがいいなあ。実際、番組の中で赤影は最後まで仮面を取った顔を見せないですもんね。忍者なのに髪型は七三分けって、一体どんな忍者なんだっ!って思いますけど、でもカッコ良かった。「赤影参上!」って言う時のクールさと言ったら! しっかし昔のテレビって、テーマソングが良かったなあ。何十年前のテレビでも、テーマソングだけは思い出せます。 ま、だからといって、「忍者のテーマ」を歌いながら起床するワタクシもどうかと思いますが・・・。 それにしても『赤影』、好きだったなあと思って、起きてからちょいと調べてみたら、これ、横山光輝原作なんですってね。やっぱり、そうか・・・。ワタクシ、横山光輝ものって、基本的に好きなんですよ。『鉄人28号』も『魔法使いサリーちゃん』も好きでしたから。『魔法使いサリーちゃん』の後、赤塚不二夫の『秘密のアッコちゃん』が始まった時、子供心に「ちっ、『サリーちゃん』の方が良かったな・・・」と思ったことをハッキリ覚えていますから。また、同じロボットものでも『鉄人28号』は夢中になって見ましたが、手塚治虫の『鉄腕アトム』は全然、ぜーんぜんっ面白くなかった。手塚アニメは、私にはまったくアピールしない、というか、いつ見ても不愉快にさせられたもんです。 その他、私が子供の頃に見て面白かったアニメと言いますと(順不同・思いついた順)・・・『ルパン三世』(初代のみ。2代目以降は腹立たしいまでにレベルが低い!!)『アルプスの少女ハイジ』(宮崎アニメはヨハンナ・シュピリの原作を越えている!)『サスケ』(白土三平は、私の祖父も認めていた!)『宇宙戦艦ヤマト』(『銀河鉄道999』になると、もう私には分かりません)『妖怪人間ベム』(原作は誰かと思ったら、韓国マンガなんだそうです)『花のぴゅんぴゅん丸』(原作は驚いたことに、つのだ・じろうさんなんだそうです)『スーパー・ジェッター』(30秒時間が止められたらいいでしょうな・・・)『魔法使いサリーちゃん』(既述) ・・・ほれ、手塚治虫が一つもない・・・。手塚だけでなく、トキワ荘系が一人もいない。どうもダメなんです。ワタクシと手塚治虫の相性って、どういうわけか悪いんですよね。 ちなみに、ちょっと調べたところによりますと、横山光輝マンガの特徴は「笑いがない」ことなんですって。「笑い」ではなく、力強いストーリーだけで引っ張っていくタイプのマンガなんだそうです。 ふーむ。なるほどね。そうかもね。 ということは、そういうマンガが好きだった私は、マンガに対してすら、笑いよりストーリーを求めていたのかも知れません。おお! そういえば、確かに思い当たるフシがあるかも・・・。 いやー、勉強になるなあ。今朝は、「忍者のマーチ」で目が覚めたおかげで、何だか、自分に対する知識が増えてしまったのでした。 ところで、これをお読みの皆さんにとって「記憶に残るマンガ・アニメ」って何ですか? 閑な方のご回答をお待ちしてマース。
August 8, 2006
コメント(9)
-
女ってしんどい!? 『シンデレラ・コンプレックス』を読む
数日前のブログにちょっと言及したコレット・ダウリング著『シンデレラ・コンプレックス』(柳瀬尚紀訳・三笠書房・知的生きかた文庫)を読了しました。ま、最初はさほど期待せずに読み始めたんですけど、読んでみたら結構説得力のある本でしたよ。読みながら、自分の身の回りを見渡して、なるほどと思うケースがしばしばあるんですもん。 たとえば「女性は自分の業績を過少評価する」というところとか。これなんか、私の姉そのものズバリです。子供の頃、姉は試験か何かがある度に、「難しかった」「できなかった」と言いながら帰ってくるんです。で、私は逆に「ちょろい、ちょろい」とか言って帰ってくる。しかし蓋を開けてみると姉の試験は満点、私はせいぜい70点、なんてことがよくありました。子供の頃だけでなく、私の姉はいつもそんな感じで、私なんかよりよっぽど賢いのに、いつも謙遜していた。 で、自分の業績を低く見積もる女性は、常に「成功」を他者のせいにするんですって。「たまたま運が良かった」「周囲の人に助けられた」ってな感じです。つまり、「成功恐怖」というのがあって、成功を自分で引き受けられないんですな。で、逆に、「失敗」の方は進んで自分で引き受けちゃうんですって。「うまく行かないのは、自分のせい」と思い込みがちなわけ。つまり「自己否定」をすることに慣れちゃうんです。 で、こうなるともう悪循環ですよ。学校で勉強している時はすごく成績のいい女の子が、将来を嘱望されながら、「いや、自分にはそんなこと、勤まらない」と自分から引いてしまって、つまらない(と言っては失礼ですが)事務職かなんかをちょろっとやって、すぐに結婚してしまう。キャリアなんて積んでいたら女性として魅力がないと思われるのではないか、という自己否定の恐怖があるからです。 で、一旦結婚してしまうと、例の「依存体質」が全面に出て、夫に全面的に依存してしまうわけですよ。でまた、自分は夫の収入に依存しているという後ろめたさがあるので、夫の要求には必死で応えようとしてしまう、と。 そうなると、もう召使ですよ。「夫:飯。」「妻:はいはい。」、「夫:風呂。」「妻:はいはい。」、「夫:これやれ。」「妻:はいはい。」「夫:あれやれ。」「妻:はいはい。」ってなもんです。これは結局、夫に対して「あなたは何もしなくていいです、家のことは私が全部やりますから」というメッセージを終始発しているようなもんですから、夫は家庭のことをどんどん顧みなくなっていく。 で、召使に成り果てた妻は、夫のこと、子供のこと、家のこと、ぜーんぶさせられ、その挙げ句、夫には浮気されちゃったりするわけですよ。で、そうやって家庭が崩壊したとき、妻は「何で?」と思うわけですが、夫をそのような方向に駆り立てた責任の一端が自分にもある、ということには気づかないんですな。 もちろん、家庭と仕事を両立させようという女性もいます。しかし、それなりの収入を得ている女性ですら、自分の収益は家系の「足し」に過ぎない、と考えがちで、やはり依存体質からは抜けきらず、夫に悪いと思って家事を引き受けてしまう、というのですって。で、仕事で疲れ、家事で疲れ、年がら年中くたくたになってしまう、と。 それから、たとえば同じような学歴を持ち、同じような将来の目標があるカップルなんかでも、まず女性の方が自分から身を引いて、「私が働いて稼ぐから、その間、あなたは勉強を続けて」みたいな感じになるらしいんです。そう言われたら、男の方は「ラッキー!」ってな感じで勉強を続け、自己実現してしまう。しかし、一旦、男の給料で生活が成り立つようになると、例の依存体質が出て、奥さんの方は中断した勉強を続ける気にはならなくなるらしいんですな。そうなると、奥さんの方は「夫を立たせた偉い妻」という美談にはなるかも知れないけれど、ただそれだけの話で、結局自己実現はできなかったということになってしまう。 女性ってのは、損ですなあ。 だからこそフェミニストたちは、こういう女性に押しつけられた損な役割は不当だ、と言ってきたわけですが、『シンデレラ・コンプレックス』の著者は、そうではない、こういう損な役割は女性に「押しつけられた」のではなく、「女性自身が勝手に引き受けた」んだ、ということを主張したんですな。そこが新しいところ。 つまり、コレット・ダウニングによれば、「女性の自立」という時に必要なのは、経済的な自立ではない、と言うわけですよ。必要なのはもっと精神的な意味での自立、すなわち「自己否定」からの自立であり、「成功恐怖」からの自立であり、「依存体質」からの自立だ、というわけ。それらを踏まえた上でないと、いくら経済力をつけてもダメなんだ、というんですな。まず己を知れ、ということでしょうか。 とまあ、『シンデレラ・コンプレックス』の言わんとしているところをかい摘んで述べてみましたが、上に述べたようなことを、著者が見聞きした実例を踏まえて実証しているので、とても説得力があります。実際、よく似た例が読者の身の回りにいくらでもありますからね。というわけで、この本、特に女性の方にはお薦めします。男の私だって「なるほど」と思うのだから、女性だったらなおさら、「!」と思われるのではないか知らん・・・。ちなみに、楽天ブックスではすべて「在庫なし」になっていましたので、興味のある方は古書店で捜してみて下さい。ベストセラーになった本ですから、案外簡単に見つかると思いますよ。 ところで、偶然というのはオソロシイもので、私がつい先日読み終えた『マージョリー・モーニングスター』という小説、あれもよく考えてみれば、才能もあり、美貌もあり、チャンスもあった女優志望のマージョリーが、結局自己実現することなく、平凡な家庭の主婦になってしまう話だっんですよね・・・。それから、今読んでいる『ダ・ヴィンチ・コード』、あれだって結局、古代からの「女性信仰」が、キリスト教、特にカトリックの父権的世界観によって潰され、歴史から抹消される、という話でしょう? そこへ持ってきて『シンデレラ・コンプレックス』ですから、なんだか「女性の受難・3部作」みたいになっちゃった。 女に生まれるってのはしんどいもんだなあって、つくづく思いますね。
August 7, 2006
コメント(2)
-
花火の夜を楽しむ
昨夜は家から車で20分ほどのところにある「三好池」というところで行われた花火大会に、家内と連れ立って行って来ました。 毎年8月の第一土曜日の夜に行われるここの花火大会、見に行くのはこれで3度目かな? ま、打ち上げ花火数1200発、観客3、4万人程度の小規模な地元のお祭りですけど、なにせ近くて行き易いのでね。普通、花火大会というと、交通手段や駐車場の問題があるわけですが、三好池の花火大会の場合、近くにあるジャスコの大駐車場に車を止めることができるので、ノープロブレムなんです。ジャスコもその点は太っ腹で、明らかに花火目当てで車を止める客がいても、別に咎め立てはしません。実際、花火客の多くが、行きか帰りにジャスコで何か買いますからね、それなりに商売になるのでしょう。 で、3度目ともなると、もう準備も万端。最初に行ったときは手ぶらで行ったのですが、「折り畳み椅子があると便利だよね」ということになり、前回からは椅子を持参。また前回は花火が終わった後、9時半頃になってようやくファミレスでの夕食にありつくことになってしまったので、今回は弁当持参で行く事にしました。会場に向かう前に「サブウェイ」に立ち寄り、サブウェイ・サンドを買って行ったんです。 ということで、今回は花火が始まる30分に好位置に椅子を据えて陣取り、サブウェイ・サンドをもりもり食べ、食べ終わった頃に花火の打ち上げが始まるという最高のシチュエーションとなりました。人間、過去から学ぶと、いいことがあるもんでございます。 で、その花火ですが、やっぱりきれいでしたよ! 最初のうちこそ、一発打ち上げてはスポンサーの名前なんか述べ立てるので、少々迫力不足でしたが、最初のスターマインで盛り上がり出し、最後の方では尺玉がそれなりにガンガン上がるので、なかなかのもの。 それで、大きい花火がお腹に響く大音声で「ドーン!」と炸裂する度に、隣に座っている家内がビクッとするのが、ちょっと可愛かったりして・・・。 しかし、こういう花火大会を見ると、つくづく「花火師」になりたいなーって思います。スターマインを連続で打ち上げる時とか、きっと誇らしい気持ちなんでしょうなあ。 ところで、やっぱりこういう花火大会は、最後の最後が最大の見どころです。三好池の花火大会では、会を締めくくる最後のスターマインの時に「水上花火」も一緒にやるんです。夜空ではスターマインが、池の水面では水上花火が、それぞれ炸裂するさまは、それはもうすごい迫力です。 そしてその後、今度は「ナイアガラ」が光のシャワーを演出! 池の水に反映してきれいなこと! 私たちのすぐ後ろに陣取ったおじさん、おばさんたちが、「三好の花火なんて馬鹿にしてなめとったけど、大したもんやなー」と喜んでいましたが、まったくその通りでしたね。 そして花火が終了してから、浴衣姿も数多く混じる他の花火客と一緒にぞろぞろと歩いてジャスコに戻ってみると、帰り車で駐車場は大混乱。ということで我々はもう少々ジャスコで時間潰しをすることにしました。ここ、一般の店舗は10時まで、スーパーマーケット自体は11時まで営業しているのでね。ま、本屋を覗いたり、ジェラート屋でジェラートを食べたり。ちなみに、三好ジャスコ内のジェラート屋さん「Gクレープ」って、結構レベルが高いんですよ。お近くの方は一度お試しを。 で、もうそろそろいいだろうということで、10時過ぎに我々も帰路につきました。家までは20分ほどのドライブですが、真夏の夜、こんな時間にドライブするのって、いい気分です。気分が若返ります。ちなみに私の気分はもともと18歳くらいなので、これが若返ると15歳くらいの気分になるっちゅーことですが。 とまあ、そんなわけで、昨夜は夏の夜を存分に楽しむことができたのでした。今日も(昨夜も)、いい日だ!
August 6, 2006
コメント(0)
-
世の女性たち! 軟禁された時、あなたはどうする?
今、コレット・ダウリングという女性が1981年に書いた『シンデレラ・コンプレックス:自立にとまどう女の告白』って本を読んでいまして・・・いや、別に好きで読んでいるわけじゃないですよ、仕事、仕事。たまたま古本屋で柳瀬尚紀訳の三笠書房版を見かけたので、今、自分がやっている研究に少しは役立つかと思って買ってみたわけ。これ、ベストセラーですよね、確か。「シンデレラ・コンプレックス」という言葉も結構流行ったし。 あれ? 柳瀬尚紀って、数年前に翻訳不可能と言われたジェイムズ・ジョイスの『フィネガンズ・ウェイク』を訳して話題になった人ですよねぇ。くそー、こんなところで小金を稼いでいたのか! ・・・まあ、それはともかく。 で、この本の著者が何を言っておるかと申しますと、要するに女性ってのは、常に誰か自分を扶養してくれる人、自分を引っ張って行ってくれる人を求める「依存体質」があるって言うんです。 子供の頃はまだいい、って言うんですね。子供の頃は女の子も男の子と同様、自分の可能性に対する夢を持てるわけ。成績だって、むしろ男の子よりいいし。しかしその時代っていうのは、結局(父)親の庇護下にあるわけですから、見かけは好き勝手にやっているようでも、実際には頼れる人の下で遊んでいるに過ぎないわけですよ。 ところが大学も出て、社会に出て、初めて給料もらって自由を得て、楽しい楽しいと言いながら数年が過ぎる頃には、もう女性は不安になってくるっていうわけ。「私、いつまでこうやっているのかしら、いつまで自分の生活を自分で支えていないといけないのかしら」っていう不安ですね。 で、これが出始めると、女性はもうおしまい。たとえ出世できるよって言われても、出世なんかより、もうさっさと結婚して、夫の庇護下に入りたいって思うようになっちゃうんです。もちろん、そこまで露骨に「結婚相手捜し」をしない人でも、自分の目の前に広がるぼんやりとした将来を、どうやって埋めていけばいいか分からなくなってしまうんですな。 そんな状態ですから、社会で働くことと、家庭に入ることの選択肢があれば、たいていの女性は後者を選んでしまう。アメリカでの様々な調査によれば、子供の時に優れたIQを示した女性の多くが、結局そういう形で家庭に入ってしまい、自らのキャリアを存分に伸ばしている人なんてほとんどいないんだそうです。 つまり、ウーマン・リブだ、フェミニズムだといって、苦労して「男女同権」を手に入れたとしても、女性の心の奥に根強い依存体質が、つまり「シンデレラ・コンプレックス」がある以上、せっかく勝ち得た権利ですら実際には行使できないんですよ、と、コレット・ダウニング女史はおっしゃるわけ。 ・・・ま、この本、もう四半世紀前に出た本ですから、この理論が今どのくらいの説得力を持っているか、私には分かりません。ひょっとすると、「もうそんなの、古い古い」っていうことなのかも知れない。 それに、この本の文体もね・・・。たとえばこんな感じ・・・「『他者』を必要とし、『他者』に執着する気持ちは、ありとあらゆる点で、女の生産的能力を阻止する---独創性、熱意、傾倒を禁じるのだ。女の救いは他者への執着にあるという神話は、女が働くことを要求されることは決してないのだという暗黙の結果を孕んでいる。突如として働くことの必要に迫られたとき、多くの女は内心、激しい憤りに燃える。働かなくてはならないということは、なにかしら自分が女として失格した徴なのだ」・・・。直截的に畳みかけるような感じで、無駄がないのはいいけれど、遊びがないので息が詰まってしまう。差別的なことを言いますけど、こういう文章こそ、古い典型的なフェミニストの文章って感じがします。芸がないよ、芸が。 しかし・・・。しかし、ですね。私が思うに、この人の言っていることは、かなりの程度当たっている、というか、現代でも通じる話しじゃないかな、という気はするんです。確かに、女性の依存体質ってのは抜き難いところがあるな、と。 さて、ここで話はポーンと飛びます。 時々あるじゃないですか、軟禁される女性の話。つい最近も、大阪の方でどこかのマンションに数ヶ月も軟禁されていた女性が保護されましたよね。もっと前には、数ヶ月どころか、何年も軟禁されていた女の子がいました。 で、私、こういう報道がある度に、不思議な話だなーって思ってたんです。 つまりね、もし私が軟禁された女性と同じ立場だったら、うまく逃げるだろうなと思うんですよ。 だって今回の大阪の事件だって、たかだかマンションの入り口のドアに外側から鍵をかけられただけでしょ? なんでベランダから逃げないの? ベランダの仕切りってのは、破ろうと思えば簡単に破れるようになっているのだから、ベランダに出てどんどん隣に逃げればいいじゃん? あるいはベランダから外の通行人に助けを求めるとか・・・。それだけじゃなく、逃げ方なんて他にいくらでもあると思うんです。 それに今回の事件で被害者の女性は、メールで友人に「軟禁されて、会社にもお料理教室にも行けない」なんて連絡しているみたいですが、そんなことしている間に、警察に電話しろって話ですよね? 私、間違ってます? ま、とにかく、こういう報道がある度に不思議だなー、何で逃げないのかなーって思っていたんですが、今回、『シンデレラ・コンプレックス』って本を読んでいて、ははーん、と思ったんですよね。ひょっとして、こういう軟禁事件の被害者の女性たちは、依存するものに事欠いて、とうとう犯人に依存しちゃったんじゃないか、と。自分自身の創意工夫で逃げ道を切り拓くより、犯人がいつか逃がしてくれるのを気長に待つ、みたいな感じ? 逆に言うと、「依存体質」のない男性は、理論的に軟禁できないわけですよ。自分でアクションを起して逃げようとするから。そう考えると、「自分だったら、逃げてみせるのに」という私自身の思いにも説明がつきます。 どうなんでしょう、世の女性方。あなた自身が軟禁された時、どうします? やっぱり、囚われのお姫様になっちゃうんですか? その辺、どうぞご意見をお寄せ下さい。白馬に乗った誰かさんが、すぐに助けに来てくれるとは限りませんぞ~!
August 5, 2006
コメント(4)
-
脱力! 世紀の大(アンチ)ロマンス『マージョリー・モーニングスター』を読む
このところ仕事の合間や寝る前などの半端な時間を使ってずっと読んでいた『マージョリー・モーニングスター(Marjorie Morningstar)』という小説を読了しました。『ケイン号の反乱』などの作品でも知られるハーマン・ウォークというアメリカ作家が書いた、大判565ページという電話帳みたいな本ですけど、1955年、アメリカで大ベストセラーとなった小説です。 内容は、と言いますと、うーん、ま、一応「恋愛小説」なんだろうなぁ・・・。でもある意味、強烈な「アンチ・ロマンス」でもありますね。とにかくその内容に、ワタクシ、仰天しました・・・。ちなみにこの小説、かつて大久保康雄訳で翻訳されたことがあるらしいですが、当然絶版ですし、今頃こんな長編恋愛小説を読む人がいるとは思えないので、以下、筋書きを言ってしまいますね。 主人公のマージョリーは、ロマンスの定石通り、最初はハイティーンの設定です。若く、美しく、希望に満ちあふれ、自分の目の前には輝かしい未来が開けているような気がしている。そして彼女の将来の夢とは、ずばり、女優になること。そしてその時には、「モーゲンスターン」なんていうユダヤ人っぽい名前ではなく、「モーニングスター」という芸名を使う予定。「マージョリー・モーニングスター」なんて、いささか気恥ずかしいような芸名ですが、フレッシュな新進のスターにはぴったりかも知れません。 でまた、マージョリーがそんな大それた夢を見るのは、無理もないんです。というのも、輸入業を営む彼女の父親の仕事がそれなりに順調で、一家は庶民的なブロンクスのアパートを引き払い、マンハッタンはセントラル・パークを見下ろす高級アパートに引っ越したばかり。ま、彼女自身は学費の安い公立の短大みたいなところに通うことになりましたが、それにしたって彼女ほどの美貌であれば、コロンビア大学などのアイヴィーリーグに通うイイトコの坊ちゃんたちが放っておくはずがない。また上昇志向のあるマージョリーの母親も、娘がイイトコのボンボンと付き合うことにまったく異議なし、と来ているのですから、マージョリーが数多のボーイフレンドにチヤホヤされ、いささか大それた夢を見たとしても不思議ではありません。それに、大学の演劇祭で主役を務めたマージョリーは、今や花形です。 ま、そんな彼女がブロンクス時代からつきあっていた年上のボーイフレンドからの求婚を反故にしたのも、親父さんの経営するガススタンドでバイトする貧しい青年では、彼女の青雲の志に釣り合わないと判断したからだったんですな。その辺は若さゆえの残酷さと言いましょうか。 しかし、そんな彼女に、ついに「運命の人」が登場します。演劇の勉強をしがてら、バイトに行ったサマーキャンプで、演劇関連総合プロデュースをしていた9歳年上のノエル・エアマン。劇作家志望で、作曲もし、既に何曲かのヒット曲も持っているこの青年、背は高く、ブロンドで、魅力的な顔立ちであることはもちろん、ピアノはうまいし、ダンスもうまい。そして当意即妙、才気煥発の人を逸らさぬ話しぶり。ただ一点、片腕に若干の障害を持つものの、マージョリーからすれば「大人の男の魅力」のすべてを持ち合わせているようなノエルの出現に、彼女は一発でノックアウトされてしまいます。 と言えば、もちろん誰にも想像がつくように、『マージョリー・モーニングスター』という小説は、マージョリーとノエルとの大恋愛のお話なんですな。でありますから、ここから先はまさに恋の駆け引き。嬉し、楽しい状況です。 しかし、そんな恋する二人の間にも、それなりに障害物があります。たとえばマージョリーの家は敬虔なユダヤ教徒ですが、一方のノエルの家は、同じくユダヤ系とは言え、宗教とは無縁のモダンな生活ぶりです。またノエルの父親は有名な裁判官で、バックグラウンドの点では文句はないものの、ノエル自身は名門大学を中途退学して「劇作家」などというあやふやなものを目指しており、堅実さを尊ぶマージョリーの親(特に母親)の目から見ると、娘にふさわしい相手とは思えないところがある。 ま、そんなこともあったりして、マージョリーとノエルの恋は進展と後退を繰り返します。片方が押せば、片方は逃げる。片方が他人行儀を決め込めば、もう一方がやきもきする、という展開で、ある時はノエルがマージョリーを捨て、ある時はマージョリーがノエルを袖にし、そんなことが延々と繰り返されるわけ。たとえばマージョリーと結婚するため、ちゃんとした仕事に就こうと、ノエルは広告エージェントの仕事などを始めたりするのですが、やはり演劇への野望を捨てきれず、このままマージョリーと結婚してしまったら自分の才能が潰されると感じて、彼女のもとから出奔したりする・・・ま、そんなことの繰り返しです。 で、二人の仲がうまく行っていない時など、ノエルの後輩でマージョリーの熱烈なる讃美者にして、小説を通してピエロ的な役割を果たすワリー・ロンケン君がマージョリーに言い寄ったりもするのですが、もちろん彼女としてはノエル以外の男なんてつまらないゴミですから、ワリーはいつも子供扱い(実際、ワリーはマージョリーより1歳年下)されて追い払われてしまう。ま、ノエルにしたってマージョリー以外の女なんてつまらんと心の底では思っているのですから、二人とも素直になって、さっさとくっ付いちまえばいいようなもんですが、ヒーローとヒロインがくっつきそうでなかなかうまく行かないというのが、ロマンスの醍醐味ですから・・・。 しかし、そんな別れと再会を繰り返している時、ついにノエルのオリジナル戯曲がブロードウェイで上演されることになります。その開幕の直前、ノエルとの再会を果たしたマージョリーは、栄光を手にしようとしているノエルのオーラに圧倒されるように、ついに彼と一夜を共にしてしまう・・・。なーんて言うと大袈裟に聞こえますが、なにせ設定が1930年代末ですから、結婚前の女性が男性とことに至るというのは、それこそ清水の舞台から飛び下りるようなものなんですね。ですから、この時点でマージョリーはノエルとの結婚を確信したと言っていい。 ところが。ノエルの劇は3日で打ち切りになるという大失敗、彼のブロードウェイ・デビューは惨憺たるものになります。(ええ!? それまで読者はノエルのきらめく才能について嫌というほど聞かされていたのにぃ?) で、これに衝撃を受けたノエルは、マージョリーと演劇を捨て、パリに行ってしまうんです。 しかし捨てられたマージョリーはますますノエルの愛を信じ、1年間働いてお金を貯め、ノエルを最終的に射止めるために彼の後を追ってパリに行きます。パリ行きの船の中で、ナチス支配下のドイツからユダヤ人を逃亡させる裏家業に携わっているマイク・イーデンという年長の人物と出会い、彼の過去、そして現在の生き方に強く惹かれるものはあったのですが、やはりノエルには替え難いと知ったマージョリーは、パリでついにノエルを見つけ出すんです。 そして1年前には残酷な言葉と共にマージョリーを捨てたはずのノエルも、この再会でついに心を決めることになります。ついに、ついに、彼の口から求婚の言葉が! ほぼ500ページにわたって延々と述べられてきたマージョリーとノエルの恋は、ついにここに至って成就の瞬間を迎えた! ・・・はずなのに!! ワタクシが仰天するのはここですわ。なんと、なんとですよ、なんと、マージョリーはノエルのプロポーズをすげなく拒絶するんです。19歳の時から5年間、この日、この時を待ち続けたマージョリーにして、求婚の言葉がノエルの口からこぼれた瞬間、「ノー」という答えが確信として心に浮かんだってんですから・・・。 ちょっと! ちょっと、ちょっと! 意味不明。 で、帰国したマージョリーはほどなく堅実な、しかし平凡な法律家と結婚。ニューヨーク郊外に家を構え、4人の子供に恵まれ、地元の主婦連の間のリーダー的存在にはなるものの、どこにでもいる主婦となります。彼女の夫となったミルトン・シュワルツとマージョリーの仲は、結婚の時にマージョリーが処女ではなかったということがきっかけで、当初期待されたような熱烈なものではなくなってしまったものの、ごく平凡な夫と妻という関係を築き上げることには成功する。 小説の最後は、マージョリーの讃美者にして、今ではブロードウェイで成功を納めたワリー・ロンケンの視点から見たマージョリーの姿で締めくくられます。マージョリーの結婚から15年経った頃、偶然、ワリーはマージョリーと再会するんですね。 そこでワリーが見たものは、40歳を前にしてすっかりオバアサンになってしまった白髪のマージョリーだったんです。あの生き生きとした、輝くばかりの美しさでワリーを子供扱いし続けたマージョリーは、かすかにその面影を残すばかりになってしまっています。 で、ワリーは若干の復讐心から、自分のブロードウェイでの成功を印象づけつつ、ノエルのその後を知らせます。ノエルは、今や三流のテレビドラマ作家としてハリウッドで落ちぶれた暮らしをし、横暴な妻に養われている状態。しかし、そうしたことも、今のマージョリーにはもはや意味を持たなくなっている様子なんですな。結局、「マージョリー・モーニングスター」という華々しい存在は、実在することのないまま、ごく平凡な「マージョリー・モーゲンスターン」の中に、いや、「ミセス・ミルトン・シュワルツ」の中に消えてしまった。あれはやっぱり、遠い夢だったんだ、というところでこの小説は終わります。 いやー。びっくりでしょ? マージョリーとノエルのキラめくばかりのロマンスを565ページ読まされた上で、この仰天の結末。特にノエルの没落ぶりには愕然です。ちなみにワタクシ、一応「アメリカにおける大衆向けロマンス小説」ってのを現在の研究テーマにしているんざますけど、その見地からするとこの小説、ロマンスの概念に対する痛烈なアンチテーゼですね。「こうして二人は結婚し、末永く幸せに暮らしました」というロマンスの形式は維持しながら、読者を脱力させるほどの空虚感を与えてくれますから・・・。 しかし、びっくりし、脱力はしましたけど、ある意味、リアリティある小説ではありましたね。時代背景、状況描写、それぞれの人物造形など、どれをとってもしっかりしていたし。特に物語の主筋とは直接関係ないけれど、マージョリーと彼女の母親との関係、なんてのも、よく書けていると思いました。娘と母親の関係って、こうだよなーと思わせるところが大いにありましたからね。それにストーリー展開にしたって、たとえば「無限の夢を抱いていたけど、実現はしなかった」とか、「惚れた男の才能を過信したけど、実際は大したことなかった」なんてことは、現実にいくらでもあることであって、そういうふうに物語を展開させた方が、確かに現実的ではあるわけですよ。 結局、現実ってのはそうなんだよなぁ・・・と思わせつつ、「色々あったけど・・・いい時もあったじゃない・・・」と、読者にまで深い感慨に陥らせるところが、この『マージョリー・モーニングスター』のベストセラーたる所以なんでしょうな。 ということで、昨夜は20世紀半ばの一大恋愛叙事詩を読み終わって、いささか途方に暮れたワタクシだったのでした。 さて、私の「アメリカ大衆小説を読み続ける」試み、次はぐっと現代になりまして、ダン・ブラウンの『ダ・ヴィンチ・コード』を読んでみるつもりです。この間映画版を見ていま一つだったので、原作は面白いのかな、と。また読み終わったら、読後感などお知らせするつもりです。それでは、また!
August 4, 2006
コメント(3)
-
幻の「レモンカレー」を作る
今日は久し振りに私が腕を奮って夕食を作ることにしました。メニューはカレーです。 なーんだ、カレーなんて珍しくもない、なんて言う勿れ。今日作ったのは、「レモンカレー」なんですから。前にこのブログでご紹介した小淵沢のギャラリー「折々」でいただいた、段ボール・アーティストの本杉琉さん考案になる逸品です。 といっても、別に私は本杉さんから作り方を教わってきたわけではなく、ただ単になんとなく真似してみた、というだけなんですが。 で、普通にカレーを作る時のように市販のカレー・ルウを使ってしまうと、ちょっと感じがでないかなと思い、もう少し本格的なものはないかと探した結果、私が見つけ出したものはと言いますと・・・ ニチレイが出している「カレーBOOK」なるものでーす! これ、私も今日初めて見つけたんですけど、まあ、市販のカレー・ルウと、カレーパウダーから作る本格カレーの中間を行くようなものなんですね。つまり、本格的なカレーを作るのに使う各種スパイスが適宜調合され、5つの袋に分けて入れられているので、これを順に加えていけば、一応、本格的なカレーが出来上がるという次第。「辛さ自由自在。簡単、手作り感覚」というのがキャッチ・コピーです。 で、この「カレーBOOK」を用いながら、あとは私の思いつきで、幻の「レモンカレー」を再現しようというわけ。 さて、じゃ、どんなふうにしたかと言いますと、まず鶏肉の細切れ適量をオリーブオイルで炒めます。で、ある程度炒まったところで「カレーBOOK」の「炒め・煮込みスパイス」を加え、そこにタマネギの細切り、セロリと人参とニンニクを荒微塵にしたもの、シメジ一株分を加えてさらによく炒めます。そして白ワインを少々加えてアルコールを飛ばしたあと、水を600ccほど加え、さらにトマトの水煮缶を一缶分加えて40分ほど煮込みます。灰汁は掬って下さい。 さて、ここでいよいよカレーの味付けです。「カレーBOOK」に入っている「カレーフレーク」というのを一袋加えて5分ほど煮、さらに「仕上げスパイス」と「辛味スパイス」を加えて煮ます。「辛味スパイス」は2種類あって、黒胡椒ベースのものと赤唐辛子ベースのものが入っていますが、今日はトマトの赤を強調したかったので、赤唐辛子ベースのものだけを加えました。 さて、これで一通りカレーができました。で、最後にレモンを一個取り出しまして、こいつを丸ごと一個分、カレーの中に絞り込みます。できればスプーンで房も掻き出してカレーの中に入れちゃって下さい。これで「釈迦楽流レモンカレー」の完成です! で、昼過ぎには完成していたこのレモンカレーを、市販のナンと一緒に夕食として食べたのですが、そのお味はと言いますと・・・ うまーい!! 唐辛子系の辛味が効いて、さっと汗が出るような辛さではあるんですけど、それがレモンの酸味と合わさって微妙に中和され、爽やかな辛さを演出しています。もちろん、辛いといっても極端な辛さではないので、中辛のカレーが食べられる方ならまったくノー・プロブレムでしょう。これ、ナンだけでなく、カレーライスにして食べてもおいしそうです。いやー、しかしカレーとレモン味ってのは、本当によく合いますね。本杉さんのヒラメキに感動です。皆さんも一度、騙されたと思ってカレーの中にレモンを絞り込んでみて下さい。絶対、おいしいですって! さてさて、そんな感じで今日は昼過ぎから時間をかけてじっくり男の手料理を作りましたので、午後は気晴らしに少し勉強をしました。(注:本当は「今日は朝から沢山勉強したので、夕方、気晴らしに料理を作ってみた」が正しい学者のあり方です。良い学者の皆さんは、ワタクシの真似をしないように!) それから不義理をしている各方面に手紙を書いたり。そんなことをしていると一日があっと言う間に過ぎてしまいますが、ま、夏休みの一日なんて、こんなもんでしょ。 で、このあとは少し読書をしようと思います。ずっと読み続けている大部のアメリカ小説が、いよいよクライマックスなんです。また読み終わったら、読後感など書きますからお楽しみに! それでは、また明日!
August 3, 2006
コメント(6)
-
亀田勝利? うっそ~!?
先程、亀田選手の世界チャンピオン初挑戦を見ました。 試合は予想した通り、両者ほとんど足を使わないままの打ち合い。亀田選手の出だしは上々でしたが、第1ラウンド終了間際、まともに一発くらって不運なダウン。ゴングに救われた感じです。 その後の試合運びは、どう見ても相手選手の方が老獪でした。手数から言っても相手の方が倍くらいあったのではないでしょうか。さほどのパンチではないようでしたが、あれだけ当たれば効いてもきます。 実際、後半、11ラウンドあたりでは亀田はもうフラフラ、立っているのもやっと、というところ。12ラウンド、よく持ったという感じでした。亀田のパンチ、特にボディーへのパンチは、ある程度効いてはいたようですが、相手はその後のリカバーがうまいので、印象としてアピールできなかった感じ。 で、最後まで見終わって、あ、完全に負けたと思いました。で、テレビを消してしまった。 ところが、なんと! あとで聞いたら、判定で亀田勝利ですって? うそ~! ダウンもしたし、最後はあんなにフラフラだったのに? それはないんじゃないの? 私はもちろん亀田を応援してましたけど、贔屓目に見ても相手側勝利じゃない? なーんか、納得できないなあ。この試合、どうせすごい視聴率で、見た方も多いと思いますが、亀田が負けたと思ったのは私だけでしょうか。この判定じゃ、会場が日本だったから勝った、と言われても仕方がないんじゃないかなあ・・・。 うーん、わけ分からん! 皆さんのご意見や如何に?!
August 2, 2006
コメント(6)
-
フジ・ロックフェスティバル
昨日のブログで、雑用を大学院生に手伝ってもらった、と書きましたが、その際、彼から「フジ・ロックフェスティバル」についての話を聞きました。今年のフジ・ロックはつい先日、7月28日から30日にかけて新潟県の苗場で行われたのですが、彼、I君は、これに参加してきた、というのです。それも、タダで。 なぜタダか、というと、名古屋の某ラジオ局でフジ・ロックのペアチケット(3日間通し券で8万円相当)が当たるイベントか何かをやっていて、I君はこれに応募し、見事チケットをゲットしたんですな。 ちなみに彼は私のゼミ出身なのですが、どういうわけか私のゼミに入ってくる男子学生は揃いも揃ってロック好きのギター好き、そしてやたらに筆の立つ天性の文章家ばっかりなんです。で、I君もその例外ではなく、ものすごく文章がうまい。その彼がフジ・ロックにかける熱い思いを認めてプレゼントに応募し、それが主催者の目に留まった、というわけですから、彼が手にしたチケットにしても、それは偶然引き当てたのではなく、まさに実力で入手したと言っていいでしょう。彼の書いた文章は、ラジオでそのままオン・エアされたそうです。 ところでその「フジ・ロック」ですが、これがどういう種類のイベントかと申しますと、要するに苗場の広大な敷地に特設ステージを幾つも設け、3日間の間、ほとんど昼夜ぶっ通しで国内外の大物ロック・ミュージシャンたちがコンサートを開く、というものなんだそうです。あっちのステージでもこっちのステージでも、有名どころがガンガン演奏するわけですから、ロックファンにはたまらないビッグ・イベントなんですね。で、ここに集まってくるのは、筋金入りのロックファンばかりですから、3日間、あちこちのステージを見て回っているうちに自然と顔見知りも出来るのだそうで、そこで意気投合した急ごしらえのロックファン仲間が、夜な夜なキャンプの酒盛りでさらに盛り上がる、なんてこともあるらしい。 またフジ・ロックのいいところは、変な言い方ですが、チケットの値段が高いことなんですって。つまり、この値段では高校生などの若年ロックファンには手が届かず、フェスティバルの参加者の年齢層が20代後半から30代、場合によっては40代・50代となるので、ロックの祭典と言っても変にキャーキャーせずに、「落ち着いて音楽を楽しもう」という雰囲気が漂うのだとか。大人のフェスティバルなんですな。 それから、もう一つ、このフェスティバルのいいところは、食事がうまいことなんだそうです。会場ではあちこちに本格的な食事のできる屋台が出るらしいのですが、これがことごとく安くてうまいんですって。I君は、一日5食、3日間で15食、全部違う屋台で食べたそうですが、どれも皆うまかった、と言ってました。ふーん、なるほど。 なんか話を聞いていたら、私もちょっと興味が出てきましたよ。 ま、フェスティバルに登場するアーティストの顔ぶれを聞くと、たしかに有名どころではありますが、私の好みかというと、ちょっと違うかな、というところはあります。でも、真夏の夜、「苗場」という非日常的な空間で、大人たちが好きな音楽に興じる、というのは、なんとなく心惹かれるものがありますね。食事がいい、というのも魅力ですし。ペアで8万円というチケットは、ちょっと高過ぎる気がしますが・・・。 ・・・あ、そうか。私も熱い熱い文章を書いて、ラジオ局に送ればいいのか。弟子のI君にできるのですから、師匠格のワタクシにできないはずはないし・・・。 ちなみに、今私が読みかけているアメリカの小説の中に、「大人のためのサマーキャンプ」というのが登場するんです。夏の間、ニューヨーク近郊のとある島に、大人だけのキャンプが開かれ、そこで一夏を通して様々なコンサートや劇などのイベントが行われるんですな。もちろん、大人だけの、というところがミソで、滞在客の間で色々なアバンチュール(?)が生じ、それこそがここで夏を過ごす主たる目的であったりするわけですが、とにかく、そういうイベントがあるらしいんです。 ま、それとフジ・ロックは違うでしょうけれど、小説で読んだことと、I君から聞いた話がごっちゃになって、なんだか面白そうだな、と思った次第。 この夏、私自身はあまり大きな旅行とかイベントの類は計画していないのですが、昨日はフジ・ロックの興奮醒めやらぬI君の話を聞いて、なんだか自分もそのフェスティバルに参加してきたような気になってしまったワタクシだったのでした。 さて、今日は久し振りにアフィリエイトもしておきましょう。先日、東京の実家に戻った際、町を歩いている若者たちが、ラガシャのバッグを手にしているのを何度か見ました。結構流行っているみたいですね。ということで、フリーページの「教授の鞄」を改装し、ラガシャのバッグを仕入れてみました。値段はお手頃、しかもデザイン的には今風ですから、なかなかいいですよ。ビジネス・トートからボストンバッグ、さらにはセカンドバッグや長財布まで取り揃えていますので、興味のある方はぜひ覗いてみて下さい。これこれ! ↓教授の鞄
August 2, 2006
コメント(2)
-
痛ましいプールの事故
埼玉県ふじみ市の市立プールでの事故、亡くなられた女の子は気の毒ですなあ。 いやー、実は私、子供の頃にこれと同じようなプールの事故を遠巻きに見たことがありまして。 母方の祖父母の家(群馬県安中市)のすぐ目の前に市営のプールがあって、私は夏休みなどで帰省する度にそのプールで遊んでいたのですが、ある時、いつものように遊びに行こうと思ったら、なんだかやけに騒がしいんですよ。いつもは閑散としているプールなのに、その日に限って黒山の人だかり。プールを見下ろす道にも、人が沢山出ています。 しかもそれだけではない。消防車が何台も停まっていて、それらがプールの水をポンプで汲み出し、隣を流れる河に放水しているんです。 で、あとで聞いたら、プールの排水口に子供が吸い込まれたんですと。 もちろん、その子も亡くなりました。なにせすごい水圧で穴に吸い込まれるので、人間の身体が細いパイプの形に押しつぶされてしまうのだそうです。 いやー、今回の事故の報道を聞いて、子供の頃に見たプール事故の映像をまざまざと思い出してしまいましたよ。コワイですなあ。それ以来、私もプールの排水口にはたとえしっかり蓋がしてあっても、なるべく近づかないようにしておりますです。もっとも、最後にプールに入ったのは何年前だったか、覚えてないほど昔の話ですが。 ま、どうも報道を見る限り、こういうのは人災という感じが強いですが、元来、そういう人災が起こらないように工夫してプールを設計するのが筋だと思います。この事故をきっかけに、プールの安全性を確認する動きが出ているようですが、そうすることで亡くなられたお子さんのせめてもの供養になればいいですなあ。 しかし、今回のようなことで、事故にあわれたお子さんが通っていた小学校の校長先生まで取材したりするのはどうなんでしょうか。その小学校のプールで起こった事故ならともかく、夏休み中の他施設での偶発的な事故のことまで、校長先生に取材する必要などないですよ。学校ってところは、そんな365日、24時間体制で子供のことに責任を負わなければならないところじゃないです。それは親の仕事だ。自分の子供の安全を、他人に託してどうするんだって。 ついでに言えば、その学校の子供たちの「心のケア」とやらもする必要ないです。なんですか、「心のケア」って? 馬鹿馬鹿しい。大人がそんなこといって甘やかすから、ひ弱な子供が育つんですわ。そういう事故があって危険だから、そういうところに近づくなよ、と親が一言、言えばいいだけのことじゃないですか。いや、そんなこと親に言われなくったって、子供が自分で怖いと思えばいい。簡単なことです。まったく、「心のケア」なんて嫌な言葉、誰が使い出したんだろう・・・。閑話休題。 今日は野暮用があって大学で雑用をこなしておりました。雑用ってのは、ほんとに雑用なのであって、印刷物を折って封筒に入れる作業です。 ちなみに、この印刷物というのは、お手製の「同窓会報」なんですな。大学全体の、ではなく、うちの科の卒業生だけに向けて年一回出される手作りのニューズレターです。 ま、本当はこういうのは同窓会自体がやる仕事なんでしょうけど、現在のところこの卒業生組織が十全に機能していないので、結局、原稿執筆依頼・編集・印刷・袋詰め・宛て名書き・郵送に至るまでのすべてのプロセスを私一人がやっているんです。今日の袋詰め作業に関しては、大学院生の指導学生を一人応援に呼んで手伝ってもらいましたけどね。 でも、この同窓会報が、卒業生と我々教員をつなぐ唯一の絆なものでね。でまた郵送してから1週間ほど経つと、ぼちぼちと反響があったりするんですよ。「会報を読んで、学生時代が懐かしくなりました」とか、「同窓の皆がそれぞれ頑張っていると知って、励まされました」なんて頼りが、私のもとに届くわけ。数はそんなに多くはないですが。 しかし、一人でもそういう反響があったりすると、「止められないよなあ」と思うんですよね。面倒臭いと思いながらも、発送まで済んでしまうと、早く反響が来ないかなあ、なんて期待しちゃったりして。 ま、とにかく、今日のところで今年も同窓会報の発行という恒例の行事が一つ済みました。よかった、よかった。今日も、いい日だ。
August 1, 2006
コメント(4)
全33件 (33件中 1-33件目)
1