2007年09月の記事
全16件 (16件中 1-16件目)
1
-
企業は人なり
「企業は人なり」と言うが,有能な人材は一体何処にいるのだろう.僕のやり方はもちろん,身近な社内から探すということだ.万能な人材は,少なくとも中小企業にはいない.多少名の知れた上場企業にだってそんなに優秀な人はいない.社外を探しても殆どいない「青い鳥」を求めても仕方がない.そして本当に必要な人は,実は社内にいると思うのだ.もちろん社内を見ても,「こいつは優秀だ」と明らかに思える人材はいないに決まっている.もし本当に優秀だと思うのなら経営者をその人に代わるのが「合理的」だし,逆に言うと「まあ自分の方が優秀だ」と(贔屓目に)思っているから経営者を続けていられるのかも知れない.そうするとどうするのか.僕は「人単位」で評価しないで「特定能力単位」で考えるようにしている.「「この人は事務能力は皆無だけど,交渉能力はある」,「基本は全くなっていないけれど,事態は何とか収める」,「要領は全然駄目だけど,人は良くて知識がある」,「殆ど何も出来ないけど,真面目で人望はある」などなど,欠点は誰でもあるけれど,同時に,長所がひとつもない人間なんていないのだ.大事なのは,素直な心と真面目な生き方である.それさえあれば,必ず何処かに長所があって,会社としては「それ」だけを発揮してもらうように組織を作っていけば良い.よく「パズルの様」と言うのだが,適材適所でパズルのピースを埋めるように,長所を出し短所を隠し,全体としてひとつの機能が発揮できる会社組織を構築していけば良いと思っている.経営者にとっては,「人を見る目」,「人の長所を見る目」,そして真面目な生き方をする人を評価する心があればいいってことだと思う.それにはまず自分がしっかりとした価値観を持たないといけないのだ.
Sep 27, 2007
コメント(7)
-
システム検討
最近は,システムの点検,検討,改善の打ち合わせをすることが多い.当社の場合,情報共有のためのグループウェア,営業情報管理のための専用ソフト,もちろんメールやメーリングリスト,さらにはブログなども組み合わせて社内外の情報を出来るだけ共有している.最近いろいろな所で言われているのは,「情報は共有するとそれだけで,自発的な個人・集団により改善される傾向がある」ということだ.「可視化経営」とか,「プロセスの見える化」とかいわれているのがそれで,ブラックボックスに入ってわからなかったものをきちんと整理して,リアルタイムで目の前に差し出すと,人々は普通改善を始める.元はと言えば,トヨタのカンバン方式だってそうで,「今この工程で必要な部品は何と何がいくつだ」という情報を,カンバンに書いて一目瞭然にするだけで,工程が改善され,部品がジャストタイムに納品され,生産効率が上がる.実際はそんなに簡単なものではないが,要するに,実態を見えるようにするのが効率改善の第一歩となるのだ.どこの企業でも,すべての情報が整理されて目の前に提示される訳ではない.だからこそ悪気はなくても顧客を怒らせてしまったり,商品開発ニーズを見過ごしたり,事業機会を逸したりするのだ.わかりさえすれば,常識的に良心のある個人は,目の前の課題に取り組むものだと思うのだ.当社では以上を踏まえて,情報共有化の努力を続けている.システムも改善しないといけないし(お金がかかる),個人の能力も上げていかねばならない.でも最終的にはそれは顧客のため,社会のため,社員の物心両面の充実のためだと思うから,引き続きがんばっていきたいと思います.
Sep 25, 2007
コメント(0)
-
組織戦略
会社の組織をどう構築するか,よく考えている.組織図というより,企業として一番効率的効果的にパフォームするのに,どういう意思決定の仕組みが適しているか,考えるのだ.とても参考になるのが,他の企業のやりかただ.梅田望夫氏がその代表的著作のウェブ進化論で書いている.「私が、はてなで仕事を始めてまず不思議に思ったのは、彼等が社内で電子メールをあまり使わないことだった。その代わり社員全員が、ビジョンや戦略の議論、新サービスのアイデアから、日常の相談事や業務報告に至るまで、ほぼすべての情報を、社内の誰もが読めるブログに書き込む形で公開し、瞬時に社員全員で共有するのである。特定の誰かに指示を仰ぐための質問、それに対する回答、普通なら直属の上司にまず報告すべき内容、すべていきなり全員に向けて公開するのである。」そして続けて,以下の様に書いている.「モティベーションの高いメンバーだけで構成される小さな組織で、すべての情報が共有されると、ものすごいスピードで物事が進み、それが大きなパワーを生む。」そう,当社の組織戦略もこれに近い.情報は共有が基本で,モチベーションの高いメンバーが積極的に発信していく.逆に言うと,上司が必ずしも正しい答えを持っているとは限らないから(その代表が僕),リスクヘッジの意味でもみなに何でも知ってもらった方がいい訳だ.ここで大事なのは,基本の面子を能力の高い人たちでそろえていくことだ.情報に接してピンときて,自ら発信しまた行動する人でなければならない.さて,現状はどうだろうか.望むらくは,感度の高い人たちであって欲しいと思います.
Sep 24, 2007
コメント(0)
-
目標
この間出席した,盛和塾全国大会の間に決心したことがある.これまで,先代の経営者が築いた基盤の上に事業を拡大してきた.これから数年の間に,少なくともそれに匹敵する事業,または商品開発をしていきたいと思う.「それに匹敵する」とは,現在が十数億円の売り上げだから,少なくとも十億円の事業,それも利益率が高いものを考えたい.そして人数は最小限にしか増やさずにとも思っている.それに成功すれば,既存のものとあわせて二つ目の事業・商品が成功することになる.そうすれば,三つ目,四つ目の道も開けると思う.盛和塾に入っている人たちは,大変な苦労をして起業したり事業を拡張したりしている.僕も負けないように,頑張っていきたいと思います.
Sep 24, 2007
コメント(0)
-
事業の目的
京セラには,稲盛さんが考え出した経営十二ヶ条があって,その第一条に「事業の目的・意義を明確にする」というのがある.当社の事業目的と意義は何だろうとこのところ,ずーっと考えている.目の前に顧客がいて売る商品があって,会社を成長させるためにひたすら売るということだけが事業目的であるはずはない.事業の目的とは,会社の「存在意義」というものである.当社は何のために存在しているのだろう.たまたま全国の害虫駆除業者さんが当社の主な顧客で,彼らは害虫防除を通じて衛生環境の改善を行っている.白蟻駆除業なら,家の維持管理が仕事だ.そうすると,当社は彼らに対するサポート業だから,彼らが仕事をしやすく,かつより社会的に尊敬され,事業としても伸びていくための後押しをするということが当社の役割か.「害虫駆除業界をサポートし,社会的地位を向上させることで,衛生環境を改善し,住宅を長寿命化させる」ということが,当社の現在の存在意義,つまり事業目的ということになる.当社と取引をいただいて,「本当に良かった,事業が伸びた,そして社会貢献できた」と言ってもらえることが,一番の目的だ.そして,当然,そのことを通じて当社の事業を伸ばし,社員の物心両面の充実を図るということを実現しなければならない.こういう基本的な立ち位置はとても重要だと思う.自分だけが儲けようと,事業目的も忘れてその時売れれば良いという態度では,長期的な成長は望めないと思う.やはり,しっかり原点に戻ることが必要だ.これから数年,当社も転機に直面することがあると思う.そのときは原点に戻り,「事業目的」をしっかりと思い出したいと思う.
Sep 22, 2007
コメント(2)
-
セミナー開始
昨日から,秋の全国セミナーが始まった.今回も内容はとても充実していて(と思う),技術的な内容から僕の経営セミナーまで,盛り沢山である.今回の僕の話は,「IT技術と経営」というテーマだ.Web2.0とかチープ革命とか言われる現象など,ここ数年でIT技術は相当進歩していて,それに伴って企業経営に使える技術の自由度が高まっている.セミナーでも話しをするけど,例えば,面倒くさい入力作業なんかを中国の大連やインドにアウトソースすることが一般的になっているし,検索技術の発展により,膨大なウェブの世界から本当に大事な情報を探しあてることも簡単になってきている.これだけ技術が進んでくると,どんな業界でも「やり方」を変えないと,生き残っていけなくなる.ある日突然,外国の会社がライバルとして出てくることもありえるし,逆にうまく技術を利用することで,これまで出来なかったことが出来るようになったりもする.そう,当社の属している害虫駆除の業界でさえ,大変革が起きつつあるのだ.続きはセミナーで,ってとこだが,内容もなかなかだと自画自賛しているので,ぜひ参加してもらって意見交換していただきたいと思っています.
Sep 21, 2007
コメント(2)
-
盛和塾全国大会
昨日今日の二日間,盛和塾の全国大会に出席してきた.今回も京都の国際会議場での開催だが,とことん勉強するつもりで泊りがけでの参加である.入塾して10年以上経つから,これまでも既に十数回,この全国大会に出たことになる.しかし今回の大会は,一番衝撃が強かったような気がする.経営体験発表者の多くは,非常に不遇な幼少時代を送り,そこから這い上がって成功してきた人ばかりである.盛和塾では,「魂を磨くこと」が目的となっているから,成功と言っても会社が大きくなったということだけでなく,以下に人格的に成長したかが重要だ.マイナスからのスタート,苦労に苦労を重ね,最後にはすべてに感謝しながら成功しながらも謙虚に生きる,っていう話が多かった様に思う.僕が衝撃を受けたのは,そういう明らかに底辺から這い上がった人の方が,一旦成功し始めたら,むしろ恵まれていた人よりも上の方まで行くということだ.考えてみれば当たり前で,何もかも恵まれない環境で這い上がる苦労に比べたら,ある程度のレベルでのんびりしている連中が競争相手の「普通の環境」では,楽に競争に勝っていけるということだ.「若いうちの苦労は買ってでもしろ」という言い方があるが,地でそれを行く体験発表だった.僕も恵まれた二世経営者である.ビジネスの基盤は既にあったし,まじめな社員も良い顧客にも恵まれている.ただでさえ恵まれないのに徒手空拳で起業してきた人たちに比べれば苦労も足らないし,経営も甘いのかも知れない.しかしそれでも社会という場所に出れば,自分を磨き,会社を成長させていかねばならない宿命だ.これまでは苦労らしい苦労もせずに生きてきたけれど,そろそろ壁にぶち当たって懸命に努力する時期なのかもしれない.こう言ったレベルの高い経営体験発表は本当に勉強になる.甘い当社(つまり自分自身)を見直す良い機会だなあと思いました.
Sep 19, 2007
コメント(0)
-
オープンソース化
このところ,「過程をオープンにすること」について書いている.つまるところ,今流行の「見える化」とか「可視化経営」とかいうものは,プロセスを誰でも見えるようにすれば,「自然に自発的な誰かが集まって良い様に改善されていく」という思想みたいなものだ.大きな話で言えば,リナックスという基本OSは,ほぼ完全に世界中のボランティアのソフトウェアエンジニアたちが創り上げた非常に優れたソフトだ.僕もよく使っているウィキペディアというネット百科事典も,ボランティアで誰でも書き込み,編集ができる.トヨタの「かんばんシステム」も,その工程で必要な部品を「あんどん」に明記して,多過ぎず少な過ぎず供給しようというものだ.課題を見せればきちんと対処するという人間の美質を生かしたシステムともいえる.京セラのアメーバ経営も,誰でも家計の管理ができるなら,小さく区切ったアメーバ単位の採算なら自分たちで創意工夫できるという考えに基づく.売上げを最大に,経費に最小にという経営の原則を,一人一人の社員が実践するために,自分たちがコントロールできる範囲で結果を見えるようにして,知恵を出し合うのだ.鉛筆を節約したからいくら,休み時間に電気を消したからいくらと,小さい金額の積み重ねが自分が属するアメーバの成績に反映され,見えるようになっている.会社という組織でも,もはや送り手が受け手を選ぶメールという手段でさえ,時代遅れになりそうだ.送り手は(多分名指しはしつつも)ある多人数の組織に向けてメールを送り,受け取ったグループの中から,自分こそはと思う人が返信するというスタイルになるのではないか.あまり意味のないメッセージだと誰からも無視されるし,面白そうな企画なら人が集まってきて自発的にタスクフォースが出来上がる.組織のあり方も,これからどんどん変わっていくに違いない.当社も社内でなるべく情報を共有化すべく,さまざまな工夫を凝らしている.当社も,知っていることはすべてセミナーなどの機会に顧客にぶつけてしまう.僕も今興味のある経営課題について話をしたり,他の講演者も最新の情報,最近得られた実験結果などを発表する.そうすれば,自然と参加者の皆さんと情報交換が始まり,なにか新しいものが生まれると思っている.こういうのって,まずこちらから情報をぶつけないと反応も返ってこないものなのだ.過程をすべて見せるって勇気がいるけど,これだけ社会が複雑になって顧客のニーズも様々なら,手の内をさらして一緒に考えるっていう姿勢が逆に正解なのかなあと思っています.
Sep 17, 2007
コメント(0)
-
ネットワーク型組織
「ネットワーク」という言葉は,現代の経営のあり方を示している良い言葉だと思う.企業は自分が得意なことに集中して,その他のことはそれを専門にする他企業に任せていく.いわゆるアウトソーシングである.このことはあのドラッカーが大昔にうまく表現していて,「その業務をやっていて社長にまで出世できない業務は外注した方がいい」と言っている.つまり,オフィス掃除を業務として正社員を雇っていても,その人がそれを極めることで社長に昇進することはないだろう.しかしオフィス掃除会社なら,当然本業である掃除を極めることで,社長に昇進したっておかしくない.要するに,周りの専門企業と協力しながら,自社の社員は「自社が本当にやるべきこと」に集中せよということだ.このネットワーク型企業とでも言うべきやり方は,実は社内にも通じる考え方だ.グーグルでは,創業当初から「自社の情報をすべての社員に公開するやり方」を採ってきた.メールや電話で,上司が部下に命令したり部下が上司に報告したりするのではなく,最初から組織全体へメッセージが発信される.そうすると,自然としかるべき人がしかるべき回答をすばやく返信される.タスクフォースが立ち上がり,数人がチームを組んで課題に取り組む.イメージとしてはフラットな組織というよりも,多数の小組織が自発的に立ち上がって課題を素早く解決・実現し,また他の組織とも競争しあっている状況に近い.情報を公開することは,想像以上に効率的で,競争を刺激する原則のようだ.当社も日報を社内で公開し,社員全員が情報を共有しつつ自分の役割を踏まえて貢献する仕組みを採っている.そういえば僕も,社員にかしこまって発表する前に,こうしてブログに今の考えを書いてる.これもひとつの公開のあり方かも知れない.いずれにせよ,ネットワークを組むには,自社の得意なこと,自分のコアスキルを磨いていかねばならない.その意味では経営も,個人としても勉強,努力の継続が大事ってことか.
Sep 16, 2007
コメント(2)
-
これからの経営
昨日も書いたけど,これからの経営は,「如何に顧客と共同して事業を育てることができるか」にかかっていると思う.雑誌を読んでいたら,プロミスドランドという携帯オンラインゲームのことが書いてあった.ユーザーがゲーム内で稼いだポイントを,飲食店のクーポン券に交換できるというもので,規模はまだまだ小さいが,急成長しているらしい.この会社の経営者は,飲食店コンサルティングをやっていた人なのだが,もちろん,オンラインゲームなんて経験も実績もないところから始める.この社長のインタビューで,「プロミスドランドはゲームの企画書の書き方から学び,アイデアはネットから広く募集して,ユーザーとともに育ててきたゲーム」と言っていた.まさしくそうなんだよなあ.「ユーザーと共に育ててきた」というのは,昔なら「素人のユーザーに何が分かる」ってもんで,プロを自認する作り手は軽視してきた考えだと思う.職人しか分からない世界とか言って,結局は提供する側が一方的にユーザーにモノやサービスを押し付けてきたのではなかったか.一方で,「ユーザーと共同して育てる」というのは,口で言うほど簡単ではないのも事実だ.聞けば教えてくれるっていうものではないし,忙しい中,他社の商品開発にかかわっている暇も義理も本来はないはずだから.それでも「共同してやる」というには,それなりの仕組みや共通した利益,それに理念も共有していかなければならない.ユーザーとの距離を縮め,本当にお互いの利益になるように信じあえる基盤を築くため,これからも頑張っていきたいと思っています.
Sep 14, 2007
コメント(0)
-
現代の経営
現代の経営の仕方って,このところ急速に「ネットワーク型」に変貌していると思う.ネットワーク型経営とは,ヒト・モノ・カネという経営資源が,社内外はもとより,国境も越えてつながって,もっとも効率の良い姿に進化していく経営スタイルのことだ.今までのようなピラミッド型の命令系統ではなく,ウェブやメール,携帯電話などのモバイル端末を通じて,まず,社内の人たちが有機的に結びついていく.「有機的」とは,上下の垂直の関係ではなく,人々が上下左右に,蜘蛛の巣の様に対等に結びついて,知恵を出し合う「つながり方の」ことである.当社でも,担当者が書く日報に対して,リアルタイムに上司・リーダー・技術者・他の担当者が議論をしている.そしてそのネットワークは社内にとどまらない.製品開発にしても,メーカーやユーザー,学識経験者も含めて,「共同作業」で進めていく.今までは,メーカーが良かれと思って開発した商品をユーザーに提案する「プッシュ型開発」だったけれども,現代はやはり,「共同開発」が重要になっていると思う.その際に特に意味を持ってくるのが,「コーディネーター」の役割である.コーディネーターは,本来結びつかないユーザーとメーカーを親密に結びつけ,自らも知恵を当社はコーディネーターとして,付加価値を追求していきたいと思っている.さらに,経営資源が容易に国境を越えていくのも現代の姿である.顧客との折衝は国内で膝を突き合わせて行い,実際の作業や生産活動は世界中でもっとも効率の良いところで行うように既になっている.いわゆる運搬作業の要らないソフトウェアなどの知的商品は既にインドや中国に下請けに出される割合が高まっているし,IT技術の進歩で,今まではアウトソースしにくかったものまでが国外に出されることが多くなってきた(中国にアウトソースされるコールセンター業務など.もちろん日本語である).こうやって,ネットワーク型が進んでくると,自分が果たす役割は何なのかをしっかり持っていないといけない.「私は彼の上司だから偉い」というのは通用しなくて,今ではそんなのをすっ飛ばして,横同士や部の垣根を越えて,さらには社外にまでアドバイスを受けて仕事をするようになる.そうすると直属の上司のやることがなくなってしまって,そんなの要らないってことにもなる.自社における自分の役割,業界における自社の役割,世界における自社の役割なんかを意識しないと,社会的に「すっ飛ばされる」ってことになりかねないのだ.時代の進歩は速い.当社も取り残されないように,頑張ってリードしていきたいと思っています.
Sep 13, 2007
コメント(0)
-
利益率
結局,ビジネスにおける「利益率」が,市場からの企業に対する評価なのかなと思う.つまり,粗利率が高い商売は,それだけ独自性があって,顧客からの評価も高い,社会からのニーズもあるってことだ.ある商品やサービスが,原価が低いのに高く売れるってことは,それだけ評価され,独自の世界を築いているってことだ.どうせビジネスをするなら,知恵を絞って利益率の高い,したがって顧客からも評価も高いことをやりたいものだ. 逆に,どれだけ必要であっても,ユニークでなければ普及財になってしまって,大が勝つ価格競争の世界に入る.単純に,他社がやっているのと同じように,同じようなサービスや商品を提供している限り,利益率は高くなりようもないし,顧客から見ても,どうしても当社からっていう理由もあまりなくなってしまうのだ.小さくてもやっていくには,利益率の高い商売をしないといけないが,それは必要性と同時に,「独自性」という知恵を入れて初めて可能になる.もちろん,当社は提供すべきはきちんと提供する,そして知恵を出して独自性の高いサービス,商品を提供していきたい.それが中小企業として生きる道であり,同時に,社会における存在意義ともなるのだから.
Sep 12, 2007
コメント(0)
-
ぬるい経営
今日久しぶりに,盛和塾例会に参加した.いつもながら出席すると反省させられるのだが,当社は,と言うよりより正確には僕は,本当に「ぬるい経営」をしているなあと思い知らされる.今日は経営体験発表で,塾生の発表内容に稲盛和夫塾長がコメントする形式だ.発表者は当社と似たような中小企業で,でも当社よりも相当努力しながら経営に奮闘されている.結局,講演者も自分で,今までの不満足な業績は,(1)経営者としての努力不足,(2)数字へのこだわり,(3)どうしてもやりたいという願望の弱さ,に起因すると感じておられた.今日の塾長のコメントで,特に印象に残ったのは,「企業は結局は人で決まる」ということ.最近流行で,いつも僕も必死で考えている「ビジネスモデル」や「うまい稼ぎ方」みたいなものは後からついてくるもので,本当に頼りになり,哲学を共有し,苦楽を共にできる人材をどれだけ社内に育てていけるかが,企業経営の要諦である,と言っていた.「企業は人なり」というのはよく言われることだけど,ここまで徹底して言われると説得力がある.同じ哲学で同じ方向で,経営者が最大限努力し,それと同じ思想を共有する社員がいれば,怖いものはなさそうだ.どうも僕みたいな(世間的には)教育がある(?)人たちは,理に流れ過ぎるきらいがある.それはそれで生い立ちでしょうがないのだけど,人材育成は本当に大事だなと思った次第である.それにしても,いつまでも「ぬるい経営」なんかしている場合ではないなあ.まずは僕自身がしっかりとしないといつまでたっても二流のままである.ちょっと反省.
Sep 10, 2007
コメント(0)
-
適者生存
顧客や実際の使用者の意見を直接聞きながら,少しずつ形にしていったり常に改良していくのが,今日の商品開発の手法,そして企業経営のあり方だと思う.企業が自分の思いで,顧客にとって良かろうと思って開発するものは,たいてい失敗する.ニーズが多様化して,製造側・サービス提供側の想像以上に現場は細かいニーズを持っていて,しかもその違いが致命的になっているからだ.あるべき姿は,顧客の声に真剣に耳を傾け,できれば共同開発とでも言える位に「一緒に」開発していくことが理想だ.顧客からのクレームがあって,「これではニーズに応えられない」と思い知るのは,実は正常の状態であって,何も不幸なことではない.ニーズに合うように変えていけばいいだけで,その意味ではチャンスですらある.価格競争に巻き込まれている場合も,顧客はコストパフォーマンスに多少の不満を持っているということだ.価格を単に下げるべきなのか,どこで省力化できるのか,他のサービスと統合して効率を上げれないかなどを出来れば顧客とともに詳細に検討しないといけない.資本や腕力に優る強い企業が生き残るのではなく,「適者生存」が企業社会では本当なのだと思う.「適者」とは言うまでもなく,顧客のニーズの変化や多様性に対して,自らを変えていける会社のことだ.さらに難しいのは,顧客が言うことが,その言葉そのものが意味するところでない場合もあることだ.案外,「言ってみただけだけど,よく考えたらそんな機能要らないなあ」ってことさえあるから要注意である.聞き込みを正確にし対案を出し,こちらも十分に考えをぶつけないと「顧客の真意」が掴めずに振り回されるだけということもある.その意味で単なる「御用聞き」でもうまくいかないのだ.意見を聞くには,意見をぶつけないと返ってこない.そして謙虚に耳を傾け,熟慮を重ね,「適者」として経営を進化させていきたいと思っています.
Sep 8, 2007
コメント(0)
-

マレーシア出張
日曜日からマレーシア出張で,今朝夜行便で帰ってきました.主な目的は,日頃から付き合いのあるDr. Chow Yang Leeの教授就任記念講演に出席するためだ.彼は僕より年下の37歳だけど,マレー人優先が国策になっているマレーシアにあって,中華系ながらしかもこの若さで教授になった.これは結構,大変なことらしい.そしてこの国の習慣らしいが,国内外から人を招待して,盛大に記念講演とランチが振舞われた.この会には,もちろん学術関係者,それにペストコントロールの産業分野からも,各メーカーをはじめとして,相当たくさんの人が来ていた.僕も彼に頼まれて一昨年にシンガポールで講演をしたから,結構知っている人も多い.こうやって,業界のネットワークが広がっていくのだろう.実は彼の元には,日本のPCOを辞めて留学中の人がいる.今回,家族を伴っている様子も見にいった.相当大変だと思うし,決して経済的にも楽ではないのだが,こうやって海外に出て行って勉強してくる人たちがいて,頼もしく思える.僕もできるだけサポートしていきたいと思っています.
Sep 6, 2007
コメント(2)
-
JR
電車に乗っていたら,ちょっと笑えるJRの告知ポスターがあった.「経営者補佐委員会」(だっけ?)というのが設置され,社長に代わって現場の声を聞いて改善に役立てるというものだ.なんでも,4人の各業務に精通した人が委員として行動し,現場を回って現場の声を聞き,経験を生かしていろいろな業務改善を提言したりすると言うもの.笑えたのがその例で,「運転士からの意見で,木の枝が邪魔になって信号機が見えにくいというのがありました.委員会では組織の垣根を越えて関係箇所に指示し,木を伐採しました.」とういもの.信号の邪魔になっている木の枝を多少切ることが,社長直轄の経営補佐委員会が出てきて,「組織の垣根を越えて」までやる大変なことなのかと思う.しかもたった4人だから,木を切るのにこの人たちが必要なら,日本中の鉄道が木だらけになってしまう.さすがJRだと思うけど,これを滑稽に思わない企業体質は相当問題だと思う.当社の標語の一つに,「クロスオーバー」というのがある.もちろん中小企業の所帯だから,一人一人が部署が違うからとか担当でないからといって,周りの人を助けない余裕はない.いったん事あれば,部署や普段の担当を離れて,クロスオーバーして皆で協力するというのは当たり前の話だ.邪魔な枝を落とすのに,社長の決裁も補佐委員会も要らない.気がついた人が自分で,もしくはそこにいる他部署の人にでも頼んで切ればいいのだと思う.まあ一事が万事,当社もセクショナリズムに陥らないように,クロスオーバーを徹底したいと思う.
Sep 2, 2007
コメント(2)
全16件 (16件中 1-16件目)
1
-
-
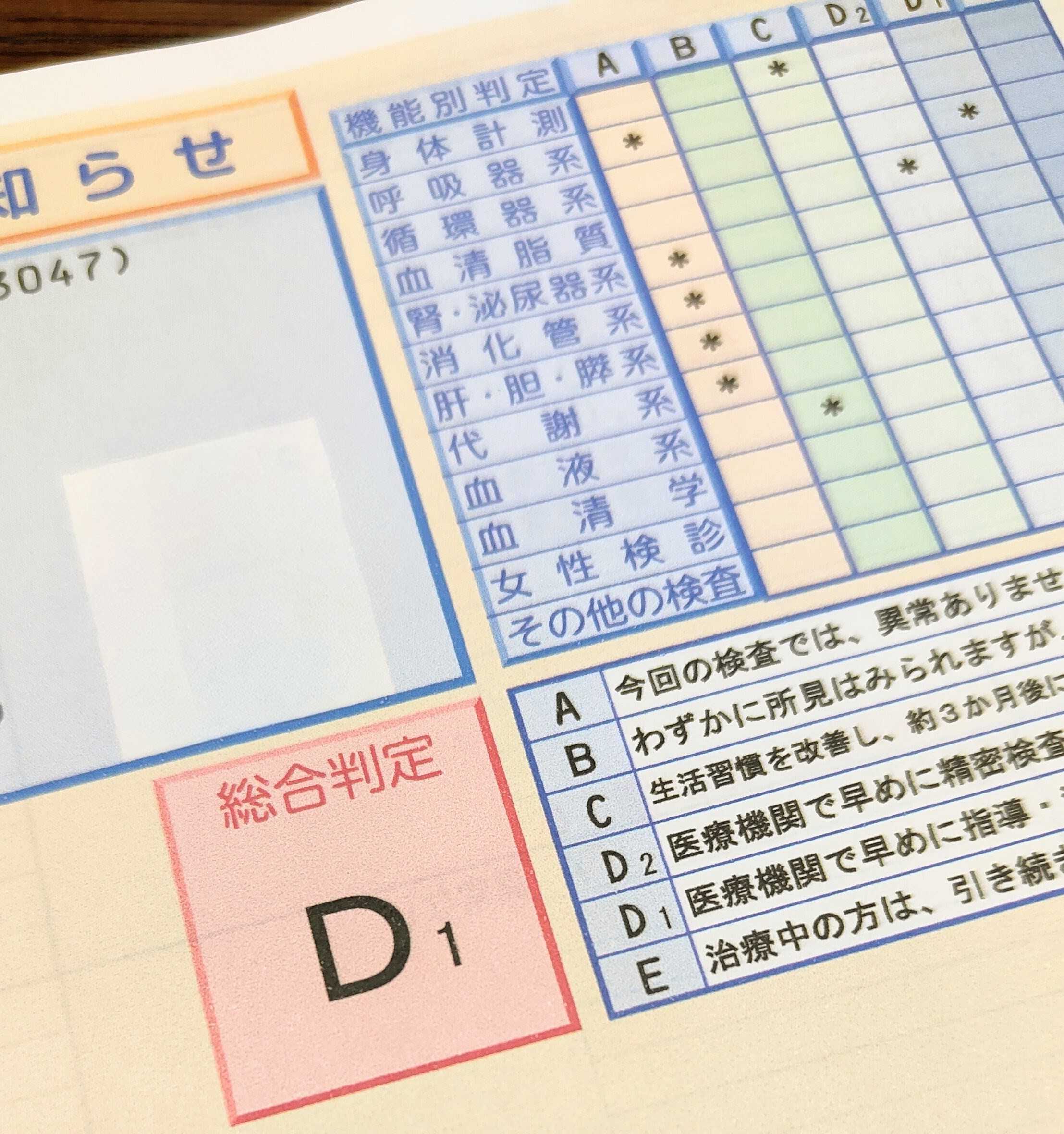
- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…
- 🍅 My Healthy Life! [Recommended I…
- (2025-11-24 11:12:06)
-
-
-

- 徒然日記
- 大阪発動機 ミゼット
- (2025-11-23 17:17:45)
-
-
-

- 楽天写真館
- MUFG カード Global POINT
- (2025-11-24 07:44:58)
-







