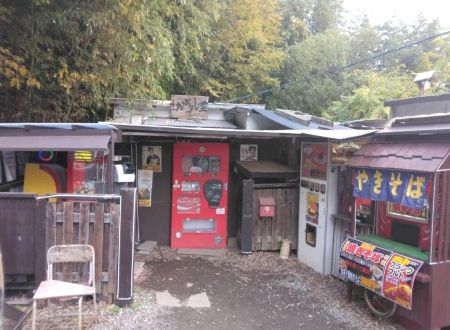2010年10月の記事
全15件 (15件中 1-15件目)
1
-

暦考
よく拝見している小松島JC理事長のブログで暦についての話がありました。あっちゃんの知恵袋vol.1西暦と年号の変換方法についての話です。ところで・・・日本人が西暦を使う必要あるのでしょうか?ウィキぺディアによれば、「西暦(せいれき)とは、イエス・キリストが生まれたとされる年の 翌年を元年(紀元)とした紀年法である」キリスト教徒の暦ではないですか!さらに普及した理由は「西暦が国際社会でもっとも用いられる年号となったのは、 キリスト教圏であるヨーロッパ各国の世界進出や植民地拡大により 非キリスト教国でも西暦が普及したからである。」う~ん。植民地に伴なって拡大したのか!国際的にも広く使われているので、現在使用するのは問題がないかもしれません。(少なくとも日本では)しかし、将来的には、植民地主義に使われた暦として使われなくなる可能性もないとはいえませんね。また、日本に西暦が普及したのは戦後だそうです。西洋でも15世紀ぐらいからしか普及していない暦を遥かに遡って使うのは歴史教育の点からもいかがなものか?鎌倉幕府とか関ヶ原の戦いとか西暦で勉強していますが、その当時使われていなかった暦で勉強するのはどうよ!そんな疑問がわいてきますね。ちなみに、日本には皇紀暦があります。神武天皇即位から数えた年数で今年は皇紀暦2670年。戦前までは現実に使われていたので、こちらで統一するのは無理がないように思われます。ただ、一方で、神武天皇の即位自体が歴史的な根拠がなく伝説になってしまう。同じく明治以前は使われていないという点が問題にならないとはいえません。では、歴史的にも根拠がある暦としては大化から始めてはいかがでしょうか?今年は大化紀元1365年また、仏教徒の国では仏滅紀元というのも使われており、お釈迦さんの入滅から数えています。今年は仏滅紀元2553年。こうなったら真言宗用の暦も作ろう!弘法大師の生誕から数える。 生大師紀元 1234年入定から数える。 入大師紀元 1175年来年から真言宗で採用してもらえませんか?ついでに出来たら太陰太陽暦(旧暦)にしませんか?月の満ち欠けをベースにした太陰太陽暦は、一日が新月、15日・16日(時には17日)が満月と決まっています。これが祈願などで重要なんですよ!満月と新月はいずれも太陽・月・地球が一直線に並びます。それに毎晩月を見ながら満ち欠けを観察して「今日は何日かな?」と思いを馳せるスローライフが忙しい現代には必要ではありませんか?いかがでしょう?ちなみに、西暦が新暦、太陰太陽暦が旧暦といわれているので太陰太陽暦は旧式のように思われていますが、そんなことはありません。日本で最後に使われていた太陰太陽暦である天保歴(江戸時代作)は平山清次の計算によれば、平均太陽年365.24219日・平均朔望月29.530589日に対して、天保暦の太陽年は365.24223日・朔望月29.530588日であり、グレゴリオ暦(西暦)の太陽年365.2425日よりも誤差が小さいとされている!いかがでしょう?人気ブログランキングに参加しています。クリックよろしくお願いします。 ↓
2010年10月31日
コメント(14)
-

嘘つく乞食はもらいが少ない!
だらだらと感情的な文章を書いてしまいましたので、読みにくいと思った方はパスしてください。夕方、久々に、乞食さんが来られました。「すいません、少し恵んでいただけませんか?」「食べ物でいいですか?」「足が悪いので、列車で帰るので、少しでも結構ですから お金を下さい」「・・・」「200円でも300円でも結構なんですが」「すぐそばに交番ありますが・・・」見るところ、乞食まがいというよりも、本当に乞食みたいなので場合によっては少しあげてもいいのかなと思ったのですが・・・次からの話で気が変わりました。「昔悪いことをしていたので、交番は苦手なんです」「どこまで帰られるんですか?」「松山のほうまで・・・」「ええ~松山!、200円では無理でしょう。やはり交番で・・・」「実は自宅ではなく親戚の所へ行くんですが、その親戚に役所で お金を借りるなといわれているんです。」「しかし、200円ではいくらも進めませんが」「それで、あちこちのお寺を回ってお金をいただいて・・・」「もう夕方になるのでそれは無理でしょう」「いえ、列車で進めるところまで進んで、またそこで・・・」「そんなの無理でしょう」ついに怒ってしまいました!(;一_一)「食べ物もないので、何か下さいというならともかく、 お金が欲しいというのはおかしいでしょう。そう思いませんか?」「だめですか?」「だめです!」私は以前乞食まがいの生活をしていたこともあるので、乞食にも理解があるつもりですが・・・嘘をつくな!(怒)嘘をつく余裕があるなら乞食なんかするな!乞食で思い出しましたが、「歩き遍路」「野宿遍路」に対しても私は厳しい意見を述べると思われているようですが、それも事実に反しています。「歩き遍路」「野宿遍路」の方も、「遍路」に対して興味を持っておられるのは判りますが、もう少し、「なぜ四国が霊場なのか」考えてほしいと思いますね。自分の仕事がありながら、休みを取って、「わざわざ四国で野宿をして遍路する」っておかしくないか?帰る場所もある、仕事もある人間が「遊び」で「野宿」しながら遍路して何がわかる?四国で野宿をしながら遍路するのなら、家屋敷も引き払って仕事も辞めて本気で取り組んでほしいですね。それでこそ判るものがあるというものです!少なくとも、行くあてもなく四国を彷徨う人が結構いるにも関わらず、帰るところがある人が「遊び」で「野宿」しながら「遍路」ってふざけていませんか?「野宿」は外してほしいです。「歩き遍路」の方にも、徒歩旅行が目的なら他所でお願いしたいですね。四国は「霊場」です。お参り重視でお願いしたいです。それと「歩き遍路」は特別だと思っている人はやめてほしいです。ただ、最近思ったことですが、四国の人の感覚も変わってきましたね。昔はそんな人もいなかったのでしょうが、お遍路さんで儲けようと考えている人もいるようです。それこそ、昔のお遍路さんは四国の人よりも貧しかったし、四国遍路も大変だった。しかし、最近はお遍路さんのほうがお金を持っているようですし、何より、お遍路さんに余裕がある。「元気でないと歩き遍路なんかできない」四国の人からそういう言葉を何度も聞きました。それはないでしょう。「元気じゃないからお大師さんにすがってお遍路するんですよ」昔は歩けない人や眼が見えない人が周りに助けられながら歩いて治したものです。最後に、その乞食さんが寂しそうに帰っていく姿を見ながら、なんとなく後味が悪い感じがしました。人気ブログランキングに参加しています。クリックよろしくお願いします。 ↓
2010年10月30日
コメント(16)
-

再び四国別格霊場
広島・山口紀行が間に入ったので、話が飛んでしまいましたが四国別格霊場巡拝の続きです。17番札所は神野寺です。このお寺は日本最大のため池の満濃池のほとりにあります。満濃池は周囲20キロという巨大な人工池です。かなり水位が下がっているにもかかわらず、対岸ははるかかなたです。なぜ、このような巨大なため池が必要になるのか?それは讃岐の風土が関係しています。四国には阿波の吉野川、土佐の四万十川のような大河もあります。しかし、讃岐は山が低くしかも傾斜がきついため、降った雨が一気に海まで流れて留まりません。それゆえ多くのため池が造られました。この池は弘法大師が改修に関わったことで有名です。弘法大師は朝廷が3年かかってできなかった改修を、護摩を焚き、結界を張って、わずか3カ月で成し遂げました。この池には、3つの特徴があります。1、堤防をアーチ型にして、水圧に耐える2、余分な水を抜く、水抜きを設けた3、土砂の崩壊防止の護岸工事がしていたまさに、最新技術の粋を集めた大工事でした。さらに弘法大師は工事の成功のために護摩を焚いて祈願します。護摩をたいた場所がこちらです。弘法大師のカリスマと唐からもたらした最新技術、それに期待した讃岐の人々の力が合わさって、奇跡を起こしたといえます。さて、こちらが杖を忘れた18番札所海岸寺です。仁王門に郷土力士が祀られているのが面白いですね!さらに、巡拝団が飛ばした奥の院はこちらです。江戸時代、善通寺と海岸寺の間で弘法大師の御誕生所について争いがありついには朝廷にまで持ち込まれました。嵯峨御所からの御理解書には、善通寺を「誕生所」、海岸寺を「産湯所」ということで決着しました。門をくぐった境内は平日だからでしょうか、静かでした。正面に見えるのが奥の院の本堂です。ここが弘法大師の産井跡です。以前にも書きましたが、お誕生所はやはり海岸寺かもしれません。人気ブログランキングに参加しています。クリックよろしくお願いします。 ↓
2010年10月26日
コメント(16)
-

乗り物考
先日の山口・広島旅行ですが、公共交通機関に沢山乗りました。ビックリしたのは新幹線が変わってしまっていたこと。確か、最後に乗ったのは10年ぐらい前だと思うんですが・・・これが700系「のぞみ」ですね。写真で見るとアヒルみたいだと思っていたんですが、実物はかっこいいです。こちらが500系の「ひかり」実際見てもあまり変わらないような気がしたんですが、観察しました。「のぞみ」のほうが窓が小さく、車両の継ぎ目に覆いがかけられていて空力を意識した設計でした。さらに驚きがこれこの流線型の未来都市の超特急みたいで一番かっこいい車両知ってます?「こだま」です!!!(@_@;)「こだま」って以前はこんな感じでしたよ新幹線の中でもトロいイメージ(失礼)だったんですが・・・ところで、新幹線の駅はえらく増えましたね。それに、昔は「ひかり」は東京を出ると、名古屋・京都・新大阪が停車駅だったんですが、最近は品川新横浜・・・で止まりますね。あまり止まるとスピードアップの意味がないんですが(*^_^*)こちらは広島の路面電車。ファッショナブルですね!路面電車というとチンチン電車のイメージがあるんですがこれは地下鉄の車両みたいですね。しかも、お金を払っている人がほとんどなく、皆、カードで乗ってます。広島の人が結構足に使っているのもうなずけます。ただ、宮島までは遅い(*^_^*)広島ー宮島間はJRなら30分程度ですが、この路面電車ですと1時間10分ぐらいかかります(*^_^*)路面を走っているときに車掌さんに「時間かかりますね」と言ったら、「もう少ししたら道路から離れて鉄道に入りますから早いですよ」しかし・・・JRの駅の一区間に路面電車の駅が3つも4つもあります。速いわけがない(*^_^*)ただ、地元の人は便利ですし、使い分けができますね。ところで、これが山口で乗ったコミュニティバスです。失礼ながら座席がチャチですね。普通の路線バスと比べても、安っぽいです。乗った時はガラガラだったんですが、駅に近づくにつれ、どんどん人が乗ってきます。ついには立ったままの人まで出ます。路線バスを走らせてもいいのにと思ったんですが、予算の関係上路線バスは維持できないんでしょう。徳島でも民間バス会社が路線を廃止しており、自家用車を持たない人の足が無くなりつつあります。大都市の公共交通機関の充実に比べて、地方都市の交通機関の整備状況は寒い限りです。人気ブログランキングに参加しています。クリックよろしくお願いします。 ↓
2010年10月24日
コメント(20)
-

厳島神社
原爆ドームの後に、宮島へ向かいました。宮島口からフェリーで渡ります。15分おきにフェリーが出て、それも二路線あるのはさすがに世界遺産です。宮島のシンボルの大鳥居が見えてきました。船着き場から厳島神社までは結構距離があります。さらに山上まではロープウェイで時間がかかります。宿もありますので、一泊しながらゆっくり回るのがいいかもしれません。今回はとりあえず、厳島神社だけお参りしました。ちょうど干潮で鳥居のそばまで行けました。しかし、結構濡れていて近づくのは大変でした。近くで見た鳥居です。大きさもさることながら、丸太を皮むきしただけで色を塗ったでけで使っているのにビックリ!(@_@;)これが大鳥居から見た本殿です。さらに本殿から見た五重の塔ところで、ここが毛利元就を中国の覇者へと押し上げた厳島合戦の舞台です。ここで、2万の大軍に対して4000で奇襲を仕掛け勝利したというのですが・・・こんな平地もない島になぜ2万もの大軍を上陸させたのか?兵糧だけでも大変でしょう。しかも、軍隊を展開するスペースがありません。毛利元就はここへ陶晴賢を呼び込んだというのですが・・・逆に元就を包囲して殲滅させる方法もあったはずで、かなり際どい勝利でしたね。毛利元就がこの神社を復興したというのもうなずける話です。今回は訪問しませんでしたが、この宮島の山頂の弥山には虚空蔵菩薩求聞持法を行うお堂があります。人気ブログランキングに参加しています。クリックよろしくお願いします。 ↓
2010年10月22日
コメント(20)
-

広島原爆ドーム
なんぜんたろうさんを訪問後に、広島へ帰り翌日の平和記念公園での法要に参加しました。こちらが原爆ドームです。想像していたより、やや小さい感じがして、ところどころコンクリートで補修されています。今をさかのぼること65年前。8月6日にこのドームのほぼ真上500メートルで原子爆弾が炸裂したのです。一瞬の内に万単位の人間の生命が失われました。実物を目の前にすると、その情景が浮かんでくるような感じがしました。その前で記念撮影をしている人に出会いましたが、流石にそんな気にはなれません。ちょうど原爆ドームを挟んで道路の反対側に、広島復興のシンボルとしての役目を終わった広島市民球場がまだ残っていました。アメリカの戦争犯罪の象徴である原爆ドームの反対側に広島市民球場があるのも、不思議な感じがしました。こちらが法要が行われた原爆慰霊者供養塔です。かの有名な慰霊碑はこちらですね。慰霊碑にはたくさんの人が訪れていました。同じく、記念撮影をする方がいましたが、記念撮影などする気にはなりませんね。核兵器に関しては、一般の日本人は圧倒的に反対が多いのですが、なぜかネット上のアンケートでは核武装論者が60%(@_@;)広島を訪れたら唯一の被爆国である日本は核兵器に賛成する気にはならないだろうというのが、反対論者の意見ですが、逆に賛成論者は被爆国だからこそ、核武装して二度と核兵器による悲劇が起きないように核武装するべきであるという主張。さらに言えば核武装論者と言えば、過激な軍拡主義者と思われがちですが、核武装論者=核攻撃論者ではなく、「核を持つかどうかの議論を進めるべき」「核武装を外交カードに使うべき」という方がほとんどと思われます。国家を守るために軍備は必要です。現在のように、中国、北朝鮮、ロシア、アメリカの核兵器が日本に標準を向けて狙われている状況では、日本が話し合いを前提として手段として核兵器を保有することが有効かどうかという議論はあってもいいような気がします。核反対論、核武装論どちらの議論にしても広島で行うことは意味があるように思います。人気ブログランキングに参加しています。クリックよろしくお願いします。 ↓
2010年10月21日
コメント(14)
-

なんぜんたろうさんを訪問させていただきました
18日に広島で高野山の同窓会があり、それに参加すべく広島行きを決定しました。広島と言えばずいぶん遠いイメージがあったんですが、最短3時間ぐらいで到達できます。(@_@;)これならばどこか寄れるのではないかと思いついて候補に挙げたのがなんぜんたろうさんのお寺です。以前にも申し上げましたが、臨済宗といえば「日本の僧侶」の原風景?のようなものです。すなわち臨済宗は教義・修行・寺院の存在などが一般の人が思い浮かべる「坊さん」のイメージにもっとも近い形を体現していると思われます。その中でも、ブログを拝見する限り、その「日本の僧侶」のイメージに近い方ではないかと思われるのが「なんぜんたろうさん」です。さて、しかし、訪問にはかなり葛藤がありました。なんぜんたろうさんは臨済宗に対し当方は真言宗なので気軽に訪問というわけにもいかず、かといって正装に近い形でのあまり堅苦しい訪問もいかがなものかと悩んでしまいました。もう一つは意識の問題。本来なら一年を通して同じようにたゆまぬ努力をすべきですが、冬から春にかけてはなぜか行者としても修法などを集中的に行っているのですが夏から秋にかけては今一つ。それの良し悪しは置いておいても、現実には僧侶としてのモチベーションの下がっている時期なので、他宗の僧侶のところへ赴くのはいかがなものか?出来たらよいコンディションの時期に、訪問したいところです。しかし、今回行けるとしたら千歳一隅のチャンスです。何しろ、広島さえ今まで訪問したことがありません。思い切って出かけることにしました。本来ならあらかじめご連絡すべきですが、当方の予定もはっきりとは決まっておりません。状況によっては、同窓会の参加自体を見合わせる可能性もあります。誠に失礼ながら御連絡なしでお伺いしました。これも実はリスクの高い選択です。ずいぶん昔の話ですが、四国遍路中にある真言僧にお会いしました。「近くに来たらお寄りください」と言われたので、後日、本当に訪問させていただいたところ、「あらかじめ来る時は連絡ください」と面会を断られたことがあります。流石にそれはないだろうと思いましたが、なんぜんたろうさんがご不在の可能性もあります。また、手が離せないほどお忙しいかもしれません。その時は、ご縁がなかったものと諦めて、雰囲気だけでも感じさせてもらおうと思いました。徳島から特急・新幹線を乗り継いで、山口駅に降り立ったのは13時過ぎです。バスもすぐにやってきました。山口県庁へと向かう途中には商店街がありました。バスに中から見ただけですが、徳島に比べてまだ活気がある商店街にビックリ!(@_@;)山口県庁で降りてしばらく歩くと藩庁門がありました。池の周りで優雅に泳ぐ鯉と白鳥なんとなく維新の雰囲気が伝わってくるようで、趣があります。しばらく歩くとなんぜんたろうさんのお寺の山門がありました。ちょっと写真に収めようとカメラを構えていると「こちらのお寺にご用ですか?」と車に乗っている若い僧侶から声をかけられてビクッ(;一_一)なんとなく怒られたような恥ずかしいような気持があって「え~あの~」と、どぎまぎしながら「○○さん(なんぜんたろうさん)ですか?」とお尋ねするとそうでした。お出かけだったにも関わらず、戻っていただいて大変申し訳なかったです。後からブログで拝見したところでは、私の姿を拝見してわざわざ戻ってくださったとのことでした。本堂をお参りさせていただき、お茶までごちそうになりました。きれいに整備された境内と本堂が印象的でした。また、なんぜんたろうさんは想像していたよりお若い感じがして、こちらにお気遣いいただきながらお話いただきました。後から考えたのですが、なんぜんたろうさんのお立場上、やはりのいきなり訪問は配慮が足りなかったかと反省いたしました。(;一_一)「危犬」と書かれた名犬マルの寝姿なんぜんたろうさんにいただいたお茶菓子は帰りの列車でいただきました。人気ブログランキングに参加しています。クリックよろしくお願いします。 ↓
2010年10月20日
コメント(12)
-

四国別格霊場15番箸蔵寺ー秘められた真実が今よみがえる
先日の巡拝の報告です。まず、15番札所箸蔵寺から向かいます。昔なら歩いて上がるところを、ロープウェイで向かいます。本当は下から登山道がありますので、それを登ったほうが有難味がありますが、参加者の方の体力の関係上こちらを選ばざるを得ません。このまったての階段を見よ!金毘羅宮の奥の院ということで、本物の金毘羅さんには及ばずといえども石段が続いている巨大な寺院です。なぜ、ここが金毘羅の奥の院かは謎です。しかし、昔は金毘羅までの山道があったそうです。階段を上ると巨大な本堂が姿を現わします。この装飾の細かいこと!(@_@;)こんな山奥のお寺が深い信仰のもとに維持されてきたのは驚きです。実はこのお寺にはもう一つの売り物があります。ミニ八十八お砂踏み道場!ミニ八十八自体は結構多くのお寺にあるのですが、ここの特色は仏像が古くいにしえの内容が書き遺されていることです。まずはこれ八坂八浜と言えば、徳島の四国別格霊場4番の鯖大師!しかし・・・鯖瀬庵?行基菩薩?実は以前も書きましたが、鯖大師は弘法大師の話ではなくもともと行基菩薩の話です。それがこういう形で残されているのは面白いですね。次は四十一番 稲荷 龍光寺 地蔵菩薩別に問題なさそうに見えますが、現在の41番の本尊様は十一面観音!本尊様が変わった???こちらはまだ未解決事件?です。ただ、間違えただけという説が有力ですが、何箇所かで四十一番の本尊様は地蔵菩薩とありますので、そう思われた根拠があったはずです。五十七番 石清水八幡宮ここは江戸時代札所だったにも関わらず、私が見た四国遍路ガイド等で紹介されていることがありません。お参りの方はぜひおいでください。場所は現在の五十七番札所の山上です。本尊 勢至菩薩の寺院 (@_@;)浄土宗を開いた法然上人は勢至菩薩の生まれ変わりとも言われて信仰を集めていますので、もともとは浄土宗の寺院何でしょうかこの月照寺というお寺は現在は月山神社という名前に変わっています。月型の謎の石がご神体!月照寺は通称「月山」と呼ばれ、篠山観世音寺「篠山」とともにお遍路さんはどちらかをお参りしなければならないというしきたりがありましたが、ご存知の方も少なくなりました。人気ブログランキングに参加しています。クリックよろしくお願いします。 ↓
2010年10月17日
コメント(14)
-

お大師さんをお迎えに行きました。
昨日は香川県の別格18番札所の海岸寺までお大師さんをお迎えに行ってきました。お大師さんとは四国遍路用の金剛杖のことです。以前も書きましたが歩き遍路を4度経験した「突かずの杖」を忘れてしまいました(;一_一)ことの発端は、10月13日の四国別格霊場巡拝です。某さぬきうどん店に入ったところ・・・注文したうどんがなかなか出てこない(;一_一)予定が大幅に遅れてしまいました。さて、18番海岸寺を本堂をお参りし終わって、巡拝団は大師堂を探しに行っています。納経所でも「大師堂は200メートル先ですよ」しかし・・・時間が押しています。巡拝団を呼び寄せ「出発いたします」「え~大師堂行かないんですか?」「20番札所まで行けるかどうか際どいので、大師堂には ここでお参りしたことにしましょう」さて、19番札所の香西寺につき、「さて、お大師さん、お参りに行きましょう!」と金剛杖を持とうとしたが・・・金剛杖がない(;一_一)香西寺で電話番号を聞き海岸寺に電話します。「もしもし、海岸寺さんですか、先ほど巡拝したものですが、 金剛杖を忘れました。」「そうですか、ではしばらくお待ちください」しばらく待たされるので、ジリジリします。「おまたせしました、三人文殊寺さんですか?」「はいそうです」「ありました」「ありがとうございます」「三人文殊寺へお送りしたらよろしいですか?」「いえ、近日中にお伺いします」実は私のお大師さんには「住所 氏名 寺院名」が明記してあり「もし、この杖をお届いただいたら、謝礼いたします」とも書いてあります。巡拝団の方に話したら、「では、ここをお参り終わったら取りに行きましょう」と言っていただいたが・・・それでは、何のために進んできたか判りません。「では20番終わった後に取りに行きましょう」ありがたい申し出ですが、それは時間的に無理!帰るのが午後9時くらいになってしまします。そこで、昨日お迎えに行きました。海岸寺の大師堂(奥の院)へも丁寧にお参りしてきました。もし、ここへお参りしていたら、海岸寺に杖を忘れたことが判ってすぐに取りに行けたはずです。海岸寺と言えば、弘法大師産湯の井戸があり、お大師さんがここでお生まれになったとも言われています。そこを飛ばして四国霊場のお参りというのは、「巡拝の常道に反する」のかもしれません。私は弘法大師畿内誕生説を支持していますが、こんなことがあったら、「やはり海岸寺でお生まれになったのでは?」と考えてしまいました。人気ブログランキングに参加しています。クリックよろしくお願いします。 ↓
2010年10月16日
コメント(14)
-

コンピューターが人間を上回る日
昔、ラジオを聴いていて、こんな話を聞いた記憶があります。ある主婦からの投稿「テレビが出始めのころ、私の家庭教師をしていた大学生が こんな話をしたのを覚えています。」「僕はテレビは普及しないと思う。ラジオは何かしながら聴けるが テレビは何かしながら見れないからだ」「私は当時は流石に大学生と思いましたが・・・」読みが甘いですね!似たような話があります。30年ほど前、理科系の大学に籍を置いていた私はコンピュータについてある人と討論したことがあります。「コンピューターは普及するか?」私は普及しないと見た。当時はマイコンと呼ばれていた個人用コンピューターは価格が100万を超えていた。使ったことはなかったが、大学のコンピュータはパンチカードだったはず。使うには自分でプログラムしなければいけない。精密な計算を必要とする専門家ならともかく、こんなものが普及するはずがない。しかし、その人いわく、ソフトが誰でも使えるようになったら普及するという。それはないやろ~と思いましたが・・・10年もしないうちにソフトは普及しました!(;一_一)最近、驚いたのがこのニュースです。コンピューター将棋が女流王将に勝利~~~~~以下引用~~~~~ 将棋の清水市代女流王将と情報処理学会のコンピューター将棋システム「あから2010」の対戦が2010年10月11日、東京大学本郷校舎で行われ、後手のあからが86手で勝利した。中盤までほぼ互角で進んだが、終盤、残り時間を使い果たした清水女流王将をコンピューターが追い詰め、形勢有利となり対局をものにした米長邦雄日本将棋連盟会長は「時間配分でミスをしたことが大きい。今後の対戦は決まっていないが、清水女流王将と再戦するのがいいのではないか」と語った。 2010年10月12日 日経パソコン~~~~~以上引用~~~~~ニュースでも大々的に報道していました。チェスの世界では既に1997年5月、チェスの世界王者、とIBMの高性能コンピューターが六番勝負を行い、コンピューターが勝利しています。現在では人間側にハンデをつけて戦っている状態。将棋も時間の問題ではあったのですが・・・ネットでコンピューター圧勝という書き込みがあったので、棋譜を並べてみてビックリ!>中盤までほぼ互角>時間配分でミスをしたことが大きいこれはかなり将棋界に配慮した発言でしょう(*^_^*)素人目で見る限りコンピュータが全く攻められていない状態でのギブアップ!普通はプロ同士で快勝といっても一手違いと言って、一手待ったらもう片方が勝ちそうなスタイルに持ち込むのですがこれは二、三手待ったところで勝てそうもありません。>清水女流王将と再戦するのがいいのではないか将棋の世界では、なぜか男子プロのほうが女子プロより圧倒的に強いのが常識、いわゆるトーナメントプロの中には女子プロが一人もいません。しかし、その差を割り引いても男子のトッププロが出てきても結構負ける可能性があるんではないですかね?そのうちゲームではなく人間の思考を上回るようなコンピュータが出来てくるんでしょうか?ターミネーターのスカイネットみたいに自我を持ったコンピュータも出てきたりして?人気ブログランキングに参加しています。クリックよろしくお願いします。 ↓
2010年10月14日
コメント(20)
-

漢文の素読
最近、漢文の素読を行っています。素読しているのは「菩提心論」先日の講義でも先生について「菩提心論」の素読を行うのですが、ほとんど講習参加者が声を出していません(;一_一)というより、ほとんど先生一人で読まれています(;一_一)先生はこんな話をされていました。「この講習会は『菩提心論を読む』のが目的です」「昔の高野山ではまず素読をさせます。うまくできなかったら『勉強する資格がない』ということで、その時点で脱落です」おお~全員脱落か?(;一_一)しかし、前講義の「般若心経秘鍵」では、皆、先生の素読に付いて行っていたような気がします。なんで???事務局のU僧正に尋ねてみました。「菩提心論の素読は難しいのですかね?」「う~ん、難しいですね」「般若心経秘鍵は皆読んでましたが・・・」「いや~あれは書き下しもあるし・・・」なんと、皆、小技使ってたんですね!(@_@;)格なるうえは、私が勉強会の提案者の責任として「菩提心論」の素読を完璧に!(大袈裟に宣言するほどのことでなく当たり前の話です)そう思って始めたのですが、大変ですね(;一_一)15分ぐらい読み続けると、疲れてきますね。そうでなくても、23字×10行の漢字で埋まっている真ん中あたりは眼が散って読めないですね(;一_一)漢文はレ点で引っくり返るし、一,二,三ならともかく、上中下、さらには甲乙丙まであると、どこへ戻るかわからなくなりますね!(;一_一)先生は普通に読み下しのように読まれていますが、そこまではとても無理(;一_一)まだ、一巻15ページを通しで読んだことはありません。そこまでできるようにするのが目標です。人気ブログランキングに参加しています。クリックよろしくお願いします。 ↓
2010年10月09日
コメント(14)
-

放生葬ってどうよ!
某葬儀社では、出棺に際し司会者の方が「故人を極楽浄土へと導く案内として放鳥を行います」と言って、白い鳩を放します。なんか意味が違うような???白い鳩が極楽へ行くとかいう話は聞いたことないし・・・それに鳩は戻ってくるし(多分)鳩を放すのは、もともとは放生では無いですかね?「放生」とは、捕獲した魚や鳥獣を野に放し、殺生を戒める宗教儀式です。仏教の戒律である「殺生戒」を元としています。こんな話があります。お釈迦さんの前世であった流水(るすい)長者が、大きな池で水が涸渇して死にかけた無数の魚たちを助けて説法をして放生したところ、魚たちは三十三天に転生して流水長者に感謝報恩したとそうです。そこから転じて、生き物を放してやると功徳を積めるとなったようです。台湾、タイ、インドでは今でも放し亀屋や放し鳥屋といった商売があるそうです。そこで、亡くなった方に功徳を振り向ける方法として、お墓を作る従来の先祖供養の方式に加えて、「樹木葬」などがありますが、「放生葬」というのはどうでしょう?故人の代わりに、遺族が金魚を池に放して、功徳を積んでもらう!いかがでしょうか?人気ブログランキングに参加しています。クリックよろしくお願いします。 ↓
2010年10月07日
コメント(12)
-
パソコン復活しました!
買って二年余りのパソコンですが不調でいきなりシャットダウンを繰り返しましたので、買ったY電気に修理に出しました。初期化したというのですが・・・不調が治りません。今度はメーカーに再修理に・・・しかし・・・戻って来たその日に立ち上がりが遅い(@_@;)再び再修理に出して昨日ようやく戻ってきました!これで顔文字も使えますよ!(*^_^*)
2010年10月06日
コメント(22)
-

尖閣諸島問題ー日本人は一家で5億円損する!
相変わらず進展がない尖閣諸島問題です。ネットでも「日本は多少譲っても良い」「中国にも言い分がある」ような主張がありますが、いかがなものか?尖閣諸島を譲ったら、どれ位日本は損するか?以前も書いたように尖閣諸島沖の石油の埋蔵量は1000億バレル超。10月2日の石油の先物相場は81.58ドル一ドルは83円ぐらいですから、尖閣諸島沖の埋蔵量は金額換算で650兆円ぐらい!つまり、叩き売っても650兆円になるということです。日本がその石油を使用しながら製品としたら、その2~3倍にはなるでしょう。さらに、その経済効果は10倍以上になりませんか?すなわち、尖閣諸島沖を確保することは、日本に対して1京3000兆円~2京円の利益を確保するということです。ちょっと単位が大きいので実感がありませんが、日本人一人当たり1億円~1億5千万円が儲かるということです。4人家族なら4億円~6億円!今、譲ったらこの利益がパーになります。後から中国と話し合えば、と考える方もあるかもしれませんが、それはありえません。あと、10年たったら、日本の海上戦闘能力は中国に遥かに劣るかもしれません。その時になって中国が譲るかどうか?中国にとっても1京3000兆円~2京円の利益は欲しいのです。譲るはずがありません。今こそ強く出て尖閣諸島を確保し、強い交渉で尖閣諸島沖の石油を確保したいところです。人気ブログランキングに参加しています。クリックよろしくお願いします。 ↓
2010年10月05日
コメント(18)
-

梵習字の講習会
昨日は梵習字の講習会がW僧正のお寺でありました。実用的な講習なので多くの方が参加されると思いましたが・・・参加者は10人ぐらい?少ない!最初に私が梵習字を学んだのは高野山専修学院です。講師はS先生。最初の数時間は梵習字の前段階として仏教史から入ります。梵字が成立してきた過程から勉強して行くということです。次いで、梵習字の実践にはいるのですが、「梵字はサンスクリットのデバァナガリー書体を イメージにに置きながら書く」「梵習字のテキストを見て書いてはいけない」「何回も書いていたら形が安定してくる」ということで、梵習字でありながら、「きれいに書く」ということがあまり重視されていませんでした。ちなみにサンスクリットは母音が10、子音が33あり、それが組み合わせによって形を変えるので鬼のよう!先生としては、「もともとの文字の形を無視した梵字を書いてはいけない」という指導方針だったのでしょう。それゆえ、他の人の塔婆などを拝見すると、「これは崩しすぎでは?」と気になることがしばしばあります。ひどいのは「納経」少なくとも仏様をあらわす「梵字」は正確に書いてほしいです。「これなんて書いてあるんだ???」四国八十八カ所などは、素人の納経書きの人が崩して書いているので最悪!読めないような梵字はレッドカードでしょう。ちょっと外れてしまいましたが、「もともとの文字の形を無視した梵字を書いてはいけない」ということでこれまでは書いてきました。ところが、以前W僧正に「梵字はサンスクリットのデバァナガリー書体を イメージにに置きながら書く」「梵習字のテキストを見て書いてはいけない」「何回も書いていたら形が安定してくる」という話をしましたらビックリされていました。W僧正は今でも塔婆を書くときに、「梵字の手本を見ながら」書かれるそうです。なんと丁寧な!W僧正いわく「梵字は見ながら書くもの」だそうです。さて、W僧正の梵習字の講義です。最初は梵字の話からと思っていたら・・・まず「キャ字はこう書きます」とホワイトボードに書かれ、「私が手本を書きますから、紙を持ってきてください」「その手本にしたがって、梵字を練習して持ってきてください。 添削します」いきなり、実践!書くのは不得意じゃ~徳島市仏教会89カ寺のうち、2番目に字が下手と自称している私としては厳しい(汗)添削に持って行ったら・・・「こんな字でよく書くな」と思われそう(汗)他の人はどんな字を書くかな~と密かに偵察!しかし、間が悪いことに、隣の机で書いているK僧正は書道教室を開かれている書道の先生!筆の動きが見るからに滑らか(汗)そのK僧正ですら「うまく書けんな~」W先生が近づいて来られます。「三文さん!筆の持ち方が悪いな~」と持ち方から直されます!基本が出来てない(汗)なかなか大変でした(汗)しかし、もともとレベルが低いので、たった一日でも多少うまくなりましたよ!人気ブログランキングに参加しています。クリックよろしくお願いします。 ↓
2010年10月03日
コメント(16)
全15件 (15件中 1-15件目)
1