2021年03月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-

3月31日(水)…2021ラウンド21…
3月31日(水)、晴れです。気持ちの良い青空が広がり、黄砂もやや少ないか…。そんな本日はホーム1:GSCCの東コースでのプライベートラウンドです。9時48分スタートなので7時00分に起床。新聞に目を通し、朝食を済ませ、ロマネちゃんと戯れる。身支度をして、8時15分頃に家を出る。8時45分頃にはコースに到着。フロントで記帳して、着替えて、練習場へ…。ショット…マアマア…、パット…イマイチ…。本日は東コースのホワイトティー:6512ヤードでのお遊びです。お遊びですが、オリンピックと茶店の前のホールで損長さんを…。コ君、シさん、ミ君と若者たちとのプレーです。OUT:2.1.1.0.1.1.0.2.1=45(20パット)1パット:0回、3パット:2回、パーオン:2回。ミスショット…たくさん…。握りもすべて負けています…。10番ホールのスタートハウスでドーピング…。IN:1.0.0.2.1.1.0.1.1=43(20パット)1パット:0回、3パット:2回、パーオン:4回。アプローチとパットが悪いです…。45・43=88の40パット…。ことごとくに負けました…。レストランでしばしの雑談…。お風呂に入って、会計を済ませて、早々に退散です。本日のフィジカルチェック…170.0cm,63.9kg,体脂肪率18.4%,BMI22.1,肥満度+0.5%…でした。帰り道にいつものゴルフ工房に寄り道して試打クラブを返却。帰宅すると17時30分頃。京都土産の和菓子とお茶で遅いおやつタイム。夕食は春野菜の天ぷらのようです。何か美味しそうな日本酒を用意しましょう。1USドル=110.58円。1AUドル=84.23円。昨夜のNYダウ終値=33066.96(-104.41)ドル。本日の日経平均終値=29178.80(-253.90)円。金相場:1g=6626(-59)円。プラチナ相場:1g=4601(-27)円。本日の東京市場ではチェック中の日本株30銘柄中の8銘柄が値を上げて終了しましたね。重点3銘柄では1銘柄が値を上げて終了しましたね。5%以上の大きな変動は見られませんね。ドイツ、アストラゼネカ製は60歳以上のみ 副反応懸念朝日新聞社 ドイツ政府は30日、英アストラゼネカ製の新型コロナウイルスワクチン接種について、60歳以上に限ることを決めた。比較的若い世代で、血栓症が改めて確認されたため。ドイツでは、副反応への懸念から同社製ワクチンの接種をいったんやめた後、19日から再開していた。 同社製ワクチンは、日本も1億2千万回分を調達する契約を結んでいる。 ドイツのワクチン接種常任諮問委員会は30日、まれだが非常に重い血栓症が発生する事例があるとして、同社製ワクチンの接種を「60歳以上のみ推奨する」と発表。これを受け、連邦政府と各州の話し合いで、委員会の勧告を受け入れることを決めた。60歳未満については、個別事例を医師が判断し、十分な説明のうえで接種する。 ドイツではこれまで、1317万回のワクチンを接種し、約2割が同社製だ。シュパーン保健相によると、31件の脳静脈血栓症が報告されたという。 メルケル首相は各州首相との緊急会議後の記者会見で「ワクチンの特性については日々、新たな発見がある。私たちは都度、バランスのとれた方法で判断せねばならない」と述べた。 アストラゼネカ製のワクチンをめぐっては、欧州各地で接種後に血栓が生じ、死亡する事例が報告され、今月半ばまでに各国で使用がいったん止められた。 その後、欧州医薬品庁(EMA)が「接種と血栓の因果関係は認められず、安全だ」と表明。19日以降、各地で使用を再開した。フランスでは、55歳以上に限って接種している。 ただ、EMAも「極めてまれな事例」ではワクチンが血栓を引き起こした可能性が排除できないとして、検証を続けている。EMAは近く、最新の検証結果を報告する予定だ。 欧州各地で同社製へのワクチンに疑念が生じるなか、フランスのカステックス首相(55)は19日、信頼を取り戻そうと、同社製ワクチンを接種。メルケル氏(66)も30日の記者会見で「自分の順番が来れば、アストラゼネカのワクチンを受ける」と述べた。日本株下落、米金利上昇やアルケゴス影響懸念-金融中心に幅広く安い 東京株式相場は下落。米インフラ計画の詳細を見極めたいとの手控えムードが強い中、米金利上昇懸念やレバレッジ取引への警戒から、三菱UFJフィナンシャル・グループなど金融や電機株など内外需とも安い。 TOPIXの終値は前日比23.86ポイント(1.2%)安の1954-続落 日経平均株価は253円90銭(0.9%)安の2万9178円80銭-5日ぶり反落 東証33業種では銀行やその他金融、陸運、パルプ・紙、証券・商品先物取引などが下落-輸送用機器と鉄鋼は上昇 市場関係者の見方 三井住友信託銀行の瀬良礼子マーケット・ストラテジスト アルケゴスに絡む損失がどれぐらいなのか、まだ全体がみえてないところがやや不安要素、金融株の下げが大きくなってきている自動車などが下振れるなど鉱工業生産は良くなかった、先行きについても不透明要素がある いちよしアセットマネジメントの秋野充成執行役員 米金利は年末まで上昇が予想され、成長株のバリュエーション調整は今後も続くだろう三菱UFJ証券ホールディングスのようなレバレッジ取引に関連する損失はまだ出てくる可能性米インフラ計画のプラス面は株価に織り込んだことで市場の注目点は増税の規模と時期に移り、内容次第では嫌気する懸念 背景 30日の米国10年債利回りは一時1.77%と1年2カ月ぶりの高水準 金融機関のアルケゴス関連損失、最大100億ドルにも-JPモルガン バイデン米大統領、2兆ドル規模のインフラ支出のビジョン公表へMUFG株続落、アルケゴスで損失可能性-間接影響含め状況注視 三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の株価が一時前日比4%安の591.1円まで下落した。傘下の証券会社が米アルケゴス・キャピタル・マネジメント関連の取引で330億円規模の損失を計上する可能性があることが分かり、市場では間接的な影響も含めて状況を注視したいとの見方が出ている。 三菱UFJ証券ホールディングスは30日、欧州子会社での米顧客との取引において多額の損失が生じる可能性があると発表した。29日時点での損失の見込み額は約3億ドル(約330億円)。顧客先については明らかにしていないが、関係者によるとアルケゴス関連の取引によるものだという。 JPモルガン証券の西原里江アナリストは30日付リポートで、「MUFG全体の最終利益への影響は限定的との印象だ」と指摘。一方、「アルケゴス関連損失は、メガバンクの中では米国事業が大きいMUFGにおいて潜在的に大きくなり得る」などとして、「金融市場への影響の広がりによる間接影響を含め、引き続き状況を注視したい」との見方を示した。【米国株動向】インデックスファンドをアウトパフォームするとみられるハイテク株3銘柄モトリーフール米国本社、2021年3月10日投稿記事より投資の初心者にとって、いきなり個別銘柄を買うよりも、S&P500指数などの主要株価指数のパフォーマンスに連動するインデックスファンドから始めるのは賢い方法です。インデックスファンドはパッシブ運用であり、アクティブ運用の米国のミューチュアルファンド、日本の投資信託やヘッジファンドと比べて手数料は低く設定されています。自動的に分散投資が実現されるため、いっぺんに全資産を失うリスクは低くなります。ところが、投資について少し勉強してみると、S&P500指数を常にアウトパフォームしている銘柄が多くあることが分かります。ハイテクセクターは最近、恐怖に駆られた投資家によるグロース株からバリュー株へのローテーションに伴ってやや弱含んでいますが、それでも市場をアウトパフォームする銘柄群という点では銘柄が豊富な投資領域です。国債利回りが上昇している状況下で、バブル気味のハイテク株に投資するのはやや危険ですが、それほど加熱していないハイテク銘柄であれば、2021年にS&P500指数を簡単にアウトパフォームできるかもしれません。 S&P500指数を常にアウトパフォームしている3銘柄S&P500指数は過去5年間でほぼ2倍になりましたが、マイクロソフト(NASDAQ:MSFT)、アップル(NASDAQ:AAPL)、マイクロン・テクノロジー(NASDAQ:MU)の3社はこれをはるかに上回るペースで上昇しています。過去のパフォーマンスは将来のリターンを保証するものではありませんが、3社とも今年は2桁の増収・増益が見込まれます。 3社の短期的カタリスト3社には明らかなカタリストが目前に控えています。マイクロソフトは、法人向けソフトウェアの低調をゲームやクラウド事業の成長が相殺して、パンデミックを乗り切りました。昨年11月のゲーム機Xboxの新型機の発売やクラウド事業の拡大に加えて、パンデミック収束後に法人向けソフトウェアが回復すれば、2022年6月期にかけて成長が期待されます。アップルは、2021年9月期のiPhone 12の出荷台数が過去最高を更新する見通しです。シリーズ初の5G対応機種とのことで買い替えを考えるユーザーが多く、機種の売れ行きに伴ってサービス部門も成長が見込まれ、有料会員数は2020年10-12月期に6億人を超えました。マイクロンはDRAMおよびNANDメモリーの世界最大手の1社で、2019年から2020年上半期にかけて価格の落ち込みに見舞われましたが、2020年下半期に底打ちしています。PC販売台数の増加、5G対応スマートフォンや新型ゲーム機の増産、データセンター市場からの旺盛な需要などにより、今後数年間は増収・増益が見込まれます。 ディフェンシブなハイテク銘柄に妙味ハイテク銘柄に対する最近の売りは、マイクロソフト、アップル、マイクロンにはそれほど及んでいないようです。市場のローテーションがしばらく続くとみられる中、これらの企業はS&P500指数やそれに連動するインデックスファンドを大きく引き離すかもしれません。【本日のNYダウ見通し】バイデン大統領が発表するインフラ計画に注目【NYダウ予想レンジ:32,800~33,300ドル】30日のNYダウは反落。前日比104.41ドル安の33,066.96ドルで取引を終了しました。バイデン大統領が本日に発表する予定のインフラ計画を控え、景気回復と同時に財政赤字拡大を織り込み、米10年債利回りが1.77%まで上昇。昨年1月以来、14カ月ぶりの高値水準に達したので、相対的な割高感が意識されやすいハイテク株が売られました。スマートフォンのアップルは1.23%、ソフトウエアのマイクロソフトは1.44%下落しています。そして、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数も、14.253ポイント安の13,045.394で取引を終了しています。本日の経済指標では、ADP全国雇用者数と中古住宅販売保留が注目されます。昨日発表された消費者信頼感指数は、前月比19.3ポイント上昇の109.7と、市場予想の96.8を大きく上回りました。本日の経済指標でも、景気回復が確認されるのかどうかに注目です。また、バイデン大統領がどのようなインフラ再構築計画を発表するのかに、マーケットの関心が集まるでしょう。期末の日経平均は前年比54.2%高、東証再開以来3番目の上昇率[東京 31日 ロイター] - 日経平均の2020年度の期末株価は、前年度末比1万0261円79銭高の2万9178円80銭となり、54.2%の上昇率を記録した。この上昇率は1952年度の75%、1973年度の64%に次ぐ、1949年に東証が再開してから史上3番目の上昇率となる。上昇幅は過去最高。一方、TOPIXの期末株価は1954.00で前年比で39.3%の上昇となった。昨年の期末は、その直前となる3月18日の取引時間中に日経平均が昨年来安値1万6358円19銭を付けるなど、株式市場ではコロナショックのピークだった。その後、今年に入ってから3万円を回復するなど大幅に上昇したことで、期末株価は前年度末を大きく上回ることが確実視されていた。そのため「期末が接近するに従い、機関投資家などは決算対策に苦労することはなく、いつでも益出しが出来る状況だった。3月に入って米長期金利の上昇で不透明感が強くなる中で、決算対策売りを急ぐ投資家が増え、結果的に昨年来買われていたグロース株が直近の相場で厳しい下げに見舞われた」(国内証券)という。52年度は朝鮮戦争特需、72年度は日本列島改造論による過剰流動性と、それぞれ上昇の背景には日本経済史に残る出来事があった。20年度は新型コロナウイルスによる超金融緩和策と大規模な財政出動などを背景に、歴史に残る上昇率が記録されることになった。30日の米国市場で株が下落、国債利回りが上昇した背景とは財政支出の拡大を意識、金は続落ブルームバーグ30日の米株式相場は下落。バイデン政権が計画する一段の財政支出による影響が意識され、米10年債利回りは一時14カ月ぶり高水準を付けた。S&P500種株価指数は公益や情報技術、生活必需品を中心に下落。一方、金融株は上昇し、アルケゴス・キャピタル・マネジメントに絡む問題を受けた前日の下げから持ち直した。アップルの下げに押され、ナスダック総合指数もマイナス圏で引けた。S&P500種は前日比0.3%安の3958.55。ダウ工業株30種平均は104.41ドル(0.3%)安の33066.96ドル。ナスダック総合は0.1%下落。米国債相場は、ニューヨーク時間午後4時59分現在では、10年債利回りが1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の1.70%。一時は1.77%まで上昇する場面もあった。5年債は一時0.95%と13カ月ぶり高水準を付けた。TDアメリトレードのチーフ市場ストラテジスト、JJ・キナハン氏は「どんなトレードを手掛けるべきか、市場はまだ見極めようとしている。在宅関連銘柄は過去1年間のトレードだった」と指摘。「今はワクチン接種が増えている一方で、多くの州で感染者が増え始めている。混迷した状況と言え、相場もしかりだ」と述べた。バイデン大統領は31日にピッツバーグで、格差是正とインフラ強化を目指す大型財政支出の詳細を発表する。外国為替市場ではドルが上昇。ドル指数は昨年11月半ば以来の高水準付近で推移した。一方、商品価格の下落を背景に、資源国通貨の大半は軟調だった。主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.4%上昇。ドルは対円で0.5%高の1ドル=110円36銭。1年ぶり高値を付けたあとは、伸び悩んだ。ユーロは対ドルで0.4%安の1ユーロ=1.1717ドル。ニューヨーク原油先物相場は3営業日ぶりに下落。ドル高に加え、需要回復を巡る短期的リスクが意識されたことが背景。石油輸出国機構(OPEC)と非OPEC主要産油国で構成する「OPECプラス」の共同技術委員会(JTC)はこの日、2021年需要予測の下方修正で合意した。OPECプラスは今週、5月の生産水準について協議する。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物5月限は1.01ドル(1.6%)安の1バレル=60.55ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント5月限は84セント安の64.14ドル。金相場は続落し、スポット価格は9カ月ぶり安値近辺での取引となった。米国でのワクチン接種進展や追加の財政支出計画が意識され、ドルや国債利回りが上昇したのを受けた動き。ニューヨーク時間午後3時8分現在では1.8%安の1オンス=1680.80ドル。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物6月限は1.7%安の1オンス=1686.00ドルで終えた。【市況】明日の株式相場に向けて=新年度相場は広角打法で臨む きょう(31日)の東京株式市場は、日経平均株価が253円安の2万9178円と5日ぶりに反落。振り返ってみれば、3月相場はAIアルゴが闊歩したこともあって日経平均は連勝もしくは連敗が目立った。今月19日から週をまたいだ24日にかけて日経平均株価は4営業日続落となったが、これ自体は特筆する話ではないものの、下げ幅が大きく投資家は肝を冷やす場面に遭遇した。この4営業日のうち3日間は波乱安といってもいい大幅な下げとなり、4日間合計で日経平均は1800円強も水準を切り下げた。 そして、25日からは上り坂に転じ、今度は前日まで4営業日続伸。市場関係者も安堵の胸をなでおろしたわけだが、ちょっと嫌な感触を残している。なぜなら、この間に日経平均がどれだけ水準を切り上げたかといえば1000円程度であり、リバウンドとしては物足りないからだ。きょうは前日の米国株市場が軟調だったこともあって、底値で掬(すく)った目先筋の売りを誘発して不思議のないタイミングではあったが、深押しとはいえないまでも250円あまりの下げをみせ、名実ともに新年度相場入りが目前となるなか少々気勢を削がれた感は否めない。 アフターコロナの景色を経済的観点から描き出すマーケット。景気敏感セクターやそれらを含めたバリュー株に火がつき底上げ本番を思わせるが、米国では政府や中央銀行の大盤振る舞いの反動がそろそろ顕在化するのではないかという恐怖心も綯い交ぜ(ないまぜ)となっている。31日にはバイデン政権が、先日成立させた1兆9000億ドル規模の巨額経済対策に続き、今度は3兆ドル規模の新たな対策を打ち出す方針が伝わっている。 経済の鏡に位置づけられる株式市場にとってはこの上ないポジティブストーリーに思えるが、「新型コロナ対応とはいえ、ちょっとやり過ぎでは?」という“本音”が前日のNYダウやナスダック指数など主要株価指数の動きに投影されている。それとセットでついてくる「増税の思惑」がもはや拭い切れないからだ。その意味で米長期金利の上昇は、市場の動揺を如実に映すウソ発見器の針のような役割を示す。グロース株からバリュー株へのシフトを促した米10年債利回りの上昇だったが、更に跳ね上がった場合は、バリュー株選好が一段と強まるというような単純なものではないことは明らかで、投資家はそれなりの防御姿勢を取る必要はある。 とはいっても、4月は新年度入りに伴うニューマネーが流入する月だ。ゴールデンウイーク手前までは強い地合いが続くという前提をメインシナリオとして個別銘柄戦略を考えたい。きょうの相場では、再生可能エネルギー関連とりわけ太陽光発電関連に投資マネーが群がった。バイデン政権が打ち出す3兆ドル規模といわれる第2弾の大型経済対策ではインフラ投資を主眼とし、太陽光発電など再生エネ分野への投資で雇用を創出する方針が伝えられている。これを手掛かりに前日の米国株市場では太陽光発電関連株が買われたが、その流れが東京市場にも押し寄せてきた。レノバ、ウエストホールディングス、霞ヶ関キャピタル、エヌ・ピー・シー、Abalanceなどが投資資金を誘引したが、米国の太陽光発電インフラ拡充で恩恵を受ける企業という切り口では、エヌ・ピー・シーが中期的にみて優位性を持っている。 もちろん、再生エネ関連に特化して銘柄を探す必要性もない。新年度相場突入に際し投資テーマは決め打ちせず幅広い視点を心掛ける。きょうはパワー半導体関連でMipoxの上値追いが加速。前日は上ヒゲをつけたが、きょうは値を保ち大陽線を示現した。アフターコロナという視点にはそぐわないが、防護服のアゼアスも業績大幅増額を契機に非常に強い足をみせている。ここ新車販売の好調を背景に賑わいをみせている自動車周辺株ではダイカスト大手のアーレスティの押し目や上値追いに勢いがある計測器大手の共和電業に着目してみたい。銅市況関連では黒谷、そして脱炭素の絡みでテーマ性が加わった鉄鋼株では電炉大手の東京製鐵をマークしたい。また、バーチャル系の銘柄も強い株は多い。DX関連の株価3ケタ銘柄ではシステムインテグレータが26週移動平均線を上回った矢先、中期スタンスで妙味あり。 あすのスケジュールでは、3月の日銀短観、3月の新車販売台数など。海外では2月の豪貿易収支・小売売上高、3月の中国製造業PMI(財新)、3月の米ISM製造業景況感指数など。なお、フィリピン市場は休場となる。(銀)出所:MINKABU PRESS明日の戦略-アノマリー通り月末は下落、4月相場に入り物色に変化は出てくるかトレーダーズ・ウェブ 31日の日経平均は5日ぶり反落。終値は253円安の29178円。米国株安を嫌気して、寄り付きから3桁の下落。その後はマイナス圏での一進一退が続いた。下げ幅を200円超に広げて29100円台に突入してくると押し目を拾う動きが出てきた一方、下げ幅を2桁に縮めてくると押し戻された。後場も大勢に変化はなく、29200円台で推移する時間帯が長かったが、取引終盤に売りに押され、安値圏で取引を終えた。TOPIXは安値引け。大型株の手掛けづらさが意識される中、新興市場に資金が向かっており、マザーズ指数は後場一段高で2%近い上昇となった。 東証1部の売買代金は概算で2兆9000億円。業種別では上昇は輸送用機器と鉄鋼の2業種のみで、サービスが小幅な下落。一方、銀行、ゴム製品、その他金融などの下げが大きくなった。上期の見通しを引き上げた明光ネットワークジャパンが後場に買いを集めて大幅高。半面、米IT企業の買収観測が伝わった日立は、買収額が1兆円規模になるとの内容が嫌気されて後場に入って急落。7%を超える下落となった。 東証1部の騰落銘柄数は値上がり491/値下がり1650。トヨタが3%を超える上昇。ドル円の110円台乗せや、証券会社の目標株価引き上げが強い支援材料となった。エムスリーやソフトバンクGなど、グロース株の一角が強い動き。BASEやAIインサイド、フリーなどマザーズの主力どころの銘柄が買いを集めた。好決算や株主還元強化が好感された西松屋チェーンが大幅高。上方修正と増配を発表したヤマシタヘルスケアがストップ高まで買われた。 一方、傘下の証券会社で多額損害の可能性が判明した三菱UFJが4%近い下落。三井住友やみずほなど他の銀行株にも警戒売りが広がった。キーエンスや任天堂、ファナックなど値がさ株が軟調。総務省の有識者会議でSIMロックを原則禁止とする案が盛り込まれると伝わったことから、乗り換え競争過熱への警戒が強まり、NTTやKDDIが大きく売られた。ほか、業績見通しが失望を誘ったブロッコリーや、上期が営業減益着地となったストライクが急落した。 日経平均は253円の下落で5日ぶりに反落。大幅安というほどではないが3桁の下落で、終始さえない地合いとなった。また、終値(29178円)が始値(29278円)を下回り、例年の年度末のアノマリー通り陰線を形成した。きょうに関しては、過去の傾向を参考に買いを手控えていた投資家も多いと思われる。ただ、多くの業種が下落し、値がさ株も弱かった中では、そこまで下に値幅は出ておらず、かなり健闘したと言える。 物色に関してはいびつな動きが見られた。昨晩の米国市場では長期金利が上昇したことを材料に、銀行株が買われ、テクノロジー株が売られた。しかし、きょうの東京市場では、銀行株の下げが目立った。米ファンドに絡む悪材料を材料に三菱UFJが売られ、他にも連想が広がったという格好ではあるが、地銀株まで軒並み大幅安となっており、売り材料にされたような感もある。一方で、金利上昇が逆風となるマザーズ銘柄は強さが目立った。あすからは、名実ともに新年度相場となる。バリュー株が相対的に強く、グロース株が敬遠されていたこれまでの傾向に変化が出てくるのかには注意を払っておきたい。明日の日本株の読み筋=米イベントにらみで神経質な展開かモーニングスター あす4月1日の東京株式市場は、名実ともに新年度入りとなるが、米イベントをにらみ神経質な展開が予想される。現地3月31日には、バイデン米大統領が巨額なインフラ投資計画を明らかにする。大規模財政出による米長期金利の上昇が改めて懸念されるほか、増税に言及するとの見方もあり、株価押し下げ要因になる可能性がある。さらに、週末2日に発表される米3月雇用統計は大幅増加が観測され、景気回復の強さが意識されれば、米金利高に動き、グロース(成長)株売りにつながる不安もある。いずれにしろ、無難に通過できるかが注目されるが、結果次第で投資家心理が揺れることも考えられる。 31日の日経平均株価は5営業日ぶりに大幅反落し、2万9178円(前日比253円安)引け。朝方は、米長期金利の上昇を背景に30日の米国株式が下落した流れを受け、売りが先行した。きのう4日続伸した反動もあり、上げ幅は一時260円を超えた。一巡後は、円安歩調を支えに輸出関連株の一角が買われ、一時80円強安まで下げ渋ったが、その後は上値が重くなり、大引けにかけては株価指数先物に大口の売り物が出て、安値圏に押し戻された。20年度の日経平均、1万0261円上昇=戦後最大の上げ幅―東京株式市場時事通信 2020年度最後の取引となった31日の東京株式市場は、利益確定売りが優勢となり、日経平均株価の終値は前日比253円90銭安の2万9178円80銭と反落した。ただ、19年度末からは54%上昇。上げ幅は1万0261円に達し、年度ベースでは戦後最大となった。新型コロナウイルス感染拡大が続く中、世界的な金融緩和やコロナワクチンの普及による景気回復期待が株高を後押しした。 19年度末は新型コロナ感染が深刻化し、株価が約3年ぶりの底値を付けた直後だった。20年4月に緊急事態宣言が発令され経済活動が萎縮したが、日米の大規模金融緩和などが好感され、日経平均は上昇。6月にはコロナ禍で急落する前の水準に回復した。 11月の米大統領選でバイデン氏が勝利し追加経済対策への期待が高まると、日米の株価は一段高。ワクチン開発の進展や海外での接種開始も材料視され、21年2月には日経平均が30年半ぶりに3万円台を回復した。その後は米長期金利上昇への警戒感で頭打ちとなった。 伊藤高志野村証券シニア・ストラテジストは20年度の株価上昇について、「財政出動と金融政策のサポートが大きかった。企業業績が通期で小幅減益にとどまるとの見通しも影響した」と指摘した。 大和証券の木野内栄治理事チーフテクニカルアナリストは、1918年に始まったスペイン風邪流行後の米国株上昇などを引き合いに、「感染爆発が起きると長期大幅株高になる過去の歴史が繰り返された。今後もこの流れが続くだろう」との見方を示した。(了)本日の夕食は春の山菜の天ぷらでした。一緒に楽しんだのは廣戸川でした。美味しくいただきました。日立、1兆円で米IT企業買収 海外でデジタル事業強化時事通信 日立製作所は31日、米IT企業グローバルロジック(カリフォルニア州サンノゼ)を買収すると発表した。買収額は96億ドル(約1兆368億円)となる見込みで、日立の企業買収としては過去最大級。海外でデジタル関連事業を強化するのが狙い。7月末までの買収完了を目指す。 グローバル社は、米国やインドなど世界14カ国に拠点を置く。企業のデジタル化を支援するサービスを手掛け、400社超の顧客を持っている。 日立の東原敏昭社長は31日、オンライン形式で記者会見し、「(デジタル事業の)グローバル展開を加速するための買収だ」と説明した。グローバル社の技術や人材、顧客基盤を取り込み、デジタル事業の海外での売上高比率を現在の3割程度から5割超に高める考えだ。NY株見通しー経済対策第2弾発表を控え様子見かトレーダーズ・ウェブ 今晩のNY市場は様子見か。昨日は長期金利の上昇を嫌気して主力ハイテク株が下落したことで、ダウ平均が4日ぶりに反落し、S&P500とナスダック総合も2日続落した。ただ、強い経済指標を好感し、空運やクルーズなどの景気敏感株の一角が堅調に推移し、おおむね底堅い展開だった。投資家の不安心理を示すVIX指数は前日比-1.13ポイントの19.61ポイントと、再び20ポイントを下回った。 今晩は、引け後にバイデン米大統領が経済対策第2弾を発表する予定で、発表を控えた様子見姿勢が強まりそうだ。また、寄り前には週末の3月雇用統計を占う3月ADP民間部門雇用者数の発表もあり、結果を受けた長期金利の動向が注目される。 今晩の米経済指標は3月ADP民間部門雇用者数のほか、2月中古住宅販売仮契約指数、EIA週間原油在庫など。企業決算は寄り前にウォルグリーン、引け後にマイクロン・テクノロジーが発表予定。(執筆:3月31日、14:00)〔NY外為〕円、110円台後半(31日朝)時事通信 【ニューヨーク時事】31日午前のニューヨーク外国為替市場では、早期の米景気回復期待を背景にドル高基調が継続し、円相場は1ドル=110円台後半に下落している。午前9時現在は110円65~75銭と、前日午後5時(110円30~40銭)比35銭の円安・ドル高。 米長期金利の上昇を眺め、海外市場では円を売ってドルを買う流れが加速。円相場は一時110円96銭近辺まで下落した。その後は売買が一巡し、ニューヨーク市場は110円75銭で取引を開始した。 米民間雇用サービス会社ADPが朝方発表した3月の民間就業者数は前月比51万7000人増となり、市場予想(ロイター通信調べ)の55万人増をやや下回ったが、反応は限定的。市場は、バイデン大統領がこの後行うインフラ投資を軸とした成長戦略に関する演説に注目している。 ユーロは同時刻現在、対ドルで1ユーロ=1.1720~1730ドル(前日午後5時は1.1711~1721ドル)、対円では同129円75~85銭(同129円27~37銭)と、48銭の円安・ユーロ高。(了BMW&MINI純正ドラレコ【Advanced Car Eye 2】信頼性と操作性が◎〔米株式〕NYダウ、もみ合い=ナスダックは反発(31日午前)時事通信 【ニューヨーク時事】31日午前のニューヨーク株式相場は、バイデン米大統領によるインフラ投資に重点を置いた成長戦略の発表を控え、もみ合いとなっている。優良株で構成するダウ工業株30種平均は午前10時15分現在、前日終値比23.04ドル安の3万3043.92ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は195.71ポイント高の1万3241.11。 バイデン大統領は31日、インフラ投資を重点に8年間で2兆ドル超を支出する成長戦略を発表する。財源確保のため、連邦法人税率や米企業の海外利益に対する課税率などの引き上げなどを提案する。市場ではインフラ投資計画による早期景気回復期待が広がっているものの、詳細を見極めたいとの思惑が強く、ダウは買い先行で始まった後、もみ合いに転じている。 米民間雇用サービス会社ADPが朝方発表した3月の全米雇用報告によると、非農業部門の民間就業者数は前月比51万7000人増と、市場予想(ロイター通信調べ)の55万人増をやや下回った。ただ、増加幅は2月の17万6000人増(改定)から拡大したため、市場への影響は限定的だった。 個別銘柄では、IBM、シェブロンは1%超安となり、ダウ平均を下押し。ルルレモン・アスレティカは前日発表した四半期決算が市場予想を上回る内容だったものの5%近く下落している。一方、ウォルグリーン・ブーツ・アライアンスは6.0%上昇。アップルは2.4%高、ボーイングも1.8%高といずれも堅調。(了)ファイザーのワクチン、子供対象の臨床試験で100%の有効性=米国株個別みんかぶFX ファイザーは、ドイツのビオンテックと開発した新型ウイルス向けワクチンについて、12歳から15歳の子供を対象にした臨床試験の最終段階で有効性が100%だったことを明らかにした。 臨床試験は2200人以上の子供を対象に実施され、安全性に関する懸念は報告されなかったという。今回の結果を受けて両社は今後数週間のうちに、ワクチン接種の対象を12~15歳の子供に拡大するよう米当局に要請すると述べた。 ただ、株価の反応は限定的でファイザー株は小幅高に留まっている。(NY時間10:20)ファイザー 36.16(+0.05 +0.14%)今夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中の17銘柄が値を上げてスタートしましたね。ショッピファイ、スクエア、トゥイリオが大きく上げていますね。
2021.03.31
コメント(0)
-
3月30日(火)…
3月30日(火)、晴れです。暖かですが、黄砂で煙っています…。そんな本日は7時15分頃に起床。新聞に目を通し、朝食を済ませ、ロマネちゃんと戯れる。本日のノルマは1階の掃除機ですか…。ハイハイ…。朝のコーヒーブレイクはネスプレッソで…。残り物のいろいろなチョコレートをいただく…。そして恒例の母親宅の後片付けですが、本棚の書籍を処分してとりあえず一段落…。続いて、仕事をしていたころの応接兼事務室の整理整頓…。昼食前に終了とする。1USドル=109.92円。1AUドル=83.90円。昨夜のNYダウ終値=33171.37(+98.49)ドル。現在の日経平均=29375.34(-9.18)円。金相場:1g=6685(-69)円。プラチナ相場:1g=4628(-27)円。昨夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中の7銘柄が値を上げて終了しましたね。5%以上の大きな変動は見られませんね。本日の東京市場ではチェック中の日本株30銘柄中の10銘柄が値を上げていますね。重点3銘柄では1銘柄が値を上げていますね。Jフロント、野村マイクロ、テクノホライゾンが上げて、長谷工、スクロールが下げていますね。ファイザー とモデルナのコロナワクチン、実世界でも高い予防効果 米ファイザー、モデルナがそれぞれ開発した新型コロナウイルスのワクチンは、発症だけでなく感染自体を高い割合で防ぐことが米疾病対策センター(CDC)のデータで明らかになった。両ワクチンは初回接種後2週間で相当の予防効果を発揮した。 CDCが29日公表した調査データによると、いずれかのワクチンを2回接種した後では感染を90%抑制する効果があった。これ以前の臨床試験では、両ワクチンが発症や重症化、死亡を防ぐ効果を持つことが実証されている。 CDCは広範なワクチン接種が進められた昨年12月半ばから3月半ばにかけ、医療・福祉従事者や教師ら現場に立つ約4000人を対象に調査した。この集団は新型コロナ感染リスクが高いため、基礎疾患のある高齢者らと並んで最も早くワクチンを接種した。 ファイザー・ビオンテック製、モデルナ製とも数週間の間隔を空けて2回接種する必要がある。今回の調査によると、初回接種から2週間後には80%の予防効果が見られ、接種が完了したと見なされる2回目の接種から2週間後では予防効果は90%に上昇した。 調査結果は無症状感染や軽度の有症状をどれだけ防いだかなど、詳細な内訳は明らかにしていない。クレディSが目指したアルケゴス混乱回避策、各行の合意なく事態悪化 先週半ば、ウォール街の中枢では警報が鳴り響いていた。1990年代のロングターム・キャピタル・マネジメント(LTCM)以来最大のヘッジファンド関連の突発事件に直面しかねない状況に経営陣が気づいたからだ。 世界の投資銀行は急ぎ手配された電話会議に集まった。何十億ドルもの銀行損失と市場への連鎖反応の可能性を回避するため、ビル・フアン氏のファミリーオフィス、アルケゴス・キャピタル・マネジメントの問題への対応で速やかな停戦が必要だった。ただ、26日までには各行が自行のために動き出した。 アルケゴスのポジションの強制的清算は先週、主要銘柄の株価急落を招き、資本市場全般に衝撃を送り続けている。事情に詳しい複数の関係者によれば、この事態に先立ち国際金融の世界の上層部では論争があり、すぐに責任のなすり合いや怒りに転じたという。各行は損害の集計を始めている。 これまでのところ、クレディ・スイス・グループと野村ホールディングスは「多額」の損失を被る可能性があると株主に伝えた。ポジション巻き戻しで同業より一歩抜きんでたゴールドマン・サックス・グループは業績への影響は軽微な可能性が高いと投資家に通知した。ドイツ銀行は損失を回避したとしている。28日夜までブロック取引をしていたというモルガン・スタンレーはまだ、損失を明確にしていない。 26日午前にこの問題が公になる前に、世界の大手プライムブローカレッジの担当者らはフアン氏との電話会議を開き、大混乱の回避を図った。クレディ・スイスが打ち出したこのアイデアは、パニックを引き起こさずにポジションを整理する方法を見いだすため、ある種の一時的停戦状態に持ち込む狙いがあったという。 しかし、合意は見通せず、25日夜までには一部銀行が潜在的な損失を抑えるべくアルケゴスにデフォルト(債務不履行)通知を行って担保差し押さえに動いた。ただ、その時でさえ、アルケゴスとの契約条件に基づいていつ売却を進めることができるかは不明だったと関係者1人は話した。 その後すぐに、誰が抜け駆けしているかの責任追及が始まった。クレディ・スイスが売却凍結に十分にコミットしていないと疑う話も一部に浮上。26日午前までには、ゴールドマンが表向きはアルケゴスを支援するためとして一部ポジションの売却を計画したという話が広がり、これを聞いたライバル行が不快感をあらわにした。さらにモルガン・スタンレーはブロック取引で世間の関心を集め始めた。 各行の担当者はコメントを控えた。アルケゴス絡みブロック取引、29日は2900億円-ウェルズF21.4億ドル タイガー・マネジメントの元トレーダー、ビル・フアン氏のファミリーオフィス、アルケゴス・キャピタル・マネジメントが株式の売却を迫られたことに伴う市場の混乱は週明け29日も続き、26億4000万ドル(約2900億円)相当のブロック取引が行われた。 非公開情報を理由に事情に詳しい関係者1人が匿名を条件に語ったところでは、総額21億4000万ドル相当のブロック取引5件が、米銀ウェルズ・ファーゴにより実行された。取引開始前に米メディア企業バイアコムCBS株1800万株が1株48ドルでオファーされたという。 関係者によれば、取引時間中の他のオファーは次の通り。 百度(バイドゥ)の米国預託証券(ADR)280万単位(1株198ドル) ファーフェッチの株式500万株(同47ドル) 唯品会(ビップショップ・ホールディングス)のADR1200万単位(同28.50ドル) 愛奇芸(iQiyi)のADR850万単位(同16.50ドル) これとは別に米ロケット・カンパニーズの株式約2000万株が、モルガン・スタンレーを通じて1株25.25ドルで売却されたと複数の関係者が明らかにした。取引額は約5億ドルに上るという。 ウェルズ・ファーゴの担当者はコメントを控えている。モルガン・スタンレーとアルケゴスの担当者にもコメントを求めたが、これまでのところ返答はない。「アルケゴス銘柄」が続落-ブロック取引の余波を警戒 先週26日の200億ドル(約2兆1960億円)規模の株式ブロック取引の対象となった銘柄の多くが、29日の米株式市場でも大幅下落した。投資家の間ではさらなる余波に対する警戒が強い。 米メディア企業バイアコムCBSの終値は前週末比6.7%安。28日の別のブロック取引で、バイアコム株21億ドル相当がレンジ上限の価格で売り出されたと、関係者は明らかにした。中国企業、跟誰学(GSXテクエデュ)の米国預託証券(ADR)も続落。ビル・フアン氏の財産を管理・運営するファミリーオフィス、アルケゴス・キャピタル・マネジメントに関連するポジションの強制的な清算を受けた売りが続いた。百度(バイドゥ)のADRも下落。テンセント・ミュージック・エンターテインメント・グループ(騰訊音楽娯楽集団)のADRは一時の下げを埋めて1.2%高。 オアンダのシニア市場アナリスト、エドワード・モヤ氏は、プライムブローカレッジ部門はどこもマージンコール(追加証拠金の請求) で帳簿の見直しを余儀なくされるはずだと指摘した。 アルケゴスの大規模な株式ポジション巻き戻しで「多額の損害」を被る可能性がある野村ホールディングスとクレディ・スイス・グループの株価も29日の取引で急落した。モルガンS経由でロケット株のブロック取引、約550億円相当-関係者 大量の株式ブロック取引は週明けも続き、29日には米ロケット・カンパニーズの株式がモルガン・スタンレーを通じて売却されたことが、事情に詳しい複数の関係者の話で分かった。 関係者の1人によると、この日の取引時間中にロケット株は1株25.25ドルで約2000万株売却された。株価は上げ幅を縮小し、0.5%安で取引を終えた。ロケットは、米住宅ローンを手掛けるリテール専門ノンバンク金融会社最大手クイッケン・ローンズの親会社。 モルガン・スタンレーにコメントを要請したが回答はない。 26日に始まった大量のブロック取引でロケット株が対象となったのは初めて。提示価格に基づくと、ロケット株のブロック取引は約5億ドル(約550億円)相当。関係者によれば、オファー価格は1株25.25ー26.25ドルだった。S&P横ばい、ヘッジファンド懸念で銀行株に売り[ニューヨーク 29日 ロイター] - 米国株式市場は、S&P総合500種がほぼ横ばいで終了した。米ヘッジファンドのアーケゴス・キャピタル・マネジメントがマージンコールに対しデフォルトを起こしたことを受け、銀行株が売られたものの、米経済に対する楽観的な見方が出ていることで影響は限定された。ダウ工業株30種は上昇。航空機大手ボーイングが2.3%値上がりした。同社は、サウスウエスト航空から旅客機「737MAX─7」100機を受注したと発表した。クレディ・スイス(CS)は29日、米拠点のヘッジファンドがマージンコールに応じなかったことを受けて、このファンドのポジション解消を進めており、第1・四半期の業績に影響が及ぶ可能性があると明らかにした。野村ホールディングスも、米国子会社と取引先との間で多額の損害が発生する可能性を公表した。関係筋は両社の発表がアーケゴスに関連していると指摘しており、銀行業界への影響が懸念されている。この日は大手行だけでなく地銀の株も売られた。KBW銀行株指数は2.3%安で終了。一時は3.5%近く値下がりした。プルデンシャル・ファイナンシャルのチーフ市場ストラテジスト、クインシー・クロスビー氏は「米銀に影響があるのか、またあるとすればどの銀行が影響を受けるかが懸念されている。ただこれまでのところ、市場は基本的に(ニュースを)冷静に受け止めている」と話した。主要株価3指数はいずれも、日中安値から反発して引けた。クロスビー氏は、新型コロナウイルスワクチン接種の広がりや大規模な景気刺激策を巡る楽観ムードや明るい企業決算見通しが、底堅い展開につながっていると指摘した。メディア大手のディスカバリーやバイアコムCBS、米上場の中国インターネット企業バイドゥ(百度)、唯品会(ビショップ・ホールディングス)は、アーケゴスに絡み軒並み下落した。ナスダック総合は月間ベースで5カ月ぶりに下落する見通しだ。米取引所の合算出来高は110億2000万株。直近20営業日の平均は136億株。ニューヨーク証券取引所では値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を1.93対1の比率で上回った。ナスダックでは3.12対1で値下がり銘柄数が多かった。30日の日経平均、「配当権利落ち」のマイナス影響はいかほどか銀行や商社が安いブルームバーグ東京株式相場は株価指数が高安まちまちで方向感を欠く展開。3月期決算企業の配当権利落ちが響いている。銀行や商社が安く、好業績株の一角は高い。市場関係者の見方大和証券投資情報部の石黒英之シニアストラテジスト•配当権利落ちはきょうの最大のマイナス要因•アルケゴスだけでなく他のヘッジファンドも苦境に陥っていないのかはまだ不透明で、金融株などの重しになる•半面、一時的な需給要因での売り場面では、米国のワクチン接種進展や企業業績の改善から投資家の押し目買いも入りやすい背景•配当権利落ちのマイナス影響分-TOPIX17.3、日経平均177円•米国株は高安まちまち-S&P500種株価指数は0.1%安、米ダウ工業株30種平均は0.3%高•ドイツ銀がアルケゴスでリスク、クレディSと野村は多額の「損害」も楽天を提訴したIBM、「怒り心頭」の理由は何か「意味ある議論への参加を拒んできた」ブルームバーグIBMは29日、消費者にキャッシュバックを提供している楽天のウェブサイトとモバイルアプリが自社技術を無断で使用し、特許4件を侵害しているとして提訴した。デラウェア州ウィルミントンの連邦地裁に提出した訴状でIBMは、賠償金の支払いと自社技術のさらなる無断使用を禁止する裁判所命令を求めている。IBMは、約6年にわたりライセンスに関する交渉を試みてきたが、楽天側が「あらゆる意味ある議論への参加を絶えず拒んできた」と主張。「IBMの技術革新の恩恵を違法に享受している」とし、楽天を提訴する以外の選択肢はなかったとしている。2兆2000億円が強制精算! アルケゴスショックの裏に「CFD」秘密裏にポジション積み上げブルームバーグビル・フアン氏の投資会社、アルケゴス・キャピタル・マネジメントに関連する200億ドル(約2兆2000億円)のポジションが強制的に清算されたことで、同社が密かに投資先企業の持ち分を積み上げるのに利用していたデリバティブ(金融派生商品)に注目が集まった。同社の取引について知る関係者によると、アルケゴスが利用していたレバレッジの多くは野村ホールディングスやクレディ・スイス・グループなどの銀行が、スワップや「差金決済取引(CFD)」を通じて提供していた。この取引ではアルケゴスが実際に原資産を保有することはない。米国の上場企業の株式を5%以上保有する投資家は通常なら、持ち分を開示する必要がある。しかしアルケゴスが利用していたとみられるデリバティブ(金融派生商品)を通じてポジションが構築された場合はそうではない。取引所外で取引されるこの商品を使って、フアン氏のような運用者らは開示することなく上場企業の持ち分を積み上げることができる。ゴールドマン・サックス・グループやモルガン・スタンレーなどの銀行が、アルケゴスがレバレッジを使って積み上げた巨額の投資を強制的に売り、アルケゴスの転落は世界に影響を及ぼした。百度(バイドゥ)やバイアコムCBSなどの株価は大きく変動し、野村ホールディングスとクレディ・スイス・グループは巨額の損害を被る可能性を明らかにした。影響を大きくしたのは借入金を使った賭けだ。レバレッジを効かせた大規模な賭けが外れるとマージンコール(追加証拠金の要求)がかかり、ヘッジファンドなどの投資家は損失をカバーするための追加担保として現金か証券を差し入れなければならない。アルケゴスが差し入れを求められた額は恐らく、ポジション全体に比べれば小さなものだっただろう。しかし担保が差し出せなかったため強制的にポジションが清算されることになり、影響が広がった。ヘッジファンドが資本市場で演じる役割があらためて浮き彫りになった。リテール投資家の熱狂がゲームストップ株を押し上げた際は同銘柄を空売りしていたヘッジファンドが大打撃を受け、米証券取引委員会(SEC)や政治家の監視の目を引き付けた。今回は、1つの会社がデリバティブを利用して秘密裏に大規模なポジションを構築できたという事実が、ヘッジファンドには市場を不安定化させる力があるという批判を再燃させるかもしれない。エクイティースワップとCFDは持ち高を開示しないで済むことに加え税制上の有利さから、ヘッジファンドの間で人気が高まってきた。銀行も実際に証券を売買する場合ほど多くの資本を割り当てることなく大きな利益が得られるこの取引を好む。フアン氏の取引の多くはまだ不明だが、市場のポジションから見て同氏の資産は50億-100億ドル程度とみられており、ポジションの総額は500億ドルを超えている可能性がある。フアン氏にコメントを求めたが応答はない。【市況】前場に注目すべき3つのポイント~買い一巡後の底堅さを見極める相場展開に~30日前場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。■株式見通し:買い一巡後の底堅さを見極める相場展開に■セ硝子、21/3上方修正 営業利益30.0億円←20.0億円■前場の注目材料:ユーグレナユーグレナなど、バイオプラ利用促進で新組織■買い一巡後の底堅さを見極める相場展開に30日の日本株市場は、買い一巡後の底堅さを見極める相場展開になりそうだ。29日の米国市場ではNYダウは98ドル高だった。投資会社による強制的なポジション解消取引関連の報道を受け、金融システム混乱懸念に売り先行となった。しかし、米国内大手金融各社は同社が顧客ではない、あるいは、関連取引による影響が「軽微」であることを明らかにすると警戒感が後退。さらに、バイデン大統領による3兆ドル規模のインフラ計画の詳細発表を今週控えているほか、政権が4月19日までにワクチン接種対象をさらに拡大する計画を発表すると経済活動再開への期待からNYダウは上昇に転じている。シカゴ日経225先物清算値は大阪比250円高の29330円。円相場は1ドル109円70銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から買い先行で始まろう。昨日は後場半ばから急速に軟化する展開となっていたが、懸念要因であった米国でのブロック取引による金融市場の混乱が避けられたこともあり、買い戻しの流れが優勢になりやすいだろう。日経225先物のナイトセッションでは前日の高値水準まで戻す場面もみられており、朝方はインデックスに絡んだ売買による上昇が意識されそうである。また、需給要因としては改めて配当再投資に伴う買い需要が意識されやすいと見られ、相場全体の底堅さにつながる可能性はありそうだ。もっとも、米長期金利の上昇を受けてナスダックは下落していることもあり、ハイテク株の動向は見極めが必要となろう。インデックス主導で上昇した後はこう着感が強まる可能性はありそうだが、下値の堅さが意識される場面においては、次第に新年度を意識した物色もみられてくることも考えられよう。マザーズ指数は25日、75日線に上値を抑えられる格好で下落となっていたが、政策テーマなどを材料に個人主体の売買も次第に活発化してこよう。米国ではバイデン米大統領のインフラ計画の発表を控えていることもあり、先高期待は根強いと考えられる。そのほか、足元ではNT倍率は緩やかではあるが上昇傾向を見せてきており、長期金利の動向を睨みつつ、ハイテク株の押し目狙いのスタンスになるだろう。■セ硝子、21/3上方修正 営業利益30.0億円←20.0億円セ硝子は2021年3月期業績予想の修正を発表。営業利益は20.0億円から30.0億円に上方修正している。半導体用途の特殊ガス関連製品等の販売が想定より好調に推移したことから、予想を上回る見通しとなった。■前場の注目材料・日経平均は上昇(29384.52、+207.82)・NYダウは上昇(33171.37、+98.49)・シカゴ日経225先物は上昇(29330、大阪比+250)・1ドル109円70-80銭・米原油先物は上昇(61.56、+0.59)・海外コロナワクチン接種の進展・世界的金融緩和の長期化・株価急落時の日銀ETF買い・ユーグレナユーグレナなど、バイオプラ利用促進で新組織・三菱重艦艇・官公庁船を取得、三井E&SHDから・野村2200億円損失も、ドル建て社債の発行中止・三菱ガスJ?オイル子会社買収、接着剤を一貫生産・日産自「GT?R」補修向け部品を再供給、新技術活用・新明和工業自動運転車向けに自動入出庫技術確立、機械式駐車設備で・IDEC協働ロボシステム増産、新工場を来月稼働・ワキタ九州北部の建機賃貸2社子会社化・ミネベアミツミリコーとベッドセンサー機能絞り半値、介護現場からのニーズ反映・東芝オンプレミス版の疑似量子計算機開発・日本ユニシスセブン銀と業務提携・富士フイルムアストラゼネカと肺がん「CRT症例」検索でシステム開発・エーザイ「レンビマ」を胸腺がん治療薬に追加承認取得・ロート製薬オリンパスRMSを子会社化、整形外科領域を追加・日立スイス社と精密医療分野で協業・日本金属設備投資250億円、10カ年経営計画策定・住友化学接着剤原料を28円値上げ☆前場のイベントスケジュール<国内>・08:30 2月有効求人倍率(予想:1.09倍、1月:1.10倍)・08:30 2月失業率(予想:3.0%、1月:2.9%)<海外>・特になし《ST》 提供:フィスコルネサス-大幅安 工場の再開「1カ月以内」に暗雲 被害装置台数が拡大=日経トレーダーズ・ウェブ現在値ルネサスエ 1,175 -33 ルネサスエレクトロニクスが大幅安。30日付の日本経済新聞朝刊は、火災で停止中の同社那珂工場(茨城県ひたちなか市)で目標とする「1カ月以内」の稼働再開に暗雲が漂っていると報じた。 記事によれば、使用できない装置が当初把握の11台から20台以上に増えたようだ。市場にあまり流通していないものもあり、代替装置を確保できるかは不透明な要素もある。車載半導体不足の長期化につながる恐れがあるとしている。東京為替:ドル・円は109円95銭まで上昇し、一段高の展開フィスコ30日午前の東京市場でドル・円は109円90銭近辺で推移。日経平均は90円安で推移しているが、米長期金利の高止まりを意識してリスク回避的なドル売り・円買いは抑制されている。ここまでの取引レンジは、ドル・円は109円75銭から109円95銭で推移、ユーロ・円は129円13銭から129円37銭で推移、ユーロ・ドルは1.1763ドルから1.1772ドルで推移している。・NY原油先物(時間外取引):高値62.27ドル 安値61.73ドル 直近62.00ドル【売買要因】・欧米と中国の対立は長期化の可能性・米長期金利の高止まり・米国の量的緩和策は長期間維持される可能性ワクチン選択可能の小林補佐官発言「勇み足」 河野氏が撤回産経新聞 河野太郎ワクチン担当相は30日午前の記者会見で、新型コロナウイルスワクチン接種をめぐり、希望するワクチンを選択できるとした小林史明ワクチン担当大臣補佐官の28日の発言について「完全に勇み足だ。撤回しておわびする」と述べた。 小林氏は28日に出演したフジテレビ番組内で、「接種会場ごとに打つワクチン(の種類)を決めていく。それは公表されるので、会場を選べば打つワクチンを選ぶことができる」と述べていた。 河野氏は記者会見で「ワクチンを接種するかどうかを選択できるが、現在ワクチンは(米製薬大手)ファイザー1社しか承認されていない」と説明。今後、米モデルナと英アストラゼネカの承認が予定されているとしつつ、「それをどのような形で接種していくか戦略を検討しているところで、まだ何も決まっていない」と述べた。小林氏に対しては発言に気を付けるように注意したことも明らかにした。 また、加藤勝信官房長官が29日の記者会見で複数社のワクチンの接種が可能となった場合、国民が希望するワクチンを選択できるかどうかについて慎重に検討する考えを示したことに対しても、河野氏は「まだ何も決めてない。複数が流通することも決まってない」と述べるにとどめた。おかしいと思いました。ホテル予定地は駐車場に、簡易宿所の長屋はひっそり 「お宿バブル」後の京都を歩く京都新聞 世界遺産・清水寺に近く、観光客の急増が住民生活に影響を与える「オーバーツーリズム」(観光公害)の象徴的なエリアだった京都市東山区の六原学区。路地沿いに並ぶ昔ながらの長屋などが、簡易宿所や住宅宿泊事業法に基づく民泊へ相次いで姿を変え、レンタル着物姿の訪日外国人観光客が多く歩いていたが、昨年からの新型コロナウイルスの世界的流行に伴い、一変した。 「お宿バブル」最盛期だった2018年11月、記者は六原まちづくり委員会の菅谷幸弘委員長(68)と同学区を巡った。今月中旬に再び一緒に歩いて見えてきたのは宿泊施設の休業や撤退、建設計画変更だった。 複数の借家が取り壊されてホテル建設の予定だった土地は、広大なコインパーキングになっていた。五条通に面した陶器販売店など4軒があった場所は、昨年3月に着工して今月に完成予定という看板が掛かったまま、更地の状態だった。 長屋が相次いで簡易宿所に変わった路地では、今は多くの宿がのれんを外し、郵便受けにチラシがあふれそうなほどたまっており、観光客が出入りする様子は感じられなかった。 「お宿バブル」の頃、この路地一帯では観光客がキャリーケースを引く音が響き、ごみが路上にポイ捨てされた。近くの住民によると、簡易宿所と間違って自宅に入ってこられたり、自宅前に止めていた自転車を勝手に使われたりしたこともあった。住民たちは今、一様に「見知らぬ人が歩かなくなり、静かになった」と安堵(あんど)する。 オーバーツーリズムがピタリと止まった今、果たして、まちは元通りに戻ったのか。さらに奥へと歩みを進めた。 オーバーツーリズムに揺れ、新型コロナウイルス禍の現在は静けさを取り戻した京都市東山区の六原学区。市が公表しているホテルや簡易宿所、民泊などの一覧に登録されている数は、今年1月時点で計127件。2015年時点の計24件から、約5年で5倍以上に増えた。「学区は30町内あるが、1件もないところはなくなった」と、六原まちづくり委員会の菅谷幸弘委員長(68)は語る。 六原学区は清水寺からほど近い位置とはいえ、もともと「観光のまち」ではなかった。敷地が小さい家などが密集した古い街並みが広がり、京の伝統産業を支える職人らが暮らした。高度経済成長期以降に若い世代が流出したものの、近年は市立小中一貫校が学区内に誕生したのを機に、高齢化で多く発生した空き家再生を通じ、まちづくりに地道に取り組んできた。 ところが、訪日外国人観光客が急激に増えると、空き家や民家は宿泊施設に次々と変わった。不動産業者が歩き回り、高額な取引が相次いだ。19年に「老後資金2千万円問題」が広がると、菅谷さんのもとには、高齢の住民から「家を売って老後資金に充てたい」という相談も相次いだ。 コロナ禍で宿の建設ラッシュは収まり、休業や撤退が目立つようになった。しかし、学区が望む住宅への転用は進んでいない。原因は高止まりした地価。今も路地中の場所が坪250万円と、オーバーツーリズム前の5倍以上で取引されている。外国人が簡易宿所にしていた長屋の売値が7千万円と知った菅谷さんは「その値段を出して住みたいのは地縁者ぐらい。住宅として普通に手が出る金額まで下がるのは、いつになるのか」と浮かない顔だ。 菅谷さんが最後に案内してくれたのは、地域との関係がよかったという大規模な簡易宿所だ。町内会費を納め、ロビーを開放して住民がくつろぐ姿も見られたが、昨春に営業をやめた。 六原学区はまちに宿泊施設が急増した当初、「反対」の立場を取ろうとしたが、国を挙げての訪日客誘致を受け、まちと観光の接点を探る現実策にかじを切った。この簡易宿所はその好例とも言えたが、開業後わずか2年あまりで撤退。地域は観光に翻弄(ほんろう)された。 「オーバーツーリズムはあくまで冬眠状態。コロナ終息後、訪日客は戻るだろう。学区内では実際、東京資本による一部の宿泊施設は着々と建設が進んでいる」と菅谷さん。「地域は今後も環境に応じ、したたかに生き抜かないといけない。そのためにも、オーバーツーリズムがまちに何をもたらしたのか、京都市には腰を据えて検証してほしい」〔東京外為〕ドル、一時110円台=米国の金利上昇や回復期待で(30日午後3時)時事通信 30日午後の東京外国為替市場のドルの対円相場(気配値)は、米国の金利上昇や経済回復への期待を背景に堅調に推移し、午後3時すぎには一時1ドル=110円台に乗せた。2020年3月26日以来、約1年ぶりのドル高水準。午後3時現在は109円98~110円02銭と前日(午後5時、109円65~69銭)比33銭のドル高・円安だった。 ドル円は早朝、109円80銭台で取引された。午前9時以降、米長期金利の上昇や米国のインフラ投資による景気回復観測から仲値過ぎに109円90銭台に浮上。午後も買い優勢で推移している。 110円前後での攻防について、市場関係者からは「110円のオプションストライクは多くはなく、押し戻す動きがそれほど厚いわけではないようだ」(国内証券)などの声が聞かれる。ただ、事前に「節目の110円に達すれば達成感からいったん調整に入るだろう」(銀行系証券)と指摘されており、110円台に乗せた後は弱含んでいる。 ユーロは正午と比べ、対円は横ばい圏、対ドルは軟調。午後3時現在、1ユーロ=129円35~35銭(前日午後5時、129円23~30銭)、対ドルでは1.1760~1761ドル(同1.1784~1788ドル)。(了)ほぼ、差損は消えるのではないか…。〔東京株式〕小幅高=経済正常化期待根強く(30日)☆差替時事通信 【第1部】経済正常化に対する期待の根強さを背景に、日経平均株価は前日比48円18銭高の2万9432円70銭と小幅高。一方で東証株価指数(TOPIX)は15.48ポイント安の1977.86と下落した。 銘柄の25%が値上がりし、値下がりは72%だった。出来高は13億4076万株、売買代金は2兆7235億円。 業種別株価指数(33業種)は海運業、空運業、ゴム製品の上昇が目立ち、下落は保険業、電気・ガス業、パルプ・紙など。 個別銘柄ではソフトバンクGがしっかり。ファーストリテは急騰した。東エレク、レーザーテックが上伸。コマツは大幅高。郵船が急伸し、ANA、JALも値を上げた。ブリヂストンは買われた。半面、トヨタが軟調。三菱UFJ、三井住友が弱含み、野村も小甘い。キーエンス、ソニーがさえない。かんぽが急落。関西電も売られた。王子HDは値を下げた。 【第2部】小幅続落。MCJ、松尾電が反落し、日本KFCも値を下げた。野村マイクロは続伸。出来高1億9375万株。 ▽午後は様子見ムード 日経平均株価は取引開始直後は弱含んだ値動きだったが、その後はプラス圏に浮上。午後は様子見ムードが広がり、前日の終値を挟み方向感に乏しい推移となった。 3月期末配当の権利落ち日に当たるため、値下がりする銘柄が多かった。 ただ178円程度とみられる配当落ち分を差し引けば、日経平均は底堅く推移。手掛かり材料に乏しい中、新型コロナウイルスのワクチン接種が進み、経済が正常化に向かうことへの期待感が相場を下支えした。 市場では「権利獲得後の売却で得られた資金があす以降に再投資されることを見越し、買いも入った」(インターネット系証券)との声も聞かれた。 225先物6月きりは上昇。株価指数オプション取引はプットは値下がり、コールは値上がり。(了)日経平均は4日続伸、配当落ち分即日埋め 強い基調を確認[東京 30日 ロイター] - 東京株式市場で日経平均は4日続伸。配当権利落ち分を考慮すると、実質的に前日比で200円高前後で推移し、市場では「配当落ち分を即日埋め切ったことで、強い基調を確認する格好となった」(国内証券)との声が聞かれる。ただ、朝方に買いが一巡した後は手掛かり材料難となり、全体的に小動きとなった。29日の米国株式市場は、S&P総合500種がほぼ横ばいで終了。米ヘッジファンドのアーケゴス・キャピタル・マネジメントがマージンコールに対しデフォルトを起こしたことを受け、銀行株が売られたものの、米経済に対する楽観的な見方が出ていることで影響は限定された。日本株は、日経平均がマイナスで始まったものの、約180円の配当権利落ち分を考慮した場合、実質的には終始堅調な動きとなった。配当取り後の利益確定売りが出る一方で、受け渡しベースの年度末最終日を通過したことで、決算対策に絡んだ実需売りは一巡したとみられ、底堅さを示す格好となっている。ただ、手掛かり難から後半は模様眺めムードが強くなり、市場では「下値は堅くなってきたが、期末目前で身動きが取れない状況だ。新規のポジション取りが活発化するのは名実共に新年度入りしてからになるのではないか」(岡地証券・投資情報室長の森裕恭氏)との声も聞かれた。TOPIXは、0.78%安。東証1部の売買代金は2兆7235億6700万円となった。東証33業種では、保険業、電気・ガス業、パルプ・紙などが値下がりし、上昇した業種は海運業、空運業など7業種にとどまっている。個別では、東京エレクトロン、日本郵船などが上昇したが、トヨタ自動車など主力銘柄に下げたものが目立つ。東証1部の騰落数は、値上がり541銘柄に対し、値下がりが1564銘柄、変わらずが55銘柄だった。午後3時のドルは一時110円、米長期金利高で1年ぶり高値[東京 30日 ロイター] - 午後3時のドル/円は、前日ニューヨーク市場午後5時時点に比べ、ドル高/円安の109円後半。午後3時過ぎに110.01円まで上昇した。月末・期末を控えた実需の売買が交錯する中、ドルは米長期金利の上昇に歩調を合わせて買い進まれ、対円では1年ぶり、対ユーロでは4カ月半ぶりのドル高となった。ドルは朝方の安値109.75円から110.01円まで上昇し、昨年3月26日以来1年ぶりの高値をつけた。米長期金利の大幅高がドル/円をけん引したほか、ユーロに対するドルの強さがドル/円にも波及した。過去2営業日の間、上値抵抗線として意識されていた109.85円を上抜けたことでドルの上昇に弾みがついた。リフィニティブによると、米10年国債利回りは朝方の1.7063%(ビッドサイド)から上昇し続け、一時1.7510%と、3月18日につけた1年2カ月ぶり高水準となる1.7540%に迫った。米国関連の新規材料がない東京時間での米長期金利の大幅な上昇について市場では、米ヘッジファンドのアーケゴス・キャピタル・マネジメントとの取引を巡り、「複数の金融機関で発生したとみられる損失をカバーするために、(それらの金融機関が保有する)米国債のポジション解消売りに動いている可能性がある」(ストラテジスト)との見方が聞かれた。市場では、今回の損失問題について、1998年の米ヘッジファンド大手LTCM(ロング・ターム・キャピタル・マネジメント)の破綻や、2007年にBNPパリバ傘下のファンドが解約停止に陥り、サブプライムローン(信用度の低い借り手向け住宅ローン)問題の入り口となったパリバ・ショックになぞらえる向きもいる。米国債の利回り曲線はスティープ化し、2・10年国債の利回り格差は前日の海外市場でつけた1週間ぶり高水準の157.90ベーシスポイント(bp)から160.10bp付近まで拡大した。長期ゾーンの金利上昇の背景には、ポジション解消売りのほか、米国での新型コロナウイルスワクチン接種の広がりが景気回復を後押しするとの期待や、バイデン大統領による大型インフラ投資計画が成長を支援し国債増発につながるとの見方などがある。欧米の金利差や景況感の格差が意識された結果、ユーロは1.1761ドルまで売られ、4カ月半ぶりの安値圏となった。焦点:コロナで溢れるマネー、「低成長バブル」で際立つ日本の二極化[東京 30日 ロイター] - 新型コロナウイルス渦中に各国が競うように供給した「緩和マネー」が、株や暗号資産(仮想通貨)などの高騰を通じ、世界的に富裕層の懐を膨らませている。日本では1億円以上の別荘が短期間で完売し、高級ブランド時計が市場から姿を消す異常な事象が起きている。日本中が沸いた1980年代のバブル景気と異なり、低成長時代に溢れるマネーは通貨価値の下落と資産の膨張を同時に引き起こし、「持てる者」と「持たざる者」の格差を一層際立たせている。<ロレックスが中古市場で新品の3倍>東京都内で会社を経営する41歳のTDさん(インターネット上のハンドルネーム。本名は本人の申し出で掲載せず)は昨年8月、資産1億円の一部でアルトコイン(ビットコインを除く暗号資産の総称)を購入した。その後に相場が大きく上昇、コインを貸し出すことで得られる「金利収入」が転がり込むなどし、TDさんが投資した3000万円は5億円まで膨らんだ。仮想通貨ビットコインの名称が一般的な認知を得て、2017年に最初の暗号資産バブルが起きてから約4年。「仮想通貨市場は再びバブルが来ている」と、TDさんは言う。ビットコインの価格はこの半年間で8倍に跳ね上がった。背景にあるのが、コロナの感染拡大で落ち込む景気や下支えしようと、各国が次々と打ち出した財政支援と一段の金融緩和だ。米国では今後給付される分を含め、3回にわたって1人あたり最大3000ドルを超える給付金を実施。日本では10万円の定額給付金以外に、売上が減った個人事業主に休業支援金や無利子無担保融資など財政資金が供給されてきた。09年のリーマン危機以降に供給されてきた「緩和マネー」がコロナの経済対策でささらに増え、カネの価値が一段と下落。そのヘッジとして、暗号資産や現物資産に資金が流れ込んでいる。「コロナ禍による家計や企業支援策として各国政府がかつてない規模でマネー給付を実施したことから、法定通貨の価値が下落している」と、オークション事業などを手掛けるShinwa Wise Holdingsの倉田陽一郎社長は言う。「資産を防衛するため、マネーを実物資産へシフトさせている」と指摘。オークションでは美術品をはじめ、希少性の高いブランドウイスキーなどにも人気が出てきているという。象徴的なのが、高級腕時計のロレックス。人気モデルは新品が手に入らず、転売目的が多い中古市場で定価の2ー3倍に当たる300万ー400万円で取引されている。日本ロレックスによると、世界中で人気モデルの引き合いが強く、商品の提供が需要に追い付かないという。高級別荘地として知られる長野県の旧軽井沢地区では、昨年秋に東急リゾートが売り出した「億ション」が半年ほどで完売した。建物はもちろん、モデルルームさえまだ存在しなかったが、広さ90ー185平方メートル、1億─2.5億円程度の物件は抽選になるほどの人気を集めた。実体経済からかい離し、株や不動産、その他の現物資産が膨張する光景は、30年前に日本が経験したバブル景気と重なる。当時は円高不況を乗り切るための金融緩和マネーが投資や投機に回り、日経平均株価は4万円に迫った。今回も株価はそのとき以来となる3万円台に乗せ、当時の水準を回復しつつある。<富裕層は濡れてに粟で格差拡大>しかし、30年前のバブル期と今とでは大きく異なる点がある。1986年から91年の実質成長率は年5%を超え、日本中が好景気に沸いた。一方、戦後2番目に長い景気拡大を記録した2012年から18年の成長率は年1%強。コロナが直撃した20年は4.8%のマイナス成長となった。低成長の中で資産価格だけが膨らみ、限られた「持てる者」だけが恩恵を受けている。「89年ごろのバブルは日本経済がまだ成長していた。今は人口が減少している中でお札だけ増えている。過剰流動性相場だ」と、前出の倉田社長は話す。日銀の資金循環統計を見ると、昨年12月末の家計の金融資産残高は1948兆円と過去最高を大きく更新。野村総合研究所によると、資産1億円以上の富裕層の純金融資産(金融資産から負債を差し引いたもの)は19年に333兆円と全体の2割を占め、17年から11%増加した。一方、全体の8割を占める3000万円未満は17年より世帯数が増える一方で、純金融資産は減少した。リーマン危機後から続く過剰流動性で、コロナ前から格差は拡大していた。同総研コンサルティング事業本部の宮本弘之・パートナーは、コロナ禍にさらされた20年は富裕層の金融資産が一段と増えていると指摘する。その上で、「過去のバブル期には国民の多くが同じような方向を向いていたが、今はそうではない。差が開いている。明暗はバブルの最中にあってもすでに生じている」と話す。 コロナの感染拡大で休業や失業を余儀なくされた業界の従事者たちを中心に、多くの人にとって資産バブルは縁遠い話だ。東京足立区では、生活資金の相談件数が昨年末に前年比で3割増にのぼり、同区のハローワークでは失業給付申請件数が今年1月に3割増えた。日本最大のフードバンク「セカンドハーベスト・ジャパン」によると、個人向けの無償提供件数はコロナ前の2倍以上に増加した。日銀内からも、金融緩和の長期化が所得の再分配に何らかの影響を及ぼすことは排除できないとの声が聞かれる。一方で、金融緩和がなければ景気がより悪化していた可能性があるとして、プラスマイナス差し引きで考えないと公平な評価にならないとの反論の声もある。コロナの経済対策として財政支援を進めてきた財務省の関係者は、「コロナ禍でふたを空けてみたら格差が拡大しているのではないか、持てるものと持たざるもの差が広がっているのではないか、それは日本だけでなく世界的のもの、という指摘はある」と話す。「その中で困った人に手を差し伸べる、ということをやっている。給付金にしてもある程度そういう趣旨はあると思う」と語る。アルトコインで元手が16倍に増えた冒頭のTDさんは最近、デジタル資産の一種である「NFT(非代替性トークン)」を購入した。TDさんは、ITへの関心と知識次第で、これからも資産格差が広がる時代になると話す。第一生命経済研究所の熊野英生・首席エコノミストは、世界の中央銀行が供給するマネーによる資産効果や景気刺激は今後も過剰気味に継続するとみる。「それをうまく利用できる人達は濡れ手で粟(あわ)、利用できない人々は副作用だけを被ることになる」と語る。30日のTOPIXが4営業日ぶり反落となった「3つの背景」商社、情報・通信、医薬品が安いブルームバーグ東京株式市場でTOPIXは4営業日ぶりに反落。ファンドのポジション清算の影響を見極めたいといった警戒から買い手控えムードが広がった。3月期決算企業の配当権利落ちも重しとなり、商社や情報・通信、医薬品といった好配当業種中心に安い。市場関係者の見方三井住友DSアセットマネジメントの市川雅浩チーフマーケットストラテジスト・需給面で特別な要因である配当関連の取引が影響・アルケゴス問題の影響はいまのところ落ち着いている印象・米国で明日発表される新しい経済対策の内容を見極めたいとの雰囲気がある大和証券投資情報部の石黒英之シニアストラテジスト・昨日の米国株の動きをみる限り、市場は今回のアルケゴスのポジション解消に関して単体の問題だと受け止めているようだ・米国のワクチン接種進展や企業業績の改善期待から、好業績株には押し目買いも入りやすい・1日の企業短期経済観測調査で企業の景況感が順調に戻っていることが確認される見通しで、配当権利落ち分は早期に埋めるだろう背景・配当権利落ちのマイナス影響分-TOPIX17.3、日経平均177円・アルケゴス巡り見解対立-レバレッジリスク顕在化の兆しか特殊事例か・29日の米国株は高安まちまち-アジア時間の米先物、方向感乏しく本日の東京市場ではチェック中の日本株30銘柄中の13銘柄が値を上げて終了しましたね。重点3銘柄では2銘柄が値を上げて終了しましたね。Jフロント、藤倉コンポ、テクノホライゾンが上げて、スクロールが下げましたね。【本日のNYダウ見通し】連日で過去最高値を更新するかに注目【NYダウ予想レンジ:33,000~33,400ドル】29日のNYダウは続伸し、前週末比98.49ドル高の33,171.37ドルで取引を終了。連日で過去最高値を更新しました。ヘッジファンドのアルケゴス・キャピタル・マネジメントが200億ドル規模の保有株売却を迫られて大量のブロック取引をした余波で、寄付きは安く始まりました。しかし、新型コロナウイルスワクチン普及による経済正常化期待は強く、主力株に買いが入ったことからNYダウは上昇に転じたのです。また、大型コンテナ船の座礁で遮断されていた運河の通行が再開したと、エジプトのスエズ運河庁が発表したことも好感されました。ただ、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は79.078ポイント安の13,059.647で取引を終了しており、指数によって強弱はまちまちでした。本日の経済指標では、消費者信頼感指数に注目です。また、クオールズFRB副議長やウィリアムズNY連銀総裁の発言にも関心が集まりそうです。【市況】東京株式(大引け)=48円高、景気敏感株中心に下値支える展開 実質新年度入り相場となった30日の東京株式市場は、売り買いが交錯し主要株指数は高安まちまちの展開となった。日経平均は小幅ながら上値追い基調を継続、TOPIXは反落した。 大引けの日経平均株価は前営業日比48円18銭高の2万9432円70銭と4日続伸。東証1部の売買高概算は13億4076万株、売買代金概算は2兆7235億6000万円。値上がり銘柄数は541、対して値下がり銘柄数は1564、変わらずは55銘柄だった。 前日の米国株市場では新型コロナワクチンの普及を背景とした経済活動の正常化期待から景気敏感株が買われ、NYダウが上昇した。ただ、ハイテク株比率の高いナスダック総合指数は軟調となり、東京市場も朝方は前日終値近辺で売り買いを交錯させる方向感に乏しい動きだった。しかし、後場に入ると日銀のETF買いの思惑が市場心理を支え、全体相場は強含みで推移。韓国や香港など堅調な値動きをみせるアジア株もポジティブに作用した。海運や空運など景気敏感セクターが上昇し、日経平均寄与度の高い値がさ株への買いも堅調な株価推移に反映された。きょうは3月期末の配当権利落ち日にあたることから日経平均ベースで178円程度の下押し圧力が発生していたが、それを吸収して上昇。ただTOPIXはマイナス圏で着地しており、全体の7割強にあたる銘柄が下落した。 個別では、ファーストリテイリングが高く、東京エレクトロン、レーザーテック、アドバンテストなど半導体製造装置関連が揃って買われた。日本郵船も買われた。東洋エンジニアリングが商いを伴い急伸したほか、マネックスグループも物色人気。大阪チタニウムテクノロジーズが値を上げ、J.フロント リテイリングなども上昇した。 半面、トヨタ自動車が軟調、任天堂も売りに押された。村田製作所が値を下げ、武田薬品工業も売りに押される展開。日本郵政が水準を切り下げ、三菱商事も安い。オリエンタルランドも下落した。このほか、エイベックス、日本アジアグループなどが大幅安となった。出所:MINKABU PRESS明日の戦略-配当落ちを埋めて4日続伸、月末の大幅安には警戒をトレーダーズ・ウェブ 30日の日経平均は4日続伸。終値は48円高の29432円。小安く始まり、早々にプラス転換。上げ幅を広げて29500円に接近したところでは、押し戻されて下げに転じたものの、下げ幅を3桁に広げたところでは押し目買いが入り、前引けは15円安(29369円)と小幅な下落。後場に入ると前日終値近辺での一進一退が続いた。配当落ちの影響で多くの銘柄が下落したが、ファーストリテイリングや東京エレクトロンなど値がさの一角が強く、強弱感が交錯した。取引終盤に強めの買いが入り、プラスを確保して終了。180円程度の配当落ち分を即日で埋めた。 東証1部の売買代金は概算で2兆7200億円。業種別では海運、空運、ゴム製品などが上昇した一方、保険、電気・ガス、パルプ・紙などが下落した。通期最終利益のレンジ見通しを引き上げたサムティが後場プラス転換から上げ幅を広げて大幅高。半面、新日本空調は後場に上方修正を発表して一時プラス圏に浮上したが、買いが続かず失速して大幅安となった。 東証1部の騰落銘柄数は値上がり541/値下がり1564。日本郵船、川崎汽船、商船三井の海運大手3社と、JAL、ANAの空運大手2社が大幅上昇。これらは前日に大きく売られていたが、強い切り返しを見せた。海運株に関しては、スエズ運河で座礁したコンテナ船が離礁に成功したことも強い買い材料となった。米国の運用会社が手掛ける宇宙関連のETFに組み入れられていると伝わったコマツが大幅高。証券会社の新規カバレッジが入ったグレイステクノロジーが急伸した。 一方、IBMによる提訴の観測が報じられた楽天が軟調。日本郵政や三菱商事、SBなどが、権利落ちの影響で大きく水準を切り下げた。エイベックスやWDB、鴨川グランドホテルなど、優待人気の高い銘柄には大きく値を崩すものも散見された。期末配当の見送りを発表した久世が急落。海外での新株発行が嫌気されたダブル・スコープが大幅安となった。NaITOは今22.2期の大幅増益計画を提示したが、前期の見通し引き上げを受けて先んじて大きく買われていたため、決算確認後は利益確定売りが優勢となった。 本日はAppier Groupとスパイダープラスの2社が新規上場。どちらも公開価格を大きく上回る初値をつけたが、終値は初値を下回った。 日経平均は後場にプラス転換して4日続伸。配当落ちの影響を加味すれば実質200円超の上昇で、強い動きであったと言える。きのう急落した野村HDはほぼマイナス圏で推移したものの、引けでは1%以下の下げにとどまった。先週に大きく売られたファーストリテイリングが相場を下支えするような動きを見せたことで、日銀のETF買い入れルール変更に伴う混乱が収束しそうな雰囲気も出てきた。 あすは3月の月内最終日となる。このところ、月の最終日の日経平均は大幅安となることが多く、1月(29日)は534円、2月(26日)は1202円下落した。1月、2月とも月間ではプラスとなっており、相場のトレンドを崩すまでの下げにはなっていないが、3月はきょう時点で2月末比では約466円上昇しており、上昇分のいくらかは削られてしまうかもしれない。ただ、最終日が弱いことに明確な理由はない。また、1月末、2月末とも結果的には下げたところが良い買い場となっている。2月末の終値が28966円で、5日線(30日時点)が29025円。再度29000円割れを見に行くくらいの下げはあるかもしれないと構えておき、押し目があれば丹念に拾っておきたいところだ。今晩のNY株の読み筋=米景気回復期待が支え、重要イベント控え様子見もモーニングスター 30日の米国株式市場は、米景気回復への期待が支えになる。きょう発表の米1月S&Pコアロジック・ケース・シラー住宅価格指数、米3月消費者信頼感指数は前月から改善する見込みとなっており、市場予想通りなら株価にとって追い風。ただ、米長期金利が上昇を続ければバリュー株を中心に上値の重い展開が予想される。また、米3月ADP(オートマチック・データ・プロセッシング)雇用統計のほか、バイデン米大統領の会見もあり、週末には米3月雇用統計の発表を控えることから、様子見ムードも広がるとみられる。<主な米経済指標・イベント>米1月S&Pコアロジック・ケース・シラー住宅価格指数、米3月消費者信頼感指数クオールズFRB(米連邦準備制度理事会)副議長が講演◎投資関連情報は投資の参考として情報提供のみを目的としたものであり、株式の売買は自己責任に基づき、ご自身で判断をお願いします。明日の日本株の読み筋=上値の重い展開か、期初の益出し売り警戒もモーニングスター あす31日の東京株式市場で、主要株価指数は上値の重い展開か。30日の日経平均株価は4日続伸し、前日比48円高の2万9432円となり、3月期末の配当落ち分(180円程度)を即日で埋めた。基調の強さを改めて印象付けた格好だが、相場全体の動きを映すTOPIX(東証株価指数)は前日比15.48ポイント安の1977.86ポイントと配当落ち分(17ポイント強)に近い下げとなり、押し目買い意欲は限定されたいえよう。実質新年度入りに伴い、機関投資家の期初益出し売りが上値を抑えたとの見方が出ており、あす以降もこの手の売りが警戒される。 米投資会社アルケゴス・キャピタル・マネジメントの巨額マージンコール(追加証拠金の差し入れ義務)に伴う投げ売りの影響はいったん織り込んだとの見方もあるが、先行きの不透明感は払しょくされていない。3月期決算の発表シーズンをにらみ、積極買いが出にくい場面でもあり、「日経平均3万円以上を買う材料は見当たらない」(銀行系証券)との声も聞かれた。 30日の日経平均株価は朝方、配当落ちの影響を受け、軟化して始まったが、配当再投資目的の先物買い期待もあって指数寄与度の高い銘柄の上昇を支えに上げに転じ、一時90円超上昇した。その後、利益確定売りに下げ幅は一時100円に達したが、一巡後は持ち直した。昼休みの時間帯にアジア株が総じて堅調で、日銀のETF(上場投資信託)買い観測もあって後場は再度プラス圏に浮上し、底堅く推移した。〔ロンドン外為〕円、1年ぶり110円台(30日午前9時)時事通信 【ロンドン時事】30日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、昨年3月以来、約1年ぶりに1ドル=110円台に下落している。午前9時現在は110円20~30銭と、前日午後4時(109円70~80銭)比50銭の円安・ドル高。 対ユーロは、1ユーロ=129円35~45銭(前日午後4時は129円10~20銭)で、25銭の円安・ユーロ高。ユーロの対ドル相場は1ユーロ=1.1730~1740ドル(1.1760~1770ドル)。 バイデン米政権による追加経済対策や新型コロナウイルスワクチンの普及などを背景に、米経済の回復に期待感が広がった。安全資産とされる円は売りが優勢となった。(了)NY株見通しーもみ合いか 長期金利の上昇に要警戒トレーダーズ・ウェブ 今晩のNY市場はもみ合いか。昨日は受注を好感したボーイングやプロクター・アンド・ギャンブルなどのディフェンシブ株が上昇し、ダウ平均が史上最高値の更新を続けた一方、エネルギー、金融、IT株の下落が重しとなり、S&P500は3日ぶりの小幅反落となった。長期金利の上昇を受けてハイテク株主体のナスダック総合も0.6%安と3日ぶりの反落となり、年初から主要3指数を大きくアウトパフォームしたラッセル2000は2.8%安の大幅反落となった。懸念されたアルケゴス・キャピタルの持ち株処分の影響は限定的だったが、投資家の不安心理を示すVIX指数は 20.74ポイントと前日比1.88ポイント上昇した。 今晩は、バイデン米大統領が大型インフラ投資を含む経済対策第2弾を翌日に発表するほか、ワクチン接種進展による景気回復期待も支援材料に景気敏感株の堅調が予想される一方、足もとでの米10年債利回り上昇がハイテク・グロース株の逆風となりそうだ。 今晩の米経済指標は1月ケースシラー住宅価格指数、3月消費者信頼感指数など。企業決算は寄り前にマコーミック、引け後にPVHコープが発表予定。(執筆:3月30日、14:00)〔NY外為〕円、110円台前半(30日朝)時事通信 【ニューヨーク時事】30日午前のニューヨーク外国為替市場では、米景気の早期回復期待を背景に円売り・ドル買いが進み、円相場は1ドル=110円台前半に下落している。午前9時現在は110円30~40銭と、前日午後5時(109円78~88銭)比52銭の円安・ドル高。 ニューヨーク市場は、110円34銭で取引を開始。バイデン米政権が進める新型コロナウイルスワクチンの接種拡大や31日に発表される大型インフラ計画への期待から景気回復ペースが加速するとの観測が台頭。投資家のリスク選好意欲が高まる中、ドルを買う動きが活発化し、円は未明に、約1年ぶりに110円台を付けた。米長期金利の指標である10年物国債利回りが再び1.7%台半ばに上昇し、ドル買い圧力がかかっている。 ユーロは同時刻現在、対ドルで1ユーロ=1.1725~1735ドル(前日午後5時は1.1761~1771ドル)、対円では同129円40~50銭(同129円22~32銭)と、18銭の円安・ユーロ高。(了)〔米株式〕NYダウ、反落(30日午前)時事通信 【ニューヨーク時事】30日午前のニューヨーク株式相場は、米長期金利の上昇が重しとなり、反落している。午前10時現在は、優良株で構成するダウ工業株30種平均が前日終値比61.83ドル安の3万3109.54ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数が102.69ポイント安の1万2956.96。 米長期金利の指標である10年物国債利回りが再び上昇し、1.7%台半ばで推移。金利上昇への警戒感からハイテク銘柄などを中心に売りがかさんだ。前日に史上最高値を2営業日連続で更新した後で利益確定の売りも出やすい。 一方で、バイデン米大統領が31日に発表するインフラ投資計画や新型コロナウイルスワクチンの普及に対する期待は根強く、相場の下値は限定的。米投資会社アルケゴス・キャピタル・マネジメントによる株式関連の取引失敗による損失の広がりが懸念されるものの、金利上昇で恩恵を受けやすい金融関連銘柄が買い戻されている。 個別銘柄では、アップルやマイクロソフトなどのハイテク株やテスラ、ネットフリックスなどの下げが目立つ。イェルプが投資判断の引き上げを受けて買われた。(了)今夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中の6銘柄が値を上げてスタートしましたね。5%以上の大きな変動は見られませんね。アブセレラが上昇 売上高が予想を上回る=米国株個別みんかぶFX カナダのバイオ医薬品のアブセレラ・バイオロジクスが上昇。同社は抗体ベースの薬剤の開発に従事し、米製薬大手のイーライリリーと共同で新型ウイルスの抗体治療薬を開発している。2020年通期の決算を発表しており、売上高が2.33億ドルと予想(2.13億ドル)を上回った。通期の1株利益は0.45ドルとなっている。 イーライリリーと共同開発の抗体治療薬「バムラニビマブ」のロイヤルティー収入が1.98億ドルとなった。 アナリストからは、すべての変異株に対する「バムラニビマブ」の臨床前段階での有効性の強さと、幅広いパイプラインにおける長期的な可能性への言及が聞かれた。(NY時間10:13)アブセレラ 25.99(+2.70 +11.59%)ノバンが上昇 同社のCEOが自社株を購入=米国株個別みんかぶFX 医薬品のノバンが上昇。同社のスタッフフォードCEOが約10万ドル分の株式を購入したことが米証券取引委員会(SEC)への提出文書で明らかとなった。同CEOは3月26日に平均1.43ドルで7万株購入した。今回の購入により、同CEOの保有株数は15万693株となり、87%増加した。(NY時間09:51)ノバン 1.54(+0.17 +12.41%)
2021.03.30
コメント(0)
-

3月29日(月)…
3月29日(月)、晴れです。晴れて暖かです。ただ黄砂でかすんでいますが…。そんな本日は7時15分頃に起床。新聞に目を通し、朝食を済ませ、ロマネちゃんと戯れる。身支度をして、9時20分頃に迎えのタクシーに乗り込み最寄りのJRステーションへ。JRは少し遅れていましたが、名古屋駅で予定通りの新幹線に乗り込んで、GoToKYOTO!京都駅に着いてすぐタクシーに乗り込んで「室町和久傳」さんへ。四十九日の法要で1週間先延ばしになった僕のバースデイ会食です。松本料理長の美味しいお食事と、美味しいお酒に満足!!タクシーで東寺へ桜を見に向かう。ここで問題発生…。このまま京都駅へ向かって新幹線に乗り込むと名古屋駅での接続が大変に悪い…。急遽1時間30分の京都観光を企画…ということで、東山の将軍塚・青龍殿へ向かう。青不動をお参りして、枝垂桜や庭園を拝見して、大舞台から京都市内を眺める。黄砂に煙る京都御所方面です。16時30分頃に京都駅について、駅伊勢丹でお買い物。17時30分頃の新幹線で帰路に就き、19時15分頃には帰宅。楽しい京都弾丸ツアーでした。夕食は「ハツダ」の肉弁当でした…。1USドル=109.61円。1AUドル=83.83円。本日の日経平均終値=29384.52(+207.82)円。金相場:1g=6754(+37)円。プラチナ相場:1g=4655(+117)円。本日の東京市場ではチェック中の日本株30銘柄中の15銘柄が値を上げて終了しましたね。重点3銘柄では1銘柄が値を上げて終了しましたね。藤倉コンポジットが大きく上げましたね。グラファイトデがストップ高気配、前期着地見通しを増額ゴルフクラブシャフトを製造するグラファイトデザイン(7847)が買いを集めている。朝方から買い気配が続き、午前9時48分現在、制限値幅の上限となる前週末比80円高の575円での買い気配となっている。26日引け後に発表した2021年2月期業績・配当予想の上方修正が好感された。営業利益は前期比3.2倍の1億9800万円になったもよう。従来予想は1億3500万円だった。ゴルフが「3密」を避けられるスポーツとして見直されており、ゴルフ場入場者数が増加傾向にある中、主力商品の2021年モデル発売に合わせてSNSを活用したプロモーション活動やゴルフクラブメーカーへの販売活動に努めたのが奏功。旧モデルをリニューアルしたものが大手クラブメーカーのメインカスタムシャフトに採用されたのも寄与した。同時に、期末一括配当の年間配当予想を前回の1株当たり15円から20円に増額した。決算発表は4月14日の予定。(取材協力:株式会社ストックボイス)藤倉も同様に大きく上げましたからね。日本株はきょうで3連騰、買い優勢の支えとなった要因証券や銀行など金融株は安いブルームバーグ東京株式相場は3日続伸。米国のワクチン接種加速による経済正常化への期待が根強く、電機や機械、自動車、化学株が上げた。一方でTOPIX(東証株価指数)は一時下落した。米国で大規模な損失の発生する可能性があると発表した野村ホールディングスには米ファンドとの取引が影響しているとの見方が出て株価が大幅に下落し、証券や銀行など金融株は安かった。・TOPIXの終値は前営業日比9.18ポイント(0.5%)高の1993.34・日経平均株価は207円82銭(0.7%)高の2万9384円52銭・東証33業種では小売業、ゴム製品、機械、電機、化学が上昇・証券・商品先物、海運、空運、その他金融、銀行は下落市場関係者の見方岡三アセットマネジメントの前野達志シニア・ストラテジスト・米国のブロックトレードや野村HDの件などの弱い材料があり上値は重いが、2021年は景気回復の年という大きなトレンドには変わりはなく、今後1~3週間で考えれば悲観的になる必要はない・今週発表予定の米国ISM製造業景況指数など経済指標では良い結果、日銀短観は最悪期を脱したという結果が予想できる・ただ良い結果がでればインフレや長期金利上昇にもつながるため注意は必要東京マーケット・サマリー(29日)■レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値<外為市場>ドル/円 ユーロ/ドル ユーロ/円午後5時現在 109.64/66 1.1784/88 129.22/26NY午後5時 109.64/67 1.1796/00 129.33/37午後5時のドル/円は、ニューヨーク市場午後5時時点とほぼ同水準の109円後半。ドルは月末・期末・年度末を控えた実需の売買やクロス円での円買い戻しで、じり安の展開となった。スエズ運河の座礁船が離礁しつつあるとの報道を受けて原油先物が下落したことに反応して、資源国通貨が売られた。<株式市場>終値 前日比 寄り付き 安値/高値 日経平均 29384.52 +207.82 29478.12 29,200.88─29,578.37TOPIX 1993.34 +9.18 2004.11 1,975.09─2,005.75東証出来高(万株) 182632.00 東証売買代金(億円) 37153.05東京株式市場で日経平均は3日続伸した。前週末の米国株市場で、主要3指数がそろって上昇した流れを引き継いだほか、きょうは実質年度末の最終売買日にあたり、配当権利取りの動きが活発になった。後場には一時400円高となる場面もみられたものの、米株先物が軟調に推移したことなどが重しとなり、200円超高で取引を終えた。東証1部の騰落数は、値上がり1225銘柄に対し、値下がりが900銘柄、変わらずが68銘柄だった。<短期金融市場> 無担保コール翌日物金利(速報ベース) -0.014%ユーロ円金先(21年6月限) 100.045 (-0.005)安値─高値 100.045─100.0503カ月物TB -0.096 (-0.001)安値─高値 -0.096─-0.096無担保コール翌日物の加重平均レートは、速報ベースでマイナス0.014%になった。「週末要因が剥落しても良さそうな日ではあったが、ビッドサイドは新型コロナオペのおかげで総じて取り意欲が強い状況だ」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。<円債市場> 国債先物・21年6月限 151.47 (+0.11)安値─高値 151.27─151.4710年長期金利(日本相互証券引け値) 0.065% (-0.010)安値─高値 0.080─0.065%国債先物中心限月6月限は前営業日比11銭高の151円47銭と続伸して取引を終えた。現物市場の10年物国債利回り(長期金利)は同1bp低下の0.065%。【市況】明日の株式相場に向けて=米ファンド損失の波及はあるか 29日の東京株式市場は、後場に入り値の荒い展開となった。権利取り最終日で配当狙いの買いも流入し、日経平均株価は一時400円を超す上昇となったが、その後、午後2時過ぎから売りが膨らみ20円強の上昇まで上げ幅は縮小した。しかし、引けにかけ配当再投資の買いが流入し、結局207円高で取引を終えた。 クレディ・スイスが「米ヘッジファンドが不履行となった」と発表したことを受け、短期筋が売りを出したことが波乱の要因となったようだ。損失を出したのは米投資会社のアルケゴス・キャピタルとみられており、米メディア株などの運用に失敗したとの観測がある。NYダウ先物は軟調に推移しており、同ファンドの損失問題に米株式市場がどう反応するかが関心を集めている。 アナリストからは「損失を被ったヘッジファンドが1社だけなら影響は限られそうだ。ただ、表面化していない複数のファンドが同様に損失を抱えていることもあり得る。とりあえずは、今晩のNY市場の動向が今後の展開を左右することになるだろう」とみている。NY市場が調整するようなら、JR東日本のようなディフェンシブ株やレノバのような調整が進んだ環境関連株に物色のシフトが進むこともあり得る。 明日は日経平均の配当権利落ちが180円前後あり、その分だけ値を下げてスタートすることになる。この権利落ちを埋めることができるかが注目される。更に2月失業率・有効求人倍率が発表される。また、東証マザーズにスパイダープラスとAppier Groupが新規上場する。特にAppier Groupは台湾発のAIベンチャー企業であり、その株価動向に関心が集まっている。出所:MINKABU PRESSビリー・ホーシェルがマッチプレー制覇! スコッティ・シェフラーが2位、マット・クーチャーが3位<WGC-デル・テクノロジーズ・マッチプレー 最終日◇28日◇オースティンCC(米テキサス州)◇7108ヤード・パー71>世界ゴルフ選手権シリーズ「WGC-デル・テクノロジーズ・マッチプレー」は全日程を終了。ビリー・ホーシェル(米国)がスコッティ・シェフラー(米国)との決勝を2&1で制して、見事優勝を飾った。準決勝でビクトル・ペレズ(フランス)を3&2で撃破したホーシェルは、序盤シェフラーにリードを許すも5番のバーディでタイとすると7番でリードを奪ってからは主導権を渡さず。最終ホールを待たずして勝負を決めた。3位決定戦はマット・クーチャー(米国)がペレズを2&1で下している。33歳ジョエル・ダーメンがうれしいツアー初V 全米OP覇者が4位タイフィニッシュ<コラレス・プンタカナ リゾート&クラブ選手権 最終日◇28日◇コラレスGC(ドミニカ共和国)◇7670ヤード・パー72>世界ゴルフ選手権シリーズの「WGC-デル・テクノロジーズ・マッチプレー」の裏で行われている「コラレス・プンタカナ リゾート&クラブ選手権」は全日程が終了。トータル12アンダーまで伸ばしたジョエル・ダーメン(米国)が33歳にしてうれしいツアー初優勝を挙げた。1打差の2位タイにラファエル・カンポス(プエルトリコ)とサム・ライダー(米国)。トータル10アンダーの4位タイに2010年の「全米オープン」覇者グレアム・マクドウェル(北アイルランド)とマイケル・グリジック(カナダ)が入った。その他、2016年「マスターズ」覇者のダニー・ウィレット(イングランド)はトータル8アンダーの8位となっている。なお、日本勢で唯一出場した小平智は予選落ちとなっている。明日の戦略-後場失速も3日連続で3桁の上昇、証券株の変調には要警戒トレーダーズ・ウェブ 29日の日経平均は3日続伸。終値は207円高の29384円。米国株高と円安進行を好感して、寄り付きから300円を超える上昇。29500円台に乗せた後はいったん萎んだが、盛り返して前場では高値圏を維持した。後場も開始30分あたりまでは上を試す流れとなり、上げ幅を400円超に拡大。しかし、そこから先は失速感が強まった。野村HDの急落を受けて証券株全般に売りが波及したほか、銀行や海運、空運など、値持ちの良かった銘柄群に手仕舞い売りが広がった。TOPIXが14時過ぎに下げに転じると、日経平均も急速に上げ幅を縮小。ただ、TOPIXが下げ加速とまではならず踏みとどまったことから、終盤にかけては持ち直して200円を超える上昇となった。TOPIXもプラスを確保して終えた。新興市場が弱く、マザーズ指数が1.8%安と大きめの下落となった。 東証1部の売買代金は概算で3兆7100億円。3月の権利付き最終売買日で配当再投資の買いも入ったと思われる中、商いは膨らんだ。業種別では小売やゴム製品、機械などが上昇。一方、証券・商品先物が8%を超える下落となったほか、海運や空運が大きな下げとなった。上方修正を発表した山田コンサルティンググループが急騰。半面、上期が大幅な営業赤字となった出前館が急落した。 東証1部の騰落銘柄数は値上がり1225/値下がり900。SOX指数の大幅高を受けて、東京エレクトロンやレーザーテックなど半導体株が大幅上昇。円安進行を受けて、トヨタやSUBARUなど自動車株に買いが入った。政府がレアメタルを再利用する拠点を整備するとの報道を受けて、住友鉱山や三菱マテリアルなど非鉄株が上昇。自己株取得を発表したMonotaROや、株式分割を発表した日本パレットプールが急伸した。 一方、寄り前に米国子会社における多額損害の可能性を発表した野村HDが16.3%安と急落。大商いで市場の注目も大きく集めており、同業他社にも警戒売りが広がった。日本郵船、川崎汽船、商船三井の海運大手3社がそろって大幅安。JAL、ANAなど空運株や、三菱UFJ、三井住友など銀行株も弱く、バリュー系の銘柄が軟調となった。新興市場がさえない中、メルカリやBASE、弁護士ドットコムなどマザーズの主力銘柄が大幅安。ゲームの中国本土配信時期が見込みよりも後ずれするとの発表が嫌気されたバンク・オブ・イノベーションが値を崩した。 日経平均は3営業日連続で3桁の上昇。後場の急失速に関しては、クレディ・スイスに関するニュースが引き金を引いたようではあったが、指数は終盤には持ち直しており、ヘッドラインに過剰反応したのか内容を織り込み切れていないのかは判断が難しい。ただ、野村HDがリリースを材料に派手に売られており、金融機関に対する警戒感が浮上してきたことは気になる材料。株高が収益拡大につながるとの期待から、野村HDの株価は先週末の26日に昨年来高値を更新していた。きょうは同銘柄が下げ止まらない中で証券株が軒並み売られており、影響が長引くようだと全体市場の重荷にもなり得る。銀行株も失速した部類に入っており、短期的には金融株は敬遠される可能性がある。また、そうなった場合には、金利への感応度が相対的に小さく、「モノ作り」に強みを持つ企業の選好が強まると予想する。明日の日本株の読み筋=配当落ち分即日埋めなるか、「米ファンド債務不履行」報道見極めもモーニングスター あす30日の東京株式市場は、3月期末の権利落ち日となり、配当落ち分(日経平均株価ベースで180円程度)を即日で埋めきれるかどうかが注目される。即日埋めとなれば、基調の強さを改めて印象付けることにもなる。株価指数連動型ファンドを運用する投資家から将来受け取る見込みの配当金を再投資する先物買いが引き続き入るとみられ、需給面での支えとして意識されよう。 一方、スイス金融大手クレディ・スイス・グループは29日、同社をはじめとする一部金融機関が実施した米ヘッジファンドへのマージンコール(追加担保の差し入れ要求)が債務不履行(デフォルト)になったと発表したと報じられた。これをきっかけに29日後場の日本株は急速に上げ幅を縮小した経緯があり、市場では「その影響がどの程度広がるか、海外株動向を含め、見極める必要がある」(準大手証券)との声も聞かれた。日経平均株価は直近3連騰(合計979円上昇)で戻りピッチが速い面もあり、海外要因に不透明感が増すようだと利益確定売りに傾く可能性がある。 9日の日経平均株価は大幅に3営業日続伸し、2万9384円(前週末比207円銭高)引け。朝方は、前週末の米国株高を受け、買いが先行した。時間外取引での米株価指数先物安もあって、いったん伸び悩んだが、次第に盛り返した。3月期末配当取りの動きや、大引けにかけての配当再投資目的の先物買い観測が支えとなり、上げ幅は一時400円超えた。ただ、買い一巡後は、米ファンドの債務不履行が伝えられ、株価指数先物にまとまった売り物が出て、一時24円高まで大きく上げ幅を縮小する場面もあった。NY株見通しー今週は経済対策第2弾、3月雇用統計などの経済指標に注目トレーダーズ・ウェブ 今週のNY市場は堅調か。先週はワクチン接種進展による経済活動正常化期待が高まったことや、長期金利の上昇が一服したこと、経済指標が総じて良好な結果となったことも安心感につながり、ダウ平均とS&P500が史上最高値を更新した一方、ナスダック総合は週央までの大幅安が重しとなり、2週続落となった。今週は、ダウ平均とS&P500が史上最高値を更新したことで、高値警戒感が強まることが予想されるものの、ワクチン接種進展による経済活動正常化期待が続くことが予想されるほか、31日に公表予定の巨額経済対策第2弾も追い風となりそうだ。経済指標は3月雇用統計や3月ISM非製造業PMIなど注目度の高い指標の発表が多い。企業決算はマコーミック、PVHコープ、ウォルグリーン、マイクロン・テクノロジー、カーマックスなどが発表予定。 今晩は米投資会社アルケゴス・キャピタルの破綻の可能性が伝えられており、影響に要警戒か。米経済指標・イベントは3月ダラス連銀製造業景況指数、ウォーラーFRB理事講演など。主要な企業の決算発表はなし。(執筆:4月29日、14:00)そして、今週の運勢は…よしよし!!〔NY外為〕円、109円台後半(29日朝)時事通信 【ニューヨーク時事】週明け29日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、ユーロが取引の中心となる中、1ドル=109円台後半で小動きとなっている。午前9時現在は109円65~75銭と、前週末午後5時(109円63~73銭)比02銭の円安・ドル高。 欧州での新型コロナウイルス感染再拡大に伴い、域内の景気先行きに懸念が広がり、ユーロが対ドル、対円で売られている。一方、円の対ドル相場は四半期末を控えたポジション調整などの商いが中心。独自の材料に欠け、レンジ内の狭い値動きにとどまっている。 ユーロは同時刻現在、対ドルで1ユーロ=1.1780~1790ドル(前週末午後5時は1.1789~1799ドル)、対円では同129円25~35銭(同129円30~40銭)と、05銭の円高・ユーロ安。(了)〔米株式〕NYダウ、反落=金融機関の損失警戒(29日朝)時事通信 【ニューヨーク時事】週明け29日朝のニューヨーク株式相場は、ヘッジファンドとの取引関連の損失を警戒し、金融株が売られ、反落して取引が始まった。午前9時35分現在、優良株で構成するダウ工業株30種平均は前週末終値比30.34ドル安の3万3042.54ドル。米市場に上場する野村ホールディングスは一時、14%超下落。ゴールドマン・サックスやモルガン・スタンレーなど金融大手も軒並み売られた。 ハイテク株中心のナスダック総合指数は8.41ポイント安の1万3130.32となっている。(了)今夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中の3銘柄が値を上げてスタートしましたね。テラドックが下げていますね。変異株陽性の男性が死亡 岐阜県、新たに5人が新型コロナ感染 岐阜県は29日、新たに3市で計5人の新型コロナウイルス感染と、12人の変異株陽性を確認したと発表した。感染者数は累計4813人となり、うち変異株陽性は累計36人となった。入院していた変異株陽性の60代男性の死亡を確認し、死亡者数は計124人となった。県内での変異株陽性者の死亡は初となる。 県によると、変異株の陽性が判明した12人のうち4人は、安八郡神戸町で28日に確認された外国人を中心とする6人規模のクラスター(感染者集団)の20代女性だった。変異株クラスターの確認は県内2件目。県は残り2人の感染者のほか、女性が勤務する職場で60人余りを検査する。 新規感染者のうち、1人は大垣市の接待を伴う飲食店のクラスター関係で、6人規模となった。追加検査でこのクラスターの5人が新たに変異株陽性であることが判明。これまで確認している1人を含め、6人全員が変異株陽性であることが分かった。 変異株陽性の12人のうち、2グループ3人の感染経路は分かっていない。 県内でこれまで変異株陽性が判明していた7人の型が新たに判明。4人が英国型、3人が推定も含め南アフリカ型だった。 岐阜市柳ケ瀬地区のフィリピンパブ「ココナッツ」(同市弥生町)のクラスター関連では、同店の従業員が介護職として勤務する各務原市の老人保健施設「サンバレーかかみ野」の利用者1人の感染が判明し、23人規模となった。 県内の重症者2人のうち1人が重篤化し、人工心肺装置「ECMO(エクモ)」での治療となった。28日時点の入院者数は115人、病床使用率は16・6%となった。県は29日、運用を一時休止していた羽島市の宿泊療養施設について、感染者の増加に伴い運用を再開した。岐阜地域のコロナ病床も30床増やした。 新規感染者の居住地別は大垣市と各務原市が各2人、可児市が1人。年代別は40代1人、60代2人、80代1人、90代1人。多治見市で夏日 岐阜県内、全観測地点で今年最高の気温 岐阜県内は29日、高気圧に覆われた影響で気温が上昇し、多治見市で今年県内初となる最高気温25度以上の夏日となったのをはじめ、23観測地点の全てで今年最高を観測した。 多治見市の最高気温は例年より8・6度高い25・1度で、5月中旬並みの暑さ。下呂市萩原町では22・9度と3月の観測史上最高を記録した。県内は他に飛騨市神岡町で24・9度、揖斐郡揖斐川町で23・9度まで上がり、各地で5月上旬から6月上旬並みの暑さとなった。 平年より8・2度高い24度となった岐阜市では、日傘を差したり、アイスを食べたりしながら花見を楽しむ人の姿が見られた。 岐阜地方気象台によると、30日は日中は晴れるが、朝晩を中心に曇りとなる見込み。4月3日以降は下り坂という。
2021.03.29
コメント(0)
-

3月28日(日)…
3月28日(日)、曇り時々雨…。夜間には雨が降っていたようですが、起床時には曇り空で時々雨がパラパラと…。お昼からは雨が強くなるとの予報ですが…。そんな本日は6時30分に置きましたが、二度寝して7時30分に起床…。本日はホーム1:GSCCの西コースで開催の研修競技に9時00分スタートでエントリーしていましたが、ゴルフに対する意気込みの低下というか気力の減退というか、天気予報を見てキャンセルです…。新聞に目を通し、朝食を済ませ、ロマネちゃんと戯れる。本日のノルマは2階の掃除機と階段のモップかけですか…。ハイハイ…。朝のコーヒーブレイクはネスプレッソで…。モロゾフのチョコレートと共に…。本日でモロゾフも終了です。明日以降はどうする…?次いで恒例の母親宅の後片付けです。本日からは書棚関係へとなりました。本…重いです…。昼食前に作業を終了です。でも、だいぶスッキリとしてきましたね。【米国株動向】 5Gサービスを提供するベライゾンとTモバイル、どちらが有望かモトリーフール米国本社、2021年3月10日投稿記事よりベライゾン・コミュニケーションズ(NYSE:VZ)とTモバイル(NASDAQ:TMUS)にAT&Tを加えた3社は、次世代通信規格5Gのサービスで寡占状態にあります。その背景には高水準の固定費負担や最速の通信速度といった要因があります。5Gの利用可能エリアが広がる今、ベライゾンとTモバイルではどちらのリターンが高くなるでしょうか。 ベライゾン・コミュニケーションズ:最速の5Gサービスを提供ベライゾンは、2019年4月にシカゴとミネアポリスの一部で5Gサービスを開始しました。現在、顧客は1,800以上の都市で2億人におよびますが、55都市では通信速度が秒速4ギガバイトの5G最速サービスを導入しています。5Gはベライゾンのドル箱です。2020年は設備投資182億ドルに対し、236億ドルのフリーキャッシュフロー(FCF)を生み出しました。これは2020年の配当負担額102億ドルを十分上回ります。2020年は14年連続で増配しましたが、さらに増配の可能性があります。執筆時点での年間配当2ドル51セントで計算される配当利回りは4.4%、株価収益率(PER)は13倍とAT&Tの19倍を下回り、キャッシュフローの観点からは割安に見えます。しかしPERが低いのは、売上げの鈍化が原因と見て間違いなさそうです。TモバイルやAT&Tとの競争で、ベライゾンの純増契約数と売上高は長い間伸び悩んでいます。2020年の売上高は前年を3%下回る1,283億ドルとなり、1株当たり利益(GAAPベース)も前年を8%下回る4ドル30セントでした。さらにネットワーク整備費用によって有利子負債は約1,290億ドルに膨らみました。純資産が693億ドルのベライゾンにとっては過大で、負債資本比率は1.9倍弱となっています。有利子負債増加の一方で手元流動性も200億ドル増加したため、新型コロナウィルスの感染拡大期も同社は流動性を確保できました。キャッシュフローで支払利息の42億ドルを賄えたことも負債に対する懸念を緩和しますが、有利子負債は株価に重くのしかかります。昨年はS&P500指数が31%上昇したのに対し、ベライゾンの株価は横ばいでした。過去10年間でも同社の株価上昇率58%に対し、S&P500の上昇率は192%です(執筆時点)。 Tモバイル:巨額の投資を回収へワイヤレス通信の専業会社Tモバイルは、同業のスプリント買収によって割当周波数を拡大し、最近の電波オークションでも成功を収めています。周波数が割当てられれば、特定の地域の周波数管理を独占でき、通信品質の競争で有利になります。Tモバイルは当初、低料金で顧客を集め、株主もそれを評価しました。今年株価は年初来45%を超えて上昇し、過去10年間の上昇率は320%です(執筆時点)。無配でありながら、株主はベライゾンよりも高いリターンを得て、執筆時点のPERは45倍とベライゾンの約3倍です。Tモバイルの2020年売上高は684億ドルとベライゾンを下回りますが、スプリント買収によって前年比では52%増加しました。営業費用や支払利息、負債償還費用などスプリント買収にかかわる費用の増加で、純利益は前年を12%下回る31億ドル弱でした。買収によって有利子負債は2019年の273億ドルから736億ドルに急増しましたが、純資産653億ドルに対する負債資本比率は約1.1倍と、ベライゾンを下回ります。それでも、費用の増加などはFCFを押し下げ、2020年は約30億ドルでした。他にもスプリント買収時に利用した金利スワップ清算費用が23億ドルあり、同社の実質的なFCFは6億5,800万ドルにすぎませんでした。投資家は、同社が5Gインフラのために土地と設備に110億ドル超を投資したことにも注意する必要があります。営業キャッシュフローは86億ドルにとどまり、31億ドルの買収代金の繰延べがなければ、キャッシュフローは赤字になっていたでしょう。 ベライゾンかTモバイルかバリュエーションは割高ですが、投資家にはTモバイルが有望でしょう。割当周波数の拡大で通信品質が向上する上に、売上高、利益の伸び率は常にベライゾンを上回っています。今後は巨額の投資が実を結ぶ可能性も高まりそうです。焦点:コロナ禍でさらに太った超富裕層、「逆風」に備え防衛策[チューリヒ/ロンドン 25日 ロイター] - 世界が新型コロナウイルスの大流行で激動し、第二次世界大戦後で最悪の景気後退に見舞われた昨年、超富裕層の富はさらに膨らみ、過去最大に達した。コロナ大流行による破壊の跡は全世界に散乱しているが、超富裕層の一部は財産を維持し、一層強固にする手だてについて資産運用会社と相談を進めている。また政府や社会全体から復興コストの負担を求められることを想定し、先手を打った対応の方法を考えている超富裕層もいる。富裕層は貧富の格差縮小にもっと取り組むべきだとの主張を掲げる政治団体「パトリオティック・ミリオネアズ」の代表、モリス・パール氏によると、米株式市場が1年前に暴落したが、パール氏の運用資産は昨年7月ごろまでに暴落前の水準に回復、今ではこれを大幅に上回っている。「根本的な問題は全体的な不公平が深刻化しつつあることだ」と言う。<富裕層増税まえに資産売却の動き>富豪が模索している対応策は、慈善活動への資金拠出から、信託基金への資金・事業移転、税制上有利な国・州への転居に至るまで幅広い。「ミリオネア(富裕層)」と「ビリオネア(超富裕層)」7人と、資産運用担当者20人余りへの取材で明らかになった。スイスの富裕層向け資産運用会社ティーデマン・コンスタンシアのロブ・ウィーバー最高経営責任者(CEO)は「すべての人にツケが回ってくるのは火を見るより明らかだ」と話した。一部の顧客は事業など主要資産を増税前に売却することも検討しているという。富裕層向け資産運用会社によると、米国はバイデン大統領が富裕層増税に動く見通しとあって、顧客から信託設立の需要が特に強いという。現在は信託を使うと相続で1人当たり1170万ドル(約12億7800万円)まで控除が受けられる。バイデン氏は選挙期間中、この控除上限を2009年の水準の350万ドルに戻すことを提案していた。ウィルミントン・トラストのアルビナ・ローによると、顧客の大半は昨年第4・四半期まで様子見姿勢だったが、昨年11月の米大統領選・議会選後に動きが加速したという。<機敏な動きで市場変動を活用>フォーブスによると、昨年は大規模な景気対策が追い風となり、超富裕層の3分の2近くが富を増やし、最も増加幅が大きい層は保有資産が過去最高となった。超富裕層全体では、昨年12月半ばまでに推計20%資産が増えた。UBSのマクシミリアン・クンケル氏によると、超富裕層の多くは一般的な個人投資家には無縁の投資機会を享受、短期のデリバティブ(金融派生商品)取引などを駆使して、相場の急変動から利益を得た。資産価格が急落したとき、UBSの最大級の富裕層顧客は最終的に相場が回復すると見込み、プットオプション(売る権利)を売却したり、より複雑なリスクリバーサルを利用したりして利益を得た。クンケル氏は「顧客の一部は並外れて機敏に動き、過去最大級の市場の変調に便乗した」と述べた。各国政府が負債を膨らませ、社会不安が高まる今、超富裕層は自分たちの富へのスポットライトが強まるであろうことを自覚している。富裕層の多くは、税務当局からの要求が迫っていることを意識し、相続のために資金を信託基金に移す計画を加速している。ボストン・プライベートのジェーソン・ケイン氏によると、富豪一族は超低金利や資産価格の下落などコロナ禍で生じた特異な環境を利用し、将来の納税額を圧縮するため、事業など資金以外の資産も信託基金に移そうとしている。<税負担軽い地域への転居も>超富豪に親切な国や地域に移転するという、もっと大胆な行動を取る人々もいる。クレディ・スイスのババク・ダストマルトシ氏によると、透明性が高く、開かれ、国際的に認知されているなどの条件を備えた国・地域が候補で、スイスやルクセンブルク、シンガポールなどが人気だという。ヘンリー・アンド・パートナーズによると、富裕な個人からの転居の問い合わせはコロナ流行期に急増。昨年は米国の顧客からの問い合わせ件数が前年から206%増加し、ブラジルからは156%増えた。新興国の多くでは公共サービスのひっ迫が社会不安を引き起こすとの懸念が高まり、特に比較的若い富裕層が海外への転居を目指している。ジュリアス・ベアのベアトリス・サンチェス氏は「コロナは王様を裸にした。人々は突然気付いたのだ。自分たちの医療体制はぜい弱で、社会の安全網は実際には手に入らないということに」と話した。クレアフェルド・シチズンズ・プライベート・ウェルスのシンディー・オストラガー氏によると、富豪の多くがニューヨーク市から、ロングアイランドの高級避暑地ハンプトンズなどに転居した。当初はコロナ感染を避けるためだったが、その後は税負担の軽さが理由になった。プライベート・ウェルス・グループのクリスティ・ハンソン氏によると、テキサス、フロリダ、ワシントンなど税の軽い州も人気がある。<注目浴びる慈善活動>各国は引き続きコロナ禍への対応に苦しんでいるが、エコノミストはより大きな問題が切迫しつつあると指摘する。全般的な景気動向と超富裕層とのかい離だ。シンクタンクの政策研究所とアメリカンズ・フォー・タックス・フェアネスの調査によると、米国の富裕層の保有資産はコロナの流行開始から今年3月初旬までに1兆3000億ドル、50%近く増えた。富裕層の保有資産総額は4兆2000億ドルと、昨年の米国内総生産(GDP)の約20%に達した。これは全国民3億3000万人のうち所得水準が下位半分の保有資産総額の2倍に相当する。ノーベル経済学賞受賞者で米コロンビア大学教授のジョセフ・スティグリッツ氏はトランプ前米政権の富裕層向け大規模減税を念頭に、「不平等を称賛する4年間が過ぎ、人々は今、あれは正しい答えではなかったと口にしている」と述べた。UBSのジュディー・スパルソフ氏によると、コロナ流行で多くの超富裕層は社会的理念に関心を向けるようになった。特に若い富裕層の間で格差問題が話題に上ることが目立って増えたという。「確かにわれわれは成功した。一所懸命に働いて成功を手に入れた。だが回りの世界に目を閉ざすのはやめよう。自分たちだけの世界から踏み出せるようになろう」といった会話が富裕層一族の間で頻繁に聞かれると、スパルソフ氏は話した。多くの富裕層にとって、それは慈善活動への資金拠出を意味する。スパルソフ氏のチームでは、反貧困活動「アクション・アゲンスト・ハンガー」などに資金を提供するUBSオプティマス財団と提携する顧客が急増し、昨年の寄付金は1億6800万ドルと前年から74%増加した。市場シェアトップクラスで高ROEが続く「増配株」厳選3銘柄ヘルメット、福利厚生、メンテ…増配株シリーズ第7弾は、高水準のROE(自己資本利益率)を持続している企業に着目しました。ROEは「純利益÷自己資本」で算出され、効率的に経営できているかを測る指標です。長期にわたり高ROEの企業は、同業他社に対して競争優位性を持っていると考えられます。その中でも、配当を毎年増やしている増配株であれば、好業績に伴う株価の上昇と配当金収入という2つの投資メリットを得られますね。MonotaRO(3064)はROE30~40%前後が長年続いており、増配も継続している銘柄の代表格といえます。第2弾で取り上げたアイ・アール ジャパンHD(6035)やトリケミカル研究所(4369)も高ROEが続いている銘柄です。ちなみに、ROEは次のように分解できます。ROE=純利益率×総資産回転率×財務レバレッジ =(純利益÷売上高)×(売上高÷総資産)×(総資産÷自己資本)財務レバレッジの数値は、総資産における負債(他人資本)の比率が高まると大きくなります。そのため、借入金などの負債を増やすことでROEが高くなっている場合もあります。ROEを参考にする際は、財務状況も要チェックです。 SHOEI(7839):8期連続増配中1銘柄目は、高級感・デザイン性・安全性を兼ね備えたプレミアムヘルメット市場で世界シェア6割以上のSHOEI(7839)を取り上げます。世界50カ国以上で販売され、海外売上高は8割近く。2012年9月期までは主力のヨーロッパ市場の停滞もあって苦戦が続き、一時ROEは1%台まで下がりましたが、その後は復調し、過去7期のROEは20%前後で推移。連結配当性向50%をメドに配当金を出す方針で、8期連続増配中です(分割調整後、以下同)。Made in Japanにこだわっており、茨城と岩手の2工場での自社一貫生産体制を確立しているのが当社の強みです。オーダーメイド型のパーソナルフィッティングサービスや、ロードレース世界選手権「MotoGP」のライダーと契約していることも特徴ですね。前2020年9月期の営業利益率24.3%、営業キャッシュフローマージン(営業CF÷売上高)23.3%、自己資本比率75.0%と収益性、キャッシュ創出力、財務面のすべてにほれぼれする企業です。株価は非常に堅調ですが、市場全体の調整に伴って下落したときは買いのチャンス。2020年には株主優待も導入されています。 ベネフィット・ワン(2412):9期連続増配中パソナグループ(2168)子会社のベネフィット・ワン(2412)は、福利厚生サービス代行で業界首位級の会社です。”テンバガー”どころか、10年で株価が約50倍になった銘柄でもありますね。ROEは過去5年間20%以上で推移。さらに、上場した2005年3月期以降で見ても10%以上で推移しており、リーマンショックのような不況にも強い銘柄だといえます(2005年3月期と2011年3月期は単体決算)。大企業や自治体など1万以上の組織が導入し、868万人の会員数を誇っています。コロナ禍でも年間87万人増と堅調です。私の勤め先も当社の福利厚生サービスを導入していますが、便利でいいですね。前々回に紹介したDOE(株主資本配当率)は10%以上、配当性向70%以上を目標に掲げており、9期連続増配中です(2019年3月期は記念配当6円)。ストック型のビジネスを展開し、景気に左右されることなく安定した業績を出していることが、手厚い株主還元にもつながっているようです。前2020年3月期は営業利益率22.5%、営業キャッシュフローマージン14.7%、自己資本比率55.4%と3指標とも良好で魅力的。安定的な高ROE銘柄として投資しました。気になるのは、ここ数年、売上高が連続で期初予想未達ということ。増収率を見るとやや成長が鈍化しており、今期もコロナ禍で中小企業の会員獲得に苦戦しています。そんな中、当社は給与天引きプラットフォームなど決済事業によるマネタイズを模索しています。来期以降の成長に向けて、システム投資計画を前倒しで実行するとのことです。新規事業を軌道に乗せることができれば、成長の再加速を期待できるかもしれませんね。 ジャパンエレベーターサービスHD(6544):4期連続増配中エレベーター・エスカレーターの独立系メンテナンス会社でトップクラスのシェアを誇る会社です。国内では約100万台のエレベーター・エスカレーターが稼働しており、そのうち約8割は三菱電機(6503)や日立製作所(6501)などのメーカー系列の会社がメンテナンスを手がけていますが、当社は残りの2割の中で約25%のシェア。強みは、メーカー系列よりも2~5割低いコストでメンテナンスできることや、故障の予兆をいちはやく察知できる「PRIME」というリモート点検システムを独立系で唯一、手がけていることです。上場は2017年と最近ですが、過去3期30%以上の高ROEが続いています。増配も2017年3月期から数えて4期連続です。前2020年3月期は営業利益率12.7%で、ここ数年は上昇傾向。自己資本比率は35.9%とやや低いものの、ネットD/Eレシオは1倍以下と健全な水準です。当社の保守契約台数は約6万0800台(2020年9月末)で年々伸びており、安定した経営が期待できます。また、同業のM&Aに積極的なこともポイントです。M&Aも駆使しながら着実にシェアを伸ばしています。九州など手薄な地域もあり、成長の余地はまだまだあると考えます。海外展開の検討を始めている点も見逃せないですね。 投資は早く始めて長く続けるのが吉さて、もうすぐ新年度になります。新しい生活がスタートし、心機一転、何かを始めようと考えている方も多いと思います。投資を始めたばかりの方や、これから始めたいと考えている方もいるでしょう。私の経験で恐縮ですが、20代で投資を始めたもののすぐにやめてしまい、数年間投資していない期間があります。今ではものすごく後悔しており、なぜ続けなかったのかと悔やんでも悔やみきれません。当時は持続可能な投資の仕方を考えられず、行き当たりばったりで結果が出なかったのが大きな要因です。今は増配株を中心に、中長期で含み益を伸ばしつつ、配当によるキャッシュインも重視した投資をしており、持続できるようになりました。そして、年100万円以上の配当収入を得るまでになっています。早く始めて長く続けることで、複利効果などのメリットが出るのが株式投資です。「余剰資金で投資する」ことを忘れずに、「自分で考えて投資する」「継続的にインプットとアウトプットを繰り返す」「退場しない」ことで次第に結果も出てくるはずです。株式投資は資産を増やすだけでなく、自分の知る世界を広げてくれるツールでもあります。投資をすることでちょっとしたニュースや、手に取った商品、サービスなどあらゆるものが以前とは違った目線で見ることができます。新年度に何かしたい! と考えている方は、その選択肢にぜひ「株式投資」を入れてみてください。数年後、振り返った際に「あのとき投資を始めてよかった!」と思える日がきっと来るでしょう。【特集】大相場への夢いま再び、「お宝」中低位株とっておき7選 <株探トップ特集>―ワクチン普及でアフターコロナの世界を織り込む、究極のバリュー系材料株を追え―●ハイボラティリティな1週間 東京株式市場は3月期末を目前にしてハイボラティリティな相場展開が続いている。週末の日経平均株価は400円を超える上昇で続伸、4営業日ぶりに終値で2万9000円台を回復した。とはいえ、今週は投資家にとってはかなり不安を掻き立てられた波乱要素満載の週であった。 前週末19日の日銀金融政策決定会合後に、日銀はETFの買い入れ対象から日経平均連動型の除外を決めたと発表、これが波紋を呼び、同日にファーストリテイリング を筆頭とする日経平均寄与度の高い値がさ株を中心に大きく売り込まれる格好となった。このリスクオフの流れは、今週に入ってからも続き、週明け22日に日経平均は600円あまりの下げを演じ、更に23日、24日も下げ止まらず、結局前週末からの4営業日合計であっという間に1800円を超える急落に見舞われた。●口実に使われた「日銀ETFショック」 しかし、昨年来の過剰流動性を背景とした上昇相場において、日銀のETF買いがどのくらいの重要性を持っていたかというのは未知数である。全体相場が前引け時点で安かった時(TOPIXベースで0.5%超下げた時というのが暗黙のコンセンサス)、日銀は後場に買い入れを行うというのが、これまでのETF購入に際してのスタンスである。当然ながら、全体市場が上値指向の強い局面ではなかなか出番は訪れない。下値でセーフティーネットが敷かれていることへの安心感は与えたかもしれないが、実際に上昇相場のエンジンとなったのは米国を先導役とする世界株高であって、少なくとも日銀ではない。 買い入れ対象から日経平均連動型を除外することで、ファーストリテが波乱安の展開を強いられたのは仕方ない部分があるが、結局はTOPIX連動型の銘柄も十把ひとからげに売られ、日経平均・TOPIXともに大幅な調整を余儀なくされた。冷静に考えれば、金利の動向や企業業績(見通しも含む)といったファンダメンタルズから離れたところで、金額の規模はともかく銘柄入れ替えにも等しいテクニカル的な要因が、全体相場のトレンドの向きを180度変えてしまうようなことはない。日銀の発表は急落のトリガーを引く損な役回りとはなったが、それ以外には何のネガティブ要素もなく、行き過ぎた株価調整場面における口実に使われただけである。●振れ幅は大きくても振り子は戻ってくる つまり、前週末から今週央にかけての急激な株価調整は、願ってもない買い場提供場面であったといえる。週後半の25日には75日移動平均線を足場にきれいな切り返しをみせ、週末はここぞとばかりに仕切り直しの買いが流入してきた。現在の相場はAIアルゴリズム取引の絡みもあって、同一方向に走り過ぎる傾向がある。“生身の”投資マインドであれば躊躇するところでアルゴリズムは売りも買いも上乗せする。また、それを見込んで便乗する売買も加わり、振り子の振れ幅は想定外に大きくなる。しかし、ひとつの摂理として振り子はすぐにまた戻ってくるのである。売りのタームと買いのタームは人間の呼吸と同じく交互にやってくる。 全体が想定以上にイレギュラーな下げに見舞われたのであれば、そこは買いの姿勢を貫いて正解となるが、問題はその投資資金の振り向け先である。全体指数を投資の対象と考えるならNF日経レバやNF日経ダブルインバースなどを拾えばよい理屈だが、それよりもこのバーゲンハンティングチャンスを生かして、中長期投資で大きく利益を取りにいくスタンスをとりたい。個別株に照準を合わせるのであれば銘柄選別は重要となる。●ハイテク値がさ株よりも中低位株に利あり 日銀のETF購入手法の変更は、全体相場の方向性を変えるものではないが、日経平均寄与度の高いハイテク系グロース株などの値がさ株には上値を重くする材料となる。ファンダメンタルズは好実態であっても、株式需給面でファンド系のポジション調整に伴う売りをこなす時間が必要となるからだ。現在は、米国を先頭に新型コロナウイルスワクチンの普及期待が高まるなか、景気敏感セクターを中心としたバリュー系銘柄に光が当たる順番となっている。株価水準的にも、これまで機関投資家の組み入れが進んでいなかった中低位の銘柄に優位性がある。今の東京市場には、実態は決して悪くないのにPBRなど株価指標面から割安な銘柄がゴロゴロしている。 そしてポイントとなるのは、視点を前方に置き足もとの収益に惑わされないということだ。3月決算企業についていえばカギを握るのは今期ではなく来期業績に対する展望である。また、12-2月期決算企業であれば前期の業績は不問で、今期の業績がどうなるかが重要となる。直近は欧州での新型コロナ感染再拡大で油断のできない状況ではあるが、それでも株式市場はアフターコロナを見据えた動きにある。コロナ禍から脱出し、経済活動正常化のプロセスにおいて輝きを放つのはどういう銘柄か。今回の特集では、それに該当する条件を備え、なおかつ個人投資家の土俵で戦いやすい中低位の有望株を7銘柄厳選した。●注目必至の「お宝3ケタ株」7銘柄【新日本電工はリチウム電池材料で見直しへ】 新日本電工 は3月15日に331円の高値をつけた後、調整を入れているが75日移動平均線をサポートラインに切り返しを期待。信用買い残の整理も進んでおり、300円ラインを通過点に中勢500円を目指す動きが期待できる。日本製鉄系の合金鉄大手で粗鋼生産の回復を背景に収益環境の改善が進んでいる。20年12月期は黒字転換し復配も実現させたが、21年12月期も増収増益基調を維持し増配も視野に入る。ハイブリッド車(HV)用水素吸蔵合金や電気自動車(EV)用リチウムイオン電池正極材などのOEM生産で実績が高く、EV関連の有望株として大きく見直される可能性がある。【藤コンポは超低PBRで新エネ材料も】 藤倉コンポジット は年初から一貫した上昇波を形成。19年11月につけた戻り高値543円払拭から上げ足に勢いがつきそうだ。PBRは0.5倍近辺と解散価値の半値水準で、仮に1株純資産並みのPBR1倍に買われたとして1000円大台までの上値余地がある。ゴム加工品や産業用資材大手で幅広い需要を捉える。特に、自動車販売の好調を背景にエンジンやブレーキ用部品の伸びが予想され、22年3月期業績は急回復が有望視される。非常用マグネシウム空気電池で高実績を有し、風力発電機用保護シートも手掛ける。アフターコロナではゴルフコンペが復活し、ゴルフシャフトにも追い風が強い。【クロスマーケはDXで株価変貌の緒に就く】 クロス・マーケティンググループ の400円台のもみ合いは次の上昇ステージに向けた踊り場として強気対処したい。時価は昨年来の戻り高値の強力なフシであった440円ラインをブレイクし新波動入りを暗示している。ネット調査を祖業に現在はデジタルマーケティング事業や、顧客企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)支援に経営の重心を置く。ITソリューションではIT系人材ビジネスに引き合いが強く今後に期待が大きい。21年6月期は6ヵ月の変則決算となり比較はできないが、22年6月期については営業利益段階で過去最高水準を上回り14~15億円への拡大が視野に入る。【シンニッタンはEV電池用パレットに期待】 シンニッタン は3月に入ってから急速に上値指向にあるが、PBRは依然として0.5倍前後と解散価値の半値水準で株価修正余地が大きい。目先の押し目は買い向かって報われそうだ。自動車や建設機械向け鍛造品を主力とし、世界的な自動車販売需要の回復を受け収益環境の改善が急だ。21年3月期業績は営業赤字を余儀なくされる見通しながら、今期での底入れが濃厚で22年3月期は急回復に向かうことが想定される。財務健全で配当はゆるぎなく実施、配当利回りも3%超と高い。EVバッテリー向けパレットを展開しており引き合いは旺盛、世界的なEVシフトを背景に今後の需要獲得が期待されている。【nmsは製造業大手のニーズ捉え復活へ】 nms ホールディングス [JQ]は1月下旬に急速に上放れた後、上げ下げを繰り返しながらも次第に下値を切り上げる展開。300円台後半に歩を進め昨年2月下旬のコロナショック急落前の水準に近づきつつある。電機や精密機械など製造受託サービスや人材サービスを手掛け、パナソニック やソニー などを主要顧客に来期業績回復に向けた足場を固めている。育成中の電源事業も家庭用、産業用、医療用の各種機器向けに幅広く対応した電源製品を開発し需要獲得が進む。業績は21年3月期が底で22年3月期は大幅増収増益が濃厚、営業利益は10億円台に乗せてくる公算が大きい。【ジオスターは15兆円国土強靱化で出番】 ジオスター [東証2]は調整一巡から再び上値追いの動きを強めそうだ。400円近辺の株価は値ごろ感がある。道路やトンネル向けなどを主力とするコンクリート2次製品の大手で、セグメントや鋼製土木建材の製造技術にも強みを発揮。シールドトンネル用セグメントでは業界随一の実力を持つ。21年度からスタートする国土強靱化 5ヵ年計画は事業規模15兆円と巨額だが、トンネルの老朽化への対策は待ったなしの状況にあり、同社は中期的に強力なフォローの風を受けることになる。21年3月期営業利益は従来予想から増額し、前期実績比横ばいの14億円を見込むが、22年3月期は2ケタ成長が有望視される。【IJTTはトヨタといすゞの提携で思惑】 IJTT [東証2]は3月中旬を境に動兆しきり。ただ、PBRは0.3倍台と評価不足が著しく今は水準訂正の初動。500円台後半で売り買いを交錯させている現状は仕込み場といえる。いすゞ系自動車部品メーカーで自動車販売回復の追い風を享受するが、ポイントとなるのはトヨタ自動車 といすゞ自動車 の資本提携だ。両社は小型トラック分野でのEV化や自動運転などで協業を進める方針で、これはIJTTのビジネスチャンスにもつながる。既にこれに先立って電動駆動システムの開発などに積極的な取り組みをみせている。足もとの業績悪も織り込み済みで来期のV字回復に期待がかかる。株探ニュースマット・クーチャー、ビリー・ホーシェルらが勝ち上がり 準決勝4人が決定<WGC-デル・テクノロジーズ・マッチプレー 4日目◇27日◇オースティンCC(米テキサス州)◇7108ヤード・パー71>世界ゴルフ選手権シリーズ「WGC-デル・テクノロジーズ・マッチプレー」決勝トーナメント2回戦が終了し、準決勝に進む4人が決定した。2019年大会で2位のマット・クーチャー(米国)がブライアン・ハーマンを破り準決勝進出。米ツアー5勝のビリー・ホーシェル(米国)がトミー・フリートウッド(イングランド)を19ホール目で下して勝ち上がった。準決勝の組み合わせは、ビクトル・ペレズとビリー・ホーシェル、マット・クーチャーとスコッティ・シェフラーで現地時間28日に行われる。J・ダーメンらが首位 マスターズ覇者D・ウィレットが1打差3位<コラレス・プンタカナ リゾート&クラブ選手権 2日目◇26日◇コラレスGC(ドミニカ共和国)◇7670ヤード・パー72>世界ゴルフ選手権シリーズの「WGC-デル・テクノロジーズ・マッチプレー」の裏で行われている「コラレス・プンタカナ リゾート&クラブ選手権」の第3ラウンドが終了。ツアー未勝利のジョエル・ダーメン(米国)、ラファエル・カンポス(プエルトリコ)がトータル10アンダー・首位タイに浮上した。首位と1打差の3位タイには、2016年「マスターズ」覇者のダニー・ウィレット(イングランド)、マイケル・グリジック(カナダ)の2人、2打差の5位タイにはエミリアーノ・グリジョ(アルゼンチン)、トーマス・ピータース(ベルギー)が続いた。新型コロナワクチン、選択可能に 接種会場ごと種類分け 小林補佐官時事通信 新型コロナウイルスワクチン担当の小林史明大臣補佐官は28日のフジテレビ番組で、国民がどの種類のワクチンを接種するか自ら選択できるようにする考えを明らかにした。 小林氏は「接種会場ごとに打つワクチン(の種類)を決めていく。それは公表されるので、会場を選べば打つワクチンを選ぶことができる」と説明した。 小林氏は接種に関し「(副反応など)自身の事情で打ちたくないという判断をされる方もいると思う」と指摘。各会場に用意されたワクチンの種類を知らせることで、「選べる環境をつくっていきたい」と語った。 高齢者向け接種は4月12日から始まり、米製薬大手ファイザー社製のワクチンが提供される。今後、一般向けなどは英製薬大手アストラゼネカと米バイオ医薬品企業モデルナからも供給を受ける予定だ。岡山絵里が5打差逆転で3年ぶりV 河本結2位、渋野日向子15位<アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI 最終日◇28日◇UMKカントリークラブ(宮崎県)◇ 6568ヤード・パー72>2021年国内女子ツアー4戦目の最終ラウンドが終了した。首位と5打差から出た岡山絵里が5バーディ・1ボギーの「67」をマーク。トータル13アンダーで逆転し、18年の「リゾートトラスト レディス」以来となるツアー2勝目を果たした。単独首位で出た河本結は「73」と落とし、トータル12アンダー・2位で大会連覇はならなかった。トータル10アンダー・3位タイには原英莉花、高橋彩華、ペ・ソンウ(韓国)が入った。来週の海外メジャー「ANAインスピレーション」に出場する渋野日向子は、4バーディ・1ボギーの「69」でラウンド。渡米前最終戦をトータル4アンダー・15位タイで終えた。本日の夕食は、森山ナポリのトリュフのビザ、ソーセージ、ブロッコリーの炒め物、トマトと野菜のスープでした。一緒に楽しんだのは…リュイナールのブラン・ド・ブランでした。美味しくいただきました。変異株陽性者含むクラスターを県内初確認 岐阜県、新たに12人が新型コロナ感染 岐阜県と岐阜市は28日、新たに6市町で計12人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。変異株の陽性者を含む新たなクラスター(感染者集団)が県内では初めて大垣市で確認された。日曜日発表の新規感染者が2桁となるのは、緊急事態宣言解除前の2月21日以来5週間ぶり。感染者数は累計4808人となった。 大垣市のクラスターは、接待を伴う飲食店の従業員と利用客、従業員の友人とその家族ら5人。県によると、うち1人は既に変異株の陽性が判明しており、県は他の4人についても変異株かを判定する検査を検討している。飲食店は、感染が拡大する可能性のある期間の利用客が4、5人しかおらず、不特定多数の利用はないという。 また、安八郡神戸町では、同居する20代の女性5人ら計6人のクラスターを新たに確認した。同居女性はいずれも外国籍で、同じ会社で働いている。県は、会社での感染拡大がないかなどを調べる。 関市、各務原市などの3家族のクラスターは、感染者の職場や家族など中学生を含む3人が新たに感染。10人規模となった。 岐阜市柳ケ瀬地区のフィリピンパブ「ココナッツ」(同市弥生町)などの22人のクラスターでは、新規感染者は確認されなかった。 27日時点の入院者は109人で、病床使用率は15・7%と前日より2・3ポイント上がった。入院者が100人を超えるのは19日ぶり。県は、岐阜地域で確保しているコロナ病床の増床や、運用休止中の宿泊療養施設の再運用を検討する。 県健康福祉部の堀裕行次長は記者会見で「若い人や外国人、接待を伴う飲食店などで感染者が増えており、非常に心配している」と懸念を述べた。 新規感染者の居住地別は安八郡神戸町4人、大垣市3人、岐阜市2人、各務原市、関市、美濃市が各1人。年代別は10代2人、20代4人、30代1人、40代1人、50代2人、60代2人。
2021.03.28
コメント(0)
-

3月27日(土)…
3月27日(土)、晴れです。春ですね。暖かくて気持ちの良い天気です。そんな本日は7時45分頃に起床。ベッドパッドを干して、新聞に目を通し、朝食を済ませ、ロマネちゃんと戯れる。本日のノルマは1階のモップかけですか…。ハイハイ…。朝のコーヒーブレイクはネスプレッソで…。モロゾフのチョコレートと共に…。次いで恒例の母親宅の後片付けです。いつまで続くんでしょうね…。本日も衣類を中心にゴミ袋が10ケほど…。近くのゴミステーションが古着の回収をしてくれるのでそちらまで車で2往復…。昼食前に作業終了…。午前中で疲れてしまいます。1USドル=109.64円。1AUドル=83.72円。昨夜のNYダウ終値=33072.88(+453.40)ドル。昨夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中の19銘柄が値を上げて終了しましたね。キーサイト、クアルコムが上げていますね。ファイザー製ワクチン、1回接種で強い免疫効果=英調査[ロンドン 26日 ロイター] - 英オックスフォード大学などが行った調査から、米ファイザー製の新型コロナウイルスワクチンの1回の接種で99%の人が強い免疫反応を示し、実際の感染で産生される免疫と同様の効果を得られる可能性があることが分かった。英保健当局も2月、ファイザー製ワクチンの初回接種で医療従事者らのコロナ感染が約70%減少したほか、高齢者の入院や死亡も75%強低減したと発表していた。さらに調査では、過去に新型コロナに感染した人への接種では未感染の人よりも高い反応がみられ、変異株に対し予防効果がある可能性も示されたという。とりあえず接種の日時の連絡は来ましたが、まだしばらく先ですね…。米国株式市場=ダウ453ドル高、景気回復期待で幅広い銘柄に買い [ニューヨーク 26日 ロイター] - 米国株式市場は上昇し、ダウ工業株30種は453ドル高で取引を終えた。景気回復への期待から金融、ハイテク、ヘルスケアなど幅広い銘柄に買い注文が集まった。 バリュー(割安)株も底堅く推移。ラッセル1000バリュー株指数は1.6%高だった。同指数は年初からの伸びが10%を超え、ラッセル1000グロース(成長)株指数よりも好調だ。 オッペンハイマー・アセット・マネジメントのチーフ投資ストラテジスト、ジョン・ストルツファス氏は「ハイテク株からの脱却というよりも、グロース株やバリュー株を含め、株式に対する幅広い投資意欲がうかがえる」と分析した。 週間ではダウが1.4%高、S&P総合500種指数が1.6%高。一方、ハイテク株の多いナスダック総合指数は0.6%安。 銀行株はこの日1.9%高。米連邦準備理事会(FRB)は25日、新型コロナウイルス感染拡大を受けて導入した銀行の配当支払いと自社株買いに対する制限について、6月に行う次回のストレステスト(健全性審査)後に「大半」の銀行を対象に解除する方針を示した。 エネルギー株は2.6%高。エジプトのスエズ運河で起きた大型コンテナ船座礁事故の影響が長期化するとの懸念から原油が値上がりしたことにつられた。 個別銘柄では、アパレルのLブランズが3.7%高。追加景気対策が後押しになるとして今四半期の利益見通しを再び引き上げた。 米取引所の合算出来高は122億3000万株。直近20営業日の平均は136億7000万株。 ニューヨーク証券取引所では値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を3.30対1の比率で上回った。ナスダックでも1.81対1で値上がり銘柄数が多かった。ドル横ばい、円は10カ月ぶり安値=NY市場[ニューヨーク 26日 ロイター] - 終盤のニューヨーク外為市場ではドルが主要通貨に対しておおむね横ばい。2月の米個人消費が寒波の影響で大きく落ち込んだものの、市場は反応薄だった。一方、円相場は一時109.80円と10カ月ぶりの水準に値下がりした。ドルは通貨バスケットに対し92.7200。週間では0.7%高。2月の個人消費支出は前月比1%減少し、昨年4月以来の大幅なマイナスとなった。寒波による経済活動の停滞などが響いたもようだが、その後の天候の回復や今月成立した新型コロナウイルス追加経済対策法、ワクチンの普及が後押しとなり、消費の落ち込みは一時的にとどまるとみられる。ドル/円は足元109.64円。シリコンバレー・バンクのシニア為替トレーダー、ミン・トラン氏は「ドルが第2の風を受けている」と指摘。ドル高トレンドが強気相場と同様に勢いづく可能性があると指摘した。米10年債利回りはこの日上昇したものの、先週付けた1年ぶりの高水準からは後退している。ユーロ/ドルは0.26%高。独IFO経済研究所が発表した3月の業況指数は96.6と2019年6月以来の高水準となった。ただ、域内での新型コロナウイルス感染の拡大やワクチン普及の遅れがユーロの重しとなっている。ドイツのロベルト・コッホ研究所(RKI)のヴィーラー所長は、同国を見舞っている新型コロナウイルス感染の第3波がこれまでで最悪となる「明白なシグナル」があるとし、1日当たりの新規感染者数が10万人に達する恐れもあると警鐘を鳴らした。暗号資産(仮想通貨)のビットコインは4.5%高の5万3654ドル。【米国市況】S&P500最高値、ワクチン展開を楽観-円1年ぶり安値 26日の米株式相場は上昇。世界的にリスク選好ムードが戻り、S&P500種株価指数は終値ベースの最高値を更新した。ワクチン展開を巡る楽観が支えたほか、大半の銀行について増配の制限を6月で終了する米金融当局の決定が好感された。 米国株は上昇-エネルギーやヘルスケア好調、自動車は安い 米国債は下落、10年債利回り1.67% 円が1年ぶり安値、1ドル=109円台後半-資源国通貨は高い NY原油は反発、週間では下落-ロックダウンで短期需要見通し曇る NY金は反発、ドル下落や利回り上げ縮小で S&P500種は終盤に上げが加速し、週間ベースでも上昇した。エネルギーやヘルスケア関連銘柄の好調が目立った。自動車株は世界的な半導体不足の深刻化が意識され、下落した。バイデン米大統領が前日、就任後100日の新型コロナウイルスワクチン接種目標を2倍に引き上げたことが、米国の見通しを明るくした。 S&P500種は前日比1.7%高の3974.54。ダウ工業株30種平均は453.40ドル(1.4%)高の33072.88ドル。ナスダック総合指数は1.2%上昇。ニューヨーク時間午後4時10分現在、米10年債利回りは4ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の1.67%。 ランド・マーチャント・バンクのストラテジスト、ネマ・ラムケラワンバナ氏は、「市場のトーンが不安から楽観に変化した」とし、それは「バイデン大統領がワクチン接種目標を倍に引き上げたことや、米金融当局の配当制限解除が手掛かりになった」とリポートで指摘した。 外国為替市場では円が下落。リスク選好が優勢となる中、対ドルで一時は昨年3月以来の安値となった。資源国通貨は原油相場の反発を支えに、逃避先通貨をしのぐパフォーマンスを見せた。 主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.2%低下。週間ベースでは0.7%上昇した。ドルは対円では0.4%高の1ドル=109円63銭。一時は0.6%高の109円85銭をつけた。ユーロは対ドルで0.3%高の1ユーロ=1.18ドル。 ニューヨーク原油先物相場は反発したが、週間ベースでは小幅に下落。一部地域での新たなロックダウン(都市封鎖)措置で短期的な需要見通しが鈍り、スエズ運河での船舶立ち往生の影響が弱まった。 ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物5月限は、前日比2.41ドル(4.1%)高の1バレル=60.97ドルで終了。週間では1%未満の下げ。ロンドンICEの北海ブレント5月限は2.62ドル高の64.57ドル。 ニューヨーク金市場ではスポットと先物が反発。週間での下げ幅を縮小した。ドルの下落や米国債利回りが日中の高水準を離れたことを手掛かりに、金の買いが優勢になった。 ニューヨーク時間午後2時18分現在、金スポット価格は前日比0.2%高の1オンス=1730.41ドル。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物6月限は7.40ドル(0.4%)上げて1734.40ドルで終了した。最後の勝ち組はやはりアマゾンか、拡大するオーディオブック市場みなさんは、「オーディオブック」をお試しになった事はありますか?オーディオブックとは、出版されている書籍を読み上げている音声を聞くもので、従来の本は手に取って活字を読むものですが、このオーディオブックは、「本を聞く」ものです。このオーディオブックは本を好む人にとっては賛否があるようですが、今まであまり本に対して親しみが無かった人にとっては、新しいタイプの読書方法となっているようで、新しいIT産業として注目されています。ひと昔前に比べ、世界的に読書者数は減少傾向にありますが、データによると、紙の本を読む人が減っていく反面、電子書籍(PC、携帯、タブレットなどにて読めるもの)やオーディオブックでの読者数は増えている傾向にあるようです。日本能率協会総合研究所の調査によると、オーディオブック市場は2024年には260億円規模に成長すると推計されています。2020年以前は100億円未満の市場だったので、5年ほどで2倍以上の成長余地がある市場となります。そんなオーディオブック市場に参入している企業は主に下記の会社があります。Audible (Amazon(NASDAQ:AMZN)の子会社)Apple (NASDAQ:AAPL)イード(東証1部:6038) オーディオブックで注目の企業この他、日本の音声コンテンツサービスの会社として、radiko、voicy、 audiobook.jpという会社がありますが、それぞれ非上場です。Audible(オーディブル)は、アメリカニュージャージー州に本社があり、プロのナレーターが朗読するオーディオエンターテイメント・情報・教育関連のコンテンツを制作・配信している会社です。自社の製作スタジオを持っていて、アメリカ、ヨーロッパ、日本などでサービスを展開しています。2008年よりアマゾンの傘下になりました。Apple(アップル)はiPhoneやPC関連で有名な会社ですが、iTunes(アイチューンズ)で音楽や動画を配布・販売しています。このアイチューンズ上でオーディオブックも販売しています。オーディブルとアップルの製品は、世界の市場で販売していますが、日本国内のメーカーで上場している企業となるとイードがあがります。イードは、東京に本社があるIT関連企業で、RBB TODAYやResponseなどのニュースサイトの運営、リサーチ事業、メディアコマース事業などを行っています。2019年あたりから音声コンテンツ市場に参入しています。その他のradiko(ラジコ)、voicy(ボイシー)はオーディオブックの販売は現在はまだ行っていませんが、インターネット上で声のブログ、ニュース、ラジオなどが聞ける音声メディアとしてオーディオブック同様に注目されています。オーディオブック市場が拡大するにつれ、同社のような同様のサービスも同じように伸びていくでしょう。audiobook.jpは非上場の企業ですが、(株)オトバンクが運営する、日本最大のオーディオブック配信サービスです。2007年よりサービスを開始していて、オーディオブックの配信のみならず、ポッドキャストの有料配信サービスや、新聞社、ラジオ局と提携したコンテンツの配信も行っています。日本経済新聞社の「聞く日経」や毎日新聞社の「毎日ウィークリー」などがあります。 急成長している音声コンテンツ産業オーディオブックを始めとする音声コンテンツ産業は、ここ5年ほどで急成長していますが、人々のコンテンツに対する需要が、従来の紙の本や電子書籍から音声コンテンツにどう移っていくのかが注目される点です。それと同時に、YouTubeなどのコンテンツとどうユーザーを奪い合うのかが更に注目する点でもあると思います。いづれにせよ、オンライン販売では世界的に有名なアマゾンがオーディオブック産業でも上位に入ってくるのではないでしょうか。アマゾンは従来の紙の本や電子書籍、オーディオブックを始め、画像コンテンツの販売も行っており、人々の需要がどの産業に傾いても対応できる市場を持っています。よって最後はアマゾンが抜き出るのではないでしょうか。今後の展開が楽しみです。ノバルティス(NYSE:NVS)の最新業績や最新コロナ対応について解説していきます。言わずと知れたグローバル大手製薬企業であり、世界の製薬ランキングではトップにランクされており、かつムーディーズなどの格付け会社から高い評価を得ています。5年間の株価を見てみると、右肩上がりであり、今回のパンデミックを契機にさらに伸びていくかもしれません。コロナ禍でも2020年のノバルティスの業績は順調ノバルティスの最新業績などから解説していきます。パンデミックへの対応ノバルティスは2−3種類のコロナ治療薬開発に取り組んでおり、現在、臨床試験のフェーズ2あるいは3の段階にあります。ノバルティスとはノバルティスはスイスの大手製薬企業であり、ニューヨーク証券取引所にも上場されています。同社が参入している疾患領域は、がんや神経疾患、心臓疾患、皮膚疾患、免疫疾患などです。様々な疾患領域に取り組んでいますが、比較的バランスよく売り上げを得ている印象です。また、同社の売り上げは世界の製薬企業ランキングでは上位にランクされており(2019年では3位)、かつムーディーズおよびスタンダード&プアーズから高い評価を得ています。約10年間の同社の売上高は伸び悩んでいますが、今回のパンデミックを契機に業績が伸びていくかもしれません。コロナ禍でも順調な業績ノバルティスの第4四半期(Q4)の決算報告書は今年の1月26日に発表されました。年間の業績の方が概観しやすいので、ここではQ4でなく2020年の年間業績(FYE: Financial Year End)を見ていきます。同社の決算報告書によれば、年間の売り上げや純利益やEPS(1株当たり利益)は順調に上昇しました。以下に、具体的な数字や原因について説明します。トータルの売上高:3%増加(2020年FYE: 486.5億ドル、2019年FYE: 474.4億ドル)純利益:13%増加(2020年FYE: 80.7億ドル、2019年FYE: 71.4億ドル)売上増の主な要因は、前年比で増加した心臓疾患の治療薬や脊髄性筋萎縮症の遺伝子治療薬の売り上げの大幅な増加です。特に眼科や皮膚科の領域がコロナの影響を受けたようですが、全体の業績には特に大きな影響は見られなかったようです。今後の見通しノバルティスの最新業績やコロナ対応に関して解説しました。米国の製薬企業ではありませんが、世界の製薬企業売り上げランキングが上位にランクされていることなどから、世界のヘルスケア市場では重要な位置を占めます。また、5年間の株価は右肩上がりです。業績が順調であることから、今後はしばらくその傾向は続くのではないかと思います。【市況】富田隆弥の【CHART CLUB】 「彼岸底で打診買い」株式評論家 富田隆弥◆やはり、3月下旬に日経平均株価は荒れた。アノマリー(経験則)の通りである。3月18日に3万485円(ザラバ値)まで戻したが、そこから4日続落し24日に2万8379円の安値を付けた。18日の高値から4日間で2100円幅(6.9%)という厳しい下げであり、チャートは二番天井と二段下げの懸念を募らせた。◆19日時点で、騰落レシオが127%に上昇し、RCI短期線(9日線、13日線)は高値圏に集まり、信用買い残の評価損率が-5.99%(3年1ヵ月ぶり)に改善するなど、テクニカル指標は再び過熱を見せていた。バリュー株物色が過熱したこともあり、ここでの調整は仕方がなかったと言える。◆だが、年度末で機関投資家などがいったんポジション調整(売り)に動くところで、昨年は3月19日に、2019年は3月25日、18年は3月26日といずれも3月後半に安値を付けている。だとすると、今年もこのあたりで安値を打ってもおかしくない。いわゆるアノマリーの「彼岸底」である。◆日足チャートは75日移動平均線(25日時点2万8420円)や一目均衡表の「雲」下限(同2万8520円)の節目に差し掛かった。配当落ちのある30日まで下値模索を続ける可能性はあるものの、4月になれば新年度入りで機関投資家が買いに動くことも想定され、日本株は5月に向けて反発しやすくなる。◆ならば、この調整局面で「買い」に動いてみる価値はあるだろう。もちろん、日本株のカギを握る米国株の調整入りに注意が必要だが、金融・財政政策を背景とした需給相場が継続しており、すぐに崩れるようなことはまだないと思われる。 (3月25日 記、毎週土曜日に更新)ラームを除く第一シード15名が姿を消す大波乱! ガルシア、スピースら16名が決勝Tへ<WGC-デル・テクノロジーズ・マッチプレー 3日目◇26日◇オースティンCC(米テキサス州)◇7108ヤード・パー71>世界ゴルフ選手権シリーズ「WGC-デル・テクノロジーズ・マッチプレー」3日目の競技が終了。4選手総当たりで行われるグループステージを終え、決勝トーナメントに出場する16選手が決まった。グループステージを勝ち上がった顔ぶれを見てみると、ジョン・ラーム(スペイン)を除く、15のグループで第一シードが敗退するという大波乱。世界ランキング1位のダスティン・ジョンソン(米国)がいるグループ1では、ジョンソンがケビン・ナ(米国)に敗れて1勝1敗1分けとなり、グループステージ敗退。11番パー3では、バーディパットを外して勝手にボールを拾い上げるミスもあった。さらに、グループ2ではジャスティン・トーマス(米国)、グループ4ではコリン・モリカワ(米国)、グループ5ではブライソン・デシャンボー(米国)、グループ11ではローリー・マキロイ(北アイルランド)といった世界ランク上位のメジャーチャンプたちも姿を消した。なお、初日、2日目と連敗を喫し、グループステージ敗退が決まっていた松山英樹は、世界ランキング10位のパトリック・キャントレー(米国)と対戦し、4&2で勝利。再来週に控える「マスターズ」の前週は空けずに、来週の「バレロ・テキサス・オープン」に出場する予定となっている。また、グループ8では2勝1敗で並んだセルヒオ・ガルシア(スペイン)とリー・ウェストウッド(イングランド)のプレーオフとなり、4ホール目の4番パー3で後から打ったガルシアがなんとホールインワンで劇的勝利。決勝にコマを進めている。そのほか、歴代チャンピオンに名を連ねるバッバ・ワトソン、マット・クーチャー(ともに米国)イアン・ポールター(イングランド)が週末のマッチに残った。【決勝トーナメント1回戦の組み合わせ】トミー・フリートウッド vs ディラン・フリッテリビリー・ホーシェル vs ケビン・ストリールマンセルヒオ・ガルシア vs マッケンジー・ヒューズロバート・マッキンタイア vs ビクトル・ペレズスコッティ・シェフラー vs イアン・ポールタージョン・ラーム vs エリック・ヴァン・ローエンバッバ・ワトソン vs ブライアン・ハーマンマット・クーチャー vs ジョーダン・スピースラファエル・カンポスら3人が首位で並ぶ 小平智は2打足りず予選落ち<コラレス・プンタカナ リゾート&クラブ選手権 2日目◇26日◇コラレスGC(ドミニカ共和国)◇7670ヤード・パー72>世界ゴルフ選手権シリーズの「WGC-デル・テクノロジーズ・マッチプレー」の裏で行われているドミニカ共和国にあるコラレスGCで「コラレス・プンタカナ リゾート&クラブ選手権」は2日目の競技が終了。日本勢唯一の出場となる小平智はトータル3オーバーとカットラインに2打届かず予選落ちとなった。ラファエル・カンポス(プエルトリコ)、ファブリツィオ・ザノッティ(パラグアイ)、ジャスティン・ソ(米国)がトータル7アンダーで首位タイ。1打差の4位タイにはジョエル・ダーメン、タイラー・ダンカン(いずれも米国)が続いている。2016年の「マスターズ」覇者ダニー・ウィレット(イングランド)がトータル4アンダーの12位タイ。米公式サイトで優勝候補筆頭に挙げられたチャーリー・ホフマン(米国)、昨年覇者のハドソン・スワフォード(米国)はトータル3アンダー・21位タイにつけている。京都・醍醐寺、夜の一般公開 枝垂れ桜も見ごろ毎日新聞 世界文化遺産・醍醐寺(京都市伏見区)で春季初となる夜の一般公開が実施されている。見ごろを迎えた枝垂れ桜などが夜空に浮かび、参拝者の目を楽しませている。同寺は「ウィズコロナで閉塞(へいそく)感が漂う時代に桜で心を癒やしてほしい」と話す。4月11日まで。 期間中は、大枝垂れ桜のある三宝院と霊宝館を午後6~8時に公開。日によって公開する施設は異なる。三宝院では、豊臣秀吉が「醍醐の花見」のために造らせた庭園もライトアップする。鑑賞するにはホームページ(http://www.daigoji.or.jp/)での事前予約が原則必要。拝観料は2000円で小学生以下無料。 一方、霊宝館では特別展「醍醐寺の春の祈り」が5月5日まで開催中。秀吉・秀頼父子や前田利家らによる「醍醐花見短籍(たんざく)」(重要文化財)のほか、平安時代から続く法要「清瀧権現桜会(さくらえ)」に関する史料で、国宝の「醍醐寺雑要」「桜会類聚(るいしゅう)」など104点(国宝9点、重文34点を含む)が展示されている。 入館は午前9時~午後4時半。文化財維持寄付金は500円以上(任意)だが、夜間公開時は拝観料のみで入館できる。 4月の第2日曜恒例の「豊太閤花見行列」は、コロナ禍で2020年に続いて中止となった。株式週間展望=正念場も4月需給良好か―TOPIX上昇基調維持、米インフラ投資は増税懸念も個別株照準モーニングスター現在値Fリテイリ 85,650 +750信越化 18,725 +380太平洋セメ 2,948 -24コマツ 3,300 +25竹内製 3,040 +60 株式市場の不安が「金利」から「増税」「新型コロナ再拡大」へと移った今週(22-26日)、日銀のETF(上場投資信託)購入枠組み変更の余波も重なった日経平均株価が一時2万9000円を割り込んだ。ファーストリテイリング が下げを主導する「ユニクロ・ショック」の様相もある一方、全般相場の状況をより正確に映すTOPIX(東証株価指数)は上昇基調を崩していない。来週(3月29日-4月2日)は良好な需給性を持つ4月相場へ向けた正念場だ。 日経平均は今週、23日に2万9000円台が陥落して24日の取引時間中には2万8379円まで値下がり。昨年11月以降下回っていなかった75日移動平均線を瞬間的に割り込むなど、テクニカル的な危機に差し掛かった。2月16日の高値3万714円をその後上回れず、逆に直近安値の3月5日2万8308円に肉薄した。 この間、指数の下落に拍車を掛けたのがファーストリテ。今週の日経平均の23日時点の下落幅(前週比1386円)の2割は同銘柄のウエート。日銀が購入するETF(上場投資信託)をTOPIX型に一本化すると発表したことを受け、日経平均を象徴するファストリテなど値がさ株の一角から資金が離れたことが影響した。 また、米国では増税懸念が株価の上値を重くしたほか、欧州で変異株の感染が急増している新型コロナの状況も不安材料として意識されている。それでも日経平均は直近安値を割り込むことなく週後半に反転した。TOPIXは2月高値を既に奪回し、その後の調整でも25日線付近で切り返す底堅い動きを見せた。 来週の最大の焦点は、バイデン米大統領が31日にペンシルベニア州ピッツバーグで発表する予定のインフラ投資計画だ。 その規模は4兆ドル(437兆円)とも予想され、実現すれば恩恵を受ける日本企業も少なくない一方、巨額投資は増税を連想させる。このため、短期的には全般相場へのマイナスインパクトを意識しつつも、米インフラ関連株を拾いたい。信越化学工業 や太平洋セメント 、コマツ 、竹内製作所 、キトー 、東京製綱 などが該当する。環境ではエヌ・ピー・シー も有力だ。 中期的には4月ならではの需給が期待材料だ。外国人投資家(特に米国投資家)が4月に日本株を買い越す傾向が強い上、年度末へ向けた国内年金などの売りも一巡が見込まれる。トレンドを維持するTOPIXに加え、日経平均も足元の局面を乗り切れば、今度こそ2月高値の奪回が視野に入る。 来週は国内で、転機となった前回(3月18、19日)の日銀金融政策決定会合の「主な意見」が29日に公表される。31日に2月鉱工業生産。海外では30日に米国でCB消費者信頼感指数、4月1日に中国で3月の製造業・非製造業のPMI(購買担当者指数)が出るほか、「OPECプラス」のビデオ会合も。2日には米3月雇用統計。日経平均の予想レンジは2万8500-3万円とする。(市場動向取材班)NY株式:米国株式市場は続伸、経済の強い回復期待が支援フィスコダウ平均は453.40ドル高の33072.88ドル、ナスダックは161.05ポイント高の13138.73で取引を終了した。バイデン大統領がワクチン接種目標を従来の2倍に引き上げたほか、3月ミシガン大学消費者信頼感指数がパンデミック前の水準に戻したため、強い回復期待が広がり寄り付き後、上昇した。長期金利の上昇がハイテク株の上値を抑制する局面もあったが、引けにかけて、主要株式数は上げ幅を拡大。セクター別では半導体・同製造装置、耐久消費財・アパレルが上昇した一方、自動車・自動車部品が下落した。銀行のJPモルガン(JPM)、バンク・オブ・アメリカ(BAC)は、連邦準備制度理事会(FRB)が本年下半期から大手銀による配当、自社株買いの再開を承認する計画を発表したことが好感され、上昇。石油会社のエクソン・モービル(XOM)やシェブロン(CVX)は原油価格の反発を好感し、上昇した。一方で、メディアのバイアコムCBS(VIACA)やディスカバリー(DISCA)は株価が過大評価されているとの見方や、アナリストによる投資判断引き下げが影響し、軒並み下落。イベントやコンサートホールを運営するマディソン・スクエア・ガーデン・エンターテインメント(MSGE)はメディアのMSGネットワーク(MSGN)の買収を発表したが、両社とも株価は下落した。民主党のサンダース上院議員は、オンライン小売アマゾン(AMZN)のアラバマ物流倉庫で働く従業員による労働組合結成の動きを支援するためこの倉庫を訪問。同社株は下落した。(Horiko Capital Management LLC)米雇用統計は大幅改善か 進むワクチン接種「飲食店」復活の兆しTHE PAGE 新型コロナウイルスの世界的大流行(パンデミック)でダメージを受けた経済活動が、ワクチン接種の進む米国で力強い回復ぶりを見せています。中でも特に影響を受けた飲食店の復活ぶりが目につき、4月2日夜(日本時間)に発表される米雇用統計でも大幅な改善が予想されるといいます。第一生命経済研究所・藤代宏一主任エコノミストの解説です。 製造業は目覚ましい回復ぶり 速報性に優れたデータは3月に入った後の米経済が目覚ましい回復基調にあることを示唆しています。製造業の指標ではNY連銀製造業景況指数、フィラデルフィア連銀製造業景況指数がいずれも著しく改善しました。前者はコロナパンデミック発生後の最高水準、後者は1973年3月以来の異常値ともいうべき高水準を記録しました。 自動車を筆頭にスマホやタブレット端末といったITデバイス、家具、家電など耐久消費財の販売好調を受け、メーカーが生産活動を活発化していると思われます。これら2つの指標から判断すると、4月1日公表予定のISM製造業景況指数は非常に強い結果になりそうです。 飲食店の予約が7割強まで戻る そして、ここへ来て特筆すべきは対面型サービス業の復活です。ワクチン接種が進展し、コロナ感染状況が好転する中、飲食店の営業制限が段階的に解除されたことで、急速に息を吹き返しつつあります。レストラン予約サイトのオープンテーブルが提供する日次データに基づくと、3月中旬の予約件数は2019年の同時期対比で7割強の水準まで持ち直しています。ニューヨークやロサンゼルスといった大都市を抱える州は依然として厳しい状況にある一方、テキサスなどでは2019年の水準を超えており、全体としてみればコロナパンデミック発生以降で最も高い水準にあります。 飲食店などの接客業は、需要減少が失業発生に直結し、コロナパンデミックで最も多くの失業を生み出した業種です。パンデミック発生前の2020年1月時点で同業種が全体の雇用者数に占める割合は1割程度で、最悪期にはその約半分の雇用が失われました。2021年2月までに8割ほどの水準に回復したとはいえ、それ以外の業種が96%程度まで戻しているのと比べると苦境が際立ちます。 今度はその逆で、力強い雇用回復が期待されます。というのも、飲食店は労働集約型産業ですから、良くも悪くも経営効率化に限界があるからです。したがって客足が回復すると、店側は直ちに従業員を増やす必要性が生じます。グラフをみる限り3、4月の雇用統計(それぞれ翌月第1金曜日に公表)では飲食店などの接客業の雇用者数が大幅に増加し、全体の失業率が低下することが見込まれます。 雇用の改善自体は良いことだが… そのこと自体は世界経済にとって好感すべき材料です。しかしながら、金融市場目線ではやや複雑です。失業率が大幅に低下するとFRB(米連邦準備制度理事会)の金融緩和が終わりに近づくとの懸念が生じ、長期金利が上昇し、株価が下落するといった事態が想定されるからです。2020年は景気急減速が金融緩和期待を高めたことで株価は上昇しましたが、その反対に2021年は景気回復が金融緩和終了観測につながり、株価下落圧力を生じさせる可能性があります。午後からは、知人宅を訪問して雑務処理…。いつものゴルフ工房を訪問。頼んでおいたドライバー用のシャフトと、5番アイアンに代わる5番ユーティリティーを受け取る。雑談をしながら情報収集。新しいフェアウェイウッドをトライファスのシャフトで制作するか…、トライファスの新しいTFW-55Rで組んだ4Wを借りてくる。帰り道にリカーワタナベさんに寄り道。九平次・別誂の2019ものがアルコールがちょっと効いた酒体の強い味わいでちょっと好みでないことを告げると代わりに楽しんで欲しい候補をいくつか推奨してくれたので3本(宮寒梅EXTRA吟髄・廣戸川純米大吟醸無濾過生・みむろ杉純米大吟醸)をいただく。お使い物に菊姫の吟とノンアルコールシャンパーニュをいただく。帰宅してのおやつタイムは、昨日の「ジークフリーダ」のフルーツタルトとコーヒーを楽しむ。国内女子ツアーのTV放送を観戦。河本Pは原Pと同じくらいに飛ばしていますね。ショットの精度で上回りましたね。河本結がレコードで連覇に王手 稲見萌寧と申ジエが4差追走、渋野日向子は後半失速で32位<アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI 2日目◇27日◇UMKカントリークラブ(宮崎県)◇ 6568ヤード・パー72>国内女子ツアー21年の4戦目「アクサレディス」は2日目の競技が終了。前回大会覇者の河本結が9バーディ・ノーボギー。2013年堀奈津佳の持っていた「64」を上回る「63」のトーナメントコースレコードで、トータル13アンダーまで伸ばし単独首位に浮上。連覇に王手をかけた。4打差の2位タイに今大会が21年初戦の申ジエ(韓国)と今季2勝の稲見萌寧。トータル8アンダーの4位タイに岡山絵里、ペ・ソンウ(韓国)。トータル7アンダーの6位に河本と同組でプレーした原英莉花が続いている。渋野日向子は上がり2ホールの連続ダボが響き、トータル1アンダーの32位タイ。そのほか、今大会が21年初戦のキム・ハヌル(韓国)はトータル1オーバーの48位タイとギリギリで予選通過している。国内株式市場見通し:新年度相場入りで買い気強まる展開期待フィスコ■前半下値模索も後半に踏ん張り今週の日経平均は週半ばまでは下値模索の展開となったが、後半に底堅さも見せた。週明け22日は、大手銀に対する資本規制(補完的レバレッジ比率「SLR」)の緩和措置を延長しないとした米連邦準備制度理事会(FRB)の方針を受けた米株安を背景に日経平均は続落スタート。上場投資信託(ETF)の買い入れ対象から日経平均型を除外するとした先日の日銀の政策方針変更も重しとなって下げ幅を拡げる展開となり600円超の下落となった。23日は、米バイデン政権による最大3兆ドル規模の大型公共投資に関する報道を背景に米国市場は上昇していたものの、将来的な金利上昇が警戒され、アジア市場も大幅下落となるなか3日続落した。24日は、欧州で新型コロナウイルスが収束せず、ドイツがロックダウン(都市封鎖)を延長するなど世界経済の回復に不透明感が広がったことから、原油価格の急落も相まって日経平均は590円安の大幅下落となった。年度末に伴うリバランスの売りが出やすい一方、新規の買いが入りにくいという需給面の要因も重しとなった。ただ、25日は、ドイツがロックダウン強化計画を撤回したほか原油価格も大幅反発したことで市場心理が改善。前日までの4営業日で1800円も下げていただけに自律反発狙いの買いも入りやすく300円以上の上昇に。週末26日も、バイデン大統領がワクチン配給目標を倍増させるとの報道で市場心理が向上し、日経平均は反発、29000円を回復して週を終えた。■金利耐性ついたか来週の日経平均は堅調か。市場の最大の関心事となっていた米国10年物国債利回り(以下、「米長期金利」)について、株式も良い意味で大分反応が鈍ってきた。今週の米長期金利は一貫して落ち着いていた。債券需給の悪化要因として警戒されていたSLRの規制緩和については打ち切りがあったものの、米長期金利は1.7%台から1.6%台へと低下。また、先日1.9兆ドル規模の経済対策が成立したばかりにも関わらず、矢継ぎ早に3兆ドル規模の大型公共投資に関する話が出てきた。しかし、それでも米長期金利はほぼ無反応。その後、金利急騰劇の発端になった米7年債の入札結果が前回に続き低調となったことで若干上昇する動きが見られたが、それでも1.6%台前半に収まった。週末は米株高のなか1.67%まで上昇してきたが、直近高値の1.75%からは低い水準だ。また、良い意味でサプライズだったのがパウエルFRB議長の発言だ。米国時間で25日、「政策目標に向けて大きな進展がみられた場合には資産購入額を徐々に縮小するだろう」と量的緩和の縮小を示唆するような発言があった。むろん、「経済が完全に回復した時に、時間をかけて非常に漸進的かつ高い透明性をもって」という慎重な前置きを付けてのことだが。しかし、それでも先日の米連邦公開市場委員会(FOMC)で2023年末までのゼロ金利政策の据え置きなど緩和策の維持が再表明され市場が安堵したばかりということを考えれば、かなり早いタイミングでのテーパリング(量的緩和縮小)の示唆だったと思える。そうした中でも、当日の米国市場では長期金利は微増にとどまり低位安定。株式については、ワクチン配給目標の倍増を好感して上昇した。市場は、FRBや金利に対する耐性がついてきているようにも見える。こうした中、相場はいよいよ日本では新年度相場入りとなる。来期を見越した新規買いの動きなどが期待される。また、その前に、週前半の3月最終週の初日29日は配当・優待権利付き最終日で権利取りを狙った売買の活発化が予想される。加えて、29日大引けと30日寄り付きにかけてはインデックスファンドの配当金投資に伴う先物買いが発生する見込みで相場を下支えしよう。そのほか、3月第3週(15-19日)の投資主体別売買動向によると、海外投資家は現物を4000億円程買い越してきており、再び日本株買いに勢いが見られる。一方、信託銀行は2000億円超の売り越しを継続するなど機関投資家の期末のリバランス売りなどの様子がみえる。しかし、期末のリバランス売りは3月で終わることに加え、企業の政策保有株の売却なども例年3月末までには一巡してくることが多い。今まで主体だった売り方の存在が薄れる一方で、海外投資家の買い越しが続けば、相場の上昇に繋がる可能性があろう。■メインは景気敏感株、短期でアフターコロナ物色対象としては引き続き景気敏感株やバリュー(割安)株が優位となりそうだ。金利耐性が付いてきたとはいえ、景気回復に伴う今後の再びの長期金利上昇は時間の問題だ。そうしたなかグロース株を積極的に選好するのは難しいと考えられる。ワクチン接種の加速、バイデン政権の公共投資策の追加報道、中国を始めとした相次ぐ各国景気指標の上振れ可能性なども踏まえると景気敏感系が優位となりそうか。そのほか、時短営業を強いられ依然厳しい環境ではあるが、アフターコロナを見据えて飲食やサービスといった未だコロナ前水準を回復できていない銘柄に短期割り切りで挑戦するのも一考か。■中国製造業PMI、米ISM製造業景気指数など来週の主な国内外予定は、30日に2月有効求人倍率、米3月消費者信頼感指数、31日に2月鉱工業生産、中国3月製造業PMI、米3月ADP全米雇用リポート、4月1日に3月日銀短観、中国3月財新製造業PMI、米3月ISM製造業景気指数、2日に米3月雇用統計などが予定されている。パナソニックの"7000億円買収"が市場から厳しく評価される2つの理由プレジデントオンライン編集部 「ブルーヨンダー」の買収報道に社内は沸いているが…パナソニックがサプライチェーン(供給網)の効率化を手掛ける米ソフトウエア大手、ブルーヨンダーを買収する方針を固めたと、3月8日に日経新聞電子版が報じた。投資額は7000億円を軸に調整しているとされ、実現すれば同社にとって過去最大級のM&A(合併・買収)になる。ブルーヨンダーは1985年にJDAソフトウエアとしてカナダで創業した。在庫管理や物流の効率化を手掛け、2018年に人工知能(AI)開発に強い同業の独ブルーヨンダーを買収。20年に現社名に社名変更した。米プロクター・アンド・ギャンブル(P&G)や独DHL、米スターバックスなどが同社の業務改善ソフトを導入している。世界に40以上の拠点を持ち、従業員は5000人超。19年度の売上高は前年度比8%増の約10億ドル(約1085億円)だった。売上高に対するEBITDA(利払い・税引き・償却前利益)比率は24%と、パナソニックより一ケタ大きい。液晶や太陽光パネル事業に次ぎ半導体事業を売却するなど身を縮める発表が相次いだ中での久々の「攻め」の施策と社内では沸く。 「買収額が大きすぎる」と「競合が多すぎる」という2大要因しかし、市場は今回の買収を必ずしも好感しているわけではないようだ。買収協議が報じられた翌日、3月9日のパナソニック株の終値は前日比7%の下落となった。その理由は大きく2つある。ひとつは7000億円という「買収額の大きさ」だ。パナソニックは1兆4713億円(20年3月期)という多額の有利子負債を抱えており、今回の大型買収で財務のさらなる悪化が懸念されている。もうひとつの理由は「競合の多さ」だ。パナソニックの狙いは「企業向けのソリューション・ビジネスの強化」だろう。ブルーヨンダーは人工知能(AI)を活用し製品の需要や納期を予測するソフトを手掛け、顧客企業のサプライチェーンを見直し、収益改善を支援する。かつて米IBMもパソコンやサーバーなどハードウエアの販売がデルコンピュータなどライバルの台頭で消耗戦に陥った時に、ソフト・サービス路線に舵を切った。同時にコンサルティングなども手掛け、顧客企業との継続的な取引を目指す戦略に活路を見いだした。 買収を主導したのは、“異例の出戻り役員”の樋口泰行専務か欧州でも同じ電機大手の独シーメンスが強みだった工場の制御機器を基に、ソフト分野の企業買収を通じサービスを組み合わせて収益力を高めた。日本でも「すでに製造業ではない」(東原敏昭社長兼CEO)と言い放つ日立製作所が、独自のIoT基盤「ルマーダ」を軸に利用で稼ぐ継続課金ビジネスを手掛けている。世界の電機大手は「モノづくり」から「ソフト・サービス」の展開を急いでいる。さらに「企業向け業務改善システム」の分野では、IBMや日立、米アクセンチュアなどコンサルティング企業のほか、最近では米アマゾン・ドット・コムのクラウドサービス部門「AWS」が参入するなど、競合がひしめいている。今回の買収を主導したのは、新卒でパナソニックに入社したあと、アップルやマイクロソフトなどを渡り歩き、2017年に古巣のパナソニックの幹部として呼び戻された樋口泰行専務執行役員とみられている。樋口氏は企業向け取引を担うコネクティッドソリューションズ社を率いる立場にある。 「ソフト」をやり続けたソニーとは時価総額で大差しかし大手証券アナリストからはこんな声があがる。「いまだに売り上げの4割が家電を占めるパナソニックがBtoB(企業向けビジネス)をできるのか。むしろ知見のあるBtoC(個人向けビジネス)を深掘りしたほうが復活を遂げやすいのではないか」こうした見方の背景にあるのがソニーの復活だ。ソニーは今や時価総額ではパナソニックの4倍超となる14兆円と、大きく差をつけている。たが、1990年代にはハード事業に行き詰まり、パナソニックと同じく事業転換に悩んでいた。当時は、韓国・サムスン電子やLG、中国勢が台頭。日本の電機業界はハード主体のモノづくりから、ソフト・サービス路線への転換が模索されていた。1988年、ソニーはCBSレコード(現:ソニー・ミュージックエンタテインメント=SME)を買収。さらに89年にはコロンビア・ピクチャーズ・インダストリーズ(現:ソニー・ピクチャーズ・エンタテインメント=SPE)を買収した。買収後、ソニーはCBSから乗り込んできた米幹部に「食い物」にされた。幹部らはプライベートジェット機や豪邸を買いあさり、ウォルト・ディズニーに対抗して「ソニーランド」の建設案まで持ち込むなど、やりたい放題だった。95年3月期には約3000億円の赤字に転落。狼藉を働いていた米幹部を追い出し、健全な経営状態に戻ったのは90年代後半になってからだ。 「CBS買収」といった夢も社内抗争で潰えてしまったその後、ソニーの「ソフト・サービス」は大きく花開く。2002年には映画『スパイダーマン』が興行収入8億ドルの大ヒットとなり、その後も映画やゲームが立て続けにあたった。それまで同社を牽引していた「ウォークマン」や「トリニトロン・テレビ」などのハード事業も、「ソフト・サービス」事業を補完する位置づけに変わっていった。その象徴がCMOSセンサーだ。ソニーは世界で初めてリチウムイオン電池や有機ELの開発を手掛けるなど世界の先端を走っていた。だが、これらのデバイスがコモディティー化すると、さっさと撤退。ハード事業を「勝てる領域」に絞り込んだ。そこで選んだのが高精細な画像を作成するのに必要なCMOSセンサーだ。いまやiPhoneなどにも用いられ、応用の領域は映像機器やゲームのコンテンツ制作など、ソニーの手掛ける多くの事業にも広がっている。一方、パナソニックも91年に米映画大手のMCAを7800億円で買収。ハリウッドへの進出を試みた。当初、MCAの事業は良好だったが、ソフト化路線を進めた谷井昭雄社長が不祥事で失脚すると、「ソフト・サービス」路線から身を引いてしまう。MCAには英ヴァージン・レコードの買収や、テーマパーク「ユニバーサル・スタジオ」の建設、さらには米3大地上波放送局のCBSの買収案件もあったが、すべて却下してしまった。結局、95年には株式の8割をカナダのシーグラムに売却。メディア企業となる夢は潰えてしまう。 強みだった電池事業は、世界トップの地位を追われたその後、パナソニックはノキアのブラウン管工場の買収やプラズマテレビへの集中投資など、ハード回帰にのめりこみ、失敗を重ねることになる。近年の課題は電池事業だ。電池に強い三洋電機を買収。米テスラとの大型投資を試みるが、国を挙げて電池産業を育成する中国勢に世界トップの地位を追われている。かねてパナソニックは「マネシタ電器」と揶揄(やゆ)されるなど、ヒットした製品が世に出ると、その資本力・販売力を生かしてライバルを駆逐するスタイルをとってきた。その戦略は高度成長期に国内市場が拡大する中では功を奏した。しかし、国内市場が縮小し、世界でも中韓勢が台頭する中で通用しなくなった。新興する中韓勢との競合をさけるために打ち出した「ソフト・サービス」路線も、まだ成果が出ているとはいえない。ブルーヨンダーの買収が現実となり、「ソリューション・ビジネス」に乗り込んだとしても、国内では日立、欧米では米ゼネラル・エレクトリック(GE)や独シーメンスといった競合が控えている。 9年ぶりの社長交代を新展開の機会に変えられるかパナソニックは34ある事業部を再編し、22年に持ち株会社化し、傘下に8つの事業会社を抱える体制に移行する。全社の成長をけん引する基幹事業と位置づける4社は白物家電や住宅設備の「パナソニック」、電池事業の「パナソニックエナジー」、電子・機械部品の「パナソニックインダストリー」、企業向けシステムの「パナソニックコネクト」になる。6月には12年から9年間トップとして業績の立て直しに奔走してきた津賀一宏社長から常務執行役員の楠見雄規氏にバトンを渡す。「マネシタ電器」から脱却し、新たな製品・サービスをどう生み出していくのか。新たなビジネスモデルをどう築くのか。持ち株会社化が「各事業会社の収支を見える化し、採算管理を徹底する」ということにとどまれば、パナソニックの前途は厳しい。市場の低評価をひっくり返すような次の一手が求められている。会食した3家族のクラスター発生、フィリピンパブクラスターの規模拡大 岐阜県内で17人が新型コロナ感染岐阜新聞社 岐阜県と岐阜市は27日、新たに7市で17人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。関市の親族らの飲食に伴う7人規模のクラスター(感染者集団)が新たに確認された。新規感染者が2桁となるのは5日連続。感染者数は累計4796人となった。 新たなクラスターは、関市、各務原市、美濃加茂市に住む3家族が関市で宿泊し、食事などを介して、感染が広がったとみられる。感染者の職場などで数十人規模の検査を予定している。 岐阜市柳ケ瀬地区のフィリピンパブ「ココナッツ」(同市弥生町)のクラスター関連では、同店の従業員が介護職として勤務する各務原市の老人保健施設「サンバレーかかみ野」で職員の同居家族の陽性が判明。22人規模となった。 岐阜市は27日、同店の近くにある飲食店2店舗を対象に外国籍の従業員を含めた予防的検査を実施した。市によると、22人全員が陰性だった。 一方、瑞浪市の東濃厚生病院と土岐市の高井病院で確認されていた感染者34人のクラスターは終息した。 26日時点の病床使用率は13・4%で、前日より1・2ポイント増えた。◆牡羊座 やりたいと思っていることをスタートさせるのにいいときです。この期間に始めたことは、わりと短時間で順調に進んでいきそうです。ただし、そこで「自分は才能がある、このことにむいている」とうぬぼれて、調子にのってしまうのが牡羊座の悪い癖です。やりたいことでお金を稼げるようになるにはまだまだ時間がかかります。もう少し地道な努力を続けていきましょう。 ラッキーアイテム:愛用のペン◆お金持ちの持ち物は、長い目で見ると出費も抑えられる お金持ちは「良いもの」や「資産性の高いもの」を持ちます。 お金持ちの多くは、「良いものを長く使う」という傾向があります。税金対策で車を頻繁に乗り換えるなど例外はありますが、洋服や家具や食器などなど、良いものを少数だけ絞り込んで買い、それを丁寧にメンテナンス・管理しながら長期にわたって使います。 だから買い替えの頻度は多くなく、長い目で見ると出費も抑えられます。もちろん良いものであるがゆえに満足感も高い。 また、資産性が高いというのは、長期にわたって価値が色あせない、目減りするとしてもそのスピードが遅いものを選びます。 お金持ちは本能的に高級住宅地に家を買ったり、一等地にマンションを買ったり、絵画や時計も高級品を選ぶことが多いのですが、リセールバリューも高いために、手放すときや買い替えるときに負担が少なくなります。 もちろん何でもかんでも高級品を買うわけではなく、高級なものに興味がないというお金持ちも少なくありません。見栄をはる必要がありませんから、ただのフツーの人にしか見えない人もいます。とはいえ、最寄駅からバス便のマンションや郊外の激安戸建てを買うことはまずありません。
2021.03.27
コメント(0)
-

3月26日(金)…
3月26日(金)、晴れです。良い天気です。朝の外気温は10度程度。そんな本日は7時15分頃に起床。新聞に目を通し、朝食を済ませ、ロマネちゃんと戯れる。朝食はインスタ映えを意識した…レインボーパンのフルーツサンドです。身支度をして、出かける前に、車にゴミ袋14ケを積んでゴミ集積所を往復。8時45分頃に家を出る。ゴルフではありません、本日もアルバイト業務です。本日は10:00~16:00です。移動の合間に「緑の館」でロイヤルブレンドとトーストを楽しむ。仕事の帰り道には「ジークフリーダ」でバースデイケーキを受け取る。帰宅して、コーヒーと「アンリ・シャルパンティエ」の焼き菓子で遅いおやつタイム。それではしばらく休憩です。1USドル=109.47円。1AUドル=83.40円。昨夜のNYダウ終値=32619.48(+199.42)ドル。本日の日経平均終値=29176.70(+446.82)円。金相場:1g=6717(-9)円。プラチナ相場:1g=4538(-47)円。昨夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄についてはチェックできませんでした…。ただ終値を見ると僕の購入希望価格には達していませんでした…。本日の東京市場ではチェック中の日本株30銘柄中の28銘柄が値を上げて終了しましたね。重点3銘柄ではすべてが値を上げて終了しましたね。5%以上の大きな変動は見られませんね。新型コロナワクチン大量廃棄の現状 医療従事者は接種に不安の声も 都内有名医大病院に設けられた接種会場。そこで、3月中旬に新型コロナウイルスのワクチンを接種した看護師Aさん(30代女性)が当日の様子を明かす。 「翌日に発熱する可能性があるという理由で、接種はオフの日の前日。私は夜勤明けのお昼頃に接種しました。1時間で30人ほどが順番に打ちましたね。私がワクチンを打ったのは利き手ではない左腕。6時間後に筋肉痛のような痛みが現れ、翌日は腕がまったく上がらないほどでした。ただ、ほかの副反応が出なかったのでホッとしました」 コロナ禍を終息させるためのカギとなるワクチン接種。日本では現在、約480万人の医療従事者に対して米ファイザー製ワクチンの先行接種が進むが、現場にはある困惑があるという。都内大学病院勤務の看護師Bさん(20代女性)が話す。 「今回接種している『mRNAワクチン』は人類初のワクチンなので、医療従事者の中でも不安がある。接種は任意だけど、うちの病院では上司から『怖いのが理由で接種を拒否することは許されない』と遠回しに言われていて、事実上の強制です。 ワクチンが怖いのは異変がすぐに起こるとは限らない点です。数年後に障害が出たら誰が責任を取ってくれるのでしょうか……。接種に不安が残ることやコロナ禍の過酷な勤務に疲れ果てたこともあり、私は病院を辞めることにしました。他院では接種反対の署名運動をしようという動きがあるそうです」 実際、三重県の病院が院長名で「接種を受けた職員は評価の対象とする」というメールを全職員に送り、数日後に撤回したと報じられた。 混乱を極める中、現場では別の困惑の声が上がっている。都内大学病院に勤務する医師が打ち明ける。 「供給量が限られているのに、余ったワクチンを相当数、廃棄しているのが現状です。インフルエンザワクチンなら、次の瓶と合わせて打つこともできるのに、もったいない」 ファイザー製のワクチンは1バイアル(瓶)で6回の接種を前提とする。しかし、日本にはこれに対応できる注射器の調達が間に合っておらず、1瓶で5回しか接種できない。その余った分が、廃棄されているのだ。 「当初、余ったワクチンを集めて1人分にするという話を他院の医師から聞きましたが、衛生上の問題があり、その計画はなくなったそうです。コロナワクチンは瓶を解凍して、希釈すると6時間以内に使わなければならないんです。 たしかに瓶にはあと1回分が取れそうなほど薬液が残ります。なので、もう1回分取った方がいいのではと考えてしまいますが、現場では打つ回数に神経を使うより、安全に接種することを考えています。政府が、初めから6回打ちの注射器を準備していれば、こんな問題も起きなかったんですが……」 そんな中、京都の宇治徳洲会病院が3月8日、インスリン用注射器があれば7回接種できると発表した。しかし、河野太郎規制改革相は「糖尿病患者のための注射器である」と否定的だ。医療ガバナンス研究所理事長の上昌広さんが解説する。 「基本的にワクチンは1割程度多めに作られており、規定の人数以上にワクチンを打つことは可能です。国は推奨していませんが、現場の判断で接種することに問題はない」 別の理由でワクチンを大量廃棄した事実も明らかになった。2月26日深夜、ワクチンを保管する冷凍庫の故障により1000回分以上のワクチンが無駄になるハプニングが、先行接種を実施している医療機関で起きたのだ。 「コンセントに複数の機器を接続し、冷凍庫に充分な電力が供給されなかったのが原因でした。そんな初歩的なミスが起きるなんて、と思いますが、すべて初めてのこと。現場はそれほどバタバタしています」(別の都内大学病院に勤務する医師) 医療の最前線で働く医療従事者たちが、休まる日は来るのだろうか。日本株は続伸、新型コロナワクチン期待や為替の円安-東証全業種上昇 26日の東京株式相場は続伸。新型コロナウイルスのワクチン接種が加速することによる景気回復への期待や為替の円安傾向を好感し、電機や自動車など輸出関連、銀行、医薬品株などを中心に東証33業種全てが上昇した。 TOPIXの終値は前日比28.61ポイント(1.5%)高の1984.16 日経平均株価は446円82銭(1.6%)高の2万9176円70銭 〈きょうのポイント〉 バイデン米大統領、就任後100日のワクチン接種目標を2億回に倍増 米新規失業保険申請、予想以上に減少-パンデミック以降で最少 米連邦準備制度理事会(FRB)、大半の銀行で増配と自社株買いの制限を6月末に終了 ドル・円相場は一時1ドル=109円30銭台、東京株市場の前日終了時点108円94銭 丸三証券の柏原延行執行役員は「バイデン政権の追加経済対策で、米国の個人消費が今後良くなることは間違いない。同時にワクチン対策をしっかりと行うことも、景気への信頼感につながり株価にプラス」と語る。また、為替は1ドル=110円の大台に接近しつつあるとして、「コロナ禍で内需セクターは痛みを伴っている。円安は輸出に頼る日本経済をサポートする」とも評価した。 ワクチン期待と雇用改善から米国で金融や資本財、素材を買う流れが継続したことを受け、国内でも景気敏感業種への買いが先行。円安基調の中で輸送用機器セクターなどが幅広く買われた。アジア時間の米ナスダック100Eミニ先物が堅調に推移したことも追い風となり、午後にはレーザーテックなどグロース(成長)株にも見直し買いが強まった。 みずほ証券の倉持靖彦マーケットストラテジストは「米経済全体が良くなる中でバリュー株には引き続きフォローの風が吹いている」と指摘。ただ「現在は景気拡大局面のまだ序盤。序盤から中盤にかけてはグロース株、バリュー株の双方が循環物色しながら底上げしていくのが通常」だとみていた。 東証33業種では海運や精密機器、陸運、ゴム製品、サービス、医薬品、輸送用機器が上昇率上位【米国株動向】アマゾンが今年アンダーパフォームすると予想する3つの理由とはモトリーフール米国本社、2021年3月15日投稿記事より年初の2カ月半で、ナスダック総合指数は3%を超える上昇、S&P500指数は5%上昇しましたが、eコマース大手のアマゾン・ドット・コム(NASDAQ:AMZN)の株価は約5%下落しました。アマゾンは筆者のポートフォリオの中で保有比率が最大の銘柄であり、先月もポジションを積み増しました。アマゾンに強気の見通しをしていますが、一方で同銘柄が今年市場をアンダーパフォームすると考える理由も多く存在します。 新型コロナ特需の終焉コロナ禍で消費者のオンラインショッピングへのシフトから最も恩恵を受けた企業の1つがアマゾンです。米国勢調査局の発表によれば、米国のeコマース市場全体の売上は直近3四半期で36%超増加しました。eMarketerの予測では通年で約32%の増加、世界全体で見ても28%の増加です。しかし、今後実店舗が営業を再開していけば、消費者が買い物を一部オンラインから従来の対面の店にシフトすることが考えらえます。eMarketerは世界のeコマース売上成長率は今年、14%に鈍化すると見ています。アナリスト予想では、米国単体では6%まで減速が見込まれます。売上成長の鈍化に投資家は敏感に反応します。売上が市場予測を下回るようなことがあれば、株価は簡単に下落に転じます。 ロジスティクス事業への多額の設備投資2021年はアマゾンのロジスティクス事業にとって変革の年となるでしょう。同社は年内にシンシナティ/ノーザンケンタッキー国際空港内に、一日当たり200フライトをこなすことが可能なエアハブのオペレーションを開始する予定です。さらに、ロジスティクス事業の拡大をはかるため航空機の追加保有の契約を進めています。今年、既に11機を購入しています。また、貨物機をリースしているエア・トランスポート・サービス・グループの新株予約権を行使し、同社の株主となっています。他の貨物機企業とも同様の権利行使を行う可能性があります。今年は自社のロジスティクス網の拡大に多額の投資を行い、来年以降も投資を継続する見込みです。最高財務責任者のブライアン・オルサフスキ氏は、第3四半期の業績コンファレンスコールの際に投資家に設備投資の増大を予告しており、「特に輸送分野に重点をおく」と説明しています。アマゾンはこれまで配送やロジスティクス能力の増強への投資に成功してきました。ロジスティクス網の所有およびコントロールまで踏み込んだ事業の拡大は、小売り事業にとって配送の効率性向上という点でさらに大きな機会創出につながります。しかし投資の増加は短期的には利益やキャッシュフローの足かせになるでしょう。株価が高値のアマゾン株を保有する投資家には懸念材料です。 規制強化のリスク三つ目は全ての巨大ハイテク企業に共通するものですが、企業に対して大幅な経営方針の転換や分割を余儀なくさせる政府の規制強化です。アマゾンは小規模の外部出店者の商品を扱うサービスや広告事業に力を入れてますが、自社の小売りサービスや商品に不利な競争を排除するような環境を作り出していないか、益々厳しい監視の目にさらされています。しかし当のアマゾンの関心の先は、外部出店者事業、広告プラットフォーム、その他サービスの魅力を最大化することにあります。これは、同社の中核である小売り事業より利鞘が大きく、売上成長の可能性も高いからに他なりません。新たな規制の可能性は短期的にはアマゾンの株価に打撃となり得ますが、事業や利益へのマイナス影響は最小限に留まるはずです。 長期的な成長は続くアマゾンの株価が引き続き市場をアンダーパフォームするようなら、新たな買いの機会と捉えるべきです。最近の株価軟調で投資対象としての魅力は増していますが、今年後半、さらに買いの機会が到来する可能性も十分あります。【本日のNYダウ見通し】個人消費支出とミシガン大学消費者信頼感指数に注目【NYダウ予想レンジ:32,400~32,800ドル】25日のNYダウは3日ぶりに反発。前日比199.42ドル高の32,619.48ドルで取引を終了しました。朝方はパウエルFRB議長のインタビューで、年後半に量的緩和の縮小が検討されるとの思惑が強まり、300ドルほど下げる場面もありました。しかし、新規失業保険申請件数が684,000件と前週から減少したことや、バイデン大統領が就任後初の記者会見で就任100日後までに新型コロナワクチンの2億回の接種を目指すと表明したことから、景気敏感株中心に買いが入り、NYダウはプラス圏で引けたのです。また、IT・ハイテク株にも買いが入り、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数も、前日比15.79ポイント高の12,977.680で取引を終了しています。本日の経済指標では、個人消費支出とミシガン大学消費者信頼感指数に注目。とくに前回の個人消費支出は、前月比2.4%増と7カ月ぶりの大きな伸びとなりました。今回の市場予想は前月比0.7%増ですが、この予想を上回るかどうかに関心が集まりそうです。日経平均は続伸、446円高 米株高好感で買い戻し活発化[東京 26日 ロイター] - 東京株式市場で日経平均は続伸した。25日の米国株式市場で景気回復への楽観的な見方から主要3指数が上昇した流れを引き継いだほか、年度末の最終売買日を控え、配当権利取りの動きが活発化。24日までの4日営業日で日経平均が1800円以上下落した反動も継続し、幅広い業種で買い優勢となった。時間外取引での米株先物やアジア株が上げ幅を拡大する動きも支えとなり、日経平均は一日を通して底堅い動きをみせた。TOPIXも続伸し1.46%高。東証1部の売買代金は2兆8093億2900万円。東証33業種では、全業種が値上がり。海運業、精密機器、陸運業、ゴム製品、サービス業、医薬品などが上位を占めた。フィリップ証券のリサーチ部長、笹木和弘氏は「年度・四半期末は機関投資家によるリバランスで日米市場ともに株が売られやすい時期だが、きょうは最終売買日を月曜日に控えた配当権利取りで日本株は底堅く推移した。日銀が前週末に上場投資信託(ETF)の買い入れ対象をTOPIX連動型のみと決定したことなどを受け、日経平均への指数寄与度が高い銘柄はこのところ軟調な動きをみせていたが、きょうは買い戻す動きがみられる」との見方を示した。個別では、東京エレクトロン、アドバンテスト、信越化学工業などの半導体関連株がしっかり。アドバンテストは4.65%高となった。そのほか、IHI、川崎重工業、三菱重工業などの重工株も大幅高。出遅れ株の業績改善に対する期待が高まり、IHIは5.13%高となった。任天堂は4.16%高、HOYAは3.11%高。市場では「日銀の政策決定会合以降、日経平均に採用されてなく、かつTOPIXウエートが高い銘柄が底堅い動きをみせている」(国内証券)との声が聞かれた。東証1部の騰落数は、値上がり1781銘柄に対し、値下がりが350銘柄、変わらずが62銘柄だった。新年度も底堅い、NT倍率の動向に注目=来週の東京株式市場[東京 26日 ロイター] - 来週の東京株式市場は底堅い展開となる見通しだ。新型コロナウイルスのワクチン普及などで世界的に景気回復期待が高まっており、新年度相場でも買いが優勢になるとみられている。注目はNT倍率で、日銀の上場投資信託(ETF)の購入を4月1日からTOPIX連動型のみにすることで、低下する可能性がある。日経平均の予想レンジは2万9000円―3万円。26日の日経平均は446円高で取引を終了した。24日までの4営業日で1800円を超す下落となったこともあり、市場では「自律反発の範囲内」(国内証券)との見方もあるが、需給的には好材料が多くなるとみられている。29日に年度末の最終売買日を控え、配当権利取りが活発化しやすい。また市場筋によると7500億円から8000億円の配当再投資が発生する可能性があるという。一方、日銀は上場投資信託(ETF)の購入を4月1日からTOPIX連動型のみに変更すると発表。これを受け日経平均への指数寄与度の高い銘柄は売られる展開となり、日経平均をTOPIXで割ったNT倍率は下落基調をたどっている。直近の最高値の15.68倍(2日)から14.62倍(22日)まで大幅に低下した。物色面ではこのところ変化がみられており、米長期金利の上昇に伴い、ハイテク株やグロース株をはじめとする日経平均の値がさ株が売られた。こうした傾向が続くのかも注目点だ。来週の主なスケジュールは、国内で2月鉱工業生産、3月の全国企業短期経済観測調査(日銀短観)、中国で3月製造業・非製造PMI、米国でISM製造業景況指数、3月雇用統計などの経済指標の発表を控えている。30日にはAppier Group、スパイダープラスがそれぞれマザーズ市場に新規上場する。2日は聖金曜日に伴い、米国、欧州、アジア主要などの市場が休場となる。銀行株がしっかり、米国ワクチン接種の加速で金利上昇三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306)など銀行株がしっかり。12時30分時点では前日比11円(1.7%)高の630.5円付近で推移。みずほフィナンシャルグループ(8411)も34円(2.0%)高の1684円と買いが先行している。特段、個別材料は確認されていないが、前日にアメリカのバイデン大統領がワクチン接種の加速を表明しており、経済活動の回復期待からアメリカ10年債利回りは1.640%付近まで上昇。株式市場ではバンクオブアメリカやJPモルガンチェースなどが買われ、きょうの日本市場もこの流れを引き継いでいるようだ。バイデン氏は就任から100日が経過する4月末までにアメリカ国内で1億回のワクチン接種目標を掲げていたが、これを2億回に引き上げると表明した。(取材協力:株式会社ストックボイス)百貨店Jフロントリテ続伸、今期下方修正は織り込み済みか百貨店の大丸や松坂屋、パルコを運営するJ.フロント リテイリング(3086)が続伸。前引けは前日比20円(1.8%)高の1102円だった。前日に現在集計中の前2021年2月期連結業績の下方修正を発表したが、株式市場ではすでに織り込まれていたとみられ、今日はむしろアク抜け感が強いようだ。売上高は従来予想の3375億円から3190億円(前期比34%減)に修正。営業損益は206億円の赤字から242億円の赤字(前期は402億8600万円の黒字)と、赤字幅が拡大する。最終損益も186億円の赤字から260億円の赤字(前期は212億5100万円の黒字)に修正した。緊急事態宣言の影響で客数や売上高、店舗賃貸収入が大きく減少したという。(取材協力:株式会社ストックボイス)JCRファーマが4日続伸、今3月期予想の上方修正を好感JCRファーマ(4552)が買い優勢で4日続伸。午前10時6分現在で前日比85円(2.5%)高の3465円で売買されている。当社はヒト成長ホルモン製剤が主力の製薬会社だが、25日の引け後に今2021年3月期の連結業績予想の上方修正を発表しており、好感買いが流入している。売上高は従来の272億円から300億円(前期比21.1%増)、当期純利益も48億円から71億円(同2.7倍)にそれぞれ増額した。契約金収入が当初の予想から21億8000万円ほど増える見込みになったのが主因。契約金の内容は明らかにしていないが、当社は英アストラゼネカから新型コロナウイルスワクチンの原液製造を受託しており、それが伝えられた1月下旬に株価が急騰した経緯がある。(取材協力:株式会社ストックボイス)25日のアメリカ株式相場が反発したワケ、上昇銘柄は?欧州株はほぼ変わらずブルームバーグ欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。 ◎米国市況:株反発、ボーイングなど輸送株高い-原油は反落25日の米株式相場は反発。米国で新型コロナウイルスワクチンの配布が進展する中、経済成長やインフレの見通しを見極めようとする動きとなった。S&P500種株価指数の構成銘柄では、銀行株や輸送関連株の上昇が目立った。ボーイングは787ドリームライナーの納入が近く再開する見通しとなったことも好感された。バイデン大統領が就任後100日間で2億回のワクチン接種を実施するという新たな目標を明らかにし、小型株で構成する指数は2%余り上昇。一方、ナイキは中国で不買運動の標的となるリスクが懸念されて売られた。S&P500種は前日比0.5%高の3909.52。ダウ工業株30種平均は199.42ドル(0.6%)高の32619.48ドル。ナスダック総合指数は0.1%上昇。バーデンス・キャピタル・アドバイザーズのポートフォリオ戦略担当ディレクター、メーガン・ホーネマン氏は、「株式市場は金利動向から多少の方向性を得る踊り場的な相場にとどまっている」と指摘。「今は、次の相場動因になる世界的材料がさらに出てくるのを待っている段階だ」と分析した。米国債市場では年限長めの国債が値下がり。ニューヨーク時間午後4時59分現在、10年債利回りは2ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の1.63%。米財務省が実施した7年債入札(規模620億ドル、約6兆7700億円)では最高落札利回りが1.3%と、入札前取引(WI)の応札締め切り時点の水準1.275%を上回った。それでも、先月の7年債入札ほど不調な結果にはならなかった。外国為替市場ではユーロが下落。欧州のワクチン接種プログラムの難航が経済成長を妨げるとの見方が広がり、対ドルで11月以来の安値となった。主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.1%上昇。ドルは対円で0.4%高の1ドル=109円19銭。200日移動平均の108円99銭を上回った。ユーロは対ドルで0.4%安の1ユーロ=1.1764ドル。ニューヨーク原油先物相場は反落。スエズ運河を巡る混乱で原油タンカーが足止めされている影響が意識されたものの、ドルの上昇に加え、欧州でロックダウン(都市封鎖)措置が強化されていることが売りを誘った。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物5月限は前日比2.62ドル(4.3%)安い1バレル=58.56ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント5月限は2.46ドル安の61.95ドル。ニューヨーク金市場ではスポットと先物が反落。米7年債入札を受けて利回りが上昇したことを嫌気し、売りが優勢になった。金スポット価格は一時、前日比0.7%安い1オンス=1721.91ドルとなった。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物6月限は8.2ドル(0.5%)下げて1727.30ドルで終了した。 ◎欧州市況:株ほぼ変わらず、景気回復ペースを疑問視-ドイツ債上昇25日の欧州株はほぼ変わらず。新型コロナウイルスの感染拡大抑制や景気回復ペースが依然疑問視された。ストックス欧州600指数は0.1%未満の下げ。1%安まで下落した場面もあった。パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長が、顕著な進展が見られた場合に当局は緩和策を漸進的に縮小していくと示唆すると、同指数は一時大きく下げた。エネルギー株は大幅安。原油安に連れた。トレーダーは、コンテナ船座礁で通行が遮断されているスエズ運河の再開に向けた作業を注視している。この日は自動車株が買いを集め、下げを相殺した。ドゥナス・カピタルのアルフォンソ・ベニト最高投資責任者(CIO)は、「新型コロナを巡る状況は複雑化しつつあり、一部の相場では年初に過度の上昇もあった。ある程度リスクオフの地合いが見られるのは正常だ」と指摘した。欧州債はドイツ債が5日続伸。昨年10月以降で最長の連騰となった。利回り曲線はフラット化した。英国債は総じて堅調。同国は4月7日まで入札を予定していない。イタリア債はほぼ変わらず。【市況】来週の株式相場に向けて=年度末・新年度入りで基調転換なるか 来週は年度末と新年度相場を迎える。21年3月期はコロナ禍に襲われるという特殊な1年となったが、株式相場は日経平均株価が前年度末比で5割近く上昇する、極めて良好なパフォーマンスを記録することになりそうだ。 来週は年度越えとなることもあり、重要イベントが目白押しだ。まず、29日は権利付き最終日で、30日が権利落ちとなる。今年の年度末の配当権利落ちの影響は180円弱とも推測されている。この権利落ちに絡み、29日大引けや30日寄り付きにかけては、インデックスファンドなどによる配当再投資の買いが流入することが予想されている。その規模は1兆円規模に膨らむとの見方もあり、需給の好転が期待されている。 また、4月1日からは名実ともに新年度入りする。新年度入りとともにニューマネーがどう動くかが注目される。今週は日経平均が大幅安となるなか、一時2万8300円台まで下落する場面があった。ただ、「典型的な彼岸底を形成するのでは」との観測も少なくない。市場関係者からは「2万9500円を抜くことができるかが、最大の焦点」とみる声が出ている。 来週は海外では31日に中国3月製造業PMIと米3月ADP雇用統計、翌4月1日に米3月ISM製造業景況指数、そして2日に米3月雇用統計が公表される。国内では30日に2月失業率・有効求人倍率、31日に2月鉱工業生産が発表され、翌1日には3月日銀短観が予定されている。 また、30日にはスパイダープラスとAppier Groupが東証マザーズに新規上場する。特に、Appier Groupは台湾系のAIベンチャー。時価総額は1600億円近い大型上場となるが市場の関心は高く、その株価動向が注目されている。来週の日経平均の予想レンジは2万8700~2万9600円。(岡里英幸)出所:MINKABU PRESS松山英樹は連敗でグループステージ敗退 ローリー・マキロイが今大会初勝利<WGC-デル・テクノロジーズ・マッチプレー 2日目◇24日◇オースティンCC(米テキサス州)◇7108ヤード・パー71>世界ゴルフ選手権シリーズの「WGC-デル・テクノロジーズ・マッチプレー」は2日目の競技が終了。松山英樹はブライアン・ハーマン(米国)に敗れ、グループステージ敗退が確定した。序盤にリードを許したものの6番で獲り返しタイに戻した松山だったが、11番パー3のティショットを池に入れて再びリードを許すと最終ホールまでもつれるも逆転ならず。この日同グループのパトリック・キャントレー(米国)が2勝としたため、決勝トーナメント進出の可能性を失った。世界ランキング1位のダスティン・ジョンソン(米国)はロバート・マッキンタイア(スコットランド)と引き分け。ローリー・マキロイ(北アイルランド)がラント・グリフィン(米国)を下して今大会初勝利。そのほか、ジョン・ラーム(スペイン)をはじめ、セルヒオ・ガルシア(スペイン)、ケビン・キスナー、マット・クーチャー(ともに米国)、マッケンジー・ヒューズ(カナダ)、ディラン・フリッテリ(南アフリカ)、エイブラハム・アンサー(メキシコ)が2勝目を挙げている。スティーブン・ジェイガーが単独首位発進! 小平智は112位タイと出遅れ<コラレス・プンタカナ リゾート&クラブ選手権 初日◇25日◇コラレスGC(ドミニカ共和国)◇7670ヤード・パー72>世界ゴルフ選手権シリーズの「WGC-デル・テクノロジーズ・マッチプレー」の裏ではドミニカ共和国にあるコラレスGCで「コラレス・プンタカナ リゾート&クラブ選手権」が開幕。日本勢唯一の出場となる小平智は4オーバーの112位タイと出遅れた。6アンダー・単独首位に立ったのはスティーブン・ジェイガー(ドイツ)。1打差の2位タイにはジョエル・ダーメン、アンドリュー・ユン(いずれも米国)が続いている。米公式サイトで優勝候補筆頭に挙げられたチャーリー・ホフマン(米国)は3アンダー・10位タイと上々の立ち上がり。昨年覇者のハドソン・スワフォード(米国)も2アンダー・19位タイにつけている。今季2勝の稲見萌寧が単独首位発進 河本結8位、渋野日向子14位<アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI 初日◇26日◇UMKカントリークラブ(宮崎県)◇ 6568ヤード・パー72>2021年国内女子ツアー4戦目は第1ラウンドが終了した。今季2勝目を挙げている稲見萌寧が7バーディ・ノーボギーの「65」をマーク。7アンダー・単独首位発進を決めた。5アンダー・2位タイに渡邉彩香、葭葉ルミ、宮田成華、穴井詩、酒井美紀、テレサ・ルー(台湾)。4アンダー・8位タイには前回大会覇者の河本結、原英莉花ら6人が続いた。渋野日向子は「69」をマークし、3アンダー・14位タイ発進。2週連続優勝がかかる小祝さくら、香妻琴乃、鈴木愛らも同順位で初日を終えた。医師20人にリベート4億3千万円 米系企業に厳重警告朝日新聞 世界的な米系医療機器メーカー「グローバスメディカル」の日本法人(東京)が機器を購入した病院の医師側にリベートを提供していた問題で、業界団体でつくる医療機器業公正取引協議会(公取協)は24日、医師20人に5年間で約4億3千万円を支払っていたとして、同法人を厳重警告の処分とした。患者のための機器選択を、医師への資金提供によってゆがめようとしたと判断した。 この問題は、朝日新聞が昨年11月、関東や関西、九州の大規模な民間病院の約20人の医師側に、2019年の1年間で総額1億円超のリベート提供があったと報じて発覚。報道を受けて公取協が調査していた。その結果、景品表示法に基づく公正競争規約に違反すると認定し、最も重い処分とした。 公取協によると、リベートの提供先は20社。この20社は医師や親族が役員となっていたが、公取協はいずれも医師本人への提供だと判断した。また、同法人が不当な資金提供があったとしてコンプライアンス上問題だと判断した取引先が21社あった。これら計41社への不当な資金提供は5年間で約10億円にのぼる。同法人は41社との契約を解除したか、今後解除する方針だという。明日の戦略-連日の大幅高で下値不安が和らぐ、来週は戻り基調が継続かトレーダーズ・ウェブ 26日の日経平均は大幅続伸。終値は446円高の29176円。米国株高を追い風に寄り付きから300円を超える上昇となり、29000円台を回復。上げ幅を500円超に広げたところでいったん萎んだが、29000円を下回ったところで盛り返すと、再び上げ幅を広げた。前場を435円高(29164円)で終えると、後場はこの近辺で値動きが落ち着き、引けまで静かな動きが続いた。良好な地合いが維持される中、前場から強い動きを見せていたマザーズ指数が後場に入って一段高。引けでは3%高と大きく上昇した。 東証1部の売買代金は概算で2兆8000億円。業種別では全業種が上昇しており、中でも海運や精密機器、陸運が強い動きとなった。一方、水産・農林や繊維、ガラス・土石の上昇が限定的となった。上方修正と増配を発表したアクセルが急騰。半面、今期の大幅営業赤字見通しや、ホテル建て替えに絡む巨額投資計画を発表した帝国ホテルが大幅安となった。 東証1部の騰落銘柄数は値上がり1781/値下がり350。任天堂が3%を超える大幅上昇。ドル円が109円台に乗せてきたことから、トヨタや日産自、マツダなど自動車株の動きが良かった。アドバンテストやレーザーテックなど、半導体の一角にも強い動きが見られた。新興銘柄にも資金が向かう中、フリーやBASEが急伸。きのう初値をつけた後の動きがさえなかったシキノハイテックとベビーカレンダーは、きょうは大賑わいとなりストップ高まで買われた。ほか、証券会社のリポートを手掛かりに、Speeeが一時ストップ高となるなど急騰した。 一方、キーエンスが逆行安。ワークマンやしまむら、神戸物産など、小売株は売られるものが多かった。良品計画がウイグル問題を取り上げた記事を手掛かりに大幅安。MBOが不成立となったサカイオーベックスが値を崩した。きのう初値をつけたジーネクストは、同日に初値をつけた2社が急騰する中、9%を超える下落。前日にストップ高まで買われたハイパーが一転急落した。 IPOでは2社が新規上場したが、イー・ロジット、ブロードマインドとも高い初値をつけた後は軟調な展開。ともに終値は初値を大きく下回った。 日経平均は連日の大幅上昇。戻したところでの売り圧力も限られており、終値で29000円を上回った。日足では75日線までで下げ渋って5日線上を回復。週足では13週線を割り込んだところで長い下ヒゲをつけた。不安定ではあったが、しっかり週内で反転攻勢の足掛かりは作ったと言える。週間ベースでは、日経平均の2.1%安に対して、TOPIXが1.4%安。TOPIX(終値1984.16p)は直近高値(2013.71p、3/19)が射程圏内にあり、早々にこれを上回ることができるかが焦点となる。業種別では、空運(-9.0%)、銀行(-3.5%)、輸送用機器(-3.2%)など、直近で注目を集める場面が多かったところが大きく売られた。これらが難なく反発してくるのか、それとも上昇一服感が出てくるのかを注視しておきたい。【来週の見通し】 堅調か。直近の急落に対する戻りを試す流れが続くと予想する。今週の日経平均は大きく下落したが、ファンダメンタルズが悪化したわけではなく、日銀の影響が大きかった。3月は配当が多い分、権利落ち後は見た目の水準が切り下がるが、今週、週後半に強い上昇が見られたこともあり、3万円より下では投資家の買い意欲が強い状態が続くと考える。4月相場に入り新年度が始まることから、ニューマネー流入への期待も高まる。ただし、週末には米国の3月雇用統計が控えており、それ以外にも国内外で経済指標の発表が多い。指標の結果や米国の長期金利の動向には、引き続き注意を払っておく必要があるだろう。【今週を振り返る】 荒い値動きとなった。先週、日銀が発表したETFの買い入れルール変更の余波が続き、日経平均の寄与度が大きいファーストリテイリングやソフトバンクG、値がさ株などを敬遠する動きが強まった。これが株安加速への警戒を強め、週半ばまでは売りが売りを呼ぶ展開。日経平均は19日から24日の4営業日で1800円以上下落し、28300円台まで水準を切り下げた。一方、米国の長期金利の変動に対しては、米国株が神経質な反応を示す場面が少なくなるなど、グローバル市場は落ち着きを取り戻し始めた。これを支えに25日、26日には大きく上昇。29000円台を回復して週を終えた。日経平均は週間では約615円下落し、週足では2週連続で陰線を形成した。【来週の予定】 国内では、日銀金融政策決定会合の主な意見(3/18~19開催分)、配当・優待権利付き最終日(3/29)、2月失業率、2月有効求人倍率、2月商業動態統計(3/30)、2月鉱工業生産、2月住宅着工統計(3/31)、3月日銀短観、3月新車販売台数(4/1)などがある。 企業決算では、アークランド、大光、NaITO(3/29)、西松屋チェ、ストライク、サムティ、ハニーズHLD、マルマエ、日創プロ、アルテック、岡山製紙、ERI HD、ヤマシタヘルケア、ハピネス&D、パレモ・HD(3/30)、ニトリHD、トシンG、フィードフォー、TAKARA&C、スターマイカHD、日本エンタ、日プロセス、テクノアルファ(3/31)、象印、セキチュー、地域新聞(4/1)、平和堂、不二越、大有機、エスプール、キユソー流通、カネコ種、霞ヶ関キャ、東海ソフト、エクスモーション、岡野バル、クラウディアH、KTK(4/2)などが発表を予定している。 海外では、米1月S&Pコアロジック・ケース・シラー住宅価格指数、米3月消費者信頼感指数(3/30)、中国3月製造業PMI、米3月ADP全米雇用リポート、米2月NAR仮契約住宅販売指数(3/31)、中国3月財新製造業PMI、米3月ISM製造業景気指数(4/1)、米3月雇用統計(4/2)などがある。 なお、4/2の米国市場は聖金曜日のため休場となる。来週の日本株の読み筋=米増税懸念も需給改善傾向の4月相場に期待かモーニングスター 来週(3月29日-4月2日)の東京株式市場は、米インフラ投資による増税懸念がくすぶるが、需給改善傾向の4月相場に期待をつなぐところか。 来週の最大の焦点は、バイデン米大統領が31日に発表する予定のインフラ投資計画。その規模は4兆ドル(437兆円)とも予想され、実現すれば恩恵を受ける日本企業は少なくないが、巨額投資は増税を連想させる。このため、短期的には全相場へのマイナスインパクトが意識され、調整につながる可能性もある。 一方、4月特有の需給関係は期待材料になる。外国人投資家、特に米国投資家は日本株を買い越す傾向が強く、需給面でのフォロー役として注目される。また、年度末に向けた国内年金などの売りも一巡するとみられる。 スケジュール面では、国内で29日に3月18、19日開催の日銀金融政策決定会合の「主な意見」、30日に2月失業率・有効求人倍率、4月1日に3月調査日銀短観などが発表される。海外では30日に米3月CB消費者信頼感指数、31日に中国3月製造業PMI、中国3月非製造業PMI、中国3月コンポジットPMI、米3月ADP雇用統計、4月1日に中国3月Caixin製造業PMI、米3月ISM製造業景況指数、2日に米3月雇用統計などが予定されている。 26日の日経平均株価は大幅続伸し、2万9176円(前日比446円高)引け。バイデン米大統領が就任100日後の4月末までに新型コロナワクチンの接種目標倍増を目指すと表明し、25日の米国株式が上昇した流れを受け、前場早々に上げ幅は510円に達した。一巡後は、利益確定売りに上げ幅を縮小する場面もあったが、次第に持ち直した。時間外取引の米株価指数先物が高く、中国・上海総合指数や香港ハンセン指数などのアジア株高も支えとなり、後場入り直後には前場高値に接近する場面もあった。市場では、「下げ基調の25日線を超えられるかどうかがポイントになる。一方、75日線でいったん下げ止まっており、当面は両移動平均線間でのもみ合いになるのではないか」(準大手証券)との声が聞かれた。〔ロンドン外為〕円、109円台半ば(26日午前9時)時事通信 【ロンドン時事】週末26日朝のロンドン外国為替市場では、米長期金利の上昇を眺めてドル買い・円売りが先行し、円相場は1ドル=109円台半ばに下落した。午前9時現在は109円45~55銭と、昨年6月上旬以来約10カ月ぶりの安値圏。前日午後4時(109円10~20銭)比では35銭の円安・ドル高。 ユーロの対ドル相場は1ユーロ=1.1785~1795ドル(1.1770~1780ドル)。対円では同129円00~10銭(128円45~55銭)。(了)本日の夕食は冷しゃぶの春野菜添えでした。夕食後のデザートは…「ジークフリーダ」にお願いしたフルーツタルトのバースデイケーキでした。コーヒーと共に美味しくいただきました。夫婦2人だけになるとこの12cmサイズでちょうどいいですね。今晩のNY株の読み筋=方向感の見い出しにくい展開かモーニングスター 26日の米国株式市場は、米長期金利動向をにらみながらも目先は材料出尽くしで方向感の見い出しにくい流れになるとみられる。 25日は、週間の新規失業保険申請件数が市場予想を下回ったほか、バイデン米大統領が就任後初の公式記者会見を行い、新型コロナワクチンの接種に関し、4月末までに1億回としていた接種目標を2億回に倍増させると表明したことなどを受け、経済活動正常化への期待が高まり、主要3指数はそろって上昇した。 26日はイベント通過で材料出尽くしとなることや、週明けに3月ISM(米サプライマネジメント協会)製造業景況指数など注目度の高い経済指標が控えているため、いったんポジションを手じまう動きもありそうだ。なお、前日のバイデン大統領の記者会見はワクチン接種の推進強化がマーケットに好感されたが、会見では自身が24年大統領選に出馬・再選する考えも示している。24年に81歳になるバイデン大統領の意欲をマーケットが織り込みに行くのはまだまだ先になりそうだが、目先では、大統領選への出馬に意欲を示すトランプ前大統領や、中国の習近平政権へのけん制など、地政学リスクにつながる可能性もゼロではないので気を付けたい。<主な米経済指標・イベント>2月個人所得・個人支出(日付は現地時間)◎投資関連情報は投資の参考として情報提供のみを目的としたものであり、株式の売買は自己責任に基づき、ご自身で判断をお願いします。NY株見通し-堅調か 経済指標は2月コアPCEデフレーターなどトレーダーズ・ウェブ 今晩のNY市場は堅調か。昨日は朝方に下落したものの、バイデン米大統領が就任100日目を迎える4月末までに2億回のワクチン接種を目指すとしたことや、新規失業保険申請件数の改善などを受けて旅行関連株や小売り株などの経済活動正常化恩恵銘柄が大きく上昇し、主要3指数がそろってが上昇した。主要3指数の週初からの騰落率はダウ平均が0.03%安、S&P500が0.09%安とほぼ先週末水準を回復し、ナスダック総合の下落率は1.80%に縮小した。週末の取引となる今晩もワクチン接種進展による景気回復期待が続くと見込まれることや、FRBが取引終了後に米銀の株主還元規制を6月末に解除すると発表したこと、来週発表予定の数兆ドル規模のインフラ投資を含む経済政策への期待などを背景に堅調相場が予想される。ハイテク・グロース株については長期金利の動向が引き続き焦点で、2月コアPCEデフレーターなどの経済指標が注目される。 今晩の米経済指標は2月個人所得・個人消費支出・コア PCEデフレーター、3月ミシガン大消費者信頼感指数確報値など。主要な企業の決算発表はなし。(執筆:3月26日、14:00)〔NY外為〕円、109円台後半(26日朝)時事通信 【ニューヨーク時事】週末26日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、米長期金利の上昇を背景にドル買いが進行した海外市場の流れを引き継ぎ、1ドル=109円台後半に下落している。午前9時現在は109円75~85銭と、前日午後5時(109円13~23銭)比62銭の円安・ドル高。 バイデン米大統領は25日の記者会見で、最優先課題としてきた新型コロナウイルス克服を目指し、政策発足100日間のワクチン接種目標を1億回から2億回に引き上げた。また、同日に発表された週間新規失業保険申請件数も約1年ぶりの低水準に改善。早期の景気回復期待が高まる中、米長期金利が再び上昇基調にあり、ドルは円やスイスフランなど安全資産とされる通貨に対し強含んでいる。 朝方に発表された2月の個人消費支出(PCE)物価指数も前年同月比1.6%上昇と、1年ぶりの高い伸びを記録し、ニューヨーク市場入り後も円売り・ドル買いの流れが続いている。 ユーロは同時刻現在、対ドルで1ユーロ=1.1770~1780ドル(前日午後5時は1.1759~1769ドル)、対円では同129円25~35銭(同128円40~50銭)と、85銭の円安・ユーロ高。(了)〔米株式〕NYダウ、続伸(26日午前)時事通信 【ニューヨーク時事】週末26日午前のニューヨーク株式相場は、米景気の早期回復を期待した買いが継続し、続伸している。午前10時現在は、優良株で構成するダウ工業株30種平均が前日終値比141.00ドル高の3万2760.48ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数が45.20ポイント高の1万3022.88。 バイデン米大統領は大型の追加経済対策を実現。前日の記者会見では、4月末までの新型コロナウイルスワクチンの接種目標を2倍に引き上げたほか、インフラ投資の強化なども表明した。これを受けて景気回復への期待が高まり、景気敏感銘柄や、経済活動正常化で恩恵を受ける航空など旅行関連銘柄などが買いを集めている。 また、米連邦準備制度理事会(FRB)が25日、新型コロナウイルス危機を受けて一時的に導入した大手銀の配当や自社株買いを制限する措置について、今年のストレステスト(健全性審査)合格行を対象に6月末で撤廃すると発表。これを好感した買いが金融関連銘柄にも入っている。 ただ、米商務省がこの日発表した2月の個人消費支出(PCE)物価指数は、前年同月比1.6%上昇と、1年ぶりの大きな伸びとなった。インフレ懸念は相場の重し。欧州で新型コロナウイルス感染が再拡大していることも圧迫材料。 個別銘柄では、アプライド・マテリアルズやクアルコムなどの半導体も高い。一方で、アパレルのLブランズが急伸。米経済対策の現金給付を受けて足元の業績見通しを再び引き上げたことが好感された。(了)今夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中の13銘柄が値を上げてスタートしましたね。5%以上の大きな変動は見られませんね。
2021.03.26
コメント(0)
-

3月25日(木)…
3月25日(木)、曇りのち雨のち晴れ…。天候はころころと変わり気温もそれほど上がらず…。そんな本日は6時頃に起床。新聞に目を通し、朝食を済ませ、ロマネちゃんと戯れる。身支度をして、7時15分頃に家を出る。ゴルフではありません、アルバイト業務です。本日は8:30~15:30とのこと。朝の通勤風景です。ランチタイムは1時間20分ほど…スタバでのんびりと思いましたが、意外に混んでいました…。帰り道のいつものGSで愛車に燃料補給。帰宅して、和菓子とお茶で遅いおやつタイムです。それではしばらく休憩です。1USドル=109.09円。1AUドル=82.91円。昨夜のNYダウ終値=32420.06(-3.09)ドル。本日の日経平均終値=28729.88(+324.36)円。金相場:1g=6726(+42)円。プラチナ相場:1g=4585(+39)円。本日の東京市場ではチェック中の日本株30銘柄中の25銘柄が値を上げて終了しましたね。重点3銘柄ではすべてが値を上げて終了しましたね。5%以上の大きな変動は見られませんね。ダウはわずかに下げて終わりましたが、僕がチェックしている米国株は多くが下げましたね。しかし、買い希望の価格には届きませんでしたね…。日本株反発、原油高で景気先行き懸念和らぐ-景気敏感など全業種上げ 25日の東京株式相場は反発。原油市況の大幅高に加え、米国株市場で金融や素材など割安株が堅調だったことで景気への過度の懸念がやや和らいだ。機械など輸出関連、商社や鉄鋼などの景気敏感業種が高い。銀行や建設なども上がり、東証33業種全てが上げた。 TOPIXの終値は前日比26.97ポイント(1.4%)高の1955.55-4営業日ぶり反発 日経平均株価は324円36銭(1.1%)高の2万8729円88銭-5営業日ぶり反発 〈きょうのポイント〉 ニューヨーク原油先物は5.9%高の1バレル=61.18ドルと大幅高-米在庫統計受け世界景気の回復ペースに対する不安後退 米S&P500種株価指数は情報技術などが下げて0.6%安と続落-業種別11指数でエネルギーや資本財・サービス、素材、金融は上昇 日本銀行の黒田総裁:上場投資信託(ETF)購入は引き続き必要、買い入れ方針も当面維持 野村証券の伊藤高志シニアストラテジストは、寒波や半導体不足の影響があったことから、米耐久財受注が市場予想に届かなかったことへの過剰反応はなく、むしろ足元ではガソリン需要の堅調さが確認できたと評価。米景気は一部で過熱感が懸念されるくらいの高圧経済の状況にあるが、長期金利は落ち着いてきているとし、「日本株にとっては居心地が良い」と述べた。 昨日の米国株市場では情報技術中心に主要3指数が下落した一方、原油高の中で景気敏感業種は上昇。東京市場でもTOPIXが過去3日間に景気敏感業種中心に大幅下落した後とあって、見直し買いが優勢となった。野村証の伊藤氏は「日米とも決算シーズンの谷間とあって米金利動向で株価が不安定となっていたが、この間もリビジョン・インデックスはしっかりしている」と良好なファンダメンタルズには変化がないとみる。 日銀は24日、通常の上場投資信託(ETF)を701億円と金額を増やして買い入れた。黒田東彦総裁は25日の参院予算委員会で、ETF購入は大規模な金融緩和の一環として「引き続き必要な施策」だと説明した。しんきんアセットマネジメント投信の藤原直樹運用部長は、TOPIXを買うことは日経平均を構成する225銘柄も買うことにつながるため、日銀の政策変更自体は「売り材料でも買い材料でもない」とし、本質的な下げの要因ではないとしていた。 東証33業種では海運や非鉄金属、鉱業、鉄鋼、建設、銀行、電気・ガスが上昇率上位ハイリターンを誇るファンドが保有する、売上高成長率が特に高い3銘柄 ロク2002年創業の同社(NASDAQ:ROKU)は、シリコンバレーに拠点を置くストリーミングサービスで全米トップのプラットフォーマーであり、コロナ禍の外出制限による動画配信需要の拡大を追い風に2020年末時点での稼働口座数が51万件と過去最高を更新しており、ケーブルTV国内最大手の契約アカウント数に対して、2倍以上のユーザー数を獲得しています。同社のビジネスモデルはTV視聴者へ完全にカスタマイズされたコンテンツを配信する一方で、動画制作会社や広告主のターゲットとなるユーザへのアクセスを可能にする事で、より多くの参加者がストリーミングサービスの恩恵を享受できるエコシステムを構築しており、ユーザ数の増加と共に、そのスケールメリットによる収益の拡大が期待されます。事業セグメントとして、「Platform」では、ストリーミングの基幹機能を担う「Roku OS」や映画やドラマ等の幅広い動画コンテンツを手掛ける「The Roku Channel」を中心にOSライセンス、サブスクリプション、広告費用といった収益源をベースに、売上げ全体の7割超を稼ぐ主力であり、20年通期のストリーミング再生時間の前年比約4割増に貢献しました。他方、ストリーミング及び音響機能を装備した最新の動画受信機器「Roku Streambar」等の販売事業も20年通期で売上高が前年比31%の増収、また足元のユーザー当たり平均売上額も同24%増と契約ユーザー数増加に伴う関連機器の売れ行きも好調を維持しています。直近発表の第4Q決算では、売上高が前年同期比58%増の増収かつ、前期に続いて最終黒字を確保する中、EBITDAマージンも17.5%と着実に改善を見せており、背景にはスマートTV向け内蔵OSシェアでトップの「アンドロイド」に次ぐ同社の動画配信プラットフォームの競争優位性があり、今後の利用者増加と広告収入の拡大に不可欠な収益基盤となる事が期待されています。 ペロトン・インタラクティブ2012年創業の同社(NASDAQ:PTON)はインタラクティブ型フィットネス業界において、世界最大のプラットフォーマーであり、忙しい現代人向けに従来の店舗型ジムのコミュニティ感や興奮を家庭でも再現可能なフィットネス機器として提供する事で、場所を選ばずにいつでも理想の自分を実現するというミッションを掲げ、昨年末時点の登録会員数は440万人以上にも及びます。特に、ワークアウトで使用する音楽へのこだわりが強く、米著名アーティストのビヨンセとコラボしたオリジナルテーマのヨガやブートキャンプのクラスは四半期で100万回以上開催され、またソニーミュージックといった大手音楽レーベルと提携して、メンバー専用のリミックスを開発する等、コンテンツの差別化を重要な戦略に位置付けています。主な事業セグメントには、売上げ全体の8割超を稼ぐ「Connected Fitness」を中心に、「Peloton Bike」等の自宅用フィットネス機器及び、各種プログラムの提供を行う他、オンラインでインストラクターの指導が受けられるサブスクリプション(継続課金型)サービスでは、登録数が10-12月期に前年同期比88%増と急成長を見せています。直近の第2Q決算では、売上高が前年同期比128%増と、主要セグメントの2部門いずれにおいても売上高が倍増しており、特にコロナ禍の自宅エクササイズの需要拡大を背景に、オンラインの継続課金プランの契約者数が同3.7倍に急増した事で、サブスクリプション部門の粗利益が約60%にまで改善した結果、6四半期連続の増収達成と収益率が高まっています。更に、昨年末にはフィットネス機器生産で40年以上の歴史を持つ同業他社の米プリコー社の買収を発表しており、国内の生産体制の強化と共に、同社の主力取引先であるフィットネス業界にまで顧客層の拡大が見込まれる一方で、今年後半には海外拠点として、欧州に次いで、アジア初の豪州でのサービス開始と今後のブランド力の向上が期待されています。 ピンタレスト昨年に創業10周年を迎えた同社は、画像検索・共有サービスのプラットフォーマーとして、料理レシピやファッション等の興味関心のある「ピン」と呼ばれる画像や動画を保存管理する事で、利用者の生活をより豊かにする様々なアイデアの発見機能を持つSNSを運営しており、2020年末時点の月間アクティブユーザー数は世界で約4.59億人に及びます。同社のアプリケーション上では、ユーザーが気になる情報のURLだけでなく、画像や動画としてブックマークが可能な「ピン留め」機能で保存し、「ボード」というフォルダで管理する事で、結婚式やリフォームのイメージ作成や美容室でのカウンセリングに利用される等のコロナ禍でもソーシャルディスタンスを維持しながら活用できる画像共有機能が好評です。業績面では、第4Qの売上高が前年同期比76%増かつ、米国外の売上高が同146%増と倍増した事で、海外販売比率は足元で約17%と4四半期連続で上昇しており、世界の月間利用者数(MAU)が同37%増と過去最高を更新する中、海外ユーザー数は約3.6億で、1人あたり平均売上高の伸び率が67% (Y/Y)と今後の増収達成の原動力となっています。また、足元では四半期ベースで約2年ぶりの最終黒字に転換しており、販管費等の営業費用が前年同期比で約1割増えた一方で、増収効果が下支えとなり通期の赤字幅は前年比9割減少かつ、調整後EBITDAマージンは18%の過去最高更新と収益率が著しく改善する中、第1Qのガイダンスでは、売上高成長率を約70%を見込み、良好な経営環境が予想されています。【本日のNYダウ見通し】バイデン大統領の記者会見に注目【NYダウ予想レンジ:32,200~32,700ドル】24日のNYダウは続落。前日比3.09ドル安の32,420.06ドルで取引を修了しました。米国で新型コロナワクチンの接種が進み、経済活動正常化への期待から一時360ドル超上昇し、高値32,787.99ドルをつけました。しかし、ハイテク株などグロース株に売り圧力が強まり、NYダウは小幅安で引けたのです。また、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は大幅に続落し、前日比265.807ポイント安の12,961.890で取引を終了しています。スマートフォンのアップルが2%安、交流サイトのフェイスブックが2.92%安、ネット通販のアマゾン・ドット・コムが1.61%安など、主力ハイテク株が下げました。四半期末が迫っているので、ポジション調整の売りがでた恐れもあります。しばらく上値の重い展開が続きそうです。本日の経済指標では、新規失業保険申請件数と第4四半期GDP(確報値)に注目。また、バイデン大統領が就任後初の記者会見をするので、マーケットの関心を集めそうです。25日の日経平均は5日ぶり反発、景気敏感株中心に買い戻し[東京 25日 ロイター] -東京株式市場で日経平均は5日ぶりに反発した。オーバーナイトの米国株式市場は下落となったものの、日経平均は前日までに4日続落した反動から自律反発狙いの買いが活発化。下落が目立っていた景気敏感株を中心に買い戻しが入り、日経平均は一時前営業日比416円31銭高の2万8821円83銭で高値を付けた。ニッセイ基礎研究所のチーフ株式ストラテジスト、井出真吾氏は「自律反発の範囲内で、特段良い材料があるわけではない。前日の世界的な株安は多くの投資家にとってサプライズであり、やや過剰に反応している部分もあった」と指摘する。「米長期金利に対する警戒感は残っているほか、米中、北朝鮮、ロシアなどの外交を巡る地政学リスクも気掛かり。上昇基調を取り戻したとみるのはまだ早いのではないか」(同)という。TOPIXは4日ぶりに反発し1.40%高。東証1部の売買代金は2兆7080億4800万円。東証33業種では全業種が値上がり。海運業、非鉄金属、鉱業、鉄鋼、水産・農林業、石油・石炭製品などが値上がり率上位に入った。個別では、日本郵船、商船三井、川崎汽船などの海運株がしっかり。直近の急な下げによる突っ込み警戒感から買い直す動きが出ているほか、「スエズ運河で起きた座礁事故の影響によって、市況が上昇するとの思惑が生じている」(国内証券)との声が出ていた。東証1部の騰落数は、値上がり1925銘柄に対し、値下がりが228銘柄、変わらずが40銘柄だった。アンジェスが急反発、新型コロナ治療薬の臨床試験良好遺伝子治療薬を核にした創薬ベンチャーのアンジェス(4563)が4日ぶりに急反発した。午後0時48分現在、制限値幅上限の前日比150円(15.0%)高の1147円ストップ高買い気配で推移している。本日午前8時30分に、カナダのバイオ企業と共同開発している新型コロナウイルス治療薬「AV-001」の第1相臨床試験で良好な結果を得られたと発表し、買い材料視された。第1相臨床試験では20~63歳の健康成人48人を対象に、単回投与・連続投与の安全性、忍容性、薬物動態を評価した。今後データをFDA(アメリカ食品医薬品局)に提出し、重度の新型コロナウイルス感染症の患者に対する有効性を評価する前期第2相臨床試験について協議していく予定となっている。(取材協力:株式会社ストックボイス)24日のアメリカ、ダウ横ばいでもナスダック下落の理由国債は小幅高、原油価格が急反発ブルームバーグ24日の米株式相場は続落。新型コロナ禍で勝ち組となっていたテクノロジー銘柄から、経済再開の恩恵を受ける銘柄へのローテーションが進んだ。ナスダック100指数の構成銘柄では、ズーム・ビデオ・コミュニケーションズやペロトン・インタラクティブ、ドキュサインの下落が目立った。景気敏感株を買う流れの中、エネルギーや銀行、輸送に関連する銘柄は比較的好調。S&P500種株価指数が前日比0.6%安の3889.14。ダウ工業株30種平均は3.09ドル(0.1%未満)安の32420.06ドル。ナスダック総合指数は2%低下。ニュビーンのチーフ投資ストラテジスト、ブライアン・ニック氏は「経済分野が期待を上回り続ける限り、私自身はそう考えるが、シクリカル銘柄のトレードはまだ続くだろう」とブルームバーグテレビジョンで語った。米国債相場は小幅高。ニューヨーク時間午後4時59分現在、10年債利回りは1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の1.61%。米財務省が実施した5年債の入札(610億ドル、約6兆6300億円)では、投資家の需要を示す応札倍率が前回入札から改善し、安心感が広がった。25日には7年債620億ドルの入札が控えている。先月の7年債入札は不調に終わり、債券相場急落の引き金となっていた。外国為替市場ではノルウェー・クローネとカナダ・ドルが堅調。スエズ運河での大型コンテナ船座礁などを受けた原油相場の反発が背景にある。ドルはその他の主要通貨に対して上昇した。 主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.3%上昇。ドルは対円で0.1%高の1ドル=108円72銭。一時は108円96銭に上昇していた。ユーロは対ドルで0.3%安の1ユーロ=1.1811ドル。ニューヨーク原油先物相場は急反発。昨年11月以来の大幅高となった。米在庫統計でガソリン需要が強まる兆候が示され、世界経済の回復ペースに対する不安が和らいだ。スエズ運河を大型コンテナ船がふさいでいる問題は、座礁した同船を動かす作業が25日まで中断されている。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物5月限は、前日比3.42ドル(5.9%)高い1バレル=61.18ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント5月限は3.62ドル高の64.41ドル。こちらも11月上旬以来の大幅高となった。ニューヨーク金市場ではスポットと先物が反発。米国債利回りの上昇に失速の兆候が出てきたことを好感した。米耐久財受注が予想外に減少したことも、逃避先資産としての金の魅力を高めた。金スポット価格はニューヨーク時間午後2時37分現在、前日比0.4%高い1オンス=1734.79ドル。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物6月限は、8ドル(0.5%)上げて1735.50ドルで終了した。【市況】明日の株式相場に向けて=好実態・低PBR株の逆襲 きょう(25日)の東京株式市場は、日経平均株価が324円高の2万8729円と5日ぶりに反発。前週末の日銀金融政策決定会合後に、日銀はETFの購入手法について日経平均連動型を排除することを発表、これを受けて相場は大きく売り優勢に傾き、そのリスクオフの流れは今週も続いていた。前日までの4営業で日経平均は1800円以上も水準を切り下げ、中長期波動の分水嶺である75日移動平均線との上方カイ離を一気に解消し、ほぼ並びの水準となった。 日経平均はこの75日線を、新型コロナ感染第1ステージにあった昨年5月下旬に上回ってから、10カ月間にわたり下に抜けたことがない。あえて言えば昨年10月末に同移動平均線に接触し、瞬間下回ったことがあるのみだ。この時は徳俵の踏ん張りをみせて切り返しに転じた。したがって、この75日線を巡る攻防は結構な重みをもつ。今回も前日の“徳俵”からくしくも押し戻す格好となっているが、日柄的にもそろそろリバウンドのタームに入っている。“日銀ETFショック”だけで相場の大勢トレンドが変わるとは思えないし、仮に変わるとすれば他の要因である。基本的に今の過剰流動性相場は米国株主導であり、NYダウ、ナスダック総合指数の動きの方に目を凝らしておくのが正しい。 個別では、株価が低位もしくは中低位で、低PBRにも関わらずファンダメンタルズからのアプローチでも十分魅力を有する銘柄に動意が相次いでいる。 その流れを象徴するのが、目先急動意し、ストップ高を演じたリリカラだ。壁紙を主体とするインテリア商品卸大手だが、テレワーク導入によるリフォーム需要が追い風となっている。21年12月期は4円50銭の復配を計画し、株価が低位に位置することもあって現状は2%前後の配当利回りが確保されている。にもかかわらず、0.3倍台のPBR(急騰前は100円台)はあまりにも割安圏に放置されていたといってよい。ここからの追撃はさすがに躊躇するが、このリリカラが巻き起こした突風は横に広がっていく公算が大きい。 同じく低位では株価200円台の塩水港精糖が売買高を膨らませウネリを伴った上げ足をみせており注目となる。PBR0.7倍台と割安なうえ、ここ売り残が膨らみ信用倍率が0.4倍台と取り組み妙味が意識されるようになっている。抗菌・抗ウイルス効果で期待されるシクロデキストリン(環状オリゴ糖)関連として人気化素地を持つ。 もう少し株価水準を引き上げた中低位株では、駅探がなかなか見られないチャートを形成中。もちろん偶然の産物と思わるが、上ヒゲを引きながらこのまま500円台後半で煮詰まれば、ある意味芸術的な三角もち合いが完成する。経路探索サービスは緊急事態宣言が外れたことでいきなり需要が伸びるというものでもないが、風向きは追い風であることに変わりはない。 窓を開けて買われた後、800円台で売り物を吸収しているダイセキ環境ソリューションもマークしておきたい銘柄だ。汚染土壌の調査・浄化処理の大手でリサイクルにも展開しており、環境保全関連の有力株として位置づけられる。22年2月期は処理案件の増加が収益に反映され利益は2ケタの伸びが見込まれる。 1000円トビ台の銘柄ではダイトーケミックスの好業績が光る。PER12倍台でPBRも1倍台を下回っているが、半導体関連の一角として業績成長力が高い。感光性材料のトップメーカーで、旺盛な需要を背景に供給不足に陥っている半導体向けで受注を獲得し、22年3月期も好収益環境を享受すると思われる。 あすのスケジュールでは、3月の東京都消費者物価指数が朝方取引開始前に発表される。また、ジャスダック市場にイー・ロジット、マザーズ市場にブロードマインドが新規上場する。海外では、2月の米個人所得・消費支出、3月の米消費者態度指数(ミシガン大学調査・確報値)、3月の独Ifo企業景況感指数など。(銀)出所:MINKABU PRESS明日の戦略-売り出尽くしを意識させる大幅上昇、13週線まで戻せるかトレーダーズ・ウェブ 25日の日経平均は5日ぶり大幅反発。終値は324円高の28729円。米国株の下落を受けても50円近く上昇して始まった。前場では200円超上げた後に上げ幅を一桁に縮め、そこからまた上げ幅を300円超に広げるなど、かなり不安定な値動きとなった。しかし、前引け間際に強含むような反応も見られたことから、後場に入ると3桁高の状況が定着した。上では戻り売りも出てきたが、それをこなしながらも終盤に向けて上げ幅を拡大。高いところでは400円超上昇する場面もあった。米ナスダックが弱かったためマザーズ指数は小幅に下げて終えたが、終盤にはプラス圏に浮上する場面もあるなど、後場に入って持ち直した。 東証1部の売買代金は概算で2兆7000億円。業種別では全業種が上昇。海運や非鉄金属、鉱業などの動きが良く、その他製品や情報・通信、医薬品などの上昇が限定的となった。値がさ株が強く、ファナック、SMC、キーエンスが大幅高。半面、前日にトヨタ、いすゞとの協業に絡んで荒い動きとなった日野自動車が大幅安となった。 東証1部の騰落銘柄数は値上がり1925/値下がり228。原油価格の反発を受けて国際帝石が大幅上昇。三菱UFJや三井住友など、前日に大きく売られた銀行株に強い買いが入った。三井金属は上方修正が好感されて6%近い上昇。配当見通しの引き上げやウーバーとの連携観測が報じられたエディオンが買いを集めた。期末配当見通しの公表が好感された東海東京HDが大幅高。フェローテックとの提携を材料に大泉製作所がストップ高比例配分となった。 一方、米国でナスダックの下げが大きかったことから、ソフトバンクGが大幅下落。前日に急伸したレーザーテックや東京エレクトロンが反動売りに押された。フリーやBASE、AIインサイドなど、マザーズの主力どころにも大きく売られるものが散見された。シンバイオ製薬がリリースを材料に荒い値動きとなり、9%超の下落。売買代金は全市場でトップ10入りする大商いとなった。 本日は持ち越し含めて3社の初値がついたが、シキノハイテック、ベビーカレンダー、ジーネクストはいずれも終値が初値を下回った。 日経平均は5日ぶり大幅反発。特段の買い材料がない中でしっかり上昇した。前日の米国株は終盤に値を消したがパニック的な売られ方ではなかっただけに、そろそろ買い戻しが入りやすいタイミングではあった。きのうの同欄で、きょうの値動きが短期的な方向性を左右する可能性があると指摘したが、強い上昇となったことで、上方向への期待が高まったと考える。終値(28729円)は13週線(28829円、25日時点)に迫ってきた。ファーストリテイリングが5日ぶりに反発し、ほかの値がさ株にも大幅高となったものがいくつかあっただけに、この先は売り方が手仕舞いを急ぐ展開も想定される。あすはきっちり13週線を超えてくるかが注目点で、29000円や5日線(29019円)を上回る展開に期待したいところだ。明日の日本株の読み筋=戻り待ちの売りや週末要因から軟調展開かモーニングスター 26日の東京株式市場は、戻り待ちの売りや週末要因などから、軟調な展開となりそう。今年に入り、金曜日の日経平均株価は前週19日までで、3勝8敗とさえない動きが多いことも不安要因として意識されそう。市場では「日経平均株価は、値幅の調整はほぼ済んだとみられるが、日柄の調整がもう少し必要ではないか」(中堅証券)と慎重な声が聞かれたほか、「手がかり材料に乏しいなか、消去法的に個別株物色が中心になりそう」(他の中堅証券)との見方があった。 25日の日経平均株価は、前日比324円36銭高の2万8729円88銭と5日ぶりに大幅反発して取引を終えた。東京証券取引所が25日引け後に発表した、3月第3週(15-19日)の2市場1・2部等の投資部門別売買状況によると、金額ベースで海外投資家は4088億円の買い越しとなり、3週連続の買い越し。〔東京株式〕5日ぶり反発=米株先物高を好感(25日)☆差替時事通信 【第1部】日経平均株価は前日比324円36銭高の2万8729円88銭と5営業日ぶりに反発し、東証株価指数(TOPIX)も26.97ポイント高の1955.55と上昇した。時間外取引の米国株先物の上昇を好感し、買い戻された。 88%の銘柄が値上がりし、値下がりは10%。出来高は12億4341万株、売買代金は2兆7080億円。 業種別株価指数(全33業種)は銀行業、輸送用機器、小売業、海運業など全33業種が上昇した。 個別では三菱UFJ、三井住友の買いが厚く、野村、東京海上も上伸した。トヨタ、ホンダが上げ、キーエンス、ファナックも買い戻された。郵船、商船三井は大幅高。JAL、ANAは締まり、JR東日本は堅調だった。半面、ソフトバンクGが大量の売りで7営業日続落。東エレク、アドバンテスが売りに押され、ソニーは小幅安。楽天、ZHDは軟調だった。 【第2部】小反発。千代化建が堅調で、Abalanceは切り返した。Gダイニング、MCJは続落。出来高1億4724万株。 ▽一時400円超上昇 25日の東京株式市場は、米国株先物の上昇や前日の米長期金利の落ち着きを好感してほぼ全面高で取引を終えた。日経平均株価の上げ幅は一時400円を超えた。前日までの4営業日で日経平均が1800円超安と急落したため、値頃感が強まっていた。 大手銀行や自動車、産業機械といった主力業種の大型株中心に買われた。中小型銘柄では、3月期末株主の権利確定日を29日に控え、「個人投資家が配当や株主優待を狙って買いを入れ、株価を押し上げた」(インターネット証券)という。 ただ、電子部品などIT関連株は売り注文が厚かった。「欧米の機関投資家が世界の株式市場で、業績対比で割高感の強いIT株の持ち高を減らしている」(外資系証券)という。 225先物も買い戻しが進んだ。オプション4月きりのうちコールは全面高。プットは軒並み値下がりした。(了)〔東京外為〕ドル、108円台後半=材料難で小動き(25日午後3時)時事通信 25日午後の東京外国為替市場のドルの対円相場(気配値)は、売買の手掛かりが見当たらず方向感を欠き、1ドル=108円台後半の狭い値幅で推移している。午後3時現在、108円93~93銭と前日(午後5時、108円60~60銭)比33銭のドル高・円安。 前日の海外市場では、欧州の新型コロナウイルス感染再拡大への懸念に伴うユーロ売りなどにつられ、ドルは一時108円90銭台半ばへ強含んだ。ただ、米5年債入札を無難に終えて米長期金利が小幅低下したため、やや押し戻された。 東京時間は朝方、108円60~70銭台で取引された。その後、事業会社の決済が集中する「五・十日」で輸入企業の決済資金調達が目立ったのに加え、日経平均株価や時間外取引の米長期金利の上昇を眺めたドル買いで一時109円00銭に迫った。北朝鮮による弾道ミサイルの発射については「大きな影響はなかった」(FX業者)もようだ。 午後は材料に乏しく、米金利の動きも落ち着いたことで様子見気分が広がり、108円90銭台でこう着気味となっている。「109円台では輸出企業の持ち高調整が活発とみられるほか、期末を控えて多くの市場参加者が利益確定目的のドル売りに出る」(外為仲介業者)との観測から、上値を追う勢いは鈍い。 市場参加者は、バイデン米大統領の就任後初の記者会見に関心を寄せている。成長戦略などの財源となる増税に言及すれば、「金利・株価を通じてドル円にも波及する可能性がある」(邦銀)との見方が出ている。 ユーロは午後に入って対円、対ドルとも小動き。午後3時現在は1ユーロ=128円76~76銭(前日午後5時、128円37~37銭)、対ドルでは1.1819~1820ドル(同1.1819~1823ドル)。(了)今晩のNY株の読み筋=バイデン大統領の記者会見に注目モーニングスター 25日の米国株式市場は、バイデン大統領の就任後初の公式記者会見に注目が集まる。 バイデン大統領は1月21日に大統領就任以降、米国民に対する新型コロナウイルスワクチン確保と接種の実施、1.9兆ドル(約200兆円)の新型コロナ対策財政支援の法案成立に注力してきたことから歴代大統領に比べ就任後の記者会見が遅れていた経緯がある。新型コロナ感染拡大抑止や変異ウイルス対策、法人税引き上げなど先行きの景況感に影響を与えそうな質問が飛び交うことが想定されるが、マーケットに安心感をもたらす内容となれば、株式市場も買い戻し機運が広がる可能性がある。 一方、今週は新発債の入札ラッシュできょうは7年債の入札がある。また、クラリダFRB(米連邦準備制度理事会)副議長、ボスティック・アトランタ連銀総裁、エバンス・シカゴ連銀総裁に発言機会がある。利上げ観測に言質を与えるような発言が出れば、米長期金利の急伸を招きかねないので、注視しておきたい。<主な米経済指標・イベント>10-12月期GDP(国内総生産)確報値、週間新規失業保険申請件数、7年国債入札、バイデン米大統領が就任後初の公式記者会見、クラリダFRB副議長、ボスティック・アトランタ連銀総裁、エバンス・シカゴ連銀総裁が講演ダーデン・レストランツなどが決算発表予定(日付は現地時間)◎投資関連情報は投資の参考として情報提供のみを目的としたものであり、株式の売買は自己責任に基づき、ご自身で判断をお願いします。〔ロンドン外為〕円、109円台前半(25日午前9時)時事通信 【ロンドン時事】25日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、ドルが買われた海外市場の流れを引き継ぎ、1ドル=109円台前半に下落した。午前9時現在は109円10~20銭と、前日午後4時(108円75~85銭)比35銭の円安・ドル高。 ユーロの対ドル相場は1ユーロ=1.1800~1810ドル(1.1825~1835ドル)。対円では同128円75~85銭(128円70~80銭)とほぼ横ばい。(了)Jフロント、赤字260億円に拡大=コロナ再拡大で苦戦―21年2月期時事通信 J・フロントリテイリングは25日、2021年2月期の連結業績予想を下方修正し、純損益が260億円の赤字(従来予想は186億円の赤字)になると発表した。新型コロナウイルスの再拡大や緊急事態宣言の再発令を受け、主力の百貨店事業が想定を下回って推移。総額売上高も7660億円(同8104億円)に下方修正した。 NY為替見通し=米3月雇用統計調査対象週の失業保険継続受給者数に要注目かトレーダーズ・ウェブ 本日のNY為替市場のドル円は、米3月雇用統計の調査対象週(3月12日週)の失業保険継続受給者数に注目する展開となる。 3月期末決算に向けて、株式市場から債券市場へのポートフォリオ・リバランスや今月末で終了する補完的レバレッジ比率(SLR)条件緩和策の変更点などが警戒されており、関連ヘッドラインに要注目となる。 米3月雇用統計の調査対象週(3月12日週)の失業保険継続受給者数の予想は、404.3万人で、2月雇用統計調査対象週の441.9万人からの減少が見込まれている。予想通りならば、米3月雇用統計の改善期待が高まることになり、バイデン米政権の第1弾としての新型コロナウイルス救済法案(1.9兆ドル)や第2弾としての「ビルド・バック・ベター(より良き再建)」計画による財政出動もあることで、米10年債利回りの上昇、米連邦準備理事会(FRB)のテーパリング(資産購入の段階的縮小)観測が高まることからドル買い要因となる。 パウエルFRB議長は下院金融委員会で「今年は年を通じてインフレ率が上昇すると予想している。インフレへの影響は特段に大きくはなく、持続的でもないだろうというのが最もあり得る展開だとみている」と証言した。本日は、ウィリアムズ米ニューヨーク連銀総裁、クラリダ米連邦準備理事会(FRB)副議長、ボスティック米アトランタ連銀総裁、エバンズ米シカゴ連銀総裁の講演にも要注目となる。・想定レンジ上限 ドル円の上値の目処(めど)は、3月15日の高値の109.36円。・想定レンジ下限 ドル円の下値の目処(めど)は、3月8日の安値の108.27円。【独自】県内観光支援に1人7000円 山梨や兵庫などの事業に補助FNNプライムオンライン「GoToトラベル」の停止が続く中、政府が新たに、自治体独自の県内観光支援策に対し、1人あたり最大7,000円を支援する制度を調整していることがわかった。新たな支援制度は、山梨や兵庫など、多くの県がすでに実施したり、今後、実施予定の自治体独自の県内観光支援策を国が補助するもの。1人あたりの補助額として、最大5,000円、さらに地域共通クーポンとして、最大2,000円の支援を検討しているという。地域の感染状況などによって、開始や終了の時期を検討する方針。GoToトラベルをめぐっては先週、32の県が連名で、県内旅行からの段階的再開を要請した一方、赤羽国交相は23日、「再開は難しい」との認識を示していた。帝国ホテル 148億円の赤字へ=約2000億円強で帝国ホテル東京を建て替え東京商工リサーチ帝国ホテル東京としてのホテル営業は継続する予定 新型コロナウイルスの影響が重い(株)帝国ホテル(TSR企業コード: 291097006)は3月25日、これまで未定だった2021年3月期(連結)の当期純利益が148億円の赤字になりそうだと発表した。同時に、約2000億円から2500億円を投じ、三井不動産(株)(TSR企業コード:291023142)と共同で帝国ホテル東京の本館やタワー館などを建て替えることも発表した。 2021年3月期(連結)の業績予想は売上高217億円(前期実績545億5800万円)、当期純利益148億円の赤字(同24億400万円の黒字)と赤字に転落する見通し。新型コロナの影響と、帝国ホテル大阪の減損と帝国ホテル東京の建て替えに伴う損失計上が響く。 帝国ホテル東京は、日本の迎賓館の役割を担い1890年に開業。数度の建て替えをこれまで実施していたが、現在の本館建物は竣工から50年、タワー館も38年が経過していた。顧客の利用環境を絶やさず、帝国ホテルの歴史も継承するため、建て替え期間中も帝国ホテル東京としてのホテル営業は継続する予定だ。 建て替え実施時期は新本館が2031年度~2036年度、新タワー館が2024年度~2030年度を予定し、建て替え後は新本館がグランドホテル、新タワー館がオフィス、商業、サービスアパートメント等を計画している。近鉄グループHD、「都ホテル 京都八条」など8件売却 資産を「持たない」経営へ 近鉄グループホールディングス(HD)は3月25日、保有するホテル8件を、投資ファンドのブラックストーングループに譲渡すると発表した。譲渡後も運営は続ける。新型コロナウイルスの影響でホテル事業が苦戦する中、「アセット(資産)を保有する経営」から方針を転換し、一部のホテルでは、運営に特化した「ノンアセット経営」を進める。 譲渡するホテルは「都ホテル 京都八条」(京都市)、「ホテル近鉄ユニバーサル・シティ」(大阪市)、「都ホテル 博多」(福岡市)、「神戸北野ホテル」(神戸市)、「都リゾート 志摩 ベイサイドテラス」「奥志摩 アクアフォレスト」(いずれも志摩市)、「都ホテル 岐阜長良川」(岐阜市)、「都ホテル 尼崎」(尼崎市)の8件。帳簿価額は合計約423億円(2020年3月末時点)。 10月1日に譲渡を予定している。譲渡額は非公開。近鉄グループHDは「ブラックストーンとの協業により、ホテル運営に特化した事業戦略を展開し、さらなる成長を実現する」としている。 取引の対象外である「ウェスティン都ホテル京都」「シェラトン都ホテル東京」「シェラトン都ホテル大阪」「大阪マリオット都ホテル」など16件は、近鉄グループHDが引き続き経営していく。 同社が2月に発表した21年3月期第3四半期(20年4~12月)連結決算は、売上高が前年同期比47.0%減の4833億円、営業損益が596億円の赤字(前年同期は505億円の黒字)、純損益が354億円の赤字(同313億円の黒字)と減収減益だった。日立金属売却候補、日米2連合に 7000億円超、今年最大級のM&A時事通信 日立製作所が上場子会社、日立金属の売却先候補を二つの日米投資ファンド連合に絞り込んだことが25日、分かった。急速な社会のデジタル化に伴う企業グループ再編の一環で、来月にも売却先が内定する見通し。買収総額は7000億円を超え、今年最大級の企業の合併・買収(M&A)になる可能性がある。 今週半ばに締め切った2次入札の結果、政府が後押しする官民ファンド、産業革新投資機構(JIC)と米コールバーグ・クラビス・ロバーツ(KKR)の連合と、米ベインキャピタルと国内独立系の日本産業パートナーズの組み合わせが残った。KKRとベインは世界的な大手投資ファンド。 日立製作所は2陣営の提案を精査し、4~5月に予定する2021年3月期決算発表までに日米連合の一方に優先交渉権を与える。 情報通信網や航空分野の製造に欠かせない先端材料部門を持つ日立金属の売却をめぐっては、政府が海外への技術流出を警戒し、JICを軸に日本勢の買収への関与を求めた。このため、JIC・KKR連合が有利との見方もある。 日立金属株はM&Aへの期待などから高値で推移し、時価総額は25日時点で約7831億円に達した。金融関係者は「市場価格が実際の企業価値よりも高くなる恐れがある」と指摘する。 日立製作所はデジタル分野に注力するため、相乗効果の小さい事業を再編する計画だ。約53%を出資する日立金属も対象で、昨年末に1次入札を実施。KKR、ベインのほかに米ファンドのアポロ・グローバル・マネジメントとカーライル・グループも買収提案を示していた。 NY株見通し-上値の重い展開か 経済指標は10-12月期GDP確報値などトレーダーズ・ウェブ 今晩のNY市場は上値の重い展開か。昨日は上昇してスタートしたものの、ハイテク株に売りが強まり、主要3指数がそろって安値引けとなった。ダウ平均は3ドル安と小幅な下落にとどまったが、S&P500が0.55%安となり、ハイテク株主体のナスダック総合は2.01%の大幅安となった。今晩の取引ではワクチン接種の進展による経済活動正常化期待から景気敏感株の堅調が予想される一方、ハイテク・グロース株売りの流れが続くことが予想され、上値の重い展開となりそうだ。 今晩の米経済指標は10-12月期GDP、同個人消費支出 (PCE)確報値、新規失業保険申請件数など。クラリダFRB副議長、ウィリアムズ米ニューヨーク連銀総裁、ボスティック米アトランタ連銀総裁、エバンズ米シカゴ連銀の講演も予定されている。企業決算は寄り前にダーデン・レストランツが発表予定。(執筆:3月25日、14:00)〔NY外為〕円、109円台前半(25日朝)時事通信 【ニューヨーク時事】25日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、円売り・ドル買いが優勢となった海外市場の流れを引き継ぎ、1ドル=109円台前半に下落している。午前9時現在は109円10~20銭と、前日午後5時(108円67~77銭)比43銭の円安・ドル高。 ドイツやフランスなどの欧州各国では、新型コロナウイルスワクチン普及の混乱に加え、感染再拡大の阻止に向けたロックダウン(都市封鎖)の期限延長などの動きが広がっている。こうした中、域内の早期経済回復への期待が薄れ、海外市場で対ユーロでドル買いが進行。このドル買いが対円相場にも波及した。 ニューヨーク市場に入ってから米商務省が発表した2020年10~12月期の実質GDP(国内総生産)確定値や米新規失業保険申請件数は、ともに市場予想よりも良好な内容となったものの、相場の反応は限定的だった。 ユーロは同時刻現在、対ドルで1ユーロ=1.1790~1800ドル(前日午後5時は1.1809~1819ドル)、対円では同128円65~75銭(同128円36~46銭)と、29銭の円安・ユーロ高。(了)〔米株式〕NYダウ、ナスダックとも続落(25日朝)時事通信 【ニューヨーク時事】25日のニューヨーク株式相場は、バイデン米大統領の就任後初の記者会見を前に様子見気分が強まる中、続落して始まった。優良株で構成するダウ工業株30種平均は午前9時35分現在、前日終値比197.62ドル安の3万2222.44ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は88.07ポイント安の1万2873.82。(了)今夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中の5銘柄が値を上げてスタートしましたね。テラドックが下げていますね。5%以上の大きな変動は見られませんね。BMWアルピナB3リムジン アルラット(4WD/8AT)スーパーな実用派セダン
2021.03.25
コメント(0)
-

3月24日(水)…
3月24日(水)、晴れです。良い天気です。春ですね。そんな本日は7時50分頃に起床。新聞に目を通し、朝食を済ませ、ロマネちゃんと戯れる。本日のノルマは1階の掃除機ですか。ハイハイ…。朝のコーヒーブレイクはネスプレッソで…。モロゾフのチョコレートと共に…。そしていつもの母親宅の後片付けです…。本日もゴミ袋が10個以上作られました…。1USドル=108.46円。1AUドル=82.52円。昨夜のNYダウ終値=32423.15(-308.05)ドル。現在の日経平均=28690.02(-305.90)円。金相場:1g=6684(-62)円。プラチナ相場:1g=4546(-99)円。昨夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中の6銘柄が値を上げて終了しましたね。5%以上の大きな変動は見られませんね。ハイテク・グロース株は買い希望価格まで下がりませんでしたね…。本日の東京市場ではチェック中の日本株30銘柄中の1銘柄が値を上げていますね。重点3銘柄ではすべてが値を下げていますね。大きく下げている銘柄が散見されますね。【新型コロナ】ファイザーが錠剤治療薬、EUワクチン規制強化の動き(ブルームバーグ): 米ファイザーは新型コロナウイルス感染症(COVID19)の治療薬として錠剤を新たに開発し、人を対象とした安全性の試験を開始したと明らかにした。感染初期に服用すると効果を発揮する可能性があるという。 世界保健機関(WHO)のテドロス事務局長は、死者数と感染者数の最近の増加は「本当に懸念すべき傾向」だと述べた。 英アストラゼネカはコロナワクチンの臨床試験の最終段階に関し、最新の分析結果を48時間以内に公表すると明らかにした。ワクチンの有効性を巡る同社の分析に古い情報が含まれていたとする米当局の批判に対応する。 欧州連合(EU)と英国はアストラゼネカ製ワクチンの供給を巡る対立の解消に向けて一歩前進した。ドイツは新型コロナウイルスの「第3波」急拡大に対処するため、イースター(復活祭)期間中に厳格なロックダウン(都市封鎖)を実施する。 世界の新型コロナとの闘いは、足踏み状態にある。米国と英国で死者数の伸びが鈍化している一方、インドや東欧などでは再び状況が悪化している。ハンガリーでは医療関係者が不足し、職業訓練を受けていないボランティアの募集を余儀なくされている。 米ジョンズ・ホプキンズ大学がまとめたデータによると、世界の感染者数は1億2390万人を超え、死者数は272万人を上回った。ブルームバーグのワクチン・トラッカーによれば、世界全体のワクチン接種は計4億5800万回を超えた。 ギリシャが23日報告した新規感染者数は3586人と、パンデミック(世界的大流行)開始以来最多となった。同国では前日にロックダウン措置が一部緩和され、美容院やネイルサロンが営業を再開できるようになっていた。 EUは、現在ワクチン輸出許可の適用免除対象としている約90カ国のリストを廃止するほか、EUとの供給契約を履行している製薬会社に対しても輸出制限を設ける可能性があると、EU当局者が明らかにした。新指針は24日公表される見通し。 米テキサス州は29日付でコロナワクチンの接種対象を全成人に拡大する。 英医学研究支援団体ウェルカムトラストのジェレミー・ファラー代表は会議で、「パンデミック終焉(しゅうえん)には程遠い」と発言。「私が考えるに、一つの特効薬で全てが解決するという楽観が依然として行き過ぎている」と指摘した。新たな感染の波が世界各地で見られており、パンデミック開始から1年が経過した現在でも、収束よりも開始時に近い状況のままだとも述べた。 香港の林鄭月娥(キャリー・ラム)行政長官は先月、香港初となるコロナワクチン接種を受けた際、中国本土企業の科興控股生物技術(シノバック・バイオテック)製のワクチンに断固たる支持を表明した。しかしその後、同社製ワクチンと香港当局のワクチン接種促進活動への信頼は急低下。第1弾接種が行われた後、7人の死亡事例と数十件の副反応が報告されたためで、住民は香港で他に唯一利用可能なビオンテック・ファイザー製ワクチンの接種申し込みに殺到し始めている。「パジェロ」消える町、公示地価3%下落 岐阜・坂祝の全3地点毎日新聞 国土交通省が23日公表した公示地価(1月1日時点)で、前年と比較可能な岐阜県内376地点(住宅地、宅地見込地、商業地、工業地)の平均変動率(全国平均0・5%下落)は1・4%下落となり、1993年以降29年連続の下落となった。 三菱自動車の子会社「パジェロ製造」が9月までに工場を閉鎖する坂祝町(人口8162人)では、調査対象の全3地点がそれぞれ約3%下落した。同社は約1000人の従業員の雇用は維持するが、岡崎製作所(愛知県岡崎市)などに再配置する見通しで、県内の取引会社への影響もありそうだ。雇用や町財政を支えてきた工場の閉鎖に、町民は今も将来に不安を抱く。 「コロナに加えて工場の閉鎖。町がさびれてしまう」。町内で飲食店を営む60代女性はため息をついた。新型コロナウイルスの感染拡大で客足が遠のく中でも、多い日で同社の取引先や工場のメンテナンス業者ら20人ほどが利用してくれた。「今では工場に関係する人は全く来なくなった。うちの店の経営も心配だ」とこぼす。 工場が立地する茶屋自治会の菅沼誠嗣会長(65)は町の税収の減少が気掛かりと語る。同町によると、2019年度の全ての税収11億5727万円のうち、法人税や固定資産税など同社からの税収入は1億8038万円だった。多くの住民が福祉や教育のサービス低下を懸念しており「『クルマのまち』としてPRしてきた町は、これからどうするのかが見通せない」(菅沼さん)と話す。 パジェロ製造は1976年に名古屋市内から坂祝町に工場を移転して以来、県内の少なくとも75社と取引があった。県と町は工場閉鎖の発表直後の昨年7月、従業員の再就職を支える協議会を発足。県によると、昨年8月時点の従業員1078人のうち、493人が三菱自動車の関連工場への配置転換を求めており、429人が地元企業への再就職を望んでいる。新たな企業誘致や若年世代の移住促進を目指す坂祝町の柴山佳也町長は「土地を求めている人には買いやすくなる。自然が豊かで子育てしやすい町として積極的にPRしていきたい」と、地価下落をチャンスと捉える。日本株続落、新型コロナの感染再拡大で景気不透明感-景気敏感売り 24日の東京株式相場は続落。欧州を中心とした新型コロナウイルスの感染再拡大で景気の先行き不透明感が高まり、銀行など金融、海運や陸運など景気敏感中心に内外需広く売りが優勢となっている。 TOPIXは前日比26.66ポイント(1.4%)安の1944.82-午前10時25分現在 日経平均株価は290円75銭(1%)安の2万8705円17銭 〈きょうのポイント〉 世界保健機関(WHO)事務局長、新型コロナウイルス死者数と感染者数の最近の増加は「本当に懸念すべき傾向」 英アストラゼネカ、ワクチン試験の最新分析結果を公表へ-米当局の批判受け 米国株は反落、ニューヨーク原油先物は6.2%安-10年債利回りは1.62%と7ベーシスポイント低下 米インテル、半導体生産の大規模投資を発表-TSMCと直接競争へ 水戸証券投資顧問部の酒井一チーフファンドマネジャーは「米金利上昇が止まってきて、景気正常化トレードが手仕舞いの感じ」だと述べた。足元の調整色強まりの背景には、月末に向けた「債券買い・株式売り」のリバランスの流れがあるという。 ドイツで厳格なロックダウン(都市封鎖)実施やギリシャでの23日の新規感染者数の過去最多など、欧州では新型コロナウイルスの第3波が急拡大している。23日の米国株市場で経済再開による恩恵が大きい銘柄が売られた流れは国内にも波及し、空運や陸運、サービスなどの下げが拡大。インテルの設備投資の恩恵を受ける半導体関連は堅調なものの、株価指数への影響は限定的となっている。 いちよしアセットマネジメントの秋野充成執行役員は、新型コロナはワクチン普及によって収束へと向かっていたが、再び拡大していると指摘。感染再拡大によって「景況感が足踏みするのでないかとの疑念が出ている。景気敏感の日本株にとって厳しい」とみていた。 東証33業種では空運や海運、鉱業、銀行、鉄鋼、石油・石炭製品、陸運、サービスが下落米ダウ308ドル安、インフラ投資コストや増税を懸念[ニューヨーク 23日 ロイター] - 米国株式市場は下落し、ダウ工業株30種は308ドル安で取引を終えた。インフラ投資にかかるコストや増税を巡る懸念が相場の重しになった。イエレン米財務長官は下院金融委員会の公聴会で証言し、米経済は新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)による危機から脱却していないとの認識を示した。またバイデン政権が検討しているとされるインフラ投資について、資金を賄うため歳入増を図る必要があると指摘した。チェリー・レーン・インベストメンツのパートナー、リック・メクラー氏は、政府のインフラ投資計画を巡る発言が、株価の割高感に懸念を抱く投資家の警戒感を誘ったと述べた。米連邦準備理事会(FRB)のパウエル議長は同じ公聴会で、パンデミック後の物価上昇が手に負えなくなり、破壊的なインフレの発生につながることはないとの見解を示した。欧州の新たなコロナ規制やワクチン接種の遅れが需要回復を遅らせるとの懸念から原油価格が急落し、エネルギー株を圧迫した。米10年債利回りが先週付けた1年2カ月ぶり高水準から低下していることを受け、今年に入ってアウトパフォームしていた金融やエネルギーも軟調となっている。小型株中心のラッセル2000は3.5%安で、2月25日以来の大幅な下げとなった。個別銘柄では、決算発表を控えてゲームストップが6.5%下落した。バイアコムCBSは9.1%安。動画配信事業への投資資金を調達するため30億ドルの増資計画を発表した。中国のインターネット検索大手、百度(バイドゥ)の米上場株は1.7%安。23日に香港証券取引所に上場したが、公開価格と変わらずで終了した。米取引所の合算出来高は121億株。直近20営業日の平均は140億4000万株。ニューヨーク証券取引所では値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を3.42対1の比率で上回った。ナスダックでも6.64対1で値下がり銘柄数が多かった。ドル指数約2週間ぶり高値、安全資産需要高まる=NY外為[ニューヨーク 23日 ロイター] - ニューヨーク外為市場では、ドル指数が主要通貨バスケットに対し上昇し、約2週間ぶりの高値を付けた。安全資産としてのドルへの投資妙味が高まった。テンパスの通貨トレーダー兼ストラテジスト、フアン・ペレス氏は、24日から米指標の発表が相次ぐことを指摘し、ファンダメンタルズが注目されていると述べた。さらに、新型コロナのパンデミック(世界的大流行)は「まだ終わったわけではなく」、ドル押し上げにつながったとの認識を示した。新型コロナのワクチン接種が順調に進み、大型財政刺激策が米成長加速につながるとの見方から、ドル指数は年初来約2.4%上昇。しかし、世界市場にはなお懸念がくすぶっており、株式市場は世界的に下落した。米連邦準備理事会(FRB)のパウエル議長が議会証言で、新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)後の物価上昇が手に負えなくなることはなく、破壊的なインフレの発生につながることはないと述べたことを受け、米債利回りも低下した。ドル指数は前日の下げから戻し、終盤の取引で通貨バスケットに対し0.65%高の91.8を付けた。ユーロ/ドルは0・71%安の1.1847ドル。ニュージーランドドルは一時3カ月ぶり安値に沈み、約2.27%安の0.70米ドルで推移した。ニュージーランド政府は23日、住宅価格の高騰抑制に向け、投資家を対象とした税制措置や住宅供給拡大など一連の措置を発表した。豪ドルも1.54%安の0.763米ドル。トルコリラは下げ一服商状。終盤は対ドルで約1.79%高で取引された。22日の取引では、エルドアン大統領が金融引き締めを進めてきたトルコ中央銀行のアーバル総裁を解任したことが嫌気され、約7.5%下落していた。オンコリスが買い気配、開発中のコロナ薬が変異型にも有効 がん治療薬などを開発するオンコリスバイオファーマ(4588)が買い先行。午前9時14分現在、前日比150円(13.2%)高の1284円での買い気配となっている。23日引け後、開発中の新型コロナウイルス感染症治療薬「OBP-2011」について、変異型コロナウイルスに対する有効性を実験で確認できたと発表。同治療薬への期待が高まり、買いが向かっているようだ。 ヒトレトロウイルス学共同研究センター・鹿児島大学キャンパスの研究グループとの共同研究で有効性を確認。将来、変異型コロナウイルスが再びパンデミックを起こした場合にも早期感染患者の治療に用いられることが期待される結果だとしている。 現在、OBP-2011の前臨床試験や治療薬GMP製造を進め、2022年の臨床試験開始を目指している。今回の結果を受け、変異型コロナウイルス陽性患者を含めた臨床試験を実施していく予定という。(取材協力:株式会社ストックボイス)【市況】前場に注目すべき3つのポイント~物色の流れとしては個人主体の材料株などにシフト~24日前場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。■株式見通し:物色の流れとしては個人主体の材料株などにシフト■久光薬、21/2下方修正 営業利益106億円←129億円■前場の注目材料:船井電機、秀和システム、240億円で船井電機買収■物色の流れとしては個人主体の材料株などにシフト24日の日本株市場は、引き続きこう着感の強い相場展開になりそうだ。23日の米国市場はNYダウが308ドル安だった。欧州で新型コロナウイルスが収束せずドイツがロックダウンを延長するなど、世界経済の回復に不透明感が広がった。長期金利の低下にもかかわらず四半期末にかけたリバランスなども影響しハイテク株も下落。引けにかけて、原油価格の下落、北朝鮮が短距離ミサイルを先週末に発射したとの報道を受けた地政学的リスク上昇への警戒感も強まり、下げ幅を拡大した。シカゴ日経225先物清算値は大阪比130円安の28680円。円相場は1ドル108円60銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から売り先行の展開から始まることになろう。ドイツのロックダウン延長に原油価格の下落、北朝鮮の地政学リスクが重なった格好であり、朝方はインデックスに絡んだ売りが集中しやすい。また、長期金利は低下しているものの、ハイテク株への反応がみられなかったこともあり、より方向感を掴みづらくさせそうである。ただし、外部要因の影響は早い段階で織り込まれると考えられ、基本的には年度末接近によって大きくポジションを傾けてくる流れにはなりづらいところである。大きく調整する場面においては、短期的なカバーを想定した押し目狙いのスタンスといったところ。また、先週末から日経平均型からTOPIX型へのリバランスの流れが強まってきているが、目先的にはこの流れが一段と強まるかを見極めるところであろう。日銀のETF買い入れ対象の変更がきっかけとはなったものの、足元では過剰に反応している面もあるため、NTショートの巻き戻しも徐々に意識されてくる可能性はあるとみておきたい。とはいえ、長期金利の低下にハイテク株の反応がみられなかったこともあり、積極的な上値追いの流れは期待しづらいところである。そのため、物色の流れとしては個人主体の材料株などにシフトしやすく、北朝鮮のミサイル発射報道を受けた防衛関連など、テーマ株などへは短期的な値幅取り狙いの資金が向かいやすそうである。■久光薬、21/2下方修正 営業利益106億円←129億円久光薬は2021年2月期業績予想の修正を発表。売上高は1270億円から1150億円、営業利益を129億円から106億円に下方修正している。20年7月に公表した業績予想においては、新型コロナ拡大が今期末にかけて緩やかに収束する前提で見通していた。しかし、第4四半期には緊急事態宣言の影響を受け、計画値を下回る見込みとなった。また、想定以上の売上高減少に伴い、結果として売上原価率が上昇した。■前場の注目材料・米長期金利は低下・海外コロナワクチン接種の進展・世界的金融緩和の長期化・株価急落時の日銀ETF買い・船井電機秀和システム、240億円で船井電機買収・大日印仮想空間で顧客開拓、企業向け支援・住友商事物流倉庫に最適な人員配置、6月めどツール実用化・日産自EVの使用済み電池回収を本格化・日本精工電動車駆動モーター用玉軸受、高速回転で小型化・トヨタ足踏み式消毒スタンド好調、「カイゼン」で磨き・スズキ印で乗用車値上げ、原価高響く・不二家チョコ工場にロボ導入、個包装向けフィルム運搬・エスペックワクチンの小口保管庫、超低温域に対応・日立建機商品戦略部を新設、市場別の開発迅速に・日本ガイシ日揮グローバルとモンゴルで太陽光発電設備受注、NAS電池活用・任天堂米社とアプリで提携、スマホ向け開発・荒川化学5カ年中計、売上高25年度900億円、ロジン誘導体伸ばす・神戸製鋼所溶接材料を10%超値上げ、5月納入分☆前場のイベントスケジュール<国内>・08:50 日銀政金融政策決定会合議事要旨(1月20-21日分)<海外>・06:45 NZ・2月貿易収支(予想:+1.81億NZドル、1月:-6.26億NZドル)《ST》 提供:フィスコ【材料】日医工が続落、厚労省などが立ち入りと報じられる 日医工が続落している。日本経済新聞電子版で「厚生労働省と富山県などは24日、医薬品医療機器法に基づき、主力の富山第一工場(同県滑川市)を立ち入り調査した」と報じられており、これが嫌気されている。 記事によると、品質管理体制の改善状況の確認などが目的で、違法と指摘された医薬品の製造手順が改訂されているかどうかや、従業員への指導の状況などを業務再開前に確かめるとしている。出所:MINKABU PRESS【材料】レノバ、ウエストHDなど太陽光発電関連が高い、気候変動サミットにらみ再攻勢 レノバが3日続伸で上値指向を強めているほか、ウエストホールディングスもここ戻り足が鮮明で、中期波動の分水嶺である75日移動平均線とのマイナスカイ離をほぼ埋める状況となった。全体相場は軟調ながら、両銘柄とも今年1月下旬から調整トレンドで売り物がこなれていたことで、目先資金シフトの動きがみられる。太陽光発電関連のツートップ銘柄に位置づけられ、4月下旬にバイデン米政権が主催する温暖化ガスの主要排出国などを集めた気候変動サミットを前に、上値を見込んだ買いが流入している。バイデン政権では3兆ドル規模の巨額の経済対策を近く提示する計画が伝わっており、環境インフラ整備の拡充に力を入れる方針にあることから、再生可能エネルギー周辺株には追い風となる公算が大きい。出所:MINKABU PRESS〔東京外為〕ドル、108円台半ば=リスクオフで上値重い(24日正午)時事通信 24日午前の東京外国為替市場のドルの対円相場(気配値)は、欧米での新型コロナウイルス感染再拡大懸念を背景にしたリスクオフムードの高まりで、1ドル=108円台半ばで上値重く推移している。正午現在、108円50~50銭と前日(午後5時、108円76~76銭)比26銭のドル安・円高。 前日の欧州市場では、ドイツのロックダウン(都市封鎖)延長などを受けて安全資産とされる円が買われ、ドルは一時108円40銭前後に下落。米国時間には一時108円70銭台まで値を戻したが、米2年国債入札の結果などを受けて米金利が低下し、ドルもつれ安となった。東京時間に108円50銭台で始まったドル円は日経平均株価の大幅安や米金利低下を眺めて上値が重く、正午にかけて同水準で小動きしている。 強いリスクオフではドルも円も買われる傾向にあるが、市場関係者からは「ドルより円が買われており、4月に向けて107円台前半まで下落するのではないか」(銀行系証券)との声が聞かれた。また、25日未明の米5年国債入札が引き続き金利の波乱要因として投資家の注目を集めている。 ユーロは午前9時と比べ、対円、対ドルで強含み。正午現在、1ユーロ=128円52~53銭(前日午後5時、129円46~50銭)、対ドルでは1.1845~1845ドル(同1.1904~1904ドル)。(了)〔東京株式〕4日続落=感染再拡大を警戒(24日)時事通信 【第1部】日経平均株価は前日比590円40銭安の2万8405円52銭と4営業日続落。東証株価指数(TOPIX)は42.90ポイント安の1928.58と3日続落。新型コロナウイルスの感染再拡大への警戒感からリスクを避ける動きが強まり、業種を問わず幅広く売られた。出来高は15億9135万株。 【第2部】続落。Gダイニングが急落し、ギグワークスも売られた。半面、千代化建はしっかり。出来高1億6048万株。 ▽金利先高観も重し 東京市場は前場から全面安となり、後場も下値模索の展開が続いた。欧州中心に新型コロナウイルスの感染が再拡大。ワクチン接種による感染収束・経済活動正常化というシナリオに遅れが生じる可能性が意識され、「海外勢中心に機関投資家が、最近値上がりしていた景気敏感株に利益確定売りを出したようだ」(銀行系証券)という。 景気敏感株の下落については「米金利の先高観が消えないことが、売りを加速させた」(大手証券)との指摘もあった。各国がコロナ対策で財政支出を膨らませており、金利上昇加速への警戒感はくすぶる。 この日は米インテルによる大規模な設備投資計画を受けて半導体製造装置など値がさ株の一角が上昇した。しかし、相場の地合いが悪化する中で買いは広がらず、リスク回避色の強い一日となった。 225先物6月きりも4日続落。朝方は押し目買いが入って下げ渋る場面もあったが、長続きせず、アジア株の軟化と歩調を合わせるように下げ幅を拡大。午後は2万8200円台に突っ込む場面もあった。225オプションは下値不安の強さを映してプットが買われ、コールは値を下げた。(了)〔東京外為〕ドル、108円台半ば=方向感定まらず(24日午後3時)時事通信 24日午後の東京外国為替市場のドルの対円相場(気配値)は、欧米の新型コロナウイルス感染拡大などを受けたリスク回避ムードの中、方向感の定まらない展開となり、1ドル=108円台半ばで推移している。午後3時現在、108円54~54銭と前日(午後5時、108円76~76銭)比22銭のドル安・円高。 前日の海外市場では、欧州時間にドイツのロックダウン(都市封鎖)延長などを背景にリスク回避の姿勢が強まって円買いが優勢となり、一時108円40銭前後に下落した。米国時間には、108円70銭台まで買い戻されたものの、終盤、米長期金利の低下を眺め軟化した。東京時間早朝は、108円60銭前後を中心に取引された。午前10時にかけては輸入企業のドル買いでやや上昇したものの、午前11時にかけて時間外取引の米金利の低下などで108円40銭台へ弱含んだ。午後は「リスク回避のムードの中、(安全資産とされる)ドルも円も買われやすい」(FX会社)とされ、108円40~50銭台でもみ合って推移している。 市場では、欧米での新型コロナ拡大や米中関係への懸念のほか、米国のバイデン政権が検討する新たな財政出動についての報道を受け、「増税への警戒感が高まっている」(大手邦銀)とされ、リスク回避の雰囲気が広がっている。24日は欧米で3月のPMIが発表される予定となっており、「景気回復の遅れが懸念されている欧州のPMIの結果が注目」(同)との指摘が聞かれた。このほか、「3月末が近づいているので、ポジション調整でドル円はやや軟化しやすい」(同)との見方も出ていた。 ユーロは午後に入って、対円、対ドルともにやや軟調。午後3時現在、1ユーロ=128円52~52銭(前日午後5時、129円46~50銭)、対ドルでは、1.1840~1840ドル(同、1.1904~1904ドル)。(了)日経平均590円安と大幅に4日続落、7週ぶり2万8500円割れ、値下がり銘柄数2000超=24日後場モーニングスター現在値JAL 2,372 -200ANA 2,463 -191.50国際帝石 746 -45石油資源開 2,089 -122郵船 3,700 -200 24日後場の日経平均株価は前日比590円40銭安の2万8405円52銭と大幅に4営業日続落。2万8500円割れは2月4日(終値2万8341円95銭)以来ほぼ7週間ぶり。朝方は、売り優勢で始まった。欧州主要地域での新型コロナウイルス変異種の感染拡大による経済への影響が懸念され、23日の米国株安やNY原油先物安も重しとなった。アジア株安も意識され、株価指数先物売りを交えて下げ幅を拡大し、後場終盤には2万8379円06銭(前日比616円86銭安)まで下落した。後場入り後には日銀のETF(上場投資信託)買い期待を支えに下げ渋る場面もあったが、買いは続かなかった。 東証1部の出来高は15億9135万株、売買代金は3兆2154億円。騰落銘柄数は値上がり139銘柄、値下がり2026銘柄、変わらず28銘柄。 市場からは「変異ウイルスの感染拡大で景気回復期待先行の動きが変わってきた。高値圏で売りが出やすく、スピード調整は致し方ない。ただ、金融緩和継続をバックに下降トレンドにはならないだろう」(準大手証券)との声が聞かれた。 東証業種別株価指数は全33業種が値下がり。業種別では、JAL 、ANA などの空運株や、国際帝石 、石油資源 などの鉱業株が下落。郵船 、商船三井 、川崎汽 などの海運株や、日本製鉄 、JFE 、神戸鋼 などの鉄鋼株も安い。三菱UFJ 、三井住友 、りそなHD などの銀行株や、JR東日本 、JR西日本 、JR東海 などの陸運株も売られた。フジクラ 、三菱マ などの非鉄金属株や、野村 、大和証G などの証券商品先物株も軟調。 個別では、わかもと がストップ安となり、ハブ 、キャリアL 、セントケアH 、オーケストラ などの下げも目立った。半面、船井電機 (監理)がストップ高となり、理想科学 、レーザーテク 、ニコン 、ミダック などの上げも目立った。【本日のNYダウ見通し】耐久財受注と米5年債の入札に注目【NYダウ予想レンジ:32,200~32,600ドル】23日のNYダウは反落。前日比308.05ドル安の32,423.15ドルで取引を終了。序盤は様子見ムードで小幅な値動きでしたが、原油相場が急落するとリスク回避ムードが高まりました。また、欧州で新型コロナウイルスの感染が再拡大していることから、旅行やレジャー関連など、最近上昇が続いていた銘柄を中心に売られました。そしてハイテク株の一部は買われたものの、ナスダック総合株価指数も3営業日ぶりに反落し、前日比149.845ポイント13,227.697で取引を終了しています。注目されていたパウエルFRB議長とイエレン財務長官の公聴会証言ですが、これまでの発言を踏襲する内容で、マーケットに与える影響は軽微でした。ただ、本日の引き続き公聴会での証言があるので、最近の長期金利上昇に関しての言及があるのかどうかに関心が集まりそうです。本日の経済指標では、耐久財受注に注目です。また米5年債の入札があるので、金利動向に影響がでるかに市場の関心は向かうでしょう。先端半導体、開発事業者にキヤノンや東京エレクなどを選定=経産省[東京 24日 ロイター] - 経済産業省は、先端半導体製造技術の開発企業として、東京エレクトロン、キヤノン、SCREENセミコンダクターソリューションズ(京都市)、産業技術総合研究所を選んだと発表した。台湾積体電路製造(TSMC)など海外のファウンドリ(半導体受託製造)も含めて協力していく。23日に発表した。今回の事業では、ポスト5Gで必要となる先端的な半導体を将来的に国内で製造できる技術を確保するために、先端半導体の製造技術の開発に取り組む。具体的には、2nm(ナノメートル、ナノは10億分の1)以降の次世代半導体の製造技術を開発するとともに、国内にない先端性を持つロジック半導体の製造技術を確立する。研究開発期間は5年。産総研は試験ラインを設置し、半導体デバイス(半導体チップ)を生産する海外ファウンドリを含めて「先端半導体製造技術コンソーシアム」を構築する。半導体受託生産大手の台湾TSMCは産総研の事業所がある茨城県つくば市に研究開発を目的とした子会社の設立を決めている。経産省は「ポスト5G」や半導体の技術開発を支援するために20年度3次補正で900億円を積み増し、計2000億円規模の基金を作っている。これまでにも、5Gの情報通信システム開発などで支援を決めており、今回も、この基金から支援を行う。保有ETF、「処分を検討する時期ではない」=日銀総裁[東京 24日 ロイター] - 日銀の黒田東彦総裁は24日、参院予算委員会に出席し、2%の物価安定目標の実現に時間がかかることが見込まれ、金融緩和の出口のタイミングや具体的な対応を検討する局面には至っていない、と述べた。購入したETF(上場投資信託)についても「処分を検討する時期ではない」と明言した。日銀は3月の金融政策決定会合で、年間6兆円程度としてきたETF購入の目安を撤廃し、同12兆円程度の上限を維持した。熊谷裕人委員(立憲)が「購入した株は売却しない限り日銀の保有が続く。市場が安定しているうちに売却すべきではないか」と質問したことに答えた。日銀は、展望リポートを決める年4回の決定会合で金融機構局から金融システムの動向について報告を受けることにした。黒田総裁は金融緩和策の長期化を踏まえ、金融システムの動向に一層目配りする必要がある、と説明。「現状、金融システムが不安定化しているとか、すぐに不安定化する恐れがあるということではない」と語った。物価について黒田総裁は、新型コロナウイルス感染症の影響もあり足元はマイナスで推移しているものの、徐々に上昇率を高めていくとの見方を示した。その上で、物価目標達成に向けて強力な金融緩和を粘り強く続けていくと述べた。焦点:大手生保、米10年金利2%も想定 外債投資再開のタイミング計る[東京 24日 ロイター] - 国内大手生保が外債投資再開のタイミングを計っている。昨年後半から売り越してきたが、米国を中心に景気回復期待から債券利回りが急上昇し、国内債との対比で魅力度が増しているためだ。一方、ロイターが聞き取り調査を行った大手4社とも、金利上昇局面が終了したとはとらえていない。米10年国債利回りが年内に2%程度まで上昇することを想定しつつの運用となりそうだ。<米金利上昇で戦略練り直し>第一生命保険の岡崎健次郎外国債券部長は、健全な金利上昇ならば容認する米連邦準備理事会(FRB)のスタンスやワクチン普及と経済再開のスピード感を受けて、米金利上昇のタイミングの想定を前倒しせざるを得なくなったとしたうえで、10年債利回りは早ければ4─6月にも2%に達する可能性があると話す。その上で、外債について「金利に先高観がある限り、なかなかアロケーションを大きくシフトして買いに行くことにはならないが、低い金利で買ったものの入れ替えなどを含めて、為替や金利を見ながら、国内債とのバランスをとりつつ機動的な運用を行う」と述べた。コロナショックで、昨年3月に史上最低の0.318%をつけた米長期金利は、その後も低水準での推移が続き、生保各社は昨年は国内債に回帰する動きを見せていた。財務省の統計によると、日本の生保は昨年7月以降、外国債券を過去最長の8カ月間連続で売り越しており、この間の売却額は合計2兆円に達する。しかし、今年に入って米国債利回りが大半の市場関係者の予想を上回るスピードで上昇、先週には1年2か月ぶりの高水準となる1.754%をつける中、各社とも外債投資戦略を練り直し始めている。<クレジット中心との声も>長期金利が大幅に上昇する一方で、FRBが2023年までゼロ金利を継続すると打ち出したことで同国の短期金利は抑えられており、結果としてドルのヘッジコストが比較的低位で安定していることも、外債投資の大半に為替ヘッジをかける日本の投資家にとっては追い風となっている。ただ、今後インフレ懸念がさらに高まれば、米国が早期に利上げを迫られる可能性もある。その場合にはヘッジコストも上昇する可能性が高いため、投資対象としては、米国債よりも利回りの高い、社債などクレジットものがメインと考える会社も多いようだ。住友生命保険の藤村俊雄運用企画部長は「利上げが当面行われずヘッジコストが低位の環境下では、ヘッジ付き外貨建て資産の投資妙味は高まる。ヘッジ付き米国債投資の妙味も一時的には高まるものの、将来のヘッジコスト上昇リスクを視野に入れ、外貨建てクレジット資産などスプレッドの取れる資産を中心に投入を検討する」と話す。ヘッジコストの上昇リスクを見込みつつ、大手4社の中でも米国債にやや慎重なスタンスをとるのは日本生命保険だ。同社の執行役員財務企画部長の岡本慎一氏は「コロナ禍前の19年以前は米長期金利が2%を超えていたこと、またヘッジコストも中長期的には上昇する可能性が高いことなどに鑑みると、現在のヘッジコスト控除後の米国債は投資妙味に乏しい」と話す。その上で、「外債投資は引き続き、スプレッド収益を獲得できて長期投資の観点から妙味のある海外社債を中心に投資していく」としている。<オープン外債も検討>為替ヘッジをつけないオープン外債についても検討余地があるとの声が出ている。明治安田生命保険の運用企画部運用企画グループマネジャー、北村乾一郎氏は、米国の金利上昇を受けた日米金利差拡大に伴い、ドル高に振れる可能性があると指摘する。「(投資対象の)年限は金利上昇の程度次第だが、長期・超長期の米国債についてはオープン外債も選択肢の1つ」という。もっとも、当面はドルのヘッジコストが低位で推移すると見られることから、「年限を短めに構えながら(ある程度中短期の投資として)ヘッジ付き外債投資も可能」だとしている。ただ、依然として為替リスクに慎重姿勢を示す向きは多い。第一生命の岡崎氏は「円高懸念は後退しているが、ボラティリティーはまだ高い。オープン外債を増やすには、もう少し様子を見る必要がある」と話している。<円金利の上昇余地は限定的との見方>国内金利の見通しについては、「足もとの円金利は米金利に連動して上昇しているものの、円金利の上昇余地は限定的」(日本生命)との見方で、各社ほぼ一致する。住友生命の藤村氏が「25年の経済価値ベースの資本規制導入に向けて国内金利リスクを削減する必要があるため、国内債券については継続して超長期債へ投資していく」と話す通り、生保による投資も円金利上昇を抑制する要因となりそうだ。アングル:日銀ETF購入、新手法で小型株上昇か ファーストリテの筆頭株主も視野[東京 24日 ロイター] - 日銀は19日に公表した政策点検で、上場投資信託(ETF)買い入れに伴うリスクプレミアムの縮小効果を初めて示し、識者から評価する声が出ている。しかし、買い入れ対象をTOPIX連動型に一本化することで、小型株が上昇しやすくなり株価に新たなゆがみが生じるとの懸念が浮上。企業統治を巡る懸念も解決されておらず、ファーストリテイリングでは日銀が筆頭株主に浮上することが視野に入ってきた。日銀は4月から新手法に移行するが、買い入れ縮小には市場の安定化が必要だとの声が市場関係者から出ている。<初めて示された「リスクプレミアム」>日銀は今回、株式市場のリスクプレミアムを捉える様々な指標やデータの中から、オプション価格に含まれる株式リスクプレミアムの変化幅と個別銘柄のイールドスプレッドの変化幅の2つを挙げて、ETF買い入れの効果を検証した。ETFの買い入れによって株式市場のリスクプレミアムが有意に押し下げられていることを示すとともに「市場が不安定な時ほど、買い入れ規模が大きいほど、買い入れ1単位当たりの効果が大きいことが示唆される」と結論づけた。中央大学商学部の原田喜美枝教授は「リスクプレミアムをどのように捉えればいいのかということと、日銀が考える効果の在り方が分かったということは前向きに評価できる」と話す。日銀がどういう場面でETF買い入れに動くのか、これまでは雨宮正佳副総裁が2019年5月の国会答弁で示した国債と株価の利回り差、PER(株価収益率)、PBR(株価純資産倍率)、VIX指数、市場参加者からの聞き取り情報の5つが参考にされてきたが、市場で幅を利かせてきたのは「前場でTOPIXが0.5%以上下がると日銀がETFを買い入れる」といった「ルール」だ。ただ、2月下旬にはこのルール通りに日銀が買い入れない日もあり、市場では新たなルールを見いだそうとする動きがある。<小型株が押し上げられる可能性>日銀は19日、ETFの買い入れ対象をTOPIX連動型に一本化することを決めたが、新たな問題も浮上している。黒田東彦総裁は22日の参院財政金融委員会で「個別銘柄に偏った影響ができるだけ生じないように、指数構成銘柄が最も多いTOPIX連動型のみにした」と説明した。しかし、中央大の原田教授は、TOPIX連動型に一本化することでファーストリテイリングやアドバンテストなど日経平均株価の構成銘柄で浮動株比率の低い銘柄の株価への「今後の負荷は軽減される」ものの、「小型株への影響は今後もより大きく出る」と指摘する。<ファーストリテの保有比率、近づく「柳井氏超え」>日経平均連動型を購入しなくても、TOPIX型の購入が続くことで、個別銘柄における日銀の間接保有比率は緩やかながらも上昇を続ける。日銀はファーストリテで筆頭株主への浮上を射程圏に収めている。ニッセイ基礎研究所の井出真吾上席研究員によれば、TOPIX型をもう6兆円購入すれば、会長兼社長の柳井正氏の保有比率21.58%を追い抜く。しかし、今回の政策点検で、市場関係者や有識者が指摘してきた日銀のETFの大量保有に伴う企業統治への弊害は解決されないまま残った。日銀は、企業統治への影響について「ETFを構成する個別株式の議決権については、スチュワードシップ・コード(機関投資家の行動指針)の受け入れを表明した投資信託委託会社により適切に行使される扱いとなっている」と従来の見解を繰り返した。「先行き、保有ETFの残高がさらに増加するにつれ、こうした懸念は高まる可能性がある」と述べるにとどまり、具体的な対処法は示さなかった。中央大の原田教授は「日銀はバイ・アンド・ホールドで絶対に売らないから株価は下がりにくいし、安泰だと思っている経営者も多いと思う。株式市場では、出資者は投資家として企業経営の監視という役割を担うのだが、日銀はこういった点を意識していない」と指摘する。市場では「日銀は運用会社にガバナンスの監視を任せきりにしているが、運用会社は経営監視に興味はないのではないか」(アナリスト)との声が出ている。<めりはりのある買い入れの実現は>日銀は4月1日からETFの買い入れ対象をTOPIX連動型に一本化する。年12兆円を上限に、市場が落ち着いている場面では買い入れ額を落とし、市場が大きく不安定化した場合には大規模な買い入れを行い、政策点検で目指しためりはりのある買い入れを模索する。ニッセイ基礎研の井出氏は「将来的に買い入れを縮小して、いずれゼロにしていくための初めのほんの一歩。実際に買い入れ額が減るかどうかは市場環境次第だ」と話している。【材料】シンバイオが急落、東証が上場廃止にかかる猶予期間入り銘柄に指定 シンバイオ製薬が急落している。東京証券取引所がこの日、上場廃止にかかる猶予期間入り銘柄に指定したことが嫌気されている。 同社がきょう提出した有価証券報告書などで、最近4事業年度(17年12月期から20年12月期まで)における営業利益及び営業活動によるキャッシュ・フローの額がマイナスであることが確認されたためという。猶予期間は22年12月31日まで。出所:MINKABU PRESS明日の戦略-大幅安だが75日線はサポートに、そろそろ急反発にも備えをトレーダーズ・ウェブ 24日の日経平均は大幅に4日続落。終値は590円安の28405円。米国株の下落を受けて、200円以上下げて始まったが、寄り付き直後を高値にその後も下を試す展開。世界的なコロナ感染の再拡大が懸念される中、景気敏感株やアフターコロナ関連の多くが値を崩し、全面安の様相が強まった。前場で節目の28500円を割り込むと、後場は一段安となって下げ幅を600円超に拡大。28300円台でようやく売り一巡感が出てきたものの、戻りは限られ、安値圏で取引を終えた。マザーズ指数が3%を超える下落となった。 東証1部の売買代金は概算で3兆2100億円。業種別では下げが軽微な電気機器、精密機器、ガラス・土石でも1%を超える下落。空運が7%を超える下落となり、鉱業や海運が5%近い下落となった。トヨタとの共同会見に関するニュースを手掛かりにいすゞが後場急伸。半面、東証が上場廃止に係る猶予期間に入ることになったと発表したシンバイオ製薬が後場に入ってストップ安まで売られた。 東証1部の騰落銘柄数は値上がり139/値下がり2026と、値下がりが2000を超えた。インテルの新工場建設発表を材料に、東京エレクトロン、レーザーテック、ニコンが大幅高。イオンが逆行高となったほか、コスモス薬品やウエルシアなどドラッグストアの一角が上昇するなど、巣ごもり恩恵のある銘柄を物色する動きが見られた。上方修正を発表した理想科学が急伸。リリースを材料にオンコリスバイオファーマが値を飛ばした。 一方、空運株と海運株が叩き売られており、JAL、ANA、日本郵船、川崎汽船、商船三井が急落。原油価格の下落を受けて国際帝石が売られたほか、米長期金利の低下を受けて三菱UFJや三井住友などメガバンクも厳しい下げとなった。日経平均が下げ止まらない中、ファーストリテイリングやソフトバンクGなど指数寄与度の大きい銘柄が大幅安。新興市場も弱く、メルカリやBASEが大きく売られた。直近IPOのココナラは15%を超える下落と手仕舞い売りが殺到した。 本日マザーズに新規上場したSharing Innovationsは高い初値をつけたものの、地合いが悪い中、ストップ安で終えた。ジャスダックに上場したシキノハイテックは、買いが殺到して初値は持ち越しとなった。 日経平均は下げ止まらず4日続落。ただ、東証1部の値下がり銘柄が2000を超え、業種別でも全業種が下落となった割には、後場に売り崩す動きは限定的であった。前引け時点で530円下げていたことを鑑みると、きょうは1000円近く下げて一気に28000円に接近していても不思議ではない。終値28405円は75日線(28394円、24日時点、以下同じ)に近く、これがサポートとして機能しているようにも見える。来週には新年度相場入りすることから、資金の流れにも変化が出てくる可能性がある。直近4日間では1800円以上下落した。ある程度の売り出尽くし感は出てきており、そろそろ急反発のシナリオにも意識を払っておいた方が良い。週足ではきょうの下げで13週線(28804円)を割り込んでおり、大きな戻りがないまま週を終えると、チャート形状は悪化する。一方、ここで切り返して週末値で13週線を超えてくれば、75日線のサポートと併せて底打ち感が強まる。あすの値動きが短期的な方向性を大きく左右する可能性がある。明日の日本株の読み筋=コロナ変異ウイルスの感染拡大懸念根強く値の荒い動き継続かモーニングスター あす25日の東京株式市場は、海外中心に新型コロナウイルス変異種の感染拡大懸念が根強いなか、ボラティリティ(価格変動率)が高まり、値の荒い動きが続く可能性がある。ドイツは23日、新型コロナの変異ウイルスのまん延を受け、28日までとしていた現行のロックダウン(都市封鎖)期限を4月18日まで延長すると発表した。フランスやイタリアでも前週に一部地域で規制の強化を行っており、欧州主要地域での感染拡大による経済への影響の長期化が引き続き警戒される。市場では、「買い材料がなく、来月のSQ(特別清算指数)算出日に向けて下げ基調になるのではないか」(銀行系証券)との見方も出ていた。 24日の日経平均株価は大幅に4営業日続落し、2万8405円(前日比590円安)引け。朝方から、売り優勢の展開となった。新型コロナ変異種の感染拡大への懸念とともに、23日の米国株安やNY原油先物安も重しとなった。アジア株安もあって、株価指数先物売りを交えて一段安となり、下げ幅は一時610円を超えた。チャート上では、2月7日以来ほぼ7週間ぶりに2万8500円を割り込み、75日移動平均線(2万8394円)に急接近。同線を下回ると心理的なフシ目となる2万8000円が意識されてくる。〔ロンドン外為〕円、108円台後半(24日午前9時)時事通信 【ロンドン時事】24日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、薄商いの中を1ドル=108円台後半で推移した。午前9時現在は108円60~70銭と、前日午後4時(108円55~65銭)比05銭の円安・ドル高。 ユーロは軟調。対ドル相場は1ユーロ=1.1820~1830ドル(1.1865~1875ドル)。対円では同128円45~55銭(128円90銭~129円00銭)。(了)今晩のNY株の読み筋=欧州のコロナ感染再拡大懸念が重しかモーニングスター 24日の米国株式市場は、上値の重い展開とみる。欧州における新型コロナの感染再拡大懸念から売り圧力が強まりやすいムードにある。今晩の米国ではパウエルFRB(米連邦準備制度理事会)議長やイエレン米財務長官が米上院で証言するが、前日から大きく内容が変わるとは思えず、特に材料視されない可能性がある。 欧州ではユーロ圏やドイツなどの製造業PMIが相次いで発表されるが、市場は前月から大きく変わると見込んでいない。仮に予想に反して改善しても、足元でコロナ感染拡大が警戒されるなかでは大きな買い材料にはなりにくいだろう。 一方、米5年債入札には関心を払っておきたい。好調な結果となれば米長期金利の落ち着きが期待され、米国株にとってもプラスだが、入札が不調に終わると金利上昇によりハイテク株を中心に売りが強まる恐れがある。<主な米経済指標・イベント>米2月耐久財受注、パウエルFRB(米連邦準備制度理事会)議長が米上院で証言、米5年債入札◎投資関連情報は投資の参考として情報提供のみを目的としたものであり、株式の売買は自己責任に基づき、ご自身で判断をお願いします。NY株見通し-底堅い展開か 経済指標は3月マークイット製造業PMI速報値などトレーダーズ・ウェブ 今晩のNY市場は底堅い展開か。昨日は欧州などでのコロナ感染第3波が拡大し、ドイツでロックダウンが4月18日まで延長されたことなどで、経済活動正常化期待が大きく後退した。経済活動再開の恩恵を受ける銘柄を中心に幅広く売られ、主要3指数がそろって0.76-1.12%下落したほか、小型株指数のラッセル2000は3.58%安と昨年6月以来の大幅安を記録した。引け後の動きでは、200億ドルを投じてアリゾナ州に新工場を建設すると発表したインテルが時間外で6%超上昇した。今晩の取引では世界的なコロナ感染拡大を受けて景気敏感株の軟調が予想されるものの、インテルを中心に半導体株の堅調が予想されるほか、昨日下落した銘柄に押し目買いが入ることも期待されることから底堅い展開となりそうだ。 今晩の米経済指標・イベントは2月耐久財受注、3月マークイット製造業PMI速報値、EIA週間原油在庫のほか、パウエルFRB議長とイエレン米財務長官の米上院銀行委員会での証言や、バーキン米リッチモンド連銀総裁、ウィリアムズ米ニューヨーク連銀総裁、デイリー米サンフランシスコ連銀総裁の討議参加・講演など。企業決算は寄り前にゼネラル・ミルズが発表予定。(執筆:3月24日、14:00)〔NY外為〕円、108円台後半(24日午前8時)時事通信 【ニューヨーク時事】24日のニューヨーク外国為替市場の円相場は、午前8時現在1ドル=108円59~69銭と前日午後5時(108円52~62銭)比07銭の円安・ドル高で推移している。 ユーロは同時刻現在、対ドルで1ユーロ=1.1828~1838ドル(前日午後5時は1.1845~1855ドル)、対円では同128円52~62銭(同128円61~71銭)。(了)〔NY外為〕円、108円台後半(24日朝)時事通信 【ニューヨーク時事】24日午前のニューヨーク外国為替市場では、欧州での新型コロナウイルス感染拡大懸念を背景としたリスク回避の円買い・ドル売りが一巡し、円相場は1ドル=108円台後半で小動きとなっている。午前9時現在は108円65~75銭と、前日午後5時(108円52~62銭)比13銭の円安・ドル高。 ニューヨーク市場は108円64銭で取引を開始した。新型コロナ感染の第3波が警戒される中、欧州経済の停滞懸念を背景としたリスク回避の円買い・ドル売りの流れは早朝までにひとまず一巡。IHSマークイットがこの日発表した英国とユーロ圏の製造業購買担当者景況指数(PMI)速報値がともに上振れしたことも材料視された。 一方、米商務省が朝方発表した2月の耐久財受注は、前月比1.1%減と、市場予想(ロイター通信調べ)の0.8%増に反してマイナスとなったものの、市場の反応は限定的だった。 ユーロは同時刻現在、対ドルで1ユーロ=1.1830~1840ドル(前日午後5時は1.1845~1855ドル)、対円では同128円55~65銭(同128円61~71銭)と、06銭の円高・ユーロ安。(了)〔米株式〕NYダウ、反発=ナスダックは続落(24日午前)時事通信 【ニューヨーク時事】24日午前のニューヨーク株式相場は、半導体工場の新設を発表したインテルが上昇を主導し、反発して始まった。午前10時現在は、優良株で構成するダウ工業株30種平均が前日終値比227.92ドル高の3万2651.07ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は51.91ポイント安の1万3175.79と、続落している。 世界的に半導体不足が深刻化する中、インテルは23日、200億ドルを投じて西部アリゾナ州に二つの新工場を建設する計画を発表。アジア勢が高いシェアを占める半導体の製造受託事業にも乗り出すとした。これを受け、インテルのほか、ラム・リサーチやアプライド・マテリアルズなどの半導体関連企業が上伸し、朝方の株高をけん引している。 この日発表された米経済指標は、2月の耐久財受注が10カ月ぶりにマイナスに転じたほか、IHSマークイット調査の3月の総合購買担当者景況指数(PMI)速報値も59.1と、前月の59.5から低下。ややさえない結果となったものの、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長とイエレン財務長官による2日目の議会証言などを前に、ダウ平均は堅調を維持している。 個別銘柄を見ると、化学大手ダウ、キャタピラーなどの景気敏感株や、アメリカン・エキスプレス、シェブロンなどに買い戻しが先行。半面、新株発行の可能性が明らかになったゲームストップは18%超急落している。(了)今夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中の2銘柄が値を上げてスタートしましたね。エッツィが下げていますね。さあ希望価格まで下りてきますかね~?
2021.03.24
コメント(0)
-

3月23日(火)…
3月23日(火)、晴れです。良い天気です。そんな本日は7時15分頃に起床。新聞に目を通し、朝食を済ませ、ロマネちゃんと戯れる。本日は母の四十九日の法要です。10時からですから、それまでにお寺さんを迎える準備…。法要が済んだところで、お墓で納骨を済ませ、お寺でお参りをして、可児市のフレンチ「ラ・ミラベル」さんで会食。会食のメインは牛茶でした。帰宅して、着替えて、来客を送り出して、お寺へ挨拶に伺う。ここで一大事…。帰宅したらロマネちゃんがいません…。来客の送り出しでバタバタしている時に外へ出てしまったのだろうか…?どこを探しても見つかりませんからしばらく玄関を開けて様子見です…。1USドル=108.74円。1AUドル=83.57円。昨夜のNYダウ終値=32731.20(+103.23)ドル。本日の日経平均終値=28995.92(-178.23)円。金相場:1g=6746(-6)円。プラチナ相場:1g=4645(-2)円。昨夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中のすべてが値を上げて終了しましたね。5%以上の大きな変動は見られませんね。本日の東京市場ではチェック中の日本株30銘柄中の4銘柄が値を上げて終了しましたね。重点3銘柄ではすべてが値を下げて終了しましたね。ひらまつが大きく下げましたね。日本株続落、米金利一服や欧州新型コロナ拡大重し-銀行など広く下げ 23日の東京株式相場は続落。米国の長期金利の上昇が一服する中で、銀行などのバリュー(割安)株に売りが広がった。欧州での新型コロナウイルスの感染懸念も重しとなり、海運や鉄鋼株など直近の上げが目立った業種を中心に内外需とも広く下げた。 TOPIXの終値は前日比18.70ポイント(0.9%)安の1971.48 日経平均株価は178円23銭(0.6%)安の2万8995円92銭 〈きょうのポイント〉 22日の米国10年債利回りは1.69%と3ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下 メルケル独首相、復活祭期間中の厳格なロックダウンで州首相らと合意 アジア時間23日の米S&P500種Eミニ先物は軟調推移 バイデン米政権、最大330兆円規模の長期経済プログラムを検討中-関係者 東洋証券の大塚竜太ストラテジストは「このところ上昇が目立っていた銀行や海運など割安株に利益確定売りが出ている。景気回復期待を前提として、株価が上げ過ぎた面がある」と述べた。米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長は23日の議会証言で、米経済は力強さを増しているとみられるものの、新型コロナウイルス禍による打撃からの完全回復にはなお程遠いとの認識を示す見込みだ。 米金利低下を好感して朝方こそ電機や情報・通信株が上昇して株価指数は高くなったものの、金利上昇が追い風となっていた銀行などバリュー株の下げのほうが次第に強まり株価指数は失速した。東証33業種で直近1カ月の上昇率上位だった銀行と同様に、海運や鉄鋼などにも売りが膨らんだ。 過去1カ月で新規感染者の増加ペースがほぼ倍増したドイツでは、復活祭期間中の厳格なロックダウンで合意した。りそなアセットマネジメントの下出衛チーフストラテジストは「足元では欧州で新型コロナ感染拡大の話が出ている」とし、市場の期待している景気回復に逆行するような動きもあるとみていた。 一方、日銀の上場投資信託(ETF)買い入れでの日経平均連動型の除外方針を受けて以降は主要株価指数にボラティリティー(変動性)が高まる場面はあったが、この日は株価指数間の動きは小康状態だった。 東証33業種では空運や海運、陸運、銀行、鉄鋼、非鉄金属、機械が下落 その他製品は上昇米国株上昇、ハイテク中心に買い-国債利回り低下が支え 22日の米株式相場は上昇。米10年債利回りが低下し、約1年2カ月ぶり高水準を離れたことを追い風に、テクノロジー銘柄中心に買われた。 米国株は主要3指数が上昇、ハイテク銘柄が主導 米国債は上昇、10年債利回り1.69%に低下 ドル下落、米国債利回り低下で投資妙味が後退 NY原油は小幅続伸、需要回復見通しが市場の焦点 NY金は反落、米国債入札を控え神経質な展開 大型ハイテク銘柄中心のナスダック100指数は、S&P500種株価指数を上回る伸びとなった。小型株は比較的振るわなかった。一連の米国債入札が控えているほか、米金融当局が大手銀行の資本優遇策を予定通り今月末で終了すると決定したこともあり、国債市場の動向が引き続き注目を集めている。 S&P500種は前週末比0.7%高の3940.59。ダウ工業株30種平均は103.23ドル(0.3%)高の32731.20ドル。ナスダック総合指数は1.2%上昇。ニューヨーク時間午後4時55分現在、米10年債利回りは3ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の1.69%。 ベアードの投資戦略アナリスト、ロス・メイフィールド氏は「長期債利回りの上昇は、高成長銘柄の売り浴びせから景気敏感銘柄へのローテーションに至るまで、株式市場で見られたほぼ全ての動きに影響している」と指摘。「金利が多少安定する局面は常に、ハイテク株の上値追いのきっかけになる」と説明した。 米リッチモンド連銀のバーキン総裁は、経済成長の加速が望ましくないインフレ加速につながったり、金融政策調整の必要性をもたらしたりする兆候は見られないとインタビューで指摘。望まないインフレが根付くためには、物価上昇期待が動き、経営判断や賃金交渉に織り込まれ始める必要があると説明した。 外国為替市場では、主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数が下げ、ほぼ2週間ぶりの高水準を離れた。米国債利回りが低下し、ドルの投資妙味が後退した。ポンドはドルとユーロに対し下落。新型コロナウイルスワクチンの配布を巡る英国と欧州連合(EU)の対立継続が背景にある。 ドル指数は0.1%低下。早い時間にはトルコ・リラ急落を受けたリスク回避ムードの広がりで上昇していた。ドルは対円で0.1%安の1ドル=108円82銭。ユーロは対ドルで0.3%高の1ユーロ=1.1934ドル。一時は1.1947ドルまで値上がりした。ポンドは対ドルで0.1%安の1ポンド=1.3865ドルと、一時の0.4%安から下げ幅を縮小した。 ニューヨーク原油先物相場は小幅続伸。欧州の一部でロックダウン(都市封鎖)が再開、もしくは延長されるなど、国・地域によって需要回復ペースにむらがあることが嫌気されたが、バイデン政権による景気刺激策を背景に米国での消費回復に期待が集まっている。 ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物4月限は前営業日比13セント(0.2%)高い1バレル=61.55ドルで終了。4月限は22日が最終取引。実質の中心限月となった5月限は12セント高の61.56ドルで引けた。ロンドンICEの北海ブレント5月限は9セント上昇し64.62ドル。 ニューヨーク金市場ではスポットと先物がいずれも反落。米国債の入札を控え、投資家は利回りがまた上昇する可能性に身構えている。金相場は先週までは週間ベースで2週連続で上昇していた。 金スポットはニューヨーク時間午後2時19分現在、0.3%安い1オンス=1740.24ドル。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物6月限は、0.2%下げて1740.40ドルで終了した。アップルとテスラ、時価総額3兆ドル到達も-ウォール街で予想増える 電気自動車(EV)や自動運転車の販売に後押しされ、米アップルとテスラの時価総額が2030年までにそれぞれ3兆ドル(約330兆円)に達するとの見方がウォール街の専門家の間で増えている。 ただ両社の株価は今年に入って低迷している。アップルは7%、テスラは約5%それぞれ値下がりし、S&P500種株価指数(4.9%上昇)のパフォーマンスを大幅に下回る。それでも自動運転車の将来に大きな期待をかける一部のアナリストや投資家の熱狂は衰えを知らない。 キャシー・ウッド氏が率いるアーク・インベストメント・マネジメントは、テスラが5年以内に完全な自動運転車を実現する確率を50%と試算する。ウッド氏はテスラの目標株価を3000ドルに引き上げた。この水準に基づく時価総額は約3兆ドル。ニュー・ストリート・リサーチのアナリスト、ピエール・フェラギュ氏も同社の時価総額が30年までに2兆3000億ー3兆3000億ドルに達し得ると予想している。 一方、シティグループのアナリスト、ジム・スーバ氏はアップルカー開発で同社の売上高は2024年以降に最大15%増える可能性を指摘した。 パーパス・インベストメンツのグレッグ・テイラー最高投資責任者(CIO)は「テスラは、将来への楽観論と手掛けている事業に関する楽観論を重視するモメンタム株の典型例だ」と指摘。「逆にアップルは、ほぼ新しいディフェンシブ銘柄になっている。バランスシートはトップクラスだ。株式市場全体が買い優勢の時にアップル株も買われる」と述べた。 テスラの株価は22日に2.3%高の670ドルで取引を終え、これに基づく時価総額は約6430億ドル。一方、アップルの時価総額は約2兆ドルで、既に世界最大。【本日のNYダウ見通し】パウエルFRB議長とイエレン財務長官の公聴会証言に注目【NYダウ予想レンジ:32,500~32,900ドル】22日のNYダウは3営業日ぶりに反発。前週末比103.23ドル高の32,731.20ドルで取引を終了しました。米10年債利回りが前週の1.7%台から1.6%台に低下。相対的な割高感が低下したIT・ハイテク株に押し目買いが入りました。注目を集めたのがテスラ株です。著名投資家のウッド氏の率いるアーク・インベストメントが、テスラの株価が2025年に3,000ドルに達するとの見通しを述べ、テスラ株は2.31%の上昇となりました。ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数も、前週末比162.307ポイント高の13377.542で取引を修了しています。本日の経済指標では、新築住宅販売件数が注目されます。また、パウエルFRB議長とイエレン財務長官の公聴会での証言があるので、マーケットの関心を集めるでしょう。日経平均は3日続落、米長期金利の動向巡る不透明感続く[東京 23日 ロイター] -東京株式市場で日経平均は3日続落した。前日の米株高を好感し朝方は堅調に推移したものの、依然として、米長期金利など外部環境の不透明感がくすぶる中、日経平均はマイナス圏で取引を終えた。このところ物色が活発になっていたバリュー株でも利益確定売りの動きがみられ、幅広い業種で売りが先行した。市場の関心が集まる米10年債利回りは、足元では高止まりとなっている。米長期金利の動きをにらみ「市場はナーバスになっている」(岡三オンライン証券のチーフストラテジスト、伊藤嘉洋氏)との指摘が聞かれ、「金融相場から業績相場へ移行する過程でマーケットは不安定な動きになりやすい」(伊藤氏)という。一方、相場全体がさえない動きとなる中、業績見通しの上方修正など個別材料を手掛かりにした物色もみられた。米長期金利の動向に神経質になりやすい環境が続くが、今後緩やかな金利上昇がみられたとしても、「企業業績に関して上方修正や増配などのよいニュースが出れば、市場にとって追い風になるだろう」(野村証券のエクイティ・マーケット・ストラテジスト、澤田麻希氏)という。日経平均は当面、2万9000円台で値固めの動きが続くとみられており、「上値としては25日移動平均線(2万9596円79銭=23日)の水準が意識されそうだ」(伊藤氏)との見方も出ていた。TOPIXは0.94%安で取引を終了。東証1部の売買代金は2兆8900億円。東証33業種中、その他製品以外の32業種は値下がり。空運業、海運業、陸運業などが値下がり率上位に入った。個別では、日本取引所グループが続伸し、2.7%高。前日の昼休み中に発表した業績見通しと配当の上方修正が引き続き好感された。昭文社ホールディングスは16%高となり、ストップ高。お昼過ぎごろ、子会社の昭文社とポニーキャニオンが地方創生事業で業務提携すると発表したことが好感された。「低位株で買いやすく、好材料をきっかけに短期筋の個人投資家による値幅取りを狙った買いが集中したようだ」(国内証券)という。東証1部の騰落数は、値上がり391銘柄に対し、値下がりが1748銘柄、変わらずが55銘柄だった。16時頃にひょっこりロマネちゃんが現れる…。いったいどこにいたの~?どうやら片付け物をしている時に押し入れの奥へ入ったようですね…。そのまま爪切りされました。巨大病院クラスター収束 岐阜、231人陽性共同通信社 岐阜県は22日、231人まで拡大した木沢記念病院(美濃加茂市)のクラスター(感染者集団)が収束したと発表した。死者は高齢者を中心に入院患者ら26人に上った。県によると、PCR検査した上で入院させていたが、感染者なのに陰性の結果が出た人が複数いたため、気付かぬまま、患者や職員を介し、病室や病棟を越えて拡大した可能性があるという。 県によると、2月2日に病院から最初の感染報告があった。3月7日までに職員97人、患者94人、職員や患者の家族ら40人の陽性が判明。その後、新たな感染者が14日間出なかったとして、22日に収束を確認した。 調査に携わった「ぎふ綜合健診センター」の所長、村上啓雄(むらかみ・のぶお)・岐阜大名誉教授は「全ての患者を個室に入れ、検査を繰り返した上で、大部屋に移す運用」が望ましいとする一方で、「現実的には難しい」と指摘。同病院の事例を県内の病院に周知、工夫して可能な対策を取るよう注意喚起しているとした。 また、感染しやすい場面として食事や入浴の介助、口腔(こうくう)ケアを挙げ「マスクができない状況もある。できることを最大限していくしかない」と述べた。国の対策班が詳しい報告をまとめる方針。【Cクラスの最上位モデル】メルセデスAMG 次期C 63eにF1技術導入 2022年発売予定〔東京外為〕ドル、108円台後半=材料難で様子見気分広がる(23日午後3時)時事通信 23日午後の東京外国為替市場のドルの対円相場(気配値)は、材料難のため様子見気分が広がり、1ドル=108円台後半で動意薄となっている。午後3時現在、108円74~75銭と前日(午後5時、108円68~68銭)比06銭の小幅ドル高・円安。 前日の海外市場では、米金利の上昇を受けてドルが108円60銭台から108円80銭台半ばへ強含んだ後、金利の上昇一服で伸び悩んで108円70銭台を中心に取引された。 東京時間は午前中、輸入企業による決済資金調達に加え、日経平均株価の3営業日ぶりの反発を受けた円売りで108円80銭台を付けた。しかし、日経平均が伸び悩み、米金利が1.7%を割り込んだのと歩調を合わせる形で一時108円60銭台へ軟化した。 午後に入ると、売買の手掛かりが見当たらないため取引は低調で、108円70銭台でこう着気味に推移している。日本時間夜にパウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長の議会証言や米2年債入札が予定されることもあり、「模様眺めの市場参加者が多い」(邦銀)という。ドル円相場について、市場では「米金利に左右される基調が続く」(同)との見方が根強い。ただ、このところ値動きは一定の範囲にとどまり、「上値が重く、下値も堅い状況を変える材料がない」(外為仲介業者)格好だ。 ユーロは午後に入って対円、対ドルとも小動き。午後3時現在は1ユーロ=129円66~73銭(前日午後5時、129円17~24銭)、対ドルでは1.1923~1927ドル(同1.1884~1884ドル)。(了)〔東京株式〕3日続落=売り優勢に(23日)☆差替時事通信 【第1部】前日の米株高の流れを受け反発で始まったが、アジア主要株式市場の下落を横目に、午後に入って売りが優勢となり、日経平均株価は前日比178円23銭安の2万8995円92銭と、3日続落した。東証株価指数(TOPIX)も18.70ポイント安の1971.48と続落。 銘柄の80%が値下がりし、値上がりは18%だった。出来高は13億7129万株、売買代金は2兆8900億円。 業種別株価指数(33業種)は空運業、海運業、陸運業、銀行業の下落が目立ち、上昇はその他製品。 個別銘柄ではソフトバンクG、ファーストリテが売られ、トヨタも小甘い。三菱UFJ、三井住友が軟調。JAL、ANAが値を下げ、楽天、資生堂も急落。半面、任天堂がしっかり。東エレク、ソニー、キーエンスが小高い。エムスリー、Jパワーは堅調で、NTT、KDDIは小じっかり。 【第2部】反落。千代化建、ギグワークスが値を下げた。半面、Gダイニングがストップ高。黒田精も高い。出来高2億1524万株。 ▽個人の買い意欲続かず 日経平均株価は午前の寄り付きで反発して始まり、一時2万9500円近くまで値を上げた。しかし、その後は米欧との対立が顕著な中国の景気への先行き懸念から、アジア主要株式市場が軟調に推移するのを横目に下落に転じた。 日経平均への寄与度が高いファーストリテが値を消すなど、値がさ株に軟調な動きが相次いだ。市場では「個人投資家中心の相場で、買い意欲が持続しなかった」(国内証券)との指摘が聞かれた。空運業や海運業など人やモノの動きに関係する銘柄が売られがちとなり、「変異した新型コロナウイルスが経済の先行きに悪影響を及ぼすとの懸念も消えていない」(大手証券)との声も聞かれた。 225先物6月きりは軟調。(了)日経平均は3日続落、米金利上昇への警戒感根強く、29000円割れで安値引け/相場概況フィスコ現在値Fリテイリ 86,800 -90ソフトBG 9,775 -89トヨタ 8,304 -58三菱UFJ 632.7 -21.20郵船 3,900 -165 日経平均は3日続落。22日の米国市場でNYダウは反発し、103ドル高となった。長期金利の上昇一服が好感され、ハイテク株比率の高いナスダック総合指数は1.2%の上昇。本日の日経平均はこうした流れを引き継いで207円高からスタートすると、朝方には29496.83円(前日比322.68円高)まで上昇する場面があった。ただ、米政権が新たな経済対策を計画しているとの報道などから米金利上昇に対する警戒感は根強く、香港などのアジア株が軟調だったこともあり、後場の日経平均はマイナスに転じ安値引けした。 大引けの日経平均は前日比178.23円安の28995.92円となった。終値で29000円を下回ったのは今月8日以来。東証1部の売買高は13億7129万株、売買代金は2兆8900億円だった。業種別では、空運業、海運業、陸運業が下落率上位で、その他も全般軟調。上昇したのはその他製品のみだった。東証1部の値下がり銘柄は全体の80%、対して値上がり銘柄は18%となった。 個別では、ファーストリテが小安く、ソフトバンクGやトヨタ自はさえない。このところ堅調だったバリュー(割安)株に売りが出て、三菱UFJなどのメガバンク株や郵船などの海運株は軟調ぶりが目立った。JALやANAといった空運株は国内線予約の増加が伝わったが、材料出尽くしムードから大きく下落。また、わかもとが急反落し、ストップ安水準で取引を終えた。 一方、米ハイテク株高の流れから任天堂、東エレク、ソニー、エムスリーといった値がさグロース(成長)株が堅調。ポニーキャニオンとの提携を発表した昭文社HDはストップ高を付け、ミクシィとの提携を発表したハブは買い気配のままストップ高比例配分となった。株式分割の実施等を発表したコーア商事HDなども東証1部上昇率上位に顔を出した。《HK》明日の戦略-3日続落で29000円割れ、混乱長期化を懸念もどっしり構える局面かトレーダーズ・ウェブ 23日の日経平均は3日続落。終値は178円安の28995円。米国株の上昇を好感して3桁高からのスタートとなり、早々に上げ幅を300円超に広げた。しかし、節目の29500円に迫ったところで伸びが止まると、一転して値を消す展開。ファーストリテイリングやファナックなど、このところ弱い値がさ株が買い先行から失速したことで、全体にも警戒感が広がった。前場ではプラス圏を維持したものの、後場の早い時間にマイナス転換。そこからは失望売りが優勢となり、下げ幅を3桁に広げた。29000円を割り込むかというところでは、しばらく踏みとどまった。しかし、引けにかけての売りで29000円を割り込み、安値引けとなった。TOPIXも後場に下げに転じて安値引け。ジャスダック平均は13日ぶりに反落した。 東証1部の売買代金は概算で2兆8900億円。業種別では上昇はその他製品の1業種のみで、電気・ガスやゴム製品が相対的に値を保った。一方、空運と海運が突出した下げとなったほか、陸運が大きく売られた。ミクシィとの業務提携を発表したハブが、場中は値が付かずストップ高比例配分。半面、ミクシィは上昇して始まったものの、買いが続かず大幅安となった。 東証1部の騰落銘柄数は値上がり391/値下がり1748。Nianticとアプリを共同開発していると発表した任天堂が強い上昇。東京エレクトロンは米国のハイテク株高を好感した買いが入った。グロース株が見直される中でエムスリーやソニーも上昇。今期の営業黒字見通しを提示したRIZAPが大幅高となった。Eストアーが日経新聞の特集記事を手掛かりに急騰。子会社による大口受注を発表したナガオカがストップ高まで買われた。 一方、米国の長期金利低下を嫌気して、三菱UFJが3%を超える下落。バリュー系を中心に足元で高値圏にある銘柄を手仕舞う動きが多く見られており、JAL、ANAなど空運株や、日本郵船、川崎汽船、商船三井など海運株が大きく値を崩した。メディア報道を材料に楽天が急落。海外でのファイナンスを発表したフリーが大幅安となった。わかもと製薬は前日までストップ高が連発していたが、きょうは一転して売り気配スタート。売り場がほとんどなくストップ安となった。 日経平均は一時300円超上げたところから3桁の下落となり、29000円も割り込んだ。きょうのファーストリテイリングは失速しただけで0.1%の下げにとどまっており、指数への直接的な悪影響は限定的。しかし、同社やファナックなど値がさ株が敬遠される状況が続けば、日本株に対する先高期待が後退する。日銀のETF買い入れルール変更により相対優位が見込まれるTOPIXも安値引けとなっており、混乱が長引くようだと値持ちの良かったものを売り急ぐ傾向が強まる可能性がある。 ただ、日銀は金融引き締めにまで舵を切ったわけではない。ルール変更の悪影響があまりにも大きいのであれば、施策を再見直しすることもあり得る。これまで株高を支えてきたワクチン普及や経済活動正常化への期待に対する見方に変化が生じたわけでもない。テクニカル面では、13週線(28850円、23日時点、以下同じ)までで反転する展開に期待したいところだが、26週線(26935円)が控える27000円あたりまでの下げはあるかもしれない。しかし、そこまで下げてもまだ調整の範囲内。日本株弱気論者からすれば、日銀の限界が露呈して暴落シナリオが始まったように見えなくもないが、そこまで悲観に傾くのは早計だ。本日はゴミ出しもありました。朝にはゴミ袋15個を集積所まで車で運ぶ…。夕方には粗大ごみ3点を集積所まで車で運ぶ…。それぞれ2往復でした。今晩のNY株の読み筋=パウエルFRB議長、イエレン財務長官の議会証言に注目モーニングスター 23日の米国株式市場は、米長期金利の動きをにらみつつ、パウエルFRB(米連邦準備制度理事会)議長およびイエレン財務長官の下院での証言に注目が集まりそうだ。 22日の米国株式市場は、長期金利の上昇が一服し、ハイテク株を中心に買い戻しの動きが広がり、主要3指数は揃って上昇した。 23日も2月新築住宅販売件数を受けて、米長期金利や株価指数が反応する場面もあるとみられるが、午後のパウエルFRB議長、イエレン財務長官の議会証言までは小幅な推移にとどまるとみられる。一方、議会証言ではコロナウイルス支援・救済・経済安全保障法がテーマ。市場との対話を意識したフェーバーなコメントが出されれば、米長期金利の上昇を抑制し、株式市場に買い安心感が広がるとみられる。 このほか、複数のFRB高官に発言機会がある。17日のFOMC(米連邦公開市場委員会)で23年末までゼロ金利政策を維持する方針が示されたが、FRB高官の見解の違いが鮮明となれば、早期利上げ観測再燃につながりかねないので、注視したい。<主な米経済指標・イベント>20年10-12月期経常収支、2月新築住宅販売件数、2年国債入札、パウエルFRB(米連邦準備制度理事会)議長およびイエレン財務長官が下院金融サービス委員会で証言、ボスティック・アトランタ連銀総裁、バーキン・リッチモンド連銀総裁、ブレイナードFRB理事、ウイリアムズNY連銀総裁が講演会・討議会に参加(日付は現地時間)◎投資関連情報は投資の参考として情報提供のみを目的としたものであり、株式の売買は自己責任に基づき、ご自身で判断をお願いします。明日の日本株の読み筋=不安定な相場付きか、米長期金利にらみ続くモーニングスター あす24日の東京株式市場で、主要株価指数は不安定な相場付きか。米長期金利にらみの展開が続くとみられ、米国の金利・株式が落ち着けば、日経平均株価は直近3連敗の反動で上昇する可能性がある。ただし、23日の同指数が朝高後に失速したように押し目買い意欲は一時に比べて後退しており、外部要因のフォローがないと調整が尾を引くことも予想される。市場では、「業績・景気回復やワクチンへの期待などがいったん一巡し、材料的に行き詰まった感がある」(国内投信)、「月末や年度末を控えて、やりにくく、目先はもみ合いか」(中堅証券)などの声が聞かれ、新たな手掛かり材料がないと買い気は高まりにくいとみられる。 23日の日経平均株価は3営業日続落し、2万8995円(前日比178円安)と安値で引けた。朝方は、米長期金利の低下を背景に22日の米国株式市場でハイテク株中心に上昇した流れを受け、買いが先行した。きのう大幅続落した反動もあり、前場の早い段階で上げ幅が一時320円を超えた。ただ、先行きの米金利上昇への警戒感もあり、一巡後は上げ幅を縮小し、後場入り後には下げに転じた。時間外取引の米株価指数先物が安く、中国・上海総合指数や香港ハンセン指数の下げも重しとなり、大引けにかけて弱基調となった。チャート上では、心理的なフシ目となる2万9000円を割り込み、下げに歯止めが掛かるかどうかが注目される。〔ロンドン外為〕円、108円台後半(23日午前9時)時事通信 【ロンドン時事】23日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、持ち高調整の中を1ドル=108円台後半で推移した。午前9時現在は108円70~80銭と、前日午後4時(108円60~70銭)比10銭の円安・ドル高。 ユーロの対ドル相場は1ユーロ=1.1895~1905ドル(1.1925~1935ドル)。対円では同129円35~45銭(129円60~70銭)。(了)ミナミ、地価28%急落の衝撃 「爆買い」の手痛い反動朝日新聞デジタル 23日に公表された公示地価は、新型コロナウイルスの影響を色濃く映した内容となった。都心の繁華街を中心に地価が急落し、住宅地などを含めた全用途の全国平均が6年ぶりに下落に転じた。昨年後半には一部に下げ止まりの兆しも見られたが、コロナの収束が見通せないなか、先行きは不透明なままだ。 グリコの看板でおなじみの大阪・ミナミの道頓堀の一角。フグの大ちょうちんで有名な老舗フグ料理店「づぼらや」が昨年9月に閉店した。コロナの影響で4月に休業し、そのまま100年の歴史に幕をおろした。閉店から半年がたつ今でも看板が残り、テナントは決まっていない。 ビルを管理する大貴不動産(大阪市)によると、問い合わせは数件だけで、いずれも具体的な賃料交渉には至っていない。営業担当は「コロナ前の相場ならビル全体(6階)で月1200万円の賃料が見込めた。賃料は二の次で連絡が殺到する好立地物件だったのに」と話す。 コロナ前は、一帯は訪日外国人客が「爆買い」に押し寄せ、飲食店もにぎわっていた。このビルの前年の公示地価も1平方メートルあたり805万円と、7年間で4・7倍に上がり、前年も23・8%の上昇だった。ところが、今年は一転、28・0%の下落と急降下。全国最大の下落率となった。 訪日客の激減に加え、飲食店も時短営業で撤退が相次いだ。全国の商業地の下落率トップ10のうち、大阪市の繁華街は8地点を占める。大阪の繁華街は、訪日客の需要で地価が急上昇していただけに、反動も大きかったとみられる。 不動産サービスJLLの大東雄人ディレクターは最近の大阪の地価について、「ドラッグストアなどは爆買いで『そんな高くて払えるのか』というくらい賃料が上がっていたが、コロナで剝落(はくらく)した」と解説する。 づぼらやが面していた通りを500メートルほど歩くと、20を超す店のシャッターが閉じている。ほとんどがコロナ禍で休業や閉店に追い込まれた。不動産関係者は「以前は1平方メートルあたり30万円超でも複数社から引き合いがあった。今は6万円ほどでも借りてくれない」とため息をつく。 コロナで地価が反転したのは、ほかの都市部でも同じだ。東京では、商業地の価格で毎年全国1位の銀座4丁目が前年の0・9%上昇から7・1%の下落に。名古屋も中心地の久屋大通駅前が同11・5%上昇から15・2%の下落へと急落した。マイクロソフトがディスコード買収で交渉、100億ドル強-関係者 米マイクロソフトは、ビデオゲーム・チャットコミュニティーを運営するディスコードの100億ドル(約1兆880億円)余りでの買収を目指し、同社と交渉している。事情に詳しい複数の関係者が明らかにした。 非公開情報を理由に関係者が匿名を条件に語ったところでは、ディスコードは複数の潜在的な買い手と接触しており、マイクロソフトも名乗りを上げているが、差し迫って合意が成立する見通しはないという。ディスコードは身売りよりも株式を公開する可能性の方が高いと関係者の1人は述べた。 マイクロソフトとディスコードの担当者は、いずれもコメントを控えている。ディスコードの身売り協議についてはベンチャービートが22日に先に伝えていた。 ディスコード(本社サンフランシスコ)は、ゲーム愛好家がビデオ・音声通話で交流できる無料サービスで知られるが、新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)の下で、研究会やダンス教室、読書会などバーチャルコミュニティーの利用が拡大し、月間のアクティブユーザー数が1億人を超えた。 マイクロソフトは昨年、北京字節跳動科技(バイトダンス)が運営する短編動画投稿アプリ「TikTok(ティックトック)」の米国事業などの買収を目指し、画像検索収集サービスのピンタレストにも買収を打診したと伝えられた。事情に詳しい関係者によると、マイクロソフトは盛んなユーザーコミュニティーへのアクセスを提供する資産を物色しているという。【市況】明日の株式相場に向けて=中低位バリュー系材料株に照準 きょう(23日)の東京株式市場は、日経平均株価が178円安の2万8995円と3日続落。日銀がETF購入手法について日経平均連動型を除外すると発表したことが、予想以上に全体相場のバランスを崩す要因となった。 世界的な株高に乗って日経平均が3万円台の景色を普通に見るような状況になってから、果たして日銀のETF買いは必要なのかという議論、そして出口戦略に向けた思惑は当然出てくる。それについて日銀が言及することをマーケットはひそかに恐れていたわけだが、日銀のETF買いを自転車の補助輪に例えるならば、最近の東京市場はほとんどそれを必要としないで、純粋な2輪の状態で快走していたというのが実際のところである。押し目を拾いたくても日銀が拾ってしまうのはむしろ迷惑で、補助輪は邪魔というのがひとつのコンセンサスでもあった。結果として、ファーストリテイリングの急落は想定されたことだが、理屈に反しきょうはメガバンクの三菱UFJフィナンシャル・グループなども大幅に値を下げ前週末の終値を既に下回っている。 つまりこれは日銀ショックとみるのはあくまで表向きで、本質は期末の機関投資家の決算対策売りに売り方の仕掛けが加わって演出された部分が大きい。現実問題、前日に日銀は今月5日以来となるETF砲を轟かせ501億円を買い入れている。今はテーパリングに向けた動きは匂わせたくないというのが日銀の胸の内のはず。投資家サイドは、押し目買いのチャンスを得ているが、その際どこに資金を振り向けるかは結構重要となってくる。 “日銀ETFショック安”を契機に値がさグロース系の銘柄に不利なイメージがコンセンサスとして醸成されるなか、相対的に中低位株は追い風とは言わないまでも風向きが良くなっている。ポイントとなっているのは今期ではなく、来期業績回復のシナリオに乗る銘柄ということ。そしてバリュー系の銘柄、低PBR株の一角に復権の兆しがある。今のグロースからバリューへのシフトは長期的なトレンドになるとは思えないが、ワクチンの普及によって新型コロナウイルス収束が実現性を高め、それに比例して金利上昇に対するマーケットの関心が高まっている過程においては今の流れが基本的に続くと思われる。 昨年来何度か取り上げてきた藤倉コンポジットは、派手な上昇パフォーマンスこそないが、年初から一貫した上値追いトレンドを形成している。依然としてPBRが0.5倍弱。前期実績比2円減配とはいえ今3月期年間配当12円を実施する会社が、解散価値の半値以下というのはさすがにまだ安いと判断される。空気電池や風力発電向け保護シートなど新エネ関連の材料も内包している。これに来期業績の回復シナリオが加われば、というのが現在流入している投資資金の言い分であろう。 藤コンポもそうだが、自動車部品や部材など自動車周辺に位置する銘柄群は来期業績の回復シナリオに乗りやすい。自動車向けダイカスト大手のアーレスティは今3月期大幅赤字を余儀なくされそうだが、来期は黒字転換が有力視される。無配ながらPBRは0.2倍ソコソコで解散価値の半値どころか5分の1であり、目先の押し目は買い向かって妙味がある。また、自動車生産回復でハイブリッド車(HV)向け水素吸蔵合金など電池材料の回復が期待される新日本電工も低PBRで株価は300円台と値ごろ感があり、電気自動車(EV)関連の穴株として光が当たる可能性がある。EV電池材料では関東電化工業も強い足でマークしておきたい。 きょうは反動安に見舞われたが、ここ急速人気化していた海運株はコンテナ市況の高騰に加え、ばら積み船市況の急回復が追い風となっている。その収益環境が様変わりしている海運業界の恩恵を受けるのが、リース案件組成を手掛けるFPG。きょうは9日ぶりに反落しているが、前日まで7営業日連続で陽線が続いており、短期トレードではないファンド組み入れ系の実需買いが入っている感触がある。このほかでは、材料株素地が高くアフターコロナで恩恵の大きい国際チャートなどにも目を配っておきたい。 あすのスケジュールでは、日銀金融政策決定会合の議事要旨(1月20~21日分)、2月の企業向けサービス価格指数など。なお、ジャスダック市場にシキノハイテック、東証マザーズ市場にSharing Innovationsが新規上場する。海外では、3月のユーロ圏PMI速報値、3月の米製造業PMI速報値、2月の米耐久財受注など。また、パウエルFRB議長が米上院で議会証言を行う。(銀)出所:MINKABU PRESSNY株見通し-金利をにらみ神経質な展開か パウエルFRB議長議会証言に注目トレーダーズ・ウェブ 今晩のNY市場は神経質な展開か。昨日は長期金利が低下したことやバイデン米大統領が3兆ドルのインフラ投資を検討と報じられたことで主要3指数がそろって上昇した。投資家の不安心理を示すVIX指数は昨年2月以来となる18.88ポイントまで低下するなどセンチメントも改善した。今晩の取引では、ワクチン接種進展による経済活動の正常化や3兆ドルのインフラ投資期待が下値支援となると予想されるものの、パウエルFRB議長とイエレン米財務長官の米下院金融サービス委員会での証言が予定され、両氏の発言を受けた長期金利の動向が引き続き焦点となりそうだ。 今晩の米経済指標・イベントはパウエルFRB議長とイエレン米財務長官の議会証言のほか、2月新築住宅販売件数、3月リッチモンド連銀製造業総合指数など。ブレイナードFRB理事、ブラード米セントルイス連銀総裁、ウィリアムズ米ニューヨーク連銀総裁などの当局者の講演や討議参加も多数予定されている。企業決算は寄り前にアドビ、ペイチェックスなどが発表予定。(執筆:3月23日、14:00)〔NY外為〕円、108円台半ば(23日午前8時)時事通信 【ニューヨーク時事】23日のニューヨーク外国為替市場の円相場は、午前8時現在1ドル=108円47~57銭と前日午後5時(108円78~88銭)比31銭の円高・ドル安で推移している。 ユーロは同時刻現在、対ドルで1ユーロ=1.1875~1885ドル(前日午後5時は1.1927~1937ドル)、対円では同128円88~98銭(同129円85~95銭)。(了)〔NY外為〕円、108円台半ば(23日朝)時事通信 【ニューヨーク時事】23日午前のニューヨーク外国為替市場では、円買い・ドル売りが優勢となった海外市場の流れを引き継ぎ、円相場は1ドル=108円台半ばに上昇した。午前9時現在は108円50~60銭と、前日午後5時(108円78~88銭)比28銭の円高・ドル安。 新型コロナウイルスの感染再拡大などを背景に欧州株が軟調。投資家のリスク回避姿勢が強まる中、安全資産とされる円が買われた。朝方の早い段階では米主要経済指標の発表もなく、ニューヨーク市場に入ってからも円高・ドル安の流れ。ただ、この日に行われるパウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長とイエレン米財務長官の議会証言を控えて様子見ムードも広がり、円相場は108円台半ばでもみ合っている。 ユーロは同時刻現在、対ドルで1ユーロ=1.1885~1895ドル(前日午後5時は1.1927~1937ドル)、対円では同129円05~15銭(同129円85~95銭)と、80銭の円高・ユーロ安。(了)〔米株式〕NYダウ、ナスダックとも反落(23日朝)時事通信 【ニューヨーク時事】23日のニューヨーク株式相場は、パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長らの議会証言を控えて様子見気分が広がる中、反落して始まった。優良株で構成するダウ工業株30種平均は午前9時35分現在、前日終値比79.50ドル安の3万2651.70ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は10.23ポイント安の1万3367.31。(了)今夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中の11銘柄が値を上げてスタートしましたね。5%以上の大きな変動は見られませんね。買い希望のハイテク・グロース株はまだ届きませんね。
2021.03.23
コメント(0)
-
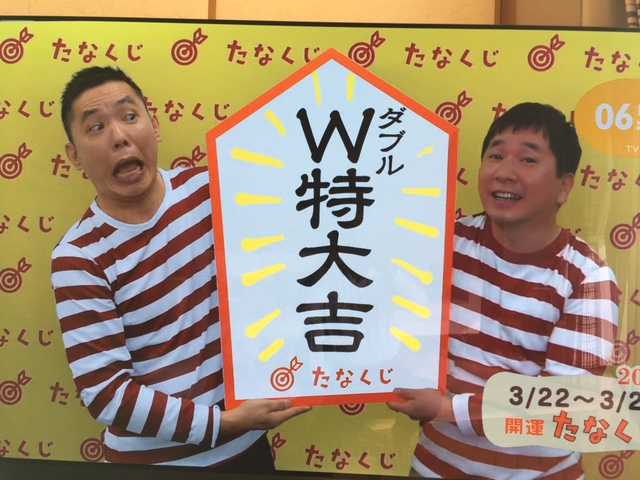
3月22日(月)…
3月22日(月)、晴れです。晴れて暖かですが、外へ出ると風が強いです。そんな本日は8時頃に起床。今週のたなくじは…新聞に目を通し、朝食を済ませ、ロマネちゃんと戯れる。本日のノルマは2階の掃除機と階段のモップかけですか…。ハイハイ…。朝のコーヒーブレイクはネスプレッソで…。もらい物のモロゾフのチョコレートと共に…。寸評は控えておきます…。母親宅の後片付け…。本日は簡単に…。お墓の掃除とお参りに…。風が強いので線香・ろうそくは止めですね。帰宅して庭に猫除け顆粒を散布。昨夜のロマネちゃんが庭へ侵入したよそネコとにらみ合っていましたからね…。ロマネちゃんは今朝も庭を眺めていますね…それでは一休みです。1USドル=108.83円。1AUドル=84.01円。現在の日経平均=29263.45(-528.60)円。金相場:1g=6752(+15)円。プラチナ相場:1g=4647(-64)円。本日の東京市場ではチェック中の日本株30銘柄中の14銘柄が値を上げていますね。重点3銘柄では1銘柄が値を上げていますね。5%以上の大きな変動は見られませんね。米株式市場がまもなく大暴落に至る仕組みを詳解 改めて断っておくが、私は悲観論者ではない。また、常に「大恐慌が来る」と脅かしてきたわけではない。 2009年2月に執筆した『日本「復活」の最終シナリオ 「太陽経済」を主導せよ!!』では、2008年9月に起きたリーマンショックから「戦前型大恐慌が起きない理由」を説明した。 事実、大恐慌が起きるどころか、今年までに米株式市場は最高値を更新してきた。 しかし、アフターコロナが見えてきたことで、今後大暴落すると想定せざるを得ない。しかも、リーマンショックとは違って、株式だけでなく債券とドルも大暴落するリスクが高い。 リーマンショックに際しては瞬時に形成された国際協調体制は、今は機能不全だ。そうなると、第2次世界大戦後初の事態である。 マーケットの大暴落から「21世紀型大恐慌」に至るリスクが高い。 どうしても警告しなくてはいけないと思い、昨年、2020年11月に、『21世紀型大恐慌 「アメリカ型経済システム」が変わるとき』(PHP出版)を書いた。詳しくはこちらを参照してほしい。米マーケット全体が大暴落のリスク 先進国を中心にワクチンの接種が進み、世界最大の犠牲者を出してきた米国でもアフターコロナが見えてきたと思われている。 新型コロナウイルス感染症の被害が世界に広がった昨年の初めから、米国を中心に世界の株式市場は上昇を続けた。アフターコロナになれば、世界のマーケットはどう動くのだろうか? このシリーズの前回のコラムでは、「アフターコロナが見えてきた米株式市場は大暴落すると想定せざるを得ない。しかも、リーマンショックとは違って、債券とドルも大暴落するリスクが高い」と述べた。 なぜだろうか。マーケットの上昇や暴落のメカニズムはどうなっているのだろうか。メカニズムが分かれば対処法も見えてくる。FRBがコントロールできない時代に 米国の経済と金融、そしてマーケットの仕組みの中心に存在するのが米国の中央銀行、FRB(連邦準備制度理事会)だ。 コロナはFRBにも影響を与え、FRBはマーケットに影響を与える。1980年からコロナ以前の2019年までは、FRBの政策をよく理解すれば、経済もマーケットも十分に予測可能だった。 しかし、FRBも常に万能ではない。1970年代まではFRBは経済もマーケットもコンロールできなかった。スタグフレーションと呼ばれた時代だ。 そして、2020年からのコロナをきっかけとして、再びFRBが経済とマーケットのコントロールできない時代に入ろうとしている。FRBの最大の道具がFF金利 下に示しているのがFRBの最大の道具であり政策金利といわれるFF金利(Fed Fund Rate)とインフレ率の過去60年間のグラフ①である。 驚くほどの変動を示しているのがお分かりいただけるだろう。 40年前にはFF金利は20%に近かった。歴史的にみたら今のゼロ金利やゼロインフレはとてもノーマルとは言えない。 なぜ、当時はそんな高金利になったのだろうか? 1970年代の米国は、「偉大な社会」建設を目指した福祉支出拡大とベトナム戦争支出で財政が急速に悪化した。 その上、中東戦争とイランイラク戦争を契機とした2つの「石油ショック」に見舞われ、インフレに襲われて市場の金利が急上昇した。急速に経済が悪化した。 当時のFRBは、景気刺激のために金利を引き下げようと通貨供給量を増やしたが、逆にインフレを高進させる「過剰流動性」を発生させて、金利はさらに上昇してしまった。 高金利に圧迫されて、企業の収益は急速に悪化し、消費や住宅需要は低迷した。 不景気とインフレーションが一緒にやってきたから、「スタグフレーション」という洒落た名前が作られたが、国民はたまったものではなかった。FF金利でインフレを退治したボルカー インフレを退治するのに成功したのが、ジミー・カーター政権末期の1979年にFRB議長に就任したポール・ボルカーだった。 ボルカーは、それまでとは逆の発想で、FF金利を大幅に引き上げて、市場に出回る通貨の量を大きく減らした。厳格な「通貨供給量政策」といわれた。 昨今のようにFRBが国債を大量に買って「流動性」つまりお金を供給することなどボルカーには論外だった。 FF金利の大幅な引き上げによってボルカーはインフレ率の大幅低下に成功し、金利も低下して、1980年から始まったロナルド・レーガン大統領時代の「強いアメリカ」を経済から支えた。 ボルカーによってようやく、FRBがFF金利で経済をコントロールできる時代が到来した。FRBの株式市場操作の道具もFF金利 次に掲げるグラフ②には、アメリカの経済とマーケットのエッセンスが詰まっている。 まず、黒い線が米国の金融当局であるFRBが決定するFF金利だ。FRBが民間銀行に強制的に預けさせる「準備預金」に付ける金利だから、民間銀行の「仕入れ値」であり、金利の「元締め」のような役割を果たす。 FF金利は、FRBが米国の経済とマーケットをコントロールする最大の道具である。 冷え込んでいる時にはFF金利を下げて温め(緩和)、過熱だと判断すればFF金利を引き上げて冷まそうとする(引き締め)。FF金利でマーケットをコントロール もちろん、FF金利は株式市場も動かす。 ゼロ金利になると、企業の収益が好転するだけでなく、ヘッジファンドや投資銀行といった米国株を動かしている主力投資家の「借入コスト」が劇的に改善する。 なぜなら、彼らは巨額の「レバレッジ」、つまり借り入れを行なっているから、金利が低下すると借入コストも「レバレッジ」、つまり自己資本に対する借入の倍数分低下するからだ。 例えば、レバレッジが5倍の場合、1%金利が上下すれば、自己資本に対する借入コストは5倍上下する。5%金利が上下すれば、自己資本に対する借入コストは25%変化する。 だから、金利を上げられればレバレッジ投資家の収支は大きく悪化し、金利が下がれば収支は大きく改善する。 投資家に投資資金を貸すのは民間銀行だが、銀行の金利は仕入れ値であるFEDのFF金利によって上下する。 つまり、FRBはFF金利を上下させることで、FRB→民間銀行→株式投資家の借入コスト→株式投資の収益性、という経路で株式市場に影響を与えることができる。 こうして、FF金利上げ(引き締め)→株式投資の収益性悪化、FF金利下げ(緩和)→株式投資の収益性改善、という経路で株式市場の上げ下げに影響を与えてきた。過去30年の米株式市場の上昇パターン 再び、グラフ②を見ていただきたい。 1990年から2019年末までは、米国の中央銀行であり金利と金融政策を決定する連邦準備制度(FRB)の政策金利であるFF金利と、米国の株式市場との間には、顕著な「因果関係」が存在した。 FRBが米国の株式市場を相当程度コントロールしてきたからだ。その間のパターンは①FRBの政策金利であるFF金利が低い時から、経済成長、好景気、株高が継続②FRBが市場は過熱と判断、FF金利を継続的に引き上げ、それでも株は上昇③FF金利をさらに引き上げ高金利に、やがて株式暴落④FF金利を大幅に引き下げ、金利の低下により債券価格は暴騰することで株式市場の暴落ショックを緩和する⑤は①のパターンに戻り、経済と株式が上昇開始 過去2回の株式市場の暴落であった2000年のITバブルの崩壊と2008年のリーマンショックの双方では以上の①から⑤のパターンが見られた。 いずれの場合にも、経済と株式の上昇はFF金利が低い時に始まり、FRBが金融を引き締めるためにFF金利を引き上げても株式の上昇は止まらず、さらにFF金利を引き上げてから株式「暴落」が起きた。 すると、FRBはFF金利を直ちに5%以上大幅に引き下げたから、それと同時に債券市場は「暴騰」し、低金利をテコに経済活動も活発化して、大底からの経済成長と株価上昇が始まった。 つまり、「FF金利の大幅低下は株式の買いチャンス」というパターンがみられた。「マエストロ」と言われたグリーンスパン このパターンを確立したのが、1987年から2006年まで19年間にわたり米国の金融政策のトップであったFRBのアラン・グリースパン議長である。 金融だけでなく経済と株式市場の長期成長までもたらしたグリースパン議長は、その絶頂期には「マエストロ」と呼ばれた。 グリースパン議長は、低金利政策により株式や不動産などの資産価値を高めて富裕層の消費を拡大して経済成長を持続させ(その間に貧富の格差は拡大したが)、マーケットが加熱すると金利を引き上げ続けた。 一旦マーケットが暴落すると瞬時に大幅に金利を引き下げて債券価格を上昇させて暴落を緩和し、超低金利効果による経済と株式市場の回復を導いた。 2000年のITバブルの崩壊から回復と成長をもたらし、2006年の退任の直前までは過熱する株式市場を抑制するために金利を引き上げ続けた。 グリースパンの後継者であるベン・バーナンキFRB議長もグリースパン路線を踏襲して金利を引き上げ続け、リーマンショックの暴落が発生すると直ちに金利を低下させて危機を乗り切り、その後の株式と経済の成長に道をつけた。FRBは株式市場に責任を持つ ではなぜ、米国の中央銀行であるFRBは株式市場を動かすのだろうか。 FRBが雇用の最大化、つまり経済に責任を持っているからだ。そして、株式市場が株式上昇→消費→雇用→経済、という経路で米国経済に及ぼす影響が大きいからだ。 米国は資本主義の総本山であり、米国資本主義の最大の装置が株式市場であることは過去100年間変わらない。1929年の米国発の大恐慌は株式市場の突然の暴落から始まった。 FRBを含めた米政府にとって、株式市場をコントロールすることは、経済に直結する死活問題である。 1990年代以降の米国の財務長官に、私も共同経営者(パートナー)であったゴールドマンサックスから3人も就任していることも、マーケット重視の表れだ。日銀には制度上、株式市場に責任がない ここで注意しなくてはいけないのは、日本の中央銀行である日本銀行が法律で定められた責任を持っているのは「物価の安定」だけだ。 日銀は雇用にも経済にも株式市場にも、制度としては責任がない。 日銀が1980年代の株式や不動産のバブルを放置したことも、1990年代以降のバブルの崩壊にも手をこまぬいたことにも、こうした制度上の日米の違いが作用した。 ただし、日銀史上最も国際金融論に通暁した現在の黒田総裁が、2013年の就任以来、日銀の伝統的な手法ではなく、FRBによく似た「金融による成長戦略」をとり、ここまで株式市場を上昇させ、少子高齢化が進む日本経済のマイナス成長を緩和してきたことは特筆すべきだ。 もちろん、世界最大の対外純資産を持つ点では米国と対極的だが、日本の黒田日銀の政策にも、FRBと共通するリスクが内包されている。コロナが変えたパターン ドナルド・トランプ政権が誕生した2016年から2019年にはFRBはFF金利をゼロから3.5%まで引き上げていた。 株式市場の上昇が続き、経済は好調で物価上昇の兆候が見られたためだった。 しかし、2020年から始まったコロナ禍により、FRBはFF金利をゼロにまで引き下げた。ここから、米株式市場、特にGAMFAを擁するナスダック(NASDAQ)市場の暴騰が始まった。「FF金利の大幅低下は買い」という過去の経験則から個人投資家を含む世界中の投資家が米株式市場に資金を流入させたからだ。共同幻想が消えるとき 大いなる錯覚である。 過去のFRBによる大幅な金利低下は、株式市場の暴落に対応するためだった。しかし、今回の大幅な金利低下の前には株式市場の暴落は起きていない。 それどころか、米株式市場は歴史的な高値水準にまで上昇した。 この本質的な違いを無視して、「ゼロ金利は買い」という過去の成功の方程式を信じた資金が米国株を押し上げた。 株式市場がどの程度「バブル」状態なのかを表す指標にPER(株価収益率)という「倍数」がある。株価が年間の純利益の何倍なのかを表す。 日本経済がバブルと言われた1989年末で、PERは時期にもよるが、およそ50倍程度であった。 直近の2021年1月末のナスダックの平均PERは約71倍、つまり年間利益の71年分、株が買われているということだ。 グラフ②を見ても、ナスダックがこの1年間でいかに上昇したかが分かる。 この大いなる錯覚が米国株急上昇の最大の原因である。「共同幻想」が消えた時には、暴落の危険をはらんでいる。コロナはきっかけに過ぎない パンドラの箱を開けたらあらゆる災いが人類にもたらされたとギリシア神話ではいう。 トランプ大統領が開けたパンドラの箱に、コロナという突風が吹き込んで、これからの米国と世界には「21世紀型大恐慌」のリスクが高まっている。日本株大幅安、米インフレ懸念や五輪海外客断念-自動車など広く売り 22日の東京株式相場は大幅安。米国金融当局が大手銀行に対する資本優遇策を打ち切ることや東京五輪での海外観客断念が嫌気され、自動車や機械など輸出関連、不動産株などが安い。先週末の日本銀行の上場投資信託(ETF)買い変更に伴う余波も重しとなっている。 TOPIXの午前終値は前営業日比22.25ポイント(1.1%)安の1989.96 日経平均株価は543円15銭(1.8%)安の2万9248円90銭 〈きょうのポイント〉 米連邦準備制度理事会(FRB)は補完的レバレッジ比率(SLR)の条件緩和措置を予定通り失効させると発表 米S&P500種株価指数は小幅続落、10年債利回りは2ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の1.73% 東京五輪の海外観客受け入れ断念を決定、5者協議で合意 セゾン投信運用部の瀬下哲雄運用部長は東京五輪について、「海外からの観客が来ないと経済効果がなくなるので、改めてそこが確定したことはネガティブ」と述べた。また先週に日銀が決定したETF買いの修正についても「ある程度織り込み済みだったが、高ければ買わないのはやはりネガティブインパクト」とも付け加えた。 国内外でマイナス要因が複数重なったことから、きょうの主要株価指数は取引開始後に下げが拡大した。東海東京調査センターの平川昇二チーフグローバルストラテジストはFRBの決定について、「補完的レバレッジ比率の条件緩和措置が失効すると、米銀は債券を買う状況ではなくなる。市場ではインフレ上昇リスクとして捉えやすい」と語る。 ルネサスエレクトロニクスの那珂工場の火災を受け、車載半導体の供給不足が深刻化するとの懸念から午前の東京株市場では自動車株に売りが増加。東京五輪の決定からオリエンタルランドや資生堂などのインバウンド関連の一角が安い。さらにファナックやキッコーマンといった日経平均の指数ウエートが相対的に高い銘柄も売り圧力が強まり、日経平均をTOPIXで割ったNT倍率は一段と低下した。 東証33業種では輸送用機器や保険、機械、サービス、不動産、電機、化学が下落 海運や鉄鋼、石油・石炭製品、電気・ガスは上昇前場の日経平均は大幅続落、一時700円弱の下げ 調整ムード広がる[東京 22日 ロイター] - 前場の東京株式市場で、日経平均は前営業日比543円15銭安の2万9248円90銭と大幅続落した。米長期金利が一時1.7%台に再び乗せ、警戒感から幅広い業種で売りが先行した。日銀による上場投資信託(ETF)の買い入れ対象がTOPIX連動型に限定されたことや、ルネサスエレクトロニクスの工場火災など複数の売り材料が重なり、日経平均は一時684円42銭安の2万9107円63銭の安値を付けた。前週末19日の米国株市場はまちまち。フェイスブックやエネルギー株の上昇に押し上げられ、ナスダック総合が反発。一方、米連邦準備理事会(FRB)が大手行を対象にした自己資本規制である補完的レバレッジ比率(SLR)に関する緩和措置を延長せず、期限の3月末で終了すると発表したことを受け、金融セクターは軟調に推移した。ピクテ投信投資顧問のシニアフェロー、市川眞一氏は「悪材料が重なったことが背景にあるが、根本の部分は米国の長期金利上昇にあり、しばらく日柄調整が続くとみている」との見方を示した。「これまで株価上昇の要因になっていた金余り状態に変化はないため、目先的に大きく崩れることもないだろう。今回の調整は値幅ではなく日柄がポイントになり、当面は、もみあう展開になるとみている」(同)という。TOPIXは10日ぶりに反落し1.11%安で午前の取引を終了。東証1部の売買代金は1兆4352億6400万円。東証33業種中、輸送用機器、保険業、機械などの27業種が値下がり。半面、海運業、鉄鋼、石油・石炭製品などの6業種は値上がりした。個別では、ルネサスエレクトロニクスが3.91%安。19日に同社の那珂工場(茨城県ひたちなか市)で発生した火災が嫌気された。半導体の供給懸念が広がり、トヨタ自動車、ホンダなどの自動車株も総じて軟調となった。そのほか、日経平均への指数寄与度が高い銘柄が引き続き売られる展開となり、ファーストリテイリングは3.2%安。1銘柄で日経平均を約106円押し下げた。東証1部の騰落数は、値上がりが753銘柄、値下がりが1352銘柄、変わらずが89銘柄だった。【市況】後場に注目すべき3つのポイント~日銀政策要因が重しに、29000円近辺での正念場22日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は大幅続落、日銀政策要因が重しに、29000円近辺での正念場・ドル・円は底堅い、欧州通貨の軟調地合いで・値下がり寄与トップはファーストリテイリング、同2位がダイキン工業■日経平均は大幅続落、日銀政策要因が重しに、29000円近辺での正念場日経平均は大幅続落。543.15円安の29248.90円(出来高概算7億0298万株)で前場の取引を終えている。前週末の米国株式市場ではNYダウは続落した。米中外交トップ会談を受けた米中対立への警戒感から寄り付き直後から下落。また、米連邦準備制度理事会(FRB)が新型コロナウイルパンデミックによる金融市場混乱を受け昨年4月から実施していた大手銀に対する資本規制の特例的な緩和措置「補完的レバレッジ比率(SLR)」を計画通り3月末で終了することを発表。これが嫌気される形で金融株を中心に売りが出てダウは終日軟調に推移した。一方、押し目からの買いにハイテクは持ち直し、ナスダック総合指数は堅調推移となった。このダウの下落やSLRに関する緩和措置の終了を巡る米長期金利への警戒感などから、日経平均は347円安の大幅続落でスタート。その後も、日銀が先週の金融政策決定会合で上場投資信託(ETF)の買い入れ対象から日経平均連動型を除外すると決めたことなど国内の特殊要因も重荷となり、下げ幅を拡げる動きとなった。個別では、那珂工場の火災発生で主力ラインが生産停止になったルネサスが大きく下落。業績モメンタムの鈍化が嫌気された日本オラクルは大きく売られた。業績下方修正で赤字幅拡大・配当減配となったAOKIHDも大幅反落となった。また、21年2月期営業利益は前期比約3割増の1400億円弱になったようだと観測報道が伝わったニトリHDは材料出尽くし感から売りに押されて反落に転じた。そのほか、日銀の政策変更を引き続きネガティブ視した動きからファーストリテ、ファナックなどの値がさ株の下落が大きい。一方、期末配当予想の増配を発表した岩井コスモが大幅上昇。業績上方修正で一転営業増益見通しとなったパスコも急伸した。また、高水準の自社株買いを発表した日住サービスは一時ストップ高を付けた。そのほか、売買代金上位では、任天堂、武田薬、日本郵船などが上昇した。セクターでは、輸送用機器、保険業、機械、非鉄金属、サービス業などが下落率上位に並んだ。一方、海運業、鉄鋼、石油・石炭製品、電気・ガス業、卸売業などが上昇率上位となった。東証1部の値上がり銘柄は全体の34%、対して値下がり銘柄は61%となっている。週明けの日経平均は想定以上の下落となっている。米国でのSLRに関する緩和措置については警戒されてはいたが、大方の市場の声としては、期限延長はされず終了となる可能性が高いのではないかという意見が多かった。そのため、材料が出ても、市場の反応は限定的と考えていた。実際、米国市場でも、確かに金融株は売られたがダウの下落率は0.71%程度にとどまった。また、SLR緩和措置が終了されれば、米国債需給が悪化することで長期金利が更に上昇するとの懸念もあったが、前週末の米国市場での10年物米国債利回りは1.75%前後と、ほとんど緩和措置終了の発表前と変わらない水準での推移となった。加えて、金利は高止まりしていたが、同日のナスダック総合指数は0.76%高、フィラデルフィア半導体指数(SOX指数)にいたっては1.18%高と上昇していた。さらに、本日の東京市場では、時間外取引での米長期金利は1.68%前後とむしろ低下してきている。そうした中でも、本日の日経平均は一時700円近い下落幅となり、米国株と比べて下落率が大きい。東証株価指数(TOPIX)と比べても下落率が大きいところを見る限り、やはり、前週末の日銀金融政策決定会合において発表された政策修正の影響がまだ響いているようだ。ETFの買い入れ枠「原則年6兆円」という目標値撤廃自体は想定内ではあったが、買い入れ対象から日経平均連動型を除外し、TOPIX連動型のみに絞るとした点はサプライズ感があり、市場も前週末だけでは織り込め切れなかったようだ。実際、ファーストリテやファナックのほか、ダイキン、信越化などの日経平均採用銘柄で値がさ株の下落率が本日は大きい。また、個人投資家による売買が少なくインデックスによる売買動向を表しやすいとされるキッコーマンの下落率が4.57%と、前週末の4.0%に引き続き大きいところからも、日銀政策変更による需給面での影響が大きいことが窺える。ただ、本日も海運業や鉄鋼は堅調で石油・石炭製品も上昇している。海運については、世界経済の回復に加えて上昇し続けるコンテナ船運賃といった需給のひっ迫感が明確な材料として引き続き買い材料視されているようだ。鉄鋼や石油・石炭製品などの資源関連分野の堅調さはやはりインフレ懸念などを反映したものか。米国での今後最大10年間における予想物価上昇率を示す「ブレークイーブンインフレ率(BEI)」は2.31%と17日の2.30%を超え、2013年4月に付けた2.34%に次ぐ約8年ぶりの高水準を記録している。こうした中、かねてからインフレ加速懸念を訴えているサマーズ元米財務長官は、米国が「かなり劇的な財政・金融不調和」に直面していると指摘。向こう数年間でインフレが加速し、米国がスタグフレーション(インフレと景気後退が併存する現象)に陥る確率は3割強と予測したとも伝わっている。力強い景気回復が意識されるなか、インフレの脅威をヘッジできる資源関連株がとりわけ堅調なのは、こうした背景からも窺えよう。さて、本日の後場は安値圏でのもみ合い展開となりそうだ。前場の日経平均の下落率は1.82%と一時は2%を超えていたところからやや下げ渋って終えている。TOPIXも下げ幅を縮め1.11%程度で終えている。こうした中、政策修正したばかりの日銀によるETF買いが実施されるかは不透明。値がさ株やグロース(成長)株が軟調ななか引き続き資源関連株が堅調となろう。また、電気・ガス業なども堅調なところから、期末の配当権利取りを狙った買いも強いようだ。財務基盤が良好な高配当利回り銘柄にも引き続き物色が向かいそうだ。■ドル・円は底堅い、欧州通貨の軟調地合いで22日午前の東京市場でドル・円は底堅く推移し、108半ばから108円後半に持ち直した。序盤は、トルコ中銀総裁の更迭や日経平均株価の大幅安でリスク回避の円買いが先行。ただ、ユーロ・ドルなどの軟調地合いで、ドル・円は下げづらい展開となった。ここまでの取引レンジは、ドル・円は108円60銭から108円96銭、ユーロ・円は129円01銭から129円47銭、ユーロ・ドルは1.1873ドルから1.1893ドル。■後場のチェック銘柄・Shinwa Wise Holdings、MICS化学など、5銘柄がストップ高※一時ストップ高(気配値)を含みます・値下がり寄与トップはファーストリテイリング、同2位がダイキン工業■経済指標・要人発言【経済指標】・カナダ・1月小売売上高:前月比-1.1%(予想:-3.0%、12月:-3.7%←-3.4%)【要人発言】・バーキン米リッチモンド連銀総裁「2021年の価格圧力を予想」「米経済は恐らく回復完了が間近だ」・黒田日銀総裁「物価2%目標の早期実現という金融政策の大元は変更すべきでない」「ETFの買入れ中止や売却を検討していることはまったくない」<国内>・14:00 1月景気動向指数・先行改定値(速報値:99.1)<海外>特になし《CS》 提供:フィスコマット・ジョーンズが7年ぶり2勝目! 小平智は36位タイ<ザ・ホンダ・クラシック 最終日◇21日◇PGAナショナル・チャンピオン・コース(米フロリダ州)◇7125ヤード・パー70>米国男子ツアーの「ザ・ホンダ・クラシック」は全日程が終了。トータル10アンダーまで伸ばしたマット・ジョーンズ(オーストラリア)が2位以下に5打差をつける完勝で2014年の「シェル・ヒューストン・オープン」以来、7年ぶりとなるツアー通算2勝目を挙げた。5打差の2位にはブランドン・ヘイギー(米国)、トータル6アンダーの3位タイにはラッセル・ヘンリー、ブレンダン・スティール、チェイス・サイファート、デニー・マッカーシー(いずれも米国)が入った。そのほか、フィル・ミケルソン(米国)はパープレーでトータル2アンダーの25位タイ。「マスターズ」出場に暗雲漂うリッキー・ファウラー(米国)は最終日も1つ落としてトータル7オーバーの65位タイとなった。日本勢で決勝ラウンドに進出した小平智は、2バーディ・1ボギーの「69」で回り、トータル1オーバー・36位タイでフィニッシュ。なお、もう一人の日本勢・石川遼は予選落ちとなっている。ジャスティン・ハーディングが2年ぶり2勝目 次戦は中一日で同コース<マジカル・ケニアオープン 最終日◇21日◇カレンCC(ケニア)◇6921ヤード・パー71>ケニアのナイロビで行われている欧州男子ツアー「マジカル・ケニアオープン」は全日程が終了。ジャスティン・ハーディング(南アフリカ)がトータル21アンダーまで伸ばし、19年の「コマーシャルバンク・カタールマスターズ」以来ツアー2勝目を挙げた。2打差の2位にカート・キタヤマ(米国)、4打差の3位にコナー・サイム(スコットランド)。トータル16アンダーの4位にはセバスチャン・ガルシア・ロドリゲス(スペイン)が入った。なお、この試合と次戦の「ケニア・サバンナクラシック」は同じケニアのカレンCCで行われる。今週は18日(木)~21日(日)、来週は月曜日を挟んで23日(火)~26日(金)の変則日程。コロナ対策のため、移動をなくし滞在期間を少なくする狙いがある。〔東京外為〕ドル、108円台後半=米金利低下眺めじり安(22日正午)時事通信 22日正午の東京外国為替市場のドルの対円相場(気配値)は、米金利の低下を眺め1ドル=108円台後半でじり安で推移している。正午現在、108円77~77銭と前日(午後5時、108円74~75銭)比03銭のドル高・円安。 前週末は米国でFRBがコロナ対策で導入した金融資本規制の一部緩和を3月末で終了すると発表し、米金利が一時1.7%台半ばへ急上昇。ただ22日は1.6%台後半に水準を戻したことから、東京市場のドルは108円80銭台で取引が始まった。日経平均株価下落を眺めてもみ合ったが、正午にかけて、上昇一服した米長期金利を背景に108円70銭前後に値を落としている。 FOMC、日銀金融政策決定会合を消化し、市場は年度末のポジション調整の動きが中心となっているとの見方が強い。「先週の米金利上昇で円売りポジションが十分に積み上がったので、円売りは一段落したのではないか」(国内銀行)との指摘があった。今夜はパウエルFRB議長の講演が予定されているが、「FOMC直後でスタンスを変えることは考えづらく、あまり材料視されないだろう」(同)との声も聞かれた。 ユーロは午前9時と比べ、対円で小動き、対ドルで小高い。正午現在、1ユーロ=129円36~36銭(前日午後5時、129円77~77銭)、対ドルでは1.1892~1893ドル(同1.1932~1933ドル)。(了)〔東京株式〕大幅下落=米株安を嫌気、半導体不足に警戒感(22日前場)☆差替時事通信 【第1部】米国の銀行に対する自己資本規制緩和措置の終了が決まり、前週末に米ダウ工業株30種平均が続落したことで売りが優勢となった。半導体大手ルネサスエレクトロニクスの工場火災により半導体不足への警戒感も広がった。日経平均株価は前営業日比543円15銭安の2万9248円90銭、東証株価指数(TOPIX)は22.25ポイント安の1989.96と、いずれも大幅に下落した。 62%の銘柄が値下がりし、値上がりは34%だった。出来高は7億0298万株、売買代金は1兆4352億円。 業種別株価指数(33業種)では輸送用機器、保険業、機械の下落が目立った。上昇は海運業、鉄鋼、石油・石炭製品など。 個別銘柄ではトヨタ、ホンダ、デンソーが軟調。ルネサス、キーエンス、ダイキンも値を下げた。東エレク、ソニーは弱含み。東京海上の下げがきつく、三菱UFJはさえない。ファーストリテが続落。ソフトバンクGは小幅安。半面、郵船、商船三井が値を上げた。任天堂、武田、ENEOSがしっかり。日本製鉄、JFEも堅調。 【第2部】小幅続伸。アトム、野村マイクロが締まり、日アビオは大幅反発。千代化建は軟調だった。出来高8759万株。 ▽一時600円超安 22日前場の東京株式市場は売りが優勢だった。東証1部市場全体の値動きを示すTOPIXが前週末まで9営業日続伸しており、「過熱感を冷ます動きが広がった」(銀行系証券)という。また。半導体大手ルネサスエレクトロニクスの工場火災による悪影響も警戒され、自動車や部品会社の株に売りが膨らんだ。日経平均株価は前営業日比347円安でスタート。その後もじりじりと下落し、下げ幅は一時、600円を超えた。 前週末に日銀が日経平均連動型ETFの買い入れをやめると公表した余波はきょうも続いた。直近では日銀の買い入れに占める日経平均型の比率は小さかったが、「指数連動のETFを好む投資家には印象が悪かった」(同)。日経平均の値動きへの寄与度が高い値がさ株も売り物がちとなった。 225先物6月きりは、大阪夜間取引終値を下回る2万9250円で寄り付いた。売り優勢は現物株取引開始後も続き、2万8920円まで一時下落した。225オプション4月きりはプットが堅調、コールはさえない。(了)午後は天候とは裏腹にやや重苦しい空気の中で…。〔東京外為〕ドル、108円台後半=方向感なく推移(22日午後3時)時事通信 22日午後の東京外国為替市場のドルの対円相場(気配値)は、日経平均株価の下落や時間外取引の米長期金利の低下を眺めてやや軟化した後、1ドル=108円台後半で方向感なく推移している。午後3時現在、108円80~80銭と前日(午後5時、108円74~75銭)比06銭の小幅ドル高・円安。 前週末の海外市場では、米国時間に米連邦準備制度理事会(FRB)が新型コロナウイルス対策で実施した金融資本規制の緩和を3月末に終了すると発表し、米金利が上昇。ドルが買われて一時109円00銭近辺を付けたが、その後、米株安を背景に伸び悩み、終盤は108円80銭台に軟化した。 東京時間早朝は、一時108円50銭台に下落。FRB規制緩和終了のほか、「トルコリラの急落でリスク回避ムードが広がった」(外為仲介業者)ため、円が買われやすかった。その後は、国内輸入企業のドル買いなどで108円90銭近辺に上昇したが、午前11時から正午にかけて日経平均株価の大幅安や米金利の低下が意識され、108円70銭近辺まで軟化。午後は108円70銭台を中心にもみ合っている。 市場関係者からは「先週半ばからやや上値の重い展開となっている」(国内証券)と指摘されている。本日は、FRB規制緩和終了やトルコリラ急落、日経平均安などで「リスク回避のムードが広がっている」(先の外為仲介業者)とみられ、やや円買いが進みやすい地合い。ただ、「日本時間早朝に108円台半ばで下げ止まった」(同)ため、大幅な円高にはならないとの指摘が聞かれている。 ユーロは午後に入って対円、対ドルともにもみ合い。午後3時現在、1ユーロ=129円40~41銭(前日午後5時、129円77~77銭)、対ドルでは1.1894~1894ドル(同1.1932~1933ドル)。(了)〔東京株式〕大幅続落=米金利高止まりや半導体不足を警戒(22日)☆差替時事通信 【第1部】米長期金利の高止まりや半導体不足の深刻化に対する警戒感が強く、大型株を中心に値下がりした。日経平均株価は前営業日比617円90銭安の2万9174円15銭と大幅続落。東証株価指数(TOPIX)は22.03ポイント安の1990.18と10営業日ぶりに反落した。 54%の銘柄が値下がりし、値上がりは41%だった。出来高は13億8426万株、売買代金は3兆0338億円。 業種別株価指数(33業種)では輸送用機器、保険業、機械の下落が目立った。上昇は海運業、鉄鋼、電気・ガス業など。 個別銘柄ではファーストリテ、東京海上が大幅安。ソフトバンクG、マネックスG、三菱UFJ、三井住友はさえない。トヨタ、ホンダ、デンソーが安く、ルネサス、キーエンス、ダイキンも売られた。半面、郵船、商船三井が値を上げた。三菱商、関西電も高い。任天堂、武田がしっかり。日本製鉄、JFE、出光興産、国際帝石も堅調。 【第2部】小幅続伸。Abalanceが買われ、アトムはしっかり。千代化建、アライドHDは売られた。出来高1億3908万株。 ▽大型株中心に下落 22日の東京株式市場は売りが優勢だった。「米長期金利の高止まりや、半導体大手ルネサスエレクトロニクスの工場火災に伴う減産が警戒された」(大手証券)といい、金融、自動車などの大型株が売られた。 日経平均株価は前営業日終値から347円下落して始まり、下げ幅は600円を超えた。前週末に日銀が日経平均連動型ETFの買い入れをやめると発表した余波はこの日も継続。日経平均の値動きへの寄与度が大きく、割高感が強かった値がさ株の一角で値下がりが目立った。 また、東証1部全体の値動きを示す東証株価指数(TOPIX)は前週末まで9連騰しており、「過熱感を冷ますスピード調整」(銀行系証券)との指摘も聞かれた。午後は押し目買いが入り、上昇に転じる銘柄が増えた。 225先物6月きりは安値もみ合い。午前は売り優勢で始まり、2万8920円まで値下がりした。午後は2万8900~2万9200円のレンジで上下した。225オプション4月きりは、プットが値を上げ、コールは軟調。(了)日経平均は617円安と大幅続落、安値圏での推移で今年に入り3番目の下げ幅に=22日後場モーニングスター 22日後場の日経平均株価は、前週末比617円90銭安の2万9174円15銭と大幅に続落して取引を終了。600円を超える下げ幅は、4日(628円99銭)以来の下落で、今年に入り3番目の大きさ。朝方から前週末19日の弱い動きが継続。株価指数先物に断続的な売りもあり下げ幅を拡大し、午前10時34分には、同684円42銭安の2万9107円63銭を付ける場面もみられた。後場に入り、やや下げ幅を縮小する場面があったが、模様眺めムードが広がるなか、安値圏での推移となった。時間外取引での米株価指数先物は、ダウ先物が下落する一方、ナスダックミニ先物は上昇するなど、まちまちの動きだった。為替相場は、ドル・円が1ドル=108円70銭台(前週末19日は108円74-76銭)で、朝方の水準からはやや円高方向にあることも、意識されたもよう。東証1部の出来高は13億8426万株、売買代金は3兆338億円。騰落銘柄数は値上がり908銘柄、値下がり1190銘柄、変わらず97銘柄だった。 市場では「日経平均株価は採用銘柄のなかでも株価の高い銘柄が下げた影響を大きく受けた。東証1部の騰落銘柄数をみると、値上がり銘柄数は900超あり、当面は個別株物色での対応となりそう」(中堅証券)との声が聞かれた。 業種別では、トヨタ 、ホンダ などの輸送用機器株や、第一生命HD 、東京海上 などの保険株が下落。コマツ 、ダイキン などの機械株や、住友鉱 、住友電工 などの非鉄金属株も安い。ソニー 、キーエンス などの電機株や、オリエンタルランド(OLC) 、リクルートH などのサービス株も軟調。三井不 、三菱地所 などの不動産株や、アステラス薬 、中外薬 などの医薬品株も下げた。東証業種別指数は、24種が下落、9業種が上昇。 個別では、ワタベ 、グリムス 、日本オラクル 、AOKIHD 、IBJ などが下落。半面、わかもと 、岩井コスモ 、gumi 、キッセイ薬 、パスコ などが上昇した。日経平均は大幅続落、国内外要因の重なりで売り優勢/相場概況フィスコ 日経平均は大幅に続落した。前週末の米国株式市場でのNYダウは続落。米中対立再燃への警戒感から寄り付きから下落した後、大手銀に対する資本規制の緩和措置を延長しないとした米連邦準備制度理事会(FRB)の方針が嫌気された。ただ、押し目買いからハイテク株は持ち直した。米銀大手の資本規制を巡るFRBの決定を受けたダウの下落を背景に、週明けの日経平均は347円安の大幅続落でスタート。その後も、前週末の日銀金融政策決定会合において上場投資信託(ETF)買い入れ対象から日経平均連動型が除外されたことを嫌気した国内需給要因も相まって下げ幅を拡大。後場は安値圏でのもみ合いに終始した。 大引けの日経平均は前日比617.90円安の29174.15円となった。東証1部の売買高は13億8426万株、売買代金は3兆0338億円だった。セクター別では輸送用機器、保険業、機械、非鉄金属、電気機器などが下落率上位に並んだ。一方、海運業、鉄鋼、電気・ガス業、鉱業、石油・石炭製品などが上昇率上位となった。東証1部の値上がり銘柄は41%、対して値下がり銘柄は全体の54%であった。 個別では、那珂工場の火災発生で主力ラインが生産停止になったルネサスが大きく下落。ルネサスの一件から車載半導体不足による自動車生産の減少が警戒されトヨタやホンダなどの自動車関連も大きく下落した。また、業績モメンタムの鈍化が嫌気された日本オラクルや、業績下方修正で赤字幅拡大・配当減配となったAOKIHDも大幅に売られた。21年2月期営業利益は前期比約3割増の1400億円弱になったようだと観測報道が伝わったニトリHDは材料出尽くし感から売りに押さる場面もあったが、終始もみ合いとなった。そのほか、日銀の政策変更を引き続きネガティブ視した動きからファーストリテ、ファナック、ダイキンなどの値がさ株の下落が目立った。 一方、期末配当予想の増配を発表した岩井コスモが急伸。業績上方修正で一転営業増益見通しとなったパスコも大幅高。高水準の自社株買いを発表した日住サービスは一時ストップ高を付けた。海運業界での需給ひっ迫感に加えてノルウェー社に出資し液化した二酸化炭素(CO2)の輸送事業に参入すると発表した商船三井も大きく買われた。また、日本製鉄、三菱商事、国際石油開発帝石、コスモエネHDなどの資源関連株や、九州電力、中国電力などの電気・ガス業も堅調だった。そのほか売買代金上位では、任天堂、武田薬、JALなどが上昇した。《YN》(マーケット概況)本日の東京市場ではチェック中の日本株30銘柄中の12銘柄が値を上げて終了しましたね。重点3銘柄では1銘柄が値を上げて終了しましたね。5%以上の大きな変動は見られませんね。明日の戦略-際立つ日経平均の弱さ、13週線までで売りは止まるかトレーダーズ・ウェブ 22日の日経平均は大幅続落。終値は617円安の29174円。ダウ平均の大幅安を受けて、寄り付きから300円を超える下落。ファーストリテイリングやファナックなど、値がさ株がスタートから厳しい売られ方となったことで、日銀のETF買い入れルール変更が日経平均に悪影響を及ぼすとの警戒が強まった。安く始まった後も売りが売りを呼ぶ流れとなり、前場のうちに一気に29100円台まで下落。後場は前場の安値こそ割り込まなかったものの、下値模索が継続し、終値でも600円を超える下落となった。 東証1部の売買代金は概算で3兆0300億円。業種別では海運、鉄鋼、電気・ガスなどが上昇した一方、輸送用機器、保険、機械などが下落した。昼休みに上方修正を発表した高見沢サイバネティックスが後場に買いを集めてストップ高。半面、ファーストリテイリングは売りが止まらず、後場一段安で4%を超える下落。19日との2営業日で10%を超える下落となった。 東証1部の騰落銘柄数は値上がり908/値下がり1190。商船三井、川崎汽船、日本郵船の海運大手3社がそろって大幅高。日本製鉄やJFEHDなども強く、市況関連の一角に資金が向かった。任天堂は225採用銘柄でないことが意識されたか、値がさ株が嫌われる中で逆行高。1都3県の緊急事態宣言が解除となったことで、JR東海やJALなどレジャー関連が堅調となった。ほか、株主還元を強化した岩井コスモや、上方修正を発表したケアサービスが急伸した。 一方、キーエンスやダイキンなど値がさ株の多くが大幅安。工場火災の影響が懸念されたルネサスエレクトロニクスが5%近い下落となり、ホンダや日産自動車、デンソーなど自動車および部品関連に警戒売りが広がった。破綻した英金融会社に関する損失拡大が懸念された東京海上や、ワクチン開発に遅れが生じていると報じられたアンジェスが値を崩した。業績関連のリリースが嫌気された日本オラクルやAOKIHDが急落。地合いの悪化を受けて直近IPO銘柄の多くが手仕舞い売りに押されており、i-plugがストップ安となった。 日経平均は600円を超える下落となったが、東証1部では値上がり・値下がりはほぼ均衡と言えるレベル。ジャスダック平均は12連騰と、日経平均の変調はどこ吹く風といった状況。先週末の19日も日経平均の指数としての弱さが際立ったが、しばらくこういった状況が続くかもしれない。ファーストリテイリングは一企業としての評価では、他の小売企業に比べるとPERは高めではあるが、それを許容できるくらいの成長性と安定性を有している。足元で売られている他の225構成銘柄に関しても、人気と実力を兼ね備えていたからこそ、株式市場の中で存在感が高まっていたと言える。 ただ、日銀のETF買いに関しては、施策が長期化する中でその弊害を指摘する声も多かった。それだけに、今回のような弱い動きが出てくると、それに追随する売りも出てきやすい。この先、米国株が強い上昇となっても日経平均だけが弱いという状況が続くようであれば、どこかで修正はされると考える。ただ、米国市場も長期金利が高止まりするなど微妙な状況。弱材料には神経質となりやすいだけに、米国株が失速するようだと、下に値幅が大きく出る展開も想定される。日経平均はここ2日間の下げは大きいが、週足チャートで見れば、まだ強い基調は崩れていない。13週線(28863円、22日時点)を割り込む前に強い反転が見られるかが注目される。明日の日本株の読み筋=落ち着きどころを探る展開かモーニングスター 23日の東京株式市場は、落ち着きどころ探る展開となりそう。日経平均株価は前週末19日と22日の2日間で1040円強(約3.45%)の下落となった。3%を超える下げとなった後だけに、短期的なリバウンドを狙った買いが期待される。ただ、22日の日経ボラティリティインデックスが24.39に上昇し、10日(24.91)の水準となった。変動率の大きさが警戒され、主力の大型株には様子見姿勢が強まる場面もありそう。市場では「消去法的に値動きの軽い中小型株に物色の矛先が向かいそう」(中堅証券)との見方があった。 22日の日経平均株価は、前週末比617円90銭安の2万9174円15銭と大幅に続落し、今年に入り3番目の下落となった。朝方から売り優勢の展開で、一時680円を超える下げをみせる場面もあった。市場では「日銀のETF(上場投資信託)買いの方針が変更され、TOPIX型のみとなったことから、機関投資家のポジションの組み換えが行われたようだ」(他の中堅証券)との声が聞かれた。 軽くて丈夫なオーダーメードインソール 美濃加茂市の企業、岐阜県と共同開発 航空機にも使用される軽くて丈夫な素材を使ったインソール(靴の中敷き)「RQ(アルク)」を、県産業技術総合センター(関市)と義肢装具製造業ヒューマニック(美濃加茂市)が共同で開発した。一人一人の足に合わせたものを容易にオーダーメードで作ることができる。23日に発売する。 炭素繊維強化熱可塑性プラスチック(CFRTP)という素材を使った。熱を加えると軟らかくなる特徴があり、軽くて丈夫。航空機や自動車の部材に使われる。 この素材を使ったインソールは通常、足の石こうの型を取り製造する。時間と手間がかかり、スキーなどスポーツ用に限定されているという。 同社は県の補助で3Dプリンターを導入した。利用者は自身で足の型を取った器具を同社に郵送。データを基に対面しないで製造できる技術を確立した。両者は2014年度からCFRTP製下肢装具や加工技術を共同で研究開発してきた。 下肢装具付きのタイプ「RQ plus」も開発した。「RQ」は1枚1万円(通販の場合は送料を含めて3千円追加)、「RQ plus」は一つ3万5千円(同)。 同社の社長で、義肢装具士の堀江耕太さん(39)は「インソールを利用するとより快適に歩くことができる。まひや障害のある人だけでなく、ない人にも利用してほしい」と話す。問い合わせは同社、電話0574(66)5544。別の占いで今週の運勢を見ると…NY株見通し-今週はパウエルFRB議長発言を受けた長期金利の動向に注目トレーダーズ・ウェブ 今週のNY市場はもみ合いか。先週は長期金利の上昇やFRBが銀行の資本規制に関する特例措置を延長しないことを発表したことで週後半に失速した。今週は1.9兆ドルのコロナウイルス救済法案の経済効果や、経済活動正常化による景気回復期待を背景に景気敏感株の堅調が期待される一方、長期金利の上昇トレンド継続が引き続きハイテク・グロース株の重しとなりそうだ。22日にパウエルFRB議長のパネルディスカッション参加、23、24日にパウエルFRB議長とイエレン米財務長官の議会証言が予定されており、両氏の発言を受けた長期金利の動向が注目される。このほかの経済指標は2月中古住宅販売件数、10-12月期GDP確報値、2月コアPCEデフレーターなど。企業決算はアドビ、ペイチェックス、ダーデン・レストランツなどが発表予定。 今晩の米経済指標・イベントはパウエルFRB議長発言、2月中古住宅販売件数など。主要な企業の決算発表はなし。(執筆:3月22日、14:00)〔NY外為〕円、108円台後半(22日朝)時事通信 【ニューヨーク時事】週明け22日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、新規の手掛かり材料待ちで、1ドル=108円台後半で小動きとなっている。午前9時現在は108円80~90銭と、前週末午後5時(108円82~92銭)比02銭の円高・ドル安。 トルコの中央銀行総裁が解任されたことをきっかけに、この日は同国通貨リラが急落した。安全資産とされる円は買われ、海外市場で一時108円50銭付近に上昇。その後も米長期金利の上昇が一服する中で堅調を維持し、同70銭でニューヨーク市場の取引が始まった。 朝方は主要な米経済指標の発表もなく、静かな商い。この後、パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長がオンライン討論会に参加するほか、23、24日には新型コロナウイルス危機対応の経済対策をテーマに議会で証言する。また、週内には2、5年物など米国債の入札も予定されており、市場の注目を集めそうだ。 ユーロは同時刻現在、対ドルで1ユーロ=1.1915~1925ドル(前週末午後5時は1.1900~1910ドル)、対円では同129円70~80銭(同129円59~69銭)と、11銭の円安・ユーロ高。(了) 「変異株が市中に定着」と専門家 岐阜県、新型コロナ5人感染、1人死亡 岐阜県と岐阜市は22日、新たに県内3市町で計5人の新型コロナウイルス感染と、入院していた美濃加茂市の80代男性の死亡を確認したと発表した。感染者数は累計4721人、死者は計122人となった。 クラスター(感染者集団)の新規感染者はおらず、感染者5人のうち4人は感染経路が不明だった。 また、県は、これまでの感染者のうち新たに3人が変異株陽性だったと発表した。いずれも陽性者との接触があった。 県内での変異株の陽性者は累計19人となった。県の専門家会議のメンバーで、ぎふ綜合健診センターの村上啓雄所長は記者会見で「市中に(変異株が)定着している。相当程度、広がっていると思っていい」と指摘した。 新規感染者の居住地別は岐阜市3人、土岐市と揖斐郡大野町が各1人。年代別は10代1人、20代2人、60代と80代が各1人。〔米株式〕NYダウ、もみ合い(22日午前)時事通信 【ニューヨーク時事】週明け22日午前のニューヨーク株式相場は、新規材料難の中、方向感なくもみ合っている。午前10時現在は、優良株で構成するダウ工業株30種平均が前週末終値比42.93ドル高の3万2670.90ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数が115.08ポイント高の1万3330.32。 売り買いのきっかけとなる新たな材料に乏しく、持ち高調整目的の売り買いが交錯している。これまでの米長期金利の上昇を背景に割高感から売りを浴びたハイテク関連銘柄に買い戻しが先行。一方、米連邦準備制度理事会(FRB)が前週末に銀行の資本規制を緩和した特例措置を延長しないと発表したことを受け、ゴールドマン・サックスやJPモルガン・チェースなど金融関連への売りが継続し、相場の上値は重い。 個別銘柄では、アップルやマイクロソフトなどの主要ハイテク銘柄の他に、テスラが上伸。一部投資会社が2025年までにテスラの株価が3000ドルに達すると予想した。一方、ロイヤル・カリビアン・グループは、カリブ海クルーズの運航を6月に再開すると発表したが、売りが先行している。(了)今夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中の18銘柄が値を上げてスタートしましたね。5%以上の大きな変動は見られませんね。ハイテクグロース株に買いを入れていますが、希望価格まで下がってこないですね…。
2021.03.22
コメント(2)
-
3月21日(日)…
3月21日(日)、雨です。雨ですが、当初の予報で聞いていたような大雨ではないですね。本日はホーム1:GSCCの西コースで開催のアゲンスト・パー競技に参加という選択肢もありましたが、天候と連戦回避ということでキャンセル済です。ということで7時50分頃に起床。新聞に目を通し、朝食を済ませ、ロマネちゃんと戯れる。本日のノルマは1階のモップかけですか…。ハイハイ…。朝のコーヒーブレイクはネスプレッソで…。ピエール・ルドンのチョコレートと共に…。美味い!!本日でピエール・ルドンも終わりこれからどうなるのでしょうか…。土岐のアウトレットでリンツを仕入れるか…。そして恒例の母親宅の後片付けです…。本日もゴミ袋がどんどんと出来上がります…。その数12を過ぎたあたりで終了…。それではしばらく投資関係の作戦会議ですかね…。米国株はとりあえずハイテク・グロース株の価格が下がったところで買いに入る候補を6銘柄ほど選定済み。日本株にはあまりグロース/バリューの線引きがはっきりとしない部分もあるからいろいろと…。取り合えず候補を5銘柄ほど選出してみる。新型コロナワクチンの製剤化開始 アストラ製、日本供給用 KMバイオ(熊本市)熊本日日新聞社 医薬品製造販売のKMバイオロジクス(熊本市)は19日、英製薬大手アストラゼネカが日本向けに供給する新型コロナウイルスワクチンの製剤化を始めたと発表した。同社から提供されるワクチン原液の容器への充塡や包装を手掛ける。 アストラゼネカは、厚生労働省に新型コロナワクチンの製造販売承認を申請中。事前に供給体制を整えることで、承認後に迅速に出荷できるようにする。KMバイオは2月に製剤化を受託する契約を結んでいた。受託数量や期間などは明らかにしていない。 製剤化は合志事業所(合志市)の設備を活用する。アストラゼネカは日本政府と1億2千万回分(6千万人分)の供給契約を結んでおり、輸入または国内製造する原液をKMバイオと第一三共が製剤化する。第一三共も12日に製剤化開始を発表した。コロナワクチンの材料「RNA」とはそもそも何か 複数のワクチンが世界で承認され、有効性が報告される一方、安全性に対する懸念も出始めている。独ビオンテックと米ファイザーのワクチン接種が広がったことで、名前を聞く機会の増えているのがワクチンの材料である「RNA」だ。 筆者は医療関連のレポートなどで、遺伝子の説明をする機会が多いが、毎回どこまでDNAやRNAをかみ砕いて説明するかに頭を悩ませている。 いつもできるだけ簡単に書くように心がけているが、とりわけRNAの説明はDNAとタンパク質にも触れた方がいいので複雑になりやすい。世にある数多の記事ではあまり深入りせず、RNAについてはさらりと触れる程度が多いかもしれない。 ここでは何か考えるヒントにもなるのではないかという趣旨から、RNAについて詳しく書いてみようと思う。網羅すれば切りがないので、主に歴史を中心にしながら基本的な仕組みを理解してもらえるように書いてみよう。 遺伝子の解明に寄与したメンデル RNAの役割が解き明かされ始めたのは1950年代になってからなので、実態が科学的に理解されてからそれほど年月はたっていない。それから70年間、あらゆる角度の研究を経て、現在のワクチンにたどり着いた。後述の通り、ワクチンに使われる技術の基礎は1960年代に見出されている。RNA発見以前を含めた歴史を振り返れば、その実態に容易にたどり着いたわけではないということは言える。 全体像としては「タンパク質」「DNA」、そして「RNA」の順で、体を形成するための「情報」の正体は解明された。 最初に分かったのはタンパク質である。1800年から1900年にかけて少しずつ明らかにされた。その実態は、わずか20種類のアミノ酸が組み合わせの違いで、種類豊富なタンパク質を作り分けられるという絶妙な仕組みだった。この頃の科学者では進化論のダーウィンが有名だが、彼はその当時、遺伝の仕組みを知らなかった。 20世紀に向けてタンパク質の解明からリレーをつなぐように、遺伝という現象がどうして起こるかの研究が進む。親子が似るなど、遺伝は古代から認識されたが、理由は不明であり続けた。 遺伝の解明に大きく寄与したのは、生物の教科書にも名前が出てくるチェコの修道士メンデルである。伝記によると本業は全くできない男だったようだが、観察力と忍耐力に長けていたのか、メンデルは1万株ものマメの観察から、メンデルの法則と呼ばれる一定の遺伝のルールを見出し、「エレメント」が関係すると報告した。1865年のことで、まさに遺伝子に最接近した瞬間だった。だが、メンデルの発見は40年近くも科学界では無視された空白期間がある。 同時期の1870年代に、ドイツではフレミングという科学者が細胞分裂を当時最新鋭の顕微鏡で観察し、分割した細胞に分かれる「糸」として報告。その後「染色体」と呼ばれる存在が明らかになっていた。こうした発見はあったが、遺伝子は信じられず、遺伝の正体は分からずじまいだった。 その後、1900年代に入り、メンデルの説が追認され、ようやく遺伝子の原理は受け入れられた。事実、1903年に初めて「gene(遺伝子)」という名称が誕生している。ただ、正体はブラックボックスのままで、複雑な構造が既に見えていたタンパク質の性質から、その遺伝子の正体はタンパク質だろうと信じられた。遺伝子が優生思想と関連づけられるなど、戦前には歪んだ捉え方がなされた時代もあった。遺伝子の実態が見えないまま、誤解は実に1940年代まで放置された。 遺伝子の正体の先に見えたRNAの存在 転機は1944年に訪れた。米国のアベリーという科学者が、遺伝子を形作るのは「核酸」であると発表したことだ。核酸の一つ、DNAによって細菌の病原性が移動して、しかも遺伝する現象を突き止めたのだ。もっとも、遺伝はあまりに複雑な現象ゆえに、核酸などでは対応しきれないとの見方は依然として根強く、科学者でさえも「遺伝子の正体=核酸」を疑う状況が9年近くも続いた。 その状況を変えたのが「二重らせん」である。1953年、英ケンブリッジ大学で研究していたワトソンとクリックという科学者が2ページの論文で、DNAが連なって鎖になり、しかも2本が並走した「ねじれたハシゴ」のようだと報告したのだ。当時のワトソンは20代、クリックも30代の若さだった。 タンパク質はわずか20種類のアミノ酸からなったが、DNAはアデニン、チミン、グアニン、シトシンという4種類のヌクレオチド(塩基)からハシゴを形成していた。2本の柱の間には、アデニンとチミン、グアニンとシトシンが必ず対になっており、一方の鎖はもう一方をコピーする時の鋳型になれる。その羅列する構造はタンパク質と似ており、同様の暗号構造が浮かび上がった。ワトソンとクリックは、すぐさま今に続くまで揺らいでいない、DNAと遺伝との関係を見極めることになる。 さらに、タンパク質は遺伝子から作られると考えられていたが、ワトソンとクリックはタンパク質の型となる遺伝子の役割もDNAが担っていると理解した。DNAに含まれる何らかの情報に従ってタンパク質が作られる。 この時に一つの謎が生じた。DNAは細胞の中の丸い核の中にあり、糸と呼ばれた染色体に収まっていると分かっていたが、タンパク質は核の外で生産される。DNAからタンパク質が作られるとしても、DNAが核の外に出ないので、タンパク質を直接的に作ることが不可能だという問題だ。 ここで謎の物質だったRNAがようやく登場する。DNAとタンパク質の間をつなぐ存在として、細胞の中に含まれる核酸の中で2番目に多いRNAが注目されたのだ。「DNA⇒RNA⇒タンパク質」。これはセントラルドグマと呼ばれた。 コロナワクチンの実用化を支えるmRNAとは何か DNAからタンパク質に至る流れをざっと説明すると以下のようになる。 DNAのヌクレオチドの配列に従って、いったんRNAという別の核酸に情報が転写される。RNAもDNAと同じヌクレオチドが鎖状になっている。RNAは、ウラシル、アデニン、グアニン、シトシンと、DNAと比べるとチミンがウラシルになっているが、同じ4種類であり、DNAを写し取れるようになっている。このRNAが核の外に運ばれる。核の外では、別のタイプのRNAがアミノ酸を運んでおり、核の中からRNAの情報に基づいてアミノ酸をつなげていく。こうしてタンパク質ができる。 この一連の流れの中で、先に判明したのは、細胞の核の外で進むタンパク質合成においてアミノ酸を運んでいるRNAの役割だ。米国のザメクニクという科学者が、RNAがアミノ酸の運び屋であると1950年代に突き止めた。アミノ酸を運搬することからトランスファーRNA(tRNA)と呼ばれた。核の外に存在して、リボソームというタンパク質合成が行われる場所にアミノ酸を運ぶ役割を果たしている。 その後に、核の中にあるDNAから情報を写し取って核の外に運び出すつなぎ役としてのRNAも突き止められる。米国ジェイコブとモノドという2人の研究者が、DNAから情報を転写して核の外に移動するRNAの役割を1961年に報告した。いわば情報の運び屋としてのRNAであり、これは「メッセンジャーRNA(mRNA)」と名付けられた。これが、新型コロナウイルス感染症のワクチンとして60年後に実用化されることになる。 だが不思議なことに、RNAの役割について掘り下げる研究は、新しい展開が出てくる1990年代まで30年近くも滞った。RNAは「せいぜいDNAとタンパク質のつなぎ」と高をくくられたようだ。 重要な転機は、人のDNAを織りなす30億個の配列を読み取る国際プロジェクトだ。このプロジェクトは2003年までに完全解読に至る。タンパク質の情報につながる遺伝子は全体の2%にしか含まれなかったが、当初は無益と思われた残りの98%にRNAの情報が豊富に含まれることが次々と明らかになったのだ。「iRNA」「miRNA」などの新しい概念、ゲノム編集といった新技術につながっていく。 前述の通り、こうしたRNA研究の進化の恩恵の一つとして、mRNAワクチンがある。コロナウイルスは約3万のRNAを保有する。コロナウイルスのほかにも、遺伝情報をRNAとして持っているウイルス(RNAウイルス)は、エイズで有名なレトロウイルス、インフルエンザで有名なオルソミクソウイルス、はしかのパラミクソウイルス、エボラのフィロウイルスなどがある。中でもコロナウイルスはこれらの中でも保有しているRNAのサイズが最大規模となっている。 このRNAの持っている情報を生かして、RNAの断片を人工的に作り出して、ワクチンに活用できるのではないかという発想が生まれた。 RNA情報を変えれば変異にも対応可能 まず着目されたのがウイルスの表面にある突起部分、スパイクタンパク質である。スパイクタンパク質はウイルスの持っているRNAから生み出されており、このタンパク質を作るRNAをワクチンにしようという考え方だ。事実、ウイルスのスパイクタンパクのかけらを生み出す、いわば設計図を人工的にこしらえたものがコロナワクチンだ。しかも、RNA自体に免疫が発動しないように細工をしたり、細胞に送り込むためのカプセルのような技術も投入したりして製品化した。 3万の配列のどこを使うかは、その企業の研究次第で、ワクチンの機能と関係してくる。暗号を生成していくような研究だ。原理的にスパイクタンパク質は1000個強のRNAから翻訳されて生産されており、ワクチンはこのRNAのうち10個から数十個程度を選んで作られる。1000個強のRNAの中でもワクチンのために選ぶ場所が違えば異なるワクチンになる。またスパイクワクチン以外のタンパク質に関係したRNAをワクチンにすることもできる。現在、変異が問題になっているが、ワクチンになるRNAの情報を変えれば作り替えも原理的に可能であり、今後アップデートが続くと考えられる。 mRNAの発想自体は既に半世紀を超えるものであり、現在の技術からすれば十分対応は可能だ。こうした仕組みを知ることで、これからの展開も理解しやすいのではないかと考える。医師会の「ごり押し」で現場は混乱…ワクチン個別接種が“危険な賭け”である理由 それにしても、日本医師会の中川俊男会長の動きは周到だった。新型コロナワクチンの接種で想定されていた集団接種の計画を土台からひっくり返し、診療所の医師による個別接種への道を切り開いた。政府や各業界へ根回しをしながら実現にこぎつけた手腕は鮮やかだった。だが、個別接種を強引に進めたことに起因する各方面の混乱は深刻だ。4月中旬には高齢者への接種が始まるが、個別接種の「ごり押し」は、地域の接種プランの遅れにつながっている。 昨年暮れから、ワクチンを巡る政府の対応のちぐはぐさが際立つ。 ワクチン課題を担う河野太郎行政改革相は、3月12日の記者会見で5月中には約2150万人分(1瓶当たり6回接種で計算)を確保する見通しだと述べた。だが、どの自治体に、いつ、どれくらいの量が送られるのかは依然として不透明だ。 1バイアル当たりの接種回数も、6回が5回に変更され、6回分を確保できる特殊な注射器を探して右往左往する。ワクチンを生理食塩水で希釈するためのシリンジ(注射器の筒)が不足していると分かったのも、つい最近だ。 そもそも米国ファイザー社製のワクチンは、扱いが難しい。マイナス75℃前後で各自治体が設置する、超低温冷凍庫のディープフリーザーに運ばれて、そこで保管される。厚生労働省は当初、体育館などの大型施設での集団接種を考えていた。温度管理だけでなく揺れや衝撃にも弱いファイザー社製ワクチンを移送するのは、最小限にとどめたいからだ。 1月27日、日医の中川会長が記者会見でこうぶち上げた。「住民への接種は、普段の健康状態を把握しているかかりつけ医で安心して受けられることが重要」 小分け移送のデメリット つまり、集団接種と並行して個別接種を柱の一つに加えるよう提言したのだ。となれば、小分けして診療所に移送する手段が必要になる。ワクチンは摂氏2~8℃を保つ保冷ボックスで移送し、5日以内に使い切らなければならない。 確かにかかりつけ医で接種できれば、患者ごとのアレルギー体質や病歴などを把握しているから安心につながる。 だが、デメリットも少なくない。小分けの際には、どのロットのワクチンを、いつ、どこの診療所に、どれほどの量を送るのかなど管理手続きが煩雑になる。なにより小分けするほど、貴重なワクチンに無駄が生じる。また、診療所での接種を実施すれば、集団接種を担う医師や看護師の確保にも困難をきたす。 ところが、中川会長の会見以降、事態は一気に動き出す。 政府への根回しはできていた 記者会見5日前の1月22日、中川会長は河野行革相と面談して「個別接種」を申し合わせているという。政府への根回しはできていたのだ。そして会見2日後の29日、それまで大量の小分け移送に後ろ向きだった厚労省が、突然、動き出す。個別接種を中心とした「練馬区モデル」を「先進的な取組事例」として自治体に紹介したのだ。いわば個別接種を奨励したに等しい。 それを知った自治体から、医薬品卸に問い合わせが殺到した。医薬品卸とは、実は医療においては重要な役割を担っている。製薬会社に代わって医薬品を医療機関に届けるだけではなく、薬の説明や、それに付随する医師の要望に応える医薬品供給のプロ集団だ。 2月2日には、その医薬品卸を束ねる日本医薬品卸売業連合会(卸連)の渡辺秀一会長が、日医の中川会長に呼び出された。個別接種のための小分け配送に協力を求められた。 成功するかどうかは“賭け” だが、ファイザー社製のワクチンに関しては「携わることはない」と厚労省から何度も説明を受けていた医薬品卸は、戸惑う。医師会からの要請は意気に感じるが、いきなり配送せよと言われても情報が足りない。医師会や厚労省、製薬会社の狭間で立場の弱い医薬品卸だが、異例ともいえる文書を厚労省に送付する。 突然の方針変更で「現場は大変混乱している」との抗議だ。 中川会長は、この医薬品卸を抜きにして小分け移送はうまくいかないと踏んでいる。だが、問題は山積みだ。新たに導入したワクチン管理システムが煩雑であったり、地方によっては医師会の熱意に温度差がある。3月中旬になっても、現場の混乱は続いている。 壮大な個別接種計画だが、これが成功するかどうかは、ある意味で賭けに近い。政府の無策と、日医のごり押し……果たしてワクチン接種はうまく機能するだろうか。「文藝春秋」4月号および「文藝春秋digital」掲載のレポート「 政府の迷走、医師会のゴリ押し 」で、その経緯を報告している。キャシー・ウッド氏率いるアーク、テスラ株3000ドル見込む-25年まで キャシー・ウッド氏が率いるアーク・インベストメント・マネジメントは、米テスラの株価が2025年までに3000ドルに達すると予想している。現在の水準は655ドル。実現すれば、発行済み株数に基づく時価総額は3兆ドル(約327兆円)近くとなる。 アークはテスラが完全自動運転車を5年以内に実現する確率を50%とみている。成功すれば、同社が計画中の「ロボタクシー」のサービスを迅速に拡大できる可能性があると、アークは19日にウェブサイトに掲載したリポートで指摘した。 アークはさらに、テスラの保険事業も予測モデルに追加。現在はカリフォルニア州に限られているが、向こう数年間で他州でも平均を上回るマージンで保険サービスを提供できると予想している。「非常に詳細な運転データ」をテスラが収集していることを理由に挙げた。 ウッド氏は最も熱心なテスラ支持者の1人で、アークの旗艦ファンドはテスラ株を大量に保有している。2月に株価が下げた際には追加購入した。 アークの新モデルでは、最善のシナリオでテスラ株が25年に4000ドルに達し、弱気シナリオでは1500ドルと予測。資本効率性の向上を前提に、25年の販売台数を500万-1000万台と見込む。 ブルームバーグが集計したアナリストのテスラ目標株価は1200ドルが最高で、アークはこれを大きく上回る水準をターゲットとしている。テスラの株価は昨年、740%余り上昇。S&P500種株価指数の構成銘柄でパフォーマンス首位だった。コラム:独VWがついにEV戦略で好発進、株価一段高への道も[ロンドン 16日 ロイター BREAKINGVIEWS] - ドイツ自動車大手フォルクスワーゲン(VW)がついにエンジンを吹かし始めた。同社は16日、コロナ禍で傷ついた収益性をてこ入れするため、電気自動車(EV)の納車台数を今年倍増する計画を公表。これを好感して株価は7%近く上昇した。ディース最高経営責任者(CEO)が株式バリュエーションの向上に注力するなら、株価には一段の上昇余地がある。VW株は年初から約33%上昇し、STOXX600自動車株指数の16%高をしのいでいる。株高の主な要因は、VWにとって最大の市場である中国の経済がコロナ禍から速やかに回復したことと、同社の画期的なEV戦略にある。電池車とハイブリッド車を合わせた販売台数は昨年、前年比で約3倍の42万2000台に急増した。ディース氏は今年、これをさらに100万台まで伸ばすとともに、急拡大するすべての自社EV向けに新たなソフトウエアも投入する意向だ。この事業を後押しするための資金調達法としては、傘下スポーツカー・ブランド「ポルシェ」の一部上場が考えられる。最終的に電池車部門を丸ごとスピンオフ(分離)すれば、さらに多額の資金を確保できるかもしれない。UBSの推計では、VWの2025年までのEV販売台数は、自社目標の300万台には届かないが257万台にはなりそうだ。1台当たりの平均価格を3万9000ユーロ、利益率を5%と想定すると、営業利益は50億ユーロを超える可能性がある。この計算に用いた想定価格は同社の廉価版EV「ID.3」の基本価格で、想定利益率はUBSが推計するVWの内燃エンジン車ゴルフの利益率並みとした。営業利益見通しに20倍の株価収益率(PER)を適用すると、EV部門の事業価値は1000億ユーロとなる可能性がある。この倍率は、EV事業の急成長を「適切に」反映するとアナリストが考える水準だ。米EV大手テスラのPERが115倍まで膨張してこととは、訳が違う。これに、Breakingviewsが推計するソフトウエア部門の潜在価値1860億ユーロを足すと、2部門合わせた価値はVWの現在の株式時価総額から2倍以上に増えるかもしれない。これは予見可能な将来、VWの売上高の多くを占め続けるであろう旧来型の内燃機関搭載車を除外した数字だ。確かに、これらの部門を実際に別法人化することは夢物語かもしれない。これまでもポルシェ、ピエヒ両一族や強大な労働組合の影響力によって、同じく過小評価されている高級車ブランド、ランボルギーニなどの売却が阻まれてきた経緯がある。しかしディースCEOがこうした案を示唆し、投資家を潜在的な事業価値に注目させるのは自由だ。たとえ同氏が実行には移さないとしても。●背景となるニュース*VWは16日、コスト削減によって数年中に利益率を上昇させられるとの自信を示した。数日前には野心的なEV事業拡大計画を示したばかり。*ディースCEOは発表文で「危機に見舞われた2020年にわれわれの業績が良好だったことは事業変革の加速に勢いをつけるだろう」と述べた。同社は今年、EVの納車台数を2倍以上の100万台にする見通しを示した。昨年は電池車の販売が3倍以上に増えた。*VWは15日、欧州で6つのEV向け電池工場を建設し、世界中でEV充電インフラを拡大する計画を発表した。*VWは21年以降の数年間で営業利益率7―8%を目指すと発表した。今年については、5―6.5%の目標レンジの上限に達するとの見通しを確認した。ルネサスの半導体工場で火災、被害生産ラインで製造停止業績への影響については精査中ブルームバーグ ルネサスエレクトロニクスは20日、那珂工場(茨城県ひたちなか市)で19日未明に発生した火災で、生産ラインの設備や装置に被害が出ていると発表した。 発表によると、同工場のN3棟(300ミリメートルライン)の純水供給装置や空調装置など一部の用役設備や製造装置に被害が出ているという。建屋の被害はない。 また警察と消防による現場検証で、出火元は生産ラインの工程にあるめっき装置だと特定された。同装置で過電流が発生したことで発火したとみて、原因などを調査している。この火災ではN3棟の全製造装置の約2%、11台の装置が被災しており、面積では1万2000平方メートルのクリーンルームの約5%相当が焼損したという。 火災は19日午前2時47分ごろに発生し、同8時12分ごろに鎮火した。従業員の人的被害はない。N3棟は生産を停止しており、再開のめどは分かり次第発表する。仕掛品の被害や業績への影響についても精査中としている。N2棟(200ミリメートルライン)とウエハーのテスト工程が入るWT棟は稼働しており、製品の出荷も継続している。マット・ジョーンズが単独首位 小平智は55位Tで最終日へ<ザ・ホンダ・クラシック 3日目◇20日◇PGAナショナル・チャンピオン・コース(米フロリダ州)◇7125ヤード・パー70>米国男子ツアーの「ザ・ホンダ・クラシック」3日目。マット・ジョーンズ(オーストラリア)が一つスコアを伸ばしトータル10アンダーで単独首位に浮上した。3打差の2位タイにJ.B.ホームズとアーロン・ワイズ(ともに米国)。トータル6アンダーの4位タイにはキャメロン・トリンガル、サム・ライダー(ともに米国)、C.T.パン(台湾)の3人が続いている。フィル・ミケルソン(米国)は1つ伸ばしてトータル2アンダーの27位タイ。リッキー・ファウラー(米国)は「78」と苦しみトータル6オーバーの66位タイまで後退している。日本勢で決勝ラウンドに進出した小平智は、4バーディ・5ボギーの「71」で回り、トータル2オーバー・55位タイで最終日に入る。なお、もう一人の日本勢・石川遼は予選落ちとなっている。50歳のP・ミケルソンが27位Tに浮上 予定されている当地への引越は…!?<ザ・ホンダ・クラシック 3日目◇20日◇PGAナショナル・チャンピオン・コース(米フロリダ州)◇7125ヤード・パー70>米国男子ツアーの「ザ・ホンダ・クラシック」3日目。50歳のフィル・ミケルソン(米国)が「69」と伸ばしトータル2アンダーで27位タイに浮上した。大会が開催されているのはフロリダ州パームビーチ。ミケルソンが今年引越する予定のジュピターアイランドもフロリダ州南部で、同コースからは車でわずか30分圏内。引越しが実現すれば地元の大会となるのだが…。「本当は今年、引っ越す予定だったが今は未定となった」と3日目を終えて地元紙のパームビーチポストに明かした。ミケルソン夫妻は出身地のカリフォルニア州ランチョサンタフェに自宅を構えていたが、昨年ジュピターアイランドに土地を購入。自宅を建設して娘の学校が終了する2021年には引っ越すと公言していた。しかしその自宅建設はいまだ始まっていないという。「土地はあるのだが…、今はここに引っ越すことは選択肢の一つとして考えている」とミケルソン。フロリダ州ジュピターアイランドはフロリダ半島の東海岸で、マイアミより北へ約150キロの位置。昨今は多くのプロゴルファーが自宅を構える“エピセンター(震源地)”といわれる。その名を列挙すると…、タイガー・ウッズを始め、ジャスティン・トーマス、ダスティン・ジョンソン、リッキー・ファウラー、ブルックス・ケプカと米国トップ勢がずらり。さらにローリー・マキロイ(北アイルランド)、ルーク・ドナルド(イングランド)、シェーン・ローリー(アイルランド)ら欧州勢にアーニー・エルス(南アフリカ)とジャック・ニクラス(米国)、ゲーリー・プレーヤー(南アフリカ)、グレッグ・ノーマン(オーストラリア)らレジェンドもずらり。そんなゴルフエピセンターにミケルソンもジョインする予定だったのだが…。「少なくとも今年中の移転はできそうにない」ようだ。ジャスティン・ハーディングが単独首位浮上 カート・キタヤマらが2打差追走<マジカル・ケニアオープン 3日目◇20日◇カレンCC(ケニア)◇6921ヤード・パー71>ケニアのナイロビで行われている欧州男子ツアー「マジカル・ケニアオープン」はムービングデーが終了。「64」を叩き出したジャスティン・ハーディング(南アフリカ)がトータル16アンダーで単独首位に躍り出た。2打差の2位にカート・キタヤマ、ヨハネス・バーマン(ともに米国)、スコット・ヘンド(オーストラリア)の3人。トータル13アンダーの5位にはスコットランドのカルム・ヒルが続いている。なお、この試合と次戦の「ケニア・サバンナクラシック」は同じケニアのカレンCCで行われる。今週は18日(木)~21日(日)、来週は月曜日を挟んで23日(火)~26日(金)の変則日程。コロナ対策のため、移動をなくし滞在期間を少なくする狙いがある。午後になると雨がひどくなってきましたね…。国内女子ツアーのTV中継を観戦しながらのんびりと過ごします。臼井Pがトップタイですね。応援してあげましょう。小祝さくらが3打差逆転で今季3勝目 鈴木愛2位、渋野日向子11位<Tポイント×ENEOSゴルフトーナメント 最終日◇21日◇鹿児島高牧カントリークラブ(鹿児島)◇6424ヤード・パー72>2021年国内女子ツアー3戦目の最終ラウンドが終了した。小祝さくらが3バーディ・1ボギーの「70」をマーク。トータル10アンダーで3打差を逆転し、今季3勝目、ツアー通算4勝目を果たした。トータル8アンダー・2位タイに鈴木愛、ペ・ソンウ(韓国)、サイ・ペイイン(台湾)。トータル7アンダー・5位タイに渡邉彩香、臼井麗香が入った。渋野日向子は3バーディ・1ボギー・1ダブルボギーの「72」。自身初のホステス大会をトータル5アンダー・11位タイで終えた。大会連覇がかかっていた上田桃子はトータル1アンダー・33位タイ。2週連続優勝を狙った稲見萌寧も同順位でフィニッシュした。終盤の安定感が違いましたね。臼井Pも一時は単独トップでしたが、15番ミドルで獲れず、16番ロングはミスショット2発でボギー…、17番ショートもグリーンオーバーしてのボギー…と終盤に崩れましたね…。【米国株動向】市場が急落する局面で注目すべきブランド株5銘柄モトリーフール米国本社、2021年3月8日投稿記事より新型コロナウイルスを巡る不確実性は依然として残っていますが、株式のバリュエーションは過去2番目に高い水準にあります。住宅ブームを阻止する恐れのある国債利回りの上昇など他の要因と重なった場合、株式相場の暴落が現実味を帯びてきます。目下の株式相場の調整が本格的な暴落になった場合、投資家が取るべき最も賢明な行動は、実績のある事業モデルを備えた収益性の高いブランド株を購入することかもしれません。以下、市場が急落する局面で注目すべき5つのブランド銘柄を紹介します。 ビザ世界的な決済プラットフォームを運営するビザ(NYSE:V)の株式を購入することは、自分に有利なゲームに参加するようなものです。同社の収益は、同社の決済ネットワークに参加する小売店で企業や消費者が支払う金額に比例します。つまり同社の成長は経済成長に依存しています。景気循環の中でマイナス成長や景気後退が起きるのは当然ですが、景気後退と株式相場の暴落はほとんどの場合、数ヵ月で収束します。一方、景気拡大と強気市場の期間は多くの場合、長年にわたり継続します。つまりビザの株式を所有すると、下落するのは非常に短い間で、その後は数年にわたる上昇が期待できます。ビザは、支払いに対する保守的なアプローチからも恩恵を受けています。決済事業者の中には、消費者にショッピングの代金を貸し付けることを選択し、それにより景気拡大局面で利息収入と手数料を稼げるようになった企業もありますが、ビザは貸し手ではありません。つまりビザには、マイナス成長や景気後退の局面で貸倒損失をカバーするための資本を確保しておく必要がありません。これは、同社の利益率が恒常的に50%を超えている大きな理由です。 コストコ・ホールセール会員制の大型量販店チェーンのコストコ・ホールセール(NASDAQ:COST)の株式のトータルリターンは12年連続でプラスとなっています。コストコの株価は、消費者による大量の生活必需品の購入によって牽引されています。消費者による裁量的な買い物が同社の利益率を押し上げるのは確かですが、同社が販売する食料品や飲料の販売数量が、株価暴落や景気後退の影響をあまり受けないことも事実です。コストコは会員制のビジネスモデルからも恩恵を受けています。会員が支払う年会費が利益率を押し上げ、従来の小売業者や食料品店よりも価格を引き下げるのに役立っています。同社は一括購入により仕入れの規模を大きくしており、一般的に食料品などは営業利益率が非常に低いですが、その低い営業利益率の改善に役立っています。年会費は買い物客のコストコ・ブランドへのロイヤリティを維持するのにも役立っています。しかも、同社のeコマース事業はパンデミックを受けて勢いが増しています。 ネクステラ・エナジー株式相場が急落する局面で投資するためのもう一つの賢明な方法は、非常にディフェンシブなセクターの銘柄を購入することです。思い浮かぶブランド銘柄の1つが、米国の電力会社の中で時価総額が最大のネクステラ・エナジー(NYSE:NEE)です。電力と天然ガスへの毎年の需要は、全体として見ればあまり変化しません。電気は全ての住民が必要とするものなので、投資家は電力会社が毎年創出するキャッシュフローの水準を予想することができます。さらに、同社の再生可能エネルギー発電能力は米国で最大です。風力・太陽光発電によるグリーンエネルギープロジェクトの設備投資はかさみますが、発電コストを引き下げ、1桁後半の成長を維持することが可能になります。通常の公益電力会社の成長率は1桁前半です。ネクステラの投資は今後も続き、2019~2022年には500億~550億ドルの設備投資を行う計画です。その多くは再生可能エネルギーに向けられます。フロリダ州に3,000万枚の太陽光パネルを2030年までに設置するなど、大胆な計画を立てています。 ブリストル・マイヤーズ・スクイブ電力会社よりも成長性の高い企業を探していて、なおかつディフェンシブセクターの安全性を望むのであれば、ヘルスケア株は完璧な選択肢となり得ます。特に、医薬品銘柄のブリストル・マイヤーズ・スクイブ(NYSE:BMY)はお値打ちかもしれません。ブリストル・マイヤーズは、2019年にがん治療薬開発企業セルジーンの大型買収を実施して耳目を集めました。2020年には、多発性骨髄腫薬レブリミドの売上高が120億ドルを超え、2桁台の年間成長率を続けています。同薬は、適応拡大の機会、強力な価格設定力、使用期間の長期化、患者のがんの早期発見に役立つスクリーニング診断の改善などによる恩恵を受けています。一方で、同社の既存事業も成長しています。世界有数の経口抗凝固剤であるエリキスの2020年の純売上高は92億ドル弱となり、がん免疫療薬であるオプジーボの売上高は約70億ドルとなりました。単剤療法または併用療法として臨床試験中のものも数十件に上ります。適応の拡大はオプジーボの年間売上高を100億ドル以上に押し上げる可能性があります。 フェイスブック最後に、投資先にはそれぞれの業界を絶対的に支配するブランド銘柄を選ぶことを検討してください。その典型的な例が、ソーシャルメディア最大手のフェイスブック(NASDAQ:FB)です。フェイスブックの2020年末時点の月間アクティブユーザー数は28億人です。これとは別に、WhatsApp(ワッツアップ)やInstagram(インスタグラム)など同社の傘下にあるソーシャルメディアには5億人のユーザーがいます。つまり、世界の人口の40%以上に相当する33億人が少なくとも毎月1回、フェイスブックが所有する資産を訪問していることになります。広告主は、他のソーシャルメディアではこうしたターゲットオーディエンスを得られないことを十分に理解しています。さらに驚かされるのは、フェイスブックとインスタグラムの2020年の広告収入が840億ドルを超えたことです。同社は、ワッツアップやメッセンジャーについても、ユーザーが選択するソーシャルメディアの上位5つに既に入っているにもかかわらず、収益化に向けたアクセルペダルを緩める気配はありません。これらの資産が収益化されると、同社のキャッシュフローは爆発的に増える可能性があります。数十年に一度の不況の中、フェイスブックの広告収入が年率21%で成長することができれば、市場の急落にも耐えられるはずです。ひらまつ、株主優待を拡充! 3月に開業した軽井沢のホテルでも割引が適用されることになり、株主向けの食事会やレストラン・ワインの割引がますます充実!ダイヤモンド・ザイ 株式会社ひらまつが、株主優待の利用範囲を拡充することを、2021年3月16日に発表した。 ひらまつの株主優待は、毎年9月末と3月末時点の株主を対象に実施されており、内容は「100株以上の株主を対象に、①自社系列レストランの飲食代やホテル宿泊代金、及び飲食代の10~20%割引(500株以上の保有で割引率アップ)、②フェアへの有償招待、③(自社レストランで株主本人が披露宴を行う場合)婚礼飲食代割引、④自社オンラインショップでのワイン購入20%割引を実施」というもの。 今後もこれらの内容に変わりはないが、2021年3月16日にひらまつが展開するホテルブランド「HIRAMATSU HOTELS」の6施設目にあたる「THE HIRAMATSU 軽井沢御代田」がオープンしたことに伴い、「THE HIRAMATSU 軽井沢御代田」でも宿泊・飲食代の割引が適用されるようになる。割引の適用にあたっては、株主本人が同伴のうえ、利用当日に「優待カード」を提示する必要がある。 「優待カード」は、対象期間中(3月株主の場合は7月~12月末、9月株主の場合は翌年1月~6月末)であれば、何度でも利用することができる。 なお、ひらまつの株主優待で割引が適用されるホテルは、沖縄や京都、伊勢などにもあり、近年、少しずつ数を増やしている。 レストランについては、優待対象店舗がかなり多いが、例外的に「国立新美術館カフェ」「カフェ・デ・プレ」「カフェ・ミケランジェロ」「レストランひらまつ パリ」「オーベルジュ・ド・ぷれざんす 桜井」は対象外となるので注意。●ひらまつの株主優待制度の詳細は? 基準日9月末・3月末 100株以上①系列レストラン・ホテル料金(一部除く)10%割引②フェア(株主向け食事会・有償)招待③婚礼飲食代10%割引④自社オンラインショップでのワイン購入20%割引 500株以上①系列レストラン・ホテル料金(一部除く)20%割引②フェア(株主向け食事会・有償)招待③婚礼飲食代10%割引④自社オンラインショップでのワイン購入20%割引 ひらまつの株主優待は、高級レストランやホテルが10~20%割引になるほか、株主向けの食事会も人気が根強い。同社は近年、ホテル事業に注力しており、徐々に株主優待を利用できるホテルが増加しているのも魅力。旅行好きの人などは、長期保有する価値があるだろう。ただ、ひらまつは業績が低迷しているため、投資するにあたっては注意が必要だ。 ひらまつは1982年に「ひらまつ亭」というレストランからスタート。その後、「リストランテASO」「ブラッスリー ポール・ボキューズ」などのレストランを全国に展開するほか、ウェディング事業、ホテル事業にも参入する企業へと成長。2021年3月期の連結業績予想は、売上高64億8300万円(前期比34.4%減)、営業利益22億3200万円の赤字、経常利益23億円の赤字、当期純利益29億100万円の赤字。コロナ禍の打撃が甚大。
2021.03.21
コメント(0)
-

3月21日(土・春分の日)…2021ラウンド20…
3月21日(土・春分の日)、晴れ~曇りです。終盤には少し雨も降りましたが…。そんな本日はホーム1:GSCCの西コースで開催の春分の日杯に参加させていただきました。競技内で同業者コンペ(6組)も開催です。9時32分スタートとのことで6時40分頃に起床。新聞に目を通し、朝食を済ませ、ロマネちゃんと戯れる。身支度をして8時05分頃に家を出る。8時35分頃にはコースに到着。フロントで記帳して、着替えて、練習場へ…。ショット…マアマア…、パット…マアマア…。本日の競技は年代別競技で西コースのホワイトティー:6177ヤードです。ご一緒するのはいつものモ君(13)、フ君(15)、サ氏(36)です。本日の僕のハンディは(8)とのこと。OUT:1.1.2.1.0.1.0.1.3=46(17パット)1パット:2回、3パット:1回、パーオン:2回。1打目のミスが5回、2打目のミスが3回、3打目のミスが4回、バンカーのミスが1回、アプローチのミスが1回、パットのミスが2回…。10番のスタートハウス前でドーピング…。IN:0.1.0.0.0.1.0.0.1=39(13パット)1パット:6回、3パット:0回、パーオン:1回。1打目のミスが3回、2打目のミスが3回、パットのミスが1回…。参りました…。46・39=85(8)で77の30パット…。何の期待もできませんね。カートからスコアの登録を済ませて、靴を磨いて、お風呂に入って、パーティー会場へ。挨拶、新入会員のあいさつ、成績発表、新年度の計画案…等々。同業者コンペではWペリア戦ですから、85(9.0)=76.0でベスグロ・3位/24人でした。ラッキ~~~~16時頃に会計を済ませて早々に退散です。本日のフィジカルチェック…170.0cm,63.2kg,体脂肪率19.5%,BMI21.9,肥満度-0.6%…でした。帰宅すると16時30分頃。お茶とお団子で遅いおやつタイム。クラブを数本持っていつものゴルフ工房へ…。ドライバー用の交換シャフトと、5Iに代わる5Uの作成依頼。本日の競技の成績速報が出ていますね。翁組は22人が参加して、トップは87(20)=67とのこと。寿組は23人が参加して、トップは80(14)=66とのこと。松組は44人が参加して、トップは79(12)=67とのこと。僕は85(8)=77で18位。モ君は92(13)=79で32位。竹組・梅組の成績は出ていませんね…。お疲れ様でした…。昨夜のNYダウ終値=32627.97(-234.33)ドル。昨夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中の16銘柄が値を上げて終了しましたね。5%以上の大きな変動は見られませんね。ハイテク・グロース株の購入計画は頓挫でしょうか…。【米国市況】ハイテク株が反発、10年債利回り上げ縮小-原油上昇 19日の米株式市場ではテクノロジー株が反発。米国債利回りは日中の高水準を離れた。市場では経済成長加速に伴うインフレのリスクが意識されている。 米国株はナスダックが反発-S&P500とダウは続落 米10年債は小幅安、利回り1.73%-一時急上昇 ドルは上げ縮小、対円では108円後半 NY原油先物、6日ぶり上昇-買いの好機とウォール街が指摘 金スポットは上昇、ドル不安定で妙味高まる-週間で続伸 S&P500種株価指数は取引終了間際に下げに転じ、小幅安で引けた。銀行株の売りに押され、ダウ工業株30種平均も下落。米連邦準備制度理事会(FRB)は補完的レバレッジ比率(SLR)の条件緩和措置について、予定通り失効させると発表。銀行株を圧迫した。同発表を受けて、米10年債利回りは一時急上昇した。 フェイスブックに支えられ、ハイテク銘柄中心のナスダック100指数は反発。この日はオプションと先物取引が期限を迎える四半期ごとの「クアドルプル・ウィッチング」だったことも、ボラティリティーを増幅させた。 S&P500種は前日比0.1%安の3913.10。ダウ平均は234.33ドル(0.7%)安の32627.97ドル。ナスダック総合指数は0.8%上昇。ニューヨーク時間午後4時34分現在、10年債利回りは2ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の1.73%。 エドワード・ジョーンズの投資ストラテジスト、クレイグ・フェール氏は「金利上昇というテーマが株式と債券の両市場を依然として支配している」と指摘。「現時点では、金利が全般的な景気回復に悪影響を及ぼす局面にあるとは考えていない」と述べた。 パウエルFRB議長は米紙ウォールストリート・ジャーナルに寄稿した論説で、米金融当局は「必要な限り長期にわたって」景気支援を提供するとあらためて表明した。 外国為替市場ではドル指数が上げ幅を縮小。米国債利回りが日中の高水準を離れたことが背景にある。主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は、0.1%上昇。ニューヨーク時間午後4時35分現在、ドルは対円でほぼ変わらずの1ドル=108円92銭。ユーロは対ドルで0.1%安の1ユーロ=1.1903ドル。 ニューヨーク原油先物相場は6営業日ぶりに上昇。ゴールドマン・サックス・グループやモルガン・スタンレーは、最近の売り浴びせは行き過ぎで買いの好機が訪れていると指摘した。 ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物4月限は1.42ドル(2.4%)高の1バレル=61.42ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント5月限は1.25ドル(2%)上げて64.53ドル。 ニューヨーク金市場ではスポット相場が上昇。ドルがやや不安定な動きとなり、代替資産の金を買う動きにつながった。またインフレヘッジとしての金の需要も意識された。週間では1月以来で初の続伸。 金スポットはニューヨーク時間午後2時26分現在、0.4%高の1オンス=1743ドル。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物6月限は0.5%(9.30ドル)高の1743.90ドルで引けた。ルネサスの半導体工場で火災、被害受けた生産ラインで製造停止 半導体メーカー、ルネサスエレクトロニクスの茨城県内の工場で19日未明に火災が発生し、生産ラインの一部に被害が出た。 ルネサスが同日夜に発表した資料によると、生産子会社ルネサス・セミコンダクタ・マニュファクチュアリングの那珂工場にあるN3棟(300ミリメートルライン)で午前2時47分ごろに火災が起き、同8時12分ごろに鎮火した。従業員の人的被害はないという。 N3棟は生産を停止しており、再開のめどは分かり次第発表するとルネサスは説明。仕掛品の被害や業績への影響については精査中だとしている。NYダウの週報(3月15日週)と来週の見通し19日のNYダウは続落し、前日比234.33ドル安の32,627.97ドルで取引を終了。週間では150.67ドルの下落となりました。今週の注目は、16~17日に行われた米連邦公開市場委員会(FOMC)。金利・経済の見通しで、2023年末まで利上げがないとの見方が示されると、早期利上げ観測が後退し、株式市場に買いが広がりました。NYダウは18日に33,227.78ドルまで上昇し、過去最高値を更新しています。しかし、FRBのゼロ金利政策の長期化がインフレを加速させるとの見方から、米10年債利回りが1.75%と1年2カ月ぶりの水準まで上昇。長期金利の上昇によって、株価の割高感が意識されやすいハイテク株中心に売りが広がり、NYダウは18日、19日と連続で下落しました。ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数も、週間で104.63ポイントの下落となっています。 NYダウ来週の見通し来週も引き続き米10年債利回りの動向が注目されるでしょう。19日にFRBは、大手銀行を対象にした自己資本規制である、補完的レバレッジ比率(SLR)に関する緩和措置を延長しないことを発表。大手銀行は規制遵守のために米国債を売却する可能性があり、米10年債利回りの上昇につながる恐れがあります。米10年債利回りが2%に接近してくると、ナスダック総合株価指数だけでなくNYダウも売り優勢になる可能性があるので注意が必要です。来週は24日にパウエルFRB議長とイエレン財務長官が、米上院銀行委員会の公聴会で証言を行います。引き続きパウエルFRB議長の発言内容に関心が集まるでしょう。また、経済指標では26日の個人消費支出(2月)に注目。2月は経済対策の効果が薄れたことに加え、寒波の影響で個人消費は落ち込む見通しです。ただ、3月は追加経済対策が成立し、個人消費の拡大が予想されています。今後、物価の上昇圧力が高まるかどうかに関心が集まりそうです。米株はまちまち、米債利回り上昇一服でナスダックは反発[19日 ロイター] - 米国株式市場はまちまち。最近急上昇していた米債利回りが低下する中、フェイスブックやエネルギー株の上昇に押し上げられ、ナスダック総合は反発した。また、最近の流れが反転し、グロース株が経済再開の恩恵を最も受けるとされるバリュー株をアウトパフォームした。週足では、ダウ工業株30種が0.5%安、ナスダックとS&P総合500種は0.8%安となった。米10年債利回りは低下。しかし、14カ月ぶりの高水準近辺で推移している。USバンク・ウエルス・マネジメントのシニア投資ディレクター、ビル・ノーゼイ氏は「金利環境が幅広い期限で安定化する中、株式市場では上昇を主導する銘柄が一部入れ替わる動きとなった」と述べた。フェイスブックは4.1%高。ザッカーバーグ最高経営責任者(CEO)は、アップルが近く実施する広告販売を巡るプライバシーポリシー変更によってフェイスブックの地位が強化されるとの見方を示した。S&P銀行株は1.6%安。米連邦準備理事会(FRB)が大手行を対象にした自己資本規制である補完的レバレッジ比率(SLR)に関する緩和措置を延長せず、期限の3月末で終了すると発表したことを受け、利食い売りが広がったことが指摘された。S&Pグロース株は0.35%高、バリュー株は0.48%安だった。個別銘柄ではクレジットカード大手ビザが6%超下落し、時価総額で約300億ドルを消失。米司法省の調査を受けているという報道が嫌気された。宅配大手フェデックスは6.1%高。第3・四半期(12─2月)決算は、特別項目を除く純利益が前年同期比で2.5倍に増え、市場予想を上回った。新型コロナ禍でのオンライン通販向け商品配送の急増と料金値上げが寄与した。一方、ナイキは4%安。第3・四半期(2月28日まで)決算は売上高が予想を下回った。オンライン販売は拡大したが、新型コロナウイルス流行で店舗売り上げが低調だった。19日はオプションや先物の決済日が重なるクアドルプルウィッチングだったものの、取引は比較的穏やかだった。米取引所の合算出来高は165億株。直近20営業日の平均は144億株。ニューヨーク証券取引所では値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を1.25対1の比率で上回った。ナスダックでも1.70対1で値上がり銘柄数が多かった。174兆円!今年の株式市場には桁外れの資金が流入するバンク・オブ・アメリカのストラテジストらが予測ブルームバーグ 投資家が現在のペースで株式ファンドに資金を投じ続けた場合、今年の株式市場に流入する資金は1兆6000億ドル(約174兆円)という「驚異的な」規模になる。バンク・オブ・アメリカ(BofA)のストラテジストらが予測した。 18日付の同行のリポートによれば、債券利回り上昇やインフレ見通しを背景に市場でボラティリティーが見られたものの、17日までの1週間に株式ファンドには過去最大の683億ドルの資金が流入した。年率ベースに換算すると1兆ドル台という桁外れの規模に膨れ上がり、2017年に記録した従来の年間最高額である3000億ドルを優に超えると、マイケル・ハートネット氏率いるBofAのアナリストが記した。 テクノロジー銘柄など株価が押し上げられていた一部のセクターは最近下落しているものの、今回のリポートは株式が引き続き投資対象として最も人気が高いことを示唆している。債券への資金流入は年初から1100億ドルと、株式ファンドの3470億ドルに比べて3分の1にすぎない。借り入れコストが歴史的に低い中で、株式投資がもらたすリターンは引き続き投資家にとって魅力的だ。 BofAとEPFRグローバル・データによれば、主要な株式市場の中でも今年、投資家が選好しているのは米国株で、これまでに約1380億ドルの資金が流入。欧州株への流入はわずか2億6400万ドルだった。【市況】今週の【早わかり株式市況】小幅続伸、週末に米金利上昇と日銀ETF買い入れ方針変更で失速■今週の相場ポイント 1.日経平均は2週連続の上昇、米長期金利の動向に振り回される展開 2.景気回復期待を背景に海運、鉄鋼など市況関連株への買いが目立つ 3.FOMCはFRBがゼロ金利の長期化を明示、ポジティブ視される 4.週後半に米長期金利が1.7%台まで上昇しハイテク株に逆風強まる 5.日銀の会合ではETF買いの日経平均連動型除外を発表し波乱呼ぶ■週間 市場概況 今週の東京株式市場は日経平均株価が前週末比74円(0.25%)高の2万9792円と小幅ながら2週連続の上昇となった。 今週は日米の金融政策会合が絡み不安定な値動きで、米長期金利の動向に振り回される展開となった。景気回復期待を背景に市況関連株が買われ全体を牽引したが、半導体関連などハイテク株は逆風の強い展開に。金利上昇がプラス材料となる銀行や生保株は買われた。 15日(月)は米国の追加経済対策成立や新型コロナワクチン普及を背景とした景気回復期待の高まりが海運、空運、鉄鋼など市況関連株に買いを誘導した。前週から数えて日経平均は5日続伸。ただハイテク株が安く上げ幅は限定的だった。16日(火)は米長期金利が上昇一服となったことを受けハイテク株が買い戻され6日続伸となった。海運株の上昇も際立った。17日(水)はFOMCの結果発表とパウエルFRB議長の記者会見を前に様子見気分が強く日経平均は小動きに終始。結局、日経平均はわずかに安く引け7日ぶりに反落。しかし18日(木)は300円あまりの上昇と再び強気に傾いた。FOMCではFRBが23年末までゼロ金利政策維持の方針を示したことで日米ともに安心感が台頭、米国ではNYダウが初の3万3000ドル台に乗せ、東京市場もこの流れに追随した。ところが、19日(金)は波乱含みの展開に。前日の米国株市場では10年債利回りが1.7%台に急上昇したことを受けナスダック指数が大幅安となり、東京市場もリスク回避ムードを余儀なくされた。日経平均の下げ幅は一時600円近くに及んだが、これは日銀の金融政策決定会合でETF買い入れについて日経平均連動型を除外すると発表したことが大きく嫌気されたことによる。ファーストリテイリング の下げ幅は一時6630円に達した。ただ、TOPIXはプラスを確保した。■来週のポイント 日銀がETF買い入れについて日経平均連動型の除外を打ち出したことから来週の日経平均は不安定な値動きになりそうだ。ただ、幅広い業種が買われており、TOPIXは上値追いが期待される。 重要イベントとしては、国内では22日発表の1月景気動向指数[改定値]が注目される。海外では23日に発表される米国10-12月経常収支と米国2月新築住宅販売件数や、26日に発表される米国2月の個人所得と個人消費支出に注視が必要だろう。■日々の動き(3月15日~3月19日)【↑】 3月15日(月)―― 5日続伸、市況関連や自動車株が高く買い継続 日経平均 29766.97( +49.14) 売買高15億4166万株 売買代金 2兆9345億円【↑】 3月16日(火)―― 6日続伸、米株高を受け一時3万円大台を回復 日経平均 29921.09( +154.12) 売買高14億1937万株 売買代金 2兆9091億円【↓】 3月17日(水)―― 7日ぶり反落、日米の中銀会合を控え様子見ムード 日経平均 29914.33( -6.76) 売買高12億5284万株 売買代金 2兆5794億円【↑】 3月18日(木)―― 急反発、米株高を追い風に3万円大台回復 日経平均 30216.75( +302.42) 売買高15億9934万株 売買代金 3兆3544億円【↓】 3月19日(金)―― 急反落、日銀の政策修正で再び3万円割れ 日経平均 29792.05( -424.70) 売買高21億0187万株 売買代金 4兆4456億円■セクター・トレンド (1)全33業種中、31業種が上昇 (2)郵船 など海運、JFE など鉄鋼といった景気敏感株の買い続く、海運は2週連続で値上がり率トップ (3)三菱UFJ など銀行、マネックスG など証券、第一生命HD など保険といった金融株が大きく買われた (4)トヨタ など自動車、キーエンス など電機といった輸出株も上昇 (5)三井不 など不動産、大和ハウス など建設、楽天 などサービスといった内需株も総じて高いが ソフトバンクG など情報・通信は軟調 (6)国際石開帝石 など鉱業は値下がり率トップ■【投資テーマ】週間ベスト5 (株探PC版におけるアクセス数上位5テーマ) 1(2) 全固体電池 ── 2次電池革命に向け開発競争加速 2(1) アンモニア 3(3) 半導体 4(7) デジタルトランスフォーメーション(DX) ── 行政デジタル革命、覚醒する「DX関連」"現実買い"の舞台へ 5(6) 再生可能エネルギー ── 経産省が基金の基本方針を策定 ※カッコは前週の順位株探ニュースワイズが2勝目へ3打差首位 小平智58位で決勝へ 石川遼は予選落ち◇米国男子◇ザ・ホンダクラシック 2日目(19日)◇PGAナショナル(フロリダ州)◇7125yd(パー70)ツアー1勝のアーロン・ワイズが2日続けて「64」をマークし、通算12アンダーとして後続に3打差をつけて首位に立った。通算9アンダーの2位に前日首位のマット・ジョーンズ(オーストラリア)とブランドン・ハギー。サム・ライダーが8アンダー4位につけた。「全英オープン」王者のシェーン・ローリー(アイルランド)ら4人が7アンダー5位で並んでいる。前年大会でツアー初勝利を挙げたイム・ソンジェ(韓国)は4アンダーでアダム・スコット(オーストラリア)らと同じ16位タイで決勝ラウンドに進んだ。イーブンパーの43位から出た小平智は3バーディ、4ボギーの「71」とスコアを落としたが、カットライン上の1オーバーの58位で予選を通過した。初日に135位と出遅れた石川遼は3バーディ、3ボギー「70」で8オーバーのまま117位で予選落ちした。サイ・ペイインが暫定首位 渋野は2ホール残し6打差◇国内女子◇Tポイント×ENEOS ゴルフトーナメント 2日目(20日)◇鹿児島高牧CC (鹿児島)◇6424yd(パー72)午後3時25分に降雨によるコースコンディション不良のため中断され、26選手がホールアウトできず午後3時45分に順延が決まった。暫定首位には8バーディ、1ボギーの「65」でプレーしたサイ・ペイイン(台湾)。ツアー初優勝へ通算11アンダーで9位からトップに浮上した。初日首位の高橋彩華は14ホールを消化し、2つスコアを伸ばして通算10アンダー暫定2位。イ・ミニョン(韓国)が「65」でプレーして通算9アンダー。小祝さくらが4バーディ、ノーボギーの「68」でプレー。山内日菜子と並んで通算8アンダーで続いた。ホステスプロの渋野日向子は16ホールをプレーして3バーディ、3ボギー。通算5アンダーとしている。2週連続優勝を目指す稲見萌寧は通算2アンダーでホールアウトし、暫定41位。原英莉花は「76」をたたき、通算4オーバーで予選落ちが確実。今年初戦から2位、3位と好成績だった森田遥はスタート前に、左足痛のため棄権した。第2ラウンドは21日午前7時20分に再開される。国内株式市場見通し:インフレ懸念、米長期金利の動向を睨む展開継続フィスコ■FOMC通過であく抜け感で一時3万回復も週末失速今週の日経平均は週末にやや失速したものの、米連邦公開市場委員会(FOMC)を無難に通過したことで概ね堅調な動きとなった。米長期金利(10年物国債)が再び上昇したことで週初はグロース(成長)株が売られたが、景気敏感株などは堅調で日経平均も49円高と底堅さを見せた。16日は米長期金利の上昇一服とともにFOMCを前とした売り方の買い戻しなどもあって日経平均は一時3万円に乗せる場面も見られた。17日はFOMCの公表結果とパウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長の記者会見を見極めたいとする思惑から方向感に欠ける展開に。18日は、少なくとも2023年いっぱいは政策金利がゼロ付近で維持されるとの見通しが示されたFOMCの結果を受けて安心感が高まり、一時は30485.00円まで上値を伸ばし、終値でも3万円を保持した。19日は、FRBの緩和政策の継続によりインフレ期待が高まったことでかえって米長期金利が1.75%まで上昇するなど警戒感が再燃したことで、ハイテク株などが再び売りに押された。また、日銀金融政策決定会合で上場投資信託(ETF)の「原則年6兆円増」の買い入れ枠が撤廃されたほか、買い入れ対象が東証株価指数(TOPIX)連動型のETFのみで、日経平均型は外れると決まったことが伝わると、後場からは下げ幅を拡げる展開となった。結局、週末の日経平均は424円安の29792.05円まで下げて終えた。ただ、東証株価指数(TOPIX)は3.70pt高の2012.21ptで終えており、1991年5月以来となる大台2000pt台乗せに成功している。■警戒感くすぶるも過度な悲観は不要来週の日経平均はもみ合いか。注目だったFOMCでは23年末までのゼロ金利据え置きのほか、量的緩和についても現行の資産購入ペースの維持が示された。しかし、その後は一転して緩和政策の継続が景気回復を更に強めるとの予想から期待インフレ率が一層上昇し、かえって米長期金利が上昇するという動きに変わった。これを受けて、週末には再びハイテク株などが売られる展開になった。本来、景気回復期待による良い金利上昇と株高は長期的には共存できる。ただ、あまりに速いスピードでの金利上昇は市場の警戒感を強め、短期的な株価調整の要因となりかねない。FRBは政策により短期金利を誘導することはできるが、長期金利の水準は主として市場が決めるものだ。市場が先走る形でインフレ懸念が一層強まり、米長期金利が更に上昇する可能性もあろう。その場合、FRBも現在の緩和政策の変更を迫られるかもしれない。もともとインフレ懸念で長期金利が上昇していることを背景に、インフレ抑制のための早期利上げ見通しが示されるのではないかという警戒があったわけだが、結局、緩和政策を強調しても景気回復を強めるとの見方から「インフレ期待→長期金利上昇」という動きが続いたわけで、皮肉な話だ。バンク・オブ・アメリカ(BofA)による3月のグローバルファンドマネジャー調査では、いまや最大のテールリスクは「インフレ」と「長期金利の上昇」であり、新型コロナウイルスに取って代わっている。今後も期待インフレ率と米長期金利の動きを注視する必要があろう。週次イベントとしては、米長期金利の上昇のきっかけにもなった米7年国債入札が25日(木)に予定されており、債券需給が注目される。ここまでネガティブなことを書いてきたが、株式市場の先行きが暗いわけではない。米長期金利が上昇しているとはいっても、期待インフレ率を差し引いた実質金利はいまだマイナスで、これは当面保たれる見込み。実質金利がマイナスである限りは、株式益回りと債券利回りの差であるイールドスプレッドの縮小もある程度は許容できると思われる。FRBの政策スタンスが現状のままである限りは、各種アセットクラスの中での株式の相対的な魅力は劣らないだろう。実際、米長期金利が1.75%まで上昇した直後の東京市場は大きくは崩れなかった。TOPIXに至ってはバブル崩壊後の最高値だ。過度な悲観は不要だろう。ただ、留意が必要なのは、日銀がETFの買い入れ対象から日経平均型を外したことだ。ファーストリテなどの値がさ株がこれまで需給要因主体で買われていたのだとすれば、週末の同社株の急落に伴う日経平均の軟調ぶりも続く可能性がある。TOPIXは堅調でも日経平均は軟調という二極化の動きを想定しておく必要があろう。■インフレ下に強い景気敏感株を選好物色対象としては金利動向に敏感なグロース株は避けた方が無難だろう。有望なのは、バリュエーション面での割高感も薄い景気敏感株と考える。今年の株式市場での最大のテーマは「景気回復」だからだ。実際、昨年秋以降しばらくの間は日経平均の上昇が目立っていたが、最近はTOPIXの上昇ぶりが顕著だ。中でも、足元で最大の懸念要素であるインフレリスクをヘッジできるセクターが好ましいだろう。具体的には、鉱業、鉄鋼、化学、金融あたりが相対的に他をアウトパフォームしそうだ。そのほか、3月の終わりに近づいてきたことで、配当や株主優待の権利取りを狙った動きも活発化すると予想されよう。■米国2月耐久財受注、米国2月個人消費所得・個人支出など来週の主な国内外スケジュールは、22日に米国2月中古住宅販売、23日に米国2月新築住宅販売、24日に日銀金融政策決定会合議事要旨(1月20-21日開催分)、米国2月耐久財受注、25日にEU首脳会議、米国10-12月期GDP確報値、米国7年国債入札、26日に独3月Ifo景況感指数、米国2月個人消費所得・個人支出などが予定されている。●EV関連の最強ニューフェース6銘柄◎三益半導体工業 シリコンウエハー の研磨加工の先駆で筆頭株主の信越化学工業 からの受託業務を主力としており、電子部品や半導体装置関連の販売も行っている。EVのモーター製造に使用される大口径シリコンウエハーや、EV向けで旺盛な需要のあるパワー半導体向け製造装置など高採算商品が収益に貢献、今後一段と拡大する見込みだ。21年5月期業績は減収ながら営業利益は60億円と前期実績を小幅に上回る見通し。株価は今月9日に下ヒゲでつけた2380円をターニングポイントに緩やかな戻り波動を形成中。5日・25日移動平均線のゴールデンクロスでトレンド転換を示唆、2800円ラインが当面の上値のフシとして意識される。◎竹内製作所 ミニショベルなどを主力に小型建設機械を手掛けている。クローラーローダー開発などでも持ち前の技術力の高さを発揮している。欧州や北米向け中心に売り上げの99%が海外向けという異色企業で、「脱炭素」のテーマにも積極的な取り組みをみせている。ESGなどの観点から排気ガスを出さないEV建機の開発に注力している点は、海外機関投資家の視線を集め、株式組み入れニーズを喚起しそうだ。21年2月期は営業利益段階で従来予想の111億円から131億円に大幅増額し一転して増益を確保したもよう。今夏にも電動ショベル投入が見込まれている。株価は18年9月につけた上場来高値3120円を奪回し青空圏への突入を果たしている。◎日本電気硝子 FPD用ガラスや電子デバイス用ガラス、車載用ガラス繊維などを手掛ける。車載用ガラス繊維は世界的な新車販売の回復でフォローの風が強い。また、液晶ディスプレーや有機ELディスプレーの基板として使用されるFPD用ガラスは台湾、中国、韓国の液晶メーカー向けに需要が拡大している。車載用ではホンダの新車EV「ホンダ e」にディスプレー用カバーガラスが採用されている。ハンマーで叩いても割れない高強度のガラスで、今後も自動車業界向けに需要開拓が期待されている。21年12月期は営業2ケタ増益が濃厚。株主還元にも前向きで4%近い配当利回りは魅力。株価は昨年来高値圏を走り3000円台活躍を目指す。◎東光高岳 電力機器や計量器などを製造販売する。変電・配電設備や監視制御設備など電力インフラで重要な役割を担うほか、EV用の充電インフラでも今後中期的に活躍の機会を広げていくことが予想される。直流出力で充電を行う急速充電器で業界を先駆し、トップシェアを獲得している点を評価。また、EV用のパワーコンディショナーでも高い商品競争力を有している。21年3月期第3四半期累計の営業利益は前年同期比7.2倍の19億2100万円と急拡大、通期23億円予想に対する進捗率は83%に達している。年間配当50円を続けているが、配当利回りは3%前後と高い。一方でPBRは0.5倍台に放置されており、昨年12月の高値1949円更新が期待される。◎明電舎 重電メーカー中堅で水処理制御システムや自動車用試験装置で優位性を持っている。EV用モーターやインバータの開発を1980年代から手掛けており、EV駆動システムの先駆として存在感を示す。EV用自動車試験装置でも強みを有し、EV駆動用バッテリーをリユースした定置型蓄電システムの構築やこれを活用したバーチャルパワープラント実証試験などでも実績を示している。21年3月期は大幅減益見通しながら、営業利益は期初予想の70億円から77億円に上方修正している。既に業績は底入れ反転局面にあり、22年3月期は100億円の大台に再び乗せてくる公算が大きい。今年1月14日につけた高値2927円奪回から3000円台指向。◎大豊工業 軸受けやアルミダイカスト製品、金型製造などを手掛け、摩擦工学分野の深い知見が強み。EV向けバッテリー、モーター、パワーコントロールユニットなど電動化製品への取り組みに余念がなく、トヨタグループに属していることもポイントとなる。EVと並行して燃料電池車(FCV)とも密接で、トヨタが販売する“新型ミライ”向けにアルミダイカスト製品を供給している。21年3月期は営業7割減益見通しながら株価には織り込まれており、世界的な新車販売回復を背景に22年3月期は利益を急激に復元させる可能性が高い。ここ戻り足に拍車がかかっているが、有配企業にしてPBRは依然0.5倍前後と割安。株価は4ケタ台を地相場とする展開が想定される。株探ニュース(minkabu PRESS)本日の夕食は…飛騨牛コロコロステーキ、ブロッコリースープ、野菜サラダ、パン、デザート(イチゴ)でした。一緒に楽しんだのは…2008シャトー・モンローズでした。美味しくいただきました。
2021.03.20
コメント(0)
-
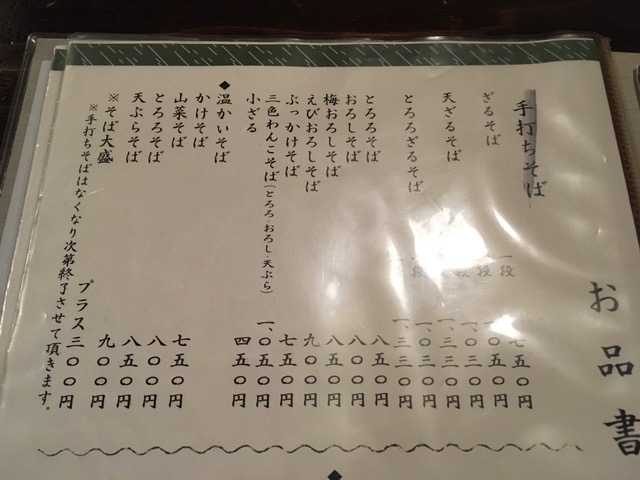
3月19日(金)…
3月19日(金)、晴れです。週末の連休は天候が悪そうですが、本日はよい天気です。そんな本日は7時20分頃に起床。新聞に目を通し、朝食を済ませ、ロマネちゃんと戯れる。身支度をして、8時40分頃に家を出る。ゴルフではありません、アルバイト業務です。本日は10:00~16:00です。ランチタイムは…庶民派そば店「法扇」で天ざるそばをすすり、「緑の館」でロイヤルブレンドをすする。帰宅すると奥の名古屋土産は桜餅&団子でした。それではしばらく休憩です。1USドル=108.74円。1AUドル=84.39円。昨夜のNYダウ終値=32862.30(-153.07)ドル。本日の日経平均終値=29792.05(-424.70)円。金相場:1g=6737(-51)円。プラチナ相場:1g=4711(-56)円。昨夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中の1銘柄が値を上げて終了しましたね。本日の東京市場ではチェック中の日本株30銘柄中の15銘柄が値を上げて終了しましたね。重点3銘柄では1銘柄が値を上げて終了しましたね。TOPIX上昇転換、日銀ETF購入方針変更で-日経平均は下げ拡大 19日の東京株式相場は午後にTOPIXが上昇に転じた。9日続伸となりバブル後の戻り高値を再び更新した。日本銀行が金融政策決定会合で上場投資信託(ETF)の買い入れをTOPIX型のみに変更することを決め、銀行をはじめ幅広い銘柄に買い注文が先行した。米長期金利上昇や原油高で下落していた日経平均株価は対照的に午後に下げ幅を拡大した。 TOPIXの終値は前日比3.70ポイント(0.2%)高の2012.21 日経平均株価は424円70銭(1.4%)安の2万9792円05銭 〈きょうのポイント〉 日銀、長期金利の変動幅を上下0.25%程度に拡大-市場機能を維持 ETF買い入れ、TOPIXに連動するもののみに 米国債利回り上昇、10年債1.75%に上昇-インフレ観測急速に広がる NY原油先物、半年で最大の下げ-景気と需要の回復に不透明感 金融政策決定会合を終えた日銀は午後、ETF買い入れについて「今後、指数の構成銘柄が最も多いTOPIXに連動するもののみ買い入れることとする」と発表した。また買い入れ額について年間約12兆円の上限を感染症収束後も継続するとしたが、約6兆円の原則については削除した。 これを受けて午後にTOPIXの水準が切り上がった。逆に日経平均株価の寄与度の高い銘柄に売りが大きく膨らみ、ファーストリテイリングは一時6.8%安と昨年8月以来の日中下落率となった。SMBC信託銀行の佐溝将司シニアマーケットアナリストは、日経平均は一部銘柄に偏る問題点が前から指摘されており「日銀が買うことによりゆがみを大きくしていた」と指摘。その上で「今の水準であれば気にする必要はなく、TOPIXのほうが市場に合った買い入れ割合になる」と述べた。 野村証券の9日時点の試算によると日銀ETF買いの指数別買い入れ比率はTOPIX型が84%、日経平均型が15.3%、JPX日経400型が0.7%となっている。 三井住友DSアセットマネジメントの市川雅浩チーフマーケットストラテジストはETF購入について、年間約6兆円の原則を削除したことは上限は維持しつつも柔軟な買い入れを続けるということであり、引き締め方向にはならないとのメッセージを伝えるための工夫だとみている。 東証33業種では海運、鉄鋼、銀行、証券・商品先物、不動産、保険、輸送用機器が上昇率上位 鉱業、情報・通信、ゴム製品、電機は下落率上位【本日のNYダウ見通し】米10年債利回りの動向に振り回される展開か【NYダウ予想レンジ:32,500~33,000ドル】18日のNYダウは反落。前日比153.07ドル安の32,862.30ドルで取引を終了しました。米連邦準備理事会(FRB)のゼロ金利政策の長期化がインフレを加速させるとの見方から、米10年債利回りが一時1.75%まで上昇。長期金利の上昇によって、相対的な割高感が意識されやすいハイテク株中心に売られました。ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数も4営業日ぶりに反落し、前日比409.035ポイント安の13,316.618で取引を終了しています。電気自動車のテスラが7%安と大きく値下がりしたほか、ソフトウェアのマイクロソフトやスマートフォンのアップルも売られました。また、原油相場が急落してWTIが60ドルを割り込む中で、エネルギー株の下げも売り要因となりました。本日は重要な経済指標の発表はないので、長期金利の動向に一喜一憂する展開になりそうです。日経平均は急反落、日銀点検受け物色面で跛行色 TOPIXは9日連騰[東京 19日 ロイター] - 東京株式市場で日経平均は急反落。日銀政策決定会合で行われた点検で、日銀が上場投資信託(ETF)の買い入れ対象をTOPIX連動型のみとしたことを受け、ファーストリテイリングなど値がさ株が売られたものの、バリュー株を中心に幅広く物色されるなど、物色面で跛行(はこう)色が強まった。日経平均が一時500円を超す下落となったのに対し、TOPIXはプラスとなり、バブル後最高値を更新。9連騰となっている。東証1部の売買代金は4兆円を超え、今年2番目の大商いとなった。日銀が明らかにしたETFの購入法に関しては、原則6兆円の年間買い入れめどを削除。引き続き12兆円を上限に買い入れを行うとしたが、これについては想定通りだったとみる関係者が多い。しかし、TOPIX連動型のみを購入するという点についてはサプライズ感が生じ、指数寄与度が大きい値がさ株が総じて軟調となり、日経平均の下げ幅を拡大させた。一方、決定会合の内容全体については、株式市場が好感できるものとみる関係者が多く、経済正常化で収益回復が見込まれるバリュー株が物色された。市場では「今後の相場はバリュー株主導が鮮明になり、今回の点検はそのきっかけを与えた。折しも、年度末を控え配当権利取りが活発化し、目先はTOPIX優勢の相場展開が続くとみている」(東海東京調査センター・シニアストラテジストの中村貴司氏)といった声が聞かれる。TOPIXは0.18%高。東証1部の売買代金は4兆4456億2300万円と膨らんだ。東証33業種では、海運業、鉄鋼などの上昇が目立ち、値下がりは鉱業など12業種で値上がり業種の方が多い。個別では、ファーストリテイリングが急落したほか、ソフトバンクグループもさえない。半面、三菱UFJフィナンシャル・グループなど銀行株のほか、三菱重工業もしっかり。ホンダが連日の昨年来高値更新となった。東証1部の騰落数は、値上がり1491銘柄に対し、値下がりが623銘柄、変わらずが銘81柄だった。午後3時のドルは108円後半、日銀決定会合後に小幅な上下動[東京 19日 ロイター] - 午後3時のドル/円は、前日のニューヨーク市場午後5時時点とほぼ同水準の108円後半。ドルは日銀決定会合の結果を受けて109.14円まで上昇したが、まもなく小幅に下落した。前日急伸した米長期金利が反落したことや、株安によるリスク回避の円買い圧力もあり、109円台に定着することはできなかった。実質的な五・十日にあたるきょうは、仲値にかけて期末を控えた実需の買いが流入し、ドルは108.10円まで上昇したが、その後は日銀金融政策決定会合を控えた様子見が広がった。午後にその結果が明らかになるとドルはいったん109.14円まで上昇しものの、108.83円まで下落した。日銀は19日の声明に、長期金利の変動幅を「プラスマイナス0.25%程度」とすることを明記した。一方、上場投資信託(ETF)については年12兆円を上限に引き続き買い入れを行うとし、これまでの原則6兆円の買い入れめどは削除した。三井住友銀行チーフストラテジストの宇野大介氏は、あくまでも緩和政策の続行を前提として、金融緩和の領域内での選択肢を検討したものと指摘。「円売りを手掛ける海外投機筋が怖れる『出口戦略』を検討した気配はみじんもない」とし、足元の円高は勢いづくことなく早晩に修正され、ドル高/円安の流れに回帰する」とみていた。午後の取引では、ドルを押し上げてきた米長期金利が足元で反落したことや株安がドル/円の重しとなった。リフィニティブによると、米10年国債利回りは現在1.6980/6962%の気配。前日ニューヨーク市場午後5時05分時点の1.7064%から低下した。前日の欧州時間から米国時間にかけて米長期金利は急伸し、一時1.7543%と昨年1月以来の高水準に達した。金利上昇のきっかけは欧州の投資家や短期筋によるロングの投げ(買い持ちポジションの解消)だという。来週の外為市場では四半期末や年度末を控えた実需の売買が交錯するとみられる。米連邦準備理事会のパウエル議長の発言や米国債の入札も予定される。富士製薬が大幅反発、発行株の20%超の自己株式を消却女性医療と急性期医療に強い後発薬メーカーの富士製薬工業(4554)が3日ぶりに大幅反発した。午後0時34分現在、前営業日比63円(4.73%)高の1396円で推移している。一時は1479円まで上伸した。18日に自己株式の消却を発表し、株式需給の改善や1株利益の上昇を期待した買いが流入した。消却前の発行済み株式総数の20.80%に当たる650万株を3月25日付で消却する。消却後の保有自己株式は44万3379株。2021年9月期の連結営業利益は28億5700万円(前期比9.0%減)と減益を見込んでいるが、株価は20年4月以降、1200円を軸にした狭いレンジの中で緩やかに下値を切り上げており、今回の自己株式の消却を受けモミ合い上放れの機運が台頭してきた。(取材協力:株式会社ストックボイス)米国株式相場はインフレ懸念で国債利回り急上昇し反落原油は大幅安ブルームバーグ欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。◎米国市況:株反落、インフレ懸念で国債利回り急上昇-原油急落18日の米株式相場は反落。米国債利回りは上昇し、節目の水準を次々に突破した。米金融当局がインフレ加速を容認するリスクを冒しているとの懸念が広がった。原油は大幅安。リスク資産は原油の売りを手始めに、午後になって下げ足を速めた。米国債利回りの急上昇を受けて、バリュエーションが高いテクノロジー株が売られ、ハイテク銘柄中心のナスダック100指数は3.1%下落した。オプションと先物取引が期限を迎える四半期ごとの「クアドルプル・ウィッチング」を19日に控えていることも、ボラティリティーを増幅させた。S&P500種株価指数は前日比1.5%安の3915.46。ダウ工業株30種平均は153.07ドル(0.5%)安の32862.30ドル。ナスダック総合指数は3%下落。FBBキャピタル・パートナーズの調査責任者、マイク・ベイリー氏は「米10年債利回りの不穏な急上昇が、ハイテク株の割高感を株式投資家に思い出させるというパターンがみられる」と述べた。米国債相場はニューヨーク時間午後4時59分現在、10年債利回りが7ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の1.71%。一時は1.75%と昨年1月以来の水準に上昇した。30年債利回りは一時2.5%を上回り、19年8月以来の高水準に達した。パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長が景気支援の継続に前向きで、景気の過熱を容認しているとの見方から、成長とインフレが加速するとの観測が強まった。市場のインフレ期待は数年ぶりの高水準になっている。外国為替市場では、カナダ・ドルが3週間ぶりの大幅安となるなど、資源国通貨が下落。原油が下げ幅を拡大したことが影響した。一方、ドルは主要10通貨に対して全面高。米国債利回りの上昇に支えられた。主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.5%上昇。ドルは対円で0.1%高の1ドル=108円89銭。ユーロは対ドルで0.5%安の1ユーロ=1.1915ドル。ドルは対カナダ・ドルで0.7%高の1ドル=1.2487カナダ・ドル。ニューヨーク原油先物相場は急落し、昨年9月以来の大幅安となった。新型コロナワクチン接種が順調に進んでいない国・地域があることから、景気改善ペースと原油需要の完全回復を巡り不透明感が広がった。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物4月限は4.60ドル(7.1%)安い1バレル=60ドルちょうど。これで5営業日続落となった。ロンドンICEの北海ブレント5月限は4.72ドル(6.9%)下落の63.28ドル。ニューヨーク金市場ではスポット相場が下落。米国債利回りが大きく上昇し、投資妙味が低下した。10年債利回りは一時、昨年1月以来の高水準を付けた。金スポットはニューヨーク時間午後3時12分現在、0.6%安の1オンス=1734.79ドル。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物4月限は、5.40ドル(0.3%)反発し1732.50ドルで終了した。マット・ジョーンズが「61」と爆発し9アンダーで単独首位 石川遼135位T、小平智43位T<ザ・ホンダ・クラシック 初日◇18日◇PGAナショナル・チャンピオン・コース(米フロリダ州)◇7125ヤード・パー70>米国男子ツアー「ザ・ホンダ・クラシック」の初日の競技が終了。石川遼は1バーディ・7ボギー・1ダブルボギーの「78」で、8オーバー・135位タイと出遅れ。小平智は3バーディ・3ボギーの「70」で、イーブンパー・43位タイで初日を終えた。オーストラリアのマット・ジョーンズが9バーディ・ボギーなしの「61」と爆発し、単独首位発進。3打差の6アンダー・2位タイにアーロン・ワイズとラッセル・ヘンリー(ともに米国)が続く。4アンダー・4位タイには、スコット・ハリントン、ケビン・チャペル、スティーブ・ストリッカー、ジョセフ・ブラムレット(いずれも米国)、キャメロン・デービース(オーストラリア)の5人がつけている。昨年の今大会で米国男子ツアー初優勝を飾ったイム・ソンジェ(韓国)は2アンダー・15位タイ発進。2週連続で2位に入っている47歳のリー・ウェストウッド(イングランド)は、イーブンパーで43位タイにつけている。高橋彩華が大会コース記録タイ「64」で首位発進 渋野日向子は3差4位<Tポイント×ENEOSゴルフトーナメント 初日◇19日◇鹿児島高牧カントリークラブ(鹿児島)◇6424ヤード・パー72>2021年の国内女子ツアー3戦目は第1ラウンドが終了した。黄金世代の高橋彩華が1イーグル・7バーディ・1ボギーの「64」をマーク。大会コースレコードタイとなるビッグスコアで8アンダー・単独首位発進を決めた。6アンダー・2位タイにペ・ソンウ、ユン・チェヨン(ともに韓国)。5アンダー・4位タイには渋野日向子、成田美寿々、金田久美子、宮田成華、淺井咲希が続いた。渋野は今大会、自身初めてホステスプロとして参戦。後半「32」とチャージを見せ、まずは5アンダーと上々のスタートとなっている。大会連覇がかかる上田桃子は1アンダー・43位タイ。2週連続優勝を狙う稲見萌寧も同順位で初日を終えた。【アルピナD3 Sリムジン試乗】アルピナがディーゼルに仕掛けたマジックに浸る明日の戦略-日経平均は大幅安もTOPIXは上昇、バリュー優位の流れが一段と強まるかトレーダーズ・ウェブ 19日の日経平均は大幅反落。終値は424円安の29792円。米国でナスダックが大きく下げた流れを受けて、300円超の下落で29900円台からのスタート。しかし、前場では寄り付いてすぐに切り返すと、3万円近辺まで値を戻した。後場に入ると日銀の政策に関するアナウンスが出てきたが、その中で、日銀のETF買い入れをTOPIX連動型のみにするとの発表があった。これを受け、日経平均の寄与度が大きいファーストリテイリングが急失速。この動きが売りを誘う格好となり、指数も下げ幅を広げた。600円近く下げたところで売りは一巡したものの、その後の戻りは限られた。一方、TOPIXはETFの買い入れルール変更を受けて後場に強含み、終値でプラスを確保した。 東証1部の売買代金は概算で4兆4400億円。業種別では海運、鉄鋼、銀行などが上昇した一方、鉱業、情報・通信、ゴム製品などが下落した。自動車株に資金が向かっており、ホンダや日産自動車が大幅上昇。半面、下値模索が続いたファーストリテイリングは6%を超える下落となった。 東証1部の騰落銘柄数は値上がり1491/値下がり623。日経平均が400円以上下げる中でも値上がり銘柄の方が多かった。米国の長期金利上昇を受けて、三菱UFJや三井住友などメガバンクがしっかり。富山第一銀行や島根銀行など、地銀株の多くにも見直し買いが入った。直近で値幅が出ていたマネックスGや日本郵政が大幅上昇。上方修正を発表したイノテックや興研が急伸した。 一方、ファストリ同様、指数寄与度の大きいソフトバンクGが2%を超える下落。米ナスダックの大幅安を嫌気して、東京エレクトロンや太陽誘電などハイテク株が軒並み売られた。グロース劣位の地合いの中、BASE、フリー、メルカリなどマザーズの主力どころが大幅安。下方修正を発表した内海造船が急落した。 IPOでは持ち越し含めて3社の初値がつき、いずれも高い初値となった。ココナラと2日目初値のi-plugは終値が初値を上回った一方、T.S.Iは初値を大きく下回って終えた。 日経平均は後場に入って下げ幅を広げたが、東証1部では後場に入って値上がり銘柄が増加した。TOPIXに至っては上昇しており、日銀政策見直しの悪影響をファーストリテイリング1銘柄がかぶったような1日。日銀はETFの原則年6兆円、REITの原則年900億円の購入目安を削除。ETFの買い入れに関してはTOPIX連動型のみとすることなどを決定した。ファーストリテイリングは日銀ETF買いの恩恵を受ける象徴との見方も強かっただけに、この銘柄に関しては目先の需給が悪化する可能性がある。ただ、だからといって日経平均もこれに連動して弱くなるということは考えづらい。この先は、TOPIXの方が日本株の実態をより表している指数との見方が強まるだろう。物色面においても、バリュー株が相対優位の状況がまだしばらく続くと予想する。【来週の見通し】 もみ合いか。FOMCを通過した後に米長期金利が一段と上昇してきたことから、引き続き金利変動に神経質となる展開が想定される。来週、米国では2月耐久財受注や10-12月期GDP確報値、2月の新築および中古の住宅販売など、注目度の高い指標の発表が多い。指標の良し悪しと、これを受けた米国株の反応に一喜一憂が続くだろう。一方、足元では金融株が強含み景気敏感株が買われるなど、金利上昇を好感する動きも多く見られる。また、3月も後半に入り、ここで大きく下押すような場面があれば、権利取りの実需買いが活発となりやすい。上値追いには慎重となる一方で、下値も堅いと考える。【今週を振り返る】 不安定な展開となった。週半ばまでは米国の長期金利上昇を警戒しつつも、FOMCや日銀会合で混乱が収束するとの期待から、買いが優勢。概ねマーケットフレンドリーとなったFOMC結果を確認した18日には、300円を超える上昇で3万円台を回復した。しかし、FOMC通過後も長期金利の上昇に歯止めがかからなかったことや、日銀のETF買い入れ方針見直しに伴って指数寄与度の大きいファーストリテイリングが急落したことなどから、翌19日は400円を超える大幅下落。中央銀行イベントを消化する中で、値動きが荒くなった。日経平均は週間では約74円上昇したが、週足では十字に近いながらも陰線を形成した。TOPIXが週間で3.1%高と日経平均(0.2%高)を大きくアウトパフォーム。昨年来高値を更新し、2000ポイント台に到達した。【来週の予定】 国内では、日銀金融政策決定会合議事要旨(1/20~21開催分)、2月企業サービス価格指数(3/24)、3月都区部消費者物価指数(3/26)などがある。 企業決算では、ダントーHD(3/23)、出前館、ジャステック、YE DIGIT、ヒマラヤ、ミタチ(3/26)などが発表を予定している。 海外では、海外の経済指標の発表やイベントでは、米2月中古住宅販売(3/22)、米10-12月期経常収支、米2月新築住宅販売、米2年国債入札(3/23)、米2月耐久財受注、米5年国債入札(3/24)、EU首脳会議、米10-12月期GDP確報値、米7年国債入札(3/25)、独3月Ifo景況感指数、米2月個人消費所得・個人支出(3/26)などがある。来週の日本株の読み筋=下値固めか、需給改善に期待モーニングスター 来週(22-26日)の東京株式市場は、下値固めの展開か。日銀は19日の金融政策決定会合で長期金利目標のレンジをプラスマイナス0.25%(従来は同0.20%)に拡大したほか、ETF(上場投資信託)の購入の目安となる年間6兆円を撤廃した。事前報道通りの内容となったが、ETF(上場投資信託)の買い入れ対象を見直したことで19日後場の日経平均株価の一段安につながった。ETF購入に際し、日経平均型をやめ、TOPIX(東証株価指数)型に一本化したことで、日経平均寄与度の高い銘柄を中心に値を下げ、下げ幅を拡大した。 一方、同日のTOPIXは9営業日続伸し、1991年以来の高値を更新中だ。日経平均以上に市場全体の値動きを示すTOPIXが堅調さを保っていることは、個人投資家を中心に余裕が広がりつつあるとも言える。需給面では、年度末に向けた年金の売り一巡が見込まれる。また、米追加経済対策に基づく現金給付が始まり、米株への資金流入を通じて日本株にも好影響をもたらす公算があり、需給改善も期待される。 スケジュール面では、国内で24日に1月20、21日開催の日銀金融政策決定会合議事要旨が発表される。海外では22日に米2月中古住宅販売件数、23日に米20年10-12月期経常収支、25日に米20年10-12月期GDP確報値、26日に独3月Ifo景況感指数などが予定されている。 なお、19日の日経平均株価は大幅反落し、2万9792円(前日比424円安)引け。前場は、米長期金利の上昇を背景に18日の米国株式市場で主要3指数が下落した流れを受け、300円超安で寄り付いた。直後にいったん持ち直したが、買い続かず、上値が重くなった。後場は一段安となり、下げ幅は一時590円を超えた。日銀のETF買い入れ対象の見直しがファーストリテ などの指数寄与度の高い銘柄の売り圧力につながった。一方、TOPIXは2012.21ポイント(同3.70ポイント高)と上げが続いた。今晩のNY株の読み筋=米長期金利動向に左右される展開続くかモーニングスター 19日の米国株式市場は、引き続き米長期金利の水準感に右往左往することになるとみられる。 18日は、17日のFOMC(米連邦公開市場委員会)で23年末までのゼロ金利政策維持の方針が示されたにもかかわらず、米長期金利は1.7%を上向けて上昇し、これを警戒した米株式市場では、ハイテク株が原油安で急落したエネルギー株に次いで売られた。 19日東京株式市場の場中の米国債時間外取引では、長期金利がやや低下したが、依然高止まりの域にある。きょうの米国株式市場で長期金利が上昇方向に振れれば、神経質な展開を嫌気した売りが出やすくなるとみられる。<主な米経済指標・イベント>特になし(日付は現地時間)◎投資関連情報は投資の参考として情報提供のみを目的としたものであり、株式の売買は自己責任に基づき、ご自身で判断をお願いします。ドル、買い戻しの動き ユーロドルは1.19ドル割れトレーダーズ・ウェブ ドルは買い戻しの動き。欧州序盤は米長期金利低下によるドル安が目立つ為替相場だったが、欧州各国での新型コロナ第3波に対する懸念から徐々にユーロ安にシフトしている。ユーロドルは1.19ドルを割り込み1.1898ドルまで下押し。ドル円は108.61円を底に108.82円付近まで下げ幅を縮めている。〔ロンドン外為〕円、108円台後半(19日午前9時)時事通信 【ロンドン時事】週末19日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米長期金利の下落を背景にドル売り・円買いが進み、1ドル=108円台後半に上昇している。午前9時現在は108円60~70銭と、前日午後4時(108円90銭~109円00銭)比30銭の円高・ドル安。 対ユーロは、1ユーロ=129円50~60銭(前日午後4時は129円90銭~130円00銭)で、40銭の円高・ユーロ安。ユーロの対ドル相場は1ユーロ=1.1920~1930ドル(1.1920~1930ドル)。(了)NY株見通し-底堅い展開か 下落銘柄の反発に期待トレーダーズ・ウェブ 今晩のNY市場は底堅い展開か。昨日は長期金利が上昇し、割高感が強まったハイテク・グロース株が売られ、ナスダック総合は3%超の大幅反落となった。朝方に史上最高値を更新したダウ平均も153ドル安と反落して終了した。週初からの騰落率は、ダウ平均が0.26%高とプラス圏にとどまったものの、S&P500が0.71%安、ナスダック総合が1.53%安なった。今晩は週末の取引となるほか、主要な経済指標や企業決算の発表もないが、指数先物・オプション、個別株オプションなどの満期日が重なるクワドルプルウィッチングに絡んだ売買の活発化が予想されるほか、昨日大きく下落した銘柄の押し目買いも期待できそうだ。 今晩は主要な米経済指標・イベント、企業決算はなし。(執筆:3月19日、14:00)KMバイオ、ワクチン製剤化開始=英アストラ製、承認後出荷―新型コロナ 明治ホールディングス傘下のKMバイオロジクス(熊本市)は19日、英製薬大手アストラゼネカが承認を申請中の新型コロナウイルスワクチンについて、国内での製剤化を始めたと発表した。ワクチン原液を容器に充填(じゅうてん)・包装し、国の承認後、速やかに出荷できるようにする。 アストラ社は、日本政府に供給する1億2000万回(6000万人)分のワクチンのうち、9000万回(4500万人)分を日本で生産・供給する。製剤化はKMバイオと第一三共が担う。ワクチン接種後にコロナ感染判明 東大阪の看護師産経新聞 大阪府東大阪市の市立東大阪医療センターは19日までに、ワクチン接種を受けた50代女性看護師の新型コロナウイルス感染が、接種後に判明したと発表した。看護師は今月12日に1回目の接種を受け、夜勤明けの15日以降、せきや頭痛などの症状を訴えて16日にPCR検査を受診。17日に陽性と判明した。新型コロナは発症までの潜伏期間が5~6日程度とされ、看護師が接種前に感染していた可能性もあるが、感染経路は不明としている。二転三転の末…アストラゼネカ製ワクチン、仏で接種再開朝日新聞社 フランスのカステックス首相は18日の記者会見で、英アストラゼネカ製のワクチン接種を19日から再開すると明らかにした。血栓などの副作用の有無を調べていた欧州医薬品庁(EMA)が18日、「ワクチンは安全で効果が見込める」と結論づけたためだ。だが、同社製ワクチンをめぐる政府の評価はこれまで二転三転してきており、市民の不安解消には時間がかかりそうだ。 変異株が猛威を振るうフランスは、1日の感染者数が3万人を超える。病床は逼迫(ひっぱく)し、パリ首都圏などでは20日から少なくとも4週間、市民の外出が禁じられることが決まった。ただでさえ供給が遅れているワクチンは「1本たりとも無駄にできない」(カステックス氏)状況だ。 だが、今週の世論調査で同社製ワクチンを「信頼できる」と答えた仏国民は20%にとどまった。同社製ワクチンをめぐる政府の評価がこの2カ月、めまぐるしく変わってきたためだ。 マクロン大統領は1月末、同社製ワクチンについて十分な情報がないとして「65歳以上にはほとんど効かないと考えられる」などと懐疑的な見方を示した。 ところがその後、EMAが18歳以上のすべての世代の接種を認めると、フランスも65歳以上の高齢者への接種を認めることにした。同社製はワクチンの供給不足を挽回(ばんかい)する一翼を担うと期待され、3月半ばまでにフランスで接種した約530万人のうち、4分の1が同社製の接種だった。 一方で、同社製ワクチンを優先的に接種できる医療スタッフや介護施設の職員では、3人に1人しか接種していないことが3月上旬に判明。カステックス氏は「普通ではない」などといらだちを示し、接種を強く促した。 その後、北欧の一部の国が副作用の懸念から同社製ワクチンの接種を見送り始めても強気を貫いた。14日夜のテレビ番組で、カステックス氏は「アストラゼネカのワクチンを信頼しないといけない」と力を込めた。だが、マクロン大統領はその翌日、「用心のため」として突如中断を表明。混乱に拍車がかかった。 カステックス氏は接種再開を発表した18日の会見で、「信頼できる(ワクチンだ)と示すため」、19日に自ら先頭に立って接種を受けることを明らかにしている。LINE個人情報ずさん保護、他IT企業も疑問視…2年半にわたり中国企業が閲覧可能読売新聞 無料通信アプリLINEの利用者情報が中国企業から閲覧可能だった問題で、LINEの親会社Zホールディングス(HD)は19日、問題の経緯を検証する第三者委員会の初会合を23日に開くと発表した。国内で8600万人が利用するLINEは、行政機関や民間企業で幅広く活用されており、早期の実態把握と再発防止の取り組みが求められる。 第三者委は、個人情報保護に詳しい大学教授や弁護士らで構成される。問題の経緯を詳細に検証するほか、再発防止策に関する提言も行う方針だ。 関係者によると、LINEと経営統合する前のZHDのもとに1月下旬、問題に関する指摘があった。LINEに照会したところ、委託先の中国企業から日本の利用者の個人情報が約2年半にわたり、閲覧可能だったことが明らかになった。 ZHDの中谷昇・常務執行役員は19日、自民党本部の部会で問題の経緯を説明した。中谷氏は部会出席後、記者団に「(個人情報を)中国から見られる状態だった。不適切だった」と述べた。 LINEのずさんな個人情報保護のあり方は、他のIT企業からも疑問視されている。楽天の場合、安全対策を講じたうえで、海外子会社の一部技術者がサービス開発などのために個人情報を閲覧できるようになっている。別のIT大手幹部は「グローバル企業は個人情報の取り扱いに慎重になっている。なぜ徹底できていなかったのか」と指摘する。〔NY外為〕円、108円台後半(19日朝)時事通信 【ニューヨーク時事】週末19日午前のニューヨーク外国為替市場では、米長期金利の低下を受けた円買い・ドル売りが一巡し、円相場は1ドル=108円台後半で小動きとなっている。午前9時現在は108円85~95銭で前日午後5時と同水準。 ニューヨーク市場は、108円82銭で取引を開始。10年物米国債利回りは前日、景気回復期待を背景に1.75%近辺まで上昇した後、いったん1.6%台に低下した。これを受けて、円は未明に一時108円60銭近辺まで上昇。ただ、円買い・ドル売り一巡後はもみ合う展開となった。 日銀の金融政策決定会合では、長期金利の誘導目標の変動容認幅を実質的に拡大したが、結果はほぼ織り込み済みだったため、影響は限定的だった。 ユーロは同時刻現在、対ドルで1ユーロ=1.1895~1905ドル(前日午後5時は1.1911~1921ドル)、対円では同129円50~60銭(同129円72~82銭)と、22銭の円高・ユーロ安。(了)〔米株式〕NYダウ、ナスダックとも続落(19日午前)時事通信 【ニューヨーク時事】週末19日午前のニューヨーク株式相場は、前日の米株安要因となった米長期金利の動向に引き続き注目が集まる中、週末を前に利食い売りが先行し、続落している。午前10時10分現在は、優良株で構成するダウ工業株30種平均が前日終値比250.04ドル安の3万2612.26ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数が59.60ポイント安の1万3056.57。 米連邦準備制度理事会(FRB)はこの日、新型コロナウイルス危機を受けて導入された銀行自己資本規制の緩和特例を期限の3月末で終了すると発表した。危機後の市場混乱が落ち着いたとの判断が背景にある。ただ、特例打ち切りで米国債の市中消化に悪影響が及ぶとの懸念も根強く、米長期金利の指標である10年物国債の利回りは朝方、再び上昇。前日に続き、約1年2カ月ぶりの高水準となる1.75%付近で推移している。 また、大型経済対策を実現したバイデン政権が、環境インフラ投資など次の成長戦略の実行に向け、富裕層や企業への増税に動くとの観測が一部で浮上。これが米株高トレンドにブレーキをかける可能性があるとの警戒感もくすぶり、持ち高調整の売りが先行した。このほか、この日は先物やオプションの決済日が重なる「クアドルプル・ウィッチング」に当たり、不安定な値動きが誘われやすい地合い。 個別銘柄を見ると、18日夕に20年12月~21年2月期決算を発表したナイキが5%近く下げ、ダウ平均全体を下押し。半面、同四半期の純利益が約2.8倍に膨らんだと発表したフェデックスは5.4%高。(了)今夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中の13銘柄が値を上げてスタートしましたね。エッツィが上げていますね。
2021.03.19
コメント(0)
-
3月18日(木)…
3月18日(木)、晴れです。気持ちの良い天気ですね。そんな本日は7時30分頃に起床。新聞に目を通し、朝食を済ませ、ロマネちゃんと戯れる。今朝のノルマは1階の掃除機ですか…。ハイハイ…。身支度をして、9時頃に家を出る。アルバイト業務ではありません、ゴルフではありません、運転免許の書き換えです…。9時40分から10時が受け付けとのことですが、駐車場はいっぱいです…。すでに20人位が並んでいますが、中からぞろぞろと出てくる人も…。別講習で朝早くから来ている人なんですかね…。受付が終わって、書類を書いて、視力検査して、写真を撮って、お話を聞いて、1時間ほどで新しい免許を受け取って終了。帰宅して休憩です。1USドル=109.07円。1AUドル=85.38円。昨夜のNYダウ終値=33015.37(+189.42)ドル。現在の日経平均=30402.46(+488.13)円。金相場:1g=6788(+53)円。プラチナ相場:1g=4767(+26)円。昨夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中の11銘柄が値を上げて終了しましたね。テラドックが下げていますね。ハイテク・グロース株の仕込み計画はどうなるのか…。本日の東京市場ではチェック中の日本株30銘柄中の26銘柄が値を上げていますね。重点6銘柄では5銘柄が値を上げていますね。5%以上の大きな変動は見られませんね。いくつかの株を利益確定の処分に回しましたが、もう少し価格設定を高くしても良かったですね…。日本株大幅高、FOMC政策維持や宣言解除方針-TOPIX大台回復 18日の東京株式相場は大幅高。TOPIXは1991年5月以来となる2000ポイントの大台を回復した。米連邦公開市場委員会(FOMC)を政策維持で通過した安心感や首都圏の緊急事態宣言が21日に解除される方針が固まったことを受けて、鉄鋼や海運などの景気敏感業種やハイテク関連など幅広い業種が買われている。 TOPIXは前日比18.14ポイント(0.9%)高の2002.17-午前9時8分現在 日経平均株価は415円94銭(1.4%)高の3万0330円27銭 〈きょうのポイント〉 FOMC、ゼロ付近の金利維持を引き続き予想-物価急伸は短期間 米国株はS&P500とダウが最高値-ナスダック続伸 首都圏の緊急事態宣言、21日で解除の方針-菅首相 SCREENホールディングスやアドバンテスト、東京エレクトロンなどの半導体関連の上昇率が高く、日経平均株価は3万円台を回復している。野村証券の伊藤高志シニアストラテジストは、米FOMCは金融政策を明示的に変更することはなく、パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長は物価上昇は一時的と新たな見通しに整合性のある発言をしていることから「イベント通過の安心感が広がる」と話す。 緊急事態宣言の解除方針が決まったことに加えて、日銀金融政策決定会合もサプライズはないとの見方が強いことから、「日本株は全業種に幅広く買いが広がる」とみていた。 東証33業種では、海運、建設、鉄鋼、輸送用機器、電機、機械が上昇率上位 電気・ガスは下落FRB議長「米国債利回り上昇押し返す理由ない」-タイト化なら懸念 パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長は17日、現行の金融政策は適切であり、過去1カ月間の米国債利回り上昇を押し返す理由はないとの考えを示した。 連邦公開市場委員会(FOMC)会合終了後、バーチャル形式で記者会見したパウエル議長は、「現在の金融政策スタンスは適切であると考えられる」と述べ、月額で米国債800億ドル(約8兆7000億円)、住宅ローン担保証券(MBS)400億ドルという形での資産購入についても適切であるとの認識を示した。 新型コロナウイルスワクチン接種の進展や、1兆9000億ドル規模の追加経済対策の成立を受けた経済見通しの改善に伴い、米国債利回りはここ1カ月で急上昇しており、米金融当局による利上げ開始の時期が従来の示唆よりも早まるのではないかとの観測が、投資家の間で高まっている。 米10年債利回りは17日、新型コロナのパンデミック(世界的大流行)が1年余り前に本格化して以降で最も高い水準に達し、30年債利回りも2019年以来の高水準を付けた。 それでもパウエル議長は「金融環境を巡るさまざまな指標を見れば、金融情勢が全般に極めて緩和的である様子を示しているのが分かるだろう。そして、それは適切なことだ」と語った。 パウエル氏はその上で、「われわれの目標達成を脅かすような、市場の無秩序な状況や金融環境の持続的なタイト化が見られれば懸念するだろう」と今月に入り示した見解を繰り返した。FOMC、ゼロ付近の金利維持を引き続き予想-物価急伸は短期間 米連邦公開市場委員会(FOMC)は16、17両日に開催した定例会合で、フェデラルファンド(FF)金利の誘導目標レンジを0-0.25%で据え置くことを決定した。またFOMC参加者は、少なくとも2023年いっぱいは金利がゼロ付近で維持されると引き続き予想。一方で経済見通しは上方修正された。金融市場ではインフレに対する懸念が強まっている。 FOMC参加者の四半期経済予測では23年末までに利上げを見込む参加者が増えたものの、米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長は、なお少数意見だと強調した。 議長は声明発表後の記者会見で、「委員会の大半は、この予測期間中の利上げを見込んでいない」と指摘。資産購入の縮小について議論する時期は「まだ訪れていない」と加えた。 声明と同時に発表された経済予測では、FOMC参加者18人のうち7人が2023年末までに利上げが実施されると予想。昨年12月の会合ではそう予想したのは参加者17人のうち5人で、超金融緩和策の早めの巻き戻しを見込む参加者の割合が今回やや増えたことが示された。昨年12月下旬に就任したウォラー理事は、今回初めて予測に加わった。 声明では、「経済活動と雇用情勢を示す指標はここ最近に上向いたが、パンデミック(世界的大流行)による悪影響が最も深刻だったセクターはなお脆弱(ぜいじゃく)だ」と指摘。「インフレ率は引き続き2%を下回っている」と説明した。 FOMCは年内に見込まれる物価急伸について短期間にとどまると予想。経済予測によれば参加者らは、当局が重視するインフレ指標について21年は2.4%に急伸するが、来年は2%に鈍化すると見込んだ。食品とエネルギーを除いたベースでは、インフレ率は今年2.2%に達し、22年に2%に減速すると予想した。 米国債市場では、10年債利回りが声明発表後も1年ぶり高水準付近を維持。米株式市場ではS&P500種株価指数が上げに転じた。 このところの米国債利回りの動きについて、議長は「今後も緩和的な環境が維持されることが重要だ」とし、「市場が無秩序な状況になれば」懸念するだろうと説明。今月初めの発言を繰り返した。 資産購入については月額1200億ドル(約13兆円)を維持し、最大限の雇用と物価安定の達成に向けて「一段と顕著な進展」があるまでこのペースを継続すると再表明した。 ワクチン接種が拡大し、巨額の経済対策法が成立したものの、米経済はなお金融当局の目標から程遠い状態にある。パウエル議長は「今回の景気低迷では、多くのマイノリティーを雇用する分野が直接の打撃を受けた」と指摘した。 一方で、FOMCは経済成長と労働市場の予想を上方修正。参加者の中央値では失業率は21年末で4.5%、23年には3.5%にそれぞれ低下すると予想。国内総生産(GDP)は今年6.5%増と、前回予測での4.2%増から上向きに修正された。原油先物は続落、米在庫が増加[東京 18日 ロイター] - アジア時間の取引で原油先物価格は5日続落している。米在庫統計で、原油在庫が前週に続き増加し、ガソリン在庫も市場予想に反して増加したことが圧迫材料となっている。新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)により、今後の需要は不透明となっている。0119GMT(日本時間午前10時19分)時点で、ブレント先物は0.12ドル(0.2%)安の1バレル=67.88ドル。米WTI先物は0.12ドル(0.2%)安の64.48ドル。米エネルギー情報局(EIA)が17日発表した週間の石油在庫統計によると、原油在庫は240万バレル増加した。市場予想は300万バレル増だった。原油在庫は4週連続で増加している。ガソリンとディーゼルオイルの在庫は、アナリストの予想に反して増加した。キャピタル・エコノミクスは顧客向けリポートで、寒波の影響で閉鎖していた製油所は稼働を再開しているが、先週の米原油在庫は増加したとコメントした。米国はS&P・ダウ最高値、FRBが景気回復加速を予想[17日 ロイター] - 米国株式市場は上昇。S&P総合500種とダウ工業株30種が最高値を更新して引けた。米連邦準備理事会(FRB)は17日まで開いた連邦公開市場委員会(FOMC)で景気支援に向けあらゆる手段を行使する姿勢を改めて表明すると同時に、米景気が新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)から速いペースで回復するとの見通しを示した。FRBは最新の金利・経済見通しで、今年の経済成長率は6.5%に達すると予想した。FRBのパウエル議長はFOMC後の記者会見で、テーパリング(量的緩和の縮小)について協議を始める時期ではないとの認識を示した。これを受け、米株市場は上げ幅を拡大した。レノックス・ウェルス・アドバイザーズのデビッド・カーター最高投資責任者(CIO)は「今回のFOMC声明は、予想より楽観的だった。FRBは経済成長と労働市場の見通しをともに引き上げた。市場では声明はかなり楽観的だったと受け止められている」と述べた。1兆9000億ドル規模の新型コロナウイルス追加経済対策やワクチン接種を受け、経済再開による恩恵を受けるとみられるバリュー株に資金が流入している。一方、大規模な刺激策が景気過熱につながりインフレ上昇を招く可能性への懸念から米長期債利回りが上昇し、テクノロジーなどのグロース成長株の魅力は薄れている。テクノロジー株の比率が高いナスダック総合もこの日、上昇したが、2月12日に付けた終値での最高値は依然として約4%下回っている。S&Pの主要11セクターでは6セクターが上昇。工業と一般消費財がともに1%超高と上げを主導した。米FRB、景気見通し引き上げ ゼロ金利と量的緩和は維持[ワシントン 17日 ロイター] - 米連邦準備理事会(FRB)は16─17日に開いた連邦公開市場委員会(FOMC)で、政策金利の据え置きと国債などを買い入れる量的緩和の継続を全会一致で決定し、景気支援に向けあらゆる手段を行使する姿勢を改めて表明した。同時に、新型コロナウイルス感染拡大が収束に向かうに従い、今年の米経済成長率とインフレは大きく上昇するとの見方を示した。FRBは最新の金利・経済見通しで、今年の経済成長率は6.5%に達すると予想。失業率は年末までに4.5%に低下するとの見通しを示した。昨年12月公表の前回見通しでは成長率が4.2%、失業率は5%との見方が示されていた。上方修正後の成長率は1984年以来の大きさとなる。インフレ率は今年中に2.4%と、FRBが目標とする2%を上回ると予想。ただ、インフレ率の上昇は一時的で、政策金利の見通しに影響を与えないと強調し、22年には2%に戻るとの見方を示した。FRBは声明で、「この厳しい局面で米経済を支援するためにあらゆる手段を行使し、雇用最大化と物価安定という目標を促進することに全力で取り組む」と表明。「新型コロナウイルスのパンデミックは、米国および世界中で多大な人的および経済的苦難をもたらしている」とし、「回復ペースが鈍化した後、経済活動と雇用の指標は最近上向いた」との認識を示したものの、「このパンデミックによって最も悪影響を受けた業種は脆弱なままだ」とした。景気見通しの改善は政策担当者の金利見通しの変更には直接つながらなかったものの、見通しの重心は若干変化した。今回は当局者18人のうち7人が23年の利上げを予想。前回12月にこうした見方を示したのは5人だった。また、当局者4人が来年にも利上げが必要になるとの見方を示した。パウエルFRB議長はFOMC後の記者会見で、連邦政府とFRBの積極的な支援策により、パンデミックに起因する経済に対する最悪の影響は回避されたとの認識を示した。「今後力強い経済指標が発表される」と述べ、「(景気刺激策による)現金給付が行われ、新型コロナウイルスの感染者も減少している。ワクチン接種は順調に進んでいる」と説明した。ただ、米国ではパンデミックで950万人の雇用がなお失われたままになっているほか、インフレ率もFRBの目標を下回っているとし、見通しが明るくなったもののFRBは景気支援策を解消しないと強調。「FOMCメンバーの大半は見通しの期間内に利上げはないとの見方を示している」と述べた。見通しの期間内とは21─23年を示す。FRBは四半期ごとに金利・経済見通しを発表。今回のものは新型コロナウイルスワクチン接種開始と政府の大規模な景気対策の影響などが織り込まれている。JPモルガンのチーフ米国エコノミスト、マイケル・フェロリ氏は「政策金利が長期にわたり現行水準に維持される中、テーパリング(量的緩和縮小)が金融政策運営の次の重要な局面になる」と述べた。パウエル議長は記者会見で金融機関の自己資本規制の一つである補完的レバレッジ比率(SLR)の除外措置について、近く新たな情報を発表すると明らかにした。FRBは新型コロナ対策の一環としてSLR規制を一時的に緩和したが、同措置は今月31日に期限が切れる。<ハト派的な内容、市場は安堵>ハト派的な内容に市場は安堵し、米株価は上昇。S&P総合500種とダウ工業株30種は最高値を更新して引けた。米国債は、長期債利回りが上昇する一方、短期債利回りは低下した。ウィーブルの最高経営責任者(CEO)、アンソニー・デニール氏は、これまで強い不安感から債券利回りが上昇していたが、経済見通しがかなり強い中でFRBの反応が非常にハト派的だったのは大きな安心感となったと述べた。HSBCのプライベートバンキング・ウェルスマネジメント最高投資責任者、ウィレム・セルズ氏は、「FRBがきょう発したメッセージは、段階的なプロセスになるというわれわれの見方と合致する内容だった。テーパリングへの言及が市場を揺るがし、実質利回りが急激に著しく上昇するとともに株式や金、リスク資産が売り込まれた2013年とは状況が異なることを意味する」とコメントした。アメリカ金融市場の不安は本当に消えたのか「騒ぎ」は意外に早く収まる?ブルームバーグ パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長は17日、このところの米国債市場の変調について、懸念に当たらないとの認識をあらためて表明した。一方、2023年中の利上げを見込む米金融当局者の人数は昨年12月時点よりも2人増えた。 ほんの数週間前であれば、このどちらの出来事も市場の動揺を招くのに十分なインパクトがあったかもしれない。だが17日の米金融市場で株価は上昇し、国債利回りは上げ幅を縮小した。ハト派姿勢を維持するとの金融当局のメッセージの方が材料視された形だ。 同日の連邦公開市場委員会(FOMC)会合後に公表された最新の四半期経済予測によれば、23年中に少なくとも1回の利上げを予想する当局者は18人中7人と、昨年12月の前回予測の17人中5人から増加した。 しかし、こうした予想は依然少数意見であるとパウエル議長が指摘したのを受けて、ナスダック100指数は上昇に反転。債券購入プログラムの縮小は検討を開始する時期にもなっていないとの議長発言を好感し、1年強ぶりの高水準を付けていた10年債と30年債の利回りの伸びは縮小した。 FBBキャピタル・パートナーズの調査責任者、マイク・ベイリー氏は「23年いっぱいは低金利が続くとの予想が示され、投資家は株式市場について少なくともあと2年間は、混じりけのないカフェインのような興奮作用を強く期待している」と話した。 早ければ23年中の利上げを予想する当局者の増加幅は小さかったものの、少なくとも経済予測の内容が伝わった当初の段階では市場の関心を引き、米国債利回りが早い段階で一時上昇した一因とも理解される。 ただ、ワラックベス・キャピタルのシニアストラテジスト、イリヤ・フェイギン氏は「そうした推論は間違っていると考えられ、無視すべきではないか。いったん騒ぎが収まったら、10年債利回りは1.60%ないしそれを下回る水準が予想される」と話した。【市況】日経平均は大幅反発、FOMCで「資産インフレ」思惑続く?/ランチタイムコメント 日経平均は大幅反発。488.13円高の30402.46円(出来高概算7億2000万株)で前場の取引を終えている。 17日の米株式市場でNYダウは189ドル高と反発し、初の33000ドル台乗せとなった。注目された連邦公開市場委員会(FOMC)では、市場予想どおり政策金利の据え置きが決まった。また、2023年末までゼロ金利政策を続ける可能性が示唆されたため、早期の金融引き締めへの警戒感が後退。ハイテク株比率の高いナスダック総合指数も0.4%の上昇となった。本日の日経平均はこうした流れを好感し、節目の30000円を上回って234円高からスタート。朝方は上げ幅を広げる展開が続き、一時30485.00円(570.67円高)まで上昇した。 個別では、トヨタ自、ファーストリテ、東エレク、三菱UFJや三井住友といったメガバンク株が堅調。とりわけ東エレクなどの値がさグロース(成長)株は先行き懸念の後退で上げが目立つ。楽天が急反発しているほか、ビットコインを巡る一部報道を受けてマネックスGなどの関連銘柄が急伸。また、わかもとやセレスはストップ高水準で前場を折り返した。一方、売買代金上位ではソフトバンクGが逆行安。出資先の中国アリババ集団について、中国EC(電子商取引)利用者数で首位陥落したなどと伝わっている。また、丸運など従前まで賑わっていた中小型海運株は利益確定売りが広がり、東証1部下落率上位に顔を出している。 セクターでは、証券、サービス業、その他金融業などが上昇率上位で、その他も全般堅調。一方、陸運業、電気・ガス業、倉庫・運輸関連業の3業種が下落した。東証1部の値上がり銘柄は全体の54%、対して値下がり銘柄は41%となっている。 本日の日経平均はFOMCを無難に通過したことで大幅反発し、3万円台を回復してきた。主力株はバリュー(割安株)・グロース(成長株)を問わず軒並み堅調で、とりわけグロース株の先行き懸念が後退したことで新興株中心のマザーズ指数も戻り歩調を強めている。 従前に当欄で述べたことがあるが、米連邦準備理事会(FRB)は過度な資産高をけん制しつつも、積極的な財政支出を催促してきた経緯があるだけに、それが実現した局面で自ら金融引き締めに傾くことは政治的に難しいところだろう。ただ、注目点の1つだった米銀の資本規制である「補完的レバレッジ比率(SLR)」の特例延長については、「数日中に発表する」として今回判断は示さなかった。民主党政権に復帰し、潤沢なマネー供給を継続しつつも資本規制や取引規制を強化するシナリオは十分考えられる。今後も米金融政策を注視する必要はあるだろう。 また、FOMC通過後にいったん上げ幅を縮めた米長期金利だが、足元の時間外取引では再び強含んでいるもようで、上昇継続への懸念も依然くすぶるだろう。テーパリング(金融緩和縮小)のスケジュールを考慮すれば来年の利上げ開始は現実的でないとの見方がある一方、市場参加者の念頭にあるのは「景気過熱」による金融政策の急転換なのかもしれない。実際、米国のブレークイーブン・インフレ率(期待インフレ率の指標)は上昇が続き、2.3%台に乗せてきた。直近の消費者物価指数(CPI)を見ると日米とも生活物価の下押し圧力は強そうだが、潤沢なマネー供給のもと「資産インフレ」観測は根強い。 景気敏感株が軟調というわけでないが、値上がりが目立つのが株価指数の上昇に連動する主力株、それに業種別でも株高の恩恵を受ける証券セクターというのが、先行きに関する市場参加者の見方を映しているように思われる。(小林大純)《AK》 提供:フィスコドル円 一時108.70円割れ、日銀関連の報道を受けトレーダーズ・ウェブ ドル円は109円台から108.63円まで売り戻された。日経新聞による日銀金融政策に関する報道、長期金利変動を小幅拡大する方向や上場投資信託(ETF)買い入れは年6兆円とする目安をなくす見通しなどを受けた動き。12時11分時点では108.80円前後で推移している。午後からは、金融機関、同業者組合事務局、ゴルフショップ等を巡回…。本日の東京市場ではチェック中の日本株30銘柄中の27銘柄が値を上げて終了しましたね。重点3銘柄ではすべてが値を上げて終了しましたね。今までは重点6銘柄でしたが、本日このうちの3銘柄は売却処分されましたので…。〔東京外為〕ドル、108円台後半=日銀の金利変動幅拡大報道で(18日午後3時)時事通信 18日午後の東京外国為替市場のドルの対円相場(気配値)は、日銀が長期金利変動を小幅に拡大するとの報道を受け、1ドル=108円台後半に下落した。午後3時現在、108円86~90銭と前日(午後5時、109円15~16銭)比29銭のドル安・円高。 未明のFOMCの結果で早期利上げ観測が後退したことで下落したドルは、東京時間には108円90銭近辺まで値を戻した。午前9時以降、堅調な日経平均株価を受けたリスク選好の円売りで仲値過ぎに109円10銭台まで浮上したが、正午前後に「日銀が長期金利変動を小幅に拡大する」との報道を受けて108円60銭台に急落した。午後はやや値を戻して108円80~90銭台で推移している。 「FOMCがハト的な内容で終わったので日銀も金利変動幅を拡大しないだろう、というのが市場のコンセンサスになりつつあったので、報道がサプライズとなった」(国内銀行)もようだ。報道を受け、日経平均株価が上げ幅を縮小したため午後はリスクオンの円売りも弱まっている。 ユーロは正午と比べ、対円、対ドルで弱含み。午後3時現在、1ユーロ=130円25~26銭(前日午後5時、129円80~80銭)、対ドルでは1.1965~1965ドル(同1.1890~1891ドル)。(了)これで少しばかり損失が出ましたね…。〔東京株式〕反発=主力株に買い(18日)☆差替時事通信 【第1部】日経平均株価は前日比302円42銭高の3万0216円75銭と反発、東証株価指数(TOPIX)は24.48ポイント高の2008.51と続伸した。米連邦公開市場委員会(FOMC)が無難な結果に終わり、主力株が買われた。 銘柄の66%が値上がりし、値下がりは30%だった。出来高は15億9934万株、売買代金が3兆3544億円。 業種別株価指数(33業種)は銀行業、証券・商品先物取引業、ゴム製品の上昇が目立ち、下落は陸運業、不動産業、その他製品など。 個別銘柄ではトヨタが急伸。三菱UFJ、三井住友、みずほFGも買われ、マネックスGは急騰。ファーストリテが強含み、楽天は上伸した。ブリヂストンは大幅高。半面、ソフトバンクGが下押し、任天堂は小甘い。JR東日本、JR西日本が大幅安、JR東海は弱含み。三井不、菱地所、住友不も売られた。 【第2部】堅調。アトムが買いを集め、ユニバンスは急騰。半面、大運は大幅安。出来高1億6978万株。 ▽午後、上げ幅縮小 17日の米国市場での株高を好感し、朝方は買いが膨らんだ。米連邦公開市場委員会(FOMC)で大規模な金融緩和の維持が確認されたことを受け、投資家に安心感が広がった。日経平均株価は3万円の大台を回復した後も上昇し、一時は500円超高まで値上がりした。 ただその後、外国為替相場が円高傾向となり、日経平均も午後に入ると上げ幅を縮めた。株価指数への寄与度の高い銘柄を中心に買いが優勢だったものの、東証1部市場全体で見ると値上がり銘柄数は6割程度にとどまった。 市場では「最近の相場は、株価が上昇すると利益確定売りが出やすい傾向がある。2022年3月期の企業業績見通しが明らかになる5月ごろまでは、一段高とはなりづらい」(大手証券)との声が聞かれた。 225先物6月きりは上伸。株価指数オプション取引はプットは値下がり、コールは値上がり。(了)明日の戦略-FOMCを通過して3万円台を回復、日銀政策点検の織り込みも進むトレーダーズ・ウェブ 18日の日経平均は大幅反発。終値は302円高の30216円。FOMCの結果が米国株の買い材料となったことを好感して、寄り付きから200円を超える上昇。早い時間に上げ幅を500円超に広げて、30400円台まで水準を切り上げた。30500円を前にしては伸び悩んだものの、前場では高値圏を維持。しかし、昼休みに入って日経新聞から日銀会合の政策修正に関する観測報道が流れると、為替市場では鋭角的に円高が進行。これを警戒して後場は前引けから270円近く上げ幅を縮めて始まった。ただ、3万円に接近したところで持ち直すと、その後は改めて買いが入る展開。終値では300円を超える上昇となった。日経平均は3万円台を回復し、TOPIXは2000ポイント台に到達した。 東証1部の売買代金は概算で3兆3500億円。業種別では銀行、証券・商品先物、ゴム製品などが上昇した一方、陸運、不動産、その他製品などが下落した。日銀が容認する金利変動幅を拡大するとの観測が出てきたことから、三菱UFJや三井住友など金融株が後場に入って上げ幅を拡大。半面、任天堂が株高の流れに乗り切れず、後場に下げに転じた。 東証1部の騰落銘柄数は値上がり1444/値下がり654。レーザーテックやSCREENなど半導体関連が上昇を先導。トヨタが為替が不安定な動きを見せる中でも4%超の上昇と強さが目立った。ビットコインの上昇を手掛かりに暗号資産関連が賑わっており、マネックスGが急伸し、セレスはストップ高。決算が好感されたエニグモが商いを伴って急騰し、株主優待の導入を発表した大和重工がストップ高まで買い進まれた。 一方、ソフトバンクGが逆行安。日立や資生堂、アサヒGHDなどが軟調となった。西武HDやJR西日本など鉄道株は多くが下落。三井不動産や住友不動産など不動産株は、日銀の金利変動容認が借り入れ負担の増加につながるとの懸念から売りに押された。新株予約権を発行すると発表した識学が急落。直近で急伸した大運、丸運、玉井商船が一転値を崩した。 FOMCは株式市場の波乱を呼び起こす材料とはならず、日経平均は大幅高で3万円台を回復した。FRBが景気を著しく弱いとみているわけではなく、この先も米国の長期金利の上昇は続くかもしれないが、米国株がそれに対して神経質となる場面がこの先は減ってくるだろう。あすは日銀会合の結果を確認する日となるが、本日、日経新聞の観測報道も出てきたことから、ある程度の政策見直しに関しては、既に織り込みが進んでいると思われる。観測記事ではETFに関して、原則年間6兆円を削除するという内容も出ていた。ETFの買い入れに関しては議論も分かれるところだが、これが失望材料であるのなら、きょうはプラスでは終わっていない。今週ここまでが強い動きとなっている分、結果発表は利益確定売りの材料にされてしまうかもしれないが、足元の強い基調を揺るがすようなネガティブな反応が出てくる可能性は、かなり低下したと考える。明日の日本株の読み筋=堅調で3万円台固めの展開かモーニングスター 19日の東京株式市場は、日経平均株価が3万円台固めの展開となりそう。18日に3週間ぶりに終値ベースで3万円台を回復。一時上昇幅を縮小する場面もみられたが、上げ幅を取り戻して取引を終えており、投資家心理の好転が見込まれる。市場では、日銀の金融政策決定会合で、長期金利の誘導策は変動を認める幅を現状より若干広げ、プラスマイナス0.25%程度とすると報じたられたことで「同程度の変更であれば、織り込み済みとして無難に通過しそう」(中堅証券)との見方があった。ただ、決定会合後の黒田東彦総裁の記者会見は、取引終了後の午後3時すぎに予定されていることから「取引終了にかけて、リスク回避の売りで押される場面もありそう」(他の中堅証券)との声も聞かれた。 18日の日経平均株価は、前日比302円42銭高の3万216円75銭と大幅に反発。終値ベースでは2月25日(3万168円27銭)以来、3週間ぶりに3万円台を回復した。東京証券取引所が18日引け後に発表した、3月第2週(8-12日)の2市場1・2部等の投資部門別売買状況によると、海外投資家は3008億円買い越しで、2週連続で買い越しとなった。〔東京外為〕ドル、109円台前半=思惑交錯で乱高下(18日午後5時)時事通信 18日の東京外国為替市場のドルの対円相場(気配値)は、米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果を受けて米国の早期利上げ観測が後退する一方、日米の金融政策や金利をめぐる思惑を背景に乱高下、1ドル=108円台後半から109円台前半で推移した。終盤は米長期金利の一段の上昇を手掛かりにドルが買い戻され、午後5時現在は109円20~20銭と前日(午後5時、109円15~16銭)比05銭の小幅ドル高・円安。 前日の海外市場では、米連邦準備制度理事会(FRB)による事実上のゼロ金利政策が2023年末まで維持される可能性が高まったことを受け、109円30銭前後から108円80銭台に下落した。この日の東京時間は朝方、海外の流れを引き継いで小安く始まったものの、その後は押し目買いと日経平均株価の大幅高で109円10銭台まで値を戻した。 ただ、正午すぎに日銀が長期金利の変動容認の範囲を小幅拡大するとの一部報道が伝わると、「日米金利差が縮小するとの見方によるドル売り」(外為仲介業者)で短時間のうちに108円60銭台へ急落。その後は、時間外取引の米長期金利がじり高となり、米株先物の上昇も追い風となって底堅く推移し、終盤にかけては米10年債利回りが1.7%を付けるのを眺めて109円20銭台へ強含んだ。 米国が早い段階で現在の金融緩和策から転じるとの見方は下火になったとはいえ、市場では「米景気の回復期待は根強く、ドルの堅調が続く」(信託銀)とみる向きが大勢だ。一方、「日銀の姿勢を確認したい」(邦銀)とする意見も根強い。 ユーロは終盤、対円で上昇、対ドルでは軟調。午後5時現在は1ユーロ=130円47~48銭(前日午後5時、129円80~80銭)、対ドルでは1.1946~1950ドル(同、1.1890~1891ドル)。(了)TOPIX8日続伸、FOMC通過で安心感-日経平均も3万円台回復 18日の東京株式相場はTOPIXが8日続伸となり2000ポイントの節目を上回った。米連邦公開市場委員会(FOMC)が政策維持となった安心感が支えとなった。銀行や証券などの金融や自動車などが買われた。あすの金融決定会合で日銀がETF買い入れで年6兆円とする目安をなくす見通しと伝わり、一時上げ幅を縮小する局面もあった。 TOPIXの終値は前日比24.48ポイント(1.2%)高の2008.51 1991年4月18日以来の高値水準 日経平均株価は302円42銭(1%)高の3万0216円75銭 〈きょうのポイント〉 日銀が長期金利変動幅を拡大へ、上下0.25%程度とする方向-報道 ETF買い入れは年6兆円とする目安をなくす見通し FOMC、ゼロ付近の金利維持を引き続き予想-物価急伸は短期間 首都圏の緊急事態宣言、21日で解除の方針-菅首相 日銀が長期金利の変動幅を拡大するとの報道を受け、東証33業種では午後になって銀行や証券・商品先物取引、保険など金利上昇メリット業種への買いが膨らんで上昇率上位となった。 JPモルガン・アセット・マネジメントの前川将吾グローバル・マーケット・ストラテジストは報道後の伸び悩みについて、日銀によるETF買い入れペースが鈍化することによる需給面での懸念が高まったと話した。 一方でETF買い入れ政策の変更についてはある程度織り込まれてきていたので、サプライズではなく下げは限定的という印象としている。世界景気の回復や米金利上昇に伴って海外投資家の日本株買い入れ意欲が引き続き強いことも下げ幅が限定的であることの理由とみていた。 野村証券の伊藤高志シニアストラテジストは、米FOMCは金融政策を明示的に変更することはなく、パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長は物価上昇は一時的と新たな見通しに整合性のある発言をしていることから「イベント通過の安心感が広がる」と話していた。 東証33業種では銀行、証券・商品先物、保険、ゴム製品、輸送用機器が上昇率上位 陸運や不動産は下落【本日のNYダウ見通し】続伸の展開か【NYダウ予想レンジ:32,800~33,300ドル】17日のNYダウは反発。前日比189.42ドル高の33,015.37ドルで取引を終了し、過去最高値を更新しました。朝方はFOMCへの期待から米10年債利回りが上昇。一時1.67%まで上昇したことを嫌気し、IT・ハイテク株は売りが優勢になりました。しかし、米連邦公開市場委員会(FOMC)での金利・経済見通しで、2023年度末まで利上げはないとの見方が示されると、早期利上げ観測が後退し株式への買い安心感が広がりました。ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数も続伸し、前日比53.636ポイント高の13,525.203で取引を終了しています。FOMC 後の記者会見で、パウエルFRB議長が「一時的にインフレ率が2%を超えたとしても、売り上げの要件は満たしていない」「テーパリングの議論を始める時ではない」と述べたことも好感されました。12時40分時点の NYダウ先物は86ドル高なので、本日もしっかりの展開が予想されます。ただ、新規失業保険申請件数やフィラデルフィア連銀景況指数、景気先行指数などの重要指標が多く発表されるので、値動きが荒くなる可能性がある点に注意が必要です。18日の日経平均は大幅反発、3週ぶり3万円台で引け[東京 18日 ロイター] -東京株式市場で日経平均は大幅反発し、終値では3週間ぶりに3万円台を回復した。米国で金融緩和が継続されるとの安心感で朝方から買いが優勢で、一時は570円高まで上昇。その後、日銀が長期金利の変動許容幅を小幅に拡大させるとの報道を受け上げ幅を縮小したが、大台は維持した。TOPIXも堅調で、2000ポイントを回復し連日のバブル後高値更新となった。米連邦準備理事会(FRB)のパウエル議長が前日、テーパリング協議を始める時期ではないとの認識を示したことで、日経平均は寄り付き直後には3万円台を回復した。午後に入ると日本経済新聞が、日銀が今回の金融政策決定会合で長期金利の誘導策として変動を認める幅をプラスマイナス0.25%程度に若干拡大させる方向だと報道、株価は上げ幅を縮小した。黒田日銀総裁はこれまで繰り返し長期金利の変動幅を拡大する必要があるとは考えていないと発言しており、市場では「長期金利の上昇を抑制していくんだという安心感が少なからずあった。だが、小幅ではあるが、変動幅を拡大するとの観測報道を受けて、警戒感が広がったようだ」(ソニーフィナンシャルHD・金融市場調査部シニアエコノミスト、渡辺浩志氏)という。また、報じられたプラスマイナス0.25%程度の幅についても「今後その変動幅が拡大するのではないかという懸念もあり、市場の様子見姿勢が強まったのではないか」(渡辺氏)との指摘もあった。もっとも、売りが一巡すると日経平均は高値もみあいとなり、3万円を維持して大引けを迎えた。TOPIXは1.23%高で取引を終了。朝方に一時、取引時間中としては1991年4月以来の高水準となる2011.58ポイントの高値を付けた。東証1部の売買代金は3兆3544億円。東証33業種中、銀行業、証券業、ゴム製品など29業種は値上がり。一方、陸運業、不動産業、その他製品、情報・通信業の4業種は値下がり。個別では、トヨタ自動車が3%高となり、2月12日に付けた昨年来高値8497円を更新。市場からは「期末接近に伴う機関投資家の決算に絡んだ売りが前倒し的に出ていたが、それが一巡してきた様子がうかがえる。売りが尽きれば、決算内容の良い銘柄を中心に買われることになりそうだ」(国内証券)との声が聞かれた。その他、四国電力が後場急伸し7%高となった。愛媛県の伊方原発3号機の運転再開の見通しが強まったことで買いが先行した。東証1部の騰落数は、値上がり1444銘柄に対し、値下がりが654銘柄、変わらずが97銘柄だった。コラム:FEDウォッチャーが見逃さなかった米SLR、日本株上昇のカギに[東京 18日 ロイター] - 日本株の上昇幅を左右する要因として、米国で実施されている大手銀を対象にした補完的レバレッジ比率(SLR)の規制緩和が継続されるかどうかに大きな関心が集まっている。延長が決まれば日経平均が大幅に上昇するとの声が浮上しているが、実体経済とのギャップは一段と拡大しかねない。そこで、この先予想される日本の追加経済対策について、自動車の電気自動車(EV)化やデジタルトランスフォーメーション(DX)を進める設備投資に対して減税する方針を打ち出すべきだと提案したい。政府にはこの投資減税案を盛り込んでほしい。<SLRに言及したパウエル議長>18日の日経平均は一時前日比500円超上昇し、3万円台を回復した。連邦公開市場委員会(FOMC)を開いた米連邦準備理事会(FRB)のパウエル議長が、2023年までのゼロ金利維持を明確にし、国債などの購入額減額もしばらく行わないスタンスも提示。市場の安心感を誘った。ただ、市場の注目点はそこだけではなかった。今年3月末で有効期限が来るSLRの緩和措置について、近く新たな情報を発表するとパウエル議長が会見で述べたことを、FRBの動きをつぶさに観察するFEDウオッチャーは見逃さなかった。SLRは2008年のリーマ・ンショック後に導入された自己資本規制の1つ。分母は国債を含む有価証券保有額やデリバティブ取引などのエクスポージャー額などで算出。分子を中核的自己資本として算出する。新型コロナウイルスの感染拡大で経済が冷え込んだ対策の一環として、FRBは昨年4月、銀行が保有する米国債やFRBに預ける準備預金を分母の算定から外す緩和策を決定。今年3月末までの時限措置とした。この結果、米銀は米国債を購入しやすくなっていたが、3月末に有効期限が切れると米国債売却に米銀が走り、米長期金利が急上昇するのではないかとの懸念も広がっていた。もし、この緩和措置が延長されれば、米長期金利の上昇圧力が緩和され、米株上昇の勢いが増し、今回のパウエル議長の発言も相まって、米株上昇の幅と期間の両方とも拡張されるとの観測が台頭している。<日本株にも上昇加速期待>米株上昇の勢いが持続すれば、米系投資家のリスク許容量が増大し、日本株への投資も増えそうだとの観測が、東京市場でもジワジワと広がっている。海外勢の比重が大きい東京株式市場では、慎重な国内投資家を尻目に海外勢の買いで勢いが付き、国内勢が追随するパターンが何回も繰り返された。今回も、SLRという米国の規制が材料であることもあり、国内勢が米系投資家の動きをじっと見守っているとの声も聞かれる。SLR緩和措置の延長が決まれば、日経平均が3万3000円台に乗せるという予想が早くも一分でささやかれている。<EV・DX投資に減税必要>一方、実体経済はコロナ禍の影響を受け、サービス分野を中心に落ち込んでいる業種が目立ち、日本の今年1─3月期の国内総生産(GDP)は前期比マイナスの公算が大きい。株価とのギャップは開く一方だ。ギャップが拡大し続ければ、株価急落のトリガーを引きやすくなり、それが企業と個人の心理を冷やし、景気後退に陥る可能性を高める。また、日本では今年、どんなに遅くとも10月中には衆院選が行われる。景気の冷え込みは与党に不利となるため、2021年度予算案が3月末までに成立すれば、4月以降に追加の経済対策を求める声が与党から湧き起こり、政府が本格的に検討を始めるのもそう遠くないだろう。その際に、さまざまな景気対策の要望が出てくるだろうが、中長期的な視点に立てば、日本経済の潜在成長率を高める政策の優先順位を一段と高めるべきだ。筆者から見て最も政府が力点を置くべきところは、自動車のEV化に向けた積極投資だ。先行指標である機械受注の動向をみても、ガソリンエンジンの製造に関連した受注は減少しているが、EV化に不可欠な電池や半導体などへの投資は、まだ、大規模には展開されていない。企業の重い腰を持ち上げるためにも、EV関連に「投資減税」を行うことが急がれる。同様にリモートワークもままならない中小企業も含めたDX投資への思い切った減税も果敢に打ち出すべきだ。リモートワークの長期化に伴って、自宅を改装するサラリーマンや自営業の人々にも、改装を促す支援策を展開するべきではないか。一律の給付金に対する政府・与党内での批判があるなら、政策効果を勘案した「工夫」が、まさに今の段階で求められていると指摘したい。シンワワイズHDがストップ高気配、NFT生成・販売事業を開始美術品の公開オークションの企画・運営で最大手のShinwa Wise Holdings(2437)が3連騰した。朝方から値付かずの展開となる中、午後2時20分現在、制限値幅上限の前日比100円(19.9%)高の603円ストップ高買い気配で推移している。17日に当社が取り扱うアート作品を元にしたNFT(代替不可能なトークン)の生成・販売事業を開始すると発表し、買い材料視された。NFTはブロックチェーン上に生成され、実物資産にひも付けることで権利の所在を明確化することが可能になるとしている。生成したNFTとブロックチェーン上に記録されたアート作品をセットで販売していく。今後、デジタルアートやデジタルコンテンツをNFT化して流通させていき、同事業の領域をさらに広げていくとしている(取材協力:株式会社ストックボイス)【市況】明日の株式相場に向けて=仮想通貨関連に風雲急の気配 きょう(18日)の東京株式市場は、前日の米株高を受けリスクオンのスイッチが入り、日経平均株価が302円高の3万216円と反発。終値では2月25日以来の3万円大台回復となった。 世界の耳目を集めたFOMCの結果とパウエルFRB議長の記者会見は、株式市場にとっては最高のシナリオで、満額回答に想定外のボーナスまでついてきたようなフレンドリーな内容であった。FRBは少なくとも2023年末までゼロ金利政策を維持する方針を表明、一方で21年の米実質GDP成長率を4.2%から6.5%に大幅上方修正するなど景気先行きに対する強気な見方を示した。会合後の記者会見でもパウエルFRB議長は一時的な物価の上昇は利上げの根拠とはならないと改めて言及。つまり、「経済は思っていたより大分好調ですが、強力な金融緩和も続けます」と言っているのである。 いうなれば、いいとこ取りのゴルディロックス(適温)相場のデラックス版みたいな環境が続くということを担保したようなもの。これを受けてNYダウは上げ幅を広げ、初の3万3000ドル台乗せとなった。上げ幅があまり伸びず189ドル高で終わったのは、かなり早い時期から見切り発車的に上値を買い進んでいた反動といえるが、少なくとも出尽くし売りを浴びることはなかった。恐怖指数と呼ばれるVIX指数は19.23まで下落、通常20を下回ると波乱モードは完全解除という解釈だから、今の米国株市場は再び楽観が支配していることがうかがえる。 これを受けてきょうの東京市場もリスク選好ムード。日経平均は寄り付き230円あまりの上昇でスタートした後もグングンと水準を切り上げ、例によって先物へのアルゴ買いを絡め取引開始1時間後に571円高の3万485円の高値をつけた。この時点では2月16日につけた3万467円のバブル崩壊後高値を上回っていた。パウエル効果恐るべしというところであったが、後場寄りはいきなり上げ幅を縮小して始まる展開となった。 市場関係者によると「あすに控える日銀の金融政策決定会合の結果を前に、内容が小出しにリークされメディアを通じて投資家の顔色を窺っているフシがある」(ネット証券アナリスト)とし、その内容については「ETF買いの下限撤廃(これまでは6兆円が下限)と、長期金利の変動幅を従来の上下0.2%から0.25%に拡大するというもの」(同)であるという。つまり、ETF買いは最大で年間12兆円まで買う枠を維持するが、最低いくらまで買うというような義務はなく、極論すれば全く買わなくてもいいという解釈になる。また、長期金利の変動幅拡大は、上下どちらに対してもというのが前提だが、今は金利が上がることに神経質となっているわけで、事実上の長期金利上昇容認とも受けとめられる。 パウエルFRB議長は“筋金入りの鳩”だが、どうやら黒田日銀総裁はそうでもない。場合によっては爪を隠しているのではないか、というような疑心暗鬼がマーケットに巡ったことが後場の伸び悩みの真相のようだ。金利に対する意識はことのほか強い。後場に入るなり三菱UFJフィナンシャル・グループなどメガバンクや第一生命ホールディングスなど大手生保の株価が跳ね上がったのはその証左だ。一方で半導体関連などが、この金利上昇懸念をどこで吹っ切るかが今後の相場を見るうえでのポイントとなる。 個別ではビットコイン価格の上昇で仮想通貨関連株が一斉高に買われたが、どうもビットコイン価格と単純にリンクしている感じでもない。カギを握っているのはNFT、いわゆる非代替性トークンのようである。Shinwa Wise Holdingsが1本値でストップ高をつけ買い物を残したが、このインパクトは大きい。今後、第2、第3の急騰銘柄を生む可能性のあるテーマだ。直近、業績下方修正でマドを開けて売り込まれたLink-Uや、昨年12月から3ケタ台でのもみ合いを続け売り物をこなしていたフーバーブレイン、このほかgumiやGameWithなどのゲーム関連2社。更に、ここ上げ足を一気に強め、きょう値幅制限いっぱいに買われたセレスなど、NFT周辺銘柄が風雲急の気配を漂わせている。 あすのスケジュールでは、2月の全国消費者物価指数、日銀金融政策決定会合の結果と黒田日銀総裁の記者会見。また、東証マザーズ市場にココナラ、T.S.Iの2社が新規上場する。海外ではロシアの金融政策決定会合など。(銀)出所:MINKABU PRESS心房細動、エドキサバン半量が全量投与より転帰良好JACC2021年3月18日 (木)配信 ENGAGE AF-TIMI 48試験で、心房細動患者1万4014例を対象にエドキサバン低用量(LDER、30mg)と高用量(HDER、60mg)の臨床転帰(NCO)を無作為化二重盲検試験で比較した。 その結果、一次NCO[脳卒中/全身性塞栓症(SEE)、大出血、死亡]は、LDERがHDERより低頻度だった(7.26% vs. 8.01%、ハザード比0.90、95%CI 0.84-0.98、P=0.014)。二次NCO(障害をきたす脳卒中、生命を脅かす出血、全死因死亡)と三次NCO(脳卒中、SEE、生命を脅かす出血、全死因死亡)は2用量で同等だった。LDER群は、脳卒中/SEEリスクがHDER群より有意に高かった(2.04% vs. 1.56%、同1.31、1.12-1.52、P<0.001)が、大出血、頭蓋内出血、消化管大出血、生命を脅かす出血の発生頻度は、LDERが有意に低く、薬物動態データでも裏付けられた。今晩のNY株の読み筋=FOMC無難通過、買い戻し機運強まるかモーニングスター 18日の米国株式市場は、前日のFOMC(米連邦公開市場委員会)が無難に通過し、買い戻し機運が広がる可能性があるとみられる。 FOMCでは、21年の経済成長・物価見通しがいずれも上方修正されたほか、金利見通しも23年末までゼロ金利据え置きを示すものとなり、利上げ前倒し観測が後退。米長期金利の低下が買い安心感につながり、主要3指数はそろって上昇。NYダウとS&P500は史上最高値を更新した。 18日は3月フィラデルフィア連銀製造業景気指数、新規失業保険申請件数の発表がある。週初の3月NY連銀製造業景気指数は市場予想を上回ったものの、長期金利上昇への警戒感が意識され、一時マイナス圏に沈む場面があった。FOMC通過で利上げ前倒し観測が後退する中、3月フィラデルフィア連銀製造業景気指数が市場予想を上回るものとなれば、先行きへの期待感が膨らみ、グロース株などを中心に買い戻しが広がる可能性がありそうだ。<主な米経済指標・イベント>3月フィラデルフィア連銀製造業景気指数、新規失業保険申請件数ダラー・ゼネラル、ナイキ、フェデックスなどが決算発表予定(日付は現地時間)◎投資関連情報は投資の参考として情報提供のみを目的としたものであり、株式の売買は自己責任に基づき、ご自身で判断をお願いします。〔ロンドン外為〕円、109円台前半(18日午前9時)時事通信 【ロンドン時事】18日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果などを背景に、1ドル=109円台前半でもみ合いとなっている。午前9時現在は109円10~20銭と、前日午後4時(109円15~25銭)比05銭の円高・ドル安。 対ユーロは、1ユーロ=130円30~40銭(前日午後4時は129円95銭~130円05銭)で、35銭の円安・ユーロ高。ユーロの対ドル相場は1ユーロ=1.1940~1950ドル(1.1900~1910ドル)。 FOMCを受けて、一部で浮上していた米連邦準備制度理事会(FRB)による金融緩和の早期縮小観測が後退。一方、日銀の金融政策決定会合を前に日経新聞が「日銀が長期金利の変動容認幅を拡大する」と報じたことで、急激に円高・ドル安に振れる場面もあった。(了)NY株見通し-上値の重い展開か 経済指標は新規失業保険申請件数などトレーダーズ・ウェブ 今晩のNY市場は上値の重い展開か。昨日はFOMCで2023年末までのゼロ金利政策の継続が示されたことや、テーパリングへの警戒感が後退したことで主要3指数がそろって上昇し、ダウ平均とS&P500は史上最高値を更新した。一時、昨年1月以来となる1.689%まで上昇した米10年債利回りはFOMCの結果を受けて前日比2Bbp程度高い1.64%台で終了した。今晩はFOMCを無事に通過し、追加経済対策やワクチン普及加速による景気回復期待が引き続き支援となることが期待される一方、最高値更新による高値警戒感が上値圧迫要因か。長期金利の上昇トレンドも、将来の利益の現在価値を押し下げるため、グロース株には逆風が続きそうだ。 今晩の米経済指標・イベントは新規失業保険申請件数、3月フィラデルフィア連銀業況指数、2月景気先行指数など。企業決算は寄り前にダラー・ゼネラル、アクセンチュア、引け後にフェデックス、ナイキが発表予定。(執筆:3月18日、14:00)〔NY外為〕円、109円台前半(18日午前8時)時事通信 【ニューヨーク時事】18日のニューヨーク外国為替市場の円相場は、午前8時現在1ドル=109円03~13銭と前日午後5時(108円79~89銭)比24銭の円安・ドル高で推移している。 ユーロは同時刻現在、対ドルで1ユーロ=1.1936~1946ドル(前日午後5時は1.1975~1985ドル)、対円では同130円18~28銭(同130円36~46銭)。(了)〔NY外為〕円、109円台前半(18日朝)時事通信【ニューヨーク時事】18日午前のニューヨーク外国為替市場では、米長期金利の上昇を背景に円売り・ドル買いが先行した海外市場の流れを引き継ぎ、円相場は1ドル=109円台前半に下落している。午前9時現在は109円05~15銭と、前日午後5時(108円79~89銭)比26銭の円安・ドル高。 海外市場では、日銀が長期金利の変動容認幅を拡大するとの一部報道を受け、日米金利差が縮小するとの見方が広がり、円買い・ドル売りが一時進む場面があった。半面、米長期金利が1.7%台に大幅上昇する中で、ドルは買われやすく、ニューヨーク市場に入ってからもドル高の流れとなっている。 ただ、前日の米連邦公開市場委員会(FOMC)後に発表された経済見通しで、少なくとも2023年末まで事実上のゼロ金利が続くとの予想が維持され、早期の利上げ観測が後退したこともあり、円は109円台前半で下げ渋っている。 ユーロは同時刻現在、対ドルで1ユーロ=1.1920~1930ドル(前日午後5時は1.1975~1985ドル)、対円では同130円10~20銭(同130円36~46銭)と26銭の円高・ユーロ安。(了)〔米株式〕NYダウ続伸、一時最高値=ナスダックは反落(18日朝)時事通信 【ニューヨーク時事】18日のニューヨーク株式相場は、米経済の早期回復を期待した買いが継続し、続伸して始まった。優良株で構成するダウ工業株30種平均は寄り付き直後に一時取引時間中の史上最高値を更新。午前9時35分現在は前日終値比34.07ドル高の3万3049.44ドルとなった。ハイテク株中心のナスダック総合指数は174.10ポイント安の1万3351.10と反落。(了)今夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中の1銘柄が値を上げてスタートしましたね。ダウは上げていますから、僕が見ているのとは違う部分が上がっているのでしょうね。ナスダックは下げていますから、ハイテク・グロース株からは資金が逃げているのでしょうね。長期金利が1.7%台に乗ったことが大きいですかね…。日経平均先物も下げていますから明日の日本市場は…。いい時に利確できたのかな…。
2021.03.18
コメント(0)
-

3月17日(水)…2021ラウンド19…
3月17日(水)、晴れです。晴れていますが、風が強くて、体感温度は低めです…。そんな本日はホーム1:GSCCの西コースで開催のプロ・アマ研修会に参加させていただきました。10時44分スタートですから、7時30分頃に起床。新聞に目を通し、朝食を済ませ、ロマネちゃんと戯れる。身支度をして、9時頃には家を出る。9時30分頃にはコースに到着。フロントで記帳して、着替えて、練習場へ…。ショット…イマイチ…、パット…イマイチ…。今の体調でゴルフしてはだめですかね…。本日の競技は西コースのブルーティー:6613ヤードです。ご一緒するのはシニアグループのヤさん(12)、モさん(15)、キさん(15)です。本日の僕のハンディは(9)とのこと。OUT:2.0.2.0.1.0.1.2.2=46(17パット)1パット:2回、3パット:1回、パーオン:2回。1打目のミスが5回、2打目のミスが2回、3打目のミスが1回、アプローチのミスが2回、パットのミスが3回…。ひどいゴルフです…。10番のスタートハウスの前でドーピング休憩…。IN:1.2.1.1.1.1.2.0.1=(16パット)1パット:2回、3パット:0回、パーオン:0回。1打目のミスが6回、2打目のミスが1回、3打目のミスが1回、バンカーのミスが1回、アプローチのミスが1回、パットのミスが4回…。ひどいゴルフです…。46・46=92(9)=83の33パット…。本日もいいとこなしゴルフです…。ゴルフ…、やめようか…。カートからスコアの登録を済ませて、靴を磨いて、お風呂に入って、会計を済ませて、予約の確認を済ませて、早々に退散です。本日のフィジカルチェック…170.0cm,64.1kg,体脂肪率19.8%,BMI22.2,肥満度+0.8%…でした。帰宅すると16時30分頃。コーヒーブレイクしていると奥が名古屋からご帰還…。お土産は…M坂屋とTシマヤをはしごしてきたようですが、どこぞのケーキショップのケーキでした。本日のクラブ競技の成績速報が出ていますね。本日の競技には31人が参加して、トップは86(12)=74とのこと。僕は92(9)=83で20位…。お疲れ様でした。1USドル=109.12円。1AUドル=84.31円。昨夜のNYダウ終値=32825.95(-127.51)ドル。本日の日経平均終値=29914.33(-6.76)円。金相場:1g=6735(-3)円。プラチナ相場:1g=4741(-6)円。本日の東京市場ではチェック中の日本株30銘柄中の19銘柄が値を上げて終了しましたね。重点6銘柄では5銘柄が値を上げて終了しましたね。メディカルシステムが上げましたね。EU薬事当局「効果がリスクを上回る」 アストラゼネカ製ワクチン© FNNプライムオンライン使用中断の動きがさらに広がる一方で、あらためて「効果がリスクを上回る」と強調。アストラゼネカ製のワクチンの接種を受けた人に、血栓の症状が報告されていることを受け、ドイツ、フランス、イタリアなどで、使用を中断する動きが出ていて、新たにスウェーデンも使用を見合わせると発表した。こうした中、ヨーロッパ医薬品庁は、16日に会見を行い、引き続き、ワクチンと血栓の症状との関連を調査し、結論を18日に公表すると述べた。また、あらためて「接種で得られる効果は、副反応のリスクを上回る」との見解を示している。全高齢者分のワクチン確保も…予断許さぬ変異株リスク 感染者数はリバウンド傾向 尾身会長「カラオケに行ってるような高齢者も要因」 コロナ禍収束の切り札と期待される米ファイザー製ワクチンについて、河野太郎行政改革担当相は6月末までに約1億回分(約5000万人分)を調達できると表明。全高齢者約3600万人分の接種のめどが立った。一方で変異株の拡大と感染者数のリバウンドは予断を許さない。専門家は「高齢者のカラオケも一因」と警鐘を鳴らす。 ワクチンについて河野氏は、欧州連合(EU)の承認が得られれば、5月に毎週、最大約1000万回分が日本に到着、6月は「5月を上回る供給」を見込むと述べた。 全高齢者約3600万人分については6月末までに市区町村に届ける方針も重ねて示した。7月以降の一般向け接種へ向けて前進した格好だ。 不透明感のあったワクチン接種計画がようやくクリアになってきたが、21日が期限の首都圏の緊急事態宣言解除については微妙な情勢だ。 厚生労働省が公表した10日時点の病床使用率は、千葉県が44%、埼玉県が41%、東京都が27%、神奈川県が26%。いずれもステージ3(感染急増)の水準で、一定の成果は出ている。 ただ、東京の直近7日間で平均した1日当たりの人数は12日時点で273・6人となり、前週から横ばい。都のモニタリング会議では、「変異株などにより急激に再拡大が起こる可能性があり、対策を徹底する必要がある」と指摘された。 宣言を解除した大阪府でも12日、新たに11人の変異株の陽性が確認され、計103人になった。担当者は「直ちに市中感染と判断する状況ではない」と話す。 フィリピン由来の変異株も空港検疫で確認されるなど国内を急速に侵食している様子がうかがえる。 最近のリバウンド傾向をめぐり、政府の新型コロナ感染症対策分科会の尾身茂会長は、感染者の下げ止まりについて「アクティブなシニア」の行動を挙げる。「カラオケに行ってるような高齢者と同時に、若者も元の生活に戻っていることが1つの要因になっていることはたぶん間違いない」との見解を示した。 ワクチン接種と変異株感染抑制の二正面作戦はこれからが正念場だ。TOPIX小幅続伸、医薬品や銀行が高い-米FOMC控え様子見強い 17日の東京株式相場はTOPIXが小幅に上昇。医薬品株の上げがけん引して7日続伸となり、連日でバブル後の戻り高値を更新した。米連邦公開市場委員会(FOMC)会合後に政策当局者が発する市場へのメッセージへの注目が集まり投資家は動きづらく、日経平均株価は小幅下落した。 TOPIXの終値は前日比2.53ポイント(0.1%)高の1984.03 日経平均株価は6円76銭(0.02%)安の2万9914円33銭 〈きょうのポイント〉 米国株式市場ではS&P500種が6日ぶり反落-SOX指数は続伸 米国債は小動き、10年債利回り1.62% FOMCは行動迫られる、インフレで-ブリッジウォーター共同CIO SBI証券の鈴木英之投資調査部長は、「米FOMCのイベントリスクを警戒した売りと緊急事態宣言の解除の判断が近いことによる経済正常化への期待がせめぎあう相場だった」と話した。 りそなアセットマネジメントの下出衛チーフストラテジストは、日経平均株価が高値を取りに行くためには金利が急ピッチで上昇しないことが前提としながら「それが確認されるのは今晩であるため、投資家はリスクは取りにく」と話した。FOMCで少しタカ派なニュアンスなメッセージが出てきた場合は金利が跳ね上がり、グロース(成長)株が調整する可能性もあると述べた。 東証33業種では医薬品、不動産、陸運、化学、保険、銀行が上昇率上位 鉱業、鉄鋼、空運、精密機器は下落【本日のNYダウ見通し】パウエルFRB議長の発言に注目【NYダウ予想レンジ:32,600~33,100ドル】16日のNYダウは8営業日ぶりに下落。前日比127.51ドル安の32,825.95ドルで取引を終了しました。前日まで7営業日で2,000ドルあまり上昇していたので利益確定売りが優勢になったほか、米10年債利回りが1.6%台で推移したことにより上値の重い展開になりました。ただハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は、11.859ポイント高の13,471.567で取引を終了しています。アップルやマイクロソフトなど主力ハイテク株の一部がしっかりだったのに加え、半導体株も堅調に推移したからです。本日は住宅着工件数や建設許可件数などの重要指標もありますが、FOMCの金融政策およびパウエル FRB 議長の記者会見にマーケットの関心は向かうでしょう。とくに最近の長期金利上昇について、パウエル FRB 議長がどのような発言をするのかに注目です。17日の日経平均は7日ぶり反落、FOMC控え様子見[東京 17日 ロイター] -東京株式市場で日経平均は7日ぶりに小幅に反落した。米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果発表と米連邦準備理事会(FRB)のパウエル議長の会見を17日午後(日本時間18日未明)に控え、1日を通して様子見ムードに支配される展開となった。全体的に値動きに乏しく、日経平均は前日終値を挟んだ動きとなり、値幅は上下約159円にとどまった。TOPIXは7日続伸し0.13%高。連日のバブル崩壊後の高値更新となり、1984.03ポイントで高値引けとなった。東証1部の売買代金は2兆5794億2200万円。東証33業種中、医薬品、不動産業、陸運業、化学工業などの20業種は値上がり。半面、鉱業、鉄鋼、空運業などの13業種は値下がりとなった。市場の関心は、パウエル議長の発言を受けた後の米長期金利の動向だ。市場では「米長期金利の上昇が警戒される中で、パウエル議長がどのような発言をするか想像がつかないため、動きづらい。国債市場も含め、マーケットがどう反応するか見極めたい」(岡三アセットマネジメントのシニアストラテジスト、前野達志氏)との声が出ていた。個別では、ファーストリテイリング、アドバンテストが上昇。ソフトバンクグループ、テルモは下落した。東証1部の騰落数は、値上がり1409銘柄に対し、値下がりが682銘柄、変わらずが104銘柄だった。コラム:超V字回復の豪ドル円、米株が握る快進撃の行方=植野大作氏[東京 17日] - 早春の外為市場で豪ドル/円の快進撃が目立っている。昨年3月19日、新型コロナウイルスの感染拡大を不安視した市場パニックの荒波にのまれて一時59円90銭付近まで急落した豪ドル/円は、その後一気に切り返し、今年2月25日には一時84円95銭付近まで買い進まれた。約11カ月で25円以上、4割を超える値上がりだ。その後は日本の年度末接近を見据えた投資家の持ち高調整も意識され、上昇の勢いは鈍ったが、82円前後では底堅く推移、現在も84円台で取引されている。この間の豪ドル/円の動きを俯瞰(ふかん)すると、週足チャートの比較的細かい部分に至るまで、概ね円建て換算のMSCI世界総合株価指数と相関していたのが印象的だ。世界中の国々が、コロナとの戦いに明け暮れたこの約1年、グローバルな景況感の寒暖の差に敏感に反応して動く豪ドル/円の特徴が極めて鮮明に表れていた。市場心理が好転する時期に買われやすい豪ドルと、暗転する局面で買われがちな日本円の組み合わせである「豪ドル/円」という通貨ペアは、豪州国内から配信されるローカルなニュースより、地球的規模での景況感の伸縮に強く反応して激しく動く場面がしばしば観測される。戦後最悪のコロナ不況において豪ドル/円が示した超V字回復は、まさにその典型例だったと言えるだろう。<メインシナリオは高値安定か>円やその他の主要通貨に対する豪ドルの一方的な値上がりが目立っていた間、豪州準備銀行(RBA)は、翌日物政策金利と3年国債利回りの誘導目標を0.25%から0.1%に引き下げたほか、資産購入プログラムによる量的緩和を強化しながら豪ドル高をけん制する口先介入や公文書介入も連発したが、グローバルな株高の追い風を受けて勢いづく豪ドル高を止められなかった。そのような認識を踏まえた上で、来月から始まる新年度の豪ドル/円相場を展望すると、端的に言って「株価次第」という分かりやすい構図になる。コロナ不況下における豪ドル/円の先行指標の役割を務めてきた世界総合株価指数の中味をみると、約3分2近くの圧倒的シェアが米国株で占められている。新年度の豪ドル/円の売買戦略を練る上で、鍵を握るのはやはり米国株の動向だ。今後に予想される3つのシナリオを考えてみよう。まず米国株が今後も一段と上昇し続け、史上最高値圏にある今のレベルからさらに15%を超えて高値更新の旅を続ける場合、これまでの株価の動きと豪ドル/円の関係から類推すると、豪ドル/円の巡航高度も現在の80円台から90円台にアップしそうだ。ただ、近年の豪ドルは昔のように金利が主要7カ国(G7)通貨の金利水準を何倍も上回る「超」のつく高金利通貨ではなくなっている。かつての豪ドルは投資家の高値警戒感を麻痺(まひ)させるほど強烈な高金利の魅力を備えていたが、今はそこまでの高金利通貨ではなくなったので、高値を追いかけてまで買い続ける熱狂的な豪ドルファンはいなくなっている。よほど株価が上がらないと100円台は難しそうだ。ちなみに、筆者はこのシナリオの実現確率は25%程度だと思っている。次に米国株が現在の歴史的高値圏での安定飛行で落ち着く場合、豪ドル/円の巡航高度は、現在とあまり変わらぬ80円台での水平飛行になりそうだ。良くも悪くも前向きな参加者が多い株式市場では、将来のことを先読みして動く傾向が強いが、昨年3月にダウ平均株価が記録した安値1万8000ドル台から今月つけたこれまでの高値3万2000ドル台に至るまで、同株価は約1年間で既に8割以上も値上がりしている。これからも同じ勢いで上昇すると、来年の今頃には5万9000ドル台を試す計算になる。さすがにスピード違反の疑いが濃厚であり、そろそろブレーキがかかるとみるのが妥当なのではないか。今後、新型コロナワクチンの普及とバイデン政権の経済対策の追い風を受け、米国の国内総生産(GDP)や企業業績が順調に伸びてくれば、歴史的な高値圏で足踏みしながら待ってくれている株価に追い付き、株価にらみで値上がりしてきた豪ドル/円も高値で安定するだろう。筆者が想定しているメインシナリオはこのパターンであり、実現確率は65%くらいだと踏んでいる。最後に、あまり気乗りはしないが、株安加速のリスクシナリオについても触れておく。今後、米長期金利の上昇に歯止めが掛からなくなったり、せっかく開発したワクチンの効かない新々型コロナの変異株が猛威を振るったりして米国の株価が3割以上の深い調整を余儀なくされた場合、来年度の豪ドル/円は70円台でも下げ止まらず、60円台に逆戻りする可能性もある。ただ、その場合でも、米国経済の二番底が一番底より深くならなければ、さすがに50円台まで差し込む可能性は低そうだ。実際、昨年3月に起きたコロナパニックの最悪期でも豪ドル/円は59円台までしか下がらず、60円割れの滞空時間もわずか30秒しかなかった。<大幅な経常黒字が「縁の下の力持ち」に>過去、豪ドル/円は「ITバブル崩壊」、「対米同時多発テロ」、「リーマン危機」など世界中で株価が値崩れする事件が起きると、60円の節目もあっさり割り込んで55円台まで急落した。しかし、昨年は「戦後最悪」のコロナ不況に撃墜されても、昔ほど派手には下がらず切り返している。当時の豪ドル/円を59円台で踏み留まらせ、その後の超V字回復に誘った「縁の下の力持ち」がいたはずだ。そこでオーストラリアの国際収支をみると、近年の経常収支は対外利払いの縮小と貿易黒字の膨張で過去最高の黒字を計上している。巨額の対外利払いと鳴かず飛ばずの貿易収支の組み合わせで恒常的な経常収支赤字国の通貨だった豪ドルのイメージは、今や昔の物語になりつつある。そのような国際収支構造の変化を受け、近年の外国為替市場では経常収支黒字を背景に発生している豪ドル買い切りのフローが、株価の急落局面における豪ドル/円の下値を固めるバックストップの役割を果たすようになったと推測される。今後、米国株が多少調整しても、よほどひどく暴落しない限り、50円台まで差し込むリスクは小さいだろう。筆者はこのシナリオの確率は最も低いとみており、せいぜい10%程度だと考えている。以上が現時点で想定される来年度の豪ドル/円相場の「3択シナリオ」だ。「ウィズ・ワクチン」、「アフター・コロナ」の世界経済正常化を見越して歴史的な高値圏まで一気に駆け上がってきた米国株価の行方が、今後の豪ドル/円の命運を左右することになるだろう。もちろん、米国株の予想は簡単ではない。ただ、「株価続伸」なら「押し目買い」、「株価安定」なら「逆張り」、「株価反落」なら「戻り売り」と、シンプルに考えられるのが豪ドル/円の長所である。実際のトレードに臨む際のエントリー(買い)とエグジット(売り)の水準については、各種のテクニカル指標を参考にしつつ、趨勢(すうせい)判断の軸足は「株価の目利き」に据えて動かさない姿勢が大切になるだろう。午後3時のドル109円前半、FOMC控え膠着[東京 17日 ロイター] -午後3時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から小幅高の109円前半。米連邦公開市場委員会(FOMC)を前に、主要通貨は小動きが続いた。東京市場のドルは108.99─109.21円と狭いレンジ内で推移。「108円後半に買いが、109円前半には売りが控えており、身動きが取れない」(外銀)状況だったという。市場の関心は、FOMC後に公表されるメンバーの経済見通しサマリー(SEP)やパウエル議長の記者会見に注がれている。前回12月のSEPでは、17人中12人のメンバーが2023年末まで政策金利の誘導目標が据え置かれることを想定した。ただ、3人は1回の利上げ、2人はそれ以上の利上げを見込んだ。今回はメンバーが1人増えて18人となるが、市場では、失業率見通しの引き下げとインフレ率見通しの引き上げにより、追加的に4人以上が2023年中の利上げ(ゼロ金利解除)を想定する可能性があるとの予想も出ている。最近、日米金利差との相関を高めてきたドル/円は「FOMCの結果、米国金利がどう反応するかが焦点になる」(別の外銀)見通しだ。米国株式市場=S&Pとダウ反落、FOMCに注目[ニューヨーク 16日 ロイター] - 米国株式市場は、エネルギー・工業株主導でS&P総合500種が下落して終了した。ダウ工業株30種も下落した。市場ではこの日から2日間の日程で始まった米連邦公開市場委員会(FOMC)が注目されている。S&P総合500種とダウ工業株30種は前日に終値としての最高値を更新。これを受け、この日は終日、方向感に欠ける展開になった。ナスダック総合は上昇して引けた。投資調査会社エバーコアISIの目標株価引き上げを受け、アップルが1.3%値上がりした。リフィニティブのデータによると、エバーコアの目標株価は、アップルをカバーしているアナリストの間で最も高い水準となった。ナスダックは2月12日に付けた最高値を3月初めに11%下回っていたが、現在は約4%下回る水準に回復している。グローバルト・インベストメンツのシニアポートフォリオマネジャー、トム・マーティン氏は「FOMCは市場にとって、ここしばらくで最も重要なイベントの一つだ。最近インフレ率が上昇し、インフレ懸念が高まってから初めての会合となる」と語った。今回のFOMCは、経済見通しを引き上げた上で、予見可能な将来において緩和的なスタンスを維持する方針を改めて表明するとみられている。S&Pの主要セクターではエネルギーセクターが原油価格の下落を背景に約3%安となった。金融、工業セクターも1%超値下がりした。一方、通信サービスと情報技術は上昇した。ラッセルのグロース株指数は0.37%高、バリュー株指数は0.71%安となり、テクノロジー株など高成長株からシフトする最近の動きが後退した。20億ドルの転換社債発行計画を発表した自動車大手フォード・モーターは5.4%下落した。ニューヨーク証券取引所では値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を1.77対1の比率で上回った。ナスダックでは2.31対1で値下がり銘柄数が多かった。米取引所の合算出来高は122億株。直近20営業日の平均は144億株。「バリュー株」は「モメンタム株」に化けるのか上昇に一段の弾みもブルームバーグかつてモメンタム株に太刀打ちできなかったバリュー株は、今や自らがモメンタム株になりつつある。この傾向は今後の数週間にさらに強まり、バリュー株上昇にあらためて弾みを付けそうだ。3月23日は、MSCI・ACワールド・バリュー指数が8年ぶり安値を付けてから1年。多くのクオンツモデルは買い対象のモメンタム株を選ぶのにこの期間を基準にする。また、5月6日はバリュー株が成長株・モメンタム株に対する比較で底を付けてから6カ月。ジョー・バイデン氏の大統領選挙勝利後にバリュー株のアウトパフォーマンスが始まった。モメンタム株で構成するMSCI・ACワールド・モメンタム指数の資料によれば、同指数は過去12カ月と6カ月のパフォーマンスに基づいて銘柄を選ぶ。バーンスタインのストラテジスト、サラ・マッカーシー氏は17日のリポートで、「バリュー株とモメンタム株の間に大きな重なりができ始めている。自動車、銀行、素材、エネルギー株の中にバリュー株とモメンタム株の両方に該当する銘柄が多数ある。これはクオンツとバリュー投資にとって渇望の的だ」と指摘した。ソフバンクグループから外国人幹部の離職が止まらない広報グローバル責任者ギンズバーグ氏退社ブルームバーグソフトバンクグループで広報担当のグローバル責任者を約2年にわたり務めていたゲーリー・ギンズバーグ氏が退社した。同社では幹部の離職が相次いでいる。ソフトバンクGの広報担当者は、ギンズバーグ氏が昨年12月に辞任したことを確認した。その後は同氏が2019年に採用したサラ・ラブマン氏が代行を務めているという。同社では、ロブ・タウンゼンド最高法務責任者(CLO)とチャド・フェントレス最高コンプライアンス責任者が昨年いずれも辞任。佐護勝紀副社長も今月末で退社する見通しだ。ソフトバンク・ビジョン・ファンドでも、マネジングパートナーのコリン・ファン、ジェフ・ハウゼンボールド両氏らが退社している。ギンズバーグ氏はルパート・マードック氏の元アドバイザーで、18年11月にソフトバンクGに加わり、社内外のグローバルコミュニケーションの全てを統括。孫正義社長およびマルセロ・クラウレ最高執行責任者(COO)の直属だった。ソフトバンクGによると、ギンズバーグ氏は19年に2カ月休職。米大統領選の民主党候補指名を争っていたマイケル・ブルームバーグ氏を支援するためだった。ブルームバーグ氏はブルームバーグ・ニュースの親会社ブルームバーグ・エル・ピーの創業者で、過半数株式を保有している。【市況】明日の株式相場に向けて=舞い踊る中小型材料株 きょう(17日)の東京株式市場は、日経平均株価が6円安の2万9914円と7日ぶりに小反落。FOMCと日銀の金融政策決定会合を目前にして、狭いゾーンでの往来を繰り返し、結局ほぼ前日比横ばい圏で着地した。売買代金も2兆5000億円台と最近にしては少な目で、この日米のビッグイベントに敬意を表するがごとく様子見ムードの地合いであったかに見える。しかし、それは指数連動型の大型株に限っての解釈であり、中小型株の物色意欲は以前にも増して旺盛であった。値上がり銘柄数は1400を超え、値下がり銘柄数の2倍以上となった。また、マザーズ指数などをみても、ひと頃の崩れ足から完全に立ち直り25日移動平均線とのマイナスカイ離を綺麗に埋めている。 日米の中銀会合に波乱要素なしという見方が強い。実際は蓋を開けてみなければ分からないが、箱の中から出てくるのは日米合わせて2羽の白いハトであることをマーケットは見切っている。そして、仮に予想が外れて、株価が波乱展開となったとしてもそこを拾いたいと考えている投資家が多い。「むしろ、新年度入りを前に最後の買い場とばかり、プチ波乱を望んでいる買い方は多い」(ネット証券ストラテジスト)という。まさに、メディアを交えて狐とタヌキの化かし合いというところか。 前週後半から始まった海運ビッグウェーブ相場も大手海運から2番手、3番手のポジションに位置する銘柄に資金が下りてきている感触。タンカーやばら積み船の明治海運や港湾運送の大運などが雄叫びを上げる相場となったが、これが倉庫株にも波及し、きょうは杉村倉庫がストップ高に買われた。ホットマネーが海から陸へと上がってきた趣きだが、更に走り出すとすれば陸運株周辺にも及ぶ可能性がある。 今は、海運株の延長線上にある倉庫株が動意含みだ。何といっても純資産からみた株価は超割安圏に放置されている。1倍を大きく下回る低PBR銘柄の宝庫である。見方によっては企業として“代謝が機能していない”という厳しい評価も下されるところだが、ある意味過熱気味に買われたグロース株のクールダウン現象が起きている今の地合いでは、買いやすさがあるのも事実だ。例えばPBR0.5倍ということであれば、株価は2倍に買われてやっと会社の解散価値と同等ということになる。安田倉庫はPBR0.4倍、株式需給面も買い残が枯れ切った状態で良好、直近信用倍率は0.25倍だ。このほか、トランスシティ、東陽倉庫もPBRは0.6倍台で、黒字の有配企業である以上、株価が見直される“資格”を十分に持ち合わせている。 このほか、直近紹介した銘柄ではインプレスが強い動き。株価は依然として200円台で、電子コミック人気はスマホ全盛時代が続くなか新型コロナへの恐怖が取り除かれても廃れることはない。また、同じ低位株の範疇では非全農系の飼料会社日和産業は目立たないが、着実な歩みで新値街道を進んでおり引き続き注目しておきたい。同社株も有配企業にしてPBRは0.3倍台で水準訂正途上であることをうかがわせる。 これ以外では関通が2500円ラインを軸としたもみ合いが煮詰まっておりマークしておきたい。在宅で物品を購入する巣ごもり消費需要は、コスト面や手軽さを考慮すればアフターコロナでも消滅することはない。同社はeコマース中心に物流作業の代行・支援ビジネスを展開しており、伸び率は鈍化しても成長トレンドが続くとみられる。楽天が日本郵政との資本・業務提携でサプライズを与えたが、関通は既にこの楽天と資本・業務提携している。 少々気が早いがアフターコロナで活気づくスポットはどこかと考えた場合、それは3密回避の鉄則に反する場所。真っ先に浮かぶのは映画館だ。それを踏まえたうえで映像制作大手のIMAGICA GROUPのチャートを見ると、コロナ収束後のバラ色の景色を先取りするかのような値運びをみせており、ここからどういうトレンドを描くのか興味がそそられる。 あすのスケジュールでは、日銀の金融政策決定会合が19日までの日程で開催されるほか、2月の首都圏・近畿圏のマンション販売が発表される。また、東証マザーズ市場にi‐plugが新規上場する。海外では1月のユーロ圏貿易収支、3月の米フィラデルフィア連銀製造業景況指数、2月の米景気先行指数などが発表される。(銀)出所:MINKABU PRESS明日の戦略-7日ぶり反落も好地合いは継続、FOMCを波乱なく通過できるかトレーダーズ・ウェブ 17日の日経平均は7日ぶり小幅反落。終値は6円安の29914円。FOMCの結果発表をあすに控え、方向感に乏しい展開となった。ダウ平均の下落を受けて下げて始まったものの、寄り付き直後を安値に切り返してプラス転換。ただ、上げ幅を広げたところでは節目の3万円が壁となった。前場は小幅高で終えたが、後場は下落からのスタートとなり、マイナス圏でのもみ合いが長く続いた。前場の安値は下回ることなく、終盤には盛り返したものの、小幅な下落で取引を終えた。TOPIXもプラス圏とマイナス圏を行き来したが、こちらは終盤の買いでプラスを確保。4日連続で高値引けとなった。 東証1部の売買代金は概算で2兆5700億円。業種別では医薬品、不動産、陸運などが上昇した一方、鉱業、鉄鋼、空運などが下落した。期末配当見通しを引き上げたヤマックスが後場急騰。半面、今22.1期の見通しが失望を誘ったcolyが大幅安となった。 東証1部の騰落銘柄数は値上がり1409/値下がり682。ナスダック高を受けてアドバンテストや日本電産などハイテク株が上昇。分割や情報修正など好材料の多かったアスクルや、ホテルの建て替え観測が報じられた帝国ホテルが大幅高となった。わかもと製薬が連日でストップ高、業績下振れ観測が伝わった久光製薬が売り先行から切り返して3%近い上昇と、薬品株の動きの良さが目立った。トレイダーズHDは通期見通しを引き下げたものの、復配実施見込みが好感されて5%超上昇した。 一方、ソフトバンクGが2%を超える下落。柏崎刈羽原発に関する懸念材料が出てきた東京電力が10%を超える下落となった。直近で跳ねたユーグレナや楽天が手仕舞い売りに押されて大幅安。米国で景気敏感株が弱かったことから、日本製鉄や神戸鋼など鉄鋼株が軟調となった。ツルハは決算が嫌気されて大きく値を崩した。 日経平均は続伸記録は6で途切れたものの、ほぼ横ばい。TOPIXに至っては4日連続の高値引けとなっており、足元の強い基調は崩れなかった。あすはFOMCの結果を受けた米国株の反応に振らされることになるだろう。ただ、ここからマーケットが再び不安定になるのではなく、直前に荒れた分の最後のひと波乱があるかどうかというくらいで構えておいた方が良い。FRBが急に早期の利上げを示唆する可能性は低く、足元では米国株も落ち着きを取り戻しつつある。米国株がFOMC結果やパウエル議長の発言に神経質となって下に振れ、日本株もこれに連動するような場合には、慌てることなく押し目を拾っておきたい局面だ。明日の日本株の読み筋=FOMC、パウエル会見が無事通過なら投資家心理改善もモーニングスター あす18日の東京株式市場は、現地の17日のFOMC(米連邦公開市場委員会)結果や、その後のパウエルFRB(米連邦準備制度理事会)議長の記者会見を受け、米長期金利および米国株式がどう反応するかがポイントになる。政策金利見通しでは23年末までゼロ金利政策が続くとみられ、パウエル氏の会見で金利上昇容認と受け止められるような発言がなく、無事通過となれば、投資家心理の改善につながろう。一方、18-19日開催の日銀金融政策決定会合を控え、見極めたいとの空気を引きずる可能性はあるが、これまでの緩和策の「点検」では、ETF(上場投資信託)買い入れを市場の状況に合わせて調節する方法に変更されるとの見方が浸透しており、「大きな影響はない」(準大手証券)との指摘があった。 17日の日経平均株価は7営業日ぶりに小反落し、2万9914円(前日比6円安)引け。朝方は、直近6連騰で利益確定売りが出やすく、下げ幅は一時90円を超えた。一巡後は上げに転じる場面もあったが、買いは続かず、再度マイナス圏入りした。17日のFOMCを前に手控え気分が強いなか、持ち高調整売りに押された。その後は持ち直したが、戻りは限定された。〔ロンドン外為〕円、109円台前半(17日午前9時)時事通信 【ロンドン時事】17日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果発表を控えて様子見気分が広がる中、1ドル=109円台前半の小動きとなった。午前9時現在は109円10~20銭と、前日午後4時(108円95銭~109円05銭)比15銭の円安・ドル高。 対ユーロは、1ユーロ=129円80~90銭(前日午後4時は129円60~70銭)で、20銭の円安・ユーロ高。ユーロの対ドル相場は1ユーロ=1.1895~1905ドル(1.1890~1900ドル)。(了)「タンス預金」増え、個人保有の現金初の100兆円突破…前年比5・2%増読売新聞オンライン 日本銀行が17日発表した2020年10~12月の資金循環統計(速報)によると、昨年12月末時点で個人(家計部門)が保有する現金が、初めて100兆円を突破した。前年同期と比べ、5・2%増の101兆円と過去最高となった。高齢者を中心に、自宅で現金を保管する「タンス預金」を増やす傾向が強まっている。 家計部門の「現金・預金」は4・8%増の1056兆円となった。預金は4・8%増の955兆円だった。 日本銀行の大規模な金融緩和政策で、ほぼ金利が付かない状況が続いているが、預金残高も増えている。政府は昨年、1人あたり一律10万円の定額給付金を支給したが、その一部が貯蓄に回った可能性がある。 株式なども含めた家計部門の金融資産残高は、2・9%増の1948兆円と、過去最高を更新した。 金融資産のうち、「現金・預金」が54・2%と半分以上を占めた。株価の上昇を背景に、「株式等」は0・7%増の198兆円、「投資信託」は5・1%増の78兆円となった。 金融機関を除く民間企業の現金・預金は、16・6%増の311兆円と大幅に伸びた。新型コロナウイルスの感染拡大で景気の先行きが読みにくくなっていることから、企業が手元資金を厚くしているとみられる。 一方、国債保有者の内訳では、日本銀行がトップで、全体の44・7%(545兆円)を保有している。「保険・年金基金」は20・7%(252兆円)、民間銀行などの「預金取扱機関」は14・3%(175兆円)だった。「ワクチンは殺人兵器」稲田朋美議員のお膝元で自民党重鎮県議が文書配布文春オンライン 福井県の自民党重鎮県議が、「ワクチンは殺人兵器」などとする、新型コロナウイルスに関する独自の見解をまとめた文書を配布していたことが「週刊文春」の取材で分かった。 文書を配布したのは坂井市選出の斉藤新緑県議(64)。坂井市は、防衛相や政調会長などを歴任した稲田朋美衆院議員の選挙区(福井1区)だ。 斉藤県議は、2月下旬から1万6500部を配布した活動報告「ほっとらいん」102号で、次のように記していた。〈ワクチンなど必要ありません。今回のワクチンは人類初の遺伝子組み換えワクチンで、「殺人兵器」ともいわれています〉 さらに、斉藤氏はこの文書で、コロナ騒動は「ディープ・ステート」という「闇の勢力」が計画したものであり、マスコミが恐怖心を煽り、世界中の人々にワクチンを強制接種させて人口削減を進めるつもりだなどと主張している。 斉藤県議は県立高校を卒業後、34歳で三国町(現・坂井市)議員に。1999年の県議選で初当選して以来、連続当選して現在は県議6期目。県会議長や党県連幹事長などを歴任した。 「一昨年の県知事選では元総務官僚の杉本達治氏の選対本部長を務め、初当選に導いた立役者です。福井自民党のナンバー2で、“若頭”と評される。国会議員も彼に一目置いています」(地元記者) 斉藤氏に聞いた。 「全部、人類初の遺伝子組み換えワクチン。中身は何なのかを誰も吟味していない。看護師に打つというから、これは早く書かなあかんと。政治家の信念として見過ごせなかった。『その毒饅頭を食べたら死ぬ』とわかっていて、黙っていたら、俺、殺人者やん?」 稲田氏と会ったとき、ワクチンの話題も出たという。 「稲田さんはたまたま正月に挨拶に来たで。『私は打ちませんよ』って」 また、斉藤氏は河野太郎ワクチン担当相に「ワクチンを遅らして」とメールしたが、返事は来ていないという。 稲田氏に事実確認を求めると、書面でこう回答した。 「防衛大臣時代、マラリアの予防薬により重度のアレルギー反応に見舞われ、数日間入院した経緯があるため、ワクチン接種を慎重に考えたいというお話はしたと思います」 政府はワクチン接種を「感染拡大防止の決め手」と位置づけ、推進している。3月16日、菅義偉首相も「ワクチンは発症や重症化予防に効果が期待され、感染症対策で極めて重要。国民の皆さんにも接種していただける環境もしっかり作っていきたい」と語っている。 与党自民党に所属する重鎮県議が、ワクチン接種に異論を唱える文書を配布したことは、混乱を招きそうだ。 3月17日(水)16時配信の「週刊文春 電子版」及び18日(木)発売の「週刊文春」では、斉藤氏が文書を書いたきっかけや、斉藤氏の危惧する“シナリオ”などを詳報する。今晩のNY株の読み筋=FOMCおよびパウエルFRB議長の発言に注目モーニングスター 17日の米国株式市場は、午後に行われるFOMC(米連邦公開市場委員会)およびパウエルFRB(米連邦準備制度理事会)議長の会見に注目が集まる。 今回のFOMCでは3カ月ぶりに最新の経済・金融政策見通しが発表される。市場では足元の景気回復基調を受け23年の利上げを織り込んでいるが、FOMCメンバーによる経済見通しが前回から上方修正されれば、利上げ前倒し観測が強まり、株式相場の重しとなるとみられる。 また、足元の米長期金利上昇に対し、パウエル議長がどのような見解を明らかにするかも注目点だ。金利上昇を容認するようなら、利上げ前倒しが一段と意識されそうだが、けん制姿勢やハト派スタンスが示されれば、相場に買い安心感が広がる可能性がある。<主な米経済指標・イベント>2月住宅着工件数、米2月建設許可件数、FOMC(米連邦公開市場委員会)およびパウエルFRB(米連邦準備制度理事会)議長の会見(日付は現地時間)◎投資関連情報は投資の参考として情報提供のみを目的としたものであり、株式の売買は自己責任に基づき、ご自身で判断をお願いします。各務原市消防本部でクラスター 岐阜県、変異株感染者は4人増の14人に 岐阜県は17日、これまでに新型コロナウイルスの感染が判明している県内在住の4人について、変異株陽性を確認したと発表した。県内の変異株陽性者は累計14人となった。 県によると、変異株の陽性が確認された4人のうち50代の男性と女性の2人は、フィリピンに滞在し2月末から3月上旬までに帰国した。空港での検査では感染の陽性が判明しなかったが、その後、県内で確認された。 50代男性の関係者で、20代と30代の男性2人も変異株の陽性が確認された。4人はいずれも、県の追加検査で分かった。今後、国立感染症研究所で遺伝子解析を行い、型を特定する。県による変異株の検査は152人となった。 また、県と岐阜市は17日、3市町などで計8人の新型コロナウイルス感染と、入院していた揖斐郡揖斐川町の70代女性の死亡を発表した。県内の感染者数は累計4698人、死者は119人となった。 クラスター(感染者集団)は、各務原市消防本部の消防隊員5人と隊員の家族2人の計7人で新たに確認された。規模の拡大はなかった。 16日時点の入院患者は57人で、病床使用率は8・2%。前日より0・3ポイント減。宿泊療養施設の入所者はゼロとなった。 新規感染者の居住地別は岐阜市5人、各務原市1人、羽島郡笠松町1人、愛知県1人。年代別は20代6人、30代1人、50代1人。NY株見通し-FOMC結果公表やパウエルFRB議長会見に注目トレーダーズ・ウェブ 今晩のNY市場はFOMCの結果とパウエルFRB議長会見に注目が集まる。昨日はFOMCの結果公表を翌日に控え、持ち高整理中心の動きとなり、ダウ平均とS&P500が反落し、ナスダック総合が小幅続伸と高安まちまちとなった。今晩は、取引時間午後にFOMCの結果公表とパウエルFRB議長の会見が予定され、結果を受けた長期金利の動向が焦点となりそうだ。FOMCでは経済見通しやメンバーの金利見通し(ドットチャート)などが注目されるほか、パウエルFRB議長の会見では足もとの長期金利上昇をけん制する発言の有無に注目が集まる。 今晩の米経済指標・イベントはFOMC結果公表のほか、2月住宅着工件数、EIA週間原油在庫など。企業決算は寄り前にシンタス が発表予定。(執筆:3月17日、14:00)行政デジタル革命、覚醒する「DX関連」"現実買い"の舞台へ <株探トップ特集>株探ニュース●売られる展開続くも割高な株価の是正進む 昨年、新型コロナウイルスが感染拡大して以降、まずはテレワークやオンライン関連などに注目が集まったが、次第にこうしたものも含め、あらゆる場面でデジタル化を加速させていくDXの重要性が広く認識されるようになった。民間の取り組みが進むなか、特別定額給付金の支給を巡って行政におけるデジタル化の遅れも浮き彫りとなり、「デジタル庁」創設などを掲げた菅政権の発足によって関連銘柄の物色人気は一段と高まっていった。一方、11月に入ると米バイデン政権誕生を見据えて再生可能エネルギーや電気自動車(EV)関連に、また新型コロナワクチンの普及期待から景気敏感株に物色の流れが移り、DXへの注目度は相対的に低下していった。 直近の決算発表では、DX関連銘柄の業績は比較的好調だったものの、株価への反応は限られ、逆に売られてしまうものもあった。昨年に期待先行で大きく買われたことから、好業績であっても株価にはすでに織り込まれているとの見方が強いようだ。また、3月初旬にかけての米金利上昇を背景とする全体相場波乱にツレ安する格好で、関連銘柄も下押しする場面があった。ただ、売りに押される展開がここまで続いてきたことから、割高だった株価水準の是正は概ね進んだとみられる。今後、9月のデジタル庁発足に向けて再びDXへの関心が強まってくるとみられ、関連銘柄の見直し機運も高まることになりそうだ。●幅広い顧客基盤に強み、傘下で多様なビジネス展開 フューチャー は、情報システムの設計・構築に定評があるITコンサル会社。製造や物流、アパレル、金融など幅広い顧客基盤を持っており、業務改革を進める企業のIT投資ニーズを捉えている。同社は、グルメ関連メディア「東京カレンダー」の運営のほか、プログラミングのオンライン学習サービス、スポーツ関連システムの開発など、傘下の企業がさまざまな事業を手掛けている。また、通販向け在庫管理システムを提供するロジザード [東証M]を関連会社に持つ。21年12月期の連結営業利益は、前期比36.6%増の71億5000万円と過去最高益を更新する見通し。株価は昨年10月の急落後、1800円前後の狭いレンジで3ヵ月近く横ばいの動きが続いていたが、今12月期見通し発表前後の2月上旬に急動意。その後、再度1800円割れまで押し戻されたものの、そこを起点に切り返す動きをみせている。●官公庁向け主力、医療分野でAI用いたシステム開発も フォーカスシステムズ は独立系のソフト開発会社で、官公庁などからの受託開発を主力とする。21年3月期第3四半期累計(20年4-12月)決算では、営業利益が11億2600万円(前年同期比5.9%増)で着地し、通期の営業利益見通しに対する進捗率は8割近くに達した。同社では、人工知能(AI)やRPA、 IoTといった先端技術への取り組みを積極化させており、昨年11月には医療分野でのAI活用に向けてFRONTEO [東証M]と資本業務提携を行っている。フォーカスが持つ画像系AIとフロンテオのAI技術を組み合わせ、心血管疾患に関する発症予測や治療法の革新、発症後の患者動向の予測に関するシステム開発などを目指す。株価は、昨年9月の高値1090円から11月初旬には871円まで売られたが、その後はもみ合いながらも200日移動平均線を足場に下値を切り上げる展開。直近の信用倍率が0.5倍台と売り長である点もポイント。●昨秋に新規上場、フィンテック・IoTなど人気素地内包 昨年9月に東証マザーズへ新規上場したアクシス [東証M]は、金融機関や官公庁向けを軸に業務アプリ開発やインフラシステム構築・運用保守サービスを手掛ける。昨年のIPO銘柄物色の流れに乗る形で、上場直後の10月7日には9350円の高値まで買われた。現在の株価は4000円前後での推移となっている。20年12月期決算は営業2.1倍増益と業績が急拡大し、続く21年12月期も前期比8.3%増と増益基調を維持する見通し。今後、主力の金融分野向けで フィンテック対応を進めていくほか、車両の位置情報や走行距離などを把握するIoTサービスの展開強化も図っていく。●高進捗率のテクノスJ、KYCOM テクノスジャパン は、独ソフトウエア大手SAP製を中心に統合基幹業務システム(ERP)の導入支援を手掛ける。同社は1月下旬、21年3月期の連結業績予想について、営業利益を8億円から9億円(前期比3.2倍)へ上方修正した。コロナ禍による企業のIT投資抑制といったマイナス影響を見込んでいたものの、既存案件の深耕や新規案件の獲得に取り組んだことが業績押し上げにつながった。あわせて発表した第3四半期累計(20年4-12月)決算では営業利益が8億2600万円となり、上方修正した通期計画に対する進捗率は92%に達した。同社は16年3月期から前20年3月期まで連続で、通期の決算発表時に営業利益が上振れて着地している。 独立系ソフト開発会社のKYCOMホールディングス [JQ]は、通信や公共向けを中心にシステムの受託開発を手掛け、データ関連サービスでも強みを持つ。20年4-12月期決算では、営業利益が2億9200万円(前年同期比86.8%増)と通期見通しの3億円にほぼ到達している。株価は昨年8月ごろから上昇が加速し、10月には1137円の高値をつけたが、現在はそこから4割近く下回った水準にある。200日移動平均線をはさみ一進一退の展開で、ここからもみ合い上放れとなるかが注目される。●キーウェアやキューブシスにも注目 キーウェアソリューションズ [東証2]は官公庁をはじめ、通信、金融、医療など幅広い業種向けにシステム開発などを手掛ける総合ITソリューション企業。同社は医療ICTサービスとして院内感染対策ソリューションを手掛けていることから、昨年のコロナ禍初期に一躍脚光を浴びた経緯がある。株価は昨年6月高値を頂点に半年以上も調整を続けていたが、600円台後半を下値に目先底打ち感が漂う。業績面では、第3四半期時点での対通期進捗率が35.4%(経常利益ベース)にとどまっているが、これは同社の業績が第4四半期に偏重する傾向にあるためで、通期業績への期待も膨らむ。有配企業でPBR1倍割れ水準は割安感が強い。 キューブシステム は、金融・通信・流通向けを強みとするシステム開発会社。昨年はDX関連の一角として注目されたほか、年後半には地銀再編に向けた思惑を背景にマーケットの視線を集めた。21年3月期第3四半期累計(20年4-12月)決算は、売上高105億9100万円(前年同期比0.5%増)、営業利益7億9200万円(同28.2%増)と好調。通期の連結業績予想は売上高160億円(前期比8.8%増)、営業利益11億2000万円(同16.8%増)の見通しで、営業利益は6期ぶりに過去最高を更新する見込みとなっている。〔NY外為〕円、109円台前半(17日午前8時)時事通信 【ニューヨーク時事】17日のニューヨーク外国為替市場の円相場は、午前8時現在1ドル=109円14~24銭と前日午後5時(108円95銭~109円05銭)比19銭の円安・ドル高で推移している。 ユーロは同時刻現在、対ドルで1ユーロ=1.1887~1897ドル(前日午後5時は1.1897~1907ドル)、対円では同129円87~97銭(同129円70~80銭)。(了)「最低で1000万円」ヘルパー会社社長が認知症の男性から現金窃盗ABEMA TIMES 岐阜市で今月、認知症の男性から現金3万円を盗んだ疑いでヘルパーが書類送検された。 カメラに映っているのは、重度の認知症を患う90代男性と35歳の訪問介護ヘルパー。男性に何かの書類に記入させている間、ヘルパーは腕を伸ばして何かを手にする。紙幣だ。 ヘルパーは「盗りすぎた」と思ったのか、何枚かは戻したが、一部はしっかりポケットに入っている。もう少し欲しくなったのか、男性が引き出しの中を探している隙に、さらに手にした数枚の紙幣を先ほどの分と揃えてからポケットに入れた。 支援するために訪れているはずのヘルパーが、支援が必要な認知症男性の金を盗む瞬間がはっきりと映像に残されていた。なぜカメラが室内に設置されていたのか。「お金の流れがおかしい」と気づいた訪問介護事業会社の関係者が、本人の同意を得て設置したのだ。 「前回の引き出しから、3か月たらずで50万円がなくなっていた。お金の流れがおかしいなということで本、人さんの同意を得て、とりあえずカメラを設置させていただくことになりました」(訪問介護事業会社の関係者) 訪問介護会社では、買い物への付き添いや、奥さんの入院費の支払いのため男性に代わって、銀行口座から毎月50万円を引き出していました。ところが、家に残っているはずの金額が足りないことが続いた。そこで誰が盗んでいるのか調べるために、カメラを設置。その1週間後から定期的に犯行が映るようになったという。 窃盗を繰り返していたのは、4年ほど前から男性を担当していたヘルパーで、この訪問介護会社の当時の社長だった。今年1月、映像を突き付けられたヘルパーは窃盗行為を認め、同意書に「出来心、交遊費に使った」「100回くらい 多い時で1回20万円ほど」「最低で1000万円」と記している。ヘルパーは認知症の男性から現金3万円を盗んだ疑いで、今月書類送検された。〔米株式〕NYダウ、もみ合い(17日午前)時事通信 【ニューヨーク時事】17日午前のニューヨーク株式相場は、この日午後に発表される米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果に注目が集まる中、もみ合いとなっている。午前10時現在は、優良株で構成するダウ工業株30種平均が前日終値比59.17ドル高の3万2885.12ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数が114.80ポイント安の1万3356。77。 この日午後に予定されているFOMC声明や経済・金利見通しの発表、パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長の記者会見を見極めたいとの思惑から、様子見ムードが広がっている。一方で、金利見通しで利上げ想定時期の前倒しが示唆されるとの観測から米長期金利が大幅に上昇。金利高で買われやすい金融関連銘柄が上昇し、株価を支えている。 米商務省が17日発表した2月の住宅着工件数は前月比10.3%減、先行指標である住宅着工許可件数は10.8%の減少と、ともに市場予想を下回ったことも相場の下押し材料。 個別銘柄では、住宅建築大手のレナーが上昇。20年12月~21年2月期決算は1株当たり利益、売上高ともに市場予想を上回った。最近の金利上昇にもかかわらず需要は引き続き好調だという。マイクロン・テクノロジーも高い。米国内の半導体工場の一つを売却する計画だと伝わった。(了)アッヴィが反落 FDAが「ウパダシチニブ」の審査終了目標日を延長=米国株個別みんかぶFX 医薬品大手のアッヴィが反落。前日は婦人薬部門の売却交渉のニュースが伝わっていた。きょうは同社の活動性乾癬性関節炎の治療薬「ウパダシチニブ」についてFDAが、処方薬ユーザー・フィー法に基づく審査終了目標日を第2四半期後半に延長したと発表した。 FDAは最新の恩恵とリスクの評価を再確認するためにさらに時間が必要になったと説明している。アッヴィはFDAの要請に応えて、「ウパダシチニブ」の恩恵とリスク分析の最新評価を提出したと述べた。(NY時間10:21)アッヴィ 103.69(-7.15 -6.45%)今夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中の2銘柄が値を上げてスタートしましたね。テラドッグが大きく下げていますね。
2021.03.17
コメント(0)
-
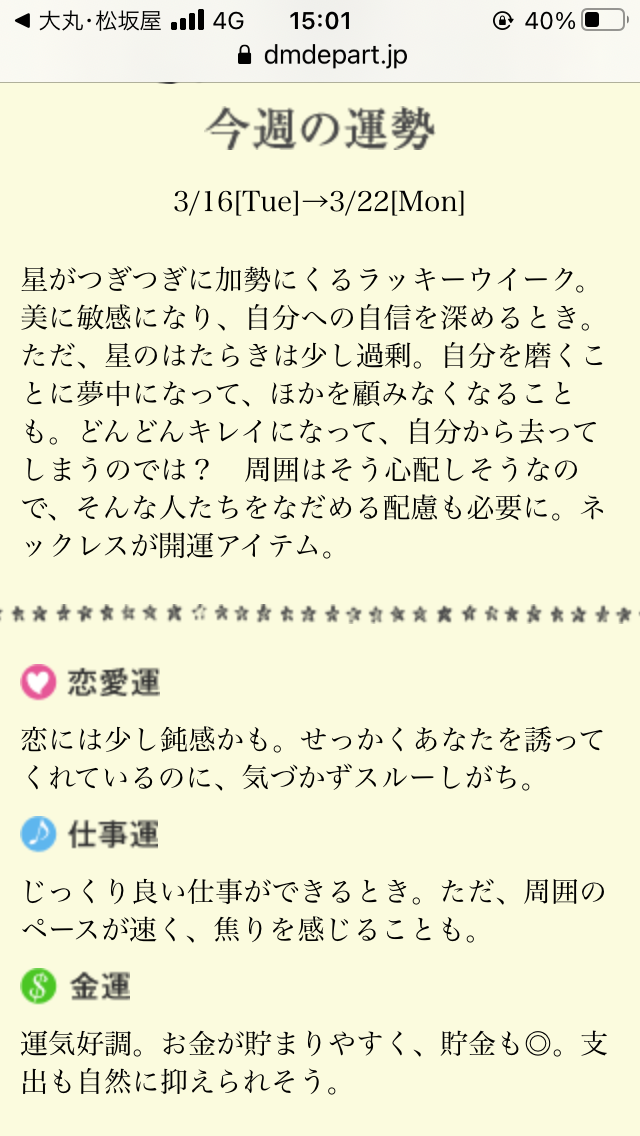
3月16日(火)…
3月16日(火)、曇りです。午後からは雨のようですね…。そんな本日は7時40分頃に起床。新聞に目を通し、朝食を済ませ、ロマネちゃんと戯れる。本日のノルマは2階の掃除機と階段のモップかけですか…。ハイハイ…。朝のコーヒーブレイクはネスプレッソで…。ピエール・ルドンのチョコレートと共に…。美味い!!10時頃には税理士さんが来訪。確定申告の書類のサインと相続の相談…。昼食を済ますと、葬儀会社のスタッフが雑務処理で来訪。予報通りは雨がパラパラとしてきましたね…。1USドル=109.14円。1AUドル=84.57円。昨夜のNYダウ終値=32953.46(+174.82)ドル。現在の日経平均=29930.22(+163.25)円。金相場:1g=6738(+25)円。プラチナ相場:1g=4747(+24)円。昨夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中の16銘柄が値を上げて終了しましたね。5%以上の大きな変動は見られませんね。本日の東京市場ではチェック中の日本株30銘柄中の14銘柄が値を上げていますね。重点6銘柄では3銘柄が値を上げていますね。レノバが上げていますね。アストラ製ワクチン、EU主要国が使用中断-血栓を懸念(ブルームバーグ):ドイツやフランスなど欧州連合(EU)主要国は英アストラゼネカ製の新型コロナウイルスワクチンの使用を中断した。進まないEUのワクチン接種がいっそう遅れるとの懸念が生じている。 欧州医薬品庁(EMA)は同ワクチンへの支持を繰り返しているが、接種後に深刻な血栓が生じる事例が複数報告されているのを受け、EU各国政府が配布を停止した。 報告について調査が完了するまでは接種を継続するとしていた一部の国は、姿勢を転換させた。イタリアとスペインもアストラゼネカ製ワクチンの接種を中断。これら4カ国は保健当局者による緊急会議後に、使用停止を明らかにした。 EU保健担当相は16日にビデオ会議を開く予定。15日の発表文によると、ドイツは接種中断の理由として過去数日間に深刻な血栓症の事例が追加で複数報告されたことを挙げた。 欧州各国はワクチン問題の解決と同時に感染拡大への対応にも追われており、一部では活動の再制限を余儀なくされている。イタリアは15日から過半の地域が再びロックダウン(都市封鎖)となった。 EMAは、アストラゼネカ製ワクチンの恩恵は引き続きリスクを上回ると指摘。同社のほか、同ワクチンの接種で先行していた英国の医薬品規制当局を含む各国の保健当局者と緊密に連携していると説明した。 EMAはこれまで、血栓の事例について調査期間中は接種を続けるべきだとし、このワクチンを接種した約500万人のうち血栓の問題が生じたのは30人だけだと指摘していた。発表文によると、EMAの安全性委員会が16日に情報を再度検証する予定で、追加的な措置が必要な場合に備え18日に臨時会議を招集した。 使用停止についてのアストラの担当者にコメントを求めたが、今のところ返答はない。KMバイオロジクスがアストラゼネカのワクチンの製剤化を近く開始(熊本)テレビ熊本 新型コロナワクチン、イギリスの大手製薬メーカーアストラゼネカの国内生産が本格化します。熊本市北区のKMバイオロジクスが、アストラゼネカのワクチンの製剤化を、近く開始することがTKUの取材で分かりました。アストラゼネカは、日本政府と約1億2000万回分の新型コロナワクチンを供給する契約を結んでいます。熊本市北区のKMバイオロジクスは、アストラゼネカから原液を提供してもらう形で、薬剤の瓶詰めや包装などの製剤化を行うことになっています。KMバイオロジクスは、国から助成を受け生産体制を強化していて、準備が整い次第、近く製剤化を開始するということです。アストラゼネカのワクチンは、現在、厚労省に承認申請されていて、承認後すぐに供給されるよう準備が進められています。同じくアストラゼネカのワクチン製剤化を図る東京の第一三共は、製剤化を開始したことを3月12日に発表しています。米モデルナ、新たなコロナワクチンの初期治験開始[15日 ロイター] - 米バイオ医薬品企業のモデルナは、新型コロナウイルス向けの新たなワクチンについて、初期段階の臨床試験(治験)を開始したと明らかにした。同ワクチンは冷蔵庫での保存が可能。治験では健康な成人を対象に3種類の用量を用い、それぞれ1回のみと28日間隔の2回投与を実施。安全性や免疫効果を調べる。TOPIX戻り高値、景気への楽観や金利上昇一服-半導体関連高い 16日の東京株式相場は続伸。TOPIXはバブル崩壊後の日中戻り高値を更新した。景気への楽観の高まりや米長期金利の上昇一服が安心感につながっており、半導体関連やソフトバンクグループ、任天堂などの大型株に買いが広がっている。 TOPIXの午前終値は前日比9.47ポイント(0.5%)高の1978.20 日経平均株価は189円85銭(0.6%)高の2万9956円82銭 一時3万円台を2月25日以来回復 〈きょうのポイント〉 新たな新型コロナワクチン登場へ、最大8種類も-WHO主任科学者 NY連銀製造業景況指数、3月は2018年11月以来の高水準 【米国市況】株が連日で最高値、景気への楽観強まる-ドル上昇 大和証券の木野内栄治チーフテクニカルアナリストは、前日の米株市場でダウ平均よりもナスダックの上昇率が高く、給付金への期待が株式市場に回り始めて「グロース(成長)株に資金が少しずつ戻り始めた」とみる。これを受けて日本株市場でも日経採用銘柄だけでなくTOPIXの大型成長株である任天堂などが買われていることが指数を押し上げる原動力となっていると話した。 さらに木野内氏は期末のリバランス前の株売りがSQを経て止まり、上値が少し軽くなった可能性があるという。日米金融政策への様子見姿勢もあるが、「コロナから完全に経済が回復していない状況で、株式市場を冷やすことになるような結果にはならないだろう」とみていた。 東証33業種では海運、空運、情報・通信、電機、不動産が上昇率上位 石油・石炭、銀行、証券・商品先物、鉄鋼、輸送用機器が下落債券上昇か、米長期金利低下で買い-流動性供給入札は波乱なしとの声 債券相場は上昇が予想されている。前日の米国市場で長期金利が低下したことを受けて、買いが優勢となる見通し。この日に実施される流動性供給入札は一定の投資家需要を背景に波乱なく通過するとの指摘が聞かれている。 長期国債先物(6月物) 151円00銭台半ば~151円20銭台半ば(前日151円7銭) 新発10年物国債(361回債)利回り 0.095%~0.105%程度か(前日0.105%) 先物夜間取引では6月物が取引序盤にいったん151円3銭まで軟化したが、米長期金利の低下を背景に水準を切り上げた。結局は、前日の日中取引終値比6銭高の151円13銭で高値引けした。 長期国債先物6月物の夜間取引推移 市場関係者の見方 三菱UFJモルガン・スタンレー証券の稲留克俊シニア債券ストラテジスト 米長期金利の先高観は残るものの、小幅ながらいったん低下したということは安心材料 円債先物も夜間取引で高値引けとなっており、日中の相場は強含みもみ合いのイメージ 流動性供給入札は品薄な銘柄を中心に一定のニーズがあるゾーンで、波乱なく通過すれば相場のザポートになり得る 先物中心限月の予想レンジは151円5銭~151円25銭 流動性供給入札 対象は残存期間5年超15.5年以下、発行予定額は5000億円程度 備考:過去の流動性供給入札の結果一覧 海外市場の流れ 15日の米10年物国債利回りは前週末比2ベーシスポイント(bp)低い1.61%程度。一時1.59%台前半まで低下する場面があった バイデン大統領、1993年以来の本格増税検討-経済プログラムの財源で【米国株動向】スクエアは偉大な成長株になるのかモトリーフール米国本社、2021年3月3日投稿記事よりスクエア(NYSE:SQ)はパンデミックを通じて大きく成長しました。同社の第4四半期(10-12月)決算は好調であり、株価は上昇し続けました。しかし、スクエアはパンデミック後も成長し続けるでしょうか? スクエアのビジネススクエアは、2つの決済システムを運営するフィンテック企業です。人気のスクエアのカードリーダーは、実店舗に提供されていました。そのため、パンデミックの間に成長は鈍化し、売上高は5%増、粗利益は13%増にとどまりました。スクエアは、より多くの顧客を獲得するために、実店舗とECサイトの情報管理システムを統一しました。その結果、スクエアの総決済量は30%以上増加しました。スクエアは中堅企業を成長のための大きなターゲットとみなしています。同社はこのカテゴリーで高い収益性を示し、粗利益は他のカテゴリーの2倍の速度で成長しました。同社の「CashApp」は、大成功を収めました。それは、ロックダウンの間に多くの人がデジタル決済に依存し始めたためです。しかし、スクエアの業績に最大の影響を与えたのはビットコイン(CRYPTO:BTC)の購入でした。第4四半期に売上高は141%増となりましたが、ビットコインなしでは23%しか増加していません。第4四半期には「Cash App」のアクティブ顧客は前年比50%増の3,600万人になり、顧客1人あたり単価は5ドルとなりました。「Cash App」システムで少なくとも1回取引したことのある顧客は8,000万人にものぼり、スクエアは顧客のロイヤリティーを維持するために様々なサービスを生み出すことに注力しています。その成果として、新規顧客はキャッシュカードやビットコイン取引などの機能を活用しています。そのため、第4四半期の顧客1人あたりの粗利益は前年比70%増となっています。新サービスは、収益性を高めるための鍵になっています。ビットコインはキャッシュアプリの重要な部分になりつつあります。ビットコイン取引は前年比250%以上増加しました。スクエアは、第4四半期に1億9,000万ドルの仮想通貨を購入しました。ジャック・ドーシーCEOは最近の決算発表で「ビットコインは今後の社会において、さらに使いやすいものになっていくだろう」と述べました。 成長は終わったのかその答えは「ノー」です。パンデミックの間、実店舗では苦戦しましたが、ロックダウンが緩和されるにつれて売上高は増加するはずです。電子決済、特に「CashApp」は成長を続けており、スクエアはまだ高成長モードにあります。スクエアの最も良い点は、時代の先を行く新しいビジネスを行っているところです。スクエアのカードリーダーは革新的なものであり、また「CashApp」の機能はユーザーフレンドリーなものです。ビットコインの動きに焦点を当てると、同社の株価はリスクが高いといえます。しかし、同社は仮想通貨に対する時代を先読みしており、いち早くトレンドの波に乗るのではないかと思われます。 株価についてスクエア株は、記事執筆時点で株価収益率(PER)約600倍という 非常に高いバリュエーションで取引されています。しかし、過去3年で株価は400%以上上昇しており、同社の明るい未来を考えると、今後も成長を続けることができると考えられます。米株はS&Pとダウが終値で最高値、FOMCに注目[ニューヨーク 15日 ロイター] - 米国株式市場は上昇し、S&P総合500種とダウ工業株30種が終値で最高値を更新した。金利上昇への懸念が根強い中、市場は景気回復に期待しているほか、今週の米連邦公開市場委員会(FOMC)も注目される。デルタ航空、サウスウエスト航空、格安航空会社(LCC)ジェットブルー・エアウェイズの3社は15日、新型コロナウイルスワクチンの接種が進むつれレジャー目的の航空便の予約が増えていると明らかにし、感染拡大で大打撃を受けた航空業界が最悪期を脱した可能性が示唆された。3社の株価は軒並み値上がりした。主要株価3指数はいずれも取引終盤に買いが加速した。S&P1500航空株指数は4%超上昇し、1年ぶりの高値を付けた。旅行関連株のクルーズ船運航大手カーニバル、カジノ運営のウィン・リゾーツ、MGMリゾーツは2─5%高。S&Pの主要11セクターでは9セクターが上昇。公益事業と不動産がともに1%超高となり、上げを主導した。この日はラッセルのグロース株指数がバリュー株指数をアウトパフォームし、テクノロジー株など高成長株からシフトする最近の動きがやや後退した。AXSインベストメンツのグレッグ・バサク最高経営責任者(CEO)は、ワクチンに関するポジティブなニュースや景気刺激策を受けて、新型コロナウイルス禍で上昇してきた銘柄からのシフトは今後も続くだろうと指摘。「金融サービスとエネルギーセクターについて強気な見方を持っている」と語った。S&Pは年初来では約6%、ダウは約8%、それぞれ上昇している。また、ダウは6営業日連続で日中最高値を更新した。ワクチン接種の進展や1兆9000億ドル規模の新型コロナ追加経済対策が成立したことが支援となっている。ナスダックもこの日上昇したが、2月12日に付けた終値での最高値は依然として約5%下回っている。16─17日のFOMCでは、政策当局者らは予見可能な将来においてハト派スタンスを維持する方針を改めて表明するとともに、2021年の米経済について数十年ぶりのペースで拡大するとの見通しを示すとみられている。電気自動車(EV)大手テスラは約2%高。同社は、マスク最高経営責任者(CEO)に「テスラのテクノキング」という肩書を追加した。医薬品イーライリリーは9.1%高。同社は13日、開発中のアルツハイマー型認知症治療薬「ドナネマブ」が、同症の初期段階の患者272人を対象とする18カ月の中期臨床試験(治験)で、認知機能の低下ペースを32%遅らせたと発表した。米取引所の合算出来高は125億株。直近20営業日の平均は145億株。ニューヨーク証券取引所では値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を1.78対1の比率で上回った。ナスダックでは1.35対1で値上がり銘柄数が多かった。ドル上昇、FOMC控え警戒感=NY市場[ニューヨーク 15日 ロイター] -ニューヨーク外為市場ではドルが上昇。最近の米債利回り上昇を踏まえドル安観測が後退しているほか、16─17日の米連邦公開市場委員会(FOMC)を控え警戒感が強まっている。FOMCに加え、週内に開催される日銀や英中銀の金融政策決定会合にも注目が集まっている。このところ上昇していた米10年債利回りは欧州債券利回りの低下に追随し、終盤の取引で1.61%近辺。一時1.639%まで上昇し、前週末の1.642%に迫った。クラレイティFXのエグゼクティブディレクター、アモ・サホタ氏は「FOMC待ちとなる中、相場は様子見気分が強い。米連邦準備理事会(FRB)がイールドカーブについて討議するか、長期債利回りの上昇に対処するかが注目される」とし、FRBが何も行動しなければ「ドル上昇に拍車が掛かる可能性がある」と述べた。終盤の取引で、ドル指数は0.1%高の91.799。ドルは対ユーロやポンドで上昇が目立ち、ユーロ/ドルは0.2%安の1.1926ドル。ドル/円も0.1%高の109.15円。一時、昨年6月以来の高値となる109.36円を付ける場面もあった高利回り通貨の豪ドルも0.1%安の0.7750米ドル。暗号資産(仮想通貨)ビットコインは5万6046ドル。週末に付けた過去最高値の6万1781.83ドルから5%強下落した。【市況】後場に注目すべき3つのポイント~「根強い株買い」と「大台回復・イベント前の売り」16日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は6日続伸、「根強い株買い」と「大台回復・イベント前の売り」・ドル・円は底堅い、日本株にらみ・値上がり寄与トップはソフトバンクG、同2位がファーストリテイリング■日経平均は6日続伸、「根強い株買い」と「大台回復・イベント前の売り」日経平均は6日続伸。189.85円高の29956.82円(出来高概算7億3000万株)で前場の取引を終えている。15日の米株式市場でNYダウは7日続伸し、174ドル高となった。4日連続で過去最高値を更新。3月のNY連銀製造業景気指数が2018年以来の水準を回復したほか、インフラ計画や経済活動の再開に期待した買いが相場を押し上げた。また、16日からの連邦公開市場委員会(FOMC)を前に長期金利が伸び悩み、ハイテク株比率の高いナスダック総合指数も1.0%の上昇。一方、本日の東京市場では高値警戒感から利益確定の売りも出て、日経平均は3円高からスタートした。朝方は29800円台でやや伸び悩んだが、前場中ごろにかけて上げ幅を広げ、30026.40円(259.43円高)まで上昇する場面があった。個別では、ソフトバンクGが2%超、任天堂が3%超の上昇。その他売買代金上位でもファーストリテ、ソニー、東エレクといった値がさ株が堅調となっている。業績上方修正を発表したしまむらは伸び悩みつつも2%の上昇となり、決算が好感された三井ハイテクは急伸。また、バイオジェット燃料が完成したと発表したユーグレナは東証1部上昇率トップとなっている。一方、前日ストップ高の楽天は反落し、3%近い下落。三菱UFJなどのメガバンク株やトヨタ自は小安い。神戸物産は堅調な決算ながらサプライズなしとの見方から売り優勢。建転換社債型新株予約権付社債(CB)の発行を発表したセイノーHDなどは大きく下落している。セクターでは、空運業、海運業、その他製品などが上昇率上位。半面、石油・石炭製品、証券、鉄鋼などが下落率上位だった。東証1部の値上がり銘柄は全体の55%、対して値下がり銘柄は39%となっている。本日の日経平均は米国株の上昇を追い風に6日続伸し、2月25日以来の3万円台に乗せる場面もあった。米国では追加経済対策の柱となる個人向け現金給付の手続きが始まったと伝わっており、ハイテク株を中心に個人マネーの再流入が期待される。また、度々当欄で取り上げているブレークイーブン・インフレ率(期待インフレ率の指標)は2%台後半で高止まり。積極的な財政・金融政策を背景に「資産インフレ加速」の思惑は根強いとみられ、インフレヘッジ目的の株買いを誘っているのだろう。半面、米国では16日から17日にかけてFOMCが開催されるが、大規模な追加経済対策の成立や経済活動再開の流れから長期金利が大きく上昇するなか、参加者の政策金利見通し(ドットチャート)などが注目点として挙げられている。日銀も18~19日に開催する金融政策決定会合で緩和策の「点検」を行うとしており、その結果が注目されるところ。また、日経レバETFの動向を見ると、日経平均が29000円を割り込んだ局面を中心に純資産総額が増え、足元では昨年6月以来となる3000億円台乗せ。日経平均が節目の3万円台を回復する場面では、個人投資家から目先の利益を確保するための売りが出やすいと考えられる。根強いインフレ観測に基づく買いと、重要イベント前の持ち高調整や大台回復による売りが交錯するタイミングか。後場の日経平均も堅調もみ合いが続くとみておきたい。(小林大純)■ドル・円は底堅い、日本株にらみ16日午前の東京市場でドル・円は底堅く推移し、109円台前半で小幅に値を上げた。米10年債利回りはやや低下するものの、欧州での新型コロナウイルスまん延でユーロ・ドルに下押し圧力がかかり、ドル・円は下げづらい。また、日本株高を背景に円売りも観測されている。ここまでの取引レンジは、ドル・円は109円10銭から109円25銭、ユーロ・円は130円14銭から130円31銭、ユーロ・ドルは1.1922ドルから1.1934ドル。■後場のチェック銘柄・わかもと製薬、プレミアアンチエイジングなど、3銘柄がストップ高※一時ストップ高(気配値)を含みます・値上がり寄与トップはソフトバンクG、同2位がファーストリテイリング■経済指標・要人発言【経済指標】・米・3月NY連銀製造業景気指数:17.4(予想:15.0、2月:12.1)・米・1月対米証券投資収支・長期有価証券(株式スワップ等除く):+908億ドル(12月:+1210億ドル)・米・1月対米証券投資全体:+1063億ドル(12月:+80億ドル←-6億ドル)【要人発言】・加藤官房長官「緊急事態宣言、1都3県全体として取り扱う方向で検討中」<国内>・13:05 黒田日銀総裁あいさつ(フィンテック会議)・13:30 1月鉱工業生産改定値(速報値:前月比+4.2%)<海外>特になし《CS》 提供:フィスコNTTデータがBlockTrace事業を開始──証券・アート・不動産をトークン化CoinDesk Japanブロックチェーンの研究開発チームを作り、2017年からその取り組みを強化してきたNTTデータが、同技術を活用した統合型サービス「BlockTrace」を開始する。ユーザーのニーズに合わせて、証券や不動産、アート作品などをデジタルトークン化して新たな市場を創設したり、生鮮食品や医薬品などの位置情報や温度管理情報をブロックチェーン上で可視化することができる。NTTデータは16日、これまで開発を進めてきたBlockTraceの詳細を発表。例えば、証券や不動産の所有権、絵画や骨董審などのアート作品を、デジタル証券化(セキュリティトークン)すれば、小口化でき多くの個人が取引できる市場を創ることができる。NTTデータはこのサービスにおいて、セキュリティトークンの発行・流通技術を開発する米セキュリタイズ(Securitize)と共同で展開していく。消費者が手にする商品の情報に対するニーズが世界的に高まるなか、NTTデータはこの領域でもBlockTraceの利用拡大が期待する。発表では、NTTデータは、低温で輸送される必要のある商品にフォーカスを当てたユースケースを強調している。輸送中の位置情報や、温度管理の状況をブロックチェーン上に記録することで、生鮮食品の品質状態を常時モニターできるようになる。また、ワクチンなどの医薬品や化学品などの温度管理輸送にも応用することができる。また、サプライチェーンのDX化は、NTTデータが想定するBlockTraceのユースケースの1つに据えるエリアでもある。あらゆる業界におけるサプライチェーンのデジタル化は、急ピッチで進められている。製品の原料や部品の調達から製造、配送、販売、消費までの流れをデータ化して、ブロックチェーン上に記録すれば、トレーサビリティ性は向上し、モノの流れにおけるコストと時間を大幅に削減することが可能だ。旭化成-7日続伸 リチウムイオン二次電池用セパレータの生産能力を増強トレーダーズ・ウェブ現在値旭化成 1,287 +5.50 旭化成が7日続伸。同社は15日、リチウムイオン二次電池用セパレータの生産能力を増強すると発表した。約300億円を投じ、宮崎県日向市にある既存工場の生産能力を増強する。これによって生産能力が年間で19億平方メートルになるが、今後も需要の伸びに合わせて積極的な能力増強を行うとしている。2023年度上期の運転開始予定。〔東京株式〕6日続伸=ハイテク株が押し上げる(16日)時事通信 【第1部】日経平均株価は前日比154円12銭高の2万9921円09銭、東証株価指数(TOPIX)は12.77ポイント高の1981.50と、ともに6営業日続伸。半導体や情報技術などハイテク業種の一角が大きく値を上げて、株価指数を押し上げた。出来高は14億1937万株。 【第2部】堅調。ケミプロがストップ高で引け、千代化建は小幅高。半面、REMIXは下落した。出来高1億9554万株。 ▽FOMC控えて上値は追えず 東京市場では、引き続き米国の大規模な経済対策による景気浮揚効果や、ワクチンの普及による新型コロナウイルス感染の収束への期待感が買いを後押しした。前日に米金利上昇を嫌ったハイテク株売りが出た反動も加わり、日経平均株価は一時3万円台に乗せた。 もっとも、米国の金利動向に金融市場全体が敏感になる中、「米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果と、その後の米債券市場の反応を確認する前に、上値は追えない」(中堅証券)とされ、3万円に乗せると買いの勢いは鈍った。日経平均を構成する225銘柄だけを見ても半数が下落しており、物色にもさほど広がりは見られなかった。後場は2万9000円台での小幅なレンジ内での行ったり来たりが長く続き、重要イベント前らしい様子見ムードの強い相場だった。 225先物6月きりは反発。小高く始まった後、午前中は上値を試すような動きも見られたが、FOMCを前に買いの勢いは続かなかった。午後はこう着状態となった。225オプション4月きりはプットが下落し、コールは値上がりした。(了)〔東京外為〕ドル、109円台前半=様子見でもみ合い継続(16日午後3時)時事通信 16日午後の東京外国為替市場のドルの対円相場(気配値)は、米連邦公開市場委員会(FOMC)などを控えて様子見ムードが広がる中、1ドル=109円台前半でのもみ合いが継続している。午後3時現在、109円17~18銭と前日(午後5時、109円18~22銭)比01銭の小幅ドル安・円高。 東京時間のドル円は109円10銭台で始まった。午前9時以降、堅調な日経平均株価を受けて買いが入り、仲値前後は109円20銭台に浮上。上げ一服後の午後は日経平均の伸び悩みを眺めて上値重く推移し、109円10銭台を中心とする小動きが続いている。時間外取引で米長期金利が低下していることもドル円の重しになっている。 市場では16日から開かれるFOMCが強く意識されており、積極的な取引が手控えられている。経済見通しの改善を考慮して利上げの一部前倒しが検討されるとの観測が出ており、「2023年中に利上げを1回行う方針が示されれば、米長期金利上昇でドルはしっかりとなりやすい」(国内証券)との声が聞かれた。 ユーロは正午と比べ、対円、対ドルで小高い。午後3時現在、1ユーロ=130円30~31銭(前日午後5時、130円16~16銭)、対ドルでは1.1934~1935ドル(同1.1919~1923ドル)。(了)日経平均は154円高と6日続伸、一時3万円回復後は伸び悩む、FOMC控え様子見=16日後場モーニングスター 16日後場の日経平均株価は前日比154円12銭高の2万9921円09銭と6営業日続伸。朝方は、15日の米国株式市場でNYダウの最高値更新が続き、ナスダック総合指数が反発した流れを受け、買いが先行した。いったん下げに転じる場面もあったが、すかさず切り返した。株価指数先物にまとまった買い物が入ったこともあり、上げ幅を拡大し、前場後半には3万26円40銭(前日比259円43銭高)まで上昇した。一巡後は、利益確定売りに伸び悩み商状となった。16-17日開催のFOMC(米連邦準備制度理事会)を控え、様子見気分が強まった。 東証1部の出来高は14億1937万株、売買代金は2兆9091億円。騰落銘柄数は値上がり1529銘柄、値下がり592銘柄、変わらず74銘柄。 市場からは「日経平均は3万円タッチ後に伸び悩んでいるが、今週は米日で金融イベントを控えており、なかなか強気にはなれない。結果に対し、市場の解釈の仕方次第では下がる要因になる可能性もあり、様子見にならざるを得ない」(国内投信)との声が聞かれた。 業種別では、川崎汽 、商船三井 、郵船 などの海運株や、JAL 、ANA などの空運株が上昇。任天堂 、アシックス などのその他製品株も堅調。住友不 、三井不 、菱地所 などの不動産株や、ソフバンG 、ZHD 、KDDI などの情報通信株も高い。丸井G 、ニトリHD などの小売株や、JR東日本 、JR西日本 、JR東海 などの陸運株も買われた。 半面、JFE 、日本製鉄 、神戸鋼 などの鉄鋼株が軟調。三井住友 、みずほ 、ゆうちょ銀行 などの銀行株も売られた。ENEOS 、コスモエネH などの石油石炭製品株もさえず、マネックスG 、マネパG などの証券商品先物株も下落。トヨタ 、日産自 、スズキ などの輸送用機器株も安い。 個別では、わかもと 、明治海 がストップ高となり、ユーグレナ 、モバファク 、GMOペパボ などの上げも目立った。半面、システムソフ 、LinkU 、セイノーHD 、ACCESS 、トリケミカル などの下げが目立った。なお、きょう東証1部に新規上場のウイングA は公開価格1590円に対して410円高の2000円で初値を付け、後場終値は同390円高の1980円。なお、東証業種別株価指数は全33業種中、24業種が上昇した。下げるかもしれない…、ということでグロース株を安く入手するチャンスがあるかも…、ということで米国株にちょっと触手を伸ばしてみましょう…。セイノーHDが大幅反落、CB発行で希薄化を懸念路線トラック業界最大手のセイノーホールディングス(9076)が大幅反落。午後2時00分現在、前日比90円(5.4%)安の1591円で推移している。一時は1590円まで下落した。15日にユーロ円建て新株予約権付き社債(CB)の発行を発表し、売り材料視された。潜在的な株式需給の悪化や1株利益の希薄化を懸念する動きとなった。調達資金約250億円はロジスティックス・トランス施設の建設や建設用地取得などに充てるとしている。当社は輸送・管理を行うだけでなく、顧客の製造工程の一部を担うファクトリー機能として、製造・組み立て・検査・分解・流通加工まで行い、顧客の最適在庫配置を実現するロジスティック機能の強化に取り組んでいる。2021年3月期の営業利益は240億円(前期比19.2%減)、純利益160億円(同38.1%減)の見込み。(取材協力:株式会社ストックボイス)【特集】「全固体電池」関連が2位、2次電池革命に向け開発競争加速<注目テーマ> みんなの株式と株探が集計する「人気テーマランキング」で、「全固体電池 」が2位となっている。 世界的に「脱炭素」への取り組みが加速するなか、排ガス規制などを背景にガソリン車から電気自動車(EV)をはじめとした電動車シフトの動きが顕著となっている。現在、車載用電池としては リチウムイオン電池が主流となっているが、発火リスクが問題視されていることから、EVが本格普及する段階では、現行のリチウムイオン電池に代わる次世代電池の開発が切望されている。その最右翼に目されているのが全固体電池である。 全固体電池 とは電解質に液体ではなく固体を用いた2次電池のことを指す。電解質は、電池のプラス極とマイナス極の間にあるイオンを移動させる機能材料であり、ここが“電解液”の場合は液漏れや発火リスクが常につきまとうことになる。固体に変えることでこの弱点を解消できるのが最大の強みとなる。また、同じ体積であればより多くの蓄電ができることで、EVの航続距離の延長も可能とし、構造がシンプルで積層化が容易なためコンパクト化する際にも融通が利くというメリットがある。 トヨタ自動車を筆頭に大手自動車メーカーはこの全固体電池の実用化に積極的に取り組んでおり、世界的にみても同分野は日本が先駆しているだけに今後の展開に期待が大きい。トヨタは全固体電池搭載のEV実用化に野心を燃やしており、年内にも試作車が公開される可能性が高いとみられている。既にパナソニックとの連携で同分野の商品開発に取り組んでおり、今後も主導的な役割を担うことになりそうだ。 固体電解質の開発では非鉄大手の三井金属や石油元売り大手の出光興産などが傾注している。このほか、TDKや村田製作所、マクセルホールディングスなども全固体電池分野の開発で既に実績を示している。最近では日立造船が脚光を浴びた。同社は、今月初旬に世界最大級の全固体電池を開発したことが明らかとなり株価の居どころを大きく変えた経緯がある。これは産業機械や宇宙用途での需要を見込み、自動車向けでの活用はハードルも多いとみられているが、株式市場における全固体電池の現実買いのステージが近いことを暗示する形となった。 全固体電池はEVや再生可能エネルギー分野で注目必至の分野といえ、足もと関連各社動きをみせていることもあり、投資テーマとして改めて投資資金の食指を動かす可能性が高まっている。 このほか関連銘柄としては東レ、旭化成、第一稀元素化学工業、カーリットホールディングス、三洋化成工業、日本ガイシ、大阪チタニウムテクノロジーズ、東邦チタニウム、ホソカワミクロン、FDKなどが注目される。出所:MINKABU PRESSおうちに置ける「宅墓」を考案「こんなのがほしかった」 先祖を祭る新しい形〈AERA〉AERA dot. 部屋に置けるお墓「たくぼ(宅墓)」。台座の上の石を持ち上げると、中に納骨スペースがある。骨壺はオプションで1千円。 コロナ禍で部屋に置ける「お墓」に注目集まる。お墓の形は変わっても、供養の気持ちをかなえられるという声も上がっている。AERA 2021年3月15日号から。 部屋に置ける小さな「お墓」も、コロナ禍で注目される葬祭サービスだ。コロナ禍で墓参りを敬遠する動きがある中、「自宅墓」「家墓(かぼ)」などとして石材店が売り出している。 部屋に置けるお墓の先駆けが「たくぼ(宅墓)」。滋賀県豊郷町にある創業約140年の老舗の石材店「浦部石材工業」4代目社長の浦部弘紀(ひろき)さん(49)が、5年前に考案した。 「5年くらい前から先祖代々の墓を閉じて『墓じまい』をする人が増えてきて、亡くなった人を拝むところがなくなる状態になりました。しかし、せめて手元に置いて拝むところを残せたらという思いがありました」 故人の遺骨や遺灰をそばに置いて供養する「手元供養」は00年ごろから広まった。「たくぼ」も手元供養の一種だが、室内に置ける「墓」はそれまでなかったという。■1人用や夫婦2人用も 1人用から夫婦で入れる2人用まで全4種類、色は黒、白、赤、ピンクなど全5色。価格は1人用が7万円で、2人用は14万円。サイズは1人用の「たくぼ台座小」が幅17×奥行き23×高さ17.2センチ。 自宅に墓を置いていいのか心配になるが、墓地埋葬法では自宅の庭に遺骨を埋葬することはできないが保管して安置するのは問題ない。 たくぼの注文は月に1、2基だったが、昨年末に新聞やテレビで紹介されると、コロナ禍もあり一気に広まった。今や全国から注文が入り、月平均40基の注文がある。「こんなのがほしかった」 という声とともに、お礼の手紙も届くという。浦部さんは言う。「お墓の形は変わっても、亡くなった人を偲ぶ気持ちに変わりありません。墓参りに行きたくても、体調が悪かったり遠くて行けなかったりする人もいます。そういう人たちにとって、自宅に墓を置いて先祖を祭るのが新しい形になるといいですね」今週(3/16から)の運勢は…これならまずまず…。明日の戦略-6日続伸で3万円台も一時回復、ただし若干バブルの兆候もトレーダーズ・ウェブ 16日の日経平均は6日続伸。終値は154円高の29921円。小高く始まった後に下げに転じる場面もあるなど、序盤は方向感に乏しい展開。しかし、開始1時間後くらいから買いに勢いがつき、上げ幅を200円超に広げて3万円台を回復した。3万円より上での時間は短く、節目に乗せた後は上値が重くなった。ただ、伸び悩んでも大きく失速することはなく、後場に入ると29900円台でのもみ合いが長く続いた。前日に終値ベースで昨年来高値を更新したTOPIXは、取引時間中の昨年来高値も更新した上に、連日の高値引けとなった。 東証1部の売買代金は概算で2兆9000億円。業種別では海運や空運、その他製品などが上昇した一方、鉄鋼や銀行、石油・石炭などが下落した。上方修正を発表したプレミアアンチエイジングがストップ高。半面、1Q決算が失望材料となったGAテクノロジーズが急落した。 東証1部の騰落銘柄数は値上がり1529/値下がり592。ナスダックの強い上昇を好感して、任天堂やソフトバンクGなど主力グロース株が大幅高。アドバンテストやTDKなどハイテク株にも幅広く買いが入った。米国で空運株が急伸した流れを受けてJALとANAが強く買われたほか、1Qが大幅な営業赤字となったHISが上昇するなど、レジャー関連の動きが良かった。日本郵船など海運株への買いが続く中、関連の深掘りが進み、明治海運や大運がストップ高。バイオジェット燃料が完成したと発表したユーグレナが商いを伴って値を飛ばした。 一方、三井住友や三菱UFJなど銀行株が軟調。マネックスGや楽天、日本郵政など、直近で大きく上げた銘柄が売りに押された。神戸物産は1Q決算は好調だったが、株価は売りで反応。土屋HDやジェネレーションパスが決算を受けて急落した。 きょうは2社が新規上場したが、いずれも高い初値をつけた後の動きは案外。ウイングアーク1stの終値は初値を若干下回る程度であったが、ヒューマンクリエイションホールディングスの終値は初値を大きく下回った上に安値引けとなった。 日経平均は6連騰。寄り付きはほぼ横ばいであったが、場中に上げ幅を広げて3万円台に乗せる場面もあった。グロース株の方が動きが良かったが、バリュー株の一角にも買いが続いており、楽観的なムードが支配的になりつつある。ただ、きょうのユーグレナの26.4%高や、15日の楽天のストップ高などは、好材料があったとは言え、バリュエーションを度外視した買いのようにも見える。また、東証2部やジャスダックなどニッチな市場では、普段商いの少ない銘柄がいきなり急騰するといった動きも散見されており、局地的には過熱感も強い。マネーゲームの様相が強まることは金融緩和の弊害でもある。個別の値動きが派手になりすぎた場合には、FOMCや日銀会合が相場を冷やすイベントになる可能性があるだけに、一定の注意を払っておきたい。今晩のNY株の読み筋=FOMC前で様子見ムード強そうモーニングスター 16日の米国株式市場は、きょうから17日のFOMC(米連邦公開市場委員会)を前に様子見ムードが広がりやすく、方向感の乏しい展開が予想される。FOMCでは直近の長期金利上昇にどのような見解を示すかが注目されそう。前週発表の米2月CPI(消費者物価指数)は市場予想を下回り、インフレ懸念は後退しているものの、景気回復期待から米長期金利は上昇圧力が高まっており、FOMCの姿勢次第では再び上昇基調を強め、株式市場の重しになる恐れがある。 米経済指標では、米2月小売売上高、米2月鉱工業生産などが注目となり、小売売上高は前月よりも減少し、鉱工業生産は伸びが鈍化する見通し。FOMCを前に積極的にポジションを取る動きにはなりにくいとみられ、市場予想通りの結果となって株式市場の重しになっても下値は限られそうだ。<主な米経済指標・イベント>2月小売売上高、2月鉱工業生産、FOMC(1日目)◎投資関連情報は投資の参考として情報提供のみを目的としたものであり、株式の売買は自己責任に基づき、ご自身で判断をお願いします。明日の日本株の読み筋=米日の金融イベントにらみ手控え気分かモーニングスター あす17日の東京株式市場は、米日の金融イベントをにらみ、手控え気分か。16-17日開催のFOMC(米連邦準備制度理事会)、18-19日開催の日銀金融政策決定会合と続き、結果を見極めたいとの空気が広がりやすい。内容いかんでは米長期金利や為替相場が変動する可能性があり、とりあえずイベント通過待ちの状態と言えよう。市場では、「結果に対し、解釈の仕方次第では下がる要因になる可能性もあり、様子見にならざるを得ない」(国内投信)との声が聞かれた。 16日の日経平均株価は6営業日続伸し、2万9921円(前日比154円高)引け。朝方は、15日の米国株式市場でNYダウの最高値更新が続き、ナスダック総合指数が反発した流れを受け、買いが先行した。いったん下げに転じる場面もあったが、すかさず切り返した。株価指数先物にまとまった買い物が入ったこともあり、上げ幅は一時260円近くに達した。一巡後は、利益確定売りに伸び悩み商状となった。FOMCを控え、様子見気分が強まった。ただし、直近6連騰(合計1177円上昇)で一時3万円を回復したこともあり、短期的な戻りピッチの速さから利益確定売りが出やすいとの見方は少なくない。16日の米国株動向次第では反動安に向かうケースも想定されよう。変異株感染6人は全員南ア由来 岐阜県内で新たに5人が新型コロナ感染 岐阜県は16日、新型コロナウイルス変異株の感染が判明している県内在住の患者6人について、南アフリカ由来の変異株かその可能性が高いと発表した。 県によると、うち3人は国立感染症研究所の解析で確定した。他の3人はウイルス量が少ないために確定できなかったが、患者の接触状況などから南ア由来と推定している。これまでに判明している4人を含め、県内の変異株感染者10人全員が南ア由来。10人はいずれも海外渡航歴はなく、不特定多数との接触もないという。県による変異株の検査人数は145人となった。 16日発表の新規感染者は5人で2日ぶりに感染者が確認され、県内の感染者数は累計4690人となった。15日時点の入院患者は59人。病床使用率は8・5%で、前日より0・3ポイント減った。国産ワクチン年内供給困難に 塩野義、大規模治験難しく産経新聞 塩野義製薬が開発を進める新型コロナウイルス予防ワクチンの年内供給が、困難な見通しであることが16日、分かった。先行するワクチンの実用化が進み、偽薬を用いた数万人規模の最終段階の治験(臨床試験)を年内に実施することが難しい状況となっているため。同社では、ワクチンの安定供給と、日本特有の変異株出現に備えるため、安全性を担保した上で使用を認める緊急使用許可の仕組みの必要性を訴えている。 塩野義が開発を進める新型コロナウイルス予防ワクチンは現在、治験の第1、2段階にあたる第1/2相試験を国内で実施している。同時に、最終段階の治験となる、偽薬を用いた、世界の流行地域の数万人を対象にした治験に向けて準備を進めており、その予算は数百億円規模を見込む。 ところが、世界では米ファイザー製や英アストラゼネカ製など実用化したワクチンの接種が広まっていることから、未承認のワクチンの治験参加者の確保が難しくなり、年内に大規模な治験を実施できる国が少なくなっている。 塩野義はこれまで、開発と同時に国内工場を拡充し、年間3千万人分を供給できる生産体制の構築に取り組んでいた。同社は引き続き、大規模治験に向けて模索するが、米国では、コロナ禍の非常事態を考慮した緊急使用許可の仕組みで米ファイザー製などのワクチンが実用化されたことなどから、国内でも同様の枠組みの必要性を訴えている。 国産ワクチンで現在、人に接種する治験に入っているのは、第2/3相試験中の創薬ベンチャーの「アンジェス」と、第1/2相試験中の塩野義で、第一三共とKMバイオロジクスが今月中に治験に入る予定となっている。【本日のNYダウ見通し】節目の33,000ドルを超えるかに注目【NYダウ予想レンジ:32,800~33,200ドル】15日のNYダウは7日続伸。前日比174.82ドル高の32,953.46ドルで取引を終了し、過去最高値を更新しました。前週に追加経済対策が成立し、景気回復期待から消費関連株中心に買いが入ったからです。米10年債利回りが1.6%台前半と横ばいで推移したことから、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数も、139.843ポイント高の13,459.708で取引を終了しています。ただ、投資家の関心は、今週おこなわれるFOMCに向かっています。今年に入り米10年債の利回りが大きく上昇していることから、米連邦準備制度理事会(FRB)がどのような見解を持っているかに注目が集まっているからです。しかし、恐怖指数と呼ばれるVIX指数は一時20を割り込んでおり、投資家心理は改善しています。長期金利のさらなる急上昇がない限り、NYダウはしっかりの展開が続くでしょう。本日の経済指標では、21時30分の小売売上高と22時15分の鉱工業生産に注目。また、米20年債の入札があるので関心が集まるでしょう。本日のNYダウは、節目の33,000ドルを突破できるかどうかに注目しています。16日の日経平均は続伸、TOPIXはバブル後最高値[東京 16日 ロイター] -東京株式市場で日経平均は6日続伸。一時3万円大台を回復した。TOPIXは2月16日に付けたバブル後最高値1974.99を1か月ぶりに更新。値がさのグロース株が全体の上昇を先導する格好となった。15日の米国株式市場は上昇。S&P総合500種とダウ工業株30種が終値で最高値を更新した。金利上昇への懸念が根強い中、市場は景気回復に期待しているという。ナスダック総合もしっかりだが、最高値まで距離を残している。これを受けて日本株は、前日の好地合いを引き継ぐ格好となり、上値を追ってスタート。ただ、物色面では直近物色されていたバリュー系の銘柄が一服する一方、半導体関連株を中心に値がさのグロース株が買われ、指数の上昇をリードする格好となった。日経平均は立ち会い時間中としては、2月25日以来となる3万円を回復。TOPIXはバブル後最高値を更新し1991年5月以来の水準となったが、FOMC(米連邦公開市場委員会)を控えていることから、徐々に模様眺めムードが支配し、後場に入ってからは動きに乏しい展開となった。市場では「前日の米国株式市場で投資家の恐怖感を示すVIX(ボラティリティーインデックス)指数が、ナスダックが調整に入る前の2月12日以来の低水準まで下落したことで、投資家心理が改善していることが読み取れる」(野村証券・投資情報部投資情報二課課長代理の神谷和男氏)との声も聞かれる。一方、きょう1部市場に新規上場したウイングアーク1stは買い気配でスタートし、公開価格を25.78%上回る2000円で初値を形成した。TOPIXは0.65%高。東証1部の売買代金は2兆9091億0600万円だった。東証33業種では、海運業、空運業、その他製品などが上昇し、鉄鋼、銀行業などの値下がりが目立つ。個別では、東京エレクトロンなど半導体関連株が買われたほか、ソフトバンクグループ、任天堂がしっかり。半面、トヨタ自動車、三菱UFJフィナンシャル・グループなどがさえない。東証1部の騰落数は、値上がり1529銘柄に対し、値下がりが592銘柄、変わらずが74銘柄だった。【市況】明日の株式相場に向けて=ビッグウェーブに乗る海運株 きょう(16日)の東京株式市場は、日経平均株価が154円高の2万9921円と6日続伸。今週は中銀ウィークということで、神経質な展開というよりは様子見ムードが拭えない状況であり、いずれにしても週前半に上値は追いにくいとみる向きが多かった。しかし、米国株市場は待ちきれないとばかりにNYダウとS&P500が最高値街道を驀進、調整局面入りが濃厚だったハイテク株比率の高いナスダック総合指数も直近は切り返し波動を鮮明としている。東京市場もそれに追随しないという選択肢はなく、日経平均、TOPIXともに上向きの5日移動平均線を絡め上値指向を明示。TOPIXは5日・25日移動平均線のゴールデンクロスを示現し、日経平均もゴールデンクロスが目前だ。 早い話、株式市場は見切り発車状態にある。パウエルFRB議長はハト派姿勢を明確に打ち出しているが、もはや“筋金入りの鳩”といってよい。あす17日に予定されるFOMC後の記者会見でどういうコメントを発するかにマーケットの関心が集中しているが、「(パウエル氏が)長期金利上昇を容認したと解釈され株式市場はいったん波乱含みとなった経緯があるが、これを踏まえて彼は何があっても同じ轍は踏まないと考えているのではないか。少なくとも今参戦している投資マネーはそうみている」とベテランの市場関係者は言う。 更に、今週後半は日銀の金融政策決定会合が開催される。最近はFOMCにばかりスポットライトが当たり、日銀の会合の方は最初から無風通過と決めつけられていたようなフシがあるが、少なくとも今回の会合はビッグイベントの名にふさわしい。金融政策の点検結果と称してテーパリングを匂わすであろうことは予想がつく。具体的にはETF買いの上限枠である年間12兆円の撤廃もしくは減額だが、既に1回当たりのETF買い入れ額縮小で、これ見よがしのステルステーパリングを行っており、市場はかなりの部分織り込んでいる。ETF買い入れについて、出口戦略を想起させるような内容とならない限り「寝耳に水」ということは全くない。 日銀のETF買いは2010年12月から始まったが、当初は年間4500億円が上限だった。それが、徐々に購入規模を拡大し約4年後の14年10月には3兆円に、更に16年7月には6兆円、そして昨年3月、コロナショック暴落に対応して12兆円に倍増させた。どう考えても今この水準に固執することに意味は感じられない。今年も既に3月半ばだが、日銀のETF買い累計は3500億円あまりにとどまっている。ちなみに保有残高は45兆円を超え、買いコストを差し引いた含み益は約10兆円に及んでいる。安物ヒーローの常套句ではないが「ピンチにはいつでも駆けつけるよ」で十分なのである。 個別株は引き続き海運株にビッグウェーブが訪れている。これは新型コロナワクチンの普及加速によってもたらされた経済活動正常化の流れが、グローバル物流を突き動かすとの思惑がベースとなっている。明治海運のストップ高だけならよくあることだが、物色の裾野がどんどん広がっており、文字通り流れ込む資金にウネリが生じている。前日紹介した大運はストップ高で買い物を残し、栗林商船も一時ストップ高目前まで上値を伸ばした。ちなみに大運は資本金こそ超小型だが流動性に富んでいて、意外に上値の重い銘柄であり、ここでの突発的なストップ高は相場の流れというよりない。同じ大阪銘柄では杉村倉庫などもマークしておくタイミングと思われる。 市況関連では鉄鋼株も強い。海運株同様に低PBR株の宝庫であり、中小型株では高周波熱錬や日亜鋼業のほか、ステンレス鋼商社のUEXなどにも目を配っておきたい。 あすのスケジュールでは、2月の貿易統計、2月の訪日外国人客数など。海外ではFOMCの結果発表とパウエルFRB議長の記者会見に注目度が高い。このほか2月の米住宅着工件数の発表など。(銀)出所:MINKABU PRESSNY株見通し-神経質な展開か 経済指標は2月小売売上高などトレーダーズ・ウェブ 今晩のNY市場はもみ合いか。昨日は経済活動正常化の恩恵を受ける空運やレジャー関連株が大幅高となったほか、金利上昇を嫌気して下落したハイテク・グロース株も買い直され主要3指数がそろって上昇。ダウ平均とS&P500の史上最高値更新が続いた。ダウ平均は昨年8月以来の7連騰を記録し、33000ドルに肉薄した。今晩の取引では連騰による高値警戒感の高まりが予想されるほか、翌日にはFOMC結果公表を控えており様子見姿勢が強まりそうだ。2月小売売上高などの経済指標の結果を受けた長期金利の動向を睨んだ神経質な展開か。 今晩の米経済指標は2月小売売上高、2月鉱工業生産、3月NAHB住宅市場指数など。企業決算は引け後にレナーが発表予定。(執筆:3月16日、14:00)〔NY外為〕円、109円近辺(16日午前8時)時事通信 【ニューヨーク時事】16日のニューヨーク外国為替市場の円相場は、午前8時現在1ドル=109円00~10銭と前日午後5時(109円08~18銭)比08銭の円高・ドル安で推移している。 ユーロは同時刻現在、対ドルで1ユーロ=1.1942~1952ドル(前日午後5時は1.1924~1934ドル)、対円では同130円16~26銭(同130円16~26銭)。(了)シクリカルバリューの代表「金融株」に本格上昇機運 <株探トップ特集>株探ニュース―世界的な金利上昇に再評価強まる、高配当利回りで買い好機に― 大手銀行株を中心とする金融株に物色機運が高まっている。足もとでは新型コロナウイルスに対するワクチン接種拡大で経済正常化期待が膨らみ、景気回復観測から長期金利が上昇し始めている。こうしたなか、三菱UFJフィナンシャル・グループ や三井住友フィナンシャルグループ など大手銀行株を中心とする金融株に対する見直し買いが本格化している。先行きの金利動向に不透明感は残るものの、割安放置されてきた 金融株の上昇余地は大きい。●銀行株上昇でTOPIXはいち早く2月高値抜く 株式市場では、出遅れの割安景気敏感株を買う動きが強まっている。その象徴がTOPIXの堅調さだ。この日、TOPIXは1981まで上昇と6連騰し、1991年5月以来、29年10ヵ月ぶりの高値圏に上昇した。日経平均株価は一時3万円を回復したものの2月高値奪回に手間取っているのとは対照的にいち早く調整から脱出した格好だ。日経平均株価がハイテクなど値がさ株の影響が高い指数なのに対し、TOPIXはメガバンクなど時価総額の大きな銘柄の寄与度が大きい。銀行株の上昇が貢献する格好で、市場からは同じく91年5月以来となる「TOPIXの2000乗せは近い」とみる声が出ている。●米長期金利は景気回復期待で上昇機運に 銀行株を中心とする金融株は金利上昇の追い風に乗っている。米国では、新型コロナウイルスに対するワクチン接種が進み経済正常化への期待が膨らんでいるほか、1兆9000億ドルの追加経済対策が成立したことで景気回復観測が強まり米10年債利回りは1.6%台に上昇した。新型コロナウイルスによる影響が懸念された2020年4月には0.5%前後の水準だっただけに、足もとの上昇は急ピッチだ。いちよしアセットマネジメントの秋野充成取締役は「米国の金利上昇は景気回復期待を背景にしたものであり、先行き2.5%前後まで上昇してもおかしくない」という。 この米国の長期金利上昇は銀行株には長短金利差の拡大となり業績回復期待が浮上。米国ではJPモルガン・チェースやシティグループ株が買われ、主要銀行などで構成するKBW指数は指数算出以来の最高値水準に上昇している。●「良い金利上昇」なら金融株には追い風 もちろん明晩に結果が発表される米連邦公開市場委員会(FOMC)や18~19日にかけての日銀金融政策決定会合の内容次第では、金利が大きく動くこともあり得る。ただ、足もとでNYダウが連日高で最高値を更新し日経平均株価が3万円を回復する動きは「金融当局の決定で、相場のトレンドが大きく変わることはないと判断した国内外の投資家の買い姿勢を反映したもの」(市場関係者)ともみられている。 市場の見方は、足もとの金利上昇は「景気回復を前提にした良い金利高」というものであり、そのなかでは、シクリカルバリュー(景気敏感の割安株)の代表である銀行株など金融セクターは絶好の買い場となる。前出の秋野氏は「短期的にはハイテク株の戻りが狙い目だが、業績回復が見込める銀行株は中長期的な投資妙味がある」とみている。●りそなHDや野村、T&D、アコムなど妙味も 今後、景気回復を背景にした良い金利上昇を迎えるのなら、三菱UFJや三井住友FG、みずほフィナンシャルグループ といった大手銀行株には再評価余地が広がる。三菱UFJや三井住友FG、みずほFGの配当利回りは4%台と高く、3月末の権利取りは絶好の投資機会となる。倒産リスクが抑えられ与信費用が低位で収まれば、金利上昇は長短金利差の拡大となり大手銀行株には追い風となる。中小企業や個人に強いりそなホールディングス なども再評価されそうだ。ただ、システム障害が続くみずほFGには、今後の業績面への影響を警戒する見方もある。 野村ホールディングス や大和証券グループ本社 といった証券株は、世界的な株高に伴い金融市場が活況となるなか、株価面での再評価余地は大きい。オンライン証券では、ビットコイン急騰による仮想通貨人気でマネックスグループ が大幅高となったが、SBI証券を傘下に持つSBIホールディングス や松井証券 にも出遅れ物色期待が強い。対面主体の岩井コスモホールディングス や丸三証券 なども上昇基調を強めている。 更に、生保では第一生命ホールディングス やT&Dホールディングス 、ノンバンクではオリックス やアコム 、みずほリース 、芙蓉総合リース 、業界再編機運が高まる地銀株ではコンコルディア・フィナンシャルグループ や静岡銀行 、千葉銀行 、名古屋銀行 などにも市場からはチャート妙味が指摘されている。〔NY外為〕円、109円近辺(16日朝)時事通信 【ニューヨーク時事】16日午前のニューヨーク外国為替市場では、米連邦準備制度理事会(FRB)の金融政策決定会合を控えて様子見ムードが広がる中、円相場は1ドル=109円近辺で推移している。午前9時現在は108円95銭~109円05銭と、前日午後5時(109円08~18銭)比13銭の円高・ドル安。 米商務省が朝方発表した2月の小売売上高(季節調整済み)は前月比3.0%減と、市場予想(0.5%減=ロイター通信調べ)を大きく上回る落ち込みとなった。これを受けて安全資産としての円が若干買われた。 この日から2日間の日程で行われる米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果を見極めたいとの思惑から動意は薄い。金利・経済見通しのほか、パウエルFRB議長の発言が焦点となっている。 ユーロは同時刻現在、対ドルで1ユーロ=1.1920~1930ドル(前日午後5時は1.1924~1934ドル)、対円では同129円90銭~130円00銭(同130円16~26銭)と、26銭の円高・ユーロ安。(了)〔米株式〕NYダウ、小反落=ナスダックは続伸(16日朝)時事通信 【ニューヨーク時事】16日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会(FRB)の金融政策発表を翌日に控えて様子見気分が強まる中、小反落して始まった。優良株で構成するダウ工業株30種平均は午前9時35分現在、前日終値比47.02ドル安の3万2906.44ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は続伸し、89.21ポイント高の1万3548.92。(了)〔米株式〕NYダウ、反落=ナスダックは続伸(16日午前)時事通信 【ニューヨーク時事】16日午前のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会(FRB)の金融政策発表を翌日に控えて様子見気分が強まる中、反落している。午前10時15分現在は、優良株で構成するダウ工業株30種平均が前日終値比80.35ドル安の3万2873.11ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数が114.04ポイント高の1万3573.75。 新型コロナウイルスワクチンの普及に伴って経済活動の規制緩和が進む中、景気の先行きに対する楽観的な見方が拡大。米金融市場では最近の株買い・債券売りの流れが続いているものの、ダウ平均は前日まで7営業日続伸した反動で、この日は調整の売りに押されている。一方、米長期金利は約1年ぶりの水準で高止まりしており、市場は景気の過熱や急激なインフレ高進を警戒。FRBが17日午後に公表する連邦公開市場委員会(FOMC)声明や最新の経済・金利見通しで、量的緩和縮小や利上げ時期の前倒しを示唆する可能性があるとして、やや神経質なムードが広がっている。 朝方に発表された2月の米経済指標は、小売売上高が2カ月ぶりにマイナスに転じたほか、鉱工業生産・設備稼働率もそろって市場予想を下回る低調な内容だった。 ダウ構成銘柄を見ると、ボーイングとシェブロンの下げがきつい。半面、アップル、インテルなどのハイテク関連企業に活発な買いが入っている。(了)本日の東京市場ではチェック中の日本株30銘柄中の19銘柄が値を上げて終了しましたね。重点6銘柄では3銘柄が値を上げて終了しましたね。レノバが上げましたね。今夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中の15銘柄が値を上げてスタートしましたね。スタートの時点では5%以上の大きな変動は見られませんね。FOMCを前にして様子見ムード、長期債の利率アップで株価低迷下と思ってのハイテク・グロース株を中心とした買い入れ作戦は現状では厳しいかな…。しばしの様子見ですな…。
2021.03.16
コメント(0)
-

3月15日(月)…
3月15日(月)、晴れです。気持ちの良い青空が広がります。そんな本日は7時頃に起床。PGAツアーはジャスティン・トーマスの優勝ですね。新聞がないので、朝食を済ませ、ロマネちゃんと戯れる。本日は三十五日目の法要なので、住職さんを迎える準備を…。しばらくするとお寺から電話で、遠方の葬儀のために本日はお休みさせていただくとのこと…。あらら…。1階の掃除機は済んだのでノルマ完了か…。朝のコーヒーブレイクはネスプレッソで…。今朝からチョコレートはピエール・ルドンとなりました。美味い!!今週のたなくじは…よしよし!!1USドル=108.99円。1AUドル=84.67円。現在の日経平均=29843.69(+125.86)円。金相場:1g=6713(+31)円。プラチナ相場:1g=4723(+33)円。本日の東京市場ではチェック中の日本株30銘柄中の24銘柄が値を上げてスタートしましたね。重点6銘柄ではすべてが値を上げてスタートしましたね。テクノホライゾン、OKI、日本コンクリートが上げていますね。英アストラゼネカ、ワクチンと血栓の因果関係示す「証拠なし」[14日 ロイター] - 英製薬大手アストラゼネカは14日、同社が英オックスフォード大学と開発した新型コロナウイルスワクチンの接種データを検証した結果、血栓との因果関係を示す証拠は見つからなかったと発表した。同社は欧州連合(EU)と英国で同社製ワクチンを接種した1700万人以上のデータを検証。その結果、「どの年齢層、性別、バッチ番号、国についても、肺塞栓症、深部静脈血栓症、血小板減少症のリスクが高まったと示す証拠は見つからなかった」とした。アイルランド、デンマーク、ノルウェー、アイスランドの当局は、同ワクチンの接種後に血栓ができる事例が報告されたことを受け、接種を一時中止。オーストリアは接種後に1人が死亡したため、国内接種を一時中断して調査を行っている。欧州医薬品庁(EMA)は同ワクチンと血栓の因果関係は示されていないとの見解を示しており、世界保健機関(WHO)もまた、12日に同様の見方を表明した。アストラゼネカによると、これまでに深部静脈血栓症の事例が15件、肺塞栓症が22件報告されているが、他の使用許可を受けているワクチンと状況はあまり変わらないという。また、同社と欧州保健当局が追加の試験を行っているが、懸念材料は出ていないとした。アストラゼネカ製ワクチンはEUや多数の国で使用許可が下りているが、米国ではまだ許可されていない。同社は今月終盤もしくは4月初旬をめどに、同ワクチンの緊急使用認可を米食品医薬品局(FDA)に申請する用意を進めていると、関係筋が12日明らかにした。アストラゼネカのワクチン、EU域内で使用停止広がる-副反応受け(ブルームバーグ):英アストラゼネカ製の新型コロナウイルスワクチンを巡り、安全性への懸念から使用を見合わせる動きが欧州で広がっている。また同社製ワクチンの供給に一段の遅れが生じる中、世界各国では既に確保した分を保持しようとする動きが強まっている。 欧州では既に10カ国余りがアストラゼネカ製ワクチンの接種を中断しており、14日には新たにアイルランドも使用を停止した。2回必要な接種で起こり得る副反応への懸念が背景にある。欧州医薬品庁(EMA)は問題の兆候はないとしているが、接種後に深刻な血栓の問題が生じたとの報告が複数寄せられたことから、タイなど欧州域外でも使用を中断する動きが見られている。 アストラゼネカ製ワクチンを巡っては既に供給面で問題が発生している。同社は欧州連合(EU)内での供給不足分を域外から調達しようとしているが、各国は自国への供給分を保持しようとする動きを強めており、同社の取り組みは難航している。アストラゼネカ製ワクチンの緊急使用許可がまだ下りていない米国も、既に確保している分を保持すべく出荷要請に応じていない。 こうした状況を背景にアストラゼネカ製ワクチンを巡る動きはEUで大きな政治問題となっている。一方、EUはワクチン接種で英国と米国に大きく後れを取りつつある。 ワクチン生産が計画に追いついていないことに加え、オランダのある工場は当局による許可をなお待っている状態だ。この工場はオランダ企業ハリックスが保有し、アストラゼネカ向けにワクチンの成分を生産。EUと英国の両方でサプライチェーンの一部となっている。 アストラゼネカの広報担当は承認のタイミングについて、当初の計画通りであり、EUへの配布に何ら影響していないと説明。ハリックスには通常の営業時間外に連絡を取ったが、これまで返答はない。コロナワクチン「副反応は女性に多い」~福井勝山総合病院の副院長が指摘福井テレビ新型コロナウイルスワクチンの先行接種が進む福井勝山総合病院の調査で副反応は女性に多いことが分かった。先行してスタッフへの接種が始まった福井勝山総合病院。県内で最初に接種を受けた須藤弘之副院長が14日朝放送の福井テレビ報道番組「タイムリーふくい」に出演して、指摘した。同病院で接種を受けた約270人の調査結果によると、頭痛や倦怠感など全身の症状が出た人が1割前後でほとんどが女性だった。また、男女問わず腕の痛みを訴えた人が9割近くいた。ただ、アナフィラキシーなど深刻な症状が出たり、仕事や生活に支障が出たりしたケースはなかった。【今朝の5本】仕事始めに読んでおきたいニュース 英アストラゼネカ製の新型コロナウイルスワクチンを巡り、安全性への懸念から使用を見合わせる動きが広がっています。同社ワクチンは出荷も遅れており、欧州では大きな政治問題となっています。そんな中、ドイツでは与党が地方選で大敗を喫しました。以下は一日を始めるにあたって押さえておきたい5本のニュース。 使用停止欧州では既に10カ国余りがアストラゼネカ製ワクチンの接種を中断しており、14日には新たにアイルランドも使用を停止した。欧州医薬品庁(EMA)は問題の兆候はないとしているが、接種後に深刻な血栓の問題が生じたとの報告が複数寄せられたことから、タイなど欧州域外でも使用を中断する動きが見られている。同社は14日、血栓のリスクを高めるとの証拠はないと反論した。 歴史的大敗ドイツ2州で州議会選挙が行われ、メルケル首相率いる与党キリスト教民主同盟(CDU)が戦後最悪の敗北を喫した。新型コロナへの対応とワクチン接種ペースの遅さを巡る政府への不満が選挙結果に表れた。出口調査によると、バーデン・ビュルテンベルク州でCDUの得票率が低下した一方、「緑の党」は票を伸ばして第1党の座を堅持した。ラインラント・プファルツ州でもCDUは得票率が低下した。 理解に苦しむ米国立アレルギー感染症研究所(NIAID)のアンソニー・ファウチ所長は、一部の人が新型コロナワクチン接種に消極的なことが感染を制御する上で大きなリスクになっていると指摘した。特に男性の共和党支持者の多くがワクチン接種を望んでいないとの世論調査結果について問われ、「理解に苦しむ」と回答。「常識や頭を悩ませるほどもない問題から政治的信条は切り離す必要がある」と述べた。 制御可能イエレン米財務長官はインフレリスクについて、「小さなリスクはあるが、制御可能だと私は考えている」と説明。物価の一部は回復するものの、「それは一時的な動きだ」と述べた。労働市場については、「パンデミックを打ち負かせば、来年に完全雇用に近い状態に戻れると期待している」と述べた。 金利上昇に動じず株式市場のプロは、金利上昇に伴うボラティリティーの高まりに動じていない。ブルームバーグ・ニュースが市場関係者を対象に実施した調査によると、利回り上昇ペースとその理由を注視しているとしつつも、株式相場の転換点となるような特定の水準到達を警戒して待ち構えているわけではない。彼らが注目しているのは、経済と企業利益の力強い回復だ。主要中銀が緩和的な金融政策を続ける限り、株式の強気相場は今後も前進できるとみている。寄り付きの日経平均は続伸、米株の動きが安心感誘い幅広く物色[東京 15日 ロイター] - 寄り付きの東京株式市場で、日経平均は前営業日比86円67銭高の2万9804円50銭となり、続伸してスタート。前週の米国株式市場が長期金利が上昇しているのにもかかわらず堅調な動きとなったことが安心感を誘い、主力銘柄を中心に幅広く物色された。ただ、米株では大型のハイテク株が軟化したことを受け、半導体関連など値がさのグロース株にさえない銘柄が目立つ。米金融当局は23年に利上げへ、金利予測分布図には示されずともエコノミスト調査見通しブルームバーグ新型コロナウイルス禍による不況からの力強い景気回復で米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長ら当局者は2023年に利上げに動く可能性が高いが、今週の連邦公開市場委員会(FOMC)が公表する予測にはそれは示されない。エコノミスト調査でこうした見通しが示された。ブルームバーグ・ニュースが調査したエコノミスト予想では、23年は0.25ポイントの利上げが2回。ただ、FOMCが米東部時間17日午後2時(日本時間18日午前3時)に声明とともに公表する政策金利予測の中央値は同年末までゼロ付近になるとエコノミストは予測している。こうしたエコノミスト調査の結果は、米金融当局の昨年12月の予測に一致する。その後、バイデン大統領による3月11日の署名で成立した1兆9000億ドル(約207兆円)規模の追加経済対策を含め、3兆ドル近い財政出動を議会が承認し、ワクチン接種の加速が経済見通しが改善しているにもかかわらずだ。「強力な3要素」調査に回答した米ポイント・ロマ・ナザレン大学のエコノミスト、リン・リーサー氏は、「巨額の財政出動と金融支援、累積需要の強力な3要素がワクチン接種の普及で自由になった経済に影響を及ぼすという未知の状況を、米金融当局は今調査している」と指摘した。FOMCが今年2回目となる今週の会合で、政策金利をゼロ付近に維持し、資産購入ペースを現行の月額1200億ドルに据え置くのはほぼ確実。パウエル議長は当局の目標とする完全雇用に依然として程遠いと繰り返し強調し、金融支援の縮小議論は時期尚早としている。それでも、エコノミストの4分の3は23年末までの利上げを予測しており、利上げ幅予想の中央値は約0.5ポイント。一方、ブルームバーグが昨年12月に実施した調査の中央値では、24年ないしそれ以降まで政策金利の据え置きが見込まれていた。ブルームバーグ・エコノミクスのエコノミスト、カール・リカドンナ氏は、「経済予測に変化はあるだろうが、金利予測はあまり動かないだろう」と述べ、金利予測分布図の「ドットが幾つか上昇修正されるかもしれないものの、出口スケジュールの変化を認めないという点でFOMCの予測中央値は現状維持となろう」との見方を示した。寄り付き直後の日本株は小幅続伸、円安推移も追い風自動車や銀行、鉄道などに買いブルームバーグ15日の東京株式相場はTOPIXが小幅に続伸。米長期金利の急上昇への市場の許容度が高まり、景気回復が意識されて相場を押し上げている。また、首都圏での緊急事態宣言が来週で解除の方向と伝わり、改めて経済活動の拡大に対する期待が高まっている。円安推移も追い風で、自動車や銀行、鉄道などに買いが入っている。・TOPIXは前日比5.07ポイント(0.3%)高の1856.13-午前9時8分現在・日経平均株価は25円18銭(0.08%)高の2万9743円01銭〈きょうのポイント〉・1都3県の緊急事態宣言を21日解除へ、病床指標が改善傾向-報道・イエレン財務長官、米国のインフレリスクは小さく「制御可能」・S&P500とダウ平均は連日で最高値・ナスダックは反落-米10年債利回り急上昇で東海東京調査センターの平川昇二チーフグローバルストラテジストは、前営業日の米国市場では米国長期金利が急上昇しても指数が最高値を付けるなど、株価へのマイナスの影響は織り込まれつつあり「日本株にとっては景気回復を示唆するとしてプラスに働くだろう」と指摘。また、来週で緊急事態宣言が解除となれば経済活動の拡大につながるとして、「景気に敏感な業種に買いが入りそうだ」と話した。一方で、日経平均株価はソフトバンクグループのほか、東京エレクトロンやアドバンテストなど大型の半導体製造装置メーカー株が売られ、一時下落に転じる場面もあった。・東証33業種では海運、鉄鋼、銀行、繊維製品、非鉄金属、輸送用機器が上昇率上位・情報・通信、電機は下落【市況】前場に注目すべき3つのポイント~年度末接近ながらも押し目買い意欲は高まりやすい~15日前場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。■株式見通し:年度末接近ながらも押し目買い意欲は高まりやすい■シャープ、3Q営業利益0.4%増 620億円、コンセンサス上回る■前場の注目材料:日米豪印、海洋安保で協力、中国念頭、初の首脳声明■年度末接近ながらも押し目買い意欲は高まりやすい15日の日本株市場は、利食い優勢ながらも底堅い相場展開が見込まれそうである。12日の米国市場ではNYダウが293ドル高と連日で最高値を更新する半面、ナスダックは下落した。1.9兆ドル規模の追加経済対策法案の成立後、バイデン大統領は11日夜の演説で5月1日までにワクチン接種の対象を全成人に拡大、独立記念日7月4日までには正常化を目指す方針を示したため景気循環株中心に買われた。一方で、長期金利が再び上昇したためハイテク株に売りが広がっていた。シカゴ日経225先物清算値は大阪比50円安の29540円。円相場は1ドル109円00銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする格好からやや利食い優勢の展開から始まりそうである。しかし、先週末には500円を超える上昇をみせていたこともあり、一定の利益確定の流れは想定されるところであろう。長期金利上昇を警戒したハイテク株への利食いが意識されやすく、日経平均の重荷となりそうだ。しかし、先週のナスダックは12600Pt割れの水準から11日には13400Ptを超えるリバウンドをみせていたこともあり、上値抵抗として意識されていた25日線に接近していたことから、12日の下落については想定の範囲内であろう。また、VIX指数は低下していることもあり、売り一巡後は底堅さが意識されてくる可能性はあるとみておきたい。日経平均は先週末の上昇で29700円を回復し、上値抵抗として意識されていた25日線を突破している。25日線は29500円近辺に位置していることもあり、まずは同線を支持線として機能させてくるかが注目されるところである。同線での底堅さが意識されるようであれば、年度末接近で積極的には手掛けづらいものの、押し目買い意欲は高まりやすいとみておきたい。また、週末にリバウンドをみせていたマザーズ指数は75日、25日線が射程に入ってきているが、米国の追加経済対策法案の成立によりロビンフッターと呼ばれる個人投資家の売買が再燃しやすいほか、ビットコインが高値を更新していることもあり、中小型株への物色が再燃しやすいところである。また、FOMCや日銀会合を受けた市場反応を見極めたいとする模様眺めムードも意識されやすいなか、個人主体の資金は中小型株への物色に向かわせやすいだろう。■シャープ、3Q営業利益0.4%増 620億円、コンセンサス上回るシャープが発表しただ3四半期業績は、売上高が前年同期比3.8%増の1兆8168.60億円、営業利益は同0.4%増の620.11億円だった。営業利益はコンセンサス(595億円程度)を上回っている。新型コロナウイルス禍で車載向け液晶パネルの販売などが落ち込んだほか、持ち分法適用会社の堺ディスプレイプロダクトの減損処理で158億円の持ち分法投資損失を計上。衛生意識の高まりで空気清浄機が好調だった。■前場の注目材料・日経平均は上昇(29717.83、+506.19)・1ドル109円00-10銭・NYダウは上昇(32778.64、+293.05)・VIX指数は低下(20.69、-1.22)・日銀のETF購入・海外コロナワクチン接種の進展・世界的金融緩和の長期化・日米豪印、海洋安保で協力、中国念頭、初の首脳声明・五輪会場、観客50%上限、最大2万人、来月中に基準・終電、首都圏最大35分早く、JR一斉ダイヤ改正・中絶に夫の同意求めず、厚労省指針、DVなど婚姻破綻想定・復興住宅、増える空室、自治体に負担☆前場のイベントスケジュール<国内>・08:50 1月機械受注(船舶・電力を除く民需)(前月比予想:-5.5%、12月:+5.2%)<海外>・11:00 中・1-2月鉱工業生産(前年比予想:+32.2%)・11:00 中・1-2月小売売上高(前年比予想:+32.0%)《ST》 提供:フィスコJ・トーマスが逆転で“第5のメジャー”を制す 「タイガーも喜んでくれていると思う」<ザ・プレーヤーズ選手権 最終日◇14日◇TPCソーグラス(米フロリダ州)◇7189ヤード・パー72>“第5のメジャー” 「ザ・プレーヤーズ選手権」最終日。首位と3打差のトータル10アンダー・3位タイからスタートしたジャスティン・トーマス(米国)が、トータル14アンダーまでスコアを伸ばし、昨年8月の「WGC-フェデックス・セントジュード招待」以来のツアー通算14勝目を挙げた。トーマスは8番パー3でボギーが先行。しかし、ここで火が付いたのか怒濤のゴルフを見せる。9番パー5ではグリーンの右サイドの傾斜を利用して2オン・2パットのバーディ。10番パー4では、残り131ヤードからウェッジで打ったセカンドショットをバックスピンで戻して2メートルにつけ、連続バーディを奪った。そして11番パー5では、残り240ヤードから2オンに成功。6メートルのイーグルパットを沈めてトータル13アンダーとし、首位のリー・ウェストウッド(イングランド)を一気に逆転、単独首位に立った。続く12番パー4でもバーディを奪い、9番からの4ホールで5つスコアを伸ばした。14番パー4の3パットで1つ落とし、一度はウェストウッドが並ばれたが、16番パー5では再び2オンに成功してバーディを奪い、後続を突き放した。18番ホールではティショットがあわや池ポチャかと思われたがギリギリで左サイドに残り、きっちりパーセーブ。“第5のメジャー”のタイトルを手中に収めた。トーマスはこれで四大メジャー、世界ゴルフ選手権、フェデックスカップ王者、そしてザ・プレーヤーズ選手権のタイトルを獲得。これはタイガー・ウッズ(米国)、ヘンリック・ステンソン(スウェーデン)、ローリー・マキロイ(北アイルランド)に続く4人目の快挙となった。トーマスはプレー後のインタビューで「プレーヤーズに勝てて本当にうれしい。きょうは辛抱強くプレーできた。ショットはいままでで一番良かった」と試合を振り返った。さらにプライベートでも親交がある療養中のタイガー・ウッズ(米国)についても触れ、「タイガーがいままで言ってくれたことを思い出しながらプレーした。彼が早く健康になることを祈っている。私の優勝を見て喜んでいると思う」とコメントした。前週に引き続き最終日を首位でスタートしたウェストウッドは、4バーディ・4ボギーの「72」とスコアを伸ばすことができず、2試合連続で悔しい1打差の単独2位。前週の「アーノルド・パーマー招待」に勝ち、2試合連続優勝がかかっていたブライソン・デシャンボー(米国)は、ブライアン・ハーマン(米国)と並んでトータル12アンダー・3位タイに終わった。【M3と同じ直6と8速AT】BMW M4 コンペティションへ試乗 最新G82型 不思議な違和感午後からは郵便局や銀行を回る…。おやつタイムはコーヒーとレーズンウィッチをいただく。本日の東京市場ではチェック中の日本株30銘柄中の26銘柄が値を上げて終了しましたね。重点6銘柄ではすべてが値を上げて終了しましたね。テクノホライゾン、OKI、日本コンクリートが上げていますね。日本株は5日続伸、米金利上昇許容や経済拡大期待-海運や空運高い 15日の東京株式相場は5日続伸。米長期金利急上昇への市場の許容度が高まり、景気回復が意識されて相場を押し上げた。首都圏での緊急事態宣言が来週で解除の方向とも伝わり、改めて経済活動の拡大に対する期待から空運や海運などの業種が上昇した。円安推移は自動車など輸出株を押し上げた。 TOPIXの終値は前日比17.67ポイント(0.9%)高の1968.73 日経平均株価は49円14銭(0.2%)高の2万9766円97銭 〈きょうのポイント〉 1都3県の緊急事態宣言を21日解除へ、病床指標が改善傾向-報道 イエレン財務長官、米国のインフレリスクは小さく「制御可能」 S&P500とダウ平均は連日で最高値 ナスダックは反落-米10年債利回り急上昇で 中国経済指標、1~2月は大幅なプラス-落ち込んだ1年前の反動も 銀行株が高く、TOPIXを押し上げた。日経平均株価も一時マイナスに転じながら上昇を維持した。日本郵政との資本提携を発表した楽天株が大幅高だった一方、ソフトバンクグループや東京エレクトロン、アドバンテストなど値がさハイテク株は値下がりした 水戸証券投資顧問部の酒井一チーフファンドマネジャーは、米長期金利はピークを越えてグロース(成長)株への売りが止まったようにみえたとしながら「米FOMCを控えてボラティリティが高まる可能性に警戒した売りが上値を押さえている」と述べた。 東証33業種では海運、空運、銀行、鉄鋼、輸送用機器が上昇率上位 情報・通信、電機が下落ナスダック100に弱気シグナル-急落あり得る兆候とガンドラック氏 テクノロジー株中心の米ナスダック100指数は2月の高値からの下げ1兆5000億ドル(約164兆円)の半分を一時は回復したが、反発の持続をアナリストらは疑問視している。 懸念は債券市場から来ている。債券利回り上昇はテクノロジー株などの割高な株価への圧力になる。10年物米国債利回りが50ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇するとナスダック100の弱気相場入り、つまり20%の下落につながり得るとのネッド・デービス・リサーチの調査もある。 投資家はエネルギーなど景気回復の恩恵を受ける銘柄を選好し、テクノロジー株に背を向ける。このローテーションの影響を測る指標の一つが、S&P500種に対するナスダック100の割高度合を示す数字だ。この差は2000年のピークを短期間上回った後、最近は縮小している。ヘッジファンド運用のダブルライン・キャピタル創業者ジェフリー・ガンドラック氏も、次の急落が起こり得る兆候だと指摘する。 ナスダック100は9日に4%、11日に2.4%上昇したおかげで先週、週間ベースで4週間ぶりに上げたが、下落局面での単日の反発は珍しくない。 マーケットフィールド・アセット・マネジメントのマイケル・シャウル最高経営責任者(CEO)は「弱気相場の初期段階には大きく反発する日が混じるものだが、最終的に重要なのは上昇の持続性であって1日の上昇幅ではない」と述べ、「テクノロジーセクターが遂に株式市場のリーダーとしての地位を放棄したことを示す証拠は増え続けている」と指摘した。【米国株動向】エヌビディアはグラフィックカードでAMDを上回り続けているモトリーフール米国本社、2021年3月14日投稿記事よりAMD(NASDAQ:AMD)が最善の努力をしているにもかかわらず、競合のエヌビディア(NASDAQ:NVDA)はディスクリートグラフィックスカード市場を支配しています。さらに、AMDはGPUの覇権をめぐる戦いでも遅れをとっており、今後エヌビディアはAMDにさらなる打撃を与える可能性があります。 AMDへの打撃調査会社のJon Peddie Researchの2020年第4四半期のGPU市場のレポートでは、エヌビディアは、ディスクリートGPU市場の82%を独占しており、前年同期の73%から拡大しています。エヌビディアのグラフィックカード市場のシェアは、一年前は70%を下回っており、AMDのシェアを取り戻した形になります。一方AMDは、エヌビディアと比較してサプライチェーンの面で大きな問題を抱えています。これらの要因は、エヌビディアが今後もGPU市場のシェアをAMDから獲得するのを支える可能性があります。その理由を見てみましょう。 エヌビディアはグラフィックカードの需要を取り込むために全力を尽くすグラフィックカードは、圧倒的な需要とコンポーネントの不足のために供給が追いついていません。エヌビディアは、2月24日の決算電話会議で、供給を増やす努力をしているにもかかわらず、「チャネル在庫は第1四半期を通して低いままである可能性が高い」と認めました。またAMDは、2021年上期まで供給をそれほど提供できないことを見込んでいます。JPモルガンは、GPUの供給が需要に追いつくまでに3〜4四半期かかる可能性があり、在庫が通常レベルに達するまでに、さらに2〜3四半期かかる可能性があると見積もっています。ただし、エヌビディアはこの供給不足を克服するための戦略を展開しています。同社は、エンドマーケットの需要に対応するために、旧世代のグラフィックカードの生産を増やしています。エヌビディアが供給を増やすために行っているもう1つの方法は、専用の暗号通貨マイニングプロセッサ(CMP)を使用することです。エヌビディアは、このCMPは、ディスプレイ出力がないため、「グラフィックスを実行しない」プロ向けであると説明しました。CMPはマイニング効率を高めるために、ピーク電圧と周波数が低くなっています。これらは、エヌビディアがビデオゲーム市場のシェアを広げ、AMDに対するリードを拡大するのに役立つはずです。ビデオゲーム事業は前四半期に25億ドルの売上高を上げ、エヌビディアの総売上高が前年比61%増の50億ドルを達成するのを牽引しました。また、エヌビディアは、今四半期に前年比72%増の53億ドルに達することを予想しています。GPU市場のシェアを獲得するために展開している戦略のおかげで、エヌビディアのビジネスはさらに大きくなる可能性があると言えるでしょう。アングル:グロース安・バリュー高の二極化、デフレ脱却織り込みの見方も[東京 15日 ロイター] - 昨年来の上昇相場をリードしてきた値がさグロース株の厳しい下げが止まらない。米国株式市場で大型ハイテク株が下落したことを受けた動きだが、一方ではワクチン接種に伴う経済正常化期待からバリュー株物色が活発化するなど物色面での二極化が鮮明になってきた。こうした一連の動きについて、金融相場から業績相場への移行を象徴するとともに、その先にあるデフレ脱却を織り込み始めたとの指摘もある。12日の米国株式市場では、ダウ工業株30種が5日連続で最高値を更新しながらも、楽観的な米景気見通しから米10年債利回りが再び上昇する中でインフレ高進懸念が再燃、大型ハイテク株が下落しナスダック総合は反落した。これらを受けて日本株でも、東京エレクトロン、SCREENホールディングス、信越化学工業などの半導体関連株のほか、キーエンス、任天堂も売り優勢となっている。象徴的なのは機械株で、寄り付き前に発表された1月機械受注が予想を上回ったことから、比較的低位の工作機械株は総じて堅調となったが、ファナック、SMCなど値がさ株は軟化した。日米ともに、これらグロース株と言われる銘柄群に、悪材料が出た訳ではない。それでも下げたのは、米長期金利の上昇で、PER(株価収益率)が高い米国の大型ハイテク株の相対的な割高感が意識されていることが背景にあるという。また、日本のグロース株に関しては「昨年の上昇相場で内外機関投資家が腹いっぱい買っていたため、利益確定の動きが断続的に出ているようだ」(国内証券)との声が聞かれる。とくに、国内の値がさグロース株は、昨年3月の株価水準が極めて安い水準だったことで、いつでも利益確定できることが、期末を控えたこのタイミングで需給面のあだになった格好だ。こうした動きの一方で、銀行株や鉄鋼株などを中心にバリュー株、出遅れ株に物色の流れがシフト。値がさ株の下落で日経平均の動きが伸び悩む中で、バリュー株の堅調からTOPIXの値上がり率が大きくなっている。「経済正常化に伴う景気回復が前面に押し出されるような物色動向となる」(野村証券・エクイティ・マーケットストラテジストの澤田麻希氏)一方で、過剰流動性が支えになっていたグロース株が売られることで、市場では金融相場から業績相場に移行しているとみる関係者が多い。また「本来なら金利が上昇に転じる初期局面では、企業業績の好調を示すものであり、ここでの株価上昇はロジックとして成り立つ」(三菱UFJモルガンスタンレー証券・チーフ投資ストラテジストの藤戸則弘氏)と指摘されるだけに、業績上向きという実態の裏付けが十分なグロース株も期末接近に伴う決算対策売りが一巡した後は、再び物色される期待もある。一方、最近のバリュー株物色においては、PBR(株価純資産倍率)が1倍割れの銘柄の修正高が目立つ。これについて岡地証券・投資情報室長の森裕恭氏は「PBR1倍割れの銘柄が多かったのは、デフレ下で資産持ちの会社は買えないというロジックがあることが大きい」と指摘した上で「先行き日本で長期金利が上昇に転じた場合は、デフレ脱却が期待されるようになるため、米長期金利が上昇したここで、業績相場への移行とともにデフレ脱却を織り込み始めた可能性もある」とコメントしていた。午後3時のドルは一時109.35円、9カ月ぶり高値[東京 15日 ロイター] -午後3時のドル/円は、前週末ニューヨーク市場の午後5時時点から小幅高の109円前半。米国金利の上昇を受けて9カ月ぶり高値を更新した。ドル/円は週明けも「米金利にらみの展開」(外銀)。アジア時間の取引で米10年国債利回りが1.60%台まで低下するとドルも108.92円まで下落したが、その後1.63%台へ切り返すとドルも109円台へ反発した。午後3時過ぎには一時109.35円まで上昇し、昨年6月8日以来の高値をつけた。円安進行の側面を指摘する声もあった。日銀が19日に発表する金融緩和策の「点検」では、上場投資信託(ETF)の購入を市場環境に合わせて調整する方法に変更する可能性があるとして「思惑的な円売りが広がる余地がある」(外為アナリスト)という。商品先物取引委員会(CFTC)が発表したIMM通貨先物の非商業(投機)部門の取組によると、3月9日時点の円ロングは6514枚と、前週の1万9270枚から大幅に縮小した。「買い持ちの取り崩しによる円売りはほぼ一巡した。これから円安進行のピッチは緩むのではないか」(別の外銀)との指摘もあった。三井住友FGなど銀行株が軒並み高、金利上昇に加え配当狙いも三井住友フィナンシャルグループ(8316)が2020年1月9日につけた昨年来高値をおよそ1年2カ月ぶりに更新してきたほか、三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306)、りそなホールディングス(8308)、千葉銀行(8331)、岩手銀行(8345)、大分銀行(8392)など地銀株を含めて銀行株がほぼ軒並み高。三井住友FGは午前9時58分時点で前週末比97円(2.4%)高の4093円で売買されている。アメリカで1.9兆ドル規模の追加経済対策が成立したことに加え、世界的に新型コロナウイルスのワクチン普及が進んで経済正常化への道筋が見えてきた。これに伴って12日のアメリカ債券市場では長期金利の指標となる10年物国債の利回りが前日比0.08%高い1.62%で取引を終了。一時は2020年2月以来となる1.64%をつけた。日本や欧州でも金利は上昇傾向にあり、今後の資金利ザヤの改善が期待できるという見方から銀行株には見直しが増えている。メガバンクを中心に高い配当利回りも魅力で3月期末を控えて配当狙いの動きも強まっているようだ。(取材協力:株式会社ストックボイス)原油相場が一時66ドル突破、景気回復を材料視「OPECプラス」の減産維持も寄与ブルームバーグ原油相場が週明け15日午前のアジア時間帯の取引で一時1バレル=66ドルを上回った。新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)からの一段の回復見通しや、石油輸出国機構(OPEC)と非加盟の主要産油国で構成する「OPECプラス」の減産維持に伴う世界的な需要拡大の見込みが材料視された。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物4月限は一時0.8%高。シンガポール時間午前7時39分(日本時間同8時39分)現在では0.6%高の66.03ドル。ICEフューチャーズ・ヨーロッパの北海ブレント先物5月限は一時0.6%高の69.60ドル。新型コロナウイルスによる米死者数が週間ベースで4カ月ぶりの低水準となり、新たな感染者数も減少していることで、米国のエネルギー消費の見通しが押し上げられた。ただ香港での新たな感染拡大などアジア太平洋の一部で懸念はある。先週はワクチン普及に後押しされたパンデミックからの回復や供給抑制を維持するOPECプラスの決定という年初来の材料に加え、サウジアラビアの石油インフラに対するイエメンの武装組織フーシ派の攻撃拡大が原油相場を押し上げ、 北海ブレント先物は一時71ドルを上回った。明日の戦略-後場伸び悩むも5日続伸、TOPIXの昨年来高値更新に安心感トレーダーズ・ウェブ 15日の日経平均は5日続伸。終値は49円高の29766円。上昇スタートも早々に失速してマイナス圏に沈んだが、押し目ではすぐに買いが入って盛り返した。ただ、そこから上げ幅を3桁に広げると伸び悩んだ。米国の物色動向を受けて景気敏感株には買いが入った一方、ハイテク株は売りに押された。後場は前引けから水準を切り下げて始まった後に再び下げに転じるなど、上値の重さが鮮明となった。ただ、前場同様にマイナス圏での時間帯は短く、プラス圏に再浮上した後は小高く推移した。値上がり銘柄は多く、TOPIXが終値で昨年来高値を更新。一方、マザーズ指数は序盤に下げに転じた後は、マイナス圏が定着した。 東証1部の売買代金は概算で2兆9300億円。業種別では海運、空運、銀行が強い上昇。下落は情報・通信、電気機器の2業種のみで、機械の上昇が限られた。ビットコインの6万ドル乗せを手掛かりに、マネックスグループが急騰。半面、1Qが最終赤字となったオハラが急落した。 東証1部の騰落銘柄数は値上がり1800/値下がり338。日本郵政Gとの資本業務提携を正式発表した楽天がストップ高。米国の長期金利上昇上昇を材料に三菱UFJや三井住友など銀行株が大幅高となり、ドル高・円安を材料にホンダやトヨタなど自動車株が買いを集めた。日本郵船、川崎汽船、商船三井の海運大手3社は上を試す流れが続き、そろって昨年来高値を更新。日経新聞の藻類培養に関する記事を受けてユーグレナが急伸した。決算では東建コーポレーションや山王が大幅高。リストラに絡む損失を計上しながらも通期の見通しを引き上げた日本アビオニクスは、買いが殺到してストップ高比例配分となった。 一方、ナスダック安が嫌気されて、ソフトバンクGが2%を超える下落。東京エレクトロンや日本電産などハイテク株も売られるものが多かった。メルカリ、BASE、フリーなどマザーズの主力どころが弱く、直近IPOのQDレーザはマザーズトップの売買代金で7%を超える下落。ストリームやヤーマンは決算が売りを誘って急落した。 週明けの日経平均は概ね堅調で、これで5日続伸。値上がり銘柄の多さの割に小幅な上昇となったが、過熱感が高まらなかったという点ではポジティブと言えなくもない。どのみち3万円に近付けば戻り売りは出やすくなる。FOMCや日銀会合を通過しての節目超えであれば売りは手控えられるだろうが、このタイミングでは単に振れ幅が大きくなるだけの可能性もある。そのような中、TOPIXが終値ベースで昨年来高値を更新してきたことは特筆される。しかも後場に日経平均がダレる中での高値引け。バリュー系銘柄の上昇はまだ続くとの期待を高める動きと言え、全体としても下値不安が大きく後退することになるだろう。TOPIXは取引時間中の昨年来高値1974p(2/16)を超えて、2000pを目指しに行ってほしいところ。そういった動きが見られれば、日経平均がこの先、再度3万円台を超えてきたとしても天井感は高まらず、中期での上昇トレンドに変化なしとの見方が強まるだろう。なお、あすは2社が新規上場するが、3月末までの残り12営業日で13銘柄のIPOが予定されている。短期志向の投資家がこちらに流れやすくなることを鑑みると、マザーズの主力どころを敬遠する傾向はもうしばらく続く可能性がある。和解案拒否は河村市長が「責任を避けた」 がん施設を巡り市長の元部下が証言 名古屋メ〜テレ(名古屋テレビ) 事業を一時凍結した、陽子線がん治療施設を巡り、名古屋市の河村たかし市長が和解案を拒否したのは、「自分の責任問題になることを避けたかったからでは」と、かつての部下が証言しました。 名古屋市北区の陽子線がん治療施設は、市と日立製作所が2008年に契約して建設が始まったものの、河村市長が事業を一時凍結しました。 工期延長の費用などを巡って訴訟となり、名古屋市は3億8500万円を支払う和解案を、市議会に提出しています。 15日の財政福祉委員会には、この問題を担当した岩城正光元副市長が出席しました。 日立の提訴前に裁判外紛争解決手続きで示された、今回の半額以下の約1億5000万円を支払う和解案を、河村市長が拒否した理由について述べました。 「陽子線施設の工事をストップさせた市長の責任に跳ね返ってくる。自分の責任問題になることは避けたいという気持ちでいたのではないか」(岩城正光元副市長) 「自分の保身のためというのはまったく逆。市民の皆さんのために結論を出した」(名古屋市河村たかし市長) また岩城副市長は当時、河村市長の秘書が日立側へ、和解案を受け入れる代わりに市側に5千万円を寄付するよう持ち掛けたと証言しました。いかさま署名問題もあるし、この人も終わるのかな…。明日の日本株の読み筋=好地合いが継続し堅調な展開かモーニングスター 16日の東京株式市場は、堅調な展開が期待される。15日の日経平均株価は、25日移動平均線(15日時点で2万9549円)を上回る位置をキープした。良好な地合いもあり、支えとなりそう。東証業種別指数では33業種のうち、上昇が31業種で、下落が情報通信と電機機器の2業種だった。情報通信ではソフバンG が、電機機器では東エレク が、それぞれ反落したことが、重しとなった。両銘柄は、日経平均株価への寄与度が高い銘柄でもあるため、引き続き値動きが注目されそう。市場では、米FOMC(米連邦公開市場委員会)が16-17日、日銀の金融政策決定会合が18-19日に開催されることから、外国人投資家や機関投資家は大きく動きづらいとみられ、「値動きの軽い中小型株に物色の矛先が向かいそう」(中堅証券)との声が聞かれた。 15日の日経平均株価は、前週末比49円14銭高の2万9766円97銭と5日続伸した。朝方から方向感に乏しい展開で、午後零時35分には、同47円52銭安の2万9670円31銭を付ける場面もみられたが、押し目を拾う動きから下げ渋り、地合いの良さをみせた。〔ロンドン外為〕円、109円台前半(15日午前9時)時事通信 【ロンドン時事】週明け15日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米連邦公開市場委員会(FOMC)などを控えて様子見気分が広がる中、1ドル=109円台前半で小動きとなった。午前9時現在は109円05~15銭と、前週末午後4時(108円95銭~109円05銭)比10銭の円安・ドル高。 対ユーロは、1ユーロ=130円15~25銭(前週末午後4時は130円05~15銭)で、10銭の円安・ユーロ高。ユーロの対ドル相場は1ユーロ=1.1930~1940ドルで、前週末午後4時と同じ水準。(了)コロナワクチン、定期的にブースター必要に=英コンソーシアム[ケンブリッジ(英イングランド) 15日 ロイター] - 新型コロナウイルスのゲノム解析を手掛ける英国のコンソーシアム「COVID-19(新型コロナウイルス感染症)ゲノミクスUK(COG-UK)」は、感染力の強い変異株により定期的にブースター(追加免疫)のワクチン接種が必要になるとの認識を示した。新型コロナウイルスは約2週間ごとに変異している。インフルエンザウイルスやエイズウイルス(HIV)よりも緩慢ながら、ワクチンの調整が必要になる水準だ。COG-UKトップのシャロン・ピーコック氏(ケンブリッジ大学教授)はロイターに対し、ウイルスとの「いたちごっこ」の戦いで国際協力が必要だと指摘。「常にブースター・ワクチンが必要になることを十分理解しなければならない。コロナウイルスに対する免疫は永遠には続かない」と指摘。その上でワクチンが十分なペースで開発され、人々に接種できるとの自信を示した。同コンソーシアムは、英政府の首席科学顧問パトリック・バランス氏の支援を受けて、1年前にピーコック氏が設立した。NY株見通し-今週は長期金利の動向を睨んだ神経質な展開かトレーダーズ・ウェブ 今週のNY市場は長期金利の動向を睨んだ神経質な展開か。先週は1.9兆ドルのコロナ対策法案が成立したことや、ワクチン接種進展により景気敏感株が軒並み高となったほか、ハイテク・グロース株も買い直されたことで、ダウ平均とS&P500が史上最高値を更新し、ナスダック総合も最高値からの下落率を大きく縮小した。今週は、景気の早期回復期待を背景に景気敏感株の堅調が続くことが期待される一方、ハイテク・グロース株は長期金利の動向を睨んだ神経質な展開が続きそうだ。金融政策では16-17日のFOMCで、足もとの米国債利回り上昇への当局の対応や、メンバーの金利見通しが注目されるほか、経済指標では2月小売売上高、2月鉱工業生産、2月住宅着工件数などが発表され、それらを受けた長期金利の動向に注目が集まる。企業決算はレナー、フェデックス、ナイキなどが発表予定。 今晩の米経済指標は3月NY連銀製造業業況指数など。主要な企業の決算発表はなし。(執筆:3月15日、14:00)〔NY外為〕円、109円台前半(15日午前8時)時事通信 【ニューヨーク時事】週明け15日のニューヨーク外国為替市場の円相場は、午前8時現在1ドル=109円13~23銭と前週末午後5時(108円98銭~109円08銭)比15銭の円安・ドル高で推移している。 ユーロは同時刻現在、対ドルで1ユーロ=1.1917~1927ドル(前週末午後5時は1.1948~1958ドル)、対円では同130円16~26銭(同130円29~39銭)。(了)〔米株式〕NYダウ、最高値更新(15日午前)時事通信 【ニューヨーク時事】週明け15日午前のニューヨーク株式相場は、米経済の早期回復期待を背景に買いが先行し、続伸している。優良株で構成するダウ工業株30種平均は一時取引時間中の史上最高値を更新した。ダウは午前10時現在、前日終値比37.79ドル高の3万2816.43ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数が28.44ポイント高の1万3348.30。 大型経済対策法の成立で1人最大1400ドル(約15万円)の現金給付が始まり、新型コロナウイルスワクチンの接種が拡大する中、景気回復や経済活動再開への楽観的な見方が広がり、買いが継続している。米ニューヨーク連邦準備銀行が15日発表した3月のNY州製造業景況指数が17.4と、市場予想(ロイター通信調べ)の14.5を上回ったことも、支援材料。 ただ、ダウは前週末まで6日続伸し、終値での史上最高値も3日連続更新となっていただけに、高値警戒感から利益確定の売りも出やすく、上値は重い。米連邦公開市場委員会(FOMC)の開催を16、17両日に控え、様子見ムードも広がっている。 個別銘柄では、ユナイテッド航空やデルタ航空など航空関連が高い。米運輸保安局(TSA)が空港での保安検査数が1年ぶりの高水準だと発表したことがきっかけ。また、経済対策の給付金が消費に回るとの期待から、ロウズやベスト・バイ、ホーム・デポなどの小売り関連の一角も高い。一方、米長期金利の落ち着きを背景にJPモルガン・チェースやバンク・オブ・アメリカなどの大手金融が安い。アルコアやユナイテッド・ステーツ・スチールなど素材関連も下げている。(了)〔NY外為〕円、109円台前半(15日朝)時事通信 【ニューヨーク時事】週明け15日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、日米の金融政策決定待ちで様子見ムードが広がる中、1ドル=109円台前半で弱含みに推移している。午前9時現在は109円10~20銭と、前週末午後5時(108円98銭~109円08銭)比12銭の円安・ドル高。 大型の追加経済対策法の成立や新型コロナワクチン接種ペースの加速を背景に、米国経済が日本や欧州などより早く回復するとの期待が拡大。15日朝、米長期金利の指標である10年物国債利回りは1.6%台を維持しており、ドルが対主要通貨で買われやすくなっている。ただ今週は、米連邦準備制度理事会(FRB)が16~17日、日銀が18~19日に、それぞれ金融政策決定会合を予定しており、結果によっては金利が動く可能性もあるとして様子見ムードが強い。 ニューヨーク連邦準備銀行が発表した3月の同州製造業景況指数は17.4となり、前月の12.1から上昇。2カ月連続で改善し、市場予想(14.5=ロイター通信調べ)も上回ったが、市場の反応は限定的だった。 ユーロは同時刻現在、対ドルで1ユーロ=1.1920~1930ドル(前週末午後5時は1.1948~1958ドル)、対円では同130円15~25銭(同130円29~39銭)と、14銭の円高・ユーロ安。(了)ダウは少し下げて、ナスダックは少し上げていますね。今夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中の10銘柄が値を上げてスタートしましたね。5%以上の大きな変動は見られませんね。
2021.03.15
コメント(0)
-
3月14日(日・ホワイトデイ)…2021ラウンド18…
3月14日(日・ホワイトデイ)、晴れです。良い天気ですが風が強い…。そんな本日はホーム1:GSCCの月例杯・西コースの部に参加させていただきました。9時08分スタートとのことですから6時15分に起床。BSでPGAツアーの中継を見ながら、新聞に目を通し、朝食を済ませ、ロマネちゃんと戯れる。身支度をして、7時40分頃に家を出る。8時10分頃にはコースに到着。フロントで記帳して、4/11のエントリーを確認して、ちょっと問題ありでコンペの幹事に連絡して、着替えて、練習場へ…。ショット…マアマア…、パット…練習できず…。本日の競技は西コースのブルーティー:6613ヤードです。ご一緒するのはいつものウ君(18)と、同業者のモ氏(14)とノ氏(15)です。本日の僕のハンディは(9)とのこと。OUT:0.1.1.1.1.1.0.2.2=45(17パット)1パット:2回、3パット:1回、パーオン:2回。1打目のミスが1回、2打目のミスが5回、3打目のミスが2回、アプローチのミスが4回、パットのミスが3回…。腰から右足の調子が悪いです…。ひどいゴルフを展開していますね…。10番のスタートハウスでドーピング…。役に立ちませんが…。IN:1.1.0.1.0.2.1.2.2=46(17パット)1パット:1回、3パット:0回、パーオン:1回…。1打目のミスが4回(終盤にはOBも池ポチャもあり)、2打目のミスが1回、パットのミスか2回…。45・46=91(9)=82の34パット…82の34パット…。またとてもいいとこなし…。握りも大敗…。カートからスコアの登録を済ませて、靴を磨いて、握りの清算を済ませて、お風呂に入って、会計を済ませて、早々に退散です。本日のフィジカルチェック…170.0cm,63.8kg,体脂肪率19.4%,BMI22.1,肥満度+0.3%…でした。帰宅すると15時頃。コーヒーとレーズンウィッチでおやつタイム。雑誌、新聞、段ボールがたくさん溜まっているのでゴミステーションへ排出に。それではしばらく休憩です。本日の競技の成績速報が出ていますね。月例杯・西コースの部には85人が参加して、トップは94(21)=73とのこと。ウ君が96(18)=78で19位。僕が91(9)=82で47位。月例杯・東コースの部には94人が参加して、トップは89(21)=68とのこと。ヒ君が88(12)=76で24位。オ君が102(20)=82で64位。お疲れ様でした…。株式市場のプロ、最近の利回り上昇に動じず-強気相場継続見込む ブルームバーグが50人以上の市場関係者を対象に非公式調査を実施 回答者の多くは景気・業績回復見通しに注目、中銀にも安心感示す 最近の金利上昇はボラティリティーの高まりをもたらしたものの、株式市場のプロを安全な場所に避難させるまでには至っていない。 世界の主要ファンドマネジャーらは米国債などの利回り上昇はあるものの、株式相場は耐え抜いて上昇を継続できると指摘する。こうしたプロは力強い景気や企業利益の回復見通しに目を向けている。 ブルームバーグ・ニュースが50人以上の市場関係者を対象に実施した非公式調査によると、JPモルガン・アセット・マネジメントを含め回答者の多くは、利回り上昇ペースとその理由を注視しているとしつつも、株式相場の転換点となるような特定の水準到達を警戒して待ち構えているわけではない。主要中央銀行が緩和的な金融政策を続ける限り、株式の強気相場は今後も前進できるとみている。 JPモルガン・アセット・マネジメントのグローバル市場ストラテジスト、ヒュー・ギンバー氏(ロンドン在勤)は「中銀の考え方が変わらない限り、利回りが株式相場を幅広く下押しする水準まで上昇するとは思っていない」と指摘。米金融当局が「ガイダンスを維持し、落ち着いたまま一時的なインフレ上昇には目をつぶる姿勢であるなら、利回りが株式に広く問題になる形で上がる環境は予想しない」と付け加えた。 過去1カ月の米国債を中心とする利回り急上昇はテクノロジーやディフェンシブ銘柄など一部株式からの資金流出を招き、ナスダック100指数は一時11%下げた。しかし主要国で進む新型コロナウイルスワクチン接種に加え、景気や個人消費の回復見通しを根拠に株式強気派は、金利が上昇してもリターンを維持できると確信している。 さらに新型コロナ禍の底値から株価が70%余り上昇したことで、金利上昇下でファンドマネジャーは投資先の銘柄をより慎重に選ぶようになっている。バリュエーションが高くなったセクターからより安価で出遅れているため景気回復の恩恵を期待できる銘柄へのローテーションが、債券売りによって加速するとの声がマニュライフ・インベストメント・マネジメントやHSBCアセット・マネジメントなどから聞かれた。【新型コロナ】ノルウェー、アストラ製ワクチン接種3人に血栓 アストラゼネカ製新型コロナウイルスワクチン接種を一時中断した国・地域の一つであるノルウェーは、ワクチン接種者のうち「比較的若い」3人が深刻な血栓および脳出血で治療中だと13日明らかにした。ただし、ワクチンとの関連性を判断するには時期尚早だとしている。 オーストラリアのシドニーでは、帰国者の一時隔離に使われるホテルで働く男性1人が新型コロナ検査で陽性反応を示した。これで同地の新規感染者ゼロ記録は55日連続で終わった。14日の記者会見によると、47歳のこの男性は2回の接種が必要とされるファイザー製ワクチンの1回目を済ませていた。 中国は香港から入国する外国人が申請するビザについて、中国製コロナウイルスワクチン接種者には要件を緩和する。12日の政府発表によると、15日から実施する。 ビジネス目的で中国本土を訪れる外国人は中国製ワクチン接種済みの証明書を示せば、ビザ申請の書類手続きが軽減されるほか、コロナ検査や渡航申告書記入を免除されるという。 香港は13日、外国人駐在員に人気の居住地区でビル4棟を対象とするロックダウン措置に踏み切った。同地区にあるスポーツジムから始まったコロナ感染拡大に対応するためで、ロビンソン・プレイスとブレッシングス・ガーデンそれぞれ2棟の高層マンションを封鎖し、全ての住民に14日現地午前2時(日本時間同3時)前までに検査を受けるよう義務付けた。 香港時間同時刻時点で、マンションの住民1855人が検査を済ませ新規感染者は確認されなかった。香港当局が声明を出した。同9時に検査は完了、取り締まりも同11時前後に終わった。同当局はこの日、強制的な検査対象とする学校や住居用ビル、職場を増やすとし、そのリストにはUBSグループやキャセイパシフィック航空、スタンダードチャータードが含まれている。 ブラジルの新規感染者と死者数は週間ベースで過去最悪を記録。変異株が猛威を振るう同国では4週連続で新規感染者が増加し、直近の週は50万722人増と、昨年夏のピーク時を約18万人上回った。死者増加数も1万2777人と過去最悪で、ピーク時を約5000人上回った。感染者は合わせて1144万人近く、死者は計27万7102人。 米国の12日の新規感染者は5万7741人となり、週ベースでは10月初め以来の低水準に向かった。ジョンズ・ホプキンズ大学とブルームバーグの集計データが示した。この週の1日当たり新規感染者は平均すると、前週比で15%減少。死者も同様の比較で20%余り減った。 同データによると、世界の感染者数は1億1950万人を超え、死者数は264万人を上回った。ブルームバーグのワクチン・トラッカーによれば、世界のワクチン接種は計3億5400万回を超えた。【米国株動向】スクエアのアプリ「キャッシュアップ」の新規ユーザーは利益率が極めて高いモトリーフール米国本社、2021年3月1日投稿記事よりソフトウェア企業スクエア(NYSE:SQ)の送金アプリ「キャッシュアップ」が2020年に獲得した新規ユーザー数は1,200万人でした。ユーザーはこの金融版のスイスアーミーナイフアプリ(Android携帯電話でツールを最適化するアプリ)を大いに活用しています。同社がこれまでよりも迅速に新規ユーザーを獲得しているだけでなく、新規ユーザーが従来のユーザーよりも多くの機能を利用していることにより、同社の売上と利益が増加しています。 コホート経済学スクエアのアムリータ・アフジャ最高財務責任者(CFO)が同社の第4四半期決算を説明する電話会議と株主への書簡で繰り返し取り上げたトピックのひとつが「コホート経済学」です。コホートとは、あるサービスに同じ時期に登録したユーザーの集団を意味します。スクエアの株主宛書簡では、「キャッシュアップ(消費者向けサービス)」と「セラー(販売事業者向けサービス)」のコホートが年別で示されています。同社は、各コホートの粗利益が毎年増加していると考えています。アフジャ氏によれば、キャッシュアップのすべてのコホートで過去3年間、いずれの年も粗利益継続率(既存顧客の前年度の粗利益額に対する今年度の粗利益額の比率)が130%を超えているとのことです。2020年に登録したキャッシュアップユーザーが生んだ粗利益は莫大(ばくだい)でした。 2020年がアウトパフォームした理由と今後の見通しキャッシュアップの2020年のコホートがこれほど力強い結果を出せたのにはいくつかの理由があります。第一に、年央の政府による景気刺激策で新規登録者とダイレクトデポジット(給与などの口座振込)機能の利用者が増加しましたが、一般的に同機能の利用者はこの機能を使用したことがないユーザーよりもアプリを多く使用し、多くの利益を生みます。同社のデビットカードである「キャッシュカード」のユーザーのうちキャッシュアップへのダイレクトデポジットもあるユーザーは、他のキャッシュカードユーザーの2倍から3倍の支払いを行うことがわかっています。ただし、今年後半になると、ダイレクトデポジット利用者の増加を維持するのはより困難になるでしょう。二番目の理由は、拡大を続けるエコシステムです。スクエアはキャッシュアップの新たな機能の展開を続けており、ユーザーの反応も良好です同社経営陣によれば、同アプリの株式投資機能は同社の歴史で最も迅速に利用が拡大した機能とのことです。一方、ビットコイン取引機能もこの暗号資産の価格が上昇するにつれ、この数カ月で利用が拡大しています。キャッシュアップのユーザーが採用する製品が増えれば増えるほど、一連のサービスの使用量が増加し、スクエアの利益は増加します。例えば、前四半期に同社は同社のキャッシュカード上に対象となる取引で即時割引を受けるための「ブースト」機能を追加しましたが、その結果ビットコインとダイレクトデビットの設定に対する関心が高まりました さらなる成功に向けて経営陣はマーケティング活動を通じたユーザー層の拡大に対する支出を増やす計画であり、アフジャ氏によれば2021年の営業費用は8〜9億ドルの増加が見込まれます。これは第3四半期末時点の予想額に対する増価額であり、うち約60%はキャッシュアップに割り当てられたものです。重要なのは、キャシュアップの顧客1人当たりの獲得コストは5ドルを下回っていることです。顧客1人当たりの年間粗利益額は41ドルであり、同社にとってユーザー層の拡大に注力することは非常に大きな収益拡大のチャンスとなります。3月の投資家向けプレゼンテーションで同社はキャッシュアップの潜在的な市場規模を600億ドルとしましたが、2020年の売上高(ビットコイン取引を含む)がわずか14億ドルであり、市場浸透率はわずか2%強にすぎません。コラム:長期金利上昇は景気回復のサインか 問われるFOMCの説明力=尾河眞樹氏尾河眞樹 ソニーフィナンシャルホールディングス[東京 11日] - 3月に入り、ドル/円の上昇が加速。早くも一時109円台に乗せる場面がみられた。正直なところ、筆者の想定よりも速いペースの上昇だ。ドルの名目実効為替レートをみると、2月下旬頃から上昇が鋭角になっている。 ドル急上昇の背景にあるのは足元の米実質金利の上昇だ。これが「良い金利上昇」なのか、それとも「悪い金利上昇」なのか、この先の展開を予想するうえで重要になるのは3月16、17日に開かれる米連邦公開市場委員会(FOMC)の判定だ。<改善示す米経済指標>昨年3月のコロナショック以降、米長期金利は米連邦準備理事会(FRB)の強力な金融緩和によって低く抑えられ、今年1月末までは1.0%付近で推移してきた。一方、期待インフレ率(BEI=ブレークイーブンインフレ率)の右肩上がりのトレンドは続き、2%を超す水準が継続。実質金利(名目金利-期待インフレ率)は概ね-1.0%前後と、大幅なマイナス圏にあった。しかし、2月に入り、米長期金利は景気回復への期待感などから上昇ペースが速まった。2月下旬に、期待インフレ率の上昇が2.2%台を天井に歯止めがかかってきたところで、実質金利はマイナス0.6%付近まで急上昇した。景気回復への期待感の高まりは、各経済指標が軒並み改善していることが背景にある。2月17日に発表された1月の米小売売上高は前月比5.3%増と、市場予想の同1.1%を大幅に上回った。2月の米ISM製造業景況指数は60.8と、2018年2月以来、3年ぶりの高水準を記録。2月の米雇用統計も非農業部門雇用者数は前月比37.9万人増と市場予想の20万人を大幅に上回るなど、米経済の改善を示す兆候は随所に現れている。コロナワクチン接種の急速な普及やバイデン政権による追加の経済対策、さらには金融緩和からの出口戦略を先取りする見方などがあいまって、金利の上昇モメンタムはなお残っている。<イエレン財務長官は「良い金利上昇」と指摘>実質金利の上昇は、企業にとって資金調達コストの上昇を意味し、景気を冷やすことになる。この実質金利の急上昇が警戒され、2月末にはNYダウが2日間で1000ドルを超えて下落するなど、米株価が崩れる局面がみられた。 現在の金利上昇は、経済にとって「良い」のか、「悪い」のか。「良い金利上昇」とは、実体経済の回復を伴った穏やかなインフレの上昇と、これによる長期金利の上昇を示す。一方、「悪い金利上昇」とは、たとえば財政懸念や、あるいは供給不足の中での急激な需要増などによりインフレ率が急伸し、これと共に長期金利が急上昇することを表している。市場参加者は現在、足元の長期金利上昇がこのどちらなのか判断しかねており、神経質になっているようだ。2月の米コアCPIが前年比1.3%と伸びが鈍化したことで、インフレに対する不安はいったん和らぎ、2月末の株価急落時にみられたような市場の混乱はとりあえず収まったかに見えるが、まだしばらくは市場のボラティリティーが高まる局面はあるかもしれない。 イエレン米財務長官は3月5日、メディアのインタビューで、「米長期金利の上昇は、インフレ懸念の高まりではなく、市場参加者がより強い回復を期待している兆しだ」との考えを示し、「良い金利上昇」であるとして、市場参加者の懸念を一蹴した。イエレン財務長官は、FRB議長時代に「高圧経済」、つまり経済の過熱感をある程度容認し、金融緩和や財政刺激策を続けることを主張していたが、その考えは今も変わらないようだ。 一方で、FRBの金融政策は、極めて微妙な時期に差し掛かっている。足元の米長期金利の上昇を抑えつつ、同時に将来の出口戦略を徐々に市場に刷り込んでいくという、難しいかじ取りが求められる。その際に株価暴落などのショックを与えないようにするためにも、市場とのコミュニケーションは重要だ。パウエルFRB議長にとって、そうしたコミュニケーション力が試される局面は早々に訪れそうだ。3月16、17日のFOMCでは、メンバーの政策金利見通し(ドットチャート)が公表される。米国経済のV字回復や大型経済対策を受けて、利上げの見通しの分布は、前倒しの方向に変化しよう。また、経済・インフレ見通しも上方修正されることになるだろう。<ドル円、当面は高値圏のレンジ相場か>こうしたメッセージが、今後金融環境が引き締まるという危機感につながれば、市場が再びリスクオフに傾く可能性が高い。それを抑えるために、パウエル議長は記者会見等で、緩和スタンスを維持する姿勢を強く示すかもしれない。市場では一部、米長期金利のさらなる上昇を抑えるために、FRBがツイスト・オペ(長期国債の購入を増やし、短期国債の購入を減らす)に踏み切るとの期待もあるようだ。もしFRBがコミュニケーションに失敗すれば、株価の急落を招く可能性もある。その場合は、米長期金利の上昇とともにドル高が進む一方、リスクオフの円高圧力も強まるなか、ドル円はやや円高に振れ、ユーロ円や豪ドル円などのクロス円は全般的に下落することになるため、注意が必要だ。ドル/円は、昨年3月のコロナショック後の高値111円71銭から今年1月安値の102円59銭の61.8%戻し(108円23銭)を終値ベースで上抜け、76.4%戻しの109円56銭や、昨年6月高値の109円85銭などが次の上値メドとして視野に入る。相場は勢いづくとオーバーシュートしがちなため、同水準までの上昇は見ておいたほうがよさそうだが、110円の大台を一直線に超えていくかといえば、それは難しいように見える。理由は、日米実質金利差の水準と比較した際に、ドル/円にやや行き過ぎ感があるからだ。年明けから米10年物の実質金利は-1.09%をボトムに低下に歯止めがかかり、この頃から徐々に日米の実質金利差とドル円相場の相関性が回復してきた。2月以降、日米実質金利差が拡大(マイナス幅が縮小)するに従ってドル円は上昇。ただ、実質金利差との相関からみた適正水準(107円ちょうど付近)を足下のドル円は大きく上回っている。FRBによるテーパリングの開始を市場が早々と織り込むなかで、ドル高に一時的に勢いがついたようだ。パウエル議長が繰り返し述べているとおり、インフレ率、失業率ともにFRBの目標には及ばず、FRBはしばらく現行の緩和策を維持する構えだ。となれば、短期金利がゼロ付近に抑えられるなか、足下の長期金利上昇も、徐々に勢いが衰えていくと予想する。したがってドル/円が上昇トレンドに入ったとの見方に変わりはないものの、少なくともこの1-2カ月は、足下の高値圏でのレンジ相場に入るとみている。一方で、景気の回復が顕著になってきた際に、それでもばく大な資金を投じる景気刺激策とFRBの強力な緩和が継続された場合には、将来市場がショックにさらされるリスクもはらむ。市場がインフレによる「悪い金利上昇」を織り込み始めれば、思わぬ株安や円高を招くリスクもあるため、注意したいところだ。リー・ウェストウッドが首位 B・デシャンボー2位 2週続けて最終日最終組で激突<ザ・プレーヤーズ選手権 3日目◇13日◇TPCソーグラス(米フロリダ州)◇7189ヤード・パー72>米国男子ツアー“第5のメジャー”3日目。順延となっていた第2ラウンドと第3ラウンドが行われた。トータル13アンダーの首位にリー・ウェストウッド(イングランド)。名物浮島グリーンの17番パー3でバーディを奪うなど絶好調。2週続けて3日目を終えてトップに立っている。2打差の2位にブライソン・デシャンボー(米国)。こちらは前週ウェストウッドに続き2位でスタートし、逆転優勝を飾っている。最終日は先週に続きこの二人の最終組。47歳で大会史上二番目の最年長優勝を目指すウェストウッドと世界一の飛ばし屋の組に注目が集まる。この日8つ伸ばしたジャスティン・トーマス(米国)、ダグ・キム(米国)がトータル10アンダーで3位タイにつけている。松山英樹は1打足りずに予選落ちとなっている。稲見萌寧がプレーオフ制し今季2勝目 永井花奈2位、渋野日向子57位<明治安田生命レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント 最終日◇14日◇土佐カントリークラブ(高知県)◇6228ヤード・パー72>2021年の国内女子ツアー第2戦は最終ラウンドが終了した。トータル6アンダー・首位に並んだ稲見萌寧と永井花奈がプレーオフ(18番繰り返し)を行い、3ホール目をパーとした稲見に軍配が上がった。稲見は昨年の「スタンレーレディス」に続く今季2勝目、ツアー通算3勝目。永井は17年「樋口久子 三菱電機レディス」以来となる4年ぶりVを目前としていたが、最後に力尽きた。トータル5アンダー・3位タイに森田遥、比嘉真美子、藤本麻子。トータル4アンダー・6位タイに林菜乃子、武尾咲希が入った。渋野日向子は「77」と苦しみ、トータル7オーバー・57位タイに終わった。BMW〝ディーラーいじめ〟の実態 「過剰なノルマ」「月末に恫喝まがいの電話」弁護士ドットコムニュースドイツの自動車メーカー「BMW」の日本法人で起きていたとされる、ディーラー(販売店)に対する過剰ノルマ問題で進展がありました。BMW側が、公正取引委員会に対して、自主的な改善案を提出するに至ったのです。あるディーラーの元社員は「月末になると電話を取るのが恐くなりました」と当時を振り返ります。いったいどんなことが行われていたのか。実態を取材しました。(ライター・谷寛彦)●「確約手続き」が意味するところ〝ディーラーいじめ〟と言われた販売方法に公取委のメスが入れられたのは一昨年秋。1年6カ月の時を経て、ようやく事態は動き出しました。3月3日、独BMW社の日本法人ビー・エム・ダブリュー(以下、BMW社)が公正取引委員会に改善計画を提出していたことが報じられました。これは公取委が同社を独占禁止法違反(不公正な取引方法)の疑いで立ち入り調査したことに関して、自主的な改善を申し出た「確約手続き」だと言われています。自主的な改善案を約束することで排除命令などの措置が免除されるもので、今後、公取委が改善案を審査して違反状態が解消されたと認められれば行政処分は免除されます。 「BMW社はかねてから新車販売においてディーラーに過酷なノルマを課し、ノルマを達成できないときにはディーラーに買い取らせるなどしているとして問題視されていました。 公取委は独禁法上の『優越的地位の濫用』──取引上の優位な立場を利用して相手に不利益を与えている──として立ち入り調査に入っていましたが、今回の『確約手続き』で同社はこれを認めた形です」(全国紙記者)●競争激化の輸入車市場 躍進の陰に〝ディーラーいじめ〟国内の自動車販売は1990年をピークに落ち続けていますが、輸入車は比較的健闘してきました。しかし、その一方で古くからのブランドであるメルセデス、BMW、VWに加えてボルボやジープなどの新規参入勢も加わり、メーカー間の競争は激化していると言われています。そんな中でBMWは08年の3万1928台から18年の5万886台と新車販売数を大きく伸ばしています。その躍進の陰にはメーカーによる〝ディーラーいじめ〟があったのだと、かつてディーラーに勤務していたというA氏は語ります。 「13年ごろからノルマが急に厳しくなりました。BMW社からは毎年『販売目標』というノルマが送られてきます。正確には『計画台数』というのですが、計画台数=お客様に販売する台数、ではありません。これに加えて自社登録した車の台数が含まれるのです」●「自社登録」して新古車に ディーラー経営のからくり自社登録とはディーラーが新車を買い取って名義人としてナンバーを登録すること。登録された車は中古車扱いとして販売されます。新車同然の〝新古車〟として市場に出回ることになるのです。新車と同様のコンディションでありながら格段に安い〝お買い得車〟として見たことがある人も多いのではないでしょうか。もちろん新車よりも安くなるぶんはディーラーが損をかぶることになるのですが、それでも自社登録をしなければならない理由があるのです。 「『計画台数』を達成するとBMW社から数千万円単位のボーナスが出るのです。このボーナスをもらえなければ、そもそもディーラーの経営は成り立たないので、自社登録すること自体は珍しいことではありません。 しかし、BMW社からのノルマが厳しくなり『計画台数』の4割以上を自社登録しなければならない状態になると、ボーナスをもらっても赤字を補填できなくなりました」やがてノルマが達成できなくなるとBMW社側から圧力がかかるようになったそうです。毎月月末になると催促の電話が鳴り、恫喝まがいの言葉を浴びせられた従業員もいたそうです。 「私も『自社登録をしていないのはお宅だけだ』『ディーラー権をはく奪するぞ』などと言われ、月末になると電話を取るのが恐くなりました。私のところだけでなく全国のディーラーが同じような目に遭っていたと思います」その後、A氏が勤務していたディーラーは契約を打ち切られ、負債を抱えて倒産したそうです。●群を抜いて多かったBMWの新古車ノルマ達成のための自社登録自体はどこのメーカーのディーラーでもやっていることだそうです。しかし、BMWの場合、その数は桁違いだったと言われています。その影響は中古車市場にも表れ、実際にBMWの新古車が一時期市場にあふれるという現象が起きていました。 「走行距離は僅か数十km程度。それでいて価格は新車と比べて100万円以上安いといった新古車が今、急増している。特にBMWなどは過去に例を見ないほど買い得な新古車が多い」(ベストカーweb 18年4月24日)また、あるデータによると19年7月に走行20㎞未満の車を検索したところ、メルセデスが99台、アウディが6台ヒットしたのに対して、BMWはなんと849台がヒットしたといいます。前出のA氏はメーカーとディーラーとの関係について次のように語ります。 「メーカーとの契約は2年ごとの更新で『ディーラーが販売目標を達成できず、また目標達成の努力をしていないと見なされる場合、BMWはディーラーとの契約を解除できる』との文言があったと聞いています。 このディーラー側に不利な契約とノルマ達成のボーナスがなければ経営が立ち行かないという商売のやり方に問題があると思います。これを解消しない限りディーラーという商売は立ち行かなくなるのではないでしょうか」より多く商品を販売しようとするのは営利企業であれば当然の行動です。しかし、それで売る側の誰かが損をかぶらなければならないとなるのは本末転倒です。●「販売台数」を競う業界の弊害かある自動車ジャーナリストは、販売台数で成果を競うこと自体に限界が来ているのではないかと指摘しています。 「携帯電話や家電業界などでは販売台数ではなくシェアで数字が出ます。それに対して自動車業界では台数で競っているので、競争がより熾烈になっている側面があります。 また、今、環境問題が取りざたされている中で、ガソリンエンジンの車をたくさん売ることがどれだけ誇れることなのかという点にも疑問があります。 例えば欧州では自動車メーカーごとに一台あたりの車のCO2排出量をもとにランキングが出されています。このような数字で競うようになれば、無理に台数を売らなければならない必要はなくなるのではないでしょうか」過剰なノルマに関してBMW社はすでに取りやめているとも言われています。BMW社に今回公取委に提出した改善案の内容について尋ねると次のような回答でした。 「現時点において正式発表されている事ではないため、当方としては、コメントは致しかねる状況でございます」今回の〝改善案〟を経てメーカーとディーラーの関係は変わっていくのでしょうか。
2021.03.14
コメント(0)
-
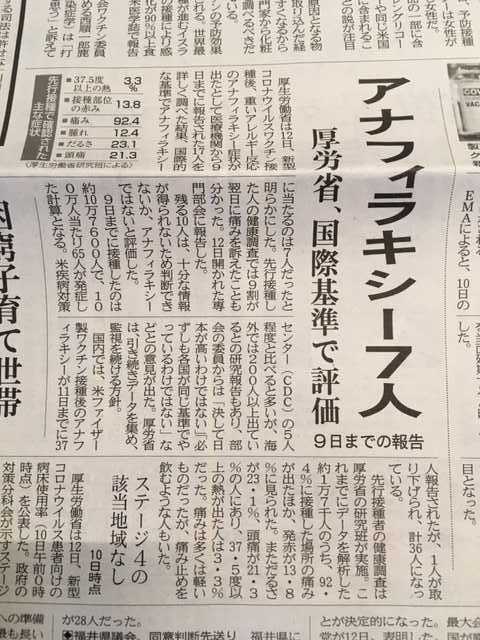
3月13日(土)…
3月13日(土)、雨です。明け方には、雨・風・雷と春の嵐でしたが…。そんな本日は7時30分頃に起床。新聞に目を通し、朝食を済ませ、ロマネちゃんと戯れる。本日のノルマは1階のモップかけですか…。ハイハイ…。朝のコーヒーブレイクはネスプレッソで…。ドゥバイヨルのチョコレートと共に…。美味い!!これでドゥバイヨルも終わり残すはピエール・ルドンのみ…。そして本日も母親宅の後片付けです。一般可燃ゴミが9袋、不燃ゴミ・金属が少々、不燃ゴミ・ガラスが少々…。ゴミ袋の置き場が無くなります。その他にも段ボール箱やプラスチックケースなど…。昼食前に作業終了。疲れました…。1USドル=109.00円。1AUドル=84.64円。昨夜のNYダウ終値=32778.64(+293.05)ドル。昨夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中の4銘柄が値を上げて終了しましたね。ドキュサインが大きく下げていますね。しかし、NYダウは大きく上げていますから僕がチェックしているのとは違う傾向の銘柄が優勢なんでしょうね…。来週の初めに買いに入るべきか…。悩ましい…。【米国市況】株が連日で最高値、国債利回り急上昇でハイテクは安い 12日の米株式相場はS&P500種株価指数が小幅ながら上昇し、連日で最高値を更新した。一方、米国債利回りが急上昇し、引き続きテクノロジー株の重しになった。 米国株はS&P500とダウが連日で最高値-ナスダック反落 米国債は下落、10年債利回り一時1.64%上回る ドル上昇、対円では109円前半-カナダ・ドルも高い 原油先物、北海ブレントが週間ベースで2カ月ぶりに下落 NY金先物は下落、利回りとドルの上昇で妙味低下 S&P500種では金融株や資本財銘柄の上昇が目立った。バリュー株へのローテーションの動きが再開した。ダウ工業株30種平均も最高値を更新した。一方、ハイテク銘柄中心のナスダック100指数は下落。米国での新型コロナウイルスのワクチン接種ペース加速や1兆9000億ドル(約207兆円)規模の経済対策成立を背景に、米10年債利回りが一時1.64%を上回った。 S&P500種は前日比0.1%高の3943.34。ダウ平均は293.05ドル(0.9%)高の32778.64ドル。ナスダック総合指数は0.6%下落。ニューヨーク時間午後4時25分現在、10年債利回りは9ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の1.63%。 グレンミード・トラストのマイケル・レイノルズ最高投資責任者(CIO)は、「通常よりもボラティリティーがやや高い状況だ。追い風と向かい風の両方の材料が複数存在することが、特にその背景にある」と述べた。 外国為替市場ではカナダ・ドルが2018年2月以来の高値となった。2月のカナダ雇用者数の伸びが市場予想を大幅に上回った。商品価格が高値圏にとどまったことも材料。米国債利回りの上昇を背景に、米ドルも上昇した。 主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.3%上昇。ニューヨーク時間午後4時25分現在、ドルは対円で0.5%高の1ドル=109円04銭。ユーロは対ドルで0.3%安の1ユーロ=1.1955ドル。ドルは対カナダ・ドルで0.4%安の1ドル=1.2483カナダ・ドル。一時は1.2462カナダ・ドルを付けた。 原油先物市場では北海ブレントが下落し、週間ベースでも2カ月ぶりの値下がりとなった。世界の需要回復が地域によってばらついている兆候が見られるほか、ドルの上昇も重しとなった。 ロンドンICEの北海ブレント5月限は41セント(0.6%)安の1バレル=69.22ドルで終了。週間では0.2%下げた。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物4月限はこの日41セント(0.6%)下落の65.61ドル。週間では0.7%安だった。 ニューヨーク金先物相場は下落。債券利回りとドルの上昇で、代替資産としての金の魅力が低下した。 ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物4月限は0.2%安の1オンス=1719.80ドルで終了。米ダウ5日連続で最高値、経済再開期待で景気循環株が高い[ニューヨーク 12日 ロイター] - 米国株式市場はダウ工業株30種が5日連続で最高値を更新。米経済再開に伴い恩恵を受ける銘柄の買いが膨らんだ。S&P総合500種も小幅高で取引を終えた。ナスダック総合は反落。楽観的な米景気見通しを反映し、米10年債利回りが昨年2月以来の水準に上昇する中、インフレ高進懸念が再燃し、ハイテク株を圧迫した。米国で1兆9000億ドル規模の新型コロナウイルス追加経済対策法の成立を好感し、週間ではS&Pが2.6%上昇、ナスダックも3.1%上昇し、2月初旬以来の大幅高となった。ダウも4.1%高と、昨年11月以来の大幅な伸びを記録した。 グレート・ヒル・キャピタルのトーマス・ヘイズ会長は、追加経済対策によって今年の米成長率が7─9%に達する公算が大きく、金利上昇圧力が高まると指摘。「予想よりも早期に、かつ力強い経済再開になるとの期待から利回りは上昇し、バリュー株やシクリカル株、景気動向に敏感な銘柄がアウトパフォームした」と述べた。朝方発表された3月の米ミシガン大消費者信頼感指数(速報値)は上昇し、昨年3月以来の高水準を付けた。新型コロナワクチンの接種が進み、感染件数が減少しつつあることを反映しているとみられるバリュー株は約0.8%高、グロース株は0.62%安となった。航空機大手ボーイングは6.82%上昇し、ダウ押し上げに寄与した。これまで相場の上昇を主導してきたフェイスブックやアップル、アマゾン・ドット・コム、ネットフリックス、アルファベット、テスラなどは軒並み下落した。S&Pの主要セクターでは情報技術、通信サービス、一般消費財の下げが目立った。一方、金融や工業は上昇し、銀行も1.83%高となった。中国の電子商取引大手、京東商城(JDドットコム)は6.7%安。関係筋によると、JDドットコムが国金証券株式の一部または全部の取得で協議している。取得総額は最大で約15億ドルに上るという。米取引所の合算出来高は116億4000万株。ニューヨーク証券取引所では値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を1.24対1の比率で上回った。ナスダックでは1.14対1で値上がり銘柄数が多かった。米利回り上昇でドル高、来週のFOMCに注目=NY外為[ニューヨーク 12日 ロイター] - ニューヨーク外為市場では、米国債利回りが再び上向いていることを受け、ドルが上昇した。国債利回り上昇に何らかの言及があるか、16─17日の米連邦公開市場委員会(FOMC)に注目が集まっている。市場ではこのところ、消費需要が積み上がっている中で大規模な景気支援策が実施され、インフレが高進するとの懸念が出ている。こうした中、労働省が朝方発表した2月の卸売物価指数(PPI、最終需要向け財・サービス)は前月比0.5%上昇。前年同月比では2.8%上昇し、2018年10月以来、2年4カ月ぶりの大幅な伸びとなった。米国では11日、1兆9000億ドル規模の新型コロナウイルス追加経済対策法が成立。バイデン大統領は同日夜のテレビ演説で、州政府などに対し5月1日までに全ての成人にワクチン接種をできるよう指示する方針を示したと明らかにした。景気見通しを巡る楽観的な見方が台頭していることで、米国債利回りの上昇はオーバーナイトの取引に続き、米国時間に入っても継続。10年債利回りは一時1.6420%と、約1年ぶり高水準を付けた。BKアセットマネジメントのマネジング・ディレクター、キャシー・リエン氏は「国債利回りはかなり力強く上昇していたが、卸売物価指数が予想を幾分か上回ったことで、上昇が加速した」と指摘。欧州中央銀行(ECB)が債券買い入れ加速を決定し、一段とハト派的になる中、米国債利回り上昇はおおむねドル支援要因になっていると述べた。ECBは11日の理事会で、利回り上昇に歯止めをかけ、景気を支援するために、パンデミック緊急購入プログラム(PEPP)の買い入れを次の四半期に拡大すると決定した。主要6通貨に対するドル指数は0.25%高の91.668。ユーロ/ドルは0.3%安の1.19505ドル。ドル/円は約0.52%高の109.050円。高リスク通貨は軟調。対米ドルで豪ドルは0.35%、ニュージーランドドルは0.68%、それぞれ下落した。暗号資産(仮想通貨)ビットコインは1.1%安の5万7150.97ドル。日本郵政、全国の郵便局で高齢者に楽天スマホを販売へ楽天が現在獲得できていない顧客層に拡販ブルームバーグ楽天はモバイル事業での高齢者層の獲得を狙い、資本提携した日本郵政と郵便局網を使って新規申し込みができるよう協議を始める考えだ。楽天の古橋洋人常務執行役員が12日夕、ブルームバーグのインタビューで明らかにした。全国に2万4000局ある日本郵政のネットワークに段階的に担当者を派遣したり、特設ブースなどでオンライン申し込みを受け付けたりすることを想定しており、「できるだけ早期に」新たな取り組みを開始したいと話した。規模や詳細は未定で、今後詰めるという。国内の携帯電話市場では、菅義偉政権による料金値下げの要請もあってNTTドコモやKDDI、ソフトバンクなど大手各社との間で顧客獲得競争が激化している。楽天は1月、データ使用料が20ギガバイト(GB)以下なら月額1980円、1GB以下は無料とする新料金プランを発表。大手3社もインターネット経由の申し込みで低料金にするなどサービスの見直しを進めている。古橋常務は、これまで楽天モバイルには300万件超の申し込みがあったが、「モバイルリテラシーの高い」比較的若い層だと説明。一方、郵便局やゆうちょ銀行を訪れる人々の年齢層は高く、楽天が現在獲得できていない顧客層との認識を示した。今後対面での新規顧客の開拓などにより、「ナンバーワンのモバイルキャリアになる」と抱負を語った。楽天のモバイル事業は基地局設置の前倒しなど先行投資負担がかさんでおり、前期(2020年12月期)決算では同事業の損失が2270億円と前の期の765億円から赤字が拡大した。また、古橋常務は今回中国テンセント・ホールディングスの子会社が楽天株式を3.65%を保有することで、ゲームの開発や国内出店業者の中国市場への進出を視野に、テンセントと連携する可能性についても言及した。楽天と日本郵政は12日、資本業務提携の締結を発表。楽天が実施する第三者割当増資を日本郵政が引き受け、約1500億円を出資する。出資比率は8.32%となり、物流や金融、モバイルなど幅広い分野での連携強化を図るという。47歳のリー・ウェストウッドが暫定首位 松山英樹は予選落ち危機、大会は日没順延<ザ・プレーヤーズ選手権 2日目◇12日◇TPCソーグラス(米フロリダ州)◇7189ヤード・パー72>米国男子ツアー“第5のメジャー”2日目。順延となっていた第1ラウンドと第2ラウンドが行われ、この日も日没により順延となった。暫定首位にはトータル9アンダーまで伸ばしたリー・ウェストウッド(イングランド)。トータル8アンダーの暫定2位にマシュー・フィッツパトリック(イングランド)が続く。初日4オーバーと出遅れた松山英樹は5バーディ・2ボギーで3つスコアを伸ばしたが、トータル1オーバー・暫定72位タイ。現時点の予選通過ラインはトータルイーブンパーのため、微妙な位置となっている。前週優勝のブライソン・デシャンボー(米国)がトータル6アンダーで暫定5位タイ。世界ランキング1位のダスティン・ジョンソン(米国)はトータル1アンダーの暫定37位タイ。ローリー・マキロイ(北アイルランド)はトータル10オーバーの大乱調で予選突破を逃した。株式週間展望=日本株、反撃開始―25日線奪回で上昇維持、日米金融イベントも不安薄モーニングスター 市場で一段の金利上昇のきっかけとなることが警戒されていた米国債の入札を無難に通過した今週(8-12日)、日本株相場も後半にかけて反撃開始の様相を強めた。来週(15-19日)はFOMC(米連邦公開市場委員会、16、17日)と日銀金融政策決定会合(18、19日)が焦点となるが、百戦錬磨の金融当局者らが市場に冷や水を浴びせるとも考えにくい。日経平均株価は25日移動平均線の奪回により勢いづきそうだ。 日経平均は5日の取引時間中に付けた安値2万8308円を底に切り返し、12日は2万9717円(今週末比853円高)まで上り詰めた。2月16日高値(3万714円)から下落する過程で割り込んだ25日線を奪回。史上最高値を更新したNYダウの後を追う。 日経平均は昨年10月末以降の上昇波動において、同線を割り込むたびにチャージを済ませ、高値を更新するパターンを繰り返してきた。その意味で足元の値動きは投資家に安心感をもたらす。12日はハイテク株が息を吹き返した一方、小型株の急伸も散見された。 今週の米国債の入札は、10年債を中心に心配されたほどの不調には至らなかった。米10年債利回りの水準も再び1.5%を下回り、市場のリスクオフムードを押し込めた格好。もっとも、12日の日経平均の上昇はハイテクの買い戻しが集中した要素もあり、より安定した資金の流入が本格化するかが業績相場に移行していく上で重要となる。 来週はまずFOMCが控える。金利上昇を抑制する具体的措置が講じられる可能性は低い上、経済見通しに上方修正圧力が掛かるだけに、内容次第で再び金利を押し上げかねない。しかし、マーケットを重視するパウエルFRB(米連邦準備制度理事会)議長は声明などでその点を考慮することが期待される。 続く日銀金融政策決定会合は、これまでの緩和策の「点検」を実施する。 黒田総裁が範囲調整に否定的な見解を示した直後に雨宮副総裁が肯定するなど、スタンスのばらついた「長短金利操作」における長期金利の変動幅が焦点。ただ、市場では現行の「0%上下0.2%」のレンジを拡大する方向でコンセンサスが形成されつつあるとみられ、金利や株価への織り込みも先行した感がある。また、指数連動型ETF(上場投資信託)の購入も、事実上は既に新方針での運用が始まっている。 来週の日経平均は、日米の金融イベントに先立つ様子見色に、今週後半にかけての騰勢の反動が相まって、序盤は低調なスタートとなるかもしれない。ただ、それも一時的にとどまり、力強さを取り戻す展開が見込まれる。想定レンジは2万9000-3万700円。 経済指標は15日の1月機械受注や中国2月工業生産、小売売上高など、17日の米2月住宅着工件数・建設許可件数など。NY市場概況-ダウ293ドル高 5日連続で最高値更新 金利上昇を受けてナスダックは反落トレーダーズ・ウェブ 12日のNY株式相場は高安まちまち。1.9兆ドルのコロナ対策法案の成立やコロナワクチン接種進展期待により景気敏感株の堅調が続いた一方、長期金利が上昇したことでハイテク・グロース株が再び売られた。米10年債利回りは一時昨年2月以来となる1.64%台まで上昇した。ダウ平均は307ドル高まで上昇し、293.05ドル高(0.90%)と6日続伸して終了。5日連続で取引時間中の最高値を更新し、終値でも3日連続で最高値を更新した。ボーイングが6.82%高、キャタピラーが4.20%高となったほか、ゴールドマン・サックスも2%近く上昇し、ダウ平均を押し上げた。S&P500は一時0.61%安まで下落したが、0.10%高と小幅に4日続伸して終了。前日に続いて最高値を更新した。一方、ナスダック総合は終日マイナス圏で推移し、0.59%安と反落して終了。アルファベット、フェイスブックが2%以上下落し、アマゾン、アップル、マイクロソフトも0.6-0.8%下落した。 週間ではダウ平均が4.07%高、S&P500が2.64%高とともに2週続伸し、ナスダック総合は3.09%高と4週ぶりに反発。小型株指数のラッセル2000は7.32%高と4週ぶりの大幅反発となった。年初来では、ダウ平均が7.10%高、S&P500が4.99%高、ナスダック総合が3.35%高となり、ラッセル2000は19.14%高と主要3指数を大きくアウトパフォームした。NY株式:米国株式市場はまちまち、回復期待を受け景気循環株への移行再開フィスコ ダウ平均は293.05ドル高の32778.64ドル、ナスダックは78.81ポイント安の13319.86で取引を終了した。 1.9兆ドル規模の追加経済対策法案の成立後、バイデン大統領は11日夜の演説で5月1日までにワクチン接種の対象を全成人に拡大、独立記念日7月4日までには正常化を目指す方針を示したため景気循環株中心に買われ寄り付き後、上昇した。ダウは終日堅調に推移。一方、回復期待に長期金利が再び上昇したためハイテク株に売りが広がりナスダックは下落した。セクター別では、銀行や資本財が上昇した一方、半導体・同製造装置、メディア・娯楽が下落した。 製薬会社のノババックス(NVAX)は、開発中の新型コロナウイルスワクチンの最終治験で有効性96%の効果が見られたとする好結果を受け、当局への承認申請に近づいたとの期待に上昇した。通信のAT&T(ATT)は動画配信サービス「HBOマックス」契約者数の見通しを引き上げ、上昇。インフラ構造物の工事会社のエイジオン(AEGN)は投資会社による買収の思惑で急伸した。一方、化粧品小売りチェーンのアルタ・ビューティ(ULTA)はCEOの辞任発表に加えて、既存店売り上げや収益見通しが市場予想を下回ったことが嫌気され。下落。動画配信のネットフリックス(NFLX)はパスワードの共有取り締まりを試行していると発表し、下落した。 バイデン大統領は、経済対策法案が2021年に700万人の雇用を創出すると自信を表明した。(Horiko Capital Management LLC)今週の【早わかり株式市況】3週ぶり急反発、バリュー株が買われ週末グロース株も買い戻される株探ニュース■今週の相場ポイント 1.日経平均は3週ぶり急反発、週末に500円を超える大幅高演じる 2.米国での大型追加対策法の成立もバリュー株など中心に買いを呼び込む 3.米長期金利の動向には神経質な展開、グロース株には向かい風強い 4.中国政府系ファンドが株価対策に動いているとの報道はプラス材料 5.週末は半導体など買い戻され日経平均は一気に2万9700円台に■週間 市場概況 今週の東京株式市場は日経平均株価が前週末比853円(2.96%)高の2万9717円と3週ぶりに急反発となった。 今週は米長期金利の動向を横目に不安定な動きが予想され、週末のメジャーSQ算出を控えボラティリティが高まることへの警戒もあったが、結局日経平均は上方向に大きく振れる格好となった。半導体関連などハイテク株が週末に買い戻され全体を押し上げた。 8日(月)は売りに押される展開。前週末の米株高を受け日経平均は朝方高く始まったものの、その後は値を崩す展開となり3日続落となった。9日(火)は日経平均が4日ぶりに切り返した。米長期金利の動向を警戒して上下に不安定な値動きだったが、中国の政府系ファンドが株価対策に動いているとの報道などがプラスに働いた。10日(水)は強弱観対立のなか売り買いが拮抗し8円高とわずかにプラス圏で着地。前日の米国市場では半導体銘柄で構成されるSOX指数が急伸したが、東京市場での反応は限定的だった。11日(木)は米国で1兆9000億ドル規模の追加経済対策法の成立が確実な状況となったことで、バリュー株に買いが入り日経平均は3日続伸。ただ、グロース株は引き続き弱い動きに終始した。そして12日(金)はメジャーSQ算出日だったが、SQ通過後に一気に上値が軽くなった。前日のNYダウが追加経済対策法の成立で景気回復期待が高まり過去最高値を更新したことも追い風となり、これまで売りが続いていた半導体や電子部品株が買い戻され、日経平均は後場に上げ足を一気に強めた。500円を超える上昇で2万9700円台に駆け上がり今週の取引を終了した。■来週のポイント 日経平均は25日移動平均線を上回ってきており、来週は3万円大台乗せから2月16日の高値3万0714円を目指す展開が期待される。 重要イベントとしては、国内では15日朝に発表される1月機械受注統計や17日朝に発表される2月貿易統計、18日-19日に開催される日銀金融政策決定会合、19日朝に発表される2月全国消費者物価指数が注目される。海外では15日に発表される中国2月の小売売上高と鉱工業生産、16日-17日に開催されるFOMC(米連邦公開市場委員会)、17日発表の米国2月住宅着工件数に注視が必要だろう。■日々の動き(3月8日~3月12日)【↓】 3月 8日(月)―― 3日続落、朝高も米先物安でリスク回避の売り優勢 日経平均 28743.25( -121.07) 売買高15億1102万株 売買代金 2兆9862億円【↑】 3月 9日(火)―― 4日ぶりに反発、米景気回復期待や円安で買い優勢 日経平均 29027.94( +284.69) 売買高16億2114万株 売買代金 3兆2706億円【↑】 3月10日(水)―― 小幅続伸、強弱観対立し狭いレンジでの往来に終始 日経平均 29036.56( +8.62) 売買高13億9336万株 売買代金 2兆8999億円【↑】 3月11日(木)―― 3日続伸、NYダウ最高値を受け景気敏感株中心に買い優勢 日経平均 29211.64( +175.08) 売買高13億7793万株 売買代金 2兆8692億円【↑】 3月12日(金)―― 4日続伸、米株高好感されハイテク株中心に買い継続 日経平均 29717.83( +506.19) 売買高15億8290万株 売買代金 3兆6235億円■セクター・トレンド (1)全33業種中、32業種が上昇 (2)郵船 など海運、日本製鉄 など鉄鋼といった景気敏感株が値上がり率1位、2位を独占 (3)東電HD 、東ガス など電力・ガスが大幅高 (4)三菱UFJ など銀行、SBI など証券、日立キャピ などその他金融といった金融株が買われた (5)ソフトバンクG など情報・通信、武田 など医薬、大成建 など建設といった内需株も高い (6)コマツ など機械、トヨタ など自動車、HOYA など精密機器といった輸出株も堅調 (7)唯一、任天堂 などその他製品が低調■【投資テーマ】週間ベスト5 (株探PC版におけるアクセス数上位5テーマ) 1(1) アンモニア ── カーボンフリー燃料として関心高い 2(6) 全固体電池 3(2) 半導体 4(5) 2020年のIPO ── 迫る3月IPO、年度末飾る大化け候補ルーキー銘柄を狙え 5(4) 人工知能 ※カッコは前週の順位午後になって日が射してきましたね。キャンセル待ちになっていた明日の月例杯のエントリーもできたようですし、楽しみましょう。今後に期待のバリュー株…米国株もグロース株中心からバリュー株へシフトしないといけないかな…。金利の上昇が1.5%超えて続くようだと要注意ですね。国内株式市場見通し:米FOMC通過後のあく抜け感で3万円回復なるかフィスコ■米金利の落ち着き受けて週末にかけて安心感今週の日経平均は、しばらく相場の調整要因になっていた米長期金利の上昇に落ち着きが見られたことで週末にかけて安心感が強まる展開となった。週前半は米長期金利の動向を左右しかねない経済指標やイベントを見極めたいとの思惑から様子見ムードが強く、指数もこう着感の強い展開が続いた。ただ、経済協力開発機構(OECD)による2021年世界経済成長見通しの引き上げや、懸念されていた米3年債入札が好調な結果となったことによる米長期金利上昇の一服感を受けて米ハイテク株が持ち直すと、これを受けた10日の東京市場でもアドバンテストなどの半導体関連株が大きく上昇した。また、2月の工作機械受注額(速報値)が前年同月比36.7%増の1055億円と、受注の好不況ラインとされる月1000億円を19カ月ぶりに上回ったことを背景に、ファナックなどのFA関連株も動意づいた。その後も、週後半にかけて、米10年債および30年債の入札が無難に終わったことや、市場予想並みに留まった米消費者物価指数(CPI)の結果がインフレ懸念の後退、米長期金利の落ち着きに寄与した。こうした安心感が浮上するなか、週末の先物・オプション特別清算指数算出(メジャーSQ)を波乱なく通過すると、買い戻しの動きが強まり、週末の日経平均は大引けまで上げ幅を拡げ、506.19円高の29717.83円まで上昇した。■強含み、イベント通過後の上放れに期待来週の日経平均は強含みか。週後半の日米中央銀行による金融政策決定会合を終えるまでは指数の大きな動きは見込めなさそうだが、米長期金利の落ち着きを背景に今週後半から見られるハイテク・グロース(成長)株の持ち直しが継続すれば、強含みの展開が想定され、金融政策イベントを終えた後には、あく抜け感による上放れの展開が期待される。米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果を反映するのは18日になり、日銀金融政策決定会合の結果は週末19日の場中に反映される。米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長は、先に行われたウォールストリートジャーナル主催のイベントでのインタビューにおいて、その折上昇中だった米長期金利について「注意を払うものだった」としながらも、長期金利の上昇を抑制する具体策には特段言及しなかった。これが失望感を誘う形で一時は再び長期金利が急伸し、日米の株式相場に短期的なショックをもたらしていた。このような背景から、既に、しばらくの間はFRBからは特段の具体策の発表はないだろうという市場コンセンサスが形成されつつあると考えられる。そのため、今回のFOMCはそこまでの大きな波乱にはならないとも考えられる。むしろ、すでに一度期待を裏切られる形で期待値が下がっている分、何もなければ想定通りという形で市場は過敏な反応を示さず、反対に、具体策への言及などがあればポジティブサプライズとなって相場上昇に弾みをつける可能性がある。テーパリング(量的緩和の縮小)など現状では想定しにくい議論に踏み込みでもしない限り、イベント通過に伴うあく抜け感から相場はポジティブに反応する可能性が高いのではないか。また、今週末は場中に日銀が来週の金融政策決定会合で年6兆円ペースとしている上場投資信託(ETF)購入原則を削除する方針との報道もあったが市場の反応は限定的だった。このため、週末の日銀金融政策決定会合についても波乱は起こりにくいと考えられる。イベント通過後の一段の上昇に期待したい。また、米バイデン政権が掲げる1.9兆ドルの大規模な追加経済対策が11日に成立し、早ければ来週から家計への現金支給が始まる予定だ。米個人投資家の懐が潤えば、再び人気グロース銘柄が動意づき、東京市場にも同様の動きが波及する可能性もあろう。もちろん、今年4月頃からは、前年比ベースでの物価指標の上振れが警戒されており、インフレ懸念による長期金利の上昇というリスクシナリオがなくなったわけではない。しかし、上述の背景から、目先は上目線でいてよいと考える。■優良グロース株の買い直し時期を図る頃合いか国内要因としては、そろそろ年度末に向けた機関投資家によるリバランスや、企業の政策保有株の圧縮といった需給要因が一巡してくる頃合いか。直近の米長期金利上昇の一服と合わせて、こうした需給要因の一巡も、足元で過度に売られ過ぎた優良グロース銘柄への買い直しに繋がる可能性がある。そうした傾向として、今週は後半から日本電産やエムスリーといった調整色が濃かった銘柄に持ち直しの兆しが見られた。来週いっぱいはまだ上述の需給要因が続く可能性もあるが、下値固めが進むようであれば買い直しのタイミングを見計らいたいところだ。また、週初に中国2月の鉱工業生産などの経済指標も発表予定で、結果が良好なものであれば、先の工作機械受注とも相まってファナックや安川電機などのFA関連株の一層の刺激材料にもなろう。■米中2月鉱工業生産、米中2月小売売上高など来週の主な国内外スケジュールは、15日に1月機械受注、中国2月鉱工業生産、中国2月小売売上高、中国2月固定資産投資、16日に米国2月小売売上高、米国2月鉱工業生産、米国3月NAHB住宅市場指数、米国FOMC(~17日)、17日に2月貿易収支、米国パウエルFRB議長会見、米国2月住宅着工件数、18日に日銀金融政策決定会合(~19日)、米国3月フィラデルフィア連銀景気指数、19日に黒田日銀総裁会見などが予定されている。来週の相場で注目すべき3つのポイント:日米金融政策決定会合、IPO5社、米中経済指標(小売売上高フィスコ■株式相場見通し予想レンジ:上限30500-下限29200円来週の日経平均は強含みか。週後半の日米中央銀行による金融政策決定会合を終えるまでは指数の大きな動きは見込めなさそうだが、米長期金利の落ち着きを背景に今週後半から見られるハイテク・グロース(成長)株の持ち直しが継続すれば、強含みの展開が想定され、金融政策イベントを終えた後には、あく抜け感による上放れの展開が期待される。米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果を反映するのは18日になり、日銀金融政策決定会合の結果は週末19日の場中に反映される。米連邦準備理事会(FRB)のパウエル議長は、先に行われたウォールストリートジャーナル主催のイベントでのインタビューにおいて、その折上昇中だった米長期金利について「注意を払うものだった」としながらも、長期金利の上昇を抑制する具体策には特段言及しなかった。これが失望感を誘う形で一時は再び長期金利が急伸し、日米の株式相場に短期的なショックをもたらしていた。このような背景から、しばらくの間はFRBからは特段の具体策の発表はないだろうという市場コンセンサスが既に形成されつつあると考えられる。そのため、今回のFOMCはそこまでの大きな波乱にはならないとも考えられる。むしろ、すでに一度期待を裏切られる形で期待値が下がっている分、何もなければ想定通りという形で市場は過敏な反応を示さず、反対に、具体策への言及などがあればポジティブサプライズとなって相場上昇に弾みをつける可能性がある。テーパリング(量的緩和の縮小)など現状では想定しにくい議論に踏み込みでもしない限り、イベント通過に伴うあく抜け感から相場はポジティブに反応する可能性が高いのではないか。また、今週末は場中に日銀が翌週の金融政策決定会合で年6兆円ペースとしている上場投資信託(ETF)購入原則を削除する方針との報道もあったが、市場の反応は限定的だった。このため、週末の日銀金融政策決定会合についても波乱は起こりにくいと考えられる。イベント通過後の一段の上昇に期待したい。また、米バイデン政権が掲げる1.9兆ドルの大規模な追加経済対策が11日に成立し、早ければ今週末から家計への現金支給が始まる予定だ。米個人投資家の懐が潤えば、再び人気グロース銘柄が動意づき、東京市場にも同様の動きが波及する可能性もあろう。もちろん、今年4月頃からは、前年比ベースでの物価指標の上振れが警戒されており、インフレ懸念による長期金利の上昇というリスクシナリオがなくなったわけではない。しかし、上述の背景から、目先は上目線でいてよいと考える。■為替市場見通し来週のドル・円はドル・円はもみ合いか。3月16-17日開催の連邦公開市場委員会(FOMC)の会合では、長期金利の過度な上昇を抑えるための具体的な措置について議論される可能性がある。少なくとも、緩和的な政策方針を改めて示すとみられ、ドル買い・円売りはやや縮小する可能性がある。日本銀行は18-19日開催の金融政策決定会合で、金融政策の現状維持を決定すると予想され、10年金利の変動幅を拡大する可能性は低いとみられる。日本の長期金利は伸び悩む可能性が高いが、米長期金利が上げ渋った場合、リスク選好的なドル買い・円売りは一服しよう。ただ、パウエルFRB議長をはじめ、米金融当局は長期金利の上昇について、「米国経済の回復を反映している」との見方を伝えている。新型コロナウイルスの感染抑制によって景気見通しは改善しつつあること、1.9兆ドル規模の追加経済対策法案の成立を意識して、リスク回避的なドル売り・円買いが広がる可能性は低いとみられる。■来週の注目スケジュール3月15日(月):日・コア機械受注(1月)、中・鉱工業生産指数(2月)、中・小売売上高(2月)、米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(3月)など3月16日(火):ウイングアーク1stが東証1部に新規上場、ヒューマンクリエイションホールディングスが東証マザーズに新規上場、米・小売売上高(2月)、米・鉱工業生産指数(2月)、米・連邦公開市場委員会(FOMC)(17日まで)など3月17日(水):日・貿易収支(2月)、米・住宅建設許可件数(2月)、米・パウエルFRB議長記者会見など3月18日(木):i‐plugが東証マザーズに新規上場、日銀政策委員会・金融政策決定会合(19日まで)、米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(3月)、米中外交トップが会談など3月19日(金):黒田日銀総裁が会見、ココナラが東証マザーズに新規上場、T.S.Iが東証マザーズに新規上場など3月21日(日)日・首都圏1都3県に発令中の緊急事態宣言の期限稲見萌寧が「66」で独走態勢 3打差2位に永井花奈、渋野日向子は38位<明治安田生命レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント 2日目◇12日◇土佐カントリークラブ(高知県)◇6228ヤード・パー72>21年の国内女子ツアー第二戦「明治安田生命レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント」は2日目の競技が終了。7バーディ・1ボギーの「66」と猛チャージを見せた稲見萌寧がトータル10アンダーで単独首位浮上。独走態勢に入った。3打差の2位にこの日ノーボギーで3つ伸ばした永井花奈。トータル6アンダーの3位タイに比嘉真美子と森田遥。トータル5アンダーの5位には林菜乃子が続いている。首位から出たプラチナ世代の安田祐香は2つ落としてトータル3アンダーの8位タイ。先週の「ダイキンオーキッドレディス」でツアー通算3勝目を挙げた小祝さくらはイーブンパーの20位タイ、渋野日向子はバーディを1つも獲れずトータル2オーバーの38位タイまで後退。その他、前回大会の覇者・鈴木愛、2012年、16年の覇者イ・ボミ(韓国)も同じくの38位タイ。明治安田生命所属のホステスプロ・勝みなみはトータル9オーバー・104位タイで予選落ちを喫している。病院クラスターで新たな感染者 岐阜県内で4人が新型コロナ感染、1人死亡 岐阜県は13日、新たに3市町で計4人の新型コロナウイルス感染と、入院していた土岐市の80代女性の死亡を確認したと発表した。県内の感染者数は累計4683人、死者は計117人となった。 瑞浪市の東濃厚生病院と土岐市の高井病院のクラスター(感染者集団)では、高井病院の医療従事者の家族1人の感染が判明し、34人規模となった。 12日時点の入院患者数は62人で、病床使用率は8・9%。前日から1・2ポイント下がった。 新規感染者の居住地別は、大垣市2人、土岐市、安八郡輪之内町が各1人。年代別は30代、40代、50代、60代が各1人。
2021.03.13
コメント(0)
-

3月12日(金)…
3月12日(金)、曇りのち雨…。予報通りに午後からは雨となりましたね。そんな本日は7時15分頃に起床。我が家の庭の紅梅が見頃を迎えています…。新聞に目を通し、朝食を済ませ、ロマネちゃんと戯れる。身支度をして、ゴミステーションへゴミ袋11ケを2往復して排出。まだまだ続きますね…。8時40分頃には家を出る。ゴルフではありません、アルバイト業務です。本日のアルバイト業務は10:00~16:00ですが、時間配分がイレギュラーなのでランチタイムが前倒しです…。ということで11時頃にサンドイッチを食べようと「緑の館」を訪問すると、まだモーニングが付いています…。時間的にきついのでモーニングをいただく。コーヒーはロイヤルブレンドで、モーニングはシナモン・バターです。仕事を終えての帰り道には「ジークフリーダ」に寄り道するもほとんどケーキはなくなっていたので、コーヒーとショートケーキをいただく。帰宅して、ロマネちゃんのお世話をして、しばらく休憩です。1USドル=109.13円。1AUドル=84.61円。昨夜のNYダウ終値=32485.59(+188.57)ドル。本日の日経平均終値=29717.83(+506.19)円。金相場:1g=6682(+7)円。プラチナ相場:1g=4690(+52)円。昨夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中のすべてが値を上げて終了しましたね。大きく上げているものもかなり見られますね。本日の東京市場ではチェック中の日本株30銘柄中の23銘柄が値を上げて終了しましたね。重点6銘柄では5銘柄が値を上げて終了しましたね。5%以上の大きな変動は見られませんね。デンマークなどアストラ製ワクチン接種を中断 接種後に血栓事例毎日新聞 デンマークやノルウェー、イタリアなど欧州の複数の国々は11日、英製薬大手アストラゼネカの新型コロナウイルスワクチンの接種を一時停止すると発表した。接種後に血栓ができる事例が報告されたためで、死亡したケースもあった。ただ、ワクチンと血栓の因果関係は明らかになっていない。欧州連合(EU)の欧州医薬品庁(EMA)は血栓事例について調査しつつ、現時点では「ワクチンが血栓を引き起こしたことを示すものはない」として接種の継続が可能だと説明している。 デンマークは11日、「予防措置」としてアストラゼネカ製ワクチンの2週間の接種中断を発表した。ノルウェー、アイスランドも同様の措置を取った。イタリアも同社製ワクチンの一部について使用を停止した。 アストラゼネカ製ワクチンを巡っては、オーストリアが7日、女性看護師が接種後に血栓症を発症して死亡したことなどから接種停止を発表していた。ロイター通信によると、デンマークでは60歳の女性が接種後に血栓症で死亡。イタリアでも50歳の男性らが死亡したという。 EMAによると、10日時点で英国などを除く欧州で約500万人が同社製ワクチンの接種を受け、血栓塞栓(そくせん)症を発症したのは30人。EMAは「一般的に確認される割合よりも多くはない」とする見解を示している。英国は「血栓がワクチンによるものだとは確認されていない。ワクチン接種のメリットは(新型コロナ感染や重症化などの)リスクを上回っている」(医薬品・医療製品規制庁)と強調。フランスやオランダなども接種を継続する方針を示している。アストラゼネカ製ワクチン、数か国が使用見合わせ 血栓症懸念AFPBB News 【AFP=時事】(更新)英製薬大手アストラゼネカ(AstraZeneca)が開発した新型コロナウイルスワクチンについて、デンマークを含む欧州数か国は11日、接種した患者の一部が血栓症を発症したことを受け、使用を一時的に見合わせると発表した。欧州医薬品庁(EMA)はこれを受け即座に声明を出し、同社製ワクチンに健康リスクは確認されていないと説明した。 11日は、新型コロナウイルスのパンデミック(世界的な大流行)が宣言されてからちょうど1年に当たる。アストラゼネカ製ワクチンをめぐり今回浮上した問題は、ワクチンが生活正常化への道を開くとの期待に影を落とした。 同社製ワクチンについてはデンマークに続き、ノルウェー、アイスランドが使用を中断。イタリアも予防措置として同社製ワクチンの一部の使用を禁止したが、同国の医薬品規制当局は、血栓症との関連は今のところ確認されていないとしている。 EMAはAFPに送付した電子メールで、「現在ある情報からは、接種を受けた人々の間での血栓塞栓症の発症数は一般人口での発症数より高くはないことが示されている」と述べ、懸念の払しょくに努めた。 英政府は、アストラゼネカ製ワクチンは「安全で有効だ」と主張。フランスのオリビエ・ベラン(Olivier Veran)保健相も、同社製ワクチンの使用を停止する「必要はない」と言明した。第一三共、ワクチン製剤化開始=英アストラ製時事通信社 第一三共は12日、英製薬大手アストラゼネカの新型コロナウイルスワクチンについて、国内での製剤化を開始したと発表した。輸入したワクチン原液を容器に充填(じゅうてん)・包装し、承認が下りれば、速やかに出荷できる状態にする。 アストラゼネカは2月にワクチンの薬事承認を厚生労働省に申請しており、国内治験のデータ提出を進めている。大丈夫か、第一三共…。ノババックスのワクチン、従来型ウイルスで有効性96% 認可申請へ[11日 ロイター] - 米ノババックスは11日、英国で実施した新型コロナウイルスワクチンの後期臨床試験(治験)で、従来型のウイルスに対し96%の有効性が示されたと発表した。ノババックスは今回のデータを用い、複数国の規制当局に承認申請を行う見通し。英国で感染が広がっている感染力の強い変異株に対する有効性は約86%で、従来型と英国型のデータを合わせた全体としての有効性は約90%だった。感染力の強い別の変異株が広がっている南アフリカで実施された小規模な治験では、エイズウイルス(HIV)未感染者に対する有効性は約55%にとどまった。HIV感染者を含めると有効性は約49%に低下した。ただ、英国と南アのいずれの治験でも、重症化や死亡を防ぐ効果は100%となった。ノババックスの株価は時間外取引で22%急騰し、229ドルとなった。同社がコロナワクチン開発を発表した昨年1月21日時点の株価からは10ドルを下回っていた。同社のフィリップ・ドゥボフスキー最高医療責任者(CMO)は、南アの治験結果に基づくと、南ア型変異株の感染が拡大している地域で同社のワクチンを使用する妥当性は依然あるかもしれないと説明。変異株に対応するワクチンも開発中で、今年第2・四半期に治験を開始する計画。ノババックスのワクチンは、2回接種が必要。同社は複数の国で当局に承認申請を行う方針だが、米国での申請時期や、米規制当局が同国内で実施されている治験の完了を求めるかどうかは不透明。米国の治験データは4月初旬までにそろうと見込む。ドゥボフスキー氏は、英国での認可申請は今年第2・四半期の早い時期を引き続き予定していると述べた。ノババックスのアーク最高経営責任者(CEO)は今月ロイターに対し、米当局が英国の治験データのみで十分と判断すれば、早ければ5月にも米国での使用が許可されるとの見方を示した。一方、米国での治験結果を待つ場合、さらに2カ月程度かかる可能性があるという。ドゥボフスキー氏は「米当局が最終的に、提出済みのデータで十分なのか、米国の治験データがそろうのを待つべきかを決めることになる」と述べた。ノババックスの幹部によると、ワクチン生産工場は4月までに完全に稼働可能となる見通し。アークCEOは、米国の承認取得に合わせて出荷できるよう数千万回分を備蓄しておく考えを示している。同社はインドのセラム・インスティテュート・オブ・インディアなど8カ所でワクチンを生産する計画。ワクチンのアナフィラキシー37例と河野氏共同通信社 河野太郎行政改革担当相は12日の記者会見で、新型コロナウイルスワクチンを巡り、11日までに重いアレルギー反応のアナフィラキシーが37例報告され、いずれも症状が改善したと説明した。日本株は4日続伸、米経済対策成立と金利上昇抑制-電機や機械高い 12日の東京株式相場は大幅に続伸。米国で大型追加経済対策が成立し景気回復が期待される中、上昇傾向にあった米長期金利がいったん落ち着いたことで電機や情報・通信、機械などを中心に幅広い業種が買われた。日本銀行が来週の金融政策決定会合で年6兆円ペースとしている上場投資信託(ETF)購入原則を削除する方針と報じられたが、市場の反応は限定的だった。 TOPIXの終値は26.14ポイント(1.4%)高の1951.06 日経平均株価は506円19銭(1.7%)高の2万9717円83銭 <きょうのポイント> 【米国市況】株が最高値、ハイテク中心に買い-大型刺激策を意識 バイデン米大統領、1兆9000億ドル規模の追加経済対策法案に署名 日銀、「年6兆円ペース」のETF購入原則を削除する方向-報道 岡三アセットマネジメントの前野達志シニア・ストラテジストは「米国の追加経済対策が決まり金利上昇も落ち着いている。景気は悪くなく企業収益もそのうちついてくるということで悪い材料はない」と指摘した。 一時下落に転じるなど朝方の主要指数は方向感に乏しかったものの、午後にかけて堅調に推移し、日経平均の上げ幅は500円を上回った。米長期金利の上昇が小康状態なのも支えとなり、ソニーやキーエンス、出資先が米国上場したソフトバンクグループ、日本郵政の出資が報じられた楽天などが買われた。 日銀のETF購入で「年6兆円ペース」原則が削除方向との報道に関して、みずほ証券の倉持靖彦マーケットストラテジストは、「観測はすでに出ておりマーケットへの影響は限定的」と指摘した。 東証33業種では、金属製品や電機、海運、機械、鉄鋼、情報・通信などが上昇 電気・ガス、不動産、陸運が下落【日本株週間展望】底堅い展開、日米金融政策にらむ-景気期待根強い 3月3週(15ー19日)の日本株は底堅い展開となりそうだ。内外金融政策の行方を確認したいとして全般は様子見ムードが強いものの、米国景気の根強い回復期待に加えて金融緩和の継続姿勢が確認できれば下支えとなる。 注目イベントは16、17日に開催される米連邦公開市場委員会(FOMC)と、18、19日の日本銀行の金融政策決定会合。米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長は4日にハト派メッセージを発したものの、市場は失望して株価下落の引き金となった。パウエル議長はより緩和的な政策をより長くというスタンスを再確認するとの期待がある。 一方、日銀が予定している金融緩和の「政策点検」では、上場投資信託(ETF)購入を市場の状況に合わせて調節する方法に変更されると9割のエコノミストが予想。ただ、2月からETF買い入れの基準を厳格化したとの観測が出ている市場では織り込み済みとする見方が多い。 米国では大型の追加経済対策が成立し、個人への直接給付が始まる見通しで景気先行きへの期待が高まりやすい環境にある。米金利上昇の勢いが鈍化し、内外金融政策イベントはマイナスに働きにくい。このほか、経済指標では米国で15日に3月のニューヨーク連銀製造業景況指数、16日に2月の小売売上高などがある。中国では15日に1-2月の工業生産や都市部固定資産投資などが公表される。2週のTOPIXは週間で2.9%高と続伸だった。 《市場関係者の見方》 三井住友トラスト・アセットマネジメントの上野裕之シニアストラテジスト 「イベントの多い週だが、底堅さを示しそうだ。米国では経済対策成立でリーマンショック後を上回る巨大な財政支援が続くことになり、個人消費は相当に戻る可能性がある。市場は金利をみて動いているため、金融政策当局のスタンスが変わらないことは重要。欧州中央銀行(ECB)に続き、FOMCで米国の緩和スタンスが明確になって各国中銀の足並みがそろうことが安心感につながり、米テクノロジー株が多少戻すことも考えられる。日銀は政策を点検するにすぎず、基本的に政策の方向性は変わらない」 岡三アセットマネジメントの前野達志シニア・ストラテジスト 「日米中銀は市場を驚かすことはなく、日経平均のレンジは2万9000円-3万円を予想。日銀の点検では、いろいろな人が何が出てくるかを匂わせる発言をしており織り込まれているとは思う。米国については見方は分かれている。米国がインフレだった時期を知っている人はFRBがインフレに対して楽観過ぎと思う人もいれば、知らない人は今のままでいいのではないかという人もいる。FRBが何を言うのかと同時に、市場がどう反応するか注目だ」米国株が最高値、ハイテク中心に買い-大型刺激策を意識 11日の米株式相場はハイテク銘柄中心に上昇。S&P500種株価指数とダウ工業株30種平均が最高値を更新した。連邦政府による1兆9000億ドル(約206兆円)規模の追加経済対策が意識された。 米国株は上昇、S&P500とダウが最高値-ナスダック反発 米国債は下落、10年債利回り1.54% ドル下落、対円では108円半ば NY原油は約1週間ぶり大幅高、需要回復の兆しで 金スポットは上げ失う、米国債利回り持ち直しで S&P500種はテクノロジー株や一般消費財銘柄などが幅広く上昇。大型ハイテク銘柄中心のナスダック100指数は、2月に付けた最高値を11%下回った下落局面からの持ち直しが続いた。半導体銘柄がハイテクの上昇を主導した。 ツイッターも大幅高となり、テスラも株価回復が続いた。上場初日となった韓国の電子商取引大手クーパンは41%値上がり。 S&P500種は前日比1%高の3939.34。ダウ平均は188.57ドル(0.6%)高の32485.59ドル。ナスダック総合指数は2.5%上昇。 米国債市場では、30年債入札後に10年債利回りが上げ幅を縮小。ニューヨーク時間午後4時59分現在、同利回りは2ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の1.54%。先週の米新規失業保険申請件数は前週比で予想よりも減少し、昨年11月初め以来の低水準となった。バイデン大統領は1兆9000億ドル規模の追加経済対策法案に署名した。 TIAAバンクの世界市場担当プレジデント、クリス・ギャフニー氏は「米政権は法案によって株式市場に若干の追加燃料を注入した。これはロケット燃料になる」と指摘。「最高値更新の背景には、刺激策で世の中に投じられる資金の存在がある。最初数回の景気対策プログラムよりも広範なものだ」と述べた。 外国為替市場ではドルが下落。ドル指数は3日続落し、1週間ぶりの安値を付けた。主要10通貨ではスイス・フランの上昇が目立ったほか、原油高を追い風に資源国通貨も値上がりした。 主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.5%低下。ドルは対円では0.1%高の1ドル=108円51銭。ユーロは対ドルで0.5%高の1ユーロ=1.1986ドル。 ニューヨーク原油先物相場は続伸。約1週間ぶりの大幅高となった。米国の州間幹線道路で車両走行距離が増加したとのデータや、英国での道路利用拡大を示すデータなど、燃料消費の回復が勢い付いている兆候が注目された。 ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物4月限は1.58ドル(2.5%)高の1バレル=66.02ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント5月限は1.73ドル高の69.63ドル。 金スポット相場は米10年債利回りの持ち直しを背景に上げを失った。ニューヨーク時間午後2時35分現在では前日比変わらずの1オンス=1721.40ドル。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物4月限は0.1%高の1722.60ドルで終えた。アドビ世界的にデジタル化の加速が止まりません。消費者はこれまで以上にオンライン経由で買い物をし、モバイルアプリやSNSを通じて人とつながり、無数のデジタルチャンネルからコンテンツをストリーミングしています。顧客のロイヤルティを獲得するには企業はこうした変化について行かなければなりません。つまり、マーケティングのコンテンツをより個々の顧客に合った適切なチャネルを通して行うことが、意図した顧客へのアプローチに必要になります。この点では、アドビ(NASDAQ:ADBE)のエクスペリエンス・クラウドはAIベースのソフトウエアやサービスを取り揃えており、マーケティング企業が消費者データを利用して個々の顧客に高い精度で合ったデジタルエクスペリエンスを作り出すこと支援をします。この市場における同社の競合はセールスフォースやオラクルですが、クリエイティブなコンテンツとデータ・サイエンスを融合する能力においてアドビに並ぶものはありません。アドビのクリエイティブ・クラウドのアプリのラインナップには写真加工のPhotoshop、SNSやウェブデザイン作成ソフトのSpark、ビデオ編集のPremiere Pro、ウェブやモバイルアプリデザインソフトのAdobe XDなど、よりトータルなソリューションの提供でライバルのずっと先を走っています。こうした強みから売上は急激に伸びていますが、フリーキャッシュフローの拡大はそれをしのぐ勢いを見せており、今後の利益率の上昇が期待できます。2017年度と2020年度の比較では、売上は73億ドルから129億ドルに増加(CAGRは21%)、フリーキャッシュフローは27億ドルから53億ドルに増加(CAGRは25%)していますアドビは最近、マーケティングワークフロー管理プラットフォームを提供するワークフロントを買収しました。コンテンツ作成者とマーケティングチームとの連携をより円滑にする支援ツールを自社の製品ポートフォリオに加えたことで、アドビは顧客により大きな価値を提供することが可能になります。また注目すべきは、アドビの顧客の上位100社のうち、同社製品を3種類以上利用する顧客の割合は2015年の61%から2020年には93%に増えました。これは、より多くの顧客が同社のエクスペリエンス・クラウドへの依存度が高くなっているという意味で、ベンダー乗り換えにかかるコスト増を背景に、顧客の囲い込みが成功しているということです。今後については、投資家は同社の売上成長と粗利益率に注目すべきです。マーケティングは競争が激しい分野です。アドビの売上成長の鈍化や利益率の縮小が見受けられれば、強みが後退している現れです。しかし、同社経営陣は自社の市場機会は2023年までに直近12カ月の同社売上の10倍に相当する1470億ドルに達すると予測しており、長期的な成長に楽観的です。【本日のNYダウ見通し】連日で過去最高値を更新するかに注目【NYダウ予想レンジ:32,300~32,700ドル】11日のNYダウは5日続伸。前日比188.57ドル高の32,485.59ドルで引け、過去最高値を更新しました。朝方に発表された新規失業保険申請件数が71.2万件と予想以上に減少し、労働市場回復への期待がでてきたことを好感した買いが入りました。また、12日に予定されていたバイデン大統領の追加経済対策法案への署名を、11日に前倒しすると発表。1,400ドルの直接給付が3月中に実施される見通しとなったことも、マーケットの期待を高めました。そして30年債の入札が無難な結果となり、米10年債利回りも1.5%台前半で推移。金利上昇懸念が薄れたことでハイテク株にも買いが入り、ナスダック総合株価指数も329.841ポイント高の13,398.673と大幅に反発しています。14時半時点のNYダウ先物は86ドル高となっており、しっかりとした展開で始まりそうです。本日の経済指標では生産者物価指数とミシガン大学消費者信頼感指数に注目。本日もNYダウ過去最高値を更新して終了するかどうかに関心が集まるでしょう。米10年債利回り上昇が加速、1.60%上回る=ロンドン市場[アムステルダム 12日 ロイター] - 12日序盤のロンドン市場で、米国債の利回りが急上昇。10年債利回りが1.60%を上回った。アジア市場でも上昇基調にあったが、ロンドン市場の寄り付きととともに上昇が加速した。0735GMT(日本時間午後4時35分)時点では6ベーシスポイント(bp)上昇の1.58%で推移している。米30年債利回りは8bp上昇し2.371%。約2週間超ぶり高水準を付けている。日経平均は506円高、米長期金利上昇一服で安心感:識者はこうみる[東京 12日 ロイター] - 東京株式市場で日経平均は4日続伸した。米長期金利の上昇が一服したことに加え、メジャーSQ(特別清算指数)算出を通過したことを受け、市場全体に安心感が広がり、ハイテク株を中心に買い戻す動きが活発化した。市場関係者に見方を聞いた。●やれやれ売りと配当権利取りの買い交錯に<岡三オンライン証券 チーフストラテジスト 伊藤嘉洋氏>メジャーSQ(特別清算指数)算出を通過したことによって、上ぶたが外れた格好になったが、週末という事情、さらに来週は米連邦公開市場委員会(FOMC)や日銀の金融政策決定会合など重要イベントが控えていることを考慮すると、先物の買い戻しによって大幅上昇したと思われる日経平均が2万9500円前後に位置する25日移動平均線を上回ってきたため、短期筋にとっては買い戻さざるを得ない状況になったのだろう。ここにきて相場が戻り歩調となったのは、急上昇していた米長期金利が落ち着いたことにほかならない。上昇相場が過剰流動性に支えられてきた現実がある以上、今回の調整は当然の流れだった。金利上昇は景気回復期待を示す好材料であるのは事実としても、需給面でみれば「良い金利上昇」などはあり得ない。日本株については、戻り相場に弾みを加えてきたが、日経平均で3万円以上では商いを消化していたためシコリ感が強く、やれやれの売りがかさみそうだ。一方、期末を控えて配当の権利取りが活発化するとみられ、売り買いが交錯して伸び悩む可能性がある。目先は、FOMCや日銀政策決定会合などのイベントが注目される中、神経質な展開となりそうだ。●パウエル議長の市場との対話が注目点<三菱UFJモルガンスタンレー証券 チーフ投資ストラテジスト 藤戸則弘氏>急騰によって株式市場の調整を促した米長期金利は、1.5%台前半で落ち着いており、日米の株価は反発に転じている。本来なら、金利が上昇に転じる初期局面は、企業業績の好調を示すものであり、その意味で4日のパウエル米連邦準備理事会(FRB)議長発言は正論である訳だが、あまりにも市場との対話が下手過ぎた。その意味で、2013年のバーナンキ・ショックを思い出す。当時は、発言後に米ダウは1カ月で6%下落、日経平均は22%下落。米長期金利上昇は他国の通貨安も伴うため、とりわけ新興国へのダメージが大きく、ブラジルのボベスパ指数はおよそ半値までの下落を演じた。今回も、現時点でテーパリング(量的金融緩和の縮小)に踏み込むことになれば、同様の状況が訪れても不思議ではない。長期金利については、緩慢な上昇であれば、そこから企業業績の好調を買い、株価が上昇するというロジックが成り立つが、急激な上昇となれば今回のように明らかに株価のマイナス材料になるだろう。当面はパウエル議長の市場との対話が注目点となってくる。いずれにせよ、経済が正常化に進んでいることは確かなため、大きな流れとしての株価上昇トレンドには変化がない。ただし、日本株については、米国との間に景況感格差、その根底にはワクチン業績の格差が生じており、今後、日本株は米中好景気による輸出増から上昇するとしても、出遅れる可能性がある。バーナンキ・ショックのような事態になれば、下げ方も相対的に大きくなるかもしれない。テーパリングの議論による大きな調整が想定されるため、通常のバイ・アンド・ホールドではリスクがあり、ポートフォリオのきめ細かなケアが必要になりそうだ。●日欧金融当局のサポートで市場に安心感<大和証券 チーフテクニカルアナリスト 木野内栄治氏>来週に米連邦公開市場委員会(FOMC)や日銀の金融政策決定会合など重要イベントを控えている中、懸念される米長期金利の上昇についてパウエル連邦準備理事会(FRB)議長が歯止めに失敗したことを日銀、欧州中央銀行(ECB)と日欧でサポートした格好となり、これが株式市場で安心感を誘ったようだ。米国を含めて各国中央銀行とも、長期金利の上昇を好んでいないとみられ、パウエル議長がFOMC後に長期金利上昇に対して明確にくぎを刺すことが期待されている。一方、当面の株式市場で注意しなければならないのは需給面だろう。きょう算出されたメジャーSQ(特別清算指数)に絡んだ注文は買い優勢だったと推測されるものの、板が厚くなったところに実需売りがぶつけられた形跡がある。投資主体別売買動向で信託銀行の売りが注目されているが、3月期末を控えてこうした売りによる需給悪化が懸念される。特に、昨年来買われた銘柄については注意が必要になりそうだ。米株はS&Pとダウが最高値更新、経済対策法案の成立などで[11日 ロイター] - 米国株式市場は主要株価3指数が上昇して取引を終えた。S&P総合500種とダウ工業株30種は最高値を更新。インフレ懸念が緩和する中、新規失業保険申請件数の減少や新型コロナウイルス追加経済対策法案の成立を受け、景気回復への期待が強まった。最近値下がりしていた大型ハイテク株のマイクロソフト、アップル、フェイスブック、アマゾン・ドット・コムが上昇を主導し、S&Pは2月16日に付けたこれまでの最高値を上回った。ダウが最高値を更新するのは4営業日連続。ハイテク銘柄が多いナスダック総合は、2月12日に付けた最高値を今週初めに10%超下回り調整局面入りが確認されたが、現在は5%弱下回る水準まで持ち直している。バイデン大統領は11日、1兆9000億ドル規模の新型コロナ追加経済対策法案に署名し、同法は成立した。11日に発表された3月6日までの1週間の新規失業保険申請件数は71万2000件と、前週の75万4000件から減少。市場予想は72万5000件で、予想以上に改善した。この日の上昇はテクノロジー株が主導したものの、昨年11月以降グロース(成長)株をアウトパフォームしてきたバリュー株に資金をシフトさせる動きも続いた。11日に実施された240億ドルの30年債入札は、先月の7年債入札のような低調な結果とはならず、インフレ懸念の高まりにはつながらなかった。グレンミードのプライベートウェルス部門最高投資責任者(CIO)、ジェイソン・プライド氏は、2月の消費者物価指数(CPI)統計が落ち着いた内容となったことに言及し、インフレ懸念は緩和しているとの見方を示した。S&Pの主要セクターでは工業と通信サービスが最高値を付けた。投資家の不安心理を示すシカゴ・オプション取引所(CBOE)のボラティリティー・インデックス(恐怖指数、VIX)は2週間ぶりの低水準を付け、インフレ懸念が後退している兆候を示した。ソフトバンクグループが出資する韓国のネット通販大手・クーパンはこの日、ニューヨーク証券取引所に上場。初値は63.50ドルと公開価格(35ドル)を81%上回った。終値は40.7%高の49.25ドルで、時価総額は850億ドルとなった。同社のIPOは米市場としては今年最大。同社は新規株式公開(IPO)で1億3000万株を売却し、46億ドルを調達した。マッチングアプリ運営のバンブルは10.8%高。第4・四半期売上高が予想を上回ったことや需要見通しが好感された。映画館チェーン大手、AMCエンターテインメントは4.36%高。新型コロナワクチンの普及や大作映画の公開により今年の売上高が押し上げられるとの見通しを示した。ソフトウエア大手・オラクルは6.5%下落。アマゾンやマイクロソフトとの競争が激化し、四半期決算でクラウド部門の売上高が市場予想に届かなかったことが嫌気された。米取引所の合算出来高は130億2000万株。直近20営業日の平均は148億7100万株。ニューヨーク証券取引所では値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を3.10対1の比率で上回った。ナスダックでは3.87対1で値上がり銘柄数が多かった。【市況】来週の株式相場に向けて=今春最大のヤマ場「中銀ウイーク」に突入 来週の株式相場は、米国と日本の金融政策の行方を注視することになる。日経平均株価の予想レンジは2万9400~3万200円。3万円奪回なるかが焦点となる。 この週の日経平均株価は前週に比べ853円(3.0%)高と3週ぶりに上昇。週末にかけ値を上げ2万9700円台に乗せ25日移動平均線(2万9490円前後)も上回ってきた。来週は、何といっても16~17日の米連邦公開市場委員会(FOMC)と18~19日の日銀金融政策決定会合に関心は集中する。FOMCでは金融政策は据え置きの見通しだが、パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長の発言や政策金利見通し(ドットチャート)などが関心を集め、米長期金利がどう反応するかがポイントだ。 11日に開催された欧州中央銀行(ECB)理事会では、国債などの資産買い入れペースを加速することが決められ、その結果、金利上昇への過度な警戒感は和らいだ。「米長期金利の上昇は徐々に市場に織り込まれつつある」(市場関係者)との声もある。足もとの日米株価の上昇はFOMCを経て市場が落ち着きを取り戻すことを先取りしているようにみえる。 日銀会合では金融政策の点検結果が公表される。長期国債の変動幅拡大があるかに加え、株式市場ではETF買い入れ方針の変更が公表されるかが高い関心を集めている。来週の「中銀ウイーク」は今春相場の大きなヤマ場であり、ここを無難に乗り切れば3月下旬にかけて株式市場の一段の上昇が見込める。その場合、長期金利上昇で波乱状態にあった高PERのハイテク株などに見直し買いが入ることが期待される。 来週は、国内では15日に1月機械受注が発表され、週後半にかけて21日に期限を迎える首都圏1都3県の緊急事態宣言解除の是非を政府は判断することになる。個別企業では、15日に神戸物産とパーク24の決算が発表される。 更に3月IPOが始まり、16日にウイングアーク1stが東証1部に、ヒューマンクリエイションホールディングスが東証マザーズに新規上場する。18日にi‐plug、19日にはココナラとT.S.Iがともに東証マザーズに上場する。(岡里英幸)出所:MINKABU PRESS初日は日没サスペンデッド 幻の「63」から1年、松山英樹は暫定112位タイと出遅れ<ザ・プレーヤーズ選手権 初日◇10日◇TPCソーグラス(米フロリダ州)◇7189ヤード・パー72>第5のメジャーと呼ばれるPGAツアーのフラッグシップ大会、「ザ・プレーヤーズ選手権」の初日は日没サスペンデッドに。中止となった昨年大会の初日に「63」を叩き出した松山英樹だったが、今年は苦戦。1バーディ・3ボギー・1ダブルボギーの「76」で4オーバー・暫定112位タイと出遅れた。暫定首位に立ったのは7アンダーまで伸ばしたセルヒオ・ガルシア(スペイン)。2打差の暫定2位にブライアン・ハーマン(アメリカ)、4アンダーの暫定3位にはマシュー・フィッツパトリック(イングランド)、コリー・コナーズ(カナダ)、シェーン・ローリー(アイルランド)の3人がつけている。前週パー5で1オンを狙い話題を呼んだブライソン・デシャンボー(アメリカ)は3アンダー・暫定6位タイ。世界ランク1位のダスティン・ジョンソン(アメリカ)は1オーバー・暫定60位タイ、ローリー・マキロイ(北アイルランド)は「79」で7オーバー・暫定140位タイと大きく出遅れている。“プラチナ世代”安田祐香がプロ初の首位発進 渋野日向子10位、小祝さくら21位<明治安田生命レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント 初日◇12日◇土佐カントリークラブ(高知県)◇6228ヤード・パー72>2021年の国内女子ツアー第2戦は第1ラウンドが終了。6バーディ・1ボギーの「67」をマークした“プラチナ世代”安田祐香が、5アンダーで2019年のプロ入り後初となる首位発進を決めた。安田と同じく「67」で回った武尾咲希は首位タイで2日目へ。4アンダー・3位タイには永井花奈、森田遥、稲見萌寧、上原彩子が続いた。渋野日向子は3バーディ・1ボギーの「70」。2アンダー・10位タイと上々の位置で初日を終えた。2週連続優勝がかかる小祝さくらは1アンダー・21位タイ。連覇を狙う鈴木愛は1オーバー・47位タイ、明治安田生命所属のホステスプロ・勝みなみはトータル6オーバー・111位タイと大きく出遅れた。明日の戦略-4日続伸で週間でも大幅高、日米中銀イベントを前に地合いは急改善トレーダーズ・ウェブ 12日の日経平均は大幅に4日続伸。終値は506円高の29717円。米国株高を好感して上昇して始まったが、序盤の値動きは不安定となった。しかし、瞬間的に下げに転じた後は強い基調となり、上げ幅を大きく広げる展開。前場のうちに節目の29500円台に乗せると、後場はこれより上が定着して一段高となった。値上がり銘柄も増加する中、14時近辺では29700円台に到達。買いの勢いは緩まず、終値でも500円を超える上昇となった。TOPIXとマザーズ指数は高値引けとなり、マザーズ指数は3%近く上昇した。 東証1部の売買代金は概算で3兆6200億円。業種別では金属製品や電気機器、海運などが上昇した一方、電気・ガスや不動産、陸運などが下落した。資本提携観測が伝わった楽天と日本郵政が後場に入って急伸。半面、3Qは上期比で営業赤字が拡大した大塚家具が大幅安となった。 東証1部の騰落銘柄数は値上がり1243/値下がり844。SOX指数の大幅高を受けて、東京エレクトロンやアドバンテストなど半導体株が大幅高。ソフトバンクGやエムスリーなどグロース株が強く、ダイキンやキーエンスなど値がさ株にも買いが入った。航空部門の損益が改善すると報じられたIHIが急伸。上期決算が好感されたラクスルがストップ高まで買い進まれた。業績関連のリリースを材料に鎌倉新書がストップ高比例配分、はせがわが12%近い上昇と、エンディング関連を手掛ける銘柄が急騰した。 一方、ファーストリテイリングが逆行安。東急不動産や野村不動産など不動産株が軟調となった。相鉄や西武が大幅安となるなど、鉄道株も多くが下落。リスクオンの様相が強まる中、東北電力や九州電力など電力株が敬遠された。前期の着地が計画を下振れたCasaが大幅安。大型株優位の中でcolyやQDレーザ、アピリッツなど直近上場株が売りに押された。 来週は日米の中央銀行イベントが注目を集める。FOMCに関しては、直近のパウエルFRB議長の発言などから、早期の利上げなどタカ派的なアナウンスが出てくる可能性は低い。足元の長期金利の荒い値動きに関しても、ある程度容認するスタンスを示しており、このことが金利に対するケアがないとして蒸し返されるのかどうかが、一つの焦点となる。再度の金利上昇を促した場合には、グロース株には逆風となる。 日銀に関しては、ETFの買い入れ方法の見直しなどが出てくる可能性がある。ただ、指数寄与度の大きいファーストリテイリングなどには先んじて調整が入っている。マイナス金利の深掘りなど、不人気策が浮上してきた場合には、株式市場を大きくかく乱する可能性もあり要注意。とは言え、日銀もこの時点で緩和スタンスそのものを修正してくるとは考えづらい。来週はまだ上下に振れるかもしれないが、中央銀行イベント通過後には、遅かれ早かれマーケットは落ち着きを取り戻すと予想する。冷静に対処したい局面だ。 もう一つ、1都3県の緊急事態宣言が解除されるかどうかも重要なポイントとなる。延長期限が3月21日に控えているが、今のところ新規感染者の明確な減少は確認できていない。再延長ということになった場合、2週間程度ではおさまらない可能性がある。また、その際には外食などにはさらに厳しい制限が加えられることも想定される。解除した場合でも、花見シーズンで「密」状態が大量発生する懸念があり、政府の判断も難しい。関連ニュースとともに、外食、レジャー関連の動向を注視しておく必要がある。「アフターコロナ」関連が失速してしまうようだと、バリュー株には逆風となる。【来週の見通し】 不安定な展開か。FOMC(3/16~17)、日銀金融政策決定会合(3/18~19)と中央銀行イベントが続く。足元では米国の長期金利がマーケットをかく乱していること、また、日銀は今回の会合でこれまでの政策の点検を行う予定であることから、両イベントともに通常以上に注目を集めることになるだろう。FOMCの結果を東京市場で消化するのは18日木曜、日銀の結果を消化するのは19日金曜の午後で、週前半は動きづらく、後半は荒くなりそう。金曜の後場だけでそれまでの流れが一変するといった展開もあり得る。両イベント前に不安定な動きも出てきたことから、これらを通過して株高加速というシナリオも十分期待でき、その可能性も高いとみる。ただ、黒田総裁の会見は金曜の引け後で、材料のすべてを消化しきれないという状況でもあることから、週末まで神経質な状況が続くと予想する。【今週を振り返る】 堅調となった。引き続き米国の長期金利やこれを受けた米国株の動向に振り回されたものの、長期金利の上昇に一服感が出てきたことや、米国株に強い上昇が見られたことなどから、下値不安が和らいだ。物色では景気敏感系を中心としたバリュー株とハイテクを中心としたグロース株の綱引きのような状況が続いたが、金利上昇一服でグロース株に持ち直しの動きが見られたことは安心材料となった。日経平均は29000円や29500円など節目の水準をあっさり突破し、目先の底打ち期待が高まった。日経平均は週間では約853円の上昇となり、週足では3週ぶりに陽線を形成した。【来週の予定】 国内では、1月機械受注(3/15)、2月貿易収支(3/17)、日銀金融政策決定会合(~3/19)、2月首都圏マンション販売(3/18)、黒田日銀総裁会見、2月全国消費者物価指数(3/19)などがある。 企業決算では、神戸物産、パーク24、三井ハイテ、トリケミカル、GA TECH、正栄食、Pアンチエイジ、セルソース、JMHD、ポールHD、シーアールイー、ACCESS、Hamee、稲葉製作、グッドコムA、ビジョナリー、MacbeeP、REVOLUTI、コナカ、システムディ、フロンティアI、イムラ封筒、ツクルバ、SKIYAKI、フィット、ジェネパ、HyAS&Co.、ジェイック(3/15)、ツルハHD、アスクル、ブシロード、coly、プロレド、フリービット、モロゾフ、バルニバーヒ、アールプランナ、LeTech(3/16)、サンバイオ、エニグモ、アルデプロ、ダブルエー、Mマート(3/17)などが発表を予定している。 海外では、中国2月鉱工業生産、中国2月小売売上高、中国2月固定資産投資、米3月ニューヨーク連銀景気指数(3/15)、独3月ZEW景況感指数、米2月小売売上高、米2月鉱工業生産、米3月NAHB住宅市場指数、FOMC(~3/17)(3/16)、パウエルFRB議長会見、米2月住宅着工件数(3/17)、米3月フィラデルフィア連銀景気指数(3/18)などがある。<週末コメント> ─ 来週の相場展望 ─ 2021年3月12日株探ニュース 今週の日経平均終値は2万9717円で、前週末比853円高でした。 日経平均は3週ぶりに反発し目先の下値を確認した格好となっています。今週も週前半に下値を一時的に試す場面がありましたが、13週移動平均線(2万8437円)に支えられる従来の形どおりの展開を維持しています。日々の東証1部の出来高も今週は先週より1~2割増しの状態でマネー流入の図式へ転換。バリュー株中心に幅広い物色がなされており安定感はかなり戻ってきているといえるでしょう。そうした市場の動きは東証1部上場全銘柄で算出される指数トピックスに反映されており、こちらは週間の終値ベースで昨年来の高値を更新。先々週の週足大陰線を埋めるなど上昇基調回帰が鮮明です。今の市場の動きはバリュー株中心の緩やかな底上げが進行しているということを裏付けています。一部のハイテク(グロース)株だけで指数がけん引される相場よりも健全で内容あるものとなっています。これは日米などの景気回復がベースにあるためで、金利の一段の上昇は気にする必要がありますが、基本的にはしばらく安定した基調を続けることを示唆しています。(ストック・データバンク 編集部)日経平均寄与度ランキング(大引け)~大幅に4日続伸、ソフトバンクGと東エレクの2銘柄で約140円分押し上げフィスコ現在値ソフトBG 10,635 +345東エレク 42,220 +1,810ダイキン工 22,975 +930ファナック 27,230 +900信越化 18,425 +89012日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり168銘柄、値下がり54銘柄、変わらず3銘柄となった。日経平均は大幅に4日続伸。11日の米国市場でNYダウは188ドル高と5日続伸し、連日で過去最高値を更新した。1.9兆ドル規模の追加経済対策が成立し、30年物国債入札が無難な結果で長期金利も落ち着きを見せた。本日の日経平均はこうした流れを好感して76円高からスタートすると、朝方こそマイナスに転じる場面があったものの、先物・オプション3月物の特別清算指数(SQ)算出を通過したこともあって上げ幅を拡大。後場には29744.32円(前日比532.68円高)まで上昇する場面があった。大引けの日経平均は前日比506.19円高の29717.83円となった。なお、SQ値は29282.41円。東証1部の売買高は15億8290万株、売買代金は3兆6235億円だった。業種別では、金属製品、電気機器、海運業が上昇率上位だった。一方、電気・ガス業、不動産業、陸運業など4業種が下落した。東証1部の値上がり銘柄は全体の57%、対して値下がり銘柄は38%となった。値上がり寄与トップはソフトバンクGとなり1銘柄で日経平均を約75円押し上げた。同2位は東京エレクトロンとなり、ダイキン工業、ファナック、信越化、アドバンテスト、エムスリーなどがつづいた。一方、値下がり寄与トップはファーストリテとなり1銘柄で日経平均を約5円押し下げた。同2位はTOTOとなり、アステラス製薬、住友不動産、宝ホールディングス、京成電鉄、SUBARUなどがつづいた。〔ロンドン外為〕円、109円台前半(12日午前9時)時事通信 【ロンドン時事】週末12日朝のロンドン外国為替市場では、米長期金利の上昇を眺めてドル買いが先行し、円相場は1ドル=109円台前半に下落した。午前9時現在は109円05~15銭と、前日午後4時(108円45~55銭)比60銭の円安・ドル高。 ユーロの対ドル相場は1ユーロ=1.1925~1935ドル(1.1955~1965ドル)。対円では同130円10~20銭(129円70~80銭)と、2年余ぶり高値圏。(了)病院クラスター1人増 岐阜県で新たに3人新型コロナ感染、1人死亡岐阜新聞Web 岐阜県は12日、新たに3市町で計3人の新型コロナウイルス感染と、入院していた土岐市の80代女性の死亡を発表した。県内の感染者数は累計4679人、死者は116人となった。 瑞浪市の東濃厚生病院と土岐市の高井病院のクラスターは、高井病院の医療従事者1人の感染が分かり、計33人規模となった。 一方、瑞浪市の市立みどり幼児園で確認されていた18人規模のクラスターは、終息を確認した。 11日時点の病床使用率は10・1%で、前日から2・1ポイント下がった。新規感染者の居住地別は土岐市、可児郡御嵩町、養老郡養老町が各1人。年代別は10代1人、20代2人。夕食の前にはこんなモノが届きました…2月26日のワインオークションでゲットした、2001&2002シャトー・マルゴーですね。暫くセラーでお休みください。今晩のNY株の読み筋=米2月PPIと米長期金利の動きに注意モーニングスター 12日の米国株式市場は、米2月PPI(生産者物価指数)を受けた米長期金利の動きに反応する可能性がありそうだ。 11日、バイデン米大統領が米両院で可決された1兆9000億ドル(約200兆円)規模の追加経済対策法案を1日前倒しで署名したことなどを好感し、NYダウ、S&P500が史上最高値を更新した。 追加経済対策法案が晴れて成立したことで、きょうのところは材料出尽くしとなり、高値警戒感からの利益確定売りや、週明けにFOMC(米連邦公開市場委員会)を控えることによるポジション調整の売りが出やすいとみられる。ただ、PPIが10日のコアCPI(消費者物価指数)同様に市場予想を下回り、米長期金利上昇を抑制できれば、金融緩和継続観測が相場を支援する可能性もありそうだ。<主な米経済指標・イベント>2月PPI(生産者物価指数)(日付は現地時間)◎投資関連情報は投資の参考として情報提供のみを目的としたものであり、株式の売買は自己責任に基づき、ご自身で判断をお願いします。来週の日本株の読み筋=上昇基調キープか、日米金融イベントは不安薄、日経平均の25日線奪回で安心感もモーニングスター 来週(15-19日)の東京株式市場は、上昇基調キープか。米長期金利上昇のきっかけになると警戒された米国債の入札を無難に通過し、いよいよ日米金融イベントを迎える。16-17日開催のFOMC(米連邦準備制度理事会)に続き、18-19日開催の日銀金融政策決定会合を控え、結果を見極めたいとの空気もあるが、金融当局が市場に冷水を浴びせるとは考えづらく、不安は薄いとみられる。 日経平均株価は、4日に25日移動平均線を下回った後、同線が上値抵抗線として意識されたが、それも12日の大幅高でクリアした。昨年10月末以降の上昇相場において、同線を割り込むたびに充電を済ませ、高値を更新するパターンを繰り返しており、足元の値動きは投資家に安心感をもたらす可能性がある。 スケジュール面では、上記以外に国内で15日に1月機械受注、19日に黒田日銀総裁の会見が予定されている。海外では15日に中国2月工業生産、中国2月小売売上高、中国2月都市部固定資産投資、16日に独3月ZEW景況感指数、米2月鉱工業生産・設備稼働率、17日にパウエルFRB(米連邦準備制度理事会)議長会見、米2月住宅着工件数などがある。 12日の日経平均株価は大幅に4日続伸し、2万9717円(前日比506円高)引け。朝方は、11日の米国株式市場で追加経済対策の成立や経済指標の改善を背景に主要3指数がそろって上昇した流れを受け、買いが先行した。いったん軟化し、小幅安に転じる場面もあったが、すかさず切り返した。先物主導で上昇し、上げ幅は一時530円を超えた。時間外取引で米ダウ先物が堅調となり、支えとして意識された面もある。市場では、「過剰流動性も先高期待も続いている」(準大手証券)との声が聞かれた。NY株見通し-底堅い展開か 経済指標は2月PPIなどトレーダーズ・ウェブ 今晩のNY市場は底堅い展開か。昨日は1.9兆ドルのコロナウィルス救済法案の成立が好感されたほか、長期金利の落ち着きを受けてハイテク・グロース株が買い直され、ダウ平均、S&P500、ラッセル2000が史上最高値を更新し、ナスダック総合は2.5%超の大幅反発となった。業種別ではITが2%超上昇したほか、コミュニケーション、一般消費財、不動産も1.5%以上上昇した。週初来ではダウ平均が3.14%高、S&P500が2.54%高、ナスダック総合が3.70%高となり、ラッセル2000は6.67%の大幅高となった。今晩の取引では、週末の持ち高整理の動きが上値圧迫要因となることが予想されるものの、追加経済対策やワクチン普及加速による景気の早期回復期待が引き続き相場の下支えとなりそうだ。 今晩の米経済指標・イベントは2月生産者物価指数(PPI)、3月ミシガン大消費者信頼感指数速報値など。主要な企業の決算発表はなし。(執筆:3月12日、14:00)〔NY外為〕円、109円近辺(12日午前8時)時事通信 【ニューヨーク時事】週末12日のニューヨーク外国為替市場の円相場は、午前8時現在1ドル=108円92銭~109円02銭と前日午後5時(108円45~55銭)比47銭の円安・ドル高で推移している。 ユーロは同時刻現在、対ドルで1ユーロ=1.1929~1939ドル(前日午後5時は1.1981~1991ドル)、対円では同130円02~12銭(同129円99銭~130円09銭)。(了)〔NY外為〕円、109円台前半(12日朝)時事通信 【ニューヨーク時事】週末12日午前のニューヨーク外国為替市場では、米長期金利が再び上昇する中、円売り・ドル買いが優勢となり、円相場は1ドル=109円台前半で推移している。午前9時現在は109円05~15銭と、前日午後5時(108円45~55銭)比60銭の円安・ドル高。 長期金利の指標である米国債10年物の利回りが海外市場で再び1.6%台に上昇した。これを受けて、円売り・ドル買いの流れとなり、ニューヨーク市場もこれを引き継いで始まっている。 米労働省が12日発表した2月の卸売物価指数(PPI)は前月比0.5%の上昇、エネルギーと食料品を除いたコア指数は0.2%の上昇だった。ほぼ市場予想通りだったことから、相場の反応は限定的だった。 ユーロは同時刻現在、対ドルで1ユーロ=1.1925~1935ドル(前日午後5時は1.1981~1991ドル)、対円では同130円05~15銭(同129円99銭~130円09銭)と、06銭の円安・ユーロ高。(了)〔米株式〕NYダウ、もみ合い=ナスダックは反落(12日朝)時事通信 【ニューヨーク時事】週末12日のニューヨーク株式相場は、米追加経済対策の実現が支えとなる一方、長期金利上昇への警戒感が重しとなり、もみ合いで始まった。優良株で構成するダウ工業株30種平均は午前9時35分現在、前日終値比64.24ドル高の3万2549.83ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は192.44ポイント安の1万3206.23。(了)今夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中の1銘柄が値を上げてスタートしましたね。大きく下げているものも散見されますね。来週の前半に買いに入って、来週の後半に売る…が正解でしょうか…。「BMW」の日本法人 販売店に過剰ノルマ 公取委が改善策を認定ドイツの自動車メーカー「BMW」の日本法人が、販売店に過剰なノルマを設定し、達成できない台数分を買い取らせていたとされる問題で、公正取引委員会は、BMW側の自主的な改善策を認定したことを明らかにしました。公正取引委員会は、おととし9月、BMWの日本法人「ビー・エム・ダブリュー」が、国内の販売店に過剰なノルマを設定し、達成できない台数分を買い取らせ、販売店の名義で新車登録するよう要求していたとして、独占禁止法違反の疑いで立ち入り検査し、調査を進めてきました。公正取引委員会によりますと、およそ60ある販売店のうち、40ほどの店で同様の行為が確認されたということです。これについて、12日、公正取引委員会は、ビー・エム・ダブリューが自主的に提出した、再発防止のための改善策を認定したことを明らかにしました。違反の疑いが持たれた行為は、おととし12月に取りやめられたということで、改善策では、販売目標は、販売店と協議して合理的な内容とすることや、販売店がトラブルを訴えられるよう外部の窓口を設けることなどが盛り込まれています。これにより排除措置命令などは出されないことになりますが、改善策が実行されない場合は認定は取り消されます。ビー・エム・ダブリューは「認定を真摯(しんし)に受け止めています。すでに、認定された計画の履行を開始しており、今後も順守してまいります」とコメントしています。国際基準アナフィラキシーは7人 厚労省、ワクチン安全性問題なし共同通信社 厚労省は12日、新型コロナワクチン接種後、重いアレルギー反応のアナフィラキシー発症が疑われた36人のうち、9日までに報告された17人を詳しく調べた結果、国際基準でアナフィラキシーに当たるのは7人だったと明らかにした。先行接種した人の健康調査では9割が翌日に痛みを訴えたことも分かった。12日開かれた専門部会に報告した。 残る10人は、十分な情報が得られないため判断できないか、アナフィラキシーではないと評価した。部会では「現時点で安全性に重大な問題はない」との結論になった。 9日までの接種は約10万7600人で、100万人当たり65人が発症した計算となる。
2021.03.12
コメント(2)
-
3月11日(木)…2021ラウンド17…
3月11日(木)、晴れです。風も程よく良い天気ですね。そんな本日はホーム1:GSCCの西コースで開催のシニア・レディス競技に参加させていただきました。10時20分スタートとのことですから7時15分頃に起床。新聞に目を通し、朝食を済ませ、ロマネちゃんと戯れる。身支度をして、8時45分頃に家を出る。9時15分頃にはコースに到着。代車のM135iは走らせる分には楽しいですね。フロントで記帳して、着替えて、練習場へ…。ショット…イマイチ…、パット…マアマア…。本日の競技は西コースのホワイトティー:6177ヤードです。ご一緒するのはセ君(12)、イさん(18)、ツ君(22)です。本日の僕のハンディは(8)とのこと。OUT:1.0.0.0.0.1.0.1.2=41(13パット)1パット:5回、3パット:0回、パーオン:2回。1打目のミスが5回、2打目のミスが1回、3打目のミスが1回、4打目のミスが1回、バンカーのミスが1回、アプローチのミスが3回…。なんとも締まりのないプレーです…。10番のスタートハウスでドーピング…。IN:1.1.0.1.0.1.0.0.1=41(14パット)1パット:4回、3パット:0回、パーオン:1回。1打目のミスが2回、2打目のミスが3回、3打目のミスが1回、アプローチのミスが4回、パットのミスが1回…。41・41=82(8)=74の27パット…。またしてもいいとこなしで終わりましたね…。コースに大量に砂がまかれてほぼ全面バンカー状態…。言い訳です…。カートからスコアを登録して、靴を磨いて、お風呂に入って、会計を済ませて、週末のゴルフをキャンセルして、早々に退散です。本日のフィジカルチェック…170.0cm,63.9kg,体脂肪率19.5%,BMI22.1,肥満度+0.5%…でした。近くのインターで高速に乗るとそのまま愛車のディーラーへひとっ走り…。ディーラーでリコール対応の澄んだ愛車を引き取って帰宅。コーヒーとレーズンサンドで遅いおやつタイム。本日の夕食はギョーザパーティーとのこと。それではしばらく休憩です。本日のクラブ競技の成績速報が出ていますね。ゴールドシニア(東コース)の部には22人が参加して、トップは89(19)=70とのこと。グランドシニア(東コース)の部には23人が参加して、トップは92(26)=66とのこと。シニア(西コース)の部には28人が参加して、トップは84(12)=72とのこと。僕は82(8)=74で6位。ツ君は96(22)=74で7位。レディス(西コース)の部には19人が参加して、トップは99(29)=70とのこと。お疲れ様でした…。1USドル=108.42円。1AUドル=84.37円。昨夜のNYダウ終値=32297.02(+464.28)ドル。本日の日経平均終値=29211.64(+175.08)円。金相場:1g=6675(+23)円。プラチナ相場:1g=4638(+77)円。昨夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中の5銘柄が値を上げて終了しましたね。5%以上の大きな変動は見られませんね。僕のチェックしている株とは違うところで上げていますね…。本日の東京市場ではチェック中の日本株30銘柄中の17銘柄が値を上げて終了しましたね。重点6銘柄では4銘柄が値を上げて終了しましたね。大阪有機化学が上げましたね。米ウィルと英GSK、コロナ治療薬の緊急使用許可を米などで申請へ[10日 ロイター] - 米ウィル・バイオテクノロジーと英製薬大手グラクソ・スミスクライン(GSK)は10日、共同開発した新型コロナウイルス抗体治療薬の良好な治験結果を受け、米食品医薬品局(FDA)に緊急使用許可を申請すると発表した。米以外でも許可申請を行う。治験の暫定データで、抗体治療薬「VIR―7831」がコロナ患者の入院と死亡の数を偽薬と比較して85%減らす効果が示されたのを受けた。両社によると、独立委員会は「高い有効性」が示されたため、後期臨床試験への被験者の追加登録を停止するよう勧告した。また、新たな臨床検査で英国、南アフリカ、ブラジル型のコロナ変異株に対しても同等の有効性があることが示されたとした。ウィルとGSKは昨年、コロナ治療薬開発での提携を発表した。きょうの国内市況(3月11日):株式、債券、為替市場Bloomberg News●日本株は続伸、米インフレ抑制と経済対策可決-サービスや小売り高い 東京株式相場は続伸。米国でインフレ圧力が抑制されていることが示され、金利が急上昇する懸念が後退した。米追加経済対策が下院で可決したことによる景気期待も加わり、サービスや小売り、銀行などの景気敏感業種の上げが目立った。 TOPIXの終値は前日比5.18ポイント(0.3%)高の1924.92 日経平均株価は175円08銭(0.6%)高の2万9211円64銭 野村証券の伊藤高志シニアストラテジストは「米消費者物価指数の結果が市場予想とほぼ一致したことでサプライズがなかったことは良い結果」と指摘。1.9兆ドルとほぼ満額の米追加経済対策が可決され、高額所得者は除かれるがこれまでで最大額の現金給付は「経済を押し上げると好感されるだろう」と話した。 東証33業種では、海運、非鉄金属、電気・ガス、サービス、建設、情報・通信が上昇 ゴム製品、陸運、空運、不動産、食料品、精密機器は下落●債券は大幅高、20年入札順調で超長期債中心に買いー利回りフラット化 債券相場は大幅高。日本銀行の政策運営を巡る不透明感がくすぶる中で実施された20年国債入札の結果が順調だったことで買い安心感が広がった。超長期債を中心に買い進まれ、利回り曲線はフラット(平たん)化した。 新発20年債利回りは一時、前日比4ベーシスポイント(bp)低い0.47%、5日以来の低水準 新発30年債利回りは一時4.5bp低い0.645% 新発10年債利回りは2bp低い0.10% 長期国債先物3月物の終値は16銭高の151円27銭。夜間取引軟調の流れで売りが先行して150円98銭まで下落したが、20年入札結果を受けて水準を切り上げ、一時151円28銭まで上昇 SBI証券の道家映二チーフ債券ストラテジスト 日銀サイドの情報発信をもろもろ考えると20年債入札には懸念があったが、事前の調整にもつながったことで結果は順調 米国債利回りの上昇一服もサポート要因となり、取りあえず買い安心感が生じている 3月は国債の償還も多いので、これまで債券の保有残高を落としていた投資家の需要もあったとみられる 20年債入札 最低落札価格は99円65銭、ブルームバーグがまとめた市場予想は99円60銭 投資家需要の強弱を反映する応札倍率は3.40倍、前回3.13倍 小さければ好調を示すテール(最低と平均落札価格の差)は10銭、前回11銭●ドル・円は上昇、米長期金利上昇でドル買い・円売り優勢―108円台後半 東京外国為替市場のドル・円相場は上昇。前日の海外市場で低下した米長期金利が上昇に転じたことでドル買い・円売りが優勢となった。短期筋の買い戻しが入ったほか、午後には国内勢のドル買いなどが相場を押し上げたとみられている。 ドル・円は午後3時23分現在、前日比0.3%高の108円75銭。朝方付けた108円36銭を安値に一時108円81銭まで上昇 円は主要10通貨全てに対して下落 米10年物国債利回りは時間外取引で1ベーシスポイント(bp)上昇1.52%程度。一時は約1.54%まで上昇 みずほ証券の鈴木健吾チーフFXストラテジスト ドル・円は4日連続で108円台前半で下値が固かったので短期筋のショートカバーが入ったほか、午後には年金勢とみられる国内信託勘定からのドル買いなどで一段高に 為替市場では米国のインフレ期待と10年金利が全てを握っている感じ。日本銀行による政策修正の可能性は国内債券市場の関心は高いが、為替市場では米金利がどう動くかが大事 米10年金利は1.6%台を維持できておらず、1.5%割れまで調整するとみており、ドル・円も徐々に上値が重くなってくるのではないか【本日のNYダウ見通し】本日もしっかりの展開か【NYダウ予想レンジ:32,000~32,500ドル】10日のNYダウは4日続伸。前日比464.28ドル高の32,297.02ドルで取引を終了し、2週間ぶりに過去最高値を更新しました。朝方発表された2月の消費者物価指数(CPI)は、総合指数が前年比で1.7%上昇したものの、食品・エネルギーを除くコア指数は1.3%となり予想を下回りました。マーケットではインフレ期待が高まっていますが、今回のCPIではその傾向がでなかったので米10年債利回りも1.5%台前半で落ちつき、株式市場の支援材料になったのです。また、バイデン大統領が提案した1.9兆ドル規模の経済対策が下院で可決。家計への現金給付(1人最大1,400ドル)などが景気を回復させるとの見方から、景気敏感株を中心に買いが入りました。ただハイテク株の上値は重く、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は4.993ポイント安の13,068.832で取引を終了しています。本日の経済指標では新規失業保険申請件数が発表されますが、米30年債の入札にも関心が集まるでしょう。本日もNYダウは続伸し、連日で過去最高値を更新するかどうかに注目です。日経平均は3日続伸、景気敏感株物色が下支え[東京 11日 ロイター] - 東京株式市場で日経平均は3日続伸した。前日の米国株式市場では、ダウ工業株30種が最高値を更新、日本株市場でも景気敏感セクターを中心に物色が活発になり、相場を下支えした。ただ、指数寄与度の高い半導体関連株が軟調に推移したことが重しとなり、上値を追う勢いは限定的だった。米追加経済対策の成立見通しが立ち、景気回復への期待感からマーケットでは景気敏感株を買う流れが加速している。市場からは「これまでは指数銘柄の上昇で日経平均は上値を追ってきたが、バリュー株は寄与度も低く、指数にはあまり影響が出ない。景気敏感株の物色は相場を下支えはするが、積極的に上値を追うのは難しそうだ」(岡三オンライン証券のチーフストラテジスト・伊藤嘉洋氏)との声が聞かれた。「目先としては、2万9000円―2万9500円のレンジ内で値固めの動きが続くのではないか」(伊藤氏)という。日経平均は先月末に急落して以降、徐々に値は戻しているが上値の重い状況が続いている。市場では「主要投資主体の動向をみると、信託銀行が1、2月は大きく売り越している。2月後半から株価が上昇し、株式のウエートが上がったとみられるが、足元ではリバランスの株売りが起きているのではないか。上値が重いのは、こうした需給要因が関係している可能性がある」(国内証券)との見方も出ていた。TOPIXは0.27%高で取引を終了。東証1部の売買代金は2兆8692億円。東証33業種中、海運業、非鉄金属、電気・ガス業、サービス業など21業種は値上がり。半面、ゴム製品、陸運業、空運業、不動産業など12業種は値下がりした。個別では、川崎汽船が12%高、日本郵船が7%高となるなど、海運株がしっかり。10日のバルチック海運指数が、前日比4.2%(79ポイント)高の1980ポイントとなり、2020年10月7日以来の高水準となったことが材料視された。東証1部の騰落数は、値上がり1558銘柄に対し、値下がりが570銘柄、変わらずが67銘柄だった。ダウが最高値更新、S&Pも上昇 インフレ懸念緩和[10日 ロイター] - 米国株式市場は、ダウ工業株30種が最高値を更新して取引を終えた。S&P総合500種も上昇。2月の消費者物価指数(CPI)データが落ち着いた内容となり、インフレ懸念が緩和した。バイデン大統領が掲げる1兆9000億ドル規模の新型コロナウイルス追加経済対策法案が下院で再び可決されたことも支援材料となった。経済再開に伴う消費支出拡大への期待から、エネルギーや金融といったセクターでは小型株と大型株の双方に買いが入り、昨年3月以降の市場の上げを主導してきた大型テクノロジー関連株から資金をシフトする動きが続いた。前日に4カ月ぶりの大幅な上昇率を記録したナスダック総合はこの日、値動きの荒い展開となる中、小幅に下落して引けた。新型コロナウイルスワクチンの普及で景気回復が加速するとの見方や大規模な追加経済対策を背景にしたインフレ懸念の高まりから米国債利回りが上昇し、ナスダック総合は数日前、2月12日に付けた終値での最高値を12%下回り調整局面入りしていた。しかし、10日に実施された380億ドルの10年債入札は、懸念されていたほど低調とはならず、入札結果を受け10年債利回りは一時1.506%に低下した。[nL4N2L8441]ジャニー・モンゴメリー・スコットのチーフ投資ストラテジスト、マーク・ラスチーニ氏は「市場は落ち着きを見せているようで、国債価格は上昇した。ただ、ハイテク(株)を支援するには至らなかった」と語った。アップル、アマゾン・ドット・コム、フェイスブック、テスラ、マイクロソフトは軒並み下落。一方、S&Pの小型株指数の上昇率はS&P総合500種をアウトパフォームした。ニューヨーク証券取引所に上場したオンラインゲームプラットフォーム、ロブロックスは活発に取引され、54%高で終了。時価総額は約450億ドルとなった。ゲーム販売のゲームストップは、1月下旬の急騰時に付けた水準に迫る中、ニューヨーク証取が複数回にわたって売買を停止し、株価が乱高下した。その他の「ミーム株」(ネットの情報拡散で取引される銘柄)であるステレオ・ヘッドフォン製造のコスは約70%高となった。米取引所の合算出来高は138億2000万株。直近20営業日の平均は151億5500万株。ニューヨーク証券取引所では値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を2.97対1の比率で上回った。ナスダックでは1.79対1で値上がり銘柄数が多かった。11日の日本株は続伸、上昇が目立った業種は?アメリカの追加経済対策可決を好感ブルームバーグ東京株式相場は続伸。米国でインフレ圧力が抑制されていることが示され、金利が急上昇する懸念が後退した。米追加経済対策が下院で可決したことによる景気期待も加わり、サービスや小売り、銀行などの景気敏感業種の上げが目立った。野村証券の伊藤高志シニアストラテジストは「米消費者物価指数の結果が市場予想とほぼ一致したことでサプライズがなかったことは良い結果」と指摘。1.9兆ドルとほぼ満額の米追加経済対策が可決され、高額所得者は除かれるがこれまでで最大額の現金給付は「経済を押し上げると好感されるだろう」と話した。債券相場は大幅高。日本銀行の政策運営を巡る不透明感がくすぶる中で実施された20年国債入札の結果が順調だったことで買い安心感が広がった。超長期債を中心に買い進まれ、利回り曲線はフラット(平たん)化した。東京外国為替市場のドル・円相場は上昇。前日の海外市場で低下した米長期金利が上昇に転じたことでドル買い・円売りが優勢となった。短期筋の買い戻しが入ったほか、午後には国内勢のドル買いなどが相場を押し上げたとみられている。シンバイオが続騰、アデノウイルス感染症治療薬の臨床試験申請がんや血液領域を軸にした希少疾患薬に特化して新薬を開発しているジャスダックのシンバイオ製薬(4582)が続騰している。午後0時31分現在、前営業日比111円(10.7%)高の1146円で推移している。一時は1155円まで上伸した。本日午前8時30分に、主に小児を対象としたアデノウイルス感染症に対する抗ウイルスブリンシドフォビル注射に関する第2相臨床試験に向けて、FDA(米食品医薬品局)に治験許可申請を行ったと発表し、好感された。(取材協力:株式会社ストックボイス)銀行株への資金流入続く、金利上昇と資金シフトが追い風三菱UFJフィナンシャルグループ(8306)など銀行株が強含み。当社は11時05分時点で前日比5円(0.8%)高の596.5円、三井住友フィナンシャルグループ(8316)が37円(0.9%)高の3999円、みずほフィナンシャルグループ(8411)が5円(0.3%)高の1602.5円といずれも買いが優勢。特段、個別材料は確認されていないが、足元のアメリカの長期金利上昇による業績改善期待が続いているようだ。直近の同国10年債利回りが1.5~1.6%付近で推移、きょうも時間外で1.533%付近となっている。また、日米株式市場では年金ファンドとみられる大口投資家が前年の相場を牽引したハイテク・グロース株からバリュー株へ資金をシフトする動きが出始めており、バリューの代表格で特に出遅れ感の強かった銀行株を見直す動きがあるようだ。(取材協力:株式会社ストックボイス)ナスダック軟調でも、NYダウがあっさり最高値更新のワケNYダウは終値で初の3万2000ドル台ブルームバーグ10日の米株式相場はS&P500種株価指数とダウ工業株30種平均が続伸。米消費者物価指数(CPI)が低調だったことを受けて、バリュー株へのローテーションの動きが再開した。米国債利回りは10年債入札後に下げに転じた。S&P500種は金融株や素材銘柄を中心に上昇。2営業日の上昇率としては、2月初旬以来で最大となった。2月の米CPIで食品とエネルギーを除くコア指数の伸びが市場予想を下回ったことを受け、経済成長が上向いた場合に物価が急上昇するとの懸念が和らいだ。ダウ平均は最高値を更新し、終値で初めて3万2000ドルを上回った。前日に反発していたテクノロジー株は下落。S&P500種は前日比0.6%高の3898.81。ダウ平均は464.28ドル(1.5%)高の32297.02ドル。ナスダック総合指数は0.1%未満の下落。ニューヨーク時間午後4時59分現在、米10年債利回りは1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の1.52%。ニューヨーク・ライフ・インベストメンツのポートフォリオストラテジスト、ローレン・グッドウィン氏は、債券利回りの上昇トレンドは経済成長の見通しと整合的だと指摘。こうした環境はディフェンシブ資産よりもシクリカル資産に有利で、「債券よりも株式の支えになるほか、ドル安を促す」と述べた。外国為替市場ではドルが下落。カナダ・ドルはほぼ変わらず。カナダ中銀は量的緩和を現行ペースで維持し、フォワードガイダンスも変更しなかった。主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.3%低下。ドルは対円で0.1%安の1ドル=108円38銭。ユーロは対ドルで0.2%高の1ユーロ=1.1929ドル。ニューヨーク原油先物相場はもみ合いの末に反発。2週間ベースで最も大幅なガソリン在庫減を示す米週間統計と、需要回復の兆しが注目された。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物4月限は43セント(0.7%)高の1バレル=64.44ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント5月限は38セント高の67.90ドル。ニューヨーク金先物相場は続伸。ドルの下落に加え、米10年債入札後に利回りが下げに転じ、金の代替投資需要が持ち直した。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物4月限は0.3%高の1オンス=1721.80ドルで終了。金スポットはニューヨーク時間午後3時31分時点で0.4%高の1723.90ドル。【市況】明日の株式相場に向けて=「青天井相場」は幻か きょう(11日)の東京株式市場は、日経平均株価が175円高の2万9211円と3日続伸。2月下旬以降はボラティリティの高い地合いが強く意識されるようになったが、それは全体指数が下りのエスカレーターに乗ったからという事情もある。 日経平均3万円大台近辺では強弱感が対立して日々の値幅も小さかったが、ひとたび下に放れると“引力の作用”が働くのが相場だ。エスカレーターではなくジェットコースターに乗せられたような気分になりがちで、実際の値幅以上に下値リスクに対する緊張感がそうさせる。「天井三日底百日」という有名な言葉も人間の頭で考えた相場格言らしさが出ている。少なくとも、2012年12月のアベノミクス相場スタート後の8年間あまりを振り返って、実際問題として底百日とは無縁であった。売り方の立場に立てばよく分かる。昨年3月のコロナ暴落後の直近1年はどうだったかといえば「底三日で青天井」という空売り筋にとっては非常に怖い相場が繰り広げられた。 今は新型コロナウイルスという未知の敵と遭遇し、相場との距離感がつかみにくくなっている。ここ1年間の株高が行き過ぎた超金融相場によるもので、眼前に業績相場につなぐ橋が架けられていないとすれば、いったんは大幅な株価調整局面やむなしということになる。しかし、日米欧の中央銀行がうまくバランスをとりながら金融政策を軟着陸させれば、つまり業績相場へつなぐ時間を稼げるのであれば、コロナマネーが縮小しても株式市場は巡航速度で上値追い態勢を維持できる。その意味で今は重要な時期にきていると思われる。やや短絡的な言い方ながら、来週のパウエルFRB議長の会見とそれに対するマーケットの受け止め方は、今後を占ううえでも一つの分岐に差しかかっているといえそうだ。 きょうの相場で圧巻だったのは、何といっても海運株。前日取り上げた明治海運や前週紹介した飯野海運、共栄タンカーはもちろん、日本郵船、商船三井、川崎汽船の大手3社の株価が文字通りビッグウェーブに乗った。この流れが幕間つなぎではないバリュー株投資の入口となるのかどうかに注目したい。 個別では、インタートレードが再びエンジン始動の気配。同社株は急騰性があるが、株価が急速に切り上がると空売りの仕掛けが入るのか下押すスピードも速い。そうした需給事情を踏まえたうえで、値動きを読む必要がある。暗号資産関連であり、ビットコイン価格が再び上昇傾向にあることから、ここはタイミング的には狙い目となる。また、ルーデン・ホールディングスも上向きに変わった5日移動平均線を足場に再浮上の兆し。 2次電池関連株も調整一巡から動兆する銘柄が出てきた。そのなか、次世代電池としての魅力を内包する「バイポーラ電池」を手掛ける古河電池が上値慕いの動きをみせておりマークしておきたい。また、藤倉コンポジットは非常用マグネシウム空気電池「WattSatt(ワットサット)」を手掛け、順調に需要獲得が進んでいる。このほか風力発電機用ブレード保護シートなど再生可能エネルギー周辺の商品を製造販売していることでテーマ買いの流れに乗るが、PBRが0.5倍を下回っていることは水準訂正余地の大きさを示唆する。 バリュー株の資質を有する低PBR銘柄は鉄鋼セクターにも多い。JFE系の鋳造専業メーカーの日本鋳造は25円配当を実施しながらPBRが0.4倍台と安値圏に放置されているが、程よい仕手性を内在させていることで個人投資家の短期トレード対象としても人気が高い。また、栗本鐵工所はPER、PBRともに極めて割安なだけでなく高配当利回りで技術力も高い。ナノテク技術から派生した磁気粘性流体の商品化などで需要を捉えている。鉄鋼セクター以外では、西日本を地盤とする配合飼料会社の日和産業がある。PBRは0.3倍台で300円台の株価には値ごろ感もある。最近はアクティビストが株価を突き動かすケースも増えているが、近い将来、超低PBR放置というわけにはいかない会社が相次ぐ可能性がある。その流れに乗って同社株などは意外高に進む素地がある。 あすのスケジュールでは、1~3月期法人企業景気予測調査、株価指数先物・オプション3月物のSQ算出など。海外では1月のユーロ圏鉱工業生産、2月の米生産者物価指数、3月のミシガン大学米消費者信頼感指数(速報値)など。(銀)出所:MINKABU PRESS新型コロナワクチンでのアナフィラキシー、原因物質調査を「10万人で17人」も精査の必要性、アレルギー疾患対策推進協議会(m3.com編集部) 厚生労働省のアレルギー疾患推進協議会(会長:東田有智・近畿大学病院病院長)は3月10日の会議で新型コロナウイルス感染症(COVID-19)ワクチン接種によるアナフィラキシーについて取り上げた。国立成育医療研究センター研究所免疫アレルギ ー・感染研究部 部長の松本健治氏は、同日までに約10万人への接種でアナフィラキシー疑いが17例報告されていることについて「10万人中17人は多い。1億人になると1万7000人くらい起こる可能性があるので、原因物質は調べないといけない」と指摘した(資料は厚労省のホームページ)。 松本健治氏は、これまでに原因物質としてポリエチレングリコール(PEG)の可能性が指摘されていることを紹介。一般に流通しているほとんどの化粧水や乳液などに使われており、国内の17人全員が女性、海外でも圧倒的に女性が多いことから、「茶のしずく石鹸を思い浮かべる現象だ。女性に多いのは化粧水などをよく使っていることが関わっているのではないかと考えている。もちろん今すぐ使用をやめるべきということではない」として、原因物質を調べる必要性を強調した。 国立病院機構三重病院院長の藤澤隆夫氏は、アナフィラキシーに関しては原因と診断の2つの問題があるとして、「PEGを使った皮膚テストが提唱されているが、感度・特異度が分からないので、事前にテストして偽陽性が出た場合にワクチンを打てる人が打てなくなるという問題がある」と指摘。また、報告例については注射の痛みやストレスで血管迷走神経反射を起こしているケースもあるのではないかとして、アナフィラキシーの正しい診断や対処方法の啓発を早急に行うよう求めた。東海大学医学部内科学系呼吸器内科学教授の浅野浩一郎氏も、米国CDC(疾病予防管理センター)に報告された175例のうち最終的にアナフィラキシーと診断されたのが21例にすぎないとして、「診断するかどうかで2回目の接種ができるかどうかに関わってくるので、非常に重要な問題だ」と述べた。 松本健治氏は、COVID-19流行の陰で他の呼吸器感染症が非常に少なくなっていることにも言及。インフルエンザが今シーズンはほとんどゼロに近く、ヘルパンギーナやアデノウイルス感染症、RSウイルス感染症も例年の数分の1から10分の1以下となっており、「感染症の減少は、アレルギーをはじめとする免疫疾患の増加と相関する」という衛生仮説から、乳幼児期にこうした感染症にならなかったことで「今のまま続くと、5年や10年後に喘息や花粉症が増える現象があるのではないかと心配している」と述べた。明日の戦略-3日続伸で底打ち期待が高まる、ECB理事会は株高を促すかトレーダーズ・ウェブ 11日の日経平均は3日続伸。終値は175円高の29211円。まちまちの米国株を受けて小安く始まったが、序盤にもみ合った後は、じわじわと上方向に勢いがつく展開。ダウ平均の最高値更新を受けて景気敏感株に改めて買いが入ったことに加えて、ナスダック安を受けてもグロース株売りがそこまで強くならなかったことから、全体としては底上げが進んだ。前場のうちに上げ幅を3桁に広げると、後場に入っても米株先物の上昇を横目で見ながら堅調相場が継続。29200円台に乗せて高値圏で取引を終えた。 東証1部の売買代金は概算で2兆8600億円。業種別では海運が7.7%高と突出した上げとなっており、ほか、非鉄金属や電気・ガスなどが強い上昇となった。一方、ゴム製品や陸運、空運などが軟調となった。ファーストリテイリングが後場に一段高となり、3%を超える上昇。半面、キーエンスが商いを伴って売られており、2%を超える下落となった。 東証1部の騰落銘柄数は値上がり1558/値下がり570。証券会社のリポートや海運指標の上昇を材料に、川崎汽船、商船三井、日本郵船の海運大手3社が急騰。明治海運や飯野海運など中堅どころにも買いが波及した。非鉄株が強く、大阪チタニウムと東邦チタニウムのチタン2社が大幅高。エムスリーや日本電産など、直近で売り込まれたグロース株にも見直し買いが入った。中期経営計画を発表した大阪ガスや、上方修正を発表したアゼアスが大幅高。2月の月次が好感されたスギHDが買いを集めた。 一方、ナスダック安への警戒から村田製作所やレーザーテック、SUMCOなどハイテク株が軟調。下方修正を発表した富士急行が値を崩しており、JR東海や西武HDなど鉄道株全般に売りが広がった。円安一服でブリヂストンやTOYOTIREなどタイヤ株が下落。決算が失望を誘ったトビラシステムズやアセンテックが急落した。 日経平均は3日続伸。2月10日に4日続伸となって以降は3日続けての上昇がなかっただけに、いったんの底打ちを期待させる動きである。直近の失速度合いが大きかったファーストリテイリングやエムスリーが大きく上昇していることも、下値不安を和らげる。本日、欧州ではECB理事会が開催される。来週のFOMCと日銀会合の予行演習という意味合いで、欧州中銀のアナウンスやラガルド総裁の発言がマーケットを大きく動かす材料となるかが注目される。先に荒れた分、中央銀行イベントはマーケットに落ち着きをもたらす可能性が高いとみており、欧州、米国、日本の3段ロケットで日経平均は3万円回復といったシナリオも十分考えられる。逆噴射にも警戒しておかなければいけない局面だが、まずはECBの手綱さばきに注目したいところだ。明日の日本株の読み筋=週末要因から上値の重い展開かモーニングスター 12日の東京株式市場は、休日を前にリスク回避姿勢が強まる週末要因から、上値の重い展開となりそう。また、3月限株価指数先物・オプションSQ(特別清算指数)値算出日にあたることから、市場速報値が意識される場面も想定される。市場では「日経平均株価が早い段階で25日移動平均線(11日時点で2万9449円)を上抜ければ、出直り体制に入りが期待される」(中堅証券)との見方があった。また、「消去法的に、3月配当狙いや業績の裏付けのある銘柄に物色が向かいそう」(他の中堅証券)との声も聞かれた。今年に入り金曜日の立ち合いは9日あるが、2勝7敗とさえないことから週末安が意識される場面もありそう。 11日の日経平均株価は、前日比175円08銭高の2万9211円64銭と3日続伸した。午後2時50分に、同218円86銭高の2万9255円42銭と同日の高値を付ける場面がみられ、ジリ高基調となった。東京証券取引所が11日引け後に発表した、3月第1週(1-5日)の2市場1・2部等の投資部門別売買状況によると、海外投資家は417億円買い越しで、3週ぶりに買い越しとなった。〔ロンドン外為〕円、108円台半ば(11日午前9時)時事通信 【ロンドン時事】11日朝のロンドン外国為替市場では、米長期金利の低下を眺めてドル売りが先行し、円相場は1ドル=108円台半ばに上昇した。午前9時現在は108円40~50銭と、前日午後4時(108円55~65銭)比15銭の円高・ドル安。 ユーロの対ドル相場は欧州中央銀行(ECB)による金融政策決定を控えて1ユーロ=1.1960~1970ドル(1.1890~1900ドル)と急伸。対円では同129円70~80銭(129円15~25銭)と2週間ぶり高値圏。(了)今晩のNY株の読み筋=週間新規失業保険申請件数や米金利動向などに注意モーニングスター 11日の米国株式市場は、週間新規失業保険申請件数や30年国債入札などが手掛かりになるとみられる。 10日は、米2月コアCPI(消費者物価指数)が市場予想を下回り、インフレ過熱観測が後退。米長期金利の上昇が一服したほか、米下院で追加経済対策の修正法案が可決されたことも追い風となり、NYダウは史上最高値を更新した。 CPIや経済対策法案の下院可決とイベントを通過しただけに、NYダウの連日最高値更新にはやや材料が足りない感はあるが、週間新規失業保険申請件数が前週に引き続き良好な結果となり雇用環境改善の観測が強まれば、相場の支援しそうだ。ただ、30年国債の入札も控えており、前日の10年債入札に引き続き応札倍率が低調な結果となれば、米長期金利が急伸する可能性もあるので、注意したい。このほか、ECB(欧州中央銀行)理事会後のラガルドECB総裁の会見にも注目したい。<主な米経済指標・イベント>30年国債入札、週間新規失業保険申請件数グッドRxホールディングス、ドキュサインなどが決算発表予定(日付は現地時間)◎投資関連情報は投資の参考として情報提供のみを目的としたものであり、株式の売買は自己責任に基づき、ご自身で判断をお願いします。NY株見通し-堅調か 30年債入札を受けた金利動向に注目トレーダーズ・ウェブ 今晩のNY市場は堅調か。昨日は長期金利が小幅に低下したことや、1.9兆ドルのコロナウィルス救済法案が今週中に成立する見通しとなったことでセンチメントが大きく改善。ダウ平均は464ドル高と4日続伸し、終値で初めて32000ドルを突破した。一方、ハイテク株主体のナスダック総合は一時1.55%高まで上昇したものの、わずかながらマイナス圏で終了した。今晩の取引では1400ドルの現金給付を含む1.9兆ドルのコロナウィルス救済法案がバイデン米大統領の署名により12日に成立する見通しとなったことが引き続き相場の支援となりそうだ。景気敏感株の堅調持続が見込まれるほか、長期金利が落ち着いた動きとなれば、ハイテク・グロース株も堅調が期待できそうだ。金利をめぐっては、米国30年債入札が予定され、結果を受けた長期金利の動向に要警戒。 今晩の米経済指標・イベントは新規失業保険申請件数、1月JOLTS求人件数、米国30年債入札など。企業決算は引け後にアルタ・ビューティーが発表予定。(執筆:3月11日、14:00)変異株陽性新たに3人判明し計9人に 岐阜県、新型コロナ新規感染者は1人 岐阜県は11日、これまでに新型コロナウイルス感染が判明している感染者3人が、変異株の陽性だったと発表した。うち1人は重症。県内の変異株陽性者は累計9人となった。 県によると、3人は2月下旬から3月上旬までに感染が判明しており、県の追加検査で変異株の陽性が確認された。3人とも海外渡航歴はなかった。国立感染症研究所で遺伝子解析を行い、型を特定する。 11日発表の新規感染者は安八郡神戸町の1人で、感染者数は累計4676人となった。10日時点の病床使用率は12・2%。〔NY外為〕円、108円台半ば(11日午前8時)時事通信 【ニューヨーク時事】11日のニューヨーク外国為替市場の円相場は、午前8時現在1ドル=108円46~56銭と前日午後5時(108円34~44銭)比12銭の円安・ドル高で推移している。 ユーロは同時刻現在、対ドルで1ユーロ=1.1949~1959ドル(前日午後5時は1.1924~1934ドル)、対円では同129円58~68銭(同129円25~35銭)。(了)〔NY外為〕円、108円台後半(11日朝)時事通信 【ニューヨーク時事】11日午前のニューヨーク外国為替市場では、米長期金利の低下を受けた円買い・ドル売りの流れが一巡し、円相場は1ドル=108円台後半で推移している。午前9時現在は108円50~60銭と、前日午後5時(108円34~44銭)比16銭の円安・ドル高。 ニューヨーク市場は、108円51銭で取引を開始。前日の米消費者物価指標や10年物米国債入札結果を受けて、長期金利の指標となる10年物債利回りは1.5%台で落ち着いた動きとなっている。 米労働省が朝方発表した週間新規失業保険申請件数は前週比4万2000件減の71万2000件と、2週ぶりの改善。市場予想(ロイター通信調べ)の72万5000件を下回ったが、ドル買いの動きは限定的だった。 ユーロは同時刻現在、対ドルで1ユーロ=1.1950~1960ドル(前日午後5時は1.1924~1934ドル)、対円では同129円75~85銭(同129円25~35銭)と、50銭の円安・ユーロ高。(了)〔米株式〕NYダウ、連日の最高値更新=ナスダックも反発(11日朝)時事通信 【ニューヨーク時事】11日のニューヨーク株式相場は、米雇用関連指標の改善や長期金利の落ち着きを受け、続伸して始まった。優良株で構成するダウ工業株30種平均は寄り付き直後に再び史上最高値を更新し、午前9時35分現在は前日終値比93.67ドル高の3万2390.69ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数も240.81ポイント高の1万3309.64と反発している。(了)今夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中のすべてが値を上げてスタートしましたね。トゥイリオ、エッツィ、ザイリンクスが上げていますね。
2021.03.11
コメント(0)
-

3月10日(水)…
3月10日(水)、晴れです。少し風はありますが、暖かくて気持ちの良い日ですね。そんな本日は7時45分頃に起床。新聞に目を通し、朝食を済ませ、ロマネちゃんと戯れる。本日のノルマは1階の掃除機ですか…。ハイハイ…。身支度をして、10時頃に家を出る。水曜日ですが、ゴルフではありません…。愛車のディーラーからリコール対応の準備ができたとのことで訪問です。新しい車がたくさん並んでいます…。2ドアクーペだと8シリーズ、4シリーズ、2シリーズですか…。愛車は1泊2日コースでお泊りなので代車はM135iです。ボディカラーがホワイトなので迫力はありませんが、エンジン音はなかなかに…。代車に乗ってTPO(土岐プレミアムアウトレット)へ。到着時は駐車場も空いていましたが、お昼頃には埋まりましたね…。平日だけど、春休みですか…。とても年金世代とは思えない若いカップル・家族連れが多いです。「マンシング」で春のセーターとベストをゲット。「アンテプリマ」で掘り出し物がたくさん見つかったようです。フードコートでランチタイム。「コールハン」で僕は出会いなし…、奥は出会いがあったようです。その後、「ギャップ」「ラルフ・ローレン」と奥が回る間に荷物を車に乗せて、「タリーズ」でコーヒーブレイクです。帰り道に仏壇屋で位牌を受け取る。帰宅して、「ヴィタメール」のケーキとコーヒーでおやつタイム。それではしばらく休憩です。1USドル=108.82円。1AUドル=83.61円。昨夜のNYダウ終値=31832.74(+30.30)ドル。本日の日経平均終値=29036.56(+8.62)円。金相場:1g=6652(+95)円。プラチナ相場:1g=4561(+99)円。昨夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中のすべてが上げて終了しましたね。半数は大きく上げましたね。見直しの必要はないか…。これだけ上げて下げてだと買いに入るタイミングが取れないですね。本日の東京市場ではチェック中の日本株30銘柄中の17銘柄が値を上げて終了しましたね。重点6銘柄では2銘柄が値を上げて終了しましたね。5%以上の大きな変動は見られませんね。日本株は小幅続伸、米金利上昇の一服で電機や機械高い-金融株は安い 10日の東京株式相場は小幅に続伸。米国市場で長期金利の上昇一服に伴いハイテク銘柄が値上がりした流れを受けて、電機や情報・通信、機械株などに買いが入った。一方、銀行や保険株は下落した。 TOPIXの終値は前日比2.06ポイント(0.1%)高の1919.74 日経平均株価は8円62銭(0.03%)高の2万9036円56銭 <きょうのポイント> 米S&P500種株価指数1.4%高-ナスダック100指数4%高 9日の米10年物国債利回りは1.53%-前日比6ベーシスポイント(bp)低下 世界経済は21年に急回復へ、米国が主導-OECDが予想上方修正 前日の米国市場でハイテク比率の高いナスダック指数が大幅に上昇し、10日の東京市場でもソニーや日本電産などが買われた。9日発表の2月工作機械受注が好調だったため、DMG森精機や牧野フライス製作所などの株価も大きく上げた。 ただ株価指数は下落に転じる場面があり、前日の終値を挟んでもみ合う展開が続いた。11日の欧州中央銀行(ECB)政策委員会、来週の米連邦公開市場委員会(FOMC)や日銀政策決定会合を控え、市場では金利上昇に対する警戒が根強い。 SMBC信託銀行の佐溝将司シニアマーケットアナリストは「主要中銀の足元の金利上昇に対する判断をこれから見極めていく形になり、投資家は様子見の状況」と話した。 東証33業種では医薬品や電機、情報・通信、機械が上昇 鉱業や鉄鋼、水産・農林、石油・石炭、海運は下落米10年債利回りのピークまだ来ていない、弱気バイアス続く-BofA 米国債には弱気バイアスが残っており、10年債利回りは上昇が続くとバンク・オブ・アメリカ(BofA)がリポートで予測した。 BofAのテクニカルストラテジストのポール・シアナ氏は9日のリポートで、過去のトレンドの規模とデュレーション、テクニカルパターン、モメンタムを検証した結果、「10年債利回りのピークはまだ見られず弱気バイアスが続いており、5年債、さらに2年債についてさえそうした傾向が強まっている」との見解が裏付けられたと説明した。 シアナ氏はその一方で、30年債利回りが「2021年8月から22年1月の間に2.24-2.69%でピークに達するのではないか」と予想。5年債利回りは4月から9月の間に1.5%前後で最も高くなる可能性があるという。米国株上昇、リスク選好でハイテクに買い戻る-ドル全面安 9日の米株式相場は上昇。市場にリスク選好ムードが戻り、押し目買いの動きでナスダック100指数は昨年11月以来の大幅高となった。米国債は3年債入札後に上げ幅を拡大した。 米国株は上昇、ナスダックの上げ目立つ 米国債は上昇、10年債利回り1.53% ドル全面安、対円は108円半ば NY原油は続落、テクニカル指標が上昇の行き過ぎ示す NY金は大幅高、ドル下落や利回り上昇一服で フィットネス機器を手掛けるペロトン・インタラクティブが14%高となるなど、在宅関連の勝ち組だった銘柄に再び勢いが戻った。ワクチン接種が進み、1兆9000億ドル(約206兆円)規模の追加経済対策が実現に近づく中、こうした銘柄はこのところ敬遠されていた。この日に限ってみると、グロース株からバリュー株へのローテーションは大きく反転した格好だ。テスラは20%値上がりし、約1年ぶりの大幅高となった。 S&P500種株価指数は前日比1.4%高の3875.44。ダウ工業株30種平均は30.30ドル(0.1%)高の31832.74ドル。ナスダック総合指数は3.7%上昇。 Eトレード・ファイナンシャルのトレーディング・投資商品担当マネジングディレクター、クリス・ラーキン氏は「1年足らず前には市場の歴史で最大級のネガティブなマクロイベントが買いの好機と解釈されていたことを忘れてはならない。足元のポジティブなシグナル全てを考慮すれば、今回は違うと考える理由はほとんどない」と指摘。「ナスダックがこの日上昇しているのは驚きではない。ファンダメンタルズは強気相場の継続を支えている」と述べた。 米国債相場は上昇し、利回りは最近の高水準から低下。ニューヨーク時間午後4時59分現在、10年債利回りは6ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の1.53%。 外国為替市場ではドルが主要10通貨に対して全面安。リスク資産が再び買われ、ドルロングで利益確定の動きが出た。 主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.6%安。ドルは対円で0.4%安の1ドル=108円48銭。ユーロは対ドルで0.5%高の1ユーロ=1.1901ドル。 ニューヨーク原油先物相場は続落。テクニカル指標で、原油相場の上昇が行き過ぎかつペースも速過ぎだったことが示された。原油相場は先週の上昇でボリンジャーバンドの上限を上回り、近く下落する兆候が出ていた。 ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物4月限は1.04ドル(1.6%)安の1バレル=64.01ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント5月限は72セント下げて67.52ドル。 ニューヨーク金相場は大幅高。ドルが下落したことで代替資産としての金の妙味が高まった。また債券利回りの上昇が一服したことも金買いにつながった。 ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物4月限は、2.3%高の1オンス=1716.90ドルで終了。【本日のNYダウ見通し】消費者物価指数と米10年債の入札に注目【NYダウ予想レンジ:31,600~32,100ドル】9日のNYダウは3日続伸。前日比30.30ドル高の31,832.74ドルで取引を終了しました。米10年債利回りが前日比0.07%低い1.52%で取引を終了。これまで割高感が意識されやすいハイテク株に買いが入り、相場を支えました。ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は464.66ポイント高の13,073.82で引け、上昇率(3.69%)は今年最大となっています。上院で可決した1.9兆ドル規模の追加経済対策は下院で再審議され、14日までに成立する見通しです。一人当たり1,400ドルの現金給付がおこなわれ、3~4月の個人消費はかなり強含むとの見方もあります。本日は消費者物価指数が発表されるので、予想を上回る内容になれば買い優勢の展開になる可能性があります。また、10年債の入札があるので、長期金利の動向にも注目です。日経平均は小幅続伸、朝高後は材料難で伸び悩み[東京 10日 ロイター] - 東京株式市場で日経平均は小幅に続伸した。寄り付きでは、前日の米国株式市場でナスダック総合が3.69%上昇した流れを引き継ぎハイテク株中心に買い優勢で始まったものの、その後は伸び悩み、前日終値を挟んだ一進一退の値動きが継続した。全体的に手掛かり材料に乏しく、時間外取引の米株先物の値動きに左右される展開となった。TOPIXは0.11%高。東証1部の売買代金は2兆8999億7400万円。東証33業種では、医薬品、電気機器、情報・通信業などの12業種が上昇。鉱業、鉄鋼、水産・農林業などの21業種は下落した。市場では「9日のナスダックは大幅高となったものの、ハイテク株は依然として過熱感があり、日本株は流れを引き継ぐ展開にはならなかった。加えて、今週末はSQ値算出、来週はFOMC(米連邦公開市場委員会)や日銀政策決定会合など重要イベントを控えており、上値は追いづらい。当面は割安株・出遅れ株を物色する流れが継続するのではないか」(証券ジャパンの調査情報部部長、大谷正之氏)との声が聞かれた。個別では、牧野フライス製作所、ツガミ、DMG 森精機、ファナック、安川電機、オークマなどの機械株が総じてしっかり。日本工作機械工業会が9日発表した2月の工作機械受注(速報値)は、前年比36.7%増の1055億5300万円と、4カ月連続でプラスとなったことなどが好感された。その他、ファーストリテイリングは2.41%安、エムスリーは6.19%安。東京エレクトロンもさえない動きとなった。東証1部の騰落数は、値上がり879銘柄に対し、値下がりが1218銘柄、変わらずが97銘柄だった。午後3時のドルは108円後半、米10年債入札の結果を注視[東京 10日 ロイター] - 午後3時のドル/円は、前日ニューヨーク市場午後5時時点に比べ、ドル高/円安の108円後半。米長期金利の小幅な上昇、豪ドルの下落、アジア株の上昇によるリスク選好の円売りなどに支えられ、ドルは底堅い展開となった。きょうは米10年国債の入札が予定されており、入札結果を受けた米長期金利の動向に注目が集まっている。ドルは午前7時過ぎに108.50円まで下落したが、アジア時間の取引で米長期金利が小幅に持ち直したことや、豪ドルの対ドルでの下落などに支えられ、108円後半まで持ち直した。午後の取引では日経平均や中国株の上昇が好感された。市場では「動きの速い投機筋の円売り戻しは一服となったが、ファンド勢はまだ円買い持ちを残しているところが少なくないようだ。米金利に上昇圧力がかかれば、ドルはもう一段上昇する可能性がある」(証券)との指摘が出ていた。ただ、急伸してきたドルが109円台を再び上抜け、一段高となる可能性を疑問視する声も出ている。「ドル/円の上昇ピッチが米金利高を上回る場面も出てきた。テクニカル的な過熱感もあり、109円台はいったん戻り売り」(FX会社)とみる向きも少なくないという。オーストラリア準備銀行(RBA、中央銀行)総裁が市場の利上げ観測を明確にけん制したことで、豪ドル/円は朝方の高値83.87円付近から、83円半ばまでじわじわと売られた。豪ドル/米ドルは朝方の0.7718米ドル付近から、0.7674米ドル付近まで下落した。RBAのロウ総裁は10日、完全雇用の達成には少なくとも2024年までかかるとの見方を示し、豪中銀は必要な限り「景気刺激的な金融状況」を維持することにコミットしていると、あらためて表明した。前日海外市場では、不調が警戒されていた米国債入札が順調だったことで米金利が低下、ドルが売られる展開となった。対円では一時108.42円と、前日夕に付けた9カ月ぶり高値の109.23円から1円弱下落した。リフィニティブによると、米10年国債利回りは1.54%付近と、前日ニューヨーク市場午後5時05分時点の1.5281%から上昇した。市場では「10年国債の入札が低調なら、米長期金利が上昇し、ドルが再び109円台に乗る展開もあり得る」(アナリスト)との声が出ていた。コラム:ドル円、トランプラリー再現の可能性はあるか=内田稔氏[10日 ロイター] - いくつものオシレーター系のチャートは、急ピッチで上昇したドル/円に対し、以前のトランプラリー(トランプ氏の米大統領当選で2016年11月から続いた株価急上昇)時に匹敵する「買われ過ぎ」を警告している。もちろん、足元の水準で日柄調整をこなせば、その警告も解消され、新たな高値圏へと浮上することも可能だが、問題は今のドル/円にそこまでの上昇力があるかどうかだ。<トリプルブルーでドル/円反転>トランプラリーの発端は、大統領および上下両院の過半数を全て共和党が占めるトリプルレッドの実現だった。予想外の選挙結果を踏まえ、市場も巨額の減税を織り込みにいった。景気回復と利上げペースの加速が意識され、2年物や10年物の米国債利回りが上昇し、これがドル高を招いた。しかも、それまで停滞感が強かった株式相場まで息を吹き返して堅調に推移。その後の1カ月あまりでS&P500指数も6%以上の値上がりをみせた。一方、最近のドル/円急上昇も、今年1月5日の米ジョージア州での上院議員選の決選投票を経て、民主党が大統領と上下両院を制し、トリプルブルーを実現するという予想外の展開になったことが大きい。バイデン政権の大規模な財政支援策の実現を織り込む過程でやはり米長期金利が上昇し、ドル/円の反転をもたらしたためだ。こうしてみると、足元のドル/円上昇は、さしずめバイデンラリーとみることもでき、トランプラリーにも匹敵するドル/円の急騰劇が、これから待ち受けているのかもしれない。<2016年のマネー構造>ただ、ドル/円相場を取り巻く環境を細かくみると、2016年当時と今とでは、大きく異なっている。そのことを確認するために、まず、トランプラリー時のドル/円急騰の突出ぶりを振り返っておこう。ドル/円は、大統領選挙の投票日前日(2016年11月7日)の終値104.46を起点とすると、12月15日の終値118.17まで13.1%も上昇した。同じ期間に2年物国債の利回りは0.82%台から約46bp、10年物国債の利回りも1.82%台から約77bpとそれぞれ上昇。これらがドル高を招いたとされる。とは言え、それで説明できるのは、せいぜい110円程度までだ。なぜなら、円を除く他の主要通貨に対する当該期間中のドルの上昇率は、平均5.1%に過ぎなかったからである。しかも、加ドルと英ポンドに対しては、ドルは下落している。国境の壁建設の可能性が嫌気され、為替市場で特に弱かったメキシコペソに対してでさえ、ドルの上昇率は9.3%とドル/円を下回った。当時のドル/円上昇率の異様さが明らかであり、それだけにそのかなりの部分に関し、日本固有の要因によるドル買い/円売りが出回ったとみるのが妥当だ。<ドル/円急騰の真相>2016年の市場では、ドル資金の需給が逼迫していた。米連邦準備理事会(FRB)は金融政策の正常化に着手しており、既にマネタリーベースの拡大を停止していた。その上、金融危機の教訓から米国では2015年より、金融規制が相次いで強化され、大手米銀を中心にドル資金を出し渋る動きがみられていた。さらに2016年10月のマネーマーケットファンド(MMF)規制改革も加わって、市場に対するドル資金の供給が細っていたからだ。これに対し、同年2月にマイナス金利政策が導入された日本では、それまでの国債投資の代替策として、為替ヘッジ付き外債投資が活発化。本邦勢のドル資金に対する調達需要は以前にも増して旺盛になっていた。そこに年末といった季節要因も加わり、2016年11月に入ると、ドル資金の調達コストが急騰。為替ヘッジ外しも含め、スポット市場における巨額のドル買い/円売りが、一段とドル/円を押し上げたとみられる。<2021年の特徴>現在のFRBは毎月1200億ドルの資産買い入れを継続し、ドルの調達環境にさほど緊張はない。また、労働市場を重視する方針に転じているだけに、金融政策の正常化までに、かなりの時間を要する見込みだ。このため、全体的なスティープ化は進んでいるものの、為替相場への影響が強い2年債の利回りに足元で顕著な変化はみられていない。また、長期金利が1%台半ばを超えて上昇する場面では、株式相場が不安定な動きを繰り返している。いずれ市場の目が慣れていく可能性もあるが、2016年との違いは株式相場の割高感だ。例えば、S&P500指数の益回り(予想株価収益率の逆数)と長期金利との格差(イールドスプレッド)は、このまま長期金利が1%台後半へと上昇し、2%に迫れば、一段と縮小し、株式相場の急落がFRBに金融政策正常化方針を翻意させた2018年10月の水準と一致する。つまり、長期金利の一段の上昇は、ドル高/円安ではなく、リスク回避的な環境をもたらす公算が大きく、その場合、ドル高とともに円高圧力も高めよう。必然的にクロス円の反落が見込まれ、ドル/円への下押し圧力となりそうだ。特に、ここ最近の米長期金利上昇とドル高を受け、新興国ではトリプル安の様相を呈している。コロナ禍から脱却する途上にある世界経済にとって、当面の間、米長期金利上昇とドル高は、「不都合な現実」をまき散らすため、持続性に乏しい。こうしてみると、バイデンラリーによるドル/円の上昇率は、トランプラリー時の円以外の通貨に対するドルの上昇率である概ね5%から、そう大きくかい離しないはずだ。今の相場の騰勢を考慮すれば、一時的に110円の大台を回復する可能性も否定できないが、さらなる続伸は考えにくい。上昇が一服した後は、再び緩やかなドル安・円高へと戻るだろう。しかも、長期金利の上昇が和らぎ、リスクオン相場に回帰するなら、円安を上回るドル安によって、適温相場であった2017年と同じくドル/円はやはり軟化する可能性が高い。<ドル/円が続伸する条件>結局、このままドル/円が上昇軌道を描き続ける条件は、トランプラリー時と同様、長期金利のみならず、利上げを織り込みながら、短期ゾーンの金利も上昇し、それでいて株式相場も底堅さを保つことだろう。おりしも2月の米雇用統計は、市場予想を大きく上回り、市場も米経済の先行きに対する自信を深めたはずだ。また、原油先物相場(WTI)が現在の水準を保つだけで、3月以降の前年比でみた伸び率は100%を大きく超えてくる。一般物価の上昇にも波及するとみられ、しばらくの間、景気好転によるインフレ圧力の台頭と映る可能性もあるだろう。以上の点を踏まえると、今月の米連邦公開市場委員会(FOMC)における政策金利見通し(いわゆるドットチャート)は重要だ。昨年12月時点に比べ、2022年末、2023年末までの利上げが妥当であるとする回答者が増えていた場合、市場でも利上げの前倒しが意識されそうだ。こうした点を念頭に、予断を持たず緊張感をもって臨んでいくほかないであろう。米国株は上昇、ナスダック約4%高 テクノロジー株が高い[9日 ロイター] - 米国株式市場は上昇して取引を終えた。米国債利回りが低下し、このところ売られていたテクノロジー株に買いが入ったことからナスダック総合が約4%上昇し、前日の下げから持ち直した。ナスダックの上昇率は昨年11月4日以来の大きさ。ダウ工業株30種は取引時間中の最高値を更新した。テスラは約1年ぶりの大幅な上げを記録。アマゾン・ドット・コムとマイクロソフトは過去数週間で最大の上昇となった。テクノロジー株は、利回りの上昇を受けたバリュエーション懸念からここ数週間売り込まれていた。1兆9000億ドル規模の新型コロナウイルス追加経済対策法案が近く可決されるとの期待から前日には国債利回りが上昇。ナスダックは2月12日に付けた終値での最高値を10%超下回り、調整局面入りしていた。前日に1.613%と約13カ月ぶり高水準を付けた米10年債利回りは9日に一時1.523%まで低下した。インベスコのチーフグローバルマーケットストラテジスト、クリスティーナ・フーパー氏は、今年はシクリカル(景気循環)株や小型株がアウトパフォームすると指摘。テクノロジー株も上昇するが、昨年のような市場の上げを主導する状況にはならないとの見方を示した。「きょうは10年債利回りがやや低下し、バリュエーションへの圧力が和らいだため、テクノロジー株が上昇した」と述べ、市場は新たな金利水準に適応しつつあると指摘した。米取引所の合算出来高は138億8000万株。直近20営業日の平均は152億5000万株。ラッセル2000グロース指数はこの日3.3%上昇。ラッセル2000バリュー指数は0.1%高。テスラは19.6%上昇し、S&P総合500種とナスダック100指数の上げを主導した。前日に14年ぶり高値を付けたS&P銀行株指数は1.7%下落。景気動向に左右されるセクターである金融、素材、工業はいずれも最高値圏で推移した。前日に40%超値上がりしたゲーム販売ゲームストップはこの日も26.9%上昇。電子商取引へのシフト戦略などが支援材料となっている。ニューヨーク証券取引所では値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を1.78対1の比率で上回った。ナスダックでは2.83対1で値上がり銘柄数が多かった。塩野義が後場に上げ幅を拡大、出資先のHIV試験が良好結果医薬品大手の塩野義製薬(4507)が後場に入り、上げ幅を拡大した。前引けは前営業日比140円高の5879円だったが、午後1時45分現在、同195円(3.40%)高の5934円で推移している。一時は5931円まで上伸した。本日午後0時30分に、英グラクソと米ファイザーとの共同出資先の英ViiV HEALTHCAREがカボテグラビルとリルピビリンのATLAS-2M試験で良好な結果を得たと発表し、買い材料視された。2カ月に一回の投与によりHIV感染者が96週でもウイルス抑制を維持できることが示されたとしている。今後患者の利便性がさらに向上することでHIV治療におけるパラダイムシフトが起こる可能性を示唆しているとしている。(取材協力:株式会社ストックボイス)エムスリーは7営業日続落、外国人等の手じまい売り続く医療従事者向け情報サイト運営のエムスリー(2413)は1月につけた上場来高値からの下落率が3割を超えたが、なお下げ止まらず7営業日続落。2020年11月11日以来およそ5カ月ぶりの安値に売られて時価総額は5兆円を割り込む場面もみられており、午後1時44分時点で前日比353円(4.6%)安の7390円で取引されている。日本を含め世界的に新型コロナウイルスのワクチン接種が進みつつあり、今後は医療体制も正常化へ向かう公算が高まる中で株価の割高感が外国人投資家などの手じまい売りを誘発。これを吸収する買い手が乏しくなっている。国内外での製薬会社向けマーケティング支援事業などは中長期的にも成長が見込まれるものの、来2022年3月期の1株利益のアナリスト予想の平均値は67.2円で、これを基にした9日終値でのPERは115倍と高水準。景気や企業業績の回復傾向を背景に市場全体が業績相場への移行を探る局面にきており、出遅れ感のある割安な景気敏感株へ資金をシフトさせる動きが強まっている。(取材協力:株式会社ストックボイス)9日のアメリカ市場でのハイテク株急反発の流れは続くのかストラテジストが持続に疑問符ブルームバーグ ハイテク株中心の米ナスダック100指数はテクニカル調整に入った翌日の9日、目覚ましい復活を遂げた。構成銘柄の約4分の1が5%を超える値上がりで、同指数は昨年11月以来の上昇率となる4%高で引けた。 30年ぶりの売られ過ぎが示唆されるほど下落した直後のハイテク株反発だった。スワン・グローバル・インベストメンツの顧客ポートフォリオマネージャー、マーク・オド氏は「押し目は買いという考えは人々の心理に深く根付いているので、売りが数日続いた後は反発することになる。何もかもを変えるような大きなイベントのニュースでもない限り、これは避けられない」と話した。 9日について言えば、押し目買いは奏功したと言える。しかし、ハイテク株の売りが終わったかというと、ストラテジストらは懐疑的だ。 同日反発したもう一つの理由は、割高な成長株への圧力となってきた債券利回り上昇に落ち着きの兆しが見られたことかもしれない。10年物米国債利回りは5日に1年ぶり高水準の1.62%となったが、その後は低下している。 オアンダのシニア市場アナリスト、エドワード・モヤ氏は「今のウォール街は一方通行で、米国債市場の方向に従って動く。テクノロジー株の反発は米国債上昇と同じタイミングで起きた。このため、この反発が続くかどうかについて多くのトレーダーが懐疑的だろう」と話した。 また、RBCキャピタル・マーケッツの米株戦略責任者ロリ・カルバシナ氏は、最近の値下がり後もハイテク株のバリュエーションの問題は解決していないと指摘。ソフトウエアおよびインターネット株の株価収益率(PER、予想ベース)26.2倍は同セクターの過去の平均的水準やS&P500種と比較して高いという。さらにファンドのポジションを分析する同社モデルは、相場の底を通常示す水準までセンチメントがまだ達していない状況を示唆している。 カルバシナ氏はリポートで「大型ハイテク株の巻き戻しは少なくとも半分済んだかもしれないが、まだ終わってはいない」としている。バリュー投資への波が一大ムーブメントになりつつあるコロナ禍での損失回復し資金流入ブルームバーグ しばらく人気が下火となっていたバリュー株投資が盛り返している。新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)以降に記録した損失を全て取り戻した。 割高な銘柄を売って割安株を買うこの投資戦略のトータルリターンはコロナ禍前の水準を回復した。ブルームバーグのロング・ショート指数が示した。 昨年の苦境で景気循環株はバリュエーションが下がったが、1兆9000億ドル(約207兆円)規模の米追加経済対策を控え、新型コロナの流行収束に伴う景気回復が見込まれる中で、大量の資金が急ピッチで戻りつつある。 バリュー株に投資する上場投資信託(ETF)は10週連続で新規資金を呼び込んだ。資金流入と株式相場上昇に後押しされ、運用資産は昨年11月初め以降で1000億ドル増加。四半期ベースの純流入は過去最高を記録する勢いで、運用資産はあと50億ドル増えれば成長株のETFを追い抜く。 言ってみれば、ここ10年に不調だった投資手法が今や、強気相場で最も人気の高い手法の1つに取って代わる方向にありそうだ。 景気への楽観論を背景にした利回り上昇で、割安株への短期的な投資がこれまで以上に魅力的になっている。サクソ・キャピタル・マーケッツのストラテジスト、エレノア・クレイ氏はリポートで「利回りが上昇するほど、ローテーションへの圧力が増す」と分析した。 こうした構造的変化を受け、投資家は成長株など過去に好んだ銘柄を記録的なペースで手放し、出遅れた銘柄の確保に向かっている。 目覚ましい回復を遂げたバリュー投資は9日の取引では影を潜めた。代わりに、1カ月足らずで1兆5000億ドルの時価総額が吹き飛んだハイテク株が上昇した。 ただ設備投資が回復しており、たとえローテーションが一服しても景気循環株の上昇が続く余地はあると、エバコアISIはみている。デニス・デブシェール氏ら同社のストラテジストは「マクロの状況はなお割安株とボラティリティーに有利だ。ただリターンのペースは鈍化するだろう」とリポートで指摘した。【市況】東京株式(大引け)=8円高、米ナスダック高受け続伸も上値重い 10日の東京株式市場は強弱観が対立し、日経平均株価は終日方向感の定まりにくい展開となった。結局プラス圏で引けたものの上げは小幅にとどまっている。 大引けの日経平均株価は前営業日比8円62銭高の2万9036円56銭と小幅続伸。東証1部の売買高概算は13億9336万株、売買代金概算は2兆8999億7000万円。値上がり銘柄数は879、対して値下がり銘柄数は1218、変わらずは97銘柄だった。 きょうの東京市場は朝方高く始まったものの上値が重く、日経平均は2万9000円大台近辺の狭いレンジでもみ合う展開となった。前日の米国株市場でハイテク株比率の高いナスダック総合指数が大幅高で切り返したほか、半導体銘柄で構成されるSOX指数も急伸したことで、東京市場でも主力輸出株に追い風が期待されたが、反応は限定的だった。今週末がメジャーSQ算出日にあたるほか、あすにはECB理事会の結果とラガルドECB総裁の記者会見を控えており、積極的に買いポジションを高める動きはみられなかった。下値では押し目買いも厚く、大引けはかろうじて前日終値を上回った。値下がり銘柄数は1200を超え値上がり銘柄数を上回っている。商いは活況だったが、売買代金は2兆9000億円と3兆円台には届かなかった。 個別では、ソニー、任天堂がしっかり、日本電産も切り返しに転じた。武田薬品工業が堅調、デンソーも買いを集めた。レーザーテック、アドバンテストが上昇、ファナックも高い。サインポストがストップ高。東洋エンジニアリングも値を飛ばした。東京製綱も大幅高、大豊工業も物色人気に。 半面、ファーストリテイリングが大きく値を下げ、エムスリーも大幅安。東京エレクトロンも朝高後に軟化した。トヨタ自動車が売りに押され、マネックスグループも安い。東京電力ホールディングスの下げも目立った。ケイアイスター不動産が急落となり、くら寿司も大幅安。ユー・エム・シー・エレクトロニクス、ビックカメラも下落した。出所:MINKABU PRESSアナフィラキシー5人発症 コロナワクチン接種後共同通信社 厚生労働省は8日、新型コロナウイルスワクチンを接種した20~50代の女性5人が、重いアレルギー反応のアナフィラキシーを発症したと発表した。いずれも投薬をするなどして症状は改善した。うち2人が経過観察の目的で入院した。 5人のうち3人について、報告した医師はワクチンと因果関係があるとみており、残りは「評価不能」など。コロナワクチン接種後のアナフィラキシー発症は国内で計8例となり、全てが女性。厚労省は今後、専門部会で因果関係などの評価を行う方針。8日までに約7万人の医療従事者に接種されている。 厚労省によると、発症した5人はいずれも8日に米ファイザー製のワクチン接種を受け、5~30分以内にのどの違和感やじんましん、息苦しさなどの症状が出た。4人はアレルギーやぜんそくなどの基礎疾患があったという。 厚労省の医薬品安全対策に関する専門調査会長を務める岡明(おか・あきら)・埼玉県立小児医療センター病院長は「海外のデータでも女性に多いことが示されている」と指摘する。 米国の報告では、ファイザー製ワクチンで接種20万回に1回程度の頻度でアナフィラキシーが発生している。同省のワクチン分科会副反応検討部会長の森尾友宏(もりお・ともひろ)・東京医科歯科大教授は「発生頻度が海外の報告よりも高いように見える。アナフィラキシーに該当するかを含めて詳細を評価する必要がある」としている。〔東京株式〕小幅続伸=米株高も上値重い(10日)時事通信 【第1部】日経平均株価は前日比8円62銭高の2万9036円56銭、東証株価指数(TOPIX)は2.06ポイント高の1919.74と、小幅続伸した。前日の米国株高を好感して買われたが、米長期金利上昇に対する警戒感から上値は重かった。出来高は13億9336万株。 【第2部】小幅高。ユニバンス、アルチザ、野村マイクロが続伸。アトムは反落し、千代化建も安かった。出来高2億4589万株。▽一時200円超高も買い続かず 10日の東京株式市場は前日の米国株上昇を好感して買いが先行し、日経平均株価の上げ幅が一時前日比200円を超えた。しかし、米国の長期金利上昇に対する警戒感や円安進行の一服から買いは続かず、日経平均は小幅の値下がりに転じる場面があった。 前日の米国市場でIT関連株が買われた流れを引き継ぎ、東京市場では半導体など電子部品株や設備投資関連株が買いを集めた。「海外の短期ファンドの買いが入った」(銀行系証券)とみられる。ただ、東証1部全体では買い注文が薄く、売り物を吸収できずに値下がりする銘柄が半数を超えた。市場では「個人投資家が買値を上回った銘柄を売っている」(インターネット証券)との指摘もあった。 225先物は朝方に付けた2万9250円を天井に2万9000円前後でのもみ合いが続いた。オプション3月きりは先物の価格変動率の縮小を反映してコール、プットともに値下がりした。特別清算指数(SQ)算出を12日に控え、時間的価値の減少もオプション価格低下の要因となった。(了)〔東京外為〕ドル、108円台後半=米10年債入札控え様子見(10日午後3時)時事通信 10日午後の東京外国為替市場のドルの対円相場(気配値)は、日本時間11日未明に実施される米10年債入札などを控えて様子見ムードが漂い、1ドル=108円台後半で小動きに推移している。午後3時現在、108円88~88銭と前日(午後5時、108円81~85銭)比07銭の小幅ドル高・円安。 前日の米国時間終盤にかけては、米長期金利の低下を背景にドル売りが強まり、108円40銭台に下落。この日の東京時間早朝は、やや買い戻され、108円60銭前後で取引された。午前は、時間外取引の米金利上昇を眺めてドルが買われ、108円80銭前後までじりじりと値を上げた。午後は、今夜の2月の米消費者物価発表に加え、米10年債入札が予定されていることから、市場では「これらの結果を受けた金利動向を見極めたい」(外為仲介業者)との思惑で様子を見る向きが目立った。 市場関係者からは「110円手前を意識してもおかしくない水準だ」(FX会社)との指摘がある一方、「前日、109円台に定着しなかったことから108円台後半では伸び悩んでいる」(先の外為仲介業者)との声も聞かれた。前日の東京時間夕方に大きく動いたため、「本日も欧州時間に向けて雰囲気が変わる可能性がある」(先のFX会社)との見方もあった。 ユーロは午後に入って、対円でもみ合い、対ドルでは軟化。午後3時現在、1ユーロ=129円29~30銭(前日午後5時、129円26~27銭)、対ドルでは、1.1875~1875ドル(同、1.1879~1880ドル)。(了)明日の戦略-伸び悩むもプラスは確保、ナスダック急伸で金利上昇への耐性はつくかトレーダーズ・ウェブ 10日の日経平均は小幅続伸。終値は8円高の29036円。米国でナスダックが大幅高となったことを好感して上昇スタート。開始直後には上げ幅を200円超に広げた。しかし、強めに始まったグロース株に勢いがなく、早々に失速。値を消してマイナス圏に沈んだ後は、一段と売り込む動きにはならなかったものの、買いも手控えられた。後場に入っても基調に大きな変化はなく、マイナス圏に沈むと持ち直すが、プラス圏に浮上すると上値が重くなった。終値ではかろうじてプラスを確保した。 東証1部の売買代金は概算で2兆9000億円。業種別では医薬品、電気機器、情報・通信などが上昇した一方、鉱業、鉄鋼、水産・農林などが下落した。株主優待導入を発表した築地魚市場が買いを集めてストップ高比例配分。半面、日医工が大幅安。日本ジェネリック製薬協会が同社を5年間の正会員資格停止処分にしたと伝わったことが売り材料となった。 東証1部の騰落銘柄数は値上がり879/値下がり1218。工作機械受注の好内容を受けてファナックが大幅上昇。ツガミや牧野フライス、DMG森精機など機械株の選好が強まった。ハイテク株は伸び悩んだものの、日本電産やアドバンテスト、レーザーテックなどはしっかり上昇した。KDDI、ソフトバンク、NTTなど通信株が強い動き。ワクチン治験に関するリリースを材料にアンジェスが急伸した。ほか、上方修正を発表したビューティガレージや、子会社が大口受注を獲得したナガオカが買いを集めた。 一方、エムスリーが6%を超える大幅下落。東京エレクトロンが買い気配スタートからマイナス圏に沈んでおり、これらの弱い動きがグロース株を買い上がる流れにブレーキをかけた。ファーストリテイリングが2%を超える下落。原油価格の上昇一服を受けて、国際帝石やENEOSが大きく売られた。直近で騰勢を強めていた日本製鉄やJFEなど鉄鋼株が軟調。決算が失望となったくら寿司が急落した。 米国株の動向からは、グロース株が爆騰して日経平均も大幅上昇といった展開が期待された。しかし、ふたを開けてみればグロース株の戻りは恐る恐るで、売られ続けるものも散見された。長期金利上昇や原油高、円安には一服感も出てくる中、バリュー株は利食い売りに押されるものが多く、結果、全体としては方向感が出なくなった。テスラ株の20%近い上昇を見ても強いリスクオン相場とならなかったことには、物足りなさはある。しかし、見方を変えれば市場が冷静であったとも言える。今晩の米国株が反動で売られたとしても、それに対するネガティブな反応は限られるだろう。ナスダックが強く切り返したことで、この先、米国の長期金利に神経質となる地合いに変化が出てくるかが注目される。今晩米国では2月の消費者物価指数が発表される。FOMC(3/16~17)までの日程を鑑みると、同指標が金利の大幅な上昇や米国株安を引き起こすことがなければ、株式市場は徐々に金利離れして落ち着きを取り戻すと予想する。明日の日本株の読み筋=もみ合い商状か、国内は手掛かり材料難、日柄調整入りの見方もモーニングスター あす11日の東京株式市場は、もみ合い商状か。相場のかく乱要因となる米長期金利については、足元で低下し、投資家心理の落ち着きにつながっているものの、上昇への警戒感は依然くすぶっている。とりあえず、現地10日の米10年物国債の入札結果を受け、金利がどう反応するかが注目される。ただし、国内では手掛かり材料に乏しく、外部要因に恵まれないと積極買いは期待しにくい。市場では、「日柄調整に入ったのではないか。米長期金利上昇への警戒感は解けず、買い戻しも一巡したとみられ、上は重い。一方、3月期末配当取りの買いが下値を支えそうだ」(準大手証券)との見方も出ていた。 10日の日経平均株価は小幅続伸し、2万9036円(前日比8円高)引けとなった。朝方は、米長期金利の低下を背景に9日の米国株式市場でハイテク株中心に値を上げた流れを受け、上げ幅は一時200円を超えた。ただ、一巡後は先物売りを交えて下げに転じ、67円安まで軟化した。その後は上げ下げを繰り返し、大引けにかけては前日終値近辺でもみ合った。新規の手掛かり材料に乏しく、全般は売買が交錯し、方向感を欠く展開となった。〔ロンドン外為〕円、108円台後半(10日午前9時)時事通信 【ロンドン時事】10日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、持ち高調整の中を1ドル=108円台後半で推移した。午前9時現在は108円65~75銭と、前日午後4時(108円75~85銭)比10銭の円高・ドル安。 ユーロの対ドル相場は1ユーロ=1.1890~1900ドル(前日午後4時は1.1880~1890ドル)。対円では同129円25~35銭(129円25~35銭)と横ばい。(了)接触歴なく経路は不明…新型コロナ「変異ウイルス」60代・80代女性2人の感染が判明 岐阜県内で6人に東海テレビ 岐阜県で新たに60代と80代の女性2人が、変異した新型コロナウイルスに感染したことが確認されました。 2人は変異ウイルスの感染が確認された人との接触歴はなく、感染経路は不明です。 岐阜県内で変異ウイルスへの感染者はこれで6人となりました。今晩のNY株の読み筋=米2月CPIや米10年国債入札に注目モーニングスター 10日の米国株式市場は、米2月CPI(消費者物価指数)が注目となる。市場予想の平均値はコアCPIが前月比0.2%上昇となっている。足元ではインフレ懸念が根強いことから市場予想通りであれば過度の懸念が高まらないとみられるが、予想を上回ると上値圧迫要因になる可能性がある。 また、米10年国債入札にも関心を払っておきたい。9日の米3年国債入札は好調だったため、米長期金利の上昇も一服。ハイテク株が中心のナスダック総合指数をはじめ、米国株は堅調だった。きょうの入札も無難な通過となれば米長期金利の上昇も抑制されるとみられる。ただ、低調な結果となれば米長期金利の上昇が促され、ハイテク株を中心に売り圧力が強まりそうだ。<主な米経済指標・イベント>米2月CPI、米2月財政収支、米10年国債入札(日付は現地時間)◎投資関連情報は投資の参考として情報提供のみを目的としたものであり、株式の売買は自己責任に基づき、ご自身で判断をお願いします。新たに変異株陽性2人判明 岐阜県、合わせて6人に 岐阜県は10日、新たに3人の新型コロナウイルス感染と、これまでの感染者のうち2人が変異株の陽性であることを確認したと発表した。県内の感染者数は累計4675人に、変異株の陽性者は計6人となった。 変異株の陽性が確認された2人は、今月上旬に感染が判明して入院している60代、80代の女性で、県の追加検査で分かった。国立感染症研究所で遺伝子解析を行い、型を特定する。 県によると、2人は同じ自治体に住んでおり、接触していた。いずれも海外渡航歴はなく、感染経路は不明。2人の接触者として既に感染が判明している1人についても、変異株かどうかを判定する追加検査を行う。 変異株は感染力が強いとされ、県は新型コロナ陽性者の5~10%を追加検査して変異株かどうかを判定している。県担当者は「県内のどこで(変異株の陽性が)発生してもおかしくない状況」との懸念を示した。 10日発表の新たな感染者は岐阜市、養老郡養老町、愛知県の20代、30代、80代の男女3人。クラスター(感染者集団)での新たな感染者はいなかった。9日時点の入院者は97人で、100人を切ったのは11月17日以来。病床使用率は14・0%で、前日より0・4ポイント下がった。上昇トレンド崩れたナスダックはまだ危機脱せず、一時的反発の可能性Bloomberg News テクノロジー株の強気派は9日の米国株反発で安堵のため息をついているだろう。だが、死んだ猫でも高いところから落とせば跳ね返るという意味の投資用語「デッド・キャット・バウンス」で表現される一時的反発の可能性を、ナスダック100指数が完全に払拭(ふっしょく)するにはまだ課題が残ることも分かっているはずだ。 テクノロジー株の比重が大きいナスダック100指数は1年にわたる上昇トレンドを割り込んだ後、フィボナッチ比率の戻しの水準できっちり反発した。しかし、その上昇トレンドを早期に上回らない場合、一段安となる方向性が示され、新たな下値支持線を試す展開となる可能性もある。焦点:海外勢の日本株売り、本腰か調整か 個人は逆張り継続[東京 10日 ロイター] - 海外投資家の日本株売りが強まっている。年初からの累計では売り越しに転じた。ただ、日本独自の売り材料が出たわけではなく、米国の長期金利上昇をきっかけとして利益確定売りに動いた可能性がある。個人投資家は足元では買い向かっており、逆張り姿勢は健在だ。 <株価のピークを境に反転>日経平均株価が30年半ぶりに3万円を回復したのは2月第3週の15日。翌16日に取引時間中のバブル崩壊後高値(3万0714円)を付けたが、その週を境に海外投資家の姿勢は反転した。東京証券取引所と大阪取引所が公表する投資部門別売買動向によると、海外投資家による日本の現物株と先物合計の売買は、2月第1─2週の合計で1兆3284億円の買い越しだったが、第3─4週は8854億円の売り越しに転じた。特に2月第4週は7006億円の売り越しと、前年9月第5週の7540億円以来の規模となった。1月が5753億円の売り越しであったことから、年初からの累計でも1323億円の売り越しに転じている。海外投資家は、米国で大統領選挙が終わり新型コロナウイルスのワクチン開発に進展がみられた昨年11月以降に日本株買いを活発化。11月に3兆1030億円、12月に4782億円の計3兆5812億円買い越している。昨年11月から今年2月までの累計では依然3兆4489億円の買い越しであり、日経平均は今年2月末時点で、昨年10月末比で5988円(26%)、前年末比で1521円(5.5%)上昇した地点に位置する。しかし、足元では景気回復期待を背景に積み上げてきた株式ロングポジションの利益確定売りに動いた可能性がある。 <株式と債券のスプレッド縮小>海外勢が利益確定売りに動いたきっかけの一つは、米国の長期金利の上昇だ。米10年国債利回りが約1年ぶりに1.3%台に乗せた2月16日の翌日以降、ナスダック総合指数が下落するなどマーケットの一部で変調がみられている。豪AMPキャピタルの投資戦略部門責任者兼チーフエコノミスト、シェーン・オリバー氏は「債券売りが一部株式のバリュエーションに関する懸念をもたらし、米国、日本、中国などグローバルでの株式売りにつながった」と指摘する。歴史的にみれば、金利上昇と株高が併存しているケースは少なくない。金利上昇の要因が、景気回復(期待)であるためだ。最近ではトランプ氏が米大統領選に勝利した2016年11月からの局面がそれにあたる。ただ、金利上昇が短期的な株価の調整(下落)を引き起こすこともある。今回のリフレトレードが調整を迎える前、株式の益回りと、債券の利回り差である「イールドスプレッド」が縮小していたことが注目されている。株式と債券は「ライバル関係」にある。投資家はどちらのリターンが高いかを比較検討し、資金を配分する。先行きの見通しやボラティリティーなど複雑な要素が絡むため、そう単純ではないが、イールドスプレッドの低下で株式の相対的な魅力度が低下するとみれば、利益確定売りのきっかけになりやすい。 <買い主体が交互に登場>海外勢が売り越しに転じたからといって、相場が崩れるとは限らない。海外勢が日本株を大きく買い越したのは昨年11月だけで、その後は売り買いまちまちだ。1年間に15兆円買い越した「アベノミクス相場」初期の2013年のような継続性や規模感は乏しい。それでも日本株を30年半ぶりの高値に押し上げたのは、買い主体が入れ替わり立ち代わり表れたためだ。年金の売買動向を示す信託銀行は、昨年11月に3997億円売り越したが、海外勢の買いがペースダウンした12月に3564億円の買い越しに転じた。今年1月は海外勢、信託銀行ともに売り越しとなったが、個人投資家が買い越しに転換。個人投資家は、昨年11─12月に2兆3410億円売り越したものの、今年1月は5091億円の買い越し。2月1─2週は9271億円売り越したが、3─4週に6967億円買い越しと、海外勢の売買に対して「逆張り」を続けている。海外勢の日本株売りも、現時点では調整の範囲内と野村証券のクロスアセット・ストラテジスト、高田将成氏はみる。「CTA(商品投資顧問業者)は一部ポジションの圧縮にとどまり、マクロ系ヘッジファンドの景気見通しに変化はなくヘッジ売りにすぎない。ロング・ショートも銘柄入れ替えの範囲だ」と指摘する。ただ、相場観に違いはあっても、日本株独自の買い材料は依然乏しく、グローバル・マーケットとの高い連動性は変わらない。足元の米金利上昇はドル高/円安要因となっているが、昨年後半の円高は株売り材料とされておらず、今回プラス材料として認識されない可能性もある。米長期金利などの動向に神経質な展開が続きそうだ。テスラなどの「ヴェルカダ」監視カメラに侵入、ハッカーが明かす[9日 ロイター] - 監視カメラメーカー「ヴェルカダ」の管理上のアクセスを手に入れた小規模なハッカー集団が、米電気自動車(EV)大手のテスラを含む企業数百社の監視カメラ映像を過去2日間にわたって視聴していたことが分かった。ハッキング行為に携わった関係者の1人がロイターに明らかにした。サラエボで2018年3月撮影(2021年 ロイター/Dado Ruvic)モバイルアプリといったシステムのセキュリティー上の欠陥を見つけることで知られるスイスのソフトウエア開発者、ティリー・コットマン氏はロイターに対するメッセージの中で、カリフォルニア州のテスラ倉庫やアラバマ州の刑務所の内部のスクリーンショットをシェア。同氏はハッカー集団のその他メンバーの身元は明らかにしなかった。コットマン氏は、ヴェルカダの管理上のツールに関するログイン情報が今週にオンラインで公になっているのが分かり、人々の監視が広まっていることに注目させようとしたと語った。ヴェルカダは、侵入行為を把握しており、不正アクセスを防ぐために全ての内部管理アカウントを無効にしたと説明。内外のセキュリティーチーム・会社がこの問題を調査しているほか、司法機関にも通報したという。コットマン氏によると、ブルームバーグが9日にこの侵入行為を最初に報じるよりも数時間前にハッカー集団のアクセスがヴェルカダによって遮断された。また、ハッカー集団はテスラのほか、ソフトウエアメーカーのクラウドフレアやオクタの企業ネットワークのその他部分にアクセスするためカメラ装置を利用することが可能だったという。クラウドフレアは自社のセキュリティー措置について、小さな漏れが侵入行為の拡大につながらないよう設計されており、顧客データへの影響はなかったとしている。テスラからはコメントを得られなかった。オクタは、調査を続けているが、自社のサービスに影響は出ていないと述べた。ハッカー集団から提供されたヴェルカダユーザーアカウントのリストには、スポーツクラブチェーンの「ベイ・クラブ」や輸送技術スタートアップの「バージン・ハイパーループ」といった数千の組織が含まれている。両社からもコメントを得られなかった。【市況】明日の株式相場に向けて=SQ前「魔の水曜日」の静寂 きょう(10日)の東京株式市場は、日経平均株価が8円高の2万9036円と小幅続伸。続伸と言うには憚られる上げ幅で上値の重さが露呈した。米国株の方も主要株指数がちぐはぐな動きをみせていて、NYダウとナスダック総合指数の足並みがなかなか揃わない。前日も米長期金利の急低下を受けてナスダック指数が464ポイント高と目の覚めるような切り返しをみせたが、NYダウは終盤つるべ落としで値を消し30ドル高にとどまった。 もっともNYダウは一時最高値圏で推移していたから文句はいえない。日経平均は、このNYダウではなくハイテク株比率の高いナスダック指数との連動性が高い。であればこそ、きょうはハイテク株への買い戻しを軸に、もう少し素直な上げ足が期待されたところ。2万9000円大台絡みで右往左往するような展開は、株式需給関係があまりよくないということを示唆している。 今週は週末にメジャーSQ算出を控える。きょうは俗に言う「SQ前の魔の水曜日」であったから値下がり銘柄数が多かったとはいえ、日経平均、TOPIXともにプラス圏でおとなしく着地したというだけでも良しとすべきかもしれない。市場では、「日本時間の今晩に米10年債の入札があり、この結果次第で長期金利が跳ね上がる可能性があるから、うかつには手を出しにくい」(ネット証券ストラテジスト)という指摘も出ていた。 個別では電気自動車(EV)関連の日本電産が久しぶりにリバウンドの動きをみせた。EVは「脱炭素」が株式市場でテーマ性を帯びる以前からスポットライトが当たっていた人気テーマだ。最近は米テスラ株反落の影響も大きかったが、東京市場でも関連株は総じて需給調整局面にあった。しかしEVというテーマ自体が色褪せたわけではない。テスラの株価についてはそもそもバブル的色彩が強いが、きのうの米株市場で20%高と驚異的な切り返しをみせた。空売り筋にすればコーナーポストまで追い詰めたところで渾身のアッパーカットを食らったようなものだ。同日に、中国のEV3社のADR(米預託証券)が香港市場上場観測を材料に急騰したことも話題を提供した。 東京市場では鉄鋼、非鉄、海運など市況関連株に投資マネーが流れ込んでいる。そのなか東邦チタニウムの900円台前半は来期以降の業績回復を前提に仕込みどころと思われる。高度なチタン関連技術を生かし電子材料分野でも実績が高い。全固体電池や空気2次電池に応用されるリチウムランタンチタン酸化物(LLTO)という有望素材を手掛け、EV時代のキーカンパニーの一角として浮上する可能性も内包している。海運では、出遅れている明治海運の400円割れ水準は押し目買いを考えたい。ホテル関連事業も手掛けていることで、アフターコロナでは収益環境に吹く風向きが一変しそうだ。 東京五輪は無観客開催の可能性が出てきたが、新型コロナウイルスの影響はもとより、既に世界がリモート時代に突入していることを暗示している。株式市場では当面は「コト消費」など“人の流れ”を必要とする業態に投資資金が還流する公算が大きいが、巣ごもり化によって、リモート分野など既に不可逆的な領域まで進んでしまった感もある。5Gによる通信インフラの高付加価値化がそれに輪をかけている。ここで、重要性を増すのがサイバー犯罪への対処だ。今夏の五輪開催も視野に置きつつサイバーセキュリティー関連株が再び動意づくタイミングを迎えている。セキュアヴェイルは値ごろ感もあり25日・75日移動平均線絡みの時価は狙い目かもしれない。 このほか、介護DX関連でセントケア・ホールディングがいい動きをみせており注目したい。同社は人工知能(AI)搭載のロボットプラットフォームを手掛ける米アイオロス社に出資している。1月25日につけた上場来高値1069円をクリアすれば戻り売り圧力から解放された青空圏が広がる。また、AI関連ではアドバンスト・メディアも拾い場か。2月上旬に着目し、その後急速に上値を追ったものの、900円台前半で買いが途切れ往って来いの形となっているが、ここにきて75日移動平均線をターニングポイントに仕切り直す動きをみせている。 あすのスケジュールでは、2月の企業物価指数、2月のオフィス空室率など。海外ではECB理事会の結果発表とラガルド総裁の記者会見が注目される。インドとインドネシア市場は休場となる。(銀)出所:MINKABU PRESSAWH(旧:淡島ホテル)の関係会社が債権者より破産を申し立てられる帝国データバンク (株)長泉ガーデン(TDB企業コード:076001717、資本金1億円、登記面=静岡県駿東郡長泉町東野646、代表古矢誠一郎氏)と長田事業(株)(TDB企業コード:989614602、資本金1000万円、同所、同代表)は、3月10日に債権者より破産を申し立てられた。 申立代理人は原和良弁護士(東京都豊島区南大塚3-36-7、弁護士法人パートナーズ法律事務所、電話03-5911-3216)ほか3名。 (株)長泉ガーデンは、2009年11月「ホテル・長泉ガーデン計画」におけるホテル運営を目的として設立。長田事業(株)は2003年9月に設立。2社は、2019年2月に破産手続き開始決定を受けた(株)AWH(旧:(株)淡島ホテル、TDB企業コード:410137341)の関係会社。淡島ホテルは、アニメ『ラブライブ!サンシャイン!!』にも取り上げられ、ファンの間で高い知名度を誇っていた。 (株)AWHの破産手続きが進められる中、同社の資産がグループ会社に流出することを危惧した債権者団体がその対抗措置並びに被害の全面解決、真相究明を目的として、今回の措置となった。 負債は(株)長泉ガーデンが2018年8月末時点で約112億円。長田事業(株)が2019年10月末時点で約75億円。2社合計で約187億円。バブル華やかなりし頃の東京相互がらみの素敵なホテルでしたよね。NY株見通しー経質な展開か CPI、10年債入札を受けた金利動向に要警戒。トレーダーズ・ウェブ 今晩のNY市場は神経質な展開か。昨日は長期金利の上昇一服を受けて足もとで大きく下落したハイテク・グロース株が買い直され、ナスダック総合は3.69%高と急反発した。S&P500も1.42%高と反発したが、ダウ平均は一時347ドル高まで上昇し最高値を更新したものの、30ドル高と小幅高で終了した。今晩の取引では急反発したハイテク・グロース株の反動安が警戒される一方、1.9兆ドルのコロナ対策法案が下院を通過する予定で、バイデン米大統領の署名による今週中の法案成立見通しが下値支援となりそうだ。金利を巡っては、寄り前にインフレ指標の米2月消費者物価指数(CPI)が発表されるほか、午後には米国10年債入札も予定され、CPI、10年債入札の結果を受けた長期金利の動向に要警戒。 今晩の米経済指標・イベントは2月CPI、米国10年債入札のほか、EIA週間原油在庫、2月財政収支 など。企業決算は寄り前にキャンベル・スープが発表予定。(執筆:3月10日、14:00)〔NY外為〕円、108円台後半(10日午前8時)時事通信 【ニューヨーク時事】10日のニューヨーク外国為替市場の円相場は、午前8時現在1ドル=108円72~82銭と前日午後5時(108円45~55銭)比27銭の円安・ドル高で推移している。 ユーロは同時刻現在、対ドルで1ユーロ=1.1880~1890ドル(前日午後5時は1.1896~1906ドル)、対円では同129円18~28銭(同129円06~16銭)。(了)〔NY外為〕円、108円台半ば(10日朝)時事通信 【ニューヨーク時事】10日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、米物価指標の発表を受け、1ドル=108円台半ばと、同後半から下げ幅を縮小した。午前9時現在は108円50~60銭と、前日午後5時(108円45~55銭)比05銭の円安・ドル高。 10年物米国債入札を午後に控え、米長期金利が小幅に上昇。これがドル買いを支援し、円は108円77銭に弱含んでニューヨーク市場入りした。 インフレ高進観測が広がる中、市場は朝方発表の2月の米消費者物価指数(CPI)に注目。米労働省によると、CPI全体は前月比0.4%上昇、変動の大きいエネルギーと食料品を除いたコアは0.1%上昇。市場予想(ロイター通信調べ)はそれぞれ0.4%上昇と0.2%上昇で、発表後はドルが幾分売り戻されている。 ユーロは同時刻現在、対ドルで1ユーロ=1.1905~1915ドル(前日午後5時は1.1896~1906ドル)、対円では同129円15~25銭(同129円06~16銭)と、09銭の円安・ユーロ高。(了)今夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中の17銘柄が値を上げてスタートしましたね。スタート時点では5%以上の大きな変動は見られませんね。ダウ平均の上げ幅一時300ドル超に=米国株速報みんかぶFXNY株式10日(NY時間09:43)ダウ平均 32116.71(+283.97 +0.89%)ナスダック 13196.12(+122.29 +0.94%)CME日経平均先物 29120(大証終比:+140 +0.48%)〔米株式〕NYダウ、最高値更新=ナスダックも高い(10日朝)時事通信 【ニューヨーク時事】10日のニューヨーク株式相場は、2月の米消費者物価統計を受けて過度なインフレ懸念が後退して買いが先行し、続伸して始まった。優良株で構成するダウ工業株30種平均は取引時間中の史上最高値を更新。午前9時45分現在、ダウは前日終値比325.90ドル高の3万2158.64ドルとなった。ハイテク株中心のナスダック総合指数は156.64ポイント高の1万3230.46。(了)
2021.03.10
コメント(0)
-

3月8日(月)~9日(火)…
3月8日(月)の昼食を済ませると、身支度をして、13時30分頃に家を出る。宣言解除を待っていたわけではありませんが…。GoToAichi!特に渋滞もなくスムーズに走って、15時頃には美浜町・河和のパフェが有名な「フレベールラデュ」へ。近くに戸塚ヨットスクールもありますね…。この日の気温ではパフェを食べる気になれず…。レモンのケーキをいただきましたが、僕にはちょっと乳脂肪分がくどいかな…。トアルコ・トラジャのコーヒーは美味しくいただきました。お店を後にして16時頃には本日のメイン「海のしょうげつ」に到着。ロビーでチェックインを済ませるとお部屋へ移動。いつもメゾネットのお部屋をお願いしていましたが、今回は平屋タイプで。ほぼ満室ですが誰にも会わない大浴場(定員は3人ですが)でお風呂に浸かって、ラウンジでコーヒーブレイクして過ごす。夕日が伊勢湾の対岸に沈んで、19時から夕食です。今回はメニューを一部変更していただいて好物がずらりと並びました。蓬莱泉の飲み比べセットをいただいて、空をさらに追加でいただく。今月が誕生月だと記録に残っていたのでサプライズのデザートも…。この後も食後の温泉、寝る前の温泉とお風呂を楽しむ。3月9日(火)、曇り。6時15分頃に目が覚めました。新聞に目を通して、コーヒーブレイクして、まずはお風呂へ…。気持ちいいです。さらに大浴場でお風呂に入って、8時30分からは朝食。食事を終えて、部屋で1時間ほど眠りに落ちる…。チェックアウト前のお風呂を楽しんで、10時30分を過ぎた頃にチェックアウト。隣町の「えびせんの里」に寄り道。そのまま名古屋市内へ。M坂屋さんには12時頃に到着。地下でお茶と和菓子と夕食の食材を調達。「ヴィタメール」でバースデイプレゼントのケーキをいただく。帰宅すると14時頃。お留守番のロマネちゃんがあれていたらしい…。お世話をして、おやつタイムにケーキをいただく。今月で67歳ですね…。あな恐ろしや…。1USドル=109.01円。1AUドル=83.61円。昨夜のNYダウ終値=31802.44(+306.14)ドル。本日の日経平均終値=29027.94(+284.69)円。金相場:1g=6557(-44)円。プラチナ相場:1g=4462(+28)円。昨夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中の2銘柄が値を上げて終了しましたね。押しなべて大きく下げた銘柄が多いですから、僕がチェックしている銘柄は潮目が変わってしまったようですね…。本日の東京市場ではチェック中の日本株30銘柄中の24銘柄が値を上げて終了しましたね。重点6銘柄では5銘柄が値を上げて終了しましたね。5%以上の大きな変動は見られませんね。日本株は反発、米追加経済対策で景気期待-自動車や情報・通信高い 9日の東京株式相場は反発。大規模な米追加経済対策が今週中にも成立する見通しであることから景気回復が期待され、自動車や銀行など景気敏感業種を中心に、情報・通信や医薬品など幅広い業種が上昇した。 TOPIXの終値は前日比24.10ポイント(1.3%)高の1917.68 日経平均株価は284円69銭(1%)高の2万9027円94銭 <きょうのポイント> イエレン米財務長官、インフレ招くとの懸念を一蹴-大規模経済対策 労働市場は来年までに元の軌道に戻ると予想 8日の米10年物国債利回りは1.59%程度-前週末比2ベーシスポイント(bp)上昇 JPモルガン・アセットマネジメントの前川将吾グローバル・マーケット・ストラテジストは、世界景気が強含み企業業績の見通しが改善していく中で、「量的金融緩和による株高が基本線として根強くある」と指摘。それを阻害していたのが米長期金利の急な上昇ペースで、「景気が強い限りは金利の上昇基調は変わらないが、最近は1.5~1.6%に慣れてきたところもあり株価はいったん上昇している」と話した。 日本株は朝方の方向感を欠く動きから午後にかけて上げ幅を拡大した。日経平均株価の終値は4営業日ぶりに2万9000円を上回った。東証マザーズ指数も一時3%安を付けたが午後にプラス圏に浮上し0.5%高となった。 三井住友DSアセットマネジメントの市川雅浩チーフマーケットストラテジストは「米追加経済対策が上院を通過し、今週中にも成立との見方から金融や小売り、自動車など景気敏感株が買われ、半導体などのグロース(成長)株は売られやすい」と指摘した。9日のTOPIXバリュー指数は1.9%上昇したのに対し、グロース指数は0.6%の上げにとどまった。 ただ、11日に欧州中央銀行(ECB)理事会、来週は米連邦公開市場委員会(FOMC)が控えており、米長期金利に対する警戒は根強い。JPモルガン・アセットの前川氏は「金利上昇ペースが止まらなければ株価の再度調整は短期的にはあり得る」と話した。 東証33業種では、不動産や電気・ガス、輸送用機器、鉄鋼、陸運、ゴム製品などが上昇 鉱業や電機、その他製品は下落ダウ平均とナスダック100の乖離、1993年以来の大きさに 成長株からバリュー株へのローテーションは、ナスダック100指数とダウ工業株30種平均の乖離(かいり)に顕著に表れている。 8日の米株市場では125年の歴史を持つダウ平均が日中ベースの最高値を更新した一方、大型ハイテク銘柄中心のナスダック100は調整局面入りとされる水準に下落した。ダウ平均が上昇して最高値から1%の範囲で取引を終了した日にナスダック100が最高値から10%余り安い水準となったのは、1993年以降では初めて。 FBBキャピタル・パートナーズの調査責任者、マイク・ベイリー氏は「投資家は景気回復に自信を深めつつあり、ハイテク株に比べてバリュエーションが妥当な大型株の中でファンダメンタルズの改善を取り込もうとしている」と指摘。「合理的な価格でファンダメンタルズ改善を重視する動きが、ダウ平均を新高値に押し上げているようだ」と述べた。 この日はダウ平均を構成する30銘柄のうち、下落したのは5銘柄のみ。ウォルト・ディズニーが6.3%高で上げを主導したほか、ビザ、ゴールドマン・サックス・グループ、ホーム・デポはいずれも2%を超える上昇となった。 一方、アップルとテスラの下落がナスダック100の重しとなった。また、マイクロソフトやネットフリックスなど、巣ごもり需要の追い風を受けて昨年は大きく値を伸ばした銘柄も売られ、ズーム・ビデオ・コミュニケーションズは8%近く下げた。 ローテーションの動きは、特別買収目的会社(SPAC)ではさらに厳しいものとなっている。幅広いSPACのパフォーマンスを追跡するIPOX・SPAX指数は2.6%安と、この5営業日で4日目の下落となった。 FBBキャピタルのベイリー氏は「投資家は新型コロナ禍の勝ち組銘柄があまりにも割高になったため、バリュエーションを見直す時だと決断した」と述べた。【本日のNYダウ見通し】NYダウが過去最高値を更新するかに注目【NYダウ予想レンジ:31,700~32,200ドル】8日のNYダウは反発。前週末比306.14ドル高の31,802.44ドルで取引を終了しました。米上院が6日に可決した追加経済対策が下院で再審査されており、今週にも成立する見通しと伝わったことが好感されました。追加経済対策には最大1,400ドルの現金給付を含み、個人消費の押し上げが期待されています。また新型コロナウイルスワクチンの接種が進んでおり、経済が正常化するとの期待が高まっているのです。NYダウは高値32,148.04ドルまで上昇し、取引時間中の過去最高値を更新。ただ米10年債利回りが1.6%台まで上昇するなか、割高感が意識されやすいハイテク株が売られました。ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は、310.99ポイント安の12,609.16で取引を終了しています。本日は重要度の高い経済指標の発表はありませんが、米3年債の入札があるので金利動向に影響があるのかどうか注目です。ただ、12時30分時点のNYダウ先物は200ドル近く上昇しており、しっかりの展開が予想されます。日経平均は反発、円安を好感 バリュー株物色が下支えに[東京 9日 ロイター] - 東京株式市場で日経平均は反発。外為市場でドル/円が109円台まで円安に進んだことが好感された。物色面では、値がさのグロース株が引き続き売られる一方、バリュー株が幅広く物色され、これが相場全体を下支えする格好となっている。8日の米国株式市場は、ダウ工業株30種が上昇。1兆9000億ドル規模の新型コロナウイルス追加経済対策法案の最終的な議会採決を週内に控え、経済再開による恩恵を受けるとみられる銘柄が上げを主導した。一方、大型テクノロジー関連株が売り込まれ、ナスダック総合は2月12日に付けた終値での最高値を約10.5%下回り、調整局面入りした。これを受けて日本株も、経済正常化期待を手掛かりに景気敏感株が買われる一方、値がさのグロース株が売られて始まり、物色の跛行(はこう)性が強まった。後場になってから、グロース株の一角に押し目買いが入り、日経平均は上げ幅を拡大。ただ、終日を通してTOPIXが優勢の相場展開となった。市場では「先月3万円を回復した日経平均は引きずり降ろされる展開となっており、マーケットは荒れ気味。ナスダックが最高値から10%以上の下落率となったことを受けて、調整は長引くとみた投資家が多いのではないか」(SBI証券・投資調査部長の鈴木英之氏)との声が聞かれる。TOPIXは1.27%高。東証1部の売買代金は、3兆2706億0300万円と膨らんでいる。東証33業種では、不動産業、電気・ガス業、輸送用機器などの上昇が目立ち、値下がりは鉱業など3業種にとどまった。個別では、トヨタ自動車など自動車株が円安を好感して物色されたほか、日本製鉄が連日の昨年来高値更新となるなど景気敏感株や電鉄、不動産といった内需関連株に高い銘柄が多い。三菱UFJフィナンシャル・グループなどの銀行株しっかりだが、東京エレクトロン、キーエンスなどの値がさ株が軟調に推移した。東証1部の騰落数は、値上がり1848銘柄に対し、値下がりが302銘柄、変わらずが44銘柄だった。テルモ、ワクチン7回接種可能な注射器を開発 3月末に生産開始[東京 9日 ロイター] - テルモが、米ファイザー製の新型コロナウイルスワクチン1甁で7回の接種が可能な注射器を開発した。5日に厚生労働省が製造・販売を承認した。3月末から生産を始める見通し。初年度は2000万本の生産を予定する。ワクチンの効果を高めるよう、皮下注射を想定した注射器に比べ針を3ミリ長くして薬液が筋肉まで到達しやすくした。出荷時期は今後、行政と相談して決める。ファイザー製のワクチン接種を巡っては、1容器から6回の接種が想定されていたが、確保された注射器では5回しか接種できないことが明らかとなっていた。ダウ上昇、追加経済対策の採決控え ナスダックは調整入り[8日 ロイター] - 米国株式市場は、ダウ工業株30種が上昇して取引を終えた。1兆9000億ドル規模の新型コロナウイルス追加経済対策法案の最終的な議会採決を週内に控え、経済再開による恩恵を受けるとみられる銘柄が上げを主導した。一方、大型テクノロジー関連株が売り込まれ、ナスダック総合は2月12日に付けた終値での最高値を約10.5%下回り、調整局面入りした。ダウは取引時間中に最高値を更新したが、上げ幅を縮小して引けた。米上院は6日、下院案に修正を加えた新型コロナ追加対策法案を可決。バイデン氏はこれを受け、下院が修正法案を迅速に可決し、自身の署名によって国民への直接給付を開始できることを望むと表明した。追加刺激策が導入され、景気回復ペースが加速するとの見方を背景にインフレ懸念が高まり、米10年債利回りは約1年ぶりの高水準を付けた。ただ、イエレン米財務長官は8日、新型コロナ追加経済対策が「非常に力強い」米景気回復を促進させるとの見解を示した上で、財政支出拡大に伴う景気過熱は想定していないとした。S&P総合500種の主要セクターでは、国債利回りの上昇を背景に金融が大きく値上がりし、最高値を付けた。工業も最高値に上昇。素材は最高値に迫った。一方、情報技術(IT)は下げが最もきつかった。ウェドブッシュ・セキュリティーズの株式トレーディング部門マネジングディレクター、マイケル・ジェームズ氏は、国債利回りの上昇に伴い、グロース(成長)株やIT株のバリュエーションを巡る懸念が高まり、このところナスダックの圧迫要因になっていると指摘。その一方で、金融株やレストラン、旅行関連株など経済再開の恩恵を受けるセクターが上昇を主導していると述べた。ナスダックでは、アップル、エヌビディア、テスラ、アルファベットが下げを主導した。S&Pの銀行株指数は約2%高。航空株指数は約5%高。娯楽大手ウォルト・ディズニーは約6%上昇。カリフォルニア州の保健当局が、ディズニーランドなどのテーマパークやスタジアムといった屋外の娯楽施設について、早ければ4月1日にも営業再開を認める新たな規則を策定したことが背景。ゲームストップは約42%急伸。同社は、電子商取引事業への移行に向けた取り組みを主導するポストを巡り、株主のライアン・コーエン氏に打診したと明らかにした。米取引所の合算出来高は140億3000万株。ニューヨーク証券取引所では値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を1.39対1の比率で上回った。ナスダックでは1.03対1で値下がり銘柄数が多かった。パナソニックが続落、ブルーヨンダー買収観測で財務負担など懸念 パナソニック(6752)がまとまった売り注文を浴びて大幅続落。午後1時29分時点では前日比93円(6.5%)安の1331円で、東証1部の値下がり率ランキングの2位となっている。 アメリカのソフトウエア大手であるブルーヨンダーを買収する方針を固めたと報じられたのが手がかり。投資額は7000億円を軸に調整とも伝えられた。資金は自己資金を軸とするが市場からの調達も検討する見込みで、株価はそれに伴う財務負担を懸念した売り注文に押されている。 ブルーヨンダーの2019年度の売上高は前期比8%増の約10億ドル(約1085億円)とされるが、一部には割高感を懸念する向きもあるようだ。パナソニックは本日午前に「企業価値向上に向け様々な検討をしておりますが、本件について決定した事実はありません」とするコメントを出している。(取材協力:株式会社ストックボイス)【市況】東京株式(大引け)=284円高、米景気回復期待と円安など追い風 9日の東京株式市場は日経平均が上下に不安定な値動きとなったが、後場は買いに厚みが加わり下値を切り上げる展開で2万9000円台を回復して引けた。 大引けの日経平均株価は前営業日比284円69銭高の2万9027円94銭と4日ぶり反発。東証1部の売買高概算は16億2114万株、売買代金概算は3兆2706億円。値上がり銘柄数は1848、対して値下がり銘柄数は302、変わらずは44銘柄だった。 きょうの東京市場は、強弱感が対立し上下に荒い値動きとなったものの、総じて買い意欲の強さが目立つ地合いとなった。前場は前日終値をはさみ右往左往する展開だったが、後場は一段高でスタートし、いったんは戻り売りに伸び悩むも後半にかけじりじりと下値を切り上げた。米国株市場では追加経済対策を背景とした景気回復期待が高まる一方で、長期金利の動向に神経を尖らしハイテク株への売りが目立った。その流れは東京市場も波及している。ただ、下げたのはハイテクセクターの一角で全体的には押し目買いニーズが旺盛だった。為替が円安に振れたこともプラス材料。中国系の政府系ファンドが日本株買いに動いているとの一部メディア報道もあり、全体株価の上昇を後押しした。値上がり銘柄数は1800を上回り、東証1部全体の84%の銘柄が上昇した。売買代金は3兆2000億円台に膨らんだ。 個別では、ソフトバンクグループが群を抜く売買代金をこなし高い。三菱UFJフィナンシャル・グループ、三井住友フィナンシャルグループなどメガバンクへの買いも目立った。トヨタ自動車が大きく買われ、武田薬品工業も堅調。ワタベウェディングがストップ高に買われたほか、安永、大紀アルミニウム工業所、インプレスホールディングスなども値上がり率上位に食い込んだ。 半面、任天堂が売られ、ソニー、日本電産、キーエンスなども値を下げた。レーザーテックも軟調。パナソニックが急落したほか、日立造船の下げも目立つ。ジーエス・ユアサ コーポレーションが下落、東洋インキSCホールディングス、浜松ホトニクスなども売りに押された。出所:MINKABU PRESS明日の戦略-後場上げ幅拡大で29000円台乗せ、5日線も上回り反転の準備が整うトレーダーズ・ウェブ 9日の日経平均は4日ぶり反発。終値は284円高の29027円。小高く始まった後、前場ではプラス圏とマイナス圏を行き来した。米国でダウ平均が大幅高、ナスダックが大幅安となったことから、景気敏感株には強い買いが入った一方、グロース株が売り込まれ、全体では強弱感が交錯した。しかし、後場は前引けから大きく水準を切り上げて始まると、プラス圏が定着した。グロース株の多くが持ち直してきたことから、指数は一気に上げ幅を300円超に拡大。29000円台に乗せたところでは上値追いに慎重姿勢が見られたが、戻り売りも手控えられ、引け間際に高値をつけた。前引けでは下落していたマザーズ指数もプラスに転じて取引を終えた。 東証1部の売買代金は概算で3兆2700億円と、強い動きが出てくる中で商いも高水準となった。業種別では不動産や電気・ガス、輸送用機器などが大幅上昇。下落は鉱業、電気機器、その他製品の3業種のみとなった。ソフトバンクGが売り気配スタートから下を試した後に切り返し、3%を超える上昇。半面、キーエンスが連日弱く、3%を超える下落となった。 東証1部の騰落銘柄数は値上がり1848/値下がり302。円安進行を材料に、トヨタ、三菱自動車、スズキなど自動車株全般に買いが入った。景気敏感株が強く、三菱UFJや三井住友など金融株や、日本製鉄や中山製鋼所など鉄鋼株の物色が活況となった。東京電力、関西電力、東北電力など電力株にも非常に強い動きが見られた。ラウンドワンや三越伊勢丹などアフターコロナ関連の一角が急伸。上方修正と増配を発表した大紀アルミニウムが値を飛ばした。 一方、任天堂やソニーなどゲーム株が軟調。日本電産やアドバンテスト、レーザーテックなどハイテク株は、下げ渋ったものの大きめの下落となった。パナソニックは過去最大級のM&A観測が伝わったが、市場の反応は厳しく6%を超える下落。新株予約権の発行が嫌気されたアンジェスが大幅安となった。バリュー株が強く、大型ハイテク株を見直す動きも出てくる中、coly、アピリッツ、 WACULなど直近IPO銘柄が手仕舞い売りに押された。 日経平均は後場に入って買いの勢いが強まり、3桁の上昇で29000円台を回復した。グロース株がきょうで下げ止まったとみるのは気が早いが、グロースに買いが入れば指数は上に値幅が出やすくなることが改めて確認できた。そして、きょうのバリュー株の値動きは特筆される。きのう昨年来高値を更新した日本製鉄や三菱UFJは、後場に伸び悩みはしたものの、しっかりとした基調が続いた。グロース株が見直され始めれば真っ先に利益確定売りに押されても不思議ではなかったが、資金は逃げなかった。グロースが持ち直す局面でもバリューが崩れなければ、指数の方向は必然的に上となる。終値(29027円)ではきっちり5日線(29024円、9日時点)を上回った。あす、29000円や5日線より上をキープできるようなら、そこから先は調整一巡期待の買いが指数を押し上げることになるだろう。現代のラグジュアリィスポーツはボタン1つで“ジキル”と“ハイド”に今晩のNY株の読み筋=神経質な展開か、米3年国債入札に関心もモーニングスター 9日の米国株式市場は、神経質な展開とみる。注目したい米経済指標の発表や要人発言の機会がない代わりに、きょうから11日まで、3年、10年、30年と、連日で米国債の入札が予定されている。足元の金利上昇は低調だった2月の米7年債入札がきっかけ。入札が無難な通過となれば引き続きバイデン米政権による1.9兆ドル規模の経済対策への期待が株価の支えになるが、低調な結果となって利回りが上昇すればグロース株への売り圧力が強まる恐れがあり、ハイテク株比率の高いナスダック総合指数は調整が続く可能性がある。<主な米経済指標・イベント>米3年国債入札◎投資関連情報は投資の参考として情報提供のみを目的としたものであり、株式の売買は自己責任に基づき、ご自身で判断をお願いします。明日の日本株の読み筋=不安定な相場付きか、米金利高警戒くすぶる、メジャーSQ控え先物売買には注視モーニングスター あす10日の東京株式市場は、不安定な相場付きか。米長期金利上昇への警戒感がくすぶるなか、現地10、11日にそれぞれ10、30年債の入札が予定され、来週にはFOMC(米連邦公開市場委員会、16-17日開催)を控えるというスケジュールをにらみ、結果を受けた金利動向が気になる。一方、週末12日には日経平均先物・オプション3月限のメジャーSQ(特別清算指数)算出日を迎えるが、SQ週の中日となる水曜日は機関投資家の持ち高調整の売買が膨らみ、相場が荒れる傾向があり、先物売買には注視する必要がある。市場では、「米長期金利への警戒感がぬぐえず、週末のメジャーSQ算出を控え、荒っぽい動きになるのではないか」(中堅証券)との指摘は少なくない。 9日の日経平均株価は4営業日ぶりに大幅反発し、2万9027円(前日比284円高)引け。前場は上げ下げを繰り返し、方向感に乏しい展開だったが、後場は上げ幅を拡大して始まり、一時300円超上昇する場面があった。時間外取引の米株価指数先物が堅調に推移するとともに、中国政府関係の複数ファンドが中国本土株の購入に動き相場の下支えを図っていると報じられ、材料視された。伸び悩む場面もあったが、先物買いを交えて終盤に向け引き締まった。チャート上では、4日に割り込んだ25日移動平均線を下回ったままであり、早期に同線を回復しないと上値抵抗線として強く意識されることになろう。NY株見通し-堅調か 経済指標は2月中小企業楽観度指数トレーダーズ・ウェブ 今晩のNY市場は堅調か。昨日は追加経済対策の成立見通しやワクチン普及による経済活動の早期正常化期待を受けて景気敏感株が上昇した一方、長期金利の上昇を受けてアップルなどのハイテク・グロース株に利益確定売りが続いた。ダウ平均は一時史上最高値を更新し、306ドル高と2日続伸した一方、ハイテク株主体のナスダック総合は2.41%安と大幅反落した。今晩の取引でも追加経済対策への期待やワクチン普及による景気の早期回復期待から景気敏感株の堅調持続が期待されるほか、長期金利の上昇が一服となれば、軟調が続くハイテク・グロース株にも押し目買いが期待できそうだ。 今晩の米経済指標・イベントは2月NFIB中小企業楽観度指数、米国3年債入札など。主要な企業の決算発表はなし。(執筆:3月9日、14:00)【市況】明日の株式相場に向けて=中小型株のバリュースマッシュ相場続く きょう(9日)の東京株式市場は上下に不安定な動きではあったものの、後場に入って上値指向を強め、日経平均株価は284円高の2万9027円と4日ぶりに反発した。取引時間中は米株価指数先物やアジア株市場の顔色をうかがいながら、神経質な値動きとなるのは避けられない。ただ、きょうは後場寄りに日経平均が一段高に買われた。タイミング的に違和感の伴う上昇だったが、「一部報道で中国の政府系ファンドが動き出したとの見方が浮上している」(中堅証券ストラテジスト)という。ポジティブ材料として先物主導の上げに結びついた。「これは中国政府系資金が日本株に投資するというニュアンスではないが、間接的ではあっても海外マネーの日本再上陸の思惑を生む。ハイテク株の後場の戻りは、この報道が影響した」(同)としている。 直近では、外国人投資家が日本株に再び攻勢をかけているとの観測がある。投資対象はずばり三菱UFJフィナンシャル・グループなどメガバンクを中心とする金融セクター。米長期金利の上昇で運用利ザヤが拡大することに加え、国内でも日銀が長期金利上昇を許容するとの思惑が出ているためという。来週の日銀金融政策決定会合は、FOMCと並び久しぶりに注目度の高いイベントとなりそうだ。 個別では、バリュー系の中小型株に物色の矛先が向いている。通常バリュー株というと景気敏感セクターの大型株がイメージされやすいが、実際はそうではない。比較的時価総額の小さい銘柄でも、業績面がしっかりしていて有配にもかかわらず、指標面で割安に放置されている銘柄は数多くある。グロース株投資の観点であれば、PERやPBRはむしろ高い方が成長性の高さを代弁するようなところが無きにしもあらずだが、バリュー株に流れが向いてくると、これまで蚊帳の外に置かれていた低PERや低PBR銘柄ががぜん輝きを放ち始める。 昨年来のコロナ禍にあって、バリュー系銘柄であっても利益が一時的に落ち込むのは仕方ない状況にあり、その意味で足もとではPERよりも、その企業の純資産にリンクされたPBRにマーケットの視線が向かいやすい。低PBR株というのは、グロース株に資金の流れが向いている局面では株高に向けたアピール要素はほぼ皆無といってよいが、今のように全体相場がアフターコロナを見込んだ地合いに変化してくると、トラディショナルな指標として威力を発揮する。 机上の論理には違いないものの、例えばPBR0.5倍というのは、当該会社の全株式を買い占めた後、その会社をすぐに解散して保有していた資産をキャッシュ化するだけで、買収に費やした資金の2倍を手にすることができるという理屈である。逆にいえば、PBRが大幅に1倍を下回る企業は、買収後ただちに解体してお釣りがくるのだから、現在営んでいる事業の成長性はおろかビジネスモデルそのものを否定されているに等しい。経営者側にとってはきつい評価だ。しかし実際はそんなことはなく、買い手側には理論上かなりのアドバンテージが付与されていることになる。 今は短期トレードの視点でも、低PBRで株価の瞬発力のある銘柄にスポットライトが当たりやすい地合いである。鉄鋼株では直近にきて三菱製鋼が急騰しているが、PBRは急騰後でも何と0.3倍台である。不動産関連では明和地所やフジ住宅、更に前日取り上げた高田工業所、関電工、大同メタル工業、ソディックや、急動意したインプレスホールディングスなども、それぞれの株高材料を内包してはいるものの、共通項として低PBRがひとつのポイントとなっている。 このほか、PBR1倍割れ銘柄でマークしてみたいのは独立系システムインテグレーターのNCS&A。あるいはカー用品販売でアフターコロナの有力株であるイエローハットなど。また、PBRは1.3倍台ながら選挙関連株としての思惑でマクロミルの動きも目先注目しておく価値がありそうだ。 あすのスケジュールでは、1月の特定サービス産業動態統計速報など。海外では2月の中国消費者物価指数、2月の中国生産者物価指数、2月の米消費者物価指数、2月の米財政収支など。(銀)出所:MINKABU PRESS〔NY外為〕円、108円台後半(9日午前8時)時事通信 【ニューヨーク時事】9日のニューヨーク外国為替市場の円相場は、午前8時現在1ドル=108円81~91銭と前日午後5時(108円87~97銭)比06銭の円高・ドル安で推移している。 ユーロは同時刻現在、対ドルで1ユーロ=1.1883~1893ドル(前日午後5時は1.1840~1850ドル)、対円では同129円36~46銭(同128円97銭~129円07銭)。(了)ペイパル、暗号資産カストディ企業「カーブ」を買収CoinDesk Japanペイパルは8日、イスラエルに拠点を置く暗号資産カストディ企業「カーブ(Curv)」の買収に合意したと発表した。買収金額などは明らかにされていないが、ペイパルは「暗号資産(仮想通貨)およびデジタル資産に関連する事業を拡大」させることが目的だと説明した。米CoinDeskは3月2日、買収が進行中と最初に報じた。買収は今年上半期に完了する見通しだ。「カーブの買収は、より包括的な金融システムに向けた我々のビジョンを実現するために、優秀な人材とテクノロジーに投資する取り組みの一環だ」と、同社バイスプレジデント兼ブロックチェーン・暗号資産・デジタル通貨担当ゼネラルマネージャーのホセ・フェルナンデス・ダ・ポンテ(Jose Fernandez da Ponte)氏は述べた。「カーブのチームと協議を進めてきたなかで、カーブの技術的才能や起業家精神、そしてこの数年間開発してきたテクノロジーの背景にある考え方に感銘を受けた。カーブのチームをペイパルに迎え入れられることを大変うれしく思っている」(ポンテ氏)カーブの共同創業者兼CEOのイテイ・マリンガー(Itay Malinger)氏は「今、デジタル資産の普及が加速するなか、イノベーションを推進し続けていくために、ペイパルほど最適な場所はないと感じている」と語った。 ペイパルの暗号資産における動きペイパルが、暗号資産カストディ企業の買収を考えていることは周知の事実だった。ペイパルは過去に、ビットゴー(BitGo)に7億5000万ドルでの買収を提示したと伝えられたが、買収は成立しなかった。暗号資産業界では、カーブやファイアーブロックス(Fireblocks)のようなカストディ企業が不足している。ファイアーブロックスは、伝統的資産での世界最大のカストディアンであるバンク・オブ・ニューヨーク・メロン(BNYメロン)と暗号資産カストディに取り組んでいると伝えられている。関係者によると、カーブは過去にフェイスブックの暗号資産部門「ノビ(Novi)」からの買収提案を退けてきた。カーブはイートロ(eToro)やファルコンエックス(FalconX)など、ヨーロッパに軸足を置いた大手暗号資産企業と提携しており、今回の買収は、ペイパルがより幅広いサービスを提供すると同時に、アメリカ以外でも暗号資産における影響力の拡大を目指していることを示唆している。大手銀行がカストディ分野での提携や企業買収による人材獲得を目指すなか、2021年は暗号資産業界での合併や買収が増える可能性がある。今夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中のすべてが値を上げてスタートしましたね。多くの銘柄が大きく上げていますね。〔NY外為〕円、108円台後半(9日朝)時事通信 【ニューヨーク時事】9日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、米長期金利の低下を眺め、1ドル=108円台後半でもみ合っている。午前9時現在は108円85~95銭と、前日午後5時(108円87~97銭)比02銭の円高・ドル安。 ニューヨーク市場は、108円86銭で取引を開始。長期金利の指標となる10年物米国債利回りは前日に1.6%台に上昇した後、低下した。米追加経済対策の成立見通しなどを背景に長期金利は依然高止まりしているが、ひとまずポジションを調整する動きになり、円売り・ドル買いの勢いは失速した。海外市場で一時109円20銭近辺まで軟化した円は、未明に108円台後半に戻した。 この日は主要な米経済指標の発表もなく、新規の手掛かり材料不足から方向感に乏しい展開となっている。 ユーロは同時刻現在、対ドルで1ユーロ=1.1890~1900ドル(前日午後5時は1.1840~1850ドル)、対円では同129円45~55銭(同128円97銭~129円07銭)と、48銭の円安・ユーロ高。(了)〔米株式〕NYダウ、続伸=ナスダックは大幅反発(9日朝)時事通信 【ニューヨーク時事】9日のニューヨーク株式相場は、米長期金利の低下を眺めてハイテク株を中心に買いが先行し、続伸して始まった。優良株で構成するダウ工業株30種平均は午前9時35分現在、前日終値比141.97ドル高の3万1944.41ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は324.43ポイント高の1万2933.59と大幅反発している。(了)インビデが大幅高 筆頭株主のウッド氏が同社を称賛=米国株個別みんかぶFX 遺伝子診断のインビデが大幅高。投資会社アーク・インベストメントのウッド氏がテレビ番組で同社を称賛したことが買い手掛かりとなっている模様。「ゲノム革命において同社は最も重要な企業の1つ」と述べた。アークはインビデ株を13.7%保有し、筆頭株主となっている。(NY時間09:50)インビテ 38.37(+3.61 +10.38%)トゥイリオ、テラドック、スクエア、ドキュサインが大きく上げていますね。
2021.03.09
コメント(2)
-
3月8日(月)…
3月8日(月)、曇りです。夜間の雨も上がって曇りですが、さして寒くもありませんね。そんな本日は7時15分に起床。新聞に目を通し、朝食を済ませ、ロマネちゃんと戯れる。本日は四七日の法要がありますからまずは1階の掃除機をかけてお寺さんを迎える準備…。法要も終わったところで一息…。朝のコーヒーブレイクはネスプレッソで…。ドゥバイヨルのチョコレートと共に…。美味い!!1USドル=108.39円。1AUドル=83.49円。現在の日経平均=29138.73(+274.41)円。金相場:1g=6601(+78)円。プラチナ相場:1g=4434(+96)円。本日の東京市場ではチェック中の日本株30銘柄中の25銘柄が値を上げてスタートしましたね。重点6銘柄では5銘柄が値を上げてスタートしましたね。武田、JFE、エノモトが上げて、レノバが下げていますね。コロナワクチンでアナフィラキシー3例目共同通信社 厚生労働省は7日、新型コロナウイルスワクチンを接種した30代女性が、重い副反応のアナフィラキシーを発症したと発表した。投薬後に症状は改善したが、経過観察の目的で入院した。国内3例目の発生。富裕層爆買い、「コロナで格差拡大」は日本の大問題 日経平均株価が一時、3万円を突破し、実体経済との乖離が激しくなっている。株価上昇によって資産家は富を増やしており、コロナ危機であるにもかかわらず高額商品が飛ぶように売れている。現在の株価高騰は、量的緩和策による金余りとポストコロナ社会(デジタル化社会)への期待感が交錯した構造的なものであり、しばらく継続すると見る市場関係者は少なくない。もしその見立てが正しければ、資産の有無による格差が今後、さらに拡大する可能性がある。(加谷 珪一:経済評論家) 宝飾品や貴金属の販売が絶好調 昨年(2020年)10月まで2万3000円前後で推移していた日経平均株価は2月に入ってとうとう3万円の大台に乗せた。米国を中心に全世界的な株価高が続いており、日本市場もその流れに乗った格好だ。その後、株価は米国金利の上昇などもあって調整に転じているが、大幅な下落には至っていない。 株価が上昇すると資産効果によって富裕層を中心に高額商品の消費が増えることは経験則的によく知られているが、今回もそのパターンが当てはまるようだ。 日本百貨店協会によると2020年12月における飾品・貴金属の売上高は、他の商品が軒並み大幅なマイナスになっているにもかかわらず2%の増加となった。百貨店における宝飾品・貴金属の販売実績は富裕層の消費動向を示す有力な指標のひとつといわれており、大抵の場合、株価や不動産価格と連動して消費が増える。 首都圏における新築マンションの平均販売価格も上昇しており、2020年はとうとう6000万円を突破した。コロナ危機で開発案件が減り、その分だけマンション供給も減ったが、高額物件を中心に消費者の購入意欲は強く、逆に価格が引き上げられている状況だ。 一般的に海外旅行は、富裕層における高額消費の対象のひとつだが、今はコロナ危機で自由に海外に行くことができない。一方で、コロナの影響を受けなかった富裕層はフラストレーションがたまっており、別なところで消費欲を満たそうとする。同じタイミングで株価や不動産価格が上がっているため資産額が増えており、これが高額消費を拡大させる作用をもたらしている。 コロナ危機で大変な思いをしている人からすると、納得できるものではないだろうが、今、起こっている出来事を冷静に分析するとこのような状況になる。 では、コロナ危機で経済が大きな打撃を受けているにもかかわらず、なぜ株価や不動産価格だけが上昇しているのだろうか。そこには大きく分けて2つの要因がある。 ポストコロナ社会へのシフトが急加速 1つは量的緩和策がもたらした「金余り」である。安倍政権が実施した量的緩和策によって、日本の金融市場には空前の規模のマネーが供給された。2020年12月時点において日銀が保有する国債残高は536兆円に達しており、購入した株式の残高も35兆円を超えている。 日本のGDP(国内総生産)とほぼ同額のマネーを市場に供給すれば当然の結果として金余り現象が生じる。企業は経済の先行きを悲観視しているので、借入れを増やして設備投資を強化することはしない。結果として余剰マネーが株式や不動産に殺到している構図だ。 量的緩和策の実施にあたっては、節度を持って進めないと金余りによって株価や不動産価格が高騰するといった弊害が生じるとの指摘が出ていた。だが当時の世論は「これしかない!」「思い切った決断を!」といった勇ましいものばかりであり、慎重な意見に対しては「日本をつぶす気か?」といった激しいバッシングが行われる始末だった。 結果として慎重な意見は一切、顧みられることなく、量的緩和策が十分に効果を発揮していないことが明らかになってからも政府は撤退の決断ができなかった(主要国で量的緩和策から抜け出せなくなっているのは日本だけである)。 しかしながら、金余りが株高の原因であれば単なるバブルであり、すぐにでも株価は暴落するだろう。だが、量的緩和策による余剰マネーだけが今の株高の原動力というわけではない。株価が上昇している2つめの理由は「ポストコロナ社会への期待感」である。 近年、情報技術の高度な発達によってビジネスのデジタル化が進んでいる。近い将来、単純な事務作業や営業活動の多くは非対面あるいはシステムを使ったバーチャルなものに置き換わる可能性が高く、それに伴って企業の生産性向上が期待されている。また、自動車産業に代表されるように、EV(電気自動車)や自動運転システムの導入など、産業構造が根本的に変化する業界も少なくない。 こうした産業構造の変化は10年単位で発生すると予想されていたが、これを大きく覆すきっかけとなったのがコロナ危機である。日本でも、実施率がほぼゼロだったテレワークがコロナ危機をきっかけに一気に普及するなど、ビジネスのあり方が劇変している。10年の変化が2~3年で到来する可能性が高くなっており、一連の変化を主導するIT企業を中心に投資マネーが殺到している状況だ。 格差対策は実は成長戦略でもある ビジネスのITシフトは余剰の労働力を生み出してしまうので、IT時代においては労働者の賃金には抑制の力学が働く。仮にワクチン接種が順調に進み、世界経済が正常化すれば、経済のデジタル化がさらに加速し、新技術に投資をしてリターンを得る投資家と、企業に雇われて給料を得る労働者の格差はさらに拡大していくだろう。 さらに長期的な視点では、経済全体で労働分配率が大きく下がることも十分に考えられる。経済学的に見て、供給サイドの成長要因は、資本、労働、イノベーションの3つしかなく、この3つの比率の組み合わせで経済成長率が決まる。高度デジタル化社会においては、IT資本が増加し、それによってイノベーションが進むことで経済成長が実現するので、成長率に労働が占める割合は低下せざるを得ない。 結果として労働の対価である賃金は下がり、資本の対価である利子や配当、キャピタルゲインが増えるので、資本分配率が上昇し、逆に労働分配率が低下する。つまり、高度デジタル化社会においては、圧倒的に資本を持つ側が有利になるという仕組みだ。 経済的な格差が生じることの是非については様々な意見があるので、ここではあえて議論しない。だが、純粋に経済学的な議論にとどめた場合でも、格差拡大が構造的に発生する状況というのは、健全な成長を阻害する可能性がある。 先ほどの成長メカニズムはあくまで供給サイドに立脚したものだが、IT資本の増強による成長を実現するためには、供給された財やサービスを消費してくれる需要が必要となる。今回の株高で富裕層の消費が増えたといっても、所詮、1人の人間が消費できる金額には限度がある。つまり富が一部の人に集中すると、中間層以下の消費が減り、持続的な成長を妨げる可能性があるのだ こうした事態を回避するためには、IT資本への投資から得られるリターンを何らかの形で中間層以下に還元する仕組みが必要となる。それが税の形を取るのか、資産運用支援になるのか、あるいは寄付などの社会貢献になるのかは分からないが、格差拡大がほぼ必然であるならば、何らかの対策が必要だろう。 米国のバイデン政権は富裕税の創設を打ち出しており、税を使った所得再分配について検討を進めている。日本は特に下方向への格差拡大が激しく、貧困率は米国並みに高い。日本においても資本のリターンを困窮者などに再分配できる仕組みを検討する必要がある。これは格差是正という社会問題に見えるかもしれないが、実は持続的な成長を実現するための成長戦略でもある。日本株は上昇、米労働市場改善で回復期待強まる-自動車や電機高い 8日の東京株式相場は上昇。米労働市場の改善や米追加経済対策法案の上院通過で景気の回復期待が強まり、自動車や電機、鉄鋼や化学などの素材、金融などを中心に買いが入っている。 TOPIXは前営業日比17.87ポイント(0.9%)高の1914.05-午前9時5分時点 日経平均株価は366円30銭(1.3%)高の2万9230円62銭 <きょうのポイント> 2月米雇用者数2月は37.9万人増、予想上回る-失業率6.2%に低下 バイデン米大統領の追加経済対策法案、上院通過-1兆9000億ドル 米財務長官「インフレ急進の不安当たらず」-長期金利上昇は回復期待 東海東京調査センターの平川昇二チーフグローバルストラテジストは「米雇用統計が予想より強く、賃金インフレはそれほど上昇していないということで景気が早く立ち上がることが確認された」と指摘した。また、午後に発表予定の景気ウォッチャー調査については「株価を先行する傾向があり注目、市場予想より強ければ自動車や機械などのシクリカル(景気敏感)系が上昇する可能性がある」と話した。 東証33業種では鉄鋼や鉱業、石油・石炭、精密機器、輸送用機器などが上昇 海運やゴム製品、その他製品は下落原油相場が一時71ドル台-サウジの原油ターミナルに攻撃 ロンドンの北海ブレント原油先物が8日午前のアジア時間帯の取引で一時2.6%急伸し、1バレル=71ドルを上回った。サウジアラビアにある世界最大の原油ターミナルが7日、ミサイルやドローンによる攻撃を受けたが、生産には影響がなかったもようだ。 ICEフューチャーズ・ヨーロッパの北海ブレント先物5月限は一時1バレル=71.16ドルと2020年1月以来の高値を付けた。シンガポール時間午前8時46分(日本時間同9時46分)現在では2.2%高の70.87ドル。 ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物4月限は2.2%高の67.54ドル。前営業日には3.5%急伸していた。 サウジのエネルギー省はペルシャ湾沿岸ラスタヌラの輸出ターミナルにある貯蔵タンクが海側からドローン攻撃を受けたと説明。同ターミナルは世界需要の7%弱に相当する日量650万バレルの石油輸出能力を持ち、世界で最も守りが堅いとされる石油施設の一つ。 中東ではイエメンの武装組織フーシ派がサウジに対し一連の攻撃を仕掛けるなど敵対行為がエスカレートしていた。バイデン米政権は先月、シリア東部で親イラン勢力に関連した施設に空爆を実施した。 原油相場は先週、石油輸出国機構(OPEC)と非加盟の主要産油国で構成する「OPECプラス」が予想に反して現在の水準の協調減産を維持することを決めたため急伸。この決定を受け、投資銀行による原油相場見通しの引き上げが相次ぎ、ゴールドマン・サックス・グループはブレントが今年7-9月(第3四半期)に1バレル=80ドルを突破すると予想している。【今朝の5本】仕事始めに読んでおきたいニュース 米国では黒人の失業率が2月に9.9%に上昇しました。一方で全体の失業率は6.2%に低下。人種間の格差が一段と際立つ雇用統計となりました。パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長は「完全雇用」を語る際、黒人や低賃金労働者、女性、特に母親に注目していると強調しています。回復から取り残された労働者層に光を当てたデータ「パウエル・ダッシュボード」は、金融政策の軌道を見極めるヒントになるかもしれません。以下は一日を始めるにあたって押さえておきたい5本のニュース。 名指しで警告中国の王毅外相は記者会見で、米国が「民主主義と人権の名の下に、故意に他国の内政問題に干渉している」と名指しで批判。米国ができるだけ早期にこれを認識しなければ「世界は静けさからは引き続き程遠いだろう」と警告した。同時に、世界経済や気候問題に関して共通の懸念を抑制するために、中国は米国と協力する用意があるとの立場をあらためて強調した。 スピードアップ1兆9000億ドル(約206兆円)の追加経済対策法案が議会を通過する見込みとなり、新型コロナウイルスワクチンの接種が進む中で、米経済の見通しは1月初旬に比べて明るさを増している。最新エコノミスト調査によれば、2021年第1四半期の国内総生産(GDP)伸び率は前期比年率換算で4.8%の予想。前回予想は3.2%だった。21年全体では5.5%と、1984年以来の高成長が予想されている。1月調査では4.1%が見込まれていた。 予想以上の回復今年1-2月の中国輸出は前年同期比で急増。工業製品への世界的な力強い需要を反映しているが、中国経済は昨年ロックダウン(都市封鎖)下にあり、数値は前年同期のベースの低さで歪みも出ている。1-2月の輸出はドル・ベースで60.6%増加し、エコノミストの予想中央値(40%増)を大きく上回った。輸出は2月単月では前年同月の2倍強。マッコーリー・グループの胡偉俊氏は、先進国が生産拡大を始める中で今年の中国輸出の伸びは今後緩やかになると予想している。 投票する権利バイデン米大統領は国民の有権者登録を支援する大統領令を発した。データ共有などで州政府に協力するよう指示するほか、投票関連ウェブサイトの改良を連邦省庁に義務付ける。バイデン氏は「投票を困難にする」法案が全米43州の州議会で250余り提案されていると指摘。「投票する権利に対する総攻撃」が今まさに繰り広げられていると述べた。 「進行中の脅威」マイクロソフトの企業向け電子メールソフト「エクスチェンジサーバー」へのハッカー攻撃が世界的なサイバーセキュリティー危機に発展している。中国政府が支援するハッカー集団「ハフニウム」によって開始されたとマイクロソフトが主張する今回の攻撃では、これまでに世界全体の被害が少なくとも6万件とされている。ホワイトハウス当局者は電子メールで、「依然として進行中の能動的脅威であり、ネットワークオペレーターに深刻に受け止めるよう促す」と注意を促した。【米国株動向】市場が暴落した時に注目の2銘柄モトリーフール米国本社、2021年2月25日投稿記事より私はタイミング投資が好きなわけではなく、また、株価が下落した際には当然面白くない気持ちになります。しかし、たいていの投資家は恐らく、買い逃したと思う銘柄リストがあるはずです。市場が大幅に調整または暴落した時こそ、失った時間を取り戻すチャンスかもしれません。ドキュサイン(NASDAQ:DOCU)とフレッシュペット(NASDAQ:FRPT)は、筆者がずっと前から応援しながらも買わずにいた銘柄ですが、次にこれらの株価が下落したら、今度こそ迷わずに買おうと思っています。 ドキュサイン電子署名サービス大手のドキュサインは、パンデミックによる混乱期における明らかな勝ち組です。ニューノーマルの時代になっても契約には署名が必要であり、同社は電子署名市場を圧倒的に支配しています。売上高は加速的に伸びており、8-10月期(2021年1月期第3四半期)は前年同期比で54%の増収でした。利益も過去5四半期中、3四半期で市場予想を100%以上上回り、しかもそのうちの2回はパンデミック以前の話です(直近の第3四半期は予想を69%上回りました)。つまり、ドキュサインはコロナ禍以前から勝ち組だったのです。第4四半期決算は3月11日に発表される予定ですが、市場予想を常に上回ってきたこれまでの傾向を考えると、市場が調整しなくても決算発表日までに同社株を買うべきか迷うところです。 フレッシュペット高級冷蔵ペットフードを手掛けるフレッシュペットの特殊性は明らかな優位性であり、将来の成功に疑いの余地はなく、2019年12月に筆者が推奨して以来、株価は168%上昇しています(執筆時点)。人々がペットを家族の一員として扱い、高級な食事を与えて甘やかす傾向は、フレッシュペットにとって追い風です。同社は大手のスーパーマーケットや量販店に自前の冷蔵庫を設置しています。店側もペットフードと人間用の食品を同じ冷蔵庫に入れるのは嫌でしょうから、これは理にかなった話です。その上、この戦略は競合の排除にもつながります。現在設置されている同社の冷蔵庫は2万2,000台以上に上りますが、需要に追い付かないという嬉しい課題に直面しています。パンデミックでペットを飼う家庭が増加したことも同社にとっては追い風で、子犬や子猫のうちからフレッシュペットのペットフードに慣れれば、その後は10年以上、継続消費が見込まれます。同社は1年前、同社製品を購入する世帯数を2025年までに800万世帯に増やすことを目標としていましたが、現在は1,100万世帯に目標が引き上げられています。売上高は4年連続で増加しており、2020年は30%近い増収でした。以前から推奨していたにもかかわらず、自分で同社株を買っていなかったことを悔やむばかりです。【米国株動向】ハイグロース株になる可能性のある半導体銘柄モトリーフール米国本社、2020年2月25日投稿記事より半導体大手のアナログ・デバイセズ(NASDAQ:ADI)は、ここ数四半期にわたり成長加速のための努力を重ねてきましたが、その成果が第1四半期(11-1月期)決算に表れました。 加速に成功少し前まで伸び悩んでいた同社ですが、第1四半期の売上高は前年同期比20%増の15億6,000万ドル、調整後1株当たり利益(EPS)は同40%増の1.44ドルと大きく伸びました。いずれもアナリスト予想の15億1,000万ドルと1.32ドルを上回っています。売上高の89%を占める産業用、通信用、自動車用の3大部門が揃って2桁で伸びました。中でも産業用部門は前年同期比24%の増収を記録し、全社売上高に占める割合は55%でした。第2四半期(2-4月期)のガイダンス中央値は売上高が16億ドル、調整後EPSが1.44ドルで、こちらもアナリスト予想の15億5,000万ドルと1.39ドルを上回っています。ガイダンス通りなら前年同期比21%以上の増収、33%の増益となり、ハイペースの成長が続くことになります。ここ数年は業績が低迷し、2020年は世界各地でのパンデミックによる工場閉鎖が産業用部門と自動車用部門の売上に打撃を与えました。しかし当初から同社が見込んでいたように業績は回復し、今やハイグロース株になりつつあります。 今後さらに成長主要なエンドマーケットはハイペースで拡大しています。中でも資本財市場では産業用ロボットの設置台数が今後5年で60%伸びる見込みだと、前回のカンファレンスコールで説明がありました。同社はコネクティビティ、省電力、センシングなど、この市場で求められる幅広いチップを提供しています。産業用ロボットで使われるモーターの消費電力を4割減らすことができるというチップにより、産業用半導体市場で顧客基盤を強化していきそうです。この市場は長期的成長が見込まれ、コロナ禍終息後の自動化の加速によって世界全体の市場規模は2027年には1,070億ドルと、昨年の490億ドルの倍以上になると予想されています。自動車市場でも運転車支援システム、衝突警報、バーチャルコックピットなどエレクトロニクスの使用が増えており、同社にとって追い風が吹いています。電気自動車へのシフトも、同社のバッテリーマネジメントシステム(BMS)にとってプラスとなっています。調査会社のモルドール・インテリジェンスによると、自動車半導体市場は2026年まで年率18%のペースで伸びていく見込みで、同社の2桁成長が今後も続く可能性は十分にありそうです。 バリエーション実績ベースの株価収益率(PER)は執筆時点で43.4倍で、これは2020年の平均である45倍強に比べると低くなっています。また、予想ベースのPERは執筆時点で27倍で、昨年度を超えるペースで売上高と利益が伸びていることを踏まえると、今の時点で買うことを検討する価値のある銘柄と言えるでしょう。コラム:米2月雇用大幅増の裏にある労働市場の根深い問題[ワシントン 5日 ロイター BREAKINGVIEWS] - 米国の労働市場の回復は、見かけほど強くはない。2月の非農業部門雇用者数が37万9000人増えた主な理由は、新型コロナウイルス感染防止の規制措置が緩和され、それまで一時解雇されていた労働者が再雇用されたことにある。しかしパウエル米連邦準備理事会(FRB)議長が、完全雇用まで相当長い道のりを覚悟していることを示唆する証拠が山ほど存在する。2月の非農業部門雇用者数の伸びは、ロイターがまとめたエコノミスト予想の2倍に達し、失業率も1月から小幅低下して6.2%となった。最も雇用が増えたのは、冬のロックダウン(制限措置)再導入で痛手を受けたセクターで、娯楽・接客は35万5000人増、小売りは4万1000人増だった。労働参加率は横ばいの61.4%。これらで考える限り、労働市場は申し分ない。だが他のデータは別の状況を教えてくれる。例えば長期失業者数は1月とほぼ変わらず、約410万人だ。生産年齢人口に占める雇用者の割合は1年前の61.1%から57.6%に下がった。さらに、やむなく非正規で働く人など不完全雇用者を含めた、実質的な失業率は11.1%だ。人種や学歴での雇用格差も鮮明だ。黒人の失業率は1月に下がったが、2月は再び上昇に転じて9.9%となったのに、他の人種グループは白人が5.6%、中南米系が8.5%にそれぞれ低下。高卒資格のない人の失業率は10.1%だったが、大学卒以上の学歴保有者は3.8%にとどまった。トランプ前大統領と異なり、バイデン大統領は雇用統計結果について勝ち誇るような態度は見せていない。それどころか大統領経済諮問委員会はブログで、雇用者数は昨年2月よりまだ950万人も少なく、雇用水準が新型コロナウイルスの大流行前に戻るには今回の増加ペースならあと2年余りかかると厳しい評価を下した。パウエル氏は、FRB議長として推進している完全雇用において、社会のあらゆる層の人々に経済成長の恩恵を行き渡らせると強調している。4日には、米経済がそうした目標に到達するにはなお程遠く、FRBは利上げを急がないと念を押した。最新の雇用データは、パウエル氏の見解の正しさを一段と裏付けている。【市況】前場に注目すべき3つのポイント~ナスダックの理想的なリバウンドに安心感~8日前場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。■株式見通し:ナスダックの理想的なリバウンドに安心感■日駐、2Q営業利益12.2%減 17.5億円、進捗率53%■前場の注目材料:旭化成、素材各社、電池用部材で増産体制急ぐ、EV普及に対応■ナスダックの理想的なリバウンドに安心感8日の日本株市場は、先週の調整に対する自律反発が見込めそうである。5日の米国市場ではNYダウが572ドル高だった。2月雇用統計の予想を上回る改善を受けて長期金利の急伸を警戒したハイテクの売りに拍車がかかる場面がみられたが、売り一巡後は急速に切り返す展開だった。1.9兆ドル規模の追加経済対策が速やかに成立する可能性があること、いくつかの州が来週からパンデミック対策の規制緩和を計画していることから経済活動の再開を期待した買いが支えた。シカゴ日経225先物清算値は大阪比420円高の29180円。円相場は1ドル108円40銭台で推移している。米株高の流れを受けて、シカゴ先物にサヤ寄せする形から買い先行の展開となり、29000円を固めてくることが期待されよう。ハイテク主導でナスダックは大きく切り返しており、指数インパクトの大きい値がさハイテク株などへの支援材料になりやすい。NT倍率は先物中心限月で先週、15.68倍から週末には15.18倍まで低下しており、75日線にタッチしてきている。バリューシフトが意識される中ではあるものの、いったんはNT倍率の修正をみせてくる可能性はありそうだ。日経225先物はナイトセッションでの上昇により、5日線レベルを捉えてきており、この水準をクリアしてくるようであれば、25日移動平均線が位置する29350円辺りを試してくる展開も意識されてきそうである。もっとも、足元で調整トレンドは継続しており、この水準で上値を抑えられるようだと、戻り待ちの売り圧力が警戒されてくるだろう。週末にはメジャーSQを控えていることもあり、基本的には大きなトレンドは出難い需給状況でもあるため、インデックスに絡んだ売買のほかは、積極的にポジションを取りに行く流れは期待しづらいところでもある。とはいえ、ナスダックの理想的なリバウンドによってマザーズなど中小型株への自律反発狙いが意識されよう。マザーズ指数は先週末までの調整で昨年12月安値まで下げており、ダブルボトム形成も意識されやすいところである。指数寄与度の大きい値がさ株などへの見直しが強まるようであれば、個人投資家のセンチメント改善にもつながりそうである。■日駐、2Q営業利益12.2%減 17.5億円、進捗率53%日駐が発表した第2四半期決算は、売上高が前年同期比1.7%減の120.38億円、営業利益が同12.2%減の17.50億円だった。通期計画に対する営業利益の進捗率は53%となる。あわせて350万株(発行済み株式数の1.06%)、5億円を上限に自社株買いを発表している。■前場の注目材料・NYダウは上昇(31496.30、+572.16)・ナスダック総合指数は上昇(12920.15、+196.68)・シカゴ日経225先物は上昇(29180、大阪比+420)・1ドル108円30-40銭・SOX指数は上昇(2920.75、+89.12)・VIX指数は低下(24.66、-3.91)・米原油先物は上昇(66.09、+2.26)・日銀のETF購入・海外コロナワクチン接種の進展・世界的金融緩和の長期化・旭化成素材各社、電池用部材で増産体制急ぐ、EV普及に対応・神戸鋼三浦工業と資本提携、汎用圧縮機で競争力強化・武田薬モデルナワクチン承認申請、供給準備開始・大日住薬抗がん剤の臨床試験中止、損失269億円・明星電気水位監視、気象情報と連動、来月新サービス・横河電機培養装置を米市場で展開、米社と連携・リコー国連環境活動に参画、廃水処理技術を開放・キヤノン5カ年計画、営業利益率12%超、構造転換急ぐ・デンカ高断熱素材開発、CO2を60%削減効果・日本製鉄25年度までの新中計策定、国内、集中生産に挑む・宇部興産高圧水素タンク用ナイロン6樹脂、トヨタ「ミライ」に供給☆前場のイベントスケジュール<国内>・08:50 1月経常収支(予想:+1兆2981億円、12月:+1兆1656億円)<海外>・特になし《ST》 提供:フィスコ【材料】BASE---大幅に続伸、ネットショップ作成サービスの開設数が140万ショップ突破朝高後、値を消す。ネットショップ作成サービス「BASE」のショップ開設数が140万ショップを突破したと発表している。また、2月に実施した「直近1年以内にネットショップを開設する際に利用したネットショップ作成サービスの調査」でネットショップ開設実績が4年連続でトップになった。今後、ショップオーナーの負担を軽減するために顧客管理機能のアップデートなどを予定しているという。《FA》 提供:フィスコブライソン・デシャンボーが逆転V 松山英樹は18位タイ<アーノルド・パーマー招待 最終日◇7日◇ベイヒルC&L(米フロリダ州)◇7466ヤード・パー72>米国男子ツアーの「アーノルド・パーマー招待」最終日が終了。スコアを落とす選手が続出する中、「71」をマークしたブライソン・デシャンボー(米国)が逆転優勝を決めた。首位と1打差・2位にリー・ウェストウッド(イングランド)、2打差・3位にコリー・コナーズ(カナダ)が続いた。松山英樹は4バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「72」で終え、トータル2アンダーで現在18位タイで大会を終えた。そのほか注目選手では、ジョーダン・スピース(米国)がトータル6アンダー・4位タイ、18年大会覇者のローリー・マキロイ(北アイルランド)はトータル3アンダー・10位タイとなった。アストラゼネカ製ワクチン、オーストリアで接種中断 1人死亡[チューリヒ 7日 ロイター] - オーストリアの当局は7日、英アストラゼネカ製の新型コロナウイルスワクチンの国内接種を一時中断すると発表した。同ワクチンの接種後に1人が死亡し、1人に副反応が出たためで、現在原因を調査しているという。49歳の女性がワクチン接種後に深刻な凝固障害によって死亡したという。また、35歳の女性は、肺の血管が詰まる肺塞栓症を発症したが、回復しつつあるという。地元メディアによると2人は看護師。当局は、現時点でワクチン接種との因果関係を示す証拠はないとしている。また、血液の凝固障害は、ワクチン接種による副反応としては知られていないとし、原因究明に向け調査を行っていると説明した。
2021.03.08
コメント(0)
-
3月7日(日)…2021ラウンド16…
3月7日(日)、晴れのち曇り時々雨ですね。天候は悪化ですね…。そんな本日はホーム1:GSCCの西コースで開催の弥生杯に参加させていただきました。10時44分スタートですから、7時30分頃に起床。BSでPGAツアーの中継を見ながら、新聞に目を通し、朝食を済ませ、ロマネちゃんと戯れる。身支度をして、9時頃には家を出る。9時30分頃にはコースに到着。この時間だと駐車場は野天ですね…。フロントで記帳して、4月の理事長杯のエントリーを済ませ、着替えて、練習場へ…。ショット…イマイチ…、パット…イマイチ…。本日の競技は西コースのホワイトティー:6177ヤードです。ご一緒するのはいつものヒ君(8)、ウ君(16)、ム君(16)です。本日の僕のハンディは(8)とのこと。OUT:1.0.1.0.1.1.0.1.0=41(16パット)1パット:2回、3パット:0回、パーオン:2回。1打目のミスが4回、2打目のミスが3回、3打目のミスが2回、パットのミスが2回…。戦意を喪失しそうなプレーが続きます…。10番のスタートハウスでドーピング…。IN:1.1.1.0.-1.1.1.2.1=43(14パット)1パット:4回、3パット:0回、パーオン:1回。1打目のミスが5回、3打目のミスが3回、アプローチのミスが2回…。41・43=84(8)=76の30パット…。またしてもいいとこなしですね…。救いは握りに負けなかったことですね…。カートからスコアの登録を済ませて、靴を磨いて、お風呂に入って、会計を済ませて、早々に退散です。本日のフィジカルチェック…170.0cm,64.2kg、体脂肪率19.7%、BMI22.2、肥満度+1.0%…でした。帰宅すると16時30分頃。国内女子ツアーのTV放送を見ながら、和菓子とお茶で遅いおやつタイム。それではしばらく休憩です。本日の競技の成績速報が出ていますね。本日の競技には110人が参加して、トップは88(26)=62とのこと。ム君が87(16)=71で14位。ツ君が95(22)=73で20位。僕が84(8)=76で50位。ヒ君が86(8)=78で76位。ウ君が105(16)=89で110位。お疲れ様でした。本当に疲れました…。【米国株動向】長期的に勝ち組となる要素を2つとも備える5銘柄モトリーフール米国本社、2021年2月21日投稿記事よりアリゾナ州立大学W.P.キャリー・ビジネススクールのグループが株式市場のリターンの研究中に発見したことによれば、1926年以降の米国株式市場の利益の約半分がわずか86銘柄によるものでした。これは本当に驚くべき数字で、インデックス・ファンドよりも個別株を選択する方が大きな富を築けるということになります。ただ、その前提として、こうした希少な宝石ともいえる銘柄を見つけて投資をする必要があります。銘柄選択は科学というよりは匠の技というべきものであり、魔法の公式などありません。とはいえ、勝ち組となる企業には共通する性質があることが多く、銘柄選択の手がかりになり得ます。私が投資をする際に重視している2つの要素は、従業員の支持率の高さ(具体的には、匿名の従業員によるレビューサイトであるグラスドアにおける評価)と、市場を上回る株価パフォーマンスの実績があることです。これから紹介する5銘柄はどちらの要素も備えていることから、今後大きな富をもたらす比較的少数の銘柄になる可能性があると私は考えています。 エヌビディア2021年グラスドア・ランキング:2位5年間の株価リターン:2,000%高パフォーマンスのコンピューター会社エヌビディア(NASDAQ:NVDA)はすべてのことを正しく行っているようです。従業員は同社で働くことを気に入っており、同社のジェンスン・フアン最高経営責任者(CEO)を圧倒的に支持しています。幸せな従業員はパフォーマンスが高くなることが多く、その結果、好業績につながります。保証はありませんが、間違いなく何らかの相関性があり、それが同社のパフォーマンスが市場を大幅に上回っている理由の一部であると思われます。世界のいくつかのトレンドを考えてみてください。パンデミックによって遠隔勤務や動画配信がこれまでになく普及したため、データセンターの運営企業は増加するインターネット活動をサポートするために能力を増強しています。そして、ビデオゲームは急速にエンターテインメントの主流となりつつあり、調査会社のNPDグループによれば、2020年の売上額は過去最高を記録しました。最後に、より投機的なトレンドとしては、暗号資産(暗号通貨)の受容拡大や自動運転車実現への強い期待があります。こうしたトレンドのすべてでエヌビディア製品の利用が見込まれます。こうした追い風要因を踏まえたうえで今後の5年間を予想すると、同社製品に対する需要はさらに拡大すると思います。したがって、強力な企業文化と株式市場における成功の実績があるエヌビディアは、今後も株主の期待に応え続けると私は考えています。 アプフォリオ2021年グラスドア・ランキング:なし5年間の株価リターン:1,100%クラウドベースのソフトウェア企業アプフォリオ(NASDAQ:APPF)は2021年のグラスドアの上位100 位リストからは脱落しました(2020年は45位)が、同社の企業文化は引き続き高い評価を受けています。新型コロナウイルスで経済が打撃を受けている間も同社は抵抗力を見せ、2020年1-9月期の売上高は前年同期比で26%増加しました。さらに、2020年に法律事務所向けソフトウェアの子会社マイケースを1億9,300万ドルで売却し、無借金になると同時に現金の持ち高を増加させています。アプフォリオの売上高の約90%はすでに不動産業界の顧客からのものでしたが、マイケースを売却することにより、テクノロジー変革の初期の段階にある不動産業界に資源を集中させ、不動産賃貸業者の物件管理を支援しています。パンデミックによって、リースのオンライン取引とテナントの遠隔スクリーニングが本格化することになりましたが、パンデミック終息後もデジタル化は進み、より一般的になると私は考えています。2020年第3四半期末時点の同社の不動産業界の顧客数は、前年同期比9%増の1万5,000社でしたが、調査会社フォーチュン・ビジネス・インサイトの推定によれば、不動産管理ソフトウェア業界は2026年までに236億ドルの市場になると予想され、アプフォリオが獲得しているのは、まだその小さな部分にすぎません。 ルルレモン2021年グラスドア・ランキング:8位5年間の株価リターン:450%ルルレモン・アスレティカ(NASDAQ:LULU)は単なるヨガパンツの企業ではありません。同社は昨年6月にオンライン接続のフィットネス機器企業ミラーを5億ドルで買収しました。ミラーが製品を発売したのは2018年ですが、買収時点ですでに2020年通年ベースの売上高が1億ドルに達するペースに達していました。ルルレモンに買収されて以降、成長が加速し、経営陣によれば2020年通年の売上高は1億5,000万ドルになる見込みです。これは、ルルレモンによる買収が事業内容を熟知した抜け目のないものであったことを示しています。両社の事業は補完的であり、ブランドの認知度と売上の成長をお互いに高め合うことが可能です。ミラーのハードウェアの販売は利益率の高い定額料金プランがセットになっており、ルルレモンの長期的な利益成長に貢献するのは言うまでもありません。ミラーの買収以外にも海外事業拡大などの成長戦略があり、同社のことを調べていただければ、さらに気に入ってもらえると思います。 マスターカード2021年グラスドア・ランキング:28位5年間の株価リターン:280%決済ネットワークであるマスターカード(NYSE:MA)は、世界の長期的なキャッシュレス化のトレンドに投資をするうえで素晴らしい候補先であり、同社のような金融会社には強い追い風が吹いています。しかし、私が特に同社を気に入っているのは、その国際的な存在感です。2020年第4四半期の金額ベース取扱高(残高の付け替えを含む同社のネットワークを経由した資金の移動)の70%近くが米国外からのものでした。多くの海外市場がeコマースおよび電子取引のごく初期の段階にありますが、消費者がそうした取引に移行する際、マスターカードのブランド認知度は競争上の優位性となります。それが、私が同社の将来性にワクワクする理由のひとつです。成長ストーリーが実現していく間も、同社の経営陣は株主に報いています。パンデミックのため2020年度の売上高は減少しましたが、同社は自社株買いと配当で61億ドルを株主に還元しており、長く保有すればするほど、リターンも成長します。 SVMK2021年グラスドア・ランキング:43位5年間の株価リターン:該当情報なし(2018年上場のため)最後に、サーベイモンキーの名でも知られる、顧客満足度や従業員の満足度を調べるためにオンラインでアンケートが簡単に作成できるプラットフォームを提供するSVMK(NASDAQ:SVMK)です。あまり注目されていませんが、潜在力のある企業です。2018年に株式を公開したばかりの同社の株価は、最近まで市場を上回るパフォーマンスを示していましたが、2021年度の業績予想がウォール街に評価されず、株価は20%以上下落しました。しかし、私はサーベイモンキーが予想を上回る業績を上げるとみています。同社の使命は、すべての声が届くようにすることですが、同社がこれをいかに効果的に実現しているかは、グラスドアの素晴らしい評価が証明しており、同社の経営陣は明らかに自社従業員の声を聞いています。しかし、会社の存在意義を強化できるのは業績だけです。2020年度の売上高は前年比22%増の3億7,500万ドルとなり、フリーキャッシュフローは4,500万ドルとなりました。2021年度の予想売上高は4億3,600万ドル~4億4,300万ドルで前年比16~18%の増加となりますが、2020年度より成長が鈍化することから株価下落の原因となりました。私が興味深いと思うのは、同社の企業顧客からの売上高の成長率(2020年度は65%の増加)が売上高全体の成長率よりも高いことです。企業向けの売上が個人向けの売上を上回れば、全体の成長率が再度加速する可能性もあります。データに基づく意思決定が必要だと考える企業は増え続けており、サーベイモンキーのソフトウェアはそのために必要とされる情報を提供できることから、これは遠い先の話ではありません。確実に成功するとは言えませんが、同社の株価売上高倍率(PSR)は8倍にすぎず、今ならフリーキャッシュフローが良好なバリュー株に、売上高に占める企業向け事業の比率が増加する前の段階で投資をすることが可能です。 最後にこれらの株が一夜にして富をもたらす可能性は低いことを覚えておくとよいでしょう。市場を上回るパフォーマンスをする株を見つけることで生涯にわたって資産を増やすことができると私は信じていますが、完璧な銘柄選択の実績を持つ人はいません。したがって、分散されたポートフォリオの構築をお勧めします。その際、エヌビディア、アプフォリオ、ルルレモン、マスターカード、およびサーベイモンキーのすべてが検討に値します。【米国株動向】大手資産運用会社が買わずにいられないグロース株5銘柄モトリーフール米国本社、2021年2月22日投稿記事より2月16日(火)は重要な日でした。なぜなら、運用資産額1億ドル超の資産運用会社が、米証券取引委員会(SEC)に義務付けられている通り、四半期末から約45日後の同日にフォーム13Fを提出したからです。13Fは、ウォール街で最も聡明な人々が直近四半期にどの銘柄に投資していたかという内部情報を明らかにするものです。少し遅れてはいるものの(今回は2020年12月31日時点)、ウォール街と投資家は13Fによって、資産運用会社を引き付けている企業やトレンドを知ることができます。2020年10-12月期には、グロース株が大手資産運用会社から引き続き大きな注目を集めました。とりわけ、以下のグロース株5銘柄は積極的に買われていたようです。 テラドック・ヘルス遠隔医療サービスを手掛けるテラドック・ヘルス(NYSE:TDOC)が、大手資産運用会社に期待されていることは間違いありません。ブラックロックは既存のポジションに317万株を追加し、サスケハナ・インターナショナル・グループは保有株数を29万株超も増やしました。テラドックに強気な見方を取る根拠は、非常に分かりやすいものです。治療のプロセスが患者一人ひとりに合ったものとなるのにつれて、利便性とコスト効率が極めて重要となります。オンライン通院によって、患者は家でくつろぎながら医師に相談することができます。医師にとっては、1日当たりの診察件数を増やすことが可能です。保険会社にとっても、患者が現実の病院に通院する場合に比べて、通常は支払保険金が減少します。従って、オンライン通院は時とともに普及するでしょう。テラドックは、昨年11月に医療サービス会社リボンゴ・ヘルスを買収したことで投資家を驚かせました。リボンゴは健康データ応用サービスの分野をリードする企業で、慢性疾患の患者がより健康な生活を送るための支援を目標としています。同社は50万人以上の糖尿病患者が登録しており、体重管理や高血圧の分野に事業を拡大すれば膨大な登録者が増える可能性があります。 ファストリーエッジクラウドサービス(ユーザーの近くにサーバーを設置し、距離を短縮することで通信遅延を短縮するクラウドサービス)を提供するファストリー(NYSE:FSLY)の第4四半期決算は期待に届かない内容だったものの、同社は大手資産運用会社の前四半期のお気に入り銘柄でした。13Fを提出した全投資家の合計保有株数は前四半期比で23%近く増加しました。ファストリーをめぐる熱狂は、コンテンツをエンドユーザーに安全かつ迅速に配信する上で同社が果たす役割に関係しています。オンラインとクラウドに移行する消費者や企業が増える中、エッジクラウドサービスの重要性は時とともに高まる一方でしょう。これはファストリーの2020年の売上が45%増加したことからも明白です。一方、同社の顧客数の伸びは第4四半期に顕著に低下し、正味顧客維持率は7%ポイント低下して115%となりました。既存顧客は依然として前年よりも支出額を増やしていますが、増額のペースはやや鈍化し始めています。ファストリーは現在も素晴らしい長期的なグロース株であるとみられます。しかし、割高な株価売上倍率(PSR)に業績が追いつくまでは、株価が多少停滞しても驚くには当たらないでしょう。 パランティア・テクノロジーズビッグデータ解析を手掛けるパランティア・テクノロジーズ(NYSE:PLTR)は、13F提出者の合計保有株数が前四半期比で82%増となり、同社を保有するファンドは2倍以上に増加しました。ファストリーと同様に、パランティアは通期で素晴らしい成長を遂げましたが、第4四半期決算以降の投資家の非常に大きな期待に応えるのには苦労しています。2020年通期の売上は47%増の11億ドルとなり、政府向けプラットフォームのゴッサムが主に成長を牽引しました。ここ数四半期の新規顧客の獲得によって売上は大幅に増加しており、同社は安定して黒字を計上できるようになりました。しかし、パランティアの長期的な成功のカギは、法人顧客向けビッグデータ分析プラットフォームのファウンドリーでしょう。ファウンドリーによって業績に弾みがつくまでは、PSRが割高なために上値余地が限られる可能性があります。 スノーフレーククラウドベース・データウェアハウス企業のスノーフレーク(NYSE:SNOW)も、大手資産運用会社が買わずにはいられないハイテク株の1つです。同社の株式を保有する13F提出ファンドは、第4四半期に約100本増加しました。同社の事業モデルは非常にユニークです。例えば、同社はサブスクリプションサービスではなく、顧客の保存データ量や消費クレジットに基づく都度払いモデルを採用しています。またスノーフレークは、広く利用されている複数のクラウドインフラに上乗せする形でサービスを提供しており、本来なら競合するプラットフォームを超えてクラウドデータをシームレスに共有することができます。上場後初めての四半期(2020年8-10月期)において、スノーフレークは115%の売上の伸びを計上し、第4四半期(11-1月期)の売上ガイダンスの中間値は前年同期比 100%増となりました。新型コロナウイルスのパンデミック(世界的流行)以降、企業はクラウドへ継続的に移行しており、同社はこれによって間違いなく恩恵を受けるでしょう。問題は、多額の赤字を計上していながら、現在の極めて高いバリュエーションを維持できるかという点です。 テスラ電気自動車(EV)大手テスラ(NASDAQ:TSLA)を保有するファンドは1,949本に上り、前四半期比で318本増加しました。ブラックロックは同社の保有株数を約1,210万株、サスケハナは150万株増やしています。テスラをめぐる強気な見方は、同社が量産型の手頃なEVの開発に成功したことに関係しています。同社は過去50年以上で、ゼロから大量生産までこぎ着けた初めての自動車会社です。昨年、テスラはイーロン・マスク最高経営責任者(CEO)が定めた50万台の納車台数目標を下回りましたが、その差はわずかに450台でした。また同社は初めて通期で黒字を計上しました。しかし、テスラの黒字は、他の自動車会社への温室効果ガス排出枠(クレジット)の販売に依存しています。これらのクレジットを除くと、50万台近く販売したにもかかわらず、同社は依然として黒字ではありません。テスラはバッテリーの出力、航続距離、容量に関して明確な競争優位性を持っていますが、これらの優位性を維持するのには苦戦する可能性があります。アメリカの経済成長は急加速の見通し、第1四半期は4.8%増ブルームバーグ調査 バイデン米大統領が推進する1兆9000億ドル(約206兆円)の追加経済対策法案が議会を通過する見込みとなり、新型コロナウイルスワクチンの接種が進む中で、米経済の見通しは1月初旬に比べて明るさを増している。 ブルームバーグの最新エコノミスト調査によれば、2021年第1四半期の国内総生産(GDP)伸び率は前期比年率換算で4.8%の予想。前回予想は3.2%だった。21年全体では5.5%と、1984年以来の高成長が予想されている。1月調査では4.1%が見込まれていた。 エコノミスト67人を対象とした調査は2月26日から3月3日に実施された。 民主党は1月のジョージア州での上院決選投票で勝利し、上院多数派を奪回。エコノミストは1兆ドル前後の追加経済対策を予想していたが、民主党主導でその約2倍の規模の法案が上院で可決され、法案の一部修正に伴い下院で9日に再度採決される見通しだ。 バイデン大統領は6日、上院の同法案可決後にホワイトハウスで記者団に対し、「これだけで600万人強の新たな雇用が予想されている。GDPを1兆ドル押し上げるだろう」と述べた。 アマースト・ピアポント・セキュリティーズのチーフエコノミスト、スティーブン・スタンリー氏は個人への1400ドルの直接給付や失業保険給付の上乗せ、ワクチン接種の加速が21年を通じた成長維持を支援するだろうとの見方を示した。 一方、21年の力強い成長が見込まれることはバイデン大統領が目指す数兆ドル規模のインフラストラクチャー計画で民主党と共和党の意見対立が生じる可能性を意味する。 民主党はインフラ計画で超党派の支持が得られることを期待するが、共和党や一部の穏健派の民主党議員も同計画の財源や、特に米経済が今後数カ月間に持続的な成長を示した場合、計画全体の規模を懸念する公算が大きい。彼女がキャディのL・ウェストウッドが単独首位に浮上 B・デシャンボー2位T、松山英樹35位T<アーノルド・パーマー招待 3日目◇6日◇ベイヒルC&L(米フロリダ州)◇7466ヤード・パー72>米国男子ツアーの「アーノルド・パーマー招待」3日目の競技が終了。リー・ウェストウッド(イングランド)が1イーグル・8バーディ・3ボギーの「65」とスコアを7つ伸ばし、トータル11アンダーで単独トップに躍り出た。今大会のキャディはガールフレンドのヘレン・ストレーさんが務めている。ウェストウッドを1打差で追う2位タイには、前日単独トップに立っていたコリー・コナーズ(カナダ)とブライソン・デシャンボー(米国)。さらに1打差の4位タイに、「64」を出したキーガン・ブラッドリーと、ジョーダン・スピース(ともに米国)のメジャータイトルホルダーが続く。スピースは222ヤードの2番パー3で、グリーン右手前の傾斜を利用してホールインワンを達成した。18年大会覇者のローリー・マキロイ(北アイルランド)は「72」とスコアを伸ばせず、トータル7アンダーで前日の3位から7位に後退した。トータル1オーバー・53位タイでスタートした松山英樹は、トータル2アンダー・35位タイまで順位を上げている。4つあるパー5で1イーグル・3バーディとしっかりスコアを伸ばした。首位とは9打差で最終日を迎える。B・デシャンボーが6番パー5でついに1オン狙い?! 370ヤードの池越えに大興奮<アーノルド・パーマー招待 3日目◇6日◇ベイヒルC&L(米フロリダ州)◇7466ヤード・パー72>「水を越えたとき、試合に勝ったほど興奮した」とガッツポーズのデシャンボー。「フォローの風が吹けば…狙う」と宣言していたブライソン・デシャンボー(米国)が、C字型の左ドッグレッグの6番パー5でついにグリーン方向に目標をとった。「アーノルド・パーマー招待」第3ラウンド、6番パー5は531ヤード。グリーン方向に目標を取るとドライバーを強打!グリーンに1オンとはならなかったが、370ヤードのショットはグリーン右約70ヤードに落ちるとラフまで転がった。集まったファンはデシャンボーのトライに大歓声。デシャンボーは池を越えると両手を大きく上げて大喜び。ファンの歓声には右手でガッツポーズを作って応えた。「ものすごく興奮した」とデシャンボー。「まるで試合に勝った気分だった」と高揚する。「水しぶきあがらずに超えたとわかったときは『やったぜ!』と身震いがした。ファンが望んでいることができたから」とラウンド後も興奮冷めやらぬ様子だ。実際はデシャンボーが狙ったのはこのグリーン右のフェアウェイ。ピンまで70ヤードの第2打はグリーンをショートし、花道からの約12メートルのイーグルパットはカップに沈まず。最終的にはバーディーしか奪えなかった。ちなみに、放映する米NBC放送では解説のポール・エイジンガー(米国)が「キャリーは346ヤードだ」と試算した。それでも3日目は「68」と伸ばしてトップをいくリー・ウェストウッド(イングランド)に1打差2位。「フォローがもう少し強ければ、もうちょっと左を狙っていける。グリーンサイドバンカーに入るものいい」と残り1日のトライに自信を見せる。「ファンの歓声は優勝したときと同じだった。もし明日アーノルド・パーマーの試合に勝つことができれば…本当に素晴らしい。下部のコーンフェリーで勝ったとき、手紙をくれた。それは他界するわずか1週間くらい前だった。旅立つ間際まで手紙を書いていたんだ。今もトロフィーと一緒に飾ってある」とキングへの思いも語った。小祝さくらが逆転で2021年初戦V 森田遥2位、渋野日向子13位<ダイキンオーキッドレディス 最終日◇7日◇琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県)◇6561ヤード・パー72>国内女子ツアー2021年初戦の最終ラウンドが終了した。トップと2打差から出た黄金世代の小祝さくらが5バーディ・1ボギーの「68」をマーク。トータル14アンダーで逆転し、昨年の「ゴルフ5レディス」に続く今季2勝目、ツアー通算3勝目を果たした。トータル13アンダー・2位に森田遥。トータル12アンダー・3位に田辺ひかり、トータル11アンダー・4位タイに西郷真央、上田桃子が入った。渋野日向子は3バーディ・4ボギーの「73」と振るわず。トータル5アンダー・13位タイで4日間を終えた。ホステスプロの新垣比菜はトータル7アンダー・10位タイ。大会連覇がかかっていた比嘉真美子はトータル3アンダー・20位タイだった。二つの病院関連のクラスター 岐阜県内で3人が新型コロナ感染、2人死亡 岐阜県は7日、県内で3人の新型コロナウイルス感染を確認し、入院していたいずれも美濃加茂市の80代男性と70代男性が死亡したと発表した。県内の累計感染者数は4666人、死者数は114人となった。 二つの病院関連のクラスター(感染者集団)で規模が拡大した。県内最多の感染者が確認されている木沢記念病院(美濃加茂市)関連では医療従事者の男性に感染が分かり、規模は231人となった。 東濃厚生病院(瑞浪市)と高井病院(土岐市)で広がるクラスターでは、高井病院に入院している男性患者の感染が新たに判明。29人に増えた。 また、県は6日に重症患者が前日から2人増の11人になったと発表したが、うち80代の患者は入院先からの報告に誤りがあったとし、重症患者は10人と訂正した。 新規感染者の居住地別は美濃加茂市、土岐市、養老郡養老町が各1人。年代別は30代、60代、90代が各1人。
2021.03.07
コメント(0)
-
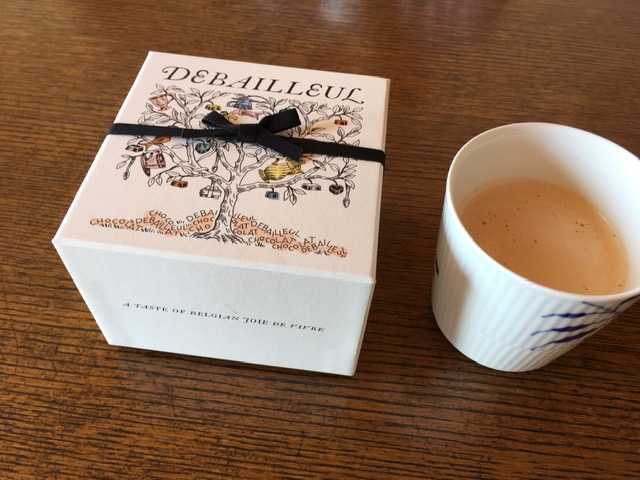
3月6日(土)…
3月6日(土)、晴れです。もう春ですね。窓を開けても気持ち良いです。そんな本日は8時10分頃に起床。新聞に目を通し、朝食を済ませ、ロマネちゃんと戯れる。本日のノルマは1階のモップかけですか…。ハイハイ…。朝のコーヒーブレイクはネスプレッソで…。ドゥバイヨルのチョコレートと共に…。美味い!!そして恒例の母親宅の後片付けです…。がれき・陶器類が段ボール箱に6箱…。明日の収集に向けて集積所へ搬入です。さらに一般ゴミも袋にいくつか…。こちらは来週まで出せませんね…。お昼前に作業をやめる。お疲れです。1USドル=108.34円。1AUドル=83.27円。昨夜のNYダウ終値=31496.30(+572.16)ドル。昨夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中の13銘柄が値を上げて終了しましたね。ブルックフィールドが下げましたね。アナフィラキシーを国内で初確認 ワクチン接種後にせき朝日新聞社 厚生労働省は5日、米製薬大手ファイザー社製の新型コロナワクチンの接種を受けた30代女性が、重いアレルギー反応の「アナフィラキシー」を起こしたと発表した。アナフィラキシーが厚労省に報告されたのは初めて。5日に接種を受けた後、5分以内にせきが出て、まぶたの腫れや全身のかゆみ、呼吸が速いといった症状もみられた。アドレナリンの投与を受け、症状は改善したという。 厚労省によると、女性はぜんそくや甲状腺機能低下症、副甲状腺機能低下症の持病があるという。報告した医療機関は症状とワクチン接種に因果関係があるとし、ぜんそくが要因になった可能性も指摘している。 ワクチンは現在、医療従事者に対して優先接種が進められている。5日午後5時時点で計4万6469人が接種を受けた。 厚労省の薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会の岡明・会長は「適切な治療で症状は軽快をしたものと考えられる。どのワクチンもアナフィラキシーをおこす可能性はあり、接種後少なくとも15分以上の観察期間の周知とアナフィラキシーによる症状が疑われた場合の適切な対応が重要」とコメントした。上田崇宏(関ケ原)ら24人が本戦切符 岐阜オープンアマ最終予選岐阜新聞社 ゴルフの第38回岐阜オープンクラシック2021アマチュア最終予選(岐阜新聞社 岐阜放送主催)は5日、各務原CC(6818ヤード、パー72)で25歳以上の部を行い、25~49歳が全体でも最高の2オーバーで回った上田崇宏(関ケ原)ら12人、50歳以上は横山浩康(ローモンド)ら12人の計24人が本戦(4月10、11日・同CC)に進んだ。 各年齢区分の出場者数に応じて本戦切符24枠を配分。2部門全体で計109人が出場し、18ホールストロークプレーで競った。 本戦出場の当落選は、25~49歳が8オーバー、50歳以上は11オーバー。◆やりがいがあった 上田崇宏(関ケ原) グリーンが難しかったが、やりがいがあって楽しかった。(好結果は)マネジメント力に尽きる。トップだったが、これで満足せず、本戦はプロと回るので気持ちも入る。もっともっといいスコアを出したい。=予選通過者▽25~49歳 ①上田崇宏(関ケ原)74(38、36)②丹羽正樹(南山)75(38、37)③続木達也(ぎふ美濃)77(39、38)④桂川博行(岡崎)77(38、39)⑤大橋元(中仙道)78(42、36)⑥坂口英昭(岐阜国際)79(40、39)⑦長井智佐臣(同)79(38、41)⑧本田頼平(デイリー瑞浪)80(44、36)⑨臼井達也(三好)80(41、39)⑩政岡悟(WF森林公園ゴルフ場)80(41、39)⑪源野智紀(朱鷺の台)80(40、40)⑫蟹江俊郎(葵)80(38、42)▽50歳以上 ①横山浩康(ローモンド)80(42、38)②洞口真次(岐阜本巣)80(40、40)③原田英明(瑞陵)81(43、38)④杉浦茂樹(日本ライン)81(36、45)⑤沢田勉(春日井)82(43、39)⑥本林勝輝(金沢)82(42、40)⑦伊藤功巳(関ケ原)82(42、40)⑧新美金之介(愛知)82(41、41)⑨山川修司(岐阜北)82(41、41)⑩加藤浩(岐阜稲口)82(40、42)⑪長尾福治郎(日本ライン)83(42、41)⑫服部潤(ぎふ美濃)83(39、44)【米国市況】株反発、押し目買い入る-ドル指数は11月以来の高水準 5日の米株式相場は反発。早い時間には売り優勢でナスダック100指数が過去最高値から10%下落したが、その後の押し目買いで持ち直した。 米国株は反発、押し目買いで持ち直し 米国債は雇用統計後の下げ縮小、10年債利回り1.57% ドル指数が昨年11月以来の高水準に上昇、予想上回る米統計受け NY原油は3日続伸、66ドル台ー生産据え置きがなお買い材料 NY金はほぼ変わらず、米国債利回りが高水準から低下 S&P500種株価指数の業種別指数は全て上昇。アマゾン・ドットコムやアップルといった大型株が下げを埋めてプラス圏に浮上し、ナスダック100は1.5%を超える上昇率となった。株取引アプリ運営の米ロビンフッド・マーケッツは予定する新規株式公開(IPO)について、ナスダックを上場先に選択したと伝わった。 朝方には2月の米雇用統計が予想を上回ったことで景気過熱やインフレ高進の懸念が強まり、米国株は下落に転じる場面があった。 S&P500種は前日比2%高の3841.94。この日の反発により週間ベースでもプラスを確保した。ダウ工業株30種平均は572.16ドル(1.9%)高の31496.30ドル。ナスダック総合指数は1.6%上昇。 シチズンズ・バンクの世界市場担当責任者、トニー・ベディキアン氏は「投資家の多くはこうした押し目で買いを入れる見通しで、株式への資金流入は継続する」と指摘。債券利回りは今でも「驚くほど低いため、株式の益回りは依然極めて魅力的だ」と説明した。 米国債市場ではニューヨーク時間午後4時25分現在、10年債利回りが1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)未満上昇の1.57%。雇用統計の発表後には1.62%に急伸する場面もあった。 外国為替市場ではドルが上昇。主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は昨年11月以来の高水準となった。米雇用統計が予想を上回り、景気回復に対する信頼感を強めた。その他の通貨では、ノルウェー・クローネとカナダ・ドルが原油高を背景に上昇。円は対ドルで約9カ月ぶり安値となった。 ドル指数は0.4%上昇。ドルは対円では0.4%高の1ドル=108円38銭。ユーロは対ドルで0.4%安の1ユーロ=1.1917ドル。 ニューヨーク原油先物相場は3日続伸。ほぼ2年ぶりの高値となった。石油輸出国機構(OPEC)と非加盟の主要産油国で構成する「OPECプラス」が前日に大方の予想に反し、生産据え置きを決めたことが引き続き買い材料となった。 ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物4月限は2.26ドル(3.5%)高の1バレル=66.09ドルで終了。2019年4月以来の高値を付けた。週間では7.5%上昇し、1カ月ぶりの大幅高。ロンドンICEの北海ブレント5月限は前日比2.62ドル高の69.36ドル。 ニューヨーク金相場はほぼ変わらず。米国債利回りが一時1年ぶり高水準を付けたものの、その水準からは低下し、金は小幅な動きにとどまった。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物4月限は0.1%安の1オンス=1698.50ドルで終了。米財務長官「インフレ急進の不安当たらず」-長期金利上昇は回復期待 イエレン米財務長官は最近の米国債利回りの上昇について、インフレが突発的に急加速する見通しを反映しているとの不安は当たらないとの認識を明らかにした。 イエレン財務長官は5日、PBSニュースアワーとのインタビューで、米連邦準備制度の目標(2%)を上回る水準までインフレが高進すると「市場が予想しているとは思わない」と発言。「長期金利は幾分、だが主に市場参加者がより力強い回復を見込んでいるという理由で上げたと私は考える」と語った。 2月の非農業部門雇用者数が前月比37万9000人増と、市場予想を大幅に上回る伸びとなったことについては、「37万9000人という雇用者数は大きく聞こえるが、そのペースでも完全雇用に達するには2年余りかかるだろう」と指摘し、400万人が職を失って労働力から離脱したことを考慮すれば、「実質的」な失業率はむしろ10%に近いとの見解を示した。 景気回復の兆しを考えると、バイデン米政権が推進する1兆9000億ドル(約206兆円)規模の追加経済対策案は行き過ぎではないかとの批判に対しては、「われわれは急回復を望むべきだと思う。長期の失業者は多く、今回の感染症パンデミック(世界的大流行)が人生に変えようのない影響を与えるほど彼らが打撃を受けないよう確実を期す必要がある」と述べた。米国株反発、ダウ572ドル高 ハイテク株に買い戻し[5日 ロイター] - 米国株式市場は荒い値動きの中、大幅に反発して取引を終えた。ナスダック総合は今週、最高値から約10%落ち込んだが、この日は約1.5%高となった。主要3指数はともに序盤の下落から切り返して上昇した。マイクロソフトが2.15%高で、S&P総合500種の上昇をけん引。アルファベット、アップル、オラクルも押し上げ要因になった。米労働省が5日発表した2月の雇用統計は、非農業部門雇用者数が前月比37万9000人増と、市場予想の18万2000人増を上回る伸びとなった。これを受け、米10年債利回りは1.626%に上昇し、1年ぶり水準を更新した。議会上院で始まった1兆9000億ドル規模の新型コロナウイルス追加経済対策法案の審議も注視されている。週間ではS&P総合500種が0.8%上昇。ダウ工業株30種は1.8%高。ナスダックは2.1%下落した。米国債利回りの急上昇でテクノロジー株への買いが弱まり、ナスダックは3週続落。2月12日に付けた終値での最高値から約8%下落している。一方、ロングボウ・アセット・マネジメントのジェイク・ダラーハイド最高経営責任者(CEO)は、最近の株安で下げた成長企業の株式をここ数日は購入しているとし、来週はボラティリティーが継続するだろうが、売られた銘柄が反発する可能性もあるとの見方を示した。原油高を受けエネルギー株が3.9%上げ、1年ぶり高値を付けた。個別銘柄ではオラクルが6%超上昇。IT関連の支出環境が改善しているとして、バークレイズが投資判断を「オーバーウエート」に引き上げた。ニューヨーク証券取引所では値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を2.86対1の比率で上回った。ナスダックでも2.12対1で値上がり銘柄数が多かった。米取引所の合算出来高は174億株。直近20営業日の平均は153億株。FRB当局者、長期金利上昇に動じず 回復支援へ緩和維持強調[5日 ロイター] - 米連邦準備理事会(FRB)当局者は5日、最近の米国債利回りの上昇を懸念していないと述べ、今月中旬に開かれる連邦公開市場委員会(FOMC)で長期金利の上昇が追加緩和を行う根拠にならないという考えを示した。この日は2月の雇用者数の伸びが予想を大幅に上回ったことを受け、10年債利回りが一時1.6%を突破。一部では、FRBが長期債利回りを押し下げるために債券購入プログラムを強化するという見方もある。ミネアポリス地区連銀のカシュカリ総裁はワシントン・ポスト紙のオンラインイベントで、実質金利が上昇すればFRBが対応する必要もあるが、現在はこうしたことは起きていないと指摘。FRBは完全雇用が達成され、インフレ率が2%に達してからも上向く兆候が出るまで現行の超緩和的な金融政策を維持すると表明しているが、国債市場で現在見られている動きは、FRBのこうした新たな枠組みが機能していることを如実に示していると語った。FRBは昨年夏、物価の一時的な上振れを容認し、雇用の最大化に重点を置いた新戦略の導入に踏み切った。セントルイス地区連銀のブラード総裁は、シリウスXMラジオのインタビューで、長期債利回りのこのところの上昇は景気見通しの改善を反映していると表明。懸念すべき特定の水準は念頭に置いていないとした上で、米10年債利回りはパンデミック(世界的大流行)が始まる6カ月前の水準に戻っているにすぎず、「まだかなりの低水準にある」と述べた。また、償還期限が長い国債の買い入れに軸足を傾ける「ツイストオペ」をFRBが近く実施して、国債利回りの上昇を抑制する必要はなく、「現時点でこれ以上ハト派的になる必要はない」と強調した。<回復になお道のり>米経済については、新型コロナウイルスワクチンの接種が進み経済が再開されることで、失業率は年末までに4.5%近辺に低下し、経済成長率は6.5%近辺になると予想。ただ、労働市場は「まだ改善の余地が大きい」と述べた。クリーブランド地区連銀のメスター総裁は2月の雇用統計について、景気回復が正しい方向に向かっていることを示しているものの、経済の現状は完全雇用と物価安定というFRBが担う2つの責務達成に程遠いとの見方を示した。さらに「政策に関する自分自身の見方に基づくと、回復の裾野を広げるには当面、緩和策を維持する必要がある」と話した。他にもアトランタ地区連銀のボスティック総裁がスタンフォード大学が主催したオンラインイベントで、「われわれは必要な限り長く、強力に回復を支援する準備があり、その能力もある」と指摘。「パンデミック危機による長期的な被害を最小限にとどめ、回復が可能な限り広範に、そして包括的になるように、できる限りのことをする必要がある」と述べた。また、インフレ期待の高まりともみられる国債利回り上昇に対応するためにFRBが行動を起こす必要があるかとの質問には、インフレは今のところ懸念ではないとし、物価上昇の兆候を引続き監視していくと語った。【市況】今週の【早わかり株式市況】小幅続落、米長期金利巡り乱高下も週末後場に買い戻し (訂正)■今週の相場ポイント 1.日経平均は2週連続の下落、売り先行で一時2万8000円前半に値を下げる 2.米長期金利は高止まり状態となり、債券市場の動向に一喜一憂する展開が続く 3.パウエルFRB議長による4日の「金融政策は適切」発言で週末の市場は波乱 4.米金利上昇による日米金利差拡大を受け、1ドル=108円台へと円安が進行 5.IT関連など高PER銘柄は金利上昇による株価調整懸念で上値は重い展開に■週間 市場概況 今週の東京株式市場は日経平均株価が前週末比101円(0.35%)安の2万8864円と2週連続の下落となった。ただ、TOPIXは前週末比31.69ポイント(1.70%)高と2週ぶりに上昇となった。 今週も米長期債の動向に左右される展開。週初は米10年債利回りが低下したことが好感され日経平均は上昇したが、週末はパウエル米連邦準備理事会(FRB)議長の発言が警戒され米金利は上昇。NYダウが下落し日経平均も一時2万8000円台前半まで売り込まれる場面があった。為替は急激な円安が進行した。 週明けの1日(月)は前週末に米長期金利の急上昇で急落した反動もあって、日経平均は697円高と急反発。前週末のNYダウが大幅安となったことが警戒されたが、東京市場では時間外取引の米長期金利が1.4%台に低下したことが好感された。東証1部の9割近い銘柄が上昇した。2日(火)は255円安と反落。朝方は上昇したが、米株価指数先物がさえず中国・上海株や香港株の下げが重荷となった。3日(水)は150円高と反発。米バイデン政権による大型追加経済対策や新型コロナウイルスワクチンに対する期待が膨らみ、景気敏感株が買われた。4日(木)は628円安と急反落。前日の米株式市場が下落したことが警戒売りを誘った。特にハイテク株比率が高いナスダック指数が急落。米長期金利が上昇したことで、高PERのIT系などハイテク株には売りが先行した。東京市場もハイテク株などが売られ一時800円を超す下落となった。5日(金)は荒い値動きとなるなか、後場に買い戻され65円安と小幅続落にとどまった。パウエルFRB議長が「現在の金融政策のスタンスは適切」と発言したことで、米長期金利上昇に対するけん制を期待した市場の失望感を誘い、米国株式市場は大幅安。これを受け、日経平均株価も売られ一時600円超の下落となった。ただ、下値に買いが入り引けにかけ下げ渋った。米長期金利の上昇による日米金利差拡大で為替相場は1ドル=108円台に円安が進行した。■来週のポイント 週末の後場に大きく切り返したうえ、昨日の米国市場が大幅反発しており、来週は底固めから上値を模索展開が期待できそうだ。 重要イベントとしては、国内では8日に発表される1月国際収支と2月景気動向指数、12日朝に発表される1-3月期法人企業景気予測調査が注目される。12日にはメジャーSQを迎える。海外では10日に発表される中国の2月消費者物価指数と2月生産者物価指数、米国2月消費者物価指数のほか、11日に行われるラガルドECB総裁の記者会見に注視が必要だろう。■日々の動き(3月1日~3月5日)【↑】 3月 1日(月)―― 急反発、米長期金利の上昇一服で不安心理が後退 日経平均 29663.50( +697.49) 売買高12億5001万株 売買代金 2兆4773億円【↓】 3月 2日(火)―― 反落、朝高もアジア株安や米先物安で売り優勢 日経平均 29408.17( -255.33) 売買高12億9267万株 売買代金 2兆6132億円【↑】 3月 3日(水)―― 反発、景気敏感株中心に自律反発狙いの買いが優勢 日経平均 29559.10( +150.93) 売買高12億0650万株 売買代金 2兆4664億円【↓】 3月 4日(木)―― 急反落、米金利上昇やアジア株安で2万9000円割れ 日経平均 28930.11( -628.99) 売買高12億8561万株 売買代金 2兆7612億円【↓】 3月 5日(金)―― 小幅続落、一時600円超安も後場に入り下げ渋る 日経平均 28864.32( -65.79) 売買高14億3043万株 売買代金 3兆1752億円■セクター・トレンド (1)全33業種中、29業種が上昇 (2)マルハニチロ など水産・農林が値上がり率トップ (3)日本製鉄 など鉄鋼、AGC などガラス・土石、昭電工 など化学といった素材株が買われた (4)国際石開帝石 など鉱業、ENEOS など石油株は買い継続 (5)日産自 など自動車、ダイキン など機械、リコー など電機といった輸出株は買い戻された (6)野村 など証券、日本取引所 などその他金融、三菱UFJ など銀行といった金融株も堅調 (7)内需株は積水ハウス など建設、アサヒ など食品などは高いが リクルート などサービスは値下がり率トップ■【投資テーマ】週間ベスト5 (株探PC版におけるアクセス数上位5テーマ) 1(3) アンモニア 2(1) 半導体 ── 米長期金利上昇でも中期成長性に変化なし 3(4) 旅行 ─── 目先上昇一服も中長期での出直りに期待 4(7) 人工知能 ── ZHDとLINE統合でAI開発に巨額投資 5(5) 2020年のIPO ※カッコは前週の順位株探ニュースR・マキロイが2打差3位T 松山英樹は53位Tで決勝Rへ、単独首位にC・コナーズ<アーノルド・パーマー招待 2日目◇5日◇ベイヒルC&L(米フロリダ州)◇7466ヤード・パー72>米国男子ツアーの「アーノルド・パーマー招待」は2日目の競技が終了。コリー・コナーズ(カナダ)がトータル9アンダーで単独首位に立っている。1打差にマーティン・レアード(スコットランド)、さらに1打差の3位タイに2018年大会覇者のローリー・マキロイ(北アイルランド)に加えビクトル・ホブラン(ノルウェー)、ラント・グリフィン(米国)がつけた。初日3オーバーと出遅れた松山英樹は、4バーディ・2ボギーの「70」で回り、トータル1オーバー・53位タイで決勝ラウンドに進んだ。トータル6アンダーの6位にブライソン・デシャンボー(米国)。ジョーダン・スピース(米国)ら4人がトータル5アンダーの7位タイで並ぶ。〔米株式〕ダウ反発、572ドル高=金利上昇一服で(5日)☆差替時事通信 【ニューヨーク時事】週末5日のニューヨーク株式相場は、米長期金利の上昇が一服したことを好感した買いに、大幅反発した。優良株で構成するダウ工業株30種平均は前日終値比572.16ドル高の3万1496.30ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は196.68ポイント高の1万2920.15で引けた。 ニューヨーク証券取引所の出来高は前日比9311万株減の14億7580万株。 2月の米雇用統計が好内容だったことを受けて米長期金利が上昇したため、株価は序盤、不安定な値動きを見せた。雇用統計では、景気動向を反映する非農業部門就業者数が前月比37万9000人増と、市場予想(18万2000人増)や好調の目安とされる20万人増を上回った。 景気回復観測やインフレ加速懸念から債券が売られ、長期金利の指標である10年債利回りが一時1.63%と、昨年2月中旬以来の高水準に上昇。低金利を背景に買われてきた成長株を中心に、株価の重しとなった。 ただ、その後は値頃感から債券に買い戻しが入り、10年債利回りが1.56%付近まで下げると、株式市場の警戒感も後退。株も買い戻され、終盤にかけ上げ幅を広げた。ダウ平均が前日までの3日間で計600ドル超下落していたことから、安値を拾う動きも出た。 個別銘柄(暫定値)では、オラクルが6.7%高、シェブロンが4.3%高、インテルが4.1%高、エクソンモービルが3.8%高など、エネルギー株や一部のIT株が相場をけん引。一方、テスラが3.8%安、ボーイングが0.7%安、コストコ・ホールセールが0.5%安、モルガン・スタンレーが0.3%安となった。(了)〔NY外為〕円、108円台前半(5日)時事通信 【ニューヨーク時事】週末5日のニューヨーク外国為替市場では、堅調な米雇用統計を受けて円売り・ドル買いが先行し、円相場は1ドル=108円台前半に下落した。午後5時現在は108円35~45銭と、前日同時刻(107円92銭~108円02銭)比43銭の円安・ドル高。 米労働省が5日に発表した2月の雇用統計では、景気動向を敏感に反映する非農業部門の就業者数が前月比37万9000人増と、市場予想(ロイター通信調べ)の18万2000人増を上回り、好調の目安とされる20万人増を大きく越えた。これを受けて、米景気の回復ペースに期待が広がり、円売り・ドル買いが先行した。 雇用統計の結果を受けて、長期金利の指標となる10年物の米国債利回りが朝方に再び1.6%台に上昇した。ただ、景気先行きに楽観的な見方が広がる中で、米株価が一時600ドル余り上昇。長期金利の騰勢の落ち着きを眺め、円相場は下げ幅を圧縮した。 ユーロは同時刻現在、対ドルで1ユーロ=1.1903~1913ドル(前日午後5時は1.1967~1977ドル)、対円では同129円07~17銭(同129円22~32銭)と、15銭の円高・ユーロ安。(了)株式週間展望=「総悲観」時期を見極め―企業業績が下支えに、米国債入札で警戒感先行もモーニングスター 米長期金利の上昇が投資家の肝を冷やす中、世界的な株価の調整が本格化し始めた。今週(1-5日)は、日経平均株価が一時約1カ月ぶりの安値水準まで調整する軟地合いに、需給が大きく悪化したとみられる。ただ、企業業績が回復に向かう状況に変化はなく、しかるべきタイミングで株安に一定の歯止めが掛かりそうだ。「総悲観」のタイミングを見極めたい。 週前半には落ち着きを取り戻し掛けていた米10年債利回りが再び1.5%のフシを抜け、グロース(成長)株売りが再燃した。5日の日経平均は4日に前日比628円安、5日も一時621円まで下げ幅を広げたが、その後下げ渋った。日銀のETF(上場投資信託)買い期待と買い戻しが相まっての動きとみられるが、予断を許さぬ状況が続く。 米金利の上昇をめぐってパウエルFRB(米連邦準備制度理事会)議長は、4日の経済イベントにおいても、前月の議会証言と同様に強い懸念を示さなかった。マーケットはこれを失望。低金利を前提に買われてきたハイテクやネットサービスなどのグロース株が崩れ、幅広い銘柄に売りが広がった。 来週(8-12日)は米国で9、10、11日にそれぞれ3、10、30年債の入札が予定されている。今回の金利急騰の引き金は前月行われた7年債の入札不調だっただけに、市場で警戒感が先行しやすい。また、本稿では締め切り時間の都合で内容を確認していないが、5日日本時間夜発表の米2月雇用統計が市場心理に与える影響も無視できない。 相場はこの上昇局面で何度も短期的な下落を経験しているため、足元の調整から逃げ遅れた向きのシコリが上値に滞留している状態。また、信用買い残の水準も高く、切り返すには相当のエネルギーが求められる。陰の極に当たる総悲観に達するまでは、買い方への逆風はやまないだろう。 それでも、確かな指針となるのが企業業績だ。コロナ禍でコスト体質の強化が進んだこともあり、経済正常化がもたらす利益回復の勢いは強そう。主要企業の業績見通しを直近更新した野村証券と大和証券は、2020年度の経常減益幅を従来から縮小した上で、21年度は3割近い伸びを予想。業績相場を迎える準備は着実に整ってきている。 今週の日経平均は高値で2万9996円、安値で2万8308円と当欄で想定したレンジ(2万8000-3万円)の上下いっぱい近くに乱高下した。12日がメジャーSQ(特別清算指数)の算出日に当たることも踏まえると、不安定な動きはまだ続く可能性がある。国内では8日に2月景気ウオッチャー調査、9日に10-12月期GDP(国内総生産)確報値、12日に1-3月期法人企業景気予測調査が発表される。海外は中国で開催されている全人代(国会に相当)発の情報が注目される。 来週の日経平均の想定レンジは2万7500-2万9500円と今週に続き広く取る。クローズアップ銘柄は商船三井 、SECカーボン 。(市場動向取材班)NY市場概況-ダウ572ドル高と4日ぶりに反発 ナスダックも急落後に1.55%高トレーダーズ・ウェブ 5日のNY株式相場は大幅反発。米2月雇用統計が強い結果となり早期景気回復期待が高まったほか、一時、今年最高まで上昇した米10年債利回りが反転したことも安心感につながった。ダウ平均は100ドル以上上昇してスタート後、157ドル安まで下落したが、長期金利の低下を受けて656ドル高まで上昇し、572.16ドル高(+1.85%)とほぼこの日の高値圏で終了。S&P500も1.02%安まで下落後、1.95%高で終了し、ナスダック総合は2.57%安まで急落後、1.55%高で終了。主要3指数そろっての4日ぶり反発となった。米10年債利回りは前日の1.55%から一時、今年最高となる1.62%台まで上昇したが、1.57%台で終了した。2月雇用統計では、非農業部門雇用者数が37.9万人増と前回の4.9万人増から大きく改善し、市場予想の18.2万人増も上回った。失業率も6.2%と市場予想や前回の6.2%から改善した。 業種別では原油高を好感したエネルギーの3.87%高を筆頭にS&P500の全11セクターが上昇。資本財、コミュニケーション、素材、生活必需品、ヘルスケアも2%超上昇し、ITと金融も1.9%以上値上がりした。一方、一般消費財が0.72%高と騰落率の最下位。ノルウェー・クルーズ・ライン(-12.3%)、ロイヤル・カリビアン・クルーズ(-5.6%)、カーニバル(-4.8%)のクルーズ株が軒並み下落したほか、時価総額上位のテスラも3.8%下落し業種指数の重しとなった。 週間では、ダウ平均が563.93ドル高(-1.82%)と大幅に反発し、前週の下落幅(561.95ドル)を回復。S&P500も0.81%高と3週ぶりに反発したが、ナスダック総合は2.06%安と3週続落となった。業種別週間騰落率は、エネルギーが10.09%高、金融が4.29%高、資本財が3.08%高となり、コミュニケーション、素材、公益も2%超上昇。一方、一般消費財が2.82%安となり、ITと不動産がともに1.36%下落した。NY株式:米国株式市場は反発、強い2月雇用統計で成長期待フィスコ ダウ平均は572.16ドル高の31496.30ドル、ナスダックは196.68ポイント高の12920.15で取引を終了した。 2月雇用統計の予想を上回る改善を受けて寄り付き直後、上昇した。しかし、長期金利の急伸を警戒したハイテクの売りに拍車がかかると、ダウも下落に転じた。ただ、安いところでは、1.9兆ドル規模の追加経済対策が速やかに成立する可能性があること、いくつかの州が来週からパンデミック対策の規制緩和を計画していることから経済活動の再開を期待した買いが支えた。行き過ぎ感から利回りも低下に転じると、再び主要株式指数は上昇。引けにかけて上げ幅を拡大した。セクター別では、エネルギーや運輸が上昇。自動車・自動車部品が下げた。 衣料小売りのギャップ(GAP)は第4四半期決算が予想を下回ったものの、2021年の売り上げ回復見通しが好感され上昇。映画関連会社のアイマックス(IMAX)も2021年の楽観的な見通しが好感され上昇した。ソフトウェアのオラクル(ORCL)やITのシスコシステムズ(CSCO)はアナリストによる投資判断引き上げでそれぞれ上昇。一方で、クルーズ船運営のノルウェージャンクルーズ(NCLH)は株式売り出し計画を発表し大幅下落。電動トラックメーカーのニコラはアナリストによる投資判断引き下げが嫌気され下落した。 ブラード・セントルイス連銀総裁は、インフレが非常に低い水準から上昇しており、当面動向を様子見する方針を確認。また、無秩序な取引は懸念だがまだその段階にないとし、長期金利の上昇を抑制するなどの措置を速やかに講じる必要性がないとの考えを示した。(Horiko Capital Management LLC)午後らは、段ボール、雑誌、新聞をゴミステーションへ…。SCでスポーツドリンクやアルバイト時の缶コーヒーを調達。マエシマ製パンのタルトとコーヒーでおやつタイム。暖かいので支援戦闘機のタイヤ交換をいつものタイヤショップで…。ちょうど前のお客が帰るところで待ち0人のグッドタイミング。タイヤの積み下ろしでちょっと疲れましたね。国内株式市場見通し:米FOMC前に一進一退かフィスコ■米金利動向に神経質な展開、パウエル議長発言で週末急落今週の日経平均は引き続き米長期金利(10年物国債)の動向に一喜一憂する展開となった。週初は急騰していた米長期金利の落ち着きを受けて、半導体など中心にハイテク株が大きく買い戻され、日経平均も700円程反発して2月26日の急落分の半値戻しを達成。翌2日は米ISM製造業景況指数が市場予想を上回る数値だったが、過度なインフレ加速懸念には繋がらずにむしろ相場はポジティブに反応、米株高の流れを受けて日経平均も一時3万円目前まで上昇。しかし、3万円を一歩手前に失速すると上値の重さが嫌気され戻り売りに押された。米連邦準備制度理事会(FRB)のブレイナード理事が直近の債券市場について「非常に注意を払っている」とし、金利動向をけん制する発言もあったが、2日の米株市場は週明けの相場急伸後に伴う利益確定売りが優勢となりハイテク中心に軟調となった。これを受けた3日の東京市場でもハイテク株が弱含んだ。一方、鉄鋼や非鉄金属、商社など資源関連株が賑わった。ADP雇用統計やISM非製造業景況指数が予想を下回ったほか、金利の高止まりが嫌気され、ハイテク中心に売りに押された米株市場の流れを引き継いで、4日の日経平均は大幅反落。半導体などのハイテクのほかファーストリテといった値がさグロース株も大きく売りに押された。また、高騰していたニッケル価格の下落を受けて前日に急騰していた住友金属鉱山など非鉄金属の景気敏感系も利益確定売りが優勢に。週末5日は、注目されていたパウエルFRB議長の発言において、期待されていた程の金利上昇をけん制する内容が確認されなかったとして、米長期金利が上昇するなか失望売りが優勢となり、日経平均は一時600円程下落する場面があった。しかし、その後はアジア市場の堅調な動きもサポート材料となり、後場から急速に下げ渋る動きもみられ、下落幅は小幅にとどまった。■メジャーSQなど前に神経質な展開か来週の日経平均は、翌週に控える日米の中銀イベントを前に引き続き米国の期待インフレ率や長期金利の動向に神経質な展開が想定される。まず週初は米雇用統計の結果を受けた米株市場の動きを吸収する動きか。その後は、週末のメジャーSQ(特別清算指数)を前にこう着感を強めそうだ。ただ、週後半の海外材料には注意を払いたい。米国時間10日には米2月消費者物価指数(CPI)が発表される。これを反映するのは日本時間で11日。足元で過大とも指摘される財政支出による景気過熱、インフレ加速、これを反映した米長期金利の上昇が相場の関心事になっている。FRBはインフレは起きても一時的なものとしているが、先走りがちな市場においては依然としてインフレ懸念がくすぶっている。CPIで仮に強い数値がでると、相場も神経質に反応するかもしれない。飲食・レジャーなどのサービス業はまだまだ弱く、食品・エネルギーを除くコアであれば弱い数値が出るであろうが、これが市場に安心感を与えるとは考えにくい。むしろ、ある程度想定内ではあるがエネルギーを含んだCPIで強い数値が出た場合には敏感に反応する可能性もある。地合いが悪い場合は周知の事実でも弱い材料に反応しやすいことに留意しておきたい。特に来週はメジャーSQがあるため神経質になりやすい面もあるだろう。他方、現地時間11日には欧州中央銀行(ECB)定例理事会がある。金利上昇をけん制する発言があれば安心感をもたらす可能性もある。そのほか、週末には1-3月期の法人企業景気予測調査がある。これ自体が相場に大きな影響力を持つとは考えにくいが、足元、インフレや金利の動きに敏感になっているなか、実体経済の確かな裏付けとして企業の景況感の改善などが示されれば、長期的な強気材料にはなろう。基本的には翌週に予定されている米連邦公開市場委員会(FOMC)や日銀政策決定会合を前に週末のメジャーSQもあるため、来週は週を通じて積極的な売買は手掛けづらいだろう。ただし、広い視野でみれば実質金利は依然マイナスで、これがプラスになるほどの米長期金利の上昇は今のところ考えにくい。パウエルFRB議長もインフレや雇用の目標は程遠く緩和政策の長期化を度々強調しており、長期的な視点からみた株式の相対的な魅力が失われたわけではない。日経平均は今週末に一時日足の一目均衡表の雲上限近くまで下げた後、後場は急速に値を戻すなど強い押し目買いも見られた。こうした背景から調整一巡感もあるといえよう。■幕間つなぎ的に中小型株物色2月入り前後からみられた景気敏感株を中心とした主力大型株優位の展開は10-12月期決算以降も続いてきた。しかし、そうした動きもそろそろ一巡してくる頃合いか。米FOMCを前に大型株は手掛けにくいという背景もある。そうした中、幕間つなぎ的な形で中小型株優位な展開が期待できそうだ。中小型株は流動性の観点から大型株に比べて業績内容を織り込むのに時間がかかり、割安に放置されやすい側面もある。これまで注目されてこなかった中小型株の妙味が出てくるタイミングと考えたい。■米CPI、メジャーSQなど来週の主な国内外スケジュールは、8日に1月景気動向指数、2月景気ウォッチャー調査、9日に1月家計調査、10-12月期GDP改定値、10日に中国2月生産者物価指数、中国2月消費者物価指数、米国2月消費者物価指数(CPI)、米国2月財政収支、11日に2月企業物価指数、欧州ECB定例理事会、12日に1-3月期法人企業景気予測調査、メジャーSQ、米国2月生産者物価指数などが予定されている。《FA》西郷真央と森田遥が首位タイで最終日へ 渋野日向子は「72」で6打差12位T<ダイキンオーキッドレディス 3日目◇6日◇琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県)◇6561ヤード・パー72>国内女子ツアーの2021年初戦「ダイキンオーキッドレディス」は3日目の競技が終了。首位タイから出た西郷真央と森田遥が、ともにトータル12アンダーで終えて、首位タイに並んでいる。この日6つスコアを伸ばした小祝さくらに加え菊地絵理香、田辺ひかりがトータル10アンダーの3位タイで最終ラウンドに向かう。河本結、稲見萌寧がトータル9アンダー・6位タイ。2日目に「67」をマークして上位に浮上した渋野日向子は「72」と伸ばせず、トータル6アンダーの12位タイでファイナルラウンドに入る。なお、西村優菜と永峰咲希がホールインワンを達成。それぞれに開催コースの琉球ゴルフ倶楽部から50万円が贈られる。派遣会社のクラスターで派遣社員の家族が陽性 岐阜県で新たに9人が新型コロナ感染岐阜新聞Web 岐阜県と岐阜市は6日、県内で新たに10代~70代の男女9人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の累計感染者数は4663人となった。 可児市の人材派遣会社に関連するクラスター(感染者集団)で、派遣社員の家族1人の感染が分かり、合わせて6人に増えた。 県立大垣工業高校(大垣市)では生徒1人の感染が確認された。家族の感染を受けた検査で判明した。 人工呼吸器での管理が必要な重症者は前日から2人増え、11人となった。 新規感染者の居住地別は岐阜市と大垣市が各2人、各務原市、可児市、羽島郡岐南町、養老郡養老町が各1人、神奈川県が1人。年代別は10代と20代が各2人、30代1人、40代2人、60代と70代が各1人。株価乱高下...2社に強制調査 「コロナ新薬開発する」発表もFNNプライムオンライン 「新型コロナウイルスの新薬を開発する」と発表し、株価が乱高下した医療ベンチャー企業など2社に、証券取引等監視委員会が強制調査に入った。 テラとセネジェニックス・ジャパンは2020年4月、「新型コロナウイルスの新薬を開発する」と投資家向けに発表し、鳩山由紀夫元首相らもPRしていた。 テラの株価は、100円台から2,000円台にまで上昇したが、新薬の開発に進展がなく、その後200円台まで下がっていて、証券取引等監視委員会は、金融商品取引法違反の疑いで強制調査に乗り出した。
2021.03.06
コメント(0)
-
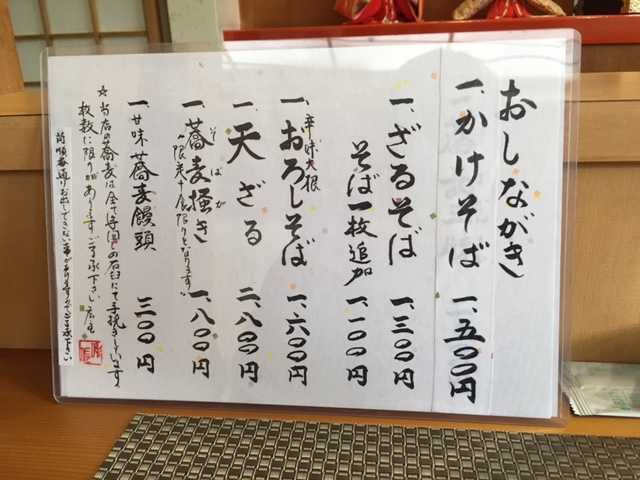
3月5日(金)…
3月5日(金)、曇りのち雨…。雨ですが寒くはありませんね、春雨に近い感じです。そんな本日は7時20分に起床。新聞に目を通し、朝食を済ませ、ロマネちゃんと戯れる。身支度をして、8時45分に家を出る。ゴルフではありません、アルバイト業務です。本日は10:00~16:00です。ランチタイムは近くの庶民的なお蕎麦屋さん「法扇」へ行ったのですが、すでに外に並んで済ます…。このご時世に並んで待つというのはどうも…。近くにある高級なお蕎麦屋さん「仲さ」へ。お店の作りも高級になりますが、お値段も2~3倍に…。このお上品な蕎麦だけを頼むと3枚は食べるでしょうね。ちなみに県内で2021年の蕎麦100名店に選出されているのは「胡蝶庵仙波」と「仲佐」の2店だけでした。午後の仕事は望外に早く終わったので、帰りに「ジークフリーダ」へ寄ろうかと思いましたが、雨が結構に降っているので中止してまっすぐ帰宅です。帰宅すると奥は不在でロマネちゃんがお留守番…。コーヒーとマエシマ製パンのコルネでおやつタイム。それではしばらく休憩です。1USドル=108.26円。1AUドル=83.33円。昨夜のNYダウ終値=30924.14(-345.95)ドル。本日の日経平均終値=28864.32(-65.79)円。金相場:1g=6523(-25)円。プラチナ相場:1g=4338(-139)円。昨夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中の1銘柄が値を上げて終了しましたね。スクエア、トゥイリオ、ショッピファイ、エッツィ、ペイパル、ザイリンクスなどが大きく下げましたね。本日の東京市場ではチェック中の日本株30銘柄中の17銘柄が値を上げて終了しましたね。重点6銘柄では4銘柄が値を上げて終了しましたね。ひらまつが大きく下げましたね。武田薬、米モデルナの新型コロナワクチンを厚労省に承認申請(ブルームバーグ): 米モデルナが開発した新型コロナウイルスワクチン(開発コード:TAK-919)の国内流通を担う武田薬品工業は5日、厚生労働省に製造販売を申請したと発表した。国内では3例目の承認申請となった。 発表資料によると、承認取得後に今年前半から5000万回接種分を日本国内で順次供給する予定だ。武田薬は1月に国内で健康な成人200人を対象にした臨床試験を開始。試験成績は5月に出そろう予定で、その後結果を追加提出する。 政府は6月までに4000万回分、9月までにさらに1000万回分の供給を受ける計画で両社と契約を結んでいる。モデルナのワクチンは氷点下20度前後で約6カ月の保管が可能とされ、長期保存に特殊な冷凍庫が必要なファイザー製のものと比べ、通常の医療用冷凍庫を利用できる。 新型コロナのワクチンを巡り、米ファイザーと独ビオンテックが開発したワクチンが2月中旬に国内初の承認を受け、既に接種が始まっている。同月に英アストラゼネカも厚労省に承認申請し、現在審議中だ。TOPIX反発、米株先物底堅く黒田発言で国内金利も低下-電機高い 5日の東京株式相場ではTOPIXが反発。アジア時間の米国株先物が底堅く推移したことや日本銀行の黒田東彦総裁発言後に国内金利が低下、為替の円安が進んだことなどから、下げ過ぎた株価を見直す動きが午後に強まった。電機や機械、鉄鋼や化学など素材株が高い。 TOPIXの終値は前日比11.44ポイント(0.6%)高の1896.18 日経平均株価は65円79銭(0.2%)安の2万8864円32銭と続落 〈きょうのポイント〉 黒田日銀総裁、長期金利変動幅「拡大は考えてない」-長期金利は低下に転じる、総裁発言を受けて買い優勢 きょうのドル・円相場は一時1ドル=108円台、前営業日の日本株終値時点は107円06銭 米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長、「無秩序」になれば懸念-具体性なく市場は拍子抜け 4日の米10年債利回りは1.5%台半ばへ上昇、アジア時間の米株先物は急速に下げ縮小 アイザワ証券投資顧問部の三井郁男ファンドマネジャーは、米金利が1.5%を超えるくると株価は大きく下がる懸念があるとし、「米金利がどういうレンジで落ち着くのかをにらみながらボラティリティー(変動性)の高い状況が続きそう」と述べた。 TOPIXは一時1.3%安までありながらも高値引けとなるなど、日米の金利や金融当局者の発言に反応して変動の大きな展開となった。みずほ証券の倉持靖彦マーケットストラテジストは昨日の米国株安について、「パウエルFRB議長から金利上昇に対して何らかのけん制が強めに出るとの期待は空振りだった」と指摘。今夜には米雇用統計が予定されており、米長期金利が急騰すると「市場にはサプライズになる」とも語る。 もっとも、朝方は大幅安だった米株先物が午前後半以降に急速に下げ渋り、日本銀行の黒田総裁が長期金利の変動幅について拡大が必要とは考えてないと発言すると、午後にはTOPIXが上昇に転じた。日本の長期金利は低下し、為替市場では円安が進展した。 アイザワ証の三井氏は、「大きく調整して値ごろ感がそれなりに出ていたところ、国内長期金利低下で現在の株高を支える金融緩和の継続スタンスが変わらない思惑など複合要因が重なった」として、先物の買い戻しを誘ったと言う。米国株についても、持ち過ぎた成長株のポジション調整が一巡すれば落ち着くと予想していた。 東証33業種では鉱業や鉄鋼、電気・ガス、化学、電機、機械が上昇 不動産やサービス、海運、保険、非鉄金属は下落【日本株週間展望】売り優勢、金利上昇への警戒続く-金融政策注視 3月2週(8-12日)の日本株は売りに押される展開となりそうだ。米連邦公開市場委員会(FOMC)や日本銀行金融政策決定会合を翌週に控えて、急速な金利上昇を警戒した調整相場が続く。一方で、全人代開催中に明らかになる中国のインフラ政策への期待などは相場の支えになる。 11日の欧州中央銀行(ECB)政策委員会では、ラガルド総裁の発言に市場の注目が集まりそうだ。米時間4日は米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長の発言に金利を抑制する具体的な措置の言及がなかったとの受け止めから、金利が急上昇。株式相場を不安定にする要因になっていただけに金利変動への関心は高い。国内では日銀の雨宮正佳副総裁が8日に読売経済フォーラムで講演する。 11日で世界保健機関による新型コロナウイルスパンデミック宣⾔から1年となる。首都圏4都県で発令中の緊急事態宣言は21日まで2週間延長となる見通し。飲食店に対する午後8時までの営業時間短縮要請などを徹底し、感染拡大を抑える狙いがある。娯楽や外食関連株にとっては首都圏の消費が引き続き抑制されることが不安材料になる。 中国で5日に開幕した全国⼈⺠代表⼤会では政策期待が高まる可能性がある。政府主導で産業の高度化を進めるための具体的な政策方針が出てくれば、中国での収益比率の高い設備投資関連銘柄には追い風だ。 1週のTOPIXは週間で1.7%上昇。一方、日経平均株価は0.4%下落した。 《市場関係者の見方》 インベスコ・アセット・マネジメントの木下智夫グローバル・マーケット・ストラテジスト 「市場の関心は金利上昇がどこまで続くかに集まる。米FOMCまでは手掛かりとなるFRB高官の発言がない状況の中で、日本株も相場の振れ幅が大きくなる可能性がある。金利がさらに上昇すると株には悪影響がある可能性がある一方で、日米金利差の拡大で円安となれば日本の輸出株には追い風。ECBから金利上昇をけん制する発言があれば市場に安心感が広がるだろう。中国全人代では景気刺激策に積極的な姿勢は維持する一方で、規模を大幅に縮小するとなれば今後の景気減速感につながる可能性があり嫌気されそう」 三菱UFJ国際投信の石金淳チーフストラテジスト 「調整局面入りで上値の重い展開。大きな流れとしての上昇トレンドは変わりないが、米国の長期金利がどこまで上昇するか読めないことや米FOMC前で動きにくい。5日米国時間に発表される雇用統計で改善の停滞が示されれば、金融政策的にはテーパリングはまだ早いという見方が出てくるとの方向でとらえられるため悪い話ではない。市場のボラティリティが高まるなかで、企業業績を見極める相場へと徐々に移行していく」【本日のNYダウ見通し】ナスダック総合株価指数が調整局面入りになるかに注目【NYダウ予想レンジ:30,500~31,000ドル】4日のNYダウは続落。前日比345.95ドル安の30,924.14ドルで取引を終了しました。パウエルFRB議長が討論会で長期金利上昇の抑制策に言及しなかったことで、米長期金利が上昇。指標となる米10年債利回りは1.5%台まで上昇しました。とくに金利上昇で割高感が意識されやすいハイテク株が売られ、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は274.28ポイント安の12,723.47で取引を終了。2月の高値14,175.12からの下落率は9%近くとなり、調整局面とされる10%が近づいています。恐怖指数と呼ばれるVIX指数も30台まで上昇。マーケットの警戒感は高まっています。11時30分時点のNYダウ先物は133ドル安となっており、本日は弱いスタートとなりそうです。経済指標では、注目の雇用統計が発表されます。予想よりも悪い内容だと売りが加速する恐れもあるので注意が必要です。とくにナスダック総合株価指数が調整局面入りとなる、2月高値からの10%以上の下落になるかどうかに注目しています。米株安で円安も、ドル/円異例の動きに警戒=来週の外為市場[東京 5日 ロイター] - 来週の外為市場では、米金利の上昇を支えに、一段のドル高/円安が進むと予想する声が出ている。金利上昇が株安を招いても、株価の調整が極端なものとならなければ、ドルの上昇圧力が勝る形で、円が下げる異例の展開になる可能性があるという。予想レンジはドルが106━109円、ユーロが1.18―1.21ドル。2月半ばまで過去最高値を更新していた米ナスダック総合指数が4日、年始の水準を下回り、年初来マイナス圏へ転じた。2月12日の最高値から下落率は9.7%に達し、調整局面入りが濃厚な情勢だ。S&P総合500種も2月12日の最高値から4%超下落しており、年初来マイナス圏入りが目前に迫る。一方、外為市場では年初来、米ドルが英ポンドや豪ドルに次ぐ強さを見せていることで、ドル/円はじり高展開が継続。株安下で円が売られる場面も増えてきた。米金利の急速な上昇によるドル高圧力が、リスク回避の円高圧力を上回っている。8カ月ぶりに108円台へ上昇したドルは、テクニカル的には上抜けが明確で、目先は買いが集まりやすい。年初来のドル/円と米金利の相関度から試算すると「仮に米10年債金利が2%弱へ上昇すれば、ドルは110円に到達する」(SMBC日興証券チーフ金利ストラテジストの森田長太郎氏)ことになる。しかし、1月の年初来安値102.59円から2カ月で108円台へ駆け上がった反動で、スピード調整が起こる公算は小さくない。「対ドル以外では株安時に円が買われる動きも依然あり、米株が大きく崩れれば、リスクオフの円買いは対ドルでも加速するのではないか」(トレーダー)との予想もある。米国以外の長期金利上昇にも留意が必要だ。豪は年始の0.9%台から1.8%台へ、英国も同0.2%台から0.8%台へ水準を切り上げた。先に金利上昇をけん制したラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁が、11日の理事会後会見でどう言及するかが注目される。焦点:楽観砕いたコロナ変異種、免疫仮説の抜本修正必要に[シカゴ 3日 ロイター] - 米ワシントン大学保健指標評価研究所(IHME、シアトル)のクリス・マーレイ所長が新型コロナウイルスの感染数と死者数について示す予測は、世界中から注視されている。しかし、同氏は今、流行の先行きについて仮説を修正しつつある。マーレイ氏は最近までは、幾つかの有効なワクチンの発見が集団免疫の達成を助ける可能性があることに希望を抱いていた。あるいは接種と過去の感染が組み合わさることで、他人への感染をほぼゼロにできる可能性があるとも期待していた。しかし、先月に明らかになった南アフリカでのワクチン臨床試験データは、感染力の強い変異株がワクチンの効果を弱める可能性があるだけでなく、感染したことのある人の自然免疫をもくぐり抜ける恐れがあることを示した。このデータを見た後は「眠れなかった」とマーレイ氏はロイターに打ち明けた。「コロナ流行は一体いつ終わるのか」と同氏は自問する。現在は変異株が自然免疫をかいくぐる能力を考慮に入れるため、自分の研究モデルを修正中で、早ければ今週中にも最新の流行予想を発表するつもりだ。<ここ数週間のデータで希望は後退>コロナ流行を追跡分析したり、その影響の抑制に取り組んだりしている18人の専門家にロイターがインタビューした結果、新たなコンセンサスが急浮上していることが明らかになった。専門家の多くによると、昨年の遅い時期に約95%の有効性を示す2種類のワクチンが登場したことで、「はしか」のようにコロナウイルスもおおむね抑制できるとの希望がいったんは強まっていたという。しかし、南ア型やブラジル型の新たな変異株を巡ってここ数週間に出てきたデータは、そうした楽観的な見方を打ち砕いたという。専門家らは今、コロナは一定の地域や季節に一定の罹患率で広がり続けるウイルスとして地域社会に残るというだけでなく、今後何年も発症者や死者の多大な犠牲を招く可能性が大きいとの見方に変わっている。こうしたことから、人々は、特に高リスクの人々は、習慣としてのマスク着用や、感染急増時の混雑回避などの対策が今後も必要になるとみられるという。バイデン米大統領の医療顧問トップを務める米国立アレルギー感染症研究所のファウチ所長はインタビューで、ワクチン接種後であっても、変異株が出てきているのならば「自分はこれからもマスクを着用したい」と語った。ちょっとした小さな変異株が出現するだけで、これが次の流行急増を誘発し、いつ生活が正常化するかの見通しをがらりと変えてしまうとも指摘した。マーレイ氏をはじめ一部の科学者は、予想が改善する可能性もあるとも認める。記録的なスピードで開発された新しいワクチンは、変異株が感染力を高めている中でもなお、入院や死亡は防いでいるように見える。変異株に高い有効性を維持し得る再接種用や新規接種用のワクチン開発も、多く手掛けられている。そもそも、免疫システムがコロナウイルスと闘う能力について、分からないことはまだたくさんあるという。既に多くの国で、年明け後に感染率の低下が見られた。優先接種された人々の重症化や入院が劇的に低下した例もある。<死者はインフルエンザの4倍にも>マーレイ氏によると、南ア型や同様の変異株が急速に広がり続けた場合、次の冬のコロナによる入院数や死亡数はインフルエンザ流行の4倍に高まる可能性がある。これは有効性65%のワクチンがその国の国民の半数に接種されたと仮定しての話だ。米連邦政府によるインフル死者の年間予測に基づくと、最悪の場合は次の冬に米国だけで最大20万人がコロナ関連で死亡する可能性があるとの計算になるという。マーレイ氏の研究所が現在出している今年6月1日までの予測では、コロナ死者は米国でさらに6万2000人、世界でさらに6万9000人と推定されている。モデルにはこの期間のワクチン接種率の予想や、南ア型とブラジル型の流行見込みを加味している。専門家の考え方が変わってきたことは、流行がいつ終わるかを巡る各国政府にも影響しており、発表のトーンは慎重になってきている。ワクチン接種を世界最速で進めている国の一つである英国は先週、世界でも最も厳しい部類の移動制限措置について、解除はゆっくりになるとの見通しを示した。米政府が予測する生活様式の正常化の時期も、何度も後ずれしている。最近では昨年夏の終わり頃からクリスマス時期になり、さらに今年3月ごろに修正された。イスラエルが発行する免疫証明書「グリーンパス」は、コロナ感染から回復した人やワクチン接種を済ませた人に与え、持っていればホテルや劇場の利用を認める仕組みだが、有効期間は半年しかない。免疫がどれだけ長く持続するか、よく分かっていないからだ。米ジョンズ・ホプキンズ大学公衆衛生大学院のステファン・バラル氏は「コロナ流行の緊急事態局面が過ぎるというのは一体何を意味するのか」と問い掛ける。一部専門家はワクチン接種や厳しい制限措置を通じて感染が完全に根絶され得るかどうかを論点にしているが、バラル氏は目標をもっと控えめに、しかし意味がある内容に置いている。「私が想定するのは、病院が満杯でなくなり、集中治療室もいっぱいでなくなり、人々が悲劇的な死を迎えなくて済む状態だ」と説明する。<コロナは当初から「動く標的」>そもそも最初から、コロナウイルスは専門家にとって、いわば「動く標的」だった。流行の初期にも、有力専門家らはコロナウイルスが一定の地域や季節に一定程度、繰り返し流行が続いていく可能性があり、「完全に消え去ることはないかもしれない」と警告していた。これは世界保健機関(WHO)の緊急対応責任者マイク・ライアン氏の意見でもあった。彼らには解明しなければいけないことがたくさんあった。ウイルスに対抗できるワクチンの開発は可能か。このウイルスはどれだけ急速に変異していくのか。高い実施率で予防接種を行えば地域全体をほぼ感染から防ぎ続けられる「はしか」のようなものか。あるいは毎年世界で何百人もが感染するインフルエンザのようなものか――といった疑問だ。昨年の大半を通じて、多くの科学者はコロナウイルスが感染力を高めたり致死性が強まったりする大きな変異をしなかったことに、意外感を覚え、胸をなで下ろしてもいた。大きな展開があったのは昨年11月だ。米ファイザーとドイツのビオンテックの連合と、米モデルナ がそれぞれ、臨床試験(治験)で約95%の有効性が示されたと発表した。これは今開発されているどのインフルエンザワクチンよりも高い有効性だ。ロイターが今回取材した少なくとも数人の専門家は、こうしたデータを受けても自分たちは、そうしたワクチンがコロナウイルスを一掃するとは予想しなかったと話した。しかし、多くの専門家は、このデータが出現したことで、研究界では世界が十分なスピードで接種を進めることができさえすれば、実質的な根絶は可能だろうとの希望が持ち上がったと指摘する。英インペリアル・カレッジ・ロンドンの感染症疫学専門家、アズラ・ガーニ氏は「昨年のクリスマス前の時点では、われわれは皆、こうしたワクチン登場を極めて楽観的に受け止めた」と話した。「コロナワクチン第1世代で、これほど高い有効性のワクチンが可能になるとはわれわれは必ずしも予想していなかった」<「むち打ちを食らったような」見通し変更>しかし楽観論は短命に終わった。12月末には英国が感染力の強い新たな変異株が見つかったと警告。この変異ウイルスは英国内で急速に感染の主流になった。ほぼ同じ頃、研究者は南アとブラジルで、感染力のさらに強い変異株が流行し始めたことを知ることとなった。ファイザー所属のワクチン専門家、フィル・ドーミツアー氏は昨年11月の時点では、ロイターに対し、同社ワクチンの成功はコロナウイルスが「免疫に対するぜい弱性」を持つことを示していると話し、「人類にとって画期的な出来事」と強調していた。しかし今年1月初めには、同氏は変異株が新たな局面到来の予兆となっていることを認めざるを得なかった。1月下旬には、ワクチンに及ぼす影響がさらに明らかになってきた。米ノババックスのデータが、英国の治験では89%の有効性を示した半面、南アでの治験ではわずか50%だった。1週間後には、英アストラゼネカ のワクチンが南ア型による軽度の発症に対して限定的な予防効果しかないとするデータも示された。何人かの専門家は、直近で迫られた見通しの変更はかなりのものだったと話す。米ラホヤ免疫研究所(サンディエゴ)のウイルス学者、シェーン・クロッティー氏は、科学者たちがあまりの衝撃に「むち打ち」を食らったような状況だと描写した。同氏は昨年12月の時点では、コロナウイルスをはしかウイルスのように「機能的に根絶する」ことは可能だと考えていた。今はどうだろうか。「状況打開のための答えや進むべき道は、できるだけ多くの人に接種することだ。それは今も、12月1日時点や1月1日時点と変わらない」という。しかし、そうした努力から期待できる「成果」はもはや、以前と同じではないと警戒心をあらわにした。日経平均は続落、急な下げへの警戒で後半は買い戻し優勢に[東京 5日 ロイター] -東京株式市場で日経平均は続落。米長期金利の上昇が嫌気され朝方は売りが先行して一時は600円を超す下落となったものの、直近の急な下げに対する警戒感から買い戻しが活発化し、後半は戻り歩調となった。輸出関連株にとっては、円安も好材料だった。TOPIXは前日比プラスで大引け。4日の米国株式市場は続落、ナスダック総合は2月に付けた過去最高値から10%近く下落して取引を終えた。米長期金利の上昇を懸念する投資家の間でパウエル米連邦準備理事会(FRB)議長の発言に失望が広がった。パウエル議長はウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)主催の会合で、最近の米国債利回りの急上昇について「注目に値し、留意している」と述べつつも、「無秩序な」動きとも、FRBによる介入が必要とも考えていないとし、「FRBの現在の政策スタンスは適切だ」との認識を示した。資産買い入れの変更は示唆しなかった。米長期金利の動向に神経質になっているため、日本株は朝方から大幅続落の展開。ただ、急ピッチでの下げに対して警戒感も生じており後半は買い戻しが活発化、日経平均は急速に下げ幅を縮小する一方、TOPIXは前日比プラスで大引けた。物色面では、値がさのグロース株は引き続き軟調だったが、景気敏感株が買われ相場を下支えする格好となっている。外為市場でドル/円が108円台まで円安に振れたことで、輸出関連株に底堅い銘柄が目立った。市場では「前日の米株下落がパウエルFRB議長の発言が材料になった点を考慮すると、16─17日の連邦準備理事会(FOMC)まで投資家は疑心暗鬼となり、不安定な相場展開が続くとみられる」(野村証券・エクイティマーケットアナリストの澤田麻希氏)との声も聞かれる。TOPIXは、0.61%高。東証1部の売買代金は、3兆1752億0300万円とやや膨らんでいる。東証33業種では、鉱業、鉄鋼、電気・ガス業などが上昇し、値下がりは不動産業など6業種にとどまった。個別では、後半にトヨタ自動車など主力の輸出関連株が買われたほか、大幅安で始まったソフトバンクグループも前日比プラスまで戻した。また、日本製鉄など景気敏感株の一角が高いが、ファーストリテイリングはさえない。東証1部の騰落数は、値上がり1352銘柄に対し、値下がりが753銘柄、変わらずが89銘柄だった。米株はFRB議長発言受け続落、ナスダック年初来でマイナス[4日 ロイター] - 米国株式市場は続落し、ナスダック総合は2月に付けた過去最高値から10%近く下落して取引を終えた。米長期金利の上昇を懸念する投資家の間でパウエル米連邦準備理事会(FRB)議長の発言に失望が広がった。パウエル議長はウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)主催の会合で、最近の米国債利回りの急上昇について「注目に値し、留意している」と述べつつも、「無秩序な」動きとも、FRBによる介入が必要とも考えていないとし、「FRBの現在の政策スタンスは適切だ」との認識を示した。資産買い入れの変更は示唆しなかった。一部投資家の間では、FRBが長期金利の上昇抑制に向けて国債買い入れを長期債にシフトさせるのではないかとの見方があった。議長の発言を受けて米10年債利回りは1.5%台に上昇した。レイモンド・ジェームズのチーフエコノミスト、スコット・ブラウン氏は「パウエル議長の発言は長期金利上昇を押し返すものではなかった。市場は一段上昇の可能性を示すシグナルと受け止め、実際に利回りは上昇した」と述べた。ナスダックは年初来の上昇分が帳消しになり、2月12日に付けた過去最高値を9.7%下回る水準で取引を終えた。10%下落すれば調整局面入りとなる。S&P総合500種は2月12日の最高値から4%超下落している。アップル、テスラ、ペイパル・ホールディングスなどの下げがS&P500を圧迫。テスラは5%近く下落した。一方、原油価格の上昇を受けてS&P500エネルギー指数は2.5%高となった。米労働省が4日発表した2月27日までの1週間の新規失業保険申請件数(季節調整済み)は74万5000件と、前週の73万6000件から悪化した。ただ予想の75万件ほどは増えなかった。市場の注目は5日発表の雇用統計に集まる。米取引所の合算出来高は180億株。直近20営業日の平均は150億株。ニューヨーク証券取引所では値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を3.79対1の比率で上回った。ナスダックでも5.62対1で値下がり銘柄数が多かった。ドル3カ月ぶり高値、パウエル発言で米債利回り上昇=NY市場[ニューヨーク 4日 ロイター] -終盤のニューヨーク外為市場では、ドルが3カ月ぶり高値に上昇。米連邦準備理事会(FRB)のパウエル議長が4日に出席したイベントで、このところの米国債売りにさほど懸念を示さなかったことで利回りが上昇、ドル需要も強まった。パウエル議長はFRBの「政策スタンスは適切」とし、最大雇用達成まで現行の緩和的な政策を維持すると再表明。最近の米債利回りの急上昇については「注目に値し、留意している」としつつも、「無秩序な」動きとも、FRBによる介入が必要とも考えていないとした。シリコンバレー・バンクのシニアFXトレーダー、ミン・トラン氏は、「一部の投資家は少なくとも利回り急上昇について懸念があることをパウエル氏が認めると予想していたたが、そうしなかった」と指摘。「経済が一貫して力強さを示し、物価と労働市場の両方で新型コロナウイルス流行前の状態に戻るまで基本的に緩和政策を維持するというメッセージは総じて変わっていない」と述べた。ドル指数は一時、昨年12月1日以来の高値となる91.663まで上昇。その後は0.53%高の91.561。ユーロは0.73%安の1.1973ドルと2月5日以来の安値を付けた。米10年債利回りは一時1.555%まで上昇したが、先週付けた1年ぶりの高水準である1.614%は下回って推移している。市場の関心は5日に発表される2月の米雇用統計に移っている。スイスフランと円はこのところの下落が継続。フランは対ドルで0.9297フランと昨年7月23日以来の安値。円も昨年7月1日以来となる107.93円まで下げた。TDセキュリティーズのシニアFXストラテジスト、マゼン・イッサ氏は「ユーロ、円、スイスフランなどの伝統的な(資金調達通貨)は、米国の利回り上昇を背景にした環境では特に後退しているようだ」と述べた。一方、オーストラリアドルをはじめとする高リスク通貨は世界的な成長回復を受けてアウトパフォームの可能性が高いとみられるが、この日の豪ドルは株安に伴い序盤の上昇を吐き出した。終盤では0.57%安の0.7730米ドルで、先週付けた3年ぶり高値の0.8007米ドルを下回っている。暗号資産(仮想通貨)のビットコインは5.36%下落し、4万7691ドル。イーサは3.21%安となった。ひらまつ、10-12月期(3Q)最終は赤字縮小 ひらまつ が3月5日大引け後(16:30)に決算を発表。21年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終損益は28.5億円の赤字(前年同期は14.9億円の赤字)に赤字幅が拡大した。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結最終損益は0.4億円の赤字(前年同期は5.9億円の赤字)に赤字幅が縮小する計算になる。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結最終損益は7.8億円の赤字(前年同期は15億円の赤字)に赤字幅が縮小したが、売上営業損益率は前年同期の8.3%→-9.3%に急悪化した。株探ニュース松山英樹は3オーバー・87位タイ R・マキロイらが首位発進<アーノルド・パーマー招待 初日◇4日◇ベイヒルC&L(米フロリダ州)◇7466ヤード・パー72>米国男子ツアーの「アーノルド・パーマー招待」初日が終了。松山英樹は3オーバーと出遅れてのスタートとなった。松山は前半から連続ボギーなど4バーディ・5ボギー・1ダブルボギーの「75」と苦戦。87位タイ発進となった。首位タイには、6アンダーまで伸ばしたローリー・マキロイ(北アイルランド)とコリー・コナーズ(カナダ)、首位と1打差・3位にブライソン・デシャンボー(米国)、2打差・4位タイにはジェイソン・コクラック(米国)ら3人が続いた。そのほか、昨年覇者のタイレル・ハットンは5オーバー・107位タイと出遅れ。森田遥、西郷真央が首位で決勝へ 渋野日向子は4差5位<ダイキンオーキッドレディス 2日目◇5日◇琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県)◇6561ヤード・パー72>国内女子ツアー2021年初戦の第2ラウンドが終了。この日のベストスコアタイとなる「66」をマークした森田遥と19歳・西郷真央がトータル10アンダー・首位に並んだ。トータル9アンダー・3位に田辺ひかり。トータル7アンダー・4位に菊地絵理香が続いた。渋野日向子は6バーディ・1ボギー「67」の好スコアをマーク。トータル6アンダー・5位タイと好位置で決勝ラウンドにコマを進めた。一方で、賞金ランキング1位の笹生優花は「73」と振るわず、トータル2オーバー・63位タイで予選落ち。そのほか、安田祐香、イ・ボミ、イ・ミニョン(ともに韓国)や、2年ぶりのツアー出場となった諸見里しのぶも2日間で姿を消した。適切な筋肉注射の手技を解説、日医注射針は斜めではなく「必ず直角に刺入」 日本医師会は2月26日、新型コロナウイルスワクチンの適切な筋肉注射の手技を解説する「新型コロナウイルスワクチン速報【第5号】」を公表した。注射針を皮膚に対して斜めに刺入する報道が見受けられるとしているが、「注射針は必ず直角に刺入してください」などと、イラスト付きで正しい接種法の実施を呼びかけている。 速報では、注射部位は三角筋の肩峰より2-3指下中央の位置で、三角筋をつままずに広げて圧迫固定するこつを紹介。皮下組織が手繰られて厚くなると、針先が三角筋に届かなくなるのを避けるためとしている。針を刺入する深さは体型によって13-20mmが目安で、シリンジ陰圧確認を行わないことで、筋肉組織損傷による免疫獲得減弱のリスクを回避するという。ワクチンの注入は、神経損傷を避けるため刺入時に異常の訴えがないことを確認した上で行い、抜針後は軽く圧迫するだけでよく、揉まないように求めている。また、「逆流を確認している報道が見受けられる」と指摘し、皮膚はつままず逆血を確認せずに適切な深さで接種することとしている。 参考動画として、日本プライマリ・ケア連合学会が作成した動画も紹介している。その中でも実際の手技を見せながら、逆血確認が不要なことや接種後に部位を揉まないこと、万が一針の先端が骨に当たったとしても問題はなく、そこから数mm引いた位置で注入するコツなどを説明している。 日医では、これらの情報は2021年2月26日時点での確定情報とし、必要とされているにもかかわらず不確定な情報については、確定され次第案内するとしている。明日の戦略-長期金利に振り回された一週間、パウエルは何も悪くないトレーダーズ・ウェブ 5日の日経平均は続落。終値は65円安の28864円。パウエルFRB議長の発言が強い失望を誘った格好で、米国株が大幅安。これを受けて寄り付きから200円を超える下落となり、しばらく下を試す流れが続いた。前場では600円超下げる場面もあり、28300円台まで下落した。一方、後場は前引けから100円程度戻して始まると、急速に下げ幅を縮める展開。2桁の下落となったところでいったん売り直されたが、終盤には盛り返し、大引け直前に高値をつけた。TOPIXは後場にプラス圏を回復し、こちらはしっかり高値引けとなった。 東証1部の売買代金は概算で3兆1700億円。業種別では鉱業や鉄鋼、電気・ガスなどが上昇している一方、不動産やサービス、海運などが下落した。上期が大幅な営業増益となったアルチザネットワークスが急騰。半面、直近で買いを集め、きょうも逆行高となっていた直近IPOの室町ケミカルが、14時辺りから急失速し、マイナス転換から下げ幅を広げた。 東証1部の騰落銘柄数は値上がり1352/値下がり753。前日にストップ高比例配分となったリコーが大幅上昇。キーエンスが売り先行から切り返して3%超上昇した。任天堂やソニー、村田製作所、信越化学など主力グロースの一角が、後場に全体が持ち直す中でプラス圏に浮上。東芝が6%超の上昇と騰勢を強めた。決算や株主還元拡充が好感された積水ハウスが大幅高。ほか、シチズン時計やカシオなど、時計株に非常に強い動きが見られた。 一方、ファーストリテイリングが連日の大幅安。マネックスGやリクルートが値幅を伴った下げとなった。ハイテク株には切り返すものも多かった中で、東京エレクトロンは軟調。金利上昇が嫌気されたが、住友不動産や三菱地所など不動産株の弱さが目立った。前日ストップ高の日立造船は一転急落。シルバーライフは上方修正発表も、株価の反応は強い売りとなった。 日経平均は続落とはなったが、後場に大きく値を戻し、ローソク足では下に長いヒゲをつけた。4日の米国株はパウエルFRB議長の発言が失望と受け止められて大きく下げたが、これは過剰反応。史上最高値圏で推移していた米国株が長期金利の上昇に多少動揺したくらいでFRBが金融政策の変更を示唆するようなことがあれば、それこそバブルを生みだす。そもそもパウエル氏は、景気が回復に向かう局面においては、ある程度の金利上昇は容認するスタンスを採っている。この先、米国の長期金利が制御不能のような状況になるのであれば、その時には当然適切な対応を取るはずだ。今回、発言が株安を招いたことで、3月のFOMC(3/16~17)に向けては、警戒感が広がるかもしれない。しかし、ここでグロース株がクールダウンして、一握りの銘柄に資金が集中する流れが修正されることは、長期的な観点で見れば、株式市場にもプラスに作用すると考える。【来週の見通し】 一進一退か。翌週にFOMC(3/16~17)と日銀金融政策決定会合(3/18~19)が控えている。足元で米長期金利の動向にマーケットが大きく振り回されているだけに、これらの中央銀行イベントが強く意識されることになるだろう。現状水準から一段と下げてリスクオフムードが強まった場合には、FRBや日銀がストッパーになるとの見方が強まる。かといって、そういった期待から前のめりで買いが入るようなら、戻り売りが上値を押さえる可能性が高い。結果、上下どちらかに大きく振れたとしても、週の中でそれを修正する動きが出てくると予想する。方向感が出づらい中、物色もグロースとバリューの綱引きのような状況が続くだろう。【今週を振り返る】 軟調となった。3月相場に入り、1日の日経平均は700円近い大幅上昇。しかし、翌2日に節目の3万円に迫ったところで失速すると、以降は下げ基調が強まった。米国で長期金利が再び上昇し、これに対して米国株に不安定な動きが見られたことが警戒材料となった。ハイテクを中心にグロース株にまとまった売りが出てくる中、4日は600円を超える下落となり、29000円を割り込んだ。ただ、5日は一時600円超下落しながらも終値では2桁の下落にとどめるなど、押し目ではリバウンド狙いの買いも入った。日経平均は週間では約101円の下落となり、週足では2週連続で陰線を形成した。【来週の予定】 国内では、1月景気動向指数、2月景気ウォッチャー調査(3/8)、1月家計調査、10-12月期GDP改定値、2月マネーストック、5年国債入札(3/9)、2月企業物価指数、2月都心オフィス空室率、20年国債入札(3/11)、1-3月期法人企業景気予測調査、メジャーSQ(3/12)などがある。 企業決算では、学情、萩原工業、アスカネット、アイ・ケイ・ケイ、ミライアル(3/8)、サトウ食品、Bガレージ、Eインフィニティ、不二電機、ピースリー、ビーアンドピー(3/9)、テンポスHD、楽天地、アセンテック、ギグワークス、トビラシステム、神島化、ハウテレビ(3/10)、ドーム、ラクスル、菱洋エレク、ステムリム、鎌倉新書、アイモバイル、サムコ、ネオジャパン、シルバーライフ、巴工業、スバル興、トーホー、Casa(3/11)、クミアイ化、ヤーマン、ソフトウェアサー、シーイーシー、オハラ、スマレジ、HEROZ、丹青社、CAICA、丸善CHI、J.S.B.、MSOL、gumi、イトクロ、エイチーム、ギフト、Link-U、トーエル、ベステラ、菊池製作、カラダノート、さくらさ、クロスプラス、モルフォ、VALUENEX、バリュゴルフ、シャノン(3/12)などが発表を予定している。 海外では、中国2月生産者物価指数、中国2月消費者物価指数、米2月消費者物価指数、米2月財政収支(3/10)、ECB定例理事会(ラガルド総裁記者会見)(3/11)、米2月生産者物価指数(3/12)などがある。今晩のNY株の読み筋=米2月雇用統計に注目モーニングスター 5日の米国株式市場は、米2月雇用統計が焦点となる。 米雇用統計の前哨戦とされる3日発表の2月ADP雇用統計は雇用者数の伸びが市場予想を下回り、労働市場の回復鈍化が示された。ただ、過去数カ月のADP雇用統計と政府発表の雇用統計との相関性は薄れているとの見方もある。一方、足元の米長期金利はかつてのように、リスクオンの株高・金利上昇(債券価格下落)の反応とはならず、利上げ再開を想起させ、株式市場には警戒要因となっている。4日のパウエルFRB(米連邦準備制度理事会)議長講演で金利上昇封じ込めのための対応策が示されなかったことから、金利上昇圧力は一段と強まっている。 こうした中で、2月雇用統計が発表されるが、ADP雇用統計に反するように強い結果が出れば、前日大幅安となった反動もあり、NYダウは素直に買いで反応するとみられる。ただ、FRBの金融緩和継続姿勢に懐疑的な市場関係者が早期利上げ再開を織り込み、米長期金利上昇が進むと、NYダウの上値が重くなる展開も想定されるので、注意したい。<主な米経済指標・イベント>2月雇用統計、1月貿易収支、1月消費者信用残高ボスティック・アトランタ連銀総裁が講演(日付は現地時間)◎投資関連情報は投資の参考として情報提供のみを目的としたものであり、株式の売買は自己責任に基づき、ご自身で判断をお願いします。来週の日本株の読み筋=落ち着きどころを見極める、米国債入札で警戒感先行もモーニングスター 来週(8-12日)の東京株式市場は、落ち着きどころを見極める段階か。米10年債利回りが再び1.5%のフシを突破し、4日の米国株安が5日の日本株安につながった。売り一巡後は下げ幅縮小の動きを強めたが、依然として予断を許さぬ状況が続く。米金利上昇をめぐって、パウエルFRB(米連邦準備制度理事会)議長は、4日のオンライン討論会においても前月の議会証言と同様に強い懸念を示さず、マーケットに失望を呼び、金利上昇が再燃した。米国では9、10、11日にそれぞれ3、10、30年債の入札が予定されている。今回の金利急騰の引き金は前月行われた7年債の入札不調だっただけに、市場に警戒感が先行しやすい。 主要指数は2月16日に高値を形成して以降、何度も短期的な下げに見舞われ、足元の調整から逃げ遅れた向きのシコリ玉が上値に滞留している。信用買い残の水準も高く、切り返すには相当なエネルギーが求められよう。 スケジュール面では、国内で8日に2月景気ウォッチャー調査、9日に1月家計調査、20年10-12月期GDP確報値、12日に1-3月期法人企業景気予測調査、メジャーSQ算出日など。海外では10日に中国2月消費者・生産者物価、米2月消費者物価、11日にECB定例理事会(ラガルド総裁会見)、12日に米2月生産者物価が予定されている。 5日の日経平均株価は続落し、2万8864円(前日比65円安)引け。朝方は、現地4日の米長期金利上昇を背景に米国株式が下落した流れを受け、売りが先行した。時間外取引(日本時間5日)の米株価指数先物安も重しとなり、下げ幅は一時620円を超えた。一巡後は下げ渋り、大引けにかけて大きく持ち直した。米株先物や上海・香港株が上げに転じ、日銀のETF(上場投資信託)買い観測も下支え要因として指摘された。市場では、「米金利高・株安が止まらないと反転できない」(中堅証券)との声が聞かれた。ダウ先物100ドル安でドル高、対円108.45円、対ユーロ1.1923ドルトレーダーズ・ウェブ ダウ先物が100ドル程度下落していることで、ドル円は108.45円、ユーロドルは1.1923ドル、ポンドドルは1.3846ドルまでドル強含み。〔ロンドン外為〕円、108円台半ば(5日午前9時)時事通信 【ロンドン時事】週末5日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長の発言で急激なドル買い・円売りが進んだ海外市場の流れを引き継ぎ、1ドル=108円台半ばに下落している。午前9時現在は108円40~50銭と、前日午後4時(107円55~65銭)比85銭の円安・ドル高。 対ユーロは、1ユーロ=129円25~35銭(前日午後4時は129円50~60銭)で、25銭の円高・ユーロ安。ユーロの対ドル相場は1ユーロ=1.1925~1935ドル(1.2035~2045ドル)。(了)南ア由来の新型コロナ変異株、新たに3人の感染を確認 岐阜県内の新規感染者は6人 岐阜県は6日、県内で新たに20代~80代の男女6人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は4654人。3日に県内の50代女性への感染が確認された南アフリカ由来の変異株について、国立感染症研究所は2月下旬に発症した女性の接触者3人も同じ変異株に感染していることを確認したと公表した。 変異株の感染が分かったのは県内の50代男性2人と40代女性。3人とも海外渡航歴や不特定多数との接触はない。変異株への感染を調べる県の検査で陽性となり、研究所が調査していた。3人は咳や発熱などの症状があったが重症ではなく、うち1人は陰性になったことを確認した上で退院したという。 病院に関連した二つのクラスター(感染者集団)の規模が拡大した。美濃加茂市の木沢記念病院関連では医療従事者の家族1人の感染が分かり、230人に増加。東濃厚生病院(瑞浪市)関連では医療従事者1人のほか、同病院から転院した患者の感染が分かった高井病院(土岐市)で医療従事者2人、患者1人の計4人の陽性が判明し、感染者数は合わせて28人となった。 人工呼吸器での管理が必要な重症者は前日から1人増え、9人となった。 新規感染者の居住地別は土岐市3人、大垣市、美濃加茂市が各1人、愛知県1人。年代別は20代2人、30代、40代、50代、80代が各1人。女子生徒とホテルでいやらしい行為疑い 公立中学の33歳教員を逮捕 岐阜県警少年課は3日、児童福祉法違反の疑いで、岐阜市の教員の男(33)を逮捕した。 逮捕容疑は昨年12月30日、県内のホテルで自身を相手に県内の女子中学生にいやらしい行為をさせた疑い。 同課によると、男は県内の公立中学校に勤務。女子はこの学校の生徒だった。2月26日に男の関係者から相談があり、捜査を進めていた。同課は認否を明らかにしていない。NY株見通し-2月雇用統計を受けた長期金利の動向に注目トレーダーズ・ウェブ 今晩のNY市場は2月雇用統計に注目。昨日はパウエルFRB議長の発言を受けて長期金利が上昇したことで、主要3指数がそろって3日続落した。ハイテク株主体のナスダック総合は昨年末水準を割り込み、史上最高値からの下落率が10%を超え「調整相場」入りとなった。今晩の取引でも長期金利の動向を睨んだ神経質な展開が予想され、寄り前に発表される2月雇用統計に注目が集まる。市場予想は非農業部門雇用者数が18.2万人増(前回:4.9万人増)、失業率が6.3%(同:6.3%)、平均賃金が前月比+0.2%(同:+0.2%)、前年比が+5.3%(同:5.4%)。雇用統計が強い結果となり、長期金利が一段と上昇すれば、ハイテク・グロース株売りの流れが強まることが警戒される。 今晩の米経済指標・イベントは2月雇用統計のほか、1月消費者信用残高、ボスティック米アトランタ連銀総裁講演など。主要な企業の決算発表はなし。(執筆:3月4日、14:00)看護師長パワハラ賠償命令 昭和大藤が丘病院共同通信社 昭和大藤が丘病院(横浜市青葉区)の看護師だった女性(61)が、上司の看護師長からパワハラを受け病気になったとして、大学に約2千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は3日、看護師長の威圧的な言動と発症との因果関係を認め、約600万円の支払いを命じた。 判決によると、女性は2015年3月、通勤中の電車内で急病人を救護し、出勤が遅れた。電話で別の上司に伝えていたが、看護師長から「責任者の私に連絡しなさい」と怒鳴られた。女性はその後、胸の痛みを訴えて倒れ、心臓疾患と診断された。心的外傷後ストレス障害(PTSD)も発症した。 中吉徹郎(なかよし・てつろう)裁判長は「看護師長は事情を聴かず威圧的に叱責し、非常に大きな心理的負荷を与えた。業務上必要な範囲を逸脱し、極めて不適切だ」と指摘した。看護師長の言動を放置した大学には、安全配慮義務違反があるとした。 判決は、看護師長が女性に対し、やむを得ない理由以外では、有給休暇の取得を認めていなかったことも認定し「休暇制度の趣旨を無視する対応で、精神的負荷を与えた」とした。 昭和大は「判決内容を精査中だ」としている。米2月雇用統計、雇用は10月来で最大の伸び、ドル上昇フィスコ 労働省が発表した2月雇用統計で失業率は6.2%と、予想外に1月6.3%から低下し昨年3月来で最低となった。非農業部門雇用者数は前月比+37.9万人となった。伸びは1月+16.6万人から拡大し10月来で最大となった。1月は14.7万人、12月は23.3万人それぞれ上方修正された。平均時給は前月比+0.2%、前年比では+5.3%と予想通り。労働参加率は61.4%、不完全雇用率(U6)は11.1%でそれぞれ1月と同水準となった。 同時刻に商務省が発表した1月貿易収支は―682億ドル。赤字幅は12月670億ドルから予想以上に拡大した。 良好な雇用統計の結果を受けて米国債相場は下落。10年債利回りは1.62%まで上昇した。ドル買いも強まり、ドル・円は108円23銭から108円64銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.1940ドルから1.1894ドルまで下落した。 【経済指標】・米・2月失業率:6.2%(予想:6.3%、1月:6.3%)・米・2月非農業部門雇用者数:+37.9万人(予想:+20.0万人、1月:+16.6万人←+4.9万人)・米・2月平均時給:前年比+5.3%(予想:+5.3%、1月:+5.3%←+5.4%)・米・1月貿易収支:―682億ドル(予想:-675億ドル、12月:―670億ドル←-666億ドル)米雇用、37万9000人増=失業率6.2%に改善―2月時事通信 【ワシントン時事】米労働省が5日発表した2月の雇用統計(季節調整済み)は、景気動向を敏感に反映する非農業部門の就業者数が前月比37万9000人増となった。好調の目安とされる20万人を上回った。失業率は6.2%と0.1ポイント改善した。 【指標】2月米非農業部門雇用者数変化 +37.9万人、予想 +18.2万人ほかトレーダーズ・ウェブ2月米失業率 6.2%、予想 6.3%2月米平均時給(前月比) +0.2%、予想 +0.2%2月米平均時給(前年比) +5.3%、予想 +5.3%1月米貿易収支 -682億ドル、予想 -675億ドル2月米雇用統計非農業部門雇用者数変化〔予想 +18.2万人〕 (前回発表値 +4.9万人)失業率〔予想 6.3%〕 (前回発表値 6.3%)平均時給(前月比)〔予想 +0.2%〕 (前回発表値 +0.2%)平均時給(前年比)〔予想 +5.3%〕 (前回発表値 +5.4%)1月米貿易収支〔予想 675億ドルの赤字〕 (前回発表値 666億ドルの赤字)強い米雇用統計でドル高・米債利回り上昇=NY為替みんかぶFX 2月の米雇用統計は予想以上に強い結果となり、米10年債利回りは一気に1.62%台まで上昇、為替市場ではドル高が一段と進行した。 ドル円は108.64レベルまで高値を更新。ユーロドルは1.1894レベル、ポンドドルは1.3779レベルまで安値を更新。 2月の米非農業部門雇用者数は37.9万人増と事前予想20万人を大きく上回った。前回1月も4.9万人から16.6万人へと大幅に上方修正された。失業率は6.2%に低下、労働参加率は前回と同様の61.4%だった。USD/JPY 108.53 EUR/USD 1.1916 GBP/USD 1.3807〔NY外為〕円、108円台前半(5日朝)時事通信 【ニューヨーク時事】週末5日午前のニューヨーク外国為替市場は、米長期金利の上昇を背景とした円売り・ドル買いの流れが続き、円相場は1ドル=108円台前半に下落している。午前9時15分現在は108円20~30銭と、前日午後5時(107円92銭~108円02銭)比28銭の円安・ドル高。 パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長は前日の発言で、米長期金利の急上昇をけん制したが、市場が期待していたほど踏み込まなかったことで、長期金利が一段と上昇。海外市場で昨年6月初旬以来約9カ月ぶりの安値を付け、ニューヨーク市場に入ってからもこの流れが継続している。 米労働省が5日発表した2月の雇用統計は、非農業部門就業者数が前月比37万9000人増となり、伸びは前月から加速したほか、市場予想も大幅に上回った。これを受けて、米雇用情勢の回復ペースに期待が広がり、円売り・ドル買いの流れが一時強まった。ただ、急ピッチでの円安進行に警戒感も広がり、円相場は108円前半で下げ渋っている。 ユーロは同時刻現在、対ドルで1ユーロ=1.1930~1940ドル(前日午後5時は1.1967~1977ドル)、対円では同129円15~25銭(同129円22~32銭)と、07銭の円高・ユーロ安。(了)〔米株式〕NYダウ、ナスダックとも反発(5日朝)時事通信 【ニューヨーク時事】週末5日のニューヨーク株式相場は、予想を上回る改善となった米雇用統計を好感し、反発して始まった。優良株で構成するダウ工業株30種平均は午前9時35分現在、前日終値比323.34ドル高の3万1247.48ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は78.99ポイント高の1万2802.46。(了)今夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中の12銘柄が値を上げてスタートしましたね。スタートの時点では5%以上の大きな変動は見られませんね。
2021.03.05
コメント(4)
-

3月4日(木)…
3月4日(木)、晴れです。晴れ時々曇り時々雨ですかね…。暖かいです。そんな本日は6時50分頃に起床。新聞に目を通し、朝食を済ませ、ロマネちゃんと戯れる。身支度をして、8時頃に家を出る。ゴルフではありません、アルバイト業務です。本日は8:45~16:00とのこと。後半は大変に効率的に事が進み予定より早くに終了。帰り道にいつものゴルフショップでゴルフボールとティーペグを補給。さらに帰り道のいつものGSで愛車に燃料補給してタイヤの空気圧調整を済ませる。帰宅すると名古屋へ出かけていた奥も帰宅していてお土産は…「ハーブス」のケーキでした。コーヒーと共に少し遅いおやつタイム。相変わらずのサイズでお腹が膨れてしまいました…。1USドル=107.12円。1AUドル=83.61円。昨夜のNYダウ終値=31270.09(-121.43)ドル。本日の日経平均終値=28930.11(-628.99)円。金相場:1g=6548(-74)円。プラチナ相場:1g=4477(-138)円。昨夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中のすべてが値を下げて終了しましたね。エッツィを筆頭にトゥイリオ、テラドック、スクエア、ペイパル、ショッピファイ、ドキュサインと大きく下げていますね。本日の東京市場ではチェック中の日本株30銘柄中の7銘柄が値を上げて終了しましたね。重点6銘柄では2銘柄が値を上げて終了しましたね。5%以上の大きな変動は見られませんね。日本株は大幅反落、米金利高や米株先物安を警戒-内外需売り (訂正) 4日の東京株式相場は大幅反落し、日経平均株価は終値で2万9000円を割り込んだ。米国の長期金利上昇や米株先物安からリスク回避の動きが強まり、電機や精密機器、情報・通信、医薬品など内外需ともに売られた。 TOPIXの終値は前日比19.80ポイント(1%)安の1884.74 日経平均株価は628円99銭(2.1%)安の2万8930円11銭 2万9000円割れは2月26日以来 〈きょうのポイント〉 米国株はテクノロジー中心に売り-米10年債利回りは1.48%と9ベーシスポイント(1bp=0.01%)上昇 アジア時間4日の米株先物は軟調推移 米地区連銀経済報告:企業は楽観的な見方維持、ワクチン普及で 首都圏4都県の緊急事態宣言、2週間程度延長が必要-菅首相 プリンシパル・グローバル・インベスターズの板垣均社長は「これからインフレ指標は前年比で高めに出てくる」として、「金利上昇シナリオが早くきたことで市場は過剰流動性が揺らぐことを恐れてパニック売りになっている」と述べた。 金利上昇が嫌気されて昨日続落した米国株は、アジア時間4日も下げ止まりの気配がみえず、日経平均の下げ幅は午後に800円を超え、先週2月26日安値2万8966円を下回った。セゾン投信運用部の瀬下哲雄運用部長は「インフレにはならず中央銀行もずっと低金利を持続するという話が怪しくなり、中央銀行が本当にコントロールできるのかという話になってきている」として、株価が下げ止まる要因が見当たらないと言う。 米国時間4日は、パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長が米国経済についてオンラインイベントで講演するほか、週末には雇用統計も控える。三菱UFJモルガン・スタンレー証券の藤戸則弘チーフ投資ストラテジストは、「市場は週末の雇用統計の結果が良好なら米長期金利が1.5%超となるリスクを見始めている」と言う。 もっとも、取引終盤にかけて銀行や不動産は持ち直して指数は底堅さもみせ、TOPIXは先週26日安値を維持した。プリンシパルの板垣氏は株価下落が大きくなったことについて、「ワクチンなどで新型コロナに関して楽観を先読みして上げ過ぎたための調整。景気は前年比で加速するところにあり、あわてて売る場面ではない」と話していた。 東証33業種では非鉄金属や情報・通信、精密機器、電機、医薬品、サービス、機械が下落 海運や不動産、銀行、石油・石炭製品は上昇孫氏の個人資産、1年足らずで4倍超-ソフトバンクGの株価上昇で 孫正義氏ほど、個人資産の額が大きく浮き沈みする人はあまりいないだろう。 ソフトバンクグループの創業者である孫氏は今世紀初め、ハイテク株が急落する前には個人資産額でビル・ゲイツ氏を上回ったこともある。2020年3月には、新型コロナウイルスの感染拡大が株式市場を直撃し、ソフトバンクGの投資戦略にも疑問が渦巻く中、孫氏の資産は16年以降で最も少ない84億ドル(現在の為替レートで約9000億円)に落ち込んだ。 ブルームバーグ・ビリオネア指数によると、それから1年足らずで同氏の資産は4倍超の380億ドルに増えた。同指数の集計が12年に始まって以降で最高だ。 資産額の急増は、同氏の純資産の95%余りを占めるソフトバンクGの株価上昇と密接に結びついたものだ。同社株も昨年3月の安値からほぼ4倍に上昇している。同社は資産売却や自社株買いを実施し、シェアオフィス事業を展開する米ウィーワークから起こされていた裁判では和解に至った。20年10-12月期(第3四半期)決算はビジョン・ファンドが四半期ベースで過去最大の利益を計上した。 また、ポール・シンガー氏率いるヘッジファンド運営会社のエリオット・マネジメントが昨年、株価が過小評価されているとの理由でソフトバンクG株の取得を明らかにするなど、同社に対する支持も集まっている。 グレート・ヒル・キャピタルのトーマス・ヘイズ会長は「ソフトバンクの現在の主要資産は巨額のキャッシュフローがあり、今後も成長が見込まれる」と指摘。「勝ち組の収穫と適切なタイミングでの自社株買いをバランス良く行えば、たとえハイテク株が減速したとしても、2000年の繰り返しは避けられるだろう」と述べた。 一方、ソフトバンクGと孫氏の命運は深く絡み合っているだけに、最近ではコーポレートガバナンス(企業統治)上の問題も指摘されている。 当局への届け出によると、2月9日時点で孫氏は保有するソフトバンクG株式の約3の1を計16余りの金融機関に担保提供していた。昨年9月時点の38%からは減少したが、まだ約180億ドルに相当する。 ソフトバンクGの担当者はこの記事へのコメントを控えた。 ソフトバンクGにはトラブルも少なくない。事情に詳しい複数の関係者によると、ビジョン・ファンドは金融ベンチャーのグリーンシル・キャピタルへの投資15億ドル(約1600億円)について、評価額を大幅に引き下げた。最終的には評価額をほぼゼロにすることを検討しているという。株式から債券へのシフト招く転換点は米10年債利回り1.75%-BofA 債券市場のストレスの高まりはいつ、株式投資家にとって問題になるのだろうか。バンク・オブ・アメリカ(BofA)によれば、それは米10年国債利回りが1.75%に達した時だ。 債券利回りが過去最低水準近くで推移していたため多くの資産配分担当者は株式への投資を余儀なくされていたが、米10年債利回りがこの水準を突破すれば伝統的な債券に戻る可能性が高いと、サビタ・スブラマニアン氏率いるBofAのストラテジストが指摘した。この水準が「資産配分担当者が債券への回帰を始める転換点」になることを歴史が示唆しているという。 米10年国債利回りは先週に一時、S&P500種株価指数の配当利回りを上回り、BofAは「株式に代わる選択肢はある」と論じた。 この言葉は、ここ数年間に米国債利回りが過去最低水準に低下し、インフレが抑制される中で広がったスローガン「TINA」(there is no alternativeの略で、株式に「代わる選択肢はない」の意味)の逆だ。TINAは、高リスク資産へのシフトや、S&P500種の高いバリュエーションを正当化する助けになった。 ただ、1.75%の水準は見かけよりも遠い可能性がある。ロイトホルト・グループの主任投資ストラテジスト、ジム・ポールセン氏は、米国債利回りがさらに上昇する前に、1.5%前後で一時停止する可能性があると指摘。同氏は理由の一つに最近の寒波を挙げ、この結果として小売売上高が減速するなど、今後1カ月の経済指標が弱含む可能性があると説明。これによって景気過熱を巡る懸念が和らぐとの見方を示した。 「利回りは今年まだ上昇する余地があるが、その場合も一度に上昇するのではなくゆっくり断続的な動きとなり、経済と株式市場への悪影響ははるかに小さいだろう」と述べた。【本日のNYダウ見通し】パウエルFRB議長の講演に注目【NYダウ予想レンジ:31,000~31,400ドル】3日のNYダウは続落し、前日比121.43ドル安の31,270.09ドルで取引を終了しました。バイデン大統領が5月末までに成人全員分の新型コロナワクチンを確保できると表明したことで、経済正常化への期待が高まり、景気敏感株は上昇。しかし、米10年債利回りが1.5%近くまで上昇すると、割高感が意識されやすいハイテク株に売りが出ました。ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は、361.04ポイント安の12,997.75と節目の13,000を割り込み、2カ月ぶりの安値となったのです。とくにコロナ禍で需要の恩恵が高かった銘柄が売られました。動画配信のネットフリックスは4.95%安の520.70ドル、ビデオ会議のズーム・ビデオ・コミュニケーションズは12.1%安の298ドル、ネット通販のアマゾン・ドット・コムは2.89%安の3,005ドルで取引を終了しています。本日はパウエルFRB議長の講演があるので、マーケットの関心が集まるでしょう。ただ、明日に雇用統計を控えているので、積極的な買いは見込みづらい状況です。NYダウは節目の31,000ドル台をキープできるかどうかに注目しています。日経平均は大幅反落、628円安で2万9000円割り込む 値がさ株軟調[東京 4日 ロイター] -東京株式市場で日経平均は大幅反落した。前日の米国株式市場では米長期金利の上昇に伴う割高感からハイテク株が軟調に推移。東京株式市場でもその流れを引き継ぎ、日経平均は4営業日ぶりに2万9000円を下回り、終値ベースで2月5日以来の安値となった。個別では、ファーストリテイリング、ソフトバンクグループがともに5%超安となり、日経平均を約326円押し下げる要因となった。日経平均は前営業日比360円安で寄り付いた後も下げ幅を拡大し、後場では848円06銭安の2万8711円04銭で安値を付けた。米10年債利回りが1.47%にやや上昇したことを受け、主力銘柄を中心に売りが先行した。TOPIXも反落し1.04%安。日経平均をTOPIXで割ったNT倍率は15.35倍となり、2月15日以来の低水準まで調整した。 東証一部の売買代金は2兆7612億6500万円。東証33業種中、非鉄金属、情報・通信業、その他製品、空運業などの26業種は値下がり。半面、海運業、不動産業、銀行業などの7業種は値下がりとなった。個別では指数寄与度の高いファーストリテイリング、ソフトバンクグループが5%超安となったほか、東京エレクトロン、ファナック、エムスリー、アドバンテストなどのハイテク株が総じて軟調。SBI証券の投資調査部長、鈴木英之氏は米長期金利の急激な上昇が利益確定売りを促したと指摘する。「米長期金利の上昇は必ずしも日本株にとって悪い材料ではない。金利上昇の背景には、経済正常化があるのは確か。現局面は金融相場から業績相場に移行する端境期にあると言える。金利上昇が一時的なものと確認できれば、株式相場は落ち着きを取り戻すだろう」とみている。東証1部の騰落数は、値上がり787銘柄に対し、値下がりが1295銘柄、変わらずが112銘柄だった。米株続落、ハイテク株への売りでナスダック大幅安[3日 ロイター] - 米国株式市場は続落し、ナスダック総合が大幅安で取引を終えた。財政出動や新型コロナウイルスワクチンの接種進展への期待から、ハイテク株を売って景気回復の恩恵を受けやすいセクターにシフトする動きが広がった。マイクロソフト、アップル、アマゾン・ドット・コムが2%超下落し、S&P総合500種の重しとなった。S&P500の金融、工業指数は取引時間中の最高値を更新したが、他のセクターは大半が下落した。ワクチン配布が景気回復を支援すると予想されているものの、オートマチック・データ・プロセッシング(ADP)とムーディーズ・アナリティクスがこの日発表した2月の全米雇用報告は、民間部門雇用者数の伸びが予想を下回った。米供給管理協会(ISM)が発表した2月の非製造業総合指数(NMI)も前月から低下し、市場予想を下回った。米10年債利回りは1.47%にやや上昇し、割高感の出ているセクターの重しとなった。10年債利回りは前週に付けた約1.61%の水準は下回っている。金利上昇は高成長ハイテク株への影響が特に大きい。投資家はこれらの企業の価値を将来見込まれる利益に基づいて評価するが、金利が上昇すると将来の利益の価値が短期的な利益の価値より大きな打撃を受けるためだ。BMOウェルス・マネジメントの最高投資責任者マイケル・ストリッチ氏は「利回りが1.5%の水準を超えれば、間違いなく株式に逆風となる。大半の投資家は利回り上昇のペースを注視している」と述べた。バイデン米大統領は1兆9000億ドル規模の新型コロナ追加経済対策法案の上院通過に向け、中道派の民主党上院議員に譲歩し、1人当たり1400ドルの個人向け一時金の受給資格を厳格化することに同意した。個別銘柄ではエクソンモービルが0.8%高。支出を削減し、配当を増やす計画を明らかにした。ニューヨーク証券取引所では値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を1.31対1の比率で上回った。ナスダックでも1.95対1で値下がり銘柄数が多かった。米取引所の合算出来高は140億株。直近20営業日の平均は149億株。NY外為市場=ドル上昇、成長格差に注目 円安進み107円前半[ニューヨーク 3日 ロイター] -終盤のニューヨーク外為市場ではドルが上昇。米経済の底堅い成長を織り込む動きとなった。一方、円は一時107円台前半に値下がりした。ウエスタンユニオン・ビジネスソリューションのシニア市場アナリスト、ジョー・マニンボ氏は「米経済の回復と低迷する欧州との成長格差に市場は注目している」と述べた。2月のユーロ圏の総合購買担当者景気指数(PMI)改定値は48.8と、好不況の分かれ目となる50を大きく下回った。新型コロナウイルスの流行で引き続きサービス業が打撃を受けており、ユーロ圏経済が二番底を付けるのはほぼ確実とみられている。こうした中、2月のADP全米雇用報告は、民間部門雇用者数の伸びが11万7000人と予想に届かなかった。ただ、前出のマニンボ氏は5日発表の雇用統計で底堅い内容が予想されると指摘。2月の雇用統計は、非農業部門雇用者数の伸びが18万人と、前月の4万9000人から拡大すると見込まれている。ドルは通貨バスケットに対し0.14%高の90.924。ユーロ/ドルは0.19%安の1.2068ドル。米国債利回りが上昇したこともドルを支えたとみられる。円相場は下落が継続し、対ドルで一時107.15円と、昨年7月23日以来の安値を付けた。シティのテクニカルアナリストは、4日に予定されるパウエル連邦準備理事会(FRB)議長の講演後に米国債利回りが低水準で安定すれば、円相場は強含む可能性があると指摘。106.11─106.22円もしくは105.33─105.44円を付けるかもしれないと予想した。豪ドルは0.4%安の0.7788ドル。先週は0.8007ドルと3年ぶり高値を付けていた。3日のナスダックが急落、2カ月ぶりの安値となったワケ4日以降の市場の注目点は何かブルームバーグ3日の米株式相場は続落。米国債のボラティリティーが再び高まって利回りが急上昇し、株価の圧迫要因となった。投資家の間では株式のバリュエーション伸長が懸念されている。銀行株やエネルギー関連銘柄は上昇したが、アップルやアマゾン・ドット・コムといった大手テクノロジー株が大きく下落。ハイテク株中心のナスダック100指数は2.9%下げ、2カ月ぶり安値となった。米経済指標では、新型コロナ禍で陥ったどん底からの回復は緩やかでまだら模様であることが示唆された。S&P500種株価指数は前日比1.3%安の3819.72。ダウ工業株30種平均は121.43ドル(0.4%)安の31270.09ドル。ナスダック総合指数は2.7%下げた。米国債相場は下落。英国債が大きく売られたことや社債の新規発行を多く控えていることなどが重しとなった。ただ、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長の講演を4日に控え、取引終盤にかけては安定を取り戻した。ニューヨーク時間午後4時59分現在、10年債利回りは9ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の1.48%。一時は1.5%に接近する場面もあった。債券相場が織り込む5年先のインフレ期待は2008年以来の高水準となっている。DAデービッドソンのウェルスマネジメント調査担当ディレクター、ジェームズ・ラガン氏は「ボラティリティーが若干高くなった。これまでも大幅に高まる日があれば、低下する日もあった」と指摘。「金利上昇と、それが一部の割高セクターのバリュエーションにどう影響しているかに引き続き注目が集まっている」と述べた。外国為替市場ではドルが主要10通貨の大半に対して上昇。米国債利回りの上昇が背景。リスク回避の動きで、資源国通貨が値下がりした。主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.3%高と、3営業日ぶりの上昇。ドルは対円で0.3%高の1ドル=107円01銭。一時は107円15銭と、昨年7月以来の高値を付けた。ユーロは対ドルで0.2%安の1ユーロ=1.2063ドル。ニューヨーク原油先物相場は4営業日ぶりに反発。約1週間ぶりの大幅高となった。米エネルギー情報局(EIA)の週間統計では、米南部を襲った寒波の影響で製油所の稼働停止が続いたのを受け、ガソリン在庫が1990年以来の大幅減少となった。一方、原油在庫は増加した。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物4月限は1.53ドル(2.6%)高の1バレル=61.28ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント5月限は1.37ドル高の64.07ドル。ニューヨーク金相場は反落。米国債利回りが上昇し、景気回復が意識される中、金の投資妙味が低下した。コメルツ銀行のアナリスト、カルシュテン・フリッチ氏は、利回り上昇とドル高が「このところの金相場には悪い組み合わせ」になっていると述べた。金スポットはニューヨーク時間午後2時27分現在、前日比1.4%安の1オンス=1713.74ドル。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物4月限は、1%安の1715.80ドルで終了。【市況】明日の株式相場に向けて=“気迷い相場”で迷わないために きょう(4日)の東京株式市場は再びリスクオフの大波に揉まれる展開となり、日経平均株価は628円安の2万8930円と急反落。米10年債利回りの動向に振り回される状況だが、そもそも利回りが1.4%台になったからリスク選好で株を買い、1.5%台に浮上したからリスク回避で株を売るというような単純なものではない。株式市場でも、今後1.5~2%くらいまでは許容するというムードが出てくると思われるが、いずれにしても長期金利に先高観が拭えないなか、当面ハイテクセクターには向かい風が強い。 今の全体相場の地合いをひとことで言えば「迷い」が生じている、ということだと思われる。株式市場という大きな枠のなかでどこにマネーを振り向けるかということは投資家サイドにとって重要なポイントだが、もう一つ重要なのはそのタイミング、いわゆる時間軸の概念である。いつも収穫に恵まれる季節ばかりではない。実る時に資金を投下するのは当然として、実らぬ時には資金を引かなければならない。新型コロナウイルスは人類にとってエイリアンにも等しい難敵であったが、これも人類の知を結集したワクチンの開発で収束の道筋が見えてきた。新型コロナがいったん収束したとしてもこれまでのような日常は戻らず、企業もウィズコロナ時代とどう向き合って経営を進めていくかということが課題として残される、と考えられていた。ところが現在のコンセンサスは、マーケット目線としては明らかにウィズコロナではなくアフターコロナ(コロナがない世界)に傾いている。 経済が正常化の方向たどり、依然と変わらない我々の日常が戻ってくることは誰もが望んでいる最高の景色のはずだが、株式市場は必ずしもそうではない。例えばここから先、資金を寝かせておいてよい時間がどのくらいあるのか、ということを慎重に計算しはじめたようなフシがある。全体指数の動きでいえば、2月19日以降きょうまでの9営業日、日経平均もTOPIXも日替わりで交互に上げ下げ(前日比プラスとマイナス)を繰り返してきたが、これは気迷い相場を象徴するものだ。また、上げ下げの繰り返しだけでなく、日々のボラティリティ(株価変動率)の高さが市場センチメントの不安定ぶりを映し出す。 これまでマーケットを支えてきた過剰流動性、マネーの絨毯(じゅうたん)が強力なセーフティーネットとなっていたが、これが取り除かれることへの恐怖がある。緊急事態宣言の発令に伴い飲食店へ一律支給された1日6万円の協力金が、受ける側によっては過剰支援となっている実態が報じられたが、株式市場にとっても世界の中央銀行の徹底的な金融緩和策、そして各国政府による掛け値なしの財政出動は、表現は悪いがコロナマネーによる“焼け太り”的な超金融相場の土壌を生んだ。今は現実問題として、アフターコロナ後の経済を見積もるには時期尚早だが、「景気は気から」と言われるように、人々の新型コロナに対する恐怖感が急速に薄まっていく時、そこが株式市場の上昇トレンドが勢いを失う時で、少なくとも数カ月の調整は覚悟しておく必要はあると思われる。 ただ、今月の中下旬にかけての調整は買い場である可能性が高い。市場筋からは「GPIFをはじめ国内の年金系資金による1兆円規模の利益確定売り需要が顕在化する。それが分かっているから、外国人も今は資金を待機させている」(ネット証券マーケットアナリスト)という指摘がある。週初の当欄で、3月の月間パフォーマンス(前月末比較)は過去10年間を振り返って日経平均・TOPIXともに勝率4割、しかし4月は勝率7割ということに触れたが、機関投資家の期末に向けた益出しによる下り坂で仕込み、4月新営業年度でのニューマネー流入で値上がりを期待するというのは単純だが分かりやすい考え方だ。 個別では、証券会社の目標株価引き上げなどもあって海運株が強い動きをみせている。大手海運以外で、原油市況上昇を追い風に共栄タンカーや含み資産が豊富な飯野海運などに注目。また、不動産株にも資金シフトの動きがみられる。バリュー株の素地が光るフジ住宅やテーオーシーの押し目買いに妙味がある。短期リバウンドを狙うのであれば、QDレーザに売り一巡感があり、振り子が戻ってくるタイミング。民生用網膜走査型レーザアイウェアでグローバルニッチトップの資質を持つ。 あすのスケジュールでは、2月上中旬の貿易統計が朝方取引開始前に財務省から発表される。海外では中国で全国人民代表大会(全人代)が開幕するほか、2月の米雇用統計に注目度が高い。このほか、1月の米貿易収支、1月の米消費者信用残高なども発表される。(銀)出所:MINKABU PRESS積水ハウス、今期経常は8%増益、前期配当を2円増額・今期は2円増配へ 積水ハウス が3月4日大引け後(15:45)に決算を発表。21年1月期の連結経常利益は前の期比13.7%減の1846億円になったが、22年1月期は前期比8.3%増の2000億円に伸びる見通しとなった。6期連続増収になる。 同時に、前期の年間配当を82円→84円(前の期は81円)に増額し、今期も前期比2円増の86円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比0.3%増の530億円となり、売上営業利益率は前年同期の7.4%→7.6%とほぼ横ばいだった。19歳・西郷真央が単独首位発進 渋野日向子は7打差20位<ダイキンオーキッドレディス 初日◇4日◇琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県)◇6561ヤード・パー72>国内女子ツアー2021年初戦の第1ラウンドが終了した。ジャンボ尾崎を師とする19歳・西郷真央が1イーグル・7バーディ・1ボギーの「64」をマーク。8アンダー・単独首位発進を決めた。5アンダー・2位タイにホステスプロの新垣比菜、山路晶、菊地絵理香、田辺ひかり、高橋彩華、宮里美香。4アンダー・8位タイに上田桃子、吉本ひかるら4人が続いた。大会初出場の渋野日向子は3バーディ・2ボギーの「71」。首位と7打差の1アンダー・20位タイで2日目を迎える。そのほか、連覇がかかる比嘉真美子は2アンダー・13位タイ発進。賞金ランキング1位の笹生優花は1オーバー・53位タイとやや出遅れた。宣言は解除されたけど…岐阜の病院クラスター収束せず、医師らの緊張続く読売新聞 新型コロナウイルス対策として10都府県に発令されていた緊急事態宣言が6府県(大阪、京都、兵庫、愛知、岐阜、福岡)で解除された。しかし、岐阜県では、美濃加茂市の木沢記念病院で発生しているクラスター(感染集団)が収束せず、医療関係者の緊張が続いている。 同病院では1日も医療従事者2人の感染が発表され、クラスターは228人に上る。内訳は医師や看護師など医療従事者を含む職員が95人、患者が94人、医療従事者や患者の家族らが39人。 最初に陽性が確認された2月2日以降、一気に感染者が判明し、県が院内や感染者の家族らの検査を続けている。一度、陰性となった職員や患者にも再検査を行うなど、これまでに約8400件検査してきた。 県や厚生労働省のクラスター対策班は感染者らへの聞き取り調査を行ってきたが、感染が広がった原因は判明していない。3病棟に感染が集中しているが、全11病棟から感染者が出ており、県の担当者は「医療従事者経由で複数の病棟に拡大した可能性がある」とみている。 美濃加茂市を含む中濃圏域は面積の割に病院が少ないとされ、地域医療への影響も大きい。同病院は救急の受け入れを停止したり、外来診療を予約のみとしたりしており、県病院協会は「圏域内はコロナ用の病床がいっぱいになり、ほかの圏域にも受け入れてもらわなければならないこともあった」と厳しい状況を明かした。 中京圏の緊急事態宣言解除が話題になり始めてからも、岐阜県の古田肇知事は同病院のクラスターを挙げ、「(感染の収束を)全て見届けるところまで行かないと安心できない」と、解除に慎重な姿勢を見せていた。 国が6府県の緊急事態宣言解除を決めた2月26日、古田知事は記者会見で「まだ収束というところまで行っていない。注意深くフォローしていく必要がある」と述べ、飲食店の時短営業を3月7日まで続けることなどを表明した。明日の戦略-大幅安で直近安値を下回る、チャート形状悪化で下振れを警戒トレーダーズ・ウェブ 4日の日経平均は大幅反落。終値は628円安の28930円。金利上昇への警戒からナスダックが大きく下落したことを嫌気して、300円超下げて始まった。3万円が遠のいたことでその後も売りが続き、前場のうちに下げ幅を500円超に広げた。後場に入ってもしばらくは下値を試す流れとなり、安いところでは800円超下げる場面もあった。13時以降は持ち直す動きが見られたものの、戻りは限られ、終値で29000円を下回った。 東証1部の売買代金は概算で2兆7600億円。業種別では海運や不動産、銀行などが上昇している一方、非鉄金属や情報・通信、その他製品などが下落した。主力株を手掛けづらい地合いの中で、直近IPOの室町ケミカルが商いを集めて20%超の上昇。半面、ファーストリテイリングが後場に入って下げ足を強めて5%を超える下落。終値で10万円を下回った。 東証1部の騰落銘柄数は値上がり787/値下がり1295。リコーが大規模な自己株取得と消却を発表し、場中は値が付かずストップ高比例配分。日経新聞で容量が世界最大級の全個体電池を開発したと報じられた日立造船がストップ高と、好材料のあった銘柄には資金が殺到した。証券会社のリポートなどを材料に海運株が強く、日本郵船、商船三井、川崎汽船の大手3社がそろって大きく上昇した。米長期金利上昇を受けて、九州FGや西日本FGなど銀行株が買われており、新生銀行は5%近い上昇。上期の見通しを引き上げたナトコが急伸した。 一方、金利上昇でグロース株が売られる中、ソフトバンクGが5%を超える下落。任天堂やソニー、日本電産、エムスリーなど、グロースの代表格的銘柄が大幅安となった。BASEやメルカリなどマザーズの主力銘柄も軟調。住友鉱山や三井金属など、非鉄株の一角にも非常に弱い動きが見られた。前日に大きく上昇したJALやANAは利益確定売りに押されて下落。ファイナンスが嫌われたアルファクスフードが急落した。 日経平均は大幅安。安値は28711円まであり、2月26日の安値28966円を下回った。終値(28930円)では25日線(29292円、4日時点、以下同じ)も明確に割り込んでおり、テクニカル面からは一段の下振れも懸念される。週末の米雇用統計が反転材料になるとの期待も出てくるが、あすに関しては、まだ売りが止まらないかもしれない。とは言え、週足で見ればチャートは大きく崩れてはいない。今週は週初に大きく上昇しており、週間ではきょう時点でわずか36円の下落にとどまる。下には13週線(28206円)が控えており、この手前の28500円辺りまで下げるようなら、短期勝負での突っ込み買いにも妙味がある。夕方になるといろいろなものが配達されてきました…BALDO-CORSAの7W(21)とUT(27)です。さらに…UT用のATTAS MB-HY 55Sです。おいおいと組み立てていきましょう。明日の日本株の読み筋=手控えムードが広がりそう、金曜日は3週連続で下落モーニングスター 5日の東京株式市場は、手控えムードが広がりそうだ。2月に入り金曜日は、5日に上昇した後は3週連続で下落している。特に先週の2月26日は、今年最大の下げとなっていることもあり、積極的な売買にはつながりづらいとみられる。市場では、「日経平均株価は、今年の高値(3万714円52銭)から、1割程度の調整があっても健全な調整の範囲」(中堅証券)との声が聞かれた。また、「個人投資家は、森(市場全体)ではなく木(個別株)で、材料や業績の裏付けのある銘柄に物色が向かいそう」(他の中堅証券)との見方があった。 4日の日経平均株価は、前日比628円11銭安の2万8930円11銭と大幅に反落。下げ幅は2月26日(1202円26銭安)に次ぎ今年2番目の大きさとなった。東京証券取引所が4日引け後に発表した、2月第4週(2月22-26日)の2市場1・2部等の投資部門別売買状況によると、海外投資家は3811億円の売り越しで、2週連続で売り越しとなっている。病院クラスターで2人の感染確認 岐阜県内で5人が新型コロナ感染岐阜新聞Web 岐阜県と岐阜市は4日、県内で新たに5人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の累計感染者数は4648人となった。 クラスター(感染者集団)では東濃厚生病院(瑞浪市)関連で、感染が分かっている患者の知人男性1人に感染が新たに判明。同病院から転院した患者が感染していた高井病院(土岐市)で、感染が確認されている医療従事者の家族の30代男性に広がり、合わせて規模は24人となった。 岐阜清流病院(岐阜市)と、外食した同市の高校生を中心に広がったクラスターはいずれも終息が確認された。 人工呼吸器を装着している重症患者は前日から1人増え、8人となった。 新規感染者の居住地別は岐阜市、大垣市、瑞浪市、中津川市、羽島郡笠松町が各1人。年代別は30代3人、60代、70代が各1人。本日の夕食はM坂屋の地下の「ディーン&デルーカ」で調達されたアンガス牛の赤身ローストをメインに赤ワインに合うセットでした。一緒に楽しんだのは…2009ローザン・セグラでした。良い香りです。さすがシャネル。今晩のNY株の読み筋=パウエルFRB議長の講演に注目モーニングスター 4日の米国株式市場は、パウエルFRB(米連邦準備制度理事会)議長の講演が注目となる。16-17日にFOMC(米連邦公開市場委員会)を控え、まもなく「ブラックアウト」期間に入ることから、きょうの講演にも注目が集まっている。直近では雇用関連の経済指標に弱いものが目立っており、市場心理がやや冷え込むなかでは上値の重さが意識されそうだが、パウエルFRB議長が講演でハト派的なスタンスを維持すれば米長期金利の上昇圧力も弱まり、足元で軟調なハイテク株などへの買い戻しが期待できそうだ。<主な米経済指標・イベント>米新規失業保険申請件数、米10-12月期労働生産性指数、米1月製造業受注、パウエルFRB(米連邦準備制度理事会)議長が講演◎投資関連情報は投資の参考として情報提供のみを目的としたものであり、株式の売買は自己責任に基づき、ご自身で判断をお願いします。NY株見通し-パウエルFRB議長発言に注目トレーダーズ・ウェブ 今晩のNY市場はパウエルFRB議長発言に注目。昨日は長期金利が再び上昇したことで、ハイテク株主体のナスダック総合が2.70%安と大幅に下落し、S&P500とダウ平均もそれぞれ1.31%安、0.39%安となった。先週一時、1.61%台まで上昇した米10年債利回りは週初に1.40%前後まで低下したが、昨日は1.49%まで上昇した。市場ではFRBがコントロールを失っているとの警戒感も強まっており、長期金利の動向が引き続き焦点となりそうだ。今晩はパウエルFRB議長の会議での発言が予定されており、足もとの金利上昇に対する議長の発言を注視したい。 今晩の米経済指標・イベントはパウエルFRB議長発言のほか、新規失業保険申請件数、1月製造業新規受注など。企業決算は寄り前にクローガー、引け後に ブロードコム、コストコ、ギャップが発表予定。(執筆:3月4日、14:00)〔NY外為〕円、107円台前半(4日午前8時)時事通信 【ニューヨーク時事】4日のニューヨーク外国為替市場の円相場は、午前8時現在1ドル=107円34~44銭と前日午後5時(106円96銭~107円06銭)比38銭の円安・ドル高で推移している。 ユーロは同時刻現在、対ドルで1ユーロ=1.2027~2037ドル(前日午後5時は1.2057~2067ドル)、対円では同129円17~27銭(同129円00~10銭)。(了)〔NY外為〕円、107円台半ば(4日朝)時事通信 【ニューヨーク時事】4日午前のニューヨーク外国為替市場では、海外市場での円売り・ドル買いの流れを引き継ぎ、円相場は1ドル=107円台半ばに下落している。午前9時現在は107円40~50銭と、前日午後5時(106円96銭~107円06銭)比44銭の円安・ドル高。 ニューヨーク市場は、107円39銭で取引を開始した。米追加経済対策や新型コロナウイルスワクチンの普及などで早期に景気が回復するとの期待が広がる中、米長期金利は上昇基調を維持。日米金利差拡大をめぐる思惑もあり、円売り・ドル買いの流れが続いている。 パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長が参加する討論会を午後に控え、最近の長期金利の変動についての発言が注目されている。 一方、米労働省が朝方発表した最新週の新規失業保険申請件数は前週比9000件増の74万5000件と、3週ぶりに悪化したが、市場への影響は限定的だった。 ユーロは同時刻現在、対ドルで1ユーロ=1.2030~2040ドル(前日午後5時は1.2057~2067ドル)、対円では同129円30~40銭(同129円00~10銭)と、30銭の円安・ユーロ高。(了)今夜のNY市場ではチェック中の米国株20名画中の9銘柄が値を上げてスタートしましたね。5%以上の大きな変動は見られませんね。〔米株式〕NYダウ、ナスダックとも反発(4日朝)時事通信 【ニューヨーク時事】4日のニューヨーク株式相場は、パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長のこの日の会合での発言に関心が向かう中、反発して始まった。優良株で構成するダウ工業株30種平均は午前9時35分現在、前日終値比148.23ドル高の3万1418.32ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は69.11ポイント高の1万3066.86。(了)
2021.03.04
コメント(0)
-

3月3日(水)…2021ラウンド15…
3月3日(水)、晴れです。ひな祭りですね。そんな本日はホーム1:GSCCの東コースで開催の水曜杯に参加させていただきました。9時40分スタートとのことですから6時50分頃に起床。新聞に目を通し、朝食を済ませ、ロマネちゃんと戯れる。身支度をして、8時10分頃に家を出る。8時40分頃にはコースに到着。フロントで記帳して、研修競技の競技内コンペでの賞品をいただいて、先々の水曜杯のエントリーを済ませて、着替えて、練習場へ…。ショット…イマイチ…、パット…イマイチ…。グリーンがエアレーションの穴だらけ…。これ、ダメなんですね…。本日の競技は東コースのホワイトティー:6512ヤードです。ご一緒するのはいつものモ君(14)、オ君(17)、ツ君(23)です。本日の僕のハンディは(10)とのこと。OUT:0.0.2.2.0.1.1.3.0=45(19パット)1パット:0回、3パット:0回、パーオン:4回。1打目のミスが2回、2打目のミスが4回、3打目のミスが1回、アプローチのミスが1回、パットのミスが4回…。全くパットが決まりません…。このグリーンでは僕は戦えません…。10番のスタートハウスでドーピング…。IN:-1.1.4.0.1.1.1.0.1=44(18パット)1パット:1回、3パット:1回、パーオン:3回。1打目のミスが2回(OBあり)、2打目のミスが3回、バンカーのミスが1回、アプローチのミスが2回、パットのミスが3回…。お話になりませんね…。45・44=89(9)=80の37パット…。いいとこなしのゴルフでした…。握りも完敗…。カートからスコアの登録を済ませて、握りの清算をして、靴を磨いて、お風呂に入って、会計を済ませて、早々に退散です。MSAに遭遇したことが救いか…。本日のフィジカルチェック…170.0cm,63.8kg,体脂肪率20.7%, BMI22.1,肥満度+0.3%…でした。帰宅すると15時00分頃。奥も岐阜からほぼ同時に帰宅。御座候とコーヒーでおやつタイム。それではしばらく休憩です。ゴルフ場の玄関にロールスが停めてありました。以前には2ドアのレイスが停めてありましたね…。ひな祭りということでちらし寿司をいただく。1USドル=106.81円。1AUドル=83.63円。昨夜のNYダウ終値=31391.52(-143.99)ドル。本日の日経平均終値=29559.10(+150.93)円。金相場:1g=6622(+42)円。プラチナ相場:1g=4615(+25)円。昨夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中の2銘柄が値を上げて終了しましたね。スクエアが上げて、トゥイリオが大きく下げましたね。本日の東京市場ではチェック中の日本株30銘柄中の19銘柄が値を上げて終了しましたね。重点6銘柄ではすべてが値を上げて終了しましたね。ひらまつ、JFEが大きく上げて、Jフロント、東海カーボン、日本コンクリートも上げましたね。日本株反発、米景気回復期待で内外需広く上げ-緊急事態関連報道も 3日の東京株式相場は反発。米国の追加経済対策やワクチン早期普及への期待、銅など市況高を好感し、自動車や商社、非鉄金属、海運など海外景気敏感業種が広く買われた。 TOPIXの終値は前日比9.69ポイント(0.5%)高の1904.54 日経平均株価は150円93銭(0.5%)高の2万9559円10銭 〈きょうのポイント〉 2日の米10年債利回りは1.39%と安定、米ナスダック総合指数1.7%安 米上院、早ければ3日に経済対策について審議へ-シューマー院内総務 米メルクがJ&Jの新型コロナワクチン生産を支援-バイデン大統領 緊急事態宣言「2週間延長」検討、政府が4日までに方針判断-報道 ニッセイアセットマネジメント運用企画部の松波俊哉チーフ・アナリストは「米金利上昇には短期達成感が出ており、株価急落局面はいったん終了した可能性がある」と指摘。その上で、ワクチン普及や米景気対策も後押しして「今年は世界経済は同時回復が見込まれ、バリュー中心に景気敏感の日本株が買われやすい」と述べた。 きのうの米国株市場でテクノロジーなど成長株が売られた流れが重しとなり、午前は株価指数の方向感が乏しい場面もあった。経済正常化期待からアジア時間3日の米先物が強含むとともに、割安業種や景気敏感業種の買いの勢いが次第に強まった。いちよしアセットマネジメントの秋野充成執行役員は「米景気対策は現在議論されているものだけでは終わらないだろう」とし、バリュー人気は長くなりそうと予想した。 一方、政府は1都3県に発令されている新型コロナの緊急事態宣言の期限を2週間延長することを視野に検討に入り、4日までの感染状況を見極めて判断するとFNNが政府関係者の話を基に報じた。三井住友DSアセットマネジメントの市川雅浩チーフマーケットストラテジストは宣言の長期化について、「ワクチンの接種も広がりそうで、今のところそんなに懸念は強まっていない」とみており、きょうの株式市場への影響は限定的だった。 東証33業種では鉄鋼や非鉄金属、海運、輸送用機器、卸売が上昇 電機やその他製品、サービスは下落【本日のNYダウ見通し】ADP雇用者数とISM非製造業景況指数に注目【NYダウ予想レンジ:31,200~31,700ドル】2日のNYダウは反落。前日比143.99ドル安の31,391.52ドルで取引を終了しました。前日に603ドル高と約4カ月ぶりの上げ幅だっただけに、利益確定売りが優勢になりました。テスラやアップル、アマゾン・ドット・コムなどハイテク銘柄も上値が重く、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数も、230.04ポイント安の13,358.79で取引を終了しています。ただ、来週にも追加経済対策が成立する見通しや、新型コロナワクチンの普及による経済正常化期待によって、プラス圏で推移する時間帯もありました。本日の経済指標では、ADP雇用者数とISM非製造業景況指数に注目。13時時点のNYダウ先物は105ドル高となっており、本日は反発スタートが見込まれます。ただ、NYダウは下値では押し目買いが入るものの、高値警戒感から利益確定もでやすいので、方向感がでにくい展開です。また明日のパウエルFRB議長の講演や5日の雇用統計を控えているので、様子見ムードが高まるでしょう。日経平均は反発、景気敏感株中心に底堅い動き[東京 3日 ロイター] -東京株式市場で日経平均は反発。相場環境に不透明感が残りながらも、ワクチン接種による経済正常化の期待から、景気敏感株を中心に底堅い動きとなった。為替相場が円安基調にあることも好感されている。上海市場などアジア株や、時間外取引で米株先物が堅調に推移したことも支援材料になった。2日の米国株式市場は反落して取引を終了。アップルやテスラの下げが重しとなったが、追加経済対策成立への期待から、素材株には買いが入ったという。これを受けて、日本株も素材など景気敏感株を中心に物色され、日経平均、TOPIXはともに堅調に推移した。とりわけ目新しい材料はないながらも、経済正常化への期待から押し目買い意欲が強い。また、為替市場でドル/円が106円台後半と円安に振れていることも、買い安心感を生じさせている。市場では「直近の法人企業統計で、国内の設備投資が低調だったために、景気敏感株に目を向ける場合、中国の経済状況が判断材料になる。きょうの上海市場などアジア株の上昇もプラス材料になった」(岡地証券・投資情報室長の森裕恭氏)との声が聞かれた。TOPIXは0.51%高。東証1部の売買代金は、2兆4664億3800万円となった。東証33業種では、鉄鋼、非鉄金属、空運業などが上昇し、値下がりは電気機器など3業種にとどまった。個別では、神戸製鋼所が昨年来高値を更新したほか、東洋エンジニアリングが大幅上昇。ソフトバンクグループが堅調に推移した。半面、東京エレクトロン、任天堂などがさえない。東証1部の騰落数は、値上がり1338銘柄に対し、値下がりが776銘柄、変わらずが80銘柄だった。3日の日経平均株価は反発、米景気回復期待で内外需広く上げ長期債は上昇、円相場には売り圧力ブルームバーグ 東京株式相場は反発。米国の追加経済対策やワクチン早期普及への期待、銅など市況高を好感し、自動車や商社、非鉄金属、海運など海外景気敏感業種が広く買われた。 ニッセイアセットマネジメント運用企画部の松波俊哉チーフ・アナリストは「米金利上昇には短期達成感が出ており、株価急落局面はいったん終了した可能性がある」と指摘。その上で、ワクチン普及や米景気対策も後押しして「今年は世界経済は同時回復が見込まれ、バリュー中心に景気敏感の日本株が買われやすい」と述べた。 東証33業種では鉄鋼や非鉄金属、海運、輸送用機器、卸売が上昇電機やその他製品、サービスは下落超長期債が大幅上昇債券相場は超長期債が大幅上昇。ブレイナード米連邦準備制度理事会(FRB)理事が米長期金利上昇をけん制したことを受けて買い安心感が広がった。日本銀行が18、19日の金融政策決定会合で行う政策点検で、超長期金利のスティープ(傾斜)化策の導入を見送るとの観測も買いを誘った。 三井住友DSアセットマネジメントの深代潤上席参与のコメント: 内外の中央銀行関係者から長期金利上昇をけん制するメッセージが発せされたことが買い安心感につながっている特にブレイナードFRB理事の発言を受けて米長期金利が落ち着いたことが大きい日銀はプラスマイナス0.2%の変動幅を重視しているという週初の報道を受けて、政策点検では何もないだろうとの観測もドル・円は106円台後半、円売り圧力東京外国為替市場のドル・円相場は1ドル=106円台後半で推移。米長期金利の落ち着きや堅調な株価を背景にリスク選好に伴う円売り圧力がやや優勢となった。 みずほ証券の鈴木健吾チーフFXストラテジストのコメント:・株がしっかりしているのでクロス円(ドル以外の通貨の対円相場)がしっかり。あすにパウエル米連邦準備制度理事会(FRB)の発言を控えて、米長期金利は急騰する感じもないが、下げ渋ってもいる中でドル・円も小じっかり・ドル・円のトレンドは上方向。ただ、直近の急上昇などを考えると、107円台は投機筋の利食いや実需の売りがいったんは出やすいだろう2日の米国株は反落、過度な楽観警戒、テクノロジー銘柄軟調原油続落の一方で金相場は反発ブルームバーグ 2日の米株式相場は反落。前日はS&P500種株価指数が約9カ月ぶりの大幅高を記録しており、投資家は過度に楽観に傾いているとの見方が広がった。米国債は最近の利回り急上昇と比べると、総じて安定した動きとなった。 ニューヨーク時間午後4時過ぎの暫定値では、S&P500種が0.8%安の3870.29。ダウ工業株30種平均が143.99ドル(0.5%)安の31391.52ドル。ナスダック総合指数は1.7%下げた。米国債では10年債利回りが1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下し、1.41%。 S&P500種の構成銘柄では、特にテクノロジー株の下げが目立った。アップルやテスラが売られ、ナスダック100指数を押し下げた。テスラは終値で4%超の下落。利益率の見通しがアナリスト予想を下回ったディスカウントチェーンのターゲットも安い。 バンク・オブ・アメリカ(BofA)の強気指標は現在、歴史的に見て株価に弱気材料となる水準付近にある。同行のチームは1日のリポートで、売りシグナルの引き金となる水準に極めて近いと指摘した。中国銀行保険監督管理委員会(銀保監会)の郭樹清主席は2日、高値圏にある世界の金融相場など多くのリスクに懸念を示した。 ドル相場は下落 外国為替市場ではドルが主要10通貨全てに対して下落。前日に続いて資源国通貨が買われ、ノルウェー・クローネやオーストラリア・ドルの上昇が目立った。 主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.3%低下。一時は0.4%上昇し、2月5日以来の高値に達した。ドルは対円ではほぼ変わらずの1ドル=106円74銭。一時は106円96銭と、昨年8月以来の高値をつける場面もあった。ユーロは対ドルで0.3%高の1ユーロ=1.2089ドル。 ニューヨーク原油先物相場は続落し、バレル当たり60ドルを割り込んだ。石油輸出国機構(OPEC)と非加盟の主要産油国で構成する「OPECプラス」は今週開く会合で、減産縮小で合意するとみられている。事情に詳しい複数の関係者によれば、市場は供給増加を吸収できるとの見方が参加国の間で広がっている。 ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物4月限は89セント(1.5%)安の1バレル=59.75ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント5月限は99セント安の62.70ドル。 ニューヨーク金相場は反発。金スポットはニューヨーク時間午後3時35分現在、前日比0.6%高の1オンス=1736.03ドル。一時は8カ月ぶり安値を付ける場面もあった。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物4月限は、0.6%高の1733.60ドルで終了。 金を裏付けとする上場投資信託(ETF)からの資金引き揚げは加速し、保有高は昨年7月以来の低水準となっている。【市況】明日の株式相場に向けて=最高峰に臨むソフトバンクG きょう(3日)の東京株式市場は、日経平均株価が150円高の2万9559円と反発。前日の米国株市場でNYダウが引け際に崩れて140ドルあまりの下落となり、ハイテク株比率の高いナスダック総合指数については230ポイント安と下げがきつかった。こうなると、きょうの日経平均も続落歩調やむなしで、せっかく週初に見せた切り返しが霞んでしまう展開になるかと思われたが、売り物をこなしプラス圏で推移する粘り腰をみせた。 日経平均寄与度の高いソフトバンクグループが頑強な値動きを示したことが大きかった。200円程度の上昇で日経平均押し上げ効果という点では大したことがなかったが、きょうは場合によっては日経平均を押し下げるほうでスポットライトを浴びかねなかっただけに、売り方としては当てが外れた感もあるだろう。 前日のナスダック指数の下げが大きかったことは、米ハイテク企業に積極投資するソフトバンクGにとってはネガティブ材料。加えて、前日はスイスの資産運用大手GAMインベストメンツが、経営危機陥っている英金融サービス会社グリーンシル・キャピタルと手掛けていたファンドの凍結を発表した。グリーンシルはソフトバンクGが15億ドル程度出資しているとされるが、仮に破綻した場合は損失を被ることになる。しかし、SBGの株価はどこ吹く風で1万円大台をキープしたまま頑強な値動きを示し、日経平均への指数面でのマイナス影響が回避されただけでなく、市場心理を強気に傾ける役割も果たした。 市場筋によれば「(SBGのグリーンシルへの出資額は)日本円にすれば1600億円程度で、仮に焦げついた場合のダメージは小さくないと思われる。しかし、同社の場合は中国のドアダッシュなど大成功した案件も多くあり、その懐の深さを考えれば大勢に影響なしといってよい」(ネット証券マーケットアナリスト)という。以前に米シェアオフィス大手のウィーワークの経営難の問題で巨額支援を実施した時にもSBGの株価は荒い値動きを余儀なくされたが、その後は安定飛行に戻っている。揺れやすいが非常に頑丈な飛行船であり、いまや時価総額は22兆円に達し、首位のトヨタ自動車の背中が見えてきた。 そして株価は2000年のITバブルの時につけた19万8000円の上場来高値が再びクローズアップされている。これは分割後修正値に引き直して1万1000円となるが、時価はそこまであと400円、21年ぶりの更新が目前だ。直近、野村証券が同社株の目標株価を「1万1010円」に引き上げたのにも茶目っ気を感じるが、当時ITバブルのアダ花として咲かせた究極の株価に、ついに現実買いでたどり着くシーンを迎えた。 このほか個別株の動きを見る限り、相場の流れは完全に「アフターコロナ」である。「もし、新型コロナウイルスが地球上に存在しなかったとしたら、売られ過ぎている株は何?」という質問の答えに該当するような株を買い漁る、そんな地合いである。これは欧米などでワクチンの普及が予想以上に速く進んでいることが背景にあるが、変異種の出現などを考えればまだ全く油断はならない状況のはず。それでも株式市場というのは良くも悪くも近未来のMAX(予想されるシナリオの上限)を買う傾向があり、理屈で説明できる段階では既に周回遅れとなってしまう。当然、行き過ぎた修正局面はあるがそれは今ではない、ということを理解したうえで買っているのが相場巧者の業だ。 新たに注目したいのは建設株の周辺。銘柄としては、例えば前田製作所に穴株妙味がある。建機最大手のコマツの総代理店でもあり、産業機械の製造も行っている。また建設コンサルの長大も実質的な青空圏突入が接近している。建築設備工事大手の三機工業は年初から一貫した上昇波を形成しているが依然割安感が強い。 このほか消費関連では、ビジョナリーホールディングスの株価に勢いが感じられる。メガネスーパーの持ち株会社でエムスリーの傘下企業だが、ここにきて新波動入りを示唆する値運びだ。また、婦人服のハニーズホールディングスの1000円トビ台も意外性がある。番外ではAI関連のロゼッタ。VR上の通訳システムを来週9日に発表会を開催する予定でマーケットの注目を集めている。また、それ以上にインパクトがあるのが全社員への「英語禁止令」だ。 あすのスケジュールでは、2月の消費動向調査など。海外では1月の豪貿易収支、1月のユーロ圏小売売上高、1月のユーロ圏失業率、1月の米製造業新規受注など。(銀)出所:MINKABU PRESS明日の戦略-気迷い相場が続くもバリュー株の大幅高には安心感トレーダーズ・ウェブ 3日の日経平均は反発。終値は150円高の29559円。米国株は下落したが、きのうの米株先物の動向からネガティブな影響を先取りしていたこともあって、プラススタート。開始早々には上げ幅を3桁に広げた。29500円より上では戻り売りも出てきて失速し、前場ではプラス圏とマイナス圏を行き来した。しかし、後場に入ると売り圧力が和らぎ、プラス圏が定着。14時を過ぎた辺りからは買いに勢いがつき、取引終盤にきょうの高値をつけた。一方で、マザーズ指数が2%安と弱さが目立った。 東証1部の売買代金は概算で2兆4600億円。業種別では鉄鋼や非鉄金属、空運が大幅上昇。下落は電気機器、その他製品、サービスの3業種のみとなった。北海道宝島旅行社との包括連携を発表したJALが大幅上昇。半面、株式の売り出しを発表したアトムが大幅に下落した。 東証1部の騰落銘柄数は値上がり1338/値下がり776。鉄鋼株が強く、神戸鋼、JFEHD、日本製鉄が急伸。ホンダや日産自、SUBARUなど、自動車株の一角が大きく上昇した。武田はワクチンに関するニュースを材料に、商いを集めて3%超の上昇。月次を手掛かりにABCマートや良品計画が大幅高となったほか、証券会社が目標株価を引き上げた寿スピリッツが値を飛ばした。 一方、米国でナスダックが弱かったことから、日本電産や信越化学、東京エレクトロンなどハイテク株の多くが軟調。グロース株が嫌われる中、colyやWACULなど直近IPO株が手仕舞い売りに押されており、アピリッツはストップ安となった。月次が弱かったアスクルが大幅安。新株予約権の発行を発表したダイヤモンドエレクトリックHDがストップ安をつける場面もあるなど急落した。 日経平均は反発。きょうは米株先物が強かったこともあり、概ねプラス圏でしっかりとした基調が続いた。ただ、今晩の米国株の上昇を先取りしている可能性があるため、あすの期待値は下がる。先週金曜の急落はまだ記憶に新しく、週後半にかけては買いは手控えられるとみておいた方が良い。きょう回復した29500円近辺でひとまず値を固められるかが注目点となる。 そのような中、バリュー系銘柄の多くに強い動きが見られたことは特筆される。鉄鋼、空運、自動車などが中でも強かったほか、1都3県の緊急事態宣言が2週間程度延長されるとの見方が出てくる中でも、レジャーや百貨店関連で大幅高となるものが散見された。バリュー株の上昇はTOPIXの反転期待を高める。この先、TOPIXの底打ちが鮮明となるようであれば、日経平均もそう遠くないうちに3万円台に復帰する流れになるだろう。明日の日本株の読み筋=もみ合い商状か、米金利上昇懸念拭えず、重要日程にらみ手控えもモーニングスター あす4日の東京株式市場で、主要株価指数はもみ合い商状か。先週の相場波乱要因となった米長期金利の上昇は足元落ち着いているが、依然として先行き上昇の懸念は拭えておらず、重要日程をにらみ手控え気分に傾く可能性がある。現地4日にはパウエルFRB(米連邦準備理事会)議長の講演が予定されている。大規模緩和を継続する姿勢を示すとみられるが、発言内容を受けてインフレ率の上昇を容認したと受け止められれば、長期金利上昇に伴う株安が再燃する可能性が指摘されている。また、週末5日には米2月雇用統計が発表されるが、予想を上回る結果となればインフレ懸念の高まりにつながりかねず、とりあえず見極めたいとの空気が先行しそうだ。市場では、「米長期金利の上昇懸念が尾を引き、積極的には動けず、材料待ちの状態だ」(準大手証券)との声が聞かれた。 3日の日経平均株価は反発し、2万9559円(前日比150円高)引け。朝方は、時間外取引(日本時間3日)での米株価指数先物高を受け、買いが先行し、いったん2万9500円台を回復した。その後、利益確定売りに下げに転じる場面もあったが、一巡後は盛り返した。先物にまとまった買い物が入ったこともあり、大引け近くには一段高し、上げ幅が190円を超えた。中国上海総合指数や香港ハンセン指数が堅調に推移し、支えとして意識された。チャート上では、2月26日に25日移動平均線を割り込み、週明け3月1日にはすかさず復帰したが、その後は上値を抑えられており、同線を維持できるかどうかが注目される。三井住友FG、石炭火力の新規融資を全面停止 高効率発電も=関係筋[東京 3日 ロイター] - 三井住友フィナンシャルグループは、石炭火力発電への新規融資を全面停止する方向で調整に入った。「原則実施しない」としていたこれまでの方針を厳格化し、政府が高効率と位置付ける発電所も融資対象から外す。投資家をはじめ環境問題への関心が世界的に高まる中、日本の金融機関も気候変動への姿勢を強化する必要に迫られている。複数の関係者が3日、ロイターに明らかにした。今後打ち出す新たな融資方針に明記する。三井住友FGは現行の融資方針で、新設の石炭火力発電所への支援を「原則実施しない」とする一方、政府がエネルギー基本計画の中で高効率と位置付ける「超々臨界圧火力発電」などへの融資については裁量の余地を残してきた。今回の改定で、すべての石炭火力発電を対象から除外し、厳格な融資姿勢を明確にする。環境問題への取り組みが世界的な課題となる中、二酸化炭素(CO2)の排出増につながる動きには投資家や環境団体、国際機関が厳しい目を向けている。国連のグテレス事務総長は2日、国際組織「脱石炭連合」の会合にビデオ演説を寄せ、経済水準の高い経済協力開発機構(OECD)加盟国に対し、2030年までに石炭火力発電を廃止するよう呼びかけた。経済活動を支える金融機関の融資姿勢も国際社会から注目を集めており、関係者の1人は今回の三井住友FGの動きについて、世界的な圧力の高まりを踏まえたものであることを示唆した。同関係者は「環境団体からなどの風当たりが相当強いのは事実だ」と語った。三井住友FGはロイターの取材に対し「当社として決定した事実はない」と回答。その上で、政府の脱炭素化目標などを踏まえ、「今後も環境や社会へ大きな影響を与える可能性が高い事業・セクターへの方針をプロアクティブ(積極的)に見直していく」とした。超々臨界方式は、石炭を燃焼させて作る蒸気を従来より高温・高圧にして発電効率を上げる仕組みで、CO2排出量を削減できる。三菱UFJフィナンシャルグループとみずほフィナンシャルグループはいずれも、現在の融資方針の中で同方式への融資を完全には排除していない。MUFGは今後の方針について「足元の情勢を踏まえ、従来にも増して、国家レベルでの政策や方針と国際的な議論の流れ、また、ステークホルダーの声といったさまざまな要素を考慮し検討していく」とコメント。みずほFGは、投融資の取り組み方針を「定期的にレビューし、方針の見直しと運営の高度化を図る」とした。石炭火力発電所を巡っては、三菱商事がベトナムで計画中の「ビンタン3」から撤退する方針を固めている。今晩のNY株の読み筋=ベージュブックに注目モーニングスター 3日の米国株式市場は、引き続き米長期金利をめぐる動向から目が離せない展開となりそうだ。 2日のNYダウは、ブライナードFRB(米連邦準備制度理事会)理事のけん制的な発言で米長期金利の上昇が一服し、押し目買いが入る場面もあったが、結局、前日1日の大幅高の反動安となった形で引けた。 3日も引き続き米長期金利動向が注目されそう。2月ADP雇用統計、2月ISM非製造業景況指数が好結果なら、素直に買いで反応するとみられるが、午後発表のベージュブック(地区連銀経済報告)で利上げ再開が想起される内容が示されれば、再び米長期金利の上昇への警戒感が相場の重しとなる可能性があるので注意が必要だ。また、複数のFRB高官の発言にも注目したい。<主な米経済指標・イベント>2月ADP雇用統計、2月ISM非製造業景況指数、ベージュブック、ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁、ボスティック・アトランタ連銀総裁、エバンス・シカゴ連銀総裁が講演ダラー・ツリー、スノーフレーク、スプランクなどが決算発表予定(日付は現地時間)◎投資関連情報は投資の参考として情報提供のみを目的としたものであり、株式の売買は自己責任に基づき、ご自身で判断をお願いします。ひらまつ---大幅反発、ひらまつ総合研究所との和解成立で買い安心感 FISCOひらまつ2764は大幅反発。創業者で元代表取締役社長の平松氏が設立・運営するひらまつ総合研究所から提起されていた損害賠償等請求訴訟について、3月1日に和解が成立し、円満に全ての紛争が解決したと発表している。総額12.4億円の請求を内容とする訴訟が提起されていたが、1.7億円の支払いなどで和解したもよう。リスク要因の払しょくによって、買い安心感が強まる形になっているようだ。病院クラスターで新たな感染者 岐阜県内で9人が新型コロナ感染、1人死亡岐阜新聞Web 岐阜県と岐阜市は3日、県内で9人の新型コロナウイルス感染と入院していた岐阜市の80代女性の死亡を確認したと発表した。県内の累計感染者数は4643人、死者数は112人となった。 クラスター(感染者集団)では、東濃厚生病院(瑞浪市)関連の規模が拡大。同病院から転院した患者に感染が判明した高井病院(土岐市)で、感染した職員の同居家族で50代女性の感染が新たに分かり、一連の感染者は22人となった。 新規感染者の居住地別は関市と土岐市が各3人、大垣市、多治見市、安八郡輪之内町が各1人。年代別は10代と20代が各2人、40代と50代が各1人、60代2人、80代1人。NY株見通し-堅調か 決算発表はADP民間部門雇用者数、ISM非製造業PMIなどトレーダーズ・ウェブ 今晩のNY市場は堅調か。昨日は長期金利の上昇が一服したものの、前日の大幅高の反動で幅広い銘柄が利益確定売りに押され、主要3指数がそろって反落した。引け後の動きでは、ジョンソン・エンド・ジョンソンが開発した1回の接種で済むコロナワクチンを同業のメルクも生産を担い、バイデン米大統領は5月末までに米国の全成人にワクチンを供給できると発表した。今晩の取引では、長期金利の上昇一服や、ワクチン普及の加速による経済活動の早期正常化期待などを背景にリスクオンの流れが再び強まりそうだ。経済指標では、週末の米2月雇用統計の前哨戦となる2月ADP民間部門雇用者数や、非製造業の景況感を巡り2月ISM非製造業PMIが注目される。 今晩の米経済指標・イベントは2月ADP民間部門雇用者数、2月ISM非製造業PMIのほか、ベージュブック、ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁、ボスティック米アトランタ連銀総裁、エバンズ米シカゴ連銀総裁裁の講演など。企業決算は寄り前にブラウン・フォーマン、ダラー・ツリーが発表予定。(執筆:3月3日、14:00)進む都市のDX化、今春「スーパーシティ関連株」が舞い上がる <株探トップ特集>株探ニュース―トヨタのプロジェクト始動で注目度アップ、国家戦略特区の選定に関心高まる― トヨタ自動車 が中心となって進める未来の実証都市「Woven City(ウーブン・シティ)」の建設が本格的にスタートした。このプロジェクトは、あらゆるモノやサービスが情報でつながっていく時代を見据え、技術やサービスの開発と実証のサイクルを素早く回すことで、新たな価値やビジネスモデルを生み出し続けることが狙い。先端技術を導入・検証できる場とし、社会課題を解決するイノベーションに取り組むという。都市のデジタルトランスフォーメーション(DX)化を巡っては、内閣府が未来社会を先取りした「スーパーシティ」構想を実現する対象区域の公募(4月16日まで)を行っており、関連企業のビジネス機会が広がりそうだ。●先端技術で社会課題を解決へ ウーブン・シティは、トヨタ自動車東日本の東富士工場跡地(静岡県裾野市)を活用し、将来的に約70万平方メートルに2000人以上の住民が暮らす都市が想定されている。このプロジェクトでは、 自動運転やモビリティ・アズ・ア・サービス(MaaS)、パーソナルモビリティ、ロボット、人工知能(AI)技術など、さまざまな領域の新技術をリアルな場で実証する予定。地上に自動運転モビリティ専用、歩行者専用、歩行者とパーソナルモビリティが共存する3本の道を網の目のように織り込み、地下にはモノの移動用の道を1本つくる計画だ。こうしたトヨタの取り組みは、100年に一度といわれる自動車業界の大変革に対する危機感が背景にあるとみられ、豊田章男社長は2月23日に行った地鎮祭でのスピーチで「未来に向けた歩みを進めていく」と述べ、自動車会社からモビリティカンパニーへの変革を目指す意向を改めて示した。 トヨタはウーブン・シティの実現に向けて多くの企業や研究者と連携するとしており、2020年3月にNTT と技術基盤(プラットフォーム)づくりを目的に資本・業務提携。同年10月にはKDDI と通信技術及びコネクテッドカー(ICT端末としての機能を持つ自動車)技術の研究開発を促進するため新たに資本・業務提携した。また、今年2月下旬からウェザーニューズ とコネクテッドカー情報を用いて道路凍結を推定する実証実験を行っている。 このほか、トヨタの自動運転システム構築を支援しているALBERT [東証M]や、トヨタと取引関係にあるヴィッツ などにも注目したい。●国家戦略特区を目指す動き続々 一方、政府は30年頃に実現される未来社会を先取りした「スーパーシティ」構想を掲げており、今年4月の公募締め切り後に国家戦略特区が決定される見通しだ。スーパーシティではAIやビッグデータといった先端技術を活用し、自動走行・自動配送、キャッシュレス、行政手続きのワンスオンリー化(最初の手続きを行えば、その後のすべての申請・手続きは個人端末からインターネットで簡単に処理できること)、遠隔医療・介護、遠隔教育などを積極的に導入した便利で快適な最先端都市が想定されている。 国家戦略特区の区域指定に名乗りを上げている茨城県つくば市は、安藤・間 、鹿島 、アイサンテクノロジー [JQ]、楽天 、三菱電機 、CYBERDYNE [東証M]、凸版印刷 、丸紅 など51事業者と連携。インターネット投票やドローンによる配送、健康寿命延伸・救急医療の高度化などのサービスを実現する構えだ。 同じく特区指定を目指している群馬県前橋市では、関電工 、日本工営 、チェンジ 、ユーザベース [東証M]、ニューラルポケット [東証M]、ドリームインキュベータ 、ギフティ 、サイボウズ 、日本通信 、エムティーアイ 、学研ホールディングス 、NTTデータ など154の連携事業者が選ばれた。 また、長野県松本市はツクイホールディングス 、エア・ウォーター 、沢井製薬 、ENEOSホールディングス 、エラン など59事業者と連携。神奈川県小田原市は教育分野でISID 、データ連携基盤でNEC 、医療・健康分野でJMDC [東証M]と長大 を選定し、香川県高松市はTIS 、エルテス [東証M]、穴吹興産 、ソフトバンク 、ゼンリン 、富士ソフト などが連携事業者として名を連ねている。●アイリッジ、スマバなどにも注目 これ以外の関連銘柄では、スーパーシティ向けセキュリティー構想を掲げるラック [JQ]、スーパーシティ実現に有益なデジタルツイン構築を目指して先進の道路計測車両システムの運用を開始したパスコ 、内閣府及びスーパーシティに取り組む企業を中心に設立されたスーパーシティ・オープンラボに参加しているHEROZ や自律制御システム研究所 [東証M]などにも注目したい。 加えて直近では、アイリッジ [東証M]が2月、子会社でフィンテック事業を展開するフィノバレーが熊本県人吉市のスーパーシティ構想の連携事業者に選ばれたと発表。同社はデジタル地域通貨プラットフォーム「MoneyEasy」による地域経済活性化などのノウハウを生かした人吉市の復旧・復興に資する事業を提案している。 スマートバリュー は2月、まちづくりのDX化のためのデータマネジメント基盤「Open-gov Platform(オープンガブ プラットフォーム)」の提供を開始した。スーパーシティでは各種IoT・デジタルサービスから生じるデータを連携・利活用することが必須とされており、「都市OS」(都市に存在するエネルギーや交通機関をはじめ、医療、金融、通信、教育などのデータを集積・分析し、それらを活用するために自治体や企業、研究機関などが連携するためのプラットフォーム)をサービス化する。 日立製作所 は2月、NECやアクセンチュア(東京都港区)、データ社会推進協議会と共同で、内閣府が推進するスーパーシティ構想の実現に向けたデータ連携基盤に関する調査業務を受託した。株探ニュース(minkabu PRESS)「アウディ RS5 クーペ」獰猛でありエレガンス。ライバルとは一線を画す、秘められたスポーティネス【2021 Audi RS SPECIAL】〔NY外為〕円、106円台後半(3日朝)時事通信 【ニューヨーク時事】3日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、米長期金利の上昇を眺め、1ドル=106円台後半で弱含みに推移している。午前9時現在は106円85~95銭と、前日午後5時(106円64~74銭)比21銭の円安・ドル高。 米長期金利が再び上昇に転じる中、海外市場ではドル買いが進行し、円相場は早朝の時間帯に一時107円台に下落。ニューヨーク市場は106円90銭で取引を開始した。 米民間雇用サービス会社ADPが朝方発表した2月の全米雇用報告では、非農業部門の民間就業者数が前月から11万7000人増加。増加ペースは1月(19万5000人増=改定)から減速し、市場予想(17万7000人増=ロイター通信調べ)も下回った。この結果を受け、一時円買い・ドル売りの動きが台頭したものの、その後は寄り付きの水準近辺での取引となっている。 ユーロは同時刻現在、対ドルで1ユーロ=1.2050~2060ドル(前日午後5時は1.2086~2096ドル)、対円では同128円80~90銭(同128円98銭~129円08銭)と、18銭の円高・ユーロ安。(了)今夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中の5銘柄が値を上げてスタートしましたね。5%以上の大きな変動は見られませんね。〔米株式〕NYダウ、反発=ナスダックはもみ合い(3日朝)時事通信 【ニューヨーク時事】3日のニューヨーク株式相場は、米追加経済対策の早期成立期待などを背景とした買いが先行し、反発して始まった。優良株で構成するダウ工業株30種平均は午前9時35分現在、前日終値比51.25ドル高の3万1442.77ドル。一方、ハイテク株中心のナスダック総合指数は21.18ポイント安の1万3337.61。(了)
2021.03.03
コメント(0)
-
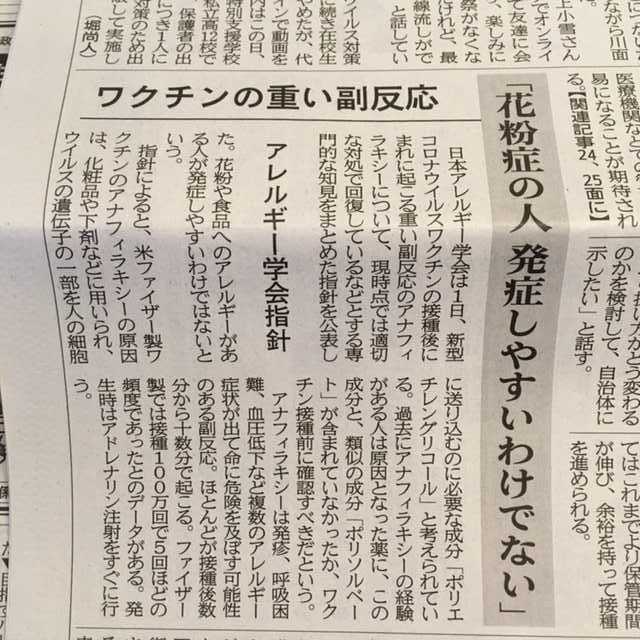
3月2日(火)…
3月2日(火)、雨です。予報通りですね。そんな本日は7時50分頃に起床。新聞に目を通し、朝食を済ませ、ロマネちゃんと戯れる。本日のノルマは2階の掃除機と階段のモップかけですか…。ハイハイ…。朝のコーヒーブレイクはネスプレッソで…。ヴィタメールのチョコレートと共に…。美味い!!そして恒例の母親宅の後片付けです。大量のゴミ袋です…。ゴミの収集日ですからゴミ袋を車に積んで集積所まで3往復・18袋…。昼食前には作業終了とする。疲れます…、これがいつまで続くのでしょうか…。1USドル=106.78円。1AUドル=82.87円。昨夜のNYダウ終値=31535.51(+603.14)ドル。現在の日経平均=29554.75(-108.75)円。金相場:1g=6580(-40)円。プラチナ相場:1g=4590(-20)円。昨夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中の18銘柄が値を上げて終了しましたね。エッツィが大きく上げていますね、スクエア、トゥイリオ、アップル、ドキュサイン、ペイパルも上げていますね。本日の東京市場ではチェック中の日本株30銘柄中の10銘柄が値を上げていますね。重点6銘柄では1銘柄が値を上げていますね。日本コンクリートが大きく下げていますね。イギリス ワクチンで入院・死亡確率減 接種の効果「確認」© FNNプライムオンラインイギリスでは、ワクチンの接種を受けた高齢者について、入院や死亡する確率が大きく減少していると発表した。イギリス政府が1日に発表した調査結果によると、80歳以上でファイザー、もしくはアストラゼネカのワクチンの1回目の接種を受けた人たちで、3週間から4週間経過した場合、入院する確率が80%以上減少した。死亡率もファイザーワクチンで83%減少したとし、遅れて接種が始まったアストラゼネカワクチンの調査も続けている。イギリスでは、2月半ばまでに70歳以上の高齢者への1回目の接種を終えていて、ハンコック保健相は「実社会でのワクチンの効果が確認された」と期待感を示している。ワクチンで80歳超のCOVID-19重症化リスクが8割減=英イングランド調査© BBCニュース 提供英イングランドで公衆衛生当局が行った調査の結果、オックスフォード/アストラゼネカやファイザー/ビオンテックの新型コロナウイルスワクチンを1回受けただけで、80歳超の人の重症化リスクが80%以上減ることが1日、明らかになった。イングランド公衆衛生庁(PHE)が公表したデータによると、ワクチンの防御効果は接種から3~4週間に出始める。イギリスでは昨年12月から80歳以上の人に優先的に予防接種を進めており、今回のデータはその人たちの状態にもとづく。データは査読を受けていない。アストラゼネカ製より1カ月早くイギリスで接種を始めたファイザー製のワクチンについては、死亡率が83%下がったという。これも初期の接種対象だった80歳以上を対象としたデータをもとにしている。さらに、1回目の接種から3週間後の時点で、70歳以上の人たちが発症するリスクも約6割下がったという。 「かなり違う世界に到達できる」政府の科学顧問たちはこのPHE発表を歓迎したが、新型コロナウイルス感染症COVID-19に対する最も効果的な防御を獲得するには2回の接種が必要だと強調した。これに先立ち英スコットランドの保健当局も、同様の「素晴らしい」調査結果を発表している。英政府のマット・ハンコック保健相は1日、首相官邸で記者団に対し、ワクチン接種による最新の調査結果は「とても力強いものだ」と評価。「イギリス全体でここ数週間、集中治療を必要とする新規のCOVID-19患者の人数が1桁に減っているのも、これが理由かもしれない」と述べた。記者会見に同席したイングランドの副主任医務官、ジョナサン・ヴァン・タム教授は、ワクチン接種事業によって「今後数カ月の間に私たちがこれまでとかなり違う世界に到達できるようになる」とし、その展望が今回のデータからうかがえると歓迎した。その上で教授は、2回目の接種の重要性を強調し、継続することが「絶対に不可欠だ」と述べた。 2回接種で「免疫反応が成熟」ヴァン・タム教授は、1回しか接種しない場合と比べて、2回目のワクチン接種が「免疫反応を成熟させ、もしかすると免疫対象を拡大させ、ほぼ確実に長期化させる」「可能性がきわめて高い」と説明した。イギリスではこれまでに成人人口の3割以上に当たる2000万人以上が、1回目の予防接種を受けている。一方で、英政府の3月1日統計によると、ウイルス陽性判定から28日以内に新たに亡くなった人は104人、新たに感染が確認された人は5455人だった。 アストラゼネカ製は高齢者にも有効とヴァン・タム教授は、オックスフォード/アストラゼネカ製のワクチンを高齢者に提供する判断は有効だったと、「明らかに示された」と述べた。これまで欧州の一部では、治験で効果が確認されたのは若い成人が主だったことから、65歳以上には使用しないことにした国々が出ている。ヴァン・タム教授は、ワクチンが若者にしか効かないなど「あり得ない」というイギリス保健当局の判断が正しかったと述べた。さらに、イギリスの今回のデータには諸外国の関心も集まるはずだと話した。PHEの予防接種責任者、メアリー・ラムジー博士は、ワクチンによって感染者が減り、人命が救われていると示す証拠が積み上がっていると述べた。「今後もっとデータは出てくるが、今回の結果は頼もしいし、ワクチンが具体的な変化を実現しているとますます自信を強めている」と博士は話した。ただし、ブラジルで特定され、最近イギリスでも確認された「E484変異」について現行のワクチンがどれだけ効くのかは、まだはっきりしていない。モデルナ製ワクチン用の冷凍庫、ファイザー製のバックアップへ© 産経新聞社 河野太郎ワクチン担当相は2日午前の記者会見で、米製薬大手ファイザー社製の新型コロナウイルスワクチンが日本でも零下15~25度で最大2週間保管できるようになったと発表したことに関し、米バイオ企業モデルナ社製ワクチンのために調達していた冷凍庫もファイザー社製ワクチンの輸送や保管のバックアップとして活用していく考えを示した。モデルナ社製ワクチン用の冷凍庫は零下20度で保管できるという。 一方で接種日程については「変更は今のところ考えていない」と語った。 また、冷凍庫の故障でワクチン最大1032回分が使用不能になった問題について、河野氏は同じ業者が納入した冷凍庫は2月末現在で全国に約100台あるものの、「今のところ、保管温度の逸脱の報告はない」と説明。再発防止に向けて原因究明に取り組む考えを示した。情報BOX:J&Jコロナワクチン承認、米接種計画への影響と効果[ニューヨーク 27日 ロイター] - 米医薬品大手、ジョンソン・エンド・ジョンソン(J&J)が開発した1回接種型の新型コロナウイルスワクチンが27日、米食品医薬品局(FDA)から緊急使用を許可され、近く米国で接種が始まる。先に承認された米ファイザー/独ビオンテック、米モデルナの両ワクチンとの組み合わせにより、米国の接種計画がどのような影響を受けるか、幾つかの角度で検討した。 ◎J&Jのワクチンの有効性は、他の2つに匹敵するかファイザー/ビオンテックとモデルナのワクチンは、メッセンジャーRNA(mRNA)と呼ばれるウイルスの遺伝子材料を駆使した新しい技術に基づいており、大規模な臨床試験(治験)で約95%の発症抑制効果が示された。これに対し、J&Jのワクチンの同有効性はおよそ66%だ。しかし、双方の治験には複数の重要な違いがあるため、直接的な比較はしにくい。ファイザーとモデルナの治験は、軽度から中程度の症状抑制に効くことを重視しているが、J&Jは中程度から重度への進行抑制効果に特に目を向けている。また、J&Jの治験は実施時期が遅れたため、感染力の強い複数の変異株が広がっている地域から相当数の被験者が参加しており、有効性を見る条件が厳しくなった可能性もある。大事なのはJ&Jのワクチンが、重症化や入院の観点で見れば他社のワクチンと同等の有効性を備えており、治験の死亡抑制効果も同じく100%だった点だ。3種類のワクチンが示す副反応も、ほぼ共通する。倦怠(けんたい)感、体のどこかや注射部分の痛み、吐き気、発熱といった副反応が短期間、そして、ほとんどの場合は軽度から中程度の範囲で生じるという。 ◎J&Jワクチンの効果が、低くても接種を受けるべき理由J&Jのワクチンは1回接種型で、ファイザー/ビオンテックとモデルナのワクチンは3週間ないし4週間の間隔を開けた2回の接種が必要だ。より軽い発症はもちろんだが、重症化や死亡を防ぐ点でJ&Jのワクチンは非常に効果がある。ジョンズ・ホプキンス健康安全保障センターのアメシュ・アダルジャ上席研究員は「こうしたワクチンは、あなたが日常生活を取り戻すための道筋だ。提供される機会があれば、接種をためらうべきではない」と強調した。J&Jのワクチンは、南アフリカ由来の変異株を対象にした治験を行っている数少ないワクチンの1つでもある。この変異株に感染した人でも、重症化や死亡を防ぐ効果が示された。ファイザーとモデルナも自分たちが開発したワクチンについて、変異株に対しても有効性は維持されるとの見方をしているものの、まだ、実験室試験でそれぞれのワクチンを試しただけの段階だ。 ◎接種を受けるワクチンの種類は選べるようになるか専門家の話では、今後数カ月間は医療提供者側がワクチンの選択肢を設定するほどの十分な供給は期待されない。ほとんどの接種現場では、3種類のうちどれか1つが用意される状況にしかならないだろう。特定のワクチンを希望している患者は、接種されるワクチンがどこのメーカーの製造かを医療提供者に尋ねることは(米国では)できるだろう。年内には、それぞれのワクチンの供給量が大幅に増える可能性があり、患者にとって選択の余地が広がる局面がやってきてもおかしくない。しかし、専門家は接種を受けられるワクチンがあるなら、何であっても受けるべきだと強く推奨している。 ◎接種可能なJ&Jワクチンの量接種開始からの1週間に約400万回分を出荷するというのがJ&Jの想定だ。出荷開始の予想時期は2月28日夜か3月1日朝。同社は3月末までに計2000万回分、今年半ばまでに最大1億回分の配布を見込んでいる。米連邦政府は医薬品卸売り会社・マッケソンと提携し、同社を通じて全米の州や準州、海外領土などにJ&Jのワクチンを配布する。医療サービスを十分に受けられない人々に確実にワクチンが行き渡るようにするため、別途、特定の薬局や地域の医療センターにも供給する方針だ。米国では3種類のワクチンの合計で、3月末までに2億4000万回分の供給を受けられる態勢。1億3000万人に完全に接種できる量だ。各社が合意している7月末までの供給量は計7億回分で、米国民(人口約3億6660万人)全員の接種を終えて、なお余る規模だ。それでも消えない新型コロナワクチンの長期的リスクの可能性 日刊ゲンダイ ヘルスケア 【コロナ第4波に備える最新知識】新型コロナワクチンの国内先行接種が始まり1週間以上が経過した。気になるのはワクチン接種による副反応だ。新型コロナワクチンが劇的な効果を生み、深刻な副反応が起きないことを切に願うが、医学とはあくまでもメリットがデメリットを上回る場合にのみ成立するもの。メリットだけしかない医学はあり得ない。ワクチン予防医学においてもそれは変わりなく、短期のみならず長期的なリスクの可能性についても考えるべきである。厚労省の発表によると2月24日午後5時時点でワクチン接種を受けたのは計1万7888人。報告された副反応の疑いは「じんましん」「冷感・悪寒戦慄」「脱力で手足が上がらない」の3件で、「アナフィラキシー」など重篤な発生報告はないという。海外ではどうか。日本より2カ月早くワクチン接種が始まった米国ではCDC(米疾病対策センター)が昨年12月14日から1月13日までの最初の1カ月の「予防接種後副反応報告システム」(VAERS)のデータを公開している。この期間中1379万4904回の接種で寄せられた6994件の副反応報告は次の通りである。6354件(90・8%)は軽度で、頭痛(22・4%)、倦怠感(16・5%)、めまい(16・5%)の順に多かったという。深刻な報告は640件(9・2%)で、アナフィラキシーは100万接種当たり4・5件。インフルエンザ1・4件、肺炎2・5件、ヘルペス9・6件で目立って高かったわけではなかった。一般的にワクチン接種に伴う副反応の報告頻度は短時間のものが高い。たとえば、血管迷走神経反射は接種後から30分程度、アナフィラキシーは接種後4時間以内、発熱・腫脹は2日以内、Ⅳ型アレルギーは1週間以内で、血小板減少性紫斑病、ギラン・バレー症候群でも1カ月以内の場合が多いとされる。■抗体依存性感染増強のリスクもしかも、ワクチンは副反応報告制度により、危険なシグナルをキャッチする体制も整っている。だからこそ、以前よりもワクチンは安全性が高いと言えるが、残念ながら副反応は必ずしも短期間に表れるものだけではない。副反応が接種後すぐの発熱やアレルギーショックといったわかりやすい形ではなく、長期的な感染リスクの増強という形で表れることもある。ワクチン接種後に、実際のウイルスに自然感染すると、通常よりもウイルスを取り込みやすくなる「抗体依存性感染増強(ADE)」という現象がまさにそうだ。これは、ワクチン接種した人が自然感染した場合に起こる可能性があるとされるもので、ワクチン接種で誘導された抗体がウイルスに結合。ウイルスが結合した抗体ごとにヒト細胞内に取り込まれることで、ウイルスがヒト細胞に感染するのを助長するというもの。2016年にフィリピンでデング熱ワクチン「Dengvaxia」を接種後に、小児が死亡した原因のひとつとして指摘されたことを機に広く知られるようになった。コロナウイルスに関しても、重症急性呼吸器症候群(SARS)や中東呼吸器症候群(MERS)ワクチンを接種する動物実験で、接種後にADEのような現象が確認されている。日本株は反落、商品市況安や米株先物の軟調推移-市況関連や素材安い 2日の東京株式相場は反落。米国の長期金利の先行きを見極めたいとして買いが手控えられる中、原油など商品市況安や米株先物安から鉱業など原油関連、非鉄金属などといった市況関連、鉄鋼など素材株が安い。 TOPIXの午前終値は前日比9.07ポイント(0.5%)安の1893.41 日経平均株価は108円75銭(0.4%)安の2万9554円75銭 〈きょうのポイント〉 1日の米ニューヨーク原油先物は1.4%安の1バレル=60.64ドルと約1週間ぶりの安値-OPECプラスの会合控え ロンドン金属取引所(LME)の金属市況も下落 1日の米10年債利回りは1.42%、1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇 米供給管理協会(ISM)製造業景況指数は3年ぶり高水準-仕入価格が上昇 しんきんアセットマネジメント投信の藤原直樹運用部長は「過剰流動性相場の中で金利上昇を深刻にみていない投資家の押し目買い意欲が強い」とする半面、「ここまで一本調子で来たので利益確定は出てくる。皆が皆強気なわけではない」とも述べた。その上で、ことしの株式市場は、金利とインフレの状況をにらみながらの展開になりそうだとみていた。 朝方こそ上昇して始まったものの、東証1部では値下がり銘柄が次第に増加し、主要指数は失速した。米国株が不安定な中でアジア時間2日の米S&P500種Eミニ先物など米株先物が軟調に推移していることも重しとなっている。 今週は米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長が4日に米経済について発言予定など、米金融当局者の発言が相次ぐ予定。大和証券投資情報部の石黒英之シニアストラテジストは、欧州中央銀行(ECB)が急激な金利上昇を看過しない姿勢を示したのに続き、「米金融当局者のスタンスが今週に明らかになれば金利は落ち着いてくる可能性がある」と予想している。 東証33業種では空運や海運、鉱業、石油・石炭製品、鉄鋼、非鉄金属が下落 精密機器やガラス・土石、証券・商品先物取引は上昇【米国株動向】株式市場が暴落したときに注目したいグロース株4銘柄モトリーフール米国本社、2020年2月18日投稿記事より市場の暴落の原因、程度、期間を予測することはできませんが、投資サイクルの中で暴落や調整が一般的に起こることは過去の歴史が物語っています。過去71年間にS&P500指数は10%以上の下落局面を38回経験してきました。しかし、朗報もあります。暴落や調整が起こるたびに優良銘柄を割安な価格で購入する機会がもたらされてきたのです。以下、次に暴落が起こったときに注目したい4つのグロース銘柄をご紹介します。 アマゾン(NASDAQ:AMZN)アマゾンは米国で時価総額第3位の上場企業です。市場調査会社eMarketerによると、同社は2021年に米国のeコマース市場で39.7%のシェアを握ると予想されています。米国のオンライン支出額1ドルにつき0.40ドルがアマゾンに流れる計算になります。アマゾンは世界で1億5,000万人を超えるプライム会員から会費収入を得ており、これが従来型の実店舗よりも安い価格を提供し、顧客ロイヤルティを確保する上で役立っています。アマゾンはトップクラスのクラウド・インフラ・プロバイダーでもあります。アマゾン・ウェブ・サービス(AWS)の2020年売上高は30%増加し、2020年第4四半期売上高は127億ドル、年率換算で510億ドルに達しました。クラウド事業の利益率は小売事業よりも格段に高いため、同社のキャッシュフローは2023年または2024年までに3倍に拡大すると予想されています。つまり、世界最大級の企業である同社には成長余地がまだ大いにあるというわけです。 クラウドストライク・ホールディングス(NASDAQ:CRWD) デクスコム(NASDAQ:DXCM) イノベイティブ・インダストリアル・プロパティーズ(NYSE:IIPR)【米国株動向】資金1,000ドルを投資するならペイパルに注目すべき10の理由モトリーフール米国本社、2020年2月17日投稿記事より資金1,000ドルを投資する場合、株価300ドル前後のペイパル・ホールディングス(NASDAQ:PYPL)は3株しか買えないので、低位株を多数買った方が得だと思われるかもしれません。しかし、投資で重要なのは株式数ではなくリターンです。ペイパルは年率20.75%という市場平均を大きく上回るリターンを上げており、今後も高水準のリターンを生み出し続ける可能性を十分に秘めています。以下で同社に注目すべき10の理由を挙げていきます。1.キャッシュの重要性が低下しているここ数年、現金決済は減り続け、それに伴いペイパルなどのフィンテック会社が存在感を高めています。生活を大きく変えつつあるフィンテック会社からは、勝ち組銘柄が複数生まれる可能性がありますが、ペイパルはその中でも以下の9つの理由によって特に有利な立場にあります。2.顧客数が年平均16%で成長オークションサイトのイーベイから分離した2015年に1億8,100万件だった口座数は、2020年末に3億7,700万件と、2倍以上に増えています。年率換算で16%というこの顧客数の伸び率の高さは、キャッシュレス化の流れ、そしてフィンテック業界での同社の優位性を物語っています。さらに、アクティブ口座数を2025年に現在のほぼ倍の7億5,000万件に伸ばす計画です。成長の大部分が見込まれるのは、キャッシュレス化がまだ進んでいない米国外の市場です。中南米でメルカドリブレ、中国でアント・グループのアリペイと提携するなど、既に国際市場での成長加速に向けて動いています。3.エンゲージメントが向上顧客数だけでなく、エンゲージメント(サービス利用率)も伸びています。2015年には年間平均28.1件だったユーザーの取引件数は、クーポン情報提供会社ハニーの買収などによる外部成長分を除いても、2020年には40.9件に達しました。昨年10月に米国で「バイ・ナウ・ペイ・レイター」という信用販売サービスを開始しましたが、このサービスを利用するユーザーの週間支出額は12%増加しています。4.エンゲージメントは今後さらに伸びる見込み同社は顧客によるサービス利用をどんどん増やしていくことを目指しており、そのためにさまざまな方策をとっています。たとえば今年、ビットコインを含む仮想通貨の取り扱いを拡大する予定です。現在提供している仮想通貨取引サービスは限定的ですが、同社によるとそれだけでも日次ユーザーログイン数は50%増えました。株式取引や料金自動引き落としなどの新サービスも計画しており、エンゲージメントをさらに高めようとしています。5.堅調な売上拡大顧客数が伸び、各顧客がサービス利用を増やしていることで、同社は大型株としては非常に高い増収率を実現しています。2015年から2020年までの間に、売上高は100億ドル未満から210億ドル超に増えました。そして今後5年間では伸びがさらに加速し、売上高は年平均20%以上増加して2025年には500億ドルを超える計画です(今後の買収による効果を含めない内部成長分のみ)。非現実的に思えるかもしれませんが、2020年の同社の取扱高は9,360億ドルで、これはマスターカードの6兆3,000億ドルに比べればまだ小さいと言えます。キャッシュレス化の流れも踏まえると、成長の余地は十分に残されているということです。6.フリーキャッシュフローの伸びが加速フリーキャッシュフロー(FCF)マージン(売上高に対するFCFの比率)が安定的に高く、2020年で23%となっています。今後5年間のFCFは400億ドルを超え、2025年以降は年額100億ドル以上になる計画です。7.自社株買いを優先その潤沢なキャッシュフローを活かし、同社はこれまで自社株買いを中心に株主還元を行ってきました。その方針は今後も変わらず、FCFの30%~40%を自社株買いに使う計画です。つまり、これから2025年までの間に120億~160億ドルの自社株買いが実施され、1株当たり利益(EPS)を押し上げる見込みです。8.買収による外部成長への期待豊富なキャッシュは他社買収にも使えます。2018年に中小企業向けモバイル決済会社アイゼトルを22億ドルで買収した時のように、同社は他社買収によってアクセス可能な市場を広げてきました。今後もキャッシュフロー獲得力を活かした買収を通じて、公共料金引き落としサービスや資産取引など、同社にとって未開の市場を開拓していく可能性があります。アクセス可能な市場が増えれば、株価の上限もおのずと高まります。9.さまざまな利害関係者に恩恵フォーチュン誌が選ぶ急成長企業100社は、3年間の増収率、収益性、株式リターンなどをもとにした成長性のランキングで、同社は78位に入っています。株主に十分な恩恵をもたらしているということになりますが、企業にとっての利害関係者は株主だけではありません。従業員の満足度を公表する口コミサイト「グラスドア」が最近発表した2021年の働きやすい企業ランキングでも、同社は59位に入っています。これらのランキングで両方ともトップ100に入っているのは3社のみで(他の2社はマスターカードと運動用アパレルのルルレモン・アスレティカ)、ペイパルはさまざまな利害関係者に恩恵を及ぼしてきた実績を持つ、信頼できる企業ということになります。10.既に勝者既に優位な立場にあることは、長期的に成功を収める上で重要な好材料です。今から7年~10年後に同社が時価総額1兆ドル超えの一握りの企業に入っていたとしても、それほど驚くべきことではありません。それが実現するとすれば、株価は現在の約3倍に膨らむことになります。米国株式市場=大幅高、債券市場の落ち着きや景気回復期待で[1日 ロイター] - 米国株式市場は大幅高で取引を終えた。債券市場の売りが落ち着いたほか、新型コロナウイルスワクチンや追加経済対策に関連した動きを受けて早期の景気回復への期待が高まった。S&P総合500種は昨年6月以来の大幅な上昇となった。米食品医薬品局(FDA)は2月27日にジョンソン・エンド・ジョンソン(J&J)の新型コロナワクチンの緊急使用を許可した。同社は出荷を開始し、株価は0.5%高で引けた。米下院は1兆9000億ドル規模の新型コロナウイルス対策法案を27日未明に可決した。今後、上院で審議が行われる。米国債利回りはここ1カ月間、景気回復に伴うインフレ加速の観測を背景に上昇してきたが、この日は低下した。グローバルトの運用担当者キース・ブキャナン氏は「地合いはリスクオンで、シクリカル(景気循環)銘柄に関心を示す投資家が増えている。ワクチンを巡る前向きな展開やマクロ指標の改善は成長環境の改善を示唆している」と述べた。米供給管理協会(ISM)が発表した2月の製造業景気指数は3年ぶりの高水準となった。新規受注の伸びが加速した。S&P500の主要11セクターは軒並み上昇。金融や情報技術が主導した。前週に売り込まれていたアップル、マイクロソフト、フェイスブック、アマゾン・ドット・コムはいずれも持ち直し、アップルは5%超上昇した。小型株中心のラッセル2000も3.37%高となり、年初来の上昇率は15%を超えた。S&P500は年初来およそ4%上昇している。バークシャー・ハザウェイは3.6%高。同社を率いる著名投資家のウォーレン・バフェット氏は年に一度の「株主への手紙」で、コロナ禍が続く中でも米国やバークシャーに対する強い期待は揺らいでいない、との自信を示した。ボーイングは5.8%高。ユナイテッド航空ホールディングスが737MAX型機を25機発注したことなどを好感した。ヘルスケア用品のペリゴも4.7%上昇。後発医薬品事業を15億5000万ドルで売却すると発表した。引け後の取引では、四半期決算を発表したズーム・ビデオ・コミュニケーションズが10%急伸した。ニューヨーク証券取引所では値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を3.81対1の比率で上回った。ナスダックでも4.29対1で値上がり銘柄数が多かった。米取引所の合算出来高は121億株。直近20営業日の平均は151億株。ノババックス、米で5月にも新型コロナワクチン使用許可=CEO[1日 ロイター] - 米バイオ医薬品企業ノババックスのスタンリー・アーク最高経営責任者(CEO)は1日、同社が開発している新型コロナウイルスワクチンについて、4月完了予定の英国の臨床試験(治験)の結果に基づき米当局が承認すれば、5月にも国内で使用が許可されるとの見方を示した。アークCEOはインタビューで、ノババックスは量産の用意を整えていると表明。米政府に対し第3・四半期末までに1億1000万回分を供給すると確約したが、早くて7月にも実現できる可能性があるとした。ただ米当局が米国内で実施された治験の結果を待つ場合、国内での承認は6月、もしくは7月にずれ込むとの見通しを示した。ノババックスは米国内で3万人を対象とした治験の参加者募集を2月に終了。英国の治験の初期データによると、ワクチンの有効率は従来株に対して約96%、英国で検出された変異株に対して約86%だった。ノババックスは米政府から16億ドルの資金を受け取り、新型コロナワクチンの開発に着手。この日に発表した2020年第4・四半期決算は、純損失が1億7760万ドル(1株当り2.70ドル)と、前年同期の3180万ドル(同1.13ドル)から拡大。ただ売上高はワクチン事業に押し上げられ、2億7970万ドルと、880万ドルから増加した。1日のS&P500が「9カ月ぶりの大幅高」となった事情主要3指数がそろって大幅上昇(ブルームバーグ):1日の米株式市場では主要3指数がそろって大幅に上昇。S&P500種株価指数は約9カ月ぶりの大幅高で引けた。米国債利回り上昇の影響に対する投資家の懸念が和らぎ、市場に信頼感が戻った。S&P500種は2.4%高の3901.82。ダウ工業株30種平均が603.14ドル(2%)高の31535.51ドル。ナスダック総合指数は3%上昇した。この日は全般的に買われた。小型株で構成するラッセル2000指数の上昇率は3.4%と、ナスダック総合指数も上回った。個別銘柄ではゲームストップ株の上昇が目立った。先週は週間で150%余り上昇したが、ソーシャルメディア上で個人投資家がはやす動きが続いている。ズーム・ビデオ・コミュニケーションズが時間外で大幅上昇。通常取引終了後に発表した売上高見通しが市場予想を上回った。ブリークリー・アドバイザリー・グループのピーター・ブックバー最高投資責任者(CIO)は「株価収益率(PER)が高い銘柄などは先週一部揺らいだが、株式投資家は金利上昇をまだおおむね『良いこと』だとみており、脅威には感じていない」と指摘した。米国債市場では年限が長めの債券が再び売られた。中期債は堅調。トレーダーらは今週予定されている米金融当局者の発言を注視する構えだ。ニューヨーク時間午後5時現在、10年債利回りは1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇し、1.42%。外国為替市場ではノルウェー・クローネやオーストラリア・ドル、カナダ・ドルなどの資源国通貨が、主要10通貨の大半を上回る上昇率。リスクテーク意欲が戻り、株式相場が世界的に上昇したことが背景にある。主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.1%低下。一時は0.4%下げる場面もあった。ドルは円に対しては0.2%高の1ドル=106円76銭。一時106円89銭と、昨年8月以来の高値をつけた。ユーロは対ドルで0.2%下げ、1ユーロ=1.2049ドル。ニューヨーク原油先物相場は続落し、約1週間ぶりの安値となった。今週予定されている石油輸出国機構(OPEC)と非加盟の主要産油国で構成する「OPECプラス」の会合では、急速に引き締まりつつある市場への供給増加を決める可能性がある。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物4月限は86セント(1.4%)安の1バレル=60.64ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント5月限は73セント安の63.69ドル。金スポット相場は5営業日続落。日中はプラス圏で推移していたが、米国債利回りが上昇する中、下げに転じた。ニューヨーク時間午後2時46分現在では前日比0.6%安の1オンス=1723.74ドル。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物4月限は、0.3%安の1723ドルで終了した。超富裕層に対して超富裕税!ウォーレン上院議員らが提案純資産5000万ドル超で2%、10億ドル超で3%ブルームバーグ その名も「ウルトラ・ミリオネア・タックス(超富裕税)」。純資産が5000万ドル(約53億円)を超える個人に2%、10億ドルを超えたら3%を課税する案を、エリザベス・ウォーレン上院議員ら民主党議員が提示しました。コロナ禍で資産が「40%増えた」超富裕層に相応の負担を背負わせることで、10年間で少なくとも3兆ドルの税収増が望めるそうです。上院通過のハードルは高いようですが、著名なビリオネアたちが何とコメントするか興味深いです。以下は一日を始めるにあたって押さえておきたい5本のニュース。 製造業に明るさ米供給管理協会(ISM)が発表した2月の製造業総合景況指数は60.8と、3年ぶりの高水準となり、エコノミスト予想の58.9を上回った。部品不足という逆風で、原材料コストが大きく上昇。仕入価格指数は4ポイント近く上昇して86と、08年7月以来の高水準に達した。 1600億円の重みソフトバンクグループのビジョン・ファンドは、サプライチェーンファイナンス会社グリーンシル・キャピタルへの投資15億ドル(約1600億円)について、評価額を大幅に引き下げたと関係者が明らかにした。これより先、クレディ・スイス・グループはグリーンシル・キャピタルを保有するグリーンシル氏が手掛けるサプライチェーンファイナンスの債権に投資するファンドを凍結した。 ぜい弱さを是正米連邦準備制度理事会(FRB)のブレイナード理事は金融システムの改善を目指し、今後数カ月に取り組む規制改革の課題を示した。現行の金融システムは新型コロナによる衝撃に耐えられなかったことが分かった上、公的資金を後ろ盾とした緊急ファシリティーという前例のない支援を要したと説明した。規制見直しの対象として、具体的には米国債やマネーマーケットファンド(MMF)などを挙げた。 あらゆる手段欧州中央銀行(ECB)は正当な理由のない債券利回りの上昇には対応しなければならないと、ECB政策委員会メンバーでフランス銀行(中銀)のビルロワドガロー総裁が述べた。まずはパンデミック緊急購入プログラム(PEPP)を活用し、好ましい金融環境を保つため利下げも排除されないと明確にすべきだと論じた。ECBはこれより先、PEPPの買い入れペースが先週減速したことを明らかにした。 タイガーに移籍ゴールドマン・サックス・グループで資産運用事業の共同責任者を務めてきたエリック・レーン氏が、同ポジションに就いて6カ月足らずで退社する。関係者によればレーン氏は、チェース・コールマン氏率いるヘッジファンド運用会社、タイガー・グローバル・マネジメントに社長兼最高執行責任者(COO)として加わる。【市況】後場に注目すべき3つのポイント~市場は落ち着くも「懸念」の解は見えず2日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は反落、市場は落ち着くも「懸念」の解は見えず・ドル・円は失速、アジア株安で円売り後退・値下がり寄与トップはファーストリテイリング、同2位がリクルートホールディングス■日経平均は反落、市場は落ち着くも「懸念」の解は見えず日経平均は反落。108.75円安の29554.75円(出来高概算6億7000万株)で前場の取引を終えている。週明け1日の米株式市場でNYダウは大幅反発し、603ドル高となった。日用品・製薬大手ジョンソン・エンド・ジョンソンの開発した新型コロナウイルスワクチンが食品医薬品局(FDA)の緊急使用の承認を受け、ワクチン接種が加速するとの期待が強まった。米国債相場が落ち着きを取り戻し、2月のサプライマネジメント協会(ISM)製造業景況指数が市場予想を上回ったことも好感された。ハイテク株比率の高いナスダック総合指数は3.0%、フィラデルフィア半導体株指数(SOX)は3.3%の上昇となった。本日の日経平均もこうした流れを引き継いで276円高からスタートすると、寄り付き直後には一時29996.39円(332.89円高)まで上昇。ただ、節目の3万円に届かず失速し、前場中ごろを過ぎるとマイナス転換した。個別では、ファーストリテ、任天堂、ソニーが軟調。前日にLINEとの経営統合を果たしたZHDは3%超の下落。統合効果が期待されつつも、目先は材料出尽くし感が優勢のようだ。JALなどの空運株やH.I.S.などの旅行関連株も下げが目立つ。また、第三者割当増資の実施を発表したサンデンHDはストップ安水準で前場を折り返した。一方、米ハイテク株高を受けてSUMCOが堅調で、ソフトバンクGやキーエンスは小じっかり。ビットコイン価格の再上昇でマネックスGなどの関連銘柄も買われている。また、業績上方修正を発表したヒマラヤはストップ高水準で前場を折り返した。セクターでは、空運業、海運業、鉱業などが下落率上位。半面、精密機器、ガラス・土石製品、その他金融業などが上昇率上位だった。東証1部の値下がり銘柄は全体の72%、対して値上がり銘柄は24%となっている。日経平均は前日の米株高を手掛かりに続伸スタートとなったが、節目の3万円に届くことなく失速する格好となった。「恐怖指数」とされる米株の変動性指数(VIX)は23.35(-4.60)に低下、同様に債券版のMOVE指数も低下し、金融市場はひとまず落ち着きを取り戻したかに見えた。朝方には日経平均の3万円台回復を予想する声も多かったが、「押し目は買いたいが上値追いには慎重」なムードが思いのほか強いのかもしれない。アジア市場でもやはり香港株や上海株は買いが先行したものの、上値の重さが拭えない。前日は日経平均が700円近い上昇となったが、気になる点はあちこちに見られた。まず、日経平均は2月26日の下落分(1202.26円安)の半値戻し水準で上値が重くなり、東証1部の売買代金は2兆4773億円とやや低調だった。値幅の割に様子見ムードが強かったことが窺える。また、この日の先物手口を見ると、野村證券やモルガン・スタンレーMUFG証券が日経平均先物の買い越し上位、みずほ証券やJPモルガン証券が東証株価指数(TOPIX)先物の買い越し上位に浮上する一方、ゴールドマン・サックス証券がTOPIX先物を売り越していた。海外勢を中心とする機関投資家も買い戻しで歩調が合っていたわけではないようだ。米国では2月のISM製造業景況指数が市場予想を上回る水準となったが、今週は3日にADP雇用統計とISM非製造業景況指数、5日に雇用統計と重要な経済指標の発表が多く控えている。とりわけ、金融政策のかじ取りが難しくなってきただけに、雇用関連統計の内容を見極めたいという思惑は強まるだろう。また、先週末の当欄で触れた「マネーの変調」こそ回避できそうな情勢だが、「未来図」に関する懸念に明確な解が示されたようには思われない。需要の不足分を大幅に上回る米経済対策とそれによる政府債務の増大、主要中央銀行による過去に例のない規模の金融緩和…これらが行き着く先として先週来浮上している「インフレ加速」などといった懸念はいまだくすぶるのだろう。本日は日経平均の失速とともにマイナス転換したが、ファーストリテは朝方に取引時間中の上場来高値を更新。「ユニクロ」「GU(ジーユー)」ブランドで良質・安価な衣料を提供する同社の経済圏は拡大、躍進が続く。他方、百貨店各社の2月売上高を見ると高額品の底堅さが窺え、百貨店株も戻り歩調を崩していない。ファーストリテ株の躍進には、資産インフレが加速しても一般消費者の節約志向は変わらないという市場の見方が透ける。また、米国の大規模な財政・金融政策を受けて、株高の一因として「マネーの減価」が改めて意識されているのではないかとも思う。長くなってきたのでこのあたりの話はまた次回以降としたい。(小林大純)■ドル・円は失速、アジア株安で円売り後退2日午前の東京市場でドル・円は失速し、106円70銭台にやや値を下げた。ランチタイムの日経平均先物は軟調、上海総合指数も下げに転じ、アジア株安により円買い方向に振れやすいようだ。一方、欧米株安観測でリスクオフのドル買い地合いとなり、対円では下げ渋っている。ここまでの取引レンジは、ドル・円は106円74銭から106円92銭、ユーロ・円は128円27銭から128円77銭、ユーロ・ドルは1.2015ドルから1.2050ドル。■後場のチェック銘柄・ビットワングループ、ユニバンスなど、5銘柄がストップ高※一時ストップ高(気配値)を含みます・値下がり寄与トップはファーストリテイリング、同2位がリクルートホールディングス■経済指標・要人発言【経済指標】・日・1月有効求人倍率:1.10倍(予想:1.06倍、12月:1.06倍)・日・1月失業率:2.9%(予想:3.0%、12月:2.9%)・日・2月マネタリーベース:前年比+19.6%(1月:+18.9%)【要人発言】・ホークスビーNZ準備銀行総裁補佐「必要に応じてキャッシュレートを引き下げることが可能」「景気回復についてはぜい弱で見通しは弱い」<国内>特になし<海外>・12:30 豪準備銀行が政策金利発表(0.10%に据え置き予想)・16:00 独・1月小売売上高(前月比予想:+0.5%、12月:-9.1%)《CS》 提供:フィスコ【材料】JCRファが反発、国内有力証券が投資判断「オーバーウエート」でカバレッジ開始 JCRファーマが反発している。三菱UFJモルガン・スタンレー証券が1日付で、投資判断を新規に「オーバーウエート」、目標株価4400円としてカバレッジを開始しており、これが好材料視されているようだ。 同証券では、主力品グロウジェクト(ヒト成長ホルモン)は製剤工夫による使いやすさもあり安定的な成長を続けており、適応拡大も含め中期的にも成長が続くと評価。また、同社の開発したJ-Brain Cargoの技術プラットフォームを用いたライソゾーム病治療薬は、最初の開発プログラムJR-141(ハンター症候群を対象)が国内では申請済み(21年3月末承認見込み)、海外ではフェーズ3開始目前となっており、続くライソゾーム病を対象としたプログラムも順調に開発されているという。JR-141は国内外複数社との導出交渉が進み、今年度内には締結の見通しで、JR-141を含むライソゾーム病フランチャイズの商業ポテンシャルが株価に十分に織り込まれてはいないとしている。出所:MINKABU PRESSみのひだフォーカス:木沢記念病院のクラスター 原因究明・防止が急務 すでに225人…「対策はしてきたはず」 /岐阜毎日新聞社 県内に出ていた新型コロナウイルスの緊急事態宣言は1日、解除されたが、医師や看護師、患者のコロナ感染が判明した木沢記念病院(美濃加茂市古井(こび)町・452床)では、全国的にも有数な規模となった「病院クラスター(感染者集団)」が収束していない。2月25日現在で計225人の感染が確認され、亡くなった人も複数いる。原因究明とさらなる対策が求められている。【黒詰拓也】 病院で最初に感染者が確認されたのは2月2日。医師や入院患者ら16人の感染が分かり、接触者を中心にPCR検査(遺伝子検査)を進めたところ、新規陽性が連日判明し、全11病棟に感染が広がっていた。感染者225人のうち、医師や看護師ら職員は92人、患者は94人、患者の家族らが39人。患者94人のうち13人は、退院した後に検査を受けて陽性となった。病院は2日から救急患者、8日から新規外来患者の受け入れを停止している。 病院ではクラスターが起きる前から、入院を控えた全ての患者にPCR検査を受けてもらい、県内で感染者が急増した昨年末以降は家族の面会を全面的に停止していた。もともと地域のコロナ感染者を受け入れ治療していたこともあり、検温や消毒、防護服の使用といった「対策はきちんと講じてきた」(担当者)はずだったが、感染拡大を防ぐことはできなかった。 県は厚生労働省のクラスター対策班に調査を依頼。班に所属する国立感染症研究所の医師2人と看護師1人が10日から22日まで現地で調査、原因分析をした。入院中に呼吸状態が悪化した患者の感染判明後に、担当スタッフの陽性が分かったケースがあったことが分かった。ただ「感染が全ての病棟まで広がった原因は分かっていない」(県健康福祉部の堀裕行次長)。 ◇200人超は全国で10件 厚労省のクラスター対策班によると、医療機関で2人以上の感染が確認されたケースは全国で延べ903件(2月22日現在)。そのうち200人を超えたクラスターは10件程度あった。感染拡大が広がった共通の要因に「初動の遅れ」があるという。スタッフや入院患者が自身の感染に気付かないまま病室や病棟を移動し、持病があるなど抵抗力が落ちている人に次々と感染が広がった事例もある。 コロナに感染しても無症状であったり、コロナ以外の疾患で発熱していたりすることがあるため、コロナの感染を素早く見つけることが困難な場合も多い。マスクの着用や消毒などの基本的な対策を徹底し、患者のわずかな体調変化を医療スタッフ間でしっかり引き継ぐことが、感染予防には欠かせない。 昨年2月に医師と入院患者計5人の感染が判明し、国内初の病院クラスターとされた済生会有田病院(和歌山県湯浅町・184床)では、医療従事者の手指を介して感染が広がった可能性が高いことが和歌山県の調査で分かった。 戸田中央総合病院(埼玉県戸田市・517床)では、昨年11月から2月24日までにスタッフと患者計324人の陽性が判明。感染者数は国内最大規模となった。対策班と埼玉県の調査によると、認知症でマスクを常に着用できない患者がいたほか、その患者の担当スタッフの陽性も判明するなどしていた。休憩室や更衣室でスタッフがマスクを外して会話していたことも、感染拡大の一因となったという。 ◇患者にも不安 木沢記念病院は、31の診療科を持つ地元の基幹病院だ。2月8日以降は、予約のある再診患者のみ受け入れているが、患者からは不安の声が聞かれた。 病院の近くに住む女性(65)は、持病である糖尿病と高血圧の状態を調べるため、5年ほど前から2カ月に1度、血液検査を受けてきた。2月13日も検査を受ける予定だったが、夫や息子が感染を心配したため見送り、病院に電話して看護師による問診のみ受け、薬の処方箋を出してもらった。 女性によると、この病院はスタッフの体制が充実しており、最新の機器も備えていることから各地から多くの患者が訪れているという。「今は体調に問題はないが、持病が悪化したらすぐに診てもらえるのだろうか。クラスターが早く収まることを願うしかない」と表情を曇らせた。 坂祝町酒倉の会社員、糸数龍士さん(43)は2月27日、歯科口腔(こうくう)外科で虫歯の治療を受けた。本来は13日に受ける予定だったが、病院から診察日を延期してほしいと頼まれたという。「理由は聞かなかったが、コロナだろう。歯の状態が無事で良かった」と胸をなでおろしていた。 病院はホームページに「感染経路と感染拡大の要因は調査中」と掲載している。佐合茂樹事務長は27日、毎日新聞の取材に「原因などあらゆることが分かっておらず、ホームページに書いてあること以外のコメントはできない」と話した。永寿総合病院(東京) 400床 235人(収束) 密となる部屋での対策の不徹底旭川厚生病院(北海道) 499床 311人(収束) 無症状の入院患者から拡大戸田中央総合病院(埼玉) 517床 324人 職員や患者のマスク着用不徹底木沢記念病院(岐阜) 452床 225人 (調査中)ヒマラヤが続急騰で昨年来高値を更新、上期および通期の業績予想を上方修正モーニングスター現在値ヒマラヤ 1,062 +150 ヒマラヤ が続急騰。1日引け後に、21年8月期上期(20年9月-21年2月)および通期の連結業績予想を上方修正したことが好感された様子。株価は前日比150円ストップ高の1062円まで値を上げ、1月22日の昨年来高値1035円を更新している。 21年8月期上期について、予想売上高を従来の278億円から306億1000万円(前年同期比4.1%増)に、営業損益を5000万円の赤字から7億6000万円の黒字(前年同期は5億4900万円の赤字)にそれぞれ修正。通期は売上高を588億円から610億円(前期比5.7%増)に、営業損益を5億5000万円の黒字から13億7000万円の黒字(前期は4億8700万円の赤字)に引き上げている。上期において、コロナ禍の下、「新しい生活様式」への親和性が高いとされるゴルフ、アウトドアが好調に推移したこと、気温の低下や降雪に恵まれたことに加え、全般に季節の推移が順調に進んだことから、大きな在庫消化負担が生じず売上総利益率が改善したことが主な要因。 午後零時34分現在はストップ高買い気配で差し引きの3万7000株の買い越し。本日の東京市場ではチェック中の日本株30銘柄中の12銘柄が値を上げて終了しましたね。重点6銘柄では1銘柄が値を上げて終了しましたね。日本コンクリートが大きく下げて、ひらまつ、レノバも下げましたね。〔東京外為〕ドル、106円台後半=午後は手掛かり欠き動意薄(2日午後3時)時事通信 2日午後の東京外国為替市場のドルの対円相場(気配値)は、売買を促す手掛かりを欠き、1ドル=106円台後半の狭い値幅で推移している。午後3時現在は、106円82~82銭と前日(午後5時、106円60~60銭)比22銭のドル高・円安。 東京時間は106円70銭台で始まり、輸入企業の決済資金調達に加えて日経平均株価の上昇を眺めた「リスク選好の円売り」で106円90銭前後まで上昇した。しかし、107円付近では輸出企業や短期筋のドル売り注文が厚いとされる上、日経平均がマイナスに転じたこともあって上値は重かった。 午後は、主に106円80銭台で小動きとなっている。ユーロ圏の2月消費者物価指数(CPI)など欧州の経済指標発表を日本時間夜に控え、様子見気分も漂う。 米国の追加経済対策や新型コロナウイルスのワクチン接種による景気回復期待からドルは堅調を持続しているものの、米長期金利の上昇が一服したことで、市場参加者からは「一段のドル高にはきっかけが必要」(邦銀)といった声が出ている。欧州通貨・資源国通貨が「調整局面を迎えている」(外為仲介業者)との見方も広がる中、方向感を定める新たな材料を待っている状況だ。 ユーロは午後に入って対円で小幅高、対ドルでは小動き。午後3時現在は、1ユーロ=128円42~42銭(前日午後5時、128円73~74銭)、対ドルでは1.2022~2022ドル(同1.2076~2076ドル)。(了)〔東京株式〕反落=米株先物安で輸出株売り(2日)時事通信 【第1部】日経平均株価は前日比255円33銭安の2万9408円17銭、東証株価指数(TOPIX)は7.63ポイント安の1894.85と、反落して取引を終えた。買いが先行して取引が始まった後、米国株先物の下落を受けて輸出関連株を中心に売られた。出来高は12億9267万株。 【第2部】小幅安。ユニバンス、Abalanceが売られた。REMIXは反発。千代化建は続伸。出来高2億1922万株。 ▽高値と安値681円の差 2日の東京株式市場は乱高下に見舞われた。日経平均株価の朝方に付けた高値と午後の安値の差は681円と大きかった。 朝方は前日の米国株高を好感して幅広い銘柄が買われたが、米国株先物が時間外取引で下落すると、東京市場では買い注文が減少する一方、売り注文は急激に増え、値下がりに転じる銘柄が相次いだ。米国の景気や株価と連動性の高い電子部品や産業機械など輸出関連銘柄の値下がりが目立った。 日経平均は朝方に買いが優勢となる場面でも節目の3万円に届かなかった。市場関係者から「3万円に近い日経平均を割高とみる投資家が多く、当面の利益を確保する売りが出やすい」(インターネット証券)との指摘があった。 225先物は朝方に付けた3万0010円を天井に、午後は2万9310円まで売られた。オプション3月きりは先物の下落からコールが軒並み売られ、プットは総じて堅調だった。(了)日経平均は255円安と大幅反落、先物売り交え一段安、米株先物安に上海・香港株の下げも重し=2日後場モーニングスター現在値商船三井 3,220 -120郵船 3,005 -85川崎船 1,947 -62JAL 2,465 -89ANA 2,521.5 -55 2日後場の日経平均株価は前日比255円33銭安の2万9408円17銭と大幅反落。朝方は、1日の米国株高を受け、一時2万9996円39銭(前日比332円89銭高)まで上伸したが、一巡後は下げに転じた。先物売りを交えて一段安となり、後場早々には2万9314円82銭(同348円68銭安)まで下落する場面があった。時間外取引の米株価指数先物が安く、中国上海総合指数や香港ハンセン指数の下げも重しとなった。その後、いったん下げ渋ったが、戻りは限定され、大引けにかけて2万9400円前後でもみ合った。 東証1部の出来高は12億9267万株、売買代金は2兆6132億円。騰落銘柄数は値上がり745銘柄、値下がり1346銘柄、変わらず103銘柄。 市場からは「これまで一本調子で上がってきただけに当然の調整とみている。米追加経済対策法案が成立する見通しとなり、業績回復期待やコロナワクチンの話などが出ているが、材料出尽くしの面もあり、日柄調整に移るのではないか。ただ、基本的に過剰流動性は続いており、上昇トレンドに変わりはない」(国内投信)との声が聞かれた。 業種別では、商船三井 、郵船 、川崎汽 などの海運株や、JAL 、ANA などの空運株が下落。国際帝石 などの鉱業株や、日本紙 、大王紙 などのパルプ紙株も安い。近鉄エクス 、三井倉HD などの倉庫運輸関連株や、出光興産 、コスモエネH などの石油石炭製品株も値を下げた。東レ 、帝人 などの繊維製品株も売られた。 半面、マルハニチロ 、サカタのタネ などの水産農林株が堅調。クレセゾン 、JPX などのその他金融株も買われた。日立造 、クボタ などの機械株や、テルモ 、セイコーHD などの精密株も高い。 個別では、サンデンHD がストップ安となり、日本アジアG 、日東精 、エスクリ 、ラウンドワン などの下げも目立った。半面、ヒマラヤ がストップ高となり、セレス 、プロパティA 、ダイヤHD 、BEENOS などの上げも目立った。なお、東証業種別株価指数は全33業種中、25業種が下落した。【本日のNYダウ見通し】本日は様子見ムードが高まる展開か【NYダウ予想レンジ:31,300~31,700ドル】1日のNYダウは大幅反発。前日比603.14ドル高の31,535.51ドルで取引を終了しました。先週末に米下院が1.9兆ドル規模の追加経済対策を可決したほか、米食品医薬品局(FDA)が米ジョンソン・エンド・ジョンソンの新型コロナウイルスワクチンに、緊急使用許可をだしたことが好感されました。また、前週のNYダウ急落のきっかけになった米10年債利回りが、1.4%台前半で落ちついた動きになっていることも買い安心感につながっています。ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数も、396.48ポイント高の13,588.83と大幅高となりました。ただ、先週の木・金の2日間で1,000ドル超下落しているのでその反動の面も大きく、このまま上値追いの展開になるのは難しいでしょう。本日は重要な経済指標の発表はありません。4日のパウエルFRB議長の講演や5日の雇用統計を控え様子見ムードが高まりそうです。2日の日経平均は反落、"重し"となった3つの要因商社など市況関連株に売りブルームバーグ 2日の東京株式相場は反落。米国の長期金利の先行きを見極めたいとして買いが手控えられる中、原油など商品市況安や米株先物安が重しとなった。商社や鉱業、非鉄金属などといった市況関連をはじめ、サービスや小売りなど内需関連も売られた。 〈きょうのポイント〉 しんきんアセットマネジメント投信の藤原直樹運用部長は「過剰流動性相場の中で金利上昇を深刻にみていない投資家の押し目買い意欲が強い」とする半面、「ここまで一本調子で来たので利益確定は出てくる。皆が皆強気なわけではない」とも述べた。その上で、ことしの株式市場は、金利とインフレの状況をにらみながらの展開になりそうだとみていた。 朝方こそ上昇して始まったものの、午前半ばに主要指数は失速。今週は米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長が4日に米経済について発言する予定など、米金融当局者の発言や重要経済指標が相次ぐ。米国株のボラティリティー(変動性)が高まっているだけに、アジア時間2日の米株先物が軟調に推移したことで日本株の見直し買いも続かなかった。 ただ、大和証券投資情報部の石黒英之シニアストラテジストは、「商品市況の上昇による物価への影響を米金利は一気に先回りして織り込んだが、投機的な動きは一巡しつつある」と分析。欧州中央銀行(ECB)が急激な金利上昇を看過しない姿勢を示したのに続き、「米金融当局者のスタンスが今週明らかになれば金利は落ち着いてくる可能性がある」と話していた。 東証33業種では海運や空運、鉱業、石油・石炭製品、非鉄金属、電気・ガスが下落。機械や精密機器、証券・商品先物取引は上昇。ナノキャリアが大幅反発、遺伝子治療製品がアメリカで投与開始がん領域に特化した創薬ベンチャーのナノキャリア(4571)が大幅反発した。午後2時30分現在、前日比14円(4.2%)高の346円で推移している。一時は354円まで上伸した。本日午前9時30分に、提携先であるイスラエルの創薬会社VBLセラピューティクスが遺伝子治療製品「VB-111」を、アメリカで実施中の再発悪性神経膠芽腫を対象とした第2相臨床試験において投与を開始したと発表し、買い材料視された。同製品は当社がVBL社から国内開発販売権を取得している。「VB-111」はVBL社がアメリカを中心にプラチナ抵抗性卵巣がん、大腸がんを対象に開発を進めている。当社は、プラチナ抵抗性卵巣がんを対象にした第3相臨床試験に日本が参画するための治験計画書を、昨年11月に医薬品医療機器総合機構へ提出済み。現在は国内の治験実施施設での手続きが進んでいる。(取材協力:株式会社ストックボイス)明日の戦略-3万円に届かず大幅安、TOPIXは25日線を割り込むトレーダーズ・ウェブ 2日の日経平均は大幅反落。終値は255円安の29408円。米国株の大幅上昇や円安進行を手掛かりに、寄り付きは200円を超える上昇。しかし、そこから上げ幅を300円超に広げて3万円に迫ったところで、戻り売りに上値が抑えられた。これによりセンチメントが急速に悪化。値を消してマイナス圏に沈むと、一気に下げ幅を3桁に広げた。前場では29500円がサポートになったが、後場はスタートからこれを割り込むと、弱いところでは下げ幅を300円超に広げる場面もあった。売り一辺倒ではなく押し目を拾う動きも見られたが、終値では200円を超える下落となり、29500円を下回った。 東証1部の売買代金は概算で2兆6100億円。業種別では水産・農林やその他金融、機械などが上昇した一方、海運や空運、鉱業などが下落した。上方修正を発表したヒマラヤがストップ高。半面、第三者割当による新株発行を発表したサンデンホールディングスがストップ安となった。 東証1部の騰落銘柄数は値上がり745/値下がり1346。SMCやキーエンスなどFA関連が上昇。マネックスGやリミックス、セレスなど、暗号資産関連が急伸した。中国フリマアプリとの連携を発表したメルカリが大幅高となり、マザーズ指数の上昇に貢献。上方修正や増配を発表したNCS&Aが買いを集めた。 一方、ファーストリテイリングが上場来高値を更新した後に失速して3%近い下落。JALとANAが大きく売られたほか、HIS、串カツ田中、ベストワンドットコム、ラウンドワン、TKPなど、アフターコロナ関連が軒並み値を崩した。月次が失望を誘ったワークマンやクスリのアオキが軟調。LINEとの経営統合完了を発表したヤフーが大幅安となった。 日経平均は大幅安。米国株の強い上昇を受けて3万円乗せへの期待が高まったが、場中の動きが弱く、底打ちへの期待が後退した。失速の度合いが大きくなった背景には、米株先物の軟調があったと思われる。そのため、今晩の米国株が下落しても常識的な下げであれば、あすの売り圧力は限られるだろう。ただ、先物に大きく振らされる状況が続く間は、買いは恐る恐るとなりやすい。週末の米雇用統計を確認するまでは神経質な地合いが続きそうだ。日経平均は安値(29314円)でも25日線(29247円、2日時点、以下同じ)は下回らなかったが、TOPIXは終値(1894p)で25日線(1896p)を若干ではあるが下回った。2月に日経平均が大きく水準を切り上げる局面では、TOPIXが上昇を先導するような動きも見られた。それだけに、TOPIXがここで踏みとどまって反転できるかが、あす以降の大きな注目点となる。武田薬が続伸、三菱UFJモルガン証は「オーバーウエート」・目標株価6900円でカバレッジ開始モーニングスター現在値武田薬 3,676 +63 武田薬品工業 が続伸。三菱UFJモルガン・スタンレー証券では1日付で、レーティング「オーバーウエート」(強気)、目標株価6900円でカバレッジを開始した。2019年1月8日に完了したシャイアー社の経営統合は順調に進んでおり、買収時の財務目標であったノン・コア事業などの売却目標やネット有利子負債の圧縮、コストシナジーの実現などは目標を上回るスピードで進められているとコメント。 2024年度までに承認取得を見込むWAVE1の開発プログラムも着実に進捗してきており、投資家のマネジメントに対する信頼度は合併のアナウンス当時より高くなりつつあるとみるとコメントしている。同社マネジメントは2021年1月12日、2019年度から2030年度までの売上収益50%成長とする新たな目標を発表、これにはWAVE1からの寄与も当然見込まれており、投資家からのパイプラインへの注目度は今後高まる可能性が高いと考えるとしている。 2日の終値は、前日比63円高の3676円。今晩のNY株の読み筋=下値の限られた展開かモーニングスター 2日の米国株式市場は、下値の限られた展開とみる。 きょうはブレイナードFRB(米連邦準備制度理事会)理事やデイリー米サンフランシスコ連銀総裁の発言機会があるほかは注目したい米経済指標の発表も少ない。手掛かり材料が乏しいなか、米国株は前日に大きく上昇した反動もあり、利益確定売りが上値を抑えそう。 一方、米2月ISM製造業景気指数では雇用指数を含めて良好な結果だったことから、あすの米2月ADP雇用統計や週末の米2月雇用統計などへの期待も高い。引き続き米長期金利の動向を見ながら神経質な展開が予想されるが、金利が落ち着いている限り、下値では押し目買いが入りそうだ。<主な米経済指標・イベント>ブレイナードFRB(米連邦準備制度理事会)理事、デイリー米サンフランシスコ連銀総裁が講演◎投資関連情報は投資の参考として情報提供のみを目的としたものであり、株式の売買は自己責任に基づき、ご自身で判断をお願いします。明日の日本株の読み筋=様子見ムードか、米長期金利にらみ続き重要指標など控えるモーニングスター あす3日の東京株式市場は、様子見ムードか。引き続き米長期金利や海外株式動向にらみの展開ながら、現地3日に米2月ADP雇用統計、米2月ISM非製造業景況指数、4日にパウエルFRB(米連邦準備理事会)議長の講演、週末5日には米2月雇用統計の発表が予定されており、見極めたいとの空気から積極的な売買が手控えられる可能性がある。ただ、日経平均株価のボラティリティ(価格変動率)はなお高く、外部要因に振られやすい面もある。 2日の日経平均株価は大幅反落し、2万9408円(前日比255円安)引け。朝方は、1日の米国株高を受け、上げ幅は一時330円を超えたが、買い一巡後は下げに転じた。時間外取引の米株価指数先物が安く、中国上海総合指数や香港ハンセン指数の下げも重しとなり、下げ幅は一時350円近くに達した。その後は下げ渋ったが、戻りは限定された。市場では、「先週の急落を見ているだけに上は買いづらい。米長期金利は折に触れ上昇しやすく、米日ともに調整局面入りの可能性がある」(銀行系証券)との声が聞かれた。ワクチン接種した60代女性、3日後に死亡…因果関係不明(読売新聞) 厚生労働省は2日、新型コロナウイルスワクチンの接種を受けた医療従事者の60歳代の女性が死亡したと発表した。厚労省によると、女性は2月26日に接種を受け、3月1日に亡くなった。死因はくも膜下出血とみられる。接種との因果関係は不明で、厚労省は慎重に調べる。二つの病院クラスターで規模が拡大 岐阜県内で新たに9人の新型コロナ感染確認 岐阜県と岐阜市は2日、県内で新たに20代~80代の男女9人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の累計感染者数は4634人となった。 病院で発生した二つのクラスター(感染者集団)で規模が拡大した。 木沢記念病院(美濃加茂市)関連では、新たに医療従事者1人の陽性が判明し、合わせて229人に。瑞浪市の東濃厚生病院関連では、転院後に患者の感染が分かった高井病院(土岐市)の医療従事者2人と入院患者2人の計4人の感染が分かり、21人規模となった。新たなクラスターの確認はなかった。 新規感染者の居住地別は土岐市2人、岐阜市、多治見市、中津川市、各務原市、可児市、羽島郡岐南町、同郡笠松町が各1人。年代別は20代2人、30代3人、50代1人、60代2人、80代1人。NY株見通し-底堅い展開か 決算発表はターゲットなどトレーダーズ・ウェブ 今晩のNY市場は底堅い展開か。昨日は追加経済対策期待が続く中、ワクチン接種の進展期待でエネルギーや金融などの景気敏感株が軒並み上昇したほか、長期金利の上昇が一服したことでハイテク・グロース株も大きく上昇し、主要3指数がそろって大幅上昇した。今晩の取引では、昨日の大幅高の反動安が懸念されるものの、追加経済対策やワクチン普及による景気回復期待、長期金利の上昇が一服したことが引き続き相場の支援となりそうだ。ターゲットなどの消費関連株の決算発表や金融当局者の発言にも注目。 今晩の米経済指標・イベントは2月ニューヨークNAPM指数、2月ISM NY景気現況指数のほか、ブレイナードFRB理事、デイリー米サンフランシスコ連銀総裁の講演など。企業決算は寄り前にターゲット、ロス・ストアーズ、引け後にヒューレット・パッカード・エンタープライズなどが発表予定。〔NY外為〕円、106円台後半(2日朝)時事通信 【ニューヨーク時事】2日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、1ドル=106円台後半でもみ合っている。午前9時現在は106円85~95銭と、前日午後5時(106円71~81銭)比14銭の円安・ドル高。 米長期金利の上昇基調が一服する中、この日の朝方は米主要経済指標の発表がなく円相場は、新規材料難から107円付近で小動きとなっている。ただ、米大型追加景気対策が間もなく成立するとの観測や、新型コロナワクチンの普及による早期の経済正常化に期待が強まる中で円売り・ドル買いの動きは依然として根強い。高金利通貨に対してドルを買う動きが対円相場にも波及し、円を押し下げている面もある。 ユーロは同時刻現在、対ドルで1ユーロ=1.2025~2035ドル(前日午後5時は1.2044~2054ドル)、対円では同128円55~65銭(同128円55~65銭)と同水準。(了)〔米株式〕NYダウ、もみ合い=ナスダックは小安い(2日朝)時事通信 【ニューヨーク時事】2日のニューヨーク株式相場は、前日の騰勢が一服し、もみ合いとなっている。優良株で構成するダウ工業株30種平均は午前9時35分現在、前日終値比9.94ドル高の3万1545.45ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は24.39ポイント安の1万3564.44。(了)今夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中の11銘柄が値を上げてスタートしましたね。5%以上の大きな変動は見られませんね。モデルナ、5日にも承認申請 ワクチン3社目、2500万人分 共同通信社 (AP=共同) 米バイオテクノロジー企業モデルナと武田薬品工業が、5日にもモデルナが開発した新型コロナウイルスワクチンの承認を厚生労働省に申請することが2日、分かった。複数の関係者が明らかにした。国内での承認申請は3社目。既に承認された米ファイザー製より、輸送や保管が容易とされる。 日本政府は、6月末までに4千万回分、9月末までに1千万回分の供給を受けることで同社と契約済み。接種は28日の間隔を空けて2回で、契約供給量は2500万人分に相当。 厚労省は、国内外の臨床試験(治験)のデータを基に承認の可否を審査する。ワクチンは海外の工場で製造し、武田薬品は国内の流通を担う。富山県が日医工に業務停止命令へ北日本放送 富山市に本社を置くジェネリック医薬品製造大手の「日医工」に対し、富山県が3日、業務停止命令を出す方針を固めたことがわかりました。記録の不備など、管理体制に問題があったと判断したもので、期間はおよそ1か月となる見込みです。 日医工は去年3月から滑川市の工場で製造工程や品質管理の状況を調査しました。その結果、品質試験の際の記録の不備などが発覚し、高血圧薬など75製品を自主回収しています。 健康被害は確認されていませんが、富山県は、自主回収した製品数が多いことから、管理体制に問題があったと判断し、行政処分を出す方向で検討を進めていました。 処分は、「許可取り消し」「業務停止」「業務改善」のうちの「業務停止」で、期間は、富山第一工場の製造部門が30日前後、子会社などから医薬品を仕入れ販売することなどを含む製造販売部門が20日前後となる見込みです。
2021.03.02
コメント(0)
-
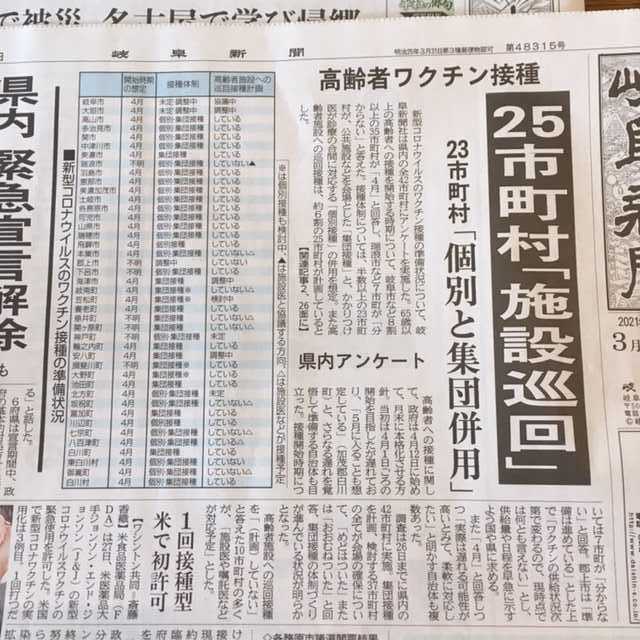
3月1日(月)…
3月1日(月)、晴れです。もう春ですね。そんな本日は7時15分頃に起床。新聞に目を通し、朝食を済ませ、ロマネちゃんと戯れる。身支度をして、三七日でのお寺さんの来訪に向けて1階の掃除…。9時から三七日の法要。朝のコーヒーブレイクはネスプレッソで…。ヴィタメールのチョコレートと共に…。美味い!!今朝の新聞より…今週の運勢は…1USドル=106.61円。1AUドル=82.75円。現在の日経平均=29573.43(+607.42)円。金相場:1g=6620(-93)円。プラチナ相場:1g=4610(-24)円。本日の東京市場ではチェック中の日本株30銘柄中の21銘柄が値を上げてスタートしましたね。重点6銘柄では5銘柄が値を上げてスタートしましたね。日本コンクリートが大きく下げて、TOWAが上げていますね。【今朝の5本】仕事始めに読んでおきたいニュース 今週は金曜日に2月の米雇用統計が発表されます。イエレン財務長官は「900万人余りの国民がなお失業している」と危機感を隠しません。同氏や米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長が注目するのは、回復から置き去りにされている「女性と人種的マイノリティー」です。金融・財政両面からの景気支援がいつ変化を迎えるのか見極めるヒントは、雇用統計のヘッドラインの数字よりも、人種や性別、年齢層、学歴別のデータにあるかもしれません。以下は一日を始めるにあたって押さえておきたい5本のニュース。 解除は慎重に米国立アレルギー感染症研究所のファウチ所長は、新型コロナのワクチン普及が加速しても、自信を持って経済活動を再開するには新規感染者数のベースラインが一段と低下する必要があると指摘した。同氏はNBCの番組で、新規感染者数が30万人から7万人前後に減少したものの、「なお高過ぎる」と発言。特にカリフォルニア州やニューヨーク州などで懸念される変異株が確認されていると指摘し、「高止まりを回避しなければならない」と述べた。 オマハの賢人から手紙著名投資家ウォーレン・バフェット氏のバークシャー・ハサウェイは、過去最大となる247億ドル(約2兆6300億円)相当の自社株を買い戻した。同氏は投資家への年次書簡で、今後も継続する可能性が高いことを示唆。また1200億ドル規模になったアップルへの投資が、長年育てた鉄道事業資産と同等の重みを持つことを明らかにした。保有額上位15銘柄には伊藤忠商事が含まれた。書簡では新型コロナに一度だけ触れたものの、米議会乱入事件や人種問題など政治的な話題に踏み込まず、一部では「残念だ」との指摘もあった。 一緒に移籍ゴールドマン・サックス・グループのコンシューマーバンキング進出を率いるオマール・イスマイル氏は同社を退社し、ウォルマートのフィンテックベンチャーを率いる。関係者らによれば、同氏の右腕だったデービッド・スターク氏もこのベンチャーに参加する。ゴールドマンはイスマイル、スターク両氏の責務を拡大したばかりだった。伝統的な投資銀行の殻を破ろうとしていた同社にとって予想外の痛手となる。 春節マイナス効果中国の製造業活動を測る政府の指数が2月も低下した。春節(旧正月)の連休に伴う生産の中断があったほか、新型コロナ感染拡大を防ぐための旅行自粛でサービス業向けの支出が減少した。2月の製造業購買担当者指数(PMI)は50.6と、9カ月ぶりの低水準。ブルームバーグのエコノミスト調査で見込まれていた51(中央値)にも届かなかった。製造業活動を示すデータは、年ごとに時期が異なる春節の連休でゆがみが生じるのが一般的。今年の春節は2月だった。 流血のデモミャンマー国軍のクーデターに抗議する週末のデモ活動で、少なくとも18人が治安当局による弾圧で死亡した。国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)の報道官は28日の声明で、ミャンマー6都市で軍や警察が鎮圧に実弾を使用し、デモ隊に死者が出たと非難。負傷者は30人を超えたという。ミャンマー政府は一方で、死者数を12人としている。バフェット氏、アップル投資の重要性を指摘-伊藤忠が上位15位入り 米投資家のウォーレン・バフェット氏は27日公表した年次書簡で、1200億ドル(約12兆7860億円)規模になったアップルへの投資が、長年育てた鉄道事業資産と同等の重みを持つことを明らかにした。保有額上位15銘柄には伊藤忠商事が含まれた。 バークシャー・ハサウェイは2018年までアップル株を買い増ししてきたが、それ以降は持ち分を縮小する傾向にあり、2020年には110億ドルの売却益を手にしている。ただアップルが自社株買いを実施したことで、発行済み株式数が減少し、結果的にバークシャーの保有比率は上昇した。 バフェット氏は「バークシャーは株式を売却したのに、何とアップルの5.4%を保有する」と指摘。「われわれは何もコストを払わずに保有率を高めることができた。それもアップルが継続的に自社株を買ってくれるからだ」と説明した。 書簡ではバークシャーの保有額上位15銘柄の一つとして、伊藤忠株の5.1%、時価総額にして23億3600万ドル(約2490億円)が記載されている。日本株反発、米金利上昇一服や米株先物堅調推移-輸出など広く高い 1日の東京株式相場は上昇。米国の急激な長期金利上昇が一服したことや為替の円安、国内緊急事態宣言の一部解除を好感し、電機や自動車など輸出関連、情報・通信、不動産株など内外需とも広く高い。 TOPIXは前営業日比28.21ポイント(1.5%)高の1892.70-午前9時4分現在 日経平均株価は571円59銭(2%)高の2万9537円60銭 〈きょうのポイント〉 先週末の米10年債利回りは11ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の1.41% 週明け1日アジア時間の米株先物は堅調推移 きょうのドル・円相場は1ドル=106円50銭台で推移、前営業日の日本株終値時点は106円20銭 緊急事態宣言、大阪など6府県で2月末に解除-首都圏は継続 2月の中国製造業購買担当者指数(PMI)は9カ月ぶり低水準-サービス業も低迷 東海東京調査センターの平川昇二チーフグローバルストラテジストは「10年債利回りが一方的に上がる状況は小休止した。緊急事態宣言が一部地域で解除されるのも国内景気にプラスだ」と指摘した。その一方、米国株は不安定で「まだ安心できる状態にはない」とも話していた。 東証33業種では精密機器や機械、電機、不動産、情報・通信が上昇 鉱業や空運、海運は下落【米国株動向】今後10年間保有したいハイテク銘柄3選モトリーフール米国本社、2020年2月17日投稿記事よりテクノロジーには革新的な変化が起きる傾向があるため、ハイテク銘柄を賢く選ぶことはとても重要です。まずは、継続的に革新を起こし、独自の市場を先導し続けることができる企業を見出すことです。また、そのような立場を少なくとも10年間は維持するとみられる銘柄を見つけると良いでしょう。アップル(NASDAQ:AAPL)、アルファベット(NASDAQ:GOOG)(NASDAQ:GOOGL)、フェイスブック(NASDAQ:FB)はこの条件に当てはまります。さらに、これらの企業は収益性が高く、四半期ごとに多額のキャッシュフローを創出しています。 アップル同社は継続的に革新を起こし、ハイテク業界で重要な位置にあることを示し続けています。iPhoneの新モデルが昨年終盤に発売開始されたことから、直近四半期の端末売上高は前年同期から17.2%増加しました。同社のハードウェア製品事業の成長を補うのが、AppleCare(保証サービス)、アップストア(アプリダウンロードサービス)、Apple TVプラス(ビデオ・オン・デマンドサービス)などを扱うサービス部門で、同部門の売上高総利益率はハードウェア製品部門の2倍近くにのぼります。サービス部門の2021年第1四半期(2020年10~12月)売上は同社売上全体の14%を占め、前年同期から24%増加しました。同部門の売上成長は会社全体の伸びよりも早いことから、収益性が高いサービス事業が全体に占める割合は年々拡大していくとみられます。自社株買いと利益の増加により、過去10年間に1株あたり利益は年平均19.7%で伸びました。今後10年間も同社には良好なリターンを期待できるでしょう。 フェイスブック同社はソーシャルメディア企業として人気のアプリで人々をつなげるだけでなく、株主を利益に結び付けることでも知られています。過去10年間にフェイスブックは1株あたり利益を年平均50.4%で増やしました。そして同社は既に巨大にもかかわらず、一連のアプリ群(Family of apps)を通じていまだにユーザーを増やし続けています。同社の全アプリ(フェイスブック、インスタグラム、ワッツアップ)の月間アクティブユーザー(MAU)は2020年の間に3億人増え、33億人に達しました。フェイスブックの予想利益ベースの株価収益率(PER)は24.25倍と(執筆時点)、競合のピンタレスト、ツイッター、スナップと比較するとずっと割安です。 アルファベット試算によれば、同社のグーグル検索エンジンは世界の市場で91.9%ものシェアを占め、その主導的位置づけから今後何年にもわたり健全な利益を創出するとみられます。グーグルクラウド部門は全社に占める割合としては未だ小さいものの、急激に伸びています。同部門の2019年および2020年の売上はそれぞれ53%と46%伸びました。グーグルクラウドはまだ利益を出していませんが、黒字化は時間の問題とみられます。過去10年間にアルファベットの売上は年平均20%で伸び、営業利益も少なくとも同20%を維持しました。同社は中核事業で支配的な位置づけにあることから、投資家は同様の伸びを今後も期待できるでしょう。【市況】前場に注目すべき3つのポイント~米金利動向を警戒しつつ、いったんは調整一巡感~1日前場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。■株式見通し:米金利動向を警戒しつつ、いったんは調整一巡感■Jパワー、21/3業績予想 営業利益700億円、コンセンサス下回る■前場の注目材料:武田薬帝人ファーマに糖尿病薬4剤を1330億円で売却■米金利動向を警戒しつつ、いったんは調整一巡感1日の日本株市場は、先週末の大幅下落に対する自律反発が意識されやすいだろう。2月26日の米国市場ではNYダウが469ドル安となる一方でナスダックは反発。長期金利上昇への警戒から売り優勢の相場展開となり、月末でヘッジファンドなどが損失確定のための持ち高解消に動いたなどとの憶測も重しとなった。ただし、米国債相場が行き過ぎ感などから反発し、金利が低下に転じたため足元で大きく下げていたアップルやマイクロソフトなどを中心にハイテク株が買い戻され、ナスダックはプラス圏で推移した。シカゴ日経225先物清算値は大阪比35円高の29285円。円相場は1ドル106円50銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする格好から買い先行の展開になろう。先週末の日経平均は1200円を超える大幅下落となり29000円を割り込んでいる。1月末以来の25日線を割り込んでおり、いったんは自律反発が意識されやすいところである。足元では米長期金利の上昇が警戒視されており、上値追いは慎重になりやすく戻りの鈍さは想定されるものの、月末のリバランス需給は通過している。そのため1月末同様、25日線レベルからのリバウンドをみせてくるかが注目されそうである。一方で米長期金利の上昇基調が一段と強まるとの見方がされている。ワクチン接種が進むことによる経済活動の正常化への期待や1.9兆ドル規模の追加経済対策が3月中旬までに速やかに成立する可能性なども景気回復へ向かわせるとして金利先高観は強いだろう。金利は依然歴史的に低い水準で、実質金利はマイナス。回復期待に伴い、インフレや金利の上昇が予想されるが、その速さが問題となっており、上昇ピッチが強まる場面においては割高感が指摘されているハイテク株などへの利益確定の流れが強まる可能性はありそうだ。日経平均はリバウンドの鈍さが意識される場面においては、テクニカル面では75日線が位置する27500円辺りが下値のターゲットとみる向きが増えそうである。ただし、日銀は先週末の下落場面において2月に入り初めてETFを501億円買い入れた。金融緩和の点検公表まではETF購入は見送られるとの見方もあっただけに、心理的に売り込みづらくさせることになるだろう。■Jパワー、21/3業績予想 営業利益700億円、コンセンサス下回るJパワーは未定としていた2021年3月期業績予想を発表。現在電力市場価格の高騰が収束し、今後の業績見通しを合理的に算定できる環境になったとして、営業利益は前期比16.3%減の700億円とした。コンセンサス(790億円程度)を下回る。■前場の注目材料・ナスダック総合指数は上昇(13192.34、+72.91)・シカゴ日経225先物は上昇(29285、大阪比+35)・1ドル106円50-60銭・SOX指数は上昇(3067.62、+68.46)・VIX指数は低下(27.95、-0.94)・米長期金利は低下・日銀のETF購入・海外コロナ向けワクチン接種の進展・世界的金融緩和の長期化・武田薬帝人ファーマに糖尿病薬4剤を1330億円で売却・日産自「eパワー」向け発電専用エンジンで熱効率50%実現・トヨタFCシステム、外販、豊田織機は小型用開発・三菱重CO2利用技術の米社に出資・蛇の目両手操作式サーボプレス、欧州に続き国内投入・宇部興産宇部藤曲工場でアンモニア生産を再開・日華化学環境・健康・先端材料に重点、23年12月期売上高500億円狙う・日本コークス伊藤忠とベルギー社と事業化調査、水素地産地消で☆前場のイベントスケジュール<国内>・特になし<海外>・10:45 中・2月財新製造業PMI(予想:51.3、1月:51.5)《ST》 提供:フィスコ【材料】伊藤忠---大幅反発、米バークシャーの大量保有が明らかになり伊藤忠は大幅反発。著名投資家ウォーレン・バフェット氏率いる米バークシャー・ハザウェイが週末に「株主への手紙」を公開、同社株が日本企業として初めて保有額上位15銘柄に入ったことが明らかになっている。保有時価は約23億ドルであり、約5億ドルの含み益となっているもよう。長期的な投資対象としての位置づけが高まる形となり、評価の動きが一段と高まる格好になっている。《ST》 提供:フィスココリン・モリカワがツアー4勝目 松山英樹は崩れ15位T、稲森佑貴は48位T<WGC-ワークデイ選手権アット・ザ・コンセッション 最終日◇28日◇コンセッション・ゴルフ・クラブ(米フロリダ州)◇7564ヤード・パー72>世界ゴルフ選手権シリーズ今季初戦の最終日。首位からスタートしたコリン・モリカワ(米国)がトータル18アンダーまで伸ばし、今季初優勝。昨年8月の「全米プロゴルフ選手権」以来のツアー4勝目を飾った。3打差の2位タイにブルックス・ケプカ、ビリー・ホーシェル(ともに米国)、ビクトル・ホブラン(ノルウェー)が入った。首位と5打差からスタートした松山英樹は3バーディ・3ボギー・1ダブルボギーの「74」と崩れ、トータル8アンダーの15位タイ。稲森佑貴は「78」のラウンドでトータル3オーバーの48位タイでフィニッシュした。ローリー・マキロイ(北アイルランド)はトータル12アンダーの6位タイ。ジャスティン・トーマス(米国)は松山と同じトータル8アンダーの15位タイ。世界ランキング1位のダスティン・ジョンソン(米国)はトータル5オーバーの54位タイに沈んだ。メジャー「62」の記録保持者、ブランデン・グレイスが優勝 小平智は49位T<プエルトリコ・オープン 最終日◇28日◇グランド・リザーブCC(プエルトリコ)◇7506ヤード・パー72>世界ゴルフ選手権シリーズの裏で開催されている米国男子ツアーの「プエルトリコ・オープン」最終日。首位と1打差から出たブランデン・グレイス(南アフリカ)が6つ伸ばしトータル19アンダーで逆転。2016年の「RBCヘリテイジ」以来の米ツアー2勝目を挙げた。終盤の17番パー4で2打目入れてイーグル。最終ホールもバーディとしたグレイス。17年の「全英オープン」3日目に「62」を叩き出して海外メジャー最少ストロークの記録を持っており、爆発力を証明してみせた。1打差の2位にジョナサン・ベガス(ベネズエラ)。首位タイ発進で地元のラファエル・カンポス(プエルトリコ)はトータル16アンダーの4位に終わった。32位タイから出た小平智は3バーディ・3ボギーの「72」で回り、トータル5アンダーの49位タイで大会を終えた。マツモトキヨシ---大幅反発、ココカラファインとの経営統合契約締結を発表フィスコ現在値マツキヨH 4,625 +445マツモトキヨシは大幅反発。ココカラファインとの経営統合契約締結を先週末に発表している。10月に共同の持ち株会社「マツキヨココカラ&カンパニー」を発足させ、両社グループが傘下に入ることになる。20年1月に経営統合で基本合意し、ここまで組織体制や統合の段取りについて協議してきた。ココカラファイン1に対して同社株1.70株が割り当てられる。本日は両社ともに株価が上昇、正式発表受け統合でのスケールメリットなどを期待する動きが優勢に。《ST》<米国株情報>メルク、バイオ医薬品パンディオンを買収へモーニングスター現在値NF NASDAQ-100 14,120 +460NF NYダウ30種 32,500 +150P500米株 4,445 +60P500 ETF 40,950 +500SAM NYダウETF 29,220 +20 医薬品大手メルク<MRK>は2月25日、自己免疫疾患治療部門を強化するため、バイオ医薬の中堅企業で自己免疫疾患治療向けTALON(治療用自己免疫制御たんぱく質)薬剤を製造するパンディオン・セラピューティクス<PAND>を18億5000万ドル(約1970億円)の現金で買収すると発表した。 パンディオンの株主は1株につき60ドル受け取る。これはパンディオンの2月24日終値に対し、134.1%のプレミアム(上乗せ額)となっている。買収手続きは6月までに完了する予定。米国株の強気派ひるまず、先週の債券波乱でも株式ETFに資金流入Bloomberg(ブルームバーグ): 債券市場を1年ぶりに襲った高いボラティリティーに株式投資家は悩まされる素振りを全く見せていない。勇敢な決意からか、途方もない純朴さによるものか、いずれにせよひるんでいない。米国債利回りが急上昇し、株式市場全般に下押し圧力がかかった先週、米国の上場投資信託(ETF)には資金が一貫して流入。市場の波乱がピークに達した2月25日には27億ドル(約2900億円)が殺到した。ブルームバーグの集計データによると、2月の合計ではETFへの資金流入は過去12カ月平均の4倍の800億ドルに上った。背景にはS&P500種株価指数を11カ月で70%上昇させてきたのと同じ楽観がある。利回りの急上昇で株式バリュエーションの支えが1つ損なわれるものの、強気派はそれを経済の力強さのサインとし、企業収益を後押しすると受け止めている。バンテージポイント・インベストメント・アドバイザーズのウェイン・ウィッカー氏は「投資家は今の市場を見て、『思ったよりも早く回復しそうだ。それに応じて自分の態勢を整える必要がある』と話している」と述べ、「チャンスを逃し投資が不十分になることへの不安がある」と指摘した。株式相場に強気な見方は最近、試練にさらされている。先週は米10年国債利回りが1年ぶりの高水準に達し、バリュエーションが高かった人気株が大きな打撃を受けたほか、ナスダック100指数は昨年10月以来の週間下落率を記録した。それでも投資家は押し目を買った。25日の相場急落中も、パニックの兆候はほとんどなかった。同日の出来高は年平均とほぼ同水準で、シカゴ・オプション取引所(CBOE)ボラティリティー指数(VIX)のスポット価格は先物の第1限月と第2限月を下回る水準にとどまり、逆ざやを形成しなかった。ボケ・キャピタル・パートナーズのキム・フォレスト最高投資責任者(CIO)は、「投資家が押し目買いに慣れた理由は多い。米国内総生産(GDP)成長率は6%以上になるとほぼすべてのエコノミストが考えている。泡立ちかねないインフレの見通しは一部あるが、生活を変えるような恐ろしいインフレは経験していないため、インフレは警戒されていない」と語った。午後からは金融機関を回ったりと雑務処理…。〔東京外為〕ドル、106円台半ば=米長期金利眺め下落(1日午後3時)時事通信 1日午後の東京外国為替市場のドルの対円相場(気配値)は、一時買いが強まったものの、米長期金利の軟化を受けて1ドル=106円台半ばに下落した。午後3時現在は、106円53~53銭と前週末(午後5時、106円08~08銭)比45銭のドル高・円安。 ドル円は早朝、106円40~50銭台で推移した。午前9時以降は米長期金利が水準を上げたことから買い優勢となり、実需の売りも加わったことから一時106円70銭近辺まで浮上。米国の景気回復への期待感から安全資産とされる円が売られたこともドルの支援要因となった。ただ、ドル買いは続かず、午後3時にかけては軟調な米長期金利を眺め106円50銭台に水準を切り下げている。 今夜はブレイナードFRB理事の講演や2月の米ISM製造業PMI発表などが予定されている。ブレイナードFRB理事の講演については「足元の金利水準について、これまでのFRB要人の発言と同様に静観姿勢ならば、長期金利は高止まりとなりドル円はしっかりの流れになるだろう」(国内証券)との指摘があった。 ユーロも正午と比べ、対円は小安く、対ドルでは横ばい。午後3時現在、1ユーロ=128円73~73銭(前週末午後5時、128円72~72銭)、対ドルでは1.2083~2087ドル(同1.2134~2134ドル)。(了)〔東京株式〕大幅反発=投資家心理落ち着く(1日)☆差替時事通信 【第1部】米長期金利の上昇が一服したことで投資家心理が落ち着き、直近の相場下落で値頃感が強まった銘柄に押し目買いが入った。日経平均株価は前営業日比697円49銭高の2万9663円50銭、東証株価指数(TOPIX)は37.99ポイント高の1902.48と、いずれも大幅反発。 88%の銘柄が値上がりし、値下がりは10%だった。出来高は12億5001万株、売買代金は2兆4773億円。 業種別株価指数(33業種)は全て上昇した。パルプ・紙、情報・通信業、建設業の上昇が目立った。 個別銘柄ではソフトバンクG、NTTデータが値を上げた。ファーストリテ、リクルートHD、三井住友はしっかり。ソニー、東エレク、村田製が買われた。王子HD、大和ハウスも高い。トヨタは強含み、キーエンスは小幅高。半面、マネックスG、商船三井、JR東海がさえない。イオンは続落。シャープは軟調。キリンHD、アサヒが小幅安。 【第2部】堅調。ツインバードがにぎわい、千代化建はしっかり。半面、REMIXは売りに押された。出来高1億6598万株。 ▽自律反発 1日の東京株式市場は押し目買いが優勢となり、日経平均株価は自律反発した。前週末(2月26日)の米国株式市場でハイテク株が堅調となった流れを引き継ぎ、情報通信株や半導体関連株などが人気を集めた。 日経平均株価は453円高で始まり、ほどなく上げ幅は700円超に拡大した。その後は頭打ち感が強まる場面もあり、売り買い交錯となった。 ある市場関係者は「最近は月初や週初に相場が強くなる傾向があり、きょうも同様だった。ただ、腰の入った(長期投資家の)資金が入っているとは考えにくかった」(中堅証券)と指摘。前週末の日経平均急落の余波で、米長期金利の先行きに対する警戒感はまだ強いとみていた。別の関係者は「買いは個人が主体で、商いが伸びない」(大手証券)と話していた。 225先物3月きりは買い優勢で始まった後、午後はプラス圏で小動き。225オプション3月きりはプットがさえず、コールはまちまち。(了)日経平均は697円高と大幅反発、全33業種が上昇、米株先物高にアジア株高も支え=1日後場モーニングスター 3月1日後場の日経平均株価は前週末比697円49銭高の2万9663円50銭と大幅反発。東証業種別株価指数は全33業種が上昇した。朝方は、前週末に米長期金利の上昇が一服し、米ナスダック総合指数が反発した流れを受け、ハイテク株中心に買い戻しが先行した。前週末の大幅反落(1202円26銭安)の反動や、時間外取引(日本時間1日)の米株価指数先物高も後押しし、前場の早い段階に2万9686円39銭(前週末比720円38銭高)まで上伸した。その後、利益確定売りに伸び悩む場面もあったが、中国・上海総合指数や香港ハンセン指数などのアジア株高も支えとなり、大引けにかけて高値圏で推移した。 東証1部の出来高は12億5001万株、売買代金は2兆4773億円。騰落銘柄数は値上がり1931銘柄、値下がり229銘柄、変わらず34銘柄。 業種別では、王子HD 、大王紙 、北越コーポ などのパルプ紙株が上昇。ソフバンG 、NTTデータ 、トレンド などの情報通信株も高い。大和ハウス 、清水建設 、大林組 などの建設株や、7&iHD 、マツモトキヨ などの小売株も堅調。ダイキン 、クボタ などの機械株や、東エレク 、アドバンテスト 、京セラ などの電機株も買われた。日水 、マルハニチロ などの水産農林株も値を上げた。 個別では、中外炉 、ips 、ユニデンHD 、日産東HD 、オンワードH などの上げが目立った。半面、ランド 、沢藤電機 、学研HD 、バリューHR 、エアトリ などの下げが目立った。本日の東京市場ではチェック中の日本株30銘柄中の26銘柄が値を上げて終了しましたね。重点6銘柄では5銘柄が値を上げて終了しましたね。長谷工、ひらまつ、TOWAが大きく上げて、野村マイクロ、レノバも上げましたね。最も裕福な1%の仲間入り、ハードル高いのはモナコやスイス 世界の国・地域で最も裕福な1%の仲間入りを果たすのは決して容易ではないが、モナコでは特に難しい。 不動産仲介のナイト・フランクの調査によると、モナコでは約800万ドル(8億4500万円)持っていないと1%クラブに入れない。スイスは510万ドル、米国は440万ドルと、両国ともハードルが高い。シンガポールは290万ドル。 モナコの住民は通常、所得税を払わなくていい。ナイト・フランクのグローバル調査責任者リアム・ベイリー氏は、「ランキングトップには税制の影響が顕著だ」と指摘。米国については 「市場の幅と深さ」に言及した。 調査結果は新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)が国・地域間の貧富の格差を広げたことを浮き彫りにする。モナコで最も裕福な1%に入るための最低資産額は、30カ国・地域で最下位のケニアの400倍近くだった。 調査によると、超富裕層の人数では中国や香港などアジア太平洋地域で最近見られる富の急拡大にもかかわらず、米国が依然リードしている。ただ、ナイト・フランクによれば同地域の超富裕層の増加ペースは2020-25年にかけて引き続き世界を上回る見込みで、資産3000万ドル超の人の数がインドやインドネシアを中心に33%増えると予想されている。【本日のNYダウ見通し】買い戻し優勢の展開か【NYダウ予想レンジ:30,800~31,300ドル】26日(金)のNYダウは469.64ドル安の30,932.37ドルで取引を終了。米10年債利回りの上昇により2日間で1,000ドル超の下落となりました。ただハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は、72.96ポイント高の13,192.35で取引を終了しており、IT・ハイテク株には押し目買いも入っています。週明けのアジア市場は買いが優勢の展開。13時時点のNYダウ先物も210ドル高と大幅に上昇しています。先週末に米下院で1兆9,000億ドル規模の追加経済対策案が可決。上院通過は難しいと見られているものの、追加経済対策の進展への期待が高まっているのです。今晩のNY市場でも買いが優勢になる展開が予想されます。本日の経済指標ではISM製造業景況指数に注目。また、ブレイナードFRB理事やボスティック・アトランタ連銀総裁の発言に関心が集まりそうです。日経平均は大幅反発、697円高と今年1番の上げ幅 米長期金利の上昇一服[東京 1日 ロイター] -東京株式市場で日経平均は大幅反発した。前週末の日経平均は1202円26銭安の2万8966円01銭と急落したが、米長期金利の上昇が一服したことを好感し、きょうは自律反発で上値を追う展開となった。終値の上げ幅としては、今年1番の大きさ。値がさ株を中心に買い戻しの動きが活発となり、一時720円超高となる場面もあった。市場からは「米長期金利の動向にマーケットの注目が集まる状況は当面続きそうだが、足元ではいったん上昇に一服感が見られ、投資家心理は改善している。ただ、市場は新型コロナウイルスのワクチン普及や企業業績の改善を既に織り込んでいる面もあり、日経平均が3万円を回復しても、そこからさらに上値を追うには強材料が必要になりそうだ」(SMBC信託銀行・投資調査部長、山口真弘氏)との声が聞かれた。また、「前週末に日銀が通常のETF(上場投資信託)を501億円購入したことも、投資家の安心感につながったようだ」(国内証券)との見方もあった。TOPIXは2.04%高で取引を終了。東証1部の売買代金は2兆4773億円。東証33業種では全業種が値上がりし、パルプ・紙、情報・通信業、建設業、小売業などが値上がり率上位に入った。個別では、マツモトキヨシホールディングスが14%高と大幅反発し、東証1部の値上がり率第1位となった。ココカラファインとの経営統合契約締結の発表が好感された。ココカラファインは9%超高。東証1部の騰落数は、値上がり1931銘柄に対し、値下がりが229銘柄、変わらずが34銘柄だった。情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者1億1412万人超 死者約263.52万人[ベンガルール 1日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で1億1412万人を超え、死者は263万5198人となった。68人に1人がコロナウイルスに感染した。2954人に1人がコロナウイルスで死亡した。ワクチン接種で重篤な副反応が出る確率よりはるかにリスキーですよね。ワクチン接種で重篤な副反応が40万人に1人出たとしても、コロナウイルスによる発症リスクを5%以下にできるのであれば、ワクチン接種ですよね。長谷工が急反発、自己株取得で需給改善期待が台頭 マンション建築首位の長谷工コーポレーション(1808)が急反発した。午後0時40分現在、前営業日比54円(4.10%)高の1372円で推移している。2月26日に自己株式の取得を発表し、株式需給の改善や実質1株利益の上昇を期待した買いが活発化した。 自己保有株を除く発行済み株式総数の2.63%に当たる740万株、取得金額74億円を上限に自己株式を取得する。株主還元の拡充と資本効率の向上を図るためとしている。取得期間は本日3月1日から9月30日まで。2021年3月期の営業利益725億円(前期比15.6%減)、純利益490億円(同18.1%減)の見通し。株価は2019年以降、1300円を軸にした1000~1600円のボックス相場が続いている。(取材協力:株式会社ストックボイス)ゴルフクラブの切り替え作業が進行中です。FWはプログレスのBB4の3W~5Wか、バルドのCORSAの3W~5W~7Wですね。どちらにしても7Wはバルドということですね。ということでバルドの7Wのヘッドは手配済。UTは現在使用中のバルドのCORSA-4U(24)がいい感じなので、これに繋がる5U(27)のヘッドを手配済。シャフトも同様にATTAS MB-HYの55Sで。アイアンも地クラブで統一してしまうか、キャロウェイのAPEXにしてみるか…。ドライバーはBB4を愛用していますが、ドライバーは別物という考えでいけば、FWはバルドで統一か…。明日の戦略-3月は大幅上昇スタート、一段高なら底打ち反転への期待が高まるトレーダーズ・ウェブ 3月に入り1日の日経平均は大幅反発。終値は697円高の29663円。先週末の米国市場では、ダウ平均は大幅安となったものの、米国の長期金利上昇が一服したことで、ナスダックが上昇。ナスダック高を好感する格好で、400円超上昇して始まった。その後、節目の29500円をあっさり突破して上げ幅を拡大。700円超上昇したところで一服感が出てきたが、戻り売りは手控えられて値を保った。後場に入るとこう着感が強まったが、終盤にかけて買いが入り、高値圏で取引を終えた。マザーズ指数は上昇スタートから一時下げに転じたが、後場に入るとプラス圏を回復した。 東証1部の売買代金は概算で2兆4700億円。業種別では全業種が上昇。中でも動きが良かったのがパルプ・紙や情報・通信、建設で、陸運、海運、鉄鋼などの上昇が限定的となった。今期の大幅増益計画を提示した小僧寿しが後場急騰。半面、公募・売り出しを発表した学研ホールディングスが大幅安となった。 東証1部の騰落銘柄数は値上がり1931/値下がり229。米ナスダックの上昇を手掛かりにソフトバンクGが5%を超える上昇。先週金曜に下げた分を取り戻し、1万円台を回復した。村田製作所や日本電産、アドバンテストなどハイテク株も多くが大幅高。本社売却観測が流れたリクルートHDが買いを集めた。強い地合いではあったが急落を見た後だけに手垢のついていない銘柄に資金が向かっており、直近上場のcolyが商いを集めてストップ高。アピリッツは場中に値が付かずストップ高比例配分となった。 一方、HISや247、TKPなど経済活動再開の恩恵を受ける銘柄の一角が大幅安。直近で急伸したロゼッタが利益確定売りに押された。リミックスポイントやマネックスGなど、仮想通貨関連銘柄が軟調。デジタルガレージとの資本業務提携解消やファイナンスの発表が嫌気されたアイリッジが急落した。 3月の日経平均は大幅上昇スタート。先週金曜の下げはかなり大きかったが、このところは月末に大きく崩れることが多い。2月は月間では大きく水準を切り上げており、強かった分、短期的な過熱感を冷やす売りが一気に出てきたとも考えられる。きょうは買い先行から大きな失速もなく700円近く上げており、過度な警戒はいったん和らぐだろう。今晩、米国では2月のISM製造業景気指数が発表予定で、これが長期金利を刺激するか否かが注目される。米株先物は強かったため、今晩の米国株が上昇しても、一定程度は織り込んでいると思われる。それだけに、あすもう一段の上昇が見られるようなら、きょうとあすで金曜の下げ分を取り戻す展開も期待できる。明日の日本株の読み筋=上値の重い展開か、米金利上昇への警戒感くすぶる、戻り売り出やすいとの声もモーニングスター あす2日の東京株式市場で、主要株価指数は上値の重い展開か。前週末に米長期金利の上昇が抑えられ、週明けの日本株高につながったが、米金利上昇への警戒感は依然としてくすぶっており、その動向を見極めたいとの投資家は少なくない。米下院は現地2月27日、1.9兆ドル(200兆円)規模の米追加経済対策を可決、米上院で法案が修正される可能性はあるが、バイデン米政権および米民主党は3月14日までに成立を目指す。さらにはインフラ支援法案も控えている。コロナウイルス感染症が収束に向かい、経済活動が強まれば、インフレ懸念とともに米金利上昇が再燃する可能性もある。 1日の日経平均株価は大幅反発し、2万9663円(前週末比697円高)引け。前週末に米長期金利の上昇が一服し、米ナスダック総合指数が反発した流れを受け、ハイテク株中心に買い戻しが先行した。前週末の大幅反落(1202円26銭安)の反動や、時間外取引(日本時間1日)の米株価指数先物高も後押しし、上げ幅は一時720円に達した。利益確定売りに伸び悩む場面もあったが、アジア株高も支えとなり、大引けにかけて高値圏で推移した。チャート上では、前週末に割り込んだ25日移動平均線(2万9216円)をすかさず回復したことで、目先調整一巡感を指摘する向きもあるが、一部では「日経平均3万円台ではかなり商いをこなしており、心理的なフシ目として意識され、戻り売りが出やすい」(中堅証券)との声が聞かれた。病床使用率、ステージ3を脱する 岐阜県で新たに1人死亡、10人の新型コロナ感染確認 岐阜県と岐阜市は1日、県内で新たに10代~80代の男女10人の新型コロナウイルス感染と入院していた美濃加茂市の80代男性の死亡を確認したと発表した。県内の累計感染者数は4625人、死者は計111人となった。 新規感染者の減少に伴い、病床使用率は2月28日時点で19・7%に下がり、緊急事態宣言が発令された1月13日以来、初めて「ステージ3(感染急増)」を脱した。 一方、病院で発生した2つのクラスター(感染者集団)は規模が拡大した。美濃加茂市の木沢記念病院関連では、医療従事者2人の感染が分かり、228人に増えた。 瑞浪市の東濃厚生病院関連では、同病院の医療従事者と患者の各1人と、同病院から転院した患者の感染が確認されている高井病院(土岐市)の医療従事者1人、患者3人の計6人の陽性が判明。17人規模となった。 新たなクラスターの発生はなく、海津市で親族や知人を通じて広がったクラスターの終息を確認した。 新規感染者の居住地別は土岐市5人、岐阜市、多治見市、関市、瑞浪市、美濃加茂市が各1人。年代別は10代1人、20代2人、40代と50代、60代が各1人、80代4人。ワクチン1000回分を廃棄…冷凍庫故障し保管温度が上昇読売新聞 厚生労働省は1日、新型コロナウイルスワクチンの先行接種を実施している医療機関に設置した超低温の冷凍庫が故障し、保管していた約1000回分のワクチンが使えなくなったと発表した。2日に業者が冷凍庫を回収し原因を調査する。 同省によると、1日午前、1032回分のワクチンが入った、氷点下約80度に設定した冷凍庫の温度が27度まで上昇しているのを、医療機関の職員が発見。データを確認したところ、2月26日の午後11時頃から温度が上昇していた。週末は温度を確認する職員がおらず、発見が遅れたという。 この医療機関には2月15日の週に1170回分のワクチンが搬入され、接種を進めていた。未接種の1032回分のワクチンは廃棄処分される。 厚労省によると1日午後9時現在、先行接種が進む施設に設置された100台の冷凍庫のうち、故障が報告されたのはこの医療機関の1台のみという。同省は「原因を究明し、必要な対策を急ぎたい」とした。搬入から1週間以上をかけてたった30人ほどしか接種していないってどういう非効率的な仕事をしているんですかね…。ふつうは1日に最低でも200人は接種するだろう…。NY株見通し-今週は金利動向を巡り2月雇用統計などの経済指標に注目トレーダーズ・ウェブ 今週のNY市場はもみ合いか。先週は長期金利が急上昇したことで週後半に大きく下落し、主要3指数がそろって週間で下落した。長期金利の上昇でハイテク・グロース株に割高感が強まり、ナスダック総合は週間で10月以来の大幅安を記録した。今週は巨額経済対策への成立期待や、ワクチン普及による経済活動の早期再開期待が下値の支援となることが期待される一方、1年ぶりの水準まで上昇した長期金利の動向が引き続き懸念材料となりそうだ。今週発表される2月ISM製造業・非製造業PMIや2月雇用統計(非農業部門雇用者数・失業率・平均賃金)に注目が集まる。企業決算は、ターゲット、ロス・ストアーズ、ダラー・ツリー、コストコ・ホールセール、ギャップなどの消費関連のほか、ペリゴ、ヒューレット・パッカード・エンターなどS&P500の16社が発表予定。 今晩の米経済指標は2月ISM製造業PMI、1月建設支出など。ブレイナードFRB理事の講演やウィリアムズ米ニューヨーク連銀総裁、ボスティック米アトランタ連銀総裁、メスター米クリーブランド連銀総裁、カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁の挨拶や討議参加も予定されている。企業決算は寄り前にペリゴ、デンツプライ・シロナ、引け後にプログレッシブ・コープなどが発表予定。(執筆:3月1日、14:00)〔NY外為〕円、106円台後半(1日朝)時事通信 【ニューヨーク時事】週明け1日午前のニューヨーク外国為替市場では、世界的な株高を受けた海外市場での円売り・ドル買いの流れを引き継ぎ、円相場は1ドル=106円台後半に軟化している。午前9時現在は106円60~70銭と、前週末午後5時(106円49~59銭)比11銭の円安・ドル高。 アジアや欧州での株高を眺めて、ニューヨーク市場は106円76銭で取引を開始した。米議会下院は27日未明、新型コロナウイルス危機に対応した1兆9000億ドル規模の追加経済対策法案を可決。バイデン政権が公約に掲げる最低賃金引き上げについては上院で修正される可能性があるが、早期成立する見通しとなり、投資家のリスク警戒感が後退した。 米長期金利の上昇には一服感が出たが依然として高止まりしており、ドル買いの下支え要因となっている。 市場では、次の手掛かり材料として、この後発表される2月の米サプライ管理協会(ISM)製造業景況指数や米連邦準備制度理事会(FRB)高官の発言に注目している。 ユーロは同時刻現在、対ドルで1ユーロ=1.2050~2060ドル(前週末午後5時は1.2066~2076ドル)、対円では同128円50~60銭(同128円57~67銭)と、07銭の円高・ユーロ安。(了)〔米株式〕NYダウ反発、一時500ドル超の上げ=ナスダックは続伸(1日朝)時事通信 【ニューヨーク時事】週明け1日のニューヨーク株式相場は、米長期金利の上昇一服を受けて買いが先行し、反発して始まった。優良株で構成するダウ工業株30種平均の前週末終値比での上げ幅は一時500ドルを超えた。午前9時35分現在、ダウは493.63ドル高の3万1426.00ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は223.85ポイント高の1万3416.19。(了)今夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中のすべてが値を上げてスタートしましたね。トゥイリオが上げていますね。
2021.03.01
コメント(0)
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
-

- ☆バイクでツーリングに行こう=3=3
- 山梨 百目柿買い出し〜富士川クラフ…
- (2025-11-24 03:35:28)
-
-
-

- バイクヘルメット
- ◎バイク スモール ジェット ヘルメッ…
- (2025-11-23 09:37:55)
-
-
-

- F1ニュース・レース
- Mclaren MP4/5B GP Car story 50
- (2024-12-15 20:31:43)
-







