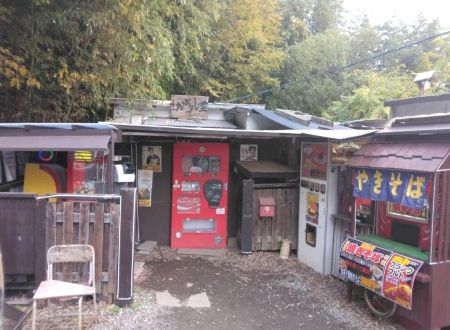2025年04月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
展示会がバブル状態?
「最近、展示会がすごく盛り上がっている」、そう感じている方は、決して少なくないはずです。 コロナ禍が明け、行動制限が解除された今、リアルでの“出会い”が注目を集めています。特にBtoB業界では、Web広告やSNSマーケティングが飽和状態になり、クリック単価の高騰や、広告疲れによる反響率の低下が顕著になっています。 BtoCビジネスにおいても同様に、「本当にいい商品かどうかを、実際に“触れて”確かめたい」という消費者の心理が復活しつつあります。そんな中で、脚光を浴びているのが――そう、展示会です。今、企業がこぞって展示会に出展しているのには、明確な理由があります。 それは、「リアルの接点こそが、信頼と記憶に残るきっかけになる」からです。 どれだけ精巧なランディングページを作っても、どれだけ緻密にターゲティング広告を打っても、一瞬で心を掴むリアルな出会いのインパクトには、なかなか敵いません。 「一度会って話した」「実際に手に取って体感した」、この“体験”が、オンラインでは得難い“信用”を生み出し、ビジネスチャンスを生み出すのです。2023年以降、国内外の主要展示会では軒並み来場者数が右肩上がりとなり、2024年の実績を見ても、コロナ前を上回る来場者数を記録するイベントが続出しています。しかも来場者のモチベーションが高く、「情報収集」「取引先探し」「課題解決」が目的のビジネスパーソンが真剣にブースを回っている。 だからこそ、本気で商談につながる可能性が高いのです。この“熱量の高いマーケット”を、活用しない手はありません。しかし、展示会に出るだけでは成果は出ません。 出展企業数が増えている今、「埋もれない工夫」が不可欠なのです。 私たちアサヒ・ドリーム・クリエイトでは、この展示会バブルに挑む企業様をサポートすべく、「3秒で認識されるブース」という独自のコンセプトで、出展支援を行っています。その名の通り、「来場者がブースの前を通ったわずか3秒で、何の企業で何を提案しているかを伝える」これが、私たちの設計思想です。・通路からパッと目に入るキャッチコピー ・視線誘導を計算し尽くした造作設計 ・一瞬でコンセプトが伝わるグラフィックデザイン この3点を軸に、ただ“目立つ”だけでなく、“意味ある印象”を残すブースを実現しています。 展示会バブルの今こそ、出展の絶好機です!展示会は、決して「名刺を配るだけの場」ではありません。 戦略的にブースを設計し、ストーリーを持った接客をすれば、その場で商談が動き、半年後の売上をつくる場にもなります。 いま、リアルな接点の価値が見直されているこのタイミングは企業にとって絶好のチャンスです。 「自社の魅力を、3秒で伝えられるか?」 、この問いに真正面から挑むのが、アサヒ・ドリーム・クリエイトの役目です時代がどう変わっても、人と人とのビジネスは「信頼」がすべてです。 展示会というリアルな場だからこそ、信頼が生まれ、未来につながる「ご縁」が生まれます。 あなたのブースは、3秒で語れていますか? もしその答えが“NO”なら、今こそ私たちにご相談ください。 展示会という舞台で、「一目惚れされるブース」を一緒に創りましょう!
2025年04月30日
コメント(0)
-
60期に向けたADCの新たな決意
私たちアサヒ・ドリーム・クリエイト株式会社(ADC)は、節目となる第60期を迎えるにあたり、幹部メンバーが集結し、10時間にわたる合宿を実施しました。この合宿の目的はただ一つ。これからのADCをどのような未来へ導くのか、そのために私たちは何を目指し、どう行動するのかを、リーダー全員で真剣に向き合い、コミットすることでした。10時間という長時間にも及ぶ議論の末に、私たちが掲げた目標はこちらです。「お客様感動を通して、全社一丸となって社員幸福度右肩上がりを続けるADCになる!」この言葉に、私たちのこれからのすべてを託すことを決めました。ADCは販促ツールの企画・製作を通じて多くのお客様のビジネスを支援してきました。しかし、私たちが本当に提供しているのは「モノ」ではなく、「心が動く体験」であり、「期待を超える感動」です。今期からは、この「お客様感動」をより一層深く追求し、単なる満足ではなく事前期待以上の体験を届けることを全社員が日々意識し、実践する組織であり続けると、全員で誓いました。私たちはまた、「社員の幸福度」を大切な指標に位置付けました。「幸福度」という言葉は決して軽いものではありません。給与や福利厚生といった表面的な満足だけでなく、仕事に対するやりがい、仲間との信頼関係、自己成長の実感など、それらすべてを含めた『心からの充実』を意味しています。お客様に感動を届けるためには、まず私たち自身が幸せでなければなりません。社員一人ひとりが、笑顔で、誇りを持って働ける環境を創り出す。それができてこそ、ADCは社会にもっと大きな価値を提供できるのだと、幹部全員が確信しました。そして、その「幸福度」を一過性のもので終わらせることなく、「常に右肩上がりで成長させていく」これを、60期の挑戦とします。このビジョンは、単なる理想論ではなく、リーダー全員が「絶対にやり切る」と胸に誓いました。リーダー一人ひとりが、自分自身とチームに100%責任を持ち、目標に向かって行動し続けることを誓いました。困難に直面することもあるでしょう、思うようにいかないこともあるでしょう、しかしだからこそ私たちは幹部合宿という時間を使い、未来への揺るぎない覚悟を固めたのです。一人ではできないことも、目標にコミットしたリーダーを中心に、全社一丸となれば、きっと成し遂げられると信じています。私たちアサヒ・ドリーム・クリエイトは、60期を単なる「通過点」ではなく、「新たな出発点」と捉えています。お客様感動を起点に、社員の幸福を追求し続ける、その歩みを止めることなく、これからの未来を自らの手で切り拓いていきます。そしてその先に、より多くのお客様、社員、そして社会全体に対して、ADCならではの価値を届けていきます。これからのADCに、どうぞご期待ください!
2025年04月29日
コメント(0)
-
幸せに働くために必要な権利と義務のバランス
人は幸せになるために生きていると言っても過言ではありません。幸せに生きるために、働くことは大きな要素ですが、幸せに働くことにおいて権利と義務のバランスがとても大切だと考えています。社会で働く上で、「権利」と「義務」は切っても切り離せない存在で、どちらか一方だけが強調されても、健全な職場環境や自分らしい働き方は実現できません。働くことで幸せを感じたいのであれば、この二つのバランスを意識することが欠かせないのです。まず、「権利」とは何か?を考えると、働く上での「権利」とは、自分の尊厳や安全が守られること、正当な評価を受けること、そして健やかに働く環境を享受することが挙げられます。たとえば、労働基準法に定められている「労働時間」「休憩」「休日」「最低賃金」などは、その最たるものです。また、ハラスメントを受けない権利や、キャリアアップのための教育・研修の機会を得る権利もあります。最近では、リモートワークやフレックスタイム制といった柔軟な働き方を選択する権利も広がっています。これらの権利は、心身ともに健康を保ち、自分らしい働き方を実現するための土台となります。しかし、この「権利」は、主張するだけでは得ることは出来ず、自分自身がその存在を知り、必要な時には声を上げることが大切です。知らなければ、当然守られることも改善されることもないので、まずは「知ること」が権利を活かす第一歩なのです。では、「義務」とは何か?、これは、社会の一員として、また組織の一員として果たすべき責任です。時間を守る、成果を出す、協力し合う、ルールを遵守する、誠実に業務を遂行するなど、これらが代表的な義務です。義務を果たすことで、信頼関係が築かれ、チームや会社の成長に貢献できます。自分が義務を果たすことで、他の人の権利も守られ、結果として自分の働きやすさにもつながるのです。例えば、チームでの会議時間を守ることは、他の人の時間という権利を尊重することになりますし、自分の役割を果たすことは、他のメンバーが安心して自分の仕事に集中できる環境づくりにもなります。この「お互い様」の精神こそが、義務を果たす意義です。権利ばかりを主張して義務を果たさなければ、周囲からの信頼を失い、働きづらくなります。一方で、義務ばかりを意識して、自分の権利を犠牲にして働き続けると、心身ともに疲弊し、最悪の場合は燃え尽きてしまいます。大切なのは、お互いに支え合う関係性の中で、権利と義務のバランスを取ることであり、自分の権利を大切にしながら、相手の権利を尊重し、義務を果たすことで、その循環が安心して働ける環境を生み出すのです。権利と義務、この両輪が揃ってこそ、私たちは安心して、幸せに働くことができるのです。経営者として、そのことを肝に銘じて、社員の権利を整えることは大切ですし、果たすべき義務を深く理解してもらって、全体最適を実現することにこだわっていきます。当社のミッションである「HAPPY♾️HAPPY」は、社員との権利と義務の関係でも同じなので、しっかりと深めていきます!
2025年04月28日
コメント(0)
-
白い煙が世界を変える
カトリック教会の最高指導者である教皇(ローマ法王)を選出する「教皇選挙(コンクラーベ)」。これは世界中の注目を集める、最も神聖で厳粛な選挙の一つです。なぜこれほどまでに注目されるのか?その背景には、長い歴史と独特の儀式、そして現代社会においても影響力を持つカトリック教会の存在感があります。そして、まさに今、世界が次の教皇選挙が開催されるこのタイミングで、教皇選挙を題材にした映画が公開されるというのは、偶然にしては出来すぎていると感じる方も多いのではないでしょうか。まるで歴史の流れとエンターテインメントが交差する、絶妙なタイミングです。「コンクラーベ(Conclave)」という言葉は、ラテン語の「cum clave(鍵付きの)」に由来します。これは文字通り、枢機卿(カトリック教会の高位聖職者)たちが鍵のかかった場所に閉じ込められ、教皇が選出されるまで外に出られないという意味があります。この厳格な仕組みは、外部の影響を一切排除し、神の意志に従った純粋な選択を行うためのもの。場所はバチカンのシスティーナ礼拝堂で、ミケランジェロの「最後の審判」が見下ろすその空間で、115人以内の枢機卿たちが投票を重ねます。新教皇を選ぶには、全体の3分の2以上の得票が必要で、もし決まらない場合は何度も投票が繰り返されます。投票のたびに、選挙の進捗は煙で知らされ、票が割れて決まらなければ「黒い煙」、教皇が決まれば「白い煙」が煙突から立ち上るのです。この白い煙が世界中のメディアで速報される瞬間は、まさに歴史が動く瞬間といえるでしょう。世界約13億人のカトリック信者の頂点に立つ存在である教皇。その発言や行動は、宗教界のみならず政治・社会・文化にまで影響を及ぼします。気候変動、移民問題、貧困、戦争などのグローバルな課題に対して、教皇が発するメッセージは世界中で大きな反響を呼び、場合によっては国際政治にも影響を与えることすらあります。だからこそ、新しい教皇がどんな人物か?どんな価値観を持っているのか?が、全世界から注目されるのです。実際、映画を観てきましたが、教皇選挙の舞台裏、枢機卿たちの葛藤や駆け引き、人間味あふれるストーリーが描かれることで、普段は神秘に包まれたこの選挙のリアルな一面が垣間見えるのです。映画はエンタメですが、世界的な宗教行事や伝統行事を知る入口としても大きな役割を果たしています。コンクラーベという独特な仕組みで行われる教皇選挙。そこには歴史の重みと、現代にも通じる大きな影響力が存在します。映画という形でその舞台裏を覗き見ることで、私たちは宗教という枠を超えた「人間ドラマ」として、この選挙を理解する機会を得られるのかもしれません。果たして次の教皇はどんな人物なのか?、白い煙が上がるその日まで、世界は注目を続けます。
2025年04月27日
コメント(0)
-
深く掘ることが最強への道
ビジネスの世界で「差別化」は、生き残りと成長のために欠かせないキーワードです。しかし、ただ「他社と違うことをする」という表面的な工夫だけでは、競争が激しい市場で長く勝ち続けることはできません。本当に必要なのは、自社の「強み」を深く掘り下げ、それを誰よりも尖らせることであり、このプロセスこそが、真の差別化につながります。強みを掘り下げたメーカーの成功事例で思い浮かぶのは、掃除機メーカーとして世界的に知られるダイソンです。ダイソンの強みは「吸引力が変わらない」という一点にありますご、これは単なるキャッチコピーではありません。モーターの開発から、ゴミと空気を分離するサイクロン技術まで、あらゆる工程において“吸引力”にこだわり抜いています。他社が多機能や価格競争に走る中、ダイソンは吸引力という一点突破で差別化を図り、結果としてプレミアムブランドとして確立しました。この「一つの強みを極める」姿勢は、まさに強みの掘り下げの好例です。世界トップクラスの自動車メーカーであるトヨタの強みは「生産性の高さ」と「品質管理の厳しさ」にあります。しかし、これも一朝一夕に築かれたものではなく、「カイゼン(改善)」という企業文化を根付かせ、現場の社員一人ひとりが小さな改善を積み重ねることで、生産ラインの無駄を徹底的に排除することにより、高品質でありながらコスト競争力も持つ車づくりが実現できています。トヨタはこの強みをさらに深掘りし、ハイブリッド車(プリウス)などの環境技術にも応用し、単なる“製造業”の枠を超えた、世界のトップブランドとしての地位を築いています。「強みの掘り下げ」における重要な視点は、まずは自社の過去の成功体験であり、蓄積された技術、独自のノウハウを見直すことです。自社にとって「当たり前」になってしまっていることでも、他社から見れば大きな強みであることがあります。そこに光を当てることで、新たな差別化のヒントが見つかります。また、お客様から“なぜ選ばれているか”を掘り下げることも重要です。「なぜ競合ではなく、あなたの会社を選んだのか?」を徹底的にヒアリングすることで、言語化されていない価値を見つけ出すことが出来ます。ダイソンも「吸引力」にこだわったのは、ユーザーが最も不満を感じていたポイントに着目したからです。表面的な機能や価格ではなく、競合が簡単には真似できない「本質的な強み」を見極めることが大切です。それは技術力、ブランド力、文化、ネットワークなど、さまざまな形で存在します。これをさらに磨き上げることで、差別化はより盤石になります。差別化というと「派手なアイデア」や「目新しい商品」をイメージしがちですが、実はそうではありません。自社の強みを深く掘り下げ、それをお客様に届けることで、誰にも真似できないポジションが築けます。まさに“深さが差を生む”のです。自社にとって、まだ気づいていない強みが必ずあるはずです。その一つひとつを掘り下げ、尖らせていくことで、競争優位は自然と生まれていきます。時代が変わっても揺るがない、自社ならではの価値を深く深く掘り下げることで見つけ出しましょう。
2025年04月26日
コメント(0)
-
全ては社員の成長のために
我が社の経営理念は、「ハッピートライアングル〜社員がチャンス&トライアルで成長し、お客様が感動し、会社が信頼と利益を得るハッピートライアングルを形成し、社会貢献を目指します」というものです。社員の成長とお客様感動と会社の信頼と利益の三つがつながるハッピートライアングルが、私たちのすべての活動の根幹にあります。その中でも、最も大切にしているのが「社員の成長」です。なぜ、社員の成長が最優先なのか? それは、社員一人ひとりが輝き、自らの可能性に挑戦し続けることで、すべての幸福が生まれると信じているからです。私たちは販促ツールの企画・制作を通して、お客様の課題を解決し、心を動かす提案を行っていますご、その原動力となるのは、社員一人ひとりの「成長したい」という情熱です。新しいアイデアを考え、試行錯誤し、失敗しながらもチャレンジを続ける、その積み重ねが、唯一無二の提案を生み、お客様の感動につながるのです。成長とは、知識やスキルを磨くだけではなく、新しい視点を持つこと、過去の自分を超えること、そして仲間と共に壁を乗り越えることです。私たちが大切にしているキーワード、それが「チャンス&トライアル」です。社内では、年齢や経験に関係なく、誰にでも挑戦の場が与えられます。新しい企画に手を挙げる、提案営業にチャレンジする、自分自身のアイデアを形にするなど、そうした小さなチャレンジの積み重ねが、大きな成長へとつながります。もちろん、失敗することもありますが、それでいいのです。失敗から学び、次に生かす、そのプロセスこそが、真の成長だからです。社員一人ひとりの挑戦を、全力で応援し、支える環境がここにはあります。社員が成長し、心からお客様に向き合い、感動を届ける。その結果として、会社は信頼を得、利益を生み出します。そして、その利益を通じて、社会に新たな価値を提供していく、これがアサヒ・ドリーム・クリエイトが掲げる「ハッピートライアングル」の真髄です。販促ツールを通して地域活性化に貢献したり、新卒採用を積極的に行い、若者の未来を応援したり、そうした活動も、すべて「社員の成長」があってこそ実現できることです。成長した社員が、自らの仕事に誇りを持ち、社会のために行動する、その循環が、私たちの目指す社会貢献の形なのです。私たちは、社員一人ひとりが持つ可能性を信じています。どんなに小さな一歩でも、それが未来を切り拓く力になる。その成長こそが、お客様を感動させ、会社を信頼される存在にし、ひいては社会全体をより良くしていくと、心から信じています。だからこそ、アサヒ・ドリーム・クリエイトは「社員の成長」を何よりも大切にしています。社員の成長こそが、すべての幸せの源泉であり、私たちの未来を創る力なのです。
2025年04月25日
コメント(0)
-
無意識を変えれば、人生が変わる
私たち人間の脳には、RAS(Reticular Activating System:網様体賦活系)という、無意識に情報を取捨選択する強力なフィルター機能が備わっています。 このRASをうまく使いこなせれば、日々の行動、思考、そして人生そのものを大きく変えることができるのです。「脳は見たいものしか見ていない」と言われています。街を歩いていて、ふと目に入った広告、たまたまテレビで流れてきたCM、「これ、今自分が気になってたことだ!」と感じた経験はありませんか? 実はこれ、偶然ではなく、あなたの脳がRASの力で、必要な情報だけを選び取っているのです。 脳は1秒間に1100万ビットもの情報を受け取っていると言われますが、意識できるのはそのうちたったの40ビットほどしかなく、膨大な情報の中から、何を意識に上げるかを選んでいるのが RASなのです。つまり、私たちが何を意識し、どんな目標を持つかによって、脳が拾う情報が変わってくるのです。 「RASを味方につける3ステップ」があると言われています。1.目標を明確に言語化するまず重要なのは、自分が本当に達成したい目標を明確にすることで、「いつか成功したい」ではなく、「半年以内に売上を20%アップする」など、具体的なゴールを設定します。 RASは曖昧な指示では動かず、目標が明確であればあるほど、脳はそれに関連する情報を積極的に拾い始めます。 たとえば、販促ツールの提案で「お客様の課題解決に貢献する」という目標を掲げた瞬間、街中のPOPや広告が「こうすればもっと目立つのでは?」という視点で自然と目に入るようになります。2.繰り返しイメージする次に、目標達成後の姿を繰り返しイメージすることで 、「売上が上がってお客様から喜ばれている自分」、「素晴らしい企画が通ってチームで達成感を味わっている自分」などのイメージを毎日思い描くことで、RASは「これは大事なことだ」と認識し、関連情報をどんどん拾ってくれるようになります。 まるで、脳に「これは探せ!」と命令しているようなものです。 3.ポジティブな言葉を使うRASは言葉の力でも活性化するので「できない」「無理だ」ではなく、「できる」「挑戦してみよう」といったポジティブな言葉を口に出すことで、脳は「これは重要なこと」と認識します。 逆にネガティブな言葉ばかりだと、RASは失敗や不安に関連する情報ばかり拾ってしまいます。 だからこそ、自分にかける言葉を意識的にポジティブにすることが大切なのです。例えば、POP企画で「3秒でお客様の目を引くデザインを作りたい」という目標を立てたとします。 その瞬間から、RASはあなたの周りの視覚的にインパクトのあるデザインに敏感になります。 スーパーの陳列棚、ネット広告、雑誌のレイアウトなどなど普段はスルーしていたものが、「これ使えるかも」と 自然とインスピレーションの源になるのです。 そして、いつの間にか「お客様の心を掴む」提案ができるようになっている。 これがRASを味方につける威力です。RASは、あなたが意識を向けたものを、どこまでも探し続けてくれる 無意識のサポーターです。 「どうせ無理」ではなく、「どうやったらできるか?」と問いかけるだけで、脳はその答えを探し始めます。 意識が変われば、見える世界が変わる。 見える世界が変われば、行動が変わる。 行動が変われば、人生そのものが変わっていく――。 さあ、今日からあなたもRASを味方につける生き方、始めてみませんか?
2025年04月24日
コメント(0)
-
「3秒」で心を掴め!展示会ブース成功の秘訣
展示会は、限られた時間と空間で自社の魅力を伝え、ビジネスチャンスをつかむ戦場です。しかし、何百というブースが立ち並ぶ中、来場者が足を止めてくれるブースはごくわずか。では、その違いはどこにあるのでしょうか?答えは「3秒」にあります。展示会の来場者は、あらゆる情報が洪水のように押し寄せる中を歩いていますので、ひとつひとつのブースをじっくり見る余裕はありません。無意識のうちに、パッと見た瞬間に「気になる」「無関心」と判断しています。この時にかかる時間が、わずか3秒。つまり、この3秒で目に飛び込んでくる情報が、来場者の行動を決めているのです。当社では、この「3秒」に全てを懸けています。例えば、ブースのデザインにおいて、遠くからでもパッと目を引く大胆なカラーリングや、シンプルで力強いキャッチコピーを配置します。複雑な説明や細かい装飾は必要なく、来場者の目線の高さに、ダイレクトにメッセージが届く設計が重要です。人は、目にした情報を視覚、感情、そして経験で瞬時に判断します。だからこそ、ターゲット層が「自分に関係がある」と直感できるメッセージが必要なのです。たとえば、「業界最速」「コスト削減率30%」「こんなお悩みありませんか?」など、来場者の心に刺さる一言をぶつけます。この時、抽象的な言葉ではなく、具体的な数字や悩みに寄り添った言葉が有効です。さらに、視線誘導も大切で、高さを意識したデザインで遠くからでも存在感を発揮し、自然とブース中央の展示やスタッフの元へと導く動線設計を行います。この流れがスムーズであれば、興味を持った来場者は自然と足を止め、会話が生まれます。これこそが、商談の第一歩となるのです。また、展示会では来場者が受け取れる情報量に限界があるので、「全てを伝えよう」とせず、「興味を持たせること」に焦点を絞ります。詳しい説明は、足を止めた後で、スタッフが丁寧に行えば良いので、段階的に情報を渡す設計が、成果につながります。なぜ「3秒」がこれほど重要なのか?それは、現代人が日々膨大な情報にさらされており、スマホ、SNS、広告、メールなど、私たちは日常的に、無意識で情報の取捨選択をしています。展示会もその延長線上にあるので、「一瞬で心をつかむ仕掛け」が必要なのです。私たちは、単なる空間デザインではなく、「成果につながる場」を提供します。3秒で認識され、記憶に残り、行動を促す。それが、私たちの考える展示会ブースのあり方です。成果を出すブースには理由があり、その理由は、3秒で伝える覚悟にあります。ぜひ、私たちと一緒に「3秒で心を掴む」展示会を実現しましょう!
2025年04月23日
コメント(0)
-
当社が求める人財へのメッセージ
アサヒ・ドリーム・クリエイト株式会社が求める人財像を端的に表現すると~夢をカタチにする挑戦者~となります。私たちアサヒ・ドリーム・クリエイト株式会社は、「夢づくり」をテーマに、お客様の課題解決や成長支援を行う会社です。私が20年以上にわたって綴り続けているブログには、その根底に流れる思いが詰まっています。それは、「人が成長することで会社も成長する」という信念であり、そしてその成長とは、ただスキルを磨くことではなく、“夢に向かって挑戦し続ける姿勢”そのものなのです。私のブログに頻繁に登場するキーワードが 「チャンス&トライアル)」です。この精神を持つことこそ、アサヒ・ドリーム・クリエイトが求める人財の大きな要素です。現状に満足するのではなく、常に一歩先を目指して挑戦する、失敗を恐れずトライし続ける。その姿勢が、販促ツールの企画から制作、提案に至るまで、すべての仕事において求められています。販促は変化の激しい世界で、昨日までの成功が今日も通用するとは限りません。だからこそ、常に「新しい視点」で考え、「お客様に喜ばれる提案」をし続けることが大切なのです。当社では「人の成長」が最も重要だと考えており、社員一人ひとりが成長し、変化に対応できる力を身につけることで、会社全体が進化していくと考えています。そのためには、自分の可能性に蓋をせず、常に学び続ける姿勢が求められます。販促ツール企画のプロとして、時にはマーケティングの知識を、時にはデザインやコピーライティングのスキルを磨き、自分の専門領域を深めるだけでなく、幅広い視野を持つことが、お客様への提案の質を高め、信頼につながります。「成長はゴールではなくプロセス」、成長の過程で得た経験こそが、自身の糧となり、お客様に価値を提供する源泉になります。販促ツールを提供する私たちの仕事は、単なるモノづくりではなく、お客様の課題を解決し、夢をカタチにする「価値提供」です。そのためには、「感謝」と「貢献」の心を持ち、お客様の想いに寄り添うことが必要不可欠です。「お客様にとって本当に役立つことは何か?」を自問し続け、相手の期待を超える提案をする、それが、当社が大切にしている姿勢です。だからこそ、お客様の声を素直に聴く力、チームで協力しながら最善を目指す協調性、自分ができることで誰かの役に立ちたいという貢献心を持った人を求めています。アサヒ・ドリーム・クリエイト株式会社が求める人財とは、「挑戦し続ける人」、「成長し続ける人」、「感謝と貢献の心を持つ人」です。販促という枠にとらわれず、共に新しい価値を生み出し、夢をカタチにしていく。相手の想いに寄り添う心、期待を超える提案を届けたいという情熱、これが私たちの仕事の原動力です。 お客様に「ありがとう」と言っていただけた瞬間、「この仕事をしていてよかった」と心から思えます。 その喜びを共に感じられる人を、私たちは求めています。私たちが求めるのは、挑戦することを楽しめる人、学び続けることにワクワクできる人、そして 人の役に立つことに喜びを感じられる人です。 販促という枠を越え、お客様の夢を、社会の未来を、一緒にカタチにしていきませんか? その仲間として、一緒に歩んでいける人と出会えることを、私たちは心から楽しみにしています。
2025年04月22日
コメント(0)
-
パーパス経営から見たADCとは?
今年60期を迎えるアサヒ・ドリーム・クリエイト株式会社が目指すべきパーパス経営について考えてみました。 私たちアサヒ・ドリーム・クリエイト株式会社は社名の通り「夢を創る」会社であると考えています。その根底にあるのは、単なる販促ツールの制作や提案ではなく、お客様の想いをカタチにし、人と人、人と社会をつなぐ“感動のきっかけ”を創造することであり、それこそが、私たちが目指すべき「パーパス=存在意義」だと考えています。近年、企業活動において「パーパス経営」という言葉が注目を集めています。それは利益や効率の追求だけでなく、社会との関係性の中で“なぜ私たちは存在しているのか”を明確にし、その軸で事業を展開していく考え方です。大量生産・大量消費の時代を経た今、人々は「何を買うか」よりも「誰から買うか」「その企業にどんな想いがあるか」を重視するようになりました。まさに、私たちアサヒ・ドリーム・クリエイトが強みにしてきた、“人の心に届く販促ツール”の価値が問われる時代になったのです。販促ツールは、モノを売るための道具ではなく、お客様の課題に寄り添い、その想いやブランドストーリーを伝える「コミュニケーションの架け橋」です。だからこそ私たちは、販促POP一つにも、ノベルティ一つにも、作り手の温度感と、使う人の笑顔を想像して向き合ってきました。私たちの強みは、マーケティングとデザインの“間”にあります。機能だけでなく、共感を呼ぶストーリーを重ねることで、「お客様が売りたいものを売る」のではなく、「お客様の想いを届ける」販促活動ができるのです。そしてもう一つ、大切にしているのが「人が育つ会社」であること。販促という“人に届ける”仕事をする私たち自身が、人間として成長し、感性を磨き、夢を持つこと。その連鎖こそが、社名にもある“ドリーム”の本質だと思っています。若手社員が想像以上の提案でクライアントを驚かせた時、現場の声を拾って改善提案に繋げた時、チームで一つの成果を出せた時、そこには確かに「チャレンジ」があり、「成長」があります。パーパス経営とは、このような“内側から湧き上がる使命感”を、会社全体のエネルギーに昇華させることだと考えています。これからの時代、社会課題や価値観の多様化がますます進み、その中で必要とされるのは、「軸を持った企業」です。私たちは、“HAPPY∞HAPPY~ファン創りを通して笑顔あふれる世界を創る”という揺るがぬパーパスを旗印に、クライアント、パートナー、社員、そして地域社会に「HAPPYの循環」を広げていきます。
2025年04月21日
コメント(0)
-
2年連続の初戦突破!
5年前から参加しているマスターズ甲子園大会の初戦が開催され、28対2の圧勝で見事初戦を突破しました!マスターズ甲子園というのは、かつての高校球児たちが再び甲子園の舞台に立ち、野球を通じて地域や世代を超えた交流を深める素晴らしい大会です。5年間継続して来たことによって、少しずつ参加メンバーが集まって来たり、敗戦の悔しさから体を鍛え直してくるメンバーが増えて来ることで、戦力が充実してきました。5年連続で参加しているので分かることですが、初年度とは見違えるような強いチームになっていることは間違いありません。私自身もこの大会でチームに貢献するために、日頃から体を鍛えるようにしていますし、肩や足腰などの体のケアも行っています。大会理念はこのようになってます。1.個人にとってのマスターズ甲子園:夢への再挑戦による生きがいと活力の提供。2.地域にとってのマスターズ甲子園:地元高校を軸とした同窓会や世代間交流の活性化。3.社会にとってのマスターズ甲子園:生涯スポーツ文化やOB・OG文化の発展への寄与。4.未来にとってのマスターズ甲子園:野球ユース世代への文化継承と応援メッセージの発信。 この理念通り、上は76歳から下は24歳まで50歳の年齢を超えたOBが集まり、交流を深まることが出来ていることは、奇跡としか言いようがありません。今日の試合は、ヤングチームで6点のリードを奪い、ミドルチームでも9点を取り、最後のシニアチームでも13点を奪う猛攻でした。そして何より、相手チームを2点に抑えたことはマスターズ甲子園大会ではかなり珍しいことで、投手力は元より、堅い守備も光りました。目立ったエラーもなく、大量点を取りながらも内容のある試合運びで完勝でした。私自身もミドルチームから4イニング出場して、5打席で3打数2安打、2四球、3度の守備機会もノーエラーでしたし、1イニングもノーヒットで0点で抑えることが出来ました。5年前の情けない姿とは違い、ある程度戦力として貢献することが出来ています。次の目標は去年果たせなかった2回戦突破です。相手は過去の大会で甲子園出場を果たしている強豪校です。今日のような試合運びが出来れば、それなりの戦いは出来ると思います。夢の甲子園へ、しっかり準備して臨みます!
2025年04月20日
コメント(0)
-
バッハの音楽で集中力が高まり、かつリラックス出来る?
バッハの音楽が集中力やリラックスにとても効果的だという話を聞きました。実際試してみると、前頭葉の部分がめちゃくちゃ安まるというか疲れが癒えていくような感覚を持ちました。なぜバッハの音楽にそのような効果があるのか調べてみると、偶然ではなくしっかり設計されているものだということが分かってきました。「なんだか今日は集中できない…」「頭がごちゃごちゃして落ち着かない…」そんなとき、ふとバッハの音楽を流すと、自然と気持ちが整ってくるのです。バッハの音楽には、現代の私たちが求める“集中力の向上”や“リラックス効果”に繋がる秘密が詰まっているのです。ヨハン・セバスチャン・バッハの音楽は、「音楽の建築」とも呼ばれるほど構造が緻密です。特にフーガやインヴェンションなどは、複数の旋律が数学的に絡み合いながらも美しい調和を保ちます。この秩序正しい構造が、私たちの脳に「安定感」を与えるのです。情報過多の現代において、脳は常に“何を優先すべきか”を処理しています。バッハの音楽はその整理整頓の“お手本”のような存在で、規則性と予測可能性のある旋律進行が、脳のワーキングメモリを落ち着かせ、集中力を取り戻すきっかけを与えてくれるのです。脳波の中でも“α波”は、リラックスと集中の両方を司る波形として知られています。バッハの音楽は、一定のテンポと安定したリズムを保っているため、α波が出やすい環境をつくってくれるのです。特に「平均律クラヴィーア曲集」や「ブランデンブルク協奏曲」は、そのリズム感と音の間の“間”が絶妙で、思考が深まる空気を作り出します。まさに“考えるための音楽”。作業BGMとしても人気が高いのは、こうした脳への影響が理由の一つです。バッハの音楽の根底には、敬虔なルター派の信仰が流れています。彼の音楽には“神聖な静けさ”があり、聴く者の心に“包まれている”という安心感を与えてくれます。特に「マタイ受難曲」や「無伴奏チェロ組曲」などは、悲しみや喜びといった感情を包み込むように奏でられ、感情を整える作用があります。緊張状態が続いているとき、ふとバッハを聴くだけで、肩の力がすっと抜けるような感覚を得られるのは、まさにこの精神的作用ゆえなのです。実際に、バッハの音楽は音楽療法の現場でも積極的に使われています。ADHDの子どもたちや、高齢者の認知症ケア、さらには心療内科などの分野でも、“バッハを流すだけで穏やかな状態を保てる”という事例が多く報告されています。音楽の力は、薬とは違い副作用がなく、心の深部に直接働きかけることができます。バッハの音楽は、まさに“天然の精神安定剤”として、多くの人の心を整える役割を果たしているのです。テクノロジーの進化により、常に刺激に晒され続けている私たちの脳。そんな時代だからこそ、バッハの音楽は“デジタル・デトックス”とも言える役割を果たします。整った構造、穏やかなリズム、深い精神性――その全てが、集中力を取り戻し、心を静かに整えてくれるのです。コーヒー片手に、静かな時間にバッハを一曲、たったそれだけで、今日の自分が少し整う、そんな習慣を持ってみてはいかがでしょうか?
2025年04月19日
コメント(0)
-
バッハの音楽で集中力が高まり、かつリラックス出来る?
バッハの音楽が集中力やリラックスにとても効果的だという話を聞きました。実際試してみると、前頭葉の部分がめちゃくちゃ安まるというか疲れが癒えていくような感覚を持ちました。なぜバッハの音楽にそのような効果があるのか調べてみると、偶然ではなくしっかり設計されているものだということが分かってきました。「なんだか今日は集中できない…」「頭がごちゃごちゃして落ち着かない…」そんなとき、ふとバッハの音楽を流すと、自然と気持ちが整ってくるのです。バッハの音楽には、現代の私たちが求める“集中力の向上”や“リラックス効果”に繋がる秘密が詰まっているのです。ヨハン・セバスチャン・バッハの音楽は、「音楽の建築」とも呼ばれるほど構造が緻密です。特にフーガやインヴェンションなどは、複数の旋律が数学的に絡み合いながらも美しい調和を保ちます。この秩序正しい構造が、私たちの脳に「安定感」を与えるのです。情報過多の現代において、脳は常に“何を優先すべきか”を処理しています。バッハの音楽はその整理整頓の“お手本”のような存在で、規則性と予測可能性のある旋律進行が、脳のワーキングメモリを落ち着かせ、集中力を取り戻すきっかけを与えてくれるのです。脳波の中でも“α波”は、リラックスと集中の両方を司る波形として知られています。バッハの音楽は、一定のテンポと安定したリズムを保っているため、α波が出やすい環境をつくってくれるのです。特に「平均律クラヴィーア曲集」や「ブランデンブルク協奏曲」は、そのリズム感と音の間の“間”が絶妙で、思考が深まる空気を作り出します。まさに“考えるための音楽”。作業BGMとしても人気が高いのは、こうした脳への影響が理由の一つです。バッハの音楽の根底には、敬虔なルター派の信仰が流れています。彼の音楽には“神聖な静けさ”があり、聴く者の心に“包まれている”という安心感を与えてくれます。特に「マタイ受難曲」や「無伴奏チェロ組曲」などは、悲しみや喜びといった感情を包み込むように奏でられ、感情を整える作用があります。緊張状態が続いているとき、ふとバッハを聴くだけで、肩の力がすっと抜けるような感覚を得られるのは、まさにこの精神的作用ゆえなのです。実際に、バッハの音楽は音楽療法の現場でも積極的に使われています。ADHDの子どもたちや、高齢者の認知症ケア、さらには心療内科などの分野でも、“バッハを流すだけで穏やかな状態を保てる”という事例が多く報告されています。音楽の力は、薬とは違い副作用がなく、心の深部に直接働きかけることができます。バッハの音楽は、まさに“天然の精神安定剤”として、多くの人の心を整える役割を果たしているのです。テクノロジーの進化により、常に刺激に晒され続けている私たちの脳。そんな時代だからこそ、バッハの音楽は“デジタル・デトックス”とも言える役割を果たします。整った構造、穏やかなリズム、深い精神性――その全てが、集中力を取り戻し、心を静かに整えてくれるのです。コーヒー片手に、静かな時間にバッハを一曲、たったそれだけで、今日の自分が少し整う、そんな習慣を持ってみてはいかがでしょうか?
2025年04月19日
コメント(0)
-
「ナッジ」で人は動く、販促ツールに行動経済学を生かす新常識
最近よく耳にする「ナッジ(nudge)」という言葉。直訳すると「ひじで軽く突く」という意味ですが、行動経済学では「人が無意識のうちに、より良い選択をするよう背中を押す仕組み」として注目されています。実はこのナッジ、販促ツールに応用するととても効果的なのです。たとえば、スーパーの売り場で「80%の人がこれを選んでいます」というポップを見かけたことはありませんか?これは「社会的証明」というナッジの一種。人は周囲の人の選択に影響を受けやすいという心理を利用しています。同じ商品でも、「人気No.1」と書いてあるだけで購買率はぐんと上がる。それが人間の行動パターンなのです。ナッジが持つ最大の魅力は、「強制しない」という点にあります。割引や限定キャンペーンのように「損をしたくない」と思わせる販促も有効ですが、ナッジはもっと穏やかで、自然に「自分で選んだ」と思わせる仕掛け。これが、ブランドの好感度を下げずに購買を促せる理由です。では、実際にどのような販促ツールにナッジを取り入れられるのでしょうか?以下にいくつかの具体例をご紹介します。1.選択肢の提示方法を工夫するパンフレット「Aプラン、Bプラン、Cプラン。おすすめはBです!」と中央に強調されたプランを配置すると、自然と人はその選択肢に目を向けやすくなります。これは「デフォルト効果」と呼ばれるナッジの一種。パンフレットや比較表を使う際は、この視線誘導を意識するだけで反応率が上がります。2.QRコード誘導の工夫で「今すぐ行動」を後押しチラシや店頭ポップにQRコードを入れる際、「今、70人がアクセス中」といった数字を添えるだけで、「自分も見てみようかな」と行動が促されます。これは「バンドワゴン効果(多数派に乗りたくなる心理)」を応用したナッジです。3.商品POPで“自分ゴト化”を促すコピー「30代女性の7割が選んでいます」など、ターゲットに近い人の行動を明示することで、「私も選ばなきゃ」と無意識に感じさせます。特にリアル店舗では、こうしたPOPが一瞬で印象を与える重要な武器になります。4.LINE登録・クーポン施策での“損失回避”ナッジ「今登録すると、限定クーポンが“もらえる”」よりも、「今登録しないと、限定クーポンが“もらえない”」の方が、人の行動を促すことがあります。これは「損を避けたい」という人間の心理を利用したナッジです。販促とは「気づかせ」「行動させる」こと。ナッジのアプローチは、まさにこの本質に合致します。価格競争や押しつけ型の営業に疲れている今こそ、ナッジのような“やさしい販促”が選ばれる時代。小さな工夫が、心地よい動機づけとなり、結果として売上やブランドの好印象につながるのです。販促ツールにナッジを活用してみませんか?次の一手は、「人の心の動き」に寄り添う設計から始めてみてはいかがでしょうか?
2025年04月18日
コメント(0)
-
トランプ関税に一喜一憂しないために
トランプ関税に世界が日々揺れています。実際に実行されると大きな影響が出ることは避けられませんが、これだけ毎日目まぐるしく変わると何を根拠に動いて良いのか、迷ってしまいのも致し方ないかも知れません。そんな変化する環境の中で一喜一憂せず、どっしりと構えるために必要な経営者の心得について考えてみました。経営者にとって「環境変化」は避けられない現実です。日本企業にとっては輸出入コストの変動やサプライチェーンの混乱が頭をよぎるでしょう。しかし、ここで問いたいのは、「一時の風に心を乱すべきか」ということです。結論から言えば、経営者として最も大切なのは「変化に反応するのではなく、変化に備える」視点を持つことです。関税の上下、為替の変動、国際情勢の変化など、こうした事象に一喜一憂していたら、経営判断がぶれ、社員にも不安が広がります。経営者の役割は「感情の錨(アンカー)」となることです。不確実な時代にあって、経営者がどっしりと構えられるかどうかで、組織の安定は大きく左右されます。たとえば、トランプ関税が再発動されたとしても、すべての業界が同じようにダメージを受けるわけではありません。むしろ、ローカル製造回帰、サプライチェーンの多様化、FTA(自由貿易協定)の活用など、「適応した者」が勝つ環境に変わるとも言われるように『ピンチはチャンス』なのです。そのために必要なのが「思考の柔軟性」と「未来視点でのシナリオ設計」となり、今もし原材料コストが上がったらどうするか?円安が進んだら?特定国への依存度が高いときに起こるリスクは?などそうした問いを経営会議で常に持ち出すことが、「揺るがない強さ」につながります。また、経営とは「逆風に耐える力」と同時に、「先に進む推進力」が求められます。トランプ関税を「外部要因」として捉え続けるのではなく、「自社がどう成長するか」の問いに置き換えられる企業は、実はどんな政権になろうとも、生き残っていけると考えています。加えて、経営者として最も重要なマインドは「自社のミッションに忠実であること」です。関税が上がろうが下がろうが、お客様の悩みを解決するという本質的な使命にブレがなければ、道は自然と開けていきます。外の風に揺れない経営の軸を持つことこそ、「政治や経済に反応する経営」ではなく、「自社の価値に基づいた能動的な経営」に転じるチャンスではないかと考えています。
2025年04月17日
コメント(0)
-
親密度が深まる交流会
世の中には沢山の経営者交流会が存在します。ビジネスの第一線で活躍する経営者同士が出会い、情報交換や協業のきっかけを生み出すこの場には、明確な「ビジネスモデル」が存在しています。ただの名刺交換イベントではなく、しっかりと仕組み化された収益構造があるんです。まず、経営者交流会の主な収益源は以下の通りです。・参加費:1回数千円〜数万円の参加費が基本。規模や内容によって変動します。・会員制(月額課金):定期的な参加ができる月額会員制を導入することで、安定収益を得られます。ゴールド会員やプレミアム会員など、ランク制を取り入れるケースもあります。・スポンサー収入:会場でのPRやチラシ配布、登壇機会などを企業に提供し、広告費を得ます。・イベント内サービス販売:例えば、登壇枠の販売、動画撮影サービス、名刺スキャンによる後日連絡代行など。このように、交流会は「人が集まる場所=価値が生まれる場所」として、うまくビジネスとして成立しているんです。私も色んな経営者交流会に参加しているのですが、最近は「ゴルフコンペ形式」の交流会が、特に親密度を深めることに繋がっています。それの理由は、共に過ごす「時間」と「距離感」が通常のイベントとはまったく異なるからです。ゴルフコンペでは、1ラウンドにかかる時間は約4〜5時間、しかも、プレー中はほぼ常に同伴者と行動を共にします。ビジネスの場でこれほど長く、自然体で他人と過ごす機会はなかなかありません。加えて、ゴルフというスポーツの特性上、打った後の移動時間や待ち時間に会話が生まれやすいんです。お互いのプレースタイルやマナーから人柄が滲み出るため、「この人とは信頼できそう」と直感的に感じる瞬間も多くなります。また、打ち解けた後の懇親会や表彰式での再会が、さらに距離を縮めてくれます。実際、ゴルフコンペで知り合った相手と、その後ビジネスパートナーになったり、資本提携に発展したケースも少なくありません。一方で、通常の異業種交流会や立食パーティーでは、会話の時間は数分から10分程度。名刺交換はできても、相手の深い部分までは見えません。その点、ゴルフは「その人がどういう人か」を知る、絶好のフィールドです。さらに言えば、「平日の昼間に時間を取って参加する」というスタンス自体が、一定の経営層やフリーな裁量を持つ人々のフィルターにもなっています。参加者同士の共通点が多く、信頼関係が築かれやすいのです。もしあなたが人脈を広げたい、信頼できるビジネスパートナーと出会いたいと考えているなら、一度ゴルフコンペに参加してみるのもアリかもしれません。
2025年04月16日
コメント(0)
-
私の信念『チャンス&トライアル』の核心
私が20年以上・7115日にわたり日々綴っているこのブログ『年中夢求!!「ダントツ夢創り」の道』には、私の経営哲学や人生観が色濃く表現されています。その中でも特に重要視されているのが、「チャンス&トライアル(チャントラ)」という行動指針です。「チャンス&トライアル」とは、目の前にある機会を積極的に捉え、恐れずに挑戦する姿勢を意味します。挑戦することによって、人は必ず『成長』という素晴らしい果実を得ることが出来ます。私はこの精神を、会社経営や人財育成の根幹に据えています。私自身、リクルートでのキャリアを経て、父親が経営する会社の再建に取り組む中で、多くの困難に直面しました。借金5億円という厳しい状況下でも、「チャンス&トライアル」の精神で新規事業に挑戦し、大きな失敗を経験しながらも会社を立て直してきました。この考え方は、社員教育にも反映されており、社員一人ひとりが自らの可能性を信じ、新しいことに挑戦する文化を育むことを重視しています。その結果、管理職の約8割が女性であるなど、多様な人財が活躍する組織が形成されています。また、在宅勤務や時差出勤など、柔軟な働き方を導入し、社員が自分らしく働ける環境づくりにも力を入れています。さらに、「真価発伝」という考え方を大切にしており、商品の真の価値を見出し、それを社会に伝えること我々の仕事として位置付けています。販促ツールの企画・製作を通じて、顧客の商品やサービスの魅力を最大限に引き出し、ファンを創り出すことを目指しています。このような取り組みは、単なる当社の売上向上だけでなく、社会全体への貢献にも間違いなくつながっています。「チャンス&トライアル」の精神は、私自身の人生哲学であり、会社の文化としても根付かせようと努めています。このブログでも、日々の出来事や社員とのエピソードを通じて、この考え方の重要性を繰り返し語っています。挑戦を恐れず、常に前向きに行動することで、個人も組織も成長し続けることができるという信念が、色濃く反映されているのです。このように、「チャンス&トライアル」は、私の経営哲学の核心であり、アサヒ・ドリーム・クリエイト株式会社の成長を支える原動力にもなっています。私のブログを通じて、多くの人々がこの考え方に触れ、自らの人生や仕事に活かしていくことを期待しています。
2025年04月15日
コメント(0)
-
先読みサービスは人間力の証
サービス業に限らず、あらゆる人との関わりの中で「この人、すごいな」と感じる瞬間があります。それは、相手がこちらのニーズや気持ちを“先回り”して察し、行動してくれた時、いわゆる「先読みのサービス」ができる人に出会うと、ただの親切以上の“人間力”を感じずにはいられません。では、なぜ先読みのサービスが「人間力」の証とまで言えるのでしょうか?先読みのサービスを提供するには、まず相手をよく観察する必要があります。お客様の表情、しぐさ、声のトーン、持ち物や服装などちょっとした情報の中から、「何を求めているか」「今、どう感じているか」を想像する力が求められます。例えば、カフェでお冷が減ってきたタイミングでさりげなく注ぎに来てくれるスタッフ。何も言っていないのに、「この人、よく見てるな」と感じます。その行動の裏には、観察と想像という二つの“人としての力”が働いています。また、先読みとは、「自分だったらこうしてほしいな」と想像し、行動することでもあります。つまり、相手の立場に立って考える“共感力”が不可欠です。単なるマニュアル対応ではなく、目の前の一人ひとりに向き合おうとする姿勢、これはAIやロボットにはなかなか真似できない、人間ならではの力です。気配りは時に「気づかれない優しさ」として表れることもあります。お客様が気づかないレベルで快適さを提供する、そんな“目立たない心遣い”こそ、先読みの真髄であり、高い人間力の証明なのです。もちろん、最初から完璧に先読みできる人なんていません。先読みのサービスができるようになるには、たくさんの経験と、そこから学ぶ姿勢が必要です。「このときはうまくいかなかったな」「あのお客様はこんなことで喜んでくれた」――そうした経験の蓄積が、次の“先回り”に活きてくるのです。つまり、先読みができるということは、それまでに多くの経験を積み、試行錯誤を重ねてきたという証であり、人としての成長を続けていることの表れでもあります。忙しいと、つい目の前のことで精一杯になりがちです。しかし、先読みのサービスができる人は、どんなに忙しくても、どこかに“心の余白”があります。そのゆとりが、周囲を見渡す視野の広さを生み、相手の気持ちに寄り添う余裕につながっているのです。だからこそ、先読みできる人と一緒にいると、こちらも安心できたり、穏やかな気持ちになれたりします。それって、結局“人間力”が高い人の放つ空気なのかもしれません。「先読みのサービス」は、ただのテクニックではありません。それは、相手を思いやり、自分を磨き続ける姿勢から生まれるもの。観察力、共感力、経験、そして心のゆとり――そのすべてを備えた人が持つ力です。だからこそ、先読みのサービスができる人は、誰から見ても信頼され、選ばれ続ける存在になるのです。これは、接客業に限らず、家庭でも職場でも、どんな人間関係にも通じる“生きた人間力”なのではないでしょうか。
2025年04月14日
コメント(0)
-
離島の洗礼
今日は屋久島から鹿児島、そして熊本への移動の予定でしたが、強風によりフライトが欠航になり、その他のフライト予約が取れず、明日のキャンセル待ちも難しいということになりました。その状況で船での移動に切り替えて、鹿児島への移動を目指しました。宮之浦港まで行き、まだ出航が決まってない船便のキャンセル待ちをすることにしました。キャンセル待ちの番号は58番、かなり絶望的な順番でしたが、奇跡を信じて待ちました。その間も他の手段はないか、鹿児島でのレンタカーの変更などバタバタとした時間を過ごしました。結局、呼ばれた番号は54番まてで、今日中の鹿児島移動の希望は完全に絶たれてしまい、明日の高速フェリーの予約が生きることになりました。そこから、今日の宿の手配、宿泊予定のホテルやレンタカーのキャンセルなどを矢継ぎ早に連絡し、屋久島3泊目が決まりました。今朝のフライトまでの時間、屋久島一周のドライブをしていました。宿の近くのトローキの滝(漢字で書くと、轟の滝)、千尋の滝、そして大川の滝を見に行きました。どの滝も圧倒的な水量で、スケールの大きさはこれまで目にしたことがないくらいの迫力でした。特に大川の滝は、水飛沫がかかるほど間近で見ることが出来る、私の中ではこれまで見た滝の中で断トツでナンバーワンの迫力でした。その後、西部林道では野生のシカやサルと何十匹も遭遇するので、慎重に運転しながら進みました。途中で何度も車を停めて、シカやサル達が道を通り過ぎるのを待ちました。そんな自然体の野生のシカやサルに出会うのも初めての体験でした。その後、屋久島神宮への参拝を終えて、レンタカーを返しに行ったところ、自分達が乗るフライトが欠航することを知った次第です。屋久島一周の際も強風を感じていましたが、まさか飛行機が欠航するまでのものとは夢にも考えていませんでした。しかし、屋久島のような離島では、それほど珍しいことではなく、かなりの頻度で発生していることを後で知りました。自分の未知を恥じるとともに、危機管理能力の欠如にも課題を残しました。一部のスケジュール変更は余儀なくされましたが、絶対に外せない予定だけはなんとかしたいので、明日の高速フェリーが無事動いてくれることを願っています。
2025年04月13日
コメント(0)
-
57歳の誕生日に縄文杉からパワーをもらいました!
今日、57歳を迎えました。健康に産んでくれた両親、日々を幸せに過ごさせてもらっている妻や家族、そして一緒に働いてくれている社員への感謝の気持ちが湧いて来ました。今年の誕生日は、人生で初めて屋久島に来ていまして、朝3時半に起きて縄文杉ツアーに参加しました。往復10時間もかかる道中、しかも1カ月35日雨が降ると言われる屋久島で、90%の雨予報でしたので、悪天候での屋久杉ツアーを覚悟していたのですが、ゴール直前の夕方に少し雨に降られたくらいで基本的に好天に恵まれました。今日もなんとか晴男の面目を保つことが出来ました。屋久島の縄文杉について少し解説します。屋久島の「縄文杉(じょうもんすぎ)」は、日本を代表する神秘的な存在であり、屋久島のシンボル的な世界遺産です。場所は鹿児島県の屋久島、標高1,300m付近の深い山中、樹齢は推定2,000年~7,200年(諸説あり。中でも有力説は約2,170年)、樹高は約25.3m、 幹回りは約16.4m(日本の杉の中で最大級!)となります。縄文杉という名前は、縄文時代に生まれたほどの古さだと言われることから名付けられました。その堂々たる姿は、時の重みと自然の力を全身で感じさせてくれます。1993年、屋久島全体がユネスコの世界自然遺産に登録されました。縄文杉はその象徴的存在であり、「人の手がほぼ加わっていない原生的な自然」が高く評価されています。途中には「ウィルソン株(巨大な切り株の中からハート型に見える空)」「大王杉」「夫婦杉」など人気のスポットもあります。また道中で沢山の野性のサルに出会いました。木の上でエサの果実を食べていたり、赤褐色の鉄分を含んだ水を飲んでいたり、人間の存在を無視したような野性の姿に感動しました。私もお願いしたいのですが、ガイド付きのツアーが人気で、初心者でも安心して挑戦できます。ガイドさんに様々な知識を教えていただきながら、さらには参加メンバーに応じたペース配分を考えてもらいながら導いてもらうことで、安心・安全なツアーになります。それでもかなりの体力が必要になることは間違いありません。実際に目の当たりにした縄文杉は、「数千年の時を超えて、いまもなお生き続ける存在」であり、圧倒的な存在感を感じました。思わず手を合わせて拝みたくなるような神々しさを感じ、まさに命の根源に触れるような体験ができる場所でした。57歳を迎えた日に、このような神秘的な体験が出来たことは何か意味があると感じましたし、縄文杉を始めとする屋久島からもらったパワーを今日から存分にエネルギーにして生きていきます!
2025年04月12日
コメント(0)
-
退職代行のニュースを見て経営者が感じたこと
近年、退職代行サービスの需要が急増しており、特に4月1日の入社式後に依頼が殺到しているという記事を目にすることが増えました。社員が新しい職場に馴染む間もなく退職を選び、代行サービスを利用するという現象は、経営者として非常に考えさせられるものがあります。一方で、退職代行サービスが存在し続ける理由を深掘りすることで、現代の労働環境や働き方についてのヒントを得ることも可能です。退職代行サービスの社会性についての考察をしつつ、経営者としての退職代行についての適切な捉え方を深掘りしてみます。退職代行サービスとは、従業員が自ら会社に退職を伝えることができない場合に、第三者がそのプロセスを代行するサービスです。これは、退職交渉の負担軽減や精神的ストレスの軽減を目的としており、特に若い世代に支持されています。このサービスの存在そのものが、現代の働き方や労働関係における課題を浮き彫りにしています。退職代行サービスの社会性=世の中に良い影響を与えることは一体何でしょうか?一つは、働き手の心理的負担を軽減することで、上司や会社に退職を直接伝えるのが困難な状況に対応します。特にハラスメントや職場の文化が原因の場合、心理的ストレスを和らげる役割を果たします。二つ目は、労働者の権利保護退職時に必要な手続きが適切に進められることで、権利が守られ、トラブルを防ぐことができます。そして三つ目は、現代社会の価値観に対応にすることで、働くことに対する価値感が多様化し、個人の自由や幸福追求が重視される時代にマッチしています。では、経営者として考えるべき視点はどんなことになるでしょうか?私もその一人ですが、退職代行サービスに否定的な感情を抱く経営者は少なくないでしょう。社員が直接話し合うことなく退職を選び、さらに第三者にそのプロセスを委任するという行為は、会社と従業員の信頼関係が崩壊しているようにも見えるからです。しかし、この現象を単なる「責任感の欠如」として片付けるのではなく、深く考えることが必要です。社員が退職代行を利用する理由は、単に会社に不満があるからではなく、心理的な負担や職場環境に原因がある場合があります。『上司とのコミュニケーションが難しい』、『職場の文化が合わない』、『ハラスメントや過剰なプレッシャー』、『社会的スキルや自己肯定感の欠如』などが主に報道されている内容です。もし社員が退職代行を選ばざるを得ない理由が会社側の問題に起因するなら、それを改善する責任が経営者にはあります。退職代行サービスは労働者の選択肢を広げ、退職時の心理的負担を軽減するという側面で社会性を持っていますが、同時にその利用増加は、職場環境や労働文化の問題を指摘するシグナルとも言えます。経営者としては、このサービスを否定するだけでなく、対話や文化構築を通じて「退職代行が必要ない職場」を目指すべきです。社員が退職すること自体は、必ずしも悪いことではなく、退職という選択が必要になる場合もあります。しかし、退職の際に退職代行を使わざるを得ない状況は、会社側と個人との信頼関係が欠如している可能性を示しています。信頼関係を再構築するためには、対話を促進し、社員が率直に意見を言える環境を作ること、職場の文化を改善し社員が心理的に安全だと感じる職場を目指すこと、定期的なフィードバックで従業員の声を経営に反映させる仕組みを創ることなどが考えられます。退職代行サービスの台頭は、ひとつの警鐘でもあります。現代の従業員は、業務内容だけでなく職場環境、関係性、そして心理的安全性を求めています。退職代行は「退職の合理化」を支援するツールであると同時に、会社内部のコミュニケーションや文化が改善されていないことを示す指標とも言えます。経営者として、この現象を単なる批判で終わらせるのではなく、「退職代行が使われざるを得ない職場になっていないか」と問い直すことが重要です。退職代行サービスは存在し続けるかもしれませんが、その利用を最小限に抑える職場作りを目指すことが、経営者としての使命と言えるでしょう。退職代行サービスは、個人の権利を守り、心理的負担を軽減するという社会的役割を担っています。その存在を否定するのではなく、それが必要とされる背景を理解し、職場環境を改善するきっかけとして捉えることが重要です。経営者が進化することで、社員が安心して働き、退職の際も直接対話を選べる職場を作ることができます。退職代行の利用が急増する現代だからこそ、経営者として信頼と対話を中心とした職場づくりに取り組むべきという警鐘と捉えたいと思います。
2025年04月11日
コメント(0)
-
自問自答で道を拓く
私たちは日々の生活や仕事の中で沢山の意思決定を行っています。その意思決定の数は一日に3万5000回とも言われています。その多くは、外部の情報や他者からの意見に影響されることが少なくないでしょうが、本当に重要な決断ほど、最終的には自分自身の内面と向き合い、「自問自答」を通じて答えを導き出すことが鍵となります。自問自答は、自分との対話を通じて内省を深め、自分にとっての最適解を導き出す効果的な方法なのです。では、なぜ自問自答が効果的なのか、そしてその質を上げるために何をすればよいのか、について考えてみたいと思います。自問自答は、他者や環境からの影響を一時的に排除し、自分自身の本音、価値観、願望にアクセスする方法です。情報が溢れる現代では、外部要因に引っ張られることが多く、時に自分の本心を見失いがちです。自問自答はその外のノイズをシャットアウトし、自分の内側に意識を向けることで、真に自分らしい選択を可能にします。自問自答を通じて決断をした場合、その結果に対して自分が責任を持ちやすくなります。誰かの意見に従って決断した場合、「あの人のせいでこうなった」と他責にしてしまいがちですが、自問自答による決断は内なる自分に根ざしているため、結果を引き受ける覚悟が生まれます。自問自答は一種の内省のプロセスとも言えます。表面的な問題を解決するだけでなく、「なぜこの問題が生まれたのか」「これは本当に解決すべき優先事項なのか」といった深いレベルで問題を分析する訓練になります。これにより、盲目的に行動するのではなく、根本的な解決策を見出すことができます。自問自答は効果的な意思決定の手段である反面、その質が低ければ間違った答えを導き出してしまう可能性もあります。自問自答の質を高めるためには、どんなことが必要でしょうか?自問自答の質は、質問の質にかかっており、「どうすればいい?」のような漠然とした問いではなく、「なぜこれをしたいと思うのか?」「この選択がもたらす長期的な影響は何か?」といった具体的な質問をすることが、深い思考を引き出すカギです。良い質問は、自分の価値観や目標を明確にし、解決の方向性を示してくれます。考えを頭の中だけでまとめるのは難しいこともあるので、ノートや紙に質問と答えを書き出すことで、思考が整理され、漏れのない結論へと導くことができます。また、時間を置いて見返すことで、自分の思考を客観視することができます。感情は意思決定に深く影響を与えるので、自問自答の際に「今、自分はどんな感情を持っているのか」を正直に認識することで、感情に流されることなく合理的な決断が可能になります。例えば、焦りや不安がある場合、それが思考を曇らせていないかを確認することが大切です。重大な決断ほど、急いで答えを出すのは避けるべきです。自問自答には時間が必要であり、何度も同じ問いを繰り返すことで、より深い答えを得られることがあります。焦るのではなく、じっくりと自分自身と向き合う時間を取ることが質を高める秘訣です。自問自答は、自分自身の意思決定を形作るだけでなく、成長や学びのプロセスにも寄与します。意思決定を振り返り、「その選択は正しかったのか」「どう改善すべきだったのか」と再び自問自答を繰り返すことで、自分自身の思考力や判断力を高めることができます。この「振り返りの自問自答」を習慣化することで、より洗練された意思決定が可能になるでしょう。『自問自答』は、人間の意思決定における重要なプロセスであり、自分自身と対話することで本来の価値観や目標を引き出せる効果的な手法です。その質を高めるためには、良い質問をし、考えを整理し、感情を認識することが重要です。自分にしか答えられない問いを持ち、自問自答を通じて自分らしい選択を導き出すことが、真の意味で主体的な人生を生きる鍵となります。答えはいつも自分自身の中にあるので、自問自答で幸せな道を切り拓いていきましょう!
2025年04月10日
コメント(0)
-
友達ではなく仲間が必要
今日、経営者仲間とのミーティングの中で、「仲の良い友達がそれほど必要ではなくて、同じ価値観を持つ仲間は必要」という話が出ました。私が尊敬するマーケッターの森岡毅さんも「仲間がいないと淋しい」と主張する若者に対して、「友達はいなくても良くて、仲間は必要だ」と語っておられました。特に経営者にとって「仲間」がいかに重要であるかを深掘りしてみました。まず、「友達」と「仲間」の違いについて考えてみると、友達とは、共通の趣味や価値観を持ち、リラックスして過ごせる相手です。プライベートな関係が主であり、お互いの幸せを喜び合い、支え合う存在です。しかし、友達関係には、仕事の厳しさや成長を促すための挑戦的な意見を求めることが難しい場面もあります。一方、「仲間」とは、共通の目標やビジョンを持ち、困難に立ち向かうために力を合わせる相手であり、仕事や事業においては、仲間はただの支え手ではなく、お互いを切磋琢磨し、より高みを目指すための存在です。仲間は「共に成長し、共に成果を出す」ことに強く関わっており、時には厳しい意見や反論を受け入れることで、より良い方向へ進んでいくことができます。経営者にとって仲間は、単なる助け合いの存在ではありません。仲間は、経営者が直面する難局を乗り越えるための重要なパートナーであり、企業の成長を目指すには、単独では達成できないことが多く、仲間の協力が不可欠です。経営者がビジョンを掲げ、その実現に向けて事業を進めていく中で、仲間の力は欠かせません。企業の成長には戦略的な思考や計画が必要ですが、実行段階で仲間の協力がないと、アイデアや戦略は空回りしてしまいます。仲間とは、目標を共有し、実現に向けてどんな役割を果たすべきかを共に考え、実行する存在なのです。経営者は日々、決断を下し、リスクを取る立場にありますが、その中で精神的なプレッシャーやストレスを感じることも多いでしょう。そんなとき、経営者一人ではその重圧に耐えきれないことがありますが、仲間がいれば、意見を交換し、助け合いながらそのプレッシャーを分担できます。また、仲間が経営者の決断に対してフィードバックをくれることで、視野が広がり、より良い意思決定ができるようになります。仲間はお互いの強みを活かし合い、足りない部分を補い合う存在です。経営者として成長するためには、時に仲間の異なる視点や経験から学ぶことが必要ですし、自分が気づかなかった問題点や改善策を指摘してくれる仲間がいることで、経営者としてのスキルが向上し、企業の戦略もより強固なものになります。経営者として仲間を選ぶ際には、いくつかの重要なポイントがあります。まず、最も重要なのは、共通の価値観やビジョンを持っていることです。企業の成長を目指す上で、異なる価値観やビジョンを持つ仲間とは、協力が難しくなることが多いですが、経営者が掲げるビジョンに共感し、その実現に向けて自分の力を尽くしてくれる仲間を選ぶことが大切です。仲間は単なる「YESマン」ではなく、時には経営者に対して建設的な意見をぶつけてくれる存在でなければなりません。経営者がうまくいっていないとき、問題点を指摘し、改善策を提案してくれる仲間は、非常に貴重です。仲間が挑戦的であることで、経営者は自分の視野を広げ、新たな気づきを得ることができます。企業の成長には時間がかかることが多く、その間に数々の困難や挫折が待ち受けています。そんなとき、仲間が共に歩んでくれることで、経営者は孤立することなく、最後まで諦めずに進み続けることができます。忍耐力と信頼関係を築ける仲間こそ、企業を支える柱となるのです。「友達はいなくても良くて、仲間は必要だ」という言葉は、一見淋しい言葉に感じるかも知れませんが、経営者にとって非常に大切な教訓です。その言葉を肝に銘じて、仲間創りに尽力していきます!
2025年04月09日
コメント(0)
-
誰と一緒にバスに乗るのか?
新規事業立ち上げのために日々行動しまくっているのですが、その中でようやく事業の方向性が見えて来ました。事業の方向性が決まった後に必要になって来るのは、事業に相応しい人を集めることです。世界的なベストセラーである「ビジョナリーカンパニー」シリーズの中で語られる「誰をバスに乗せるか?」というテーマは、事業パートナー選びにおいて非常に重要な考え方です。この問いは、組織やビジネスの成功において、適切な人材を集めることの大切さを説いています。バスに乗せるべきは、単にスキルや経験だけでなく、ビジョンや価値観を共有できる人であり、共通の目標に向かって進むためには、信頼と相互理解が不可欠です。ビジネスパートナー選びは、単なる能力だけでなく、理念や情熱の一致を重視するべきだという教訓が込められています。ひと昔前でしたら、相応しい人を採用するかパートナーとなる会社を探すことが必要でしたが、令和のプロジェクト進行は全く違う世界があることが分かってきました。その最たる例が「ダオ(DAO)」という考え方です。ダオとは、分散型自律組織(Decentralized Autonomous Organization)の略で、中央集権的な管理者を置かず、コミュニティやメンバーによって運営される組織の形態を指します。この組織運営をプロジェクトに取り入れることには、いくつかの重要な価値とメリットがあります。まず、ダオは透明性の向上をもたらし、すべての意思決定や資金の流れがブロックチェーン上で公開され、誰でもアクセスできるため、プロジェクトの進行や資源の使用がオープンであることが保証されます。この透明性が信頼を生み、ステークホルダーが積極的に関与する動機となります。次に、ダオは分散型であるため、中央集権的なリーダーシップがない状態での意思決定が行われます。これにより、リーダーに依存せず、コミュニティ全体の意見を反映させることができ、より多様で包括的なアイデアが生まれやすくなります。さらに、従来の組織構造にありがちなボトルネックを避け、迅速かつ効率的な意思決定が可能となります。また、報酬制度に関してもダオは柔軟です。メンバーが貢献度に応じて報酬を受け取ることができるため、参加者のモチベーションが高まり、プロジェクトへのエンゲージメントが深まります。これは、一般的な企業のような給与体系とは異なり、貢献が直接的に報われる仕組みとなります。これらの要素が組み合わさることで、ダオは革新的なアイデアを生み出し、効率的かつ協力的にプロジェクトを推進するための強力なフレームワークとなるのです。このダオの考え方でプロジェクトを始めたことによって、本当に素晴らしい人財が集まり始めています。素晴らしい人財と一緒のバスに乗ることによって、事業のスピードは上がりますし、成功確率も格段に上がっていきます!これからのプロジェクトの成長がとても楽しみです。
2025年04月08日
コメント(0)
-
強固なつながりが生まれるリファラルマーケティング
現代のビジネス環境では、効率的で信頼性の高いマーケティング手法が求められています。その中でも「リファラルマーケティング」は、特に注目される手法の一つです。リファラルマーケティングとは、既存の顧客やビジネスパートナーからの紹介を通じて新たな顧客を獲得する方法であり、信頼を基盤としたマーケティング戦略です。この手法は、単なる広告やセールス活動とは異なり、人と人とのつながりを活用することで、より深い関係性を築きながらビジネスを拡大することができます。そんなリファラルマーケティングを最大限に活用するためのプラットフォームとして注目されているのが、「コーポレートコネクションズ」略称CCです。今回は、コーポレートコネクションズの特徴を踏まえながら、リファラルマーケティングの有用性についてお伝えします。リファラルマーケティングの最大の魅力は、「信頼」が基盤となっている点です。紹介を受ける際には、紹介者が自分自身の信頼を担保にしているため、単なる広告や知らない企業からのアプローチよりも、受け取る側は安心感を持ちます。この信頼感は、成約率や顧客満足度に直結します。さらに、リファラルマーケティングは質の高いリード(潜在顧客)を獲得できる点でも優れています。紹介者は相手のニーズや状況を理解した上で紹介するため、ターゲットが適切である可能性が高くなります。これにより無駄な営業活動を減らし、効率的なビジネス展開が可能になります。私がお世話になっているコーポレートコネクションズは、ビジネスリーダーや企業経営者が集まり、互いに信頼関係を築きながらリファラルマーケティングを実践するためのプラットフォームです。このコミュニティ型ネットワークは、単なるビジネス交流会ではなく、以下のような特徴があります。コーポレートコネクションズには各業界で活躍する経営者や専門家が参加しており、高い専門性と信頼性を持つネットワークが形成されています。メンバー同士が互いに価値観や目標を共有しながら協力し合うことで、質の高いビジネス機会が生まれます。また、単なる交流ではなく、定期的なミーティングや活動を通じて具体的なビジネス紹介(リファラル)が行われます。これにより、「ただ知り合うだけ」ではなく、「実際に成果につながる」関係性が構築されます。加えて、コーポレートコネクションズは世界中に広がるネットワークを持っており、国内外でのビジネス展開にも役立ちます。特にグローバル市場への進出を目指す企業にとっては、大きなメリットとなります。2週間に一回、定期的に顔を合わせることで長期的な信頼関係を築くことが出来ます。 この継続的な関係性によって、新たなビジネスチャンスが次々と生まれる仕組みになっているのです。コーポレートコネクションズでは、メンバー同士が互いに紹介し合うことで、新たな顧客やパートナーとの接点を生み出します。質の高い紹介によってターゲット層へのアプローチが効率化され、「売り込み型」の営業ではなく、「信頼型」の営業へと転換できるため、高い成約率が期待できます。信頼あるメンバーから紹介されることで、自社ブランドへの信頼感も向上し、紹介元との関係性がブランドイメージにもポジティブな影響を与えます。グローバルネットワークや異業種交流によって、新たな市場や分野への進出機会が広がります。 一度得た顧客との関係性だけでなく、その顧客からさらに新しい紹介につながる可能性があることからもリファラルマーケティングは「循環型」の成長モデルと言えるでしょう。リファラルマーケティングは、人と人とのつながりによって成り立つ非常に効果的な手法です。そして、その価値を最大限に引き出すプラットフォームとして「コーポレートコネクションズ」は単なる営業活動では得られない信頼感と質の高いビジネスチャンスが、このコミュニティ型ネットワークによって実現されます。現代社会では、人間関係や信頼こそが最も重要な資産と言える時代です。もしあなたが新しい顧客獲得方法や効率的な営業活動を模索しているのであれば、ぜひリファラルマーケティングとコーポレートコネクションズという選択肢について考えてみてください。それは単なる取引以上に、人と人との絆によって未来を切り拓く方法なのです。
2025年04月07日
コメント(0)
-
エネルギーが高い人の特徴
私は人に良い影響力を与えるエネルギーが高い人間になりたいと常日頃から意識しています。そんなエネルギーが高い人とはどんな特徴があるでしょうか?特徴一つ目は、「この人と一緒にいると元気が出る」「何かポジティブなエネルギーを感じる」というような高いエネルギーを持ち、自然と周囲に良い影響を与えることができます。エネルギーが高い人々の二つ目の特徴は、基本的にポジティブな思考を持っていることです。様々な困難に直面しても、そこから学び取る姿勢を大切にし、ネガティブな状況でも前向きな面を見つけることができます。このような姿勢は周囲に良い影響を与え、周りの人々も前向きな気持ちを持ちやすくなります。ポジティブな人の周りには、自然と笑顔が溢れ、良いエネルギーが循環します。エネルギーが高い人三つ目の特徴は、日常の中で感謝の気持ちをしっかりと持っていることです。彼らは小さなことにも感謝し、その気持ちを周りに表現することができます。感謝の気持ちは、人間関係をより良くし、周囲の人々に安心感を与えます。また、感謝することで自分自身のエネルギーも高まり、良い循環が生まれます。感謝の気持ちを持つことで、人々はその温かさに触れ、ポジティブな影響を受けるのです。エネルギーが高い人四つ目の特徴は、自己肯定感がしっかりと確立されていることです。自分自身を大切にし、自分の強みや弱みを理解しているため、他人と比較することなく自分らしく生きることができます。このような人は、周りの人にも自己肯定感を育てる手助けをすることができ、周囲の人々も安心して自分を表現できる環境を作り出します。また、自分を大切にできる人は他人にも優しさを持ち、良いエネルギーを与えます。エネルギーが高い人五つ目の特徴は、行動力があり、常に動き続けることができることです。自分の目標に向かって積極的に取り組み、困難があっても粘り強く努力を続けます。このような姿勢は周りの人々に刺激を与え、周囲の人たちも自分の目標に向かって積極的に動き出すようになることがあります。エネルギーが高い人の行動力は、まさにその人の周りを引っ張り、良い影響を与える力を持っています。エネルギーが高い人の六つ目の特徴は、他人を励ます力があることですす。彼らは人々の苦しみや悩みに共感し、適切なタイミングで温かい言葉をかけ、励ますことができます。このような励ましの言葉や行動は、受け手にとって大きな励みとなり、困難を乗り越える力を与えることができます。他人を元気づけることで、エネルギーが高い人自身もその力を受け取り、さらにエネルギーを高めていくことが出来ます。エネルギーが高い人の七つ目の特徴は、周りの人に関心を持ち、しっかりと耳を傾けることができふことです。人々は自分の話を聞いてもらうことで安心感を感じ、その人との信頼関係が深まります。聞き手に徹することで、相手の気持ちを理解し、より良いコミュニケーションが生まれます。こうした姿勢は、周囲の人々にとって非常に心地よく、良い影響を与える要因となります。最後に、エネルギーが高い人の九つ目の特徴は笑顔を大切にしていることです。笑顔は人に安心感を与え、周囲を明るく照らす力があります。エネルギーが高い人は、意識的に笑顔を作り、周りの人々にもそのエネルギーを伝えます。笑顔がもたらすポジティブな影響は計り知れず、その笑顔が周りの人たちを癒やし、元気づけるのです。最後にまとめますと、エネルギーが高い人々は、ポジティブな思考、感謝の気持ち、自己肯定感、行動力、励ましの力、そして他者への関心や笑顔を通じて、周囲に良い影響を与えています。彼らの存在は、まるで太陽のように周囲を照らし、温かいエネルギーを広げていきます。私たちも、こうしたエネルギーが高い人々の特徴を見習い、日々の生活に活かすことで、より良い人間関係を築き、ポジティブなエネルギーを周囲に広めていくことができるでしょう。
2025年04月06日
コメント(0)
-
2000年の歴史を感じる貴重な時間
今日は毎月参拝させてもらっている大神神社に行って来ました。いつものように祓戸神社、巳杉、神宝神社、成願稲荷神社、大神神社、狭井神社、貴船神社、檜原神社、久延彦神社の順番で参拝しました。大神神社の崇敬会に入っているので、誕生日のお祝いの祈祷に参加させていただきました。宮司さんからのありがたいお話にもありましたが、改めて大神神社の魅力をお伝えします。大神神社は奈良県桜井市にある、日本最古の神社の一つであり、古代から続く神道の聖地として非常に重要な存在です。この神社の魅力は、単にその歴史や宗教的な意義にとどまらず、周辺地域の自然美や文化的背景にも深く根ざしていることです。大神神社は、大和の国の守護神として崇敬され、古事記や日本書紀にも登場する神社で、主祭神は、大物主神(おおものぬしのかみ)で、農業や商業の神、また家庭の守り神としても信仰されています。神社自体は、今からおよそ二千年前に創建されたと伝えられており、その長い歴史が感じられる場所です。神社の境内には、古代の神道の風景が色濃く残り、まるでタイムスリップしたかのような気分に浸ることができます。特に、境内の大鳥居は圧巻で、鳥居をくぐることで、神聖な空間に足を踏み入れる感覚を味わえます。このような歴史的背景を感じながらの参拝は、大神神社を訪れる魅力の一つです。大神神社の参道を歩くと、すぐに目を引くのが大きな鳥居です。この鳥居は、特に高さがあり、神社の重要性を感じさせるシンボルとなっています。鳥居をくぐると、静かな空気が包み込み、神聖な気持ちが自然と湧き上がります。この場所は、古代の神々が宿るとされる聖域であり、参拝者は日常の喧騒から離れ、静けさの中で心を落ち着けることができます。本殿に入れた時にだけ参拝出来る三ツ鳥居は非常に珍しい構造を持つ鳥居として知られています。通常の鳥居が2本の柱と1本の横木(笠木)で構成されるのに対し、三ツ鳥居は3本の柱が使われており、3本目の柱が中央に追加されています。この鳥居は、神社の神聖さや、三位一体の神の存在を象徴しているとも言われています。また、大神神社の三ツ鳥居は、神社自体の祭神である「大物主神(おおものぬしのかみ)」に関連していると考えられており、大物主神が三つの神格を持つことから、三つの柱を使った鳥居が建てられたともされています。この三ツ鳥居を外で見ることが出来るのが檜原神社で、そのフォルムの美しさと荘厳さはいつ見ても強いインパクトがあります。展望台の桜はちょうど満開で、本当に美しかったです。57年の人生の中でも一、二番ではないかと思えるほどの絶景でした。自然と一体になった空間で、深い精神的な体験ができるのも大神さんの魅力です。大神神社の周辺には、たくさんの自然や文化的な見どころがあります。特に、「三輪山」(みわやま)は大神神社と深い関わりがあり、この山自体がご神体であり、神の住処とされています。山頂までの登山道も整備されており、登山を通じて神聖な場所に足を踏み入れる感覚を体験できます。大神神社一帯の参拝は、ただの観光ではなく、心の洗濯をする場所です。歴史的な背景、神話の世界、そして美しい自然の景観が織り成すこの神社は、訪れるたびに新たな発見があり、深い感動を与えてくれます。現代の喧騒から離れて、静かな時間を過ごすことができる大神神社の魅力をぜひ感じてみてください。
2025年04月05日
コメント(0)
-
高校生の新卒採用にチャンス&トライアル!
アサヒ・ドリーム・クリエイト株式会社は、企業の販促活動を支える“ファン創り”を企画・提案するプロフェッショナル集団です。私たちの仕事は、ただモノを作ることではなく、「この売り場でどう買ってもらうか?」 、「このブランドの魅力をどう伝えるか?」 、そんな“売れる仕組み”をつくるためのアイデアを企画し、カタチにしていくのが、私たちの仕事です。このたび、私たちは高校生の新卒採用へのチャレンジという新たな一歩を踏み出します。 これまでの新卒採用は、大学卒の方に絞って採用してきましたが、今あえて高校生という若い世代に目を向けたのには理由があります。それは、製造加工部門を将来を支えてくれるフレッシュな人財を探しているからです。販促ツールの企画という仕事は、経験や知識ももちろん大切ですが、それ以上に必要なのは「人の心を動かしたい」という感性や、「こんなモノを作ってみたい」という純粋な好奇心です。まだ社会の色に染まりきっていない高校生の柔らかな発想力、フレッシュなエネルギーにこそ、私たちは未来を感じています。実際、当社で活躍している社員たちも、最初から企画や提案が得意だったわけではありません。大切なのは、「成長したい」と思えることです。アサヒ・ドリーム・クリエイトでは、社員一人ひとりが自分らしく成長できるよう、丁寧な育成制度と、実践の中で力をつけられるチャンスを多数用意しています。最初は先輩について現場を学びながら、徐々に企画や提案のプロセスにも関わっていき、少しずつ“お客様に頼られる存在”へと成長していくのです。私たちは“人”を大切にする会社として、誰かの意見を頭ごなしに否定することはありません。 年齢や経験に関係なく、良いアイデアがあればしっかりと形にしていきますので、若手の提案から、大手企業の販促ツールが生まれたことも珍しくありません。高校生の皆さんにとって、社会に出るというのは大きな決断ですから不安もあるでしょう。「自分にできるのかな」「こんな仕事向いているかな」と思うかもしれません。それでも高校生の“まっすぐな気持ち”を強く求めています。販促の仕事は、毎回がゼロからのスタートで、お客様によって、商品によって、求められる答えは違います。だからこそ、型にはまらず、柔軟な発想を持つあなたのような存在が必要なのです。「モノづくりに興味がある」 、「人を喜ばせたい」 、「アイデアをカタチにしてみたい」 、そんな思いを持っている高校生の皆さんのチャンス&トライアルを全力で応援します。私たちと一緒に、販促の未来をつくっていきましょう!あなたの中に眠る「まだ知らない可能性」と出会える日を、楽しみにしています。
2025年04月04日
コメント(0)
-
リーダーの価値は忍耐と覚悟の強さ
リーダーの資質とは何か?と問われたらどう答えますか? 戦略的思考、実行力、コミュニケーションスキルなどなど、、、確かにそれらは重要です。しかし、本質を突き詰めていくと、「リーダーの真価は、忍耐と覚悟にこそ宿る」だと私は確信しています。ビジネスの現場は、決して綺麗ごとだけでは動きません。計画はズレる、メンバーは悩む、結果は遅れるなどは日常茶飯事です。そんな中でも、リーダーは歩みを止めてはならなりません。理不尽に見える壁にぶつかっても、誰よりも冷静に、誰よりも前を見据えなければならず、成果が出ない中で進み続ける、これこそが、リーダーに求められる忍耐の真の意味になります。そしてもうひとつ、欠かせないのが「覚悟」であり、逃げない姿勢を貫くことです。リーダーは決断を求められる存在で、時には厳しい判断を下さねばなりません。誰かを泣かせる選択もあったり、現場の反発を受けることもあったりしますが、それでも組織の未来のために必要なら、迷わずその道を選択する胆力が求められます。 「人気ではなく、信頼を取りにいく」、その決意こそが、覚悟の証です。リーダーシップとは、目立つことではなく、声を張ることでもなく、結果が出るまで信じ続け、行動し続けることであり、全責任を自らが引き受ける覚悟を持つことです。 このふたつを貫ける人に、チームは自然とついてくることになります。もし、あなたがリーダーとして道を切り拓こうとしているのなら、自らに問うてほしい。「10回折れかけても、11回立ち上がる準備はできているか?」 「誰よりも重い責任を背負う覚悟があるか?」リーダーの価値は、派手な実績や肩書きでは測れません、静かに、粘り強く、未来を信じ続ける“姿勢”にこそ、その真価があります。リーダーは、生まれ持った才能では決まりません。必要なのは、苦しいときにも前を向き、仲間を信じ、自分の決断に責任を持つ覚悟を持つことであり、結果が出るまでやり抜く“しつこさ”です。 組織を動かすのは、完璧な人ではなく、信念を持って動き続ける人なので、失敗してもいい、迷ってもいい、大切なのは、そこから逃げずに学び、もう一歩を踏み出せるかどうかです。 あなたの中にある理想を大切にして進めば、その一歩がやがて人を動かし、未来を切り拓く大きな力になります。 最近、そんなことを感じることが多くなってきました。私は忍耐と覚悟を持ったリーダーになりたいです!
2025年04月03日
コメント(0)
-
好きなことしか成長しない!
自分自身を振り返っても確信していることなのですが、尊敬するマーケッターの森岡毅さんが明確におっしゃっている「好きなことしか成長しない」は、人間の持つ本質的な特徴だと考えています。「人は、好きなことしか本気で伸びない。」これは、USJ(ユニバーサル・スタジオ・ジャパン)のV字回復を牽引したマーケター・森岡毅さんの、人材育成における根本的な哲学でもあります。数字で語る戦略家でありながら、人の“情熱”や“好奇心”の力を誰よりも信じている──それが彼の真骨頂です。森岡さんは、スキルや経験よりも「好きなことに打ち込んでいるかどうか」を重視します。なぜなら、好きなことに取り組んでいる人は、自発的に考え、工夫し、何より継続します。逆に、いくら才能があっても興味のない分野では努力が持続せず、結果として大成しないのです。「努力できるのは才能」と言われますが、その“努力”を引き出す最強の燃料こそが“好き”なのです。一般的な教育や人事評価では、「苦手を克服する」ことに重点が置かれがちですが、森岡さんは、この考えに異を唱えます。「人の脳は、生まれ持った“配線”で得意・不得意が決まっている。不得意を直すより、得意を磨いたほうがはるかに効率的でパワフルだ」つまり、全員を“平均的な人財”に育てるのではなく、“尖った強み”を持った人財を育てる方が、組織としてのパフォーマンスが何倍にも跳ね上がるというのです。人財育成というと、「この人はこの仕事に向いていそうだから」と配置する「適材適所」が定番ですが、森岡さんはさらに一歩踏み込みます。「その人が“やりたい”と思っているかどうか」を重視し、可能な限り「好きなことをやらせる」ことを優先します。これは一見甘いように聞こえますが、実は“最も厳しく、成果に直結する”戦略なのです。やらされ仕事では人は動かない。けれど、自ら“やりたい”と思って取り組む仕事なら、自走し、学び、試行錯誤を繰り返す──その結果、爆発的に成長するのです。とはいえ、「好きなことなんて分からない」という人も多いはず。森岡さんはそこにも明確なヒントを与えてくれます。「最初は小さな“面白い”でいい。少しでも楽しいと感じることを続けていくうちに、やがて情熱に育つ」つまり、“好き”は才能のように見つけるものではなく、日々の行動の中で深めていくもの。だからこそ、上司やリーダーは、メンバーの「好きの芽」を見逃さず、引き出し、育てることが求められるのです。森岡毅さんの人財育成術は、数字や効率に頼るマネジメントとは一線を画します。一人ひとりの「好き」を尊重し、それを軸に成長を設計する。これは、機械的な管理ではなく、人間らしさを土台にした、本質的な育成です。そして何よりこの哲学は、仕事だけでなく、子育て、教育、自己成長にも応用できる深いメッセージを含んでいます。「人は、好きなことしか成長しない。」その一言に、すべてが詰まっているのかもしれません。
2025年04月02日
コメント(0)
-
VUCA時代に生きる古典とは?
今日は毎月恒例の伏見稲荷への「朔日参りの会」に参加しました。今月で参加させていただいてから丸2年になります。毎月、健康体でお参り出来ていることは本当に感謝です。この「朔日参りの会」は、12年前に発足したのですが、立ち上げた代表の方はとても博学でお参り後の朝食会の際に、本当に色んなコトを教えていただいています。今日は「日本の現代の経営において、荘子の考え方を参考にするのが望ましい」というお話をされました。正直、私は荘子のことを深く知りませんでしたので、早速Perprexityに聞いてみました。私が記入したプロンプトは「古代中国の知恵が現代経営を照らす - 荘子の教えと経営の深い関係について教えて」です。Perprexityが出してくれた回答はこちらです。~ここから~ビジネスの世界では常に新しい理論や手法が生まれていますが、時として古代の知恵が驚くほど現代に通じることがあります。今回は、中国古代の思想家・荘子の考え方が、現代の経営においていかに重要であるかを探ってみましょう。1.柔軟性と適応力の重視荘子は「水の如く」柔軟であることの重要性を説きました。現代のビジネス環境は急速に変化し、固定観念にとらわれていては生き残れません。荘子の教えは、市場の変化に柔軟に対応し、新しい機会を捉える重要性を示唆しています。2.全体論的視点荘子は、物事を個別に見るのではなく、全体として捉えることの重要性を強調しました。現代経営においても、部分最適化ではなく全体最適化が求められます。組織全体の健全性や長期的な持続可能性を考慮することの大切さを、荘子の思想は教えてくれます。3.無為自然の経営「無為」とは、不必要な干渉をせず、物事の自然な流れに従うことを意味します。過度の管理や介入を避け、従業員の自主性や創造性を尊重することの重要性を、荘子の思想は示唆しています。4.相対主義的思考荘子は、絶対的な価値観や基準の存在を疑問視しました。これは、多様性を重視し、異なる視点や意見を尊重することの重要性を教えています。グローバル化が進む現代のビジネス環境では、この考え方が特に重要です。5.心の平静の重要性荘子は、外部の状況に左右されない心の平静さを重視しました。激しい競争や予測不可能な変化にさらされる現代のビジネスリーダーにとって、この教えは精神的な強さを保つ上で非常に重要です。6.プロセス重視の姿勢荘子は結果よりもプロセスを重視しました。これは、短期的な利益追求ではなく、持続可能な成長と長期的な価値創造を重視する現代の経営哲学と通じるものがあります。7.パラドックスの受容荘子の思想には、一見矛盾するものを受け入れる姿勢があります。現代のビジネスにおいても、効率性と創造性、グローバル化とローカライゼーションなど、相反する要素のバランスを取ることが求められます。8.自然との調和荘子は自然との調和を重視しました。持続可能性や環境への配慮が重要視される現代において、この考え方は特に重要です。企業の社会的責任(CSR)や環境・社会・ガバナンス(ESG)への取り組みにも通じる思想です。9.謙虚さと学習の姿勢荘子は、自分の無知を認め、常に学び続けることの重要性を説きました。急速に変化する現代のビジネス環境では、この姿勢が特に重要です。「学習する組織」の概念とも通じるものがあります。10.直感と洞察力の重視荘子は、論理的思考だけでなく、直感や洞察力の重要性も説きました。データ分析が重視される現代においても、直感的な判断力や洞察力は、イノベーションや戦略的決定において重要な役割を果たします。荘子の思想は、2000年以上前に生まれたものですが、その本質は現代の経営にも深く通じるものがあります。複雑化し、急速に変化する現代のビジネス環境において、荘子の教えは新たな視点と洞察を与えてくれます。古代の知恵を現代に活かし、より深い経営の在り方を探求することは、今後ますます重要になっていくでしょう。~ここまで~現代社会が抱える本質的な課題である気候変動・AI倫理・働き方改革・メンタルヘルスに対して、荘子の思想は次の点で有効です・柔軟な価値観:絶対的真理が崩れた相対主義時代の羅針盤となる・エコシステム思考:人間中心主義から脱却する視点を提供・創造的破壊:既存の枠組みを超えるイノベーションを奨励・精神的自由:管理社会における生きづらさを解消する智慧孔子や孟子の思想が「どうあるべきか」を説く規範哲学であるのに対し、荘子は「どう在るか」を問う存在哲学です。不確実性が支配する現代において、完璧な答えを求めるよりも、変化に適応する生き方を指南する荘子的アプローチが、多くのビジネスリーダーや起業家から注目されている所以でしょう。せっかくの機会ですから、さらに荘子を深掘りしていきます!
2025年04月01日
コメント(0)
全31件 (31件中 1-31件目)
1