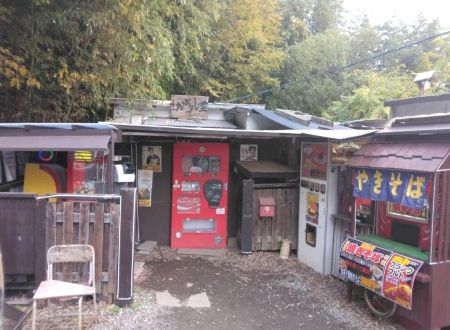2025年09月の記事
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-
シェアを奪い合わず、高め合うビジネスモデル
会社を成長させるための方策は、それこそ百花繚乱のように存在します。新しい商品開発、マーケティング手法の革新、人材育成や組織改革、DX推進や海外展開など、どれを選択するかによって道筋は大きく変わります。経営者として22年、私も日々「次の成長のカギは何か」と自問自答しながら、新しいビジネスモデルを模索してきました。ドラッカーは「経営とは顧客の創造である」という言葉を遺しましたが、この言葉の重みは、経営の本質を突きつけます。顧客の数を増やすこと、顧客の満足を高めること、顧客の未来を創り出すこと、経営は常に顧客と共にあります。しかし、多くの経営者は「顧客をいかに自社に引き込むか」という発想に偏りがちです。つまり「シェアを奪い合う」発想で、そこには競争という宿命があり、限られたパイを取り合う構図が生まれます。ところが今日、私はこれまで考えもしなかった「新しいビジネスモデル」に出会いました。中身をここで詳しく書くことはできませんが、例えるならば「奪い合うのではなく、互いにシェアを高め合う」モデルです。競争ではなく共創、対立ではなく調和、ゼロサムではなくプラスサム、そんな世界観に近いイメージです。正直に言えば、まだアイデアの端っこを掴んだにすぎませんので、漠然とした輪郭しか見えていない状態です。しかし、この発想には従来の私の考えにはなかった新しい可能性を強く感じます。もし本当に実現できれば、業界全体の価値が高まり、参加するすべての企業や顧客が恩恵を受けるモデルになるかもしれません。これまでも多くの新規事業を構想し、挑戦してきました。その中には成功もあれば失敗もありました。成功の裏には必ず試行錯誤と改善があり、失敗の中にも大きな学びがありました。今回のモデルも同じで、いきなり完成形が見えるわけではありません。むしろ、実践の中でしか磨かれないものだと思います。大切なのは、着想を掴んだ時点で「これは面白い」と感じた直感を信じてみることです。未来を切り拓くのは論理だけではなく、時に勇気ある第一歩です。思えばこれまでも、直感から始まった挑戦が大きな成果につながったことは何度もありました。だからこそ今回も「チャンス&トライアル」の精神で取り組みたいと考えています。この「奪わず、高め合う」という発想は、経営だけでなく人生そのものにも通じる気がします。人間関係においても、相手から何かを奪おうとすれば摩擦が生まれますが、互いの価値を認め合い、高め合う関係を築けた時、信頼が生まれ、成果は何倍にも膨らみます。企業と企業も、社会と企業も同じです。これからの時代、人口減少や市場縮小といった課題は避けられません。従来型の「奪い合い」ではますます消耗戦になってしまいますので、その中で「高め合う」モデルは、未来を照らす希望の光になるのではないでしょうか。私は今、その光の入り口に立っています。小さな閃きから始まる挑戦が、やがて強固なビジネスモデルとなり、顧客や社員、そして社会を幸せにする仕組みへと育っていくことを願ってやみません。これからの実践を通じて、その道筋をしっかりと形にしていきたいと思います。
2025年09月30日
コメント(0)
-
価値観採用に妥協なし!
当社の採用活動には、明確な大きな方針があります。それは「価値観が合う人しか採用しない」というものです。スキルや経験はもちろん大切ですが、それ以上に重視しているのが価値観です。価値観が合っている人とそうでない人とでは、同じ時間を過ごしていても充実感や一体感に大きな違いが生まれます。だからこそ、当社では価値観を採用の最重要ポイントとしています。では、価値観とは何でしょうか?、私はそれを「人生観・人間観・仕事観」という三つの軸で捉えています。中小企業の場合、経営者の価値観が会社全体に大きな影響を与えます。組織文化や社風、さらには意思決定のスピードや方向性まで、経営者の価値観が色濃く反映されるのです。そのため、経営者である私自身の価値観に共感できるかどうかが、会社にフィットするかどうかを決定づけると考えています。私の人生観は「全ての因は我に在り」と「チャンス&トライアル」です。前者は、起こる出来事の原因を外に求めず、自分に原因があると捉える姿勢で、そうすることで人のせいにすることなく、常に自分を磨くことにつながります。後者は、人生に訪れるチャンスを逃さず、まずは挑戦することを大切にする考え方で、失敗を恐れず挑戦することでしか、本当の成長はありません。人間観については、「無限の可能性」と「切磋琢磨」を信じています。人は誰しも無限の可能性を持っており、それを引き出すのは環境と仲間の存在で、一人では到達できない領域も、互いに刺激し合い、切磋琢磨することで突破することができます。社員同士が尊重し合いながら高め合う組織こそ、持続的に成長できると考えています。そして仕事観は、「ハッピートライアングル」と「志魂商才」です。ハッピートライアングルとは「社員の成長・お客様感動・会社信頼と利益」の三つを同時に実現することを目指す考え方で、どれか一つに偏るのではなく、三方よしの精神でバランスを取りながら高めていくことが理想です。中でも「社員の成長」を一番に考え、それを徹底的に磨き上げることを一番の目的にしていると言っても過言ではありません。また、志魂商才は「志ある魂を持って商いに臨む」ことを意味しており、単なる利益追求ではなく、志を持って世の中に貢献する商いをするという姿勢です。これらの価値観に心から共感できるかどうか、それが当社の採用における大切なポイントです。もちろん、価値観を強要するつもりは毛頭ありません。価値観は人それぞれであり、どちらが正しいかというものではありません。ただ、当社においては、この価値観に共感し、自然体で共有できる人と一緒に働きたいと考えています。無理に合わせたり、正当化したりしても意味がなく、むしろ、自然体で心から共感できるかどうかが大切です。同じ価値観を共有できる仲間と出会えたとき、そこには強固な信頼関係が生まれ、困難を乗り越える力が育まれます。採用は「人を選ぶ」場ではなく、「同志を探す」場だと私は思っています。当社の価値観に共感し、ともに未来を築いていける仲間と出会えることを心から楽しみにしています。
2025年09月29日
コメント(0)
-
人間の持つ無限の可能性を引き出す周波数432HZ
人間にはまだまだ計り知れない無限の可能性が秘められていると、私は信じていますが、その可能性をどうやって引き出すかという問いは、古今東西の哲学や科学、そしてスピリチュアルの世界で繰り返し語られてきました。その中で最近、私が特に注目しているのが「周波数」の力です。音の周波数が心や体に大きな影響を与えるという考え方は、既に多くの研究や実践によって裏付けられつつあります。数ある周波数の中で、私が試してみて最も効果的だと感じているのが「432Hz」です。これは一般的な音楽の基準である「440Hz」チューニングに対して、やや低めに調整された音階です。YouTubeで「432Hz」と検索すれば、リラクゼーションや瞑想用の音源が数多くヒットします。最初は半信半疑で聞き始めたのですが、不思議と心が落ち着き、頭がすっきりしていく感覚を得ました。特に集中力が高まり、仕事に取り組むスピードや効率が上がることを強く実感しました。しかし、ここで一つ注意点があります。ネット上には「432Hz」と書かれた音源が数多くありますが、実際には周波数が微妙にずれているものも少なくありません。見た目には分からないのですが、よく聴いていると「なんとなく落ち着かない」とか「心地よさが半減している」と感じることがあります。これは私だけの感覚かと思っていたのですが、調べてみると同じように指摘している人は多く、さらには「わざとずらしているのではないか」という都市伝説まであるのです。無限のパワーを人々に出させないための操作ではないか、という話まで存在します。そんな疑問を持っているときに、「周波数を計測できるアプリがある」という情報を耳にしました。早速インストールして調べてみると、案の定「432Hz」と表示されている音源でも実際には434Hzや428Hzなど、微妙にずれているケースがあることが分かりました。この差はほんのわずかですが、耳や心には確かに伝わるもので、逆に言えば、正真正銘の432Hzを体験した時、その心地よさと安心感は圧倒的でした。まるで体の奥深くに響き渡り、全身を整えてくれるような感覚があります。本物の432Hzを聴いていると、不思議なくらいに作業がスムーズに進みます。頭の中の雑念が消え、必要なアイデアが自然と浮かび、集中状態が持続するのです。これまで「集中力を高めるには環境を整えるしかない」と思っていましたが、音の周波数ひとつでこんなにも変わるのかと驚かされました。もちろん、これが科学的にどこまで証明されているかについては諸説ありますが、実際に体験して「心地よい」と感じること自体に価値があるのだと思います。人間の感覚は嘘をつきません、リラックスできて、仕事がはかどり、前向きな気持ちになれるのであれば、それは紛れもなく効果があるということです。世の中にはまだまだ知られていない「周波数の力」が存在します。もしかすると、私たちが自分の無限の可能性を開花させるための鍵は、こうした目に見えない世界に隠されているのかもしれません。432Hzという周波数は、その入り口に過ぎないのでしょう。これからも新しい発見や体験を積み重ね、自分自身の成長に役立てていきたいと強く思います。もしあなたが最近疲れやすいと感じていたり、集中力が続かないと悩んでいるのなら、一度432Hzの音源を試してみることをおすすめします。正真正銘の周波数を聴いた瞬間、きっとその違いに気づくはずです。そして、あなた自身の中に眠る無限の可能性が、静かに目を覚ますのを感じられるかも知れません。
2025年09月28日
コメント(0)
-
理想を実現する運命共同体を目指すには?
社内で情報を「完全一致」で共有することは、実はとても難しいことです。言葉の伝え方ひとつで違う解釈が生まれたり、受け手の知識や経験の深さによって理解が変わってしまうからです。これは誰もが日常的に体験していることではないでしょうか。リーダーが意図していたことと、メンバーが受け取ったことの間にズレが生じ、思わぬ摩擦や誤解が起きてしまいます。組織における課題の多くは、突き詰めるとこの「情報のずれ」に根ざしていると感じます。だからこそ大切なのが「コミュニケーションを通じて相互理解を深める」という姿勢です。単に情報を流すのではなく、伝えたつもりで終わらせずに、相手がどう受け止めたのかを確認し合いながら、同じゴールを見据えて理解をすり合わせていくプロセスが不可欠です。そのプロセスを繰り返すことで、誤解が少なくなり、組織全体のエネルギーが一方向にまとまっていきます。ただし、相互理解を深めるには土壌が必要で、その土壌が「心理的安全性」と「関係の質」です。心理的安全性がなければ、人は本音を言えず、本音を言えない環境では、たとえどれほど立派な理念や戦略が掲げられていても、建前と忖度ばかりが飛び交い、真の共感や一致は生まれません。逆に、安心して意見を交わせる空気があれば、誤解を恐れずに質問でき、意見の違いを率直にぶつけ合うことができます。その積み重ねが、結果として理解の深さを生むのです。また、心理的安全性を支えるのが「関係の質」で、人間関係が希薄なままでは、言葉のやり取りも表面的になりがちです。関係の質を高めるとは、互いの価値観や大切にしているものを理解し合い、リスペクトを持って向き合うことにほかなりません。つまり、単なる同僚や仲間ではなく、同じ目的実現を目指す「同志」として関わることです。同志とは、お互いの違いを認め合いながらも、根底にあるビジョンを共有する存在で、その関係性が築かれたとき、初めて「運命共同体」としての強さが組織に宿るのだと思います。私は、会社という場は「利害関係で集まった集団」であると同時に、「共通の理想を追いかける運命共同体」だと考えています。利益や数字のためだけに結ばれた組織は脆いものですが、理想や価値観を共有し、共に未来を創ろうとする意思が結びついた組織は、困難に直面しても折れることなく、逆境を力に変えて前進できます。その原動力となるのが、まさに相互理解の力です。もちろん、相互理解は一朝一夕で完成するものではなく、毎日の会話や小さなやり取りの積み重ねによって少しずつ育まれていくものです。「分かってくれているはず」という思い込みを手放し、常に相手の立場に立って確認すること。その小さな意識の積み重ねが、大きな信頼関係へとつながります。組織において、情報を完全一致で共有することは難しいですが、だからこそコミュニケーションを通じた相互理解の姿勢が何より大切になります。心理的安全性が確保され、関係の質が高まれば、社員一人ひとりが安心して意見を交わし、共に成長していける。その先にこそ、同志としての強い絆が生まれ、運命共同体としての組織が形づくられていくのだと実感しています。
2025年09月27日
コメント(0)
-
ゲーミフィケーションの無限の可能性
北海道大学で開催されたアイデアソンに参加しました。テーマは「DEPIN」「WEB3」で、難しそうに聞こえるかもしれませんが、要は最先端のテクノロジーを活用して、地域社会の課題を解決していこうという試みです。私たちのグループに与えられたテーマは「デジタルの力で関係人口を増やす」、その地域に住んでいるわけではないけれど、関わりを持ち続ける人をどう増やすかという挑戦でした。議論を重ねる中で生まれたキーワードが「ワークテインメント」。Work(仕事)とEntertainment(娯楽)を掛け合わせた造語です。働くことが遊びになり、遊ぶことが仕事にもつながる、そんな体験をデジタルの力で提供することができれば、地域に関わるハードルはぐっと下がるはずだという発想でした。具体的には、ゲーミフィケーションの仕組みを取り入れて、たとえば、地域の課題を「クエスト」に見立てて、参加者がそれを解決していくプロセスをゲームのように楽しめるようにする。地域の観光資源や文化を学ぶことも一種の「ステージクリア」に見立て、仲間と協力して次のレベルに進むような体験を作り上げます。その過程で得られるポイントやトークンは、分散型投資の仕組みと連動させ、地域の事業やプロジェクトに再投資できるモデルを描きました。「応援したいけれど、ただ寄付するだけでは長続きしない」、多くの人が抱くそんな感覚を、私たちは楽しさに変換することで解決しようと考えたのです。ゲームを通じて自然と地域に関わり、気がつけば投資者としても参加している。そんな循環が生まれれば、地域の未来はより自立的に回っていくのではないか。また、ワークテインメントのもう一つの側面は「働く人」にあります。リモートワークが普及した今、場所に縛られずに働く人が増えました。ならば、地域に滞在しながら仕事をする仕組みをエンタメ的に演出すれば、新しい関係人口が生まれるはずです。たとえば、地域ごとにテーマ性を持たせたコワーキング空間を「ゲームの拠点」として位置づけ、働く時間も一つの物語の一部に組み込む。これによって、仕事と遊びが自然に溶け合い、長期的にその地域に関わり続ける動機が生まれると考えました。議論の中では「本当にそんなことができるのか?」という疑問も当然ありましたが、WEB3の技術や分散型ネットワークの仕組みを使えば、中央集権的に管理しなくてもコミュニティが自律的に運営できる可能性があリます。むしろ今までの常識では不可能だったことを可能にするのが、この領域の魅力だと強く感じました。最終的に発表した私たちのアイデアは、単なる机上の空論ではなく、将来的に地域活性化の新しい形として実現できるかもしれないという手ごたえを得ました。デジタル技術は冷たいものと思われがちですが、それをどう設計するかで人と人とのつながりを温かく広げる道具にもなります。「ワークテインメント」という言葉に込めたのは、働くことと楽しむことを区別しない新しい関わり方。これからの社会で地域が生き残るには、こうした発想が不可欠になると実感しました。北海道大学のキャンパスで交わされた多様なアイデアと熱量に刺激を受けながら、私は未来の地域づくりに新しい可能性を感じる一日となりました。
2025年09月26日
コメント(0)
-
あまりの熱狂に圧倒されました!
今日は人生で初めて東京ゲームショーに行ってきました。これまで名前だけは知っていましたが、実際に足を運ぶのは今回が初めてでしたが、正直平日なので人はそこそこだろうと思っていたのですが、その予想は見事に裏切られました。会場に入った瞬間、目に飛び込んできたのは人、人、人。平日にもかかわらず、これだけ多くの人が集まるのかと本当に驚かされました。そして、その場を包み込む熱気に一気に圧倒され、ゲームというコンテンツが持つ底知れぬパワーを体感しました。会場のブースはどこも趣向を凝らしていて、一つひとつがまるでテーマパークのアトラクションのよう。最新技術を駆使したVR体験や、AIを取り入れた新しい遊び方、さらには懐かしのシリーズ最新作まで、幅広い層に響く展示が並んでいました。試遊スペースには長蛇の列ができ、スクリーンの前では観客が息をのんでプレイ画面を見守っている。その光景は、ただの「商品展示」ではなく、「文化祭」のような熱狂的な盛り上がりを感じさせてくれました。特に印象に残ったのは、ゲームが「一人で遊ぶもの」から「みんなで共有するもの」へと進化していることです。実況配信やSNSでの共有、さらにはその場で一緒に歓声を上げる体験が当たり前のようになっていて、プレイヤーだけでなく観客も同じ楽しみを味わえる。ゲームはもはや娯楽を超えて「共感を生むプラットフォーム」となりつつあるのだと感じました。これはまさに、現代の新しいコミュニケーションの形だと思います。また、海外からの来場者や出展者の多さにも驚かされました。英語や中国語、韓国語が飛び交い、ゲームが世界共通言語であることを肌で実感しました。日本が誇るコンテンツ産業としてのゲームが、グローバルにどれだけの影響力を持っているのかを間近に見られたのは、非常に誇らしい体験でもありました。歩き回っていると、つい夢中になってしまい、時間が経つのを忘れてしまうほど。気づけば一日中会場を歩き回り、心地よい疲労感とともに充実感が残りました。東京ゲームショーは単なる展示会ではなく、未来のエンターテインメントの方向性を示す場所であり、同時に人々の情熱が交差するエネルギーの塊でした。今日の体験を通じて、私は一つ強く感じました。それは「熱意こそが人を動かす」ということです。これだけ多くの人が平日から会場に集まり、時間をかけて体験し、共に盛り上がる。その背景には、ゲームに対する純粋な情熱と好奇心があります。その力が新しい文化を生み、未来を形作っていくのだと、会場の熱気が教えてくれました。初めての東京ゲームショーは、圧倒の連続で終始感動しっぱなしの一日でした。当社がこれから取り組むIP事業とも深い関わりがあるので、この熱気を世界に広げ、もっと多くの人にワクワクや感動を届けていきたいと強く感じました。
2025年09月25日
コメント(0)
-
未来を豊かにする人間関係を構築するために
社会人になってから、心から思いを分かち合える人間関係を築くことは、実はとても難しいことだと日々感じています。学生時代のように、時間や価値観を自然に共有できる場が少なくなり、仕事では利害や立場が絡むため、どうしても本音で語り合える関係は限られてしまいます。だからこそ、「信頼できる仲間」と呼べる存在は年齢を重ねるほどに貴重になっていくのだと思います。そんな中で私が出会ったのが、コーポレートコネクションズ(CC)渋谷チャプター、通称CC4です。ここは単なるビジネスコミュニティではなく、「ギバーの精神」を土台にした学びと尊重の場です。ギバーとは、自分の利益よりも相手に与えることを優先する姿勢のことで、与えることを当たり前とし、互いの可能性を信じ、背中を押し合う空気があります。私はその在り方に心から感銘を受けました。CC4では、メンバー同士が一方的に「教える」「学ぶ」という関係ではなく、常に「学び合う」関係性が築かれています。誰もが持っている経験や知恵に価値があると認め合い、惜しみなくシェアすることで、新しい気づきや挑戦のきっかけが生まれます。そこには上下関係も、遠慮もなく、純粋に「より良くなりたい」「貢献したい」という思いが交差し、強固な信頼関係へとつながっていきます。今はリモートワークやオンライン交流が主流の時代ですが、効率やスピードの面では非常に便利ですが、人と人との「心の距離」を縮めるには限界があるように思います。画面越しでは伝わらない熱量や、その場の空気感があるからで、だからこそ、リアルの場で深い人間関係を築くことの価値は、かえって高まっていると実感します。CC4の場では、2週間に一度直接顔を合わせ、同じ時間と空間を共有することで、言葉以上の信頼や共感が育まれています。「人は人によって磨かれる」と言いますが、まさにその通りで、互いを尊重し合うコミュニティの中でこそ、自分自身もより成長し、挑戦する勇気を持てるのだと思います。社会人になってから簡単ではないと思っていた「心から分かち合える関係」が、ここには確かに存在しています。私はこれからも、CC4での学びと出会いを大切にしながら、自らもギバーとして周囲に貢献できるよう努めていきたい。そして、利害や肩書きを超えた深い人間関係を広げていくことで、人生も仕事もより豊かにしていけると信じています。社会人になってからの人間関係は、決して数ではありません。心から信頼できる人と出会えるかどうか、その意味で、CC4との出会いは私にとってかけがえのない宝物となっています。
2025年09月24日
コメント(0)
-
新たな実践目標『あらゆる価値を認める達人になる!』
これまでの人生を振り返ると、本当に多くの学びの機会をいただき、その度に自分自身を成長させていただいたと感じます。経営者として、また一人の人間として、数えきれない出会いや経験が私を育ててくれました。けれども、学びに終わりはありません、どれだけ成長したと感じても、必ず新しい課題が見えてきます。そして今、私が新たに掲げた実践目標があります。それは『あらゆる価値を認める達人になる!』というものです。この目標を掲げるに至ったのは、自分の中にある課題を直視したからです。これまで社員の話を聞いているとき、「本当に意味があるのだろうか」と無意識に軽く見てしまったり、自分の知識や経験が邪魔をして、最後まで傾聴できないことがありました。つまり、自分が知っていることや、自分の価値基準に照らして判断してしまう癖があったのです。もちろん経営者として知識や経験をもとに判断することは大切です。しかし、それだけでは「社員一人ひとりの持つ価値」にしっかりと光を当てることはできません。むしろ自分の物差しに縛られてしまうことで、せっかくの意見や新しい視点を見逃していたのではないか、と気づいたのです。では、「あらゆる価値を認める」とはどういうことなのでしょうか?私はそれを「どんな言葉や行動にも意味があると受け止めること」だと考えています。社員が口にする小さなつぶやきにも、そこには本人なりの背景や想いがある。自分の考えと違っていても、それは否定すべきものではなく、「その人にとっての価値」なのです。この姿勢を持つことができれば、相手は安心して自分の意見を語ることができるでしょう。そして組織の中で多様な考え方が交わることで、新しい発想やイノベーションが生まれるはずです。まさに「多様性が力になる」ということを実感できる瞬間だと思います。もちろん、これは簡単なことではありません。人間はどうしても「自分の価値観」に縛られがちですが、だからこそ意識的に訓練しなければならないと思っています。まずは社員の話を最後まで遮らずに聞くこと、そして「その意見にはどんな背景があるのだろう」と想像してみること。さらに「自分とは違う視点だからこそ学びになる」という姿勢を持ち続けること。こうした小さな実践の積み重ねが、やがて「達人」への道につながるのではないでしょうか。また、これは社員に限らず、お客様や協力会社、さらには家族や友人との関係にも言えることです。人はそれぞれ違う環境で育ち、違う経験をしてきています。その一つひとつが「価値」であり、それを尊重する姿勢こそが、信頼を生み、人間関係を豊かにしてくれると感じています。これまで私は直感や行動力を武器に前に進んできましたが、次のステージに進むためには、自分の中にある「聴く力」と「認める力」を磨くことが必要だと感じています。『あらゆる価値を認める達人になる!』、この目標を胸に、日々の小さな実践を重ねていきたいと思います。そうすることで、社員一人ひとりが輝き、会社全体がより強く、温かい組織になれると信じていますし、そして何より、自分自身の人間力をさらに高める道になるのだと考えています。
2025年09月23日
コメント(0)
-
ファンダムマーケティングが未来を創る
私は、これからの日本の未来を切り拓いていくのは「ファンダムマーケティング」だと強く確信しています。ファンダムとは、単なるファンの集まりではなく、作品やキャラクター、ブランドに熱狂的な愛着を持ち、仲間同士で価値を共有し合うコミュニティのことです。近年、SNSの発達によりファン同士が国境を越えてつながり、瞬時に情報や感情を共有できるようになりました。日本のIP(知的財産)が世界へ広がるうえで、このファンダムの存在こそが最大の推進力になっているのです。アニメ、マンガ、ゲーム、キャラクターなど、日本のIPはその独自性と世界観の深さによって、世界中の人々を魅了してきました。しかし、従来は「日本で生まれた作品をそのまま海外に輸出する」というモデルが中心であり、どうしても現地の文化や価値観との間にギャップが生まれていました。そこで重要になるのが「ファンダムマーケティング」です。ファン自身が自発的にコンテンツを翻訳したり、SNSで拡散したり、二次創作を通じて文化をつなぐ。その熱量が国境を越えて広がり、結果的に市場が拡大していくのです。特に中国や東南アジアでは、現地の若者たちが日本のアニメやキャラクターをベースに、自分たちの文化や言語に合うようアレンジして楽しんでいます。それは単なる消費ではなく「共創」に近い現象であり、日本のIPの強みをさらに高めてくれる存在でもあります。これからの時代、日本のIPを世界に広げていくためには、ただ輸出するのではなく「カスタマイズ」や「ローカライズ」を徹底することが求められます。例えば、キャラクターの台詞や物語の背景を現地の言語や価値観に沿う形に翻訳するだけでも、ファンの受け止め方は大きく変わります。また、現地のイベントやフェスティバルで体験できるコンテンツとして展開すれば、「自分たちの文化の一部」として定着していきます。このプロセスにおいて、ファンの声を拾い上げることが何より重要です。ファンダムは単なる顧客ではなく、共にブランドを育てるパートナーなのです。ファンが望む形に寄り添い、共にコンテンツを育てていくことで、日本のIPは「世界の共通文化」へと進化していくでしょう。ファンダムの力を活用したマーケティングの価値は、単なる売上拡大にとどまりません。ファン同士のコミュニケーションが新たな創作を生み、そこからまた次のビジネスや文化が広がっていくという循環を生み出します。これはまさに「文化的エコシステム」と呼べるものであり、持続的に日本のソフトパワーを世界へ広げていくための基盤になります。さらに、この動きは日本の若いクリエイターや企業にとっても大きなチャンスをもたらします。自分たちの作品が世界中のファンに支持され、共に育てられていく体験は、次世代の創作意欲をかき立てるからです。つまり、ファンダムマーケティングは単なる手法ではなく、日本の未来そのものを創り出す「文化運動」だといえるのです。日本のIP産業は、いまや自動車に次ぐ規模の輸出産業へと成長しています。その背景にあるのは、世界中に広がるファンダムの存在です。これからの課題は、彼らの声を聞き、現地の文化に合わせた形でカスタマイズし、共にコンテンツを育てていくことです。ファンダムマーケティングは、日本のIPを単なる輸出品から「世界の共通財産」へと進化させる力を持っています。私は、この力こそが日本の未来を切り拓く最大の原動力になると信じています。
2025年09月22日
コメント(0)
-
これから生かす3つ学び
高野山での三日間の学びを終えて、まさに心に刻むべき集大成が3つの項目に凝縮されたように思います。一つひとつの項目は独立しているようでありながら、根底では深くつながっており、これからの人生の指針となるものでした。1.自利利他で生きる仏教における大切な概念である「自利利他」。今回の学びで改めて強く心に響いたのは、利他こそが人生の目的であるという点です。人のために生きることが、最終的に自分の幸せへとつながっていきます。ところが、利他を実現するには土台としての「自分磨き=自利」が不可欠です。未熟なまま利他を語っても、相手の役には立てないので、自分を律し、磨き続けることが人の役に立つ準備であり、そこに人生の意義が生まれるのだと実感しました。つまり、自利と利他は対立するものではなく、利他を成すための自利として一体となっているのです。人生の目的が利他だと明確になり、そのために自利で自分を磨き続けることこそが最重要になります。2.自然体で生きる次に心に刻んだのは「自然体」。無理に背伸びをするのでもなく、過去の成功や失敗に縛られるのでもなく、あるがままの自分で生きる姿勢です。極端な表現をすれば「赤ちゃんのように生きる」ことで、赤ちゃんは欲望や駆け引きではなく、ただ純粋に存在そのものを発しています。その姿は周囲に笑顔や癒しを与え、自然に人を惹きつけますが、大人になるにつれて複雑な思考やしがらみが増え、無意識のうちに自然体から遠ざかってしまいます。だからこそ意識的に、心を澄ませ、シンプルに、赤子のような無垢さを取り戻していくことが必要だと学びました。3.あらゆるものを認識するそして三つ目は「あらゆるものを認識すること」。これは私自身にとって大きな課題であり、これから重点的に取り組むべきテーマだと痛感しています。人はとかく自分の考えを正しいと思い込み、相手に押し付けがちですが、本当に大切なのは相手を徹底的に理解し、認識することです。相手の背景、立場、想いを深く知ろうとする姿勢があってこそ、本当の対話や信頼が生まれます。認識とは、単に相手の言葉を聞くことではなく、心の奥にある本質を受け取ることだと思います。自分中心の視点から離れ、あらゆるものをありのままに見ていく力を磨いていきたいと感じました。この三つの項目を改めて振り返ると、「利他を目的とし、自分を磨き、自然体で生きながら、相手を深く認識する」という流れが見えてきます。 単なるスローガンではなく、日々の実践の中で積み重ねるべき生き方の型です。特に3つ目の認識は、これまでの自分の課題を突きつけられたような感覚があり、これを克服していくことで人生の幅が大きく広がる予感がします。高野山での3日間は、単なる研修や学習の場ではなく、生き方を問い直し、これからの指針を心に刻む時間でした。空海が説いた「生かせいのち」という言葉にも通じる学びを、この三つの項目として胸に抱き、これからの人生に生かしていきたいと思います。共に学んだ「善友」との出会いに感謝し、お互いに切磋琢磨していきます!
2025年09月21日
コメント(0)
-
「生かせいのち」の意味
高野山での学びの場2日目。昨日に続き、山の行に身を置くことで、心と体が自然と調和していく感覚を味わいました。高野山の開祖・空海の教えのひとつに「生かせいのち」という言葉があります。まさにこのフレーズが、今日一日を通じて私の中で深く響いています。朝の凛とした空気の中での行は、ただの修行ではなく、自分の心と自然のリズムを合わせる時間でした。鳥の声、風の音、木々が揺れる気配など、その一つひとつが「いのち」の鼓動であり、私自身もその一部であることを強く感じました。日常生活では意識することのない呼吸や鼓動も、山の中で静かに向き合うことで、これ以上ない「生かされている実感」として浮かび上がってきます。現代社会は効率や成果を求められる場面が多く、知らず知らずのうちに「生き急ぐ」ような感覚に陥りがちです。しかし、空海が説いた「生かせいのち」とは、ただ生命を維持することではなく、いただいた命をどう輝かせ、どう他者と響き合うかという問いかけなのだと感じます。山の行を通じて、命は独立したものではなく、自然や人、あらゆる存在と繋がり合っていることを改めて実感しました。不思議なことに、体は疲れているはずなのに、心の奥からエネルギーが湧き上がってくる感覚がありました。それは「自分ひとりの力」ではなく、「自然と先人の教えからいただいている力」だと気づかされます。高野山の空気に包まれ、空海が残してくれた教えを追体験することで、自分の中に眠っていた潜在的な力が呼び覚まされていくような感覚でした。この「山のパワー」を持ち帰り、日常にどう落とし込むかが次の課題です。職場や家庭、地域社会の中で「生かせいのち」を実践するとは、誰かのために小さな行動を積み重ねることだと思います。たとえば、笑顔で人に接すること、感謝の気持ちを言葉にすること、困っている人に手を差し伸べること。それらは大きなことではなくても、命を生かし合う営みになるのだと学びました。高野山の行は、単なる宗教体験ではなく、「命の意味」を深く見つめ直す時間でした。空海の「生かせいのち」という言葉は、現代を生きる私たちに対して「自分の命をどう生かすのか」という問いを投げかけています。山で感じた鼓動と自然のパワーを胸に、これからの日常を「生かす」選択をしていきたいと思います。
2025年09月20日
コメント(0)
-
テーマは「自然に委ねる」
今日から3日間、経営者仲間とともに高野山に滞在しています。弘法大師・空海が開山したこの聖地は、1200年の歴史を刻み、世界遺産として人々を惹きつけ続けています。深い杉木立、澄み切った空気、厳かな寺院群に囲まれていると、自分がいかに小さな存在でありながらも、大いなる自然と歴史の流れに包まれて生かされているのだと実感します。今回の私のテーマは「自然に委ねる」。経営でも人生でも、時には力んで抗うのではなく、大いなる流れに身をゆだねることが大切だと気づかされます。私たちは日々、計画を立て、戦略を描き、実行を繰り返しますが、そのすべてが思い通りにいくことは稀で、むしろ計画通りに進まないことの方が多いでしょう。そのたびに「なぜうまくいかないのか」と焦ったり悩んだりすることもあるかも知れませんが、高野山の大自然の中に身を置くと、思わず肩の力が抜けて、「自然の摂理に任せればいい」という安心感が湧いてきます。芽吹きの時が来れば芽は出るし、実りの時が来れば実がなる、人間の都合ではなく、宇宙や自然のリズムに従って万物は動いているのです。経営においても、私たちは「結果を出さなければ」とつい力んでしまいますが、結果はあくまで「種まき」と「育てる環境」が整ってこそ与えられるもので、焦って引っ張り上げても芽は伸びません。社員の成長も同じで、本人の力とタイミングを信じて見守ることが必要です。経営者としての役割は、無理に方向を変えることではなく、自然の流れを見極め、その流れに逆らわずに舵を切ることだと改めて感じました。また「自然に委ねる」とは、決して何もせずに待つことではありません。種をまき、水をやり、太陽の光を浴びられる場所を選び、その上で「芽が出るタイミングは自然に任せる」ということです。つまり「準備は自ら、結果は自然に」、このバランスが心に落ちた瞬間、肩の重荷がすっと軽くなりました。高野山の時間はゆっくり流れています。朝のお勤め、鐘の音、参道を歩く僧侶の姿、それらが心を鎮め、「委ねる」という心境をさらに深めてくれます。都会で過ごしているとつい忘れがちな「人は自然の一部である」という感覚、ここに身を置くと、自然と一体になり、心が透明になっていくようです。この3日間、「自然に委ねる」というテーマを胸に、力まず、焦らず、流れを受け入れることを実践してみたいと思います。そして下山した後の日常の中でも、この感覚を忘れずに活かしていきたい。経営も人生も、すべては自然の大きなリズムの中で巡っている。その流れに感謝し、身をゆだねながら、一歩一歩前へ進んでいくことこそ、本当の意味での成長と幸福につながるのではないでしょうか。
2025年09月19日
コメント(0)
-
直感から実行への進化
これまでの自分を振り返ると、直感に従って動き、数々の壁を乗り越えてきたことが多かったように思います。瞬間的に「これだ」と感じた方向に舵を切り、結果としてその判断が道を拓いてきた経験も少なくありません。直感は、過去の経験や学びが無意識のうちに積み重なり、瞬時に形を成したものです。だからこそ直感を信じて行動することは、決して間違いではありません。むしろ直感がなければ、大胆な挑戦も思い切った決断もできなかったでしょう。しかし、さらに飛躍を目指すなら「直感だけ」では限界があることも感じ始めています。直感で決めることは出発点として大切ですが、その後に「計画」と「実行」というプロセスをしっかり積み重ねなければ、大きな成果にはつながりにくいのです。つまり、直感は羅針盤であり、そこから先の航海を成功させるには、地図と行動力が不可欠なのだと思います。直感が「方向性」を示すなら、計画は「道筋」を描くものです。たとえば新しい事業に取り組むとき、直感で「これは伸びる」と感じることがありますが、そこからどの顧客層を狙うのか、どのチャネルを活用するのか、どのタイミングで仕掛けるのかといった計画を練らなければ、せっかくの直感も活かされません。計画を立てることで、直感が単なる「思いつき」から「実現可能な戦略」へと進化します。逆に計画がなければ、直感は時に空振りとなり、努力が拡散してしまうリスクもあるでしょう。直感のエネルギーを成果につなげるためには、やはり計画は欠かせないステップなのです。そして、どんなに素晴らしい直感や緻密な計画があっても、それを形にするのは「実行」です。実行してみなければ何も始まりませんし、成果も得られません。しかも実行の中でしか、本当に必要な修正点や改善点は見えてこないのです。実行とは、未来を現在に引き寄せる行為だと思います。計画が頭の中の地図だとすれば、実行はその道を一歩一歩歩いていくことです。小さな一歩でも進めば景色が変わり、新しい情報が得られ、次の一歩がより確かなものになります。つまり、実行を重ねることでしか「直感+計画」が真の成果へと変わることはないのです。これから自分が目指したいのは、「直感・計画・実行」の三位一体のスタイルです。直感で方向性を掴み、計画で道筋を整え、実行で現実に変えていく。この流れを意識的に回していけば、これまで以上に大きな飛躍ができると確信しています。直感だけに頼っていた頃は、どうしても結果が安定せず、成功と失敗が波のように訪れました。けれども、直感を起点に計画と実行を組み合わせれば、その波をコントロールし、安定した成長曲線を描けるのではないかと思うのです。直感はこれまで自分を導いてくれた大切な力ですけれども、これからさらに大きな成果を得るためには、直感を「出発点」とし、計画と実行によって「到達点」へと結びつける必要があります。直感から実行への進化こそが、次のステージに進むための合言葉。そう心に刻んで、これからの日々を歩んでいきたいと思います。
2025年09月18日
コメント(0)
-
日本のIP産業の無限の可能性
日本のIP(知的財産)産業は、アニメ・マンガ・ゲームなどを中心に、「ものづくり」に代わる「ことづくり/想像力づくり」としての輸出の柱に育ちつつあります。特に中国市場との親和性・成長性には大きな可能性があり、ローカライズを徹底することでさらなるマーケット開拓が期待できます。以下、中国での現状と将来展望を、具体的な数字も交えてブログ調にまとめます。まず、全体としての数字を押さえると、日本のコンテンツ産業(マンガ、アニメ、ゲーム等を含む)の海外売上は、2022年時点で約5.8兆円に達し、自動車産業に次ぐ輸出額第2位となっています。また、アニメ関連市場そのものも飛躍的に成長しており、2023年の日本国内市場規模は約3兆2465億円。そのうち海外売上が約1兆7222億円に達し、国内売上の約1.06倍と、ついに「海外>国内」の構図が明確になってきました。政府も「クールジャパン戦略」において、2033年までに日本IP輸出(海外展開)を約1300億ドル(約20兆円程度)にまで拡大させることを目指しています。現在の3兆円規模から見れば、その目標は約6−7倍の成長ということになります。では、中国市場はどのくらいポテンシャルを持っているのか、以下が中国に関する最近のデータです。中国アニメ市場(国内)の規模は、2017年から2022年にかけて着実に拡大しており、2022年には126億元(日本円で2600億円)規模に達し、年平均成長率はおよそ7.8%となります。日本のマンガIPも中国で非常に強く、日本のデジタルマンガ作品やアニメ作品が正式配信プラットフォームで高い人気を誇っており、若年層ファンを中心に支持が広がっています。また、中国国内のキャラクター市場(アニメ・ゲーム関連キャラクターグッズなどを含む)は、2024年時点で約12兆円規模にまで成長しているとの推計があり、5年前と比べて約2倍という大幅な拡大です。これらの数字から、中国は「単なる消費先」ではなく、IPの供給者にとっても戦略的な市場であることが見て取れます。成長可能性が高いとはいえ、中国市場で成功を収めるには、いくつかの工夫が不可欠です。一つ目は、言語・文化のローカライズです。日本のストーリーやキャラクターは魅力的ですが、文化的な背景やユーモア、価値観などが中国のファンに伝わりやすい形に「翻訳」することが重要です。単なる字幕・吹き替えだけでなく、キャラクターの設定や社会的文脈を中国の文化・歴史的な視点で調整するケースもあります。二つ目が、正式配信と権利保護です。海賊版対策や公式プラットフォームでの配信体制を整えることで、きちんと収益化できるモデルを構築することが鍵です。中国では規制や検閲、コンテンツ審査の制度も複雑なので、それらに対応できる体制を持つことが、長期的に見て成功への必要条件となります。三つ目が、キャラクターIPの多角展開です。アニメ・マンガから入って、グッズやイベント、体験施設、コラボ商品などに展開するルートを確保すること。中国ではキャラクターグッズ市場が非常に大きく、ブランドコラボや公式ストアなどのリアル展開も成功例が出ています。四つ目が、現地パートナーとの協業です。中国のプラットフォーム運営会社、配信先、物流や販売代理店など、現地のネットワークを持つパートナーとの協業は不可欠です。市場慣習、法規制、審査制度に精通した現地の会社とのアライアンスが、リスクヘッジとスピードを両立させます。これらを踏まえると、ローカライズと戦略的展開を進めた場合、日本IPが中国市場でさらに獲得できる規模について以下のような見通しが立ちます。アニメ市場の年成長率が現在7〜8%前後ということから、今後5年で中国アニメ市場は 126億元 → 約180〜200億元程度の規模に拡大する可能性があります。ローカライズされた日本コンテンツがこの拡大のシェアを取ることができれば、相当な売上が見込めます。キャラクター関連市場の成長ペースを維持すれば、現在の約12兆円規模からさらに+30〜50%の拡大、すなわち15〜18兆円程度になる可能性もあります。その中で、日本の有力IPが1〜2割の市場シェアを持てれば、3〜4兆円規模の売上が期待できる領域になります。日本全体のIP輸出目標(20兆円規模など)の中で、中国市場が占める割合が高まることが予想されます。たとえば、日本の海外売上を20兆円に引き上げる中で、中国がそのうち30〜40%を占めるとすると、6〜8兆円規模の輸出先として非常に戦略的です。まとめると、日本IP産業が自動車関連に次ぐ輸出産業の地位を確立している現状において、中国市場は「成長ドライバー」として非常に大きな役割を果たすポテンシャルを持っています。中国アニメ市場の継続的な成長、キャラクターグッズ市場の急拡大、日本のマンガ・アニメIPの人気など、複数の指標が“中国での成功の可能性”を示しています。ただし、その成功は「ただ日本の作品をそのまま持っていく」だけでは達成できず、文化・言語・流通・法制度に応じたローカライズ戦略、現地パートナーとの協業、権利保護の確立などの地道な取り組みが伴うことが不可欠です。これらをしっかり構築できれば、日本IPの中国市場での売上は今後5〜10年で数兆円規模の成長が期待できるでしょう。日本IPを世界の舞台でさらに輝かせるために、中国という巨大市場をいかに「自分事化」するかが、これからの鍵だと確信しています。
2025年09月17日
コメント(0)
-
経営者150人が集った大運動会、感動の優勝!
今日は「ざぶとんの会」主催の大運動会が、おおきに舞洲アリーナで盛大に開催されました。総勢150人を超える経営者仲間が一堂に会し、普段のビジネスの場とは全く異なる、笑顔と熱気に包まれた一日となりました。プログラムは大縄跳び、綱引き、ドッジボール、◯❌クイズ、玉入れ、イントロ当てクイズ、華のステージ、そして最後を飾るリレーまで、全部で8競技で、優勝賞金100万円をかけて、8チームが真剣勝負を繰り広げました。私はチーム最年長ということもあり、20人のオレンジチームのキャプテンを務めさせていただきました。途中、オンラインミーティングで中抜けしないといけない中でしたが、まとめ役としてチーム全体の士気を高めることを心がけました。ありがたいことに、本当に素晴らしいメンバーに恵まれ、息の合ったチームワークが次々と花開いていきました。競技が始まると、会場全体が大歓声に包まれます。大縄跳びでは一丸となって声を掛け合い、綱引きでは力と気迫で勝負、ドッジボールでは最後までボールを追いかけ、玉入れでは一分間集中した時間を過ごし、◯❌クイズやイントロクイズでは頭脳戦で盛り上がり、華のステージでは狭いスペースに18人が立つという奇跡を体感しました。そして最後のリレーは、全員が総力を尽くして走り抜ける姿に胸が熱くなりました。勝ち負け以上に「本気でやることがこんなにも楽しい」という気持ちが、会場全体に広がっていました。そして結果は、オレンジチーム、見事に優勝!まさかの100万円を手にすることが出来ました。優勝が決まった瞬間、仲間たちが私を胴上げしてくれて、思わず涙が出そうになるほどの感動でした。年齢に関係なく、全員が全力で挑み、互いに声を掛け合い、励まし合いながら掴んだ優勝は、ただの結果ではなく「仲間の力」の象徴だったように思います。さらに、このような素晴らしい企画を実現してくださった宮下代表には感謝しかありません。200人を超える参加者が一日中笑顔で、最高に盛り上がる時間を過ごせたのは、準備や運営を尽くしてくださったおかげです。運動会という場を通して、経営者同士が垣根を超えてつながり、信頼関係を築ける機会はそうそうありません。ほとんど初めてお会いする方々とも、チームとして一緒に汗を流すことで、一日で深いご縁が生まれました。ビジネスの場では得られない「人と人との本当のつながり」を実感できたことは、何よりの宝物です。勝ち負け以上に、仲間と共に本気で笑い、本気で挑んだ一日。私にとっても、これからの経営人生において忘れられない思い出となりました。今日の経験を胸に、何事にも真剣に、そして全力で楽しむことで、人生を豊かにしていきます!
2025年09月16日
コメント(1)
-
「無理」を「どうやったら出来る」に変えるだけで人生が好転する
松下幸之助さんは「経営の神様」と呼ばれるほど数多くの成功を収めた方ですが、その根底には極めてシンプルでありながら力強い言葉があります。それが「無理」という言葉を「どうやったら出来る」に置き換える、という考え方です。私自身、この言葉を聞いたときにとても納得しました。私たちは日常の中で無意識に「無理だ」「できない」と口にしてしまうことが多いですが、その言葉が大きなロスを生んでることを体感しているからです。例えば仕事で大きな課題を与えられたとき、「時間がないから無理だ」「予算がないからできない」とすぐに考えてしまいがちですが、その瞬間に可能性の扉を自ら閉ざしてしまっているのです。「どうやったら出来るだろう?」と問いかけるだけで、思考の方向は180度変わり、足りないものを理由にするのではなく、足りないものをどう補うかに知恵が働くのです。この言葉は単なるポジティブシンキングではなく、根拠のない「できる」と信じ込むのではなく、現実を直視しつつも前に進む姿勢を持つことです。松下幸之助さん自身、学歴も資産も人脈もないところからのスタートでした。まさに「無理」と思える状況ばかりだったはずですが、それでも一つひとつを「どうすれば?」と考え続けたからこそ、世界的な企業を築き上げることができたのでしょう。思考の枠を変えると、行動が変わり、行動が変わると結果が変わります。小さな例で言えば、チームで新しい取り組みを始める時に「そんなのやったことがないから無理」と言ってしまえば、そこで議論は止まります。しかし「やったことがないからこそ、どうすればできるかを考えてみよう」と言えば、自然とアイデアが出てきます。試してみること、工夫すること、協力を求めること、挑戦すること、そのすべてが前進につながります。人生を振り返ってみても、「あのとき諦めずに工夫したから今がある」という経験は誰にでもあるのではないでしょうか。逆に「無理」と思った瞬間に、まだ見ぬ可能性を捨ててしまったこともあったかもしれません。人は言葉に影響されるので、だからこそ、意識して「どうやったら出来る」と言葉を選ぶことは、未来を形作る大切な習慣なのです。もちろん、全てが理想通りにいくわけではありませんが、それでも「どうやったら出来る」という姿勢を持ち続けることで、人との出会いや新しい知識、予想もしない助けが引き寄せられてくるものです。松下幸之助さんの人生は、その実例にあふれています。「無理」と言ってしまうのは簡単ですが、それでは何も変わりません。ほんの少し思考の言葉を置き換えるだけで、人生は大きく好転する。今日からぜひ、「どうやったら出来る?」と自分に問いかける習慣を持ちたいと思います。
2025年09月15日
コメント(0)
-
女性管理職が多い製造会社
日本のビジネス社会において、製造業で女性管理職が多いというのは、確かに珍しいことのようです。最近、私たちの会社にも「なぜ女性管理職が多いのか?」という取材が相次ぐようになりました。その質問に対して、私は正直に「実力を反映しているだけです」と答えてきました。なぜなら、もし男性社員の実力が際立っていれば、当然のことながら男性管理職が増えていたはずだからです。つまり、性別による優遇や逆差別ではなく、あくまで“実力主義”を貫いた結果が現状である、というのが率直な答えでした。しかし、取材を重ねていくうちに、もっと深い気づきがありました。それは、日本の「男性社会」と言われる状況が、必ずしも男性が女性よりも優秀だから成り立っているわけではない、ということです。むしろ、多くの職場では、最初から「男性しか選択肢にない」状態になっている、つまり、スタートラインに立つ前から女性が外されていることが多いのです。これは実力主義とは程遠い姿だと言わざるを得ません。だからこそ、私たちの会社では「真の実力主義」を貫くことを大切にしています。性別に関係なく、成果や努力、リーダーシップを発揮した人を正当に評価する、それが積み重なることで、自然と女性管理職が増えていったのです。決して「女性だから登用した」という発想ではなく、「実力がある人を正当に評価した結果、女性が多くなった」というだけのことです。ただし、この「だけのこと」が実はとても大きな意味を持っています。なぜなら、社会全体を見渡せば、まだまだ女性が正当に評価されにくい環境が多く残っているからです。そうした中で、私たちが女性を適切に評価し、登用している姿は、逆に大きな注目を集めることになります。つまり、実力主義を貫くこと自体が、社会にとって一つの「新しい常識」を提示しているのかもしれません。もちろん、男性社員の中にも素晴らしい実力を持った人は数多くいますし、その人たちもまた、同じ基準で正当に評価されています。ですから、これからの会社の姿は、男性が増えることもあれば女性がさらに増えることもあるでしょう。重要なのは、性別ではなく「誰がより良い成果を残し、より周囲に良い影響を与え、よりお客様や仲間に貢献できているか」という一点に尽きるのです。これからの時代は、人口減少や人材不足の中で、多様な人材をどう活かすかがますます大事になります。女性だから、男性だからという固定観念に縛られていては、貴重な人材を眠らせてしまうことになります。私たちが目指すのは、「性別を超えて、誰もが輝ける職場」、そして、そのためには、真の意味での実力主義を徹底することが不可欠だと考えています。取材のたびに思うのは、私たちの会社が特別なのではなく、むしろ「本来あるべき姿」を実現しているだけだということです。社会の多くが“男性社会”という言葉に象徴されるような旧来の仕組みを続けている中で、私たちは少しだけ一歩先を歩んでいるのかもしれません。これからもその歩みを止めずに、実力を正当に評価する文化を広げていくことで、社員一人ひとりが輝ける未来をつくっていきたいと思います。
2025年09月14日
コメント(0)
-
「決める」ことの大切さ
今日の少年野球の出来事は、単なる練習の一コマに留まらず、子ども達の成長にとって大切な学びの時間になりました。チームの中で「当たり前のこと」「決め事」がなかなか徹底できない、という課題が浮かび上がったため、思い切って子ども達とのミーティングを設けました。普段は声を出して元気に練習している子ども達も、いざ「意見を出す場」になると口が重く、なかなか自分の考えを伝えることができません。その様子を見て、私は一つの結論に至りました。それは、「子ども達は“決める”という経験そのものをしてこなかったのではないか」ということです。家庭や学校での環境を思い返すと、多くの場合、親や大人が先回りして道を整えてくれます。転ばぬ先の杖を差し伸べてもらえる環境は、一見すると優しさにあふれていますが、実は「自分で決める力」を育てる機会を奪ってしまうことにもつながります。小さな選択の積み重ねが「決断力」を鍛えるのに、その機会が少なければ少ないほど、子ども達は「自分で選ぶ」という感覚を身につけられません。そこで今回のミーティングでは、二つのルールを子ども達と確認しました。第一に「自分で決めること」。人任せにせず、自分の意志で選ぶことが重要であると伝えました。第二に「選択肢があれば、より難しい方を選ぶこと」。簡単な道ではなく、あえて難しい道を選ぶことで人は強くなり、成長するのだと話しました。この二つを軸にチーム全員で取り組むことを決めたのです。すると不思議なことに、ミーティングの直後から子ども達の表情が変わりました。自分で決める意識を持ったことで、声も大きくなり、練習全体に活気が出てきたのです。これまでは「やらされている」という雰囲気がどこかに漂っていましたが、「自分で決めたこと」に取り組む姿勢は全く違います。声のトーンや表情、動きのキレにまで違いが現れました。改めて感じたのは、子ども達には本来大きな力があるということです。ただ、その力を引き出すためには「決める」という経験が不可欠だということ。決断力は才能ではなく、日々の小さな選択の積み重ねから磨かれていくものです。そして、より難しい方を選ぶ勇気を持つことで、その成長はさらに加速していくのだと思います。野球はもちろん、人生そのものも「選択」の連続です。打つか、振らないか、走るか、止まるか、挑戦するか、逃げるか、その一つひとつの選択が、その後の結果を大きく左右します。だからこそ子ども達には、今のうちから「自分で決める習慣」を身につけてほしい。そして迷ったときには「難しい方を選ぶ勇気」を大切にしてほしいと願っています。今回の小さなミーティングが、子ども達のこれからの大きな成長につながる一歩になったと感じています。私自身も監督として、彼らの決断を信じ、見守りながら背中を押す存在でありたい。これからも野球を通じて、子ども達と共に学び合い、成長していけるチームをつくっていきたいと強く思った一日でした。
2025年09月13日
コメント(0)
-
お天道様は見ている!
「お天道様は見ている」という言葉には、人知れずとも正しい行いをしていれば必ず報われるという深い意味が込められています。それは単に因果応報という考え方に留まらず、自分の心に嘘をつかず、誠実に生きる姿勢そのものを指しているように思います。長年お付き合いをさせていただいている経営者の方が、まさにこの言葉を体現するような出来事を経験されました。彼はこれまでにも数々の困難を乗り越えて来られましたが、今回直面した状況は、経営者人生の中でも特に厳しい試練でした。前が見えなくなるような暗闇の中を歩むような時間が続いたといいます。それでも彼は常に前を向いて、ただ「自分にできることを正しくやり続ける」ことに徹していました。その姿勢は、周囲の人間に勇気を与え、社員や仲間をも動かしていったのです。私が特に印象的だったのは、彼がどんなに厳しい状況でも「誠実さ」を失わなかったことです。短期的には得になるような誘惑もあったはずですが、彼は決して安易な道を選びませんでした。人を裏切ることも、ごまかすこともせず、ただ一つ「お天道様に胸を張れるかどうか」を基準に判断していたのです。その選択の積み重ねこそが、やがて大きな信頼となり、状況を打破する力につながっていったのでしょう。そして結果として、彼は大きな困難を見事に乗り越えられました。それは単なる回復ではなく、新しい未来への可能性を拓くものだったのです。厳しい時期に培われた社員との絆、顧客からの厚い信頼、そして経営者仲間からの支援。それらが合わさって、新たな道を切り拓くことができたのだと思います。私はその姿を間近で見ながら、「お天道様は見ている」という言葉の真実味を改めて実感しました。人は結果だけを見れば「運が良かった」と片付けてしまうかもしれません。しかし、そこに至るまでには、心を曲げずに正しい行いを積み重ねてきた日々があります。誰も見ていないと思うような小さな選択の一つひとつが、未来を決定づける力を持っているのです。今の世の中、短期的な成果や効率ばかりが重視されがちですが、本当に大切なのは「自分の心に嘘をつかない生き方」なのだと思います。表面的には遠回りに見えても、正しい行いを重ねることでしか得られないものがあります。それが「信頼」であり「人の縁」であり、そして「未来の可能性」なのです。今回の経営者の姿から学んだのは、困難は避けられなくとも、どう向き合うかで未来は変わるということです。正しい行いを選び続ける勇気さえあれば、必ず道は拓ける。そしてその道を照らしてくれるのが「お天道様」であると感じています。彼の生き方は、そのことを雄弁に物語っていました。お天道様は見ている、だからこそ、これからも誠実に、正しく、心に嘘偽りのない人生を歩んでいきたいと、私は強く思います。
2025年09月12日
コメント(0)
-
外国人採用から見えた光
今日は、当社にとって新しい一歩となる出来事がありました。二人のネパール人の方が、面接を兼ねて会社訪問に来られたのです。これまで国内の採用活動を中心に行ってきた当社にとって、外国人採用は大きな挑戦でした。特に現場の社員が採用から関わるのは、初めての経験であり、受け入れの準備には不安と戸惑いがありました。しかし、いざその日を迎えてみると、その不安は大きな希望へと変わる素晴らしい時間になりました。外国人を迎えるというのは、単に面接の場を設けるだけではありません。言葉の壁や文化の違い、生活習慣の差にどう対応するのかといった懸念がありました。現場の社員たちも「自分たちにうまく対応できるだろうか」と不安を口にしていました。しかし、だからこそ「まずは笑顔で迎えよう」「相手の立場に立って考えよう」と、普段以上にホスピタリティを意識した準備を進めてくれたのです。そのプロセス自体が、すでに当社にとっての大きな学びであり、成長の一歩でした。当日来社されたお二人は、とても誠実で真面目な雰囲気を持っていました。会社訪問ということで緊張されていた様子でしたが、社員の温かい対応に少しずつ表情が和らぎ、やがて笑顔で会話が弾むようになりました。言葉の壁は多少ありましたが、それを超えて伝わってきたのは「働きたい」という真剣な気持ちと、人柄の良さでした。そして、その気持ちが当社のホスピタリティと不思議なほどにマッチしたのです。私自身も面接を通じて、お二人の眼差しに強い志を感じましたし、彼らは「自分の未来を切り拓きたい」「家族のために頑張りたい」という思いを胸に来日しています。その真剣さが、当社が大切にしている「明・元・素(明るく・元気で・素直)」の価値観と重なって見えましたし。国籍や文化を越えても、人の本質は共通しているのだと改めて実感しました。今回の会社訪問は、単なる面接の時間を超えた意味を持っていました。外国人採用という未知の挑戦に対して、現場が不安を抱きながらも準備し、実際に受け入れてみることで「やればできる」という自信を得られたのです。そして、お二人と当社との間に良い関係性が生まれる可能性を大きく感じられました。これは今後の採用に向けて、非常に大きな手応えとなりました。もちろん、採用が決まれば生活面でのサポートや文化の違いを乗り越える努力が必要になります。しかし、それは同時に会社の成長の糧でもありますし。多様性を受け入れ、新しい価値観を学び合うことで、社員一人ひとりが成長し、会社全体の幅も広がっていくでしょう。今回の経験は、その未来の第一歩だと感じています。外国人採用は簡単なことではなく、準備も大変ですし、不安もつきものです。しかし一歩踏み出してみれば、そこには人と人との出会いがあり、国境を越えた共感があります。今日の二人の訪問は、当社にとって単なる採用活動以上の意味を持ちました。「人柄」と「ホスピタリティ」という共通の価値を軸にすれば、国籍や文化の違いを超えてつながれるのだと実感できたのです。これから始まる新しい挑戦に、大きな希望を抱いています。
2025年09月11日
コメント(0)
-
強力な引き寄せの法則が働く時
最近、まるで出来過ぎたかのようなご縁が次々と舞い込んできています。昨日も今日も、思わず鳥肌が立つようなピンポイントでの出会いやチャンスが引き寄せられてきました。これまで「引き寄せの法則」という言葉は耳にしてきましたが、ここまで強力に現実化するとは正直驚きを隠せません。その背景を冷静に振り返ってみると、どうやら「社会性」「独自性」「収益性」の3つが高い次元で揃ったときに、最も強い引き寄せが起こるようです。まず「社会性が高い」ということが最もパワフルに引き寄せを発動させます。自分の活動や事業が社会にとって意味がある、役に立つということで、単に自分のためだけの取り組みではなく、社会全体や周囲の人に良い影響を与えるものであればあるほど、人は共感し、応援し、自然と仲間が増えていきます。利他の心に基づいた行動は、人の心を自然に動かします。その結果、必要な人や情報、資源までもが磁石のように引き寄せられてくるのです。次に「独自性が高い」ことが重要なのですが、これは他にはない特徴や価値を持っているということです。ありふれたものでは人の心に響きませんが、独自の視点や発想、他にはない強みがあると、そこに人は惹きつけられます。独創的で尖った価値こそが、人をワクワクさせ、心を動かし、「一緒にやりたい」という気持ちを呼び起こすのです。独自性とは、言い換えれば「自分らしさ」を全開にすることでもあります。偽りなく、自分の想いをストレートに発信することが、人と人との深いつながりを生みます。そして忘れてはならないのが「収益性が高い」ことです。社会性や独自性がどれほど高くても、そこに収益性が伴わなければ継続性がなくなります。お金は単なる道具に過ぎませんが、その道具がなければ事業も活動も続けられません。収益が上がることで再投資が可能になり、より大きな社会貢献につながっていきます。つまり、収益性は理想を現実化させるためのエンジンであり、ここがしっかり回っているからこそ、引き寄せが現実的な成果に結びつくのです。この3つの要素が同時に高いレベルで揃った時、まるで宇宙が味方してくれるかのようなシンクロニシティが起こります。偶然に見える出来事も、実は必然の流れの中にあったことに気づきます。出会うべき人に出会い、必要な情報が手に入り、思いがけない協力者が現れる。その連続は、まるで見えない力に導かれているような感覚さえ覚えます。強力な引き寄せを呼び込むために大切なのは、この3つを意識して磨き続けることです。社会にどう役立てるかを考え、独自性を恐れず発揮し、収益性を冷静に追求する。すると、自分の行動や存在そのものが大きな磁石となり、望む未来を次々と引き寄せていくのです。今、私の周りで起こっている現象はその証明です。驚きと感謝の気持ちでいっぱいですし、これからますます大きな引き寄せが加速していく予感がしています。引き寄せは偶然ではなく必然、心の在り方と行動が整ったとき、未来は必ず開けていくのだと確信しています。
2025年09月10日
コメント(0)
-
経営者の志が会社の原動力
会社というものは、経営者一人の力だけで運営できるものではありません。社員とそのご家族、協力会社様、仕入れ先様、そしてお客様、さらに同じ経営者仲間や地域社会といった多くの人々の力が結集して、初めて会社は前進していくことができます。まさに「一人の力は小さいが、多くの人の力を合わせれば大きな推進力になる」という原理そのものです。では、その結集の中心にあるものは何でしょうか。それこそが、経営者自身の「志」なのです。「志」とは単なる夢や目標とは異なります。夢は自分が叶えたい未来を指すことが多いですが、志は「他者のため」「社会のため」に自らを突き動かす力です。利他の心に根差しているからこそ、多くの人が共感し、その想いに呼応して力を貸してくれます。志の高さとはすなわち、どれだけ広い視野で社会を見渡し、どれだけ多くの人に良い影響を及ぼそうとするかということの表れです。経営者の志が利己的であれば、その会社に集まる人々も利己的になり、やがてはバラバラに崩れてしまいます。しかし、志が「人を幸せにしたい」「社会を良くしたい」という利他的なものであれば、その想いは自然と社員や協力会社に伝わり、共感の輪が広がります。だからこそ経営者の志は、会社の最大の原動力だといえるのです。では、どうすれば経営者は自らの志を高めていけるのでしょうか。私は三つの方法があると考えています。第一に「自己を磨き続けること」です。経営者が学びを止めた瞬間、会社の成長も止まります。読書や研修、異業種交流を通じて自らの知見を広げ、常に高い視座を持つことが大切です。第二に「人とのつながりを大切にすること」です。志は一人の中だけでは磨かれません。社員との対話や、お客様の声、経営者仲間からの刺激によって磨かれ、より大きな志へと育っていきます。人とのご縁の中で、自分の役割を再確認できるのです。第三に「感謝の心を忘れないこと」です。会社が存在できるのは、多くの人の支えがあるからこそです。その支えに感謝し、その恩に報いる気持ちが、さらに志を高めていきます。利他の心は感謝の心から生まれるのです。経営者の志は、会社のビジョンや方針に直結します。そしてそのビジョンが社員に浸透すれば、社員は「自分の仕事は誰かの幸せにつながっている」と感じることができます。これは単なる給与や待遇を超えた、働く意味や誇りとなります。また、志ある経営者の元には、自然と同じような志を持った人材や協力者が集まります。つまり、志は会社の文化を形づくり、長期的な成長を支える最大の源泉なのです。会社経営とは、決して一人で成し遂げられるものではありません。多くの人の力を結集するために必要なのは、経営者自身の志です。志は利他の心であり、その高さは社会的な視座の高さを映し出します。自らを磨き、人とのご縁を大切にし、感謝の心を持つことで、経営者の志は磨かれ続けます。その志が社員や協力者を動かし、結果として会社の成長と社会の発展へとつながっていくのです。志こそが経営の出発点であり、未来を切り拓く最大の原動力なのです。
2025年09月09日
コメント(0)
-
成長のための選択肢を与えるリーダーシップ
社員の成長を願うリーダーにとって、一番大切な役割は「機会を与えること」だと私は考えています。人は環境によって変わり、環境によって成長します。逆に言えば、どれほど本人に潜在能力があったとしても、その能力を引き出す舞台やきっかけがなければ、宝の持ち腐れとなってしまいます。だからこそリーダーは、社員に「挑戦の場」や「新しい役割」という機会を提供し続けることが重要なのです。別の言い方をすれば、それは「選択肢を与えること」と言えるでしょう。選択肢があるからこそ、人は自分で考え、選び、決断することができます。リーダーが一方的に道を決めて指示するのではなく、「こういう挑戦もある」「こういう学びの場もある」と選択肢を提示することで、社員は自らの意思で一歩を踏み出すことができるのです。その一歩が、成長の速度を大きく加速させます。もちろん、選択肢を与えることにはリスクも伴います。新しいプロジェクトに挑戦させれば失敗することもあるでしょうし、思ったような成果が出ないこともあります。しかし、成長とはそもそも成功体験だけで積み上がるものではなく、失敗や悔しさを経験するからこそ、次にどうすればよいかを考え、学び、そして成長していくのです。リーダーの役割は、その挑戦を安全に支え、必要以上に恐れず飛び込める環境を整えてあげることだと言えるでしょう。私は、社員の成長を「セーフティーゾーンを壊すこと」と捉えています。慣れた環境や得意な業務の中にいるだけでは、人は変わりません。だからこそリーダーは、少しだけ背伸びをしなければならない場や、未知の領域に挑むきっかけを与える必要があります。それが「選択肢」という形で差し出されると、社員は自らの意思で挑戦を選び、結果として自分の殻を破っていけるのです。また、選択肢を与えることは、社員への信頼の表れでもあります。「君ならできる」というメッセージが込められているからこそ、社員は「期待されている」と感じ、挑戦へのモチベーションを高めることができます。信頼されているという実感は、何よりのエネルギー源です。リーダーの小さな一言や、任せるという行為が、社員の人生を変えるほどの力を持っているのです。最後に強調したいのは、選択肢を与えることは「押し付け」ではないという点です。リーダーが与えるのはあくまで「可能性」であり、その中から何を選ぶかは社員自身の自由です。だからこそ、成長の実感が本人に残り、やらされ感ではなく「自分で選んで進んだ道」として誇りを持つことができるのです。社員の成長は会社の成長につながり、会社の成長はまた社員の幸福につながっていきます。その循環を生み出す第一歩は、リーダーが社員に成長の機会=選択肢を与えることから始まるのです。
2025年09月08日
コメント(0)
-
阪神タイガース史上最速V!ファン歴50年の喜びを込めて
ついにこの日がやって来ました。我らが阪神タイガースが史上最速でセ・リーグ優勝を決めてくれました。物心ついた頃から虎一筋、半世紀以上応援を続けてきた私にとって、これが生まれてから5度目の歓喜の瞬間です。毎年のように一喜一憂しながらも、「今年こそ!」と祈るような気持ちで過ごしてきました。その積み重ねの上に、ようやく訪れたこの優勝は、言葉に尽くせないほどの感慨深さがあります。今年のチームを率いたのは、新任1年目の藤川監督。かつては火の玉ストレートでファンを魅了した投手が、今度は指揮官としてグラウンドを熱くしてくれました。生え抜きの日本人選手たちを中心にしたチーム作り、そして強固なチームワーク。まさに「育てながら勝つ」姿を体現したシーズンでした。打線を見ても、1番の近本、3番森下、4番佐藤輝明、5番大山と、いずれもドラフト1位で入団した選手たちが堂々と主軸を担っています。さらには中野、木浪、小幡、梅野、糸原といったここ10年以内の入団選手たちが脇を固める。かつて「ドラフト下手」「育成下手」と揶揄された球団とは思えないほど、見事に世代交代を果たしたのです。今年は特に高寺、中川、豊田、熊谷、前川といった若手も随所で爪痕を残し、未来への希望を大いに感じさせてくれました。一方で、今年の阪神を語る上で欠かせないのが投手陣の充実です。才木、村上、伊藤将司、大竹、デュプランティエ、伊原、高橋遥人、ビーズリー、門別と並ぶ先発陣は安定感抜群でした。そして何より、藤川監督が「チームの心臓」と称した鉄壁の中継ぎ陣。岩崎をはじめ、無失点記録を更新する石井、さらに及川、桐敷、湯浅、ドリス、ネルソン、岩貞、島本、冨田、木下、石黒、漆原、畠と、次々に信頼できる投手が登板し、チーム防御率は驚異の2点台前半。接戦をことごとく勝利に導いていったのです。そこに欠かせないのが坂本捕手のインサイドワーク、彼の存在が、投手陣の力を最大限に引き出したと言っても過言ではありません。振り返れば、今年の優勝は「個人の力」ではなく「総合力」でつかみ取ったもの。沢山の選手が名前を挙げられるチームこそ、本当に強いチームの証です。ファンとして嬉しいのは、ただ勝つだけではなく「育ちながら勝つ」姿勢が貫かれていること。次代を担う若手の躍動に胸を熱くし、熟練の選手たちの働きに安心を覚える。この二つが融合して、今年の優勝は実現したのです。50年以上応援してきて、思えば勝てないシーズンも数え切れないほどありました。それでも信じて応援し続けてきたからこそ、この優勝の味わいは格別です。藤川監督の下、チームは新たな黄金期の入り口に立っているように感じます。ここから先、日本一、そしてその先へと続く物語が楽しみで仕方ありません。ありがとう、阪神タイガース。史上最速Vはファン全員の誇りです。そして、これからもずっと、虎と共に歩んでいきたいと思います。トラキチ歴50年、感謝と歓喜を込めて!
2025年09月07日
コメント(0)
-
お墓参りと感謝の心
今月も無事に鳥取のお墓参りに行くことが出来ました。毎月のように車を走らせて往復するその時間は、決して短いものではありませんがしかし、この習慣を続けられていること自体が、私にとって大きな意味を持っています。道中の風景や季節ごとの空気感を味わいながら、心を整える時間でもあり、ご先祖様との心の対話の時間でもあります。墓前に手を合わせると、自然と「今月もありがとうございます」という言葉が口をついて出ます。ご先祖様が直接何かをしてくださっているわけではないかもしれませんがしかし、命のつながりの中で私が存在していること、そして健康で仕事に打ち込める日々を過ごせていることを思うと、そこには確かに見えない力の後押しがあるように感じます。そうした感覚を得られるのが、このお墓参りの最も大きな価値かもしれません。また、この習慣を通じて気づくのは「継続の力」です。忙しさにかまけて一度でも行かなくなれば、そのまま足が遠のいてしまうかもしれません。しかし、どんなに予定が立て込んでいても「今月も必ず鳥取に行く」と決めて動くことで、自然と生活や仕事のリズムが整っていきます。まるで「月に一度、自分をゼロに戻すリセットボタン」を押しているような感覚です。だからこそ、会社経営においてもぶれない軸を持ち続けられるのだと思います。お墓の前では、日々の出来事や会社の状況、家族のことを心の中で報告します。うまくいったことも、悩んでいることもすべてさらけ出すことで、不思議と気持ちが軽くなります。そして「よし、また一ヶ月頑張ろう」と新たな決意が生まれるのです。まさにご先祖様は、見えない形で私を励まし続けてくださっている存在なのだと実感します。現代社会はスピードが速く、変化も激しい時代です。その中で、変わらない場所、変わらない習慣を持つことは、心の安定に欠かせません。鳥取のお墓参りは、私にとって単なる儀式ではなく、「感謝を形にする時間」であり「未来へ向かうエネルギーを充電する時間」でもあります。この感謝を忘れずに、これからも日々を大切に生きていきたいと思います。感謝を伝える習慣は、自分を強くし、未来を明るくします。鳥取へのお墓参りを続けながら、そんな確信を深めています。
2025年09月06日
コメント(0)
-
イメージ出来たことは実現する!
我が社のDX推進を加速させるべく、総勢9名でモデル企業を訪問させていただきました。「イメージできないことは実現しない」という言葉がまさにその通りで、DXのような大きな変革を進めるには、まず目指すべきゴールを鮮明に描けることが欠かせません。そのために、同業で実際に成果を出している企業を訪れ、リアルな成功事例を肌で感じることを目的としました。今回ベンチマーク先を選んだ理由は、製品の違いこそあれど、ほぼ同業であること。だからこそ自社に置き換えやすく、課題も重なる部分が多いという確信がありました。机上の空論ではなく、まさに「百聞は一見にしかず」で、訪問したメンバーが目の前で見て、聞いて、触れたことで、これまで漠然としていた理想像が一気に具体的に結びついた瞬間でした。参加メンバーの感想は実に率直で力強いものでした。「想像以上に素晴らしかった」、「こんな事が本当に実現できるなんて」、「当社でも絶対にやりたい!」、言葉からあふれる熱量は、単なる見学にとどまらず、心に火がついたことの証拠です。今後のDX推進に向けて、社内に確かな推進力が芽生えたと実感しています。さらに大きかったのは、訪問先企業のご厚意です。丁寧に説明してくださり、実際のデータや現場の様子まで見せていただいたことで、「自分たちにもできる」という確信が生まれました。そのおかげで、我が社のDX推進スピードはこれまでの3倍にも加速するのではないかと感じています。新しい風を吹き込んでいただいたことに、心から感謝の気持ちでいっぱいです。振り返れば、今回の訪問は単なる情報収集ではなく「仲間と共に未来を描く体験」でした。古い諺に「早く行きたければ一人で行け、遠くに行きたければみんなで行け」という言葉がありますが、今回の体験から学んだのは、それを超える真理です。「早く行くにも、遠くに行くにも、みんなで行くのが最高だ」ということです。9名それぞれが感じ取ったイメージを持ち寄り、社内に還元していけば、その相乗効果は計り知れません。DXは単なるデジタル化やシステム導入ではなく、会社の在り方そのものを変える挑戦です。その挑戦を一人で背負うのではなく、仲間と一緒に進めていくことで、より早く、より遠くまで到達できる。今回の訪問で得た一番の成果は、その確信だったのかも知れません。これから我が社のDX推進は、確実に新しいフェーズに突入します。目指すゴールが明確になり、そこに向かう仲間の心が一つに結ばれた今、未来はきっと大きく開けていくことでしょう。
2025年09月05日
コメント(0)
-
言葉よりも行動が大事!
「言葉よりも行動が大事」とは、多くの人が口にする真理です。どれほど立派なことを語っても、実際に伴う行動が伴わなければ、その言葉は空虚なものに過ぎません。 逆説的に言えば、「言っていることは建前、やっていることが本音」ということになります。人間の本質は、言葉ではなく行動の積み重ねの中にこそ表れます。言葉は一瞬で取り繕うことができます。「利他の精神で生きたい」と誰もが語ることはできますが、実際に困っている人に手を差し伸べるかどうかは、行動によってしか証明できません。例えば、仲間が苦しんでいる時に「頑張って」と声を掛けるのは簡単ですが、その人のために時間を割き、実際に手を動かして支援するかどうかで、その人の本質が試されるのです。行動には必ず動機があります。その動機が「自分のため」だけに偏っていれば、周囲の人はいつか離れていきます。反対に、行動の根源が「利他」に基づいていれば、不思議と人は集まり、信頼とつながりが生まれます。利他の行動とは、相手を思いやり、相手にとって価値あることを自然体で行うことです。これは偽善ではなく、自らの心が喜びを感じるからこそできる行動でもあります。利他は与えることによって巡り、結果的に自分自身の幸福へとつながるのです。「言葉」と「行動」が一致している人は、周囲から絶大な信頼を得ます。逆に、言葉では立派なことを語っても、行動が伴わなければ不信感を招きます。信頼とは時間をかけて積み重ねるものですが、その核心は「言っていることと、やっていることが一致しているか」に尽きます。利他の心から出た言葉は自然と行動に反映され、一貫性を持ちます。その一貫性こそが、人間としての魅力を高め、周囲の人の心を動かすのです。一人ひとりが利他の心で行動することは、社会全体に波紋のような影響を及ぼします。小さな思いやりの行動が積み重なり、やがて大きな信頼の連鎖を生み出していきます。例えば、電車で席を譲る、ゴミを拾う、仲間の挑戦を応援するなど、こうした小さな行動が誰かの心を温め、また別の利他的な行動を引き出します。その連鎖が広がっていくことで、私たちの社会はより良い方向に進んでいくのです。言葉は理念を伝える手段であり、行動は理念を体現する実践です。逆説的に言えば、言葉は飾れるが、行動は誤魔化せません。だからこそ、行動の根源が利他であることが大切です。利他を基盤とした行動は信頼を築き、周囲を動かし、やがて社会全体を変えていく力になります。言葉よりも行動を大切にし、そしてその行動の源泉に「利他」を置くこと、これこそが人間としての成長であり、真の幸せへの道ではないでしょうか。あなたの普段の行動は「利己」でしょうか?それとも「利他」でしょうか?言葉ではなく、行動が答えを教えてくれます。
2025年09月04日
コメント(0)
-
就活のゴールは内定ではない!
就活に臨む多くの学生が、どうしても目の前の「内定獲得」をゴールだと考えてしまいます。もちろん内定は一つの大きな成果であり、努力が報われた瞬間でもあります。しかし本当のゴールはそこではありません。就職活動のゴールとは、社会人として働き始めたその先に「幸せな人生を築けるかどうか」にあるのです。内定はスタートラインに過ぎず、そこからの歩み方こそが真の就活の意味を決定づけます。では「幸せな人生」とは一体何でしょうか。これは人によって答えが異なります。例えば、ある人にとってはキャリアアップや昇進が幸せの形かもしれません。別の人にとっては、家族と過ごす時間を大切にできる働き方が幸せかもしれません。大切なのは、他人が定義した「幸せ」ではなく、自分にとっての幸せの基準を見つけることです。就活を「逆算」で考えるなら、まず最初にこの幸せな未来のイメージをしっかりと描くことが必要です。自分はどんな働き方をしていたいのか、どんな人たちに囲まれていたいのか、どんな価値観を大切にしていたいのか。それを明確にすることが、就活のすべての判断軸になります。多くの学生が「有名企業に入りたい」「安定している会社がいい」と思いがちです。確かにブランド力や待遇は安心感をもたらしますが、それが必ずしも幸せにつながるとは限りません。むしろ、自分の価値観と会社の価値観が合っているかどうか、自分の強みを活かせる環境があるかどうかの方が、長期的な幸福度を大きく左右します。例えば「挑戦することが好き」な人が、安定重視で変化を嫌う企業に入社すれば、いずれ窮屈さを感じてしまうでしょう。逆に「人とじっくり関わりたい」と思う人が、数字ばかりを追い求める会社に入れば、やりがいを見失ってしまうかもしれません。だからこそ、自分の価値観と企業文化との一致点を探すことが、就活においてもっとも大切な視点なのです。就活を逆算思考で取り組むとは、すなわち「理想の社会人としての姿」を描き、その姿に近づくための選択を今することです。ゴールイメージが明確であれば、企業研究も自己分析もただの作業ではなく、自分の未来を形づくるためのプロセスになります。たとえば「成長を実感し続けたい」というゴールがあるなら、教育制度や挑戦機会が整っている企業を優先すべきでしょう。「人の役に立つ喜びを感じたい」というゴールなら、顧客との距離が近く、感謝の言葉を直接受け取れる仕事を選ぶべきです。このように、ゴールを先に設定することで、就職活動の迷いはぐっと減っていきます。就職活動は、単なる「就職先探し」ではありません。人生の幸福度を左右する大きなターニングポイントです。だからこそ、内定をゴールとするのではなく、幸せな未来から逆算して選択することが大切です。内定はスタートラインであり、そこから始まる社会人生活の中で「この会社を選んでよかった」と心から言える自分を思い描いてみてください。その未来を描きながら行動することで、就活は単なる活動ではなく、自分の人生をデザインする大切な時間へと変わっていくはずです。
2025年09月03日
コメント(0)
-
新たなグローバル展開モデルでさらなる飛躍へ
日本のアニメコンテンツがいまや世界市場において確固たる地位を築いていることは、もはや疑いようのない事実です。2023年の市場規模は約5.8兆円に達し、半導体や鉄鋼といった基幹産業を上回り、自動車産業に次ぐ輸出産業へと成長しました。これは日本人にとって大きな誇りであると同時に、文化が国境を越えて人々の心を動かす力を持つことを示しています。しかし、この成長を一時的なブームで終わらせず、持続的な発展へとつなげていくためには、従来の枠組みにとらわれない「持続可能なグローバル展開モデル」が不可欠です。日本のアニメが魅力的である最大の理由は、その世界観、キャラクター、物語の深さにあります。けれども、どれほど完成度が高くても、現地の文化や価値観と乖離していては共感が生まれにくいのも事実です。世界中の視聴者は、日本的な感性に新鮮さを覚える一方で、自分たちの生活や社会と接続できるポイントを求めています。そのためには、単なる「輸出」ではなく「共同製作」や「ローカライズ」が鍵となります。例えば、ストーリーの背景設定に現地の歴史や風土を取り入れたり、人気声優だけでなく現地のタレントを吹替に起用するなど、文化的な橋渡しが必要です。グローバル展開において注目すべきは、単純な販売モデルではなく「共同製作」という形です。これは日本側が持つ優れたアニメーション技術や企画力と、現地の価値観や生活習慣を理解したパートナーの感性を融合させる取り組みです。そうすることで、単なる日本発の輸出品ではなく、世界中の人々が「自分たちの物語」として感じられる作品が生まれます。さらに、共同製作は現地のクリエイターを育て、持続的な産業基盤を築くことにもつながります。これはアニメを「日本だけの宝」から「世界の共通財産」へと進化させるための大きな一歩です。今後の課題は、急速に拡大した市場をいかに持続可能な形にするかです。短期的な収益を追い求めるだけでは、やがて消費者の熱は冷め、模倣や低価格競争に巻き込まれてしまいます。だからこそ、日本のアニメ産業は「長期的なブランド戦略」を持たなければなりません。具体的には、作品そのものに加えて、キャラクターグッズやイベント、ライブ配信、ゲームなど多角的な展開を組み合わせる「メディアミックス戦略」を深化させることです。これにより、ファンとの関係性を長期的に育むことができます。アニメは、単なる映像作品を超えて「文化そのもの」を輸出する力を持っています。今後は、日本的な感性と世界の多様な価値観をつなぐ「共創」の姿勢がますます重要になるでしょう。現地化の工夫や共同製作を通じて、日本発のアニメは世界の共通言語となり、人々の心を結びつける存在へと進化していくはずです。5.8兆円という数字の先にあるのは、経済的な成功だけでなく、文化的な架け橋としての使命なのです。日本のアニメは、まさに「持続可能な夢の輸出産業」として未来を切り拓いていくのだと確信しています。
2025年09月02日
コメント(0)
-
伏見稲荷大社の朔日参り、30か月目を迎えて
今日から早くも9月が始まりました。月の初めの節目にあたり、私にとって欠かせない習慣が「伏見稲荷大社への朔日参り」です。2023年4月から欠かさず続けてきたこの参拝も、今日でついに30か月目となりました。振り返れば、あっという間のようでありながら、毎月の積み重ねの重みを感じます。朔日参りは、ただの参拝ではありません。朝6時に伏見稲荷大社の鳥居をくぐり、山頂まで足を運ぶ。その道のりは決して楽ではなく、体調管理を怠れば続けることはできません。さらには、仕事や家庭のスケジュールを調整しなければ、この時間を確保することは難しいものです。つまり、朔日参りを継続できるということは、自分の体調が整い、経営が順調であり、家族の理解や支えがあってこそ実現するものなのです。「継続は力なり」とはよく言いますが、それは単に自分一人の努力だけで成り立つものではありません。会社を守ってくれている社員の頑張り、お客様からいただくご縁やご愛顧、そして日々支えてくれる家族の存在。そのすべてがあって初めて、この毎月の参拝を継続できているのです。当たり前のように感じてしまいがちな日常の裏側には、数えきれないほどの「ありがたさ」が詰まっています。人はともすれば、自分の努力や意思の強さだけで物事を継続できていると錯覚しがちです。しかし実際には、一人の力で出来ることには限りがあります。30か月もの間、欠かさず続けてこられたのは、間違いなく周囲の協力があったからこそ。そこに気づき、感謝の心を忘れずに持ち続けることが何より大切なのだと改めて感じます。朔日参りは、私にとって「感謝を新たにする場」でもあります。朝一番の清々しい空気の中で、頂上から街を見渡すと、自分の歩んできた時間と、これからの未来とがつながっていくような感覚があります。祈りを捧げると同時に、これまで支えてくれた人々への感謝の言葉が自然と胸に浮かんできます。そしてまた新しい月の始まりに向けて、自分を律し、前を向く力をいただけるのです。30か月という節目を迎えて思うのは、「続けられること自体が奇跡」であるということです。健康を害していたら登れなかったかもしれません。経営に行き詰まっていたら、参拝どころではなかったかもしれません。家庭の事情で時間を割けなかった可能性もあるでしょう。そうしたあらゆる条件が整い続けてきたからこそ、今日も無事に頂上まで足を運ぶことができたのです。これから先、40か月、50か月と続けていく中で、また新しい気づきや出会いがあることでしょう。しかし、どれだけ続けようとも「当たり前」になってはいけないと肝に銘じています。毎月の参拝は、支えてくれるすべての人への感謝を新たにする儀式であり、自分を原点に立ち返らせてくれる大切な時間です。9月の始まりに、改めて「感謝」と「継続」の意味をかみしめながら、これからも朔日参りを大切に続けていきたいと思います。そして、その積み重ねが、必ずや自分自身の成長と、会社の繁栄、そして周囲の人々の幸せへとつながっていくと信じています。
2025年09月01日
コメント(0)
全30件 (30件中 1-30件目)
1