2012年08月の記事
全121件 (121件中 1-50件目)
-

本年度17回目の計測 9月1日のデータ m-07の畑の分
本年度17回目の計測 9月1日での野菜の育ち具合の目処として高さの最大を計測してみた 平均値ではない m-7の畝の在庫 11 01九条ネギ 02大根 03枝豆 04ョウガ 0577ツマイモ 06ゴーヤ 07ニンジン 08ゴボウ 09オクラ 10スイカ11カボチャ月-05---05---06---06---07---07---08---08---09日-01---13---01---13---01---13---01---13---0101-40---40---45---45---45---45---45---40---4002-05---15---20---30---30---30---30---30---3003-10---20---30---35---35---35---35---35---3504-00---00---00---05---15---20---20---20---2005-10---10---15---25---50---80--100--100--10006-20---40---60---90--150--200--200--200--20007-00---00---00---10---15---20---25---25---2508-00---00---00---10---15---20---25---25---2509-00---00---00---10---30---40---50---50---5010-00---00---00---10---70--100--200--200--20011-00---00---00---30--300--500--600--600--600これが9月1日のm-07の畑の在庫 11はた坊
2012.08.31
コメント(0)
-

本年度17回目の計測 9月1日のデータ m-06の畑の分
本年度17回目の計測 9月1日での野菜の育ち具合の目処として高さの最大を計測してみた 平均値ではない m-6の畑の在庫 0801サトイモ 02スイカ 03ニンジン 04ゴボウ 05ナスビ 06唐辛子 07キュウリ 08マクワウリ 月-05---05---06---06---07---07---08---08---09日-01---13---01---13---01---13---01---13---0101-05---10---15---20---50---70--100--100---8002-05---20---25---30---60--200--200--200--20003-05---08---10---20---25---30---30---30---3004-05---08---10---20---40---40---40---40---4005-00---00---00---05---25---30---30---30---3006-00---00---00---05---10---15---20---20---2007-00---00---00---10---30--100--200--200--20008-00---00---00---10---15---30--200--200--200これ9月1日のm-6の畝の在庫 08はた坊
2012.08.31
コメント(0)
-

本年度17回目の計測 9月1日のデータ m-20の畑の分
本年度17回目の計測 9月1月での野菜の育ち具合の目処として高さの最大を計測してみた 平均値ではない m-20の畑の在庫 0701茗荷 02イチゴ 03アスバラガス 04ピーマン 05タカノツメ 06トマト 07ミニトマト 月-05---05---06---06---07---07---08---08---09日-01---13---01---13---01---13---01---13---0101-00---10---20---30---35---40---40---40---4002-13---15---15---15---20---20---20---20---2003-40---80--100--100---50---40---30---30---3004-10---15---20---25---30---30---30---30---3005-10---15---20---25---30---30---30---30---3006-20---40---60---90--150--200--200--200--20007-25---40---60---90--150--200--200--200--200これが9月1月のm-20の畝の在庫 07はた坊
2012.08.31
コメント(0)
-

本年度17回目の計測 9月1日のデータ g-10の畑の分
本年度17回目の計測 9月1日の育ち具合の目処として高さの最大を計測してみた 平均値ではない g-10の畑の在庫 0601下仁田ネギ 02インゲン 03ニンジン 04ゴボウ 05キュウリ 06マクワウリ 月-05---05---06---06---07---07---08---08---09日-01---13---01---13---01---13---01---13---0101-30---30---30---25---20---20---20---20---2002-00---10---15---25---30---35---35---35---3503-00---05---10---15---20---25---25---25---2504-00---05---10---20---25---30---30---30---3005-00---10---15---30--200--300--300--300--30006-00---05---10---20---50--100--200--200--200これが9月1日のg-10の畝の在庫 06はた坊
2012.08.31
コメント(0)
-

本年度17回目の計測 9月1日のデータ g-22の畑の分
本年度17回目の計測 9月1日での野菜の育ち具合の目処として高さの最大を計測してみた 平均値ではない g-22の畑の在庫 0701ニラ 02落花生 03オクラ 04ニンジン 05ゴボウ 06キュウリ 07かぼちゃ 月-05---05---06---06---07---07---08---08---09日-01---13---01---13---01---13---01---13---0101-25---30---30---30---30---30---30---30---3002-00---00---10---15---20---25---25---25---2503-00---00---10---15---20---60---70---70---7004-00---00---00---00---05---10---15---15---1505-00---00---00---00---05---10---15---15---3006-00---00---00---00---15---30--200--200--20007-00---00---00---00---50--200--300--300--300これが09月1日のg-22の畝の在庫 07はた坊
2012.08.31
コメント(0)
-

まくわうり 畑でもう1個の収穫をした 東日本大震災538日後に
昨年のうりまずは まくわウリ 2個の苗を買ってきた04月03日 2個のマクワウリ とりあえず購入しておいた04月10日 畑のm-20に植え付けした05月08日 そのままのサイズ 成長はしていない まだ 早すぎなのかな ??05月15日 そろそろ 苗も生長してきそうだ そろそろ かな ??05月28日 蔓が延びてきている 成長を開始したようだなあ ok/ok/ok06月12日 すこし伸びているが あまり元気はないかな ??07月10日 まくわうりの1個の実がなっている 収穫したついでに 種からの栽培も05月03日 種まきした 庭で potに種まき05月11日 発芽してきた おお 雨がふったので 発芽だな05月13日 あら あら ない ?? ナメクジさんが食べてしまった 失敗だまた 種まきしよう トライ アゲイン05月22日 再度の種まきをする05月28日 まだ発芽していない が なめくじさんが入れないようにカバーをつける06月05日 発芽した 大成功だなあ06月12日 畑に移動 m-08に植え付けをした07月10日 苗も大きくなりつつある そのうち実もなるだろう 期待は大07月31日 そろそろ実が付き出した ゴロゴロとしてきている08月06日 2個の収穫をした 黄色のまくわうりだ08月14日 8個の収穫をした08月20日 青い実も5個あった08月21日 黄色の実20個を収穫しておいた これで終了no1からは 実が1個no3からは 実が35個 これにて 終了今年もうりさんまずは ニューメロンから04月08日 とりあえず hcで買い物をしてきた まだ寒そうもう すこし待とう04月22日 種まきを開始 庭でpotに8個 種まきしておいた04月29日 まだ発芽せず05月05日 発芽した 遅いなあ 畑に移動 g-10に植えておく06月03日 そのご 生育していたが 小さいまま 気温が低いのかな 06月17日 残っているのは1本くらい すこし成長してきている06月24日 1本のみ残り すこし成長してはいるが 1本のみ07月15日 1本のみ なんとか育っているが 実がつくのかどうか ?????07月29日 実が2個ついていた マクワウリ次に 第二弾05月27日 庭で種まきをした06月06日 やっと発芽してきている 06月10日 畑に移動した m-06の畑に06月17日 すこし落ち着いてきている 何本残るか ????06月24日 8本くらいは残っている が 小さいな07月15日 蔓が延びてきている なんとかなるかなあ ???07月29日 実ができていない なし ???08月05日 小さい実がすこしついてきている 08月19日 6個の実があったので 収穫しておいた08月26日 1個の実がついていた今年のマクワウリ畑で8本くらい g-10では生育中野は1本だけ 消えた 実が2個ついた庭で発芽したのが8pot m-06に植えている 8本残っている 実は小さいの 数個会社でも2本 育てている これは150cmくらいになっている07月15日 蔓は良く伸びている2mくらいになっている 実も3個ついている07月29日 実が6個目がついている 収穫したのは2個 08月03日 実がまた6個ついている 2個 また収穫しておく08月19日 追加の実が4個 また 出来ている08月26日 4個の収穫をした まだ 実は付きそうだ結果畑のは実は2+6+1で 合計9個会社のは実が合計14個に 畑の負け東日本大震災 3月11日発生08月31日は 既に538日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------人生の節目・衝撃の一言・・・それじゃ、広報費を増やしましょう今から3年ほど前でしょうか、原子力委員会の研究開発部会で原子力予算の分配をしている時に、私は次のように発言しました。「ここにおられる原子力関係の方は原発が安全だと考えておられますが、日本人の多くが原発に不安を持っています。この際、私たちが間違っている可能性があるので、原発の安全研究のお金を増やす方が良いと思います。」これに対して委員長代理の先生が「わかりました。それでは広報費を増やしましょう」と言われたので、私は「いや、原発が安全と言う広報をするのではなく、原発は危険だという前提のもとで安全を見直す研究にお金を投じたいという意味です」と説明しました。科学者は自然に対して謙虚で、研究をする過程でイヤと言うほど自分の考えが未熟であることを知ります。厳しい研究をすればするほど、自分の至らなさを感じるものですから、その点で、この委員長代理(東大教授)は「科学者ではない」と言うこともできるでしょう。また、人の意見が自分と違うとき、人の意見が正しいかも知れないと思うことが民主主義の基本と思うのです、この時の委員長代理の発言はまだ良く覚えている衝撃の一言でした。「これでは日本の原子力もダメだ」と感じたものでした。(平成24年8月28日んだ んだはた坊
2012.08.31
コメント(0)
-

オクラ 今週は2個のみ 東日本大震災538日後に
昨年のオクラ5月03日 種まきした 昨年の保存した種5月15日 まだ 発芽しない5月22日 まだ 発芽しない 種みるが そのまま 発芽しないようだなあ ???今年の発芽は どうも失敗となったみたい 種の保存がよくなかったのかな ??種を買ってきて 再度 種まきをしよう5月22日 種をかってきて再度の種まきをした5月28日 まだ発芽していない 遅いなあ5月30日 発芽した おお 結構と時間がかかるが カバーもしているので okだ06月05日 畑に移動した g-10に移動ok 20本06月19日 苗は無事に育ちつつある ok06月29日 苗はすこし生長してきている 雑草を取り除いておく07月10日 そのご 苗も大きくなりつつある07月17日 初の収穫だ 4個あり第二弾の種の種まき06月05日 2回目も種まき06月11日 すこし発芽してきている06月12日 移動だ m08の畑に移動した 8本06月19日 苗は無事に育ちつつある ok06月29日 こちらの苗もok 無事である 問題はなし07月10日 そのご 苗も大きくなりつつある 07月17日 初の収穫だ 4個あり 花があちこちで咲いている07月24日 25個の収穫をしておく 本格的に実が付き出した07月31日 30本の収穫をしておく 合計59個08月07日 30個の収穫をしておく 合計89個08月13日 20個の収穫をしておく 合計109個08月20日 20個の収穫をしておく 合計129個08月28日 20個の収穫をしておく 合計149個09月04日 20個の収穫をしておく 合計169個09月11日 20個の収穫をしておく 合計189個09月18日 20個の収穫をしておく 合計209個09月23日 30個の収穫をしておく 合計239個10月01日 30個の収穫をしておく 合計269個10月10日 20個の収穫をしておく 合計289個10月16日 10個の収穫をしておく 合計299個10月22日 10個の収穫をしておく 合計309個7月17日より収穫を開始 ただいま 309個今年のオクラ04月08日 オクラの種を買ってきておいた今年も5月より種まきをしよう04月30日 庭で種まきをしておく05月10日 発芽してきている 16pots 10日かかる05月13日 g-22の畑に移動 植え付けしておいた05月20日 苗は無事 16本くらいある06月17日 なんとか育ちつつある これでokだなあ06月30日 花がついている 順調に育ちつつある予備として オクラの種まき 第二弾05月27日 追加で庭で種まきをしておく06月03日 発芽した すこしだけ 5本くらいかな残っているのは06月10日 畑に移動する m-06に植え付けた06月17日 残っているのは 2本だけ まあ 予備なのでokオクラ 花も咲き出した なんとか育ちつつある07月08日 良く見ると 実があちこちに付いている 収穫をしておいた15個07月11日 2回目の収穫をした15個07月16日 3回目の収穫をした30個07月19日 4回目の収穫をした20個07月22日 5回目の収穫をした20個07月29日 6回目の収穫をした30個08月05日 7回目の収穫をした30個08月12日 8回目の収穫 8個08月19日 9回目の収穫 2個08月26日 10回目の収穫 2個勢いが弱ってきている7月8日から 15+15+30+20+20+30+30+8+2+2=172個東日本大震災 3月11日発生08月31日は 既に538日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------人生の節目・衝撃の一言・・・それじゃ、広報費を増やしましょう今から3年ほど前でしょうか、原子力委員会の研究開発部会で原子力予算の分配をしている時に、私は次のように発言しました。「ここにおられる原子力関係の方は原発が安全だと考えておられますが、日本人の多くが原発に不安を持っています。この際、私たちが間違っている可能性があるので、原発の安全研究のお金を増やす方が良いと思います。」これに対して委員長代理の先生が「わかりました。それでは広報費を増やしましょう」と言われたので、私は「いや、原発が安全と言う広報をするのではなく、原発は危険だという前提のもとで安全を見直す研究にお金を投じたいという意味です」と説明しました。科学者は自然に対して謙虚で、研究をする過程でイヤと言うほど自分の考えが未熟であることを知ります。厳しい研究をすればするほど、自分の至らなさを感じるものですから、その点で、この委員長代理(東大教授)は「科学者ではない」と言うこともできるでしょう。また、人の意見が自分と違うとき、人の意見が正しいかも知れないと思うことが民主主義の基本と思うのです、この時の委員長代理の発言はまだ良く覚えている衝撃の一言でした。「これでは日本の原子力もダメだ」と感じたものでした。(平成24年8月28日んだ んだはた坊
2012.08.31
コメント(0)
-

ゴーヤ 今週も6個 東日本大震災537日後に
昨年のゴーヤ04月03日 hcでゴーヤの苗を購入 2本04月10日 畑のm-07に植え付け04月17日 枯れそうだけど まだ もっている04月23日 黄色になっている 持つかな ????04月24日 追加で1本の苗を植えておいた 合計で3個 風除けをつけておいた05月03日 苗の3本 緑色になりつつある 元気になってきた 水槽が役に立つ05月08日 ゴーヤが成長を開始している 水槽が役に立っている05月15日 支柱をつけておく これで3本が順調に生育していくだろう05月22日 その後無事05月29日 m-07の昨年の場所からこぼれ種の2本が発芽してきている 楽しみゴーヤ 枯れそうだったけれど これで安心3本とこぼれ種2本で 合計で5本となっている06月19日 2箇所でゴーヤの支柱を補強しておく07月17日 実がまだついていない 遅いなあ ????07月23日 やっと実がついていた けど 小さいのばかりだなあ とりあえず3個の収穫07月24日 追加で2個 小さいの収穫した07月31日 大きな実が取れだした 14個あり 葉の下に隠れていた08月07日 4個の収穫08月14日 4個の収穫08月21日 1個の収穫08月28日 1個の収穫09月02日 1個の収穫09月04日 1個の収穫09月11日 10個の収穫09月18日 3個の収穫09月23日 3個の収穫10月02日 3個の収穫ゴーヤの収穫50個にて 終了 不作だったけど まあまあ 今年のゴーヤ04月22日 hcでのなえ 58円のが売っていたので 即 お買い上げ 畑に植えた04月30日 そのご 畑で水槽をかぶせておいたので暖かくて 成長している風を防いで暖かくするには カバーが必要 暖かいとすぐに成長してくれている05月05日 カバーをつけて支柱をつけておいた これでok05月13日 その後もまだそのまま そんなに急には成長しない05月20日 鶏糞をどかーんといれておいた06月02日 先端の芽をカットしておく06月03日 小さい実がついてきている06月10日 蔓があちこちに延びてきている 06月24日 まだ 実はできていない もうすこしかかりそう07月01日 支柱にのびて2m-3mは蔓が延びている そろそろ 実もあるはず日曜は ゴーヤの実を捜そう07月08日 ゴーヤの実 1個はあった まだあるかもと探していたら 雀がいた 関係ないか07月11日 初の実 3個の収穫07月15日 2回目は6本の収穫07月19日 3回目は7本の収穫07月22日 4回目は6本の収穫07月28日 5回目は7本の収穫08月04日 6回目は10本の収穫08月05日 7回目は05本の収穫08月11日 8回目は22本の収穫08月19日 9回目は06本の収穫08月26日 10回目は06本の収穫ゴーヤ 7月11日より 3+6+7+6+7+10+5+22+6+6 =78個今年のゴーヤは昨年より良い9月まで ゆっくりと収穫しよう東日本大震災 3月11日発生08月30日は 既に537日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------対立の構図 対立を煽る人たちと知的犯罪さて、理科系の学問は30年以内には事実が判明してしまうので、無理な「学説」というのは通りにくい。だから、やや対立を避けてみんなで力を合わせて研究をしようということになる。それでも、リサイクルや地球温暖化のように単純な自然科学の活動ではなく、自然科学と社会活動が混在すると、途端にもめ事や言い争いが発生する。時には立派な学者を罵倒する素人(その分野の専門知識が無い人という意味)が出てきたり、逆に立派な学者であっても社会的なことに負けて発言する人(最近では御用学者といい、少し前は曲学阿世の徒と言った)が現れたりするから面倒だ。また、文科系の学問は現在でも2000年以上まえのギリシャ文学、哲学などが研究されているように、「なにが真実か」というのがわかりにくいものが多い。最近の学問でも経済学などは常に対立していて、かなり高名な学者でも「懺悔の書」という名前の「自分の学問は間違っていた」という書籍を出版したりする。自分の「学問的結論を懺悔する」というのは実に矛盾した表現だ。というのは、少なくとも自然科学では「学問的結論」というのは、確定された事実あるいは理論から論理的に導き出された結論であるから、一人の人間が心の問題として「懺悔する」という対象ではないからである。それは単に計算を間違ったとか、論理展開でミスをしたという類いのもので、それほど高級なものではあり得ない。つまり自然科学から見ると学問は頭脳活動だから、懺悔というのはあり得ず、もし懺悔ということがあるなら、それは「故意に実験データをねつ造した」という類いのものである。この経済学者の「懺悔」というのは、「自分に学力が無かった」という意味での懺悔であるが、その学力が無かった人が日本の経済学者のトップが就任するような役職に長く就いて政策の指導を行ってきた。ということは経済学者の多くが彼を支持したことを意味している。ここまで整理をすると一つの簡単な結論が得られる。それは「どうも文科系の学問は、学問的結論が得られるための事実と論理の20%ぐらいしか分かっていないときに、100%分かったような答えを出す」ということだ。なぜ、20%しか進んでいないのに100%の答えを出すかというと「社会に求められるから」ということになる。理科系(特に工学系)の感覚で言えば「5回に4回は墜落するヒコーキでも、社会が欲しいと言うから飛ばす」ということであり、「もし墜落したら懺悔する」という感じである。ヒコーキを運航する時に5回に4回は墜落する可能性があることが分かっていて(学問的に言えば全体像の20%しか分かっていないことを提案している学者が分かっていて)、ヒコーキを飛ばし、墜落して人命を失ったら、社会は「懺悔ではすまない」と言うだろう。それでも、経済学に懺悔が許されるのは、もともと文科系の学問自体が「学問ではなかった」のか、「学問を逸脱する人たちが主流を為していた」のかどちらかと考えられる。たとえば、経済活動として大きな負の結果を出したと言われるリーマンショック(サブプライムローンや多重保障などの経済システム)の中心となったのはノーベル経済学賞を受賞したアメリカの経済学者たちだったのだが、それを考えると経済学とは学問ではないか、知らず知らずのうちに逸脱した学問になってしまったのだろう。・・・・・・・・・ところで、自然科学でも同じようなことが起こったのがタバコ、リサイクル、地球温暖化、そして最近では被曝の問題などである。静かな自然科学の中に突如として「罵倒、バッシング、懺悔」など人間的な要素が持ち込まれた.その様子を見ると、自然科学の専門家以外の人が自然科学者の発言や著作物を罵倒する、新聞がそれに追従する、そのうち、自然科学の専門家の中に「曲学阿世の徒」が現れて事態が混乱するという経過をたどってきた。そのうち、専門以外の人が「事実を隠蔽して対立を煽る」という行動にでる。その背景には、1)思想的、2)金銭的、3)有名になりたい、などがあり、それらは学問的ではないので、到底、従来の学者は太刀打ちできない。たとえば、私自身のことで言えば、地球温暖化について一般的に言われていることと異なることを書いたら、私のウィキベディアが悪意に満ちたものに変わった。ウィキペディアというのは多くの人が「ネットの百科事典」として知られており、それを使って個人を誹謗するという手段に出たのである。この著者はおそらく引用文献、文体から見て東北大学か東大の教師であると推定されるが、私自身は警察ではないので、捜査をすることはできない。実に巧みな方法である。もちろん著者は名前を出さないし、自らウィキペディアを書いたとも公表しない。もちろんやましいからである。ウィキベディアに書き直しを求めたら酷く複雑な手続きを言ってきた。「書き直したいなら、複雑な手続きにそってやれ」と居丈高である。つまり民間の会社が勝手に個人を誹謗する手段を作り、それに苦情を述べる個人に対して「おれの決めたことに従え」というのだから、まったく困ったものである(ぼやきではない)。このような場合、相手は私を誹謗する事だけが目的では無い(私と利害関係はない)。売名などの目的を持っているからなかなか対応が難しく、相手はそれを知って攻撃をしてくる。対立を煽る人というのには共通点があって、まず「人物、人格を攻撃してくる」、そして「事実と違うことを言う」というという二つである。つまり、対立を煽る人というのは、「事実に近づきたい」という私たちの目的とは全く違い、「事実から遠ざかることによって、対立を深めたい」という目的をもっているので、事実の確認や議論はまったく意味をなさないのである.・・・・・・・・・このように社会に「人物、人格を罵倒し、事実を故意に違えて言う」ことによって対立を深め、事態を混乱させたいという行動にでる人たちが居るのは仕方が無いことだろう.まさに「世に盗人の種は尽きまじ」ということだが、もっとも大きな問題は「対立を煽る人」がこの民主主義の社会、学問的な活動が許されている社会の「悪」であるということがまだ確定していないことだ。盗人とは違い、サギ、虚偽、名誉毀損、分かっていないのに分かっていると言う経済学者などは知能的犯罪で、しかもその影響が知的社会では甚大なのにまだ犯罪として認知されなかったり、認知されてもどのような行動が知的犯罪に属するのかの議論が明確では無いことによる。私は、経済学ばかりではなく、医学、環境問題、原発問題などに見られるような知的犯罪について、その定義をハッキリさせ、犯罪として社会的に措置をとることによって、民主主義というものが成長していくと考えている。マスコミの誤報、NHKや朝日新聞の問題も、「知的犯罪」の定義が明確ではないところに根があると考えている。(平成24年8月26日)なるぼとはた坊
2012.08.30
コメント(0)
-
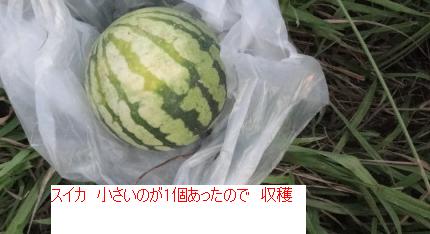
スイカ 今年はさっぱり 最期の1個のみ収穫した 東日本大震災537日後に
昨年のスイカ赤いスイカの苗を買ってきた畑の隅っこに植えておこう04月10日 スイカの苗 1本を購入 畑に植えておこう 適当に04月17日 ついでに安い苗がうっているので 追加で1本 また 買っておいた05月05日 また安い苗があるので1本追加でかっておいた06月01日 3本のスイカ つるが延びだした06月19日 小さい実が あちこちに 06月26日 1個は大きくなっている これは楽しみ どんどん大きくなあれ 07月03日 3個が大きくなりつつある 07月10日 4個が大きくなりつつある 1個をまずは収穫とした07月17日 2個目の収穫をした 1個は壊れてしまっていた 残りは2個07月24日 3個目を収穫した 残りはあと1個 これは来週に07月31日 4回目の収穫をした これで お終いに結局はm-06に2本 実は3個が付いている 3個の収穫をした 残りは0個g-10に1本 実が1個ついている 収穫をした 会社に1本 パチンコの玉くらいのが1個 大きくなるかな ???会社にも1本 これは 実がつくのかどうか ??? 観察中ただいま パチンコの玉くらいのがついている ???今年のスイカ04月22日 hcで苗があったのて2本を購入 即 畑に植えておく カバーかけておく05月06日 苗はそのままのサイズ まだまだ生長してくれいないなあ05月12日 すこし成長してきているかな05月13日 hcで まだスイカの苗が58円で売られてた また2本 購入した05月20日 最初のスイカ 蔓が延びてきている05月20日 追加がまた2本 会社に植えておいた05月27日 第二弾の2本もすこし水槽の中なので 成長しているかな06月01日 会社の1本 枯れてしまう 残りは1本になる06月08日 会社に追加のスイカの苗 2本をうえておく07月01日 畑のスイカは4本 適当に伸びてきている 会社のは少しだけ伸びている08月05日 1個だけ収穫08月26日 2個目で 最期になった今年も スイカ 植えた 最初のスイカ 蔓が延びてきているM-06 2本のスイカ すこし成長 ただいま2mくらいにM-07 2本のスイカ 小さいけど 無事 ただいま4mくらいに会社に3本のスイカ ただいま 1mくらいに合計で4+3=7本の苗 しかし 畑のスイカは カボチャに囲まれて ダメだった カボチャは沢山と収穫したがスイカは さっぱり ダメとなり 失敗ということに会社にも植えていたが こちらも 実はつかずまあ 小さいのが 2個だけ 収穫ということで お終いに東日本大震災 3月11日発生08月30日は 既に537日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------対立の構図 対立を煽る人たちと知的犯罪さて、理科系の学問は30年以内には事実が判明してしまうので、無理な「学説」というのは通りにくい。だから、やや対立を避けてみんなで力を合わせて研究をしようということになる。それでも、リサイクルや地球温暖化のように単純な自然科学の活動ではなく、自然科学と社会活動が混在すると、途端にもめ事や言い争いが発生する。時には立派な学者を罵倒する素人(その分野の専門知識が無い人という意味)が出てきたり、逆に立派な学者であっても社会的なことに負けて発言する人(最近では御用学者といい、少し前は曲学阿世の徒と言った)が現れたりするから面倒だ。また、文科系の学問は現在でも2000年以上まえのギリシャ文学、哲学などが研究されているように、「なにが真実か」というのがわかりにくいものが多い。最近の学問でも経済学などは常に対立していて、かなり高名な学者でも「懺悔の書」という名前の「自分の学問は間違っていた」という書籍を出版したりする。自分の「学問的結論を懺悔する」というのは実に矛盾した表現だ。というのは、少なくとも自然科学では「学問的結論」というのは、確定された事実あるいは理論から論理的に導き出された結論であるから、一人の人間が心の問題として「懺悔する」という対象ではないからである。それは単に計算を間違ったとか、論理展開でミスをしたという類いのもので、それほど高級なものではあり得ない。つまり自然科学から見ると学問は頭脳活動だから、懺悔というのはあり得ず、もし懺悔ということがあるなら、それは「故意に実験データをねつ造した」という類いのものである。この経済学者の「懺悔」というのは、「自分に学力が無かった」という意味での懺悔であるが、その学力が無かった人が日本の経済学者のトップが就任するような役職に長く就いて政策の指導を行ってきた。ということは経済学者の多くが彼を支持したことを意味している。ここまで整理をすると一つの簡単な結論が得られる。それは「どうも文科系の学問は、学問的結論が得られるための事実と論理の20%ぐらいしか分かっていないときに、100%分かったような答えを出す」ということだ。なぜ、20%しか進んでいないのに100%の答えを出すかというと「社会に求められるから」ということになる。理科系(特に工学系)の感覚で言えば「5回に4回は墜落するヒコーキでも、社会が欲しいと言うから飛ばす」ということであり、「もし墜落したら懺悔する」という感じである。ヒコーキを運航する時に5回に4回は墜落する可能性があることが分かっていて(学問的に言えば全体像の20%しか分かっていないことを提案している学者が分かっていて)、ヒコーキを飛ばし、墜落して人命を失ったら、社会は「懺悔ではすまない」と言うだろう。それでも、経済学に懺悔が許されるのは、もともと文科系の学問自体が「学問ではなかった」のか、「学問を逸脱する人たちが主流を為していた」のかどちらかと考えられる。たとえば、経済活動として大きな負の結果を出したと言われるリーマンショック(サブプライムローンや多重保障などの経済システム)の中心となったのはノーベル経済学賞を受賞したアメリカの経済学者たちだったのだが、それを考えると経済学とは学問ではないか、知らず知らずのうちに逸脱した学問になってしまったのだろう。・・・・・・・・・ところで、自然科学でも同じようなことが起こったのがタバコ、リサイクル、地球温暖化、そして最近では被曝の問題などである。静かな自然科学の中に突如として「罵倒、バッシング、懺悔」など人間的な要素が持ち込まれた.その様子を見ると、自然科学の専門家以外の人が自然科学者の発言や著作物を罵倒する、新聞がそれに追従する、そのうち、自然科学の専門家の中に「曲学阿世の徒」が現れて事態が混乱するという経過をたどってきた。そのうち、専門以外の人が「事実を隠蔽して対立を煽る」という行動にでる。その背景には、1)思想的、2)金銭的、3)有名になりたい、などがあり、それらは学問的ではないので、到底、従来の学者は太刀打ちできない。たとえば、私自身のことで言えば、地球温暖化について一般的に言われていることと異なることを書いたら、私のウィキベディアが悪意に満ちたものに変わった。ウィキペディアというのは多くの人が「ネットの百科事典」として知られており、それを使って個人を誹謗するという手段に出たのである。この著者はおそらく引用文献、文体から見て東北大学か東大の教師であると推定されるが、私自身は警察ではないので、捜査をすることはできない。実に巧みな方法である。もちろん著者は名前を出さないし、自らウィキペディアを書いたとも公表しない。もちろんやましいからである。ウィキベディアに書き直しを求めたら酷く複雑な手続きを言ってきた。「書き直したいなら、複雑な手続きにそってやれ」と居丈高である。つまり民間の会社が勝手に個人を誹謗する手段を作り、それに苦情を述べる個人に対して「おれの決めたことに従え」というのだから、まったく困ったものである(ぼやきではない)。このような場合、相手は私を誹謗する事だけが目的では無い(私と利害関係はない)。売名などの目的を持っているからなかなか対応が難しく、相手はそれを知って攻撃をしてくる。対立を煽る人というのには共通点があって、まず「人物、人格を攻撃してくる」、そして「事実と違うことを言う」というという二つである。つまり、対立を煽る人というのは、「事実に近づきたい」という私たちの目的とは全く違い、「事実から遠ざかることによって、対立を深めたい」という目的をもっているので、事実の確認や議論はまったく意味をなさないのである.・・・・・・・・・このように社会に「人物、人格を罵倒し、事実を故意に違えて言う」ことによって対立を深め、事態を混乱させたいという行動にでる人たちが居るのは仕方が無いことだろう.まさに「世に盗人の種は尽きまじ」ということだが、もっとも大きな問題は「対立を煽る人」がこの民主主義の社会、学問的な活動が許されている社会の「悪」であるということがまだ確定していないことだ。盗人とは違い、サギ、虚偽、名誉毀損、分かっていないのに分かっていると言う経済学者などは知能的犯罪で、しかもその影響が知的社会では甚大なのにまだ犯罪として認知されなかったり、認知されてもどのような行動が知的犯罪に属するのかの議論が明確では無いことによる。私は、経済学ばかりではなく、医学、環境問題、原発問題などに見られるような知的犯罪について、その定義をハッキリさせ、犯罪として社会的に措置をとることによって、民主主義というものが成長していくと考えている。マスコミの誤報、NHKや朝日新聞の問題も、「知的犯罪」の定義が明確ではないところに根があると考えている。(平成24年8月26日)なるぼとはた坊
2012.08.30
コメント(0)
-
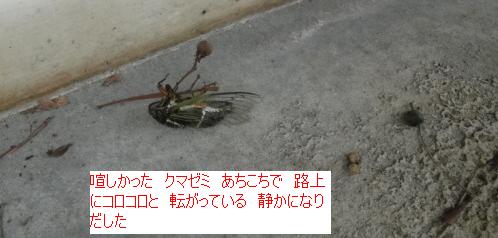
クマゼミ 弱って 道路で転がっている 東日本大震災537日後に
会社にいく途中の道でクマゼミ 弱ったので あちこちに落ちているフラフラの状態になっているが静かになるので こちらは歓迎だなあクマゼミのうるさい事 尋常ではない鳴き声は「シャアシャア・・・」または「ワシワシワシ・・・」と聞きなされる。腹部を激しく上下に動かしてリズムを作り、鳴きながら枝を歩き、また鳴き移りを頻繁にする。非常に活動的な鳴き方をする。音量はかなり大きく力強く、 捕獲したときの悲鳴音は極めて大きくうるさい。晴れていれば、午前中6~7時頃鳴き始めて11時頃鳴き終わり、 午後以降はほとんど鳴かない。これは日照や温度によるというよりも、体力的な原因からと考えた方がよいと思われる。毎日5時間 2週間 大騒音を流し続けて迷惑なセミだこのセミの子孫は また6年後に出てきて 大騒音を立ててくれる見込みやかましーーーい セミだ東日本大震災 3月11日発生08月30日は 既に537日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------対立の構図 対立を煽る人たちと知的犯罪さて、理科系の学問は30年以内には事実が判明してしまうので、無理な「学説」というのは通りにくい。だから、やや対立を避けてみんなで力を合わせて研究をしようということになる。それでも、リサイクルや地球温暖化のように単純な自然科学の活動ではなく、自然科学と社会活動が混在すると、途端にもめ事や言い争いが発生する。時には立派な学者を罵倒する素人(その分野の専門知識が無い人という意味)が出てきたり、逆に立派な学者であっても社会的なことに負けて発言する人(最近では御用学者といい、少し前は曲学阿世の徒と言った)が現れたりするから面倒だ。また、文科系の学問は現在でも2000年以上まえのギリシャ文学、哲学などが研究されているように、「なにが真実か」というのがわかりにくいものが多い。最近の学問でも経済学などは常に対立していて、かなり高名な学者でも「懺悔の書」という名前の「自分の学問は間違っていた」という書籍を出版したりする。自分の「学問的結論を懺悔する」というのは実に矛盾した表現だ。というのは、少なくとも自然科学では「学問的結論」というのは、確定された事実あるいは理論から論理的に導き出された結論であるから、一人の人間が心の問題として「懺悔する」という対象ではないからである。それは単に計算を間違ったとか、論理展開でミスをしたという類いのもので、それほど高級なものではあり得ない。つまり自然科学から見ると学問は頭脳活動だから、懺悔というのはあり得ず、もし懺悔ということがあるなら、それは「故意に実験データをねつ造した」という類いのものである。この経済学者の「懺悔」というのは、「自分に学力が無かった」という意味での懺悔であるが、その学力が無かった人が日本の経済学者のトップが就任するような役職に長く就いて政策の指導を行ってきた。ということは経済学者の多くが彼を支持したことを意味している。ここまで整理をすると一つの簡単な結論が得られる。それは「どうも文科系の学問は、学問的結論が得られるための事実と論理の20%ぐらいしか分かっていないときに、100%分かったような答えを出す」ということだ。なぜ、20%しか進んでいないのに100%の答えを出すかというと「社会に求められるから」ということになる。理科系(特に工学系)の感覚で言えば「5回に4回は墜落するヒコーキでも、社会が欲しいと言うから飛ばす」ということであり、「もし墜落したら懺悔する」という感じである。ヒコーキを運航する時に5回に4回は墜落する可能性があることが分かっていて(学問的に言えば全体像の20%しか分かっていないことを提案している学者が分かっていて)、ヒコーキを飛ばし、墜落して人命を失ったら、社会は「懺悔ではすまない」と言うだろう。それでも、経済学に懺悔が許されるのは、もともと文科系の学問自体が「学問ではなかった」のか、「学問を逸脱する人たちが主流を為していた」のかどちらかと考えられる。たとえば、経済活動として大きな負の結果を出したと言われるリーマンショック(サブプライムローンや多重保障などの経済システム)の中心となったのはノーベル経済学賞を受賞したアメリカの経済学者たちだったのだが、それを考えると経済学とは学問ではないか、知らず知らずのうちに逸脱した学問になってしまったのだろう。・・・・・・・・・ところで、自然科学でも同じようなことが起こったのがタバコ、リサイクル、地球温暖化、そして最近では被曝の問題などである。静かな自然科学の中に突如として「罵倒、バッシング、懺悔」など人間的な要素が持ち込まれた.その様子を見ると、自然科学の専門家以外の人が自然科学者の発言や著作物を罵倒する、新聞がそれに追従する、そのうち、自然科学の専門家の中に「曲学阿世の徒」が現れて事態が混乱するという経過をたどってきた。そのうち、専門以外の人が「事実を隠蔽して対立を煽る」という行動にでる。その背景には、1)思想的、2)金銭的、3)有名になりたい、などがあり、それらは学問的ではないので、到底、従来の学者は太刀打ちできない。たとえば、私自身のことで言えば、地球温暖化について一般的に言われていることと異なることを書いたら、私のウィキベディアが悪意に満ちたものに変わった。ウィキペディアというのは多くの人が「ネットの百科事典」として知られており、それを使って個人を誹謗するという手段に出たのである。この著者はおそらく引用文献、文体から見て東北大学か東大の教師であると推定されるが、私自身は警察ではないので、捜査をすることはできない。実に巧みな方法である。もちろん著者は名前を出さないし、自らウィキペディアを書いたとも公表しない。もちろんやましいからである。ウィキベディアに書き直しを求めたら酷く複雑な手続きを言ってきた。「書き直したいなら、複雑な手続きにそってやれ」と居丈高である。つまり民間の会社が勝手に個人を誹謗する手段を作り、それに苦情を述べる個人に対して「おれの決めたことに従え」というのだから、まったく困ったものである(ぼやきではない)。このような場合、相手は私を誹謗する事だけが目的では無い(私と利害関係はない)。売名などの目的を持っているからなかなか対応が難しく、相手はそれを知って攻撃をしてくる。対立を煽る人というのには共通点があって、まず「人物、人格を攻撃してくる」、そして「事実と違うことを言う」というという二つである。つまり、対立を煽る人というのは、「事実に近づきたい」という私たちの目的とは全く違い、「事実から遠ざかることによって、対立を深めたい」という目的をもっているので、事実の確認や議論はまったく意味をなさないのである.・・・・・・・・・このように社会に「人物、人格を罵倒し、事実を故意に違えて言う」ことによって対立を深め、事態を混乱させたいという行動にでる人たちが居るのは仕方が無いことだろう.まさに「世に盗人の種は尽きまじ」ということだが、もっとも大きな問題は「対立を煽る人」がこの民主主義の社会、学問的な活動が許されている社会の「悪」であるということがまだ確定していないことだ。盗人とは違い、サギ、虚偽、名誉毀損、分かっていないのに分かっていると言う経済学者などは知能的犯罪で、しかもその影響が知的社会では甚大なのにまだ犯罪として認知されなかったり、認知されてもどのような行動が知的犯罪に属するのかの議論が明確では無いことによる。私は、経済学ばかりではなく、医学、環境問題、原発問題などに見られるような知的犯罪について、その定義をハッキリさせ、犯罪として社会的に措置をとることによって、民主主義というものが成長していくと考えている。マスコミの誤報、NHKや朝日新聞の問題も、「知的犯罪」の定義が明確ではないところに根があると考えている。(平成24年8月26日)なるぼとはた坊
2012.08.30
コメント(0)
-
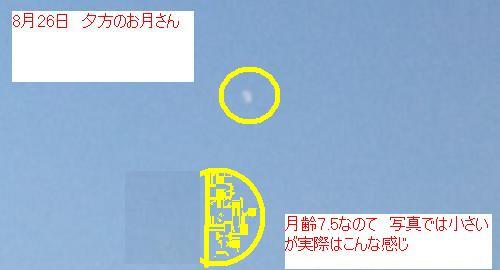
日曜の夕方のお月さん 写真では小さいな 東日本大震災537日後に
日曜の夕方のお月さん 右の半分の形だなあ月をみても ああ 綺麗だなあで お終いはた坊は何も考えていないが 古代ギリシア 古代ギリシアの人々は、月をすでに観察していて、月食が起きるのは満月の時であること、また月食時に月の表面に丸い影が徐々に現れることを観察して、それらのことからその影というのは自分たちの住む地の影で、地は球体であると推定したといい、アリストテレースの時代(紀元前4世紀ころ)には、その知識はギリシア世界では広くゆきわたっていたという。へーーえ古代のギリシャの人は 月をみて 地球が丸いと知っていたとかなんとか wikiに書かれているへーえ 2400年前の人も 偉かったんだなあ東日本大震災 3月11日発生08月30日は 既に537日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------対立の構図 対立を煽る人たちと知的犯罪さて、理科系の学問は30年以内には事実が判明してしまうので、無理な「学説」というのは通りにくい。だから、やや対立を避けてみんなで力を合わせて研究をしようということになる。それでも、リサイクルや地球温暖化のように単純な自然科学の活動ではなく、自然科学と社会活動が混在すると、途端にもめ事や言い争いが発生する。時には立派な学者を罵倒する素人(その分野の専門知識が無い人という意味)が出てきたり、逆に立派な学者であっても社会的なことに負けて発言する人(最近では御用学者といい、少し前は曲学阿世の徒と言った)が現れたりするから面倒だ。また、文科系の学問は現在でも2000年以上まえのギリシャ文学、哲学などが研究されているように、「なにが真実か」というのがわかりにくいものが多い。最近の学問でも経済学などは常に対立していて、かなり高名な学者でも「懺悔の書」という名前の「自分の学問は間違っていた」という書籍を出版したりする。自分の「学問的結論を懺悔する」というのは実に矛盾した表現だ。というのは、少なくとも自然科学では「学問的結論」というのは、確定された事実あるいは理論から論理的に導き出された結論であるから、一人の人間が心の問題として「懺悔する」という対象ではないからである。それは単に計算を間違ったとか、論理展開でミスをしたという類いのもので、それほど高級なものではあり得ない。つまり自然科学から見ると学問は頭脳活動だから、懺悔というのはあり得ず、もし懺悔ということがあるなら、それは「故意に実験データをねつ造した」という類いのものである。この経済学者の「懺悔」というのは、「自分に学力が無かった」という意味での懺悔であるが、その学力が無かった人が日本の経済学者のトップが就任するような役職に長く就いて政策の指導を行ってきた。ということは経済学者の多くが彼を支持したことを意味している。ここまで整理をすると一つの簡単な結論が得られる。それは「どうも文科系の学問は、学問的結論が得られるための事実と論理の20%ぐらいしか分かっていないときに、100%分かったような答えを出す」ということだ。なぜ、20%しか進んでいないのに100%の答えを出すかというと「社会に求められるから」ということになる。理科系(特に工学系)の感覚で言えば「5回に4回は墜落するヒコーキでも、社会が欲しいと言うから飛ばす」ということであり、「もし墜落したら懺悔する」という感じである。ヒコーキを運航する時に5回に4回は墜落する可能性があることが分かっていて(学問的に言えば全体像の20%しか分かっていないことを提案している学者が分かっていて)、ヒコーキを飛ばし、墜落して人命を失ったら、社会は「懺悔ではすまない」と言うだろう。それでも、経済学に懺悔が許されるのは、もともと文科系の学問自体が「学問ではなかった」のか、「学問を逸脱する人たちが主流を為していた」のかどちらかと考えられる。たとえば、経済活動として大きな負の結果を出したと言われるリーマンショック(サブプライムローンや多重保障などの経済システム)の中心となったのはノーベル経済学賞を受賞したアメリカの経済学者たちだったのだが、それを考えると経済学とは学問ではないか、知らず知らずのうちに逸脱した学問になってしまったのだろう。・・・・・・・・・ところで、自然科学でも同じようなことが起こったのがタバコ、リサイクル、地球温暖化、そして最近では被曝の問題などである。静かな自然科学の中に突如として「罵倒、バッシング、懺悔」など人間的な要素が持ち込まれた.その様子を見ると、自然科学の専門家以外の人が自然科学者の発言や著作物を罵倒する、新聞がそれに追従する、そのうち、自然科学の専門家の中に「曲学阿世の徒」が現れて事態が混乱するという経過をたどってきた。そのうち、専門以外の人が「事実を隠蔽して対立を煽る」という行動にでる。その背景には、1)思想的、2)金銭的、3)有名になりたい、などがあり、それらは学問的ではないので、到底、従来の学者は太刀打ちできない。たとえば、私自身のことで言えば、地球温暖化について一般的に言われていることと異なることを書いたら、私のウィキベディアが悪意に満ちたものに変わった。ウィキペディアというのは多くの人が「ネットの百科事典」として知られており、それを使って個人を誹謗するという手段に出たのである。この著者はおそらく引用文献、文体から見て東北大学か東大の教師であると推定されるが、私自身は警察ではないので、捜査をすることはできない。実に巧みな方法である。もちろん著者は名前を出さないし、自らウィキペディアを書いたとも公表しない。もちろんやましいからである。ウィキベディアに書き直しを求めたら酷く複雑な手続きを言ってきた。「書き直したいなら、複雑な手続きにそってやれ」と居丈高である。つまり民間の会社が勝手に個人を誹謗する手段を作り、それに苦情を述べる個人に対して「おれの決めたことに従え」というのだから、まったく困ったものである(ぼやきではない)。このような場合、相手は私を誹謗する事だけが目的では無い(私と利害関係はない)。売名などの目的を持っているからなかなか対応が難しく、相手はそれを知って攻撃をしてくる。対立を煽る人というのには共通点があって、まず「人物、人格を攻撃してくる」、そして「事実と違うことを言う」というという二つである。つまり、対立を煽る人というのは、「事実に近づきたい」という私たちの目的とは全く違い、「事実から遠ざかることによって、対立を深めたい」という目的をもっているので、事実の確認や議論はまったく意味をなさないのである.・・・・・・・・・このように社会に「人物、人格を罵倒し、事実を故意に違えて言う」ことによって対立を深め、事態を混乱させたいという行動にでる人たちが居るのは仕方が無いことだろう.まさに「世に盗人の種は尽きまじ」ということだが、もっとも大きな問題は「対立を煽る人」がこの民主主義の社会、学問的な活動が許されている社会の「悪」であるということがまだ確定していないことだ。盗人とは違い、サギ、虚偽、名誉毀損、分かっていないのに分かっていると言う経済学者などは知能的犯罪で、しかもその影響が知的社会では甚大なのにまだ犯罪として認知されなかったり、認知されてもどのような行動が知的犯罪に属するのかの議論が明確では無いことによる。私は、経済学ばかりではなく、医学、環境問題、原発問題などに見られるような知的犯罪について、その定義をハッキリさせ、犯罪として社会的に措置をとることによって、民主主義というものが成長していくと考えている。マスコミの誤報、NHKや朝日新聞の問題も、「知的犯罪」の定義が明確ではないところに根があると考えている。(平成24年8月26日)なるぼとはた坊
2012.08.30
コメント(0)
-

キュウリ 今週は1本のみ 東日本大震災536日後に
今年もきゅうりhcでの苗は売っているが まだ寒そうとりあえず 種のほうは買っておいた苗は来週くらいにしようかな ???04月22日 hcで苗を探しに行く 小さいが北進があったので6個をかっておく 植え付け04月28日 苗は畑で無事だ サイズは変わらず 05月06日 まあまあ すこしは成長しつつある05月20日 上に伸びてきている 支柱が必要05月27日 支柱をつけておく ついでに小さいキュウリを収穫しておく06月01日 2回目の収穫は2本を06月03日 3回目の収穫は4本06月06日 4回目の収穫は6本06月10日 5回目の収穫は3本06月13日 6回目の収穫は5本06月17日 7回目の収穫は8本06月20日 8回目の収穫は8本06月23日 9回目の収穫は6本06月26日 10回目の収穫は4本06月29日 11回目の収穫は10本07月01日 12回目の収穫は02本07月04日 13回目の収穫は05本07月08日 14回目の収穫は04本07月11日 15回目の収穫は10本07月14日 16回目の収穫は08本種まき 第二弾04月22日 同時に種まきを開始しておく 8potsを04月28日 1個の芽が出てきている しめしめ05月06日 g-10の畑に移動した05月20日 8本ともに無事 すこし成長した05月27日 蔓が延びてきている06月06日 第二弾のキュウリの生長も開始 実もそろそろかも06月17日 かなり横に横に伸びてきている 実も小さいがついている06月23日 1回目の収穫 19本もあった 多すぎだなあ06月26日 2回目の収穫 11本06月29日 3回目の収穫 20本07月01日 4回目の収穫 07本07月04日 5回目の収穫 15本07月08日 6回目の収穫 16本07月11日 7回目の収穫は10本07月19日 8回目の収穫は08本第三弾のキュウリ05月27日 庭で種まきをしておいた06月02日 発芽した06月06日 次に日曜には畑に移動しよう06月10日 畑に移動 m-06の畑に植え付けた07月08日 蔓は延びてきている07月19日 1回目の収穫 12本07月28日 2回目の収穫 07本 落ち着いてきている第四弾の種まき06月10日 庭で8potに種まきをしておいた06月15日 発芽してきている06月23日 畑に移動 g-22に植え付けておいた07月08日 5本くらいは 無事第五弾は会社で種まき08月09日 会社で通行人からキュウリの種をもらう08月10日 もらった種 会社の土に植えておく08月13日 発芽した08月19日 双葉になっているが 育つかな ????08月28日 追肥しておいた 収穫した分は 第一弾 5月27日から 合計で5+2+4+6+3+5+8+8+6+4+10+2+5+4+10+8+8+6=104本第二弾 6月23日から 合計で19+11+20+07+15+16+10+8+10=116本第三弾 7月19日から 合計で12+2+7+5+10 =36本第四弾 8月04日から 合計で1+2+1 =4本第五弾 キュウリ 次は第4弾の分 そろそろ お終いかな ????第五弾を育てているが これは会社で育てている 実がつくかな ?????東日本大震災 3月11日発生08月29日は 既に536日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------尖閣、竹島、四島・・・領土と国(1) 台湾尖閣列島、竹島、そして根室四島(北方四島という呼び名はいかにも「日本ではない」という感じがするので、ここでは根室四島と呼ぶ)が注目を集めています。そこで、この問題を整理することにしました。「領土」と言うからには、その前提として「国」がなければならないのは当然です。そして、日本に住んでいると歴史が長いことと、四方が海なので国というのは「大昔からあるもの」と考えがちですが、世界では「国」や「国境」がハッキリしている方が珍しいということをまずは頭に入れなければなりません。その意味で「固有の国土」などというものはほとんど無いのです。たとえば、台湾ですが、明治初期の台湾は「清」という中国の国が軍隊を派遣していましたが、「清の国土」なのか「清の勢力範囲」なのかはハッキリしていませんでした。明治4年に琉球王国のご用船が難破して台湾に漂着した時、乗員69人の内、54名が斬首されるという事件がありました。今の常識では考えられませんが、「今の常識」はまさに「今の常識」であり、これを歴史的なことにそのまま適応するのは不適切です。ともかく、琉球王国も「国かどうかハッキリしない」という時期だったので、琉球政府に代わって日本政府がこの事件について清に賠償を求めます。難破して漂着した人を殺害するのですから、もし「国」であればその国の政府が賠償しなければなりません。ところが清は「台湾の中国人がやったのなら別だが、現地人がやったのだから俺には責任がない」と回答しました。この回答でわかることは台湾は清のものではなく清の一部が台湾に駐留していたということです。私たちは現代人ですから、どうしても「どこの国か?」と聞きたくなりますが、昔(たった150年ほど前)でも、「地域」があっても「国」ではないところは多かったのです。かくして紆余曲折はあったのですが、日本軍が台湾に上陸して報復します。ところが、中国の守備隊は台湾を守るのではなく、台湾の人を殺戮し、台北を放棄して逃げてしまいます。このことも、台湾は「清の領土」ではなく「清の軍隊が駐留していた」と言うことを示します。後に整理しますが、「中国」というのは「地域」の名称であって、「中国」という「国」ができたのは共産党が中国を統一したごく最近の事です。建国は1949年ですからまだ60年ほどしか経っていません。これは政治的な意味合いではなく学問的な解釈で、詳しくは歴史学者宮脇先生とシアターテレビジョンの「現代のコペルニクス」で詳しく解説をしています。結局、台湾は歴史的に「国」であったことはなく、日本と清の間の戦争(日清戦争)のあとの下関条約で「清の統治下」から「日本の統治下」に入り、まもなく1915年に「内地延長主義」、つまりそれまでの「植民地統治」から「日本国の延長」ということにかわり、歴史的にははじめて台湾は「日本国」という国の一部になったのです。私が「日本国は千島列島(占守島)から台湾まで」と言っているのは、政治的とか、良い悪いではなく、単純に歴史的には有史以来、台湾が国になったのは日本国の一部になってからという意味です。たとえば、アメリカ合衆国というのは最初は北アメリカの一部に13州を作って独立したのですが、その後、西に進み、インディアンやメキシコなどと戦って、州を増やして今のアメリカ大陸の「国」ができたのです。カリフォルニアがアメリカ合衆国の一部であるということと同じく、台湾は日本であるということになります。その後、日本が戦争に負けて台湾を放棄し、そのすぐ後(日本が降伏した1945年8月の2ヶ月後)、中華民国という国(中国ではない)が台湾に進駐して「実効支配」している状態です。200年前の状態という意味では台湾は台湾人(中国は台湾を植民地にしていたので、インドとイギリスの関係と同じ)のもの、100年前というと日本国、そして50年前というと誰のものでもないということになります。もし、台湾をもともとの人に返すということなら台湾人(1945年に移ってきた中華民国人ではなく、もともとの台湾人)という事になります。もちろん、領土は政治的、感情的なものですから、このようなことを言うと日本を支持してくれている今の台湾の人からも文句を言われますが、歴史的にはこのような事だったということです。そうなると、台湾と琉球の間で台湾に近い尖閣諸島は誰のものなのでしょうか?少し長くなりましたので、また書きます。(平成24年8月28日なるほど だなはた坊
2012.08.29
コメント(1)
-

緑のカボチャ 3個を追加で収穫した 東日本大震災536日後に
2011年今年は苗を2本かってきて畑においておく04月23日 hcで苗が売られていたので2本買っておく04月30日 畑に植えておく m-06の畑の畝に05月08日 その後 そのまま 成長はまだ始まらないまま ??05月22日 かぼちゃの蔓が延びている2本 花も付き出した06月05日 小さい実があちこちについてきている 楽しみだなあ昨年は作らなかったので 今年は2本のみ 場所もあるので 育ててみようそろそろ 実も付いてきそう 楽しみだあーーー06月19日 かぼちゃ 2個の実が付いている まだまだ たくさん出来そうだ06月26日 かぼちゃ 3個の実がついている かなり大きくなっている07月03日 かぼちゃ 3個の実はどんどん大きくなっている 昨年は7月12日に収穫07月10日 かぼちゃ 1個を収穫した 07月17日 かぼちゃ 2個を収穫した これで 終了 かぼちゃは撤去しよう 今年のかぼちゃは 3個にて終了したあーーー終了したはずのかぼちゃツルが残っていて また 伸びだしたm-07の畑の畝の端っこにツルが伸びていて また 実が2個ついている07月24日 m-07の畝の端っこに かぼちゃのつるが延びている07月31日 また実が2個ついてきている もう少しは様子を見てみよう08月07日 追加で2個のかぼちゃも収穫をしておいた08月21日 最後に収穫 1個と思っていたら4個もあった びっくりだなあ日曜に収穫して かぼちゃも 終了した 合計で9個となった2012年今年もまずは2本から m-0705月13日 HCで2本かってきておいた05月20日 なんとか2本 無事だけと やや貧弱になっている05月27日 まだ無事 okとしよう m-07の畑に植えている06月24日 やっと成長してきている あちこちに蔓が延びて 元気が良い07月01日 通路をあちこちと走りまわっている 茂りすぎになってきている07月08日 実がつきだした 07月22日 緑の実がついている07月28日 緑のかぼちゃ3個を収穫した07月29日 緑のカボチャ7個を収穫08月05日 緑1個の収穫08月11日 緑が1個08月26日 緑が3個 また収穫したg-2206月24日 こぼれ種からの発芽したかぼちゃ 3本ある 1本は伸びて大きい 2本は小さい07月01日 1本は通路を成長して伸びている 小さいのもそろそろ成長しつつある07月08日 蔓があちこちと延びてきている07月22日 白い実がついている07月28日 白のかぼちゃ 1個を収穫した07月29日 白が2個 収穫した08月05日 白が1個かぼちゃ緑が15個収穫した白は4個の収穫をした合計で19個 かなり沢山の収穫となった白いカボチャ品種をnetでみたら タキイのカボチャ夢味 ユメミ 良食味で栽培容易! 果皮が美麗な白皮カボチャ! 東日本大震災 3月11日発生08月29日は 既に536日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------尖閣、竹島、四島・・・領土と国(1) 台湾尖閣列島、竹島、そして根室四島(北方四島という呼び名はいかにも「日本ではない」という感じがするので、ここでは根室四島と呼ぶ)が注目を集めています。そこで、この問題を整理することにしました。「領土」と言うからには、その前提として「国」がなければならないのは当然です。そして、日本に住んでいると歴史が長いことと、四方が海なので国というのは「大昔からあるもの」と考えがちですが、世界では「国」や「国境」がハッキリしている方が珍しいということをまずは頭に入れなければなりません。その意味で「固有の国土」などというものはほとんど無いのです。たとえば、台湾ですが、明治初期の台湾は「清」という中国の国が軍隊を派遣していましたが、「清の国土」なのか「清の勢力範囲」なのかはハッキリしていませんでした。明治4年に琉球王国のご用船が難破して台湾に漂着した時、乗員69人の内、54名が斬首されるという事件がありました。今の常識では考えられませんが、「今の常識」はまさに「今の常識」であり、これを歴史的なことにそのまま適応するのは不適切です。ともかく、琉球王国も「国かどうかハッキリしない」という時期だったので、琉球政府に代わって日本政府がこの事件について清に賠償を求めます。難破して漂着した人を殺害するのですから、もし「国」であればその国の政府が賠償しなければなりません。ところが清は「台湾の中国人がやったのなら別だが、現地人がやったのだから俺には責任がない」と回答しました。この回答でわかることは台湾は清のものではなく清の一部が台湾に駐留していたということです。私たちは現代人ですから、どうしても「どこの国か?」と聞きたくなりますが、昔(たった150年ほど前)でも、「地域」があっても「国」ではないところは多かったのです。かくして紆余曲折はあったのですが、日本軍が台湾に上陸して報復します。ところが、中国の守備隊は台湾を守るのではなく、台湾の人を殺戮し、台北を放棄して逃げてしまいます。このことも、台湾は「清の領土」ではなく「清の軍隊が駐留していた」と言うことを示します。後に整理しますが、「中国」というのは「地域」の名称であって、「中国」という「国」ができたのは共産党が中国を統一したごく最近の事です。建国は1949年ですからまだ60年ほどしか経っていません。これは政治的な意味合いではなく学問的な解釈で、詳しくは歴史学者宮脇先生とシアターテレビジョンの「現代のコペルニクス」で詳しく解説をしています。結局、台湾は歴史的に「国」であったことはなく、日本と清の間の戦争(日清戦争)のあとの下関条約で「清の統治下」から「日本の統治下」に入り、まもなく1915年に「内地延長主義」、つまりそれまでの「植民地統治」から「日本国の延長」ということにかわり、歴史的にははじめて台湾は「日本国」という国の一部になったのです。私が「日本国は千島列島(占守島)から台湾まで」と言っているのは、政治的とか、良い悪いではなく、単純に歴史的には有史以来、台湾が国になったのは日本国の一部になってからという意味です。たとえば、アメリカ合衆国というのは最初は北アメリカの一部に13州を作って独立したのですが、その後、西に進み、インディアンやメキシコなどと戦って、州を増やして今のアメリカ大陸の「国」ができたのです。カリフォルニアがアメリカ合衆国の一部であるということと同じく、台湾は日本であるということになります。その後、日本が戦争に負けて台湾を放棄し、そのすぐ後(日本が降伏した1945年8月の2ヶ月後)、中華民国という国(中国ではない)が台湾に進駐して「実効支配」している状態です。200年前の状態という意味では台湾は台湾人(中国は台湾を植民地にしていたので、インドとイギリスの関係と同じ)のもの、100年前というと日本国、そして50年前というと誰のものでもないということになります。もし、台湾をもともとの人に返すということなら台湾人(1945年に移ってきた中華民国人ではなく、もともとの台湾人)という事になります。もちろん、領土は政治的、感情的なものですから、このようなことを言うと日本を支持してくれている今の台湾の人からも文句を言われますが、歴史的にはこのような事だったということです。そうなると、台湾と琉球の間で台湾に近い尖閣諸島は誰のものなのでしょうか?少し長くなりましたので、また書きます。(平成24年8月28日なるほど だなはた坊
2012.08.29
コメント(2)
-

お米 穂が入りだしている 新米ができつつある 東日本大震災536日後に
m07の貸し農園の隣の水田お米の穂が入りだした順調に育っている猛暑だけど お米は着実に育っている一方で 子供が米つくりしなくなって 雑草だらけの水田も出てきているg-22の畑の横の水田は 遺産相続でもめていて 米作りも何故かストップしているもめていても米をつくれば良いのに 喧嘩となつて 米作りができていないもったいないな 使わない畑なら はた坊に貸してくれればうれしいのになあ????東日本大震災 3月11日発生08月29日は 既に536日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------尖閣、竹島、四島・・・領土と国(1) 台湾尖閣列島、竹島、そして根室四島(北方四島という呼び名はいかにも「日本ではない」という感じがするので、ここでは根室四島と呼ぶ)が注目を集めています。そこで、この問題を整理することにしました。「領土」と言うからには、その前提として「国」がなければならないのは当然です。そして、日本に住んでいると歴史が長いことと、四方が海なので国というのは「大昔からあるもの」と考えがちですが、世界では「国」や「国境」がハッキリしている方が珍しいということをまずは頭に入れなければなりません。その意味で「固有の国土」などというものはほとんど無いのです。たとえば、台湾ですが、明治初期の台湾は「清」という中国の国が軍隊を派遣していましたが、「清の国土」なのか「清の勢力範囲」なのかはハッキリしていませんでした。明治4年に琉球王国のご用船が難破して台湾に漂着した時、乗員69人の内、54名が斬首されるという事件がありました。今の常識では考えられませんが、「今の常識」はまさに「今の常識」であり、これを歴史的なことにそのまま適応するのは不適切です。ともかく、琉球王国も「国かどうかハッキリしない」という時期だったので、琉球政府に代わって日本政府がこの事件について清に賠償を求めます。難破して漂着した人を殺害するのですから、もし「国」であればその国の政府が賠償しなければなりません。ところが清は「台湾の中国人がやったのなら別だが、現地人がやったのだから俺には責任がない」と回答しました。この回答でわかることは台湾は清のものではなく清の一部が台湾に駐留していたということです。私たちは現代人ですから、どうしても「どこの国か?」と聞きたくなりますが、昔(たった150年ほど前)でも、「地域」があっても「国」ではないところは多かったのです。かくして紆余曲折はあったのですが、日本軍が台湾に上陸して報復します。ところが、中国の守備隊は台湾を守るのではなく、台湾の人を殺戮し、台北を放棄して逃げてしまいます。このことも、台湾は「清の領土」ではなく「清の軍隊が駐留していた」と言うことを示します。後に整理しますが、「中国」というのは「地域」の名称であって、「中国」という「国」ができたのは共産党が中国を統一したごく最近の事です。建国は1949年ですからまだ60年ほどしか経っていません。これは政治的な意味合いではなく学問的な解釈で、詳しくは歴史学者宮脇先生とシアターテレビジョンの「現代のコペルニクス」で詳しく解説をしています。結局、台湾は歴史的に「国」であったことはなく、日本と清の間の戦争(日清戦争)のあとの下関条約で「清の統治下」から「日本の統治下」に入り、まもなく1915年に「内地延長主義」、つまりそれまでの「植民地統治」から「日本国の延長」ということにかわり、歴史的にははじめて台湾は「日本国」という国の一部になったのです。私が「日本国は千島列島(占守島)から台湾まで」と言っているのは、政治的とか、良い悪いではなく、単純に歴史的には有史以来、台湾が国になったのは日本国の一部になってからという意味です。たとえば、アメリカ合衆国というのは最初は北アメリカの一部に13州を作って独立したのですが、その後、西に進み、インディアンやメキシコなどと戦って、州を増やして今のアメリカ大陸の「国」ができたのです。カリフォルニアがアメリカ合衆国の一部であるということと同じく、台湾は日本であるということになります。その後、日本が戦争に負けて台湾を放棄し、そのすぐ後(日本が降伏した1945年8月の2ヶ月後)、中華民国という国(中国ではない)が台湾に進駐して「実効支配」している状態です。200年前の状態という意味では台湾は台湾人(中国は台湾を植民地にしていたので、インドとイギリスの関係と同じ)のもの、100年前というと日本国、そして50年前というと誰のものでもないということになります。もし、台湾をもともとの人に返すということなら台湾人(1945年に移ってきた中華民国人ではなく、もともとの台湾人)という事になります。もちろん、領土は政治的、感情的なものですから、このようなことを言うと日本を支持してくれている今の台湾の人からも文句を言われますが、歴史的にはこのような事だったということです。そうなると、台湾と琉球の間で台湾に近い尖閣諸島は誰のものなのでしょうか?少し長くなりましたので、また書きます。(平成24年8月28日なるほど だなはた坊
2012.08.29
コメント(0)
-

ニラ 猛暑でも ニラサンだけは元気 東日本大震災535日後に
昨年 ニラの収穫の予定今年は3月から どんどんと収穫している庭のニラ あちこち どんどん葉が出てきている-収穫中g-22 ここも発芽してきた 3月6日m-08 発芽してきたのは2月28日庭のニラ たくさんあるのでどんどん収穫収穫3月05日 初の収穫をした 今年は早いぞ3月12日 2回目の収穫をした3月20日 3回目の収穫をした3月27日 4回目の収穫をした4月03日 5回目の収穫をした4月12日 6回目の収穫をした4月20日 7回目の収穫をした4月28日 8回目の収穫をした5月08日 9回目の収穫をした5月22日 10回目の収穫をした5月29日 11回目の収穫をした6月05日 12回目の収穫をした6月12日 13回目の収穫をした6月26日 14回目の収穫をした7月03-10-17-24-31日 収穫しなかった8月07日 15回目の収穫をした8月21日 花の蕾があちこちに出てきている8月28日 g22のニラ 3wkでやっと回復した しかし花蕾だらけになってきている9月18日 m08のニラ 収穫をしておいたニラは元気だなあ3月-4回4月-4回5月-3回6月-3回と もう14回の収穫をした7月- 0回 7月は収穫していない さすがに ニラも多すぎた感じになっている8月- 1回 これで15回目の収穫 g229月- 1回 これで16回目の収穫 m0810月 -1回 これで17回目の収穫 g-2211月 -m08の分 まだ冷蔵庫に在庫があるので 収穫はしなかった12月 -庭のニラ すこし収穫した 1回 合計で18回の収穫をした 今年 01月09日 m08のニラは枯れ草になっていたニラが枯れてしまった 在庫はなしになった次は3月になると 新芽が出るだろう02月26日 ニラ 新芽が出てきている 春だなあ そろそろ青くなってきてくれそう03月04日 ニラ 新芽が増えてきている 早く青くなれーーーーー03月18日 ニラ かなり前面に芽が出てきている今年のニラ 収穫は4月から 開始だなあ04月08日 今年の収穫は1回目となる 初の収穫だけど 昨年より遅い04月22日 2回目の収穫した05月03日 3回目の収穫をした05月13日 4回目の収穫をした05月20日 5回目の収穫をした06月10日 6回目の収穫をした06月30日 7回目の収穫をした07月08日 8回目の収穫をした07月15日 9回目の収穫をした07月22日 10回目の収穫をした08月05日 11回目の収穫をした08月12日 12回目の収穫をした08月19日 13回目の収穫をした08月26日 14回目の収穫をしたにら 庭にもあるので 便利 いつでも収穫 どんどん 食べよう猛暑だけど ニラは元気に育っているすばらしーーーい すんばらしーーい東日本大震災 3月11日発生08月28日は 既に535日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------1978年、1988年、そして1998年1978年の気象観測人工衛星、1988年のハンセン証言、そしえ1998年の気温急上昇と10年ごとに温暖化でエポックがありました。科学を長くやっていると、自然というのが実に複雑で到底、人間の頭で考えられるようなものではないことに常に気づかされます。私が温暖化に冷ややかなのは、自然を理解できない人間はこれから寒冷化するか温暖化するか分からないのに、温暖化対策などをすると私たちの孫は「寒さと農業の不作」で酷い目に遭うのではないかと心配しているからです。1988年の少し前、アメリカは天候が不順で、干ばつ、寒い夏などが続き農業はとても困っていました。その頃はまだ「バイオ燃料」などはなかったので、食料を燃料にするなどという大胆なことは行われていませんでした。だから、値段は上がらず、収穫は少ないというような状態が続いていました。このグラフは1980年代のアメリカ農業がいかに不調だったかを示したものです。そして、いよいよ1988年が訪れます。この年、気象庁の言い方では「過去に経験の無いほどの干ばつ」に見舞われた(本当は20,30年に一度はあるのですが)北アメリカはトウモロコシの収穫が実に20%も減りました。2012年8月、アメリカのトウモロコシの不調が話題になっていますが、14%の不作ですから、1988年よりは良い方です。(テレビでは「歴史的な不作」と言っていましたが、勉強していないのでしょう。最近、気象庁やテレビが豪雨や台風で極端に強い言葉を使っています。今日は沖縄に来た台風15号について「史上最強」といっていましたが、本当は「2003年の台風14号と同じ規模」のものを「史上最強」と表現しているようです。)そこで、上院議員、テレビ局、銀行資本が手を組んで、一騒ぎをおこします。それが1988年6月23日にアメリカ上院で開かれた「気象変動の公聴会」でした。5月のシカゴ商品相場の動きを見て、さらに6月23日というワシントンで有名な「熱い特異日」を公聴会の日に選び、それに加えて朝早く議会に来た担当者が冷房を切るという丁寧な作戦を組んだのが成功して、ものすごく熱い議場の中でNASAのハンセン博士が証言したときのグラフがこのグラフです。それから23年経った今では、温暖化の予測がまったく外れたことを示しています。科学的根拠がなかったからです。しかし彼は「もし、これから世界が協調してCO2を減らさなければ世界の気温はさらにあがり、気候が変動して大変なことになる」と演説し、それを受けて農業議員が「工業がだすCO2が原因だから、農業に金を回せ」と工作をします。これが地球温暖化騒動のもとでした。しかし、自然と人間の関係は実におもしろいものです。ハンセンが証言した1988年以後、二つのことが起こったのです。一つが「気温が上がらなくなった」ということ、もう一つが「農業が好調になった」ということでした。「夜明け前がもっとも暗い」とはよく言ったものです。ところが、この話を聞いて「しめた!」と思った人は多かったのです。まずゴア元副大統領は「これは原子力に有利」、サッチャー元イギリス首相は「北海油田の後、原子力をしなければ」、ヨーロッパは「アジアの植民地を失って困っていたが、これこそアジアの発展を止められる」、日本の橋本元首相「政治的に苦しい情勢を打破できる」、環境省は「このビッグテーマで環境庁と省にするぞ」、環境産業「3兆円の利権だ」と言うことになったのです。かくして人間社会は温暖化騒動でわいたのですが、地球は人間の言う事を聞いてはくれません。CO2の温暖化なら真っ先に気温が上がるはずの人工衛星で測定した上空の気温はいっこうにあがらなかったのです。でも突然、1998年だけ上がったのですが、この理由は何でしょうか?もともとCO2によって気温が上がるならだらだらと上がるはずですし、まして「急激に下がる」などということは起こらないのですから、この変化はどうにも説明できなかったのです。数1000メートル上空の気温が半年から1年だけ上がってまた元に戻るなど言うことが起こるには、なにか全く別のことを考えなければならないからです。ところが、その頃、日本の四国沖でも不思議なことが起こっていました。黒潮の水温はペルー沖の影響を受けて少し高くなっていましたが1988年になって急激にあがり、また下がったのです(高知大学論文による)。この水温の上昇で温帯性の藻類が高知の沿岸から消えて、熱帯性の藻類に変わったのです。この現象を「CO2による温暖化のせい」と新聞などが報じました。マスコミがいい加減であることは、ここで特に書くまでもないですが、CO2によって上がる温度は大気ですから、大気の温度が上がって海水温が突如、上昇するということはありません。空気から水への伝熱量は物理的に分かってみるものでとても小さいからです。また温暖化というのは水温が上がったり下がったりするものではなく、徐々にあがるのです。そうすると、上空の気温でも、海水温でもこの1998年の急上昇は温暖化とは別の原因としなければなりません。また、上空と海水温の両方を同時に説明できるものでなければならないのも当然です。ところで「温暖化騒動」が社会に出てきた頃には多くの人は「これまで地球の気温はどのように変化し、何が問題だったか」について欲知らなかったのは当然ですが、すでに20年ほど経ったので、そろそろ「冷静に歴史を振り返る」ことも必要と思います。このグラフは今から40万年ほど前からの地球の気温の変化で、だいたい12万年ごとに暖かくなったり(間氷期)、寒くなったり(氷期)しています。氷期になると北極海から台湾ぐらいまでがすべて氷河に覆われますから、日本列島は誰も住めないでしょう。もし今までの寒暖の周期がこれからも続くなら(その可能性が最も高い)、しばらくすると気温はドンドン下がっていくはずなのです。「厳冬の前の小春日和をなぜ怖がるのか?」と言ったのはアメリカの物理学者ですが、私も温暖化について同じ心配をしているのです。この12万年の周期より短い周期が500年で、ローマ帝国の東西分裂、ノルマンディーの北方進出、世界的な戦国時代、そして今の温暖化騒動と、過去に500年ごとの変化があり、そのたびにアルプスの氷河は頂上まで融けてはまた麓まで進むということをくり返しています。グリーンランドの氷も同じです。このブログで再三、指摘していますが、科学的なことで知らない人を脅しお金を取る・・・ということはこの温暖化ばかりではなく「町にゴミがあふれるからリサイクル」、「東海地方に地震が来るから耐震補強」、「タバコを吸うと肺がんになる」など枚挙にいとまがありません。専門家がその魂と誠実さを失ったのはヨーロッパで1920年と言われていますが、日本こそが専門家の魂(武士の魂)と誠実さ(日本人の誠)を保ってもらいたいものです。(平成24年8月27日)ふむふむはた坊
2012.08.28
コメント(0)
-
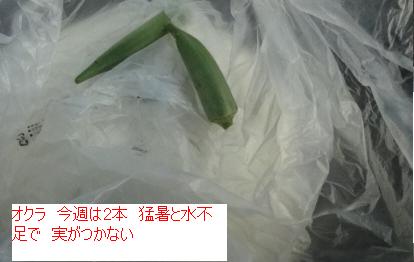
オクラ 今週も2個のみ 東日本大震災535日後に
昨年のオクラ5月03日 種まきした 昨年の保存した種5月15日 まだ 発芽しない5月22日 まだ 発芽しない 種みるが そのまま 発芽しないようだなあ ???今年の発芽は どうも失敗となったみたい 種の保存がよくなかったのかな ??種を買ってきて 再度 種まきをしよう5月22日 種をかってきて再度の種まきをした5月28日 まだ発芽していない 遅いなあ5月30日 発芽した おお 結構と時間がかかるが カバーもしているので okだ06月05日 畑に移動した g-10に移動ok 20本06月19日 苗は無事に育ちつつある ok06月29日 苗はすこし生長してきている 雑草を取り除いておく07月10日 そのご 苗も大きくなりつつある07月17日 初の収穫だ 4個あり第二弾の種の種まき06月05日 2回目も種まき06月11日 すこし発芽してきている06月12日 移動だ m08の畑に移動した 8本06月19日 苗は無事に育ちつつある ok06月29日 こちらの苗もok 無事である 問題はなし07月10日 そのご 苗も大きくなりつつある 07月17日 初の収穫だ 4個あり 花があちこちで咲いている07月24日 25個の収穫をしておく 本格的に実が付き出した07月31日 30本の収穫をしておく 合計59個08月07日 30個の収穫をしておく 合計89個08月13日 20個の収穫をしておく 合計109個08月20日 20個の収穫をしておく 合計129個08月28日 20個の収穫をしておく 合計149個09月04日 20個の収穫をしておく 合計169個09月11日 20個の収穫をしておく 合計189個09月18日 20個の収穫をしておく 合計209個09月23日 30個の収穫をしておく 合計239個10月01日 30個の収穫をしておく 合計269個10月10日 20個の収穫をしておく 合計289個10月16日 10個の収穫をしておく 合計299個10月22日 10個の収穫をしておく 合計309個7月17日より収穫を開始 ただいま 309個今年のオクラ04月08日 オクラの種を買ってきておいた今年も5月より種まきをしよう04月30日 庭で種まきをしておく05月10日 発芽してきている 16pots 10日かかる05月13日 g-22の畑に移動 植え付けしておいた05月20日 苗は無事 16本くらいある06月17日 なんとか育ちつつある これでokだなあ06月30日 花がついている 順調に育ちつつある予備として オクラの種まき 第二弾05月27日 追加で庭で種まきをしておく06月03日 発芽した すこしだけ 5本くらいかな残っているのは06月10日 畑に移動する m-06に植え付けた06月17日 残っているのは 2本だけ まあ 予備なのでokオクラ 花も咲き出した なんとか育ちつつある07月08日 良く見ると 実があちこちに付いている 収穫をしておいた15個07月11日 2回目の収穫をした15個07月16日 3回目の収穫をした30個07月19日 4回目の収穫をした20個07月22日 5回目の収穫をした20個07月29日 6回目の収穫をした30個08月05日 7回目の収穫をした30個08月12日 8回目の収穫 8個08月19日 9回目の収穫 2個08月26日 10回目の収穫 2個勢いが弱ってきているかな さすがに7月8日から 15+15+30+20+20+30+30+8+2+2=172個東日本大震災 3月11日発生08月28日は 既に535日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------1978年、1988年、そして1998年1978年の気象観測人工衛星、1988年のハンセン証言、そしえ1998年の気温急上昇と10年ごとに温暖化でエポックがありました。科学を長くやっていると、自然というのが実に複雑で到底、人間の頭で考えられるようなものではないことに常に気づかされます。私が温暖化に冷ややかなのは、自然を理解できない人間はこれから寒冷化するか温暖化するか分からないのに、温暖化対策などをすると私たちの孫は「寒さと農業の不作」で酷い目に遭うのではないかと心配しているからです。 1988年の少し前、アメリカは天候が不順で、干ばつ、寒い夏などが続き農業はとても困っていました。その頃はまだ「バイオ燃料」などはなかったので、食料を燃料にするなどという大胆なことは行われていませんでした。だから、値段は上がらず、収穫は少ないというような状態が続いていました。このグラフは1980年代のアメリカ農業がいかに不調だったかを示したものです。そして、いよいよ1988年が訪れます。この年、気象庁の言い方では「過去に経験の無いほどの干ばつ」に見舞われた(本当は20,30年に一度はあるのですが)北アメリカはトウモロコシの収穫が実に20%も減りました。2012年8月、アメリカのトウモロコシの不調が話題になっていますが、14%の不作ですから、1988年よりは良い方です。(テレビでは「歴史的な不作」と言っていましたが、勉強していないのでしょう。最近、気象庁やテレビが豪雨や台風で極端に強い言葉を使っています。今日は沖縄に来た台風15号について「史上最強」といっていましたが、本当は「2003年の台風14号と同じ規模」のものを「史上最強」と表現しているようです。)そこで、上院議員、テレビ局、銀行資本が手を組んで、一騒ぎをおこします。それが1988年6月23日にアメリカ上院で開かれた「気象変動の公聴会」でした。5月のシカゴ商品相場の動きを見て、さらに6月23日というワシントンで有名な「熱い特異日」を公聴会の日に選び、それに加えて朝早く議会に来た担当者が冷房を切るという丁寧な作戦を組んだのが成功して、ものすごく熱い議場の中でNASAのハンセン博士が証言したときのグラフがこのグラフです。それから23年経った今では、温暖化の予測がまったく外れたことを示しています。科学的根拠がなかったからです。しかし彼は「もし、これから世界が協調してCO2を減らさなければ世界の気温はさらにあがり、気候が変動して大変なことになる」と演説し、それを受けて農業議員が「工業がだすCO2が原因だから、農業に金を回せ」と工作をします。これが地球温暖化騒動のもとでした。しかし、自然と人間の関係は実におもしろいものです。ハンセンが証言した1988年以後、二つのことが起こったのです。一つが「気温が上がらなくなった」ということ、もう一つが「農業が好調になった」ということでした。「夜明け前がもっとも暗い」とはよく言ったものです。ところが、この話を聞いて「しめた!」と思った人は多かったのです。まずゴア元副大統領は「これは原子力に有利」、サッチャー元イギリス首相は「北海油田の後、原子力をしなければ」、ヨーロッパは「アジアの植民地を失って困っていたが、これこそアジアの発展を止められる」、日本の橋本元首相「政治的に苦しい情勢を打破できる」、環境省は「このビッグテーマで環境庁と省にするぞ」、環境産業「3兆円の利権だ」と言うことになったのです。かくして人間社会は温暖化騒動でわいたのですが、地球は人間の言う事を聞いてはくれません。CO2の温暖化なら真っ先に気温が上がるはずの人工衛星で測定した上空の気温はいっこうにあがらなかったのです。でも突然、1998年だけ上がったのですが、この理由は何でしょうか?もともとCO2によって気温が上がるならだらだらと上がるはずですし、まして「急激に下がる」などということは起こらないのですから、この変化はどうにも説明できなかったのです。数1000メートル上空の気温が半年から1年だけ上がってまた元に戻るなど言うことが起こるには、なにか全く別のことを考えなければならないからです。ところが、その頃、日本の四国沖でも不思議なことが起こっていました。黒潮の水温はペルー沖の影響を受けて少し高くなっていましたが1988年になって急激にあがり、また下がったのです(高知大学論文による)。この水温の上昇で温帯性の藻類が高知の沿岸から消えて、熱帯性の藻類に変わったのです。この現象を「CO2による温暖化のせい」と新聞などが報じました。マスコミがいい加減であることは、ここで特に書くまでもないですが、CO2によって上がる温度は大気ですから、大気の温度が上がって海水温が突如、上昇するということはありません。空気から水への伝熱量は物理的に分かってみるものでとても小さいからです。また温暖化というのは水温が上がったり下がったりするものではなく、徐々にあがるのです。そうすると、上空の気温でも、海水温でもこの1998年の急上昇は温暖化とは別の原因としなければなりません。また、上空と海水温の両方を同時に説明できるものでなければならないのも当然です。ところで「温暖化騒動」が社会に出てきた頃には多くの人は「これまで地球の気温はどのように変化し、何が問題だったか」について欲知らなかったのは当然ですが、すでに20年ほど経ったので、そろそろ「冷静に歴史を振り返る」ことも必要と思います。このグラフは今から40万年ほど前からの地球の気温の変化で、だいたい12万年ごとに暖かくなったり(間氷期)、寒くなったり(氷期)しています。氷期になると北極海から台湾ぐらいまでがすべて氷河に覆われますから、日本列島は誰も住めないでしょう。もし今までの寒暖の周期がこれからも続くなら(その可能性が最も高い)、しばらくすると気温はドンドン下がっていくはずなのです。「厳冬の前の小春日和をなぜ怖がるのか?」と言ったのはアメリカの物理学者ですが、私も温暖化について同じ心配をしているのです。この12万年の周期より短い周期が500年で、ローマ帝国の東西分裂、ノルマンディーの北方進出、世界的な戦国時代、そして今の温暖化騒動と、過去に500年ごとの変化があり、そのたびにアルプスの氷河は頂上まで融けてはまた麓まで進むということをくり返しています。グリーンランドの氷も同じです。このブログで再三、指摘していますが、科学的なことで知らない人を脅しお金を取る・・・ということはこの温暖化ばかりではなく「町にゴミがあふれるからリサイクル」、「東海地方に地震が来るから耐震補強」、「タバコを吸うと肺がんになる」など枚挙にいとまがありません。専門家がその魂と誠実さを失ったのはヨーロッパで1920年と言われていますが、日本こそが専門家の魂(武士の魂)と誠実さ(日本人の誠)を保ってもらいたいものです。(平成24年8月27日)ふむふむはた坊
2012.08.28
コメント(0)
-

今週のトマト ミニトマト まだまだ 東日本大震災534日後に
昨年のトマト 桃太郎 4本を購入した トマトも栽培を開始04月03日 hcで苗を4本 桃太郎を購入して 畑に植えておいた m06に植え付け04月03日 hcでブチトマト アイコの苗も2本を購入した これもm06に植え付け04月09日 畑にいくと苗がなくなっている 綺麗に消滅して何もない ????04月10日 あわてて またhcにトマトの苗を買いに行く 桃太郎4個と赤のブチトマト204月10日 すぐに また 苗を植えておく04月17日 再度の苗の6本は今回は無事に残る04月23日 ミニトマトの苗画1本 何かにかじられて枯れた 04月24日 補修でミニトマト2本をhcで購入して植えつけた04月28日 ついで またミニトマト2本を増やしておいた05月01日 ミニトマトには花がついている トマトはまだまだ05月08日 ミニトマト また2本 20円で安売りしていたので買って会社に植えた05月15日 ミニトマトm06の分に実が付き出した 支柱をつけておいた05月22日 ミニトマトm07の分にも実が付き出した05月29日 ミニトマト庭のものにも 会社のものにも実が付き出した06月19日 初のミニトマト 真っ赤なのが1個 初の収穫した 美味06月22日 すこし赤みがついた実も4個 とっておいた06月29日 ようやく赤くなつた実が増えてきた これから毎週 赤いミニトマトが収穫可能07月03日 トマトの赤い実もやっと2個収穫できた これから どんどん収穫へ 07月06日 2回目のトマトの収穫10個 ミニトマトも20個トマト桃太郎 4本 m-06 実が付いた 7/3-2個赤くなったブチトマト赤 5本の苗 m06-3本 m07-2本 m-20-2本 実が付いた会社にも 2本のトマトと2本のブチトマトを植えておいた 実が付いた 7/3-1個赤家の庭にも 2本のブチトマトを植えておいた 実が付いた 7/3-4個赤くなるミニトマト 6月19日 初の実の収穫6個 6月22日 4個6月29日 20個の収穫7月03日 40個の収穫7月04日 家の庭のミニトマトも赤くなっている4個の収穫をした7月06日 20個の収穫7月09日 20個の収穫7月13日 20個の収穫7月17日 100個の収穫7月24日 50個の収穫7月31日 50個の収穫8月06日 100個の収穫 合計430個8月14日 20個の収穫 合計450個トマト 7月03日 初の2個の収穫をした7月04日 会社でも赤くなっていた 1個の収穫をする7月06日 2回目の収穫は10個7月09日 3回目の収穫は10個7月13日 4回目の収穫は10個7月17日 5回目の収穫は20個7月24日 6回目の収穫は10個7月31日 7回目の収穫は10個8月06日 8回目の収穫は10個 合計87個8月14日 9回目の収穫は2個 合計89個8月20日 10回目の収穫は1個 合計90個家の庭のトマトは 終了した会社のトマトも そろそろ終了畑のトマト ミニトマト もう勢いはなし今年のトマト04月22日 hcで苗を2本買ってきた 桃太郎すぐに畑に植えておいたトマトも植え付け開始 カバーを付けておいた 05月06日 花も咲き出している05月13日 ワキメ 庭に移動して育てている05月27日 かなり大きくなってきている 支柱をつけておく06月04日 下には実がどんどんついてきている 楽しみだなあ 06月17日 下から1-2-3-と実がついている まだ青い06月23日 1個が赤くなりつつある06月26日 初の1個の収穫をした めでたい07月01日 その後はゆくりとしている07月08日 やっと5個 どんどん増えている07月19日 6個の収穫07月22日 6個の収穫今年のミニトマト04月22日 4つの苗 中サイズの実のつくのを購入 畑に植え付けたミニトマト ブチのサイズは中玉とした05月06日 花も咲き出している05月13日 ワキメ 庭に移動して育てている05月27日 かなり大きくなってきている 支柱をつけておく06月03日 下のほうに実がついている 中サイズなので おおきい実になりそう 楽しみ06月17日 下から1-2-3-と実がついている 実は赤くなりだしたのもある06月23日 赤くなっての7個の収穫をした06月26日 続いて10個 どんどん収穫していこう07月01日 続いて5個 まだ 少ないなあ07月08日 12個くらい まあまあ07月19日 30個くらい そろそろ大量の収穫できそう07月22日 40個くらい どんどん赤くなる07月28日 40個 完熟になっている07月29日 40個 追加で収穫ワキメから どんどん増やそう05月27日 庭で刺し芽をしておいた ただいま10本のワキメは育ちつつある06月03日 追加で庭でまた刺し芽をした これで 合計20本の刺し芽となった06月10日 m-08の畑に刺し芽の20本を移動 全部20ともに畑に定植した06月17日 支柱をつけて追肥をしておいた 06月24日 刺し目の分 どんどん成長してきている 楽しみ07月15月 やっと実の収穫 まずは2個07月19日 10個くらい そろそろ実が一杯に付き出している07月22日 10個くらい どんどん赤くなりつつつある07月29日 40個くらい収穫した収穫トマト2本 収穫は6月26日から 1+1+5+1+5+6+6+6+6+6+10+6+4 =63個ミニトマト4本収穫6月23日7+10+10+5+12+20+48+30+40+40+40+40+50+40+20=412個 刺し芽の20本 収穫は7月15日から 2+10+10+10+40+20+40+60+80=272個会社ミニトマト2本 収穫は7月08日から 4+1+3+4+10+10+10+6+10+4 =62個会社トマト2本 収穫は7月22日から 1+2+6+2+4+2 =17個収穫はそろそろ お終いになってきているそろそろ 実の付き方が ゆっくり 皮も固くなりつつある東日本大震災 3月11日発生08月27日は 既に534日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------教育談義 1 教育はなぜ進歩しないのか?教育の議論は難しい。何が難しいかというと、いつも「一」(イチ)から始めなければならないからだ。私が専門とする物理学では、まず「ニュートンの肩の上」に学生を乗せる。そこは30年前に物理を学んだ先生でも、たったいま勉強した学生でもまったく同じ問題に同じ答えがでる。ここで言う「ニュートンの肩の上」というのは「古典力学」ということではなく「既存の体系だった学問」という意味だ。その中に若干の疑問があっても、ほぼ「全員がそれでよいと認める理論」である。その上で、個別のことや最新の学問を学ぶ。学問は永遠に続くので、私たちの知識は不完全で、間違っている。だから私は講義の最後に、「私は君たちをニュートンの肩の上にのせた。君たちはその肩の上から遠くを見ることはできるだろう。でも、その景色は本当ではない。つまり、私が教えたことは間違っているからだ。」「なぜ、間違っているということが分かるかというと、今からわずか1000年前。平安時代の物理の先生は、私と違うことを「正しい」として教えた。今から1000年後の先生は、「かつては・・・・なことも分かっていなかったと言うだろう」と言われるだろう。」平安時代には電気という概念がなかった。だから「雷は雲の上にいる雷神が起こしている」と教えた。現在の我々も似たようなものだ。・・・・・・・・・ところが、教育というのは、「ニュートンの肩」が見えない。だから誰でもどこからでも議論をする。共通の真理というものがないように思える(本当はあるにしても)。第二に、その結果として、長く教育をしてきた人と、一回も学校で教えたことが無い人が同じ知識と経験を持つという前提に立つ。そうすると、「教育理論に詳しく、長い教師経験を持つ」という人と、「教育を勉強したことがなく、教育経験がない」という人の意見がかみ合わない。かみ合わないのも当然でもある。ある人の考えというのは勉強したり、経験したりすることによって変わるものだから、同じ人間でも過去の自分と今の自分で意見が違うはずだから、他人同士ならなおさら合わないだろう。もし「教育」というものが進歩するものであれば、これまでの理論や経験で「これは正しい」というものが確定しているはずである。・・・・・・・・・ただ、物理学とは違い、人間も変化するし、社会も変わるので、それに応じて教育も変化する。でも、それは「人間と社会の変化に合わせて補正していく」ということであって、教育という学問の真理が変化するのではない。・・・・・・・・・フランスのルソーやペスタロッチぐらいから近代教育学が始まって、日本では吉田松陰、伊沢修二かも知れない。大学の教育学部では、膨大な数の教育学を学ぶのだが、それでも教育学というのがなかなか確立しない一つの理由に、教育の結果として育てられる人間像が確定しない、もしくは確定しなければならないという「妄想」があるからと思う。教育はしばしば「政治」と直結し、「宗教、道徳」とも密接な関係になる。「どういう人間を育てるか」とか、「平和を愛する人」などという「教育外」の問題にとらわれるのである。日教組が政治活動をしたのも、そこを錯覚したからだろうし、今、また教育に逆の政治活動や信念に基づく意見が出ている。「若者は礼儀正しくあるべきだ」とか、「日本人は日の丸に尊敬の心を持たなければならない」というのは教育には関係がない。その点では「環境」と似ている。環境学の基本は「このような環境にどうしたら到達するか」ということが定まったら、それに至る道を示すものであって、環境学自らが「このような環境が望ましい」と言うものではない。たとえば「一度使った物を、もう一度、使うようにしたい」というのは社会の希望であり、それをどのように達成するかは環境学である。もう一つ踏み込めば、「資源最小で最大の幸福を得たい」というテーマに対して、「それならこのような社会構造」というのも環境学かもしれない。ところが、多くの人が「環境」に「哲学」を入れる。そうすると、「ものを大切にしなければならないのに、なぜリサイクルに反対するのか」というような支離滅裂な議論がでる。「ものを大切にする」ということと、それが「リサイクルという手段で達成される」というのは違う。前者は「希望」であり、後者は「それを達成するための手段」だからだ。・・・・・・・・・・「こういう若者を育てたい」というのは希望であり、「それならこのような教育方法で」というのが手段である。「こういう若者を育てたい」という希望は時代によって変わる。「立派な軍人を育てたい」という場合と、「融和な家庭人が理想だ」という場合もあり、また家庭というのが無くなれば「個人として自立して生きていける人間」ということになる。それぞれに応じて、教育方法があるはずで、教育談義をするときには「希望」は固定(仮定)しておかなければならず、もし「希望」を論じるなら、教育とは切り離した方がよい。「希望」が社会で統一できないなら、統一できるところを教育の目標にするか、あるいは統一されなくてもある程度の目標を置くかを決める必要がある。いずれにしても、教育は「人間や社会の理想」とは無関係で、それらが決まれば「方法が決まる」ものである。(平成22年7月11日 執筆)なるほどはた坊
2012.08.27
コメント(2)
-

17回目のシソの葉の収穫 東日本大震災534日後に
昨年のしその葉まずは 2個の苗を購入した04月03日 hcでの青しその葉の苗 2個をみつけて購入した04月10日 1本が枯れた あーあ04月17日 hcで追加の苗を2本かって植えた04月24日 苗は合計で3本が無事に こぼれ種の発芽 すこし 出てきている04月29日 こぼれ種のしその葉も大きくなりだした これで しそは大量に出来る05月08日 初の葉の収穫をしておく こぼれ種の青と赤のしその発芽も確認 okだな05月15日 2回目の青しその葉の収穫をしておく05月22日 3回目のアオシソの葉を収穫しておく05月29日 4回目のアオシソの収穫をした06月05日 5回目のアオシソの収穫をした06月12日 6回目のアオシソの収穫をした06月19日 7回目のアオシソの収穫をした06月26日 8回目のアオシソの収穫をした07月03日 9回目のアオシソの収穫をした07月10日 10回目のアオシソの収穫をした07月17日 11回目のアオシソの収穫をした07月24日 12回目のアオシソの収穫をした07月31日 13回目のアオシソの収穫をした08月07日 14回目のアオシソの収穫をした08月13日 15回目のアオシソの収穫をした08月20日 16回目のアオシソの収穫をした09月02日 17回目のアオシソの収穫をした09月09月 18回目のアオシソの収穫をした 葉は終了だなこぼれ種の発芽青しそ 昨年は3月22日に 今年は4月24日に 赤しそ 昨年は4月11日に 今年は5月08日に 今年は寒かったみたい??? しその収穫 5/8---開始青しそ 18回赤しそ 0回青そしの葉も もうダメ 穂がでて 花が咲いてきている10月23日 しその実がたくさんある 香りが良い しかし 手間暇がかかるので放置しその実 香りも楽しんだで じゃまなので そそろそろ 全部を撤去しよう今週の日曜は全部 撤去としよう今年まずは hcでの苗から04月15日 hcでの苗があったので まずは1本 58円なり m-08の畑に1本 植え付けた05月20日 初の収穫 すこしこぼれ種の発芽は 05月20日 あちこちにたくさん発芽している05月26日 2回目の収穫をしたあ05月31日 3回目の収穫をしたーあ06月03日 4回目の収穫をしたーーーあ06月10日 5回目の収穫をしたーーーーーーあ06月17日 6回目の収穫をしたーーーーーーーーーーあ06月24日 7回目の収穫をしたーーーーーーーーーーーーーあ06月30日 8回目の収穫をしたーーーーーーーーーーーーーーーあ07月08日 9回目の収穫をしたーーーーーーーーーーーーーーーーーあ07月11日 10回目の収穫をした----------------------------------あ07月16日 11回目の収穫をした---------------------------あ07月22日 12回目の収穫をした----------------------あ07月29日 13回目の収穫をした------------------あ08月05日 14回目の収穫をした--------------あ08月12日 15回目の収穫をした----------あ08月19日 16回目の収穫をした------あ08月26日 17回目の収穫をした--あもう 1-2回 収穫できそう東日本大震災 3月11日発生08月27日は 既に534日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------教育談義 1 教育はなぜ進歩しないのか?教育の議論は難しい。何が難しいかというと、いつも「一」(イチ)から始めなければならないからだ。私が専門とする物理学では、まず「ニュートンの肩の上」に学生を乗せる。そこは30年前に物理を学んだ先生でも、たったいま勉強した学生でもまったく同じ問題に同じ答えがでる。ここで言う「ニュートンの肩の上」というのは「古典力学」ということではなく「既存の体系だった学問」という意味だ。その中に若干の疑問があっても、ほぼ「全員がそれでよいと認める理論」である。その上で、個別のことや最新の学問を学ぶ。学問は永遠に続くので、私たちの知識は不完全で、間違っている。だから私は講義の最後に、「私は君たちをニュートンの肩の上にのせた。君たちはその肩の上から遠くを見ることはできるだろう。でも、その景色は本当ではない。つまり、私が教えたことは間違っているからだ。」「なぜ、間違っているということが分かるかというと、今からわずか1000年前。平安時代の物理の先生は、私と違うことを「正しい」として教えた。今から1000年後の先生は、「かつては・・・・なことも分かっていなかったと言うだろう」と言われるだろう。」平安時代には電気という概念がなかった。だから「雷は雲の上にいる雷神が起こしている」と教えた。現在の我々も似たようなものだ。・・・・・・・・・ところが、教育というのは、「ニュートンの肩」が見えない。だから誰でもどこからでも議論をする。共通の真理というものがないように思える(本当はあるにしても)。第二に、その結果として、長く教育をしてきた人と、一回も学校で教えたことが無い人が同じ知識と経験を持つという前提に立つ。そうすると、「教育理論に詳しく、長い教師経験を持つ」という人と、「教育を勉強したことがなく、教育経験がない」という人の意見がかみ合わない。かみ合わないのも当然でもある。ある人の考えというのは勉強したり、経験したりすることによって変わるものだから、同じ人間でも過去の自分と今の自分で意見が違うはずだから、他人同士ならなおさら合わないだろう。もし「教育」というものが進歩するものであれば、これまでの理論や経験で「これは正しい」というものが確定しているはずである。・・・・・・・・・ただ、物理学とは違い、人間も変化するし、社会も変わるので、それに応じて教育も変化する。でも、それは「人間と社会の変化に合わせて補正していく」ということであって、教育という学問の真理が変化するのではない。・・・・・・・・・フランスのルソーやペスタロッチぐらいから近代教育学が始まって、日本では吉田松陰、伊沢修二かも知れない。大学の教育学部では、膨大な数の教育学を学ぶのだが、それでも教育学というのがなかなか確立しない一つの理由に、教育の結果として育てられる人間像が確定しない、もしくは確定しなければならないという「妄想」があるからと思う。教育はしばしば「政治」と直結し、「宗教、道徳」とも密接な関係になる。「どういう人間を育てるか」とか、「平和を愛する人」などという「教育外」の問題にとらわれるのである。日教組が政治活動をしたのも、そこを錯覚したからだろうし、今、また教育に逆の政治活動や信念に基づく意見が出ている。「若者は礼儀正しくあるべきだ」とか、「日本人は日の丸に尊敬の心を持たなければならない」というのは教育には関係がない。その点では「環境」と似ている。環境学の基本は「このような環境にどうしたら到達するか」ということが定まったら、それに至る道を示すものであって、環境学自らが「このような環境が望ましい」と言うものではない。たとえば「一度使った物を、もう一度、使うようにしたい」というのは社会の希望であり、それをどのように達成するかは環境学である。もう一つ踏み込めば、「資源最小で最大の幸福を得たい」というテーマに対して、「それならこのような社会構造」というのも環境学かもしれない。ところが、多くの人が「環境」に「哲学」を入れる。そうすると、「ものを大切にしなければならないのに、なぜリサイクルに反対するのか」というような支離滅裂な議論がでる。「ものを大切にする」ということと、それが「リサイクルという手段で達成される」というのは違う。前者は「希望」であり、後者は「それを達成するための手段」だからだ。・・・・・・・・・・「こういう若者を育てたい」というのは希望であり、「それならこのような教育方法で」というのが手段である。「こういう若者を育てたい」という希望は時代によって変わる。「立派な軍人を育てたい」という場合と、「融和な家庭人が理想だ」という場合もあり、また家庭というのが無くなれば「個人として自立して生きていける人間」ということになる。それぞれに応じて、教育方法があるはずで、教育談義をするときには「希望」は固定(仮定)しておかなければならず、もし「希望」を論じるなら、教育とは切り離した方がよい。「希望」が社会で統一できないなら、統一できるところを教育の目標にするか、あるいは統一されなくてもある程度の目標を置くかを決める必要がある。いずれにしても、教育は「人間や社会の理想」とは無関係で、それらが決まれば「方法が決まる」ものである。(平成22年7月11日 執筆)なるほどはた坊
2012.08.27
コメント(0)
-

落花生 なんとか 無事 東日本大震災533日後に
昨年の落花生種は購入したが 植え付けは4月か5月くらい04月03日 hcでの種を1つ買っておいた04月17日 庭でpotに種まきをした05月05日 やっと発芽した05月15日 畑のg-10のほうに移動して植え付けした 20個05月22日 無事に畑で定着している なんとかなるだろう ok06月22日 花も開花して どんどん咲いている07月24日 まあまあ無事に生育している 雑草とりをしておく08月07日 再度 雑草とりをしておく すぐに雑草は伸びてしまうなあ08月28日 雑草の中で 落花生 黄色の花をつけている 09月04日 間違って雑草をとっていたら落花生 実ができていた okだなあ10月10日 収穫はちかいな 後はタマネギさんに場所をゆずろう10月30日 残りを全部を収穫した まあまあ実がついていた ok落花生も 今年も植え付けは20個雑草とりしているが 雑草に負けている残っているのは10本くらいに減っている10月30日には収穫した まあまあの収穫であった11月06日 実は乾燥させている まあまあ今年の落花生04月29日 庭でpotに種まきをした05月16日 やっと17日目で 1個発芽してきている05月19日 まだ2本だけ 遅いなあ05月22日 やっと3本目の発芽 ゆくりゆくり05月27日 やっと15本の発芽がした で 畑に移動した g-22に植え付け06月17日 その後も苗は無事 生長もまだ なし07月01日 見ると花が1つ 良くみると あちこち花が咲きつつあるぞ07月22日 花はあちこちに たくさん咲き出した okだなあ08月19日 まあ なんとか ぶじだなあ 10月に収穫の予定9-10月と まだ2ヶ月も先になる雑草とりはこまめにやろう でも 実際はあまりやっていないなあ東日本大震災 3月11日発生08月26日は 既に533日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------対立の構図 ヘルムホルツ「対立の構図」を整理し始めて、バッシング覚悟で「理科系」、「文科系」ということをまず書いてみました。もちろん、理科系・文科系というようなおおざっぱな区分で物事を見るのは不適切なのですが、整理というのは、少し問題のある表現で切り込む方が鋭く本質に迫ることができる場合もあり、その意味もありました。次に進もうと思っておりましたところ、読者の方から非常に有意義なご指摘をいただき、「ヘルムホルツ」という題名で一つ書きたくなりました。19世紀の後半、熱力学の大家にヘルムホルツというドイツの学者がいました。なにしろ「ヘルムホルツの自由エネルギー」という名前がついているぐらいの立派な学者だったのですが、彼が大学を退官するときに次のようなことを述懐しています。「ギリシャの哲学なら2000年前の書物も残っているかも知れないけれど、科学(自然科学)は30年も経ったらどんな立派な本も捨てられる。だから私は名著を書けない」確かに彼は熱が専門でしたから、晩年は懸命になって「太陽はなぜ光っているのか」という問題に取り組んだのですが、なにしろまだキュリー夫人が核分裂を発見する前でしたから、太陽の熱を解明することができませんでした。また、絶対温度の単位にその名前が残っているケルビンは、ライト兄弟が初飛行する10年ほど前、「空気より重たいものは空を飛ぶことができない」と書きました。これもまた人間の知恵の限界を示しています。そんなことを言えば、後のコンピュータの世界最大の会社になるIBMの創始者は、ノイマンが発明したコンピュータを知って事業にのりだしますが、その時に「この機械は全世界で5台ぐらいは売れるだろう」と言っています。このような科学の難しさと人間の頭の限界をイヤと言うほど味わっている自然科学では、「自分が正しいと考えている事は正しいはずはない」という確信があります。それが「相手を罵倒する対立」にはならない一つの理由ではないかと思うのです。それは同時に「人間の知恵に対する畏敬の念」でもあります。人間の脳は大したことはありませんが、その反面、長い時間の中では今、思いつかないようなものや論理を生み出していく力があります。「知恵を信じる」、「教育を信じる」、「自分は小さい」という「発展に対する素直な尊敬の心」が科学にはあるような気がします。対立のない静かな研究環境の中にあった私が、人を罵倒する学問を身近にしったのはリサイクルと資源の関係について学会で発表したときであることは何度か書いたことがあるのですが、それから以後、対立の構図の中に投げ込まれ、いまでもうろうろしているように思います。ただ、対立の構図を書き始めて、対立の原因は「事実認識が違う」、「論理展開が違う」と言うほかに、「錯覚・誤解」、「ウソ・曲解」、そして「思想・利害」があることを強く感じます。(平成24年8月25日)そうだっぺはた坊
2012.08.26
コメント(7)
-

g-10のヤマノイモも 元気だなあ 東日本大震災533日後に
2011年 今年も昨年と同様に50個の種芋を植え付ける予定今年の植え付け用のヤマノイモの種むかご 大量に拾っている 100個くらいムカゴの発芽して種芋になった分 30個くらいその2年目の種芋 25個くらい収穫した芋のカットした分 25個くらい今年の収穫予定の種芋は50個 翌年用にうえるムカゴなどもたくさんある03月27日 種芋のやまのいも 様子を見てみた 根っ子と芽が出てきている ok04月03日 m-08の畑に30個を植え付け 残りは20個04月10日 追肥をかけておく04月16日 まだ発芽していない まあ1ヶ月はかかるかな 残り20個はまた植え付けよう09月02日 そのまま 同じく 雑草だらけ10月02日 おなじく 雑草だらけヤマノイモ m08-30本以上 m20-3本 m07-2本 m06-2本 合計37本以上g10-むかご多数 g22-むかご多数 合計 多数今年のヤマノイモ まあまあ 育っていたが雑草の季節になり 葉が雑草に隠れている7月になり またまた雑草だらけに すぐに雑草だらけになってしまう 8月になっても 雑草のみが目立つ とっても また雑草が伸びて 同じ9月になっても そのまま 雑草のびつづけている 参った10月になっても もう 雑草さんに完敗さて 芋もできているのかな ????庭でツルが1本あったのでひっぱると ヤマノイモの小さいのが出てきたこれは 昨年の芋のかけらを捨てていた分 小さいヤマノイモが1個 出てきたさて 畑のは ???10月09日 m20-3本の分を掘り出した 半分のところを掘り出して これだけ 小さい10月23日 m08-15本の分を掘り出した が やっぱし 小さい10月30日 残りの15個の芋 ほってもなし 小さいのが2個くらい 消滅していたみたい7月くらいにツルがなくなったので 芋はそのときのサイズで成長はストップしたようだ今年は芋は成長せず すこし大きいのは食べられる残りは来年の種芋になる 今年は種芋がおおかった 雑草に負けたということでお終いに2012 ヤマノイモ03月18日 昨年のヤマノイモの種芋の包みをみてみた まだ芋に芽は出ていないなことしの植え付け用の種芋 まだ 芽はでてない が 3月の末には 畑に植え付けよう04月01日 種芋 m-08の畑の畝に植え付けておく04月15日 発芽していないかよく見る しかし まだ04月29日 予想とおり発芽した 今年は畝を変えた これで良く育てば もうけもの m-08の畑05月04日 畝に支柱をつけて 紐をつけておいた05月13日 ツルが支柱にどんどん登りだしている05月27日 どんどん蔓ができて 支柱に上がりだしている06月03日 支柱にどんどんあがりだしている06月17日 支柱の上にまで蔓が伸びている ok07月01日 見た目にも ヤマノイモらしくなってきている庭をみると ヤマノイモのツルが出ていた04月28日 庭で1本 ヤマノイモのツルがある このまま育ててみよう 05月03日 これにも支柱をつけておいた05月10日 いものつるが3mになってきた 順調に大きくなってきている05月16日 2fにまで届きそうになってきている05月19日 2fに届いている どんどん伸びて頂戴 3.5M05月26日 2Fの真ん中まできている 4M05月31日 2fの上にいきつつある 5mになった06月06日 2fの上に上に上にいく 6mになった06月13日 2fの蔓をすこし下に移動して 再度 上に上るようにset ただいま7mに06月17日 雄花がたくさんついているm-20の畑こちらに 前の芋が残っていたのが 発芽してきている05月04日 たくさん発芽してきている これらも育てていこう 支柱をつけておいた05月13日 ツルは支柱を登り 空中にツルがぶらぶらしている06月03日 むかこの蔓がたくさん 他にも2-3本ある06月17日 2mくらいで蔓がなんども上がったり下がったりしているm-07の畑05月05日 ここにも1本 ついでに支柱をつけておいた 1個でも収穫するぞーーー05月13日 支柱にはつるがしっかりと巻いている これで良し06月03日 こちらも3-4本の蔓がある06月17日 2mくらいで蔓がなんども上がったり下がったりしている今年は山の芋さんの成長は順調なり庭の蔓は8Mを超えた雄花がたくさんついてきている畑の蔓は2mくらいで ウロウロしているが 見た目はヤマノイモらしくなってきている庭のヤマノイモが10mに届くか 観察中06月29日 8m40cmになった07月01日 8m80cmになった07月06日 9mとなった もうすこしで10mになる07月11日 9.4mとなった あと60cmで10mになる ムカゴがたくさん付き出した07月22日 庭に もう1本のヤマノイモの蔓が出ている これは4mくらいになっている庭のヤマノイモ 9.4mのが1本 4mのが1本 合計2本が蔓を伸ばしている庭のヤマノイモ 晴れが続いていて 9.5mくらいで止まっているさすがに 10mには いかないみたいだ 雨が少なくなり 成長しなくなったみたい08月04日 m-08の畑のヤマノイモ 無事に育っている08月25日 g-10の畑のヤマノイモ これも無事に育っているok/ok/okだ東日本大震災 3月11日発生08月26日は 既に533日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------対立の構図 ヘルムホルツ「対立の構図」を整理し始めて、バッシング覚悟で「理科系」、「文科系」ということをまず書いてみました。もちろん、理科系・文科系というようなおおざっぱな区分で物事を見るのは不適切なのですが、整理というのは、少し問題のある表現で切り込む方が鋭く本質に迫ることができる場合もあり、その意味もありました。次に進もうと思っておりましたところ、読者の方から非常に有意義なご指摘をいただき、「ヘルムホルツ」という題名で一つ書きたくなりました。19世紀の後半、熱力学の大家にヘルムホルツというドイツの学者がいました。なにしろ「ヘルムホルツの自由エネルギー」という名前がついているぐらいの立派な学者だったのですが、彼が大学を退官するときに次のようなことを述懐しています。「ギリシャの哲学なら2000年前の書物も残っているかも知れないけれど、科学(自然科学)は30年も経ったらどんな立派な本も捨てられる。だから私は名著を書けない」確かに彼は熱が専門でしたから、晩年は懸命になって「太陽はなぜ光っているのか」という問題に取り組んだのですが、なにしろまだキュリー夫人が核分裂を発見する前でしたから、太陽の熱を解明することができませんでした。また、絶対温度の単位にその名前が残っているケルビンは、ライト兄弟が初飛行する10年ほど前、「空気より重たいものは空を飛ぶことができない」と書きました。これもまた人間の知恵の限界を示しています。そんなことを言えば、後のコンピュータの世界最大の会社になるIBMの創始者は、ノイマンが発明したコンピュータを知って事業にのりだしますが、その時に「この機械は全世界で5台ぐらいは売れるだろう」と言っています。このような科学の難しさと人間の頭の限界をイヤと言うほど味わっている自然科学では、「自分が正しいと考えている事は正しいはずはない」という確信があります。それが「相手を罵倒する対立」にはならない一つの理由ではないかと思うのです。それは同時に「人間の知恵に対する畏敬の念」でもあります。人間の脳は大したことはありませんが、その反面、長い時間の中では今、思いつかないようなものや論理を生み出していく力があります。「知恵を信じる」、「教育を信じる」、「自分は小さい」という「発展に対する素直な尊敬の心」が科学にはあるような気がします。対立のない静かな研究環境の中にあった私が、人を罵倒する学問を身近にしったのはリサイクルと資源の関係について学会で発表したときであることは何度か書いたことがあるのですが、それから以後、対立の構図の中に投げ込まれ、いまでもうろうろしているように思います。ただ、対立の構図を書き始めて、対立の原因は「事実認識が違う」、「論理展開が違う」と言うほかに、「錯覚・誤解」、「ウソ・曲解」、そして「思想・利害」があることを強く感じます。(平成24年8月25日)そうだっぺはた坊
2012.08.26
コメント(3)
-

台風15号は 超巨大 東日本大震災533日後に
今年の空の雲まあ のんびりとしているが 少し 変今年の台風は 西に 西に これも 変天気予報によると最強台風、沖縄本島を直撃へ!大型で非常に強い台風15号が、沖縄本島を狙うように北上中です。 しかも、まだ発達途中。 30℃近い海面上で水蒸気の補給を多量に受けながら、更に発達する見込みで、あすには、中心気圧920hPa、最大風速50メートル、最大瞬間風速70メートルにまで発達すると予想されています。 そして、問題はこの台風のコース。 沖縄本島のすぐ近くをこのような台風が通過した例はありますが、沖縄本島をまともに直撃したような例は過去に一度もありません。 (2004年に925hPa、最大風速45メートルで本島を通過した台風18号がありました。)いくら台風銀座の沖縄本島と言えども、今回の台風には最大級の警戒が必要になります。 ちなみに今回予想される最大瞬間風速70メートルというのは、竜巻の強さに例えると、F2~F3にほぼ相当し、車の横転が多数発生したり、大きな木はもちろん、電信柱なども倒れてしまうほどの暴風になります。 雨の方も、あさって(月)の朝までに、最大で750ミリが予想され、こちらの方も記録的な豪雨となるかもしれません。 とにかく今回の台風は想像を絶する破壊力を持っていると思われ、直撃が予想される沖縄本島では、暴風や大雨に対して最大級の警戒が必要です。 もちろん、高波や高潮などにも厳重な警戒を要します。 一方、本州付近は今日も猛烈な残暑が継続。 こんな状態が来週にかけても続く見込みですが、特に台風15号が朝鮮半島より北へ進む、来週の半ば頃は、非常に暖かな南風とそれに伴うフェーン現象などが重なり、とんでもない高温に見舞われるかもしれません。 お盆前から始まったこの猛烈な暑さ(残暑)は、先週、このブログでも書いたとおり、おととしの記録的な残暑に匹敵するおそれが出てきました。今後も、熱中症はもちろん、農作物の管理などにも万全の注意をはらった方がいいでしょう。 台風15号も蝶巨大の ハリケーン並み猛暑も とんでもなく 暑くなるとか なんとか ????東日本大震災 3月11日発生08月26日は 既に533日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------対立の構図 ヘルムホルツ「対立の構図」を整理し始めて、バッシング覚悟で「理科系」、「文科系」ということをまず書いてみました。もちろん、理科系・文科系というようなおおざっぱな区分で物事を見るのは不適切なのですが、整理というのは、少し問題のある表現で切り込む方が鋭く本質に迫ることができる場合もあり、その意味もありました。次に進もうと思っておりましたところ、読者の方から非常に有意義なご指摘をいただき、「ヘルムホルツ」という題名で一つ書きたくなりました。19世紀の後半、熱力学の大家にヘルムホルツというドイツの学者がいました。なにしろ「ヘルムホルツの自由エネルギー」という名前がついているぐらいの立派な学者だったのですが、彼が大学を退官するときに次のようなことを述懐しています。「ギリシャの哲学なら2000年前の書物も残っているかも知れないけれど、科学(自然科学)は30年も経ったらどんな立派な本も捨てられる。だから私は名著を書けない」確かに彼は熱が専門でしたから、晩年は懸命になって「太陽はなぜ光っているのか」という問題に取り組んだのですが、なにしろまだキュリー夫人が核分裂を発見する前でしたから、太陽の熱を解明することができませんでした。また、絶対温度の単位にその名前が残っているケルビンは、ライト兄弟が初飛行する10年ほど前、「空気より重たいものは空を飛ぶことができない」と書きました。これもまた人間の知恵の限界を示しています。そんなことを言えば、後のコンピュータの世界最大の会社になるIBMの創始者は、ノイマンが発明したコンピュータを知って事業にのりだしますが、その時に「この機械は全世界で5台ぐらいは売れるだろう」と言っています。このような科学の難しさと人間の頭の限界をイヤと言うほど味わっている自然科学では、「自分が正しいと考えている事は正しいはずはない」という確信があります。それが「相手を罵倒する対立」にはならない一つの理由ではないかと思うのです。それは同時に「人間の知恵に対する畏敬の念」でもあります。人間の脳は大したことはありませんが、その反面、長い時間の中では今、思いつかないようなものや論理を生み出していく力があります。「知恵を信じる」、「教育を信じる」、「自分は小さい」という「発展に対する素直な尊敬の心」が科学にはあるような気がします。対立のない静かな研究環境の中にあった私が、人を罵倒する学問を身近にしったのはリサイクルと資源の関係について学会で発表したときであることは何度か書いたことがあるのですが、それから以後、対立の構図の中に投げ込まれ、いまでもうろうろしているように思います。ただ、対立の構図を書き始めて、対立の原因は「事実認識が違う」、「論理展開が違う」と言うほかに、「錯覚・誤解」、「ウソ・曲解」、そして「思想・利害」があることを強く感じます。(平成24年8月25日)そうだっぺはた坊
2012.08.26
コメント(3)
-

柿の木の葉に アリさん 東日本大震災532日後に
庭の柿の木の葉に ありさんがいた何をしているのか ??アリさん 木登りが結構とうまい庭には 探せば20種類くらいのありがいるらしい ??netみたら 1m2あたりの人口と蟻の人口の話が載っていた生物学のほうでは、ある種類の生物がどのくらい棲息しているか、を示すのに生存量(バイオマス)で示す。トラやライオンのような動物なら、何平方キロメートルに1頭、いうぐあいアリはどれだけの面積に1匹とはいかない。そこで、1平方メートル当りの目方でいく。関東地方でいうと、よほど生活条件のいいところで、1平方メートル当り1グラム、平均0.2グラムぐらいである。この0.2グラムは、小さなアリなら40-50匹、大きなアリなら3匹程度だろうこれに対して人間は、私の住んでいる神奈川県でいえば、大まかだが1平方メートル当り7グラム。アリやミミズは生物としては生存量は圧倒的に多いほうなのだが、とても人間にはかなわない。なんといっても、人間はあまりにも過剰なのである。つまり、それだけほかの生物の生活圏を圧迫していることになるつまり 蟻さんのようにつつましく生きないと ダメということらしいなるほどなあ ???東日本大震災 3月11日発生08月25日は 既に532日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------科学教室 豪雨被害とかけて外来種排斥ととく、その心は?毎年のように梅雨の終わりには豪雨被害が続き、そのたびごとに「記録的な」とか、今年は「過去に例の無いような」という修飾がつく。日本人は忘れやすいと言われるけれど、「記録的」、「過去に例がないような」と言われる豪雨、たとえば今年の九州の豪雨はちょっと前の諫早、長崎などの雨に比較して、たった「2分の1かそれ以下」である。でも、なぜ、それをNHKは報道せずに、被害に遭った人をテレビに出して「私の人生で初めてですね・・・」と語らせるのだろうか? これには国民が知らない大きな策略がある。毎年、「記録的な」豪雨が降り、被害と犠牲者が出る。そして、国土交通省は「旧に復す」と言って元の危険な地形に戻し、気象庁は「定量的な数値を曖昧な表現にして防災ができなくする」という方向に熱心で、いつまで経ってもコンピュータによる予想を詳しく出して防災と提携しようとしない。かくして毎年、被害がでると「旧に復し」、またしばらく経つと同じ規模の豪雨で工事をして儲け、そしてまた「旧に復す」事を続けている。つまり、旧に復するというのは「また災害に遭う」ということだが、その方が好都合な人が多い。人の命よりお金なのかも知れない。・・・・・・・・・このところ、すこしなりを潜めているが、「外来種の排斥」が盛んだったことがある。日本というのは大陸から少し離れているので、歴史的に見ると、時々外来種が入ってきて日本に定着する。オーストラリアやガラパゴス諸島ほど離れていないので、日本に完璧に独自の生物が住んでいるという訳でもなく、完璧に外来種と交配しているわけでもない。それが日本列島の生物の多様性を産んでいる。食材でも、キャベツ、サツマイモ、唐辛子・・・外来種ばかりだ。また、日本の紅葉が世界でも色鮮やかなのは適当な外来種が入っているからである。外来種というのは排斥できない。もしその種が日本の気候風土に合っていて競争力が強ければ残って、2,300年経つとすっかり「日本の生物」になる。だから生物学的には問題はない。このことは生物学者にも確認してある。ところが、外来種排斥で一儲けしようとする人たちがいる。「日本で競争力のある」外来種に目をつけ、「駆除しなければならない」という世論作りをして、外来種排斥補助金を獲得する。実に巧みで、数年ごとにかなりのお金をせしめて外来種を駆除する。でも100%の駆除は行わない。100%駆除すると一回しかお金をもらえない。だから90%駆除する。そうすると残りの10%がまた数年後に100にふえるので、また駆除するための補助金をもらえるというわけだ。・・・・・・・・・豪雨被害とかけて外来種排斥と解く、その心は「金」。だから、これは科学の問題ではない。科学の問題ではないものを科学教室に持ち込むことが学校ではやっているけれど、やはり科学教室は科学の心で進めたいものだ。(平成24年8月18日)なるへそはた坊
2012.08.25
コメント(2)
-

ニラ 猛暑でも 元気 東日本大震災532日後に
昨年 ニラの収穫の予定今年は3月から どんどんと収穫している庭のニラ あちこち どんどん葉が出てきている-収穫中g-22 ここも発芽してきた 3月6日m-08 発芽してきたのは2月28日庭のニラ たくさんあるのでどんどん収穫収穫3月05日 初の収穫をした 今年は早いぞ3月12日 2回目の収穫をした3月20日 3回目の収穫をした3月27日 4回目の収穫をした4月03日 5回目の収穫をした4月12日 6回目の収穫をした4月20日 7回目の収穫をした4月28日 8回目の収穫をした5月08日 9回目の収穫をした5月22日 10回目の収穫をした5月29日 11回目の収穫をした6月05日 12回目の収穫をした6月12日 13回目の収穫をした6月26日 14回目の収穫をした7月03-10-17-24-31日 収穫しなかった8月07日 15回目の収穫をした8月21日 花の蕾があちこちに出てきている8月28日 g22のニラ 3wkでやっと回復した しかし花蕾だらけになってきている9月18日 m08のニラ 収穫をしておいたニラは元気だなあ3月-4回4月-4回5月-3回6月-3回と もう14回の収穫をした7月- 0回 7月は収穫していない さすがに ニラも多すぎた感じになっている8月- 1回 これで15回目の収穫 g229月- 1回 これで16回目の収穫 m0810月 -1回 これで17回目の収穫 g-2211月 -m08の分 まだ冷蔵庫に在庫があるので 収穫はしなかった12月 -庭のニラ すこし収穫した 1回 合計で18回の収穫をした 今年 01月09日 m08のニラは枯れ草になっていたニラが枯れてしまった 在庫はなしになった次は3月になると 新芽が出るだろう02月26日 ニラ 新芽が出てきている 春だなあ そろそろ青くなってきてくれそう03月04日 ニラ 新芽が増えてきている 早く青くなれーーーーー03月18日 ニラ かなり前面に芽が出てきている今年のニラ 収穫は4月から 開始だなあ04月08日 今年の収穫は1回目となる 初の収穫だけど 昨年より遅い04月22日 2回目の収穫した05月03日 3回目の収穫をした05月13日 4回目の収穫をした05月20日 5回目の収穫をした06月10日 6回目の収穫をした06月30日 7回目の収穫をした07月08日 8回目の収穫をした07月15日 9回目の収穫をした07月22日 10回目の収穫をした08月05日 11回目の収穫をした08月12日 12回目の収穫をした08月19日 13回目の収穫をしたにら 庭にもあるので 便利 いつでも収穫 どんどん 食べよう猛暑だけど ニラは元気に育っているすばらしーーーい東日本大震災 3月11日発生08月25日は 既に532日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------科学教室 豪雨被害とかけて外来種排斥ととく、その心は?毎年のように梅雨の終わりには豪雨被害が続き、そのたびごとに「記録的な」とか、今年は「過去に例の無いような」という修飾がつく。日本人は忘れやすいと言われるけれど、「記録的」、「過去に例がないような」と言われる豪雨、たとえば今年の九州の豪雨はちょっと前の諫早、長崎などの雨に比較して、たった「2分の1かそれ以下」である。でも、なぜ、それをNHKは報道せずに、被害に遭った人をテレビに出して「私の人生で初めてですね・・・」と語らせるのだろうか? これには国民が知らない大きな策略がある。毎年、「記録的な」豪雨が降り、被害と犠牲者が出る。そして、国土交通省は「旧に復す」と言って元の危険な地形に戻し、気象庁は「定量的な数値を曖昧な表現にして防災ができなくする」という方向に熱心で、いつまで経ってもコンピュータによる予想を詳しく出して防災と提携しようとしない。かくして毎年、被害がでると「旧に復し」、またしばらく経つと同じ規模の豪雨で工事をして儲け、そしてまた「旧に復す」事を続けている。つまり、旧に復するというのは「また災害に遭う」ということだが、その方が好都合な人が多い。人の命よりお金なのかも知れない。・・・・・・・・・このところ、すこしなりを潜めているが、「外来種の排斥」が盛んだったことがある。日本というのは大陸から少し離れているので、歴史的に見ると、時々外来種が入ってきて日本に定着する。オーストラリアやガラパゴス諸島ほど離れていないので、日本に完璧に独自の生物が住んでいるという訳でもなく、完璧に外来種と交配しているわけでもない。それが日本列島の生物の多様性を産んでいる。食材でも、キャベツ、サツマイモ、唐辛子・・・外来種ばかりだ。また、日本の紅葉が世界でも色鮮やかなのは適当な外来種が入っているからである。外来種というのは排斥できない。もしその種が日本の気候風土に合っていて競争力が強ければ残って、2,300年経つとすっかり「日本の生物」になる。だから生物学的には問題はない。このことは生物学者にも確認してある。ところが、外来種排斥で一儲けしようとする人たちがいる。「日本で競争力のある」外来種に目をつけ、「駆除しなければならない」という世論作りをして、外来種排斥補助金を獲得する。実に巧みで、数年ごとにかなりのお金をせしめて外来種を駆除する。でも100%の駆除は行わない。100%駆除すると一回しかお金をもらえない。だから90%駆除する。そうすると残りの10%がまた数年後に100にふえるので、また駆除するための補助金をもらえるというわけだ。・・・・・・・・・豪雨被害とかけて外来種排斥と解く、その心は「金」。だから、これは科学の問題ではない。科学の問題ではないものを科学教室に持ち込むことが学校ではやっているけれど、やはり科学教室は科学の心で進めたいものだ。(平成24年8月18日)なるへそはた坊
2012.08.25
コメント(0)
-

オクラ 実がすこしだけ 猛暑のせいかな 東日本大震災532日後に
昨年のオクラ5月03日 種まきした 昨年の保存した種5月15日 まだ 発芽しない5月22日 まだ 発芽しない 種みるが そのまま 発芽しないようだなあ ???今年の発芽は どうも失敗となったみたい 種の保存がよくなかったのかな ??種を買ってきて 再度 種まきをしよう5月22日 種をかってきて再度の種まきをした5月28日 まだ発芽していない 遅いなあ5月30日 発芽した おお 結構と時間がかかるが カバーもしているので okだ06月05日 畑に移動した g-10に移動ok 20本06月19日 苗は無事に育ちつつある ok06月29日 苗はすこし生長してきている 雑草を取り除いておく07月10日 そのご 苗も大きくなりつつある07月17日 初の収穫だ 4個あり第二弾の種の種まき06月05日 2回目も種まき06月11日 すこし発芽してきている06月12日 移動だ m08の畑に移動した 8本06月19日 苗は無事に育ちつつある ok06月29日 こちらの苗もok 無事である 問題はなし07月10日 そのご 苗も大きくなりつつある 07月17日 初の収穫だ 4個あり 花があちこちで咲いている07月24日 25個の収穫をしておく 本格的に実が付き出した07月31日 30本の収穫をしておく 合計59個08月07日 30個の収穫をしておく 合計89個08月13日 20個の収穫をしておく 合計109個08月20日 20個の収穫をしておく 合計129個08月28日 20個の収穫をしておく 合計149個09月04日 20個の収穫をしておく 合計169個09月11日 20個の収穫をしておく 合計189個09月18日 20個の収穫をしておく 合計209個09月23日 30個の収穫をしておく 合計239個10月01日 30個の収穫をしておく 合計269個10月10日 20個の収穫をしておく 合計289個10月16日 10個の収穫をしておく 合計299個10月22日 10個の収穫をしておく 合計309個7月17日より収穫を開始 ただいま 309個今年のオクラ04月08日 オクラの種を買ってきておいた今年も5月より種まきをしよう04月30日 庭で種まきをしておく05月10日 発芽してきている 16pots 10日かかる05月13日 g-22の畑に移動 植え付けしておいた05月20日 苗は無事 16本くらいある06月17日 なんとか育ちつつある これでokだなあ06月30日 花がついている 順調に育ちつつある予備として オクラの種まき 第二弾05月27日 追加で庭で種まきをしておく06月03日 発芽した すこしだけ 5本くらいかな残っているのは06月10日 畑に移動する m-06に植え付けた06月17日 残っているのは 2本だけ まあ 予備なのでokオクラ 花も咲き出した なんとか育ちつつある07月08日 良く見ると 実があちこちに付いている 収穫をしておいた15個07月11日 2回目の収穫をした15個07月16日 3回目の収穫をした30個07月19日 4回目の収穫をした20個07月22日 5回目の収穫をした20個07月29日 6回目の収穫をした30個08月05日 7回目の収穫をした30個08月12日 8回目の収穫 8個08月19日 9回目の収穫 2個勢いが弱ってきているかな さすがに7月8日から 15+15+30+20+20+30+30+8+2=170個東日本大震災 3月11日発生08月25日は 既に532日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------科学教室 豪雨被害とかけて外来種排斥ととく、その心は?毎年のように梅雨の終わりには豪雨被害が続き、そのたびごとに「記録的な」とか、今年は「過去に例の無いような」という修飾がつく。日本人は忘れやすいと言われるけれど、「記録的」、「過去に例がないような」と言われる豪雨、たとえば今年の九州の豪雨はちょっと前の諫早、長崎などの雨に比較して、たった「2分の1かそれ以下」である。でも、なぜ、それをNHKは報道せずに、被害に遭った人をテレビに出して「私の人生で初めてですね・・・」と語らせるのだろうか? これには国民が知らない大きな策略がある。毎年、「記録的な」豪雨が降り、被害と犠牲者が出る。そして、国土交通省は「旧に復す」と言って元の危険な地形に戻し、気象庁は「定量的な数値を曖昧な表現にして防災ができなくする」という方向に熱心で、いつまで経ってもコンピュータによる予想を詳しく出して防災と提携しようとしない。かくして毎年、被害がでると「旧に復し」、またしばらく経つと同じ規模の豪雨で工事をして儲け、そしてまた「旧に復す」事を続けている。つまり、旧に復するというのは「また災害に遭う」ということだが、その方が好都合な人が多い。人の命よりお金なのかも知れない。・・・・・・・・・このところ、すこしなりを潜めているが、「外来種の排斥」が盛んだったことがある。日本というのは大陸から少し離れているので、歴史的に見ると、時々外来種が入ってきて日本に定着する。オーストラリアやガラパゴス諸島ほど離れていないので、日本に完璧に独自の生物が住んでいるという訳でもなく、完璧に外来種と交配しているわけでもない。それが日本列島の生物の多様性を産んでいる。食材でも、キャベツ、サツマイモ、唐辛子・・・外来種ばかりだ。また、日本の紅葉が世界でも色鮮やかなのは適当な外来種が入っているからである。外来種というのは排斥できない。もしその種が日本の気候風土に合っていて競争力が強ければ残って、2,300年経つとすっかり「日本の生物」になる。だから生物学的には問題はない。このことは生物学者にも確認してある。ところが、外来種排斥で一儲けしようとする人たちがいる。「日本で競争力のある」外来種に目をつけ、「駆除しなければならない」という世論作りをして、外来種排斥補助金を獲得する。実に巧みで、数年ごとにかなりのお金をせしめて外来種を駆除する。でも100%の駆除は行わない。100%駆除すると一回しかお金をもらえない。だから90%駆除する。そうすると残りの10%がまた数年後に100にふえるので、また駆除するための補助金をもらえるというわけだ。・・・・・・・・・豪雨被害とかけて外来種排斥と解く、その心は「金」。だから、これは科学の問題ではない。科学の問題ではないものを科学教室に持ち込むことが学校ではやっているけれど、やはり科学教室は科学の心で進めたいものだ。(平成24年8月18日)なるへそはた坊
2012.08.25
コメント(2)
-

キュウリの第五弾 生育中 でも 育つかな ??? 東日本大震災531日後に
今年もきゅうりhcでの苗は売っているが まだ寒そうとりあえず 種のほうは買っておいた苗は来週くらいにしようかな ???04月22日 hcで苗を探しに行く 小さいが北進があったので6個をかっておく 植え付け04月28日 苗は畑で無事だ サイズは変わらず 05月06日 まあまあ すこしは成長しつつある05月20日 上に伸びてきている 支柱が必要05月27日 支柱をつけておく ついでに小さいキュウリを収穫しておく06月01日 2回目の収穫は2本を06月03日 3回目の収穫は4本06月06日 4回目の収穫は6本06月10日 5回目の収穫は3本06月13日 6回目の収穫は5本06月17日 7回目の収穫は8本06月20日 8回目の収穫は8本06月23日 9回目の収穫は6本06月26日 10回目の収穫は4本06月29日 11回目の収穫は10本07月01日 12回目の収穫は02本07月04日 13回目の収穫は05本07月08日 14回目の収穫は04本07月11日 15回目の収穫は10本07月14日 16回目の収穫は08本種まき 第二弾04月22日 同時に種まきを開始しておく 8potsを04月28日 1個の芽が出てきている しめしめ05月06日 g-10の畑に移動した05月20日 8本ともに無事 すこし成長した05月27日 蔓が延びてきている06月06日 第二弾のキュウリの生長も開始 実もそろそろかも06月17日 かなり横に横に伸びてきている 実も小さいがついている06月23日 1回目の収穫 19本もあった 多すぎだなあ06月26日 2回目の収穫 11本06月29日 3回目の収穫 20本07月01日 4回目の収穫 07本07月04日 5回目の収穫 15本07月08日 6回目の収穫 16本07月11日 7回目の収穫は10本07月19日 8回目の収穫は08本第三弾のキュウリ05月27日 庭で種まきをしておいた06月02日 発芽した06月06日 次に日曜には畑に移動しよう06月10日 畑に移動 m-06の畑に植え付けた07月08日 蔓は延びてきている07月19日 1回目の収穫 12本07月28日 2回目の収穫 07本 落ち着いてきている第四弾の種まき06月10日 庭で8potに種まきをしておいた06月15日 発芽してきている06月23日 畑に移動 g-22に植え付けておいた07月08日 5本くらいは 無事第五弾は会社で種まき08月09日 会社で通行人からキュウリの種をもらう08月10日 もらった種 会社の土に植えておく08月13日 発芽した08月19日 双葉になっているが 育つかな ????収穫した分は 第一弾 5月27日から 合計で5+2+4+6+3+5+8+8+6+4+10+2+5+4+10+8+8+6=104本第二弾 6月23日から 合計で19+11+20+07+15+16+10+8+10=116本第三弾 7月19日から 合計で12+2+7+5+10 =36本第四弾 8月04日から 合計で1+2 =3本第五弾 キュウリ 次は第4弾の分 いよいよ収穫に入るしかし 第四弾のキュウリ 実が付かなくなった もう そろそろ お終いかな ????第五弾を育てているが これは会社で育てている 実がつくかな ?????東日本大震災 3月11日発生08月24日は 既に531日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------時事寸評 イワシにプルトニウムか? シロアリ駆除にも??福島県沖のアイナメに規制値の285倍(法律的に合理的な規制から言えば、712倍になる。つまり今の食品安全基準は法律の規定に反して「内部被曝だけで1年1ミリ」になっている。本当に法規を守るなら 、「外部+内部」だから、1年0.4ミリ程度となる)のセシウムが観測されました。この測定が東電の測定であることに多くの人が違和感を感じています。東電も事故発生の原因を作ったのだから、当然、周囲環境のモニタリングは義務ですが、国が国民を守る立場なのだから、国からも同じような測定が必要でしょう。でも、もっと厳しい内容のものがイワシで出ています。千葉県産のイワシでトリウム234とプルトアクチニウム234mという聞き慣れない放射性物質が検出されました。読者の方からの情報で私も知りました。7月30日に鹿島沖から水揚げされたもので、セシウムが1キロ0.3ベクレル程度、そのほかに上記の元素が10から30ベクレル程度、検出されています。1)一体、トリウムとかプルトアクチニウムってなにか?2) それは何を意味しているか?3) 現実に危険か?について解説をいたします。ウランなどの重たく不安定な元素は、その元素ができたときから放射線を出し続けて崩壊しています。多くの放射性元素も崩壊するのですが、ウラン、トリウムなどの元素は、「ウランが壊れてできたトリウムがさらに崩壊し、それがラジウムやラドンなどとドンドン崩壊して最後に鉛になるまで14ぐらいの放射線元素を出します。このことを普通「崩壊系列」といって、ウラン(ウラン238)があれば、次から次へと放射性物質ができて、ウランがなくなるまでその系列にある放射性元素はほぼ同じ放射線を出しています。イワシの中で見つかったトリウムやプルトアクチニウムというのは、このウラン系列のもので、つまりイワシの中にはウラン系列の放射性物質がまんべんなくあるか、もしかするとイワシがトリウムやプルトアクチニウムだけを選んで取り込んだか、どちらかです。だから、この系列のものが一つ見つかると、普通は14から15ヶの放射性元素が同時に見つかり、どの元素も同じ放射線を出しますから、一つが30ベクレルなら、キログラム450ベクレルはあると推定されます。ウランの崩壊元素の規制値はほぼ1キログラム1万ベクレルで、通常はその10分の1の1000ベクレルで注意をしますので、まだそこには達していないことになります。でも、ウランは「核分裂でできたもの」ではなく「原料」です。その意味ではウランがあればプルトニウムもある(3号機)ということになりますから、この測定値はかなり危険な事になると言うことです。しばらく注意をします。・・・・・・・・・ところが、ほぼ同時にシロアリ駆除剤として、ウラン系列と同じようなネプツニウム系列の放射性物質が使われていることがわかりました。これも読者の方からのご連絡ですが、読者の方が放射線がないはずのところで線量計で測ったら毎時0.20マイクロシーベルトだったので、ビックリして、その原因を探したらシロアリ駆除剤であることが分かったのです。シロアリ駆除剤にネプツニウム系列の元素が使われていることは知られていますが、それでも法規で決まっている1年1ミリ以下になるように(つまり毎時0.11マイクロシーベルト以下。自然放射線の0.04マイクロを足しても0.15マイクロシーベルトを超えてはいけないので、違法なシロアリ駆除剤ということになります。普段なら放射線の被曝が少ないので、問題にならなかったと思いますが、今は、イワシからも、アイナメからも、シロアリ駆除剤からも、地面からも放射性物質の被曝を受ける(足し算)ですので、政府はもっと本腰になって国民の被曝を止めなければならないでしょう。放射性ヨウ素の問題も謎のままで、次々とこのようなことが起こるのを一刻も早く止める必要があります。このようなことは前向きに進めればすぐ解決します。風評もなくなります。つまり政府が「法規を守る」と宣言し、法規に基づいた具体的な規制を決め、それをシッカリ守る姿勢を示せば、解決することです。また日本には多くの国立研究所がありますから、でてくるデータを次々と解析して説明をすれば良いとおもいます。特に巨大な地球コンピュータなどを「税金」で保有しているのですから、それを有効に使うべきです。また原発の再開に当たっては、2011年の福島の方の苦痛が、次の事故の時に起こらないように至急、検討をしておく必要があります。今でも政府、東電は「福島原発事故は事故ではない。死人がでていないのだから、誰も被害を受けていない。だから原発は再開できる」というスタンスですが、私には国民に責任を持った政治、社会的責任のある企業とは考えられません。(平成24年8月22日なるぼどはた坊
2012.08.24
コメント(0)
-
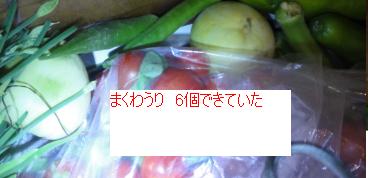
まくわうり 畑の分も6個を収穫をした 東日本大震災531日後に
昨年のうりまずは まくわウリ 2個の苗を買ってきた04月03日 2個のマクワウリ とりあえず購入しておいた04月10日 畑のm-20に植え付けした05月08日 そのままのサイズ 成長はしていない まだ 早すぎなのかな ??05月15日 そろそろ 苗も生長してきそうだ そろそろ かな ??05月28日 蔓が延びてきている 成長を開始したようだなあ ok/ok/ok06月12日 すこし伸びているが あまり元気はないかな ??07月10日 まくわうりの1個の実がなっている 収穫したついでに 種からの栽培も05月03日 種まきした 庭で potに種まき05月11日 発芽してきた おお 雨がふったので 発芽だな05月13日 あら あら ない ?? ナメクジさんが食べてしまった 失敗だまた 種まきしよう トライ アゲイン05月22日 再度の種まきをする05月28日 まだ発芽していない が なめくじさんが入れないようにカバーをつける06月05日 発芽した 大成功だなあ06月12日 畑に移動 m-08に植え付けをした07月10日 苗も大きくなりつつある そのうち実もなるだろう 期待は大07月31日 そろそろ実が付き出した ゴロゴロとしてきている08月06日 2個の収穫をした 黄色のまくわうりだ08月14日 8個の収穫をした08月20日 青い実も5個あった08月21日 黄色の実20個を収穫しておいた これで終了no1からは 実が1個no3からは 実が35個 これにて 終了今年もうりさんまずは ニューメロンから04月08日 とりあえず hcで買い物をしてきた まだ寒そうもう すこし待とう04月22日 種まきを開始 庭でpotに8個 種まきしておいた04月29日 まだ発芽せず05月05日 発芽した 遅いなあ 畑に移動 g-10に植えておく06月03日 そのご 生育していたが 小さいまま 気温が低いのかな 06月17日 残っているのは1本くらい すこし成長してきている06月24日 1本のみ残り すこし成長してはいるが 1本のみ07月15日 1本のみ なんとか育っているが 実がつくのかどうか ?????07月29日 実が2個ついていた マクワウリ次に 第二弾05月27日 庭で種まきをした06月06日 やっと発芽してきている 06月10日 畑に移動した m-06の畑に06月17日 すこし落ち着いてきている 何本残るか ????06月24日 8本くらいは残っている が 小さいな07月15日 蔓が延びてきている なんとかなるかなあ ???07月29日 実ができていない なし ???08月05日 小さい実がすこしついてきている 08月19日 6個の実があったので 収穫しておいた今年のマクワウリ畑で8本くらい g-10では生育中野は1本だけ 消えた 実が2個ついた庭で発芽したのが8pot m-06に植えている 8本残っている 実は小さいの 数個会社でも2本 育てている これは150cmくらいになっている07月15日 蔓は良く伸びている2mくらいになっている 実も3個ついている07月29日 実が6個目がついている 収穫したのは2個 08月03日 実がまた6個ついている 2個 また収穫しておく08月19日 追加の実が4個 また 出来ている結果畑のは実は2個+6個 で 合計8個会社のは実が10個 その後追加で4個の実がついた 合計14個に 畑の負け東日本大震災 3月11日発生08月24日は 既に531日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------時事寸評 イワシにプルトニウムか? シロアリ駆除にも??福島県沖のアイナメに規制値の285倍(法律的に合理的な規制から言えば、712倍になる。つまり今の食品安全基準は法律の規定に反して「内部被曝だけで1年1ミリ」になっている。本当に法規を守るなら 、「外部+内部」だから、1年0.4ミリ程度となる)のセシウムが観測されました。この測定が東電の測定であることに多くの人が違和感を感じています。東電も事故発生の原因を作ったのだから、当然、周囲環境のモニタリングは義務ですが、国が国民を守る立場なのだから、国からも同じような測定が必要でしょう。でも、もっと厳しい内容のものがイワシで出ています。千葉県産のイワシでトリウム234とプルトアクチニウム234mという聞き慣れない放射性物質が検出されました。読者の方からの情報で私も知りました。7月30日に鹿島沖から水揚げされたもので、セシウムが1キロ0.3ベクレル程度、そのほかに上記の元素が10から30ベクレル程度、検出されています。1)一体、トリウムとかプルトアクチニウムってなにか?2) それは何を意味しているか?3) 現実に危険か?について解説をいたします。ウランなどの重たく不安定な元素は、その元素ができたときから放射線を出し続けて崩壊しています。多くの放射性元素も崩壊するのですが、ウラン、トリウムなどの元素は、「ウランが壊れてできたトリウムがさらに崩壊し、それがラジウムやラドンなどとドンドン崩壊して最後に鉛になるまで14ぐらいの放射線元素を出します。このことを普通「崩壊系列」といって、ウラン(ウラン238)があれば、次から次へと放射性物質ができて、ウランがなくなるまでその系列にある放射性元素はほぼ同じ放射線を出しています。イワシの中で見つかったトリウムやプルトアクチニウムというのは、このウラン系列のもので、つまりイワシの中にはウラン系列の放射性物質がまんべんなくあるか、もしかするとイワシがトリウムやプルトアクチニウムだけを選んで取り込んだか、どちらかです。だから、この系列のものが一つ見つかると、普通は14から15ヶの放射性元素が同時に見つかり、どの元素も同じ放射線を出しますから、一つが30ベクレルなら、キログラム450ベクレルはあると推定されます。ウランの崩壊元素の規制値はほぼ1キログラム1万ベクレルで、通常はその10分の1の1000ベクレルで注意をしますので、まだそこには達していないことになります。でも、ウランは「核分裂でできたもの」ではなく「原料」です。その意味ではウランがあればプルトニウムもある(3号機)ということになりますから、この測定値はかなり危険な事になると言うことです。しばらく注意をします。・・・・・・・・・ところが、ほぼ同時にシロアリ駆除剤として、ウラン系列と同じようなネプツニウム系列の放射性物質が使われていることがわかりました。これも読者の方からのご連絡ですが、読者の方が放射線がないはずのところで線量計で測ったら毎時0.20マイクロシーベルトだったので、ビックリして、その原因を探したらシロアリ駆除剤であることが分かったのです。シロアリ駆除剤にネプツニウム系列の元素が使われていることは知られていますが、それでも法規で決まっている1年1ミリ以下になるように(つまり毎時0.11マイクロシーベルト以下。自然放射線の0.04マイクロを足しても0.15マイクロシーベルトを超えてはいけないので、違法なシロアリ駆除剤ということになります。普段なら放射線の被曝が少ないので、問題にならなかったと思いますが、今は、イワシからも、アイナメからも、シロアリ駆除剤からも、地面からも放射性物質の被曝を受ける(足し算)ですので、政府はもっと本腰になって国民の被曝を止めなければならないでしょう。放射性ヨウ素の問題も謎のままで、次々とこのようなことが起こるのを一刻も早く止める必要があります。このようなことは前向きに進めればすぐ解決します。風評もなくなります。つまり政府が「法規を守る」と宣言し、法規に基づいた具体的な規制を決め、それをシッカリ守る姿勢を示せば、解決することです。また日本には多くの国立研究所がありますから、でてくるデータを次々と解析して説明をすれば良いとおもいます。特に巨大な地球コンピュータなどを「税金」で保有しているのですから、それを有効に使うべきです。また原発の再開に当たっては、2011年の福島の方の苦痛が、次の事故の時に起こらないように至急、検討をしておく必要があります。今でも政府、東電は「福島原発事故は事故ではない。死人がでていないのだから、誰も被害を受けていない。だから原発は再開できる」というスタンスですが、私には国民に責任を持った政治、社会的責任のある企業とは考えられません。(平成24年8月22日なるぼどはた坊
2012.08.24
コメント(0)
-

今週は6個のゴーヤの収穫 東日本大震災530日後に
昨年のゴーヤ04月03日 hcでゴーヤの苗を購入 2本04月10日 畑のm-07に植え付け04月17日 枯れそうだけど まだ もっている04月23日 黄色になっている 持つかな ????04月24日 追加で1本の苗を植えておいた 合計で3個 風除けをつけておいた05月03日 苗の3本 緑色になりつつある 元気になってきた 水槽が役に立つ05月08日 ゴーヤが成長を開始している 水槽が役に立っている05月15日 支柱をつけておく これで3本が順調に生育していくだろう05月22日 その後無事05月29日 m-07の昨年の場所からこぼれ種の2本が発芽してきている 楽しみゴーヤ 枯れそうだったけれど これで安心3本とこぼれ種2本で 合計で5本となっている06月19日 2箇所でゴーヤの支柱を補強しておく07月17日 実がまだついていない 遅いなあ ????07月23日 やっと実がついていた けど 小さいのばかりだなあ とりあえず3個の収穫07月24日 追加で2個 小さいの収穫した07月31日 大きな実が取れだした 14個あり 葉の下に隠れていた08月07日 4個の収穫08月14日 4個の収穫08月21日 1個の収穫08月28日 1個の収穫09月02日 1個の収穫09月04日 1個の収穫09月11日 10個の収穫09月18日 3個の収穫09月23日 3個の収穫10月02日 3個の収穫ゴーヤの収穫50個にて 終了 不作だったけど まあまあ 今年のゴーヤ04月22日 hcでのなえ 58円のが売っていたので 即 お買い上げ 畑に植えた04月30日 そのご 畑で水槽をかぶせておいたので暖かくて 成長している風を防いで暖かくするには カバーが必要 暖かいとすぐに成長してくれている05月05日 カバーをつけて支柱をつけておいた これでok05月13日 その後もまだそのまま そんなに急には成長しない05月20日 鶏糞をどかーんといれておいた06月02日 先端の芽をカットしておく06月03日 小さい実がついてきている06月10日 蔓があちこちに延びてきている 06月24日 まだ 実はできていない もうすこしかかりそう07月01日 支柱にのびて2m-3mは蔓が延びている そろそろ 実もあるはず日曜は ゴーヤの実を捜そう07月08日 ゴーヤの実 1個はあった まだあるかもと探していたら 雀がいた 関係ないか07月11日 初の実 3個の収穫07月15日 2回目は6本の収穫07月19日 3回目は7本の収穫07月22日 4回目は6本の収穫07月28日 5回目は7本の収穫08月04日 6回目は10本の収穫08月05日 7回目は05本の収穫08月11日 8回目は22本の収穫08月19日 9回目は06本の収穫ゴーヤ これからどんどんと7月11日より 3+6+7+6+7+10+5+22+6 =72個今年のゴーヤは昨年より良い9月まで ゆっくりと収穫しよう東日本大震災 3月11日発生08月23日は 既に530日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------穏やかで常識的な政策 エネルギー政策このところ、日本の政策は振れ幅もおおきく、政策もあまりにも極端になっています。ここではエネルギー政策や環境政策から検討を始めますが、このような「科学系」の内容を含む政策ばかりではなく、「年金」、「減税」、「教育」などのお金や子供の政策もおおきくぶれて、国民が将来に安心感を持てなくなっています。そこで、このシリーズでは「穏やかで常識的な政策」を提案していきたいと思います。第一回は「エネルギー」で、順次、お金、外交などに進みたいと思います。・・・・・・・・・石油、石炭、天然ガス(シェールガスを含む)がいつ無くなるかは難しい問題です。石油会社は40年、国家レベルでは200年、そして資源学では1000年というところでしょうか。なぜ、このような違いが出てくるかというと、石油会社は「資源がないと言わないとガソリン価格が下がる」という事情があり、資源学は「鉱脈から言って、簡単にはなくならない」と考えていて、国家は利害関係があるので、中間的な数字を使っているということです。このような場合、「誰が何を言っているか」ではなく、「誰が何をしているか」から考えた方が正確に判断できます。石油、石炭、天然ガスなどを扱う会社はものすごく規模がおおきく、メジャーとかスーパーメジャーとか言われます。それらの会社は「残りあと40年」と口では言っていますが、心の中でそのように考えている節はありません。というのは、石油などは発見してからそれが出荷されるまで早くても20年ほどはかかります。だから、もし彼らの言うとおりに40年でなくなるとすると、彼らの仕事はおおむねあと20年でなくなってしまいます。比較的、小さな会社でも「残り20年のビジネス」ということになると、「それに変わる仕事を作っておかなければ」と考えます。つまり、「後40年」が本当であって、日本で話題になっている「自然エネルギー」が有望とすると、彼らは常に100年ほどの展望でビジネスをしていますので、自然エネルギーの開発に手を出しているはずですが、本腰は入っていません。つまり、素直に考えれば「資源がなくなるというのは価格のことを考えてのことで、100年以上は持つと内部では結論が出ている」と考えるべきでしょう。日本以外の外国の政府もそのように考えているからこそ、今後30年は化石燃料に依存する計画なのです。また、1970年代の第一次石油ショックで、「あと30年」と言われ大騒ぎをして、大きな損を出した日本ですが、もうすでに一回、ダマされていることを思い出す必要があります。「技術と資源」の話は別の機会にしますが、「日本には資源がない」と言いますが、それは「資源が枯渇しそうな場合に問題」であって、資源が充分にあれば、「資源セキュリティー」の問題は発生しません。今は、資源が比較的豊富にあるので、日本に技術があれば資源は容易に手に入るからです。たとえば、「自動車」という製品も資源の塊ですが、「自動車セキュリティー」という言葉はありません。自動車を生産していない国では「我が国は自動車を生産していないので、もし外国が輸出してくれないと困る」ということになりますが、そんな心配はしていないのです。つまり、資源も自動車も、資源であり、工業製品ですから(資源は今や工業製品)、食料などと違って国際的な商品なのです。ましてシェールガスは全世界に広がっていて少なくとも34カ国以上でとれるといわれています。自動車生産国以上の国の数です。・・・・・・・・・原発がエネルギーから外れた今、日本の基本政策は「当面、100年程度は化石燃料に依存する。技術を高めておく」というのが穏やかで常識的な政策なのです。世界各国が化石燃料に依存しているのに、日本だけが特殊な考えに染まっているのは、それなりの理由があるのですが、そろそろ「国際的感覚」をもって「日本に有利」に政策を切るべきと思います。そうしないと、私たちの世代は良くても、子供の世代はひどく貧乏な国になってしまいます。(平成24年8月20日)そうだなあはた坊
2012.08.23
コメント(0)
-

今週はナスビは3個のみ 東日本大震災530日後に
昨年のなすびhcで苗が売られていたので 6本を購入した04月03日 hcで苗を6本を購入した 苗はm06の畑に植え付けた04月09日 なすびが枯れてしまった ?? 強風と水が不足したのかな ??04月10日 再度hcでまた なすびの苗を6本を投入した 今度は枯らさないぞーー04月17日 追加の苗2本をさらに投入 ついでに なすびの種も購入しておいた 時差用04月24日 なすびの苗は 合計で8本 無事である 種もまこう どんどん作ろう05月08日 苗は元気だ 紫の色の葉はいきいきとしている05月15日 内の4本 調子が悪くなった ??? なんで ???05月22日 hcで代わりの4本の苗 追加で植えておく06月05日 ナスビの苗 10本くらいになっているが 育ちがまた悪くなってきた06月12日 2-3本が枯れてきた ??? どうなるかな よくないな ?07月03日 ナスビが雑草に隠れてしまっている 雑草取りをしたが背が低いままだなあ 07月17日 もう あとは枯れるだけみたいになってきた 小さい実をときどき収穫しているついでに 種からの栽培も 第二弾05月03日 種まきした 庭で potに種まき06月05日 畑に移動 g-10に植えておいた07月03日 3本は残って 成長中07月17日 こちらは そろそろ実が出来そう第三弾の種まきこれは 来週くらいにやろう06月05日 種まきしよう07月17日 こちらも大きくなりつつあるナスビの苗m06の苗 5本くらいが残っている 雑草に埋もれていた 雑草とりした 実がすこしno2-は 3本が生育中 大きくなりつつあるno3-は 10本くらいが生育中 大きくなりつつある会社では 2本の苗が生育中 実もついている 7/21日1本の収穫をしたナスビ 雑草とトマトとミニトマトに囲まれて 生育不調のままno2-3などに期待している no1は小さい実がすこし 収穫をしておいた07月03日 収穫は10個07月10日 収穫は2個 もう 小さい 小さい さっぱりだなあ07月13日 収穫を水曜に6個 これも小さいまま とりあえず 収穫たけはしておく07月17日 収穫は日曜に2個 さっぱりだなあ 07月24日 収穫は日曜にまた2個のみ さっばり ダメ07月31日 収穫は日曜に3個のみ08月07日 収穫は日曜に7個のみ ミニミニさいずのみ08月14日 収穫は日曜に10個のみ ミニミニばかり08月20日 土曜に10個 ミニミニ収穫08月21日 日曜に10個 ミニミニなど08月22日 会社のナスビ5個 収穫 これは大きい08月28日 日曜にナスビ10個ミニミニ収穫09月04日 日曜にナスビ10個ミニミニ収穫09月11日 日曜にナスビ30個ミニミニ収穫 実が増えてきている09月18日 日曜にナスビ30個 どんどん 収穫中09月25日 日曜にナスビ30個 収穫中10月02日 日曜にナスビ30個 収穫中10月10日 月曜にナスビ20個 収穫中10月16日 日曜にナスビ20個 収穫中10月22日 土曜にナスビ20個 収穫中10月30日 日曜にナスビ20個 これにて収穫を終了したなすび ミニミニも入れて287個にて 終了した後半の雨で 実も沢山ついてくれた まあまあということでナスビさんも撤去した今年のナスビ暖かくなるまで ゆっくりとする04月22日 今年はゆっくりして 暖かくなるまで待って 本日ナスビの苗6本を買ってきた04月30日 苗は無事にそだっている ok m-08の畑に植えている05月20日 なんとか持ちこたえている すこしは大きくなっている05月27日 6本のうち 5本が枯れそう 水遣りが日曜だけなので枯れてきた05月27日 追加で4本の苗をかってきて m06に植えておいた06月03日 さらに追加が4本の苗を庭のプランターに植えておくで 結局は6-5=1 で+4+4=合計9本の苗を育てている次は第二弾 種蒔きして秋茄子を育てる予定04月30日 庭で種蒔きをしておく 8potで種まきした05月20日 発芽せず これはダメだなあ第二弾の種まきのは 失敗 発芽せず時差でナスビをどんどん育てよう第三弾05月27日 庭でpotに種まきをしておく06月06日 やっと発芽している これで発芽したので そのまま育てていこう06月10日 発芽したのは畑に移動 m-06の畑に移動06月17日 苗は無事 07月08日 4本は無事 実もすこしだけ収穫できている08月05日 すこし大きくなりだしたくらい 実はすこしつきだした種がまだあるので ついでに第四弾だ06月10日 庭でpotに種まきしておく06月17日 まだ発芽せず いつも遅いなあ06月19日 やっと発芽してきている06月23日 畑に移動した g-22の畑の畝07月08日 何本かは 無事08月05日 2-3本はそだちつつある最期に第五弾06月24日 庭でpotに種まきをしておいた これで最終の予定07月01日 発芽していないけど そのまま畑に移動した m-20の畑に移動07月08日 何本かは 苗が無事に残っている08月05日 こちらも2-3本は育ちつつあるナスビの在庫畑 m07に6本 6本枯れてなくなった 実が1個のみ収穫畑 m06に追加で4本 収穫はまずは4個 その後4個の収穫 そのごすこし収穫畑 m06に発芽した苗すこし 4本くらい残っている畑 g22に発芽した苗をすこし 2-3本くらい残っている畑 m20にすこし こちらも2-3本くらい残っている庭 予備の苗3本 会社 4本のナスビ これが一番に元気にそだっている 苗で残っているのは 4本くらい 発芽したのはすこし そのうち 残っているのは8本くらい会社でのナスビ 収穫は15個畑のナスビ 15個の収穫畑のは 秋まで 待とう東日本大震災 3月11日発生08月23日は 既に530日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------穏やかで常識的な政策 エネルギー政策このところ、日本の政策は振れ幅もおおきく、政策もあまりにも極端になっています。ここではエネルギー政策や環境政策から検討を始めますが、このような「科学系」の内容を含む政策ばかりではなく、「年金」、「減税」、「教育」などのお金や子供の政策もおおきくぶれて、国民が将来に安心感を持てなくなっています。そこで、このシリーズでは「穏やかで常識的な政策」を提案していきたいと思います。第一回は「エネルギー」で、順次、お金、外交などに進みたいと思います。・・・・・・・・・石油、石炭、天然ガス(シェールガスを含む)がいつ無くなるかは難しい問題です。石油会社は40年、国家レベルでは200年、そして資源学では1000年というところでしょうか。なぜ、このような違いが出てくるかというと、石油会社は「資源がないと言わないとガソリン価格が下がる」という事情があり、資源学は「鉱脈から言って、簡単にはなくならない」と考えていて、国家は利害関係があるので、中間的な数字を使っているということです。このような場合、「誰が何を言っているか」ではなく、「誰が何をしているか」から考えた方が正確に判断できます。石油、石炭、天然ガスなどを扱う会社はものすごく規模がおおきく、メジャーとかスーパーメジャーとか言われます。それらの会社は「残りあと40年」と口では言っていますが、心の中でそのように考えている節はありません。というのは、石油などは発見してからそれが出荷されるまで早くても20年ほどはかかります。だから、もし彼らの言うとおりに40年でなくなるとすると、彼らの仕事はおおむねあと20年でなくなってしまいます。比較的、小さな会社でも「残り20年のビジネス」ということになると、「それに変わる仕事を作っておかなければ」と考えます。つまり、「後40年」が本当であって、日本で話題になっている「自然エネルギー」が有望とすると、彼らは常に100年ほどの展望でビジネスをしていますので、自然エネルギーの開発に手を出しているはずですが、本腰は入っていません。つまり、素直に考えれば「資源がなくなるというのは価格のことを考えてのことで、100年以上は持つと内部では結論が出ている」と考えるべきでしょう。日本以外の外国の政府もそのように考えているからこそ、今後30年は化石燃料に依存する計画なのです。また、1970年代の第一次石油ショックで、「あと30年」と言われ大騒ぎをして、大きな損を出した日本ですが、もうすでに一回、ダマされていることを思い出す必要があります。「技術と資源」の話は別の機会にしますが、「日本には資源がない」と言いますが、それは「資源が枯渇しそうな場合に問題」であって、資源が充分にあれば、「資源セキュリティー」の問題は発生しません。今は、資源が比較的豊富にあるので、日本に技術があれば資源は容易に手に入るからです。たとえば、「自動車」という製品も資源の塊ですが、「自動車セキュリティー」という言葉はありません。自動車を生産していない国では「我が国は自動車を生産していないので、もし外国が輸出してくれないと困る」ということになりますが、そんな心配はしていないのです。つまり、資源も自動車も、資源であり、工業製品ですから(資源は今や工業製品)、食料などと違って国際的な商品なのです。ましてシェールガスは全世界に広がっていて少なくとも34カ国以上でとれるといわれています。自動車生産国以上の国の数です。・・・・・・・・・原発がエネルギーから外れた今、日本の基本政策は「当面、100年程度は化石燃料に依存する。技術を高めておく」というのが穏やかで常識的な政策なのです。世界各国が化石燃料に依存しているのに、日本だけが特殊な考えに染まっているのは、それなりの理由があるのですが、そろそろ「国際的感覚」をもって「日本に有利」に政策を切るべきと思います。そうしないと、私たちの世代は良くても、子供の世代はひどく貧乏な国になってしまいます。(平成24年8月20日)そうだなあはた坊
2012.08.23
コメント(0)
-

干しネギ20本を購入した 東日本大震災529日後に
昨年の九条ネギの在庫ネギ坊主の種蒔きした苗 消滅したので 在庫は0ネギ坊主の残っているネギ 在庫は10本くらい10本のネギさん それぞれ分ケツして かなり大きくなってきている12月31日 1本の収穫01月04日 5本の収穫01月30日 2本の収穫02月06日 2本の収穫 で お終い種まきをしよう一年かけて ゆっくりと ネギつくり開始しよう畑をみたら 九条ネギ m08-1本とm20に1本 合計で2本あった これは 種用03月27日 hcで九条ネギの苗 2個を購入 これも畑に植えよう04月03日 苗の2個は 家のプランターでしばらく育てておこう04月10日 畑の葱坊主が どんどん出てきている04月17日 苗も無事 ネギ坊主も元気04月24日 そのごはok05月08日 在庫のネギはまあまあ 元気である05月22日 ネギ坊主の種を収穫した 乾燥させて 種まきしよう06月05日 種を乾燥したさせてから 種まきした 在庫のネギも植え替えとした22本06月12日 プランターの苗も畑に移動した 20本くらい畑に植えたネギ坊主も種を収穫し種まき06月05日 庭でネギ坊主からの種を種まきした06月12日 発芽してきている 数はたくさん無数にある 生き残りは20本くらい?07月10日 畑に移動した m07の畑の畝に植えた追加の種まき07月10日 庭で種まきをした プランターで2個に残りの種をばら撒いておいた07月17日 発芽してきている07月24日 そのままプランターで放置 大きくなったらまた畑に移動しよう干しネギの購入 20本09月04日 hcで安売りの99円で10本のネギ 苗を2つ購入してm-06の畑に植えた九条ネギの在庫ネギ坊主の2本の分 畑の在庫のネギ10本は m-07の畝に植え替えしたm20の1本の分 畑のm08の畝に移動 これは成長中 20本苗 20本 プランターで栽培中のは畑に移動した m-07に10本ネギ坊主の種 庭で種まきをして発芽した 10本 これもm-07に移動第二弾の種まき 発芽した 20本くらいを期待 サイズは松葉くらい もうなし干しネギ 20本をm-06に植えつけた 残ったのは6本くらい全部で 合計10+20++10+10+6=56本くらいになりそう これを12月に収穫する??松葉サイズの20本は無理 その後に育てるとする56本の在庫08月05日 雑草とりをしておいた ネギさん無事である09月28日 土寄せをしておいた10月16日 九条ネギ 追肥してやや大きくなりだした 元気である 在庫は56本10月23日 まあまあ 順調に成長している 小さい苗もすこしは生長しているようだ11月20日 籾殻をかけておく これで根っ子が白くなってくれるはず11月27日 まあまあ成長してくれている12月04日 籾殻がたっぶりなので やわらかくなりつつあるネギの苗 まったく小さい20本10月23日にみたら すこしは大きくなりだしているみたい ?? かな ??11月06日 残りの小さい苗も畑に移動した これで生育もよくなるはず ???11月20日 なんとか畑に残っているが 小さいまま12月04日 こちらは そのまま 特に変化はなし九条ネギ あとは12月の末まで 待つのみ 収穫は1月から01月04日 九条ネギも収穫した 根っ子が白い いい感じになっている 小さいが01月15日 つづいて少しを収穫しておいた01月22日 残りもほとんど収穫した 残りはわづか01月29日 すこし収穫した02月05日 すこし収穫した02月12日 すこし収穫した02月19日 すこし収穫した02月26日 すこし収穫した03月04日 これでお終い九条ネギ 収穫は終わり今年の九条ネギの在庫これから また 残りを来年用として 育てようm07 50本くらい残っているm08 12本くらいの小さい苗g-10にも1本ネギがあった家の庭で小さい中が10本合計73本 これをこれから育てていこう04月01日 m-08-30本のネギ坊主さんかできてきているぞ04月08日 m-07-30本のには ネギ坊主はついていない05月03日 m-07のネギにも ネギ坊主がたくさんついてきた ネギ坊主を収穫しておく05月20日 全部のネギのネギ坊主をどんどんCUT/CUT/CUT06月10日 ネギ坊主がまだまだ出てきているが cut/cut/cut07月22日 その後のも 九条ネギは元気である さすがに九条ネギ 元気だなあ08月05日 九条ネギの在庫は元気だもう ネギさん 固く固くなってきている下仁田ネギは元気はないけど九条ネギは元気そのもの 見た目も元気だ 分ケツも盛んなりhcで 干しネギの九条ネギが販売されているが 在庫があるので 干しネギは不要なりと 思っていたが 気がつくと hcでの干しネギを2束も買ってしまったあらあら 不要の予定が ついつい 買い物していると いうのは m07-50本が消滅したそれに 庭の在庫も0本となっているあるのは m08-12本とg10-1本のみとなっている73本もあったのが 13本のみとなってしまっているで hcの干しネギ20本を購入したこれで 在庫は33本となった東日本大震災 3月11日発生08月22日は 既に529日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------穏やかで常識的な政策 外交政策竹島、尖閣諸島、北方四島、中国の防衛線などの近隣諸国との領土や海の問題がこじれています。外交の基本から言って、「穏やかで常識的」な外交政策とは何でしょうか?外交の第一は「力」です。力には三種類あって、1)防衛、2)経済力(技術)、3)文化 です。強大な防衛力をもって他国を抑えることを本格的にやっているのがアメリカで、だからこそ、アフガニスタン、日本のように本国から遠く離れているのに、力を持っています。日本は自衛隊がかなり強い戦力ですが、軍隊ではないので、それなりに弱いところがあります。戦後70年、日本人が軍事をどのように考えるのか、それが外交問題の第一であることは間違い有りません。軍事力の議論ができない国が外交で失敗するのは仕方が無いことでしょう。第二には「経済力(技術力)」です。かつて日本の技術に頼る必要があった時には中国は日本に余る強くでることができませんでしたが、最近ではGDPが日本を上回り、独自の技術もできてきたので、日本をおおっぴらに非難することが可能になりました。第三には文化です。文化の力は短期間には弱いものですが、国と国の力のように長い間のものでは力を発揮します。フランスがその良い例で、フランスという国は人口6300万人ほどの小さな国で、しかも農業国ですが、フランス大統領はアメリカ大統領をそれほど違わないように振る舞えます。フランスと言えば花のパリ。その歴史と文化は誰もが認めるところです。アジアでも最近の中国はお金だけのように見えますが、かつては漢字文化を持ち、文化の力で周囲の国に光を与えたこともありました。どうも最近の中国は強面で、軍事力とお金を背景に脅してくるような感じもしますが、かつてのように高い文化で影響を与えて欲しいものです。従って、外交の第一の条件、中国という世界の3大国に囲まれた国は、力が大切です。この世界は「人格」や「犠牲」、「恩」などで力を発揮するところまで言っていません。でも、日本はサボってきました。自衛隊の予算は年々、減少していますし、もちろんその状態は中国も韓国もよく知っています。技術は「日本が1番でなくても良い」という有名な発言ですが、日本はアメリカ、ロシア、中国に囲まれていますから、世界一でなければやられてしまいます。「ゆとりの教育」は創造性や考える力を養うという点では間違っている訳ではありませんが、単に「ゆとり」だけを作ってしまえば日本は崩壊してしまいます。技術者が圧迫される社会は日本では危険です。学力、文化ともに日本の力はあまり上がっていません。そこに隙があります。・・・・・・・・まず、外交の基本は「力」ですから、日本は力を持たないと外国と対抗することはできない。外国は隙を狙っているのです。それを警戒しない日本人の方に間違いがあると考えるべきでしょう。・・・・・・・・外交のもう一つが「口先」です。常に日本の正当性と近隣諸国との親善を言い続けるということです。尖閣諸島も竹島も北方四島も歴史的に日本の領土ですから、それを常に国際社会に対して訴え続ける必要があります。いきなり「竹島は日本の領土だ」というのではなく、その理由や歴史的背景をしっかり整理して機会があるごとに言うことです。イギリスが世界を制したのは「どんなことでも相手国にイギリスが正しいと思わせる力」と言われてきました。自分の論理をシッカリしておくこと、これがイギリスという小国が世界を支配した力だったのです。また、近隣諸国に常に親善を呼び掛けることでしょう。中国、韓国内で政府などが「反日言動」をしたら、そのたびに「親善第一」と訴えることです。すでにドイツとイギリス、フランスなどヨーロッパは老獪で自分たちの中で争いをできるだけ表面化しないようにしています。その点では日本を含めて中国も韓国も子供のようなものでしょう。韓国は長く中国の属国でした。ロシアも朝鮮半島を取ろうとしていました。長さだけではないですが、日本の35年をあまりにも強調することは両国にとって良いことではありません。日本には多くの中国人、韓国人がおられますし、日本の発展にも寄与しています。だから、反感を持つのではなく、共存共栄としての日本の主張をくり返すことです。ただ、南京事件のように中国が「しかけてくる」ものに対して朝日新聞などが両国の対立を激化するキャンペーンをすることが大きな問題です。特に日中関係を破壊してきたのは、朝日新聞で、この際、朝日新聞は過去の報道を総括し、反省し、日本の将来のためにその結果を紙面で公表するべき時のように感じます。・・・・・・・・・外交政策は「力」を背景に、「口先」をしっかりして、常に「国際親善」を強調した平和外交を展開することです。軍事力を高めることも平和外交の一つです。外交でも激憤することなく、冷静に、しかも力を背景にして口先で優位に立つことを政策とするべきです。日本のように「男は黙って・・・」というのは外交には通じません。今、領土問題に火がついていますが、それでも「日本は今後も強い国になるぞ」、「日本はあくまで国際親善だ」ということを明確にすれば、紛争も後退していきます。それが歴史の示す外交政策です。(平成24年8月20日もちろん これは正論だなあはた坊
2012.08.22
コメント(2)
-

らっきょうも1kgの分を買っておいた 東日本大震災529日後に
昨年のラッキョウhcでラッキョウの苗の売り出しがあったので1kgを購入8月21日 植え付けする予定猛暑が過ぎたら 植え付けしよう今年もラッキョウを作ろう猛暑が過ぎた もう 秋だなあで 来週にラッキョウさんを植え付けだ09月11日 g-22の畑に植え付けした 1kgを植え付け09月25日 すこし発芽してきている10月10日 かなり大きくなっている 勢ぞろい 見た目もばっちり10月16日 上には何か蕾のようなのが皆についている 何かいな ??10月23日 花蕾が大きくなってきている もうすぐ花が咲きそうだなあ11月06日 花が盛りとなっている 11月20日 まだ 花か゛たくさん咲いている 華やかなり 小さい花だけど12月04日 まだまだ 花が咲いている出だしも快調なり結構と大きくなっている 花も咲き ただいま花盛り 賑やか今年02月12日 まあまあ大きくなっている 順調に育っている03月04日 追肥しておいた03月11日 元気に大きく のびのびとしてきている04月15日 追肥したら 雑草のほうが元気になっている ???やばい 雑草のほうが良く伸びていた ????05月06日 雑草とりしてみたら らっきょう 細いのばかりだなあでも 今月いっぱい ゆっくりと日光をあたれば 大きくなるだろう ???05月27日 日光があたり やや成長してきているかな ???収穫は来月 6月の10日くらいとしよう06月17日 やっと収穫をした 出来具合は 結構と良い 結果は良しhcで ラッキョウの売り出し中即 購入とした08月19日 hcでラッキョウ1kgのを買っておいた9月になれば 畑に植え付けしよう畑の準備をそろそろと東日本大震災 3月11日発生08月22日は 既に529日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------穏やかで常識的な政策 外交政策竹島、尖閣諸島、北方四島、中国の防衛線などの近隣諸国との領土や海の問題がこじれています。外交の基本から言って、「穏やかで常識的」な外交政策とは何でしょうか?外交の第一は「力」です。力には三種類あって、1)防衛、2)経済力(技術)、3)文化 です。強大な防衛力をもって他国を抑えることを本格的にやっているのがアメリカで、だからこそ、アフガニスタン、日本のように本国から遠く離れているのに、力を持っています。日本は自衛隊がかなり強い戦力ですが、軍隊ではないので、それなりに弱いところがあります。戦後70年、日本人が軍事をどのように考えるのか、それが外交問題の第一であることは間違い有りません。軍事力の議論ができない国が外交で失敗するのは仕方が無いことでしょう。第二には「経済力(技術力)」です。かつて日本の技術に頼る必要があった時には中国は日本に余る強くでることができませんでしたが、最近ではGDPが日本を上回り、独自の技術もできてきたので、日本をおおっぴらに非難することが可能になりました。第三には文化です。文化の力は短期間には弱いものですが、国と国の力のように長い間のものでは力を発揮します。フランスがその良い例で、フランスという国は人口6300万人ほどの小さな国で、しかも農業国ですが、フランス大統領はアメリカ大統領をそれほど違わないように振る舞えます。フランスと言えば花のパリ。その歴史と文化は誰もが認めるところです。アジアでも最近の中国はお金だけのように見えますが、かつては漢字文化を持ち、文化の力で周囲の国に光を与えたこともありました。どうも最近の中国は強面で、軍事力とお金を背景に脅してくるような感じもしますが、かつてのように高い文化で影響を与えて欲しいものです。従って、外交の第一の条件、中国という世界の3大国に囲まれた国は、力が大切です。この世界は「人格」や「犠牲」、「恩」などで力を発揮するところまで言っていません。でも、日本はサボってきました。自衛隊の予算は年々、減少していますし、もちろんその状態は中国も韓国もよく知っています。技術は「日本が1番でなくても良い」という有名な発言ですが、日本はアメリカ、ロシア、中国に囲まれていますから、世界一でなければやられてしまいます。「ゆとりの教育」は創造性や考える力を養うという点では間違っている訳ではありませんが、単に「ゆとり」だけを作ってしまえば日本は崩壊してしまいます。技術者が圧迫される社会は日本では危険です。学力、文化ともに日本の力はあまり上がっていません。そこに隙があります。・・・・・・・・まず、外交の基本は「力」ですから、日本は力を持たないと外国と対抗することはできない。外国は隙を狙っているのです。それを警戒しない日本人の方に間違いがあると考えるべきでしょう。・・・・・・・・外交のもう一つが「口先」です。常に日本の正当性と近隣諸国との親善を言い続けるということです。尖閣諸島も竹島も北方四島も歴史的に日本の領土ですから、それを常に国際社会に対して訴え続ける必要があります。いきなり「竹島は日本の領土だ」というのではなく、その理由や歴史的背景をしっかり整理して機会があるごとに言うことです。イギリスが世界を制したのは「どんなことでも相手国にイギリスが正しいと思わせる力」と言われてきました。自分の論理をシッカリしておくこと、これがイギリスという小国が世界を支配した力だったのです。また、近隣諸国に常に親善を呼び掛けることでしょう。中国、韓国内で政府などが「反日言動」をしたら、そのたびに「親善第一」と訴えることです。すでにドイツとイギリス、フランスなどヨーロッパは老獪で自分たちの中で争いをできるだけ表面化しないようにしています。その点では日本を含めて中国も韓国も子供のようなものでしょう。韓国は長く中国の属国でした。ロシアも朝鮮半島を取ろうとしていました。長さだけではないですが、日本の35年をあまりにも強調することは両国にとって良いことではありません。日本には多くの中国人、韓国人がおられますし、日本の発展にも寄与しています。だから、反感を持つのではなく、共存共栄としての日本の主張をくり返すことです。ただ、南京事件のように中国が「しかけてくる」ものに対して朝日新聞などが両国の対立を激化するキャンペーンをすることが大きな問題です。特に日中関係を破壊してきたのは、朝日新聞で、この際、朝日新聞は過去の報道を総括し、反省し、日本の将来のためにその結果を紙面で公表するべき時のように感じます。・・・・・・・・・外交政策は「力」を背景に、「口先」をしっかりして、常に「国際親善」を強調した平和外交を展開することです。軍事力を高めることも平和外交の一つです。外交でも激憤することなく、冷静に、しかも力を背景にして口先で優位に立つことを政策とするべきです。日本のように「男は黙って・・・」というのは外交には通じません。今、領土問題に火がついていますが、それでも「日本は今後も強い国になるぞ」、「日本はあくまで国際親善だ」ということを明確にすれば、紛争も後退していきます。それが歴史の示す外交政策です。(平成24年8月20日もちろん これは正論だなあはた坊
2012.08.22
コメント(0)
-

ニンニク hcで売り出し中 即 購入した 東日本大震災529日後に
昨年 秋のニンニクの植え付けだあ先週にニンニクの種の袋を購入さあ 今週には 植え付けをしよう第一弾 宮崎産 ニンニク09月11日 0.5kgの宮崎産のニンニクを植え付けした 75個 g-22に植え付け09月25日 発芽はまだ10月02日 ニンニクもすこし発芽してきている 10月10日 全部が発芽した10月16日 雑草とりをしておいた10月23日 順調に生育中 ok11月13日 かなり大きくなっている11月27日 その後もokだなあ 雑草とり少ししておく12月23日 霜にうたれて やや弱っているが がんばっている 第二弾 中国産 芽ニンニク09月18日 0.5kgの芽ニンニク 中国産のも購入 m-20の畑に植え付けた10月02日 芽ニンニクは全部が発芽してきている10月10日 こちらは より大きくなっている 元気だなあ10月16日 雑草とりをしておいた10月23日 順調に生育中 ok11月13日 かなり大きくなっている11月27日 その後もokだなあ 雑草とり少ししておく12月23日 霜にうたれて やや弱っているが がんばっている どちらも 今は 同じくらいのサイズになっている霜にうたれて 弱りながらも 頑張っている01月04日 芽ニンニク やはり寒そう 見ているのも寒いなあ やっぱり冬だなあ02月12日 ニンニクは葉が黄色のなっているのもある まあ なんとかなっている03月11日 ニンニクが青々してきている 春だなあ 03月18日 ニンニクに追肥しておいた どんどん 大きくなーーれ 雨も良く降る03月18日 芽ニンニクも元気だ 追肥もしておいた04月15日 雑草とりをしておく ニンニク 芽ニンニク ともに元気は良い04月30日 芽ニンニク たくさん出ているのて収穫しておいた g-22の分 20本くらい05月03日 芽ニンニク たくさん出ているのて収穫しておいた g-22の分 20本くらい05月12日 中国産のニンニクにもやっと芽ニンニクができた m-20 40本 収穫05月13日 追加で また 芽ニンニクを20本くらい 収穫しておいた05月20日 追加の追加でまたメニンニク20本の収穫をした06月02日 ニンニクもそろそろ収穫できるようになってきているm-20の中国産のニンニク メニンニク60本収穫g-22の宮崎産のニンニク こらちも60本の芽ニンニクを収穫したどちらも 良く育っているニンニクの本体の収穫できる もう 良く育っている06月03日 m-20の芽ニンニクの半分を収穫した 数は45個あり 残りは来週に06月10日 残りの芽ニンニクを収穫した 数は46個あり 合計で91個宮崎産の ニンニクがまだある06月17日 宮崎産のも収穫した 58個だった これは まあまあの出来具合だったこれにて ニンニクは 結果は良しということで終了したhcでニンニクが売り出されていた早速 ニンニク 購入した08月13日 ニンニク 宮崎さん 500gを購入した植え付けは9月くらいにやろう畑の準備が必要だなあ東日本大震災 3月11日発生08月22日は 既に529日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------穏やかで常識的な政策 外交政策竹島、尖閣諸島、北方四島、中国の防衛線などの近隣諸国との領土や海の問題がこじれています。外交の基本から言って、「穏やかで常識的」な外交政策とは何でしょうか?外交の第一は「力」です。力には三種類あって、1)防衛、2)経済力(技術)、3)文化 です。強大な防衛力をもって他国を抑えることを本格的にやっているのがアメリカで、だからこそ、アフガニスタン、日本のように本国から遠く離れているのに、力を持っています。日本は自衛隊がかなり強い戦力ですが、軍隊ではないので、それなりに弱いところがあります。戦後70年、日本人が軍事をどのように考えるのか、それが外交問題の第一であることは間違い有りません。軍事力の議論ができない国が外交で失敗するのは仕方が無いことでしょう。第二には「経済力(技術力)」です。かつて日本の技術に頼る必要があった時には中国は日本に余る強くでることができませんでしたが、最近ではGDPが日本を上回り、独自の技術もできてきたので、日本をおおっぴらに非難することが可能になりました。第三には文化です。文化の力は短期間には弱いものですが、国と国の力のように長い間のものでは力を発揮します。フランスがその良い例で、フランスという国は人口6300万人ほどの小さな国で、しかも農業国ですが、フランス大統領はアメリカ大統領をそれほど違わないように振る舞えます。フランスと言えば花のパリ。その歴史と文化は誰もが認めるところです。アジアでも最近の中国はお金だけのように見えますが、かつては漢字文化を持ち、文化の力で周囲の国に光を与えたこともありました。どうも最近の中国は強面で、軍事力とお金を背景に脅してくるような感じもしますが、かつてのように高い文化で影響を与えて欲しいものです。従って、外交の第一の条件、中国という世界の3大国に囲まれた国は、力が大切です。この世界は「人格」や「犠牲」、「恩」などで力を発揮するところまで言っていません。でも、日本はサボってきました。自衛隊の予算は年々、減少していますし、もちろんその状態は中国も韓国もよく知っています。技術は「日本が1番でなくても良い」という有名な発言ですが、日本はアメリカ、ロシア、中国に囲まれていますから、世界一でなければやられてしまいます。「ゆとりの教育」は創造性や考える力を養うという点では間違っている訳ではありませんが、単に「ゆとり」だけを作ってしまえば日本は崩壊してしまいます。技術者が圧迫される社会は日本では危険です。学力、文化ともに日本の力はあまり上がっていません。そこに隙があります。・・・・・・・・まず、外交の基本は「力」ですから、日本は力を持たないと外国と対抗することはできない。外国は隙を狙っているのです。それを警戒しない日本人の方に間違いがあると考えるべきでしょう。・・・・・・・・外交のもう一つが「口先」です。常に日本の正当性と近隣諸国との親善を言い続けるということです。尖閣諸島も竹島も北方四島も歴史的に日本の領土ですから、それを常に国際社会に対して訴え続ける必要があります。いきなり「竹島は日本の領土だ」というのではなく、その理由や歴史的背景をしっかり整理して機会があるごとに言うことです。イギリスが世界を制したのは「どんなことでも相手国にイギリスが正しいと思わせる力」と言われてきました。自分の論理をシッカリしておくこと、これがイギリスという小国が世界を支配した力だったのです。また、近隣諸国に常に親善を呼び掛けることでしょう。中国、韓国内で政府などが「反日言動」をしたら、そのたびに「親善第一」と訴えることです。すでにドイツとイギリス、フランスなどヨーロッパは老獪で自分たちの中で争いをできるだけ表面化しないようにしています。その点では日本を含めて中国も韓国も子供のようなものでしょう。韓国は長く中国の属国でした。ロシアも朝鮮半島を取ろうとしていました。長さだけではないですが、日本の35年をあまりにも強調することは両国にとって良いことではありません。日本には多くの中国人、韓国人がおられますし、日本の発展にも寄与しています。だから、反感を持つのではなく、共存共栄としての日本の主張をくり返すことです。ただ、南京事件のように中国が「しかけてくる」ものに対して朝日新聞などが両国の対立を激化するキャンペーンをすることが大きな問題です。特に日中関係を破壊してきたのは、朝日新聞で、この際、朝日新聞は過去の報道を総括し、反省し、日本の将来のためにその結果を紙面で公表するべき時のように感じます。・・・・・・・・・外交政策は「力」を背景に、「口先」をしっかりして、常に「国際親善」を強調した平和外交を展開することです。軍事力を高めることも平和外交の一つです。外交でも激憤することなく、冷静に、しかも力を背景にして口先で優位に立つことを政策とするべきです。日本のように「男は黙って・・・」というのは外交には通じません。今、領土問題に火がついていますが、それでも「日本は今後も強い国になるぞ」、「日本はあくまで国際親善だ」ということを明確にすれば、紛争も後退していきます。それが歴史の示す外交政策です。(平成24年8月20日もちろん これは正論だなあはた坊
2012.08.22
コメント(0)
-

今週もミニトマト 大量に収穫 皮がやや固くなってきている 東日本大震災528日後に
昨年のトマト 桃太郎 4本を購入した トマトも栽培を開始04月03日 hcで苗を4本 桃太郎を購入して 畑に植えておいた m06に植え付け04月03日 hcでブチトマト アイコの苗も2本を購入した これもm06に植え付け04月09日 畑にいくと苗がなくなっている 綺麗に消滅して何もない ????04月10日 あわてて またhcにトマトの苗を買いに行く 桃太郎4個と赤のブチトマト204月10日 すぐに また 苗を植えておく04月17日 再度の苗の6本は今回は無事に残る04月23日 ミニトマトの苗画1本 何かにかじられて枯れた 04月24日 補修でミニトマト2本をhcで購入して植えつけた04月28日 ついで またミニトマト2本を増やしておいた05月01日 ミニトマトには花がついている トマトはまだまだ05月08日 ミニトマト また2本 20円で安売りしていたので買って会社に植えた05月15日 ミニトマトm06の分に実が付き出した 支柱をつけておいた05月22日 ミニトマトm07の分にも実が付き出した05月29日 ミニトマト庭のものにも 会社のものにも実が付き出した06月19日 初のミニトマト 真っ赤なのが1個 初の収穫した 美味06月22日 すこし赤みがついた実も4個 とっておいた06月29日 ようやく赤くなつた実が増えてきた これから毎週 赤いミニトマトが収穫可能07月03日 トマトの赤い実もやっと2個収穫できた これから どんどん収穫へ 07月06日 2回目のトマトの収穫10個 ミニトマトも20個トマト桃太郎 4本 m-06 実が付いた 7/3-2個赤くなったブチトマト赤 5本の苗 m06-3本 m07-2本 m-20-2本 実が付いた会社にも 2本のトマトと2本のブチトマトを植えておいた 実が付いた 7/3-1個赤家の庭にも 2本のブチトマトを植えておいた 実が付いた 7/3-4個赤くなるミニトマト 6月19日 初の実の収穫6個 6月22日 4個6月29日 20個の収穫7月03日 40個の収穫7月04日 家の庭のミニトマトも赤くなっている4個の収穫をした7月06日 20個の収穫7月09日 20個の収穫7月13日 20個の収穫7月17日 100個の収穫7月24日 50個の収穫7月31日 50個の収穫8月06日 100個の収穫 合計430個8月14日 20個の収穫 合計450個トマト 7月03日 初の2個の収穫をした7月04日 会社でも赤くなっていた 1個の収穫をする7月06日 2回目の収穫は10個7月09日 3回目の収穫は10個7月13日 4回目の収穫は10個7月17日 5回目の収穫は20個7月24日 6回目の収穫は10個7月31日 7回目の収穫は10個8月06日 8回目の収穫は10個 合計87個8月14日 9回目の収穫は2個 合計89個8月20日 10回目の収穫は1個 合計90個家の庭のトマトは 終了した会社のトマトも そろそろ終了畑のトマト ミニトマト もう勢いはなし今年のトマト04月22日 hcで苗を2本買ってきた 桃太郎すぐに畑に植えておいたトマトも植え付け開始 カバーを付けておいた 05月06日 花も咲き出している05月13日 ワキメ 庭に移動して育てている05月27日 かなり大きくなってきている 支柱をつけておく06月04日 下には実がどんどんついてきている 楽しみだなあ 06月17日 下から1-2-3-と実がついている まだ青い06月23日 1個が赤くなりつつある06月26日 初の1個の収穫をした めでたい07月01日 その後はゆくりとしている07月08日 やっと5個 どんどん増えている07月19日 6個の収穫07月22日 6個の収穫今年のミニトマト04月22日 4つの苗 中サイズの実のつくのを購入 畑に植え付けたミニトマト ブチのサイズは中玉とした05月06日 花も咲き出している05月13日 ワキメ 庭に移動して育てている05月27日 かなり大きくなってきている 支柱をつけておく06月03日 下のほうに実がついている 中サイズなので おおきい実になりそう 楽しみ06月17日 下から1-2-3-と実がついている 実は赤くなりだしたのもある06月23日 赤くなっての7個の収穫をした06月26日 続いて10個 どんどん収穫していこう07月01日 続いて5個 まだ 少ないなあ07月08日 12個くらい まあまあ07月19日 30個くらい そろそろ大量の収穫できそう07月22日 40個くらい どんどん赤くなる07月28日 40個 完熟になっている07月29日 40個 追加で収穫ワキメから どんどん増やそう05月27日 庭で刺し芽をしておいた ただいま10本のワキメは育ちつつある06月03日 追加で庭でまた刺し芽をした これで 合計20本の刺し芽となった06月10日 m-08の畑に刺し芽の20本を移動 全部20ともに畑に定植した06月17日 支柱をつけて追肥をしておいた 06月24日 刺し目の分 どんどん成長してきている 楽しみ07月15月 やっと実の収穫 まずは2個07月19日 10個くらい そろそろ実が一杯に付き出している07月22日 10個くらい どんどん赤くなりつつつある07月29日 40個くらい収穫した収穫トマト2本 収穫は6月26日から 1+1+5+1+5+6+6+6+6+6+10+6 =59個ミニトマト4本収穫6月23日から7+10+10+5+12+20+48+30+40+40+40+40+50+40 =392個 刺し芽の20本 収穫は7月15日から 2+10+10+10+40+20+40+60 =192個会社ミニトマト2本 収穫は7月08日から 4+1+3+4+10+10+10+6+10 =58個会社トマト2本 収穫は7月22日から 1+2+6+2+4 =15個収穫は8月もどんどん 大量に収穫しようそろそろ 実の付き方が ゆっくりとしてきている皮も固くなりつつある東日本大震災 3月11日発生08月21日は 既に528日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------100年後まで「新エネルギー」は無関係・・・技術の本質とはなにか?日本人の多くが「新しいエネルギーが必要」と信じている。実は今から30年前の私も同じで、「石油、石炭、天然ガスなどの化石燃料」がそのうち無くなると錯覚していたからだ。私がエネルギー分野の研究をするようになって、化石燃料が数100年でなくなることはなく、人間が使うエネルギーというのは1000年と言わず、300年ぐらいでガラッと変わるので、現在の知識で余り考える必要が無いことが分かったのは、30年前だった。どんなに悲観的に見ても(世界の鉱山の常識と各国政府の政策から見ても同じだが)、化石燃料は数100年はある。もちろん、生活の中で普通に使えるような値段で得られるもので、2009年から本格的に掘り出したシェールガス(本当の意味の天然ガス)などは寿命数1000年、値段3分の1と予想されている。値段が上がらず、数100年は持つ化石燃料があるのに、世界で日本だけが省エネ、節電、それに新エネルギーに熱心だ。世界の情報から隔絶された日本を感じる。世界の石油系の企業は「メジャー」、「スーパーメジャー」と呼ばれるぐらいの大きな会社で資本力もある。もし、石油系の燃料が短期になくなるのだったら、これほど悠々としているだろうか?アメリカや中国の政府もそうだ。あれほど大きな国だから、エネルギー政策やもし温暖化などが大変だったら、国はつぶれてしまうだろう.それなのに、形式的には少しやったり発言したりしているが、本格的に代換えエネルギーの政策を進めたり、ましてCO2を減らしたりしていない。これに対して日本の識者は「それはメジャーも、アメリカや中国もバカだから」と言うけれど、本当にそんなに簡単な結論を出して良いのだろうか?40年前は原子力発電は実質的になかった。100年前にやっと石油を使い始めた。石炭を燃料に使ったのは200年前だ。だから、安い化石燃料が200年持てば、エネルギー資源のことは専門家に任せておいて、普通の人は生活をエンジョイすればよい。まして「足りない」と言われる税金を使って新エネルギーとか太陽光発電にお金を投じる必要は無い。技術にはある経験則がある。基礎的な研究を始めて40年経っても実用化(既存の技術を凌駕するような状態)にならないものは有望ではないということだが、太陽光発電は基礎研究は長く、今から40年前にサンシャイン計画という膨大な税金を投入して国家プロジェクトを始めている。だから、今更、太陽光発電がキロワット時で42円もするなら、技術として成功する見込みが少ない。でも技術のことだから思わぬブレークスルー(新たな着想による画期的技術の出現)があるかも知れない。でも、それは国家のお金を投じればできるというのではなく、むしろ、お金を投じると新しい技術は誕生しない。技術の本質、世界の動向、人間の進歩など大きい目で一つ一つのことを判断するのも大切なように思う。(平成24年8月18日これは 実に面白いはた坊
2012.08.21
コメント(0)
-

ニラ また元気になってきている 東日本大震災528日後に
昨年 ニラの収穫の予定今年は3月から どんどんと収穫している庭のニラ あちこち どんどん葉が出てきている-収穫中g-22 ここも発芽してきた 3月6日m-08 発芽してきたのは2月28日庭のニラ たくさんあるのでどんどん収穫収穫3月05日 初の収穫をした 今年は早いぞ3月12日 2回目の収穫をした3月20日 3回目の収穫をした3月27日 4回目の収穫をした4月03日 5回目の収穫をした4月12日 6回目の収穫をした4月20日 7回目の収穫をした4月28日 8回目の収穫をした5月08日 9回目の収穫をした5月22日 10回目の収穫をした5月29日 11回目の収穫をした6月05日 12回目の収穫をした6月12日 13回目の収穫をした6月26日 14回目の収穫をした7月03-10-17-24-31日 収穫しなかった8月07日 15回目の収穫をした8月21日 花の蕾があちこちに出てきている8月28日 g22のニラ 3wkでやっと回復した しかし花蕾だらけになってきている9月18日 m08のニラ 収穫をしておいたニラは元気だなあ3月-4回4月-4回5月-3回6月-3回と もう14回の収穫をした7月- 0回 7月は収穫していない さすがに ニラも多すぎた感じになっている8月- 1回 これで15回目の収穫 g229月- 1回 これで16回目の収穫 m0810月 -1回 これで17回目の収穫 g-2211月 -m08の分 まだ冷蔵庫に在庫があるので 収穫はしなかった12月 -庭のニラ すこし収穫した 1回 合計で18回の収穫をした 今年 01月09日 m08のニラは枯れ草になっていたニラが枯れてしまった 在庫はなしになった次は3月になると 新芽が出るだろう02月26日 ニラ 新芽が出てきている 春だなあ そろそろ青くなってきてくれそう03月04日 ニラ 新芽が増えてきている 早く青くなれーーーーー03月18日 ニラ かなり前面に芽が出てきている今年のニラ 収穫は4月から 開始だなあ04月08日 今年の収穫は1回目となる 初の収穫だけど 昨年より遅い04月22日 2回目の収穫した05月03日 3回目の収穫をした05月13日 4回目の収穫をした05月20日 5回目の収穫をした06月10日 6回目の収穫をした06月30日 7回目の収穫をした07月08日 8回目の収穫をした07月15日 9回目の収穫をした07月22日 10回目の収穫をした08月05日 11回目の収穫をした08月12日 12回目の収穫をした08月19日 13回目の収穫をしたにら 庭にもあるので 便利 いつでも収穫 どんどん 食べよう東日本大震災 3月11日発生08月21日は 既に528日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------100年後まで「新エネルギー」は無関係・・・技術の本質とはなにか?日本人の多くが「新しいエネルギーが必要」と信じている。実は今から30年前の私も同じで、「石油、石炭、天然ガスなどの化石燃料」がそのうち無くなると錯覚していたからだ。私がエネルギー分野の研究をするようになって、化石燃料が数100年でなくなることはなく、人間が使うエネルギーというのは1000年と言わず、300年ぐらいでガラッと変わるので、現在の知識で余り考える必要が無いことが分かったのは、30年前だった。どんなに悲観的に見ても(世界の鉱山の常識と各国政府の政策から見ても同じだが)、化石燃料は数100年はある。もちろん、生活の中で普通に使えるような値段で得られるもので、2009年から本格的に掘り出したシェールガス(本当の意味の天然ガス)などは寿命数1000年、値段3分の1と予想されている。値段が上がらず、数100年は持つ化石燃料があるのに、世界で日本だけが省エネ、節電、それに新エネルギーに熱心だ。世界の情報から隔絶された日本を感じる。世界の石油系の企業は「メジャー」、「スーパーメジャー」と呼ばれるぐらいの大きな会社で資本力もある。もし、石油系の燃料が短期になくなるのだったら、これほど悠々としているだろうか?アメリカや中国の政府もそうだ。あれほど大きな国だから、エネルギー政策やもし温暖化などが大変だったら、国はつぶれてしまうだろう.それなのに、形式的には少しやったり発言したりしているが、本格的に代換えエネルギーの政策を進めたり、ましてCO2を減らしたりしていない。これに対して日本の識者は「それはメジャーも、アメリカや中国もバカだから」と言うけれど、本当にそんなに簡単な結論を出して良いのだろうか?40年前は原子力発電は実質的になかった。100年前にやっと石油を使い始めた。石炭を燃料に使ったのは200年前だ。だから、安い化石燃料が200年持てば、エネルギー資源のことは専門家に任せておいて、普通の人は生活をエンジョイすればよい。まして「足りない」と言われる税金を使って新エネルギーとか太陽光発電にお金を投じる必要は無い。技術にはある経験則がある。基礎的な研究を始めて40年経っても実用化(既存の技術を凌駕するような状態)にならないものは有望ではないということだが、太陽光発電は基礎研究は長く、今から40年前にサンシャイン計画という膨大な税金を投入して国家プロジェクトを始めている。だから、今更、太陽光発電がキロワット時で42円もするなら、技術として成功する見込みが少ない。でも技術のことだから思わぬブレークスルー(新たな着想による画期的技術の出現)があるかも知れない。でも、それは国家のお金を投じればできるというのではなく、むしろ、お金を投じると新しい技術は誕生しない。技術の本質、世界の動向、人間の進歩など大きい目で一つ一つのことを判断するのも大切なように思う。(平成24年8月18日これは 実に面白いはた坊
2012.08.21
コメント(1)
-

しその葉の収穫 まだまだ 東日本大震災528日後に
昨年のしその葉まずは 2個の苗を購入した04月03日 hcでの青しその葉の苗 2個をみつけて購入した04月10日 1本が枯れた あーあ04月17日 hcで追加の苗を2本かって植えた04月24日 苗は合計で3本が無事に こぼれ種の発芽 すこし 出てきている04月29日 こぼれ種のしその葉も大きくなりだした これで しそは大量に出来る05月08日 初の葉の収穫をしておく こぼれ種の青と赤のしその発芽も確認 okだな05月15日 2回目の青しその葉の収穫をしておく05月22日 3回目のアオシソの葉を収穫しておく05月29日 4回目のアオシソの収穫をした06月05日 5回目のアオシソの収穫をした06月12日 6回目のアオシソの収穫をした06月19日 7回目のアオシソの収穫をした06月26日 8回目のアオシソの収穫をした07月03日 9回目のアオシソの収穫をした07月10日 10回目のアオシソの収穫をした07月17日 11回目のアオシソの収穫をした07月24日 12回目のアオシソの収穫をした07月31日 13回目のアオシソの収穫をした08月07日 14回目のアオシソの収穫をした08月13日 15回目のアオシソの収穫をした08月20日 16回目のアオシソの収穫をした09月02日 17回目のアオシソの収穫をした09月09月 18回目のアオシソの収穫をした 葉は終了だなこぼれ種の発芽青しそ 昨年は3月22日に 今年は4月24日に 赤しそ 昨年は4月11日に 今年は5月08日に 今年は寒かったみたい??? しその収穫 5/8---開始青しそ 18回赤しそ 0回青そしの葉も もうダメ 穂がでて 花が咲いてきている10月23日 しその実がたくさんある 香りが良い しかし 手間暇がかかるので放置しその実 香りも楽しんだで じゃまなので そそろそろ 全部を撤去しよう今週の日曜は全部 撤去としよう今年まずは hcでの苗から04月15日 hcでの苗があったので まずは1本 58円なり m-08の畑に1本 植え付けた05月20日 初の収穫 すこしこぼれ種の発芽は 05月20日 あちこちにたくさん発芽している05月26日 2回目の収穫をしたあ05月31日 3回目の収穫をしたーあ06月03日 4回目の収穫をしたーーーあ06月10日 5回目の収穫をしたーーーーーーあ06月17日 6回目の収穫をしたーーーーーーーーーーあ06月24日 7回目の収穫をしたーーーーーーーーーーーーーあ06月30日 8回目の収穫をしたーーーーーーーーーーーーーーーあ07月08日 9回目の収穫をしたーーーーーーーーーーーーーーーーーあ07月11日 10回目の収穫をした----------------------------------あ07月16日 11回目の収穫をした---------------------------あ07月22日 12回目の収穫をした----------------------あ07月29日 13回目の収穫をした------------------あ08月05日 14回目の収穫をした--------------あ08月12日 15回目の収穫をした----------あ08月19日 16回目の収穫をした------あこぼれ種のしそ 大量にあるもう しばらく 収穫できそう東日本大震災 3月11日発生08月21日は 既に528日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------100年後まで「新エネルギー」は無関係・・・技術の本質とはなにか?日本人の多くが「新しいエネルギーが必要」と信じている。実は今から30年前の私も同じで、「石油、石炭、天然ガスなどの化石燃料」がそのうち無くなると錯覚していたからだ。私がエネルギー分野の研究をするようになって、化石燃料が数100年でなくなることはなく、人間が使うエネルギーというのは1000年と言わず、300年ぐらいでガラッと変わるので、現在の知識で余り考える必要が無いことが分かったのは、30年前だった。どんなに悲観的に見ても(世界の鉱山の常識と各国政府の政策から見ても同じだが)、化石燃料は数100年はある。もちろん、生活の中で普通に使えるような値段で得られるもので、2009年から本格的に掘り出したシェールガス(本当の意味の天然ガス)などは寿命数1000年、値段3分の1と予想されている。値段が上がらず、数100年は持つ化石燃料があるのに、世界で日本だけが省エネ、節電、それに新エネルギーに熱心だ。世界の情報から隔絶された日本を感じる。世界の石油系の企業は「メジャー」、「スーパーメジャー」と呼ばれるぐらいの大きな会社で資本力もある。もし、石油系の燃料が短期になくなるのだったら、これほど悠々としているだろうか?アメリカや中国の政府もそうだ。あれほど大きな国だから、エネルギー政策やもし温暖化などが大変だったら、国はつぶれてしまうだろう.それなのに、形式的には少しやったり発言したりしているが、本格的に代換えエネルギーの政策を進めたり、ましてCO2を減らしたりしていない。これに対して日本の識者は「それはメジャーも、アメリカや中国もバカだから」と言うけれど、本当にそんなに簡単な結論を出して良いのだろうか?40年前は原子力発電は実質的になかった。100年前にやっと石油を使い始めた。石炭を燃料に使ったのは200年前だ。だから、安い化石燃料が200年持てば、エネルギー資源のことは専門家に任せておいて、普通の人は生活をエンジョイすればよい。まして「足りない」と言われる税金を使って新エネルギーとか太陽光発電にお金を投じる必要は無い。技術にはある経験則がある。基礎的な研究を始めて40年経っても実用化(既存の技術を凌駕するような状態)にならないものは有望ではないということだが、太陽光発電は基礎研究は長く、今から40年前にサンシャイン計画という膨大な税金を投入して国家プロジェクトを始めている。だから、今更、太陽光発電がキロワット時で42円もするなら、技術として成功する見込みが少ない。でも技術のことだから思わぬブレークスルー(新たな着想による画期的技術の出現)があるかも知れない。でも、それは国家のお金を投じればできるというのではなく、むしろ、お金を投じると新しい技術は誕生しない。技術の本質、世界の動向、人間の進歩など大きい目で一つ一つのことを判断するのも大切なように思う。(平成24年8月18日これは 実に面白いはた坊
2012.08.21
コメント(2)
-

キュウリ 第四弾の実は あまり付かなくなった 東日本大震災527日後に
今年もきゅうりhcでの苗は売っているが まだ寒そうとりあえず 種のほうは買っておいた苗は来週くらいにしようかな ???04月22日 hcで苗を探しに行く 小さいが北進があったので6個をかっておく 植え付け04月28日 苗は畑で無事だ サイズは変わらず 05月06日 まあまあ すこしは成長しつつある05月20日 上に伸びてきている 支柱が必要05月27日 支柱をつけておく ついでに小さいキュウリを収穫しておく06月01日 2回目の収穫は2本を06月03日 3回目の収穫は4本06月06日 4回目の収穫は6本06月10日 5回目の収穫は3本06月13日 6回目の収穫は5本06月17日 7回目の収穫は8本06月20日 8回目の収穫は8本06月23日 9回目の収穫は6本06月26日 10回目の収穫は4本06月29日 11回目の収穫は10本07月01日 12回目の収穫は02本07月04日 13回目の収穫は05本07月08日 14回目の収穫は04本07月11日 15回目の収穫は10本07月14日 16回目の収穫は08本種まき 第二弾04月22日 同時に種まきを開始しておく 8potsを04月28日 1個の芽が出てきている しめしめ05月06日 g-10の畑に移動した05月20日 8本ともに無事 すこし成長した05月27日 蔓が延びてきている06月06日 第二弾のキュウリの生長も開始 実もそろそろかも06月17日 かなり横に横に伸びてきている 実も小さいがついている06月23日 1回目の収穫 19本もあった 多すぎだなあ06月26日 2回目の収穫 11本06月29日 3回目の収穫 20本07月01日 4回目の収穫 07本07月04日 5回目の収穫 15本07月08日 6回目の収穫 16本07月11日 7回目の収穫は10本07月19日 8回目の収穫は08本第三弾のキュウリ05月27日 庭で種まきをしておいた06月02日 発芽した06月06日 次に日曜には畑に移動しよう06月10日 畑に移動 m-06の畑に植え付けた07月08日 蔓は延びてきている07月19日 1回目の収穫 12本07月28日 2回目の収穫 07本 落ち着いてきている第四弾の種まき06月10日 庭で8potに種まきをしておいた06月15日 発芽してきている06月23日 畑に移動 g-22に植え付けておいた07月08日 5本くらいは 無事収穫した分は 第一弾 5月27日から 合計で5+2+4+6+3+5+8+8+6+4+10+2+5+4+10+8+8+6=104本第二弾 6月23日から 合計で19+11+20+07+15+16+10+8+10=116本第三弾 7月19日から 合計で12+2+7+5+10 =36本第四弾 8月04日から 合計で1+2 =3本キュウリ 次は第4弾の分 いよいよ収穫に入るしかし よれよれのキュウリばかりになってきている第四弾のキュウリ 実が付かなくなったもう そろそろ お終いかな ????東日本大震災 3月11日発生08月20日は 既に527日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------対立の構図 論争に負けない人が優れた学者(文科系)(内容が挑戦的なので一言:ここでいう「文科系」とは文科系の学問の全体的な傾向を示していて、個別には異なる学問もあることを最初にお断りしておきたい・・・対立の構図を整理したら、新しい対立ができるというのも可笑しいので)先回の「対立の構図」で「理科系の人間は対立を恥ずかしいと思う」と書いた。もし学問が進んでいればほぼ全員が同じ結論になるはずだし、結論が異なれば研究が足りないので、不明な部分があるか、誰かがウソをついているということになる。いずれにしても、意見が対立したところで議論を中断し、なにが不足しているのかを検討し、「じゃ、もう少し研究してからもう一度、議論しよう」と言うことになる。人間は事実を確認して、人間の頭脳で論理的に導き出される結果が「知的財産」であり、論理的に考えて複数の結論があるときには「おれは・・・思う」というその人のワガママに過ぎないと理科系は考える。それに対してどうも文科系の人(たとえば経済学、社会学、心理学など)は意見が違っても恥ずかしくないように見える。それどころか、むしろ意見が違うのが当たり前で、「論争」に勝ってこそ立派な学者だという雰囲気もある。論争をよく見ていると、まず「事実を共有しようとしない」、そして「論理的に詰めていこうとしない」、さらに時によっては「人によって(学問とは別の)目的があるらしい」という感じがする.経済学や心理学分野では、学者同士で罵倒し合っていることがある。実に不思議なことだ。いがみ合う前に事実を共有する努力をすればよいのに、なぜ、事実を共有しようとしないかというと、「事実」が余りに多くあって、どれが事実なのか分からない。もしくは、どれもこれも「事実」なのだが、どれが大切な事実なのか、なにが些末なのかということすら選択基準を持っていないように見える.・・・・・・・・・また「論理的に詰めていく」ことをせずに、突然、飛躍する.私がこのことを強く感じたのは「世代間倫理」という倫理の分野が登場してきた頃、この分野で有名な哲学者の書いた書籍を3冊ほど読んだことがある.文章は難解だし、本は厚く、なかなか大変で、ものすごい量の文字が並んでいる.でも、私の知りたかった事は書いていなかった。つまり「なぜ、現世代は未来世代に対して責任があるのか?」、「これまでの世代が未来世代に対して責任を取った例があるのか?」、「これからどうなるかを予想できる手段はあるのか?」といった基本的な事が書いていない.その代わりに、あるところに突如として「世代間には倫理があるから、現世代は未来世代に責任がある」という原理が登場する.名古屋大学時代だったので(総合大学だからという意味)、哲学の先生にどうしてこのような論理が通るのですか? その人がなぜ有名になるのですか?とお聞きした.そうしたら「いやあ、その通りです.最も大切なことはえてして直感なんですね」と言われた.学問分野が違うから、私が哲学の考え方を批判しても仕方が無いが、直感でもっとも重要なことを決めるなら、それ以下の小さいことを精密に議論しても意味が無いように思った。もう一つ別の例: 今、南京事件というものに取り組んでいるが、おもしろいことに無限に議論がある。いわば研究者一人に一つの意見があるといっても言い過ぎではない.また研究者と違っても、この事件に関心のある人が多く、その人達がまたいちいち違う見解を述べておられる。南京事件の本は大量に販売されているし、事件を扱った雑誌の論評などを入れると膨大な数に上る.それらの多くが「同じ事を別の表現でくり返している」に見える.それらを読んでいるとなんとなく「時間を無駄に使うのを楽しんでいる」ような感じさえするのだ.上海から南京への日本軍の進撃と中国軍の後退、その間における日本軍の増強と南京政府の動向、南京攻撃の直前の南京城内の動き、人間の数などは、研究者によってほとんど差が無い.さらに南京攻略戦が始まってからも、おおよその戦闘時間、戦闘の様子、結果なども明らかで、紛れがない.問題なのは南京が陥落して大量の投降兵(投降したからと言って捕虜ではない)が出たあたりから2,3日のことだけが問題だが、これも、両軍と市民の動向を追っていくと、人間の動き自体にはそれほど事実認識に差が無いようだ。問題は最後の最後、つまりその人達が「どうなったか」というところで、無限に発散する.そして、どこが問題なのか「差を示す明確な比較表」すら作られていない.「理科系」である私はここで唖然とする。問題は最後の最後にあるのだから、そこを整理するために研究しているはずなのだが、その結果が見当たらないのである。これを「世代間倫理」と同じように解釈すれば「明確な比較表を作ると議論が単純になって、論争が終わりになり、ケンカができない」という感じすらする.・・・・・・・・・理科系の私が言うと文科系から激しいバッシングが来るかも知れないが、自然科学でいうところの「科学」ができるのを待っていると現実の社会に役立たないのでフライングしているように見える.つまり「まだ墜落の可能性のある航空機だが、どうしても飛ばさなければいけない。悠長なことは言ってられない」という感じだ.「ニューヨークに行く必要があるのだから、墜落するという人も居るし、墜落しないという学者もいるから、飛ばしてしまえ!」と言っているようだ。経済学なども特にそうで、バブルが起こったら、それまでバブルのバの時も言っていなかった経済学者が悠々とバブルを解説しているのを見て、強い違和感をもったものだ.自分の学問が間違っていたのだから、しばらくは発言ができないはずだが、そうでもない。政治学者などが選挙結果を予測し、まったく外れているのに、再び同じ人がテレビに出てくるなども同じである.予測が当たらないのは学問が完成していないからだから、その人が話すことは学問ではなく、素人と同じという事になる。文科系の学問が、理科系が考える学問ではないかどうかについては、また機会を見て文科系の人に聞いて見たいと思う.まだ、だれも学者としてなにも語れない初歩的段階にあるのか、そんなことを言っていたらいつまでも学問的成果をあげられないので、少しのフライングを承知で苦労されているのかもしれない。ところで、理科系と文科系がハッキリ分かれている国は少ないが・・(平成24年8月16日なるほどはた坊
2012.08.20
コメント(4)
-
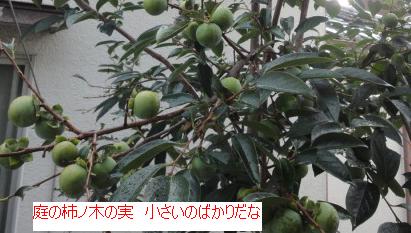
柿ノ木の実 40mmでお終いに ちいさいままだな 東日本大震災527日後に
2012年の柿01月03日 干し柿が完成した 1個を食べてみる ok02月03日 もらった干し柿もあるので これから食べておく自分のは後とする03月04日 干し柿 まだ すこし残っている 新芽のふくらみがすこし 春だなあそろそろ 春だ 柿の芽が膨らんできた04月08日 おお芽が膨らんでいる04月14日 葉が一杯に出てきている やったーー04月22日 葉は広がって 葉が大きくなってきている 葉だらけ04月30日 ワキメには柿の実の芽がついている ちゃんとついている05月10日 柿の実の芽 かなり沢山になってきている 多すぎるくらいだなあ05月16日 柿の花が咲いている 白い花でたくさん05月19日 柿の花 葉の上に落ちていた あらあら 落下も早いなあ05月26日 小さいが実がついている グッド05月31日 実がはっきりと見えてきている 10mmになっている06月08日 実が15mmとなってきている すぐに大きくなってくる06月13日 実が18mmとなってきている 成長は早い 目に見えて大きくなりだした06月19日 実が22mmとなってきている どんどん大きくなる06月24日 実が23mmとなってきている どんどん大きくなってきている06月29日 実が29mmとなってきている どんどん どんどん 大きくなってきている07月06日 実が32mmとなってきている いい感じ07月13日 実が38mmとなってきている 順調なり08月19日 実は40mmで お終いになっている 小さいままだなあ柿の木初代は2003-06-1日に芽がでていた二代目は2012-05-20日に芽が出ていた 9年目に二世が誕生した今年はめでたい 芽出度い メデタイ05月26日 二代目 双葉がでてきている05月31日 二代目の双葉 2つめの双葉が出てきている06月08日 二段目の姿 元気そうだ 楽しみだなあ07月01日 葉がすこし増えてきている 3-4の葉も出てきている07月11日 葉が3-4-5の分も出てきている すこし成長してきている柿の実 40mmでおしまいに ちいさいが数は多い東日本大震災 3月11日発生08月20日は 既に527日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------対立の構図 論争に負けない人が優れた学者(文科系)(内容が挑戦的なので一言:ここでいう「文科系」とは文科系の学問の全体的な傾向を示していて、個別には異なる学問もあることを最初にお断りしておきたい・・・対立の構図を整理したら、新しい対立ができるというのも可笑しいので)先回の「対立の構図」で「理科系の人間は対立を恥ずかしいと思う」と書いた。もし学問が進んでいればほぼ全員が同じ結論になるはずだし、結論が異なれば研究が足りないので、不明な部分があるか、誰かがウソをついているということになる。いずれにしても、意見が対立したところで議論を中断し、なにが不足しているのかを検討し、「じゃ、もう少し研究してからもう一度、議論しよう」と言うことになる。人間は事実を確認して、人間の頭脳で論理的に導き出される結果が「知的財産」であり、論理的に考えて複数の結論があるときには「おれは・・・思う」というその人のワガママに過ぎないと理科系は考える。それに対してどうも文科系の人(たとえば経済学、社会学、心理学など)は意見が違っても恥ずかしくないように見える。それどころか、むしろ意見が違うのが当たり前で、「論争」に勝ってこそ立派な学者だという雰囲気もある。論争をよく見ていると、まず「事実を共有しようとしない」、そして「論理的に詰めていこうとしない」、さらに時によっては「人によって(学問とは別の)目的があるらしい」という感じがする.経済学や心理学分野では、学者同士で罵倒し合っていることがある。実に不思議なことだ。いがみ合う前に事実を共有する努力をすればよいのに、なぜ、事実を共有しようとしないかというと、「事実」が余りに多くあって、どれが事実なのか分からない。もしくは、どれもこれも「事実」なのだが、どれが大切な事実なのか、なにが些末なのかということすら選択基準を持っていないように見える.・・・・・・・・・また「論理的に詰めていく」ことをせずに、突然、飛躍する.私がこのことを強く感じたのは「世代間倫理」という倫理の分野が登場してきた頃、この分野で有名な哲学者の書いた書籍を3冊ほど読んだことがある.文章は難解だし、本は厚く、なかなか大変で、ものすごい量の文字が並んでいる.でも、私の知りたかった事は書いていなかった。つまり「なぜ、現世代は未来世代に対して責任があるのか?」、「これまでの世代が未来世代に対して責任を取った例があるのか?」、「これからどうなるかを予想できる手段はあるのか?」といった基本的な事が書いていない.その代わりに、あるところに突如として「世代間には倫理があるから、現世代は未来世代に責任がある」という原理が登場する.名古屋大学時代だったので(総合大学だからという意味)、哲学の先生にどうしてこのような論理が通るのですか? その人がなぜ有名になるのですか?とお聞きした.そうしたら「いやあ、その通りです.最も大切なことはえてして直感なんですね」と言われた.学問分野が違うから、私が哲学の考え方を批判しても仕方が無いが、直感でもっとも重要なことを決めるなら、それ以下の小さいことを精密に議論しても意味が無いように思った。もう一つ別の例: 今、南京事件というものに取り組んでいるが、おもしろいことに無限に議論がある。いわば研究者一人に一つの意見があるといっても言い過ぎではない.また研究者と違っても、この事件に関心のある人が多く、その人達がまたいちいち違う見解を述べておられる。南京事件の本は大量に販売されているし、事件を扱った雑誌の論評などを入れると膨大な数に上る.それらの多くが「同じ事を別の表現でくり返している」に見える.それらを読んでいるとなんとなく「時間を無駄に使うのを楽しんでいる」ような感じさえするのだ.上海から南京への日本軍の進撃と中国軍の後退、その間における日本軍の増強と南京政府の動向、南京攻撃の直前の南京城内の動き、人間の数などは、研究者によってほとんど差が無い.さらに南京攻略戦が始まってからも、おおよその戦闘時間、戦闘の様子、結果なども明らかで、紛れがない.問題なのは南京が陥落して大量の投降兵(投降したからと言って捕虜ではない)が出たあたりから2,3日のことだけが問題だが、これも、両軍と市民の動向を追っていくと、人間の動き自体にはそれほど事実認識に差が無いようだ。問題は最後の最後、つまりその人達が「どうなったか」というところで、無限に発散する.そして、どこが問題なのか「差を示す明確な比較表」すら作られていない.「理科系」である私はここで唖然とする。問題は最後の最後にあるのだから、そこを整理するために研究しているはずなのだが、その結果が見当たらないのである。これを「世代間倫理」と同じように解釈すれば「明確な比較表を作ると議論が単純になって、論争が終わりになり、ケンカができない」という感じすらする.・・・・・・・・・理科系の私が言うと文科系から激しいバッシングが来るかも知れないが、自然科学でいうところの「科学」ができるのを待っていると現実の社会に役立たないのでフライングしているように見える.つまり「まだ墜落の可能性のある航空機だが、どうしても飛ばさなければいけない。悠長なことは言ってられない」という感じだ.「ニューヨークに行く必要があるのだから、墜落するという人も居るし、墜落しないという学者もいるから、飛ばしてしまえ!」と言っているようだ。経済学なども特にそうで、バブルが起こったら、それまでバブルのバの時も言っていなかった経済学者が悠々とバブルを解説しているのを見て、強い違和感をもったものだ.自分の学問が間違っていたのだから、しばらくは発言ができないはずだが、そうでもない。政治学者などが選挙結果を予測し、まったく外れているのに、再び同じ人がテレビに出てくるなども同じである.予測が当たらないのは学問が完成していないからだから、その人が話すことは学問ではなく、素人と同じという事になる。文科系の学問が、理科系が考える学問ではないかどうかについては、また機会を見て文科系の人に聞いて見たいと思う.まだ、だれも学者としてなにも語れない初歩的段階にあるのか、そんなことを言っていたらいつまでも学問的成果をあげられないので、少しのフライングを承知で苦労されているのかもしれない。ところで、理科系と文科系がハッキリ分かれている国は少ないが・・(平成24年8月16日なるほどはた坊
2012.08.20
コメント(0)
-
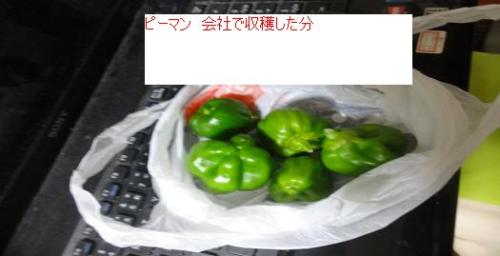
さっぱりのピーマン 今週にすこし収穫 東日本大震災527日後に
昨年のピーマン まずは 2本の苗を購入した04月03日 ピーマンの苗2本を購入した04月10日 風と寒さと水不足で 枯れた あーあ 最初より 失敗だなあ04月17日 hcで苗を探すがない ない ない04月24日 やっとhcで 苗があったので 4本を購入しておいた今年は失敗しないようにしよう と思っていたが最初よりこけた2回目の苗 今度は 失敗しないように 05月24日 今回の4本はなんとか無事に残っている06月05日 実が付き出した06月12日 初の実 3個を収穫した これからだなあ06月26日 2回目の収穫をした07月03日 3回目の収穫をした07月10日 4回目の収穫をした07月17日 5回目の収穫をした07月24日 6回目の収穫をした08月21日 7回目の収穫をした09月04日 8回目の収穫をした09月11日 9回目の収穫をした09月18日 10回目の収穫をした09月25日 11回目の収穫をした10月02日 12回目の収穫をした これで終了 撤去ピーマンの4本 12回の収穫をして73個のみ さっぱり ダメでした 今年も ピーマン 4本を植えた04月22日 hcで苗が売り出されていたので4本を購入 即 畑に植えておいた今年は失敗しないようにしよう05月06日 無事に畑で育っている ok06月10日 その後 やはり成長してこない 小さいまま06月13日 小さい実がついていたので収穫しておく 4個のみ06月24日 とりあえず 2個のみ 収穫06月26日 2個の収穫07月04日 2個の収穫07月08日 4個の収穫07月11日 1個の収穫07月15日 1個の収穫07月16日 6個の収穫 08月05日 5個の収穫今年も ピーマン 小さいまま どうも 不調である ????6月13日より収穫 4+2+2+2+4+1+1+6+5 =27個 会社での収穫は 合計10個会社のピーマンは トマトとミニトマトの日陰になって 実がつかない会社のは 小さいが実はすこし付いている東日本大震災 3月11日発生08月20日は 既に527日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------対立の構図 論争に負けない人が優れた学者(文科系)(内容が挑戦的なので一言:ここでいう「文科系」とは文科系の学問の全体的な傾向を示していて、個別には異なる学問もあることを最初にお断りしておきたい・・・対立の構図を整理したら、新しい対立ができるというのも可笑しいので)先回の「対立の構図」で「理科系の人間は対立を恥ずかしいと思う」と書いた。もし学問が進んでいればほぼ全員が同じ結論になるはずだし、結論が異なれば研究が足りないので、不明な部分があるか、誰かがウソをついているということになる。いずれにしても、意見が対立したところで議論を中断し、なにが不足しているのかを検討し、「じゃ、もう少し研究してからもう一度、議論しよう」と言うことになる。人間は事実を確認して、人間の頭脳で論理的に導き出される結果が「知的財産」であり、論理的に考えて複数の結論があるときには「おれは・・・思う」というその人のワガママに過ぎないと理科系は考える。それに対してどうも文科系の人(たとえば経済学、社会学、心理学など)は意見が違っても恥ずかしくないように見える。それどころか、むしろ意見が違うのが当たり前で、「論争」に勝ってこそ立派な学者だという雰囲気もある。論争をよく見ていると、まず「事実を共有しようとしない」、そして「論理的に詰めていこうとしない」、さらに時によっては「人によって(学問とは別の)目的があるらしい」という感じがする.経済学や心理学分野では、学者同士で罵倒し合っていることがある。実に不思議なことだ。いがみ合う前に事実を共有する努力をすればよいのに、なぜ、事実を共有しようとしないかというと、「事実」が余りに多くあって、どれが事実なのか分からない。もしくは、どれもこれも「事実」なのだが、どれが大切な事実なのか、なにが些末なのかということすら選択基準を持っていないように見える.・・・・・・・・・また「論理的に詰めていく」ことをせずに、突然、飛躍する.私がこのことを強く感じたのは「世代間倫理」という倫理の分野が登場してきた頃、この分野で有名な哲学者の書いた書籍を3冊ほど読んだことがある.文章は難解だし、本は厚く、なかなか大変で、ものすごい量の文字が並んでいる.でも、私の知りたかった事は書いていなかった。つまり「なぜ、現世代は未来世代に対して責任があるのか?」、「これまでの世代が未来世代に対して責任を取った例があるのか?」、「これからどうなるかを予想できる手段はあるのか?」といった基本的な事が書いていない.その代わりに、あるところに突如として「世代間には倫理があるから、現世代は未来世代に責任がある」という原理が登場する.名古屋大学時代だったので(総合大学だからという意味)、哲学の先生にどうしてこのような論理が通るのですか? その人がなぜ有名になるのですか?とお聞きした.そうしたら「いやあ、その通りです.最も大切なことはえてして直感なんですね」と言われた.学問分野が違うから、私が哲学の考え方を批判しても仕方が無いが、直感でもっとも重要なことを決めるなら、それ以下の小さいことを精密に議論しても意味が無いように思った。もう一つ別の例: 今、南京事件というものに取り組んでいるが、おもしろいことに無限に議論がある。いわば研究者一人に一つの意見があるといっても言い過ぎではない.また研究者と違っても、この事件に関心のある人が多く、その人達がまたいちいち違う見解を述べておられる。南京事件の本は大量に販売されているし、事件を扱った雑誌の論評などを入れると膨大な数に上る.それらの多くが「同じ事を別の表現でくり返している」に見える.それらを読んでいるとなんとなく「時間を無駄に使うのを楽しんでいる」ような感じさえするのだ.上海から南京への日本軍の進撃と中国軍の後退、その間における日本軍の増強と南京政府の動向、南京攻撃の直前の南京城内の動き、人間の数などは、研究者によってほとんど差が無い.さらに南京攻略戦が始まってからも、おおよその戦闘時間、戦闘の様子、結果なども明らかで、紛れがない.問題なのは南京が陥落して大量の投降兵(投降したからと言って捕虜ではない)が出たあたりから2,3日のことだけが問題だが、これも、両軍と市民の動向を追っていくと、人間の動き自体にはそれほど事実認識に差が無いようだ。問題は最後の最後、つまりその人達が「どうなったか」というところで、無限に発散する.そして、どこが問題なのか「差を示す明確な比較表」すら作られていない.「理科系」である私はここで唖然とする。問題は最後の最後にあるのだから、そこを整理するために研究しているはずなのだが、その結果が見当たらないのである。これを「世代間倫理」と同じように解釈すれば「明確な比較表を作ると議論が単純になって、論争が終わりになり、ケンカができない」という感じすらする.・・・・・・・・・理科系の私が言うと文科系から激しいバッシングが来るかも知れないが、自然科学でいうところの「科学」ができるのを待っていると現実の社会に役立たないのでフライングしているように見える.つまり「まだ墜落の可能性のある航空機だが、どうしても飛ばさなければいけない。悠長なことは言ってられない」という感じだ.「ニューヨークに行く必要があるのだから、墜落するという人も居るし、墜落しないという学者もいるから、飛ばしてしまえ!」と言っているようだ。経済学なども特にそうで、バブルが起こったら、それまでバブルのバの時も言っていなかった経済学者が悠々とバブルを解説しているのを見て、強い違和感をもったものだ.自分の学問が間違っていたのだから、しばらくは発言ができないはずだが、そうでもない。政治学者などが選挙結果を予測し、まったく外れているのに、再び同じ人がテレビに出てくるなども同じである.予測が当たらないのは学問が完成していないからだから、その人が話すことは学問ではなく、素人と同じという事になる。文科系の学問が、理科系が考える学問ではないかどうかについては、また機会を見て文科系の人に聞いて見たいと思う.まだ、だれも学者としてなにも語れない初歩的段階にあるのか、そんなことを言っていたらいつまでも学問的成果をあげられないので、少しのフライングを承知で苦労されているのかもしれない。ところで、理科系と文科系がハッキリ分かれている国は少ないが・・(平成24年8月16日なるほどはた坊
2012.08.20
コメント(0)
-

街路樹 まてばしい 東日本大震災527日後に
会社の近くにある街路樹 まてばしいマテバシイ(馬刀葉椎、全手葉椎)ブナ科の常緑高木である。学名 Lithocarpus edulis(シノニム Pasania edulis)。別名 マテバガシ、マテガシ、マタジイ、サツマジイ、アオジイ。 分布 日本固有種で本州の房総半島の南端、紀伊半島、九州から南西諸島の沿岸地に自生。 樹高 15m 幹 暗褐青灰色、滑らか、若枝は無毛。 葉 互生、楕円形で全縁。厚く平滑で、光沢がある。 花 5~6月頃、黄褐色の雌雄花穂を結ぶ。 果実 堅果(どんぐり)で長楕円形。 用途 樹木 街路樹、防風樹、防火樹 材 建築材・器具材。 果実 実はタンニンをあまり含まないため、アク抜きを必要とせず、そのまま炒って食用になる。粉状に粉砕してクッキーの生地に混ぜて「縄文時代のクッキー」として味わうこともできる。 おお 食べられるらしい しいの実東日本大震災 3月11日発生08月20日は 既に527日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------対立の構図 論争に負けない人が優れた学者(文科系)(内容が挑戦的なので一言:ここでいう「文科系」とは文科系の学問の全体的な傾向を示していて、個別には異なる学問もあることを最初にお断りしておきたい・・・対立の構図を整理したら、新しい対立ができるというのも可笑しいので)先回の「対立の構図」で「理科系の人間は対立を恥ずかしいと思う」と書いた。もし学問が進んでいればほぼ全員が同じ結論になるはずだし、結論が異なれば研究が足りないので、不明な部分があるか、誰かがウソをついているということになる。いずれにしても、意見が対立したところで議論を中断し、なにが不足しているのかを検討し、「じゃ、もう少し研究してからもう一度、議論しよう」と言うことになる。人間は事実を確認して、人間の頭脳で論理的に導き出される結果が「知的財産」であり、論理的に考えて複数の結論があるときには「おれは・・・思う」というその人のワガママに過ぎないと理科系は考える。それに対してどうも文科系の人(たとえば経済学、社会学、心理学など)は意見が違っても恥ずかしくないように見える。それどころか、むしろ意見が違うのが当たり前で、「論争」に勝ってこそ立派な学者だという雰囲気もある。論争をよく見ていると、まず「事実を共有しようとしない」、そして「論理的に詰めていこうとしない」、さらに時によっては「人によって(学問とは別の)目的があるらしい」という感じがする.経済学や心理学分野では、学者同士で罵倒し合っていることがある。実に不思議なことだ。いがみ合う前に事実を共有する努力をすればよいのに、なぜ、事実を共有しようとしないかというと、「事実」が余りに多くあって、どれが事実なのか分からない。もしくは、どれもこれも「事実」なのだが、どれが大切な事実なのか、なにが些末なのかということすら選択基準を持っていないように見える.・・・・・・・・・また「論理的に詰めていく」ことをせずに、突然、飛躍する.私がこのことを強く感じたのは「世代間倫理」という倫理の分野が登場してきた頃、この分野で有名な哲学者の書いた書籍を3冊ほど読んだことがある.文章は難解だし、本は厚く、なかなか大変で、ものすごい量の文字が並んでいる.でも、私の知りたかった事は書いていなかった。つまり「なぜ、現世代は未来世代に対して責任があるのか?」、「これまでの世代が未来世代に対して責任を取った例があるのか?」、「これからどうなるかを予想できる手段はあるのか?」といった基本的な事が書いていない.その代わりに、あるところに突如として「世代間には倫理があるから、現世代は未来世代に責任がある」という原理が登場する.名古屋大学時代だったので(総合大学だからという意味)、哲学の先生にどうしてこのような論理が通るのですか? その人がなぜ有名になるのですか?とお聞きした.そうしたら「いやあ、その通りです.最も大切なことはえてして直感なんですね」と言われた.学問分野が違うから、私が哲学の考え方を批判しても仕方が無いが、直感でもっとも重要なことを決めるなら、それ以下の小さいことを精密に議論しても意味が無いように思った。もう一つ別の例: 今、南京事件というものに取り組んでいるが、おもしろいことに無限に議論がある。いわば研究者一人に一つの意見があるといっても言い過ぎではない.また研究者と違っても、この事件に関心のある人が多く、その人達がまたいちいち違う見解を述べておられる。南京事件の本は大量に販売されているし、事件を扱った雑誌の論評などを入れると膨大な数に上る.それらの多くが「同じ事を別の表現でくり返している」に見える.それらを読んでいるとなんとなく「時間を無駄に使うのを楽しんでいる」ような感じさえするのだ.上海から南京への日本軍の進撃と中国軍の後退、その間における日本軍の増強と南京政府の動向、南京攻撃の直前の南京城内の動き、人間の数などは、研究者によってほとんど差が無い.さらに南京攻略戦が始まってからも、おおよその戦闘時間、戦闘の様子、結果なども明らかで、紛れがない.問題なのは南京が陥落して大量の投降兵(投降したからと言って捕虜ではない)が出たあたりから2,3日のことだけが問題だが、これも、両軍と市民の動向を追っていくと、人間の動き自体にはそれほど事実認識に差が無いようだ。問題は最後の最後、つまりその人達が「どうなったか」というところで、無限に発散する.そして、どこが問題なのか「差を示す明確な比較表」すら作られていない.「理科系」である私はここで唖然とする。問題は最後の最後にあるのだから、そこを整理するために研究しているはずなのだが、その結果が見当たらないのである。これを「世代間倫理」と同じように解釈すれば「明確な比較表を作ると議論が単純になって、論争が終わりになり、ケンカができない」という感じすらする.・・・・・・・・・理科系の私が言うと文科系から激しいバッシングが来るかも知れないが、自然科学でいうところの「科学」ができるのを待っていると現実の社会に役立たないのでフライングしているように見える.つまり「まだ墜落の可能性のある航空機だが、どうしても飛ばさなければいけない。悠長なことは言ってられない」という感じだ.「ニューヨークに行く必要があるのだから、墜落するという人も居るし、墜落しないという学者もいるから、飛ばしてしまえ!」と言っているようだ。経済学なども特にそうで、バブルが起こったら、それまでバブルのバの時も言っていなかった経済学者が悠々とバブルを解説しているのを見て、強い違和感をもったものだ.自分の学問が間違っていたのだから、しばらくは発言ができないはずだが、そうでもない。政治学者などが選挙結果を予測し、まったく外れているのに、再び同じ人がテレビに出てくるなども同じである.予測が当たらないのは学問が完成していないからだから、その人が話すことは学問ではなく、素人と同じという事になる。文科系の学問が、理科系が考える学問ではないかどうかについては、また機会を見て文科系の人に聞いて見たいと思う.まだ、だれも学者としてなにも語れない初歩的段階にあるのか、そんなことを言っていたらいつまでも学問的成果をあげられないので、少しのフライングを承知で苦労されているのかもしれない。ところで、理科系と文科系がハッキリ分かれている国は少ないが・・(平成24年8月16日なるほどはた坊
2012.08.20
コメント(1)
-

ゴーヤ 黄色の実になって 種は真っ赤 東日本大震災526日後に
ゴーヤつる性の一年生草本。成長すると長さ4~5mになる。果実は細長い紡錘形で長さ20~50cm、果肉を構成する果皮は無数の細かいイボに覆われ、両端は尖り、未成熟な状態では緑、熟すと黄変軟化し裂開する(収穫しても、常温で放置しておくと同じ状態となる)。完熟した種子の表面を覆う仮種皮は赤いゼリー状となり甘味を呈する。腐敗しているわけではなく食すこともできるが、歯ごたえのある食感は失われる。元来野生状態では、この黄色い果皮と赤くて甘い仮種皮によって、果実食の鳥を誘引して種子散布を行っていたものと考えられる。比較的病害虫に強く、日照と気温と十分な水さえあれば、肥料や農薬はほとんど使わなくても収穫が得られ、家庭菜園の作物にも適している。このためもあってか、2010年前後から緑のカーテン(グリーン・カーテン)と呼ばれる日除けのために栽培されることが多くなった。丈夫で栽培は容易である反面、大きく育ち過ぎるのが欠点である。つまり栽培に必要なスペースと土の確保が問題になる。十分な収穫を得るには、地面に植える場合は畝幅が1,2メートルで株の間隔は1メートル以上必要薩摩料理をはじめとする南九州の郷土料理でも好まれる食材であり、九州ではおひたし・和え物でよく食べられる。鶏肉とキャベツと炒めたり、天ぷらや(揚げて)チップスにもする。実を細かく砕いて焙じたものは、ゴーヤー茶として沖縄県で販売されている。味はほうじ茶に似て苦味は無い。キュウリと似ている青い実を食べて 大きくなると黄色になるどちらも あまり 虫がこないキュウリはサラダと漬物にするがゴーヤは ゴーヤチャンブルが良いどちらも 家庭菜園では人気がある東日本大震災 3月11日発生08月19日は 既に526日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------日本と日本人 日本の気候風土過度に愛国心を鼓舞してはいけないけれど、自分の国に誇りを持つことは決して悪くない。というより良いことだ。私が講演で「日本人は、孫たちが中国の孫に負けないようにしてあげなければならない」というと、「そんなことを言うと中国の人に悪い」と言われるけれど、中国のお爺さんも孫のことを心配しているはずだ。どの国も、まずは自分の国が繁栄することを考える。子供や孫の為に良い環境を残すことが大切で、まずはそれができないで外国や世界のことを心配しても空しい。・・・・・・・・・この写真が好きで、かなり前になるが、写真家の方に使っても良いと言われて、時々、使わせてもらっている。日本は穏やかな気候だ。春夏秋冬、山紫水明、実に素晴らしいところで、私は多くの国に行ったが、日本より良いところは無かった。それは、温帯の大きな島国で中央に山脈があるというのが日本だけだからだろう。気温は少し低めだ。もし、沖縄が台湾当たり、北海道の宗谷岬が青森ぐらいだったら、申し分ないが、無い物ねだりをしても仕方がないので、今のところで満足したい。島国というのは、気温の変化が少なく(海洋性気候)、水が豊富で綺麗、それにサカナが捕れるというような自然環境ばかりではなく、外敵が襲ってこないということもあり、やや閉鎖的で穏やかになるが、本当に日本は「この世の天国」である。世界で苦しんでいる人には申し訳ないが、私はなんと幸運なのだろう。(平静21年10月27日執筆いいねえはた坊
2012.08.19
コメント(4)
-

雷ゴロゴロ すぐに雨がやんで 虹さんでてきた 東日本大震災526日後に
8月18日 土曜日 夕方雷がゴロゴロ ドカーンと落雷1つで 雨が降り出してきて すぐにやむそのあとは 虹が出てきていた天気予報によると昨日発表された1か月予報の1週目(8月18日~24日)の気温予想は、北日本を中心にかなりの高温確率となっています。2週目(8月25日~31日)も、太平洋高気圧の勢力が、引き続き、北日本方面へも及ぶ予想のため、同じく、北日本を中心に高温確率が高くなっています。この予想が当たるとするならば、思い出されるのがおととし(2010年)の夏、お盆を過ぎてからの長期間に及んだ猛烈な残暑。果たして、お盆を過ぎてからの今年の猛烈な残暑は、どれくらいのレベルになるのか?特に、上記2週目以降の高気圧の盛弱が気になるところです・ とか なんとかスーパーコンピューターを使った天気予報あたるのか 外れるのか ?????平年より太平洋高気圧が強いので、まだまだ夏は終わりそうにありません。 ただ、来週末には、その太平洋高気圧が勢力を弱め南下傾向を示す資料があり、来週末には残暑も少しおさまるかもしれません。まだ不確定要素ありなので、あまり期待はしないでください との事ですまあ しばらくは 暑い ということらしい東日本大震災 3月11日発生08月19日は 既に526日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------日本と日本人 日本の気候風土過度に愛国心を鼓舞してはいけないけれど、自分の国に誇りを持つことは決して悪くない。というより良いことだ。私が講演で「日本人は、孫たちが中国の孫に負けないようにしてあげなければならない」というと、「そんなことを言うと中国の人に悪い」と言われるけれど、中国のお爺さんも孫のことを心配しているはずだ。どの国も、まずは自分の国が繁栄することを考える。子供や孫の為に良い環境を残すことが大切で、まずはそれができないで外国や世界のことを心配しても空しい。・・・・・・・・・この写真が好きで、かなり前になるが、写真家の方に使っても良いと言われて、時々、使わせてもらっている。日本は穏やかな気候だ。春夏秋冬、山紫水明、実に素晴らしいところで、私は多くの国に行ったが、日本より良いところは無かった。それは、温帯の大きな島国で中央に山脈があるというのが日本だけだからだろう。気温は少し低めだ。もし、沖縄が台湾当たり、北海道の宗谷岬が青森ぐらいだったら、申し分ないが、無い物ねだりをしても仕方がないので、今のところで満足したい。島国というのは、気温の変化が少なく(海洋性気候)、水が豊富で綺麗、それにサカナが捕れるというような自然環境ばかりではなく、外敵が襲ってこないということもあり、やや閉鎖的で穏やかになるが、本当に日本は「この世の天国」である。世界で苦しんでいる人には申し訳ないが、私はなんと幸運なのだろう。(平静21年10月27日執筆いいねえはた坊
2012.08.19
コメント(0)
-

わけぎ 在庫のもの 発芽してきている 東日本大震災526日後に
昨年のワケギの予定種の保管は納屋でやっている たくさん種ワケギは用意しているが畑の放置している ワケギを見てみると 発芽しているのもある庭のわけぎ 発芽しているg-22のわけぎ これも発芽したm-20のわけぎ これも発芽した納屋のわけぎ これは大量にある 発芽はまだ在庫は大量にある わけぎの植え付けの予定は8月21日だったけど今年の8月は猛暑の予定 猛暑が過ぎるまで植え付けは延期しよう第一弾のわけぎ g-2209月11日 g-22の畑で昨年のわけぎを植え付けした09月18日 発芽していたので無事09月25日 どんどん発芽してきている10月02日 これで安心 追肥した10月23日 収穫できるくらいに大きくなってきている11月27日 大きく 青々としている 収穫できる12月11日 わけぎ 収穫はokとなっている12月30日 すこし収穫をしておく第二弾のわけぎ m-0809月18日 残りのわけぎm-08の横にならべておく09月25日 発芽しつつある 10月02日 発芽したのでm-08の畝に移動した 10月23日 こちらは 生育は遅い まだ 小さいなあ11月27日 すこし大きくなってきているが まだ 小さいかな 小ぶりのまま12月11日 わけぎ 収穫はokとなっているわけぎ 第1-2弾とも 収穫できる12月30日 収穫を開始 わけぎ いい感じになっている今年01月09日 2回目の収穫をしておく 大きくなっている01月15日 3回目の収穫をしておく 美味い01月21日 4回目の収穫をしておく 出来具合も良い01月29日 5回目の収穫をしておく まあまあ02月05日 6回目の収穫をしておく いい感じ02月12日 7回目の収穫をしておく 新鮮だあ02月19日 8回目の収穫をしておく 良く分ケツしている02月19日 8回目の収穫をしておく 春らしいわけぎになってきている03月04日 9回目の収穫をしておく まだまだ収穫はできそう03月11日 10回目の収穫をしておく どんどん収穫するぞーーー03月18日 11回目の収穫をしておく まだまだ どんどん収穫するぞーーー03月25日 旅行で収穫できず04月01日 12回目の収穫をしておく まだまだ収穫するぞーーー04月08日 13回目の収穫をしておく これで 柔らかさもなくなってきたので お終いに 在庫は大量 たくさんあるーーーーうが 柔らかさがなくなってきたで これで お終いとしよう残っているワケギは雑損さんに負けている全部 引っこ抜いて 干して 保存夏に再度 植えつけよう05月13日 残っていたワケギ 追加でほりあげておいたこれで 全部のワケギを納屋において 保存中08月19日 在庫のわけぎ 発芽してきているぞそろそろ わけぎ 植え付けしてもよさそうになってきている今年も9月には 植え付けしよう 在庫はたっぷりとある東日本大震災 3月11日発生08月19日は 既に526日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------日本と日本人 日本の気候風土過度に愛国心を鼓舞してはいけないけれど、自分の国に誇りを持つことは決して悪くない。というより良いことだ。私が講演で「日本人は、孫たちが中国の孫に負けないようにしてあげなければならない」というと、「そんなことを言うと中国の人に悪い」と言われるけれど、中国のお爺さんも孫のことを心配しているはずだ。どの国も、まずは自分の国が繁栄することを考える。子供や孫の為に良い環境を残すことが大切で、まずはそれができないで外国や世界のことを心配しても空しい。・・・・・・・・・この写真が好きで、かなり前になるが、写真家の方に使っても良いと言われて、時々、使わせてもらっている。日本は穏やかな気候だ。春夏秋冬、山紫水明、実に素晴らしいところで、私は多くの国に行ったが、日本より良いところは無かった。それは、温帯の大きな島国で中央に山脈があるというのが日本だけだからだろう。気温は少し低めだ。もし、沖縄が台湾当たり、北海道の宗谷岬が青森ぐらいだったら、申し分ないが、無い物ねだりをしても仕方がないので、今のところで満足したい。島国というのは、気温の変化が少なく(海洋性気候)、水が豊富で綺麗、それにサカナが捕れるというような自然環境ばかりではなく、外敵が襲ってこないということもあり、やや閉鎖的で穏やかになるが、本当に日本は「この世の天国」である。世界で苦しんでいる人には申し訳ないが、私はなんと幸運なのだろう。(平静21年10月27日執筆いいねえはた坊
2012.08.19
コメント(2)
-

ナスビ 今週は1個のみ 東日本大震災526日後に
昨年のなすびhcで苗が売られていたので 6本を購入した04月03日 hcで苗を6本を購入した 苗はm06の畑に植え付けた04月09日 なすびが枯れてしまった ?? 強風と水が不足したのかな ??04月10日 再度hcでまた なすびの苗を6本を投入した 今度は枯らさないぞーー04月17日 追加の苗2本をさらに投入 ついでに なすびの種も購入しておいた 時差用04月24日 なすびの苗は 合計で8本 無事である 種もまこう どんどん作ろう05月08日 苗は元気だ 紫の色の葉はいきいきとしている05月15日 内の4本 調子が悪くなった ??? なんで ???05月22日 hcで代わりの4本の苗 追加で植えておく06月05日 ナスビの苗 10本くらいになっているが 育ちがまた悪くなってきた06月12日 2-3本が枯れてきた ??? どうなるかな よくないな ?07月03日 ナスビが雑草に隠れてしまっている 雑草取りをしたが背が低いままだなあ 07月17日 もう あとは枯れるだけみたいになってきた 小さい実をときどき収穫しているついでに 種からの栽培も 第二弾05月03日 種まきした 庭で potに種まき06月05日 畑に移動 g-10に植えておいた07月03日 3本は残って 成長中07月17日 こちらは そろそろ実が出来そう第三弾の種まきこれは 来週くらいにやろう06月05日 種まきしよう07月17日 こちらも大きくなりつつあるナスビの苗m06の苗 5本くらいが残っている 雑草に埋もれていた 雑草とりした 実がすこしno2-は 3本が生育中 大きくなりつつあるno3-は 10本くらいが生育中 大きくなりつつある会社では 2本の苗が生育中 実もついている 7/21日1本の収穫をしたナスビ 雑草とトマトとミニトマトに囲まれて 生育不調のままno2-3などに期待している no1は小さい実がすこし 収穫をしておいた07月03日 収穫は10個07月10日 収穫は2個 もう 小さい 小さい さっぱりだなあ07月13日 収穫を水曜に6個 これも小さいまま とりあえず 収穫たけはしておく07月17日 収穫は日曜に2個 さっぱりだなあ 07月24日 収穫は日曜にまた2個のみ さっばり ダメ07月31日 収穫は日曜に3個のみ08月07日 収穫は日曜に7個のみ ミニミニさいずのみ08月14日 収穫は日曜に10個のみ ミニミニばかり08月20日 土曜に10個 ミニミニ収穫08月21日 日曜に10個 ミニミニなど08月22日 会社のナスビ5個 収穫 これは大きい08月28日 日曜にナスビ10個ミニミニ収穫09月04日 日曜にナスビ10個ミニミニ収穫09月11日 日曜にナスビ30個ミニミニ収穫 実が増えてきている09月18日 日曜にナスビ30個 どんどん 収穫中09月25日 日曜にナスビ30個 収穫中10月02日 日曜にナスビ30個 収穫中10月10日 月曜にナスビ20個 収穫中10月16日 日曜にナスビ20個 収穫中10月22日 土曜にナスビ20個 収穫中10月30日 日曜にナスビ20個 これにて収穫を終了したなすび ミニミニも入れて287個にて 終了した後半の雨で 実も沢山ついてくれた まあまあということでナスビさんも撤去した今年のナスビ暖かくなるまで ゆっくりとする04月22日 今年はゆっくりして 暖かくなるまで待って 本日ナスビの苗6本を買ってきた04月30日 苗は無事にそだっている ok m-08の畑に植えている05月20日 なんとか持ちこたえている すこしは大きくなっている05月27日 6本のうち 5本が枯れそう 水遣りが日曜だけなので枯れてきた05月27日 追加で4本の苗をかってきて m06に植えておいた06月03日 さらに追加が4本の苗を庭のプランターに植えておくで 結局は6-5=1 で+4+4=合計9本の苗を育てている次は第二弾 種蒔きして秋茄子を育てる予定04月30日 庭で種蒔きをしておく 8potで種まきした05月20日 発芽せず これはダメだなあ第二弾の種まきのは 失敗 発芽せず時差でナスビをどんどん育てよう第三弾05月27日 庭でpotに種まきをしておく06月06日 やっと発芽している これで発芽したので そのまま育てていこう06月10日 発芽したのは畑に移動 m-06の畑に移動06月17日 苗は無事 07月08日 4本は無事 実もすこしだけ収穫できている08月05日 すこし大きくなりだしたくらい 実はすこしつきだした種がまだあるので ついでに第四弾だ06月10日 庭でpotに種まきしておく06月17日 まだ発芽せず いつも遅いなあ06月19日 やっと発芽してきている06月23日 畑に移動した g-22の畑の畝07月08日 何本かは 無事08月05日 2-3本はそだちつつある最期に第五弾06月24日 庭でpotに種まきをしておいた これで最終の予定07月01日 発芽していないけど そのまま畑に移動した m-20の畑に移動07月08日 何本かは 苗が無事に残っている08月05日 こちらも2-3本は育ちつつあるナスビの在庫畑 m07に6本 6本枯れてなくなった 実が1個のみ収穫畑 m06に追加で4本 収穫はまずは4個 その後4個の収穫 そのごすこし収穫畑 m06に発芽した苗すこし 4本くらい残っている畑 g22に発芽した苗をすこし 2-3本くらい残っている畑 m20にすこし こちらも2-3本くらい残っている庭 予備の苗3本 会社 4本のナスビ これが一番に元気にそだっている 苗で残っているのは 4本くらい 発芽したのはすこし そのうち 残っているのは8本くらい会社でのナスビ 収穫は15個畑のナスビ 12個の収穫会社のほうが成績が良い畑のは 秋まで 待とう東日本大震災 3月11日発生08月19日は 既に526日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------日本と日本人 日本の気候風土過度に愛国心を鼓舞してはいけないけれど、自分の国に誇りを持つことは決して悪くない。というより良いことだ。私が講演で「日本人は、孫たちが中国の孫に負けないようにしてあげなければならない」というと、「そんなことを言うと中国の人に悪い」と言われるけれど、中国のお爺さんも孫のことを心配しているはずだ。どの国も、まずは自分の国が繁栄することを考える。子供や孫の為に良い環境を残すことが大切で、まずはそれができないで外国や世界のことを心配しても空しい。・・・・・・・・・この写真が好きで、かなり前になるが、写真家の方に使っても良いと言われて、時々、使わせてもらっている。日本は穏やかな気候だ。春夏秋冬、山紫水明、実に素晴らしいところで、私は多くの国に行ったが、日本より良いところは無かった。それは、温帯の大きな島国で中央に山脈があるというのが日本だけだからだろう。気温は少し低めだ。もし、沖縄が台湾当たり、北海道の宗谷岬が青森ぐらいだったら、申し分ないが、無い物ねだりをしても仕方がないので、今のところで満足したい。島国というのは、気温の変化が少なく(海洋性気候)、水が豊富で綺麗、それにサカナが捕れるというような自然環境ばかりではなく、外敵が襲ってこないということもあり、やや閉鎖的で穏やかになるが、本当に日本は「この世の天国」である。世界で苦しんでいる人には申し訳ないが、私はなんと幸運なのだろう。(平静21年10月27日執筆いいねえはた坊
2012.08.19
コメント(0)
-

ニラ 刈り取っても 1週間で元に戻る 東日本大震災526日後に
昨年 ニラの収穫の予定今年は3月から どんどんと収穫している庭のニラ あちこち どんどん葉が出てきている-収穫中g-22 ここも発芽してきた 3月6日m-08 発芽してきたのは2月28日庭のニラ たくさんあるのでどんどん収穫収穫3月05日 初の収穫をした 今年は早いぞ3月12日 2回目の収穫をした3月20日 3回目の収穫をした3月27日 4回目の収穫をした4月03日 5回目の収穫をした4月12日 6回目の収穫をした4月20日 7回目の収穫をした4月28日 8回目の収穫をした5月08日 9回目の収穫をした5月22日 10回目の収穫をした5月29日 11回目の収穫をした6月05日 12回目の収穫をした6月12日 13回目の収穫をした6月26日 14回目の収穫をした7月03-10-17-24-31日 収穫しなかった8月07日 15回目の収穫をした8月21日 花の蕾があちこちに出てきている8月28日 g22のニラ 3wkでやっと回復した しかし花蕾だらけになってきている9月18日 m08のニラ 収穫をしておいたニラは元気だなあ3月-4回4月-4回5月-3回6月-3回と もう14回の収穫をした7月- 0回 7月は収穫していない さすがに ニラも多すぎた感じになっている8月- 1回 これで15回目の収穫 g229月- 1回 これで16回目の収穫 m0810月 -1回 これで17回目の収穫 g-2211月 -m08の分 まだ冷蔵庫に在庫があるので 収穫はしなかった12月 -庭のニラ すこし収穫した 1回 合計で18回の収穫をした 今年 01月09日 m08のニラは枯れ草になっていたニラが枯れてしまった 在庫はなしになった次は3月になると 新芽が出るだろう02月26日 ニラ 新芽が出てきている 春だなあ そろそろ青くなってきてくれそう03月04日 ニラ 新芽が増えてきている 早く青くなれーーーーー03月18日 ニラ かなり前面に芽が出てきている今年のニラ 収穫は4月から 開始だなあ04月08日 今年の収穫は1回目となる 初の収穫だけど 昨年より遅い04月22日 2回目の収穫した05月03日 3回目の収穫をした05月13日 4回目の収穫をした05月20日 5回目の収穫をした06月10日 6回目の収穫をした06月30日 7回目の収穫をした07月08日 8回目の収穫をした07月15日 9回目の収穫をした07月22日 10回目の収穫をした08月05日 11回目の収穫をした08月12日 12回目の収穫をしたにら 庭にもあるので 便利 いつでも収穫 どんどん 食べよう東日本大震災 3月11日発生08月19日は 既に526日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------日本と日本人 日本の気候風土過度に愛国心を鼓舞してはいけないけれど、自分の国に誇りを持つことは決して悪くない。というより良いことだ。私が講演で「日本人は、孫たちが中国の孫に負けないようにしてあげなければならない」というと、「そんなことを言うと中国の人に悪い」と言われるけれど、中国のお爺さんも孫のことを心配しているはずだ。どの国も、まずは自分の国が繁栄することを考える。子供や孫の為に良い環境を残すことが大切で、まずはそれができないで外国や世界のことを心配しても空しい。・・・・・・・・・この写真が好きで、かなり前になるが、写真家の方に使っても良いと言われて、時々、使わせてもらっている。日本は穏やかな気候だ。春夏秋冬、山紫水明、実に素晴らしいところで、私は多くの国に行ったが、日本より良いところは無かった。それは、温帯の大きな島国で中央に山脈があるというのが日本だけだからだろう。気温は少し低めだ。もし、沖縄が台湾当たり、北海道の宗谷岬が青森ぐらいだったら、申し分ないが、無い物ねだりをしても仕方がないので、今のところで満足したい。島国というのは、気温の変化が少なく(海洋性気候)、水が豊富で綺麗、それにサカナが捕れるというような自然環境ばかりではなく、外敵が襲ってこないということもあり、やや閉鎖的で穏やかになるが、本当に日本は「この世の天国」である。世界で苦しんでいる人には申し訳ないが、私はなんと幸運なのだろう。(平静21年10月27日執筆いいねえはた坊
2012.08.18
コメント(0)
-

街路樹 こぶし 東日本大震災526日後に
会社の近くの街路樹のこぶしコブシ(辛夷、学名:Magnolia kobus)モクレン科モクレン属の落葉広葉樹の高木。早春に他の木々に先駆けて白い花を梢いっぱいに咲かせる。別名「田打ち桜」。果実は集合果であり、にぎりこぶし状のデコボコがある。この果実の形状がコブシの名前の由来である。高さは18m、幹の直径は概ね60cmに達する。3月から5月にかけて、枝先に直径6-10cmの花を咲かせる。花は純白で、基部は桃色を帯びる。花弁は6枚。枝は太いが折れやすい。枝を折ると、 芳香が湧出する。アイヌ地方では「オマウクシニ」「オプケニ」と呼ばれる。それぞれ、アイヌの言葉で、「良い匂いを出す木」「放屁する木」という意味を持つ。樹皮は煎じて茶の代わりや風邪薬として飲まれる。果実は5-10cmで、袋菓が結合して出来ており、所々に瘤が隆起した長楕円形の形状を成している。北海道のコブシは「キタコブシ」と呼ばれることもある。遠くより見ると桜に似ていること、花を咲かせる季節が桜より早いことから、ヒキザクラ、ヤチザクラ、シキザクラなどと呼ばれる。これらの呼称は北海道、松前地方を中心に使われる。九州、本州、北海道および済州島に分布。「コブシ」がそのまま英名・学名になっている。 日本では「辛夷」という漢字を当てて「コブシ」と読むが、中国ではこの言葉は木蓮を指す。東日本大震災 3月11日発生08月19日は 既に526日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------日本と日本人 日本の気候風土過度に愛国心を鼓舞してはいけないけれど、自分の国に誇りを持つことは決して悪くない。というより良いことだ。私が講演で「日本人は、孫たちが中国の孫に負けないようにしてあげなければならない」というと、「そんなことを言うと中国の人に悪い」と言われるけれど、中国のお爺さんも孫のことを心配しているはずだ。どの国も、まずは自分の国が繁栄することを考える。子供や孫の為に良い環境を残すことが大切で、まずはそれができないで外国や世界のことを心配しても空しい。・・・・・・・・・この写真が好きで、かなり前になるが、写真家の方に使っても良いと言われて、時々、使わせてもらっている。日本は穏やかな気候だ。春夏秋冬、山紫水明、実に素晴らしいところで、私は多くの国に行ったが、日本より良いところは無かった。それは、温帯の大きな島国で中央に山脈があるというのが日本だけだからだろう。気温は少し低めだ。もし、沖縄が台湾当たり、北海道の宗谷岬が青森ぐらいだったら、申し分ないが、無い物ねだりをしても仕方がないので、今のところで満足したい。島国というのは、気温の変化が少なく(海洋性気候)、水が豊富で綺麗、それにサカナが捕れるというような自然環境ばかりではなく、外敵が襲ってこないということもあり、やや閉鎖的で穏やかになるが、本当に日本は「この世の天国」である。世界で苦しんでいる人には申し訳ないが、私はなんと幸運なのだろう。(平静21年10月27日執筆いいねえはた坊
2012.08.18
コメント(0)
-

街路樹 あきにれ 東日本大震災526日後に
会社の近くの街路樹 あきにれアキニレ(秋楡、学名:Ulmus parvifolia)ニレ科ニレ属の落葉高木。別名、イシゲヤキ、カワラゲヤキ、ヤマニレ。 特徴本州中部以南、四国、九州、台湾に分布する落葉高木で、開花期は9月で両性花を咲かせる。名前は同属の中で唯一秋に開花することから。葉は長さ5cmほどの卵形で鋸歯がある。翼果は10月-11月に葉の黄葉と平行して色づき、風に乗って落葉と同時期に散布されるが、落葉が終わっても一部が枝に残っていることがある。大気汚染に強いため街路樹や公園、学校の校庭などによく植栽されている。自生地域ではないが、植栽されたものは関東地方にも多い。空気の悪い場所に植栽されたものは、葉があまり大きくならない。木材としては利用されない。『ネバの木』とも 呼ばれ、カブトムシや クワガタムシが 好む。東日本大震災 3月11日発生08月19日は 既に526日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------日本と日本人 日本の気候風土過度に愛国心を鼓舞してはいけないけれど、自分の国に誇りを持つことは決して悪くない。というより良いことだ。私が講演で「日本人は、孫たちが中国の孫に負けないようにしてあげなければならない」というと、「そんなことを言うと中国の人に悪い」と言われるけれど、中国のお爺さんも孫のことを心配しているはずだ。どの国も、まずは自分の国が繁栄することを考える。子供や孫の為に良い環境を残すことが大切で、まずはそれができないで外国や世界のことを心配しても空しい。・・・・・・・・・この写真が好きで、かなり前になるが、写真家の方に使っても良いと言われて、時々、使わせてもらっている。日本は穏やかな気候だ。春夏秋冬、山紫水明、実に素晴らしいところで、私は多くの国に行ったが、日本より良いところは無かった。それは、温帯の大きな島国で中央に山脈があるというのが日本だけだからだろう。気温は少し低めだ。もし、沖縄が台湾当たり、北海道の宗谷岬が青森ぐらいだったら、申し分ないが、無い物ねだりをしても仕方がないので、今のところで満足したい。島国というのは、気温の変化が少なく(海洋性気候)、水が豊富で綺麗、それにサカナが捕れるというような自然環境ばかりではなく、外敵が襲ってこないということもあり、やや閉鎖的で穏やかになるが、本当に日本は「この世の天国」である。世界で苦しんでいる人には申し訳ないが、私はなんと幸運なのだろう。(平静21年10月27日執筆いいねえはた坊
2012.08.18
コメント(0)
-

会社でキュウリの栽培を今から 実がつくかな ??? 東日本大震災525日後に
会社でキュウリの種をもらったので発芽させようと種まきした8月09日 種をもらう 水につける8月10日 発根しているので 土に植えておく8月13日 発芽してきているで 15本くらいあるので 会社の植木の横に植えておいたさて こんなに遅くに種まきしたが実がつくかどうか ???しばらくは 様子見をしよう東日本大震災 3月11日発生08月18日は 既に525日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------人生講座(3) お金の巡り方・損しない方法さて、人生講座の第一回、第二回で、貨幣経済の中では「節約」は「消費を促進する」と言うことがわかり、そのお金を狙っている人は「政治家、お役人」などであることも理解できました。お金のことを考える時には、「国家」と「家計」を分けることが大切です。「国家としては・・・すべきだ」ということと、「自分のお金は・・・しなければならない」というのは違うからです。経済学者は国全体のことを考えているので、「国家はこうすべきだ」という話が多いし、それで良いのですが、「では、個人は?」とお聞きすると「まずは国家だ」と言うことになります。でも、国家がまともになるには時間がかかり、そのうちに自分の人生が終わってしまう、少なくとも「人生を楽しむ時期」を逸してしまうので、とりあえず、「現在の社会ではどうするか?」ということと「社会が改善されたらどうするか?」を分けておいた方が良いことになります。家庭のお金を考える時に、まず第一にお金の流れが、当面、1)現在の社会があと10年は続くこと、2)民間の活力がないのでお金があまりそれが国債になること、3)国債を償還(返す)ために国は増税を続けること、4)増税のもともとの責任は国民にあるけれど、国民がお金を借りたくなるのに時間がかかること、5)ややデフレ傾向で進むこと(お金を持っている方が得)、であることを理解しておきます。つまり、日本経済はじり貧になりますが、お金回りがバブルが崩壊してしばらくした状態の2分の1ぐらいになるまで、国民の不満は爆発しませんから次の時代には行かないでしょう。もう一つは「年金と相続税」の関係です。こちらの方は、1)年金は少ししか払われない、2)相続税は高くなる、3)だからよくよく自分の寿命を考えて老後の計画を立てる、4)その結果、ある程度、質素な生活をしなければならないし、それは結果として消費を促進するので環境的にも良くないけれど、仕方が無い、5)貯めたお金の半分ぐらいは帰ってくる。後はお役人とかお役人の腰巾着に使われてしまう、6)もっとも良い方法はお役人の腰巾着になって、多くの人が貯めた預金(国債)、税金(消費税)を食い物にする(道徳的にはダメだが、個人としては成立する)、7)次に良い方法は「優しいお母さん方式」(自分の身を捨てて近い人に献身する)、ということになります。・・・・・・・・・政府が本当に国民のことを考えてくれれば良いのですが、そういう時代ではありません。先日、「原発を止めると誰が困るの?」という質問に偉い人が「政府、電力、関係会社」と答えていました。もちろんまともな政府なら「誰が困る」と聞かれたら間髪を入れずに「国民」と答えなければならないわけで、それができないことを前提にしなければなりません。税金は財務省のお役人の出世に、年金は厚労省のお役人の隠れ蓑に、環境関係のことは環境省のだましに使われるだけですが、これも国民との力関係ですから、今のところやむを得ないというところです。救いがあります。それは「まだ、日本は世界一強い」ということです。それは「円の相場」を見ればどんな理屈よりハッキリ分かります。確かに「ドルをもらっただけ円を刷れば円が下がる」と言うのも確かですが、円を刷らないことそのものも含めると、「円が高い間は日本は大丈夫」と言うことでもあります。人間というのは自分の収入が2分の1になるまで暴動を起こさないものです。これは日本ばかりではなく諸外国でもほぼ同じで、我慢できる範囲は我慢してしまうのが人間というものです。だから2020年まではあまり大きな事は起こらないと言うことになります。もともと財産は、現金性、他人性(株、献身)、物質性(ゴールド、土地)の3分割方式が良いのですが、当面は現金性のものをやや多くし、2020年までに徐々に他人性、物質性を増やして次の時代に備えるということでしょう。年金と老後の生活については次回に整理してみたいと思います。(平成24年8月17日)これは 面白いはた坊
2012.08.18
コメント(0)
-
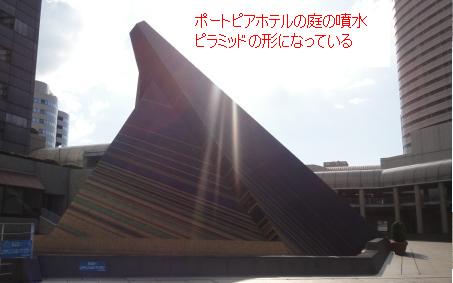
ピラミッドみたいな噴水 東日本大震災525日後に
会社の近くの公園の噴水ポートアイランドには 珍しい噴水が多いいるかの泳いでいる噴水プロペラの噴水これは ピラミッドみたいな噴水変なのが 多いなあ芸術か へんちくりんか ????東日本大震災 3月11日発生08月18日は 既に525日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------人生講座(3) お金の巡り方・損しない方法さて、人生講座の第一回、第二回で、貨幣経済の中では「節約」は「消費を促進する」と言うことがわかり、そのお金を狙っている人は「政治家、お役人」などであることも理解できました。お金のことを考える時には、「国家」と「家計」を分けることが大切です。「国家としては・・・すべきだ」ということと、「自分のお金は・・・しなければならない」というのは違うからです。経済学者は国全体のことを考えているので、「国家はこうすべきだ」という話が多いし、それで良いのですが、「では、個人は?」とお聞きすると「まずは国家だ」と言うことになります。でも、国家がまともになるには時間がかかり、そのうちに自分の人生が終わってしまう、少なくとも「人生を楽しむ時期」を逸してしまうので、とりあえず、「現在の社会ではどうするか?」ということと「社会が改善されたらどうするか?」を分けておいた方が良いことになります。家庭のお金を考える時に、まず第一にお金の流れが、当面、1)現在の社会があと10年は続くこと、2)民間の活力がないのでお金があまりそれが国債になること、3)国債を償還(返す)ために国は増税を続けること、4)増税のもともとの責任は国民にあるけれど、国民がお金を借りたくなるのに時間がかかること、5)ややデフレ傾向で進むこと(お金を持っている方が得)、であることを理解しておきます。つまり、日本経済はじり貧になりますが、お金回りがバブルが崩壊してしばらくした状態の2分の1ぐらいになるまで、国民の不満は爆発しませんから次の時代には行かないでしょう。もう一つは「年金と相続税」の関係です。こちらの方は、1)年金は少ししか払われない、2)相続税は高くなる、3)だからよくよく自分の寿命を考えて老後の計画を立てる、4)その結果、ある程度、質素な生活をしなければならないし、それは結果として消費を促進するので環境的にも良くないけれど、仕方が無い、5)貯めたお金の半分ぐらいは帰ってくる。後はお役人とかお役人の腰巾着に使われてしまう、6)もっとも良い方法はお役人の腰巾着になって、多くの人が貯めた預金(国債)、税金(消費税)を食い物にする(道徳的にはダメだが、個人としては成立する)、7)次に良い方法は「優しいお母さん方式」(自分の身を捨てて近い人に献身する)、ということになります。・・・・・・・・・政府が本当に国民のことを考えてくれれば良いのですが、そういう時代ではありません。先日、「原発を止めると誰が困るの?」という質問に偉い人が「政府、電力、関係会社」と答えていました。もちろんまともな政府なら「誰が困る」と聞かれたら間髪を入れずに「国民」と答えなければならないわけで、それができないことを前提にしなければなりません。税金は財務省のお役人の出世に、年金は厚労省のお役人の隠れ蓑に、環境関係のことは環境省のだましに使われるだけですが、これも国民との力関係ですから、今のところやむを得ないというところです。救いがあります。それは「まだ、日本は世界一強い」ということです。それは「円の相場」を見ればどんな理屈よりハッキリ分かります。確かに「ドルをもらっただけ円を刷れば円が下がる」と言うのも確かですが、円を刷らないことそのものも含めると、「円が高い間は日本は大丈夫」と言うことでもあります。人間というのは自分の収入が2分の1になるまで暴動を起こさないものです。これは日本ばかりではなく諸外国でもほぼ同じで、我慢できる範囲は我慢してしまうのが人間というものです。だから2020年まではあまり大きな事は起こらないと言うことになります。もともと財産は、現金性、他人性(株、献身)、物質性(ゴールド、土地)の3分割方式が良いのですが、当面は現金性のものをやや多くし、2020年までに徐々に他人性、物質性を増やして次の時代に備えるということでしょう。年金と老後の生活については次回に整理してみたいと思います。(平成24年8月17日)これは 面白いはた坊
2012.08.18
コメント(0)
-

街路樹 楠木 東日本大震災525日後に
会社の近くの街路樹 楠木クスノキ(樟、楠、Cinnamomum camphora)クスノキ科ニッケイ属の常緑高木である。一般的にクスノキに使われる「楠」という字は本来は中国のタブノキを指す字である。別名クス、ナンジャモンジャ(ただし、「ナンジャモンジャ」はヒトツバタゴなど他の植物を指して用いられている場合もある)。暖地で栽培される変種としてホウショウがある。食用となるアボカドや、葉が線香の原料となるタブノキ、樹皮が香辛料などに利用されるシナモンは近縁の種である。幹周囲10m以上の巨樹になる個体も珍しくない。単木ではこんもりとした樹形をなす。木肌は綿密で、耐湿・耐久性に優れている。葉はつやがあり、革質で、先の尖った楕円形で長さ5~10cm。主脈の根本近くから左右に一対のやや太い側脈が出る三行脈である。その三行脈の分岐点には一対の小さな膨らみがあり、これをダニ室という(後述)。4月末から5月上旬にかけて大量に落葉する。5月から6月にかけて、白く淡い黄緑色の小さな花が咲く。10月から11月にかけて、直径7~8mm程度の青緑色で球形の果実が紫黒色に熟す。鳥が食べて種子散布に与るが、人間の食用には適さない。中には直径5~6mm程度の種子が一つ入っている。各部全体から樟脳の香りがする。樟脳とはすなわちクスノキの枝葉を蒸留して得られる無色透明の固体のことで、防虫剤や医薬品等に使用される。カンフル注射のカンフルはこの樟脳を指しており、“camphora”という種名にもなっている。クスノキの葉に2つずつ存在するダニ室にはクスノキにとって無害なフシダニの一種が生息している。ダニ室で増殖したフシダニは少しずつダニ室の外に溢れ、これをダニ室には侵入できないサイズの捕食性のダニが捕食することでクスノキの樹上には常にフシダニ捕食性のダニが一定密度で維持されている。このダニ室を人為的に塞いでダニ室のフシダニやこれを捕食する捕食性のダニを排除すると、クスノキにとって有害な虫えいを形成するフシダニが増殖し、多くの葉がこぶだらけになることが知られている。従って、クスノキの葉のダニ室はクスノキに病変を引き起こすフシダニの天敵の維持に役立っていると考えられている。東日本大震災 3月11日発生08月18日は 既に525日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------人生講座(3) お金の巡り方・損しない方法さて、人生講座の第一回、第二回で、貨幣経済の中では「節約」は「消費を促進する」と言うことがわかり、そのお金を狙っている人は「政治家、お役人」などであることも理解できました。お金のことを考える時には、「国家」と「家計」を分けることが大切です。「国家としては・・・すべきだ」ということと、「自分のお金は・・・しなければならない」というのは違うからです。経済学者は国全体のことを考えているので、「国家はこうすべきだ」という話が多いし、それで良いのですが、「では、個人は?」とお聞きすると「まずは国家だ」と言うことになります。でも、国家がまともになるには時間がかかり、そのうちに自分の人生が終わってしまう、少なくとも「人生を楽しむ時期」を逸してしまうので、とりあえず、「現在の社会ではどうするか?」ということと「社会が改善されたらどうするか?」を分けておいた方が良いことになります。家庭のお金を考える時に、まず第一にお金の流れが、当面、1)現在の社会があと10年は続くこと、2)民間の活力がないのでお金があまりそれが国債になること、3)国債を償還(返す)ために国は増税を続けること、4)増税のもともとの責任は国民にあるけれど、国民がお金を借りたくなるのに時間がかかること、5)ややデフレ傾向で進むこと(お金を持っている方が得)、であることを理解しておきます。つまり、日本経済はじり貧になりますが、お金回りがバブルが崩壊してしばらくした状態の2分の1ぐらいになるまで、国民の不満は爆発しませんから次の時代には行かないでしょう。もう一つは「年金と相続税」の関係です。こちらの方は、1)年金は少ししか払われない、2)相続税は高くなる、3)だからよくよく自分の寿命を考えて老後の計画を立てる、4)その結果、ある程度、質素な生活をしなければならないし、それは結果として消費を促進するので環境的にも良くないけれど、仕方が無い、5)貯めたお金の半分ぐらいは帰ってくる。後はお役人とかお役人の腰巾着に使われてしまう、6)もっとも良い方法はお役人の腰巾着になって、多くの人が貯めた預金(国債)、税金(消費税)を食い物にする(道徳的にはダメだが、個人としては成立する)、7)次に良い方法は「優しいお母さん方式」(自分の身を捨てて近い人に献身する)、ということになります。・・・・・・・・・政府が本当に国民のことを考えてくれれば良いのですが、そういう時代ではありません。先日、「原発を止めると誰が困るの?」という質問に偉い人が「政府、電力、関係会社」と答えていました。もちろんまともな政府なら「誰が困る」と聞かれたら間髪を入れずに「国民」と答えなければならないわけで、それができないことを前提にしなければなりません。税金は財務省のお役人の出世に、年金は厚労省のお役人の隠れ蓑に、環境関係のことは環境省のだましに使われるだけですが、これも国民との力関係ですから、今のところやむを得ないというところです。救いがあります。それは「まだ、日本は世界一強い」ということです。それは「円の相場」を見ればどんな理屈よりハッキリ分かります。確かに「ドルをもらっただけ円を刷れば円が下がる」と言うのも確かですが、円を刷らないことそのものも含めると、「円が高い間は日本は大丈夫」と言うことでもあります。人間というのは自分の収入が2分の1になるまで暴動を起こさないものです。これは日本ばかりではなく諸外国でもほぼ同じで、我慢できる範囲は我慢してしまうのが人間というものです。だから2020年まではあまり大きな事は起こらないと言うことになります。もともと財産は、現金性、他人性(株、献身)、物質性(ゴールド、土地)の3分割方式が良いのですが、当面は現金性のものをやや多くし、2020年までに徐々に他人性、物質性を増やして次の時代に備えるということでしょう。年金と老後の生活については次回に整理してみたいと思います。(平成24年8月17日)これは 面白いはた坊
2012.08.18
コメント(0)
-

街路樹 しだれ柳 東日本大震災525日後に
会社の近くの街路樹 しだれ柳ヤナギ(柳、英語: Willow)ヤナギ科 Salicaceae ヤナギ属 Salix の樹木の総称。世界に約350種あり、主に北半球に分布する。日本では、柳と言えば一般にシダレヤナギを指すことが多い落葉性の木本であり、高木から低木、ごく背が低く、這うものまである。葉は互生、まれに対生。托葉を持ち、葉柄は短い。葉身は単葉で線形、披針形、卵形など変化が多い。雌雄異株で、花は尾状花序、つまり、小さい花が集まった穂になり、枯れるときには花序全体がぽろりと落ちる。ただし、外見的には雄花の花序も雌花の花序もさほど変わらない。雄花は雄しべが数本、雌花は雌しべがあるだけで、花弁はない。代わりに小さい苞や腺体というものがあり、これらに綿毛を生じて、穂全体が綿毛に包まれたように見えるものが多い。すべて虫媒花(ただしケショウヤナギ属をヤナギ属に含める場合はこの限りではない)。冬芽は1枚のカバーのような鱗片に包まれ、これがすっぽりと取れたり、片方に割れ目を生じてはずれたりする特徴がある。これは、本来は2枚の鱗片であったものが融合したものと考えられる。果実はさく果で、種子は小さく柳絮(りゅうじょ)と呼ばれ、綿毛を持っており風に乗って散布される。 なお、中国において5月頃の風物詩となっており、古くから漢詩等によく詠み込まれる柳絮だが、日本には目立つほど綿毛を形成しない種が多い。しかし、日本においても意図的に移入された大陸品種の柳があり、柳絮を飛ばす様子を見ることができる。特に北海道において移入種の柳が多く、柳絮の舞う様が見られる。主に温帯に生育し、寒帯にもある。高山やツンドラでは、ごく背の低い、地を這うような樹木となる。日本では水辺に生育する種が多いが、山地に生育するものも少なくない。東日本大震災 3月11日発生08月18日は 既に525日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------人生講座(3) お金の巡り方・損しない方法さて、人生講座の第一回、第二回で、貨幣経済の中では「節約」は「消費を促進する」と言うことがわかり、そのお金を狙っている人は「政治家、お役人」などであることも理解できました。お金のことを考える時には、「国家」と「家計」を分けることが大切です。「国家としては・・・すべきだ」ということと、「自分のお金は・・・しなければならない」というのは違うからです。経済学者は国全体のことを考えているので、「国家はこうすべきだ」という話が多いし、それで良いのですが、「では、個人は?」とお聞きすると「まずは国家だ」と言うことになります。でも、国家がまともになるには時間がかかり、そのうちに自分の人生が終わってしまう、少なくとも「人生を楽しむ時期」を逸してしまうので、とりあえず、「現在の社会ではどうするか?」ということと「社会が改善されたらどうするか?」を分けておいた方が良いことになります。家庭のお金を考える時に、まず第一にお金の流れが、当面、1)現在の社会があと10年は続くこと、2)民間の活力がないのでお金があまりそれが国債になること、3)国債を償還(返す)ために国は増税を続けること、4)増税のもともとの責任は国民にあるけれど、国民がお金を借りたくなるのに時間がかかること、5)ややデフレ傾向で進むこと(お金を持っている方が得)、であることを理解しておきます。つまり、日本経済はじり貧になりますが、お金回りがバブルが崩壊してしばらくした状態の2分の1ぐらいになるまで、国民の不満は爆発しませんから次の時代には行かないでしょう。もう一つは「年金と相続税」の関係です。こちらの方は、1)年金は少ししか払われない、2)相続税は高くなる、3)だからよくよく自分の寿命を考えて老後の計画を立てる、4)その結果、ある程度、質素な生活をしなければならないし、それは結果として消費を促進するので環境的にも良くないけれど、仕方が無い、5)貯めたお金の半分ぐらいは帰ってくる。後はお役人とかお役人の腰巾着に使われてしまう、6)もっとも良い方法はお役人の腰巾着になって、多くの人が貯めた預金(国債)、税金(消費税)を食い物にする(道徳的にはダメだが、個人としては成立する)、7)次に良い方法は「優しいお母さん方式」(自分の身を捨てて近い人に献身する)、ということになります。・・・・・・・・・政府が本当に国民のことを考えてくれれば良いのですが、そういう時代ではありません。先日、「原発を止めると誰が困るの?」という質問に偉い人が「政府、電力、関係会社」と答えていました。もちろんまともな政府なら「誰が困る」と聞かれたら間髪を入れずに「国民」と答えなければならないわけで、それができないことを前提にしなければなりません。税金は財務省のお役人の出世に、年金は厚労省のお役人の隠れ蓑に、環境関係のことは環境省のだましに使われるだけですが、これも国民との力関係ですから、今のところやむを得ないというところです。救いがあります。それは「まだ、日本は世界一強い」ということです。それは「円の相場」を見ればどんな理屈よりハッキリ分かります。確かに「ドルをもらっただけ円を刷れば円が下がる」と言うのも確かですが、円を刷らないことそのものも含めると、「円が高い間は日本は大丈夫」と言うことでもあります。人間というのは自分の収入が2分の1になるまで暴動を起こさないものです。これは日本ばかりではなく諸外国でもほぼ同じで、我慢できる範囲は我慢してしまうのが人間というものです。だから2020年まではあまり大きな事は起こらないと言うことになります。もともと財産は、現金性、他人性(株、献身)、物質性(ゴールド、土地)の3分割方式が良いのですが、当面は現金性のものをやや多くし、2020年までに徐々に他人性、物質性を増やして次の時代に備えるということでしょう。年金と老後の生活については次回に整理してみたいと思います。(平成24年8月17日)これは 面白いはた坊
2012.08.18
コメント(0)
-

ショーガ すこしだけ 残っている 東日本大震災524日後に
2年前のショーガ03月21日 hcで種ショーガの買物 大ショーガの種800gの物 980円04月25日 発泡スチロールの箱にいれている分 すこし発芽してきているのもある05月05日 g22の畑に植え付けした 20個06月06日 畑の雑草取りをしておく06月13日 また 雑草取りをしておく06月19日 20個のうち やっと 2個の発芽を確認 遅いなあ ?? また雑草だらけ07月04日 15の発芽となった07月08日 発芽したのは17本となった あと3つがまだ07月17日 それぞれ17本に2つ目の発芽を開始してきている 賑やかになりつつある07月25日 3-4本目の芽も出てきている 雑草でマルチをしておいた08月15日 雑草の追加のマルチをしておいた 水が不足気味 やや元気がなさそう08月22日 晴天が続いて高温の猛暑がつづく かなり水不足が弱ってきているようだ08月25日 水曜の朝の5時に水遣りに行く08月29日 日曜にも水をたっぶりとやっておく09月05日 またまた水をたっぶりとやっておく09月12日 またまたまた水をたっぶりとやっておく09月19日 葉も黄色くなってきているので収穫をした かなり小さい 匂いのみ水不足でショーガさん 弱って葉も黄色くなったショーガの匂いはブンブンしているが 掘り出してみると小さい8-9月と猛暑が続き 降雨もすくなく水が不足ショーガは生育気温が25-28cくらいで水が不足すると弱い気温も高すぎ 水も極端に不足したので こんなに小さいショーガになりました昨年のショーガ03月20日 hcで大ショーガ800g-980円のを買ってきた これは昨年と同じだなあ04月23日 芽がついてきている そろそろ発芽用の箱にいれよう04月24日 庭で 発泡スチロールの箱にいれて しばらく暖かくして発芽させよう05月05日 安い半額の種芋が売られていた ついつい 安いので買い物した05月22日 発芽したショウガ24個 m-07の畑に植え付けた発芽用の発泡スチロールに保管して 5月に芽は見えていた24個 全部 m07の畑に植え付けておいた06月05日 発芽はまだしてこない そろろそかなと期待していたが あと10日かかる06月17日 2本の発芽 確認した これで 安心だなあ07月17日 なんとか無事に育っている08月14日 猛暑が続いているので やや夏バテになっている感じ09月10日 やや不良だけど 何とか かんとか という感じ そろそろ 収穫時に09月18日 全部を収穫しておいた 雑草に囲まれた割には なんとかなったかなショーガ やや 夏バテ気味だったけど 香りが良いのが収穫できた 良しとしよう今年のショーガhcで ショーガの種 売り出し中03月04日 大ショーガの800gのもの 1つ 買ってきた03月11日 家の庭で箱にいれて芽だしをしておく今年も ショーガ 作ろう04月22日 芽もすこしできてきているので畑に移動した 4つを12個に分割して植え付けした芽が出るのは6月くらい かなり先になる06月03日 やっと発芽してきている まだ1本だけやっと 発芽したあーーーーー07月01日 発芽下のは7-10本くらいになっている08月01日 その後もあまり育っていない08月12日 うーん 残っているのは4-5本だけ 小さいまま今年のショーガ 雑草にまけて さっぱり残っているのは4-5本だけ東日本大震災 3月11日発生08月17日は 既に524日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------対立の構図 対立は恥ずかしいこと(理科系)人間には「対立」というのがある。自分の意見が正しくて、相手が間違っているという論理をたてるのだが、理科系の私にはなかなか理解ができない。もし自分が「何の意図もなく、先入観も無い」状態で、相手も「ウソをついていない」場合は、「違う意見になる」ということがあり得ないように思うからだ。多くの人は「そんなことはない。事実、この世は意見が違う事ばかりだ」と言われるだろう。でも「理科系」の私には「意見が違う」と言うこと自体がおかしいように思われるのである。第一の問題は、自分が正しくて相手が間違っているのか、自分が間違っていて相手が正しいのかは、自分とその相手がいくら議論しても決まるものではなく、お釈迦様に聞いて見なければならない。「なぜ、ご自分のご意見が正しいと思うのですか?」と聞くと「私がそう思うから」という自信たっぷりの方がおられるが、ある人間が「正しい」と判断したことが「本当に正しい」かどうかは本人には分からないはずだ。「自分の生きているうちはごまかせる」というぐらいはいけるだろう.・・・・・・・・・この「対立の構図」で整理をしてみたいと思っているのは、このことではなく、第二の問題:「意見が対立するというのは、分からないことか、隠していることがあるから」ではないかということだ。自然科学(普通には科学ということが多い)は「自然現象を解明する」ことが主な仕事で、ついでに「それを応用して工学、農学、医学などを発展させる」という仕事もある。自然現象というのは太古の昔からある原理原則で成り立っているので、「人間が分からない」ということがあっても、「意見が存在する」と言うものではない。たとえば、かつて人間は「宇宙の中心は地球だ」と信じていて、科学もそれを支持した。でも、これには前提があり「人間の目で見る限りの空」ということであり、かつ「ある種の星(後に惑星であることが分かるが)が逆行することがあること、太陽は往復運動をするはずなのに毎日東から出てくる・・・などはまだ解けない疑問として残すという仮定に基づけばということである。しかし、望遠鏡が誕生すると「地球は太陽の回りを回っていて、太陽も宇宙の中心ではない」ということがわかる。でもそれも「望遠鏡でみるという前提つき」である。でも今のところ、それが科学なので「地動説」に異議を唱える学者はいない。ガリレオが「地動説」を唱えたとき、有力な科学者がガリレオに反撃を加えたのではなかった。聖書を信じる教会が彼をバッシングした。科学者は事実を明らかにしようとしているので、ガリレオの地動説が事実ならそれは進歩であり、なにもバッシングする対象ではないからである.ダーウィンが「進化論」を唱えたとき、それにバッシングを加えたのはこれも牧師であって科学者ではなかった.もし科学者がダーウィンを批判するなら、ダーウィンのデータの科学的な解釈に誤りがあるか、あるいは自分がダーウィンと同じように世界一周をしてきて、つぶさに生物の生態を観察し、反論をしなければならない。でも、科学者は基本的には「自然を明らかにする」と言うことだから、反論をしても意味が無い。「そんなこともあるのですか!」と感心するのが普通だ.・・・・・・・・・科学の論文というのは、実験データ(理論でも良い)を示し、それを整理し、専門家なら誰でも合意できないと結論にならない。実験や理論で合理的と(誰もが)判断できる段階にないと結論は出せないのだ。それまでは単に「酒場の独り言」にしか過ぎない.私たちは良く仲間や学生と飲んで話をする.その時には「あのデータはこんな風に思うのだけれどどうだろうか?」と話す。そうすると、そこで議論になり、不足が分かり、研鑽を積む.私たちはただ「自然を明らかにする」というのが目的だから、別にいがみ合う必要などない。若い頃から私がやってきた分離工学、資源、材料などの分野で、「科学的論争」などはなかったし、まして「バッシング」などを経験したことなかった。議論して私が不十分だったら、頭をかきかき再登場するだけである。ところが、忘れもしない1998年のある学会で、私と学生が「リサイクルは資源を余計に消費する」という計算結果を発表した.そうしたら、私は会場から「売国奴!」とバッシングを受け、学生は攻撃を受けて真っ青になって帰ってきた.その頃、私はリサイクルでお金をもらっている訳でもなく、先入観もなく、ただ社会がリサイクルを始めようとしていたので、それを分離工学と材料工学の手法を使って解析したに過ぎなかった.正直言って、当初はなにを非難されているのかということ自体が不明だった.そこで、慌てて関係した文献を調べ直してみたら、やはり学問的に計算しているものは「リサイクルは消費を高める」というものがほとんどだった.ただ、当時、「ライフサイクル・アセスメント(LCA)」という新しい学問の手法が登場して、私たちのような伝統的な学問で計算した結果と違っているものもあった。そこで、LCAで計算している人と何回も研究会をしたが、結局、どちらが正しいかはなかなか分からなかった.新しい学問は大切なものだが、まだ未熟なので、これまでの学問と内容を合わせるということができなかった。それでも、お互いにバッシングするとか、そういうことは無かった.ただ、伝統的な学問で計算するとリサイクルは資源を余計に使い、LCAで計算すると有効な場合があるということがわかり、「研究を続けましょう」と言うことになっただけだった.・・・・・・・・・ところが、そのうち、雲行きが怪しくなった.私が書いた最初のリサイクルの本は「フランケンシュタインの息子たち」という題名が、出版時には「リサイクルしてはいけない」となった。私がフランケンシュタインを出したのは、自分が科学の力で作ったものが、自分を襲ってくる(フランケンシュタイン博士が作った怪物が博士を襲う)ということと、現代の環境問題が類似であるという解釈を題名にしたのだった。それからというもの、私も世の中の動きに巻き込まれ、対立の中に入っていく。それから程なくしてある本に「武田邦彦はウソをついているのか」という題名がついたとき、「ああ、科学者でもウソをつくとみんなが思っているのだな」ということを知った.(平成24年8月15日)そうだはた坊
2012.08.17
コメント(0)
全121件 (121件中 1-50件目)











