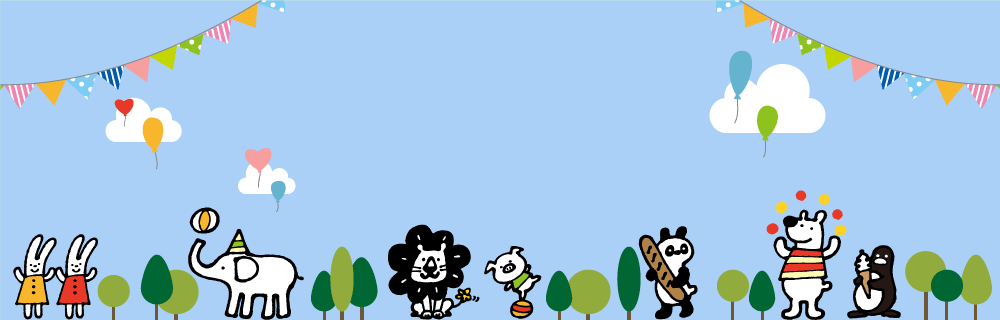2021年04月の記事
全19件 (19件中 1-19件目)
1
-
その後のミャンマー
その後のミャンマークーデタで実権を握った軍政による弾圧は続いていますが、弾圧の仕方はスマートのなってきていることを前回記しました。少なくとも、都市部のデモ隊に、無差別に発砲するような、国際的非難を浴びるようなことは無くなっています。ASEAN首脳のソフトな忠告が効を奏したのでしょう。一方で夜間に住まいを急襲して逮捕連行するような一種の闇討ちは続いています。そしてミャンマーの辺境地帯、少数民族地域では、独立志向の強い少数民族の武装勢力とミャンマー軍との戦闘が激しくなっています。チン族の武装勢力がミャンマー正規軍の拠点を急襲して占領すると、正規軍はチン族の基地を空爆して、数十人の犠牲者を出していたりします。さて、CRPH(連邦代表委員会)とNUG(挙国一致政府)では、少数民族出身者の割合が高くなっているのが気になります。CRPHの顔ともいえるササ医師は、チン族の出身ですし、NUGが任命した閣僚の半数は少数民族の出身者です。 NLDの主要メンバーのビルマ人がほとんど拘束されていますので、残った少数民族出身者が反体制運動の主力を担うことになったのでしょうが、その結果少数民族の武装勢力との連携を重視することになり、ロヒンギャとの連携を呼び掛けることにも繋がってきます。問題は、こうした体制と方針に、全人口の6割強を占めるビルマ人が、離れてしまわずについて行くのか、一抹の不安があります。まずロヒンギャに対して、ビルマ人の大部分は否定的な感情を持っています。それゆえにスーチー女史も、軍部のロヒンギャ虐殺を静観して評判を落とす結果に繋がったのです。ロヒンギャとの連携となると、ビルマ人はCRPHを支持できなくなる可能性が強まります。現在は、国軍憎しで市民は一体となっており、CRPHの発信力は国の内外を問わず大変高いので、民主派の代表として、何処からも認められています。しかしCRPHのメンバーは、NLDの指導部や中核メンバーではなく、NLDの議員だったメンバーも数十人程度に過ぎません。従ってCRPHの正統性については、限界があります。現在の劣勢の苦しい状況が続くとなると、ビルマ人とその他のメンバーの間で、亀裂が生じるリスクが避けられなくなる可能性があります。国軍が仲間割れを誘うようなネガティブキャンペーンに出ることも考えられます。軍部の分裂が起こらない限り、今は人的損失を極力抑え、とりあえずは面従腹背の精神で、軍政の臨時政府を一時認め、民主派の力をためる時期に来ていることを、残念ですが認めるしかないようです。勝ち目のない戦はすべきではありません。
2021.04.29
コメント(8)
-
その後のミャンマー
その後のミャンマーASEAN(東南アジア諸国連合)は、24日首脳会談を開き、ミャンマーの軍事政権トップも参加した席で、5点のコンセンサスを得たとする議長声明を発表しました。新聞にも載りましたので、ご存知の方も多いと思います。(1)暴力の停止と全ての当事者の自制(2)平和的解決に向けた全ての当事者間の建設的対話(3)ASEAN特使による仲介(4)人道支援(5)ASEAN特使のミャンマー訪問と全ての当事者との会談ただし、アウンサン・スーチー女史やNLD幹部らの解放については、コンセンサスに含まれず、議長声明で「外国人を含むすべての政治犯の釈放を求める声もあった」と述べられるに留まりました。少なくとも、東南アジアというインドと中国という二つの大国に囲まれた地域の諸国家連合が動いて、クーデタ後、国際的非難という予想以上に強い批判を浴びて、暴走傾向を強めていたミャンマー軍事政権の代表を、国際会議の席に引っ張り出し、近隣の友人たちから親身のアドヴァイスを受けたことで、クーデタ反対派への暴力的弾圧に、僅かながら変化が出てきたように思われます。まず、4月13~18日のミャンマーの正月休みが明けた頃から、大規模なデモと治安部隊との衝突が大きく減少しています。衝突による死者も大きく減り、ゼロか数人に留まっています。国軍や治安警察も虐殺への非難に音をあげ、抗議運動の中心人物の隠れ家を探し当てて、夜間に急襲して隠れ家に踏み込み逮捕連行する手段をとるようになっています。先日の日本人ジャーナリストの逮捕もその一例です。日本人ばかりか各国の抵抗勢力よりの報道を続けるジャーナリストが次々夜間に住まいに乗り込まれて連行されています。当然大使館を通じての抗議が行われていますが…こうした状況の中、ヤンゴンなど都市部の商店などは営業を再開しており、日常生活が戻りつつあります。逮捕を免れているNLDの議員らを中心に組織された連邦議会代表委員会(CRPH)は、挙国一致政府(NUG)を組織して、抵抗を続けていますが、有力幹部を逮捕されているため、少々厳しい状況に追い込まれています。 どういうことか、明日続きを書きます。
2021.04.27
コメント(10)
-
米軍のアフガン撤退
米軍のアフガン撤退4月14日に、バイデン米大統領は、9月11日までにアフガン駐留米軍を全面撤退させると正式に発表しました。バイデン大統領は決断の根拠を次のように説明しています。1,そもそも2001年のアフガン侵攻の根拠は、米国を攻撃したテロリストたちがアフガンに逃げ込んで 保護されていたので、彼らを打倒し、再びアフガンを拠点に米国にテロを仕掛けることを、出来ないよ うにすることだった。2,既にアルカイダの勢力は弱体化し、オサマ・ビンラディンも殺害した。テロの脅威は残るけれど、テ ロリストたちは、既にアフガンを引き払い、世界各地に拠点を移しており、米国にとっての直接的な脅威 としては、アルカイダよりも他地域のテロリストたちの脅威の方が大きい。こうした状況下に、アフガン だけに米軍の部隊を長期駐留させておくのは、理に適っていない。3,現実にアフガンにおける対テロ作戦の95%は、アフガン治安部隊が行っている。まだ状況は不安定だ けれども、米軍撤収に適した条件というのは何か? いつなら最適なタイミングと言えるのか?今撤収し ないなら、何時撤収するのか?1年後なのか、2年後なのか、それとも10年後か? この問いに適切に応え られないなら、今撤退させるべきである。バイデン大統領はこう述べたのです。彼はまた、「目の前の難題に照準を合わせるべきだ。」とも述べており、「中国との厳しい競争に対処するために、米国の競争力を強化しなければならない。」とも語っています。アフガンへの駐留を続けて、多額の駐留経費をかけるのではなく、中国との派遣競争に資源を集中するのだということなのです。米軍の撤退は5月1日から始める予定が発表されており、9月を待たず、7月前半には完了する予定だそうです。米軍撤退後、アフガンが不安定化する可能性は残っています。そうなった時困るのは、米国よりも中国を含む近隣の国々であり、そうした近隣諸国が対処すべきなのだと考えているようです。バイデン大統領は、「我々は他の国々、とりわけパキスタン、ロシア、中国、インドやトルコに、アフガンを支援するために、もっと協力するよう呼びかける。彼らは皆、アフガンの将来の安定が重要だと、考えているだろうからである。」とも述べています。アフガンが内戦状態になり、再びイスラム過激派の巣窟になったら、米国以上に困るのは近隣の国々であり、アフガンと地続きで過激派の影響が及んで困るのは、ロシアや中国ではないか。彼らの利益となるアフガンの安定化のために、米国が資源を投入し続けることは、割に合わない話である。米国がアフガンから手を引くことで、困るのは米国ではなく、近隣諸国とりわけロシアであり、中国なのだから、彼らの負担を大きくすことは、米国にとっても大きなプラス要因なおだと、考えているようです。バイデンさん、老獪ですね。
2021.04.26
コメント(8)
-
サウジ、UAE、ヨルダン、エジウト
サウジ、UAE、ヨルダン、エジプトトランプ政権の腕押しによて、イラン包囲網のスクラムを組んできた中東のアラブ諸国とイランとの、関係修復の動きが、ここにきて急速に活発化してきました。4月9日、イラクの仲介でイランとサウジの政府高官がバクダッドで直接に協議したことが伝えられました。この事実は、その後イラン政府が公式に認め、「イラン政府は、常にサウジとの対話を歓迎してきた」とも付け加えました。協議では、イエメン情勢やレバノン情勢などが主要議題となり、イラン側は革命防衛隊コッズ部隊のガニア司令官、サウジ側は総合情報庁(GID)のアル・フライダーン長官という大物同士が代表を務めており、両国の本気度がくっきりと浮かび上がります。ヨルダンとイラン、エジプトとイランの間の代表者会談も開かれました。サウジを筆頭にアラブ諸国が、イランとの関係改善に大きく舵を切ったのは、米・イランの核協議が進展する可能性が高く、中東地域の戦略バランスが大きく変化するだろうことを見込んで、イスラエルのように、バイデン政権の対イラン政策に正面から抵抗するのではなく、米国に先駆けてイランとの関係を修復して、併せてイエメンやレバノンのような地域紛争の解決の道筋をつけ、場合によっては、イランと米国の関係改善に一肌脱いで、双方から一目置かれることを狙っていると考えられます。こうした動きが、うまく結実するなら、中東地域のゴタゴタはかなり整理され、イラクやシリアの情勢にも、良い方向に働く可能性も出てくるのですが、中東地域の不安定が、自国の平和のために望ましいと考えているお邪魔虫のイスラエルは、そうはさせじと妨害工作を練っています。早速伊イスラエルのメディアは、「4月6日に、イスラエルがイランの貨物船(紅海の洋上基地でした)を爆破したのは、サウジからの要請があったからだ」とする暴露記事を載せました。サウジとイランの仲を裂こうと必死になっている様子が分かります。今後もあの手この手を使っての、イスラエルの妨害工作は続き、米国の政界にも強力な働きかけを行うでしょうから、紆余曲折がまだまだありそうですから、今後も折に触れて、様子を報告させていただきます。
2021.04.25
コメント(10)
-
イラン核合意
イラン核合意4月11日に、イランの最重要な核施設のひとつナタンズで、イスラエルのテロによる電源システムの爆破という大きな事件がありました。それを受けてイランは、イスラエルの核テロに対する報復だとして、4月16日に今まで20%に抑えてきたウランの濃縮度を60%に引き上げました。 核合意への復帰をチラつかせながらも、一向に前向きのサインを送ってこない米国が、イスラエルのテロの背後にいるのではないかと疑ったからです。このイランの行動に対し、バイデン米大統領は、「核合意に反する行為だ」と非難しながらも、「一方でイランが核協議を続けるとしたことは歓迎すべきことだ」とも述べ、欧州諸国を仲介役としたウィーンでの間接的核協議を米国から打ち切ることはしないし、協議を継続する意思を明確にしました。その後、米国とイラン双方の意向の伝達厄を続ける欧州連合の担当者から、「合意までにはまだ時間がかかるが、進展があった。」とのコメントが出され、協議に参加しているロシアの代表者からも、「目標に向けた具体的なステップについての話し合いに移行している。」との発言があり、協議の進展がうかがわれたのです。18日、米国のサリバン大統領補佐官(安全保障問題担当)が「新たな共通理解が生まれている」とのコメントを出し、イランの報道官も、まったく同じ表現を使って、交渉の進展を伝えており、イラン・米国の双方が、交渉の進展を評価していることがうかがえました。その上、イランのロウハニ大統領は「進捗率は60~70%だ」と述べ、「米国側が誠実に対応するのであれば、短期間に結果を出すことも可能だ」と述べ、交渉の進展をはっきりと認めたのです。21日には、「核合意の全面復活まで、米・イ両国がとる具体的なステップの順序を協議する専門部会の設置が発表されました。核合意を一方的に破棄した米国が、全ての制裁を解除するのが先決だと主張し続けてきたイランが、そういう要求を「非現実的だ」と主張し続けてきた米国と、共通理解を持つようになり、イランも実際には、極めて現実的な話し合いに応じている様子が分かります。バイデン大統領は、14日にアフガン駐留軍の全面撤退を正式に発表。イエメン紛争のためのサウジへの軍事支援も大きく縮小しました。こうしてみると、中国との本格的対決に備えて、中東やアフリカなどを含め、中国との対決に全ての資源を集中するため、西アジアから中東、アフリカの地域紛争からは手を引く意向であることが読み取れます。そのため、「イランが核合意を順守することが分かれば、こちらも核合意に復帰し、合意を順守する」意向を示しているのです。サリバン補佐官は、21日にCNNに出演し、「我々は少し前進したが、まだ長い距離を進まねばならない」と述べ、楽観的になることを戒めていますが、「最終的には米国は、相手が合意を順守するなら、こちらも遵守するというペースで核合意に復帰することになろう」と述べています。問題は、核合意絶対反対のイスラエルとその支持者が、どんな妨害工作に出るかにあうように思われます。
2021.04.24
コメント(8)
-
台湾リスク
台湾リスクそれでは、中国の台湾侵攻リスク、即ち台湾有事の可能性はどの程度あるのかを考えておきましょう。習近平は、2019年1月2日の「台湾同胞に告げる書」40周年記念式典での挨拶で、中・台統一に向けての強い意欲を強調しました。彼自身の在任中に実現したいとする意欲が感じ取れました。習近平の2期目の任期は22年秋までですが、彼は最高指導部は任期中に70歳を超える場合は、70歳前でも引退しなければならないという、党の決まりを改め、22年の任期満了後も3期目に入る足場を固めていますから、22年までに台湾との統一を実現しようとは考えていないでしょう。今年2021年は、中国共産党の創立100周年にあたります。そして来年2月には北京冬季オリンピックが控え、そして22年秋には第20回党大会が控えています。そういう慌ただしい時に、失敗すれば自らの続投を危うくするような、危険な賭けに出ることは考えにくいように思われます。となると、次のターゲットは2027年の中国人民解放軍の創立100周年が考えられ、続いて彼自身の3期目の任期満了となりますが、この時彼は74歳ですから、現在すでに独裁権力を固めている彼は、4期目も視野に入れている可能性があります。台湾侵攻となれば、これは中国にとって失敗の許されない大きな国家的プロジェクトです。もし失敗したら、失脚するだけでなく、過去の栄誉もすべて消し去られるほどの痛手になります。 中国の世界的地位は、今後もしばらくは上昇を続けますから、台湾統一は時間をかけてゆっくりと、熟柿が落ちるのを待つつもりなのではないかと見ています。現在中国は、台湾の防空識別圏(ADIZ)への侵入を執拗に続けて、米国や日本を牽制しています。これは、台湾の独立宣言や米国の「一つの中国政策」の変更といった現状の根本的な変更がなされることへの危惧感からくるものでしょう。 ADIZへの侵入は、95年~96年の台湾海峡危機の際に行われた軍の再配置やミサイルの発射実験に比べると、偶発的な戦争を誘発する危険は抑えられています。つまり、台湾に対し軍事的圧力を加えつつ、外交的な孤立に追い込み、時間をかけて台湾をあきらめの境地に追いやり、それによって統一を余儀なくさせる作戦のようにも思われます。ただ、中国にとってのジレンマは、中国の現状の強圧的な姿勢が、台湾内部で中国に対して融和的な国民党の支持を下げ、中国に対して最も強硬なスタンスを取る民進党の支持を高めてしまっていることにあります。偶発的な衝突が起きないよう、様子を見て行きましょう。
2021.04.22
コメント(11)
-
日米共同声明と中国の反応
日米共同声明と中国の反応18日のブログに記した、日米共同声明の台湾問題の言及に対し、中国はどのように反応したかを検討してみます。日米共同声明は、数多くありますが、マスコミでも記されている通り、日本政府が台湾について言及したのは、1969年の佐藤・ニクソン会談以来、52年ぶりの事とされていますが、69年の声明は、沖縄返還に重点を置いた、極東地域の平和と安全を強調するトーンの中で、台湾(中華民国)について、触れたものでした。尤も、この段階では、日米両国とも大陸中国とは国交がない状態でしたから、台湾への言及がなにか問題になることもなかったのです。日中、米中の国交回復後で考えると、台湾問題への言及は今回が初めてです。文言はとっても慎重に練り上げられたことが良くわかる文章でした。「日米両国は、台湾海峡の平和と安定の重要性を強調すると共に、両岸問題の平和的解決を促す」ここでは、台湾国家を問題とせず、台湾海峡の船舶の通航を問題にしています。つまり、国家としての台湾に言及することは、意図的に避けられています。米側のプレスリリースでは、この表現は中国との間に強い波風を起こしたくない日本側の立場に配慮したと説明されています。中国側も、そうした配慮を受け止めたようで、外国部や駐日大使館は、日本非難の談話を発表していますが、野田内閣が尖閣諸島の国有化を決定した時の激しい非難に比べれば、極めて抑制されたもので、いたって波静かです。北京五輪(2022年冬)を控え、あまりことを荒立てたくないし、米中関係の先が見通せない段階で、日本とことを構えるのは、得策ではないと考えているように見えます。さて、この先日本政府は、どのような方向に進むつもりなのか、日本の特に自民党のタカ派議員の妙に威勢の良い言動が気になります。
2021.04.21
コメント(6)
-
イスラエルリスク
イスラエルリスク米国のオースティン国防長官のイスラエル訪問中に、イスラエルはイランにとって最も重要な核施設の一つナタンズの原子力施設にサイバー攻撃を仕掛け、電気系統を故障させて大爆発を起こさせ、数千個に及ぶ遠心分離機を破壊しました。イスラエルは、米国が核合意に復帰知ることを何とかして思い留まってもらおうと、ひたすら妨害工作に熱中しています。さすがに、米国に攻撃の矛先を向けることはできませんから、矛先はもっぱらイランで、イランが怒ってイスラエルに報復攻撃を仕掛けてくれば、そんな状況で米国が核合意に戻ることは出来なくなる(米国の国内世論がイスラエル支援に傾くからです)と読んでいるからです。バイデン大統領は、副大統領時代の2010年にイスラエルを訪問しているのですが、その時もイスラエルは滞在中に、ヨルダン川西岸のパレスティナ自治区に入植地を拡大する計画を発表して、米国のメンツを潰しています。 共和党中心に米国にはイスラエル支持者が沢山いるから、民主党政権の言うことなんか聞かないぞと、主張しているようです。今のところイランが自重して、イスラエルへの報復を自重しているため、大事に至らずに済んでいますが、この先は分かりません。今のところ米国とイランは、共に核合意の復活について、強くそれを望む姿勢で共通しており、イスラエルの妨害を無視して、交渉の席に着く意向を示しています。イスラエルの妨害工作を無視して、イランはウランの濃縮度を20%から60%に引き上げると発表しました。核兵器に利用可能な濃縮度は90%ですから、まだ核兵器は作れないのですが、60%は90%に近く、90%への引き上げは容易なため、この発表は米国や欧州に対する揺さぶりであることは間違いありません。ただ一方でイランは、核兵器を開発する意図はないと、常に一貫して表明していることも事実であり、濃縮度の高いウランは、少量の生産に留めている可能性もあります。いまのところ、イスラエルによるイラン揺さぶり作戦は、イランに被害を与えることでは成功していますが、イランと米国を引きはがす点では、まったく得点を挙げることは出来ずにいるのです。さて、今後どうなってゆくのか? 中東情勢にも眼は離せません。
2021.04.20
コメント(6)
-
台湾とはどんな国?
台湾とはどんな国?台湾は、明治日本の最初の植民地でした。この時期既に大陸から渡ってきた中国人がかなりの数居住しており、彼らが原住民の上に立って、台湾の支配層を形成していました。そんな彼らを内省人と呼びます。日本の支配は、ポツダム宣言の受諾と日本の降伏によって終わりを告げました。日本の降伏後に、大陸から台湾に渡ってきた人たちが外省人と呼ばれます。外省人の一番手は、連合国に降伏した日本軍の武装解除のためにやってきた約1.2万人の国民政府軍兵士と、約200人の官吏でした。彼らは日本軍から台湾の施政権を受け取り、台湾統治に乗り出しました。ここに台湾の実情を知らない外省人に依る台湾支配が始まったのです。日本人の支配は、細かな規制も多く、息苦しい支配でしたが、少なくとも治安は良く、強盗、殺人等々は厳しく処分されるため、殆ど起きなかったのです。ところが国民党軍が支配者としてやってくると、彼らは規律正しさなど微塵もなく、婦女暴行や強盗殺人などが、あちこちで起き、内省人や少数民族などは、外省人支配に不満を募らせたのです。官吏も腐敗堕落が激しく、役所は汚職の横行する世界となり、たまりかねた内省人は、1947年2月28日、国民党政府と軍に対し、蜂起し革命運動を起こしたのです。大陸では、国民党勢力と共産党勢力の内戦が華々しく展開されていた時期です。台湾にまで共産党の勢力が及ぶことになっては大変と、疑心暗疑のなった蒋介石は、事件を徹底的に弾圧して、台湾省を設置して、恐怖政治を敷いたのです。事件以後、国民政府は内省人中心の「台湾人」の抵抗意識を徹底的に抑え込むことに熱中し、知識階層や共産党の支持者と思しき人物を中心に、数万人を処刑したと言われています。こうした内省人に対する弾圧は、1975年の蔣介石の死後、息子の蔣経国にも受け継がれた。国民党の独裁が続く中、叛乱を恐れる蔣経国は戒厳令を解除せずに恐怖政治を続けたため、民主化運動は、日本を経由してアメリカに亡命した人々によって担われてゆきます。そうした構造に変化が生じたのは、1988年の蔣経国の死によって、蔣王朝が終わりを迎え、李登輝が総統、国民党主席に就いてから始まります。李登輝は、台湾の民主化を進め、96年には台湾初の総統民選(任期は4年)を実施し、自ら初代民選総統に就任します。高齢の李登輝は4年後2000年の総統選には立候補せず、民進党の陳水扁候補が総統に選出され、ここに国民党支配も終わりを迎えたのです。陳水扁は、台湾独立路線を掲げたため、大陸との将来の統一を党是とする国民党と激しく対立し、政局は混迷します。台湾経済は工業化が進展しますが、同じ中国語圏として14億の人口を抱える広い中国市場を主たる取引先としているため、足りくとの関係を切ることは出来ず、台湾財界は国民党支持者が圧倒的に多く、独立支持の多い若者とは好対照をなしているのです。2004年の総統選は、国民党と民進党の支持が拮抗して縺れに縺れたのですが、民進党の陳水扁が僅差で勝利します。しかし、2008年と12年の選挙では、国民党の馬英九が勝利し、両岸抬頭、共同協議、市場拡大を掲げて、大陸との協調路線を進めたのですが、16年選挙では、民進党の初の女性候補、蔡英文が勝利し、20年の選挙はコロナ禍のため先送りされているため、今も蔡英文政権が続いている状態です。
2021.04.19
コメント(10)
-
菅訪米と共同声明
菅訪米と共同声明菅・バイデン会談が終わり、共同声明が発表されました。いろんなことが書き込まれていますが、中心は何といっても、大陸中国対策だったことがはっきり打ち出されているように見えます。そもそも、菅訪米が当初の発表から1週間遅れた理由が良くわからず、何故?と思っていたのですが、その疑問は、4月13日に氷解しました。この日米軍のアフガンからの撤退が表明されたからです。2001年の9/11テロに対する報復として、ブッシュジュニア政権がアフガンのタリバン政権を攻撃して始めた「テロとの戦い」は、次いでイラクさらにはシリアへの介入と地域を広げながら泥沼化して、20年もの月日を重ねてきました。バイデン政権は、その「テロとの戦い」からは足を洗い、今後はアジアに、と言うことは対中国に全力で取り組む姿勢を世界に表明し、その姿勢を明確にして菅首相を迎えたことになります。それは、同盟国の中で、米国の方針に最も忠実な日本を巻き込んで、中国との長くなるであろう様々な競争を共に戦ってゆく、ただし、軍事衝突にはならないように細心の注意を払いながらという、姿勢をきっちり示すことにあったのです。共同声明の文言は、以下のようになっています。「日米両国は、台湾海峡の平和と安定の重要性を強調するとともに、両岸問題の平和的解決を促す」この文章は、「台湾海峡は国際的な海上輸送ルートになっているのだから、その商品流通ルートが使えなくなるような無茶はするなよ」と中国に念押ししていることは間違いないでしょう。ただし、その後に「両岸問題の平和的解決を促す」とあるのがミソなんです。「中・台合併を話し合いで平和的に解決するなら何も言わない。どうぞ自由にやってください。」と中国に伝えているのです。実は、日本も米国も、対中国境の正常化を図るに対して、どちらも台湾との国交を断絶して、大陸中国との国交を回復しています。当時大陸の共産党政府も、台湾の国民党政府も、共に中国は一つ、二つの中国は認めないと奇妙に歩調があっていたのです。台湾には台湾人の政府ではなく、台湾を占領した中国人(具体的には国民党)の政府があったのです。そんな調子ですから、台湾の国民党政府は中華民国を名乗り、大陸の共産党政府は中華人民共和国を名乗って、共に譲らなかったのです。大陸での覇権争いに敗れた国民党政府は、台湾に亡命政府を作り、国連の議席も欧米の支持を得て持ち去っていました。当時大陸の人口は7億と言われていたのですが、7億人(現在は14億人)の政府が国連の議席を持てず、現在でも2,300万人台に過ぎない台湾が中国を名乗って国連の議席を維持したのです。この奇妙な状態は、介入したヴェトナム戦争が泥沼化して、ヴェトナムから手を引きたい米国が大陸中国に接近し、当時ソ連との仲が険悪化していた中国も米国を敵(ソ連)の敵と考えて、対米接近を是としたため、両国の関係が改善し、当時米国べったりだった日本も対中関係の改善を目指し、台湾との国交を絶って、大陸中国を唯一の中国政府と認めたのです。従って、日本も米国も、台湾とは国交を持たず、しかし交流はしているという不思議で変則的な関係を維持しているのです。で、両岸関係の平和的解決となるのです。これは中国に対し、「中国は一つの原則は忘れていませんよ」ただし「武力統一は認めませんから、平和的に解決してくださいね」と、念を押しているのですね。対中関係の決定的悪化は避ける知恵が、凝縮したなかなか巧みな表現を生み出したなと、私もちょっと感心しました。共同声明発表後、早速中国は声明に反発する談話を発表しましたが、声明のトーンは、曽於名に激しいものではなかったですね。 中国側にも米日両国の真意が伝わったのではないでしょうか。当面この声明で、今以上に台湾海峡問題がエキサイトすることは避けられるのではないか、そんな印象を持った、共同声明でした。
2021.04.18
コメント(7)
-
ミャンマーはどうなる その11
ミャンマーはどうなる その11さて、日本政府に出来ることは何か。首相や外相が出かけるよりも、政府特使として大物政治家を派遣し、丸山大使とタッグを組んで、軍事政権とスーチー女史並びにそのチームを、対話の場に就くように説得することしかありません。政府特使の候補となる大物政治家として、どんな人物が相応しいかと考えると、元外相の岸田文雄氏とか、元防衛相の中谷元氏などが適任なのではないかと、私は見ています。2人は立場は違いますが、日本と東アジアの情勢の厳しさも熟知していますし、日本との関係も良く親日家のおおいミャンマーとの関係の重要さも良く承知している方のように見ています。先ずは、軍事政権側に反軍政のデモ隊の暴力的鎮圧が、軍政に対する国際的評判を悪化させていることを強調して、デモに参加するミャンマー国民に死者が出続けている状態を続ければ、軍政は国際的に孤立し、それは軍部の関係の深い企業群の存続にも影響することを、具体的に伝えて、そういう犠牲を払っても、力づくの弾圧を続けるメリットが何かあるのかと、諄々と説くことでしょう。するとおそらく、こちらは対話の意志があるが、スーチー女史とNLDが頑固で、現状での対話を拒否しているという話になるでしょう。そこでスーチー女史並びにNLDとの対話の順番になります。ここでは、軍政側に対する以上に、厳しくきつい説得を行う必要があります。皆さんからもそれはどうかと不賛成のコメントを戴くことになりそうですが、軍政側以上の譲歩をするよう、スーチーさんとNLDの幹部を説得することが必要になります。何故か。軍や警察の内部で、反軍政のデモ隊やNLDに好意的で、上の命令に批判的で、デモ隊側に好意を寄せる警官や兵士は、残念ながら少数派に留まっているからです。元々ミャンマー政府との折り合いが良くなく、独立志向までくすぶっている少数民族地帯の兵士たちが、逃亡してきた反軍政の人々を匿い、軍政側の部隊と交戦する事態も生まれていますが、少数の派遣部隊が相手なので善戦できていますが、軍事禄の規模でいえば、10:1程度にとどまりますから、本格的な内戦になれば、ミャンマー正規軍の圧勝に終わることは見えています。そうなると、逃れた少数民族の兵士たちは、山岳地帯に逃げ込んでのゲリラ戦を展開することになり、アフガンやシリアのような内戦になりかねません。つまり、国家権力につき物の暴力装置を軍政側が握っている以上、国民虐殺をやめさせるためには、NLDとスーチー女史の側が、より大きく譲歩する以外にないのです。欧米側がミャンマーの議会政治を守るために、反軍政の軍事干渉に踏み切るなら、話は変わってきますが、米英EUにその気はありません。軍部を非難し、経済制裁を科すことが限界で、それ以上の介入は口先だけに留まるのです。もう53年近く前になりますが、1968年のメキシコ五輪の年でした。人間の顔をした社会主義を目指したチェコのドプチェク政権が実現した「プラハの春」は、ソ連軍の戦車によって潰されました。その時敗者となったドプチェク氏は、「皆さん今は耐える時です。私や仲間たちの力が足りなかったことを、皆さんにお詫びします。今は耐える時です。何年いや何十年かかるかもしれませんが、いつか我々は必ず勝利できます。今は抵抗をやめて、ミンさんの命を守ってください」と訴えました。 その訴えは、21年後の1989年に実現いたしました。スーチーさんは、ミャンマー国民の命を守ってこそ、ミャンマーの民主主義と議会政治のシンボルであり続けることが出来るのです。自分とNLDのメンツの為に、国民を犠牲にして良いわけはないのです。ここは忍び難きを耐える局面です。 軍政と協力して、部分的な議会政治になっても、残された灯をともし続けるべきなのです。交渉で少しでも多く、民主化の火種を確保する立場をとるよう、何とか彼女と仲間たちを説得するとすれば、それが出来るのは日本人だけなのではないかと、私は考えています。
2021.04.15
コメント(9)
-
ミャンマーはどうなる その10
ミャンマーはどうなる その10中国は、ミャンマーの混乱を恐れています。中国版シルクロード計画の一帯一路計画は、ミャンマーを通ります。ここが混乱し内戦状態になれば、当然道路は寸断され遣いものにならなくなります。さらに、中国企業は政府の支援を得て、ミャンマーに進出しており、中国企業の社員であるミャンマー人が反政府デモに参加して、工場の開店休業状態が長引くと経営そのものが成り立たなくなる危険も出てくるからです。そんなわけで王毅外相を派遣して、必死の調停工作を展開しているのです。それに比べ日本の動きは鈍いです。菅総理は外交経験の乏しい内向きの政治家ですから、彼がミャンマーに飛んで軍部とスーチー女史やNLDとの間を調停することはできないでしょうが、自民党の外相経験者や外交通のメンバーを首相特使として派遣したり、ミャンマーに知己の多い民間人に仲裁を依頼したり、丸山大使とタッグを組んで両者を説得することなどが考えられます。明日15日に、菅首相は米国訪問に飛び立ちますが、バイデン大統領からもミャンマー情勢の好転に向けての日本の積極的な貢献を約束させられることもありうる話です。少なくとも、これ以上ミャンマー国民の血を流さないで済むよう、1日も早く調停作業をまとめ上げることが期待されているのです。軍にはデモ隊の力づくでの封じ込めをやめるよう説得し、スーチー女史とNLDには、民衆を守るために、軍部と話し合うテーブルに着くよう、説得することが期待されているのです。 続く
2021.04.14
コメント(6)
-
ミャンマーはどうなる その9
ミャンマーはどうなる その9さて、それでは日本はどうすべきなのか。欧米と同じように経済制裁を科して、クーデタを起こした軍政を批判し、民政に戻せと圧力をかけるのが良いのか? それとも欧米とは異なる態度をとる方がよいのか? NLDやデモの参加者からは、日本政府は何故軍政を批判してくれないのかと言った声が聞こえますし、評論家や一部国際政治学者からも、軍政を批判しない日本政府批判が聞こえます。私はこういう評論家や「政治学者」は批判しません。軍部批判から経済制裁に走った米英やEU諸国も、日本に自分たちに同調してほしいと言ってくる機運はありません。日本の立ち位置は、欧米とは異なっているのです。それはNLDとも軍部とも良好な関係を持っていることにあります。つまり、予想外の民衆の抵抗にあって焦りまくっている軍幹部にも、意地になって軍側との妥協を頑なに拒否し続けているスーチー女史とNLD幹部にも、相互の妥協でこれ以上の民の犠牲を避けることが出来ること、ともかく妥協点を探すためのテーブルに着くように懇切丁寧に説得し続けることです。欧米が日本に期待していることも、この点です。しかし残念ながら日本政府の動きは鈍いです。実は、スーチーさん側と軍部側の双方とも良好な関係を保っているのは、日本と中国の2か国なのです。その中国は日本に先駆けて王毅外相をミャンマーに派遣、軍部とNLDの双方に積極的に対話を呼びかけ、場合によっては仲介の労をとるとまで伝えているのです。中国にはミャンマーと国境を接している利点もあります。日本の利点は、ビルマ語に堪能で、ミャンマーの駐在歴も長い丸山市郎大使を持っていることにあります。日本の大使職は、本省の次官クラスに匹敵する特別職で、キャリア官僚の上りのポストでもあります。そんな大使職なのですが、丸山大使はノンキャリアから大使に抜擢された例外中の例外のケースなのです。苦労人ですから、ミャンマー民衆との付き合い方もしっかり心得ており、2月の下旬ですが、市民のデモ隊が日本大使館に陳情に訪れ、日本政府への要望書を手渡そうとしたとき、自ら応対に出てデモ隊との対話に応じ、ミャンマー警察がデモ隊を強制排除に動く機会を封じたのです(大使館は治外法権ですから、大使館に被害が出ることは国際信用にかかわる問題になるため、外国大使館へのデモ隊の登場は、政府にとって(この場合は軍政)にとって、あってはならないことだったのです)。大使は、日本政府への要望書を自ら受け取ると、ビルマ語で約2分ほどデモ隊に対して、君たちの要望はしっかりと日本政府に伝える。さらに皆さんへの必要な支援は惜しまないと短い演説をしたのです。大変有能なミャンマー大使が控えているのですから、もう少し本腰を入れた時の氏神役に精を出すべきだと、私は考えています。 では具体的にどんな説得をするのか? 続く
2021.04.13
コメント(8)
-
ミャンマーはどうなる その8
ミャンマーはどうなる その82月1日の軍部のクーデタに、国民は激しく反発、2か月半近くを経過した現在も、国民の抗議行動は衰えることなく続いています。これに対し軍部は力で対抗する姿勢を崩さず、最近は少ない日で、数10人規模、多い日は100人を超える犠牲者が出ています。親についてデモ隊についてきた子供が狙い撃ちされるケースも複数起きており、最年少は6歳の子までもが、銃で撃たれて死亡しています。反クーデタは、少数民族地域にまで広がっており、軍幹部も計算違いの連続に、頭に血がのぼってしまったのでしょう、飴と鞭を使った硬軟両様で民衆を懐柔することを忘れた、銃剣による暴力的鎮圧にのみ傾斜する愚策を続けています。これでは、仮に一時は軍政側が勝利したとしても長くは続かないでしょう。当初は軍は後景に退いて、治安警察によるデモ隊への対処を行っていたのですが、一般警察官の多く(軍部による分け前の提供に預かれない平の警察官)がデモ隊への暴力行使を嫌って出動を拒否するようになり、軍部が表に出るしかなくなったのです。軍人の中にも、国民に銃を向けることを嫌がり、出動を休む兵士もおりましたが、残念ながらそうした国民の側に立つ兵士は、いまだ少数派に過ぎず、兵士の一部が反軍幹部を掲げ、民衆の側に立つところまでは行っていません。少数民族の兵士たちは、軍部に自分たちのテリトリーを冒されることに拒否反応があり、自分たちのテリトリーに逃げてきた反軍政の人々を匿い、共に戦う姿勢を見せていますが、彼らの武力は国軍ほどに強力ではなく、自己のテリトリーの防衛が主たる目標なのです。ですから、軍事クーデタ政権を倒し、民政を取り戻すためには、現在は軍幹部に忠誠を尽くしている若手将校たちを説得して、彼らをアンチ幹部の民衆派に鞍替えさせるオルグ活動を展開する必要があるのです。それには一定の時間が必要です。それでも若手将校たちは、軍兵士に殺された幼い子供たちと、年齢の近いわが子を持っている年齢層です。子供すら容赦をしない弾圧を指示する軍幹部に対する相当な違和感を、彼らが抱いている可能性はあります。武力の殆どをクーデタ派に握られたままでは、反クーデタ派に勝ち目はありません。外国の干渉に頼るようでは、国土にしっかり根を張った揺るぎのない民主政府は出来ません。主役はあくまでミャンマー国民でなければならないのです。さてそのためには何をすべきなのか。そして日本の取るべき態度は…私は、香港の民主派に同情心を持っておりません。彼らは取るべき道を間違えた馬鹿者だと考えているからです。彼らの間違いは、味方にすべき対象を間違えたことにあります。香港の若い人たちが頼るべき相手は、外国の若者や政府ではなく、大陸中国の若者だったのです。人口14億人の大陸中国には、数億人の若者がいるのです。謙虚に彼らと連帯していれば、大陸の若者たちが味方してくれ、党中央の香港政策を和らげる役割を果たしてくれる可能性があったのです。その中国の若者を、言論の自由のない世界に安住しているうつけ者と見下した態度をとり続け、そうした上から目線を、敏感に感じ取られて、ソッポをむかれてしまった驕りが、今の事態を招いたのです。いわば自業自得ですね。誰に対しても上から目線などとるべきではないのです。 続く
2021.04.12
コメント(6)
-
ミャンマーはどうなる その7
ミャンマーはどうなる その7左眼のご心配ありがとうございます。風の強い日に異物が入ってしまい、タチの悪い物がまじっていたのか、腫れあがってしまったのです。もう落ち着きましたので大丈夫です。さて、ロヒンギャ問題ですが、ロヒンギャはバングラデシュとの国境地帯を行き来する少数派のイスラム教徒です。スーチー女史と親密な関係にあった反イスラム主義の団体969運動がロヒンギャ虐殺を扇動したことが知られており、スーチー女史は虐殺を黙認しています。その結果、欧米の彼女を見る眼は大変厳しくなっています。ところで民主化の当初、スーチー女史と軍部は、良好な関係を築いており、郡部とNLDもまた蜜月の関係にありました。軍がミャンマー経済を握っており、経済の好調は軍幹部の懐を豊かにしたからです。民主化はスーチー女史を広告塔として欧米や日本からの投資を呼び込み、外資と提携した軍部系企業の儲けは天井知らずの状態になったからです。民主化で一番儲かったのが軍幹部だったのです。ですから、この時点では、軍部に民主化を否定する動きは見られなかったのです。何処で歯車が狂ったのでしょうか。それが昨年11月の総選挙でした。軍部も政党登録を済ませ、選挙で一定の議席確保を目指したのです。しかし軍部の期待は裏ぎられ、軍部支持の保守政党は惨敗、NLDは全議席の85%以上を占め、文字通り圧勝したのです。圧勝で気の緩んだスーチー女史とNLDは、軍保守派の聖域だった禁断の裏ビジネスにメスを入れたのです。合成麻薬の取引です。話を聞いたことのある方もいらっしゃると思いますが、タイ・ミャンマー・ラオス3国の国境地帯は、ゴールデン・トライアングル(黄金の三角地帯)と呼ばれる合成麻薬の生産と販売の聖域でした。軍の腐敗幹部たちは、この取引をお目こぼしして、年間数千億円規模の利益を上げていたのです。この取引について、NLDとスーチー女史が裏で手を回したのか、2019年の春ごろから、ミャンマーの有力紙に、麻薬取締にかんする記事が出るようになり、軍幹部が警戒していたところへ、麻薬取引にメスを入れるつもりらしいと情報が入ったのです。これは力で阻止するしかない。相手の一番触れられたくない急所に切り込むためには、万全の準備、絶対に負けない準備をして、一機に締め上げなければなりません。政治家として未熟なスーチー女史と、彼女以上に政治家として経験不足なNLD幹部は、絶対に負けない準備を怠ったのです。軍部は選挙に不正があったと、トランプ政権とその支持者の造語を失敬して、そのセリフを金科玉条にして、クーデタを正当化しようとしているのです。ミャンマー国民のこれほどの抵抗は、軍部にとっても予想外だったのでしょうが、子どもを含めた国民に対する無差別殺傷は、軍自身にとっても、痛手になっているのでしょうが、それだけ引くに引けないとばかり、頭に血が上っているのでしょう。 それにしても、日本政府動きが鈍すぎますね。 やっと日本政府は何をすべきかのところへ辿りつけました。本論はこれからです。 続く
2021.04.11
コメント(8)
-
ミャンマーはどうなる その6
ミャンマーはどうなる その6しばらくご無沙汰しました。左眼がおかしくなり、自重しておりました。さて、2015年選挙でNLDは圧勝したのですが、スーチー女史には憲法の規定によって、国家を率いる立場の大統領になる資格はなかったのです。家族が外国で暮らしている者は、国家に損害を与える決定をする危険がないとは言えないので、国家指導者の地位を与えてはならないとなっているのです。ここでスーチー女史の発言と行動に問題がありました。彼女はNLDは自分の政党であり、NLDのことは全て自分が仕切ってきたので、党を指導しているのは私だけだと自負し、そう思い込んでいたのです。それは今現在も変わらない彼女の驕りでした。NLDはスーチー女史に代わって、彼女の側近のテイン・チョー氏を大統領に立てたのですが、彼女は「今の大統領は傀儡に過ぎない。実権は私にある」と言い放って引かなかったのです。そこには、仲間と共に頑張ってきたことを訴えて、仲間を立てる謙虚さのカケラも見られない驕慢さがむき出しになっているように見えました。「実ほど、頭を垂れる 稲穂かな」と言われる日本的な謙虚さを学んでいれば違ったのでしょうか、アメリカとイギリスで教育を受けた彼女には、そうした姿勢は皆無だったのです。彼女は、テイン・チョー大統領に関して、「憲法上、アウンサン・スーチーの大統領就任が禁じられていることに合せた措置に過ぎず、彼は何らの権限も持たない傀儡であり、私が全てを決定する。」と断言したのです。NLD幹部の立場、大統領の立場を何一つ配慮せず、私が…私が…と、主張したのです。実際彼女は、外務大臣、大統領府大臣外二つの大臣を兼務し、その上に大統領に国家顧問という椅子を新設させて、そこに座りました。当然、NLD並びにスーチー女史自身と軍部の関係は悪くなります。そこに起きたのが、ロヒンギャ問題でした。 続く
2021.04.09
コメント(9)
-
ミャンマーはどうなる その5
ミャンマーはどうなる その5テイン・セインの下で、なお軍政は続きましたが、NLDの活動も認められ、建前上は民政に移管したことになりました。欧米や日本にとって大きかったのは、アウンサン・スーチー女史の自宅軟禁が解かれ、彼女の活動の自由がある程度認められ(軍部批判を控えることが条件でした)、海外要人に合うことなども認められ、しばらくして外遊も認められたことでした。彼女の自宅軟禁を解き、一定の行動の自由を認めたのは、諸外国にミャンマーへの投資や経済進出を促す広告塔の役割を期待したからでした。自国の経済力を上げ、国民所得を引き上げることで、最貧国から脱して、国民の生活水準を切り上げる。ここにテイン・セイン政権の狙いがありました。スーチー女史も、国民の生活水準を引き上げることに異存はなく、積極的にミャンマーのメッセンジャー役を引き受けたのです。2015年、遂にNLDも参加した国会議員の選挙が行われ、NLDが過半数を獲得して、第一党となり、軍部はなお一定の力を保持しましたが、議会多数派が政権を担当する議会政治の形式が整ったのです。
2021.04.05
コメント(9)
-
ミャンマーはどうなる その4
ミャンマーはどうなる その431日のその2の続きです。1988年、アウンサン・スーチー女史を中心にNLDが結成されましたが、その政党活動は軍に制限され、スーチー女史は長期にわたって、自宅軟禁の状態に置かれました。軍部は外国に亡命したいのならいつでも軟禁を解くと宣言し、出来れば彼女を国外に出したいとの姿勢を露骨に表明していました。細身の彼女の健康状態を心配する姿勢を強く示していたのは、かつての宗主国イギリスでした。実はイギリスは今でもミャンマーをビルマと呼び、最大都市ヤンゴンについても自ら名付けたラングーンと呼び続けるほとんど唯一の国です。スーチー女史を手中にして、あわよくばビルマで再び大儲けが出来るかもしれないと考えたのでしょう。ずるがしこいイギリスらしいやり口でした。しかし、軍部とイギリスの露骨な狙いは、スーチー女史とNLDの受け入れるところとはなりませんでした。軍部独裁を耐え忍んでいる国民にとって、軟禁生活に堪えるスーチー女史が不自由に耐えながら、なおミャンマー国内で頑張っていることが、将来に対する一筋の光明に見えていたのです。外国亡命はそんな国民の希望を打ち砕く裏切りと認識され、スーチー人気は一瞬のうちに失われるだろうことを、彼女もNLDの仲間たちも、良く知っていたのです。こうして、長期の軟禁と、ほんの一瞬の外部との接触許可を繰り返しながら、20007年10月、テイン・セイン将軍が首相に就任します。彼は傷んでいるミャンマー経済の立て直しには、欧米諸国や日本の協力を得て、外資を呼び込む必要があることを認識して、先ず新憲法を作成して国民投票を経て施行、国内の一定の民主化を図ります。直後に超大型サイクロンの襲撃にあい、選挙どころではなくなったため、選挙の実施は2010年11月にずれ込みましたが、無事実施され、選挙直後にスーチー女史の自宅軟禁が解除され、NLD(国民民主連盟)も政党として正式に認められたのです。翌年召集された国会で、テインセインは大統領に選出され就任します。 続く
2021.04.03
コメント(8)
-
ミャンマーはどうなる その3
ミャアンマーはどうなる その3コメントで気にされている方が多いことが分かりましたので、先へ行く前に中国共産党との関係を知る入ておきます。ミャンマー特に軍隊と中国との関係は、決して良いわけではありません。むしろミャンマー軍の幹部は、過去の苦い経験から、中国軍に強い警戒心を持っており、中国政府もスーチー女史やNLDに接近していました。事情は、建国当初からウ・ヌー首相時代、さらにネ・ウィン軍事政権の時代に遡ります。当初は国共内戦に敗色濃厚となった国民党軍の一部が当時のビルマに逃げ込み、中国との国境地帯を占拠して、そこを中国共産党軍に対する反抗基地として軍事浅慮、強制的にビルマ東北部を戦場にしてしまったのです。その中国国民党の残党は、49年の中華人民共和国の建設時には駆逐されましたが、今度は大陸中国を制覇した共産党軍が、国境地帯に多い少数民族をたきつけ、当時のビルマ政府からの独立を唆したりしたため、政府は中国共産党が裏で手を引く反政府独立運動の鎮圧に悩まされることになったのです。最後は、ウ・ヌーもネ・ウィンも、アプローチの仕方は異なるのですが、ビルマ的社会主義を標榜するに至るのですが、毛㏍として、中国の介入がビルマ国内の混乱を助長し、ビルマ経済の成長を阻害し、ビルマ現ミャンマーを、長く最貧国の状態に押し込めることになったのです。ミャンマー軍は、こうした中国に対する警戒心をと良く持っています。そして中国は、隣国ミャンマーへの影響力の強化を狙って、ミャンマーへの出資をつづけ、ミャンマー企業との合弁会社を通じて、出資を続けています。そんな状態ですから中国もミャンマーの政治的混乱は望んでいません。一時の混乱が落ち着けば、再びNLDとスーチーさんの政府が復活するとでも踏んでいるのでしょうか。最初は、介入の姿勢は見せませんでした。こうしたミャンマーと中国の微妙な関係は、先刻承知しているアメリカやヨーロッパは、そのため大変歯切れの悪い経済制裁でお茶を濁しています。不仲の中国の側へミャンマーを動かしたくないからです。強力な経済制裁で、ミャンマー政府を中国の側へ押しやることは、何としても避けたいからです。軍部はその辺まで読んでいて、強硬姿勢を崩さずにいるのかもしれません。ですから、ミャンマー政府を中国に近づけないようにしながら、国民一般への殺戮をやめるように、軍部を説得する必要があるというこのことになるのです。
2021.04.02
コメント(8)
全19件 (19件中 1-19件目)
1