2008年07月の記事
全29件 (29件中 1-29件目)
1
-
(またまた)「自由について」
ここのところややこしい話で申し訳ありません。でも、一度考え始めたら納得できるところまで考えないと気が済まない性格なのでもう少し“自由”について書かせてください。“自由”には“感覚の自由”、“感情の自由”、“行動の自由”、“思考の自由”、“思想の自由”などがあります。それは“自由に考えていいんだよ”というような意味での自由ではなく、“自由に考えることが出来るかどうか”という意味での自由です。つまり、正解からの自由ではなく、より多くの選択肢を持つことが出来る可能性への自由という意味です。この自由がなければ、“自由に考えていいんだよ”と言われても自由に考えることは出来ません。また自由に表現してもいいんだよと言われても自由に表現することは出来ません。あまりこういう視点からの自由を考える人は多くないようです。みんな、“正解がない自由”、“束縛されない自由”は求めますが、よりよい正解を求めるための自由には関心がないのでしょうか。確かに表現にも子育てにも正解はありません。でも、矛盾するようですが正解はあるのです。だからこうやっていろいろと書いているわけです。でも、その正解は固定されていません。その人の心やからだ、そして周囲や相手の状況などによって自在に変化してしまいます。でも、その時、その状況での正解は確かにあるのです。そして、どんな時でもその状況での正解をつかむことが出来る人が自由な人なわけです。ですから、正解に至る選択肢をいっぱい持っている方がより自由に生きることが出来るわけです。正解が一つしかない世界に生きているから不自由になるのです。だからといって、正解のない世界では人は成長しません。そして、自分の思いや欲求を実現することが出来ないので不自由になります。放任育児を受けた子どもは自由ではなく、不自由になってしまうのです。短いですが、今日はこれくらいで・・・。
2008.07.31
コメント(5)
-
「学生運動と若者たち」(闘争していた時代)
今日はまず昨日の訂正から始めます。昨日のブログのおしまいの所でそして現代は、子どもたちが“未来”という時間軸を持つことが難しい時代なのです。ただし、それは未来に希望が持てない時代だからではありません。そうではなく、“未来”という時間軸が自然との関わりや、からだの活動を通して育っていくものだからです。子どもたちにとって“未来”とか“時間”というものは、概念や観念ではなく、からだの中のリアリティーとして存在するのです。子どもたちは自然との関わりや、からだの遊びを通して、その時間感覚を育てているのです。と書いたのですが、その後いろいろと考えて高野悦子の問題を考える時にはそれだけでは足らないということに気づきました。それは高野悦子が子どもの頃は、まだ自然との関わりや、仲間との遊びが普通に存在していた時代だからです。(昭和24年生まれ)だから高野悦子は強い意志を育てることが出来たのでしょう。本来はその強い意志が未来を生きる力になるはずなのですが、でもこの世代の多くの若者たちがその強い意志を戦いのために使ってしまいました。それに対して、南条あやの場合は意志が育っていないことを感じます。それは自然や仲間とからだを使った遊びが不足している今の子どもたちの特徴です。だから未来を生きる力を持つことが出来なかったのでしょう。私は昭和26年生まれです。つまり、高野悦子よりちょっと後に生まれました。ですから、高野悦子の世代の若者たちがやってきたことを見て育ちました。それは、私より後の世代の人には分からない時代の空気でした。当時、若者たちはいつも戦っていました。特に大学に行っているインテリ層にその傾向がありました。思想闘争です。すごかったんですから。浅間山荘事件もテレビにかじりついて見ていました。学生運動と言う言葉を聞いても今ではそのイメージが分からないかも知れませんが当時は大学の内部で学生同士による暴力対立が日常的に起きていました。私が行っていた大学でも学生と機動隊の戦いがしょっちゅう起きていました。何百人という数の学生が武装した機動隊と血だらけになって戦うのです。今では中国や外国などでしか見ることが出来ないような情景です。私は、卒業後も大学に就職して大学にいたのですが、メインストリートで演説している声がしていたかと思うと、ぎゃーと言う叫び声に変わり、あわてて飛び出していくと反対派の学生たちからボコボコに殴られて血だらけだったなどということもありました。また、学生の集団が団交を求めて職員と対立し、学長質を占拠した事件もありました。まったく、大学が闘争の場になってしまっていたのです。それでも私の頃は学生運動が下火になり始めた頃でした。私が高校の頃、体育祭で使うため赤い旗を作って窓にかけていたら先生たちが血相を変えて飛んできました。先生たちも非常に過敏になっていたのです。当時の若者は戦いによって未来を切り開こうとしていました。戦わないと何にも変えられないと思いこんでいました。そこには、戦争を経験してきた親の世代への共鳴もあったのかも知れません。戦うことへの記憶がまだ強く残っていた時代なんです。だから毎日戦い合っていました。そして、絶望していきました。結局、戦いでは何にも変えることが出来なかったからです。戦いは目的を消してしまいます。最初は“○○のための戦い”なのですが、戦っているうちに相互に恨みが生まれ“戦いのための戦い”になってしまうのです。つまり、最初は観念的、理念的な闘争だったのに、次第に個人的な感情のぶつかり合いのただの暴力事件になってしまうのです。また、ビジョンを共有できなくなった時、仲間同士で戦い始めます。そうして、学生運動や若者たちの闘争はただの内部抗争として、社会の隅へと消えていきました。そして、その団塊の世代の闘争のエネルギーが競争のエネルギーへと転換され、爆発的に日本の経済を発展させてきたのです。でも、そのエネルギーを他者との競争の世界へと転換できなかった高野悦子の場合は自分との闘争に追いつめられ、未来を失ってしまいました。今の若者は昔の若者のように闘争はしません。競争も反抗も対立もしません。そんなことする理由が見つからないからです。昔の若者は未来を変えようとして闘争しました。でも、闘争は闘争を生み出すばかりで未来を変える力にはなりませんでした。でも、今の若者には“変えたい未来”そのものが存在していません。変えようとする意志も育っていません。
2008.07.29
コメント(1)
-
「自由と未来」(高野悦子と南条あや)
先日ご紹介した「友だち地獄」(「空気を読む」世代のサバイバル」 土井隆義著/ちくま新書)の中で高野悦子と南条あやという二人の女性の日記が紹介されています。高野悦子の日記「二十歳の原点」は1971年に出版され、南条あやの「卒業式まで死にません」はブログとしてネット上に書き込まれ、2000年に出版されました。いずれの日記も彼女たちの死後、父親が編集して出版しました。ちなみに、高野悦子は20才で、南条あやは18才で自殺しています。私はこの日記を直接読んでいないのでその内容について書くことは出来ないのですが、「友だち地獄」に書いてあることから判断すると、二人とも自由が欲しかったのだろうなと思うのです。ただし、この本にそう書いてあるわけではありません。著者は“若者たちの生きにくさ”を時代を経て比較するためにこの二人の日記が引用されています。ですから、私がここで書くことはこの本の内容とは関係ありません。ご了承下さい。また、著者はこの二人の違いに焦点をあてているのですが、私は共通性について考えています。昨日も書いたように、自由に生きているように見える子どもたちも、子ども社会の中ではそれなりに不自由に生きています。さらには身体的能力、経済的能力、思考能力の未熟などからの制限もあるし、親や大人からの管理という制限もあります。お気楽に見える子どもたちも結構不自由に生きているのです。でも、だからといって子どもたちがそれを“不自由と感じているのか”というとそういうわけではありません。赤ちゃんは何にも出来ませんが、だからといって“不自由”を嘆いたりはしません。なぜなら子どもは何でも出来る大人を見て、そこに自分の未来を見ているからです。子どもは大人の姿を通して自分の可能性を知り、それを感じることが出来るのなら、空想の中でその自由を味わうことが出来るのです。ごっこ遊びもその中で生まれます。私は子どもの頃は一日中空想していました。無人島に行ったり、ロケットに乗って月に行ったりしていました。これらの空想は空想ではあっても“いつか自分にもこんなことが出来るかも知れない”という未来への想いでもあったのです。心の中で、自分の可能性の延長上に未来をシュミレーションすることに夢中になっていたのです。ところが、高野悦子の日記にも、南条あやの日記にもこの“未来”がないのです。高野悦子は“変わりたい”と想っていたようですが、でも実際にやっていたのは過去と現在を否定することだけです。過去と現在を否定すれば新しい未来が生まれてくると思っていたのかも知れません。でも、未来は過去と現在の延長上にしか生まれませんから、過去と現在を否定してしまうと未来まで否定することになってしまいます。南条あやは“私は変わりたくない”とひたすら自分にしがみつきます。そして、このままの私を受け入れてくれる他者に依存しようとします。彼女の中には過去もないのです。そして、今生きている自分を確認するために自傷行為を繰り返します。二人の日記は一見似ていないのですが、でも、意識の中に未来がなく、“自分へのこだわり”ばかり書いているという点では共通しているのです。だから“出口”がないのです。いつまでも同じところをぐるぐると回っているだけなのです。それで、“死”という出口を通って、この閉鎖空間から脱出したのでしょう。自由になりたかったのだろうと思います。“希望”は未来にしか存在しません。ですから、“未来”という時間軸を持っていない人には希望がないのです。そして、“未来”がない人は“自分”にこだわるのです。そして現代は、子どもたちが“未来”という時間軸を持つことが難しい時代なのです。ただし、それは未来に希望が持てない時代だからではありません。そうではなく、“未来”という時間軸が自然との関わりや、からだの活動を通して育っていくものだからです。子どもたちにとって“未来”とか“時間”というものは、概念や観念ではなく、からだの中のリアリティーとして存在するのです。子どもたちは自然との関わりや、からだの遊びを通して、その時間感覚を育てているのです。ですから観念的な生活ばかりを送っていると時間感覚が喪失してしまいます。それはつまり“未来”が消えてしまうことを意味します。<続きます>
2008.07.29
コメント(7)
-
(続)「子どもと自由」
子どもは自由か?、不自由か?これは難しい問題です。自分を縛る自意識や自我や常識がないという視点から見たら全く自由です。だから荒唐無稽なことを考え、裸で走り回り、どこでも大きな声で泣き、自由に遊ぶのです。また、絵を描いても“絵はこう描かなくてはいけない”という先入観がないから自由に描きます。でも、4,5才くらいになって上手、下手という意識が目覚め始めると自由には描かなくなります。これが“自意識”の目覚めです。自意識が目覚めると不自由が始まるのです。だから、子どもたちは改めてまたここから自由を得るための学びをするひつようがあります。そうでないと自意識に縛られたままになってしまい、自由に考えたり、自由に感じたり、自由に行動することができなくなってしまいます。一見、自由に見える子どもたちですが、子どもは子どもでなかなか不自由なんです。大人の基準に従って行動していないので大人の目には自由に見えるだけで、子ども同士の社会の中では子どもは意外と不自由なんです。時として大人の社会以上に不自由かも知れません。言葉によるコミュニケーション能力が未熟なのでその関係を変えようがないからです。でも、子どもにはその自意識のタガがはずれる時があります。それは大好きな人に囲まれている時や、仲間と楽しく遊んでいる時などです。幼稚園などでは恥ずかしがってやらないようなことでも家の中では平気でやったりするでしょ。かなり年齢が高くなるまで裸で走り回ったりしていませんか。10才頃までは自意識はまだ大人のように固定していなくて、状況に依存しているのです。ですから大人の関わり方が子どもの自意識の状態に非常に大きく影響します。安心できる状況でいろいろな人、いろいろな仲間と関わりながら成長している子は“自意識”だけでなく“仲間意識”も育っていきます。すると、自意識へのこだわりが減っていきます。仲間の中に自分を見いだすことが出来るようになるからです。でも、不安の強い子、遊びや生活体験の少ない子ほ仲間意識が育たず、自意識が“自分へのこだわり”という形で強化されます。<続きます>
2008.07.28
コメント(0)
-

「子どもと自由」
昨日は毎年恒例の「たぬき囃子の会」で夜遅くまで茅ヶ崎の海岸で太鼓を叩きなががら飲んで踊りました。今日は友人の幼稚園のキャンプで簡単な造形をやってきました。以下がその写真です。みんな思い思いにいろいろな作品を作っていました。表現の世界には正解がなく、自由ですからね。表現と、遊びと、いたずらの世界には正解はありませんが“よい子”と“お勉強”の世界には正解があります。ですから、正解のない世界でいっぱい遊んだ子は自由な感性を育てることが出来ます。でも、よい子とお勉強だけの世界で育った子には自由がありません。そして、自由がない子は自立が出来ません。自立するということは自由になると言うことだからです。
2008.07.27
コメント(2)
-
「しつこいですがまた“自由”について」
さてさて、自由の問題はなかなか難しいです。主婦の仕事、子育て中のお母さんは自由か、不自由かという問題も一概には言えません。同じような状況の中でも、自分の状態を“不自由”だと感じている人もいれば、“自由”だと感じている人もいるからです。その違いはどこから来ているのかというと“自分がやりたいことができるか、できないか”ということなのでしょう。つまり、子育てが楽しい人は子育てに自由を感じているし、子育てが苦手な人、社会に出て働きたい人は不自由を感じているのでしょう。ですからこれは当事者が決めることであって周りが“子育て中って不自由よね”などと決めることではありません。だとしたら、どうせやらなければならないことは覚悟を決めてちゃんと向き合おうとする時自由になるのです。つまり、自分が自由であるかどうかは自分で決めることができるということです。そして、不自由だと思っている人は自分で自分を不自由にしているのです。確かに、生理的な欲求を阻害されていたら誰でもが不自由を感じます。お腹がすいているのに食べさせてもらえない、動きたいのに動けない、静かなところにいたいのに周りがうるさい、眠りたいのに眠れない、疲れているのに休めない、などです。そして、子育てにはこのような不自由がいっぱいあります。ただ、こんな時でも自分の不自由の意味を前向きに理解しているのなら、苦しくてもそれは苦痛にはなりません。必ずしも、不自由=苦痛ではないということです。高い山に登る時には結構苦しいです。でも、苦しい=苦痛ではありませよね。だから自分の意志で山に登るのです。そして、同じように不自由だからといってそれがイコール苦痛になるわけではありません。不自由が苦痛になるのは、前向きに取り組んでいない時です。逃げようとしている時です。山に登る時には地図を見て見通しを立てます。すると、今は苦しくても、やがて尾根に出るとか、休憩所があると言うことが分かります。すると、頑張ることが出来ます。でも、山登りが好きな人でも地図もなく、見通しもつかない山を延々と登り続けるだけなら、山登りや景色を楽しむ余裕もなくなって、嫌になってしまうでしょう。そうすると不自由になるわけです。何を言いたいのかというと、自由な人は自分がやっていることを楽しむことが出来るだけではなく、ちゃんと情報を持って見通しを立てている人でもあるということなんです。でも、実際にはその見通しを持たないまま子育てをしている人が非常に多いのです。また、子どもの発達に関する情報を持たずに、ただ自分の願望だけで見通しを立てている人もいっぱいいます。現実を無視して見通しを立てているのです。そういう人は現実に振り回されてしまいます。すると不自由になり、子育てが苦痛になります。そして、お母さんが不自由になって苦しくなると子どもを支配することでその不自由から逃れようとします。山登りでは山を支配することは出来ませんが、子育てでは子どもを支配することは可能だからです。すると子どもの自由が奪われてしまい、依存しなければ生きていけない不自由な子どもたちになってしまいます。自由になるためには、昨日書いたことだけでなく、正しい知識を学び、現実に即したしっかりとした見通しを持つことも大切なんです。
2008.07.26
コメント(6)
-
「自由になりたい人へ」
自由になりたい人は億劫がらずにからだを動かしてください。からだを動かす意志があきらめない心を育てます。自由になりたい人は思いついたことはすぐ行動してください。心とからだがつながるからです。自由になりたい人は詩や本をいっぱい読んでください。心の世界が広がるからです。狭い心は息苦しいものです。自由になりたい人は出来ないことにこだわらずに、今の自分でも出来ることを探してやってください。出来ないことばかり考えていて自由になるわけがないのです。自由になりたい人は背筋をまっすぐにして、遠くの方を見るようにして歩いてください。広い空間を心の中に取り入れるのです。広い空間を見ているだけで心の中の空間も広くなるものです。自由になりたい人は鳥の声を聞き、風の音や肌に触れてくる感覚に心を澄ませてください。感覚に意識を向けていると心の使い方が上手になります。自由になりたい人はお腹の底まで深く呼吸をして下さい。呼吸が浅いと意識が暗くなります。自由になりたい人は100年前、100年後のことを考えてください。心が“目先のこと”に縛られなくなります。自由になりたい人は世界のことを考えてください。自分のことばかり考えていると自分で自分を縛ることになってしまいます。自由になりたい人は手を使って何かを作って下さい。創造する喜びは自分の可能性を目覚めさせてくれます。自由になりたい人は歌を歌って下さい。歌は心を元気にします。自由になりたい人は言い訳や愚痴を言わないでください。言い訳や愚痴は心の世界を狭くします。自由になりたい人は人の短所をけなすのではなく、長所を探して褒めてください。相手の長所を褒めると、その長所を自分の中に取り込むことができます。逆に、欠点を探してけなしていると、その欠点を取り込むことになります。人は自分が褒めている人、けなしている人に似ているものです。自由になりたい人は子どもに遊んでもらってください。子どもは最高の先生になってくれるでしょう。最後に・・・実は、私たちは生まれた時からずーっと自由なんです。でも、自分のことばかり考えているから世界が閉じてしまって不自由だと感じるのです。上に書いたことはその閉じた世界を開く方法です。でも、人は本来みんな自由だと言うことは覚えておいてください。苦しみや悲しみによって自分のことばかり考えるようになってしまったために、それを忘れてしまっているだけなのです。子どもたちは今その自由な世界を生きています。どうか、その世界を忘れないで済むように育ててあげてください。
2008.07.25
コメント(6)
-
「“自由になる”ということはどういうことか」
日本には明治になるまで今私たちが使っている意味での“自由”という言葉はなかったそうです。それで、明治になって外国から様々な文書が入ってきた時“Freedom”とか“Liberty”という言葉を訳すことが出来なかったそうです。それで似たような意味があった仏教用語の“自由”という言葉を充てて訳したわけです。でも、そのため私たちは“Freedom”、“Liberty”という二つの“自由”の概念を区別しないまま“自由”という言葉を使うようになりました。また、元々の仏教用語としての“自由”という概念との違いもはっきりとさせないまま一緒くたになってしまっています。ですから私が“自由な子どもを育てる”という時、その解釈は人によって様々だと思います。日本語は意味を突き詰めない非常に曖昧な言葉なんです。というより、日本人がもともと意味を突き詰めるような考え方をしない民族なのかも知れません。ちなみにgoo辞書には以下のように書いてありました。「free・dom」━━ n. 自由; 自由独立; (市民・会員などの)特権 ((of)); 解放; 免除 ((from)); (the ~) 自由使用権 ((of)); 自由奔放; 慣れ慣れしさ, 無遠慮; (動作の)自由自在.「lib・er・ty」━━ n. 自由; 解放; 使用[出入り]の自由; 上陸許可; 気まま, 勝手; 無遠慮; (pl.) 特権. at liberty 監禁されないで; 自由[随意]で; 暇で; (物が)使われないで.私はそれほど英語に詳しくないのでみなさんにお聞きしたいのですが、○ボールを自由に操る○水が自由に流れる○体を自由に使う○自由に生きる(自由な生き方)○水が流れるように自由に○自由に楽しむ海外旅行などの言葉は英語に訳した時にfree(freedom)やlibertyは使われるのでしょうか。使われたとしても元の日本語と同じ意味になるでしょうか。英語の“Freedom”とか“Liberty”という言葉を使う時には必ず想定された相手(他者)がいます。両方とも“関係性の中の自由”なんです。ただ、“Freedom”と“Liberty”とではその関係性が違うと言うことです。それに対して、日本語の“自由”という言葉が使われる時には必ずしも相手を必要としません。あるサイトで英語に訳してもらえますか?「自分自身の障害を気にせず、自由に生きる」みたいな意味を、できるだけ簡潔な文章で・・・よろしくお願いしますという質問があって、それに対してlive freely despite one's handicapor live free overcoming one's handicapという訳がベストアンサーになっていました。確かに、一見意味は似ています。でも、同じではありません。この英訳ではhandicapがfreeの相手として考えられています。でも、「自分自身の障害を気にせず、自由に生きる」という日本語では“障害”は“自由”の相手ではありません。むしろ“障害を相手にしないこと”が日本語的な意味での“自由”なのではないでしょうか。この日本語の意味は、“障害があるにもかかわらず”でも、“乗り越えて自由になる”のでもなく、むしろ、“障害を受け入れて障害と共に生きていく”ということなのではないでしょうか。きちんと調べたわけではありませんが、多分これが日本語のもともとの“自由”の意味なのではないかと思います。よく、障害を持った人が普通の人にも出来ないようなことをやると、“障害を乗り越えて・・・”というような表現を使いますが、これは違いますよね。障害を乗り越えたのではなく障害を単なる自分自身の環境としてとらえて自分の持っている能力をその環境の中で自由に使いこなすことが出来るようになったということですよね。“それを障害を乗り越えてと表現しているんだ”という言い方も出来ますが、でも“乗り越えて”と“共に”では全く意味が違うはずです。欧米的には“死を乗り越えて自由になる”というように考えるのかも知れませんが、日本的(仏教的)には“死と共に生きることで自由になる”と考えるのではないでしょうか。対立する相手を自己の内側に取り込んで相手を消してしまうのです。それが仏教的な意味での“自由”なのではないかと思います。だから、“Freedom”、“Liberty”と“自由”とは似ているけど違う言葉なのです。“重力から自由になる”という言葉の意味は“無重力の状態になる”ことや“空を飛ぶ”ことだけではありません。重力と仲良くなることも自由になることなんです。野口体操はそのような“自由”を目的としています。“からだが自由になる”ということは束縛がなくなるという意味だけでなく、自分の意志や心とからだがしっかりとつながって一体化するという意味もあります。すると、自在になるのです。束縛がなくなっても自在でなければ自由ではないのです。大人になって自活しても、さらにお金には困っていなくても、自分自身を主体として自在でなければ自由ではないということです。逆に言えば外見的にはどんな束縛の中にあっても、その環境の中で自在なら、自由なんです。両手両足を縛られて、牢屋に入れられていてもその環境の中で自分が自分の主体として自在なら自由なんです。この“自由”には“相手”がいません。他者に束縛されない自由ではなく、最初から他者が存在していない絶対的な自由なんです。どこまでも“自分”しかいないのですから。お釈迦様が生まれた時に最初に言ったとされる“天上天下唯我独尊”という言葉はその自由な状態を意味したものなのではないでしょうか。自由になりたいと思っている人は多いでしょうが、実際問題として子どもやご主人や会社といった相手がいる場合にはなかなかそこを乗り越えて自由になることは困難です。“自由になりたい”と言って子育てを放棄してしまったり、離婚をしてしまったり、会社を辞めてしまっても、また新しい束縛につながれるだけの話です。だったら、いっそのことそれをしっかりと受け止めることで自由になってみるという方法もあるのです。そうすると愚痴や文句が出てこなくなります。自由なんですから。嫌々振り回されているから不自由を感じるのです。ちなみに私は、“子どもが自由になる”ということは、“自在になっていく”ということなのではないかと理解しています。今日は面倒くさい話で申し訳ありませんでした。PS)今日、ちょっと人と話していて“調教されている子ども”と“自立している子ども”の違いを説明しました。指示されればいろいろなことが出来るのに、“自分で考えてやってごらん”と言われた時、途方に暮れてしまう子は調教されている子です。上手でなくても、うまくいかなくても自分なりに考えてやろうとする子が自立している子です。どっちの子の方が自由でしょうか。もっとも、最近指示されても出来なくて、自分で考えても出来ない子が増えてきています。生活の中での他者との関わり合いも生活体験も少ない子どもたちです。こういう子が人間らしく生きていくのは困難なのではないでしょうか。
2008.07.24
コメント(9)
-
「自由になりたい子どもたち」(子どもの意志を大切にする)
大人たちは子どもを“いい子”にしたがりますが、“いい子”になりたい子なんていないのです。まず、このことをしっかりと認識しておく必要があります。そういうことを言う子がいたとしたらそれはお母さんやお父さんが望んでいるからです。心優しい子どもはお母さんやお父さんが望んでいることを自分の目標にしてしまう子もいるのです。ただし、そのような子がいたとしても7歳くらいまでだと思います。7歳くらいまでの子どもにとってお母さんやお父さんは絶対的な存在だからです。じゃあ、子どもは何を望んでいるのだと思いますか。それは“自由になりたい”ということなんです。寝たままだった赤ちゃんがハイハイするようになった時、自由になります。“ハイハイ”しか出来なかった赤ちゃんが歩くことが出来るようになった時、自由になります。お話が出来なかった子がお話が出来るようになった時、自由になります。木登りが出来なかった子が木登りが出来るようになった時、自由になります。けん玉が出来なかった子がけん玉が出来るようになった時、自由になります。1+1=2が分からなかった子がその意味が分かるようになった時、自由になります。世界のことが分からなかった子が世界のことを知る時、自由になります。昨日、今日のことしか考えることが出来なかった子どもが、何億年も昔のことや未来のことを考えることが出来るようになった時、自由になります。子どもたちが自由になるためには能力と知識が必要なんです。そしてその自由を得ることで子どもたちは“人間らしい人間”に成長していくのです。そして、“自由になりたい”というのは、人間としての本能なんです。この本能があるから、人間は文化や文明を創り出してきたのです。言葉を得ることで自由を手に入れました。道具を作ることで自由を手に入れました。考える力を得ることで自由を手に入れました。様々な機械を発明することで自由を手に入れました。そうして、人類はここまでやってきたのです。人類は自由を求める生き物なんです。それは“可能性を手に入れるための自由”です。子どもの成長は人類の歴史と同じです。ただし、上に書いたようなことでも押しつけられたら子どもたちは拒否します。不自由を感じるからです。子どもたちはあくまでも自分の力で学びたいのです。人間はそういう意味では子どもの頃から自立しているのです。その自立を支えているのが“意志”の働きです。そして、“遊び”はその意志の現れです。子どもの意志は自由な活動の中でないと働くことが出来ないからです。(大人になると意識で意志をコントロールすることが出来るようになります。)その“意志”があるから子どもは自由を手に入れながら成長していくことが出来るのです。でも、その意志があるからその自由を束縛してくるような親の言葉は無視するのです。というより、正確に言うと“親の言っている言葉の意味”が分からないのです。子どもは自分が知りたいこと、もしくは自分で発見したことでないと理解することが出来ないのです。そして、それを無視した働きかけに対しては“押しつけ”だけを感じます。これは大人でも同じなのではないですか。人は誰でも自分が知りたいこと、自分が体験したことしか理解することが出来ないのです。ですから、子育てや教育ではその子どもの意志に寄り添えばいいのです。そうすれば子どもの意志は強化されます。そうして子どもはますます自由になっていきます。でも、大人がその意志を無視して大人に都合のよいことばかり押しつけていると子どもの意志の働きは弱まってしまいます。そして、不自由になっていきます。ちなみに、お分かりだと思いますが、“自由な子どもを育てる”ということは“好き勝手に行動する子を育てる”ということではありませんからね。子どもを自由にさせても“自由な子ども”には成長しません。けん玉を一生懸命に練習する子は自由を得るために不自由を乗り越えるのです。この自分の意志で不自由を乗り越える体験が自由な子どもの成長には不可欠なんです。子どもはそうやってやがて親から離れて生きていくための準備をしているのです。でも、今の子どもたちは親から離れて生きていくための準備ができないまま大人になっていきます。自由を与えられていても、自由に生きるための能力を育てることが出来ないまま大人になっていきます。そして、親はいつまでも子どもを束縛しようとします。自由に生きるための能力が充分に育った子なら思春期になってからだにエネルギーが満ちてきた時、自然な形でその親からの束縛をはねのけることが出来ます。でも、その能力が充分でない子は必要以上に暴力的になったり閉じこもったりします。そして時には親を殺します。親の束縛から自由になりたいからです。親が憎いわけじゃないのです。ただ、自分が自由になるためには邪魔だったのです。あの中3の女の子もお父さんが目の前に立ちふさがって、自分が自由になる邪魔をしていたので取り除いただけのことです。でも、実際にはそれで自由になることが出来るわけではないのです。束縛は保護でもあるわけですから束縛を排除することは保護を排除することになってしまうからです。そして、ずーっと束縛されてきた来た子は、保護がないと生きていけないのです。この、矛盾が子どもを苦しめるのです。束縛は苦しい、逃げ出したい。でも、保護がないと生きていくことが出来ない・・・。こういう事件が起きると識者は親と子の間の恨みやトラブルを探ります。でも、そんなところに原因はないのです。
2008.07.23
コメント(6)
-
「ノーと言えない子どもたち」(中3少女の事件から)
青森から帰ってきました。青森はこちらより幾分涼しく夜などは過ごしやすかったです。初日は黒石市という財政破綻寸前の街でした。町を歩くとシャッターが降りたままのお店がいっぱいで、町も全体に活気がなく寂しい感じでした。会場となった会館の隣にある文化会館(?)は維持できないので閉鎖したと言っていました。市民活動の拠点になるべき文化会館のような施設を閉鎖してしまうのですから、もう先は見えています。一方、翌日は五所川原市というところでここは一転して大型店舗が軒を並べて活気のある町でした。ホテルのすぐ周囲にもエルムというイトーヨーカ堂の巨大な店舗、ヤマダ電機、ケーズ電機、スーパー銭湯、などなどほかにも大きなお店がいっぱい並んでいました。それで黒石市の人はここまで買い物にきてしまうらしいのです。それでよけいに黒石市がさびれてしまったようです。それで宿も初日と翌日とでは天と地の差があったのですが、その初日の夕食を食堂で食べているときテレビで“中学3年生の女の子が父親を刺殺した”というニュースが流れていました。それでまた例によって、成績がよく、友達もいっぱいいて、明るくて、家族とも仲がよくて、問題行動などなくて・・・というように非の打ち所がない子どもで、テレビに出てくるコメンテイターの人たちも一様に“訳が分かりません”というようなことを言っていました。その後の取り調べで、お父さんに“勉強しろと言われてイヤだった”とかいうような証言が流れてきましたが、そんなのどこの家庭でも普通にあることですから本質的な原因ではありません。どうですか、みなさんは分かりますか。実は、この今の子どもたちの問題の深刻さは大人の視点、大人の価値観から見ていたら決して分からないのです。そもそも大人が“あの子はいい子だ”という場合、そのほとんどの場合においてそれは“大人の価値観に適合した子どもである”ということを意味しています。違いますか。大人たちは一生懸命に子どもたちに子どもの価値観を捨てさせ、大人の価値観に適合するように“しつけ”という名目で調教しています。これは、親だけでなく社会全体でやっていることです。今の日本の社会は子どもらしさを認めない社会なんです。そもそも“文明”と“子ども”が共存すること自体が難しいのです。子どもは本質的に1万年前からほとんど変わっていない原始的で素朴な心とからだで生きているからです。今では子どもは生まれる時から“子どもとしての主張”を否定されています。自然分娩では胎児は自分が生まれる時を自分で決めているといいます。その時が来たら“もういいよ”という合図を母胎に送るらしいのです。すると陣痛が起きます。でも、今では病院のスケジュールに合わせて無理矢理押し出されてしまいます。また、胎盤も時期が来れば自然に出てくるのに無理矢理引っ張り出すので出血がひどくなり母胎を傷つけています。赤ちゃんの肺から水を吸い出すのも同じです。うちの子は、上の二人は普通の病院で普通に産まれましたが下の二人は水中出産でした。3番目は片桐助産院で(故)片桐先生に取り上げてもらいました。4番目は自宅で斉藤先生立ち会いの元、子供用プールの中で産まれました。斉藤先生は茅ヶ崎近辺で熱心に活動をしているユニークな先生です。“立って産んでも、座って産んでも何で取り上げてあげるよ”と言ってくれた先生です。うちは全員破水してから産まれてきているので、上の二人も病院のスケジュールに合わせなくて済んだのですが、下の二人の時には全くお産に対する考え方が変わっていました。それは、“子どもを産む”ではなくて“一生懸命に産まれて来ようとしている赤ちゃんを大人がサポートする”という形のお産だったのです。ですから、赤ちゃんの主体性を大事にして大人たちは待って、受け止めるのです。病院で産まれるとすぐに肺の中の水を機械で吸い出しますよね。あんなこともしませんでした。3番目の時、水の中に産まれた赤ちゃんを取り出したら、水鉄砲のように自分の力で鼻や口から水を吹き出しました。吸い出す必要なんかなかったのです。それに泣きません。泣いたのはへその緒の“ドクドク”が止まるときでした。自力呼吸の必要が生まれたからでしょう。へその緒を切るのも、“ドクドク”という脈動が止まるまで待ってから切りました。そして、待っていたら自然に胎盤が降りてきました。だから、出血も少なくプールがピンク色になった程度です。このように全部“生命のリズム”に沿って赤ちゃんを迎えたのです。ちなみに4番目の時にはへその緒が巻いていて大騒ぎしていたので、よく覚えていません。それでも、斉藤さんがすぐに異常に気づいて対処してくれたので大事に至らず、今では元気に遊び回っています。このように、子どものからだの中にはちゃんと自分を成長させるメカニズムが働いているのです。ですから、大人がそれを感じてうまくサポートしてあげていればちゃんと子どもは自分らしさのバランスを保ちながら自立していくのです。それは生まれた後からの成長でも全く同じです。子育てはまずその子どもの成長力を信じることから始まります。大人の価値観で子どもの成長をコントロールしようなどと考えてはいけないのです。昔は、大人たちが忙しくて子どもに構っている暇などありませんでした。また、多くの大人が、基本的に心と体が元気であればそれ以上を子どもたちに望むこともありませんでした。子ども同士を競争させる必要などなかったからです。今、大人たちはみんな競争しています。そして、子ども同士も競争させています。“○○ちゃんの方が成長が早い”、“○○ちゃんはもう字が書ける”、“○○ちゃんはじっとお椅子に座っていることが出来る”、等々・・・お母さんたちは子どもの成長の一つ一つをほかの子どもと比較して競争意識を持ってしまっています。そして、子どもを大人の価値観、大人の都合に合わせてアメとムチで調教し、競争させています。なぜなら、子どもには競争することの意味と価値が理解できないので、放っておいたら競争しないからです。子どもの本能としては“みんなと一緒”の方がうれしいのですからそれは当然です。子どもが自分の成長に必要なものを学んでいるときにはアメもムチも必要がありません。自分の成長に必要なことを学んでいるときには学ぶことが楽しくて仕方がないからです。そして、それお子どもは“遊び”という形で学びます。叱ったり、怒鳴ったり、ご褒美をあげたりしなければやらないようなことは子どもの成長には必要のないものばかりです。でも、今本当に必要なものは与えず、子どもの成長を阻害するようなものばかりを子どもに押しつけています。そのように育てられている子どもは自分を主張することが出来なくなります。しっかりとした“自分”というものを持っていない子は自分を主張することが出来ないのです。また、不安ばかりが強くて自信がないからです。大人に反抗することも出来ません。“ノー”と言えないのです。ですから、嫌なときには“無視をする”という手段を使います。学級崩壊も無視から生まれます。昔、“ツッパリ”という子どもたちがいた時代には子どもたちは先生たちに面と向かって反抗していました。でも、今の子どもたちは反抗しません。言うことを聞いてしまうのです。他にどうしたらいいのか分からないからです。そして、言っていることが分からない時、言葉に従えないときには“分かりません”とは言わずに無視します。すると結果として学級が崩壊した状態になります。今、先生は“言うことを聞かないのなら家に帰りなさい”などと子どもを叱ることが出来ないそうです。そんなことを言ったらほんとに帰ってしまう子が珍しくないからです。ですから、学級が崩壊しているクラスの子でも一人一人はみんな素直でいい子なんです。学級崩壊状態でも先生に反抗などしないのです。ただ、無視するだけです。“無視”という穏和な形で処理することで自分も先生も傷つけないようにしているのかも知れません。今、「友だち地獄」(土井隆義著/ちくま新書)を読んでいますが、ここにも“ノーと言えない子どもたち”の姿が描かれています。みんな“いい子”を一生懸命に演じているのです。そして、ある時“本当の自分がいない”ことに気づくのです。ノーと言えない子どもがその相手から逃げるためには相手を殺すしかないのです。と、いろいろと書いていて日米関係に似ているな・・・と感じました。日本はアメリカの“いい子”から抜け出せませんからね。
2008.07.22
コメント(10)
-
21日までお休みします
今日はこれから青森で仕事(親子遊び)なので仕事でゆっくりと文章を書いている時間がありません。ということでお休みさせていただきます。21日の夜中に帰ってくるので次回は22日に書きます。
2008.07.19
コメント(2)
-
「子どもの表現と大人の表現」(感情が表現を創る)
昨日は、9月から始める「表現共育クラス」の体験日でした。大勢の方が参加して下さって非常に楽しい遊びができました。それで、新しいメンバー募集はしばらくしませんのでご了承下さい。但し、昨日は遠くから参加して下さった方も多く、“やはり時間的に難しい”とおっしゃっていた方も数人いらしたので、9月になり、メンバーが落ち着いて余裕があるようでしたら、またブログなどでお知らせします。でも、表現遊びは本当に面白いです。子どもたちが生き生きとしてきます。そして生き生きとしている子どもはホントに素敵です。“見えないボール”を回すワークでは、ボールを運ぶ子どもも、ボールを待っている子どもも真剣で、それでいてワクワクしていて、言葉では表せないくらい子どもたちが素敵でした。そういう時の子どもは宝石のように輝いているのです。また、大人たちも素敵でした。子どものように素敵なお母さんやお父さんばかりでした。子どもたちが輝くのは子どもたちの魂が満たされている時です。そして、そういう体験が子どもたちの魂を育てていきます。そして、魂が満たされている子どもは素晴らしく素敵な表現をするのです。子どもに対しては表現は教えるものではありません。満たされれば自然に自分らしい表現が生まれてくるからです。教えなければ伝わらない表現は大人の表現です。実は、子どもの表現を育てる方法と大人の表現を育てる方法は同じではないのです。大人は、“自分の表現”というものがもう固まってしまっています。“表現が苦手”と思いこんでいる人でも、しっかりと“自分なりの表現”は持っているのです。そして、その“自分なりの表現”は何十年もかかってって出来上がってきているので、滅多なことでは変わりません。そして、それが“その人らしさ”を作っているのです。ですから、大人に対して新しい表現を伝えようと思ったら、それまでの“自分流の表現”を壊さなければなりません。大人はそれまでのやり方を壊さないと新しいやり方を学ぶことが出来ないのです。でも、それまでの自分のやり方を壊すということは、それまでの自分を否定すると言うことです。だから、心とからだが抵抗するのです。そんな時、心だけでいくら頑張っても無駄です。心よりからだの方が強いからです。おしっこが溜まって漏れそうな時に冷静に感じたり考えたり出来ますか。出来ないでしょ。人間は理性でからだをコントロールすることは出来ないのです。これはどんな聖人だって出来ないのです。そんな時は“冷静になれ”と頑張るよりお便所に駆け込んだ方が効果的です。つまり、からだを変えてしまうのです。からだを変えれば心も変わり、それまでの自分流は自然に消えてしまうのです。そして、新しいやり方を学ぶことが出来ます。聖人と呼ばれる人はそのからだの変え方が上手なんです。つまり、おしっこの我慢が上手なのではなく、溜めないようにするのが上手なんです。(下品な例えばかりでゴメンナサイ。)でも、それには心とからだのつながり方をよく知っている優秀な指導者が必要です。手間も時間もかかります。何十年もかけて強固に作り上げた“自分流”を壊すのは非常に困難だからです。それは恐怖と不安との戦いになります。高い崖の上の小さくて不安定な足場のところで、必死に崖にしがみついている人がいます。それで、“そんなとこあぶないからこっちへ来なさい”と、すぐ脇にあるもっと広くて安全な場所へ誘っても、必死で崖にしがみついている人にはそんな場所見えません。見えない所に足を出して、今しがみついている手を離すなんてことはできないのです。また、何十年もそのまましがみついてきたのでからだが固まってしまって動きません。時として、もうすでに崖が消えてしまっていることもよくあるのですが、その状態で固まってしまっている人は崖が無くてもイメージで崖を作りだして、イメージでしがみついています。どんなに不安定で怖い場所でも、手を離したら落っこちて死んでしまうという恐怖心がからだに染みついてしまっているからです。そして、実際にはそういう人が多いのです。それをトラウマといいます。そういう人がその崖のイメージを手放すためには、“もうそこには崖なんて存在しないんだ”ということを自分のからだで確認することが必要になります。こんな時、マニュアルを使って表面的な状態だけを変えても、不安や恐怖は消えません。だから、今度はマニュアルにしがみつきます。とにかく、何かにしがみついていないと怖いのです。このように、大人の表現を変えるのはこれだけ困難なんです。大人の表現を変えることは過去を変えることなのです。でも、子どもたちには変える過去がありません。しがみつくものもまだありません。だから、状況が変わってしまえば簡単に表現も変わってしまうのです。(但し、思春期に近い子どもは困難です。思春期は過去が固まる時期でもあるからです。)子どもの表現は子どもの感情の状態で変化します。ですから、表現を見ているだけで子どもの感情が見えてきます。非常に分かりやすいのです。それはつまり、言い換えると子どもの表現を育てるためには子どもの感情を育てることが必要だということなのです。子どもたちは、自分の感情を表現する必要の中で自分の表現を創っていくのです。ですから、子どもにマニュアル的な出来合の表現を教えてはいけません。それは子どもの感情の否定につながってしまいます。大人がマニュアル的な表現を教えてしまうと子どもは“自分の表現”を創らなくなってしまうのです。大人が出来るのは子どもが自分の表現を創り出す手助けをすることだけです。でも、実際には“表現は教えるもんだ”と考えている大人が多いのです。特に、学校や教育熱心な大人たちです。でも、それでは逆に子どもは表現できなくなるのです。
2008.07.18
コメント(6)
-
「感情のコントロールとイメージ」(怒りは燃やそう)
先日、大したことではないのですがちょっと腹が立っていました。それで丁度いいからイメージを使ってこの怒りを効果的に静める方法を考えてみようと思いました。それで色々と試した見たら、一番簡単で効果的だったのは心の中でたき火をイメージして、そこにボンボン怒りを投げ込んで燃やしてしまう方法でした。その延長で“悲しみ”はどうしようか、と考えて見ました。それで一番効果的に思われたのは大きな青い川をイメージしてそこに流してしまうことでした。それで、“そうか、怒りは燃やして、悲しみは流してしまえばいいんだ”と気付いたわけです。ただし、これは私の場合であって他の人でも同じイメージが有効かどうかは分かりません。でも、何かしら有効なイメージはあるのではないかと思います。私はどうもケチな性格なので、腹が立っている時にも“せっかく腹が立ったのだからこんな時にしか分からないものを見つけよう”などと考えてしまうのです。駅で階段とエスカレーターがあったら、“せっかく運動用の階段があるんだからこれを使わないともったいない”とか、電車の中でも“立っているとバランス感覚や全身の筋肉のトレーニングになるな”と考えてしまうのです。道を歩いている時にも、歩き方や姿勢を変えたら、何がどう変わるのかを実験しながら歩いています。だって、ただ歩いていたらもったいないじゃないですか。私はそれなりに本はいっぱい読みます。でも、基本的に本は信用していません。それはその本を書いた人にとっての事実でしかないことが多いからです。へそ曲がりの私は、自分で試してみないと納得出来ないのです。でも、それだけでは自分のことしか分かりません。ですから、ワークで他の人にも試してもらいます。すると、少しずつ本当のことが見えてきます。先日は、“怒り”をイメージで収める方法を考えましたが、ある時にはからだへのアプローチで怒りを静める方法を考えたこともあります。でも、基本的に私はあまり腹が立たない人なのでそういう機会はあまりないのです。だから、怒りが湧いた時にはそれを大切に使うのです。怒っている時にはからだ全体が緊張して硬くなっています。お腹も緊張して呼吸が浅くなっています。顔の筋肉も緊張しています。からだが硬くなっているせいか真っ直ぐ前を向いて歩くことは出来ますが、下を見たり、上を見たりすることができません。首がゆるまないのです。ですから、首だけを横に向けるのも難しくなります。そして、見たり、聞いたりという感覚の働きが鈍くなってしまって心の中で同じことばかり考えています。そんな時は私は“見る”ことに集中します。雲を見たり、お花を見たりするのです。無心に集中して絵を描く時のように見るのです。また、胸が閉じてしまっていますから胸を開いてみたり、腕や手を開いてみたり、上を見たりします。“怒り”に特有の心やからだの状態があるのですから、その心やからだの状態を変えてしまえば怒りも消えてしまうのです。それを、それらをそのままにして怒りを静めようとするから怒りに振り回されてしまうのです。皆さんも、腹が立った時など、その怒りを無駄にしないで自分にぴったりの方法を探してみてください。ただ、私は怒っている時の状態が不快なので色々と怒りを静める方法を考えますが、人によってはその状態が気持ちがいい人もいるようです。軽い興奮状態になって気持ちが大きくなるのでしょうか。そういう人はいつも怒っています。
2008.07.17
コメント(12)
-
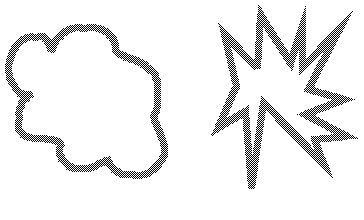
「言葉とイメージ」
17日の「表現共育クラス」の体験ワークの募集は締め切りました。明日体験して頂いて9月以降参加可能かどうかをあらためてお聞きします。予想以上に反響が大きかったので、しばらくの間新しい募集はしないと思います。ご了承下さい。**************************人間には「共感覚」という不思議な感覚があります。この感覚が異常に敏感な人の場合では色を見たら音が聞こえたり、数字を見たら色が見えたりということが起こります。つまり、一つの感覚に対する刺激が他の感覚への刺激になってしまうのです。鳥の声が色に見えてしまうというようなことです。ここまで来ると異常ですが、でも普通の私達でも多少はその共感覚を感じています。ザラザラしたものを見ると、何となく触覚的にもザラザラしたものを感じます。また、ドレミファソラシドという音にどんな色が合いますか、と多くの人に聞いてみると共通した傾向が現れます。これは子どもに聞いてみると面白いですよ。結構はっきりと答えてくれます。○は何色、△は何色と聞いてみても面白いです。以下の図は「ブーバーとキキ」というその共感覚の簡単な実験に使われるものです。(私が描いたのでちょっと印象が違ってしまっていますけど)この図を世界中の人に見せて“この二つはそれぞれ別々のキャラクターです。そして、名前は一方がブーバーで一方がキキです。さて、どちらがブーバーでどちらがキキだと思いますか”と聞くと、9割の人が丸っこい方をブーバーと答え、とんがった方をキキと答えたそうです。私もしょっちゅうワークでこの図を見せて聞いていますが、ほとんどの人が同じように答えます。でも、これって不思議でしょ。だって形だけから名前を類推出来てしまうんですから。どうしてこんなことが起きるのかというと全ての感覚はからだの中でつながっているからです。“キキ”という名前を声に出そうとする時、喉の奥を緊張させます。そして鋭く短い音を連続させます。その感覚がからだの中に尖った印象を引き起こすのです。“ブーバー”という名前を声に出そうとする時には喉をゆるめて唇を閉じて空気で風船のように膨らませてからゆっくり吐き出します。口の中がふくらんだ風船から空気が抜けていくような状態になるのです。そういう感覚が視覚的な図から音を連想させるのです。また、その逆もあります。このように人間は言葉や音をからだ全体の感覚で聴いているのです。色や形も同じです。私達は“青”という色を“あお”という音で感じているのです。“あ-お-”とゆっくり声に出してみて下さい。そして青い色を思い浮かべてみて下さい。そこに違和感はないはずです。でも、“あーおー”といいながら赤い色を思い浮かべてみて下さい。どうですか、違和感を感じませんか。私はかなりの違和感を感じます。つまり、言葉というものはデタラメに作られたのではなく、その事物の身体的な印象をもとに感覚的に生まれてきたのです。シュタイナー教育におけるオイリュトミーという身体芸術ではそこをつなげて表現します。例えば、“て”という言葉が最初につく言葉てっぺん/底辺/抵抗などは舌が口蓋にしっかりとくっつく印象とつながっています。“く”という音は喉がつまる感じです。“くるしい”時には喉がつまっているのです。ですから苦しい時には、“く”という音が出しやすいのです。逆に“しあわせ”とか“うれしい”という声は出しにくくなります。じゃあ、外人はどうなんだ、と思われる方もいらっしゃるでしょうね。日本語では“あお”でも、英語では“ブルー”ですからね。結論から言うと“あお”と“ブルー”は同じではありません。日本人にとっての青と英語を使う人たちにとってのブルーでは印象が違うのです。色的には同じでも、その色に対する印象が違うのです。言葉が違えば印象が違うのです。ですから、言葉というものは厳密には翻訳不可能なんです。“こんばんわ”と、“おばんです”は訳せば同じですが、印象はまったく違います。“バカ”と“アホ”も全然違います。実際、相手の反応も違います。そして私達は言葉をその“意味”ではなく、からだの感覚とつながった印象で使っているのです。ですから、状況に合わせて自在に使い分けることが出来るのです。言葉というものはからだの“印象”を音声化したものなんです。文字はその印象を形に現したものです。(但し、抽象的な言葉、観念的な言葉に関してはその限りではありません。“人類”という言葉はからだの印象とはつながっていません。)実際、ブーバーのBはブーバーの形に似ています。キキのKはキキの形に似ています。“しあわせ”と“ハッピー”も同じではありません。“おはようございます”と“グッドモーニング”も同じではありません。これをジェスチャーを入れて表現してみれば両者が全く別物であることがすぐに分かります。その“おはようございます”を印象的に“グッドモーニング”に近づけるためには、“ございます”を取って“おはよう”だけにします。“さようなら”を“グッバイ”に近づけるためには“う”を取って、“さよなら”にします。つまり、言葉を変えないと同じ印象にはならないのです。この“印象”が“言葉のイメージ”とつながっています。言葉はイメージの固まりなんです。だから、言葉を伝えることが心を伝えることにもつながるのです。まただから、言葉育ては感覚育てとつながっているのです。そして、イメージ能力ともつながってきます。言葉を使うのが上手な人はイメージのコントロールも上手なんです。だから子どもたちにもっともっと言葉を伝えてあげて欲しいのです。ただし、印象とつながらない言葉はオウムやロボットの言葉と同じです。そして、印象とつながった言葉は生活体験の中でしか学ぶことが出来ません。木に触れ、登り、匂いをかぎ、その下で遊ぶことで“木”という言葉と“木の印象”がつながり、言葉に生命が吹き込まれるのです。印象とつながっていない言葉はただの“記号”に過ぎません。記号では自分の心を表現することが出来ません。そんな言葉いくらいっぱい知っていても使えません。
2008.07.16
コメント(15)
-
「イメージと空想とファンタジーと魔法」
9月から始める表現共育のクラスと6月17日の体験会の参加者募集を締め切ります。沢山の応募がありました。有り難うございました。******************************先日、キーロさんさんから>大変興味深く読ませていただきました。>イメージするだけで心が豊かになりますよね。>私は、イメージの中で「ハワイ」に行きますよ。>時には、違う人物になって恋愛もします。というコメントを頂きましたがこのコメントをお借りして“イメージ”と“空想”の違いを考えてみます。イメージ(image)を辞書で引くと、(goo辞書)━━ n. 像; 肖像, 画像, 彫像; 映像; 形; 生写し (the ~ of his father); 典型; 象徴; 【心】心像; 面影; 全体的印象; 【修辞】比喩(ひゆ).と書いてあります。一方、“空想”は名)スル(1)現実にはありそうにもないことをあれこれ頭の中で想像すること。「―にふける」「未来の生活を―する」[哲学字彙(三版)](2)〔仏〕「空見(くうけん)」に同じ。と書いてあります。ですから、ハワイの空や海やブーゲンビリアや温かさなどをイメージするのはイメージですが、“恋愛”の方は空想になります。イメージは感覚の記憶によって生まれます。ですから、イメージすると感覚が蘇ります。それでハワイの気分を味わうことが出来るのです。でも、空想は感情とつながっています。欲求や願望や恐怖や不安といった感情が空想を生み出します。ですからイメージは開かれていて、空想は閉ざされています。イメージを共有することは難しくありませんが、空想を共有するのはなかなか困難です。だって、感覚は基本的にみんな同じですが、感情はみんな違いますから。例えば、青い色を見た時に感じる感覚にはあまり個人差がありませんが、一人の女の子(男の子)を見た時に感じる感情は人それぞれです。その異なった感情が空想を引き起こします。もちろん、感覚と感情は密接につながっていますからこの両者を厳密に分けることは出来ませんが、でも、同じものではありません。イメージは“言葉”や“詩”に近いのです。イメージに音を与えると言葉になり、その言葉でイメージを表すと詩になります。ですから、豊かなイメージ力を育てるためには豊かな感覚体験と言葉との出会いが必要になります。それに対して、空想は言葉とはあまりつながっていません。感情の動きが勝手に空想を引き起こすのです。ただし、イメージ力が弱い子が空想すると感情に振り回されすぎて妄想になってしまいます。イメージ力が心を現実とつなげてくれているからです。そして、そのイメージと空想の中間にあるのが“ファンタジー”です。ファンタジーを“物語”と訳すこともありますが、でも実はファンタジーは“物語”より、言葉そのものや詩の世界にもっと近いものなのです。そして、それが子どもが生きている世界です。空を飛ぶ馬を空想することはできます。でも、そのままで空を飛んでいたら何か変です。馬がそのままの姿で空を飛ぶのは現実的ではないのです。だから“羽”が必要になります。羽を付けることでより(実際にはそんな馬はいなくても)現実的になるのです。その馬に羽を付けるのがイメージの働きです。羽のある馬なんていません。現代人はだからこんなことを考えた昔の人をバカにします。でも、この“羽”は“空想”と“現実”をつなげる大切な働きをしているのです。羽が取れてしまえば普通の馬に戻ることが出来る仕掛けになっているのです。かぼちゃが馬車になどなるわけがありません。そんなことは子どもだって知っています。だから“魔法”が必要なんです。多くの大人は魔法なんて馬鹿げている、それは子どもが無知だからだと考えますが、それは違います。魔法は子どもや古代人の知恵なのです。現実から空想の世界に入るためにはそのつなぎとしてメージの働きによる魔法が必要なのです。だから、魔法が解けてしまえば現実に戻ることが出来るのです。言っている意味が分かりますか。馬の羽や、カボチャを馬車に変えたりする魔法は現実の世界から空想の世界に入るための仕掛けであると同時に、空想の世界から現実の世界に戻るための仕掛けでもあるということです。ありえない空想の世界で遊ぶためには魔法が必要なんです。言い換えると魔法を信じている子は現実の世界をちゃんと分かっている子だと言うことです。空を飛ぶために妖精の粉を必要としている子はちゃんと現実のことも分かっているのです。そして、現実の世界と空想の世界との間をイメージの働きで自由に行き来しながら生まれて来るのがファンタジーの世界なんです。だから、豊かなイメージ能力が、豊かなファンタジーの世界を創り出すのです。でも、イメージ能力が弱い子は正しく魔法を使うことが出来ないので、現実の世界と空想の世界をちゃんと分けることが出来ません。ごちゃまぜになってしまうのです。すると、空想ではなく、妄想になってしまうのです。空想は還ってくることが出来ますが、妄想は還ってくることが出来ません。イメージ力という魔法の力を持っていない子が妄想の世界に入ってしまうと還ってくることが出来なくなってしまうのです。荒唐無稽な事ばかり言う子どもに不安を感じているお母さんはいっぱいいます。でも、子どもの頃にいっぱいファンタジーの世界で遊ぶことが出来た子は、ちゃんと現実の世界に還る能力も身につけることが出来るのです。そして、大人になった時には身につけた魔法の能力で今度は現実世界を変える事が出来るようになるのです。実は、生き生きと生きている素敵な人はみんな魔法を使っているのです。イメージという魔法です。逆に、勉強ばかりしていたり、自然の中で遊ばせてもらえなかったり、お話を聞かせてもらえなかったり、豊かな言葉と出会えなかったり、イメージで遊ぶ遊びを否定されてしまった子が妄想に走るのです。そして、魔法の力がないのでいつも不安に怯え、誰かに依存して生きる事しか出来なくなるのです。
2008.07.15
コメント(4)
-
「心の世界はイメージの世界」(子どもはイメージの世界を生きる)
たまごさんが書いて下さった以下のコメントから話しを始めます。相手のイメージをわかせる授業-感覚に働きかける授業- 先輩の先生が 詩を子供たちに書かせるのに、まずお花を観察させました。観察させるポイントは 色、におい、動き、音 など。お花にも動きや音がするといって 古い木の幹に耳をつけると 幹に水が流れている音がするのだというお話をするのだそうです。そして こどもたちに観察させて 絵を描かせるそうです。そして 最後に 詩を書かせます。すると いつもなかなか集中しない児童でも 表現力豊かな ことを書いていて 驚きました。子どもは主観的に感じ、考えます。客観的に見たり、聞いたり、感じたりということがそれなりに出来るようになるのは10才を過ぎてからです。これは子どもの絵を年齢ごとに並べて見ていればすぐ分かります。10才を過ぎると急に視点が固定され、一点透視的な構図になり、絵の世界の中にも物理法則が導入されてきます。それ以前の子どもの絵は基本的にシャガールやピカソのようです。物理的な視点が固定されていないし、様々な視点から見えるものが同時に一枚の絵の中に表現されます。物理法則も全く無視されています。子どもたちはまるで魔法の世界のように絵を描くのです。この時期の子どもたちは目に見えるものを写すことができません。ただ、知っていることを描くのです。つまり、心の中のイメージを描くだけなんです。子どもの絵は子どもの心の世界そのものなんです。だから、子どもの絵に評価を付けたり、手を加えてはいけないのです。それは子どもの心への侮辱です。子どもがおかしな絵を描くのは絵が下手だからではなく、心の中がそういう状態だからに他なりません。子どもは自分の心の中のイメージを見ながら絵を描くのです。だから、平気で手のない絵を描いたり、棒人間を描いたり、頭足人などを描くのです。また、大好きな人が家より大きかったりするのです。ですから、少なくとも低学年頃までの子どもに写生などさせない方がいいのです。幼稚園などでも写生させるところがあるみたいですが、子どもたちは見て描くことが出来ないのでテクニックで描くようになります。そして、生き生きとしていない大人好みの絵ばかりを描くようになります。また、部分だけは見ることが出来るので、部分をつなぎ合わせることで結果として絵になるような絵を描かせる技術も存在します。でも、私にはそこまでして上手な絵を描かせる意味がよく分かりません。子どもは上手な絵が描けて満足するでしょうが、自分の心の中のイメージと対話する能力が損なわれてしまうでしょう。ですから、子どもたちが生き生きとした絵を描くためには子どもたちの心の中に生き生きとしたイメージを作ることから始める必要があるのです。それがたまごさんの先輩の先生達がやっていることの意味です。子どもたちはお花であろうと、雲であろうと、ザリガニであろうと、自分と同じ生命を持った生き物のように心の中にそのイメージを作るのです。そして、そのイメージと心の中で遊ぶのです。心の中には“イメージとしての自分”も存在しているのです。実はイメージというのは心の中の生き物なんです。昔話やファンタジーに書かれていることはそのイメージの世界の中での出来事です。そして、大人でも夢の中でその生命を持った状態のイメージと出会うことが出来ます。ある、友人のお子さんの女の子は小6の頃朝起きて泣いていたそうです。それでお母さんが“どうしたの”と聞いたら、“お母さんを殺した夢を見てしまった”というのです。それで、私が彼女に“よかったね”と言い、彼女もまた“よかったです”と言いました。この夢は娘さんがお母さんを乗り越えた象徴だからです。“子ども”から“仲間”になったのです。その通過儀礼の象徴として、“お母さんを殺す”というイメージが現れたのです。これを昨今の現実世界の親殺しと混同して解釈してはいけません。むしろ、心の中で殺すことが出来ないから、現実世界で殺してしまうのです。心の中で殺してしまえば、現実世界で殺す必要がなくなってしまうからです。悪いオオカミはちゃんと殺さなくてはいけないのです。そうでないと、いつまでもオオカミの影におびえることになってしまいます。もちろん、これは心の世界の中のお話しです。そして、子どもの頃に作られたこの“イメージ”という生き物たちは大人になってもズーッと心の中で生き続けています。子どもの頃に“怖いお母さん”のイメージが住みついてしまうと、そのイメージを殺す(乗り越える)のは容易ではありません。先の、娘さんのお母さんは優しいお母さんなので心の中で殺す(乗り越える)ことが出来ましたが、そのイメージの中のお母さんのパワーがあまりにも強いとお母さんが心の世界の中の支配者になってしまって、自分はその影に怯えて生きるようになってしまうのです。そして、一生お母さんに支配されてしまうのです。(それを乗り越えるためにはイメージを作り替える必要があります。)また、大人になってもしっかりとしたそのイメージがあるから詩を聞いたり、物語を聞いたり、絵を見たり、様々な芸術作品を見てその世界の中に入ることが出来るのです。生き生きとしたイメージの世界を持っていない人は芸術の世界の中で遊ぶことが出来ないのです。人間は現実世界と、心の中の世界との二つの世界で生きています。その心の中の世界を支えているのは子どもの頃に心の中に生まれたイメージ達です。ですから、そのイメージが生き生きとして活発ならその人の心も活発になります。そして、現実世界でも活発になるでしょう。ちなみに、その現実世界とつながっているのが“文明”です。そして、心の中の世界とつながっているのが“文化”です。ですから、文明は文化の働きの結果生まれたのです。(猿の世界には文明はありませんが、文化はあります。)でも、現代では文明が文化を支配してしまっています。ですから、心の中の世界が呼吸困難になってしまっているのです。
2008.07.14
コメント(2)
-
「幼稚園の選び方」
今日はちょっと時間がないのである会に頼まれて書いた「幼稚園の選び方」を載せさせて頂きます。 多くのお母さん達が幼稚園選びで悩んでいます。でも、その基準は人それぞれです。自宅との距離、お弁当の有無、園庭の広さ、園バスの有無、保育時間、保育方針の内容、園庭の状態、先生達の様子、園舎の広さ、保育料、規模、園の雰囲気、友達が一緒かどうか、また子どもの個性に合っているかどうか、などなどその基準を数え上げたらキリがないかも知れません。 それに対して、そんなこと悩みもせずに近いからという理由だけで幼稚園を決めてしまうお母さんもいっぱいいます。そういうお母さんにとっては、保育方針などに拘ってわざわざ遠くの幼稚園まで子どもを通わせている人の気持ちが理解出来ません。それで“お宅は教育熱心よね”などと、嫌みを言われます。 でも、多くの幼稚園を卒園した子どもたちと関わってきた印象としては幼稚園が子どもに与える影響は大人が思っている以上に大きいのではないかと思っています。なぜなら、人間としての価値観の基礎、心とからだの感性の基礎がこの時期に作られてしまうからです。多くのお母さん達にとっては、○○が出来るようになる、文字を教えてくれる、おイスに座っていることが出来るように仕付けてくれる、などということが大切なのかも知れませんが、でも、そんなことは後からでも充分に間に合うのです。そして実際、7才までに心とからだの準備が出来ている子なら小学校に入ってからでも無理なくすーっと出来てしまうのです。最初、他の子がみんなできるのでちょっとあせるだけです。 でも、その心とからだの準備を整えずに、何かを出来るようにばかり仕付けられた子は、後で困ったことになります。何かが出来る状態で小学校に入ると、最初のうちは安心していることが出来ます。でも、その貯金も3年生頃には尽きてしまいます。そして、そこで止まってしまう子が多いのです。貯金を使うことに慣れてしまって稼ぐ(学ぶ)ことに気持ちが向かないのです。だから、アメとムチで子どもを追い立てなければならなくなってしまうのです。 ということで、幼児期に育てなければならないことは「人間としての価値観の基礎」、「心とからだの感性の基礎」なのです。そしてこれは何かをやらせることで育つものではありません。先生がお手本として子どもと向き合い、子どもと子ども、子どもと自然、心とからだなどの多様な関わりを通して自然に育っていくものなのです。ですから、“○○をやらせます”、“○○が出来るようにします”といううたい文句の幼稚園はお勧めしません。 また、意外かも知れませんが“創造性を育てます”、“個性を育てます”という幼稚園もちょっと気を付けてください。子どもというものは最初から創造的で個性的なんです。ですから、子どもらしさを大切にしているのなら子どもは自然な形で自分の創造性や個性的を伸ばしていくことが出来るのです。それを大人が大人の価値観に合わせて創造性を育てようとする時、子どもは自分の創造性を否定されたように感じるのです。つまり、言っていることとやっていることが逆になってしまうのです。ただし、子どもらしさの延長に大人が遊びや課題を工夫して提示することは素敵なことです。そういう活動を通して子どもは自分の成長を実感することが出来ます。 大切なことは、それが大人を喜ばせるためではなく、子どもが自分の成長を実感出来るような活動かどうか、ということです。 それと、幼児期の子どもにとって園庭の広さはあまり関係がありません。幼児期の子どもにとって必要なのはサッカーやかけっこが出来るような平面的に広い園庭ではなく、隠れんぼや鬼ごっこや木登りが出来るような立体的な空間の方なのです。そういう空間は子どものイマジネーション(ファンタジー)を刺激します。だから、そういう空間の中で子どもは心とからだ丸ごとで遊ぶことが出来ます。そして、そういう空間の中で遊んでいる子は“お話しの世界”にも違和感なく入っていけるのです。何もない、便利で、合理的なただ広いだけの空間は“お話し”を受けいれる感性を育ててくれません。 また、同じことが幼稚園の構造にも求められます。学校の教室のような整理され、便利で管理しやすい園舎は、子どもには居心地が悪い空間です。そのような人工的な空間は子どもの不安を刺激します。また、走り回ることが出来るような明るく広い空間が好きな子どももいますが、その逆にあまり明るくなく落ち着いた空間の方を好む子どももいます。一般的に、胆汁質や多血質の子どもたちは明るく開放的な空間を好み、粘液質や憂鬱質の子どもたちはあまり明るくなく落ち着いた空間を好みます。ただし、粘液質の子には広い空間が見える窓が必要です。 あまり開放的ではなく落ち着いた空間を好む子を“子どもらしくない”といって否定する人もいますが、それは気質ですから仕方がないのです。 ですから、理想を言えば広く開放的な空間と、狭く落ち着いた空間の両方が備わった園舎だと色々なタイプの子どもが自分の居場所を見つけることが出来ます。そして、広い空間が好きな子も狭く落ち着いた空間の良さに触れることが出来るでしょう。また、逆に狭い空間に閉じこもりがちな子も広い空間から聞こえてくる楽しそうな声に影響を受けるでしょう。色々なタイプの子が安心出来る居場所があるからこそ、そういう子どもたちが出会うことが出来るのです。広い開放的な空間だけでは落ち着いた空間が必要な子は否定されてしまいます。そして、狭く落ち着いた空間だけでは開放的な空間を必要とする子は否定されてしまいます。するとお互いに出会えなくなってしまうのです。ちなみに、ここで言う“空間”とは必ずしも物理的な空間の広さを意味していません。“そのように感じることが出来る空間”ということです。 また、「○○教育」とか、「○○メソッド」、「○○法」という主義を掲げている幼稚園も多くありますが、そういう看板で幼稚園を見ない方が身のためです。看板倒れのところが結構あるからです。あくまでも中身で判断してください。 全体的な注意点としては、先生の怒鳴り声が聞こえる、先生達が生き生きとしていない、先生が子どもの話を聞く時、子どもに話しかける時に子どもの目線に立っていない、子どもたちが自由に遊んでいない、飾られている絵や作品がみんな似ている、本棚に絵本が少ない、しつけ絵本やアニメ絵本のようなものがいっぱい置いてある、テレビを見せている、読み聞かせやお話しに力を入れていない、園庭に遊具ばかりがいっぱいある、先生が子どもと遊んでいない、ドロンコ遊びや水遊びをさせない、“ダメ”、“ヤメナサイ”、“早くしなさい”というようなことばかり言っている、子どもが“ぼく字(漢字)が書けるんだ”とか“算数が出来るんだ”と自慢してくる、園長さんが園の自慢ばかりする、そういう幼稚園はご注意下さい。 最後に、幼稚園に過大に期待しないでくださいね。子どもの育ちにとっては幼稚園よりお母さんや家族からの影響の方が大きいのですからね。家族や夫婦関係を崩壊させてまで理想の幼稚園を選ぶのは本末転倒です。お母さんとの信頼関係、お母さんとお父さんの信頼関係こそが幼児期の育ちにとっては一番大切なことなのです。あとは、現実とのバランスで考えてください。
2008.07.13
コメント(4)
-
「イメージと感覚と感情と表現」(生きることを楽しむ方法)
人間の人間としての特質は色々とありますが、その中でも人間の人間らしさを支えている最大の働きはその“イメージ能力”です。心もこのイメージ能力の働きによって生まれます。何かを想像したり、空想したりすることが出来ない心なんてありえません。思考も創造性もこのイメージ能力の現れです。何かを理解するのもこのイメージ能力の働きです。そして、過去のことや未来のことを考えたり、悩んだり、喜んだりするのもこのイメージ能力の働きです。勇気や希望や生命といったものも、イメージ能力が創りだしています。ですから、イメージをコントロールする力が弱い人は他の人のイメージや、勝手にわき上がってくるイメージに振り回されてしまいます。普通の人でも麻薬の中毒になるとそういう状態になります。そうすると“悩み”から抜け出ることが出来なくなります。人を傷つけるようになります。勉強が分からなくなります。イメージをコントロールする能力が低い人は抽象的な思考が出来ないからからです。また、イメージ能力は意思の働きとも関係しています。人間以外の動物の意志は生きるために使われます。獲物を追いかけ、敵と戦うために意志が必要なのです。そして、風下から回ったり、音がしないように動いたり、相手を威嚇する時にはイメージ能力が働いています。意志は行動を引き起こすと同時に、イメージを作り出すのです。状況に合わせて的確な行動をするためにはイメージが必要なのです。ですから、イメージ能力は複雑な状況で的確に行動するために必要な能力として発達してきたのだろうと思います。動物はパワーだけでは生き延びることが出来ないのです。そしてそれが思考の始まりなのでしょう。このイメージ能力はネズミも持っています。ネズミに複雑な迷路を覚えさせる実験がありますが記憶はイメージの仲間なのです。でも、人間以外の動物は自分の意志でイメージする能力は持っていません。ただ状況に合わせて生理的反応としてイメージが作られるばかりです。ですから、迷路のイメージを持つことは出来ても、その迷路を心の中で操作してみることはできないのです。でも、人間だけが意志の働きでそのイメージを自由にコントロールすることが出来るようになりました。肉体だけでなく心の中でも動くことが出来るようになったのです。そして、時間と空間と物理法則に縛られることがなくなりました。イメージの世界の中では時間や空間すら自分の意志で自由に操ることが出来るのです。イメージは心の中のからだなんです。そして、その心の中のからだは肉体によるからだと密接につながっています。感覚と感情が両者をつなげているのです。ですからその人の感覚と感情の状態をみると、その人の意志とイメージ能力の状態を知ることが出来ます。感覚と感情に偏りがある人はイメージ能力にも偏りがあります。それが偏った行動につながり、トラブルを起こすのです。私は9月から茅ヶ崎で表現共育のクラスを始めますが、そこで大切にしたいのも感覚や感情と関わりながらこのイメージ能力を育てると言うことです。(これがそのチラシです。ご覧になってみて下さい。7/17に体験会をします。)ですから、一般的に“表現”という言葉でイメージされるような活動ばかりをやるのではありません。絵本やお話しを聞いたり、音や色を感じたりということもします。触れてみたり、触れてもらったりしながら温かさや、動きや、気配などを感じたりもします。そういう活動がイメージ能力を育ててくれるからです。そこから自然に溢れてきたものが自然な表現なのです。私の考える“表現”とはそのようなものです。“作るもの”ではなく、“溢れてくるもの”という考え方です。また、多くの人が、“表現”を“役に立つ道具”のように考えていますが、“役に立つ表現”をいっぱい学んでもそれは表面的なものに過ぎません。そして、限定された条件の中でしか使えません。確かに、多くの表現を学ぶことで自信はつくでしょう。でも、基本的な能力が高くなるわけではありません。それにイメージ能力が育っていないと、感覚や感情に振り回されてしまって“自分”が自分の人生の主人公になることが出来ません。そして、“生きている”ということを楽しむことが出来なくなってしまいます。それに、せっかく学んだ“役に立つ表現”も使いこなすことが出来ないでしょう。そして、学んだことに縛られてしまうでしょう。
2008.07.12
コメント(4)
-
「感覚を伝える方法」(イメージに働きかける)
一昨日のたまごさんへのご返事の続きです。感覚はからだに属していますからそのままでは伝えることが出来ません。私がいくら熱いものに触れても、私がいくら美味しいものを食べてもその感覚をそのまま他の人に伝えることは出来ません。これは当然のことです。これは感情も同じです。私がどんなに嬉しくても、どんなに怒っていてもそれをそのまま他の人に伝えることは出来ません。確かに、“熱い”とか、“嬉しい”などという言葉でその意味や状態を伝えることは可能ですが、感覚や感情そのものを伝えることは出来ません。子どもが他の子をぶった時、お母さんは“○○ちゃんは痛かったんだよ”などと言いますが、でも、それでは“○○ちゃんが痛かった”という知識を伝えることは出来ますが、“○○ちゃんの痛み”を伝えることは出来ません。また時々、“あんただってこんなことされたら痛いでしょ”とお母さんが子どもがやったことをそのまま子どもにやって痛みを感じさせようとすることもありますが、でもここで子どもが感じるのは“自分の痛み”だけであって、“○○ちゃんの痛み”ではありません。だから、子どもの反省にはちっともつながりません。ただ、“お母さんは怖い”という記憶が残るばかりです。ではどうしたらいいのか、ということです。確かに、テレパシーでも使わない限りからだの感覚や感情をそのまま相手に伝えることは不可能です。でも、ちょっとここで考え方の転換をしてみます。今、私は確かに何かを感じ、何らかの感情を持っています。でも、その感覚や感情はその感覚や感情が過ぎ去ってしまえば自分ですらよく想い出すことが出来ません。大病をして苦しくても、病気が治ってしまえばその苦しみは記憶としても曖昧になってしまいます。今、子育てでどんなに苦しんでいても、子どもが立派に成長してしまえばそんな苦しみ忘れてしまいます。実は感覚や感情というものは影のようなものなんです。常に何かが写っていますが、そこに実体はないのです。だから、他の人にそれをそのまま伝えることも出来ないし、過ぎ去ってしまえば自分でも忘れてしまうのです。では一体何の影だと思いますか。実はそれが“イメージ”なんです。人間の人間らしい感覚や感情の大部分はイメージが作り出しているのです。確かに、イメージではなく、生身の肉体から生まれる生理的な感覚や感情も存在しています。でも、それはより複雑で人間的なイメージを作り出すためのきっかけに過ぎません。生身の肉体から生まれる感覚や感情は、そのイメージの世界をもっていない猿や犬のレベルの感覚や感情と似たようなものです。でも、今問題としている感覚や感情はそういうものではないですよね。だから、感覚や感情は人それぞれなんです。そしてだから子どもは“イタイのイタイの飛んでいけー”で泣きやむのです。猿にはそんな魔法は効きません。バカと言われて怒る人もいれば、悲しくなる人もいます。それはその人のその状況におけるイメージが違うからです。だから、催眠術などで自由に感覚や感情を引き出すことも出来ます。熱いものに触れていないのに火傷をさせることだって可能です。また、だから鬱病などの心の病にかかると、感覚を感じなくなったり、感情を感じなくなったりすることがあるのです。それは心が生き生きとしたイメージを作り出すことが出来なくなるからです。心とからだは一体なんです。その証拠に、人はイメージを操作することで、相手の感覚や感情を操ることが出来ます。物語やテレビや映画などはその手法を使っています。映画を見ていて、自分の問題ではないのに悲しくなるのはそのせいです。また、からだのどこかが痛い時に冷静にその痛みを見つめさせると痛みが弱まるのもそのせいです。子どもをくすぐる時に、“いくぞ いくぞ”と気分を盛り上がると触れる前からくすぐったがるのはそのせいです。そして、“生命”というものを大切にする人と、大切にしない人では“生命”に対するイメージが違うのです。ですから、ただ“生命を大切にしよう”と叫んでも無駄だということです。ですから、子どもたちに豊かな感覚や感情を伝えたいと思ったら子どもたちのイメージに働きかけるのです。お話しや物語を読んだり、聞いたりすることはその子どもたちのイメージに働きかけます。そして、豊かなイメージ能力を持つことが出来るようになれば、豊かな感覚や、豊かな感情を持つことが出来るようになります。その逆に、豊かなイメージ能力を持つことが出来ない子どもたちは灰色で無味乾燥とした世界を生きることになります。子どものイメージに働きかける言葉が子どもの感覚と感情に働きかけるのです。そして、イメージに働きかける言葉はイメージから生まれてくるのです。
2008.07.11
コメント(0)
-
「人間らしい生活とは」(豊かさは人間らしさか)
シャオカオさんが書いて下さった社会は面白くない・・・とぼやいておりましたが、美味しくないお料理を強制的に食べさせようとしている様子が想像され、せっかく時間を過ごすのにもったいない!!と残念に思いました。ということ。sohakuさんが書いて下さったまた、「音読」のルールとして、正しい姿勢で、大きな声で読む、というのがあるのですが、暗誦すると棒読みで「大きな声」が怒鳴るようになるのです。ということ。みけ猫さんが書いて下さった芸術、特に絵画や彫刻などの授業は点数はつけたら変ですよね。前からずっとそう思っていました。という事の中に今の日本の教育や子育ての状態が現れています。それはつまり、大人たちが“どうやって教え込もうか”ということしか考えることが出来なくなってしまっているということです。これは日本の子どもの成長を考える時の最大の問題点です。スウェーデンのやり方をいくら学んでも、このことに対する反省がない限り全く無駄なことです。そして、この考え方は子育ての場にまでしっかりと浸透しています。お母さん達が教え込むことばかり考えているのです。でも、強制は反感を生みます。これは100%間違いのないことです。すると当然動きません。そこで“アメとムチと脅迫”で子どもを操作しようとします。そうすると、子どもは大人に依存しないと生きていけませんから、生きるために嫌々従います。そして、自分の意志で生きることを放棄します。そして、ゲームなどの快楽でその虚しさを紛らわせます。また、ちょっと成長した子はSEXや様々な薬などで自分をごまかそうとすることもあります。そして、“生きている”という実感を得るために様々な精神的、肉体的な自傷行為を繰り返します。最近では自傷行為も怖くて出来ないので、他の人を傷つけることで生きていることを実感しようとする子まで現れています。自分で自分を責めて悩み苦しむのも一種の自傷行為です。自分で自分を責めることで自分の存在を確認しようとしているのです。この自傷行為ばかりやっているお母さんはいっぱいいます。そういう人はただ、悩むことで自分の存在を確認しているだけなんです。その証拠にそういう人のほとんどは実際に問題を解決するような考え方をしないし、実際の行動も起こしません。そして、手助けしてくれる人が現れても動こうとしません。悩むことの中に自分の居場所を見つけてしまっているからです。と、こういうことを書くと時々、“なんで子どもを非難するんですか、お母さんを非難するんですか、みんな一生懸命に生きているのに”と反論してくる人がいます。でも、私は誰も非難などしていません。ただ、私が見聞きしている事実を分かりやすく書いているだけです。みんなが見ようとしていないことを物語的に分かりやすく書いているだけです。もちろん、そうでないお母さんも大人も子どももいます。でも、日本全体の流れとしてはここに書いた通りの方向に進んできています。そして、一人一人が被害者であると同時に、加害者になってしまっています。私はその“流れ”を指摘しているのであって、個々のお母さんや子どもを非難しているわけではありません。被害者意識の強い人ほど自分が加害者になっていることには気付かないものです。お母さんが自分一人を守ろうとする時、お母さんは加害者になって子どもを傷つけるのです。そして、歴史は繰り返されます。そして、この流れに気付いて、この流れと向き合い、先ず自分の生活の中でこの流れを変えていくようにしないと、これから先もっともっと子どもも、お母さんも苦しむことになってしまいますよ、ということを伝えたいのです。確かに、子どももお母さんも大人たちもみんな一生懸命に生きています。自殺してしまう若者だって一生懸命に生きてきたのです。虐待を繰り返しているお母さんだって一生懸命に生きているのです。でも、人間はただ一生懸命に生きるだけではダメなんです。人間は牛や馬とは違うのです。頑張っているだけでは幸せにはなれないのです。人間は人間らしく生きなければいけないのです。だって、人間なんですから。その、人間らしく生きるということを犠牲にしてまで頑張るのは自滅行為です。そして、私には人類がその自滅への道を進んでいるようにしか思えないのです。でも、今その“人間らしく生きる”ということさえみんな分からなくなって来ています。衣食住が足りて教育を受ける権利が保障されていれば人間らしい生活だと思いこんでしまっているのです。でも、食べ物や住むところや安全に困らない生活をしている動物園のライオンの生活はライオンらしい生活ですか。先日、湘南台文化センターでチベット族の人の写真展示を見ました。みんな汚れた服を着て、貧しそうです。家の中は土間だし清潔そうにも見えません。また、電気機器もあまりないようです。学校にだって行けているかどうか分かりません。でも、子どもたちも、大人たちもその笑顔は素敵で人間の匂いがします。そして、“ああ、ここでは人間が人間らしく生きている”と感じたのです。その中に、大きなゲル(テント状の家)の前に立って笑っているお母さんと子どもの写真がありました。その写真をジーッと見ていたら遠い記憶を想い出したかのように心臓がドキドキしてきました。人間らしく生きるとはどういう事なのか、私達はもう一度しっかりと考え直した方がいいのではないでしょうか。誰が一体、「人間らしい生活=豊かな生活」などというあやまった考えを私達に押しつけてきたのでしょうか。貧しくても人間らしくて豊かな生活はあるのです。そのような生活によってつながっている社会では、みんな押しつけ合うのではなく、支え合います。そして、人間の感じる力やイメージする働きは他の人や人間以外の生命を支えようとする時、そしてみんなとつながろうとする時にこそ大切な働きをするのです。感じる力やイメージする働きが弱くなってしまった人は他の人や他の生命の立場に立って感じたり考えたりすることが出来ません。また、人と人がつながるためには大切なものを共有する必要があるのですが、それはイメージ以外にないのです。人は“物”を共有することはできないのです。一見、“物”を共有しているように見えても、実際にはイメージが共有されているのです。仏像でも、土地でも、川でも、そういうものが共有されている時にはそのものにまつわるイメージが共有されているのです。決して、物そのものが共有されているわけではないのです。イメージは共有出来ても、物は共有出来ないのです。ですから、それまで共有されてきた物でもそこからイメージが失われてしまえば、もうそれ以上共有されることはなくなります。そして誰かの所有物になります。そうやって山も川も仏像も誰かの所有物になってしまいました。ですから、イメージ能力が衰えてくると戦いや争いが増えてくるのです。押しつける教育、押しつける子育てもイメージ能力の衰えから必然的に生まれてきたのです。
2008.07.10
コメント(4)
-
「感覚に響く言葉」(子どもに感覚を伝える)
昨日、たまごさんがBBSに以下のような書き込みをして下さったので、今日はそれについて書いてみます。こんにちは。30代になって縁あり初めて小学校で図工を教える立場になったものです。以前のブログで 小学校の時は感覚に働きかける言葉が 成長にプラスになる?というようなことを書かれていたと思うのですが、例えばどのようなことでしょうか?授業の進め方の参考にしたいと思いしばらく考えていたのですが、わかりません。 教えて頂ければ幸いです。 (2008.07.08 14:56:13) 最初にお断りしておきますが、このような話題を文字だけで伝えることはできません。でも、イメージを働かせてお読み頂くことで何となく分かって頂くことは可能だと思います。理屈ではなく、イメージを働かせてお読み下さい。まず、言葉が生徒の感覚に働きかけるためには、その言葉が先生の感覚から出たものであることが必要です。感覚から出た言葉は感覚に響き、感情から出た言葉は感情に響き、知性から出た言葉は知性に響くからです。同じ、“きれいだね”という言葉でも、その言葉が感覚から出たのなら相手の感覚に響きます。感情から出たのなら感情に響きます。知性から出たのなら知性に響きます。ですから、“これこれが感情に響く言葉です”というような説明は出来ません。“地球は太陽の周りを回っているんだよ”という科学的な言葉ですら子どもたちの感覚に働きかけることは出来るのです。そして、上手な先生は算数ですら子どもたちの感覚に響くように教えることが出来ます。だから子どもたちは夢中になります。でも、下手な先生は音楽や絵画のような芸術ですら理屈でしか語ることが出来ません。だから子どもたちは退屈します。実際、シュタイナー教育の算数の進め方のようなものを読むと、算数ですら芸術のように子どもたちの感覚に働きかけながら授業することが可能であることが分かります。ブログ仲間の科学寅さんも子どもたちの感覚に働きかけるように科学の授業をしているようです。そのような授業をするためにはどうしたらいいのかというと、まず、先生が子どもたちに教えることを心の中で何回も反芻してしっかりとしたイメージを作ることです。知識をイメージ化するのです。そして身体化するのです。すると“感覚”が働き始めます。その感覚が子どもの感覚に働きかけるのです。“地球は太陽の周りを回っているんだよ”ということですら単なる知識として説明することも、生き生きとしたイメージとして伝えることも可能です。そして、イメージとして伝えようとする時子どもたちは感覚を働かせてそのイメージを受け取ろうとします。言葉が感覚に働きかけるとはそういうことです。また、先生がそんな子どもたちの心とからだの状態を感じながら授業することも大切です。“さあ、きょうもいっぱい覚えさせるぞ”という気持ちで子どもたちの前に立てば子どもの感覚は閉ざされます。でも、先生が子どもの心とからだの状態を感じながら子どもたちの前に立てば、子どもたちは先生に向けて感覚を開きます。大人が開けば子どもも開いて、大人が閉ざせば子どもも閉ざすのです。それは大人同士の会話でも同じです。だから人は相手によって使う言葉や伝えたいことを無意識に選んで変えているのです。子どもの心とからだの状態を感じながら“ほら 見て!”と言う時、子どもの感覚はパッとそちらの方を向きます。でも、自分の都合だけで“ほら 見て”と言っても無視されます。それで、“見なさいって言っているでしょ!”と怒鳴ることになるのです。以下は宮沢賢治の「風の又三郎」と征矢かおるの「なないろ山のひみつ」からの引用です。「風の又三郎」 さわやかな九月一日の朝でした。青ぞらで風がどうと鳴り 日光は運動場いっぱいでした。黒い雪袴(ユキバカマ)をはいた二人の一年生の子がどてをまわって運動場にはいって来て、まだほかに誰も来ていないのを見て「ほう、おら一等だぞ。一等だぞ。」とかわるがわる叫びながら大悦(オオヨロコ)びで門をはいって来たのでしたが、ちょっと教室の中を見ますと、二人ともまるでびっくりして棒立ちになり、それから顔を見合せてぶるぶるふるえました。がひとりはとうとう泣き出してしまいました。というわけは そのしんとした朝の教室のなかにどこから来たのか まるで顔も知らないおかしな赤い髪の子供がひとり一番前の机にちゃんと座(スワ)っていたのです。そしてその机といったらまったくこの泣いた子の自分の机だったのです。もひとりの子ももう半分泣きかけていましたが、それでもむりやり眼(メ)をりんと張ってそっちの方をにらめていましたら、ちょうどそのとき川上から「ちょうはあかぐり ちょうはあかぐり。」と高く叫ぶ声がしてそれからまるで大きな烏(カラス)のように嘉助(カスケ)が かばんをかゝえてわらって運動場へかけて来ました。と思ったらすぐそのあとから佐太郎だの耕助だのどやどややってきました。この文章を読むと感覚にビンビン響いてきます。これらの言葉は賢治の感覚から生まれてきたのでしょう。「なないろ山のひみつ」さちが、おいていかれたのは、みたこともないどんぐり林の中でした。 ぼうっと、つったっていると、とおくから、きいきいさわがしい声がきこえてきました。 さちは、声のするほうにむかって、あるきだしました。するとそのとき、林の中に、どこからともなく、きいろいひかりがながれてきて、あたりをつつみこみました。 「なんのひかりだろう。さいしょがあかで、つぎはおれんじ、それからきいろ」さちのしんぞうが、どくどくっと大きく音をたてました。「はやく、はやくきつねにあわなくちゃ」 それなのに、だるまふくろうのせいで、滝へいく道がぜんぜんわからなくなってしまったのです。さちは、とにかく、きいきい声のするほうへといそぎました。この文章は感情に響いてきます。これらの言葉は征矢かおるさんの感情から生まれてきたのでしょう。この二つの文章で書いていることは一見似ています。でも、読んでいて響いてくるところが全然違うのです。そういうことです。たまごさん、分かりにくい説明だったかも知れませんが、こんなもんでよろしいでしょうか。
2008.07.09
コメント(6)
-
「イメージ能力を育てる方法」(感覚を覚える)
イメージ能力を育てるための方法を続けます。マニアックな話題で申し訳ありません。アクセス数がどんどん減っています。体験によって感覚が刺激されそれが体験の記憶とともに心やからだの中に記憶されていきます。私は秋風が吹き始めるとスペインを想い出します。ジャスミンの匂いがするとインドを想い出します。このようなことは、一般的にみなさんにも体験がありますよね。イメージは単なる出来事の記憶ではなく、出来事の記憶と感覚の記憶がセットになった時に作られます。体験が感覚の記憶とつながった時に、からだ丸ごとの記憶になるのです。その感覚とつながったからだ丸ごとの記憶がイメージなのです。ですから、ただの知識はすぐに忘れてもイメージ化されたものはなかなか忘れません。人はからだと感覚の記憶は忘れないのです。そして、人が何かのイメージを心の中に思い浮かべる時には、今度はその感覚を想い出しているのです。例えば、皆さんが自分のお母さんのことをイメージする時心の中でどのような作業をしているか分かりますか。身長や体型や顔つきといったデータを想い出すことでイメージを作っているわけではありませんよね。そんな時みなさんは、“お母さん”につながる感覚を想い出しているのです。お母さんにつながる感覚を想い出すと自動的に心の中に“お母さん”のイメージが現れてくるのです。これは自動的に現れるのです。だから、事故などによって怪我をした人などは大きな音を聞いただけで事故のイメージが蘇ってしまうのです。いわゆる、PTST(心的外傷後ストレス症候群)というのも日常的な感覚刺激がその事故のことを想い出させてしまうから苦しいのです。ただ、PTSTなどで現れるイメージは受動的なものです。だから束縛されてしまうのです。でも、これを能動的なものに変えていくことでイメージのコントロールが可能になるのです。そして、束縛されにくくなります。絵を描いたりすることがPTSTの治療に効果があるのはそのためです。想い出さないようにするのではなく、冷静に想い出す訓練をするのです。想い出さなくても心の中にはしっかりと残っていますからいつまでも振り回されてしまいます。そのトレーニングは難しいものではありません。例えば、水道から流れ出る水を手で受けて“水の感覚”を味わって見て下さい。充分その感覚を覚えたら、今度は水がない状態でその感覚を想い出してみて下さい。すると面白いことに心の中に“水”が見えてくるはずです。野原に行って、風の感覚を充分に味わって覚えて見て下さい。そして、家の中にいる時にでもその感覚を想い出してみて下さい。すると、心の中に野原が見えてくるはずです。自分のからだに触れて自分のからだが感じる感覚を充分に味わって見て下さい。手に触れる、頭に触れる、胸に触れる、足に触れる・・・・。そうすると、その感覚を想い出すことで自分のからだを想い出すことができます。そのようなトレーニングを積んでいくと、家の中にいながら心だけを自由に遊ばせることが出来るようになります。すると息が詰まらなくなるのです。そして、視点を自由に変えることが出来るようになります。すると、色々な発見や気付きがやってきます。心の中で色々なイメージを組み合わせることで色々な体験をすることが可能になるのです。いわゆる“思考実験”というものです。すると、ポジティブ思考など必要なくなります。ポジティブ思考は頑張るためのテクニックです。それも一つのイメージですが、論理と知識だけで作り上げたイメージなので、感覚とつながっていません。ですからリアリティーがないのです。そのため、自分の感覚を大切にしている人にとっては自分をごまかすことにつながってしまうのです。知識や論理で作られただけの、感覚とつながらないイメージには自由がありません。内容的には違っても構造的には思い込みや偏見や洗脳といったものものと同じなのです。このイメージは人を縛るだけで自分の意志でコントロールすることが出来ません。私がマニアルやハウツーやそれと似たようなものを信用しないのはそのためです。即効性があるということはその人の感覚を無視しているということです。だから、マニアルやハウツーで行動することに慣れてしまうと自分の感覚に鈍感になってしまうのです。そのことがイメージ能力を低下させ、自分の人生を生き生きと生きる能力を低下させてしまうのです。感覚に目覚めると言うことは“生きる”ということに目覚めることなんです。そのことを忘れないでください。
2008.07.08
コメント(12)
-
「イメージ能力の育て方」(能動的に生きる)
イメージは“意識”と“無意識”をつなぐものです。ですから、明るいイメージを持つことで表情や考え方や行動まで変わります。また、“あの人は浮気をしているのに違いない”というイメージを持っていれば、その人の行動や表情の全てが疑わしく見えてみます。“一つの考え”は“一つのイメージ”であり、考えることはイメージを操作することなんです。ですから、イメージをコントロールする能力を高めることは、考える力を育てることと直結しています。逆に言えば、イメージをコントロールする能力が低い人は考える力も低いということです。それが今の子どもたちや大人の状態です。子どもたちはそのイメージ能力を仲間とのごっこ遊びや様々なからだを使った遊びを通して成長させて行きます。イメージ能力はただ空想するだけでは育たないのです。考えることと現実をつなげることでイメージの扱い方が分かってくるのです。そして未来の予測が出来るようになるのです。一人で空想ばかりしていると妄想の世界に入り込んでしまいます。イメージを自分の意識でコントロールできなくなるとき、妄想が勝手に動き出すのです。イメージ能力を育てるためにはからだを使う必要があります。イメージはからだの記憶によって創られていくものだからです。からだの記憶が脳の中に一つの回路として形成されることでそれがイメージになっていくのです。そして“言葉”はそのイメージから出てきて、相手のイメージの中に入っていきます。そこで“言葉が通じる”という現象が起きるのです。(この辺りのことは最近の脳科学の本をお読みになれば書いてあることです。)“からだ”は一つの現実です。この“現実”と自分の“意識”や“想い”がつながる過程でイメージが生まれます。また、そのからだを使って仲間と活動することで、社会的なイメージが形成されていきます。また、“物語”の体験も非常に重要です。物語はイメージの扱い方を教えてくれる教科書のようなものだからです。昔話やファンタジーはイメージの世界の中での出来事なんです。オオカミや魔女もイメージの象徴なのです。だから、そのイメージを乗り越えるためには最後にしっかりと殺しておく必要があるのです。これを現実の世界のことと混同してしまう人はイメージ能力が低い人なのでしょう。でも、今の子どもたちの多くはそのいずれも体験することが出来ない状況で生活しています。そのような子どもたちはテレビとゲームから出来合のイメージを得るばかりで、自分の心でイメージする能力を育てることが出来ません。だからすぐに妄想や幻想に縛られ、振り回されてしまうのです。そして、だから学力も低いし、訳の分からない事件を起こすのです。勉強時間を増やしても、イメージ能力が低い子は覚えることだけしか出来ません。理解するためにはイメージの働きが必要だからです。また、道徳教育を増やして“正しいイメージ”を与えようとしても、イメージ能力が低い子はそれを自分の問題として理解し、吸収することが出来ません。ただ、“大人はこういうものが好きなんだ”という知識が増えるだけです。ですから、道徳の時間を増やすより、(例えば)造形の時間を増やした方が間違いなく子どもは道徳的な理解を得ることが出来るのです。でも、そんなことをいう人はいません。(だから私は悲観的になってしまうのです。)子育てでも、ただ子育ての知識を得るだけでは子育てを変えることは出来ません。自分の生き方も同じです。お母さんがしっかりと自分のからだを使った活動に向き合ったり、物語をいっぱい体験することが必要なんです。そのためには毎日の生活で行っていることにしっかりと気持ちを向けることです。そして、丁寧に動くことです。“簡単に、手早く処理してしまおう”と作業しているだけの様な生活ではイメージ能力は育ちません。以下は、今ドイツに住んでいらっしゃる友人から頂いた詩です。私が愛おしいと思うもの遊びすぎて穴のあいたズボン泥だらけの茶色いパンツ底のすり減ったボロボロのズック子どもたちがたくさん遊んでいっぱい笑った証だから・・・子どもの汚れ物からもこんなに素敵なイメージを得ることも出来るのです。このようなイメージはどこからか自動的にやってくるものではありません。子どもに心を向けて自分の意志でイメージすることによってしか生まれてこないのです。また、何か表現につながる創造的な活動をやることです。造形でもからだでの学びでも絵画でも文章を書くことでも、今までやったことのない様な創造的な活動にチャレンジしてみて下さい。表現活動はイメージ能力を育ててくれます。そういうことは一見子育てとは関係がないようですが、イメージ能力が高くなれば子育ては格段と楽になるのです。見通しが付くようになるからです。そして些細なことに振り回されなくなります。
2008.07.07
コメント(7)
-
「イメージと人間」(“未来”はイメージが作る)
今日の話しは、昨日の茶々さんからのご質問ともつながってきます。私は“からだ”の事に興味を持って色々な本を読み、自分でも色々と試しています。からだのことは自分でも試すことが出来るので便利です。また、ワークなどで多くの人の実例を見ながらサンプリングもできます。それと、からだの働きと脳の働きとのつながりにも興味があり、脳の働きに関する本も色々と読んでいます。ちなみに、ここでひらがな表記で“からだ”と書いているのは、肉体のことではなく心や感覚なども含めた“生きて働いている丸ごとの身体”のことです。これは、私が始めたことではなく、からだ関係の人はみなつながりの中で生きている肉体を“からだ”とひらがな表記します。そのような学びの中で見えてきた事実が色々とあるのですが、その一つが“脳はからだをコントロールするために進化してきた”ということです。そして、活動が複雑になるに従ってその要求に応えるために脳も複雑になってきました。感情も、知性もその延長に目覚めてきました。つまり、感情や知性はそれだけが目覚めてきたのではなく、環境に対する適応に迫られた人間の活動の結果としてからだをコントロールするために進化してきた脳の一部が機能分化したものだと言うことです。そして、赤ちゃんはお母さんの胎内で肉体の進化を繰り返しますが、その実際的な機能は生まれた後からのからだの活動によって、ここでも進化を繰り返すように目覚めていきます。子どもはいきなり抽象的な思考など出来ないのです。まず、指を使い、ハイハイし、色々となめまくり、ピョンピョン跳びはね、走り回り、仲間と群れ、ケンカし、遊び、というようなからだの活動が次の段階の脳の機能を目覚めさせていくのです。ですから、人間は脳だけでは人間になりません。からだの活動が脳の機能を目覚めさせていくのです。勉強をいくら教えても、その勉強に使われる脳の機能はからだの活動によってしか目覚めないように出来ているのです。からだの活動がコンピュータとしての脳のOSを目覚めさせるのです。勉強で使われる脳の機能はそのOSの上で動くアプリケーションソフトのようなものです。この脳の成長過程は人間だけでなく、高等な哺乳類ではみな同じです。ですから、生まれた直後に親から離して、身体的な活動が出来ない状態で育ててしまうとちゃんとした成体になることが出来なくなります。肉体は大きくなっても、その動物固有の活動が出来なければその個体は生きていくことが出来ません。狩りが出来ないライオンは死ぬしかないのです。そして狩りのやり方もからだで学ぶものです。でも、人間の脳と、他の哺乳類の脳との決定的な違いは能動的にイメージする機能の有無です。人間はそのイメージを使って実際に活動しなくても脳の中でシミュレーションすることが出来ます。思考は脳の中のイメージを使ったシミュレーションなのです。でも、他の動物の脳にはそのような機能はありません。犬や猿でもイメージは持つことが出来ます。そのイメージがあるから指示や命令を理解することが出来るのです。“新聞を取ってきて”というような抽象的な指示だけで新聞を取ってくることが出来るためには“新聞をとってっくる事に対するイメージ”が形成されている必要があるのです。でも、そのイメージを自由に使って頭の中で色々とシミュレーションすることは出来ません。犬や猿にとってはイメージは複雑な行動を処理するための道具に過ぎないのです。人間は、いつの頃からかそのイメージを頭の中で自由に組み合わせて、まだ体験したこともないことまでシミュレーションすることが出来るようになったのです。つまり未来の予知ができるようになったのです。そこで時間という感覚が生まれました。犬や猿には過去はあっても未来はないのです。未来という観念、感覚を持っているのは人間だけなんです。実は、“未来”は人間の脳の中にしかないのです。そして人間は未来を変える能力を手に入れ、無限の可能性を手に入れました。でも、それと同時に未来に縛られるようにもなりました。犬や猿は明日のことなんか心配しないのです。明日屠殺される予定の豚だって今日の餌があれば満足して寝るのです。人間だけが何十年も後のことを心配して生きているのです。だからこそイメージに振り回されずに、イメージをコントロールする能力を身につけることが非常に大切なんです。何年も先のことを心配して、自殺などしてしまうのはおかしなことです。
2008.07.06
コメント(0)
-
「感情のコントロール」(イメージ力)
6月25日に、「感情との付き合い方」の中で“感情はコントロール出来ないのです”と書きましたが、今日はその感情のコントロールの仕方について書きます。矛盾していますか。矛盾していませんよ。だって、今日書くのは直接感情をコントロールする方法ではなく、間接的にコントロールする方法ですから。異常気象を直接コントロールすることは出来ません。でも、地球環境のバランスを保つことで大きな視点では異常気象をコントロールすることが出来ます。それと同じ方法です。みんな感情を直接コントロールしようとするから失敗するのです。怒りがこみ上げている時に、その怒りそのものを抑えようとしても無理なんです。でも、“上司に腹が立って殴ってやろうかと思ったけど、可愛い子どもや家族のことを考えてぐっとこらえた”というような話しはよく聞きますよね。ここでは感情のコントロールが成功しています。このメカニズムが理解出来ますか。つまり、イマジネーションの働きが感情の暴走を押さえているのです。実際、“こんなことをしたらどうなるのだろう”というイマジネーションが働くようになるだけでかなりの割合の事故や犯罪やイタズラが減るはずです。そして、このイメージする能力を使うことが出来れば感情をコントロールすることができます。怒ってしまった後で泣いている子どもを見て反省をするのではなく、怒る前に子どもの泣いている姿をイメージ出来たら怒りは違う感情に転換出来るのです。家族のためを思ってぐっと怒りを抑えたお父さんはその怒りを“くそ、負けるもんか、頑張るぞ”という別の感情に転換することで怒りを抑えることが出来たのです。つまり、実際には怒りの感情を押さえ込んだのではなく、イメージの働きで別の感情に転換したのです。このイメージ能力こそが感情をコントロールする能力なんです。感情で感情を抑え込むことは不可能ですが、他の感情に転換することで結果としてコントロールすることができるのです。そのためにイメージが必要なんです。でも、今子どもも大人もそのイメージ能力が非常に低下してしまっています。ですから、みんなメディアが作りだしたイメージに振り回されるばかりで自分の心でイメージを創り出すことができません。以前、ホームレスの人を殺した少年が、“ゴミを掃除しただけなのにつかまるとは思っていなかった”などと供述した事件がありました。この少年も自分の心でイメージすることが出来なかったのでしょう。また以前、本当の人間の死体を処理して標本のように見せる展覧会をやっていました。写真で見るとまるでリアルな作り物のように見えます。そこには生命の痕跡が消され、物としてのみ存在している肉体が展示されていました。(私は写真を見ただけで見には行っていません。)でも、私はついでにこの標本(人)が生きていた頃の写真と、履歴と、名前と、家族の写真も一緒に展示したらどうなるだろうか、とイメージしてしまいました。それでも多くの人が見に行ったでしょうか。人のからだは物ではありません。でもその本当の姿はイメージを通して見ることが出来ません。そして、そのイメージ能力が低下した人にとっては生きている人間すら“物”になってしまいます。だから簡単に殺して、簡単に分解して、ゴミ箱に捨てることが出来てしまうのです。“生命を大切にしよう”などといくら叫んでも生命は見ることも触れることも出来ません。“生命”はイメージの中にしか存在することが出来ないのです。ですから、そのイメージ能力が低下した人には“生命”にリアリティーがないのです。それは、勇気や希望も同じです。みんなイメージの世界の中にしか生きることが出来ない存在なのです。造形や表現の場でも子どもたちのイメージ能力の低下は深刻です。イメージ能力がないから全体や流れを理解することが出来ません。だからマニアルを欲しがるのです。でも、自由な造形や表現はマニアルでは処理出来ません。それで“わかんない”、“できない”、“せんせいやって”ということになります。また、人の言葉を理解することも出来ません。言葉から意味を抽出するためにはイメージ力が不可欠だからです。もともと言葉はイメージを伝えるためのものなんです。言葉はイメージなんです。また、イメージ力が弱くて全体や流れを見ることが出来ない子は論理的に考えることが出来ません。ですから当然学力も育ちません。お母さん達も同じです。虐待の増加の背景にはイメージ能力の低下があります。“やってしまってから後悔する”などという人はイメージ力が乏しいのです。また、イメージ力が弱い人はイメージに振り回されてしまいます。だから操作しやすいのです。そのため、“勉強しないと負け組になってしまう”というイメージを与えれば簡単に子どもを追い回して勉強を強制するようになります。そして、特定のイメージに固執してしまいやすいので自分や他の人などに対する偏見を持ちやすくなります。また、妄想にもとらわれやすくなります。じゃあどうして現代人はこれほどまでにイメージ能力が萎えてしまったのかと言うことです。文明は進歩してきましたが、このイメージ力に関する限り現代人は古代人や自然の中で素朴な生活をしている人たちには全くかないません。それはつまり、文明の進歩と共に心の中の世界がますます狭くなってきてしまっているということを意味しています。でも、このイメージ力が文明や文化を成長させてきたのだということを忘れてはいけないのです。人間はイメージ力を失ってしまったら退化するしかないのです。そして、どうしたらそのイメージ力を育てることが出来るのかと言うことです。ということで続きます。
2008.07.05
コメント(4)
-
「忘れてください」(知識の感覚化)
7月17日の「表現共育クラス」(茅ヶ崎)の体験日の時間は3:30~5:00です。最初、チラシの時間が間違っていたので訂正させて頂きます。これがそのチラシです。ご覧になってみて下さい。*******************************昨日のダージリンさんとのやりとりの中で以下のように書きましたが今日はこのことから思いついたことを書いてみます。ただし、ダージリンさんに対するご返事ということではありません。話しのきっかけとして昨日のコメントを引用させて頂きます。>森の声さんが、とても自然に子ども達に(特に小さな子どもや障害のある子にも)寄り添える理由が分かるような気がします。その子の視点に立ってみればいいだけのことなんですよね。特別な技術の問題ではありません。ただ、障害に対する知識は必要です。そのファクターを加味して視点を作るのです。赤が見えない子なら心の中で赤を消してみるのです。障害を持っている子だけでなく、普通の子に対してもまたお年寄りや異文化の人に対しても、その人のことを深く理解しようとしたら知識は必要です。実際、子育てで苦しんでいる人の話を聞くと子どもに対する無知が原因の場合も少なくないからです。ちなみに、子育てが苦しくなる要因としては以下のようなものが考えられます。・子どもに対する無知。・自分の感情のコントロールが出来ない。・過去のトラウマに支配されている。・コミュニケーション能力の不足。・想像力の欠如。・楽しいことを見つけるのが下手。ただし、これらはバラバラのものではなくお互いに密接につながっています。コミュニケーション能力が弱い人は感情のコントロールも苦手で、想像力も弱く、楽しいことを見つけるのも上手ではないというようにです。さらには、依存心も強いでしょう。また、この中にはありませんが“疲れやすい”というのも、感情のコントロールとつながっています。疲れやすいのは体力だけの問題ではないのです。ストレスが溜まりやすい人、疲れやすい人は呼吸が浅いです。そしてそれは多くの場合、防御の感情が胸や背中の筋肉を緊張させているからです。そして、手足は弛緩しています。ですから、冷え性の人が多いと思います。それで、今日書きたかったことは“知識は必要だ”ということの延長で、“知識は忘れてください”ということです。へ!・・・ という感じですか。“知識は必要です”と書いて、すぐに“知識は忘れてください”と書くのは変ですか。実は、確かに知識は必要なんですが、でも、それを覚えているだけでは何の意味もありません。知識に縛られてしまうばかりです。知識は自分の魂とつながる必要があるのです。でも、そのためには一度忘れる必要があるのです。もう少し具体的に説明すると知識が感覚とつながる必要があるのです。1mは100cmです。子どもはこれを覚えます。でも、覚えているだけの子どもは“長さという感覚”をまだ使うことはできません。ですから、造形などでも“箱もの”をちゃんと作ることが出来ません。九九も同じです。感覚とつながらないと実際には使えないのです。そして、感覚とつながれば想い出せなくても使えるのです。“自転車の乗り方”という本を読んでもそれだけでは自転車には乗れません。知識がからだとつながる必要があるからです。それは、知識が感覚化することで可能になるのです。そして、知識にこだわっていると知識が感覚化出来ないのです。知識を想い出しながら自転車の練習など出来ないのです。少し感覚がつかめるようになって来た時に、“あの言葉にはそういう意味があったのか”と知識の意味が分かるのです。“偏見”が手強いのも間違った知識や中途半端な知識が感覚化してしまっているからです。最初はただの知識だったものが感覚化して、生理的なレベルまで落ちてしまうとなかなか変えることができないのです。それは障害を持っている人や、外国の人や、病気の人や、子どもに対しても同じです。例えば、エイズの人とハグしてもエイズはうつりません。でも、エイズに対する怖い知識が感覚化してしまうと、頭では分かっていてもからだが言うことを聞かなくなってしまうのです。知識が感覚化すると言うことはそういうことです。「幼い子どもには自他の感覚があまりありません。現実と非現実の間の境もあまりありません。」知識としてはこういうことです。でも、これを覚えているだけでは子どもに寄り添うことはできません。子どもに関する知識で子どもを支配することになってしまいます。私は「気質」の講座もやっているのですが、気質も同じです。いくら知識をため込んでも感覚とつながらなければ知識に支配されるばかりです。そして、正しい知識を学ばなければ“偏見”につながってしまいます。偏った知識が感覚とつながった時に偏見が生まれるのです。(書きながら今の学校教育が怖くなってきました。)その自分の感覚が正しいのかどうかは相手との共鳴によって確認することが出来ます。障害に対する知識をいっぱい持っていても、実際に障害を持った子と共鳴出来なければその感覚は間違っています。子どもに関する知識をいっぱい学んでも、子どもと共鳴出来なければその感覚は間違っています。その場合は正しい知識を学び直すことと、相手との対話を繰り返しながらその相手と共鳴出来るように感覚の方を矯正していくことが必要になります。すると、自分で発見しながら自動的に知識も矯正されていきます。逆に言うと、本など読んだことがない人でもこの感覚のすりあわせが上手な人は、いっぱい本を読む人よりずっと正しい知識を知っています。でも、一般的には正しい知識を学ぶことから感覚育てをしていくのが一番確かだと思います。なぜなら、知識によって原理原則を学んでおくと、相手が変わっても色々と応用が効くからです。その点、体験だけから学んだ知識はその相手以外には応用が効かないことが多いのです。そして、知識がないので感覚の矯正が出来ないのです。現場一辺倒でやってきた人などにこのようなタイプの人が多いのではないでしょうか。
2008.07.04
コメント(13)
-
「子育てと相対性原理」(視点を変えよう)
昨日駅の方へ買い物で出かけました。そして、ヤマダ電機の前の通りを歩いていて気が付いたのです。その通りには人が大勢歩いていました。でも、私はその人を見ないで光を見たり、風を感じたり、自分のからだの感覚を感じたりしているのです。つまり、森の中を歩くように人混みを歩いているわけです。どうもこれは癖のようです。それで、昨日書いたように私は子どもの頃のことを想い出しても人間が出てこないで自然や本の事ばかりになってしまうのでしょう。それは幼児期に自然はいっぱいあったけど人間が少ない環境で育ったせいなのかも知れません。以前、友人に誘われて「アルプスの少女ハイジ」の映画を見た時、都会に連れて行かれたハイジが突然“風の音が聞こえる”と窓を開けるシーン(だったと思います)が強く心に響いたのもそのせいなのでしょう。自分でもやっと納得が出来ました。で、これはどういうことなのかなということを“認識”という視点で考えてみたのですが、どうも私はみんなが“図”だけを見ている時に“地”も一緒に見てしまうということのようです。つまり、みんなが島を見ている時に海も一緒に見えてしまうのです。雲を見ている時に空も見えてしまうのです。そして、変化するものを見ている時には、変化しないものも一緒に見えてしまうのです。つまり、“図”と“地”を分けて見ることが出来ないのです。子どもの頃から親からもずーっと、“お前の言っていることは意味が分からない”と言われ続けてきたのもそのせいでしょう。私は、他の人も私と同じものを見ていると思っていたので、相手が分からない理由が分からなかったのです。それで、議論で相手を説得することに夢中になりました。勝つか負けるかではなく、全く当たり前のことを否定する友人達を説得することで、自分に見えている世界の正しさを確認したかったのです。私は、明らかにつながっているいるものをバラバラのものとして考える考え方がどうしても理解出来なかったのです。確かに、つながっている物でも一度バラバラに分けて考えると考えやすくなります。ですから、一時的にそのような考え方をしてみることも時として大切です。でも、それは元のものと同じではありません。それと、元のものと同じだと考えてしまうとおかしなことになります。でも、みんなそれがなかなか分かっていないのです。例えば、みんなは“島と島は離れているから”というようなことを言います。でも、島は海でつながっています。だから私は、“いや、島と島はつながっているよ”と言います。でも、海が見えない人にはこの考えは理解出来ないのです。私はみんなにも海が見えていると思っていたのですが、どうもそうではなさそうだぞ、と気付いたのは高校生くらいになってからです。ある時はグループで話し合っていたのですが、全員から“君の考えは変だ”と言われて納得出来ず、その話し合いが終わった後でその中の一人の友人をつかまえて1時間くらい議論しました。そして、最後にその友人が“君の考えの方が正しいということが分かった”と言ってくれたのです。私は難しいことなんか言っていません。当たり前のことしか言っていません。その当たり前がどうして伝わらないのか、それが悔しかったのです。でも、見えていない人には“見えていない”ということが分かりません。だから説得するのが非常に困難なんです。一生水の中で暮らしている魚に、“水”の存在を説明するようなものです。物を上に投げ上げれば落ちてきます。これは当たり前のことです。でも、みんな投げ上げたものと、落ちてきた物を別々の物として考えているのです。自分が投げた物が落ちてきたのに、それが自分に当たると災害にあったかのように騒ぐのです。そしてたまたま上にいた人のせいにします。“あいつが投げたんだ”と・・・・。これが理解出来ません。私は大学は物理学科なのですが、そのきっかけは中学生の時にアインシュタインの「相対性原理」に出会ったことです。相対性原理的な考え方と私の考え方がぴったりと来たのです。それまではよく見えなかったものが、その相対性原理的な考え方を使うとなんと見通しよく見えるのか、それに驚いたのです。それで物理を勉強しようと思ったのです。みんなは電車が動いて駅が止まっていると思っています。これは常識なのでしょう。でも、アインシュタインは電車が止まっていて駅の方が動いていると考えても同じなんだよというのです。目から鱗です。ただし、これは宇宙規模で考えてくださいね。当然のことですが、日常生活規模ではこれは成り立ちません。日常生活規模での出来事を説明するのはニュートンの物理学の方です。そして、私は子育ての問題を考える時にも相対性理論的に考えます。動いていると思われているものを、その動いているものから見たら何がどう見えるのだろうか。AからBを見ている時に、これをBからAを見たらどのように見えるのだろうか。成長が止まってしまった大人から成長しつつある子どもを見るのが一般的ですが、これを成長しつつある子どもから成長が止まってしまった大人を見たらどのように見えるのだろうか。お母さんに怒鳴られている子どもの目には怒鳴っているお母さんはどのように見えているのだろうか。また、日常的には一分単位で見ている物を一時間単位、日単位、もっと言えば年単位、万年単位でで見たらどう見えるのだろうか。子どもの日常を子どもの一生という視点で見たらどう見えるのだろうか。何十年後かに大人になった子どもが、お母さんの今の子育てを見たらどう思うのか。木の生長も一見止まっているように見えますが、これを100年を5分に編集したビデオで見たら、木も動物と同じように動いている姿を見ることが出来るでしょう。などなど、このように考えるのです。分かりにくい言い方をすれば座標軸を固定せず、視点とスケールを自在に転換するということです。みなさんもやってみませんか。そうするとそれまで見えなかったものが見えるようになりますよ。
2008.07.03
コメント(9)
-
「私達の世界」(子どもにとって仲間とは)
昨日は、大人は“私の世界”を生きていますが、子どもたちは“私達の世界”を生きているのです。ですから、“私達の世界”を持つことができない子は非常に辛いことになります。と書きました。でも、書いた後で私自身にとっての“私達の世界”は何だったのだろうかと考えてしまいました。なぜなら私には小学生時代までの友達の記憶がほとんど残っていないからです。(中学、高校の時の友達の記憶もあいまいです。)私は幼稚園の年中まで鎌倉にいて引っ越し、小2まで東京の葛飾にいて、さらに小3にまた鎌倉の同じ家に戻ってきました。その鎌倉の家は裏が山で海までは歩いて5,6分のところで自然はいっぱいだったのですが、家の周囲に子どもはあまりいませんでした。隣の家と前の家には似たような年齢の子がいましたがあまり遊んだ記憶はありません。何となく気が合わなかったのです。子どもの群れもありませんでした。2才下の弟がいたので弟と遊ぶことが多かったのかも知れませんが、なぜかいつも一人で遊んでいた記憶しかありません。葛飾に引っ越した時にその子どもの多さに驚きました。子どもの群れを見て驚きました。でも、それまで一人で遊んでいたのでなかなか群れには入ることができません。いまでも、どこかの陰から大勢でベーゴマをやっている子どもたちをジーッと見ていた記憶が残っています。それでも、次第に地域の群れの中で遊ぶようになりました。でも、その仲間の子達のことを全く想い出せません。中学生のリーダー的なお兄ちゃんのことはちょっと覚えていますが、他にどんな子がいたのか全く記憶がないのです。そのお兄ちゃんも、その子の家に行くといつもおばちゃんがバター飴をくれたので覚えているだけなのかも知れません。どうも幼児期に仲間体験がなかったせいなのか、感覚的に友達と遊んでいても“私達の世界”に入ることができないのです。仲間と遊んでいなかったわけではありません。学校から帰ってきたら毎日のように友達と遊んでいました。でも、“私達の世界”の記憶がないのです。遊びの記憶はあっても友達のことを想い出せないのです。小学校の時のクラスメイトのことすらよく覚えていないのです。それで、私には“私達の世界”がなかったのかな、とちょっと思ったのですが、すぐにあることに気付きました。私には人間の友達の記憶はあまりないのですが、“自然”の記憶と“本の中で出会った仲間”の記憶はいっぱい残っているのです。小さい時に庭に植えていたイチゴの色と匂いははっきりと覚えています。裏山に登って大きな木の根本に座っていた時の感覚も覚えています。海で群れになって泳ぐ魚をずーっと見ていたことも覚えています。イチジクの木に集まってきていたカミキリムシのことも、庭の地面をモコモコやりながら走るモグラのことも良く覚えています。また、「西遊記」の孫悟空や「長靴下のピッピ」のピッピや、ドリトル先生、幸福な王子、などなどに出てきた登場人物のことも良く覚えています。つまり、どうも私にとっては自然や本の中の世界が“私達の世界”だったようなのです。実際、私は本ばかり読んでいました。“私達の世界”が“自然”と“本の中”にあったのですから、私は自然と本があれば他には何にもいらなかったのです。そしてその“私達の世界”に浸っていることが幸せだったのです。そして、その“仲間感覚”はいまでもそのままです。子どもの時に身につけた仲間感覚はそう簡単に変わらないようです。と、ここまで考えて、“こういう私達の世界もあるんだ”ということに気付きました。それもそれでOKなんだ、ということです。“自然”とか“本”という私の仲間達は大きな世界とつながっています。その仲間は私を過去にも未来にも地球の果てにも、宇宙の果てにさえ連れて行ってくれます。また、大勢の人間の仲間と出会い、様々な活動をするきっかけにもなってくれます。そして、一生仲間で居続けることが出来ます。でも、ゲームや携帯やネットの中だけに“仲間の世界”を求めている子どもたちはどうなるのでしょうか。広い世界へ出ていくことが出来るのでしょうか。そして、一生仲間でいることができるのでしょうか。
2008.07.02
コメント(6)
-
「子どもが幸せを感じる時」(幸せのセンサー)
昨日、“子どもは守るものではなく、育てるものです”と書きました。子どもへの害が社会の外から来るものならその害から子どもを守ることは必要です。そして、子どもを守ることも出来ます。でも今、ほとんどの“子どもへの害”は社会の内側からやってくるのです。それは友達であり、近所の人であり、時として親であり、先生なのです。それに、毎日の食べ物や、テレビや、ゲームや、自動車も子どもに害を及ぼしています。そのような内側からやってくるものから身を守ろうとすれば、疑心暗鬼になって、自分の周りに壁を作るしかありません。でも、そうすると子どもが社会のつながりの中で生きることが出来なくなります。社会との楽しい想い出を作ることが出来なくなります。社会との関わりを通して色々なことを学ぶことが出来なくなります。そして、人を信じることが出来なくなります。そして、事件が増えます。今、私達の社会はそのような悪循環にはまってしまっているのです。幼稚園などでは乱暴な子、イタズラ坊主が叱られて、排除されます。先生がそのような態度を取ると子どもたちも真似をしてその子を排除しようとします。お母さん達も“○○ちゃんには近付かないように”と子どもに言うようになります。公園グループや共同保育などの場でも同じことが起きています。そして、確かにその問題児が排除されてしまえば平和は戻ります。でも、それは子どもたちがその子との関わりから大切なことを学ぶきっかけを失ってしまったことになります。そして、偏見を植え付けられたことになります。私は乱暴な子、イタズラ坊主が好きです。乱暴をする子、いたずらをする子にはそれだけの理由があるのです。だから、ただ否定しているだけではもっと行動がエスカレートしていきます。私はそのような子を守り、そのような子を中心に遊びを展開します。すると、面白いことが起きるのです。みんながその子を受けいれ始めるのです。じゃあ、その乱暴やイタズラは放っておいていいのかというと、そういうことではありません。はっきりと“ダメ”、“ヤメナサイ”と言います。でも、その子は私が仲間であることを知っています。そして、自分のためを思って言ってくれていることを感じています。だから反発しないのです。(素直に言うことを聞くわけでもありませんけどね)そんな時、排除しようとするからもっと問題児になってしまうのです。そして、そのような経過を通して子どもたちはトラブルとの向き合い方を学んでいきます。人を信じることを学んでいきます。そして、その問題児も仲間とつながることが出来るようになり、次第に問題児ではなくなっていきます。ただし、親が子どもに害を与えている時にはなかなか困難なことになります。そして、ヒステリックにわが子だけを守ろうとしている親に限って子どもに害を与えていることがよくあるのです。友人の先生から聞いたことですが、ある先生が一人の生徒を叱ったら親が怒鳴り込んできたそうです。そして、“先生の虐待だ、イジメだ”と先生達を糾弾したそうです。でも、その子は親から虐待を受けていてしょっちゅうからだにアザがあったそうです。それで、一昨日のグーテンタークさんからの以下のようなコメントに話しをつなげていきます。>だから、親は“幸せの道を探すためのセンサー”の感度を高めて上げる必要があるのです。これは、子どもが元気になる方向、笑顔になる方向に親がそっと向けてあげるということなのでしょうか?もう少し詳しく説明していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。まず、子どもを自分の所有物であるかのような考え方をやめてください。“私の子ども”ではありません。“私達の子ども”です。子どもの友達も“私達の子ども”です。実際、子どもと子どもは分離出来ないのです。そして分離してはいけないのです。子どもはつながりの中で生きているのだし、つながりのなかで成長していくからです。そして、子どもに“私の幸せ”ではなく、“私達の幸せ”の体験をさせてあげて下さい。みんなの笑顔の中に自分の笑顔がある時、子どもは幸せを体験します。子どもは自分だけでは幸せになれないのです。親は“わが子だけ”を幸せにしようとしますが、子どもにとってはそれは幸せではないのです。そういう点で子どもは大人より神様に近いのです。(大人は“私の世界”を生きていますが、子どもたちは“私達の世界”を生きているのです。ですから、“私達の世界”を持つことができない子は非常に辛いことになります。)仲間の笑顔を一緒に喜ぶことが出来る子は幸せな子どもです。そして、そういう子どもは大人たちが“わが子だけ”という考え方を止めて“私達の子ども”という考え方で子どもに向き合う時に育っていきます。そのような体験をいっぱいして育った子は感度の言い“幸せのセンサー”を持つことが出来るようになるでしょう。
2008.07.01
コメント(8)
全29件 (29件中 1-29件目)
1
-
-

- 軽度発達障害と向き合おう!
- 障害書かされ自殺、遺族敗訴 社会福…
- (2025-11-25 16:15:08)
-
-
-

- 高校生活~生徒の立場から・親の立場…
- 大宮科学技術高校
- (2025-10-20 13:16:42)
-
-
-

- おすすめの絵本、教えてね♪
- 【自分で着る!】ペネロペ ひとりで…
- (2025-11-26 07:00:04)
-







