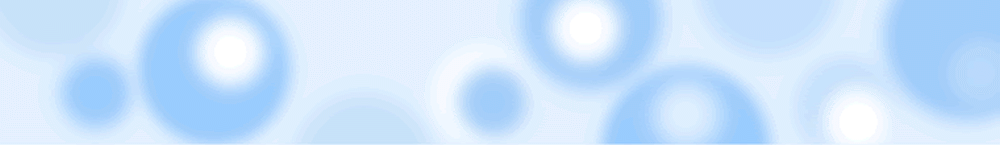2019年12月の記事
全9件 (9件中 1-9件目)
1
-
★早い!早すぎる‥と思うのは私だけ!?
一通のエアーメイルが届いた。私のところにエアーメイルが届くといったら、アメリカに住む親友からしか、有り得ない。開封してみると「あけましておめでとうございます」の文字だった。1日早い賀状だった。今年は思いがけず彼女が日本に来たので、会うことができた。何十年振りの再会だっただろうか?私の為に限られた日本滞在時間の中の、貴重な一日を提供してくれた。ヨガとオカリナが有る日だったので、彼女にも飛び入り参加してもらった。どちらも町内でやっている行事なので、先生方も快く参加を許して貰えた。だから、彼女に会っている時間も有効に使えたのである。彼女も、普段通りの私と会えて、嬉しかったと言ってくれた。これが会社に行っていたら、絶対出来ない二人での経験である。今時海外なんて、すぐ行けるじゃん~と思う人ばかりだろうけど、私は国内の移動すら、最小限しかしない。出来れば、どこにも行かずに過ごしたい人間である。だから彼女から来てくれなければ、会えることは無いのだ。心は一番近くに居る人だけど、一番遠いところに住んでいる親友である。今年の最期の締めくくりで、思いがけない手紙をもらうことになった。それだけで、今年1年が宝物になった。振り返ってみると、色々有った1年‥出会いも多かった。占いとかレイキマスターとかやっているから、普通の人より出会いは多いと思うけれど‥。でも、それだけでなく出会いが多かったと思う。しかも、良い出会いが多かった。考えさせられる1年でも有った。体調を無視して感情で動こうとして、ガツンと警告をもらったりした。指導する立場で、何をやってるのか!というお叱りだと感じた。「病気は気づき」‥そうセミナーで講義している身の私。だからこそ真摯に受け止めて反省し、前進していかなければならない。1年がアッという間に終わってしまった。この感じって、毎年味わうことになるのだろうか?仕事をしている時よりも、びっくりするほど早く過ぎていった今年。でも時間の流れは緩やかだった。たっぷり有る時間の中なのに、一日が過ぎ去るスピードが速い。なんだぁ?この相反するものが同居している状態は??仕事を辞めた今のほうが、とてつもなく有意義に過ごすことができている。そんな世界が来るなんて、考えてもいなかった。でもそれは、しっかり仕事をしてきたからこそのご褒美だと思っている。3つの会社を、トータル42年間働いてきた。それが有っての、今の安らぎのひとときだと思うのである。私の生活様式は、仕事をしている時と比べると、ガラッと変わった。42年間と、全然違う今の私の一日。でも、とても良い具合に一日が回っている。良いも悪いも、経験すること自体が宝だと思っているから、どんな時も、前向きに生きていける。色々なことが起こってきても、乗り越えて生きていけるのは、私も見守っていてくださる宇宙?‥大いなる存在のお蔭?私にとって宇宙って、故郷のようなもので、結構身近に感じるもの‥。「なに言ってるの?この人」と思われるだろうけどねぇ‥。実家で暮らしている私は、ここが故郷なんだけど、魂の故郷は、どういうわけだか宇宙だと感じているのである。感じることって、中々言葉に表せられないよね?宇宙のことを考えると、心や体が震えるような感動が、そこに有る。ねぇ、みんな‥沢山経験を積もうよ!魂に刻む経験というのが分かりにくかったら、DNAに刻む経験をしよう!←(もっと分かりにくいって!‥ゴメン)だから色々有ったけど、良い1年だったと思う。ブログを読んでくださっている皆さんにも感謝している。明日は令和2年、みんなで素敵な1年を迎えましょう~。
2019年12月31日
コメント(12)
-
★必要だけど多過ぎない?(笑)
「私ってカバン類が沢山あるのよね。しかも普通使うカバンだけでなく、何処にも旅行に行かないのに、キャリーバックが一杯有る!」(笑)私が何処かに行きたいと思う時というのは、先週芦屋へ行ったように、学びたいことが出来た時だ。いつも思うんだけど、肝心なことを学ぼうとすると、だいたいが東京か大阪なんだよね。私はこれを「名古屋飛ばし」と言っている。(トホホッ)なんで名古屋には、学びが根付かないんだろうねぇ‥。学ぶことにお金を使わないのが、名古屋人なのかも!‥そうなのかぁ?まぁ、東京や大阪以外の他県の人に比べれば、名古屋でも結構学べるじゃん~と言われたりするけれど‥。私が学びたいと思う内容が、特殊なのかもしれないけどね。今回も芦屋に行く前に一泊の準備をするのだが、A4やB5サイズのテキスト類を、数冊持って行くので、キャリーバックの出番になる。衣類は嵩張っても軽いけれど、テキスト類は束になったら重くなる。場所も取れば重くもなるので、やっぱりキャリーバックが必要だ。なので、どのキャリーバックで行こうかと見渡して、(何処かに行くことが殆ど無いのに、ホントにキャリーバック多いなぁ‥)と溜め息をついてしまった。一生の内、マジで何回使うのだろうか?「使用頻度を考えると、ぜったい高くつく買い物だよなぁ‥」見渡して、自分ながら呆れてしまった。私のカバン選びは、実用的であるか否かだ。そういう目で、ついついお店の中のカバンをキョロキョロと見る。そして自分が持っている物より、更に使い勝手が良さそうなものを目にすると、ついつい買ってしまう。だから買ったカバンを、全部使いこなしているか?と聞かれたら、殆ど使わずに終わってしまうカバンも、結構有ったりする。なのでカバン類が可愛そうだなぁ‥と思うのだが、やっぱり買ってしまうのだ。これって、何処かに行きたいことの表れになる??学び以外で何処にも行きたくないはずなのだけど、心のもっと奥底では、何処かに行ってみたいと思っているとか‥。そういうことなのか?まぁ、一応考えてみたけれど、やっぱり学び以外の旅行は面倒臭い。母が生きていた時には、旅行好きの母のために計画をたてて、出掛けはしたけどね。だから誰かの為なら行くかもしれないけど、だからといって、こんなにキャリーバックはいらないだろう。なんでこんなに沢山買ったかなぁ‥。(苦笑)でも女性はカバンが好きだよね?カバンは、洋服や靴同様に沢山買いたくなってしまう。よく弟に「手は2本しかないよ。一度に持てるバッグ類は幾つ?」と聞かれてしまうけど‥、わかっちゃいるけどねぇ。行く先を考えて、どのカバンを持っていこうかと考えるのも、楽しい作業である。贅沢かもしれないが、こんな幸せも有ってもいいと思う。この間、カバンのレンタルが有るとテレビで見てブログにも書いたけど、行先によってカバンを変えたいという気持ちは、とてもよく分かる。私の場合、高級なお店へ行くわけでないけれど、ヨガにはこのカバンを使うとか、バレトンにはこのカバンとか、オカリナと楽譜を入れて行くのは、このカバン‥という感じかな。やっぱりカバンは好き!この間、タロットに私のカバン好きってどうよ‥と聞いてみたら、このままで楽しそうだからいいんじゃない?と、カードが答えてきた。違う答えが出ると思っていたけど、カードは今の私を肯定してきた。なので暫くこのままでいくことになるだろう。今日は出掛けないので、カバン類はお休み。すぐに出番がくるから宜しく!という感じかな?(笑)
2019年12月28日
コメント(12)
-
★楽しい時間は何故早い?(笑)
土日に芦屋へ行ってきた。芦屋市民会館で2日間、セミナーが有ったからだ。私の師である、現代レイキの創始者土居先生のセミナーに参加してきた。いつものように奥様もいらっしゃったので、お二人共にお会いできた。夢のような時間だった。お会いしたことのあるレイキ仲間もいたのだが、なにせ、全世界から受講に来るセミナーなので、初めてお会いする仲間も、勿論多数いらっしゃった。土居先生は私より丁度20歳年上なので、ここ数年色々なことを縮小されつつある。海外へ行かれることを、数年前から止められているし、交流会はこの12月‥先々週で、止められてしまった。最後の交流会は、80数名が国内外から集まってこられたようである。海外は、海外の生徒さんから来て欲しいと依頼があるから出掛けるのだが、国内でのセミナーだけはまだ続けていって頂けるようなので、海外の生徒さんも、土居先生にお会いする機会は残っている。交流会を止められるとホームページで知った時は、胸がざわついてしまった。なのですぐに再受講を申し込んだというわけだ。土居先生には、会える時に会っておきたい。セミナーの言葉も、一字一句聞き漏らさないで自分のものにしたい。悔いのないように‥。夢のような二日間であり、内容が濃いので慌ただしい二日間でも有った。芦屋市民会館内に食堂があって、今回初めてそこで昼食を取った。いつもは、会館の外に出てお昼休憩をしていたのだが、今回空模様が怪しかったので、会館内で休憩を取ることにしたのだ。すると数名の受講生と共に先生もいらっしゃって、思いの外、お昼をご一緒することが出来たのだ。昔は、奥様がお弁当を作っていらっしゃっていて、館内でお二人が楽しそうに食べていらっしゃったのだが、どうやらいつ頃からか、この食堂を使われるようになったようだ。私も二日間共にお昼休憩を、ご夫妻とご一緒出来て幸せだった。どうやら食に関しては、お二人の好みが違うということも、今回知ることが出来た。まぁ、特に必要のない情報なんだけどね‥。懇親会も、前は土日の二日間共に行なっていたのだが、今は土曜の夜だけのようだ。私もだが、歳を取ったから体力に問題があるからだろうね。だから有れば参加したと思うのだが、それから新幹線に乗って帰ってくることを考えると、やっぱり日曜の懇親会は無くてよかったのかもしれない。土曜の懇親会では、先生を囲んで仲間と盛り上がった。やっぱり同じ方向を向いている仲間は良いよね!説明無しで、相手の懐奥深くまで入っていける。今回近畿地方出身の受講生が多かったのだが、愛知出身の私や石川と富山からの受講生もあったので、中部地区も負けてはいなかった。(いや、負けてるか‥笑)北陸地方の人たちは、新幹線が途中止まってしまったので、不本意ながら遅れてやってきての受講になったが、海外からも参加者が有った。石川の人が通訳できるので、きっと海外からの人たちは助かっただろうと思う。同時通訳というものを、私は初めて真近で体験したのだが、それはそれは‥スゴイなぁ~の一言だったなぁ‥。今や土居先生が認定したマスター仲間は、国内1100人以上、国外960人以上というから、その内、国外のほうが上回るのではないかと思う。日本発祥のレイキなのだから、日本の普及が遅れているのは寂しいものである。私が認定したマスターも居るわけだから、マスター仲間の数は、その何十倍何百倍と計り知れないが、それでもきっと海外のほうが普及しているだろう。病院関係にまで浸透しているのは、海外のほうが圧倒的である。私のところの生徒さんも医療関係者は居るのだが、病院自体がレイキを必要としているかというと、中々難しいものがある。ただ嬉しいことに、今年は縁が有って病院関係者‥、特に経営に近いところに居る人たちに、レイキを教えることができた。日本も海外に負けないポジションに、レイキが普及していって欲しいものだ。今回も沢山の刺激を得て、日常生活に戻ってきた。これを生徒さんを含む私の周りの人たちに、多く還元していきたいと思っている。芦屋でのセミナー再受講は、素敵な1年の締めくくりになった。なのでまた、素敵な新年が迎えられそうである。
2019年12月24日
コメント(12)
-
★こんなことろにも筋肉?声帯筋
昔、20代前半だったと思うのだが、アマチュアの合唱団に入っていたことがあった。あの団体を、どうやって調べて入ったのだろうか?その合唱団の存在をどうやって知ったのか、全然思い出せない。御園座の近くにレッスン場があり、30人以上の人たちが在籍していたように思う。一人前に中日劇場で、公演もした。数少ない友達にも、聞きに来てもらったと思う。でも一番覚えているのは、レッスン後にみんなで居酒屋へ行ったことである。(笑)合唱団だったので、当時たばこを吸うのが当たり前の時代に、誰もたばこを吸っていなかった。喉をとても大事にしていたのである。でも、じゃぁお酒は?‥なんか、そこは良いみたい。(笑)陽気なお酒で、レッスン後なのでその居酒屋にとっても遅い時間。他のお客様がちらほら状態なので、誰からともなくレッスン曲を歌い始める。するとそのメロディーに合わせて、他のパートの人たちが自分のパートを歌い始め、まるでその場が、一瞬にしてミニコンサートのようになる。今考えると、よくその居酒屋さんがそれを許していたなぁ‥と思う。合唱に興味が無い人たちにとって、迷惑でしかないからだ。居酒屋の大将も合唱団(?)だったという記憶は無いので、おおらかな時代だったんだと思う。私はソプラノ担当だった。その合唱団にはソロを歌う人がいたのだが、これがうっとりする声の持ち主で、私はその声に憧れていた。今の「アナと雪の女王2」を歌うシンデレラ歌姫のように、高い音域が簡単に出て、しかも音を持続させられる‥。あのようになりたいと思うのだが、まぁ‥難しいよねぇ。高望みはしないのだが、せめて普通にソプラノを出したいと思っても、レッスンしているわけではないので、高音域が出なくなっている。だからといって、アルトの領域の声が出るわけでないから、結局何も歌えない状態だ。(泣)しかも肺活量も減っているので、一定の音量を保つことができない。う~ん、イヤんなっちゃうなぁ~。こんなことを考えたのは、前回の「チコちゃんに叱られる」で取り扱っていた裏声についてであった。「裏声はなぜ出る?」という問いかけに、「喉が諦めるから‥」という答え‥禅問答?(笑)いつも思うのだが、答えが突飛過ぎて、私たち凡人にはピンとこない。しっかり解説をしてもらわないと、その答えに辿り着けない。(苦笑)どうやら普通の高い声は、声帯筋の張り具合で出るのだが、裏声は声帯筋の厚さに関係しているようなのだ。地声の限界がくると、声帯筋は「これ以上引っ張られたら壊れる!」と悲鳴をあげるらしい。なので声帯は限界になると、声帯の厚さを保つことを諦めてしまう。その結果、声帯が合わさる面積も小さくなって、裏声が出るという。ここで私が注目したのが、声帯筋。やっぱり筋肉というか筋力が関係しているんだよねぇ‥。握力が弱くなった、足腰に力が入らなくなった、荷物が沢山持てなくなった‥老いは、そんなところだけではない。筋力が衰えていくのは、体のあちこちで起きているのである。だから、体のあらゆる面を鍛え上げなければならないのだ。カラオケで鍛えるのもいいかもね?鍛えるというと構えてしまって大変だと思ってしまうが、やっぱり楽しく知らない内に鍛えられていた!というのが理想だ。目標は若き日の自分の声の高さと音量だ。楽しく鍛えるをモットーに、声を出していきたいと思う。
2019年12月20日
コメント(12)
-
★小さな幸せが家庭に有る
「温泉は好きだけど、時間と労力を考えるとねぇ‥。」というわけで、私はスーパー銭湯で満足している。今時のスーパー銭湯は、様々な工夫をしている。それぞれの風呂の温度も変えていて、水風呂やぬるい湯や熱い湯など、色々取り揃えているのは、いまや当たり前である。最近のスーパー銭湯は、炭酸風呂が普通に有る。それ以外にも濁り湯とかジェットバスとか打たせ湯とか、沢山の工夫が施されている。その中に日替わり湯として、薬湯とかショウガ湯とか美肌湯とか、色々な成分を入れた湯船も用意されている。日替わり湯は、入浴剤を使うことによって、今では家でも味わえる。様々な効用の入浴剤が、売られている。色とか香りとか効能とかを追求する会社が沢山あって、選び放題である。その中で、株式会社バスクリンは大手の会社。「カンブリア宮殿」では、バスクリンの会社が、世界一売れている入浴剤と認められ、ギネス世界記録に認定された話しから番組は始まった。株式会社バスクリンは、粉末タイプのバスクリンの売り上げが53億円。年間販売数が1,300万個にもおよぶ。日本の風呂が銭湯から家庭へと広がっていったことで、バスクリンは成長していった。世界自然遺産シリーズが、126種類も有るって知っていた?凄い数だねぇ‥。それと日本の名湯シリーズを、1986年に発売したようで、今では17ヶ所の名湯を商品化したという。その商品の箱には「共同企画」という言葉が入っている。ということは、それぞれの名湯と一緒に開発したことになる。では、バスクリンのことをライバル視しなかったのだろうか?バスクリン社長の古賀和則さん(65歳)は、最初それを売り出すのが大変だったと言われる。名湯の人たちは、当初自分たちの温泉地の成分が商品化されるのを、良い顔をしなかったのだ。これが各家庭で簡単に楽しめるようになってしまうと、遠いところまで足を伸ばさないようになるのではないか?という、懸念が有ったに違いない。その考えを変えていった営業マンは、苦労が多かっただろう。でも今ではそれがなんと!真逆の反応なんである。名の知れた色々な温泉地の人たちのほうから、古賀社長に挨拶をするのである。どうやら今では、バスクリンが選んだ温泉地の一つということで、温泉地のほうのインパクトが強くなるようだ。だから自分の温泉地のお湯も、バスクリンに使ってもらおうという、逆転状態になったようなのだ。古賀社長は言う。「一般家庭で入浴剤を使ってもらい、本物の名湯へ行きたいという気持ちを膨らませてもらう。私たちは、その橋渡しをさせてもらっている。」‥と。私はバスクリンの恩恵に与っている。色と匂いと効能と、皆さんはどれを重点的に考えて買っているだろうか?多分効能を一番に考える人が多いのではないだろうか?でも私は効能はどうでもよくて、色と匂いが重要なんだなぁ‥。色は一定の色が良いというわけでなく、目に楽しめるように、毎日違った色で楽しむ感じで使っている。匂いは、嫌いな匂いでなければ気にならない。嫌いな匂いは、甘ったるい匂いとか森林の匂いなので、それは避けて買っている。まぁ、私の場合温泉地の人が最初に懸念したような、バスクリンで済ませてしまっている人間なのだが、これがきっかけで温泉地に足を運ぶ人も、きっと居るだろうと思う。なにはともあれ、私はバスクリンには感謝している。毎日プラスアルファーの幸せを頂いているからだ。幸せを、ありがとう。
2019年12月17日
コメント(10)
-
★ルームシューズでなく介護シューズ
高齢者の転倒による救急搬送は、平成28年東京消防庁の発表によると、5万人以上で、平成29年厚生労働省の発表によると、全国での死者が8千人以上。‥って、結構な数字だよねこのデータ。転倒事故は、意外に家の中で起こることが多い。私の知り合いの意見の一つに、家の中までバリアフリーにすると、それに慣れてしまうから外でも転倒しやすくなってしまうと言うが、私はその考えには反対である。家ってリラックスする場所だよね?足の運び方のことまでも考えて、家の中を歩いていないよね?家の中では、油断して当たり前だと思うのである。だから家では、少しでも転倒のリスクを減らしたほうが良いと思う。なので、バリアフリーにするのが理想だが、現時点でバリアフリーにするというのは、ハードルが高い構想である。でも、出来る範囲で理想に近づけたいとは思っている。「逆転人生」では、中小企業の社長が、介護シューズの開発で、倒産を免れてきた経緯を話していた。介護シューズを作ったのは、香川県さぬき市の小さな町工場の社長、十河(とごう)孝男(当時の社長)72歳だった。1989年‥30年前に、小さな縫製会社を営んでいたのだが、仕事は大手の製品の製造を請け負っていた。その頃はバブル絶頂期なので、仕事は順調よくいっていた。問題は、バブル崩壊後である。1992年に大手企業から受注減とコストダウンを言い渡された。海外からの安い製品が、簡単に手に入ってしまうからだった。言われるままにコストダウンした品物を持っていくと、「こんな物しか作れないのか!」と、大手企業の担当者から罵られる十河社長。担当者が変わっただけで、自分の会社の業績を左右されてしまうなんて、大手企業担当者の、あまりに大きな影響力に、言葉を失ってしまう。中小企業で大手企業の下請けをしていると、大手企業の方針一つで、下請けは簡単に切られてしまう。一蓮托生じゃぁ無いんだよねぇ‥信頼関係なんて無いんだよなぁ‥。でも、そこに社長を別の方向に向かわせる友人の一言があった。これが苦悩の始まりであり、また倒産を免れた一言でもあった。その友人は、高齢者施設の園長の石川憲さんで、施設のお年寄りの転倒事故が相次いでいるので、年寄りが転ばない靴が作れないか?というものだった。今から25年位前には、介護シューズそのものが無かった時代。これは会社が生き残れる道ではないか!と社長は考え、独自ブランドを立ち上げる決意をする。その頃の介護施設では、スリッパかサンダルだったらしい。それは、着脱しやすいから‥という理由だった。それで社長が大手企業の下請けで扱っていたルームシューズを改善して、それを友人に渡し、お年寄りに試し履きをしてもらった。ところがこれが全く不評で、一度そのルームシューズを履いたら、もう二度と履かないと言って、突っ返されてしまったという。社長は慌ててすぐにその施設に行き、靴を履くことの問題点を、直接お年寄りに聞いて回ったところ、いくつもの不満点が出てきてしまった。靴が重いから足が上がらない‥とか、床が滑って転びそうになってしまい怖い‥とか言う声だった。どうやら社長はルームシューズの延長線で介護シューズを考えていたのだが、根本的に、それでは駄目だということを思い知らされる。社長曰く、今思えばルームシューズを改良するという発想自体が、浅はかだったと告白‥つまりは、大手企業に依存してきた現実を、思い知らされたわけである。大手企業からは、言われるままの商品を作っていただけで、商品を改良して、もっと良い物を作ろうという思考回路が無かったのだ。やっぱりルームシューズでは駄目だということで、靴での改良を考えるのだが、靴作りのノウハウが全く無かった社長は、そこから寝る暇を惜しんで、介護シューズ作りに没頭したのだった。逆転人生になるまでは、ここからも幾つもの試練があった。会社内での亀裂や、新商品の売り込みの仕方の安易さ等々‥。でも、だからこそ倒産を免れた中小企業の物語。やっぱり苦労してこそ逆転人生が待っていると、感じる話しだった。
2019年12月13日
コメント(12)
-
★それは病気でなく個性
NHKの「フロフェッショナル」という番組で扱っていたのだが、今の私が知るのにタイムリーなお話しだった。10月の終わりに放送されたものである。約1ヶ月半たってここに書くには、それなりの理由がある。つまりはその間、ずーっとその件に携わっていて、先に見てしまうのは私の中で、どうなんだろう?と思ったからだった。あっ、だからビデオなんだよね。(そんなん誰でも分かるやん、笑)神様は不思議とタイムリーに物事を進められる。いつもびっくりするぐらい、私に必要なことを必要な時に教えてくれる。なので私は勝手に「神様に愛されている」と思っている。(笑)私は四柱推命による占い師をしているのだが、これは占いにも通じる話しだと思ったのだ。扱った内容は「発達障害」というものである。何故それが占いに通じるのかというと、私たちは色々な星を持って生まれてくるのだが、その色々な星を均等に持って生まれてくるわけでない。むしろ、均等に持って生まれてくるほうが珍しいと言ってもいいほどだ。均等に持って生まれてくると、バランスの良い性格になるし、色々な星を持っているからこそ、この世の中を生き抜いていくことが、楽に出来る。というのも、世の中を渡り歩いていける道具を、色々手に入れている状態だからだ。人間だからどんな人でも悩むだろうが、その悩みを解決に導く道具を手に入れているので、悩みから抜け出しやすいのである。私もそうなのだが、星は揃っていない。だからこそ、人一倍悩んできた。んっ?君ぃ、信じてる?(笑)多分そういう人が占いを頼るし、占いをする側になるのだろうと思う。番組では、小、中学校の15人に一人が、発達障害の可能性が有ると言っていた。信州大学医学部付属病院の本田さんは、「どこまでを障害と見なすのか‥どこからは普通と見なすのか‥」精神科医の本田さんが、30年間、すーっと考えていることだと言う。そして、本田さんの仕事の流儀は、「治療しない」だった。「僕は基本的に自分がやっているのは、診療であって治療ではないと思っているんです。」‥成るほど。今の世の中が‥特に日本においてであるが‥、集団意識を大切にして、個性を美徳としない傾向にある。はみ出してしまう個性を、時には潰そうとしてしまう‥それが日本。人と違ったことをする人は、弾き飛ばされてしまうのである。本田さんは、発達障害はその人の個性の一部であり、治療して無くなるものではないと考えている。その為、それを訓練や薬によって、無理に押さえようとはしない診療方法だ。彼曰く、「自分の役目は発達障害からくる生きづらさを和らげ、意欲を引き出すことだ」と言うのである。彼の診療を見ていると、どんな悩みも笑顔で受け止めて、「絶対相手を否定しない。相手の全てを尊重する。」やり方であった。彼のこの診療方法は、彼の若い頃、どうしたら治療が出来るかと悩んだ結果だった。そしてそのヒントがある日の診察の風景にあった。それは‥診療にきたお子さんが、おもちゃで遊び続け、いくら話しかけても答えようとしない、という状況からだった。困った先生は、遊びを止めさせないで一緒に遊んでみた。するとその子は落ち着き、問いかけにも答えるようになったという。この経験がヒントになり、治療をして子供を変えることが、本当に正しいのか?と考えたことにある。先生は最後にこう言った。「ゆっくりと、ゆっくりと歩こう。」
2019年12月09日
コメント(14)
-
★本当は遅刻常習犯だった!?
「まさか、[日本人のおなまえっ!]という番組で、日本人の時間に対する正確さのルーツを聞くことになるとは、思いもしなかった。考えてみたら時代劇では、子の刻とか丑の刻といった時間の表現をしているわけだから、江戸時代にはまだ、大雑把な時間の概念しかなかったわけである。「刻」って、どういう単位?時間の単位に十二支を使っていた時代である。一日を十二で割って考えていたということは、一日が24時間だから、子の刻から丑の刻までが2時間ということになる。分とか秒単位で動いている現代社会から考えると、到底想像できない生活だということになる。江戸時代でもお侍さんたちはお勤めをしていたわけで‥。ということは、あれっ?どうなるの?なんと!それが2時間位は遅刻にならなかったと言うではないか!出社の刻が決められているが、その刻の幅は2時間有るわけで、その次の刻にならなければ遅刻ではないという考えになるようだ。そりゃぁ理屈ではそうだけど‥とはいえ、武士の世界は縦社会。絶対そんな風に都合良く、遅刻を許したとは思えないが‥。セイコーミュージアムが、東京墨田区にある。あの時計メーカーのセイコーである。そこには入口に徳川家の家紋が置かれていた。そこにある時計は和時計で、時計の針は1本だけだったのだ。江戸時代は「一刻」という単位しか、使用していなかった、分の単位は無かったのである。では、何時どうやって分の単位が生まれたのかと言うと、文明開化で外国との交流が活発になったことで、福沢諭吉が広めたようである。というのも、幕末の頃ヨーロッパから来た人が日本人と約束すると、日本人が約束通りの時間に来ないということで、多くの外国人の反感をかってしまったからだった。当時、和時計で動いていた日本人は、遅刻常習犯ばかりだったわけで、外国人は日本人の遅刻する姿に、大変ご立腹になった。つまり、外国人との摩擦を避けるために「分」を広めたのである。それを後押ししたのが、鉄道だった。列車の発車する時間の5分前に、駅の外で鐘を鳴らし、更にその後発車2分前にはホームで鐘を鳴らしたという念の入れよう。それまで移動は馬車とかカゴだったわけで、これらは個人の乗り物である。それに比べて列車は沢山の人たちを運んでいく。個人の事情で走らせるわけでないから、そこに統一した時間の概念が必要となった‥と思ったけど、違うかしら?また、列車という新しい乗り物を広めるわけで、何事も最初が肝心、という考えで、正確に列車を走らせたのでは?とも思った私である。こうして明治政府は、日本人の時間の概念を変えていったのである。こうすることで日本人に「分」という時間の単位が生まれていった。今ではどこの国よりも正確な時間で動く国民となったわけである。なんとなんと‥まだ最近の話しなんだ‥。日本人は農耕民族だから、日の出と共に動き出し、日の入りで作業を終えることを考えると、刻という単位すら、不確かなものだったと思う。夏と冬とでは、日中太陽が昇っている時間が違うからである。どうやら夏は一刻が2時間40分で、冬は1時間50分だったらしい。冬は夏ほど働かなくて良かったことになる。‥面白い!私が会社に入った40年前は、最初の頃まだタイムカードが有った。アルバイトやパートでは、タイムカードが当たり前だが、正社員でも昔はタイムカードが有ったのである。いつの間にかそれも無くなったのだが、だからといって誰も遅刻をしては来ないわけで、日本人は時間をとても意識した生き方をしていると言える。時間に正確なのは日本人特有で、さも昔からだと考えていたけれど、これもまだ最近培った時間の概念なんだと、認識を新たにした話しだった。
2019年12月05日
コメント(10)
-
★仲間に入れてくれない常在菌
「えぇー、どういうこと?ヨーグルトって腸内細菌を増やすんだよね?」私を驚かせたのは、10年毎日ヨーグルトを食べ続けている女性が、原因不明のお腹の張りに悩んだことにあった。その女性は2年前、お腹にガスが充満してしまい、いつもトイレにいって、ガス抜きをする毎日だったと言う。愛知県の山下病院の「腸内細菌外来」を尋ねたというが‥、腸内細菌の外来が有るの?‥まず、それに驚いた。これはお馴染み「ガッテン!」の情報である。山下病院の消化器内科の泉先生によると、この病院では、便から菌の種類と量まで把握できるという話しだ。なので、早速に便を検査。結果、この女性のビフィズス菌が、異常に少ないことが判明。健康な人は、ビフィズス菌が8~10%無いとダメだというのに、彼女は2.33%しかなかったという。あれっ?毎日ヨーグルトを食べているんだよね?しかも10年という長い間だよ。実はこれが新事実‥ヨーグルトのような外から入ってくる菌は、腸の中に簡単には、定着しないというのだ。定着しないから食べ続けなければならない。どうして定着しないかというと、健康な体には元々存在する菌が居て、その在来する菌が、新しい菌を入れさせないようなのである。なんですと!これは腸内で起こっているイジメじゃないの?在来する菌のことを「常在菌」と言って100兆個存在するらしい。ヨーグルトの善玉菌は数百億個程度というから、割合としては少ない。いやぁ‥単位が大きすぎて、すぐにピンとこないじゃん。じゃぁ、ヨーグルトは必要ないんじゃないの?というと、そういうことではなく、腸を通過する時に体に良い物質を出していくから、意味がある。ようするに食べ続けなければ意味がないということのようだ。ところがここで、京都の京丹後の話しになった。京都の一部の地域である京丹後には、浦島太郎伝説が有るという。あの有名な浦島太郎の話しである。浦島太郎が海から戻ってきた時、そこを歩いていた107歳のお婆さんに、「私の家は何処でしょう?」と聞いたというのである。107歳のお婆さん?浦島太郎って、何時の時代の話しだっけ!?京丹後には、そんな長生きの人が、大昔から居たことになる。これは凄い!しかもその京丹後には、今でも多くの人が長生きしている。京都市内は全国平均の1.2倍の長寿の街であるのに対して、京丹後は2.7倍だというから、滅茶苦茶長生きの場所になる。もう今は亡くなってしまったのだが、男性で長生きした人が、ギネス世界記録に認定されている場所らしい。木村次郎右衛門という人で、116歳で亡くなった。そういえば、何年か前に聞いたことがある。そんな大昔から長生きしているところでは、何を食べているのだろう?京都市内と京丹後の人たちと、食べる物を比べてみると、その違いは海藻類の摂取量の違いだったようだ。わかめとかひじきとか海苔とか‥。京丹後の人たちは、これらを週に3~7日食べているようだ。食べる率が、京都市内44%に対して京丹後では66%というから、これが長生きの秘訣の一つかもしれない。毎日ヨーグルトを食べていたが、お腹にガスが溜まってしまった彼女。先生から海藻類とか野菜(食物繊維)を食べるように言われ、それを実行したところ、短期間で2.33%から4.69%へ、ビフィズス菌が増えたようだ。ヨーグルト単体では、ビフィズス菌が定着しないんだねぇ‥。やっぱり食生活は、片寄らないことが一番大事である。
2019年12月02日
コメント(12)
全9件 (9件中 1-9件目)
1
-
-

- 医師による催眠療法
- 「催眠療法 初めての一歩」——親との…
- (2025-11-16 07:30:11)
-
-
-

- スピリチュアル・ライフ
- 物理次元で管理人に起きてきた変化に…
- (2025-11-16 07:00:05)
-
-
-

- 聖地・神社仏閣・パワースポット
- A Day at Mitsumine Shrine — One of…
- (2025-11-16 12:02:40)
-