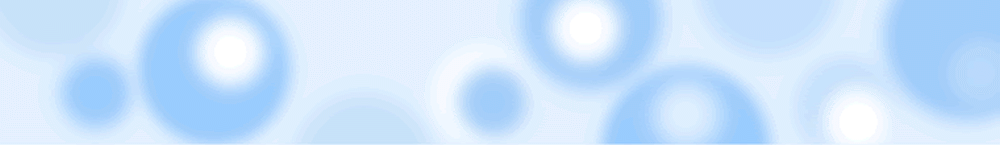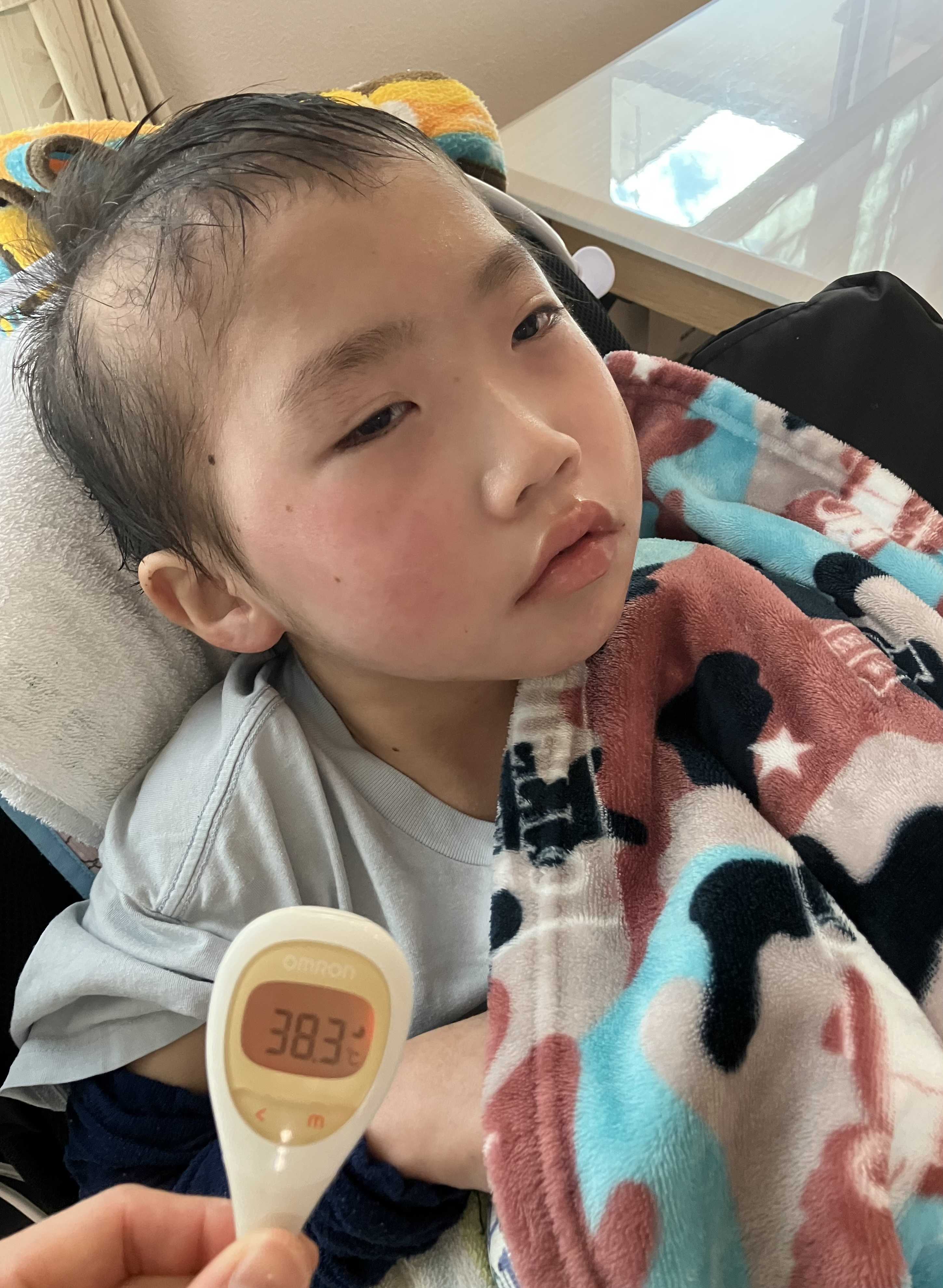2019年07月の記事
全10件 (10件中 1-10件目)
1
-
★子育て支援のナイスアイデア
「ガイアの夜明け」で、働き方改革を特集していたことがある。人手不足の折り、どうやって働き手を雇うことができるか‥。実はこの働き方改革を逆手にとって、働き手を集めることができたのだ。それが常識破りのそばチェーン「そば助」だった。ある主婦がお昼に働き、時間がきて仕事が終わりお店をあがる。お店を出て向かった先は、近くのアパート。そこには1歳の自分の子供が待っていた。この部屋は、子供の面倒を見てもらえる「そば助」の休憩所。子育てに追われて、働きたくても働けない人たちのために、借りてくれたアパートの一室である。飲食業というと、中々働き手が集まらないものである。その中で、主婦に短い時間を働いて貰えれば、お店はとても助かるし、主婦もお金を稼ぐことが出来る。ただ、ネックになっているのは、まだ手がかかる小さい子供。その子供を預けるところがあるならば、問題なく幾らでも働ける。子供を預けるところが無いから、働きたくても働けない‥それが実情だ。それを「そば助」では、或る驚きのシステムで解決した。実は1歳の子供が預けられていた休憩所で子供を預かっていた人は、そば助の同僚の従業員だったのだ。そば助の従業員は、お店で働くか自分や仲間の子供の面倒を見るか、どちらかを選択することが出来るのである。そして、どちらで働いても賃金は発生する。しかもその賃金は、お店で働く賃金と同じ額が支払われるのである。このシステムは「安心して預けられて仕事ができる」と好評である。子育て世代の人たちを、サポートする取り組みだ。このシステムを勧めているのが、そば助の創業者の八木さんだ。まだ49歳と、とても若い。この創業者の八木さんは、母子家庭で育っている。子育てをしながら働く母親の大変さを、誰よりも知っている立場だ。子供がいるから働けないと苦しんでいる人がたくさんいることに、なんとかしたいと、こういうシステムを作ったのだ。いくつか支店を出しているやり手の若い社長のようで、やはり商売は、携わる全ての人が幸せになることが重要だと感じた。
2019年07月29日
コメント(10)
-
★脱水症状に注意の季節
テーマが良かった。テーマは、私の大好きな「水」についてであった。来週の温度が、ほぼほぼ36度という恐ろしいデータが、週間天気予報に出ていて‥まださぁ、7月だよね?このままでは人間の体が、8月に溶けて流れていってしまうのでは?いやぁ~この長い夏を、どうやって過ごそうかなぁ~。「林修の今でしょ!講座」で、林先生が一日の摂取水分量が、3~4リットルだと知った。私もお水大好きだけど、4リットルは脅威の水分量だと思った。昨日、オカリナの食事会が有ったのだけど、私が水をよく飲むので、周りに居る仲間が、「これは別料金で、お水代を払わなくてはいけないような‥」なんて、言われてしまったぐらいである。お茶はテーブルに出ていたけど、私はお茶が嫌いなので、お水を別に頼むことになる。店員さんも面倒だと思ったのか、水差しを置いてくれた。それを見ての仲間の発言だった。お水の摂取量は、体重×30ミリリットルだと番組では言っていた。なので、結構考えているより水分を取らなくてはいけない。人の体自体が、60~70%水分で出来ていることを考えると、確かに多くの水分を取るべきだと思う。特に温度が高い夏は、汗で流れていってしまうから、摂取量を増やすべきである。驚いたのは、体から何%の水分が失われると、脱水症状になるか?という問いに対する答えだった。まさか、まさかの3%だった。たった3%水分が体から失われるだけで、脱水症状を起こすというのだ。こまめな水分補給が必要だということが分かる。3%失われると、汗が出なくなり、めまいや吐き気が起こり、6%失われると、手足の震えがきて、頭痛、脈拍異常が起こってくる。更に10%失われると失神、20%失われると生命の危機が訪れる。これを踏まえて、睡眠中に2%水分が失われているということを、重く受け止めなければならない。何故2%も寝ているだけで減ってしまうのか?それは、呼吸することも水分を減らす要因だからである。寒い冬に、窓ガラスへ息を吹きかけると窓ガラスが曇る。これは、息を吐くと体から水分が抜けていく証拠である。なので寝る前の水分摂取と、起きた後の水分摂取が重要だということだ。亡くなった母が夜中にトイレに行くのが嫌で、寝る前水分を控えていた事が、朝方脳こうそくを引き起こしてしまった。その頃の私にそういう知識が無かったことが、今でも悔やまれる。これからの暑い夏を健康で過ごすためにも、水分と塩分の補給を、しっかり行ないたいと思う。
2019年07月26日
コメント(12)
-
★日本人特有のことって、結構有るんだねぇ‥
日本人は、英語を勝手に短く略して会話する。例えば、エアコンはエアーコンディショナーの略だし、スマホはスマートフォンで、リモコンはリモートコントローラーの略だ。「新説!所JAPAN」では、どうやら言葉を省略するのは、日本人だけではないか?と考え、日本人と外国人両方に、街頭インタビューをしていた。すると、日本人には省略した言葉で話しが通じたのだが、外国人には通じなかったのである。単語を省略して使っている外国人は、居なかった。だから外国人に「スタバ」と言っても通じない。きちんと、スターバックスと言わなければ、なんのことを指している言葉なのか、分からないのである。スターバックスとしか言い方が無いという外国人から、日本では何て言うの?と、逆に質問されていた。「スタバ」だと答えると、「スタバ!‥あ~ぁ、良いわね~とてもカッコイイじゃない!」と、笑って返された。では、どうして日本人は単語を省略してしまうのだろうか?古代民族研究所代表の大森さんによると、日本人は言葉を省略することで、仲間意識を強くしているというのである。仲間同士に分かる言葉を、ワザと作って、仲間内で話しが通じることを、喜んでいるのである。昔はこういう言葉を「奴詞(やっこ ことば)」と言っていたらしい。奴詞が生まれたのは、江戸時代だった。江戸時代に裏社会で生きる侠客が、仲間内で使っていた隠語が、現在の日本人にも好まれていることになる。どうやら外国人には、省略する発想すら無いようだ。(@_@。ゲストのパックンも日本に来た時、省略語に困惑したと言うのである。今の若い子は、スマホがスマートフォンであるということは知っていても、リモコンがリモートコントローラーであることを、知らない始末だ。若い女の子がリモコンのことを「テレビリモコン」と答えていた。(笑)そんな偉そうに言う私も、この番組の中で一つだけ知らなかった言葉が有った。それが、ボールペン。ボールペンが何の略語なのかを、知らなかったのである。ボールペンって、ボールポイントペンの略だって、知ってた!?びっくりして、思わず奇声を上げてしまった私である。(・。・;仲間意識を持ちたいからと、勝手に略す日本人なのはいいが、本来の元の単語を忘れてはいけないだろうね。中々面白い‥しかし、反省すべきことでもあるお話しだった。
2019年07月23日
コメント(10)
-
★忘れるとは、無邪気な出来事
「男って‥幾つになってもだ‥ねぇ~」認知症の父親を、愛の家という認知症専門のグループホームで、預かってもらっている。時々一緒に住んでいる弟と一緒に会いにいく。私のことを名前で呼べる時もあれば、妹の名前と間違えることもある。「どちらさん?」と、言われたこともあった。と思えば、私の名前を何度も呼んで、会いたがっているようだと、スタッフさんに言われたこともある。そんな中、先日会いに行った時に、父から言われた言葉に、面食らってしまったことがあった。それが‥「僕と結婚してください」だった。最初何を言っているのか理解が出来ずに、えっ?と頭の中がハテナマークで一杯になったのだが‥、次にスタッフの人たちと、大爆笑をすることになった。娘にプロポーズをする父親に、大笑いである。「全く!男って奴は、幾つになっても‥困ったもんだ。」男の性ってヤツなんだろうか‥。取り敢えず身近な異性にアタックをして、男の役割を果たそうとする。認知症になっても、生まれてきた根源を、忘れないわけか。なんか悲しいような、感心するような‥、色々な感情が入り混じった出来事だった。スタッフに散々からかわれた父だったのだが、からかわれているという意味も、全然分かっていない。とにかく結婚を申し込んで、喜んでいるだけだった。(-"-)無邪気に喜んでいる父に私も便乗して、「指輪が欲しいわ~」とか、「式場を何処にしようかしら?」とか、話しを合わせて、父の気持ちをよくして話しを進ませる。父が、自分の言った言葉の意味を理解する日は、もう永遠に来ることは無いと思うと、悲しいなぁ~と思いつつも、これも後々良い思い出になるだろうと思った。認知症は、家族にとって非常に迷惑な病気なのだが、当の本人にとっては、ある一面だけ取り上げると、面倒の無い病気なのかもしれない。
2019年07月20日
コメント(12)
-
★充実した地元の音楽芸能祭
大治町の音楽芸能祭が開催された。私の友達が琴で出場するので、それを見に行った。というより、オカリナをやっているんだから行くべきだろう。(笑)私は今オカリナ同好会に入っている。町が出している広報に、オカリナ同好会の事が掲載されていたのだが、そこには「発表会に出ても出なくても良い」と書いてあった。その文言に惹かれて申し込んだので、私は芸能祭には出ない。音楽関係は、若い頃イヤというほどやってきた。幼稚園の頃のオルガンから始まって、ピアノや電子オルガンに進み、中学の部活でクラリネット、社会人になってフルートを始めた。他にはクラシックギターや合唱、ゴスペル、ミュージカルもやった。ありとあらゆる音楽関係をやり、様々な舞台に立った。だからやりつくした感が有って、もう立ちたいとは思わない。今は音楽が好きだからやる‥。音楽は、健康にプラスされるからやっている‥というわけだ。なので音楽芸能祭も、出場する側でなく観客側で楽しんでいる。音楽芸能祭は、琴やオカリナだけでなく、バトンクラブ、舞踏クラブ、民謡クラブ、タップダンス、ジャズダンス、コーラスクラブ等々‥。私より大先輩の人たちが、舞台上を所狭しと動いている。なかには「おてもやん」のように、見ているだけで楽しいものも有った。80歳を過ぎたお婆ちゃんたちが、頬を赤く塗って舞台に上がる。昔の子供が着る、丈の短い着物を着て踊る様子は、とても可愛らしく、微笑ましいものだった。夫婦で踊るものもあれば、子供たちだけの、こどものおどりクラブもあり、子供たちは初等部と中等部に分かれて披露していた。そうそぅ、詩吟クラブとか、琴も色々有り、大正琴クラブはプログラムの最初のほうだったので、遅れて行ったので、見るのが間に合わなかった。全部で19の団体が、それぞれ日頃練習しているお稽古事を披露した。「2019年音楽芸能祭プログラム」を片手持って、大治町立公民館で、半日の間楽しんだ。「大治町っていいなぁ~」つくづく自分が住んでいる町を、誇らしく思ったのだった。
2019年07月17日
コメント(14)
-
★手のひらか脇の下か?
クリームシチューの上田が司会を行なっている番組は沢山ある。「ハナタカ優越感」がその一つである。日本人の3割しか知らないこと‥ということをコンセプトに、2割しか知らないとか、1割しか知らないとか‥、逆に4割とか5割が知っていることは何か?を問題にしていた。その中で、熱中症対策を取り上げていた。熱中症になるのは、8月よりも7月が多いというデータがあるからだ。殆どのゲストが、対策として脇の下を冷やすという解答だったのだが、その中でケンコバが正解を導き出した。それは、手のひらだった。レイキ実践者である私にとって、この答えは頷けるものだった。何故なら、エネルギーの多くは手のひらから出ているからである。勿論、体のいたるところからエネルギーは出ているのだが、一番出ている場所が、手のひらだからである。体の何処かに痛みを感じたら、その場所に手のひらを当てる。それは、極自然で普通の行動だと思うのだが、何故みんな当たり前のように、そうするのだろうか?何故なら、生まれる前より知っている情報だからである。手のひらを当てることで、安心感を得ているのではないだろうか?話しは戻るが、熱中症を予防するには深部体温を下げる必要がある。体の奥底の温度が急上昇してしまっては、人間本来の体温を保てないからである。末端の血液を冷やせば、そこから体全体に行きわたるわけで、深部体温を下げるための、一番良い方法なのだ。末端で受け取った冷たい温度は、そこから体全体に行き渡る。太陽の熱で温まってしまった体の体温を、その方法で下げるのである。私は真冬以外は、手のひらと足の先を布団から出している。深部体温を下げないと、体全体が暖かいので寝られないからだ。気温が上がってきたら、水分と塩分補給を行いながら、手のひらに冷たい物を持つとかして、深部体温を下げ、この時期、熱中症にならないように気を付けたいものである。
2019年07月14日
コメント(10)
-
★心と体は繋がっている
「り~ん、り~ん!」なんだぁ?うるさいなぁ‥何処から聞こえてくるの?家の中かぁ??ふと時計に目をやると、まだ朝の4時半である。音が聞こえてきたのは‥、どうやら弟の部屋だった。弟は夜勤で会社‥部屋に居ないものだから、ドアを開けっ放しで出勤している。お蔭で目覚ましの音が、私の部屋まで聞こえてきたわけだ。う、うるさいったら~。なんで目覚ましを止めておかなかったのかなぁ~もぅ‥。その為、1時間も早く起きなければならないハメに陥ってしまった。しかもその日はセミナーを開催する日で、7~8時間喋ることになる。なにもよりによって、この日なくてもいいのに‥。弟も滅多に目覚ましを止め忘れることが無いというのにねぇ。私ったら何か悪いことをしたとでもいうの?でも、睡眠不足にも関わらず、セミナーは無事終了した。私って、まだまだ体力が有り余っているのかしら?←自画自賛(笑)そぅなんだ!この日は雨になるハズだったけれど雨にもならず、部屋には涼しい風も入ってきて、とても気持ちよくセミナーを開くことが出来た日となった。朝の1時間の睡眠不足以外は、全てが順調よくいった日になった。出だしは最悪だったが、すぐに気持ちを切り替えたことが、一日を良い日として、締め括ることができたのである。やはり悪いがあっても、気持ちを早く切り替えて、次の行動に移すことが大切なのだと、感じた次第だ。すぐに切り替えて良い日にするのも、切り替えずにそのまま悪い日にしてしまうのも、全て自分の気持ち一つである。この日は私だけの問題でなく、数人の生徒さんにも関わってくるわけで、私の気持ちの切り替え一つで、ハッピーな一日を提供できる。そして、不思議なことに講義を始めてしまうと、何故か体調のほうも整っていく。心と体の連携プレイ‥いつもこうあって欲しいものだ。
2019年07月11日
コメント(12)
-
★人生、山あり谷あり
「やっぱり伝統を守っているだけじゃ、ダメなんだよね。現代に合う物に変化させないと、生き残っていけないんだよね。」色々な伝統文化が、伝統文化だけでは生き残っていけないので、元々有る伝統を現代風に変化、というか進化させて、今の世代に好まれるようにアレンジしている。それは、それぞれの分野の職人技だと言える。私が見たのはその中の、お酒の分野だった。「逆転人生」という番組の中で、山口県で日本酒を造る桜井社長(68歳)を取り上げていた。山口県で日本酒?‥馴染が無いのだけど‥。日本酒の原料はお米なので、米どころの県が有名になる場合が多いのだが、山口県なの?‥ん??桜井社長が社長になったのは34歳の時で、父親が急死したためだった。その時の売り上げは、前年比85%‥10年ずーっと下降し続けていた。その当時の忘れられない思い出があると、桜井社長は言う。それが‥子供が通う小学校の廃品回収のことなのだが、酒瓶が2000~4000本集まる中で、自分の会社の銘柄が、3~4本しか無かったというのだ。どの酒も有名処で、テレビやラジオで流れている銘柄ばかりだったようだ。(地元だというのに、自分の会社の銘柄がたった4本!?)社長の落胆ぶりは、大きかっただろうと思う。社員に言わせると「日本酒全体が右肩下がりなのだから仕方がない。」もうすっかり諦めムードのようである。社長にしてみたら、このままではいつか倒産するという危機感。だから生き残るためには、現状を変えなければならないという強い想い。当時のお酒は、ただ酔えさえすれば良い‥というのがお酒の立ち位置。酔って酔い潰れる‥そのためにお酒を飲む、という感覚だったのである。この現状を打破するには‥。社長はその頃まだ馴染みが薄かった大吟醸に目を付けた。その大吟醸は、米の雑味を削って米の芯の部分だけを使う。10年という年月をかけて、米を4分の3も削って雑味を無くしていく。4分の3も削るということは、米の量も桁違いに使うことになる。それ以外に酵母菌や米の質も関係してくる。それらを毎年研究して、ようやく納得のいくお酒を造ることができた。社長就任当時の売り上げが1億円だったのが、10年後3億円に上がる。ここから現在の135億円の売り上げにしたのは、市場を世界に変えたからである。その市場も、従来の日本食のお店や日本食を販売しているお店でなく、アメリカやヨーロッパで、地元のレストランに売り込んで開拓した。地元の食材にも日本酒は合う!という信念で、開拓していったのだ。この話しは「獺祭」という銘柄なのだが、ご存じだろうか?アルコール大好きな私は、この話しを興味深く聞いた。雑味が無くフルーティーな香りのお酒。良いものは日本だけに留まらず、国境を越えて生き残るのだと思った。
2019年07月08日
コメント(14)
-
★家焼き肉の臭い消し
焼肉屋さんに私はそんなに行かないのだが、皆さんは行かれるのだろうか?どちらかというと、私は家で焼肉を行なう派である。でも夏となると、家でもやりたいとは思わない。部屋の温度を、これ以上上げることには反対だからである。ガッテン!を、チラッと見た時は、テーマが焼き肉だったので、これはもう、何か家の片付けをやりながら見るテーマだと思った。でも、家でやる焼き肉のお困り事を解消しようという趣旨だったので、途中から座ってメモを取りながらに、態度が変わった。(笑)番組では、極小さな微粒子でも、とらえることが出来るレーザー発生装置を使って、家で焼き肉をした時の、煙りが立ち上る瞬間を写し出していた。焼き肉をする前は、ほこりやチリが空気中に舞っていた。ホットプレートで焼き肉をやり始めたら、なっ、なんだぁ~この得体のしれないウネウネとした物って‥?それは衝撃的な映像だった。どう見ても、焼き肉を焼いた時の煙りではなかったのだ。では、煙りだと思っていたこの正体はいったい何!?それは‥オイルミスト‥聞きようによっては、美しいけど‥。オイルなんだって!!結局焼き肉を焼くと、空気中にはオイルが飛び散ることになる。それが空気に乗って、髪や衣服に、カーテン、壁、家具、床等々‥。だから焼いた焼き肉の臭いが、中々家の中から無くならないわけだ。家の窓を全開したところで、いつまでたっても臭いは消えてくれない。それは‥煙りでなく油だったからなのだ。なるほどねぇ~、油がこびりついているからなのね~。油の頑固さは、食器洗いをしたことが有る人なら、みんな知っている。これではお手上げ‥ですか?いえいえ、そこはガッテンである、プロの人たちから良い知恵を頂いた。オイルミストが220度以上で飛ぶということで、ホットプレートを全開の250度にしないで、200度に設定する。200度ならば水蒸気だけが発生するので、それなら大丈夫‥でなく、200度では肉を置くと温度が下がってしまい、美味しくならない。そこで考えたのが、200度で肉を少しずつ動かす作戦。同じ場所にずーっと置いているから、温度が下がって美味しく焼けないのだから、少しずつずらして焼く。ゲストのサッシーこと指原さん曰く「ムーンウォーク焼き」(笑)ジューっという肉の焼ける音を探して、少しずつ動かしながら焼くのだ。同じ肉でも、こうやって工夫したら美味しくなるならば、やってみる価値がありそうだ。但し200度なので、生焼けにならないように気を付けなければならない。ホルモンとか鶏肉や豚肉のような、生焼けで食中毒を起こしてしまっては駄目だから、注意が必要になる。それでも家で嫌な臭いが残らない方法があったなんて、これは楽しみが一つ増えたと思った。
2019年07月05日
コメント(12)
-
★ルーズになっていく自分
日々、追われている‥というスタンスは、私の嫌いなスタンスだ。子供の頃の夏休みの宿題も、8月上旬には終わらせていた。先にやっておけば、気持ちにゆとりが出てくるからだ。なので、8月終わりにアタフタとしている人がいると、追い詰められても問題無い、精神状態の強い人だと思ったものである。宿題をやっていないという不安を抱かない人ということは、度胸が有るのか、やれる自信が有る人だろうと思う。それが‥そのスタンスが、年々崩れていく。流石に、8月終わりにアタフタするタイプとまではいかないが、始める日時が、少しずつ遅くなっているからだ。少しでも後回しにしようとしてしまうのは、何故だろうか?気持ちにゆとりを持ちたいのなら、早く終わらせてしまうのが一番良いはずだというのに‥。億劫になっている!?気持ちが、前のめりになっていない私。さっさと、やっちゃえ~という瞬発力が‥無くなっている。特に暑くなると、その傾向にある。寒いのも億劫になる要因ではあるが、暑いと体が怠くて、やる気が起こってこないのである。温暖化傾向にある地球を考えると、暑さに強い自分へと、変えていかなければならないのだが‥。この案件、あっ、あたまが、‥いっ、いたい。私の体の何処かに、押したらなんとかなる「やる気スイッチ」は、付いていないのだろうか!?面倒臭がり屋の私は、こんなバカなことを考えてみたりする。そんなことを考えている時間に、さっさと始めたらいいというのに‥。時間が押してくると、さっさと始めなかった自分に自己嫌悪を覚える。やっぱり早めに始めないと、精神衛生上良くない。時間の管理をしっかりしないと、ダメだよねぇ。もう少し、計画性を持って毎日を過ごそうと、決意を新たにした。
2019年07月02日
コメント(12)
全10件 (10件中 1-10件目)
1