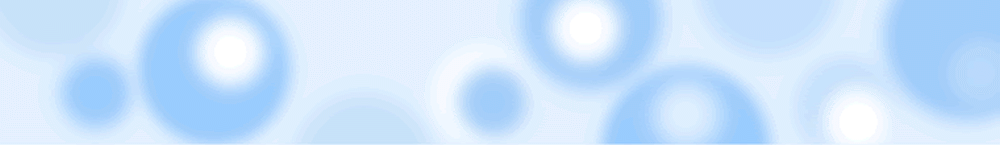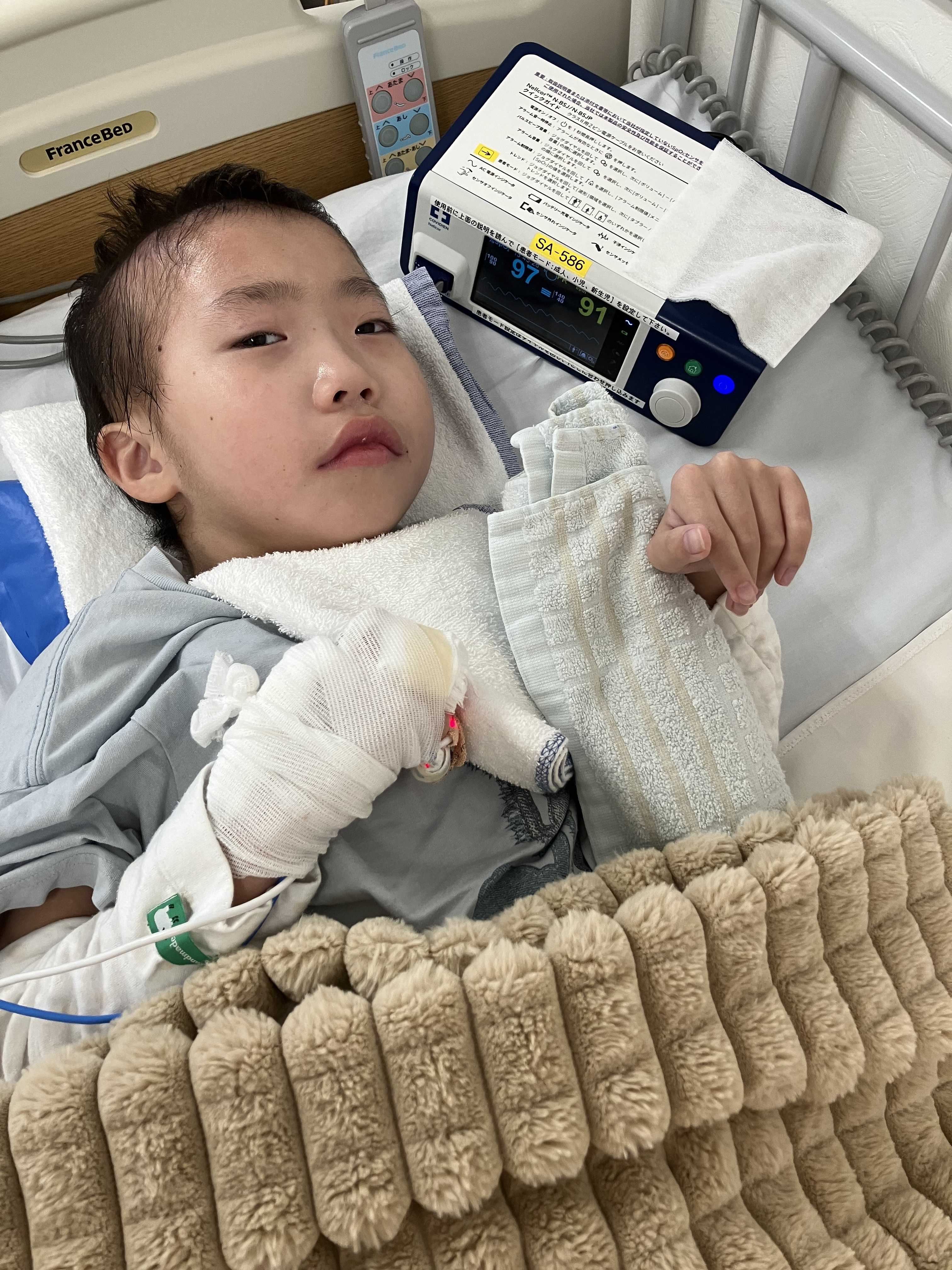2019年04月の記事
全12件 (12件中 1-12件目)
1
-
★大型連休は余裕が生まれる
ヌルッと10連休が始まった。世間でいう楽しみである大型連休は、去年会社に行っている時とでは全く違う気持ちで迎えたことになる。まぁ、定年退職して365日お休みの毎日になったのだから、休みの有り難味が、全然違って当たり前なのかもしれない。会社に行っている時の大型連休は、「家の中が片付く」という歓びが大きかった。連休明けからの毎日を乗り越える為の、準備期間でもあったから、無ければ非常に困る連休でもあった。とはいえこの連休は、新しく始まった私の人生からしても、お休みが多い連休でもあるので、やっぱり家の片付けに時間をかけられるから嬉しい。大型連休にも関わらず、建築関係の勉強に休みが無い。これは‥チョッと驚きの事実だった。(普通、休まないかぁ‥?)ヨガは、先生自体ヨガが好きだということと、生徒さんの中で、連休中もやって欲しいという意見が多かったことから、当初休みのはずだったのだが、行なうことになった。2日の木曜のヨガの日が、丁度連休の真ん中であることで、生徒さんも中だるみになるだろう心や体を、引き締めたいと思ったのかもしれない。先生はヨガ大好き人間なので、喜んでやってくれることになった。先生にとって5月2日のヨガは、月謝が増えることにならない。ある意味ボランティアでの開催日になるのだ。というのも、通常1ヶ月は4週なのだが5月は木曜が5週ある。1ヶ月定額料金なので、先生にはメリットがある開催にならない。好きでなければ開催しない‥有難い先生だ。後、占いの依頼が入っているのは、仕事なのでカウントしないが、他に私がやっているバレトンとかオカリナとかタロットとか、連休中はお休みなので、時間的に余裕がある週となった。なので、家の中が片付く。(笑)そして、勉強している色々なことの復習する時間が出来た。これは超~嬉しい時間である。ヌルッと始まった大型連休だが、まだ2日しかたっていないというのに、目に見えて色々なことが整理整頓されていっている。2日しかたっていないことを考えると、本当は大型連休でなくても出来ることになる。(あらっ?私‥ダメじゃん)多分いつもより、物事がはかどるのは、時間を存分に使えるという心の余裕だろうと思う。さて残りの8日間を、私流にエンジョイしますか!
2019年04月29日
コメント(12)
-
★京都の老舗の生き残り術
京都の下京区にある開花堂カフェを紹介していた番組は、「カンブリア宮殿」であった。40年前までは市電の車庫として機能していた場所に、3年前カフェとしてリノベーションしてお店を開いたのが、開花堂だった。実はこのカフェ、京都の意外な老舗が経営していた。「開花堂カフェ」は、飲食業が本業ではなかったのである。このカフェで、珈琲豆を保管して使っているのは、本業で作っている茶筒だという。このカフェの正体は、京都の茶筒の老舗で「開花堂」。茶筒の素材はブリキ、真鍮、そして銅の三種類。値段は‥高い、ちょっと買うのに勇気が必要になるお値段だった。でも、これが次々売れている。というのも、その茶筒の機能の素晴らしさにある。茶筒の蓋を軽く上に乗せるだけで、勝手に蓋の重みで降りて行き、ピタッと閉まるのである。「凄い!なんて気密性が高い茶筒なの!」これはこれは、大変な職人技である。創業は1875年、日本で初めてブリキを使って茶筒を作ったお店である。それまではお茶を、大きな木箱に入れて保管していた。簡単に持ち運びなど出来ない大きさの木箱である。現在の職人は8人で、分業制で行なっている。全て手作りで、創業当時から作り方は同じである。この茶筒を作る工程が、130以上もあるというから驚く。なので一日に作れる量は多くない‥40個ほどしか作れないという。海外展開もしていて、これが随分と売れているというのだが、えっ?何故海外で茶筒が??その答えというのが、日本では茶筒として使っているが、海外ではその気密性の良さから、お茶ではなく、色々な食材の保管として使っているのである。私がもう一つ驚いたのが、とんでもない進化を遂げた茶筒だということ。見た目は茶筒なのに、使い方にびっくりした。一見普通の茶筒なのだが、蓋を開けると何と!音楽が聞こえてきた。何と何と‥スピーカーとしての機能が付いているのである。そして蓋を閉めると(重さで勝手に閉まる)音が消えてしまうのである。これはパナソニックと開花堂が共同開発したスピーカーで、商品名が「響筒」と言う。なんて画期的な考え、なんて素晴らしい発想だろうか!かつて廃業寸前の危機があった開花堂。こういう現在に合う商品作りが、廃業を回避して生き残り、更に売上を伸ばしていくことになる。我々も、常に頭を柔軟にして、枠に捕らわれない発想をすることが生き残っていく道だと、教えられた番組であった。
2019年04月26日
コメント(12)
-
★一期一会
「同席してもよろしいですか?」上品そうな、そしてスポーティーな女性が、私に話しかけてきた。私は勿論二つ返事で同席を促した。ここはスーパーの一角で、誰が使ってもよい休憩所である。一人占めしてはいけない場所でもあるわけだ。ここ、地元の多くの人が訪れるアオキスーパーは、愛知県内に51店舗を展開する、中堅処のスーパーである。本店は名古屋市中村区に有るビルなのだが、アオキスーパーの原点は、大治町で青果店だった。私は当然その頃から知っているし、使わせてもらっているお店である。四十数年前、4店舗目を作るということで、名古屋市中村区でも人員募集をかけていた時に、そこでレジのアルバイトをしたこともあるお店なのである。今は三代目の青木さんが社長になっているようだが、私は二代目の社長と、生意気にも喧嘩腰になって仕事をしたことがある。恐れを知らない十代の、無謀な時期の思い出である。今思うとアルバイトの身で「怖っ!」と、冷や汗ものである。(笑)ここでは、お茶やお水の無料サービスが行われている。ただ、同じ大治町内でも南店となるとそのサービスが行われていないので、アオキスーパーの原点のお店ならではの、サービスかもしれない。同席した女性に「暑いですねぇ~」と声をかけた。昨日は最高温度が26度の予定だった。今日改めて昨日との温度差を確認すると、どうやら昨日は28度まで上がったというから、暑いはずだった。その女性は去年旦那様を亡くしたらしく、近々息子夫婦が居る名古屋市内に引っ越すことになるらしい。片付けが進まなくて‥と溜め息まじりにお話しされた。私が驚いたのは、今のご自宅が津島市内の中心部で、そこから自転車で来られているということだった。いやぁ~私も、津島のハローワークに失業保険を貰う為に通っていた頃、自転車で行けばよかったとつくづく思ったのだが、その頃は、四十数年ぶりに自転車を買って乗ったばかりだったので、自信が無いため止めてしまったのだ。そのご婦人が、大治町に寄ったのも中継地点のようで、名古屋市の北区から津島市へ帰る途中だというのである。「えーっ、自転車で行ったの!」聞くと片道1時間半というから、往復3時間の自転車乗りである。途中、庄内川という一級河川があるし、橋は津島から最低でも4つ有るはずだから、アップダウンが激しい。失礼ながら年齢を聞くと、71歳だというから驚く。いやぁ~彼女を通じて、自分の体力不足を思い知らされてしまった。(もっと運動をして筋肉を付けなければ‥)体の線が細い彼女を前にして、秘めたるエネルギーに驚かされたのだった。
2019年04月23日
コメント(11)
-
★花粉症とワセリンの関係
花粉症って‥200年前からなんだって!!そんなに前? まだ最近かと思ってたよ~。というのも、戦後暫くすると各家族になっていき、家を建てることが多くなった。その為、木を多く伐採することになる。しかし、そのままでは将来資源不足になるわけで、将来の木材を育成する為、植林をすることになった。その植林した樹木が受粉のために花粉が飛ぶようになっていった。というのが、私の認識である。なので、極々最近のことだと思っていたのだ。まさか花粉症が200年の歴史を持っていたなんて、本当にびっくりである。それを教えてくれたのが、かの有名な「ガッテン!」だ。相変わらず花粉症に100%効く薬は無い、という前置きと共に、番組は始まる。そんな中でガッテンが伝えたのは、従来の方法にプラスする花粉症対策である。えっ?今にプラスするアイテムが、まだ有るの?マスクでしょ、ゴーグルとかスプレーのように侵入を防ぐものと、鼻うがいで花粉を洗い流すもの。そして飲み薬や目薬などの、アレルギー反応を抑制するものがあるが、それ以上に有効なアイテムが有るというのか?ガッテンのスタッフが、それを知るためにイタリアへ飛んだ。去年イタリアのフェレンツェで、世界アレルギー機構、国際科学会議があったからだ。全員がアレルギーの専門家が集まる、国際会議である。この会議に出向き、36ヶ国88人の専門家に聞いたところ、イギリス出身の一人の専門家が、花粉症に有効なアイテムが有るという話しだった。そして花粉症を名付けた国が、なんと!このイギリスであることが判明した。だから花粉症に関しては、イギリスが先輩国家なのである。何をプラスすればいいの?それがワセリン、乾燥肌に塗るワセリンを塗ると有効だと言うのだ。イギリスでは、どの家庭にもワセリンが、洗面所の棚に置いてあるというからびっくりする。塗り方は‥まず綿棒もしくは清潔な指で、鼻の穴の入り口に塗る。塗る量は、綿棒の先が薄く覆われるくらい少量で良い。3回くらい鼻の穴の入口を回して塗るのだが、鼻血が出やすい内側は優しく塗って、奥まで突っ込み過ぎない。後は小鼻の上から押さえて全体に伸ばすようにする。もし鼻からワセリンが出てきてしまったら、それは拭き取ればよい。そしてこの作業は、一日3~4回行い、時々鼻をかんで、花粉がついた鼻水を出し、ワセリンをもう一度塗る。これは多くのイギリス人が行なっている花粉症対策だというから、やってみる価値があると思う。鼻が良くなれば、内部で繋がっている目のほうも、必然的に改善されるというから、一石二鳥の方法だと思った。
2019年04月21日
コメント(11)
-
★陰陽五行から青春という字が生まれる
NHKのチコちゃんは、私たちに色々な疑問を投げかけて、それに答えてくれるのだが、目の付け所が素晴らしい。先週もう一つ心に残ったお話しがあった。残ったというか、気づかなかったというか‥占い師なのに(笑)「陰陽五行思想」のことである。私は四柱推命を行なうので、占いの依頼者に必ず陰陽五行の話しをする。なので、いつも口にするお話しのはずなのだ。それでも気づかないから、チコちゃんの着目点は凄い!「なんで、青春は青い春(と書く)なの?」という投掛けである。それに対して聞かれたナインティナインの岡村さんは、返事に詰まった。そういえば、青春って甘酸っぱいし薄いピンク色を感じるし‥。決して青くはないなぁ‥、んっ?どうしてなのだぁ?岡村さんの疑問‥その通りじゃん!何故私は気づかなかったのか!!いつも言っていることだからといって、分かっているはずでも、咄嗟に答えが出てこないこともある。陰陽五行思想は、宇宙のあらゆるものが、陰陽思想と五行思想から成り立っていると、二千数百年前の古代中国で決まった。宇宙を含む物全般には、陰と陽があり、五行(木・火・土・金・水)との組み合わせで成りたっている、という思想である。これらに色々なものが割り当てられたのだが、その代表的なものに、色と季節を当てはめたのである。五行の「木」に対応する色は青色、「火」に対応する色は赤色、同様に「土」は黄色、「金」は白色、「水」は黒色である。そして「木」に対応する季節は春、「火」に対応する季節は夏、同様に「土」は無し(間とする)、「金」は秋、「水」は冬である。そう‥「木」は青色であり、春なのである。青と春で青春、青春という言葉は、ここから生まれたのである。(気づけよ私‥笑)明治大学の加藤徹教授によれば、日本で青春という言葉が使われ始めたのは、奈良時代。但しこの頃の青春の定義というのは、年齢が若い‥、という意味だけだった。今のように、淡い恋愛的な要素とかは入っていない。そういう意味付けをしたのは、夏目漱石が書いた「三四郎」だった。彼の書いた本「三四郎」のヒットが、「青春」という言葉を、我々に定着させたのだった。私にとって身近な陰陽五行が、青春という言葉を生んだなんて、結構身近なことでも、分かっていないことの多さに驚かされる。
2019年04月18日
コメント(10)
-
★猫の主食は国によって違うの?
NHKの「チコちゃんに叱られる!」の番組は、本当に面白い。この間の設問は、二つとも私の心にドンぴしゃのものだった。一つ目の設問が「なぜ猫は魚が好きなの?」というもので、その答えが「日本人が魚好きだから」であった。えっ?日本人限定??‥ということは、日本の猫限定の答えなの?これがその通りで、世界各国の猫の好物は、その国の人間が好きな食べ物だったのだ。専門家によると「猫はライオンなどと同じ肉食動物なので、本来ネズミなどの小動物を好んで食べる」という解答だった。あっ、確かにそうだ!‥猫=ねずみだ!でも‥猫=魚に考え方がすり替わっているなぁ‥。キャットフードも、魚入りだし‥。しかし実は、猫が魚好きと思っているのは日本だけだというのである。日本以外のキャットフードは、牛肉入りだったり鶏肉入りだったり、中には猪の肉入りのものまであるらしい。では、何故日本の猫は魚好きになったのだろうか?本来人類の何万年前からの悩みは、畑や蔵などの穀物を食い荒らすネズミだったのである。そのネズミの駆除のために、猫を家畜として飼ったのが最初だった。そして古代エジプトから、世界各国へと猫が伝わっていったのである。一方、日本にはペットとしての猫は居なかった。奈良時代に中国から伝わって、貴族など一部で猫を飼い始めた。猫は日本人の食べ残しの魚を食べていた。そう、飼われ始めた猫の主食は、人間の食べ残しだったのである。その頃の日本人は、お米と魚を主に食べていたので、動物的タンパク源が必要な猫は、必然的に魚を食べたのである。番組では、猫の食べるものの世界各国の例を出していたのだが、その日本との違いに、私は驚いた。例えば主食がトウモロコシのメキシコでは、猫もトウモロコシを食べる。同様にスイスではチーズ、イタリアでは何と!パスタなのだ。イタリアの猫には、麺をすする猫も居るようで、イタリア人が麺をすすれないのに、猫はすすれるという奇妙なことに‥(笑)なんと、猫=魚だと思っていたのは日本人だけだという、井の中の蛙状態だったと知った時だった。
2019年04月16日
コメント(14)
-
★マジか~、プロの集団じゃん
「あっちもこっちも、プロの仕事じゃん!」2ヶ月前の2月のまだ寒い中で、羽田空港の国際線ターミナルの特設舞台に、桜の花が咲いた。一足早く桜見を楽しんでもらいたいという作り手の意図が、ものの見事に的中したわけだ。2月だよ!?しかも狙ったその日に桜を咲かせるなんて‥。フラワーアーティストの赤井勝氏も凄い人ならば、その注文を受けて、発注日に開花するように桜を育てた人たちも‥スゴい!みんなスペシャリストだ!!エネルギッシュな赤井勝氏を映像で取り上げていた番組は、かの有名な「情熱大陸」である。赤井氏は1965年大阪生まれ、祖父母は花農家、実家も生花店で、父を2歳で亡くしている。赤井氏は、ローマ法王にブーケを献上したことのある男である。「僕は花人で、花屋なんで、それ以上もそれ以下でもない」花に囲まれて生きてきた赤井氏の言葉である。この4月から地元大阪で新しい仕事が始まる。それは大阪の追手門学院大学で、月に一度の講義。「花と向き合う人生を話してくれ」と、大学側に依頼される。断わる理由は、当然見つからなかった。花の素晴らしさを、一人でも多くの人たちに伝えたかったからである。更に幼稚園児の為にも、年に何度かの体験教室を開いている。子供たちに、色々な沢山の花に触れ合ってもらうのが狙いである。「子供たちに、セレクトするのをやってもらいたい」好みとか決断とか、好きなものを選んで、好きなものを小鉢に入れる。彼は、子供らしい発想を期待するのである。子供たちを見ていて赤井氏が舌を巻く。とてつもない発想が生まれたからである。それを見た赤井氏曰くは‥「追い越されているやん、なんかもう悔しい~」と、感情を露わにして言ったのだが、その顔は悔しいだけの表情ではない。悔しさの中に、嬉しさも混じっている顔だった。花と触れ合って、花を好きだと言う子供たち‥。赤井氏の嬉しそうな満面の笑みは、輝いていた。
2019年04月13日
コメント(10)
-
★日本人と外国人の触感の差
「日本人って外国人と違って、唾液が少ないの?」新説!所JAPANで、面白い街頭実験をしていた。ビスケットを1枚持って、外国人の夫と日本人の妻に食べてもらうという実験だった。外国人の夫は普通に食べて平気な顔だが、日本人の妻は水分が欲しいと言う。勿論実験はこの夫婦だけでなく、色々な外国人や日本人の老若男女に聞いていたが、どの外国人も平気なのに対して日本人は大抵一言、水が欲しいだの牛乳が欲しいだのと口にしていた。私もきっと飲み物を欲しいと言うだろう。それに対して司会の所さんは、「僕は平気、ビスケットは1枚だけでなく何枚でも平気」だと言っていた。周りの人から外国人かっ!というツッコミを受けていたが~(笑)元々この実験をした最初の疑問は、柔らかい食パンを日本人は行列してでも買うのだが、外国人は一人も並んでいないというところの違いについてだった。突き詰めていくと、日本人の唾液の少なさに辿り着いたという話しである。どうやら日本人は、水分をパンで補給しているから、柔らかいパンを好むというのである。えっ?歯が衰えているからではないの??それはご年配の場合有り得る話しなのだが‥。そういう一部の人だけでなく、日本人全般が食パンに望んでいることが、ふわふわしていて、しっとりとした感触のようなのだ。成る程‥日本人は唾液が少ないから、食パンに水分を必要として、食べ物を飲み込む力に変えているわけか‥。もう一つ番組では、パンの耳を美味しく食べる方法を教えてくれた。どうやらパンの耳は、硬いのではなくて上手く焼けていないだけ!と言うのである。食パンを焼いて食べても、耳の部分はサクッという音がしない。それは耳の部分が生焼けだからである。なぜ生焼けになるかといえば、耳が焼けることを重視してしまうと、耳以外の部分が焼け過ぎてしまい、黒焦げになってしまうからである。ではどうすれば耳も焼けて、サクッという音がして美味しく食べられるのだろうか?その方法とは‥。食パンの耳に沿って、包丁で切り込みを入れるだけ‥。耳と内側の間に切り込みを、四方向に四ヶ所入れるだけ。切り離さないよう四隅をしっかりと残すこと。そして、四隅以外はしっかりと姦通させることも重要である。耳の水分が切り込みを入れることで、水分が飛んでサクサクになる。「これ、日本中でみんなやってみるんじゃない?」サクッという音を立てながら食べる、所さんたち全員の感想だった。
2019年04月10日
コメント(12)
-
★平成30年間でよく読まれた本‥上位3冊
「平成で売れた実用書 ベストセラーランキング」として、世界一受けたい授業で、上位30冊を出していたのだが、最近本を読んでないなぁ‥と、実感した。30冊の中には読んでいた本も有ったが、数冊しか無かったし、順位もかなり低いところで紹介されていた。平成で起こった事件とか事故や災害なども、売り上げに影響してくる。なので本を出版するタイミングも関係するだろう。その時の運、不運も影響するだろうと思われる。1~3位の本は、聞いたことはあったが、買って読むまでには至らなかった。第3位は「チーズはどこへ消えた」平成12年に発売され、著者はスペンサー・ジョンソン氏で、400万部の売り上げである。内容は、チーズが消えた時にとった小人二人の行動である。一人の小人は考えただけで行動を起こさなかったのだが、もう一人の小人は探しに出かけた。何故出掛けられたかというと、チーズを見つけたとイメージ出来たから‥。探し出したという成功のイメージが、脳裏に浮かんだからである。イメージ力が行動に繋がったという話しである。こちらの本は、今年19年ぶりに続編が発売されたとのこと。タイトルは「迷路の外には何がある?」のようだ。第2位は「脳内革命」平成7年発売で、著者は春山茂雄氏。410万部の売り上げだった。内容は、プラス思考によって脳から出るホルモンが、心身にとって最高の薬になることを、科学的に解説した本のようだ。これ‥読みたかったなぁ~。平成7年というから、もう手には入らないかもしれない。そして、栄えある第1位は「バカの壁」平成15年発売の本で、著者は養老孟司氏、売り上げは443万部である。内容は、我々の頭を妨害しているのは、結局こうだって思い込んでいるからだ‥ということ。思い込みは、私たちの成長を阻む壁になってしまっている。名言が沢山あるようで、どうしたらいいんですか?と、すぐに人に聞くのではなく、まず自分で考えるべきだとか、自分の個性に価値があると考える人は進歩しない‥というもの。個性と思っている内は、そこから次の成長過程へ進めない。それが「バカの壁」というタイトルに繋がるのだろうと思う。私の家には、買っただけで読んでいない本が結構有る。買って満足してしまった本たちである。時間の有る今、少しずつ読んでいかなければと思っている。
2019年04月08日
コメント(10)
-
★平成最初と最後の奇跡を東邦がみせる
1本のドラマを見るのような巡り合わせ‥東邦優勝、おめでとう!!新聞の見出しは「春の東邦 5度目V」そしてサブ見出しが、「選抜最多 最初と最後 平成の快挙」となっていた。タイトルの情報、多っ!奇跡のような巡り合わせも有りで、東邦の春の甲子園が締め括られた。なんだって?5度の選抜制覇は、中京大中京(愛知)と並んでいた優勝回数で、単独トップになったって!なんでも中京大中京の五十五勝を上回る五十六勝で、単独一位になったということだった。しかも平成元年の優勝と平成最後の優勝には、沢山のドラマが有った。その両方の年に関わったのが、森田監督と石川選手。最初のニュースで聞いた時は、この石川選手というのが、平成元年に東邦が優勝した時に居た選手の、息子さんだということ。石川選手は平成元年でお父さんが、平成最後の年に息子さんが、それぞれ優勝に一役かっている選手だということ。いや、一役ではない、大いに貢献している選手である。でも、それから関連記事を中日新聞で読んで、それ以外のドラマが有ることを知った。平成最後の年に東邦を優勝に導いた森田監督は、平成元年にはコーチとして、優勝を経験している。森田さん自身は、昭和の時代の1977年に東邦の主将として、夏の甲子園で準優勝を経験している人である。そして60歳の森田監督は、本年度限りで退任の決意を固めているということだった。「最後の年に石川に巡り合えた」と、感謝の言葉を口にしている。石川親子のことだけでも、感動する話しだというのに、監督の森田さんにもドラマが有った。なんだかイチローといい東邦といい、愛知の野球熱が熱い!日頃運動関係に疎い私でさえ、興奮するニュースが続いている。平成最後の年であり月である平成31年4月に、野球界から、沢山のパワーを頂くことが出来た。
2019年04月06日
コメント(12)
-
★インテリアのプレゼン
プレゼンが終わって、心底ホッとした。まぁ、ここ数日頑張ったからなぁ~。結構な時間を費やしてプレゼンの準備をしてきた。A3用紙×3枚を二通りと、A3用紙×2枚を一通り、計8枚のA3用紙を創り上げた。一部の良く出来る人たちは、これにまだ壁紙とか床材を追加して、計11枚を提出している。私にはそれだけの余裕が、全く無かった。数日間‥その作業に時間を費やした。そんな大きなものを創るような机が、自分の家にあるほずもない為、必然的に畳の上でやることとなった。なので、体を何度も曲げての作業なので、腰が痛いといったら‥。あぁ~もう大変だったよぉ‥。でも大変だったからこそ、やり終えた後の充実感は大きかった。プレゼンは下手だったけど、プレゼン用に創った作品には満足している。プレゼン用の作品はカラ-コピーをして提出した。提出した作品は、戻ってこないと言われてしまったが、元の原稿は残っているので、まぁいいかなぁ~。その後、仲間とランチに行く。この日を境にもう勉強をご一緒しない人たちが沢山居る。4月から入った人たちである。私は10月に入ったので、まだ後半分の半年残っている。4月からは実務編でなく、知識編となる。なので4月の第2週からは、新たな人たちとの出会いが待っている。今回はいままでも一緒にランチに行った人だけでなく、今回初めて行った人もいて、より楽しいランチになった。その中に、22歳の若い子が居た。22歳?もう私とは孫の関係の年齢差である。若いとは思っていたけどねぇ~びっくりする若さだ。彼女は私と一緒の10月入校の人だと思っていた。というのも4月からの人たちは、私より半年長いので、教室の中では、もう下の名前で呼び合っていたからだ。私はそこの中にすぐに溶け込んだ。でも私を除く10月からの人たちは、少しぎこちなかった。だからこの22歳の彼女も、私と同じ10月入学だと思い込んでいたのだ。でもこのランチでよくよく聞くと、どうやら夜間からの編入生だと知った。仕事の都合とかで平日午前中から、夜間や日曜日に編入する人もちらほら居る。私と同じ町内に若い頃住んでいたという人も、転職した為に、途中から日曜日のコースへと編入していってしまった。スゴク残念だった。なんだぁ~この若い子ともお別れなんだぁ~。もう半年一緒だと思っていたからあまり接触しなかった‥。今はそれを後悔している。彼女のプレゼンは、他の人と目をつける角度が違っていた。住宅用でなく、店舗を創るコーディネートだった。先生も彼女の作品を見て、そういう方向性で転職すると良いという、アドバイスだったのだが、みんなも納得のコンセプトだった。一期一会、別れる人出会う人の多い3月と4月。苦労した仲間は、やはり一味違う。別れは寂しいけれど、新たな出会いに向かって力強く歩いていきたい。
2019年04月03日
コメント(10)
-
★新旧交代、新元号は?
4月1日といえば、新年度。1月1日もそうだが、色々なことが新しくなる日である。今年の4月1日は大きく変わることを発表する日である。その発表とは、勿論新元号である。どうやら9時半に5つの案を出して、そこから一つに絞る流れのようだ。そして11時半頃、菅官房長官からの発表となる。その時間バレトンをやっているので、生では聞けない。チョッと残念である。新元号はとっくに決まっていて、発表するだけだと思っていたのだが、どうやらそうではなく、今から一つに絞るという‥。まぁ、そう言われればそうだなぁ‥。決まっていてしまったら、何処かで漏れてしまう可能性が高くなるから、候補を絞るところまでで留めておくほうが、間違いないだろう。さて、何になるだろうか?タロットの勉強で、そのことを題材にして、大いに盛り上がった。へぇ~こういう遊び方もあるんだ‥。私は今のタロットの先生がどうも苦手で、いつも四苦八苦して勉強している。どうして苦手なのかが、この間判明した。私が左脳的な人間に対して、先生は右脳的な人だからである。タロット自体が右脳的なものだから、私はそれ自体も苦手ということになる。なので左脳を使う統計学である四柱推命が、私には合っていることになる。とはいえ漢字は苦手なので、これも習得するのも大変だったんだが‥。この間、タロット仲間とお茶をしていて、新事実を発見した。というか仲間に教えてもらったのだが、タロットの先生にも、左脳的な人と右脳的な人が居るということだ。そうか!ならば私にもやっていける分野になるなぁ‥。今の先生が苦手には違いないが、それもタロット自体のことを考えると、習っていてプラスになるに違いない。(大変だけどねぇ‥)話しはそれたが、どういう遊びかというと、どのアルファベットで始まる元号かを、タロットに聞くというものだった。勉強の場では、二つの候補に絞られた。生徒と先生がインスピレーションでそれぞれ出したアルファベット。カードが二つの候補に集中したのである。まぁ、最初のインスピレーションが外れたら、全く意味がないけれど、それはお遊びなので、それで良しとするべきだろう。ちなみに私が出したインスピレーションは、カードに拒否された。元々右脳的で無いのだから無理はないかな。(苦笑)こんなことをやった後なので、今日の新元号の発表は楽しみである。さてさて、どんな元号になることやら‥。
2019年04月01日
コメント(12)
全12件 (12件中 1-12件目)
1