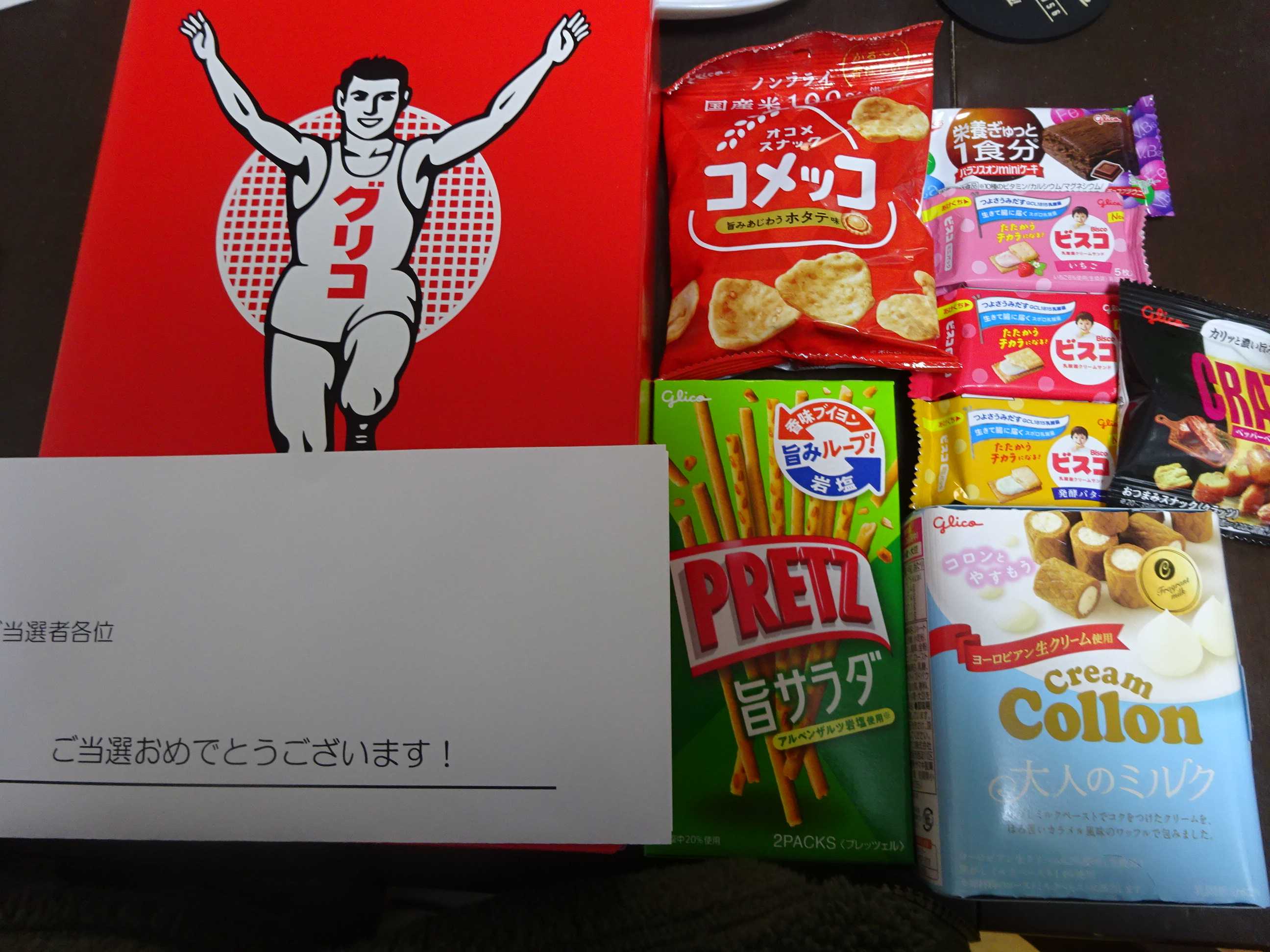2012年09月の記事
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-
パンドラの函
我が家のテレビですが、どういうわけか9月30日まで、BS放送の「FOX238」という局が1年間無料で見られることになっていて、『Xファクター』とか、『アメリカン・アイドル』、はたまた『ウォーキング・デッド』などの番組が見られる仕組みになっていたのですが、明日10月1日からは、別途料金を払わないといけないのだそうで。 で、もうすぐ始まる『ウォーキング・デッド』の新シリーズも見たいし、ここは一つ、受信料を払ってでも見ようということになり、そのような契約をしたわけ。 しかし、これがひょっとしたら命とりだったのかも・・・。 というのは、この契約によると、単に『FOX238』が見られるだけでなく、その他にも色々な有料チャンネルが見られるらしいんですわ。で、その中に洋画関連の局が3つもある。 で、その3つの局がですね、代わる代わる、いい映画を放送するのよ。ちょっと前に一度観たことがあって、面白かったという記憶があるような映画を、バンバン流す。 となると・・・やっぱりもう一度観たくなるのが人情ってもんじゃないの・・・。 となると・・・もう、ワタクシは映画チャンネルの奴隷よ。今日はコレとコレを観て、明日はコレとコレ、明後日は・・・なんて調子で観ていたら、ほとんどテレビの前から動けやしない。明日から後期が始まり、その予習とかも大変なのに・・・。 ということで、止せばいいのに開けてしまったパンドラの函。いかにテレビの前から離れるか、来る日も来る日も意志の力を試される、そんな日々が始まってしまったのでございます。あーん、困ったよーーーん!
September 30, 2012
コメント(0)
-
常滑ドライブで急須を買う
さてさて、今週末でついに夏休みも終了、来週から後期が始まります。 というわけで、『サザエさん』終了後の絶望感に似たものを抱きながら、最後のひと遊びをしようということで、常滑にドライブに行ってきました。 最近、仕事やら何やらで常滑に行くことが多かったので、道は熟知。有料道路を適宜使いながら小一時間のドライブで陶芸会館まで到着。ここにクルマを止め、「やきもの散歩道」を歩き始めます。 今日の目的の一つは、「古窯庵」という蕎麦の店で昼食をとること。前に仕事で常滑に来た時にここで食べ、非常においしかったので、今日は家内にその味を紹介しようというわけ。 古窯庵はやきもの散歩道(Aコース)の中ほどにあります。古民家を改造した趣のある建物で、中に入るとジャズが流れていて、和と洋、古さとモダンさが混じり合った落ち着く空間が現出する。おすすめは何と言っても「鴨せいろ」。私好みの腰のある細麺を、鴨肉と鴨つくねがたっぷり入ったアツアツのつけ汁につけて食べる幸せは何とも言えません。家内も感激の旨さ。蕎麦喰いのワタクシは、以前、「名古屋には旨い蕎麦屋が一軒もないっ!」と嘆いておりましたが、このところ旨い蕎麦屋を発見することも多く、前言撤回しなければなりますまい。 さて、お腹がくちくなった我らは、そのまま散歩道を先へ進み、道沿いにある焼き物の店を冷やかしていくことに。 まず我々が立ち寄ったのが、「リチャード&ミエコ・ポッタリー」。テレビなどで取り上げられることも多い店でございます。我々が立ち寄った時にはリチャードさんはご不在で、ミエコさんとだけ少しお話が出来ましたが、お二人はもうすぐここを引き払ってフランスに新たに窯を築くべく移住されるとのこと。それで、今は在庫処分サービス実施中。 で、我々の目にはミエコさん作の5枚組小皿(3,000円也)あたりが購入ターゲットに入ってきたのですが、しかし、焦ってはいけない、まだ先がありますから、他のお店も見た上で最終判断することにしましょう。 で、再びやきもの散歩道を歩き始めると、ほどなくしてまたまた魅力的なお店発見。常滑焼専門店「SPACEとこなべ」です。ここもお昼を食べた古窯庵同様、古民家を改造してモダンなテイストを加えたようなお店で、置いてある品も店主の趣味を反映してか、洗練されたモダンなデザインのものが多い。 で、この店はイイゾ、と思いながらじっくりと見て行くうち、なかなかスッキリしたデザインの急須を発見。 常滑焼というのは、瓶とか土管など、実用性の高い焼物が多く、また急須に関しては朱泥の急須が有名ですが、ここに展示してあった急須は黒色なんです。しかし、下地はやはり朱泥で、それを黒く発色する土でコーティングし、焼き締めてあるのだとのこと。で、その上で蓋のはまる円周部分だけ少し削り出してあるので、黒い急須でありながら、かすかに朱泥の色が一筋だけ丸く浮き出ている。その黒と赤のコントラストがまた、実に上品でモダンなんだなあ。 しかも、常滑焼の急須の凄いところは、急須の内側の茶漉し部分。茶漉しの穴がものすごく細かく開いていて、微細な茶殻も逃さないんですな。この部分の技術は、常滑焼の急須ならでは。ちなみに、私たちが目をとめた急須の作者は「鯉江 廣」さんとおっしゃる陶工さんで、天皇皇后両陛下がお使いになる湯呑を作ったこともある方。まさに名人ですな。 ということで、前からちゃんとした急須が欲しかった我々は、半ばこの作品を買おうと思い始めたのですが、しかし、やはりもう少し他の店も見てから決めようということになり、一旦この店を出て、またやきもの散歩道に戻ります。 で、そこからまたのんびり散歩を続けながら、色々なお店を冷やかして行ったのですが、最近ではこの道沿いに陶芸以外のショップ、例えばガラス工芸の店とか、布を扱う店、あるいはパン屋さんやカフェなんかも増えてきたので、見る方としても楽しみ倍増。我々もパンを買ったり、自然派化粧品の店で「アレッポの石鹸」なんかを買ったりしながら、散歩を楽しみます。 で、とうとう道の外れまで来たところで、色々見たけれども、やっぱり「SPACEとこなべ」で見た急須を超えるものはなかったと判断、もう一度道を戻って、先に見た急須を買うことにしました。少々お高いですけれども、人間、一生のうちにいくつ急須を買うだろうかと思えば安いもの。でまた、「SPACEとこなべ」のお店の方お二人(兄弟?)が非常に親切で感じのいい方だったので、実に気分よく買い物をすることが出来ました。 かくして念願の急須を手に入れた我々は、振り出しの陶芸会館に戻り、もう少しドライブを続けることに。向かうは野間の灯台です。 野間の灯台の真ん前に「NOA NOA」というカフェがありまして、海を見晴らす絶好のシチュエーションなもので、このあたりに来ると必ず寄るのですけど、この日もここで一休み。そして、その後、目の前の灯台のところまで行き(灯台ってのは、何故だか見るだけでテンション上がるよね!)、またその前の砂浜でしばし波と戯れてから、この日のドライブを終了することといたしました。 というわけで、今回の常滑ドライブ、おいしいお蕎麦を食べ、前から欲しかった急須を手に入れ、さらに久しぶりに海を見ることも出来、なかなか充実のドライブとなったのでした。
September 29, 2012
コメント(2)
-

猪熊弦一郎展を見る
昨日の続きなんですが、そう、それで出張の帰りに刈谷市美術館に立ち寄り、今開催中の猪熊弦一郎展「いのくまさん」を見てしまったわけですよ。 猪熊弦一郎は1902年生まれの画家で、東京芸大(の前身)では藤島武二に師事。その後戦時下のパリに遊学してマチスの薫陶を受け帰国、戦後再びパリに向かうものの、途中で立ち寄った1950年代のニューヨークのアートシーンに刺激を受け、結局そのまま20年ほどニューヨークに滞在して活躍。晩年はハワイと日本の両方に拠点を置き、1993年に亡くなるまで絵筆をとり続けた、という経歴の持ち主。 で、私は寡聞にして猪熊弦一郎のことをあまりよく知らず、辛うじて名前を聞いたことがあるくらいのものだったのですが、今回、この美術展を機にその画業の何たるかを知ることができました。 時代区分を考慮せず、モチーフをもとに彼の画業を区分しますと、初期には具象的な、いわゆる「洋画」という言葉から連想されるような一連の作品がある。ヴィヴィッドな原色を組み合わせたインパクトのある風景画があるかと思えば、ピカソの青の時代を彷彿とさせるような肖像画(『M夫人の肖像』など)があったり、さらには自分の奥さんをマチス風の平面的なタッチで描いた肖像画もあったりして、若き日、パリで自らの手法を模索していたであろう頃の猪熊弦一郎の奮闘ぶりが伺えます。 そして次に「鳥」の時代がやってくる。これは猪熊さんの頭の中に浮かんだ鳥のイメージを次々に描いて行ったものなのですが、これが素晴らしい! 私はこの時代の猪熊さんの絵が一番好き。特に大きなキャンバスに描いた2枚の連作、一枚は黄色ベース、もう一枚は青ベースの作品があるのですが、この二枚が並んで展示されているのが圧巻で、私はこの二枚の絵の前でしばし動くことが出来ませんでした。欲しい! 二枚とも! それから今度は「猫」シリーズ。これは絵というよりはイラストですな。様々なポーズをとる猫ちゃんたちを鉛筆などで沢山描いているのですが、めちゃくちゃ可愛い。 そして猫シリーズの軽さは、いのくまさんが遊びで作った「針金アート」にも通じます。禁煙中の手持無沙汰を解消するために、針金をひねくり回して作った様々なオブジェがあって、これは人と話をしながらでも作れることから「対話彫刻」と命名していたらしいですが、これも実に楽しい。 そして「顔」シリーズ。長年連れ添った奥様を亡くされてから、いのくまさんは人の顔を描くようになったそうですが、人間の顔を簡素化し、子どもが描くようなタッチの顔の絵を大量に描いていて、その描いた顔の数々をさらにモザイクのように組み合わせたりして、全体で一つのデザインを構成するようになっていたりする。そんな無数の顔を描きながら、亡き奥様の表情を思い出しておられたのでしょうか。 それからニューヨーク時代の作品群も展示されていました。これは無機的でもあり、有機的でもある大都市ニューヨークからインスピレーションを得て制作された一連の作品で、一応、無機的な形を組み合わせた抽象画のようでありながら、その形の連続が例えばニューヨークの摩天楼に見えたりして、無機的なものの向こうに大勢の人間の暮らしが感じられもする。そんな画風の作品でございます。 とまあ、時代によって様々な画風を生み出していったいのくまさんですが、1902年生まれ、しかも東京芸大で小磯良平や荻須高徳らと切磋琢しながら鍛え上げられた方にしては画風がポップと言いましょうか、詩人の谷川俊太郎が「猪熊弦一郎」といういかめしい名前を親しみ易い「いのくまさん」と呼び換えたのも分かる気がする。 それから意外なところでは、三越の包装紙、あのふんわりした赤い雲みたいなデザイン、あれもいのくまさんの作品なんですって。あれは、いのくまさんが千葉の犬吠崎の海岸で拾った石がモチーフなのだとか。 ということで、私は今回の展覧会で、いのくまさんの画業の何たるかを知ることが出来、実に楽しかったのであります。刈谷市美術館で開催中の猪熊弦一郎展、教授のおすすめ!です。 それにしても、いつも思いますが、刈谷市美術館の企画力は素晴らしい! 小さな地方美術館でもこういう優れた展覧会を開催できることを、証明しております。スタッフの頑張りに拍手!【送料無料】いのくまさん [ 猪熊弦一郎 ]価格:1,575円(税込、送料別)
September 28, 2012
コメント(2)
-

出張の楽しみ
今日は大学の公務で、知多半島の常滑(とこなめ)というところに出張に行ってきました。 公務自体はものの30分ほどで終了する性質のものでしたので、あとはその後をどう楽しむかに掛って参ります。せっかく常滑くんだりまで行ったのですから、そのまま大学に戻るというのも芸がないですからね。 ということで、帰りがけに刈谷市美術館というところに立ち寄り、同館で現在開催中の「いのくまさん」という展覧会でも見ようかと、とりあえずクルマを走らせ始めたところ、いくらも走らないうちにちょっと私の目を引く看板がありまして。 それは「蔵元」の二文字。どうやら、日本酒の醸造所らしい。確かに、良い感じに古びた、風情のある蔵があるじゃないですか。 で、来客用の駐車場にクルマを停めてみたものの、ここはあくまでもお酒を作っているところで、お酒を売っている店の感じがない。あら、ここではお酒は買えないのかしら? と思いながらウロウロしていると、蔵の中から女性の方が出ていらした。 明らかにこちらのおかみさんのようでしたので、「蔵元の看板に惹かれて来たのですが、こちらでお酒は買えますか?」と尋ねてみたところ、もちろん買えます、とのこと。そこで蔵の中に入ってみると、確かに入口近くにある事務所の脇で、ここで作っている何種類かのブランドのお酒が展示してある。 それで判明したのですが、ここは「澤田酒造」という古い蔵元さんで、「白老」というお酒が、ここのブランドなのですって。 で、応対してくださったおかみさんが実に感じがよく、押しつけがましくなく、かつ親切だったので、すっかり嬉しくなってしまった私は、その白老なるお酒を買うことにいたしました。なにせ蔵元から直に買うわけですから、なおさら趣があるというもの。ちなみに、こちらのお酒はキレよりもコク重視、味のある酒を作ることをモットーとしていらっしゃるとのこと。 ところで、澤田酒造さんでは、自社製品のお酒だけでなく、知多周辺の産物として、お酢や醤油なども売っていまして。で、どうせならおいしい醤油も買っちゃおうかと物色していると、醤油の隣に魚醤が置いてある。ナニナニ、豊浜水産物加工業協同組合の「しこの露」とな? 原材料はカタクチイワシか。 で、おかみさんに尋ねると、この魚醤を使って海老だとか烏賊だとかをつけ焼きしたりすると、すごくおいしいのだとか。そう言われたら、もう買うしかないでしょう。値段も500円くらいのもんですしね。 というわけで、思いもかけず、澤田酒造直売の清酒「白老」と、魚醤「しこの露」をゲットし、出張の良い土産となったのでした。これこれ! ↓白老 からから 本醸造1800ml価格:1,890円(税込、送料別)愛知豊浜産低温で造られるので良い香りに仕上がっていますしこの露魚醤250ml価格:525円(税込、送料別) さてさて、この後、私は刈谷市美術館で「いのくまさん」の展覧会を見ることになるのですが・・・、その話はまた明日にしましょうかね。
September 27, 2012
コメント(4)
-
太陽のカフェ初見参!
オムライスが食べたい、って時、ありません? オムライスなんていうと、子どもの食べ物のようで、大の大人が、しかも男が、食べたいっていうのもどうかな、と思うのですが、たまにそういう時ってあるんですよね。 で、今日がそんな日だったと。 オムライスといえば「Hello Egg」なんて専門店がありましたが、うちの近くにあった店がつぶれてしまいまして。となると、どこへ行けばいいのか・・・。 で、思い出したのが名東区極楽にある「太陽のカフェ」。数年前にできたのは知っていましたが、人気店ゆえランチ時はいつも大混雑で、敬遠していたんです。でも興味はあった。 ということで、今日はここに行ってみることに。 行ってみると、夜は昼ほどの混雑ではないらしく、すんなり座れました。で、今日は私も家内も「秋の大人のオムライス」を注文。牡蠣が入っていて、デミグラス・ソースの代わりに味噌ソースが掛かっているとのこと。牡蠣と味噌なんて、合いそうじゃないですか。 で、実際出てきたオムライス。かなりの高得点。 しかし、この店の売りは、セットメニューにあるのだ! なんと、オムライスに野菜料理ブッフェ+パフェバー+ドリンクバーをつけて、それで1,530円なのであります。 というわけで、オムライスに加え、10種類くらいの各種野菜料理を堪能し、パフェも3回くらいお代わりし、ドリンクも飲みまくってしまったワタクシ。なんか、とっても幸せな気分。 ということで「太陽のカフェ」、ファミレスに毛が生えたようなもんかな~と多寡をくくっていたら、意外や意外、結構ハイレベルな料理とコストパフォーマンスの高い値段設定で、私を驚かせてくれたのでした。うーん、ちょっと、贔屓にしちゃおうかな~!
September 26, 2012
コメント(0)
-
「走れメロス」って、一体・・・
何の因果か、「教育実習の事前指導」というのをやらされまして。で、たまたま担当になったのが国文科の学生たちだったのですが、とりあえず彼らに「指導案」を書かせ、それを基に模擬授業をやらせてみたわけ。そしたらその中の一人が、太宰治の「走れメロス」を主題に取り上げたと。 実は私、この作品を読んだことがないんですな。もちろん、メロスが自分の身代わりになった友人の命を救うため、必死に走って戻る、みたいな話だということは、なんとなく知ってはいましたが。 で、学生の模擬授業を聞きながら、不明な点を問い質したりしていたのですが、その結果、この話の驚くべきストーリーを知ることに。 大体、どうしてメロスがどこぞの王様に捕まるのか、その理由を知らなかったので尋ねてみたら、メロスがたまたまその国を訪れたんだったか、通過した時に、その国の王様の暴虐ぶりを知り、それで激怒したメロスが王様の暗殺を企てた、というのですな。 ええ~っ! そうなの? いやあ、意外。じゃあ、メロスは暗殺者だったのね? しかも、急な思いつきで、無謀かつ無計画な暗殺を企てたと。 うーん、私だったら、そういう行動はとらないな。万が一取るとしても、暗殺を企てるなら、もう少し綿密に計画を練るな。 で、そんな無謀な計画だから、当然、捕まって処刑されることになる。 しかし、王様の暗殺を企てて捕まったのだったら、処刑されるのは覚悟のうちなんじゃないの? にも関わらず、メロスは「自分、ちょっと都合がありますので・・・」とか言って、無二の親友を自分の代わりに差し出す。 うーん! 私だったら、そういう行動はとらないな。いくらなんでも、それはしない。それはちょっと、人としてどうなのか・・・。自分の責任でやったことなんだから、甘んじて処刑されるというのが普通なので、無実の友人を巻き込むというのは言語道断なのではないかと。 で、親友を身代わりに立てておいて、自分勝手な行動をした挙句、もう少しで親友を見捨てるところまでいく。 しかし、結局、メロスは王様の下に戻って親友を救う(この状況をもって「救った」などと言えるのかどうか疑問とはいえ・・・)わけですが、その心の変化はどうしてもたらされたのかと学生に問うたら、「岩清水を飲んだから」だと。 ええっ! 良心の問題というより、「リポD飲んで元気が出たから」みたいな、体力的な問題だった、ってこと? 分からんなあ・・・。 で、戻ったメロスは、当然、処刑されたのかと思ったら、処刑されなかったんですって?! それも分からん。王様は、一体、どういう性格なのか。暴虐の限りを尽くしたかと思うと、温情溢れるところを見せたりして、一貫性がない! で、その模擬授業の学生は、「・・・このようにして、メロスの心の動きを生徒に理解させます」というのですが、私に言わせれば、メロスの心の動きや行動は、最初から最後までまったく分からないな。ついでに言うと、王様の行動も理解できない。普通、自分を暗殺しに来た奴に対して、こういう対処の仕方をするかね? というわけで、私には「走れメロス」という小説が、一から十までまったく理解できなかったのでした。だけど、学生たちに聞いてみたら、ほぼ全員が中学校くらいの時に、この小説を国語の時間に読まされた、というんですよね・・・。 一体、日本の国語の教科書って、どういう基準で作品を選定しているのだろうか。常識では考えられないような行動をとるメロスや王様の話を読んで、一体何が引き出せるというのだろうか。 私にはさーーーーーーっぱり分からないのでした。
September 25, 2012
コメント(4)
-

出色の映画本
久しぶりに面白い映画本を読みました。町山智浩・柳下毅一郎著『ベスト・オブ・映画欠席裁判』(文春文庫・895円)というのですが。 町山智浩氏については、以前『<映画の見方>がわかる本』(洋泉社・1,600円)という本を読み、そこそこ面白かった記憶があるのですが、これは折り目正しい真面目な本。一方『映画欠席裁判』の方は、柳下毅一郎さんという相棒を得、二人でその時々に見た映画について、過去の映画との関連も含めながら面白可笑しく漫談するという趣向の本で、まさに映画漫才。ハチャメチャな本でございます。 しかし、ハチャメチャにおふざけな本でありながら、そこはそれ、ほとんど誰も見ていないようなB級・C級の映画も含め、古今東西の無数の映画についてのディープな知識を基にしていますので、芯のところでの評価や批判は実に的確・適切。そして辛辣。爆笑しながら読み進めているうちに、「なるほど!」と思わされることが多く、また自分の中でバラバラに存在していた知識が、彼らの爆笑漫才の示唆によって有機的につながってくることもしばしば。もちろん、本書を通じて新しい知識を得たことも数限りなし。 例えば『千と千尋の神隠し』の話題でも、町山・柳下両氏の手に掛かると、この映画で舞台となる「湯屋」が実は赤い柱と赤ちょうちんに彩られた売春宿であり、千尋が「今日からお前は千だ」と言われるのも、源氏名をつけられたことを意味するのだ、というようなことが指摘され、そこからこの映画が千尋という少女の性的成長を描くものであり、かつ、その辺が本作のM監督の趣味なのであって、例の「カオナシ」は監督自身のリビドーなのだ、という話になっていく。 あるいは、『スター・ウォーズ』について、あれは主人公ルークの周りの人達が幸福になる一方、肝心のルークだけが孤独になっていくという構造の映画であり、またダース・ベイダーとルークの親子関係をめぐるいざこざが銀河系全体を巻き込んだどたばたにつながっていくという構造から言っても、『巨人の星』に極めて似ているなどという指摘がなされたりする。もちろん、ジョークとしてそういう指摘をしているわけですが、確かに星一徹・星飛雄馬の親子関係が日本の野球界全体に影響していくという構造、そして花形や左門が幸福な結婚をするのに、星飛雄馬だけが幸福を得られないという構造は、『スター・ウォーズ』に似ていると言えば似ている。 しかも、星一徹と星飛雄馬の親子対決は、いわば「星」同士の戦い、英語に直せば「スター・ウォーズ」だ、とまで指摘されると、もう、完成された漫談という感じさえしてきます。町山智浩という人、真面目な本を書くより、こういう本を書いている時の方が、キャラに合っているのではないかと。 ま、そんな感じで、おふざけと言えばおふざけ、しかし、示唆に富む指摘満載でもある本書、映画好きにはたまらない本でございます。めちゃくちゃ面白い! 教授の熱烈おすすめ!です。これこれ! ↓【送料無料】ベスト・オブ・映画欠席裁判 [ 町山智浩 ]価格:940円(税込、送料別) それにしても、映画についてこれだけ面白可笑しく、しかも示唆に富む本が書かれ得るなら、アメリカ文学についても、こういう本が書かれてもいいんじゃないでしょうか。勿論、文学の優れた読み手同士の対談ということであれば、これまでに何冊も例がありますが、しかし、やっぱりまだまだ硬いよね! 真面目過ぎ。『映画欠席裁判』レベルのハチャメチャ本は、まだ書かれていないのではないかと。 やっぱ、文学研究者って、基本的に真面目過ぎるんでしょうな。ワタクシを含め・・・。
September 24, 2012
コメント(0)
-
お見舞い
同僚の「叔父貴」ことO教授が入院されてしまったとの報せを受け、今日、お見舞いに行ってきました。 O先生、私がロンドンに行っていたのとちょうど同じ頃、アメリカはニューヨーク、ボストン、ノースカロライナと3都市をめぐる出張に行ってらしたのですが、帰国して成田空港に降り立ち、新幹線で名古屋に到着、さらに地下鉄に乗ってご自宅に戻ろうとされた刹那、猛烈な腹痛に見舞われたというのですな。ほうほうの体で自宅に着き、腹痛の薬を飲んで休んだのですが、痛みは増すばかり。 で、翌日、病院に行って診てもらったところ、胆石による急性胆嚢炎と判明、即入院と相成ったと。 胆石ですから、石を取り除けばいいわけですが、しかし、炎症が強いので、今開腹手術なんかするとばい菌が散って腹膜炎などの深刻な病気になりかねない。というわけで、今は炎症が鎮まるまで、待機中なのだそう。 しかし、ここからがえぐい話になるわけよ。 胆嚢が詰まっているわけですから、胆汁が分泌されてしまうと、それが圧力となって炎症を引き起こしてしまうんですな。だから、その分泌された胆汁を抜かなくてはならないわけ。 だから、お腹に30センチくらいの針をぶっ刺して、肝臓を刺し貫いて胆管に到達させ、そこから分泌された胆汁を抜くんですって! で、その針は刺しっぱなしだというのですから、さらにコワイ。 お腹にそんな長い針を刺しっぱなしって、どんな気分よ! 想像するだに怖すぎる。 O先生はここ2年程、重い責務の仕事に就いていらしたこともあり、ストレスというか、心労があって、それが最終的に胆石となって、まさに「結実」しちゃったんですかねえ。 まあ、これは神様が「少し休め」と言っているようなもんですから、O先生も仕事のことは放りだして、まずは胆石・胆嚢炎の治療に専念してもらいたいものでございます。叔父貴、頑張れ!
September 23, 2012
コメント(2)
-
横井製麺所
セルフ方式のうどん店、増えてますなあ。 家の近くにも、パッと思い浮かぶだけで丸亀製麺、讃岐製麺、きっちょううどん、製麺大学などなど、色々ある。で、ちょこちょこ試してみるのですが、まあ、どれもそこそこおいしいものの、記憶に残る旨さ、というほどでもない・・・かな・・・。 ところがね、最近、頭一つ抜き出た旨さのうどんのお店を見つけちゃった。日進市竹の山というところにある「四代目 横井製麺所」という店なんですが。 まあ、店のしつらえとか、セルフ方式のサービス方法とか、そういうのは他のセルフうどんチェーンとまったく変わりないのですが、肝心要のうどんがおいしかったのよ。 私がいただいたのは「とろろぶっかけ」という奴で、これにえび天をプラス。しめて400円くらいだったかしら。 で、食べ始めたら旨いんだわ。しこしこのうどんもさることながら、とろろとミックスした出汁の味が絶妙。久々に、しみじみ「旨いなあ」と思いながら、うどんを堪能しました。ロンドン帰りで日本の味に飢えていたということを差し引いても、記憶に残るほどの味でしたねえ・・・。 最近できた讃岐系のうどんチェーンは、大体どこもレベルが高いとはいえ、私の舌には「横井製麺所」が一番、アピールして参りました。今後は、ここを贔屓にしたいと思うのであります。 それにしても、昔はねえ、セルフうどんの店といえば国道沿いの「山田うどん」(←ひょっとして関東の人間しか分からないとか?)くらいしかなく、それもトラックドライバー御用達みたいな感じでなんとなく侘しい雰囲気が漂い、とてもわざわざ食べに出かけるようなところではなかった記憶がありますが、その頃のことを思い出すと、21世紀に入って讃岐うどんチェーン全盛の時代が来るなんて、予想もしなかったね。 逆に、今、山田うどんって、どうなんだろう。怖いもの見たさで、一度、食べてみようかな・・・。
September 22, 2012
コメント(0)
-
「にやける」の意味にビックリ
今朝の新聞に、日本人の日本語能力の衰退についての特集記事が掲載されていて、例えば66%の人が「漢字を書く力が衰えた」と自覚している、といったデータが出ており、メールの普及などで、手書きで文章を書く機会が減ったことなどが、こうした現象の要因として挙げられておりました。 で、それに加えて、「言葉の誤用」についても言及されていて、最近、慣用句の誤用が非常に多いという指摘もなされておりまして。 例えば「失笑」とかね。もちろん、「思わず吹き出してしまう」という意味ですが、そういう意味だと思っているのはわずかに28%ほどで、7割方の日本人は「笑いも出ないほど呆れる」という意味だと思っているのだそうで。「失笑」だから、「笑いを失う」と思うのですかね? 同じく「割愛する」も、本来の「惜しいと思っているものを手放す」ではなく、「不必要なものを切り捨てる」という意味だと思っている人が65%もいるとのこと。 あと、言い方自体を誤解しているケースも多くて、「舌先三寸」のことを「口先三寸」だと思っている人が57%、「二つ返事」という言い方を、誤って「一つ返事」と覚えている人が46%もいるらしい。 で、そんな記事を読みながら、ふむふむ、日本人の日本語力低下にも困ったものだのう、などと思っていたワタクシ。 が! 他人事ではなかった! かく言うワタクシも、一つ、重大な言葉の誤用をしていたことが判明! それは「にやける」という表現なのですが、皆さん、この言葉の意味、ご存じ? 私はまたてっきり、「にやにやする」という意味だと思っておったのでございます。ところがね、本当はそうではないんだそうです。 「にやける」という日本語の正しい意味は、「なよなよする」だったのだ! がーん! ショック。知らなかった。今まで「にやにやする」の意味でこの言葉を使ってた。 まあ、一つ慰められるのは、76%の日本人が、この言葉を「にやにやする、薄ら笑いを浮かべる」の意味で誤用しているということ。つまり、4分の3、圧倒的多数が誤用しているということですな。だから、この言葉を「なよなよしている」という本来の意味で使うと、逆に、大多数の日本人に意味が伝わらないということにもなる。 言葉なんてのは、結局、コミュニケーションのツールですから、大多数の人がそう思っている意味が通用していくのであって、いくら「本来この言葉の意味は・・・」と言ったところで多勢に無勢。近い将来、「にやにやする」という意味の方が勝って、「なよなよする」という意味は欠落していくことでございましょう。 それにしてもね、「自分は日本語を正しく使っている」などという過信は、しない方が無難だ、ということは言えそうですな。
September 21, 2012
コメント(0)
-
久々の道場
帰省やらロンドン出張やらがあったこともあって、今日は1か月ぶりに道場に行き、汗を流してまいりました。久々に受ける八光流の技の数々は、相変わらず猛烈に痛くて、汗というより冷や汗をかきっぱなしでしたけどね。 ところで、道場に行けない間、せめてイメトレだけでもしようと、動画サイトで八光流をはじめ、各種柔術の技を研究していたのですが、その中で、「この技、カッコいい!」と思ったのがありまして。これこれ! ↓巻き肘投げ これはまあ八光流の技ではないですが、練習仲間のMさんに「ちょっと、面白い技、かけていい?」とか言って、これを掛けてみたわけ。 すると、これがまあ、面白いように決まるのよ。八光流の技って、見かけ以上に難しくて、ビデオを見て真似して掛けてみたって、決まることなんかほとんどないのですが、この流派の柔術の技は、多分、誰が掛けても簡単に決まるのでしょう。 ただ、これは肘の関節を逆に極めているので、やりようによっては、相手に怪我をさせる技かもね。(ちなみに、八光流には関節を極める技というのは存在しません。) というわけで、基本的には私は八光流の信奉者ですけれども、習得が簡単で効果的という意味で、こういうのもちょっと勉強してみたいな、と、チラッと思う今日この頃なのでございます。
September 20, 2012
コメント(0)
-
ナンバープレート取得
愛車のナンバープレートを盗まれたことある人、手を挙げて~! その中で、自分で陸運局行って、プレートの再交付を受けたことある人、手を挙げて~! なかなか居ないよね、そういう経験の持ち主・・・。 ワタクシ、先日、愛車のナンバープレートを盗まれまして。再交付してもらうため、ディーラーに相談に行ったら、「代行してもいいですけど、ご自分でやられた方が安く、早くつきますよ」とアドバイスされ、意を決して陸運局行ってきましたよ。 行ってみて、ビックリ・・・。 市役所のようなところなのかと思っていたら、全然そんな感じじゃない。要するに、陸運局に用があって来る人の9割9分は業者なのよ。自動車関連業界の業者。「○○モータース」とか「○○オート」とか、そんな感じ。 だから、そこに居る人の半分くらいがつなぎを着ているというね。つなぎ着用率があんなに高いところ、行ったことなかったわ。 で、ほぼ全員が業者だから、慣れているわけ。例えば新車や中古車を売るので、ナンバーの取得が必要とか、そういう理由で、ほぼ毎日、陸運局に用があって来るような人たちばっかりだから、もう手続きに関しては熟知している。で、陸運局の方も、そういう人達相手だから、これまた慣れきっている。 だから、陸運局には、市役所なんかによくいる「案内係」的なポジションの人なんかいやしない。みんながみんな、ルーティン・ワークをもくもくとこなしている、という感じ。 一方、ワタクシは、こんなところに来るのは初めてなわけですから、まずどこへ行けばいいのかすら分からない。もうね、「途方に暮れる」とはこのことよ。 それでもどうにか、まずは必要書類を買わなくてはならないらしいということが判明して、35円で用紙を買い、それに必要事項を記入して提出。どうにかこうにか、新しいナンバープレートを入手することに成功。ナンバープレートって、1,440円なんですよね~。意外に安いものですな。 で、さて、新品のナンバーもらったので、こいつを愛車に取りつけてもらうにはどうすりゃーいいのかしら?と思って尋ねてみたら、「はい、これ」って、ドライバーを渡されました。 そう、陸運局には、ナンバープレートを取り付けてくれるセクションなんかないの。自分で取り付けるの。しかも私の場合、後ろのナンバーは盗られてなかったので、まずはこの古いナンバーを外さなくてはならないわけ。 で、後ろのナンバーって、封印されているでしょ? あの封印を自分でぶち壊し、古いナンバーをはずしてから、もらったばかりのナンバーを自分で取り付けるわけよ。慣れないワタクシにとっては、それだけでひと苦労。 で、最後の最後、取り付けたナンバーに封印をするところだけ、これは陸運局の人がやる。 というわけで、半日かけて、苦労して苦労して、新しいナンバープレートを愛車に取り憑けたワタクシ。疲れた~! まあ、ナンバーを盗まれるなんて経験、する人は少ないでしょうけど、盗まれるとこういう苦労が待っているんだ~ということが分かった私なのでありました、とさ。長く生きていると、色々な経験をするもんですなあ・・・。
September 19, 2012
コメント(2)
-
トイレだけは・・・
イギリスの話も、もうそろそろ仕舞いにしようと思うのですが、最後に一つだけ。 イギリス・・・に限らず、日本人が外国に行って何が一番不都合かと言うと、ずばり、トイレじゃないですかねえ。 人類の歴史と共に長い歴史を刻んできたはずのトイレの形。その最終形というか、行きついた最良最高の形が「シャワートイレ」ではないかと。 そして日本においては、この人類の英知とも言うべきシャワートイレの普及が進み、今や中以上のホテルなどにおいては付いていて当たり前になりつつある。これはもう、「日本に住んでいて良かった!」の世界であります。 が! これほど顕著に優れた発明物が、なぜに西洋先進国においてすら、一向に普及しないのかっ! 21世紀の「世界7不思議」と言っても過言ではないでありましょう。 ホント、不思議だよね~! だって、西洋人だって観光で日本に来るでしょう? それでホテルに泊まってシャワートイレに遭遇するでしょう? 使うでしょう? その良さが体感できるでしょう? なのになぜ、「これと同じものを、我が家でも使いたい!」と思わないのか。完全に理解不能だ。 イギリス滞在中、トイレだけはね~、日本が恋しくなりました。だから、帰国してシャワートイレに腰かけた時は、ほっとしましたねえ。 が! 日本のトイレにも一つだけ注文をつけたいことがありまして。 腰かける位置が低すぎる。 イギリスのトイレに身体が慣れたところで帰国し、日本のトイレに腰かけると、日本の方が腰かける位置が10センチくらい低いわけ。身体が期待している位置よりさらに低いところに便座があるものだから、およよっとなってしまう。 いやあ、日本のトイレ、非常に優れてはいるのですが、日本人全般の体格が良くなった今日、もう10センチくらい高い位置に便座がくるようにしつらえた方がいいのではないでしょうか。この便座の低さで腰を痛めていることが、結構あるんじゃないかなあ。 ということで、イギリス・レポートの最後は、尾籠な話で失礼いたしました~!
September 18, 2012
コメント(4)
-
紅茶の渋み
イギリスは紅茶の国、ってなわけで、本来紅茶好きのワタクシとしては、イギリス滞在中、喜び勇んで紅茶を飲んでいたわけですけれども、確かに旨い。その辺のスーパーで買ってきたごく普通の紅茶でも旨い。 で、そんな紅茶を日本に持ち帰って飲んでいるわけですが・・・これがね、どうも旨くないんだなあ。先日まで飲んでいた同じ紅茶とは思えないほど苦い。って言うか渋い。 で、家内共々「なんか違うよね。やっぱり水のせいかね」などと言い合っていたのですが、林望氏の『イギリスは愉快だ』(文春文庫)を再読していたら、次のような一節に出会いました: それゆえ、お茶といっても特にまた高価な、特別な種類を飲むというのではない。概してイギリスでは紅茶は呆れるほど安く(概ね二百五十グラムで二百円、ティーバッグ八十包で四百円というところである)、びっくりするほど豊富に種類があって、しまもどれもたいてい素晴らしくおいしいのである(イギリスのお茶がおいしいことについては、この国の水が非常な硬水であって、茶の中の苦みや渋みが溶け出さないということにも一つの原因があるだろうと思うのだが、そのことはここでは深く追及しないでおくことにしよう)。 なるほど、これを読むとやはり問題は「水」で、イギリスの硬水で淹れると旨いが、日本の軟水で淹れると苦み・渋味が出てしまうと、そういうことらしいのですな。ううむ、納得。 しかし、この一件も含めて思うのは、人間が本のみによって仕入れた知識が、如何にダダ漏れで頭の中から抜け落ちて行くか、ということですな。 例えば、こういうこともありました。 イギリスで「オーガニック」と表示のある牛乳を買って飲んでいたのですが、これね、蓋をあけて飲もうとすると、蓋の周辺にこってりと乳脂肪がクリーム状に固まってくっ付いていたりするのよ。で、そのことに感動したワタクシは、「なるほど! これが本来の牛乳というものであったか! 日本で売っている牛乳は、「成分無調整」などといいながら、しっかりホモジナイズ加工されているので、乳脂肪が固まるということがないのであるな・・・」と、あたかも大発見をしたようなつもりになっていたわけ。 ところが、先ほど挙げた林望氏の『イギリスは愉快だ』を読むと、こう書いてある: 牛乳は・・(中略)・・これまた安くて素朴で自然な味がするのだった。日本の牛乳のように均質化されていないので、瓶の口のところに、二、三センチ程の厚さにクリームが分離して浮いている。それを良く振って撹拌し、それからミルクジャーに冷たいまま入れて、これも食卓へ運んでいくのである。 ね、イギリスの牛乳の何たるかについて、ちゃんと書いてある。 私は林望さんのこの著書を、前々から何度か読んでいるはずなのですが、実際には細かいところまでは覚えてないのか、読み飛ばしているのか、頭に入ってないんですな。 あと一番びっくりしたのは、イギリスにおける養豚のこと。イギリスでは日本の養豚業で使用されるような、大型の「養豚舎(豚小屋)」というのはなくて、広い敷地に蒲鉾兵舎型の小さな小屋点在し、この小屋の中で豚さんたちが「家族単位」で飼育されるのですが、コッツウォルズに向かうバスの中でこうした豚さんたちのマイホームを見かけ、ふうむ、同じ養豚と言っても、イギリスの場合は随分人間味があるなあ、と思ったわけ。 そうしたら、なんと『イギリスは愉快だ』の中に「豚の個人主義」なる一章があり、この中で林氏は、イギリスのこうした養豚業のあり方に触れ、これをイギリス特有の個人主義の一つの顕れであろうと、堂々と論じておられたんですな。ひゃー、この章だって読んだはずなのに、全然覚えてなかったわ~。 というわけで、私の結論としては、「人間、本だけ読んでたって、なーんも知識は増えない」ってことですね。やはり、実際にモノを見ないとダメ。 その一方、ただ実際のモノを見るだけでもダメだと思うんですよね。知識を下敷きにして実際のモノを見ないと、見えてこないものがある。例えば、イギリスの博物館・美術館等で宗教画の傑作を幾つも見ましたが、宗教画なんて、知識がなければ、何を描いているのかなんて分からないし、意味が分からなければ、その良さも分かりませんから。 つまり、本を読んで知識を増やし、実際のモノを見て確かめ、さらにもう一度本を読んで確認する。このサイクルを繰り返さないと、本当の意味では知識は身につかないと。 私もそれなりにイギリスの小説を読んでいるつもりですけれども、それはもう頭だけで読んでいるので、今回イギリスに実際に行ってみた経験を踏まえて読み直すと、また色々分かってくることもあるのではないかと思うんです。そう考えると、楽しみが増えますなあ。
September 17, 2012
コメント(2)
-
イギリス人のプリンシプルと日本の黒い霧
イギリス滞在中、大英図書館でたまたま「Writing Britain」という特別展示をやっておりまして。これはどういうものかと申しますと、時代の変遷によって変わりゆくイギリスという国を、それぞれの時代の作家や詩人たちはどのように描写し、表象したか、ということを示す企画でございます。まあね、イギリス文学は専門外とはいえ、私も文学研究者の端くれ、こういう企画があるのならば、是非見たいと思ったわけですよ。 でね、イギリスってのは昔から緑豊かな大地でございまして、特に田舎なんかに行くと深い森がある。と、そこから例えば「ロビンフッド伝説」とか、そういう類の文学的表象が現れるわけ。いい時代でございます。 ところが18世紀に入りまして産業革命が起こる。産業革命ってのは、要するに蒸気機関の時代ですが、この時代、蒸気をどうやって作るかってーと、もちろん、石炭を燃やして作る。石炭ってのは、イギリスで採れる唯一の天然資源みたいなもんですからね。じゃんじゃん燃やす。 で、これがですね、イギリスの、とりわけロンドンの風景を一変させる。工場から排出される黒い煤煙、これが黒い霧となって大英帝国の首都を黒々と包み込んでしまうわけ。実際、この頃のロンドンを描いた絵も展示されていましたが、川沿いに工場の煙突が延々と立ち並び、モクモクと黒い煙が上がっている不気味な風景が描かれておりました。そのため、誰だったか、この時代の有名な作家さんが、首都ロンドンを評して「目に映るもの、煙突以外になし」という一文を綴っているのだとか。 しかも、煤煙を出すのは工場だけではない。家々の暖房、これだって石炭ストーブでやっているわけですから、冬になると住宅地の家々の煙突からもモクモクと煤煙が上がる。だからロンドンでは、とりわけ冬になると煤煙被害というのが酷いんですな、昔から。どのくらい酷いかというと、人が呼吸困難に陥って何百人単位で死ぬほど酷い。特に赤ん坊が死ぬケースが多かったようです。 で、この「黒い霧に包まれたロンドン」ってのを文学表象するのが、19世紀後半のディケンズだったりするわけよ。それからその暗さに乗じて犯罪が行われれば、シャーロック・ホームズも活躍することになる。「切り裂きジャック」だって、ロンドンの黒い霧の向こうからふいに現れると。 一方、中流の上より上くらいの人達は、そんな煤煙に煤けたロンドンなんかはおさらばしちゃって、田舎の本宅に引きこもり、しかし田舎じゃすることもないので、せいぜい隣近所で社交に精を出すことになる。これが、ジェイン・オースティンの世界ですな。 とまあ、そんな感じでイギリスの姿と、それを作家たちがどう描いたかというところが、時代ごとに展示されている。なかなか面白い企画でしょ? ところで、こんな感じで歴史的に石炭の煤煙に悩まされてきたイギリスですが、この「黒い霧のロンドン」がいつ頃から改善されたかというと、これが案外遅くて、1956年以降でございます。 これより少し前、1952年にこれまた想像を絶する煤煙被害というのがあって、この年の12月に1万人が死亡するという「ロンドン・スモッグ事件」というのが発生する。で、さすがにこれが契機となって、「どげんかせんといかん」ということになり、その結果、1956年に「空気清浄法」というのが出来る。これで、工場だけではなく(工場に関しては、既に石炭から石油の時代に移り変わっていた)、各家庭の石炭ストーブの使用が禁じられることになる。 で、この法律によって、急にではないですが、徐々にロンドンの黒い霧は少なくなり、今日に至ると、まあ、大雑把に言えばそういう具合らしい。 それにしても各家庭の暖房の要だった石炭の使用を法律で一気に禁じてしまうというのは、大変なことだったのではないかと思いますなあ。電気・ガス・灯油といったものへの転換は、スムーズに行ったのでしょうか。その辺は、文学者たるワタクシには、それこそ専門外なのでよく分かりませんが。 しかし、一つ思うのは、「黒い霧の根本原因は石炭なのだから、その改善のためには石炭の使用を法律で制限するしかない」というプリンシプルを一度決めたら、それが大変だろうがなんだろうが、実際に法律を作って「石炭禁止」を粘り強く断行するという、そのイギリス人のガッツね。これがスゴイ。って言うか、エライ。 ま、大体イギリス人ってのは、昔から「プリンシプルを決めて、方法を決めたら、あとは何が何でも断行」というスタイルでやってきたわけで、これがこの国の強さなんでしょうな。スペインの無敵艦隊を破り、フランスのナポレオン軍を破り、さらにはドイツのヒトラーをも打ち破った、その国としての強さの根っこは、多分、このスタイルにあるような気がします。ヒトラーがV2ロケットの「重力の虹」をイギリスに向って描いた時ですら、チャーチルは「ヒトラーには負けない」というプリンシプルを打ち出し、そのプリンシプルに国民も応えるだろうと期待し、実際、国民はこれに応えた。一旦、何かを断行するとなった時のイギリス人の頑固さを、ヒトラーは読み切れなかったんでしょうな。 で、そんなイギリスで教育を受け、イギリス人の気質を呑みこんでいた白洲次郎は、「日本にはプリンシプルがない」と嘆いた。我慢することにかけては日本人だってイギリス人に負けないはずなのに、プリンシプルがないばかりに・・・と。 さて、そんなことを考えながら日本に帰ってきたワタクシが、ですよ、日本に帰って一番に目にしたのが、自民党総裁候補者数名を並べてのインタビュー番組でございました。 で、インタビュアーの人が、「民主党は2030年代までに原発ゼロにすると言ってますけど、あなたのご意見は?」と尋ねると、数名の総裁候補者全員が否定的な答えをした。曰く、「代替エネルギーのめども立っていないのに、原発ゼロを宣言するなんて、民意におもねっているだけで、責任政党のやることとは思えない。それに原発に関するノウハウが失われれば、使用済み核燃料の処理すらままならない」と。 えーーー、イギリスじゃあ、庶民の暖房の要だった石炭の使用を禁止する法律をバンッと作って、ロンドンの黒い霧を追い払ったのにぃぃ?? 「石炭ストーブを禁止なんかして、イギリスの家庭を凍えさせるつもりかあ!」とか、そういう政治家が当時のイギリスにも居たかも知れませんけれど、そういう政治家の言う通りにした方が良かっただろうと、彼らは言うのでしょうか・・・? ま、日本の民主党にプリンシプルがあるかどうかは分かりませんが、自民党の総裁候補にプリンシプルがないことは見て取れるな。 大体、「原子力」っていうと、依然として「未来のエネルギー」的なイメージがあるようですけど、戦後から数えたってもう60年とか、そのくらいのお歳のエネルギーでしょ。還暦ですよ。そろそろ、このかなりのお歳を召したエネルギー源に代わるものを探そう、的なヴィジョンを持つ政治家とか、居ないの? 短期間とはいえ、イギリスに行って帰ってきて、色々なことを考えさせられるものでございます。
September 16, 2012
コメント(0)
-
「Eton Mess」の魅力
「イギリスは、料理が不味い不味いと言われているが、言われているほど不味くない」というのが、最近のイギリス料理事情についての一般的意見ではないかと思うのですが、実際、イギリスでの食事、不味くなかったですよ。 旅をしている中での食事ですから、外食とか、買い食いでの話ですけど、たとえば買い食いの定番、サンドイッチにしても、イギリスで食べるサンドイッチはすごくおいしかった。 これがね、アメリカの場合ですと、不味いのよ、サンドイッチが。不味いというか、飽きるのね。2、3回、サンドイッチが続くと、もう、身体の細胞が拒否し出す。 ところがイギリスの場合、飽きないんだよね! パン自体も旨いわけ。滋味があるというか。そして具もね、シンプルだけど素直に旨い。だから、サンドイッチを一口一口、ゆっくり噛み取りながら、ゆっくり咀嚼していくと、じんわりと旨味が伝わってくる。 そういうこともあって、今回の滞在では「日本食が食いたいっ!」という禁断症状を一度も感じなかったです。 それどころか、イギリスで、「こいつは旨いっ!」と思ったデザートも一つ見つけちゃいました。それが「Eton Mess」。イギリスの伝統的なデザートなんだそうですが。 これね、作り方は簡単。メレンゲを適当な大きさに崩し、そこにホイップ・クリームとフレッシュな苺を加え、さらに苺シロップをちょいとたらして、ぐるぐるとかき混ぜる。これだけ。簡単でしょ? メレンゲのサクサクとした歯触りとなめらかなホイップ・クリーム、そして苺の組み合わせが最高。メレンゲが甘いので、ホイップ・クリームの方は甘さ控えめにするのがポイント。 だけど、作り方も簡単だし、めちゃくちゃ旨いのに、日本のレストランで「イートン・メス」を出すところなんかないですよね? ケーキ屋さんでも見たことない。ま、ケーキとかの修行をする人の目ってのは、多分、フランスの方を向いているので、イギリスのデザートを研究しようなんてアレはないのかな。 だけど、「人のやらないことをやる」というのが、「釈迦楽イズム」ですから。私がもし、飲食店を経営するのだったら、まだ日本でなじみがない「イートン・メス」を日本に紹介して、話題を取りに行きますけどねえ。 もちろん、ちょっと自分なりの工夫も加えたりして。ホイップ・クリームの代わりにアイスクリームで代用したらどうかな? とか、苺だけじゃなく、ブルーベリーやラズベリーも加えてみたらどうかな? とかね。 ま、それはともかく、不味いと言われるイギリス料理にも、見るべきところは沢山あるということを自分の体験として感じてきたワタクシなのでありました、とさ。
September 15, 2012
コメント(2)
-
パブなるものとサイダー
イギリスと言えば、パブ、なんでしょ? なんか、そんなようなことをあちこちで読んでいたもので、私も今回初めてイギリスの地に渡るに際し、一度はパブってところに行ってみようと、まあ、そう思っていたわけですよ。 で、実際に行ってみた。 パブにはパブの作法ってのがありまして、パブに行ったらまず席(テーブル)を確保するというのが重要なんですな。テーブルにはそれぞれ番号が振ってあるので、その番号を覚えておく。 で、カウンターに行きまして、飲み物と、つまみを食べる場合はつまみを注文する。フィッシュ&チップスとか、そういう奴ですな。で、飲み物はその場で出されるので受け取ればいいのですが、料理の方はテーブル番号を伝えておいて、後から運んできてもらうと。お金は注文するときにそのままカウンターで支払います。 さて、パブで飲むものと言えば、ビールですが、ラガー、ビター、スタウトと種類がある。ラガーは日本のビールに近いですが、ビターはもう少し色が濃く、味も濃い。ビターの中でも古来の製法で作られたものをエールといい、まあこの二つは同じようなもの。で、スタウトはいわゆる黒ビールで、たいていの人は「ギネス」銘柄を選びます。 で、イギリスのビールってのは、日本のビールと異なり、喉で飲むのではなく、舌で飲む。あまり冷やさず、じっくり時間をかけ、味わいながら飲むものでありまして、これが日本のビールのようにキンキンに冷やしちまうと、逆に苦味だけが強調されてしまう。とろとろと、ビール本来の甘みと苦みを堪能しながら飲むのが流儀。 ま、この辺までの情報は、モノの本にはいくらでも書いてあるから、大したことじゃないわけ。 ところがね、実際にイギリスに行って驚くのはそういうことじゃないの。 あれは金曜日の午後6時頃でしたか。たまたまバスに乗って、ロンドン市内を移動していたんですな。イギリスの9月というと、8時頃にならないと暗くならないので、6時というとまだまだ午後、という感じ。 で、そんな中、ワタクシの目をくぎ付けにしたのは、通りに面した一軒のパブだった。 いわゆる「黒山の人だかり」って奴。ほぼ全員がスーツを着ていましたから、あれは多分、ほぼ全員が会社帰りのサラリーマンとOLだったのでしょう。それがパブに密集しているわけ。店の中には入りきらず、道にまで溢れ出し、なかば道で飲んでいる。それも、びしっとスーツを着こなした人たちが。ほとんど、通勤電車に近い混雑ぶりでございました。 で、さらに驚いたのは、20メートルほど離れたもう一軒のパブが、やはり同じ状態だったということ。 ああ、イギリスの会社員は、老いも若きも、会社帰りにパブで飲むんだ、ということ。この実態を目の当たりにして、仰天よ。 ロンドン市内には6千軒のパブがあるそうですが、ほんとに彼らはパブという施設を愛し、これなしではいられないんだ~・・・ということが「黒山の人だかり映像」によって、私にも実感としてはっきり分かりましたわ。 ところで、イギリス人はかくもパブとビールを愛好するわけですが、もうひとつ、彼の地で人気のある酒にサイダーというものがある。リンゴとか洋ナシから作る発酵酒ですな。 で、酒としてのサイダーは、私も日本に居る時から何度か飲んだことがありますが、やけに甘ったるい酒、という感じがして、それほど好きではなかった。 ところが、イギリスで飲むサイダーは旨かったのよ。 なんかね、にごりのある褐色をしていて、さほど甘くはなく、ビールに近い味わいなんですな。さりとて、ビールほど苦いわけでもない。その辺の塩梅が、癖になると癖になる。 私のお勧め銘柄は、「Bulmers」という奴。黄色くて目立つパッケージなので、スーパーなどでもすぐ分かる。日本でも売ってないかしら? 今度お酒屋さんに行った時、探してみようっと。 ただ、サイダーという飲み物は、ビールとの飲み合わせが極端に悪いらしく、この二つを一緒に飲むことを「snakebite」と呼ぶのだそうです。毒蛇にかまれたように、シビレルらしい。だから、サイダーを飲む時は、それだけを飲むのが安全なようです。既にビールで乾杯しちゃった人には、絶対に勧められないそうですから、その点はご注意を。
September 14, 2012
コメント(2)
-
何、この暑さは?!
はーい! 名古屋に舞い戻ってきました~! 今回、イギリスとの往復に初めて Finnair を使ってみたわけですけれども、いいね。いい。気に入っちゃった。 何がいいって、パイロットの腕がいい。ヘルシンキ経由なので、往復で4回離陸と着陸を繰り返すわけですけれども、特に着陸のスムーズさは特筆もの。着陸の時に飛行機酔いする傾向のある家内も、今回は一度も気分が悪くならず、快適な旅を楽しめました。ま、天候に恵まれたせいもあるかと思いますが、アメリカ往復でよく使うあのアメリカの飛行機会社より、いい感じがしたなあ。フィンエアは値段も安いしね! ま、それはさておき、2週間ぶりに祖国の土を踏んで、その蒸し暑さにあらためて仰天。何、この暑さは! 2週間前と全然変わってないじゃん? もうチョイ秋方向に進行してくれているのかと思ったら、さにあらず、ですなあ。既に日本の11月初旬くらいの気候だったイギリスから、8月とまるで変わらない日本の暑さに戻ると、こたえるわ~。 そんなこともあり、また若干の時差ボケもあり、なんかボンヤリしちゃって、旅装を解くのもままならず。ま、本格始動は明日からということにしましょうか。 ってなわけで、とりあえず無事安着のお知らせだけで今日のところはご勘弁を~。
September 13, 2012
コメント(0)
-
明日は帰国
さて、2週間の短いイギリス滞在でしたが、それも今日まで。明日は名古屋に向けて帰国の途につきます。 今日もロンドン最後の一日を充実させるべく、色々なことをやったのですが、またその辺のことについては日本に帰ってからちょこちょこ報告して行きましょう。 それでは、飛行機嫌いの私のために、道中の無事を祈っていて下さい。名古屋からのお気楽日記の再開をお楽しみに!
September 12, 2012
コメント(0)
-
業界人よ、イギリスに『劇的ビフォー・アフター』を売れ!
イギリスで朝食を食べながら何とはなしにテレビを見ていると、やたらに「家のリフォーム番組」を放映しているんですよね。で、面白いからつい見ちゃう。 イギリスの場合、新築の家を建てる、ということはまずなくて、中古物件を買うのが普通なんですな。そのため、家の売買のためのオークションがあちこちであるらしい。家を買いたい場合は、不動産屋さんで中古物件をいくつか回り、気に入ったものがあればその物件をオークションで競り落とすと。 しかし中古物件ですから、中には内装がぼろぼろということもある。それを、新しい持ち主になった人が自分の好みにリフォームしていく。だから、テレビ番組でもリフォームをテーマにしたものがやたらにある。 で、私、思うのですが、日本のテレビ番組にある『劇的ビフォー・アフター』という奴、アレをですね、イギリスのテレビ局に売り込んだら、売れるんじゃないかと。リフォームを「リフォーム番組」ではなく「エンターテイメント番組」にするという発想、あれはまだイギリスにはありませんからね。 かつて日本のテレビ局が作った『料理の鉄人』という番組、あれは料理を作ることをバトルに仕立てるという形で、非常に面白い料理番組に仕立てた。で、それがアメリカで大受けし、『料理の鉄人』そのものも放映していましたし、それに類する番組が立て続けに出来た。あれは日本のテレビ番組がアメリカのテレビ界に貢献した一例であります。 だからさ、『劇的ビフォー・アフター』をイギリスのテレビ局に売り込めば、絶対受けるって。 ちなみに、今、イギリスで見られる日本のテレビ番組が何か、ご存知? なんと、『風雲たけし城』ですよ。これだけ。若々しいビートたけしさんの勇姿が、今、イギリスで見られるという。 しかし、いくら何でも四半世紀も前の番組だけというのは、あまりにも寂しい。日本のテレビ文化の実力を、もっと海外に示そうではないですか。 ということで、日本のテレビ業界のみなさーん! イギリスに『劇的ビフォー・アフター』を売りなさーい! このリフォーム番組がイギリスで受けることは、私釈迦楽が保証いたします。
September 10, 2012
コメント(0)
-
オックスフォード大学
オックスフォード大学に行ってきました。「クマのパディントン」でおなじみ、パディントン駅から電車で約1時間、英国最古にして最高の学府に到着した次第。 偶然、今日は年に2回しかないという大学開放デーだったため、有名なクライストチャーチ・コレッジはもとより、普段は一般人には公開しないクイーンズ・コレッジまで見学することができたのですが、まあ、圧倒されましたね。 もうね、なんつーの、日本の薄っぺらい書き割りみたいな校舎で学んで来た私たちが、オックスフォード大学の広大かつ重厚かつ数百年に亘る歴史が塗り込められたコレッジの数々を見ますと、「ああ、これが大学ってものなのか・・・」と痛感されるわけ。今まで「大学」だと思ってたものは何だったのだろうと。 アメリカの名門諸大学、例えばUCLA、バークレー、スタンフォード、シカゴ、ハーバード、ボストンなど、色々見てきて、確かにこれらの大学もすごいなと思いましたが、いたく感心こそすれ、「負けた・・・」って感じはしなかったんです。「想定内」のすごさでしたからね。 だけど、オックスフォード大学みたら、完全に「負けた」と思いました。想定外のすごさだもん。 こういうところに留学とかして、営々と続けられて来た学問の積み重ねの歴史に耐えながら、その歴史に連なるというような経験をしていたら、どうだったのか、なんてね、つい考えちゃいましたわ。もう一度生まれ変われるなら、若い時に思い切ってこういうところに飛び込んでみたいなと。 ってなわけで、今日見たものを思い起こしながら、自分の勤務先大学の安普請の校舎や研究室の光景を思い出すと、そのあまりの落差にめまいがしてくるワタクシなのでありました、とさ。
September 10, 2012
コメント(0)
-
コッツウォルズ行
ロンドンから200キロほど北西に足を伸ばし、コッツウォルズという地域に行ってきました。19世紀末のイギリスで起こった「アーツ&クラフツ運動」の主導者、ウィリアム・モリスがイギリスで最も美しい町と絶賛したバイブリーという町を含む、イギリスの古い宿場町のある地域でございます。ま、最近では日本の観光客にも人気のあるところですから、詳しい人は私なんぞよりよっぽど詳しいのでしょうが。 そもそもコッツウォルズ地域というのは、ロンドン周辺の4つの都市、すなわちオックスフォード、バース、チェルトナム、そしてシェイクスピアの生誕地として有名なストラトフォード・アポン・エイボンを結ぶ交通の要衝であり、また羊毛の産地として栄えたところなんですな。 ところが産業革命が起こって木綿生産がイギリスの主要産業となると、コッツウォルズの羊毛産業は廃れてしまう。また産業革命に欠かせない石炭がコッツウォルズではまったく採れなかったことも、この地域が産業革命と歩みをともにすることが出来なかった理由の一つ。しかも、コッツウォルズというのは海抜200メートルから300メートルくらいの高地(1000メートルを超える山がないイングランドにおいて、海抜200メートルというのは立派に高地と言えた)にあるため、鉄道の敷設もなされなかったと。 つまり、産業革命以後のイギリスの経済構造の中で、コッツウォルズは完全に取り残されて行くわけ。 で、往年の栄光はどこへやら、コッツウォルズの村々はすっかり落ちぶれていくのですが、ここでウィリアム・モリス登場。彼は、産業革命後、画一的な既製品がイギリスの市場を席巻していくことを嘆き、昔ながらの手作りの良さ、手工業の重要さを訴えるとともに、そうしたものを基礎に成り立つ昔ながらの人間の生活を、現代生活の中に出来る限り取り戻そうとした。 で、そんなモリスには、産業革命の波に取り残されたコッツウォルズこそ、自分の主張する生活がまだ残っている地域と映ったわけ。で、コッツウォルズの村々の美しさをことあるごとに称揚し、自分の芸術家仲間にも喧伝した。で、モリスの影響を受けた芸術家らがこぞってコッツウォルズを訪れるようになって、次第にこの地域の村々が、いわばイギリスの心のふるさと、一種の理想郷と見なされるようになっていくんですな。そして、その当然の帰結として、一度は落ちぶれた町、コッツウォルズは、観光産業で食っていけるようになると。 禍福はあざなえる縄のごとしと言いますけれども、文化の進展から取り残されたからこそ、それが逆に幸いして、一大観光地となり、今日の繁栄をつかんだ、それがコッツウォルズというところなのでございます。 こういうコッツウォルズの成り立ちを聞くと、色々考えさせられることがありますね。進化の競争で、トラックの一番後ろをよろよろと走っているうち、一周遅れでいつのまにか自分が集団の先頭になっていた、みたいなことが、この世にはあるんだなと。 ま、それはさておきまして、私はもうまさにツーリズムの奴隷と成り果て、ブームに乗ってこの地を見物に訪れたわけでありまして、ウィリアム・モリスの志からすると大分落ちるのでございますが、まあ、その辺はご勘弁ということで。 で、先ほど一大観光地となり、と言いましたが、実際にこの目で見るコッツウォルズは、当地に産出する「ハチミツ色」の砂岩を積み上げて作った石造りの家々が立ち並ぶ静かな村々でありまして、一時期の清里のような、浮かれ果てた観光地ではまったくありませんでした。一つ一つの村は、それこそ10分も歩けば端から端まで歩けてしまうような小さな村に過ぎません。 が、そのたたずまいがね、いいのよ、やっぱり。噂の通り。ああ、こんなところに別荘でも持って、四季の移り変わりを楽しみながら老後の数年でも暮らしたらどうなんだろうと、つい思っちゃいました。 ま、地元の不動産屋を覗いて、ちょっといいなと思う物件の値段を見たら、日本円で8千万円くらいして、あら〜、ちょっと無理かしら〜、という感じではありましたけどね。 ってなわけで、おとぎ話の頁からそのまま切り取って来たようなコッツウォルズの村々を夢見心地に散策しながら、色々なことを考えたワタクシだったのでした、とさ。
September 9, 2012
コメント(2)
-
七三分けを見直す
ロンドンの地下鉄に乗っていると、地下鉄の雰囲気が東京の地下鉄の雰囲気に似ているので、妙に落ち着く、というところがあります。これがNYの地下鉄だと、もう少しヤバい感じがして、気が抜けないんですが。 ま、地下鉄に乗っている人の多くが、新聞かなにかを一心に読んでいるあたりが、東京っぽいのかな。 ということで、ロンドンの地下鉄って、なんか心落ち着くところがあるのですが、ただ一点、ちょっと東京と違うなと思うところがありまして。それは何かと言いますと・・・ 「七三分け」です。 なんかね、ロンドンのサラリーマンって、髪型が七三分けの人が多いんですよね。きっちり、キレイに七三に分けている人が。でまた、それが似合う人が多いんですな。「私、オックスフォード出ですけど、それが何か?」みたいな雰囲気を出しつつ。 翻って、今東京とか日本で、そこまでキレイに七三分けにしている人って、中井貴一くらいしか思いつかない、でしょ? やっぱり、基本、紳士の国って感じがしますね。折り目正しい七三分け。カッチョいい! で、家に帰って、自分も七三分けにしてみた、と。 なんか、変。 やっぱり、アレですね。七三分けも、気合いとある程度の年期が必要な気がしますな。 ま、それだけのことですけど。
September 8, 2012
コメント(0)
-
ブッククラブなるもの
今回、短期滞英の理由の一つは、イギリスの読書事情を調べる、ということだったのですが、中でも「ブッククラブ」というものに興味がありまして、イギリスに多いブッククラブとはいかなるものか、というのを現在調査中なのでございます。 で、文献を調べるのもいいのですが、実際にブッククラブに参加しちまえば、一番手っ取り早くブッククラブの何たるかが分かるのではないかと。まあ、そのように思いまして、とあるブッククラブに飛び入り参加して参りました。 日本では、「読書」と言いますと、個人個人の営為、という感じがします、よね? それぞれが好きな本を買うなり借りるなりして読む。以上、終わり、みたいな。もちろん、文学には「研究」という側面がありますから、文学研究者が学会などで特定の文学作品を論じ合うということはあります。しかし、それはかなり特殊なケースなので、普通の人は、文学作品を読んで、それについて語り合うということはまずしない。 ところが、イギリスではブッククラブというのがかなり定着しておりまして、探せば無数にある。文学作品の王道を読むブッククラブ、SFを読むブッククラブ、ロマンスを読むブッククラブ、探偵小説を読むブッククラブ・・・と、よりどりみどり。で、そういうクラブのメンバーとなって、例えば月一くらいのペースで会員が集まり、読んだ本について語り合うという場がある。 で、先日私が参加したブッククラブは、割と真面目な小説を読むクラブでして、今月の課題作品はアメリカのユダヤ系作家シンシア・オジックの『Foreign Bodies』でした。 ま、私はこの作品を読んでいないので、メンバーの討論の細かいところまではついて行けませんでしたが、それでも討論は活発。といって、学会のような雰囲気ではなく、ごく普通の本好きが、この本のこういうところが好き、だとか、この辺の書き方がどうも下手なんじゃないかとか、自分としては全然共感できなかったとか、そういうごく自然な好悪を披瀝し合うわけ。個人的な経験に引きつけて作品を語る人もおり、まあ、話題百出と言う感じ。 で、最後に皆でこの作品に点数をつける。「私は10点中7点」とか、「私はもうちょっと低い。5点」とか。で、一通り論じ合ったところで、次の会合までに読む本を決め、そして解散と。そんな感じでございました。 とにかく、難しいことはなんにもなくて、ただ読んだ本について自由に語り合い、互いに意見を交換しあう。そういうのを楽しむわけですな。 その意味で、この地では、読書はきわめて社会的な経験である、と言ってもいいでしょう。 とまあ、その辺の感覚を、実際にブッククラブに参加してみて、私はひしひしと感じたのでございます。ま、この先、この話題について書く時に、今回の体験は非常に役に立ちそう。旅の恥はかき捨てといいますが、思い切って見知らぬ人たちの間に飛び込んでみて、面白い経験をさせてもらいました。
September 6, 2012
コメント(2)
-
「サービス・アパートメント」礼賛
イギリスに居ると日本のニュースはネットで確認するしかないのですが、時折チェックすると、それこそ目を疑うようなニュースがありますね。大学生が小学生の女の子を鞄に詰めて持ち運んでいたんですって? 京極夏彦の『魍魎の匣』という小説に、(殺した)女を匣に隙間なく「みっしり」詰めて運ぶ男の話が出てきますが、なんかその話を思い出しますなあ。ま、今回の女の子は殺されなくて良かった。 それはともかく、今日は私のイギリスでの宿を紹介しましょう。 「Booking.com」というサイトで見つけ、日本で予約をしていったアパートなんですが、日本で言う「ウィークリー・マンション」みたいなものでしょうか。ちゃんとしたキッチンがついていて自炊も出来るというところがいいところで、まあ、普通のアパートのように使えるわけ。 しかし、アパートよりさらに優れているのは、「サービス付き」というところでありまして、こちらが断らない限り、毎日掃除をしてくれ、ベッドメイクもしてくれ、リネン類も全部替えてくれ、流しに使用済みの皿やコップがあればそれも全部洗って行ってくれるんですな。だから、午前中にどこかに出かけ、夕方帰って来ると、もう部屋が全部きれいに片付いている。それはもう、実に気持のいいものでございます。 もちろん、そういうサービスがある分、家賃は高いわけですが、しかし、自分で独自に家政婦さんを雇うコストを考えれば、よほど安いとも言える。こういう「サービス・アパートメント」というのは、多分まだ日本にはあまり存在しないのではないかと思うのですが、例えば多少経済的に余裕のある老夫婦が、もう自分で家事をするのは面倒だけれど、かといって老人ホームに入るのも剣呑だ、というような場合、もしこういうサービス付きのアパートがあったらいいのではないでしょうか? で、今回、こういうタイプのアパートを借りてみて、なかなか良かったなあと思っているわけですけれども、もう一つ、良かったと思っているのは、アパートの立地。ロンドンのことに詳しいわけではなく、たまたまサウスケンジントン辺りの治安がいいらしいと小耳に挟んだために「グロスター・ロード」という地下鉄の駅の近くのアパートを借りたわけですが、結果としてこれが大成功。というのは、グロスター・ロード駅は地下鉄の路線が3つ、乗り入れていて、この3つを駆使すると、ホント、何処に出るのにも楽なんです。 ということで、もしまた次にロンドンに来ることがあるとしても、私は絶対、「サウスケンジントン」駅か「グロスター・ロード」駅か、この二つのうちのどちらかから近いところに宿を取ることにするつもり。 とまあ、そんな感じで、偶然にせよ、我ながらなかなか上手いところに宿を定めたものだと、自画自賛しているワタクシなのであります。
September 5, 2012
コメント(3)
-
チャリングクロス街見参!
古本をこよなく愛す者として、イギリスに行ったら是非行ってみたいと思っていたのがチャリングクロス街。そう、イギリスの神保町とも呼ばれる、古本屋が並ぶ通りでございます。 チャリングクロスの古書店街に行くには、地下鉄のチャリングクロス駅ではなく、もう一つ先の「レスター・スクエア」で降りるのでありまして、そこから少し南に下ったところに「セシルコート」という路地があり、ここがイギリスの古書のメッカ。で、私もそこに行った訳ですよ。 が! 確かにいかにも由緒正しい感じの古書店が並んではいるものの、いかんせん規模が小さい。イギリスの古書の中心地がこの程度かあ、という感じ。また、ここの通りに並んでいる店は専門的過ぎ、私のようにどちらかというと雑書の方に興味がある向きにはちょっと縁遠い感じ。神保町で言えば、昔の北沢書店みたいな感じと言いましょうか。分かる人には分かると思いますが。 で、セシルコートは早々に退散し、チャリングクロス・ロードを北上、もう少し庶民派の古本屋をあたる事に。 と、確かに南北に延びるチャリングクロス・ロードの東側に庶民的な古本屋が何軒か並んでおります。ただ、道の東側に並んでいるというところが日本の神保町と違うところで、神保町だったらこういう場合、道の西側の方に店が並ぶんですけどね、西日を避けるために。古書にとって最大の敵は、お天道様なのよ〜。 ま、それはともかく、この辺りにある古書店を片端から覗いて行くと、一軒だけ、何だかものすごい人だかりの店がある。その店は2時開店らしく、その開店を待ちわびるように、行列が出来ているわけ。 で、開店前に行列が出来る古本屋って、一体何なんだ? と思い、もちろん私も列の最後尾に並んでみましたよ、とりあえず。 待つことしばし、ついに開店時間となった。と、それまで大人しく列をなしていた平均年齢58歳くらいのおっさん達が、前の人を押しのけるように店に突入していくではありませんか。で、私も、訳も分からず、負けじとばかり店に入ってみた。と、おっさん達は、店の奥にある細い階段を使って地下にまっしぐら! 私もまっしぐら! で、ようやく事情が分かったのですが、どうやらこの店は月に一回、地下の書棚の商品(=本)を全取っ替えするらしいんですな。で、その月一の日が今日だったと。だからイギリスの古本マニアたちが、この店の新入庫の古本を見るために、わざわざ並んでまで開店時間を待っていたというわけ。 というわけで、ほんの偶然から、チャリングクロス街名物の新入荷本セールに私は立ち会ってしまったのであります。我先に新入荷の古本に飛びつき、鵜の目鷹の目でたちまち十冊ばかりの本を選び出して小脇に抱え、さらに獲物はないかと目を皿にして書棚を睨んでいるイギリスの古本マニアのおっさん達を見ていて、古本マニアの生態に彼我の違いはないのだ、ということが分かりましたわ。おっさん達の中には、古本マニアとして互いに顔見知りの人もいるようで、「よう、また会ったな」などと言葉を交わしているところなどは、日本のヲタクとまったく変りませんな。 とまあ、そんな感じでチャリングクロス街を堪能したわけですけれども、私としては収穫なし。ま、私が探す本は特殊ですからね、そう、おいそれとは手に入らないのよ。だけど、いいの。古本というのは釣りと同じで、釣れたかどうか、というのは、楽しさとはあまり関わりはないの。探していた本が見つかれば楽しいけれど、別に見つからなくてもいいので、ただ期待を持って探すこと自体が楽しい訳。だから、収穫がなくても私は満足。 しかし、神保町を知り尽くす私としては、チャリングクロス街、口ほどにもなし、というところかな。規模の点でも、神保町の古書店街というのは、世界に冠たるものであって、あれを凌駕するものは、多分、世界広しといえども、ないんじゃないかな。 ま、今回は無理そうですけれども、もし次の機会があれば、今度はイギリスの古書のもう一つのメッカ、「ヘイ・オン・ワイ」に行ってみたいものでございます。
September 5, 2012
コメント(0)
-
お湯沸くの早っ!
イギリスで何が驚くって、お湯の沸く早さね。電気式のポットでお湯を沸かすのですけど、スイッチを入れた途端に沸くという感じ。さすが240ボルトのお国柄。100ボルトの日本とは訳が違う。以前、イギリス生活経験者から「お湯沸くの早いよ〜」って聞いてはいましたけど、ここまで早いと笑ってしまいますな。 イギリス生活4日目ですけど、日に日にイギリスという国の豊かさに気づかされる日々でございます。 確かに資源という点から言えば、日本と同じ位大したことない国ではありますが、日本と同じ位の国土に人口が半分しかいない。で、人の立ち入りを拒むような峻厳な山と森だらけの日本とは異なり、基本的に高山がなく、国土の全部がゴルフ場みたいな環境だけに、土地に余裕があるんですな。で、さらに地震がないから、数百年前の石造りの建物がそのまま現在に引き継がれている。つまり、富の蓄積が可能なわけ。 ま、そういうこともあってか、ほんと、同じ島国とは思えないほど、ゆったりしております。今日は家の近くにあるケンジントン・パークをちらっと散歩してきましたけど、まあ、広大でのんびりしていて、いいところでございました。でまた、この広大な公園の回りにあるマンション群の壮麗なこと。 外国かぶれと言われるかも知れませんが、なんかちょっとどこかの国とは違うなあと。GDP世界第何位という尺度でははかれない豊かさを、そろそろ我が国も考えなくてはいかんのじゃないですかねえ。
September 4, 2012
コメント(0)
-
イギリスは、意外に景気がいいよ!
生憎、というべきか、たまたま選んだアパートの立地がやたらに良かったものですから、今日も地下鉄で一駅先のサウスケンジントンまで行き、ヴィクトリア・アルバート博物館に行ってしまいました。 世界最大級の博物館だけあって、まあ広大。その中に、絵画・彫刻はもちろんのこと、宝飾品から銀器、家具から本、電気製品から服飾に至るまで、ありとあらゆるジャンルのお宝が展示してある。一言で言えば、「金銀財宝がざっくざく」という奴。すごいよ。 特にラファエロの部屋なんざ、体育館かってな広大な部屋に、巨大としかいいようのないラファエロのタペストリーが何枚も展示してある。一番有名なのは「奇跡の大漁」という奴ですが、私にとって一番面白かったのは「聖ジョージの殉難」を描いたタペストリー。このジョージ、ドラゴンを退治してヒーローになったところまでは良かったものの、その後はキリスト教徒嫌いの王様にとっ捕まって、「台の上で拷問を受ける」とか、「なんとかの上で拷問を受ける」とか、とにかく拷問されまくった挙げ句、「しまいに首を切られる」とか言って殉教してしまう。どこまでつらい生涯だよっ、と思うのですが、そういう聖ジョージの生涯をラファエロが漫画のコマ割りみたいな感じでタペストリーにしているんですな。確かにこれ見たら、聖ジョージに興味が出ますわ。 でまた、こういうお宝をたーくさん展示してある巨大なこの博物館、イギリスの美術館の多くと同様、入館料がタダ。それがすごいなと。 そもそもこの博物館は、その昔、ヴィクトリア女王の旦那さんのアルバート公が、労働者階級の臣民に少しは世界の文物を見せて教化啓蒙してやろうってんで作ってしまったわけですが、その高飛車な設立理由は措くとして、とにもかくにも、文化的なものを人々に無料で提供しようという、そのイギリスの伝統がすごいじゃない。それに引き換え、日本なんてお宝を見せるとなれば、1,500円くらいの入館料はすぐ取る。彼我の違いは大きいと言わざるを得ないでしょう。 ところで、上に述べたような文化にまつわる太っ腹さ加減もそうなんですけど、イギリスって、今、景気がいいんですかね? ま、サウスケンジントンというところが高級住宅街だってこともありますが、しかし、今、イギリスの町中を走り回っているクルマがすごいことになっていて、高級車の展示会か、ってなくらい。で、道ばたを見ても、高級車がばんばん路駐されてるの。ベンツ、BMWなんてのは貧乏人の乗るクルマで、マセラティとかね、レンジローバーとか、アストンマーティンとか、ポルシェとか、フェラーリまで平気で路駐ですからね。日本の道を走っているクルマと、イギリスの道を走っているクルマ、それこそ5倍くらい値段の開きがある。 何なの、この景気の良さは? ひょっとして、アラブ・マネーが流れ込んでいるとか? というのも、ちょっと高級な店を覗くと、買っている人はみんなアラブ系の人たちばかり。まあ、あの人たち、どんだけお金持っているんだろうって感じです。 まあ、その辺、一体何がどうなっているのか、私なんぞには皆目分かりませんが、日本に居たのでは到底分からないような世界のお金の動きが、ここイギリスでは何となく感じられるというところはあります。 そういうことを知るためにも、やっぱり、たまに日本の外に出ないといけないんでしょうな。
September 3, 2012
コメント(0)
-
イギリスの印象
イギリス滞在二日目。そろそろこの国に対する印象が幾つか固まってきました。 まずですね、「イギリスって、いいな」と思うことから言いますと、人が親切。ただし、その親切さの質がアメリカ人の親切さとちょっと異なる感じ。 アメリカ人の場合、親切だということを前面に出して来るというか、親切な行為自体をエンターテイメントにしようというところがあって、ハイテンションに親切なことが多いのですが、イギリス人のそれは、もっと内に秘めた親切という感じなんですよね〜。 要するにね、見た目、不親切そうなのよ、誰も。で、あれ〜、この人不親切なのかな〜、嫌な感じだな〜、と多少身構えていると、その予想に反して意外に親切にしてくれるということが多いわけ。表情はぶっきらぼうなんだけど、こちらのためにやってくれることはちゃんと行き届いているというか。だから、結果としては決して嫌な感じはしない。むしろ、最初のイメージが悪かった分、余計に親切さが身にしみるというね。ま、とにかく、今のところ、現地の人との応対で、嫌な思いをしたことは一度もありません。そこがまあ、まず第一に有り難い、 それから、もう一ついいなと思ったのは、地下鉄ですかね。 さすがに世界で最初に地下鉄を通した国だけあって、充実しているんですな、地下鉄網が。だから、ロンドン市内であれば、地下鉄に乗っちまえばとりあえず何処にでも行ける。もちろん、東京だってそうだといえばそうですが、アメリカではそうは行かないですからね。NYの地下鉄網なんて、ロンドンのそれと比べたら貧弱なもんだ。旅行者にとって、移動手段があるということは、実に有り難いですからね。ロンドンの地下鉄はいいわ〜。 一方、これはいかがなものかと思うのは、コインね。イギリスのコイン、分からないなあ。 まず、コインの数が多すぎませんかね。 日本の場合、500円、100円、50円、10円、5円、1円だから6種類か。アメリカですと、1ドル、50セント、25セント、10セント、5セント、1セントですが、1ドルコインと50セントコインはほとんど出回ってないので、実質4種類。 一方、イギリスの場合、2ポンド、1ポンド、50ペンス、20ペンス、10ペンス、5ペンス、2ペンス、1ペニーの8種類。これはいかになんでも多すぎる。このうち、2ポンド、20ペンス、2ペンスは削っていいのではないでしょうか? 必要ありますかね? でまた、全部のコインにエリザベス女王の顔が描いてあって、しかも額を示す数字の方はごく小さくしか書いてないものだから、老眼が進みつつあるワタクシには、一体どれがどの額のコインだかわかりゃーしない。でまた、記念コインみたいなのがやたらに出回っているので、さらに判別を難しくしているわけ。イギリス二日目のワタクシにとって唯一パッと分かるのは、分厚い1ポンドコインと、大柄で7角形をしている50ペンスコインだけ。だから、現金で買い物をする時に、細かいのをコインで払おうとすると、困るんだな〜。 ということで、とりあえず今の時点でのイギリスのいいところ、悪いところは、こんな感じ。ま、今後滞在期間が長くなるに従って、更に色々と発見があったり、修正があったりするでしょうけど、今後ともそういうのを一つ一つ意識して、出来るだけ明確なイギリスのイメージをつかんで行きたいと思います。
September 2, 2012
コメント(0)
-
ロンドンだより
はーい、当ブログご愛読者の皆様〜! お元気ですか〜! 到着しましたよ、ロンドン。フィンランド航空を使ったのでヘルシンキ経由。 着いたロンドンは・・・寒い! まあ、日本で言えば11月初旬くらいの感じですかね。私としては半袖なんて論外、薄手のセーターも論外、フリースのやや厚手のセーターか、ライナーなしのコートくらい欲しいかな、というところ。もっとも、現地の皆さん(あるいは外国からの観光客かも知れませんが)は、この寒さの中でノースリーブとか着て平気で居る人も居れば、既に分厚いダウンジャケットを着ている人も居るという具合で、人々の着ているものでは季節が全く分からないという・・・。彼等の皮膚感覚と言うか、体温調整の具合は一体全体どういう具合になっているのでしょうか。 で、今回はホテルではなく「サービス・アパートメント」という施設に泊まっているのですが、これが80平米はあろうかという立派なアパートで、しかもどこかに出かけて部屋を開けている間、勝手に掃除までしてくれるという優れもの。なかなか豪勢であります。 で、一晩明けた今日は、早速勉強に明け暮れました。と言っても、研究のための勉強ではなく、社会勉強ね。ま、人によっては「観光」という言い方をする場合もあるかと思いますが、要するに、とりあえずバッキンガム宮殿とか、ウェストミンスター寺院とか、ビッグベンとか、ナショナル・ギャラリーとか見ちゃった、っていうことですな。 中でも印象的だったのは、ウェストミンスター寺院。ま、英国国王の戴冠式を執り行うことでも有名な大寺院ですが、なんと行ってもワタクシ、専門がアメリカ文学ということもあり、今まで外国と言えばアメリカばかり行っていたもので、千年以上の歴史を持つ大寺院なんて行ったことがなかったわけ。生まれて初めて実物を見る大建築なわけですな。つまり、歴史そのものを初めて見た。 で、こういう西欧の大寺院って、寺院そのものが墓場じゃないですか。日本のように、寺の裏に墓場があるというのではなく、寺院そのものが墓場。で、ウェストミンスター寺院にしても、寺院の中にエリザベス一世の墓があったり、ニュートンの墓があったりする。寺院の中に埋めちゃうわけですな。だから、寺の中のあちこちに死体が埋めてある。死体じゃなくて、遺体か。 そういうのがね、やはり日本人的な感性からすると、ふうむ、って言う感じがするわけよ。 ま、そのこともさることながら、ミーハー的な興味からいうと、ウェストミンスター寺院って、文学者の墓だらけなんですよね。シェイクスピアから初めてドライデン、サミュエル・ジョンソン、キーツにシェリー、ディケンズ、ジョージ・エリオットにT・S・エリオット、オーデン、ディラン・トーマス等々、ほとんど英文学史に名を連ねる人々がことごとくここに眠っている。これはね、ちょっと興奮しますね。 まあ、ワタクシが文学研究をする者だから、ということもあるかも知れませんが、王族の墓より、文学者の墓の方に余計感銘を受けるんですな。つまり、文学者は死後に王に勝つと。ペンは剣に勝つと。 その感覚を得たということがですね、ワタクシにとっての今日の収穫ではないかと。こういう感覚は、現地に行かないと分からないことですからね。 ほーら、遊んでいるようで、ちゃんと勉強しているのよ、ワタクシは。 ということで、観光を勉強と無理無理に言い換えつつ、ロンドンの一日は暮れていったのでございます。
September 1, 2012
コメント(4)
全30件 (30件中 1-30件目)
1