2006年05月の記事
全34件 (34件中 1-34件目)
1
-

in 『CHIKAKU/4次元との対話』@岡本太郎美術館
ドイツ語版とスペイン語版のカタログが置いてあったので、国際的に、お客様が来ているんですかねぇ?と首を傾げていたら、紺洲堂主人さんが受付の方に確認して下さいました。オーストリアの「フレンドリー・エイリアン」クンストハウス・グラーツ、ならびにスペインのビーゴ現代美術館をめぐっての帰国展、なのだそうです。日本の現代美術の紹介、ということで、作家さんも日本人が中心。-----美術館を入ったところに、森脇裕之さんの「Lake Awareness」。あまりにも自然な展示なので、常設なのかと思っていました。天井から吊り下げられた、ブルーの半球。小さな三角形のLED基盤の組み合わせで出来ています。手を近づけると、それを「知覚」して、かそけき音を立てながら光度が上がり、それが漣のように広がっていきます。しゃがみ込んで、半球の内側の空間へ。360度、視覚が青の空間に満たされます。そして、自らの手が起こす、音を伴う波紋。何とも言えない揺らぎの感覚。作品とのコミュニケーションが、癒しを与えてくれます。これは面白いし、楽しい。何より、美しい。岩井俊雄さんの双方向系の作品に近いものがあります。(岩井俊雄さんの公式ページはこちら。) 『岩井俊雄の仕事と周辺』-----岡本太郎さんの常設展示に向かいますが、このプロムナードも大胆。呪術的なエネルギーに満ちている感じ。常設展示に後ろ髪を引かれつつ、企画展「CHIKAKU 四次元との対話」へ。-----とは言え、岡本太郎さんの作品がここでも導入の役割を果たします。岡本太郎さんの撮った写真を中心に、CM出演などを含めて、その業績を振り返っているのですが…凄いですね。思いつく限りのことをやり切った、というエネルギーを感じます。飛行機を飛ばして、夜空に一筆書きを描いた作品とか、今の作家の卵とかでも思いついて諦めたりしてそうですし、新宿での1時間絵画パフォーマンスとか、「岡本太郎」が行ったことに意味がある作品。何より、写真が。昨年『写真展・岡本太郎の視線』展というのがあって、私は行かなかったのですが、ご覧になられていた紺洲堂主人さん曰く、「こちらの方が、質・量共に良い」とのこと。(紺洲堂主人さんの『写真展・岡本太郎の視線』展感想はこちら。)同じ「カメラ」という道具を使っても、その切り取り方のセンスには、人それぞれのものがあり、その、「呪術的なるもの」を、呪術的なままに写し取ってしまう力は、やはり、凄いなぁ、と思います。-----写真では、森山大道さん、中平卓馬さんの作品が続きます。同じく写真つながりで、杉本博司さんについては、以前森美術館で拝見した「劇場」シリーズの出展でしたので、こちらをご参照ください。 -----やなぎみわさんの作品も、「砂女」のシリーズから、「Girls in Her Sand」。こちらに原美術館「やなぎみわ展」で同作品を観た時の感想を書いています。-----中村哲也さんの作品、多分、数年前の『Emotional Site』展で観ました。(これはかなり充実した、面白い企画展でした。はは。この頃はまだblogをやっていなかったのが悔やまれますね。こちらに少しだけ情報がありました。)今回は「Premium Unit」シリーズでの出展。有機性を持った漆芸イメージの物体が、バスタブや洗面台として、日常に置かれる不思議さ。その個性の強さに眩暈すら覚えます。でも、日常品への侵食は、やり過ぎだよなぁ…。-----笠原恵実子さんの「ラ・シャルム」は、2001年の横浜トリエンナーレで拝見したのと同じと思われます。円形に広げられた、金髪の人工毛髪が、大きさを変えて数組。ビデオ・インスタレーションでは、その円の上で、金髪女性がパフォーマンスしている風景が映されています。色々と女性をめぐる言説を喚起させられる作品であり、そこはかとない不気味さをはらんでいます。そう、まるで、髪の毛だけ残して消えて(消されて)しまった肉体の抜け殻を見るような…。うーん。「何故金髪にこだわるのか?」が、見えてこないのが、歯痒い。いろいろ深読みは出来るのですが、納得出来る説明に至りません。カタログによると、他の色を使うこともある、との説明でしたし、髪の持つ身体性と物質性という二重性、主体と客体の揺らぎ、といった視点からの解説がされていましたけど…何か違うんですよね。いや、解説としては優れているのですが(伊藤俊治さんによる解説です)、実感として、そこまで凄い作品だと思えない。実際に触れたり、真っ赤なハイヒールが上に転がされていたりすれば、全く違う印象になる気がします。-----小谷元彦さんの作品も、多分どこかで観た気がするのですが、思い出せませんねぇ。「スケルトン」鍾乳石のイメージを喚起させる、天井から垂れ下がった白い塊。何故か「乾いた戦争」という言葉が脳裏によぎります。今回展示されていなかったようですが、宇宙船の一部を思わせる真っ白な球形の「ベニレス」は、それに対するシェルターのようにも見えます。(カタログに写真掲載)両作品を並べて観たかったですね。白の色調が、清潔さではなく、ちょっとくすんだ、燃え尽きた灰の雰囲気なのですね。それが造形と相まって不安感を掻き立てているのです。-----渡辺誠さんは、クンストハウス・グラーツ、ビーゴ現代美術館、岡本太郎美術館での会場設計を担当されたそうです。写真を見る限り、クンストハウス・グラーツでの展示は秀逸。ビーゴ現代美術館での展示もコンセプトが明確で面白そう。岡本太郎美術館では…予算が足りなかったのかなぁ、と。作品としては、「FIBER WAVE」という、グラスファイバーの背の高い「草叢」が風に靡くという作品を出展。建物内部と、屋外展示の2箇所で展開。ただ、あまりに整然としすぎていて、少々物足りない感じもします。冒頭の森脇裕之さんの作品に近いテイスト。-----いやぁ、時間が足りなかったのが悔やまれます。何より、常設展の方をもっとじっくり観たかった。そう、やはり、岡本太郎作品の力強さって偉大で、思わず惹き付けられる魅力があるのです。 この「呪力」に現代美術作家は太刀打ちしていかなければならないわけで。今回の出品作家でも、森脇さんや渡辺さん、杉本さんなんかは、スマートさで勝ってはいますけど、その分、オドロオドロしい部分は捨象されています。力強さ、という基準だけで言えば、森山大道さんの作品が最もインパクトがあります。「呪術性」で言えば、やなぎみわさんや、中村さん、小谷さんが特徴的ですね。-----岡本太郎さんを含めた、先達の凄さを知れば知るほど、現代美術って大変だな、って思います。呪力を超えるために、呪縛を断ち切って、自らの呪法を確立していかなければならないのですから。ま、観る側としては、とんでもない魔法をかけてくれる術者に出会えるのが楽しみなわけで。さて、次はどこに行きましょうか?-----『CHIKAKU/四次元との対話』 - 岡本太郎からはじまる日本の現代美術[ヨーロッパ巡回帰国展]@川崎市岡本太郎美術館(向ヶ丘遊園)http://www.taromuseum.jp/[会期]2006.04/08(土)~06/25(日) 作者: 岡本 太郎 (OKAMOTO Taro;1911-1996) 森山 大道 (MORIYAMA Daido;1938-) 中平 卓馬 (NAKAHIRA Takuma;1938-) 杉本 博司 (SUGIMOTO Hiroshi;1948-) 渡辺 誠 (WATANABE Makoto;1952-) 森脇 裕之 (MORIWAKI Hiroyuki;1964-) やなぎみわ (YANAGI Miwa;1967-) 伊藤 高志 (ITO Takashi;1956-) 草間 彌生 (KUSAMA Yayoi;1929-) 笠原 恵実子 (KASAHARA Emiko;1963-) 日高 理恵子 (HIDAKA Reiko;1958-) 須田 悦弘 (SUDA Yoshihiro;1969-) 中村 哲也 (NAKAMURA Tetsuya;1969-) 小谷 元彦 (ODANI Motohiko;1972-) トリン・ミンハ (Trinh T.Minh-ha;1952-)★★★★☆
May 28, 2006
コメント(2)
-

in @川崎市立日本民家園
川崎の岡本太郎美術館に向かう道すがら、同じ公園内に日本民家園があります。民家?民家です。本当に民家なおうちがズラッと建てられています。いや、これは。寄っていきますか。ということで、岡本太郎美術館に行く前に、何気に立ち寄ったのですが、いや、びっくり。その広さと言い、ちゃんと維持管理されている様と言い、ボランティアの方々の話し好き振りと言い、しっかり運営されています。-----これはレベルが高い。最初の展示室こそ、ちょっと間違えてお金を掛けすぎた感がありましたけど、民家の揃え方が半端じゃない。入口の民家で機織体験も面白そうですし、馬宿だった民家では、ボランティアの方が、囲炉裏に火を入れています。ひき臼を回すのも初めての体験。 水車小屋に、高床式倉庫、合掌造り…。お地蔵さんに、道祖神まで持ってきているのも嬉しい。ちゃんとしたカメラ、持ってくれば良かったですねぇ。囲炉裏に座って、火吹竹を持たせてもらいました。(灰が舞うので吹くのはNG。)和服姿で来た甲斐がありました。-----今日の目的は、あくまで岡本太郎美術館でしたので、途中で切り上げてしまいましたが、これは、1日かけて回っても飽きないですね。民家を利用したお蕎麦屋さんもありますし、飽きればすぐ近くに、岡本太郎美術館も、薔薇園もありますし。-----うーむ。やるなぁ。川崎市。数年前のワタリウムさんの企画で、「川崎ミステリーツアー」と題して、街の特殊性に着目したアプローチで川崎を回ったことがありましたが、なるほど、まだまだ一面しか見ていませんでした。こういう「文化」にお金をかけて、維持管理をきちんと出来る‐やってきた実績はすごい。-----さらに、イベントとして、民家で昔話を聞く会、なんて行われてました。うわー。この雰囲気の中で昔話?お泊りは出来ないみたいですけど。聞いてみたい、より、やってみたい、と思ってしまうのは、元演劇関係者の血ですね。-----ちなみに、遠野のユースホステルでは、昔話を聞ける機会を設けているそうです。(今もやっているのかな?)「若い」うちに行っておきたいですねぇ。遠野まで行ったことはあるのですが、旅程の都合上、毛越寺のユースに宿泊したため、行けませんでしたが。-----なんて昔話はさておき。時間をかけて行ってみる価値十分。たぶん、小さい子供さんとか、おおはしゃぎじゃないかしら。-----@川崎市立日本民家園(向ヶ丘遊園)http://www.city.kawasaki.jp/88/88minka/home/minka.htm
May 28, 2006
コメント(0)
-
【特別企画】in @ with
いつも懇意にして頂いている、紺洲堂主人さんと、いつか美術館めぐりでもご一緒しましょう、と言っていた話が、にわかに具体化しました。どこにしましょうか、というやり取りを何度かして、お互い行った事のない、川崎の岡本太郎美術館で開かれている『CHIKAKU 4次元との対話』にしましょう、ということに。-----午前中に学園祭を冷やかし、ってか、「8時半に準備のため集合」。顔を知らない1年生とかもいるのに、当たり前みたいな顔をして、和服姿のまま、テント設営とか、商品陳列のお手伝い。集まり悪かったから、ちょっとは役に立った気が、って、それも何か違うなぁ。正直、「先輩は座ってて下さい。」くらいの発言を期待する、元体育会系なのですが…。もうちょっと「頼まれないと何もしない」を撤底した方が良いな。「先輩にも遠慮なく指示出来る後輩」に育ってもらいたいですからねぇ。でも、何もしないのも、居心地悪いし…。そして、他のメンバーはもう少し、「指示待ち口出し」体質は考えた方が良いのではないかい?ま、読んで欲しい人には届かないのだろうから、今後は、ちゃんとその場で言うとしましょう。その場で言って、その場で水に流した方が良いですからね。なんて、愚痴はともかく。後輩諸氏に軽く「じゃ、頑張ってね~♪」と言い残し、向ヶ丘遊園駅へ。-----いや、岡本太郎美術館、川崎にあるって言うから、私は川崎駅から近い‐品川経由で楽勝、って思ってましたよ。ううむ。JRで行けないとは。別に良いですけど。というわけで、向ヶ丘遊園にて紺洲堂主人さんと合流。直にお会いするのは初めてです。なるほど。かような方であらせられましたとは。私も3パターンくらいの予測をしていましたけど、ちょっと予想外でした。ぎりぎり3パターン目のイメージが近かったかしら。-----というわけで、紺洲堂主人さんと共に岡本太郎美術館を目指したのですが、その途中で、民家園への立ち寄りあり、同行者が増えたり、またちょっとヤバめのお話ありと、なかなか楽しい1日を過ごさせて頂きました。いや、冗談抜きで、またどこかご一緒しましょう。長くなりましたので、美術館の感想については、また後ほど。
May 28, 2006
コメント(0)
-
歳の差なんて…。
母校の学園祭に顔を出してきました。昔いた環境サークルが古着市などやっていたので、まぁ、新歓の飲み会にも顔を出したことですし、クッキーを見物料代わりに、冷やかしに。「差し入れ」とも言います。雨の中、人手不足にもめげず頑張る1年生&2年生。ひとしきり、お手伝い(苦笑)も一段落して雑談。初めて顔をあわせる方もいらっしゃいます。「ところで、先輩は何期生なんですか?」「えっとねぇ、3期生。」「ということは、え~っ!? 僕と…」「わざわざ計算せんでよろしい。来年の1年生とは干支一緒だもんな。「お前も辰年?マジで?オレもチョードラゴン♪」とか言うしかなかろう。」「既に来年用のネタを考えているんですか?」「もちろん。」なーんて会話を交わした後、のんびりしていたら、1年生の男の子がおずおずと声をかけてきました。「あのぅ。」「何でしょう?」「僕、1年なんですけど…。」「うん?」「早生まれだから、辰年なんです。」…!?・・・!!??● ● ● !!!???「いや、さっき、そういう話されてましたから…。」すいません。フツーにショックで、面白い返しが出来ませんでした。てか、ちょっと冷たい反応をしてしまったかも。だって、ココロの準備が出来てませんでしたもん、て。うーん。棒読みで「お前も辰年?マジで?オレもチョードラゴン♪」が正解だったんだろうな。てか、そんな申し訳なさそうに言われても…本気で気にしていたら、顔なんて出しませんてば。ともあれ、雨の中、9マイル…じゃなかった、古着市に講演会、ごみの分別、などなど関られた方々、お疲れ様でした♪
May 28, 2006
コメント(3)
-

講演会「熊楠の森を知る」[1]@ワタリウム美術館
第1回 「南方熊楠 生態調査から曼荼羅的世界観へ」 by 松居竜五先生 @ワタリウム美術館 -----ワタリウム美術館さんの講演会シリーズ、今年は知の巨人、南方熊楠先生がテーマです。-----南方熊楠先生の生涯にわたる業績は、余りにも多岐にわたり、かつ膨大で、私自身専門家というわけでもありませんから、wikiと南方熊楠記念館の資料を御参考に。今日のお話は、南方熊楠先生の人生観とその背景を含めた生涯のお話だったので、内容については省略。『Nature』誌に世界で一番論文(短いものも含めて)が掲載された研究者である、とか、大英博物館を出入禁止になった、とか、トリビア的なお話も。やっぱり面白い人物ですね。=====てか、明治人の「教養」のレベルって、とんでもなく高くて、しかも、それが単なる「知識」にとどまってないのが凄い。ちなみに。南方熊楠が生まれた1867年、この冬に坂本竜馬が命を落とすわけですが、この年に生まれた有名人としては、夏目漱石、正岡子規、幸田露伴、さらには、反骨のジャーナリスト宮武外骨、建築学の伊東忠太、なんてビッグネームが並びます。ついでに。さらにその5年前、寺田屋事件や生麦事件のあった1862年は、森鴎外、牧野富太郎、新渡戸稲造、黒岩涙香なんかが生まれています。(岡倉天心は1863年生。)-----山田風太郎先生や浅田次郎先生ではないですけど、若かりし頃の彼らが、どんなレベルでどんな話をしていたのか、聞いてみたいな、と夢想してしまいますね。-----「森先輩、講義室に本を忘れられてましたよ。」「ああ。ありがとう。探していたんだよ。君は夏目君だったかな?」-----なーんて会話を想像するだけでも、ドキドキ。(いや、ま、これはちと無理がありますが。)-----「あのー、嘉納先輩、もしよろしければ、我々のSportにお付き合い頂きたいのですが。」「ああ。正岡君か。一体何をするんだ?」「はぁ。Baseballです。棒球、いや、私は野球と呼んでいるのですが…。」「この前、夏目君たちとやっていたやつだな?夕刻から柔術の稽古なんだが…鍛錬前に体を動かすのも悪くないか。せっかくの頼みだから、ちょっと寄せてもらうよ。」-----とか。(柔道の祖である嘉納治五郎先生は1860年生、1877年東京帝国大学入学なので、これもちと無理なのですが。)=====さて、講義後の質疑応答で、私のした質問は、「神社合祀反対運動は、生態学者として原生林保護という視点から行われたというお話でしたが、近年のエコロジーでは、人工林・原生林の中間に位置づけられる、人と共生する形での里山というのが注目されています。南方熊楠は里山について、どのような視点を持っていたのでしょうか?」「里山運動については、私自身も関っているので、よく知っています。南方熊楠との関係で言えば、彼が持っていたのは、生態学者としての視点であり、未知の新種の発見・研究・分類を行う、ということで、人の手が入った、入っていないという観点には、あまり興味がなかった、と言って良いのではないでしょうか。南方熊楠は、エコロジーの先駆者として捉えられることも多いですけれど、時代背景もありますし、全てを南方熊楠に帰することに私は反対です。実際、生態学者としての立場から、原生林の調査が済めば、木を伐っても良い、ということも言っていますし。南方熊楠を絶対視するのではなく、彼の視点の中で、現代でも生かせるものを生かす、というのが良いのではないでしょうか。」「なるほど。良く分かりました。有難うございました。」-----今回使用された映像資料は、こちらの本(CD-ROM付)についています。『南方熊楠の森』あれ?新刊なのに写真なし?図版、というか写真が豊富で、しかも綺麗。非常に読みやすく、入門編としては最適だなぁ、と。=====和多利さんによると、ワタリウムさんで来年『南方熊楠』展、並びに関連旅行企画を計画されているそうです。これは是非行きたいですね♪ 楽しみです。
May 27, 2006
コメント(2)
-
「初夏を感じる夕食会」レシピ♪
「初夏を感じる夕食会」と題し、環境関連の後輩数人と、うちで夕食会。私が「初夏らしい食材」として選んだのは、空豆、スナックエンドウ、新生姜、ミョウガ、ヤングコーン、ミニトマト、青ジソ。さらに、冷製の肴として、鶏皮の煮凝り。後輩が用意してくれたのは、各国の変り種ビール。世界地図と、変わった名前の話なんかをつまみに。さて、作った料理をご紹介。=====「初夏の浅漬」「さくらづくし。」の時は、大根を桜で漬けましたが、今回は初夏らしく、ということで、青ジソ、ミョウガ、新生姜と共に。大根をスライスして軽く塩を振り、しなっとなったところで絞ります。それと香味野菜を交互に入れて、漬け込むだけ。今回は、色変わりを防ぐため、少量の酢と砂糖を加えました。甘酢漬けですね。青ジソは切らずに漬け込んだので、お出しするときにざく切りにして。そうそう、大根を桂剥きにした時の皮は、千切りにして揚げ、サラダに使います。=====「できたて豆腐」茹でて薄皮を剥いた空豆と、刻んだ青ジソを器に入れ、にがりを入れた豆乳を注ぎます。ラップをして、レンジで1分半。え? 簡単ですが、何か?ただし、これ、豆乳によって、味が全く違います。面白いくらい。是非、美味しい豆乳を使ってくださいね。=====「鶏皮の煮凝り」先日、みづきさんより『(男の手料理)』バトンを頂いた時、「昔、煮凝りなんて作ってましたよね」と振られて、そう言えば、最近作ってないなぁ、と。このレシピは林望先生の『音の晩餐』で学んだのですが、この本が絶版のようですので、さっとご紹介。-----まずは、鶏皮を用意します。安くて経済的な上に、「捨てられるであろう部分を利用」ってあたりが、ちょっぴりエコ。ま、その後のガス消費を考えると、あまり「環境に良い」とは言えませんが。-----さて、鶏皮を適当な大きさに刻みます。これがちょっと大変。なにせ脂の塊なので、包丁の切れが、みるみる悪くなってしまうのです。なので、小皿を引っくり返して傍に置き、切れが悪くなったら、高台の部分で軽く砥ぐようにして脂を落とします。これで作業が楽になるはず。-----さて、フライパンに刻んだ鶏皮を入れ、弱火でじくじく熱します。焦げ付かないように時々箸で混ぜながら、のんびり構えていると、だんだん脂が溶け出して、鶏皮が自分の脂で唐揚状になってきます。キツネ色になったところで止めても良いですが、さらに少し待つと、カリカリに。これだけで塩振って食べても美味しいんだけどなぁ…という誘惑を断ち切って、もう一手間。-----とをあわせた小鍋を軽く煮立て、揚げ立ての鶏皮を投入。ジュワーッと小気味良い音が響きます。これをしばらく煮て、味が染み渡ったところで、器に移します。-----生姜の千切りと、胡麻をのせて、軽く冷まして冷蔵庫へ。あとは、鶏皮のゼラチン質が冷えて固まるのを待つだけ。これで鶏皮の煮凝りの完成です♪-----脂が抜けきっているので、「鶏皮はちょっと…」という方でも食べやすいはず。とのバランスで、薄味にも濃味にも出来ます。今回は、お酒の肴であることを考慮して、ちょっと濃い目に仕上げました。=====「初夏の野菜の香味揚げ」さて、フライパンには、大量の鶏の脂が残っています。もったいない。なので、今回は、これを使って、旬の野菜を素揚げに。油を漉しながら、揚げ物用の鍋に移します。本当は、味の薄いものから揚げるのがセオリーなのでしょうが、揚げ油に香りを付けたいので、香味野菜から。新生姜にミョウガ、ヤングコーン。(あっ!アスパラを買ったのに、使うの忘れた!)大根の皮を千切で揚げたものは、サラダのアクセントに。=====これに、空豆ごはんに、サラダが2種。持ち込みのピザ。うーん。しかし。今回は、思った風に出来ませんでした。空豆とかスナックエンドウの茹で時間が上手くなかったし、手際も良くなかった。新生姜とミョウガは、もっと上手く使えた気がする。アスパラを忘れていたのも痛い。揚げ物は、練習の余地ありあり。ごめんなさい。リベンジの機会を下さい。土曜の夜とかだったら、昼のうちにもっと仕込んで…あ、今回も部屋の片付けに時間を取っていたから…。「日頃から部屋を片付けておくこと」が料理の秘訣だとはね。
May 22, 2006
コメント(0)
-

in 『藤田嗣治展』@東京国立近代美術館
挿絵画家に、ピカソやダリといった当時(いや、今でも)一流の画家達を起用した、とんでもない聖書があると聞いたことがあります。この超有名な画家達に交じって、「フジタ」という、どうも日本人らしい人物がいるのを知ったのが、「フジタ」の名前を覚えたきっかけでした。(今回拙稿を書くにあたって調べたのですが、『ヨハネ黙示録展』のことなのかしら…見つけられませんでした。)-----しかし、美術展に行っても、ピカソやダリに出会うことはあれど、フジタの作品を観る事は稀で、かといって、作品集を買うほどの情熱はなく、なんとなくイメージの掴み所のない作家だなぁ、と。今回の展覧会で、ようやくちゃんと作品を見る機会を得、その作品の多様性とエネルギー、そしてその生き様に圧倒されました。=====まずは、芸大時代の作品。学生時代は黒田清輝先生についたものの、肌が合わなかったようです。教科書通りに上手な絵。彼は最初からパリ行きを熱望していたそうです。そして、念願のパリの自由な雰囲気と、ハイレベルな友との切磋琢磨がフジタの才能を開花させるのです。-----裸婦のシリーズ。どこまでも深い乳白色の女性の肌。それを引き立たせる繊細な墨の描線。赤瀬川原平さんが、雪舟の『慧可断臂図』について、「視線がこの白い達磨に引っかかって離れない。」という表現をされていましたが(『名画読本 日本画編』)、この表現は、フジタの乳白色にも、相応しいという気がします。ずっと見ていて飽きない白。抜けるような、違うな、陶磁器のような、いや、艶かしい(なまめかしい)、ともちょっと違って、官能的というよりは、息づいているような白。思わず、花の色で例えたくなるような、活きている白。それに息吹を与える繊細な黒の描線は、墨と面相筆という和画材によるものでした。圧到的なオリジナリティ。画家としてのアイデンティティの問題を考えれば、この他の追随を許さない作品が人気を博した理由が見えてきます。-----フジタといえば猫、でもあります。裸婦と並んで、あるいは自画像の影に、そして時には主役も演じる、小生意意な猫達。 『猫の本』藤田嗣治画文集あわせて動物絵画も。擬人化された、キツネや猫たち。彼ら彼女らは動物絵画の延長線上に、普通に存在します。単に可愛い存在とは見ていない、フジタのニヒルな視点が透けて見えるようです。-----さて、今回の目玉の一つは、彼の運命を変えたとも言える、戦争画の出品。「戦争画」の責任を一手に背負い、「日本画壇」と決別したことが、「戦後」において、彼の「評価」を下げた理由となりました。(才能に対する嫉妬や、自己責任の回避と押し付けなど、ドロッとした「画壇」-自分も含めた日本人、いや人間の精神構造の貧しさにゾッとしますが。)それにしても、とんでもない戦争画です。それまでの作風と打って変わり、巨大で緻密、沈んだ色調の画面の中に折り重なる群像。-----『戦友』という軍歌があります。これが「軍歌」とされていながら、とんでもなく反戦的なのですよ。銃弾に倒れた友に、軍律を無視して駆け寄る私。友はお国のために遅れてくれるな、と涙を流します。戦いすんで日が暮れて、生きていてくれと思いながら友を探す私。戦争の虚しさを、赤い夕日と広大な大地を背景に描いていて、よくもまぁ、検閲とか通ったなぁ、と思うのですが…。フジタの作品も同じ「際どさ」を感じます。-----例えば、『神兵の救出至る』という作品。荒らされた豪邸に、猿轡の黒人メイド。そこに銃を持って現れる日本兵。いや、このキャプションがなければ、どう見えるのだろうと。-----これが戦争協力画? 戦意高揚?私にはそう見えません。戦争という理不尽に対する怒りと哀しみ、虚しさと皮肉を私は感じます。それは私にとって都合の良い見方なのかもしれません。しかし、少なくとも、今の時代の文脈にこれらの作品を置いた時、勇壮さより、悲壮さが溢れる作品になっていることは事実だと思うのです。=====戦後、フジタは再びパリに渡り、フランス国籍を取得、キリスト教徒の洗礼を受けます。=====晩年に描かれた「子供たち」について。同じ顔に描かれる空想の子供たちを見て、一瞬、奈良美智先生を思い浮かべたのですが、いや、違うな、と。どこかで見たことがある、と思って、私の中で浮かんだ名前は、ヘンリー・ダーガーでした。どこが似ているのか、と聞かれると困るのですけど、テクニックとか、モチーフとか、そんなのではもちろんなくて、うーん、恐らくは色遣いの関係で、裸婦とか動物とかの作品に見られる「屈託のなさ」みたいなものが、子供を描いたシリーズには欠けているのですね。その「屈託のなさ」の代わりに、空間に忍び込んでいる「何か」がヘンリー・ダーガーの持っている「何か」と似ている気がするのです。平たく言って、実は、私には、ちょっと怖い。その怖さの質が似ている気がします。-----最後は宗教画。ヨハネ黙示録を描いた『黙示録』3品は、静謐な狂気を宿す地獄絵図、といった趣き。悪夢のような情景は中段より下に描かれ、凄惨なイメージは重く沈みこみ、天の世界の軽やかさが引き立てられてます。全体の色調は優しく、不快な感じはしません。=====私が大学を卒業する時、当時の総長 蓮實重彦先生はこう言われました。「こちらから微笑みかけないと、世界は微笑みかけてくれない。」日本から飛び出し、世界を舞台に名作を生み出していったフジタ。その作品のオリジナリティの高さもさることながら、世界に微笑みかけられた彼の生き様には、見習うべきものがたくさんあります。=====『藤田嗣治展』@東京国立近代美術館[会期]2006.03/28(火)~05/21(日) 作者:藤田嗣治(Leonard Foujita;1886-1968)★★★★☆=====5/30(火)~7/23(日)京都国立近代美術館にて開催中です♪
May 21, 2006
コメント(2)
-

♪Movie♪ 『陽気なギャングが地球を回す』
クール&スタイリッシュな、疾走感ほとばしる映画でした。原作は伊坂幸太郎さんの同名小説。そのポップ感を見事に演出。-----世の中から失われてしまった「ロマン」を取り返すために(!)銀行強盗を繰り返す4人組。今度の仕事もスマート&スタイリッシュに決まったはずが、待っていたのは驚きのアクシデント!めまぐるしく展開するストーリー。騙し騙され、仕掛け仕掛けられのコン・ゲーム。最後に笑うのは誰なのか?そして、大金と彼らはどこへ行くのか?-----原作とはそれなりに違ってます。純粋に映画として、はどうなんだろう?先に原作読んで、伏線の妙に感心してましたから、客観的判断は難しいです。ま、でも、原作をいじっている割には、さほど違和感なく楽しめました。原作のウェイトが、伏線の緻密さとポップさが同じぐらいに置かれているから、でしょうね。-----ただ、雪子さんの子供の年齢設定が変わったためにカットされたエピソードは、好きだったので残念。あと、個人的には恋愛エピソードはいらないなぁ。恋なんてなくても、「ロマン」は成立するのに…。----- そして、とにかく、役者に魅了されっぱなし。佐藤浩市さんの、問答無用の長広舌の魅力。大沢たかおさんの、スタイリッシュな魅力。松田翔太さんの、清潔感と透明感のある清冽な魅力。鈴木京香さんの、芝居心と慈愛に満ちた魅力。それぞれの演技のレベルがとんでもなく高い。特に、ラストの佐藤さんの語りは最高!(あの語りがなければ、映画の評価はめちゃくちゃ低くなってました。)脇を固める俳優陣も、手抜きのない人選。古田新太さんに大倉孝二さん、松尾スズキさんに大杉漣さん…。-----お気楽に楽しい映画でした♪さてさて、「ロマンはどこだ!」-----今回は劇団時代の友人、央先生とご一緒させて頂きました。我々2人の笑いどころが、他のお客様とは違うため、劇場の中で、とても浮いていたことは、公然の秘密です。=====『陽気なギャングが地球を回す』2006年 松竹 92分http://www.yo-gang.com/監督:前田哲出演:大沢たかお / 松田翔太 / 鈴木京香 / 佐藤浩市 他原作:伊坂幸太郎 『陽気なギャングが地球を回す』
May 14, 2006
コメント(3)
-
ブレイク
※後ほど編集♪
May 14, 2006
コメント(0)
-
森田の結婚♪
さて、結婚式のお話のついでに、ちと蛇足。私は、結婚だの恋愛だのとは無縁に、自由に楽しく生きているわけですが…。万が一、結婚することになったら。うーん。内容は、まぁ、相手によりけりだなぁ。(当然、独りでするものではないので。)-----あ。私が絡んで「夫婦初の共同作業」がケーキカットっていうのも「芸がない」気がするので、「初夫婦漫才」なんていかがでしょう?オープニングは、こんな感じで。(どちらがボケでもツッコミでも)=====「どうも、□□(下の名前)です。」「◇◇(下の名前)です。」「二人合わせて」「“中川家”です♪」「△☆※◆$( ̄  ̄)ノ ☆」 : :=====はっ。これをやるためには、「中川家」の名前を皆が覚えているうちに結婚せねば。(あと、ややこしいから「中川さん」との結婚は避け…いや、婿入りして「パクリやないかい ( ̄  ̄)ノ ☆」はありか?)とか、こんなくだらないことを考えているから、いつまでも相手が出来ないのだな。-----よし。ここは、孤高の女性ピン芸人、アンラッキー後藤さん(お笑いブームの前に消えてしまいましたが)の決めゼリフ(捨てゼリフ?)をお借りして〆ましょう。「というわけで、相方募集中!」
May 13, 2006
コメント(3)
-
お笑いユニット[三四郎] -「寿」の方法論。編-
大先輩と後輩(人によっては先輩)の結婚を寿ぎ、世代別に何か出し物をやることに。この脚本に、ぎりぎりまで悩んでいたため、講演会を聞くことが出来なかったという大失態。(高尾(仮)先生、お付き合い頂いて有難うございました。)結局、他の先輩方と相談して、急遽、漫才に差し替え。つまり元の企画台本はボツに。嗚呼。-----あの、いや、だって、その先輩、隙がないっていうか、卒がないのですよ。上の期で、何か暴露エピソードみたいなのを、って聞いて回ったのですが、誰に聞いても褒め言葉ばかり。いや、そんなオチのないネタは出来ませんて。捏造するものでもないですし。-----さて、先輩の特徴的なイメージは、「服装が緑色だった」「真面目な人柄」「議論のまとめ役」「いつも笑顔」こんな感じ。これらをもとに、脚本を組み上げたのですが…ふぃー。いかんせん、急な差し替えであったため、練習不足で板に上がってしまいました。失礼いたしました。=====「(先輩)です。」「(mrtk)です。」「このたびは御結婚おめでとうございます。」「ありがとうございます。」「いや、君の結婚式ちゃうから。」「ああ、そうでした。【新郎】さん【新婦】さん、この度は本当におめでとうございます。」「我々は、環境サークルが出来た時から【新郎】さんを知っているわけです。」「ええ。そうですね。」「第一印象は、どんな感じやった?」「緑!」「いや、色の印象じゃなくて。」「スーツ!」「…なんか他にあるやろ?」「すごく真面目で論理的な方だな、と。」「そうそう、そういうの。」「議論のまとめ役というか、理論派のイメージがありますね。」「でも、ゴミ拾い活動とか、率先して実行していたりもしたんよ。」「ええ~っ!意外と行動派なんですね。」「「意外と」は失礼やろ。他に何かイメージある?」「笑顔が爽やかな方だなぁ、と。」「うん、うん。」「あと「環境サークルに女性メンバーを増やそう」と、【新郎】さんがずっと仰っていたのを覚えています。」「今日、この会場に、すごく綺麗な女性の方がたくさんいらっしゃっているのも、そのお陰ということですね。」「ここだけの話、【新郎】さんの男前と笑顔につられて入ったメンバーが、9割を占めるらしいですよ。…フフフ。実は、僕もその一人なんですけどね♪」「何のカミングアウトしとんねん!」「えっと、それはさておき、【新郎】さんの緑色の服って、どこで買ってるんですかね?」「あれは、自分で緑に染めてはるんや。」「え?スーツも?」「そう。」「Yシャツも?」「そう。パジャマとか下着もな。」「うわぁ。じゃぁ、つまり、今日の白いスーツも、これから緑色に染められるわけですね。」「アホ。今日のスーツは【新婦】さん色に染められるに決まってるやろ!」「なるほど~。で、【新婦】さん、何色に染められる予定なんですか?」「緑色です♪」「ありがとうございました。」「ありがとうございました~。」=====以前Maldives氏と組んだ時は、私がツッコミでやらせて頂きましたが、今回はボケ役で。で、事前にお願いして、大オチは新婦にやって頂きました。うーん。この後行われた、後輩諸氏の素晴らしい発表を見るにつけ、最初の発表で良かったと…。ちぇっ。漫才の前に前口上をやれば良かったな。「漫才は、古来、寿ぎの芸能である萬歳がそのルーツです。本日はお二人を寿ぐ意味を込めて、漫才を準備させて頂きました。」これを言うだけで、ちょっと場が引き締まったのに。-----いやはや、本当に素晴らしい結婚式でした。結婚式前にシンポジュウム&演奏会が開かれるというのも、凄い。後輩諸氏が、嬉々としてスタッフワークにいそしんでいる姿も素晴らしい。いやはや、お二人の人徳ですねぇ。今後もお二人の幸せがずっと続きますように☆弥栄♪
May 13, 2006
コメント(0)
-
「環境の世紀を創る市民会議」
ここ数年来、OBとして時々顔を出させて頂いている環境サークルで、私は3期生。このサークルの立ち上げメンバーを含めた世代が、0期生&1期生と呼ばれ、私は、その世代から直接の薫陶を受けて育った世代になります。-----その0期のメンバーのお一方が、7期生の後輩と結婚されました♪ いやぁ。おめでたい♪で、「環境の世紀を創る市民会議」と題して、東京大学弥生講堂にて講演会並びに演奏会を開催。はい?講演会に並ぶ名前が錚々たるものなのですが…。えっと、新郎の山下さんは、現在、一橋大学で講師をされていらっしゃるのです。(公式のHPはこちら。)-----と、ここで本当は、この講演会のレポートを書くつもりだったのですが、ある事情で、演奏会の一部しか聞けず。講演会、お金払ってでも聞きたかったのですけど…。はぁ。優先順位付けが出来てないよ、私。後輩のところで、誰かレポートまとめてないか、少しだけうろうろしてみたのですが…。うーん。誰か書いていたら教えてください。
May 13, 2006
コメント(0)
-
阿佐ヶ谷住宅にて
※下記は今後編集の可能性があります。所用があって、大学時代の先輩のおうちを訪ねました。先輩のおうちは、阿佐ヶ谷住宅にあります。-----阿佐ヶ谷…芝居関係者としては、「阿佐ヶ谷スパイダース」を思い浮かべてみたり、2月に拝見させていただいた三日月バビロンさんのお芝居は、ザムザ阿佐谷だったよね、とか、先輩のうちに行く途中、迷子になったら「劇団一跡二跳」さんの稽古場らしきビルを発見してみたり、と意外と刺激的な街だったりしますが、それはさておき。-----この阿佐ヶ谷住宅という空間は…という話については、難しくなるので、いったんパス。うーん。えっと、こちらのHPの写真をご覧下さい。-----先輩のお宅では、先輩と数人の方がディスカッションされているところでした。そこでは、極論的な例えも含めての、なかなかに熱いトークがされていて、私は黙って拝聴させて頂いていたのですが、その中に、環境問題についての示唆的なお話がありましたので、少しだけご紹介。-----それは、「地球環境問題」は、世界全体で利害の一致する、会話の端緒となるネタなのではないか、というお話。すなわち、地球規模での崩壊が予測される今、世界各国が協力して取り組まねば、いや、取り組んだところで、人類の危機は免れない可能性がある。環境問題に携わる、というのは、その「死期」を少しだけ延命させるという行為なのかもしれない、と。そして、その脅威を前に、世界は今や、自国の利害を語りながらも、自国の枠組みを越えた話し合いを余儀なくされている。それは、もしかすると、世界が同じテーブルに着くことを可能としている、可能としていくのではないか、というお話。-----お話を聞きながら、私には「人類共通の敵」のイメージが浮かびました。星新一先生だったか、「他の星からの侵略があれば、人類は否応なしに結束する」というテーマのお話を読んだ覚えがあります。もしかすると、それしか「世界平和」に至る道はないのかもな、と感じました。「環境問題」を「人類共通の敵」と考える視点は、私にはなかったため(開発経済学出身としては、南北格差とか、そういったイメージで捉えてしまっていたので)、非常に新鮮な議論でした。そういう問題意識の煽り方を上手く行うことが出来れば、面白いことが出来るかもしれません。うーむ。まずは上記の文章を分かりやすく整理して、からだな…。
May 7, 2006
コメント(0)
-
End of the Journey
ようやく、GWの旅行記が上がりました~。何だか知りませんが、長かった。ほぼ毎日更新しているのに、日記の日付が進まないという…。いや、ま、のんびりと書かせて頂きましたけど、書いているうちに展覧会が終わったりしていたのは、良くないですね。うーむ。何となく、今まで「日記」というものが苦手だった理由が分かりました。「経験」をちゃんとアウトプットしようとすると、書きたいことが多すぎて、バランスが取れなくなるのですね。てか、3日間の話を書き上げるのに半月かかっちゃ…「日記」とは呼ばない気がします。-----さてさて、今回は、思い描いていた以上に、実りの多い旅行になりました。今まで得てきた知識、経験が、自分の中で 美しく交錯するのを感じることが出来、社会人になってからの自分の歩んできた道を再認識。(お前の本職は「経理」とか「システム」だろ、というツッコミは却下。)例えば、平櫛田中先生の作品を、畠山記念館で観た後で、五浦で『活人箭(かつじんせん)』を観る感動。五浦で横山大観先生について語った後、「日本の神々と祭り」展で、先生の最高傑作の一つ『屈原』を鑑賞する不思議。五浦を訪ねた翌日のETV特集で「国際人」岡倉天心の特集が組まれるタイムリーさ。武満徹展で知った「実験工房」のメンバーである、山口勝弘さんの作品展をさっそく観られる偶然。そこにあった、清家清先生の名前、丹下健三さんの名前。そして、水戸芸術館で、磯崎新先生の名前を聞き、阿佐ヶ谷住宅では前川國夫先生の名前を聞く。-----今回の旅行は図らずも、私にとっての「修学旅行」になった気がします。而立まであと数ヶ月。新たなる知見を求めて。何をどう強化して、次にどんな布石を打つか。インプットからアウトプットへ。培った知識と経験をどう生かすか。なーんてね。こうして自分を鼓舞してやらないと、「現実」に呑まれそうな私がいるものですから。負けて堪るものですか。-----「僕(ら)が旅に出る理由♪」に書いた、今回の旅行記一覧を再掲。5/5・なこそおしけれ。・五浦(いづら)へ。・『伊藤深水』展@天心記念五浦美術館・天心随想5/6・好文亭@偕楽園 (水戸)・『山口勝弘』展@茨城近代美術館・『人間の未来へ - ダークサイドからの逃走』@水戸芸術館・『本城直季』展@水戸芸術館・芝居と美術と音楽と♪5/7・鹿島逍遥。・『日本の神々と祭り』@国立歴史民俗博物館-----ところで、題名の冠詞の用法が正しいのか、自信がないのですが…。
May 7, 2006
コメント(4)
-
in 『日本の神々と祭り』@国立歴史民俗博物館
出雲・厳島・伊勢・八坂祇園社と、歴史と伝統を誇る、文字通り日本を代表する神社を軸に、最先端の研究成果を分かりやすく、というコンセプトで紹介する企画展示。「すごい」という話を聞いていましたが、いや、本当、素晴らしい展示でした。常設をぐるっとまわって、ちょうど学芸員さんによる案内が始まるタイミング…って、すごい人出だな。話を聞きながらも、皆が集まってないところを、こそこそ作品を見て回ります。いや、こうしないと、この人数でぞろぞろ、なんてありえないですから。=====まずは出雲のコーナー。銅鐸・銅剣・銅鏡…出雲の地になぜ神は舞い降りるのか。出雲周辺の発掘調査結果を踏まえ、近隣の発掘品、勾玉や火熾しの道具などが展示されています。圧巻は、出雲大社で発見された巨大柱の話。出雲の時代にこの大きさだった、ということは…そんな神木クラスの木が柱に使われていた古代の出雲大社。もちろん、柱の直径が分かったところで、高さが分かるわけではないのですが、これまでの風土記の記述とあわせて、日本で一番の巨大建築であったことの間接証明。古代ロマンをかき立ててくれます。[出雲大社]-----次に伊勢神宮の神宝が並べられています。神宝は神に捧げられたものすべてをさすのではなく、神のための武具であったり、機織機であったり…うん?つまり、神自身が使う道具?この解釈で良いのかな?それにしても美しい。日本最高の神に捧げられる「無償の愛」は、当然のことながら、日本最高の技術の結晶。その美しさは、すなわち神々しさと同義なのでしょう。いやはや、眼福にあずかりました。[伊勢神宮]-----厳島神社からは平家納経。これまた、日本の誇る宝物の一つです。目を瞠るほどに美しい巻紙に、たおやかな筆致で愚直に綴られた写経。そこに込められた祈りの意味は何であったのか。また、台風にやられても修復を続けてきたその熱意。しかも、元の神域は、台風の被害を受けない立地がされているとの事。また、島に墓を持たない意味。千畳閣に掲げられた「絵馬」の面白さ。横山大観先生の傑作『屈原』も出品されています。[厳島神社]-----最後は京都から、八坂神社の祇園祭。私はまだ行ったことがありませんが。八坂神社の植生の変遷についての話は、興味深く面白いお話でした。かっては神域といえど、人の手が入り、整備されることで保たれてきた植生が、どこぞからのお達しにより、手を触れることが禁じられ、そのため、植生が歪んでしまっている、というお話。環境関係のお話をご存知の方は「里山」という単語が浮かんだかもしれません。全く同じことが、神社の神域にも起こっているのです。海外から渡ったタペストリーが、祇園の山車に飾られるダイナミズム。山車の巨大な車軸の迫力。[祇園祭]=====ふぅ。何度も筆が滑りそうになりましたが、なんとか紹介し終えました。神社については、宗教的というより、政治的な思惑が絡んでしまうため、本当の意味での総合研究は、まだ緒についたところなのだそうです。だからこそ、そういった政治的主観性を排除した、客観研究は、この国の深層を考えていく上で重要で、それに正面から挑み、一般の人に分かりやすく展示して見せたこの企画は、本当に素晴らしい。「これだけの宝物が一堂に会すことは、もうないでしょう。」と学芸員の先生が仰っていましたが、確かにその通りだと思います。日本の神々は多岐にわたり、それぞれの由来も伝説も異説も背負っています。これらを追う、という隘路に迷い込まず、この4つを選んだのは、正に「王道」。この展覧会の企画趣旨がそこにある以上、今回は横道の議論は慎ませていただきます。-----個人的には、アニミズム的な日本の信仰、宗像信仰や白神信仰などにも興味があったのですが…これらは、なんと、常設展で(ある程度)カバーされていました。この常設展のレベルの高さについても特筆すべきなのでしょうが、長くなるので一言だけ。高校生の頃、「日本史」の授業に時々違和感を感じることがありました。今思えば、それは、「綴られた歴史」から抜け落ちた、民俗学的視点を無意識に求めていたのだ、ということがよく分かります。その渇望を癒してくれるに十分足る、「教科書」が教えない、「教科書が教えない歴史」が黙殺する「歴史」がここにあります。本当は常設展だけで、1日ここで過ごしてもまだ足りないくらい。-----心残りは、図録が売り切れだったこと。「増刷の予定はありませんか?」と聞いたら、「今のところありません」と答えられました。うーむ。残念。=====『日本の神々と祭り 神社とは何か?』 - Japanese Shrines@国立歴史民俗博物館(千葉・佐倉)[会期]2006.03/21(火)~05/07(日) 作者:-★★★★★
May 7, 2006
コメント(0)
-

鹿島逍遥。
ふぁぁ。ああ。今朝は雨ですか…。旅先で迎える朝の心地良さに、ちょっと長めに微睡んでました。さてさて、鹿島神宮へ参りましょう。-----雨の中、駅のほうからてくてく坂を歩きます。煉瓦道沿いに、塚原卜伝先生の銅像を過ぎ、しばらく行って左に曲がると、さっそく神社の門が見えて来ました。あまり遠くないですね。参道の商店街も、思ったほど立ち並んでいるわけではなかったですし。ま、まだ朝早いですから、開いてなくて気付かなかっただけかも。-----ああ。神社ですから、門内にいらっしゃるのは、阿吽の仁王像ではなくて、えっと、誰だっけ?まだ頭が働いてないなぁ…。さて、門からさほど遠くないところに本殿。二礼二拍手一礼。お祈りすることはいつも同じ。今回は、あわせて旅の無事も祈ります。まだ宝物館は空いていないので、「奥の院」と「要石」「御手洗池」へ。しかし、雨が…やんでくれれば良いのですけど。-----途中、鹿園があります。 厩舎の中で、アンニュイに寛ぐ鹿たち。「雨の中、何してるんだろ、あれは?」と言わんばかりに、こちらを気だるそうに見ています。うわぁ。なんか馬鹿にされてる気がする。さてさて、晴れていれば、木漏れ日も爽やかに、の風情ですけど、雨だと足元が気になって…。森閑とした木立の中を、独り歩きます。----- 奥の院に到着。あれ? また、あっさりと。山の上とかにあるわけではないのですね。うーん?何が御神体なんだろう?こちらの方が本殿より小振りですけど、伝統的な感じで落ち着きます。-----さて、奥の院の裏に回って、しばらく進むと、「要石」に到着です。日本の地震を抑える、この国の…あれ?これですか?鳥居と柵に囲われて、サッカーボールほどの大きさもない、小さな石の頭が出ています。掘っても掘っても、その先が見えない、というので、ものすごく大きなものをイメージしていたのですが…。なんか可愛い。これを「発見」する日本人のメンタリティに愛しさを感じます。誰がこの石に「霊性」を視たのか?それが誰であろうと、祀られることで、この石の「霊性」は高められ、今、ここで人を呼ぶわけです。そう思うと、不思議な気になりませんか?-----奥の院に戻って、脇の坂を下り、「御手洗池」へ。 おお。なんか神秘的だ。水の中に浮かぶ鳥居。禊とかをしたのですね、きっと。水の湧き口は後ろに。ただ、今日は雨なので遠慮。-----ちょうど茶屋が開いたので、お邪魔します。「お早うございます。」「はい、お早う。」おばさんが3人、のんびり喋りながら準備しています。「どうぞ」ああ、温かいお茶が有難い。「GWは人多かったですか?」「天気が良かったからね。」「今日は雨ですものね。えっと、焼だんご下さい。」今朝の朝食は、炭焼のみたらしだんごです。大きいのが3つ串に刺さって。ご馳走様でした。-----さて、宝物館に向かうため、坂を上って奥の院を経由し、本殿に戻ります。あれ? それなりにこの坂きついかも。そっか、奥の院が高い所にないのではなく、本殿も含めて高い所にあるのか。なるほどね。とすると「要石」の位置付けも…-----宝物館も開いた所です。興味深いものもたくさんありますが、ここの目玉は、何と言っても国宝「直刀」。その長さ2m。2mってすごい長さです。あまりにも真っ直ぐな剣。しかも、制作は奈良時代と想定される、とのこと。何だろう、この圧倒的なまでの神々しさは。その巨大さゆえに、実用性は失われ、武器としての禍々しさが、神への供物としての美しさへと昇華されている…なんてのは後で考えたセリフで、ただただ美しさに息を呑んでしまいました。こららに宝物の紹介があります。-----さて、問題は靴下がびしょ濡れであることと、宿のチェックアウトタイムが近付いていることですね。靴下は…おお、そういえば、「天心の湯」で貰ったのがある。雨もあがりましたし、では、いざ佐倉へ向かいますか。
May 7, 2006
コメント(2)
-

芝居と美術と音楽と♪
水戸芸術館は、日本を代表する現代建築家の1人、磯崎新先生の作品。(昨年、青山のギャラリーでやっていた、先生の展覧会を観に行ったら、日曜で閉まっていた、という目にあった覚えが…。)先生自身の設計についての解説はこちら。----- さておき、まずは、このくねくねタワー(by chobiさんのコメント)が目を惹きます。非常に目立っていたので、朝からあれは何だろうなぁ、と思いながら水戸をうろうろしていたのですよ。 そして、入口近くのモニュメント。宙に浮いた大岩に、水飛沫が注がれるダイナミックな造形。迫力十分です。(うむ。この写真では十分伝えられない。)-----芸術館内の案内ツアーをやっていたので申し込みました。係員のお姉さんが案内を…って、あの、参加者は私1人ですか?「そうですね。よろしくお願いします。」こちらこそ。-----ホールではパイプオルガンコンサートをやっているので、先に劇場から案内頂きます。をを。すごく吸音性が良い空間♪舞台の上は何もないフラットな状態。真黒な壁。縦長で円形の客席。えっと?あれ?どこかで見た事がある気が…「グローブ座ですか?」「そうです。グローブ座を模した造りになっています。」なるほど。良いですねぇ。私も何度か「東京グローブ座」でお芝居を観た事があります、って、もう5年以上行ってないですけど。せり出したような客席が、広い劇場なのに、小劇場感を高めてくれる、なかなかに素敵な造り。ちょっと息が詰まる感じはありますけど、この一体感が気持ち良いのですよ。茂山先生が来られて、狂言なんかもやられるそうです。その時は橋掛かりも用意するのだそう。また、専属の劇団も抱えていらっしゃるとのこと。公務員演出家に公務員役者?(3セク?)うーん。すごいプレッシャーだなぁ。また、市民劇団として、オーディションで一般参加者を募って、ということもしているそうです。子供の部は大盛況だとか。…ちょっと羨ましい気もします。-----次にコンサートホール。天井の高い、白と金に彩られた、豪奢な空間。舞台自体はさほど広くないのですが、その分、客席がゆったりと取られています。音の響きも、さっきと違い、吸音ではなく、反射される造り。うわぁ。何ていうか、セレブ?健全で健康的で高級な感じですが…はは。音楽に疎い身には、場違いな雰囲気ですね。さっきの劇場の方が落ち着くのは、小劇場の血だな。こちらにも専属の楽団があって、小澤征爾さんが指揮をされるコンサートを開いたりするそう。-----そして、現代美術ギャラリー。さっきも来ましたけど、今度は「器」の鑑賞です。真っ白な壁、高い天井。天井から光が入る造りですが、もちろんこれは光をさえぎることも可能です。壁は自由に使って良いそうで、直接ペインティングなどをした場合は、あとで塗り直されるのだそう。もったいない気もしますけど…。横浜美術館の『李禹※展』でも、壁に直接描いた作品があって、「残すんですか?」と聞いたら、「基本的には残しません」という返事でした。ワタリウムさんのフェデリコ・エレーロ展なんかも、壁に描いていましたけど…取っておけないですものね。-----そもそもこのギャラリー、作品を持っていない、のだそうです。気合の入った企画展を開くなぁ、と思っていたら、そういうわけだったのですね。つまり、収蔵作品がないので、常設展を開く必要もないし、開けない。だから、企画で勝負する。いや、これは本当に面白い試み。何より、実際にこれまで素敵な企画が開かれているわけで、キュレーターの方々の苦労は並々ならぬものがあるとお察しします。-----劇場にしても、コンサートホールにしても、ギャラリーにしても、運営の方法に緊張感がありますし、市民との一体感が心地良い。単なる市民ホールとしてではなく、オリジナリティがある、最先端の企画を打ち続けることによって、ソフトの価値を高く保っている。「ハコモノ行政」で終わらせない、一つの方法論をここに見た気がします。-----そして、タワーへ。高さ100mというのは、水戸市制100年を祝って造られたから、とのこと。本来、展望塔として造ったわけではなかったそうで、窓を後からつけたため、円形の窓から外を見る、面白い造りになっています。 天気が良くないので、海までは見えないか…。-----いやぁ、半日ここで過ごしてしまいました。それにしても楽しかった♪本当は今日中に佐倉まで出て、『日本の神々と祭り』を見て帰るはずだったのですが、これは一泊追加せねばなりますまい。ま、午後の美術館ツアー&芸術館ツアーに参加しようと思った時から、覚悟してましたけど。さて。となると、また水戸に泊まるのもなんだから、鹿島まで出ますか。明日は、朝一で鹿島神宮を参拝、佐倉に出て歴博、と。よし。予定が決まったところで、えっと、鹿島のビジネスホテルの電話番号は、と…。
May 6, 2006
コメント(2)
-

in 『クリテリオム67』展@水戸芸術館
写真家 本城直季さん。「ぴあ」で紹介されていて、面白い写真を撮られる方だなぁ、と思っていたのですが、偶々、水戸芸術館で作品を拝見する機会に恵まれました。-----一見、普通のジオラマ写真のよう。舞台はスキー場と海水浴場。よく出来たディテール―丁寧に配置された人々、美しいシュプール、波の造形、車や木々…。ところが、この作品、「あ、そう」とは言わせてくれません。なんと、これ、本当の風景を撮ったものなのです!入れ替わる虚と実。「嘘」を撮った 写「真」だと思っていたのに、それが、「真」を撮ったものだとは…。そして、それを知ってなお、脳は「「嘘」だろ」と呟き続けます。我々は何をもって、この作品をジオラマだと思ったのか?どういう方法で、こういう写真が撮れるのか?心地良く、頭の中を流れる疑問符の旋律。-----学芸員の方が使われている「箱庭」という言葉が、言い得て妙、ですね。もしかすると、世界は、神様にとっての箱庭なのかもしれない。願わくば、「彼」の性格の良からんことを。-----さて、こちらは先生の作品集♪どんな感じか、分かりますかねぇ?本屋さんに置いてあったら、ちょっと見てみると面白いですよ。解説に佐藤雅彦先生(「だんご三兄弟」の、あるいは「ピタゴラスイッチ」の、で通じますか?)。こちらのページに写真とインタビューがあります。=====『クリテリオム67』展@水戸芸術館[会期]2006.04/01(土)~05/07(日) 作者:本城直季(HONJO Naoki;1978-)★★★★☆待って。私より若いじゃん。もう、そんな時代なのね。
May 6, 2006
コメント(0)
-

in 『人間の未来へ - ダークサイドからの逃走』@水戸芸術館
=====人間はどこまで残酷になれるのだろう。人間はいつまで愚行を繰り返すのだろう。「宗教」が人を殺すなら、私はそんな「神」を信じない。「権力」が人を殺すなら、私はそんな「政治」を認めない。「利権」が人を殺すなら、私はそんな「会社」を許さない。「民族」が人を殺すなら、私はそんな「民族」に属さない。「思想」が人を殺すなら、私はそんな「言説」を肯定しない。私は「不偏不党無所属」。神にも悪魔にも喧嘩を売って、それでも私は生き抜いてやる。私は「不偏不党無所属」。権力にも世論にも喧嘩を売って、それでも私は幸せに生きてやる。 初出; 『大アンコール・ワット展』@そごう美術館 改訂; 『ホテル・ルワンダ』=====好評は聞いていましたが、これほど密度が高い美術展だとは…。心にズシンと響く、剛速球の展覧会。水戸に足を運んだ甲斐がありました。-----作品数自体はさほど多いわけではないのです。しかし、その一つずつのクオリティ、企画展としての思想、壁に力強く描かれた、谷川俊太郎先生、、茨木のり子先生、、トルストイの「言葉」が、展覧会を引き締め、統一感を与え、深みを加えています。-----第1室前半は、アントニー・ゴームリーさんの作品。硬質で重量感のある金属片が組み合わされ、デジタル化された人物像として立ち上がります。組み合わされた破片の間から、向こう側が透けて見えるその空疎さ。うずくまったもの、直立しているもの、寝て起き上がろうとしているもの。人間という存在から「何か」を剥ぎ取った後に残る「何か」。次の作品や、オノ・ヨーコさんの作品とのつながりで言えば、「何か」によって消炭にされた人間の残骸とも見えます。-----第1室後半。マイケル・ライトさんの≪100の太陽≫。新聞などで、この作品について「最初美しいと感じてしまった」という評を聞いていたのですが、私は、最初から凍り付いてしまいました。原水爆実験の写真です。湧き上がるきのこ雲。「もう一つの太陽」は、太陽とは別の「もう一つの影」を地面に落とします。そして、それを無邪気に、あるいは真剣に眺める米軍兵士たち。彼らは、後遺症とか、大丈夫なのでしょうか?写真ではなく、小さな文字がびっしり書かれた作品が。各実験兵器に付けられた「愛称」なのだそうです。その数、名前に込められたユーモア…「やつら」の耳元で、声を大にして「ふざけるなっ!」と叫びたくなります。-----あわせて、橋本公さんの≪1945-1998≫も紹介しましょう。何かの近未来ゲームのような世界地図が、投影されています。右上のカウンターが1945年から時を刻みます。それに応じて、地図の一部が点滅し、各国の国旗の横の数値がカウントアップされます。そう、これは世界で行われた核実験の動的地図。最後に地図はフルスピードで再度点滅します。その数、2053回。世界中が光り輝くその様は、背筋が凍る程に凄絶。淡々と冷静に、ただ「事実」を映像化した作品。しかし、この抑制の効いた距離感は、作家の「凄み」を感じさせます。伝わる静かな怒り。=====核兵器は、人間の愚かしさの証明のような兵器です。そして、この星を何度となく滅ぼせるだけの兵器が、この世界には存在しています。しかし、これを美しいと感じ、力の象徴として、叡智の結晶として、崇める人たちが、この世界には多勢いるのです。その残虐さを知ることもなく、この兵器を国の科学力と国力の証明だと無邪気に信じて熱狂する国々だってあるのです。唯一の被害国は、唯一の加害国に遠慮して、その非人道性を世界に訴えることをしません。それどころか…=====ジェームズ・ナクトウェイさん、広河隆一さんの作品は共に「戦場」を舞台にした写真作品。中にルワンダの子供の写真がありました。頭にざっくりと残る三本のナタの跡。生きていることが不思議な程の深い傷。我々は忘れてはなりません。「正義」という名の狂気は、子供の命すら簡単に奪ってしまうのだ、ということを。そして。我々もまた「正義」という名の狂気の下に、人を殺す可能性を常に抱えているのだ、ということを。目の前で家族を奪われた少女が見せる、強烈な“無”表情。チェルノブイリに漂う虚無。宗教、民族、性別、差別、優越感、嫉妬、蔑視、暴力…-----オノ・ヨーコさんの≪絶滅に向かった種族2319-2322≫。「発掘された 滅んだ人類」というSF的着想をもとにした作品。べンチの上で、まるで生きているかのような姿で「発掘」された家族。2319-2322は西暦ではなく「それら」の分類番号。作者は、それぞれの叫びを、夢を形にします。「やめて 助けて」と繰り返される墓標の形をした石板。鷲掴みにされ、えぐられる胸。その恐怖のイメージは、しかし、親の世代のもの。出色なのは、「娘のイメージ」とされる脚の石膏作品です。最初は、真っすぐ膝が揃えられた両脚。次では、片足が心もち持ち上げられます。最後は、標本箱の外へ右足が一歩踏み出されます。力強い、未来への一歩を感じさせる表現。仏像(立像)の足が、一歩前に踏み出して表現されることが多いのは、仏は衆生を助けるために前に踏み出そうとしている、その表現なのだそうです。そんなことを想起させてくれます。そして、オノ・ヨーコさん自身による詩。=====その他の作品もあわせて、心に響く、ハイレベルの企画展でした。ただ、語り続けると長くなるので、そろそろ筆を置きましょう。最後に、展覧会に掲示されていた谷川俊太郎さんの「くり返す」を引用させて下さい。くり返すことができるあやまちをくり返すことができるくり返すことができる後悔をくり返すことができるだがくり返すことはできない。人の命をくり返すことはできないけれどくり返さねばならない人の命は大事だとくり返さねばならない命はくり返せないとくり返さねばならない私たちはくり返すことができる他人の死なら私たちはくり返すことはできない自分の死を(谷川俊太郎詩集『いまぼくに』理論社 2005年)=====『人間の未来へ - ダークサイドからの逃走』 - To The Human Future Flight From The Dark Side@水戸芸術館現代美術ギャラリー[会期]2006.02/25(土)~05/07(日) 作者:-★★★★★
May 6, 2006
コメント(2)
-
in 『山口勝弘』展@茨城県近代美術館
山口勝弘さんの名前は、お恥ずかしながら、先日の『武満徹』展で「実験工房」の同人として初めて知りました。メディア・アートの先駆者として、そして、今もなおトップランナーのうちの1人として活躍する山口勝弘さん。-----お出迎えは、『武満徹』展でも拝見した「ヴィクトリーヌ」シリーズ。偏向ガラスで歪められ、見る角度によって絵が変わる、静的なのに動きのある作品です。私は「麒麟」が好き。抽象画風に描かれた、大きな黄色の生物。そのリズム感が気持ち良い。を?「ヴィクトリーヌ」との共演として会場構成に名前があがっているのは、清家清先生に丹下健三先生?清家清先生の名前をここで聞くとは…。昨年、「清家清展」観に行きましたよ♪-----布を使った作品から、ヴィデオ作品。大阪万博の三井グループ館の写真はカラフルでかっこ良い。それに連なるような台北第二美術館の『龍』のオブジェ。『夢遊桃源図』は、ビデオで投影され揺蕩う墨絵の質感と遠近感が面白い作品。大阪のビデオ・パサージュやバード・ボートは見に行ってみたいなぁ。(@大阪市立住まい情報センター)最新作の「宇宙のテアトリーヌ」は…うーん。意図は分かりますけど。=====『メディア・アート先駆者 山口勝弘展 「実験工房」からテアトリーヌまで 』@茨城県近代美術館[会期]2006.04/08(土)~05/14(日) 作者:山口勝弘(YAMAGUCHI Katsuhiro)1928-★★★★☆
May 6, 2006
コメント(0)
-

好文亭@偕楽園 (水戸)
ご存知のように、水戸の偕楽園は、岡山の後楽園、金沢の兼六園と並び称される、日本三大名園の一つです。梅や桜が有名で、おそらく少し前には人も多かったのでしょうが、今は人もまばら。そんな中、躑躅が咲き誇っていました。 うーん。あのちょっと濃い花の色と、葉っぱの粘着質な感じは、正直あまり好みではないのですけどね。-----さて、その中にある、好文亭。 いや、本当、「和風」の空間って落ち着きますね。いや、襖絵を見るだけでも、行く価値十分。ものすごい量の写真を撮ったのですが、今回は泣く泣く数枚で。 扇面散らしのセンスの良さとか、くぐり戸の形の面白さなど、見所いっぱい。 釘隠しが何種類かあるのが楽しくて、写真をそれぞれ撮っていたのですが、ケースにまとめて展示されていました。ふむふむ。 しかし、それにしても、寛ぐなぁ。-----さて、お茶室の名前は「何陋庵」。論語からの命名。 待合は外から回って拝見。 ○と□の掛物に、△の窓。このセンスは素敵。バランスも良い感じ。こういうセンスなぁ。一見陋屋に見せて、細やかな作り。-----最高の部屋は最上階の「楽寿楼」。 竹の床柱?すごい存在感。大きく取った円窓も良い塩梅。偕楽園から千波湖まで一望。 初夏の薫風吹き渡り、目にも鮮やかに萌ゆる新緑。何と気持ちの良いことか。-----三階には、なんと厨房エレベーターが設置されています。井戸と同じ仕組みで、下からの配膳を楽にするよう工夫がされているわけですね。 左から、3階に設置されている装置、覗き込んだところ、一階の装置です。いやぁ、この工夫は、面白い。-----この後、偕楽園内をうろうろ。 新緑と花々の美しさも触れたいところですが、吐玉泉には触れねば。 真っ白な寒水石の真中から、こんこんと湧き出す鮮烈な清水。近くに、井戸水の水質調査票がちゃんと置いてあるのが面白い。うん。甘い。気持ち良い。足が濡れる。あれ?えっと、行かれる時は、ご注意ください。-----さて、お土産やさんもオープンした時間。そろそろ美術館めぐりに参りますか。
May 6, 2006
コメント(2)
-

天心随想。
(五浦周辺)岡倉天心先生は、私が最も尊敬する芸術家のうちの1人であり、最も尊敬する美術評論家の1人であり、最も尊敬する思想家の1人であり、最も尊敬する教育者の1人です。29歳にして、東京藝術大学の初代学長として、横山大観、下村観山、菱田春草、近代日本を代表する日本画家の精神的な、また実践的な師匠の役割を果たし、また、フェノロサと共に、日本文化の再評価に取り組みました。藝大を追い出された後、上記のメンバー達と日本美術院を結成。日本美術の発展に力を注ぐことになります。その一方で、中国・インドに日本文化の源流を求め、各国の著名人と交わり、ボストンを皮切りに日本美術展を開いたり、『茶の本』『東洋の理想』など、日本文化を啓蒙する英著を記したりと、日本文化の紹介に大きく寄与。 -----あう。偉大すぎる。知性・教養・行動力、どれを取っても天下の逸材。絵も描けば、書も嗜み、英語で戯曲も書けば、評論も書きます。-----よくお世話になっている、ワタリウム美術館さんは、現代美術館でありながら、「岡倉天心研究会」と題する勉強会を定期的に開いています。これが本にまとめられたのがこちら。 『ワタリウム美術館の岡倉天心・研究会』そして、昨年は『岡倉天心展』を実施。(感想はこちら)五浦行きのツアー企画もあったのですが、私はツアーには参加できなかったのです。現代美術館の提唱する「温故知新」。ちょっと新鮮でしょ?-----(美術院跡の垣から)五浦美術館の中には、岡倉天心コーナーがあって、書や愛用の品などが展示されています。部屋の一室も再現。小品ながら、心惹かれる岡倉天心像があります。おっと、平櫛田中翁作だ。先日畠山記念館で見たばかりですが、また翁の作品を拝見できるとは。-----この後で行った、六角堂にある天心記念館にも、平櫛田中翁作の、釣りをする等身大の天心像、胸像、そして、『活人箭(かつじんせん)』が展示されていました。『活人箭(かつじんせん)』の写真はこちら。(てか、ここにある作品、ほとんどこちらに写真が載っていますね。)最初の『活人箭(かつじんせん)』に対する天心評がすごい。弓と矢を手にしているのに対して、「弓と箭はいらない」「あんな姿ではは死んだ豚も射れぬ。」と斬って捨てたとのこと。それを受けて、田中翁は弓と矢を省いた作品を創り上げます。弓と矢を持ったバージョンの写真があるのですが、それもそれで凄い出来。しかし、弓と矢を持たないことで、観る側の視線が作品の表現そのものに集中されることになり、緊張感がより凝縮されるのです。しかし、何故、そこまで見抜けるんだろう?美に対して、よっぽどのセンスがないと、これは出来ない。それを指摘できる天心先生もすごいし、それに答えた田中翁もすごい。評論かくあるべしの、見本のような問答ですね。-----さて、六角堂です。 六角形の和室。畳は台形でした。なるほど。赤瀬川原平さんが『千利休 無言の前衛』の中で、「楕円の茶室」を夢想されていましたが、これを思い出させます。ワタリウムさんの展覧会では、美術館内に六角堂を再現し、周辺映像をプロジェクターで流す、という素敵な演出がされていましたが、ここでは中には入れません。潮騒と松籟が遠く響き、渡る風と麗らかな日差しが空間を満たし、心落ち着く時間が流れます。一瞬、周りに人がいることすら、忘れてしまいそう。偉大なる先人が自ら選んだ景勝の地は、様々な思索を私に与えてくれました。-----本当に来て良かった。お昼ごはんが美味しかった話とか、公園で出会った美術好きのおじさんの話とか、「天心の湯」の感想とか、帰り道に街灯がないことに気付いて、日暮れまでに駅につけるか焦ったこととか、いろいろありましたが、そこらへんは割愛。今から水戸に移動しても、宿泊だけですね。ちょっと予定とずれてしまいましたが、それも良いでしょう。さてさて、いざ水戸へと参りますか。
May 5, 2006
コメント(0)
-

in 『伊東深水展』@天心記念五浦美術館
伊藤深水と言えば、美人画のイメージ。「優美にしてモダン 麗しの女性たち」と題して、初期作品から晩年の作品までが並んでいます。 -----初期作品と言った時に、鏑木清方に入門したのが13歳の時。翌年、第12回巽画会展に入選。さらに翌年には巽画会1等褒状。16歳で再興第1回院展に入選。最初にこの時期の作品が並べられているのですが、美の才能を司る神様がいるのなら、「あなたは不公平だ」と文句を言いたくなるような、完成された作品。画面構成、色調、描線の優美さ、えっと、中学生くらいの年齢ですよ?(経歴についてはwikiより)-----美人画が続く中、同じ構図で何枚も描いているのが面白い。色彩を微妙に、あるいは大胆に変えて、しかし、上品な雰囲気を保って描かれる女性像。すごいなぁ、と思ったのは、2曲1双の屏風絵。大胆に大きくうねる梅の巨木。上品なうら若き女性。左隻には樹の描写のみ。右隻に控えめに描かれる女性の姿。「美人画」の部分よりも、梅の木の美しさと確かさに圧倒されました。その描写力の確かさが、「女性の美」を引き立てています。確かなデッサン力と、美を信じる力。天賦の才。訓練された技法。いやはや。脱帽です。-----知っている人は、気になるでしょうから…。女優の朝丘雪路さんは、伊藤深水先生の娘。この展覧会にも、家族を描いた肖像画があります。少女時代の朝丘さんがちゃんと描かれています。-----ちなみに、現在、目黒区美術館では『素顔の伊藤深水』展をやっています。帰ったら、こちらも観てみますかね。(ふふふ。「ぐるっとパス」で。)=====『伊東深水展』 -優美にしてモダン 麗しの女性たち@天心記念五浦美術館(大津港・勿来)[会期]2006.04/28(金)~2006.06/04(日)★★★☆☆-----【参考】『素顔の伊藤深水』展@目黒区美術館[会期]2006.04/08(土)~2006.06/04(日)
May 5, 2006
コメント(0)
-

五浦(いづら)へ。
さて、勿来関から五浦まで。いわき市勿来関文学歴史館からちょっと下った所から、石畳の道に入って、展望台から海を望みますうーん、霞んであんまり良い写真撮れないや。 しかし、晴れてて良かった。石畳って、雨に濡れると非常に滑って危険なのですよ。私は独りで歩くのが、嫌いではありません。今回の行程も、車なら10分で行ける所をのんびり1時間かけて回っているわけで…。でもね、車で点と点を結んでしまったら、見えないものがある。出会えないものがある。「お前の旅は贅沢だ」と評されたことがありますが、ふふふ。分かってらっしゃる。-----海岸まで出ると、海に向かって鳥居。 うーん?ちょっと不思議な感じです。満潮時は海に浸るのかな?-----一旦国道に合流し、切り通しを抜けて平潟漁港へ。あんこう鍋と、さつま揚げの旗がたくさん…。さつま揚げの場げ立てとかあったら 食べたいなぁ♪-----ふと左手に鳥居、その奥にトンネル。おっと、この位置取りは、と寄り道。つまりですね、こちらの方角はさっきの切り通しの横手の山に通じているわけですよ。港の近くには、たいてい安全祈願の神社がありますが、これが高台にある場合、神様に見て頂けるよう、神社は港が一望できる位置にあるのが相場。平たく言って、景色が良いはずなのです。ま、これも独り旅の良い所で、この勘が間違えていても、誰にも迷惑はかかりませんし、当たっていれば儲けもの。今回は当たり、でした。-----私の育った関西では、海の神様と言えば「住吉さん」だった気がするのですが、こちらは「八幡様」。ふむ。ちょっと今後興味をもって調べてみますか。とりあえずwikiで…住吉さん/八幡様/日本の神々一覧-----ともあれ、参拝。旅行の無事を祈願。 本殿の裏手の岩肌に窟を穿って、そこに神像を祀っています。なるほど。本来の形式はこちらですか。そして、近年の虎の彫刻(結構大きい)が本殿の真後ろに。えっと、この位置取りで良いのかしら…?さて、思ったとおり、港を見下ろす絶景。 奥の院までは登らず、ここで引き返し。-----温泉旅館、あんこう料理のお店、地味ながら、生活の息吹が感じられる、なかなか渋い街並みです。そんな中、和雑貨のお店を発見。旧家を利用した、風情ある佇まい。 「さらま・ぽ」さん。(HPはこちら)店名はタガログ語で「ありがとう」の意…って教えて頂いたのですが、何故タガログ語なのか聞き忘れたのは問題だな。うやぁ。落ち着くなぁ。小物のチョイスのセンスも良いし、ディスプレイも雰囲気が良い。(お店の中の雰囲気は上記HPを、あるいは実際のお店を御訪問ください。)あ。いや。お茶にお菓子まで出して頂いたから褒めている、というわけではないですよ。こんなにのんびりした時間が流れる雰囲気って、奈良に旅行した時以来かも。そうそう、ランチもやっているそうなので…。もうしばらく、のんびりしたかったですけど、まだしばしの距離がありますし、今日は出来れば、水戸まで行くのが(電車でですよ)目標ですから。レターセットだけ買わせて頂いて、後ろ髪を引かれつつ、「さらま・ぽ」さんを後にします。-----しばらく行くと、長浜海岸。「鳴き砂の海岸」と地図には書いてありますが、正直良く分かりませんでした。 でも、良い景色ですね。やっぱり海は良い。-----うーん。書くかどうか、いや、写真に撮る時も迷ったのですが…。 「風船爆弾放流地跡」の碑が建てられていました。失礼とは分かっていながら、これが研究開発され、実戦に投入された「真面目な滑稽さ」に、何と言うか、切なさと虚しさを感じてしまいます。-----さてさて、海の向こうに見える建物が、五浦美術館ではないですか?ちょっとのんびりしすぎました。先を急ぐとしましょう♪
May 5, 2006
コメント(0)
-

なこそおしけれ。
歌枕として有名な「勿来の関」(なこそのせき)。「勿来」は読み下すと「来る勿(なか)れ」。「来るな」の響きの面白さ、「関」という人の行き来を堰き止める役割から、「あふさか」=「逢う坂」の関と同じように、掛詞の形で多く使われます。なーんて、私もそんなに「文学的素養」があるわけではないので、和歌を引用したりは出来ないのですが。----- 勿来の駅で降りて、駅員さんに、「えっと、勿来を抜けて、五浦まで歩きたいのですが、そんな地図とかあります?」と聞いたら、快く「駅からハイキング」の地図を下さいました。そうそう、こういうのです、欲しかったの。いや、もう、これだけでご機嫌♪うん。歩くだけなら、大体1時間強くらいのコースですね。----- 勿来は、桜の名所としても有名だそうで、既に新緑になってしまっていますけど、桜の木がとても多い。さぞかし綺麗だったのだろうなぁ、と思いつつ、緩やかな坂を上っていきます。耳に響くは鴬の声。-----岡本綺堂の戯曲に、勿来の関を舞台にした軍記モノがあるらしく、その登場人物解説と、関までの距離が書かれた案内板が設置されています。良いですねぇ。こういう気配りが有難いです。-----ただ、少々膝が痛いのと、足元が雪駄というのが…いや、勿来に来ようと決めたのが、電車の中だったため、そこまでの用意はしてなかったのですよね。いや、えっと、岡倉天心先生に敬意を表して、和服に袴、麦藁姿です、私。-----と言っている間に、関跡に到着。多くの句碑・歌碑が並ぶ公園になっています。 いわき市勿来関文学歴史館へ。勿来を織り込んだ歌が、テーマに沿って展示されていますが…あう。私にはまだちょっと早かったか。お金もかかっていて、立派な展示になっていますが、うーん、昔から、詩とか俳句を「感じる」のって苦手なんですよね。作る側にまわれば「分かる」ようになるのかなぁ?-----私が「勿来の関」を知ったのは、『枕草子』でした。「関は 逢坂。須磨の関。鈴鹿の関。岫田の関。白河の関。衣の関。ただごえの関は、はばかりの関と、たとしへなくこそおぼゆれ。横はしりの関。清見が関。みるめの関。よしよしの関こそ、いかに思ひ返したるならむと、いと知らまほしけれ。それを勿来の関といふにやあらむ。逢坂などを、さて思ひ返したらむは、わびしかりなむかし。」(こちらからコピーさせて頂きました。)私は、自分の日記でぐちぐち他人の悪口を書いていた、同世代のベストセラー恋愛小説作家よりも、花鳥風月を自分のセンスで斬ってみせ、自分の思いをはっきりと、リズミカルでポップな文体で綴った清少納言さんのファンです。文体からしても、こちらの方が断然美しいですし。明るく気丈に振舞って見せている分、心根が繊細だよなぁ、と。「好きな女性のタイプは?」「清少納言かオノ・ヨーコ。」って答える度に、困った顔をされるのですが、うーん、結構真面目に考えた結果なのですがねぇ。----- こちらは、オノは小野でも、小野小町さんの歌が、柵代わりのガラス板に書かれていて、景色の中に歌が浮かぶ仕掛け。「見るめかる あまのゆききの 湊ぢに なこその関も わがすえなくに」「海松(みるめ)刈る」と「見る目 離る(かる)」を掛詞に、「私は「来ないで」なんて言っていないのに」と切ない心情を、遠い勿来の地のイメージに託して吐露した…んだろうな。 -----なんか、新しい教育施設を建築中でした。和風の結構大きな建物。桜の季節は、人がいっぱいで良いのでしょうが、今日みたいにがらがらだと採算取れるのかなぁ。建設、維持費、教育、観光、一介の旅人が何を言えるものではないですが。-----さて、関を下り、海岸線に沿って、平潟漁港、そして向かうは五浦。楽しく参りましょう♪
May 5, 2006
コメント(0)
-
僕(ら)が旅に出る理由♪
GWは遠出をしないと決めていました。その代わり、意外と近場なのに(近場だから?)行く機会のなかった、水戸芸術館(茨城県水戸)と、国立歴史民俗博物館(千葉県佐倉)に足を伸ばそう、と。それぞれ『人間の未来へ|ダークサイドからの逃走』『日本の神々と祭り』という展覧会をやっており、評判が高いのを耳にしていたので、良い機会だな、と。そして、せっかく茨城に行くのだから、岡倉天心ゆかりの五浦まで、五浦まで行くなら歌枕として有名な勿来まで足を伸ばそう、と。また、水戸も初めてですから、偕楽園には行きたいし、茨城県近代美術館でやっている『山口勝弘』展も観ておこう、と。さらに、水戸から佐倉まで行くには、東京に戻らないとすると鹿島経由ですから、鹿島神宮も参拝しましょうか、と。-----旅の前夜には、環境サークルの同世代と語らい、最終日にはそのサークルを創設された大先輩とお会いするというおまけ付き。-----のんびり気ままな独り旅。当初の予定では、1泊2日の小旅行だったはずが、終わってみると、密度のやたら濃い、2泊3日になっていました。-----【予告】下記の順に更新していきます。5/5・なこそおしけれ。・五浦(いづら)へ。・『伊藤深水』展@天心記念五浦美術館・天心随想5/6・好文亭@偕楽園 (水戸)・『山口勝弘』展@茨城近代美術館・『人間の未来へ - ダークサイドからの逃走』@水戸芸術館・『本城直季』展@水戸芸術館・芝居と美術と音楽と♪5/7・鹿島逍遥。・『日本の神々と祭り』@国立歴史民俗博物館・End of the Journey・阿佐ヶ谷住宅※リンクは順次。先は長いなぁ…いつ普通の日記に戻れるんだろう?ま、こちらの更新も、のんびりと。
May 5, 2006
コメント(2)
-

茶会記@畠山記念館
畠山記念館でお茶を頂いてきました。5/4,5に茶室公開があり、日頃は記念館内で出しているお茶を、お茶室で頂けるとのこと。そんなお茶ですので、「お茶会」ではなく、お茶室でお茶を頂く、お気楽な形式。でも、ちゃんとお軸もお花も飾られ、お菓子も出るのですから、有難いことです。公開茶室は、「浄楽亭」と「毘沙門堂」。「浄楽亭」の方で、お茶を頂きました。 (真っ直ぐ奥が浄楽亭、左手が毘沙門堂。)-----お軸は、鍾馗様。端午の節句に相応しい掛け軸ですね。お菓子は、菖蒲と撫子をかたどった干菓子。お花は…名前が分かりません。いやぁ。それにしても美味しいお茶だこと。時折渡る風の音が涼やか。時を忘れてしまいそうになりますが、もうお茶も飲み終わりましたし、おいとましますか。-----お茶を頂いた「浄楽亭」は、10畳の広さがある大人数用で、特に茶室としての工夫が面白い、というわけではありません。普通の日本間だなぁ、と、落ち着く感じ。同じ建物の続きにある、3畳小間の「毘沙門堂」は、本当に「茶室」らしい茶室。青色の腰板?センスですねぇ。屋根には菖蒲の葉が渡されています。こんなの初めて見ましたけど、涼やかで良いですね。毘沙門堂の揮毫は、益田鈍翁先生。財界きっての数寄者。-----ちょっと離れたところに待合。 それなりに広く取られていて、しかもその裏にお手洗いを配しているのは、「気遣い」ですね。この造りは考えられているなぁ、と思います。-----ああ。しかし、このざっくばらんに形式ばらず、お茶が飲めるのは良いなぁ。茶室の貸し出しもあるそうです。畠山記念館(高輪台/白金台/五反田)東京を離れるのに、名残の茶会を開く、なーんて憧れてしまいますが…。お茶の嗜みがある人にスタッフをお願いして、とかしないと無理だものなぁ。うーん。でも、意外と安いし、やってみたいなぁ。
May 4, 2006
コメント(2)
-

in 『蒔絵の美』@畠山記念館
元首相仮公邸や、美智子妃殿下のご実家跡(ねむの木の庭)、池田山公園などがある白金台の一角に、畠山記念館はあります。ぶらぶら歩きを想った方はこちらなど。うーん。こーきゅーじゅーたくがい。こういう所って、道間違うと、本気で迷子になっちゃうんですよね。-----さて。畠山翁は荏原製作所の創設者。茶の湯から始めて美術に造詣深く、その個人コレクションを元に美術館として畠山記念館を設立。住宅街に静かに佇む、緑に恵まれた美術館です。こんな近所に、こんな素敵な美術館があるなんて…。実は知りませんでした。先週、教育園に行く途中で看板を発見。昨日も松岡美術館に行く道すがら立ち寄っていたのですけど、茶室公開が4・5日のみだったので、スルーして今日に回したのです。----- 門扉には、「○」に「二」の紋。この力強さが良いですね。余談ですが、ここから山一つ向こうの高輪には、ミッション系の清泉女子大学があります。こちらにはコンドル設計の建物が残されており、これが島津家のものだったので、「○」に「+」の紋が入っています。偶然とは言え、ミッション系らしい意匠(十字架に見えますよね)になっているのが面白い。ただし、女子大の敷地内にある建物なので、文化祭の日とか、あるいは事前に申し込まないと、こちらは見ることは出来ません。(女性はいつでも可なのでしょうけど。)----- さて、美術館入って真っ直ぐ奥に、畠山翁を象った木彫があります。彫りの線の鋭い、力強く繊細な人物像。うわぁ、と思って作者名を見たら、平櫛田中翁。いや、やっぱりすごい。-----実は、平櫛翁の作品って、それと知って見た事があまりないのです。つまり、「ウム、この作品は平櫛翁の作か、なるほどすごい。」ではなく、「この作品すごいなぁ、作者は誰だろう?」と作者名を見ると「平櫛田中」なのですね。最初の「出会い」は、彫刻家の名前なんて全く知らない大学生の頃。広島の福山城で、「この木彫すごいなぁ」と思って作者を見ると「平櫛田中」とあり、変な名前だなぁ、何と読むんだろう、と。その後も、色々な所で、「すごいなぁ…おや?これも平櫛田中?」を繰り返し、その偉大さを知るようになりました。私も大概「俗物」なので、どうしても例えば「“ゴッホ作”。だから凄い」みたいな見方をしてしまいがちですが、翁の作品は、私を「感動の原点」に立ち返らせてくれます。波長の問題もあるのでしょうね。『シュテファン・バルケンホール』展の時も書きましたが、『平櫛田中展』どこかで企画してくれないかなぁ。-----いかん。平櫛翁の1作品に時間を取りすぎた。メイン展示は2F。っと。建物の中に茶室?これ、畠山翁のアイデアだそうで、掛軸の展示が並べられるスペースを作り、そこから室内茶室にスムーズに誘導できるように設計されています。面白い。江戸時代最後の琳派、酒井抱一先生の掛軸があります。「十二ケ月花鳥図」。鮮やかで涼やか。他時代の「琳派」と並べられると、作品が優美すぎ、迫力に劣るため、あまり高く評価されないこともある酒井抱一先生ですが、「美術品」ではなく「掛軸」としてあると、装飾性の高さと優美さが相まって、上品な「気」が漂います。酒井抱一先生は、姫路藩主の弟。兵庫県民としては、ちょっと高く支持したいところです。琳派に私淑し、琳派の影響を強く受けた作品を残しました。作品からすると、琳派の「過剰性」よりも「装飾性」が好きだったのかなぁ、と。(なお、「琳派」は、そういう流派があるのではなく、時代毎に、「琳派」に私淑した人が技法を模倣しながら、受け継がれていっているのです。)酒井抱一先生のwiki解説はこちら。琳派についてはこちら。-----いかん。また酒井抱一先生で時間を取った。いよいよ「蒔絵の美」です。鎌倉時代の硯箱も含め、他のお茶道具なども取り合わせて。どれも溜め息をつくほど美しい。蒔絵の美しさもさることながら、茶杓の景色、棗の風情など、使ってみたくなります。良いなぁ。そう、こういうのの善し悪しが、お茶をはじめるまでは分からなかったのですよ。そもそも何に使う道具か分からないものもありましたし。お茶をはじめた直接の動機は、「美術品を分かりたい、触りたい」にあったのですが、何年か続けたことで得られたものは、単にそれだけではない、すごく大きなものでした。-----館内の一角、蒔絵の一環として、「印籠」が並んでいるのですけど、正直、蒔絵よりも、「根付」の凄さに目が行ってしまいました。「根付」は今で言う「携帯ストラップ」。昔は印籠などを帯に挟んでいたわけですが、それが落ちないようにするためのアイテムが「根付」です。サイズも使用目的も、「携帯ストラップ」そっくり。で、木や象牙(今はもちろんダメですけど、江戸時代でも高価だったはずです)で出来ているのですが、これが、精巧で緻密。今でいうと、海洋堂のフィギュアとかが近いのですが、それらを優に超えるクオリティ。なにせ、一点ものですもの。私が「根付」を知ったのは、星新一先生のエッセイで、小学生の頃。使う人が減っていた当時に集め始めたので、安く手に入れることが出来た、なんて話を書かれています。余談ですが、星新一先生の趣味は、この「根付」集めと、アメリカの一コマ漫画蒐集。どちらも、限られた大きさの中に、凝縮された小宇宙を創りだす、という点で、先生の作品そのものに通じるものがあると思いませんか?-----えっと、今回はやたら余談が多くなってしまいましたが…そんなに大きくはないのですけど、やたら落ち着く空間でした。誰かと一緒に、ではなくて、独りでゆっくり、寛いだ時間を楽しみたい時に良いですね。是非またお伺いしましょう。=====『蒔絵の美』@畠山記念館(高輪台/白金台/五反田)[会期]2006.04/01(土)~05/28(日) 作者:-★★★★☆
May 4, 2006
コメント(0)
-
「漢字バトン」 from shn-per
shn-per先生より、「漢字バトン」なるものを頂きました。また難しいお題を…。-----shn-per先生は、劇団時代同期の演出家兼役者。確かな技術と柔軟な思考…うーん。彼を紹介しようとすると、何故か「舌足らず」ならぬ、「舌余り」になってしまうのですね。思わず饒舌に語った後で、「ありゃ?言いたかったことと違うぞ」と。フム。語りえぬものについては沈黙しなければなりませんかね。と言いつつ、第一問は…【1】バトンを回してくれた人に対して持つイメージの漢字は? なんですよね。うーむ。これでどうかな?shn-per = 『戯』-----「戯曲(ぎきょく)」の戯 :演劇関係ですから。「遊戯(ゆうぎ)」/「戯(たわむ)れる」の戯 :遊びをせんとや生まれけむ。「戯言(ざれごと)」の戯 :誤解を招かぬよう、下に補足。西尾維新さんというミステリ作家さんがいまして、作中の探偵役を「戯言遣い(ざれごとつかい)」と呼んでいるのです。なかなか面白い表現ではないですか?(中を読まず、作品の帯で知ったので、誤解があったらごめんなさい。)私もそうなのですけど、shn-per先生の論理構成力ってすごく高いのですが、一方でそのことに対して、自分自身すごくニヒルというか懐疑的なところがあるのですね。ディベートゲームで、どちらのサイドに立っても、同じ説得力で論理展開できるだけの能力があるので、一歩引いた高みから、論理の限界に当たりをつけられるのです。だからこそ、「論理」に対して懐疑的にならざるを得ないし、一方で、自分の想像の範疇を超えた「論理」に出会うと愉しくてしかたない。違う?言葉そのもののエネルギーを引き出す「言霊遣い」ではなく、言葉を並べることで「論理という物語」を紡ぐ「戯言遣い」の末裔。-----はう。やっぱり長くなりました。ここからは手短に。-----【2】大切にしたい漢字を3つ『和』 わ・なごむ・やわらげる 平和・和解・和をもって貴しとなす『環』 わ・たまき・かん 環境・環太平洋・環礁・金環日食『輪』 わ・りん 友達の輪・輪廻「わ」で揃えてみましたが、いかがでしょ?なごむ・つながる・まわる…そんな感じ。-----【3】漢字のことをどう思う? 表意文字としての可能性。ひらがな・カタカナの祖。日本文化の重要な基層の一つ。中国・韓国へと繋がる文化ネットワークの基盤。-----【4】最後にあなたの好きな四字熟語を3つ教えてください。 『四季折々』 :『春風駘蕩』『春夏秋冬』とかも浮かんだのですが、季節感を表すものとしては、これが綺麗かな。『忘己利他』 :元 柔道家としては『自他共栄』も考えたのですが、もう少し踏み込んでみました。『温故知新』 :私の座右の銘の一つ。『世界平和』は四字熟語ではない気がしたので、こちらにしました。-----ちなみに私がshn-per先生より頂いたイメージ漢字は『和』でした。「なんかもっと他の漢字ありそうなんだけど…表象的には、和。 」とのこと。さて、このバトンを回すためには、それぞれのイメージを漢字で表さねばならず…。ここまでが限界なので、保留させてください☆
May 3, 2006
コメント(4)
-

日々是勉強。
せっかくなのでと、ぱくぱくさんと夕食をご一緒することに。-----表参道裏、ワタリウムからも程近い、とんかつ「まい泉」青山本店。その後、近くのオシャレなカフェで。(そこ、男同士で?とか つっこまない。)おっと、ここの内装は北欧系ですね。お店の名刺はスウェーデン国旗をかたどっていますし。-----色々な話をしましたが、当たり障りのない範囲で喋ると、日本における弁護士のお話などしてました。以下は会話の再録(はまずいので)ではなく、お話をして私の頭をよぎったこと。あくまで、私の個人的な意見です。----------司法制度も現在、色々な変更が加えられており、先日TVで、民間に出向研修する若手裁判官の話などがされていました。そもそも、法科大学院制度が導入されたのは、多様な価値観を持った司法試験合格者を増やすため。来年は、いよいよその一期生が誕生します。(注;法学部出身者とそれ以外では院での期間が違います。)これで司法がもっと身近になれば良いのですが。-----ただ、司法はあくまでも法律を運用する立場であって、法律を作る立場ではありません。例えば「新・治安維持法」がもうすぐ成立するようですが、これが司法テロに使われないことを…あ。「国民」自ら「正義」の名の下に「異質な国民」を裁かせ、国家の共犯者にするための「裁判員制度」?この2つはセットというか、相互補完作用を持つのか。だとすると、このシステムを考えた人達は相当頭が良い。考えたのは政治家じゃないな。ほとんどは、何も知らないのを良いことに踊らされているだけにしか見えない。でも、普通の官僚が考えるようなネタでもない。「国策逮捕」としか思えない逮捕。世論誘導的偏向報道の多いマスコミ。このシナリオを描いているのは、誰なんだ?-----おっと、これを読んでしまった人、ちゃんと反論を書き込んでおかないと、「共謀罪」で逮捕されますよ~。「反論しなかったということは暗黙の賛成だ」って言われて、お国に反対した「愛国心」のないやつの仲間として、死刑になりかねません。という世の中が近づいているのですけど…。このシナリオの先には何が描かれていて、誰が得するのだろう?陰謀説に与する気はありませんが、それにしても、世の中の閉塞感が増す方向に進んでいるのを感じています。-----先日の新聞に面白い記事が載っていて、「国家の自衛権」の前に「個人の自衛権」があり、国家の自衛権行使が、個人の安全を脅かすのであれば、異議申し立てをすることが出来るのだ、と。「国家あってこその個人」ではなく、「国民あっての国家」の視点から考えたらどうか、と。うーん。丸山真男かぁ。まずは、以前ぱくぱくさんに教えて頂いた小熊英二さんの本を読み込むところからだなぁ。 (『〈民主〉と〈愛国〉』/『市民と武装』)「個人の自衛権」のお話をされた、杉田敦先生の本も読んでみるか…。 (『社会の喪失』/『デモクラシーの論じ方』)----------ま、実際の会話は、プライベートな話から次のイベントの話まで。さてさて、私は何をしますか。
May 3, 2006
コメント(0)
-
in 『スパイラル・インディペンデント・クリエーターズ・フェスティバル』@スパイラル・ホール
書類審査を通った100組のアーティストが、割り当てられた小さなブースで作品を展示。さすがに一挙100組は無理なので、期間を前後に分けて50組ずつ。拝見したのは前期の組です。-----ワタリウムさんからの帰り、表参道ヒルズから原宿へ抜けて帰ろうと思っていたのですが、何かないかな、とスパイラルに立ち寄ってみたら、こんなイベントをやってました。へぇ。と思いながら、6組くらい観たところで、「あれ、mrtk君?」をを? ぱくぱくさんではないですか。こんにちは。知り合いのアーティストが出品していて、彼女が帰ってくるのを待っているのだが、戻ってこないのだ、とのこと。あ。その方って、先日のサンシャイン水族館の時にお会いした?-----そもそも、「師匠筋にあたる」と勝手に呼ばせて頂いている、ぱくぱくさんとも、mixi上で日記など拝見させて頂いているものの、実際にお会いするのは、その水族館企画以来。ワタリウム美術館の企画旅行で知り合った、ぱくぱくさんは、基本は普通の「社会人」なのですが、ないはずの暇を創り出して、社会に対して鋭い批評を加えながら、伝統・建築・文化などのコラボレーションを念頭に置きつつ、様々なイベン卜を仕掛けている、精力的な方。気が付けば京都でイベントを行い、東京の建築について言及し、日本女子大に出没して目白を語り、塩爺と昼食会を開き、銀座で…という幅広いスタンスでありながら、しかし地に足の着いた活動をされています。mixiの日記の毎日5本更新とか、その内容密度も含めて、どうやったら真似できるのだか…。っと、今回はあくまでフェスティバルの感想でしたね。で、ここから先は、ぱくぱくさんとご一緒させて頂きました。-----ぱくぱくさんが、面白いのがあるよ、と連れて行って下さったのが、ICHIZENさんのブース。現代の「紋」を創ろうということで、「幸せ紋」や「ドクゼツ紋」など、様々な「紋」をデザインし、缶バッチやTシャツのロゴなどで展開。ここの部分、ぱくぱくさんの「目のつけどころ」は、かなり確かで、他の展示を見回しても、これだけコンパクトにインパクトあるイメージ展開が出来ているのは、ありませんでした。ただ、惜しむらくは、アイデアとイメージに頼りすぎて、「紋」のもつ歴史的な背景とか、実際に存在する「面白い紋」への言及まで辿り付けていない。せっかく「紋」を作品として取り入れるからには、「知識」の部分もパワーアップして、作品に反映できれば、もっと説得力のある作品に昇華されるはず。それにしても、ぱくぱくさんの、「ファスト風土」からの作品に対する視座、地方自治と絡めての言及、そして、それらを結びつけるアクションへの促し、うーん、やっぱり凄いなぁ。私の描くアイデアは、どうしてもちゃちなものになりがちですし、それをアクションまで持っていく力がない。そう、私がぱくぱくさんを「師匠筋にあたる」と勝手に呼ばせて頂いているのは、何かを仕掛ける、そこのエネルギー・手法・コンセプトの立て方などを学びたい、と思っているからなのです。-----さて、私してやられたのは、毛塚さんの作品。冷蔵庫の奥の南極に帰るペンギンさん達のオブジェ。シロクマの着ぐるみを脱いで一息つくシロクマ。その他の作品も、なんともユーモラスで可愛らしく、温かい。雰囲気もアイデアも含めて、私はこういうのが好き。-----楽しい、エネルギー溢れる、センスある、気になる、といった展示はたくさんあって、「文化祭みたい」という、ぱくぱくさんの評価通り、非常に熱気のある空間。作家さんと交流できるのも楽しい♪投票に際して、私は毛塚さんに票を投じさせて頂きましたが、コラボレーションの可能性とか、ビジネス的な視点からは、ICHIZENさんも捨てがたかったなぁ、とも。後半の50組の展示は観に行きませんでしたけど、もう少し時間をかけて遊ぶ-将来、何らかのコラボレーションを真剣に模索しに行く、というのもありですね。ぱくぱくさん曰く、「僕の知っているギャラリー関連の人が結構来てるね。」さもありなん。いや、予定になかっただけに、予想外に楽しませて頂きました。=====『第7回 スパイラル・インディペンデント・クリエーターズ・フェスティバル』7th Spiral Independent Creators Festival@スパイラル・ホール(表参道)[会期]2006.05/02(火)~05/05(金) 作者:-★★★★☆※ICHIZENさんのHPはこちら
May 3, 2006
コメント(0)
-
in 『夢の中からみつけた街』@ワタリウム美術館
所蔵作品の中から、写真作品を中心にインスタレーション作品なども含めて展示。ロバート・フランク、デュアン・マルケイズ、ロバート・メイプルソープ、など…と言われても、私は良く知らないんですよねぇ。不勉強を恥じ入るばかり。マン・レイとかダイアン・アーバスくらいなら、名前を聞いたことはありますけど。-----ちょうどギャラリー・トークの時間で、顔馴染みのキュレーター、森さんが解説役です。ロバート・フランクさんとアレン・ギンズバーグさんの関係、島袋道浩さんの展示作品を撮る時に行ったイベントの話など。-----島袋道浩さんのイベント、内容を何も知らされずにワタリウムに朝5時集合って…。その時に撮られた写真が置いてありましたけど、意外と人が集まっているのにびっくり。でも、私も今同じ企画があったら、ふらふら参加している可能性高いからなぁ。いや、それだけ、参加した時に魅力的な企画が多いのですよ。(私にとっては、ね。)朝、ワタリウムの屋上(普段は立入禁止)から眺める景色。そこに鳩が飛び立ち(これの裏話をして下さったのですが、一応ナイショ。)、風船が上がります。(これを引き伸ばした写真が展示されています。)そして皆で朝食会。このイベント自体が、被写体として作品になっていくわけです。-----さて。2Fは、上記作品をはじめ、作家が切り取った街の風景。あわせて、キース・へリングなど、街を彩るパフォーマンスを仕掛けたアーティストと並べて。(ワタリウムさんの1Fは受付のみです。)-----3Fのテーマは街の中の人々。アウグスト・ザンダーさんやダイアン・アーバスさんの作品などが並びます。-----4Fは街という幻想、幻想の中の街。寺山修司さんの妖しい作品、ルネ・マグリットさんのくすぐりのある作品、デュアン・マイケルズさんのストーリー性溢れる作品などが並びます。写真を媒介に映し出された、街の中の異界。-----ストーリー性が非常にはっきりしていて、分かりやすい展覧会だったのですが…。実は、mixiの美術系コミュで、「受付で返金を頼みました」なんて書き込みがあったので、心配していたのですよ。うーん、「写真好き」の方からすると見慣れた写真ばかりでつまらない、のかな?(意見を書かれた方の論旨が、言葉足らずで意味不明なんですよね…。本人も既にmixiから抜けてらっしゃるようですし。)「写真」を見ること自体が、私には新鮮だったのですが、それ以外でも、アンディ・ウォーホルさんやルネ・マグリットさんが写真を撮っているなんて、初めて知りましたし、寺山修司さんは、もう何と言うか寺山修司でしたし、映像作品もなかなか面白い感じでしたし、小さくても密にまとまっている感じでしたけど。それに、ワタリウムさんのチケットって、期間中何度でも利用可(もちろん本人のみですよ)ですから、もともと お得感ありますし。(ちなみに私は「アート的旅行学(今年はお休み)」のメンバーなので、展覧会はタダ♪)ま、気に食わなかったら、2度と行かないでしょうから、千円そっくり損した気分だったのでしょうが…。返金ねぇ…。コミュでも話題になっていましたけど、考えさせられる問題です。今度、自分が心底つまらない、と思った展覧会の時にでも、考えたいと思います。=====『夢の中から みつけた街』I Love Art 8 写真展@ワタリウム美術館(外苑前 / 表参道 / 原宿)[会期]2006.03/03(金)~06/04(日) 作者:-★★★★☆
May 3, 2006
コメント(2)
-
in 『エコール・ド・パリ展』@松岡美術館
実業家 松岡清次郎氏が蒐集した美術品を中心にした松岡美術館。古代オリエント美術から近代画まで、幅広く収蔵されています。蒐集者のセンス、趣味、教養の幅広さが感じられる収蔵品の数々。-----入ったホールのところに『ミネルヴァ』とか『アフロディテ』の像。しかし、これら「美人」を象った作品より、小品ながらジャコメッティの『猫の給餌長』が、抜群に可愛らしい。うわぁ。これのミニチュアとか欲しい。-----コホン。さてさて。「エコール・ド・パリ」展とあったので、館内一色パリかと思えばさにあらず、常設は常設のまま、2Fの二室でエコール・ド・パリを展開。なので、一室目はギリシア・ローマ・エジプトの古代オリエント系美術、ニ室目はヘンリー・ムア、エミリオ・グレコの現代彫刻、三室目はクメール・ガンダーラ・インドの仏教彫刻です。ヘンリー・ムアの『馬』が優美で良かったですね。なだらかで優しい曲面、とぼけた味を出している目の位置、決して「リアル」ではないのですが「リアリズム」に満ちた作品です。-----さて、2Fに上がって唐三彩の展示。すげぇ。唐三彩すげぇ!馬の写実性、色彩のセンス、躍動するリアリズム。しかも、それが、陶器で創られているのですよ。いや、別に唐三彩を見るのが初めてではむろんなく、何度も色んな所で見ているのですが、唐三彩は、いつ見ても私に「新鮮」と言って良い感動を与えてくれます。正直、現代美術で、このレベルを超えることができてる作品って、そうそうありません。色彩センス、造形美、分かりやすさ、評価軸としてはこのあたりでしょうが、そのどれもが素晴らしい。「古典だからすごい」でも「すごいから古典」でもなく「すごいからすごい」のです。-----さて、いよいよ「エコール・ド・パリ」です。ユトリロやその母、フジタの作品も並ぶ中で、気になったのは、ボーシャンの『海岸』とローランサンの作品。全体として、落ち着いた、品の良い作品が集められている感じです。そういう意味では、教科書通りで面白味に欠ける、かな?でも、逆に、安心してゆっくりと作品を鑑賞できる大人な雰囲気があります。混んでいないですし。自転車で行ける距離ですし、面白い特集をやっていたら、また足を伸ばしたいですね。=====『エコール・ド・パリ展』同時開催:陶俑の美 展@松岡美術館 (目黒 / 白金台)[会期]2006.04/29(土)~09/03(日) 作者:-★★★☆☆
May 3, 2006
コメント(0)
-
4月の記憶。
4月。いろいろありまして、なかなか思うように予定を取れませんでした。うーむ。(しかも更新しているの6月入ってからだし。)=====まずは、映画から。2本かぁ。楽しみにしていた『ウォレスとグルミット』。まだ「ペンギンに気をつけろ」とか短編の方を観てないんですよね。ま、楽しみは後に取っておきましょう。あとは珍しく音楽映画。ドイツ映画だと思って観たら、使われているのは英語と日本語でした…。って映画の感想ではないですね。-----手作り感が温かい、Cute&Pretty Movie 『ウォレスとグルミット - 野菜畑で大ピンチ!』 (04/12)音楽の本質を考えさせられる映画 『Touch the Sound』 (04/16)=====美術館は、はしごをしたのでそれなりに。原美術館は、美術館としての佇まいが良いですね。『武満徹展』は、切り口が新鮮で、面白さよりも「価値」が感じられる美術展でした。-----「デザイン」が地球を包む。 『「FUROSHIKI」展』 (04/12)天才音楽家の軌跡が透けて見える 『武満徹|Visions in Time 展』 (04/23)カルティエのセンスを疑うコレクション 『カルティエ現代美術財団コレクション展』 (04/29)コンセプトの壮大さと作品の多様さ 『東京-ベルリン ベルリン-東京 展』 (04/29)デジタルと有機性の融合 『MAM プロジェクト 004 チェ・ウラム』 (04/29)映画の宣伝 『ダ・ヴィンチ・コード展』 (04/29)多様なコレクションをふわりとした空気が包む 『舞い降りた桜』 (04/30)美しく丁寧な普段遣いの食器達 『北欧のスタイリッシュ・デザイン』 (04/30)-----あと、品川のアクアスタジアム(04/20)や、国立博物館付属自然教育園(04/30)にも足を伸ばしましたね。=====お芝居は観ませんでした。面白そうなのもあったのですが…。=====お茶では初のお免状を頂きました。それに関連して、軸飾りのお稽古。また4月は釣釜。ゆらりとした風情が良いですね。 釣り釜/茶箪笥 (04/15) 軸飾り (04/22)=====4月はなんと言っても、「さくらづくし。」(04/01)で引っ張りました。美味しい食事と(自分で作っておいてそれはないか)、気の置けない友人達との楽しい会話。いやぁ、楽しかったですね。=====こんな日がいつまでも続けば良いのに、と思いながらも、二度と来ないことが分かっているのが哀しい。だからこそ、だからこそ大切なGlory Days。≪「3月の記憶」へ
May 1, 2006
コメント(0)
全34件 (34件中 1-34件目)
1
-
-

- 宝塚好きな人いませんか?
- 宙組 PRINCE OF LEGEND キャスト感…
- (2025-11-12 05:30:05)
-
-
-
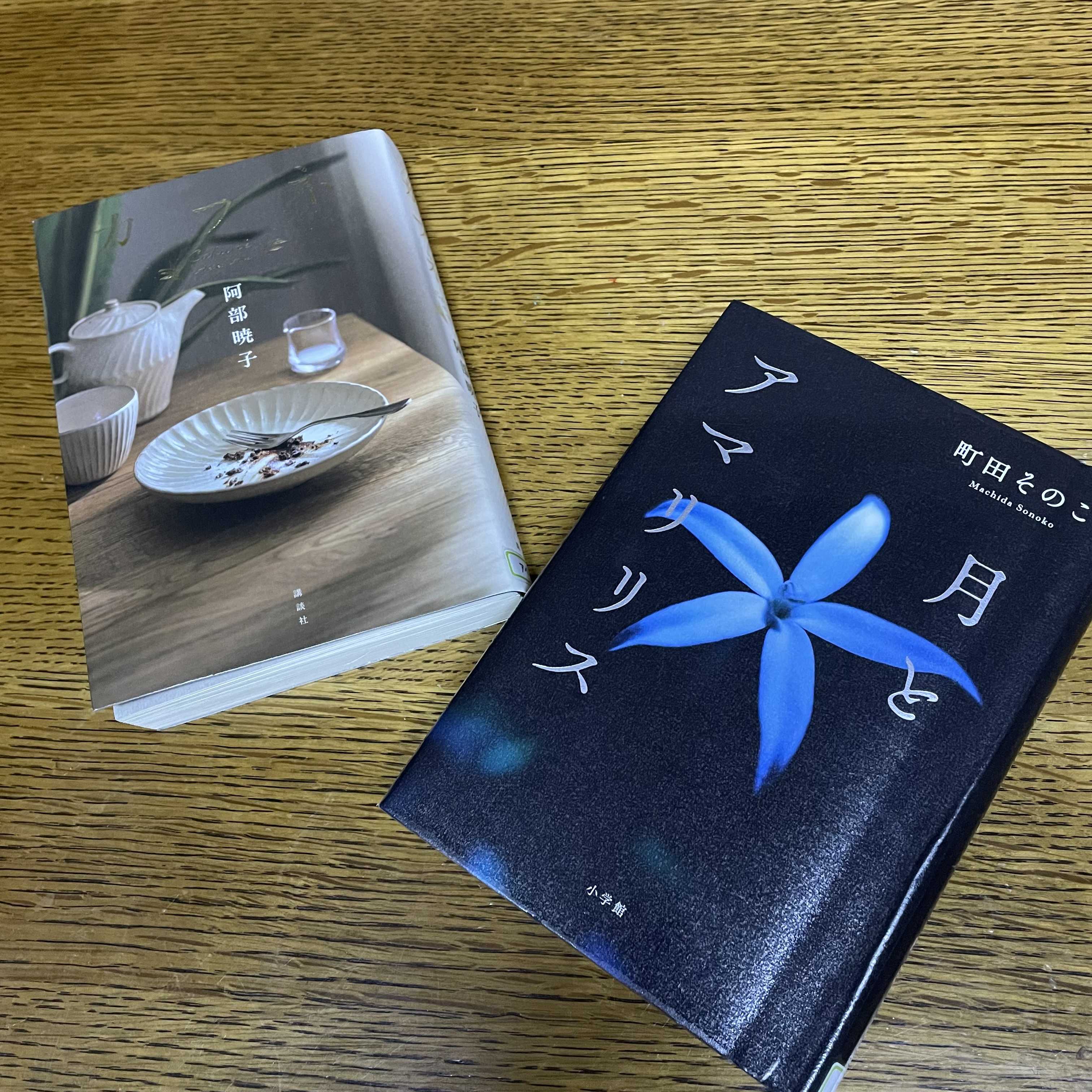
- SMAPが大好きな(興味が)ある人♪
- ハピバ☆ ・「カフネ」
- (2025-08-18 23:53:31)
-
-
-

- 東方神起大好き♪♪ヽ|●゚Д゚●|ノ
- 東方神起 20th Anniversary LIVE TOU…
- (2025-08-16 16:45:05)
-






