PR
カレンダー
カテゴリ
カテゴリ未分類
(1)読書案内「日本語・教育」
(21)週刊マンガ便「コミック」
(84)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝
(35)徘徊日記「日帰りでお出かけ」
(62)演劇「劇場」でお昼寝
(2)映画「元町映画館」でお昼寝
(94)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝
(28)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝
(90)読書案内「映画館で出会った本」
(19)読書案内「翻訳小説・詩・他」
(53)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」
(23)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり
(53)読書案内 「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」
(27)読書案内「現代の作家」
(100)徘徊日記「お泊りでお出かけ」
(69)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり
(85)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ
(48)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」
(77)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」
(31)読書案内「近・現代詩歌」
(54)徘徊「港めぐり」
(4)バカ猫 百態
(22)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」
(18)読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」
(20)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」
(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝
(2)映画「こたつシネマ」でお昼寝
(13)映画「パルシネマ」でお昼寝
(30)読書案内「昭和の文学」
(25)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05
(16)読書案内「くいしんぼう」
(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝
(5)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」
(9)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」
(34)週刊マンガ便「鈴ノ木ユウ・野田サトル」
(19)ベランダだより
(151)徘徊日記 団地界隈
(112)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり
(26)徘徊日記 須磨区あたり
(30)徘徊日記 西区・北区あたり
(10)徘徊日記 灘区・東灘区あたり
(41)徘徊日記 美術館・博物館・Etc
(5)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」
(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり
(11)読書案内「大江健三郎・司修・井上ひさし・開高健 他」
(14)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」
(3)読書案内「谷川俊太郎・茨木のり子・大岡信 あたり」
(20)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」
(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」
(11)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」
(13)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」
(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて
(5)読書案内「村上春樹・川上未映子」
(13)映画 パレスチナ・中東の監督
(6)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」
(7)映画 韓国の監督
(25)映画 香港・中国・台湾の監督
(37)映画 アニメーション
(13)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢
(53)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭
(26)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行
(16)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督
(41)映画 イタリアの監督
(21)映画 ドイツ・ポーランド他の監督
(25)映画 ソビエト・ロシアの監督
(11)映画 アメリカの監督
(99)震災をめぐって 東北・神戸・原発
(3)読書案内「旅行・冒険」
(4)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」
(13)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督
(5)映画 フランスの監督
(49)映画 スペイン・ポルトガルの監督
(10)映画 カナダの監督
(5)映画 グルジア(ジョージア)の監督
(15)映画 ウクライナ・リトアニアの監督
(7)映画 イスラエルの監督
(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督
(6)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督
(11)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督
(6)映画 トルコ・イラン・カザフスタンあたりの映画監督
(12)映画 ギリシアの監督
(3)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルー・チリの監督
(6)映画 ハンガリー・ルーマニアの監督
(5)映画 アフリカの監督
(3)映画 スイス・オーストリアの監督
(3)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家
(1)読書案内 ジブリの本とマンガ
(5)週刊マンガ便「小林まこと」
(9)読書案内「野口武彦・前田愛・橋川文三・藤井貞和」
(2)映画 インド・ネパール・ブータン・アフガニスタン・タイ・ベトナム あたりの監督
(5)週刊マンガ便 キングダム 原泰久・佐藤信介
(17)読書案内「川上弘美・小川洋子・佐伯一麦」
(9)読書案内「立花隆・松岡正剛」
(5)週刊 読書案内 パブロ・ネルーダ「ネルーダ詩集」(海外詩文庫14・田村さと子訳・思潮社)
マイケル・ラドフォード「イル・ポスティーノ」シネリーブル神戸no281
徘徊日記 2024年10月20日(日)「三島といえばウナギ!だそうです。」三島あたり その4
イ・ウォンテ「対外秘」キノシネマ神戸国際no17
笠井千晶「拳と祈り 袴田巖の生涯」元町映画館no267
週刊 読書案内 「さようなら」谷川俊太郎
週刊 読書案内 荒勝俊「日本狛犬大全」(さくら舎)
徘徊日記 2024年10月20日(日)「三島市の柿田川公園って知ってました?」三島あたり その3
徘徊日記 2024年11月14日(木)「高倉台の夕焼け!ピンボケ(笑)」須磨・高倉台あたり
コメント新着
キーワードサーチ
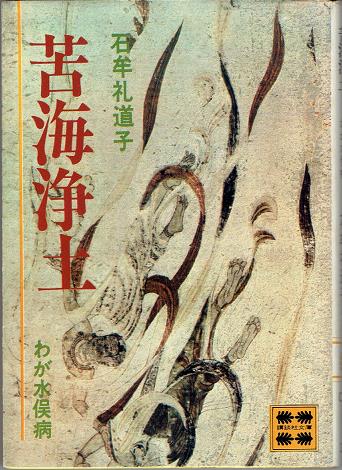
自分の生活する世界の外側や遠くの他者に対して関心を持つ時、自分のことを 「こうだ」
と思い込んでいた自己認識のあやうやさと出遇うことがある。この年齢になっても職場や近所づきあいで経験的には全く初めてのタイプの人と出会ったりする事は相変わらずあって、やっぱりうろたえる。
ドキドキしながら、一度自分の中にもどってみる。べつにどんな人とでも常に 「存在」を賭けて
真摯に付き合うことが身上というわけではない。しかし、自分の中にも、ほかの人から見れば、こういう変なタイプがいるのではないか、そんな風に考えると心当たりがある事もある。モチロンいつもという訳ではない。全く予想もつかないような人物もいる。心当たりがあるからといって必ずしも理解できたというわけでもない。かならず仲良く出来る訳でもない。
ただ、まぁそういうふうになってしまう事はありうるよな、というふうに相手に対しての、ちょっとした納得が生まれる程度のことだ。とりあえず嫌いとか好きといわなくてもよい。 鶴見俊輔
という哲学者が 『同情』
という言葉を使って考えているコトの入り口くらいかもしれない。
鶴見
の言う 『同情』
というのは英語では sympathy
だろう。
パトスが共振=シンクロナイズ= synchronize
することという意味かなと思う。 『共感』
を持って他者と出遇うこと。 孟子
が言う 『惻隠の情』
というのはこれと近い事かもしれない。
。鶴見
の言う 『同情』
や 孟子
の 『惻隠の情』
を徹底させると結構すごいコトになるということを話題にしたいのだ。
石牟礼道子 の 『苦海浄土』 が文庫新装版で講談社から新しく出たそうだ。これまでにも講談社文庫版で読むことは出来たし、国語の教科書にも取り上げられてきた。
「ほーい、ほい、きょうもまた来たぞい」と魚を呼ぶのである。しんからの漁師というものはよくそんなふうにいうものであったが、天草女の彼女のいいぶりにはひとしお、ほがらかな情がこもっていた。海とゆきは一緒になって舟をあやし、茂平やんは不思議なおさな心になるのである。
いかなる死といえども、ものいわぬ死者、あるいはその死体はすでに没個性的な資料である、と私は想おうとしていた。死の瞬間からオブジェに、自然に、土にかえるために、急速な営みを始めているはずであった。病理解剖は、さらに死者にとって、その死が意思的に行うひときわ苛烈な解体である。その解体に立ち会うことは、わたくしにとって水俣病の死者達との対話を試みるための儀式であり、死者達の通路に一歩たちいることにほかならないのである。
ゴムの手袋をしたひとりの先生が、片手に彼女の心臓を抱え、メスを入れるところだった。私は一部始終をじっとみていた。彼女の心臓はその心室を切りひらかれるとき、つつましく最後の吐血をとげ、わたしにどっと、なにかなつかしい悲傷のおもいがつきあげてきた。死とはなんと、かつて生きていた彼女の、全生活の量に対して、つつましい営為であることか。
人間な死ねばまた人間に生まれてくっとじゃろか。うちゃやっぱり、ほかのもんに生まれ替わらず、人間に生まれ替わってきたがよか。うちゃもういっぺん、じいちゃんと舟で海にゆこうごたる。うちがワキ櫓ば漕いで、じいちゃんがトモ櫓ば漕いで二丁櫓で。漁師の嫁御になって天草から渡ってきたんじゃもん。うちゃぼんのうの深かけんもう一ぺんきっと人間に生まれ替わってくる。 「苦海浄土 第 3 章 ゆき女きき書き」
水俣病で亡くなった 坂上ゆき
とういう女性をめぐって書かれた、 「ゆき女きき書き」
の一節。読み手の胸倉をつかんではなさない文章だと感じた。
「共感」
するということが、すでに死んでしまった 「ゆき女」
の病理解剖の現場にまで立ち合い、その切り裂かれた心臓の最後の一滴のしたたりまで見ることを止めない 石牟礼道子
の冷静な目と筆致を支えているように感じる。
「同情」
ということが一緒に涙を流したり、抱き合ったりすることにとどまることではないことを彼女は描いている。 「見て書く」
という行為に自分という存在をかけて表現しているといえないだろうか。そこにみなぎる気迫、それこそが、 「同情」
が行為であり、行動であって「こころのありさま」だけのことではないことが文章にくっきりとあらわれている。そこが 石牟礼道子
の強烈さだといっていいと思う。 1968
年
に出版されて 30
年以上の歳月がたっている。僕が初めてこの本に出会ったのも 30
年も昔のコトになる。
今年、彼女の全集が 藤原書店
というところから出始めている。出来ればどこの学校の図書館にも置いてもらって、ひそかに彼女に 「共感」
し、自分のなかに 「同情」
を育てる人が一人でも生まれてくれば一寸凄いのではないだろうか。
2004
年
10
月
15
日
。水俣病患者に対する国家=行政の責任を認定した判決が最高裁から下された。被害発生から
50
年以上も経ってやっと、である。いったい何人の人が、世の中から 「見捨てられた」
(
S
)
2004
・
10
・14
石牟礼道子さん はいなくなった。 鶴見俊輔さん もいなくなって久しい。この 「案内」 を教室で配布したときから15年も経ってしまったことを実感しながらも、少し驚いている。
福島の原発事故の被災者に対して 「管轄外」 と言い放つ復興庁の長官や、汚染水の 「海」 への廃棄を最後っ屁のように言い放つ大臣。とどのつまりは、公共事業の犠牲者に 「ボランティア精神」 を説く大臣迄出てきた。 石牟礼さん や 鶴見さん が生きていたらなんというだろう。
古い記事だが、捨てないで投稿しようと思った。

ボタン押してね!
にほんブログ村


-
週刊読書案内 山里絹子「『米留組』と沖… 2023.09.04
-
週刊 読書案内 米本浩二「魂の邂逅」(… 2023.03.18
-
週刊 読書案内 渡辺京二「未踏の野を過… 2023.01.31












