PR
X
カレンダー
カテゴリ
カテゴリ未分類
(2)読書案内「日本語・教育」
(22)週刊マンガ便「コミック」
(81)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝
(36)徘徊日記「日帰りでお出かけ」
(79)演劇・芸能「劇場」でお昼寝
(5)映画「元町映画館」でお昼寝
(136)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝
(62)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝
(121)読書案内「映画館で出会った本」
(20)読書案内「翻訳小説・詩・他」
(52)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」
(25)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり
(54)読書案内「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」
(29)読書案内「現代の作家」
(103)徘徊日記「お泊りでお出かけ」
(76)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり
(102)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ
(51)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」
(86)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」
(33)読書案内「近・現代詩歌」
(58)徘徊「港めぐり」
(4)バカ猫 百態
(23)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」
(21)読書案内「水俣・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」
(18)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」
(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝
(3)映画「こたつシネマ」でお昼寝
(13)映画「パルシネマ」でお昼寝
(32)読書案内「昭和の文学」
(25)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05
(23)読書案内「くいしんぼう」
(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝
(18)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」
(9)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」
(40)週刊マンガ便「鈴ノ木ユウ・野田サトル」
(22)ベランダだより
(167)徘徊日記 団地界隈
(141)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり
(27)徘徊日記 須磨区あたり
(34)徘徊日記 西区・北区あたり
(11)徘徊日記 灘区・東灘区あたり
(46)徘徊日記 美術館・博物館・Etc
(5)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」
(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり
(12)読書案内「大江健三郎・司修・井上ひさし・開高健 他」
(14)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」
(3)読書案内「谷川俊太郎・大岡信 あたり」
(21)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」
(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」
(11)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」
(22)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」
(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて
(8)読書案内「村上春樹・川上未映子」
(17)映画・読書案内 パレスチナ・中東
(19)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」
(7)映画 韓国の監督
(25)映画 香港・中国・台湾の監督
(40)アニメ映画
(24)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢
(55)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭
(25)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行
(16)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督
(41)映画 イタリアの監督
(22)映画 ドイツ・ポーランド他の監督
(29)映画 ソビエト・ロシアの監督
(14)映画 アメリカの監督
(99)震災をめぐって 本・映画
(9)読書案内「旅行・冒険」
(4)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」
(15)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督
(5)映画 フランスの監督
(53)映画 スペイン・ポルトガルの監督
(13)映画 カナダの監督
(5)映画 グルジア(ジョージア)の監督
(14)映画 ウクライナ・リトアニア・ラトビア・エストニアの監督
(9)映画 イスラエルの監督
(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督
(6)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督
(13)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督
(11)映画 トルコ・イラン・カザフスタンあたりの映画監督
(12)映画 ギリシアの監督
(3)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルー・チリの監督
(8)映画 ハンガリー・ルーマニアの監督
(5)映画 アフリカの監督
(3)映画 スイス・オーストリアの監督
(4)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家
(3)読書案内・アニメ・コミック ジブリ
(7)週刊マンガ便「小林まこと」
(9)読書案内「野口武彦・前田愛・橋川文三・藤井貞和」
(3)映画 インド・ネパール・ブータン・アフガニスタン・タイ・ベトナム あたりの監督
(5)週刊マンガ便・映画 キングダム 原泰久・佐藤信介
(20)読書案内「川上弘美・小川洋子・佐伯一麦」
(9)読書案内「立花隆・松岡正剛」
(5)徘徊日記 神戸の狛犬
(5)週刊読書案内「保坂和志・柴崎友香・磯崎憲一郎とか」
(11)読書案内・映画 沖縄
(10)読書案内 韓国の文学
(5)週刊マンガ便・映画 武田一義 こうの史代
(9)映画 ミュージシャン 映画音楽
(11)映画 「109ハット」でお昼寝
(6)読書案内 エッセイ
(4)読書案内 「茨木のり子・石垣りん」
(13)映画「キノシネマ神戸国際」でお昼寝
(5) アレクシス・ブルーム「ネタニヤフ調書」元町映画館no333
徘徊日記 2025年12月2日(火)「オッ!さんぽ 団地で紅葉狩り(笑)。」団地あたり
週刊 マンガ便 原泰久「キングダム 77」(集英社)
マヤ・チュミ「ロツロッホ」元町映画館no329
徘徊日記 2025年11月29日(土)「京都御所のイチョウ並木!」京都御所あたり
イヴ・イェルサン「小さな逃避行」元町映画館no328
徘徊日記 2025年11月29日(土)「なぜか、京都御所です!紅葉です!黄葉です!」京都御所あたり
週刊 マンガ便 富樫義博「ハンター×ハンター(4~6)」(集英社)
秋山純「栄光のバックホーム」109シネマズ・ハットno71
三宅唱「旅と日々」シネリーブル神戸no337
徘徊日記 2025年12月2日(火)「オッ!さんぽ 団地で紅葉狩り(笑)。」団地あたり
週刊 マンガ便 原泰久「キングダム 77」(集英社)
マヤ・チュミ「ロツロッホ」元町映画館no329
徘徊日記 2025年11月29日(土)「京都御所のイチョウ並木!」京都御所あたり
イヴ・イェルサン「小さな逃避行」元町映画館no328
徘徊日記 2025年11月29日(土)「なぜか、京都御所です!紅葉です!黄葉です!」京都御所あたり
週刊 マンガ便 富樫義博「ハンター×ハンター(4~6)」(集英社)
秋山純「栄光のバックホーム」109シネマズ・ハットno71
三宅唱「旅と日々」シネリーブル神戸no337
コメント新着
キーワードサーチ
▼キーワード検索
カテゴリ: 読書案内「社会・歴史・哲学・思想」
朴沙羅「ヘルシンキ生活の練習」(筑摩書房)
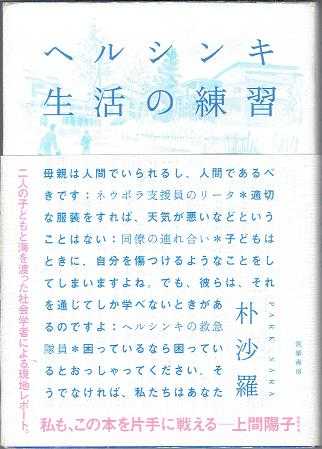 つい、先だって、 「家族(チベ)の歴史を書く」(筑摩書房)
を読んで、えらく感心した人です。まだ若い社会学者 朴沙羅
の新しい本を読みました。
つい、先だって、 「家族(チベ)の歴史を書く」(筑摩書房)
を読んで、えらく感心した人です。まだ若い社会学者 朴沙羅
の新しい本を読みました。
関西の、いくつかの大学で先生をなさっているとばかり思っていた彼女は、 フィンランド に移住していました。
ぼくは、もういい年なので、 「ふーん、フィンランドってそうなのか!?」 という、ノンビリ感心しながら、まあ、楽しく読みました。でも、一方で、今、同じくらいの歳ごろの、お母さんであったりお父さんである方がお読みなれば、彼女の真摯で正直な暮らしぶりの語りをどう感じられるのか、という興味も湧いてくるのでした。まあ、そうはいっても、ちょっと他人事に対する余裕目線という感じでした。ところが、後半に入って、彼女のこんな問いかけを前にして立ち止まりました。
ショックでした。 朴沙羅さん は 1984年 生まれ、ぼくの子どもたちと全く同世代です。その世代の人たちを 「国家」 や 「戦争」 はこんなふうに侵食し、ネット上には、いわゆるヘイトが溢れているのです。
本文は、 朴沙羅さん 自身の、子育ての中で、子どもたちに 「ぐんたい」 をどう伝えるのかについてのためらいの記述ですが、ぼくにとっては 「あなたは、こういう現実を知っていましたか?」 という、ドキッとせざるを得ない問いかけでした。
「おい、お前は子供たちを育て、孫たちをかわいがりながら、どうしてきたのか。終わったこととばかりはいえないんじゃないか?」
ぼくは、こんなふうな問いとして彼女の語りを受け取りましたが、 朴沙羅さん の結論はこうでした。
やっぱりこの人は追いかけないわけにはいきませんね。







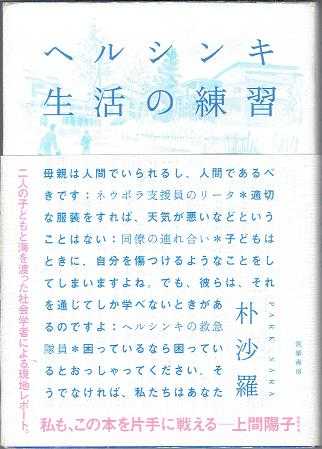
関西の、いくつかの大学で先生をなさっているとばかり思っていた彼女は、 フィンランド に移住していました。
はじめに というわけで、 二〇二〇年 の春から、二人の子供を連れた、アラフォーの社会学者の移住生活の報告の始まりです。 モッチン には日本での仕事があるようなので、子連れの母親の単身移住です。彼女は 「オーラルヒストリー」 の研究者ですが、本書は彼女自身による 「オーラル・ライフ・ヒストリー」 、聞き語りではなく、一人がたりの物語です。
二〇二〇年の二月から、私はヘルシンキで仕事をすることになった。
そもそものきっかけは、二〇一八年に初めて、フィンランドはユヴァスキュラという街に、夏の間滞在したことだった。キラキラした太陽の光と湖と森が気に入って、もし何かまたご縁があったらここに住みたいと思った。
それから一年くらいして、ヘルシンキにある、とある職場が新人を募集していた。だめでもともと、と思って書類を送ったら面接に招かれてしまった。そして―面接のときに「結果は二週間から一ヵ月の間にお知らせします」と言われたのに、一ヵ月半たっても音沙汰がなかったので不採用だろうと思っていたのだが―二か月くらいして採用通知が来た。
私は結婚していて、子供が二人いる。採用通知が来たとき、上の子(ユキ)は六歳、下の子(クマ)は二歳。連れ合い(モッチン)は日本で仕事をしていて、そこそこのキャリアがある。
家族をどうするつもりなんだ、私。
かなりびくびくしながらモッチンに「採用されちゃったみたい」と言ったら、すかさず「すごいじゃん!おめでとう!」と言ってくれた。彼にはほかの選択肢はなかったかもしれないが、そういわれて初めて、少しうれしくなった。(P005)
目次 こんな目次で、二人の子供の保育園暮らしから始まり、オネーチャンの ユキちゃん の小学校入学までの1年間の暮らしが語られています。
1 未知の旅へ―ヘルシンキ到着
2 VIP待遇―非常事態宣言下の生活と保育園
3 畑の真ん中―保育園での教育・その1
4 技術の問題―保育園での教育・その2
5 母親をする―子育て支援と母性
6 「いい学校」―小学校の入学手続き
7 チャイコフスキーと博物館―日本とフィンランドの戦争認識
8 ロシア人―移民・移住とフィンランド
ぼくは、もういい年なので、 「ふーん、フィンランドってそうなのか!?」 という、ノンビリ感心しながら、まあ、楽しく読みました。でも、一方で、今、同じくらいの歳ごろの、お母さんであったりお父さんである方がお読みなれば、彼女の真摯で正直な暮らしぶりの語りをどう感じられるのか、という興味も湧いてくるのでした。まあ、そうはいっても、ちょっと他人事に対する余裕目線という感じでした。ところが、後半に入って、彼女のこんな問いかけを前にして立ち止まりました。
それから、「ぐんたい」について子どもに話したくなかったのは、もう一つ理由があった。私は小学生のとき、埼玉県にある丸木美術館に行って、帰り道に吐いた。母曰く、そのときに私は、美術館にあった「からす」という絵を見て、あの死体の中に私がいる、と言ったらしい。長崎の原爆で殺され、差別ゆえに埋葬すらされなかった朝鮮人の死体を、カラスがつつく絵だ。 朝鮮の名前を持つ親しい同級生に 「日本と韓国が戦争になったら、お前はどちらにつくのか」 と、何の疑いもなく尋ねる「日本」の中学生がいる。2000年を超えたころからのこの国の子どもたちの生活の場面として、考えてみれば異様ともいえる 「思い出」 が語られています。
中学生あたりから、何度か「日本と韓国が戦争になったら、お前はどちらにつくのか」という質問されるたびに、口では「どっちでしょうねー」と言いつつ、心の中では「私がどうしたらいいかオロオロしている間に、お前みたいなやつが私を殺しに来るだろうから、私がその質問の答えを考える必要はない」と思っていた。
そういう感情に、あの潰れるような恐怖心に、何歳になってからなら耐えられるのだろう。耐えられるときなんて来るのだろうか。気づかないふりをできるようになるだけではないのか。そんな物事に、なるべくなら触れずにいる方がいいのではないのか。この子たちと「ぐんたい」との出会いを、なるべくあとにできないか。 (「チャイコフスキーと博物館」P201~P202)
ショックでした。 朴沙羅さん は 1984年 生まれ、ぼくの子どもたちと全く同世代です。その世代の人たちを 「国家」 や 「戦争」 はこんなふうに侵食し、ネット上には、いわゆるヘイトが溢れているのです。
本文は、 朴沙羅さん 自身の、子育ての中で、子どもたちに 「ぐんたい」 をどう伝えるのかについてのためらいの記述ですが、ぼくにとっては 「あなたは、こういう現実を知っていましたか?」 という、ドキッとせざるを得ない問いかけでした。
「おい、お前は子供たちを育て、孫たちをかわいがりながら、どうしてきたのか。終わったこととばかりはいえないんじゃないか?」
ぼくは、こんなふうな問いとして彼女の語りを受け取りましたが、 朴沙羅さん の結論はこうでした。
そういうためらいは、ユキとクマを連れてハラボジに会いに行ったときに、緑ヶ丘保育園に子どもを通わせていた古い友人に会ったときに、普天間に住む知人の本を読んだときに、宮古島で子育てをする知人と親しくなるにつれて、壊された。彼女たちには、ためらう余裕なんて与えられていない。彼女たちの子どもたちは、あの美しい海を、あんなに反対した人々がいるのに埋め立て、保育園の上にペリコプターの部品を落下させ、オスプレイの音で彼らを脅かし、基地を作ろうとする「ぐんたい」とそれを支える行政に、いつ出会えばいいかなんて選べない。 さて、ぼくは、どうするのか? 徘徊老人 などと、あたかも世捨て人ででもあるかのように、こうしてアホ・ブログを更新して暮らしていますが、 「恐怖心と怒りに出会わなければならない状態をも、私はあの人たちに押し付けて」 いないか。考えないわけにいかない鋭さで彼女の言葉が突き刺さりました。
私がためらうことができるのは、私が彼女たちに基地を押し付けているからだ。押し付けているのは基地だけではない。恐怖心と怒りに出会わなければならない状態をも、私はあの人たちに押し付けている。あの人たちは、私たちのせいで、選べない。
それなら、自分たちが誰かに「ぐんたい」を押しつけている状態にあることや、その状態を変えようとすることも、可能なかぎり教えればいい。
そういうわけで、私は二年ほど前には、ユキの質問することにはなるべく答えるようにし、私のしたいことや行きたいところに彼女がついてきたいのなら、それを止めないことにした。 (P202)
やっぱりこの人は追いかけないわけにはいきませんね。



お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[読書案内「社会・歴史・哲学・思想」] カテゴリの最新記事
-
週刊 読書案内 坂上香「根っからの悪人… 2025.08.11 コメント(1)
-
週刊 読書案内 隈研吾「日本の建築」(… 2025.07.31 コメント(1)
-
週刊 読書案内 木田元「なにもかも小林… 2025.07.26 コメント(1)
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.










