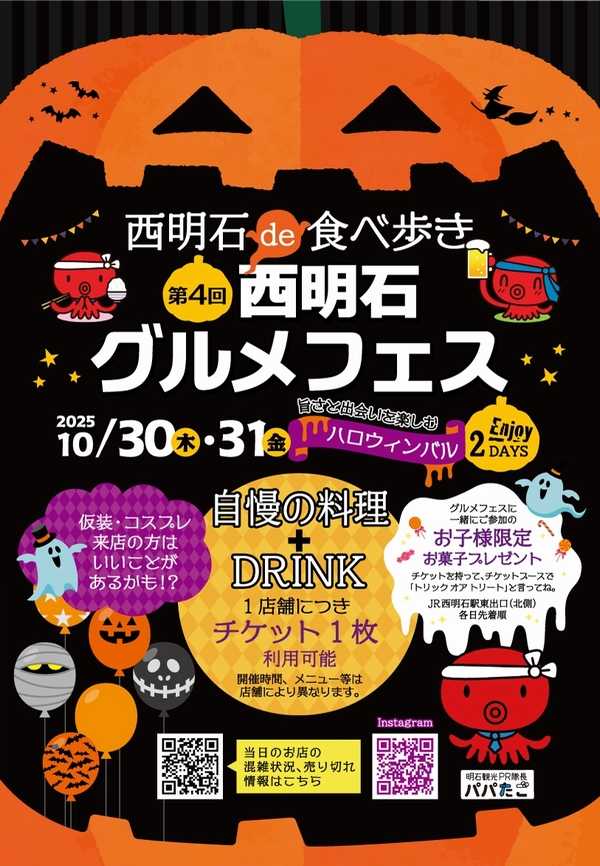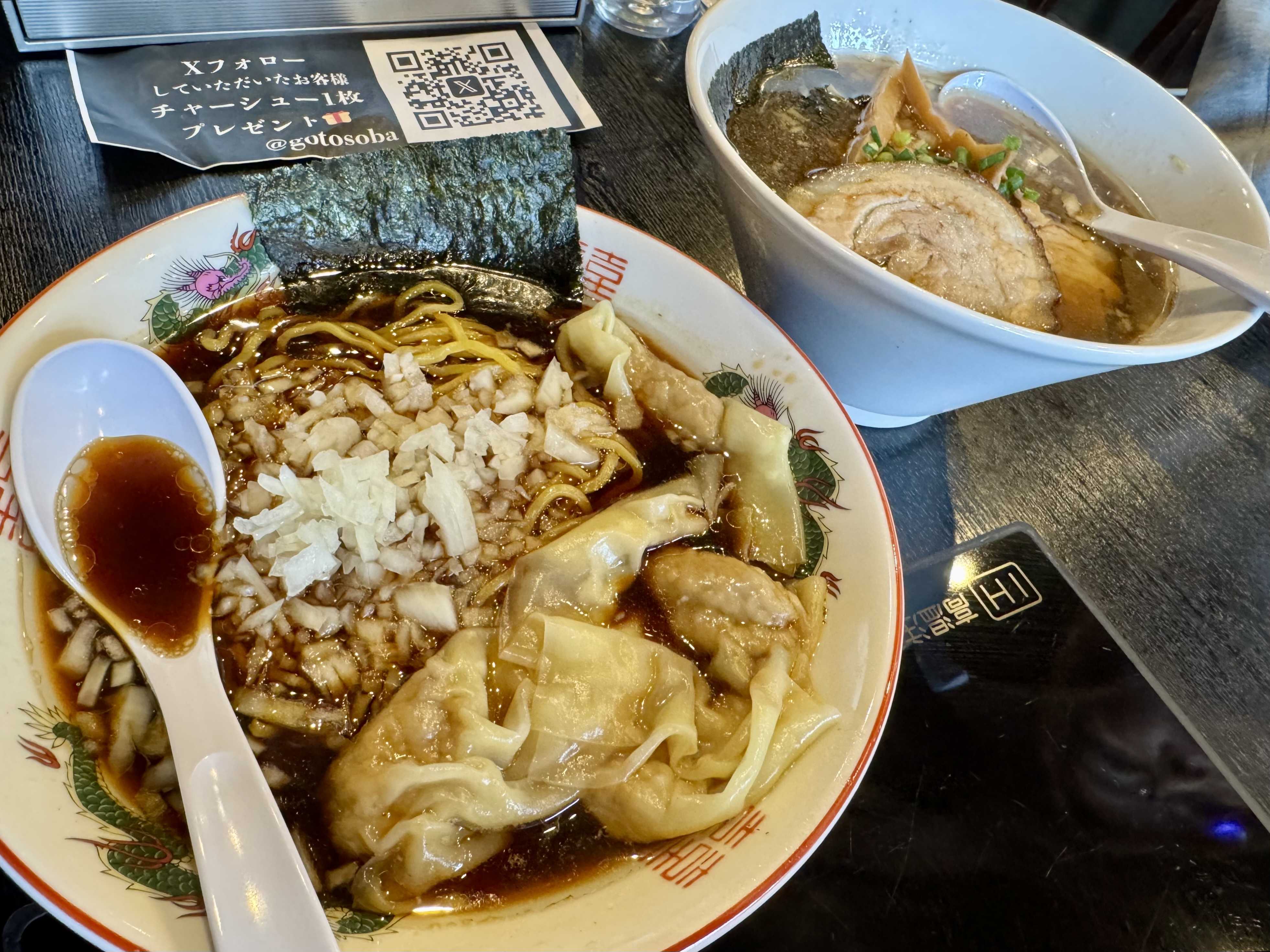2007年04月の記事
全27件 (27件中 1-27件目)
1
-

藤@豪徳寺
連休前半はよく晴れて気持ちがいいですね。をこいでると汗ばんでくるぐらいです。藤で有名だという情報を得て豪徳寺に行ってきました。まずは近くにある「世田谷城址公園」へかえでが青々と生長していました。秋が楽しみです。 ハトポッポは今日も元気です。豪徳寺に向かう途中,空き地に野草が一面に生えてました。藤もガーデニング?で栽培できるのでしょうか。近くのお宅に立派な藤が咲いてました。豪徳寺着。かえでに三重の塔がよく映えます。 藤棚が一つあって,藤は見事に花を咲かせていました。 ボタンもあちこちに植えられていました。 近くの緑道にツツジが。 新緑のこの季節もすばらしいですね。ブログランキングに参加中。毎日1回クリックで応援よろしくお願いいたします。
2007.04.30
コメント(0)
-

憲法九条を世界遺産に
太田光・中沢新一(2006)「憲法九条を世界遺産に」集英社新書.最近憲法九条に関する論争がメディアで取り上げられることが多いです。そこでこの本を読んでみました。太田光の物言いはストレートで心に響くものがあるので,それが正しいか間違っているのかは別として好感が持てます。著者二人は憲法九条を残そうという立場=護憲派です。そして本書では,憲法九条のメリットと,改憲したときのデメリットについて書かれています。まず,宮沢賢治が童話で平和を訴えたのに,宗教的な政治活動にのめり込んでいった背景を手がかりにして,戦前の日本における思想を解こうとします。宮沢賢治の童話は,誤解を伴ったディスコミュニケーションに閉ざされた世界を乗り越えたいという,強烈な宗教的願望に突き動かされているといいます。そういう思考と,戦後の平和思想で人々の間に透明なコミュニケーションと繁栄をもたらすものが強烈に求められたこととはつながっています。そういう意味で,宮沢賢治は戦前の戦争的思考と戦後の平和的思想をつないでいる存在だといいます。日本国憲法のできた背景として二人の立場は,当時のアメリカ人の中にまだ生きていた,人間の思想のとてもよいところと,敗戦後の日本人の後悔や反省の中から生まれてきたよいところが,うまく合体しているということです。この奇蹟の憲法をむやみに変えるべきではないと主張します。太田によると,憲法九条というのは,ある意味,人間の限界を超える挑戦であるが,それでも,挑戦していく意味はあるんじゃないかといいます。僕らが戦うべき相手が何なのかは分からない。人間のつくり出した神という存在なのかもしれないし,人の心に棲む何かなのかもしれない。人間はしょせん死んでいくもので,文明は崩壊していくけれど,自分が生まれて,死ぬまでは,挑戦していくほうにベクトルが向いていないと,面白くないといいます。憲法九条をわざわざ世界遺産にするということは,人間のおろかさを知るためのものとして必要な手続きだといいます。美しい景色,そこに残された精神的な価値が守られているのならば,わざわざ世界遺産にする必要はない。最後に,護憲派と改憲派が意見を戦わせることは大事で,どちらの方が戦争に巻き込まれる現実に対する覚悟ができるかに尽きるといいます。そして憲法九条を守ることで,状況によっては殺される覚悟ができるかといった議論にまで発展します。--------------------------------------------------------サンデーモーニングの「風を読む」でも憲法九条の改正について,護憲派と改憲派の大学教授がそれぞれ意見を述べていました。護憲派は,アジアの平和のために必要なものであると主張します。憲法九条は未完の体系であるから,それを完成させなければならないと述べていました。一方,改憲派は,憲法九条のおかげで主体性が奪われる。世界の国同士の関係は,パワーポリティクスの論理が働いているので,発言力を増すために改憲は必要な作業だといいます。財界からも,日本企業の海外展開が進んだことで,自衛隊に安全を守ってほしいといった願望があるといいます。憲法九条はアメリカの安保体制のもとでの単なる理想でしかないので改憲は免れないとします。街の声も,憲法九条は理想的なものだけれど,日本だけのものであるから守るべきであるという護憲派と,アメリカに押し付けられたもので,日本がアメリカから自立しなければならないとする改憲派の2つに分かれました。このような議論が最近活発になってきたのは,政治的イデオロギー対立が,冷戦の終結でなくなったことがあげられます。また近年,自衛隊が海外展開する中で,これまでは何とか憲法九条の拡大解釈で行われてきたことが限界にきつつあるというものです。憲法九条を守る一方で拡大解釈を続ける怖さも認識しておかなくてはならない。とりあえずこれまでタブー視されてきたものを議論の俎上に載せること自体は重要だと思います。自分は当初,現実の状況に合わせて自衛隊活動との論理的整合性をもたせるために改憲することはやむをえないと思っていましたが,最近は護憲派の意見に賛成しています。憲法九条で掲げられた理想を守ることの意味をもっと考えなければならないと思います。改憲派は憲法九条を他国との関係の中で現実の状況に合わせるために必要だといいます。しかし,政治的発言力を増して,アメリカと対等に話し合うための手段として改憲することの危険性をもっと考えなければならないと思います。同時に憲法九条を守ることで,戦争やテロにさらされたときに覚悟しなければならないことも考えていく必要がありそうです。次回の参院選は間違いなくこのことが争点の一つになるでしょう。ブログランキングに参加中。毎日1回クリックで応援よろしくお願いいたします。
2007.04.29
コメント(0)
-

GW開始
ゴールデンウィークが始まりましたね。国内の天気は晴れたり雨になったり、なかなか予想しにくくなってます。海外に出かける人は、連休の前後も休みにして、11連休にしてしまうこともあるそうです。休みすぎると逆に頭がすぐに仕事モードになりにくそうですね。自分は遠出をする予定がありません。今年1年は遊んでる場合でもないという気持ちもどこかにあるのもあって、近場の公園やショッピングで楽しむ予定です。しかし旧友や同僚たちとの飲みや食事会がちょくちょく入っていて予定が埋まってきました。こういうときにしか普段会わない人たちとは会えないので。こんなまったりしたGWもいいかと思います。ブログランキングに参加中。毎日1回クリックで応援よろしくお願いいたします。
2007.04.28
コメント(0)
-

新緑@駒場公園
天気がいいので駒場公園に行ってきました。春は桜が広場を囲っていますが,この時期は葉桜の緑一色です。10枚の写真のパノラマです。広場ではシャボン玉で遊ぶ園児たち。藤がきれいに咲いているお宅がありました。 いつも通る緑道のツツジもきれいです。 ハナミズキかな?歩道脇の並木になってます。ブログランキングに参加中。毎日1回クリックで応援よろしくお願いいたします。
2007.04.27
コメント(0)
-

米国銃社会の背景
サンデーモーニングの「風を読む」で,米国銃社会の背景にあるものを探っていました。今回の韓国留学生による銃乱射事件を受けて,ニューヨーク市民に個人が銃を持つことの是非を街頭インタビューしていました。銃は護身のために必要である他人の攻撃に使われる可能性があるので必要ない銃の保持はアメリカ人の不安を表しているのではないかといった意見がありました。そもそもなぜアメリカで銃が広まったのか。合衆国憲法修正第2条には,武器保有を認めています。自分で自分を守るということが憲法で正当化されています。ただ一方で,銃保有の規制が憲法違反につながらないといった意見もあります。城西国際大でアメリカ文化史専門の越智先生によると,先住民を征服し,大英帝国から独立し,奴隷に対する不安や恐怖心を克服するため,武器は身を守るための道具として定着した歴史があるということです。そこには,不安が銃の保有をもたらし,その銃の保有によってさらに不安が増すという循環があります。さらに,アメリカ国民の自由,自立,自己責任といった考え方と結びついている面もあります。対立を前提とした,白か黒かをはっきり決着をつける西洋社会の考え方があるのでしょうか。核保有をはじめとする武器の保有を通じて,アメリカ国家は不安の増大を克服しようと世界最強であり続けなければならなかった。国が世界最強の国であるために武器保有を認めているのであるから,個人が武器保有することも正当化されている現実があります。こうした流れを変えられないのは,銃のビジネス化もあるといいます。2億3000万丁もの銃が個人で所有されているそうです。これは一つのビジネスであって,全米ライフル協会といった銃に関連した組織が政治的発言力を増すことで,政府が簡単には銃規制に動きにくくなっていることがその背景にありそうです。アメリカの歩んできた歴史とともに銃の使用の歴史もあるのだと確認できました。ただ銃の使用の背景にある,自分の身は自分で守るといった考え方が日本にも浸透しつつあるのではという危惧があります。たとえば,イラクで拉致され殺害された日本人に対して,自己責任のもとで行動したので自業自得だといった非難が一斉に浴びせられました。社会,企業,地域,国といった社会や組織の責任よりも,個人の責任に帰してしまう流れは,人間的なつながりや心といった心情的な側面を軽視することにつながりそうで違和感を覚えます。ブログランキングに参加中。毎日1回クリックで応援よろしくお願いいたします。
2007.04.26
コメント(2)
-

喜来楼(シーライルー)@三軒茶屋
喜来楼@三軒茶屋ランチタイム11:00~16:00にランチバイキングがあるらしいので,中華バイキングに行ってきました。ビュッフェ形式のバイキングは1時間制限で980円,それにドリンクバーが100円でつけられます。最初に取り分けたフードは写真に撮るのをすっかり忘れていました。最初に,高菜チャーハンと麻婆豆腐,鶏肉とネギの炒め物,豚肉とニラとモヤシの炒め物,餃子,カレー味のから揚げ,小龍包をいただきました。正直に言うと,普通の味で印象に残るようなインパクトはなかったです。麻婆豆腐はペッパーのような味が強かったです。それにピリ辛の唐辛子が相まって不思議な味でした。豚肉とニラともやしの炒め物はとてもおいしい味付けになってました。これは2皿目です。時計回りで,広東風焼きそば,青菜炒め,トマトと卵の炒め物,春巻きです。トマトと卵の炒め物は甘くて,オムレツを食べているような感じです。中華料理っぽくなくて新鮮でした。これは彼女の2皿目です。麻婆豆腐,青菜炒め,鶏肉とネギの炒め物,チマキ,桃の饅頭,胡麻団子です。左上に見えているのは卵スープです。最後に,杏仁豆腐とマンゴープリンをいただきました。 杏仁豆腐もちょっと硬くて食べたことのない食感でした。マンゴープリンはおいしかったです。時間は一時間でも十分でしたが,味は値段相応といった感じでしょうか。ブログランキングに参加中。毎日1回クリックで応援よろしくお願いいたします。
2007.04.25
コメント(0)
-

体罰の是非
太田光の私が総理大臣になったら・・・秘書田中。のマニフェストでプロレスラーの蝶野さんが「体罰を認めます」法案を提出しました。先生が体罰を禁止されている現状では,生徒がそれをいいことにして,逆に騒ぎ立ててしまう。生徒のことを思った体罰であれば,生徒の心を変えるうえで必要である。といった趣旨だったと思います。賛成派では,現役教員が学級崩壊を防ぐためには最終手段として体罰を取り入れざるを得ない現状を訴えました。反対派では,太田総理を中心に,理想を捨ててはいけないといった論調で体罰を認めてはいけないと主張されました。結局この法案は否決されました。この問題は戦争を認めるかどうかという議論にまで発展しうる重要な問題だと感じました。自分が中学校のときに教わった日本史の先生は,シベリアに戦争に行った経験があったと記憶しています。その先生は自らの戦争体験をもとによくこうおっしゃいました。「言って聞かなければ手を出して聞かせるしかない」授業を聞いたときは,確かにそうかなと納得していました。しかしこの言葉の持つ危険性を今感じています。体罰というのは,最終手段であるにしても,使う可能性があるという意味で効力は同じです。体罰を受けるかもしれないという畏怖が規則破りの抑止力になっているからです。これは発言力を得るために核を保有することと似ています。不戦と非戦は違う。不戦は戦う可能性はあるが,平和である限り戦わないということです。非戦はそもそも戦うつもりなどない。この違いは大きいと思います。だから,体罰を最終手段として使う可能性はあるということと,体罰を禁止することとはかなりの差があります。抑止力としての体罰容認には,理性や忍耐を超えて,暴力で反抗する力をねじ伏せようとする論理があります。太田総理はそこで教育こそが,学問こそがそうした論理を覆す理想の世界を説くべきではないかと訴えていました。体罰の禁止を固辞するときは,どうしても心の豊かさを求めるような,想像力で解決しようとするような理想論になりそうです。一方で,体罰を容認するときは,どうしても目の前に現に起こっている生徒の暴力に対処する術として,現実的な対応を求める傾向がありそうです。体罰を使わずに済めば,それに越したことはないと誰もが思っています。しかし現実に直面したときに,理想論ではどうにも立ち行かなくなると怯んでしまうというのが教員の思いなのでしょう。こうした問題が出てきたのは,学校だけが原因でもないし,生徒個人に帰するものでもないと思います。その背景には,家庭環境がよくなかったことや,地域とのつながりが薄れてきたこと,以前から生徒同士でのコミュニケーションが取れなくていじめにあったこともあるかもしれない。そうして,パンパンに心を張り詰めた生徒に,一個人として教師ができることにはおのずと限界があると思います。だからといって,その生徒を抑えるための最終手段として体罰を加えることがあってはならないと思いました。心の豊かな,想像力のある大人に育てなければなりません。そのためには,大人が一緒になって平和とは何かを考えなければなりません。それを教師だけではなく,親や親戚,他国の人も交えてもいいかもしれません。しかしながら,現実には戦争はなくなってはいません。戦争に備えるための防衛力を身につけておくことで平和が保たれている面があります。この現実を大人は事実として,包み隠さず話すべきです。そしてこうした現状を変えるために戦争する以外に(体罰で生徒の言うことを聞かせる以外に)解決法はないのかを考えていくべきです。憲法9条の改憲論議,愛国心やいじめ,ゆとり教育を見直す教育法改正など,これまでタブーとされてきた問題に腰をすえて話し合うときが来ていると感じます。ブログランキングに参加中。毎日1回クリックで応援よろしくお願いいたします。
2007.04.24
コメント(0)
-

春の花ぞくぞく@駒沢公園
晴れた土曜日に行ってきました。春の花を探しに。桜の季節が終わったら,今度は春の花がいろんな色を見せてくれています。タンポポが草むらに黄色の斑点のように広がっていました。 花壇には別の黄色い花が。名前は何だろう。 オレンジもありました。白と黄色とオレンジと。ハトポッポはいつもどおり元気です。そして見ごろのボタン桜もありました。花びらの形がわかるようにあえて接写気味にしてみました。 ブログランキングに参加中。毎日1回クリックで応援よろしくお願いいたします。
2007.04.23
コメント(0)
-

続非常勤
土曜日の講義ということもあり、選択必修にもかかわらず、前回は5人の少人数で始まりました。しかし今回はさらに減って3人での授業になりました。男の子ばかりなのですが、みんな素直に耳を傾けてくれてありがたいです。パソコン実習ですが、使い慣れてない学生の方が多くて、かなり丁寧に操作方法を教えます。しかし口で言うのは難しいと感じます。それでも簡単な操作法が自分でできたときには感動してくれて、こちらも教え甲斐があります。パワーポイントも最初にスライドなどのアニメーションを教えて、実際に使ってみた時の反応があって面白かったです。ブログランキングに参加中。毎日1回クリックで応援よろしくお願いいたします。
2007.04.21
コメント(0)
-

ツツジ開花
今日は久しぶりの快晴ですねこんな日はまたデジカメを持って花々を撮りたくなります。ツツジが咲き始めてました。赤色ピンク白色全部違う場所で撮りました。それだけあちこちでいろんな色のツツジが咲いてるってことですね。さて学校にはツルを巻いた木が植わっています。これからどんどん葉をつけていく勢いを感じたのでパノラマ撮影ブログランキングに参加中。毎日1回クリックで応援よろしくお願いいたします。
2007.04.20
コメント(4)
-

銃社会アメリカ
アメリカバージニア州で起きた銃乱射事件。銃が手軽に買えてしまう社会だからこそこういう凶行も可能になるんでしょう。常軌を逸した行動を普段からとっていたとのことで,その背景はなにかこれからの捜査で明らかにされてくるでしょう。現時点では,韓国でもかなり貧しい家で富裕層に対する妬みをもっていた,教室ではかなり孤立していた,恋愛のもつれの対象となったのは彼の想像上の彼女だった,事前に犯行予告ビデオと爆破予告の脅迫状を作成して自分がヒーローであるかのように振る舞ったなどの行動が明らかになっています。もっと大きなバックグラウンドに,アメリカの個人主義がもたらす格差があるのか,単なる個人の狂気ととらえてよいのか判りませんが,怒りの感情を実際に行動で示すための手段として銃が使われたということに違いはありません。自分の身は自分で守らなければならないアメリカでは,銃を持つことが必然になっていると思います。しかし銃を持つために必要な教育が不十分であるために,目的外で使用される(家庭内暴力などでも)ことが多いのが事実です。きちんと銃を用いることができる個人を一人ひとり育てられるのであれば,そもそも銃を持つ必要がないですよね。だから国としては銃をどのように用いるかも含めてかなり自由で寛容にならざるを得なくなっているのではないか。そうなると,個人の銃保有に対する賛成意見は弱まることはなくてむしろ強まっていきそうです。一度持ってしまった防衛手段を放棄するのは簡単ではなさそうです。刀狩りのように武器を一斉に放棄するとともに,国家の安全保障体制を確立することができればいいのだろうけれど,それは理想論で現実にはできそうにありません。悲惨な歴史は繰り返されていくのでしょうか。ブログランキングに参加中。毎日1回クリックで応援よろしくお願いいたします。
2007.04.19
コメント(2)
-

教室の合意
新年度が始まってから学校について書くことが多いような。それだけホットで,しかも複雑かつ微妙な人間関係について考えさせられることが多いってことですね。昨日は新歓巡検について教室のみんなで議論しました。事の発端は,ある先輩が,他専攻と続けていた伝統的行事である新歓巡検を昨年度から廃止して,内輪だけで新歓をしたことに不満を漏らしたことです。個人的な言い争いだけだったのですが,教室みんなの意見を聞いて合意をとった方がいいのではないかということで,みんなで新歓巡検のあり方について話し合いをしました。詳細はややこしいので省略しますが,他専攻との交流自体はみな賛成,そのための手段としての巡検については賛成が先輩1人?反対は後輩を中心に多数といった感じ。当初自分が予想したとおり,先輩のよき伝統を残したいという思いが語られました。議論を重ねて思うのは,それぞれ自分の経験したことに照らした新歓巡検に対する思いがあるわけで,教室としての合意を取るのは簡単ではないということです。企画のとりまとめをするのは,下の学年なので,引継ぎをしっかりして,これまでの巡検の申し送りをしっかりやっておきさえすれば,あとはそのときの幹事にお任せすればいいと思います。先輩はきっと成功体験があるので,わざわざ自分たちから廃止することはないとおっしゃってました。たしかに後輩はどうやって新歓を運営していけばいいか,判断材料が少ないと思います。だから,いろんな人の少数意見も聞きつつ,自分たちの負担も考えつつ,一番ベターな方向性を当事者たちで話し合って決めれてもらえばいいと思います。あと,上の学年になれば,自分も含め,あまりお小言は言わないほうがいいなと感じました。後から文句を言うのではなく,事前にしっかり先輩のほうからコミュニケーションをとっておくべきだと思いました。上下関係は多少あるので,先輩の意見が「押し付け」になることもあるかもしれません。先輩が後輩に対して,普段から気遣いとアドバイスを細かくやっていれば,教室としてもっとまとまりあるものになっていくと思います。そのためには,できるだけ毎日学校に来て顔を合わせなきゃいけないんでしょうが。一人ひとりがそういう高い意識をもってなきゃいけないですね。ブログランキングに参加中。毎日1回クリックで応援よろしくお願いいたします。
2007.04.18
コメント(0)
-

免許更新
昨日は運転免許証の更新に行ってきました。朝起きたときはだるかったけど,先延ばしにするとますます気が乗らなくなるのは分かっていたので,いずれ済まさなきゃいけない用事は早めに済まそうと思いました。午前11時前に免許センターに着きました。そこから目の検査や写真撮影で結構並びました。その後1時過ぎにかけて2時間の講習(過去に違反したので)を受けました。前半は配られる教則本をめくりつつ,事故を検証するDVDを見ました。後半は自己診断をしました。この2時間が結構疲れます。途中で眠くなりますが,講義担当者からは寝ると判子を押せないと脅されました。自己診断の結果は,「運転への自信が足りず判断に迷いが生じがちであることがうかがえます」だそうです。心がけたいことは,「判断に迷ったり状況把握が遅れがちの人は,まず相手に進路を譲るようにしましょう。そして,その意思を譲る相手にはっきり示しましょう」でした。普段は車を運転しないので余計運転するときの状況判断がうまくできるか不安に思うことがあります。今回からICチップ入りの免許証に変わりました。本籍の欄は空白で,暗証番号を入れて機械に読み取って初めて本籍が分かる仕組みになっています。IT化の波はここにも来てます。カードに埋め込まれた分,以前より厚みが増して財布が膨らんじゃうし,取り扱いに気を使っちゃいますね。ブログランキングに参加中。毎日1回クリックで応援よろしくお願いいたします。
2007.04.17
コメント(0)
-

ににんがよん@下北沢
今日から区長選区議選が本格化しました。また選挙ですね。しかし今回は候補者が圧倒的に多くて,どの人がどんな政策を打ち出しているのかいちいちチェックしている暇も情報もありません。朝,警察署の前を通り過ぎたとき,たくさんの選挙カーが演説のスタンバイをしてました。こうやって事前にちゃんと許可を得て出陣していくんですね。さて,夜は同僚と食べ放題のカレー屋@下北沢に行きました。2×2=8と書いて「ににんがよん」と読みます。意味不明ですね。ネーミングのセンスが問われます。食べ放題は980円にワンドリンク制で350円+消費税で1396円かかります。店の前のたて看板にはそんなこと書いてなかったので,ちょっとだまされた気分になりました。インド人さん風の方が経営しています。一応,インド・パキスタンカレーと銘打っていました。カレーはマイルドな野菜カレー,ミディアムなチキンカレー,ホットなマトンカレーの3種類あります。骨付きチキンもありました。ライスは色つきのものと,白米,さらにナンから選べます。さらに,カット野菜,コーン,ワカメが並んでます。デザートはフルーツデザートと,デザートの2種類がありました。上がチキンカレー。下がマトンカレー。ナンでいただきました。カレーはマトンがちょっと辛かったけど,ダルが入ってておいしかった。チキンカレーはあらかじめ細かく割かれた肉が入っててあまり食べ応えはなかったけど,味はなかなかよかったです。野菜カレーは一番辛さが控えめで安心して食べられます。チキンもちょっと硬めだったけどおいしかったです。ただ,最後に食べたデザートがちょっと食べたことのない味で,みな戸惑っていました。お腹いっぱい食べたいときにオススメですね。ブログランキングに参加中。毎日1回クリックで応援よろしくお願いいたします。
2007.04.16
コメント(0)
-

旧友と再会
昨日は,1年ぶりに仙台時代の旧友と再会しました。自分と同じ道を別の場所で歩もうとしていたけど,途中で疎遠になってました。次に連絡があったときにはNPOに勤務していて,今回新たに民間企業に就職したと報告がありました。彼は九州で勤務することに決まりしばらく会えないので,東京を発つ前に一度飲もうとわざわざ連絡をくれました。自分の家で宅飲みを久しぶりにしました。仙台にいたときには家に近かったこともあって頻繁に夜飲んでいた記憶があります。話していて,ぜんぜん昔と変わらない雰囲気に懐かしくなりました。こちらは最近ハマっている麻婆豆腐をおもてなししました。チキンのがらスープが効いていておいしいとお褒めの言葉いただきました。彼は引越し先のアパートを決めたときに,わざわざ博多の明太子のお土産と,佐賀のいかシューマイを買ってきてくれました。いかシューマイと麻婆豆腐,枝豆や水餃子を酒の肴に,黒糖焼酎で乾杯しました。彼は研究のことだけではなく,業界の人事異動についても詳しくて,こちらがとても勉強になりました。今後も民間での仕事がこれまでの研究にもつながりそうなので,研究+仕事というほかの人にはないいい仕事をしてくれると期待しています。自分も彼の生き様に共感させられ,そして励まされました。ブログランキングに参加中。毎日1回クリックで応援よろしくお願いいたします。
2007.04.15
コメント(0)
-

非常勤開始
今日から非常勤が始まりました。昨年度と同じ土曜日ということで、予想通り生徒数は少なかったです。初対面だとこちらもどんな学生が来るのだろうと、期待と不安を抱いてしまうので説明が少したどたどしくなっちゃったかも。本当にいまどきの若者だなという雰囲気です。でも土曜日に来てるだけあって真面目そうです。毎回出席してくれることを願ってます。さて、今年度から学校でシステムが変更になって、ICカードが発行され、出欠や図書館の入室はICカードで処理できるようになりました。でも直前になってIC管理が間に合わなくなったそうで、出欠はこれまでどおり紙に書いてもらってます。IT化の波がどんどん押し寄せている感じですが、一斉に導入すると使う側はやり方に慣れるまでに時間がかかるし、一度システムがダウンすると復旧するのが大変なのではと不安なところも出てきます。万全を期して導入してほしいです。ブログランキングに参加中。毎日1回クリックで応援よろしくお願いいたします。
2007.04.14
コメント(0)
-

パノラマ
パノラマ写真にチャレンジしてみました。ためしに学校のグラウンドを撮ってみました。3枚を自動のつなぎ合わせ機能を使ってつないでます。初めてにしてはなかなかの出来です。ちょっと前に撮った桜。今はもう葉桜になってしまいました。 道路わきに一輪のオレンジの花が咲いていたので思わずシャッターを切りました。ブログランキングに参加中。毎日1回クリックで応援よろしくお願いいたします。
2007.04.13
コメント(0)
-

新年度開始
一昨日からゼミが始まりました。うちのゼミは各学年一人ずつというかなりバランスの取れた人数配分になりました。しかも毎年ちょっとずつゼミ生が減っているので,先生も面倒を見る学生が減ってきていることに安堵なさっている様子でした。今年度は変化はあまりなさそうですが,それなりに忙しい年度になりそうです。心を入れ替えて,気合を入れなければと思います。今日の研究室ゼミは春休みの進捗状況の報告でした。上の学年になるにつれて,みなそれぞれが停滞感と焦りを感じていることが伝わりました。自分も例外ではないです。焦っても仕方がないのは分かっているのに,焦ってしまいます。地道にコツコツやっていきましょう。教室全体のゼミが終わってから新入生歓迎会を兼ねた飲み会へ。社会人で入ってこられた新入生の方との話が盛り上がりました。社会の波にもまれた方は,まず礼儀がしっかりしているのだなと感じます。とても人当たりがよくて気さくな方でした。しかし社会人をしながら研究も進めようとする方のバイタリティにはいつも感心してしまいます。研究テーマもかなりぶっ飛んでいて逆におもしろいというか,院生のほうが調査ができる範囲内で結論を導こうとする傾向がありそうで保守的だなと感じることがあります。実務を経験されている生の話は,その人の人生経験そのものであると感じるので,聞いていて飽きないですね。ブログランキングに参加中。毎日1回クリックで応援よろしくお願いいたします。
2007.04.12
コメント(0)
-

ガイダンス
昨日は新入生がガイダンスを受けて教室をぐるぐる回って,うちの部屋にも来ました。期待と不安を胸にした新入生の姿がありました。自分が入ってきたときのことを懐かしく思い出しました。当初は慣れるまで必死だったような気がします。とりあえず,最初の1ヵ月,ゴールデンウィークまでは教室のいろいろな決まりごとを覚えたり,人とのコミュニケーションを図って仲良くなることを優先して。と同時に今までどおり研究を続けていかなくてはいけないという焦りもありました。そして,長いゴールデンウィークを迎えて必死だった割にはあまり成果が出ていない自分を反省していました。焦っても仕方ないので,とりあえず目の前の仕事をコツコツこなさなきゃいけないんだなとそこで思いを新たにしたわけです。それは現在の状況でも同じですね。今日からいよいよ授業開始です。長いようで短い一年が始まります。ブログランキングに参加中。毎日1回クリックで応援よろしくお願いいたします。
2007.04.10
コメント(2)
-

夜回り先生
水谷修(2004)「夜回り先生」日本評論社.夜回り先生がこれまでに出会った子どもたちのことについて書いています。特に印象に残ったエピソードは,「落とし前」です。ある日,横浜中華街近くのパチンコ屋裏で,店員から袋叩きにあっている少年を助けた。不正に玉拾いをしていたそうです。その少年は台湾人で,日本で出稼ぎした母親が日本人男性と再婚して日本で生活していたけれど,中学卒業後は進学せずにぶらぶらしていたそうです。先生は熱心に高校進学を薦めたため,夜間高校に入学することになったけれど,暴力団に入ってしまいました。必死の説得で彼は暴力団から抜けることを約束し,2人で組事務所へ直接出向くことになりました。これまでに何度も危険な目にあってきたが,正直言って,組事務所へ行くのはさすがに怖かった。私は警察ではなく,ごく平凡な高校教師である。万が一のことがあっても,自分の身を守る手段何一つ持っていない。私は覚悟を決めるしかなった。しかし予想とは裏腹に,組長との話し合いは奇跡的にうまくいった。足を洗うための条件も「少年が二度とナワバリに入らない」という軽いものだ。難なく少年を暴力団から引き離せた幸運に,私たちは喜んだ。でもそんなに甘くなかった。さらに一ヵ月後のことだ。組事務所から学校に「少年がナワバリに入ったから,捕まえている」という連絡があった。なんということだ。私は目の前が真っ暗になった。でもここで逃げても仕方がない。私はもう一度覚悟を決めて,少年が拘束されている組事務所を訪れた。ソファに座らされた少年は,真っ青な顔で震えていた。彼の両脇を何人もの組員が囲っている。その向かいで険しい顔をしていた組長が,苦々しく言った。「水谷さん。こっちもメンツを商売にしている。約束を破ったら,それなりの対応をしなければいけない。いいね?」落とし前は,私の利き腕の指一本だった。その後少年は高校に戻り,日本の永住権を取得することができた。そして現在は自分の店を持つことを夢見て,都内の中華料理店でまじめに働いている。それを思えば指一本,なかなか痛かったが,安い買い物だった。------------------------引用はここまで-----------------------------このエピソードで衝撃を受けました。先生はまさに自分の身を犠牲にして,子どもの命を救っていました。そして組事務所に2人で乗り込むのも普通の先生じゃ考えられない行動だと思います。子どもが不幸になった原因である大人の責任を,すべて水谷先生が一人で背負っているように感じます。自分だけをかわいがってできるだけ人とかかわらないように生きている人が多い世の中にあって,ここまで自己犠牲を徹底して他人のために生きる姿はそうそう真似できるものではないと思います。そして子どもたちに自分ができることは何なのかと考えさせられます。それはきっと言葉ではなく,笑顔を見せてそばに寄り添うことなんだろうな。それはきっと自分の生き様を見せて子どもに希望をもって生きてもらうということなんだろうな。ブログランキングに参加中。毎日1回クリックで応援よろしくお願いいたします。
2007.04.09
コメント(0)
-

桜散る
玄関の庭に咲いた花 投票所の前にはいろんな花が咲いた花壇がありました。学校には遅咲きの桜が満開です。満開だったソメイヨシノはあっという間に散ってしまいました。見頃はほんのわずかな間だけでしたね。寝坊した桜が葉っぱの間から顔を出してます。 春の風が吹くと,桜の花びらが雪のように舞い散りました。わかるかな??幹の間からも満開の花がちらほら。 花びらのじゅうたん。ブログランキングに参加中。毎日1回クリックで応援よろしくお願いいたします。
2007.04.08
コメント(2)
-

東京都知事選前日
いよいよ明日は東京都知事選ですね。投票に行くか街頭インタビューしたところ,8割以上が行くと回答したとのことで,この意志をみんな実行すれば,驚異的な投票率になります。実際の投票率がどうであれ,選挙戦がそれだけ注目されているということは事実のようです。しかし現段階でちゃんと各候補者のマニフェストを熟読した上で投票先を決めている人はどれくらいいるんでしょう。かくいう自分もまだちゃんとマニフェスト自体を読んでいません。でも投票する候補者は決まっていたりします。以前,無党派ブームの記事で書いたように,特定の支持政党を持たない無党派層に訴えかけるため,候補者たちも街頭演説で個人のアピールをしきりに強調しているような気がします。特に年齢の若さをウリにしたような文言を繰り返すことが多いようです。これでは,個人の身体的特徴や外見のみの印象だけで争っていてあまり実がないように思います。政策論争によって選挙戦をするならば,本来マニフェストには書けない,あるいは一番重視する政策,理想の政治をもっと分かりやすく伝えるべきではないかと自分は思います。街頭演説でどれだけの回数をこなしたかという数を競うのもよく分かりません。確かに人の目に触れる機会が多いのは支持者獲得に貢献するでしょうが,自分の名前を繰り返し言うだけでは,知識のない人に名前だけを刷り込みしているだけで実がありません。演説の仕方のうまい下手はあるにせよ,その人の熱意が伝わるようなアピールの仕方があってもいいなと思います。自分は街頭演説でまともに候補者の訴えを聞いていないので何とも判断できないのですが,もう一度マニフェストを確認してから投票したいと思います。ブログランキングに参加中。毎日1回クリックで応援よろしくお願いいたします。
2007.04.07
コメント(0)
-

新年度に向けて
学校ではいよいよ新年度が始まります。長い休みだったので休みボケしてしまって,通常の生活に戻すのが辛いかも。といっても授業はないのであまり影響はないんだけど。新年度に向けて後輩たちが学校の運営についていろいろ準備してくれてます。教室の配置換えやら,ゼミの発表順番やら,機器の入れ替えやら,新歓コンパのセッティングやら。自分はその役を担当したことがないのでその苦労が本当はわかっていないのですが。でもそこに苦言を呈する先輩もおられます。長く続いてきた伝統を守る,あるいは自分たちの意見も取り入れてほしいとの願いからでしょう。いろんな意見があるのは当然だし主張をしていいと思います。たしかに後輩たちは自分たちで決めるための判断材料が乏しいのは仕方ない一面もあります。でも先輩が自分の意見を押し付けるようなことがあっちゃまずいと思います。後輩は納得していないにもかかわらず,先輩の意見だからといって,パワハラまがいにその意見を取り入れざるを得ないことになってはいけないと思います。いろんな意見を聞いたうえで最終的に判断するのは,責任を任された後輩にあります。引継ぎのときに上の学年から申し送りをしておけば,あえていろんな先輩が口出しすることはないし,そうすることでかえって混乱してしまうでしょう。そんな状況に今なりつつあって,運営する立場になった当の本人たちは不満がたまっています。先日も後輩からいろいろ言われて困っているという愚痴を聞きました。自分は傍観する立場なのでその話を聞くことしかできませんが,あまり実のない感情的な議論を繰り返しているなと感じてしまいます。口うるさい先輩に「でも・・・」と反論したところで逆にうまく言いくるめられてしまうし余計に反感を買ってしまうこともあるので対処が難しそうです。そんなときは「はいはい。そういうこともあるかもしれませんね。」と納得したように見せつつ,自分たちで判断して方向を決めていけばいいと思います。その判断が正しいという根拠があればあまり人の意見に振り回されてはいけないと感じます。また後輩も責任者だからといって1人で抱え込むことはなくて,いろんな人に愚痴をこぼしつつ,ストレスをためないように気心の知れた人たちと協力して決めていってほしいと思います。本当に些細なこととはいえ,人間関係のもつれは本当にややこしいと感じます。新年度は新たな体制に変わるので,みなの心もちょっと不安定になるということも影響しているのでしょうか。あるいはいつもはしなくてよい準備に追われて,イライラしているかもしれません。いろんな意見のぶつかり合いもあるでしょうが,それをうまく乗り切ってひとつにまとめるという社会に出て重要なスキルを身に付けてくれればなと思っています。ブログランキングに参加中。毎日1回クリックで応援よろしくお願いいたします。
2007.04.05
コメント(0)
-

あるある大辞典検証番組
昨日22:00-23:09にかけて,フジテレビで「私たちは何を間違えたのか・・・検証あるある番組大辞典」と称した検証番組を放送しました。このテーマについて書くのは3回目。もういい加減忘れたいと思いつつも,うやむやにしてはいけない大事な問題がたくさん潜んでいると思ったので70分間しっかり見ました。前回はねつ造の内容が紹介されて終わりましたが,今回は番組制作過程と今後の再発防止策をディレクターやプロデューサー,外部調査委員会のコメントをもとに番組ねつ造の検証をしていました。それによって,フジテレビが番組を通して,どのように検証作業がなされたのか,ねつ造が行われた背景はなんだったのか,これ以外の放送回ではねつ造はないのか,今後の再発防止策はどのようなものかが明らかにされました。内容は大きく分けて4つ1.ねつ造問題発覚のきっかけとなった2007年1月7日納豆ダイエットの番組制作過程で何が起きたのかを検証番組をおもしろくしたいと制作会社のディレクターは考えていました。番組を収録するまで2ヶ月という期間が与えられ,その限られた時間の中で,なんとか納豆でやせるというロジックを見つけなければなりませんでした。ディレクターは,過去に高い視聴率を獲得した成功体験を持っており,収録直前の時期に米博士のコメントをボイスオーバー(英語のコメントに日本語のナレーションをかぶせる)でねつ造しました。真実を知るためには時間と労力が必要です。検証の過程で予想外の結果が出てくることもあるでしょう。しかし制作過程では,仮説ありきで,仮説にあう都合のよい情報だけを出し,都合の悪い情報は隠したり,改ざんしたりしてしまう。あとはインターネットで手軽に情報を入手して,その情報の信頼性を問うことはありませんでした。インターネットによる簡便な情報検索,パソコンでの動画編集など効率的に仕事のできるようになったことで,結果として「手抜きのできる」仕事が可能なったという一面があるかもしれません。2.あるある大辞典が抱えていた問題を外部調査委員会の報告をもとに検証1996年に始まったあるある大辞典では,定説といわれるものを頼りに,学者,研究者があらかじめ検証してきた実験データを追従する程度のものでした。しかし2004年にリニューアルしたあるある大辞典2では,仮説を立ててそれを実験によって検証するという番組作りに変わりました。バラエティ色が強くなり,いかに分かりやすくおもしろく伝えるかに重きが置かれました。一方で,情報の正確性がないがしろにされてしまいました。また予算が限られていたため,科学の信憑性をチェックする体制もとられないままでした。ねつ造発覚前にすでに,番組に対する批判や本まで出されましたが,10年間の実績に対する過信があったという証言がありました。視聴率維持のために,そうかもしれないという仮説的な結果についても次第に断定的な表現がとられていきました。3.フジテレビ系列に送られた今回のねつ造問題に対する意見を書いたメールや手紙を紹介4.再発防止策(社員意識アンケートより)放送局のあるべき姿を経営側が示すべき。制作担当者の良心をキープする術を身につけるべき。視聴者のニーズを測る視聴率とは異なる指標を見つけるべき。調査委員会の報告では,内部体制の強化,チェック機能の強化,視聴者との回路作りなどが提言されました。関西テレビは,コンプライアンス推進室の設置や制作会社との公正な制約などを誓約しました。視聴者は今回の放送をどれくらい見ているのでしょう。信頼を裏切られたと感じた視聴者は検証番組すら見る気が起きないかもしれません。今回の検証番組に対しての視聴者との回路をどのように担保していくのでしょう。この検証番組がどのようにして制作されたのでしょう。テレビはつくられたものです。したがって,限られた70分という時間の中で,収集された情報が制作過程で取捨選択されたはずです。どのような基準を持って取捨選択の判断がなされたのでしょうか。この番組制作に関わった人は,あるある大辞典の制作番組関係者と関係はないのでしょうか。ディレクターやプロデューサーなどの番組制作サイドのコメントは本当に真実をあらわしたものでしょうか。ふとした疑問を取り上げればキリがないです。放送業界の構造的な問題があるとのことですが,関西テレビの再発防止策の取り組みが構造そのものを変えるだけの効果があるのかは疑問です。また制作過程をチェックするための体制は現在のお金の流れで担保されるのでしょうか。今回の放送を見て,市場原理の持つ効率性と,科学の持つ信頼性とがあまりなじまないのではないかと感じました。利益を出さなければいけない構造の中では,安全や信頼は切り捨てざるを得ないのが現状なのではないでしょうか。ブログランキングに参加中。毎日1回クリックで応援よろしくお願いいたします。
2007.04.04
コメント(0)
-

簡単ポトフ
簡単ポトフのご紹介今回は余った材料が多かったので,具だくさんになりました。材料(2~3人前)にんじん 小1本ジャガイモ 1個玉ねぎ 1/2個ブロッコリー 適量ベーコン 5枚パセリ 適量ブラックペッパー 適量チキンスープ 400ml作り方1.チキンスープに一口大に切ったにんじん,ジャガイモ,玉ねぎ,ブロッコリー,ベーコンを入れて煮る。ブラックペッパーを適量入れて味を調える。2.野菜が柔らかくなるまで煮たら,最後にパセリを適量いれてできあがり。チキンスープは万能です。簡単すぎます。にんじんは一番煮えにくいので注意。あらかじめレンジに2分ぐらいかけておくといいかも。栄養たっぷりで味もしっかり染みています。すっかり春めいたので温かい料理はあまり恋しくならないけど,まだ寒い日はやってくるはず。そんなときには,このポトフで決まりです。もうお袋いらずですね。ブログランキングに参加中。毎日1回クリックで応援よろしくお願いいたします。
2007.04.03
コメント(2)
-

ジュークボックス英会話の最終回
3か月トピック英会話-ジュークボックス英会話の最終回がありました。各回で取り上げられたアーティストと曲名はこちら。このシリーズは3か月で1クールなので,出演者も内容もすぐに変わってしまいます。だからこそ出演している講師の方々が,毎回20分全12回で英語を楽しく勉強する方法を伝えようとする思いが凝縮されているように感じます。テキストにポップスで英語を学ぶことの利点がかかれていたので紹介します。その利点は,歌うこと(ビートにあわせて英語を発生すること)が,「英語の身体づくり」のためのトレーニングになるというところにあります。もちろん,歌う英語は,しゃべる英語と違います。歌う英語は韻文で,韻文には,身体が刻む韻律が備わっています。ノリのいいポップスには,この韻律を大事にする。でも,それは,ノリのいい発話についても,文章についても,同じなのではないでしょうか。日本語で,これを言ってみてください。「古池にカエルが1匹飛び込んだ。そしたら水がパシャッとはねた」言いやすいですよね。それはこの発話のベースに,こういう韻律が潜んでいるからです。1 2 1 2 3 4ふるいけ に かえるが いっぴき とびこん だちょっと難しい言い方になりますが,私たちがしゃべる言葉の深みに韻律が生きていて,僕らの喋りを引き寄せている。そこに,ストンと落ちると気持ちがいい。調子のいい発話や文章は,ベースに規則的な韻律を持っている。歌を歌うことは,「言葉の自然な律動に身体をゆだねる」ということです。--------------------------引用はここまで----------------------------なるほどと思いました。普段は洋楽でも邦楽でもこんな風に歌を聞いたことはなかったかも。英語を発音するときのリズムを音楽から学ぶということは手っ取り早い上に合理的な方法なんだろうな。講師の先生のギャグセンスをたくさん盛り込んだ番組作りにも共感しました。mixiのコミュでは「3か月じゃ足りない。もっと続けてほしい」という意見がたくさん出ています。今回のシリーズで,音楽の歌詞にこめられた内容の奥深さと,実際に歌うことでリズムと感情表現の仕方を体得できることを知りました。次回からのシリーズはハワイでの滞在型旅行を想定した実践的な英会話レッスンになりそうです。引き続き英語力アップのために見続けたいと思います。3か月トピック英会話-ハワイでハッピーステイブログランキングに参加中。毎日1回クリックで応援よろしくお願いいたします。
2007.04.02
コメント(0)
-

花見はしご-駒沢公園~二子玉川~駒場公園
都内の花見は週末が見ごろだとニュースで言っていたので,土曜日は曇りだったけど行ってきました。まずは駒沢公園へ。肌寒かったけど花見客でにぎわってました。テニスコート脇には桜の回廊ができてました。公園を出てすぐの緑道には桜の花が幹から顔を出してました。続いて二子玉川へ。駅を出てすぐの堤防は桜並木になってます。もうほぼ満開でした。接写するとつぼみのピンクがかわいいですね。満開した花よりも見栄えがいいかも。葉っぱもいつ開こうか待ってます。 堤防の両脇に桜がめいっぱい枝を広げているので見ごたえ十分。道路のすぐそばに咲いているので,車のドライバーもよそ見してしまいそう。堤防の脇にはいろんな花が咲いてました。階段の脇にはこんな花も。アブラナも彩を添えてます。紫も。この花は初めて見ました。4月になる前に満開を迎えちゃうとなんだか忙しない感じになっちゃいます。さて今日は昼間晴れていてお花見日和。東京の最高気温は24℃だそうです。緑道のベンチにはお弁当を持った人たちが花見を楽しんでいました。公園の中でもこじんまりしていて桜のきれいな駒場公園へ。花見客で一杯でした。園内の広場をぐるっと桜が取り囲んできれいでした。 もう満開を迎えて桜の葉っぱは散り始めてました。ブログランキングに参加中。毎日1回クリックで応援よろしくお願いいたします。
2007.04.01
コメント(0)
全27件 (27件中 1-27件目)
1