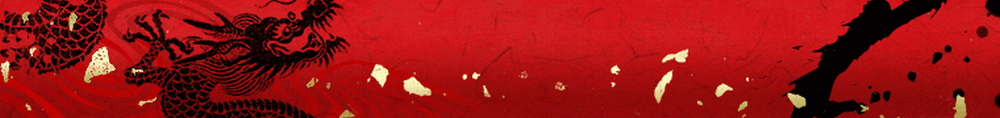2023年02月の記事
全28件 (28件中 1-28件目)
1
-
「ゾンビ企業」がどうなるかというと・・・
新型コロナの蔓延で多くの企業が窮地に陥ったといわれるが、日本政府は実質無担保のゼロ金利融資を行い救っている。しかし今度はその返済が始まったことで倒産の危機に陥る企業が増えると予想されていて「物価高倒産」が急増しているという。ロシアのウクライナ侵攻に端を発した物価高で原油や燃料・原材料などの仕入れ価格上昇や、取引先からの値下げ圧力などで価格転嫁できなかった「値上げ難」などにより収益が維持できなかった倒産だという。しかも生産活動が回復し工場の稼働率が上がるにつれ燃料費の高騰が企業経営を圧迫していつ模様で、エネルギーコストの上昇分の価格転嫁はほとんどの業界で進んでおらず、4月以降も電力会社の電気料金の引き上げ申請が控えているという。 これからコロナ禍で実質無利子・無担保の「ゼロゼロ融資」を受け延命されていた企業の借入金返済が本格的に始まるのだが、返済据え置き期間中に業績回復や経営体質強化が遅れた企業が事業継続を断念するケースが増えると予想されている。インバウンドで人流も増え企業の生産活動が本格的に再開すると競争が起こるという。駅伝やマラソンをイメージするとよくわかるのだが参加者は一斉にスタートしても、コース途中で徐々に分散しゴール近くになると脱落する選手も多くなってくる。それと同じで倒産件数は企業間の競争が激しくなる局面で増え今後は賃金上昇圧力もかかってくると、企業の生産活動や物価高だけでなく、エネルギーコストも上がる今春以降に倒産件数はさらに上積みされる可能性が高いという。 新型コロナの影響で多くの飲食店等が苦境に立たされた際に政府は、実質的に無担保のゼロ金利融資「ゼロゼロ融資」をおこなって窮地を救ったのだが、それにより多くの企業が救われ経営者や従業員が助かったといわれている。これから返済が本格化するようなので倒産する企業も多いだろうといわれており、その中には新型コロナ前から経営が傾いていて再建の見込みが乏しかった企業もあり、「ゼロゼロ融資はゾンビ企業を延命させただけだ」と批判する人も出てきそうだという。ゾンビ企業か否かをじっくり見定める時間がない場合判断ミスが生じ、そのミスには「ゾンビを延命させてしまうミス」と「健全な企業を倒産させてしまうミス」があるが、健全な企業への融資をせずにコロナ倒産を招いてしまうとその損失は大きなものとなるという。 失業対策として公共投資をおこなって無駄な道路を作るよりは未だ使える設備を使ってゾンビ企業に営業を続けてもらうほうが国民経済的にも望ましいといわれるし、ゾンビ企業を延命させてしまっても永遠に延命させるわけではないの、失うものは多くないという意見もある。一方で経営者や従業員の悲劇というのみならず店のノウハウや信用等々といった見えない資産が雲散霧消してしまうからで、いわゆる「ゾンビ企業」の退場は新陳代謝のために必要なプロセスという見方もでるという。好況期にゾンビ企業が労働力を抱え込むことは好ましくない今の日本の賃金レベルでは国内産業はさらに空洞化しかねず、物価上昇とともに賃金も上がり消費活動が活発化する好循環に日本も乗れるかが今は潮目の時期だといわれている。 このように日本経済に埋め込まれた時限爆弾ともいえる過剰債務企業は、コロナ禍で経営課題に急浮上した「過剰債務」への対応が急務であることを物語っており、労働力不足のときであればゾンビ企業が倒産しても労働者は路頭に迷うことがないことから、中小企業は地元の地方銀行や信用金庫に信用組合の経営統合の行方を注視する必要があるという。それによって経営環境の有利不利に地域差も出るからなのだが、物価高の価格転嫁をスムーズに図れるか図れないかとか、賃上げができるかできないかによって勝ち組と負け組の明暗がはっきりする時代が来年にかけてやってくるという。ビジネスは人・モノ・カネ・情報で動きだとされ、とりわけ賃金はキーになるといわれるが、賃上げしないところに人材は集まらないというのだ。
2023年02月28日
コメント(0)
-
マイナカードが新しくなるそうで・・・
マイナンバーカードとは個人番号が記載された顔写真とICチップ付きのカードでマイナポイント事業が後押しとなりマイナンバーカードの取得が進んでいるが、マイナンバーカードは健康保険証やお薬手帳に診察券や運転免許証などと一体化しスマホに格納されていく予定だといわれている。マイナポイント事業とはマイナンバーカードとキャッシュレス決済を普及させるのを目的として、キャッシュレス決済でチャージ・もしくは支払いすると当初は最大5,000円分が還元されるキャンペーンだったが、新型コロナウイルス感染対策の経済対策としてマイナンバーカード保有者へ最大2万円のポイント付与となっている。各市町村の窓口が混雑していて新型コロナウイルスの流行などの状況も踏まえ今年の2月までと2カ月間延期している。 マイナンバーカードを使うことで行政上の手続きが簡単になるといったメリットがある一方で、マイナンバーカードをかたった詐欺やセキュリティーへの不信感から取得に二の足を踏む人も多く、マイナンバー制度をかたって個人情報を不正に聞き出そうとする事例について内閣府のコールセンターなどに多くの相談が寄せられているという。自治体職員などを名乗り「マイナンバーカードの登録にお金がかかる」とか、「マイナンバーの暗証番号が漏れている。個人情報を守るためにキャッシュカードや通帳を回収して確認させてほしい」や、「マイナンバーカードと更新に必要な書類を預けてくれればマイナンバーカード更新の手続きを代理で行う」などと言って信用させ、個人情報を不正に取得したりお金を振り込ませたりする手口が多いという。 マイナンバーカードを取得する際の不安点として多くの人が挙げるのがセキュリティーに関する不信感だそうで、マイナンバーカードのICチップには署名用電子証明書や利用者証明用電子証明書といった電子証明書が標準搭載されており、署名用電子証明書は氏名・住所・生年月・性別が記載されたもので「e-Tax」の確定申告など電子文書の送信時に使うという。利用者証明用電子証明書はマイナポータルやコンビニ交付を利用する際に使用するもので、 これらの情報はマイナンバーカードと4桁の暗証番号の両方がそろって初めて使うことができることになっており、逆にいうとマイナンバーカードと4桁の暗証番号がそろえば本人以外でも情報を取得したり電子文書を送信したりできる可能性があるという。 セキュリティーを守るためにマイナンバーカードは確実に本人が作成し本人が受け取って保管することが大切なのだが、マイナンバーカードの申請に関する書類などは通常住民登録のある住所に送られてくるそうで、ストーカー被害やDVなどのやむを得ない理由で住民登録した住所に住んでおらず住所の変更もできない場合は、居所登録を行った居所地で受け取ることが可能だという。加害者が自治体の職員などの場合は届け出を出すことで避難先を知られないために被害者支援団体の事務所に送付してもらう方法もあるという。またカードを持たない人も保険診療を受けられるよう「資格確認書」を無料で発行する方針だが、有効期間は「1年を限度として各保険者が設定する」ことがわかったそうなのだ。 そしてマイナンバーカードの交付開始から10年を迎える2026年を視野に、政府が新しいカードの導入を検討しているという。現在のマイナンバーカードはカードの表面に顔写真や氏名・住所・性別・生年月日が記載されているが、こうした情報は内蔵されているICチップにも含まれているという。新しいマイナカードでは個人情報を見られたくないもしくは性別を載せたくないなどといった声にも配慮して、カードの表面にこうした情報を極力載せないことが検討されているそうで、18歳以上の場合「発行から10回目の誕生日まで」とされているカードの有効期限についても見直すことが想定されている。政府は現在のマイナカードの普及状況や関連法案の審議状況などを見極めたうえで本格的な検討に入る見通しだという。
2023年02月27日
コメント(0)
-
長寿県の食生活を見てみると・・・
厚生労働省は5年に一度都道府県ごとの平均寿命を調査しているのだが、昨年12月に2020年時点の調査結果が公表されており、都道府県トップは男性が滋賀県で女性が岡山県となり最下位は男女とも青森県だったという。過去との比較では1965年時点の全国平均は男性67.74歳の女性72.92歳だが、2020年の全国平均は男性81.49歳の女性87.60歳なので日本人は半世紀の間に13~14歳ほど寿命が延びたという。下位県は東北とその周辺の県が多くそれは現在も過去も同じだというが、男女総合で下位4県である青森県・福島県・秋田県・岩手県は1965年にも男女とも最下位グループだが、1965年と言えば東京五輪の翌年で団塊の世代が高校生だったし公害問題への関心が高まっていた時期だという。 上位についてみるとかつては大都市部の順位が明らかに高く1965年には東京が男女ともトップだったのに現在は男性が14位の女性が17位に落ち込んでいる。急速にランクを落としたのはバブル経済で東京一極集中が進んだ時期で7年前には男性20位の女性33位まで落ちたという。東京通勤圏のうち埼玉県はほぼ横ばいだが神奈川県・千葉県も順位をかなり低下させており、これは首都圏の急激な人口増加に医療体制の整備が追い付かず寿命が伸び悩んだ可能性が強いという。2020年の男女総合トップ5は滋賀県・長野県・京都府・奈良県・岡山県で大阪府が低迷しているのと対照的に関西圏が並んでいる。滋賀県と奈良県の長寿化は大阪府や京都府のベッドタウンとして総合病院が充実したからだという。 食生活について言えば驚いたことに長寿県の滋賀県は消費額ベースで肉類2位だけでなく牛肉3位の卵5位・コーヒー1位・パン4位・マーガリン7位など、かなり徹底的に洋風化された食生活となっている。日本食はヘルシーなイメージが強く健康的な食事として非常に好感触を持たれているのだが、実際に日本人の平均寿命は伸び続け世界有数の長寿国として知られていて、日本人が健康長寿である理由は欧米人と異なる特徴的な食生活に起因すると考えられていたという。ところが和食が健康的だとか発酵食品や大豆製品を摂ると長寿になると言われるのは西洋人が現状よりそちらに傾いたほうがいいということであって、日本人はむしろ逆なのではないかといわれており、国粋主義のような考え方をもちだすのはよろしくないという。 滋賀県が長寿であるもうひとつの要因は医療体制で、京都の大学出身の医師にとって近隣なので医局からの派遣先として歓迎される傾向があるほか、1974年の武村正義県政誕生時に医系技官トップの鎌田昭二郎ら京都大学医学部系の勢力が擁立の中心にあったことから、彼らの県政への発言力が強くそれが医療体制の充実に有利に働いたからだといわれている。長野県も地域医療体制に成功したと言われる県で、もともと全国有数の塩分摂取量が多い地域で冬の寒さも厳しく脳卒中による死者が多かったが、無医村への出張診療や「予防は治療に勝る」と自ら脚本を書いた演劇などによる啓発・衛生活動の推進に、健康診断のモデルとなった八千穂村での全村一斉健診などを行い健康長寿に寄与したという。 平均寿命ランキングで下位の県については東北勢が目立つが、「家計調査」で見ると酒類の消費額は青森県が1位だし福島県が7位に秋田県が5位の岩手県が6位と過度の飲酒が健康に悪いことを如実に表しているという。魚介類の消費額は青森県2位・福島県19位・秋田県4位・岩手県17位、納豆では青森県が9位・福島県が1位・秋田県が6位・岩手県が2位で、牛肉では青森県が41位・福島県が48位・秋田県が42位・岩手県が52位と、魚介類や納豆をよく食べ牛肉は控えめな県が平均寿命では下位にあるのは健康食志向の人にとっては都合の悪い事実となっている。生活習慣全般でも食生活でも過度の飲酒や栄養バランスに欠ける食事や無精な生活態度は男性において良い結果をもたらさないという。
2023年02月26日
コメント(0)
-
旅行業界も人手不足で・・・
政府の観光支援策「全国旅行支援」などで観光の需要が伸びる中でホテルや旅館の人手不足が深刻化しているというが、マンパワーでは回らず効率を高めるデジタル技術の導入が進んでいるという。JTBは基幹システムと自動精算機といったデジタルツールを連携させてチェックアウト業務などを省力化する新システムを開発しホテルや旅館に提供をスタートしており、宿泊業者はインバウンドの本格回復を見すえた採用・育成も急ぐが、低いといわれる業界の賃金水準が円安等でさらに目減りし外国人材の獲得に課題も出ているという。宿泊予約を断るケースが相次ぐなど機会損失は大きく、需要が回復しても機会損失で業績が上向かない宿泊施設は多いとされていて、このため打開に向けた取り組みが急務となっているという。 民間調査会社の帝国データバンクによると昨年10月時点で人手不足を感じる企業の割合は全国1万1632社のうち正社員で51・1%を占め、業種別では69・1%と最多だった「情報サービス」に次ぎ「旅館・ホテル」が65・4%となっている。非正社員は平均31%だが業種別では「飲食店」の76・3%に次いで「旅館・ホテル」が75%と高く、上昇幅は上位10業種で「旅館・ホテル」が最も大きかったという。業務の効率を上げるためJTBが昨年11月から本格展開を始めた新システムを試験導入していて、宿泊施設の基幹システムと自動チェックイン・精算機といったデジタルツールを連携し省力化につなげ、チェックアウトの精算のためフロントに人員を割く必要などがなくなるそうで、JTBは令和7年度までに施設への導入を目指すという。 そんな人手不足を感じるホテル業界の中で、限られた人手で生産性を最大限に高めることを追求するのは星野リゾートだとされ、全国の施設ごとに開く「魅力会議」では社員がアイデアを持ち寄り前回の反省点も踏まえて季節の催しなどを決めるという。それだけだはなく会議以外でも気づきがあればその場で議論が始まることもあるそうで、宿泊客用のパジャマのたたみ方からレストランの皿一つまで細かなことも現場の声で改善するという。そうすることで「少人数で回せたり、迅速な対応ができるようになったりしたことも多い」と唐沢総支配人は話すが、新型コロナ禍で不当な解雇や雇い止めをした企業もあり、社員をコストでなく人材として扱わなければ、持続可能なホテル経営はできないとの指摘もなされている。 観光庁が発表した宿泊旅行統計調査によればの宿泊者数は前年同月比38%増だし、こうした需要急増に人材確保が追いつかず本格回復が見込まれるインバウンドの受け入れ態勢を整えようと外国人材の獲得を急ぐホテルも増えているという。こうした状況の中で人手不足に悩む旅館・ホテル業界で外国人を活用しようという動きが出てきており、旅行最大手JTBグループの「JTB旅連事業」は特定技能人材を中心とした外国人人材のマッチングサービスを行う「トクティー」などと提携し、「JTB協定旅館ホテル連盟」に加盟する約3600施設の会員向けにサービスの説明を行うウェブセミナーなどを開催しているという。ただし外国人実習生の受け入れには手続きや研修が必要で来日には少なくとも半年ほどかかるという。 もっとも「円安進行により賃金が目減りし、日本で働く魅力が下がっている」ため優秀な外国人材を獲得するには賃上げや労働環境の改善が欠かせないというのだが、そうしたなかでも企業からは賃上げやむなしとの声が相次ぎ、「現状の資金繰りは厳しいが、人材確保のために賃金アップは仕方ない」などの意見があがっているという。早くも今年のキーワードとして重要視されている「賃上げ」は人材の獲得や定着に向けて避けては通れない要素となり得るが、活発化するであろう「賃上げの波」についていけず人手不足を解消できぬまま経営に行き詰るリスクは業界を問わず高まっており、これまで以上に懸念する必要があるとされている。そうしたなかでも何とかして賃上げを実施して人材の獲得・維持を図りたいという声は多いという。
2023年02月25日
コメント(0)
-
子供が「罰」といわれるようでは・・・
統一地方選を前にしてか各党が少子化対策としての子育て支援策の拡充を訴えているが、政策提案が矢継ぎ早に出てくるのは本当にありがたいことで、年明けに岸田首相が「異次元の少子化対策をやる」とぶち上げて以降、議論が沸騰している。岸田首相だけでなく与党幹部が発言するたびに子育て世代や若い世代の怒りを買っており、「国民生活白書」のタイトルが「少子社会の到来~その影響と対策」と名付けられて以降少子化という言葉は広がったという。それから30年余りにわたって数々の少子化対策と銘打った政策が試されてきたが、効果を上げているとは言えないそうで、場当たり的で小手先の対策が繰り返され本質的な問題が解決されていないからだが、その証拠が政治家の認識なのだという。 自民党が子育てや教育を家族や個人の責任に押し付けてきたかということだが、岸田首相の「異次元の少子化対策」後に最初に非難を浴びたのは、「少子化の一番大きな理由は出産する時の女性の年齢が高齢化しているから」という麻生太郎副総裁の発言だったそうなのだ。この男の放言にはもはや驚きもしないが、自民党の高齢重鎮政治家たちが繰り返してきたのも岸田首相は「年収の壁」の見直しにも言及し始めたからだという。パートなどで働く妻の年収が103万を超えると所得税が発生し、106万円および130万円を超えると扶養家族の対象外となり社会保険料の負担が生じることから、多くの女性がこの壁を超えないように就労時間を調整しているが、見直しを言い出したのは労働現場の「人手不足」の解消のためだといわれている。 少子化の原因を女性の社会進出や晩婚化のせいにするという発言は、シカゴ大学の山口和男教授が早くから「少子化の決定要因と対策について:夫の役割、職場の役割、政府の役割、社会の役割」という報告書で示して、急激な少子化の要因を女性の非婚化や晩婚化だけに帰することに警鐘を鳴らしており、女性の家事育児の負担が高く出産で離職した後の再就職が困難だという共通項があると指摘しているという。大企業を中心に育児休業制度や短時間勤務制度など両立支援制度は徐々に整備され仕事と子育ての両立はしやすくなったが、その制度を使っているのは誰かと言えば育休も時短勤務もほぼ女性たちで、日本で深刻にしているのが子育て中の女性は正社員としての再就職が難しいという問題だという。 家庭でも職場でも性別役割分業に晒され続け家事育児の負担に加えて仕事もという新たな重荷を背負うことになったそうで、育休から一度復職したものの両立のハードさに耐えかね職場ではやりがいを感じられないことから退職を選ぶ女性も少なくないという。そしていったん退職してしまうと再就職の際に正規雇用の道がほぼ閉ざされてしまう現実があって、仕事と子育ての両立支援策の充実が正規雇用の女性たちの出産を後押ししている一方で、幼児期の子どもを家庭で育てている世帯への支援が十分でないとされている。さらに正規雇用として収入・雇用の安定が「もう1人」という出産意欲の重要な要素になっていることも、ペナルティーの意味をもっと大きく捉えた「子育て罰」という言葉まで生まれているそうなのだ。 政策だけでなく社会や企業も「子育て罰」の拡大に貢献してきたとされており、企業は雇用や賃金・昇進などにおいて女性を差別してきたことで母親の就労は不安定化してしまい、背景にある「子育て罰」の正体は親・特に母親に育児やケアの責任を押し付け、父親の育児参加を許さず育費の責任も親だけに負わせてきた、日本社会のありようそのものだという。日本の子育てや教育に対する公的支援が主要先進国の中で少ないという指摘は少子化対策を論じる際に散々言われてきたことであるなのだが、その根本的な要因はそもそも子育ても教育も本来的には家族がするものであり、女性が家事育児をするものという性別役割分業意識が剝がれない澱のようにこびりついているという自民党を中心とした考え方だというのだ。
2023年02月24日
コメント(0)
-
70歳代になったら1日5000歩を・・・
自然の中を歩くことが精神面に良い効果をもたらすことも実験により明らかにされているが、自然の中を90分間歩いた人と都会の中を同じ時間歩いた人とを比べると、自然の中を歩いた人の方が精神疾患を引き起こす脳の領域の活動が抑えられることがわかったそうで、さらに自然の中を歩くと鎮痛・鎮静作用を持つエンドルフィンという脳内ホルモンの生成が促進され、精神状態が改善することもわかっているという。国立長寿医療センターの研究によると歩くことは高齢者の記憶力の向上にも役立ち、12週間毎日歩くように指示された高齢者のグループといつも通りの日常生活を過ごした高齢者のグループとでは、注意力やタスクの切り替え能力にワーキングメモリという必要な情報を一時的に記憶しておく能力が大幅に改善されたという。 ウォーキングは酸素を身体に取り入れながら行う有酸素運動で、ある研究によると週に3時間歩くことは全く運動しない場合に比べて早期死亡率が11%減少することがわかっており、また北海道大学の教授らが1,239人の男性を対象に行った研究では、1日1~2時間歩くことにより脳血管疾患やがんなどの重大な疾患を持つ人の死亡リスクが70%減少することも明らかになっているそうなのだ。歩数計を持って1万歩を目指す人も多いといわれているが、最も健康効果が高いのは1万5000歩だということがわかっていて、そのうえで毎日の習慣として無理なくウォーキングを続けることが大切だという。つまり一気に歩く必要はないので1日のあちこちで10分歩く時間を見つけて歩数をためていくのがよいそうなのだ。 身体活動の運動強度は低強度・中強度・高強度の3段階に分けられるそうで、健康寿命を延ばすためには強度が最適な運動強度とされていて、歩行でいうと低強度は家の中の移動や意識せずにだらだらとした歩行や洗濯や料理だけでなく掃除などの家事で、中強度は大股で地面を力強く蹴る歩行し、うっすらと汗ばむ程度の速歩きで会話が何とかできる程度の息が弾む歩行や山歩きや畑仕事などだという。高強度はきついと感じる運動や激しいトレーニングを指すのだが、中強度の歩行時間で予防できる可能性のある病気や病態の関係が報告されており、やみくもにただ歩数を多くすることが健康によいのではなく普段の買い物や通勤に犬の散歩などで行っている歩行を意識して行うことがおすすめだという。 そのウォーキングに関して歩くことで得られる長寿効果は、高齢者では1日5000~7000歩で頭打ちになるとの調査結果を早稲田大学の渡辺大輝助教らの研究チームがまとめたそうなのだが、1日1時間程度の歩行に該当するがこれが最適な長さという。この研究成果は米国の科学誌の電子版に掲載されたそうで、研究チームは京都府亀岡市の65歳以上の男女4165人を対象に、1日の歩数と死亡リスク増減の関連を調べたそうなのだ。最大約4年間追跡調査しその間に113人が亡くなってはいるが、その結果、5000歩未満の場合は1000歩増えると死亡リスクが23%低下しており、これは9~10カ月の寿命延長に当たるという。ただ5000~7000歩の人ではさらに歩数が増えても効果はなかったという。 心身機能が衰える「フレイル」が見られる場合には5000歩未満では歩数と死亡リスクの関連はほとんど見られなかったそうで、この5000歩を超えるとリスクが大きく減る上に7000歩を超えても歩いた分だけ減少しているという。調査では死因は分析しておらずフレイルの有無で差が出た理由は分からないというが、歩行などの身体活動は健康増進や寿命延長に役立つとされる日本人にとっての最適な歩数は不明だったという。1 日 30 分程度の歩行や日常生活における歩行レベルにおい、生活習慣病の予防や治療には有益であるという傾向や結果は得られているものと考えられるが、渡辺助教は「新型コロナウイルス流行で外出などが減った高齢者には、1日1時間程度歩くことを一つの目安にしてほしい」と話している。
2023年02月23日
コメント(0)
-
年収450万円家庭の実際は・・・
日本の平均年収が443万円と聞いてどんなイメージを抱くかといわれるが、「普通に暮らせてたまの贅沢もできる年収」と思えるだろうか、それとも「月々の支払いで手元に残るお金はゼロで貯金もできない」と思うのだろうかだが、年収450万円の場合に手取りはどのくらいになるかというと実は思ったよりもずっと少なくなってしまうというのだ。 20~40歳の場合で約350~365万円ほどになるそうで、ある本には平均年収前後の世帯6家族と平均年収以下の世帯5家族に取材した様子がルポ形式で掲載されており、例えば神奈川県に住む48歳の会社員で年収520万円だと娘さんと3人暮らしをする家庭の場合は、平均年収以上でも貧相な暮らしが現実で安心して子育てできる日本はどこへ行ってしまったのかという。 国税庁のホームページによると「1年間の給与所得者1人当たりの平均年収を男女別にみると、男性567万円、女性280万円」とのことだが、男性は女性の平均年収のちょうど2倍近くの水準になっていて、この年収450万という金額は30代後半~40代前半のサラリーマンの平均的な年収だという。世帯年収450万円台の割合は全体の5.0%で、およそ20世帯に1世帯が世帯年収450万円を得ている計算になるという。20代のうちは年収300万前後が多いというが、仕事で成果が出せるようになってくるキャリア層に入るとこの年収にのってくるという。あお家賃は年収の25%を目安にすると良いと言われており、30%という説もあるがこれは景気が良かった頃の話なので現代ではもう少し倹約されているそうなのだ。 また共働きの子どもを持たない夫婦の場合には、ここに至った経緯のひとつに「世帯年収を下げたくなかった」という気持ちが強くあったそうで、子育てによって女性の年収が下がることは目に見えていて、子どもが嫌いなわけではなく今の日本で女性が子を産み・育てたうえで、自分の仕事も変わらず年収もそのままで普通の家族を作ることはあまりに現実とかけ離れた理想像だと感じてしまったからだという。子どもを持たないという選択は老後も心配だし親にも悪いという気持ちもあると語ってはいるが、その夫婦が言うにはそれ以上に「自分たちの暮らし」が心配だったそうで、今の日本では「共働きで子育てして豊かに暮らすなんて夢で贅沢なこと。知らなかった、こんなはずじゃなかったと思ってからでは遅いのです」という。 思い描く日本での普通の暮らしは年収700万円でトントンだとされ、つまり平均年収443万円では普通の家族の暮らしはできないという。もちろん住むエリアや生活費によって同じ年収でも手元に残せるお金は変わるのだが、ちなみにこの会社員夫婦は「もし自分に病気が見つかったらいけないから、健康診断は受けていない」と話しているという。政府からは「人生100年時代」なんて言葉も出てきているが、「誰もが安心して暮らせる世の中って本当に作れるのだろうか」 と考えているという。さて「いくらあったら、満足できる暮らしができるの」というと、共働きで世帯年収1000万円あれば流石に余裕だということのようだが、しかし日本では子供が二人いて少し贅沢する生活ではまだまだ苦しいのが現実だという。 年収450万円といっても手元に450万円入るわけではなく、年収450万円の生活レベルは家族構成により異なり余裕資金ができたら将来につながるような使い方ができるよう意識するべきで、平均年収があっても多くは家計がギリギリ得体の知れない将来不安も抱え出費を抑えているとされ、これでは消費が落ち込み景気がよくならないのも当然だという。頑張った分だけ幸せになれ、お金持ちになれて望みが叶う、そんな日本はもうないのだという。暗い話が続くと「日本は終わった」と絶望してしまうのだが、この状況を多くの人が知ることが何より大切で、常に「なにか間違っている」とか「これはおかしいのだ」と思うことを忘れてはならず、そう思うことをやめ思考停止に陥ったとき「絶望的」という言葉から「的」の一文字が取れてしまうのだという。
2023年02月22日
コメント(0)
-
独居老人の4人に一人は・・・
よく言われてきた「高齢者は裕福だ」というイメージはもう間違いだそうで、「団塊の世代」を分水嶺として前後で状況は大きく変わるという。特に私のように1950年から1960年代前半に生まれた世代はバブル経済崩壊以降には国内外の経済危機の局面で減給されたり、リストラの対象となったりしたため老後資金を十分に蓄えられなかった人が多いそうなのだ。厚生労働省の「国民生活基礎調査」を見ると65歳以上の高齢者世帯の生活が年々苦しくなっていることがわかるそうで、生活意識について「大変苦しい」と「やや苦しい」の合計は30年位前には37.8%だったのに対して、25年前には46.1%に20年前には過半数の50.0%と上昇し続け、今から10年前には58.8%に達し過去最悪となっているという。 同じく厚生労働省の「国民年金被保険者実態調査」によると1940年代後半生まれの団塊の世代では年金未納・免除者率が30%程度であるのに対し、それ以降は1950年代前半生まれで35%前後となり1950年代後半生まれで45%前後の1960年代前半生まれでは40%台後半と上昇するという。保険料を納めていないのだから受給できる年金額はわずかでしかなく、年金受給額が最低生活費に満たないのであれば「生活苦」を感じるのは当然だという。未婚化と高齢化の進展により急激に増加する「ひとり暮らし高齢者」たちだが、今後もさらなる未婚者の増加が予想され加速度的に「独居老人」が増えていくものと予想されるという。ところが家族の養育をしない独居生活なら生活資金も潤沢なのかというと実情は少々異なるという。 高齢・未婚・貧困によって厳しい局面に立たされている人も少なからずいて、内閣府の「少子化社会対策白書」によれば50歳になった時点で一度も結婚をしたことがない人の割合である、生涯未婚率は男性が28.3%の女性は17.8%となっていて、なかには50歳を過ぎてから結婚する人もいるが極めて例外的で、したがってこの数値が「生涯独身」の割合と考えて差し支えないとされている。近年では個々考えが尊重されるようになり昭和時代のような結婚の圧力もないため、仕事や趣味に重きを置きあえて結婚を選ばない人も多いという。しかも高齢者のうち無年金や低年金は現役時代の低収入が原因だとされ、その象徴が非正規雇用者の増加で時代的背景から「独身高齢者」が増え続けているといわれている。 全国に700万人弱の独居高齢者がいるという事実なのだが、すべての方が生涯独身なわけではなく死別・離別を経て独居生活を送っている人もいるため、単純にひとくくりにはできないだろうが生涯独身だった場合はむしろ経済的なゆとりがなくなってきているという。高齢者の生活を支えるのは公的年金だが厚生労働省の調査によると、厚生年金受給者の平均受給額は14万円程度で年金のみでの生活には単身者でも心もとない金額であり、不足分をカバーする貯蓄が必要だという。「家計の金融行動に関する世論調査」によれば、「金融資産を保有していない」という人は60代で28.8%だし70代で25.1%もいるという。つまり単純に見るなら経済的に余裕のない単身の高齢者は、4人に1人以上にもなるというのだ。 金銭的な不安ばかりではなくさらにそこには誰しも避けられない「老い」の問題があって、年代別人口に占める要支援・要介護認定者の割合を見ると、70代後半は12.7%が要支援・要介護認定を受けているが、80代前半では26.4%だし85歳以上では59.8%と増加していくといわれている。逆算すると後期高齢者となった独居高齢者379万人のうち約130万人が要支援・要介護認定を受けているということになるという。ひとり暮らしの方が支援・介護を必要とする場合には事業者を頼ることになるだろうが事業者を頼れば当然費用が発生する。経済的に厳しい独居の高齢者の割合は4人に1人以上だとされると、そのような人には必要なサポートが受けられず社会からも孤立する「孤独死リスク」が懸念されているというのだ。
2023年02月21日
コメント(0)
-
冷凍食品の実態調査によると・・・
一般社団法人日本冷凍食品協会は冷凍食品の利用者を対象に「冷凍食品の利用状況実態調査」を実施しているが、スクリーニング調査によると冷凍食品を「ほとんど又はまったく使わない」という人は減少しており、新規利用者が増加しているが男女とも冷凍食品の利用頻度が1年前より「増えた」が3割近くで「減った」を大幅に上回っているという。冷凍食品の魅力として「おいしい」は女性が61.9%の男性57.1%で、女性は4年前より約17ポイント男性も8ポイント増加しているそうなのだ。コロナ禍において外食は「飲食店」・「居酒屋」など減ったが多数派だが、昼食の準備の利用で増加したものは男女とも「冷凍食品」が3人に1人だし、夕食でも「冷凍食品」の利用が増えたと回答した人が男女とも3割程度となっているそうなのだ。 日本政策金融公庫農林水産事業は「消費者動向調査」を実施しているのだが、特別調査として家庭での食の簡便化について調査しており、家庭での食に関する家事で最も簡便化したい工程は「献立の考案」が約3割と最も高く、次いで「調理」が約2割で「後片付け」の順となっているという。また年代が低くなるほど「献立の考案」を簡便化したいとする割合が高くなる傾 向となっているそうで、食の簡便化のために家庭で実践していることは「冷凍商品を活用」が最も高く、次いで「レトルト食品・缶詰・瓶詰を活用」に「品数・材 料を少なくする」の順となっているそうなのだ。全ての年代で「冷凍食品を活用」の回答割合が最も高く、家庭で最も購入量が多い冷凍食品は「そのまま食べられる調理食品」が最も高かったという。 冷凍・インスタント食品やスーパーやコンビニのお弁当・総菜等は身近な存在だが、子どもに食べさせた時に栄養の観点においてどのくらいの頻度であれば、子どもに食べさせてもいいのか等健康面での影響は気になるのではないという。便利な食品を日常生活でどう活用すればよいかとか、子どもの頃は成長に必要な鉄分やカルシウムといった栄養素を意識したいものだが、骨ごと食べられる魚の加工品はカルシウムが期待できるし、子どもに人気の冷凍グラタンなどに冷凍ホウレンソウを足すことだけでも鉄分を補強できるという。このように考えると「回数が多いからよくない」とは一概に言えなくなるが、大切なのは週に何回そういった食品を利用するかより年齢に合わせた栄養バランスと食事量が整っていることだという。 食品添加物の安全性は厚生労働省が厳しくチェックしているというのだが、習慣的に使用されてきたものや発がん性や奇形性などについて評価された食品添加物に限って使用を認め、成分に応じて使用基準を策定しているという。使用できる量は安全に使用できると確認された量よりも更に少ない量が設定されており、それほど神経をすり減らす必要はないという。ただ子供が3歳頃までは臓器が未発達であることから、油や塩が多いインスタント食品は避ける方が無難だという。食品添加物が使用される複雑な配合の食品では食物アレルギーが起こった際に原因がわかりづらくなることもあるのだが、低年齢の子供に食べさせる時にはできるだけシンプルな配合のものを選べると良いそうなのだ。 冷凍食品の手軽さから冷凍野菜を料理に取り入れるご家庭が増えているそうで、生鮮食品としての野菜と冷凍野菜では栄養面に違いがあるのかということだが、確かに冷凍野菜に加工する工程で元の生鮮の状態からは減少する栄養成分もあるが、しかしながらそもそもの生鮮野菜の栄養成分量にも個体差が存在しますので、加工による成分減少を気にしすぎる必要はないという。冷凍野菜は旬の時期に大量に収穫して加工するのが一般的なのだが、旬の時期は野菜の栄養価が高まっているため時期によっては生鮮食品を購入するよりも栄養価が高い可能性もあるという。そういった冷凍野菜を使ってメニューを1品増やせるのであれば、それにより食事バランスは向上するという。
2023年02月20日
コメント(0)
-
非正規労働者の春闘が熱いそうで・・・
春闘は労働条件の改善を巡る労使の交渉だが、名の知れた会社の賃金や一時金がどうなるかのニュースが流れ、主役は大企業とそこで働く労働者だと実感させられるという。企業ごとに組合がバラバラに賃上げなどを求めるのでなく、春闘を通して要求の水準や日程をそろえることで交渉力を高める狙いがある一方で、欧米では日本と違って産業ごとに労働組合が賃上げ交渉なども産業ごとに行うケースが多いため春闘は日本独特の取り組みといえる。ところが今回は少し状況が変わるかもしれないそうで、止まらない物価上昇で苦境に立たされる非正規雇用労働者を春闘の中心に据えようと労働組合の関係者が動き始めたからで、ヒントにしているのは昨年のクリスマスを前に繰り広げられたある労使交渉だったという。 「非正規春闘2023実行委員会」が記者会見を開き非正規労働者の春闘である「非正規春闘」の開始を宣言したが、春闘とは毎春に労働組合が一斉に賃上げ要求・交渉を行うものとされており、これまでは正社員中心の労働組合が春闘を行っていた。今年は激しいインフレの中で生活が脅かされている非正規雇用労働者たちが「非正規春闘」を始め、非正規雇用労働者の賃上げを訴え始めたそうで、すでにこの「非正規春闘」には16の個人加盟労組に所属する約300名の非正規雇用労働者が参加しており、33社に対して春闘交渉の申入れを行っているというのだ。「非正規春闘」の背景にはこの間の未曽有のインフレがあって、昨年末より物価高騰が激しくなっていたが今年に入り一段と厳しくなっているためだという。 物価高騰は光熱費や加工食品などで特に激しく、こうした必需品の物価高騰は低所得階層ほど影響が大きいとされるが、エンゲル係数に象徴されるように低所得階層の家計に占める食費あるいは光熱費といった必需品が占める割合は一般的な世帯と比較して高いからだという。今後さらに電気代や加工食品の値上げが予定されているためますます生活は苦しくなると予想されており、こうしたなか「非正規春闘2023実行委員会」は非正規雇用労働者235名に生活実感についてのアンケート調査を行っている。この調査によれば物価上昇のもとで生活費の高騰を感じると回答した人の割合は99%にもなり、「物価上昇によってあなたの生活は苦しくなりましたか」という問いに対しては9割を超える人が苦しくなったと回答しているという。 物価高騰の影響もあって今年の「春闘」は例年以上に注目されており、非正規雇用労働者の賃上げが必要だという議論も活発化してきているのだが、既存の「春闘」は正社員の賃上げが主題で今年も非正規雇用労働者の賃上げが十分に焦点化される見込みはなかった。そこで非正規雇用労働者を組織する全国各地の個人加盟労組が非正規雇用労働者の賃上げを実現するために、ナショナルセンターの枠を超えて「非正規春闘2023実行委員会」に結集し非正規春闘を始めている。これまでも大企業労組に組織されない中小企業の労働者や非正規労働者はこの「ユニオン」に個人加盟して労使交渉を行ってきた。いわばユニオンは大企業労組以外の労働者の「駆け込み寺」的な存在であるといえるそうなのだ。 その各地のユニオンが連携し新しい動きを連帯して起こしたことは非常に意義深いとされ、春闘交渉については現在のところ16の労働組合が33社へ賃上げを申し入れている。たしかに組合員数でみれば、300名程度と決して多くはないが、非正規春闘の影響を受けうる労働者の総数でみれば12万名程度にも膨れ上がり、かなり大きな規模の労働運動だということがわかるという。日本では主に女性を対象とした非正規差別制度がそのまま外国人にも適用されていると考えることができ、このように考えれば非正規女性と外国人がともに声を上げるということは非常に理にかなったことだという。つまり日本社会にあまりにも非正規雇用が拡大してきたことを反映して非常に多様な人たちが参加している労働運動だということなのだ。
2023年02月19日
コメント(0)
-
脳科学者が言うのには・・・
脳科学者の中野信子氏によると「孤独」とか「ひとり」に「待つ」という言葉はなんとなくネガティブにとらえられがちだが、視点を変えるだけでまったく違う見え方がするそうで、そんな柔軟な思考のできる脳は自分の苦しみを解放させてくれるかもしれないという。たとえば人を選ぶときに基準となる何かを一つ挙げろと言われたら、待つ楽しみを味わうことができる人かどうか、というのはかなり有力な候補となり得るそうで、見通しのよい道路で車も全然通っておらず人もおらずガラガラに空いていてそこでちゃんと信号を守っている人に、なぜ信号を守っているのか聞いてみるというのも一つの方法で、この人がただルールに従っているだけで思考停止しているというならひょっとしたら退屈を感じるかもしれないだけでなるという。 もしかしたら見えない場所でもルールを守ることを己に課すという好もしい人と映るかもしれないが、逆に信号待ちの時間だけでも待つことが苦痛で遠回りしてでも少しでも進んでいる感覚を味わいたいという変わった人もいるかもしれないというのだ。孤であることの弊害ばかりが取りざたされるが孤の楽しみというのは案外いいものなのだそうで、信号を待つ間にもこうした人間観察をするとそれはただボーッとしているだけの時を楽しいものに変えてくれるそうなのだ。赤信号を無視せずルールを守って横断歩道の前で立ち続けているだけでも、時間に追われて焦っているかまたはせっかちな人が赤信号を無視して何人も道路を渡っていく。それでもその人たちにつられて信号を無視することはしない。 気になってこの人が信号を待つ理由を聞いてみると、自分は、ズレを楽しむためにわざわざ赤信号に従ってみるのだという。この人にとって赤信号で止まるというのは盲目的にルールを守るという思考停止の所産ではなく運命を楽しむための能動的な選択で、自分は我慢しているわけではなくよりよい未来への選択を主体的にしてそうで、自分は損をしているのではないだから信号を無視する誰かを見て別に腹が立つことはない。日本は空気を読むことを求められる国で誰かといると常に圧力を掛けられてストレスが掛かってくる環境でもある。それゆえに意外に私と同じように感じて一人でいることの方を好んでそうしている人は多いのではないかと心ひそかに思っていて、一人でいることは最高のリラクゼーションだという。 極上の孤独は蜜の味がするそうで、何よりも誰にも邪魔されずにゆっくり勉強できる時間を満喫できるのだという。「絵を描き」・「音楽を楽しみ」・「楽器を練習」したりもできるだけでなく、心ゆくまで思索してこれまでの知識を再構築し、新しい現象の分析をしていくだけでも十分に楽しく満たされた時間を送ることができるという。かつてノーベル賞受賞者の中村修二氏が青色発光ダイオードの研究をはじめたとき最初はもの珍しさも手伝って人々が訪れたが、次第に誰も来なくなりついに一人で過ごす日々が常となったのだが、中村博士はこれをむしろ喜んだそうで研究室で一人静かに黙々と誰にも邪魔されずに自分のテーマを追求し続けられるという。悦楽を中村博士は存分に味わっただろうと思うが、「迷わない人は、信用できない」という 「ブレない人」・「他人の意見に左右されない人」というのは得てして称賛されがちだが、社会的存在である人間は他者の言葉を聞きながら何かを選択せざるを得ない生きものであり、迷うことこそがヒト脳が本来もつ高度で美しい機能だという。他人に認められたいということは社会集団の中で人は誰もが承認欲求と無縁ではいられないもので、無意識の情動に流されながらあいまいで不安な状態を嫌って自分を正義に置くことで他者を糾弾し安心を得たがるという。そして脳科学にもとづいてヒト脳の仕組みとはたらきをひもときながら、承認欲求と不安に行き過ぎた正義と他者へのポジティブ思考等の落とし穴など、私たちが無意識のうちに抱えこんでしまう深い闇とそれがもたらす現代社会の病理が解明されつつあるという。
2023年02月18日
コメント(0)
-
「下請けいじめ」をする大手企業は・・・
中小企業の賃上げに欠かせないのがコストの上昇を商品の値段に反映させる価格転嫁だとされているが、経済産業省は下請け企業との価格交渉でコスト上昇による転嫁に後ろ向きとされる企業を初めて実名で公表したそうで、経済産業省は中小企業の取引先として名前が多く上がった約150社がどれぐらい価格転嫁に応じているかを調査したという。その評価はコスト上昇分のすべてを転嫁したら「10点満点」とし、8割なら「8点」と転嫁の割合に応じて加点され逆に価格が下げられていれば「マイナス3点」となるとしており、中小企業の価格転嫁は政府が目指す物価上昇率を超える賃上げにも影響があることなどから、経済産業省は評価が良くなかった約30社を指導・助言し是正を促していくとしていつよしていた。 経済産業省が初めて公表したのは中小企業およそ1万5000社が回答したアンケートから大企業148社の価格交渉や価格転嫁への姿勢を点数化した実名リストで、調査結果によると価格転嫁と下請け企業の賃上げには相関関係があり、転嫁が進む企業ほど賃上げ率がアップするという。価格転嫁に応じたかの「転嫁状況」と交渉に応じたかの「交渉状況」を4段階で評価しているというが、昨年12月に実施されたアンケートの分析では価格転嫁ができていない「0割転嫁」の企業の平均賃上げ率は2.1%なのに対し、「5割転嫁」は2.7%で「全額転嫁」は3.9%とされ中小企業の値上げ要請に大企業は十分応えていないという。賃上げのためにも価格転嫁の重要性が高まっているとしているが「ない袖は振れない」のが現実だという。 このうち「交渉状況」で最低評価を受けたのは産業機械メーカーの不二越で、そして「転嫁状況」で最低だったのは全国におよそ2万4000ヵ所の郵便局を持つ日本郵便だという。日本郵便はただ一社「平均0割(価格据え置き)未満」の点数で、「費用が上昇している中、価格が減額された企業もありました」という。その日本郵便からゆうパックなどの配達を請け負っている配達業者は取材に対し取引の実態を「正直何年も請負代金の単価が上がっているわけじゃありません。やっぱりずっと不満には思っていました」と答えているが、この業者は人口密度の少ないところでも配達しているのだが、ここ6年ほどガソリン代や人件費の高騰などを理由に日本郵便に請負代金の引き上げを求めても応じてもらえていないという。 そして価格転嫁ができないため従業員の給料も上げられないともいい、そのため配達を請け負うドライバー不足に直面していると語っている。もっとも価格転嫁に応じなくても発注もとには責任がなく基本的には価格は自由に決められているのだが、民営化されたとはいえ公共性の高い「郵便局」のワーストワンは衝撃的だという。価格転嫁の状況で最低の「エ」だったのは日本郵便のみとされており、持ち株会社の増田寛也日本郵政社長は会見で「深刻な問題が内在しているのではないか」と語ったが、「ここまでの低レベルの得点ということは、深刻な問題がおそらく内在しているのではないか」として、郵便局ごとに価格交渉の状況が異なるとした上で傘下の日本郵便に実態調査を指示したことを明らかにしたそうなのだ。 この下請けいじめといえる企業の実名も公表する政府の強硬姿勢について専門家は「政府は下請けGメンをつくるなど、下請けに対するしわ寄せの解消にかなり本腰を入れ始めている。大規模調査の結果では中小企業のおよそ1割が発注元企業と価格交渉について『全く交渉ができていない』と回答し、そして2割程度が『全く価格転嫁できていない』と回答しているのだからかなり深刻」だと話している。中小企業がコスト増を価格転嫁できなければ賃上げを行うことは困難であり、そこで働く大多数の労働者はインフレから逃れることができないのだが、春闘が本格化するタイミングで公表したことは、公表により大企業が価格転嫁に前向きになり中小企業の賃上げにつながってほしいという政府の思惑だということのようなのだ。
2023年02月17日
コメント(0)
-
連合の会長が言う今年の春闘は・・・
中小企業は賃上げに苦戦しているそうで、商工中金が取引先の中小企業2284社に実施したアンケート調査によると、今年の賃上げ率は1.98%となる見込みだという。昨年実績は1.95%でほぼ横ばいにとどまりそうだというのだが、昨年の春闘はインフレ突入前で今年は消費者物価指数が前年比4%を超えており、商工中金の調査でもコスト上昇分の価格転嫁が順調な「鉄・非鉄」や「化学」では、賃上げを実施する割合は多く賃上げ率も高いという。一方で転嫁に苦戦中の「運輸業」・「印刷業」・「情報通信業」は「実施率」や「賃上げ率」ともに低いそうなのだ。賃上げ率1.98%では物価上昇率の半分にも及ばず実質賃金は大きく目減りしてしまうとされており、中小企業は昨年並みの賃上げが精いっぱいのようだという。 経済ジャーナリストは「コスト上昇分を価格転嫁できた企業は賃上げが可能でしょう。しかし、多くの中小企業は価格転嫁がうまくいっていません。賃上げに回す原資を十分に確保できず、今年は昨年よりも賃上げするのが難しい環境だといえます。昨年比横ばいの賃上げは頑張った方だと思います」という。価格転嫁がままならない中で昨年と横ばいの賃上げ率は中小企業経営者の苦労がにじみ出ていると言えるのだが、そんな中で連合の芳野友子会長から耳を疑う発言が飛び出したという。新聞のインタビューで「賃上げの流れを中小企業にいかに広げるか」との問いに「賃上げをしなければ企業は置いていかれるという雰囲気を作っていきたい」と語って、まるで賃上げに苦戦している中小企業を切り捨てるかのような発言をしたというのだ。 連合は長期的な組合員数の減少や組織率の低下に直面しており、発足時に800万人といわれた組合員数は2年前にはおよそ700万人まで減っており、連合以外の労組も含めた組織率は雇用者全体の17%にとどまっている。連合の組合員の3分の1は女性が占め非正規雇用も増えており、教職員ら公務員には働き方の改善が遅れているとの問題意識が強まっている。かつて「男性で正社員の組織」だった労組で変化が進み、経済成長率が低い状況で賃上げというわかりやすい成果は上げにくいというが、自民党政権が最低賃金の引き上げに動き連合のお株を奪われる場面も出てきており、ものづくり産業労働組合出身の会長はデジタル化を見据えながら多様な雇用形態の労働環境を整えるという新たな役割を探るのが急務だという。 物価高の中での春闘の意義を芳野連合会長は「中小企業がコストを取引価格に転嫁して賃上げを実現し消費に回すことや、デフレマインドの払拭が求められている。すごく期待され、どれだけの賃上げ幅を勝ち取れるかプレッシャーも少し感じている」としており、日本商工会議所の小林会頭と連合の芳野会長が意見交換を行なっている。それでも経団連がまとめた春闘の経営側の指針「経営労働政策特別委員会報告」では、連合の賃上げ要求水準が近年の実態と大きく乖離しているとしたという。そのうえで「踏み込みが足らず残念。経団連は企業行動を転換する正念場かつ絶好の機会としながら、過去の状況に言及する必要はなかった。ただ今回の経労委報告は全般的に前向きであり、経営者の対応に期待したい」と語っている。 また連合の芳野会長は労働所の権利であるストも構えるべきかという新聞紙者の問いに 「スト権をバックに交渉するのは労組の権利だが、スト権の確立が難しい職場環境になってきているのではないか。業績の見通しが立たない産業もあると思うが、今年は駄目でも来年は取り返すという気持ちで会社と交渉してほしい」と語ってという。女性や非正規雇用にかかわらず賃金が低いのは労働者の価値を下げられてしまっているのと同じで、教育訓練の機会が等しくあるかなどきめ細かい点検が必要だとしている。これから本格化する今年の春闘では大企業を中心に賃上げの動きが相次いでいるようだが、およそ7割の人が働く中小企業で賃上げが進むかが全体の賃上げ実現のカギとなるという。
2023年02月16日
コメント(0)
-
お祭りには欠かせないものとして・・・
新聞によると「東京都渋谷区の代々木公園で占用許可を都から得ている常設の屋台を警視庁が調べところ、全7店舗の出店者計7人について指定暴力団極東会系の関係者と分かったとして警視庁は東京都に連絡したそうで、これを受けて東京都は出店者に聞き取りし占用許可の取り消しを検討するという。7店舗のうち3店舗は現在営業していないが東京都による、都立公園で営業中の屋台に関し、暴力団の関与を理由とした占用許可の取り消しは極めて異例だ」という。同様の取り締まり強化が他所の地域に飛び火しないことを祈るばかりで、それはテキヤへの締め付けは誰にとっても益がなく、日本の原風景を継承してきた縁日の仕掛け人「テキヤ稼業」の陰にはその祭りを支える親分と若い衆の並々ならぬ苦労があるからだという。 ヤクザは人気商売だとされ地域密着型の「裏のサービス業」だといわれるが、テキヤは売る商品を持っていて顔が見えない商売ではなく、ひとつひとつの商品を対面で売って100円とか200円の利益で細々と商売している。だからテキヤは暴力団や博徒を指して「稼業違い」というそうなのだ。私の知り合いに労働基準監督署の元所長がいるのだが、テキヤは非合法なことは何もしておらず、強いていえば労働基準法に抵触する時間外労働くらいだったという。物を売るという実体のある商売でしかカネを儲けないし、恐れるのは暴対法ではなく食品衛生法で保健所に頭が上がらないという。代々木公園の常設屋台摘発は暴力団排除における当局の本気度とテキヤの肩身の狭さを象徴する出来事だったという。 神農であるテキヤは祀神がヤクザと違いテキヤは自らを神農と名乗るとともに、テキヤの業界を神農会と呼ぶ。この神農とは「古代中国の伝説的な人とも神ともつかない存在で中国の古典「淮南子」などに出てきて頭に角がある姿で描かれている。テキヤの間では良薬になる植物を発見するために自らの命の危険を冒してさまざまな植物を毒見した神とされており、現在でもテキヤの一部が神農を崇めるのは彼らの系譜につながる古い時代のテキヤが薬草を商っていた名残とされている。テキヤの盃事の儀式には中国神話の農業の神である「神農」と中国の伝説の帝王で医学の祖とされる「黄帝」の「神農黄帝」の軸を掲げるが、ヤクザの場合は「天照大神」を中央に掲げ「八幡神」と「春日大社」を左右に掲げるという。 近頃ではテキヤの規制が厳しくなり跡を継ぐ若い者が減ったりして親分不在の庭場が出てきたそうで、そうなると庭場の番人をするのはわれらが公務員であるお巡りさんにお鉢がまわってくるそうなのだ。お巡りさんもナカナカやるものでちゃんとテイタを割ってくれるそうなのだが、この警察によるテイタ割りのことを業界では「ヒネ割り」と呼ぶそうなのだが、テイタを割ったあとの保守点検までは手が回らないので、礼儀知らずの業腹な人間が出てきたとしてもそのケツを所轄署に持ち込んだところでどうにもならないという。そして屋台から食中毒が出たといって警察署長が謝罪するなという図は想像できないのでやった者勝ちになってしまうという。テキヤにとって客からのクレームは組の看板ひいては親分の顔に泥を塗ることになるというのだ。 またテキヤとヤクザの違いでは縁組の盃をはじめとする盃事については、テキヤ自身のものとテキヤが助っ人に呼ばれる場合があるそうで、前者はテキヤの代目披露や兄弟盃等の儀式であるに対して、後者はテキヤがヤクザに依頼されて媒酌人を務める盃事だという。テキヤ自体も盃事は稼業上欠かすことができないがヤクザは尚更で、盛大にやるのが代目披露で当代の親分から次の親分候補に代を授受する跡目公式発表の式だという。こうした神事は古式に則って行われるが格式張っているから作法通りにできる人間がそこらには居ないのでテキヤの出番となるという。テキヤは寺社仏閣に馴染みがあってそうした修行が行き届いているから、ヤクザの盃事があると媒酌人として白羽の矢が立てられるそうなのだ。
2023年02月15日
コメント(0)
-
高速道路を定額料金にすると・・・
日本の高速道路料金は1kmあたり約24.6円であり、これは世界水準に比べて非常に高額だといわれているが、世界の多くの国々では日本の半額以下で高速道路を利用できるという。韓国の高速道路1kmあたりの料金は10円程度の100ウォン前後だし、中国も1円くらいの0.5元でアジアでも日本とはずいぶんと大きな差があるという。続いてヨーロッパはというと、アウトストラーダの名称で呼ばれるイタリアの高速道路は0.07ユーロと同じく約9円だし、イタリア南部の14%ほどの高速道路は地域振興等の目的で無料になっている。高速道路をオートルートと呼ぶフランスは0.1ユーロの約13円とやや高めではあるものの、無料の高速道路が国中を走っているためそれほど不便はないという。 そして速度制限がないアウトバーンがあるドイツやモーターウェイと呼ばれるイギリスは原則無料だし、フリーウェイがあるアメリカは州によって異なるものの無料でカナダやシンガポールも高速道路が無料の国だという。それに対して日本は道路によって多少の増減や割引があるものの1kmあたり24.6円だけでなく、初乗り料金に相当するターミナルチャージの150円が追加されたうえさらに消費税がかかるというのだ。高速道路の建設には膨大な費用がかかるためあらかじめ道路建設費用の借り入れを行い、利用者から料金徴収し借金を返済する形で維持運営されるのが一般的となっているからだという。高速道路料金が無料の国々は道路の建設や維持を国費で賄っているため無料で高速道路が利用できるという。 高速道路が無料のドイツとイギリスは租税負担が高い国として有名であり、高速道路の建設・維持管理費も税金で賄われている。日本は山が多いため高速道路を通すためにトンネルや橋梁工事が多くなるし、また地震も多いために耐震性を高めなければならず他国に比べてどうしても建設維持費用が高くなりがちだという。そのしわ寄せが世界一高額な高速道路料金として利用者にのしかかっているのだが、日本の高速道路料金が高いのはこういった事情があるというのだ。日本の高速道路建設当初は建設時の借入金が返済されれば無料にできるものと見込まれていた。また返済を国費でまかなえば高速道路の無料化や料金値下げも可能だというのだが、高速道路利用における受益者負担原則に反することになるという。 政府は「2115年まで高速道路の無料化は先送りする」という法律案を成立させる予定だが、ジャーナリストの小川匡則氏は「日本の高速道路料金は世界一高い。やるべきことは無料化の先送りではなく、高すぎる通行料をいますぐ引き下げることだろう」という。政府は「道路整備特別措置法及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部を改正する法律案」という法案を閣議決定し国会に提出する予定で、要するには「2115年まで現在の世界一高い高速道路料金を維持する」ことを決めるという驚くべき内容の法案なのだという。国土交通省はこの法案を提出する主な理由として「平成26年度からの点検強化により、重大損傷の発見が相次いでいる」と説明し、大規模な修繕が各地で必要になっていることを挙げている。 高速道路の基本的な考え方は「ユーザーが応能負担し、かかった費用を返済できたら無料にする」というものだが、高速道路は最初に莫大な費用をかけて建設されその費用を高速道路料金として徴収し返済に充てていく。その仕組みは道路を維持していくためには一定の補修などランニングコストも必要になるが、現在は料金収入のうち2割程度がランニングコストで8割程度が償還に充てられている。今は距離料金を念頭にしたさまざまな割引制度があるが、車種別に適切な定額料金設定することが必要だという。高速道路を気軽に利用できれば国内旅行ももっと加速することは「土・日上限1000円」とした社会実験からも明らかだし、通勤圏も拡大するため地方の活性化につながることも期待できるというのだ。
2023年02月14日
コメント(0)
-
高額な賃金は天敵だとされており・・・
アベノミクスが始まった2013年以降は法人企業の従業員1人当たり付加価値が順調に増加したとされるが、とりわけ規模の大きな企業でこの傾向は顕著だったという。しかしこの間に賃金はほとんど上がっておらず増加した付加価値はほとんど企業の利益に回されてしまい、なぜこのような現象が起きているのだろうかというと、それは大企業で非正規従業者が増えているからだという。つまり「1人当たり付加価値が増えても賃金が上がらない」というこのメカニズムがいまの日本経済で最大の問題で、「格差と貧困」に「富の偏在」・「巨大資本のあまりにも圧倒的な巨大さ」これらのことに人々が不可思議さを覚え恐れを感じ憤懣を募らせているという。そしてこの時代状況に「21世紀の資本」の主張と提言が大いに響いているというのだ。 フランスの経済学者のトマ・ピケティの著作「21世紀の資本」では富裕層の不労所得の増大と集中が経済格差の拡大をもたらすメカニズムを解明しているが、グローバル化の進展とともに、富の偏在が一段と進んでいると指摘し、この分配上の歪みを是正するための方策としてピケティは国際的な資本課税の導入を提唱している。今日このテーマは国々の国際課税論議の中で大きな位置を占めていのだが、トマ・ピケティの「21世紀の資本」は決して読みやすい本ではないにもかかわらず、世界でまた日本で人々がこの著作に群がったという。その有様はさながらアダム・スミスの「国富論」の刊行時のようだったというが、アダム・スミスが1776年に「国富論」を刊行したことによって経済学という学問ジャンルが確立したのだ。 ピケティ本について最も評価されているのが「21世紀の資本」というタイトルの本だが、20世紀最後の10年から始まったグローバル化の中でヒトもモノもカネも従来にはなかったスケールで国境を越えるようになった。中でも凄まじい規模と速度で国境を越えるようになったのが「カネ」すなわち「資本」であるとされている。資本主義経済というもののカラクリをカール・マルクスが「資本論」で見抜いた頃には、資本はまだ今日のような動き方はしてはいなかったという。資本主義的生産体制というものは国民国家あるいは国民経済の仕組みが基本的に堅固な中で成り立っていたとされるが、今日の資本は「資本論」が執筆された時のようには動いていないといわれているが、労働に対する搾取の基本原理が崩れたわけではないという。 「資本論」の中でマルクスが当時の工場現場の実態を描出し、そこで行われている「剰余価値創出」のカラクリを解明してくれる時に語られていることは、まるで今日の労働現場に関するルポルタージュのようであるとされている。ただし現在では「資本論」当時の工場現場とは比べるべくもなく多様で広範な職場で、当時とは比べるべくもないあの手この手で人々から余剰価値を吸い取っているという。こうなってくると資本と対峙する関係にある労働についてもその21世紀的有り方を追求する研究や分析が展開される必要があるのだが、労働者が一定量の労働に携わることはそれに見合って自分の自由と安楽と幸福を犠牲にすることを意味しているとされており、これが労働犠牲説の労働犠牲説と言われるゆえんだという。 ニュースなどで「日本の賃金は20年以上横ばいである」と解説付きで紹介されているが、米国やカナダ・ドイツ・韓国などは右肩上がりに賃金が上昇している中、日本は20年以上「昇給ゼロ」とは悲しいものなのだが、それどころか実は日本のサラリーマンの収入は「手取りベース」で見ると横ばいどころか下がり続けているという。さらに厳しい現実があって「本質的に怠け者である労働者たちをしっかり働かせるためには、賃金は低くなければダメだ」と考えていた重商主義者たちにとって、高賃金はあらゆる意味で天敵だったというのだ。少なくとも日本に関する限りかれこれ30年間にわたって賃金低迷状態が続いているのだが、この「日本の賃金低迷は、21世紀の資本による21世紀の重商主義」の表れだと言えるかもしれないという。
2023年02月13日
コメント(0)
-
暗い年代が迫ってきており・・・
日本が直面するさまざまな問題として少子化・インフレ対策・賃上げ等さまざまな問題に待ったなしの状況なのだが、回避しようと努力すればできるものもあれば回避不可能というものもあるという。そのひとつの大問題といえるのが高齢化問題で、残り2年とカウントダウンが始まってきている「2025年問題」はひとつのターニングポイントとして、社会のさまざまな分野に大きな影響を及ぼすと予想されている。そもそも「2025年問題」とは日本人の人口のボリュームゾーンのひとつである「団塊の世代」の800万人全員が75歳以上の後期高齢者になるというもので、団塊の世代は第二次世界大戦直後の1947年~1949年の第1次ベビーブームに生まれ、日本の高度成長を牽引してきた人たちだといわれてきたのだ。 「団塊の世代」全員75歳以上になることで1億2,000万人ほどの日本人のうち実に2,180万人もの人が後期高齢者に達するのだが、厚生労働省の「今後の高齢化の進展 ~2025年の超高齢社会像」ではこの「2025年問題」の大きく5つの問題点を指摘しており、「2025年問題」の社会的影響の一つが医療費や介護費の増大とそれに伴う現役世代の負担の増大だという。厚生労働省の「医療費の動向」によると後期高齢者の一人当たりの年間医療費は、1人あたりの医療費は75歳未満で23万5,000円だが、それに対し75歳以上だと93万9,000円でおよそ4倍にもなっており、介護費も後期高齢者は大きく膨れ上がるという。その医療費を現役世代が中心となり支えてきたのですが今度は支えられる側になるというのだ。 これまで社会を支えてきた世代が今度は支えられる側に回ることによって、年金なども含めた社会保障給付費全体を予算ベースで見ると、2018年の約121兆円から2025年度には約140~141兆円になると推計されているという。2025年問題の対策として政府は「全世代型社会保障検討会議」を設置し年金・労働・医療・介護など各分野における改革のため議論を進めているそうだが、その医療・介護・年金を合わせたサラリーマンの保険料率は2025年度には31%に増えると見込まれており、年金については一部法改正をして厚生年金の加入条件緩和を検討しており、パートなどの短時間労働者が厚生年金に加入しやすくなるほか「就職氷河期」世代の非正規雇用者の低年金対策になることも期待されているという。 現役世代の負担をいかに軽減するかも大きな課題でどれほどの負担増になるかは明らかで、そこにきて「異次元の少子化対策」の財源は各保険料から拠出するという案が最有力とされているというのだ。厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」によると日本人の平均給与は30.74万円で手取りにすると24万~25万円ほどだが、この負担増に現役世代は耐えられるのかが問題だという。また「介護」の問題では日本の平均寿命は男性81.47歳の女性87.57歳となっているのだが、「日常生活に支障なく暮らせている」という健康寿命は女性75.38歳の男性72.68歳だという。つまり男性の介護期間は9年に女性の介護期間は12年と想定されており、問題は介護を必要としている人を「誰が介護するのか」ということだという。 「老老介護」の問題である夫婦の場合は男女の年齢差は平均2~3歳で、そして平均寿命の男女差を考えると「年老いた妻が年老いた夫を介護する」というケースが相当数にのぼり、その数は2025年を境に急激に増えていくと考えられている。介護を理由に離職する人は毎年7万~10万人ほどで推移しているのだが、その数も今後急激に増えていくと指摘する専門家も多くいて、2025年に起こる大問題とそれ以降の日本の社会はあまりに悲惨であることが想定されており、必ず起こる未来に対していままで以上に財政がひっ迫することが予想されるので国に期待するのは難しいという。自助努力しかないといえるのだが、賃金がなかなか上がらないなか税金を払い保険料を払いそれでも「将来の面倒は自分で」というのが現実なのだという。
2023年02月12日
コメント(0)
-
高速道路の深夜割引が改悪されると・・・
運送業界はトラックドライバーの働き方改革施行によって来年度から大きく状況が変わるといわれているが、その変容を見ると「ドライバーの負担軽減のため」と謳いながら、なぜかドライバーの首をむしろ締めにいっているような改案が多いという。高速道路料金についてトラックドライバーは「現行は0時から4時まで、1秒でも高速道路に乗っていたら、それまで走っていた高速代を含めて3割引になる」と話し、「安いがゆえに、サービスエリアで時間をつぶし長時間労働になるケースや、駐車場が埋まっていることで路肩に止める車両が出た」と明かしている。そんな運送業に携わる人たちの間では高速道路にまつわる大混乱が起きており、その元凶は国土交通省が発表した「高速道路における深夜割引の見直し」の内容だという。 この高速道路の深夜割引は車両の種類に関係なく深夜0時から4時に高速道路を利用した車に適用される割引制度だが、国土交通省の資料を見ると現在この制度を最も利用しているのはトラックドライバーたちだという。一見この深夜割引は「トラックドライバーにやさしい制度」と思われがちだが、24時間止まることのない物流を第一線で支える彼らドライバーや「働き方改革」の対応を迫られる運送企業にとって深夜割引の見直しは、ここ10年もの間の願いとなっていたといわれている。その大きな理由はこの深夜割引が「ドライバーの長時間労働」と「サービスエリア・パーキングエリアの駐車マス不足」の原因になっていて、深夜の高速道路の料金所ゲート前周辺では割引を適用しようとするドライバーの「0時待ち」が発生するからだという。 そのため各都道府県トラック協会や一部の運送事業者からはトラックドライバーの労働上のルールに存在している「8時間の休息」を守りながら深夜割引を利用できるようにするため、「適用時間を22時~5時にしてほしい」との要望が出されていたという。また現場からは根強く「終日割引」の適用をことあるごとに国土交通省に訴えてきたという。こうした各方面の現場からの強い要望に対し国土交通省が今回出した見直しは、そのどちらでもない「22時~5時に走った距離のみの割引適用」という現場の現状をより悪化させる改悪以外の何ものでもないものだったという。これは国が「高速代を安く抑えたいなら夜に走れ」と言っているようなもので、現場にはどのような影響があるかというと、確実に発生するのが「高速料金負担の増加」だという。 次に考えられるのが「ドライバーの生活の昼夜逆転」で、これまで多くの長距離トラックドライバーは深夜に「サービスエリア・パーキングエリアで停まり、法律で定められている時間とされる8時間以上の休息を取るか、深夜割引を適用するために0時00分01秒に高速を出て朝一番の仕事先である荷主周辺付近で休息を取っていたという。しかしそれが「22時~5時の間、走った分だけの割引適用」となれば、運賃を抑えるべく深夜に走り昼に休もうとするドライバーが急増する恐れがあるという。人間は基本的に夜になると眠くなるのだが、ましてやそれまでと昼夜逆転する生活に変えようとすれば体に大きな負担がかかり、睡眠も仕事のうちであるトラックドライバーにとっては事故を起こす原因にもなりかねないという。 働き方改革による労働時間の短縮もそのひとつなのだが、国や識者は労働時間短縮ばかり躍起になっているが、なぜか「運賃」や「賃金」の保障の話がなされないといわれてきた。その中でこの高速道路の深夜割引の見直しによる実質的な大幅値上げまで始まれば、高速代を負担しているトラックドライバーたちの賃金水準はさらに低下する恐れもあるという。高速代を実質上げるならば荷主に「高速代込み」の運賃形態をやめさせ実運送の運送企業やトラックドライバーに高速代を負担させない仕組みや規則をつくるのは国の役割だという。やはり運転手の言うとおり、サービスエリアや路側帯渋滞や労働環境の改善が求められるトラックは深夜割引を止め終日通行料金を値下げするというのが一番良い対応だという。
2023年02月11日
コメント(0)
-
5類に分類されるからといっても・・・
私の住む愛媛県でも感染者数が減少していて少し下火となってきた新型コロナウイルス感染病なのだが、「ウィズコロナ」に舵を切ったことから改めてひとりひとりが感染を軽く考えず、周りにうつさないよう心がけることが重要となりそうだという。そのような中で政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身茂会長は東京都内で大手新聞社のインタビューに応じ、新型コロナの感染症法上の位置づけを今年の5月に現在の2類相当から季節性インフルエンザと同じ5類に引き下げることについて「もうそろそろ社会経済活動を再開していく時期に来ている」と言及したという。焦点のマスク着用に関しては重症化リスクの高い高齢者や基礎疾患のある人が乗り合わせる電車などでは「当分、マスクを続けた方がいい」と指摘している。 尾身会長は5類移行後の医療提供体制を巡り「地域での連携が重要になってくる」と強調し、高齢者施設などでの感染者集団発生時に支援に当たる医療機関を事前に定める必要性などを訴えたという。政府は3月上旬をめどに医療費の自己負担などについて具体的な方針を示す方針だが、尾身会長は「自己負担を急にやれば混乱を生みかねないので、少しずつ段階的にやった方がいい」と述べたという。尾身会長は3年間の新型コロナ対応を振り返って最も緊張した場面として、令和3年夏の東京五輪・パラリンピックを挙げ、専門家の有志は「無観客が望ましい」とする提言を発表した経緯があってとしたうえで、「専門家として言うべきことを言わないと歴史の審判に耐えられないと思った」と語ったそうなのだ。 また日本の人口当たりの死者数が海外と比べて少なかった理由として、国民の感染対策への協力や保健所や医療機関の努力などを挙げたそうなのだが、「季節性インフルエンザ」などと同じ5類に移行するのに合わせてコロナ対策のさまざまな変更が決まりつつあるという。厚生労働省の専門家による部会では、新年度になることし4月以降の接種のあり方についての基本方針がまとまってきているそうで、まずまずワクチンの接種対象として、第1の対象を「高齢者など重症化リスクが高い人」としており、そのうえで「それ以外の全ての世代に対して接種の機会を確保することが望ましい」としている。感染拡大や変異株の状況などを踏まえ重症化リスクの高い人に頻繁に接する人にも追加して接種を行う必要性にも留意するとしているという。 次に接種時期としては、これまで年末年始に比較的多くの死者を伴う感染拡大があったことなどから「秋から冬に次の接種を行うべき」だとしており、そして接種の費用に関してはまん延を予防するため緊急の必要があるとして今は無料で行われている期限は今年の3月末までとなっているのだが、これについて4月以降も必要な接種は無料とし来月にも方針を決定する見通しだという。新型コロナウイルスのワクチンは感染や発症を防ぐ効果については変異ウイルスが広がった結果長く続かなくなってきている一方で、重症化や死亡を防ぐ効果は維持されていると考えられており、65歳以上に対する重症化や死亡を防ぐ効果を分析した結果として、比較的長い期間維持される傾向が見られているという。 マスクについても卒業式シーズンを前に厚生労働省の専門家会合のメンバーが見解をまとめているのだが、卒業式など学校での式典について「新型コロナの流行が落ち着いた状況では参列者がマスクを着用しなくてもよいとする対応も考えられる」としている。ただし5類移行でマスクを外すかどうかは人それぞれで日本がコロナ以前のようなマスクのない社会に戻るにはまだまだ時間がかかりそうだという。それよりも5類に移行すれば患者にとって大きな問題はこれまで無料だった検査や治療の費用が一部自己負担になるという。そして政府が5類移行を急ぐ背景には5月の広島サミットをノーマスクで開催したいという思惑があるからで、日本だけいまだにコロナ禍にとりのこされているというイメージを世界中に拡散したくないからだというのだ。
2023年02月10日
コメント(0)
-
リタイヤ後は公的年金だけで生活できる
定年後は現役時代より生活費が減るとしても「公的年金だけでまかなえるのか」と心配する人もいる人が多いというが、しかしこれはあまりむずかしいことではないそうで、公的年金の受給額に合わせたライフスタイルにすればよいだけのことだという。実際に厚生労働省の「国民生活基礎調査」のデータによると、公的年金を受給している世帯の約半数にあたる48.4%の人が公的年金のみで暮らしているという。家計の支出を減らすというとまっさきに「節約」ということが頭に浮かぶかもしれないのだが、節約というのはふだんの食費や光熱費を切りつめて生活費を浮かせる方法だといわれていて、ほしいものがあっても我慢するといったニュアンスもあるともいうのだが、こういった節約は面倒なうえにそれほどの効果は期待できないという。 「定年を迎えて、これから好きなことができる」というときに生活を切りつめるとかやりたいことを我慢するというのでは、これまでなんのために働いてきたのかわからないのだが、これからの人生はケチケチ生きる必要はなく、それよりも家計の無駄を徹底的になくしたほうが支出を減らす効果は絶大だという。もともと無駄で必要のないものを減らすわけなので暮らしへの影響はなくストレスもほとんど感じないという。まずいちばんに見直すべきは「保険」だそうで、60歳を過ぎて子どもが独立したならば生命保険はほぼいらなくなるという。生命保険がなくても遺族年金という制度によって配偶者の生活はある程度守ることができるし、医療保険も同様に見直しできるそうで、日本には公的医療保険という社会保険制度があるからだという。 医療費の自己負担は収入に応じて1~3割負担に抑えられており、この1~3割の負担も高額になった場合は「高額療養費制度」という費用の軽減制度により、一定額以上は支払わなくて済むという。85~89歳の医療費は105.6万円かかっているのだが、実際に払う自己負担額はわずか8.3万円だし、公的医療保険の保険料は所得に応じて変わるため収入が減少する高齢期には保険料もかなり安くなるという。年を取るほど保険料が高くなる民間の医療保険とは真逆のしくみだという。ただし入院したときの食事や個室の差額ベッド代は健康保険が使えないということには、それは貯蓄があればまかなえるので退職金や貯蓄などのまとまったお金を確保しておけば負担の大きい保険は全部解約しても問題ないという。 保険以外にも数々の無駄が家計にはひそんでいるそうで、なんとなく習慣でやめられなくなっている新聞や雑誌の定期購読も本当に必要かどうか考えてみるべきで、これらを見直しただけでも月に1万~3万円くらいの無駄は減らせるとされるという。老後のお金の管理は「年金の範囲内に日常生活費を収める」と、「医療や介護に備えて退職金または貯蓄は取り崩さない」という2つのことを守るだけで、あとのお金はどう使っても自由だという。とくに60歳以降に働いて稼いだお金は楽しみに使うための収入なので大いに好きなことに使うべきだという。また老後は「義理・見栄・恥」のためにお金を使うのはNGで、「義理欠く・見栄欠く・恥欠く」の「サンカク」を実践するべきで、リタイア後は義理や見栄にお金をかける必要はないという。 定年まで勤め上げた人であれば好きなことにお金を使い、やりたいことをやって90歳ぐらいまでに財産を使い切ってしまってもなんの心配もないそうで、日本ではそれでもお金に困ることなく暮らすのはむずかしくないというのだ。なぜなら生きているかぎり公的年金が支給されるからなのだが、90歳にもなれば今よりずっと生活費も減るため年金があれば死ぬまで安泰で生活ができるという。もちろん施設入居費ぐらいは最後まで手をつけないほうがいいというが、まずは「話すより聞く・威張るより笑う」が60代からの生き方だという。そして「逆らわず いつもニコニコ 従わず」これを実践していたら嫌われることはないし自分を見失うこともないという。人から嫌われたら孤独になるだけなので60代からは好かれることが大事だという。
2023年02月09日
コメント(0)
-
朝で大切なことは・・・
私の子供がそうなのだが「起きてすぐは食べられない」という声をよく聞くが、たしかに起きた瞬間に「お腹が空いた」とはなりにくいもので、胃もまだ動きはじめていないので食欲がわかないということも多いという。朝食抜きの人が多い背景にはそんなこともあるのだそうで、医師が「いまより30分早く起きる」ことを提唱する理由の1つはまさにそこにあって、30分の間に家の窓を開けて回ったり新聞を取りに階段を使って歩いたりすれば、それだけ体を動かすのでお腹も空き胃腸も動き出すような気がする。起き抜けには無理でもひと仕事したあとなら食欲もわくというもので、朝食は本来「一日を元気に活動するエネルギーを補給する」ためのものなので、朝食は「軽く」するのがベストだという。 とりわけ「小食」と呼ばれるお寺さんの朝食は、水っぽいお粥とゴマ塩に透けるほど薄く切ったお漬物くらいのもので、あまりにも量が少ないことも手伝って修行僧たちは食べ終わるのを惜しむようによく嚙むようになるという。そのよく嚙むということが健康にはとてもいいそうで、朝の効用でいえば嚙むごとに脳が刺激されていい感じで脳が活動モードに入り、だんだん頭がクリアになっていく感覚が得られるという。また嚙む回数が増えるにつれ徐々に空腹感が消えていき満腹感が広がっていくそうで、あまり嚙まないと脳が刺激されないうえに食べるスピードが速すぎて脳が満腹を認識するのが遅れという。食べ終わったあとで、「ああ、食べすぎた」と後悔することが多い人はとくによく嚙んでゆっくり食べることを心がけるべきだという。 現代においては夜でも街は明るくパソコンやスマートフォンのブルーライトの光を一日中浴び続けているため、昼夜のメリハリがない不規則な生活を送りがちだとされるが、不規則な生活はリラックスと緊張状態を切替える自律神経の調節などを担う体内リズムを狂わせてしまうそうなので、不眠症などの体の不調を引き起こしてしまいます。片時もスマホを手放せない人が増えているようです。それがクセなのか、習慣なのかうという。起きるとすぐに枕元のスマホを手に取り何かしらの操作をはじめる、そんな具合なのだが、「朝は忙しない」とバタバタしているのにスマホをいじる時間はあるのかとなんとも不思議な感じがするという。そしてスマートフォンとの付き合い方を改善することで睡眠のリズムが整い質の向上が見込まれるようになるという。 朝食に限らず食事全般でいえることだが「食べながら、スマホをいじっている」人のなんと多いことがもんだだというが、「スマホをいじりながら、食べている」感すらあり、そんなふうにして食事からスマホに意識が奪われると自分が何を食べているのかもわからなくなるという。また食物を嚙むことも疎かになり消化によくないことだという。禅では「喫茶喫飯」といって「お茶を飲むときはお茶と1つになり切って味わうし、ご飯を食べるときはご飯と1つになり切って味わう」ことの大切さを説いているそうなのだが、つまり「食事のときは食事に集中して、おいしさを味わいなさい」ということだという。逆にスマホを操作するなら「それだけに集中しなさい」ということで、このように禅は基本的に「ながら行動」を戒めているそうなのだ。 いまはやりの「朝活」とは朝から目的をもって活動することだというが、なんとなく軽い気持ちで始めると早起きへのモチベーションを高めることができず長続きしないという。そのため「朝活」によってどんな自分になりたいかポジティブな目標を決め、今日一日がどんな日になるかは誰もわからなくても深く考えないことだという。もちろんスケジュールがあるので日によってはワクワクしたり気分が重くなったりさまざまなのだろうが、家を出るときの気分というのはその日待ち受けている仕事に左右される部分が大きいとされていて、だからこそ「今日はいい一日になる」と声を出て確信し、明るさで向かう先を照らすように元気な一歩を踏み出すことが大切なのだという。とくに負の予測をするのはやめてとにかく気分を明るくするべきだという。
2023年02月08日
コメント(0)
-
敗れると中央銀行の信用が・・・
日銀の黒田総裁は衆議院予算委員会で日銀の保有国債の含み損の額が実に約8兆8000億円だと明かしたそうで、昨年9月末時点で8749億円のマイナスと16年半ぶりに含み損が発生したというのに、たった3カ月で約10倍に拡大したという。その主な要因は金利上昇のあおりなのだが、日銀は長期金利を抑制するイールドカーブ・コントロール政策の下で国債を購入しているが、昨年12月に容認する長期金利の上限を0.5%に引き上げたことで国債市場の金利が上昇し、債券価格は下落して含み損が一気に膨らんだという。日銀は国債を時価評価しておらず含み損が発生しても黒田総裁は「中央銀行や金融政策への信認が失われることはない」と強調して、今年1月以降も日銀は損得抜きで国債を爆買いしているという。 日・米・欧の中央銀行は近年市場と戦う存在となりつつあるといわれており、株や長期国債などのリスク資産を「下落局面で買って反発局面で売り抜ける」ヘッジファンドのようなことをやっているという。最初にそれを始めたのは米国の中央銀行である連邦準備制度理事会で、続いて欧州中央銀行そして日本銀行がリスク資産を買って勝負するようになっているという。中央銀行が市場と戦って敗北すると大きな問題が起こるそうで、買い付けたリスク資産が下落すると中央銀行の財務が痛み、保有資産が急落して巨額の含み損が発生し中央銀行が債務超過になったら大変なことになるというのだ。最悪の場合には中央銀行が発行する通貨の信用が失墜し国家全体の信用が損なわれることも考えられるという。 政策決定会合が近づくにつれ政策の追加修正への思惑から長期金利が0.5%を超え、日銀は指定した利回りで国債を無制限に買う「指し値オペ」を連発しているが、先月の国債購入額は23兆6902億円と月間で過去最大となり、専門家も「採算度外視で買いまくれば、足元の含み損は10兆円を超えているに違いない。今後も金利の低下要因は皆無に等しく、含み損は拡大の一途です。いくら時価評価しなくとも、日銀の純資産は4.4兆円ほど。それを大幅に上回る含み損を抱えた財務状況は決して健全とは言えません」という。黒田総裁の任期終了まで残り2カ月余りなのに、弊害だらけのイールドカーブ・コントロール政策を手じまいにするどころか政策決定会合では「共通担保オペ」を拡充し、金融緩和維持に固執する構えだという。 連邦準備制度理事会はリーマン・ショックで急落した金融株を大量に買い付けて急反発したところで売り抜けており、欧州中央銀行も欧州債務危機で急落した国債を大量に買い付けてその後の反発につなげている。ファンドマネージャーに例えるならば、連邦準備制度理事会も欧州中央銀行も市場と戦って勝ち続けてきた最強のファンドマネージャーだという。ところが日銀はそうではないみたいで、日銀は株や長期国債を大量に買い付けて市場と戦い続けてきたのに、戦いに敗れて債務超過に陥る危機にさらされているというのだ。日銀は市場と戦いながら巨額の日本株上場投資信託を買い付けてきたという。そして一時的に含み損を抱えたこともあったのだが最終的には市場に勝ち巨額の含み益を得ていたそうなのだ。 ところが長期国債の買い付けで大失敗をしてしまっているようで、日銀は利回りゼロ近くで巨額の長期国債を買い付けて、500兆円を超える残高を保有しているという。最近の長期国債の利回りが一時0.5%まで上昇したことで保有国債に巨額の含み損を抱えることになったという。日銀は金利の上昇を抑えようと幅広い年限の長期国債を大量に購入していて、先月の買い入れ額が23兆6902億円となったことがわかったそうなのだが、日銀は国債について満期での保有を前提とした会計処理を行っているため、「財務の健全性」について国会で問われた黒田総裁は「評価損が拡大しても影響はない」と答弁している。 その一方で「財務の健全性にも留意しつつ適切な政策運営に努める」としているという。
2023年02月07日
コメント(0)
-
子育ての費用は高齢者の負担で・・・
日本の政治はこれまで若者が選挙に行かないから若い世代向けの政策は「票にならない」と軽視されており、人口が多く投票率も高い高齢世代向けの政策は「票になる」から力を入れるといわれていた。どうやら今年からはそれが変わりそうだということのようで、高齢者の年金は目減りし社会保障費の負担は増える一方なのだが、年金が目減りする中で少しでも収入を得るために働く高齢者が増えていて生活に不安を募らせているという。とても未来の子供たちのためならと思えるような精神的な余裕はなくなっているそうで、そこに追い打ちをかけるように子育て支援を名目に増税までされるという。少子化対策の受益者は子育て世代で負担者は高齢者になるが高齢者世帯の家計にはそんな余裕はないのが現実だという。 国の少子化関連予算は年約6兆1000億円といわれているのだが、政府の言うように倍増させるというなら新たに6兆円ものカネが必要になり、その財源として浮上しているのが「子育て連帯基金」だという。この「子育て連帯基金」は年金・医療保険・介護保険という「高齢者3経費」の財源の一部を使って児童手当の基金をつくる構想で、高齢者への老後の給付を減らして児童手当として配ろうというわかりやすい政策だという。例えば75歳以上が加入する後期高齢者医療制度は昨年10月から年金など一定の収入がある人が病院や薬局で支払う窓口負担は1割から2割へと2倍に引き上げられたばかりだが、来年からはさらに保険料の上限が現在の66万円から80万円へと段階的に引き上げられるというのだ。 この保険料値上げは政府が「こども家庭庁」発足に合わせた目玉政策に打ち出した「出産育児一時金」の約10万円引き上げの財源にあてるためだが、年金制度の仕組みは若い世代が保険料を負担し高齢者が年金を受給する「世代間の仕送りの仕組み」となっている。現役世代の負担を減らすために支給額がどんどん実質減額されており、そのうえ医療保険制度ではなしくずしに高齢世代の負担を増やし資金を子育て費用に回し、「子育て連帯基金」で高齢者の財源をさらに奪おうとしているというのだ。子育て連帯基金構想を見ても政府が高齢者のための財源を少子化に回そうと考えているのは明らかで、政府は「子ども支援」と言えば高齢者だってかわいい孫の姿を思い起こし孫のためなら負担は仕方ないなと思うはずだというのだ。 また消費税率が引き上げられれば最も生活が苦しくなるのは年金生活者に他ならないが、高齢者の方が物価高は深刻だという。今年度年度の年金支給額は3年ぶりに増えるというが、年金増加局面に伸び率を抑えるマクロ経済スライドが発動され、引き上げ幅は.6%圧縮され、年金を受給している68歳以上は前年比1.9%アップにとどまり昨年の物価上昇率2.5%に及ばないという。さらに高齢者世帯の物価上昇率が全体の平均より高いことが私的されており、総務省の発表によると世帯主が65歳以上の世帯の22年の物価上昇率は2.9%で、年金支給のベースとなっている率の2.5%よりも高くなっていという。これは高齢者世帯が今の物価高騰を牽引している食料や光熱・水道費の割合が大きいからだという。 高齢者は教育や教養・娯楽への出費が少ない分食料の割合が高くなるそうなのだが、高齢者は家にいる時間が長く現役世代より光熱・水道費がかかってしまうという。東京都区部の消費者物価指数は上昇率が4.3%だったのだが、高齢者世帯の物価上昇率は足元で5%に迫っていてもおかしくないのに、年金のアップ率1.9%の年金では物価上昇の半分にも満たないといわれていてこれでは暮らしが成り立たないという。エネルギー・食品中心のインフレ負担は高齢者ほど酷なので高齢者が直面する実情に即した年金支給を求めても、政府は支え手である現役世代の負担や年金財政への影響などを挙げ対策はしないという。高齢者は少子化対策の責任を負わされ子育て増税で負担を強いられようとしているというのだ。
2023年02月06日
コメント(0)
-
建設業の人手不足は深刻で・・・
日本が人口減少社会にあることは誰もが知る常識だが、企業や政府・地方自治体といった行政機関の「仕事の現場」に起きることを正しく理解している日本人は少ないという。コロナ過にウクライナ戦争が加わって世界経済は混沌としていて、エネルギー等の価格高騰は各国を襲い日本も記録的な物価高となって押し寄せてきている。こうした経済動向の変化に伴う景気の浮き沈みは繰り返し起きるが大概は時間が解決してくれるものなのだが、日本はその時間では何ともならない課題が人口減少だという。結婚や妊娠・出産に対する人々の価値観の変化がもたらした構造上の問題であるため将来にわたってずっと続くとされていて、人口減少が社会に与えるインパクトは桁違いに大きく繰り返し起きる経済危機や不況とは比べようもないという。 いまさら少子化対策を強化しても出生数の回復は簡単には見込めないが、子供を産むことのできる年齢の女性数が激減していくためで、このため外国人労働者の大規模な受け入れを打開策として挙げる声もあるが日本の勤労世代は20年後には1400万人ほど減るが、その全てを外国人労働者で補おうというのはどだい無理だという。外国人労働者に対する需要は日本以外の国々でも大きくなっており、既に介護職など専門性の高い職種は他国に競り負けるケースが報告されている。もはや日本は就業者が減ることを前提として解決策を考えざるを得ないということなのだが、人口減少がビジネスに与える影響といえばマーケットの縮小や人手不足だとされていて、マーケットの縮小とは単に総人口が減るだけの話ではないという。 今後の日本は実人数が減る以上に消費量が落ち込む「ダブルの縮小」に見舞われ、人口は少子高齢化しながら減っていくためだが、国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば65歳以上の高齢者数だけは2042年まで増え続けるという。総人口に占める高齢者の割合である高齢化率は2050年代には38%程度にまで上昇し、少子化に伴う人手不足はやがて年功序列や終身雇用といった日本特有の労働慣行を終わらせるといわれている。年功序列は定年などで退職する人数と同等かそれ以上の採用が安定的に続くことを前提としているからだが、まずすべき、人口減少がもたらす弊害を正しく知ることで、各産業はそれぞれ独自の課題も抱えるが人口減少が主な産業や仕事にもたらす影響がでてくるという。 私の所属していた建設業なのだが、国土交通省によれば建物や建築物の生産高である建設投資は1992年度の約84兆円がピークで、一昨年度は58兆4000億円とされピーク時より30.5%減っているという。人口減少が進むと需要が現行水準を維持することは考えづらいが、一方で建設業の場合には政府投資の拡大が見込まれるという。社会インフラの多くが高度経済成長期以降に整備されていて老朽化が目立つため更新が喫緊の課題となっているからだというのだ。例えば全国に約72万カ所ある道路橋梁の場合は、建設後50年を経過する施設の割合が今の27%から7年後には52%へと跳ね上がるし、トンネルや港湾岸壁・水門といった河川管理施設なども大規模に手を入れなければならない時期を迎えているという。 建設業への人口減少の影響は他業種とは異なり就業者の減少という形で色濃く表れるといわれていて、総務省の人口推計によれば昨年における20歳男性人口は59万9000人で、女性を含めても116万9000人とされ各業種による「若者争奪戦」は激化の一途だという。これに対して国土交通省は対案を示していて、建設現場の生産性を年間1%向上させることで16万人分の人手を確保したのと同じ効果が得られると試算し、新規学卒者を1万5000人採用して外国人労働者を約3万5000人受け入れれば対応できるという。それでも全体の25.7%を占める60歳以上の技能労働者の大半が今後10年で引退すると熟練した技術も消えていくとされており、現在の人手不足は同時に技能の継承といった将来的な懸念を内在しているという。
2023年02月05日
コメント(0)
-
またもや年金を食い物にする輩が・・・
国民年金加入者への上乗せを目的とする全国国民年金基金で、年金を所管する厚生労働省や旧社会保険庁の後継組織・日本年金機構からの事実上の天下りが継続している疑いがあることが、雑誌の入手した内部資料で明らかになったという。その舞台となっているのは「全国国民年金基金」だそうなのだが、年金官僚たちの天下りはこれまでも問題になっていたのだ。10年位前に投資顧問が約2000億円の年金資産を消失させた事件で、委託元の厚生年金基金に天下った旧社会保険庁OBが顧客拡大に関与していたにもかかわらず、約8割の63基金に厚生労働省や旧社保庁が再就職していた事が判明したというのだ。再発防止のため公募での採用を徹底するようしていたというが天下りは形を変えて続いていたという。 「全国国民年金基金」の役員名簿を調べると理事長と常勤理事は金融機関出身者だが、常務理事は元厚生労働省東北厚生局長であり、非常勤理事のうち7人が年金機構か厚生労働OBだそうで、さらに今回は公開されていない全国41支部支部長のリストや人事情報の内部資料まで雑誌社は入手しているという。それらの資料に記載されている情報を照合すると支部全体の約7割にあたる29の支部長が日本年金機構や厚生労働省に在籍していたそうで、「多くが年金事務所長を務めた後、その地域の年金基金支部長に就任しています。年金機構は退職者のうち管理職しか氏名を公表しないので実態はもっと多い。基金の正職員は220人ほどですが、50人以上が厚労省や年金機構からの天下りと見られます」としている。 全国国民年金基金の前身である旧国民年金基金が役員だけでなく一般職員も公募採用を徹底するよう求められたのは13年前で、当時の厚労相として天下りの根絶を求めていた長妻昭氏は「公募を隠れ蓑にした天下りになっている可能性がある」としている。この天下り問題について年金基金と厚労省年金局は「役員、一般職員すべてについて公募をし、書類選考、一次面接、二次面接の上採用しており、問題ないと考えています。全国国民年金基金は、もともとの年金の知見や管理業務の経験を有する即戦力を求めています。日本年金機構のOBは経験が豊富なため、結果として多くなっているのは事実です。年金事務所長から支部長となっているように見えますが、事前に採用が決まっている事はありえません」 という。 そればかりか全国国民年金基金とは別の47都道府県にある社会保険協会でもでも、まったく同じスキームで天下りが行われていることがわかったという。社保協は厚生年金や健康保険の普及を目的とし、戦後しばらくして厚生省認可の公益法人として各都道府県に設立されていったというのだが、1952年にはその上部組織として全国社会保険協会連合会も設立されているという。これらの団体は過去に無駄遣いや天下りなどの問題が指摘されてきたいわくつきの団体だそうで、その社保協にいまだ多くの年金官僚の天下りが続いていたというのだ。社保協は地元の企業から従業員数に応じて、3000円~50000円程の年会費をとって年金相談や人間ドッグにレジャー施設の割引などの福利厚生サービスを提供しているという。 企業は加入をお願いされると断わりにくく「第二の年金掛け金」と揶揄されているそうで、各都道府県にある社保協の常勤理事47人の経歴を調査したところ、半数を超える25人が日本年金機構OBであることがわかったという。社会保険協会も職員数が少なく即戦力を求める結果厚生労働省等のOBが就職しているというが、民間からの人員登用や委託も叶わない団体や職種は言い訳をしつつ天下りが成り立っているそうなのだ。節税とするなら同じ公務なので嘱託扱いとなり、民間同様に再雇用扱いとなって条件が下がるのが普通なのだが、ほとんど変わらない条件や社会的地位の維持がなされているという。またも発覚した年金官僚の天下り問題だが、公募を隠れ蓑にした天下りが今も続いている疑いもあって論議を呼びそうだという。
2023年02月04日
コメント(0)
-
斜面崩壊の責任はというと・・・
神奈川県逗子市池子で3年前にマンション敷地斜面が崩落し、当時の県立高校3年の女子生徒が死亡した事故で、斜面に適切な調査を行わず危険なまま放置されたなどとして、遺族が近く神奈川県を相手に損害賠償を求めて横浜地裁に提訴することという。事故が起きたのは3年前の2月5日の午前8時で、神奈川県逗子市の住宅地にある道路脇の斜面が突然崩落しおよそ66トンの土砂が一気に崩れ落ち、下の歩道を歩いていた18歳の女子高校生の命を奪ったのだが、都内に遊びに行く途中で起きた悲劇だったという。崩れた斜面は「土砂災害警戒区域」に指定されていたそうなのだが、逗子市によると事故当時は喫緊の対策を講じなければならない場所という認識はなかったという。 ただ崩落の前日に斜面の上に建つマンションの管理人が長さおよそ4メートルで幅およそ1センチの亀裂を見つけ管理会社に報告しており、その日のうちに管理会社から神奈川県の土木事務所などに連絡があったという。ただし「土砂災害特別警戒区域の指定に向けた調査日程を教えてほしい」といった内容にとどまり亀裂については具体的に報告されなかったという。神奈川県の担当者は「できることは限られ、非常に難しかったと思うが、危険だと判断できていたら市道を管理する逗子市に情報を提供して通行止めにするなど、対応を取れた可能性もある」としていた。崩れた斜面の所有者は区分所有者であるマンションの住人たちで、マンションの敷地に斜面が含まれていることは知っていたもののまさか崩れるとは思わなかったという。 これまで斜面崩壊の被害に行政はどう対応してきたのかというと、逗子市では相次いだ土砂崩れを受けて市内の斜面およそ1万か所を調査し対策を進めようとしたそうなのだが、ある問題に直面したそうで、それは「民有地」の壁だったという。崩落の危険がある斜面や崖のほとんどが個人や企業などが所有していたそうで、行政としては所有者の同意なしに対策を進めることはできないため、所有者に対しなにか対策を取るよう促す手紙を送ることしかできないのが実情だったという。所有者の崩落のリスクについてでは、別の斜面のある家の土地を相続した際に高さ17メートルの崖が敷地に含まれていることを初めて知った人によると、その崖は風化が進んでいたため何らかの対策が必要と考え神奈川県の対策事業に応募したという。 しかし当時の神奈川県の回答は「工事までは7~8年程度かかる」というもので、対策工事は行われず年月だけが経過しているという。それもあって遺族側は「二度と同じ事故を起こさないため既に提訴し)斜面所有者や管理会社などだけでなく、県も含めて責任の所在を明らかにしたい」と訴えている。代理人弁護士などによると斜面はマンション住民らが所有し、高さは約16メートルだが、この斜面は1968年ごろできたとみられマンション建設前の地質調査で風化による強度低下や「落石防護工など対策が望ましい」と指摘されていたという。事故後に行われた国の報告書でも「崩落箇所は表土が両脇斜面より薄く、風化防止作用が不十分だった」とされことから、遺族側は「斜面は長年手付かずで放置された」としている。 斜面の崩落により下層地の建物や通行人に損害を及ぼした場合には誰がその損害賠償責任を負うのかなのだが、多くの場合はその斜面の部分所有者だそうで、ちなみに「土地の境界がはっきりしないため斜面部分の所有者がどちらか分からない」というケースの場合は、基本的には上側の人の所有とされることが多いという。自然の状態の斜面やがけが崩落した場合はどうかというと、民法717条は土地そのものの問題の場合には適用できないため、一般原則に戻り所有者・占有者ともに管理に過失がある場合に限り責任を負うことになるという。また行政側でも斜面の崩落に対してさまざまな対策を行っているというのだが、斜面やがけに関する法令の規制は正直言って非常に分かりにくいため行政の責任は問われにくいという。
2023年02月03日
コメント(0)
-
賃金は上げられないのが実情のようで・・・
経団連は春闘に向けた経営側の指針となる報告書を発表しているのだが、去年に十倉会長が就任してから初めてとなる今回の報告書は「ヒト」が最も重要な経営資源だと位置づけ、「賃金の引き上げ」と「人への投資」を強く呼びかけているのが大きな特徴だといわれている。「安い日本」というのは最近よく耳にする言葉でイヤな響きなのだが、いろいろな視点からいろいろな話があるとされてはいるという。その中でも特に注目されているのが「低賃金」ではないかというのだが、約30年にわたって賃金が上がっていないとされかなり注目されているようなのだ。政府からも通常の賃上げでなく大きめの賃上げを求める発言があるといわれているが、これから春闘の企業側の回答がでてくるようだがあまり期待はできないという。 経営側は長年にわたって人件費を「コスト」とみなしいかに減らすかに力を入れており、連合は年齢や勤務年数に応じた「定期昇給分」と基本給を引き上げる「ベースアップ」をあわせて4%程度の賃金引き上げを求めている。去年の要求と同じ水準だが働く側の切実さは増してきており、エネルギーや原材料などの価格が上がっていることそして円安の流れを受けて国内でも物価が上がっているからだという。企業の業績にも回復が見られ運輸や飲食などコロナの影響で依然厳しい業績の企業もあるが、世界的な経済回復そして国内の消費にも回復傾向がみられることから、全体として上場企業の今年度の業績は過去最高益となる勢いだという。しかも企業が抱える現金・預金も321兆円と一段と積み上がっているという。 いくら政府が望んでも簡単には賃金は上がらないそうで、多少は上がるが限定的で理由は単純で上げた賃金は下げられないからだという。「利益を還元しろ」という主張をよく耳にするが利益があれば賃上げしてよさそうなのだが、赤字のときに賃下げできないならそうもいかないという。労働契約は「契約」で「額」は契約内容で賃上げも賃下げも契約の変更にあたり、契約の変更は労使合意が原則となっているからだという。事業所が一方的に賃上げしても従業員が反対しないから契約変更が成立するが、しかし賃下げは従業員の合意を得ることが難しくなかなか成立しないという。成立するとしても従業員のモチベーションへの影響なども考えると将来賃下げしなくてよい範囲でしか賃上げもできないという話になってしまうのだという。 賃上げには企業の稼ぐ力を増す必要があるのだが、そのためには人への投資が大きなカギを握るという考えを示しているのだが、具体的には事業の見直しや効率化に必要なデジタルや環境などの技術や知識について、非正規社員を含めた社員が学ぶだけでなく能力・意欲を高めることができるよう企業主導で研修や勉強会に大学との連携など様々なプログラムを提供することが必要だという。外で自主的に学びたいという社員を支援するために柔軟な勤務制度や休暇の拡充、副業の推進など多様な働き方を整えることや、職を失った人を含め希望する多くの人が成長する分野でより高い賃金を得ることができるよう国や自治体と連携して、企業が求める技術や知識を職業訓練に反映させるよう見直していくことが大事だという。 経営者の本音としては良い人材を適正な賃金で報いたいと本気で考えているというが、今後にも期待したいから投資として可能な範囲で賃上げを検討するという。同時に新規採用時の競争力にも気を使っており、できるだけ高い賃金を提示して求人したいということなのだが、ここで「法律の示唆」との関連でどのあたりに結論を置くかが経営判断だという。厳しく難しい判断だし正解がわかないといわれるが、さらにどのように判断しても全従業員の納得は得られないという。そして多くの中小企業経営者にとっては孤独な判断でもあり、今のまま何も変わらないのなら事業所にとって大幅な賃上げはある種の博打のようなものなのだという。つまり中小企業にとっては安心して「人への投資」ができる法律的な環境の整備が必要だという。
2023年02月02日
コメント(0)
-
「あきらめ廃業」というのがあって・・・
休廃業・解散は政府系・民間金融機関による活発な資金供給やコロナ対応の補助金により経営体力に乏しい中小企業の休廃業発生を大きく抑制し、去年1年間に県内で休業や廃業・解散した企業数が3年連続で減少したという。信用調査会社「帝国データバンク」によると昨年に県内で休廃業した企業は前年より41社少ない504社で、コロナ過を受けての金融機関の支援などで3年連続となり減少したそうなのだ。 一方で休廃業した企業のうち、直前の業績が「黒字」だったのは43.6%とこれまでで最も低くなっており、帝国データバンクは今年の見通しについて「先行きが不透明な中、多くの企業で融資の返済がスタートするとみられ、体力があるうちに会社をたたむ「あきらめ廃業」の増加が懸念される」と分析しているという。 全国で休業・廃業や解散を行った企業は前年から約1300件減少の5万3426件を数えたとされているが、昨年初頭から3.66%の企業が休廃業で市場から退出・消滅したそうなのだ。また一昨年に続き3年連続で減少しコロナ前からも約6000件少ない低水準で推移したという。休廃業による影響では企業の雇用である正社員が少なくとも累計8万2千人に及び前年から約3600人分増加しているという。全ての雇用機会が消失したものではないが企業の休廃業で8万人超が転退職を迫られた計算となるそうで、そればかりか消失した売上高は合計2兆3677億円に上ったそうなのだ。しかも資産が負債を上回るなど現状の財務内容に問題がない企業で「あきらめ休廃業」選択の動きもみられるという。 企業倒産では「ゼロゼロ融資」をはじめとした緊急避難的な借入金などの猶予期間中に業績回復や筋肉質な経営体質への転換が遅れ、事業の先行きが見通せず事業継続を断念した中小企業のケースが多かったという。休廃業ではこうした良好な資金調達環境に加え金融機関をはじめ官民一体の伴走支援策によって休廃業へと傾きつつあった経営マインドに「待った」を掛けたことが、建設業だけでなく多くの業種での休廃業・解散の発生を抑制した主な要因とみられている。しかし今年からは約半数の企業で資金繰りを支えたコロナ融資の返済がスタートを迎えることだけでなく、ロシアのウクライナ侵攻を発端とした原料や燃料価格の高騰が経営を圧迫するなど経営環境は一層厳しさを増しているという。 業種別では全7業種で前年同期を下回っているが、なかでもトラック輸送など運輸・通信業は前年同期比25.8%の急減となったほか、小売業やサービス業でも2ケタの大幅減少となっているそうなのだ。小売業では引き続き飲食店が減少傾向で推移しているほか、サービス業でもリーマン・ショック後以来のハイペースだったホテル・旅館が、一昨年から一転して減少しているそうなのだ。一方で私の所属していた建設業と不動産業は前年同期からともに減少したものの減少幅が非常に小さ、ほぼ横ばいで推移しているそうで、建設業では内装工事や土木工事など、不動産では土地賃貸業などでそれぞれ増加傾向が目立っており、今後業種全体でも底打ちから増加に転じる可能性があるとの予想がなされているという。 それでも帝国データバンクが3年前の11月末にまとめた「後継者不在率」動向調査によると、事業承継の実態について分析可能な約26.6万社のうち全体の65%に当たる約17万社で後継者が不在であることがわかったそうなのだ。業種別にみると建設業の後継者不在率がもっとも高く70.5%だったそうで、建設業の後継者不在率が70%台となるのは6年連続で3年前の調査では全業種で唯一の70%台となっていたという。長引くコロナ禍に加え原材料価格やエネルギー価格の高騰に人手確保のため、人件費増などにより収益面・財務面にダメージを受けた企業の休廃業割合が高まっているが、財務内容やキャッシュなどある程度の経営余力を残している企業でも「あきらめ休廃業」の機運が高まっている可能性があるという。
2023年02月01日
コメント(0)
全28件 (28件中 1-28件目)
1