2016年06月の記事
全27件 (27件中 1-27件目)
1
-

東京は水不足
首都圏の水がめ危機 暖冬と少雨、貯水率は平年の半分首都圏の水がめが危機的な状況に陥りそうだ。暖冬による雪不足で、利根川水系のダムの貯水率は平年の半分近くまで落ち込んでいる。梅雨に入ってもダム周辺では降雨が平年より少なく、梅雨明け後も晴天が続くとみられる。今後まとまった雨が降らない限り回復は難しく、関東から九州にかけて大渇水となった1994年のようになる恐れも懸念されている。首都圏に水を供給する矢木沢ダム。利根川水系で2番目に大きい。28日現在の貯水率は17%。利根川水系八つのダム全体でも貯水率が39%に落ち込み、国交省などで作る協議会は16日、3年ぶりに10%の取水制限に踏み切った。さらに、草木ダムがある利根川支流の渡良瀬川では25日、20%に引き上げた。記録的な渇水となった94年は7月に10%の取水制限をした。6月末時点では64%の貯水率だった。今回かなり早い段階で平年の半分以下にまで貯水率が落ち込んだのは、暖冬でダム周辺の雪が少なかったからだ。藤原ダムの累積降雪量は342cmで、平年の4割ほど。過去58年で最も少なかった。通常は4月までダム周辺に残る雪が3月には消えていた。さらに、春は高気圧が日本列島に張り出して晴天が続き、5月の降水量はみなかみ町で平年の4割強だった。今回の取水制限で、東京都水道局は利根川水系の取水制限分を補うため、多摩川水系の小河内貯水池の放流量を増やした。今のところ水道利用への影響は出ていない。だが、都民1人当たり1日の使用量の約5%にあたる、10リットルの節水を呼びかけている。(以下略)---今年は、長期予報では夏場の気温は高いけれど降水量は多め、という予報だったと記憶していますが、現実には気温も高く、降水量も少なめ、となっています。引用生地にも指摘されていますが、過去最大規模の水不足だった1994年より、現在の状況はずっと深刻です。東京都水道局・水系別貯水量の推移こちらに、今年の貯水量の推移、平年値、過去の主な渇水年の貯水量の推移がグラフになっています。引用記事にある1994年も含めて、過去のどの渇水年より、現在の貯水量は少なくなっています。理由は、引用記事にもあるように、冬場の極端な小雪と、梅雨前後の降水不足です。我が家は、ここ何年か、毎年1月に水上温泉に旅行に行っているので、今年の利根川源流が、どれほど雪が少なかったか、実際に見ています。雪がない今年1月10日の上越線水上駅去年、2015年1月12日の水上駅どれだけ違うか、一目瞭然です。雪がないから、雪解け水もありません。加えて、春以降も雨が少ない。6月の降水量は例年より若干少ない程度ですが、5月が極度の少雨でした。どうも、今年は低気圧や梅雨前線が南岸に留まることが多いようで、東京では結構雨が降っているのですが(5月も6月も、東京の降水量は平年を上回っている)、北関東に位置する利根川源流までは雨雲が北上しないことが多いようです。もうひとつ、何気に重要なのは、今年は現在までまだ1個も台風が発生していない、ということです。発生していないんだから、日本に接近する台風もない。台風か降らせる雨というのは非常に強烈で、1個の雨台風の直撃で、貯水量が数千万トンも増える場合があります。(が、利根川の場合、現状は満水に1億6千万トンも不足しており、どんな強烈な台風でも、1個だけでは満水にはならないと思われます)94年の水不足は、空梅雨だったことが原因でした。この年は、おぼろげな記憶ですが、冬場の降雪量はさほど少なくなかったと記憶しています。逆に、梅雨の降雨が少なかったので、残雪があまり溶けず、夏山の残雪が多い年だったと記憶しています。今年は冬に雪が少なかった、春から梅雨にかけて雨も少なかった、台風もまだ来ていない、というわけでトリプルパンチなわけです。94年より更に深刻な事態と思われます。台風に関しては、さすがにこれから発生するでしょう。ただし、発生しても日本に接近するかどうかは分かりませんし、日本に接近しても、利根川源流の流域に強い雨雲がぶつかるかどうかは分かりません。平均的にいえば、日本に接近する台風は、夏より9月のほうが多いので、一番暑い時期に台風が来ない、という可能性はあります。現状、利根川に取水制限がかかって以降は、ダムからの放流がほとんど止まっているので貯水量の減少は収まっています。しかし、このまま梅雨が明けると、今の小康状態を維持できなくなるでしょうから、そうなると、極めて深刻な事態になるかもしれません。それにしても、自然というのはぜんぜん人間の都合どおりにはなってくれないものです。
2016.06.30
コメント(6)
-
Windows10にしてみるのは、ひとつの手かもしれない
Windows 7を当面使い続けるつもりの人は注目! Windows 10の“無償アップグレード権”だけを確保できる方法Windows 10の無償アップグレードキャンペーンも、残すところ1カ月半となった。これを逃してしまうと有償でのアップグレードとなるが、これまでのように割安の“アップグレード版”は提供されないとのことで、通常価格のパッケージ版やダウンロード版を買う必要があるという。当面はWindows 7を使い続ける必要があるが、いずれはWindows 10をと考えているユーザーにとっては痛い出費となりそうだ。しかし、これまで通りWindows 7を使い続けながら、キャンペーン期間が終了した後も無償でWindows 10へアップグレードする方法が1つある。一度Windows 10へアップグレードした後で、すぐにWindows 7へ戻してしまうというやり方だ。というのも、Microsoftによるとキャンペーン期間内に一度でもアップグレードを完了したPCにはWindows 10のライセンスが発行され、元の環境に戻した後でも再び無償でWindows 10へアップグレードできるようになるのだという。つまり、“無償アップグレード権”を手に入れられるというわけだ。(以下略)---Windows10への強制アップグレードが非難の対象になっています。我が家でも、相棒のパソコンが、ある日突然Windows10に強制アップグレードされてしまいました。私のパソコンも、いったんはWindows10にアップグレードしたものの、オンキョーのSE-U33GXVという外付のUSBサウンドデバイスが動作しなくなり、音が出なくなってしまったため、すぐにWindows7に戻した話を以前に書きました。その後、しかしそれ以外の機器やソフトの動作状況を確認するために再度Windows10にアップグレードし、2週間ほど使って、またまた現在はWindows7に戻してあります。で、なんとなく、7月末のWindows10への無償アップグレード期限が過ぎてしまうと、もうWindows10にタダでアップグレードは一切できないのだと思っていました。実はそうではないのですね。1度Windows10にアップグレードしたパソコンは、そのあとWindows7に戻しても、「無償アップグレード権」が確保されているのです。だとすると、とりあえずいったんWindows10にアップグレードしておく(すぐに元のOSに戻すにしても)のは、正しい選択ということになります。ただし、注意事項が二つあります。元のOSへのダウングレード(ロールバック)は、私は2回行って2回ともまったく何の問題も生じませんでしたが、トラブルが発生した例もなくはないようです。アップグレード後に機器の構成を変更したり、ユーザーアカウントの追加・削除を行う、ディスクのクリーンアップを行う、アップグレードから31日(1ヶ月)以上経過する、などのことがあると、もう元のOSへのロールバックはできなくなってしまいます。それからもうひとつは、元のOSにロールバックした後も、機器の構成を変えると、同じパソコンとは認識されず、無償アップグレードができなくなる可能性があるようです。どこまで変えるとそうなるのかは分かりませんが。メモリの増設程度では問題ないようですが、マザーボードを交換したら、おそらくもうだめでしょう。起動ディスクのHDDやSSDを交換した場合はどうでしょう。CD-ROMドライブを変えた場合は、起動ディスクではないデータ専用HDDを交換したり増設した場合はどうだろうか・・・・・これらに対する回答は不明です。でも、これらは私のような自作機ユーザー以外にとっては、さして深刻な問題ではないでしょう。普通は、メモリ増設以外にパーツを変えることはないでしょうから。というわけで、今までは「Windows10にアップグレードなんて必要なし」と思っていたけれど、実は、いったんWindows10にアップグレートしておく(不要なら、すぐに元のOSに戻す)方がよいのかもしれません。※もっとも、Windows7のサポート期限(2020年)まで今のパソコンを使ったら、そこで「Windows10にアップグレード」ではなく「新たしいパソコンを組もう」になるかもしれません。今のパソコンは2014年11月に組んだので、Windows7のサポート期限の時点では5年以上経過しているはずですから。
2016.06.29
コメント(2)
-
うまく行っている国はどこにもない、ということか
英月の極楽シネマ 帰ってきたヒトラー 背筋が凍るコメディー歴史上に「絶対悪」と位置付けられたヒトラー。その彼が現代のドイツによみがえり、モノマネ芸人と誤解され瞬く間に大スターに。自信に満ちた演説は完成された芸として、過激な内容は真理を突く言葉として、大衆の心をつかむという衝撃の内容。しかもコメディーです。「笑っていいのか?」との戸惑いは自分の笑い声で吹き飛ばされ、代わりに残るのは背筋の冷たさです。デビッド・ベンド監督はヒトラー役の俳優と共に独各地で人々と関わったそうです。そのドキュメンタリー風の映像が随所に織り込まれ、映画にリアリティーを与えます。俳優は言います。「真剣に話しかけてきた会話から、彼らがいかにだまされやすいか、いかに歴史から学んでいないかが分かったよ」。「彼ら」は他でもない「私」。ヒトラーという存在を生み出したのは「私たち」なのです。その自覚が背筋の冷たさを感じさせたのです。ヒトラーは悪なのか? かつて熱狂的に支持された正義ではなかったのか? 自分の正義にこだわり、世間の正義から逸脱してしまうこともあります。正義や悪って、思っているほど確かなものなのでしょうか。自分が立っている足元がいかに危ういか、気付かされる映画です。---先日、この映画を見ました。実は、原作の小説を少し前に読んで、それが非常に興味深かったので、映画も見たいと思っていたのでした。1945年、ベルリンでソ連軍に包囲されて自殺したヒトラーが2011年(映画では2014年)のドイツにタイムスリップ、コメディアンとしてデビューして人気を得てしまう、という内容です。実在、かつ現役の政治家を次々とクソミソにこき下ろす、かなりきつい風刺小説です。映画のほうは、原作とはストーリーが変わっており、ぞっとする終わり方で、ちょっと後味の悪さを感じました。しかし、よく考えてみれば、あのヒトラーが現在によみがえって人気者になるという内容の作品が、見終わって心うきうきと楽しくなるのでは、ちょっと問題かもしれません。いずれにしても、考えさせられる内容であったことは確かです。あまり細かいことを書くとネタバレになるので、小説も映画も、その内容については細かいことは書きませんが、ヒトラーが現代によみがえったら、ドイツ国内に渦巻く政治不信の波に乗って、一躍人気者になってしまうだろうというのが、この作品の見立てであるわけです。貧富の格差、失業率の高さ、外国人の流入、出生率の減少・・・・・・・・確かに現代にヒトラーがよみがえったら、受け入れられかねない素地はあるのかもしれません。しかし、あのドイツです。EUの中で一人勝ち、経済的に最強のように見られているドイツでさえ、国内的にはこれほど不満が蓄積している、ということです。ドイツでさえそうだ、ということは、日本は言うに及ばず、全世界に、「うまく行っている国」なんてひとつもない、ということになるんだろうなと、妙に納得してしまいました。ひとつだけネタバレをすると、途中に「ヒトラー最後の12日間」の有名なシーン(YouTubeなどで、「総統がお怒りのようです」というMAD動画のネタに使われている)のパクリが登場します(映画版のみ)。正直「ここまでやるか、ここは笑っていいところか?」って思いましたけどね。
2016.06.28
コメント(4)
-
内向きの主張では、広い支持は得られない
防衛予算「人を殺すための予算」 共産・藤野氏が撤回共産党衆院議員の藤野保史政策委員長は26日、NHKの討論番組で、防衛予算について「人を殺すための予算」と語った。藤野氏は同日夕、党広報部を通じて文書で「不適切であり取り消す」と発言を撤回した。番組には各党の政策責任者が出演した。藤野氏は防衛費が2016年度当初予算で5兆円を超えたことなどを指摘した際、「人を殺すための予算ではなく、人を支え、育てる予算を優先していく」と述べた。その場で公明党議員らが発言の撤回を求めたが、藤野氏は応じなかった。番組終了後の同日夕、藤野氏は文書で「海外派兵用の武器・装備が拡大していることを念頭においたものだったが、発言はそうした限定をつけずに述べており不適切」などと釈明した。---少し前に、自民党の日本会議系の極右議員たちが、憲法改正を訴える集会で、すさまじい発言を繰り返している動画が話題になったことがあります。憲法改正誓いの儀式長勢甚遠元法相が「国民主権、基本的人権、平和主義をなくさなければ、本当の自主憲法じゃない」とか、凄まじいことを言っています。これが、自民党の極右系政治家の本音なわけです。ただ、これらのトンデモ発言は、憲法改正を訴える集会、つまり仲間内だからポンポン飛び出したのであって、さすがの彼らも、選挙演説で一般聴衆の前で「国民主権、基本的人権、平和主義をなくせ」とは言わないでしょう。同じ主張を持った仲間内で通用する言葉を、そのまま一般有権者の前で吐いても通用しない、程度の計算はあるでしょうから。私も、平和運動にかかわりのある人間ですから、なんとなく想像がつくのですが、「運動」の世界では、この種の極論が「そのとおり!」なんて拍手喝采を浴びたりしがちです。左右の違いはあっても、「国民主権、基本的人権、平和主義をなくせ」という暴言に、右側の運動の中で拍手喝采が集まるのと、心理的には同根かもしれません。論理的に言えば、戦争とは突き詰めて言えば人殺しであり、したがって戦争に備えるための予算を「人殺しのための予算」というのは、間違いとはいえません。でも、間違いではないということと、多くの人の支持を得られるかは別の問題です。高級レストランでディナーを前にして「この肉はどこで屠殺してどのように解体して・・・・・・」と言ったら、どうでしょうか。それは、論理的には間違いではありません。でも、誰にも共感はしてもらえないでしょう。いやな顔をされるのがオチというものです。少なくとも、より多くの支持を集めようと思うなら、論理的に間違いでなければ何を言ってもよい、というものではないはずです。運動の狭い世界でコアな運動家から拍手喝采をいくら浴びたって、それだけで取れる票などごくわずかです。支持を大きく広げようと思うなら、そういう運動の中でしか通用しない内向き主張は捨てるべきでしょう。
2016.06.27
コメント(9)
-
スペインも総選挙
スペイン出直し総選挙 EU批判派、躍進か昨年12月の総選挙後に主要政党の議席が伯仲し、新政権が樹立できなかったスペインで26日、出直し総選挙が実施される。緊縮財政を課すEUに批判的な急進左派、ポデモスが第2党をうかがう勢いをみせている。スペインでは欧州債務危機後、EUが求める緊縮財政策の下、中道右派・国民党のラホイ首相が増税や失業保険支給額引下げなど歳出削減を続ける。景気は回復軌道に乗っているが、失業率は約20%とEU加盟国ではギリシャに次ぐ高水準。25歳未満の若者の失業率は約45%に達する。「私たちはできる」を意味するポデモスは2014年に若者らを中心に結成された新興政党で、「反緊縮」を掲げる。EUが求める緊縮財政下で、景気回復の恩恵を受けられない有権者の不満の受け皿になっている。同党はEU離脱までは訴えていないが、イグレシアス党首は英国の離脱決定後に「公平で統一された欧州ならば誰も離脱は望まない。欧州は方針転換が必要だ」とツイッターに投稿し、EU改革を訴えた。前回選挙では、国民党と穏健左派・社会労働党の2大政党が過半数を大きく下回り、ポデモスが第3党に。選挙後の連立交渉は決裂していた。再選挙前の世論調査では、少数左派政党と選挙協力するポデモスが第2党に躍進する可能性があり、今回も単独過半数を獲得できる政党はないとの結果がでている。 ---昨日の投稿で、すべての政治的主張が右と左で割り切れるものではない、ということを書きました。反EU(欧州懐疑主義)は、イギリスでは政党レベルでは保守党の右派と英国独立党という右翼陣営が主導していましたが、実際の支持者は必ずしも右派ではなく、労働党を支持する組合活動家にも、EU離脱賛成に与した人は少なくなかったようです。フランスでは、ルペン率いる極右の国民戦線が反EUを主導しています。デンマークと、ドイツ、オーストリアでも、デンマーク国民党、ドイツのための選択肢、オーストリア自由党といった、反EU(あるいはEUに批判的)の右派政党も支持を伸ばしています。一方、ギリシャではツィプラス首相率いる左翼急進連合、スペインでは、引用記事にあるPODEMOSという、EUに批判的な左派政党が大きく支持を伸ばしています。そのギリシャのツィプラス首相の急進左派連合は、第1党ではあるものの、国会の過半数は制していないため、連立政権になっています。ギリシャには、PASPK(全ギリシャ社会主義運動)とギリシャ共産党という既成の左派政党が存在しますが、ツィプラスが連立相手に選んだのはそのどちらでもなく、右派で反EUを掲げる独立ギリシャ人という小政党でした。右か左かよりも、EUの押し付ける緊縮財政への賛否のほうが鍵になったわけです。スペインでも、反EUを掲げるPODEMOSの躍進が確実視されています。第2党をうかがう、ということは、PSOE(社会労働党)と得票・議席数が逆転する見込み、ということです。スペインは、比例代表制にも関わらず、数年前までは右派のPP(国民党)※と左派のPSOEが議席の大半を制する二大政党制(比例代表なので、ほかの小党も数議席程度は確保していたものの、政権に絡むことはなく、常に二大政党のどちらかが過半数を制していた)だったのですが、EU懐疑主義の広がりとともに、両党とも急激に支持を失い、どの党も過半数を取れず、他党との連立も成立せず、昨年12月の総選挙以来内閣の組閣ができない(選挙前に首相だったPPのラホイが引き続き首相を務めている)状況で、最終的にどの党も組閣を断念して再選挙となっています。※PPは中道右派とされていますが(現在の政策では、そういうことになるのでしょう)、元をただせばフランコ将軍のファランヘ党の末裔ですから、起源は極右です。焦点は、PODEMOSがどれだけ支持を伸ばすか、ということと、もうひとつはPODEMOSとPSOEが合計で過半数を制するかどうか、です。過半数を制することができれば、おそらく、この両党で連立政権を樹立すると思われます。両党あわせても過半数に達しなければ、組閣できない状態が再び、となってしまうかもしれません。PODEMOSの躍進は確実ですが、その分PSOEが支持を失う可能性が高いので、両党で過半数を取れるかどうかは微妙、というところでしょうか。いずれにしても、左右問わず、EU体制を是とする既成政党は、いずれの国でも凋落著しいものがあります。とりわけ、中道左派の没落が急激です。前述のギリシャのPASOKは、二大政党の一方の雄として何回も政権を握り、4年前まで国会議席の過半数を制していたのに、たった4年で、今は得票率6%という惨状です。スペインのPSOEも、合計20年以上政権を握っていたものの、昨年の総選挙では得票率22%まで落ち込み、1977年の民政復帰以来最低の得票率となりました。しかも、今回PODEMOSに逆転される可能性ということは、更に得票を減らしそうだ、ということでしょう。イギリスの労働党も、国会議員の大半はEU残留派だが、支持層はEU離脱派がかなり多い、従来労働党の地盤だったスコットランドで、スコットランド国民党に支持を奪われる、などで、かなり危機的な状態です。フランス社会党も、今は与党ですが、たぶん次の選挙では惨敗するでしょう。かろうじて踏みとどまっているのはドイツの社民党くらいでしょうか。要するに、それだけEUに対して、各国の国民から厳しい視線が注がれている、ということでしょう。
2016.06.26
コメント(5)
-
右と左という切り口では分けられないことが沢山ある、ということ
地べたから見た英EU離脱:昨日とは違うワーキングクラスの街の風景「裏切られたと感じている労働者階級の人々を政界のエリートたちが説得できない限り、英国はEUから離脱するだろう」2週間前にそう言ったのはオーウェン・ジョーンズだった。郵便配達の仕事をしているお父さんは、EU残留派優勢の予測に対し「俺はそれでも離脱に入れる。どうせ残留になるとはわかっているが、せめて数で追い上げて、俺らワーキングクラスは怒っているんだという意思表示はしておかねばならん」と言っていたが、追い上げるどころか、離脱派が勝ってしまった。わたしたちは英国でもリベラルな地域として知られているブライトンの労働者だ。「離脱」と「残留」票の全国マップを見てみると、英国中部と北部は「離脱」一色。「残留」はロンドン近郊やブライトンなど南部のほんの一部、そしてスコットランド、北アイルランドだけである。わたしや郵便配達のお父さんは南部の労働者だが、きっと中部、北部の労働者たちはもっと怒っていたのだろう。離脱投票の前に気づいたのは、もはや一国の中で「右」と「左」の概念が揺らいで混沌とした状態になっていたということだ。一般に、EU離脱派陣営は、保守党右派やUKIP(英国独立党)が率いた「下層のウヨク」「英国のドナルド・トランプ現象」と理解されていたようだが、地元の人々を見ている限り、こうした単純なカテゴライズは当てはまらない。「離脱」に入れると言っていた下層の街の人々は組合系レフトの労働党支持者たちだし、レイシストにはほど遠い感じの人たちだ。それに、ふだんはリベラルで通っている人々にも、最後まで迷っている人が多かった。 労働党左派もこのムードを感じ始めたから、潔癖左翼のジェレミー・コービンでさえ「移民について心配するのはレイシストではない」と言い始めたのだろう。怒れる労働者たちを「レイシスト」と切り捨ててはいけない。むしろ、彼らをこそ説得しなければ離脱派が勝つと判断したからだ。そもそも、反グローバル主義、反新自由主義、反緊縮は、欧州の市民運動の三大スローガン。そのグローバル資本主義と新自由主義と緊縮財政押しつけの権化がEUで、その最大の被害者が末端の労働者たちだ。だから、「大企業や富裕層だけが富と力を独占するグローバリゼーションやネオリベや緊縮は本当に悪いけど、それを推進しているEUには残りましょう」と言っても説得力がない。ガーディアンのジョン・ハリスは全国津々浦々のワーキング・クラスの街を離脱投票前の1週間取材し、「労働者階級の離脱派を率いているのはUKIPのファラージでも保守党右派のボリス・ジョンソンでもなく、人々のムードそのものだった」と気づいたそうだ。(要旨)---なるほどね。政治的には右と左はわかりやすい指標だけど、すべての政治的主張が右と左で割り切れるものでもない、ということです。右派も左派も、その内部で賛否が分裂して、収拾がつかない状態だったわけですが、ありていに言えばエリート層がEU脱退反対、労働者階級が脱退賛成だったわけです。結局のところ、政治の基本は、どんな理念よりもちゃんと食べられることがもっとも重要、ということになります。どんな美辞麗句も、その基本が押さえられた上でなければ意味がない、ということになります。EUに参加したままではまともに食べていくことができない、と非エリート層の多くの人が感じてしまった、ということに尽きるのでしょう。※ただし、世論調査を見ると、それでも労働党支持層は、保守党支持層よりもEU離脱賛成派の割合は、かなり少ないようです。(こちらのグラフを参照)ただし、スコットランドではEU離脱反対派が多数を占めています。スコットランドでも、エリート層がEU残留派、労働者層が離脱派という傾向が成り立つのかどうかは、日本語の資料ではよく分かりませんでした。ただ、スコットランドはイギリスの中でも貧しい地域で、それにも関わらず残留派が圧倒的ということは、スコットランドでは貧困層もEU残留派がかなり多いと思われます。スコットランドは、経済的にEUとの結びつきが強いので、EU離脱は経済的に損であることが明確だからでしょう。話は変わりますが、おりしも日本では参院選をやっているわけですが、選挙情勢報道によると、自民党は優勢のようです。非常に残念なことです。ただ、前述のとおり、政治の基本は、どんな理念よりもちゃんと食べられることがもっとも重要、というところに尽きるのでしょう。自民党の政策が国民をきちんと食べさせていけるものだとは、私は思いません。多くの国民も、安部政権の政策には懐疑的だと思われますが、野党(とりわけ民進党)に対してはもっと懐疑的、ということなのでしょう。私は今の憲法をとても大事に思っている人間で、憲法第9条を変えてはならないと、当ブログでもたびたび主張しています。ただ、政党が選挙を戦うのに、「憲法を守れ」だけで勝てるかというと、残念ながらそれは無理と思わざるを得ません。野党陣営の中では、民進党は振るわず、共産党は躍進の勢いとか。その共産党は、現在は護憲を強く主張していますが、その護憲の姿勢に惹かれたから支持が集まっているのでしょうか。そういう側面が皆無ではないにしても、それだけで躍進は不可能だと私は思います。むしろ、現政権の経済政策に不満のある層が共産党支持に集まっているのではないかと思います。もうひとつは、共産党は党員や地方議員の数が多く(それでも、党員はずいぶん減っているようですが)地に足のついた活動をしているのに対して、民進党は国政でこそ、ある程度の勢力を保っているものの、地方議員の数は少なく、議員以外の党員など、皆無に等しい。地に足のついた活動などできるわけもありません。経済政策の面でも、党内で意見がばらばらなので、たとえば新自由主義経済に対しての賛否、TPPに対しての賛否、消費税増税に対しての賛否、どれについても、党内で意見の一致が期待できそうにありません。EU離脱問題みたいなことがあったら、民進党はイギリスの保守党同様に、党内で賛否がばらばらになって収拾がつかなくなるだろうということは容易に想像できてしまうのです。今からでも、少しでも巻き返してほしいところですが、どうなるでしょうか。
2016.06.25
コメント(4)
-
仰天の結末
イギリスの国民投票の結果、僅差ながらEU離脱賛成が過半数を取り、離脱が決まってしまいました。びっくり仰天です。なんだかんだと言っても、イギリス人の多数は、最後はEU離脱という冒険は選択しないのだろうと思っていたので、こういう結末は予想していませんでした。早くも、日本でも株価が暴落しています。ポンドも暴落、ユーロも暴落、米ドルも下がっているようです。私の米ドル預金が・・・・・・。という話はともかくとして、政治的にも経済的にも、ヨーロッパもイギリスも、将来像が一挙に不透明になりました。今回の国民投票でEU離脱反対がもっとも多かったのはスコットランドです。そのスコットランドは一昨年の住民投票でイギリスからの独立を否決しましたが、独立反対の前提条件は、イギリスがEUの一国であることですから、その前提条件が崩れれば、「やはり独立すべき」という人がかなり増加するであろうことは明らかです。すでに、スコットランド自治政府首相は独立への意思を示唆しています。どうしてこんな事態が生じたのか。肥大化したEUの統治機構とか、ギリシャ危機に代表される域内の経済格差・・・・・・いろいろな問題がありますが、移民問題が特に大きかったのだと思われます。移民問題と言っても、EU圏内における比較的貧しい国から豊かな国への移民の問題もあるし、EU圏外、具体的に言えば中東からの難民の殺到という問題もあります。どちらも深刻ですが、近年急激に深刻化したという意味で世論に大きな影響を与えたのは、中東諸国からの難民かもしれません。では、中東諸国からどうして多くの難民が出たのか。言うまでもなく「イスラム国」やその他のイスラム原理主義勢力との内乱が原因です。では、どうしてイスラム国が勢力を伸ばしたのか・・・・・・と、突き詰めて考えていくと、最終的にはイラク戦争にたどり着くように、私には思えます。「風が吹けば桶屋が儲かる」的でいささか強引なこじつけかもしれませんが、イラク戦争がイギリスのEU離脱(今後の展開次第ではEUの瓦解?)を招いた、と言えなくもないように思えます。そういえば、あの戦争にイギリスは賛成し、なおかつ参戦もしました。そのしっぺ返しが今来ている、ともいえるかもしれません。より直接的な、政治的動向ということで言うと、キャメロン首相は、本人自身はEU離脱反対にもかかわらず、国民投票を公約に掲げてしまったことが、この結果を招いたともいえます。何故そんな公約を掲げたのか。国民投票で負けはしないだろうという甘い読みもあったでしょうし、党内にEU離脱賛成派を多く抱えている(有力政治家にも支持者にも)ことから、党内事情的に国民投票を拒否できなかったのかもしれません。いずれにしても、もはや賽は投げられてしまった。これからイギリスが、そしてヨーロッパが(いや、全世界も)どこに向かうのかは、もはや誰にも予想ができないかもしれません。
2016.06.24
コメント(4)
-
誰もが持っている要素
誰もがその特性を持っている?「大人の発達障害」で注目された「自閉症」の基礎知識「大人の発達障害」という言葉は、みなさんも一度は見聞きしたことがありませんか?複雑なコミュニケーションが求められる社会になるなか、困り感を抱える当事者へのサポートや強みを生かす支援、職場など周囲の理解の重要性が指摘されています。生きづらさを抱えながらも診断されないまま大人になり、社会に出てから「発達障害」という診断に至るケースが増えているようです。これが「大人の発達障害」です。「発達」という語感から子どもの障害であるイメージが強いかもしれませんが、先天的な脳の機能障害です。成長とともに緩和するケースはありますが、治ることはありません。文部科学省が2012年に実施した調査では、発達障害の可能性のある児童が6.5%の割合で通常学級に在籍することが示されました。1クラスに2人程度いる計算になります。みなさんの職場にも、通勤電車の中にも、お子さんの学校のクラスにも、決して少なくない数の発達障害の人がいるということです。発達障害は、大きく「自閉症スペクトラム」「注意欠陥多動性障害(ADHD)」「学習障害(LD)」に分けられます。注意力や衝動性に障害があるADHDや、読み書きや計算に特異的に困難を示すLDに比べて、自閉症スペクトラムの人は、言葉の遅れや、他者の感情が分からない、パターン化した行動など障害特徴のあり方が複雑です。実際に接した感覚としても、一番特徴的に感じるかも知れません。「自閉症スペクトラム」というのは聞きなれない言葉だと思います。「スペクトラム」は「連続体」という意味で、「自閉症の人」と「自閉症ではない人」(=多くの読者のみなさん)の間に明確な境界線があるわけではないのです。健常者や軽度の自閉症傾向の人から、重度の自閉症の人まで、連続的につながっているという考え方が、この障害名の前提にあります。特性の強さや現れ方に程度の差こそあれ、誰もがその特性を持っているということです。(要旨)---今は、自閉症という言葉の認知度が高まったので、そういう誤解はかなり少なくなったと思いますが、自閉症と、いわゆる引きこもり状態を混同する人が、かつては少なくありませんでした。もちろん、両者は異なった概念です。自閉症は脳の機能障害(具体的にどこの部分がどう、というのは分かっていないけれど)であり、引きこもりというのは、原因がどうあれ、部屋に閉じこもっているという状態を指す言葉です。ただ、引きこもりの中に、発達障害が原因の一つ、という例はあるかもしれません。というか、けっこう多い可能性はあります。以前、知的障害者に関わることの多い立場だったことがあります(今も、かかわることはありますが)。で、そのとき、「自閉症の人」と「自閉症ではない人」の間に明確な境界線があるわけではないという、この引用記事の趣旨を、私は痛感しました。自閉症の人の、「ちょっと変」と思えるところを冷静に分析すると、人間なら誰もが持っている要素のある部分が、他人より強いだけなのです。要素って具体的に何か、具体的に説明するのは難しいのですが、たとえばこだわりの強さ、という表現がぴったりくる場合もあります。外面的な部分では、抑揚を欠いた独特の声のトーンがあります(知的障害を伴わないアスペルガーでは、あまり見ない気もしますが)。私が思ったのは、自閉症の人は、人が誰もが持っている特定の要素を強く持っているということと、もうひとつは、「私も、そういう要素を世の平均よりは若干強く持っているんじゃないか」ということです。彼らを見ていて、「私にもこういうところ、あるな」って、感じることが多々ありました。私は、多分自閉症でも発達障害でもないと思いますが、ただ健常者の中では、平均より自閉症や発達障害に近い位置にいるんじゃないか、とは思うのです。だから、自閉症の人と自閉症ではない人に明確な境界線があるわけではない、という話は、ものすごく腑に落ちるのです。なるほど、やっぱりそうか、と。
2016.06.23
コメント(2)
-
参院選が始まった
参院選公示、問われる安倍政治 アベノミクス・安保法第24回参議院選挙は22日公示された。経済政策「アベノミクス」や安全保障関連法の是非などをめぐり、与野党は論戦を始めた。憲法改正の国会発議に必要な3分の2の勢力が形成されるかどうかも焦点となる。第2次安倍政権発足から3年半の「安倍政治」の評価が問われる。選挙区(改選数73)225人、比例区(改選数48)164人の計389人が立候補を届け出た。期日前投票は23日から始まり、7月10日に投票、即日開票される。今回の参院選から、国政選では初めて18歳以上が投票できるようになる。また、県境をまたいだ合区も初めて導入される。自民党は、政権に復帰した2012年末の衆院選から国政選のたびに経済再生を前面に掲げており、今回もアベノミクスの成果を訴える。安倍晋三首相は22日午前、地震で被災した熊本市の熊本城内で第一声を上げた。同日午後には同じく被災地の福島県に入り、復興の実績をアピールした。首相は同県郡山市の街頭演説で「参院選の争点は経済政策だ」と指摘。「有効求人倍率は24年ぶりの高い水準だ。アベノミクスをやめてしまえば、4年前に逆戻りだ」と強調した。(以下略)---参院選が公示されました。安倍は、「参院選の争点は経済政策だ」と(表向きは)主張しているそうです。もちろん、それも重要な争点です。でも、それがすべてではないでしょう。引用記事にもあるとおり、憲法改正が発議されてしまうかどうか、安保法の是非なども、重要な争点です。どれが一番重要かは、一概には言えないでしょうが。安倍が改憲への強い意欲を持っていることは明らかなのに、それを前面に出すのは得策ではないと考えたのか、自民党の各候補者は急に「改憲隠し」に走っているようです。毎日新聞の報道によれば、選挙区の与党候補55人のうち、初日の街頭演説で改憲に触れたのは一人だけだそうです。そのまま、選挙が終わっても改憲のことは忘れ去ってくれるならよいのですが、そうではないことは明らかです。そして、安倍が争点として推奨するアベノミクスにしたところで、明らかに破綻しています。私としては、特定政党の支持者・党員ではないので、他人に対して何党に入れてください、と言うつもりはありません。ただ、少なくとも私自身は、現在の与党及び改憲に賛成の政党・陣営には、絶対に投票しません。それ以外のいずれかの党・候補に投票するつもりです。どこに入れるかは、まだ完全には決めていないですが。
2016.06.22
コメント(3)
-
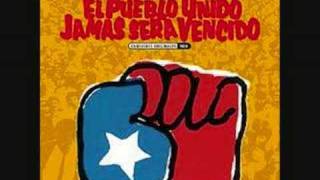
音楽に政治を持ち込むな、という政治的主張
フジロック「SEALDs奥田愛基」出演 「政治持ち込むな」vs「そもそも政治フェス」の批判合戦毎夏恒例の音楽イベントフジロックフェスティバルが2016年も開催される。そうした中、先日発表された出演者の中に学生団体「SEALDs」の奥田愛基さんの名前があったことが、インターネット上で物議を醸している。ネット上では、奥田さんの名前が出たことに敏感に反応する人が続出した。「最悪、政治活動の場になったか」「音楽フェスに政治を持ち込むな」「政治と音楽を混ぜるのは音楽に対して冒涜以外何者でもない」など、批判的な意見がいくつも寄せられた。奥田さんは今回、ミュージシャンとして出演するわけではない。「No Nukes! No War!」を掲げたイベント団体「アトミック・カフェ」が行うトークイベントに出演する。トークテーマは「参院選を振り返る。安保法制、沖縄、憲法、原発」だ。「アトミック・カフェ」は、もともと80年代に盛り上がりをみせた反核・脱原発イベント。2011年以来、フジロックでは毎年開かれており、脱原発派の加藤登紀子さんは同イベントの常連だ。過去には、反原発ソングで話題になった斉藤和義さんや、日頃から政治的発言の多いロックバンド「ASIAN KUNG-FU GENERATION」(アジカン)の後藤正文さん、ジャーナリストの田原総一朗さんらが出演している。こうした経緯もあり、今年になって、突然政治色が強まったわけではない。ただ、奥田氏の放つ印象は強かったようで、例年より反響が大きくなった側面がある。アジカンの後藤さんも同日、「フジロックに政治を持ち込むなって、フジロックのこと知らない人が言ってるよね。これまでいくつものNGOやアーティストがさまざまな主張をステージて繰り返してきたわけだし」とツイッターで批判に反論し、「『読経に宗教性を持ち込まないでください』みたいな言説だよね」と例えてみせた。(要旨)---批判している連中の言い分の、何と馬鹿馬鹿しいことか。そもそも、奥田氏はトークイベントに出るのに、音楽をやると勘違いしている人が大勢いるのが笑えます。その点はとりあえず措くとして、政治的であることを忌避するなら、この世の相当の音楽を忌避しなければならなくなります。例えば、国歌なんてものは、政治的の最たるものです。「天皇の世の中が千代に八千代に続いて欲しい」にしても、「ああ、星条旗はまだたなびいているか?自由の地 勇者の故郷の上に!」にしても、現在の国家体制を擁護したいという強い政治的意図を持った歌であることは明らかです。(フランス国歌などは、最初は反体制の革命歌だったものが、政権がひっくり返ったことで体制を守る歌になった)音楽に政治を持ち込むなと叫んでいる人たちは、では、君が代にも「音楽に政治を持ち込むな」と反対するのでしょうか。おそらく、絶対にそんなことはないでしょう。体制擁護の歌はよいが、反体制の歌は嫌いだと、そういうことでしょう。つまり、表向きは「政治を持ち込むな」と言っているけれど、実際には「自分が嫌いな政治的主張(左派的、リベラル的な主張)を持ち込むな」というだけの話です。嫌いなら嫌いで、大いに結構でしょう。嫌なら見なければよい、聞かなければよい、仮に行ったとしてもそのステージだけ避ければよい、それだけの話。で、自分たちで、安倍万歳フェスティバルでも何でも、開催すればよいのです。私自身は、音楽大好き人間ではありますが、ロックは特に好きな音楽ジャンルではなく、フジロックも行ったことはありません(ただし、出演者を見ると、ロックと銘打っていても、実際にはそれ以外の音楽もあり、ロックを中心にポピュラー音楽全般のフェスティバルというところでしょう)。私の音楽的趣味は、8割はフォルクローレ、1割はクラシック、あとはアニメ音楽、フォークソング、ラテン音楽一般や民族音楽一般等ですが、どんなジャンルの音楽だって政治的主張を音楽に託す例は山ほどあります。そもそもロックという音楽自体が、反体制から出発している、とは多くの人が指摘する事実ですが、それは別にロックに限った話ではありません。フォークソングだってそうだし、反体制から出発とまでは言えないにしても、クラシックでさえ、政治的主張と無縁ではありません。シベリウスのフィンランディアやショパンの革命のエチュード、英雄ポロネーズ、軍隊ポロネーズなんて、政治的音楽の最たるものでしょう。私の愛するフォルクローレだって、政治的主張だらけですよ。特に有名でわかりやすいのは、チリのヌエバ・カンシオン(新しい歌)です。たとえばこういうの。でも、ここまで「分かりやすく」なくても、政治的主張を伴った音楽はたくさんあります。たとえば、フォルクローレの代表曲である「コンドルは飛んでいく」は、元々はペルーの鉱山労働者の労働運動を描いたサルスエラ(スペイン語圏の民族的オペラ)の伴奏曲です。「コンドルは飛んでいく」の初演時の譜面に基づく演奏もちろんそれがすべてではなく、特に政治的メッセージのない曲でもすばらしい曲はたくさんあるけれど、フォルクローレから政治的な主張を全部排除してしまったら、魅力が半減なのは間違いありません。他のジャンルだって同じでしょうが。
2016.06.21
コメント(3)
-
時系列的に、明らかにおかしい
福島原発事故「炉心溶融、使うな」東電社長が指示 東京電力福島第1原発事故で、核燃料が溶け落ちる「炉心溶融(メルトダウン)」の公表が遅れた問題で、東電の第三者検証委員会は16日、清水正孝社長が「炉心溶融」の言葉を使わないよう指示したとする報告書をまとめ、東電に提出した。指示は電話などで広く社内で共有していたと認定。首相官邸の関与については「炉心溶融に慎重な対応をするように要請を受けたと(清水氏が)理解していたと推定される」と指摘した。報告書によると、清水氏は事故発生から3日後の2011年3月14日午後8時40分ごろ、記者会見していた武藤栄副社長に対し、社員を経由して「炉心溶融」などと記載された手書きのメモを渡し、「官邸からの指示により、これとこの言葉は使わないように」と耳打ちした。当時、炉心溶融したかが焦点となっており、会見でも繰り返し質問が出ていた。清水氏らは会見前の13日午後2時ごろ、官邸で菅直人首相、枝野幸男官房長官らと会談。清水氏がその後、報道発表については事前に官邸の了解を得るように幹部に指示していた経緯があったため、第三者委は官邸の関与を調べた。しかし、清水氏の記憶はあいまいで、第三者委は当時の官邸にいた政治家には聞き取りを実施しておらず、「官邸の誰から具体的にどんな指示、要請を受けたかを解明するに至らなかった」としている。 ---東電が炉心溶融という表現を隠したことが批判を浴びたら、何と、「炉心溶融という表現を隠せと官邸(菅政権)が指示した」という、斜め上方向の「検証」結果を出してきたわけです。もっとも、よく読むと「炉心溶融に慎重な対応をするように要請を受けたと(清水氏が)理解していたと推定される」「清水氏の記憶はあいまいで、第三者委は当時の官邸にいた政治家には聞き取りを実施しておらず」とあります。つまり、これは当時の清水社長が勝手にそう思いこんでそのように指示した、というだけの話であって、実際に官邸がそのような指示をした、という証拠は何もありません。むしろ、時系列的にみれば、この「推定」は明らかに矛盾しています。この時点で官邸が「炉心溶融」という言葉を隠そうとしていないことは、明白な証拠があるからです。枝野官房長官の会見全文〈13日午前11時〉13日午前11時すぎに枝野幸男官房長官が行った記者会見の内容は次の通り。今朝ほどの会見でも申し上げました、福島第一原子力発電所3号機に関する事象についてご報告を申し上げます。(中略)――燃料棒の露出はどうなっているか。炉心の溶融の可能性は。現時点では注水を行って、露出は水に埋まっているという風に注入した水の量から思われている。――1号機の炉心の溶融は起きたという認識か。これは十分可能性があるということで、当然、炉の中だから確認が出来ないが、その想定のもとに対応をしているし、今回の場合も可能性があるという前提で対応している。(以下略)---午前中の記者会見で、枝野官房長官自身が炉心溶融を、「十分可能性がある」と認めているのに、その3時間後に「炉心溶融という言葉を使うな」と指示することは、あり得ないでしょう。ちなみに、この時点では「十分可能性がある」という表現ですが、翌日夜、東電の問題の記者会見が始まって20分後の14日午後9時から始まった枝野官房長官の記者会見は、「1~3号機すべてで炉心溶融の可能性高い」と更に強固な表現で言っています。この一連の流れと、当の清水社長自身の「記憶はあいまい」というところ状況から考えれば、炉心溶融という言葉を使うなと官邸が指示したというのは、どう考えてもあり得ない話としか思えません。
2016.06.19
コメント(4)
-
ここにも、根拠なきネットデマを鵜呑みにする馬鹿がいた
ネット引用し蓮舫氏中傷 自民菅原氏が発言撤回自民党の菅原一秀元副財務相が東京都知事選を巡る17日の会合で、民進党の蓮舫代表代行について「日本人に帰化したことが悔しくて悲しくて、三日三晩泣いたとブログに書いているような人。選んでしまう都民はいないと思うが」とインターネット上の誤った情報を引用して中傷していたことが18日、関係者への取材で分かった。菅原氏は発言を撤回した。蓮舫氏はツイッターで「会員制交流サイト(SNS)で拡散したデマで捏造」と内容を全面的に否定し「国会議員がこのレベルの書き込みを真剣に受け取るとは」と記述した。菅原氏は自身のブログで「ネット記事を引用したことは軽率だったと反省している。帰化した人が知事になったり、立候補してはならないという趣旨ではない」とした。菅原氏は自民党のネットメディア局長を務めている。蓮舫氏は東京都出身。台湾人の父と日本人の母との間に生まれた。---国会議員ともあろう人間が、無根拠のネット・デマを、何の検証もせずに鵜呑みにしている時点で話になりません。このネットデマの元ネタは、どうも1997年10月1日の朝日新聞の天声人語ではないかと言われています。その記述は台湾人を父にもつタレントの蓮舫さんは、19歳のとき日本の国籍をとった。日本名は日本人の母の姓と、本名の「蓮舫」で申請した。すると、「本当にいいんですか、日本人じゃないことが名前でわかりますよ」と言われた。「何が悪いのですか」と言い返したが、一生忘れない言葉だ、と語っている。というものです。趣旨が全然違いますよね。日本国籍をとるときに自分の名前について誰かにケチをつけられた(この記述には、誰に言われたのかはありませんが、役所の担当者でしょうか)ことを「一生忘れない」という話(ただし、この話自体も、後述のように疑問があります)が、なぜか「日本に帰化したことが悔しくて悲しかった」という話にすりかえられています。ところで、上記天声人語の「蓮舫さんは、19歳のとき日本の国籍をとった。」という記述自体が、間違いとはいえないものの非常に誤解を招きやすいものです。蓮舫議員は、帰化なんかしていません。その必要がないからです。引用記事にもありますが、蓮舫議員は父親が台湾人、母親が日本人です(蓮舫議員のホームページに、そのように記述されています)。現在の国籍法では、父母両血統主義なので、当然に日本国籍を持っています。ただ、これは1984年の国籍法改正によるもので、それ以前は父親が日本人である場合のみ日本国籍を与える、という制度になっていました。今考えればとんでもない話ですが、母親が日本人でも父親が外国人である蓮舫議員は、この国籍法改正までは、確かに日本国籍ではありませんでした。しかし、改正国籍法の施行日である1985年1月1日(1967年生まれの蓮舫議員が17歳のとき)を以って、彼女は自動的に日本国籍を付与されています。ですから、すでに日本国籍を持っている19歳のときに日本に帰化というのはあり得ないことです。では、「蓮舫さんは、19歳のとき日本の国籍をとった。」という記述はデマなのか?おそらくそうではありません。国籍法改正によって台湾(中国)国籍と日本国籍の二重国籍になった蓮舫は、22歳までに国籍の選択を行う義務が生じました。「19歳のとき日本の国籍をとった」という記述は、おそらく、この国籍選択のことを指しているのだと思われます。ただ、そのあたりについて誤解を招きやすい記述ではあるでしょう。加えて、国籍選択は純粋に国籍を選択するだけなので、帰化のように氏名を新たに作ることはありません。そのあたり、上記天声人語のエピソードにも、何らかの勘違いが混入していそうな気がします。その勘違いが天声人語執筆者なのか、蓮舫議員本人なのか、はたまた、「本当にいいんですか」という言葉を放った人なのかは分かりませんけど。菅原議員は、謝罪は行ったものの、「帰化した人が知事になったり、立候補してはならないという趣旨ではない」という言い訳からは、依然として蓮舫議員が帰化によって日本国籍をとったという勘違いをしたままである疑いが濃厚です。一度擦り込まれた思い込みは、容易には消えないようです。
2016.06.18
コメント(0)
-
ネトウヨの根拠なき憶測をそのまま垂れ流す愚
【更新】産経が報じたやらせ疑惑に反論 ピースボート「取材なかった」→記事削除・謝罪産経新聞のニュースサイトで配信された記事が波紋を広げている。問題の記事は『TBS番組「街の声」の20代女性が被災地リポートしたピースボートスタッフに酷似していた?! 「さくらじゃないか」との声続出』。東京・新橋駅前であったTBSの情報番組の街頭インタビューに答えた女性が「被災地・熊本をレポートしたピースボートの女性と酷似していることが16日、分かった」と記している。この記事の中で、街頭インタビューの中身を紹介した。次の都知事が誰がいいのかと聞かれた女性が「蓮舫さんとか女性にどんどん活躍してもらいたいという気持ちがある」と語っている。ネット上では、この女性が以前、同じ番組でインタビューを受けていたピースボート災害ボランティアセンターの女性スタッフであるとする声があがり、産経ニュースでは「『さくらか?』 『やらせではないか』とTBSの報道姿勢を疑問視する声が続出している」とネットの噂を紹介した。BuzzFeed Newsは、ピースボート災害ボランティアセンターの山本隆代表理事に取材した。山本代表理事は「そもそもツイッターで広がった噂が間違っている。指摘されている女性スタッフは熊本県で支援活動を続けており、熊本にいるんですね。新橋駅前の街頭インタビューがあったとされる時間に東京にいるわけない。東京にいないのにどうやって答えられるのか」と否定した。山本さんはさらに続ける。「17日午前、産経新聞さんに対して正式に抗議をしました。記事の削除、訂正記事の掲載を求めています。産経新聞さんからこの女性が本人なのか、という確認もない。取材が足りないのではなく、まったく取材もなかった」BuzzFeed News が産経新聞の広報担当者に問い合わせたところ~産経新聞社広報部からFAXで回答が届いた。以下が、その回答全文だ。個別の記事についてはお答えできません。一般社団法人ピースボート災害ボランティアセンターからの抗議に対する回答は産経ニュースに掲載しましたのでご参照ください産経ニュースを確認したところ~「ピースボート災害ボランティアセンターへの回答書」という記事が配信されていた。当該記事は6月16日にインターネット上で話題になっていた事象を記事化したものです。ご指摘通り、記事化する際、TBSおよびテレビ朝日に取材するだけでなく、貴団体にも取材すべきだったにもかかわらず、これを怠っておりました貴団体およびスタッフに多大なご迷惑をおかけしましたことをお詫びいたします取り急ぎ、当該記事は産経ニュースおよび関連サイトから削除しました。代わって貴団体の抗議文を掲載しております---またしても、産経の事実無根飛ばし記事です。まったく根拠のないネット上のうわさをそのまま記事にしたら、アリバイによってそれが嘘であることが立証されてしまった、という、報道機関としては実にみっとみもない事態です。要するに、報道機関というよりもネトウヨの機関紙だから、「サヨク」攻撃のネタなら、真偽のほどをよく吟味することなく、見境なく飛びつくからこういうことになるのでしょう。過去においても、産経はピースボートについて同様のウソ記事を書いて、裁判に訴えられて敗訴したことがあります。「カメラマンの宮嶋茂樹氏の著書によると、辻元氏は平成4年にピースボートの仲間を率いてカンボジアでの自衛隊活動を視察し、復興活動でへとへとになっている自衛官にこんな言葉をぶつけたという。『あんた! そこ(胸ポケット)にコンドーム持っているでしょう』辻元氏は自身のブログに『軍隊という組織がいかに人道支援に適していないか』とも記している。こんな人物がボランティア部隊の指揮を執るとは」これを書いたのは、例の阿比留という記者の皮をかぶった政治運動屋ですが、辻元議員がこれに対して提訴、一審で産経側は敗訴し、そのまま控訴せずに確定しています。そういう過去があるにもかかわらず、それをまったく反省することなく同じ失敗を何度も繰り返す、まさしく彼らが賛美する戦時中の日本軍と変わらない。それにしても、元々のネット上のうわさですが、問題のインタビューの女性とピースボートのスタッフ女性の写真を見比べてみても、似ているとは思えません。似ているとすれば、髪の毛を同じ色に染めていることと体形がかけ離れてはいない、程度であり、これを「似ている」と言うなら、日本中の10代後半から30代前半まで、何百万人も「似ている」女性がいるんじゃないでしょうか。という程度の検証すらせず、もちろん相手に対する取材も行わず、ネット上に転がっている無根拠の噂をそのまま記事にしましたって、それで「報道機関」としてお金を取って新聞を発行しているんだから、呆れてしまいます。しかも、「回答書」って、本文では「お詫びします」と書いているのに、なぜ見出しは「回答書」なのでしょうか。お詫び、という見出しでかくのがよほど嫌なんですね。
2016.06.17
コメント(4)
-
御用組合
ワタミに初の労働組合 「ブラック」批判受け居酒屋チェーン大手のワタミで初めて労働組合が結成された。グループの正社員約2千人と、アルバイト約1万5千人の大半が入った。流通、繊維業界の労組を束ねるUAゼンセンが支援し、1月から結成の動きが進んでいた。ワタミによると、1984年の創業以来、企業別労組はなかったという。5月16日、労組「ワタミメンバーズアライアンス」(組合員数約1万3千人)が結成され、入社すると同労組に加入することになる「ユニオンショップ協定」を労使で結んだ。同社の経営陣はこれまで、「社員は家族だ」といった経営理念から労組に否定的だったが、長時間労働などで「ブラック企業」と批判され、業績も悪化。労務管理を見直してきた。(以下略)---あのワタミに労働組合、と一瞬驚いたけど、何とユニオンショップ協定を結んで入社と同時に加入だというのではねえ。実は、私inti-solは今の勤務先の前、別の会社に4年ほど勤めていたのですが(もう20年以上前の話)、その会社にあったのが、まさしくユニオンショップ協定を結んだ労働組合。私も、一応組合員でした。いわゆる労使協調の、要するに会社の言いなり労働組合でした。長時間労働も不払い残業もたくさんあったけど、それについて、その労働組合が何かを主張した、という記憶はありません。組合の委員長をやった人は、任期が明けると管理職になるのが常態だったりして、会社の出世コースの完全な一部と化していました。ワタミの労働組合というのも、引用記事を見る限り、「ブラック企業」という評に対する対策として、つまり働く人たちの権利を守るためというより、会社の外聞を守るための方便として設立されたとしか思えません。そのような労働組合で、働く者の権利がどれだけ守れるのかは疑問の余地は大いにありです。もちろん、何でもかんでも会社側と対決せよ、とは私も言いませんけど、あのようなブラック企業で働く側と野党側の利害が完全に一致することなどあり得るはずがないわけで。ただ、まあないよりはマシかもしれないし、最初は御用組合でも、良い意味で変質することもあり得なくはない(でも、それにはユニオンショップ協定が邪魔をすると思う)ので、全面否定まではしませんが・・・・・・。
2016.06.16
コメント(2)
-
公私混同は彼だけだったのか?
自民、舛添氏への不信任案提出固める 辞職決断を説得東京都の舛添要一知事をめぐる政治資金などの公私混同疑惑で、都議会最大会派の与党・自民党は14日午前、都連の幹部会を開き、舛添氏への不信任決議案を提出する方針を固めた。辞職を求める意思を表明している与党の公明党も同調する。舛添氏には自ら辞職を決断するよう説得を続けており、説得に応じなければ不信任案を出す構えだ。この日の都連の幹部会で対応を協議した。自民は2014年の知事選で舛添氏を支援。一連の問題による世論の批判は与党にも向きはじめており、参院選に影響しかねないという見方が強まった。党幹部によると、会合では「かばいきれない」との意見で一致したという。だが、不信任案が可決された場合に舛添氏が都議会解散を選択するリスクへの警戒も強く、「舛添さんが自分から辞めれば、不信任を出さなくてすむ」とし、舛添氏に自ら辞めるよう説得しているという。野党の共産党や民進党系2会派などは14日の議会運営委員会に、不信任案を提出する方針を固めている。舛添氏は13日、今夏のリオデジャネイロ五輪・パラリンピックに選挙が重なることを理由に不信任案の提出を先送りするよう求めた。自民は舛添氏の対応次第で、野党に対して、舛添氏の要望を検討するよう求める意向もある。不信任案は14日午後の議運理事会で合意されれば、15日の本会議で審議される見通しだ。---2011年4月の都知事選で石原が当選して以来、その石原が突然辞任したことによる12年12月の都知事選、更にその時当選した猪瀬知事が政治資金問題で辞任したことによる14年2月の都知事選、そして、このままいくと8月にまたまた都知事選ということになりそうです。5年間で4回目の都知事選という異常事態です。私は、前回の知事選では宇都宮候補に票を投じました。舛添は支持しなかったわけですが、正直なところを言えば、都知事当選後の舛添の政策が、そんなにひどかったとは思いません。素晴らしいとは言いませんが、石原に比べればまともな部類だったと思います。舛添があちこちに視察に行く中で、保育園と介護施設には一度も行ったことがないとか、新宿区の都有地を保育園ではなく韓国学校に貸し出そうとした、ということが批判されていますが、視察に入ったことがないにしても、舛添が知事になって以降の東京都は保育園関連の予算をかなり増額していますから、充分とはいえないまでも、保育園の整備を冷遇しているわけではないことは明らかです。韓国学校云々に至っては、騒いでいる人たちの嫌韓ネトウヨ臭がむき出しで、辟易します。もっとも、保育園・介護施設の視察ゼロというところからは、金は出すけど熱意はあんまりこもっていなかったかも、という気はしますけどね。個人の人柄はよくわかりませんが、知事に近い位置の都の幹部からは「前任の誰かみたいに怒鳴り散らしたりしない」「前任の誰かと違って、平日はちゃんと登庁している」「頭の回転が速く、記憶力が抜群によいので、ブリーフィングの理解が速く、一度した説明を全部覚えている」といった評価が聞こえてきています。(ただし、一連の騒ぎの前)それはともかく、一連の公私混同疑惑は、どうしようもない。これは批判されて当然です。疑惑そのものもそうですが、疑惑が表面化して以降の対応のまずさも火に油を注ぎました。頭は良いけれど(あるいは、そうだからこそ)他人の反応を読んで、嫌悪感を抱かれないような謝罪を行うのは不得手だったかもしれません。ただ、舛添の公私混同は確かにひどいのですが、じゃあ酷いのは舛添だけだったのか。石原慎太郎は、都知事在任中に豪華視察旅行を何回も繰り返しました。例えば2001年6月エクアドルのガラパゴス諸島視察は8人で1400万円、同年9月には米国出張で8人2100万円など。贅沢ぶりは舛添以上だったし、そもそも都庁に週2回とか3回しか登庁しない、ということも報じられていました。当時、それをちゃんと批判した人がどれだけいるのか。あえて言えば、石原のそういった態度を見た人間が、「都知事というのは、ああいう豪華旅行や休んでばっかりの勤務態度が許される」という誤ったメッセージを受け取ったとするなら、それは石原と、それをろくに批判もせずに礼賛した連中の責任でしょう。舛添が自ら辞任することはなさそうで、不信任案可決ということになりそうです。その場合、舛添には都議会解散か失職かの二者択一になりますが、都議会を解散したところで、再選挙後再び不信任案を食らって、今度こそ失職は確定的です。だから、多分解散は選ばずに失職することになるでしょう。いずれにしても都知事選は不可避ですが、果たして誰が出るんでしょうか。こんな状況で、まともな候補者が出てくるとは、とても思えません。前回は次点が宇都宮候補、僅差でその次が細川候補、主要候補中最下位が田母神候補でした。田母神は逮捕されたし、細川はその後体調を崩したので、選挙に出るのは無理でしょう。宇都宮さんはどうだろう。私の知る限りでは、現時点では名前を見ないので、さすがに3回続けて(それも4年間隔ならまだしも、1年半と2年間隔)は無理なんだろうなと思います。それ以外、取りざたされている名前には、橋下だの東国原だの、ろくな人がいません。そもそも周りが言っているだけで、本人に出る気があるかも定かではありませんが。追記 その後、周知のとおり、舛添は都議会解散という選択はせず、自ら辞任を表明しました。都知事選は7月31日になりました。
2016.06.14
コメント(5)
-

アジサイ
先週末に、アジサイの写真も何か所かで撮ってきました。今の時期には、東京ではあちこちに咲いています。花がちょっと縮れている品種です。これも同様。日比谷公園で笛の練習の合間に撮影。もっとも一般的なアジサイです。日比谷公園にはいっぱい咲いていました。これも日比谷公園で撮ったものですが、野外で見るアジサイはほとんどこの形態なので、おそらくこれがアジサイの原種なのでしょう。普通の(園芸品の)アジサイより、天然の原種(多分)のほうが好きかも。駅の出入り口にも咲いていました。青とピンクは、土壌が酸性かアルカリ性かで決まるようです。ピンク色のアジサイは、比較的稀です。花が縮れている品種再び。アジサイは、まだまだしばらくは見頃が続きます。それにしても、ついこの間ウメが咲いていたのに、あっという間に桜、ツツジ、サツキも終わり(サツキはまだ多少咲いているけど)もうアジサイか、と。時の流れの何と早いことか。
2016.06.13
コメント(2)
-
イギリスのEU離脱国民投票
英国民投票 世論調査 「EU離脱」が僅かに上回るイギリスのEU=ヨーロッパ連合からの離脱の賛否を問う国民投票まで3週間を切り、最新の世論調査では、EU離脱を支持する人が残留を支持する人を僅かに上回り、「残留」派と「離脱」派の双方の運動が激しさを増しています。今月23日にイギリスで行われるEUからの離脱の賛否を問う国民投票について、先週行われたインターネットによる2つの世論調査の結果が6日公表され、いずれも「離脱」が「残留」を僅かに上回りました。このうち、今月1日から2日間にわたって行われた世論調査では「離脱」が45%、「残留」が41%となっています。(以下略)---インターネットによる調査は、精度に問題がかなりあるように思います。実際、引用記事の調査についても、信憑性についてはかなり議論があるようです。ただ、間違いないのは、EU離脱の是非に関して、イギリスの世論は真っ二つに割れている、ということです。二大政党の保守党、労働党双方とも、党内に残留派と離脱派がいる。特に与党保守党では、党首のキャメロン首相はEU残留を主導しているものの、閣僚の半分近くが離脱派とされます。ロンドン市長を先月退任した保守党のボリス・ジョンソンの離脱派です。一方、労働党は、過去においては欧州懐疑派(欧州統合に反対する勢力)が主流でしたが、ブレア政権時代以来EU支持派が主流となり、現在ではEU離脱派は少数派になっているようです。コービン党首は、党内左派に属し、本音はEU離脱派であるものの、党内主流が残留派であること、離脱した場合のマイナス点などを考慮して、EU残留を公式には主張しています。もっとも、労働党の議員の間ではEU残留派が主流でも、支持者の間ではそうとも限らないようです。労働党の伝統的支持層であった労働者階級の間で、労働党への支持が減少し、EU離脱を主張する右翼政党英国独立党の支持が増えている、と言われます。あえて大雑把に言えば、最右派と最左派はEU離脱派、それより穏健な中道右派と中道左派はEU残留派、ともいえます。ただし、労働党左派のコービン党首が本音のEU離脱論を封印していることから類推できるのは、EU残留派は左側には支持を広げつつある、ということです。しかし、それにもかかわらずEU離脱派が支持を広げつつあるのは、右側でEU離脱派が拡大しているからでしょう。なぜ、このように左右両陣営ともにEUへの賛否が分断されているのか。EUが、政治的には人権や政治的な自由を尊重する中道左派的な価値観を重視する一方、経済的には新自由主義経済を推進している、言ってみれば政治左翼(中道左派)で経済右翼とも言うべき二律背反な状況が原因でしょう。特に最近EU離脱派が急増しているのは、EUが難民・移民に寛容な態度であるところに、シリア内戦などで多くの難民がなだれ込んできたことが直接の原因です。もっとも、そのためにEU残留派、離脱派ともに、呉越同舟的な部分があります。単純に言えば、従来の左右の枠組みだけでは割り切れない状況、ということです。私自身は、日本人であり、EU離脱への是非を言っても仕方がない立場ですが、あえて言えば、EUを離脱した場合の経済的マイナスは、どう考えたってかなり大きいでしょう。また、EU離脱が多数を占めた場合、EU残留派が圧倒的多数を占めるスコットランドは納得しないでしょう。イギリスがEU離脱となったら、「それならイギリスから独立して、スコットランドとしてEUに加盟すべき」という意見が、前回の住民投票より大幅に増えるであろうことは想像に難くありません。これらのことを考え合わせると、国民投票でEU離脱が多数を占めた場合は、イギリスという国の将来像が一気に不安定化します。そして、イギリスが抜ければEUの将来像も不安定化します。それは、あまり望ましい事態ではないように思えます。いずれにしても、あと10日余りで結果が出ます。
2016.06.12
コメント(6)
-

予測と現実の乖離
6年ほど前の2010年に、電気事業連合会が出した、日本全国の発電電力量の実績と将来予測があります。その予測グラフはこうなっています。(2008年までは実績、それ以降は予測)1980年から2000年までの電力(発電量)は、急激に増加してきましたが、21世紀に入ってからは、明らかに伸びが鈍化しています。特に2005年と2008年の間には、わずかな伸びしかありません。が、今後は再び、急激に発電量(≧電力需要)が伸びると、電力業界は考えたわけです。だから、原発をいっぱい作ろう、という考えだったのでしょう。しかし、このグラフの中で最新の実績データである2008年は、いうまでもなくリーマンショックの発生した年です。その影響は、2010年の時点でもまだ強く残っており、こんな右肩上がりに発電量が伸びるという将来予測が果たして妥当だったかどうかは、大いに疑問が残ります。(震災前の予測なので、震災の影響が盛り込まれなかったのは仕方がないでしょうが)現実の発電電力量はどう推移したか。同じく電事連のホームページに公開されています。電源別発電電力量構成比実のところ、最初のグラフでは省かれているのでわかりませんが、2008年の発電量は、その前年2007年に対して微減となっています。そして、その2007年をピークとして、2015年に至るまで、2010年(記録的猛暑だった)を唯一の例外として、一貫して、右肩下がりで発電量は下がってきています。2015年度の発電量は、9000億KWhを下回り、8850億KWhとなっています。これは1996年以来の数字で、つまり20年前の水準に戻った、ということです。冒頭に引用した予測値には、2015年の数字はありませんが、2013年の数字では、予測と実績の乖離は1000億KWhを超えます。その2013年と比べて、更に500億KWhも発電量が減っているのだから、予測との乖離は1500億KWhを超えるでしょう。実際、発電量はピークだった2007に比べて15%近く減っています。今年は、猛暑の予報なので、何年かぶりに電力量は前年度に対して増える可能性がありますが、そうだとしても、そう大幅な増にはならないでしょう。原発を巡っては、「原発を動かさないと電気が足りない」という、「電気足りない詐欺」が盛んに叫ばれましたが、現実はかくのごとしです。それに、本質的には「これからどんどん電力消費を増やしていこう」などというのが、今後の日本の進むべき姿ではない、むしろ、可能な範囲で省エネに努め、電力消費はさらに減らしていくべきだと私は思います。実際問題、今後も省エネが継続すれば、8500億KWhを下回るのはそう困難ではなさそうだし、8000億KWhを下回ることも、不可能ではないでしょう。加えて、リンク先を見てもらえると、地熱及び新エネルギーの発電割合が、まだ絶対的にはわずかながら、急激に増えてきていることが分かります。これもまた、よい傾向です。いずれにしても、電事連の予測に基づく原発の増設などは、まったく必要ないことが明白です。それにしても、原発推進派は、最初は「原発を再稼働しないと電気が足りなくなる」と叫んでいました。しかし、2014年にはとうとう原発の発電量は年間を通じて0でしたが、電気が足りなくなることはありませんでした。そこで、今度は石油の世界的高騰に目をつけて、「無駄な燃料代を払っている」と叫び始めました。しかし、そのうちに石油の価格が暴落してしまいました。次はどんな理由で「原発を動かせ」というのかな。
2016.06.11
コメント(4)
-
生理的に不可能
若狭町給食センター勤務時間中の排便禁止…食中毒受け福井県若狭町で先月下旬、ノロウイルスによる集団食中毒があり、食事を調理した同町給食センターが、調理員の勤務時間中の排便を今後禁止するよう「衛生管理マニュアル」を改定したことが分かった。再発防止に向けた衛生面での改善の一環だが、過剰ともいえる労働現場への規制に、専門家からは疑問の声が上がっている。センターは8校の小中学校の給食を調理しており、先月21日から給食を食べた教職員や児童生徒が相次いで食中毒を発症。今月4日までに計363人がノロウイルスに感染した。センターは業務停止となり、来月中旬の再開に向け、マニュアル改定を進めていた。新しいマニュアルでは、勤務時間(午前7時半〜午後4時45分)中の調理員について「保菌などの状況を確認することが難しく、センターでは原則排便しない」と規定した。センターの担当者は「緊急事態であり、規定を厳しくした。排便を我慢できない場合は、早退などの対応をとる」とし、「調理員が早退した場合に備え、予備調理員3人を確保した」と説明している。感染症に詳しいある男性医師は「聞いたことがない対策だ。手洗いの励行やトイレの消毒などが現実的だ」と指摘。文部科学省学校健康教育課も「調理員の生理現象への制約は、学校給食衛生管理基準になく、国として同様の対策は取ったことがない」としている。脇田滋・龍谷大教授(労働法)は「公共目的での緊急対策と理解したいが、働く人の権利にも配慮は必要だ」と話している。---何というか、絶句です。食中毒が危険だからトイレに行くな、と。これが「対策」として意味があるかどうかも問題ですが、そもそも実行可能なのか。勤務時間(午前7時半〜午後4時45分)中の調理員について「保菌などの状況を確認することが難しく、センターでは原則排便しない」7時半から4時45分までというと9時間15分ですが、それだけの長時間トイレに行かないことが可能なのか。どう考えたって、人間の生理現象の限界を超える事態です。だいたい、それを言うなら、出勤前に自宅でトイレに行くのは問題ないのか?それは調理開始前に手洗い、殺菌を行うから大丈夫なのだとすれば、給食センターにおいても、トイレに行った後は調理開始前と同様の手洗い・殺菌を行えば問題ないのでは?それでは不十分だとしたら、そもそも調理員は勤務時間外ですらトイレに行ってはならない、ということになってしまいます。「調理員が早退した場合に備え、予備調理員3人を確保した」のだそうですが、普通に考えれば、予備調理員だって9時間以上トイレに行くな、と言われてもそれは無理でしょう。もし、これを厳密に適用しようとしたら、勤務時間終了までに、予備調理員も含めて全員が早退しました、ということになるんじゃないでしょうか。小中学校の給食のみを調理するのであれば、調理自体は午前中に終わるでしょうが、そのあとも、回転釜等の調理器具や食器の洗浄などの後片付けがあるはずです。「全員が早退に追い込まれて、食器の洗浄ができませんでした。明日の給食は作れません。」ってことになる。まあ、実際のところは、直ちに形骸化、有名無実化して終わるだけのことでしょうけど、現実を見ないで空理空論だけで対策を考えるバカがマニュアルを作ったとしか思えない話です。
2016.06.10
コメント(5)
-
どっちもどっち、かなあ
市「過度な飲酒、パチンコ慎むように」「従わぬなら生活保護停止も」市民苦情受け掲示/四街道四街道市が生活保護受給者に対し、過度な飲酒やパチンコを慎むよう促した上で、指導に従わなければ生活保護を停止する場合がある、との趣旨の文書を約2年間、担当課の窓口に掲示していたことが6日までに、市への取材で分かった。受給者が飲酒やパチンコをすることを禁じる直接の規定はなく、市は「誤解を招きかねない内容」と認め、撤去した。受給者の支援団体は「行政と受給者の信頼関係を失わせる行為で、行き過ぎだ」と、市が掲示を続けてきたことを批判している。文書が掲示されていたのは、市生活支援課の窓口。ポスターサイズの文書が窓口正面に掲げられ、デスクマットにも文書が挟まれていた。二つの文書はともに「生活保護費受給者の皆様へ」とのタイトルで、「皆様の中には、過度な飲酒や遊興費(パチンコ、パチスロ等)に浪費している方が見受けられます」と指摘した上で、「再三の指導にもかかわらず、生活保護費の適正な支出がみられない場合は、停止や廃止といった措置を講じなければならない場合もあります」と支給の打ち切りを示唆。また、一つの文書は過度な飲酒などについて「現に(原文)慎むようお願いします」と注意していた。同課によると、「受給者がパチンコをしている」との苦情が市民から多く寄せられる状況を受け、2014年春ごろから掲示を始めた。「日々の業務の中で、パチンコ店に踏み込んで確認することも難しく、掲示に至った」と担当者は言う。また、「飲酒やパチンコを全て禁止しているわけではないが、度が過ぎると生活を圧迫してしまう。掲示は『気をつけて』という意味」と説明。しかし、生活保護法には、飲酒やギャンブルを禁じる直接の規定はない。他市の担当者は「保護費は原則、本人の裁量で使えるもので、過度の干渉はできない」と指摘する。---生活保護に詳しい知人に、この件について聞いてみました。ポスターを掲示した自治体も、それを批判する支援団体も、どっちも「大概にしろや」ということのようです。以前にも、大分の別府市で福祉事務所職員がパチンコ店に張り込んで、入店する受給者をチェックし、その一部を保護停止にする、というできごとが報じられたことがあります。いったいどういう根拠で保護停止をかけたのか、こんなのは、正当な根拠に基づかない行政処分の最たるもので、不服審査請求されたら、確実に覆るだろう、ということでした。今回の例は、実際に保護の停廃止をやったわけではありません。「やるぞ」という文書を掲げただけです。とはいえ、実際にはできない行政処分を掲げるのは、あまりに威嚇的と言わざるを得ないでしょう。ただ、「過度な飲酒、パチンコ慎むように」という注意までなら、「当り前じゃないの?」ということです。現実に、明示しているか否か、どの程度厳格に運用しているかは千差万別ですが、酩酊した人間の相談は受け付けない福祉事務所は多いそうです。もちろん、保護費の用途は自由ですし、保護費の範囲でやりくりできているなら、他人が文句をいう筋合いはない、という側面はあります。受給者が飲酒したりギャンブルを行うことを明示的に禁止する法律※もありません。ただし、現実問題として、過度な飲酒、パチンコが問題になっている人間が、保護費の範囲でやりきりできているはずなんかないこともまた事実なのです。知人や親族からこっそりお金を借りたり(借金も収入認定といって、保護費を減額する対象なのだそうですが、現実には、現金でお金のやり取りをしていたら、尻尾を掴むことは不可能です)、食べ物をもらったりしてしのいでいるだけです。それすらできなくて、「お金を落としました」「盗まれました」と言い張って「何とかしてくれ」と言ってくる受給者もいるそうです。もちろん、中には本当に落とした人もいるにしても、「大半は、お馬さんに金を盗まれた、飲み屋に金を落とした、の類に決まっているじゃん」とのことです。もちろん、仮に本当に落としたとしても、盗まれたとしても、保護費の再支給は特殊な例外を除いて一切ないそうですが。(例外とは、住居が火災や大規模災害にあってお金を失った場合)※生活保護法第60条に「被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならない。」と規定されており、酒やギャンブルで生活できなくなることは、この条文には反します。ただし、この条文に罰則規定はありません。もっとも、そういう掲示が実際に過度な飲酒やパチンコを抑止する何らかの効き目があるかといえば、まったくないのも現実です。私もそういう人については、知らないわけではありませんが、アルコールにしろギャンブルにしろ、あるレベルよりひどくなると、依存症は治らないようです。そういえば、あの中川昭一もアルコール依存の治療を受けたようですが、結局治らずに死んだ。断酒会とかAA(アルコホーリクス・アノニマス)とかもあるけれど、通えば治るというものではありません。「廃人」という言葉がリアリティをもって感じられるような人も少なくはない。いささか言葉はきついですが、社会性としては「ご臨終」状態にある人を生物学的に生かしているだけ、という状況です。アルコール依存者をイスラム諸国にでも島流しにすれば酒を絶てるでしょうが、この日本という国は、飲酒に対してきわめて寛容でかつ社会の中に誘惑がいっぱいありすぎるので、依存症者が酒を絶つのが絶望的に困難なのです。よく、アルコール依存はガンより死亡率が高いといわれます。肝臓がん、肝硬変、そのほかの内臓疾患、糖尿病、それによる人工透析や足の壊死、切断、さらには酩酊時の事故や自殺、死因はいくらでも転がっています。その前に、家賃を酒代につぎ込んで住居を失い、無常で野垂れ死にするかもしれません。かわいそうな状況ではありますが、残念ながら本人を目の前にすると、どうも、かわいそうという感情がわかない、そんな人格の持ち主が多いのも現実です。結局、「従わぬなら生活保護停止も」は対応として間違っているし、「過度な飲酒、パチンコ慎むように」は正しいけど効果はない、ということしになるようです。残念ながら、「こうすれば解決」などという方策は何もないようです。
2016.06.09
コメント(6)
-
Windows10にしてみた
Windows10への強制更新を伝える注意書きが話題「更新が強引に」17日、あるTwitterユーザーが、Windows10への強制更新を伝える注意書きを投稿し、大きな話題を呼んでいる。このユーザーは「社内に謎の注意喚起の貼り紙がw」というコメントとともに、壁に貼ってある一枚の貼り紙の画像を投稿した。その貼り紙には、「ウィンドウズ10の更新が強引になりました、注意してください」という但し書きとともに、PCの電源を付けたまま20分ほど放置すると、そのまま1時間半に及ぶOSの更新作業に入ってしまうばかりか、更新終了後も再び使用できるようになるまで10分ほどかかってしまうと説明している。この騒動の背景だが、マイクロソフトがWindows7と8.1に表示するアップグレード通知画面の仕様を変更したことにある。なんでも更新予定を自分自身で変更・キャンセルしない場合、強制的にWindows10への移行を開始する形としたそうなのだ。(以下略)---このところ、Windows10への強制アップグレードが各所で非難の的になっています。我が家でも、相棒がパソコンで作業している真っ最中に強制アップデートがかかってしまい、大パニックになってしまいました。知人の中には、ある日朝起きてパソコンを立ち上げてみたらWindows10に変わっていた、なんて事態まで起こっています。私自身は、さすがに知らないうちにWindows10にアップデートされる、という事態は避けました。マイクロソフトからアップデートの予告状が来た時点で、いろいろと準備をしてアップデートに備えました。引用記事には「1時間半に及ぶOSの更新作業」とありますが、私の場合はそこまで時間はかからなかったかな。でも、小一時間はかかっています。で、Windows10にアップデートしたのですが、致命的な不具合が生じたので、すぐにWindows7に戻してしまいました。それが先週のことです。ただ、いずれにしても4年後にはWindiws7のサポートが切れてしまうので、その時にはWindows10にしなければなりません。マイクロソフトの戦略に乗るのは腹立たしいのですが、今ならWindows10へのアップデートはタダでできるし、7に戻すのも簡単。というわけで、致命的な不具合以外の、各種ソフトや周辺機器の動作状況を確認しておこうと、再びWindows10にアップデートしてみました。まず、「致命的な不具合」のことですが、何と音が出なくなってしまったのです。私はオンボードのサウンド機能ではなく、オンキョーのSE-U33GXVという外付のUSBサウンドを使っているのですが、これが古くてWindows10に対応していないようです。何秒かに1回、一瞬だけ音が出るという、どうにもならない状態です。私にとって、音の出ないパソコンなんて、役立たずもいいところなので、とても許容できません。が、相棒のパソコンはWindows10への強制アップデート以降も音は出ています。で、今回改めてWindows10にアップデートしてみたところ、オンボードサウンドはちゃんと音が出ます。ただ、SE-U33GXVはやっぱりダメです。最初にアップデートしたときは、USB機器はつけたままだったので、今回は、周辺機器を取り外してアップデートして、そのあとで接続しなおしてみたのですが、状況は変わりません。が、USBサウンドを外して、オンボードのサウンドにしてみると、ちゃんと音が出るのです。改めて、SE-U33GXVがWindows10に対応していない、ということが確認できました。まあ、とりあえず音は出るようになりましたが、オンボードサウンドよりはUSB外付のサウンドのほうが音はいいし、外部からの音の取り込みの端子が豊富なので、オンボードサウンドのままにはしておきたくない、というのが正直なところです。で、それ以外の不具合はというと、複数のパソコンでUSB機器を共有するためのUSBデバイスサーバがWindows10非対応のようで、USBデバイスサーバを介して接続しているスキャナが、接続できなくなりました。これは、相棒のパソコンからも同じ状態です。試しに、スキャナをデバイスサーバから外して、パソコンに直接接続してみたところ、ちゃんと認識しました。で、。USBデバイスサーバのドライバを探したところ、案の定Windows8.1までしか対応ドライバがないようです。一方、スキャナ(エプソンのGT-X750という機種)は、10年くらい前の古い機種にも関わらず、エプソンのホームページでWindows10対応ドライバが公開されています。これをインストールしたところ、パソコンに直結すれば問題なく動作するようになりました。USBデバイスサーバはやめて、USB切替機か何かにすればよい、ということでしょう。プリンタは、去年3月に買ったばかりなので、さすがに何もしなくてもWindows10に対応していました。それ以外は、目下のところ不具合はなさそうです。とうの昔にサポートが切れている、マイクロソフトのOffice2000(16年も前のワードとエクセル)も、問題なく動いていますし、Windows7から非対応になっている、古いバージョンのフォトショップLEも、問題なく動いています(若干の不具合はありますが、それはWindows7でもあった不具合と同じ)。それ以外にも、前世紀の音声編集ソフト、前世紀のMIDI編集ソフト、それよりはずっと新しい(5年くらい前に買った)動画編集ソフトなども、問題なく動いています。結局、Windows10で不具合なのは、USBサウンドとUSBデバイスサーバだけ、ということです。もう一つ、CD-Rの書き込みソフトが、この記事を書いている現時点ではどこかに行ってしまいました。でも、CD-Rの書き込みくらいは、いくらでも対応ソフトがあるでしょう。というわけで、二度目のアップデートでいろいろと検証してみて、Windows10にしても、致命的な問題はないことが分かりました。が、なんだか操作が分かりにくい。それに、オンボードサウンドだと、どうしても音質がね。というわけで、今回もいろいろ検証が終わったら再びWindows7に戻す予定です。4年後までには新しいパソコンを作ることになると思うので、Windows10を本格的に使うのは、その時からでいいかな。
2016.06.07
コメント(3)
-
着実に前進
沖縄県議選 基地移設反対派が大勝…知事与党上積み沖縄県議選(定数48)が5日投開票され、米軍普天間飛行場の辺野古への県内移設に反対する翁長雄志知事を支える共産や社民などの県政与党が過半数を維持、改選前より4議席多い27人が当選を確実にした。米軍属の女性遺体遺棄事件直後に選挙戦となり、反基地感情を反映し、米軍基地所在の選挙区で着実に議席を獲得した。翁長知事が引き続き政府との対決姿勢を強めるのは必至で、移設計画に大きな影響を与えそうだ。翁長知事は「大勝利と考えている。日本国土の0.6%の沖縄に74%の米軍専用施設を置いてきたことで、連続して事件事故が起きた。『沖縄に米軍基地が集中する状況がなくならない限り、だめだ』という県民の思いが今回のような選挙の結果になった」と述べた。今年1月の宜野湾市長選で、安倍政権の支援を受けた現職が、翁長知事が事実上擁立した新人に圧勝しており、知事の与党系は今回「連敗」を回避した。参院選沖縄選挙区も移設を進める自民が公認する現職と、移設反対の翁長知事を支えるグループが推す無所属新人との一騎打ちの見通しで、反対派には追い風となりそうだ。当日有権者は105万5881人。投票率は53.31%で、過去最低だった前回52.49%を上回った。(要旨)---最近、政治がらみで良いニュースを見ることがまれだったので、これは久しぶりによいニュースです。選挙直前に米軍軍属による殺人事件他たて続けに米軍がらみの犯罪が起きた影響も大きかったでしょう。(投票日の前夜にも、米海軍の女性下士官が飲酒運転による負傷事故を起こして、更に反基地感情に輪をかけることになった)ちなみに、投票率は52%あまりで、わずかながら前回を上回ったとのことです。この数字だけを見ると、あまり投票率が高くないように思えますが、県議選としては比較的高い部類です。昨年2015年4月の統一地方選では、41道府県で道府県議選が行われていますが、その平均投票率はわずか45%、投票率が5割を下回る府県が28もある(安倍のお膝元、山口県議選もそうです)のが現実です。もともと、都道府県議選というのは、国政選挙でもなく、市町村ほど身近でもないので、投票率が苦戦しがちです。この勝利を背景に、翁長知事は、辺野古への基地移設を拒否し続けるでしょうし、実際問題として、知事の抵抗を排除して辺野古への基地移設を行うのは非常に難しいでしょう。おりしも、選挙直前の先週5月27日に、沖縄県議会は普天間基地の県内移設断念と沖縄の全ての米海兵隊の撤退を求める抗議決議を採択しています。自民党は、これに反対たら、とても選挙を戦えないと判断したのでしょうか、決議への賛否を明かさないまま退席しました。普天間基地の県内移設は許さない、ということと、海兵隊は撤退しろ、という2点に関しては、沖縄の世論はゆるぎないものになっている、ということでしょう。逆に言えば、それ以外(つまり嘉手納の米空軍基地)については、やむをえない、ということでもあります。沖縄県議会が海兵隊撤退を決議するのは初めてなのだそうです。びっくりしましたが、かつてなら、共産党や旧社会党が「なんで海兵隊だけなんだ、すべての米軍撤退要求をすべきだ」と主張し、かといって「すべての米軍撤退要求」では自民党が反対するので、こんな決議を出すことはできなかったのかも知れません。元々は自民党出身の政治家である翁長知事も、日米安保破棄とか、すべての米軍基地ば出て行けなどとは言っていません。海兵隊と普天間基地に限って、沖縄から撤退しろ、ということに過ぎません。ある意味で現実的な主張ですが、それですら、今の政府の受け入れるところではないようです。そうやって、沖縄の要求を拒絶し続けると、どうなるのでしょうか。今は極小の勢力しか持たない沖縄独立論が、何らかのきっかけで急激に高まることもあり得るのではないでしょうか。そうなったら、普天間の海兵隊を守ろうとして嘉手納の空軍も失った、という結末になるかも知れません。
2016.06.06
コメント(3)
-

サクラも好きだけど、ツツジも好きです
当ブログでは、毎年4月にはあちこちで撮影したサクラ(たいていはソメイヨシノ)の写真をアップしていますが、実のところ私はサクラももちろん好きですが、それ以上にツツジのほうが好きだったりします。ところが、ブログではあまりツツジの写真をアップしたことがないことに気が付きました。東京では、ツツジの季節もほぼ終わりに近づいています(まだサツキは咲いているけれど)が、改めて写真を紹介しようと思います。日比谷公園で今年4月20日に撮影したものです。ツツジ属というグループに属する植物の総称がツツジなので、実は、ツツジという名のツツジは存在しません。都会で広く街路樹に使われているツツジは何ツツジかなと思って調べたところ、ヒラドツツジというのだそうです。そして、このヒラドツツジは、ケラマツツジ、モチツツジ、キシツツジを掛け合わせてつくられた手園芸種なのだそうです。その意味では、ソメイヨシノと同じです。これは、知りませんでした。以下しばらく、4月20日に日比谷公園で撮影したツツジの写真が続きます。この記事をアップしている6月5日現在では、東京のツツジ(ヒラドツツジ)の花はすべて終わっていますが、それより花期が遅いサツキは、まだまだ咲いているところが多くあります。これは、5月8日に撮影したものです。サツキは、ヒラドツツジより葉も花もだいぶ小ぶりです。先週登った那須岳にもツツジは咲いていました。上り始めてすぐのところに咲いていたツツジです。何ツツジかは分かりません。こちらは、大丸温泉に咲いていたものです。ヤマツツジではないかと思いますが、正確なところは分かりません。同じツツジのアップです。2006年7月に北海道の富良野岳で撮影したエゾツツジです。北海道と秋田・岩手の高山にだけ生えているツツジです。ところで、日本語ではツツジとシャクナゲは別々の植物として区別されますが、実のところ、ツツジとシャクナゲは同じ仲間であり、落葉性のものをツツジ、常緑性のものをシャクナゲと区別しているに過ぎません。日本語以外の言語、たとえば英語などでは、ツツジとシャクナゲの区別はありません。ハクサンシャクナゲ、亜高山帯(中部地方だと1500mから2500mくらいまで)で一般的なシャクナゲです。キバナシャクナゲ、上記のハクサンシャクナゲより高い、高山帯に分布するシャクナゲです。これも先週の那須岳で撮影した写真で、すでに紹介済みのものです。アップしたときは、何シャクナゲだろうと書きましたが、アズマシャクナゲのようです。前述のとおり、東京ではサツキが一部残っている以外は、ツツジの花期は終わってしまいました。これからはアジサイの季節です。アジサイの写真も、また気が向いたらアップしようかな、と思います。
2016.06.05
コメント(2)
-
雲仙普賢岳火砕流から25年
「災害、必ず復興できる」 雲仙・大火砕流25年、島原で追悼式雲仙・普賢岳の大火砕流から25年となった3日、被災地の長崎県島原市で追悼式典が開かれ、遺族らが黙とうした。島原市主催の式典は5年ぶり。会場の「島原復興アリーナ」内に設けられた祭壇を前に、遺族や消防関係者らが参列した。古川隆三郎市長は式辞で、犠牲者らを「市民の生命や財産を守るため、災害状況の取材や火山活動の研究などのため、職に殉じた」と哀悼。熊本地震にも触れて「災害は必ず復興できる」と述べ、被災地を激励した。(以下略)---あの火砕流から、もう25年も経ったのですか。時の流れの速さにびっくりです。この火砕流では、「定点」と呼ばれる、火砕流を正面至近に捉えられる撮影ポイントに多くのマスコミ関係者が集まっていたところを火砕流の直撃を受け、合計43名が亡くなるという大惨事になりました。マスコミ関係者が安易に危険地帯に足を踏み入れて犠牲になったことから、今日では、この火砕流はマスコミ批判の文脈で触れられることが多いようです。確かに、マスコミ関係者の行動にかなり問題がありました。たとえば、避難した民家にテレビカメラが入り込んでコンセントを借用するという事態があったようです。ただ、この大惨事はマスコミの不行状だけの問題で片付けられるものではありません。私の知る限り、この災害について最も詳しく検証した資料は、九州大学理研報の「雲仙火山1991年6月3日の火砕流による人的被害」であろうと思います。これによると、死者行方不明者の内訳は報道関係者16名とマスコミがチャーターしたタクシーの運転手4名、消防団員12名、警察官2名、一般人6名(うち3名は行方不明)、火山学者の外国人3名、合計43名です。死者・行方不明者のうち、31名は現場で、12名は病院搬送後に亡くなっています。負傷者は10名、報道関係2名と消防団1名、一般人7名です。亡くなった報道関係者は、読売新聞、毎日新聞、日経新聞、NHK(病院搬送後に死亡)、日本テレビ、テレビ朝日、KTNテレビ長崎、KBC九州朝日放送、「フォーカス」誌嘱託カメラマン。負傷しながら生還したのが朝日放送、間一髪危機を逃れたのが、長崎新聞社とNBC長崎放送、たまたまその日は取材に行かなかったのが共同通信と西日本新聞社。火砕流の危険性を認識し、この場所での取材を中止していたのが朝日新聞、ということです。犠牲者と負傷者がいた場所も特定されています。「定点」には一人の生存者もなく、全員その場で亡くなっています。そのほとんどがマスコミ関係者とタクシー運転手です。中には、タクシーに4人で乗った状態で車内で発見されている人もいます。危険を察知して、車で逃げようとして火砕流に追いつかれたのでしょうか。それ以外では、火山学者の外国人3名と、地元住民が1名も定点付近で亡くなっています(遺体で発見された地元住民の妻は行方不明で、おそらくその近くにいたのでしょう)。マスコミ関係者が警戒区域に立ち入るものだから、その警戒のために警戒区域に入った消防団員も火砕流に巻き込まれた、という説がネット上には散見されますが、実際には、マスコミ関係者が集まっていた「定点」近辺に、消防団員はいませんでした。ただし、直前まで「定点」のマスコミ関係者に避難を呼びかけていた警察官2名が、下記の農業研修所まで下がったところで火砕流に巻き込まれています。「定点」から約300m下った農業研修所近辺では、死者と生存者が交錯しています。屋外にいた人は全員亡くなり、生存者は全員屋内か車内にいた人に限られます。ただし、屋内・車内にいても亡くなっている方はいます。それでも、「定点」付近では自動車内にいた人も全員亡くなっている(そもそも、自動車が吹き飛ばされたり炎上したりしている)ので、ほんの300mの差で、人間の運命は大きく変わったようです。亡くなったうち2人(消防団員と一般人)は親子で、抱き合った状態で炭化しており、当初は1人の遺体と判断された、という記述は、何と言うか・・・・・・・言葉もありません。前述のように、死者・行方不明者6名と負傷者7名は一般人です。避難先から荷物や書類などを取りに一時帰宅していた人、眉山焼(陶器)の工場で作業をしていた方、葉タバコ畑で農作業を行っていた方、選挙のポスター掲示板撤去作業の委託業者などが火砕流に巻き込まれています。このあたりには葉タバコの畑が多いのだそうですが、実は翌日6月4日には、葉タバコ農家の組合が、タバコの花摘みを行う予定になっていたそうです。加えて、6月3日は天気が悪かったため、普段に比べて報道陣もかなり少なかったようです。(消防防災博物館の記述より)つまり、もしもこの火砕流が1日遅く発生していたら、一般人もマスコミ関係者も、43人どころではなく、それよりはるかに多くの犠牲者が出ていた可能性があるのです。で、これらのことから分かることは、報道陣もそうですが、地元住民も、火砕流という存在は知っていても、それがどれだけ危険なものか、という理解がなかった、ということです。直前にバイクで辛くも生還した警察官も、避難区域立入者に避難勧告を行いながらも、5合目付近まで雨雲に覆われて視界も悪かったため,本人自身もそんなに危機感を感じなかったと、述懐しています。そもそも、火砕流が日本で一般的に認知されたのは、この雲仙普賢岳の大惨事によってです。それ以前も、たとえば「ポンペイ最後の日」とかプレー火山の悲劇など、火砕流の怖さを知っている人は知っていたでしょうが、一般的な火山の危険性への理解は、まず高熱の溶岩流であり、高速で飛来する火山弾であり、火砕流がどれだけ危険なものかが一般に浸透していたとは思えません。そのことが、このような大惨事を招いた最大の原因なのだろうと思います。話は変わりますが、この雲仙普賢岳を犠牲者数で上回り、戦後最悪の火山災害となったのが、一昨年の木曽御嶽山の噴火でした。このとき犠牲になった方々は、ほとんどが噴火に伴う火山弾の直撃を受けたことが原因でした。実は、火砕流も起こっており、それに巻き込まれた方も少なからずいるのですが、御嶽山では火砕流によって亡くなった方はいません。それは、御嶽山で起こった火砕流が、雲仙普賢岳のものに比べてはるかに低温だったからです。※もちろん、低温というのは、うずくまって耐えればかろうじて火傷を回避できる、という程度の話です。熱くて焼け死ぬかと思ったとの証言はあり、軽い火傷を負った人もいるので、低温と言っても100度を多少下回る程度だったのでしょう。しかし、普賢岳の場合は数百度なので、比較になりません。両者の差は、噴火の規模が雲仙普賢岳に比べて御嶽山ははるかに小さかったこと、普賢岳はマグマそのものによる火山爆発だったのに対して、御嶽山はマグマそのものではなく、マグマに触れた地下水の爆発による噴火(水蒸気爆発)だったことによって生じたのでしょう。それにしても、もし雲仙普賢岳の噴火がなくて御嶽山の噴火が起こっていたとしたら、火砕流とは、うずくまってやり過ごせば、生身の人間でも耐えられるもの、という誤った認識が広まっていたかもしれません。いや、実は普賢岳の噴火当時も、火砕流について「長袖を着ていれば被害を防げる」という俗説が流布していたのだそうです。そのような誤った認識を更に助長することがなかったのは、せめてもの不幸中の幸いだったかもしれません。何も火山に限ったことではありませんが、災害についての正しい知識というのは重要だなと、改めて思いました。
2016.06.04
コメント(2)
-
奇跡の生還・・・・・・
不明小2男児、陸自施設で発見…水だけで6日間3日午前7時50分頃、北海道七飯町東大沼の山中で5月28日から行方不明となっていた北斗市の小学2年が、約5km離れた鹿部町内の陸上自衛隊駒ヶ岳演習場内で6日ぶりに発見、保護された。道警によると、水だけで過ごしていたが、比較的元気だといい、函館市の市立函館病院で手当てを受けている。道警などの発表によると、行方不明となった七飯町の山中から北東に約5km離れた演習場内の「廠舎」と呼ばれる宿営施設の中で、演習のため訪れた自衛隊員に発見され、手渡したおにぎりと飲み物を口にした。発見時「(廠舎まで)1人で歩いて来た。28日夜から(廠舎の中に)いた。雨宿りをして、水を飲んで過ごした」と説明。鍵が開いていた廠舎に入り、夜は厚さ約5cmのマットレス2枚の間に入り込んでいた。廠舎には水が出る蛇口が備え付けられていた。---6月とはいえ、北海道では昨日雪も降ったそうです。行方不明当時半そでだったという小学校2年生が1週間生き延びているとは、恥ずかしながらとても予想できませんでした。一時は自衛隊が捜索に加わっていましたが、その際は1m間隔で並んでのローラー作戦と報じられており、もう生きている本人を探す体制ではなく、遺体を捜す体制だなと思ったものです。ところが、何と生きていた。それも、行方不明場所から5kmも離れたところで。建物を見つけて、その中に入り込むことができたこと、マットレスがあって寒さをしのげたこと、水だけは飲むことができたことが奇跡を呼んだのでしょう。7歳の子どもが、森の中一人ぼっちで5km移動して(直線距離での5kmなので、歩いた距離はもっと長いでしょう)、建物を見つける、大変な幸運であり、また驚くべきタフさです。だから生還できたのでしょう。まあ、それにしても、わたしも、子どもと出かけるたびに、よく子どもを置き去りにして姿をくらましたりしていた。そういうことをやる親は少なくないでしょうし、この親も、まさかこんなことになるとは思わないでやったのでしょうが、ただ私の場合は、本当に姿をくらましたわけではなく、物陰から様子は伺っていました。本当に迷子になりそうだったらすぐに飛び出して行きました。そこで本当に姿をくらますと、こんなことになってしまうんですね。街中じゃなくて山の中というのも、よくなかった。もっとも、我が家では、散々その種の「かくれんぼ」をやったおかげで、最近は子どものチェックが厳しく、私が姿をくらまそうとすると、ピタッと付いてくるのです(笑)だから、子どもは容易には私を見失わなくなりました。
2016.06.03
コメント(4)
-
それは、誤ってではないのでは?
露外務省報道官様 「産経のインタビューに応じるな」 公式文書をあろうことか産経に発送 「たるんでませんか?」拝啓 ロシア外務省ザハロワ報道官様貴職の発した公式文書がモスクワ支局に届いたのは2週間ほど前のことです。「産経新聞は日本の主要活字メディアの中で、ナショナリズムの方向性によって特別の地位を占めている。ロシアに関する多くの記事は批判的、時に攻撃的であり、事実はしばしば歪曲され、否定的な見地で伝えられる。最近の反露的な報道も踏まえ、同紙のインタビューには応じるべきでないと考える」書簡は私たちが取材を申し込んだ某国家機関に宛てたものですね。それがあろうことか、私たちのもとに届いたのです。露外務省には平素よりたいへんお世話になっており、事を荒立てるつもりは毛頭ありません。この種の文書を作成することも、貴国では外務省の重要な業務なのでしょう。「事実を歪曲」などという完全な中傷には抗議しておきますが。何より心配なのは、大国ロシアの外交を担う外務省が、公式文書を誤って発送するという初歩的ミスを犯した事実です。最近のロシアの官庁は大統領閣下の追従に熱心なあまり、本質的なところで劣化しているような気がしてなりません。日露間の最大懸案である北方領土問題には、ぜひ気を引き締めて臨んでいただきたいものです。敬具---へえ、そんなことがあったんですねえ。もしこれが事実なら、ロシア外務省のドジぶりに大笑いするところですが、だけどそれって「誤って」ではないだろうと思うのですがどうでしょう。つまり、誤った「ふり」をしてわざと送ったのだろうと。要するに、「お前らのインタビューに応じる気などない」ということを、さりげなく分かりやすく(笑)断固とした意思をもって伝える、もっとも手っ取り早いやり方だからです。もっとも、いかにネトウヨ脳の産経新聞といえども、その程度の可能性に思い至らないほどにはバカではないでしょうから、これまた、ロシア外務省が本当は「誤って」ではなかった可能性に気が付きつつも、気が付かないフリをしてこんな記事を書いているだけだろうと思いますけどね。つまり、狐と狸のばかしあい、という奴でしょうね。まあしかし、ロシア自身はどうなのか、ということを度外視して言えば、「産経新聞は日本の主要活字メディアの中で、ナショナリズムの方向性によって特別の地位を占めている。ロシアに関する多くの記事は批判的、時に攻撃的であり、事実はしばしば歪曲され、否定的な見地で伝えられる。」という評は、まったくそのとおりだと私も思いますね。もっとも、最近の産経は中国韓国攻撃に忙しいので、相対的にロシアを非難する頻度は冷戦時代よりは大幅に減っているように思いますが。
2016.06.02
コメント(2)
-

私は言ってない、と言われても
<世耕・官房副長官>釈明 首相のリーマン前発言「なかった」世耕弘成官房副長官は5月31日の記者会見で、伊勢志摩サミットでの安倍晋三首相の発言について、「『リーマン・ショック前に似ている』とは発言していない。私が少し言葉足らずだった」と釈明した。世耕氏は26日の世界経済に関する議論の後、記者団に「首相は『リーマン前の状況に似ている』と申し上げ、各国首脳と認識は一致している」と説明した。首相はサミットで、各種の経済指標がリーマン・ショック時と同様に悪化していることを示すペーパーを使い、経済の「下方リスク」を強調した。ただ、海外メディアはこの説明を「世界経済が着実に成長する中、説得力のない比較」(英紙フィナンシャル・タイムズ)などと批判的に報じた。自民党内にも異論が広がっており、火消しが必要と判断したようだ。首相自身も30日の自民党役員会で「私が『リーマン前に似ている』との認識を示したとの報道があるが、全くの誤りだ。新興国経済を巡る指標で、リーマン以来の落ち込みがあるとの趣旨だ」と語った。---いやはや、何と言うか、「首相は『リーマン前の状況に似ている』と申し上げ、各国首脳と認識は一致している」と世耕弘成官房副長官が記者団に説明し、それが記事になったら「私はそんなことを言っていない」と。ならば、悪いのはウソを伝えた世耕官房副長官、ということになります。「報道があるが、まったくの誤りだ」などと居直る前に、「官房副長官が報道陣に伝えたことはまったく誤りだ」と言いなおすべきじゃないでしょうか。でも、安倍が言ったのは「新興国経済を巡る指標で、リーマン以来の落ち込みがあるとの趣旨」だそうですが、それと「リーマン前の状況に似ている」という言葉と、大筋の趣旨としては、ほとんど違いがないように、私には見えます。世耕もそう思ったから、そのように説明したのでしょう。そもそも、「リーマンショック前に似ている」発言は、様々な場で記者団からの質問の的になっていますが、安倍自身が、31日に急に言い出すまでは、「私はそんなことは言っていない」などとは一言も言っていません。この中でも、記者からの「総理は、本日の会議で世界経済の状況はリーマンショック前に似ているとの考えを示したようですけれども?」との問いに対して「世界経済は大きなリスクに直面をしているという認識については、一致することができた」と安倍自身が答えています。「私はそんな認識は示していない」などとは言っていないのは、当の安倍自身だって、そのときまでは「リーマン前の状況に似ている」という説明が自分の発言の要約として、少なくとも目くじらを立てるほど外れたものではないと思っていたからでしょう。それが、あまりに批判が多く、特に諸外国から鼻で笑われるものだから、急に「そんなことは言っていない」と取って付けたように言い出す、実に見苦しいことです。
2016.06.01
コメント(6)
全27件 (27件中 1-27件目)
1
-
-

- ★つ・ぶ・や・き★
- 🔥世の中昨日で3連休昨日で終わり….…
- (2025-11-25 04:09:20)
-
-
-

- あなたのアバター自慢して!♪
- 韓国での食事(11月 12日)
- (2025-11-15 02:35:31)
-
-
-

- 写真俳句ブログ
- 南天の実(赤) 柊の花(白)
- (2025-11-24 22:51:14)
-







