PR
X
カレンダー
カテゴリ
カテゴリ未分類
(2)読書案内「日本語・教育」
(22)週刊マンガ便「コミック」
(81)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝
(36)徘徊日記「日帰りでお出かけ」
(79)演劇・芸能「劇場」でお昼寝
(5)映画「元町映画館」でお昼寝
(135)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝
(62)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝
(121)読書案内「映画館で出会った本」
(20)読書案内「翻訳小説・詩・他」
(52)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」
(25)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり
(54)読書案内「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」
(29)読書案内「現代の作家」
(103)徘徊日記「お泊りでお出かけ」
(76)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり
(102)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ
(51)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」
(86)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」
(33)読書案内「近・現代詩歌」
(58)徘徊「港めぐり」
(4)バカ猫 百態
(23)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」
(21)読書案内「水俣・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」
(18)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」
(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝
(3)映画「こたつシネマ」でお昼寝
(13)映画「パルシネマ」でお昼寝
(32)読書案内「昭和の文学」
(25)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05
(23)読書案内「くいしんぼう」
(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝
(18)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」
(9)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」
(40)週刊マンガ便「鈴ノ木ユウ・野田サトル」
(22)ベランダだより
(167)徘徊日記 団地界隈
(141)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり
(27)徘徊日記 須磨区あたり
(34)徘徊日記 西区・北区あたり
(11)徘徊日記 灘区・東灘区あたり
(46)徘徊日記 美術館・博物館・Etc
(5)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」
(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり
(12)読書案内「大江健三郎・司修・井上ひさし・開高健 他」
(14)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」
(3)読書案内「谷川俊太郎・大岡信 あたり」
(21)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」
(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」
(11)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」
(22)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」
(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて
(8)読書案内「村上春樹・川上未映子」
(17)映画・読書案内 パレスチナ・中東
(19)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」
(7)映画 韓国の監督
(25)映画 香港・中国・台湾の監督
(40)アニメ映画
(24)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢
(55)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭
(25)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行
(16)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督
(41)映画 イタリアの監督
(22)映画 ドイツ・ポーランド他の監督
(29)映画 ソビエト・ロシアの監督
(14)映画 アメリカの監督
(99)震災をめぐって 本・映画
(9)読書案内「旅行・冒険」
(4)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」
(15)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督
(5)映画 フランスの監督
(53)映画 スペイン・ポルトガルの監督
(13)映画 カナダの監督
(5)映画 グルジア(ジョージア)の監督
(14)映画 ウクライナ・リトアニア・ラトビア・エストニアの監督
(9)映画 イスラエルの監督
(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督
(6)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督
(13)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督
(11)映画 トルコ・イラン・カザフスタンあたりの映画監督
(12)映画 ギリシアの監督
(3)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルー・チリの監督
(8)映画 ハンガリー・ルーマニアの監督
(5)映画 アフリカの監督
(3)映画 スイス・オーストリアの監督
(4)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家
(3)読書案内・アニメ・コミック ジブリ
(7)週刊マンガ便「小林まこと」
(9)読書案内「野口武彦・前田愛・橋川文三・藤井貞和」
(3)映画 インド・ネパール・ブータン・アフガニスタン・タイ・ベトナム あたりの監督
(5)週刊マンガ便・映画 キングダム 原泰久・佐藤信介
(20)読書案内「川上弘美・小川洋子・佐伯一麦」
(9)読書案内「立花隆・松岡正剛」
(5)徘徊日記 神戸の狛犬
(5)週刊読書案内「保坂和志・柴崎友香・磯崎憲一郎とか」
(11)読書案内・映画 沖縄
(10)読書案内 韓国の文学
(5)週刊マンガ便・映画 武田一義 こうの史代
(9)映画 ミュージシャン 映画音楽
(11)映画 「109ハット」でお昼寝
(6)読書案内 エッセイ
(4)読書案内 「茨木のり子・石垣りん」
(13)映画「キノシネマ神戸国際」でお昼寝
(5) 徘徊日記 2025年12月2日(火)「オッ!さんぽ 団地で紅葉狩り(笑)。」団地あたり
週刊 マンガ便 原泰久「キングダム 77」(集英社)
マヤ・チュミ「ロツロッホ」元町映画館no329
徘徊日記 2025年11月29日(土)「京都御所のイチョウ並木!」京都御所あたり
イヴ・イェルサン「小さな逃避行」元町映画館no328
徘徊日記 2025年11月29日(土)「なぜか、京都御所です!紅葉です!黄葉です!」京都御所あたり
週刊 マンガ便 富樫義博「ハンター×ハンター(4~6)」(集英社)
秋山純「栄光のバックホーム」109シネマズ・ハットno71
三宅唱「旅と日々」シネリーブル神戸no337
徘徊日記 2025年11月27日(木)「いよいよ山茶花ですよ。」団地あたり
週刊 マンガ便 原泰久「キングダム 77」(集英社)
マヤ・チュミ「ロツロッホ」元町映画館no329
徘徊日記 2025年11月29日(土)「京都御所のイチョウ並木!」京都御所あたり
イヴ・イェルサン「小さな逃避行」元町映画館no328
徘徊日記 2025年11月29日(土)「なぜか、京都御所です!紅葉です!黄葉です!」京都御所あたり
週刊 マンガ便 富樫義博「ハンター×ハンター(4~6)」(集英社)
秋山純「栄光のバックホーム」109シネマズ・ハットno71
三宅唱「旅と日々」シネリーブル神戸no337
徘徊日記 2025年11月27日(木)「いよいよ山茶花ですよ。」団地あたり
コメント新着
キーワードサーチ
▼キーワード検索
三浦雅士 「漱石 母に愛されなかった子」(岩波新書)
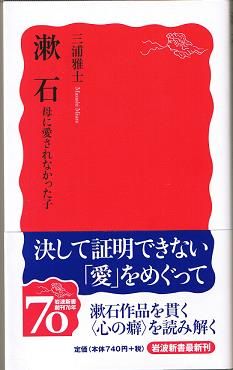
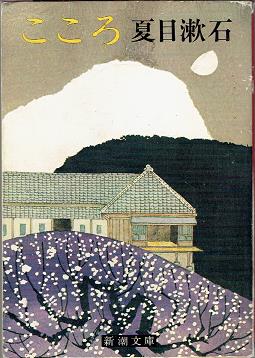 評論 「漱石」(岩波新書)
の中で 三浦雅士
は 「こころ」
のこの部分を取り上げてこういっています。
評論 「漱石」(岩波新書)
の中で 三浦雅士
は 「こころ」
のこの部分を取り上げてこういっています。
しかし、この小説の面白さ、本当の悲劇性は、そのような男たちの傍らに 「悲しくなってしようがない」 奥さんを描いているところにあるのではないでしょうか。
現代社会に生きているぼくから見て、 先生 や K のような男性にさほどのリアリティを感じることは出来ません。現代にも通じる普遍的な悲しみは、むしろ、この 奥さん の悲しみの方にこそ、真実があるのではないでしょうか。
愛し合って暮らし始めたはずの二人の人間は、互いを本当に知り合うことは出来るのでしょうか。
「こころ」 の解釈をめぐって、妻の お静 が 先生とK との間にあったことに最後まで気付かないのは不自然だという考え方があります。そうでしょうか。ぼくにはそうは思えないのです。
親子であることの 「愛」 を信じ切れなかった 漱石 が書いたから言うわけではありません。我々は、親子であるとか、夫婦であるとかという関係によって、何かをより深く知るという契機を、本当に、与えられているのでしょうか。むしろ、信じるとか、悪くいえば分かったつもりになることによって、相手を見失っているのではないでしょうか。
ぼくには、単なる他人ではなく、 夫婦だからこそ、 お静 に 先生 が抱えもっている謎を解く方法があるとは思えないのです。
一方で、人は心の奥底にある 「ほんとうの姿」 を誰かに伝えることができるのかと考えれば、 先生 の沈黙は自然だとも思います。そのような、夫の不機嫌な沈黙の謎に、妻であるお静はどうすれば近づくことができるのでしょう。
相手の心に寄り添い続けている人間だからと言って、相手の心の謎を解くことができるのでしょうか。
解くためには、ひょっとすると、寄り添うことをやめるしかないのではないかとぼくには思えます。
迂闊とも見える お静 の 「気付かなさ」 は、むしろ 「自然」 と呼ぶべきではないでしょうか。そして、その 「気付かなさ」 中にこそ人間の普遍的な哀しさがあることを小説は描いているのではないでしょうか。
実は、 先生 にも お静 の哀しさが見えていないことがそれを証していると思うのです。
三浦雅士 は、 評論「漱石」 の中で、作家 漱石 を 「母の愛を疑い続けながら、その疑いを隠し続けた人間」 として捉え、彼のすべての作品の底には、その〈心の癖〉が流れていると論じています。
たとえば、ユーモア小説として名高い 「坊ちゃん」 の下女「おきよ」に対する、偏執的とも言える坊ちゃんの甘え方は、その具体例であるという具合に。
三浦 の論に、誰もが納得できるかどうかはわかりません。しかし、ぼくには先生とお静のこの場面を引用し、ここに 漱石 の〈心の癖〉が露見しているという 三浦 の指摘はかなり納得のいくものに思えます。先程いいましたが、この場面にこそ、 漱石 のこの作品の「凄さ」があると思うからです。
先生はKのまなざしを、おそらく死ぬまで怖れ続けますが、一方で奥さんの悲しい愛のまなざしが注がれ続けていることには気付けません。それは、確かに母の愛を信じられなかった男性の宿命のようなものかもしれませんが、ひょっとすると、それは人間というものの他者との出会いの宿命であるともいえるかもしれません。
しかし 、 漱石 は、先生の「心の謎」も含めて、全てを受け入れようとする「お静」の姿をこそ描いているのです。ここが、 漱石 のすごいところだと言えないでしょうか。
良い評論というのは、論点の面白さはもちろんですが、引用の上手さに、唸るような面白さを持っているものです。 三浦雅士 の 「漱石」 は随所に目からうろこの引用の山です。この評論をガイドにして漱石を通読してみるなんていうのはいかがでしょうか。(S)2018/10/04
追記2019・05・11
以前の記事をかなり書き直しました。 三浦雅士 の紹介というより、ぼく自身の 「こころ」 に対する感想というニュアンスの方が強くなりましたが、読んでいただけると嬉しいです。
ボタン 押してね!

にほんブログ村

にほんブログ村





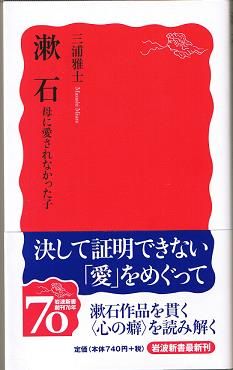
先生は「おい静」といつでも襖の方を振り向いた。その呼びかたが私には優しく聞こえた。返事をして出て来る奥さんの様子も甚だ素直であった。ときたまご馳走になって、奥さんが席へ現われる場合などには、この関係が一層明らかに二人の間に描き出されるようであった。― 中略 ― 高校の教室で出会うことがある 夏目漱石「こころ」(新潮文庫) の一節ですが、教科書には載っていない 「先生と私」 のはじめの頃に出てくる描写です。
当時の私の眼に映った先生と奥さんの間柄はまずこんなものであった。そのうちにたった一つの例外があった。ある日私がいつもの通り、先生の玄関から案内を頼もうとすると、座敷の方でだれかの話し声がした。よく聞くと、それが尋常の談話でなくって、どうも言逆いらしかった。先生の宅は玄関の次がすぐ座敷になっているので、格子の前に立っていた私の耳にその言逆いの調子だけはほぼ分った。
そうしてそのうちの一人が先生だという事も、時々高まって来る男の方の声で解った。相手は先生よりも低い音なので、誰だか判然しなかったが、どうも奥さんらしく感ぜられた。泣いているようでもあった。私はどうしたものだろうと思って玄関先で迷ったが、すぐ決心をしてそのまま下宿へ帰った。(夏目漱石「こころ」)
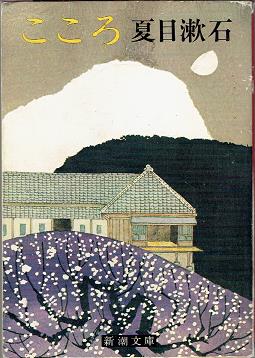 評論 「漱石」(岩波新書)
の中で 三浦雅士
は 「こころ」
のこの部分を取り上げてこういっています。
評論 「漱石」(岩波新書)
の中で 三浦雅士
は 「こころ」
のこの部分を取り上げてこういっています。
『心』 は冒頭、語り手の学生が、先生の淋しさ、奥さんの美しさを強調し、先生と奥さんは仲のよい夫婦の一対であったと断言するために、夫婦の危機などおよそ感じられないのだが、将にその断言と同時に、先生と奥さんの喧嘩もまた報告されるのである。玄関先で言い争う声を聞き、奥さんが泣いているようでもあったので語り手は遠慮して下宿に帰るのだが、約一時間後に先生がわざわざ呼び出しに出てきて一緒に散歩に出ることになる。 一人の女性をめぐって、三角関係に陥った二人の男性が、自殺することで自らの生き方の筋を通そうとする。そこのところを、たとえば教科書を作っている人たちは高校生に読ませたがる。そういう、いわば教養小説として 「こころ」 は読まれ続けてきました。
妻と喧嘩して神経を昂ぶらせたのだというのです。
どうして、という語り手の問いに、先生は、妻が自分を誤解する、それを誤解だといっても承知しないので、つい腹を立てたと答える。
この経緯は、後に、奥さんの口からも語られます。先生は世間が嫌いだ、人間が嫌いだ、従ってその一人である自分のことも嫌いだ、そうとしか思えないというのです。
私はとうとう辛抱しきれなくなって聞きました、と奥さんは続けます、私に悪い所があるのなら遠慮なくいってください、改められる欠点なら改めるからって、すると先生は、お前に欠点なんかありゃしない、欠点は俺の方にあるだけだというんです、そう言われると私、悲しくなってしようがないんです、涙が出てなおのこと自分の悪い所を聞きたくなるんです、と奥さんはそう物語るのである。
先生夫婦を危機に陥れているのいったい何か。なぞめいているその謎に気を取られてしまうために、この若くして引退したとでも言うほかない淋しい夫婦の溝は薄められるだけ薄められてしまっているのだが、しかし、危機にあることに変わりはない。
(三浦雅士「漱石」)
しかし、この小説の面白さ、本当の悲劇性は、そのような男たちの傍らに 「悲しくなってしようがない」 奥さんを描いているところにあるのではないでしょうか。
現代社会に生きているぼくから見て、 先生 や K のような男性にさほどのリアリティを感じることは出来ません。現代にも通じる普遍的な悲しみは、むしろ、この 奥さん の悲しみの方にこそ、真実があるのではないでしょうか。
愛し合って暮らし始めたはずの二人の人間は、互いを本当に知り合うことは出来るのでしょうか。
「こころ」 の解釈をめぐって、妻の お静 が 先生とK との間にあったことに最後まで気付かないのは不自然だという考え方があります。そうでしょうか。ぼくにはそうは思えないのです。
親子であることの 「愛」 を信じ切れなかった 漱石 が書いたから言うわけではありません。我々は、親子であるとか、夫婦であるとかという関係によって、何かをより深く知るという契機を、本当に、与えられているのでしょうか。むしろ、信じるとか、悪くいえば分かったつもりになることによって、相手を見失っているのではないでしょうか。
ぼくには、単なる他人ではなく、 夫婦だからこそ、 お静 に 先生 が抱えもっている謎を解く方法があるとは思えないのです。
一方で、人は心の奥底にある 「ほんとうの姿」 を誰かに伝えることができるのかと考えれば、 先生 の沈黙は自然だとも思います。そのような、夫の不機嫌な沈黙の謎に、妻であるお静はどうすれば近づくことができるのでしょう。
相手の心に寄り添い続けている人間だからと言って、相手の心の謎を解くことができるのでしょうか。
解くためには、ひょっとすると、寄り添うことをやめるしかないのではないかとぼくには思えます。
迂闊とも見える お静 の 「気付かなさ」 は、むしろ 「自然」 と呼ぶべきではないでしょうか。そして、その 「気付かなさ」 中にこそ人間の普遍的な哀しさがあることを小説は描いているのではないでしょうか。
実は、 先生 にも お静 の哀しさが見えていないことがそれを証していると思うのです。
三浦雅士 は、 評論「漱石」 の中で、作家 漱石 を 「母の愛を疑い続けながら、その疑いを隠し続けた人間」 として捉え、彼のすべての作品の底には、その〈心の癖〉が流れていると論じています。
たとえば、ユーモア小説として名高い 「坊ちゃん」 の下女「おきよ」に対する、偏執的とも言える坊ちゃんの甘え方は、その具体例であるという具合に。
三浦 の論に、誰もが納得できるかどうかはわかりません。しかし、ぼくには先生とお静のこの場面を引用し、ここに 漱石 の〈心の癖〉が露見しているという 三浦 の指摘はかなり納得のいくものに思えます。先程いいましたが、この場面にこそ、 漱石 のこの作品の「凄さ」があると思うからです。
先生はKのまなざしを、おそらく死ぬまで怖れ続けますが、一方で奥さんの悲しい愛のまなざしが注がれ続けていることには気付けません。それは、確かに母の愛を信じられなかった男性の宿命のようなものかもしれませんが、ひょっとすると、それは人間というものの他者との出会いの宿命であるともいえるかもしれません。
しかし 、 漱石 は、先生の「心の謎」も含めて、全てを受け入れようとする「お静」の姿をこそ描いているのです。ここが、 漱石 のすごいところだと言えないでしょうか。
良い評論というのは、論点の面白さはもちろんですが、引用の上手さに、唸るような面白さを持っているものです。 三浦雅士 の 「漱石」 は随所に目からうろこの引用の山です。この評論をガイドにして漱石を通読してみるなんていうのはいかがでしょうか。(S)2018/10/04
追記2019・05・11
以前の記事をかなり書き直しました。 三浦雅士 の紹介というより、ぼく自身の 「こころ」 に対する感想というニュアンスの方が強くなりましたが、読んでいただけると嬉しいです。
ボタン 押してね!
にほんブログ村
にほんブログ村



お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」] カテゴリの最新記事
-
週刊 読書案内 デイヴィッド・ピース「X… 2025.02.22 コメント(3)
-
週刊 読書案内 夏目漱石「文鳥」(「文… 2024.12.14
-
週刊 読書案内 半藤一利編「夏目漱石 … 2024.10.11
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.













